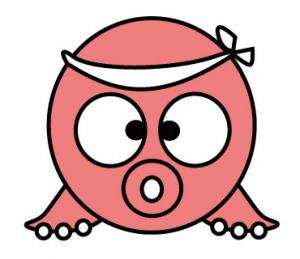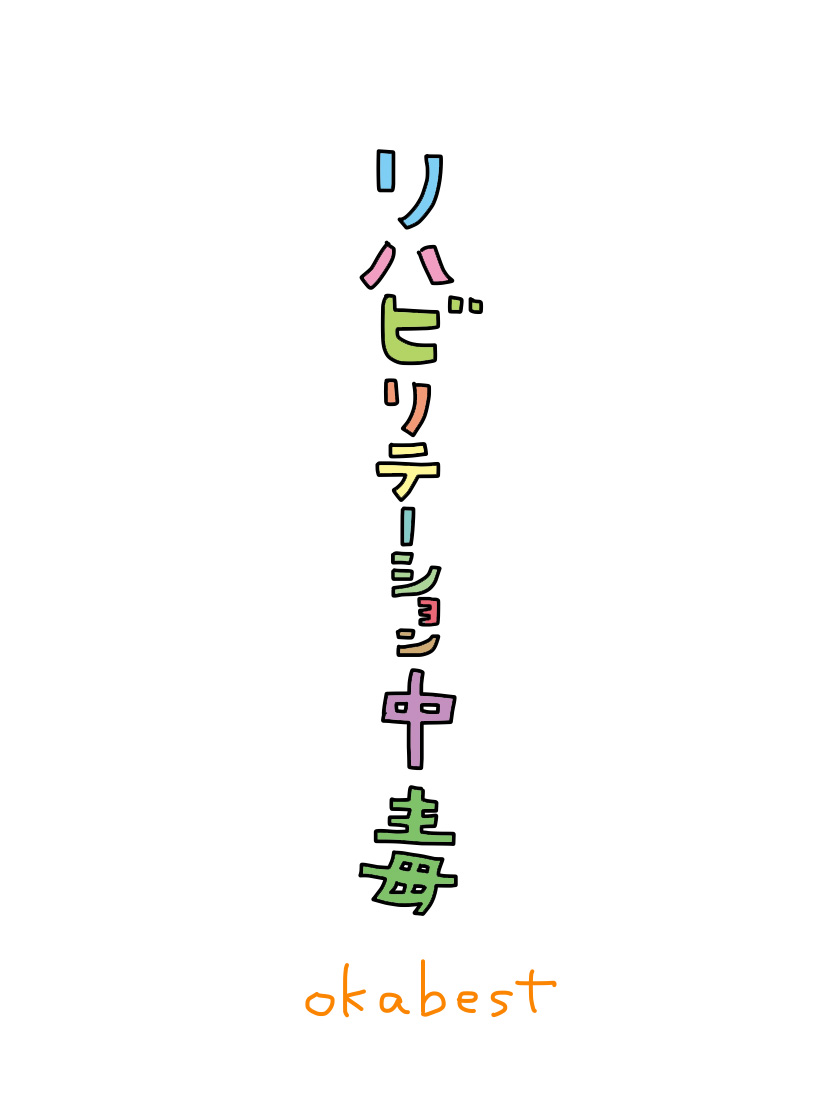
リハビリテーション中毒
第一章 麻薬(1)
生き抜く力。リハビリテーションの力。日本は世界に類を見ない超高齢社会となった。その社会を生き抜くために、政府は対策としてリハビリテーションという考えを日本全国に浸透させ、最期まで元気に過ごせるよう、長い時間費やして宣伝を行い、日本国民に浸透させてきた。
高齢社会という言葉が出始めた頃から、「今後二〇二五年には団塊の世代が全て後期高齢者となり、高齢者の人口は爆発的に増え、社会保障費は膨れ上がり、日本は破滅する。」と騒がれてきた。政府はその対策として、予防医学という第三の医療を取り入れ、「予防が大切」というスローガンを立ち上げた。その一番の対象が「リハビリテーション」であった。
政府は「リハビリテーション」を一大ブームに引き立てようと考えていた。その手段として、政府は自治体に働きかけるだけでなく、企業に働きかけてリハビリテーショングッズの開発を依頼したり、リハビリテーション体操というものを国独自で提案したりした。そして、そのリハビリテーショングッズやリハビリテーション体操を地域単位で購入または実施した市区町村には補助金を与え、税金を投入して活用を斡旋した。このようにして、地道な努力により、「リハビリテーション」という考え方をより多くの日本国民に浸透させていった。そして、二〇二〇年の東京オリンピック開催が決定したことも追い風となり、国民は運動することにさらに注目するようになった。
テレビ番組ではオリンピックの特番を放送するようになった。その特番の中で、前回のオリンピックの映像が頻繁に放送された。それを見ていた高齢者は昔を思い出し、若い頃の自分を重ねて体を動かすようになった。それに便乗した政府は「東京オリンピックリハビリテーション ~あの頃の自分になろう~」というキャッチコピーを作り上げ、高齢者のリハビリテーションに力を注いでいった。
こうした努力が実り、「リハビリテーション」という言葉は日本国民に意識高く浸透していき、二〇二〇年には流行語にノミネートするくらい「リハビリテーション」という言葉が日常的に使われるようになっていった。
政府は介護保険分野にもリハビリテーションの考え方を浸透させるために様々な方法をとった。今まで介護保険分野ではリハビリテーションに関してのみ開業権を与えることはしなかったが、この東京オリンピックの勢いを利用してリハビリテーション分野にも開業権を与え、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーションの事業者数を爆発的に増加させるよう規制緩和を行い、働きかけた。これにより、高齢者はリハビリテーションを利用しやすくなり、介護保険利用者数を増加させ、健康増進に役立てた。高齢者は元気な姿になることが増えたのだった。
こうして、町中では「リハビリテーション」という言葉は一時の流行語だけに止まらず、二〇三〇年になっても当たり前のように使われる、一般的な言葉として定着していたのだった。そして、日本は超高齢社会を生き抜く姿を世界に見本となれるようになっていた。
「リハビリテーション」という言葉が一般的になったため、リハビリテーションという仕事も注目されるようになっていた。特に、国家資格でもあり、リハビリテーションという分野の中核を担うと言われる理学療法士という資格は爆発的な人気を示していた。
理学療法士になるためには養成校に入学し、無事に卒業して、さらに国家試験に合格しなければならず、いくつもの試練を乗り越えなければ得られない資格だった。無事に養成校に入学できたとしても、最低でも三年、長くて四年通わなければならず、カリキュラムも過密であり、普通の大学よりも忙しい毎日を過ごさなければ卒業できないシステムになっていた。そして国家試験も年々難しくなっているため、合格するためには娯楽を我慢しなければ間に合わないほど、大量の学習内容となっていた。
蒲田浩一は理学療法士の養成校に指定されている帝都大学健康促進学部理学療法学科の専任講師として勤めていた。人気のある理学療法学科は入学できる倍率が三〇倍近くにもなっていた。リハビリテーションの中核として役に立てる仕事という意味で人気が高いだけでなく、開業権を与えられたことによって今後の超高齢社会を見越し、需要があると考え、起業をしたいという独立志向の強い生徒も増えたことも要因だった。そして、何よりも手に職を得るという意味から、これからまだまだ続くと考えられている超高齢社会において、リハビリテーションの必要性は途絶えることは考えにくく、安定した仕事量が見込めるため、なりたい職業ランキングでも常にトップ一〇に入るほど人気になっていた。
蒲田はこの帝都大学健康促進学部理学療法学科を卒業し、帝都大学付属病院に二十年間臨床業務を行ってこの学校の専任講師をしていた。生徒たちは高い倍率を戦い抜いてきた生徒だけあって、まじめな生徒が多かった。授業はほとんどの生徒は睡眠をとらず、一生懸命にノートやメモを取っていた。蒲田が少し冗談を言ってもあまり笑うことは無かった。それでも講師として、まじめに勉強に取り組んでくれる姿を見るのが蒲田にとってうれしかった。
そして何よりも代え難い事は、いずれ卒業していった生徒が、立派な理学療法士として育ち、同じ仲間として働くことが出来ることが、蒲田自身この仕事のやりがいとなっていた。
しかし、退学する生徒も少なくはなかった。入学してから勉強の多さに諦めて自主退学をしたり、勉強に付いていけず進学出来ない理由で退学を選択したり、授業料も多いことから経済的理由で退学する生徒も多かった。入学時に四〇名いた生徒も卒業時には二〇名ほどまで毎年少なくなっていた。そして卒業しても国家試験が残っていて、それに合格をして初めて理学療法士になれるのだが、その合格率も近年は三〇パーセントと少なく、理学療法士は狭き門の一つもなっていた。生徒を無事に国家資格である理学療法士にならせるためには、各養成学校で様々な苦労があった。
蒲田も例外ではなく、そうした悩みを常に抱えていた。その悩みを解消するために、仕事帰りに居酒屋「目黒」に行くことが多かった。居酒屋「目黒」には大学時代の同級生である竹下が毎日のように居ては日本酒を沢山飲んでいた。竹下も同じ理学療法士であり、同じ教室で勉強し会った同級生と言うことで、蒲田にとって悩みを話しやすい相手でもあった。
居酒屋「目黒」には変わった食べ物はなく、ごくシンプルなメニューを取りそろえたお店だった。お酒の種類は焼酎を初めとして、ビールや日本酒を品数は少ないものの、品質は高く、こだわって取りそろえていた。料理も和食を中心として、蒲田にとって長く居やすいお店だった。近くには激安チェーン店が建っているが、蒲田はこの居酒屋「目黒」が一番居心地良かった。値段も手ごろなため、蒲田は居酒屋「目黒」の常連客になっていた。
二人の会話はいつも理学療法士の話で、話題が尽きることはなかった。理学療法士という知名度が低かった頃の話は二人の苦い思い出でもあった。例えば、昔は知名度が低くて、高齢者に自己紹介をするときに
「理学療法士です。」
と言っても理解されないので、
「リハビリテーションの者です。」
と言って説明しなければならなかったことや、中学の同窓会の時に
「理学療法士の資格を持っている。」
と言ってもリハビリテーションを行う専門職とは理解されず、同級生からは、
「おむつ交換とか大変そうだよな。」
とヘルパーと同様の仕事内容だと間違われるような事もあった。
しかし、今では、医療ドラマが流れると必ずと言っていいほど理学療法士の役が入っているようになり、理学療法士を名乗りながら活躍するタレントも現れ、理学療法士という名前は国民の耳に珍しい感覚で聞かれるような名前では無くなっていた。その事が昔と比較したときに、蒲田も竹下も何よりもうれしく思っていた。
そして、二人が一番話題として盛り上がるのがこれからの理学療法士を語る時だった。蒲田と竹下が描く、理学療法士の将来はほぼ一致していた。その内容は、国民一人一人にかかりつけ医と同等に、『かかりつけ理学療法士制度』と言うものを設けて、困ったときにはすぐに理学療法士が駆けつけられるような制度が出来るといいのではないかと考えだった。つまり、高齢者生活とはリハビリテーションがあって、初めて安心し、安定した生活が送れるものであり、そうすることによって第三の医療である予防医学をさらに浸透させ、入院を未然に防ぎ、在宅生活を長く続けられるようなると考えていた。そうした環境作りが大切なのだと考え、そうした制度を作ることが大事なのだと話していた。二人の酔いが回り出すと、毎回その話で盛り上がり、二人の酒のつまみにしていた。
ある日、竹下は
「おまえも養成校の講師を辞めて、俺のところで一緒に働かないか?」
と誘い出した。竹下は5年前から起業をしていた。「まつば訪問リハビリステーション」を立ち上げて運営し、現在は十五事業所を構え、福生市を含む西多摩の地域では一番大きな訪問リハビリテーションの事業所だった。スタッフ数も多くなり、地域の需要には応えられる程度の人数は揃えていた。しかし、リハビリテーションの質という面では竹下は満足していなかった。
「蒲田が来てくれたら、教育と言うところでとても期待出来るんだけどなぁ。」
蒲田は竹下に言われたときは、何気なく違う話題にすり替えてその場をごまかしていた。蒲田には、まだやりたいことがあった。帝都大学には研究施設があった。理工学部、経済学部、文学部、そして医学部、歯学部、薬学部など、理系から文系、そして医療系までさまざまな分野の学部が帝都大学にはあった。蒲田が所属しているところは、健康促進学部という学部で理学療法士を中心としたリハビリテーション関係の資格である作業療法士や言語聴覚士、そして音楽療法士や健康運動指導士などをまとめた学部だった。
理学療法士の知名度が上がった一〇年前の頃に新設された学部で、蒲田はそのころから在籍していた。やっと蒲田の思い描く学部に育ってきていたところで、研究も落ち着いて出来る環境も整ってきていた。よって、蒲田はこれから研究を頑張っていきたいという気持ちが強かった。そして研究内容は、
「『かかりつけ理学療法士制度』の有効性について」
という題名であり、蒲田はこの場で話していた、かかりつけ理学療法士制度を本当に実現しようと思っていたのだった。
(リハビリテーションの知恵をさらに広げ、今よりもっと国民に浸透させていきたい。)
蒲田が今一番やりたい事でもあった。
研究にはデータの入手先が必要だった。数が多ければ多いほど、そのデータによる研究成果は信憑性が高くなることは明らかだった。よって、そのデータを常に探し求めるのだが、研究者にとって数が集まらないのが一番の悩みの種だった。その悩みの種を解決してくれる一人が竹下だった。
(竹下はデータ収集に協力してくれる。)
そのこともあって、蒲田もまた、竹下の誘いを強く断ることが出来なかった。
竹下もデータを渡すだけで自分に利益がないとも言えなかった。実は竹下も蒲田がしたい研究内容は知っていた。知っているがために、本格的に蒲田を引き抜こうとしつこく言うことが出来なかった。竹下も、本当にかかりつけ理学療法士制度を実現して欲しいと思っている一人だったからだ。
竹下は、
「かかりつけ理学療法士制度は本当に実現できるのか?」
と蒲田によく質問していた。蒲田は、
「昔よりはまだいい。今のリハビリテーションの流行を考えれば、政府は前向きに考えてくれる。あとは裏付けだけで、それさえ、ちゃんとすれば、政府は簡単に後押ししてくれるはずだ。」
このような言葉を蒲田は良く返事していた。その言葉からは着実に研究成果を出しているのが竹下にでも理解できた。竹下はその言葉で蒲田の研究の進行状況を把握していた。反対に言えば、引き抜きの話をすることで、蒲田の状況を確認していたのだった。
竹下が臨床のデータを蒲田に渡す。そして蒲田はそのデータを元に研究を行い、結果を出す。その研究内容を政府が参考にして、かかりつけ理学療法士制度を実現する。蒲田と竹下は、お互いに同じ夢を持ち、実現できるようお互いが協力し合う、切っても切れない関係であった。
ある日、二人は居酒屋「目黒」でいつものように酒を交わしていた。蒲田はビールを飲み、竹下は焼酎のお湯割りを飲んでいた。今日は蒲田が竹下に一緒に飲みたいと電話して始まった二人の時間だった。竹下はほぼ毎日来ているので蒲田が「目黒」に行けば誘う必要な無いのだが、今日の蒲田は竹下にちゃんと誘ってから飲まないと気が済まない気持ちだった。何故かというと、蒲田が研究に行き詰まっているため、竹下に意見を貰いたいと思っていたからだった。この前兆は珍しくないため、竹下も蒲田が話したい内容は解っていた。竹下は蒲田の気持ちを受け止めて、今日はいつもと違った空気の中、酒を飲んでいた。
竹下と蒲田は沢山の酒を飲みながら、いつもは話さないテレビドラマの話をしていた。しかし、話の流れは徐々にリハビリテーションの話題になり、いつの間にかお互いの意見交換を始めていた。
蒲田が今行っているデータ解析は、在宅で過ごすためには生涯リハビリテーションが必要であるという事を証明するために、訪問リハビリテーションを受けているグループと受けていないグループを分けて比較しているところだった。比較するまでは簡単なのだが、比較した結果、違う値が得られた事に対して、その理由がうまく考えられず、苦しんでいた。同じ様な研究をしている文献は沢山あるのだが、蒲田はさらに深い分析を行っていた。国民に今よりももっと深く理解してもらうために、色々な角度から考えているのだった。
そのことに対し、お互いの意見を話し合い、竹下のヒントで蒲田が予想しなかった考察を考えるきっかけが出来た。その考察は蒲田にとっても成果を出せそうな内容だった。生涯リハビリテーションは必要だという結論がより深い内容で証明でそうな気がしていた。
「ありがとう。竹下。これでまた一つ、成果が出せそうな気がするよ。」
蒲田は竹下にお礼を言った。
「こちらこそ。」
竹下も蒲田に返事をした。そして、竹下は再び蒲田の引き抜きの話をして蒲田はそれを遠慮するといういつものパターンの会話に戻っていた。
二人は会話が一段落したので、テレビを見て話の間を取っていた。テレビはニュース番組が流れていた。交通事故による死亡者が二名いたという話題や、誰かが世界チャンピオンになったという話題が流れていた。二人は半分興味を持ったようにテレビを見ながら話すも話題は続かず、口にお酒を含ませては空気の間を埋めていた。そんな会話の切れ目にニュース番組のアナウンサーが顔色を変えて話し始めた。
「ただいま入ったニュースです。政府より緊急会見を開くという内容のお知らせが入りました。三〇分後に放送を切り替えてお伝えしますので、本日のニュースは内容を切り替えてお伝えします。えー。繰り返します・・・・。」
アナウンサーは動揺しながら原稿を呼んでいた。今までにあまりない対応をしている様子だった。現場の混乱が視聴者にリアルに伝わってきてしまっていた。
二人はこの緊急記者会見は何なのだろうかという予想をし始めた。蒲田は北朝鮮関係のニュースで国交が正常化し始めたのではないかという予想を立てていた。二〇三〇年になっても北朝鮮との国交正常化は出来ていなかった。確かに大きなニュースだが、竹下は違う予想を立てていた。竹下は沖縄のアメリカ基地問題に進展があったのではないかと予想を立てていた。アメリカ基地問題は決着が付かず、ずっと先延ばしにされていた。それがようやくまとまったのではないかと考えていたのだった。二人は予想をしながら、その話をつまみにして酒を嗜んでいた。そして話題は少しずつ離れていき、三〇分後には違う話題になっていた。
ニュース番組は政府の会見を待っていた。何を緊急会見するのか事前に知らされていなかったため、ニュース番組のテロップには「緊急会見」としか書いていなかった。アナウンサーも待っているのみで予想をキャストの人達に振って番組をつないでいた。
そして、ようやく、総理大臣が記者会見上に現れはじめた。蒲田と竹下はその様子をぼんやりと見つめていた。二人は特に総理大臣からの発言に注目している訳ではなかった。ただぼんやりと見ていて、ただぼんやりと聞いていた。居酒屋に来ている周りの客も、同じ様な様子だった。総理大臣が急に記者会見を開くと言うこと事態、珍しいことなので何を話すのか不思議に聞いているようだった。中には我関せずというように、一緒に来ている飲み仲間とテレビを気にすることなく楽しんでいる客も居た。店員はやや気になるのだろうか。仕事に集中しきれない様子も見られ、チラチラとテレビを見ているような気がした。
総理大臣は壇上にあがった。そして、一呼吸の間を置いて、マイクに向かって言い放った。
「え~。国民の皆様。そして、マスコミの皆様。このような時間を設定していただき、まことにありがとうございます。国民の皆様に、早急にお知らせしなければならない事態が起こり、我々政府も、どのように国民の皆様にお知らせした方が良いのか悩みました。そして、協議した結果、こうした形式をとった方がいいだろうという結論に達したため、現在の状況に至っています。あらかじめご了承ください。
さて、発表する内容ですが、現在の日本の状況を踏まえた上で早急にした方が望ましいという考えにいたっています。現在、日本は皆様がご存じの通り、高齢者と言われる65才以上の人口が日本国民全体の25%以上となりました。数十年前。このままでは昔のように働く人達だけで高齢者を支えていくには限界だとわかっていた我が国日本は、一つのテーマとして、「元気な高齢者を増やそう。」と方向付けをし、様々な対策を考えてきました。一つは高齢者の知恵を活かし、若き労働者の指導や支援をしていただき、高度成長期を生き抜いてきた経験を存分に活かしていただこうという仕組みを作りました。希望があれば雇用するように企業に働きかけ、そして我が国日本は、新たなワークスタイルを獲得すると共に、再び景気の良い日本を取り戻し、GDPで中国に負けていたにも関わらず、再び中国を追い越し、世界第二位の経済大国を作り上げました。これは本当に素晴らしいことです。」
蒲田と竹下はこの演説に徐々に注目していた。自分たちの仕事の分野のことを話しているとわかり、慎重に聞く姿勢を取り始めた。総理大臣の話は続いた。
「しかし、人間はやがて必ず老いて行くものであります。働くことにも限界になった高齢者は今後、どのように過ごしたらいいのか。数十年前から最期まで元気な気持ちで生きる仕組みが必要だと考えていた政府は、リハビリテーションというキーワードに着目をしました。リハビリテーションを行うことにより、生きる希望を見つけ、それに向かって生きていくことが、最期まで元気な気持ちで生きるという事だと考え、国民の皆様に提供してきました。皆様もご存じの通り、今の日本国には世界にも自慢できるリハビリテーション大国になりました。
生き抜く力。リハビリテーションの力。それが、今まで政府が推進し、積極的に取り組んできたものであります。今日それが・・・・。」
総理大臣は少し間をおいた。そして、再び話し出した。
「そのリハビリテーションの力というものが、過ちであったと皆様にお伝えしなければなりません。」
蒲田と竹下の動きが一瞬止まった。居酒屋にいる客も静かになった。総理大臣は休むことなく話した。
「国民の皆様。よくお聞きください。政府が長年研究してきた結果、リハビリテーションは麻薬と同じ様な効果が脳内で作用している事が認められました。よって、リハビリテーションは政府としては推奨しないという方向転換を本日より致します。もう一度繰り返します。リハビリテーションは麻薬と同等の効果が脳内に起こっています。政府としては本日よりリハビリテーションを推奨しないという方針になります。
禁止と言うところまでは至っていません。必要最低限にとどめるよう各医療機関は努めてください。
国民の皆様。大変、急な発表になりましたが、早急にお伝えした方が良いと考え、お伝えすることに致しました。また、今後の高齢者対策等は早急に委員会を開催し対応していきたいと思います。
以上です。」
テレビ画面では記者が次々に質問をし始めていた。しかし、テレビ放送の内容はスタジオに切り替わり、アナウンサーが総理大臣の話した内容をわかりやすく解説をしていた。
居酒屋「目黒」にいた客は、動揺していた。これまでの高齢者大国を乗り切ってきたリハビリテーションの力が足下から無くなっていくような気持ちになったのだろうか。老後の心配がまた一つ増えた形になり、暗い話題が飛び交っていた。
蒲田と竹下は何も動かない状態になってしまっていた。やっと動き出したと思ったら、蒲田は持っていた箸をそのまま落とし、竹下はお湯割りを机の上にこぼしてしまっていた。
(2)
蒲田と竹下はしばらく会話が出来なかった。何が起こったのか、何故このような事になったのか、さっぱりわからなかった。そうした中で、テレビでは総理大臣の記者会見後もニュース番組が続き、総理大臣の言葉の分析を進めていた。
(リハビリテーションが麻薬と同等である。)
リハビリテーション大国として定着していた日本がそうなる事で、この国はどう変わってしまうのだろうか。予想がしにくく、テレビの進行も上手く出来ない状態が続いていた。数十分後に医療介護に精通した専門家がニュース番組に呼ばれた。番組側が急遽呼び出した感があり、呼び出された専門家も、少し戸惑っていた。
アナウンサーは早速、今回の総理大臣の発言に対して、今後、どのような影響があるのかという質問を専門家にしていた。専門家は次のように発言していた。
「えー。まず考えられるのが、リハビリテーションが麻薬と同等であるという内容だけで考えると、すぐに止められる人は止めた方がいいという事になります。麻薬というのは続ければ続けるほど、また欲しくなるという悪循環が生まれるわけですから、リハビリテーションも続ければ続けるほど、また受けたくなるという悪循環が生まれるという事になると思います。ですから、即座に中止できる人は中止をした方が良いと言うことになると思います。」
アナウンサーはその発言に対して質問をし、それに対して専門家が答える、というようなやり取りが続いた。
「リハビリテーションが中止できない人たちはいるのでしょうか?」
「はい。これに関しては恐らく病院に入院している人たちはリハビリテーションを続けなければならないと思われます。退院するために、リハビリテーションというのはとても大切なものになります。いくら麻薬だからと言って、中止した場合、今度は反対に入院期間が延びてしまうという逆効果が生まれてきます。なので、病院は多少、リハビリテーションという麻薬を処方することになったとしても、リハビリテーションは続けるでしょう。そうしなければ、病院に患者さんがあふれてしまい、新しい患者さんを受け入れられなくなってしまいますからね。」
「ではリハビリテーションを中止する人たちというのは家で受けている人たちという事になるのでしょうか?」
「そういう事になると思います。ただし、家でリハビリテーションを受けている人たちは直ちに健康に影響が出るわけではありませんので心配はないと思います。
おそらく、今後の健康的な体を維持していくために、リハビリテーションを受けているという人達が多いと思います。こうした人たちは、すぐに止めると、今後どのようにして生活をしていいのか不安になり、パニックになる可能性が高いと考えられます。なので、ケアマネージャー等の専門家に相談をしながら、徐々に辞めていくことがいいと思います。」
「なるほど、ケアマネージャーに相談をする事が、まず、最初にやらなければならない事なのですね。」
「そうです。独断で決めると返って不安になり、やっぱりリハビリテーションを受けなければ自分はどうにかなってしまう、と考えてしまうと予想されます。ちゃんと中立の専門家に相談をしてください。」
専門家はハキハキとアナウンサーからの質問に答えていた。このやりとりを見ていた竹下は飲んでいたグラスを握りしめて憤っていた。そして蒲田にその憤りをぶつけ始めた。
「おい!蒲田!これはなんだ!これじゃ俺達がやっている仕事は、麻薬を国民に提供している事と同じになるじゃないか!」
竹下が運営している「まつば訪問リハビリステーション」という事業所は、家に住んでいる人達に向けて理学療法士が直接訪問し、その家でリハビリテーションを行う介護保険が主体のサービスだった。よって、先ほどのテレビに出ていた専門家の分析によれば、竹下が運営しているまつば訪問リハビリステーションは、すべて麻薬を提供している事と同じになるという意味だった。そして、専門家によれば、今すぐにではなくとも、徐々に止めるようにと言うアドバイスまでしていた。つまり、竹下の事業所を利用している人は少なからず、近い将来、中止した方が良いという事だった。
「こうしてはいられない!蒲田!ちょっと事業所に戻る!」
竹下は慌てて精算をしてその場を離れた。蒲田は慌てて帰る竹下を見送った後、冷静になって今までの情報を整理し、今後の打開策を考えていた。
恐らく政府はこの発表を行うに当たり、何処かの研究内容を参考にして話していると考えられていた。政府が方針を決める時に、必ず客観的なデータを参考にする。よって、必ず、何処かの研究内容が使用されているに違いなかった。
そして、その研究内容が素晴らしい内容であったため、今までのリハビリテーションを推進するのではなく、リハビリテーションを麻薬として捉え、軌道修正をせざるをえなかったのだろう。
反対に言えば、今までのリハビリテーションの有効性を考えた研究内容が、あまり充実していなかったとも言えるのではないかと考えていた。
事実、
「高齢者にはリハビリテーションが大切だ。」
と、ずっと思ってはいるものの、それを証明するには難しかった。何故ならば、リハビリテーションの有効性を判定するためには身体機能の向上が一番わかりやすい指標としてとらえられているのだが、高齢と言う年齢を重ねるにつれて身体機能が低下するという習性も重なるため、有効性をはっきりと証明出来ずにいた。
例えば、歩くスピードが早くなったとか、片足立が長く出来るようになったなど、それぞれの種目のタイムをとり、それを比較する手法が一般的なのだが、その結果は短期間では証明できず、長期間でデータを取ると、低下するというデータも必ず残ってしまっていた。そして、何よりも、タイムが変わらないと言う結果が大半を占める事が多く、この結果を「現状を維持出来ている。」と有効性で訴える研究者もいれば、「リハビリテーションの効果に疑問がある。」と捉える専門家も居た。この両極の言い争いは、終止符が長年続き、未だに決着が付かない状況であった。
それでも、政府は「現状維持はリハビリテーションが有効という効果と捉える。」と判断し、今日までリハビリテーションを推進してきたのだった。
しかし、今回の流れからすれば、この「現状維持。」という事が、麻薬と捉えられ、研究として成果が出たために今回の発表につながったと考えられた。
蒲田の研究は、この「現状維持の有効性。」を証明する内容でもあった。現状維持がリハビリテーションによって効果をもたらし、加齢による身体機能の低下予防の効果を証明出来れば、今回の発表には至らなかったと考えられた。
リハビリテーションは効果があるという事を早急に証明し、その研究内容を早く政府に届ける必要があると思った。
蒲田も精算をして居酒屋「目黒」を出た。足は大学の研究室へと向かっていた。
(3)
蒲田は早速竹下の言葉を参考にしながら、研究結果をまとめていた。竹下のヒントによって、再びデータを再分析する事になった。パソコンが得意だった蒲田にとってはストレスにはならない作業だった。そして再び、在宅でリハビリテーションを受けている人のグループと受けていないグループを比較して得られた結果が出た。そして結果は蒲田の予想通り、リハビリテーションを受けた方が、効果があるということが証明出来るようになった。
一番のポイントは何を持って効果と言ったか。それは身体機能の種目の数値ではなく、生命の健康寿命が長い、という点だった。
竹下はこのような事を言っていた。
「在宅で受けているリハビリテーションというのは、ただ身体機能をよくしているだけじゃないと思うんだ。今の世の中高齢者だけですむ世帯が多くなっただろう。それによって、病気に気づかず暮らしている人が多くなったと思うんだ。俺はよく家に行くからそう感じるんだよ。家に行ったら熱が出てたとか、目が見えなくなったのは白内障が進んでいたからだとか。中にはなかなか食事が飲み込みづらくなってきたとか。そういう話をもらって、俺が医師に直接相談をして医師に診て貰うという人も増えてきている。これらに俺らが素早く対応することによって、健康を維持できる一つの指標になっているんじゃないかと思うんだ。
例えば、熱がひどくなったら入院するようになってしまったり、白内障が進んだら見えなくなって転んで骨折してしまったり、飲み込みづらくなってきた人なんかは一つ間違えれば肺に食べ物が入って息が出来なくなって死んでしまうかも知れないんだぜ。そうした事を未然に防ぎ、生命の健康寿命を長くしているのも、俺達がしている結果だと思うんだけどなぁ。」
これをヒントに比較データを健康寿命という点で調べた。結果、在宅でリハビリテーションを受けているグループの方が優位になったのだった。これで家でのリハビリテーションというものも大切だという証明が出来た。蒲田は、その研究内容に考察を交えてまとめ上げた。そして、政府が管轄する厚生労働省に提出できるよう準備した。このまとめ上げる作業が一番大変な作業であるのだが、今の蒲田にとっては苦ではなかった。夜遅い大学の敷地内に、明かりが一つだけ灯っていた。パソコンの前に必死にキーボードを打つ蒲田の姿がそこにはあった。
(4)
蒲田は研究内容をまとめ上げる作業を必死に続けた。普段あまり飲まないコーヒーを何杯も飲んだ。胃がもたれる感じがしたが、気にしないようにして必死にパソコンに向かって取り組んだ。さすがにお酒が入った後なので全く寝ないでの作業は難しく、数時間程度は横になって仮眠をとった。少し眠った方が、頭がすっきりとして作業効率が上がった。深夜になる作業は久々だったので、体には応えた。ひな型が出来ていたため、大幅に時間を短縮できたものの、ようやく完成したのが次の日のお昼頃の時間だった。
蒲田はそのままぐっすり寝たい気分だったが、そうしていられないと気持ちを切り替え、研究内容をまとめ上げたもの印刷した。印刷が終了するには時間がかかるため、その間に出かける準備をした。服装は軽装では行けないため、スーツを着用し、髪形をセットした。歯磨きをしようとした時に印刷が終了したため、歯磨きはせず、そのまま印刷物をクリップで留めて鞄に入れた。そして、歯磨きと同じような効果のあるチューインガムを口に入れて、厚生労働省へと向かって行った。
(リハビリテーションは麻薬と同等である。)そうしたニュースが報じられてから一晩が経過した。蒲田にとっては大きなニュースだったが、街中はいつもと変わらない風景だった。人が歩き、信号の色が定期的に変わり、風が吹けば木に付いている葉っぱが揺れていた。当たり前な事が目の前で起こっているが、蒲田にとっては当たり前の事が当たり前の事じゃなくなる瞬間を昨日感じたばかりだったため、変わらないと言う事実を新鮮に感じていた。
ニュース番組ではリハビリテーションの事が大きく取り立たされていた。それでも、街中を歩いている人たちは特に変わりなく日常生活を送っていた。改めて思えば在宅でリハビリテーションを受ける人はこうした街中に悠々と出られない人が多いので、本当に影響のある人はこうした場面ではわからないのだろうと思った。
変わらない街中を歩き、研究内容を提出する厚生労働省の建物の前まできた。この建物の前には沢山のマスコミの人たちがいた。昨日のニュースが影響しているのだろうか。
「リハビリテーションは麻薬!」
というフリップを持ったアナウンサーがカメラの前で説明をしていた。どこかのテレビ中継だろうか。同じ様な風景が何カ所にも見られた。ここだけはいつもと変わった風景だと感じた。
蒲田はマスコミの間をすり抜けて建物の中へと入っていった。蒲田が持っている研究内容は今までとは視点が異なる内容だった。新たな分析の視点から、改めてリハビリテーションという効果を認めてもらい、(リハビリテーションは麻薬と同等である。)という感変えから軌道修正してもらえるだろうと考えていた。
蒲田がそう考えるのには理由があった。蒲田は今までリハビリテーションに関する研究を数多く行ってきた。大学で在籍している前から、数多くの研究を重ねてきた。そして、それを厚生労働省に提出をして、それで認めてもらい、制度化になったり、助成金をもらえるようになったりした実績があったからだった。
今回の研究内容も蒲田には手応えがあった。世の中の流れをしっかりと受けながら、今後の展望としてリハビリテーションは有効であるという根拠が有る中で、しっかりと考察出来たからだった。今まで、なかなか証明出来なかった分野をやっと証明出来た手応えは、今まで以上のものがあった。
蒲田はいつものように厚生労働省の窓口に提出しようとした。いつもであれば提出依頼の表に自分の所属機関と指名と連絡先を書き、そして担当窓口の人が目を通して受け取るというのが流れだった。目を通す理由は文章の内容を見るという意味合いではなく、ちゃんと提出するための基準を満たしているかどうかのチェックをされるのだ。クリップの位置や枚数、及びデータの添付資料の形式など、基準は意外と厳しかった。蒲田は何度も提出しているので慣れていた。今回も同じように担当窓口の人は受けとってくれた。窓口の人は顔なじみの人だった事もあり、少し時間もあるせいか、向こうから話しかけてきた。
「あんた、いつも提出してくれてるよねぇ。あんたは信用できるから言うけどさぁ。なんだか最近、変なんだよ。実はこの提出される資料を厚生労働省の官僚はあまり目を通さなくなったような気がするんだよなぁ。前は提出があったがどうか良く聞かれたんだけど、この数ヶ月は何も聞かれなくなったんだよ。受け取った資料も渡してはいるけどな。あんまり興味がないような表情なんだよなぁ。
俺の仕事は受け取るだけだから何とも言えないけど、今回のリハビリテーションが麻薬だっていう放送はそれに関係しているような気がしてなぁ。
あんたはいつもリハビリテーションに関する内容の資料を提出してくれるから、きっと関係のある事だと思ってな。
あ。俺が言ってたことは内密にな。」
窓口の人は人差し指を唇に当てて静かにしてというジェスチャーをわかりやすくしてくれた。周りに人がいなかったから良かったが、声も大きかったので蒲田自信が冷や冷やしていた。
蒲田は厚生労働省の建物を出た。まだマスコミが数多くいた。そして視線を厚生労働省の建物に移した。いつもと変わらない建物であるが、まわりの空気が違うような気がした。もし、窓口の人の言っていることが正しければ、蒲田の研究内容もあまり見てくれないということになる可能性も大きい。
蒲田はこの建物の中で何が起こっているのか知りたくなった。今までは、リハビリテーションという分野は政府が常に後押ししてくれていた。何も言わなくても追い風が常に吹いていた状態だった。だから政府の中を知らなくても、今までは仕事や研究がやりやすいように出来ていたのかもしれなかった。その流れがあったから、官僚の人間も研究内容に着目してくれていたのかもしれなかった。しかし、今は違っているのかもしれなかった。やることが全て敵に変わっているのかもしれなかった。リハビリテーションの有効性を訴えても、誰も振り向いてくれない状況に等しいのかもしれなかった。
蒲田は考えた。この、(リハビリテーションは麻薬と同等である。)という発表は、どこかで研究をした結果が反映されているとなれば、研究結果を提出した研究所はどこなのだろうか。研究所を探し、そこで研究した人にこの内容の真意を聞いてみたくなった。麻薬であるという根拠はどこから来るものなのだろうか。蒲田は知りたい気持ちで一杯になった。自分と真逆の考えをする人間に会ってみたくなった。そして、自分の研究よりも説得力のある内容に仕上げたその人物と話してみたくなった。
蒲田はその場を立ち去り、足早に次の場所へと移っていった。
(5)
蒲田は帝都大学の図書室に向かった。リハビリテーションに関する書籍はこの場所が一番多く取りそろえていて、何かを調べるにはちょうどいい場所だった。そして、この図書室は、リハビリテーション以外の書籍も多くあり、最新の新聞や雑誌、そして古い百科事典まで揃えているため、最近の動向から昔の出来事まで、幅広く調べられる場所だった。
蒲田は一番奥端の座席に座り、すぐに調べるための資料を探し始めた。今日の新聞には政治経済が多く載せてあったが、今回のリハビリテーション関係の記事も多く載ってあった。特にリハビリテーションが麻薬とほぼ同じであるという事がわかった上で、人々が今後どのような暮らしを迫られるのかという解説文が大きな記事として取り扱われていた。そうした内容が主であるため、リハビリテーションが麻薬であるという証拠に関しては触れておらず、もちろん、その研究をした研究所の名前はどこにも載っていなかった。通常でもあまり研究所の名前は発表しないので、蒲田は次々と違う資料を探していた。
次に、資料を探す手掛かりとしてリハビリテーションをあまり良いように考えていない書籍に着目をした。リハビリテーションが麻薬であるという発想が、リハビリテーションそのものを快く思っていないと考えられるからだった。今回の研究をする前からそういった考えを持っている人間を探せば見つかるかもしれないと思い、次々と色んな書籍を読み漁った。しかし、調べた結果、リハビリテーションを良く思っていない人は何人かいるものの、研究をやっているわけではなく、ただの解釈として持論を述べているだけの人ばかりだった。持論をさらに研究で証明しようとしているような人は、1人もいなかった。
それでも蒲田は色々な書籍を開いては探し、開いては探した。そうして、蒲田はこの図書室で日が暮れそうになるまで時間を費やしていた。時間をかけた分、蒲田が思いつきそうな書籍は全て目を通していた。それでも、リハビリテーションを麻薬と考えそうな研究をしている研究所は見つけられなかった。
「ここ図書室ではダメか・・・。」
蒲田は諦める様に天井を見ながら深呼吸をした。書籍で探せなければどうしたらよいのか考えていた。日が暮れて暗くなりつつある空の色を見ながら、図書室を出た。また別の場所に移って行った。
蒲田は行くあてもないため、竹下が運営している「まつば訪問リハビリステーション」に向かっていた。一人で探すより協力者がいた方が効率がいいのではないか、と図書室を出た後に思いついたからだった。蒲田の一番の協力者で思いつくのは、やはり竹下だった。よき友人である竹下に協力を得ることにした。
蒲田が竹下の事務所に着いたとき、竹下は事務所の事で忙しそうにしていた。蒲田はこの事務所には滅多に来る事は無く、また、事前の連絡もなく訪れた事もあって、竹下も少し驚いていた。竹下はリハビリテーションが麻薬であるというような発表後から、利用者からのキャンセルの電話が止まらないらしかった。蒲田が訪れたときも竹下は電話の対応を次々としていた。
「もしもし?あー!福田さん!?南田園の!いつもお世話になっています!え?リハビリテーションを辞めたい?あー・・・そうですかぁ・・・・やっぱりあのテレビをみて・・・・えー・・・えー・・・はい・・・・はぁ・・・・そうですかぁ・・・・えー・・・・」
電話を出た時は明るい声をしていた竹下は、会話を進めるうちに声のトーンは少しずつ小さくなっていった。
「えー・・・まぁ・・・一応ですねぇ。私の事業所も長年やってきていますけど、麻薬と言われてもあまり心当たりないんですよ。・・・・えー・・・・えー・・・・そうですー・・・・特に幻覚が見えるとか、眠れなくなるとかあまりないんですね・・・・えー・・・・えー・・・・そうです。かえってよく眠れるという声が多いんですけどねぇ・・・えー・・・・そうですよねぇ・・・・そうですよねぇ・・・・・・えー・・・・・・今までの事も踏まえて、もう一度考えていただけますか?・・・・えー・・・・はい。・・・・はい。それではご検討ください。・・・ありがとうございます・・・。」
竹下の声は最後になると少し明るい声に変わっていた。完全なキャンセルにならなかったためだろうか。竹下はゆっくりと電話を切った。
「こういう電話が耐えないんだよ。」
竹下は蒲田の方を向いて話した。こういう電話とは、リハビリテーションを辞めたい、という電話だろうか。竹下もすぐに了解することは出来ず、何とかリハビリテーションを続けるようにくい止めているらしかった。
「急に麻薬だと言われても、症状とか副作用がわからない以上急に辞める方が、リスクがありますよ。」
こういった説明で利用者に理解を求めているようだった。それでも辞めると決断をする人は後を絶えないようで、収入が激減することは間違いないと話していた。
蒲田はこの、
(リハビリテーションは麻薬である。)
と言い出した研究所を一緒に探そうと竹下に言いたかったが、竹下はそれどころではなさそうなので、相談することを止めようとその場を去ろうとした。すると竹下は、
「何か用が会ってきたんだろ。俺は大丈夫だから。」
と蒲田を気遣い、蒲田を相談室へと案内した。
「落ち着いたらこっちに来るから。ちょっと待っててくれないか。」
竹下はそう言って相談室を離れた。事務所の方では再び電話が鳴っていた。
竹下が相談室へ来たのはそれから蒲田が座り疲れて一回立って伸びをする事を二回繰り返したときに来た。待ち始めの時間を見ていなかったのでどれくらい待ったかはわからなかったが、感覚では一時間以上は待っていたような気がした。
竹下は蒲田が来た理由をわかっていたようだった。やはり竹下もその研究所を探したい気持ちが大きいようだった。
「いつもの所で作戦を立てよう。」
竹下はそう言っていた。蒲田は素直に頷いた。蒲田には竹下が嫌な気持ちをお酒で晴らしたいという気持ちも含んでいるような気がした。
(6)
二人は居酒屋「目黒」に来ていた。二人のいつもの場所と言えばこの場所だった。そして、二人は決まっているかのように、蒲田はビールを、竹下はお湯割りを頼んだ。そして飲み物が来ないうちに二人はさっそく本題に入っていた。
蒲田は今日中に仕上げた資料のコピーを竹下に渡しながら、厚生労働省で耳にした話を竹下に伝えた。竹下はその資料を見ながら話した。
「この資料は聞いてもらえないかもしれない、ということなのか?」
竹下はこの研究内容には納得をしているようだった。これが聞いてもらえないという事に不満があるようだった。
蒲田はさらに帝都大学の図書室で調べたが何も出てこなかった事を竹下に報告をした。
「きっとリハビリテーションが麻薬であるというような内容を研究している場所を、政府は公表しないようにしているのかもしれないな。リハビリテーション関連団体は黙っていないだろうからな。」
竹下は研究所がはっきりしない理由を考えていた。
「そうなると研究内容を握っているのは厚生労働省の内部であり、それを知るためには内部に進入しなければならない、という事か?」
蒲田は竹下の言葉から次の手を考えていた。しかし、厚生労働省の内部となると、一般人は内部には入れないため、蒲田自身は見動きは取れないと考えていた。
「誰か、知り合いがいればいいんだが・・・。」
竹下はそう呟いていた。
蒲田と竹下には厚生労働省の知り合いが思い当らなかった。二人して誰か該当しないかと、携帯電話のアドレス帳を黙々と眺め始めていた。
二人とも暫く探していたが、やはり厚生労働省の人間は誰ひとりとして該当しなかった。
「誰もいないかぁ。」
蒲田は残念そうに携帯電話を机の上に置いた。
「いや。諦めるのはまだ早い。二人で登録している人の中に厚生労働省の知人がいるかもしれない。」
竹下は諦めていなかった。
「今から電話するのか?ちょっと夜遅いけど。」
「大丈夫だ!今、俺の電話帳を見た限り、ほとんどがリハビリテーション関連の人間だ。事情を話せば協力してくれるかもしれない。この勢いでやるしかないだろ。」
竹下は何かに火が付いたように、蒲田の了承を得る間もなく1人で知人に電話をし始めた。蒲田もその姿を見て、自分の知人に電話をし始めていた。
しかし、何十件電話をしても、厚生労働省の知人がいる人は見つからなかった。そして、とうとうリハビリテーションに関係のない知人にも電話をして聞いていた。
しかし、リハビリテーションに関係の無い人達からの反応は冷たかった。以前は快く協力していた人も、今は手のひらを返したように素っ気なく対応された。自分たちには負の風が自分たちに吹いているのだろうと思った。風向きが変わると、こうも前に進まないのかと思うほど、作業がやりにくくなっていた。
しかし、蒲田達は諦めなかった。二人はリハビリテーションに熱く深く考えている人間だった。そしてかかりつけ理学療法士制度を実現したく、今日まで協力して頑張ってきた。その努力を無駄にするわけにはいかなかった。その気持ちがお互いの行動を前向きにさせていた。
一通り知人に電話をし終えた二人は、ようやく二杯目の注文をした。長い時間電話でのやり取りをしていたため、一杯目を飲み終えた事を忘れてしまっていた。それほど今の事で精一杯なのだと思った。
竹下は二杯目が手元に届くと一気に飲み干した。
「ちょっと時間があると、自分の事業所の事を考えてしまうよ。」
竹下にはこの事以外にも、自分の事業所の対応も頭から離れないようだった。
「どうしたらいいんだ・・・。」
竹下は頭を抱え込んだ。内閣総理大臣の発言により、国民が受けた影響は、蒲田の想像を超えているように思えた。蒲田はまだ大学に属しているため、すぐに生活に影響が出る心配まではしなくて良かった。大学は他の学部もあるし、リハビリテーションに影響があったとしても、他の学部で収益を補える事が出来た。しかし竹下は、独立企業として経営をしていた。竹下にとっては、事業所の存続にも関わる重要な事であり、生活もかかっているため、自分よりもこの問題を大きく捉えているのだろうと思っていた。
「やはり、利用する人は減っているのか。」
蒲田は竹下に聞いた。
「ああ。急激にというまでは行かないが、問い合わせの電話が鳴りっぱなしだ。本当にリハビリテーションはダメなのかって内閣総理大臣の言葉を不思議に思って聞いてくる人もいるが、大半はリハビリテーションは麻薬という言葉をそのまま受け止めて聞いてくる人がほとんどだ。
『リハビリテーションを続けるとどうなるのか?』『かえって違う病気になりはしないか?』とか、『リハビリテーションを今止めたらどのような症状が出るのか?』とか、『副作用はあるのか?』、とか。中には、『今まで良くならなかったのはリハビリテーションそのものが原因なんじゃないか?』と言ってくる人まで現れ始めた。年齢的なものもある、という説明をするが、おそらくそれは言い訳にしか聞こえないみたいだ。すべて麻薬という効果で話をしてくる。何もかもマイナスの印象だ。」
蒲田は麻薬という内容がここまで人の想像力を膨らませてしまうのだと改めて知った。
「歯止めはかかりそうにないか?」
「ああ。恐らく今の調子だと、さらに減っていくだろうな。うちのスタッフもリハビリテーションどころじゃないって嘆いていたよ。担当の利用者から『もう辞めようかしら』って、何度も言われたそうだ。利用者側にとっては、俺たちは何か汚い者のように見えるみたいだ。利用する人はそんな印象なのかもしれない・・・。」
竹下はいつも飲んでいるお湯割りから、焼酎のロックに変更して一気に飲んだ。酔いの世界に入りたいようだった。
蒲田は思った。このままでは本当に、リハビリテーションというものが無くなってしまうのではないか。そう思い、蒲田もまた、焦りが増していた。
竹下は焼酎のロックをハイペースで飲み干していた。蒲田にも数え切れないほど飲んでいた。竹下は酔いつぶれ、その場に伏せて寝てしまっていた。蒲田は変わらず一定のペースでビールを飲んでいた。焦りはあるものの、冷静さは保っていた。しかし、何も思いつかず、酒の量だけが減っていた。
隣で竹下が酔いつぶれている横で携帯電話が鳴っていた。竹下の携帯電話だった。蒲田は誰からだろうと気になり、覗こうとすると音は切れた。携帯電話の背面には小さな液晶画面が付いていて、その液晶画面にはメールの着信の知らせが表示されていた。
さっき知人に電話をした返事かも知れないため、竹下に早く見て貰おうと竹下を起こそうとした。しかし、竹下は起きそうにないため、しかたなく、誰から来ているのかを確認した。しかし、竹下のアドレス帳には載っていない人物なのだろうか。英数字が羅列してあるだけの送り主しか表示されていなかった。竹下は酔いつぶれているため、見ても大丈夫だろうと蒲田は思い、竹下の携帯電話を取り、メールを開いた。メールのタイトルには人の名前が書いてあった。そして、その名前は蒲田も知っている人物の名前だった。
(7)
「轟信二」
竹下の携帯電話の背面にある小さな液晶画面に表示されている、その名前を見て蒲田は思い出していた。
轟信二。帝都大学時代、同じ理学療法士を目指した同級生の名前だった。
「確か・・・・就職先は・・・。」
蒲田は必死に思い出していた。そして竹下に渡した研究内容をコピーした資料を見て思い出した。
「厚生労働省!」
そうだった。厚生労働省のリハビリテーション部門に所属したと、誰かが言っていたことを思い出していた。
轟信二という人物は蒲田と竹下の大学時代の同級生というだけで、それ以上でもないし、それ以下でもない存在だった。学生時代でも二人とも会話をあまりした方でもなく、卒業後になっても会うことさえなかった。竹下からも轟の事を聞いたことが無いため、きっと竹下も会っていなかったに違いなかった。最近会っていたのなら、さっき電話をしているはずだし、ましてや厚生労働省に務めている事も知っているはずだった。きっと、竹下から轟の名前を見て厚生労働省に勤めていると言う事が繋がらなかったのは、蒲田以上に疎遠であると言うことだと蒲田は思っていた。しかし、竹下は何百人もの連絡先を登録しているのだろうか。竹下が連絡先を知っていることに、蒲田は少し驚いていた。
結果はどうであれ、蒲田にとっては願ってもないチャンスだった。厚生労働省の内部の事情がこれにより知れるきっかけが出来ることを意味していた。蒲田は竹下を叩き起こした。竹下は朝の起き抜けの顔より酷い顔で、ゆっくりと頭を上げた。
「竹下!轟と会うぞ!」
蒲田は竹下にそう話しかけた。竹下はまた机に顔を伏せて寝始めていた。
数日後、蒲田と竹下は轟を居酒屋「目黒」に呼んだ。蒲田と竹下は先に店で待っていた。遅れて轟が店に入ってきた。数十年ぶりに合う友人の顔は、学生の頃のイメージとはまったく異なっていた。大きく腹は膨れ、頭も薄くなっていた。それでも目のあたりは面影があった。近づいてくる轟に蒲田は学生の頃の姿と重ねながら思い出していた。
「久しぶりだなぁ!」
竹下は元気のいい声で轟を迎えた。数十年の時をその一言で縮める効果がその声にはあった。あまり会話の無かった三人が、今このときを一緒に過ごし、思い出話に多くの時間、咲かせた。
しかし、蒲田は学生時代の思い出話に今一つ入り込めていなかった。蒲田は同級生の轟として見る事が出来ず、厚生労働省に勤めている轟という風に見てしまっていた。蒲田はどうしてもこのチャンスを逃さないという意気込みが全面に出てしまっているのだった。
轟も久しぶりに会う蒲田と竹下に、違和感なく会話に入っていた。思い出話を本当に楽しんでいる様子だった。しかし、何処となく、轟にも何か二人に言いたいことがあるのではないか、と蒲田は感じていた。考えてみれば、久しぶりに轟から連絡をとってきたという事は、轟にもこの機会に対する思いがあるのではないか。蒲田はそう考えていた。
しかし、いったい轟は、何を言いにわざわざ連絡をとってきたのか。蒲田は心の底で、この三人の会合の状況を一歩引いた視点から見つめていた。
三人の会話は最初からずっと学生時代の事だった。当時の教員の悪口や、当時気になっていた女の子の名前を言ってお互いに意外な一面を教えあった。話は途切れることなく時間は流れていった。流れる中で今の仕事の話題になった。仕事の話題になったとき、轟の表情が少し変わったのを蒲田は見逃さなかった。轟はきっと仕事の話をしにきたのだろうと思った。
轟はおそらく、蒲田と竹下の現在の仕事内容を把握していて、何かの理由で近づいて来たのではないか。厚生労働省からの正式な実態調査の依頼だろうか。それとも、正式な依頼ではなく、陰で調査をするために、人脈を使って現場の現状を把握するために、聞き込みを行おうとしているのだろうか。
話は竹下の今の仕事の現状に変わりつつあった。轟もその話が聞きたかったのか急に聞き手に徹するようになった。やはり、竹下の仕事内容は十分に把握していて、現状を把握するために近づいたのだろうか。竹下も酔っぱらってきたのか、現状を愚痴るかのように話し出した。リハビリテーションが麻薬という話が出てから、経営がうまく行っていないと、はっきりと言った。そして、酔いは頂点に達し、竹下は轟に牙を向き始めた。
「絶対にどうかしている!何が、麻薬だ!何が、辞めるように!だ!おかげで俺らの仕事がなくなっちまったじゃないか!俺らはそんなに悪いことをしていたのかぁ?そんなに非人道的な行動をしていたのかぁ?麻薬って何だぁ?まるで俺自身が麻薬みたいじゃないか!今までずっとリハビリテーションを勧めてきたのは政府じゃないか!しかも、それを実証するために、ずっと蒲田が研究結果を出して効果があると訴えてきたはずじゃないか!それを完全に無視するっていうのはどうなんだ!おい!轟!」
竹下の矛先は鋭く轟に向いた。今までの温和な空気が一変した。蒲田は竹下と同等の意見だった。蒲田も言い方はそこまできつく言うつもりはなかったが、同じような内容を話したかったので、この言い合いを止めると言うよりも、竹下を応援するような気持ちで見守っていた。
竹下は黙って、自分の酒を一気に飲み干した。まるで何かの覚悟を決めたかのように見えた。飲み干したグラスをテーブルに叩きつけるように置いた。轟はそれに反応することなく、自分の携帯を取り出した。
「竹下。これを見てほしい。」
轟は自分の携帯の画面を竹下に見せた。蒲田もその画面を覗いた。その写真はどこかのオフィスの風景を撮っていた。どこのオフィスだろうか。近くに轟が今日持っているバッグが写って居るので、轟が関係するオフィスなのだろうか。
轟のバッグが置いてある机の横に、もうひとつ机が置いてあった。その机には何枚者コピー用紙が散乱するように置いてあった。そして、その机だけ、机の向きが周りを見渡せるように違う角度で置いてあった。おそらく、身分が上の机であるのだろうか。しかし、それ以上は何も想像が膨らまず、普通のオフィスの写真のように見えた。
それを見せられた竹下は、唖然としてその写真を見つめた。轟が何を竹下に伝えようとしているのかわからず、竹下のイライラがさらに増した。そして、轟にさらに怒りをぶつけようとしたとき、轟はその写真を拡大し始めた。竹下と蒲田はその拡大した写真を見続けた。拡大した写真の中心は轟の横の身分が高いと思われる机に移った。その机の上の散乱したコピー用紙の中に一つだけ、厚い冊子が乗っかっていた。
「この冊子のタイトルをよく見て欲しい。」
竹下と蒲田にそう言った。竹下と蒲田が凝視しているなか、轟はさらに写真を拡大した。そして、その冊子のタイトルが読めた。
『リハビリテーション中毒化現象の実際』
竹下はそのタイトルを見た瞬間、あまり理解できていない様子で、何度かタイトルを復唱していた。蒲田もリハビリテーションが中毒化しているという意味が全くわからなかった。その拡大した写真を見ても理解できなかった竹下は、さらに轟に怒りをぶつけた。轟は竹下の怒りを避けながら説明を加えた。
「よく写真をもっと見てくれ!問題はこの計画を立てた立案者だ!」
竹下と蒲田の視線は再び拡大した写真に移ったそしてタイトル以外の文字を追い、立案者が書いてある場所を見つけ、読んだ。
「ソ・ラ・リ・ス・タ・研・究・所」
立案者にはその研究所の名前が書いてあった。轟は二人の顔を見た。竹下も蒲田もこの研究所には覚えがあった。この研究所は、三人の同級生でもある「岡崎祐輔」が5年前に立ち上げた研究施設の名前だった。
(8)
岡崎祐輔。蒲田、竹下、轟の同級生でもあった。しかし、同級生とは言っても、岡崎は少し違った存在だった。
岡崎は入学当時から無口であり、やや不気味な存在をしていた。しかし、勉強には人一倍まじめに取り組み、成績は常にトップクラスを維持していた。学年が上がるにつれて、勉強内容が難しくなり、学校を辞めていく人もいたが、岡崎はそのままトップクラスの成績を保っていた。そして、一番学校を辞めていく原因となる、臨床実習、いわゆる実際の病院に行って勉強をするカリキュラムがあるのだが、そこでも岡崎はすんなりと合格をしていた。しかし、卒業間近になり、あとは国家試験のみという段階で岡崎は突然学校を辞めた。誰もがこの段階で辞めていくことは予想できず、同級生達は何故辞めていったのか不思議に思っていた。
その後、数年は音沙汰無く、岡崎が現在何をしているのか当時同じだったクラスメイトのほとんどは知らなかった。しかし、五年前頃に年賀状が突然岡崎から蒲田、竹下の所に送られてきた。轟もこの研究所の名前を知っていたという事は、轟にも届いていたのだろう。年賀状の内容は研究所を開設したというお知らせだった。突然の挨拶に当時の蒲田や竹下は驚いていたが、人のつながりを大切にすることは悪いことではないと思い、普通に返事を書いて出していた。
「轟にも年賀状が来ていたのか。」
「ああ。届いたときには岡崎って誰だかわからなかったよ。まさか、あの岡崎とはね。そして、年賀状を送ってくるなんて、なにか裏があるのかと思っていたけど、まさかこれでその研究所の名前が見られるなんてね。」
蒲田は轟が見せてくれた写真をより詳しく見ていた。蒲田は写真に写っている資料のタイトルが気になるようだった。
「リハビリテーション中毒化現象、ってなんだ?リハビリテーションが麻薬であるということがつながっているのか?」
轟は深く頷いて口に水分を補給した後話し出した。
「おそらく、つながっていると思う。実は今までリハビリテーションを勧めていた厚生労働省の内部も急に方向転換し始めたんだ。きっかけはやっぱりあの総理大臣の発言からだ。今まではリハビリテーションを推奨した社会を作っていたのが、真逆になったんだから仕方のないことだろうと思うが、何か妙なんだ。これだけ真逆なことを急にするのであれば、厚生労働省の内部も慌ただしくなるはずなんだ。いろんな部署の調整をしなければいけないし、資料を揃えなくちゃいけない。通常であれば毎日夜遅くまで働かなければならないような出来事なのに、今回は混乱なく円滑に移行している。会議などは開催されるが、手続き上というような印象が強く、あっさりと物事が決まって行っているんだ。これは何かあるのではないか。そう思っていたところに、上司の机の上にこの資料が置いてあったっていう訳だ。
部長はその資料を部下には見せたことがないと思う。同僚に聞いたけど、誰一人知らないみたいだったから。」
「誰一人見せず、物事が円滑に運んでいるという事は、上層部の方ですでに話が済んでいるという事と、あまり知られるとまずい内容が書かれている可能性があるということか?」
蒲田は轟の話した内容を確認するように轟に質問をした。轟は蒲田と視線を合わせながら頷いた。
「つまり、リハビリテーション中毒化現象ってのが裏にあるというのか!」
竹下は麻薬と言った敵が見えそうになっているという感情が高まりつつあった。それを蒲田が竹下の肩を撫でて押さえた。
「その写真を部長に見せて、資料を見せては貰えないのか。」
蒲田は写真を轟に見せながら言った。
「ダメだ。職場で写真を撮ることは禁止されている。撮ったという事実が分かった時点で俺はその場所に居られなくなるさ。
今回も写真を撮るときは携帯を見るふりをして写真を撮ったんだ。だから子の様な見にくい写真になっているんだ。」
(とりあえず、ソラリスタ研究所という情報が手には入っただけでも大きい。それの所長は昔の同級生ということで、なお今後の対策が考えられる。)
蒲田は心の中でそう思っていた。
(9)
蒲田は轟と久しぶりに再会し、轟の情報提供によってソラリスタ研究所が「リハビリテーションが麻薬と同等である」という根拠のデータ提供先であることを知ることが出来た。そして、さらにその研究所の所長が同級生である岡崎であることも、同時に知ることが出来た。
蒲田はこのような研究をした人物はリハビリテーションに悪意を持っている人間がしているのだと考えていた。岡崎がそうなのであれば学校を途中で辞めたことと何か関係があるのではないだろうか。
少なからず、岡崎は一度、理学療法士になろうとした存在であったはずだった。どういう経緯があるにせよ、倍率の高い入学試験に合格をし、多大な勉強をして成績優秀で過ごしてきた人物だ。そうした人物が、今回このような研究を行い、データを厚生労働省に提出しているとなれば、リハビリテーションに対して強い嫌悪感を持っているに違いなかった。
その真意を蒲田は知りたくなった。岡崎に会い、話をしたくなった。話せば岡崎が何を考え、このような事をしたのかわかるのではないかと考えていた。しかし、安易に研究所に乗り込んで岡崎と話をしても、危険であるとも考えていた。岡崎は頭がよく働く人物に間違いなかった。きっと、蒲田が研究している内容も把握しているはずだった。今回の岡崎の研究は、今まで蒲田が行ってきた研究を把握した中での研究だと考えざるを得なかった。蒲田の研究を覆すほどの精密な研究でなければ、政府が急にこのような方向転換をすることは考えられなかった。
よって、たとえ蒲田が岡崎に会えたとしても、蒲田がずっと研究してきたリハビリテーションの効果を岡崎に話したって、岡崎は何とも思わないのではないかと思っていた。
蒲田は悩んでいた。そして恐れていた。岡崎は平凡な研究者では無く、蒲田以上に頭の良い研究者だった。今まで、積み重ねてきた蒲田のリハビリテーションに対する効果の研究内容を一変するほどのデータ収集力と分析力。政府を動かす力という意味でも、研究する力は蒲田以上であることは間違いなかった。
「何からすればいいんだ・・・。」
蒲田は頭の中が整理できずにいた。冷静になろうと軽い深呼吸をしていると、蒲田の携帯電話に着信が鳴った。知らない番号からの電話だった。蒲田は常に知らない番号はすぐに出ないようにしていた。変な勧誘の電話が多く、対応も面倒なため、同じ番号の電話番号が繰り返しかかってくるのであれば対応するというのが蒲田のいつもの方法だった。
知らない番号からの電話は何回かコールを鳴らした後に切れた。蒲田は切れたことを確認して携帯電話をポケットにしまおうとした。その瞬間、再び電話が鳴りだした。着信番号はさっきかかってきた電話番号に似ていた。前の電話番号をはっきりと覚えていなかったため、蒲田はその電話にも出ることはしなかった。しばらく鳴って電話が切れた後、蒲田は今の電話とさっきの電話が同じかどうか調べた。調べた結果、同じ電話番号だったことがわかった。
(今度、鳴ったら出よう。)
蒲田はそう思ったが、次は鳴らなかった。誰の電話番号だろうと少し気になった蒲田は、電話番号先を調べ始めた。携帯電話に登録している電話番号であれば、携帯電話の画面には名前が表示されるはずだが、名前が表示されていないので、携帯電話に登録していない人物である事は間違いなかった。番号を別の紙に書き、インターネットで検索をかけた。検索すると一番上にさっき蒲田の頭の中でいっぱいだった文字がそこに表示されていた。その、電話番号は『ソラリスタ研究所』と表示されていた。
(10)
なぜ、蒲田の携帯電話にソラリスタ研究所から電話が来たのか。不思議に思う蒲田だったが、岡崎と接触しようと考えていた蒲田にとっては好都合だったため、即座に折り返しの電話をかけた。そして電話は繋がり、受付係のような人と蒲田は話した。
今回、ソラリスタ研究所から電話した理由は何やら蒲田を招待したいことがあるので、招待状の送り先を教えてほしいという内容だった。なぜ、蒲田が選ばれたのかと聞くと、同じ様な研究者全てにかけているという事だった。よって、決して岡崎が蒲田を指名して連絡をしていたのではないことがわかった。しかし、蒲田にとってソラリスタ研究所と接触をする絶好のチャンスだった。蒲田は、その受付係のような人に送付先を伝えた。
後日、招待状が届いた。封筒はとてもシンプルで、会場の場所と日時が書いてあるのみだった。研究者同士でこのような会場を押さえて会合をすると言うのは聞いたことがなかった。親しい研究者同士で話すことはあるにせよ、一つの研究所が声をかけて集めるという行為は今までになかった。蒲田は岡崎が何をしたいのか、わからないまま当日を迎えた。
蒲田は会場に着くと、蒲田が予想していた以上に多く集まっていた。予想では二十人くらいから三十人くらいいればいいのではないかと考えていた。しかし、それを大きく上回り、百人以上が会場を埋めていた。これだけの人がいるということは、ソラリスタ研究所に沢山興味を持っている人がいるということの証だった。蒲田はさらに周りを見た。参加する人たちが研究者以外の人たちも大勢いるのではないのかと思い始めていた。服装や持ち物が、研究をする人というよりも取材をする人というような印象を受けたからだった。
会場は席が用意してあったので、蒲田は入り口から一番近い席に座った。ちょうど一番後ろではあるが、左右で言えば真ん中の位置に座ることが出来た。そこで、座って待っていると、隣に一人座ってきた。
一声おかけすると相手も快く応じてくれた。隣の人は記者だった。記者がなぜこの場所にきているのか、蒲田は不思議だった。話を聞く中で、今回の招待方法について話が出てきた。隣の人は依頼された封筒にはちゃんとタイトルが付いていた。
「リハビリテーションと麻薬の関係性について ~厚生労働省に提出した資料から~」
というタイトルが付いていた。蒲田は目を疑った。このタイトルからすると、岡崎は研究内容をこの場で公に発表するというのだろうか。通常であれば学会などで発表するのが通例だった。通例の発表方法とは異なり、ソラリスタ研究所は自ら記者を招き、研究内容を伝えようとしているのか。
そう考えているうちに開始の時間になった。会場には雛壇が設置されていた。そこに昔から容姿が変わらない、ソラリスタ研究所の所長、岡崎がゆっくりと雛壇を上がっていった。そして真ん中まで来ると一礼をして話し出した。
「え~。このたびは私たち、ソラリスタ研究所の報告にご参加いただきまして、真にありがとうございます。先日、総理大臣から、リハビリテーションは麻薬と同等の効果がある、というような発表があったと思われます。そのデータづくりに協力させていただいた経緯がありますので、この場にて国民の皆様にお伝えした方がよいと思い、この機会を作らせていただきました。この研究所を立ち上げてから、私たち、ソラリスタ研究所はリハビリテーションというものは何なのだろうかというテーマを追い続けてきました。確かに体は動くようになり、高齢者の皆様も生き生きと暮らしている姿がよく見受けられます。しかし、私はふと疑問に思ったのです。そうしたリハビリテーションというものは、いつまで行えばいいのだろうか、と。高齢者の皆様は言います。
『リハビリテーションを受けていて良かった。』
『リハビリテーションが無いと生きていけない。』
リハビリテーションというのは心の支えであり、生きる生活の一部になっています。
そういう人達が、リハビリテーションを何らかの理由で受けられなくなった場合、どうなるでしょう。その人たちは、必死になってリハビリテーションを受けようとします。リハビリテーションが受けられる場所を探し求めます。受けられない日々が続くと、不安になり、不安が大きくなれば、体が弱ってもないのに弱ってきていると錯覚をし、痛くもない体を痛いと感じ始めます。
私は思いました。これは、何かの症状に似ていると。そうです。麻薬です。麻薬を摂取しているときは気分が高揚していい気分になりますが、辞めたとたんに探し求めてしまう習性。そして幻覚や幻聴に類似した症状。とても似ているじゃありませんか。
そうした類似現象を発見したため、それをちゃんと科学的に証明したくなりました。研究を始めて、ようやく結論が出たのです。それがこの、厚生労働省に提出した研究内容です。」
岡崎は厚生労働省に提出したと思われる資料を高々と上げ、会場の人間に見せびらかした。そして、その内容について、詳細に語りだした。
「リハビリテーションとは、そもそも『リ』がつくため、元に戻ろうとする作用が心理的に働きます。しかし、それは一種の幻覚を見せる手段で、本来は元には戻らないのに、リハビリテーションと称して麻薬を与え続け、リハビリテーションと縁が離れないようにする、いわばリハビリテーション中毒と言える現象が、現在の日本で主に見られています。
そこで、リハビリテーションを長年に渡って受けられている人を対象に、脳内麻薬の分泌量を計測したところ、麻薬と同等の脳内ホルモンが放出されている事が判明しました。これはつまり、リハビリテーションの副作用であります。
リハビリテーションを受けることで、脳内に麻薬同等の成分が分泌され、その成分でリハビリテーションから離れられない心理が働き、永遠にリハビリテーションを受けなければならない体になってしまうのです。
これを断ち切るには、リハビリテーションを辞めるしか他ありません。リハビリテーションも飲み薬と同様で減らせば減らすほど、より健康に近づく事を再認識する必要性があります。」
岡崎は自信に満ち溢れながら言いきった。
「以上が簡単な内容です。ここに来ていただいた皆様の中に、研究者もお呼びいたしました。この内容はまだまだ詳細に研究しなければならないと考えています。もしよろしければ、手を取り合って、一緒に研究をしてみませんか?これは、国家のため、国民のためでもあります。是非、一緒にやりましょう!以上です。」
岡崎の演説は終わった。記者からいくつか質問が出ていたが、丁寧に、そして親切に、岡崎は答えを出していた。そして、招待された多くの研究者は、その新しい分野に興味を持ち始めていた。岡崎の人気は上昇しているような雰囲気を蒲田は肌で感じた。
終了の時刻になると、岡崎は質問を打ち切り、雛壇からゆっくりと降りた。そして歩いてその会場から去ろうとしたとき、岡崎は蒲田を意識したかのように、一点の視線を蒲田に合わせてきた。恐らくそれは偶然ではなく、岡崎がしっかりと蒲田を凝視していた。そして、岡崎は会場を去った。最後に去る瞬間、岡崎の口は少し笑っているような形をしたのを、蒲田は見逃さなかった。
第二章 氷河期(11)
ソラリスタ研究所の会見から数ヶ月が経過した。蒲田や竹下を取り囲む、リハビリテーション関連の環境は一変した。国民はリハビリテーションを悪と捕らえるようになっていた。今まで体によいと積極的に取り入れてきた流れは嘘のように消えていた。
テレビドラマではヒーローのように扱われていた理学療法士の役が、今では悪役として登場することが多くなった。親たちは子供達に悪影響を及ぼさないように、テレビなどで放送している場面を見つけたら時は、番組を変える様にしている様だった。
それでも流行に敏感な子供たちは、親が隠せば隠すほど、隠れて何かしたがる風景が見受けられた。学校帰りなどで遊ぶときに鬼ごっこのような遊びの代わりにリハビリテーションごっこという遊びが現れ、捕まえられたら強制的に運動をさせられ、最後には
「そんな運動がやみつきです。」
と中毒症状の真似をするという遊びが流行りだした。その中毒症状をさせられた子供は、1週間ほど中毒を演じなければならず、新たないじめ問題として社会的にも取り上げられるようにまでなってしまった。それがテレビで取り上げれば取り上げるほど、子供は隠れて行い、悪循環が生じていた。
蒲田が勤務する帝都大学健康促進学部理学療法学科にも影響は出ていた。リハビリテーションは麻薬と同等であるという発表前は、夢のある職業としてもてはやされていたが、今では社会から煙たがられる職業となり、希望に満ちて入学してきた生徒達が退学を希望する事が増え、後を絶たなかった。蒲田も一人一人に対して必死に説得をするが、将来を不安視する生徒が多く、退学に歯止めがかからない状態が続いていた。
何とかして食い止めようと、ある生徒には、蒲田が積み上げてきた研究結果を見せて、リハビリテーションは効果のある者だと説得をした。しかし、生徒は聞くことさえしてくれなかった。蒲田の発言より、マスメディアの影響の方がとても大きかった。
竹下にも影響が出ていた。竹下が経営している事業所も利用者数が激減していた。やはり、リハビリテーションを受けると麻薬と同等の効果になる、ということから、
「幻覚が見え始めるのが怖い。」
とか、
「やるほどひどくなりそうな気がする。」
という負の印象が拡大していた。竹下は各利用者に一人一人説明をした。蒲田から研究結果を借りてきて見やすいように工夫し、資料を作って説明も加えた。そうした必死の努力により、竹下の利用を辞めない人もいた。そうした人は、おそらく、以前より竹下を信頼しているから可能な事であった。
しかし、それでも数としては多くは無く、辞めていく利用者は絶える事はなかった。他の同じ様な事業所は閉鎖するまでに利用者が減少しているようだった。竹下はいつ自分の番が来るか、不安でいっぱいになっていた。
最近の蒲田と竹下は居酒屋「目黒」で会う機会が減少していた。お互いに仕事が大変になり、ゆっくりと話す時間が無くなっていたのだった。そして久しぶりに2人は会うことが出来たとき、竹下はかなり痩せていた。いつものように元気よく酒を飲む姿は見られず、言葉も弱々しい感じだった。お互いに今の近況を伝えあったが、竹下は明日も朝が早いと言うことですぐに終了になった。竹下は経営をしているため、社員の給料の確保という面でも苦労しているという事だった。
「絶対に閉鎖はさせない。」
竹下はその言葉だけを頻りに繰り返していた。
最近の傾向として、リハビリテーションというブランドは一気に地に落ちているということを、蒲田は実感せざるを得なかった。町を歩けば誰かに指を刺されて
(あの人、理学療法士やっているんだって。)
と陰口を言われているような気がしていた。周りを見ても誰もそのようなことは言ってはなく、ましてやパッと見ただけでその人が理学療法士かどうかなんてわからないはずなのに、蒲田の心の中では世間の目が気になってしょうがなかった。
蒲田は街中を歩くことを嫌い、研究室に閉じこもるようになってしまっていた。そして思い詰めることが多くなった。自分が今まで積み上げてきたものが、こうも簡単に崩れるのかと思うと情けない気持ちになった。それと同時に怒りの気持ちも毎日のように涌いてきた。しかし、情けない気持ちは自分で癒す事は出来たが、怒りの気持ちだけは誰かにぶつけたくて仕方なかった。
「岡崎・・・」
蒲田は一人、研究室でその名前を繰り返し呟いていた。
(12)
蒲田が勤務している帝都大学健康促進学部理学療法学科の生徒が次々に退学届を提出していた。その数は日に日に増加し、歯止めがかからない状況が続いた。一番の打撃だったのは、就職先として毎年帝都大学の新卒を受け入れてくれていた多くの総合病院から、
「今年度の新卒の受け入れは難しい。」
という話が出てからだった。この話は職員しか知らないはずだったが、どこからか情報が漏れてしまい、生徒から真実かどうか問いつめられることもあった。何とか誤魔化すが、限界に来てしまったようだった。また、その事実を隠そうとする態度も生徒達には不信感を抱いてしまった様で、二重にマイナスイメージを植え付ける事となってしまっていた。そうした中で、退学を希望する生徒が増え続け、蒲田は対応に追われていた。
蒲田はこの状況を変えられないか、今自分に出来ることは無いだろうか、と考え始めた。生徒数が激減しているなかで、今一度、リハビリテーションというものがいかに素晴らしいものなのかを生徒達に何度も口頭で説得しようとした。しかし、一度不信感を持ってしまった生徒には聞く耳を持ってもらえなかった。蒲田は過去のデータを持ってきて生徒に見せた。解りやすいようにリハビリテーションの有用性を視覚的に見られるようにグラフを用いて説明もした。しかし、それでも納得する生徒は現れなかった。それほどまでにリハビリテーションというものは信頼を失ってしまったのだと実感せざるを得なかった。
蒲田は研究室に一人でコーヒーを飲みながら考えていた。蒲田は今までのことを振り返っていた。政府が発表する前まではリハビリテーションの業界にとって、いい時代が続いていた。蒲田が何か研究結果を出せば概ね反映してくれたし、自分の職業に関しても胸を張って言えていた。そうやって世間からいい視線を感じているからこそ、仕事がやりやすかったのだと思った。こんなにも前の環境が幸せだったのかと思った。優遇されていたことに気づけなかった自分に蒲田は腹が立っていた。
蒲田はぼんやりとする日が多くなった。生徒は減少傾向ではあるが全て退学したわけではないので授業は続いていた。にもかかわらず、今一つ教えるということに身が入らず、これではダメだと頭ではわかっているのだが、心が付いていかない状態だった。気持ちが萎えてしまい、精神的に落ち込んでいる事が自分でもわかっていた。
一人で居酒屋「目黒」に居ることが多くなった。竹下は相変わらず忙しそうにしていた。電話で誘っても断られることが多く、今では電話もしない状況になっていた。酒に酔いつぶれ、酔い始めると岡崎の顔が頭に浮かんだ。そして、今までの負の連鎖を全て岡崎のせいだと考えるようになっていた。そう考えても何も変わらないことはわかっているのだが、そう考えないと生きていけないような気がした。未来に光が無いというのは、こうも生きる気力が涌いてこないものだと体の中から理解できた。
生きる希望とはどういうことなのだろうか。生きる気力とは何を意味しているのか。今までリハビリテーションの授業をするとその事を生徒に教えることが多かった。身体機能面からの生きるという考え方と、精神機能面からの生きるという考え方と、二つの角度から常に説明を加えて、「生きる」という意味を講義していた。
『君たちは「生きる」という事はどういう事か考えた事はあるかい?
リハビリテーションにとって、「生きる」とは、「未来を楽しみにする」という気持ちに変えさせることが大切になるんだ。
私達、理学療法士は、患者様や利用者様がその気持ちになれるように、具体的な方向性を示してあげる。そうした方向性を示す事で「未来を楽しみする」事が出来るんだ。それが、私達、理学療法士の仕事なんだ。
今の日本は高齢者が増え、未来がつまらないものに感じてしまっている人たちが大勢いる。そうした精神機能が働いている人たちに、我々はリハビリテーションというものを通じて、身体機能を専門的に、かつ客観的に考え、まだ残っている身体機能を最大限に活かすことを考え、残りの人生を生きる希望に変えて差し上げるんだ。
つまり、私達、リハビリテーションとは、「生きるための希望」と言っても過言ではない。高齢になれば、体が思うように動かなくなり、動かなくなれば転んでしまうのではないかと怖くなり、怖くなればさらに体を動かさなくなる。そうした悪循環が生まれ、自分の未来が楽しめなくなってしまうんだ。
そうした人達に手をさしのべるのが、リハビリテーションであり、理学療法士の仕事でもある。だから、我々は「生きる希望」にならなければならない。それが理学療法士というものだ。』
昔はそれで多くの生徒が感動をし、勉強に苦しんでいるときでも、頑張ろうと思ってくれた。つらい授業内容でも何とか乗り切ってくれる生徒も毎年のように現れてくれた。それが今ではリハビリテーションが麻薬と同じと言われてしまう。本当にこのままでいいのだろうか。
蒲田は冷静になり始めた。蒲田は今の麻薬であるという内容に疑問を持っているため、これを否定するために今までの研究成果を表に出しても誰も聞いてくれないという事が今までの経緯だった。では、麻薬という内容を踏まえて研究をしてみることを考えた。いくら反発をしたからといって、それで話を聞いてもらえないという流れがあるのであれば、リハビリテーションは麻薬であるという事がいかに証明出来ないかという事を示すことで、麻薬という内容に疑問を投げかける方法を考えた。
蒲田は早速、研究に取り込もうとした。しかし、こうした方向性で考えた事がなかったため、何をテーマに取り組んで良いのかわからなかった。蒲田は再び頭を抱えていた。
(13)
蒲田は頭を抱えながら、リハビリテーションは麻薬ではないという事実を否定できる根拠はないのだろうかと、頭の中で整理をしていた。今までの自分の研究が正しければ、リハビリテーションが麻薬という事はありえない考えだった。きっと、この流れだと、このままリハビリテーションがあまり利用されなくなると思われた。となれば、必ず利用しなかった人には悪影響が出てくるのではないか。蒲田の頭の中に一つ光が見え始めた。
「まずはその悪影響を示すデータを集めなければならないのか。そのデータが集められるかがポイントか・・・。」
蒲田は新たなデータ収集に力を入れ始めた。いつものように、データ提供依頼を様々なところに打診した。しかし、以前の様にデータは集まらなかった。
理由は簡単だった。いつも協力してくれているリハビリテーション関係の事業所の数多くは、現在、閉鎖に追いやられている状況だった。事業所が残っていたとしても、登録している利用者数が少なく、データ協力が難しいと断られるのがほとんどだった。
困った田端は竹下にも相談したが、竹下も同じような答えが返ってきた。どこも今は厳しい状況だと竹下から教わった。蒲田はデータ収集でも一苦労するのだと実感させられていた。
蒲田は新たなデータ協力事業所を探すために、全日本理学療法士連合団体に連絡を取った。全日本理学療法士連合団体とは、日本全国にいる理学療法士の登録者を管理しているところであり、勤務場所や経験年数などの個人情報を扱っている場所でもあった。ちょうど、蒲田が勤めている帝都大学も、その連合団体に加盟しているため、何かしら協力が得られるかもしれないと思ったのだった。
蒲田は、連合団体と連絡を取り合い、要件の趣旨を説明したところ、連合団体の会長話す事が出来た。そして、会長は心よく全国に協力を要請してくれる事になった。連合団体としても、今回のリハビリテーションが麻薬と同等の効果があるという発表には足元をすくわれた思いをしている様だった。全国各地で悲鳴が聞かれているため、何とかしたいので、全力で協力するという言葉を貰った。蒲田は味方が増えた気がしていた。
しかし、世の中の流れはリハビリテーションにとって、負の方向へと流れる一方だった。テレビをつければリハビリテーションの麻薬効果の実証と題して、ニュース番組のワンコーナーで検証している番組が見られた。検証内容もあいまいで、具体的なデータで証明しているものではなく、人の感想で麻薬なのではないかという意見が多いため、リハビリテーションは体によく無いという判断をしている事が多かった。早急に反対するデータを揃え、発表する事が大切であると考えていた。
(14)
数週間後、連合団体よりデータが提出された。それは今までにないほどのデータ量で、蒲田は嬉しい半分、処理が大変になると先が思いやられる気持ちも湧いた。しかし、これが全国同じ仕事をしている人たちの思いが詰まっているものだとも取れた。自分が今からしようとしている事は、理学療法士としての将来を決める、大切な研究なのだと頭を切り替え、すぐにデータ分析をするために、机に向かった。
データは人間の生活状況を数値化したものだった。トイレ動作、入浴動作、歩行動作、更衣動作、食事動作など、人間が生きていくうえで最低限必要な動きを数値化しているものだった。しかし、そのデータにはリハビリテーションを現在受けている人のデータのみだった。今回の研究の趣旨は、リハビリテーションを受けていた人が辞めた場合の影響がどれくらいかを調べる事だった。よって、辞めた人のデータがないと比較できなかった。
再び連合団体の会長と連絡を取り、リハビリテーションを辞めた人のデータ提供の依頼をした。しかし、会長からはそのデータを提供することは困難だと言われた。連合団体側も努力をしていたそうだった。しかし、リハビリテーションを終えた人に対して追跡調査をお願いしても、麻薬からやっと離れられたと思っている人がほとんどであり、リハビリテーションと関係を断ちたいと思っている人が多いので、協力は得にくかった、と話してくれた。会長から、大変申し訳ないという気持ちの言葉を貰い、厳しい状況をより一層感じた。
蒲田は再びデータ集めに頭を悩ませた。リハビリテーションを辞めた人たちのデータをどうやって集めるかがわからなかった。竹下に相談し、竹下の事業所だけでも辞めた人たちからデータを収集できるかと聞いたところ、竹下からも難しいと答えていた。リハビリテーションは麻薬であるというところから、被害妄想は拡大して、理学療法士に会うだけで麻薬に触れてしまう事と同じと思っている人たちが数多くいるようだった。それほど、リハビリテーションという負のイメージは拡大し、影響が大きくなっているのだと思った。この影響が、全国に広がっているのだと改めて感じた。
蒲田は再び今あるデータを眺めていた。ここから吸い上げられないものは無いものなのか。ここでしか、今ある状況で結果を出さなければならない事は間違いなかった。膨大な数字の羅列が表示されているパソコンの画面を見ながらいくつものグラフを作っては消し、作っては消した。蒲田が希望するような結果は出ず、以前と同じような傾向のグラフばかりが結果として出るばかりだった。
蒲田は考え始めていた。ずっとリハビリテーションが必要だと言う信念で、今まで研究をしてきたけれど、必要ではないという観点から物事を考える事はしていなかった。もし、今回の研究で、リハビリテーションを辞めても生活に何も影響が出ないということが証明されてしまえば、リハビリテーションは必要なくなるのではないだろうか。たとえ、細かい部分で必要になったとしても、必要最小限に抑え、リハビリテーションを受けなくてもいい生活を得るという事が、ある意味大切な事になってくるのではないのだろうか。蒲田の頭の中は様々な考えが交差するようになっていた。
(15)
蒲田の研究は何一つ前に進んでいなかった。 データ分析を少し投げ出し始めていた時に、竹下から電話が入った。
「どうだ?進んでいるか?参考になるかわからないけど、俺なりの考えではあるが、迷惑じゃなければ耳に入れておこうと思って。
俺の考えはこうだ。今、リハビリテーションは麻薬だという流れがあったとしても、きっと、病院で入院している人は、リハビリテーションを受けている傾向がまだ多いと思うんだ。これは、以前から報道でも予想していた通り、病気したばかりの時は早く普段の生活に戻りたいだろうから、麻薬と分かっていてもリハビリテーションは受けると思う。でも、家に帰ってからリハビリテーションを受けるという事をあまりしないような気がする。家に帰るとあとは自分で何とかしようという考えになる傾向があるように思うんだ。
でも、それでうまくいかない事が多くある。それは退院した直後は、本人は以前の生活に戻れると思っているけれども、それは違う。今の病院側は中途半端な回復で退院させるんだ。今は在院日数が減らされている中で、病院側としても早く退院させなければ赤字になってしまう。だから、完璧に体を回復させて戻す事はあまりしていないのが現状だ。入院していた人は退院出来る、イコール元に戻ったと考えてしまう。このギャップが退院した時の生活に影響が出ていると思うんだ。
中途半端な回復で帰ると言う事は、以前とは違う身体機能になっている、という事だ。つまり、入院前と同じ動作を癖でしようとすると、出来ない事があるということだ。出来ないで終わればいいが、出来ない事を無理にして、転んでしまい怪我をしたり、中には骨折をして再び入院するという事もあると思うんだ。
俺の事業所の訪問リハビリテーションも、退院した直後に介入する依頼が少しずつ増えてきている。やはり、そこはいくら麻薬と言われていたとしても、転倒して骨折して入院するよりかはいいと考える人が増えてきているみたいだ。
少しずつだが、流れが再び戻ってきている印象もある。蒲田。この情報は役に立ちそうか?」
蒲田は竹下の意見でやるべき事が見えそうな気がした。蒲田は竹下に感謝の意を伝えた。やはり、研究者は現場の人間の情報が何よりも大切であると改めて思った。
蒲田は竹下の情報をもとに分析を行った。今、手元にあるデータはリハビリテーションを利用している人のデータだけだった。ここからリハビリテーションを受けなくなった人のデータを拾い上げる事は困難であることは間違いなかった。しかし、リハビリテーションを受けている人のデータは膨大だ。
蒲田はまず、データの中から入院してリハビリテーションを受けている人の数の総数を調べた。そして、麻薬発表前の数字と比較した。これは予想通り、数にあまり変化がなかった。これで、入院している人はリハビリテーションを受けている事は確認出来た。
次にその人達が退院した後を追った。退院した後に在宅でリハビリテーションを受けている人と受けていない人にグループを分け、そして、さらにその後、転倒して再び入院していないかどうかを調べ、比較した。結果、在宅でリハビリテーションを受けた方が再び入院する傾向は少ないという結果が出た。
つまり、病院から退院し、家に帰って生活をする場合、継続してリハビリテーションをした方が転倒率を低下させて再入院のリスクが少なくなり、リハビリテーションの効果としても認められるという事が実証された。
「まずはこれでちゃんと家に帰ってもリハビリテーションを受けて貰おう。これを、厚生労働省に提出して、必要な時はちゃんとリハビリテーションを受ける様に言ってもらおう。」
蒲田は、データを整理し、提出出来るように資料を作成し始めていた。
(16)
蒲田は研究成果をまとめた資料を厚生労働省に提出しようと再び訪れた。担当窓口は以前と変わらない人が担当していた。その人は蒲田を見ると、
(また来たのか。)
というような煙たい表情をしていた。蒲田はその人に研究内容を提出するが、担当の人は形式通り受け取るだけだった。そして、蒲田の耳元で一言言った。
「こういうことしても無駄だと思うよ。」
そう言って担当の人は裏の方へと行ってしまった。何か変わることを期待しつつ、蒲田は厚生労働省を後にした。
提出してからしばらく経った。しかし、政府の動きは変わらず、世の中の流れも変わらなかった。変わらないという事に焦りを感じ始めた蒲田は、他に出来ることはないかと考えていた。その時、ちょうど轟から電話があった。蒲田は轟と会うことにした。
蒲田は轟に会うと、すぐに以前提出した研究内容のデータの事を伝えた。そして、そのデータの重要性を訴えた。轟はそのデータのことは既に知っていた様だった。知ったからこそ、蒲田に連絡をしてきたらしかった。しかし、轟もそのデータをどのように官僚内で訴えていけばいいのか分からないようだった。轟が言うには蒲田が提出したデータは他の研究所からも提出されていて、重要性は十分に理解しているようだった。しかし、上層部の人間がそれを見て見ぬふりをしているらしく、どんどん今の流を進ませている様だった。轟は蒲田に言った。
「この流れを止める方法が今の俺には分からない。今の俺じゃ何も出来ない。蒲田。そのデータをマスコミに知らせて報道してもらってはどうだ?」
轟は知り合いの新聞記者を教えてくれた。壁にぶち当たっていた蒲田にとって一つの道があるだけで、心強かった。蒲田は轟に深々と頭を下げてお礼を言った。蒲田はすぐに、その新聞記者の居る場所へと向かって行った。
蒲田は、轟の知人である新聞記者の会社に向かった。会社は立川駅から歩いて十分位の所にあった。そこは、ビルの中の一部屋を事務所として構えていた。
その会社は新聞会社としての規模は大きくはないが、医療や介護分野にはよく精通している会社だった。本社は新宿にあるらしく、支店として立川に事務所がある様だった。轟から、その知人の新聞記者に連絡を既にとってもらっていたので、蒲田は指定された場所に行くだけだった。蒲田は事務所の前まで来てドアをノックした。中からゆっくりと人が出てきた。
中から出てきた人は待っていたかのようにやさしい笑顔で迎えてくれた。名前は渡辺純で、轟の知人、本人だった。蒲田と渡辺は簡単に挨拶を済ませると、渡辺は事務所の中へと蒲田を案内し、小さい部屋に通してくれた。恐らく普段は会議などで使用している部屋だろうと思った。隅の方には備品などが置いてあり、雑然とした部屋だった。
渡辺は轟から大まかな内容の話は聞いていたようだった。渡辺は今回の騒ぎにとても興味を示してくれているようだった。
蒲田は、渡辺の考えを確認するためにもリハビリテーションの基本的な必要性について説明をした。リハビリテーションというものは、元々病院に入院中の人に対して行っていた事が、病院という枠を飛び越えて在宅でも必要になっている事。そして、高齢社会において、入院を最小限にし、住み慣れた環境でなるべく長く過ごす事が大切であり、そのためには在宅で受けるリハビリテーションが必要な事も説明をした。渡辺はその点に関しては確認するまでもない様子で、とてもよく理解していた。さすがはそうした分野を扱っている会社だった。
さらに蒲田は今回新たに調べた研究内容を渡辺に話した。在宅でのリハビリテーションの必要性を訴えた。
その点に関しても渡辺はよく理解している様だった。新聞記者は情報が早いのか、轟と知り合いだから詳しいのかわからないが、蒲田よりも詳しそうだった。
蒲田と渡辺は話を進める中で、渡辺は一つ質問を蒲田にした。なぜ、在宅でのリハビリテーションが長い時間必要なのかという点だった。これは、蒲田がずっと訴え続きてきた、『かかりつけ理学療法士制度』
の事を示している様だった。
蒲田はかかりつけ理学療法士制度の意義や必要性を思い出す限り、渡辺に説明をした。家では気が抜けて運動をしない人が多い事や、閉じこもる傾向が多くて結局体が弱ってしまう事が多いという事を、昔のデータを思い出しながら話した。
しかし、渡辺はその事実が長い期間必要になるという決定的な証明にはならないと指摘してきた。渡辺は言った。
「私の仕事は取材などで得た資料を客観的に分析をして、国民が知りたい情報を知らせるというものだ。
今回のリハビリテーションが麻薬であるような報道には、まだはっきりとした裏証拠が得られていないので、私からは何とも言えない。ただ、別の資料からは、長期間無駄にリハビリテーションを受けさせ、リハビリテーションから抜け出せない社会を作ってきてしまっている、と主張する者も少数ではあるがあるのも事実だ。
その資料にはこう書いてあった。
『人生というものは、本来ならば、リハビリテーションからも卒業をして、自分で生きる方法を身につけさせるのが、本当のリハビリテーションである。高齢だから、年をとると体が弱るから、と、過剰に不安を抱かせて、リハビリテーションというものを必要以上に与えている』
私はこの資料も無視できないと思っている。これに関して、蒲田さんの意見が聞きたい。あなたは、『かかりつけ理学療法士制度』という観点を、ずっと研究をしてきた人ですよね。」
渡辺は蒲田の顔を見つめてきた。蒲田は、答えに少し迷っていた。蒲田はその質問に対して、以前であれば、必ず必要であるという反論がすぐに出来た。かかりつけ理学療法士制度を考え、永遠にリハビリテーションというものを提供し、在宅生活をより長くしていく一番いい方法だと考えていた。しかし、今回の麻薬騒動後に多くの人がリハビリテーションを辞めた中でのデータ分析をしても、かかりつけ理学療法士制度を推進できるデータがそろわなかった。退院直後のリハビリテーションしか必要性を見いだせてない事を考えると、ずっとリハビリテーションをやればいいというものでもないような気もしてきているのも事実だった。
しかし、今は理学療法士の連合団体より預かったデータを元に分析を進め、理学療法士という職業の名誉挽回をする事に必死だった蒲田は、渡辺への答えは以前からリハビリテーションを推奨してきた立場で話を進めた。渡辺と蒲田の話し合いは平行線で進んだ。結局、入院していた人が帰ってもリハビリテーションを受ける有意義さは説明できるので、その点に関しては記事に出来ると話してくれた。けれども、それが理学療法士の名誉を挽回できるほどの記事になるとは到底思えない、と渡辺は言っていた。
渡辺は蒲田が昔から提案していた、かかりつけ理学療法士制度が証明出来れば、一番の記事になると話してくれたが、今の蒲田にはそれを証明するデータがなかった。渡辺は蒲田に言った。
「あなたは、今後もかかりつけ理学療法士制度を本当に推進していくのですか?本当に証明できそうか?」
蒲田はうつむいたままその質問に関しては返事が出来なかった。
後日、渡辺が書いてくれた記事が発売された。しかし、やはりあまり反響は少なく、記事の扱いも小さかった。新聞も国民が知りたがっていることを記事にする事が大切だ、と渡辺は言っていた。この小さな記事は、国民の関心の大きさなのだろうかと蒲田は考えていた。
(17)
蒲田と竹下は居酒屋「目黒」にいた。蒲田は竹下に現在の状況を説明した。全国からデータを集めて解析した結果、竹下の言う通り、退院直後に優位さが出たこと。それでリハビリテーションの効果をアピールするために厚生労働省に行ったが、轟よりあまり反応がないと話されたこと。轟から知人の新聞記者を紹介してもらい、新聞にて報道して貰えないか交渉しに行った事。しかし、そこでもあまりよい反応ではなかったこと。根本的な問題は何も解決していないという現状が、今の最大の要因ではないかというところまで竹下に話した。
「やっぱり、かかりつけ理学療法士制度をちゃんと示せないと、俺達の将来はないのか・・・。」
竹下は今の経営を本当にどのようにしたらいいのだろうか、本気で悩んでいた。この蒲田の知らせがあまりにも良くない方向だったので、今後の方針がまったく見えない状況になっていた。ここでもし、蒲田からいい方向だという知らせが入ったのであれば、少しは持ちこたえようと考えていたのかも知れない。でも、そうではなかった。リハビリテーション業界のマイナスの風は一向に収まる気配はなかった。
しばらく2人で飲んでいると、轟が慌てたように居酒屋「目黒」に入ってきた。轟は蒲田と竹下に告げた。
「奴から電話が入った。」
「奴とは誰だ?」
「岡崎だ!」
岡崎の方から轟の携帯に電話をかけてきたようだった。轟が厚生労働省で働いていることを岡崎は知っていたのだろうか。岡崎はこのように話していたようだった。
「久しぶりだな。轟君。轟君が厚生労働省で働いていることはずっと前から知っていたよ。俺の研究結果を大いに取り組んでくれてありがとう。感謝するよ。おかげでリハビリテーションというものが、世の中で正義のように扱われていた傾向が、悪魔として生まれ変わることが出来たよ。総理大臣まで動かしてくれるなんて、厚生労働省もやるねぇ。おかげで俺は色々なところからお声がよくかかるようになったよ。
さて、轟君。あんたは最近、蒲田や竹下に会っているようだね。ちょっと話したいことがあるんだけど、時間作ってくれるかなぁ~。」
岡崎は轟に久しぶりに話すのに、とても慣れ慣れしい話し方をしていた様だった。しかも轟を見下すような話し方だったようだ。轟も少し頭にきているようだった。蒲田は轟に冷静になるように言った。しかし、竹下は怒りを露わにしていた。竹下もまた、岡崎に怒りをぶつけたがっていた。
蒲田と竹下は岡崎と会うことを約束した。なぜ、2人に話したいことがあるのだろうか。竹下は完全に頭に血が上っていた。会えると言うことで怒りの矛先が岡崎に向かっていた。蒲田は竹下に冷静になるように宥めていた。
(18)
岡崎は詳細な場所と時間を設定してきていた。蒲田と竹下と轟は三人でその場所へ向かった。場所は青梅線の東中神駅から南に降りて川沿いにある小さな公園だった。時間は夕飯が終わる頃の時間に設定してあった。太陽はすでに沈んでいた。
この公園は日中はにぎやかで、子供がよく遊んでいる公園だった。砂場には山のようなものが作られていて、そのまま子供が帰った形が残っていた。
指定した時間に着いた三人はあたりを見渡したが岡崎の姿は無かった。待つしかないため、三人は公園の中にあるベンチを見つけ、腰をかけて待っていた。公園にはライトが一つしかなく、公園全体を明るく照らすものではなかった。端の方は真っ暗で、明かりの下に来ないと誰だかわからないような暗さだった。蒲田はライトの下を注意して見渡していた。岡崎が来たらすぐにわかるように心がけていた。
少しすると遠いところから人影が見えた。その姿は移動するにつれて、ライトが当たる部分が増えた。そして、その姿は徐々にはっきりと人物を映し出した。その姿は岡崎だった。
岡崎は三人を見ると懐かしそうな表情をオーバーリアクションで表現し始めた。両手を天に広げ三人を歓迎するかの勢いだった。蒲田は岡崎を見るなり警戒した。竹下、轟も同じように感じているようだった。岡崎はその雰囲気を感じたのかすぐに挙げた両手をゆっくりと降ろした。
「そんなに怖い顔をしないでくれよ。」
岡崎はニコリと笑顔を作っていた。話をしようじゃないか。そう懐を大きく見せるような構えをしていた。
「何の用だ!」
竹下は敵意丸出しで岡崎に言いはなった。岡崎は怖いという表情を作ってすぐに笑顔に切り替えた。
「わかったよ。懐かしいから昔話でもしたかったんだけど、そうもいかないみたいだから、用件だけ伝えるとしよう。用件はただ一つ。君たちのつまらない研究から手を引いて、こっちの研究を手伝ってくれないかい?」
竹下はつまらないという言葉にすぐに反応し、反論した。
「何がつまらないだぁ!お前こそ、麻薬という嘘をばらまいてるんじゃねぇよ!おかげでこっちは大迷惑しているんだ!さっさと撤回しろ!!」
「まぁ落ち着いてよ。竹下君。そうカリカリすると、すぐに頭が禿げちゃうよ。ハハハ。」
「ハハハじゃねぇ!」
竹下は完全に怒りに満ちていた。蒲田は冷静になれと横から言っているがまったく聞き入れないでいた。
「君たちもよく研究してきているじゃない。リハビリテーションは絶大だ!最高だって!僕はその反対を示しただけだよ!何をそんなにも怒られなくっちゃいけないのかなぁ?」
竹下は岡崎に罵声を浴びせつづけたが、岡崎はやんわりとかわし続けていた。このやりとりを横で見ていた蒲田は、岡崎が今日何を言いに来たのかを知りたくなった。
「岡崎。」
蒲田は岡崎と竹下の言い合いの合間を縫って岡崎に話しかけた。
「久しぶり。蒲田君。」
岡崎の話し相手は蒲田に移った。
「君は帝都大学で研究をしているそうじゃないか。私と同じ感性って事だね。」
「感性は同じじゃない。」
蒲田は同じにされることを嫌がった。かまわず岡崎は話し続けた。
「研究者が大切に思うことは、世の中をどうしたいかという気持ち以外に、データに忠実に結論を出さなければ行けないと思っているんだよね。だけど、君は竹下と組みデータをねじ曲げた結論を出し続けた。」
「何を根拠に?」
「だって捏造じゃない。リハビリテーションは麻薬と一緒だったんだから。」
「何を根拠に言っている。何を根底に話している。今までそのようなデータはないし、そんな証拠もどこにもない。俺は今までずっとリハビリテーションの効果を分析して結果を出してきた。それで厚生労働省にも参考にしてもらい、世の中の流れとなる根拠を示してきた。それがなんだ。たった一回の研究発表で。」
「その研究内容が世の中を変えてしまったんじゃないのか?蒲田君?」
岡崎は自信に満ちあふれた口調で続けた。
「今までリハビリテーションの有効性だけを検討してきた結果がこれだ。リハビリテーションは最高だ、健康長寿には必要不可欠な要素だ。そう言い放って信用させてきた。
しかし、それは違う。リハビリテーションは毒素を交えた汚らしい汚物そのものだ。やればやるほど止められなくなり、やがて無しには生きられなくなる。そういうことを助長し、推進してきた結果が、本来自分で行おうとする意欲を低下させ甘える体質を作ってきたんじゃないのか?これは麻薬の中毒症状とまったく同じじゃないか。始めれば終わりがない。どんどん深みにはまっていく。何が違うんだい?え?」
「違う!」竹下は罵声を放ち、自分の主張を言い放った。
「リハビリテーションというのは生きる希望なんだ!何も出来ないという錯覚から目を覚まし、出来ることを増やして、そしてそれを希望に変える。それがリハビリテーションの本質なんだ!確かに、なかなかやめられないというのは事実だ!しかし、止めないからこそ、生きる希望が生まれ、人が最後まで意欲を持って生きられるんじゃないか!理学療法士が関わることで、日々の不安を解消し、毎日の安心を届け、そして明日の希望を与える。この循環に何がいけないんだ!」
「それが麻薬と同じだと言っているんだよ、竹下君。君たちはその事がリハビリテーションの中毒症状だと思わないのかい?リハビリテーション、リハビリテーションとまるで昔に戻れるかのような錯覚を与え、そしてその努力を美化し、リハビリテーションというものをしている人は偉い人という風潮にさせ、そして毎日の貴重な時間をリハビリテーションに費やす。私は可哀想でしかたがない。とっても可哀想だ。その人の可能性を、リハビリテーションによって潰してしまっているのだからねぇ。」
「可能性を潰している?可能性を広げているのがリハビリテーションだ!」
「いいや。違う。可能性を潰している。理学療法士が関わる時間はその人に対して何時間拘束していると思う?まさか、理学療法士が関わった時間だけを計算する訳じゃないだろうね?例えば、君が経営している訪問リハビリテーションという分野で考えてみよう。訪問リハビリテーションというのは一回だいたい多くて1時間。それが多くても週2回だったとしても2時間だけだと思っているんじゃないのかい?実はそれだけじゃない。受ける本人は前の日から準備をするんだよ。体調を整えたり、部屋を綺麗にしたりとね。よくよく考えてごらん。たとえ毎週来る人だとしても、その人にとっては外から来るお客様なんだよ。おもてなしの精神は日本の心でもあるからね。だいたいは準備というものに時間をさいているんだ。そして、何よりも、毎日のスケジュールだよ。人間スケジュールが空いていれば何かしようという気持ちになるもんだ。それがコンスタントに誰かが来てくれればそれだけでスケジュールが埋まり、自分から何かしようと思いにくくなる。これこそリハビリテーションが邪魔になっているとは思わないのかい?」
「こっちがスケジュールを埋めなければ、その人はほぼ毎日する事がなく、弱ってしまうじゃないか!俺たちが定期的に行くことで弱らないようにしているんだ!」
「ほー。弱らないようにしている。君たちは、たった1週間に2時間という時間しか関わらないのに、それで弱らないようにしていると言い切れるのかい?」
「ああ。実際に良くなっていく人もいる!これは俺たちがリハビリテーションをした効果だと言えるだろう!」
「2時間ばかりで良くなるものなのかい?」
「週2回運動すれば筋力は向上する!それは一般常識だ!」
「運動に関しても最大負荷量をかけていないのに?」
「なに?」
「僕がいいたいのは高齢者に対してきつい運動はしないでしょ?それなのに週2回という頻度だけで筋力は向上するのかと言うことだよ。」
「それは・・・」
「結局それはリハビリテーションを受けた側の満足感によって、何か自分でも出来るのではないかという自信がついただけなんだよ。自信がついたら人間は自然と何か新しいことに挑戦をしたくなるもんなんだよ。そうした挑戦をリハビリテーション以外の時間でして、人は筋力を付けていくんだ。君たちがリハビリテーションを実施した時間で筋力を向上したというのはまったくの見当違いだね。」
竹下は言い返せなくなっていた。岡崎の話は止まらない。
「いいかい。僕だってリハビリテーションというのは世の中で必要なものだと思っているよ。そこは勘違いしないでほしい。ただ、やり過ぎが良くないと言っているんだよ。病院で入院中は仕方がないと思うよ。入院している人はだいたいが皆さん家に帰りたがるからね。自然に自分で頑張るからリハビリテーションも最小限で済む。しかし、家でのリハビリテーションはどうだろうか。長く終わりのないリハビリテーションを受けるということで、自分から何かしようという心が芽生えずらくなってしまうと思わないかい?リハビリテーションというものは必要最小限に押さえ自分でする。これこそがリハビリテーション本来の姿だ。長くするのはリハビリテーションというものにたいしての中毒といってもおかしくはないと思うがね。
事実。脳内ホルモンから麻薬中毒と同等の成分が検出されてしまったんだ。つまり、科学的に証明された、というわけですよ。ねぇ、た・け・し・た・くん!」
岡崎は竹下をまっすぐに見て言った。
竹下は岡崎の主張に言い返せずにいた。しかし、麻薬という発言に我慢が出来ず、殴りかかろうとしたが蒲田と轟で抑えた。岡崎は薄笑いをして竹下を見ていた。
「リハビリテーションというのは今までは副作用のない薬のようなものだったんだよ。リハビリテーションも所詮、医者の指示がないと出来ないからねぇ。薬と変わらないでしょ。その薬に今まで副作用がないから問題だったんだよ。害のない薬なら誰もが喜んで処方するでしょ。誰だってその薬飲むよね。だってサプリメントみたいなもんなんだもんね。
処方する方も処方する方だ。患者が求めれば、拒否する理由なんてほとんどないからどんどん過剰な投与をする。医者も言われるがままに処方し、理学療法士も言われるがまま行う。だって害がないんだもん。そりゃそうなるさ。
でも今は違う。もう害があるんだよ。副作用があるんだよ。それも重篤な中毒症状が存在しちゃったんだよ。気をつけてねぇー、リハビリテーションを行うときはー。やり過ぎちゃうと、その人を一生ダメにしちゃうよー。ハハハ。」
竹下は蒲田と轟の抑えを振り払い岡崎の顔面を殴りに行った。しかし、殴りに行った拳は岡崎の顔に当たらずすり抜けた。竹下はバランスを崩し、岡崎の前で転んだ。岡崎は竹下を右足で蹴り飛ばした。竹下は苦しそうに蹴られた場所を抑えた。
「手を出してきたのは君の方だからね。僕は何も悪くない。」
目の前で横たわる竹下に言い放った。そして、岡崎は蒲田に視線を合わせた。
「いつでも連絡待っているよ。僕の研究を一緒にやれる日を待っているよ。」
そういって岡崎は公園を去っていった。竹下はうずくまったまま起きようとしなかった。
岡崎と別れてから三人は何も話さなかった。岡崎の言葉に対して意見を言い合うのが通常の流だと思うのだが、岡崎の言っていることがおそらく三人ともに理解できたのだろうか。少なくとも蒲田はとても理解できてしまっていた。前から、少しずつ自分が全て正しく、岡崎の考えが全く違うという考えに違和感を覚え始めていた。リハビリテーションが麻薬という意味も極端すぎる事だと思ってはいるが、岡崎の言葉を聞いて、ある意味正論でもあるような気がしてきてしまっていた。蒲田も今、自分の考えにブレが生じてきてしまっているような気がしていた。そのブレをどう修正して良いのか今はわからない状態だった。おそらく、竹下、轟も同様なのだろうと思った。だから何も話せないのだろうと考えていた。
三人はそのまま家路に帰って行った。別れの挨拶も聞こえないくらいの声量だった。
蒲田は家に帰ってテレビをつけた。蒲田はニュース番組にチャンネルを合わせた。すると、厚生労働省から現在の社会保障の費用について発表があったというニュースが流れていた。社会保障費用は大幅に削減出来たという内容だった。要因はリハビリテーションの利用者減少によるものだと分析をしていた。
これにより一番財政を圧迫していた社会保障費用が軽減できたという実績が、今の政権の支持率を上げていた。今ある情報は全てうまくいっているという情報ばかりだった。
蒲田は思っていた。本当にこれでよいのだろうか。わからないまま時が過ぎていった。
第三章 逆転(19)
蒲田は岡崎と会ってから、研究に手がつかなくなっていた。今まで、推奨してきたリハビリテーションという考えが本当に良いものなのだろうかと考えるようになっていたからだった。
以前からずっと、蒲田も竹下も医師がかかりつけ医という考え方があるように、理学療法士にも『かかりつけ理学療法士』というような形で高齢者に対し、ずっと関わり続けていくというような考えをしていた。その方が、世の中のためにでもあるし、高齢者が最期まで元気に暮らせる秘訣であるとも思っていた。しかし、岡崎の主張は全くの正反対で、リハビリテーションは危険なものであるという考えだった。その考えで行けば、確かにリハビリテーションというもので高齢者を餌付けしていると言われても、間違ってはいないのではないか。本当はリハビリテーションというものがなくても元気に過ごせるとしたら、その方が高齢者にとって良いことなのではないか。そういう考え方がどうしても完全に否定できなくなっていた。蒲田にとって、自分の研究が何のためにやっているのかが見いだせなくなっていた。
岡崎と会って以来、竹下とも会話をしていなかった。竹下は今頃どういった考えになっているのだろうか。蒲田は竹下に電話をしてみたくなった。
蒲田は携帯電話を取り出して竹下に電話をかけた。竹下はすぐに電話に出た。そして、竹下が電話にでると、すぐに岡崎の話題になった。竹下はあれから考えを整理したようだった。整理した結果、やっぱり必ずリハビリテーションは高齢者にとって必要なものであり、生活必需品のような考え方に変わりはなかった。しかし、声の質は以前より浮ついているように感じた。きっと、竹下は変わらないと言うよりも変えられないのだろうと蒲田は感じていた。
竹下は研究内容の進捗状況を聞いてきた。竹下からデータを貰っている以上はこの答えを返さなければならなかった。しかし、手をつけられていない状態が続いていたため、ごまかして答えた。竹下は怪しむことなく、蒲田の答えを聞いた。
「今度の木曜日、ちょっと付き合ってくれないか。」
竹下は蒲田に見せたいものがあるようだった。竹下は会うまで内容は教えてはくれなかったが、必ず研究に役立つと言うことだけは断言していた。
(20)
竹下は蒲田を車に乗せて走っていた。蒲田が見せたいものは何なのか竹下に問いつめていたが、竹下は答えようとはしなかった。実際に見て、それで感想が欲しいらしく、下手な先入観は与えたくないようだった。
竹下が向った場所は小さな平屋の一軒家だった。古い家で、強い台風が来たら壊れてしまうのではないかと思えるような建物だった。この家は竹下が訪問リハビリテーションを担当して行っている利用者の家だった。竹下は蒲田に現場の様子を見せたいようだった。
訪問した家の利用者は岸谷源吾という名前だった。岸谷さんは年齢が九十才。一人暮らしのおじいさんだった。体の状態を見させてもらった。状態からすれば一人暮らししているとは考えにくい状態だった。歩く事はほとんど出来ず、部屋の移動はいざって行っていた。一人では身の回りの事は出来ないのではないかと蒲田は感じた。
竹下に普段どのように暮らしているのかと聞くと、洗濯や掃除、買い物はヘルパーが対応していて、食事は夕食が宅配弁当で朝と昼は兼用でパンを一切れ食べるような食生活をしているとの事だった。普段の過ごし方はテレビの前の椅子に座りっぱなしで、テレビを見て毎日を過ごしているようだった。ただし、頭はしっかりしているので、電話の対応や緊急時の連絡などは自分で出来ていた。
竹下は岸谷さんを蒲田に紹介をした。岸谷さんは蒲田を快く受け入れてくれた。笑顔で答え、歓迎してくれた。竹下は普段通りのリハビリテーションを行った。リハビリテーションの内容を蒲田に説明を加える訳でもなく、淡々と竹下は岸谷さんにリハビリテーションを行っていった。最初は体調や今までの様子を聞き、軽く座りながらの体操をした。少し体が温まってきたところで、今度は足の力を付けるために立ったり座ったりする動作を繰り返し行った。岸谷さんも普段あまり歩いていないせいか、最初はグラグラしていた。しかし、回数を重ねるにつれて動作が安定してきた。それでも安定したところで疲労が増えてしまい、休憩をとりながら行っていた。
そして、竹下は歩く練習をし始めた。普段あまり歩いていないという事を聞いていたので、蒲田は驚いた。本当に歩けるか心配だったが、竹下は岸谷さんの前に迎え合わせで立ち、両肘を持ちながら手を引くように歩いていった。やはり、普段していないせいか僅か1m程度で膝がガクガクし始めてしまったので、そこで歩く練習は終了した。
全体的なプログラムもそれで終了となり、本日の岸谷さんの訪問リハビリテーションは終了した。
終わった後少しはなれた場所に移動した。そして、竹下は蒲田に話し始めた。
「今の訪問リハビリテーションの利用目的は、現状維持だ。岡崎が主張している内容からすると、この人は麻薬付けになっている対象の人だと思う。ただ、意識ははっきりしているから、自分の事は自分で決められる能力は十分にある。
本人は毎日座っていながらテレビを見ている。意識ははっきりしているからニュースもよく見ていて、今の情勢もしっかりわかっている。だから、リハビリテーションが麻薬だと言うことも岸谷さんはわかっている。このニュースを聞いて、岸谷さんは相当苦しんだ。どうしていいのかわからなくなり、俺に何度も相談の電話をくれた一人だ。
岸谷さんは、この訪問リハビリテーションの時間が唯一歩く事をしている。普段の生活では出来ない、歩くという動作をしている。この時間を無くしたら、その歩く動作が出来なくなる。そうすると、普段歩く事が出来ない岸谷さんは、訪問リハビリテーションを辞めたら、完全に歩けなくなるのが目に見えている。だからリハビリテーションは続けていきたいと本人は考え、ずっと俺もそれに応えてきた。
しかし、あのニュースが流れてから、リハビリテーションを利用することで、世間からは白い目で見られるようになったり、親戚からは利用するなという電話も入ったそうだ。
この人は今でも、とても苦しんでいる。麻薬漬けになる自分を選ぶのか、歩けなくなる自分を選ぶのか。
蒲田・・・。どうして、岸谷さんはこんな選択をしなければいけないんだ?どうしてこんな決断を迫られなくちゃいけないんだ。もちろん誰かが歩かしてくれるなら、頼みたいさ。でも誰も頼めない。こんなにバランスが不安定な人を、他の人が歩かせるのはとても危険だ。
リハビリテーションの時間で歩き、身体機能を維持していく。これは、本当にそんなに悪いことなのか?」
竹下は心の苦悩を蒲田に打ち明けていた。今日はこの事を、蒲田に伝えたかった様だった。
(21)
蒲田は竹下が伝えたいことが十分に理解出来ていた。蒲田は最初考えていた、リハビリテーションが一生必要になるという『かかりつけ理学療法士制度』は、こうした人達の為に考えた制度だった。人間、体が徐々に弱っていくことは仕方がない。だから、専門分野である理学療法士がしっかりと関わることで、身体機能の低下を予防し、最期まで活動的に暮らしていける世の中にしていくことが、発端だったことを思い出していた。
それが、徐々に拡大解釈をし、高齢者という枠が大きく広がり、誰でも早めに受けた方がいいという考えになってしまっていた。
決してそれは間違いではないとも言えた。蒲田の研究ではその方がいいという結論を導ける資料を沢山出来たし、説得力のある内容だったからこそ、政府にも認めてもらえたのだと今でも思っていた。
しかし、それが本当によい世の中なのだろうか。最期まで理学療法士が関わらなければいけない人もいる。反対に、理学療法士が関わらなくても大丈夫な人たちもいる。その違いは何なのだろうか。
蒲田は研究室に戻り、自分が今まで研究してきた内容を振り返っていた。どれも、リハビリテーションを推奨している内容がほとんどだった。そして、自分自身でリハビリテーションを否定的に考えた研究はあまりなかったのだと改めて思い直していた。岡崎が言うように、リハビリテーションが麻薬という分類に含まれるのであれば、リハビリテーションという物を使い分ける一つの理由になるのではないかと考えていた。
以前の研究の内容を振り返る中で、最近調べた退院直後の再入院についての研究データが出てきた。前に厚生労働省に提出し、さらには新聞記者の渡辺と言う人にも見て貰った資料だった。蒲田にとってはだいぶ昔の研究内容のような気がしていた。この間に、蒲田にとっても考えが変わってきたのが、時の流を必要以上に感じてしまっていた。
蒲田はその再入院の比率が今現在ではどうなっているのだろうかと思い、現在のデータで分析を行い始めた。以前お願いしていたデータの提供先には毎月同じデータを送って欲しいことは伝えていたため、すぐに分析が出来るようになっていた。パソコンに向かい、計算式を当てはめて処理をした。結果は以前の研究よりも、再入院の比率が上昇傾向にあった。そして、在宅リハビリテーションの利用率も以前より悪化していた。
蒲田はやはり、退院直後の時期には在宅リハビリテーションが必要なのではないだろうか、と改めて感じた。
「これをどうやって納得して貰えればいいのだろうか。」
蒲田は悩んでいた。ちょうど、そのとき一本の電話が鳴った。轟からだった。
轟は渡辺が以前記事にした内容を見て、その後が気になっていた様だった。仕事の合間に考えてくれていたらしく、轟は自分の考えを蒲田に伝えた。
「以前のデータは退院直後の人達は再入院をしやすいから在宅リハビリテーションを受けた方がいい、というデータを示してくれた。しかし、これでは一般の人たちには説得力がない気がする。再入院の最大の理由は転倒だとすると、一般の人が高齢者が転倒するといけないという事は理解していても、高齢者が転倒して骨折をするというところまではあまり想像しないのではないだろうか。たとえ、想像出来たとしても、一般人は骨折をしたらまた骨がくっつくのだから特に問題ないと感じてしまうのではないだろうか。
俺達は、高齢者が骨折をしたら概ね予想が出来る。しかし、一般人が予想する内容とは異なると思う。そのギャップが埋められれば、今回の研究ももっと理解して貰えるんじゃないか?」
轟は蒲田を応援する言葉を添えて電話を切った。さっそく、轟の助言を基に、蒲田は再び考えた。
『高齢者の骨折に対して、自分達が予想する内容と、一般人が予想する内容が違う。』
いったい何が違うのだろうか。骨折というのは一般人だとどういう考えなのだろうか。蒲田は若いころ、骨折をした事があったので思い出していた。
(あの頃は、骨折をしても骨さえくっつけば元に戻ると考えていた。確かに元に戻った。今でも特に影響なく生活出来ている。
そうか。高齢者が骨折をすると元には戻らない可能性が高い。元に戻らないと言う事は元の生活に戻れないという事だ。つまり生活水準が著しく低下するという事につながる。
入院生活が長くなると、体も前の状態には完全に戻らない。つまり、退院直後は生活水準が低下している状態だ。しかし、多くの人は元の生活を過ごそうとする。つまり、生活水準を下げないで体を動かそうとする。そうすることによって、体に無茶が生じて転倒するんだ。これを防ぐために在宅リハビリテーションが必要なのであり、再び入院をすると、さらなる生活水準の悪化をもたらすから早期にリハビリテーションの利用を促した方がいいんだ。)
蒲田は頭の中でどんどん整理をし始めた。そして、パソコンに向かいデータの整理を行った。
蒲田は轟が助言してくれた事をきっかけに、データ収集に努めた。以前から関わりのある病院などに声をかけ、退院してすぐに再入院してしまった人達のデータをかき集めた。そして、それが転倒である理由に絞り込み、データの解析を進めた。その結果、リハビリテーションが麻薬であるという発表前と後ではおよそ十倍近く、元の生活に戻れない傾向、つまり、生活水準が低下したことがわかった。中には在宅生活さえ戻れない人も少なくはなく、蒲田にとっても驚きの結果となった。
蒲田はこのデータを厚生労働省ではなく、新聞記者の渡辺に見て貰えないかどうか電話で尋ねた。轟の提案もあったと付け加えると、一度見てみるとの返答を貰えた。
そして早急に渡辺にデータを送り、記事にしてもらえるよう頼んだ。今回の内容は渡辺も記事にしやすいと感触を掴んでいるようだった。そして、数日後、渡辺が書いた記事が発売になった。
発売当初はさほど大きくテレビでも取り上げることはなかったが、一般人にわかりやすい説明で書いてある事や、生活水準の低下というワードが注目され、すぐに噂が広まった。そして、徐々にその情報は拡散し、数週間後には大きな反響となっていた。そして、渡辺か書いた記事の発行部数も上昇したらしく、渡辺も上機嫌だった。
そして、この記事が広まる中で、内閣支持率が低下し始めていった。本当にリハビリテーションというものが麻薬なのだろうかという疑問が世間の中で急上昇し始めたのだった。
(22)
渡辺が記事を出した事をきっかけに、リハビリテーションが本当に麻薬と同等の効果なのか疑問に思う風潮が多くなっていた。リハビリテーションを辞めてから良いことがあまりないという声がここぞとばかり国民が声を出し始めたのだった。データ上では変化はないものの、受けてきた利用者側の意見や実感として声が聞こえるようになってきていた。麻薬という概念に疑問を持ち始めた波は抑えられないでいた。
テレビではリハビリテーションが本当に麻薬かどうか検証するような番組が増えた。どこの番組も麻薬と同等の効果を得たとは言えないという結論を出してはいたが、本当に麻薬ではないという断定までは出来ずに終わっていた。
マスコミは岡崎がいるソラリスタ研究所に取材をすることが多くなった。取材の理由は麻薬という結論は違うのではないかという質問を直接聞くためだった。岡崎はその取材に対して一切答えなかった。ノーコメントで突き通していた。
その場面を、テレビを通して見ていた竹下は、
「ざまぁみろ!答えられないんじゃぁ、やっぱりリハビリテーションは麻薬なんかじゃないんじゃねぇか!ふざけんなバカヤロ!」
と、テレビに向かって叫んでいた。しかし、蒲田は岡崎が何か隠しているのではないかと考えていた。単純に引き下がるような岡崎ではない、と蒲田は思っていた。
テレビ番組ではリハビリテーション業界に追い風が流れるかのようにリハビリテーションはやはり効果のあるものだと報道する番組が増えた。竹下の事業所も徐々に利用人数が増え、経営が以前よりも改善傾向になってきた。竹下は安堵の表情を見せることが多くなった。そして、リハビリテーションが麻薬という風潮は途絶えたかのように、再びリハビリテーション大国として利用者数は増加していった。
しばらくすると蒲田の手元に再び岡崎からの招待状が届いた。
「ソラリスタの最近の研究内容についての報告」
と題してあった。最近静かになっていた岡崎だったが、蒲田の予想通り、岡崎が動き出したようだった。
この招待状は以前貰った形式と同じであった。岡崎が今まで静かにしていたこと、ノーコメントで通していた理由は、この招待状の中にあるのではないかと思った。蒲田はその中に入っている返信用はがきを探した。参加か不参加かについて印を付ける場所があった。蒲田は参加に印を付け、すぐにポストに入れた。
ソラリスタの報告会当日。蒲田は少し早めに家を出て会場に向かった。今回の会場も以前と同様の場所だった。全く同様の形式で行われていた。スケジュールも同様だった。会場内には報道関係の人たちが以前よりも多くいた。リハビリテーションが麻薬という考え方が沈静化する中でも、ソラリスタの発言に注目する人たちが、未だに多いことがわかった。リハビリテーションが注目されているのだろうか。それとも、ソラリスタの岡崎に興味があるのだろうか。どちらにせよ、今回の岡崎の発表内容は着目する価値があるという事には間違いなかった。
会場内全ての人たちは岡崎の発表を待っていた。そして、スケジュールの後半に岡崎は登場した。登場した瞬間、会場内はどよめきが起こった。そんな中でも岡崎は平然としてマイクを手にした。そして、岡崎は話し出した。
「皆様。本日はお忙しい中お集まりいただき、まことにありがとうございます。リハビリテーションが麻薬ではないという風潮が現在巻き起こっているようですが、私たちの研究では依然としてそのような結論には至っていません。リハビリテーションは麻薬です。間違いありません。」
会場にひときわ強いざわめきが起こる中、岡崎は話を続けた。
「私たちは研究を進めてまいりました。そして、新たな事実が分かったのです。リハビリテーションが麻薬の効果となる場合は、とても限定されていたことがわかりました。その内容はこうです。」
岡崎は一枚の色紙を取り出し、その場で筆をとって書き始めた。そして書いた内容を会場に発表した。書いた文字は、『触れるな。危険!』という文字だった。
会場はこの文字を不思議そうに見ては首を傾げている人が多かった。岡崎は説明を加え始めた。
「『触れるな。危険!』これはリハビリテーション関係の医療従事者が人に触れたときにのみ発せられる、ある脳内物質が危険であるので、医療従事者に触れない方がいいですよ、という意味です。そして、その脳内物質とは、皆さまご存じのとおり麻薬と同じ効果のものです。」
会場からは、その言葉に対し、疑うような声が多かった。その言葉を無視しながら岡崎は説明を加えた。
「脳内物質を計測するために、私達は苦労しました。この脳内物質を計測する機械は当研究所にしか現在ありません。よって、当研究所でしか計測出来ないため、今までテレビ番組で検証しても結果が出なかったのです。」
会場の視線は岡崎一点に向けられていた。そして、最初は疑いを持って聞いていた人たちが、徐々にうなずき始め、理解を得るように聞き入れ始めていた。
「この結果から分かることは、リハビリテーションが悪いわけではありません。リハビリテーションに関係する医療従事者の手が悪いことになります。皆様は医療従事者の手に触れられるという事を、極力避けなければなりません。よって、リハビリテーションというものは、自分の力で機能を維持していくことが望ましいと考えられます。
この間、リハビリテーションを中断してきた人たちは、身体機能が低下したと感じられる方が多かった。しかし、それはつまり、リハビリテーション関係の医療従事者による麻薬の効果が切れてきた事により、本来の自分を取り戻した事になります。そして、そこから医療従事者に触れられないようにして、リハビリテーションを実施していけばよいのです。
まとめますと、リハビリテーション関係の医療従事者の手こそが麻薬であり、それに触れられる事により、麻薬の中毒症状が出現し、自分は良くなっていると錯覚するのです。
皆様。この研究内容を参考にしていただき、今一度お考えになり、日々よりよい生活にしていけるよう努めていただけたらと思います。」
岡崎の報告は終わった。会場にいる人たちから岡崎に対して質問が飛び交った。岡崎はその質問に対し、全てわかりやすく丁寧に答えていた。その様子をみる限り、やはり今後の流れが再び岡崎の主張した内容へと転換するような気がした。
岡崎が主張した、リハビリテーション関係の医療従事者とは、理学療法士がほとんどであるため、理学療法士に触れる事が危険という事になる意味だった。
蒲田は自分の両手を見た。
「この手が・・・・麻薬・・・・」
蒲田は頭が混乱したまま会場を後にした。
岡崎の発表後、理学療法士の仕事は激減した。竹下の事業所も影響を受けた。竹下は怒り狂い、あれる毎日に変わっていた。岡崎の発表により、竹下が運営する事業所は最大の危機にさらされていた。
蒲田は考えていた。
(このままでは理学療法士という仕事が危ない。理学療法士が生き延びるには、何か対策を考えなければいけない。)
しかし、何からすればいいのかわからなかった。また、自分の両手を見て呆然としていた。
(23)
蒲田は少し考え方を変えてみようと思い始めた。今まで、理学療法士は触れながらリハビリテーションを行うという事が前提だったが、触れないで行うリハビリテーションとは何だろうかと考えた。しかし、それを考えていくと、リハビリテーションという言葉は広い意味をしている事を思い出していた。
リハビリテーションとは医療機関や在宅で行う、『医学的リハビリテーション』の他に、職業訓練校等で就労を目指すための『職業的リハビリテーション』、養護学校等で教育を受ける『教育的リハビリテーション』など三ざまに捉えられていた。そして、蒲田が注目をしたのが『社会的リハビリテーション』というものだった。
蒲田は古い書物を掘り出してきて、社会的リハビリテーションの意味を調べた。その書物には次のように書いてあった。
(『社会的リハビリテーション』とは、本人の身体的状況だけでなく、物理的、制度的、心理的状況を解消して行くことにより社会復帰や社会参加を目指すものである。)
蒲田は、この社会的リハビリテーションの意味を調べようと思い、研究所を後にした。
蒲田は自分が住んでいる福生市役所に出かけた。まずは自分が住んでいる街を知ろうと思っていた。そして、市役所には自治体で取り組んでいる高齢者対策があると以前聞いた覚えがあることを思い出したからだ。市役所には市民向けにいくつもの無料講座が沢山開かれていた。何年も前からあることは知っていたが、蒲田が予想しているよりも遙かに充実した内容の講座が沢山あった。
数年前は自治体独自で取り組んでいることが多く、自治体の単体で終わることがほとんどだったが、今はまるで運動会のように全国大会といって自治体の枠を越えた催し物が年に数回開催されていた。そして、そのプランは大手の旅行会社が作成しているという内容のものだった。
恐らく、リハビリテーションで頼っていた人達がこっちの自治体に流れたことによって旅行会社も集客が見込めると判断し、バックについて大きな企画を持ち出したのだろうか。たとえ、多くの利益に繋がらなかったとしても、企業イメージは向上し、別の分野での顧客収集に大きく役立つと考えられるのではないだろうか。きっと、理学療法士の仕事が激減している中で、仕事を増やしている分野もあるのだと思い、少し視野が広くなった気がしていた。
しかし、こうした企画はある程度動ける人達向けに計画していることが多く、重度の障害がある人に対してはあまり積極的に行われていない事が多いのではないかと蒲田は予想していた。そうした人達はどうしても外に出られず、理学療法士など、医療従事者に頼らざるを得ないのが現状だろうと考えていた。そういう所ではまだ仕事があるのではないかと思っていた。
すると、蒲田の脇を、電動車いすを利用している高齢者が、その旅行会社が企画した運動会に参加しようと市役所の人と話をし始めた。蒲田はその光景に驚き、近くまで寄ってその会話に耳を傾けた。内容はやはり、その高齢者は参加したい意向を示していた。さすがにこれは無理だろうと思っていたが、市役所の人は困ることなく、参加の受付をし始めた。そして、あっという間に手続きが終了したのだった。
電動車いすを利用している高齢者が終わると、蒲田はその受付をした市役所の人に、今みたいな人でも参加できるのかと聞いた。すると、参加条件は特になく、飛行機の席も様々な対応が出来たり、旅行先の宿も介護用ベッドの用意をしていたり、問題なく受け入れられるような状況を作り出せているという事だった。行き先が増えることで高齢者は活動的になり、自然とリハビリテーションが行われているのだと思った。これが社会的リハビリテーションであると感じた。ますます、理学療法士の仕事は減っていくと思った。
(24)
蒲田はさらにスポーツ用品店に足を運んだ。リハビリテーションは運動することに関して深い関係があるため、この分野も調べることにした。お店にはあらゆるスポーツの道具が並んでいた。その中で、高齢者向けのコーナーが大きく扱われていた。高齢者向けという中身とは、さほど難しくない優しい運動が主で、たとえ倒れても怪我をしにくいような物が多かった。例えば、高齢者向けバランスボール「バランスフリー」という商品が置いてあった。普通のバランスボールであれば上に乗って練習をするのだが、バランスを崩すと大きく倒れ、転倒して怪我をする危険性があった。その欠点を「バランスフリー」という商品は上手に補っていた。まずバランスボールという球体から正方形と球体の間のような物で、一面を下にすると不安定なのだが、その「バランスフリー」は転がらず、転倒しないという物だった。つまり、転倒も予防できて、バランス能力も向上できるという商品が売れていた。そして、運動グッズもユニバーサルなデザインというカテゴリーで考えるような商品が次々に発売されていた。
「バランスフリー」を手にして購入していた高齢者は独り言のように「最近のリハビリテーションは先生達に触られると自分の寿命を縮める事になるからなぁ。自分でやらなあかんのだよなぁ。でも自分でやる方が時間も自由に使えていいわい。グッズも増えていることだし、これでもやろうかのぉ。」と言っていた。理学療法士に頼らず、自分の体を自分で心配して購入するという人が多い印象だった。
蒲田はさらに街を歩くと「リハビリテーション型デイサービス」という看板を目にする事が多い事に気付いた。蒲田もそういった施設がある事は知っていたが、ここまで目につくように多くなっている事には気付かなかった。
リハビリテーション型デイサービスとは、介護保険で利用できる施設の一つで、通いながら運動が行える「通所介護」というサービスで、前からずっと高い人気を誇っていた。しかし、そこには理学療法士がほぼ居ないため、より専門性を求める人にとってはあまり利用しない傾向があるように思っていた。それが今では需要が伸びているようだった。
蒲田は知り合いの柔道整復師である恩田正と接触を図った。恩田はこのリハビリテーション型デイサービスを運営している経営者だった。恩田から最近の動向を聞きた。恩田が言うには、リハビリテーションが麻薬だという発表が合ってから、訪問リハビリテーション同様、急激に利用者数が激減したようだった。しかし、医療従事者が触れなければ大丈夫という発表があってから、急激に利用者数が増加したというのだった。確かに、理学療法士などのリハビリテーションスタッフはほとんど居ないため、そのような傾向になったのだろうと言っていた。
しかし、柔道整復師という医療従事者がいるため、それだけが理由ではないと思っていた。その点についても恩田は話してくれた。
元々、柔道整復師は資金力のある人が多い傾向にあった。接骨院を開業し、莫大な利益を得ていた。よって資金力を活かしてトレーニングマシーンを整備し、医療従事者が触れなくてもリハビリテーションを可能にする環境を整えたのだった。そしてそれを上手く宣伝し、利用者の理解を得られ、ここまで発展したとのことだった。
そうした結果、成功する業者が増え、さらに店舗を増やしている業者が多いと話してくれた。利用者数が急激に戻ってきた要因は、やはりこのリハビリテーション型デイサービスのプログラム内容だった。医療従事者が触れなくてもリハビリテーションが出来るという流れが成功の鍵になっていた。
恩田はその流れと平行して、職を無くした理学療法士が再就職先に、このリハビリテーション型デイサービスを選ぶ傾向が増えていることも教えてくれた。恩田の事業所にも理学療法士が居た。蒲田が不思議に思っていると、ちゃんと理由も教えてくれた。
理由としては、トレーニングマシーンを利用者一人一人に選定するときに、やはり理学療法士の力が必要になると感じた様だった。病気によって利用者の身体状況は様々で、何が一番いいトレーニングマシーンなのかわからないが理学療法士は根拠のある説明で対応が可能だから雇用価値が高いと判断している、との事だった。
柔道整復師は基本的な運動は出来るが、部位ごとに適切な運動の処方までは考えられなかったそうだ。以前は、適当に運動をすると次の日に痛みが出てしまう事もあり、それが良いものなのか、悪いものなのか判別がつかず、当たり障りのない運動ばかりさせてしまっていたそうだった。そうする事により、質の高いサービスを提供できない歯がゆさが恩田にはあったそうだった。そうした歯がゆい思いを解消してくれるのが理学療法士であり、とても頼りにしていると話してくれた。
理学療法士の仕事も利用者に触れることは無く、リハビリテーションの機械の選定を行い、利用者に行ってもらうというスタイルが定着していた。それにより、利用者も安心して運動が行え、需要が高くなったと考えられた。
蒲田はここでは理学療法士が必要とされているという事に安心感を覚えた。
(25)
蒲田は竹下に久々に居酒屋「目黒」で会うことが出来た。竹下に今まで収穫をした情報を伝えようと思い、蒲田が竹下を誘ったのだった。しかし、竹下はとてもやつれていて、余裕のない表情をしていた。蒲田が、心配すると竹下は気分転換になるから助かると言って、それ以上は言わなかった。蒲田もそれ以上は深く探らないようにしていた。
会話の流れで蒲田は先日情報を得たリハビリテーション型デイサービスの話をした。理学療法士も仕事が増えてきていることに喜びを感じながら蒲田は話していたが、聞いていた竹下は怒りを露わにし始めた。そして竹下は猛反発をし始めたのだった。
竹下の言い分では、手を加えてこそ、本当のリハビリテーションだと主張をしていた。しっかりとストレッチしないと拘縮が悪化してしまい、機械では修正できない運動も絶対にあると話していた。そして、トレーニングマシーンは力がつくが、動作は力だけでは獲得できないと話し出したのだった。特にたとえ話をし始めたのが感覚障害だった。
竹下が言うには感覚が悪ければ筋力があっても使い方がわからず、バランスを崩す事が多いとのことだった。今流行っているバランス練習の「バランスフリー」でも、練習内容によってはうまくいかない人もいるらしく、感覚を向上させるにはフィードバックを上手に働かせないとうまく上達しないと話していた。そして、何よりも、このフィードバック機構は口頭だけではうまくいかない事が多く、鏡を見ながら行う事はもちろんの事、体で触れて体の位置を教えて上げてやっと覚えてもらう事が多いそうだ。感覚障害の人は、そうした事をしなければならないのに、触れるというリハビリテーションがそこまでして否定されることに、竹下は強い反対を述べていた。
そうは言っても、竹下の事業所に寄せられる仕事量は激減し、閉鎖に追いやられることになった。竹下は言っていた。リハビリテーションにとって大切なことは体の機能を良くし、自分で出来ることを増やして上げることだ。触れなくても良くなる人も沢山いるが、触れなければ良くならない人も沢山いる。そうした人たちに、何故私たちは仕事をさせてくれないのだろうか・・・。
竹下はとても悔しそうだった。蒲田は竹下の思いも理解できた。自分もきっと、現場で働いていたらそうした答えを持っていただろうと考えていた。蒲田は自分自身、どうしたらいいのかわからなくなっていた。リハビリテーションの将来像に対して、様々な答えが自分の頭の中に転がり込んでくるようだった。その苦しい答えを自分も出さなければならないのだろうかと、考え込んでしまっていた。
(26)
竹下は医療従事者が麻薬と発表されて以降、利用者が激減し、従業員に給料が払えなくなり、事業所を閉じてしまった。仕事もなく自宅で引きこもるような生活を続けていた。昼間から酒に酔いつぶれ、見るも無惨な姿に変わり果てていた。もうすぐ家賃も払えなくなるほど、資金も低下していた。蒲田は竹下に何か力を貸せないか考えていた。
蒲田は以前、仕事が増えてきていると知ったリハビリテーション型デイサービスの話を持ち出してみた。しかし、そのトレーニングマシーンを使用しなければならないという環境が竹下にとってどうしても絶えきれない環境らしかった。
「そんな仕事をするくらいなら、理学療法士を辞めてやる!」
そんなことまで竹下の口からは飛び出していた。蒲田は考えていた。竹下はきっと、理学療法士の仕事をする上で、自分の手で利用者に触って行うということが頭から離れないのではないだろうか。直接、利用者に触れることで、利用者の筋肉の収縮を肌で感じて、そしてその反応を見てプログラムを組み立てる。そういう対応をずっとしてきている竹下にとって、利用者とのコミュニケーションの一つでもあり、信頼関係を気づき上げる一つの方法でもあるような聞がしていた。
そう考えれば、竹下は利用者とのコミュニケーション手段が奪われてしまうという怖さがあるのもわかるような気がしていた。機械だけでは得られない情報が、竹下の中ではたくさんある。機械に頼る仕事をするのであれば、理学療法士ではないという理屈も、蒲田には理解できるような気がしていた。
蒲田は必死に考えていた。それでも竹下には理学療法士として働いて欲しかった。蒲田は竹下をとても信頼していた。臨床に置いて、竹下から得られる刺激が蒲田には常にあった。筋肉を個別単位で調べ上げ、ミクロな世界で利用者の動作を分析し、そしてその予後まで考える姿は、蒲田にとっては憧れでもあった。
蒲田は何か力になれることはないだろうかと必死に考えていた。しかし、何も思いつかず、時間だけが過ぎていった。蒲田は自分の研究室でパソコンを睨みつけていると、一本の電話が入った。轟だった。
轟は蒲田と竹下の最近の動向が気になっているようだった。厚生労働省でもデータ上では傾向がつかめているようで、訪問リハビリテーションの事業所が減っていることは知っているようだった。なので、轟の心配事は蒲田ではなく、竹下の方だった。そして、事業所を閉鎖したことを轟に伝えると、轟は残念な気持ちと予想したとおりという気持ちを混ぜた声で答えていた。
轟は蒲田に一つ提案をしてきた。蒲田にというよりも、竹下に提案したいような内容だった。竹下に直接話し憎かったらしく、蒲田に電話をしてきたようだった。
内容というのは、通所介護というカテゴリーにおいてリハビリテーション型デイサービスというものがあるが、訪問介護でリハビリテーション型ヘルパーというものが無いのでそうした事は出来ないのか、というような内容だった。
蒲田は思い出していた。確かに、通所介護が人気を高めているが、訪問介護ではそうしたリハビリテーションの内容を組んだサービスはなかった。もし、それが可能になれば、訪問介護を利用している利用者数は介護保険の中で一番二番を争っているので、それだけ市場があると言う事になる。通所介護のように訪問介護でもリハビリテーションの要素を取り入れ、理学療法士の仕事を得られないか考え始めていた。
(27)
蒲田は訪問介護の内容を調べていた。訪問介護は通常、業務内容はヘルパー自身が掃除をしたり食事の支度をしたりする”生活援助”と、ベッドから車いすへの移乗の手伝いや買い物同行など利用者と関わりながら業務を行う”身体介護”の二種類があった。その中で蒲田は身体介護に着目をした。
”身体介護”というのは考え方によっては利用者の体を動かすというくくりでは同じ用な気がしたからだ。例えば、ベッドから車いすへの移乗の手伝いをする場合、利用者本人の力を利用して行うことが基本になっている。これをうまく利用して、リハビリテーションを兼ねた移乗方法が出来ればいいのではないか。具体的には移乗方法を利用者個別に訪問介護のスタッフに指導を行い、回数のコントロール、スピードのコントロールなど細かい内容を伝え、介助を行う中で筋力をつけていくという内容ではどうだろうか。このような仕組みが実現出来れば、理学療法士の仕事はまだまだあるのではないだろうか。
そして、竹下が考えている機械でするリハビリテーションとは異なるため、まだ受け入れやすいのではないだろうか。
そう考えた蒲田はこの案を竹下に提案する事にした。
竹下は蒲田の案を聞いた。やはり、竹下は受け入れがたい内容だと拒否した。やはり、ずっと竹下は利用者に触れながら肌で感じながら行ってきたスタイルを崩す事になるため、苦悩しているのだろうか。そして、何よりも、リハビリテーションのプログラムの内容をヘルパーに任せるという事が、竹下の中で考えに悔い内容だったかも知れなかった。
竹下は蒲田の話を聞いた後、しばらくの間うつむいていた。そして、
「2、3日考えさせてほしい。」
と竹下は言った。竹下は少し考えてみるような事を言い出したのだった。蒲田は少し意外だった。そして蒲田は待つ事にした。
そしてその数日後、その方法で仕事をしてみると、竹下は決心していた。
(28)
その後、竹下は以前から交流のあった複数の訪問介護事業所に接触をし、蒲田が話したことを訪問介護の事業所に提案していた。そして自分を売り込むという営業活動を積極的に行った。その結果、非常勤ではあるが週に2回雇ってくれる事業所が複数箇所見つかり、竹下は収入こそ低くなったものの、生活出来るくらいの収入は確保できるようになった。
そして、何よりも大きな成果はヘルパーの介助方法の指導により、筋力が向上しただけでなく、バランス能力も向上し、その事業所で問題となっていた利用者の転倒率が減少したのだった。転倒率が減少した結果、入院する人が減り、事業所の収入が安定した。そして何よりもヘルパーの介助時の事故も減り、さらにはヘルパーの慢性的な腰痛も軽減され、ヘルパーの業務改善に繋がったのだった。
竹下はこの方向で事業展開出来ると考え、再び自分の事業所を立ち上げた。「まつば訪問介護支援センター」として理学療法士を登録制で雇い、訪問介護事業所から要望があった場合に理学療法士を派遣するというシステムにした。そうすることにより、理学療法士の需要を掘り出すことに成功し、雇用を増やすことに成功したのだった。
蒲田もこの成功例を研究材料としてまとめ、厚生労働省に提出した。厚生労働省も今回の例を全国に広めていきたいと考えているらしく、まつば訪問介護支援センターをモデルケースとして扱った。テレビの取材も多く依頼があり、竹下の事務所は形を変えたものの、再び息を吹き返したのだった。
蒲田は竹下といつもの居酒屋「目黒」で飲んでいた。竹下が再び復活をしたことに対して蒲田は喜んでいた。竹下も落ち着いたことに安堵感を覚えていた。最近は理学療法士もヘルパーとして活動することが増えていると話していた。竹下が言うには、理学療法士が理学療法士として活動するから麻薬と捕らえられ、なにも出来ない事に気づいたらしく、ヘルパーとして活動すれば何も疑われず、しかも必要な場所には手を加えてリハビリテーションが出来ると言っていた。法律上では訪問介護が行う運動は、見守りで可能という事になっているが、竹下は運動というカテゴリーには入れず、例えば移乗という介助であれば、移乗するための準備としてとらえ、必要なリハビリテーションを行っていると話していた。
「何事にも準備体操は必要だろう。移乗に介助を必要とする利用者は、移乗そのものが高度な運動ととらえられる。俺たちでも高度な運動には準備体操をするだろう?それと同じで、彼らも準備体操が必要なんだ。自分でストレッチしたり、自分で少し足に力を入れる運動をしたりして、体調の確認も含めて行い、普段通りの方法で介助して良いのか見極めて行うんだ。こうしたことを当たり前に行うことによって、介助の事故も減ったし、安全に移乗が出来るようになった。筋力も付いたし、バランス能力も付いて転倒率も減ったという事だ。」
つづけて竹下は話し続けた。
「実は俺も介護職員初任者研修という資格を取ったんだ。そうすることにより、俺はヘルパーとして働くことも可能になった。そうする中で、理学療法士の時に行っていたストレッチや筋力トレーニングを準備体操というカテゴリーで出来る事に気が付いたんだ。運動などは、訪問リハビリテーションのときしか出来ないと思っていたが、場面にこだわらなければ可能になることに気づくことが出来た。そして、動きの中で関節可動域を確保していくという考えも出来るようになった。職種を越えて考えることによって、俺もいろんな考えが出来るようになったんだ。これは蒲田が言い出してくれなかったら出来なかった。本当に感謝している。」
竹下は深々とお礼を言った。蒲田はお礼なんてと言おうとしたが、竹下の気持ちをそのまま受け取った。
竹下はふと岡崎の事を話し出した。
「なぁ、蒲田。岡崎のような奴が現れなければ、今頃には俺たちが追い続けてきたかかりつけ理学療法士制度っていうのは出来ているんだろうなぁ。俺が臨床で示し、お前が研究としてデータ分析をして国に訴える。そうして積み上げてきたものが、あいつのせいで急にガラッと変わっちまった。おかげで俺は訪問リハビリテーションという事業所をたたむことになった。でも、何とか持ち直して、別の仕事を得られてまた、生活が出来るようになった。お前の知恵がなければ、今頃路頭に迷うところだったよ。」
そう蒲田に感謝の気持ちを伝えると、表情を少し険しく変えて話し出した。
「それだからといって、岡崎を全て恨むことが俺は最近は出来ないんだ。」
竹下は酒を一口のんで再び話し出そうとした。しかし、何か話し出そうとしたとき、テレビから「ソラリスタ所長、岡崎逮捕」というニュースが速報で飛び込んできた。2人はテレビから視線が離れられなくなっていた。
第四章 犠牲(29)
蒲田はソラリスタ研究所に足を運んでいた。研究所はマスコミで囲まれていた。岡崎はすでに逮捕されているため、その研究所には居なかった。残った従業員が押し寄せるマスコミの対応しているようだったが、何も知らないという一点張りで、ソラリスタの従業員はマスコミに対応していた。マスコミもそれでは引き下がれないらしく、しつこく質問を繰り返しているが、結局は何も真実が見えない状況には変わりなかった。そうした風景を遠くから眺められる程度の距離に蒲田はいた。そしてその動向を探るべく、蒲田はしばらくその場で様子を見ていた。
岡崎が何故逮捕になったのか。テレビの報道では、不正に収入を得た詐欺容疑での逮捕という内容だった。何故、岡崎が詐欺行為を行ったのか。マスコミもまだその情報が得られておらず、内容は曖昧な状況の中で放送されていた。
岡崎が研究を行い、発表した「リハビリテーションは麻薬である」という内容は不正なデータにより結果を捏造して導き出されたものである、という所まではマスコミも掴んでいるようだった。ただし、そこから詐欺行為までが結びつかず、情報を得ようとマスコミが研究所まで足を運んでいるようだった。つまり、不正なデータは岡崎自身で修正したものかどうか、そして、それにより何で収入を得ていたのかが注目されていた。
立川の新聞記者である渡辺もそのソラリスタ研究所まで足を運んでいた。蒲田は渡辺から渡辺が知っているテレビ以外の情報を貰えた。
岡崎は自らデータを改ざんした訳ではなさそうだった。恐らく提供先のデータが元々不正に改ざんされているらしく、岡崎はそのデータを使用して発表したため、発表内容は偽りであるということになっているらしかった。それだけでは岡崎は詐欺にはならないのではないか。不正に改ざんされたデータと解らずに使用したのであれば、岡崎も被害者に当たるのではないか。そう蒲田は渡辺に言ったが、どうもそう簡単な事件ではないようだった。
岡崎はそのデータを提供してくれた取引先と密接な関係にあったようだった。提供先は高齢者向けフィットネスクラブの最大手であるフィーブルグループのようで、そのフィーブルグループはお金を岡崎に渡していたのではないかという疑惑があるようだった。
本当に岡崎はそのような行為をしたのだろうか。蒲田は疑問に思っていた。確かに、岡崎はリハビリテーションというものをよく思っていなかった。そして、リハビリテーションは麻薬の一種であるという研究結果を出して厚生労働省に提出し、国民に訴えた。内容はともかく、自分が研究した内容を国に提出したり、周りに訴えたりすることは研究者であれば誰でもすることで、岡崎が今までの行動には多少理解が出来た。
そして何より、お金を貰うという行為は、研究の資金提供としてよくあることだった。岡崎が改ざんされていたデータを使用していたことを知っていたのであれば贈収賄として考えても良さそうだが、知らなかった場合でも、それを贈収賄として捕らえられてしまうというのであれば、蒲田自身も危険にさらされるかもしれない。知っていた、知らなかったという争点は、たとえ岡崎が知らなかったという結論になったとしても、周りの目からすれば完全に拭えることはなく、岡崎は研究者として奈落の底に落ちたことには変わりなかった。
岡崎は本当に改ざんをしたデータであったことを知っていたのだろうか。蒲田はその事については岡崎を疑いたくなかった。蒲田もまた、岡崎を研究者の一人として認めていたのだった。
数時間後、フィーブルグループの社長である中里も逮捕され、少しずつ事件の真相が明るみになってきた。そして、蒲田の願いとは反対に、岡崎は改ざんしたデータを利用した事を認めたのだった。
渡辺は別のルートでこの事件の詳細な内容を手に入れたらしく、蒲田に教えてくれた。中里社長は高齢者フィットネス産業を向上させ収益の増大を図ろうとしていた。高齢者フィットネス業界は介護保険適応外の人が主に利用する形が多かった。しかし、中里社長は介護保険分野にも参入し収益増大を考えていたそうだった。しかし、介護保険内で事業を行うと、収入は厚生労働省で決められ額しか得られなかったり、様々な規制によってやりたい事が出来なかったりで、あまり儲からないという事情があって介護保険事業には参入を断念したらしかった。しかし、介護保険利用者は年々増加傾向であることに魅力を感じていた中里は、介護保険制度を崩壊させ、介護保険を利用しにくくさせれば、高齢者フィットネス事業に利用者が流れてくるのではないかと考えたのだった。そうすることにより、自分たちの収益を増やそうと考えたのだった。
介護保険分野のリハビリテーションを崩壊させるためには何か良い方法はないかと考えている時に、リハビリテーションを快く思っていない研究者である岡崎と出会い、意気投合をしたらしい。そして、リハビリテーション崩壊という目的で岡崎と中里は手を組み、中里はデータを提供し岡崎はそれについて発表をした。しかし、思うようにデータを収集できなかった中里はデータを不正に操り、岡崎に渡した。そして岡崎はそのデータを利用して発表をしたというのが大まかな流れだった。
もし、これが本当ならば、岡崎はあえて知らなかったと言い張れば、知らないままで罪を免れられるのではないか、と蒲田は渡辺に聞いたが、渡辺によると岡崎はデータの改ざんした事実を変わらず認めているという事だった。
同じ研究者として、データ元の改ざんを見破るのは難しいことは蒲田自信わかっていた。岡崎が何故、自分から罪を認めるような発言をしているのかが理解できずにいた。
(30)
岡崎逮捕によりリハビリテーションは麻薬ではないという事が解り、数ヶ月がたった。再びリハビリテーションを利用する人たちは増えたが、以前のように介護保険を利用してリハビリテーションを頑張る人は少なくなった。おそらく、リハビリテーションというものを利用しなくても、自分の力で生きていけるという自信がついた人たちが増えたのではないかと、蒲田は思っていた。竹下も同じ事を話していた。
「なぁ、蒲田。俺たちは以前、「かかりつけ理学療法士制度」というのを考えていたよな。あれは決して悪いことではないと俺は今でも思っている。ただ、その制度が出来ることによって、それに甘えてしまう人たちも出てきてしまうこともあるような気がするんだ。ただ、今は違う。今の日本人の意識は自分で頑張ろうという気持ちが生まれている。今の状態はリハビリテーションを本当に必要な人たちが受けて生活をしているような気がするんだ。
俺は今、ヘルパーとして働いている。自立を促しながら少しずつ進めているけど、色々と形が見えてきた気がする。自立を促すと言うことは、ヘルパーの援助を少なくするという意味が込められている。ただ、ヘルパーをすると、大変だから手伝って上げたいという気持ちが生まれてくるもんなんだよ。そして、何よりも、手伝うことでヘルパーとして仕事は継続して行くし、自分の収入も安定する。利用者も喜ぶし、何も悪いことがないと思ってしまうものなんだよ。
でも、それではいけないんだ。そのヘルパーと利用者の関係は世の中にとっては悪循環なんだよ。永遠に自立を促せないという意味でね。
俺がリハビリテーション型ヘルパーという形で仕事をする事によって、最初は利用者の転倒率が低下して入院が少なくなり収入が安定したけれど、長い期間していると、今度は反対に良くなりすぎてヘルパーの仕事が減ってきたんだ。仕事仲間からはあまり良くないと思っているスタッフも居たけど、反対にそれが評判となって新規の依頼が多くなって好循環を生むようになった。
まだまだ、この好循環が決して収益を増大させているというところまでは行かないけど、きっとこれが本来のリハビリテーションという意味なんだと思う。
最近は、また訪問リハビリテーションの事業所を復活させて欲しいという声ももらえるようになってきた。もう一度、事業所を立ち上げて、頑張ってみようと思う。」
そして、竹下はその後、まつば訪問リハビリステーションを再び立て直した。まつば訪問介護支援センターも平行して行い、以前よりもさらに大きな組織となって地元に貢献する起業に変わった。竹下はきっと、地元の有志として名高い人間に変わっていくのだろうと蒲田は思った。
(31)
蒲田はテレビを付けると「将来の日本」という特番が放送されていた。その一つのコーナーに社会保障費について取り上げられていた。そして、そのコーナーのゲストとして轟が出演していた。轟も偉くなったものだと蒲田は同級生を誇りに思いながらテレビを見ていた。
轟の解説の中にはリハビリテーション麻薬事件を取り上げ、事件が解決した後でもリハビリテーション利用者が麻薬発表前よりも増えていないことにより、継続して社会保障費が抑制されている傾向にあることが話されていた。あの事件はよくない出来事ではあったが、それをきっかけにして社会が好循環に向かいつつあるという内容を話していた。
このテレビを見て、蒲田は少し違和感を覚えていた。轟がやたらとリハビリテーション麻薬事件を正当化するような発言が多いことが、蒲田にとって引っかかっていた。もし、蒲田が逆の立場だったら、あの事件のことはあまり触れたくないと思うに違いなかった。同級生が逮捕され、世間を騒がせた出来事を自ら掘り起こそうとは思わないだろうと考えていた。しかし、轟はその逆で、自ら掘り起こし、それを正当化するような話の流れに持って行っていた。
蒲田は一つの考えが浮かび上がった。あまり、考えたくないような内容だった。しかし、その考えを打ち消したくなった蒲田は轟と後日会う約束をした。
轟は蒲田の研究室まで足を運んでくれた。轟は初めて入る研究室を隅から隅まで眺めるようにしながら部屋に入ってきた。蒲田はコーヒーを入れて轟に差し出した。轟は迷わずそのコーヒーを飲んだ。そして、前に出演していたテレビの話題をした。その後に蒲田は轟に質問をした。
「轟。俺はあまり考えたくないことを思いついてしまったんだが、今日は轟に否定して欲しくて呼んだんだ。今から言うが、違うなら違うと言って欲しい。」
轟はコーヒーをさらに口に含んだ後に頷いた。蒲田はそれを見た後に話し出した。
「轟。お前は俺たちと会う前から、岡崎と面識が会ったんじゃないか?」
轟は動揺もせずに蒲田の話を聞いていた。蒲田は轟の表情が変わらないことを確認して、さらに話を続けた。
「もし、岡崎と前から面識があって、轟が岡崎に『リハビリテーションが麻薬の効果があることを証明して欲しい』というような内容を伝えていたとしたら、今回の事件の本当の黒幕は轟ということになるのではないかと思ってね。フィーブルグループの社長が今回の事件を引き起こしたような流れになっているが、もし、裏で轟が動いていたとしたら、事の発端は轟と言うことになるのではないかと。」
蒲田は轟の様子を見たが、変わらない表情だったため、話を続けた。
「でも俺も轟を信じていないわけじゃない。まさか轟がフィーブルグループの社長である中里と岡崎を会わせたとまでは思っていないさ。あれはたまたま見つかった取引先であると考えている。もし、その人脈まで手配してしまえば轟まで足が着くことになるからね。」
蒲田は轟を見ず、話を続けた。
「轟。やっぱり、お前は少なくとも、岡崎と少し前に会っているんじゃないのか。そして、リハビリテーションが麻薬であればいいのではないかという内容を岡崎に吹き込んだんじゃないのか。そして、お前はきっと、リハビリテーションが麻薬であるという様な出来事が、まさかここまで上手く行くとは思っていなかったんじゃないのか。そして、岡崎が逮捕されたことによって、岡崎に対して罪悪感を持っているんじゃないのか。だから、あの事件を正当化しようとしているんじゃないのか。」
轟は飲み干したコーヒーカップに、自分でもう一杯継ぎ足して再び飲み始めた。沈黙の時間が流れた後に轟は蒲田に背を向けながら話した。
「たとえ、もしそうだったとしても、この世の中に良い流れが出来たことには変わりないさ。リハビリテーションという名前がここまで発展して、多くの人に利用されるようになって、俺は本当にうれしかった。ようやく、俺たち理学療法士も病気の人たちだけじゃなくて、一般の人でも知ってもらえるような人材になったのだと思ってたさ。ただ、有名になるがゆえに、社会保障費の問題が膨れ上がってきていた。厚生労働省の内部では毎月のように議論があって絶えなかった。
必要な人に必要なだけリハビリテーションを提供するような世の中にしなければならない。その線引きを引くのに、俺は毎日うなされていた。リハビリテーションが受けられる期間を決めてしまい、期間が過ぎれば受けられないようにするようなシステムにすれば、リハビリテーション難民という言葉が出てくるほど大きく問題化され、やむなく制限は出来なくなった。そして、効果がなければリハビリテーションは継続して提供してはいけないというシステムを作れば、高齢というのも進行性の病気であるという概念が生まれ、進行性の病気は効果がなければリハビリテーションは提供してはいけないのかという問いに関しては、否定は出来ないから認めるしかない。そうなると結局、その制限もあるようでほぼ無意味な形になってしまった。
リハビリテーションは永遠に提供される。俺もそれでいいならその方が楽だ。でもこの国にはお金がないんだ。この日本にはお金持ちがたくさんいても、社会福祉に費やしてくれるお金がちっとも回ってこない。
俺は毎日毎日上司から威圧され、そして病気になるほど病んでしまった。そうした時に岡崎と再会した。久しぶりに再会した会話の中で、岡崎はリハビリテーションをあまり良くないと思っていることが分かった俺は、一つの妄想が生まれた。リハビリテーションがもし、毒のような存在だったら。その事を岡崎にポロっとグチをこぼすように話した。岡崎はすごく興味津々に聞いていたよ。俺はそんなことはあり得ないと付け加えたんだけどな。
それからしばらく岡崎とは会っていない。あの時、お前と竹下と一緒に会ったときが本当に久し振りに再会した。岡崎が提出した研究内容は俺も知らないところで厚生労働省の内部に出回っていたことだ。
岡崎はきっと俺を味方だと思っていたのかも知れない。なんたって、俺じゃないにしても、あいつの考えを政府が認めるまで上りつめさせたんだからな。
蒲田と竹下に近づいたのは、おまえ達なら何かしてくれるんじゃないかと考えたからだ。蒲田は同じ研究者だし、くい止められる方法がないかどうか考えて欲しくてさ。ただ、俺も立場があるから、あからさまに協力できなかった。
なぁ、蒲田。俺は本当にとんでもない事を岡崎に話してしまったと思っている。でも、もしかしたら、俺じゃなくてもこんな考えを誰かが岡崎に話していたら、同じ様な事になっているのかもしれないと考えると、反対に俺がそんな話をして良かったのかも知れないとも考えてしまうんだ。俺は・・・その事件を・・・・正当化して上げる事が・・・・」
「轟!」
蒲田は轟の会話を止めるように名前を呼んだ。
「もうお前はそれ以上言うな。」
轟は蒲田に背を向けたまま、振り向くことなくその場を去っていった。
(32)
蒲田はもう一つだけ疑問に思っていることがあった。岡崎が何故、改ざんされていたデータを利用したことを認めたのか、と言うことだった。
通常であれば、データの改ざんを知らなければ、岡崎は罪にならないのを、岡崎は認めている。そこが、蒲田にとって納得行かなかった。
蒲田は岡崎がリハビリテーションに対して良く思っていない原因を調べてみることにした。しかし、岡崎の過去のデータはあまりなく、情報収集に手詰まり状態となっていた。
蒲田はソラリスタ研究所近くにある河川敷のサッカー場を見学していた。元気に走り回る子供達を見ていると、蒲田は落ち着いた気分になっていた。子供というのは研究者にとって、非日常の刺激を与えてくれる存在だった。予測不能の動きをしたり、脈絡のない発言をする存在は、日々データと向き合っている人間にとって、温かい刺激に触れられ、それが心地よく感じるのではないかと蒲田は思っていた。
子供達の会話を聞いていると、岡崎と良く似た人の話をしていることに気がついた。蒲田はこのサッカーをしている子供達と岡崎が何か関わりがあるのではないかと考えた。蒲田は、このサッカークラブをコーチしている人に話を聞いた。
岡崎はよく、このサッカー場に来て、子供達にサッカーを教えていたらしかった。岡崎はサッカーに対する技術は素晴らしく、プロになってもおかしくないとコーチの人は言っていた。どうしてプロを目指さなかったのかと聞くと、岡崎は昔目指していた事を話してくれたそうだった。
しかし、岡崎はある日、腰部に痛みを訴え、手術をする事になり、その手術が神経に損傷をもたらしてしまったようだった。その影響で下肢筋力が低下してしまい、プロを目指すには厳しい状態だったようだった。
プロを目指したかった岡崎は、リハビリテーションをすれば元に戻れるのかと手術した医者にしつこく聞いたらしかった。手術した医者には、リハビリテーションをすれば治ると言われたらしく、それを信じてがんばっていたようだった。しかし、一向に治らなかったため、いろいろな医者や理学療法士にすがるようになっていったらしかった。行く先々の医者や理学療法士にも、手術した先生が大丈夫というのであれば、大丈夫なのではないかという返事だけだったようだった。まるで、口裏を合わせているかのようにも思えたらしかった。
それでも岡崎はその言葉を信じるしかなく、リハビリテーションに努力を惜しまなかった。朝から晩までトレーニングメニューをこなした。筋力が上がらないのは自分のせいだと言い聞かせ続けていた。なかなか効果が上がらないため、岡崎はそのトレーニングメニューを自分で開発しなければいけないのではないかと考えたらしく、岡崎は自分自身で理学療法士になり、治療しようと考えた様だった。
しかし、効果が上がらない原因は神経の損傷によるものとわかり、それは一生治らないということが、臨床実習を通してわかったところで途中退学したようだった。その後はリハビリテーションの無力さを考えるようになり、その事実を国民に知らせなければならないと考えるようになったようだった。
それがこの研究所の発端であり、今回の出来ごとの始まりなのではないかとコーチは教えてくれた。
蒲田は思った。きっと岡崎は、この研究所を立ち上げ、今回の発表により、やっと自分の思いを伝えられる事が出来た。それは今までの自分の人生が、やっと報われる瞬間だったのではないだろうか。
しかし、そのデータは不正されたものだった。きっと、岡崎はどこかで不正だと気付いたのではないだろうか。それでもそのデータを使用してまで、今回の発表にまで持って行きたかったとなれば、岡崎の思いは相当なものだったのだろう。
だから、不正したデータを利用した事を、すぐに認めたのかもしれないと、蒲田は思った。
リハビリテーションは努力。努力をすれば治る。治らないのは自分の責任。頑張れ。負けるな。根性だ。そうした一般からの無責任な声援。そして、頑張れば治るかも知れないという淡い期待をほのめかした医療従事者の無責任な助言。そしてなにより、わずかな期待にすがり、努力で生きてきた岡崎の人生。
彼もまた、リハビリテーションという麻薬にとらわれ、自分の人生を変えられなかったリハビリテーション中毒者の一人なのかもしれないと、蒲田は思った。
リハビリテーション中毒