
負けないでっ 【第一巻】
高校を卒業したばかりの女の子がいきなり家を飛び出して東京のど真ん中で生きて行くってほんとに大変だよね。でもね、負けないで挫けないで頑張って生きて行けばきっといつかは幸せになれるよ。
主人公の沙希って名前の女の子もそう信じて頑張ったんだ。この小説はそんな物語だよ。
それと、陰で沙希を支えるハードボイルドな男たちの生きる姿も見逃せないよ。
ではお楽しみに。
一 苦労の始まり

「もうっ、ひでぇ奴だ。人のことを玩具にしやがって……」
先程から島崎沙希は四畳半一間の小さなアパートの畳の上で、開いた股の前に手鏡を置いて、赤く腫れ上がった自分の陰部を見ていた。
沙希は二ヶ月前、仕事にあぶれてしまって、おんぼろアパートの月々二万八千円の家賃を払う金も厳しくなって、月初めから夕刻、JR山手線新大久保駅とJR中央線大久保駅の間の露地に立って、女を漁りに来る男を咥え込んで小銭を稼いで食い繋いでいたのだ。要するに売春をやっていたのだ。この露地は夕方薄暗くなると、どこからか女が集まってきて、それを目当てにやってくる男を捕まえてどこぞに消える溜まり場になっていた。女たちの約半分は外国人だった。見た目、外資系の金融会社かIT企業で秘書をやっていたような、すらっとした小奇麗な女も結構混じっていた。彼女たちも多分この不況で仕事にあぶれてしまったのだろう。沙希はそんな女たちに混じって、男を待った。
その日は、なかなか男に出会えなかった。大勢居た女たちの大部分は、男に出会えてどこかに消えて、残った女は少なくなっていた。
「今日は帰るかぁ」
沙希が呟いて帰ろうとした時後から、
「いくらだ?」
と低い声で近付く奴が居た。沙希は黙って指を二本、Vの字に立てた。それを見て、男は沙希の腕を取った。沙希は男の行く方についていった。指一本は一万円と相場が決まっている。男は沙希が立てた指を見て二万円でOKしたのだ。
男は近くのラブホに沙希を連れ込むと、さっさと沙希の洋服を脱がせて裸にした。自分も裸になると、いきなり沙希にのしかかり、自分のものを入れようとした。
「待ってよ」
そう言うなり、沙希は持ってきたポシェットからコンドームを取り出すと、元気良く突っ張った男の物に被せようとした。男は沙希の手を払った。
「こんなもの、オレは嫌いだ」
沙希は譲らなかった。
「こいつ嵌めないと入れてやらない」
「なにっ? 生意気な女だなぁ。それじゃ、おれは入れねぇ。その代わりお前のここを可愛がらせろ」
「その前に二枚出しなよ」
男はしぶしぶ財布から二枚取り出してベッドの上に放り投げた。沙希がそいつを拾って仕舞い込むと、男は沙希の股を広げた。沙希は我慢して男がしたいようにさせた。男は沙希の陰部に指を突っ込んで乱暴にかき回した。
「痛いっ! もう少し優しくやれよ」
男は沙希の言葉には何も反応せずに乱暴に引っ掻き回した。しばらくの間、沙希は我慢していたが、相当やられて、これじゃひどすぎると、足で男を蹴った。
「何しやがる」
と男は顔を真っ赤にして怒った。
「あんた、乱暴だからさ、これ以上やられたら、こっちがおかしくなるよ。お金、半分返すからさぁ、出て行ってよ」
男はさっさとパンツをはいて、シャツを調えると、まだ裸のままでいる沙希のヒップに軽く蹴りを入れて出て行った。結局金は返さないで済んだ。
男が帰って、シャワーで洗うと、そこがヒリヒリ痛んだ。
「くそっ、乱暴されちゃったな」
どうやら男の爪が伸びていて、沙希の柔らかい部分に傷を付けてしまったのかも知れなかった。
アパートに戻ると、沙希は先ほどから乱暴された所を手鏡で調べていたのだ。沙希は薬なんて、キンカンとカットバン、それにオロナイン軟膏と風邪薬のパブロンしか持っていなかった。仕方なく、腫れ上がった部分にオロナイン軟膏を指で塗った。今日は散々だった。オロナインを塗っているうちに、その指先でクリトリスを刺激した。間もなく、心地良い刺激が全身を覆って、沙希は気持ちが昂ぶって、独りで自分を慰めていた。
兵庫県の山陽自動車道と中国自動車道に挟まれた三木市一帯は、ゴルフ場がやたらと多い所だ。沢山あるゴルフ場の中の[オー]と言うゴルフ場で、白石沙織はキャディーをしていた。そんなある日、四国の徳島からやってきた島崎四郎と言う男に見初められて、白石沙織はゴルフ場を辞めて、島崎四郎の実家に近い鴨島町に移り住んで、そこで島崎と結婚した。間もなく、女の子が誕生して沙希と名付けた。
四郎と沙織は仲良く新婚生活をスタートさせた。沙希が生まれてから、沙織は専業主婦として、親子三人つつましく暮らしていた。
島崎沙希が三歳になった時、島崎四郎は図らずも近くのスナックに勤める女と不倫関係になって、次第に家に帰らなくなった。帰宅しない夫を不思議に思った沙織は、四郎の不倫と知って、僅かな蓄えを全部持って家を出た。沙織は自分の実家には帰らずに、そのまま東京の池袋近くに落ち着いて、沙希を保育園に預けて、昼間は商店のレジのパート、沙希を寝かしつけてから、夜、近くのスナックで女給をして働いた。
沙希は母親の沙織に何不自由なく育てられて、高校生になっていた。そんな時、母親の沙織が男を連れてきた。男は洋酒店に勤めている浜田だと名乗った。最初、沙希は母親の恋人に馴染めず、いつも顔を合わさないように避けていた。だが、しばらく同棲生活をする間に、男は沙希を可愛がったので、沙希も次第に男を許す気持ちになっていった。
沙希が高校三年生になった時、受験勉強をしている沙希の所に浜田がやってきて、いきなり抱きすくめて、沙希を犯した。沙希は抗ったが、男の腕に抱きすくめられて、身動きが出来ない内にやられてしまったのだ。そんな時はいつも、母親は相変らずパートに出ていて留守だった。一度犯してしまうと、浜田は度々沙希に手を出した。この時から、沙希は浜田を汚らわしい獣を見るように嫌った。しかし、沙希は母親にはこのことを一切話さなかった。
高校を卒業すると同時に、沙希は母親の財布から五万円を抜き取って、黙って家を出た。母親が捜索願いを出したので、間もなく警察に捕まって保護され、家に戻された。沙希の顔を見て、浜田は黙っていた。母親は、
「どうして? どうして」
と沙希を抱きしめて涙した。
次に家を出る時、
「あたし、浜田さん大嫌いだから一緒に住みたくないから」
と母の沙織に断って出た。沙織は引き止めたが沙希の気持ちは固かった。沙希は母からもらった十万円を持って出て、その足でハローワークを訪ねた。だが、携帯のセールスとか限られたアルバイトを除いて、求人は殆どなかった。職員がようやく見つけてくれたのは、大田区の蒲田にある従業員百二十名弱の小さな町工場の事務の仕事だった。沙希は選んでいる余裕がなく、職員の紹介状を持って会社を訪ねた。給与に特別な希望が無かったのが幸いしてその日から来てもいいよと言われて、そこで働くことになった。初任給は十二万五千円、手取りは十万円を切る安いものだったが、社長の紹介で近くの安いアパートに落ち着くことができた。
沙希はその工場で一生懸命働いた。それで、周囲の者たちに可愛がられて仕事に生き甲斐を感じるようになっていた。
幸せは長続きしないものだ。丸二年経って、沙希が二十歳になった時に突然会社が倒産してしまった。それで、沙希は仕事にあぶれてしまったのだ。
二 一瞬の出来事

沙希が新宿百人町の露地に立つのは週に二回位だった。初めて立った時は、相場が分らずに、男に指を一本立てて、それでOKをもらった。一発一万円だ。沙希が指を一本立てたのを見ていた女が居た。三回目だったか、その女が沙希に近付いてきて、
「あんたさぁ、一本でやらせちゃ他の人が困るんだよ。ここの相場は二本だからね。あんたに安売りされたら、相場が下がってみんなが迷惑するんだよ」
沙希は女にペコリと頭を下げた。次からはVの字に指を二本立てた。しかし、その後他の女を観察していると、Vを立てたのに値切られている女も居た。だから、最初はチョキで、客によっては下げるらしいことも分った。
その日は、夕方沙希がいつもの所に立っていたが、大勢女が集まってくる時刻になっても、立っている女はまばらだった。女を漁りに来る男もいつもよりずっと少ない。
「今夜は変だなぁ」
そう思っている内に午後八時少し前になった。辺りは真っ暗で、所々にある街灯の明かりがぼんやりと路上を照らしていた。
突然、沙希と同じように露地に立っていた女の中の三人が走り出した。路地の遠くから警官が二人こっちに歩いて来るのが見えた。路地の反対側を見ると、そっちも警官が二人、こっちに向かって歩いてくるのが見えた。先ほど走り出した女が駆け込んだ路地から、女が逆戻りして走ってきた。沙希の前を通り過ぎると、別の路地に走りこんだ。だが、走り込んだ女達はまた逆戻りをしてきた。女達が走りこんだどの路地にも警官が居たのだ。そうする間に、警官が路地の両側から距離を詰めて来た。走り出した女の一人が、民家のブロック塀に飛びついて、よじ登って塀の中に入ろうとした。そこに、距離を詰めて来た警官の一人が小走りにやってきて、塀を乗り越えようとしてしがみついている女のスカートを掴んで引き摺り下ろそうとした。
女の膝上丈のスカートがするりと脱げて、レギンス丸出しになり、
「やめてぇ~」
と女は悲鳴を上げた。そこに婦人警官が走って来て、
「降りなさいっ!」
と言って抱きかかえるようにして引き摺り下ろした。
沙希が周囲を見ると、先ほど走り出した女達三人は警官に捕まって夫々手錠をかけられていた。沙希は突然の出来事に、目の前で何が起こっているのか直ぐには分からなかった。
「あなたも一緒にいらっしゃいっ!」
沙希は声がした方を向くと、先ほど女を塀から引き摺り下ろした婦人警官が沙希の方を見ていた。沙希は自分を指さして、あたしですかと言う仕草をした。婦警は頷いた。その瞬間、沙希の背中に冷や汗が出て、足が勝手に震え出した。沙希の他に走って逃げようとしなかった女が二人居た。その女達も婦警に、
「一緒にいらっしゃいっ!」
と言われたようだ。皆大人しく婦警に従った。
狭い路地に金網を張った警察車両がバックで入ってきて、捕まった六人全員が後の観音開きのドアから押し込められた。中はトラックの荷台の両側にベンチを取り付けたような構造になっていた。先ほどの婦人警官が一緒に乗り込むと、警察車両は地下鉄西新宿駅近くの警視庁新宿警察署に向かった。警察に着くと六人は五階の生活安全課の小さな会議室に連れて行かれた。部屋に入ると、警官がやってきて、三人の手錠を外した。入れ替わりに先ほどの婦警が入ってきた。
婦警はやや太った三十代後半で世話好きそうな落ち着いた人だった。
「あんたたち、今夜なんでここに連れてこられたか、分ってるわね。言い訳しても無駄よ。あたしたち、長年ここに居るから、見ただけで勘で分るのよ。売春はダメよ」
婦警は皆の顔を見渡してキッパリと言い放った。皆黙っていた。続いて一人一人質問があった。婦警は西洋系の二人に、
「英語?」
と聞いた。一人は頷き、一人は顔を横に振った。
「スペイン語?」
女は、
「シ」
と泣きそうな声で答えた。南米系と思われる女に、
「あんたはポルトガル語?」
と聞くと日本語で、
「ハイ」
と答えた。
「日本語、分るの?」
「少し」
残った三人は沙希も入れて全部日本人だ。それで、婦警は英語、スペイン語、日本語と流暢に使い分けて質問した。沙希は婦警の言語能力に感心した。
「すごぉっ」
心の中でそう呟いた。
「売春はね、お金をやり取りした現場を押さえて現行犯逮捕をしないと、自由恋愛とかなんとか、皆屁理屈を言って逃げようとするわね。だから、あなたたちも売春容疑じゃ逮捕できないのよ。でもね、今夜はあたしの話を聞いて頂戴」
婦警は続けた。
「売春はダメよ。恐ろしい性病、麻薬、恐喝、いろんな犯罪に関わりやすいのね。だから、夫々理由はあると思うけど、明日からは絶対に売春はしないと約束してちょうだい。分った?」
六人は皆頷いた。それから婦警は一人一人に向かって質問をした。沙希の番が回ってきた。沙希は先ほど震えが来た程ではなかったが、警察にしょっ引かれたのは初めてだったので、返事はぎこちなかった。婦警は沙希が売春せざるを得なかった理由を優しくて同情する目で聞いてくれた。それで、沙希は思い切って最近の事情を素直に話した。婦警は、
「あなたのような真面目な子を売春の世界に追い込んだ世の中が間違ってるわね。あたしたちは金銭的に何も応援してあげられないけれど、頑張って正しい生き方をするのよ」
と諭した。沙希はいつの間にか頬に涙を流して泣いていた。いつも独りぼっちで頑張っていて、身近に親身に心の苦しみを聞いてくれる人が居なかったからだ。横を見ると、スペイン人らしき女も目に一杯涙を溜めて泣いていた。沙希と目が合って、また二人して泣いた。個別の質問が終わると、婦警はしばらく黙って皆を見ていた。
六人が落ち着くのを見て、婦警は夫々にA4のプリントを一枚づつ配った。上の方にやや大きめに[始末書]と書かれていた。韓国語や中国語も含めて七カ国語で併記されていた。内容は同じなのだろう。最後にサインの欄があり、そこにサインをして拇印を突かされた。
「今日は帰っていいわよ。良く反省して、二度と売春はしてはいけませんよ」
婦警はそう言って皆を帰らせた。沙希は婦警に小声で、
「ありがとうございました」
と言ってペコリと頭を下げた。婦警は沙希の頭を撫でて、
「頑張りなさい」
と言ってくれた。沙希の目にはまた涙が溢れてきた。
島崎沙希は身長163cmくらいで、小柄ではないが、沙希の年代では小さい方だ。目が大きめで、ちゃんと化粧をすればそこそこの美人に見えそうな、可愛らしい感じだった。
アパートに戻ると、警察で売春はダメだと言われたが、さりとて生活費をどうやって稼ぐのかあてがなかった。週に一回か二回ハローワークを訪ねたが、良い仕事が見付からなかった。トイレ掃除とかそんな仕事はあったが、沙希の年ではオバサンに混じって掃除婦をする元気もなかった。
「これから、どうしようかなぁ……」
考えても良いアイデアは出てこなかった。
沙希はいつまでも今のようなどん底の生活を続けてないで、いずれ、何かチャンスを掴んでいっぱいお金を稼ぎたいと夢を描いていたのだ。だが現実は厳しかった。
三 仲間
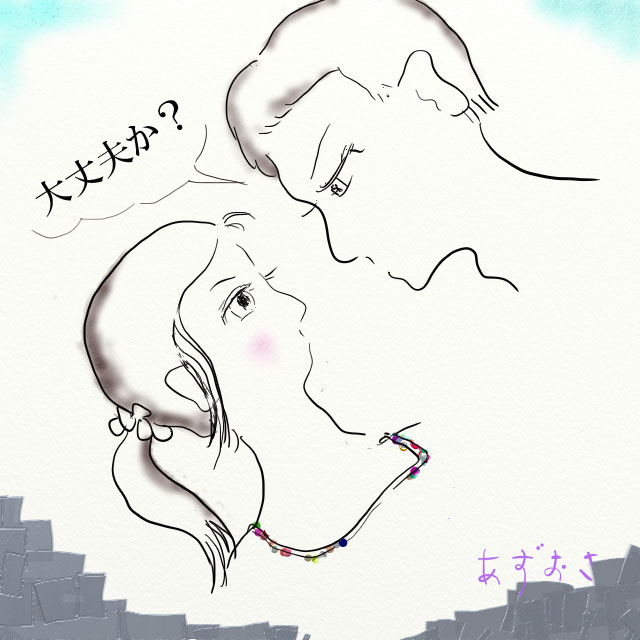
蒲田の金属部品を造っていた町工場では、女と言えば事務をやっていた自分だけで、他は全部男だった。厳密に言えば、社長の奥さんが時々手伝いに来ていたから紅一点とは言えなかったが、まあ紅一点と言えた。それで、沙希は皆に可愛がってもらえたし、同年代の話し相手も沢山居た。だが、会社が倒産して解散して皆バラバラになり、仕事にあぶれてしまった今は、話し相手もいない淋しい境遇だ。
「友達が欲しいなぁ」
沙希は先日新宿警察署の婦警に説教されてから、何でも話せる友達が無性に欲しくなった。
JR池袋駅は、サンシャインシティーのある方が東口で、東武百貨店がある方が西口だ。その西口を駅から少し歩いたあたりは、立教大学池袋キャンパスがあり、新線池袋駅前から北側の池袋二丁目界隈の路地には二十四時間営業の店が多く、若者の溜まり場になっている。明け方パスタ屋なんかに入ると、仕事を終わって朝帰りのキャバ嬢がおしゃべりをしているのが普通の風景だ。
夜九時を回った頃、沙希は先ほどから新線池袋駅前の通称ロマンス通りと呼ばれている路地の角に立って、近くにたむろしている若者のグループを見ていた。最初七人居たのが、十時を回った頃には十五人位になっていた。十人位が男で残りは女だ。見た所、二十歳前後と思われる、自分と同世代の奴ばかりだった。
沙希が見た所、ちょい背が高くてガッシリした体格の男が、どうやら仲間のリーダー格だと思われた。沙希はグループの方に歩いた。グループが集まっている場所近くの飲食店の前に、自転車が数台停めてあった。沙希は、そこで自転車によっかかるようにわざと倒れこんだ。[ガシャガシャガシャッ!!]派手な音をたてて、自転車は将棋倒しに倒れた。
案の定、リーダー格の男が、
「おいっ、大丈夫かよぉ」
と仰向きに倒れている沙希を抱きかかえて起こしてくれて、他の仲間が手伝って、自転車を元通りに立ててくれた。
沙希は男に抱きついたまま、周りの奴等に聞こえるように少し声をでかくして、
「すみません、あたしを守って下さい」
と泣きそうな顔で男の目を仰ぎ見た。周りの奴等にも聞こえたらしく、皆が沙希を見た。
「えっ? オレに言ってんの?」
「はい。お願いします」
「オレ、あんたのこと、なんも知らねぇのに、いきなりかよぅ」
「はい、すみません」
「けどよぅ、なんでオレになんだ?」
「一番強そうだから」
それで周囲の奴等が笑い出した。
「そりゃ、兄貴は強いけどさぁ、おまえ、変な奴だなぁ。どこに住んでんの?」
端っこに居たスキンヘッドにサングラスをかけた奴が口を挟んだ。
「椎名町です」
「えっ? 椎名町。兄貴の方面じゃん」
リーダー格の男は、
「分った、仲間に入れよ」
と言ってくれた。
「おい、新入りだ」
と皆に言ってから、
「あんたみんなに自己紹介しろよ」
と沙希に振った。
「サキです。よろしくお願いします。あたし、先々月会社潰れて、あぶれちゃって、仕方ないから新大久保で身体売ってつないでたんですけど、この前、サツに捕まって、今やることないし、困ってるんだ」
「それだけ?」
「はい」
「いくつ?」
「丁度二十歳です」
それでどうやらグループの仲間に入れてもらえたようだった。女の子たちが沙希の周りに来て、
「よろ」
と手を握ってくれた。みんなの手は温かかった。それで、沙希は思わず涙を出してしまった。
「あたしはモモ。あたしたちで良かったらさぁ、何でも話をしてよ」
一番年長の女の子が沙希を抱きかかえるようにして仲間の中に入れてくれた。髪を金色に染めたその子は沙希より二つか三つ年上に見えた。最初は皆の話を聞いているだけにしたが、次第に打ち解けて沙希も話しに入ることができた。それで女の子たちの名前はどうにか覚えることができた。携帯の番号とアドの交換もした。
午前二時を回った頃には半分くらい帰って居なくなっていた。
「サキ、送ってくよ」
リーダー格の男がメット(ヘルメツト)を渡してバイクの方に目をやった。
男は大型バイクのエンジンをかけると、後に沙希を乗せて走り出した。
「サキのアパートはどこだ?」
男のウエストに手を回して抱きついている沙希を振り向いて聞いた。
「この先、左に曲がって少し行ったとこです」
沙希のアパートの前でバイクを降りて、メットを返すと、
「ありがとうございました」
と頭を下げた。男はバイクの音を轟かせて去って行った。その後姿を、沙希はかっこいいなぁと思って、男が道を曲がって見えなくなるまで見送った。男の名前を聞くチャンスは最後までなかった。
四 再会
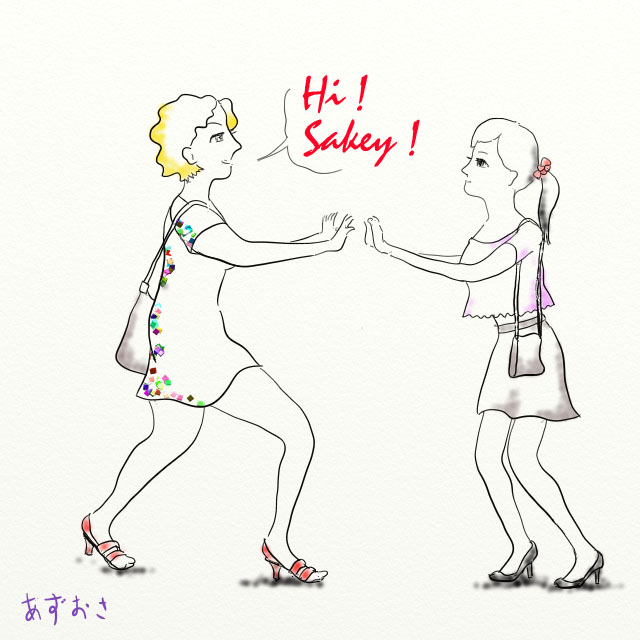
新しい仲間ができたその日から、仲間に入れてくれた五人の女の子から携帯にメールが届いた。いずれも簡単な自己紹介だったが、皆、温かく、沙希はとても良い友達ができたと思った。もちろん、丁寧に返事を返しておいた。本名かどうかは分らなかったが、年長のモモの他、アヤコ、ルリ、ミドリ、ミレの五人だ。
グループは毎週金曜日、土曜日、日曜日の夜にロマンス通りに集まることになっていて、仕事の都合で三日間になっているんだと説明された。リーダー格の男は大抵毎週日曜日に来ると言っていた。それで、沙希は日曜日に行こうと決めた。リーダー格の男は二十五歳位の奴でエグザイルのMに似た感じで身長もMのように180位あり、素的な奴だと思った。昨日横から口を挟んできたスキンヘッドの奴はエグザイルで言えばSに似た感じで、こいつもいい男だった。
手元のお金が底をついて、沙希は仕方なく、また新宿百人町の路地に立った。この前のことがあったので、同じような女が大勢来るか気を付けていたが、その日はかなり多く女たちがやってきたので、警察の手入れがない日だなと自分なりに予想した。夕方、七時を少し回った時、
「オラ、ブエナスノチェス!(Hola! Bienas noches!)」
と言って近付いてきた女が居た。沙希はこの前警察で一緒に泣いたスペイン系の女だと直ぐに分かった。沙希が手を挙げると、彼女は沙希にハグしてきた。言葉は全然通じなかったが、お互いの気持ちは十分に通じていた。沙希はポシェットからボールペンとメモ帳を取り出すと彼女に、
「ここに書いて」
と日本語で話した。沙希はローマ字で自分の名前と携帯の番号を書いて彼女に渡した。それで彼女は何を書けと言ったのか直ぐに分かったらしく、
「シィシィ(Si Si)」
と言って自分の名前と携帯の番号を書いてくれた。背後から、
「ハァイッ!(Hi!)」
と声がした。この前、英語を話していた女だと二人は直ぐに分かった。それで三人は再会を喜んでお互いにハグをした。沙希はスペイン系の女にしたのと同様に、メモ帳に自分の名前と携帯の番号を書いて渡すと、彼女も喜んで書いてくれた。外国人の歳の見分けは出来なかったが、二人とも沙希よりずっと年上で二十代後半と思われた。
その日は運良く感じの良い若い男が捕まった。男は見かけ通りラブホで優しく抱いてくれた。沙希は頑張って、その日もう一度路地に立った。四十過ぎの中年の男が沙希の客になってくれた。この男も優しくて、セックスが終わると三枚もくれた。沙希は、
「おじさま、ありがとう」
とお礼を言って、洋服を着るのを手伝った。帰り際に、男は沙希を抱きしめて、
「頑張りなさい」
と呟いた。世間では大きな会社の管理職でもやっていると思われるような落ち着いた真面目風の男なのに、どうして自分なんかを買ったんだろうと沙希は不思議に思った。立派に見える男でも夫々人には言えない理由があるのかも知れないなぁと思った。
ラブホを出て、アパートに帰ろうとすると、
「サキィ」
と後から呼ばれた。振り返ると、スペイン系のマリアが立っていた。
「もう帰るの?」
と沙希が日本語で話をすると、彼女は泣きそうな顔で頷いて、沙希の後ろをついて来た。結局、彼女は椎名町のマンションまでついてきてしまった。マンションで、沙希はあり合わせの材料でパスタを作って二人で食べた。食べ終わるとマリアは、
「ブエナ」
と言った。どうやら美味しかったと言っているようだ。
食事が終わってもマリアは帰ろうとしない。仕方が無いので、二日おきに行く近くの妙法湯と言う銭湯に一緒に連れて行った。入浴料金は四百円、二人で八百円を沙希が払って中に入った。マリアはどうやら銭湯は初めてらしい。それで、脱いだ衣服をカゴにいれるのだとか、丁寧に教えて裸になって二人で風呂場に入った。わりと混雑していたが、沙希はマリアの背中を流してやった。そうしたら、マリアも沙希の背中を流してくれた。銭湯を出てもマリアは帰る気配がなく、結局沙希の所に泊めてやるしかなかった。四畳半で狭かったが、詰めれば十分なスペースがあった。
こうして、沙希とマリアの同棲生活が始まった。どうやらマリアはホームレスだったらしい。
それで、沙希はマリアからスペイン語を教えてもらうことにして、沙希はマリアに日本語を教えることにした。二人は暇があったから、たちまちお互いに上達して、十日もすると、かなり意志の疎通ができるようになった。洗濯は近くのコインランドリーでしてくるのだが、マリアは一人でも行けるようになった。
沙希は英語も覚えたいと思った。それで、新宿警察署の婦警を訪ねるつもりで出かけた。確か婦警は佐々木と言うネームプレートを付けていたと記憶があったので、五階の生活安全課に行くと、
「婦警の佐々木さんに面会したいのですが」
と言った。応対した別の婦警が、
「佐々木さんは今外出中です。三十分くらい待てますか?」
と申し訳なさそうな顔をした。
「はい。待たせて頂きます」
二十分くらい待つと佐々木がやってきた。
「あらっ、この前の方ね。何かご用?」
「はい。ご相談したいことがあって」
「じゃ、いらっしゃい」
佐々木はそう言って奥の部屋に案内した。
「先日は、ありがとうございました」
「今日は何のお話?」
「実は、この前外国語がすごくお上手でしたので、どうしたらそんなになれるのか教えて頂きたくて」
「へぇーっ? 私の語学なんていい加減よ。それでも良かったら」
「全然構いません」
「外国語を話せるようになりたいなら、駅前の語学学校なんてダメよ。一番いいのはね、習いたい言葉を使っている親しいお友達を作ることね。単語は特別な方法はないから、そうねぇ、高校の教科書をしっかり勉強なさい。高校程度なら日常それで十分よ。文法は要らないわね。あなた、高校は卒業なさったんでしょ」
「はい。地元の公立ですけど」
「なら大丈夫よ。頑張っていいお友達を見付けてね」
沙希はマリアとの間を思い浮かべて、婦警の佐々木さんの言う通りだと納得した。佐々木は、
「あれからちゃんと止めたの?」
と聞いた。沙希は、
「はい」
とウソをついた。佐々木に礼を言って警察署を出ると、沙希は先日携帯番号を聞いた英語系のカトリーヌに電話した。運良く相手が出た。
「ハイ(Hi)、カトリーヌ」
「沙希です」
「サキィ、ハロー」
沙希はたどたどしく、
「プリーズ、ミート ミー」
と言って見た。
「ホヤー?」
と言ってカトリーヌは、
「ドコデ?」
と言い直した。
「マイ ホーム」
「ユア ホーム?」
「イエス」
何とか椎名町駅で三時に待ち合わせることを伝えることができたようだ。沙希がマリアと一緒に椎名町の改札口で待っているとカトリーヌが嬉しそうな顔をして小走りにやってきた。
三人で駄菓子をつまみながら、お互いに手振りも交えておしゃべりをした。気持ちが伝わるので思ったよりずと楽しかった。それ以来カトリーヌは時間のある時にやってきておしゃべりをした。言葉とは不思議なものだ。二週間もすると、三人は結構意志の疎通がうまく行くようになった。マリアもカトリーヌも日本語を覚えたかったらしく、沙希はスペイン語と英語を覚えたかったから三人とも上達は早かった。婦警の佐々木が言った通りだと沙希は感謝した。
五 彼の名前
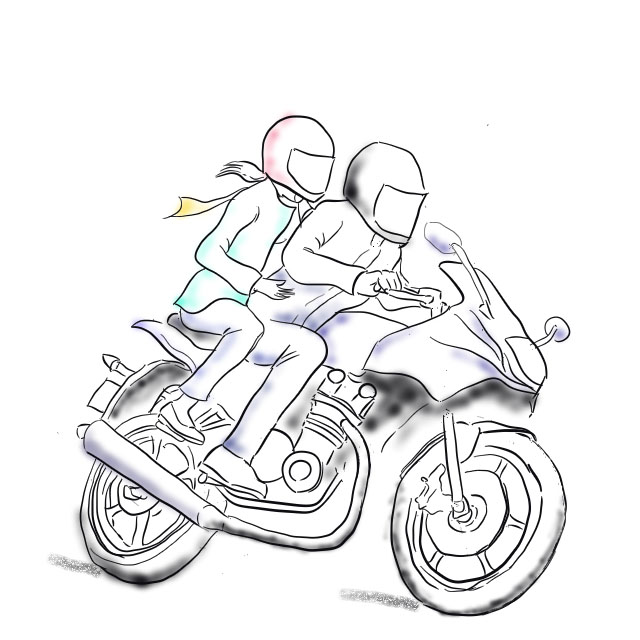
マリアと同棲生活を始めてからも、沙希は日曜日の夕方、池袋のロマンス通りに通っていた。
最初に行った時、リーダー格の男はまだ来ていなかった。けれども五人の女の子の仲間たちは揃っていたのでみんなの中に入れてもらって楽しく過ごすことができた。どこの店がつぶれたとか、どこの店がセールをやってて、洋服が安く買えたとか、話題はたわいのない情報交換だったが、沙希はそんな話を聞かされても別に嫌ではなかった。女の子は自分達の洋服やアクセのことになると話が盛り上がるものだ。その日はブーツに合うソックスの話で盛り上がっていた。今はレギンスやトレンカが流行りで、トレンカに合わせて履くソックスはどんなのがお洒落だとか、話題は尽きなかった。
鈍いバイクのエンジン音がして、グループの近くで止まった。沙希は先日のエンジン音を覚えていた。それで、リーダーの男が来たと直ぐに分かった。
「オスッ」
先に来ていた男たちは口々に挨拶した。男は沙希の姿を見ると、
「来たな」
と声をかけてくれた。沙希にはそれがすごく嬉しかった。
「やっぱ来て良かった」
と思った。
午前二時を過ぎた所で前と同様に、
「沙希、送ってこか」
と男が声をかけてくれた。
「はい、お願いします」
沙希は最初の時と同じようにバイクに乗ると彼のウエストに腕を回して抱きついた。最初は遠慮があったが、今日は遠慮なく抱きついて、彼の大きな背中の温もりを感じていた。
アパートの前で降ろしてもらった時、
「すみません、お名前を教えて下さい」
と彼に言ってみた。彼は沙希の顔を見て、「オレ、ショウゴって言うんだ」
と答えた。
「どんな字を書くんですか?」
彼は照れた顔になって、
「猪俣章吾、いのししに人偏のまた、しょうは文章のしょう、ごは漢字の五の下に口」
と説明してくれた。
「これからはショウゴさんと呼んでもいいですか?」
「いいよ」
「それから、いつもサングラスをしてる方は何て呼ぶんですか?」
「ああ、彼ね。彼はサトルだ。じゃぁな」
言い終わると、彼はエンジンをかけて、走り去って行った。
沙希は彼のバイクの赤いテールランプが見えなくなるまで、じっと見送っていた。
「いつか、あのテールランプ、あたしに五回点滅してくれる日がくるかなぁ」
沙希は心の中でそんな風に思った。
この時から、沙希の中に、ショウゴへの恋心が芽生えた。この時は、沙希自身恋してるとは気が付かない程度だったが、日が経つにつれて、沙希の心の中にショウゴの存在が膨らんでいったのだ。
ショウゴに送ってもらって四回目に、沙希のアパートの前でバイクを降りると、
「沙希、おまえタトーしてるのか?」
とショウゴが聞いた。いきなりだったので、沙希はショウゴが、
「タトーをしろよ」
と勧めるんじゃないかと思った。
「いえ、してません」
ショウゴは、
「そうか」
と別に気に留めるようではなかった。
「おまえ、まだ仕事見付からねぇのか」
「はい。ハローワークに行ってますけど、全然なくて」
「じゃ、今もあぶれてるんだ?」
「はい」
「沙希、オレのダチの兄貴がクラブをやってんだけど、面接受けてみねぇか」
これも突然の話しだった。
「……」
クラブと聞いて、沙希は一瞬返事に迷った。
「池袋あたりのクラブと違って、エッチをやらせないとこだから安心しろよ」
「ほんとうですか」
「ん。その代わり面接、厳しいらしいけど」
沙希はその話を聞いて、
「じゃ、受けて見ます」
と答えた。
「分った。今度連絡する。携帯の番号とアドを教えろよ」
沙希はボールペンとメモ帳をポシェットから取り出して、番号とメールのアドを書いて渡した。沙希はシヨウゴにアパートに寄って下さいと言いたかったが言えないで居ると、ついもの通りエンジンをかけて、
「じぁな」
と言って走り去った。
沙希はこの瞬間がすごく切なかった。彼の赤いテールランプの光が見えなくなった時、沙希の心にショウゴを思う気持ちが抑えきれないほど込み上げてきた。
六 面接

「沙希、今週の木曜日一日空けられるか」
猪俣章吾から電話がきた。
「はい。あたし、毎日お休みですから」
と沙希は返事した。
「この前話したクラブだけど、木曜日の午後三時に来いだって」
「はい。場所はどこ?」
「六本木。地下鉄の六本木一丁目駅から歩いて五分位かな。Tと言う雑居ビルの地階で、店の名前は[ラ・フォセット]、フランス語で、La fossette って書くんだけど、女の子の笑窪って意味らしいよ。店はまだ閉まってるけど、階段を降りたとこに小さいドアがあるから、中に入ったら事務所と書かれた部屋に入って。沙希の名前を言えば分ると思う。念のため、電話番号は03-356X-XXXXだ。頑張れよな」
「ショウゴさんありがとう。あたし頑張る」
電話は切れた。
木曜日の朝は早く目が覚めた。沙希はマリアに、
「あたし、今日面接に行くんだ」
と話した。
「どこなの?」
マリアはすっかり日本語が上手になっていた。
「六本木」
「そう? お店の名前は?」
「ラ・フォセット」
「あらっ、わたくしそのお店知ってます。上品でとてもいいクラブよ」
「マリア、どうして知っているの」
「わたくし、前はスペイン大使館の経済商務部でお仕事してたの。それで、日本のお客様とご一緒に時々ラ・フォセットに行ったことがあるのよ」
それで、マリアは場所を良く知っているから一緒に六本木に行ってくれることになった。
「採用されるといいわね」
マリアは心から応援してくれた。マリアは人員整理があって、日本語ができない人から順に解雇されたと前に言っていたが、まさか大使館に勤めていたとは、沙希は知らなかった。
ここのとこ就活で自分の履歴書を数枚作ってあった。沙希はその中から、文字が綺麗に書けているのを一枚抜き取って、封筒に入れ、ハンドバッグに入れて仕度を終わった。
お昼過ぎ、二人は池袋でメトロの有楽町線に乗り換えて、護国寺→江戸川橋→飯田橋を通り、市ヶ谷駅でメトロの南北線に乗り換えて、四谷→赤坂見附→溜池山王の次の六本木一丁目で降りた。マリアが居たから、場所は分っている。それで、時間が少しあったので、スペイン大使館、筋向いのスウェーデン大使館、サントリーホールなどを案内してもらって、アークヒルズでお茶をした。三時少し前に、マリアに連れられて、Tビルの地下のラ・フォセットに着いた。
「終わったら携帯に電話を下さいな」
マリアはそう言ってそこで別れた。
事務所と書かれた扉を開けると、女性が二人、男性が五人か六人居た。近くの女性に来意を告げると、直ぐに戻ってきて、
「どうぞ」
と隣の部屋に案内された。
隣の部屋は少し広く、ガランとしていた。端の方にテーブルが置いてあり、反対側にも小さなテーブルがあった。沙希はそこに座って待つように言われた。椅子に座ると、なんだか胸がドキドキして沙希はすっかり緊張してしまった。
扉が開くと、事務所に居た男が三人入ってきた。真ん中の一番偉そうな男が質問を始めた。名前や住所、生年月日を聞いた後で、
「英語は使える?」
と聞いた。
「はい。少しだけ」
と答えると、
「英語以外は?」
と聞いた。
「スペイン語を少し」
と沙希が答えると、真ん中の男は意外な答えだったらしく、ちょっと眉を動かした。
「最近、中国人のお客様が増えているから中国語も使えるといいね」
と付け加えた。
「はい」
沙希はそうか、中国語かぁ、中国人のお友達も作らなくちゃと心の中で思った。
真ん中の男が、
「こっちに出てきて、真ん中に立って」
と指示した。沙希が空いたスペースの真ん中に立つと、
「着ている物を全部脱いで」
と指示した。沙希は言われた通り、ブラウスやスカートを脱いだ。
「全部と言っただろ」
真ん中の男が睨んだ。沙希は、
「そうか、全部か」
と納得してショーツ以外のブラやレギンスも脱いだ。すると真ん中のが、
「全部だ」
と念を押した。
「えーぇっ?」
と思ったが仕方が無い、恥ずかしいのを我慢して全部脱いだ。暖房がきいていて寒くはなかったが、恥ずかしさで全身が硬直した。すると左端の男が、
「肩の力を抜いて」
と注意した。
男たち三人は沙希の身体に視線を集めて真剣な表情で沙希のボディをチェックしているようだった。その視線は沙希の身体を通り抜けると思うほど厳しかった。
「横を向いて」
また、真ん中の男が指示した。横を向いてしばらく見られているのを我慢していると、
「後を向いて」
と指示が飛んできた。沙希は大人しく後ろ向きになった。
「そのまま回って横を向いて」
と言われた。沙希は回った方向に身体を横向きにした。
「ちょっと近くに来て」
と言われて一歩男たちの方に近付いた。すると、
「太ももの内側を見せて」
沙希がもじもじしていると、
「股を開いて見せるんだ」
と厳しく指示が来た。言われた通りにするとようやく、
「終わり。元の真ん中の所に戻ってショーツを着けて」
と言われた。沙希は床に落としたショーツを拾って急いではいた。右側の男が真ん中の男に、
「猪俣君の紹介です」
と囁くのが聞こえた。真ん中の男は頷いていた。
「マキを呼んでくれ」
と真ん中の男が言うと。右の男が部屋を出て行った。間もなく首にメジャーを引っ掛けた若い男を連れて入ってきた。若い男はマキと言うらしいが沙希の所に来ると、
「失礼します」
と丁寧に頭を下げて、沙希のサイズを測った。マキは、
「身長163、バスト82、ウエスト61、ヒップ85」
と測定値を読み上げて、部屋の端から体重計を持ってきた。
「体重45.5」
と言ってからマキは、
「ありがとうございました。失礼します」
とまた丁寧に頭を下げて体重計を片付けて部屋を出て行った。いつの間にか三人の男の横に三十代半ばと思われるショートカットの男っぽい感じの女性が座っていた。真ん中の男が、
「採用決定だ。あと、細かいことを澤田さんに聞いてから帰って下さい」
と言い残すと三人の男たちは部屋を出て行った。
「洋服を着て下さいな」
澤田は沙希が着るのを待ってから、
「あなた合格よ。今から色々お話させて頂くわ」
と一緒に部屋を出た。
隣の[チェック]と書かれた部屋に案内すると、中は美容院のようになっていて、とても綺麗な内装でびっくりした。
「出勤は毎日五時、遅れないようにね。出勤なさったら、必ずここでメイクをしてもらって頂戴。メイクしてもらっている間にマキ君がその日あなたの着るドレスを持ってくるから、あちらの小部屋で着替えて、あなたの洋服はこのロッカーに仕舞って下さい」
そう言って、ロッカーの新しいネームカードに[島崎沙希]と書き込んでカード受けに差し込んだ。
「メイクが済んでドレスアップが終わったら、マキ君にチェックしてもらって、六時半にこの先のドアからお店に入って下さい」
そう言って店への通用口を教えた。
「ドレスは背中を出すデザインの物が殆どなので、ここで背中のケアもちゃんとしてもらって下さい。あなたは大切な接客係ですから、この部屋ではお客様のつもりでみんな専門のメイクさんやマキ君に任せて下さいな。お勤めは明日からでも構いませんよ。最初にいらした時、皆さんに紹介するわね」
そう言い終わると澤田は、
「事務的なお話しです」
と言って、就業規則を出して沙希に渡した。
「あなたの初任給は八十五万円ね」
就業規則と一緒に渡された辞令を見せてそう言った。
「今日は支度金三十万円が出ますから、帰りがけに事務所に寄って受け取って帰って下さい」
と付け加えた。沙希は金額の大きさに唖然とした。
「あっ、言い忘れてた。ここでは品の良いお嬢様の集まりになってますから、言葉にお気を付けて、お客様には丁寧な言葉を使って下さいね。それから、万一お客様に失礼なことや乱暴をされたりしたら、このボタンを押して下さい」
と新しいペンダントを渡された。
「ここにいらっしゃるお客様は日本の女性の美しさを求めておられる方もいます。ですから、できるだけ時間を割いて、茶道と華道の作法も覚えて下さい。お稽古は専属のスクールで無料で受けられますから、通って下さいね。今後分らないことや困ったことがあったら何でもあたしに話して頂戴。分ったわね」
「はい」
「じゃ、今日はこれで説明が全部終わりよ。明日から頑張ってね」
沙希はこれからの仕事は、自分が住んでいる世界とは別世界だと思った。日本中不景気なのに、良くこんな店がやっていけるものだと感心した。帰りがけに事務所に寄ると、先ほど質問した真ん中の男が沙希の所にやってきて、
「これからよろしく頼むよ。この支度金であんたの下着とか靴とかを新しい綺麗な物に代えて下さい。贅沢な物は必要がないが、いつも清潔を心がけて下さい」
と言って支度金の袋を手渡した。
「ありがとうございます。よろしくお願いします」
沙希は男に丁寧にお辞儀をした。
「あっ、猪俣君に逢ったらよろしくと伝えてくれ」
「はい」
ラ・フォセットを出ると、沙希はマリアに電話した。マリアは直ぐ出た。
「合格した?」
「ん。合格した」
「やったわね。じゃ、今夜は乾杯ね」
「あたし、マリアにご馳走させて」
沙希は思わぬ大金の支度金をもらったので、今夜はマリアとカトリーヌと三人で美味しいものを食べたいと思った。カトリーヌに電話をすると、六本木に来れると言った。三人はミッドタウンで食事をすることにした。
七 秘めた愛
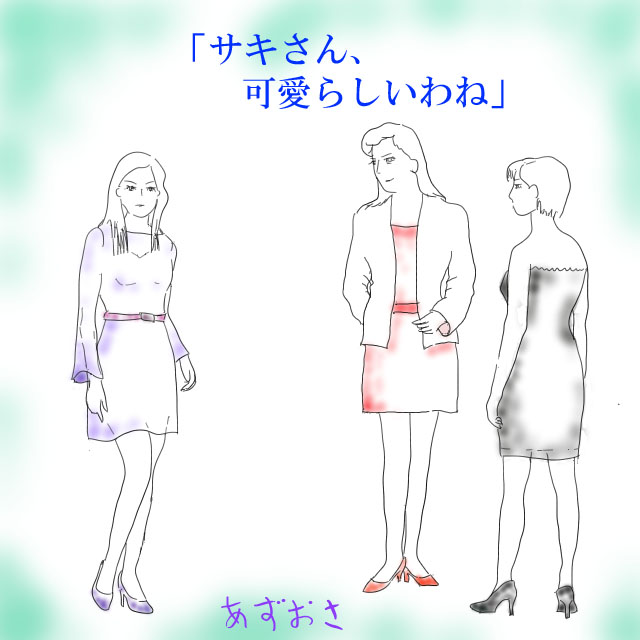
面接を受けた翌日の午前中、沙希はマリアと一緒にランジェリー専門店と靴の専門店に出かけた。折からの不況で、値札の20%や30%オフでわりと良い物が買えた。贅沢な物は買わなかったから、沙希はマリアの物も一緒に買ってあげた。アパートに戻ると、ちっちゃなキッチンで髪を洗い、マリアが作ってくれたパエリアを二人で食べた。マリアは料理が上手で、マリアのお国の料理のパエリアは美味しかった。お昼を済ますと、マリアに留守を頼んで早めに六本木にでかけた。今日から出勤だ。
ラ・フォセットに着くと澤田を見付けて、
「今日からお願いします」
と頭を下げた。早かったので、まだ誰も出勤していなかったが、メイクさんたちやマキは来ていた。澤田が居合わせた人たちに、
「今日から皆さんにお世話になる島崎沙希さんです」
と紹介してくれた。
「よろしくお願いします」
と沙希が頭を下げるとメイクさんの一人が、
「どうぞこちらに」
とベッドを指した。
「伏せて寝て下さい」
言われた通りにすると、トップスをブラまで外して裸にして、背中からウエストまでを撫でるようにして化粧液を綺麗に塗って、その上にクリームを薄く延ばした。沙希はエステなどしてもらったことはなかったが、エステってこんな感じかなぁと思った。肩からウエストまで、背中を綺麗にしてもらっている間、すごく気持ちが良くて、
「はい、できました」
と声をかけられた時はハッとなった。どうやら居眠りが出てしまったようだ。メイクさんはブラのホックを留めて、着ていたブラウスは綺麗に畳んで返してくれた。
「上は後でロッカーに入れて下さい。じゃ、そこの椅子にお座りになって」
沙希は言われた通り、美容院にあるのと同じような椅子に座った。椅子を倒すと顔や胸周りを綺麗にしてくれて、
「髪型、どうしようかなぁ、マキ君、サキさんのドレスどんなの?」
とマキに聞いた。マキがクローゼットから今日沙希が着るドレスを持ってきて見せた。淡いパープルピンクのシンプルなスキニードレスだった。
「ああ、それ? それだったら、髪は自然にこのままブローしただけでいいわね」
メイクさんは手際よく綺麗にしてくれた。鏡を見ると、沙希のやや大きめの目の縁が上手に可愛らしく仕上げられていて沙希は、
「すごっ、あたしも捨てたもんじゃないなぁ」
と思うほど別人のように魅力的に変身していた。
「じゃ、マキ君お願いね」
沙希はマキがドレスを着せてくれるに任せて鏡を見ていた。身体の線が綺麗に出るドレスで、沙希に似合っていた。もちろんサイズもピッタリだ。
「このストッキングにして下さい」
マキが差し出したストッキングはやや白味がかった織り模様のあるストッキングだった。沙希はレギンスを脱いで畳むとストッキングに替えた。ストッキングをはき終わると、マキがワインレッドのシルクのサッシュベルトを綺麗にウエストに結んでくれた。
「はい。これで仕上がりです」
鏡の中には、今迄見たことがない素敵な沙希が立っていた。
女は、化粧、衣装、甲斐性、この三つの[しょう]が揃って三勝になると誰でも綺麗になるのだ。今日の沙希はまさに三勝、全勝だった。
後から出勤してきた先輩たちは全部で九名いた。沙希を合わせて十名だ。澤田が皆に沙希を紹介した。
「今日から入った新人の島崎沙希さんです。よろしくね」
リーダー格の女性は辻村初枝だと名乗った。
「あなた、初めてで勝手が分らないと思うから、今日から当分の間、わたくしのそばで付いて回って下さい。分ったわね」
「はい、よろしくお願いします」
沙希はなんかドキドキしてきた。周囲の仲間の女たちが、
「サキさん、可愛らしいわね」
と口々に褒めてくれた。
六時半、皆は揃って通用口から店の中に入った。沙希は店の中を見て驚いた。広くてゆったりとしていて、清潔でデコレーションは控え目で上品な雰囲気があった。女たちはテーブルの上を拭いたり、活花の形を直したりした後、それぞれが適当にテーブルについた。沙希は辻村の後ろにぴったりと寄り添って、辻村の言う通りにした。
七時を過ぎると次々と客が現れ、八時にはほぼ満席に近くなり盛況だった。金曜日だったせいかも知れない。店は土曜日までで、毎週日曜日だけ休みだと言われた。初日の沙希は辻村の後ろにくっついていたのでなんとか卆なく仕事を終えることができた。
店が終わったのは午前二時過ぎだった。仲間の女たちは着替えを済ますとさっさとタクシーを停めて帰って行った。沙希もタクシーを停めようとしたが、空車がなかなか来なかった。
不意に、
「沙希、送ってくよ」
と後からメットが差し出された。驚いて振り返ると、そこに猪俣章吾が立っていた。
「オレ、ここのバックヤードやってるから、良かったらいつでも送ってくよ」
章吾の背中にぴったりと抱きついて夜中の街中をバイクで走るのは気持ちが良かった。椎名町のアパートに着くまで、沙希は至福の一時を過ごせた。勤め始めてから、そんな日が毎日続いていた。章吾はシャイな奴で、アパートに着くといつも、
「じゃな」
と言って直ぐに走り去った。けれども、いつの間にか沙希は章吾を本気で愛していた。なので、章吾が走り去って、赤いテールランプが見えなくなると、すごい切なさが押し寄せてきて、泣きたくなるほどだった。
八 森ガール
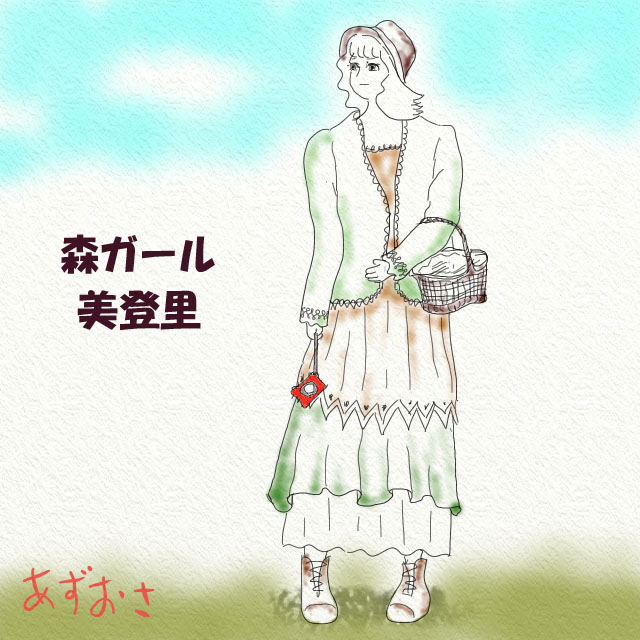
古都鎌倉には鶴岡八幡宮の前から海に向かって一直線に若宮大路が続いている。JR鎌倉駅東口駅前から北に向かって若宮大路と平行して、商店が並ぶ小町通りがある。だが、鎌倉には、若宮大路の東側に若宮大路に平行して、もう一本金沢街道に続く道がある。小町大路だ。小町大路界隈は、所番地で言えば小町一丁目~二丁目になり、この辺りは旧市外で瀟洒な住宅が並んでいて、路地を入ると観光客の喧騒が嘘みたいに静まり返った静かな住宅街だ。
その住宅街の一角に藤井美登里の家があった。美登里の父は市役所勤めの役人で、月給は多くはなかったが、祖父が残してくれた金融資産があり、贅沢ではないがゆとりのある生活をしていた。家族は祖母と両親の四人で、美登里は一人っ子だった。
美登里は幼稚園から高校までは、江ノ島からモノレールで一駅の目白山下駅で降りた所にある湘南白百合学園に通った。カトリック教、クリスチャンのお嬢様学校で、子供の頃から男性には縁が遠かった。白百合学園高等学校を卒業すると、東京千代田区三番町にある大妻女子大学の文学部に進んだ。大学は桜で有名な皇居の千鳥が淵に近く、隣は東京家政学園だったので、女ばっかの所だ。
鎌倉からは大学に通うには遠すぎる。だが、美登里には母の姉の西垣八重と言う伯母がいて、四谷に住んでいた。それで、大学の二年~卒業するまでは伯母の所に居候をしていたのだ。大妻女子大の文学部の学生は一年生の時だけ、東京郊外の狭山と言う所の分校に通うことになっていた。田舎で、四谷からは通えないので、学生寮に入って過ごした。
大学の一年生までは、美登里はパンツでもトップスでも、身体にピッチリと合う物でないと気が済まなかった。それで、田舎ではなかなか気に入るものが見付からなかったので、休日には渋谷に出て、何軒も店を回って、自分の身体をビシッと締め付けるような感じのアイテムを探すのに命を懸けていると言ってもいいくらい熱を入れていた。
運良くピッタリのが見付かると嬉しくて嬉しくて仕方がないような子だったのだ。
大学二年から三番町のキャンパスに移った。それで、今迄よりもマイファッションを見つける暇がずっと増えた。休日になると、気が合う友達と連れ立って、代官山、原宿、下北(下北沢)を遊び歩くことが多くなった。この界隈には輸入物の古着を扱う店がいくつもあって、友達に誘われてそんな店に行くことが多くなった。
この頃から、美登里の心境に変化が現れた。今迄、自分の身体を締め付けるようなピシッとしたものが大好きだったのに、古着屋に通う内に、今までとは正反対に[ゆるい]感じのアイテムが大好きになり、ライフスタイルまで[ゆるい]のが好きになってしまった。
ヨーロッパから輸入された古着の中に、上質なウールのAラインのゆったりとしたワンピやジャケ、ハーフコート、またゆったりしたギャザースカートやウールの大きなスカーフなど、色合いも淡いブラウンやグリーン系の素的なアイテムがあって、気に入った[ゆるゆる]のアイテムを探しては買ってくることにすっかりはまってしまった。美登里は元々一人っ子で甘えん坊、鎌倉の静かな家に居るときは、部屋の中でゆったりと童話を読んだりしているのが好きで、食事も時間をかけ、お風呂も一時間位かかるのが普通だったからそんな性格に[ゆるい]感じのファッションは合っていたのかも知れなかった。
昨年、三年生になった時には、美登里のファッションは一年生の時と様変わりしていた。休日に散歩をしたり、洋服探しに出かけるときは、ゆるい洋服に身を包んで、伯母に買ってもらったカシオのデジカメをぶら下げて、路傍の片隅に咲く雑草の可愛い花を撮影したり、何気ない街の風景を撮影したりするのが趣味になっていた。デジカメは優れもので、暗い所を撮ってもそこそこ明るく取れるし、連写は出来るし、何よりもYouTube撮影モードがあって、写真をブログにアップするばかりでなくて、YouTubeに動画を投稿するのも趣味になった。美登里は北欧の童話が好きだったから、ヨーロッパの、取分け英国や北欧の絵本の挿絵を参考にして、マイファッションを楽しんでいた。
そんなある日学校で友達から、
「あなた、森にいそうなおんなの子みたいね」
と言われたことが広まって、当時交流サイトのコミュで話題になっていた、[森ガール]にちなんで、美登里もみんなに[みどりの森ガール]とあだ名されるようになってしまった。名前の美登里が余計に印象を強くしたのだろう。
こうして、美登里が大学の四年生になっても、皆から[みどりの森ガール]とか[みどりの森]と呼ばれていた。初夏を過ぎたあたりから、就活に忙しくなって、リクルートスーツを着て歩くことが多くなったが、今ではリクルートスーツが窮屈で着るのが嫌になるほどだったのだ。
その日は、クラスメイトと飯田橋で遅くまで遊び歩いて、皆と別れた時は既に午前二時半を回っていた。伯母には電話で友達との飲み会で遅くなるからとは伝えてあったが、こんなに遅くなったのは初めてで、帰ったらきっと叱られるだろうと思うと、何だか気持ちが重くなった。
午前二時半と言っても、飯田橋から四谷あたりまでは車もそこそこ多く、道を歩いている人も居たから、タクシーには乗らずに外堀通りに沿って四谷までゆっくりと歩いて帰ることにした。
美登里が丁度四谷小学校前の交差点に差し掛かった時、四谷の方から飯田橋の方に向かって、一台のバイクが走って来るのが見えた。バイクは二人乗りで、後に女の子が乗っている様子だった。特にスピードは上げておらず、夜道を走るバイクとしては大人しかった。
バイクが緑の信号で交差点を突っ切る時、不意に自分から見て右、バイクから見て左の道から、赤信号なのに乗用車が突っ込み、
「キュワーッ!」
と急ブレーキをかけて停まった。
バイクは咄嗟に避けようとしたらしく、スリップして転倒した。乗っていた男は女を抱きかかえるようにして、転倒したバイクを避けて道路上に倒れこんだ。美登里は乗用車が突っ込んできた時、無意識にYouTube撮影モードで交差点の様子を撮影していた。
バイクが転倒したのは美登里が立っている所と反対側の飯田橋方面に向かう車線だった。それで、美登里が見ていると、近くの人が二人近付いて声をかけている様子だったが、その中の一人が119番に通報したらしく、間もなくサイレンをけたたましく鳴らして救急車が来て、倒れた男女を乗せて走り去った。
信号が変わると、急ブレーキをかけた乗用車はそのまま交差点を左折して飯田橋方面に走り去り、倒れたバイクだけがその場に残されていた。走り去った車の映像も美登里のカメラにバッチリ撮影されていた。少しして、パトカーがやってきて、119番に通報したらしい二人に何やら聞いているらしく、他の警官がスリップ跡などを現場検証してからバイクを舗道の脇に立てかけて、パトカーも走り去りあたりは何もなかったようになった。
美登里が気が付いた時は午前三時過ぎだった。
「今夜はすごい特種が撮れたな。明日YouTube にアップしよっと」
美登里はいましがた目の前で起こった出来事を思い出して嬉しくなっていた。
四谷の伯母の所に帰ったら、
「美登里さん、あなたは大切な預かりものですよ。いくら遅いたって、こんな時間に女の子一人歩いていてはいけません。次に同じことがあったら許しませんよ。何かあったらどうするのっ!」
とこってり絞られた。美登里は台風が過ぎ去るのを待つかのように首をすぼめて小さくなっていた。
九 加奈子の嫉妬 Ⅰ

沙希が六本木のラ・フォセットに勤め始めてから、早くも一ヶ月以上が過ぎた。最初の給料は途中入社なので日割り計算されていたから、いくらもなかったが、二回目は辞令通り支給額は八十五万円だった。だが、手取りを見てビックリした。七十万円と少ししかないのだ。明細を見ると、所得税源泉徴収額、厚生年金保険、雇用保険などがごっそりと差し引かれていた。
「へぇーっ? こんなに引かれちゃうんだ」
沙希は町工場でもらっていた給料が十二万五千円だったから、税金はゼロ、保険もわずかだったから、予期していなかった。考えて見ると、同年代のOLさんの三倍近くの金額だ。税金や保険が高くなるわけだと納得せざるを得なかった。世間で所得税が高すぎるなんて話はよく聞いていたが、ついこの前まで、沙希は全く実感がなかった。
ラ・フォセットで接客係りを務め始めて、最初はリーダーの辻村初枝の後をくっついて回ったが、沙希は直ぐに慣れて、今では一人でちゃんとお客様の応対ができるようになった。沙希は真面目に働いた。この仕事では、
「お客様への気配りと気遣いが一番大切よ」
と教えられていたから、それをきちっと守り、手抜きはしなかった。
最初はニューフェースだと紹介されてちやほやされたが、半月も過ぎると顔見知りの客が増えてきて、これからは実力の勝負だと思っていた。
接客係の女の子たちは、客に頼まれて、仕事が終わってから店外で逢うことは許されていた。ただし、店外でトラブルが発生しても店は一切無関係だと言う決まりはあった。それで、大抵の女の子はこの人と思う客の希望に応じて、オフの時に客と付き合っていた。仕事が仕事だから、当然客はHをすることも含んでいると暗黙の了解があった。
沙希は章吾に恋をしていたから、客の誘いをなんとかかわして、客と店外で逢うことは一度もなかった。だが、そのことで沙希の人気が一気に盛り上がった。何人かの客は、
「僕が必ず沙希さんを堕として見せる」
と張り合って、何かと沙希に取り入ろうと、プレゼントを持ってきたり、口説いたり、兎に角沙希に熱を燃やしたのだ。
沙希が入る前に店内のトップレディーは岩井加奈子と言う子だった。接客係の中では一番綺麗で魅力的だと言われて、加奈子を口説く客は多かった。だが、沙希の人気が盛り上がり、加奈子の存在が薄れてきた。加奈子は負けず嫌いだったので、これには腹が立った。
「沙希のやつ、それほど綺麗でもないのに、ただちょっと可愛いだけでのぼせ上がっちゃって」
加奈子はいらついた。
沙希は最近ロッカーのネームカードが逆さになっていたり、いつも使っている歯ブラシがゴミ箱に捨てられていたり、変なことがあるのに気が付いていた。だが、誰かがたまたま間違えたんだろうと、気にも留めなかった。しかし、加奈子が店の中で沙希のドレスの裾を踏んづけて通路に転倒してしまったとき、加奈子の意地悪だと気付いた。沙希は一番年下の新米だったので、我慢した。加奈子の意地悪はその後も続いた。沙希のヒップにルージュでいたずら書きをされて、客にやんやと笑われて恥ずかしい思いをさせられたり、さりげなく、テーブルから下げた汚れた器を沙希のドレスにぶつけて汚されたり、段々とエスカレートするようだった。だが、この様子はリーダーの辻村初枝がちゃんとチェックしていた。
「沙希さん、ちょっと」
「はい」
沙希が辻村に呼ばれて行くと、
「あなた、最近加奈子さんに意地悪されているわね。この世界ではよくあることなの。あなたはまだ入って間もないから我慢して下さいね。我慢できないようなことがあったら、直接加奈子さんにおっしゃらずに、わたくしに話して頂戴」
「はい、分りました」
その後、辻村が加奈子に注意したのかどうかは分らなかったがしばらく加奈子の意地悪はなかった。
「あなた、沙希さんに意地悪してるわね。わたくしの目は誤魔化せないわよ」
辻村初枝は加奈子を呼んできつい目で注意した。
加奈子は傷付いた。加奈子は沙希が辻村にちくったのだと思っていたのだ。それで、何とか沙希に仕返しをしてやろうと画策した。
「あたしの店に島崎沙希って言う新入りがいるのよ。そいつ、生意気だから痛めつけてちょうだい」
加奈子は付き合っている男に頼んだ。男は工藤と言う名前だった。それで、工藤は沙希の行動や住まいを調べてから、ダチを誘って、帰り道に怪我をさせてやることにした。沙希は店の猪俣章吾と言う奴に帰り道毎日バイクで送ってもらっているのが分かったから待ち伏せしてすっ飛ばしてやることにしたのだ。
最初、猪俣と島崎が乗ったバイクの後を尾行して彼等がいつも通る道を調べた。
店が終わると、バイクは首都高の下の一般道を溜池に向かって走り、溜池で左折して外堀通りに沿って走っていた。赤坂見附で青山通りの陸橋を潜って直進して、四谷から市ヶ谷へと外堀通りに沿って走っていた。飯田橋交差点で外堀通りを左折して、目白通りに沿って走っていた。バイクは江戸川橋交差点を右折すると、直ぐに目白坂下で左折して目白通りを走っていた。そのまま山手線をまたぐ陸橋を過ぎて、なおも直進して、山手通りに交差すると、板橋方面に右折して、一つ目の交差点を左に折れて住宅地に入った。椎名町駅前の住宅地だ。
工藤と仲間の乗った乗用車はそこまで尾行すると、尾行をやめて戻った。
目白坂下から山手通りまでの間に、バイクは急にスピードを落して自分達の車の後ろに付いた。だが、バイクは直ぐにスピードを上げて追い越して行ったので、工藤たちはそのまま尾行したのだ。
章吾は目白通りに折れた時に、尾行してくる乗用車に気付いた。それで、明治通りの交差点を渡ってすぐにスピードを落して、乗っている奴等と乗用車のナンバーを記憶してから直ぐにスピードを上げて追い越したのだ。もちろん、章吾は沙希には何も言わなかった。
十 加奈子の嫉妬 Ⅱ
猪俣章吾は、グループの女の子には平等に優しかった。初めて沙希に出逢った時沙希はいきなり、
「あたしを守って下さい」
と言い、
「章吾がどうして自分なんだ?」
と自分が選ばれた理由を聞いたら、
「一番強そうだから」
とも言った。章吾はその時の沙希の言葉を忘れてはいなかった。けれども、章吾は最近若者に多い草食系の感じで、最初は沙希に特別な感情を持ってはいなかった。だが、ラ・フォセットに沙希が入社して、一ヶ月以上になるが、沙希は随分綺麗になり、魅力的に変身していた。そのため、日毎に沙希を意識するようになっていた。毎晩バイクに乗って、章吾の後から抱きついてくる沙希が特別に可愛らしく思えるようにもなった。
女は恋をすると綺麗になると言われる。確かに沙希は章吾に恋をしていた。だが、それだけでなくて、毎日メイクさんに綺麗にしてもらい、エステのようにボディーを磨いてもらっていた。しかも、ここのとこ茶道や華道のスクールに真面目に通って、日常の所作が美しくなってきた。
女は磨かれれば綺麗になれるとは良く言ったものだ。
見知らぬ乗用車に尾行されていたことを認識した翌日、沙希を載せて帰るためバイクを出すと、その車はその日も六本木から後をつけてきた。どこにでもあるような特徴のないクラウンアスリートでナンバーは袖ヶ浦35X・XXXXで昨夜の車と同じだった。それで、章吾はバックミラーで尾行車をチェックしながら、ゆっくりと外堀通りを走った。
夜中の二時半頃だから、車は昼間よりまばらで走りやすかった。章吾のバイクが四谷を通り過ぎて二つ目の交差点を緑信号で通過する寸前に、白いワンボックスカーがいきなり交差点に飛び出して、急ブレーキをかけて停止した。スピードが出ていなかったから、章吾は咄嗟に避けて通り過ぎる余裕があった。だが、バイクの後部が飛び出した車にかすって、バランスを失い、あっと言う間にスリップして転倒してしまった。
この時、章吾は無意識に左腕で後ろの沙希を抱き押さえて、そのまま路面に倒れ、スリップして舗道の縁石に当たって止まった。そのため、転倒する時路面に左肩をぶつけ、そのままスリップしたので、革ジャンの肩の部分が摩擦熱で溶けてボロボロになるほどで、縁石に頭をぶつけて、一瞬失神していた。
救急車で病院に運ばれ、検査を受けた結果、章吾は左肩打撲で十日間の入院後、リハビリに半年は必要だろうと診断された。沙希は本当に奇跡的だが、章吾に守られてかすり傷一つ無く、一応検査を受けたが直ぐ帰宅を許された。それで、その日午前中いっぱい、沙希は章吾の看病をしていた。
その日、工藤は友達四人の内工藤ともう一人はクラウンアスリートに乗り、工藤の友達篠原ともう一人は別のワンボックスカーに乗ってもらい、四谷小学校横の道で待ち伏せしてもらうことにした。お互いは携帯で連絡を取り合い、タイミングを計ってバイクが交差点に入った時に跳ね飛ばす計画だった。
女の子を後に乗せたバイクはゆっくりと外堀通りに沿って工藤の車の少し前を走っていた。工藤は昨夜も今夜も尾行に気付かれていないと判断していた。
「よしっ! 今だっ!」
工藤の隣の助手席に座っている男がワンボックスカーに携帯で合図を入れた。工藤は速度を落して前方を注視した。その時、予定通りバイクは転倒して、二人の男女が舗道に向かって滑って止まるのを確認した。信号が変わると、ワンボックスカーは左折して市ヶ谷方面にスピードを上げて走り去った。工藤も事故を確認すると、そのまま走り去った。
「加奈子、予定通り跳ね飛ばしたよ。当分あの女、店には出られないと思うよ。怪我の状況によっては身体の傷で店を辞めちゃうことになるかもね」
工藤からの期待通りの連絡に、久しぶりに加奈子はスキッとした気分になった。
「リョウ君、ありがとう。警察は心配ないの?」
「見た目オレたち関係ないし、跳ねた篠原も見付からないと思うよ」
「そう。近い内にお友達四人一緒に美味しいものをご馳走させてね」
十一 加奈子の嫉妬 Ⅲ
章吾が入院して、検査を済ませ、病棟に移された所で、四谷警察署から警官が二人やってきた。一人は年配で一人は若かった。
「事故関係の話を聞かせて下さい」
年配の警官が章吾の様子を見てから話し出した。
「オレのバイクにぶつけて逃げた車、見付かったんですか?」
と章吾が聞き返した。
「あんたね、信号無視をして事故を起こしといて何言ってんだよ」
警官の態度が急に横柄になった。
「えっ? オレがですか?」
「あんたたちが事故を起こした時、119番に通報した人に聞いたんだがね、あんたが交差点に侵入した時は、赤信号だったと証言があるんだよ」
「そんなはずはないっす。オレ、バイク乗ってて赤で交差点に入ったことは一度もないっす」
「今回はなぁ、証人も居ることだし、あんたが信号無視したのは間違いがないんだ」
「冗談じゃないですよ。オレたち被害者ですよ」
「信号無視して交差点で事故を起こしたら加害者だよ」
「だったら何故オレにぶつけた車が通報しないんですか? 可笑しいじゃないですか?」
章吾は警察の言い方にむかついた。
「あんた、あんまり変なことを言い張ると、信号無視の他に公務執行妨害で逮捕もできるんだよ」
と年配の警官は脅した。章吾はこれ以上警官と争っても仕方ないとあきらめた。すると、若い警官が、
「主任、119番に通報してくれた人は[確か]赤だったと[思う]と言ってましたから、正確ではないかも知れません。それに、ぶつけられて110番をしなかった相手も可笑しいと思いますが」
と遠慮がちに言った。
「お前は黙ってろ。話しがややこしくなる。大体バイクに乗ってる奴等は信号無視する奴が多いんだ。今回もこの猪俣が信号無視したんだよ」
そう言って年配の警官が調書に署名しろと言ったが章吾は頑なに拒否した。
「あんたなぁ、大人しくサインした方があんたのためになるんだ。気が変わったら、退院してからでもいいから、署に来なさい」
そう言い置いて警官は帰って行った。
警官が病室を出て行くのをぼやっと見ていた沙希は急にはっとなって、病室を飛び出し、警官の後を追った。沙希は若い方の警官に追いつくと、
「すみません」
と声をかけた。警官が振り向いた。
「失礼ですが、お名前を聞かせて頂けませんでしょうか?」
若い警官は沙希の顔を覚えていた。
「あっ、先ほどの猪俣さんと一緒だった方ですね」
「はい」
「わたしは広田と言います。四谷警察署の交通課にいます」
と警官は答えた。
「ありがとうございました」
沙希は病室に戻った。
沙希は章吾に促されて、その日の夕方ラ・フォセットに出勤した。事故のことは章吾が上司に連絡するから何も言わないでくれと言われていたから、ラ・フォセットには何も報告しなかった。
沙希がいつも通り出勤すると、岩井加奈子とすれ違った。沙希は加奈子が沙希の顔を見て驚いた様子ですれ違った後、
「あれっ? おかしいな」
と呟くのを聞いてしまった。すると加奈子が戻ってきて、
「沙希、夕べも店の男の子に送ってもらったんじないの?」
と聞いた。
「……いいえ」
沙希は一瞬考えて、
「いいえ」
とはっきり答えた。加奈子とはそれだけの会話しかなかったが、メイクで背中をケアしてもらっている間、何か分らないけれど、視線を感じていた。
加奈子は沙希がメイクをしている間、腕とか外から見える部分に怪我をしてないかちらちらと横目で見ていた。だが、どう見ても全く傷はない様子だった。
「やはり、沙希は夕べバイクに乗ってなかったんだ。じゃ、後に乗ってた女は誰だったんだろう?」
加奈子は不思議に思った。工藤の報告では相当派手に転倒した様子だったから、もしかして別の女が乗っていたのかも知れなかった。それで、店の女の子たちにそれとなく注意を払ったが、誰も事故に遭遇したらしい者は居なかった。
「あいつ、もしかして店に関係のない別の彼女を乗せて走っていたのかも」
加奈子はそれしか考えられなかった。
日曜日にモモからメールが入った。
「ショウゴが事故ったらしいのよ。それで、今夜仲間揃って章吾のお見舞いに行こうって約束になったの。あなたも来ない?」
沙希は仲間には連絡を入れてなかったから、沙希が事故で一緒だったとは知らなかったようだ。事故の知らせはサングラスのサトルから入ったらしい。
池袋のロマンス通りに沙希も入れて仲間六人が揃った所で、花束と果物を買って章吾が入院している病院に行った。章吾は大分良くなって、ベッドから起きて歩けるようになっていた。だが、肩から胴まで包帯で巻かれて痛々しい感じだった。
加奈子は工藤に電話した。
「この前、店の子を吹っ飛ばしてくれたって言ってたけど、あれ、別の女の子だったみたいよ。彼女はぴんぴんしてるわよ」
「変だなぁ。店から出て来て乗ったのも確かめてあったんだけどなぁ」
「だからさ、失敗したのよ。ご馳走する話はオアズケね」
「そんなバカな」
「それより警察の方はどうなのよ?」
「そっちは全然。多分わかんねぇと思うよ。車は二台とも千葉の袖ヶ浦ナンバーだし、分かりっこないよ」
「ならいいんだけど。様子見に行くわけには行かないし」
加奈子のいらいらはまた始まった。
十二 加奈子の嫉妬 Ⅳ

沙希たち六人が章吾をお見舞いに行ったら、少し遅れてサングラスのサトルが六人男を引き連れて見舞いにやってきた。それで、章吾の周りは急に賑やかになった。
「えっ? 兄貴が信号無視だって? 兄貴がいつも信号をきっちり守ってるのはオレたち全員知ってます。理不尽だなぁ」
「みんなに心配かけて申し訳ない。オレ、納得できないことは絶対に譲らないから大丈夫だよ」
「いつ退院できるんですか?」
「あと三日ここに居ろだってさ」
沙希は本当は一人で章吾の看病をしたかった。けれども、仲間と一緒でないとあとで拙いことになるかも知れないと思って、お見舞いは仲間と一緒に来ることにした。
今日の仲間ではないが、章吾の友達の中で、オヤジが弁護士事務所をやっている奴がいた。章吾はその友達に電話して、警察と争う時オヤジに弁護を頼みたいと頼んでいた。その返事がその日の午前中に届いた。もちろんOKだった。それで、章吾は警察と戦おうと心に決めていた。
章吾の退院は午前中だったので、沙希も退院する時一緒だった。章吾は退院したその足で、四谷警察署を訪ねた。
「広田さんをお願いします」
交通課に行くと沙希が名前を聞いておいてくれた若い警官の広田を呼び出してもらった。
「色々お世話になりました。彼、今日退院しました」
と沙希が広田に挨拶した。
「ちょっと待って下さい」
広田はこの前主任と呼んでいた年配の警官を連れてきた。
「おうおう、サインをする気になったか」
年配の警官はにこにこして章吾に近付いた。
「いえ、サインはしません。そのことで話に来ました」
「えっ?」
二人の警官は意外だと言う表情をした。
「オレ、信号無視はしてませんから、この件は、そちらで起訴して下さい。オレもあんたを訴えさせてもらいますから」
「猪俣、それはどう言うことだよ」
年配の警官の顔色が変った。
「ですから、法廷できっちりとかたをつけさせてもらいます。オレの友達のオヤジが弁護士で、弁護を頼んであります。オレが信号無視をしたと証言したやつを法廷に証人として連れて来て下さい。そいつを弁護士からきっちり尋問してもらいます。オレははっきりと青信号を確認して交差点に入りました。そっちの目撃者がオレが赤で侵入したと言うなら、どっちかがウソをついてるのと違いますか? オレは絶対にウソは言ってません。だから、そっちの証人が自分は正しいですと言い張るなら法廷で白黒付けるっかないでしょう。あんたはオレの言うことを聞かずに、その証人を信じてオレを信号無視で罪人にしたんだから、オレはあんたも訴えます」
年配の警官は青筋をたてて怒った顔で聞いていた。その警官は長い警官生活の中で、こんなことを言われたのは生まれて初めてだったのだ。それで、その警官は返す言葉を失っていた。
章吾は広田に、
「事故る前の日と事故った日の二日間、このナンバーの車がオレを尾行してました。事故に関係あるのかないのか分かりませんが、オレ、運転していた奴の横顔も覚えてます。調べてもらえませんか?」
広田は車両の番号が分っているので、一応調べてみると請合ってくれた。
章吾と沙希が立ち去ると、年配の警官は直ぐにその日現場検証した時に立ち会ってくれた119番を通報した男に電話した。生憎電話が繋がらなかったので、連絡先を留守電に入れておいた。
夕方七時頃、目撃した男から電話がきた。年配の警官が電話に出ると、
「何かご用でしょうか」
と尋ねた。
「先日バイクの事故に立ち会ってもらった件ですが」
「はい」
「あの時、バイクは赤信号で交差点に進入したと証言されましたよね」
「はい」
「それを法廷で証言してもらえませんか?」
「えっ? 冗談じゃないですよ。私はあなたが赤信号だっただろ? とおっしゃるから、はいと答えましたが、自分は事故になった瞬間は見ていませんから、確か赤だったと思うと訂正したはずですが。法廷で証言してくれなんて、引き受けられません」
警官は困ったことになったなと思った。
「すまんけど、あんたが赤だったと言ってくれればそれではっきりするんだけど、赤でしたと言ってもらえんかなぁ」
警官は男に頼み込んだ。
「済みません。私は自信がないですから、お断りします」
警官は脅しに出た。
「あんたなぁ、そこまで言うなら偽証罪でしょっぴくこともできるんだよ」
「……」
「じゃ、証言してくれるんだな?」
「……」
「どうなんだ?」
電話の向うの男は考えている様子だった。それで、
「分りました。法廷で証人になりますが、その時の様子を正直に話をします。多分私の話を聞けば、赤だったか青だったかはっきりとしないと思われても仕方が無い結果になりますが、それを承知して頂けるなら応じます。でも、赤とは絶対に断言はしませんから」
年配の警官はこれじゃヤバイと思ったが、どうすることもできなかった。そのやり取りを広田が心配顔で見ていた。
「主任、本件は悔しいですけど、猪俣に頭を下げて告訴を取り下げてもらった方がいいと思いますが」
いつもは、
「お前は黙ってろ」
と言うのだが、その日は言えなかった。
二日後、年配の警官から章吾に電話がきた。その日は口調は穏やかだった。
「この前の件だが、目撃者に再度確認した所、あんたの方が正しいようだ。それで、あんたは信号無視はしてないので被害者と言うことになるんだが、了解してもらえないかなぁ。信号無視と決め付けたことは謝るよ」
章吾はあの石頭の年配の警官があっさりと取り下げたのを不思議に思った。だが、被害者になるなら文句はない。それで、
「分りました。それじゃ、オレに車をぶつけて逃走した奴を捜査して逮捕してくれるんですね?」
「そう言うことになるなぁ」
「それじゃ困ります。オレの方は治療費やバイクの修理代、休業補償、慰謝料とかを全部見てもらわんと納得できないですから、逮捕するとはっきり言って下さい」
「分った。逮捕するように全力をあげる」
警官は章吾に完敗してしまった。
年配の警官と広田警官は、運良く章吾がサインを拒んだため、まだ調書が保留だったことに気付いた。それで、章吾の話を証言として取り上げて、当て逃げ事故として作り直した調書を上げて捜査を開始した。だが、日が経っており、事故が夜間だったので、現場の聞き込みをしてもなかなか情報が取れなかった。これには稲本と言う主に捜査の仕事を分担している警官(刑事)が加わって仕事を手伝ってくれた。
稲本刑事はベテランだった。それで、広田が聞いていた尾行していた不審車の情報に興味を示した。
十三 加奈子の嫉妬 Ⅴ
稲本刑事は四谷小学校の交差点付近を聞き込みに回ったが、手がかりが掴めずに居た。今回は猪俣の信号無視による自損事故と決め付けたために、初動捜査を失敗したと言っても良かった。稲本は猪俣の了解を取って壊れたバイクを入念に調べた。その結果、バイクの左側は転倒時のスリップで大きな擦り傷がいっぱい付いているが、猪俣の話の通り、後部にスリップとは方向の違う擦り傷が付いていて、明らかに車両との衝突で発生した擦り傷だと思われた。傷跡を良く観察すると、スリップによる傷は衝突による傷の後から付いたものと判明したので、猪俣の言う通り、バイクの後部に衝突後にバイクが転倒してスリップしたものと推察された。バイクに付着していた僅かな塗料片を採集して鑑識に回した所、乗用車に使われている塗料と判明したが、相手の車両の種類やメーカーまでは解析できずにいた。
猪俣章吾の仲間にポチと呼ばれているパソコンおたくが居た。やや太り気味で丸っこく、走る姿が子犬のようだと言われ、やがてポチと言うあだ名が付いた。本人も気に入っている様子だ。そのポチがYouTubeにアップされた[目撃]と言う題名のバイク事故の動画を見つけた。それで、近くのネットカフェにみなで集まって動画を見た。上手に撮れていて、どうやらショウゴの事故を連想させた。仲間達はショウゴが沙希を後ろに乗せていたとは知らなかったから、二人乗りのバイクなので、ショウゴではないと思った。だが、沙希だけは、この動画を見た時、自分と章吾だと確信した。沙希はみんなの気持ちを考えてその日章吾の後ろに乗っていたことは伏せていた。もちろん、章吾も言わなかった。
「ポチさん、この動画、誰が投稿したか分かるの?」
沙希はポチに聞いた。
「投稿者のコードネームは出てるけど、その人がどこに住んでる誰だってのは分らないな」
「警察で調べても?」
「ん。よほどの大事故だったら警察がYouTube の管理人に情報提供を要求すれば出すかも知れないけど、普通は警察にも情報は出さないと思うよ。もしも警察に情報が漏れることが分かったら、ヤバイ内容の動画は絶対にアップされなくなるからね」
「そうなんだ。ダメかぁ」
沙希はがっかりした。
沙希はSNSに会員登録をしていて、時々日記を更新していた。町工場に勤めていた頃、事務の仕事でパソコンを使っていたから、その頃は会社のパソコンを使わせてもらって、時々ネットナビをやったり、SNSの日記の書き込みをやっていた。今はパソコンを持ってないので、たまにネットカフェに寄って更新していた。
沙希は仲間と別れて一人になった時にネットカフェに寄って、事故の事、YouTube の[目撃]と題する動画のURLをアップして、誰かこの事故のことについてご存知ならご連絡を下さいと自分の日記に書き込んでアップした。転倒したバイクの後に乗っていたのは自分だとも書いた。そうすると、二日経ってから、沙希のネット友達から日記に書き込みがあった。自分のネット友達で、同じ動画をアップされている方が居ますと書かれていた。沙希は自分のネット友達にメッセを送った。
「こんにちは。コメ、ありがとう。チビさんの動画をアップされた方のHNを教えて下さらない?」
それで、チビさんからメッセが届いた。動画は鎌倉在住のみどりの森さんご自身が撮影したものだとも分った。
沙希はこのビッグな情報に飛び上がるほど興奮した。メッセージを交換している内に、[みどりの森]さんは大妻女子大の四年生で、主に四谷に居ることが分り、早速会ってもらう約束をしてもらった。
みどりの森さんの本名は、藤井美登里さんだと分かった。その日、四谷で沙希と藤井はスタバでお茶した後、四谷警察交通課の広田に電話をして、
「広田さんに見てもらいたいものと、会って欲しい方が居るの。お手数をおかけしますが、ネットカフェまで来てもらえません?」
と電話した。広田は、
「いいですよ」
と快く応じてくれた。
広田がネットカフェにやってきた。その後の捜査の状況を聞くと、職務上話してはいけないのだが、内緒でと前置きして、全然進んでいないと答えた。
広田は藤井美登里の話を聞いて、動画を見てビックリした。動画は綺麗に写っていて、信号が赤でワンボックスカーが進入したことや、左折する時の映像を拡大すると、袖ヶ浦X3XX・XXXXと番号もはっきり読み取れた。
広田は情報を持ち帰って稲本刑事に報告し、千葉県警の協力を得て、その日の内にワンボックスカーを運転していた篠原弘一と同乗の津村明彦の二人の青年を逮捕して取り調べた。
その結果、篠原の友人の工藤と言う男が話を持ちかけ、車の修理代と謝礼金五十万円を受け取っていたことが分かった。
「おまえらなぁ、おまえらがやったことは単なる過失の衝突事故じゃなくて、立派な計画的殺人になるんだぞ」
稲本は篠原たちから何故殺人を計画したのか、理由を聞きだそうと努力したが彼等からは聞き出せなかった。それで、殺人を依頼した工藤を逮捕して締め上げた。
「お前、事故のあった日、どこに居た?」
「習志野市内のボンと言うスナックで一時過ぎまで飲んでました」
稲本は千葉県警に連絡、スナック[ボン]のママに任意同行してもらい、事情を聞いた。その結果、工藤に頼まれてアリバイ工作をしたことを白状したので、ママはその場で逮捕された。
稲本は、
「おいっ、工藤、お前やってくれたなぁ。スナックのママが全部白状したぜ。いい加減に降参したらどうだ」
工藤は堕ちた。それで尾行のこと、猪俣でなくて沙希を怪我させるためにやったと供述した。だが、何故沙希を狙ったのか、沙希と何らかの関係があるのかは、なかなか口を割らなかった。
取調べは翌日も続いた。
「お前、篠原にやった金はどっから手に入れた?」
「自分の預金からです」
稲本は工藤の預金を調べたが残高はわずかで、とても五十万円を渡せる余裕がないと思われた。それで、工藤の家宅捜査をすると、封筒に入れたままの五十万円が見付かり、封筒には100とボールペンで走り書きされていた。多分百万円だろう。
「この金、誰からもらった?」
工藤の答えは曖昧でのらりくらりと話を曲げた。それで、工藤の携帯を証拠品として没収して最近の通話記録を調べた。その結果、岩井加奈子と言う名前が浮き上がってきた。
「工藤、お前岩井加奈子を知ってるな」
「そんな名前聞いたことありません」
「バカ言えっ、お前さん携帯で最近何回も話をしてるだろ? 警察をなめんじゃねぇっ!」
稲本は更に工藤を締め上げた。
三日後、とうとう工藤は完全に堕ちた。
「工藤、最初から素直に白状してれば一日で終わったのに、手間をとらせやがって」
岩井加奈子は六本木のラ・フォセットに勤めているホステスだと分った。岩井加奈子は殺人教唆の容疑で、その日の内に逮捕された。
男女五人が共謀した怨恨による計画的殺人未遂事件だったので、翌日のテレビ、新聞に報道された。ただ、狙われた被害者の沙希と章吾の名前は実名ではなく、SとIとされていた。
加奈子は留置所の中で、沙希を恨んだ。ハラワタが煮えくり返る位だとはこのことだ。おまけに、加奈子はラ・フォセットを解雇されてしまった。
篠原が加入していた自動車保険金が適用されず、章吾は篠原自身に損害賠償を請求せざるを得なくなった。だが、友人の父の弁護士が保険会社とうまく交渉してくれて、結局わずかな慰謝料の他に入院治療費やバイクの修理代は受け取ることができた。もちろん、沙希にも僅かな慰謝料が出た。沙希はそれを全部章吾に渡した。
こうして、加奈子の嫉妬による事件は一段落した。
「美登里さん、ほんとうにありがとう。お陰で、彼は救われました」
沙希は美登里に心からお礼を言った。
このことがきっかけで、沙希と森ガール美登里は親しい友達となった。
十四 罠 Ⅰ
岩井加奈子がクビになり、沙希は六本木のクラブ、ラ・フォセットで一番人気の接客係として安定した地位を得た。当然のことながら、次の給与から昇給された。
沙希と四畳半のボロアパートに同居しているスペイン系のマリアは、沙希が教えた日本語が上手くなり、
「沙希のお陰で、就職試験の面接でうまく答えられるようになったわ」
と喜び、そうこうしている間に丸の内にある貿易商社に採用が決まった。
カトリーヌも同様に日本語が達者になって、面接試験が受け易くなり、西新宿にある機械メーカーの本社に秘書として採用されたと電話をしてきた。
沙希とマリアの収入が安定する見通しが付き、二人で相談してもう少しましなアパートに移ることにした。
最初はメトロ有楽町線の南池袋界隈とメトロ丸の内線の茗荷谷界隈で手頃な家賃のアパートを探したが、山手線の内側は家賃が高く、結局山手線の外側の池袋から一駅先のメトロ有楽町線の要町駅から歩いて七分位の六畳二間のアパートに決めた。前はシャワーも風呂も付いてなくて、銭湯通いだったが、今度は小さなユニットバス付きだった。
加奈子が仕組んだ事件が新聞やテレビで報道されて、ロマンス通りの仲間の間で沙希は章吾の彼女だと皆が認めることになってしまった。だが章吾は、
「オレ、沙希とは特別な関係はねぇよ」
と否定した。皆は納得しなかったが、沙希は章吾の気持ちがまだ分らず、片想いの状態だった。
けれども章吾に、
「あたし、お引越しします」
と告げたら、章吾はサングラスのサトルとポチを連れて引越し手伝いに来てくれた。章吾にマリアを紹介する時、沙希はスペイン語でマリアに何やら話した後でマリアが日本語で自己紹介したので、章吾もサトルも驚いた。
「ずっと二人で住んでたの?」
とポチが聞くとマリアが、
「そうよ。サキはいい方だから」
と答えた。
沙希は古い小さな冷蔵庫などは大家に置いて行っていいと断ってあったので、荷物は少なかった。
新しく借りた要町のアパート移ると、ビッグカメラから冷蔵庫やテレビ、洗濯機などが指定した時間に届けられて来た。設置は男三人がやってくれて、中古のノートパソコンの設定とテレビの設定はポチが慣れた手付きでさっさと済ませてくれた。
男三人が部屋に運び込んだ家電やパソコンがインターネットにつながるように設定をしてくれている間に、沙希とマリアは近くのスーパーに食料品やビールを買いに出かけた。
男女五人は遅いお昼になったが、賑やかに食ったり飲んだりして、男が引き上げて行くと、
「やっと落ち着いたわね」
と沙希とマリアはそのままお茶にして夕方までしゃべって過ごした。
沙希は月給の手取りが百万を越えるほどになったが、贅沢はしなかった。今までの四畳半の暮らしを考えると、少しは人並みになったような気がしたが、アパートの家賃月額十万円を二人で折半することにしたのだ。沙希は今迄貧しい暮らしをしてきたので、これでも随分贅沢だと思っていた。
「近い内にカトリーヌを招待しない?」
マリアの提案でカトリーヌを呼ぶことにした。
章吾はまだバイクで通勤するのが無理のようだった。ラ・フォセットの仕事には出ていたが、帰りは終電か終電に間に合わない時は沙希が帰るまで待っていて、一緒にタクシーで帰った。
その日も章吾は終電に間に合わなかったので沙希と帰る予定にしていた。沙希が仕事を終わるのは大体午前二時頃だ。六本木から池袋までは深夜だとタクシー代は概ね四千五百円位になる。沙希は高給取りだから毎日タクシーでも良かったが、章吾は予算的にとても毎日はタクシーで帰れなかった。それで、遅くなるとなるべく沙希と一緒に乗せてもらって帰った。バイクの時と同様に、沙希は章吾と一緒に帰る時が至福の一時になっていたのだ。
沙希が仕事を終わって店を出てくると、大抵章吾が沙希を見付けてくれた。だから、沙希は章吾を探さなくても直ぐに章吾と一緒になれた。
その日も沙希は仕事を終わって店を出た。店の前にはいつも店から出てくる客を拾おうと空車のタクシーが何台か停まっていた。沙希は今日は章吾が直ぐに来ないので、もしかして先に電車で帰ったのだと思った。
それで、空車のタクシーを目で追うと、列の後方から急に空車の一台が沙希の前に近付いてきて、運転手が降りてきた。運転手が降りてくるなんて初めてだ。
「島崎さんでいらっしゃいますよね」
「はい、そうですが?」
運転手は沙希の名前を確かめると、
「猪俣さまは先に帰られました。どうぞ」
と言ってドアを開けた。
沙希が乗り込むと直ぐにタクシーは走り出した。今迄、同じ運転手だったことが何回かあって、行き先を告げずとも黙って椎名町まで送ってくれるタクシーもあったので、沙希は別に不審には思わなかった。
タクシーが走り出すと、直ぐ首都高速に入った。
「運転手さん、もったいないですから高速でなくて普通の道を行って下さい」
この時間帯に走るタクシーはやたらと高速を使いたがる。それで、沙希はいつも高速を使わないでくれと一言声をかけるようにしていた。普通は高速に乗る前に必ず、
「高速を使わせて頂いてもいいですか」
と聞くものだ。だが、今日の運転手は沙希の話に返事もせずに高速を走った。
高速を走り出して直ぐに、沙希はタクシーが反対方向に走っているのに気付いた。
「運転手さん、方向が違うんじゃないですか?」
「……」
運転手は無言で高速を飛ばした。タクシーは両国ジャンクションから小松川線(首都高7号線)に折れて、千葉に続く京葉道路を目指して走った。沙希は何か不安になってきた。小松川線に入ると直ぐに、タクシーは錦糸町で高速を降りた。
その日、章吾は沙希が仕事を終わって店を出て来るのを待っていた。
「あれ? 見落としたかな?」
午前二時半になっても沙希が出てこないので店に入ってみた。店の者は殆ど帰った後で、運良く接客係のリーダーの澤田が残っていた。
「澤田さん、島崎さんはまだ仕事ですか」
「あら、猪俣君珍しいわね。沙希さんならとっくに帰ったわよ」
「参ったなぁ」
と章吾は呟きながら、店を出てタクシーを拾って一人で帰った。
十五 罠 Ⅱ
東京江戸川区小岩から錦糸町一帯にキャバクラ三軒、パチンコ屋五軒を営業している株式会社ゴールデンバード・エンタプライズがある。社長は七十過ぎの老人で米倉源蔵と言った。米倉は若い頃は暴力団の舎弟だったが、取締りが厳しくなり組が解散させられたのを機会に組を外れて小岩で小さなパチンコ屋を開業した。開業当初は営業成績が思わしくなかったが、パチンコ台が自動になった頃からギャンブル色が濃くなって、ギャンブラーの間で稼げる店と言う評判を取り、業績を伸ばした。源蔵には若い頃キャバレーでホステスをしていた睡華と言う彼女が居たが、パチンコ屋の業績が軌道に乗った頃、彼女を嫁さんにした。睡華は源氏名でなくて彼女の本名だ。
しばらくの間、源蔵と睡華の間には子供が出来なかったが、結婚して五年目に長男が誕生した。源蔵は長男に魔神と言う名前を付けた。睡華は粋で綺麗な女だった。それでか、魔神もなかなかのイケメンの男に育ち、現在ではオヤジに代わって実質的にゴールデンバード・エンタプライズを取り仕切っていた。源蔵の遅い子だったから、魔神はまだ三十代後半だ。
魔神は時たま子分を引き連れて六本木のラ・フォセットと言うクラブに顔を出していた。通う内に、ラ・フォセットで人気のあった岩井加奈子と知り合い、店が終わってから六本木界隈を連れ歩く内に加奈子を彼女の一人にした。魔神には他にも何人か付き合っている女の子が居たが、とりわけ加奈子を気に入っていた。魔神の子分の中に工藤、篠原、津村などが居て、いつの間にか加奈子は魔神の子分とも親しくなっていた。
加奈子は魔神に相談して、ラ・フォセットの沙希と言う女が気に入らないから、ちょっと痛めつけてくれと頼んだ。魔神はラ・フォセットに最近入った沙希も知っていた。魔神は沙希を何回も口説いたことがあるが、沙希は決して魔神の手に堕ちなかったから、沙希のことを[生意気なやつ]だと思っていたのだ。
それで、加奈子から頼まれた時、子分の工藤等四人に、
「お前等、加奈子と相談してラ・フォセットの沙希と言う女を適当に痛めつけて来い」
と指示したのだ。
「まったく、サツに上げられるなんて、ドジなヤロウだな」
魔神は工藤たちが失敗したのをニュースで知った。幸い加奈子までは警察にバレたが、魔神本人やゴールデンバード・エンタプライズなど背後関係までは警察が掴んでいない様子だった。
子分を四人と加奈子をサツに持ってかれて、魔神は腹が立った。それで、昨夜タクシーの運転手をやってる息のかかった男に、
「ラ・フォセットの沙希と言う女を拉致して来い。その子はいつも猪俣とか言う店のもんと一緒に帰るらしいから、猪俣から横取りすりゃ簡単だろ」
と持ちかけた。拉致に成功すれば、もちろん魔神から金がもらえる。
タクシーの運転手は、その日、まんまと沙希の拉致に成功した。
首都高速を錦糸町ランプで降りた沙希を乗せたタクシーはカトレアと言うキャバクラの前で停まった。事前に連絡を入れていたので、タクシーが停まると同時に店から、[黒服]以下若い男が五人バラバラと出て来た。タクシーの後部扉を開けると黒服が、
「出ろっ」
と言って沙希の腕をつかんで店の中に引き摺り込んだ。キャバクラなどで、店内を取り仕切っている男を黒服と言うのだ。
事務所に引きずりこまれると、そこに淡い色のスモークグラスをかけた背の高いちょっとイケメンの男が立っていた。仕立ての良いダークスーツでビシッと決めた姿はなかなか格好が良い。
「社長、連れてきました」
「どれ、沙希さんよ、顔を見せなよ」
と男は沙希の顎をつかんで顔を上げさせた。
「あんた、ここで見ると案外いい女だなぁ。オレの彼女にならないか? いい思いさせてやるぜ」
沙希はこれまで何度か口説かれたことがあったから、男の顔は良く覚えていた。
「どうなんだ? オレの彼女になるか? 断ってもいいぜ。断ったら、うちの店できつ~い仕事をさせてやるよ。あんたのいい方を選べよ」
「お断りします」
魔神は女に自信があったが、沙希だけは言いなりにならないので癪にさわった。
「わかった。今日からオレのとこで可愛がってやるから、せいぜい稼いでくれよ。おいっ、タツ、この女を店で使ってやれ。遠慮は要らんから、せいぜい稼がせろ」
「わっかりました」
黒服は沙希を店の方に連れて行った。
「言っとくけどよぉ、うちは賄い付きの寮制だ。二十四時間監視を付けてあるから、逃げ出しても無駄だぜ。逃げ出して捕まったら、うちの若いもんが輪姦して股から血を流して腰が立たんようになるまで可愛がってやるよ。逃げて何回も輪姦されてよぉ、最後にボロボロになって捨てられた女は今迄何人もいるんだ。オレたちを甘く見るなよ」
黒服は沙希に畳み掛けた。
新宿の歌舞伎町界隈のキャバクラは警察の指導が徹底していて、俗に言うお触りキャバ、ピンキャバなどピンクサロンやセクシーパブのように[手こき]や[抜き]はやらせない。だが、ゴールデンバード・エンタプライズではキャバ嬢に平然とそれをやらせていた。
巷では、同じ金を使うなら、歌舞伎町じゃなくて錦糸町界隈か横浜の日の出町界隈の方が楽しめると言う噂が流れていた。
「[抜き]って何ですか?」
「バカヤロー、あんたなぁ、六本木のクラブに居て[抜き]も知らねぇのかよぅ。フェラチオのことだよ。フェラチオは知ってんだろ?」
「……」
「ミルクは飲まなくてもいいぜ。おしぼりに吐き出してくれよ」
「言っとくけどな、成績が悪いと店が終わってから[お仕置き]があるからよぉ。しっかりと稼ぎなよ。お仕置きは逃げ出した時と同じだ。うちの若いもんが輪姦して可愛がってやるよ。分ったな」
「……」
沙希は覚悟を決めた。
十六 監禁キャバクラ Ⅰ
「うちの営業は夕方六時から十二時までだ。風営法があるからよぉ、0時には店を閉じるんだ。まあ帰りの客が残ってるから0時半に閉めるのが普通だ。夕方まで時間があるからよぉ、寮まで送ってやる。変な気を起こさずに大人しく仕事をしろよ」
そう言って黒服は沙希を車に乗せて寮まで送った。店は墨田区だが、寮は店から少し離れた江東区の大島と言う場所にあった。三階建てのアパートで、周囲に高さ3mのフェンスがあって、フェンスの内側に獰猛なドーベルマンが二匹、放し飼いにされていた。これでは、窓から逃亡しようとすれば、ドーベルマンに食い付かれて大変なことになる。女性なら脚がすくんでとても窓から逃亡するなんて怖くて出来ないだろう。玄関は二重の鉄扉になっていて、カギがないと出入りができない。扉は内側と外側と別の種類の錠が取り付けられていた。アパートの入り口を入って直ぐに管理人室があった。ここに閉じ込められた女達からみれば、管理人ではなくて監視人室だ。
「あんた、携帯持ってるだろ」
「はい」
「出せよ。こっちで預かっとく」
そう言って黒服は沙希の携帯を没収した。どうやら外部と連絡を取れないようにしているらしい。
「すみません、良く働いたらこの寮を卒業することはできるんですか」
「良く働かなくても卒業できるよ」
「どうすれば卒業できるんですか?」
「簡単だ。社長の彼女になれば卒業だ。社長に気に入られないやつはずっとここだね。使い物にならなくなったとき追い出されるけどよ」
沙希は目の前が真っ暗になった。この話しじゃ自分がボロボロになるまでこき使われるってことが分かったからだ。
管理人室の隣が広い部屋になっていて、食堂兼談話室のようになっていた。早朝だったから、中には誰も居なかった。
「ケイさんよぉ、新入りさんだ。名前は[サリー」にしたからよろしくな」
「あいよ。話は社長から聞いてるよ」
黒服から沙希を引き受けた管理人は、
「サリーさん、大人しく勤めればここはメシ付きの天国だよ。この部屋でメシが出るから、食いたい時にここに来て食ってくれ。時間は制限なしだ。メシの内容は評判がいいよ。ま、世間様よりはちょっと贅沢だな。果物は食べ放題だが、アルコールだけは朝の十時で打ち止めと決まってる。掟を破ったらお仕置きがあるから覚えといて。酔っ払って店に出られちゃかなわんからなぁ。それから、下着とか普段着はオレたちのとこに言ってくれれば買っておくよ。通販で買った場合はオレのとこに届くから連絡をするよ。風呂は掃除の時以外は二十四時間使っていいことになってる。共同風呂だがいいお風呂だよ」
管理人は一人ではなかった。腕っ節が隆々とした男が他に二人居た。どうやら万一を考えてガードマンの役目を兼ねている様子だった。
部屋は全部個室だからプライバシーは守られると思った。だが、それは浅はかな考えだった。部屋の中を良く見ると監視カメラらしき物が取り付けられていて、トイレにも付いていた。
十時を過ぎると賑やかになった。どうやら皆起きてきて、洗顔したり、風呂に入ったり、談話室でおしゃべりしていたり、それぞれ勝手にやっていた。誰かが沙希を紹介してくれるのでもなし、新入りの同居人としてはどう対応すれば良いのか分からなかった。
談話室に行くと十人くらいでおしゃべりをしていた。沙希は近付いて自己紹介した。
「今朝からここに入ったサリーです。よろしくお願いします」
皆が沙希の頭の天辺からつま先までジロジロ品定めをした後、
「あっそう。よろしくね」
と返事をした。すると年配の一人が、
「ここじゃボロボロにされて追い出される人が多くてね、しょっちゅう新しい人が追加されるから、新入りたって珍しくないのよ」
と言った。年齢は二十代から四十代前半まで幅が広かった。後で分ったことだが、店の照明が薄暗くてお客には顔をはっきりとは見られないから四十歳をちょっと越えていても三十歳ですで通るのだそうだ。
「下の方を可愛がってもらってる時、男は女の歳なんて気にはしないものよ」
沙希の顔を見て皆が笑った。
五時になると、皆普段着で玄関脇の談話室に集まった。総勢三十人以上はいた。間もなく、警察車両のように、窓に鉄格子を付けたマイクロバスがアパートの前に停まり、皆はぞろぞろとバスに乗せられた。逃げないように、監視人が三人、見張っていた。バスの中にも運転手の他に腕っ節の強そうな男が二人乗っていた。お仕置きの時、若いもんに輪姦させると言っていたが、どうやら輪姦する奴等はこいつらかと沙希は男たちを観察した。こんな奴等に次から次からやられたら、確かに腰が抜けてしまうかもしれないと恐ろしくなった。
店が始まると耳が痛くなほどガンガン音楽が鳴り、目が痛くなるほど照明がキラキラしていた。客は意外に多く、開店と同時に十人くらいの客が入ってきた。
沙希も覚悟を決めて真面目と言っちゃおかしいが頑張って仕事をした。ラストの客まで七人[抜いた]時にはすっかり疲れ果てた。若い客ですぐいく男がいれば、年配のオジサンでなかなかいかない男も居た。沙希は兎に角客を分け隔てなく丁寧に扱った。それでか、中には帰りがけに、
「ありがとう」
とお礼を言う客も居た。中には花びら三回転などと言って、二度いかないと気が済まない客も居た。この店はキャバクラと言いながら、やってる事はピンサロ(ピンクサロン)と同じだ。照明は時々ぱぁーっと明るくなるが、薄暗い方が長い。風営法で照明を暗くできないために、マヤカシでそんな仕掛けにしてあるらしい。
夜十二時半にはきっちりと店が閉まった。ホステスたちは全員例のマイクロバスに詰め込まれて寮に送られた。言って見れば戦争の捕虜に強制労働をやらせる収容所みたいな仕組みだ。
翌日十時頃監視人が、
「お仕置きをやるからみんな談話室に集まれ」
と各部屋に連絡して回った。
皆と一緒に沙希も談話室に行くと、営業成績が悪かったと言う三十歳前後の女が部屋の真ん中に座らされていた。女は泣いていた。
談話室の窓のカーテンが閉じられて薄暗くなった所で監視人の男や監視人とは別の男が合わせて五人部屋に入ってきた。
「おい、タマっち、お前なんでお仕置きされるか分ってるな」
「今日は体調が悪かったんです。許して下さい」
「ダメだ。体調が悪い時は出る前に申告するのが決まりだろっ」
男の一人がタマっちの着ているものを全部脱がして素っ裸にした。裸にすると男たちの輪姦が始まった。大勢見ている前だから、タマっちは恥ずかしさにワンワンと声を出して泣いた。だが、男たちは構わず次々と交代にマタっちを攻めた。
とうとう、タマっちはぐたぐたになって、文字通り腰が立たなくなってしまった。
「お仕置きは終わりだ。おいっ、お前等、お前等だって成績が悪いとこうなるんだ。覚えておけよっ」
沙希は背筋が寒くなり冷や汗が出た。
「可哀想に。地獄だね」
と呟く女も居た。
十七 監禁キャバクラ Ⅱ
沙希は何とか仲間に連絡を取ろうとした。だが、電話は監視人室にあるのしか使わせてもらえなかった。通販の電話注文などは特に問題がなく、テレビショッピング番組を見て電話で注文する者はいたが、私的な電話をする者は誰もいなかった。うっかり身内に電話したのがバレたら、あの地獄のようなお仕置きを免れない。
店に出て二日目、沙希は優しい感じの客に頼んで見ることにした。
「すみません、お店を出られてからこのメモの通り携帯にメールを一本送ってくださらない」
客はメモに目を通すと、
「いいよ」
と言ってメモをポケットの中にねじ込んだ。沙希はお礼も兼ねて、その男のものを優しく愛撫してやった。男は満足して、必ずメールをしとくからと言い置いて帰って行った。
沙希のメモには、
アドレス:satoru_kxxx@docomo.ne.jp
文:携帯は没収されてます。電話、メールはしないで下さい。錦糸町のカトレアに監禁されてます。助けて下さい。沙希
以上だった。章吾の携帯のアドレスは聞いてなかったが、サングラスのサトルのアドは覚えていた。それで、サングラスのサトル宛てに送信してもらった。
サングラスのサトルは本名栗山智だった。サトルは引越しの時にマリアに会って、すっかりマリアに惚れてしまった。一目惚れだ。マリアの方がサトルよりも五歳位年上だったが、マリアは人懐っこい可愛い感じだったので、歳の差を意識させなかった。スペイン人のマリアはラテン系で情が厚い。そのためかサトルはすっかりマリアの虜になっていた。
それで、引越しの時以来、サトルとマリアは数回もこっそりデートをしていたのだ。土曜日のその日のお昼過ぎ、サトルとマリアはJR山手線目白駅を降りて、学習院大学とは反対方向に数百メートル歩いた所にある、目白の森公園でデートをしていた。閑静な目白の住宅街の中にあるこの公園は広くはないが、昼間二人でこっそりとデートをするには最適だ。開園時間は午後四時までだから、夕方のデートはできない。
「一昨日から沙希が家に戻らないの。サトル、何か聞いてない」
マリアはいつも夜中に必ず帰ってくる沙希がアパートに帰らず、何も連絡がないのでおかしいと思っていた。サトルは誰か知らない奴から沙希の伝言らしきメールを受け取っていた。内容がかなりヤバイ感じだったので、直ぐにショウゴに電話で知らせておいた。ショウゴは、
「沙希のやつ、店を無断欠勤してるから、おかしいなと思ってたんだ」
と言っていた。
そのことをサトルはマリアに説明した。
「サキさん、大丈夫かしら」
マリアは不安そうだった。
「このことはショウゴ兄貴に連絡してあるから、その内電話が来ると思う。しばらく様子をみようよ」
猪俣章吾は沙希からの連絡情報をクラブラ・フォセット社長の柳川哲平に報告して相談した。
「錦糸町のカトレアといや、源蔵って旦那がやってる店だ。あそこはやっかいだな。源蔵は昔ヤクザの舎弟だった奴で、今でもヤクザ仲間と交流があるって噂だな。奴等はヤクザ崩れの腕の立つ若衆を数人抱えているんだ。皆匕首(ドス)を含んでやがるナイフ使いばっかだから、下手に手を出すとこっちが殺られるぜ。源蔵の息子の魔神はキザな野郎でうちの客にもなってるが、加奈子と付き合ってたんだ。加奈子が沙希にサツにチクられたから、腹いせに沙希をかっぱらって行ったんだろう。いずれにしても、沙希はうちの大事なカンバン娘だから、助けてやらにゃならんね。さぁてっと、どうするか、うちの者に相談して対策を考えてみるか」
柳川社長は親身に沙希のことを考えてくれているようで章吾はほっとした。
十八 監禁キャバクラ Ⅲ
「錦糸町のカトレアに監禁されている沙希を取り戻してきてくれ。店を襲撃すると、客にも被害が出る可能性が高い。客が怪我でもすりゃ、サツやメディアが動いてややこしくなる。お前等、二日、三日内偵して、奴等の弱い所を突いて取り戻して来い。奴等は多分五人か六人だ。全員匕首使いだから、気を付けてくれ。我々がナイフやハジキを使うとサツが乗り出して来たら後処理が面倒だ。ナイフやハジキを使わないでやってくれ」
六本木のクラブ、ラ・フォセットの社長柳川哲平は、ラ・フォセットのセキュリティ・ガード(護衛)七人を集めて指示をした。
七人の他に猪俣修吾と栗山智も加わり、総勢九名でチームを編成した。七人の素性はまちまちで、元刑事、元自衛官、元ボクサーなどがおり、夫々単独のスナイパー(狙撃手)やヒットマン(刺客)が務まる兵ぞろいだった。だから、彼等は必要とあれば、拳銃やライフルの使い手でもあったが、柳川はヤクザあがりの米倉源蔵と違って警察当局の上層部にまで太いパイプを持っていたので、彼等の顔に泥を塗るような真似はできるだけ避けてきたのだ。
チームリーダーは三十代後半の溝口と言う刑事あがりの凄腕で、サブリーダーは池内と言う格闘技あがりの奴だった。柳川に、
「猪俣と栗山はアマちゃんだからよ、前面に出さずに後方のバックアップに張り付けてくれ」
と指示を受けていたので、カトレアの用心棒と直接戦わないことになっていた。
最初の日は、めいめいバラバラになって、錦糸町のキャバクラ、カトレアと江東区の女子寮を結ぶ彼等の行動を緻密に観察することにした。顔がわれないように、あまり接近せずに、双眼鏡を使い、夜間は頭に暗視装置を装着して監視をすることにした。栗山はビデオカメラの担当にされて、大きなカメラを担いで遠くから彼等の行動を撮影する役目だった。
初日、午前0時を回った所で、章吾は双眼鏡でカトレアの様子を覗った。0時半頃、やつれた顔をしてマイクロバスに押し込まれる沙希の姿をしっかりと確認した。栗山もその様子をしっかりとカメラで捉えていた。
マイクロバスが走り出すと、皆は四台の車に分乗して、気付かれないようにマイクロバスを尾行した。女子寮の場所は分っていたから、近くまで距離を詰めずに、遠くの駐車場に停めて、後はみなバラバラに通行人を装って接近して観察を続けた。
寮の前にバスが停まると、寮の鉄扉が開いて、中から屈強そうな男が三人出て来た。バスの中には運転手の他に用心棒と思われる男が一人乗って居た。先に用心棒がバスから降りると、女達が一人一人降りてきた。外に出ている男四人は女が逃亡しないように見張っている様子だ。
「男は五人か」
と溝口が囁いた。
「沙希は降りる所で確保するのが一番だな。あの鉄の扉の中に入ってしまうと面倒だ」
「どうやら、この時点が狙い所のようですね」
女は約三十人位居た。その中に沙希も居た。女が全員が寮に入ったのを確かめると、監視人らしき三人の男たちも寮の中に入り、鉄扉がバタンと閉められた。どうやら奥にもう一枚鉄扉がある様子だ。後でビデオをリプレイすれば細かいことが分かるだろう。マイクロバスが駐車場に停められると、運転手と用心棒らしき男は別の乗用車に乗り込んで走り去った。あたりが静かになると、溝口等九人も引き上げた。
沙希は毎日一生懸命頑張った。きっと章吾が助けに来ると信じて希望を捨てなかったから、毎日を頑張れた。人は誰かを信じて希望を持てば、少しくらい厳しいことは我慢ができるものだ。
沙希が拉致されてから、早いもので一週間も過ぎた。一週間も過ぎると、沙希を指名する客が増えてきて、沙希は他のホステスより多忙になった。十日もすると、沙希は稼ぎ頭になっていた。
「やっぱ六本木でやってた女は流石だな。よく稼ぎやがる」
黒服も沙希の仕事振りに驚いていた。
カトレアのホステスは一人当たり月に百万円~百五十万円も稼がされる。だが、ホステスたちに支給される給料は、わずか五万円~十万円でしかなかった。多くのホステスはサラ金の借り残高が返済できないほどになり、行き詰まった女を、サラ金業者からカトレアが借金の肩代わりをする条件で回されて来た。そのため、稼ぎの一部はその穴埋めに使われていた。派遣社員だった女が解雇され、仕事にあぶれて食えなくなって流れてきた女も居た。この寮はそうした不幸な女の吹き溜まりだ。
溝口や章吾たち九人は、ラ・フォセットに戻ってビデオを解析して、カトレアの奴等の行動パターンを十分に掌握した。
建物の周囲には約3mのフェンスが巡らしてあり、内側に獰猛なドーベルマンが二頭放し飼いされていた。フェンスの周りはフェンスに沿って、幅3m程の細い通路になっていた。マイクロバスが通って来た道は幅が5m程度あり広いが、寮の前の駐車場から先は道幅が4mもない細い道で、街灯もなく暗かった。道の脇には所々背高泡立ち草やススキなどの雑草がまとまって生えていた。細い道を100m程先に行くと、やや広い舗装道路に出る。
「カトレアの用心棒は人を殺る心得があるだろうが、あいつらは頭が良くねぇ。だから、オレたちは戦術を立てて戦えば十分成功するな」
「前に使った誘引策を使えば効果があるんじゃないですか」
ボクサーあがりの高次が案を出した。
「ボクシングでも、試合中誘引策は結構有効なんですよ」
「そうだな、まとめて五人相手じゃ戦闘が派手になるし、戦い難いな。奴等を分断した方が戦い易いな」
検討した結果、誘引策を採用することになった。章吾とサトルは先輩が戦っている間に沙希を救い出して逃走する役目があてがわれた。彼等の車四台は少し離れた場所の時間貸し駐車場に停めておくことになった。
沙希を救出する日の夜、彼等九人は四台の車に分乗して予定通り近くの駐車場に停めた。そこから全員バラバラになり、各自眼だし帽をケツのポケットにねじ込んで、カトレアの寮付近に接近して周囲の建物や雑草の陰に潜入して夜半マイクロバスが到着するのを待った。
「池内、おまえさんがカギだ。あんたが成功すれば、ほぼ奴等を倒せる。ドジらないようにやってくれよ」
池内は先ほど溝口が言った言葉が脳裏に焼き付いていた。
窓に金網を張った白っぽいマイクロバスが女子寮に通じる道路に入ってきた。九人のメンバーは夫々持ち場に着いて息を殺して潜んでいた。
バスが停車すると、寮の中から三人が出て来た。鉄扉は開けっ放しだ。バスの乗降口と寮の出入り口の間は約4m程度あった。そこに三人の男たちが整列した所でバスのヘッドライトをスモールにすると同時に扉が開いて、用心棒の男が最初に降りてきた。夜中なのであたりは暗いが寮の入り口から漏れる光のある部分は明るかった。運転手は乗ったままだ。用心棒に続いて、女達が次々に降り始めた。先頭の女が寮の出入り口に行き着く頃、整列した三人の監視人と用心棒の背後に忍び寄る眼だし帽の男が近付いた。うまい具合にGパンを履いた女が二人続いて降りてきた所だ。眼だし帽の男が突然走り出して、Gパンの二人の女の手を掴むといきなり引っ張って、暗い幅の狭い道路の方に走り出した。
「走って!」
と男は二人の女を怒鳴りつけた。女達は驚いて眼だし帽の男と一緒に走り出した。監視人たちは一瞬目の前で何が起こったのか分らずに躊躇したが直後に、
「おいっ、コノヤロー、待てっ」
と叫ぶと、眼だし帽の男と一緒に走る女二人を追いかけた。続いて用心棒ともう一人の監視人も後を追った。全部で三人だ。
バスから降りた女達にざわめきが起こった。残った監視人一人と、バスの運転手が降りてきて騒ぐ女達を鎮めにかかった。その時、逃げている眼だし帽の男とは別の眼だし帽の男が三人近付いて、監視人と運転手の背後から手刀で首筋に一発強打した。監視人と用心棒はその場に崩れ折れた。それを更に蹴りを入れて止めをさした。監視人と運転手はあえなくその場に倒れて動けなくなった。眼だし帽の男たちはそいつ等をロープで縛り上げて、道路の暗い隅に引きずり込んだ。
女二人を引っ張って全力で逃げる眼だし帽の男を追う監視人の一人がポケットから拳銃を取り出し、走りながら発砲した。パン! と言う乾燥した音があたりに響いて、弾丸は眼だし帽の男の耳の脇をヒュンとかすって行った。続いてもう一発パン! と音がして、左側の女が急に足を引き摺った。どうやら足に命中したらしい。
その時だ、道路の路肩で、
「今だっ!」
と声がすると同時に、道路にロープがピンと張られた。ロープは二本あり、最初に走ってきた監視人が最初に張られたロープに脚を取られて転倒した。続いてもう一本のロープが後から来た拳銃を持った男と用心棒の脚をさらった。男二人は最初の奴と同様にその場に転がった。路肩の草陰から三人の眼だし帽の男が飛び出して、転がった男たちの首筋に手刀を叩き込み、鳩尾とキンタマに蹴りを入れた。悲鳴をあげて監視人二人と用心棒は倒れた。
監視人の一人が持っていた拳銃は路肩の草むらに蹴り飛ばした。
女を引き連れていた男も女の手を離して戻り、監視人二人と用心棒をロープで縛り上げた。
七人のセキュリティ・ガードがカトレアの男たちと戦っている間に、章吾とサトルはバスに乗り込み、沙希を探した。沙希は直ぐ見付かった。
「オレだ」
章吾の声に沙希は直ぐに気付いた。沙希は章吾とサトルと一緒に全速力で駐車場に走り、車に乗り込むと直ぐにサトルが運転して池袋を目指して走った。後部座席に章吾と一緒に乗り込んで、
「章吾、ありがとう」
沙希は目に涙をいっぱい浮かべて、章吾に抱きついた。
カトレアの監視人と用心棒、それに運転手を縛り上げるとその場に転がしたまま、七人は駐車場に走り、そのまま六本木方面に走り去った。
最初に女二人を掴んで走り出したのは、罠を仕掛けた細い道に相手を誘導する[誘引策]だったのだ。それと知らずに二人の女が連れ去られそうなことに注意を取られて、路上に仕掛けられたロープの簡単な罠に気付かず、まんまと罠にかかったのだ。全員が追わず、二人か三人がバスの付近に残ることは予め想定した範囲で全て計画通り作戦は遂行されたのだった。女たちの騒ぎを鎮めるのに気を取られて警戒を怠った奴等の動きも予測通りだった。
沙希の救出成功の報告を聞いた柳川は、米倉源蔵に電話をした。
「源蔵さん、お久しぶりです。早速ですが、おたくの若旦那がうちのホステスをさらって行かれましてね、今日取り返させてもらいました。その時に、おたくの若い衆にうちの者が乱暴したようで、大変申し訳なかったです」
「えっ、わしは聞いとらんな。うちの倅があんたのとこに失礼したんなら、あいこと言うことになりますかな」
「ですが、源蔵さんとは今後も穏やかなお付き合いをさせてもらわななりませんから、治療代として、五十程送らせてもらいます。少ないですが、これで幕引きにしてもらえませんか」
「あい分った」
源蔵は電話を切った。
柳川は昔ながらの仁義を重んずる源蔵の性格が分っていた。物事は先手必勝だ。それで、先方から捩じ込まれる前に手を打ったのだ。倅からはグズグス言ってくるかも知れないが、源蔵はこれで丸く納めてくれるだろう。
十九 質素な生活
テレビのサスペンス劇場は沙希もたまに見ていた。深夜に放映されていたアメリカのテレビドラマ[24(Twenty four) ]のようなドラマの中で繰り広げられる男たちの死闘なんて現実にあるものとは思ってもいなかった。それが昨夜は目の前で実際の男たちの死闘を見せ付けられた。しかも自分を救出するために、大勢の屈強な男たちが戦ったのだ。沙希はドラマの主役を演じていたみたいに感じていた。
女は誰でも深層心理として、強い男に征服されてみたい願望は持っているものだ。それは、強い子孫を残したいと言う本能に拠るものだ。だから、先日タマっちが苛められて屈強の男たちに犯された時に男たちの逞しい男根を見せられた時、居合わせた女たちの中の何人かは、自分も虐めでなくて、愛を以ってあんな強い男に征服されてみたいと思ったとしても不思議ではない。タマっちが犬のように四つん這いにされて、バックから逞しい男根で責められて、ひぃひぃと泣く姿を沙希も忘れられないでいた。
女子寮に監禁されている女たちは屈強そうな監視人や用心棒を打ち負かす男はめったにいないと信じていた。だから自分達が解放されるなんて考えてもいなかったのだ。だが、昨夜はあっと言う間に日頃見慣れた五人もの屈強な男たちが次々に倒されて、縛り上げられる姿を見て仰天した。それも、突然襲撃して来たのは、十人近くの眼だし帽を被った男たちだ。彼女たちもテレビドラマでなくて現実にこんなことがあるんだと改めて思い知らされた。
監視人が居なくなった女子寮から、少なくとも十人が逃亡した。おそらく逃亡した女たちは二度とここには戻ってこないだろう。
監視人の拳銃で左足を撃たれた女は、襲撃した男たちが立ち去ると、足に焦がされているような痛みが襲ってきて歩けなくなった。それで、右側にいた女が監視人室に飛び込んで119番に通報した。間もなく救急車がやってきて病院に担ぎ込まれた。担当した医師は、付き添ってきた女の話を聞いて、銃弾でやられたものと理解して、即座に110番をしたので、病院に警官が二人やってきた。
そうこうしている間に、あたりは次第に明るくなって朝を迎えた。逃亡せずに残った女達はロープで縛られている監視人や用心棒の縄を解いてやり、男たちは自由になった。
「やられたなぁ」
と口々に呟きながら、女達の員数を点呼した。それで十一人の女が消えてしまったことが分かった。消えた女の中には沙希もいた。彼等は先ず現状の建て直しのために、あちこちに電話をしていた。
そこに、江東区の城東警察署からパトカーがやってきて、居合わせた男たち三人がその場で逮捕された。用心棒と運転手は警察が来る前に逃亡して捕まらなかった。
警察の調べで、使われた拳銃は付近の道路脇の草むらから発見された。そのため、銃撃した監視人は主犯として、残りの二人と共に警察に連行された。
この事件が引き金になって、監禁キャバクラカトレアの全貌が明らかになり、黒服も逮捕され、カトレアは廃業に追い込まれたのだ。結局女子寮に残った約二十名の女達も職を失ってしまった。
ラ・フォセットの社長柳川哲平はこの事態を予見して、早々と馴染みの警察署の幹部に報告していた。ラ・フォセットから差し向けた男たちはナイフや銃などの武器の使用を厳禁されていたので、相手を傷付けることもなく、単なる喧嘩として始末書の提出だけで難を逃れることができた。
事件の夜、サングラスのサトルが運転する車の後部座席に章吾と座った沙希は章吾に抱きついて離さず、カーブで章吾の身体が沙希に寄りかかった隙に、沙希は章吾の唇を奪った。顔が離れると、章吾は何も言わずに、優しい目で沙希を見つめていた。沙希はサトルに気付かれないように小声で、
「好き、大好きよ」
と章吾に囁いた。この時、章吾は沙希のウエストを自分の方に引き寄せて、そのままじっとしていた。沙希には章吾が自分を愛してくれているのだと実感が伝わってきた。
初めて章吾に出逢った時、
「あたしを守って下さい」
と頼んだが、今それが現実となり、章吾に守られていると強く感じていた。章吾も心の中で、沙希を上手く救出できた満足感に満たされていた。
マリアは沙希がアパートに戻って顔を見た瞬間、心配が解けて、沙希に抱きついて泣いた。沙希がいない間、不安で夜もよく眠れなかったと言った。その時に、マリアはサングラスのサトルと付き合っていると告白して、戻った夜は章吾、サトル、マリア、沙希の四人で祝杯を上げた。
翌日から、沙希の生活は以前の調子を取り戻して、ラ・フォセットにも通い始めた。ラ・フォセットではホステス仲間からあれこれ聞かれたが、沙希は黙って何も話をしなかった。そこに柳川社長が顔を出して沙希の元気な顔を確かめると、
「沙希には色々あったが、今迄通り沙希と仲良くしてやってくれ。余計なことは聞かないことだ」
と居合わせた者たちに指示したので、皆もそれ以上は沙希に何も聞かなかった。この世界ではそれぞれ人には言えない事情を抱えている者が少なくなかったから、皆も納得したようだった。
沙希は元通りの高給取りに戻ったが、相変らず質素な生活を続けていた。変ったことと言えば、日曜日章吾も沙希も休日だったので、二人でデートをするようになったことだ。章吾はまだ肩の痛みが完全に取れず、バイクには乗れなかった。
二十 不安と恐怖
あの拉致事件に遭遇してから、沙希は毎晩仕事が終わってタクシーに乗るのが怖かった。午前二時過ぎ、クラブ・ラ・フォセットが閉店時刻になると、店の前に何台かのタクシーが客待ちで停車していた。そんな時に、ス~ッと沙希の前に空車のタクシーがやってきて停まると、背筋に冷や汗が流れて、一瞬だが、沙希の身体は固まってしまうのだ。沙希はタクシーに向かって手を×の仕草にして乗らないと意思表示をするのがやっとだった。
「待ってたよ」
章吾のいつもの声がかかると、沙希はほっとした。章吾と一緒に乗っても、タクシーが走り出した直後は帰り道と反対方向に走るんじゃないかと不安で仕方が無かった。
そんな沙希の不安な気持ちを、章吾はよく理解してくれた。
「今度安い中古の軽(軽自動車)を買おうと思うんだけど」
「中古だって40か50はするでしょ」
「オレ、金持ってないから、もうちょっと安いやつを狙ってんだ。25か30位のやつ。走れば乗り心地なんてどうでもいいと思ってさ」
「もち、あたしも乗せてくれるんでしょ」
「ん。そのつもりだけど。毎日タクシーで五千円も払ってたら沙希だって大変だろ?」
「そうね。じゃ、あたしに半分の十五万は出させて下さらない」
「沙希が構わないなら助かるなぁ。軽があれば、デートで遠くにも行けるし」
「駐車場は大丈夫なの?」
「ん。オレのとこの近所で月に一万で貸してくれるとこあるんだ。ラ・フォセットは社長に話をしたら、毎日隅っこに停めてもいいってさ」
次の日曜日に、章吾は沙希を誘って軽の中古探しに出かけた。二十二万で手頃なのが見付かったが、税金とかを入れて三十万近くになった。それを買って、午後から二人でどこまでも千円の高速に乗って水上温泉まで出かけた。沙希はまだ運転免許を取ってなかったし、車で遠くに行くなんて生まれて初めてだったから、小学生の遠足気分になり、ワクワクしたし、高速の周囲の景色も新鮮に見えた。
日曜日で東京方面は混雑していたが、反対方向はすいていて思ったより早く水上に着いた。
「日帰り温泉、入る?」
「いいわね」
それで二人は[日帰り・休憩]とカンバンがある宿を見つけて入った。古っぽい旅館だったが、温泉は良かった。露天風呂もあり、沙希は初めて旅館の露天風呂に入った。
風呂を出ると、章吾が待っていてくれた。
「ちゃんと入った?」
「あたりまえだろ」
と言って章吾は笑った。
「今度マリアも一緒にドライブに連れてって下さらない? ダメ?」
章吾は、
「ダメだ」
と笑いながら、
「いつでもいいよ。歓迎するよ」
と言い直した。
六本木のクラブ・ラ・フォセットに久しぶりに米倉魔神が顔を出した。けれども、沙希とすれ違っても知らん顔をして通り過ぎた。どうやら相当に意識をしているらしい。いつものように子分を二人連れていた。その中に、あの監禁女子寮の監視人をやっていた男が居た。そいつは沙希の顔を見ると、凄い目付きで睨んで通り過ぎた。
沙希はその日以来、カトレアに居た男たちに仕返しをされるのではないかと毎日不安でならなかった。このことを帰り道、軽の助手席に座って章吾に話をすると、
「不安なのは分るけどさ、気にしても仕方がないよ。実際に何かあれば、その時どうするか考えようよ」
と沙希をなだめた。
米倉魔神と子分の様子は、ホステスのリーダーをしている澤田がしっかりと観察していた。
澤田は、その様子をクラブ・ラ・フォセットのセキュリティーチームリーダーの溝口に報告した。
「社長に沙希さんを守れと言われているんだ。なんかおかしなことがあれば、細かいことでも報告してくれないか」
溝口は澤田に頼んでいた。
不安は現実となった。
「沙希、どうやらオレたちを尾行してくる車があるな。交差点で詰めて来たら車のナンバーを見ておいてくれないか」
章吾は沙希に後を振り向いて確かめてくれと頼んだ。
章吾はバイク事故のことがあったので、交差点に入る時は速度を落として慎重に左右を確かめるようにしていた。
沙希の不安は次第に高まって、恐怖を覚えた。
不安と恐怖は背中合わせだ。不安に思っていることが現実となってくると恐怖に感ずるものだ。だが、章吾は腹が座っているようだった。尾行してくる車は目白通りをずっとつけてきたが、章吾はそれを恐れている感じではなかった。
二十一 心に傷を付けてやれ
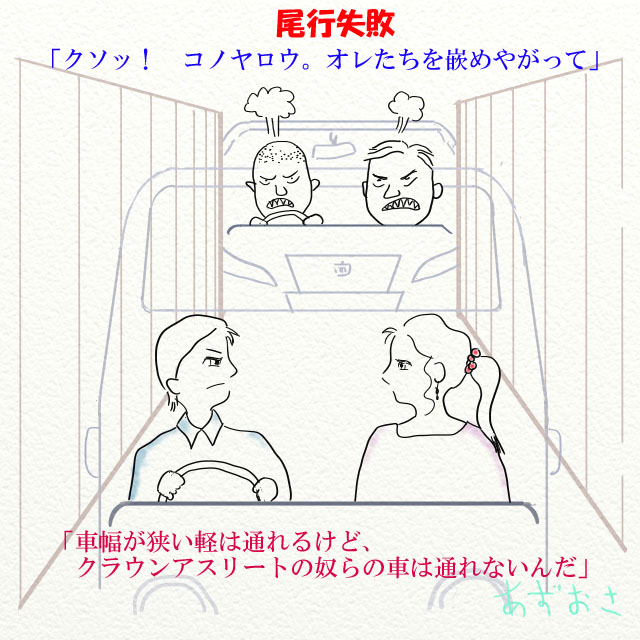
章吾は沙希と共同で買った中古のスズキ・ワゴンRの軽に乗っていた。ラ・フォセットの店を出てから、白っぽいクラウンが執拗に後をつけてきた。沙希が相手の車のナンバーを確かめるため、後を振り返った時、助手席に恐怖の監禁女子寮の監視人をやってた男の一人が乗っていた。沙希はその男の顔をはっきりと覚えているので間違いはない。ちらっとその男の顔が見えた時、沙希の背筋は恐怖で一層寒くなり冷や汗が流れ落ちた。運転していた男も見れば知っている奴だが、沙希が見た時は良く見えなかった。
章吾はクラウンに尾行されていても動じる様子はなく、制限速度を守って大人しく走った。だが、章吾は沙希のアパートがある要町に直接向かわずに、土地勘のある椎名町駅手前で、山手通りからいきなり住宅地に折れた。クラウンも折れて、章吾のワゴンRの後ろをくっついて来た。クラウンに乗っている男たちは前の車が穏やかな走りをするので、尾行には気付いてないのではないかと思った。
この辺りの住宅街は時々細い道があり、一通(一方通行)がやたらと多い。そんな道を、章吾は右に左にクネクネと曲がって進んだ。十字路は軽なら簡単に曲がれても、クラウンは曲がるのに苦労している様子だった。普通なら、尾行を振り切るためにスピードを上げて逃げる。だが、章吾は落ち着いていて、バックミラーでクラウンが曲がり終えるのを確かめてから次の十字路を曲がった。そのためか、クラウンの男たちは前のワゴンRが尾行に気付いていないと確信し油断をしていた。
住宅地の中の細い道は、一箇所か二箇所道路幅が約1・7m位しかない狭い所がある。章吾の軽は車幅が小さくて、1・7mもあれば悠々と通過できる。章吾はそこを通過するとバックミラーを見た。
クラウンを運転している男は、
「クソッ! コノヤロウ。オレたちを嵌めやがって」
とハンドルを叩いて喚いた。クラウンの車幅は1・8m弱だから、この細い道をどうしても通り抜け出来ないのだ。しかも、一通を違反してバックで戻っても、狭い十字路をバックで曲がるのは一苦労だ。
章吾はバックを確かめると、悠々と広い道に走り抜けて要町に向かった。尾行してきたやつ等は今頃あたまにきて喚いているだろうと思うと思わず笑いが出た。
「アハハ、ばかったれやろうが」
章吾が笑ったので沙希ももらい笑いした。それで、沙希の恐怖心は随分和らいだ。
章吾を尾行した男たちはどうにかバックで戻る所だったが、後から二台軽自動車が路地に入ってきてにっちもさっちも行かなくなった。扉の狭い隙間からなんとか助手席の男が這い出すと後の車に向かって、
「おまえら、下がれっ」
と怒鳴って脅し、どうにか狭い路地を脱出した。だが十字路をバックで曲がる時に側面を擦って凹ませてしまった。彼等は頭から湯気が出るくらい怒り狂っていた。
「あのやろう、覚えてやがれっ」
散々悪態はついたものの、どうにも惨めな状態を認めざるを得なかった。
米倉源蔵は息子の魔神の子分たちに、
「ラ・フォセットの女の身体には絶対に傷をつけるなよ」
と強く言い含めていた。子分たちは、
「兄貴、あの女に手を出すなって言われてもなぁ、それじゃオレたちどうすりゃいいんだよ」
と魔神に聞いた。
「お前等、頭を使え、頭を」
「……?」
「あのな、オヤジは身体に傷を付けるなと言ってんのよ。そこのとこ、分るだろ?」
「……?」
「心に傷を付けるのよ。女はな、手とか足とかにちょっと位傷をつけられても平気なもんよ。顔は別だけどよぉ。けどな、心に傷を付けてやってみろ、大抵の女は相当こたえるぜ」
「兄貴、わっかりました」
「やり方はお前等で考えろよ。アマちゃんを可愛がってやる位、お前等ならどぉってことはねぇだろ」
「兄貴、ありがとうございます」
それで子分四人で沙希にダメージを与える方法を考えた。地獄の監禁女子寮の監視人だった男二人と黒服とバスの用心棒の四人だ。先日拳銃を使ってサツにパクられている監視人は当分太陽を拝めないだろう。今は警察の拘置所暮らしだった。
彼等は沙希の様子を調べた。その結果、どうやら猪俣章吾と言う男が沙希の恋人らしいことが分かった。それで、
「あの女と一緒の時、あの猪俣ってヤロウを女の目の前で痛めつけてさ、猪俣のヤロウが見てる前で、あの女を辱めてやらないか。それだったら、あの女、そうとう堪えるぜ」
「そうだな。それで行こう。あのアマちゃんヤロウを痛め付けるなら四人は要らなねぇぜ。オレたち二人で十分だ」
翌日元カトレアの黒服と女子寮の監視人の二人が、章吾と沙希の乗った軽を尾行した。
アパートの付近で軽から二人を引きずり出して猪俣を半殺しに痛めつけてから、猪俣が見ている前で沙希をレイプする手はずだった。帰りが午前二時過ぎで、池袋に着くのが三時前後の夜中だから、人が見てない暗闇に引きずり込んだら簡単にやっつけられると思っていた。
だが、最初の尾行は住宅地の狭い路地に逃げ込まれて、完敗だった。
それで、彼等は椎名町界隈の地図を詳細に調べ、現地も確かめて、この次は絶対に失敗しないように準備した。これには、黒服と二人の他にもう一台応援を頼んで、猪俣たちの軽を待ち伏せする必要があった。
経路を詳細に調べると、一通があるので、入り込んだ路地により、出口が二つか三つあることが分かった。そこで、彼等は軽が入り込んだ路地毎に、出口にA1~C1、A2~C2、A3~C3のように入り込んだのが①番の路地なら、出口はA1~C1、③ならA3~C3のように地図に記号を付けた。ABCのどこから出てくるかは、尾行中に十字路を曲がった方向で分るから、それを携帯で待ち伏せ車両に知らせることにしたのだ。最初の計画は沙希のアパート近くでレイプする予定だったが、路地で挟み撃ちするなら、路地で沙希を辱めようと言うことに変更した。夜中だから、手早くやってしまえば、付近の住民が飛び出してくる前にかたを付けられるだろう。
その日も帰り道、章吾と沙希は尾行に気付いていた。今度はどうやら二台で尾行してきた。黒っぽいクラウンと黒っぽいマークXだった。すぐ後からついてくるクラウンは前のと違うナンバーだった。沙希は振り返って番号を確かめて、メモ用紙に書き込んだ。途中からすぐ後の尾行車はわき道に折れていなくなった。それで、沙希は次の尾行車マークXのナンバーも控えた。
最初に尾行された後で、章吾は目白警察署の顔見知りの警察官に尾行のこと、前回のバイク事故のことを話して、尾行された時に連絡を入れたらパトカーで支援してくれと頼んでおいた。警官は最初は軽く見たが、四谷署に問い合わせてもらった所、前回は大きな事件だったと知り、協力を約束してくれていた。
章吾はこの前と同様に、山手通りから急に折れて、この前とは違う路地に入った。尾行車マークXは前と同様に後をつけて来た。もちろん、途中道路の幅員が狭い所を通り、後のマークXを振り切った。章吾はそのまま十字路を折れて、広い道への出口に向かった。
路地に逃げ込んだ時に、章吾は沙希に目白警察に電話をしろと言った。沙希は言われた通り携帯から警官を呼び出して救援を頼んだ。その時、二台の尾行車のナンバーも教えた。警官は直ぐパトカーを手配すると約束してくれた。椎名町の南側一帯の住宅地は南長崎町の一丁目から三丁目になり、目白警察署の管轄だったから、番地を言うと大体の場所は分ってくれたようだ。
その時、出口の方から一通を逆走してくる先ほどのクラウンが見えた。章吾はあせった。もう一台が逆送して挟み撃ちされるとは予想もしてなかったからだ。軽は丁度両側がブロック塀の幅員の狭い部分に入ったとこだった。「ヤベェッ!」
章吾はバックして少し道の幅員が広がっている所に戻ろうとした。
その時、前方の逆送してきたクラウンから、パンッと言う乾燥した音がした。その瞬間、軽のフロントガラスに穴が開いて、そこから見る見るミシミシッと言う音と共にフロントガラスに細かいヒビが入って、前方が見えなくなった。
「ヤベェッ!」
章吾はもう一度叫ぶと、ドアを開けようとしたが、道路が狭くてドアの開いた隙間から脱出できない。
「沙希、ハンカチを出してくれ。早く!」
沙希がハンカチを出すと、章吾は座席を倒して手にハンカチを巻き付けて後部ドアの内側からガラスを思い切り殴った。ガラスは意外に強い。二度目のパンチで割れた。章吾はそこから車外に這い出して、後部のハッチバックのドアを外から開くと
「沙希、逃げろっ、早くっ!」
と叫んだ。軽自動車の後部のドアは内側から開けられないのが普通だ。だから、狭い路地に入り込んでサイドのドアから出られない時は、後部の窓ガラスを壊して出るしかないのだ。
沙希は開いた後のドアから車外に転げ出た。その瞬間、もう一発射撃音がして、章吾は仰向けに路上に倒れた。
「章吾」
沙希は章吾に抱きついて章吾を見た。章吾の頭の左上から血が出ているようだ。沙希が触るとベットリと手が汚れた。
「血だ」
沙希は握り締めた携帯で無意識に119番を打っていた。消防署の救急隊の質問に答えると、
「早くキテェッ」
と沙希は叫んでいた。
クラウンから飛び出した男二人は軽に向かって小走りに近付いた。フロントガラスがヒビ割れて前方が見えない。それで、男はジャンプして軽の屋根に上るやいなや猪俣めがけて発砲したのだ。それがどうやら相手の頭に命中したようで猪俣はのけぞるようにして路上に倒れこんだ。魔神から、
「猪俣を怪我させてもいいが、絶対に殺すなよ」
と釘を刺されていた。だから、頭を狙うつもりはなくて、肩を狙って撃った。だが、弾丸は反れて頭に当たってしまったのだ。
男は軽の屋根から飛び降りると、章吾に抱きついた女のスカートをめくり、レギンスを引き下げて女の尻をむき出しにした。これからレイプに取り掛かろうとした時、別の男が、
「ヤバイぞ、パトカーが来た。逃げろっ」
と言うなり章吾と沙希を置き去りにして軽の屋根に飛び乗り、元のクラウンの方に走った。男二人はクラウンに乗り込むと全速力で走り去った。それを見て沙希は急いでパンティとレギンスを引き上げた。沙希は恐ろしさで殆ど身体が固まり、男に乱暴に尻を剥かれても身体が思うように動かず、どうすることもできなかったのだ。
拳銃の射撃音に目を覚ました近所の住民が飛び出して来て、あたりは騒然となった。そこに救急車が到着したが、軽が道を塞いで担架が運び込めない。それで、救急隊員の一人が軽の粉々にヒビが入ったフロントガラスを叩き壊して、エンジンをかけて広い通りまで軽を移動した。章吾を担架に乗せたとき、警官が二人、マークX側から走ってきた。警官は救急隊員から状況を聞くと直ぐに本部に連絡して、逃走したクラウンの追跡を依頼した。間もなく、高速道はもちろん、都内全域に警戒網が敷かれた。マークXは置き去りにされていたが、中に居た二人の男は逃走した後だった。
沙希は救急車に同乗して病院に向かっていた。
「章吾、死なないで、ねぇ、章吾お願い」
救急車の中に沙希の悲壮な叫び声が続いていた。
二十二 章吾の運命
救急車で、章吾は椎名町近くの南長崎町にある[としま昭和病院]に搬入されて、すぐに手術室に向かった。
恐ろしい夜が明けて、窓の外が明るくなってきた。沙希は病室の前で、もう三時間も待っていた。昨夜から一睡もしていなかったから眠い。だが愛する章吾のことを想うと、眠い目をこすって、
「死なないで」
と祈り続けていた。
手術室の扉が開いて、執刀医師が出て来た。
「ご家族の方ですか」
沙希は、
「はい」
と応えた。
「手術は上手く行きました。命は助かりましたが、撃たれて倒れた時に後頭部を打って脳震盪を起こしていたようです。私としてはその方が心配です。調べて見た所、脳には異常が見付かりませんでしたが、しばらく様子を見ましょう。それと、前に肩を傷めておられたようですが、倒れた時に肩も強打して、最悪は腕の上げ下ろしに障害が残るかも知れません」
医師の説明はようやく二十一歳になる若い沙希には残酷過ぎた。一命は取り留めたとは言え、しばらくは心配だ。
沙希はここのとこ、しばらく会ってなかった森ガールの藤井美登里にメールを送った。それで、お昼頃、美登里は病院にお見舞いに来てくれた。
「沙希ちゃん、また凄いショックだわね。可哀想に。それで、彼、大丈夫なの」
こんな時は気の合う友達に慰めてもらうのが一番心強い。
目白警察署の章吾が顔見知りの警官と、もう一人年配の警官が病院にやってきた。
「通報をもらった四人の男たちは逃走中でまだ逮捕できていません。今警視庁で広域捜査をしています。猪俣さんの容態は如何ですか」
沙希は先ほど医師からあった説明の内容をそのまま伝えた。
「頭を撃たれて命が助かったのは不幸中の幸いです。本官はもしかしたら危ないかと思ってました。銃弾は頭蓋骨の内側に貫通すると、頭の中で跳ね回り、確実に命を落とします。今回は頭皮の部分を掠めたのが幸いでした。どうかお気持ちをしっかり持って看病してあげて下さい。僕等がもう少し早く現場に駆けつけておれば、こんなことにならずに済みました。大変残念です」
警官の話を聞き終わると沙希は、
「犯人は少し前のホステス銃撃事件と同じです。あたし、顔をはっきりと見ました。江東区の城東警察署に連絡をして頂ければ、犯人の手がかりはつかめると思います」
と前の事件のことを話した。警官は今回の事件の状況を詳しく聞き終わると、
「大変助かりました」
と礼を言って引き上げて言った。
その話を沙希の脇で美登里は熱心に聞いていた。
「わるいな、オレに構わず仕事にいけよ」
昼過ぎに、章吾はコンコンとした眠りから覚めたようだ。沙希は章吾がまともな口をきいてくれて、安堵した。美登里と一緒にスーパーに行って、章吾の下着など当面の細々とした物を買い揃えて眠っている章吾に、
「また来るね」
と言って病院を出た。
美登里とお茶して分かれてから、仕度をして沙希はラ・フォセットに出勤した。事件の事は誰にも話さずに、いつも通り店に出た。
帰りはタクシーだが、怖くて脚が震えてなかなかタクシーに乗る気になれなかったから、その日は近くのビジネスホテルに泊まった。
朝早く目が覚めたので、スタバでサンドイッチとコーヒーで朝食を済ますと、その足で章吾が入院している病院に向かった。
章吾は目をつむって眠っている様子だった。沙希はそっと章吾の顔を覗いて、キスをした。章吾は薄く目を開けて微笑んでいた。肩のあたりが痛んで動けない様子だった。
昨日の夕方、池袋のロマンス通りの仲間たちが大勢お見舞いに来たようだ、花束や果物がそのまま置いてあった。沙希がモモに事件のことを詳しく書いてメールをしておいたので、仲間全員に伝わったようだった。
「オレ、早く退院できたら、今度の正月、マリアとかサトルを誘って高速で遠くに旅行しないか?」
章吾は頭と肩の怪我が必ず治ると自信があるような口調で沙希の顔を見た。沙希は章吾の痛くない方の手に顔をなすり付けて、
「ありがとう。早く良くなって頂戴」
と答えたが、不安と嬉しさと章吾に恋する気持ちがないまぜになって、目から涙が溢れ落ちた。
章吾が入院したおかげで、沙希は章吾と二人っきりの時間ができて、看病に来るのが楽しみになった。たとえ章吾の肩や後頭部に後遺症が出ても、沙希は一生章吾と一緒に居たいと思った。
考えて見ると、立て続けに起こった事故は全て沙希自身のせいだ。それなのに、何も関係のない、この人を巻き込んでしまって、自分は章吾の厄病神みたいだと思ったが、そのお陰で章吾を一層愛して行こうと心に決めることができた。
二十三 逃亡

廃業に追い込まれた錦糸町の監禁キャバクラ、カトレアの黒服は武藤邦彦、バスに乗り込んでいた用心棒は笹川陽一、章吾と沙希の襲撃に加わった監禁女子寮の監視人は藤堂弘と李仁順で、既に警察に逮捕されている奴は西村勝也と言う名前だった。
黒っぽいマークXを運転していた男は黒服の武藤と助手席は用心棒の笹川、黒っぽいクラウンを運転していた男は監視人の藤堂、助手席は監視人のイ・インスンだった。イ・インスンは韓国人だが、日本名は立川勝と名乗っていた。章吾を拳銃で撃った男はクラウンを運転していた藤堂だった。
章吾たちを尾行して追い込んだマークXに乗っていた武藤と笹川は、反対側から追い込んだクラウンに乗っていた藤堂とイが車から降りて、軽自動車を乗り越えざまに猪俣を拳銃で撃った様子を見ていた。その時、後方からパトカーのサイレンが近付くのを知って、
「笹川、ヤバイぞ、逃げろ」
と言って二人は早々に現場付近からタクシーで逃走した。目白駅から電車で逃走途中、兄貴分の米倉魔神に携帯で状況を報告した。
「バカヤロー、殺すなと言っただろ。おまけにハジキなんか使いやがって。仕方ねぇ。直ぐ海外に逃亡しろ。金とかはこっちで用意しておく。羽田から一番早い中国東方航空の九時二十五分で上海に飛べ。急げっ!」
と怒鳴られた。
「藤堂とイの分もお願いします。藤堂にはこっちから連絡を入れときます」
武藤は携帯で藤堂の様子を聞いた。
「ポリ公がこっちに二人走って来たからよぅ、やべぇと思って、今車で逃げてるとこだ」
「今どのあたりだ」
「首都高5号で竹橋の方に向かってるとこだ」
「アホかぁ、首都高はやばいぜ。捕まえて下さいと言うようなもんだ。直ぐ降りて、適当なとこで電車に乗って帰って来い」
高速道路には公開されていないナンバープレート読み取り装置が随所に設置されている。沙希が黒っぽいクラウンのナンバーを警察に伝えていたので、このナンバーがチェックされていた。広域捜査網に早々と通過情報が上がってきた。高速5号線北池袋ランプを過ぎた地点で発見されたのだ。そこで、5号線全線に警戒網が敷かれた。直近の飯田橋ランプにも白バイが急行した。だが、藤堂たちは白バイが来る約一分前に高速を降りていた。飯田橋ランプを出ると、近くの時間貸し駐車場にクラウンを突っ込んで、二人はJR総武線の飯田橋駅から電車で錦糸町に向かっていた。
錦糸町の株式会社ゴールデンバード・エンタプライズの事務所に駆け込むと、武藤と笹川は既に待っていた。社長の息子の米倉魔神にさんざんどやされて、当面の費用として百万ずつ手渡された。パスポートは会社の金庫に保管されているのを一緒に渡された。写真は本人のものだが、名前が違う。緊急時用の偽造のパスポートだ。
「上海に飛べ。中国にはビザがねぇと入国できねぇ。だがな、上海に限って四十八時間以内のトランシットの場合だけ、ビザなしで入国だきるんだ。だからよぉ、万一を考えて、航空券は上海経由杭州まで買っておけ。六万か七万だ。上海の空港に着いたら、上海喃喃飯店社長のボデーガードをやってる江亢虎と言う男と接触しろ。後はやつの指示に従って行動すれば街に出られる。多分用務員に変装して出してくれると思うよ」
江亢虎と言う男は髯をはやしたいかつい男だった。上海空港に着くと、荷物受取口で、江亢虎と書いたカードを持っていたから直ぐに分かった。日本語は達者で全く問題がなかった。土産物売り場の狭い事務室に案内すると、
「これに着替えて下さい」
と空港職員用の制服に着替えさせられた。同時に中国人民共和国居民身分証を各自手渡された。もちろん偽造だ。
「身分証は絶対に失くさないように」
と厳しい目付きで釘をさした。
空港はなんなく出られた。身分証には四人共朝鮮族と書かれていた。顔が朝鮮民族と区別が付かないので怪しまれることはまずないと江亢虎は説明した。韓国語はイが達者だし、他の三人もそこそこ韓国語ができるので、中国国内を移動しても問題はないと言った。
江亢虎は四人に中国人の運転手付きで車を一台貸してくれた。上海に一泊すると、直ぐに中国奥地の重慶を目指して出発した。
飛ばして三日後重慶に着くと四人はその町の暴力組織の用心棒として雇われた。十年間位はそこで雇ってもらう手はずになっていたのだ。
警察当局は広域警戒網を広げて、成田や羽田も警戒していた。だが、顔写真が届いていなかったので、四人が偽名で中国東方航空で上海に高飛びしたのが分ったのはずっと後で、多分迷宮入りになるだろう。
魔神はここのとこ子分を次々と警察にやられて、落ち込んでいた。
「ここまで来るのに苦労したのも知らねぇで、まったくっ、どいつも役に立たねぇヤロウだ」
魔神は怒りの持って行き場所がなくて、毎日いらついていた。
二十四 メディア対策
目白の静かな住宅街、南長崎町で起こった拳銃の発砲事件があれば、普通ならメディア関係のカメラマンが押しかけてきて。辺りは騒然となったであろう。だが、この事件を担当した目白警察署の刑事は頭のきれる男だった。捜査中、つまり犯人はまだ逮捕に至っていない。こんな場合犯人が被害者の男女が搬入された病院がどこかを知れば、口封じに被害者を殺害する恐れは十分にあり、拳銃を所持している男が病院内で発砲でもすれば、それこそ大騒ぎになって、メディアの人間や野次馬を抑えきれなくなる。もしも犯人を逮捕出来なかったら警察の責任問題にもなる。それで、刑事は気転をきかせて消防署に、
「絶対に搬入先の病院を公表するな」
と厳しい緘口令を敷いた。その上で、現場検証を急がせて、ガラスを割られた軽自動車を直ちにレッカーで移動させて、粉々に飛び散ったガラスの破片を綺麗に清掃させた。
真夜中、住民が寝静まった時刻に派手な発砲事件があれば、寝ていた者はびっくりして飛び起き、何があったのか覗いて見た者は多いだろう。
それで、事件の様子を見た者の中に、新聞社に電話をした者がいた。電話を受けた新聞社では、スクープになるので、急遽事件担当記者を現場に急がせた。だが、記者が現場に到着した時は、あたりには何も無く、まだ起きて外に出ていた住民の一部に、事件の様子を聞くくらいしか成果は得られなかった。記者はすぐに目白署に押しかけて事件の全容を聞き出そうと努力したが、
「捜査中ですから現段階では何も発表するものはありません」
と冷たく突っぱねられた。
目白警察署の担当刑事は、江東区の城東警察署に問い合わせて、前回の事件について詳しい報告を受けた。同時に、逃走中の犯人の捜索の協力も要請した。前回の事件は更にその前の四谷警察署で担当した轢逃げ事件とも関連があったと報告されて、四谷警察署にも協力を依頼した。
報告の内容から、この一連の事件はどうやら六本木の元ホステス岩井加奈子の一方的な嫉妬による怨恨が原因と推察された。刑事は、被害者には後ろめたいことは何もないと考えて、被害者を公表せずとも何ら問題がないと判断した。
目白警察署の刑事の特別な配慮があったとは何も知らない章吾と沙希は、五月蝿いメディアのおっかけもなく、章吾は静かに入院を続けておれたし、沙希は章吾と過ごす病院の看病の時間幸せがいっぱいだった。
章吾の頭の怪我は手術後の経過が良くて回復が早かったが、医師の指摘の通り、左腕を動かすと痛んで、回復までにしばらく時間がかかるようだった。
沙希はお昼過ぎから六本木に出勤する前まで、毎日欠かさずに章吾の見舞いに病院を訪れた。早いもので、既に一ヶ月も経ち、十一月の下旬になっていた。珍しく、目白警察署の章吾が顔見知りの警官と担当の刑事が病室を訪ねてきた。それで沙希はしつこいメディアの詮索から守られていることを知った。同時に、自分たちを襲った株式会社ゴールデンバード・エンタプライズの元キャバクラ、カトレアの残党の四人が、上海に高飛びして、上海空港から先の足取りや消息がピタリと消えて逮捕は難しいだろうと言う観測話を聞かされ、また新たな不安ができてしまった。彼等の消息が分らない以上、いつか突然に仕返しをされる可能性があったからだ。刑事は何かあれば自分達が守るから、細かいことでも構わないから不審なことがあれば出来るだけ早く知らせて欲しいと言い置いて病室を出て行った。
沙希は週に二日か三日、華道と茶道の教室に通っていたが、章吾が入院してからは、時間が取れずにサボっていた。その代わり、ラ・フォセットに来た中国人の客に中国語を教えてくれる女性を紹介されて、最近日曜日に会ってお茶をしたりしていた。今ではすっかり仲良くなって、お友達になってくれていた。陳香凝と言う名前で、二十代半ばの美しい女性だった。陳香凝は横浜の中華飯店店主の娘で、日本の御茶ノ水大学を卒業したそうで、英語、フランス語にも精通していた。沙希のアパートに案内すると、六本木の一流のクラブの人気ホステスにしては随分粗末な住まいだったので、相当に驚いた様子だった。
森ガール、藤井美登里は来年三月で卒業だ。就活で、ここのとこ大好きな[ゆるい]洋服を着て歩く機会がなく、殆ど毎日、ピッチリとした黒いスーツ姿で会社回りをしていた。だが、折からの不況でなかなか良い所に決まらずにあせりまくっていた。こんな不況の真っ只中の年に就活しなければならないなんて、自分の運命がよほどついてないと恨まずにはいられなかった。三年前かこれから三年後に卒業だったら、どんなに楽だっただろと思うのだ。
だから、たまに就活の合間に、昼間、島崎沙希とお茶するのがすごく癒される気分になれるので、それだけが楽しみだった。
「このまま、卒業するまでどこにも決まらなかったらどうしよう」
沙希にそんな話をすると、
「あたしなんか仕事にあぶれてどん底を経験したから、あなたの場合はましよ。住む所もあるし。わたしはお風呂もシャワーもない四畳半のボロアパートのお家賃が払えなくなって、仕事も見付からないし、どうしようもなくて、身体を見ず知らずの男の人に時間貸ししてどうにか食い繋いだわ。あなたはまだ時間もあるし頑張ってね」
と励ましてくれるのだ。励ましてもらっても、どうにもならないことは分ってはいるのだが、仲良しの友達に、
「頑張って」
と一言励ましてもらうだけで嬉しかった。正直、自分は努力しているつもりなのに、どこも決まらない不安の毎日は、経験をした者でなければ分からないと思った。
美登里は沙希が、
「見ず知らずの男の人に自分の身体を時間貸した」
と言った[時間貸し]なんて言葉を始めて聞かされたが、それを想像すると自分にはそんなことはとても恐ろしくて死んでもできないと思った。
二十五 正月の予定

「島崎さん、仕事が終わったら帰る前に事務所に寄ってくれないか」
珍しく六本木のクラブ、ラ・フォセットの社長柳川哲平が沙希に声をかけた。
「はい、分りました」
沙希は先日の襲撃事件について、クラブでは誰にも何も話してはいなかった。けれども、章吾が入院して欠勤しているので、多分そのことを聞かれるのだと思っていた。
世の中は不景気だが、沙希が勤めているクラブは客足がそれ程落ちてはおらず、その日はいつもより来客が多かった。沙希はクラブに入った時から、自分の恋人は章吾だと心に決めていたから、店の外で客と付き合ったことはなかった。客たちは沙希をあの手この手で口説くのだが、沙希が決して首を縦にふらないので、それが返って沙希の人気を高めていた。他人のことには関心がなかったが、同僚の大部分は特定の客と付き合っているらしく、時々そんな噂話を小耳にはさんだ。
ラ・フォセットに出勤する前に、病院に寄ると、章吾は十二月中旬になれば退院できるだろうと担当の医師から話しがあった。
「島崎さん、良かったわね」
とここのとこ毎日看病にやってくる沙希に看護師が労をねぎらった。
「先生、退院後のリハビリは毎日ですか」
と沙希が看護師に質問した。
「そうね、最初の内は仕方ないわね。様子を見ながら次第に間隔を延ばすのが普通だわね」
その言葉に、沙希は章吾は当分大変だなぁと思った。
そこに、マリアと栗山智が見舞いにやってきた。
「ショウゴさん、大分良くなったの」
マリアが声をかけた。章吾は、
「心配かけてすみません」
とマリアに頭を下げようとして顔をしかめた。
「まだ肩が相当痛むらしいの」
と沙希がマリアに説明した。
「ショウゴさん、ごめんなさい」
マリアは済まなそうな顔をした。
「兄貴、正月には元気になるんだろ?」
「ん。その予定だ」
「頑張って治してくれよな。四人で旅行するの、楽しみにしてるんだからさぁ。あっ、運転ならオレがやるから大丈夫だ」
それで、行く先をどこにするかと言う話になった。
「正月は旅館とか混むし、そろそろ予約を入れないとヤバイからさ」
章吾とサトルは暖かい所に行こうと提案した。
「海の綺麗なとこがいいね」
と章吾が自分の希望を出した。沙希とマリアは逆に雪の降る田舎の温泉に行きたいと主張した。それで、男が折れて、東北か北海道にしようと話しが進んだ。
「高速のどこまでも千円は確か正月の五日間しかないよな。だとすると北海道は無理かもね」
それで秋田、岩手、青森の三県で適当な場所や旅行経路をサトルに調べてもらうことになった。
仕事が終わって、沙希は事務所に顔を出した。
「おっ、仕事はもう終わりでいいんだな?」
「はい。帰り仕度をして来ました」
「そうか。あまり時間は取らせないから、ちょっと話を聞いてくれないか」
「はい」
「この前、猪俣君が錦糸町のカトレアの残党にやられたらしいね」
「はい」
「君も一緒だったんだろ?」
「はい。帰り道、いつも送ってもらってますから」
「そうか、君の方は怪我はなかったようで良かったよ」
沙希はやはりこの話を詳しく聞きたいのだなと思った。
「あそこはヤクザ崩れの掃き溜めみたいなとこだからさ、奴等のやることはえげつないよな」
「はい」
「その後の話は警察から聞いているのか」
「はい。上海に逃亡して、上海空港から先は四人共足取りがつかめず、多分逮捕は難しいだろうと言ってました」
「そうか。これからの話は警察には内緒だぞ」
「はい」
「やつ等は上海の組織の人間に助けられて、今は中国のずっと奥地の重慶と言う都市で組織の用心棒に雇われたらしい。うちの溝口の調べだと、偽造だが居民身分証を受け取ったそうだから二十年間は大手を振ってあっちで仕事ができるんだ。奴等が捕まれば、最悪でも無期懲役だけれど、日本の法律じゃ殺人未遂で無期以下だと時効が十五年だから、十五年も過ぎれば日本に帰ってくる可能性はあるね。僕の予想だと多分帰ってこないだろうと思うよ。だから安心してて大丈夫だよ」
「そうなんですか。ちょっと安心したな」
「この話は誰にもするなよ」
「はい。大丈夫です」
「君が口が堅いのを分ってて話をしたんだ。どうだ、その後猪俣君の容態は良くなってるのか」
「はい。今日お医者様にうかがった所では十二月の中旬には退院できるそうです。当分リハビリは必要だそうですが」
「そうか。その程度で良かったな。頭を拳銃でやられたら、普通は即死だけれど、頭皮をかすったらしいね。それで助かったんだよ」
「はい。運が良かったです」
「所で、沙希さんは猪俣君と付き合っているのか」
「はい、そのつもりですけど」
「つもりと言うのは変な言い方だね」
「正確に言うと、多分今はあたしの片想いだと思います」
「すると猪俣君とはまだなんだね」
「はい。まだ彼の気持ちがはっきり分らなくて……。彼、シャイな人ですから」
「そうか。じゃまだお互いに恋人どうしってわけじゃないんだな」
「はい」
柳川哲平はちょっと考えている様子だった。コーヒーサーバーから熱いコーヒーを二つ持ってきて、一つを沙希に差し出した。
「ありがとうございます」
「先日横浜の陳済棠さんが、君のことをえらく褒めてくれてね、娘さんの陳香凝の良いお友達になってくれたと喜んでたよ」
「あたしの方こそ、彼女とても親しくして下さって感謝してます」
「陳さんが、君は中国語を良く勉強するので感心してたよ」
「なんだか恥ずかしいです」
沙希はちょっと顔が赤くなってきたように感じていた。社長は褒めすぎだと思った。
「陳さんとは関係のない話なんだけど、米村社長は知ってるよね」
「はい、良く存じ上げています。確か○○(まるまる)ホールディングスの社長でしたよね」
「そうだ。大会社だ。米村さんは苦労されて一代であそこまで大きくされたなかなかの人物なんだ」
「たまにお連れしたお客様との会話を伺って大体の所は聞いています」
「それでなんだけど、米村社長さんは苦労されて晩婚でね、息子さんがまだ二十代後半なんだけど、その息子さんのお嫁さんに沙希さんをくれないかって話があるんだ」
「あたし、学がありませんし、両親も居ないも同然ですから無理です」
「その点は大丈夫だ。君の履歴は僕の方から説明してある。君は英語、スペイン語、それに今度は中国語も勉強してるだろ? うちのスクールで茶道、華道も習ってるし。先方は君が身持ちが堅いって評判を高く買ってくれてるんだ」
「……」
沙希は片想いとは言え、章吾を慕っていた。だから社長から突然こんな話を持ち込まれて困ってしまった。
「息子さんは今は若いから平取締役だけど、将来は跡継ぎで社長になると思うから、良い話だと思うよ。考えてみないか? 息子さんは普段は多忙だから、お正月にでも見合いをさせたいって言ってるんだよ」
「すみません。二、三日考えさせて頂いてもいいですか」
「構わんよ。気持ちが決まったら僕に話してくれ」
それで柳川哲平との話は終わった。
お正月四人で旅行すると今日はっきり決めたばかりだ。沙希の心は揺れ動いた。
二十六 章吾の気持ち
お見合いの話を、最初にマリア、続いて美登里、最後に香凝に相談してみた。
マリアは日本の習慣がまだ良く分かっていないようだったが、
「スペインでも恋愛結婚はあるけれど、親どうしが相手を決めることが多いわね。どっちがご自分の幸せになるか良く考えて決めるといいわよ」
と言った。
美登里は就活の結果が出てなくて、正直それどころじゃない感じではあったが、仲良しの沙希の相談なので、一緒に考えてくれた。
「あたしなら、絶対自分の好きな人と結婚したいな。沙希だったら沙希が好きな章吾さんと結婚するってことになるのかな? 将来のことを今考えても今のような世の中じゃ、この先どうなるか分らないしぃ。つまりお見合いをしても、相手の性格が良く分からないわけだから、結婚してからこんなはずじゃなかったって後悔することもあるわね。章吾さんはあたしも知ってるけどいい方だし、心配がないわね」
「そうか、やっぱ美登里は恋愛結婚をお勧めね」
「女の幸せって財産とかお金じゃ決められないものってあるよね。そうでしょ? 沙希」
「ん。でも、あたし章吾さんの本当の気持ちをまだ聞いてないんだ」
「じゃ、聞いてからお見合いしたっていいじゃない。章吾さんの気持ちがあれば、お見合いなんて断ってしまったら」
「そうね、でも断ったら、社長の顔を潰しちゃうから、最悪今のお仕事を辞めなきゃならなくなるかも」
「結婚は一生だから、お仕事を辞めるのは覚悟しなくちゃ」
最後に中国人の香凝に相談した。
「○○ホールディングスってあの大きな会社?」
「そうみたい」
「あの会社、中国でも名前が通ってるわよ。すごいお話しじゃない? あたしだったら絶対にお見合いして息子さんをゲットするな。人生は色々考え方があるけれど、運命に素直に従うのがいいみたい。沙希さんの運命は元々お見合い結婚して裕福な暮らしをゲットするようになっているんだと思う」
三人が三人とも違ったアドバイスだったので、結局沙希は自分で決めなくちゃならなくなった。それで、美登里の意見を参考に、お正月旅行に行った時に章吾の本当の気持ちを聞いて決めることにした。なので、お見合いはお正月休みの後の適当な日にお願いすると柳川哲平社長に返事をすることにした。もしも章吾が、
「そのお見合い、断ってくれ」
と言ってくれたら、沙希は会社を辞める覚悟をして、お見合い話を断ってもらおうと心に決めた。
サトルが、
「案ができたぞ」
と言って旅行の計画を沙希の所にもってきた。丁度マリアも居たので、三人でサトルが立てた計画について話し合った。話し合ったと言うよりも、沙希もマリアも分らなかったから、サトルの話を聞かせてもらったのだ。
「三泊四日にしたよ。お正月だと、樹氷はまだ見れないと思うけど、最初は山形の蔵王温泉にした。ロープウェーで上まで上がると綺麗な雪が見れるし、霧氷が見れるかも」
「あら、素的ね」
「泊まるとこは民宿にした。予算が厳しいから」
とサトルは笑った。
「温泉があれば、民宿でいいわよ。マリアにもその方がいいかもね」
と沙希が賛成した。
「蔵王の次は距離があるけど、高速を一気に走って、秋田の弘前城を見てから少し戻って大鰐温泉にした。大きなゲレンデとかあるし。最後は大鰐温泉から高速で青森に出て、青森港を見たら戻るってことにした。あまり距離を走ると疲れるから、途中の八幡平に泊まって、最後の四日目は東北道を一気に東京まで戻ることにした。一箇所で三日間のんびりするのもいいかなと思ったけど、ちょくちょくは行けないからこんなプランにしたよ」
サトルが広げた東北の地図を見たマリアと沙希はワクワクして話を聞いていた。
「章吾兄貴がこれでいいって言ったらこのプランにしようよ」
沙希もマリアも異存はなかった。
病院で章吾に旅行のプランをサトルが説明すると章吾は、
「いいんじゃない?」
と一発でOKを出した。
襲撃されて前後の窓ガラスを粉々にされた軽は、沙希がディーラーに頼んで修理をしてもらって、先日仕上がっていた。沙希は自分は車を動かせないから、当分預かってもらうように頼んだ。屋根は襲った奴等が飛び乗ったため、凹んでいたそうだ。
「最近の車は鋼板が薄いから、凹むんですよ。内側から持ち上げたらボコッと元に戻りましたから、多少跡は残ってますが、目立たないのでこのままにさせてもらいました」
とディーラーは説明した。ガラスの交換だけで済んだが、約六万円も取られた。
「保険が利くかも知れませんが」
とディーラーは尋ねたが、
「よく分りませんので現金でお支払いします」
と全額現金で払った。
「お正月、北の方にドライブしますので、タイヤを取り寄せておいてもらえませんか」
と頼むとディーラーは、
「交換はいつでもできますから、出かける前に寄って下さい。それまではこちらで保管をしておきます。交換工賃はサービスとさせて頂きます」
と答えたので、
「よろしくお願いします」
と頼んでおいた。
「よしっ、車はこれでよしっ」
沙希はお正月の旅行を楽しみにしていた。
「社長、先方はお正月休みにお見合いをとのお話しでしたけれど、お正月は前から決まっていた予定がありますので、お正月を過ぎた適当な日ならお受けしてもいいですが」
と沙希は柳川哲平に先日聞かれたことの返事をした。
「そうか、会ってくれるか。お正月過ぎでも全然かまわんと思うよ。正月半ばまでは年始回りとか多忙だろうから、一月半ば過ぎで調整しておくよ」
哲平は嬉しそうだった。
「所で、ご両親とは今は交流がないんだね」
「はい。なので、困ってしまって」
「じゃ、どうだろう。僕と家内が沙希ちゃんの親代わりってことにしたら何か具合が悪いことでもあるか」
「そんなぁ、具合が悪いなんてことはありませんけど、社長に申し訳なくて」
「それならいいんだよ。この際だ、話が先方と上手く行ったら僕が沙希ちゃんの親になってやろう」
予期せぬ社長の好意に沙希はほっとした。
十二月の半ばに章吾は予定通り退院した。毎日一時間程度病院でリハビリを受けることになっていたが、特に問題はないようだった。車の話をすると、
「悪いなぁ」
と言って章吾がディーラーから受け取ってきた。綺麗に修理されていたので、沙希は感心した。だが、章吾は左腕を動かすとまだ痛みがあるらしく、当分電車通勤にして、帰りは沙希と一緒にタクシーで戻ることにした。翌日から章吾は仕事に復帰した。
まだかまだかと待っているうちに、直ぐお正月になった。六本木の仕事は三十日でおしまいになった。
翌日の大晦日はロマンス通りの仲間とマリアも加わってお台場に遊びに行った。サングラスのサトルは明日長距離運転するからとマリアと一緒に、早めに引き上げて行った。
明けて元日、午前九時頃に要町の沙希のアパートから出発した。サトルは昨夜よく眠ったからと張り切っていた。
池袋から高速に上がると、元日の早朝だったので、車は空いていた。三郷のジャンクションから東北道に入り、蔵王を目指して走った。中古の軽とは言え、最近の軽自動車は良く走る。タイヤもスタッドレスタイヤに交換してもらったので、どんどんと走った。高速道路はサービスエリアで休むのも楽しい。それで、あちこちのサービスエリアで休みながら走ったので、蔵王温泉に着いたのは二時を回っていた。民宿に着くと、すぐロープウェーで山の上に上がった。
「寒~いっ!」
四人は異口同音に震え上がった。だが、サトルが言った通り美しい霧氷が見られて、みな感嘆の声を上げた。
民宿とは言え、蔵王温泉は設備の良い所が多い。お風呂も広く、温泉は良かった。部屋は正月で客が多く、四人で一部屋だった。食後、就寝前に四人でゲームをしたりして楽しく過ごした。
お正月だからと、朝食には雑煮が出た。沙希は久しぶりの家庭的な料理に満足した。マリアはお餅が初めてで、日本のトラディショナル(伝統的)なお正月料理を興味深そうに食べていた。
「今日は高速を沢山走るから」
とサトルは早々と車の整備に外に出た。雪国なので、ガラスが凍り、その上に昨夜少し降った雪が薄く積もっていた。マリアも沙希も雪が珍しく、車の整備を手伝った。
青森港に着くと、沙希はこの海を渡ると直ぐに北海道だと感激して冬の寒々とした海を眺めていた。気が付くと章吾が隣に立っていた。
「北海道はまだ行ったことがないのか」
「ん。あたし、まだなのよ」
「じゃ、暖かくなったら、一緒に北海道に渡ろう」
沙希は章吾のこの言葉に嬉しくなって、章吾の腕に手を回した。
「いててぇっ」
「あっ、ごめん」
章吾はまだ腕を動かすと痛いようだ。
大鰐温泉も民宿で、四人で一部屋だった。まだ外が明るかったので、四人でスノボーにチャレンジした。サトルは上手で、章吾は腕をかばって無理をしなかったが、沙希とマリアはサトルに教えてもらって、尻餅をつきながら楽しんだ。沙希は初めてだったが、転んでも全然痛くなく、雪の上のスポーツは魅力的だなぁと思った。
夜は昨夜の続きのゲームをしたり楽しかった。マリアもすごく楽しそうで、ずっと笑って過ごした。
最後の日は八幡平のホテルだった。最後なので、少し予算を頑張って、サトルがホテルに予約を入れておいてくれた。
「ツインを二部屋にしたけど、男と女に分かれる?」
とサトルが皆に聞いた。
「ダメッ。あたしサトルと同じ部屋がいい」
珍しくマリアがサトルと一緒がいいと言い張った。そうなると、沙希と章吾が同じ部屋だ。
「オレと一緒でもいいのか」
と章吾が沙希に聞いた。
「あたしなら全然平気」
それでサトルとマリア、章吾と沙希が別々の部屋になった。沙希は本当は章吾と一緒に泊まりたかったのだ。マリアのお陰で、それが実現した。
八幡平のホテルの温泉はすごく良かった。沙希とマリアは周囲が雪で囲まれた露天風呂に浸かって、珍しく晴れた満天の星を眺めていた。
「日本の温泉、いいな」
マリアは露天風呂がすごく気に入ったようだった。沙希は初めて椎名町の銭湯にマリアを連れて行って背中を流してあげたのを思い出した。あれからまだ一年間も経っていないのに、マリアは沙希の姉のようにすっかりと親しくなってくれた。
夕食は食堂でコース料理が出た。朝はバイキングだとか。久しぶりに静かなお洒落な雰囲気で四人でテーブルを囲んで食事をした。周囲に雪が積もっていると、音が反射せず、すごく静かだ。章吾とサトルはビール、沙希とマリアはワインにした。四人共ほろ酔い加減で部屋に戻った。
「明日の朝は十時に出発するから。東京に着くのは遅くなるけど、最後の日はお休みだから、夜中になってもいいだろ?」
とサトルが明日の予定を話してくれた。
「じゃ、寝坊をしようっと」
と沙希が言うと皆が笑った。
部屋で、章吾と二人っきりになれた。沙希は章吾の後ろからウエストに手を回してしばらく抱き付いていた。バイクで送ってくれた時はいつもこんな感じで、章吾の大きな背中を感じていれた。今もそんな感じが蘇ってきて沙希は章吾への激しい恋を感じていた。
「このまま時計の針が止まっていてくれればいいのに」
と呟くと章吾が振り返って、
「えっ?」
と聞いた。その目はとても優しかった。
沙希は思い切って大切な話を切り出した。
「章吾、あたし、今柳川哲平社長にお見合いを勧められてるの。どうしても断り切れなくて、十五日過ぎにお見合いをしなくちゃならないの」
言い終わると、胸がドキドキして、どうして良いか分からない位になった。沙希は章吾に、
「お見合いなんか止めろっ!」
と言って欲しかった。
それで、もしもそう言ってくれたら、今夜章吾に抱いてもらおうと心に決めていた。身も心も全部章吾にあげたいと思った。
章吾はしばらく黙っていた。何か考えているようで、目は遠くの方を見ていた。
「お見合い、したら?」
章吾のかすれるような囁きが聞こえた。沙希は頭をガァーンと殴られたように、ドキドキしていた胸が破裂したようになって、真っ青になって章吾を見ていた。
章吾と別々のベッドに潜り込んで、十一月に華道教室で使った花、あれは[唐綿]と言ったっけ? その花の花言葉[行かせてください]と[心変わり]を思い出していた。章吾に、[お見合い、したら?]と言われた時の衝撃がまだ収まらずに、涙が次から次から零れ落ちて枕を濡らした。
「お見合いをして、あたし、心変わりしちゃったらどうしよう。こんなに章吾のことを好きなのに」
頭から被った毛布の下から漏れる沙希の嗚咽は章吾にも聞こえていただろう。真夜中になっても、章吾はまだ眠っていない様子だった。沙希は明け方近くまで泣き続け、夜明け前に少し眠ったようだった。
二十七 この囁きを聞いて

沙希が真っ青な顔になって、自分を見つめたあの目を、章吾は一生忘れないだろうと思った。
猪俣章吾は長野県上田市に近い上田原で生まれ、地元の高校を卒業する前に、国立信州大学を受験したが、落ちたため、上田原に近い私立長野大学の企業情報学部に進み、学生時代に就活をしたが思う所に就職できず、卒業すると東京に出た。東京でも仕事が見付からず、友人の兄が経営する六本木のクラブ、ラ・フォセットで使ってもらえることになり、現在までそこに勤めている。
東京に出てきた時は、友達が少なかったが、ラ・フォセットがサトル(栗山智)が勤めている店からワインを仕入れたのがきっかけでサトルと仲良くなり、サトルの紹介で池袋のロマンス通りに集まる若者達のグループに入った。週末グループの仲間と遊んでいる内に、いつしか章吾はグループのリーダー格になっていた。
そんなある日、
「あたしを守って下さい」
と言って転がり込んで来た沙希に出逢ったのだ。
最初は他の女の子と同様に沙希に特別な感情を持ってはいなかったが、たまたま住んでいる場所が同じ方向だったし、沙希をラ・フォセットに紹介してからは、同じ会社に勤める同僚として、帰り道バイクの後に乗せて帰るのが日常的になり、次第に沙希に関心を寄せるようになった。そんなある日、沙希と唇を合わせてしまってから、沙希に対して自分の中に特別な感情が芽生えているのに気付いた。
沙希は自分を好いて、愛してくれていることを章吾も良く分かっていた。だから、最近では、いずれ沙希と結婚して幸せにしてやりたいと思っていたのだ。
だが、度重なる事故で、左肩の痛みが取れず、最後の事故で転倒した時に後頭部を激しく打って、医者は後遺症が出るのを心配していた。こんな状態では、自分が将来元通りに元気になるとの見通しがまだ立たない。
八幡平のホテルで沙希が、
「お見合いをしなくちゃならないの」
と打ち明けてくれた時、章吾の本当の気持ちは、
「お見合いなんか止めろっ!」
と叫びたかった。多分沙希も自分にそう言って欲しかったのだと思った。だが、残念だが、今の章吾には将来の自分の健康が不透明だったから、
「沙希を幸せにしてやる」
と、沙希の気持ちをしっかりと受け止めてやる自信がなかった。その結果、見合いを勧めてしまわざるを得なかったが、そんな自分が情けなかった。あの夜、章吾も顔には出さなかったが、心の中では泣いていたのだ。
ラ・フォセットに勤めるようになってから、沙希は綺麗になり、大人らしくなってとても素的な女性になっていた。だから、沙希を失ってしまったら、二度と沙希のような女性には出逢えないだろうとも思った。
八幡平から東京に戻る途中、章吾と沙希が無口になったのと対照的に、マリアは幸せいっぱいの顔で良く笑った。
八幡平の夜、サトルとマリアが部屋に戻ると、マリアがサトルに抱きついてキスを求めてきた。サトルもそんなマリアを抱きしめて、二人はそのままベッドに倒れこんで激しく愛し合った。マリアがサトルに身体を許してくれたのは初めてだった。サトルは夢中になってマリアを愛撫した。マリアが果てて、続いてサトルが果てた時、
「サトル、結婚してね」
とマリアが囁いた。
「ん。結婚しよう」
サトルはもうとっくにマリアを自分の嫁さんにしようと心に決めていた。そんなだったから、サトルもマリアも沙希たちの気持ちに気付かなかった。
ラ・フォセットで新年の初日に簡単な新年会があった。その日は招待客だけだったので、店は午後十一時に終わった。帰り仕度をしていると、柳川社長に呼ばれた。
「お見合いの日だけど、先方は多忙の様子で日曜日がいいそうだ。沙希ちゃんは大丈夫だよね」
「はい」
「それで、一月は日曜日が大安の日は三日で過ぎちゃったから、二月の七日の日曜日にしたよ。この日は大安だから」
「はい。あたしは大丈夫です。ありがとうございました」
沙希はいよいよかと思った。だが、もうジタバタしても始まらない。章吾のことが気にはなったが、覚悟を決めてお見合いすることにした。
沙希は華道教室で使った紫色のつる性の花[ストレプトカーパス]を思い出した。扱い難い花だったが、鉢の周囲にたらすとメインの花が生きて全体としていい感じに活けることができた。確か、あの花の花言葉は[このささやきを聞いて]とか[ささやきに耳を傾けて]だと先生から説明を受けたと思い出した。他にも[真実]言う花言葉もあると言っていた。
沙希はこの花言葉が今の自分の気持ちを表してくれているように感じていた。そして、もしかして、章吾さんの気持ちにも当てはまるのではないかとも思った。
二十八 お見合い
お見合いを経験した人の中には、堅苦しくて、せっかく出て来たご馳走が胃袋のどこに納まったかも良く分からんなんて人も居るだろう。
沙希は緑の森ガール美登里の意見を参考にして、結局はお見合いをすることにしましたと報告した。
「えっ? いつお見合いするの」
「仲人兼親代わりをしてくれる社長さんが二月七日が大安だからと、先方と調整して下さって二月七日の日曜日に決まった」
「どこでお見合いするの」
「もう、美登里お姉さまは突っ込みがキツイんだからぁ」
「だって沙希のこと、気になるもん」
と美登里は笑った。
「とにかく、時間あるときお茶しない」
「いいわ。いつものカフェーでいい?」
「いいよ」
「この前の質問に、沙希ちゃん答えてくれてないよ」
「ああ、お見合いの場所ね」
「どこ?」
「紀尾井町のホテルニューオータニにあるフランス料理店トゥールダルジャンですって」
「へえーっ、肩が凝るなぁ」
先ほどから沙希と美登里は恋愛結婚か見合い結婚かで盛り上がっていた。
「あたし、お見合いか恋愛かどっちが多いか調べてみたの」
と美登里が国立社会保障・人口問題研究所の調査データの内容を話してくれた。
「今どっちが多いと思う?」
「見合い結婚か恋愛結婚かどっちがってこと?」
「そう」
「そりゃ、恋愛の方が多いんじゃない? でもお見合い結婚したって話も聞くから五分五分かな?」
「アハハ、恋愛がダントツ多いのよ」
「へぇーっ? そうなんだ。じゃあたしって少数派?」
「そうよ。今時お見合いするなんて少数派よ」
そう言って美登里は笑った。
「今どれ位の比率なの」
「ちょっと古くて五年位前のデータだけど、両方初婚の夫婦全体を100とすると87・2%が恋愛結婚だって」
「両方初婚ってことは再婚は入ってないんだ」
「そうみたいね。再婚の場合は紹介とかお見合いとかがもう少し多いかもね」
沙希は恋愛結婚がそんなに多いのかと驚いた。
「あたしたちのおじいちゃんとかおばあちゃんの時代はね、七割がお見合い結婚だったみたいね。それが一九六五年位にお見合いと恋愛の比率が逆転したみたい」
「ふぅーん、そうなんだ」
「沙希ちゃんの彼、本当は沙希ちゃんにお見合いなんかして欲しくなかったんじゃない」
「あたしもそう思うんだけど、言葉ではっきりと言って下さらないと、お見合いの話を持って来て下さった方に自信を持ってお断りできなくて」
「そうよね。はっきりしてなかったら断るにも頑張り切れないわね」
美登里は沙希の彼のことを想いつつも、沙希の複雑な気持ちを理解してくれているようだった。
ずっと先だと思っていたのに、お見合いの当日は直ぐにやってきた。快晴で良い天気だったが、風がすごく冷たかった。
柳川哲平に、
「お見合い当日の衣装はラ・フォセットで用意させとくし、メイクさんにも言っておくから沙希ちゃんはいつもの通勤の服装で十時頃来なさい」
と言われていた。十時にラ・フォセットに行くと、いつものメイクさんが出てくれていて、ドレスアップも手伝ってくれた。
「きちっと着飾ると、あなた随分お綺麗ね」
鏡に沙希の後ろに立っているにこやかな顔の、初めて見る美しい女性が写っていた。振り向くと、
「ああ、私ね、柳川の家内です」
と自己紹介された。
「初めまして。これからよろしくお願いします」
「あなた、主人が言っていた通りの感じの方ね」
沙希は少しどぎまぎした。
「どうぞ続けて頂戴」
と彼女はメイクさんを促した。柳川社長が四十歳少し前なので、奥さんは多分三十歳半ばだろう。女優かモデルでもやっていたのか、なかなかの美人だった。
十一時半に社長のベンツに乗せてもらって、紀尾井町のホテルニューオータニに向かった。
約束のトゥールダルジャンの入り口を潜ると、ウェートレスが個室に案内してくれた。先方は少し前に到着したようで、待っていてくれた。
○○ホールディングスの社長米村は沙希の顔を見ると相好を崩して、
「やぁ、沙希さん、よく来てくれたね。さ、さっ、今日は固くならないで気楽にやろうや」
と言いながら奥の席に案内してくれた。
柳川夫人は米村夫人に丁寧に挨拶をしていた。米村善太郎の息子、善雄も沙希に軽く会釈した。
席は窓側から向かい側に米村善太郎、善雄、美鈴夫人の順に、沙希の方は窓側から柳川哲平、沙希、小百合夫人の順だった。皆が着席すると、飲み物が運ばれてきた。そこで、善太郎が、
「食事の前に簡単に自己紹介させてもらおう」
と言って、善雄、美鈴夫人を紹介した。普通は柳川の方から先にするのだろうが、善太郎はそれを制して自分の方から紹介した。続いて柳川が紹介してくれた。
「良き出会いを祝って」
と柳川が乾杯の音頭をとり、一同乾杯を済ませて食事となった。
「いやぁ、変な言い方だが、僕は前々から沙希さんを狙ってたんだ。沙希さんには悪いが、お店で良く観察させてもらったよ」
と善太郎が笑った。続いて善太郎と哲平がたわいのない世間話を始めた。経済界の動向や新政権の活動など話題は政財界の話だった。
その間、沙希はうつむいて話を聞いていたが、善雄と母親の美鈴をしっかりと観察していた。
善太郎は油がギラギラしているようなやり手のビジネスマンだ。それに比べて、息子の善雄はオヤジとは対照的に清々しい感じで、ひょろっとして、もやしのような感じのやつだと思った。それで、沙希は華道教室で花材として使った[スパティフィラム]が善雄のイメージに似てるなあなどと思っていた。隣の美鈴夫人は、会う前は宝石をチヤラチャラさせた厚化粧の女だろうと想像していたが、会って見ると、そこらのスーパーでレジを叩いている普通のオバサン風で、慌てて化粧をしてきたような感じで綺麗とは言い難い感じだった。飲みもののグラスに伸ばした手を見ると、水仕事で荒れたようながさがさとした感じだった。世界に名が通った大きな会社の社長夫人だからと色々想像していたが、見事と言っていいくらい予想が外れた。
善雄は一人息子だと聞いていた。だから結婚すればこの夫人と同居することになる可能性が高かった。
先ほどからうつむき加減で黙っている善雄と沙希に善太郎が声をかけた。
「アハハ、主役を差し置いて僕等ばかり話をしてもいかんなぁ。どうだろう、沙希さん、何か話をしてくれないか?」
沙希は哲平の顔を見た。
「遠慮しなくていいよ。思っていることをそのまま話してごらん?」
哲平は沙希を促した。
「では、失礼ですが……。お見合いをしてこのまま結婚することになりますと、後日そんなはずじゃなかったと思われることがあればお互いに不幸だと思います。それで、善雄さまにお願いですが、半年か一年間位お付き合いさせて頂いて、その間に普段着のわたくしを良く見て頂いて、それから結婚するかどうか決めて頂きたいのですが、よろしいでしょうか? わたくしとしては、善雄さまだけでなくて、奥様にもお付き合い頂いて普段着のわたくしの姿を見て頂きたいのですが」
善太郎はうんうんと頷いた。
「そうだ、そうするのがいいね。柳川君どうだろう、急がずに一年以内に決めさせたらどうだろう?」
哲平も同意した。美鈴夫人と小百合夫人もお互いに、
「そうよ。それ位慎重にして丁度いいわね」
と同意した。
「善雄、お前も黙ってないで沙希さんに何かお話をしたら?」
善雄はようやく口を開いた。
「沙希さん、では今後ゆっくりとデートに付き合って下さい。今日は初めてだから、細かいことは聞きませんが、いずれデートをした時に何でも話をして下さい」
と答えた。
「じゃ、今日はこれくらいでお開きにしよう。柳川君ちょっと上のバーに付き合ってくれ。善雄と沙希さんはここの庭でも散歩して、後は適当にやってくれ」
そう言い置いて善太郎と哲平は最上階のバーに行ってしまった。美鈴夫人と小百合夫人は、
「わたくしたちはちょっとお話しがありますから」
と二人で行ってしまった。残された沙希と善雄は言われた通り素直にホテルの庭を散歩することにした。二人は散歩の途中に携帯の番号とメールのアドを交換した。帰りは、
「あたし六本木のお店に寄ってから帰ります」
と沙希はホテルからタクシーでラ・フォセットに戻った。
二十九 派遣社員エレジー Ⅰ
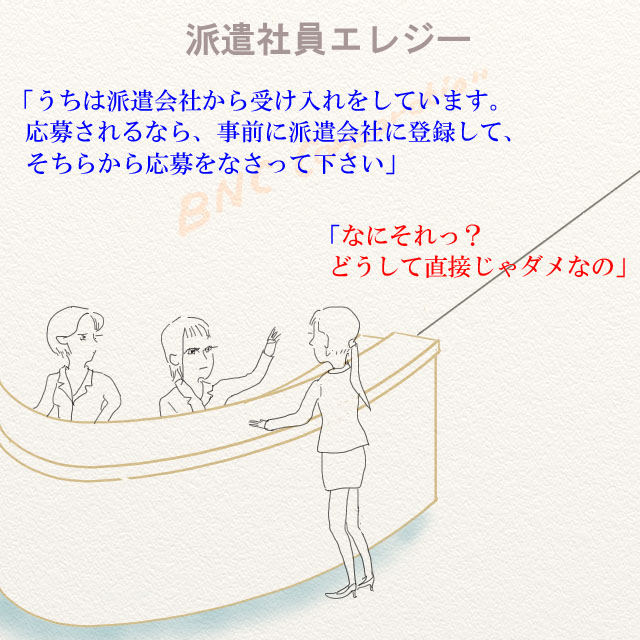
いつまで経っても、トンネルの出口が見えない、長引く就職氷河期の真っ只中を、緑の森ガールこと藤井美登里は毎日々々足を棒にして会社訪問を続けていた。
「もうっ、あたしって、なんてついてないんだろ」
今日も不発だった夕暮れ、やっかいになっている四谷の伯母の所に向かって、とぼとぼと歩いていた。
代官山、原宿、下北で買い集めた大好きな古着、ゆるいデザインのワンピやスカートは、ここのとこクローゼットの中に仕舞いこんだままだ。毎日着ていく洋服と言えば、大嫌いな黒いリクルートスーツばっかだ。
最近、面接なんて大嫌いになった。一番嫌なことと言えば、中年のメタボのオジサンたちがいっぱい並んで座っている部屋に入った瞬間だ。
名前を呼ばれて部屋に入ると、彼等が一斉に自分の身体を上から下までねちねちとしたエロい眼差しで射抜いてくる。彼等は自分を素っ裸にしてほっそりとした首筋から、オッパイやくびれたウエスト、それに程よくぷっちりと膨らんだヒップを舐め回すような目つきで見てくる。美登里はその瞬間から身体が強張って、質問の受け答えがぎこちなくなってしまうのだ。だから一日も早くこの氷河を渡り終えて内定通知をもらいたかった。一次試験のペーパーテストはパスするんだが、美登里はいつも二次試験の面接で落っこちた。
美登里は、桜で有名な皇居の千鳥が淵に近い三番町にある大妻女子大学文学部を卒業するまで、結局一通も採用内定通知を受け取ることができなかった。美登里だけじゃなく、クラスメイトの多くが内定通知を受け取れないまま卒業するはめになっていたから、そのことが幾分美登里の落ち込んだ気持ちを和らげてくれた。
美登里は、もう半年以上鎌倉の実家に帰っていなかったし、母にも気が重くて電話もしてなかった。だが、伯母には立場上就活の状況は報告していた。伯母は殆ど毎日のように母に電話をしてたわいのないおしゃべりをしているので、美登里が母に報告しなくとも、多分伯母からちゃんと情報が伝わっているのだろう。
就職口も決まらずに大学を押し出されてしまった美登里に伯母は、
「美登里さん、よかったらこのままここに住んだら」
と優しい声をかけてくれた。それで、美登里は渡りに舟と四谷の伯母の所に居座ることにした。
自分より年下の、親しい友達の沙希は今では毎月手取り百万円以上を稼いでいると聞いていた。沙希との出会いは自分がデジカメで撮影した事故の目撃情報がきっかけだった。その沙希が二月に大会社の御曹司とお見合いをするのをどうしようかと相談を受けた。美登里の気持ちはそれどころではなかったが、友達の人生の行く末を決める大切な相談だったので、真面目に返事をした。どうやらその後、上手く進んでいる様子だ。自分は今氷のような冷たい世間の風に立ち向かって戦っているのに、世の中は不公平なものだと美登里は自分勝手な不満をぶちまける相手も居なかった。
世の中は冷酷だ。就職口が決まらず、美登里は仕方なく派遣社員募集の広告を見て応募した。だが、ここでも門前払いをくらってしまった。
問い合わせた窓口に出た女性から、
「うちは派遣会社から受け入れをしています。応募されるなら、事前に派遣会社に登録して、そちらから応募をなさって下さい」
だって。
「なにそれっ? どうして直接じゃダメなの」
美登里はやけっぱちになって強い口調で聞き返した。
「あなた、世間をご理解されてませんね。直接採用すると何かとこちらが面倒なんですよ。派遣会社からなら経費で落せますが、直接採用すると人件費になるの、あなたご存知でしょ」
「……」
美登里は相手が言っている意味が良く理解できなかった。理不尽な話だ。美登里が答えないでいると、電話を切られてしまった。
仕方なく、派遣会社をインターネットで探してメールすると、手続きは簡単だった。美登里はここでも唖然とした。今まで面接を数限りなく受けて苦労してきたのに、履歴を入力してクリックすると、
「ご登録ありがとうございました。後ほど弊社から必要書類他資料を郵送しますので、折り返しご返送下されば手続きは完了です」
とメッセージが出た。
数日すると書類が郵送されてきた。規約を見ると、どうやらこの会社に登録をしておくと、仕事が見付かったら携帯に連絡が入るらしい。説明では仕事は沢山あるのでご安心下さいなどと書いてあった。
美登里の携帯に派遣会社から登録完了通知メールが届いた。
後で聞いてみて分ったことだが、この派遣会社に登録している者はなんと六千名以上も居るらしい。
「一体世の中の仕組みはどうなってんだろ」
美登里の中に新たな疑問が芽生えていた。
三十 派遣社員エレジー Ⅱ
美登里の携帯に派遣会社から[重要なお知らせ]と言う題名でメールが届いた。
[四月一日木曜日から、西新宿××商事㈱に出社して下さい。委細は人事担当の井吹さんを訪ねて指示に従って下さい]と言う書き出しで派遣先の会社の電話番号と住所、朝八時半までに出勤することなどが書かれていた。
美登里は携帯メールの指示に従って、その会社に出かけ受付で、
「人事の井吹さまはどちらへ行けばよろしいのですか」
と聞いた。
「ご用件は?」
「派遣会社から井吹さまを訪ねるようにと」
「あらそう。そっちのエレベーターで七階に上がって人事部に行って下さい」
受付の女の子は自分より二つか三つ年上と見えたが、派遣と聞いたとたんに蔑むような顔に変ってぞんざいに教えた。美登里はこれ位の洗礼は覚悟をしていたから気にもせずにビルの七階に上がった。確かに人事部と書かれたドアーがあった。ドアーを開けて中に入ると十人ほどの若い男女がぼけーっと突っ立っていた。通りがかった男に、
「井吹さまは……?」
と声をかけると、
「あっ、派遣ね。そこの人たちと一緒に待ってて下さい」
と言って忙しそうに行ってしまった。そこの人たちと言えばぼけーっと突っ立っている奴等だ。美登里はその中に入った。男が四人、女が美登里を入れて七人だ。すると少しして男が一人、女が三人遅れてきて加わったので合計十五人だ。
八時半になると井吹と言う年配の女が近付いてきた。手に持ったA4の紙切れを見て、
「男性のAさん、Bさんは五階の営業三課、C、D、Eさんの三人は八階の新プロへ行って下さい。女性はA、B、D、B、E、Fさんの六人は五階の営業三課、GさんとHさんはこの階のあちらの営業一課、残ったIさんとJさんはこの下の階の営業二課に行って下さい。それぞれ配属先に行けば仕事の指示があります。何か分らないこと、困ったことがあれば私に聞いて下さい」
そういい終わるとさっさと立ち去った。
美登里はIさんだったから、この下の営業二課だ。Jさんと思われる女と目配せして、二人で階下の営業二課に行った。
「あたし、藤井と言います。よろしく」
「あ、あたしは土屋です。よろしくね」
エレベーターの中で自己紹介を済ませた。二課に行くと山田と言う女が応対した。
「ちょっと待てて」
と奥の係長らしき男に一言告げると男が席を立ってやってきた。
「篠原です。今日からあんたたちの上司になります」
「おいっ、金本、ちっと来てくれ」
と若い男を呼んだ。
「派遣の二人だ。君に任すから適当に使ってくれ」
上司だと名乗った男は席に戻り、今度は金本と言う男がふたりを窓際の小さなテーブルに案内して、
「ここがあんたたちの今日からの仕事場です。適当に座って仕事をして下さい。仕事はこのフロアーに居る人たちが色々言いつけますが、言われた通りに処理して下さい」
と折り畳み椅子を指さした。
「早速だけど、この資料を原稿に、二人で手分けしてワープロに入力して下さい」
と分厚い資料をテーブルの上にどさっと置いた。
「いつまでですか」
と土屋が聞いた。
「早めにやってよ」
そう言って去りかけたので、
「ワープロはどれを使っていいのですか」
と美登里が聞いた。
「あそこのノートパソコンを持ってきて適当に使っていいよ」
隣のテーブルの隅に三台ノートが置いてあった。美登里と土屋はそれを自分達のテーブルに運んできて開いた。電源ケーブルをつなごうとしたが、コンセントが見付からない。探していると、通りがかった男が、床の上の丸い蓋を開けて、
「ここだよ」
と教えてくれた。
二人が並んでワープロを打ち始めると、別の男がやってきて、
「これコピー十五部」
と十枚綴り位のA4の資料を置いて行った。男がどこに座るのかを確かめて、美登里がコピー機の方に行った。
「あれっ? 動かない」
まごまごしていると近くの女が、
「あんたたちの暗唱番号は9696よ。苦労苦労と覚えておくといいわよ」
と言った。言われた通り9696とテンキーで打ち込むとコピー機の画面が出た。美登里は十五枚ずつコピーして、ページ順に並べているとさっきの女が、
「バカねぇ、最初に機械にセットしとけば機械がページ順に仕分けをしてホッチキスで留めてくれるわよ。何も知らないんだからぁ、役に立たないわね」
と意地悪な顔で教えた。
「最初にちゃんと教えてくれれば苦労しないでも済むのに」
と美登里は心の中で呟いた。ずっと後で分ったことだが、事務機の使い方は派遣会社が事前にきちっと教育をして送り込む契約になっているらしい。その基礎教育を派遣会社は全くやっていなかったと言うことになるのだ。
終業の五時近くになって、金本がやってきた。
「今日新人の歓迎会があるから。今日入った子は定時で帰るから。もちろん僕も」
と言った。
「えっ、あたしたちも歓迎会に出るんですか」
と土屋が聞くと、
「あんたたちは派遣だから関係ないよ。あそこに座ってる可愛い子だよ」
と答え、
「これ、あの子が残した仕事だけど、明日の朝までにやっといて」
とまた別のワープロの仕事を置いて行った。
「クソッ、[可愛い子]だけは余分だ」
美登里は腹が立った。その可愛い子は自分達と違って、新しい事務机に座り、周囲の男たちからちやほやされていた。今日入社したなら、多分自分と同い年だ。後で分ったことだが、その可愛い子は正社員で、初任給は美登里たちの1・5倍ももらうそうで、勿論賞与もあるのだとか。美登里たちは派遣会社との契約で月収十五万円で賞与はなしだった。
美登里と土屋はその[可愛い子]がやり残した仕事を片付けるのに一時間半も残業して六時半にようやく仕事が終わった。見ると、先ほどコピー機の扱いを教えてくれた女も派遣らしく、歓迎会には呼ばれてなくて、残業をしていた。ずっと後で分ったことだが、ここでは女子は正社員が三割で残りは全部派遣だったのだ。
三十一 派遣社員エレジー Ⅲ

沙希が米村善雄とお見合いした後、章吾は沙希のことを想う気持ちをなかなか断ち切れなかったが、沙希の幸せを考えて自分は身を引こうと決めていた。このやるせない気持ちを、章吾はリハビリと体力回復に打ち込むことで鎮めようと努力していた。
章吾の努力は体力の回復になって現れてきた。三月を過ぎると肩の痛みが退いて、今では腕を動かしても痛みを感じなくなった。担当の医師も驚くほどの回復を見た。それで、二月中は毎夜軽自動車で沙希と一緒にアパートに戻っていたが、三月に入ってバイクで通勤できるようになった。沙希は運転免許を持っていなかったが、二月から三月、毎日教習所に通ってようやく免許を取った。
沙希が軽を動かせるようになったので、章吾は米村のことを考えて、沙希に軽で通勤するように勧め、自分はバイク通勤をするようにした。
美登里は沙希の誘いで、日曜日の夕方、池袋のロマンス通りに集まる若者のグループに入れてもらった。友達が友達を誘い、仲間の数は三十人近くに増えていた。そこに集まる女の子はリーダーのモモをはじめ、十二人になっていた。勿論沙希と同棲しているマリアも居た。美登里は毎日むかつくことばかりある派遣の仕事にいい加減嫌になっていたが、さりとて辞めたら他に行くあてもなく、我慢の連続を強いられていた。だから、ロマンス通りに集まる仲間たちと一緒の時はとても癒された。それぞれ仕事は違っているが、皆優しく、仲間の苦しみや心の傷をお互いに分かち合うようにして楽しく過ごせた。
日曜日には大抵、沙希が付き合っていた猪俣章吾も来ていた。章吾はグループのリーダー格で、いつもサングラスをかけているサトルたちとグループを引っ張っていた。そんな章吾にいつしか美登里は惹かれている自分に気付いていた。無口だが男らしい所が好きだった。
その日、美登里は派遣先の会社でいつもの通りワープロの仕事をしていた。そこに金本がやってきて、
「これ、今から始まる重要な会議用の資料なんだ。二十部を大至急コピーして、新入社員の女の子に渡してくれないか」
と原稿を持ってきた。
「はい、かしこまりました。二十部ですね」
「そうだ、急いでくれ」
それで美登里は急いでコピーをして、間違いがないか、部数やコピーミスを確認して、例の可愛い子と言われた新人さんに届けた。
「二十部あります。急いでいるようですから」
と念を押して渡した。彼女は、
「あ、そう」
と言って受け取った。
例の可愛い子の新入社員は、美登里からコピーを受け取ると会議室に小走りに届けに行った。途中人とすれ違いざまに、コピーを落としてぶちまけてしまい、散らばった資料を慌てて集めた時、一部踏んづけて汚してしまった。
「参ったなぁ。まっいいか、一部や二部は予備があるはずだ」
と呟いて、残りの十九部を会議室に届け、席に戻ると汚れた一部はシュレッダーにかけて捨ててしまった。
美登里は席に戻ってワープロの仕事を続けていた。お昼少し前、ちょっと手を休めて自分で疲れた首筋を揉んでいると急に、
「資料をコピーしたやつは誰だっ!」
と大声が聞こえた。振り向くと、可愛い子を篠原係長が叱っていた。彼女は平然とした顔をして、美登里を指さした。それで篠原は美登里の所に飛んできた。
「あんたなぁ、金本君に二十部コピーしろと言われただろ」
「はい。二十部と聞いております」
「何で一部足りないんだよぅ」
篠原は相当に怒っていた。
「分りません」
「バカを言えっ、大事な会議で配ったら一部足りなかったぞ。おかげて役員に叱られたよ」
かなりご機嫌が斜めだ。
「コピーしてからちゃんと部数を確かめなかっただろ?」
「いいえ、きっちりと確認致しました」
「じゃ、何で足りないんだ。これだから派遣は仕事がいい加減で困るんだよ。今度あんたの会社にビシッとクレームを付けてやるからそのつもりでいろよ」
篠原は大きな声で怒鳴っていたから、もちろんあの新人さんにもはっきりと聞こえていたはずだ。だが、彼女は涼しい顔をしていた。
美登里は返す言葉がなかった。
「すみません。以後気を付けます」
と謝るしかなかったのだ。この様子は初日にコピーのやりかたを教えてくれた派遣のベテランの女性も聞いていた。彼女は、可愛い子の新人さんが席に戻ってから一部をシュレッダーで粉砕している所を見ていた。だが、彼女はこの件について何も言わなかった。隣の土屋は美登里が丁寧に部数を二度も確かめたのを見ていた。だが土屋も何も言わなかった。
夕方、コピー機の操作を教えてくれた派遣の女性が、
「お二人さん、今夜ちょっと飲みに行かない? 他の人も誘って」
と言って来た。美登里は今日はむしゃくしゃしていたから行きたくなかったが、せっかくのお誘いなので、
「分りました」
と返事をした。
集まった派遣の女性は美登里と土屋を入れて十人だった。西新宿は値段が高いからと皆で歩いて西部新宿駅近くの歌舞伎町にある飲み屋に連れて行かれた。
「実はね、今夜は藤井さんを慰める会なの」
と赤羽と言うコピー機の操作を教えてくれた女性が皆に言った。彼女は今日昼間起こったコピー事件のことを皆に話し、
「じつはあたし、あの新人の正規入社の子がミスしてシュレッダーで一部廃棄したのを見てたのよ」
と美登里を哀れむように皆に説明した。
「藤井さん、悔しかったでしょ? でも、これが派遣の現実よ。これからもたまに事件が起こると思うけど、そんな時はみんなで集まって慰め会をやりましょうね」
と付け加えた。
その後は派遣の理不尽な扱いについて話が盛り上がった。だいぶアルコールが回ってくるとみんなの本音が出た。
「昔はね、派遣と言えば外国語の会話ができるとか、翻訳ができるとか、法律に詳しいとか特別な技能を持った人に限られていたの。法律でもちゃんと決められていたの。所が、最近になって政府が規制緩和とか言って、普通の事務の仕事とか、組立作業とかそんな誰でもできるような仕事でも派遣社員を使えるようにしたのよ。これって政治が悪かったのね。派遣を雇った費用は経費で落ちるから、会社としては文房具を買うのと同じレベルで派遣は人間扱いでなくて、物と同じ扱いね。だから、必要がなくなったらさっさと契約を打ち切って捨ててしまうのよ。お給料だって正社員の五割から七割のとこが多いし、賞与もないとこが多いし。それを前の政権は法律で認めて正当化しちゃったのよ。だからすっごい格差社会になっちゃったのね。今日みたいに、正社員がミスしても派遣に責任を押し付けて、当の本人は知らん顔でしょ。ほんと、こんな理不尽なことって他にある?」
美登里はみなの話を聞いて、最初に派遣社員募集の広告を見て電話をした時、電話を受けた人の説明の意味が少し分ったような気がした。
飲み会が終わったら十二時近くになっていた。美登里は少し酔いが回って、夜風に当たって散歩して帰るからとみんなと別れて、十二時になっても大勢ぞろぞろ歩いている歌舞伎町の街を歩いていた。少し静かな所を歩きたいと思って、人影の少ない路地に入った。
その時、三人か四人若者が現われて、
「そこの可愛い子、ちょっと付き合ってよ」
とナンパしてきた。美登里は聞こえなかったふりをして通り過ぎようとした時、一人が美登里の腕をつかんだ。
「今、聞こえなかった? もう少しおいらと遊ぼうよ」
男たちは四人居た。その中の一人が、
「やっちまえ」
と言うなり美登里を抱きすくめた。
「やめて下さい」
男たちは聞かなかった。前から抱きついた男を振り払おうとすると、もう一人が後から抱きすくめて美登里の乳房を揉んだ。美登里の身体は固まってしまって、声も出ない。前から襲った男は美登里のヒップに手を回しヒップをいじり始め、スカートをまくって手を入れてきた。
「助けてぇ」
と美登里は声を出したつもりだが声にはなっていなかった。
三十二 章吾の優しさ
藤井美登里は鎌倉の旧市街小町の瀟洒な高級住宅街で育ち、高校まではお嬢様学校の湘南白百合に通い、大学は三番町の大妻女子大を出た。そのため、幼少の頃から男性には縁遠く、今まで父親以外の男に身体を触られるなんて経験は全くなかった。だから、歌舞伎町の路地でナンパされそうになって、突然男に身体のあちこちを無遠慮に撫で回された時、全身に恐怖が走り、身体がすっかり固まってどうにもすることもできなかった。助けを呼ぶ声さえ、喉で掠れて声にもならなかった。
男たちはそんな美登里を面白がってスカートをまくり、ブラウスの裾を引っ張り出して手を突っ込んで可愛らしい乳房を揉みしだき、乳首をつまんだり、トレンカから手を突っ込み、パンティーの裾から容赦なく指を入れてきた。力のある男たちに羽交い絞めにされた美登里は若い娘のこの世の地獄を経験させられていた。
ついに美登里は男たちの悪戯に耐えられなくなって、大きな声で泣き始めた。
その日、猪俣章吾は社長の柳川哲平に呼ばれた。
「すまんが、これを大久保の小泉八雲記念公園の脇にある淺沼組の組長に届けてくれんか」
哲平は風呂敷で包まれた重い大きな箱を指さした。
「大事な借り物だ。丁寧に運んでくれ。届けたら家に帰っていいぞ。報告は明日でいい」
でかい荷物なのでバイクには積めない。それで電車で行くことにした。淺沼組に着くと、組長はまだ会社に居た。
「おっ、戻ってきたか。そこに置いてくれ。ご苦労だったな。あんた電車で来たんだろ」
「はい」
「じゃ、そこらで一杯付き合わんか?」
「はい」
それで、近くの居酒屋に連れていかれた。暖簾を潜り席に着くと小奇麗な女将さんが、
「あら初めて見る顔やね」
と章吾にお絞りを渡した。
「哲さんは元気かい」
「はい」
「この不景気の中、相変らずしっかりやっとるようだな」
「お陰さまで」
「あんた、荷物の中味を見たんか」
「いいえ」
「知りたいやろ」
「……」
「アハハ、あんたもいい男だなぁ。わしらの仕事は何でも知りたがる奴はダメなんや。あんたは合格やで」
と笑った。
「うちはな、哲さんとこに若い衆を何人も送りこんどるんや。デカあがりの溝口もここのとこいい仕事をやっとるそうじゃないか」
「はい。溝口さんには世話になってます」
「あれもいい男だ。仲良くしてやってくれ」
「そんな、自分よりずっとすごい人ですから、普段尊敬してます」
「そうだ、あの包みの中味だがな、ゴールドのインゴットが二十個入ってたんだ」
「1kgの金塊ですか」
「そうだ。わしのとこは哲さんのとこの秘密の貯金箱だよ」
組長はまた笑った。
「あんた金相場を知っとるか? ここのとこドルの為替相場が悪くてな、みなが金を買い捲るから1grで今日の相場は三千七百円にもなっとる。二十だと七千万だよ。あんたは今日七千万を運んできたのよ。昔は1grで六千円を越えた時もあったな。だからよぅ、金相場はまだまだ上がるよ。去年の暮れで三千五百、その内あの二十も軽く一億を越えるやろ。金は安全だ。うちの蔵に積んどくだけで勝手に財産が増えるんや」
「……」
「他にもわしのとこで貸した大事なもんも一緒だったから重かっただろ」
「はい」
組長は大事な物が何だったのかまでは教えてくれなかった。組長が連れて来てくれた小料理屋はネタが良くて美味かった。酒は奈良の[風の森]と言う純米大吟醸でこれも美味かった。
「ここの女将の実家が奈良でな、いい酒だ」
組長が酔い加減になった所で章吾は失礼することにした。
「おい、女将、この猪俣も可愛がってやってくれ。こいつは六本木の哲さんが目をかけてる奴だ」
女将は色っぽい目で章吾を見て、
「よろしゅうに」
と頭を下げた。
浅沼組長に礼を言って、章吾は新宿駅の方に歩いた。八雲記念公園から新宿駅へは歩いて二十分と少しかかるが、酔い覚ましも兼ねて歩いた。
人通りの多い道は歩き難い。それで、章吾は職安通りを突っ切ると歌舞伎町の裏通りを歩いた。丁度西部新宿駅に近いヴィンテージホテルの裏側あたりに差し掛かった時、路地裏で四人位のガキに苛められてる女を見かけた。章吾は様子を見ようと近付いた。
こんな場合素人は、
「おいっ」
とか
「何してんだよ」
とか声を出すものだ。だが、玄人のアサスン(刺客)は声を出さずに無言で相手を倒す。章吾は溝口に、こんな場合の立ち回りや居合い、間合いの取り方などを訓練してもらっていた。
章吾は無言で近付くと、さっと蹴りを入れて二人を始末した。
「ヤベェッ!」
他の二人は章吾に殺気を感じたのか、倒れた二人を引き摺るようにして逃げて行った。
そこに、足首を押さえて泣いている女がいた。
「大丈夫ですか」
章吾が声をかけた。美登里は[大丈夫ですか]と声をかけた男の声に何か覚えがあった。あたりは薄暗くて顔が良く見えなかったが、男のシルエットを見て、章吾さんだぁっと分った。
「もしかして章吾さん?」
美登里は泣き声で聞いてみた。章吾は自分の名前を呼ばれて、もう一度女の顔を良く見た。顔をくしゃくしゃにして泣いている美登里だった。
「美登里?」
「はい」
「悪戯されてたのか?」
「はい」
美登里は救われた安堵と救ってくれた男が恋しい章吾だったので胸がいっぱいになって無意識に章吾に抱きついてまた泣いた。
「足、挫いたのか?」
「みたいです。痛くて」
路地は飲食店から出されたゴミのせいか饐えた臭いが漂っていた。道に倒れこんだ美登里の服も汚れていた。
「救急車は大げさだし、この時間だし、良かったらオレのとこで休んで行かないか」
美登里はこくんと頷いた。
「この近くですか」
「ん。タクシーなら直ぐだよ」
章吾は美登里を抱きかかえて職安通りまで出てタクシーを拾った。
「椎名町」
章吾のアパートには直ぐに着いた。美登里は入るのを躊躇ったが章吾に促されて部屋に入った。
「シャワーを一人で使えるか」
「はい、なんとか」
「じゃ、シャワーで汚れたとこを洗って来いよ」
「はい」
直ぐに美登里がシャワーを使う水音が聞こえてきた。美登里は男たちに触られ辱められた部分を丁寧に洗い流した。
章吾は肩を痛めた時に病院でもらって一杯余っている包帯や湿布薬を取り出した。それと自分の洗濯してある下着やシャツ、ジャージーの上下も取り出した。美登里が出て来ると、
「これ着ろよ。オレのででかいけど」
と下着とシャツなどを出した。洗濯して綺麗に畳んであった。美登里は素直に従った。美登里の身体はそう小さくはなかったが、章吾の物を着るとダブダブだった。手を広げたら章吾が笑ったので美登里もつられて笑ってしまった。
「こっちに来て、この椅子に座れよ」
椅子に座ると章吾は挫いた方の足を持って動かしたり指で押さえたりした。
「こうすると痛いか?」
「はい」
「どうやら骨折はしてないな。良かったよ」
そう言って湿布薬を塗って、その上に絆創膏を貼り、包帯でグルグル巻きにした。
「うまくすれば明日には痛みが退くと思うよ」
「章吾さん、ありがとうございました」
「オレ、コインランドリーに行ってくるからさぁ、そこでテレビを見てるか、ベッドで寝ててよ」
と言って章吾は美登里が脱いだ下着や洋服をかき集めてビニール袋に入れた。
「章吾さん、いいです。そのままにしておいて下さい」
と美登里は遮ったが、内心章吾の気遣いと優しさに涙がこぼれるほど嬉しかった。
ベッドは章吾が新しいシーツに取り替えてくれたらしく、ほんのりと洗剤の香りがした。しばらくテレビを見ている間にいつの間にか美登里は眠ってしまった。
章吾がコインランドリーから戻ると、テレビを点けっ放しで美登里はすやすやと眠っていた。先ほどは泣き顔だったが、寝顔は可愛かった。章吾は美登里の下着や洋服のしわを伸ばして畳み終えると、自分も畳みの上に毛布を敷いて包まって眠った。
朝物音で美登里が目を覚ますと、章吾が小さな流しでレタスを洗って皿に乗せているのが見えた。時計は午前七時を回っていた。章吾が美登里が起きたのに気付くと、
「シャワー使ってこいよ」
と声をかけた。
「あのぅ、包帯が……」
「新しいのと取り替えてやるよ」
「はい」
美登里は大人しくシャワーを使いに行こうとしてベッドの足の方を見た。そこに綺麗に洗濯された下着や洋服が畳んで置いてあった。それを取ると、美登里は風呂場に入った。シャワーを使ってから下着や洋服を自分のに着替えた。出ると、
「足を見せろ」
と言われたので椅子に座った。痛みは取れていた。
「どうだ?」
「だいぶ良くなったみたい」
「どれ」
と言って章吾が確かめた。
「捻挫は後のケアをちやんとやらないとダメだ」
そう言ってまた足に薬を塗って包帯をしてくれた。
「パンでも食って行けよ」
それで章吾が作ってくれたトーストとベーコンエッグにミルクで朝食を済ませた。
「西新宿なら、朝は混んでいるけどタクシーで三十分もあれば行けるよ。包帯は夜家に帰ってから外せばいいよ」
「何から何までありがとう」
「気を付けて行けよ。まだ無理はするなよ」
そこまで送って行くからと章吾は目白通りまで送ってくれて、タクシーを拾ってくれた。タクシーが来ると、
「おつりは彼女に渡してくれ」
と章吾が一万円札を運転手に渡した。タクシーは直ぐに走り出した。後を振り向くと戻る章吾の後姿が見えた。
気が付いて見ると、美登里は財布の中に五千円位しか入ってなかった。昨夜急に飲み会に誘われて割り勘したので少ししかなかった。だから、章吾がタクシーの運転手に渡してくれたお金がありがたかった。
思わぬ不幸に巡り合った結果、美登里には予想だにしなかった幸せの一時が訪れたのだ。この時、美登里ははっきりと章吾への[愛]を感じていた。
「自分の大切な人を見付けちゃった」
美登里の中にほんのりとした余韻がまだ残っていた。
昨夜の飲み会で、美登里には心の通う仲間達が出来た。それは隣の土屋も同じだっただろう。人の幸せはお金では買えないものだと、美登里はそんな風に思えた。
三十三 米村善太郎と息子の善雄

埼玉県の秩父の農家に生まれた米村善兵衛は第二次世界大戦中徴兵されて中国の戦地に送られた。幸い戦死をせずに終戦後実家に戻ることができた。だが、当時はどこも敗戦で疲弊しており、食糧難のため周囲は冷たかった。仕方が無く、善兵衛は東京に出て、板橋区の小豆沢町と言う所に借家を見つけて移り住んだ。当時はどこを見ても仕事が無く、その日食べる食料さえなかなか手に入らない厳しい時代だった。それで、善兵衛は今で言う廃品回収業のような仕事を見つけて、リヤカーを引いて廃品を譲り受けて回り、居間を仕事場にして、廃品を手直ししてまた売り歩き、何とか糊口を凌いでいた。
あれは忘れもしない一九五〇年六月二十五日、突然朝鮮半島の北部の社会主義を目指す人民軍が南側の自由主義を目指す人民に戦争を仕掛けた。世に言う朝鮮動乱の勃発だ。一時は朝鮮半島全域が北朝鮮側に侵略されてしまう勢いだったが、米国や英国の連合軍が加担して今の韓国にあたる南側の人民戦線を支援した。その時、米軍は軍需用品を日本から調達したので、戦線が激しさを増すに従って、日本では軍需用品の需要が増えて、産業界が息を吹き返した。特需景気だ。
特需景気は善兵衛の仕事にも波及した。善兵衛は日用品の修理から軍需用品の修理に切り替えて仕事をしている内に兵器用部品の製作や修理の仕事が舞い込み、借家を工場にしてしまって人を雇い毎日多忙な日を過ごすことになった。
だが、朝鮮動乱は一九五三年七月二十七日に停戦となり、あっと言う間に特需景気はしぼんでしまった。わずか四年足らずだ。
仕方が無く、善兵衛はそれまでに増やした設備を使って、当時次第に需要が回復してきた国内用の日用品の製造に切り替えた。つまり調理用の鍋や釜、魚を焼く網など色々な物を手がけた。当時はそれらが飛ぶように売れてたが問屋が安い工賃で仕事をさせるので儲けは少なかった。
この時、会社を法人(有限会社)にして、屋号を米村工機とした。
特需景気の恩恵で仕事が多忙になり善兵衛が三十六歳になった時、善兵衛の所に事務員として入った喜代と結婚した。喜代は三十二歳で、許婚が戦死して独身だった。結婚後間もなく長男が誕生した。善兵衛は自分の名前から一文字取って善太郎と名付けた。
その後小さな会社にも職人が増え、十人にもなっていた。勿論喜代も善太郎をおんぶして仕事を手伝っていた。だがにわかに集めた職人の中には怠け者でどうしようもない奴も居た。その中の一人を解雇したが、解雇された男はそれを根に持って、ある時仕返しに喜代を自分の家に引っ張り込んで、嫌がる喜代を押さえつけ強姦した。今で言うレイプだ。その男は喜代に、
「今回限りにしてやる。その代わり誰にも言うな」
と約束させて喜代を帰した。その後男は約束を守り喜代に纏わり付かなかったので、喜代は善兵衛にも、他の誰にも強姦されたことを言わなかった。
一人息子の善太郎は家が貧しかったので、小学校を卒業すると、中学、高校共に夜間部に通い、昼間は家業を手伝った。そのため高校を卒業できたのは二十歳の時だ。高校を卒業すると、早稲田大学の夜間部の第二工学部に進学した。当時夜間部は然程競争率が高くなかったから、ストレートで進学できた。専攻は精密機械にした。昼間はオヤジの会社の仕事をしたが、在学時から善太郎は将来米村工機がどんな方向に進むか考えていた。いつまでも鍋釜を作っていては面白くない。それには米軍の軍用部品の知識がおおいに役立った。当時、米軍が使用していた計測器や通信機は旧日本軍が使用していた物よりも技術的に数段勝れていて、装置の中には小型の回転器もかなり使われていたのだ。善太郎は軍用部品の中の回転器部分に着目して、在学中から軸受けの研究に力を入れた。壊れた物を修理すると、新しく組み立てるよりも多くの知識を習得できる。特に良く壊れる部品は部品の弱点を如実に表し、改良の知恵も習得できたのだ。
在学中ではあったが、善太郎は米村工機で小さな軸受けの研究開発を進めた。だが、当時は軸受けと言えば、鉄道車両用や自動車の車軸用の中・大型が主流で小型の軸受けの需要は少なく、主に大学や企業の研究所向けに細々とした受注しかなかった。それでも善太郎は球がたった三個しかない円錐形のピボット軸受けや直径が極めて細い軸の高速回転用にサファイアを使った軸受け、毎分二万回転以上の超高速回転用の空気の分子で浮かす軸受けなど次々とユニークな製品を開発していた。
所が、当時は円の対ドル為替レートが三百六十円で、今の三分の一以下の円安だったため、一九六〇年代中程から国内で生産された製品の輸出が飛躍的に伸び始めた。それに伴って現在の中国のように、日本は驚異的な経済成長の時代に入った。特に一九七二年に日本列島改造論を掲げて登場した田中角栄内閣の政策が当たり、日本は長期にわたり経済成長を続けることになった。それに伴って、家電製品、オーディオ製品、物流用機器などなど広い分野で小型軸受の需要が拡大して、米村工機も驚異的に売上を伸ばしていた。
米村工機は工場の拡張を繰り返し、従業員が三百名を超えた時に、善太郎は善兵衛から会社を引き継ぎ、株式会社米村工機の取締役社長に就任した。この時、善太郎はまだ独身だった。
この頃から、米村工機は小型軸受の専業メーカーとして業界の地位を確立しつつあった。
善太郎が仕事に邁進していた頃、東京足立区の西新井に住んでいた小出美鈴と母の小出千里は父親が癌を患い若くして他界したため、二人暮らしをしていた。当時女性の仕事は少なかったから、女手一つで母子が生活していくのは大変で、貧乏暮らしを強いられていた。そんな時、大学の助教授だった男を紹介されて、母は再婚した。男は九大出身の英文学者で肥田辰則と言う名前だった。それで娘の美鈴と母の千里は肥田姓となった。
肥田美鈴は高校を卒業すると銀行勤めだった叔父の縁故で銀行に就職した。当時は縁故がないとなかなか銀行には入れなかったのだ。
教授と違って助教授は月給が安い。それで、肥田家は貧乏暮らしが続き、美鈴も月給の大半を家計に入れていた。
美鈴の義父になった辰則は助平な奴で、教え子に手を出してトラブルを起こし、千里は苦労させられた。
辰則はそれでも懲りずに、千里が留守をした休日に娘の美鈴を手籠めにしてしまった。つまり強姦したのだ。
こともあろうか義父とは言え父親に辱められた美鈴は自殺をしようとしたが死に切れず、大きな心の傷が元で見合い話を断り続けていた。
当時銀行では二十五歳を境に女は結婚退職するのが普通で、いつまでも居座る女は煙たがれていた。美鈴は周囲の圧力に耐えながら三十歳を少し過ぎてもまだ頑張っていた。
そんな時、銀行の上司から美鈴に見合い話しが持ち込まれた。相手は取引先の米村工機の社長、米村善太郎だった。美鈴は一旦断ったが、銀行も早く追い出したい意図があって、再三見合いを勧めたため、遂に美鈴は折れて、
「お見合いをするだけなら」
とこの話を受けた。
この時善太郎は既に三十代後半で美鈴と共に二人ともとっくに婚期を逸していた。それで、一回のお見合いだけで善太郎は結婚を承諾した。美鈴もこの時は、
「どうにでもなれ」
とやけっぱちになっていたのだ。
善太郎は多忙で家事さえきっちりやってくれれば誰でも良いと思っていた。
結婚式を済ますと、新婚旅行もせずに、美鈴は直ぐに家事に忙殺された。唯一の救いは義母の喜代が質素な女で、貧乏暮らしに慣れた美鈴と性格が合い、可愛がってくれたことだ。夫善太郎の会社は売上こそ伸びていたが、運転資金は火の車で、そのために喜代と美鈴はしばしば銀行に借金を頼みに足を運ばなければならなかった。ひどい時は月末に支払うべき従業員の給与に当てる現金が不足して、金策に大変な苦労を強いられた。そんなだったから、喜代も美鈴も家計を切り詰めて粗末な生活をしていた。そんな中、結婚して間もなく善太郎と美鈴の間に男の子が誕生し、名前を善雄と付けた。
善太郎は母と女房の支えがあって、順調に業績を伸ばし、ついに東京証券取引所に上場を果たした。その結果資金調達は随分楽になったが、会社の膨張に従業員の育成が間に合わず、今度は人材育成問題と戦うことになった。そこで善太郎は当時としては珍しかった企業の買収に目を付けて、優秀な従業員がいるのに赤字で苦しんでいる企業を積極的に買収して経営刷新を行い黒字化して、従業員の積極的な活用に邁進した。善太郎は買収した企業の従業員を一人も解雇しない信念を貫き通したので、それが相手の安心感につながって、その後も買収は順調に進んだ。
結果論になるが、善太郎はたった一度の見合いで即時に結婚したにも拘わらず、自分にとって、とても良い女性と結婚できたと言える。
米村工機の本社は今は都心に移してしまったが、米村工機の発祥の地、板橋区小豆沢町にはまだ事務所が残してあった。
島崎沙希が住んでいるアパートのある豊島区の要町から約6kmほど北に行った所だ。
善太郎は晩婚であったが、息子の善雄は出来れば二十代で結婚させたかった。見合い結婚なぞ、今では珍しい時代になったが、善太郎は息子には自分が見て米村工機の跡取りの嫁に相応しい女性と結婚させたいと思っていた。そんなことを考えていた時、六本木のクラブでホステスをしている沙希が目に留まった。調べてみると、沙希と言う女は客の甘い誘いを頑なに断り、他のホステスから聞かされた噂によるとなかなか堅実な性格のようだった。それで兼ねて親しかったクラブのオーナーの柳川哲平に一肌脱いでくれないかと話を持ちかけた。
三十四 お見合いのあと……
○○(まるまる)ホールディングス米村社長の御曹司米村善雄と六本木のクラブ、ラ・フォセットのホステス島崎沙希は二月七日にホテルニューオータニでお見合いをして、ホテルの庭を少し散歩して別れた。
○○ホールディングスは米村工機を軸とする持ち株会社で、従業員は百五十名足らずで、日本橋の三井タワーに事務所を置いていた。 この会社は傘下の企業全体の財務、経営方針などを水平に見通す目的で設立された会社だ。傘下の会社は大手が八社、連結決算をしている企業を合わせると五十社以上で従業員の総数は三万五千人を越え、全世界に事業を展開していた。米村善雄は○○ホールディングスの平取締役だったが、米村工機の副社長を兼務していた。米村工機の社長は勿論父親の米村善太郎だ。主力の米村工機は従業員が三千名ほどで、事業所や研究所は全国に散らばっていた。善雄は普段○○ホールディングスに居ることが多かったとは言え、米村工機の仕事も多忙でしばしば出張をした。海外の事業所や関連会社も多く、殆ど毎月海外出張もしていた。
そんな状態なので、見合い相手の沙希とゆっくりデートを楽しむ暇は全くなかった。
沙希は善雄からのメールを待っていた。だが、一ヶ月を過ぎて三月になっても一通もメールはこなかった。
「もしかしてダメだったのかな」
と思い、その内メールを待つのがバカらしくなって沙希もほったらかしにしていた。
そんなある日善雄からメールが届いた。
「多忙で連絡もせず済みません。失礼ですが、十日の水曜日のお昼、食事の時間を取れます。日本橋の三井タワーにお越し頂くことは可能ですか?」
内容はそれだけだった。沙希は、
「はい。承知しました。三井タワーのどちらへお邪魔すれば宜しいですか」
と返事をした。
「二十階の○○ホールディングスの受付に十二時にお越し下さい」
返事はそれだけだった。
三月十日、沙希は言われた通り約束の場所に向かった。ドレスは何にしようか迷ったが、結局いつもの通勤着でGパンの上に白っぽいジャケにした。飾りっけがなく、そこらを歩いている女の子と同じだ。
受付で、
「米村善雄さんをお願いします」
と言うと受付の女性は、
「ご用件は?」
と尋ねた。
「十二時にここで待ち合わせの約束です」
と答えると、
「では」
と言って脇の小さな応接室に通された。応接室と言ってもパーティションで仕切られたテーブルと折り畳み椅子だけの商談室だ。
多分応対した受付の女性は商談に来たのだと思ったのだろう。
十二時少し過ぎて、応接室の外で声がした。
「ここに島崎さんと言う綺麗な女性が来なかったか」
「いいえ」
「おかしいな。来ているはずだけどなぁ」
「商談か何かだと思いますが、先ほどこられた方がそうかな」
「その方、今どこに居るか分るか」
「そちらの待合室でお待ちするように言いましたが」
ドアが開いて、受付の女性が顔を出した。
「米村さんなら今ここに来られてますが……」
沙希は、
「分りました」
と言って席を立った。そこに善雄が顔を出した。
「ああ、ここでしたか。ごめんなさい。奥の応接室にお通しするように言っておけば良かったな。待たせてごめんね」
受付の女性は怪訝な顔をしていた。
「お昼、付き合えますよね」
「はい。大丈夫です」
「じゃ、上のマンダリンのレストランに行こう。洋食と中華とどっちがいい?」
「どちらでも大丈夫です。お任せします」
「分った」
善雄は沙希をエスコートして三十七階のフレンチレストランに案内してくれた。
この受付の女性は善雄に淡い恋心を抱いていた。だから、善雄を訪ねて来た女にかなり興味を感じていたのだ。まさか善雄の見合い相手だったとは思いもせず、そんなことはまったく知らなかった。それなのに将来この大会社の社長の椅子が用意されている善雄が親しげに、大切な客しか連れて行ったことのないマンダリンホテルのレストランに連れて行ったのを不思議に思っていた。見た所、ろくに化粧もせず、普通のOLのような感じで、仕事でやって来た様子だったのにおかしいなと思っていた。
「バタバタしてごめんね。今日は一時から会議なんだ。ゆっくりは出来ないけど許せよな」
「はい」
「実は明日から中国、マレーシア、インドを回ってこなくちゃならなくてね。当分会えないなぁ」
「お忙しいんですね」
そこにスープから順に食事が出て来た。
「食べながら話そう」
「はい」
「僕はね、沙希さんをお嫁さんにしてもいいって決めたんだ」
「そんなぁ、まだあたしのこと何もお話していませんが」
「いいんだよ。普通なら結婚したら大切にして幸せにしてあげますくらいのことを言わないといけないんだと思うけど、僕のように多忙だと口先だけになるから、沙希さんがそんな僕を許せるなら嫁さんになってよ」
沙希は想像していたのとは全然違う展開に唖然としていた。
「それで、沙希さんが嫌でなかったら、僕の家を訪ねておふくろと話をしてくれないか?ダメ?」
「構いませんが緊張しちゃいそうです」
「そうだろうな。そこのとこをおふくろに良く話しておくから、都合のいい日に遊びに行ってよ。僕は留守だけど」
それで善雄の家の住所、電話番号を書いた下に道順を書いてくれた。住所は東京都足立区西新井六丁目××番地になっていた。
一時少し前になった。
「先に失礼するよ。ゆっくりデザートを楽しんで帰って下さい。支払いは済ませておくから、食事が済んだら帰って下さい」
「あのぅ、ありがとうございました。お母様に連絡をして近日中に必ずお邪魔します」
「ん。ありがとう。この話、断るのは沙希さんの気持ち一つでいいけど、出来れば断らないで欲しいな」
「あっ、お時間が」
と時計を指した。善雄は会計を済ますとさっさと出て行った。
レストランを出ると沙希は、
「なんだか、こんなんでいいのかなぁ?」
と不安を感じていた。
「まっ、いいか。母親に会ってから決めればいいや」
沙希は中途半端に時間が余ったので、八重洲通りのブリジストン美術館に行って見た。こんな時は静かな美術館がいい。
沙希は絵を見ながら、家を出てから今まで歩いてきた時に起こった色々なことを思い出していた。美術館を出ると、六本木に出勤するのに丁度良い時刻になっていた。沙希はそのまま六本木に向かった。
土曜日の昼過ぎに、沙希は善雄が書いてくれた番号に電話をした。
「もしもし、島崎と申します」
「はい。米村です。あっ、もしかして沙希さん?」
「はい。沙希です。ご無沙汰しております」
「そう、沙希さんね。お久しぶり。お元気だった? 善雄があんなで、ごめんなさいね」
「いいえ」
「善雄から聞いてます。是非遊びにいらして下さいな」
電話口に出たのは善雄の母親の美鈴だった。
「あのう、早速ですが、明日お邪魔させて頂いてもよろしいでしようか」
「善雄は海外に出ておりまして不在ですが、是非いらして下さいな。私もゆっくりお目にかかりたいと思っておりました。それから、初めていらっしゃる時はお土産をお持ちになられるのが普通ですが、お土産は無しにして手ぶらでいらして下さいね。これは真面目なお願いですから、どうぞそうして下さい」
「はい。何時頃ならよろしいでしょうか」
「こちらは何時でも構いませんよ。せっかくいらっしゃるんだから十時過ぎにいらして、お昼をこちらで召し上がるつもりでお出かけ下さい」
「分りました。ではお約束の時間にお邪魔させて頂きます」
受話器を下ろして、沙希はうっすらと額ににじんだ汗を拭った。
美鈴は沙希は六本木でホステスなぞしている女だから、きっと派手好きな贅沢な女だと思った。だから、恐らく自分の性格には合わないだろうなと一抹の不安を抱いていた。善雄は既に結婚すると決めてしまっているような話をしていたが、これから先一つ屋根の下でずっと暮らすことを考えると少し気が重かったが、とりあえず善雄の頼みなので沙希をゆっくりと観察しようと思った。
三十五 相性

日曜日は天気はまあまあだった。今日は善雄の家を訪ねる日だ。それで早起きをした。沙希は軽自動車で行くつもりで池袋の要町から足立区の西新井まで道路地図で道順を調べた。調べて見ると西新井六丁目までは要町から318号線、つまり俗に言う環状七号線(環7)に出て右折して環7に沿って真直ぐに走り鹿浜橋を越えた所だ。距離にして約15kmしかないので、渋滞していても三十分もあれば行ける。
それで九時半少し前に出た。大会社の社長宅だから、多分大きな屋敷だろう。沙希は生まれた時から小さな家で育ち、東京に出てからは、母親と二間の小さなアパート暮らしだったし、家を出てからは風呂もない四畳半のボロアパートだった。だから、大きな屋敷に住むのには抵抗を感じていた。
「いったいどんな家だろう?」
そんなことを考えている内に西新井に着いてしまった。所番地まで出ている地図を見ながら大きな屋敷を探した。だが、目的の場所辺りをグルグル回って見たがそれらしき家が見付からなかった。それで、車を降りて番地に近い家の人に聞いて見た。
「恐れ入ります。この辺りで米村善太郎様の家を探しているのですが」
「ああ、善太郎さんのお宅ね。その向かい側の二階屋ですよ」
「ありがとうございました」
なんのことはない。先ほどから米村家の前を何度も通り過ぎて見落としていた。大きな屋敷なんて言う先入観がいけなかった。家は普通のサラリーマンが住んでいるようなありふれた大きさの家だった。車を置くスペースは二台分あったが、玄関は小さく、敷地もせいぜい六十坪位だ。チャイムの押しボタンを押すと玄関から美鈴が顔を出した。
「あら、沙希さん。時間が正確だわね。直ぐ分かった?」
沙希は、
「はい」
と答えた。
「車でいらしたのね。そこに停めて頂戴」
沙希は軽を停めて善雄の家に上がった。
「お言葉に甘えて手ぶらで、普段着で来ました」
「そう。それがいいのよ。着飾った沙希さんでなくて、普段着の沙希さんがいいわね」
美鈴は気さくな感じだった。
誰にでも他人との相性はある。核家族で、旦那と二人っきりなら、旦那との相性が良ければいい。だが、旦那の家に旦那の親と同居するなら、旦那よりも親との相性が良くなかったら多分地獄を見ることになるだろう。特に嫁さんなら絶対条件と言ってもいいだろう。義母と相性が悪くて毎日くさくさして過ごしている嫁さんの話は良く聞く話だ。美鈴も沙希もそのことを良く分かっていた。だから双方で観察が始まったのだ。
沙希は六本木で澤田に、[気配り・気遣い・でしゃばらない]の三つを厳しく仕込まれて、今では身に付いていた。気配り、気遣いが良くてもでしゃばればそれが台無しになると言うのだ。そのバランスが難しい。やり過ぎると鼻に付くと言うのだ。沙希は華道と茶道のお稽古をしているお陰で、最近仕草も綺麗になっていた。
[あらこの子見かけによらず気配りのできる子だわ]沙希の立ち居振る舞いは早速美鈴の及第点をゲットしていた。沙希は沙希で、[思った事をズケズケ言うわりには全然嫌味のない人だなぁ]と感じていた。
沙希は将来義母になるかも知れない美鈴を[奥様]と呼んだ。最近ではこんな場合[お母様]と呼ぶことも多い。[おばさま]と呼ぶのは論外だ。婚約を済ませてしまえば[お母様]と呼んで良いが、婚約前までは[奥様]と呼ぶのが無難だと茶道教室で教わった。
[この子、礼儀作法はどこで習ったのかしら]美鈴の母は言葉遣いに五月蝿かった。それで沙希の話し方も観察していたのだ。
普通の女の子だったらこんな雰囲気を、
「ああ、嫌だ、嫌だ」
と思うだろう。だが、沙希は毎日接客をして色々な場面を経験していたから、鈍感と言うか慣れと言うか、こんな雰囲気を何とも思っていなかった。
「お昼、お寿司でもと思いましたけど、あたしの手料理でもいいですか」
「はい。その方がいいです」
「じゃ、お昼までテレビでも見てらして」
と美鈴が台所の方に行きかけた。
「済みません。あたし、お料理の方、全然ダメなんです。お邪魔でなかったらご一緒して教えて頂けませんでしょうか」
「あら、いいわね。じゃご一緒にお昼ご飯を作りましょう。何か食べたい物ある?」
「お任せしますが、出来れば簡単に出来る料理がいいです」
「そう? でもうちじゃスーパーなんかで売っているお惣菜は使いませんから最初からよ」
「あっ、あたしも出来上がったお惣菜は買いません」
美鈴はホステスなんて仕事をしているので手が汚れる台所仕事なんてしない子だと思っていた。だから[あら、この子なかなかいい子ね]とまた合格点を付けた。
「丁度買い置いた材料がありますから、八宝菜か五目中華にしましょうか」
「それ、あたし大好きです」
八宝菜は沙希も時々作るから助かった。それで、美鈴と沙希はおしゃべりをしながら並んで料理をした。沙希は子供の頃母親が外出していることが多かったので、美鈴と並んでお昼ご飯の仕度をするのがとても楽しかった。
「あなた、善雄と結婚したら、新婚旅行、どこに行きたいとか考えていらっしゃるでしょ」
「あたし、まだそこまでは考えていませんでした」
「奥様はどちらにいらしたんですか」
「それがね、主人の善太郎は風変わりな人でね、結婚したらその日から仕事。新婚旅行は行かなかったのよ」
「お忙しかったんですね」
「忙しいってことは確かだけど、あたしより仕事に恋してたのかも知れないわね」
と美鈴は笑った。
「子供は親に似るって言うけれど、善雄もそう言うとこがあるのよ。お見合いをしておいて一ヶ月も相手に何も話をしないなんて非常識よね。だから善雄には新婚旅行は絶対に行きなさいって言ってるのよ」
美鈴と沙希はこの調子で色々なことをおしゃべりした。美鈴はホステスと言う職業で相手の性格を決め付けてしまっていたことに気付いていた。美鈴は、この子は最初の予想に反して飾り気のない気立ての良い娘だと感じていた。
沙希も、しかめっつららしい怖いオバサンを予想していたが、自分の母親のような暖かさがあって、これなら一生喧嘩をするようなことはないだろうと感じていた。
帰りがけに寝たきりになっている美鈴の義理のおばあちゃんに会わせてくれた。美鈴の接し方を見ていると、自分の実の母親のように優しく丁寧だった。沙希はこの様子に高い合格点を付けた。おじいちゃんは数年前に他界したと説明してくれた。
「今日はとても楽しかったです。今度はわたくしが住んでいますアパートに是非いらして下さいませんか? 少し前まではスペイン人の女性と同居してましたが、最近結婚されて出て行きましたので今は一人です」
「はいはい、是非お伺いするわね」
美鈴は沙希が書いて持ってきた手書きの地図と電話番号のメモを見た。
沙希は善雄の家が質素に生活しているらしいことが気に入っていた。掃除は行き届いていたが、
「お金があるからって大きな家に住んでも掃除が大変だし、四人で暮らす家はこれくらいが丁度いいわね」
と言っていたことが印象に残った。
三十六 普段着の沙希
沙希が米村家を訪問して後、沙希が書いた住所と道順の略図を頼りに、米村美鈴は敢て前もって連絡をしないで沙希の所を訪れた。
「普段をありのままに見るには、予め行きますよと連絡を入れないで、不意打ちをくらわすのがいいのよ。留守の可能性はあるけれど、ダメ元で行かなくちゃ」
美鈴は、前もって連絡をすれば、沙希は必ず掃除をして小奇麗にするなど普段とは違う所を見せるだろうと思った。美鈴はそんなに人が悪くはなかったが、一生あの子と過ごすには事前にそれくらいしておくのがいいと思っていた。誰だって、突然前触れもなく訪ねられたら、どうにもこうにも見せたくない物まで見られてしまうだろう。
世の中の姑の中に、婚約前の息子の恋人や見合いの相手をこれ位の覚悟で観察する者はどれくらい居るだろう? この話を聞いたら現在姑の立場に居る女性は多分自分の場合はどうだっただろう? と振り返って見るに違いない。嫁・姑の仲が思わしくない家族は案外多いのだ。それなのに、息子の結婚相手に遠慮して、事前に策を講じずに、同居してからぶつぶつと不満を漏らす姑は、責任が自分にもあるんだと自覚してない場合が多いから始末が悪い。美鈴はそんな風に思っていた。
沙希が大会社の社長宅は立派な豪邸だろうと先入観を持ったのと同様に、美鈴は六本木の一流クラブのホステスで、収入は普通の同年代のOLの五倍以上もある人だから、多分そこそこ贅沢なマンション暮らしだと思っていた。
メトロ有楽町線の要町駅で降りると、美鈴は地図を頼りに沙希のアパートのある番地を目指して歩いた。駅前には少しましなマンションがあったが、沙希の住んでいる番地あたりには安普請の二階建てアパートがあちこちにあった。少し大き目のマンションだろうと思ったのがいけなかった。なかなか見付からずに、郵便配達の人に尋ねた。
「この辺りで[ハイジ]と言うアパートを探しているのですが?」
「ああ、ハイジね。ハイジは向うに見える二階建ての古いアパートですよ。近くに行かないと分りませんが、アパートの側面に消えかかった文字で小さくハイジと書いてあります」
「ありがとうございました」
行って見ると、確かに随分古いアパートだ。築二十年位は経っているかも知れなかった。沙希の部屋は二階の角だった。郵便受けにマジックで島崎と書いた紙が貼ってあった。
ドアチャイムなんて付いてない。それで、ドアをコンコンとノックして、
「ごめんください」
と呼んでみた。
「はぁーいっ」
中から沙希の明るい声が戻ってきた。直ぐに鍵を開ける音がカチッとして、沙希の顔が覗いた。
「あらっ、奥様!」
案の定沙希は驚いた様子だ。
「前もってご連絡を下されば、駅までお迎えにあがりましたのにぃ」
沙希は恐縮していた。
中に入って、美鈴は驚いた。玄関は勿論、部屋の中もとても清潔で掃除が行き届いていた。第一、家具と言う家具らしい物は一つもなかったのだ。だから掃除機をかけるにも手間が要らない。
美鈴は綺麗なマンションでビルトイン(作り付け)の家具か、さもなければ大きな洋服ダンスがでんと置いてあり、ゴージャスなベッドもあると思っていた。所が洋服箪笥もベッドもない。女の子なら鏡台だってあると思っていたが、ちっちゃな本箱の上にちっちゃな鏡が置いてあるだけだった。テーブルの代わりに丸い昔ながらの小さな卓袱台が足を畳んで壁に立てかけてあった。
「あら、箪笥がないのね」
「はい。洋服を少ししか持ってませんから」
「普段どこにしまっておられるの」
「ここです」
と言って沙希は押入れの襖を開けた。そこが簡単なクローゼットになっていて、プラスチックの容器に下着類が整頓して入れてあった。兎に角綺麗に整理整頓されているのには、さすがの美鈴も驚いた。自分だってここまではできていない。
「お食事、まだでしたよね」
もうお昼近くだったので沙希が聞いた。
「ええ、まだです」
「じゃ、この前みたいにご一緒にお昼ご飯作りを教えて下さいません?」
これには美鈴も参った。だが、
「いいわよ。さて今日の献立は何にしましょうか」
と話を合わせた。
「奥様 [COOKPAD]ってご存知ですか」
「聞いたことはあるわね。インターネットで色々なレシピを紹介してくれるサイトでしょ?」
「はい。この会社、今急成長してるみたいです。あたし、いつもこのサイトで紹介しているレシピを参考にしてるんです」
「それで今日の献立はどんな物を考えていらしたの?」
「まさか奥様がお出でになられるとは思いませんでしたので、あたし今日のお昼は、[簡単昼食、さっぱり梅干しレタスチャーハン]にしようかな、なんて思って、レシピをプリントしておきました」
「あら、見せて頂戴」
沙希は朝方プリントしたA4のカラープリントを持ってきて美鈴に見せた。
「あら、手軽そうでいいわね」
レシピには次の材料が載っていた。
材料(一人分)
レタス 一枚
梅干し 一個
玉ねぎ 八分の一個
ご飯 茶碗一杯分
植物油(グレープシードオイル)
小さじ二分の一程
こしょう 少々
醤油 小さじ二分の一
「じゃ、材料はあるのね」
「はい。冷蔵庫に」
美鈴は小さな冷蔵庫を開けてみた。余った材料はラップして綺麗に整頓されて並んでいた。野菜もなかなか豊富だ。冷蔵の必要がない野菜は流しの下のカゴに入れてあった。先日自分の家に来た時、
「出来合いの惣菜を買うことはない」
と言っていたが、その話は本当だった。
「じゃ、これを作りましょうよ」
美鈴は同意した。
レシピには作り方も丁寧に書いてあった。
下の方に[写真は発芽玄米を使ったものです(玄米だとパラッといい食感が利用出来ます)。梅干しを使うので、[塩]は必要ないと判断しました。特に蒸し暑い季節には、この酸っぱさで食が進みやすいと思います]と中書きまで書いてあった。
それで、美鈴と沙希は狭い流しに二人仲良くならんで一緒に二人前のチャーハンを作った。
沙希は鶏がらで作ったと言う自家製のスープの素を空き瓶に入れた物を使って簡単な野菜スープを作った。沙希が手際よく作るので美鈴は感心して見ていた。
「合格!」
不意に美鈴が呟いたので沙希は、
「えっ?」
と聞き返した。美鈴は悪戯っぽい目で沙希を見て、
「沙希さんは善雄のお嫁さんに相応しい方って言ったのよ」
と笑った。
お昼ご飯は小さな卓袱台を出して二人で楽しく食べた。味はレシピの通りとても美味しかった。
沙希はお茶受けに和菓子を出してきた。美鈴は箱を見て、
「あら、これ目黒の林菓房のお菓子ね」
と言った。
「ご存知だったんですか」
「知ってますとも。このお店の和菓子は最高よ。沙希さんはどうしてご存知なの」
「これ、通ってる茶道教室でいつも使ってますので、聞いて知りました」
「そう。あそこの社長さん、あたし面識がありますのよ。その内紹介してあげましょう」
「へぇーっ? そんなご関係だったんですか」
「いつだったか、政財界人のパーティーに出ましたらね、ファイナンスのコンサルをなさっている山田龍一って方が林社長さんをご紹介下さったのよ。林さんはあたしより少し若い方ですけど、随分苦労された方で、きっと沙希さんの良い話し相手になって下さると思うわ。あなたのように綺麗な方よ」
沙希は世の中は狭いなぁと思った。
沙希は美鈴を駅まで送って行った。美鈴は暖かな優しい目で沙希を見つめて、
「善雄の良いお嫁さんになって下さいね」
と手を添えて別れの挨拶をした。
「あなた、善雄のお見合い相手の島崎沙希さん、あの子とってもいい子ね。あたし気に入っちゃったわよ」
善太郎が帰って部屋着に着替えるのを手伝いながら、美鈴は善太郎に今日のことを報告した。
「そうか、美鈴が気に入ってくれたなら、後は沙希さんの気持ち次第だな」
「その後善雄はデートしたのかしら」
「いや、彼はここのとこ仕事が多忙だからどうかな」
「あなたからプッシュして下さらない。あんな子はなかなか見付からないと思いますよ」
「おいおいっ、見つけてきたのは僕だよ」
そう言って善太郎は笑った。
それから一ヶ月ほどして、善雄は昼食に沙希を誘った。もう五月も末で少し汗ばむ季節になっていた。
「所で、まだ結婚のOKをもらってないけど、どうなんだ」
「はい。こんなあたしでよろしければお嫁さんにして下さい」
沙希は美鈴の人柄にとても好感を覚えていた。それで、善雄と結婚しても良いと思い、この日ちゃんと返事をした。
三十七 ドバイショック

米村善雄は今は自宅が足立区の西新井だが、子供の頃は自宅は板橋区の小豆沢にあった。近くの志村四小を卒業すると、私立城北中学に進み、高校はそのまま城北高校を出た。だから、高校を卒業するまでは学校まで歩いて通った。子供の頃から家業の手伝いで忙しく、友達と泥んこになって遊んだ記憶は殆どなかった。ひょろっとして背が高くひ弱に見えたが親譲りで芯の強い子供だった。高校では受験勉強に励んでいたこともあって友達は少なかった。思い出の少ない高校生活を終えると、善雄はT大の文二にストレートで合格して経済学部に進んだ。大学に入っても家業の手伝いに忙しかったが、毎日生きた経済に接していたせいか、産業界の情報に明るく、大学では大勢の良き友達が出来た。大学を卒業するとそのまま米村工機に入社して、入社三年後には取締役に就任し、四年目の株主総会で副社長に昇格していた。善雄が取締役に就任した時、母親の実家に近い足立区の西新井に家を建てて引越しをした。同時に父親が経営する○○ホールディングスの設立に関与して、設立後取締役に就任した。設立時、入社してきた女性の中に中嶋麗子が居た。彼女はK大を卒業したが、狙っていた大手の銀行に入れず、仕方なく応募した所採用通知を受け取ったのでこの会社に入った。入社後総務部の秘書室に配属されて、役員のスケジュール管理の傍ら受け付けの仕事をしていたのだ。彼女は一番年少の役員が二十代の独身で社長の御曹司だと分ってから、淡い恋心を抱くようになっていた。だが、米村善雄は多忙で、彼女を振り返って見たことは一度もなかった。たとえば朝お茶を持って部屋に入っても、
「そこに置いといてくれ」
と言うだけで、茶碗を下げに行くと決まって冷めたお茶が残っていたのだ。
善雄の父親の善太郎は根っからの技術屋で会社経営には熱心だったが、世界の経済情勢にお構いなく前へ前へと引っ張っていく所があった。そのため、経済学部を出た善雄は、もっぱら世界経済動向を睨んで、父親のブレーキ役を務めていた。
そんな中善雄は、昨夜から経済界を嵐のように吹き荒れた第二次ドバイショックに、徹夜で対応に追われていた。忘れもしない、前年十一月二十五日に、リーマンショック以前には一泊三百五十万円もするスイートが話題になった椰子の葉をモチーフにした富裕層向けの高級リゾート地パームジュメイラの開発に多額の投資をしていたドバイ政府系の持ち株会社ドバイワールドの資金繰りが突然悪化して、前年十二月に返済期限が来る債務の資金繰りが付かなくなったと言うニュースが流れて、全世界の株式市場が暴落したのだ。おりしも米国市場は二十六日サンクスギビングデー(感謝祭)で休みだったが、欧州や新興国の市場全体の株式相場が揃って急落したのだ。
その時は原油高で潤うUAE(アラブ首長国連邦)系の金融機関が助け舟を出して事なきを得たが、半年後の今年の五月、再び信用不安が再発したのだ。前年は勿論日本の株式市場も朝から急落した。特に、国内の大手のゼネコンは多額の開発工事を請け負っていたので、大きな影響を受けるとの思惑から、朝から株価が暴落した。前年返済延期をした債務の総額は五兆円以上の巨額な金額だ。
○○ホールディングス傘下の米村工機以下の企業は事業を全世界に展開している。だから、日本の国内情勢よりも、海外の経済動向の影響をもろに受ける体質になっていたのだ。
善雄は眠い目をこすりながら、海外の経済指標のグラフに部下と共に昨夜から張り付いていた。善雄には来月六月に沙希との結婚話が控えていたが、今はそんなことは頭の隅にも無かったのだ。
ドバイショックの嵐がようやく通り過ぎて、善雄は一息ついた所だ。度重なる金融市場の信用リスクを経験した各国の経済閣僚たちは、学習効果で経済の建て直しを急いだために、リーマンショックの時のような長期間の不況には陥らずに、一時的な暴落後次第に回復しつつあった。
善雄は沙希との結婚話を思い出すと、両親と相談して、結婚式は内々で簡単に済ませる同意を得た。それで、そのことを沙希に伝えると、沙希もその方が良いと返事が来た。多忙で会っている暇がなく、夜携帯メールで片付けた。日本国内だけで事業を展開している企業を経営している者は、夜中には眠る時間がある。だが、世界中に事業を展開していると、真夜中でも容赦なく電話がかかってくるのだ。それはそうだ。日本が真夜中でも地球の裏側は昼間で、社員は皆忙しく働いているのだから仕方が無い。重要な決定事項は他人任せにはできないから、善雄は万年寝不足を我慢して電話に応対していた。
善太郎は、結婚式は内々で良いが、善雄と沙希を政財界に認知してもらうために、結婚式とは別に披露パーティーを大々的にするようにと強く善雄に言い聞かせた。それで、六月十八日金曜日の大安の日、夕方から紀尾井町のホテルの大広間を借りて政財界の有名な人を招いて、大々的に立食の披露パーティーを行った。Eと言うアーティストグループの実演も入って、あたかも人気スターのお披露目パーティーのような感じだった。
「お母さん元気?」
もう何年も音沙汰のなかった娘の沙希からの電話に母の沙織は涙が出た。
「あなたも元気だったの?」
やはり母の声は懐かしい。
「実はね、今月結婚をするの。それでお母さんだけ出て欲しいんだけど。お義父さんは絶対に嫌よ」
「沙希には伝えてなかったけど、沙希が出て行った後、浜田は新しい女を作ったから喧嘩して追い出したわよ」
「じゃ、今独りなの?」
「そう。独りで淋しく暮らしてるわよ」
沙希はそんな話を聞いても同情する気持ちは湧かなかった。
「お義父さんとは今は戸籍上も関係がないの?」
「そう。母さんは今は昔の白石沙織に戻したの」
「六月十二日の土曜日、大安の日なんだけど、式は内々で赤坂乃木坂の乃木神社なの。来てくれるでしょ」
「たった一人の娘だもの、勿論行くわよ」
「ありがとう。あたし、今の会社の社長ご夫妻が親代わりをして下さるの。だからお母さんは来賓だけどそれでもいい?」
「そう?」
沙織はかなり淋しい気持ちがした。だが、その後何も構ってやれなかった娘に返す言葉が見付からなかった。ややあって、
「会えるだけでもいいわよ」
と答えていた。
「結婚式にはあたしの方は親戚がないから、その代わりにお友達が大勢出てくれることになってるの。変った結婚式だけど、全員お式に出て頂いて、その後簡単な披露宴をしてお終いなの。招待状を出すから住所を言って」
「前と同じアパートよ」
「そう。じゃ、出しとく。必ず来てね」
母との会話はそれで終わった。
結婚式も披露パーティーも滞りなく終わって、沙希は西新井の善雄の家で両親と同居生活が始まった。新婚旅行の話は善雄からまだ何も相談がなかったが、沙希はそんなことはどうでも良かった。そればかりか、沙希は善雄と初夜さえ迎えていなかったのだ。義母の美鈴は沙希を自分の娘のように可愛がってくれた。だから沙希はすごく幸せだった。美鈴とは話も良く合ったし、することなすことに美鈴は何も小言を言わないばかりか、好きなようにさせてくれていた。
そんなある日、その日は義母の美鈴は祖母に付き添って病院に行って留守だったので、沙希が部屋の掃除を忙しくしていると、キンコ~ンと玄関のチャイムが鳴った。
「はぁーいっ」
沙希がドアを開けると、そこに浜田が立っていた。
「ようっ、しばらくだな」
浜田はいやらしい目付きで沙希を見ていた。衣服は汚れ、髪の毛はバサバサの薄汚い男がにたにたしてそこに立っていたのだ。沙希の身体は凍りついたようになって、言葉も出なかった。
三十八 恐喝
浜田の突然の来訪を予期していなかった。沙希は母から別れたと聞かされ、今は母とは何の関係もないと思っていたから、まさかこんな所にこの男が現われるとは予想もしていなかったのだ。
「お前、いい男を捕まえたようだな。ここは新居か?」
「違います。主人の実家です」
「バカ言えっ、見え透いたウソをつくなよ。あんな大会社の社長がこんなちんけな家に住んでるはずはねぇだろうが」
「ウソじゃありません。帰って下さい。でないと一一〇番をしますから」
「おいおい、可愛い沙希ちゃんよ、本当に警察に通報してもいいのかよぅ。困るのはあんたの方だろうが。オレは失って困るものは何もないんだ。昔オレとセックスしたことをバラされたら沙希の方が困るだろうが。お義父さんはな、お前の困るのを見たくないんだよ。だからさぁ、一千万位用立ててくれないか? 用立ててくれたらさぁ、今後オレは沙希ちゃんの前に姿を見せないからよぅ」
「そんなお金、ありません」
「バカ言えっ、旦那にちょいおねだりすりゃ、直ぐ出てくるだろうが。それとも何か? オレとセックス仲だったことを旦那には言ってないのか」
「兎に角帰って下さい。そんな大金を直ぐにと言われても用意できません」
「そうか、少しは考える気持ちになったか。じゃ、今日はこのまま帰ってやるよ。明日、もう一度連絡を入れるからそれまでに用意をしておいてくれよ」
そう言い捨てると浜田は帰って行った。沙希は背中に冷や汗をいっぱいかいていた。
浜田は先月一部の新聞報道で米村工機の御曹司の派手な結婚披露パーティーの記事を読んだ。新郎新婦の写真を見て仰天した。なんと、新婦は自分の義理の娘だった沙希ではないか。家出してどこかへ消えたと思っていたら、こんな玉の輿に乗ったなんて信じられない情報だ。それで、いろいろ嗅ぎまわってやっと米村家を探し当てたのだ。
浜田は女のトラブルで沙織との仲が悪くなって、気の強い沙織と喧嘩して追い出された。しばらくは池袋の近くに新しい女と同棲していたが、新しい女にも愛想をつかされてまた放り出され、サラ金で借金して競輪競馬で一儲けする積りが逆に借金を膨らませてしまい、今では一千万円以上の借金で、サラ金業者に取立てをくらって追い込まれていた。
だから、新聞を見た瞬間にゆすりを考えたのだ。
美鈴が戻って落ち着いた所で、
「お義母さん、折り入ってお話したいことがあるの」
「あら、沙希ちゃんにしては珍しいわね」
「実は今日お留守の時、母と別れた義理の父が突然訪ねてきて……」
「高校を卒業されてからずっと会ってないって言ってたわね」
「はい」
「それで上がってもらったの」
「いいえ。荒んだ生活をしている様子で、洋服は薄汚れていて、髪の毛はばさばさ、側にいるだけで臭いんです」
「へぇー? それは困ったわね」
「あたし、善雄さんにもお義母さんにも話してないことがあるんですが」
「話ってなぁに? わたしは大抵の話には驚かないから言ってごらんなさい」
沙希はなんだかドキドキして平静にはしていられなかった。その様子を美鈴は感じて沙希の頭を撫でてくれて、
「沙希ちゃん、落ち着いて話してくれない」
と先を促した。
「実はあたしが高校卒業と同時に家を出た理由なんですけど、高校生の時、母の留守を狙って義父に何度も犯されていたんです。レイプみたいに。あたしいつも我慢してましたが、もう嫌で嫌で耐えられなくて、それで卒業して直ぐに家を出たんです」
「そうだったの。そんなことがあったの。可哀想だったわね」
「それで、お母様にはお話ししたの」
「いいえ。一度も。今までにこのことを他人に話したことはないんです。お義母さんに話すのが初めてです」
「そう。お母さんに話されなくて良かったわね」
そこまで聞いて美鈴はだいたいの見当が付いた。
「それでお義父さんはいくら沙希ちゃんにせびってきたの」
「一千万円出せって」
美鈴は自分の過去のおぞましい経験については何も言わなかった。けれども沙希の経験についてよく理解できた。
「一千万とは大層な金額ね」
「あたし、自分の貯金を下ろせば何とかなるんですが、一度あげちゃうと二度、三度と続く気がして、今日は帰ってもらいました」
「沙希ちゃん、お金は一銭も出しちゃダメですよ。こんな場合はお断りするのが一番いいのよ」
「でも、善雄さんにもお義父さまにもすごいご迷惑をおかけすると思うとあたし恐ろしくて」
「大丈夫。わたしが沙希ちゃんを守ってあげますから、相手にしないで、今度連絡してきたらわたしにバトンタッチして頂戴。分ったわね。沙希ちゃんは何も心配しないでいいわよ」
沙希は先ほどから我慢していた気持ちが溢れてしまって美鈴の膝に顔を埋めて泣き出した。美鈴は沙希の頭を優しく撫でて、
「わたしが身体を張ってでもきっとこの子を守って見せる」
と気持ちを新たにした。
翌日、美鈴が在宅中に浜田がやってきた。美鈴が出ると、
「オバサンでなくて沙希を出してくれ」
と凄んだ。
「沙希はいますが、わたしがお相手をしましょう」
と美鈴が応じた。
「そうかい、それじゃ話が早いや。一千万用意出来てるのか」
「そんなお金はどこにもありませんよ」
「オバサン、分ってねぇな。払わなきゃヤバイことになるぜ」
「ええ、覚悟してますから」
「コノヤロウ、話しが分らんババアだな。五百でもいいぜ。まけといてやる」
「百でも二百でも一銭も出しませんから。手を出したら障害罪で警察に突き出しますよ。沙希に縁のある方だからと穏やかに応対しているつもりですが、どうぞ、そのヤバイことでもなんでも驚きませんから帰って下さい」
「話しが分らんババアだなぁ。覚えてろ、後で頭を下げてきた時は倍の二千だ。そのつもりでよぉーく考えておけよ」
そう捨て台詞を残して浜田は立ち去った。
「沙希ちゃん、台所からお塩を一つまみ持ってきて下さいな」
美鈴は玄関先に塩を撒いた。
「あのう、浜田様とおっしゃる方から電話がかかってますが」
と秘書の中嶋は善雄に取り次いだ。
「用件は?」
「何度聞いても、兎に角電話を回せの一点張りなんです」
「聞いたことがない名前だなぁ。とりあえずこっちに回してもらおうか」
それで善雄が電話に出ると、
「私は沙希の父親だ。沙希のことで折り入って話があるんだが、ちょっと会ってもらえないか」
「どう言うご用件ですか? 確か沙希の母親とはとうの昔に離縁されたと聞いてますが」
「そうかい、そうかい。なら話しが早いや。電話じゃ何だからどっかで会ってくれよ」
浜田は段々横柄な話し振りになった。
「忙しいですから無理ですね」
「そうかい。なら、そっちに行ってでかい声を出してやろうか。なんなら週刊誌のルポライターをぞろぞろ連れてってもいいぜ」
善雄はこの時[恐喝の手口だな]と悟った。それで、
「今日、明日は多忙なので、明後日もう一度電話をくれませんか? それと失礼ですが、そちらの電話番号か住所を教えて下さい」
と答えた。浜田はうっかり携帯の電話番号を漏らした。だがはっと気が付いて、
「この携帯は近々解約の予定だぞ。そのつもりで頼むぜ」
と付け加えた。勿論その時は携帯の解約は考えていなかった。
三十九 地獄への階段 Ⅰ
善雄が受けた電話は着信音声を常に録音できるようにセットしてある。これは客先や事業所からの大切な連絡を聞き漏らした時に後刻確認するためにそうしてあるのだ。
善雄は浜田と言う男からの音声を再生した。携帯の番号を正確に確かめるためだ。
「会える時間が取れたらよぉ、09021XX30XX に連絡をくれや」
一拍置いて、
「この携帯は近々解約の予定だぞ。そのつもりで頼むぜ」
と再生音が流れた。善雄はメモ用紙に[09021XX30XX] を書き取った。それから自宅に電話を入れた。
「もしもし、沙希さん?」
「はい」
「僕だ」
「はい。何か……?」
「浜田と言う人は沙希さんのオヤジさんか」
「はい。義理の父でした」
「今は沙希さんと関係がないんだろ?」
「はい。母が別れて関係がないと言ってました」
「分った」
その時、美鈴が受話器を貸せと仕草をした。
「ちょっと待ってね。お義母さんに代わります」
美鈴が代わると、
「浜田から電話が行ったの?」
と聞いた。
「ん。ありゃ、恐喝だな」
「この件、わたしからも話しがありますが、今夜お父さんが戻ってから相談しましょう。分ったわね。それまでは相手と連絡を取らないで下さいね」
「遂に、良くないことが迫ってきたか」
沙希はとても不安になって母の美鈴の横顔を見ていた。
「沙希ちゃんは何も心配なさらなくていいのよ。この話はね、善雄とか家を守ると言うよりわたしの大切な娘の沙希ちゃんをわたしが守って上げたいと思ってるの。だから任せといて」
沙希はこの時、美鈴が実の母親以上に自分に愛情をかけてくれていると感じた。
夜十時過ぎに、善太郎と善雄が揃って帰宅した。善雄は用が済んだらまた社に戻ると言った。
美鈴は浜田が訪ねて来た時の様子を包み隠さずに話した。善太郎は黙って聞いていた。
「善雄、お前まさかこんなことで可愛い沙希ちゃんを離縁するなんてことは考えてないだろうな」
「もちろんですよ。この先何があっても沙希は離しませんよ」
沙希は小さくなって三人の話を聞いていたが、善雄の言葉に思わず涙が零れ落ちた。この時結婚して初めて、夫の善雄が自分のことをどんなふうに思っているのかを聞けたからだ。同時に善雄が自分を愛してくれていると感じていた。
善雄の話を聞くと善太郎は、
「そうか、そうこなくちゃな」
と言って美鈴に電話機を持って来いと言った。善太郎は早速どこかに電話した。
「ああ、柳川さんか。ちょっと頼みがあってな、力を貸してくれんか」
そう言って浜田から恐喝されていることを告げた。
「手がかりなぁ……」
それを聞いた善雄が、
「相手の携帯の番号はこれです」
と背広のポケットからメモ用紙を出して見せた。
「上手い具合に善雄が携帯の番号をメモしていたよ」
柳川はそれがあれば十分だと答えたようだった。
「すまないな。経費はいつもの通りこちら持ちで急いで頼むよ」
どうやら柳川は引き受けたようだ。
「沙希ちゃんの義理のオヤジさんに頼んだよ。多分これで完全に片付くと思うから何も心配せんでいいよ」
善太郎は可愛い娘に接するいつもの穏やかな優しい目で沙希を見た。
「お父様、ありがとうございました」
沙希は自分が家族全員から守られていると思った。
「おい、溝口を呼んでくれ。猪俣も一緒にな」
柳川に呼ばれて溝口と章吾がやってきた。
「頼みがあるんだが、米村のとこに嫁に出した沙希ちゃんが浜田って名乗る義理のオヤジに脅されているらしいんだ。さっき米村善太郎さんから電話があってな、始末してくれと頼まれた。一肌脱いでくれんか」
「分りました。手がかりは?」
「これが相手の携帯だ。これがありゃ、何とかなるだろ?」
「大丈夫です」
「急いでくれや。できたら今直ぐに接触してくれ。池内の力も借りてくれよ」
「始末ですが、ザンビアの地獄谷送りってことでいいですか?」
「さすが溝口さんだな。あそこなら生きて帰ってこられんだろ。いいアイデアだ」
「じゃ、その線で動いてみます」
「頼んだぞ」
溝口、池内、猪俣の三人は直ぐに動いた。
「浜田さんか?」
「オレだが?」
「あんた、今暇してるだろ?」
「バカ言え、オレはこれでも忙しいのよ」
「逃げるのにだろ」
「逃げる?」
「借金をいっぱい抱えて追い込まれてる奴は、それっかやることがねぇだろうが」
「あんた誰だ?」
「あんたを借金の地獄から解放して楽にしてやる神様だよ」
「なんかいい話でもあるのか」
「あんた次第だな」
「どうすりゃいいんだ?」
「ちょい、甘い仕事に手を貸してもらいたいんだ」
「どんな話だ」
「おめぇ、ど素人だなぁ。素人さんはこれだから困るのよ。誰にも聞かれない所で会って話すのが常識だろうが、常識だよ」
「分った。どこへ行けばいいんだ?」
「お前新宿歌舞伎町一丁目の新宿区役所分るか」
「大体な」
「区役所裏にヒサコービルってのがあるのよ。ちっこいビルだからさ、分らんかったら聞けよ。そのビルの一階にソーラスって名前のバーがあるからよぉ、そこに十二時キッカリに来いよ。あんたが今居るとこからなら余裕だろ」
「オレが今居るとこ分るのかよ」
「池袋の近くだろ?」
「そうだ。よく分ったな」
溝口はかまをかけて池袋と言ってみた。当たりだ。
「オレはジローだ。バーテンにジローって言や分る」
「必ず行く」
溝口たち三人がソーラスで待っていると、目つきをキョロキョロさせて髪の毛がバサバサの汚らしい男が入ってきた。客は他には一組のカップルしか居なかった。それで、男は溝口たちの所にやってきた。
「ジローさんですか?」
溝口は無言で目でそこに座れと指示した。
男は章吾の隣に座った。
「臭せぇヤロウだなぁ」
と章吾は思った。事実クサイ臭いがプンプンした。
「あんたパスポート持ってるか」
「いきなりだなぁ。期限切れてる」
「直ぐ取れ」
「金がねぇ」
「分ってるさ。ほれっ!」
溝口は封筒をテーブルの上で滑らせた。
「とりあえず十だ。これでパスポートを取って、床屋に行って、こざっぱりした格好にして来い」
「海外ですか」
「バカなやつだなぁ。国内旅行でパスポートは要らんだろうが」
「はい」
「パスポートを取ったらこの携帯に連絡を入れろ」
「分りました」
「お前なぁ、パスポート取るまで余計な仕事をしたらこの話はナシだ。分ったか。それまではオレたちの組織であんたを監視してるから、余計なことを絶対にするなよ。電話でもだ」
「電話もダメですか」
「当たり前だ。これからでかい仕事をしてもらうのに、変な動きをする奴は仲間に入れないのよ。素人さんでも分かるだろ?」
「はい」
「分ったら帰りな」
浜田は封筒を持って出て行った。法外な高利貸しに激しく追い込まれてる奴は玄人の脅しには弱い。まして借金から解放してやると言われたら何でも聞くのだ。
三人はとりあえず六本木に引き揚げた。後は浜田からの連絡を待つだけだ。
四十 地獄への階段 Ⅱ
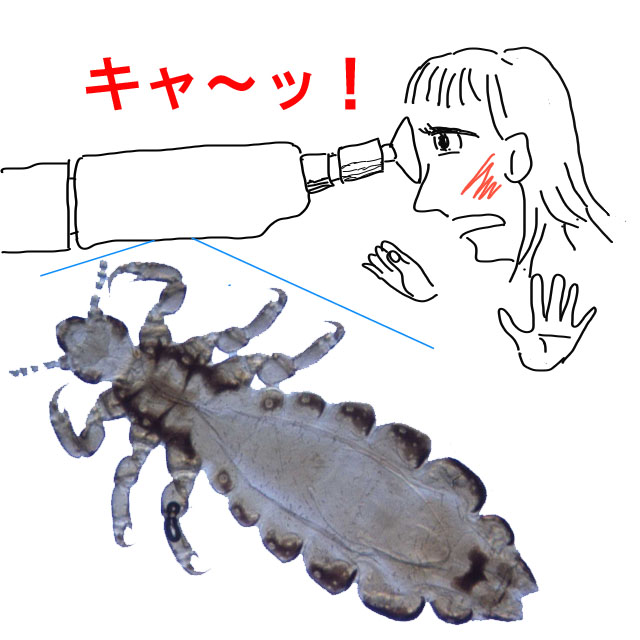
「浜田から電話が来たら直ぐ教えて下さい。ご自宅の方へはこちらからお願いをしておきます」
翌朝柳川哲平は米村善雄と連絡を取った。浜田が電話をするとすれば、善雄か沙希にするだろう。柳川は沙希にも電話をしておいた。この日はどちらからも連絡がなかったので、浜田はどうやら溝口との約束を守っている様子だった。
翌日から溝口、池内、章吾の三人は浜田からの電話待ちだった。それでいつもの通りクラブ、ラ・フォセットの仕事をしていた。
浜田は翌日豊島区役所に出かけて住民票、戸籍抄本を取り寄せた。現在はサラキンや高利貸の取立てを逃れて転々としていたが、住所は沙希の母親の沙織と別れた後、女と同棲していたアパートのままにしてあった。
本人確認は運転免許証があるから問題はなかった。書類を取り寄せると、一週間も風呂に入ってなかったので、久しぶりに銭湯に行って垢を流してから床屋に行った。
小さな古い床屋に入ると、
「伸びた毛をバッサリと切り落として七・三に分けてくれ」
と言った。オヤジは七十代後半の年寄りだったが、床屋代が安かったからそこにしたのだ。
「顔の髯は剃り落としますか」
「髯はそのままにしておいてくれ」
床屋は白い布をかぶせるとカットを始めた。浜田は目を閉じていた。ラジオから有線で歌謡曲が流れていたのでそれを聞いていた。
長く伸びた髪の毛をハサミでバサバサ切り落としていると、
「あれっ?」
床屋のじいさんは呟いた。白い布の上で何やら2ミリ位のものが動いていたのだ。
「頭虱だな」
と呟くと、そいつを爪で挟んで潰した。ブチュッとした感覚で虱は潰れて赤い鮮血が爪に付いた。虱はもう一匹いた。もちろん爪で潰した。
じいさんは、浜田の頭をいつもよりごしごしと洗い、浜田の頭を仕上げた。料金を受け取って浜田が出て行くと、切り落とした髪の毛を全部丁寧に掃き集めてビニール袋に入れて、セロテープでしっかりと封をした。次に掃除機を持ってきて、床全体を丁寧に掃除してからゴミパックをビニール袋に入れてセロテープで丁寧に封をした。毛に付いている卵が残っていたら始末が悪いと思ったのだ。
「よしっ!」
じいさんは店の扉に掛けた札を[閉店]にして、先ほどのビニール袋を二つぶら下げて保健所に向かった。
保健所に行くと若い男性職員が応対した。
「床屋だが、客の髪の毛から頭虱が落ちたので届けに来た」
「それはどうも。頭虱? ですか。それって毛虱のことですか」
じいさんは声をでかくした。
「あんたなぁ、保健所に居て頭虱と毛虱の区別も付かんのかいっ!」
大きな声だったので、奥の方から所長らしき年配の職員が席を立ってやってきた。
「頭虱ですか。わざわざお届け頂いてありがとうございます。手前どももそう言う情報を頂くと助かります」
と挨拶がてらにじいさんの労を労った。
「所長さん……ですか?」
年配の職員は頷いた。
「保健所ならもう少し教育しといてもらわんと」
「おおせはごもっともです。二十年前あたりに、頭虱は小中学生の間で広がりましてね、保健所としても対策に頭を悩ましました。所が最近の子供たちは朝シャンのお陰で清潔志向が強くなりまして、お陰で頭虱は子供たちの間では殆どなくなりました。それでうちの若い職員も見たり聞いたりしなくなりましてね。毛虱との区別も付かんとはお恥ずかしい。どうでしょう、これを機会にうちの職員に虱の話をしてもらえませんか」
予想外の展開になった。頼まれてじいさんは[虱談義]をするはめになった。所長は小さな会議室に手の空いている若い職員を集めた。
「人に付く虱にはな、三種類あるんだよ。洋服の縫代の裏側なんかに潜んでいて、夜なんかに出てきて体の皮膚から血を吸うやつだ。こいつは縫代を裏返して良く見ないとなかなか見付からないから、その様子から[虱潰しに探す]なんて言葉ができたんだ。洋服に隠れている虱は[ころもじらみ]って呼ぶんだよ。ふつう虱と言えば衣虱のことだ。虱はおかしな虫で、衣虱は頭の髪の毛には住まないんだ。頭の髪の毛専門は頭虱と呼ぶんだ。衣虱が白っぽいのに比べて頭虱は少し黒っぽいんだ。保護色かな。髪の毛に卵を産み付けて、頭の皮膚から血を吸うんだよ。虱の駆除は大変だな。終戦後わしらの子供の頃は大流行してさ、わしらは頭からDDTと言う白い薬剤をかけられたもんだ。洋服は普通に洗濯してもなかなか駆除できないんだよ。それで洋服を煮沸して、つまり鍋でぐつぐつ煮て駆除したんだ。もう一つやっかいなのが毛虱って奴だ。こいつは衣虱や頭虱よりも一回り小さくて、よほど良くみないと肉眼では見えないんだ。こいつはな、陰毛、つまりおちちんちんの回りとか女の子の股に生えてる毛が専門なんだ」
じいさんはここで言葉を切って出された水を飲んだ。女性の職員の中には最後の毛虱の話になると顔を赤くする者、恥かしげにうつむく者も居た。
「毛虱はな、セックスでもしないとうつらないんだよ。男が陰毛に毛虱を飼ってたとするだろ、そいつが女の子とセックスしてお互いの陰毛を擦り合わせている間に女の子の方の陰毛にうつるんだよ。だからな、女の子で自分のあそこの回りがむっちゃ痒くなったら、もしかして彼から毛虱をうつされたって可能性はあるな。彼が一度も他の女とセックスしてなかったら、そんなことがあるわけはないんだよ」
先ほど恥かしそうにしていた女性の職員もいつのまにかじいさんの話に引き込まれてしまったようだ。
「あのぅ、毛虱の駆除はどうすればいいんですか」
と女性の職員が質問した。
「市販されてる殺虫剤はあるけどね、柔らかいとこに付けるのはちょっとね。それよりかあんたの股に生えてる毛ッ毛を全部綺麗に剃り落として清潔にしていれば完全に駆除できるよ。少女みたいにすっぽんぽんにさ。これが一番簡単だな」
じいさんは笑った。職員はまた恥かしくて顔を真っ赤にした。
「最近は東南アジアとかアフリカに観光旅行する人が増えて、虱、特に毛虱が日本でも増えているんだ。長い間忘れかけていた結核と同じだよ。東南アジアなんかのいかがわしいとこに入り込んで売春婦からもらってくるんだよな。衣虱と頭虱はここ池袋界隈とか新宿界隈に多いホームレスのオッサンたちの間でも増えているそうだから、あんたらも知識は持っている必要はあるよ。毛虱は銭湯とか温泉でうつるって話しがあるけどな、毛虱はお湯とか水の中に入ると陰毛にしがみついて離れないから、普通はうつる心配はないんだ。どうだ、安心したか? 最近はスーパー銭湯や温泉が大好きな女の子が増えてるから参考になっただろ」
そう言ってじいさんは笑った。
「わしの話はこれで終わりだ」
会議室に拍手が沸き起こった。
所長はじいさんに丁寧に礼を言った。それでじいさんが持ってきたビニール袋を見ると、一匹頭虱が見付かったので、取り出して顕微鏡で見ることにした。
「キャーッ、怖~いっ!」
顕微鏡を覗いた女性の職員が思わず奇声を発した。顕微鏡にはアニメに出てくる怪物みたいな怖い虫が映っていた。腹の部分は赤い血でパンパンに膨らんでいた。
床屋を済ませた浜田はその足で池袋のサンシャインシティーの五階にあるワールド・インポートマートでパスポートの申請手続きをした。十年間有効は一万六千円、五年間なら一万一千円だ。それで浜田は五年間で申請した。写真も撮ってもらったが手続き全部で二万円でおつりが来た。申請が終わると、下着や洋服の上下をデパートで買い揃えてトイレで着替えて脱いだ物はゴミ箱に捨てた。トイレの鏡を見ると綺麗になった浜田が薄ら笑いをして立っていた。
「溝口さん、昨日言ってた[ザンビアの地獄谷送り]って?」
と章吾は溝口に聞いた。
「そうだ、あんたにはまだ何も話をしてなかったな」
それで溝口は、[ザンビアの地獄谷送り]について章吾に説明を始めた。
「N自動車がN電気と合弁でAESCって名前の会社を作ったんだ。この会社は電気自動車用のリチュームイオン電池を作る専門の会社で、今後全世界に工場を建設する計画なんだ。電気自動車は今は一回の充電で150kmしか走らねぇ。これを300kmまで倍にするには電池に電気を貯める能力を倍にすりゃいい。こんなことは小学生でも分るよな。だが、それには電池の改良をしなくちゃならん。それで、電池の+電極のマンガンに微量のニッケルとコバルトを加えれば上手く行く目処を付けたんだ。ニッケルやコバルトは車一台当たりに使う量は知れたものだ。だがな、近い将来電気自動車が年間何百万台も生産されるとなると、使う量はバカにならねぇ。自動車用の電池はPソニックとかS電機でも大量に作ってるよな。この意味が分るか? 電池に使うリチウム、ニッケル、コバルト、マンガンなどは[レアメタル]と呼んでいるんだ。レアメタルには他にベリリウム、チタン、バナジウム、クロム、ガリウム、ゲルマニウム、セレン、ルビジウム、ストロンチウム、ジルコニウム、ニオブ、モリブデン、パラジウム、インジウム、アンチモン、テルル、セシウム、バリウム、ハフニウム、タンタル、タングステン、レニウム、白金、タリウム、ビスマスなんかがあって、レーザーみたいに新しく発明された電子部品や昔からある電子部品の性能アップに最近いっぱい使われるようになってきたんだ。だからよぉ、鉱物資源の相場がめっちゃ上がってさ、例えばプラチナなんかは金より遥かに高い金で取引されてるんだ。自動車や家電ばっかでなくて、工具とか鉄鋼なんかにもかなりの量が使われてるんだ。[レアアース]つて聞いたことがあるだろ? 学校で化学の時間に習った希土類元素のことだ。例えば蛍光灯に使われているイットリウム、セリウム、ユウロピオム、テルビウムとか、マグネットに使われているネオジム、サマリウム、ジスプロシウムなんか、オレたちが普段聞いたこともないような元素があるんだ。善雄のとこの米村工機でも、こんなレアな素材を集めるのに苦労してるらしい。
そこでだ、世界の工業国は揃ってレアメタルとかレアアースの資源開発に力を入れているんだ。だがなどこにでもある物じゃねぇ。埋蔵されてる場所は主にアフリカ、中国のモンゴルの方や南米とかに偏ってる。中国は自分の国でも結構産出するけどな、今アフリカの新しい鉱脈探しに力を入れているんだ。アフリカでも特に南アフリカ共和国は昔から色々な鉱物が採掘されているんだけど、最近は少し北のボツワナとかザンビアにも新しい鉱脈が見付かっているんだ」
章吾は久しぶりに社会科の勉強をさせられてる気分だった。それに、溝口先輩の知識の広さにも驚いていた。
溝口は話を続けた。
「ザンビアと言う国はな、地図で見ると下の方にリビングストンと言う探検家の名前にちなんだリビングストンって町があるだろ? この町の近くに南米のイグアスの滝、カナダのナイアガラの滝に並んで世界の三大瀑布の一つ、ヴィクトリアの滝があるから、それだけは大抵の奴が知ってるよな。だがな、この国の首都はルサカと言って百四十万人位住んでるんだが、昔はイギリス領のローデシアと呼ばれてた通り植民地だったとこで、すごく貧しい国だ。全人口が約一千二百万人なんだが、その六割の七百万人以上が一日一ドル、つまり一日百円位の生活費しか稼げねぇ。平均でだぞ。だからよぉ、栄養失調は当たり前、おまけに人口の二割弱がHIVつまりエイズに感染してるんだ。親がエイズに罹って死ねば、エイズ孤児ができちゃうよな。その孤児が六十万人も居るどうしようもない国なんだ。男は栄養失調と疫病で早死にするもんだから、男手が足りねぇんだ。ルサカは標高1300m位の高原の町だが、気候はそう悪くはねぇそうだ」
溝口の長い話は続いた。
「中国の投資家で、うちの社長とも面識がある蔡季陶さんが自分のとこからザンビアに鉱脈探しの探検隊を出したんだ。ザンビアは世界でも有数のコバルト産出国なんだ。それで、その探検隊がすごく良い鉱脈を発見してさ、そこでコバルトとか色々な鉱物資源の発掘を始めたんだ。だが、人出が足りねぇ。場所は首都のルサカから400km位離れたルアングワと言う河の支流沿いだ。貧しい国だから、道路もなければ、電力の供給もない辺鄙な所だ。仕方がねぇから蔡季陶さんが自分の金で道路を作り、発電所も作ったんだ。河があるから水だけは何とかなる。それでようやく採掘所を作ったんだが、人が集まらねぇ。そりゃそうだ。一千二百万人居てもさ、みな栄養失調のガリガリで過酷な力仕事をさせると直ぐ死んでしまうんだそうだ。それで蔡季陶さんはいいことを思いついた。人間はザンビアの国内からでなくて、全世界から集めりゃいいんだと。けどよぉ、普通に集めたら工賃が高くてやってけねぇし、環境が悪くて女もいねぇ。それじゃ定着しねぇよな。それでだ、蔡季陶さんは組織を動かして、犯罪をおかしたり、借金でクビが回らなくなったどうしようもない社会のクズみたいなヤロウを集めたんだ。こいつらを奴隷みたいにして使ったところ、これが結構上手く行ったんだ。オレは現地に行ったことはねぇが、なんでも自動小銃を持ったコマンド(襲撃隊を兼ねた警備兵)を大勢常駐させて、クズ野郎どもの足に鎖を付けて監視させてさ、働かなねぇ野郎は皮の鞭で引っ叩いて仕事をさせるのよ。ここに送り込まれたクズ野郎は逃げても射殺されるか獣の餌食になるからさ、一旦入ったら生きては帰ってこられねぇ。死ぬ奴も結構いるらしいが、死んだら隣の谷に投げ捨てると動物、鳥、昆虫に肉を食われて直ぐに白骨になるんだと。それで、オレたちはそこをザンビアの地獄谷と呼んでいるんだ。女を入れると女を奪い合って闘争が起こるからよぉ、女は一人も居ねぇんだ。子供でも生まれたら始末に困るよな」
「セックスとかはどうするんですか」
「新入りでひ弱な奴は大抵餌食になるそうだ。そんな奴はケツの穴に男根を突っ込まれてバクバクやられてさ、不潔なとこだから痔なんかになると耐えられなくて自殺する奴もいるそうだ。白人も、黒人も、世界中から色々な人種のクズ野郎を集めているのよ。辺鄙な所だから、選鉱とかは自動化せずに、人力でやるのが一番いいそうだ。メシさえ食わせておけば良く働くらしいぜ。日本だけでも失踪者は年間に9万人以上も居るからよ、そんなとこにクズ野郎を五人や十人送り込んで帰ってこなくてもどうってことはねぇんだよな」
溝口は茶をすすった。
「ザンビアと言う国は貧乏だからな、不満分子が武装して強盗なんかの犯罪がすごく多いそうだ。だからよぉ、蔡季陶さんの鉱山では重武装した警備兵は鉱山ばかりでなくて、産出物を運ぶトラックにも護衛兵を必ず付けて奴等の襲撃を迎い撃てるようにしているそうだ」
「軍隊ですね」
「そうだ。軍隊だ。主に銅、ニッケル、コバルトが採れるそうだが、他のレアメタルも採れる。微量だが金やダイアモンドも産出するそうだ。それでだ、浜田の野郎が連絡してきたら、あんたと池内の三人でザンビアのルサカまで浜田を送って行くことになる。浜田にはダイアモンドの原石を入れた箱を現地から運べと言うつもりだ。成田から香港に飛んで、そこから南アフリカ航空で南アフリカのヨハネスブルグまで飛んで、そこから乗り換えてルサカまで飛ぶんだ。ルサカまで二日かかるな。ルサカで蔡季陶さんの組織の人間に引き渡す話しが付いているんだ。奴もルサカであっちの組織に引き渡したら最後絶対に逃げて帰って来られねえ。だからルサカでお終いよ。どうだ、地獄谷の話は分ったか」
「良く分かりました」
四十一 地獄への階段 Ⅲ

一週間が過ぎて浜田が連絡を入れて来た。
「パスポート、用意ができた」
「あんた、女と借金取りに電話を入れただろ」
溝口はかまをかけた。
「電話はどこにもしてねぇ」
「ウソをつくな」
「バレてるのかよぅ。仕方がねぇ、白状するよ。女と借金取りに電話を入れた」
「バカヤロー、正直に言えよ。他はかけてねぇな」
「かけてねぇ」
「だったら許してやる」
「東京駅に十四時だ。必ず来い。JR NEX31号だ。出発は十四時三十分だ。パスポートを忘れるなよ」
「必ず行く」
浜田は借金取りの取立て屋の野口に電話を入れた。
「仕事の出発が決まった。JRNEX31号、東京駅十四時三十分だ」
「分った。こっちのことは絶対に漏らすなよ」
「お前に電話を入れたことはバレてるようだ」
「分った。上手くやれよ」
「飛行機が決まったらまた連絡を入れる」
溝口は章吾と二人で東京駅で浜田を待った。約束の十四時に浜田はやってきた。溝口とは別行動で池内を同行させたが、池内はバックアップだ。
「池内、浜田は女と借金取りに電話をしたらしい。オレの感だが、場合によっちゃ取立て屋が金魚のうんこみたいに浜田についてくる可能性がある。あんたはオレたちをつけるやつを監視してくれ。ルサカまでくっついて来たら面白れぇな。女は無視していい」
そう言い含めていた。溝口は刑事生活の時代に追い込まれている奴等の行動パターンを分析して予測を立てる習慣があった。
取立て屋の野口は中背で小太りした奴だった。ブタに喩えれば美味そうに見える感じだ。落ち着かない奴であたりをキョロキョロ見ながら、浜田の姿を遠くに確かめると別の車両に乗り込んだ。乗客は多いから、この時点では池内は野口の存在を認めることはできなかった。
溝口は成田空港で航空機の搭乗券を浜田に渡した。香港経由でザンビア―ルサカになっていた。
「ザンビアってどこですか」
浜田が聞いても溝口は黙っていた。浜田は章吾に目を移したが章吾もだんまりを決め付けていた。成田の第一ターミナルに着いた。フライトは南アフリカ航空で十八時四十分だった。搭乗までは二時間ある。その間に出国手続きを済ませて搭乗口付近で待った。
「トイレに行ってもいいですか」
「携帯、ここに置いて行けよ」
浜田は困った顔をした。溝口はそれを見落とさなかった。浜田は渋々携帯を置いてトイレに行った。溝口は章吾に目配せした。章吾は浜田に気付かれないようにして、浜田の少し後からトイレに向かった。浜田はトイレの途中で公衆電話を使って何やら連絡を入れていた。
「つけてる奴がいるぞ」
溝口は池内にメールを入れた。池内から了解の返事が届いた。
「携帯、取られた。用心してるようだ。南アフリカ航空、香港経由ザンビア―ルサカだ。ザンビアってどこだ?」
「分った。南アフリカの方だな」
章吾から溝口にメールが来た。
「公衆電話。内容不明」
とだけ書いてあった。浜田が戻ってからしばらくして章吾が戻ってきた。
溝口からメールを受け取って間もなく、先ほどから南ア空港の窓口でチケットを押さえるため焦っている小太りの男が居た。他には慌ててチケットを買う者は居なかったから、尾行はあの男だと推測できた。
「らしき奴を発見。チケットを買ってるとこだ」
溝口に池内からメールが来た。
「ボーディング後も見張ってくれ」
「了解」
予定通り成田を飛び上がって、二十三時三十分頃に香港に下りた。ここでヨハネスバーグ行きに乗り換えた。池内は小太りの男もついてきているのを確認していた。
小太りの男はヨハネスバーグでルサカ行きにもついてきた。
ザンビアの空港に着くと、
「ここからがあんたの大事な仕事だ。抜かりなくやってくれ。もう少ししたら迎えの車が来る。あんたはそれに乗って数百km先の鉱山からダイアの原石を入れた箱を受け取って、明日の夕方五時きっかりにここで落ち合おう。重いからそのつもりで運んでくれ。あんたの分け前は三分の一だ。一億位にはなるから安心しな。変な気を起こしたら命がないと思ってくれ」
浜田の目が輝いた。
「そんなにもらってもいいんですか」
「当たり前だ。体を張って仕事してもらうんだからな」
小太りの男はキョロキョロ落ち着かない様子で少し離れた所から浜田たちを見ていた。三人に気を取られて背後に池内が近付いても気付かない様子だ。不意に池内が小太りの男の腕を掴んだ。池内は握力が強い。それで男は、
「いててっ」
と声を出した。池内は、
「あんた浜田の仲間だろ? こんなとこに居ねぇで俺たちの仲間に入んな」
そう言ってぐいぐいと三人の所に引きずって行った。驚いたのは浜田だ。
「なんであんたがここに居るんだ?」
と小太りの男に聞いた。
「東京駅からあんたをつけてたのよ」
と溝口が薄ら笑いした。浜田はぞっとした。
「おいっ、浜田。ついでにこいつも連れてって手伝いをさせろ。こいつの取り分はねぇからお前の取り分から分けてやれよ。いいなっ」
「そうします」
浜田は完全に牙を抜かれていた。おとなしく溝口の指示に従った。
そこにジープが近付いてきた。運転手の他に肩に自動小銃をかけてる兵士らしき男が二人乗っていた。溝口が運転手の男に中国語でなにやら話をした。男は浜田と野口に服を渡して何やら話した。二人とも中国語が分らなかった。
「お前等、これに着替えろだと」
それで二人はその場で[つなぎ]の作業用制服に着替えさせられた。着替えが終わると、男が顎で、
「乗れ」
と合図した。浜田と野口はジープに乗り込んだ。彼等二人が着替えた服はそのまま置き去りにしてジープは急発進して走り去った。
溝口は洋服のポケットを全部調べて浜田と野口の携帯や手帳、財布を抜き取って、洋服はゴミ箱に捨てた。それを見ていた黒人の少年がゴミ箱に走り寄って、捨てた物を全部持って走り去った。
溝口、池内、章吾の三人は折り返しのヨハネスバーグ往きの飛行機に乗り込んで成田を目指した。
ジープは砂煙を上げながら猛スピードで走った。
「どこに行くんだ?」
振り落とされないようにしがみついている野口が浜田に聞いた。
「分らねぇ」
他の者が無口なので、浜田も野口も黙っていた。
途中一回だけ停車して渡されたパンとジュースを飲んだ。そこらで立小便を済ますとまた猛スピードで走った。六時間以上経って、あたりが暗くなる頃、前方に明かりが見えた。ジープは事務所らしき粗末な建物の前で停まった。運転手の男に、
「降りろ」
と顎で指図されて、二人は大人しく降りた。浜田はここで箱を渡されるものと思っていた。だが、兵士らしき男が四人やってきて別の部屋に移されて、そこで足に鉄のワッパを嵌められた。左右のワッパは鎖で繋がっていた。
浜田と野口は四人にどつかれて、廊下を通って広い部屋に入れられた。入れられたと言うより兵士の靴でケツを蹴られて蹴りこまれたのだ。足に鎖が付いているので部屋の中に転がった。と、周囲から喚声が上がった。新入りの奴隷として迎えいれられたのだ。部屋に居る者たちは皆両足を鎖でつながれていた。走れないようにされていたのだ。歩くと鎖がジャラジャラする。
身長が2m近い、筋肉もりもりの男が何人もの奴隷に取り囲まれてその様子を見ていた。大男は小太りの野口を目で舐め回すとにんまりと笑った。
「あれはいいタマだ。これから可愛がってやるか」
四十二 地獄
浜田と野口はどうにか床から立ち上がって、鎖をジャラジャラ引き摺って部屋の隅の方に落ち着いた。
「お前、何て言われてここまで来たんだよぉ」
野口は浜田に聞いた。
「ここに来ればダイアの原石を入れた重い箱を渡されるから、そいつを受け取って戻って来いと言われた」
と浜田。
「お前、奴等に嵌められたんじゃねぇのか」
「ダイアの話はオレを誘い出す餌だったようだな」
「畜生! オレたちここから出られるのかなぁ」
「分らん」
「なんでこんなとこに連れて来たんだよぉ」
「お前が勝手にオレのあとを追って来たんじゃねぇの? オレはお前には責任がねぇ」
目が慣れたとこで辺りを見回すと日本人らしき奴が数人固まっていた。近付くと日本語が飛び交っていた。浜田も野口も救われた気分になった。
「すみません。日本の方ですよね」
浜田は丁寧に聞いた。
「ああ、そうだ。今日ぶち込まれた新入りだな。お前等あいつ等に気を付けろよ。新入りには必ず手を出してきやがる」
そう言って奥の隅にたむろしているでかい黒人のグループの方を見た。
「ここ、長いんですか」
「三年になるかな? ここに居るとカレンダーが分らねぇ」
「どうすりゃここを出られるんですか」
「出られんよ。死んだら出してくれるだろ」
浜田も野口もやっと自分たちの置かれた立場を理解した。
「明日の朝、手配士みたいな奴が来て、お前さんたちの仕事を割り振ると思うよ。ここじゃ指示通り動かねぇと皮のムチで引っ叩かれるから頭に入れとけ。飯は不味いけどまあまあだ。サツのブタ箱よかましだ。トイレはあそこの隅のドアを開けるとある。隣にシャワー室もある。でもよぉ、ここじゃ女が居ないから気をつけねぇとレイプされちまうぜ」
話に拠ると、ここでは大体二千人くらい働かされていて、四割は黒人、三割が東洋人、二割が白人、一割が中南米~南米のラテン系でアラブ人は殆ど居ないそうだ。黒人はアフリカでなくて主にアメリカやヨーロッパから連れてこられた者が殆どだそうだ。
「朝メシは七時に起床ラッパが鳴るからそれが合図で八時までに済まさないと食いはぐれるぜ」
と別の男が付け足した。
話を聞いている間に、隅の大男の取り巻きらしい黒人が四人、ニタニタした顔をして野口の側にやってきた。何やら話しかけられたが言葉が全然分らない。それで、野口は促されて立ち上がると奥の隅の方に連れて行かれた。
「あいつが生贄かぁ。運の悪い奴だな」
と側に居た男が呟いた。
野口は言われるままに奥までついていった。すると、いきなりテーブルの上に上半身を押さえつけられて一人が野口のつなぎの制服のケツの部分を開いた。
「おいっ、何をしやがるっ」
と野口が怒鳴った。だが押さえているやつ等は平気な顔をして手を緩めなかった。鎖で足をつながれているから、排便用にケツの部分が開くような服になっているのだ。女性用下着のコンビネゾンのような作りだ。後に回った男が開いた所に手を突っ込んでパンツを引き下げて、ケツをむき出しにした。そこに大男がやってきて、張り詰めたでかい男根を野口の肛門に突っ込んだ。
「いてぇっ、やめろっ」
野口はでかい声で喚いた。それがどうやら大男を刺激したらしい。大男は野口の肛門に入れた男根を出したり入れたり、女とやる時のようにバクバクとやった。やがて大男は野口の中に射精すると、今度は別の奴が代わってバクバクやった。五人も回されて、野口はぐったりした。野口はこんな屈辱を味あわされたのは生まれて初めてだ。日本人種や朝鮮人種は肌が白くて綺麗だ。野口は小太りした体格で丸出しにされた尻は黒人の男たちには美味しい[ブツ]に見えたに違いない。言って見ればだっこちゃん人形の代わりをさせられたのだ。
五人が終わると、床の上に放り出された。野口は歯を食いしばって這いずって日本人のグループの所まで逃げてきた。
「お前なぁ、あいつら明日もお前を捕まえて女の代わりをさせるぞ。お気の毒に」
見ていた男の一人が野口を哀れむような目でそう言った。男の言った通り翌日の夜もまた回された。野口は泣きたくなるほどの屈辱に夜は良く眠れなかった。
浜田と野口の働き場所は別の所に指定された。浜田は河原でダイアモンドの原石の選鉱作業だった。古株の男が要領を教えてくれた。野口は肛門の周りがヒリヒリして痛んだ。それを我慢しながら、銅鉱石の発掘作業をやらされていた。つるはしで岩を砕いて、砕いた岩をスコップでベルトコンベアに乗せるのが仕事だった。
二人は来る日も来る日も同じことをやらされた。手を休めると監督の男の皮のムチが飛んでくる。野口も一度やられたが、めちゃくちゃ痛かった。浜田も野口もついに地獄への階段を登りつめて、地獄に落ちてしまった。いや、落ちたと言うより溝口たちに突き落とされたのだ。
「送ってきました。今頃働かされているはずです」
「ご苦労だった。これであの二人は一生帰って来れんだろう」
「はい。地獄谷に送り込んだ奴は今までに生きて戻った奴は一人もいないそうです」
「日本の警察のブタ箱に入って税金を食いつぶしているよりましだな」
溝口は柳川に報告を終わった。柳川は受話器を取ると米村に電話した。
「頼まれた件ですが、完全に始末しました。今後浜田が何か言ってくることは絶対にありません」
「殺ったんですかな?」
「いえ、一生帰ってこれない所に送りました。毎日強制労働をさせられていると思います」
「ありがとう」
柳川は送った場所はもちろんのこと、それ以上の細かいことは一切伝えなかった。
米村は帰宅すると妻の美鈴と沙希を呼んで、浜田の話を伝えた。沙希は今まで自分の父親とまともに接することがなかった。それで今までに経験がなかった父親の優しさに触れて、ほんとうの父親とはこんなに良いものかと改めて感じていた。そう、本来なら常識的に離縁を言い渡されてもおかしくはない事件だ。なのに叱ったり嫌味を言ったりせずに、反対に家族が揃って優しく守ってくれたのだ。
章吾は章吾で、自分は沙希を守ってやると心に決めていたが、今回はそれが出来て誇らしく思っていた。これからも影になって沙希を守り続けてやろうと思っていた。
ザンビアのルサカからの帰り道、南アフリカのヨハネスバーグでトランシットするのだが、少し時間があった。章吾は、
「土産を買いたいんですが」
と溝口に言った。
「女の子にか?」
「はい」
「じゃ、金製品がいいね。知ってると思うが、ヨハネスバーグは確か一八八六年頃かな? この近くで金鉱脈が発見されてから発展した街なんだ。それで、ここは今でも南アフリカ共和国の経済の中心都市でさ、免税店で金製品を沢山置いてるからゴールドがいいね」
章吾は溝口と池内にからかわれるのを覚悟していたが、溝口はからかうどころか一緒に付き合ってくれた。
「オレには決まった女がいねぇが、心に決めた女性が居るなら大事にしてやれよ。土産物は金額でなくて、章吾の気持ちが伝わるようなのを選べよ」
とまで言ってくれた。随分と探し回ったあげく、手の込んだ彫刻が施されている純金のネックレスを買った。もちろん美登里にプレゼントするつもりだった。溝口もこれならいいねと同意してくれた。池内も女性へのプレゼントだと言ってゴールドのペンダントを買った。章吾が買ったやつはなかなか良いデザインだと思われた。ゴールド製品なので、サーティフィケートシート(保証書)が付いてきた。この地は長い間英国の植民地だった所なので、英国の昔の貴族文化の影響を受けているのか、箱は本革張りで美しい模様が付いていて、保証書も凝ったデザインで額にでも入れて飾っておくような感じの物だった。
日本に戻ると、久しぶりに心の平和を取り戻した章吾は、沙希が残してくれた軽自動車で美登里と旅行に行く約束をした。遠く南アフリカから持ち帰った純金のネックレスを渡すと美登里は飛び上がらんばかりに喜んでくれた。こんな時、心から喜んでくれるとすごく嬉しいものだ。
章吾の休みは日曜日しかない。それで、
「鎌倉のあたしの実家に遊びにいらっしゃらない」
と美登里が提案した。章吾は気持ち的に恥ずかしかったが、いずれ訪問しなければならないと思っていたので、初めて美登里の実家にお邪魔することにした。お土産は沙希に教えてもらった目黒の林菓房の箱詰めの和菓子にした。
美登里の両親は温かく娘の彼氏を迎え入れてくれた。美登里は一人っ子のため、両親の元では甘ったれ娘に変身していた。こんな可愛い美登里の素顔を見たのは初めてだと章吾は思った。
「章吾さんのご両親はお元気なんですか」
美登里の母親が尋ねた。
「長野県上田市に近い上田原に実家があり、兼業農家です」
「お父様はどちらへお勤め?」
「上田市内の精密機器のメーカーに勤めています」
「ご兄弟は?」
「弟が一人おります」
「じゃ、あなたご長男ね。将来はお家をお継ぎになられるんでしょ?」
「いいえ。自分は多分今の仕事を続けると思います。弟が家を継ぐだろうと思ってます」
母親らしい質問が続いた。
「お母さん! 初めていらしたのに、そんなこと次々聞いたら失礼よ」
美登里が遮った。
「いえ、どうぞ何でも聞いて下さい」
「じゃ、もう少しね」
と母親は尚も続けた。
「美登里のこと、どんな風に思っていらっしゃるの」
今度は父親が遮った。
「おいおいっ、母さんの気持ちは分るけど、聞きすぎだよ」
と笑った。
「美登里さんはとても可愛い方だと思っています。出来れば将来結婚を許して頂ければ嬉しいと思っています」
章吾はここまで聞かれたらはっきりと気持ちを伝えておいた方が美登里のためにも良いと思った。
「美登里さんのお気持ちもありますから、今日はこれ位で勘弁して下さい」
と章吾は付け加えた。側で聞いていた美登里は気持ち顔が赤くなっていた。
四十三 陰謀

沙希は元義父のあのおぞましい魔の手から逃れて、落ち着きを取り戻していた。夫の善雄は生活が不規則で毎晩遅く疲れて帰宅したので、結婚して二ヶ月も経ってもまだ身体を求められたことはなかった。だが、沙希は善雄が自分を大切にしてくれていることが分かっていたから、その内にきっと愛撫される機会があるだろうと思って待っていた。
そんなある日出掛けに、
「今夜中国から来ている大切なお客様の接待で六本木のラ・フォセットに案内する予定になっているんだ。オヤジも一緒だ。ラ・フォセットに行くのは気が進まないかも知れないけど、すまないが、夕方社の方に来てくれないか」
と沙希を誘った。
「分りました。お義母さまにお断りして、五時ごろ会社に伺います」
「ありがとう」
沙希は午後身支度をして出かけた。膝上丈のスカートの淡いピンク色のシルクのシャネルのスーツ、内側には青緑系の綺麗な花柄のグッチのブラウスを着た。久しぶりにヒールが10cmの靴をはいて、その上にミンクのコートを羽織った。洒落たサングラスをかけて、エルメスの白いバーキン25を下げて、つばの広い帽子を被ると映画スターのような感じだ。美鈴が沙希のそんな格好を見て、
「沙希ちゃん、おめかしをすると綺麗ね。お気を付けて行ってらっしゃい」
と褒めてくれた。沙希は普段自宅に居る時は髪はポニーテールにして、Gパンに綿のワークシャツ、出かける時はその上にジージャンを羽織るラフな格好をしていたからだ。
沙希は四時過ぎにタクシーを呼んで日本橋まで走らせた。
○○ホールディングスの受付に行くと、コートを脱いで腕にかけて受付の女性に、
「恐れ入ります。米村善雄とここで待ち合わせを致しますので」
と断った。沙希が最初に訪れた時に案内されたパーティションで仕切られた待合室に入ろうとすると、受付の女性に呼び止められた。
「奥様、どうぞこちらへ」
案内したのは沙希が初めてここを訪ねた時に応対した秘書室の中嶋麗子だった。彼女は女の鋭い目で沙希のファッションをチェックしていた。初めてここで出会った時、みすぼらしいGパン姿だった彼女がまさか善雄と結婚するなんて想像もしてなかった。だが、目の前に立つ沙希の洗練された美しさを見て、
「負けたな」
と思った。
バッグは自分も欲しいと思っていた白いエルメスのバーキンだ。あれって確か八十万円以上もして中嶋は自分のお小遣いではなかなか買えなかったのだ。
中嶋は沙希をお客様用の応接室に通した。
「お飲み物ですが、ティー、コーヒー、ジュース、他に炭酸飲料がございますが、ご希望はありますか」
と中嶋は尋ねた。
「冷たいお水にして下さいな」
五時半頃に善雄が顔を出した。
「待たせてごめん。外に車を用意したからオヤジと三人で行こう」
ビルのエントランスに下りると運転手がドアを開けて沙希を促した。善雄は、
「僕は前に乗るから」
と善太郎と沙希を後部座席に座らせた。
「沙希ちゃん、今日は随分綺麗だね」
善太郎はお世辞抜きで沙希を褒めているようだった。後からもう一台の車に客と思われる三人の男が乗り込んだ。善雄はそれを確かめて運転手に、
「出してくれ」
と指示した。
二台の車は六本木のラ・フォセットに着いた。柳川と澤田が出迎えてくれた。澤田は小声で、
「沙希ちゃんしばらく。幸せそうね」
と囁いた。柳川は義理の娘になった沙希があんなことがあってから、今落ち着いた様子を見て安心した眼差しで沙希を見ていた。
店に入ると澤田は、
「奥様、どうぞこちらへ」
と沙希を案内した。同様に柳川も、
「奥様」
と沙希を呼んだ。沙希は二人のプロフェッショナルな応対振りに流石だと感心した。
客は三人全部中国人だった。どうやら中国の会社との合弁をめぐって交渉をしている様子だ。三人とも日本語を流暢に話したので、会話の内容は沙希にも良く分った。中国人の要求は合弁の橋渡しをするについて、色々な所に根回しの必要があり、資金がかかる。だから内金として十億円を用立ててくれと言っていた。一人は相手先の会社の役員で、他の二人はM&Aに関わるコンサルティングをしている会社の役員のようだった。中国の企業は合弁で会社を設立するにしても法律関係がややこしく、役所にも十分なパイプがないと話が上手く進まないのだ。沙希は澤田に叩き込まれた[気配り、気遣い、でしゃばらない]を徹底して、にこやかな顔で座っているだけで、仕事の話には口を出さなかった。
善太郎は金額が大きいので、二、三日中に相手方の会社の銀行口座に振り込むと言った。すると、
「この話は急ぎますので、明日までに日本円で結構ですので現金で用意して下さい」
と主張した。善太郎は考えている風であったが、明日となると会社の経理に話を通して処理する必要があるからと席を立った。善雄もトイレだと言って退席した。残された沙希は中国人にどう接するか考えていた。
すると三人が中国語で何やら話を始めた。沙希は中国語が使えたが[でしゃばらず]に徹して一切口に出さずに話を聞いているだけにした。
「明日、あいつ等十億の金を用意できるかなぁ」
「大丈夫だと思うが」
「いいか、現金で受け取ったら上海に高飛びしよう。後で騙されたと気付いた時にはオレたちは霧の中よ」
話を聞いているとどうやらこの話は詐欺らしい。沙希は耳を疑った。だが、顔には出さずにただ黙って聞いていた。受け取った名刺を見ると、相手方の会社の役員は李恩涵、コンサルの二人は劉兆麟と洪基炎と名乗っていた。
善太郎が戻って来るのが見えた。沙希は中国人に、
「ちょっと失礼します」
と言って席を立ち、善太郎に駆け寄った。善太郎は、
「何?」
と怪訝そうな顔をした。
「ちょっとそちらへ」
沙希は善太郎の腕を引いて、小部屋に案内した。勝手が分った店だから、こんな時は都合が良い。小部屋に入ると、
「お義父さま、あの三人の中国人は詐欺です」
と言い切った。
「何でそう思うのかね?」
「実はお義父さまが席を立たれてから三人とも中国語で話をしていました。明日十億を受け取ったら上海に高飛びする。ウソが分った時はあの三人は霧の中と言って嘲笑していました」
「沙希ちゃん、それ本当かね」
「はい、間違いありません」
善太郎は直ぐにどこやらかに電話をした。
「洪基炎、李恩涵、劉兆麟と言う名前の中国人のバックを至急調べてくれないか?」
五分ほどして、電話がかかってきた。
「そうか。分った」
携帯の電話を切断すると善太郎の顔色が変った。
「沙希ちゃん、ありがとう。さっ、待たせちゃ失礼だから席に戻ろう」
そう言って善太郎と沙希は席に戻った。善太郎はにこやかに三人の男たちに調整の時間がかかって済まなかったと詫びた。
「十億円は明日揃いますか」
洪が尋ねた。
「それが、大金なので思うようには行きませんで、一週間はかかるようです」
「それは困りました。半額の五億でも無理ですか」
「誠に申し訳ない。無理です」
劉が口を挟んだ。
「じゃこの合弁の話はダメになるかも知れませんよ。米村さんはそれでもいいのですか」
と畳み掛けて来た。善太郎は途方に暮れた顔をして、
「困りました。大変困りました」
と答えた。それを見て善雄が、
「工機の方から立て替えて出しましょうか」
と善太郎に言うと善太郎は厳しい目で善雄を見て、
「ダメだ」
と否定した。相手側の役員の李が、
「ではこうしましょう。私が明日中国の方と相談して明日いっぱいは懸案として、それまでに米村さんの方でも善後策を考えておいて下さい。明日の夜までに現金が用意できないなら仕方がありません。この話はなかったことにしましょう」
と言うと劉が、
「米村さんのためです。明日の夜までに何としても金を集めて下さい」
と付け足した。交渉はこれで一旦物別れとなった。
善太郎は善雄と沙希と一緒に帰宅するなり、
「沙希ちゃん、大当たりだ。助かったよ。あやうく十億円をかっぱらわれるとこだった」
と沙希をねぎらった。善雄は、
「どう言うことですか」
と善太郎に聞いた。
「いやね、沙希ちゃんがあの三人は詐欺師だと言うから、警視庁公安部の友達にあの三人の背後を急いで調べてくれと頼んだんだよ。そうしたら、三人共、公安でもマークしている上海を中心に暗躍しいてる中国マフィアの幹部だと分ったんだよ。手口が巧妙だから十分に注意してくれと言ってたよ。最近新宿を拠点にして国内でも色々やってるらしいだと」
善雄は顔面が蒼白になった。
「所で、沙希ちゃん、どうしてあの三人が話をしている内容が分ったのかね」
「あたし、ほんの少しですが、中国語の会話ができるの。名刺を頂いた時、李恩涵は朝鮮族に多い名前だから北の北京の方かな? 洪基炎はずっと南の広東省に多い名前だから南方系、劉兆麟は南方でもずっと奥地の四川省に多い名前だな、なんて見てると変な話を始めたの。中国語が分らないと思ってぺらぺらと下品な言葉で話をしていたわ」
善太郎は沙希の語学に驚いていた。
「沙希ちゃんマフィアに関係すると命が危ないから、この話はここだけにしておこう」
と沙希に今後この話をしないように促した。
「お義父さま、分りました」
翌日沙希はバッグ、コート、スーツなどブランド品一式を銀座にできたブランド品レンタル会社に返送した。沙希はブランド品を買う金は持っていたが、普段使わないし、毎回同じ物を着たり持ち歩いたりするより、改まった席に行く時だけ、レンタル会社から借りた。それを聞いた美鈴も賛成してくれた。
「そうね、誰が見ても思い切った贅沢に見せるにはそれがいいわね」
そう言って自分もその内に利用したいと言った。シャネルのポシェットなんかでも、買うとなると五万円以上もするが、借りれば一日五百円で綺麗なのが使える。保険を掛けておけば万一の場合にも問題はないのだ。
翌日善太郎は李恩涵に電話をして、
「せっかく良いお話を持ってきて頂いたのに誠に残念だが不景気で資金繰りが厳しく、このお話しを断念せざるを得なくなりました。お力添えに感謝します」
と丁重に断った。電話を終わると、会社の善雄以下企画部の者を会議室に全員集めて雷を落とした。
「今回の話だが、あれだけ裏を調べておけと言っておいたのに、あやうく詐欺に引っ掛かる所だった。お前達はどこに目を付けてるんだ。下手をすると会社を潰すことになるんだ。中国のマフィアは最近膨大な金を動かす力が付いて、うちの会社から吸い取るだけ吸い取った後捻り潰すなんてことはわけはないんだぞ。今後十分に慎重に進めてくれ」
と叱った。全員真っ青になって善太郎の説教を聴いていた。
四十四 心の中の隙間
沙希は穏やかな正月を迎えた。義理とは言え善雄の両親は実の娘以上に可愛がり大事にしてくれたから、沙希はこんな正月を迎えたのは生まれて初めてだ。
だが、昨年の中国マフィアの詐欺事件以来、善雄がなんとなく沙希のことを避けているような気がして、それが心の中に満たされないものを作ってしまっているように感じていた。あの事件の時は、沙希は大変なことが目の前で起こりつつあると思って、ただ夢中で訴えただけだ。だが会社で企画部門の責任者だった善雄の立場に少なからずダメージを与えてしまったことも否めない。夫婦だからこそ、そんな場合信頼関係の修復が必要だったが、年末一杯善雄は米村工機の仕事も多忙で沙希を振り返って見てくれる暇がなかったようだった。
「あたしって、女として魅力がないのかなぁ。こんな時夫婦で愛し合えば気まずいことだって乗り越えられるのになぁ」
沙希はそんなことまで思っていた。夫の善雄と寝室は一緒なのに、とうとう一度も抱かれずに年を越してしまったのが心の中の虚ろの原因だ。
早朝初詣を済ますと、昼間は年始の挨拶に傘下の企業の社長などが相次いで訪れ、善太郎、美鈴、善雄、沙希と多忙を極めて休む暇もなかった。だが、夜は久しぶりに一家揃っての団欒となった。
「善雄、月曜日から十日ほどブラジルの視察に行って来い。月半ばには帰ってこられるだろう。今回はお前一人だ。新婚旅行もせずに沙希ちゃんに淋しい思いをさせちゃってるから、この際沙希を連れて二人で新婚旅行も兼ねてゆっくり遊んで来い」
善太郎は美鈴と沙希が一緒の所で善雄にブラジルへの出張を勧めた。それで急遽仕度して善雄と沙希はブラジルに向かった。
米村工機にはブラジル人、ブラジル二世などが大勢働いている。彼等の祖国を見ておくことも大事だが、ブラジル、ロシア、インド、チャイナ(中国)などのBRICS諸国の経済成長は著しく、米村工機のブラジルへの進出可否について調べるのが主な目的だった。
日本は真冬だが、ブラジルは真夏だ。それで二人とも軽装ででかけた。
善雄はサンパウロ出身のピコと呼ばれているブラジル二世を営業の幹部に取り立てた関係で少しはブラジルのことを聞いて知っていた。
ブラジルは国土が広い。欲張ってもそう多くは回れない。それで、南から、東京都と人口がほぼ同じのサンパウロとサントス市に続いてリオデジャネイロ市を中心に回ることにした。この三つの都市だけで人口が二千万人を越えるのだ。少し奥地になるが首都のブラジリアにも寄ることにした。ブラジリアは都市計画に基づく美しい町で、きっと沙希の想い出にもなるだろうと思った。最後に北部のアマゾン川河口のベレンに立ち寄って帰る計画だ。ベレンは人口は多くはないが、移り住んだ日系人が多いので知られている港町だ。
初めての海外旅行が遠く離れた南米のブラジルなんてと沙希は戸惑ったが、兎に角夫の善雄にぴったりとくっ付いていればいいやと思っていた。
午後三時過ぎに成田からデルタ航空でサンパウロ(GRU))に向かった。なんたって成田から二十七時間以上の空の旅だ。ブラジルの遠いことを時刻表を見て沙希は驚いた。飛行機は取りあえずアメリカのアトランタ空港に向かって飛び、そこからサンパウロを目指して飛んだ。
グアルーリョス国際空港に着陸すると、沙希は広さに驚いた。一昔前は不便だったそうで、この空港は不便を解消するために新しく作られたそうだ。現在はハブ空港になっていて、航空機がひっきりなしに発着していた。時差の関係で午前八時過ぎに着陸したので周囲の景色が良く見えた。入国手続きを済ませると、ホテルからリムジンバスに乗って五つ星のファザーノホテルに向かった。
「沙希、疲れたか?」
「はい。少し。でもビジネスクラスにして頂いたからゆったりしてたのでそれほどじゃないよ」
「僕は海外に来るとレンタカーを借りて回るんだ。良かったら一緒に来ないか」
「もちろんついて行きます」
善雄はレンタカーを借りると早速市街に出た。車はトヨタ製だった。
善雄は最初に市内のサンパウロ・ジェトロセンターに寄り、サンパウロ周辺の産業情報を仕入れた。郊外に工業団地があり、色々な企業があるが、やはり予想した通り非金属鉱物や鉄鋼、アルミなどを生産する企業が多かった。予想外だったのは木材製品のメーカーの規模が小さかったことだ。善雄は米村工機の製品の需要につながると思われる企業を選んでジェトロの紹介状を持って回った。
機械分野ではActaris、Toledo Balanças、Springer Carrierを回って見ることにしたが、電機・通信分野では送電や発電などインフラ関係が殆どだったのであきらめた。
ホテルに戻って夕食を済ますと、疲れが出て二人とも早めにベッドインをした。大きな気持ちの良いダブルベッドだった。
大きなホテルだが、周囲の物音が無く、静かな夜だった。沙希はぼんやりと成田からここまでの飛行機の旅を思い出しながら、いつものように善雄は眠ってしまったと思っていた。それで沙希もうつらうつらしていると、突然善雄の手が沙希の胸に触れた。最初は寝相が悪いのかと思っていたら、後から抱きしめられて、ネグリジェの上から乳房をゆっくりと愛撫され始めた。沙希はじっとしていたが、胸の中は嬉しさで満ち溢れていた。やがて、善雄は沙希の身体を自分の方に向けると、沙希が着ていたものを全部丁寧に脱がせて自分も裸になって、唇を重ねてきた。沙希は善雄にされるがままに素直に応じた。善雄は沙希の首筋から下腹部まで唇を這わせて愛撫してくれた。
沙希は今までに何人もの男に抱かれてきたが、自分から抱かれたいと思ったことは一度もなかったし、身体をいじられても気持ちよく感じたことは一度もなかった。だが、その夜は、善雄の愛撫に身体が反応して心地良さが続いて知らず知らずに掠れた声が漏れ出ていた。もう我慢の限界に達した時、善雄は沙希の中に入れて来た。長い間待っていたその感覚は言葉では言い表せない快感だった。善雄の動きでかすかに聞こえるベッドの軋みを聞きながら、沙希は海の上に浮かんで静かな波に揺られているような気持ちの良さの中を彷徨っていた。
突然善雄の動きと息遣いが激しくなった。沙希は善雄にしがみついている内に、
「あぁぁ、だめぇ、あたしいきそう」
と思わず声を出すと意識が遠のいて頭の中が真っ白になり身体全体が痺れたように震えた。その時、
「うっ」
と言う善雄のうめき声と共に沙希の中に善雄の物が広がったように感じた。この時善雄は沙希の上で果てたようだった。
二人はしばらくそのまま抱き合っていた。善雄の腕の中で、沙希は生まれて初めて、男の愛撫の心地良さを感じていたのだ。
長い間抱き合ってから、
「沙希、好きだよ。愛してるよ」
と耳元で囁かれたその言葉は、善雄が沙希と結婚してから初めて沙希にかけた愛の言葉だった。その言葉で、二十二歳になる沙希の心の中の隙間は善雄の愛情で埋め尽くされてしまった。
四十五 新婚旅行

ホテルで朝食をとりながら、善雄が話し出した。
「もしもだよ、沙希が僕みたいな会社の経営者だとして、部下が出張に奥さんを連れて行きたいって言ったら許可する?」
「いきなり難しい質問ね。部下のことを思ってあたしなら黙ってハンコを捺しちゃうかも」
「だろ? 心情的に考えるとつい出張命令にハンコを捺してあげたくなるよな。まして新婚旅行を兼ねてだったら」
「そうねぇ、行かせてあげたくなるわね」
「でもさ、会社の仕事は基本的に公私をごっちゃにしてはいけない原則があるんだよ」
「それって許可してはいけないってこと?」
「ん。それが正しい処理なんだ」
「じゃ、あたしたちの今回の出張はどうなるの」
「沙希には言ってなかったけど、会社に休暇願いを出してきた」
「じゃ、出張旅費は会社から出ないの」
「ん。出ない。全部自費だよ」
「へぇーっ? そうなんだ」
沙希は八千名以上もの従業員がいる米村工機の副社長なのにと思っていると、
「仮に出張扱いにしたとしても、僕には誰も文句は言わないけれど、僕が新婚旅行を兼ねて若い奥さんを連れて出張したらさ、同じことを部下がやってもダメだとは言い難くなるよね。もし、ダメだと言えば部下に不信感が生まれちゃうよね」
「でも、お義父さんはそうは言ってなかったじゃない? 新婚旅行を兼ねて出張に行って来いっておっしゃったわね」
「あはは、そこなんだよ。オヤジの奴、多分僕がどうするのか試したんじゃないかと思うんだ。この件で小言を言うことはないと思うけど、公私をごっちゃにするようじゃ、将来自分の後を任せるには少し不安が残るよね」
沙希は善雄が会社の仕事についてかなりしっかりとやってるんだなぁと感心した。普段[もやし]みたいな奴で頼りない感じもしていたが、案外そうでもない一面を見せられたように思った。
「世間じゃ事業仕分けとか言ってお役所の仕事の内容にかなり突っ込んだ議論をしているよね」
「ええ」
「あの事業仕分けをする側の人たちはそんな所を厳しく見てるんだよ。僕のとこみたいな私企業でもきちっとするのが当たり前なのに、大勢の人から集めた税金を使って出張したりするお役人さんが、出張先で女を連れて観光なんてやってたら許されないよね」
沙希は善雄が新婚旅行のためにと、ちゃんと休暇を取って連れてきてくれたのを聞いて、気が楽になった。この話を聞くまでは、仕事の邪魔をしたらいけないとかなり気を使っていたのだ。
「なんだ、気を遣って損しちゃった」
沙希が呟くと善雄が、
「えっ?」
と聞き返した。
「何でもないよ」
沙希はそんな話を聞いたので、新婚旅行気分になった。気持ちとは不思議なものだ。それに、昨夜善雄が初めて抱いてくれた嬉しさの余韻もまだ残っていた。
「今日は一社だけ回ったら、午後は飛行機でリオデジャネイロに飛ぼう。距離が遠いから車じゃ大変だからさ」
それで大きなビルの立ち並ぶ市街を抜けて、アトランタから飛んできた時とは別のコンゴニャス国際空港に地下鉄に乗って行った。電車に乗ると上の方に[東急車輛]と書かれたエンブレムが付いていた。どうやら日本から輸出した車両らしい。
コンゴニャス国際空港からリオデジャネイロのサントス・デュモン空港の間は[ポンチ・アエーレア]と呼ばれるシャトル便が飛んでいて、それが十分間隔でひっきりなしに飛んでいるのを見て沙希はまた驚いた。日本の都会の電車に乗るような感じだ。ポンチ・アエーレアは空の架け橋と言う意味らしい。
沙希たちもこのシャトル便に乗ってリオデジャネイロに向かった。ホテルや善雄が回った会社では英語で会話が通じたが、飛行機に乗ると周りはみなポルトガル語が飛び交っている。沙希はスペイン語しか知らなかったが、ポルトガル語は似た所があって、半分くらいは何を話しているのか分った。
しばらくすると、眼下に素晴らしい景色が見えてきた。
エメラルド色の青い海と起伏の多い地形。
「これがリオデジャネイロの風景かぁ」
と見とれている内に飛行機は空港に向かって降下してすぐに着陸した。
善雄は観光案内所に立ち寄った。
「工場地帯は北地区にあるそうだけど、聞いた所では治安がかなり良くないそうだ。だからリオは観光だけにした」
「そんなに悪いの?」
「南の方は金持ちが住んでいて治安は悪くないそうだけど、北の工場地帯は貧乏な人が多くて、それでぼやぼやしていると持ち物を盗まれたり車に傷をつけられたりするんだって。ブラジルではサッカー選手で有名な人がいるけど、ハングリー精神で立ち上がる人が多くて、だからサッカー選手は北の方の出身者が多いんだってさ」
「へーぇ? そうなんだ」
それでホテルに着いたらゆっくりして明日は観光をしようと善雄は言った。
ホテルは[Pestana Rio Atlântica ]と言う所にした。部屋は明るくて海が見え、ホテル付属のプールも素的だった。五つ星だ。
「ここに二泊して三日間くらいのんびりしよう。ジムもあるし」
それで二人は真夏のリオでのんびりと過ごすことにした。日本では真冬の寒い季節だ。ここにいるとそんなことを忘れてしまいそうだった。
ホテルはコパカバーナビーチに面していたが、イパネマ海岸の方にも連れて行ってもらった。海岸は人出が多かったがホテルのプールは人が少なく快適だった。善雄は夜は沙希を連れて、本場のボサノヴァを聴きにライブハウスに出かけた。ボサノヴァを聴いていると、沙希は異国の雰囲気に満たされた気がした。
善雄はその夜も次の夜も沙希を抱いて優しく愛撫してくれた。結婚した当初は実感がなかったが、善雄と愛し合っている内に、沙希はいつの間にか心から善雄を愛せるようになり、この人が自分の旦那様だと実感が湧いてきた。
既婚の女性なら誰でも経験があるだろう。やはり新婚旅行の初夜に続く桃源の世界は何にも増して幸せを感じられる一時だ。
リオの素的な一時を過ごし終わって、再び空路で首都のブラジリアに向かった。飛行機が降下を始めると、眼下に整然としてビルの立ち並ぶブラジリアの街並みが見えてきた。都市計画により何もない所に作られた都市だけあって、道路は全て直角に敷かれていて、旧い家並みのようなぐにゃぐにゃした所はない。比較的新しい街だが、世界遺産に登録されている。
「ここはね、近代的なモダン建築が沢山あるから、レンタカーであちこち回ってみよう」
それで、善雄は空港近くでレンタカーを借りて街を走り回った。大統領官邸(アルボダーラ宮)、国会議事堂、ジュセリーノ・クビシェッキ橋、大聖堂など、どれもモダンアートの展覧会を見て回るような綺麗な造形のものばかりだった。
最後はブラジル北部のアマゾン川河口のベレンに飛んだ。小さな町と言っても人口は百万人を越えるのでそこそこの規模だ。
この町は、昔ポルトガルの王族に支配されていた時代から残された建物がいくつかあり、港町なので、海からの攻撃から守る要塞はかっての大航海時代の栄華の跡を残しているようだ。海に突き出た[ベレンの塔]はヴァスコ・ダ・ガマの世界一周の偉業を記念して作られたものだそうで世界遺産に登録されている。
べレンは観光旅行だった。ホテルは国際空港から二十分位の所にある [Crowne Plaza Belem] に泊まった。清潔でなかなか素的なホテルだった。
「最後の夜になったなぁ。明日はここから一旦サンパウロのGRU に戻って、そこからデルタ航空で成田に帰ろう」
そう言いながら沙希の荷物を見て、
「沙希はお土産をずいぶん買い込んだな」
と笑った。
「だってぇ、ブラジルなんてめったに来れないところだから、お土産をあげたい人がいっぱいいるから」
沙希は弁解した。
最後の夜は沙希は積極的になって善雄に愛された。燃え上がった沙希を相変らず善雄は丁寧に愛撫してくれた。そして、一生忘れられない想い出ができたと思った。
翌朝べレンの国際空港を飛び立って成田を目指した。面白いもので、往きは随分長く感じたが、帰りは飛行機を乗り継いでもそれ程長くは感じなかった。成田空港の上空から見た眼下は雪景色一色だった。二人は地球を半周して真夏の国から戻ってきたのだ。
四十六 波紋
一月の半ば、善雄は新年になって初めて米村工機に出社した。総務課の女性がまとめて持ってきた年賀状などを見ていると、溜まった書類の間に出張旅費の精算用のブラジルへの海外出張命令書があった。
「あれっ、これゃ何だ? 休暇願いを出すように指示をしておいたはずだがなぁ」
早速総務部長の佐藤健介に電話して呼びつけた。
「お坊ちゃん、いや、副社長、明けましておめでとうございます。今年もお手柔らかにお願いします」
佐藤は父の善太郎が苦労した時代からずっと米村工機を支えてくれた大切な男だ。
「おいおいっ、健さん、お手柔らかはないだろう」
と父の善太郎と同年代の佐藤を見て笑った。
「所で、わざわざ健さんに来てもらったのは、正月休みのことだよ。僕はホールディングスの秘書の中嶋さんに、今回のブラジル行きは女房を連れて新婚旅行を兼ねて出かけるから休暇届けを出すように指示をしておいたのだけど、出張伝票が出てるな。これは健さんの一存か?」
「いや、私は坊ちゃんの性格を良く知ってますから、出張はおかしいなと思ったのですが、なんでも中嶋から、出張にするようにと言付けがありましたもんで」
社長の善太郎が不在のことが多いので、業務は善雄が社長代わりをしていたが、善雄の出張命令書は総務部長の佐藤の代印で処理するようになっていたのだ。
「そうか、分った。所で健さん、うちの会社で海外出張する者の中に仕事に関係ない女を連れて出かけた者は居るかなぁ」
「いや、それは調べてみないと分りませんが、何人かは居るんじゃないかと思います」
「健さん、そいつは健さんが目を光らしてないと、ノーチェックになっちゃうな。そうじゃないですか」
「済みません。今後気を付けます」
「ん。この際だ、新年の初仕事に、昨年の出張伝票を精査して状況を調べてくれないか」
「分りました。次回の部長会で議題にして、徹底するように指示します」
年明け早々に○○ホールディング秘書室の中嶋麗子は善雄からかかってきた携帯を耳にあてた。
「もしもし、中嶋さん? 米村だけど」
麗子は珍しく休み中に善雄から個人の携帯に電話がきたのでドキドキした。麗子は以前から善雄に気持ちを寄せていたからなお更だ。
「はい。麗子です。明けましておめでとうございます」
「おめでとう。お休み中にすまないけど、急に市場調査を兼ねてブラジルに行くことになったんだ。それでお手数だけど、ホールディングスと工機の両方に一月十五日まで休暇の申請をしておいてくれないか? この話はオヤジは承知している」
「あらぁ、いいわね。わたくし連れてって欲しいな。オリンピックあるし、前からブラジルに行きたかったんだ」
麗子は善雄に甘えるような声を出した。
「すまん、実は今回は女房を連れて新婚旅行を兼ねて出かけるんだ。それで出張ではなく、休暇届けで出しておいて下さい」
「分りました。お気を付けてお出かけ下さい」
麗子はがっかりすると同時に、ドキドキは一変に吹っ飛んで、むらむらと嫉妬の気持ちが湧いてきた。善雄が女房、つまりあの沙希と言う自分より若い綺麗な女を連れて行くと言ったからだ。
「ついてない自分。この正月休みだって彼がいないから一人だったしなぁ」
その夜、麗子は惨めな気分を断ち切れず、明日から出社だと言うのに夜更かしをしてジュジュのCDを聴きながら一人でワインをいっぱい飲んだ。
翌日出社して新年の祝賀を兼ねた朝会が終わると、米村工機の総務部長に電話をして、善雄の[出張届け]を出すように依頼した。続いてホールディングスの善雄の出張申請書に必要事項を書き込んで、社長の善太郎の所に持って行った。善太郎は書類に目を通すと黙って許可のハンコを捺して戻した。
麗子は善雄の性格を良く知っていた。だから意地悪をして、わざと出張願いを出してやった。帰って来て、清算書を見れば、あの憎たらしい女、沙希をどこに連れて行って、沙希とどんなとこに泊まって遊んできたのか知りたい興味もあったし、清算書の内容を見ておかしい所があったら、この際善雄を公私混同だと苛めて一夜自分と付き合ってくれれば許してやると脅かすつもりだったのだ。麗子は、ずっと善雄を慕い続けてきたのに、善雄は一度だって自分の方を振り向いてくれなかったばかりか、あっと言う間に善雄を横取りして行った沙希が憎たらしかった。
善雄は米村工機の書類を片付けて、午後○○ホールディングに出社した。父の社長、善太郎は外出中だった。善雄はこっちでも年賀状やら溜まった書類に目を通していると、中嶋が書いた出張命令と旅費の精算書が書類入れに入っていた。オヤジの善太郎の認印が捺印してあったから、オヤジも出張で処理するのだと思ったに違いない。善雄は総務部長を呼んだ。部長の荏田は、おめでとうございますと顔を見ると直ぐに挨拶した。
「おめでとう。今年も頑張りましょう」
そう言って、
「実はこの伝票だけど、僕は秘書の中嶋さんに、はっきりと休暇願いを出すようにお願いをしておいたんだけど、どうしてだか出張願いが出ているんだ。彼女は今まで間違いを起こしたことがないので不思議に思ってね」
「そうですか? 年が明けてお顔が見えないので中嶋さんに聞いた所、ブラジルにご出張だと聴いています」
「いや、随分遅くなったが新婚旅行だったんですよ。社長が市場調査も兼ねて行って来いとは言いましたが、女房を連れて出張なんておかしいでしょ? だから十日間の休暇をお願いしたんですよ」
そう言って善雄は荏田の見ている前で出張伝票を破り捨てた。
「所で、荏田さん、うちの社で海外出張に仕事に関係のない女を連れて行った者はいませんよね」
「さぁ、多分いないと思いますが」
「そうか、それならいいんだ。この際だから去年一年間の出張伝票を精査してもらえませんか? 部下を疑うわけじゃないけれど、やはりこう言うことは気付いた時にレビューをしておいた方がいいね。僕のとこの企画部は常々僕が厳しく言っているから、今の所そんな者は居ないな」
荏田は精査を約束して退出した。
そこに中嶋が、
「お帰りなさいませ」
と言ってお茶を持ってきた。
中嶋がお茶を置いて退出しようとした時、
「ちょっと聞きたいんだけど」
と善雄が呼び止めた。
「はい? 何か?」
「お願いした休暇願いだけど、出てなかったね?」
麗子は善雄が黙って旅費を精算して処理するものと思っていた。
「休暇願いと言うと米村取締役のですか?」
「もちろんそうだ」
「あれはご出張扱いとして伝票を出しました」
「中嶋さんは工機の方にも出張伝票を出すように佐藤部長に連絡したそうだね」
「はい」
「それっておかしくないか?」
「何がです?」
「ホールディングスと工機と両方に出張伝票を出せばうっかりするとダブルで費用を請求することになるんだよ」
「それはそうですが」
「長年僕の秘書をしているけど、今回は君らしくないね」
「……」
麗子はわざとそうしたのがバレたかと少し不安になった。
「僕はあなたに休暇願いを出しておいて欲しいと、はっきりお願いしたはずなのに、どうして出張扱いになっているんだ? 女房を連れて出張なんておかしくないか?」
善雄は畳み掛けてきた。麗子はこれ以上は突っ張れないと思った。
「すみません」
「まぁいい。先ほど総務の荏田部長を呼んではっきりと話をしておいた。それと、工機の方も佐藤部長に休暇に切り替えて処理をするようにはっきりと指示をしておいたよ」
中嶋麗子は自分の意地悪だと善雄に見抜かれたような気がして、その日は落ち着かなかった。帰宅してからも、何故か心が騒いで不安定な気持ちで居た。
工機の総務部長の佐藤は部長会で善雄に指示されたことを話題にした。従業員が八千人以上も居る会社だ。部長だけでも五十名も居た。佐藤の話で昨年一年間の出張伝票を精査すると言われて、背筋に冷や汗が流れ落ちた者が十名以上もいた。その場では皆他人事みたいにそ知らぬ顔で居たが、内心ヤバイと思った者が何人も居たのだ。その日の内に、部長の中の三人が佐藤の所にやってきて、
「実は普段どこにも連れてってやってないのでかみさんを連れて行った。申し訳なかった」
とか、
「たまたまパリにどうしても行きたいと言う知り合いの女性が居て、連れて行ってしまった。大変申し訳なかった」
とか佐藤に告白して、三人共費用の一部を会社に戻したいがどうすればいいのかなどと謝って来た。中には直接善雄の副社長室にやってきて、土下座して詫びた男もいた。
こんなことが元で、善雄は社内のだらけた空気を一気に引き締めることに成功したのだ。
不景気で経費を節約してくれと、日頃声を大にしてお願いしているのに、とんだ所に穴が開いていたと佐藤も善雄の所に来て責任を感じていると謝って来た。結局精査の結果、不正は十五名で一年間で総額三百万円と少しを会社に返納させることになったのだ。
この話は、当然のことながら社長の善太郎にも佐藤から報告が上がった。善太郎は、
「善雄のやつ、うまい具合に引き締めをやったな」
とにんまりとしていた。
「これで当分部長連中は善雄に一目置くだろう」
そう思ったのだ。
○○ホールディングスでも女連れで出張した者、私的に使った金を接待費で処理していた者など何人も居て、ホールディングスでは善太郎の意向で正式に懲戒処分として減給された者が続出した。
秘書室の中嶋麗子がこの話を聞かなかったはずがない。彼女は自分のした意地悪がとんだ所に波及して社内での大きな波紋の広がりに驚いていた。
四月の人事異動で、日本橋の三井タワーの快適な環境で秘書と受付をしていた○○ホールディングス秘書室の中嶋麗子は、ホールディングス傘下の米村工機の板橋区の小豆沢町にある旧い木造の事務所に事務員として異動を命じられた。通勤は往復一時間で済んだものが、今度は往復二時間半になり、毎日早起きを強いられた。秘書室長からは特に異動の理由について説明はなかった。板橋に変わって、麗子は毎日惨めな生活を続けることになってしまったのだ。麗子には分っていた。あの意地悪が善雄に見透かされて罰を与えられたのだと。
中嶋麗子は、善雄が頼りない草食系のもやしみたいな感じだったから、経営者としての善雄の厳しい一面を見逃していたのだ。
「甘かった」
麗子は新しい職場に馴染めず、結局退職願いを出して、会社を淋しげに去って行った。二十七歳になった麗子の、去り行く後姿は惨めだった。
四十七 赤ちゃんができたみたい

新婚旅行から戻って、善雄は相変らず会社の仕事に忙殺されていたようだが、以前と違って、少し疲れていてもベッドに入ると時々沙希を抱いてくれるようになった。
沙希はブラジルから持ち帰ったお土産を両親や六本木のクラブ、ラ・フォセットの柳川夫妻と澤田へはもちろん、章吾と緑の森ガールこと美登里、マリアとサトル、それに池袋のロマンス通りに集まる仲間たち、さらに語学の先生役をしてくれているカトリーヌと横浜の中華飯店店主の娘陳香凝などに配って歩いた。
相手によっては意味深に、
「遅い新婚旅行の方がいいでしょ?」
とか、
「彼、優しかった?」
とか色々聞かれた。今はそんな風に聞かれることがかえって嬉しくなるような気持ちの余裕があった。
特に、マリアと美登里には旅行で楽しかったことを詳しく話した。マリアとサトルは昨年結婚して、マリアのお腹には赤ちゃんが居ると教えてくれた。見るとマリアのお腹は大分大きく目立つようになっていた。章吾と美登里はその後の話を聞こうとしたら二人とも難しい顔になったので聞くのを止めた。
春になって、気候が緩んできた時、沙希は自分の身体の異変に気付いた。それを美鈴に話すと、
「もしかしたら赤ちゃんが出来たのかも知れないわね」
と言われて産婦人科を訪ねた。
「米村様、ご懐妊です。おめでとうございます」
医師と看護師に祝いの言葉をかけられて、沙希は自分が母親になったことを知った。
夜、両親と善雄に報告すると、皆すごく喜んでくれた。
「子育てのことなら何でも聞いて頂戴」
一番喜んでくれたのは善雄でなくて母親の美鈴だった。
珍しく、ラ・フォセットの柳川哲平から沙希に電話があった。
「昨日、岩井加奈子が釈放された。何もないと思うが、万一何かあったら連絡してくれ」
沙希は加奈子のことを過ぎ去ったものとして忘れようとして、最近ようやく忘れかかっていた所だ。
多分加奈子の釈放については章吾が詳しく知っているだろうと思って、沙希は今度章吾に会ったら聞いてみようと思った。とにかく今考えても仕方の無いことだ。
加奈子のことを聞かされて、沙希はあの嫌ったらしい義父の浜田はその後どうなったのだろうと思い出してしまった。浜田のことについては、今後絶対に沙希や善雄の前には現われないようになったと聞いてはいたが、どうしてなのか細かいことは何も教えられていなかった。確かに、あの恐喝事件以来、浜田は一度も沙希の前に現われなくなっていた。
悪いことは続くものだ。沙希は翌日匿名の変な封書を受け取った。宛名は[米村沙希様]となっていたから、沙希のことを知っている者からの封書に間違いないと思った。
「誰だろう?」
沙希は思い当たる人がなかった。直感で加奈子からではないような気がした。ただそんな気がしただけだ。
封書を開けると、一枚の便箋が入っていた。ワープロで書いてプリントした文の内容は、
「あなたは呪われている」
とか、
「金持ちと結婚していい気になるな」
とか、
「お前の過去を知っているぞ。バラしてやろうか」
など沙希を中傷する言葉が並んでいた。本来なら夫の善雄に見せて相談すべきものだ。だが、沙希は章吾に見せて相談してから善雄に話をしようと思った。
四十八 越えるべき壁
愛し愛される男女は、条件さえ合っていれば周囲があれよあれよと言う間に二人はゴールインするものだ。だが、全ての恋人たちがそんな上手い具合に行くとは限らない。いや、世の中ではなかなか上手く行かない方が多いかも知れない。
章吾は美登里に誘われて、鎌倉の小町にある美登里の実家に初めてお邪魔した。美登里の両親は章吾に好感を持って受け入れてくれた。それで、章吾は正式にプロポーズをしたわけではないが、話の行きがかり上、
「出来れば将来結婚を許して頂ければ嬉しいと思っています」
とはっきりと自分の意思を伝えた。
それで、美登里の母親、藤井志津江は喜んで、早速具体的な話に踏み込んできた。
「章吾さん、お勤めはどちら」
志津江は美登里から大体のことは聞いていたが確かめた。
「六本木に友人の兄が経営するクラブ、ラ・フォセットと言う高級クラブがあります。そこに勤めています」
「どんなお仕事をなさっているの」
「雑用です」
「雑用と言っても色々ありますよね」
「はい。色々です」
「そうじゃなくて、色々なお仕事の中で具体的に」
「そうですね。決まった仕事はありませんが、酒類や店で出す料理以外の食材の仕入れが主な仕事です」
「そう? お一人でですか」
「はい。手伝いはいますが、大体自分がやることが多いです」
「失礼な質問ですけど、そんなお仕事だとお給料は安いんでしょ」
「はい。安月給です」
「では、美登里と結婚なさったら、共働きを考えていらっしゃるの」
「美登里さんのお気持ちでどちらでも構わないと思ってます」
「生活、して行けますの」
「贅沢せずにつつましく暮らすなら大丈夫だと思います」
志津江は少し不安になった。
「よろしかったら、美登里と一緒になったら、鎌倉のここから通勤なさったら? うちは見ての通り今は三部屋空いてますから章吾さんと美登里が一緒に住んでも大丈夫ですよ」
「お言葉はありがたいのですが、勤めは夕方に出勤して午前二時半位までです。ですから、往きは良いとして帰りは電車がありません。車で通勤するには時間がかかりすぎて無理だと思います」
「あら、そうなの? それは困りますよね」
志津江はかなりがっかりした顔に変わった。本心は美登里が一人っ子なので、結婚したら一緒に住んで欲しかったのだ。よくある話だ。
「自分としては、美登里さんと結婚できたら、都心に小さなマンションを借りて何とかやって行けると思ってます」
「でも、今都心のマンションは家賃が高いでしょ? 大丈夫なの」
「大丈夫だと思いますが」
志津江がしつこく聞くので美登里が口を挟んだ。
「お母さん、章吾さんはしっかりしてるから、彼が大丈夫って言うなら大丈夫よ」
それで志津江はさらに穿った質問をした。
「若い方のお給料って少ないでしょ? 章吾さんはおいくら位お給料を頂いていらっしゃるの」
「はい。自分はまだ今年二十七歳ですから確かに少ないです。ですが、最近給料を少し上げてもらいましたので、今は手取りで毎月四十万円と少しです。賞与は少なくて夏冬合わせて四ヶ月分位ですが」
志津江は金額を聞いてかなり驚いた。手取り四十万円なら自分の夫の章一と比べてもそんなに少ない額じゃない。
「そんなに頂いていらっしゃるの?」
「はい。自分の同年代のサラリーマンと比べれば多いです」
志津江は章吾を鎌倉に引き寄せる口実がなくなってしまった。それで、
「章吾さん、今のお仕事をこちらから通える所に変えられませんこと?」
と新たな質問をした。
「給料の金額に拘らなければ転職できないこともないです。でも、今の仕事は自分に合ってますし、社長からも目をかけてもらってますので、出来ればずっと今の仕事を続けたいと思ってます」
志津江は益々困った顔をした。
その時、黙って話を聞いていた父親の章一が、
「母さんの気持ちは分らないでもないが、男には仕事が大事なんだよ。そうだよね、章吾君」
「お母さまのお気持ちを大切にしたいとは思いますが、確かに仕事も大事だって気持ちはあります」
「母さん、この話はこの位にしたらどうだ? これ以上とやかく言っても章吾君を困らせるだけだよ」
志津江は不満らしかったが、一旦話を引っ込めた。
章吾が帰ってから志津江は、
「美登里、うちに一緒に住んでくれるいい人は他にいないの」
と美登里に迫った。
「そんな人いるわけないでしょ? あたし、章吾さんを好きになったから、今更別の人と結婚しなさいなんて言わないでね」
美登里はなんとしてもこの壁を越えてやろうと思った。
四十九 もどかしさ

美登里は鎌倉の実家に、章吾を誘って章吾が自分のことをどんな風に思っているのか分った。その後何回か章吾とデートを重ねていたが美登里の気持ちはデートをする度に益々章吾を恋慕う気持ちが強くなった。
昨年の四月にやむを得ず派遣社員の道を選んだ美登里は、その後もだらだらと派遣の仕事を続けていて、早いものでもう一年間近くになる。美登里と同い年の正社員の女の子は樋口真理子と言う名前だったが、相変らず意地悪が続いて美登里はそれに耐えていた。だから美登里にとっては毎月一度派遣社員どうしで集まる飲み会や章吾とのデート、それに池袋のロマンス通りに集まる若者達と遊ぶ時が癒される一時だった。何でこんな子が正社員なんだと思うほど真理子はどうしようもない女で、しばしば仕事のミスをする。真理子の意地悪は真理子自身のミスを美登里のせいにして押し付け、美登里が上司に叱られているのを見て楽しんでいる風であったが、慣れとは恐ろしいもので、今ではそんなことはあまり気にならなくなった。
美登里は派遣の仲間の最初の飲み会の後、新宿歌舞伎町の路地で性質の悪い若者達にナンパされレイプされそうになった寸前に救ってくれた章吾の逞しい姿を今でも思い出す。
章吾は無言で若者達に近付いて、あっと言う間に蹴りを入れて二人を倒した。その技が普段物静かな章吾のどこにあるのかと思うほど鮮やかだった。そのあと、章吾のアパートで挫いた足を庇って湿布薬を塗って包帯を巻いてくれる時に、優しく足先を持ってくれたあの痺れるような新鮮な快感を今でも忘れられない。美登里はあの時、章吾に本当に恋をしてしまったようだった。
母は鎌倉で章吾の話を聞いて、一緒に暮らしてもらうのが無理だと分ってから、折りに触れて美登里に別の男性を探しなさいと迫った。それが嫌で、最近は鎌倉の実家が遠くなってしまったような気がするのだ。
美登里は鎌倉から三番町の大妻女子大に通うのが無理で、四谷に住んでいる西垣八重と言う伯母の所に居候をしていたが、大学を出て派遣社員として通勤しはじめてからもそのまま伯母の所に厄介になっていた。
子供の居ない伯母は、美登里を自分の娘のように可愛がったので、美登里にとってはすこぶる居心地が良かった。
「伯母さん、この前、彼を鎌倉に連れて行ったの」
「そう? それでシヅちゃんはどうだった」
美登里の母の志津江をシヅちゃんと呼んでいた。
「父も母も喜んでくれたわ」
「じゃ、良かったじゃない。結婚のこととかもお話したの」
「ええ、彼は母の前ではっきりと結婚できれば嬉しいって言ったわ」
「具体的にお式のこととかも話したの」
「それがね、今あたし悩んでるの」
「あら、どうして?」
「彼、今のお勤め、鎌倉から通勤が無理なのよ」
八重は志津江が将来娘の美登里と一緒に住むのが夢だといつも言っているのを頭に思い浮かべた。
「それは困ったわねぇ」
「それで、シヅちゃんはもう美登里と一緒に住むのを諦めてくれたの?」
「あきらめないどころか、鎌倉で一緒に住める条件に合う他の男性を探せって最近しつこくて」
「美登里は今の彼じゃなくて、他の男性でもいいの?」
「ダメ、絶対ダメ。あたし、今の彼以外考えられないな。それで悩んでるの」
「じゃ、いっそのこと、美登里が嫌じゃなかったら伯母さんとこの娘になってここで一緒に住めばいいじゃない。美登里さえ良かったらシヅちゃんにかけあってあげるわよ」
八重は毎日のように志津江と電話でおしゃべりをしているが、美登里の悩みを聞いたあと電話ついでに、
「そうそう、シヅちゃん、美登里ちゃんをわたしにくれない?」
と切り出した。
「ダメダメッ、うちの一人娘を外に出すなんて考えられないわよ」
「本当にそう思っているの? 美登里ちゃんの彼、結婚しても一緒に住めないそうじゃない? だったらそこらのマンションに住まわせるよりわたしのとこで一緒に住むようにさせるわよ」
それを聞いて志津江は怒り出した。
八重の話しがあってから、美登里の母の志津江は鎌倉で一緒に住める男性を見つけなさいと美登里に迫り、とうとう美登里と口喧嘩までしてしまったのだ。
そんなことがあって、美登里は日に日に章吾を想う気持ちが強くなった。
夜風呂に入って寝床に就くと、章吾に会いたい気持ちが昂ぶった。恋に落ちた女性なら大抵経験があるように、美登里の下腹部のその部分が愛の液でじわっと濡れてしまうのだ。
沙希はあの日受け取った不審な封書のことで章吾に相談したいと電話した。それで日曜日の午前中、しばらくぶりに章吾のアパートを訪ねる約束をした。
「こんにちは」
アパートのドアの外で声をかけると、直ぐに章吾が顔を出した。
「どうぞ」
章吾の部屋は相変らず整頓されて綺麗に片付いていた。荷物が少ないせいで、それでこざっぱりとしているのかも知れない。上がると直ぐに封書を出して章吾に見せた。
「これ、色々な人に見せた?」
「いえ、章吾が初めてです」
「そうか、先のことは何とも言えないけどさ、万一警察に連絡するとなると指紋が問題になるから気を付けた方がいいよ」
「あっあたしの指紋、きっとベタベタ付いてるな」
「沙希の指紋は問題はないよ」
章吾は自分の指紋を付けないように気を付けながら封書の中を見た。しばらくすると、
「差出人に思い当たる人がいないって言ってたよな」
「ん。今の所誰か全然見当が付かないの」
「差出人が分れば簡単なんだけど、一応柳川さんと溝口さんに相談して見るから、こいつ預かってもいいかなぁ」
「どうぞ。是非お願いします」
「旦那には話したのか?」
「まだです」
「そうか。旦那には当分伏せておいた方がいいな」
「はい」
章吾はあれこれ考えている様子だったが、結局柳川と溝口に相談するからと封書を受け取って仕舞い込んだ。その時、ドアを開ける音がして、二人ともドアの方を振り向いた。
美登里は、
「日曜日に章吾さん池袋に行く?」
と章吾に電話で聞いた。
「行くつもりだよ」
「じゃ、あたしお昼前にそっちに行って、お昼一緒に食べてから夕方一緒に池袋に行ってもいい?」
章吾の返事が少し遅れた。
「悪い。午前中、ちょっと人が来るんだ。三時ごろにしてくれないかなぁ」
「誰が来るの」
「……」
章吾は沙希が来ると言いかけて、美登里に誤解されちゃまずいと思って返事を躊躇した。
「言えない人?」
「そんなことはねぇよ」
「分った」
美登里は一旦電話を切った。だが、何となく心が騒いだ。それで、お昼少し前に章吾のアパートに行った。美登里の中で章吾を疑っているようなことはなかった。けれども、デートを何回も重ねているのに、章吾は一度だって美登里の身体に触れたことはなかった。まして手をつなぐとか唇を奪うとかは論外だったのだ。ここのとこ、章吾に会うといつも抱きしめて欲しいと思ったし、今日こそはと待っていたのに別れ際は、
「じゃな」
と言ってあっさりと立ち去って行くのがなんとも物足りなかったのだ。心が騒いだ原因は案外そんなことだったのかも知れない。
美登里は章吾のアパートに着くとドアを開けた。そこに女性の可愛らしい靴があった。美登里が部屋に上がると、びっくりした顔の章吾と沙希の顔があった。
みどりはバタンとドアを閉めると、まっしぐらに駅に向かって走った。なぜか見てはいけない光景を見てしまったような気持ちになった。
章吾は美登里の顔を見ると、
「入れよ」
と声をかけようとした。だが、その瞬間ドアがバタンと閉まったので、慌ててドアに駆け寄って外を見た。ドアの外には美登里は居なかった。それで靴をつっかけて外に出ると遠くに走り去る美登里の後姿が見えた。
五十 好きなのに……
美登里は章吾と沙希の驚いた顔を四谷の伯母の家に戻っても鮮やかに覚えていた。あの光景を見て、美登里は一目散に駅まで走った。電車に乗って四谷に帰る間も色々なことを考えてしまった。ここのとこ、母に他の男性を探しなさいときつく言われていたから、情緒不安定になっていたのだ。そんな時、見てはいけない光景を見てしまって自分でもどうしてよいのか分らなくなっていた。
「やっぱ章吾と沙希はそんな関係だったのかぁ。沙希は不倫よ。不倫」
頭に昇った血が昇りっぱなしで美登里はかっかとしていた。
「あたしってバカね。全然気付かなかった」
結局その日は池袋に行くのを止めて家でテレビを見た。見ていたテレビのドラマがいけなかった。ドラマは失恋の話だったのだ。それで、ドラマを見ながら美登里は泣いてしまった。ドラマの内容がなんだか自分にあてはまってしまってどうにもならなかった。
章吾はあれから美登里はどうしたのだろうと心配になっていた。だが、沙希が帰ったあと、三時を過ぎても美登里は来なかった。仕方なく、ドアの外に書置きをして、池袋にでかけた。思った通り美登里は来ていなかった。沙希は少し遅れてやってきたが、美登里の姿が見えないと気付くと、
「章吾は女性との付き合いが下手だから、美登里にはあたしから電話をしておくわよ」
と章吾を慰めた。案の定、章吾はどうしたらいいのか分からなかったようだ。
「沙希、すまん。どうやら美登里に誤解されちゃったみたいだな。オレってこういうのダメなんだよなぁ」
沙希は美登里の携帯に電話をしてみた。だがどうやら電源を切ってしまっているらしく、局からの不在メッセージが流れるだけだ。その日は何度電話してもつながらなかった。
翌日十二時過ぎに電話をすると美登里が出た。美登里はいきなり、
「沙希なんか大嫌い。もうお友達じゃないから」
と言って電話を切ってしまった。沙希は章吾には善雄と結婚後も何かと世話になっていたから、章吾のためにどうしても美登里の誤解をといてやりたかった。
それで、日を改めて夜に四谷の美登里の伯母の家を訪ねた。美登里は外出中だったようだが伯母の八重が相手をしてくれた。そこで、沙希は先日遭った出来事を詳しく八重に説明して、
「美登里さんの全くの誤解ですから、おばさまからどうぞお話し下さいますようお願いします」
と頭を下げた。
「今美登里ちゃん、色々あってね、悩んでいる所なのよ。それだから誤解しちゃったのね。美登里ちゃんは今でも章吾さんって言ったかしら、その方のことをすごく好きらしいわよ。恋する乙女ってとこね」
と沙希の話を理解してくれた。
章吾に一日に一回は美登里から電話があったのに、あれ以来数日が過ぎてもさっぱり電話が来なくなった。章吾は美登里のことは好きになっていたが、自分の方から電話をしたりするのは苦手だった。だから、辛抱強く美登里からの電話を待っていた。
数日が過ぎて、ようやく夜中に美登里から電話が来た。
「章吾さん、ごめんなさい。あたし、章吾さんのことを誤解していたみたい」
電話の向うですすり泣く声が聞こえた。
「良かったら、今からどっかに行こうか」
と章吾は言ってみた。時計は午前三時少し前だ。
「ん、連れてって」
美登里の返事が泣き声で消えてしまいそうだった。章吾は軽を駐車場から引っ張り出して四谷に向かった。
結局、その夜はお台場の公園に行って、明け方まで美登里と黙って海を見ていた。ファミレスで早い朝食を済ますと、美登里の顔に微笑が戻ってきた。それで美登里を四谷で落として、章吾はアパートに戻り一眠りした。
章吾は沙希から預かった不審な封書を思い出して、それを柳川に渡して相談した。柳川は直ぐに溝口と池内を呼んで沙希が嫌がらせを受けていることを伝えた。
「何か心当たりはあるか?」
「この内容からすると、浜田に何かからんでいる気がしますね。そうでなければ沙希さんの過去について云々まで書く根拠が乏しいです」
と溝口が言った。
「そうだ、浜田から没収した携帯を見れば、手がかりはありそうですね」
と池内が応じた。
「携帯を持って来いよ」
章吾が携帯を取りに行った。
浜田の携帯を開けて見ると、不在マークが出ていた。どこから電話がかかったか調べると四月に入って同じ携帯の番号から何度か着信していた。
「おかしいな。浜田はとっくの昔に圏外に送り込んでしまったから、この電話はそれを知らない奴からだな」
浜田は今頃毎日遠くアフリカのザンビア国の首都ルサカから数百キロ離れた奥地の銅やコバルトの鉱山で奴隷としてこき使われているはずだ。ひょっとしたら今頃死んでしまっているかも知れないのだ。
溝口が着信した携帯の番号に電話をした。
「もしもし」
女の声が返ってきた。溝口は受話器を覆うと、
「女だ」
と言った。
溝口は続けた。
「オレだ。何か用か?」
「今まで何度も連絡したんですが、どっかに行かれていらしたんですか」
「用件を言え」
「一度会って頂けませんか? 聞きたいことがあるんです」
「分った。明日もう一度電話して来い。会う場所と時間を知らせる」
そう言うと溝口は電話を切った。
「その女、放っておくわけにはいかんな。池内と猪俣の二人で始末してくれ。溝口は様子をみてからフォローしてくれ。女一人、単独ならいいが、男がからんでいたら全部叩き潰してくれ」
「分りました」
池内と章吾は同意した。
「声が違っちゃまずい。明日の電話はオレがやる」
溝口が付け加えた。
五十一 保険

先ほどから、新宿区大久保にある料亭の離れから、若い女のすすり泣く声が聞こえていた。
この料亭は同じ大久保の淺沼組の所有で、女将は組長の女だ。普段は組の集会所として使われることが多かった。
会社を辞職して、今は毎日暇をしてる中嶋麗子は浜田と思われる男から電話を受けて、翌日のその日、約束通り電話を入れた。浜田に会ったら米村沙希のことを色々聞きだす予定で居た。
浜田については、以前取締役の善雄にしつこく電話をして来たので電話番号を控えていたので、そのメモは今でも捨てないで持っていた。メモの番号に四月になって何度も電話をしてみたが、いつも不在だった。だから、どこか遠くにでも出かけているのだと思っていた。所が昨日思いがけず浜田から電話があったのだ。声色ははっきり覚えていなかったが、ぞんざいな受け答えなので、多分浜田に間違いないと思っていた。
「もしもし」
呼び出し音が何回か鳴った後、浜田と思われる昨日の男が電話に出た。
「オレだ。あんた千鳥が淵は分るか?」
「はい」
「メトロ半蔵門線の半蔵門駅で降りて、内堀通りに出て、つまりだな、お堀に沿った道路だ、竹橋の方に向かって歩いてくれ。イギリス大使館は知ってるか?」
「はい」
「午後一時きっかりにイギリス大使館の門の少し先の舗道で待っててくれ。車で迎えに行く。あんたの名前は?」
「中嶋です」
「時間に遅れたら会えないと思え。分ったか?」
「はい。必ず行きます」
溝口は電話を切った。
中嶋麗子は友達の佐竹茂に電話をした。
「昨日話した浜田って言う人と今日一時きっかりに千鳥が淵の手前のイギリス大使館の前で待ち合わせすることになったの。車で迎えに来るそうだから、シゲル、その車を尾行してどこに連れて行かれるか確かめてくれない」
「いいよ。麗子は電車で行くんだろ?」
「そのつもり」
「じゃ、僕もそこに行くわけだから、乗せてってあげるよ」
「助かるなぁ。変な人だから、あたしに何かあったら一一〇番に電話をしてね」
「分った。十時に麗子のとこに行くよ」
それで、麗子はシゲルの車に乗せてもらうと、ファミレスで早めの昼食を済ませて大使館の前に向かった。
内堀通りのイギリス大使館前は舗道を歩く人は殆どいない。歩く人はお堀を見ながらの方が景色が良いので反対側を歩くのだ。周囲に舗道に沿った植え込みの他は何もなく見通しの良い所だ。
溝口は章吾の他に鈴木と瀬川を連れて二台の車で現地に十二時半に着いて、少し離れた場所で、ハザードランプを点けて停車して待った。他に浅沼組の若い衆の応援でもう一台黒塗りのベンツが一緒だった。このあたりは通り過ぎる車両は多いが、車線が広く、一時停車をしていても、パトカーに文句を言われることはめったにないのだ。大抵大使館に用のある上級の役人や、大会社の役員の場合が多いので警察でもやたらと文句は言わないのだ。近くの半蔵門会館も警察関係者が使う会館で不審な車両が停車していることはまずない。
十三時きっかりに白い小型のセダンがウインカーを出してイギリス大使館の門の前で停車した。助手席から女が降りると、セダンはハザードに切り替えて女が立った場所から50m程手前で停車した。
ずっと離れた所で見ていた章吾と鈴木が乗った白いベンツは直ぐに発進して女の前で停まった。窓を開けて章吾が、
「ナカシマか?」
と聞くと女は頷いた。鈴木がドアを開けて「乗れっ」
と言って女を後部座席に押し込み一緒に乗り込んでドアを閉めると直ぐに女の口をこじ開けて注入器で液体を流し込んだ。女は抗ったがすぐにぐったりした。麻酔薬のジエチルエーテルだ。鈴木が助手席に移ると直ぐに発進して大久保に向かった。
佐竹茂は麗子を乗せた車の番号を控えて、様子を見ていた。すると黒塗りのベンツが佐竹の車の前と後に停まって挟んで発進できなくなった。
佐竹はドアを開けて出て、
「もう少し前に出て下さい」
と言うと、前のベンツから出てきた男がいきなり鳩尾に一発食らわすと佐竹を抱えてベンツに乗せて鼻と口を塞いで首を絞めた。佐竹は気を失った。後のベンツから降りた男が佐竹の車を運転して、どこかへ走り去った。
二台のベンツは木場を通って夢の島マリーナのマリーナセンターの駐車場で停まった。淺沼組の男と瀬川の二人はクルーザーに麻酔薬のジエチルエーテルを飲まされてぐったりしている男を乗せて直ぐに東京湾に出た。クルーザーは浦賀水道を抜けると南下して大島の脇を通り、利島の先の鵜渡根島(うどねしま)に着岸して男を少し小高い所に横たえると直ぐに離岸して夢の島マリーナに戻った。マリーナに戻った頃はあたりは夕闇が迫っていた。鵜渡根島は無人島だが、男が意識を回復すれば、恐らく釣り客に拾われるだろう。溝口や淺沼組の車は全部既に廃車した車のナンバープレートに取り替えてあったから、男がナンバーを記憶していて警察に通報したとしても闇の中、まず見付からないだろう。男の携帯や財布は没収されていたし、男が使ったセダンは今頃解体屋でプレスされてバーベキューだ。
中嶋を乗せたベンツは大久保の料亭の駐車場に滑り込んだ。車が入ると門が閉められてしまうので、外からは見えない。中嶋は二人の男に両側を固められて、奥の離れに連れて行かれた。既に二人の男が待っていた。
大きなテーブルの前に座らされると、目の前に計測器が置かれて、左右の人差し指を交互にセンサーの上に乗せられた。乗せて少しの時間でピッとブザーが鳴った。指紋の照合器だ。
鈴木が章吾に目配せすると、章吾は無言で沙希から預かった不審な封書を取り出して中嶋に見せた。
「バカなことをする女だ」
鈴木が言うと中嶋は、
「これ何ですか?」
と聞き返した。
「あんたが出した脅しの手紙だよ」
「あたし知りません」
「今こいつであんたの指紋とこの封書にベタベタ付いている指紋が照合されて黒と出た。それでもしらを切るのかよぉ」
麗子は観念した。
「あたしです。あたしから聞いてもいいですか」
「あんたに話すものは何もねぇ。あんたなぁ、今日はこんな脅しをやった落とし前を付けてもらうぜ」
麗子は怖くなってきた。自分の突っ張る気持ちとは裏腹に足が震えてきて、胸がドキドキしてきた。
淺沼組の男が襖を開けると次の間に布団が敷いてあった。麗子はそれを見て愕然とした。
「いやぁっ、嫌です」
この状況では男たちに辱めを受けることは明らかだ。麗子の口から自然に泣き声が出た。男たちは皆無言だったが、それが麗子の恐怖心を煽った。
「ごめんなさい。許して下さい」
何を言っても男たちは無口だ。
麗子は布団の上に押し倒された。
「お願いです。お金で済ませて頂けるならお払いします。許して下さい」
麗子の話には反応せずに男の一人がゆっくりと麗子の洋服を脱がせ始めた。麗子が抗うと男の強い力で押さえつけられた。麗子はしくしくと声をあげて泣き出した。強そうな男が四人も居るのだ。女一人ではどうすることもできない。
「あんたをこのまま帰すわけにゃいかんのよ。あんたが気が変わって余計なことをしないように保険をかけるのよ」
男は気持ちの悪い薄ら笑いを浮かべていた。
五十二 濃厚な愛VS嫉妬
「あんたに掛ける保険だけどよぉ、エイズとタトーとどっちがいい?」
「エイズって?」
「あんたにHIVを移してやるのよ」
麗子はぞっとした。
「あたし、どっちも要りません」
「どっちか選べ。両方無しはメニューにねぇんだよ」
「お願いです。許してぇっ」
麗子は泣き叫んだ。
「ダメだ。早く選べ。タトーにしとくか?」
麗子は泣きながら頷くしかなかった。
「おいっ、チーちゃんを呼んでくれ」
間もなくチーと呼ばれた女が入ってきた。
「直ぐかかってくれ。模様は任せる」
「はい」
チーは服を脱がされて布団の上で押さえつけられている麗子の胸の乳房に手を添えて、アルコールを染ませたガーゼで右の乳房の回りを消毒した。やがて麗子の乳房の下の部分にチクッ、チクッと刺激が走った。
二時間も経つと、今度は麗子のパンツが脱がされてショーツも脱がされて素っ裸にされてしまった。男が股を広げると麗子は恥ずかしくて抗ってももを閉じようと頑張ったが力尽きて股を大きく広げられてしまった。麗子は陰毛が多く、その部分が上手く覆われていた。チーは陰毛とモモの付け根の間をガーゼで綺麗に拭くと、今度はその部分にチクッ、チクッと刺激が走った。二時間も経つと、
「終わりました」
とチーが丁寧に頭を下げた後部屋を出て行った。
右側の乳房の下から乳首にかけて、黒い大きな蜘蛛が一匹へばりついていた。一本の足が乳首の下まで伸びていた。広げられた股の陰毛の部分からももの付け根の部分に乳房にへばりついている蜘蛛と同じ大きさの蜘蛛がもう一匹へばりついていた。
デジカメのシャッターの音が続けて何度もした。男は麗子の放心した顔と乳房、顔と乳房と下腹部を入れたものなど何枚も写真を撮った。
「仕上げをやってくれ」
鈴木の合図で、淺沼組の男が自分のパンツを脱ぐと麗子の部分に勃起した自分の物を入れた。
「痛~いっ」
と麗子が泣き声を出したが男は構わず麗子を攻めて、そのまま麗子の中で果てた。麗子に男が入れている様子もデジカメで撮影された。
男が麗子から離れると、鈴木が麗子を四つん這いにさせて、後から麗子の中に入れて攻めた。鈴木が麗子の中で果てると、章吾に目をやった。章吾は首を横に振った。今度はもう一人の淺沼組の男に目をやると、男は進み出て、四つん這いの麗子の上に覆いかぶさって、麗子の乳房をもみしだき、乳頭をつまんだり玩具にし始めた。指で麗子の部分をかき混ぜて麗子の泣き声が一層大きくなったとき、自分の物を突っ込んで激しく攻めて果てた。
「儀式は終わりだ。服を着ろよ」
麗子はくしゃくしゃになった服を着た。着終わると、
「あんたなぁ、今日楽しませてやったことを誰かに話したりさぁ、あんたが手紙を出した相手のお嬢さんをまた脅迫した時はな、今日よりもっと激しく泣かせてやるからそのつもりでいろよ。あんたが余計なことをすればだ、今日の証拠写真をあちこちにばら撒いてやるから、そのつもりでいろよ」
と脅した。
「分ったか?」
麗子が頷くと、また口をこじ開けられて麻酔薬のジエチルエーテルを飲まされ麗子は気を失った。
何時間経っただろう。外はしらじらと明け方になっていた。気を取り戻した麗子は、
「ここはどこだろう」
と周囲を見た。青いテントの中だ。そっと外を覗くと同じようなテントやダンボール箱が並んでいた。良く見ると公園の中だった。
麗子はテントから這い出して周囲を見て思い出した。ずっと以前に来たことがある都庁の前の新宿公園だ。麗子はホームレスのテントの中で気を失って転がされていたのだ。持っていたトートバッグはなかった。財布も携帯もなかった。
近くに居たホームレスのオジサンに、
「すみません。一〇円貸して頂けませんか」
と頼んだ。ここに集まる者はみなわけありだ。オジサンは何も聞かずにポケットから一〇円玉を三個取り出して、優しい労わるような目で麗子の手に三〇円握らせてくれた。麗子はまた涙が出た。涙を拭くと都庁の建物の中に入って、公衆電話から佐竹の携帯に電話を入れた。だが、何回かけても出なかった。
瀬川は没収した佐竹の携帯の着信音を聴いて、携帯を開いた。電話は公衆電話かららしい固定電話からだった。瀬川は受信をしないで電話を切った。何度かかかってきたがその都度切った。
「市川までどうやって帰ろうかなぁ……」
財布も携帯も何もない。ある物はホームレスのオジサンからもらった一〇円玉三個だけだった。
五十三 母親の優しさ

中嶋麗子は手元にホームレスのオジサンからもらった一〇円が三枚、それ以外には身元を証明できるもの、売って換金できるものなど何もなかった。友達の佐竹茂に電話してもつながらない。新宿駅からJRで市川駅まで三百八十円かかるから、自分のアパートにも帰れない。帰ったとしてもアパートの鍵すら盗られて何もないのだ。三月まで勤めていた会社の友達はいるが、電話番号が分からないし、助けを求める言い訳はしたくなかった。
「どうしよう。お腹もペコペコだし」
新宿駅までそんなことを考えながらとぼとぼと歩いた。そんな麗子の目に新宿駅西口交番が目に入った。
「あのう……、持ち物を全部盗られて家に帰る電車賃がなくて困っているんですが、五百円位貸して頂けませんでしょうか」
交番の前に若い巡査が二人立っていた。その片方の巡査に頼んでみた。
「いつ盗られたんですか」
「それが、多分昨夜だと思います」
「あなた盗られた時気付かなかったんですか」
「気付かなかったと言うか、返してもらえなかったんです」
「すると、どなたかに一時預けられたんですか」
「そうじゃなくて、苛められて返してもらう時に携帯とか財布とかを入れたトートバッグを返してもらえなかったんです」
「返してくれと言われても?」
「それが意識が戻った時は新宿公園のホームレスのテントの中だったんです」
「意識が戻ったとおっしゃると、昨夜泥酔されていたとか?」
「いいえ。多分フォルマリンか何かだと思いますが、かがされて意識を失ったんです」
麗子は次第に話が金を借りたい方から逸れて、段々答えるのが面倒になってきた。
「あのう……、あたし家に帰る電車賃がなくて、お借りしたくてお願いしているんですけど」
「電車賃ですが、余程のことでもなければ貸さないことになっているんです。あなたのように持ち物を盗まれたり、財布を落したりして電車賃を貸して欲しいと言って来られる方は毎日十人前後居るんです。ですから、いちいち応じている訳には行かないんですよ」
「困ったな。今手元にホームレスのオジサンからもらった一〇円が三枚しかなくて」
「ご家族に電話されたら如何ですか」
「そうですね。ありがとうございました」
結局交番は麗子にとって何の役にも立たなかった。酔っ払いにされてしまうし。麗子はこの半年間実家に帰っていなかったし、母に一度も電話すらしてなかった。だから家に電話して助けを求めたくなかった。だが、どうしようもない。仕方なしに手元の三〇円で横浜の実家に電話をかけた。
電話をすると運良く母親が出た。
「お母さん?」
「麗子でしょ? ちっとも連絡もしないでどうしてたの」
「そんなことより、今手元に三〇円しかないの。お願いだから新宿駅西口交番の前まで来てくれない? 市川のアパートに帰るお金もなくて……」
そこで電話は料金切れで切れてしまった。もう連絡を入れる方法はない。母親が新宿駅まで来てくれるのを祈るだけだ。
横浜の実家から新宿駅まで出てくるのに二時間位はかかる。それまで本屋で立ち読みでもしようとデパートに入った。トイレに行きたくなってトイレに入って鏡を見て愕然とした。髪はばさばさ、化粧もしてないから顔なんて見られたものじゃない。これじゃ交番で酔っ払いと勘違いされても仕方が無い。化粧ポーチもトートバッグの中だから手元には何もないのだ。顔を洗いたくてもハンカチすらない。
「まいったなぁ」
本屋で立ち読みするたって、二時間近くも時間つぶしをするのはきつい。それでデパートの屋上に上がってベンチに腰をかけてぼんやりしていた。
「母さん、きっと市川のアパートまで来るって言うな。どうしよう。お部屋の掃除してなくて散らかってるし、洗濯してなくて汚れ物は一杯溜まってるし、お茶碗も洗ってなくて流しに出しっぱなしで出てきたし、電車賃をもらったら横浜に帰ってもらおうっと」
そんなことが色々頭の中を駆け巡って憂鬱になった。
一時間半位過ぎた所で、先ほどの西口交番の前で立っていた。行き交う人は多い。そんな通り過ぎる人をぼんやり眺めながら待っていると、少し離れた所で、年配の女性が人を止めて場所を聞いている風なのが見えた。
「母だ!」
麗子はその女性に駆け寄った。だが顔を見ると別人だった。驚いた顔の婦人を見て、
「すみません、人違いでした」
と謝った。交番に戻ろうと交番の方を見ると、母に似た人が巡査になにやら尋ねていた。今度も人違いかもと思って少し離れた所でよく見ると母だった。
麗子はこの瞬間胸に詰まっていたものがどっと出て、
「お母さん!」
と言うなり抱きついて泣いてしまった。二時間以上前に応対してくれた巡査はまだ交番の前にいた。巡査は麗子が抱きついて泣き出した様子を見ていた。
麗子が母親に最初に言った言葉は、
「お腹ペコペコなの」
だった。それで母と一緒にデパートのレストラン街に上がって、二人で和定食を注文した。
「麗子、どうしたの? ちっとも連絡ないから心配してたわよ。ちゃんと食事をしているの」
母親は麗子の髪の毛がボサボサで化粧もしてない顔を見て、すっかり驚いていた。半年前実家に帰った時は会社の秘書室で受付もしていたから、こざっぱりして化粧も念入りにしていたから、今目の前に居る娘の姿を見て驚いても不思議じゃない。だが、麗子に文句を言うわりには母親は嬉しくて喜んでいる様子だった。母親の娘を思う気持ちはそんなものだ。
食事が終わると、思ったとおり市川のアパートまで一緒に行きたいと言った。麗子は必死にアパートに来ないように話を逸らせた。どうやら母親はアパートに行ってはまずいのだと感じて、麗子の手に三万円を握らせると、
「あたし、ついでに寄りたい所があるから」
と言って別れてくれた。麗子は母には会社を辞めて今は無職で収入なしだとは言えなかった。別れてから、麗子は母親の優しさが身に沁みていた。
無人島の鵜渡根島に置き去りにされた佐竹は、夜風と潮騒に目を覚まされた。周囲を見ると海岸近くに放り出されていたことに気付いた。周囲は岩がせり出していて、歩こうにも遠くには行けなかった。持ち物は何もなく、ポケットを探っても中の物は全部抜き取られていた。
思い出して見ると、麗子を降ろして麗子を乗せた白いベンツを尾行しようとしたら黒塗りのベンツに挟まれて動けず、車を降りたらいきなりパンチをもらって、その後のことは何も覚えていなかった。予め仕組まれていたように、サスペンス映画の一場面のように鮮やかな手口で拉致されてしまったようだ。佐竹は仕方なく朝まで待って周囲の様子を確かめることにした。
「腹すいたなぁ」
正気に戻ると空腹感が襲ってきた。だが周囲には何もない。仕方なく転がされていた場所に戻って眠った。明け方寒くて目が覚めて、周囲を見ると、なんと周囲は全部海だった。もう少し見渡すには高い所に登らなければならないが、岩の壁が立ちはだかって登れそうも無い。どうやら小さな島のようだがどこの島かも見当がつかなかった。
昼近くに近くを漁船が通った。佐竹は着ているシャツを脱いで思い切り振って助けを求めたが漁船は行ってしまった。その日は三隻舟が近くを通ったが全部気付いてもらえなかった。何も食わず、空腹は限界に達していた。 翌日漁船が気付いてくれて、ようやく救出された。その時は気力だけで戦っていたので、舟に引き揚げられるとぐったりして倒れこんでしまった。
「どこから来たのか」
とか、
「なんでこんな島に居るのか」
とか聞かれても答えようがない。漁師の話で自分が転がされていた島は東京湾から遥か南の無人島の鵜渡根島だと分った。伊豆大島のずっと南の新島の手前だと教えてくれた。漁師は伊豆半島の稲取漁港から来て夕方には帰ると言った。漁師は理由を聞いて握り飯を食わせてくれた。佐竹はそれで息を吹き返すことができた。
佐竹も市川だが、麗子と同様に何も持ってない。それで漁師に理由を言って電話を貸してもらって、友達に電話した。
「随分遠くだなぁ。明日車で迎えに行ってやるよ」
仕方ない。その日は漁師の家に泊めてもらった。翌日友達が来ると、
「お前、えらい目に遭ったなぁ。それって多分ヤクザだぜ。近付かない方がいいよ」
と忠告してくれた。
市川に戻ると、その足で警察に行って車の盗難届けを出した。だがその後、何ヶ月待っても車は戻ってこなかった。
麗子はアパートに着くとカギがなくて困った。それで大家に頼んで鍵を開けてもらった。預金通帳はアパートに置いてあったが、キャッシュカードは盗られてしまった。それで仕方なく翌日銀行に行くことにした。免許証やらクレジットカードやら、再発行を考えると気が遠くなるようだ。それは佐竹も同様だ。三日後佐竹にようやく連絡が取れた。彼は大損害だとカッカして怒っていた。
アパートの鍵を開けてもらって、早速合鍵を作った。ようやく落ち着いた所で風呂場に入ってシャワーで身体を綺麗に流した。それで、鏡を見て愕然とした。右のオッパイの下に足も入れると直径6cm位の青黒い蜘蛛がへばりついていた。
「きゃーっ」
麗子はその部分をごしごしと洗ったが刺青だ、洗っても取れない。しかも少し化膿しているらしくひりひりして、痒みがあった。股も広げて見た。そこにも同じ蜘蛛がもう一匹へばりついていた。麗子は悲しくてまた泣き出した。
五十四 恋しいのに……
「沙希ちゃんに届いた不審な手紙、始末を付けたと思っていいんだな」
「はい」
柳川は溝口、池内、章吾を呼んで確かめた。
「中嶋麗子と言う女と佐竹茂と言う麗子のダチの携帯、免許証その他を没収してありますから、住所他詳細は分かっています。今後何かあれば直ぐに始末できます」
溝口たちや浅沼組の者は、没収した携帯やカードを用も無いのに絶対に使用しない決まりになっていて、それはきっちりと守られていた。没収したクレジットカードやキャッシュカードを使ってはした金を盗って足が付くようなバカな真似は決してしなかった。
「沙希ちゃんは旦那の米村善雄には伏せていると言う話だったな」
「はい」
と章吾が答えた。
「なら、始末が済んだことは猪俣(章吾)から沙希ちゃんに伝えておけ。余計なことは何も言うなよ」
「はい。分ってます」
章吾は沙希に電話で、
「この前預かった脅しの手紙の件は今後沙希に何か手出しをしてくることはないと思う。柳川さんが伝えておくように言ってたから」
と伝えた。
「章吾、ありがとう」
章吾はまた沙希を守ってやれたことを誇らしく思った。
美登里はその後も章吾に会いたいと言ってくるので、章吾はできるだけ彼女の希望に応じてきた。章吾は美登里を嫌いではなかったし、美登里が章吾を慕ってくれていることも良く分かっていた。だが、章吾は美登里と一緒に居る時よりも、沙希と一緒に居る時の方が何か落ち着いた気持ちになると感じていた。沙希から見合い話しが出た時に、はっきりと
「その見合いを断ってくれ」
と言えなかった時から章吾は沙希のことを諦めたつもりで居たが、会うと気持ちが動いてしまう自分を持て余していた。この前に会った時に善雄の赤ん坊がお腹の中に居ると言われて、また少し沙希が遠くに行ってしまったことを悟らされた。
美登里は章吾とデートしていて、最近母親が何と言おうが全てを投げ出して章吾に身を預けたいと思う反面、思い切ってそうできない自分にもどかしさを感じていた。自分のことで四谷の伯母と母の間が最近上手く行ってないことも原因だった。
「章吾にこんなに恋しているのに、章吾にあたしの気持ちがちゃんと伝わってるのかなぁ」
美登里はふとした機会に章吾が遠くを見つめているような感じがする時があって、それが不安でもあった。
デートを重ねても、章吾はいまだに美登里を抱きしめたり唇を奪ってくれないのだ。
「あたし、今日こそはといつも待ってるのになぁ」
先日仕事だと言って二日間携帯も通じなかったし、
「メールをくれる暇もないなんて章吾はどんな仕事をしているんだろ」
と、それも不安の一因だった。章吾に仕事の内容を聞けば、
「サトルのとこからワインの仕入れたり色々」
と言うだけで、もっと細かくは説明してくれないのだ。
「五月の連休に、泊まりでバイクで遠出してみないか」
と章吾が誘ってくれた時、美登里はめっちゃ嬉しかった。
「嬉しい。景色がいいとこがいいな」
「どっち方面?」
「北海道じゃだめ?」
「ちょっと遠いけど、美登里が行きたいならいいよ」
それで北海道行きが決まった。
指折り数えて楽しみにしていた連休はすぐにやってきた。
「青森まで一気に行くのは厳しいから、途中花巻あたりで一泊だな。青森からはフェリーで函館に渡ろうか?」
「あたし分んないから章吾に任せる」
章吾は、
「往復の道順を考えて、出かける前に案を作っておくよ」
と約束した。
「バイクだからさ、荷物は少なくしてくれよな」
「はい」
沙希はお腹の中の赤ちゃんが日に日に育っているのを楽しみにして毎日を過ごした。母の美鈴も何かと心配してくれて、大事にしてくれた。
その後章吾が言った通り不審な手紙や電話もなく、毎日が平和で穏やかだった。
美鈴は、
「最近誰でも使ってる紙おむつでなくて、昔わたしたちが使ったようなおしめにしない?手間がかかるけどお父さんの浴衣のお古があるから」
とオムツの心配までしてくれた。沙希は美鈴の言うことにいつも素直に従った。どうやら生まれてくる子供はおしめになりそうだ。
マリアが女の子が生まれたと連絡してきた。それで、沙希は美登里を誘って病院にお見舞いに行った。可愛らしい赤ちゃんだった。サトルは、
「オレたちの愛の結晶だ」
とか言って自慢げな顔をしていた。
「名前、決まってるの」
と美登里が聞くとサトルは、
「考え中」
と言って笑った。
最近美登里は休日にお出かけする時は、ざっくりしたAラインのワンピを着て、ふわふわしたウールの肩掛けをしていた。色彩は淡い中間色で、それが美登里に良く似合っていてマリアは、
「美登里のファッション、童話に出てくる女の子みたいで素的よ」
と褒めた。けれども美登里は、
「バイクで旅行する時はパンツにしてくれよな。ひらひらするのは危ないし、スカートもダメ」
と言われていた。
岩井加奈子が警察から釈放された話は章吾から聞いて沙希も知っていた。
加奈子は釈放されると、六本木のクラブ、ラ・フォセットの柳川を訪ねて、もう一度ラ・フォセットで使ってくれと頼んだ。だが、
「お断りする」
と柳川に突っぱねられた。仕方なく、新宿のキャバに入れてもらって勤め始めたが、仕事がきつく、自分にも合ってなかったので、生まれ故郷の仙台に戻った。
仙台で約一月ぶらぶらした後に、金持ちの男を見付けてクラブを出させてもらい、そのクラブのママとして落ち着いた。
加奈子が頑張った甲斐があって、ようやく軌道に乗って来た時、珍しい客と出逢った。
五十五 北海道へ
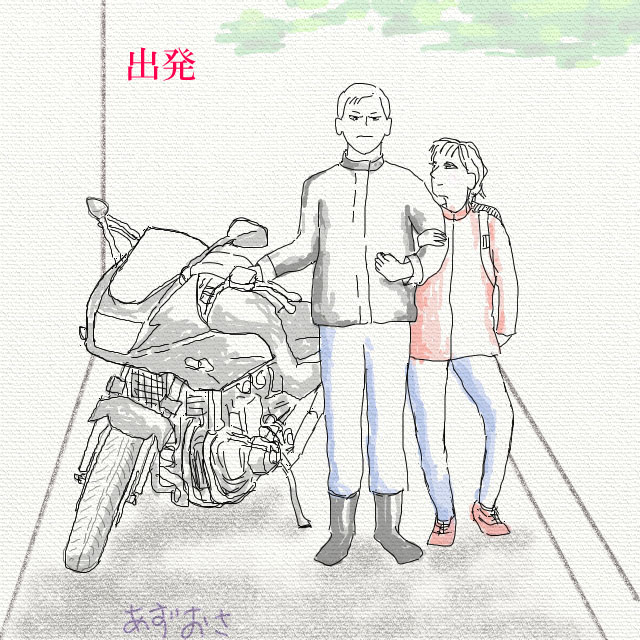
章吾の北海道へのツーリングの案は、
往き=東京―花巻―函館―(札幌)―旭川
帰り=旭川―(美瑛、富良野)―洞爺湖― (函館)―仙台―東京
だった。
「美登里が旭山動物園に行きたいって言うから結構ハードな行程になっちゃったよ」
と章吾が説明した。
「()のとこは泊まらないで通過だ。五泊六日だな。これでいっぱいいっぱいだ。一日に走る距離が長いから疲れるかも。それでもいい?」
美登里は、
「動物園まで行けるなら無理でもいいよ」
と同意した。
天気予報では、連休中はお天気が良いと報道されていたが、念のため美登里と自分の分の雨合羽を持った。美登里は着替えとか色々持ち物があって、バックパックにぎゅうぎゅう詰め込んでも入りきらず、小さなバックパックを美登里に背負わせることにした。美登里の荷物でパンパンになったバックパックは燃料タンクの上にゴムのネットで固定した。「よしっ!」
九時ごろ池袋を出ると直ぐに高速に上がって、三郷ジャンクションから東北道に入り突っ走った。途中SAで何度か休憩したので、花巻温泉の愛隣館と言う旅館に着いたのは午後四時を少し回っていた。美登里は最初の内は怖いらしくて章吾のウエストに腕を回して抱きつき、無口だったが、茨城県の鹿沼を過ぎたあたりから大分慣れたようだ。美登里を乗せて高速を時速100kmで走るのは初めてだった。章吾のバイクはホンダのCB1300スーパーツーリングで高速を走ってもパワーは余裕があって安定していたし、タンデムシート(後の座席)にはストッパーが付いているから滑り落ちる心配もなかった。章吾は少し前まではCB1000に乗っていた。だが、沙希と一緒の時に遭った事故で破損したのを修理したが調子がいまひとつ良くなかったので、1300の新しいのに乗り換えたのだ。
旅館に着くとすぐにチェックインして、ツインの部屋に入った。美登里は部屋に入ると「素的!」
と言って喜んだ。
「風呂に入ってから食事にしない?」
「はい」
時間が早かったので、二人はゆっくりと温泉に浸かることにした。
泊まった愛隣館と言う旅館は部屋はゆったりしていたし、林を眺める露天風呂も良く、料理も美味しくてなかなか素的だった。ゴールデンウイーク中なので料金は少し高かったが、それでも一人一万三千円だ。
翌日は早起きして八時半に旅館を出た。
「ぐっすり眠れたか」
「はい」
美登里は昨夜期待していたのに何もなかったので不満だったが、顔には出さなかった。
旅館を出ると、また高速に乗って、青森を目指して走った。美登里は周囲の景色を見る余裕ができた。それで、左手に次々と現われる山並みを見ていた。東北は新緑には少し早い。所々で桜の花が咲いていて綺麗だった。
花巻温泉から青森までは200km位なので、途中SAで昼食をとって、十二時五十分発の津軽海峡フェリーに余裕で乗ることができた。フェリーには出発時刻の一時間前には並ぶのが普通だ。だから十一時半にはフェリーターミナルに入った。函館には四時半に着く。
函館では夕食は街の中のレストランでとることにした。それで、ロワジールホテル函館と言うホテルに朝食付きのツインルームを予約しておいた。行って見ると大きなホテルだったが一泊六千円だ。
時間が早かったからチェックインを済ますと五稜郭のあたりをぶらぶらしてから、夕食にすることにした。
「何食いたい?」
美登里はこんな時、いつも自分で決めるのが苦手だった。
「章吾のお勧めでいいよ」
章吾は美登里のそんな性格を最近理解していたが、必ず一度は美登里の希望を聞いた。章吾は以前柳川に連れてきてもらった、函館駅近くの割烹魚清と言う和食屋に美登里を連れて行った。美登里は殆ど好き嫌いを言わなかったから、こんな時は都合がいい。
食事が終わると函館山の山麓駅からロープウェイで山頂まで登った。あたりはもう真っ暗になっていて、下の方の明かりがキラキラして綺麗だった。
「綺麗! すっごく綺麗!」
美登里ははしゃぎ気味で喜んだ。二人は函館の夜景を見てしばらくそこに佇んでいた。美登里は章吾の腕を取ると章吾の身体に頬を押し付けてじっと立っていた。いつだったか夜中にお台場に連れて行ってもらって、明け方までじっと二人で海を見ていたのを思い出していた。
その夜も美登里の期待は空振りに終わって何もなかった。次の日も早起きをして、簡単な朝食を済ますとホテルを出た。
ホテルを出ると、章吾は函館の街をバイクで一回りしてくれた。教会や旧イギリス領事館などを外から見て回って、一般国道を長万部に向かって走った。右手がずっと海岸線なので景色は綺麗だった。長万部の手前から高速に上がると札幌までは150km位しかないので、十二時前には札幌の市街に入った。
「ちょっと札幌の街の中を回ろうか?」
「嬉しい。時間、大丈夫なの?」
「ん。どうにか」
それで公園とかに立ち寄った。
公園の樹木の感じが、写真で見たヨーロッパの公園みたいな感じだったので、美登里はめっちゃ喜んだ。それで自分のデジカメであちこち写真を撮っていた。丁度ライラックが綺麗な季節で大きな樹に沢山花を付けている風景に美登里は見とれていた。
「昼飯、何食いたい?」
すると美登里は珍しく即座に、
「札幌ラーメン!」
と言ったので二人して笑いこけた。
「じゃ、食べに行こう」
ラーメンでお腹が満たされた所で、また高速に乗って旭川を目指して走った。お天気が良く、思ったより暖かかった。章吾は途中一度も休まずに旭川まで走って、高速を降りると旭山動物園に直行した。近くになると、車の列が長くつらなっていたが、バイクだ。並んでる車をどんどんと追い越して先頭に行くと案の定バイクは直ぐに駐車場に入れてくれた。こんな時はバイクに限る。車だったら一時間以上待たされただろう。二時前に動物園に入園すると、閉園時刻の五時十五分近くまでゆっくりと見て回った。美登里は子供みたいになって嬉しそうに見て回った。確かに動物が皆生き生きしていて、他の動物園では見られないようなアングルから見られるように工夫されていて章吾も結構楽しめた。
旭川駅の近くの旭川ワシントンホテルに部屋を取ると、二人で街に出て夕食をとった。
「今日は早く寝よう。明日は北海道最後の日だから、うんといいホテルにしたよ」
それで、ホテルに戻るとシャワーを使ってから少しテレビを見た後に寝た。宿泊代は高くないがビジネスホテルなので部屋は狭く寝るだけの部屋だった。
翌朝はまた早起きして、一般道を美瑛に向かって走った。今まで高速道ばかり走っていたが、やはり一般道の方が景色が良く見られて楽しいと美登里は思った。それに、バイクがすれ違う時に、必ず相手が軽く会釈して行くのだ。山歩きをしている時、見知らぬ人とすれ違っても必ず、
「こんにちは」
とか声を掛け合うのと同じだ。何回も会釈している内に、美登里は次第に派手に手を振った。すると、相手も派手に手を振って挨拶してくれるのだ。特に後に女の子を乗せたバイクとすれ違うと、後に乗った女の子とにこにこして手を振り合えて美登里はそれがめっちゃ楽しかった。
美瑛では章吾は農道を走って回ってくれた。畑の緑や所々咲いている花が綺麗だった。富良野に着くとファーム富田と言うハーブ園でゆっくりした。丁度アイスランドポピーが咲き初めで綺麗だった。この地域は観光化しているせいか、農道を走っていても綺麗で楽しかった。
富良野からしばらく一般道を走って、再び高速道に乗って洞爺湖を目指して走った。地図で見るよりも北海道は随分広い。一般道は信号が少なく道路は整備が行き届いていて走って快適だが、距離が長いので高速を使わないとなかなか目的の場所に行けないのだ。
洞爺湖で高速を降りると、湖の近くで一休みした。広々としてとても気持ちがいいと美登里は思った。
一休みが終わると、章吾はバイクを高台に走らせた。やがて前方に大きな建物が見えてきた。
「今夜はここだ」
章吾が振り向いて美登里に話した。章吾が予約したホテルは、ウィンザーホテル洞爺だった。エントランスを入るとなかなか素的なホテルに見えた。とにかく周囲にある物は何でもゆったりとしていたので、[ゆるい]のが大好きな美登里にはピッタリだった。
チェックインを済ますと部屋に案内された。美登里は部屋に入ってびっくりした。
「広~いっ!」
部屋の中も全てがゆったりしている。テレビで話は聞いたりしていたが、まさか安月給の派遣社員の自分がこのホテルに宿泊するなんて信じられなかった。美登里はそれくらい感動していた。ゆったりしたお風呂に入って、お化粧を整えると、二人でホテルのレストランに行った。
和食、洋食など色々あったが、美登里が
「北海道の最後の夕食はフランス料理にして」
と言っていたので、予め予約をしておいた。二人で四万円近くになったが、料理の内容や雰囲気で十分に満足できた。
美登里が派遣で超安月給なのを章吾は知っていたから、この旅行の費用は全部章吾が持つことで美登里も納得していた。だから、
「こんな贅沢な所に泊まって」
なんて章吾に文句は言えなかった。もしも美登里が主婦をしていたら、余程のことでもなければ、こんな贅沢なホテルには先ず泊まることはないだろうと思った。
「美登里、疲れた?」
「そうね。最初の日は疲れたけど、慣れたら全然平気」
事実、こんな強行軍のスケジュールでも美登里はあまり疲れた気がしなかった。それよりも大好きな彼と一緒に旅して回れる幸せに酔っていた。
もう一度ゆったりしたお風呂に入った後、二人でぼんやりとテレビを見てからベッドに入った。ツインだったから別々だ。
章吾がベッドに入ってから、しばらくして美登里は自分のベッドを降りて、章吾のベッドの中に潜り込んだ。東京から持ってきたネグリジェを初めて着ていた。
ベッドに入ると、章吾はまだ起きていた。美登里は章吾に抱きつくと自分から章吾の唇を奪った。そうでもしなければ、いつまで経っても章吾がしてくれないように思ったからだ。
「抱いてぇ」
消えるような声で美登里は章吾の耳に囁いた。
「オレたち、結婚前なのに、いいのか?」
章吾は静かに聞いた。
「あたし、章吾のお嫁さんになるって決めたからいいの」
美登里は小声で答えた。
章吾は改めて美登里の唇にキスをしてくれた。そして、ネグリジェのボタンをゆっくりと外すと、うなじから乳房へと唇で愛撫してくれた。そして美登里の肩を抱いて引き寄せて抱きしめてくれた。章吾への思いがずっと溜まっていた美登里は、章吾の愛撫が衝撃のようになって自分のハートを刺激しているように感じていた。全身が震えて、長い間待っていた感情が破裂して涙が溢れ落ちた。
「大好きな章吾に愛されてる」
そう思うだけで身体が震えた。
章吾はゆっくりと背中からヒップへと手で愛撫してくれて、章吾の手が太ももの内側にそっと忍び込んで来た時、美登里はずっと我慢していた気持ちが切れて燃え上がってしまった。それからは美登里は自分から章吾を愛撫して、いよいよ頂点にさしかかった時、章吾の物を自分の中に受け入れた。美登里は生まれて初めての経験だ。ただ本能に従って章吾を求めた。章吾もずっと我慢してきた美登里への想いが切れたように美登里と一緒に一つになって愛し合った。
結局二人は明け方までそうやって激しく愛し合い、その間に章吾は二度も果てた。
二人が目を覚ました時は九時を回っていた。美登里が目を覚ましたのを見て、章吾は軽く美登里に接吻して、
「美登里、おは」
と微笑んだ。二人は急いで身支度を済ませ、朝食を済ますと、十時半にホテルを後にして函館のフェリーターミナルを目指して走った。
五十六 美登里の決心
「明日は帰りが遅くなってもいいだろ?」
「はい。あたしはいいよ」
「じゃ、仙台に泊まる予定だったけど、弘前城の夜桜を見ない?」
「あっ、嬉しい。弘前って、あたしまだ行ったことないんだ」
青森から弘前は近い。青森でフェリーを降りると、国道7号線を通って弘前に向かった。弘前城の桜は満開を過ぎた所だが、まだ綺麗だった。夜桜を見終わると、弘前より少し先の大鰐温泉から十分程小高い所に登った青森ロイヤルホテルにした。料金はそれほど高くは無くいい感じのリゾートホテルだった。
遅い夕食を済ますと、温泉にゆっくりと入ってから部屋に戻った。昨夜は明け方まで起きていたが、フェリーで四時間熟睡したので、それほど眠くはなかった。
「美登里、こないか?」
ベッドに入ると珍しく章吾が誘ってくれた。美登里は嬉しくて、また泣きそうになった。美登里は一人っ子でお嬢様育ちだったので、根は淋しがり屋で甘ったれで、涙もろい所があった。美登里の泣き顔は可愛いと章吾が思う通り、子供のように可愛い感じだった。美登里が章吾の横に潜り込むと、章吾は美登里を抱いて愛撫してくれた。今までずっと触ってもくれなかったのは、章吾が結婚前だからとけじめを付けていたらしかった。だが、昨夜結婚前に越えてはいけない線を越えてしまったから、一度越えてしまえば二度越えても同じことだと思っているらしかった。その夜も美登里は章吾を受け入れて一つになって愛し合った。
「あたし、もう絶対に章吾のお嫁さんになるから」
と美登里は自分に言い聞かせるように章吾に呟いた。
翌朝は早起きして朝食後ホテルを出ると、周囲は高台で素晴らしい景色だった。ホテルから7号線に降りると、五城目街道を通って秋田に向かった。秋田市街を抜けると、酒田街道(7号線)に沿って、本荘を通り過ぎて酒田に向かった。沿線は右側が酒田までずっと日本海で人の気配の少ない淋しげな海岸線が続いていた。車も思ったより少なく、章吾と美登里を乗せたCB1300は坦々と走った。
酒田から高速の秋田自動車道に乗り、北上ジャンクションから東北自動車道に入った。あとはひたすらに東京に向かって走るだけだ。章吾は美登里が疲れないように、往きよりも頻繁にSAに入って休憩を取った。
郡山でお昼になったが、そのまま走って那須高原SAで昼食にした。
「美登里、疲れただろ?」
「全然」
美登里は言葉通り疲れた感じではなかった。
三郷ジャンクションあたりから道路は混雑して、都内に入っても混雑していたが、章吾は上手くすり抜けをして思ったより早く渋滞を抜けた。それで、夕方の五時ごろには池袋から高速を降りた。
「オレのとこに寄っていかない?」
もちろん美登里はOKした。章吾のアパートで荷物を降ろして整理すると、近所の食堂で夕飯を済ませて、軽自動車で美登里を四谷の伯母の所に送っていった。
章吾は、
「ちょっと伯母さんに挨拶するから」
と言って伯母の家に上がった。伯母が出て来ると、章吾は挨拶を済ませてから、旅行のあらましを伯母に説明した。説明が終わると、章吾は改まった姿勢で、
「鎌倉の美登里さんのご両親は僕等の付き合いを快く思われていないと美登里さんから聞いていますが、自分としては美登里さんと結婚させて欲しいと思っています。応援して頂けませんでしょうか?」
と願い出た。
「美登里はあなたのことを好きなようですから、あたしからももう一度美登里の両親に話をしておきます。もしも、それでもダメと言われたら、あなたどうなさるおつもり」
と伯母が章吾に聞いた。
「ひどい話ですが、万一そんなことになったら、僕はご両親の承諾が頂けなくても美登里さんと結婚します」
「あら、そう。そこまで考えていらっしゃるなら本気ね。それを聴いて安心したわよ。美登里を可愛がってあげて下さいね」
伯母は承知した口調だった。
「色々条件が合わないことはありますが、美登里さんと結婚してからも美登里さんのご両親は大事にしたいと思っていますので、出来れば気持ちよく結婚を認めて下さると嬉しいです。よろしくお願いします」
側で話を聞いていた美登里は、
「どんなことがあっても章吾と結婚する」
と心に決めた。
連休明け、三日ほど過ぎて、美登里の伯母の八重から章吾に電話がきた。
「美登里の両親を説得したわよ。それはもう大変だったのよ」
と八重が話してくれた。
「それで、美登里ちゃんの母親の気が変わらない内に、お式のことやら色々決めてしまいたいから、ご都合のよい時にこちらにいらして下さいな」
と付け加えた。
章吾は美登里に電話して次の日曜日にきちっと決めようと約束した。
五十七 結婚式の予定

「オレたちの結婚式だけど、七月じゃ暑いから六月にしない?」
章吾は美登里と日曜日に会って相談していた。
「ジュンブライドだわね」
「ん」
「仲人さん、どうするの?」
「オレの会社の社長、柳川って言うんだけど、話しをしたら引き受けてやるって言ってた。美登里はそれでいいか?」
「章吾に任せる」
「今年の六月は大安の日曜日は三日なんだよな。あまり日がないなぁ」
それで二人は電話をかけまくって探したが、どこも予約が詰まっていて式場が予約できなかった。
「困ったなぁ」
それで、四谷の伯母に美登里が電話をした。
伯母からの返事を待つ間に章吾は美登里に聞いた。
「美登里、さっきジュンブライドって言ったよね」
「ん。言ったよ。良く言うでしょ?」
「梅雨時でさ、お天気だっていま一つの季節なのに、何で六月なんだ?」
「あたしも正確には知らないけど、聞いた話じゃ、ヨーロッパでは六月にね、結婚すると幸せになれるって言う言い伝えがあるんだって。英語の六月はJUNEでしょ? このJUNEの語源はギリシャ神話に出てくる若い男女を護ってくれる守護神の女神、ジュノー(Juno)から来てるんですって。この女神は結婚とか出産を司る神様だそうで、特に女性の守護神なんだってよ。それで六月に結婚することが多いんですって」
「ふーん、美登里知識あるじゃん」
章吾は感心して聞いていた。美登里はこんな時知ったかぶりした言い方をしないので、章吾はいつも気軽に聞けた。
ややあって、伯母から返事がきた。
「四谷の須賀神社に聞いてみたら大丈夫だって言ってたわよ。そこに決めるなら電話で予約をしてあげるけど」
「どこもいっぱいだから伯母さんがいいって言うならそこに予約をいれて下さらない? 所で聞いたことがない神社だけど、どんなとこ?」
「美登里、四谷に住んでたら、それくらいは知識を入れとかなくちゃ」
そう言って伯母は簡単に説明をしてくれた。また長電話の始まりだ。
「須賀神社は普通は四谷のって言っているんだけど、新宿区須賀町なのよ。でも近い駅はメトロ丸の内線の四谷三丁目よ。旧い神社じゃないんだけど、江戸時代の初めは村の鎮守の神様だったらしいのよ。美登里は八俣の大蛇の話、知ってるでしょ? 須佐之男命。八俣の大蛇を退治したのは出雲の国だったんだけれど、退治した後で須佐之男命が四谷のこのあたりにやってきて気持ちがすがすがしい、つまり漢字で須賀、須賀しと言ったとかの話から今の須賀神社があるあたりを須賀と言うようになったそうよ。それで須賀神社。分った?」
「はい、伯母さん、よぉ~く分りました」
と美登里が笑った。
「あなた、笑い事じゃないわよ。伯母さんは真面目に話をしているのよ。あんたたちが結婚式を挙げる所でしょ」
「すみません」
美登里は伯母から聞いた話を章吾に説明した。
「ふーん?」
章吾はまた感心した。
「新宿の須賀町って結構交通の便がいいとこなんだよな。慶応病院のあるJR総武線の信濃町に近いし、ぶらぶらと少し歩くと学習院の初等科があってさ、その先が四谷で上智大のキャンパスなんだ」
「そうよね。ご招待した方が来やすいわね」
章吾は早速須賀神社に電話した。伯母から仮の予約が入っていた。
「美登里、披露宴、池袋の仲間も呼ぶだろ?」
「もちろんよ」
「今聞いたら須賀神社には広いホールって言うか会場がないみたい。それに、オレたちの仲間のストリートミュージシャンが神社でドンチャカはやり難いよなぁ。披露宴の場所は他にしない?」
それで披露宴の会場はマイクロバスを使えば十分とかからない紀尾井町のホテルニューオータニで会場を予約した。
問題は美登里の両親だ。オヤジは絶対に文句を言わない自信はあったが、母親は事前に相談しなかったから文句が出そうだった。それで、美登里はまた伯母の八重に間を取り持ってくれと頼んだ。
「ここまで来たんだから、伯母さんがダメ押ししてあげるわよ」
章吾は長野の実家に電話をして細かいことを説明した。
「今度の休みに彼女と一緒に行くから」
兎に角急に結婚することを決めてしまったので、バタバタしていた。
五十八 悲しみを乗り越えて
四谷に住んでいる美登里の伯母西垣八重は美登里と章吾の結婚の具体的な話がまとまってきたので、美登里の実家の母親藤井志津江を説得するために電話をした。と言っても、八重と志津江は毎日のように電話でたわいもない話をしていたのだが、今回はいつもと違った。
「シズちゃんと事前に相談してから決めれば良かったんだけど、美登里ちゃんと彼、六月三日の日曜日、大安の日に結婚式を挙げることに決まったのよ」
「それ、どう言うこと?」
「美登里ちゃんは猪俣さん以外には考えられないって言うでしょ、だからあたしは仕方ないと思って予定を進めさせたのよ」
「だって、母親はわたしよ。そんな大事な話を母親抜きに決めちゃうなんて許せない」
「シズちゃん、気持ちは分るけど、あなた美登里の気持ちを無視してずっと反対してたじゃない? それじゃ、美登里は好きな男と駆け落ちするっかないじゃない。そんなことさせちゃ可哀想よ」
「母親のわたしはどうなるのよ。将来一緒に暮らしてくれない男との結婚式にいそいそと出かけられると思う?」
「それはシズちゃんの我がままよ。美登里ちやんの気持ちをもっと大事にしてあげなくちゃ」
「我がままってどう言うこと? 何でもわたしを悪者にするんだからぁ」
「もうっ、あなたったら、どこまでそうして反対するのよ」
「八重さんだって、わたしのささやかな夢、知ってるよね。一人娘と同じ屋根の下で楽しく暮らして、やがて生まれる孫の面倒を見たいって言う、ただそれだけの希望を満たせない男と結婚なんてさせないわよ」
さすがの八重も匙を投げ出したくなったが、ここは可愛い美登里のためだと思って感情が爆発しそうになるのをこらえていた。
結局どう言っても志津江は納得しなくて、互いに平行線だった。
「美登里ちゃん、あなたのお母さん頑固ね。あたしが何を言っても反対の一点張りよ」
「伯母さん、すみません」
「一人娘の結婚式に母親が出ないなんて聞いたことがないよ。こうなったら、お式を進めて、シズちゃんが来てくれるかどうか賭けをするしか手がないわね。案内を送ってお席を用意しておいて頂戴」
八重はもしも自分が美登里の立場だったら、はたしてどうするだろうと思った。自分なら多分恋する男を諦めて、母親が納得する男性と結婚するかも知れないと思った。それは自分の幸せにならない可能性はあるけれど、次第に年老いて行く母親の幸せを優先するってことだ。
「困ったなぁ、章吾君はまあまあ良い男なのに、どうしてこうなるんだろ?」
八重は自問自答した。
それで、夜遅く帰宅した旦那の一樹にことの顛末を話して相談した。一樹は、
「分った。じゃ、僕が一度美登里のオヤジの藤井君に会って話をして見るよ。藤井君なら娘の幸せを考えて志津江さんを説得してくれるかも知れないし」
「あなた、忙しいのにごめんね」
東京の丸の内のビルの中のレストランに、西垣一樹は藤井章一を誘って昼食がてら美登里の結婚の話をした。
「僕としては猪俣君はしっかりとした良い男だし、美登里が好きになった男だからこのまま希望通り結婚させてやりたいんだよ。でもなぁ、志津江のやつがすっかり依怙地になって僕も困ってるんだよ」
と章一は言い訳した。
「それで、どうだろう、結婚式まで日がないから予定はそのまま進めさせて、当日君が何が何でも志津江さんを式場まで引っ張ってきてくれないかなぁ。母親欠席の結婚式じゃ美登里ちゃんが不憫で僕もたまらんよ」
章一はそんなやり方しか志津江を出席させるのは無理だろうと一応了解してくれた。
やはり父親は娘が可愛いのだ。娘を可愛いと思う自分の気持ちには勝てないと章一は思った。
美登里は伯父の話を伯母から聞いて本当に悲しくなって、また涙をぽろぽろ流して泣いた。その一方で、
「この悲しみをどうしても乗り越えなくちゃ章吾と一緒に幸せにはなれない」
と自分を励ました。
五十九 加奈子……その後

刑務所を出所すると、加奈子は元勤めていた六本木のクラブ、ラ・フォセットを訪ねて、使ってくれと頼んだがあっさりと断られた。当面食いつなぐ充てもなく、新宿のキャバに勤め始めたが長続きせず、生まれ故郷の仙台に戻った。だが生まれ故郷に戻っても親戚や幼馴染の目は前科者には厳しかった。クラブ、ラ・フォセットに勤めていた時代の収入が多く、贅沢な暮らしや周囲にちやほやされていたことが忘れられず、仙台では惨めな憂鬱な生活をだらだらと続けていた。幼馴染の中で唯一水商売をやっている石崎士郎と言う男だけが加奈子に親切にしてくれた。石崎士郎は仙台駅西口から広瀬通りに沿って数百メートル行った所にある飲み屋街、虎屋横丁のスナックでバーテンをしていた。
士郎の店に加奈子が行くと、士郎は親切にしてくれたので、自然に士郎の勤めるスナックに行って、ビールやカクテルを飲んで気晴らしをすることが多くなった。仙台に戻ってから、もうかれこれ一ヶ月になる。
仙台は北陸の金沢同様概して綺麗な女性が多いが、中には女好きの男ならちょっと目を引き付けられそうないい女が居る。昔なら小股の切れ上がったいい女とか言われるような女だ。加奈子もそんな感じの女の一人だった。スナックで一人でチビチビやっていると、不思議と男におごられることが多かった。地元の人間も居れば、出張などで仙台にやってきたよそ者も居た。
そんなある日、がっしりとした体格の中年の男が若い男を四人引き連れて店に入ってきた。加奈子はそんな風景には見飽きていたから、気にもせずいつものようにチビチビとやっていた。すると、士郎がやってきて、カクテルのグラスを目の前に置いて、
「あちらのお客さんからだよ」
と言った。
「士郎、知ってる人?」
「ああ、良く知ってるお客さんだ」
「地元の人?」
「そうだよ。泉区にビルを持っている仙北建設の社長だよ」
「あの中年のがっしりした人?」
「そうだよ。若いやつ等は多分社員だね。後でお礼を言っておくといいよ」
「ありがと」
若い奴等がカラオケを始めて、一人テーブルに取り残された仙北建設の社長がいた。加奈子はカクテルグラスを持って、社長の席に行った。
「ご馳走して頂いてありがとうございました」
「気にするな。あんた、時々ここに来るのか」
「はい。バーテンさんが幼馴染ですので」
「そうか。あんた、もちろん独りだよな」
「はい。貰い手がなくて」
と加奈子が微笑んだ。
「ウソを言っちゃいけない。嫁に行く気がないんだろ?」
「社長さんにはかなわないなぁ」
加奈子は笑った。
「所で、今夜は時間はあるのか」
「はい。独り身ですから」
と微笑んだ。
「そうか、オレと一軒付き合わないか」
「どうしようかなぁ」
「おいおい、そう言うのはオレは嫌いだ。嫌なら断っていいぞ」
社長は歯切れが良い。そんなとこを加奈子は気に入った。
「ついて行きます」
「そうか。そうこなくちゃ。帰りに声を掛けるからついて来いよ」
「はい。あちらに居ますから」
そう言って加奈子は席を離れた。
社長は千葉慎二と言う名前だった。仙台には千葉姓は多いから、仙台ではありふれた名前だ。名前の通り慎二は次男だ。オヤジの代までは千葉工務店だったが、慎二が市役所の建設局に食い込んで業績を伸ばして、仙北建設にした。仙北建設は今では仙台では中堅の建設会社で、一般住宅、小規模マンション建設の他に土木部門も持っていて、仙台市の建設局から河川の改修工事、市道建設、下水事業などを請け負っていて、不況下ではあったが公共事業の下支えがあって、住宅専門の建設業者が倒産するような経済環境ではあったが、業績はまあまあだった。
千葉慎二は酒が強かった。それで若い奴等の酔いが回ったのを見てお開きにした。若い奴等を先に帰すと、慎二は加奈子に目配せして席を立った。勘定を済ませて店を出る時に、加奈子は慎二の後を追った。
「すし屋に行こう」
慎二は酔いを冷ますように、虎屋横丁から定禅寺通りの方にぶらぶら歩いた。加奈子は意識的に慎二の腕に自分の腕を絡ませたが、慎二は振りほどく素振りはせず、そのまま歩いた。寿司久と書いてある暖簾を潜ると、
「奥は空いてるか?」
と聞いた。板前は、
「旦那、空いてますよ。どうぞ」
と言って奥の座敷に案内した。
「あんた、どっかでオレと会ってるよな」
「さぁ?」
「六本木に居なかったか」
それで加奈子は思い出した。一度だけクラブ、ラ・フォセットに来たのを思い出した。
「あっ、会いました。クラブ、ラ・フォセットで」
「そうか、思い出したか。流石だな」
「いいえ。体格ががっしりされていらしたので、それで記憶に残っていました」
「オレみたいなゴツイやつがタイプか?」
「はい。頼れそうで」
そこに寿司とビールが運ばれてきた。
「ここの寿司は美味いぜ、さ、食べてくれ」
加奈子は丁度腹が空いていた。それで遠慮なく寿司をつついた。
「実はな、オレのとこの客を接待するのに、今は市内の料亭、バーやスナックを使っているんだが、良い所は高くて経費が持たんし、安い所はろくなとこがないんだ。それでラ・フォセットまでは行かなくても良いが、落ち着けるクラブを持ちたいと思っているんだ」
「あら、素的な計画ですね」
「それでだ、あんた、もう一度良い夢を見てみないか」
「と言うと、あたしに?」
「そうだ。ここらじゃラ・フォセットのように一本十万円もする酒をバンバン売るわけにゃいかんが、ラ・フォセットのような雰囲気の高級クラブだ。どうだ、やってみないか」
加奈子は運が向いてきたと感じていた。
「話はそれだけだ。どうだ?」
「是非やらせて下さい」
「じゃ、話は決まりだ。これからホテルにでも行って固めの杯を受けてくれ」
「はい」
加奈子は今夜この男に抱かれるだろうと予感がした。
六十 加奈子……成功への階段
寿司久を出ると、千葉慎二はタクシーを止めた。加奈子を先に乗せてから、
「エクセルホテル東急」
と行く先を告げた。ホテルに着くと、慎二はチェックインを済ませて、加奈子を伴ってエレベーターに乗った。慎二が押したボタンを見ると高層階なので良い部屋を取ったに違いない。
エレベーターを降りて回廊を少し行った所でドアを開けた。入ると加奈子が思った通り広々とした部屋だった。慎二はルームサービスに電話をして、ワインとつまみを部屋に持ってくるように伝えた。
「固めの杯の前に、身を清めなくちゃな。先に行ってくれ」
と目でバスルームを指した。
「はい。ではお先に」
加奈子はバスルームに入った。
ややあって、ワインが運ばれてきた。
「そこに置いておいてくれ」
加奈子が出てくるまで、慎二は二箇所に電話を入れた。
電話は仕事の打ち合わせのようだった。丁度受話器を置いた時、
「お先に」
と言って加奈子が出て来た。慎二は入れ違いにさっさとバスルームに消えた。烏の行水と言うか、慎二は直ぐに出て来た。
出てくると備え付けのガウンを羽織って、ワインをグラスに注いだ。一つを加奈子の方に押しやって、
「乾杯だ」
とグラスを持ち上げた。
「乾杯」
加奈子も合わせた。
一気に飲み干すと、
「よっしゃ、これであんたはオレのパートナーだ。店を出す場所はオレが探しておく。大体目星は付けてあるけどな。あんたは店の構想と雇い入れる人間についてプランを立ててくれ。大体で良いが予算もな。インテリアデザイナーを紹介するから、良く相談してくれ」
話は具体的にどんどん進んだ。さっき会ったばかりなのに、こんなに任せてもらってもいいのだろうかと加奈子は一抹の不安はあったが、とにかく言われた通り進めることにした。
少し飲んだ所で、
「大事なパートナーだ。ちょっと可愛がってやるぞ」
そう言うと、加奈子が答えようとした時には、加奈子の身体はひょいと宙に浮かんでいた。太い腕が伸びてきて、返事をしようとした時には慎二の腕の中で抱きかかえられていた。慎二はそのまま加奈子をそっとベッドの上に横たえた。慎二はガウンの下には何も着けてなかった。
加奈子をベッドに横たえると直ぐに加奈子を愛撫し始めた。
加奈子は刑務所から出所以来男とは一度も交わっていなかった。しばらくぶりに男の素肌に触れて、それも自分のタイプのがっしりした体格の男に抱きしめられてすっかり熱くなってしまった。なので、最初は慎二に任せていたが次第に積極的に慎二を求めた。
「思った通りのいい女だ」
慎二はそう思った。加奈子はこれから先、この千葉慎二に可愛がってもらおうと思っていた。先ほど感じていた一抹の不安は完全に消されてしまった。加奈子が頂点に達して、頭の中が真っ白になってしばらく歓びを感じている間、慎二はずっと加奈子を抱いていてくれた。
洋服に着替えると慎二は、
「これは当面の経費だ。少ないがとっておいてくれ」
と背広の内ポケットから封筒を取り出して加奈子に渡した。厚さから四十か五十は入っているのだろうと加奈子は思った。
ホテルの部屋を出ると、慎二は加奈子だけタクシーに押し込むと、
「じゃ、よろしく頼んだよ」
と言って自分はまたホテルの中にもどって行った。
「いい女を見つけた。明日紹介するから良く打ち合わせをしてくれ」
慎二はインテリアデザイナーにクラブの改装を頼んだ。
また慎二は、地元で[ブンチョウ]と呼ばれている国分町通の中ほどにあるビルの二フロアーが空いている所を押さえようと思っていた。一フロアー400㎡位はあるので、十分な広さだ。
翌日加奈子は精力的に新しいクラブのプランを考えていた。加奈子の構想は殆ど六本木のクラブ、ラ・フォセットのシステムを取り入れようと思っていた。午後、慎二から電話があって、
「泉区にある仙北建設本社の事務所に来てくれ」
と伝えて来た。幸いなことに加奈子も泉区の向陽台の一角にあるアパートに住んでいたから、事務所までは遠くはなかった。
事務所に行くと受付の女性に、
「岩井と申します。社長に面会したいのですが」
と言うと、予め話を聞いていたらしく、すぐに応接室に通された。そこに一人の青年が居た。ややあって、慎二が入ってきて青年を紹介した。インテリアデザイナーの原口薫だった。いかにもデザイナーらしく、長く伸ばした髪の毛を後ろで束ねており、着ている洋服も垢抜けていた。慎二とは反対にすらっとしていて動作が綺麗なのが目に付いた。バレーかダンスでもやったら似合うような感じだ。
六十一 加奈子……人集め
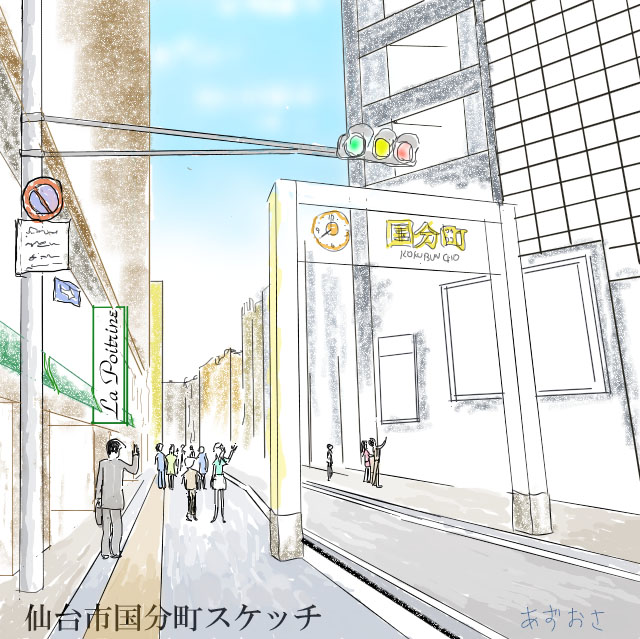
仙北建設社長、千葉慎二に新しいクラブの立ち上げを任された岩井加奈子は、インテリアデザイナー原口薫の助けを借りて、店舗の改装費、当面の運転資金などについてソロバンを弾いてみた。加奈子は経験がなかったので、ラ・フォセットに勤めていた頃のお客で店舗の開業指導などをやっている尾上と言う男に泣きついた。
「ご無沙汰してます。お元気?」
「そう言う加奈さんは元気なの? 突然ラ・フォセットから姿を消したから、もしかして死んじゃったのかと思ってたよ」
「そう、あたしね、一度死んだの。今は幽霊かな?」
「おいおいっ、足があるんだろ」
「アハハ、足はあるわよ。足が付いてる幽霊」
「所で、急に何だよ。何かあったのか」
「ん。新しくお店を開く準備をしてるんだけど、あたし何も知らなくて。ねぇ、尾上さん、至急仙台に来てくれない」
「仙台かぁ、遠いなぁ」
「新幹線で二時間よ」
「どうしても行かないとだめか」
「絶対に来てぇ」
「加奈さんを抱かせてくれるんなら考えてもいいけどなぁ」
「尾上さん、相変らずHねぇ」
「オレ、Hを取ったらタダの人だからさぁ。どうなの? Hを許してくれるの」
「お触り位にしてくれるなら許すわよ」
「じゃ、せいぜい期待して仙台まで行くか」
「嬉しいっ! OKしてくれると思ってた」
「最初から決めるなよ」
尾上は一度加奈子を抱きたいと思っていた。仙台まで行って、せいぜい恩を売って、加奈子を落としてやろうと思いつつ仙台に向かった。
尾上と加奈子は仙台駅近くのカフェで落ち合って、加奈子は早速仕事の話を持ち出した。
「おいおいっ、今日の加奈さんはお色気が全然ねぇじゃないか」
尾上はしばらくぶりに加奈子に会えて気を良くしていた。
「所でさぁ、ここのカフェの社長は上村歩って言うわりと若い女性なのを知ってる?」
「知らない。どうしてそんなことを聞くの」
「オレ、彼女に会ったことがあるんだ」
「綺麗な人?」
「綺麗と言うか魅力的な女性だな。彼女はルノアールって言う会社をやってるんだけど、このカフェとルノアール、ジャンコは皆彼女がやってる会社のカフェのブランド名なんだ。ルノアールって言う会社は従業員が7000人以上も居るんだよ」
「へぇーっ? 仙台駅周辺にジャンコもあるわね」
「ん。本社は池袋のサンシャインにあるんだけど、傘下のカフェは東京、神奈川を中心に300店舗以上を展開してるんだ」
「話は聞いて見るものね。あたし、今仙台に住んでいるけど、良く来るこのカフェがそんなだとは全然知らなかったな。ねぇ、あたしの話も聞いてよ」
加奈子は尾上に大体の構想を説明した。
「店舗は千葉さんとか言う社長が面倒を見てくれるんだな」
「そう」
「それは良かった。若い人が飲食店を開業する時に一番困るのは店舗を借りる時の保証金なんだ。百万とか二百万しか考えてないやつが殆どなんだけど、普通は家賃の半年分~一年半、平均一年分の金を要求されるんだ。繁華街のいいとこで、仮に三十坪だとすると、そうだなぁ、新宿あたりだと坪あたりの賃料は四万円前後だけど、仙台のこのあたりだと月に坪あたり一万五千~二万ってとこかな? だから三十坪の店の賃料は月に四十五万~六十万だね。だからさ、保証金を十二ヶ月分要求されたとすると、五百四十万~七百二十万も最初に用意しないと店が借りられないんだ」
「へぇーっ、そんなにぃ」
「加奈子の店、400㎡と少しだとすると、百二十坪以上だな。それだと、保証金は最初に二千二百万円位は用意しないと借りられないんだよ」
「店を借りたら、内装の改装費、これもかかるよな」
「あたしのとこはデザイナーさんに見積もってもらったら、諸々全部入れて一億二千から一億五千ですって」
「大体いい線だな」
「運転資金、これも若いやつは二ヶ月分位しか考えてないのが多いんだけど、軌道に乗るまで半年位は赤字でもやれないと困るから半年分位は考えておくといいよ。二ヶ月なんて直ぐに過ぎるから、大抵そこで資金繰りが停まって、借金を増やして雪ダルマになってさ、夜逃げするやつが多いんだよ」
「尾上さん、ありがとう。良く分かったわ。あたし、これから人と会う約束なの。ごめんね、これで失礼するわ」
「おいっ、加奈さん、それはないよな」
加奈子は尾上の最後の話をろくに聞かずにさっさと店を出て行った。
「くそっ、騙されたな」
尾上が気が付くと、カフェのコーヒー代も払われてなくて、結局尾上が全部支払うことになった。尾上はむしゃくしゃして、このまま東京に帰る気がしなかった。それで、三越デパート裏のキャバクラに入ったが、あっと言う間に十万近くふんだくられて、
「くそっ、くそっ」
と悪態をつきながら最終の列車で東京に戻った。
「どうだ、概算は出たか」
「はい。大体」
昨夜に続いて、今夜も加奈子は慎二に身体を許した。加奈子自身、慎二をすっかり好きになり、自分の中で密かに慎二が誘ってくれるのを待っていたのだ。
慎二の愛撫をたっぷりもらった加奈子は、午後に会った尾上のことなぞもう頭の隅っこに押しやって、頭の中は慎二のことで満たされていた。
翌日、加奈子は錦糸町の米倉源蔵の息子の魔神に電話を入れた。
「元気にしてたか」
「ムショに世話になっていた間一度も面会に来てくれなかったくせに」
「悪かった。次の時には必ず行くよ」
「冗談言わないでよ。刑務所なんて一度でこりごりよ」
加奈子の元恋人だった男も、加奈子が警察の世話になった途端冷たくなっていたのだ。
「そうだな。それで用があって電話して来たんだろ」
「そう。あんたとこに用心棒が務まる男、三人くらい居ない?」
「三人くらいならブラブラしている奴が居るよ」
「その三人、信用できる奴?」
「もちろんさ。オレのとこの子分はみな口が堅いぜ」
「じゃ、その三人、こっちに回してよ」
「店はどこだ?」
「仙台」
「えっ、仙台? 宮城のか?」
「そうよ」
「遠いな」
「東京に二時間よ」
「ま、そうだが。直ぐにか?」
「お店のオープンが三ヶ月後。その前に顔合わせしたいな。適当な時に寄越してよ」
「分った。可愛い加奈子のためだ」
「お願い。ご恩は忘れないよ」
「ウソつけ。いつも口先だけのくせに」
それで用心棒は何とかなりそうだった。後はホステス、メイク、エステシャン、ドレスコーディネーター、下働きの男を二人、事務の女の子を一人。それでどうにかなりそうだった。
「ラ・フォセットの澤田さんみたいな躾係りの良い人が見付かれば完璧だな」
と加奈子は呟いた。
六十二 それぞれのこと
岩井加奈子はこの三ヶ月間精力的に仕事をした。その甲斐あって、七月早々、クラブ ラ・ポワトリーヌをオープンさせた。名前は加奈子の想いを込めて付けた。フランス語の[La Poitrine] は女性の胸とか乳房だ。可愛い赤ん坊を、と言うより、仕事で疲れきった男をこの胸で抱きしめてあげたい気持ちを込めてこんな名前にしたのだ。オープンの日には、仙台に在住する名士や役人、それに親戚で店をやっている叔父も招いた。名士や役人の人選は全て千葉慎二がやってくれた。当面の運転資金や店舗の改装費、什器などを含めて資本金を三億円にして、加奈子は1%分株主になった。残りは慎二個人と仙北建設が出資した。
人とはげんきんなものだ。刑務所を出所して舞い戻った加奈子を冷たくあしらっていた親戚や友人達はオープンのパーティーに出席した叔父から噂が流れてたちまち加奈子に対する態度が変わった。綺麗にメイクしてドレスアップした加奈子の姿はかって六本木のクラブでトップレディを勤めていた雰囲気が蘇って、上品で美しい姿がフロアーの上を舞っていた。加奈子を知る叔父でさえも、驚くほどの美しさだった。
加奈子は地元出身の可愛らしいタレント、川野珠実に司会を依頼して、同じく地元出身の若者に人気のイケメンとヒップホップのキュートを呼んでオープンパーティーライブを企画したため、招待客の中から娘や息子を連れて行ってもいいかと問い合わせが続出、OKを出したものだから、来客は店を溢れんばかりで盛況になり、地元のメディアで取り上げられて、滑り出しは順調だった。
加奈子が店をオープンした少し前の六月三日に、猪俣章吾と藤井美登里は母親の反対を押し切って四谷の須賀神社で結婚式を挙げた。母の志津江は挙式直前に父親の章一に引き摺られるようにして入ってきた。それを見て、美登里はポロポロ涙が出てしまって、せっかくの化粧が崩れてしまった。
志津江は最初はぶすっとした顔をしていたが、式が進むにつれて気持ちが治まり、結局娘の美登里に押し切られてしまったことを認めざるを得なくなってしまった。
「もう、この子ったら、絶対に許さないからぁ」
とは言うものの、やはり一人娘の結婚式に感動させられていたのだ。いくら意地を張ってみても、娘の幸せを目前にして母親はその感動に勝てはしないのだ。
披露宴は近くの大きなホテルだったので、一同はマイクロバスで移動した。会場は広かったが、出席者は百五十名にもなり、おまけに池袋のロマンス通りの仲間たちの中のストリートミュージシャンが実演したため盛り上がった。沙希と善雄も招待されていて、沙希は複雑な気持ちで章吾と美登里を見ていた。
結婚式が終わると、美登里のたっての希望でハネムーンの行く先は夏の間は太陽が沈まないと言うフィンランドのラップランド地方だった。
ラップランド地方はフィンランドを中心に、スウェーデン、ノルウェー、ロシアにまたがる広い地域で、先住民族サーメがトナカイ放牧で育んできた文化を今も伝えている素的な所だ。緑の森ガールこと美登里がずっと行ってみたいと思っていた北欧に向かって、章吾と美登里は成田を飛び立って行った。
章吾と美登里の結婚式に出た時、沙希のお腹の赤ちゃんは随分大きく成長していた。丁度安定期で産科医は、
「普通に動いてもよろしい」
と許可を出していた。その話をすると、義母の美鈴も、
「そうよ、このごろの女の子は大事にし過ぎよ。わたしたちの頃は生活に余裕がなかったから、わたしだって善雄がお腹の中にいる間もお父さんの会社の仕事を手伝って忙しくしてたわよ」
と言った。
秋に男の子が誕生した。沙希はお産ってこんなに痛いのかと思ったが、聞いてみると人それぞれで、すっと産んでしまう人と、なかなか産まれなくて切開して産む人と、その中間の人が居るそうだった。沙希が一番最初に気にしたのは、やはり五体満足かと言うことだった。それで、赤ん坊の指を数えたり、足やちっちゃなオチンチンまで確かめた。それを既に出産を済ませたマリアに話すとマリアも同じ気持ちだったと聞いて、自分が異常でなくて安心した。
名前は善雄が考えて、沙希はもちろん、善太郎と美鈴にも同意してもらい決まった。善雄は沙希の[希]の字が気に入っていて、希世彦、つまり米村希世彦と決まった。分り易い[希善]と言う案も考えたと善雄は言ったが、義父の善太郎が希世彦を気に入った。
「希世はな、世の中でたぐいまれな、つまりすごく珍しいと言う意味だ。こいつが将来ノーベル賞でも取ってくれるかなぁ」
と笑った。
章吾と美登里は新婚旅行から戻って新しいアパートに引っ越した。おかしなもので、結婚にあれだけ反対して美登里を悲しませた母の志津江と伯母の八重が引越しの手伝いにやってきて、あれやこれやと世話をしてくれた。章吾は反対を押し切って美登里と結婚して良かったと思った。
「美登里、何か困ったことや変ったことがあったら母さんに言いなさいよ」
志津江が言うと、
「やはり血を分けた親子にはかなわないな」
と伯母が茶化した。
美登里は派遣の仕事を辞めて、専業主婦としてスタートした。一ヶ月が過ぎた頃、体調の異変に気付いて婦人科を訪ねると、
「おめでたですよ」
と言われた。どうやら北海道で愛し合ったときに章吾から授けてもらったみたいだった。美登里は嬉しくて嬉しくて、章吾の仕事先に電話をしてしまった。章吾は周囲に人が居たらしく、
「帰ってから改めて聞くよ」
と言って電話を切った。
美登里は章吾に初めて抱いてもらった北海道のウィンザーホテル洞爺で美登里が撮った写真アルバムを取り出してしばらくの間想い出にふけっていた。
六十三 新たな恐怖

「あなた!」
「はい」
突然睨まれて、加奈子は緊張した。
「ちょっと、こっちにいらっしゃいっ!」
千葉真砂子は有無を言わせぬ鋭い目付きで加奈子を事務室に来いと命じた。真砂子が事務室に入ると、
「邪魔だ」
と言わんばかりに鋭い目で新人の女の子を睨んだ。事務に雇った女の子は怯えたように事務室を飛び出した。
「あなた、慎二をつまみ食いしたら、わたしは許しませんからね。あんたをここから摘まみ出すなんて、わたしにはどうってことはありませんからね。そのつもりで居て下さいな。分ったっ?」
「はい。分りました」
加奈子は真砂子の凄まじい剣幕に一瞬縮み上がって、身体が固まってしまった。加奈子は今までの経験で、男の剣幕を上手く交わして鎮める術は心得ていたが女は苦手だった。
千葉真砂子はクラブ、ラ・ポワトリーヌのオープニングパーティーで慎二から、
「オレの家内だ」
と加奈子に紹介された時には周囲に来賓が大勢居たせいか、にこやかな顔で会釈した。
パーティーが終わって、加奈子は社員を総動員して掃除と後片付けを終わってほっとした時、先ほどとは打って変って、阿修羅のような顔つきで加奈子を事務室に呼び込んだのだ。
千葉真砂子の旧姓は丹野で、先祖は伊達政宗の時代に仙台藩高柳の大肝煎として勢力を伸ばし、終戦後の土地改革を乗り切って、仙台の東北部一帯の大地主として君臨していた。土地ブームで地価が高騰した時に宅地指定部分を大量に手放し、売却後金融資産を上手く運用して、真砂子の実家は大金持ちとして知られていた。
千葉慎二が家業を伸ばすために市の建設局に食い込む時に上級の役人を接待漬けにしたが、その工作資金は真砂子の持参金から捻出したと言われていた。そのため、慎二は嫁さんの真砂子にだけは頭が上がらなかったのだ。
昔、関東以西で庄屋と呼ばれた家は、関東以北、東北地方では肝煎と呼ばれていた。仙台藩の大肝煎は代官の下の位で年貢の取立てなどで実権を持っていたそうだが真砂子の実家は実在する丹野家とは関係がない。
真砂子は四十歳前後で加奈子より一回りくらい年上に見えた。慎二と同様に身体が大きく、どつかれたら細身の加奈子なぞ一撃ですっ飛ばされそうな感じだ。啖呵の切り方からして、恐らく小学校から高校あたりまでは女番町として大勢の子分を従えていたと思われた。加奈子はこんな毒蛇のようなババアに巻きつかれて身体を締め付けられたら自分なぞ一たまりも無く絞り上げられてしまいそうに思えて体が竦んだ。
加奈子が慎二に恋をして、既に身体の関係になっていることは真砂子にはバレてはいないと思われたが、女の感の恐ろしさは自分でも分かっていた。それで、加奈子は咄嗟に真砂子の前で土下座して、
「ご主人のことはよく胸にしまっておきます。これからもどうぞよろしくお願いします」
とようやく気持ちを改めて挨拶をした。加奈子は咄嗟に考えた。このババアの子分にしてもらったら、案外慎二を御し易くなると思ったのだ。だから、これからは時々真砂子のご機嫌伺いに参上して上手く真砂子に取り入ろうと思ったのだ。
加奈子が立ち上げた会社は[株式会社カナ・プロダクション]だった。オープニングパーティーで若手のアーティストを呼んだのは将来への布石だ。加奈子は昼間クラブを営業していない時間帯に若手のアーティストにライブスタジオとして提供して、若手アーティストの発掘をしたいと目論んでいた。この話を聞いて慎二は、
「一頃はな、エイベックスも浜崎あゆのブームで稼いでいたが、エグザイル以降稼ぎの中心が減って業績は低迷して、株価なんかもピーク時の半分以下、業績は右肩下がりだぜ。似た会社のアミューズもサザンの桑田佳祐や福山雅治以降稼ぐアーティストが出なくて業績が低迷してるんだ。株価なんかもピーク時の半分くらいに落ち込んでるよ。難しい業界だぞ。それを承知でやるならいいが」
とあまり乗り気ではなかった。だが、オープニングパーティーの盛況を見て、渋々同意してくれた。それで、加奈子はこの部門のスタッフとして川野珠実を誘った。
「川野さん、片手間でいいわよ。当面興行収入はなくてもいいの。遠い将来を見つめて若い素的な子をご一緒に発掘してみない」
彼女は一九九五年生まれで加奈子より十歳年下だった。
川野はフリーのタレントだったので、加奈子の誘いに気持ちよく応じてくれた。
この時から、加奈子にはクラブ・ラ・ポワトリーヌの経営者の顔に、ライブスタジオの経営者の顔が増えた。
加奈子は真砂子に脅かされて以来、慎二を恋する気持ちを抑えるのに苦労していた。慎二に誘われても、心の中では怯える気持ちが広がって、なかなか本気にはなれないのだ。性とは不思議なものだ。本気になれない自分が慎二と交わっても最初の時のように頭の中が真っ白になるほど燃え上がることはできなかった。
順風満帆でクラブ、ラ・ポワトリーヌをスタートさせたのだが、真砂子の影に怯える気持ちがあって、加奈子は憂鬱な日々を過ごしていた。
「人生って難しいな」
最近加奈子は一日の疲れをお風呂で癒している時、時々こんな風に独りで呟くのだった。
六十四 北欧旅行
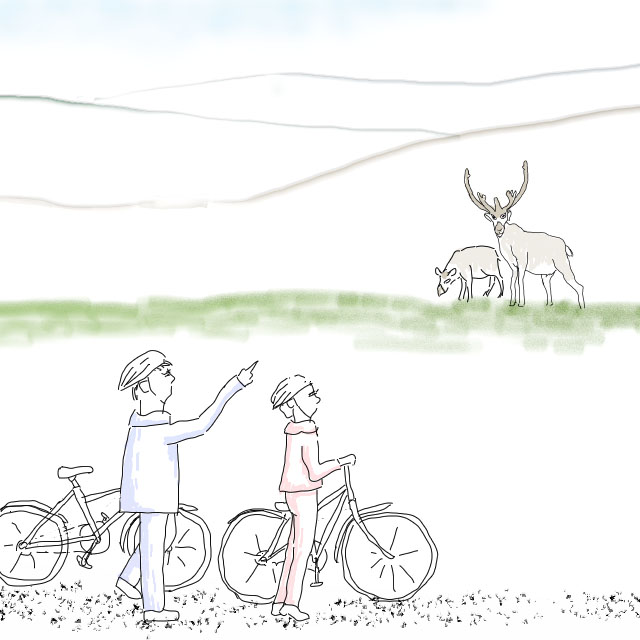
「新婚旅行だけど、美登里は北欧の森と湖の自然の中に浸りたいとか言ってたよな」
「そう。あたし、緑の森ガールってあだ名だから」
美登里はマジにそう思っていた。
「普通北欧って言うとデンマーク、スウェーデン、フィンランド、ノルウェーの四カ国を言うそうだけど、十日位じゃ全部回ると毎日飛び歩いているみたいで余裕がねぇよ」
「それは分ってる。なので、あたしはサンタクロースとムーミンの里がいいなと思ってるんだ」
「それだったらフィンランドだな。フィンランドだけでも広いから北の方のラップランド中心でプランを立ててもいいか?」
「いいよ。そうしてちょうだい」
章吾と美登里は六月三日の結婚式を前にして行く先の相談をしていた。
「引越しもあるし、六月十七日の日曜日~二十七日でどうかなぁ」
「そうね。バタバタするし、それがいいよ。あたし北海道で初体験させてもらったから、旅行はずれてもいいよ」
そう言って美登里は自分の顔が少し赤くなったと感じていた。
章吾は赤坂にある旅行代理店で相談した。都合の良いことに、北欧に詳しい若い女性が応対してくれて、ホテルや予約の必要な乗り物は全部予約を取ってくれた。その結果、
成田→航空機→首都ヘルシンキ
ヘルシンキ⇆鉄道⇆バス⇆ヌークシオ国立公園(往復)
(ヘルシンキに二泊)
ヘルシンキ⇆鉄道⇆トゥルク⇆バス⇆ナーンタリ⇆ムーミンワールド
(ナーンタリに一泊)
ナーンタリ→鉄道→ヘルシンキ→航空機→ ロヴァニエミ⇆サンタクロース村(ロヴァニエミに一泊)
ロヴァニエミ→バス→サーリセルカ⇆ウル ホ・ケッコネン国立公園
サーリセルカ⇆バス⇆イナリ⇆サーミ博物館
(サーリセルカに三泊)
サーリセルカ→航空機→ヘルシンキ→航空機→オスロ(ノルウェイ)
フィヨルド・ツアー(遊覧船)
(オスロに一泊)
オスロ→航空機→コペンハーゲン(デンマ ーク)
ワンデーツアー
(コペンハーゲンに一泊)
コペンハーゲン→航空機→成田
「これで、約十日間の旅行を楽しめます。北欧の森と湖を満喫したい奥様にきっとお喜びいただけると思います。ラップランド地方は六月だとまだ雪が残っている所もありますから、お気を付けて行ってらっしゃいませ」
応対してくれた女性は自信のある口ぶりだった。章吾は、
「ありがとうございました」
と礼を述べて旅行代理店を出た。
「これでどうだ?」
「あたし、分んないから章吾のあとをついて行く」
美登里は全部章吾にお任せのつもりでいるらしい。
「美登里は外国語、ダメなんだろ?」
「全然ダメ」
「オレ、英語を少ししか出来ねぇから聞いてみたんだ。そうしたら、フィンランドは大抵英語で大丈夫だってさ。助かったよ」
「そう、良かったぁ。旅して言葉通じなかったら最低だよね」
結婚式が終り、新居への引越しも終わって落ち着いた所で、章吾と美登里はフィンランド航空のヘルシンキ直行便で成田を飛び立って行った。
ヘルシンキの空港に着くと、空港バスで市内に出た。高層ビルは殆ど無く、街中はゆったりとして余裕のある雰囲気だった。港湾都市らしく、ホテルの前は運河のようになっていた。ヘルシンキ市内に着いた時は五時近くだったので、その日はホテルでゆっくりした。
最初の予定はヌークシオ国立公園だ。ヘルシンキから約35kmも離れている。それで、翌朝早めにホテルを出て、タクシーでヘルシンキ中央駅に向かった。そこから電車に乗って、エスポー駅で降りて、バスで公園に向かった。公園はメッチャ広く、思った通り木々と水が綺麗で、最初から美登里は感激の溜め息続きだ。夕方ホテルに戻ると、同じホテルにもう一泊した。
翌朝もヘルシンキ中央駅に向かった。ここから沢山の列車が出ている。
鉄道でトゥルクと言う町に行って、そこから更にバスに乗ってナーンタリと言う町に入った。この町の近くの小さな島全体がムーミンのテーマパークになっているのだ。
ムーミン谷その他物語の舞台が絵本で見た感じで作られていて、美登里は嬉しそうに回った。
ナータリからバスでトゥルクに戻るとホテルで一泊した。ゆったりとした部屋の雰囲気はとても良かった。美登里はようやく旅に慣れてきたとみえて、夜は章吾のベッドに潜り込んできた。静かな夜更けまで、二人は身体を絡ませて愛し合った。
翌日は電車で一旦ヘルシンキに出て、空港バスで空港に向かった。空港からそのまま国内線の飛行機でロヴァニエミに飛んだ。距離は東京から大阪くらいの感じなので、鉄道ではまる一日潰れてしまうので飛行機にした。大分北の方なので、ホテルの前にはまだ少し残雪が残っていた。
ホテルは贅沢ではなかったが、清潔で気持ちの良い部屋だった。ロヴァニエミはラップランドの中心都市で賑やかではないが、街らしい感じだった。午後、美登里が希望したサンタクロース村に行った。ちゃんとサンタの家があって、髯をはやしたサンタの爺さんに会えて美登里は感激していた。
翌日バスでサーリセルカと言う町に向かった。途中の道は森の中や小さな湖の畔を通るので、バス旅行も楽しい。着いた日はホテルでのんびりして、翌日ウルホ・ケッコネン国立公園に入った。だだっ広い公園でなので、貸し自転車を借りて章吾と美登里は仲良く公園の中を走り回った。とても一日で走り回れるような広さじゃない。一部分を走っただけだったが、途中トナカイに出会ったりして、楽しい一日を過ごせた。
このあたりは夏は一日太陽が沈まない。冬に来ればオーロラが空一面に見えるとホテルで教えてくれた。
サーリセルカの最後の日はサーリセルカより更に70kmほど北の町イナリにバスで行ってサーミ博物館を見学した。ラップランド地方はノルウェイ、フィンランド、ロシアにまたがる広い地域で、昔からこの地に住んでいるサーメ人文化が伝わっていて、サーミ博物館でその文化を紹介しているのだ。ラップランドの民族衣装は日本のアイヌの衣装が独特なのと同じで橙がかった朱色や濃い青をあしらった独特の模様の民族衣装だ。
翌日二人は自転車で回ったウルホ・ケッコネン国立公園の素晴らしい森と湖の景色を目に焼き付けて、サーリセルカの空港からヘルシンキに飛行機で戻って、別の飛行機に乗り継いで、ノルウェイの首都オスロに飛んだ。
美登里はムーミングッズやトナカイ人形、キッチン手袋など色々な小物のおみやげをどっさり買い込んだ。
オスロに一晩泊まると翌日午前中二時間ほど遊覧船でフィヨルドツアーをした。綺麗な海岸線は学生時代に写真で見たよりも実物の方がずっと素晴らしかった。午後は飛行機に乗って、デンマークの首都コペンハーゲンに向かった。
「あ~ぁっ、もう終わっちゃった。もっとゆっくりとしたいな」
あっと言う間に旅の終わりに近付いて、美登里は残念そうな顔をしていた。
オスロもコペンハーゲンも大きな街でホテルは都会的だが良かった。
コペンハーゲンでワンデーツアーをしてから、夕方スカンジナビア航空の成田直行便に乗って成田に戻ってきた。六月末の梅雨時で蒸し暑く、昨日まで居た北欧の気候とは大違いだ。
成田に着いて入国手続きを済ますと、美登里はどっと疲れが出たらしく、元気がなくなった。
「このまま池袋に帰る元気あるのか」
「なんだか熱っぽいな。あたし」
それで大事を取って成田空港近くのホテルに一泊することにした。美登里は夕飯が食えないほどで、どうやら本当に熱が出てしまったようだ。章吾はホテルのフロントに話をすると、間もなく医者が診察に来てくれた。熱は38度5分もあった。医者は、
「風邪と疲れが重なったのかも知れませんね」
と言って解熱薬を注射して帰って行った。
翌朝、美登里は元の笑顔に戻って、章吾はやれやれと一息ついた。注射のお陰で熱が下がったようだ。
「章吾、ごめんね」
美登里はちゃんと朝食が食べられるようになったので、バスで新宿まで戻った。新宿からタクシーでアパートに戻った時には美登里はすっかり元気になって、母親の志津江に電話をして、
「お母さん、ただいま。すっごく良かったよ」
などと報告している。章吾はどうやら母親も自分達をすっかり許してくれたらしいと感じてほっとした。
「日曜日に母と四谷の伯母がこっちに来るってよ。あたし、日曜日にロマンス通りの仲間におみやげを配ろうと思ってたのに予定が狂っちゃったわ」
美登里はそんなことまで言った。章吾はそんな美登里を可愛い奴だと思っていた。
六十五 銅・コバルト鉱山
沙希の義理の父親だった浜田と浜田が溜め込んだ多額の借金の取り立て屋だった野口は沙希と米村一家を恐喝した仕返しに六本木のクラブ、ラ・フォセットの社長柳川の指示で、中国人が経営する、遠いアフリカのザンビア国の奥地の銅・コバルト鉱山に奴隷として送り込まれ、両足を鎖でつながれて、毎日過酷な労働を強いられていた。
あれから何年経っただろう? カレンダーって物がないから、浜田は日月の経過が分らなくなっていた。
野口は浜田に張り付いて浜田から借金を取り立てていた頃は、でっぷり太っていい体をしていた。だが、この鉱山に送り込まれてから、毎晩のようにキャブヒッツと呼ばれている黒人の頭に呼び付けられて、おかまよろしく頭と子分の性の捌け口として玩具にされていた。だがその男野口も今は居なくなっていた。
この鉱山に送り込まれてから、浜田は日本人グループの隅で小さくなって、できるだけ目立たないようにしていたが、二千人以上も居るこの集団の中にはいくつかの島と組織が出来上がっていることが次第に分ってきた。言葉の壁があって、組織は自然に人種で別れていた。浜田が属するようになった日本人グループの頭は織田信長と自称していて、約百五十人の日本人と韓国人と何人かの中国人の仲間達を統率していた。野口は鉱山に送り込まれた最初の日に約四百人を率いるキャブヒッツに捕まってしまったので、浜田が居るグループでなくてキャブヒッツの黒人グループに入れられてしまっていた。
月に一回位ふるまわれる酒の分配、グループの子分間の揉め事、三度のメシの分配、事故や疫病で死んだ奴の届出などはグループの頭が取り仕切っていた。だが子分どうしは人種の壁を越えて付き合うことは許されていた。
野口はキャブヒッツたちに玩具にされたケツの穴(肛門)の周囲が腫れ上がり排泄をする時は毎度痛みで涙を流していた。そんなだから、でっぷり太っていた体は痩せこけて、すっかり人が変ってしまって怯えた日々を続けていた。一年も経った時に、いつの間にか移されたHIVが原因で化膿したケツの周囲の傷が治らず、ある日寝たまま冷たくなっていた。それで野口の体は隣の谷に投げ捨てられて鳥や獣の餌になってしまっていた。野口は鉱山の奴隷として儚い一生を閉じたのだ。
浜田は組織に上手く順応して生き延びていた。機会を見ては韓国人や中国人、英語を話す黒人や白人などと接触して、もっぱら言葉を覚える努力をした。ザンビアの公用語は英語だが、脱走を監視したり、鉱山の周辺を警戒している傭兵たちの多くはザンビア人で、Bemba語、kaonde語、Lozi語、Lunda語など人により違った言葉で話をしていた。浜田はそんな彼等の会話の内容も知りたくて、機会を見て覚えるように努めた。五年も経つと、いつの間にか浜田は片言だが色々な言葉で話が出来るようになっていた。
鉱山の奴隷の集団には表立って七つのグループがあることも分った。グループ毎に頭が居て、そいつ等の名前も覚えた。
だが、表立ったグループの他にもう一つ地下組織ができているのを最近知った。浜田にはその組織の目的は分らなかったが、概して大人しい目立たない者たちが多いようだった。良く観察すると、地下組織に属している者の多くは格闘技でもやっていたらしく筋肉が引き締まって敏捷な動作をする者が多いことも分った。
ある日、地下組織に属すると思われる数名の者が、宵闇に紛れて警備に当たっている傭兵を奇襲して密かに殺害して、傭兵たちが常時持ち歩いているM4カービン(フルオートカービン銃)と銃弾を奪って、金鉱の中の小さなほら穴の中に奪った武器を隠しているのを目撃した。
彼等の手口は用意周到だった。鉱山で使う道具を密かに改造して鈍器として使用、傭兵が一人で行動している時を狙って、暗闇から突然傭兵に襲い掛かり、口を塞いでから鈍器で殴りつけて倒した。死体は鉱山に引き摺っていき、予め掘ってあった穴に投げ込んで埋めてしまった。攻撃は夜間警備兵が手薄になり、必ず霧が出て視界が悪くなっている時に実行された。
どうやらそのことは浜田だけではなく、何人かの奴隷仲間が知っている様子だったが、誰も口にはせず、見ていないふりを装っていた。
浜田が信頼できると思っている仲間にその話をすると、数年前からたまに同様の事件があったと話してくれた。
傭兵は一応点呼をしている様子だが、脱走する傭兵も居て一人や二人突然に消えても問題にはされていない様子だった。
そんなことがあって、浜田は密かに調べてみた所、浜田がこの鉱山に来る数年前から今までに少なくとも三十名以上の傭兵が殺害されている模様であった。つまり、フルオートカービンが銃弾と共に三十丁以上密かに隠されている計算になるのだ。一体彼等は銃を何に使うんだろう? 浜田は次第に好奇心が湧いて来た。彼等の奇襲行動は十年間も続けられている計算になるのだが、年間に数件、警備兵には全く知られずに着々と行われてきた様子だ。いつ死んでもおかしくない奴隷生活の中では実に気長な話だ。
浜田が長い日にちをかけて、やっと調べた状況によると、地下組織に属している奴隷は、ここに送り込まれる前は世界各地のテロ集団に属しており、いずれもテロ攻撃の訓練を受けていた者が多いことが分かった。その中にはもちろん現在世界を震撼させているアルカイダの訓練組織に居た者も居るらしいことが分かった。彼等は長い長い歳月をかけて、密かに準備を進めている様子であった。
地下組織の行動について浜田が密かに調べていることは地下組織のメンバーにバレてしまった。だが、浜田はそのこと、つまり自分の行動がバレてしまっていることに気付いていなかった。
雨の降るうっとしい日に、晩飯を食ってくつろいでいる浜田の前に、突然英語で声をかける奴が居た。
「ちょっと来てくれ」
「オレにか?」
「そうだ。お前だ」
「ちょっと待ってくれ、頭に断ってくる」
「ダメだ」
「頭の許可がなくちゃ、ここを動けねぇ」
「分った。断って来い」
浜田は織田信長の所に行くと、
「あそこに立ってる白人に突然来いと言われたんですが、行ってもいいですか」
信長は立っている男を良く見てから、
「行ってもいいぞ」
と許可した。
「おいっ、明智光秀をここに呼んでくれ」
信長は近くに居た子分に命じた。間もなく光秀と呼ばれている男が信長の前にやってきた。
「何か用ですか」
「バカもん、用があるから呼んだんだ」
「はっ」
「あそこに浜田ってやろうが居るだろ」
「はい」
「あの野郎、地下組織のジョンに呼び出されたようだ。多分何かやらかしたんだろうと思うがな、浜田が殺られるようだったら助けてやれ。念のため部下を二人か三人連れて行け」
「承知」
光秀と家来の三人は浜田とジョンのあとをつけた。浜田は鉱山の物陰に連れ込まれた。
「あんた、オレたちのことを色々調べているだろ? 誰の指図だ?」
「何のことかさっぱり分らん」
浜田とジョンは英語で話をしていた。今では浜田も片言だが話はできた。
「ウソを言うな」
突然ジョンは片言の日本語で応じた。これには浜田も驚いた。
「正直に言わないとあんたを殺す」
浜田はやっとジョンの話しが真剣だと分った。
だが、浜田はジョンを甘く見ていた。のらくらと話を逸らすと、突然ジョンのパンチが浜田の鳩尾に炸裂した。
「うううっ」
浜田は息苦しくて腰を折った。そこにジョンの手刀が浜田の首を目掛けて振り下ろされようとした。その時、
「待てっ!」
と後方で声がした。光秀だ。
「おお、光秀」
「そいつの始末はオレが預かる。解放してくれ」
「信長の命令か?」
「そうだ」
「オレたちのことをこいつに調べろと命じたのは信長か?」
「いや、それにはオレたちの組織は無関係だ。浜田って野郎を殺してもらっちゃ困るだけだ」
「こいつはオレたちの組織のことを嗅ぎ回っていたんだ。だからこいつの口を封じろと命令されている」
「分った。今後あんたたちの組織に絶対に迷惑をかけさせないことを約束する」
「今回限りだぞ。今後また嗅ぎ回ったら、その時は浜田を殺す」
「承知」
「おいっ、浜田を担いで信長の所に運んでくれ」
家来の二人は浜田をかついで信長の所に戻った。
「頭、ご迷惑をおかけしました」
「お前なぁ、今度嗅ぎ回ったらオレたちの組織は守ってやらねぇ。分ったか? 何を調べたか知らんが、今後一切口外するなよ」
「はい。すみませんでした」
それで、浜田は命拾いしたのだ。
あれは忘れもしない霧の深い夜だった。タタタタタッ! 突然の銃声に起こされた。浜田は何が起こったのか一瞬分らなかったが、良く見ると外で奴隷仲間と警備兵の間で銃撃戦が繰り広げられていた。
三十分もすると、銃声は治まってあたりが静かになった。すると、足枷の鎖を外された奴隷が数百人、ぞろぞろと鉱山事務所の方に向かっていた。どうやら事務所も制圧されたらしく、ジープやトラックでどんどんと逃げていく奴隷たちが見えた。
「おいっ、オレたちのグループは何もするなっ!」
信長が大声で怒鳴るのが聞こえた。信長の命令でグループ全員はまた眠りに就いた。
それから一時間もしただろうか、また辺りが騒然となった。近くの警備兵の駐屯地から大勢の警備兵が現われて、徒歩で逃げまどう奴隷たちを片っ端から銃殺するのが霧の中のボーとした外灯の明かりに映し出されていた。地獄の中の修羅場だ。次々と銃殺される奴隷の断末魔のような叫びが夜空に響いていた。
しばらくすると数名の警備兵が浜田たちが寝ている部屋に入ってきた。皆静かに寝ているのを確かめると、
「こちらは良しっ」
と言う声がして、警備兵が出て行った。
翌朝分ったことだが、地下組織に属していた奴隷の大半は奪ったトラックやジープに分乗して逃げたらしい。解放された残りの奴隷約五百人は全て銃殺されてしまったらしいことも分った。
そのことがあってから、鉱山の機械化が進められた。バカでかい鉱山用のパワーショベルや300トン以上も積載できる超大型のダンプなどが導入された。
浜田は日本に居る間に臨時雇いで工事現場でフォークリフトやブルドーザー、パワーシャベルや20トンの大型ダンプを運転した経験があった。ここでは免許証なぞは不要だ。運転できさえすれば足枷の鎖を解かれて運転手として使ってもらえた。それで浜田は志願して運転手になった。
今まで手作業だった労働が機械化されると、組織の中の力関係が微妙に変ってきた。重機の運転に慣れた浜田は相対的に仲間に尊敬されるようになり、織田信長グループの幹部に昇進した。
ある日、浜田は地下組織が隠していた武器のある所をパワーシャベルで掘り返してみた。だが、そこには既に何も残されていなかった。全てあの霧が深かった夜に持ち出されて使われたようだった。
重機を扱う浜田は事務所の監視人とも次第に親しくなれた。そんなある日、
「一週間か十日間ほど休暇をもらって日本に帰りたいが許可はもらえるか」
と尋ねた。
「国に帰って直ぐ戻る保証があればな」
「どんな保証だ?」
「そりゃ、色々あるさ」
どうやら話の内容によっちゃ、日本に一時帰国できそうな感じだった。それで、浜田は米村工機を強請って二十億円位せしめる計画を立て始めた。
負けないでっ 【第一巻】
あとがきは全文アップしてから書きます。悪しからず。


