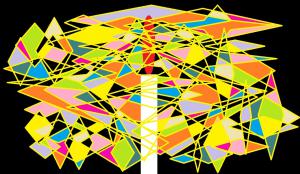En( )
初めまして、鋏といいます。この作品は、私が音楽制作をする際に出来たスキマの時間(ちょびっと)を使って書いたお話です。本当にすこーしずつ書いています。なので所々クオリティが上がったり下がったりしたり、やっぱり序盤の出来が酷いです。でも読んでほしい。そんな感じです。
Prelude
——そういえば。
自分自身を自分だと気が付き、認識したのは果たして一体いつからだっただろうか。もしくは、この記憶が始まったのは。
——この記憶が記録され始めたのは。
一体いつからだっただろうか。物心がつく事とはまた違う、思い出せる限界の過去。自身の最古の記憶とは。
霧の様な、砂嵐の様な。遠くにぼんやりと見る事ができる。両親が横にいて、どこかに出かけている時の記憶。それは現実にあった出来事ではなく、ただの夢や妄想かもしれない。
だがもし仮にそれが夢だとしたら、その夢を形作るだけの記憶は、一体どこから来たのか。
これは憶測に過ぎないがもしかすると自分の頭の中には、記憶として存在するが、自分が認識出来ていない記憶があるのかもしれない。
高校時代の葛藤。中学時代の告白。小学時代は朧げだ。あぁ、保育園時代は更に断片的に。おそらく、5歳くらいなのだろう。それこそが、記憶の始まり。
そうだ、保育園なのだ。「おれ」が始まっていたのは。おそらく当時の一人称は自分の名前だっただろうし、会話だって自分の記憶から予想した殆ど妄想の様なものだ。
あの天国の様な場所での地獄の様な出来事達はおそらく、おれという一人間の核に、何かしらの種を植え付けたのだ。そしてその種から生まれたのは、巨大で、強大な、悪魔的に凶悪な怪物であり、そしてそれは、おれに生涯をかけて取り憑き、ずっと戦い続ける事になる相手なのである。そんな怪物の種が、風に乗って運ばれて来た場所。おれに根を張った場所。
あの場所をそんな風に言い表してしまうのは何だか失礼な気がするが、もしかするとおれでなくとも。そこでなくとも、誰であっても、どこでも、平等に種は存在していて、おれはその一つを、芽吹かせた。芽吹かせてしまっただけなのかもしれない。
少なくとも、あの怪物の存在に気が付いてしまう人はいるかもしれない。あの時、周りに同じ様な事を考えている人がいたならどんなに楽な気持ちだっただろうか。所詮保育園児にそんな事を期待するのは甚だ間違いだろうが。そもそもおれはその時怪物を自覚していないのだ。目覚めるまでは。だからどうしようもなかったのだ。ただ、少しずつ惹かれていった。それだけの話。それが,
保育園の話。
ここに来るまでにたくさんの出来事があった。計り知れない、出会い、別れ、分岐点、事件、闘い、祝福、葛藤、快感、苦痛、後悔、悲哀、怠惰、憤怒、感謝、失敗、成功。その始まりだ。おそらくそこからがスタートなのだ。開始地点なのだ。きっと。そこから語ろう。おれの過去を。おれの出会った出来事達を。おれが見た現実を。そして、思い出す時が来たのだ。この身が、何でできているのか。自分自身を形成するもの達を知る為に。
これから成そうとしている事の為に。
そう、これは反省なのだ。全てを円で繋げる為の。
蒲公英
1
「おーい、ジョーン!!」
5才の頃、おれは親戚一同にいつも心配されるほど危なっかしい、実に元気な男子児童だった。・・・らしい。木登りが得意。落ち着きがない。おそらく親にとっては何をしでかすか分かったものではない。そんな子供だったとも言われた。
因みに当時の自分のあだ名はジョンだった。何とも保育園児らしからぬあだ名だ。確か、母方の実家で飼われていた、これまた落ち着きのない大きなゴールデンレトリバー、ジョンのモノマネをしたら大ウケしたのがきっかけ。だったような気がする。確か。多分。それでジョンと瓜二つ。
だからジョン。
なんとも安易な理由だ。と、そう思うかもしれないが。いや、そんなものなのだろう。5才児の基準というのは。恐ろしい程に安易であり、それでいて恐ろしい程に鋭い。そして恐ろしい程に彼らは無自覚なのだ。そしてその恐ろしい程無自覚の内におれは「それ」を始めてしまったのだった。
「三輪車で遊ぼうぜー!!」
当時、保育園には恐らく全園児待望であろう、新しい三輪車が導入されたばかりだった。勿論園児達からは大人気で、乗る事が出来るのはごく少数の運の良い園児だけで、ここは年上の年長組が優先的に乗れる、とは勿論いかず。保育園児達に年上を敬う習慣なんてものはあるはずもなく。毎日のように三輪車に乗りたい園児達による、三輪車の取り合いが毎日の様に繰り広げられていたのである。
そして3日程前に念願の新品三輪車を手に入れ(独り占めにして爆走していたところ、先生に「乗れなくて泣いている子がいるんだから交代しなさい」と強制終了させられたのだった)、ほとんど三輪車に乗る事に魅力を感じなくなっていたおれはというと、その日は大人しく建物の傍の小さな芝生の土手にうつ伏せに寝転がって、カエルを観察していた。土手の下には、控えめなグラウンドが広がっていて、可愛らしい阿鼻叫喚の世界を作り出している。そんな梅雨明けの午後。お昼休みにて。
「ねぇジョン!!早く三輪車取りに行こう?乗れなくなっちゃうよ。」
先程からうるさい声でしつこくおれを呼んでいるのは、坊主頭で短パン、派手なタンクトップと、まるで風貌は「田舎のヤンチャ坊主」だが、着ているタンクトップがなんとも絶妙に可愛いデザインなのでそこは微妙な感じの、やたらとテンションが高い男児。
「隊長ー、おれもう乗りたくなくなっちゃったんだよ。なんかよくわかんないけど、もう乗らなくてもいいんだ。」
あだ名は「隊長」。常におれという部下を所構わず一日中引きずり回そうとする悪い隊長である。因みに友達は沢山いるがこんな扱いをするのはおれしかいない。何故だ。
「ハァ!?だってジョンこの間ちょっと乗っただけじゃん!!まだ今から行けばもう一回乗れるかもよ?」
そんなに乗りたいならここにいたら乗れなくなるぞ。それに三輪車がある倉庫はグラウンドの向こう側、土手とは反対方向だ。
「今日はここで遊ぶの!」
なかなかの頑固さに隊長は、
「ちぇー、わかったよ。」
案外あっさりと切り替えて土手に寝転ぶ。ここはさすが保育園児。気の変わりようが神がかっている。これに何度大人達が振り回されていった事だろうか。気の毒な話である。
5日程前に気象庁から梅雨明けが発表された夏の入り口。そんな季節での晴れの昼下がりに、土手でカエルと戯れて寝転がる草まみれの男児二人。やってくる夏本番を前に、小さなカエルはおれの頭の上で汗を流していた。
2
当時のおれは、隊長とのやりとりを見れば分かる通り、自分のしたい事に興味が一番に、すごい勢いで向いたのである。よくある事かもしれないが。しかもそれはコロコロ変わる。一度スイッチが入ると、止まらなくなる。現に今もグラウンドの隅のサルスベリに隊長と登って二人で先生に怒られていた。登頂には成功していたから悪い気はしない。隊長は滑り落ちてリタイアしていた。
再びふらふらとさっきの土手に戻り、土手にうつ伏せになって顔を思い切り芝生に押し付け、顔いっぱいに芝生の爽やかな香りを優雅に楽しんでいた時である。不意にグラウンドを眺めていた隊長が、ある事に気が付いたのである。不意に、不穏な、こんな質問を飛ばしてくる。
「ねぇ、大将がどこにもいないぞ!いつもはグラウンドで独占した三輪車乗り回してるのに。どこいったんだろ?」
「え?三輪車乗ってるでしょ?」
「いや、いないよ。見てみろよ!」
言われてグラウンドを見渡してみる。―――なるほど確かに。いつもは友達数人を、いやあの感じは取り巻きだろうか。とにかくそいつらを連れて三輪車で大暴れしているはずなのだが。今日は休みではないはずだ。今朝、保育園に来たときにいの一番におれの所に来て頭をひっぱたいていったのだから。痛かった。
大将とは、ガッチリしたこってり系の体型、周りより少し大きめの身長をした、そのまんまガキ大将からとっての「大将」である。しかしこの大将、世間一般によく言うガキ大将の5倍くらいは悪いんじゃないかと思う様な極悪ガキ大将である。弱い者虐めは最早呼吸と同じ人体のサイクルの一つと化しているし、彼にとって先生との約束事は破るために存在している様なものだし、よく人の物を壊しては馬鹿笑いしている。そういう理由で、おれは大将が嫌いだった。大嫌いだった。
―――今朝おれの頭を叩いていった事でさらに嫌いになった。
おれは根に持つタイプであった。激しく。
また何か見えない所で悪い事でもで企んでいるのだろうか。これまでも、そんな所を何度か目撃したことがあった。その度に見つかって口封じに叩かれたが。
しかし本当は大将は拳のコミュニケーションでしかものを語れないのではないだろうか。そのくらい、言葉より先に黄金の右手が飛んでくる。あいつはきっと戦いの中で生きていくと決めているのだろう。孤高な戦士のそれだった。
今回こそは、大将の悪巧みを阻止してやりたい。見つけて先生に報告してしまおう。あいつは気にもしないかもしれないが、取り巻きは大人しくなるだろうし、先生も対策はしてくれるだろう。止める事は出来ないが。今回は何をするつもりなのだろうか。クラスの男児全員のヒロイン。ゆいちゃんのスカートめくりだったら許さん。
断じて。
兎に角、おれは猛烈にあいつの邪魔をしてやりたくなったのである。必ず捜し出して、あいつに少しでも噛み付いてやりたかった。小さな、なんとも人間的にも小さな「復讐」。おれは隊長と一緒に、大将を捜し始めたのである。こそこそと。
その時大将の取り巻きたちが、三輪車で近くを走り去っていくのに気が付いていたなら。この後の出来事は、何か変わったのかもしれない。
3
「・・・いないぞ!!」
これで何人目だろうか。皆が口を揃えて「見ていない」「グラウンドにはいない」「きっと建物の中だ」「いや帰ったのかも」「それよりゆいちゃんがいない」、手がかりの一つも見つける事が出来ない。大きな身体のくせに隠れるのは得意な奴のようだ。グラウンドは全て捜して回ったはずなのだが。ドーム型遊具の中、倉庫の中、建物内まで捜したが、お昼休み中に大将を見つける事は出来なかったのであった。
その日の夕方、お迎えの時間。園児達は室内それぞれの場所で、遊んだり、おしゃべりしたりして親の迎えを待っている。賑やかな時間。
大将が取り巻きといるのを隊長と確認する。やはり今日は保育園に来ていた。
「一体どこにいたんだ?」
「外に出てたのかな?」
しかし全く見当がつかない。他に探していない場所などあっただろうか。一体全体何処で何をしていたというのか。なんだか頭が混乱してきた。今日はもうやめよう。まだ今日は木曜日だ休みまでにまだあと一日ある。明日また、大将はどこかに行くかもしれない。その時にこっちもまた捜せばいい。しかし、
―――何故自分はこんなに、捜す事に執着しているのだろうか。
こんな感じのニュアンスで、当時のおれは思ったのであった。
「おい、さっきからなんで俺の事チラチラ見てんだよ!」
しまった。
「え?いやあ、何でもないよ?なあジョン?」
大将に、
「うんうん(笑)大将の後ろの奴見てただけだよ(笑)」
気付かれた。
「後ろは壁だろうが!!」
「いだァ!!」
左脇腹に突き刺さる、強烈な右フック。腹の中が、さっき食べたおやつごと、揺さぶられる。脇腹をおさえ、膝を付いて、馬の体勢。相変わらずいいパンチだ。馬のまま、薄暗い廊下へ逃げる。すぐに両足を掴まれ、部屋の中へと引きずり込まれる。尻を蹴られた。蹴られた所が熱い。今日はもう二人共、いい加減いつもの調子に戻った方がいい。大将は標的を隊長に切り替えたようだ。早く。早く迎えに来てくれ、
母ちゃん。
「―――くーん、お迎えきたわよー。」
きた。きた、きた。はやく、はやくかえろう。また、たいしょうがなぐってくるぞ。たいちょうは、いまやられてるさいちゅうだ。いまならにげられる。はやく、はやくはやく、はやく―――
その日、おれは隊長を見殺しにし、半泣きで帰ったのであった。
4
木々の隙間から、さらさらと葉のこすれ合う音が聞こえてくる。深い、濃いめの緑が、頭の上から影を投げかけてくる。時々、その隙間から一筋の眩しい光が放たれて、影に慣れた目を刺激してくる。そして、
「隊長、今日はずっと機嫌悪いけどどうしたの?」
「・・・・・・。」
隊長が、不機嫌な眼差しをおれにぶつけてくる。
次の日、隊長を見殺しにして早々と逃げ帰った、次の日のお昼休み。隊長を見殺しにして帰った事など完全に忘れ、おれは今日も隊長と一緒に大将の行方を捜す。昨日、帰りの車の中から保育園を見た時、思いついた場所があったのである。
そこは裏の雑木林と、建物の間。苔の匂い。少し肌寒い。園児は絶対にこないであろう場所。薄暗い林と建物の間を、息を潜めて進む。先頭は隊長、後ろはおれ。隊長の少し後に続いて進む。
建物の裏なので、室外機やタンクなどが並び、人が隠れるにはちょうどいい空間が続いている。これなら誰かが隠れていてもおかしくはない。
「・・・・・・」
隊長の鳥肌が立った二の腕を眺めていると、
「おい!」
小さな声で、隊長が叫ぶ。
「誰かいる!」
「やっぱりこっちだったんだ・・・」
10m程先にある貯水タンクの裏に、人の気配がする。話し声。一人ではないようだ。大将と、その取り巻き達であろうか。話の内容までは聞き取れない。
おれと隊長は一旦、雑木林の方に入った。林の中からタンクの裏が見える位置まで移動し、大将達を覗く作戦だ。季節が夏ということもあって、背の高い雑草が多く生えているので、見つからずに移動するのは容易い話であった。
距離を縮める事に、聞こえてくる声が誰のものかはっきりしてくる。一人の声はもう完全に理解できた。
「この声はやっぱり大将だ!」
「うん、でも取り巻き達はいないみたいだね。」
「じゃあ誰と話してるんだ?」
近づくにつれ、不自然な事に気づく。どうやら大将は、取り巻き達と悪巧みのミーティングをしている訳ではない様だった。そして、相手はどうやら女の子、そして、
「大将と、他は一人だけみたいだ。」
大将と女の子が二人で話をしているらしかった。
「え!?だれだれ!?」
「まだ分からない。もう少しで見える位置になるんだけど・・・」
もう一人の女の子の方はもっと近づかないと、顔も見えないし声も聞き取れなかった。これ以上進むのは危険な気がしたが、好奇心が強く背中を押してくるのだった。じりじりと、草木の中を移動して角度を変えていく。
もう数センチで顔が見える。と思ったその時。不意に、急に大将が動いた。
「ヤバイ・・・!!」
バレた。いや違う。大将はこっちに動いたのではない。向こうに動いたのだ。同時に相手も前に出たらしく顔が見えた。
「ゆいちゃんだ・・・」
それはクラスで一番人気の女児。男児全員の憧れの的。ヒロインというのがしっくりくる。もしこの町で一番可愛い保育園児ランキングがあったら、ダントツで、
―――いちおくまんてんで一位獲得だ。
そんなゆいちゃんと、大将が、同時に動いた。なんだろう、顔が。顔と顔が、近づいて。止まった。何をしているんだろうか。ふと隣の隊長を見ると、青白い顔で、この世の終わりを見ているかの様な顔をしている。そしてこう呟く。
「大将とゆいちゃんが・・・ちゅーしてる。」
―――ああ、なるほどね。
大将とゆいちゃんがキスをしていたのだった。
―――確かに、この世の終わりだ。
5
ああ、本当に最悪の事態だ。まさか、大将に一泡吹かせようとして、こちらが血反吐をたんまり吐く事になろうとは。
あの後の事は本当にぼんやりとしか覚えていない。ふらふらと家に帰り、失意のまま晩御飯、風呂、就寝。隊長に至っては、
「はあ?裏に大将なんていなかっただろ。昨日は三輪車乗ってた。」
などと延々妄言を吐き続けていた。正気に戻そうと説得してみようと思ったが、現実に戻った瞬間隊長が壊れかねない。隊長は少しの間そっとしておくことにしたのであった。
大将を裏で目撃した日から、土、日曜日を挟んで月曜日の昼休み。おれはまた懲りもせず裏の雑木林に潜んでいた。どうしても真相を確かめたかった。よくよく考えてみると今している事というのは、すごく酷い事なのかもしれない。他人の恋、愛という事情を踏みにじる行為なのかもしれない。そう考えると腹の奥が締め付けられる思いがしたが、おれには確かめたい事があったのである。
おれは二人が甘い言葉を交わし合い。耳が熱さで溶けそうなほど恥ずかしい台詞に耐え続けた。どうってことはない。ただの言葉だ。大丈夫、おれなら平気だ。ただの、
空気の振動だ。
そして二人はまたキスをする。もういい加減終わりにしてもらいたかった。もうおれは十分なほど、確かめたい事は確認することができた。もう十分だ。
―――おれは別に、ゆいちゃんが好きな訳じゃなかった。
もう十分だ。さっきから桃色の空間に身を置き続けているが、もう何とも思わなくなっていた。理解したのだ。おれはゆいちゃんが他の男児達から慕われているのを知っていた。そして、男児はみんなゆいちゃんが好き。おれも好き。そうやって流されていただけだった。隊長は本当に好きだったらしいが。
十分に、十二分に理解して、寒気がした。おれは今まで何回、周りに流されて、自分を殺してしまっていたのだろうか、と。流されたままなら、それは何十人というコミュニティ。いや、あれはきっと一つの生命体だ。自分を殺した、抜け殻達の集合体の、本能だけが機能した生命体。その中の一部として生きている様なものではないのか。考えただけでも気持ち悪いし、やはり恐ろしい。
おれは、抜け出せたのだろうか。
「誰だ!!」
おい、またか、またバレた。何なんだ。大将はおれの匂いでも嗅ぎ分けられるのか。
畜生。
全速力で引き返す。しかし、貯水タンクから伸びる細いパイプに足を引っ掛けてしまった。盛大に吹っ飛んで転ぶ。ああ、馬鹿。追いつかれた。
「おいジョン!!お前なに覗いてんだよ!!」
大将はいつもより熱のこもった大声で怒鳴る。
おれも息を切らしながらこれに答える。
「いや、ちょっと確かめたい事があってさ。大将がいつも裏で何してんのかなーって。あと、おれゆいちゃんの事好きなのかなーと思ってたけど全然そうじゃなかったんだよね。」
言ってしまった。否、言ってやった。絶対怒った。もう十分だ。少しすっきりした。一人で行動した結果としては、素晴らしい結果じゃないか。きっと帰ったらおれは大満足だ。隊長だって阿呆みたいに笑って話を聞いてくれるはずだ。
腹に拳が高速で到達する。耐えろ。耐えて帰れば武勇伝になるぞ。背中に拳。地面にうつ伏せで倒れる。耐えろ。倒れたまま、土を拾って大将に投げつける。頭を踏まれた。耐えろ。おれはまだ頑張れる。
―――どうしてこんなに頑張るの?大将の悪巧みを阻止して。誰が喜ぶの?そこまでしてする事なの?
自問自答。
―――誰の為?
そんなの好きな人の為に決まってるじゃないか。そうじゃなきゃこんな事やってない。大将の悪巧みが潰れて一番助かる人は―――
「先生。」
蒲公英2
6
「やめて!!」
うつ伏せになったおれの体の後ろの方から、泣き声混じりの声が聞こえてくる。ひっく、ひっくとしゃくりあげる声も聞こえる。大将が息を荒げながら、声のする方を振り向く気配。おれも息を荒げながらじっと耳を澄ませる
。逃げるタイミングを伺わなくては。
「だってコイツ覗いてたんだぞ。」
そうか、そういえばゆいちゃんもいたんだった。兎に角、大将はその蹂躙の手を止めた。助かった。少し遅い気もするが。もう全身が熱くて痛い。
「―――。」
「―――――。」
何やら言い争っているが、最早おれの耳には聞こえていなかった。
確かめたい事はもう確かめる事が出来た。もうここに用はない。早く離脱して教室へ帰ろう。
手洗い、うがいも。
「さっきはゴメンな、やりすぎた。」
その日のお迎えの時間。おれは謝られた。
大将に。
隣で隊長が口をあんぐりしているのは放っておく。
「ごめんね。大将はいっつもやり過ぎなの!私がしっかり言っておくから安心してね。」
どうやらこの辺一帯の児童達のヒエラルキーの頂点は、ゆいちゃんのようであった。恐るべし。おれは赤くなっているであろう脇腹を、掻くだけなのであった。
なるほど、大将も好きな女の子には逆らえない様だ。所詮、大将も立派な男の子だという事だ。こちらとしては大将が大人しくしてくれるのはとてもありがたい。ゆいちゃん様様である。
そんなこんなで、大将が悪として栄えていた保育園生活は、唐突に、終わりを迎えたのである。特に、おれが直接何かをした訳ではなく。大将が、自分から他人と関わりを持って、その他人が、たまたま大将を変える事が出来る人だった。当事者だけで終わった話だった。それだけの話であった。おれはというと、ただそれを目撃しただけなのであった。きっとおれが居ようが居まいが、同じ話だっただろう。おれはただの目撃者。傍観者。
そういうオチだった。
そして季節は秋。夏休み中、暴力を振るわなくなり、大人しくなった大将と、ゆいちゃん達(親を含む)からプールやバーベキューに誘われたりと、遊びには事欠かなかった。最初、隊長は大将と一緒になる度に嫌な顔をしていたが、そのうち一緒にふざけ合う仲にまでなったのであった。
そしておれは、気になっていた事を大将達に聞いてみた。二人の関係の事を。最初、大将はおどおどして答えてくれなかったが、ゆいちゃんがあっさりと答えてくれた。好き合って、付き合っていると。おれは素直に祝福したが、隊長は涙目だった。無念である。
そんな夏休みを終え、夏の終わり、残暑の秋。
運動会の季節である。
マーチングバンドの練習の後(おれは鍵盤ハーモニカ、隊長はスネアドラム、大将はバスドラムである)、保育園児独特ののろのろとした、リズム感の演奏の後。休憩の時間。隊長と水道で水の掛け合いをしていた時である。先生に、おれ、隊長、大将と他数人が先生の元に集められた。先生はサプライズ感たっぷりにこう言った。
「じゃあ、君達には運動会のリレーに出てもらいます!同じ年長クラスのの第2クラスには負けられないね!」
ここから、また事は起きるのである。
7
リレーの練習といっても、特にやる事は無かった。保育園児達にリレーのノウハウなど、教えるだけ無意味だろう。
ルールは男女混合の為、編成は男児が3人、女児も3人である。女児のメンバーについては特に秀でた選手というわけでもなく、ただ単に記憶にはっきりと残っていないので、ここでは説明は省くが。
足の速さではどうやら一番速いのは、おれか隊長のようだった。大将は身体は大きく逞しいが、少々肉が付き過ぎている様で、そこがスピードに響いてしまっている。しかしおれ達二人は、おれが痩せ型。隊長が標準。と言った所であろうか。大将にはゆいちゃんから、早急な減量を言い渡されたのだった。
運動会本番まで一週間になったある日の開会式の整列の練習後。マーチングバンドの練習までの空き時間。おれは隊長とスネアドラムと自分の鍵盤ハーモニカで魂のセッションを繰り広げていた。不協和音。通り過ぎる園児達は顔をしかめ、先生達も窓からチラチラこちらを見ている。それでも心地よい時間。そんな暑さ残る秋の昼下がり。
「なんだと!!ふざけんなよ!!」
声が聞こえてきた。大将の声だ。場所は。向こうの第2クラスの練習スペースの方からだ。
「なんだなんだ?また大将の奴喧嘩かよー。」
隊長は呆れた様に呟く。
すると、他の誰かがこう話ているのが聞こえてきた。
「おい、あれ、大将といる奴第2クラスの。」
「うん、なまえ知らないけど確か駿足ってあだ名の奴だぜ。」
駿足。そんな名前の靴があったとか無いとか。大将より少し低い位の背丈で、整った顔立ち。スポーティなイケメンである。そいつが何やら大将と睨み合い(睨んでいるのは喧嘩っ早い大将だけだが)、一触即発の事態である。おれと隊長は面白そうなので少し近付いてそれを眺めていた。どうせ喧嘩では大将の勝ちだ、そう思いながら。
「大将、それじゃあこの勝負は運動会までにお預けにしておくよ。」
「ふざけんな!テメェの勝手な勝負には乗らねぇぞ!!」
「じゃあ、僕はこれからもずっと接触し続けるよ?」
はて、一体何の話をしている事やら。
「お前、俺のゆいちゃんに近付くんじゃねぇよ!ベタベタ触ってきやがって!」
「僕はコミュニケーションをとっていただけだよ。」
どうやら大将の恋人のゆいちゃんにちょっかいを出したらしい。ああ、あの駿足ってやつ泣かされるぞ。ほら、大将が殴りかかるよりも早く。
大将が殴られた。
おれは大将が先制されるのを初めて目にしたのである。大将は苦い顔をしている大きなダメージらしい。しかし今更だが何て暴力沙汰の多い保育園なんだろう。大丈夫なのだろうか。
大将が反撃に蹴りを繰り出す。あれは痛いやつだ。しかし駿足はあっさりとこれを躱す。速い。
そして、
大将の顔面に、相手の拳がやってきた。
「運動会でアイツをぶっ殺す!!」
「オー!!!」
鼻に絆創膏を貼った大将が息巻く。
あの後、倒された大将に駿足は、こう勝負を持ちかけた。
一週間後の運動会でおれ達第1クラスと、駿足たち第2クラスで勝負をする事。幸い、本番では成績によって得点が付けられるクラス対抗のイベントになっている為、この点数で勝負をするらしい。
そして、もし第1クラスが負けた場合。大将はゆいちゃんと別れなければいけない。そんなルールらしい。なんとも腹ただしい奴である。
「でも、アイツ運動神経すごいらしいぜ?」
隊長は第2クラスの友達からそう聞いているらしい。しかも、第2クラスにはスポーツの習い事をしている人が、聞いた所第1クラスの倍はいる。勝ち目はあるのか。
「おい!ジョン、隊長!!」
こちらを呼ぶ大将は泣いていた。みんなを鼓舞しながら、こちらを見て、泣いていた。格好悪く鼻水が次々垂れてくる。他の園児達も心配そうな顔で大将を見ている。そうだ、大将はゆいちゃんと出会って変わった。今ではクラスみんなから好かれるガキ大将だ。おれはそんな彼を、助けたいと思ったのだった。
「頼む・・・、勝たせてくれ・・・。」
おれはこの瞬間、何か長い旅の始まりを感じていた。
「勿論だよ大将。」
8
雲一つ無い秋晴れとズルズルと居残る残暑の狭間。グラウンド、トラックの楕円形の外側に沿って人の群れが輪をつくっている。大人達。両親、乳幼児連れ、兄弟姉妹、祖父母、親戚、近所の小学生達。それぞれがどうでもいい話をしながら園児達の入場行進を待っている。
自分より大きな人々に周囲をぐるりと囲まれていると妙な閉鎖感、圧迫感を感じる。少しだけ、胸の辺りが重くなる様な、そんな感覚。大丈夫。そう僅かに呟いて気を紛らわす。後は軽く身体全体をプラプラと揺らし、身体をリラックスさせる。大きく息を吐いておれは入場門へと進んだ。
運動会当日。ついにこの日がやってきた。運動会。その裏で行われる。先生の知らない水面下で行われる。第1クラス対第2クラスの勝負が。子供の遊びが。御巫山戯が。
―――戦いが。
入場門に着くとほとんどが整列を終えた状態だった。既に汗だくになって大変そうな先生に促され、整列する。隊長と目が合う。彼はワクワクしている様だ。目をキラキラさせながらこちらに小声で、自分の家族が最前列に場所をとって見ているというニュアンスの言葉を、興奮している様で、滅茶苦茶な文法で伝えてくる。大将は・・・後ろの方にいた。様子は大分落ち着いている様だ。鋭い目でじっと、グラウンドを見つめている。おれは首を上に、空を見上げて入場の時を待った。
練習。というよりは最早軍議。小さな、なんとも可愛らしいミーティング。砂を弄りながら。所詮保育園児が作戦を練った所で、形にはならない。当時のおれ達はそんな事知る由もないが。それでも、最終的には統率、団結は出来たのであった。
元々第2クラスには嫌いな人ばかりいたのである。犬猿の仲なのであった。そこにこの大将の件で、クラス全体が燃え上がっていたのであった。油の水溜りに、マッチを落としたかの様に一気に燃え上がった第1クラスは、高い団結力を維持したまま当日を迎える事に成功したのだった。
そして当日。
「それでは園児達の入場です。」
入場曲が流され年長組、つまりおれ達の年代が先に、第1クラスからグラウンドに行進で足を踏み入れる。因みにおれは真ん中位の位置に並んでいた。後ろから第2クラスが続く。
「ちぇっ、駿足の奴、余裕そうな顔しやがって。」
隊長の口がそう動いているのが見える。第2クラス、駿足とその周りの奴らは何か秘策があるのか、それとも本当に負ける事などは無いと思っているのか、なんとも腹の立つ顔をして第1クラスの後ろについてくる。
やがて行進はグラウンドの真ん中に落ち着いてゆき、整列が完了する。開会式。園長先生の挨拶。準備体操は何故かダンスをした。そして退場。
「僕達の最初の競技はかけっこだね。大丈夫なのかい?」
「うるせぇバーカ!!」
退場の後、隊長が早速挑発に乗ってキレていた。実際のところ、かけっこの様な身体能力で結果がほとんど決まってしまう種目は、はっきり言ってこちらが圧倒的に不利である。先程も言った通り、第2クラスには、スポーツ経験者がこちら側の第1クラスの倍はいる。序盤から厳しいゲームになりそうであった。
かけっこでは、1位が3点、2位が2点、3位が1点と、各レースごとに加算されていく。そして、おれ達が出る、最後の速い人達のレースだけ得点が倍である。これは序盤から、点差が開いてしまう競技かもしれない。
「まあ負ける気はしないけどね。」
「おっジョン、なんだか今日はやる気だな。」
何故か今日はずっと、そう感じていた。
9
砂埃の匂い。
「位置についてー!よーい・・・」
乾いたピストル音。火薬の匂い。そして歓声。開会式からそれほど間を空ける事無く、実質第1クラス対第2クラスの年長組のかけっこが始まり、その第1レース、結果は。
―――やっぱり速い。
いきなり相手に1位、2位をとられる。これで点差は5対1の4点差に。しかしそれでは終わらなかった。次々と、第2クラスが上位を獲得してゆく。第1クラスはとれても2位。そして、おれ達のレースの順番が回ってくる頃には得点は、
5対25か。
「おいジョン、これやヤバイんじゃないか?」
確かに、これは序盤から辛過ぎる展開だ。0点じゃないだけまだマシだろうか。兎に角、最後のレースだ。特典は倍。メンバーはおれ、隊長、大将、そして相手は駿足達の合わせて6人。
ここで上位をとれなければ、状況は絶望的になってしまう。それだけは回避しなくては。とりあえず先程浮かんだ策を。姑息な、小癪な策を、隊長に伝えておいた。もしこれが上手くいけば勝てるかもしれない。
「位置についてー!」
来た。
「よーい!」
そしてピストルが鳴らされる直前。その瞬間。
「あああああああああああああ!!!」
突然、駿足の隣にいた隊長が大声で叫ぶ。これが策。スタートで身構える、何も知らない第2クラスの奴等は。突然の大声に身体が強ばる。同時にピストル音。これを知っていたおれ達は第2クラスの奴等を置いて、スタートダッシュに成功する。反応の差で、後ろから第2クラスの3人がついてくる。
「卑怯だぞ!!」
そんな声が後ろから聞こえてくるが気にしない。順番は、おれ、隊長、大将の順。
「ヤバイ!!距離が縮まってきた!!」
大将が叫ぶ。後ろをちらりと見ると、確かに大将の後ろから、瞬足が迫ってきている。急げ。早くゴールに。
「うおおおおお!!」
「くそっ、抜こうとする僕の行く手を塞ぐんじゃない!反則だぞ!!」
「そんなん知るか!!」
本当なら、中学校位の年代の徒競走、スプリントだったなら、一発で反則で記録は無効にされるであろう進路の妨害。今だから、保育園の運動会だから出来る小細工。
「もう少し!」
まずおれがゴールテープを切る。次に隊長。そして3位は、
「うはははは!とりあえずアイツにかけっこで勝ったぞ!」
「反則使ったけどな。」
「うるせぇ!」
大将だった。
1位が3点、2位が2点、3位が1点、合計6点。そしてその倍の点数の12点が追加され、
「17対25になったぞ!」
隊長が興奮気味に言ってくる。どうやらなんとか、このかけっこは乗り切る事に成功した様だ。8点差に出来れば上出来だろう。このままいけば勝機は十分にある。
そういえば、ここまで自分以外の人の為に全力で事に臨んでいるのは、初めてなのではないだろうか―。興奮冷め止まぬ周りを尻目に、おれはそんな事を考えていた。咄嗟に引き受けてしまったが、これはきっと正しい判断で、おれもそうすべきと思っていたし、大将も望んでいた事なのだ。きっとそうだ。火照った身体に、涼しいそよ風を感じながら。周りを見渡す。汗が乾いてゆく。きっかけなんてこんなものだ。何だっていい。
何だっていいから、自分の変化に気が付けないだけだ。
次の競技は綱引き。不安は、元より無かった。
10
「おいおいおいおいおい・・・」
隊長が青白い顔で、汗を体中からだらだらと流している。脱水症状で倒れてしまうのではないだろうか。その前に隊長は調子でも悪いのだろうか、この前も腹が痛いと顔を青くしていた事があった。今回もきっとそうなのだろう。
「ちげーよ!見てみろよ・・・」
「何を?」
周りを見る。今はかけっこが終わって次の綱引きの時間。入場門。今は一つ下の園児達が綱引きで戦っている所である。特に隊長の顔を青白くする様な、変わった様子はない。そういえば周りに並んでいる同じ第1クラスの奴等もなんだか同じ様な顔をしている様な気がする。
「それでもない!第2クラスだよ!」
ふと、目をそちらに向けてみる。さっきと同じメンバー。瞬足の周りにもさっき見た取り巻き達。細い奴、丸刈りの小さい奴。
力士みたいなデカい奴。
「おい何だよアイツ。あんな奴いたのかよ!」
「横綱だよ。近所の相撲のクラブ通ってる奴で、最近もちびっこ相撲大会で優勝してた本物のちびっこ横綱だ。」
隊長が知識を披露する様に紹介してくる。どうやらここら辺では有名な話らしかった。
しかしどうしたものか。横綱の力が、試合にどれほど影響してくるのかはまだ分からないが、楽な試合にはなりそうになかった。苦戦必須。踏ん張りどころ。勝負の分かれ目。ここからが頑張り時である。
入場。グランドを周り、中央へ。両クラス、向かい合って綱の左側に整列。その場にしゃがむ。先生がホイッスルを吹く。片手を上げ、もう片方を綱へ。そのままピストル音を待つ。そして、
「よーい!!」
ピストルが鳴る。
両クラス、瞬発力のある人から一気に立ち上がり、綱をたぐり寄せる。力と力が、互いに後ろ方向へと発せられる。綱が一直線にピンと張る。その瞬間、衝撃。前へ、大きな力で引っ張られる感覚。スタート直後からいきなりズルズルと持っていかれる。50cmほど、引っ張られただろうか。強い。耐えるのがやっとだろうか。このままでは負ける。
「うおおおお!!強い!!」
隊長が大声を出す。
「大将!もっと引っ張れないのかよ!!」
「やってるよ!!でも駄目だ!!」
どうする。落ち着いて考えろ。何か、何かあったはずだ。思い出せ。練習の時、先生の言った言葉。何だった?あの時先生はなんて言っていたのだったか―――
「声をかけて一斉に同じタイミングで引くぞ!!」
最初に思い出したのは大将。掛け声があがる。タイミングが少しづつ整っていく。第1クラス、第2クラス両者の力が均衡し始める。
「もっとだ!!どんどんいけ!!」
少しだけ、引っ張られた分を取り返した。もう少し。もう少しで逆転出来そうな所まで来ている。このままいけば絶対に勝てる。しかしその時、終了の合図である2回目のピストル音がグラウンドに鳴り響いたのであった。
天気は晴れ。朝より少し雲がかかって涼しげな空模様。
蒲公英3
11
昼食の時間。児童達はそれぞれ家族の所へ行き、昼食をとっている。午前の部終了時点での両者の得点は。
「28対34かー・・・」
昼食をとり終え、隊長の所でアイスをご馳走になっていたおれは、隊長と一緒に午前の部を振り返っていた。
あの後、玉入れと障害物競走があったのだが、どちらも大きな戦果は得られなかった。結果、点差は大して変わらないまま、しかも午後の部は、ダンスやマーチングバンドなど、得点の無いプログラムが続き、特典のある種目は最後のリレーだけなのである。得点のシステムは1クラス2チームが出場。1位が10点。2位が3点。つまり、自分達第1クラスは、必ず1位をとれなければ勝てないのである。もしも第2クラスに1位をとらせてしまう様な事があれば、第1クラスは敗北してしまうのだった。
「絶対に勝たせてやるから、安心しろ。」
「大将、君が元気を出さないと始まらないよ。」
大将は明らかに戦意を失いかけていた。士気が下がるクラス。
―――もしも負けたら、なんて謝ろう。
そんな事を考えてしまうおれは本当に酷い人間なのだろうか。勿論リレーには全力で臨む。しかし正直な所、現段階で勝つ確率は極めて低い。だから、弱いおれはそんな事を考えて貯金を作る。大将をなるべく悲しませない言い訳を考える。
本当におれは弱い。憎いくらいに。
「それでは最終競技になりますリレーの選手入場です。」
最後の競技、リレーの走者の順番と、それぞれ対する相手が決まった。まずこちら側第1クラスは、第1走者に隊長。2,3,4番目に女子児童達。第5走者がおれで、アンカーが大将。先生が言うには、「序盤で稼ぐ作戦」らしい。
対する第2クラスは、先ず初めにアンカーが駿足。それ以外は全員がスポーツをやっている曲者揃いである。確実に先生の作戦通りに序盤で貯金を作らなければ負ける。
おれは、果たして本当に勝つつもりで大将の頼みを引き受けたのだろうか。本当に勝てると確信があって引き受けたのか。あの時のその場の雰囲気で流されてしまったのではないだろうか。だとしたらおれは本当に酷い人間じゃないのか。あの時やるべき事は、駿足に勝負を取り消してもらう事じゃなかったのか。何故。おれは平然とこのグラウンドに立っていられるのか。本当に、純粋な気持ちで、おれは大将を助けようと思っているのか。どうなんだ。一体どうなんだ。おれは。
果たしておれは最善で行動したのか。
ふと痛みを覚える。気付けば唇を思い切り噛み締めていた。痛みで少し頭がすっきりした。さっきのモヤモヤはもう無い。見れば、もうすぐリレーが始まるという所であった。
「位置についてー!」
隊長がスタートラインに着く。
「頼むぞ・・・」
大将の口が、そう動いた気がした。
「よーい・・・」
鳴った。一斉にスタート。
「うおおおおおおおおおおお!!」
速い。やっぱり隊長は足が速い。ただスポーツをやっているだけでは隊長の足の速さには敵わないだろう。スタート直後からどんどん他の走者を引き離し、すごいスピードで前に出る。後ろに3m程差を付けて第2走者へバトンタッチ。歓声が続く。
その後も第1クラスが1位を保ったまま。おれの番が近づいてきた。2位の第2クラスとは4、5mくらいの差だろうか。コーナーを曲がり終え、バトンがおれの手に渡る。大丈夫、いける。走り出してすぐ、異変に気付く。足が、身体が重いのである。どうして。何故。おれは何ともないのに。大将を勝たせると約束したのに。自分の中の不安が、おれの足にまとわりついていた。
「くそっ!・・・くそっ!!」
情けない。口からは悔しさの言葉が溢れ出てくるのみ。後ろはどのくらいに来ているのだろうか。そもそもおれは速く走れているのだろうか。どうなんだ。分からない。
その時、聞こえてきた。後ろから。相手の息遣いが。もうそんなに距離は空いていない。みんなはおれが抜かれたらきっと、ガッカリするのだろう。情けなくて涙が出てくる。悔しくて。悔しくて我武者羅に身体を前に。全身をフル活動しておれ自身を走らせた。もっと速く。もっと滅茶苦茶に。
―――あぁ、大将が見える。もうすぐ終わりだ。
―――大将の顔、切羽詰まってるな。きっともう開いていた差がほとんど無いんだろうな。
そしてバトンは渡る。
12
バトンを大将に渡した後、おれは勝負の行方を見る事が出来なかった。おれのせいで、あんなにあった差が、無くなってしまったのだ。
おれはコースに背を向け俯き、勝負の終わりを待っていた。
「おいジョン!!何やってんだ見ろよ!」
隊長が声を荒げて言ってくる。
「ごめん、おれはいいよ。おれのせいでこうなったんだし。」
「何言ってんだ馬鹿!いいから見てみろ!!」
頭を上げて、見る。
大将が、駿足の前を走っている。決死の、必死の形相。あんな苦しそうで、本気で、覚悟を決めている大将の顔を、おれは未だかつて見た事がなかった。
「ジョン、お前が駄目だったからそこで終わりじゃねぇよ。まだ大将が、アンカーがいるだろうが!」
そうだ。
「お前が一人で勝手に諦めんなよ!!」
隊長の言う通りじゃないか。
「頑張れ大将!!!」
「いや話聞けよ!」
おれは馬鹿だ。何故大将が駿足より遅いなんて決め付けていたのか。練習の時なんて関係無い。大将は誇りを、友達を、好きな人を守る為ならいくらでも強くなれる。そういう奴だ。そんな事、
―――親友のおれ達が一番良く知っている。
駿足がじわじわと追い上げてくる。気付けば二人はほぼ並び始めている。大将の顔が歪む。歯を食いしばり、額には青い筋が立っている。血走った目はただ前を見つめ、全身は常に同じ運動を、速く繰り返そうと必死である。
しかし、それほどに追い詰められていても、おれと隊長は笑っていた。他のクラスメイトも笑っていた。皆が信じていた。分かっていた。本気になった大将が負けるはずなど無いという確信もそうだが、
既に大将はゴールテープを切っていたからである。
ゴールした大将はそのまま走り続け、空を仰ぎ、我武者羅に叫んだ。他のクラスメイト達が大将の元へ駆け寄っていく。それを眺めながらおれは、隊長にそっと話しかけた。
「ごめん隊長。あんなに勝たせるって息巻いてたのに、おれって大した事無かったよ。」
「んなこたねぇよ!とりあえず、勝ったんだからこれでその話は終わりだ。二度とそんな事言うなよ。」
「うん。ありがとう、隊長。」
自分でも何だかよく分からない、頭の中がぐちゃぐちゃだ。滅茶苦茶だ。兎に角。おれ達は第2クラスに勝った。それを滅茶苦茶に全身で感じ、喜びの感情を表現する事だけが、この第1クラスを一つの生き物の様に動かしていたのであった。
とりあえずこれで駿足はゆいちゃんを諦める約束だ。見ると、駿足は清々しい微笑でおれに視線を送り、
「負けたよ。」
口の動きでそう言ってきた。その瞬間。
おれは感じた。それはパズルの完成の様な、綺麗に収まったと、はっきり感じる感覚。鮮明に辺り一面の景色が開け、全てが明らかになり、頭がすっきりしていく。これは言うなれば、
「丸く収まったのかな。」
そんな事を呟いて仰ぐ空は晴天。遠くの山は赤茶色に染まり、少し乾いてきた風が、園児達の歓声を。優しく運ぶ。それを見た太陽は、満足そうに西へ還るのだった。
13
「うおお・・・しっかし寒いな!寒いなジョン!!」
「隊長は今日も暑苦しいね。」
「これじゃあ今日は三輪車乗れねぇな。」
「そうだね。雪積もってるし。」
「雪!!雪だぞジョン!もっとテンション上げろ!!」
冬。特に変わった事も無く。あっという間に秋が過ぎ去り、眠りの季節がやってきた。
2月も中旬に入った頃、園児達待望の大雪が一晩中降り続け、30cmほどの積雪を記録。する間も無く園児達の雪合戦大会が始まったのであった。大将が声をかけ、運動会以来仲が良くなっていた第2クラスを交えての雪合戦。おれは、開始直後に横綱からの剛速球を顔面に受け、早々にリタイアしていた。いつもの小さな土手に寝転がり、園内の狭さを感じさせないグラウンド一面に降り積もった雪を見渡していた時。そこに、敵を大量に狩り続け、流石に飽きが来たのか隊長が土手にやってきたのだった。
「なんだよ第2クラスの奴ら、気合が足りねぇな!」
「そうだね。でも、あれから仲良くなれて良かったじゃん。」
「そうだな。もう少しで卒園だし、悔いの無い様に、だ。」
「うん。」
―――悔いの無い様に。
少し胸の中で寂しさを感じた。卒園までもうそれほど日数は残ってはいなかった。
考える程に寂しくなる。この場所で過ごす時間の終わり。終着。これ程に不安で、虚しい未来図があるとは思わなかった。小学校に上がればまた皆とは会えるだろうが、ここで過ごす時間はもうない。それがたまらなく寂しくなった。怖くなった。それが故に、おれはまた、雪合戦に参加するのだった。
不安を振り払う様に。
その日の夕方。迎えの時間。おれは静かな廊下を歩いていた。トイレに行ったその帰り道。夕暮れの眩いオレンジ色が音も無くガラスをすり抜けて入ってくる。遠くからは園児達の騒ぐ声が聞こえてくるだけである。
そろそろ迎えは来ているだろうか。そう思いながら、もう園児のいなくなった別の教室の前を通り過ぎた時。ふと、耳に僅かな音が入ってくる。啜り泣く様な、鼻を啜る音。その音を聞いた瞬間、とてつもない量の鳥肌が立ったが。汗がどっと出てくるが。すぐに理解する。誰かが泣いている音だ、と。
机の上の書類を片付けていたのだろうか。机の上には色々な紙が並んでいる。カーテンの隙間からは西日が射し込んで、何か神々しさを感じてしまう。ずっと泣いていたのだろうか、目と鼻が真っ赤だった。
「先生、どうして泣いているの?」
「あれ、ジョン君・・・。」
先生の顔は直ぐにいつもの顔に戻る。
「どうしたの?皆の所に行かないの?」
「先生こそ、どうして泣いていたの?大丈夫?」
二度目の質問。先生はさっき泣いていたのが嘘の様に、少しはにかんだ様な顔で微笑み、答えた。
「ありがとう、でも大丈夫だよ。これはまだ内緒なんだけどね、先生はね、皆が卒園した後、このお仕事辞めちゃうの。」
――――――え。
卒園しても、保育園自体はそれほど離れていないので、先生には会いに行けると思っていた。しかし、先生自体がいなくなってしまうのでは、もうどうしようも無いじゃないか。そう思った。絶望。夕方の悲壮感漂うオレンジの窓際、外から聞こえる小さな喧騒は、おれの頭の中をゆっくりかき回していった。何も考えられない程に。
14
地獄。希望の終焉。夕方。黄昏に潜む闇の様な、一瞬の過ちから、気の迷いから、ふとした瞬間に混ざり、内側へと入り込んでくる闇だ。その闇は今この瞬間、帰りの車の中でもどんどん膨らんで、おれの中を内側から圧迫してくる。おそらくいつか、おれはパンクしてしまうのだ。その時がおれの、自分自身が今形を成している精神、心の敗れる時なのだ。それはとても恐ろしかった。よく解らないが、それはとても恐ろしい事なのだとその時のおれは理解できた。だから、おれは後部座席でただ震えていた。夕闇が車を追いかけてくる。来るな。この世界は、光と闇の均衡でできているのだと。目を焼くような太陽の光があれば、そのまた逆もあるのだと。そうテレビの中の誰かか、夢の中の誰かだっただろうか、言っていたのを思い出した。兎に角、おれは混乱していた。脱力。もう何が何なのか解らない。今現在、自分がどんな状況に陥っているのか。それすら解らない。先生は辞める。一緒に保育園からいなくなる。つまり卒園したらもう、会えないのだ。希望はこんなにも壊れやすく、脆い。それを身をもって知った時、その壊れた隙間から、黒い液体が溢れ出すように、闇がおれの体を満たしていった。内側から、暗い底へと沈んでゆく感覚。深く深く、おれの意識は沈み、やがて過去を思い返していた。
先生に初めて会ったのは入園してすぐの事だった。そこだけはっきりと覚えている。おれは病的に人見知りをこじらせていたため、当初は友達が、はっきり言って一人もいなかった。
そこで先生が、明るくて話しやすい竹を割った様な性格の隊長と仲良くする様にすすめてきた。当然それは上手くいって、隊長とは今の交友関係に至る訳だが。
先生はみんなから好かれていた。おれは先生の笑顔が好きだった。隊長とバカをやって先生がおれ達を叱った時、最後に必ず優しく微笑んで、正しい事を教えてくれた。それだけでおれは二度と同じ事はしないと思えた。
ある日、いつもの土手で寝転がるおれに、先生がこう言った。
「ジョンくんは優しくて強いから、困ってるみんなを助けてあげてね。先生はそうして欲しいな。だってその方がきっとみんな幸せだもの。一人が幸せよりみんなが幸せな方が、もっともっと幸せだよ、きっと。」
「うーん。できるかな?おれより隊長の方が強いよ?」
「ううん、そんな事無い。ジョンくんはみんなより人一倍、優しくて強いんだよ。みんな知らないだけ。だから、ジョンくんが良ければ、みんなを助けてあげてくれないかな?」
そう言われて、おれは素直に指切りをする。
今思い返せば、なんだかどこかそこら辺のアニメか何かから拾ってきたようなセリフだったが、そんなものだ。所詮記憶だ。
正直おれは人見知りだから人付き合いが苦手だ。しかも喧嘩だって全然強くはないし、はっきり言って隊長より弱いのである。なのに何故、その理由でおれになるのか、その時は全く分からなかった。
そしておれは、そんな生き方をすると決めたのだ。無意識の内に。先生がおれを助けてくれた様に。困ってる人は必ず見過ごさないで最低限助ける。そういう生き方をこの頃からし始めたのだった。
先生とそう約束したから。
困っている人。先生は泣いていた。やはり悲しいのだろう。悲しんでいる人がいたら、助けてあげるのがおれの生き方であり、先生との約束だ。先生が辞める事は、どうしようもない。それはとても悲しい事。受け入れられないとしても先生に、おれは何かしてあげられるのかを考えよう。あの笑顔でお別れできる様に。それでおれは、きっと諦めが付く。
涙は無かった。泣きたくなかったから。
15
「ねぇ、隊長。」
いつもの土手でおれが隣の隊長に話し掛ける。
「なんだー?」
軽く返事が返ってくる。
「おれがこれからやろうとしてる事に、意味があるのかな?」
「知らねー」
寝転がる隊長は即答する。
「そっか。でもきっと、意味があっても無くてもいいんだ。これはきっとおれの我が儘みたいなものなんだよ。したいからやってる。それだけなんだ。それで先生が喜んでくれるなら、尚更嬉しいね。中心にあるのはいつもおれなんだ。みんなが中心なんだ。友達を助けるのも、先生に何かしてあげるのも、結局は自分の我が儘なんだ。それって凄く酷い事の様な気がする。結局自分の事しか考えてない奴に助けてもらったって知ったら、きっと嫌な気落ちになると思うんだよ。」
おれは手元の草を千切り、宙へ放つ。草は微かな追い風に乗り、ゆっくりと流されてゆく。
隊長は難しい話に顔をしかめつつ、適当な口調で答えた。
「そうなのかは知らないけど、少なくとも助けてもらった事実に関しては、その人は感謝するんじゃねぇの?後は知らね。」
「ふーん。」
夕方、迎えに来た母親達が立ち話を始めたのを見計らい、隊長と土手に座る。幼い感性でもはっきりと理解出来る。夕日の素晴らしさ。3月上旬。卒園式前日。
「きっとおれ達はまだ子供だから解んねぇだけだろ!」
隊長は笑う。いつも通り。下品な笑い方。
「だよね。きっとそうだ。大人になったら、絶対に理解出来るようになってやるんだ。」
おれは子供だから。そう言って解らない事は後回しに。それで良い。はっきり言ってそんな事考えるだけ無駄だし。異常だ。そう思った。
「あ。」
ふと、目を落とした先にあるものを見つけて。
「あった。」
潰れないように。そっと、優しく手の中に入れて帰った。母親に手の中のものを問われても、おれは答えなかった。大事に。大事におれは小さな箱にしまい、眠りに付き、卒園式の朝を待った。
夢の中。そもそもここを夢と判断する材料は何なのか。それは分からない。脳が作る幻覚なのか。もしかすると現実と全く同じものでできているのかもしれない。そうなれば。夢も現実も、どちらも自分のものなのかもしれない。あるいはこっちが現実なのかもしれないし、それを確かめる術は無かった。兎に角その時おれは夢なのか現実なのかはっきり言って判断がつかないその世界を見ていたのだ。はっきりと。色彩豊かに流れ込んできたその映像を。
辺りは霧の様なもので覆われ、視界が悪い。真っ白な、早朝の湖の様な水々しさ、霧の湿っぽさがやけに現実味を帯びていて、それがおれを惑わせようとしていた。地面は草花で覆われていて、広さは視界の悪さのせいで判断がつかないが、草原の一角の様な感じがする。見えないが、自分の周り、360度から風に揺れて自らを擦り合わせる草達の音が聞こえてくる。
霧の彼方に、色が見えた。黒い。それから、自分が見えた。否、自分だった何かが見えた。次に感覚に捉えたのは、感情。悲しみ。それは寂しさ。後悔。自責の念。もしくは恨みかもしれない。そしておれは、それを恐怖する。それは未来だった。
何故。何故こんなものを見なければならないのだと、おれはその意思を、いる筈の無い相手へとぶつける。返事は勿論無いが、霧の中の黒に動きがあった。こちらに近付いてきたのだ。それに伴い、雑音が、前方から。上から。後ろから。左右から。聞こえ始める。叫びが。何かを叫ぶ声。感情の爆発。言語は聞き取れない。ただただ、感情、イメージだけが頭に直接入り込んでくる。悲観。嫌気。焦燥。後悔。憤怒。絶望。気が狂いそうになる。否定しなければ。そうしなければこの霧の中の黒が、おれの現実の世界になってしまう様な。そんな気がしたから。おれは否定した。きっぱりと。そして世界は暗転した。
おれはこの夢の全てを思い出せなくなった。
目が覚めたのは布団の中だった。時計を見る。まだ夜明けの遠い深夜。なんだか気分が悪い。気分が悪いというのは、何か嫌なものを見た後の様な。そんな感じがした。起き上がる。トイレで用を足し、そのまま深夜の無音が佇むリビングへ寄ってみた。背の低いポールハンガーにかけられた、保育園用の小さなショルダーバッグを開け、入っていた小箱の中から中身を取り出す。明日、これを先生に渡す。それだけの事だ。何もおかしな事は無い。なんだか気分が良くならない。そういえば何か夢を見ていた様な気もする。きっとそのせいなのだろう。リビングの一角にある窓を勝手に開け、新鮮な空気を肺に送り込む。さっきよりはマシになった。外の景色に目をやると、深夜の空にはひっそりと月が出ていた。形はほぼ満月の明るい月が、静かに光を投げかける。おれはなんとなく手に持っていたそれを月にかざす。綺麗だな。純粋にそう思ってしまう。
―そうか、まるだ。まるく、みんなで手を繋いで円になったんだ。
手の上で、四つ葉のクローバーは、月の光を受けて柔らかな表情をみせた。
Interlude
ここでおれの記憶は一旦途切れてしまう。そこから先の記憶は小学校入学まで空白なのだ。果たしてその後、卒園式の日に自分が何をして、どうのように保育園生活を終えたのか、先生はどうなったのか。四つ葉のクローバーを、おれは渡したのだろうか。それさえおれは全く思い出せない。
今でもそうだ。
そしてその次におれが、人助けに悦を見出すきっかけを得た保育園児時代の。その次に思い出す事が出来るのが小学校の頃の事なのだが。これもまた、途切れ途切れの記憶なのだ。ピースを無くした、否、無くし過ぎたパズルなのだ。一つが欠けているという事ではなく。所々が欠け、完全に消失してしまっていた。最早それはパズルとは言えないのかもしれない。しかし、それは第三者によって突如ピースが戻って来たり、新たに作られる事もある。
小学校低学年の記憶。覚えている人はきっと少ないだろう。おれはほぼ覚えていなかったと言っていい。これは結果的に家族、親戚、友人から聞いた自分についての話を元に出来上がった過去で、その時のおれはもしかしたらここで語られる人格とはかけ離れた人間だったのかもしれない。どちらにしても、当時の自分を自分から思い出す事はほぼ出来ないのだ。
そして、他人からの補完により修復された記憶が、事実とは限らない。そのつもりでおれはここから先の自分の過去を語る。話半分で聞いてもらうのが一番良い。ああそうなのかと、軽く聞いてもらえるのが一番良いのだ。あくまで過去を語るだけの事ならば。
だがこれは少し違う。
おれは自分の過ちを。過去の過ちを、語っているのだ。間違いを、見誤りを、失敗を、罪を。聞いて欲しい。この全てはおれの失敗談、懺悔。そして、判断を委ねているのだ。
おれはどうすれば元に戻れるのかを。
擬態の王
1
―ああ、何なんだ全く。
おれは怒る。
何に対して。
誰かに対して怒っているのではない。
この状況に。
今置かれているこの状況に対して怒っていた。
皆がこちらを見ていた。
どうしてこうなったのだろう。
季節は4月の下旬。
入学式がまだ記憶に新しい。
あの時は何も考えていなかった。
何も起こらないと考えていた。
思っていた。
ここは保育園なんかよりずっと進んだ所で。
勉強をして、学ぶための所で。
友達も保育園の比じゃない位いっぱいいて。
年上がいっぱいいて。
「問題」が沢山あって。
思っていたより酷い所だった。
裏切られたような気分。
これがここへ来て2,3週間で解った事だ。
大将達は別の学校で元気にしているだろうか。
おれはここで仲良く出来そうにない。
こんな奴らと。
こんな所で。
図書室に一人でいた方がマシだ。
最近知ったが、あそこは良かった。
静かで、本が沢山あるから飽きない。
何よりうるさい奴がいない事が一番だ。
隊長が嫌な奴ばかりだと言っていたが。
―ああ、その通りだ。
小学校。
―ここには幼稚な悪意が渦巻いている。
2
おれはこれまでに無い程に緊張していた。足元が妙にふわふわする。浮遊感。なんだか体調も悪いような気がしてきた。慣れない服装をしているからだろうか。いや、多分それは関係無いのだろう。実際には、扉の隙間から見える人の数を見てしまってから、おれはいつもの様子が一変し、顔色が悪くなってしまっていたのであった。何か胸の辺りでどくんどくん聞こえるが幻聴だろう。今は関係無い事だ。
「おい、ジョン大丈夫か?」
おれの異変に気付いた隊長が、話し掛けてくる。隊長と同じ小学校に入学だと聞いて、おれは小躍りでも始めてしまうかの様な喜びっぷりだったという。因みに隊長以外は保育園の頃の友達はいない。いてもあまり接点が無いか、仲が良く無かった奴か。因みに大将達は他の小学校に入学したのだった。クラスは一つ。30と何人か。田舎の小学校ではこれでも多い方なのだとか。
「全然。だいじょぶ。」
「いや顔真っ青だぞ本当に大丈夫か?」
「ごめん。今はあんまり話し掛けないで。」
「緊張してんの?」
「・・・。」
察してくれ。頼むから。おれは今この場に慣れたいのだ。緊張を無くす為にはそうするしか無いとおれは考えていた。集中。集中させてくれ。頼むから。一刻も早く。否、一分一秒でも早く慣れなければ、新入生の入場の時間になってしまう。
扉の向こう、体育館に収まっている人の数が、これまでの保育園生活では見たことの無い数で。そこに放り込まれる事への、不安。あるいは緊張。何だか気分が悪くなってきた気がする。いや、気持ちが悪くなってきたのか。いや少し待てよ、そういえば「気分が悪い」と「気持ちが悪い」ってどう違うのだろうか。「気分」は感情の事だ。その対象に対して快くない感情を覚えた時に「気分が悪い」というところだろうか。
そして「気持ち」これは二通りの解釈がある。感情を指す「気持ち」と
体調を指す「気持ち」があり、今のおれの場合は後者だ。体調が悪い。体調がよろしくないという意味の。
「気持ち悪い。」
隊長が無言で背中をさすってくる。止めてくれ、入場前に緊張で気持ち悪くなってる所なんて、女の子に見られたら恥ずかしいじゃないか。
「大丈夫、収まったから。」
正直全くこれっぽっちも収まっていなかったが、そう隊長に伝え、元の位置に整列する。深呼吸。そうだこんな時は深呼吸だ。
「新入生、入場。」
落ち着く間もなく、扉の向こうから。ノイズ交じりの女の人の声が大音量で聞こえてくる。ああ、始まってしまった。今抜けてものいいのだろうか、式の進行が止まってしまうのではないだろうか。おれはその時そう思っていた。勿論そんな事は無いが。
そして扉は開かれた―
こういうと聞こえも良く恰好がよろしいが。体育館のあの重い引き戸がごろごろと重々しく開いただけである。
3
気が付くとおれは体育館最前列に座っていた。隊長曰く、鼻息を荒くしてガチガチに硬い動きで入場をこなしていたらしい。やってしまった。
実際入学式といっても特別何かがあるわけではなかった。(あったとすればおれの名前が呼ばれた時、返事をする際にかなり上ずった声が出た。)気が付けば、あっという間になんだかよく分からない偉い人の話は終わり、何故か全く知らない校歌を全校生徒で歌わせられた。勿論全く歌えていない。よく分からないが、おそらく雰囲気だけでも覚えてもらう為だろう。隊長は適当な言葉を当てはめ、少し遅れ気味に大声で歌っていた。隊長は相変わらずハートの強い奴だった。
そして入学式は閉式となる。退場の際、沢山の生徒からの視線に耐えなければならなかったが、入場の時程ではなかった。
退場後、保護者と共に教室へ。説明会である。今日は母親が来ていたので同行する。体育館にいたらしいが全く気が付かなかった。
ぞろぞろと行列は進む。昇降口を通り過ぎ、2番目の教室。1-1のプレート。入口は前後にあったが、そこまで広くはない為後ろがつかえていた。誰か子供が急かしてくる声が聞こえる。何だか少し不安になった。
やっとの事で教室へ入る。壁には明るめの木材。並べられた勉強机も同じような色だ。温かみのある教室になんだか少し嬉しい気持ちになる。黒板には大きな張り紙で席順が貼り出してあった。そのまま自分の席へ向かう。横に6列ある内の、左から3番目、後ろから2番目。隊長は廊下側の右端にいた。
教室内は騒がしかったが、そのほとんどは保護者だった。自分達新入生は知り合いと離れ別々に座らされ、緊張しているのだろう。机に置かれた資料や案内を眺めていた。
こうして喧騒の中にいるとふと思い出す。
―まるで保育園にいた時の様だと。
だがここはもっと大きい所だし、人も多い。きっと楽しくやっていける事だろう。別に保育園の頃の思い出を捨てて、無碍にしようとしている訳ではない。ただ、この喧騒に囲まれていると、やはり思い出してしまうのだ。思い出さずにはいられないのだ。あの、絶望と奮起の日々を。大将との恋愛絡み(実際には違ったが)の喧嘩でボロボロになった事や、その大将を助けるために参加した、隣のクラスとの運動会での戦い。オレンジ色に染まる空き教室での、先生からの告白と、おれの絶望。そして―
「はいじゃあみんな!静かにしようねー!!」
今、5cmくらい全身が浮き上がったのではないだろうか。そのくらいの突然の大声に子供達は全員静まり返った。入ってきたのは30代位の女の人だった。隊長は椅子から転げ落ちていた。
4
「―とりあえずこれで私からの説明は以上です!」
この先生は語尾にエクスクラメーションマークを付けないと死んでしまう病気にでもなっているのではないだろうか、そう思うくらい大声で話し続けた。お陰で大体の説明の内容は頭に入ってきたが。
自己紹介で目の前の担任の先生は名前をイシオカと名乗った。イシオカ先生である。好きな科目は体育。運動が好き。特に走る事。陸上経験者。種目は長距離系。表彰台に立った事がある。一年生の担任をするのはこれで3回目。算数と音楽が苦手。でも歌うのは得意だし好き。ピアノはいくらやっても弾けるようにならなかった。算数が嫌いなのは、論理的な考え方が嫌いだから。スポーツマンなので精神論で、気合で頑張るタイプ。スポ根系熱血漫画が好き。好きな色は赤。食べ物はイチゴが好き。髪は肩ぐらいで揃えて、あまり伸ばした事が無い。ここから車で30分程の住宅街のアパートの一室に一人で住んでいる。車は四輪駆動車が好きで今もそれに乗っている。独身。彼氏募集中。家には犬が一匹いる。料理は得意な方。最近はまっている趣味は1人カラオケ。酒癖が悪いのを直したい。腹も少し出てきたのでそろそろダイエットをしたいと思っている。好きな異性のタイプは―
ここまでおれが、イシオカ先生の異様なまでに大量の自己紹介の内容を覚えているのは、あの大声のせいだと思っている。実際には事柄一つ一つにエピソード等を加えたり補足を入れたりして説明していたので、かなりの時間がかかった。小学一年生には一部が若干キツい内容の自己紹介だったし(好きな食べ物がイチゴの部分だけ妙に可愛らしくて少し嫌悪した)、いくらなんでも多過ぎだし一つ一つの話も長過ぎだ。横を見ると、隊長は既に船を大海原へと漕ぎ出している。流石に担任の自己紹介の時点で寝るのはまずい。いくらなんでも不良過ぎる。
「じゃあ今度は皆に自己紹介してもらいます!!名前の順番に立ってもらって、お名前と何か好きな事!何でもいいよ!それを言ってから座ってね!!」
そしてやっとの事で、生徒の自己紹介に入った。しかし何故だろうか。全くと言っていいほどみんなの自己紹介が頭に入ってこない。絶対に原因はこの、正面の教壇に立つイシオカ先生だと、運動狂いで独身の、イシオカ先生だと。ほぼ全員が悟っている事だろう。生徒の名前すら頭に微塵も入ってこない。なんて事をしてくれたんだ。気付けば既に順番がおれの一つ前まで来ている。何を言おうか。とりあえずおれの好きな両生類についてでも語っておくとしよう。
立つ。
「――――です。好きなカエルはアイゾメヤドクガエルです。」
そして座る。
勿論凍った。
5
「おいジョン!お前あれはダメだろ!!」
隊長が爆笑しながら言う。
「どこがだよ!全然良かったじゃないか!」
最近声のトーンや声量が、隊長寄りになってきた気がする。隊長は何も変わらないのに、おれだけが隊長の影響を受けているという現状には少し納得がいかないところである。
昼過ぎに今日の所は解散となって、おれは隊長の家に遊びに行った。実は保育園の頃、隊長の住んでいる家が歩いて行ける距離だと知ってから、よく遊びに行くようになっていた。隊長は自分の部屋を持っている事におれは憧れを持ったりしていた。羨ましい事だ。
2Dの横スクロールアクションゲームをプレイしながら隊長は、今日おれがした失敗を大いに笑った。ほとんど寝ていたくせによく覚えているものである。隊長。勿論本名ではない。あだ名。ニックネームである。保育園からの親友。言うなら田舎のヤンチャ坊主。トレードマークの坊主頭は現在、少し伸ばしてソフトモヒカン風になっている。そんな隊長が顔はテレビのゲーム画面に向けたままこう言った。
「フルヤってのには気を付けろよ。」
「え?誰?何で?」
「今日そいつに声かけられた。俺がふざけて皆の注目浴びてるのが気に食わなかったんじゃねぇかな。」
正直他のクラスメイトの名前なんてイシオカ先生の長過ぎる自己紹介のお陰で1人か2人位しか覚えられていない。とりあえず覚えておこう。フルヤ。
その時のおれは、フルヤと関わる気は微塵も無かったはずだ。否、そんな危ない奴とは関わらないのが一番。それがこの学校生活を平和に過ごせる方法だと、思っていた。思い込んでいた。だがそれは違った。間違い。本当に大きな間違いで、おれは本当に愚か者だったのだ。関わらない事が平和に過ごす方法だ。一体何を考えていたのだろうか、愚か者のおれは。
フルヤとの邂逅、そして因縁の解消こそが、おれの平和を意味していたとは、誰が想像していたであろうか。だが当時のおれはすぐに思い知る事になるのだ。フルヤこそが、小学校生活序盤の最終目標なのだ。フルヤなくして、小学校低学年は語れない。
おれはここで気付く事になる。保育園で続けた人助けまがいの行動。他人の為、友達の為に身を粉にした日々。おれがなぜ、何の為にそんな事をしているのか、その本当の理由。それに気付いた時。どちらが悪なのか、分からなくなった。
おれは愚か者で、悪人だった。
そんな記憶が、とめどなく溢れ出る。フルヤ。お前がいたから。
おれは変われた。悪人になれた。
擬態の王2
6
いつの間にか、4月も終わりになる。そんなある日の昼休み。雨が降っているので、隊長達他のみんなは廊下を元気良く走り回っている。きゅ、きゅ、と濡れた廊下に上履きの裏面のゴムが擦れる音がたびたび聞こえてくる。元気で何よりである。おれはというと、上の階、2階のとある教室の前にいた。「図書室」と書かれているプレートを確認し、扉を開け中へ入る。喧騒を遮断して静寂の中へ。正直ここへ来たのは本を読みたいという理由の為ではなく、単純に入った事の無い教室を見て回りたかっただけなのだった。好奇心。それは人を動かすのには十分な理由になりえるのだ。
貸出カウンター、新刊のコーナー、新聞のコーナー、辞典の棚、調べもの用のパソコン、大きめのテーブルに、並ぶ沢山の椅子、数人の生徒、図鑑、絵本、児童書。それら全てにおれは目を奪われ、好奇心を掻き立てられた。何を読むか少し迷ったが、とりあえず新刊のコーナーにあった真新しい絵本を手に取り、雨が降るグラウンドが良く見える窓際の席へ。正直文字を読むには、まだ時間がかかってしまう為、この位が丁度良かった。
雨の音、図書室内で数人の生徒が行動する音、紙をめくる音、椅子を引く音、また紙をめくる音。そして声。
「何読んでるの?」
横を見ると、一人の男子がおれの絵本を覗き込んでいる。確か同じクラスの男子の筈だ。顔だけしか覚えていないが。浅く焼けた肌から、屋外のスポーツの習い事でもしているのだろう。髪は少し癖毛。
「面白そうだね。」
馴れ馴れしいな。まず最初におれはそう思った。いや、おれでなくともそう思う人は多いだろう。いきなりこんな風に絡まれたら誰だって少しは嫌な気を起こすのではないだろうか。兎に角、おれは読書に集中させて欲しかった(読んでいるのは絵本だが)。
「そう?向こうにいっぱい置いてあるよ。」
絵本が読みたい様なので、とりあえず絵本コーナーに行ってもらおう。出来ればそのままこちらには戻って来ないでもらいたいが。
「いや、俺はそれが読みたいなぁ。」
ニヤニヤしながらそいつは言った。おれの読んでいる「はらぺこしゃくとりむし」とかいう、どこかで似た名前を聞いた事がある様な絵本を見ながら。
「やっぱり人が読んでるのを見ると、妙に興味を惹かれちゃって。」
なんだこいつは、気持ち悪い。せめておれが読み終わるのを待てないのか。しかもいつまでこいつはニヤニヤしているんだ。何か企んでいるのか。おれに何か仕掛けるつもりなのか。何にせよ、関わりたくない。このまま立ち去るのが賢明に思えた。また後で読もう。今日はもう駄目だ。集中できなくなった。
「じゃあこれどうぞ。おれはもういいや。」
そう言って立ち去る事にする。
「そっか。ありがとう。」
更に口角を上げながら、そいつは絵本ではなくおれから目を逸らさずに答えた。おれは早々に立ち去る。図書室を出る時、一瞬だけ移った視界に、まだこちらを見ている姿があった。
何だったんだ。あいつは。
変な奴。視線が、こちらを見る視線が。どこか不自然で、違和感があって。まるでおれを品定めしているかの様な、そんな目線を感じた。必ず何かがあるなとは思ってはいたが、特に気にする素振りはしない様にしばらく過ごした。気にするのはなんとなくあいつの思惑通りになってしまう気がしたのだ。そして、どこかで見た事がある気がしたのは、やはり気のせいではないのであった。
混乱が始まった。
7
「やっぱりアイツ、ムカつくなぁ。」
アイツのあの冷静な態度がムカつく。特に皆から好かれてはいないが嫌ってる奴がいない事がムカつく。本なんか読んで頭良さそうにしてるのがムカつく。こっちの絡みを特に気にした素振りを見せずに逃げた事にムカつく。
もうアイツの全てがムカついて仕方ない。
入学式からそうだった。アイツは目立っていた。何か独特な動き、奇怪な動きで入場をして、みんなの注目を得ていた。
調子に乗るな。正直言って目障りだ。
俺が中心なんだ。クラスの顔なんだ。
早く、早くアイツを苦しめて、見下してやりたい。
ああ、楽しみだなぁ。アイツの泣きそうな顔を想像するだけで口元が緩んでしまう。
俺はきっとそういう人種なのだ。いじめっ子というやつだ。自覚はしていた。入学する前の幼稚園でもそうだった。虐める事で、悦を得る人間なのだ。
この世の中には沢山の、それはもう千差万別に、色々な事に悦を見出す人間がいる。そう俺は考えた事がある。常識では考えられない様な事に悦を見出す人間もいるのだ。それに比べれば俺なんて何てことはない。むしろ普通だ。そう考えた。我ながらなかなか酷い。
―醜い、最低な考えだと思った。
だがその考えは、そうだ、言うなれば。
守られている。
なにも俺だけが、こう思っている訳では無いのだと。俺と同じような事を考えている人間が、他にどれだけいる事だろうか。その事がこの俺の考えを、真っ黒い考えを。
灰色に。限りなく白に近い灰色にしてしまっているのだ。
一つの異端な意見は、共感によって色を濃くし、正しい、至極真っ当な意見だと思い込む事で、強くなっていくのだ。おれは異端の人間であり、特殊な感性の持ち主なのだと。そう思い込んで一体どの位経ったのだろう。気付けば俺は、他人を落し入れる事によって悦を見出す人間になっていた。
実際アイツを―、あだ名はジョンだったか。ジョンを見ていて気付いてしまったのだ。アイツは俺と似ている異端の人間だと。きっと自分勝手な思想に他人を巻き込んで悦を得ている最低な人間だ。だから少し手加減して虐めてやろう。仕方ない。ジョンもその内、自分がどれだけ最低な人間なのか、気が付く事だろう。その時のジョンの顔を想像しただけで、顔が歪に歪む。
―ああ、やっぱりここは天国だ。
幼稚園など比べ物にならない。まるで自分の「色」が滲み出てしまっているかのようだ。清々しく、気持ちがいい。これがきっと幸せなのだ。そうだ、この時、この場所は。
―こんなにも俺を楽しませてくれる。
―ジョン、お前もきっと解るはずだ。
今は嫌いだが、きっと解り合える。俺とお前は。
―同じ部類の人間なのだから。
8
4月最終週の金曜日。土日休みを前に生徒達は浮足立ち、騒めく。家族でお出掛けだったり、友達と遊んだり。そんな予定が本当にあるのかどうか。分からないままの、そんな話題達が飛び交う教室での、お昼前4時間目の算数の授業。
1時限が45分という時間割の設定は、当時のおれにはそこそこ辛い長さだった。隊長も死にそうな顔をしているし、給食を前に少しは元気を取り戻しておきたかった。
明日から休日という事で、まだ午後の授業が残っているにもかかわらず、生徒達は興奮を隠せない様子である。因みにおれはというと、いつも通り隊長と遊ぶ約束をしていた。どちらも両親が土、日曜日はいない家庭だった。いつも通り、言う事全てに「!」を付けながら、おれ達の担任イシオカ先生が授業を進めていく。
「はーいみんなー!明日からお休みだけど、まだ今日の授業は残ってるんだからねー!!それじゃあみんなー!さんすうセットのおはじきを出してくださーい!!」
数字の勉強。序盤の算数である、ものを数える勉強。何も変ではない。だがおれは非常に焦っていた。心臓が早鐘を打つ。冷静ではなくなっていた。なにせ初めての体験だったからである。
―おはじきが、綺麗さっぱり無くなっていた。忽然と、ケースから中身のおはじきのみが消失していた。どういうことだ。ついつい周りを見渡してしまう。そんな事をしても全く意味は無いのだが。不味い、イシオカ先生が授業を進めだした。どうする。
しかしこの時、まだ幼いおれは何も知らなかった。こんな時どうしたらいいのか。初めての事だったから。こんな事が起こり得るなんて、分かりもしなかったから。予想すら出来なかったから。
傍から見ておれはどう映るだろう。まさに滑稽。大いに笑える。結局おれはそのまま慌てふためいて、イシオカ先生に気付いてもらい、隣の席の女子、名前はヒラサワさんにおはじきを分けてもらい、その授業を終えた。
授業中のおれは自分に対して思う事があった。なんて無力なのだろうと。何に対してなのかは解らないが、何か大きな悪意―。そんなものを前にしているかの様な感覚を覚えた。薄々気付いてはいた。これは人為的なものだと。悪意あってのものだと。ただ、理由が見つからない。真っ白である。
真っ白な悪意。
それゆえに、自分の無力さの次におれは恐怖を感じずにはいられなかったのだ。正体不明。原因不明。意味不明。明らかでない事への恐怖。それらを前にしても、担任のイシオカ先生の様に。嫌気がするくらいポジティブに振る舞えたらどれだけ良かっただろう。否、おそらくイシオカ先生にも恐怖を感じる事はあるだろうが。
授業中、おれは明らかに動揺して、さぞ顔色が悪かった事だろう。給食の時も食欲が無かった。混乱。これは生まれて初めて直面した問題でもある。
「ジョン君。」
給食を食べ終わり、片付けをしている最中に。話し掛けられた。
「っと、ヒ・・・ヒラサワさん?どうかしたの?」
話し掛けてきたのは、先程算数の時間に有り難くもおはじきを分けてくれた、隣の席のヒラサワさんであった。勿論当時は下の名前でちゃん付けしていたが、記憶から既に抜け落ちているので苗字で表記する。おれはギリギリの所で名前を思い出し、用件を尋ねた。
「ジョン君、あのね。・・・気を付けた方がいいよ。」
「―っ、何が?」
やはりヒラサワさんも気付いていたのだと、ここで瞬時に理解した。
「ジョン君のおはじき、多分誰かがワザと隠したんだと思うよ。」
「あー、やっぱり?なんとなくそう思ってたんだよ。ありがとうヒラサワさん、教えてくれて。」
「う、うん。どういたしまして。気を付けてね。」
どうやら男子と話す事に全く言っていいほど慣れていないらしいヒラサワさんは、顔をかなり上気させながら片付けに戻っていった。気を付けてね。そう言われてもどう気を付けていれば良いのか。しかし、これで一つ確信が得られた。おれは、何かに巻き込まれてしまった。否、何かしらの悪意の標的にされてしまった様だ。
さて、どうしたものか。
9
「ジョン、あったぞ!」
結論から言うと、おはじきは見つかった。その日の掃除の時間、ゴミ箱の中から発見された。隊長はやけに自慢げに言ってくるが、ゴミ箱の中にあったおはじきを使う気にはなれなかった。
「じゃ、じゃあわたしのおはじきあげるよ。よ、予備で余ってる分あるから。」
「ホントに?ありがとうヒラサワさん!」
「じゃあこれは俺が貰っとくぜ、ジョン。」
隊長はそんなにおはじきを集めて何に使うつもりなのだろう。結局おれはヒラサワさんに予備をもらう形になり、事なきを得る。そしておれは意外にもあっさりとこの出来事を、今日この日にあった出来事を、頭の片隅へと追いやってしまうのだった。結局の所そんなものなのだ。「おはじきを無くした」という事より「友達が出来た」という事の方が嬉しいに決まっている。それこそがこの、小学校での楽しさなのだ。正直な所、誰におはじきを捨てられようがどうでもいいのだ。あまりにも単純で、あまりにも確実な事だった。
その日の帰りの時間。既に全員が下校した後の教室には、得も言われぬ情景が佇んで、おれの網膜を焼き付けていた。美しいオレンジ。教室へ入ったおれはそれを優しく纏っていた。
宿題を教室に忘れたおれは、一緒に下校していた隊長とヒラサワさんに先に帰ってもらい、急ぎ足で戻ってきたのであった。因みにヒラサワさんは地区が隣なので、途中まで一緒に下校することになった。
もう少しであの、色々な意味で面倒な先生に怒られるところだった。ほっと胸をなでおろしながら、一人で下校する。学校自体、おれの自宅から徒歩15分程といった所なので、道のり自体はそんなに苦ではない。そんな下校の道中、学校近くの公園を通り過ぎた時、見知った生徒を見かけた。
―ヒラサワさん。と見知った4人の女子生徒。
すぐそれに気が付いた。ただならぬ雰囲気に。そしてヒラサワさんの怯えた表情を見た時、それは確信に変わった。この公園でたった今、何かが起きている。保育園の頃には無かった。そうだ、言うなれば今日のおはじきの時と同じ何か―。自然とおれは公園の敷地内へと一歩を踏み出し、そして聞いてしまった。
―聞こえてきてしまった。
それは罵倒、僻み、難癖。簡単に言えば悪口を。女子生徒4人が囲ってヒラサワさんに飛礫の如く浴びせ掛ける。
何度も、何度も。何回も、何口も。交代に、交互に、不規則に、順番に、疎らに、同時に、思い付く限り、4人分を、幾重にも、反響した音の様に、何度も、何度も、何度も、何度も。
内容は、聞き取り辛いが直ぐに解った。ヒラサワさんはあんな性格をしているが、意外にも運動神経が良い。小学生の頃は大体そうなのだが(後にもう少し大きくなってから、友達との会話にこの話題が出て初めて気付いたのだ。)足が速かったり、体育で活躍できる生徒は大体異性からモテるのだった。勿論当時のおれはそんな事を知らない。ただ、ヒラサワさんが運動神経が良い事への恨みだったり、妬みだったり。荒唐無稽、根拠の無い完全なる出鱈目を吐きかけ、それを広めるつもりらしい。
ヒラサワさんはというと、既に限界を迎えていたらしく。泣きじゃくりながら小声で彼女はそれを否定していた。だがそれも、名前の知らない女子生徒4人の罵倒の渦に吸い込まれて消えてゆく。正直うるさいくらいだった。こっちはまだ入り口にいるというのに。
「ヒラサワさんは、体育の時本当に面白いね。」「4時間目の算数もジョン君に優しくしちゃってさ!」「もしかして好きなんじゃないの?」「もしかしてそれは計算の内だったりして!」「わー怖ーい!」
「ち、違うよ!そんなつもりじゃ・・・!」
当然、おれは頭にきてしまった。今日の授業でヒラサワさんに助けてもらったから特別そうなった訳では無い。今日、ヒラサワさんと仲良くなれたから、友達になったから、その友達の為に怒っている訳でもない。誰でもそうなるのではないだろうか、4人で1人を虐げているのを見た時、おれはそう思った。その形、形式、仕方、手法、手段。酷いものだと思う。保育園の頃、先生に教わった事を思い出した。
「ねぇあそこ、誰か見てるよ。」
「ホントだ、なんて誤魔化す?」
丸聞こえだった。見つかったのなら仕方ない。頭に浮かんだそのいかにも子供向け映画の中の悪役が言いそうな台詞を、少し頭の中で笑う。おれは入り口付近で様子を見ていた状態から、そのまま前進。集団の方へと一直線で歩いて向かう。視線は常に4人の女子生徒の内のリーダー格の生徒に向けている。見続ける。どんどん近付いていく。そして、正面へ。
「何!?何か文句でもあるの?」
「キモいんだけど!」
「こっち来んなよ!」
目標を切り替える暴言の嵐。しかしおれは無言だった。実際の所、何か策があった訳では無い。元々は、女子生徒達に腹が立って、ムカついて。ここへ来てしまっただけだ。リーダー格の生徒の正面に来て初めて、おれは自分の頭の中が真っ白になっている事に気付いた。だから、
「おい!何とか言えよ!」
おれは無言で女子生徒達を見続け、睨み続けた。
一瞬、ばれない様ヒラサワさんに目を向ける。既に泣き止んではいたが、それでもまた先程の勢いで泣き出しそうな状態、そんな顔を見た。違う意味でおれも耐えられなくなりそうだった。
暴言の飛礫を食らいながら、1分程が経過しただろうか。
「もういいや、行こ。こんな奴放っとこう。充分頼まれた分はイジメたしね。」
あっけなく、女子生徒達は引いた。意味深な言葉を残して。
「大丈夫?ヒラサワさん。」
ヒラサワさんは最早聞き取れない謎の言葉と化したなにかをおれにぶちまけながら、おれに抱き着いてきた。
少し、変な気持ちになったのを覚えている。
10
「ちょっとアンタ、ヒラサワさんを助けてくれたって本当?」
次の日、1時間目の授業開始前。おれは突然知らない女子生徒から話し掛けられた。あまりにも突然だったので何事かと身構えてしまった。隊長は少し離れた所から興味津々にこちらの様子を窺っている。
登校時に昨日の話を隊長にしてみると、隊長は「おぉ!遂に本気を出す気になったのかジョンよ!いやぁしかし良くやった!さぁ、その調子でこのまま黒幕を捜し出してやろうぜ!」と大興奮していた。
「そうだけど。ええっと、ごめんまだ名前を覚えきれてなくて。」
相手をよく見てみる。吊り上がった目が、いかにも強気な感じを醸し出している。服装からしても、活発そうな印象が見て取れる。そして髪型は、長めのツインテールというやつだ。なんだろう、おれは今睨まれているのだろうか。何故こちらに向けて険しい顔をしているのか。
「そう。とりあえずありがとう。私の友達を助けてくれて。」
「いや、いいんだ。たまたま通り掛かったというか。」
「あっそう。出来ればもっと早く来てもらいたかったんだけどね。」
「・・・。ごめんなさい。」
この女子生徒の後ろ、廊下側にいる隊長が、女子生徒の背中へ向けて親指を下へ向けたポーズをとっている。
「ちょっと、マーサちゃん!そ、そんな事言わないでよ。」
どうやらこの女子生徒の真後ろに控えていたらしいヒラサワさんが、慌てておれ達2人の間に入ってくる。
「いいのよ!結局アンタを泣かせたんだからこれ位言ってやっても。」
「泣かせたのはおれじゃないぞ!」
「どっちだって同じよ!」
「おう、やれやれ!」
―なんで隊長が参加するんだ。
「マーサちゃん!」
「・・・何よ。」
「もういいから。」
ヒラサワさんが泣きそうな顔になったので、とりあえず中断した。この女子生徒は如何にも不服そうな顔だったが、ヒラサワさんが出てくると弱いようだった。どうもこういうタイプの女子は苦手だ。
名前はマサコ。で、あだ名がマーサ。そうヒラサワさんが紹介した。本人曰く、「マサコってなんだかイケてないのよね。」との事である。マーサも微妙な部類なのではと思ったが、確実に面倒な事になりそうなので言及はあえてしなかった。そして話は本題へ。
「誰かが指示してた、ねぇ・・・。」
「いや、本当だって。」
「おい!ジョンの言う事が信じらんねぇのか!」
マーサがこちらに疑っているような視線を向けてくる。どうやらまだ完全に信じてくれてはいない様だ。おれはまだしも、いい加減友達のヒラサワさんの言う事くらいは信じてやったらどうなんだ。
昨日ヒラサワさんをイジメていた女子生徒達は全員が隣のクラスだった。ヒラサワさんとの直接的な関係は無い筈だ。それなのに昨日公園であの行動に出るのは不自然だ。やはり本人達の言っていた通り、誰かに頼まれてやったというのが妥当な線なのかもしれない。理由も無く、適当に理由を付けて虐めに及んだというのもあるが、それは異常過ぎる。考えたくもない。
―いやちょっと待て、何故そんな考えが浮かぶんだ。何でそんな事を予想できる。それじゃあまるで、単純に虐めをしたいが為にしただけ。そんな可能性があると、自分が考えてしまっているみたいじゃないか。
おれは何だか自分が分からなくなる様な感覚を覚えた。そして不思議とすぐに、おれの中のこの感覚を理解できた。虐めによって自分の、欲求を満たす。それがあたかもあり得る話であるかの様な。
自分がそれをよく知っているかのような。
「じゃあ取り敢えず、昨日イジメてた奴らに、警告するついでに聞いてみましょう。それで素直に答えてくれるのかは分からないけど。もし教えてくれればラッキーだわ。」
「うん、じゃあよろしく。」
「何言ってるのアンタも来るのよ!」
正直昨日の事があったので、あの女子生徒達とは顔を合わせたくなかった。おれが同行した所で話にはならなそうだったが、マーサがもし襲われた時の盾位にはなる、との事だった。勿論おれはそんな理由で「行きたくない。」と言ったが「五月蠅い。」の一言と胸部への強烈な拳を頂いたので、渋々着いて行った。どこのガキ大将だ、こいつは。
「で?何で彼女を助けてくれたの?」
「たまたま見かけたから。」
「ホントにそれだけの理由?怪しいわね、どうせそれをきっかけに仲良くなりたかっただけなんじゃないの?あの子可愛いしね。」
「そんな事無い。おれはそういう奴なんだ、別にいいだろ。」
前にそんな事があったかの様な口振りだ。いや、本当にあったのだろう。警戒して当然だ。ヒラサワさんが、おそらくクラスで上位に入るであろう人気なのは本当の事だ。最近になってクラスに馴染んできたのでようやく分かったが。
正直そんな事を言われるのは心外だったが、おれが変わってるのは保育園の時、「先生」に会ってからの事である。ジョンは変わったし、変わっていると、そう言われた事もある。なのでおれはその度にこう説明しているのだ。「困ってる人を助けたい。前にそう約束したんだ。」マーサはつまらなそうに頷いたが、それ以上は何も言わなかった。
隣のクラスへ着くと、早速マーサはおれから昨日の3人を聞き出し、1人ずつ話を聞いていった。あまりにも凄みのある迫り方をするので、女子生徒達は半分脅されるような形でマーサに話していた。特に大きな騒ぎも無く3人から話を聞き終えると、マーサは困った様な顔で戻って来た。面倒臭い事になった。そんな感じが漂ってくる顔だ。
「手紙よ。手紙が机に入ってたんだって。」
擬態の王3
11
小学校の頃、プロフィール帳というものが大いに、それはもう鬱陶しい位に流行った時期がある。持ち主が配る可愛らしいイラスト満載の専用の用紙に自分についての詳しいプロフィール、名前、住所、連絡先、生年月日に血液型、長所と短所、好きな食べ物、気になっている異性はいるかなど。沢山の事柄に一つ一つ自分についてを書き込む。今思えばあれは一つの仲良くなれるツールの様なものだったのかもしれない。しかし、当時のおれはこの用紙を突然女子に手渡されるとかなり焦った。おれはこのプロフィール帳の用紙自体が何の目的で配られているのか理解出来なかったし、あのなんとも形容し難い、解り易く例えるなら女子っぽいノリ。それがどうにも落ち着かず、変に緊張してしまって、書き終わってみれば真面目さ100%の、読んでみても絶望的に面白い要素など欠片も存在しない不毛の大地の如き用紙が完成した。そしてそれを、今でも思い出す度に一人で恥ずかしくなって、同時に後悔もしてしまう。更には最近になって、片付けた昔の勉強机の中から、書いて途中になった用紙が出てきた時はなんとも言えない気持ちになったのだった。小学生のおれは、耐えられず投げ出してしまっていた。そんな苦い思い出のツール。
そしてその上位互換こそが手紙の交換であり、当時のおれには到底理解の出来なかったものの一つである。今回の出来事にその手紙が絡むとなると、なんだかやる気の削がれる思いだが、そこら辺はマーサに任せる事にした。寧ろやってくれなきゃ困る。
「それぞれが別々の男子から手紙をもらった、ねぇ。」
ある日突然、机の中に男子生徒からの手紙が入っていた。勿論その女子生徒生徒宛にだ。この時点でヒラサワさんを虐めた4人の女子生徒は、それぞれ別の男子生徒から手紙を貰っていた。その内容を簡単に説明するとこうだ。
まず男子生徒が、自分はヒラサワさんに酷い事をされてしまった、それに対しての仕返しがしたい。だが彼女の周りには常に友達が沢山いる為自分一人では不可能だ。そこで警戒され辛い手紙の送り先の女子生徒に、何とか懲らしめてくれないかとの依頼の手紙だった。
ご丁寧に計画当日の日付と時間、ヒラサワさんの通学路から近い公園の場所まで設定してあったらしい。そして当日の下校時間、ヒラサワさんに接触しようとすると、例の4人が不思議と合流する形になったらしい。
「それで?その手紙をくれた男子とアンタらはどんな関係なのよ。」
「それは・・・!言える訳無いでしょ!」
「何でよ!答えなさいよ!」
あぁ成程、そういう事か。
おそらく、手紙を送ってきた相手はその女子生徒が気になっている男子生徒だ。しかも貰った女子生徒毎に送り主が違う。多分全員がそういう相手なのかもしれない。それについては分かったから、あとで教えてやるからもう行こう。とマーサを説得し、取り敢えずここら辺で切り上げる。
「マーサちゃんの友達に酷い事したのは謝るわ、まさか騙されてたなんて・・・。ごめんね。」
「いいえ、こちらこそ荒っぽく聞いてごめんなさい。」
なんだ、マーサもちゃんとしてる時があるんだな。失礼ながらそう思ってしまった。ヒラサワさんの親友。友達思いで、意外と芯の通った真っ直ぐな所がある。てっきりただの粗暴な奴なのかと思ったが。これは永久に口には出さないでおこう。
次に、それぞれの送り主の男子生徒達を調べる事になったのだが、男子生徒達は全員が「そんな手紙出してはいない。そもそもヒラサワさんに酷い事などされていない。」との事であった。ヒラサワさんと一緒にいれば分かる事だ。彼女は男子生徒を虐める事が出来る程の気の強さは持っていない。逆なのだ。彼女は気が弱い為に、利用されてしまったのだ。4人の女子生徒に嘘の手紙を書き、ヒラサワさんを虐めさせた真犯人に。
しかし前回のおはじきから直ぐの事だったので、勘違いかもしれないが、この二件はどちらもおれの周囲で起こっている。これは偶然なのだろうか。真犯人の狙いがおれだとしたら、またこの様な事が身近で起こるのではないだろうか。そう思ってしまう。マーサ達は気付いているだろうか。分からない。おれは気を紛らわすように、今回の件をまとめてみる。
「まず、あの女子達の気になっている男子を真似て手紙を書く。勿論直前に彼女の下校する道順と時間を調べておく。好きな人からの直々のお願いなんだから、そりゃあ協力するに決まってる。」
「真犯人は、自分で手を下してないし、もし今回みたいに発端を調べられても気にもせず、ただただ混乱しているそいつらを見て楽しんでるのよ。本当にムカつくわ。」
「お前らも良くそんな調べられるなぁ、凄いよ。」
隊長はこういう事苦手そうだしなぁ、と思いつつ最近では若干影が薄くなってきている事を少し気に病む。たまにはかまってやるのもいいか。後でうるさく言われそうだし。
実際の所、今までは隊長と2人で遊ぶ事が多かったが、この一件以来ヒラサワさんとマーサの、女子2人が加わっての4人で遊ぶ事が普通になっていった。マーサの趣味が男子っぽいという事もあったのだろう、意外と馴染むのが早かった。
そしてこの一件の真犯人。おそらくおれのおはじきを捨てたのと同一人物と予測する人物との、長い戦いが静かに始まったのだった。
「ジョン、君は本当に面白いなぁ。」
12
「じゃあみんな!今度ね、『わたしのまちを探検しよう』って授業で、みんなには班に分かれてこの町の色んな所に行ってもらいます!その後で、このクラス手作りの地図を作ってもらうよー!!ほらそこ!マーサちゃん、ジョン君の事蹴らない!」
遂にこの時が来た。この学校の外へ出る時が。授業は基本教室内、図工や音楽で教室を移動する事はあったが所詮屋内。体育でも雨続きで体育館内での授業が続いていた梅雨入りの6月が過ぎ、暑さが目立ってきた6月下旬。
公園でのヒラサワさんの一件以来、おれの周りではよくおはじきの事件に似た事が(といっても規模はそれよりも小さいものばかりだったが)度々あったが、大きな出来事は特に起きていなかった。
それにしてもゴールデンウィークは楽しかった。隊長と近くの山を走り回ったり、マーサやヒラサワさん達と一緒に休日の校庭で遊んだりもした。人気の無い校庭というのも、なかなか新鮮で奇妙だったのを覚えている。何しろ4人で遊ぶには広過ぎだった。
授業終了直後の休み時間。マーサとの何気ない口論の末、苦し紛れにスカート捲りをしたおれはマーサから強烈なミドルキックの猛烈な反撃を食らいながらも、担任のイシオカ先生の話を聞いていた。
班別での校外学習である。まず最初のこの時間で班決めをする事になっているので、早速メンバーを集め机を固めていく。勿論組むメンバーは既に決めてある。おれと隊長、そしてマーサにヒラサワさんを加えた4人。そして、
「よろしくね、ジョン君。」
眼鏡をかけた男子生徒が挨拶をする。如何にも勉強が出来そうで、大人しそうな外見をしている。
「ええっと、青山。できれば君に班長をやってもらいたいんだけど。」
「それでもいいけど、やっぱり君が一番他のみんなと仲良いんだし、君がやるべきだよ。」
見かけ通り青山は頭が良い。こういう時は良く班長などにされがちで、時々苦労している。因みに青山は本名ではない。マーサが、「アンタは紳士服の広告に使われそうなくらい綺麗な顔してるわ。でも面白味が無いわね。つまらないわ。」との事で青山というあだ名を付けられてしまった。兎に角彼は苦労人なのだ。
頭が良さそうに見えたり、仕事が出来そうに見える。だからいつも何かある毎に指揮を頼まれたり、班長を頼まれたり、マーサの様な強引な奴に無理を押し付けられる。それらを完璧にできる人間だと、優秀な人間なのだと、周囲に勘違いされてしまう。だが彼は至極普通の人間なのだ。至極普通で、平和な人間なのだ。完璧な人間など、この世にはいない。それを知ってから、おれと青山は友達になっていた。それから彼はよく一緒になるようになったのだった。
「わかった、おれがやるよ班長は。」
「ありがとう、たまにならいいんだけど。しばらくそういうのはやりたくない気分なんだ。」
自分の町にどんなものがあるのかを調べに行く授業。班ごとに分かれ、担当の地区を歩き簡単な地図を作る。それだけだ。既におれの頭の中ではピクニックの様な感覚であるが、班長になってしまっている為責任を持って地図を完成させなければならない。問題はどの地区の担当になるかだ。どうせなら行った事の無い遠めの地区が良い。探検というより、冒険がしたい。そんな一般的な男子の願望が表立って、おれを少し興奮させた。
そして運命の時。班長ごとにジャンケンをして勝った順に担当の地区を選んでいく。
「ちょっと、遠い所になる前に勝ちなさいよね。」
と、マーサが念を押してくるが、こればっかりは運である。果たしてどうなるか、分かる人などいないだろう。
ジャンケンで物事を決めて、一喜一憂。子供の頃の風景としては、あまりに生々しく、あまりに的を得た風景。そのものと言ってもいい。何回も経験した風景だと言える。遊びの時だろうと、授業の時だろうと。
そしておれはあまり勝った記憶が無い。
13
駄目だ、勝てない。何度やっても抜けられない。もう近場は完全に埋まってしまった。終わりだ。マーサが完全に人を殺す目でおれを見ている。どうして勝てないんだ。これはおれが悪いのか、おれのせいなのか。そんな事はない、これは運だ。だから仕方が無い事だ。文句があるのだったらマーサが班長をやればよかったんだ。おれは悪くない。
「まあいいじゃねぇかジョン。マーサに殴られる代わりに遠くまで探検出来るぞ。」
長い付き合いの隊長が、隣からそう言ってくる。おれが殴られる事に関しては何も無いらしい。
そしてさらに数回のジャンケンを終え、自分達の向かう地域が決まったのであった。尚マーサから受けた鉄槌に関しては、あまりにも気分を悪くする可能性が高い為説明はしない。
「ちぇっ、隣の地域の担当はフルヤ達の班か。こりゃ途中まで一緒になるぞ。」
ため息をついて嫌そうに、面倒臭そうに説明する隊長。フルヤ。そう、「彼」だ。図書室で話し掛けてきたアイツである。そして、その後すぐおれの周りで、ろくな事ではない「何か」が始まっていった。おれはそれが未だに許せないでいる。苛立ちさえ覚える。おれだけでなく、おれの周りでも起こっている何か。それに強い怒りを覚えていた。
いい加減に目星もついていた。深く考える事も無い。フルヤだ。彼がおれのおはじきを盗み、嘘の手紙を書き、マーサの椅子を倉庫へ隠したのだ。改めて彼らの班を見てみると、やはり悪さをする事で有名な奴らが集まっていた。どうせ全員フルヤの取り巻きだろう。
「結構遠いな、山の方の住宅地?いや家もあまり無いかな。」
「そうね。人気の無い別荘地もあるみたいね。正直こんな所行って調査なんてする必要があるのかしら。」
「おいおい、当日軽く調べてすぐ帰るなんてやめてくれよな。」
それは流石に手抜きなのでしない。それより当日はすぐ近くにフルヤ達がいる。十分に警戒しなくてはいけない。当日は必ず何かがある、おれはそう予感していた。
「ちょっといい?」
放課後、隊長が今日の最後の授業だった体育の後に水道水を大量に飲み、腹を下してトイレに籠っているのを待っていた時。マーサが話し掛けてきた。なにか、ほんの僅かに違和感を覚える。
「いいけど、何?」
「ちょっと来なさい。」
なんだか少し話し方が怖い気がする。おれはそのまま人気の無い校舎裏に連れていかれる。日が当たらない場所の為、少し青臭い。涼しい風が校舎裏を駆け抜けていく。マーサがおれの顔を凝視する。先程の違和感が何なのか分かった。顔が違う。これは少し怒った時の顔に似ている。知らぬ内に何かマズい事でもしてしまっただろうか。これは非常に不味い。
「アンタさ。」
今日はこんなに寒かっただろうか。刺す様な視線を犇々と感じる。そもそもおれは最近マーサに何かしただろうか。ここに来るまでによく考えてみたが、何一つ心当たりが見つからなかった。なんだというのだ。まさか遂に、ただ単にマーサのストレス解消に、理不尽に殴られてしまうのだろうか。その可能性は十二分にあり得る。覚悟を決めるべきだろうか。歯を食いしばっておこうか。そういえば隊長はまだトイレに籠っているのだろうか。流石にもう出ただろうか。頼む、助けに来てくれ。
「ヒラサワさんと一緒に買い物に付き合ってあげてくれない?」
「イッ。」
完全に予想していなかった言葉が来た。歯を食いしばっていたせいで変な声が出てしまった。
「アンタ真面目に聞いてんの?」
「う、うん。聞いてるよ。ヒラサワさん、今日学校来てたよね?何でマーサがわざわざ言いに?しかもこんな所で。」
「アンタには関係ないでしょ。ヒラサワさんは・・・恥ずかしがりでしょ?だからアタシが。」
成程、そう言われればその通りな気もしてくる。ヒラサワさんの性格からして、教室で面と向かってこんな誘いはしてこない気がする。何か手伝って欲しい事でもあるのだろう。おれは二つ返事で承諾した。
「・・・そう。じゃあ本人に伝えておくわ。」
「え?それだけ?」
おれはマーサがそのまま引き返して帰ろうとするので驚く。
「なによ、他に何か無いといけないの?」
「いや、そんな事無いけど・・・。」
約束の日を教えてもらう。帰っていくマーサを見つめながら考えに耽る。なんだか今のマーサは変だった。怪しい。しかしヒラサワさんからの頼みだ。快く引き受けようじゃないか。楽しみだ。校舎の窓の一つから神、神と連呼する声を聞きながら、おれは帰り道へと急いだ。
14
「おいジョン!今日は何の日だ!?探検の日だぞ!」
晴天。世はこの天気をさぞ喜んだり称えたりするのだろう。しかし全ての人間がこの天気を喜ぶ訳ではない。登校中に隊長がハイテンションでおれに教えてくる事実。今日はそうか、探検の日か。雨は降らなかったのだ。受け入れよと、そうお天道様がおれに言っている気がする位豪快に晴れてしまった。
やめてくれ、最初こそは楽しみでいたが、今となっては今日の事は本当に憂鬱でしょうがない。こうなれば今日はさっさと済ませてその後に控える休日のイベントに集中したい。なぜか楽しみでしょうがない、そのイベントの詳細は全く分からないが確実に今日より楽しいものになるだろう。なぜなら一緒に行くのはあのヒラサワさんだ。人畜無害そのものを体現したような。マーサなんかとは比べ物にならない接し易さ、優しさを変え備えた完璧な人だ。平和に過ごせる事はすでに確定しているようなものだ。
「ジョン君、おはよう。」
青山だ。どうやら先に登校していたようだ。ランドセルも教室に置いてきているらしい。
「どうやら今日は集まった班から先に出発していいみたいだ。もうマーサさんとヒラサワさんも来てるし、早く出発しよう。僕達の担当地区はちょっと遠いからね。」
「分かった。じゃあすぐにランドセル置いてくるよ。」
そうか、もう出発なのか。そう憂鬱さを自分で増幅させながら教室へ向かう途中で、教室方面から来たマーサとヒラサワさんに会う。
「ジョン、アンタ班長なのに遅過ぎない?自覚が無いんじゃないの?」
いや、別に好きでやっている訳では。いや、これは言わない方がいいか。推薦してくれた青山に失礼だ。それにもし、少しでも漏らせば余計マーサの怒りを買うだけなのは知っての通りだ。暴力には屈したくないが、未然に防ぐ事も重要なのだ。
「ゴメン、マーサ。すまないと思ってるよ。反省してるし、今日は頑張って班長の仕事をするから。」
脛にローキックを食らう。結局か、否。ローキックで済んだ。という結果かもしれないが。
「ワザとらしいのよ気持ち悪い。まったく、青山なんて家が一番遠いのに最初に来てるのよ、しかも班長でもないのに。それに比べて当の班長は一番最後だし。」
青山、早く来過ぎだ。変な所で真面目過ぎだぞ。少し恨んでおく。脛の分だけ恨む。
マーサとヒラサワさんと別れ、隊長とランドセルを置きに教室へ。実は席替えを最近した。マーサが前の方でおれは後ろの方。これは本当に良かった。隊長はマーサのすぐ脇になったが。未だにあまり話した事の無いクラスメイトはいる。席替えをする度にそういった人達と関わっていくのは何回行おうが最初は慣れないものだ。そう思う様になっていく。今はまだよく分からなくとも、きっとそうなる。これからきっと必要になるから。
既に出発している生徒はまだ少ない様だ。ふと、ある一角で2、3人の取り巻きと一緒にいるフルヤと目が合う。フルヤはこちらに気付くと、
「やあ、ジョンじゃないか。今日は楽しみだね。俺の班は隣の地区だけど、もしかしたら一緒になるかもね。」
絶対に何かしてくる。いや、もう既にしているのか。分からないが、兎に角自分の班はこいつらより先に出発した方がいい。離れなければ。
青山は早く来ていたが、あれは恐ろしい位に正論で、正解だ。本人がどう思っていたかは知らないが、正しい判断だった。おれはフルヤを睨む隊長を引っ張り教室を後にする。頭の中は、今日、どうやってフルヤ達をやり過ごすか、その事でいっぱいだった。またヒラサワさんにあんな思いをさせる訳にはいかない。絶対に。
唐突に、引っかかった。隊長を引っ張りながら、廊下を速足で歩きながら。何が?先程の決意が。ぶれて見えた。先程の言葉に、引っかかった。ヒラサワさん。もうあんな思いをさせるのは、可哀想だ。見ていられない。ついつい感情移入してしまう、自分も悲しくなってしまう。それが嫌だ。自分がそんな状態に陥るのが怖い。
さっきの言葉は本当なのか。二度とあんな思いはさせない。それだけなのか。自分が面倒を被りたくないだけじゃないのか。本当におれは正しい事をしようとしているのか、「先生」との約束を、守ろうとしているのか。最近覚えた言葉でいう「正義」を果たす気で、自分は今ここにいるだろうか。果たしてそれは、本当の「自分自身」なのだろうか。黒が、絵具を極限まで混ぜ込んだような蠢く黒が、ぶわっと。背中を登った。
「ジョン君。」
気付く。もう昇降口に来ていた。マーサとヒラサワさんが待ってくれていたようだ。
「顔色、悪いよ。」
「大丈夫、さっきマーサに脛蹴られたからだよ。」
「もう一発蹴るか?」
足取りは重い。そろそろ出発の時間だった。
15
「そもそも人が住んでる地区なのか?」
「まあいるからこんな事しに来てるんでしょうけど。」
出発して大分歩いた様だ。距離的にも一番遠い地区なので仕方ないのだが。5人でくだらない会話をしながら歩いていた為、それほど長く感じることも無かった。
そこは静かな地域だった。傾斜のあるコンクリートの塀が道を両脇から挟み、視界は遮られている。塀の上は高い藪が生い茂っていた。よく見ると藪の中にうっすらと廃屋が見える。たまに現れる石の階段を使って塀を上がれば、そこは廃屋の集合する住宅地だった。上がってみて知る。近くに新しい家屋は無い。緑っぽい色の池が見えたくらいだった。
勿論この班のテンションは下がった。だが、人を見つけないと終われない。何も進まない。
「兎に角、誰か人を捜そうよ。何か良い情報が聞ければそれで終わりにできるかもしれないしね。」
「青山が言うならそうしましょう。いや、そうしないと終わらないもんね。」
マーサは青山には優しいんだな。食ってかからないし、扱いが違い過ぎる。しかし青山の言う通り、兎に角人を捜して話を聞こう。それにさっきから歩き続けているが全く景色が変わらない。はっきり言って気味が悪い場所だ。
廃屋をさらに何件か回った後、青山班長率いる一行は三叉路に出た。こちらが来た道ではない方の、その分かれ道に。分岐の丁度境目に、地蔵が立っていた。突然に現れたかの様に。屋根は無く、ほぼ野ざらし状態で。正直に、素直に言って、気味が悪いと思ってしまった。地蔵には申し訳無い事だ。おれは猛烈に自分を恥じていた。この地蔵は好きでこの様な扱いをされている訳ではないのかもしれないからだ。
「なにこの地蔵、気味悪いわね。なんでこんな道の真ん中にあるのよ。」
感じ方は人それぞれという言葉がある。その時、その瞬間に感じるもの、感情は必ずしも同じではない。世界は決して一つの意思、思考や感情で動いてなどいないのだ。だから今マーサが放った言葉も、全くおかしな事ではない。きっとそうだ、おれはそう考える。
一行は地蔵のあった分かれ道を右に。この不気味な地域を奥へ奥へと進んでゆく。もうこんな状況、テンションではもう早く帰りたいと思っていた。それはおそらくおれを含めて全員がそうであっただろう。無言で歩を進める他のメンバーを見ればすぐに察する事が出来た。天気は。曇り始めてきた。
早く帰りたい。
一件目。人気の無い別荘。車はある。青山がチャイムを鳴らす。返事は無い。次へ。
二件目。平屋建ての廃墟。屋根が落ちかけている。犬小屋があり、中に野良犬か何かが置いていったのであろう得体の知れない死骸。次へ。
三件目。少し古めの二階建て。マーサがチャイムを鳴らす。否、鳴らない。マーサが悪態をつく。次。
四件目。ガタガタの平屋建て。車は無い。青山がチャイムを鳴らす。出ない。次。いた。人がいた。おばあさん。戻ろうとして振り返ると、お婆さんがいた。何も突拍子も無く。いた。上手い表現が見つからないが、こう言うしか無い。振り返れば、そこにいたのだ。全員固まっている。ヒラサワさんは特に酷い。青い顔で、見ていてまるで今にも気絶しそうだ。全員が驚いた、というよりは完全に意表を突かれて動けなくなった、というのが正しいのかもしれない。そうだ早く、青山、話し掛けろ。頼むから。
「こんな場所に小学生が来るなんて珍しいね。何かの授業なのかい?」
そうこうしている内に向こうから優しく話しかけてきてくれた。良い人そうじゃあないか。これなら直ぐに終わるかもしれないぞ。
「え、ええッと。こんにちは。」
青山がカチカチに固まったままで話をなんとか進める。こちらで話を聞いている限り、とても人の良さそうなお婆さんである。と言うより、絶対に優しい人だ。小学生相手に、しっかり話を聞いてくれて。それにちゃんとおれ達に解り易いように話をしてくれている。メモを取るマーサにも合わせてくれている。このお婆さんが良い人だと証明するには充分である。
結果、取材は上々の結果で終わり、お婆さんから充分な成果が得られたのだった。判明した事。この地域には何も無い。何も無いという事が判明した。以上。さあ、帰ろう。そうして青山班一行はお婆さんにお礼と挨拶をして、引き返す。
「ああ、そうだった。」
お婆さんがそっと、ふっと、風を送るように。呼びかけ、呼び止める。
「アンタ達、お地蔵様を見てないかい?もし前を通ることがあって、お地蔵様が倒れたり、悪戯されたりしていたら、直してやってくれないかね?私が大事にしているお地蔵様なんだ。」
それなら。と、青山は承諾し、一行はお婆さんの家を後にする。お婆さんはおれ達が見えなくなるまで見送りしてくれた。お婆さんが言っていた地蔵は、おそらくさっきの三叉路で見た地蔵の事だろう。さっき通った時は特に何も無かったので大丈夫だとは思うが。
擬態の王4
16
驚くべき事が起こっていた。大変な事が起こっていた。恐ろしい事が起こっていた。兎に角、色々な事が起こっていた。班の全員がパニック状態だと言ってもいい。問題が。片付けるべき、処理すべき事柄が突然、どこからともなく現れて、素早く一瞬でおれ達を取り囲んだのだ。何も考えられない。考える余裕が無くなる。頭が真っ白になる、とよく言うが、この場合は違った。ぐるぐると、回る。視界が、頭の中が、回る。吐き気すら覚える。どうしてこんな事になったのか、どうすればこの状況から抜け出せるのか、一体何が起こっているのか。分からない。何も、分からなくなっていた。パニックに陥っていた。班の一人残らず。
まず、何が起こったのか。先程のお婆さんの家を後にした班の一行は、来た道をそそくさと引き返した。もう充分だと思った。何も無いという事が分かったのだから、それだけでも価値がある。否、それしかない。地区的にも少し遠いので、早めに引き上げなければならなかった。そして、先程の地蔵があった三叉路に差し掛かった時、気が付いた。誰が、というより、全員が。ほぼ同じタイミングで全員がその異変に気が付いた。両側を高い壁に囲まれた古い道が交わる三叉路、その中心。古びたボロボロの屋根の下に置かれた地蔵。全員がそれを凝視し、目を疑い、次に青ざめた。地蔵は倒され、首が折れてしまっていたからだ。当然だが最初にこの地蔵を見た時、こんな状態にはなっていなかった。その場にいた全員、確かに覚えている。この地蔵は、あの時立っていた筈だ。そしてそこから分かる事は、誰かがこれを倒したという事だ。
「いや、でもこの辺りは誰もいないんだぜ?どういう事なんだ。」
隊長の言う通り、この地区は人などいないに等しい。あのお婆さんの家からこの地蔵まで、それほど距離は空いていないし時間も経っていない。おれ達がお婆さんの家で取材をしている間に誰かが倒したのなら、まだ近くにその人物はいるのだろう。
「とりあえず、さっきのお婆ちゃんに報告してきた方が良いんじゃない?アタシ達じゃあどうしようもないわよ。ヒラサワさん?大丈夫?」
青ざめて動かなくなったヒラサワさんはとりあえずマーサに任せる。この状況では、どうやら一度お婆さんの家へ引き返した方がよさそうだった。
しかし、引き返した先で次の問題が起こった。先程の場所、取材をした家へ戻って来たのだが、お婆さんが見当たらない。ほんの数分前の話だというのに。見当たらない、と言っても外だけではない。玄関の戸を開けて読んでも返事は無いし、家の中はもぬけの殻だった。綺麗過ぎるほどに。そこは廃屋だった。比喩ではない。この場所に人がいないのは当然じゃないか。ここは廃屋なのだから。あのお婆さんはきっと他の場所に住んでいるのだろう。このままではどうする事もできない。地蔵をそのままにして帰るのは罰当たりだと、誰でもそう思った。だが不幸はまだ湧いて出てくる。次々に。
「やあ、奇遇だね、ジョン君。どうしたのさ、班のみんなが青白い顔をしてるぞ。そんなに俺が怖いのか?」
「最初からここに来るつもりだったんだろう?フルヤ君。」
「そんな事無い。担当地区の調べものが終わって、たまたま通りがかったら君らがいたんだ。なんだか困ってるみたいだから、手伝ってあげようと思ってさ。」
そう微笑を浮かべて話すフルヤ達は3人。明らかに自分の班を抜けてここへ来ている。わざわざ、おれ達の班の邪魔をする為だけに。可哀想に、フルヤ達が抜けた班は今頃こいつ等を捜し回っている事だろう。
「アンタ、この後学校へ戻ったら先生に怒られるんじゃない?知らないわよ。」
「大丈夫だろ。迷子になってた、で済む。」
フルヤは少しずつ、口調が荒くなってくる。あの雨の日に、初めて話した時とは全く違う。隠された本性が、少しずつ露わになってきていた。
「ジョン、俺はお前に聞きたい事があってさ、わざわざ会いに来たんだよ。少しは歓迎してくれよ。」
「フルヤ君、実はおれ達も聞きたい事があるんだ。それに答えてくれれば、いくらでも付き合うよ。」
「は?なんだよそれ。言ってみろよ。」
「フルヤ君。君があの地蔵を壊したのかい?」
17
「はぁ?何言ってんだよお前。バカじゃん。最初から倒れてただろうが。」
この一言を聞いて、足元の地面が消えて無くなる様な感覚を覚えた。フルヤは関係ないのか、地蔵を倒してなんかいないというのか。本人は拍子抜けしたような、本当に何を言っているのか分からないと言うかの様な顔をしている。完全なパニックに陥ってしまいそうだ。
「それより、なあジョン。」
フルヤは勝手に話し始める。話したくて仕方ない様だ。こちらはそれどころではないというのに。フルヤ。こいつがヒラサワさんを陥れ、皆を騙して、笑うような奴だ。それなのに最近は何故か皆の遊びの中心に居たり、先生に褒められたりしているのだ。その裏で他人をあざけ笑っていると、誰も知らないのだ。思い出しただけでも頭に血がぐつぐつと上る気がする。
「お前さ、俺と一緒だろ。そんな気がするんだよな。お前も誰かしら虐めたり、悪さしたりしてんじゃないのか?絶対そうなんだよ。ジョン。お前は俺と同じ。誰か他人を良い様に使って楽しんでる。そうだろ。」
何を言っているんだ。
「後は、家で独りだったりするのか?」
「フルヤ!早く自分の班の所に戻りなさいよ!」
「うるせぇな、黙ってろよ。」
フルヤは完全に素の口調になったようだ。
「そうだね、おれは君と同じかもしれないね、うん。」
フルヤの口元が緩んだ。続けて言ってやる。
「おれは虐めをするし、悪さだってする。他人を良い様に使ってる。これでいい?早く戻ってくれ。」
勿論、嘘だ。適当だ。フルヤに早く行って欲しいから適当に答えた。そんな事は絶対に無いと、他の人は知っている。フルヤは充分な答えが聞けたかの様な顔を見せるとこの場を離れる。彼は微笑のまま言う。
「じゃあな、ジョン。なんだか知らないけど、頑張れよ。」
結局、フルヤは何がしたかったのだろうか。おれからあんな事を聞き出した所で、一体何になるというのか。しかもおれがフルヤと一緒だと言っていた。それを思い出して、つい虫唾が走る。
「早くどこかに行けよ…あの野郎。」
フルヤはこの場を楽しむかの様にゆっくりと遠ざかって行く。そしてそれを隊長がまるで牙をむき出しているかの様に睨む。やがてフルヤが見えなくなると、青山が口を開いた。
「じゃあとりあえず…フルヤ君も行った事だし、このお地蔵様を起こしておこうか。」
「そうよね、そのままにしておくよりはマシだわ。」
その場にいる全員で協力して地蔵を起こす。勢いよく倒れたのが原因なのか傷が目立つ様に残ってしまった。真っ白い新しい傷が。折れた首はなんとか元の位置に乗ってくれた。なんとも痛々しい姿に、不安がよぎる。もしかすると、最初に地蔵を倒したと疑われるのは自分達なのではないか、と。
「お婆ちゃんに報告したいのに、見つからないんじゃあどうしようもないじゃない。学校に戻りましょう。先生に代わりに伝えてもらえるかもしれないわ。」
「僕もマーサに賛成かな。ジョン、君はどうだい?」
異論の出しようがなかった。もう自分達だけではどうする事も出来ない。それに子供だけでこの人気の無い場所に長居する事だって良くないに決まっている。おれは2人に続いて賛成する。
「じゃあ、学校に戻ろう。」
「まって、ジョン君。そっちは今来た道だよ。」
「え?そうだっけ?ありがとうヒラサワさん。」
「あんた達は馬鹿なの?こっちなんですけど。これ以上イライラさせないでよね。」
「え?」
「え?なんで…。」
それぞれがバラバラに方向を示していた。
18
「じゃあ次はジョンの言ってた方向へ行くわよ。それで駄目だったらいよいよ迷子よ、迷子。」
「分かってるよ、頼むから黙っててくれ。」
地蔵のある三叉路でおれとマーサ、そしてヒラサワさんはそれぞれ違う帰り道を指差した。混乱したが、とりあえず道を一つずつ試してみる事にしたのだった。しかし、最初にマーサが指し示していた道を進んだ時、たどり着いたのはこの地蔵のある三叉路。しかもヒラサワさんの指し示していた方向から出て来てしまった。これで残すはおれの指差した方向のみである。そう、これが正解だったのだ。2人とも気が動転して記憶が曖昧になってしまっていたのだろう。この道を進めばすぐにこの地区を抜けられる。そうすればすぐに学校に戻れる。簡単な事だ。フルヤの奴がこんな時に場を搔き乱して帰っていったせいで、面倒な事になってしまった。帰ったらイシオカ先生にこっ酷く怒られるに決まっている。ざまあみろだ。
さて、そろそろこの道からどこかに出そうだ。早く学校に急がなくては。集合時間に遅れてしまってはフルヤと同じくイシオカ先生に怒られる羽目になってしまう。どうやら抜けた先は三叉路の様だ。その一角には小さな小屋の様なものがある。
地蔵だ。首は不自然に体に乗っていた。
「どうして!?これって、アタシが指差してた道じゃない!」
「うっ・・・、っく・・・。」
後ろでヒラサワさんが泣き出したのを感じる。横の青山は、少し動揺して辺りを見渡している。マーサはすぐにヒラサワさんを慰めにかかっていた。
「大丈夫、ただ道に迷っただけよ。それに、帰りが遅くなれば先生達が迎えに来てくれるんだから。少し落ち着きなさい。」
少しは俺達にもそんな風に優しく接してあげられないのかね。動揺を隠すようにそうふざける隊長を横目に、おれは青山と辺りを見渡す。
「確かに、ここはさっきの場所に間違い無いみたいだね、地蔵も首が折れてるし。ジョン君、これは完全に迷ったかもしれないね。この場所がよく分かってない状態で、あまり歩き回るのもかえって危険だし。どうしようか。」
他の3人に聞かれない様に青山が言う。不安にさせない為の彼なりの優しさだろう。しかしどう考えてもこの状況は明らかに、完全に何かがおかしい。マーサの道はヒラサワさんの道と繋がっていた筈だ。なのに何故、おれの道を進んで辿り着いたのがこの場所、しかもマーサの道から出てきたというのか。さっぱり意味が解らない。
「青山、やっぱりもう少し3つの道を調べてみない?どこかで道を間違えたのかもしれない。おれにはそうとしか考えられない。」
「でもあの3つの道は、ほぼ一本道だった筈なんだ。間違えるなんて、そんな事あるのかどうか。まあもしかしたら、見落としている所があるかもしれないね。後は、誰が行くかだね。」
流石に女子だけを残してこの場を離れるのは良くない気がする。となると、隊長とおれで行った方が良いのか。とりあえず先生達が気付いて迎えに来てくれるまでは、なんとか自力で帰り道を探してみるしかない
。
「おや、アンタ達。まぁだこんな所にいたのかい?」
19
心臓が飛び出るかと思った。その声は自分の真後ろから聞こえたからだ。お婆さんが真後ろから声を掛けてきた。それだけなのだが、突然過ぎて本当に驚いたのだ。
「あ、あの。僕達帰り道がわからなくなってしまって。いや、それより前に地蔵が!」
「地蔵かい?地蔵がどうしたんだい?」
「その、倒されてしまっていて、首が・・・。」
「んん?倒してしまったのかい?首も取れてるねぇ。誰がこんな事をしたんだろうねぇ。」
「それが分からなくて、ずっと報告しないとって思って探してたんです。」
「そうなのかい、でもおかしいねぇ。」
お婆さんの口元が変に歪む。それは笑みだった。
「ここら辺に人なんてほとんどいないのに。あなた達が来た途端倒れるなんて、やっぱりおかしいねぇ。」
「そんな、アタシ達は倒してなんかいません!本当です!」
マーサが声を荒げ否定するが、お婆さんには通じていない。更に口角を尖らせ、不気味な笑みを作ってゆく。班の全員が、寒気を感じていた。なんだこの人は。何かが変だ。
「そうかい。あなたたちじゃあないのかい・・・。じゃあ一体誰が・・・。」
そう言いながらぶつぶつと呟きながらお婆さんは、無残な姿になった地蔵の周りを推理して犯人を捜すかの様ににうろつき始める。そしてそれを全員が見守った。「どうするの?」とマーサが目で訴えかけてくる。そんな事分かる訳が無いだろう。それよりもヒラサワさんが今にも泣き出しそうだ。おれは最後の頼みの綱、青山に視線を送るが、彼は青白い顔をしてお婆さんを見つめるだけだった。もうお手上げだ。こうなったら隊長にお婆さんと話してもらい、この件はもう終わりにして帰ろう。早く帰らないとそろそろ時間もまずい。
「お前達が!」
力む。一瞬で全員が震えと共に硬直してしまう。大きく背が曲がっている、その弱弱しい老体からは想像もつかないような、とてつもない大声が発せられたからだ。まるで今いるこの三叉路に、この空間そのものに大きく反響して増幅しているかのような、そんな巨大な音の爆発だった。ヒラサワさんは腰を抜かして静かに泣き出してしまっている。マーサと青山は完全に混乱した様子だし、隊長も言葉を失ってしまっていた。お婆さんは班の全員に背を向けて立っている為表情は窺えない。そして更に音の爆発は続く。
「お前達が破壊したのか!この地蔵を!」
「どうせそうに決まってる!ああそうだとも!」
耳鳴りがしてきた。頭もガンガンして思考が上手く働かない。
「ごめんなさい、ごめんなさい・・・。」
突然ヒラサワさんがなぜか謝りだした。それでも音の爆発は止まない。
「ヒラサワさん!どうして謝るの?」
近づいた所で何も聞こえない。こちらも大声を出してヒラサワさんに呼びかける。
「餓鬼共が!何をしに来た!?」
「ジョン君・・・お婆ちゃんが、なんか変なの!」
「変って!?もう全部変じゃないか!」
「何をしに来た!何をしに来た!」
「顔が!」
え、と視線を送った先。三叉路の向こう、地蔵の前に立つ老婆はこちらを向いていた。気付けば声が、あの音の爆発は止んでいた。怒りは収まったのだとほっとして、彼女の顔色を窺おうとして。息が止まりそうになった。
顔の下半分を、横に走る弓なりに下方向に曲がった線があったからだ。耳の辺りまで裂けてしまったかのような、そんな口が見えて。恐怖に目の焦点を反射的に外し、ピントを手前へ。顔の輪郭が、明かに変だった。人間の輪郭ではないし、人間の顔のパーツ配置でもない。自動的に更に焦点が手前に移動してゆき、おれは全身を見ていた。それは獣だった。人の姿形を真似た獣の様な姿。二本足で立つ。獣。更に目を動かそうとして、異変に気付いた。目線が、動かせないのだ。そこで初めて、自分の心臓が暴れ狂っている事にも気付いた。目線が動かせないのは、自分の身体自体が固まって動かせなくなっているからだ。
その時、誰かの大きな悲鳴が聞こえてきた。その瞬間、体が自由になる。動ける。逃げよう。そう一瞬で判断して、おれはヒラサワさんの手を引いてその場から逃げ出す。青山がマーサの手を引いて続く。隊長は一番先頭で道を先導する。我武者羅に走る。爆音はまた鳴り出していた。「お前達が!お前達が!」と繰り返している。もうあの三叉路に戻される事はなかった。
「お、おい!おい!あれ見て!」
青山が叫んで指差した先に、両側を傾斜のあるコンクリートの塀が挟む道、その終わりが見えた。入ってきた場所だろうか。いや何処でも構わない。ここから出られればそれでいい。声は遠くなったがまだ聞こえる。とにかく。
走れ。
20
結論から言うと、脱出は出来た。しかし何故かフルヤ達の班と合流する形になってしまい、
「あれ、ジョン。お前らここで何やってんだよ。そんなに走って、もしかしてもう時間ないのか?馬鹿だなお前ら、結局遅れてるのかよ。」
「テメェなんでこんな所に!」
無論揉めた。特に隊長が。こっちもパニックだった為、フルヤ達のお陰で平静を取り戻したのだった。そしてそのままフルヤ達を置いて小学校へ戻った。幻。そう決め付けて、その話は避けて学校へ帰った。結局、その話が再び出たのはその日の放課後。
「ジョン、アンタちょっと付き合いなさい。」
マーサと学校帰りに公園へ。少し前に、ヒラサワさんが酷い仕打ちをされていたあの公園だ。そういえばヒラサワさんの様子はどうだろう。訊くと、
「あぁ、その、何ていうか。あの子メンタルがちょっと弱いじゃない?それで、あんな事。限界を超えちゃったみたいっていうか、なんか記憶が飛んじゃってて。まあ好都合よね。うん。」
「・・・。」
少しヒラサワさんを不憫に思いつつ安堵した。
「それで、本題だけど。」
「やっぱり、あのお婆ちゃんがいた地区の話?」
「・・・狐。」
「狐?」
「私は、ね。そう見えた。最後あのお婆さんが。それで、少し調べてみたのよ。そしたら、神社とか、祀られてるものだとか。そういう神聖なものもあるらしいのよ。だから、もしかしたらあのお婆ちゃん、ていうか狐はそういう『何か』だったのかもしれない。あと、あのお地蔵さまがあった所。地図には無かったわ。それだけ。」
「そっか、やっぱりそうだよなぁ。」
「化かされた。ってやつ?」
「何か昔にあったのかもしれないね、あの地区で。それに、あんな風に、人もいなくなって。少し可哀想って思った、かな。」
「そうね・・・あっ。」
「どうしたの?」
「それ、後で記事にまとめるわよ。なんだか面白そうな記事になりそうじゃない?こんなのどこの班も、いや、今まで誰も書いてないわよ!」
因みにその後、おれ達の書いたヘンテコな記事が先生達の目に留まり、呼び出しを食らい書き直させられる事になるとは、おれとマーサは考えてすらいなかった。あの場所で起こった出来事は話していない。どうせ信じてもらえないし、あまり思い出したくもないからだ。きっともうこの話題を自分達の中で出す事も無いだろう。
「マーサは凄いね。おれはもう疲れちゃって何も考えられないよ。何て言うんだっけ。プラス思考、ってやつ?」
「そうよ、アタシはそこらの情けない男には負けないつもりよ。」
「そっか・・・。」
あ。
「そういえば、やっぱりあの時の悲鳴ってマーサの?」
答えは蹴りで帰ってきた。
21
「あの・・・ごめんね。マーサが無理矢理に誘っちゃって。」
「いや良いんだよ。どうせ暇だったしね。」
あの壮絶な体験をしてすぐの週末。おれとヒラサワさんは自転車を長めに漕いで駅前に集合していた。駅前、と言われれば聞こえは良いのだが。実際は柵があまり意味を成していないほぼほぼ剥き出しの線路に、こっそりと、そっと寄り添うようにプレハブとも倉庫とも言えるような、粗末な駅舎がおまけ程度に付いているような光景だ。他の駅はここ程ではないのだが、おれとヒラサワさんの所謂最寄りの駅にあたるのがこの駅なのである。
おれは無駄に広い駐輪場に自転車を停めると(鍵は掛けない。掛ける必要があまり無いような地域だからだ)、駅舎の入り口前、今にも落ちてきそうな屋根下の外灯。その真下を右に避けるように立つヒラサワさんと合流した。実はこの駅から数駅先が、大きな街になっている為、そこへ出かけようというのが今回の日程である。大人がいないとはいえ、あまり電車には乗らないので少し緊張していた。ホームで電車を待つ間、気を紛らわそうとして校外学習、あの狐に化かされた時の事を話してしまったが、ヒラサワさんは上手にそこだけ記憶を消した上で話を合わせてくれた。流石だ。
「今日は何か街に用事があるの?」
「えっとね、服を買いたいなって。お母さんにお小遣いいっぱい貰って来たんだ。ジョン君にも意見を聞きたいなって思って。」
「え~、おれそういうのよく分からないけど大丈夫かな・・・。」
「大丈夫だよ!あっ、ごめん大声出して。思った通りに言ってくれれば、それでいいから・・・。」
成程。まずは服を見るらしい。確かに街の駅ビルやら駅前のショッピングモールには衣料品店が大量にある。子供服とはいえ、選択肢は多そうだ。
電車がやってきて、ゆっくりと目の前で止まる。車両は一両編成。車体の至る所に錆が目立つ、年季の入った電車だ。なんともこの駅には映える見た目である。乗り込み中を見渡す。乗客はちらりと見た感じ4、5人と言ったところ。二人掛けの座席、窓際にヒラサワさんが座り、おれは通路側に座る。そして古びた電車はゆっくりと田園地帯の上を走り出す。
「そういえばね、遅くなっちゃったんだけど、この前はありがとう。まだ言えてなかったよね?ごめんなさい。」
この前、というのはきっと公園のあの一件の事だろう。おそらくフルヤが女子生徒を利用し、ヒラサワさんを虐めさせた事件である。今はもう落ち着いて影も無くなったが、あの一件以来ヒラサワさんとマーサの二人と一緒に行動する事が多くなった。あれがきっかけで、頼もしい同士が出来たのだ。フルヤに対抗する同士が。
「校外学習でもそうだったけど、わたし本当にいつも役に立てなくて。ジョン君には迷惑かけてばっかりで・・・。」
「気にしないで、ヒラサワさん。おれはそういう人を助けたいんだ。なんというか、そうすると元気になれるっていうか、気持ちがいいっていうか。兎に角おれは絶対迷惑に思ってないよ。」
ふふっと笑うと、彼女は温かい眼差しを向けてくる。
「やっぱりジョン君は凄いよ。わたしも、マーサみたいになれたらなって。いつも思ってるんだ。そうだったらきっと、この前みたいにならなかったと思う。」
「それは違うよ。」
それは違う。おれはそう思った。それは何故か。フルヤの事だ、誰か別な標的を見つけてくるに決まっている。自分の娯楽の為と、彼はあの校外学習で言っていた。娯楽の為に多少の苦労はいとわない、そんな人間だという事はもう理解した。
「兎に角、ヒラサワさんはそのままでいいんだよ、きっと。」
そのままでいいと、そう思った。理由は解らない。小学生にそんな事分かる訳が無い。でもそう思ったから、そう言った。ヒラサワさんはこちらを見つめ、少し口角を上げると、
「ありがとう。なんだかジョン君に言われると嬉しいな。」
そんな事を言った彼女の後ろに街が見えてくる。今日は楽しい休日になりそうだ。
22
「本当に失望した。」
なかなかどうして、彼は本当の事を言ってくれない。
本当の自分を認めてくれない。
どうしたらアイツと仲良くなれるのか、考えていた。いつも俺が下らない学校生活を掻き回してやろうとすると、アイツが邪魔をしてくる。割って入ってくる。何度も何度も、しつこい位に。
だから、考えてやった。アイツをこちら側だと気付かせる為の方法。そして尚且つ俺の学校生活も楽しくなる方法だ。
「なぁ、サダ、ゴウチ。」
この二人の男子は、俺の考えに賛同していつも一緒に行動している。がりがりに痩せた方がサダ。がっしりとした体格をしている方がゴウチ。この間の校外学習でも一緒にアイツの班の所に行った。
「このままアイツ等と、反発し続けることにしようぜ。この6年間、ずっとだ。アイツがボロを出すまで、続けてやる。アイツに、訴え続けてやるんだ。お前はそんな人間じゃあない、お前は他人の抱える問題を自分で解決してやって、ソイツより上だと悦に浸ってるだけだ。お前は、俺達と一緒にいるべきなんだってな。分からせた上でいつか中学へ一緒に行くんだ。これなら6年間退屈しないで済むし、アイツを引き入れて中学へ行ける。そこでもっと大きな事をするんだ。最高だろ?」
「ハハハ、 確かに!」
「ああ、いいな。それ。」
「だろ?俺は決めたぞ。絶対にやり遂げてやる。絶対に、ジョンを、解らせてやるんだ。」
―あぁ、楽しみだなぁ。
夕暮れ時の公園の隅で、フルヤ達三人は決心した。その目的は歪んでいたが、その芯はただただひたすらに真っ直ぐだった。
「どうしてそこまで人助けにこだわるんだ?どうして数ある問題の根源の俺の話をろくに聞いてくれない?どうして、お前の家の事を誰も知らないんだ?俺はお前の事をもっと知りたいんだよ。だから教えてくれよ、ジョン。俺達もう仲間みたいなものだろ。ははは、そうはならないか、まだ。でもな、ジョン。俺はお前が自覚するまで続けてやるぜ。何年かかろうとだ。小学校が終わってもいい。絶対にやめない。それが俺の、お前へのおせっかいだ。」
そして、それから長い長いフルヤ達との確執が始まったのだった。特にここで述べる程の事ではないが、入学早々の盗難や、虐め、行事の妨害などがフルヤ達によって引き起こされ続けたのだった。そして問題なのがその度におれ達はフルヤ達の前に立ち塞がり続けた。というより、「立ち塞がり続けざるを得なかった」からである。フルヤ達は、何かとおれ達のすぐ近くで問題を起こしては、ワザとおれ達をけしかける様に振舞ったりした。その度におれ達は彼等と対立したが、手を出したり教師に助けを求める事は決して無かった。それは何故か。簡単な事だ。
フルヤ達三人が、皆から慕われていたからだ。優等生だったからだ。クラスの中心だったからだ。誰も、フルヤ達がクラスメイトを騙し虐めをけしかけ、物を盗み、行事を妨害しているなどとは、微塵も思っていなかったからだ。擬態する虫の様に。彼らは学校に溶け込み、誰に疑われる事無く悪事を働き続けた。完璧に。
「ジョン、お前は何か俺に隠してる事がある。俺の目は誤魔化せないぞ。なんてったって、似た者同士だからなぁ。」
恐らく、いやきっと。彼は気付いていたのだろう。おれがその道を踏み外そうとしているのを。似た者同士である事の意味は自覚出来なくても、おれは心の何処かで気付いてしまっていたのかもしれない。これが敗北の始まりであり、自分を知る旅の始まりだという事を、当時小学1年生のおれは知らない。
白光
1
それは小学3年生の7月下旬の事だった。小学校に入学してもう既に3度目の夏休みになるも、これまでにない新鮮さを感じている。隊長やヒラサワさん達とはつい昨日、プールに行った。何故かヒラサワさんからの視線が気になったが、あれほど楽しい時間は久し振りだった。
1、2年生の時間の殆どを費やしたあの出来事。闘い、争いと表現しても何の問題も無いであろう。フルヤ、彼は失望の末あの行動に出ていた。そして、おれとフルヤは同類の存在であると言われた。それはよくわからない。だが、「それ」は3年生になっても未だに続いていた。
しかしその話は今回はあまり関係無い。言ってしまえば、これからする話はおれの小学生時代の主軸となる話ではない。ならどんなものなのかというと、その流れとは別に、裏で展開されていた、おれだけが知る秘密の話だ。
場面が高学年に上がる前に、おれが経験した話。場面が低学年である状態だから、この話は色を放つのだ。大人になってしまえば、セピア色の曖昧な風景になる。それはより強く残っている記憶、例えば楽しかったり、辛かったり。それを色濃く残してしまう。それでは駄目なのだ。おれはこの記憶を、出来るだけ詳細に話しておきたい。隊長達にも、ヒラサワさん達女子陣にも話していない。そんな、頭の片隅に大事にしまってあるもの。それを話そう。大切な、決して忘れてはいけない話を。
おれだけの、夏休みの思い出を。
2
話を戻そう。それは、まだ朝の早い時間だった。隊長達とプールに出かけ、遊び疲れていつもより早い時間に就寝してしまった翌日である。おれは突然母親に起こされた。早起きにはラジオ体操に通っていて慣れていたので問題無い。だが問題は別にあった。
両親の仕事の都合で、おれを預ける為に帰省するらしい。しかも父方の実家に。という事を突然告げられる。どうやら昨日言おうとしていたらしかったが、いつもより早くおれが寝てしまった為、伝え損ねていたらしかった。
父方の実家はおれが住んでいる県から2つ程隣に行った県の山奥にあるらしい。つまりは田舎だ。おれが3歳の時に行った事があるんだと説明されたが、そんな事覚えている方がどうかしている。早速母親から渡された服に着替えを済ませ、おれの着替えや夏休みの宿題などが入っているであろう旅行鞄を車に積む。何気なく、父親に実家までどのくらいかかるのか聞いてみた。昼には着くらしい。
出発して、高速道路に乗る。正直出発してすぐの時間は目が覚めていたが、高速道路に入ってからは景色が変わらないので眠気が来る。勿論寝た。気付けば何処かのサービスエリアに着いたらしい。正直、あの眠気の中食べるコンビニのおにぎり程記憶に残らない食事は無い。だがサービスエリアを出てすぐ、高速道路を降りると、そこはもう見慣れない山間の道だった。
車両の右側に高くそびえる山々が迫り、夏の陽射しに照り付けられた緑一面の斜面を見せ付ける。左側崖下には河原が見える。そしてその先にはやはり、右側と同じ光景が見渡す限り続いている。そんな道をひたすら進んで行く。あまり車とは擦れ違わない。おれはこの光景に新鮮さを覚えた。孤独な世界。人気の無い世界をひたすら進んでいる様な気になってくる。そんな道がずっと向こうまで続いていく。
景色を眺め楽しんでいると、車は突然左に折れた。見れば正面に、さっきまで見えていた河原を渡る年季の入った橋があった。入り口の石でできている標札に橋の名前が刻まれているらしかったが、大分風化してしまっていて読めない。どうやら、標札を残して橋だけは何回か直されている様だった。その橋を渡り、あの山々の中を分け入って行く。優しく降り注ぐ木漏れ日が美しい古い舗装路だった。標識も、信号も、道路のあの白線すら消えてしまった。そして遂に、道路は砂利道になる。それがとても、遊び盛りのおれにはちょっとした、と言うよりは大分、冒険をしているかの様な気分になれて心が踊ったのであった。
そして何の突拍子も無く、車は山道を抜け開けた場所に出る。そこは谷間だった。高低差を生かした段畑や田んぼが広がり、遠くには家らしき建物が幾つか見える。運転する父親は大きな欠伸をしていたが、おれの目は完全に覚めていた。
3
「よろしくお願いします。」
そんな風に祖母に挨拶してしまったのは、初めて会った様なものだったから。という理由を付けても不自然な事だろう。祖母にそんな事を言う孫はおそらくほぼいないであろう。両親に挨拶するように促されたのだが、こっちは顔を覚えていない。向こうは小さい頃のおれを知っているだろうが。だがありがたい事に祖母はそのまま話を続けてくれた。
「いんやぁ、大きくなったんだねぇ。」
「うん、でもクラスの中では小さい方だよ。」
祖母は多分そういう意味で言っていた訳ではないのだが、これに関しては思い出すと恥ずかしい思いが少し湧き出してくる。それがどうしても苦手なのでこの話は飛ばす事にする。
挨拶も程々に両親は早速車に乗って行ってしまったので、おれは祖母に家の中に案内された。田舎の風景によく出てきそうな、大きな木造一階建ての家だった。確かおれが住んでいる地域でもこういう造りは見た事があった。農家の家が大体はこういう造りをしていた。祖父母の家は、父親の家は代々農家をしている。おれはこの造りは農家の家だ、と変な風に覚えていったのだった。
ガラガラと大きな音をたてて開いた引き戸の玄関から家の中へ入る。すぐ近くの襖を開けると、そこは広めの和室だった。冬はコタツとして使っているのであろうローテーブルの上に、キッチン用の卓上蚊帳が落とされており、中には
「素麺食うか!?」
ざるに山盛りの素麺が盛られていた。既に昼前でお腹も空いていたので、
「うん、食べる。」
なんとか普通に接するよう試み、一応成功する。この後山盛りの天ぷらも出てきたので食べる。山菜と畑で採れた野菜、魚肉ソーセージ、鶏肉。麺つゆに沈めて食べる。風鈴。麦茶。素麺。蝉の声。これだけで既におれは夏を満喫した様な気になって、親のいない不安や、寂しさなどそっちのけで。なんだか楽しい気持ちがぐっと、喉元に押し寄せてきて。
「ごちそうさま!!」
家でも出ない様な大きな声で言った。
「あいよ。」
祖母も笑って返した。
4
「おお、もう来てたのかぁ。」
丁度昼頃、死んだ人間と再会したかの様な顔をしながら、祖父が畑から土まみれで帰ってきた。白いタンクトップに下はさつまいもの色(今でもこの色の名前は知らない)のジャージを履いている。肌は濃いめに焼けた色をしていて、仕事を長くやってきた事が窺える。
「じい、素麺あっから食え。」
「おう。ジョン、この後外に遊びに行くか?」
「うん、行きたい。」
「よし、じゃあ俺が食ったら川に行こうか。」
家の近くには田んぼ用の水路があり、それを辿って行くと大きな川に合流する。大きな川といっても、水深は浅い所が大半なのでよく子供達が遊びに来ているらしい。祖父はよくここで釣りをするらしく、釣った魚をよく祖母に調理してもらい夕食にしたりしている。
「上流はもっと綺麗な所だぞ。上流、山の方だ。」
膝まで水に浸かって小魚を追い回していたおれに、祖父はそう説明した。足の裏に当たる、大小様々な石にへばり付いた苔の感触が癖になりそうだ。
山の方か。勿論おれは行きたくなり、祖父にそれを訪ねると、
「危ない場所は俺が教えてやる。それ以外なら後で行ってみろ。虫も採れるぞ。ジョンが住んでる所にはいない様な虫が沢山いるからな。きっと楽しいだろう。」
そうだ虫採り。虫採りをしよう。夏休みと言ったら虫採りじゃないか。すぐに準備して行こうじゃないか。おれが祖父に頼むと、
「いいけど、もう夕方だぞ。帰って夕飯にしよう。」
「え?」
気が付けば、辺りはもう夕暮れ時に差し掛かっていた。子供の集中力というものを侮ってはいけない。森ではひぐらしがカナカナと鳴いて、カラスが上空を横切る。そんな短命のオレンジ色の世界に立っていた。
おれはこれまでに何度、この情景に心を奪われてきたのだろうか。明る日毎に、あの頃のおれは夏を何も知らずに消耗していった。そして慣れていった、不変のものだと勘違いをした。今でも頭が、あのノスタルジックな感覚を求めるのは、ただ単に郷愁を感じている訳ではない。きっと、またやり直したいからだ。あの夏を、何の考えも無く浪費したあの日々を、おれはただやり直したいのだ。
そうすれば、あの夏の結末は少し変わっていたかもしれない。
何故そう言うのか。それはおれがこの時、対岸に見知らぬ少女を見つけていたからだ。そう、見つけただけ。ここから話かけて、始まりを早めていたなら。何も変わらなかったかもしれないが。そしてそれこそが全てだったのかもしれない。あの夏の全てだったのかもしれない。今となってはそう思う事しかできない。
おれはこの時、初めてこの地域の子供を見つけてなんだか少し安心してしまった。元々人は少ないと感じてはいたが、子供をなかなか見かけなかったのである。後で祖父に聞いてみると、いるにはいる。しかし片手で数えられる程しかいないらしい。このような地域ではよくある話である。若者は皆都会に出てしまった。村を出られない高齢者がとり残され、極僅かな若者達が子供を授かる。歳が上がる毎に人数は増える、逆三角形の様な比率。これが現状だった。
そしておれはこの後、少女と出会う。夏休みはこれから。この夏は、一度しか無かった。
5
野に放たれた飼犬はおそらくこんな気持ちなのだろうか。まるで落ちてきそうな程に、どこまでも広がる青空は、果たして何処かで鼠色の雲を集め、雨を降らせているのだろうか。まるで地球上全ての国の空が晴れ渡り、雲が上空から完全に消失してしまったかの様な天気。空模様。
そしてその下に、ちっぽけな人間がひとり。それだけ。他には何も無い。有るのは体一つ。そして駆けるのだ。小山から草原を下り、田圃を分ける畦道を縫う。林道へ突入し、クヌギの樹液を吸う虫達を一瞥しひた走る。やがて登り道へ、河原を下に望みながら倒木を跳び、越す。林道を抜け、そして立ち止まる。眼下に広がる村と自然。おれは自由だった。
この辺境と言うべきか、村へ来て3日が経った。おれは少しずつ自分の置かれている状況を理解していた。自由。只々ひたすらに自由であった。森で虫を採り、河で泳ぎ、祖母の作る料理をひたすら食べる(食べさせられる)。それで1日が終わる。普段自分が住んでいる地域では決して出来ない事をひたすら出来る。それが最高に楽しかった。幸せだった。
そして友達もできた。近所に住んでいる3人で、歳も同じ位である。歳がおれのひとつ下で、泣き虫気味の男子、名前を仮に青(あお)とする。その二つ上の兄で、ガキ大将の赤(せき)。更に一つ上の年で、その兄弟の近くに住んでいるのだと言う黄(こう)。3人とも既にこの土地での夏休み生活に飽きて来ていた様で、かなりの歓迎っぷりだった。今にも崩れそうな佇まいの駄菓子屋(食品、衣類、生活雑貨も多少置いていたので駄菓子屋ではないと今では思うが)でお菓子を買って、山の中腹にある開けた場所。そこに建つボロ小屋、もとい秘密基地でお菓子パーティーをしてくれた。
秘密基地。男子ならおそらく多分、誰でもロマンを感じずにはいられない憧れの空間である。積み上げられた週刊漫画雑誌、何かよく分からないものが入っているブリキ箱、そして虫かご虫あみ、ハンモックもある(正直汚いのであまり使いたくない)。赤のお気に入りの様で、ハンモックはかなりの熱弁だった。
「なあジョン、虫は何か捕まえたか?」
「ああ、綺麗な蝶を捕まえたんだよ。こんなの、おれの住んでる辺りにはいなかったな。」
「馬っ鹿、カブトとかクワガタだよ!俺のを見せてやるよ!」
そしてまた熱弁が始まる。なるほど確かに、そこらのホームセンターで見掛けるより大分立派な個体が多い。天然モノである。これは凄く羨ましいぞ。
「欲しいな。」
と、自然に声が出てしまう。すると赤は待っていたと言わんばかりに、
「よくぞ言った!よし、俺は決めたぞ!明日の早朝、虫採りするぞ!全員朝の4時集合だ。」
「えー、私も行くの?」
「俺起きられないよー。」
「イロンは認めないぞ!全員集合だ!遅れた奴は駄菓子屋でラムネ奢りだからな!」
6
現在時刻は夜。では無い。朝の3時半である。うっすらと僅かづつ白んでゆく空の下、おれは1人集合場所であるいつもの山の入り口に向かう。
「あ、ちゃんと来た。」
集合場所に着くと黄が1人でそこに待っていた。おかしい。他の2人は先に行っているのかと思ったが。
「あの2人ならまだ寝てるわよ。起きそうにないから私1人で来たの。赤ったら、いつも親に起こしてもらわないと早起き出来ないのにあんな事言ってさ。本当バカよね。」
「でも昨日は、あまり乗り気じゃなかったよね?それなのに来てくれたの?」
「君が1人で山入ったら危ないから来たの。」
なんだか申し訳ない気持ちになる。悪いのは無責任な赤なのだが。あの腕白が来ないのでは話にならない。そろそろ家に帰る、そう黄に言うと、
「何言ってるの、折角なんだから行くわよ。虫くらい私でも捕り方は分かるわ。それに、この時間に山を歩くのは気持ちが良いの。ほら、行くよ。」
因みに、この後におれが初めて、人生で初めて木から捕まえる事になるのは、初心者が見ても分かる位小さめなサイズのコクワガタのオスである。初めてのクワガタだったので、特別大事にした覚えがある。飼い方もよく分かっていなかった為、一週間程で死んでしまい、祖父母の家の裏に生っている柿の木の根元に埋めた。その時は割と、否かなりショックだったのだろう。その後、祖父母から隠れ河原で1人で泣いていた朧げな記憶はきっと、その時の出来事に違いないのだから。
虫採りも終えて、早朝の透き通った空気の溢れる河原で休憩する。黄は岩に腰掛けて本を読んでいる。おれは黄から少し離れた岩の上からぼうっと、朝の静寂の中を騒がしく流れる川の流れを眺めていた。何もない。あるのは音だけの様な気がした。常にそこに存在するもの、その中で生きる、巡るもの。その音だけ。まるで自分は別の世界から窓越しにその風景を、音を、感じているかの様だ。この世から弾き出され、ただ感じるだけの存在。それじゃあまるで、幽霊だ。テレビの中で見る幽霊達、それらはまるでこんな感じの。世界の中に取り残されているのだろうか。唯一違うのは、人がいても同じ。干渉は永遠に不可能だという事だ。少し、寒気がした。
ぱちゃ。
魚が跳ねた音か、水が流れる音か。音がしたのだ。ふと、川を見る。何かが川面に映っている、横に動いている。走っている。逆さだが、人が走っている。どこを。向こう岸をだ。おれは顔を上げる。一瞬の出来事の後に目をやった川を挟んで向かい側。そこにいたのだ。確かにいたのだ。女の子が、走って行く。黄は本に夢中で気付いていない。霞の夢か幻か、山の中を1人走って行く女の子をおれは追っていた。彼女に夢中で気付かぬ間に。
7
対岸へ渡るのに苦労してしまった、彼女が通ったであろう道を進んではいるが、果たして合っているのかさっぱりだった。山道は分かれたり登ったり降ったりを繰り返し、遂に開けた空間へと導いた。静かな空間。木々の擦れ合う音以外何も聞こえない。芝生の緑と、木々の緑。それらに挟まれるように白い大きな塊。
そこには寂れた診療所があった。現在立っている場所の反対側には、綺麗にされたこちらが来た道より遥かにマシな道があった為、どうにも微妙な気持ちになる。
これはハズレだろうか。ここにあの女の子が来るとは考え難い。踵を返しかけて、気が付く。一室の窓が開いて、白いカーテンが風になびいている。やけに清潔感が漂う、真っ白なカーテン生地。芝生を泥で汚しながら、自然と足は窓際へと向かう。
果たして、そこに彼女はいた。白いカーテンだけではなかった。部屋が白い。扉も白い。天井、床、花を生けた花瓶も。彼女の座っているベッドまでもが白かった。そこに、真っ白な彼女がいたのだ。別に髪の毛から体の全てが白い訳ではない。自分でもよく分からないのだ。彼女は白かった。一目見た瞬間、そんな事を考えていた。そんな彼女は、おれを一目見るなり、
「あ、川の向こう岸にいた人だ。」
そう言って少し驚いたような顔をした。そして楽しそうに、
「君さ、ここら辺の人じゃないよね?よくここまで来れたね?しかもそっちから来たって事はあの山道を来たんだよね?よく迷わなかったよ!」
なんて言って笑うのだ。本当に、心から楽しそうに。やっと孤独から抜け出したかのように。
8
少し話をした。少しというのは、黄を1人置いて来てしまった事を思い出し、急いで戻ったからである。彼女とは、明日またここで会う約束をした。名前は教えてもらえなかった、軽く流されてしまった。この診療所で自分に会った事も、秘密にしてほしいと頼まれた。理由はさっぱりだったが、約束した。別れた後、一人で元いた場所まで戻ると、青白い顔をして駆け寄って来た黄にこっ酷く怒られた。
「怒られるの私なんだから。」
と言われたが、黄はそれなりに心配していた。年下のおれでもそれは分かった。家の方へ帰りながら、おれは黄にさっき行った診療所、あの森の中に建つ寂れた、白い女の子がいた診療所の事を聞いてみた。黄は思い出したかの様に話してくれたが、あまり詳しくは知らない様だった。白い女の子の事も、分からないと言われてしまった。
朝日が、登っていく。清々しく瑞々しい空気が少しずつ、熱を持ち始める。そんな頃。家に帰って来た。少し疲れて、ソファーで眠る。
「ほーら、起きろ。ご飯にするよ。」
一瞬だけ、寝た気がしたのだがもう昼前だった。今日は何をしようか。そう考えながら白いご飯を頬張る。ここじゃない、他のみんなは夏休みをどう過ごしているだろうか。
隊長はきっと今日も元気に走り回っている事だろう。保育園からの親友。彼はよくおれを引っ張り回していたが、最近はおれから誘う事も増えて来た。血の気が少し多いので、喧嘩などしていなければいいのだが。少し不安になる。
マーサとヒラサワさんは、おれと隊長とは違って、きちんと宿題をこなしているのだろう。こっちに来る前に会う機会があったが、もう半分は終わっていた。隊長を遥かに超える血の気の多さを持つ割に、意外としっかりしているマーサ。彼女とは真逆で、争いなど無縁。それどころか人と接する事すら慎重なヒラサワさん。あだ名が無いのは決して、彼女との間に距離があるからという訳ではない。お淑やかさと優しさを尊敬した結果がヒラサワさんという呼び名なのだ。
宿題か。そういえばまだ何も手を付けていない。どんな内容だったか。とりあえず持って来ていた宿題セットを取り出す事にする。手提げ袋にパンパンに入ったドリルやらプリントを見るとテンションが下がってくるが、仕方がない。とりあえず広げてみる。国語、算数が収録されている夏休み用ドリル。同じく国語、算数からプリントがそれぞれ数枚。読書感想文。ポスター応募用の絵画。自由研究。そして、日記。
完全に忘れていた。日記。もう8月だった。
9
なんとか日記の偽装に成功したおれは次の日、あの白い女の子と会う為に朝食の後出かける事にした。おれはどうしても気になって仕方がなかった。理由は分からないが、何かがおれを引き付けていた。
家を出て、はっとする。待ち合わせ場所を聞いていなかった。どうしよう。とりあえず、あの診療所に行けば会えるだろうか。昨日行ったあの山を目指す。川を渡り、山道を抜け、診療所へ。あの部屋の窓は開いていなかった。入り口も、今日は休みなのか開いていない。諦めて引き返す。どうしよう。川まで戻る。もう帰ろうか。帰路へ着く。田んぼに囲まれた道。一本の大木が見えてくる、その根元に人影が見える。
「あ、来た!ちょっとー、遅いよ!」
随分元気そうに彼女は、白い女の子は開口一番にそう言う。彼女の白色は、どっちだか分からない時がある。眩く輝く白か、消える寸前の色を無くした白なのか。きっとどっちもなんだろう。そんな白い彼女におれが待ち合わせ場所を聞いていなかった事を伝えると、
「あー、ごめんね?そういえば言ってなかったね。今度からはここで待ち合わせだよ!この大っきいブナの木が目印!君の家からも近いでしょ?」
「え、何でおれの家知ってるの?」
「そりゃ、こんな小さい村だし直ぐ分かるよー。君があの仲良し3人と友達になったのも知ってるの。凄いでしょ!」
…これが田舎の情報伝達力か。恐ろしい。
「そういえば君の名前まだ聞いてなかったね。それと、なんて呼べばいい?」
「ジョン?あはは!変なあだ名。あ、そうだったね。私の事はえーっと。」
「しろ、白で良いよ!ジョン。」
「本名、は。後で!もっと仲良くなったら教えてあげるかも!あはは。」
「君は昨日は川にいたよね、今日はどこ行くの?私が案内しようか?」
おれは、白く輝く光を見た。それは、夏の輝き。夏の、生命の火花。夏の、一瞬の輝きと、おれの一夏の思い出の中、色の消え掛かった1ページ。
10
白。歳は何故か教えてもらえなかったが、高学年位の見た目をしている。いつも白いワンピースを着ていた。そしてその名前の通り白い少女だった。見た目、と言うよりは雰囲気が。上手く説明は出来ない。それは今現在おれが思い出す事になっても同じ事だった。彼女は、白いのだ。その明るい性格は眩しい白だった。病室で初めて間近で顔を合わせた時の彼女の笑顔をおれは今だに覚えている気がする。おれの朧げな記憶の中に、白い小さな光が儚げに瞬いている。そんな眩い白。まるで今にも光と混ざって消えてしまいそうな白。
彼女は不意に、悲しい表情を見せる時があった。そんな時当時のおれは、彼女が消えてしまう様な気さえした。眩い夏の光と共に、一緒に
溶け合って消えてしまうかの様な感覚を覚えた。時折、彼女は只々上を見上げている事があった。森の隙間から刺す木漏れ日を見上げて、じっと見つめている。おれはその光景を素直に美しいと思った。しかしその表情を見た時、不安、と言うよりは悲しみ。そんな気持ちになった。何故そんな表情をするのか、自分も悲しくなる。そんな表情をしていたからだ。
「どうかしたの?」
何故かは分からない、分からないがおれは恐る恐る聞いてみた。しかし彼女は
「ううん、なんでも無いよ。行こうか。」
なんて事を言ってすぐにいつも通りの彼女に戻るのだった。
そしてもう一つ、彼女は絶対におれ以外とは会おうとはしなかった。
「それって、あれじゃないか?」
「あれって、なに?」
「ゆ…」
「おいやめろ!」
黄が珍しく激しい口調で赤を遮った。というか変わり過ぎではないだろうか。オカルト話は苦手の様だ。おれはその日、秘密基地で赤、青、黄の3人に白の事を聞いてみた。驚いた。3人とも白の事を、山中の診療所にいる女の子の事を知らなかった。まさか、本当にそんな事が有り得るというのか。こんなに小さな村だというのに。オカルトの類はあまり興味は無いし信じてもいなかったが、この日を境に逆転する事になったのは別の話である。
「とにかく、今からそこに行ってみないか?自分達で見に行かないと納得出来ないぞ。本当にいるのかもしれないしな。」
赤が興奮気味に言う。予想はしていたが。青と黄は青い顔をして反対したが、おれは行きたいと言った。赤は「流石ジョン、分かる男だな!」などと言ってきたが、おれは幽霊がどうこうよりも、白が本当はいないかもしれない。その不安を取り除きたかっただけだったのかもしれない。今となってはその心理はよく分からない。
白光2
11
その日の午後、赤に案内されて再び診療所へ。意外と単調な道程だった。前回の様に裏から来るよりも百倍良い。赤は恐れもせずに正面の玄関から入る。受付で直接聞いてしまう様だ。続いて黄、青。おれは入らない。直接答えを聞いてしまうのが怖かった。玄関の脇に立って、診療所の周りを囲む森から聞こえてくる蝉の声と、葉の擦れ合う音を聴いていた。初めて白と会った時も、こんな風に周りを囲む音を聞きながら彼女を見ていたな、と思う。大丈夫だ、彼女はこの診療所にいるに決まっている。だから、大丈夫だ。あの声、笑顔、あの色は、本物だから。
「おい、ジョン。」
は、と横を見ると3人がいた。3人とも真剣な表情でおれを見ている。おれは胸の中の心臓が、忙しなく跳ね回っているのを感じていた。少し苦しくなる。そして唾を飲む。無音の世界だった。おれは臆病な人間だった。それは間違いなかった。
家に帰ると、祖母が何か夕飯を作っていた。手伝いを申し出ると、宝くじが当たったかの様に喜んでくれた。出来上がった夕飯を畳の居間へ持って行くと祖父が横になってテレビを観ていた。祖母が、この料理はおれが作ったんだ、と言うと、祖父は今日で死んでも構わないかの様な喜び方をした。いただきます、と言っていの一番におれが作った料理を食べて美味い、お前は才能があるとか何とか言っていた。純粋に嬉しかった。祖父と一緒に風呂に入り、学校の事、友達の事、将来の事などを語り合った。自分の部屋で日記を付け、布団に入る。幸せだった。おれは只々幸せだった。だが白はもうそれを感じられない。感じる事が出来ない。
白どころか、子供自体あの診療所にはいなかった。ではあの白は、あの眩しい女の子は、あの消えそうな女の子は、やはり幽霊なのだ。それでも、おれは彼女に会いたかった。本当の事を聞きたかった。もし本当なら、もう会ってくれなくなるのだろうか。そんな考えが頭を過ぎっては消えて、また過ぎる。明日、白に会いに行ってみよう。そして聞こう。一応、形だけの覚悟は決めた。聞けば、それで終わる話だ。そんな事を考えている内に眠りに着く。夢の中でおれは、一緒に遊んでいた白の姿を見た。
「お前の中のお前を信じろ。」
12
次の日、おれはあの大木へ向かった。実の所、昨日はあまり眠れていなかった。信じられないという気持ちと、もし本当に白が存在しないとしたら。その2つがおれの頭の中を滅茶苦茶に搔き回し続けた。最早自分自身で確かめなければこれらは解決しなかった。だから、おれは白に会いに行く事にした。
朝食を早々に済ませ、走って家を出た。食事の後に走ったからだろう、脇腹が猛烈に痛くなる。それでもおれは足を止めずに走った。そうする事によって緊張を紛らわせたかった。余計な事を考えず、真っ白な頭で彼女と会いたかった。それだけだった。
大木の根元に、彼女はいた。いつも通り、そこでおれが来るのを待っていた。良かった。全身から力が抜けてゆくのを感じながら、彼女の元へ。彼女は約束通りそこにいた。それだけで安心した。彼女は確かにそこに居たのだから。
「どうしたのジョン?なんだか、疲れてる?」
そう言いながら白が笑いかけてくる。
「色々あってね。君が居なかったらおかしくなってたよ。」
「なにそれ、変なの。」
からからと笑う白。実際の所、あながち嘘ではなかったと思う。もし白があの場所に居なかったら、おれは事実を受け入れられずに傷心していただろう。
「赤達に、まるで君はこの世に居ないみたいに言われたんだ。」
その時、明らかに白の表情が強張ったのをおれは見た。やっぱり。そんな顔をして、こちらを見た。そしてすぐにいつもの白に戻る。
「まあそんなに気にしないでよ、きっとあの子達は私を知らないだけだから。」
その後、いつもの様に白に付いて夕方まで遊び続けた。しかし、おれは白がさっきの一瞬に見せた表情が気になって仕方がなかった。普段どおりを装ってはいたと思うが、ぎこちないものだったかもしれない。子供は素直だと、誰かが言っていたが、その通りだと思った。悪い意味で。そしてその様子を、白はきっと気付いていたのだろう。性格の割に意外と鋭い。そんな彼女は。おれの様子を感じ取った彼女は、いつも通りに振る舞い続けて。帰り際。
「あーあ、ここら辺も大きなお祭りとかあればなあ。去年のここのお祭りなんて出店が二件だったんだよ。酷いと思わない?」
確かに。この村の規模だ。そうなるのも納得がいくがなんだか悲しい。
「でも大丈夫!明後日、隣の町で花火大会があるんだよ。その花火が山の上からバッチリ見えるんだよ!」
興奮気味に語る白。素直にそれは気になるので詳しく聞いてみると、どうやらそこそこ大きな催しらしい。
「でも隣町なら車で行けるんじゃない?」
「分かってないね、君は。山の上から見た事がないからそんな事を言えるんだ!いい?明後日はちゃんと忘れずに夕飯の後集合だからね!」
13
結局、何の進展も無く花火大会当日を迎えてしまった。ただし隣町の、だが。とりあえず日中はみんなと遊びに行って夕方を待とう。不安を振り払うかの様に、思い切り遊ぼう。そして、今日こそ白に本当の事を聞くと決めている。黄達3人の言う通り、白が幽霊であろうとそれは構わなかった。幽霊であるならそれは、早朝の河原で感じたあの孤独を、感じ続ける存在なのかもしれない。おれだけが、彼女と接する事が出来るのならば、出来る限りの事を、努力をしてあげなくては。
おれは簡単に言えば人助けに生きる人間だと自分で思っていた。この頃もそうだが、更に幼かった頃にある先生と、約束した事だった。その後の小学校生活も、この約束を守って過ごして来た。だから白も、助けてあげなくては。信念に背く事は、先生との約束を破る事は出来ない。おしておれ自身が、彼女を救いたかった。その為にも今日、彼女の口から真実を聞く必要がある。
赤と青を虫相撲で負かし、木にハチミツを仕掛け終わると夕方になり始めた。3人に帰ると告げ、山を降り、祖父母の家へ急ぐ。祖父母には今日花火を見に行く話をしてあったので、準備をしておいてくれていた。黄達3人も一緒と言って嘘をついてしまったが、今夜山に入る為には仕方がなかった。後で怒られても良いと思った。早めの夕食を済ませ、早足に家を出る。緊張と興奮が入り混じる頭を、全力で走る事でクリアにしていく。じわじわと薄暗くなってゆく田んぼに囲まれた道を呻き声と共に走り抜ける。少しづつ、ブナの大木が近付いてくると、既に混濁していた頭も空っぽだった。何も要らなかった。ただ、頭に残った純粋な気持ちを直接白にぶつけたかった。と言うとまるで告白でもしに行くかの様だが。
白はいつも通りそこにいた。ブナの大木の下で、おれを見るなり笑顔で
「どうしたのジョン?凄い勢いで走って来てさ。まだ集合時間まで時間あるよ?」
「そうだね。でも。こうしないと。駄目そうだったから。」
「よく分からないけど、変なの!」
「ちょっと。聞きたい事あって。」
「えー?なになに、言ってごらんよ。」
「白ってさ、幽霊なのかなって。みんな知らないって言うし、診療所にもいないって言われたし。もう、本人に聞くしかなくて。」
ややあって、白は。笑う。
「なるほどね、そっかそっか。そうだね、そう思われても仕方無いかなー。うん、ジョンの言う通り。私は幽霊だよ。大正解!」
14
拍子抜けだった。まさかあそこまであっさりと白が認めてしまうとは。おれはどっと疲れが襲ってくるのを感じたが、白本人はとんでもない事をカミングアウトしたにもかかわらず、いつも通りの様子だった。
現在、おれと白はヒグラシの鳴き声が夕立の様に降り注ぐ山道を急ぎ足で登っていた。隣町の花火大会。それを山の上から見るためである。木々の隙間から見える空がほぼ暗く染まってきているのを確認し、おれと白はペースを上げた。
「ジョン、あのね。」
少しずつ夜の景色へと変わってゆく山道の中で、白が不意に話しかけてくる。明らかにいつもの様子ではない。おれは足を止め、白と向き合った。彼女は今まで見たことのない顔で言った。
「私の事を、他の人には話さないで欲しい。」
驚いた。彼女はこんな風に話す事もあるのかと。もちろんだと、そう力強く言おうとした。しかしそれは遮られる。白にではない。地を僅かに揺るがすかの様な爆音が、周囲の山々から反響した花火の音が、突然聴こえてきたからである。どうやら少し間に合わなかったらしい。
「あ、マズいよジョン始まっちゃった!」
気付けば彼女は元の白に戻っていて、
「急げー!」
いつも通り、おれを置いて行くのだった。
山頂からの眺めは素晴らしいものだった。微かにぽつりぽつりと浮かぶ隣町の明かり。その向こう、こちらの山とほぼ同じくらい(向こうの山の方が大きいと言うとなぜか赤に怒られた)の山の麓に視認は出来ないが川が流れており、そこから上がる花火。光、音。光、音。複雑なリズムで繰り返されてゆく音と光の爆発が、いつの間にか完全な夜となっていた空を照らし、彩る。現地の人曰く何もない、寂れてしまった。そんな土地を花火が悲しげに照らし、彩る。白黒の絵に、色を垂らす様に。そしてその様子を、年期の入ったベンチに座っておれと白は静かに、一言も発することなく見ていた。
「ん、ジョン。誰か来るよ。」
「えっ、本当だ。」
おれは本当に馬鹿だった。そのままその場にいれば良かった。なぜ白の手を引いて近くの草むらに隠れてしまったのか。今でも悔やむ。今思えばあの時だ。初めて白に触れたのは。
暗がりの道から現れたのは、高校生位のカップルだった。見た事はなかったので、おそらく花火が挙げられている隣町に住んでいるのだろう。そしてそのカップルは先程までおれと白が座っていたベンチに座ると、そのまま一つになってしまう勢いでくっ付いたまま花火を見始める。
「あの二人、付き合ってるんだね。セーシュンってやつ?」
気のせいか、白が羨ましそうに呟く。と言ってもほとんど聞こえていなかったが。確かに、興味が無い訳ではなかった。 いつか自分もあんな風に恋愛をするのだろうか、そう考えると胸の中心、少し潜った辺りがムズムズとした。白はその事についてどう思っているのだろう。少し気になってふと見ると白はこちらを見つめていた。一瞬どきりとしたが、直ぐに様子の違いに気付く。なんだか気まずそうにしているのだ。「どうしたの?」と口の動きだけで話しかけると、白は恥ずかしそうにベンチのカップルを見ない様に指差す。なんだか珍しいものを見た気がするが、とりあえず白が指差すベンチのカップルに目をやってみると。
…初めて見た。彼等は至極カップルらしい事をしていたのだから。
結局おれと白はそのまま茂みの中で花火大会を過ごした。山を降りようとも思ったが、降りるには彼等の座っているベンチの前を通らなくてはいけなかった為断念した。白はというと、顔を赤らめたまま俯いて微動だにしない。完全に詰んでしまっていた。そのまま茂みの中二人でやり過ごすしかなかった。もちろんその間もカップルはその行為をヒートアップし続けていた。
花火大会も、カップルが行なっていた事も全て終わった後、気まずそうにするおれに白は、
「えぇっと。今日はもう疲れたから、じゃあね。」
と言うと、そそくさと帰ってしまった。何とも言えない気持ちと、暴れる心臓が。おれの思考を完全に止めていた。今日は、早く帰って寝よう。目は完全に冴えたが。
15
「あれぇ、随分眠そうだねぇ。昨日は眠れなかったのかい。」
居間へ行って早々に、祖母にそんな事を言われるのも当然だ。きっとおれは今、かなり酷い顔をしているのだろう。結局自分はいつ寝る事が出来たのだろうか。現在のコンディションからして、朝方くらいなのではないだろうか。記憶の片隅に、白み始めた空と庭先の光景がある。きっとこれは本当にあった記憶なのだろう。
その時、向かいに座り1人のんびりと新聞を読んでいた祖父が、ピクリとしてこちらを向く。
「そういや、ジョン、今日の祭りは行くのか?言うの忘れちまってたけどよ、この村で唯一の祭りが神社でやんだ。隣町程じゃあねぇが、みんな頑張って準備してる。みんなで行って盛り上げに行ってやれ。」
祭り。そんな話は当然今まで聞いていなかった。
「 なんだぁ、ジョン。お前今日が祭りだって知らなかったのか。てっきり話は聞いてるのかと思ってたぜ。この後浴衣の着付けするから黄とは一旦別れるけど、夕方6時には神社に行こうと思ってる。」
白は、来るのだろうか。そんな事を、興奮げに話す赤の話を軽く聞きながら考えてしまう。昨日白はそんな話など口にしていなかった。もしかすると白も祭りの事を知らないのかもしれない。一応会いに行って話をした方がいいのだろうか。そんな事を考えている内に、身体の内側から黄色いエネルギーともなんとも表現し難い、テンションの流れが襲って来る。じわじわと、高揚させてくる。それがなんだかくすぐったく、自然と自らに笑みを浮かべさせる。きっと、あの高揚は。楽しさで心臓を高ぶらせるあの感覚は。きっと一種のドラッグだ。幼いおれ達を狂わせ、永遠にこんな時間が続けばいいなどと思わせてしまう。そんな事は哀しいだけとも知らずに。
「ジョン?聞いてんのか?」
「ん?ああ、聞いてるよ?今日の祭りは絶対に行くよ。でもゴメン、ちょっと用事済ませてから行くから3人は先に行ってて。」
「あぁ、分かった。遅れんなよ!」
「ジョン。君もしかして、山の診療所に行くつもり?」
黄は本当に鋭い。そんなに顔に出ていただろうか。
「あまり行かない方が良いと思うの。子供が1人で行っていい様な場所じゃないわ。そこそこ大きな山だし、危ないわ。」
黄は、診療所に行かせたくないらしい。なんとなく察したおれは
「あそこには行かないよ、ちょっとじいちゃんの畑手伝ってくるだけだよ。」
嘘を付いた。
「だからごめんね、今日はもう帰らないと。また後でね。」
「…そう、分かった。じゃあまた後でね、ジョン。」
きっと黄にはバレていた。それでも彼女は折れてくれた。
だから、少し申し訳無さそうな顔をして。
「うん。じゃあみんな、また後でね。」
その場を後にした。
「お前の中のお前を信じろ。」
16
そろそろ正直に話しておこう。
おれはあの時、白の事が気になっていた。いや、好きだったと言い切れる。
だがそれは別の話だ。あの頃のおれの原動力であり、生き甲斐だと思っていた事。正義感に溢れた性格とも言える。もっと言えば、ただのお人好し。そうだ、おれは単純に彼女を救いたかったのだ。何から救えばいいのかは分からない。ただ、彼女は苦しんでいた、それだけは分かる。あんな笑顔をおれに見せてはいたが。すぐに分かる。所詮は子供の隠し事だから。子供でも分かる嘘だったから。
ただ、それ以外の事でも彼女に惹かれていたと言う事を。その事実を明らかにし、知っておいてもらいたかった。でなければここまでの気にかけ方は、まるで狂人だからである。当時自覚はなかったが、おれは確かに彼女が好きだった。それだけの事。それだけで、おれはいつもよりお人好しだっただけの事。まさに、まさしく単純明快である。さて、無知で、無謀で、無力だったあの頃の話を、続けよう。事の流れは単純である。
まず、夕焼け迫る診療所に彼女はいなかったという事。
田んぼの真ん中にある大木にもいなかったという事。
おれは彼女の他の居場所を知らないと言う事。
もう何も、出来る事など無いという事。
さぁ、祭りへ行こう。みんなが待っている。
「ジョン?」
「おわ、と、何?どうしたの?」
突然青に話しかけられ、なんとも間抜けな声を上げてしまう。場所は既に祭り会場である神社の中。つい先程黄達3人と合流し、ちまちまと並ぶ屋台を冷やかして回っていた筈だ。おれは正面にいる青と目を合わせる。
「大丈夫ジョン?なんか眠そう。」
正直眠くはないのだが。青に心配されるとは、どうやら余程ぼうっとしていたらしい。
「大丈夫だよ青、その内眼が覚めると思うから。何か屋台で食べようよ。」
「そうだなぁ、俺はイカ焼きがいいな。ジョン、一緒に行こうよ。赤と黄はそこの射的屋でずっと勝負してるから、邪魔したら2人に怒られるだろうし。」
後ろを軽く確認する。赤と着物に着替えた黄が大声で言い合いながら射的に興じている。もし今少しでも邪魔をしようものなら、射的の的にでもされるだろう。なんだか赤と黄は仲が良いのか悪いのか、よく分からない。
「そうだね、付き合うよ。あっちにイカ焼きの屋台があった筈だから、行ってみよう。」
おれと青は、イカ焼きの屋台を目指した。気を紛らわす為に。
白は一体何処へ行ってしまったのだろうか。まるで幻の様だった彼女は、本当に幻だったのではないだろうか。そんな気さえしてくる。幻である以前に、彼女は幽霊なのだが。彼女はあの花火大会の後、何と言っていた?今日はもう疲れたと、そう言っていた。疲れた。おれはなんとも幼稚な可能性を感じていた。もし、彼女がもうこの世界に留まる事が出来なくなっていたとしたら。疲れた、とはそういう事なのではないのだろうか。不安が、胸から少しずつ、少しずつ身体全体へとじわじわ広がってゆく。冷たい水が、身体を包んでゆく様だった。
なんという事だ。おれは、おれは彼女を何も助けられる事なく、更には二度と会う事も出来ないかもしれないという状況の真ん中にいるのだ。冷たい。まるで身体中が、水に浸っているかの様に。
「ジョンは買わない?じゃあ買ってくるから待っててね。」
立ち尽くす。自分ではどうしようも無かったにしろ、取り返しの付かない事をしてしまった。もう二度と、白とは会えない。そう思った瞬間に、立ちくらみがした。
「うあ、は、は。は。」
気分が悪い。吐きそうだ。おれの足は自然と動き、ふらふらと屋台の脇を抜ける。元より控えめな喧騒は、少しずつ遠くなってゆく。去年、自分の家の近所でやっていた祭はもっと大きかったので感じられなかったが、ここの祭は少し離れただけで音が小さくなってゆく。それほどの規模だという事。しかしここに来て、見て、感じた。みんな幸せそうだった。ここはこれだけで充分だったのだから。イカ焼きを買う青と屋台のおばちゃん。射的屋で怒鳴り合いながらそれに興じる赤と黄、そしてその屋台のおじさん。全員が本当に楽しそうで、幸せそうだった。大きさじゃない都会だとか、街じゃないとかじゃない。ここは、村でいいんだ。これが幸せな広さだから。これでいいんだ。神社の裏手に回り、建物の壁に背を預けしゃがみ込みながら、先程会場内でそんな事を考えていたのを思い出した。
でも白は。どうなのだろうか。
「よっ!」
「え。」
ーどうして。どうして君はいつも、幽霊の様に突然おれの前に現れるのだろう。
「着替えてたら遅くなっちゃった。絶対この祭には来ると思ってたよ〜。」
「ん?どうしたのジョン?泣きそうな顔してさぁ。」
「ホラ、行くよ行くよ!…ちょっと、どうして泣いてるのよ。」
「分かったわよ、ごめんね、言うの忘れちゃってたの。ほら、あんな事があってさ。ちょっとビックリしちゃってたの。ジョンだって何だかキョドーフシンだったでしょ?」
「ね?ほら、これで仲直りだね!行こうよ。」
「…私の事、捜してくれてありがとう。」
17
「アハハ、ジョン。それじゃあ割れちゃうよ?もっと慎重にやらなきゃ!」
「白、ちょっと静かにしてくれない?もうちょっとなんだから!」
型抜き。どういう訳か白は神懸かり的に上手かった。おれはというと結局割れたのだが。
こんなに楽しいのは、ここに来て初めてかもしれない。そう思った。今までも、赤達と遊ぶ事はよくあった訳であり、勿論それらがつまらなかったと感じていた訳ではない。上手く言えないが、きっと自分の心の中で彼らに遠慮してしまっている所があったのだろう。もし無理矢理説明を付けるとするならば、そんな感じだった。
だが、今は違う。気付かなかった。自分が今、こんなにも自然に笑っているという事。心の底から、楽しいと思えていた事。未だに射的屋で怒鳴り合いながら、ケンカまがいの張り合いをしている赤と黄も。その2人を大笑いしなながら見物し、美味しそうに屋台で買ったイカ焼きを食べる青も。彼らから離れたこちら側。今も隣で屋台で一番難しい型抜きに挑戦して、失敗しつつも眩しい笑顔を向けてくる白だってそうだ。あの時、みんながみんな楽しかった。
幸せだった。
「花火上がるって!締めに一発だけだけど!」
「よっしゃ、ど真ん中で見てやるぜ!」
そんな声が聞こえた時。
―そっかぁ、もう終わりかぁ。
そんな声が聴こえた気がした。
だから、きっと不安で一杯だったであろう顔で、おれは隣の白を見た。彼女は、
「ねぇジョン。花火、よーく見ておこう。だって一発しか上がらないんだってよ!」
会場の明かりがいくつか落とされる。たった一発しかない花火をよく見える様に。
「たった一発!面白いよね。まぁこんな村じゃあ仕方ないけどさ。」
どうして、君は
「でも、私この村が大好きだよ。本当に。ねぇジョン、君は」
そんな涙混じりの声でそんな事を言うんだろう。明かりが落ちたとは言え、泣いているのはバレバレなのに。
「最初は不安だったんだ。いきなりよく知らない所に連れて来られて。でも今は、毎日がとっても楽しい。ここが凄く好きになれたんだ。白のおかげだよ。ありがとう。」
「そっかそっか、そりゃあ良かった!私に感謝しなさいよ?あと、あの3人にもね。」
「うん、分かってるよ。白、ありがとう。」
なぜ泣いていたのか。おれは訊けなかった。薄暗闇の中、彼女が必死に泣くまいとしていたその様子は、悟られたくなかった様にも思えたので訊けなかった。そしてもう一つ、白がおれと手を繋ぎ、強く握ってきたから。だから涙混じりのその声を、おれは気付かないふりをして、空を見上げた。
―ねぇ白、どうして泣いてるの?
おれにそんな事を尋ねる勇気は無かった。聞きたくなかった。怖かったから。
ひゅるるる。そんな音がして視界に一筋、川を登る魚の様に光が上がってゆく。
ゆっくりと、まるでこの世界の時間が引き延ばされて。
自分以外がスローモーションになったような感覚。
かと思うと次の瞬間、不意に光は消えてしまう。
―おれはそんな人を知っている。でも、
不安で、自分が嫌になって、嫌いになって。白の事も、分からない。頭が、散らかる。
ひかり。そしてほぼ同時に音がやってくる。
その巨大な光と音は、一瞬でおれの頭の中を真っ白にした。きっとおれは間抜けな顔をして見上げていたに違いない。ちらりと一瞬だけ、白の顔を伺えた。やはりそんな顔をしていた。
「白、おれ絶対白の事忘れないよ。あと必ず、夏休みが終わってもまた会おう。」
不意にそんな言葉を口に出していた。まるで自らに強く言い聞かせる様に。
「うん、そうしてくれると嬉しいな。絶対、忘れないでよ?」
白が優しく返す。目が光で麻痺し、暗闇に目が慣れない。それでも声のする方を向く。
「忘れないよ。」
顔は見えなかった。手が離れる。
「ジョーン!大変だよ!赤と黄が本当に喧嘩始めちゃった!」
青の声で一気に思考が戻る。どうやらあの二人は余程仲が良いらしい。
「おれが言っても止められないと思うけどなぁ。」
「そこをなんとか頼むよジョン、俺が止めようとしたら返り討ちにあった事あって。」
そんなもの、おれも返り討ちになるだけな気がするが。
「白、ごめん。ちょっと一旦向こうに…」
ふ、と。優しく風が吹いた。蒸し暑い夏の夜を、僅かに冷ましてくれる風だ。どこからやってきたのか、そしてどこへ行くのか。優しい風なら、きっとのんびり景色でも楽しめるだろう。この夏休みの様に一瞬で通り過ぎたりなどしない、そんな旅を祈ろう。ゆっくりとこの夏の思い出を、思い返しながら行く。絵日記を、一つ一つじっくり見返す様に。そんな風に、祈らずにはいられなかった。
白はもういなかった。今度こそ、消えてしまっていた。
18
また会う。そう白と約束した。だからそれほど悲しくなったりしないものだと思っていた。
どうやってまた会う?
本当に白はまた来る?
何か方法を…
でも、もう時間が。
まだ8月の半ば…
電話が…
明日迎えに…
「ジョン、聞いてるかい?明日、お父さんとお母さんが迎えに来るそうだよ。ったく、どうしてこんな急に連絡してくるかねぇ。今から少し準備をしておこうか。」
突然だった。祭から帰ってすぐの事だ。どうやらおれは、ここに何も残せず、向こうに帰る事になりそうだ。いや、出来る限りのことはした。してあげられたのだ。だから、後悔を残して行くわけではない。黄達三人とは少し寂しくなるが、また会えるからいい。白は、どうだろう。彼女は、救われたのだろうか。おれは、彼女を救えたのだろうか。ただそれを知りたかった。確かめたかった。
祖母と明日ここを出発する準備をしながら、ずっと考えていた。おれに何ができたのか、彼女はどうなったのか、知る術が無いのかどうかを。
「あのね。」
作業中の縁側からは、月が見えた。満月になりきれていない、出来損ないの様な月だった。
「ん、どうした?」
「友達がね、突然いなくなって。それで、おれはちゃんと友達でいられたのか分からなくて。その人はずっと一人で。その人は幸せだったのか。救われたのか、分からなくって。それだけなんだ。あの子は、どんな気持ちでここを離れていったんだろう。」
しばし沈黙があった。祖母は静かにおれを見ていた。
「ジョン、それは私にも分からんよ。一番知っているのはその人達だけなんだよ。ただね、きっとその子にとってジョンと一緒にいた時間は、楽しいものだったんだと思うよ。毎朝ジョンの顔を見ていれば、それは簡単に分かるよ。本当に楽しそうに家を出て行くんだもの。きっと待ち合わせていた子も同じ気持ちだったに違いないさ。」
「そうかな、そんなに分かりやすい?」
「んん。歳をとると、家族を持ったり、子供と接する時間が増えるからねぇ。」
そう言って笑いかける祖母に、少し照れて。
「そっかぁ。」
そのくらいの事しか言えなかった。
その後、おれは赤と青、黄の家に電話し、明日の朝ここを出る事を伝えた。皆驚いていたが、必ず見送りに行くと言っていた。見送りに来てもらって出発するのは初めてなので、少し変な感じがして、少し緊張した。
「お前の中のお前を信じろ。」
19
「よっ。」
「おはよう、早いね。」
6時。祖母に起こされ居間に行くと黄が来ていた。祖父と何か話していたのだろうか。よく分からない。それと迎えが来るのは9時の予定だ。どうしてこんな時間に来たのだろう。訊くと、
「最後だし、少し散歩に行きましょう。こっちに来て最初の頃、赤に言われて四時ごろ山に行ったじゃない?まぁあの時は赤は来なかったけどね。あそこに行きましょう。」
「いいよ、ちょっと待ってて。すぐ支度してくるよ。」
「うん、じゃあ外で待ってるね。」
この時間に2人で散歩なんて、珍しいものだ。と、そんな事を考えながら急いで着替えを済ませて外へ出る為玄関へ向かう。靴を履き、戸を開けようとしたところで、
「行くのか、ジョン。」
「うん。どうしたの、じいちゃん。」
「こっちでの夏休み、楽しかったか?」
「もちろん、とっても。また会いに来るよ。」
それを聴くと祖父は破顔して、
「そうか。荷物はこっちで準備しておくから、早く行ってこい。」
「うん、いってきます。」
そんな簡単なやりとりをして、家を出た。黄は家の入り口近くの、植木に紛れた石の置物に腰掛けていた。こちらに気付き、立ち上がると、
「じゃあ行こっか。少し、でもないけど。君に話があってね。」
こんな時間に来てする話だ。よほど大事な話なのだろう、と思ったのだが。全く見当が付かない。それこそ本で読んだ別れ際の告白くらいだ。よくあるパターン。主人公が出発する正にその時、ヒロインが現れ大胆に告白をするのだ。いや待て、逆だったか。いや、そんな事は今はどうでもいい。兎に角何の話なのか、黄に訊いてみる。
なんだか緊張してきた。しかし、口を開いた黄が言った話は。
「白の事よ。」
血の気が引いた。という表現は正しくなかった。ただ、ゾッとした。黄は白の事を知っていたのだから。いや、もしかすると赤と青も、白の事は知っていたのかもしれない。だが少なくとも今、田んぼ道を隣に並んで一緒に歩いているこの女の子は、白の事を知っていて。その上で今まで知らないフリをしながらおれと一緒に遊んでいたというのか。祭の時も。しかし、こちらの反応を見て黄は慌ててこう付け足す。
「赤と青なら、あの子の事は何も知らないわ。だから祭の時はジョンの兄弟か何かだと思ったかもね。だってとっても仲良さそうだったもの。でも私は、知ってるの。あの子が何者で、どうして居なくなったのか。そうね、山に入りましょう。村を一望できる場所があるわ、そこに向かいながら話しましょう。」
そう聴いて、少しホッとした。黄に従い、やがておれと黄は山道の入り口に入る。黄は、静かに淡々と語り出す。語る自分自身に、考える暇を与えないかの様に。
「まず最初に、白の母親について話すわ。彼女はこの村出身の人だったの。高校を卒業してから、都会に出て働いていたらしいわ。職業は知らない。色々やってたらしいけど、あまり良くない仕事もしてたらしいわ。或る日、都会に出ていた彼女はここへ帰って来るなりあっちで知り合った男の人と結婚して、この村で生活を始めたわ。結構早い内に結婚したみたい。ジョンの周りにもいるんじゃない?両親とか、片方の親が周りの親より若い人。あんな感じよ。で、結婚してその後すぐに産まれたのが白。」
「あっあの河原、覚えてる?早朝に二人で来て。あぁそうだった、あの日は赤と青、寝坊したんだっけ。ホント、言い出しっぺが来ないんだから、私あの後赤と青に本気で怒ったのよ?まぁそれは置いといて、あの時は私が読書してる隙に君がどっか行っちゃって、本当に焦ったわ。血の気が引いた、とも言えるわね。あ、そんなに気にしないでね。きっとその時に初めて白を見つけて、追いかけて行ったんでしょう?当たり?やっぱり。何で白があそこにいたのかって?それはこのあと話すわ。話を戻しましょう。」
「それで、周りのみんなはきっとあのままずっと幸せに暮らしていくって。そうなんだって思ってた。でも白が産まれて三年くらい経った時に、父親が蒸発したっていうか、えーっと。そう、消えちゃったらしいわ。何処かに行っちゃったの。他の女の人と。で、当時どんな状況でそんな事になったもかは知らないけれど、母親はかなりショックだったらしくて、子育てを辞めてしまったの。いや、子育てだけじゃないわ。文字通り、抜け殻みたいになって。全てを投げ出してしまった。それから、母親には常に悪い噂が付き纏っていたわ。実際そんな見た目になってしまっていたらしいし。それでここが田舎の、というか何処でもそうなのかもしれないけど、嫌なところが出ちゃったのよ。あ、因みに私は都会とかはまだ行った事無いのよねぇ。あれ、それは訊いてないって?」
「まぁまぁ、そんなに怖い顔しないで。私だってこんな話、本当は話したくないの。あの子がどんな気持ちでいたかなんて、考えただけでも辛過ぎて。無性に悲しくなって、それこそ自分が嫌になるわ。…それで、村人達はこう思った。あんな母親の子供なんだから、子供も子供に違いないって。そんな、勝手に決めつけたイメージをみんなで広めていってしまったの。こんな小さい場所だもの、直ぐに広まったわ。白だってまだ小さかっただろうけど、きっと気付いていた筈よ。その内沢山の悪口、陰口、悪意、差別を受ける事になる事も。」
「もうすぐ着くわよ。話していたらあっという間ね。ジョンって、意外と体力あるわよね。意外と。ふふ、最初はね、そんな風には見えなかったよ。学校ではどうなの?運動会とか、マラソン大会とか。」
「…そうなんだ。話を聞く限り、君って本当に色々抱える人っていうか、なんだろう。うーん、お人好し?自分から問題の中心に入って行く人だよね。本当に君は変わってる人。でも、君みたいな人を必要としてる人はいるのかな。それは何だか、勝手に首を突っ込んでるだけみたいな。まぁでも今回は違うから、関係ないけど。」
「また脱線しちゃった。えぇっと、どこまで話したっけ…。白は、そうだね。あの子は強かった。どんなに周りから言われても、学校で虐められても、明るく振舞ってた。ジョンと話してた時みたいに、笑顔を絶やさなかった。泣いているところなんて、誰にも見せなかった。それが何故かは分からない。自分に言い聞かせる為か、又は母親に安心して欲しかったのか、その他の理由か。白はずっと耐え続けたわ。でも、先に母親の方に限界が来てしまったの。母親は、永遠にここから居なくなってしまった。」
「自殺よ。家で首を吊ってたって。確かに白は必死に耐え続けていられたけど、母親への負担は耐えられる程のものではなかったのか、それ程までに弱ってしまっていたのか。兎に角、白の母親は死んだ。辛い事に、死を選んでしまった。そして白は母親に置いて行かれる形で、独りになってしまった。今まで必死に耐えてきた結果がこんな結末だなんて、白は思ってもいなかったでしょうね。辛過ぎるし、悲し過ぎる。そもそもそんな言葉では言い表せない深い悲しみ。そして孤独。遂に彼女は壊れてしまった。精神的にね。山の上にあった診療所。ジョンは初めて白に会った日、そこに行ったわね?そこにあったあの白い部屋、あれは彼女の病室だった部屋よ。彼女は何故か白い物を部屋に置きたがった。それであんな部屋ができたのよ。あ、因みに赤達と診療所行った時に中に訊きに行ったのは私よ。勿論あそこにいる人達は白の事を知っていたけど、まだあいつらには言えないから嘘をついたの。ここにそんな人はいなかったって。ごめんなさい。あいつらがもっと大人になったら、言うつもりだけど。」
「あ、着いたわね。凄い景色でしょう?ここに君を連れてきてあげたかったの。私のお気に入りの場所よ。ふふ、どういたしまして。…さてと、そんなに急かさなくても大丈夫よ。これからここで続きを全て話すんだから。」
20
確かにそこからの景色は凄いものだった。この村のほぼ全てが一望できる。しかし、そこまでこの景色に夢中になどなれるはずもなかった。黄が今まで隠していた白についての真実が、衝撃的過ぎるからだ。それにあれ程残酷な話をふわふわと語る黄も黄だ。白だって一応死んだ人だ。失礼じゃないのか。おれは少し怒りを感じながら黄を急かし、話の続きを要求する。白。君はあんな絶望を背負いながら、何故あんなに柔らかな笑みを浮かべられるんだ。君は、本当に壊れてしまっていたというのか。その真相はもう今となっては分からない。
黄はおれの隣で広大な景色を眺めていたが、やがてこちらに向き直り続きを話し始めた。
「それでは続き。診療所に移って、白はそこで静かに暮らしたわ。親も居なくなってしまったし、引き取ってくれる親戚がもうこの村にはいなかった。それに、白は身体的にも精神的にもボロボロになっていたわ。まず、精神的ショックで食べ物を身体が受け付けなくなった。ガリガリに痩せ細って、食べても吐いてしまう。そんな状態。それと、周りから追い詰められ過ぎてしまったせいで、心を完全に閉ざしてしまった。会話を全くしなくなったのよ。そういう事があって、診療所に移ったのは治療の為でもあったって訳よ。白は静かに、大人しく、人々の目に付かないように過ごした。その中で彼女はなんとか少しづつ、回復していった。」
おれが会っていた白からは想像が付かない。だが白が置かれた状況を考えれば、そうなっても何もおかしくはない事だった。どう考えても分かる。
「本当に、酷い話よね。ジョン、あなたが会った白はきっと…え?全然違う…。何で。」
―え。
「そこまで回復していたの?知らなかった…。まあ考えてみれば、結構時間が経ってる訳だし。人によっては治る人もいるのかしら。実は、私の知ってる白は大人しい子のイメージしかなくて。見た事は無いから。診療所付近にもあまり近付かないよう言われてたし。」
「さて、その後。白は少しづつ自分の壊れてしまったところを治していった。そしてある日、白の遠い親戚が彼女を引き取ってくれる事になったの。ここら辺ではない、遠い所に住んでいる子供のいない夫婦よ。私も、ジョンも知らないような土地。きっと戻ってくる事は無いでしょうね。」
ぼうっと見る風景の中に、あの待ち合わせ場所の大木があった。とても大きい。おそらくきっと、この村と一緒に育ってきたのだろう。ずっと昔から。白の好きな場所だったのだ。
「そして白は引っ越す事になったわ。でもその時、白は珍しくわがままを言って引っ越しを遅らせた。もう戻ってこれないこの村で、この夏休みを過ごしたいって。そう言ったらしいわ。村の祭を最後に、この村を出るって。きっと楽しい思い出を最後に一つ、作りたかったのよ。」
「そして白の希望通りこの村での夏休みが始まった。最初はいつもの生活と変わらなかった。でもある日、彼女はこの村に或る一人の男の子が遊びに来る事を知った。そのおじいちゃんとおばあちゃんが、たまたま診療所に来ていたから。そして、ここに来るその子がどんな子なのか二人に訊ねてみたの。」
「とっても優しい子、男の子でも女の子でも隔て無く接して、信頼し合える友達がいっぱいいて、そして兎に角お人好しで。誰でも困った人がいたり、泣いて悲しんでいる人がいたら、助けてあげないと気が済まない。そんな変な子だよって。そのおじいちゃんとおばあちゃんは教えてくれた。少しだけしか会った事がないお孫さんの事なのに、本当に詳しかった。そして白は、絶対にその子と友達になろうって、そう思ったわ。すると彼女は、夏休みが楽しくて楽しくて仕方無いものだって。気付いてしまった。それで、きっと君が見た明るい白になった。ここは予想だけどね。」
しろ。
「白はその男の子が来るのを待ったわ。何日か経ったある早朝、彼女は待ちきれなくなってこっそり診療所を抜け出して、山を降りた。夏休みは限りあるものだから、居ても立っても居られなくなったのね。それでそのまま山を降りて、川に出た所で。彼女は対岸に人がいる事に気が付いた。この村では見た事の無い男の子がいたのよ。でも実際に会ってみると、彼女は心の準備が出来てなくてね。ほら、診療所にこもってあまり人と関わらない生活を送っていたから。それでね、彼女は、ふふふ。逃げ帰っちゃったんだって。診療所に。」
白。
「診療所に戻って来るなり、部屋に窓から飛び込んで落ち着こうとした。ふと、あの頃の記憶が蘇りそうになった。視線、陰口、叱咤。もう嫌になりそうだった。窓際のベッドでカーテンが風に揺れるのを見ていた。それが彼女の無意識の癖。そうしていると、ほんの少しだけ時間を早めてくれたから。でもその時、びっくりする事が起きた。さっき川で見かけた男の子が、窓の向こうに立っていたから。開け放たれた窓越しに白はその男の子を見た。その瞬間、きっと彼女は本来の性格を取り戻したのよ。見た目の特徴が、教えてもらった特徴と一致したから。白は友達になりたいと思っていたし、これで夏休みが楽しくなるに違いない。そう思った時にはその男の子に話しかけていて。ここまで言えば流石に分かったかしら。」
どうして。
「つまり、ジョン。この男の子は君の事で、白は決して幽霊なんかじゃないわ。ちゃんと生きている。でも彼女はもうここにはいない、遠い所に行ってしまった。今まで黙っていてごめんなさい。こんな話、無関係な他所の子には言えなかったの。でも君は、白を救ってくれた。だから真実を伝えなければいけないと思ったの。文句なら幾らでも聴いてあげるわ。本当に、ごめんなさい。」
「どうして。黄は何一つ悪い事なんてしていないじゃないか。もし恨む事があるのなら、おれは大人達を恨むよ。だから、黄は関係無いし、謝る事も無い筈だよ。それに、おれは白を救えたんでしょう?それなら良かった。本当に、それだけが気掛かりだったから。」
少し強い口調で言ってしまったので、おれは不安げに黄を見る。だが黄は少し安心したような顔をしてこちらを見ているだけだった。やがて口を開く。
「そう言ってくれると私も頑張った甲斐があったわ。ありがとう、君のお陰よ。もう私がしてあげる事は無さそうね。まったく、御供物の一つでも欲しい所だわ。あっ、あの車。ジョンの家の車じゃない?」
つられて黄が指差す方、眼下に僅かだけある道路の一画を見やると、確かに見覚えのある車が祖父母の家へと向かって行くのが見える。もうそんな時間か、そう思い振り返ると。
「…黄?・・・黄!!」
黄はいなくなっていた。一瞬のうちに。
「黄、どうして。もう訳がわからないよ…。おかしくなりそうだ。」
おれは座り込んで大きく息を吐き出した。もう限界だった。短時間の間に色々とあり過ぎたし、そもそも黄が消えた事が分からない。パニックになっているとも言っていい。果たして、おれは夢でも見ていたのだろうか。声にならない叫びを空に打ち上げる。ただただ、大声を出してこの絡まった気持ちを解きたかった。顔の両頬を何度も叩き、座り込んだ膝に頭を打ち付ける。痛みが。感覚というものがずっと遠くの方へ行ってしまったようだ。早く、自分を正気に戻してくれ。そう思いながら、額を膝に擦り付け続けた。やがて、涙声が言葉を生み出す。
「御供物って、何だよ…。」
よろよろと歩き出す。ふと、視界の一画に一瞬目が向く。そこにあったのは、朽ち果ててはいるものの、最近誰かが掃除していった跡がある。綺麗な皿まで置かれている。それは祠の様なものだった。おれは、それを一瞥し家へと向かって歩き出した。祖母のある話を思い出しながら。
「ジョン、この村にはね、神様がいるんだ。と言っても、誰も見た事は無いけどね。確かにいるんだよ。動物達の中に混ざっていたり、自然と一つになって見守ってくれているんだよ。だから誰も気付けない。でもね、村の人が困っている時、子供達が辛い思いをしている時。その神様は人の姿をとって、手助けをしてくれるんだ。そしてその姿は、子供にだけ見る事が出来るんだよ。子供達は神様だと気付かないがね。私も、もしかしたら子供の頃に会っているのかもねぇ。私は、絶対にいると思ってるよ。だから、祠にいって掃除や御供物だってしてる。その度にきちんとお礼をしているんだよ。いつもありがとうございますってね。神様はちゃんと見てくださっているんだから。だからジョン、お前も既に会っているのかもしれないねぇ。」
21
それが全てである。白は幽霊などではなく、しかしおれはそれに気付けなかった。引っ越して行く彼女をそのまま気付かずに過ごしていた。なんとも滑稽で、愚かなのだろうと、自分を責める他なかった。本当に笑えてくる。泣く程に、笑えてくる。
もっと沢山、君に言いたい事があった。また会う約束をした。幽霊だとしても、訊いておきたかった。また会ってくれるかと。白はおれとまた会いたいと、思ってくれているのか知りたかった。もしかすると、白に本当の事を聞き出せたかもしれない。でもそれはしなかった。怖かったからだ。例え幽霊でも、また会えるならそれで良かったからだ。彼女の事が、白の事が好きだったからだ。そして、その約束がどれ程に難しい問題を孕んでいるかなど、当時のおれは知る由も無いのだから。夏休みが終わったら、また彼女と会う。その約束だけは必ず果たそうと思ったのは、帰りの車の中。小さくなっていく山々を見ながら、おれはこの夏休みを思い返していた。
もう一つ、黄の事である。実はこの次の年に数日だけあの村に戻る事があった。その時赤と青に黄の事を聞く事が出来たのだが、あの二人は黄の事をしっかり覚えていた。彼女が幻ではなかったという驚きと、安堵を覚えたのがおれの記憶に刻まれている。赤と青は、黄から自分は昔家の都合で越して来た事と、学校は赤達とは違う私立の小学校へ行っている事を聞かされていたという。突然消えた事に関しては、おれからその時に詳しい話をしてあげるまでは知らなかったという。
それから、三人で最後に黄と話したあの山へ行った。山頂付近には、やはりあの時と同じ様に石の祠があり、そして綺麗に掃除もされていた。赤は「また男だけになっちまった。」などと言って笑っていた。そう言う赤が一瞬だけ安心した様な、諦めを付けた様な顔をした。知っている。赤が、一番黄と仲が良かった友達だった事を。彼がそれ以上に思っていた事も。
黄がいなくなってから一度も行っていないらしい秘密基地にも行った。意外と、思っていたよりは汚れていなかった。お菓子やジュースのゴミ達。乱雑に纏められた少年誌。虫かごには蝶の死骸が入っていた。「なんだか、前より広く感じるな。」それが赤の最初の感想だった。「ここを使うのは俺達が最後なんだろうな。」「もうこの村に俺達より下の子供は居ない。」「黄が、寂しがるな。」もう聞いていられなかった。目を逸らした先、テーブルがわりの段ボールの上に何か置いてある。メモ書き。いや違う、手紙。赤がハッとして即座にそれを取る。果たしてその手紙は。おれは彼の表情で全てを察する。
「黄からだ。」
一年も放置してしまったその手紙の内容は、未だに分からないままである。あの時、手紙を読んだ赤はそのまま静かに、そして滅茶苦茶に泣き出してしまった。段ボールに突っ伏し(そのまま潰してしまったが)、その手に手紙を握り締めたまま。涙と鼻水で汚れた手紙の内容を、知る人は赤だけである。
そしてそれっきり、あの村には行けないでいる。それぞれ、みんながみんな。嫌な思い出が。悲しい事があった。何となく、距離が出来てしまう。あの時を、思い出して悲しくなってしまう。何も知らずに白を行かせてしまった事を。それを教えてくれた黄に、何も言えずに終わってしまった事。赤と青兄弟が何も知らずに大事な友達と会えなくなってしまった事。こうして並べるだけで、罪悪感で潰れそうになる。だから、おれは行くのをやめた。
しかし決して、忘れようとした訳ではなかった。心の何処かに、ずっと置いておかなければいけないと思った。決して忘れない様に。二度とこんな事はあってはならないと、自分に言い聴かせる様に。言い聴かせ続け、思い出し続ける為に。戒めとして己の中に留めておく為に。これがおれだけの秘密の話であり、秘密の夏休みの思い出である。
それらが、あの夏休みにおれが得たものだった。大切な、とても大切な事で、決して忘れてはいけない事だ。そしてもしも、いつか奇跡か何かが起きたとして。そんな風に、白と会えた時に。おれはびっくりして目を丸くしている彼女に言ってやるのだ。「ほら、約束は忘れていなかった」と。白はまた、あの白く眩しく輝く光を。笑顔を見せてくれるだろうか。木の葉の隙間から悪戯に射す太陽の光は、小さくなる振りをしておれを脅かす様に大きく輝いてみせるのだった。
そうしておれは、あの夏休みを後にした。
転がる車輪の操り手
1
おはよう。
「おはようございます。今朝のニュースです。」
今日の朝ごはんは?
「コンビニエンスストアに車が・・・」
・・・いただきます。
「店内にいた1人が・・・」
そう、じゃあまた今夜も帰ってこれない?
「1人が死亡しました。」
分かった。じゃあ鍵持っていくよ。
「警察はペダルの踏み間違いではないかと見て調査を・・・」
・・・。
「続いてのニュースです・・・」
・・・。ごちそうさま。
「——地方で、親子2人が死亡していた事件について・・・」
じゃあ、いってきます。
・・・。
2人家族。母親と俺。親と子。ただそれだけ。2人という事以外は他の家と何も変わらない。そんな俺の家の、いつもの朝の会話。父親は数年前に死んだ。母親は俺の為に1日中ずっと働いている。文字通り朝から晩までだ。俺もそれを理解しているつもりだ。それなのに周りの奴ら、親戚はこう言う。「子供に寂しい思いをさせるな」「家に帰らず一体何をしているんだ」「子供が不良になったらどうする」「あの人が死んでなければこんな事には・・・」正直、もううんざりだ。「お前らに何が分かるんだ。自分の母親がどれだけ頑張って働いているのか、お前らに分かるものか」「お前らが、どれだけ俺達の事を知っているというんだ」と、声を大にして言ってやりたくなる。でもその度に母親は「言わせておけばいい」「私は大丈夫だから気にするな」と言った。だから言わなかった。ひたすらに我慢し続けた。
そして小学校に入学したのと同時、遂に俺は別の方向にそのエネルギーを逃がし始めた。母親の為にクラスの中心であり続け、その一方ではバレない様にクラスメイトにちょっかいを出してみた。今までに感じた事の無い感情だった。自分の内から外に出たがっていたその何かが、はち切れんばかりに歓喜の声を上げて、俺はその行いに悦を見出した。それをすることで初めて他人の上に立って、見下すことが出来た気がした。母親に色々言う連中ですら、いつかこの方法でなら見下せると、そう思った。だから俺はこの快楽の為になら、回りくどい用意も自分でしっかりとこなした。放課後の教室にこっそり忍び込んだり、あたかも女子が書いた様に仕上げた嘘の手紙を、隣のクラスの女子に出したり。他にもなんだってした。真実を知った或るクラスメイトには、虐めだとも言われた事もある。他人を見下して、他人を虐げて悦に浸るのは最低な奴だと、「彼」はそう言っていた。自分の事は棚に置いて上から物を言う様な奴に言われたくはなかったが。
——本当に、ムカつく。
あれはいつだったか、たしか3学年の2学期初めの事だ。例の「彼」はいつも通りの間抜けで、見ていて腹の立つ顔だったが、いつもより少し悲しげで、大人びて見えた。夏休みに何かあったのか、聞けるような仲ではなかった。4年生になっても俺達と「彼」等の関係は変わらなかったし、未だに俺の真実を知るのは「彼」等だけだった。しかし「彼」には明らかな変化があるとそこで気が付いた。磨いていった石が鋭さを増すように、そこに確実な変化があった。本気の度合が、人助けへの真剣さがやはり3学年の2学期から確実に、遥かに増していた。違う。お前はそんなんじゃないんだ。お前は、人助けをして他人を見下しているんだろう?他人を見下す為に行動を起こしている、という点では俺達は言ってみれば同士じゃないのか。どうしてお前は、どんどん溝を深めていくんだ。もっと、もっと大きな事をしないと。お前すらを、その溝ごと飲み込む大きな穴を開けてやらないと、お前は気が付かないんだろう。
「なぁジョン、お前と俺はさぁ。」
おはようございます。
「良い友達になれると思うんだよ。違うか?」
俺を見下すクソ野郎共が。
2
6年生になった。遂に図書室で少し背伸びした内容の分厚い本を読んでも、なんとなくだが意味が理解できるようになったし、委員会などで学校に関する仕事を任されてはこなすようにもなった。校庭でリードから解放された犬の様に走り回る事も無い。以前よりは。大人になった、とはまだまだ言えないが、入学した頃と比べればかなり成長したと言える。身長だって勿論伸びた。おれは男子の中ではまだまだ小さい方だったが(マーサが男子の平均並みに身長が伸びた事が解せなかった。余計に暴力に磨きがかかっていった事もだ)、誰だって成長には個人差というものがあるのだ。5年生の時に保険の授業で色々と勉強したじゃあないか。おれを含めた隊長、青山、二等(3年生の時にできた新しい友達である。詳細は後ほど)のいつもつるんでいる男4人の中では若干の差で一番低かったが、その内その差も無くなる事だろう。例の保険の授業で先生が言っていた様に、なんたって「成長期」とやらの真っただ中にいるのだから。
フルヤ達との関係は、もちろん未だに続いていた。しかし一つ違う点を挙げるならば、前ほどに問題は起こさなくなってきていた事である。お互いに成長して、賢くなったという事だろう。中途半端に問題を起こそうものなら、自分達ももう小学6年生だ、すぐにバレてしまう事は容易に想像ができてしまう。その位に物事を考える力が育っていたという事だ。そこはおおいに褒めるべき事だろう。
しかし、フルヤ達はあくまで「機会を慎重に選ぶようになった」というだけで、なにも彼らは裏で悪事を働くのを止めた訳ではないのだ。止めていないという事は当然の如く問題は起こす。しかし問題なのはそのタイミングや、起こす問題の大きさの程度である。一丁前に頭の良いフルヤは(一丁前に。たしかこの頃にこの言葉を覚えたばかりで、よく使っていたのを覚えている)、この2つの要素を絶妙な加減で計画調整し、問題を起こすようになっていた。
たった今だってそうだ。彼は今おれの目の前でしらを切っている真っ最中で、その目は今回の件とは無関係を主張している。体育の授業中に突然喧嘩を始めた二人の男子。片方の男子が突然真後ろから思い切りボールをぶつけられたらしい。だが、それは間違いだ。それは何故か。ボールを投げたのはフルヤだからだ。しかもおれの目の前で、おれにしかバレない様にワザと行った行動だ。すぐに駆け付けた新しい担任のイノモト先生がゆったりとした口調で聞く。
「誰だ~、正直に名乗り出なさ~い。」
するとどうなるか。
「こいつが急に後ろから投げつけたんだ!」
「違う!俺は何もしてないぞ!」
この様に揉める事になる。
「おいフルヤ、いい加減この手の悪戯はやめろよ。そんなに楽しいのかよ、こうやって人を困らせて。」
「どうかな、別に最近はそうでもないんだぜ。お前もいい加減正義の味方ごっこはやめろよ。いや、やめられないんだろう?」
人だかりの外で、おれとフルヤは向き合う。やめられるもなにも、おれがこの「人助け」をやめるつもりは勿論毛頭無い。目でそう訴えるおれの意を理解したのか、フルヤが続ける。
「しっかし俺達も長いよなぁ、もう6年生になっちまったぜ?おいジョン、一体いつまで『これ』を続けるつもりなんだ?一体いつになったらお前はお前のその嘘の正義を認めてくれるんだよ。」
嘘の正義、まただ。最近フルヤはこの言葉をよく使ってくる。一体何を言いたいのか、さっぱりだ。
「いいかフルヤ、おれがしている事は自分で決めた事で、絶対に嘘なんかじゃない。分かったか。それに6年生になってもまだ続いてるのはお前のせいだ、それをお前も認めろ。」
「嫌だね、どうせもうこの1年で小学校も終わりだ。だから、」
「最後にこの1年間もっと酷い事してやろうと思ってるよ。はは、笑えるだろ。」
そういって彼はおれに笑いかけるのだ。まるで親友同士のやり取りの様に。
3
「それはマズいわね。アイツ、いつやるとか言ってなかったの?」
「いや、言ってなかった。でも一回だけじゃない、それだけは言える。」
「もしかして来月の宿泊学習とか・・・。」
朝の教室、おれとマーサから一歩引いた所で二等が意見を出す。彼は苗字が二戸部なので「ニト」と呼んでいたのだがそのうちに「二等」になった。身長はかなり高い方で、高学年に上がった途端学校で一、二位を争うサイズになった。彼と仲良くなったのは3年生の時だ、弱腰の彼がフルヤの標的にならない筈が無く、何故か目隠しで両手両足を縛られ飼育小屋の中に捨てられていたのは驚いた。どうしてそこまでされたのかを訊くと、「恥ずかしいから絶対に言わない。」と教えてくれなかった。その後、自分も力になりたいと一緒に行動するようになり、今では皆でよく遊ぶ仲になった。
「宿泊学習かー、楽しみだなジョン。」
「確かにありえそうね。いや、絶対何かやるわねアイツ。」
宿泊学習か。そういえばオリエンテーリングの班分けがまだ決まっていなかった。男女混合で組む事になっているらしいので、そろそろ皆に言っておいた方が良いだろう。宿泊の部屋割は男子だけなので自分達で丁度良く決まるだろう。
あの時、おれ達はこれまでに無かった様な緊張と興奮を覚えた。宿泊という非日常はとても刺激的で、前日に眠れないというのはあながち嘘でもなかった。5年生の時に行った宿泊学習では、先生に指示されるがままに行動しているだけで十分に非日常を味わえた。親はいない、子供だけで一晩を過ごすという事におれは緊張した。しかしどうだろう、そんな事を考えているのは自分だけだったのだろうか。周りの皆はそんな事などお構いなしに騒ぎ立て、賑やかすのだ。どうして自分の友達はこんなにも頼もしいのか。嬉しくなった。記憶にある、心の底からあんなに楽しいと思った学校行事はあれが初めてだった。そんな思い出。
「そういえば決めておきたいんだけど・・・」
「はいはい、オリエンテーリングの班分けね。どうせまたこのメンツでしょ?分かってるわよ。」
「おお、流石夫婦。そういうのを阿吽の呼吸って言うんだぞー。」
突然、いつの間にか教室に来ていたらしいイノモト先生が後ろからそんな事を投げかけてくる。
「イノモト先生!ふざけないでください、誰がこんな野郎と!」
こんな野郎とはなかなか酷いな。これでも一応1年生からの付き合いじゃないか。と言っても、この学年は1クラスで足りる人数なのでクラス替えが無い。なので自動的にそのまま、というだけなのだが。
「おいマーサ、先生はおれ達が仲良いからおちょくってるだけだろ。なんでそんなにムキになって否定するんだよ。」
はぁー、と息を吐きマーサが言う。
「まあそうなんですけどね。アンタも気にならないくらい成長したって事かしら。いや、そういうのには興味が無いだけか・・・。やっぱ男子ってコドモねぇ・・・。」
「マーサちゃん、あんまりそういう事言うのは・・・。」
あら居たのね。などとこれまた酷い事を言いながらマーサが目を向けた先、トイレから戻ってきたヒラサワさんがいる。彼女もそれなりに成長して身長も伸びたが、相変わらずよくマーサと一緒にいるので小さく見られがちである。否、小さい。撤回、小さめだ。
今思うと、1年生の時彼女とはそれなりにいい雰囲気だったと思う。だが別にそれだけだった。簡単な話だ、自分達は子供だった。その先を知らないだけだった。6年生に上がって、それこそ色々な知識を身に付けた。性教育だって去年受けたばかりだ。だが、当時のおれは1年生の時に自分とヒラサワさんがいい雰囲気だったなんて覚えていなかったし、あれが恋愛に発展するなんて到底思えなかっただろう。結局、1年生も6年生もまだまだ子供なのだから。
そしてまた今日も授業が始まる。でも今年は違う。この1年で小学校生活が終わる。そして、フルヤがラストスパートをかけてくる。またお決まりの「お前の嘘の正義を暴く為」に、6年生にもなって悪戯をするのだ。
いや、もう最近の彼らの行動は悪戯という可愛い枠には収まっていない。ある日、サダとゴウチを入れた3人で悪さを働いている所を目撃した生徒がいた。だがその生徒は、決してそれを他人に報告する事は無かった。なぜなら、彼らからの報復を恐れたからだ。最早彼らは身体の成長によって、「体格」という武器を手に入れてしまった。その結果、恐怖により俗に言う裏の番長的なポジションを得てしまった訳である。ここまではマーサの話だが。しかし一部でフルヤの正体を知った生徒が、報復を恐れて何も言えない事態になっている事は、この学校生活の中でフルヤとぶつかる事で得た紛れもない真実だ。勿論先生には報告した。信じてもらえずフルヤ達は軽く注意されたくらいで終わったが。そんな彼らが1年間でラストスパートをかけるという事は、余程の事だ。とりあえずは目の前の行事である宿泊学習に気を付けなければいけない。去年行った時は初めての行事だったので余裕が無かったのか、特に何も問題は無かった。だが今回は何かしてくるに違いない。フルヤ達との5年の付き合いが、警鐘を鳴らしていた。
思いの他あっけなく時間は流れ、無事にオリエンテーリングの班分けも、おれ、隊長、二等、青山、マーサ、ヒラサワさんで決まり、その内の男子がそのまま同じ宿泊用バンガローの班に決まったのだった。そしてこのバンガローで問題が起きる事をこの時点でまだ誰も知らないのだ。
それでは早速始めよう。二度目の宿泊学習、そこで何が起きたのか。
4
「おいジョン!今日は何の日だ!?宿泊学習の日だぞ!」
なんだか聞いた事のある台詞だな、なんて事を思いながら通学路を歩く。学校へ着いたら、そのままバスに乗り出発だ。地名は忘れたが、山の方にある大きな社会教育施設へ向かう。そこで今回の宿泊学習は行われる。
「なあ隊長。フルヤ達、仕掛けてくると思う?」
「ゴミ拾い中の山の中でも悪さするんだぜ?当たり前だろ。」
「もう6年生なんだし、大人しく言う事聞いた方が良いと思う?」
「それは絶対にしたくない!俺は絶対に負けは認めないぞ。」
そんな会話をしながら通学路を歩く。すぐ横の畑では、よく分からない植物が雑草交じりに規則正しく並んでいる。それをぼおっと眺めながら、今日から始まる宿泊学習の事を考える。フルヤが言っていた事。彼が最後まで子供じみた悪戯や虐めをする理由が、彼曰く自分であるという事。おれがフルヤと同じだと認める、そんな事は出来ない。意地でもしない。彼と同じだという事実は無いし、何よりまるで彼に負けたような気がするからだ。なんて子供じみた理由だろう。子供である事に間違いは無いのだが。
「おはよう、ジョン。」
学校付近で青山が後ろから合流してくる。眼鏡の彼は朝なのに何とも清々しい笑顔をして挨拶を投げかけてくるが、そこら辺はやはり優等生と言った所だろう。本当に、時の流れというものは恐ろしい。5年の歳月は、彼を本物の優等生にするには充分過ぎる時間だった。たしか3年生の時まではおれの方が勉強ができていた気がする。
「おはよう、今日は珍しく遅めの登校だね。」
「ああ、そうなんだ。ちょっと緊張して眠れなくてね。」
「青山でもそんな事あるんだね。」
「そりゃあ勿論あるさ。それに今回は僕が班長に決まったしね。責任重大で緊張するよ。」
「―――そうだね、まあおれも手伝うからさ。」
とある出来事があってから、おれは班長や何かしらのグループのリーダーはやらない事にしていた。あの時の事を思い出してしまうというのと、単純にそういう役割が面倒臭くなってきたという理由からである。
「お、もうバス来てるぞ。」
学校に近付くと、大型バスが校門前に陣取っているのが見えてくる。そしてそのバスの横で、イノモト先生が一人一人出欠を取りながらバスの中へと誘導している。挨拶をして出席を確認してもらうと、そのままバスに乗り込む。空いている席を探しながら奥へ向かう。勿論彼等も捜す。まだ来ていないようだ。
「5年生の方が集まり早いなぁ~。あ、ジョン君。奥に詰めて座ってもらえるかな。あとはフルヤ君達だけだから。」
こんな日に遅れるとは、いい度胸をしているじゃないかフルヤ。自分も遅かったが。とりあえず奥に詰めて座ろうとする。さて、空いているのは・・・
「おはよう、ヒラサワさん。隣座るね。」
「お、おはよう。どうぞどうぞ・・・。」
わざわざ荷物を動かして、更には自分が座っている位置を窓側に詰めてまでおれが広く座れるようにしてくれる。(少しやり過ぎだが)なんて良い人なんだろう。マーサとは大違いだ。あいつだったら、こんな事絶対してくれないし、何なら「狭いわね!もっとそっち詰めなさいよ」位行ってくるに違いない。本当に隣じゃなくてよかった。バス内を軽く見渡しながらそんな事を思う。青山は斜め前辺りに二等と座ったようだ。マーサは・・・。あれ、まだ来てないのか。
「ちょっと!朝からテンション低いわね。湿っぽいのが移るわ。やめて頂戴。アンタらもっと話す事無いわけ?」
「どあぁ!!後ろにいたのかよ!」
びっくりした。
「まったく何よ、後ろにいちゃ悪いの?」
青山と二等が哀れみの視線を送ってくる。止めてくれ。
「いや悪くないよ。隣じゃなくて良かったとは思ったけど。」
「へぇー、それどういう意味?」
「ちょっと、やめなよ・・・。」
その時、前方の乗車口からフルヤが現れた。サダとゴウチの2人と仲良く遅れて来るなんて、完全に調子に乗っている。
「ごめんなさい、遅れちゃいました!」
表面上は優等生だけあってちゃんと謝る。
「寝坊して急いで出てきて。」
寝坊した奴が3人で仲良く登校か。いいね。
「それで実は酔い止め忘れちゃって・・・。なので保険係さんの隣にいてもいいですか?」
「んー。いいぞぉー。あれ、誰だっけ保険係。」
ん?どうしたんだフルヤ。保険係?お前は車酔いなんてしないだろう。おれは知ってるぞ。その時、隣のヒラサワさんがぼそりと呟いた。
「マーサちゃんだ。」
5
「いやー、ごめんねマサコさん。お世話になります。」
「一応薬とか一通りは私が預かってるから、すぐに言って。」
なんだこの状況は。
「ありがとう。おっとジョン、なんで隠れるんだ!座席が近くで嬉しいね。道中は一緒に楽しもうぜ。」
ヒラサワさんと2人で後ろの様子を探っていたがバレてしまう。しかしどうにも腹が立つので無視してやる。それよりもフルヤがマーサを「マサコ」なんかで呼ぶから、とてつもなく機嫌が悪そうな顔をしているぞ。この「マサコ呼び」は未だに禁忌なのである。どうしてくれるんだ、早く撤回しろ。
「それで?」
「ん、どうかした?マサコさん。」
ああ、もう知らないぞ。おれとヒラサワさんはマーサと顔を合わせないよう真っ直ぐに座席に座り直し、後ろへ静かに聞き耳を立てる。
「・・・。どうして私達の所に来たのかしら?」
「酔い止めを忘れたから。」
「違う。」
低く、怒りを孕んだ声。全てお見通しだと、彼女は分かっている。いいかフルヤ。敵の陣地に乗り込むという事はとても難しいし、恐ろしい行為なんだ。
「・・・普段の君らをもっと知りたくて。」
「そんな事で?」
「そうさ、仲良くなりたい人達の事をもっとよく知りたい。当たり前の事だろ?」
勿論そんな事は絶対に思っていないと断言出来る。大方暇つぶしにおれ達の事をおちょくりにでも来たのだろう。
バスが走り出す。これから施設までは2時間ほどの道のりだ。そう考えるとフルヤと2時間も一緒に移動というのは正直嫌になってくる。いや、一番嫌なのはマーサの方なのだが。
「はあ、なんだかもう疲れてきた気がする。」
「子供のくせに何気取ってため息なんかついてるのよ。丸聞こえよ。」
「・・・・・・。」
ヒラサワさんとおしゃべりでもしていよう。そうしていた方がまだマーサの逆鱗には触れずに済むかもしれない。隊長は寝ているし。
「そういえばさ、ジョン。君とヒラサワさんはいつもよく一緒だけど、もしかして付き合ってたりするの?」
は?なんでそうなるんだ?付き合う?付き合うってあれか、テレビでよく見るあれか。男女がイチャイチャするあれの事か。どう見たらおれとヒラサワさんがそうなるっていうんだ。見てみろ、ヒラサワさんが顔を真っ赤にしている。お前が変な事を言うからだぞ。
「いつも一緒って、それはマーサだって同じだろ。」
「いや、そっちは無いかなと思って。」
「当たりだけど、アンタそれはそれでムカつく言い方ね。」
「分かったごめんよマサコさん。でも気になるだろ?もしかして君は本当の事を知ってたりする?」
「まあ・・・知ってると言えば知ってるわよ。」
「へぇ!それじゃあ教えてよ。結構気になってるんだ。」
「バーカ、アンタに教えるわけないでしょ。」
おい。何を仲良く喋っているんだ。しかも当事者はそっちのけか。
「ヒラサワさん。なんだか勝手に後ろで話が進んじゃってるけど、嫌なら止めさせるよ?」
と一応気にかけて訊いてみるが、ヒラサワさんは顔を伏せてしまっている。髪の間から除く耳が、真っ赤だった。うーむ、これはどうしたものか・・・。
「そこをなんとか頼むよ、マサコさん。」
「・・・はぁ、簡単よ。アイツが鈍いだけよ。分かったらもうこの話は終わり。アンタとは出来れば仲良くしたくないの。」
鈍い?どういう事だ・・・。全く分らない。何の事だかさっぱりだ。
「ヒラサワさん、もし可能なら詳しく教えてくれない?マーサは何について知ってるの?」
するとゆっくりとヒラサワさんが顔を上げる。真っ赤な顔、潤んだ瞳、軽い上目遣い。・・・でも何も言わない。そしてまた顔を伏せる。
・・・なんなんだよ全く。
6
「いやー、意外とあっという間に着いたなあ。」
「隊長は寝てたからでしょ。」
予定通り到着。なんだか出発してからずっと騒ぎっぱなしなので、もう既に疲れが出ている気がしてきた。あと、どうしても気になるのはバスに備え付けられていたカラオケだ。これだけは子供のおれも疑問に思って仕方が無かった。どうして始める前は皆が口々にやりたいと騒いでいたのに、いざ曲を入れると誰も歌わないのか。なんだかすごく不思議で、間抜けだ。どうせ皆は、騒ぎたいだけであって、全員の前で歌う事とは違うのだ。羞恥心が、テンションを上回る。そんなカラオケ音源の鑑賞会。そして後半はイノモト先生による全力のアイドルソングメドレー。
今思えば、共感性羞恥というものを感じたのはこの位かもしれない。皆が引いているあの空気感。耐えられずに、熱くなっていく顔を覆いたくなる気持ち。「共感性羞恥とは、羞恥ではなくただ共感性や想像力が豊かなだけ。」そんな言葉を聞いた事がある。共感性があるかどうかはともかく、想像力は。あった。
確実に。悲しい程に。
「波の音が聞こえてくるね。」
「そうね、ホラ。ここからなら見えるんじゃない?」
「うおー!見えた!!」
そこは海が見える小高い山の上に立てられた施設だった。とにかくものすごくデカいの一言だ。山の中にこんな施設があるなんて。自分達だけで使うにはあまりにも大きすぎる、なんという贅沢だろう。と思ったが、実は他の学校の生徒達も来ているらしい。「いいかー、絶対に他の学校の人達に迷惑はかけないでくれなー。」とイノモト先生から再三忠告された。その言葉は、まるで正体の分からない誰かに向けられているかのように、しんと静まり返るエントランスにふわふわと響き渡った。
エントランスを引き返し、施設の外側を迂回して建物の向こう側へ回ると、広々とした芝生の丘の上にバンガローがちらほらと見えてくる。海が見えるバンガローだ。前回の宿泊学習はこことは別の施設で行ったので、ロッジに少人数で宿泊するのは初めてだ。じんわりと、興奮が頭から広がっていく。そんな時、マーサが横からおれにぼそりと呟く。
「へぇー、こんな感じなのね。」
「ん?どうかしました?マーサさん。」
あえて「さん」を付けてふざけた調子で彼女に問い掛ける。マーサは目だけではいはい面白いわね、とでも言う様なリアクションをとり、何事も無かったかの様にこちらへ言葉を返してくる。まるで洋画で目にするような皮肉たっぷりのリアクションに、つい口元が緩む。何年も付き合って分かった事だが、彼女も意外とそういうノリをしてくる。これは本当に仲のいい人としかやらない事なので殆どの人は知らない事だ。それ程に長い付き合い。そして自分がそれ程に心を許せる相手だという事を知れて、嬉しく思った。
「アタシ、バンガローって初めて見たの。実は、てっきりただの小っちゃい家みたいなものだと思ってたわ。」
「そうなんだ、何か感想はある?」
「なんかこう、殺人事件起きそうよね。海外の映画で観た事あるわ、こんなロケーション。」
「マ、マーサちゃん!これから泊まるのにそんな事言わないでよ・・・・・・。」
「ごめんねヒラサワさん、アナタを不安がらせる為に言った訳じゃないの。ジョンが余計な事言うものだからなんかこう、ついね。」
「おれはそんな事を言わせる為に感想を聞いたわけじゃないんだぞ。それにこのバンガローはまだ全然良い方だ。」
「あら、意外と詳しいのね。それよりアンタ達だけで宿泊だなんて本当に大丈夫なのかしら。この後のオリエンテーリングはちゃんと時間通りに来るのよ?」
「分かってるよ。じゃあまた後で。」
「じゃあ行こうか。ジョン、僕達のバンガローはあっちだよ。」
バンガローは、広場の中心にある屋外調理場を囲むように、 広場南側に扇状の形に並べられている。数は10棟。東側に広場入り口があり、一番東側の2棟が先生達のバンガローになる。因みにおれ達のバンガローは最も奥側のバンガローだ。
「二等、ちょっと荷物を持っていてくれないかな?鍵を開けるよ。」
「うん、任せろ。」
そんな会話をしながら一番奥、自分達のバンガローを目指す。
「なぁ、あれ。フルヤ達じゃないか?」
隊長が顎で指す先、自分達の後ろをフルヤ達3人が歩いている。バレない様に気配だけを伺っていると、その気配は自分達のバンガローの手前で消えた。
「なぁ、フルヤ達ってもしかして。」
「マジかよ隣かよぉ・・・・・・。」
二等が大きなため息をしながら落胆する。
「あぁーとりあえず、鍵開けたし入ろうか?」
バンガローの中はまさしく、よく映画で見た様な光景だった。今頃マーサも全く同じ事を思っているにきっと違いない。そう考えると軽く噴き出しそうになる。青山が電気を点け、それぞれ荷物を一箇所にまとめて、ソファーに腰を下ろし一息を吐く。暖炉の前に置かれたソファーとローテーブルは本格的で、まるで映画のセットの様だと思った。きっとそのソファー達は、そこまで良いものではない。そんな風に分かってはいた。だがどんなに良いもの、高級なものであろうとも、憧れの光景には絶対に敵わないのだ。
「さてと、まだ集合時間までは余裕があるね。」
青山はそう言うとその場全員の視線を自分に集中させる。そして言う。
「さっきも見たよね。フルヤ達、隣のバンガローだ。何かあるかも。いや、その事に関係無く今回の行事中何かある。そうなんだろう?ジョン君。そこでだ、君の意見を今聞きたいんだ。小学校最後の年に、彼らとの決着を付ける為に。」
En( )