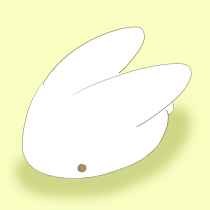ゼダーソルン タヴィ・オン文字
タヴィ・オン文字
通路をぬけた先に現れたのは、メインゲートがあるエントランスホール。野外なだけあって見晴らしのいいテラス風に仕上がってるし、ここより背の高い建物が近くにないおかげで、さっき街をながめたときには見えてなかった祭事場の構造と、その奥に広がる景色が遠くまで見わたせる。
なるほどね。いくつかの棟に分かれてるらしいこの祭事場は、大きな館を中心にしてどこまでも広がる庭園内に建てられた、数ある施設のひとつでもあるんだな。それよりも奥に立ち並ぶ高層ビル風の建物は、園とは別の敷地内にあるようで、こちらの施設とは別口みたいだ。
あっ、エントランスの脇にキレイな回廊がある。
「隣の棟と下の階をつなぐ回廊よ。あそこをわたって館内へ入るわ」
中はゆるやかなスロープだ。
「となりの中央棟にはこっちにあるより大きな野外ステージや会議場があって。そこで明日、神和ぎ祭を執り行うことになっているのだけど」
「聞いたことないな。どんなことをするの?」
「神和ぎ祭は、災いが起こらないようご機嫌をとってお願いするお祭りなのよ。その、神さまに」
「はっ?」
「この世のあらゆるところには神さまがいて。神さまが不機嫌だと災いが起こるから、そうならないようにお祭りをして、神さまに楽しんでいただくの」
「神さま、って言うと」
ああ、あれか。まだぼくらの祖先がパルヴィワンをわたっていけたその昔、異文化圏に棲む別種の知性体からそうよばれたと伝えられる――――
「うん、思いだした。アープナイムにはない言葉で『その文化や環境の法則では説明できない現象を引き起こす物体や生命をしめす総称』ってやつだ」
ところでいつの間にかぼくがこの子の後を追う形になってるのはどうしたワケだ。さっきまではぼくのほうがこの子の歩調に合わせてたのに。
「みんなが信じているワケじゃないの」
急にこの子の歩く速度が上がったか。そのうえこの不機嫌そうな声が持つ意味は。
「そりゃあ、まあ」
えっと。
怒らせるようなことはしてなかったよな。自慢じゃないけど日々ラウィンや母さん、アルファネたちに鍛えられてるから、大きなミスはないはずだ。とすると。
「結局んところ、神さまとかんちがいされたにちがいない、ぼくらの祖先がいい例だ。本物を知ってんならともかく、ニセ物を警戒して信じない者がいたっておかしくない。むしろそっちのほうが多いだろ」
「そうっ、そうなの。だからトゥシェルハーテだって信じてなんかないわ。よかった、ちゃんとわかってくれているのよね」
あれっ、なんだよ。ぼくにふり返ったその顔は、思いっきり笑顔なんじゃないか。
いままでずっと子供らしくない緊張したふうな顔つきだったし、急に不機嫌そうだったしで、てっきり話題がマズイ方向へ流れてんのかと心配したのに。わっかんないなあ。
「あっ、でも。いまは、街のみんなの心を落ちつかせるためにも必要だからって。その用意のために、今日は特別、いろんな人が出入りしていて」
また表情が変わった。今度は困ったふう、なにかを心配してるのか。
「……まさか、あわててここへ飛び込んだのって。そういうこと? 見つかっちゃまずいんだ?」
「こっちの棟に入ってきてはいないはずだけど、油断はしないで。話すのも小さな声で」
はあ、どうりでセキュリティシステムのモニターを気にしたワケだ。そのうえ飛行艇みたいなのまでが飛んできたんじゃ、屋根がある回廊へ駆けこまないほうがどうかしてる。
「わかった。とにかくいまは先を急ごう」
スロープの終点で姿を見せたパーティホールは、よし、だれもいない。
「この階段を下りるの?」
ホール奥、四角い吹き抜けの壁づたいに設えられてる階段は、ずいぶんと立派な造りのもので。
「底が深いな」
「一番下の大連絡通路までつながっているの。でもトゥシェルハーテたちはあっち。階段のとちゅうにある扉をぬけて下へ下りるのよ」
トゥシェルハーテが指差したのは、ここから数階下のあたり、階段が二手に分かれた先にある小さなフロアだ。壁側に半開きになった背の高い二枚扉が見える。
「本当は認証がないと通れないのだけど、いまならヘイキ。認証なしで通れちゃうわ」
「故障中とか?」
「それはどうかしら?」
得意そうにすましたその顔つきは、いかにも裏がありそうな。
「先に動力を切っておいたとかなんてな?」
まさかね。
二枚扉を通りすぎ、つぎの小さなゲートへ入っても反応はない。ゲートの先には大きな丸い穴が開いていて。
へえ、めずらしいな。
穴の底へと向かってのびる、これは二重らせん階段だ。
「また階段。スロープより階段のほうが多い建物なんてはじめてだ」
長ければ長いほど階段は危険だからって、段数が多くなる場合は、スロープをとりつけるのがふつうなのにな。
「半周して二階下の通路にでるわ」
「そこから外へでるの?」
「外へもでたいけど。その前に書庫へよって、あなたに見せたいものがあるの」
書庫って図書館の倉庫みたいなものだっけ?
「心配しないで。用事がすめばすぐ外へでていけるから」
それならいいけど。いや、やっぱりダメだ。この手の階段は、下を見れば見るほどぐるぐるが目について、体のバランスを失うような。つい段を踏み外しそうで不安になる。
「そこの踊り場から横の通路側へ」
「けど、この階って」
らせん階段のまわりを囲む通路があるだけ。ほかにはなにも見当たらない。
「みっつあるついたての裏側に、それぞれ書庫へ入るための扉があるの。トゥシェルハーテたちはこっちの扉から。鍵は解除されてるから手で押せば開くはずよ」
本当だ。ついたてと壁がおなじ色と素材でできてたから気づかなかったけど、ついたての裏に回ってすぐの踊り場の突き当たりに、頑丈で重そうな二枚扉がちゃんとある。。
「手で押せばってことは、自動扉じゃないんだ?」
すると、体の小さなトゥシェルハーテの力じゃ開けにくいよな。ここはぼくが開けるとするか。
「すごい。これ、植物でできてる扉じゃないか」
この色、手触り、この重み。なんてこった、滅多にお目にかかれない超高級品だぞ。
「そう? これくらいの扉ならこの祭事場に何枚もあるはずだけど」
その『これくらいの扉』のひとつも取りつけられないでいる、父さんと母さんが経営する三流ホテルのことを思うと、思わず泣けてしょうがない。
よし、開いた。さて、中は。
「まっ暗だ」
「ヘイキ。ほら、上に」
まっ暗な中に、いくつかの淡い小さな光が滲みだした。だんだんと大きく、明るさを増すところを見ると、扉が開くと同時に、自動で灯る仕掛けなのかもしれないな。数歩先に見えてきたのは、壁にそってのびる廊下と手すり。その先にある、斜めにのびる急な手すりは、いままでの造りからすると、階段のためのものなんだろう。
「外とちがって暑くない」
「書物が悪くならないよう工夫してるの。ここにはいろんな形式の書物が収められていて。しかもこの国の歴史、政治や文化について書かれたものばかりだから、とても大切にされているのよ」
それはなにより。じつは暑くてバテぎみだったから丁度よかった。
「それじゃ必要な本をとってくるわ。階段下の椅子に座ってまっていてね」
蔵書は壁側に収納された格好になってるみたいだ。そっか、だからこの部屋には窓がないんだ。階段下には、段差をつけることでみっつに分けられたフロアがある。それぞれ読書するのに丁度いい机と椅子、ライトもついて悪くない雰囲気だ。
「ねえっ、アープナイム・イムは文書を瞬時に目でとらえて読むことができるって聞いてるのだけど。本当にそう?」
トゥシェルハーテの声が反響して聞きとりにくいのは、この部屋の天井がバカみたいに高いからなんだろう。
「速読できるって本当なのって聞いたんだけど、聞こえなかった?」
「ああ、それは。できるよ」
得意と言えるほどじゃないけど、人並みに。
「ならよかった。どうしても読んでほしい本があるの」
「いいけど」
あっ、いや、まずいかも。だって、ここにある本は、歴史に関する書物だってトゥシェルハーテが言ってたんじゃないか。それだと専門用語や知らない言葉で埋めつくされてる可能性が高い。キチンと内容読みとる自信がないぞ。いまからでも断っておくべきか。
トゥシェルハーテは、
「あったわ、この本よ。念のためコピーするから待っていて」
いた。ぼくらが入ってきた壁側通路の上の階。
この部屋の明かりのほとんどは間接照明になっていて薄暗いけど、トゥシェルハーテが立つあたりから漏れる青白い光はくっきりしていて、おかげで目につきやすい。
「昔、この星にいくつもの都市国家があったときのこと。大きな戦争があって」
「えっ」
「たったニ年のうちに、都市も人も自然も、なにもかもがメチャクチャになっちゃったんですって。あわてた各国のリーダーはただちに戦争をやめて、みんなが幸せに暮らすことのできる統一国家を創ることにしたの。そして新国家の拠点にするべく、一番に造られた記念すべき街がここ」
これはおとぎ話かなにかの、にしては。
「王都ハルサソーブ、それがこの街の名前なの」
「まてよ。そんな街の名前、アープナイムには」
ないはずで。
「この祭事場も当時造られたもののひとつで。ここから法王を国の第一人者とする元首政を布いていったのですって。そのとき、初代法王の任についたネゼィール・ヴィーガ・ロップの相談役として、国家の繁栄に尽力したのが賢者セブ・ダーザイン。これはその本人が残した回想録なんだけど」
アープナイムには。
国家機関としての元首はあっても、人一人を元首とする決まりはない。どころか『法王』なんて言葉もないんだから、アープナイムの歴史でないのは確実だ。すると。
「あのさ、もしかしてトゥシェルハーテってものすごく頭がいい?」
「どうして?」
「だって、それってキミが思いついたウソ話なんだろ? にしては、まるで大人が作る物語みたいにむずかしくってしっかりした内容だと思うから、すごいなって」
「あきれた」
「なにが?」
「やっぱりなにもわかっていなかったのね」
よくわかんないけど、すごくバカになされたような気がしなくもない。
あっ、ずっと丸めてたトゥシェルハーテの背中がまっすぐにのびた。青白い光も消えたから、本のコピーが終わったのかもしれないな。階段にむかって歩きだしたトゥシェルハーテの両手が抱えてるのは。へえ、ここからでもわかるくらいにずいぶん大きい、あれはうすいシートをたばねて閉じた旧式の本だ。
「まず。なにより先にこの本を読んでちょうだい。読めばいろんなことがわかるはず。それでもわからないときにだけ、しかたがないからトゥシェルハーテが説明してあげる」
しかたがないだって。
イヤミったらしいなあ。
「重いんだから早く受けとって」
それはそうだろう。こうして目の前に差しだされた本は本当に大きくて、それに迫力の分厚さだ。
「本の表紙にあるタイトルを読んでみて」
ぼくが持っても十分重い。そのうえこのタイトルは。
「驚いたな、タヴィ・オン文字で記されたタイトルだ。いまでも一部の政府機関でつかわれてるって聞くけど、学生のぼくじゃアープナイム史の教科書で見かけるくらいで」
「読める?」
「昔、公式文書にもつかわれてた古代文字なだけあって学校でも習うから。すこしだけ自分で勉強したこともあるんだ。けど専門用語や、むずかしい言葉は参考書がないとムリだな。タイトルは『ブレン・ホウアーヴの回想録』、かな?」
そう、ちゃんと読めるはずがないんだ。
なんたってぼくが通うペイル・フォリイドじゃ、初級程度の単語がならぶ短文をいくつか読めれば、合格点がもらえることになってる。そこからよぶんに勉強したところで、その程度は知れてるワケで。
「うわっ、なんだよ。これって全文タヴィ・オン文字なんじゃないか。読めるかどうかわからないぞ、ええっと、シム? 『シム』とは、我らの、かのう……『可能態』?」
手ごわい。
これは、流し読みでわかる言葉だけひろって、あとは想像でおぎなうか。だとしても限界がありそうだ。
「笑えない、むずかしい言葉だらけだ。ページ数も多いし。読むには時間がかかりそうだけど」
ゼダーソルン タヴィ・オン文字
「巫」でも「神無き」でもありません。神を和ませる「神和ぎ」です。
またこの作品は、実在する宗教をリスペクトするものではありません。