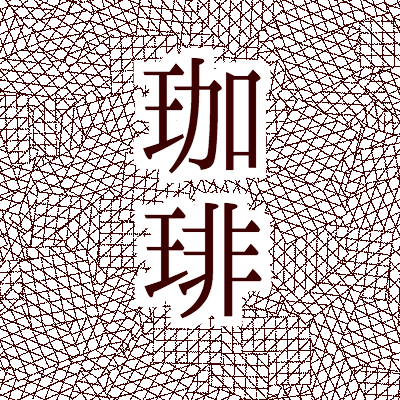
珈琲
GL要素有りにつき苦手な方はご注意下さい。
幼い頃、とある女性に恋をした。
十二歳も歳が離れていたが、それでも惹かれたのは彼女の優しさがあったからこそ、だろう。見た目も非常に可愛らしくて、美しくて、性格がにじみ出ている優しさがあった。勉強をしている私に「数を学ぶと言うのは大変ですね」、と声を掛け、悩んでいると当然の様に相談に乗って頂いた。私は少しずつ、彼女に惹かれている事に気付いていた。
しかし、それを伝える訳にはどうしてもいかなかったのだ。私と彼女は同性である上に彼女には許嫁がいた。よく物語で聞く、双方の親の間で勝手に決められてしまった愛などどこにもない、そんな関係だと言う。お互いの顔など、写真でしか見た事がないと言う。
こんな関係で、幸せになどなれるのだろうか。否、なれる筈が無い。
「酷い話よね。私にだって、想い人はいるのに」
そう言う彼女は、ひどく悲しそうな顔をしていた。聞いていた私も、相槌すら打つ事ができなかった。
「……ならば、ご両親にそう伝えれば良いのではないですか」
「伝えてしまえれば楽なのだけれどね。どうしても、そうはいかないのよ」
「そういうものなのでしょうか」
「そういうものなのよ」
——次の日、彼女は可愛らしい頬を大きく腫らして私のもとへやってきた。両親に昨夜の事を伝えて、父親に頬をぶたれてしまったのだと、辛くてたまらないのだと、彼女は私に嘆いていた。
私は彼女の頭を撫でた。それしかできなかったのだ。
それから数週間が経って、私は彼女を散歩に誘った。学校で噂になっていた、新しく開いたという喫茶へ行く事になった。
「貴女は本当に背が高いのですね。私はこの通りですから、羨ましいです」
「トシノサという奴よ、トシノサ。十二も違うんだもの」
隣をあるく彼女は背をすらりと伸ばしていて、まるで西洋画の様に美しい。赤い着物が似合っている。とても、艶やかだと思った。
「……私達は、背以外に何か違いはあるのでしょうか」
「あるんじゃないかしら。私は意見を通す事はできないけれど、貴女はできるじゃない。私にはどうしてもできないわ。恐ろしくてたまらないの」
「そんなことありません。——ああ、着きましたよ。この喫茶です」
店の名前は片仮名で書かれていた。私は珈琲しか飲まなかったので、実際どうなのかは分からないが、この店の料理はしあわせな味がするらしい。辛くてもこれを食べれば幸せになれる。そんな味。美味しい物が好きな隣のハルちゃんがそう言うのだから、きっと間違いないと思った。
「ねえ、喫茶て呼ぶの、やめない?」
「え? ではなんと呼ぶのですか?」
店に入って直ぐ、彼女は唐突にそう言って、二人分の珈琲を頼んだ。私には"喫茶"以外の呼び名が分からず、思わず彼女に聞き返すと、彼女は
「カフェ。この方が、ハイカラでしょう」
と微笑んだ。
「喫茶……ではなく、カフェですか」
「そう。私達もまだ若いのよ。貴女なんて特にそうなんだから。どうせだから、ハイカりましょう」
直ぐに珈琲を飲み終えたのか、彼女はビスケットを食べていた。とても幸せそうな顔をしているのを見て、私も幸せな気分になった。
「ありがとう。なんだか、元気が出たわ」
彼女にはやはり、笑顔が似合う。そう思った。
両親に黙って、彼女は家を出た。翌日のことであった。時折手紙で近況を私に伝えては、また別の場所から手紙を送り、別の場所に移っては、また手紙を送る。私達だけの秘密の様な気がして、毎日私は有頂天だった。
「今日は甘味処へ行きました。蒸した薩摩芋を砂糖と練って……」
「昨晩は花火を見に行きましたよ。とても綺麗でした。貴方にも見せたかった……」
文面から彼女はとても楽しそうで、日々が充実している事が伝わる。私は、彼女の辛い顔はもう見る必要がないのだと思うと、嬉しくて嬉しくてたまらなかった。
しかしそれも、飽くまで私だけの想いだったのだ。
——雨も風も雷も騒がしい日の夕方の事だった。
女学校から帰宅すると彼女から手紙が届いたと聞いて、私は母からそれを受け取り、自分の部屋を向かった。
その内容は、私にとってあまりにも酷なものだった。
「内緒にしていたけれど、恋人が出来ました。来年、その方の名字を頂く予定です……」
ああ、なぜ私の胸はなぜ膨らんでいるのだろう。私の身体は、どうして丸みを帯びているのだろう。なぜ女学校に通い、なぜ髪に蝶結びを結い、なぜ花柄の着物など来ているのだろうか。なぜ私は女なのだろう。なぜ彼女より十二も年下なのだろうか。ああ、私の方が彼女の恋人よりも、あの人を知っているというのに。私の方が、長い間一緒に居たというのに。
部屋を飛び出し縁側から庭に出た。下駄を履く余裕などまったくなかった。ただ闇雲に走って、走って、走って、走った。袴は泥だらけになって、着物は着崩れていたのだろう。走って、走って、走って、それでも走って、着いた先には閉店間近の喫茶があった。いいや、違う。あの日彼女と行った、カフェだ。
見られたものではない姿を見て、店主が私を店に入れた。入り口から一番近い席に座らせて、温かい珈琲を出してくれた。何も言わずに私の背を撫でる店主の優しさが染みた。だからなのか、珈琲に映る私は涙を流していた。
私達の間には、違いがあったのだろうか。年の差よりもずっと、大きな違いが。私にはそれがどうしても分からなかった。
ただただ泣くことしか、できなかった。
珈琲
Twitterで頂いたお題「歳の差」から。
アイコン画像のフォントは「はんなり明朝(→http://typingart.netさん。)」。
イメージは明治〜大正あたりの、14歳くらいの女の子と26歳くらいの女性。
この時代であれば26歳だと既に結婚しているのかな〜とは思いますが、まあリハビリもかねた物なのでそこは置いておきましょう。
袴が好きです。長い髪を結った蝶結びが好きです。
それだけです。


