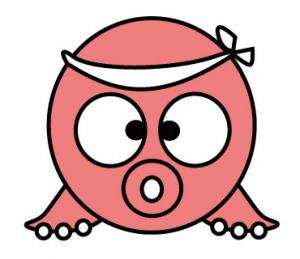あの人の生き方
作者の経験と妄想を織り交ぜて書きました。こんな事が本当に起こってはいけないと思いますが、一つの可能性としてはあるのではないかと思います。是非、読んでみてください。
【1】
「僕の病気は治りますか?」
左手を自身の右手で触りながら岸坂光一は質問していた。光一は病気を患っていた。「筋萎縮性側索硬化症」という5年後には死にいたる病気だった。今はまだ左手が利かない程度だが、今後全身の筋肉が衰え、最終的には息をする筋肉を脅かす病気だった。
細田昌守は質問を受けても黙っていた。安易には答えられない質問だったため、何と返事をしていいのか迷っていた。
二人は光一の家のダイニングで、契約の話をしていた。何の契約をしているのかというと、これから昌守が光一に「訪問リハビリテーションを提供する」、という内容のものだった。提供するに当たり、注意事項だけでなく、提供時間、料金などの内容が書いてある契約書を見せながら説明をしていた。その契約内容の説明が一通り終わったときに出た質問だった。
光一は還暦手前でまだ50歳にはいっていない様だった。髭は剃っていたが綺麗には剃れてなく、着ている服はパジャマの様な服装だった。部屋の様子を見る限り、家事が行き届いている印象はなかった。その左手が影響しているのだろうかと昌守は考えていた。
リハビリで出来ることは限られていた。今回の病気は回復という期待を持つことが出来ない病気の一つだった。それでも光一からリハビリの依頼が来た事に昌守はどのように対応したらいいのか迷っていた。
今回なぜ、光一からリハビリの依頼があったのか。それは光一のこれまでの苦労が今の状況に至っていると思われていた。
光一のリハビリ歴は決して長くなく、最初は病院の外来でリハビリを始めていた。詳細は不明だが1年前くらいからリハビリは受けているらしく、最初は体が動きにくくなった程度で仕事も出来たようだったが、1年前から業務に支障を来すようになり、当初は元の体を手に入れるために、と励んでいたようだが病気には勝てず、左手だけでなく左腕全体も動きにくくなっていったらしい。それでも光一は諦めてはなく、リハビリを懸命に続けていたが、病気が進行していく中で、自分の姿を他人に見られたくないらしく、家に来てくれる訪問リハビリに変更しようと考えたのだ。そうした流れで、今回昌守に訪問リハビリの依頼が来たのだった。
「私の腕がこんなになってしまいましてね。」
昌守の答えに困っている様子を感じたかのように、光一は笑顔を作りながら昌守に話かけた。効かなくなった左腕を自分の右手でサポートしながら左腕を動かしていた。昌守は見た目でも左腕が動きにくそうな事は見抜いていた。左腕は細く、筋肉が無いのは明らかだった。それを裏付けるかのように、光一がコップと取るときには、左側にあるコップもわざわざ右手で持って飲んでいた。
きっと着替えも大変なのだろうと予想をしながらも、光一の質問の答えを探していた。
昌守は光一と会うのは今日が初めてだった。初めて会う人に対して気をつけることは、「清潔さ」「誠実さ」そして「頼もしさ」の三つだと入職した時の研修で習っていた。事実、その三つを心掛ければ、今までの業務では概ねいい関係を築くことが出来ていた。
今回も昌守はその三つを守って接していた。髭は剃ったし、服も洗濯したものを着ていた。会話も契約内容を話しているときは丁寧に受け答えをし、光一が納得行くよう多様な角度から説明を加えた。
ただし、「治りますか?」という問いに答えられず、今回の難しいのは頼もしさだと感じざるを得なかった。やはり、光一が元の身体に戻るという願いに答えられない事を知りながら、「頼もしさ」を演出しなければならなかった。
「お医者さんは何と話されていましたか?」
昌守は少し違った視点で会話を進める事にした。左腕が動かなくなってきている原因は昌守の口から言う事でもないと判断したからだった。病気の影響かどうかは予想が出来るが、判断するのは主治医の役割でもあった。
昌守が持っている資格は理学療法士というものだった。国家資格であり、リハビリテーションを担う役割を認められていた。しかし、この資格で仕事をするには条件があった。それは、「医師の指示のもと」というものだった。よって主治医の見解を聞くのは正当な判断でもあった。
「一応、色々説明は受けましたけどね。」
光一の声は勢いが弱まっていた。その事についてはあまり触れて欲しくないようだった。きっと主治医からも病気には勝てない事は知らされているのだろうか。それでも今回依頼が来たというのは、これから新たにリハビリを受け、そして心を入れ替えて頑張ろうと心掛けている時なのだろうと思った。
「そうですか。」
昌守はそう言葉にしたあと、会話の間合いをとっていた。光一は下を向いたまま次の言葉を発しなかった。昌守は光一が次に何を言うのか、何を言いたいのかを探っていた。微妙な間合いが二人の間を漂っていた。
「念のため確認させてください。」
昌守は踏み込んだ会話をする事にした。光一の色々と説明を受けたという内容を把握しようと思った。もし、昌守が持っている病気の知識と光一が持っている病気の知識が食い違えば、足並みが揃わない事になり、いくつもの食い違いが生じると考えたからだった。医者によっては誤魔化して将来死ぬような病気だという大事な事を継げていない可能性もあり、どうしても必要なことだと判断したのだった。
「この病気は発症から五年以内に死に至る可能性の高いご病気です。」
昌守は最初にこの事実を言った。逃げても仕方ないと考えた結果だった。はっきり伝えた方が光一のためにもなるだろうとも考えていた。
光一は昌守の言葉に驚きはしなかった。やはり、その事はすでに知っているようだった。それでもリハビリに対しての期待は持っているように見えた。これから頑張っていきたいという意思は昌守に伝わっていた。
「どんな風に進めていくのですか?」
光一から今日二回目の質問が出た。昌守の言葉があまりにも残酷だったのだろうか。話題を変えるように光一が質問をした。
「まずは今の身体を診させてもらってから決めたいと思います。」
昌守は答えたが、あまり納得が行ってないようだった。しかし、それもそうだなと理解はしている様子だった。
「他に何か質問はありますでしょうか?」
契約内容の説明を終え、いくつかの質問に答えた。そろそろ次の家に行かなければならない時間になっていた。
「いえ。特にないです。」
昌守は一通り契約の説明が終わったと判断した。
「それではここにお名前と印鑑をお願いします。」
光一は自分の名前を書く場所を確認し、ゆっくりと書いた。
昌守は契約を済ませ、光一の家を後にした。その途中、今日の対応を振り返った。「清潔さ」「誠実さ」「頼もしさ」。私はそれらが出来たのだろうか。特に頼もしさについて、光一の願いを叶えられないとわかりながら、どうすれば頼もしく振る舞えるのだろうか。
昌守は悩みながら車を運転していた。
【2】
昌守は光一の主治医が書いた訪問リハビリテーションの指示書を見ていた。指示書とは文字通りリハビリに対しての指示内容が書いてある書類のことだった。書式はほぼ決まっていて、国が定めたものを使用していた。氏名、年齢、生年月日から始まり、疾患、病歴、指示内容といった項目が指示書の中にはあった。
しかし、光一の主治医である医師からの指示書の内容は空欄が目立っていた。氏名と生年月日は書いてあったが、年齢は書いてなかった。疾患もわずかに読める程度の文字が書いてあって、読もうと意識を集中して見ないと読めない程度の字だった。さらに病歴はもっとひどく、暗号が書いてあるかのように左右隣同士の文字がくっついていた。速記でも習っているのではないかと思えるほど素早く書いてあった。受け取った側からすれば伝える意志のない解読困難な書類にしか思えなかった。
昌守はその指示書の内容を確認するために、一番下に書いてある主治医がいる病院に電話をした。相手先が電話に出ると主治医の名前を出してつないでもらった。電話に出た主治医は面倒くさそうに話しながら昌守の質問に答えていた。指示書以外の事も昌守は聞きたかった。光一が「色々説明を受けた。」と言っている以上、どこまで主治医が病状を説明しているかという事が一番知りたかった。
しかし、昌守の問いに対して、主治医は「病状の説明は形式上では行っているが、ちゃんと伝わっているのかはわからない。」という返事だった。責任を追いたくないという気持ちが、昌守には充分に伝わってきた。主治医は岸坂光一という彼の生き方までには触れたくない、と言うのが本音なのだろう。昌守はこれ以上の質問は無駄だと考えて電話を切った。
電話を切った後、昌守はさらに不安が膨らんだ。結局、主治医である医師の指示内容は「難しい病気であるため、彼の意志を尊重しながら状態に合わせて行うように。」という当たり前の内容しか得られなかった。その内容は、わざわざ言わなくても医療従事者としては当たり前の行動内容であった。
【3】
昌守は光一の訪問リハビリを実際に行う初日を迎えた。いつもと変わらない朝だった。昌守はパンと熱めのコーヒーを飲み携帯電話でニュースなどの情報を眺めていた。指先一つで情報が手に取るように集まるのは魔法の機械だと今日は改めて感じていた。これだけ情報を手に入れられる時代なのだから、一般の人でも簡単に病気の事を調べられるのだろうと思った。きっと、今日から訪問する光一も病気のことを、このような機械を通して様々な情報を手に入れているのだろうと考えていた。そうなると、リハビリに対しての期待は叶わぬ夢であるかもしれないというのはうすうすわかっているのだろうと思った。それでもリハビリという医療にかけえみたいという思いなのだろうか。きっと藁でも掴む思いなのだろうか。昌守は光一に対して一体何をしたらよいのだろうか。そんな事を考えているうちに出勤の時間になった。コーヒーはコップに満たされたまま冷めてしまっていた。
光一が住んでいる場所は東京都武蔵野市にある公営住宅の一階にあった。近くに公園もあり割と緑が豊かな方だが、古い建物で外装の工事がそろそろ必要な雰囲気のある建物だった。よくみれば壁にはひび割れもみられていた。
訪問時間は午後の3時に約束をしていた。契約時に週一回で毎週木曜日のこの時間に行くと決めたのだった。午後3時といえば小学生がちょうど下校をする時刻で、ランドセルを背負った子供達が道路を危なっかしそうに横に揺れながら歩く間を車で通りながら光一が待つ公営住宅まで向かっていた。
昌守は光一が住んでいる玄関のドアまで行き、チャイムを鳴らした。扉の向こうから鳴る音がはっきり聞こえた。しかし、それに反応する物音は聞こえなかった。呼応する声も聞こえず反応もなかった。間をおいてもう一度玄関チャイムを鳴らすが同じであった。しかたなくドアノブに手をかけ、そしてゆっくり回した。しかし、昌守の動かそうとするドアノブは固く回らなかった。
時間を間違えているのかと思い時計を見ようとした時、ドアの奥から物音が聞こえた。それは次第に近づき足音だとわかった。昌守は少し安心をしてその音が近づいてくるのを待った。
鍵がガチャリと音を立てて開いた。昌守は扉が開くのを待ったが開く気配がしなかった。ドアノブに相手が手を掛ける気配がしなかった。おかしいと思って昌守が手を掛けようとしたとき、ようやくドアノブが回り出した。ゆっくりと扉が開き始めた。しかし、扉は握り拳一つ分くらい開いたくらいで止まった。その隙間を除くと光一がいた。
昌守は扉を大きく開けようとしたが様子がおかしいことに気づいてやめた。光一は扉を体に預けるようにして開けていた。今、昌守が扉を開くと扉に寄りかかっている光一がよろめいてしまうと思ってやめたのだった。
光一は昌守を確認するとすぐに室内に向かおうとした。寄りかかっていて開いていたドアが閉まりそうになったのを慌てて昌守は手で止めた。光一が寄りかからなくなった事を確認した後に、ゆっくりと扉を大きく開きながら昌守は光一の家の中に入っていった。
「お邪魔いたします。」
中に入りながら昌守は光一に声をかけても、光一は背中を向けたまま、昌守を見る素振りもせず、奥の部屋へと移動していった。部屋に移動している光一の後ろ姿を見て昌守は少しおかしい事に気付いた。歩き方が前と違うような気がした。契約の時は変な歩き方をしていることに気付かなかったのだから、その特に問題なかったのだろう。今日は明らかに歩き方がおかしかった。具体的にいえば左足を引きずるまでは行かないが、左足に体重をかけないように歩いていた。左足を痛め、軽いビッコを引いているような感じだった。
先ほどの玄関での様子といい、今の歩き方といい、今日は以前来たときとは違った。全体的に動作が鈍い印象も受けた。これはきっと、病気が進行して左足の力が入りにくくなったのだろうと思った。最後に光一と会った契約した日から数えて、まだ2週間しか経っていなかった。
【4】
昌守は光一の後を追って奥の部屋に入った。その部屋はテレビやソファー、机などが置いてあった。いわゆるリビングと言われる場所だった。しかし、部屋の広さは6畳弱くらいであり、家具が多く置いてあるために、通常より狭い印象を受けた。窓もベランダに出るための大きな窓が一つあるが、隣に大きな建物があるからか、十分に太陽の光が入ってくるような感じではなかった。
光一はソファーに勢いよく座った。そしてゆっくり昌守の方を見た。そして、重い口を開いて一言言った。
「左足が思うように動かなくなった。」
光一は事実を認めたくないように小さな声で言った。それでも言葉ははっきりと聞こえた。昌守はなんと言葉をかけて良いのかわからず、ただ黙って立っていた。ほんの一瞬の沈黙にもかかわらず、昌守にとってはとても長い時間に感じた。
(冷静に答えよう・・・。)
そう昌守は自分に言い聞かせた。
「医者には行ったのですか?」
何かあれば医師の指示を仰ぐ、というのが理学療法士の仕事だと思い出した。それに頼ることにしたがすぐに光一は言い返してきた。
「診せて何になるんだ?」
光一は昌守をギョロリと睨んだ。そして睨んでも仕方ないと思ったのか、すぐに視線をそらした。昌守は光一に見られた瞬間、言葉が詰まった。光一が言った言葉は正論だった。診せても何もならないのは昌守でも良く知っていた。特効薬があるわけでもないし、仕方がないと片づけられるだけなのはわかっていた。それでも主治医の意見が欲しかった。ただ単に、病状が悪化しているとは自分の口から言いたくなかった。
「そう言わずにちゃんと診てもらいましょうよ。」
昌守は病状を伝えるのは医者の仕事である、という事を貫こうとした。言い訳ではなく理学療法士という仕事がそういうものなのだと自分に言い聞かせていた。
しかし、光一には昌守の言葉は届かなかった。医者は当てにならない、という光一の意見は曲がらなかった。時間を掛けて説得しても光一の気持ちは変わらなかった。これ以上話しても気持ちは変わらないだろうと思って説得することを止めた。
昌守は違う考え方をしてみた。自分が同じ立場だったらどう考えるだろうか、と。光一の主治医には会ったことはないが電話ならある。その電話でさえ適当に流された感じは否めなかった。相談してもまともに取り合ってくれない歯痒さを、もう一度味わいたくない、という気持ちは十分に理解できた。そう思うとこれ以上勧めるのも光一にとってあまりよくないことかもしれないと思った。嫌なことを何度も言われるのはいい気分にはならないと思った。
「わかりました。気が向いたら先生に診てもらって下さい。」
「ああ。」
気のない返事でその話題は終わった。
その後は動きにくくなった左足を中心とした運動を行った。年齢を考えると50回くらい余裕で出来そうな運動を、光一は10回で疲労が溜まってしまった。
「これじゃ、話にならないな。」
光一はそう言って家でもこの練習をした方がいいかと昌守に聞いてきた。
「そうですね。お願いします。」
そう伝えて今日は終了した。
昌守は次の訪問日を光一に伝え、玄関まで行き外に出た。扉を閉めながら光一の姿を確認した。光一は下を向いたまま動かなかった。
【5】
昌守が勤める事業所では訪問リハビリの頻度は週一回がほとんどだった。誰が決めたのかはわからないが、事業所ではそのようなスケジュールで組むことが多かった。その事業所が特別なのではなく、他の事業所の同じ様な形態が多いと聞いていた。訪問リハビリの業界全体がそのような対応が多いのではなかと思っていた。
光一も例外ではなく、病気が特殊だからといって特別待遇という対応はしていなかった。予定で週1回。次回の訪問日まで、あと7日だった。
光一の病気は時間の流れに恐ろしさを感じるものだった。この7日間で別の場所が悪くなる可能性もあった。契約してから2週間後で左足が悪くなっていた。となれば、もう1週間でさらに悪くなっていてもおかしくはなかった。強いて言えば、別の場所が悪くなる可能性も考えられた。右腕もしくは右足の可能性も考えられた。
光一には運動をすればいいと伝えてきた。光一に真剣な目で見られたため、即座に答えを出さなければいけない状況に絶えきれず、深く考えず、昌守は安易に答えてしまった。これをすれば良くなるかもしれない、などとも言ってきてしまっていた。本当にそうなのだろうか?運動をして良くなるものなのか?
昌守は自分がしてきたことは正しい事かわからなくなっていた。光一に運動を勧める事が本当に良いことなのかわからなくなっていた。悪くなるのであれば、運動をしても意味がないのではないか。光一を傷つけるだけではないのだろうか。そう思うようになっていた。
実際に帰り際の光一の様子は失望を感じている様子だった。自分の出来なさと、自分の未来の絶望を一緒に感じている様子だった。
「来週行って、効果がなければリハビリを断ろう。」
昌守はそう気持ちを整理していた。
【6】
最初の訪問から7日が過ぎた。ちょうど光一の2回目の訪問日となった。事務所で今日のスケジュールを確認し、カルテを持って朝から回った。今日は予定どおり回ることが出来て、ちょうど3時に光一の家に着いた。
前回の訪問を思い出していた。光一のがっかりとした表情を今日も見る事になるのではないかと思うと心が痛んだ。もう、今日で終わりにしようと再び心の中で思っていた。
昌守は玄関チャイムを鳴らした。しかしすぐ反応は無かった。一瞬戸惑ったが先週も同様だったのでしばらく待った。すると先週と同じく鍵が開き、全身を使って扉を開ける光一の姿が現れた。すぐに昌守は扉に手を伸ばし、光一が扉を開けなくても済むようにした。 光一は昌守が扉を開けてられるように支えている事に気付くと、すぐに体の向きを変えて家の中へと移動していった。光一の歩く姿は先週よりも酷くなっている気がした。
「どうですか?体の調子は。」
昌守は光一に質問をした。光一は少し間をおいて、質問とは違った言葉で切り替えしてきた。
「なぁ、先生。俺は早く仕事に戻りたいんだ。よろしく頼むよ。」
昌守にとって予想もしない返事が返ってきた。光一は復職を希望していたのだ。仕事に戻るということは日常生活で使う筋力よりもさらに高い筋力を必要としていた。つまり、光一の目標は昌守が考えていた事よりも高いレベルに設定されていたのだった。
光一は仕事をすでに諦めているものだと昌守は思っていた。光一にそうした希望があるのだとは、今までの素振りからでもわからなかった。
「すいません。光一さん。復職はちょっと難しいと思いますよ。」
訪問リハビリを今日で断ろうと思っていたので、この機会にはっきりと伝えようと思い、ストレートに伝えた。昌守はこれ以上、光一からの高い希望を聞くことが苦しくなっていた。しかし、光一はギョロリと昌守を睨みつけ、今度は目を逸らさず昌守に怒鳴りだした。
「俺は仕事一筋でここまで生きてきたんだ!俺はリハビリは仕事をするために頼んだんだ!何だ!?初めから何もしないで!お前まで俺を見捨てるのか!?先生、先生って偉そうにして!結局何もしねぇじゃねぇか!体は鍛えれば力が付くんじゃねぇのか!?あぁ!?もっと色々知ってるんだろ!?教えろよ!その為に頼んだんだからよぉ!!!」
ものすごい迫力で光一は一気にしゃべった。昌守はその勢いに押され、半べそをかいていた。また、その場をやり過ごすために、光一に運動をありとあらゆる方法を伝えた。実際に光一では行えない難しい運動も伝えた。
「知ってんじゃねぇか!とりあえずまたやってみるかぁ!」
先週とは異なり威勢が良かった。これは強いて言えば自分の弱さを隠すためにわざと元気に振る舞っている様に見えた。
「んじゃぁ先生!また来週な!!」
今日はとても愛想良く見送ってくれた。その表情の奥には、リハビリが最後の希望であるとヒシヒシと伝わってくるようであった。
【7】
3回目の訪問となる。2回ほど同じ手順で玄関が開いたので、同様に玄関チャイムを鳴らし、光一が玄関の鍵を開けるまで待っていた。しかし、待っても開かないため、昌守は玄関のドアノブを回した。すると鍵がかかっておらず、そのまま扉を開くことが出来た。昌守はそのまま挨拶をしながら家の中に入っていった。光一も訪ねてくる者がわかっているためか、玄関の鍵はすでに開けてくれていたのだ。昌守は光一が居る奥の部屋に入っていった。光一はソファーに座っていた。そして昌守に顔を向けず、淡々と質問をし始めた。
「なぁ。先生。前のメニューは簡単だったから次の運動を教えてくれよ。」
光一は物足りないと訴えてきた。そんなはずはないと昌守は思った。
前回の運動は光一にとってかなり負荷が高い項目を並べたはずだった。事実、その運動をした後は息切れがみられたし、心拍数も上がっていた。その後はぐったりした表情も見せていたから間違いなかった。
確かにメニューとしては簡単だった。椅子から立ったり座ったりするのを10回。足踏みを10回。その他はベッドで横になって足を上げたり手を上げたりする運動くらいだった。
その程度なら高齢者でも息切れはしない。例えしたとしてもすぐに戻るレベルだった。それでも光一にとっては激しい運動に入ると思われた。
きっと光一にとっても屈辱だったのだろうと思った。こんな簡単な運動を少ししただけで疲れてしまう自分に苛立っていたに違いなかった。光一の目標は仕事に復帰することだから、そのためにはまだまだ不十分なのだろう。まるで現実を見たくないと言っているように自分の体とは違ったものを要求していた。
「まずは前回の運動をしてみて、それから新しいことをやりましょう。」
昌守は出来るだけやさしく言った。言葉の声量も抑えてて光一を心配するように精一杯気持ちを込めて伝えた。前回の光一から出た「俺を見捨てるのか」という言葉が昌守の心に深く響いていたため、言い方を少し変えた。
それでも、光一は譲らなかった。前回の運動は大丈夫だと言い張っていた。何度説明しても前回の運動を行ってくれる事はなかった。やはり、出来ない自分をさらけ出したくないのだろうと思った。
本当はこれ以上、負荷の高い激しい運動は紹介したくなかった。怪我をしてしまう恐れがあるため、それだけは避けたった。しかし、光一の勢いに昌守は負けるしかなかった。
しかたなく昌守はもっと難しい運動を紹介した。難しいといっても健常者ならば簡単な項目だった。片足立ちと床に座った状態から立ち上がるというものだった。
光一がこの運動が出来ないことを昌守はわかっていた。それでもその二つを紹介した。決して嫌みとかではなかった。もう光一に紹介出来る運動がなかったからだった。基本的な運動はそう多くはなかった。つまり、そこまで光一の身体機能は低下していたのだった。
さらに、光一が転ぶという意味は健常者とは違う意味を持っていた。健常者であれば受け身を自然と取ることが出来て、自分が気づかないうちに反射的にいろいろな動作をして怪我を最小限に抑えている人間本来の機能があるのに対し、光一の身体にはその機能がおそらくもうないだろうと昌守は考えていた。つまり、無理な運動をして転んだ場合、骨折をする可能性が充分に考えられた。
「試しにやってみましょうか。安全のために近くで見てますので。」
しかたないと思い、昌守は見守りながらその運動を行おうとすると光一は、
「いや。今日はいい。後でやっとく。」
と言って決して一緒に行おうとはしなかった。転倒のリスクを説明しても光一は自分の意見を曲げなかった。
昌守は考えていた。光一の職業は何なのだろうかと。事務仕事であれば座ってさえいれば片手でも出来るのではないだろうか、と。出勤する方法もタクシーなどを使ってなんとか行けないだろうか、と。そして昌守は光一に職業を確認した。光一は素直に話してくれた。
光一はうどんを提供するお店に勤めていた。高校卒業後、就職し調理師免許を取得した。自分で店を持とうとも考えたが、修行先の店主よりずっと一緒にやって欲しいと言われ、今までやってきたらしい。
「18歳から就職をして、30年以上その店で働いてきた。大変なこともあったし、楽しいこともあった。店主に早く元気になった姿を見せたいんだ。今はおそらく一人で店を切り盛りしているんだろう。あそこは意外と駅からは離れてはいるが、固定客が多い。しかも年輩が多いからよく部下を連れて来たりするんだ。昼なんかは満席になることもよくある。近頃はうちみたいな店が珍しいんだろう。老舗という貫禄がうけているらしい。その常連客が連れてきた部下がその友人を連れてくることも増えてきた。店主は息子がいないから後継ぎがいない。今頃はどうなってるのか心配でしょうがいないんだ。でも、ほら。この身体だろ?行っても邪魔になるだけじゃないか。何とか復帰して、またお店で働かなくちゃならないんだよ。」
光一の切実な思いを聞いた。職場に対しての気持ち、仕事に対しての思いを正面から受け止めていた。昌守は光一の気持ちを無駄にすることは許されるのだろうかと考えるようになっていた。せめてもう少し、光一の希望を長く持たせてあげたくなっていた。
しかし、再び冷静になり病気から言えば無理だと考え直した。一時の感情で流されてはいけないと思い直してもいた。
(無理ですよ。)
その言葉で簡単に光一の希望を切り捨てる事は出来た。しかし、その場の昌守には言えなかった。それはすでに光一が無理だと言うことを知った上で、今の会話があるような気がしたからだった。
【8】
昌守はその夜、自宅に帰った後うどんを自分で作ってみることにした。光一は左手が使えなくても右手は何とか使えるため、右手一本でうどんが打てないかどうか試したかった。
昌守はうどんを打ったことがなかったので、インターネットで探した。料理のレシピサイトにたどり着き、うどんを作るための材料を見つけた。そこには、小麦粉と塩水だけで作れるような事が書いてあった。
さっそく材料を家の中から材料を見つけ出し、そしてレシピどおりに作り始めた。混ぜるために大きめのボールが昌守の家に無かったので、少し大きめの鍋で代用した。適量の小麦粉をその鍋に入れてさらに少量の塩水を入れた。鍋はキッチンの台の上において、レシピ通り小麦粉を混ぜようとした。しかし、片手だと小麦粉を入れている鍋がキッチンの台の上に固定されず滑ってしまった。ついもう片方の手で押さえようとしたが、その手は使えないのだと考えなおして止めた。少し考えた昌守は、まだ使っていない100円ショップの滑り止めシートを入れ物の下に入れた。そしたら鍋がある程度滑らなくなったのでその問題は解決をした。
塩水を少しずつ足しながら小麦粉をこねていくと、次にこねるスピードが遅いためか小麦粉にしみていた水分が乾いてしまい、角の所が乾いてしまう事がわかった。必死にスピードを上げ、さらにホームページに記載している水分量より多く入れる事で解決した。
次にレシピにはそのこね上がった生地をのばす作業が書いてあった。丸い均一の太さをした棒を両手でころころ転がしていく動作がそのホームページでは紹介されていた。それを片手でどう行えばよいのだろうかと昌守は考えた。試しに棒を片手で転がしても生地が均一に伸びなかった。次に、ビニールに入れて足で伸ばしたが生地が均一に伸びず、踏んだ所だけが伸びている事に気づき止めた。そうして悩んでいるうちに生地がまた乾いてきてしまい、端の方からボロボロとほつれてしまった。
「やっぱり出来ないのか・・・。」
昌守はうどんを打つのを止めた。小麦粉を混ぜた鍋でお湯を沸騰させて、打った生地を一つ一つ親指大にちぎりながら丸めて鍋に入れ、すいとんにして食べた。小麦粉の固まりを食べながら、片手でうどんを作る事を諦めるしかないと思った。
【9】
(やはり復職は難しいと思います。)
その言葉を昌守は言わなければ行けないと思っていた。今日は光一の訪問リハビリの日だった。気が重くなるのが自分でもわかった。いつもよりも車をゆっくり走らせているのが自分でもわかった。早く着くのが嫌なのだと改めて思い直していた。
光一の玄関の前まで来たときに、今日は曇りなのだとわかった。今日は常に下を向いていたんだな、と思った。
玄関チャイムを鳴らし、玄関の扉を開け、光一が待つ部屋まで行った。挨拶をしながら奥の部屋まで入っていった。
部屋にはいると光一はソファーの上で寝ころんでいた。昌守を見ようともしなかった。暗い雰囲気を部屋中に漂わせるように光一は何も動かなかった。昌守はそのまま光一が横になっている部屋を見渡すとテーブルの上に一枚の封筒が置いてあった。表書きに「退職届」と書いてあった。
「それをポストに入れてきてくれ。」
昌守がその封筒に気付いたことを光一は察知していたようだ。光一が昌守に話しかけた。
「光一さん。こういうものは自分で出しに行く方がいいと思いますが。」
「もう自分じゃ仕事場には行けないし、ポストまでも行く事も出来ない。」
ソファーに寝ころんでいた光一が話しながら起きあがった。そしてそのまま下を向き、床を見つめた。動く右手で左手を大事に触った。寂しい背中がいつもより増して見えた。
(もう一度動いて欲しい。)
そう願いながら何度もその仕草をしてきたのだろうカ。左手を触る右手はとても慣れているように見えた。左手の親指、左手の人差し指、左手の中指、左手の薬指、そして、左手の小指。全ての指を光一はゆっくり自分の右手で動かしていった。手首に近い指の関節、指先に近い指の関節、ゆっくり大きく動かし、固くならないように丁寧に曲げていた。光一がするその仕草は、愛おしく、そして悔しく思う気持ちがとても伝わる動きだった。
封筒の隣に大きめのメモ紙が置いてあった。そのメモ紙には格子状になった表があり、横軸の一番上には日付が書いてあった。その下には数字が書いてあり、縦軸の一番左には項目らしい文字が書いてあった。昌守はそれを上から目で追った。
「スクワット・バンザイ・片足立ち・・・」
昌守が今まで教えた動作が書いてあった。光一は昌守が教えた自主トレの項目を忠実に行っていたのだった。昌守は日付とその数字を追った。最初は「20」という数字から始まっていたが、「18」、「16」と数は徐々に少なくなっていた。「10」という数字からは数の記入がなく、記号の「○」という物に変わっていた。そしてこの一週間でそれさえも無くなっていた。
この数字は回数を意味しているのだろうと思った。項目に対し、行った回数が記してあるのだと思った。
昌守は隣にある封筒を再び見た。昌守は光一が言った言葉を思い出していた。光一は、今この封筒を昌守に出してもらうよう頼もうとしているのだと分かった。光一は訪問リハビリが開始してから、ずっと再び仕事に復帰しようと努力してきた。しかし、もう自主トレさえ出来なくなり、仕事復帰を諦めた光一が、昌守の目の前にいた。その姿は生きる気力を無くし、これからの希望も失っているように見えた。昌守は思った。生きる希望を無くした人間というのはこんなにも無惨な姿になるのだろうか、と。生きる希望を捨てさせようとしていた自分は間違っていたのではないだろうか、と。
昌守は「退職届」と書いてある封筒を手にした。もう一度、その大きく書いてある「退職届」という文字を見た。よく見ると筆圧が弱かったらしく、力強く書けてなかった。おそらくボールペンで書いたのだろうか。文字を書く力も衰えている事も予想できた。
「この封筒は受け取れません・・・。」
昌守は声を細く聞こえないかのように小さく言った。下を向き、昌守は自分が持っている封筒を見つめながら話した。それは光一に伝えると言うよりも自分の意志を確かめるような言葉だった。封筒は昌守の握力で折れ曲がっていた。
昌守は悔しかった。復職を諦めるということの本当の意味を今知ったような気がしていた。リハビリを断ろうとしていた自分の考えが、とても浅く、自分勝手な考えなのではないかと感じていた。昌守は、自分の一方的な考えで、それを自分の逃げ道として、自分の気持ちを押しつけていただけだったのではないか、そう振り返っていた。とても自分が嫌になった。
「いや。出しといて欲しい。もう決めたんだ。」
光一は念を押すように昌守に言った。今までの言葉で一番芯のある感情が真っ直ぐに伝わってくる話し方だった。その言葉がさらに昌守の気持ちを高ぶらせた。
「いけまんせ!絶対にいけません!これは・・・これは預かっておきます!」
昌守は「退職届」を握りしめたまま、光一の家を飛び出していた。
【10】
握っていた「退職届」の封筒には住所が書いてあった。光一が勤めていた住所だった。昌守は今日の仕事が終えたらそこに行こうと思った。何か自分に出来る事を少しでも探したい気分だった。
仕事を終え、封筒に書いてある住所を頼りに車で行くと、警察署の隣の角を曲がった道幅の広い道路の脇に、その店はあった。光一が話していたとおり、駅からは遠いが古い建物で老舗の雰囲気を漂わせていた。風格のある建物だった。その建物の中に、昌守は迷わず入っていった。
店の中は外観から予想した通りの雰囲気だった。至ってシンプルな作りで、昔の様子をそのまま大事にしているようだった。机にテーブル、そしてメニューも老舗そのものの品物だった。店員は昌守を空いているテーブルに案内し、昌守が椅子に座ると店員は奥に戻って水を持ってきてくれた。
「注文はなんでしょうか?」
若いとまでは言いにくいが、品格のある綺麗な女性店員は、笑顔になって昌守に聞いた。昌守はひとまず注文をして食べてから対策を考えようと思い、歴史を感じるメニューから値段が手頃な物を選らんだ。
注文を済ますと女性店員は奥に戻って行った。昌守は注文の品を待ちながら店内を見渡すと厨房の様子が僅かに伺えた。その隙間からは調理をしている一人の男性の姿が少し見えた。一人で切り盛りするのは忙しいと光一が言っていた言葉を思い出した。光一が言ったとおり、その厨房にいる男の動きは鈍く、年齢を感じさせた。お店には客が4、5組いた。さらに奥には座敷があるようで、大人数の客が入っていた。まとまった注文に追われているのだろうと思った。
最近は若い客も来るようになった、と光一の言葉を思い出した。客層は年輩の人から若いカップルまでいた。奥の座敷からは元気のいい若そうな声も聞こえた。この客を一人でこなしていくのは大変だろうと思った。
昌守も例外ではなく、だいぶ待たされてから注文した品が来た。先ほどの女性店員が申し訳なさそうにしながら持ってきてくれた。その笑顔を見ると待っていた事を忘れてしまうほど心安らぐものだった。それでも忙しい様子は隠せず、すぐに違うテーブルの対応に行ってしまった。昌守は注文した品を食べていると、奥の座敷にいた客が帰っていく姿が見えた。人数は7,8人いた。年齢は30代くらいなのだろうか。やや落ち着いた雰囲気をした人たちが帰っていった。
そのまま視界を厨房の方へ移動すると、先ほど少ししか見えなかった男性の姿全身見えた。髪は白く、少し腰が曲がっていた。一つ一つ動く動作もどこかに手を添えてながらでないと動かないほどフラフラしていた。恐らく疲れからだろうが、これが毎日続くのかと思うと昌守でさえ心配してしまった。
昌守は注文した品をゆっくり食べていると、いつのまにか店内の客は昌守一人になっていた。気付けば時間は閉店間際だった。いつの間にか暖簾が降り、玄関の電気が消されていた。先ほどの女性店員もあわただしかった一日を終えたという気持ちが出ているのだろうか、動くスピードが最初とは大きく違い、ゆっくりとしたスピードで片づけをしていた。
「空いたお皿をお下げしてもよろしいですか?」
昌守が見ていることに気づいたらしく、その女性は昌守に声を掛けてきた。昌守は慌てて自分の皿が空いていることを確認し、うなずいた。
「ここは古くからやっているのですか?」
昌守はお皿を下げている女性店員に聞いた。女性店員は丁寧にこの店の歴史を話してくれた。話の内容は光一が話してくれた内容とほぼ同じ内容だった。駅から遠い事。最近は若い客が多くなってきた事。新しい情報では地域限定の雑誌に載るようになった事も話してくれた。話してくれた女性店員はここの店長の娘だと教えてくれた。厨房に居た人が店長で、もう年齢も高く身体が思うように動かないとの事だった。そして、店長の娘はこう続けて話した。
「後継者として働いてくれていた人がいたんだけど、病気になってからしばらく来ていないんですよ。戻ってくるのを待っているのだけど、もう大分経つからねぇ。私もやっぱりダメなのかなぁと思っているんですよ。なにか難しい病気で長い時間が掛かるそうだとまでは知っているのだけど・・・。今何してるんだろうねぇ。お父さんは電話したいみたいだけど、こっちから電話するのも催促するようで嫌だって言ってたし。やっとこの店の景気が良くなってきたのにねぇ。」
店長の娘は普段の愚痴をこぼすかのように話してくれた。後継者とはきっと光一の事を言っているのだろう。昌守も
(その人を知っています。)
と言いたくなった。しかし、言うのは止めておくことにした。個人情報の問題もあるが、光一本人が望まないと思った。望まない事をしても喜んではくれないと思った。店長の娘はまだ話し続けた。
「でもね。最近、若い人が一人入ったのよ。父は今休んでいる人が後継者だと言い張ってたんだけどね。今のお客さんに対して自分の体が追いつかないことが日に日にわかってきたみたいで。渋々、若い弟子を一人雇ったんですよ。
今は修行中ですけどね。何だかんだ行って、父はだいぶ助かっているみたいですよ。」
昌守は予想もしない情報に困惑していた。光一の居場所が無くなってしまうと思ったからだ。店長の娘に病気した人が回復して戻ってきたらどうするか聞いてみた。
「病気で休んでいる人が戻ってきたらどうするかって?そりゃぁありがたいけどね。でも、本当に治るか心配なんですよ。何か深刻そうな表情だったから。きっとなかなか治りにくい病気なんだろうと思うんですよねぇ。
そうなるとなかなか戻ってくるのは難しくなるんじゃないかなぁと思ってもいるんです。お父さんも最近はあまり期待してないみたい。今やっと弟子が使えるようになってきたって少しうれしそうになってたし。
でも本当は戻ってきては欲しいですよ。勘違いしないでくださいね。私だって戻ってきてほしいんですけねぇ。なかなかねぇ・・・。」
やはり、お店側でも完全回復を期待してはいないみたいだった。さらには病気の事まで知っているのだろうか。でも、待っているということは病名までは知らないのだろうと昌守は考えていた。
「今日は若い人が休みだから久しぶりにお父さん忙しく働いてたけど、端から見てもやっぱりキツそうだったね。味だけは守りたいみたいだから、出来るだけ厨房に立ちたいって言ってたけど。」
店長の娘はほとんどぼやきの様な状況になっていた事に気づき、反省した様子になった。
「あらやだ。余計なことをベラベラと。こんなお店だけどよろしくお願いしますね。」
と、昌守に言ってごまかして昌守の会計をし始めた。昌守もそろそろ帰ろうと思い、そのまま会計を済ませてお店を後にした。
昌守は帰り道で考えていた。この店は景気が最近よくなり忙しくなってきている。店長もやはり光一の復帰を待っていたと考えられた。しかし、やはり経営を考えると、お店のお客が増えていく中でお客を待たせるわけにはいかないと判断し、人を新たに雇ったのだろう。
忙しい店の中で光一が復帰する姿を思い浮かべた。今よりも身体機能が上がらない状態で厨房に立つ姿を想像した。光一は動けず、若い新たな新入社員に次々と仕事が任されていく様子は、光一にとってどう思うのだろうか。きっとその場所に居ることさえ苦痛になってしまうのではないか。
そして、病名からすればさらに体は動かなくなっていく事は間違いなかった。その心と体が矛盾した状況に光一は絶えられるのだろうか。
昌守は再び「退職届」を取り出した。これを出すことに否定した自分を後悔した。
(結局、自分は何も出来ないじゃないか。)
そう感じざるを得なかった。
帰り道にポストがあった。昌守はポストの前まで行き、握りしめた封筒をポストの中にゆっくり入れた。
【11】
光一から預かった退職届をポストに入れてから数日が経った。昌守は本当にこれで良かったのだろうかと考えていた。もし、ポストに入れず、店長の娘と交渉をして、店長とも話し合いが出来たのならば、仕事は少なくともあったかもしれない。仕事を辞めずに済んだ可能性もあったかもしれない。光一の病気は脳の機能は正常に保たれるから、光一が持っている知恵を使えば仕事があったかもしれない。そう考え出すとやっぱり勝手な行動をしてしまったのではないかと考えてしまっていた。
しかし、冷静になればなるほど例え復職したとしても再び仕事が出来なくなる日が必ず来る事は間違いなかった。そう考えるとまた胸が苦しくなった。筋委縮性側索硬化症という病気は筋肉という部品を急速に動かなくしていく病気だ。他人が気付かないうちにすぐに力が無くなり、今まで出来たことを平然と出来なくしていく病気なのだ。
光一はきっと仕事に戻ることが出来たとしても、再び出来なくなる日が必ず来る。再び仕事仲間に無惨な姿をさらさなくてはならない日が必ず来る。それでもきっと、おそらく光一は最後までそうした事を隠し、努力して見せないようにしていくだろう。それでも限界は必ず来る。他の店員に知れ渡るときは光一の努力が限界を超えたときだ。
昌守にはその光景が想像できた。実際にお店に入ったので想像がより具体的にできた。光一が力つきる姿を頭の中ですごく鮮明に想像出来てしまっていた。
「僕にはやっぱり勧められない・・・・。」
色々考えても、やはりそう結論づける毎日だった。次の日も、その次の日も、昌守は再び同じことを最初から考えてしまっていた。
ある日、その考えを繰り返していくうちに、なぜ光一は働きたいのだろうと考えるようになった。最初は復職したいのは光一が単にもとに戻りたいためなのだろうと決めつけていた。しかし、光一はあの家に独りで住んでいるのではないことに気づいた。光一には家族がきっといるはずだと考えるようになった。
昌守は光一が住む家の様子を思い出していた。玄関にある靴は独りではあまりにも多い数の靴があった。洗面所には整髪料などがあり、光一の都市では使わないだろう洗顔料もあった。歯ブラシも複数本あった。これを考えれば光一だけがあの家に住んでいるのではないと考えられた。
しかし、よく考えれば女物の品物がほとんど見当たらなかった。靴は男のものばかりだし、化粧水などもなかった。歯ブラシも赤やピンクなど華やかな色のものは無く、部屋の中の匂いも男臭い香だけが漂っていた気がした。
このことから考えるとおそらく光一の家には女性がいないのではないかと考えられた。しかし、光一の薬指には指輪があった事を思い出した。そこから考えれば結婚はしているのだろうか。でも女性の影がないとすれば、妻は同居していないのか。そして、男物のものが多いとなれば息子がいるのではないか。思い返せば靴も少し大きいものがあり、若者が履く派手なものがあったような気がした。
さらに光一がいつも座るソファーのある部屋を思い出していた。棚の上には剣道大会で優勝したトロフィーが飾ってあった。最初は光一本人のものだと思っていたが、日付が4~5年前になっていて、どうやら光一本人の物ではないようだった。その時はあまり気にしなかったが、今思えば息子の存在を示すものだと考えられた。
「もしかしたら息子のためにお金がいるのではないのだろうか・・・」
光一の年齢から計算をして息子の年齢を想像しても、まだ学生の可能性が高かった。となれば学費などの経済的な事を考えれば、働かなければならない理由になると思った。しかし、昌守には経済的な問題に対して何も対策が思い浮かばなかった。苦し紛れに自分がお金を出そうと考えたが、何も解決にはならないし、例え出したとしても断られるだけだと考えていた。
途方に暮れたときに外からサイレンがなった。耳をすますと
「火災が発生しました。」
と言っているようだった。住所までは聞き取れずにいると、携帯電話にメールが1通届いた。そのメールは火災があった住所を明記した内容だった。送り主は武蔵野市役所だった。
それを見て昌守は考えていた。もしかしたら、国や市の制度にある社会保障で光一の経済問題が救われるかもしれない、と考えた。昌守は明日市役所に行って探してみようと思った。
【12】
武蔵野市役所は武蔵野市の中心付近にあった。『市役所通り』と呼ばれる一直線の道路があり、市役所はその脇に建っていた。『市役所通り』は春になると両脇に植えられた桜の木が満開になり、見事なトンネルを造るのでちょっとした有名スポットだった。今は桜の時期ではないが緑の葉っぱでもトンネルは綺麗に造られ、そのトンネルの合間に市役所は建っていた。
昌守は市役所の中に入り案内人のような人がいたのでその人に聞いた。
「すいません。難病で働けなくなってきた人に対して何か経済的に補助してもらえる制度ってあるのでしょうか?」
昌守の単刀直入な質問に対して案内人は面食らったようにもう一度昌守の質問を聞いて理解しようとしていた。昌守は自分の職業を明かし、光一の名前も出して話をすれば具体的になり話も進みやすくなるのだが、今回は光一の名前は出さず話をしようと思った。個人情報はしっかり守ろうと思っていた。
案内人は昌守の質問を理解し、
「障害福祉課が担当なのでそこで質問をして下さい。」
と言われた。再び窓口に立ち手前に座っている50代半ばの男性に声をかけた。その男はしわがやけに目に付くスーツを着ていた。その男が立ち上がって昌守に向かって歩いて来た。さらにその男を良く見ると、その男の体格より一回り大きいスーツを着ていて、顔とスーツのバランスが合わなかった。昌守は少し頼りない印象を受けていたが、その男は構わず昌守の対応を始めた。
「どうされましたか?」
昌守は光一の名前は出さず、今回は制度の勉強として質問をしに来たことにして、説明を受けようとした。しかし、かえってこの事が男の機嫌を損ね、態度を急に変え、あたかも迷惑そうに話し出した。
「そうですか。勉強ですか。今はいろんな本があるのでそちらが一番勉強になるのですけどね。」
そう嫌みを小言で挟みながら、机の下にある一つのパンフレットを渡してくれた。
「障害年金」というタイトルのパンフレットだった。
「これで良いんじゃないですか?」
役所の男はこれで終わりにして欲しい様な態度で昌守を突き放そうとした。昌守も十分な資料を手に入れたのでその場を去った。しかし、とても嫌な気分になる対応をさせられて、
(だから役所の人間は嫌いなんだよ。)
と文句を言いたくなる気分だった。
【13】
昌守は障害年金の資料をみて勉強をしていた。障害年金という制度は年金の一つで、年齢が若いうちに就労が出来なくなった人に対し、障害者手帳の1級もしくは2級を持っていれば支給される制度だった。幸い、契約したときに障害者手帳を持っていることを昌守は確認をしていた。その障害者手帳には2級という文字が書かれていた。おそらく左上肢が使えないため、それが2級の適応となったのだと思った。
このパンフレットを持って行けば、光一も少しは安心してくれるのではないかと考えていた。昌守は光一のために出きることが増えた気がして少しうれしくなっていた。
数日後、光一の家に行く日になった。早く知らせてあげたい気持ちを抑えてパンフレットを持って仕事に出かけた。午後三時になり、光一の家に着いた。いつものように昌守は玄関まで行き、玄関チャイムを鳴らした。そしてすぐにドアノブに手をかけて回し、ドアを引いた。いつもであればここでドアが開けられるのだが、今日は鍵がかかっていた。ドアが開かないことを不思議に思い、もう一度確認するようにゆっくり同じ動作をしたが、やはりドアは鍵がかかっていて開かなかった。
「こんにちはー!リハビリの昌守ですー!」
昌守は玄関を叩いて光一を呼んだ。しかし、何分待ってもドアは開く気配がしなかった。
光一が留守になることは考えられなかった。今の身体能力でどこかに一人で出掛けることは難しいと思った。となれば、光一は家に居るはずだった。しかし、ドアが開かないということは故意に開けないという事なのだろうか。つまり、もう光一は昌守を必要としていないという意味の表れなのだろうか。
昌守はさらに強くドアを叩き、ドア越しで光一の名を呼んだ。
「光一さん。いらっしゃいますかー?リハビリ昌守です!」
いつもよりも一つ声を大きく出し、扉の向こう側に居る光一の耳に届くように声を大きくして呼んだ。しかし、ドアの向こう側から反応はなかった。最初は近所迷惑だと思って声を抑えていたが、昌守も感情が高まり、声が徐々に大きくなっていった。
「光一さん!居るのは解っているんです!開けてください!」
何度も声を掛けるがそれでも反応はなかった。光一にはまだ退職届を出したことは知らないはずだった。であれば開けてくれてもいいはずであった。しかし、扉は一向に開く気配がしなかった。
諦め掛けて扉を叩くことを止め、帰ろうとしたとき、ドアの向こうで物音がした。その音が徐々に近づいてくることが解った。光一の足音に違いなかった。
(やっぱりいるんだ。)
昌守は光一がドアの鍵を開けるのを待った。光一はドアの向こう側まで近づいたところで足音は止まった。しかし、光一は玄関の鍵を開けることはしなかった。
昌守は声の大きさを抑えて光一にやさしく話しかけた。
「光一さん。今日は鍵を開けてくれないんですか?」
光一は少し間をおいて返事を返した。
「退職届の受理通知が届いた。」
昌守は光一の言葉を聞いて固まった。まさか、そういう風にして退職届を出したことが光一に知らされるとは思いもしなかった。
「帰ってくれ。」
光一は冷たく低い声で言った。
「待ってください!光一さん!」
昌守は慌てて引き止めるように言った。
「もう、お前に用はない。」
それでも光一は昌守を引き離すように冷たく言った。
「光一さんには息子さんがいるんですよね?」
昌守はこれ以上会話が出来なくなることを恐れ、光一を引き止めようと考え、息子の話を出した。光一はその言葉を聞き、一瞬沈黙が生まれた。しかし、その沈黙をすぐに破るように大きな声で言った。
「息子は居ない!居てもお前には関係のない話だ!!」
光一は明らかに動揺していた。まるで二人の間に何かあるような言い方だった。それでも昌守は引き下がらなかった。一つでも光一の役に立ちたいという一心でくらいついた。
「息子さんが居るなら尚更お金が必要なんじゃないですか?今日はいい知らせを持ってきたんです!」
「うるさい!もういいだろ!帰ってくれ!!」
その言葉を最後に昌守がいくら声を掛けても、光一からは反応が無くなってしまった。もう既にドア向こうにはいないような気がした。昌守はドア越しに頭を下げ、退職届を出したことを謝った。元々は自分が何とかすると言って預かった手紙だったからだ。それを昌守の判断で勝手に出してしまったのだから光一が怒ることも無理なかった。今日はとりあえず引き返そうと思った。
それでも昌守は障害年金のパンフレットだけは早めに見てもらいたいと思った。玄関ドアにポストがあったのでそこに入れ、足早にその場を去った。
【14】
障害年金のパンフレットを置いてきて数日が経った。この数日は光一のその後の様子が気になっていた。しかし、昌守が焦ったところで何かできる事があるかと考えると何も思いつかなかった。それよりも今後どうしていけばよいか悩んでいた。
光一からはもう来なくていいと言われてしまった。光一のリハビリの目的が復職であった事を考えれば当然の事だった。しかし、本当にもう光一の家を訪ねなくて良いものなのだろうかわからなかった。もう、昌守の役目は終わってしまったのだろうか、と深く考え込んでいた。
この間の光一の話し方からすれば、息子との関係はあまり良くないと考えられた。どこまで良くないかわからないが、今後光一の体が動けなくなった時のことを考えれば、手助けしてくれる人はおそらく息子だけになると思った。となれば息子の存在はとても重要な人物となることは間違いなかった。
家族構成が示されている資料はないか昌守は光一のカルテを見返した。見返すと言っても主治医からの指示書くらいしか参考になる資料はなかった。隅々まで目を通したとき、備考欄に家族構成が記載している事に気づいた。とても読みにくい字だったため、最初見たときに見逃してしまったのだろうか。読みにくい字を何とか想像力を膨らませて読んだ。
「妻 死去。 一人息子。」
と書いてある様だった。なんども読み返してみても、そうしか読めなかった。やはり父子家庭だった事がわかった。妻はすでに亡くなっているようだった。理由はわからないが、妻のいない分、手助けしてくれる人は息子しかいない事がはっきりした。さらに言えば、妻の収入に期待できない分、経済的に苦しい事も予想できた。
息子は今何をしているのだろうか、年齢はいくつなのだろうか、光一と同じ大きさの靴がたくさんあった事から考えると、もういい大人なのだろうか。それとも中学生くらいであれば、靴の大きさくらいはすでに親と同じくらいになると聞いたことがあるから、まだ中学生くらいなのだろうか。
悩んでいるうちに昌守は光一の息子と会えないだろうかと考えるようになった。光一に内緒で会い、今の状況を直接説明すれば、親子の関わりも違ってくるのではないかと考えた。
しかし、そうした場合に光一はどう思うだろうかとも考えてみた。自分と意図しない事が勝手に進むことに対していいようには捕らえないのではないかとも考えた。
今は光一と息子との関係が良くないとなれば、今光一に黙って会うことは良いこととは思えなかった。まずは光一との関係を良くしなければいけないと思った。昌守は関係改善に全力を注ごうと思った。そして、さらに数日が経ち、光一を訪問する予定の木曜日になった。
昌守は木曜日の訪問予定を、光一を含めて行っていた。朝から普段通りに回り、午後の三時に光一の玄関の前についた。しかし、先週は断られていたため、今日の昌守は玄関チャイムを鳴らす勇気が持てずにいた。ここで断られた場合、次の手が思いつかなかったからだった。
(なんとか会って関係を改善しなくては・・・)
その考えで昌守の頭の中はいっぱいだった。
玄関チャイムを鳴らした。当たり前に響くチャイムの音が扉の向こう側で鳴っていた。いつもよりも小さい音のように感じた。しかし、自分の気の弱さがそうさせているのだと思い、自らの心を引き締めていた。
チャイムが鳴っても、扉の向こうで物音はしなかった。やはり、鍵は開けてくれないのだと思ったが、最近は昌守自身がドアを開けている事に気付いた。昌守はドアノブに手を掛けてひねった。しかし、ドアノブは回らず動かなかった。昌守はさらに握力を強めてゆっくりと捻った。やはりドアノブは固く動かなかった。
昌守は開かない玄関の前に立ち止まっていた。そして先日、同業者の友人に会う機会があり、光一の状況について何か良い解決策はないか相談した事を思い出していた。たまたま会話の中で今の悩み事の話題になり、光一の相談をした事があった。相談した結果、友人も「解決策はない。」という判断だった。もっと言えば、「それ以上、関わること事態が訪問リハビリとしておかしいのではないか。」とも言われた。そこまで関わる必要もないし、そんなに無理をする必要もない。望まれてはいないのだから行く必要もない。そう友人は言いたかった様子だった。
確かに冷静になればそのような結論になることも不思議ではなかった。訪問リハビリとはいえ、国の保険で行われている業務だ。さらに光一が患っている筋委縮性側索硬化症は国の難病指定となっていて、光一に自己負担無く実施できる状況なのだ。その制度を利用して昌守が必要のないリハビリを押し売り状態で訪ねていると言われても仕方ないとも言えた。
しかし、光一には本当に訪問リハビリは必要ないのだろうか。光一には本当に昌守が必要ではないのだろうか。昌守は頭を悩ませた。
昌守は悩んだ結果、玄関ドアの向こう側にいる光一に届くように、語り出した。
「光一さん。部屋にいるのはわかっているんです。あなたが一人で外に出られないほどの身体になっていることは私が一番よく知っています。だから部屋にいるのは知っています。知っているからこそ、今から話す内容をよく聞いてください。聞いて条件が合えば、この扉を開けてください。」
昌守は一呼吸をして一気に語り出した。
「光一さん。あなたは今、おそらく生活に困っているはずです。それは経済的だけではない。身の回りのことも少しずつ出来ない事が増えていっているはずです。解っているはずです。たとえ、今は出来ていても、そのうち出来なくなる身体になりつつある事を。今まで平然としていた動きが、努力をしなければ出来なくなってきている事を。
光一さん。今の制度で私があなたを訪れることに条件はありません。リハビリという言葉は、何にでも変えることが出来ます。とても都合のいい言葉なのです。そして、あなたには費用がいっさいかからない。
光一さん。私を利用しませんか?あなたが好きなように私を利用するのです。私はそれをリハビリと言いましょう。私はそれを訪問リハビリの仕事とするのです。あなたに費用もかからず、そして自由に私を使うのです。
光一さん。私が考えた条件は以上です。あなたがこの条件に納得するのであれば、この玄関の鍵を開けてくれませんか・・・。」
昌守の声は低く、丁寧に話していた。近隣の住民にも配慮した声の大きさだった。それでも扉の向こうには物音一つしなかった。昌守は目を閉じ、これ以上の策はないか考えた。しかし、その場では思いつかなかった。悔しさと絶望感が一つの波になって昌守の頭に押し寄せた。
そして、昌守は諦めて玄関に背を向けようとしたとき、ガチャリと金属が擦れる音がした。扉が握り拳一つ分開き、光一が昌守を凝視していた。
「入れ。」
光一は昌守にそう言ってすぐに扉を閉めた。閉めたというよりも開けている力がないのを昌守は思い出していた。昌守はすぐにドアノブを捻り、玄関を開けて中に入った。
光一は奥の部屋に入っていった。その後ろ姿は以前に増して左足を引きずっていた。
光一は全体重を預けるようにソファーに座った。ソファーは光一の体重を支える代償として金属がしなる音を出した。光一は、その音が鳴りやむと一枚の紙を手にとり、昌守に差し出した。新聞紙に挟まれているような広告紙の裏紙を使用していた。その白紙部分に食料品の項目を書き始めた。そして、沢山の品物の名前を書くと昌守に言った。
「これを買ってきてくれ。」
昌守は躊躇うことなくメモ用紙を手に取り、すぐに外に出かけていった。
しばらくして昌守は買い物を終え、光一の家に戻ってきた。量はかなり多く、片手で二つずつビニール袋を持つほどの量だった。さらには手のひらが袋の後で痛くなり、よくみれば赤い線が出来るほど重みのある量だった。買ってきた物は、総菜、パン、弁当などが多く含まれていた。内容を要約すれば、買ってきてそのまま食べられるものが多かった。調理が必要な食材は一切無かった。
買ってきた食材を光一に頼まれて冷蔵庫へ入れた。弁当は冷凍庫へ入れた。なぜ冷凍庫なのかと光一に質問したら、「解凍して食べれば賞味期限を超えても食べられるからだ。」と説明してくれた。「今までどうしていたのですか?」と質問すると貯蓄していたレトルト食品を食べていたようだった。しかし、ちょうどそこを突き始めていたようだった。
買い物の品も冷蔵庫に入れ終わり、帰る時間になった。
「来週も来ますから。」
帰り支度をしながら昌守は光一に言った。
「来たくなかったら来なくて良いぞ。」
光一の言葉は昌守を受け入れる方向へと変わっているような気がした。
「じゃぁ、また来週もお伺いします!」
昌守は今までで一番良い笑顔を作って光一の家を後にした。
【15】
昌守は週末を迎えた。昌守の事業所は日曜日が休みのため、昌守はのんびりと過ごしていた。お昼過ぎにコンビニで立ち読みをし、雑誌を読むのが昌守の休日の過ごし方だった。新聞を取っていない昌守にとって、週刊雑誌に記載されている政治やスクープを読むのが一つの情報源になっていた。
男と女が手をつないでいる写真を撮られて男女関係を記事にしているところとか、政治家の裏事情を書いて本当にそうなのって疑問を抱くところも昌守にとっては楽しい時間だった。朝のテレビでは流れないような情報が入ることに、少し得をした気分になるところが好きだった。
そうして読んでいく中で、「高齢者の孤独死」というタイトルが大きく書いている記事を見つけた。一緒に載っている写真も、高齢者が一人で住んでいるような古い家だった。
昌守はその古い家と光一のアパートを重ね合わせていた。雑誌の記事にはその家での出来事が書いてあった。その内容とは、家族内で祖父が死亡しているのにも関わらず、まったく気づかなかったという内容だった。前にも聞いたことのある内容だった。どうせ自分には関係のない出来事だと思えるような内容だったが、どうしても今の昌守には光一の家と重ねてしまっていた。
もし光一の息子が完全に接触が無かった場合、このような孤独死という可能性は十分にあった。それを前回の訪問で少しでも解消出来た事に、やはりあの行動は間違っていなかったのではないかと考えていた。
ただ、そう思うことで昌守は自分自身を正当化しようともしていた。そう思い続けることで、リハビリという内容を大幅に解釈し、光一の家に伺い続ける事に、少し後ろめたい気持ちになっていた。買い物をし、身の回りの手伝いをする事が、本当に理学療法士という資格を持った者がする仕事なのかどうかと疑問になっていた。ただ、昌守も業務として光一の家に行かなければ事務所も納得しない事は間違いなかった。
光一宅をこれからも行くという事は、リハビリには関係のない仕事なのかもしれない。それでも行かなければいけない。そういう使命を自分には持っていると考えたかった。
しかし、今後のプランは何も立っていなかった。このままどうなっていくのだろうか。昌守は頭の中が真っ白になっていた。
休日だったため、頭の中を整理しようとして外を歩いた。特に目的地もなかったが、レンタルビデオのお店に寄って見もしない映画のタイトルを眺めて、最近の映画の動向をチェックしたり、本屋によって服の流行を気にしたことがないのにファッション雑誌を読んで最近の服装をチェックしたりした。そうすることで気分転換になるのではないかと思った。しかし、それでも光一の事で頭がいっぱいになる事が多く、頭を切り替えることはできなかった。
どうしようもなく近くのショッピングモールに入り、何かいいお店はないか探していると、見たことのある50才前後の男がいた。思い出そうとしても思い出せず、その男の顔を凝視していると相手が昌守に気づいた。気付くと同時にその男は昌守から遠ざかるように歩き始めた。昌守は徐々に遠くなるその男を眺めていると、右隣にスーツ姿の人が通った。そのとき昌守は思い出した。スーツ姿と重ね合わせると、市役所の障害福祉課の職員を思い出した。
昌守は市役所の男を追いかけた。おそらく市の職員は昌守の事に気付いて遠ざかったに違いなかった。昌守も市の職員に避けられていることはわかっていたが、今の昌守は打開策が欲しかった。何かいい制度があれば、それをきっかけに光一に対応していきたいと思ったからだ。
「すいません。あのぉ、市役所の人ですよね。」
市役所の男を呼び止めた。相手は迷惑そうに振り向いたが、周りの目もあるためか渋々頷く感じだった。しかし、勤務時間外なので勘弁してほしいという態度を示していたが、そんなことはお構いなしに昌守は質問をした。
「申し訳ないのですが、非常に切羽詰まっていて、是非教えていただきたい事があるのです。50才くらいの人で筋委縮性側索硬化症という難病にかかっている場合、障害年金のほかに何か受けられる制度って何かあるのでしょうか?すいません、唐突で。でもどうしてもわからなくて・・・。」
市役所の人は勉強だったら自分で調べた方がいい、とか休日だから今資料が手元にない、など、その場しのぎの返事をしてきた。それでも昌守は食い下がった。何を調べればわかるのか、どこに行けば教えてくれるのかと聞いた。市役所の男も自分が教えなかったと言われるのも恐れたのか、一つだけ適応する制度があると教えてくれた。「介護保険」という制度だった。
昌守が光一に対しては医療保険を適応して訪問していた。介護保険制度は65歳以上が適応になるとばかり思っていたため、65歳未満でも病気によって適応になる事に気付かなかった。
昌守は市役所の人から得たヒントを元にして介護保険の制度を調べた。確かに介護保険は筋委縮性側索硬化症という診断が付いていれば50才くらいでも利用できた。これを利用する事により、訪問介護、つまりヘルパーを利用する事が出来た。つまり、今昌守が行っている買い物などもヘルパーが行ってもらえるという事になる。しかも息子の手を借りずに生活をしていくことが可能になる。これで当分は苦労しなくなるのではないかと考えた。
昌守は介護保険の本をレジに並んで買った。少し光が見えた瞬間だった。
【16】
光一の家に行く日になった。昌守は家には入れるか少し不安だったが、訪れるとすんなりと家の中に入れてくれた。そして、最初に頼まれた内容が、買い物だった。昌守が光一の家に行く頻度は週に一回のため、その時しか物を買う事が出来なかった。買い物をする量も前回より多くなっていた。
前回同様、買い物の内容は殆どが弁当だった。今の光一にとって、食べることしか楽しみがないというのも一つの理由なのだろうか。食欲だけはあるようで、昌守は少し安心していた。
買い物を終えた昌守は、弁当を冷凍庫に入れた。解凍して食べる光一の姿を少し想像すると、本当はすごくさみしいのではないかと思った。毎日一人で食事をしている姿と、日々衰えていく体を想像するととても心が痛んだ。出来るだけ、光一にしてあげる事をしてあげようと思った。
光一の話の中でマッサージをして欲しいと言いだした。基本的にはリハビリの中でマッサージのみを行うのは違っていた。マッサージであればマッサージ師という国家資格者がいるのだが、そういう事を言っている状況ではないと思い、マッサージを始めた。
光一は少しずつ気を許してくれているのだろうか。それとも今の昌守は何でもしてくれるという言葉を信じてくれているのだろうか。どちらにせよ、光一は昌守を受け入れてくれているのだろうと思った。
「もう少し昌守の訪問回数を増やしてくれないか?」
光一にマッサージをしていると、光一から要望された。
昌守は考えた。光一はきっとあの時の言葉を信じているのだろうと思った。何でもリハビリと解釈して伺えるものだと信じているのだろうと思った。しかし、後で冷静になって考えれば、さすがに医療保険で行っていくには限界があると思った。やはり、適正な制度の活用を促すのも役目だと昌守は考えていた。
そこで先日、介護保険が適応になる事を思い出した。光一の要望に対して、介護保険を紹介するにはちょうどいいタイミングだと思った。昌守は光一に介護保険の利用を勧めるために話し始めた。
すると光一は介護保険という言葉を聞いただけで急に怒り出した。まるで自分の要望を聞いてくれなかった昌守に対しての不満が爆発している様子だった。昌守は光一が乱れるのを見て、これ以上勧めることは良くないと考え、話題を変えようと話をふった。しかし、光一は怒りが収まらず、昌守に怒りを大声で怒鳴りつけ、昌守に帰るように言った。
「もうここには来なくていい!お前にはもう用はない!」
昌守は何度も食い下がった。やっと中に入れたのに再び光一の家に入れなくなる方が怖かった。しかし、光一の圧倒さ負け、気づけば昌守は光一の家の外に出ていた。
「来週も来ますから。」
玄関の扉に向かって昌守は言っていた。また同じような環境に戻ってしまったと思った。昌守自身の話し方が悪かったのだろうか。昌守は何度も反省した。今日の昌守はその場を離れるしかなかった。
【17】
昌守は自分の訪問スケジュールを調整していた。前回の訪問で最後は「来なくていい。」とは言われたものの、その前には光一からもっと来て欲しいという要望があった事は間違いなかった。少なくてもそれに答えることが、今の自分に出来ることだと考えていた。昌守は自分のスケジュールを見ていた。事業所としては一日7件回ればそれでノルマは達成しているというスタイルで、一日7件回るとだいたい帰るのが6時頃になり、そこから書類業務など行うとどうしても帰りが8時頃になってしまっていた。光一の要望に応えるために、一番良い方法は昌守が今担当している持ち分を他のスタッフにお願いし、その空いた分を光一の訪問スケジュールに当てたかった。しかし、他のスタッフに説明する場合、光一の訪問が妥当かどうかという議論になるとややこしくなる可能性があったので、今の状況ではその話は言いにくかった。買い物、マッサージ、やはりどう考えても訪問リハビリとしての役割ではなかった。他人に知られることによって、光一へのスケジュールさえも削除されそうな気がしていたため、誰にも相談できずにいた。
しかたなく、考えた結果、昌守は訪問スケジュールを一日8件として考え、増やした1件を光一の訪問スケジュールに当てた。他のスタッフに知られないように偽りのスケジュールを提出した。行った実績は殆ど事務職員が機械的に処理しているだけなので、スケジュールと合わなくても大丈夫だった。そうやって昌守は光一の家に週3回ほど行けるようにした。帰りは遅く、9時を過ぎる事になるがそれでも昌守は光一の家に何回も訪れる事を選んだ。スケジュールを組み終えた昌守は、もう光一の家に再び入れるかどうかの心配していた。
昌守は早速、組みなおしたスケジュールで光一の家に訪問した。会えるかどうか不安だったが、もう行くしかないと思っていた。昌守は光一宅の玄関前まで来ると迷うことなく玄関チャイムを鳴らした。昌守がドアノブを回して確認したらやはり鍵はかかっていた。やはり、中には入れてもらえないのかと考えていたが、冷静になれば訪問スケジュールを変更したことを光一には言っていないため、光一にとっては突然の誰かが来たことになり、玄関を開けている状態ではないのが普通だった。よって、玄関の鍵はかかっているのは当然といえば当然であり、昌守は冷静になり次の行動を考えた。電話で訪問した理由を話し、玄関を開けてもらうことが通常の流れだと思った。しかし、さらに考えると、電話では断られそうな気もしてきたため、そのまま光一の家の前で粘ろうと考えていた。
(光一さんはきっと自分を必要としているはず。)
そう昌守は思い玄関の前に立っていた。光一はもう買い物が出来る状態ではなかった。光一が困っていることに対応するのが、今の昌守が出来る唯一出来る事であり、それを積み重ねることできっと光一との関係を良好にしていくのだと考えていた。
昌守は何度も玄関チャイムを鳴らした。しかし、光一は物音さえせず静まりかえっていた。昌守は声を掛けた。光一に届くように声を掛けた。そして声は徐々に大きくなっていた。しかし、その願いは叶わず報われなかった。光一の家の中から物音さえ聞こえる事はなかった。光一は必ずこの家の中にいるはずだった。もう何処へも行ける体力は無いはずだった。
昌守が声をかけ続けていると、同じマンションに住んでいる住民が昌守をジロジロ見る人が現れた。昌守は冷静になり、他人がこの光景を見た場合、光一に何かあったと思われてしまうのではないかと考えた。昌守は声を掛けることを止めた。
昌守は諦めて帰ることにした。悔しい思いでいっぱいだった。何やっているのだろうか、と情けなさも湧き出てきた。
振り返ると、確かにあの時に介護保険の話をするのは不適切だったかもしれなかった。タイミングはあまり良くなかったかもしれなかった。高齢者が利用する制度だと印象が強かったという配慮は出来ていなかった。しかし、決して年老いた人に対しての制度ではないし、実際に光一が適応になるということは、そういう人も対象として作られた制度であって、それを利用して生活することは悪いわけでは決してなく、光一の生活がそれによって安定するのであれば利用する事がいいのではないかと考えていた。
しかし、結果として光一は介護保険という制度を受け入れることはなかった。そして昌守さえも受け入れることを拒否するまで発展してしまった。どういう理由があるにせよ、結果としては最悪の方向になっている事は否めなかった。
再び昌守の中で「孤独死」という単語が思い浮かんできた。光一がこのまま食事をとる事もなくなり、いずれ飢えで死んでいく光景が目に浮かんだ。しかし自分ではどうすることも出来なかった。
昌守は車に乗った。今日の訪問は光一で最後なので光一の家に入れないのであれば、事務所に帰るだけだった。昌守は車を走らせながら帰りの車の中でラジオを聴いた。夕方に流れるラジオから聞き慣れた司会者の声が聞こえた。その言葉の中で
「私も先日階段で転んでしまって、危なく怪我をするところでしたよ。」
という会話が聞こえた。特に「転んでしまって」というフレーズは印象深く、昌守の頭の中に留まった。そしてその単語が光一と重なり始めた。徐々にそれは膨らみ始め、そして重なりが膨らみきった瞬間、昌守は車のハンドルを切り返し、光一宅へ再び向かった。
【18】
昌守は再び光一宅の前まで戻った。そして慌てながらチャイムを鳴らした。同じように反応はなく、扉を叩いても返事はなかった。部屋の中を確認したくなった昌守は窓を探した。窓から中を覗いて確認しようとした。しかし、玄関の横にある小さな窓は曇りガラスになっていて家の中は見えなかった。鍵も掛かって開けられなかった。
昌守は表から入れないのであれば裏から入れないかと考えた。光一が居る部屋はちょうど玄関と反対側に位置していた。光一の部屋は1階なので裏庭に行くことは可能だった。昌守は裏庭にいく方向を探し周りを見た。ちょうど昌守が車から光一宅まで来るまでの通路に通り抜けられそうな小道があるのを思い出した。慌てて引き返しその道まで戻った。
その道は雑草が周りに多く茂っていて、人が一人やっと通れるような幅しかなかった。昌守は迷うことなくその道を進んだ。雑草を踏みならしながら進んでいった。
なんとか進み、ちょうど光一の部屋の前まで来た。間違えないように端から部屋の数を数えて確認もした。光一の部屋は外にベランダがあり、一段高い位置に窓はあった。中を見ようとしても下半分が曇りガラスになっていて、部屋の中は見えないように出来ていた。また、上半分もカーテンレースが取り付けられていて外からでは中を見ることは出来なかった。
それでも昌守はそのカーテンレースの隙間から中が見えるのではないかと考え、ベランダによじ登り、カーテンレースの隙間を探した。すると一カ所だけしっかり閉められていない場所があった。何か物に引っかかっているようで、閉まり方が不十分だったようだ。その隙間から部屋の様子を覗いた。
部屋の様子は昌守の記憶にある部屋の様子と変わらなかった。しかし、次に光一を探したが光一の姿は見えなかった。いつも座っているソファーやその周りを見たがいなかった。昌守はさらに部屋の隅々を確認した。しかし、それでも光一の姿は見あたらなかった。
この部屋には居ないとわかった昌守は、視線を玄関へ通じる廊下へと移した。しかし、その廊下は昌守が覗いている部屋と玄関が一直線ではないため、全てを見る事は出来なかった。それでも可能な限り見てみようと覗いた。覗く先に膝から下の二つの足が見えた。ちょうど廊下が見えなくなるところで光一は横たわっていた。
それを見た昌守は慌てて中に入ろうとした。幸い昌守が覗いてた窓は鍵が開いていたので、無事に中に入る事が出来た。そう言えば普段から窓の鍵はかけないという光一との会話を思い出していた。「1階なのに泥棒に入られますよ。」、と冗談混じりで笑いながら話した事があった。昌守は慌てていたため、今になってこのことを思い出していた。
昌守は光一に呼びかけながら近づいた。
「光一さん!光一さん!大丈夫ですか!」
光一の反応は無かった。目は殆ど閉じているが少しだけ開いていた。目はほとんど白目を向いていた。口の横からは液体が少量流れ出ていて、涎だと分かるのに少し時間を感じた。遠くから見れば完全に意識を失った人間であると解るのに、昌守はそれさえ受け入れられない心理状態だった。
昌守は目の前が真っ白になりつつあった。しかしぼんやり見ているだけではこの事態を解決できないと考え直し、昌守は頭の回転数を上げて、次に何をしたらいいのか考え始めた。
冷静になろうとして昌守は1回だけ、肺の深いところまで息が入るように深呼吸をした。普段深呼吸などしないので、奥まで息が入った肺の部分が少し痛んだ。その痛みでさらに冷静になれた。自分も変わらない人間なのだと我に振り返ることが出来た。
意識のない人に対しての対応を思い出した。手順があって、最初に意識確認、次に呼吸、最後に心臓だ。光一はその手順を頭に描きながら振り返った。たった今、意識確認をして無いことがわかった。次に呼吸だ。しかし、見た目ではわからなかった。息をしていれば胸のあたりが膨らんだり萎んだりするのだが、服を着ているせいかわからなかった。再び頭を働かせて、手を口の近くまで持っていき、息をしているのか確認をした。原始的だが一番確認が取りやすかった。昌守の手のひらは光一の息を感じ取っていた。
「よかった。生きている。」
少し安心した昌守は次に心臓を確認した。しっかりと手首から脈拍を感じた。しかし、呼吸が確認出来れば心臓は動いていているはずなので、あまり意味のないことだと振り返った。呼吸が確認できたら再び意識確認に戻る。さっきは肩口を叩いただけなのでより大きく揺すってみた。
「いてててて。」
光一は顔を歪ませながら目を開いた。昌守は安堵した。意識も戻ったという事はそれほど大きな怪我にはならなかったと思ったからだ。しかし、安堵もすぐに不安になった。どうやら光一はどこか痛みを生じているからだ。やはり怪我はしているのではないかと思った。昌守はその痛みの場所を確認した。
昌守が痛い場所を確認しようとすると、その手を払いのけて光一は自分で痛い場所を確認し始めた。光一は右手で左手持ち、光一は自分の目でどこが痛いのか観察した。光一の左の小指は人間の動きとは正反対の方に曲がっていた。
「これは折れていますよ。」
昌守は光一の左指を、深刻な状況だと訴えるように低い声で光一に話しかけた。
「これから病院へ行きましょう。」
昌守は自分の車を出そうと自分のポケットに手を入れて車の鍵を出そうとした。
「いかねぇよ。」
光一はすぐに返事をした。顔は痛みで歪んだままだった。
「でも折れていますよ。頭も打っているみたいだし。病院で見てもらった方が・・・」
そう言いながら昌守は光一の目を見た。光一は昌守の目をそらす事なく
「俺は行かない。」
とはっきり言った。昌守もそれを聞き、ポケットの中に入っている車の鍵をゆっくりと手の中から放した。
「わかりました。」
昌守は光一の威圧に負けた。自分が何を言ったとしても変わらないと思った。しかし、これを逆に利用しようとした。
「その代わりでも無いのですが、今日から週3回、お伺いします。その指じゃ、痛くて何も出来ないでしょうから。」
光一は断ろうと口を開け言葉にしようとしたが、すぐに閉じた。そして少し悩み軽く頷いて了承した。光一の指は別の部分の体を動かすだけで腰にあたり痛みを生じてしまっていた。昌守は近くにあった割り箸を添え木にし、光一の左小指を包帯で巻いて固定をした。光一はその小指を見つめ、しばらく動かなかった。
【19】
昌守は木曜日に追加して火曜日と土曜日に光一の家へ行くようにした。適度な感覚で行った方が好ましいと考えたからだ。あまり間を置いてしまうと再び断られてしまいそうな気がしていた。
週三回行くことで昌守の思惑通り、ちょっとした用事を頼まれる事が多くなった。買い物や掃除、洗濯など身の回りの事を少しずつ行うようになった。もちろん、体のメンテナンスは行っていて、体をほぐし、今の状態を維持できるよう運動もした。左手の指も折れているため、出来る限りの処置はした。しかし、しっかりと骨の折れた断片同士がちゃんとくっついているかどうかまではわからなく、これでよいのかどうかはわからなかった。それでも今の昌守にはやるしかなかった。そういう態度を見て光一も少しずつ信用してくれているのかもしれなかった。
それでも昌守は光一の様子を見ながら病院へ行くことを勧めた。行くのであれば一緒に行くことも提案した。それでも光一は動かなかった。
「自分の命は短いのだから今更使えない左指を治したところで意味はない。」
そう光一は話してくれた。時間が経っても光一の主張は崩れなかった。
昌守は本当に光一が言っていることが本心なのか考えていた。おそらく経済的な面も心配しているのではないかと考えるようになった。頼まれた買い物の内容から見ても必要最低限の物しか買っていないし、食事も少量で少ししか食べていないことも、週三回来ることで新たにわかった事だった。経済的な面を考える上で、やはり息子の事を考えているのではないかと昌守は考えていた。きっと障害年金の受け取りも、息子を思って受け取るようにし、介護保険の拒否も自己負担額を気にして断ったのだろう。今回の骨折も、きっと息子への資産を残すために、医療費を節約しようとしているのだろうと思った。きっと光一が出来る最期の親心なのではないかと考えていた。
そうなるとさらに痛むのが光一の冷え切った親子関係だった。昌守は洗濯をするようになってわかった事があった。息子の洗濯物と光一の洗濯物は別々に洗っていた。そして、自分の分は自分で洗うというシステムだった。よって光一の分を昌守は洗濯していた。息子の分も行おうかと光一に聞いたが断固拒否をしたので行わずにいた。歯がゆい気持ちを押さえることで精一杯だった。
洗濯だけではなかった。食事に関しても息子はどうしているのだろかと思うくらい、光一の分しかこの家には存在しなかった。冷蔵庫の中身を見ても光一に頼まれて買ってきた物しかない。きっと息子の食事は外ですべて済ましているのだろうと思った。
昌守の予想では、居間の隣に開かない一つの部屋があった。そこがきっと息子の部屋なのだと思っていた。玄関からその部屋に入るまでちょうど光一がいつもいる部屋から何も見えないでその部屋に入ることが出来た。絶縁状態が確保できる環境にもあった。
息子は最近の光一の姿を見たことがあるのだろうか。元気な頃のイメージしか持っていないのでは無いのだろうか。父親が転んで骨が折れても病院へ行かないでいることを知っているのだろうか。光一とその息子の関係も修復していくことも、自分の役目ではないかと昌守は考えるようになっていた。
光一は入浴をしたいと言い出した。ずっと一人でしてきたのだが、一人では恐くなってきたので手伝って欲しい、とのことだった。光一が弱音を昌守に言うことは初めてだった。昌守は少しずつ自分が頼られているのがわかってうれしくなった。自分の行動が光一の生活に溶け込んできていると思った。自分の行動が身になってきているというのが実感できてうれしくなった。今までこんなに頼られようと努力をしたことがあまり無かったからだ。
理学療法士という職業は、「リハビリの先生」と一つ上に見られるような存在のことが多かった。昌守が願ってなくても頼られることから始まることが多かった。今回も同様に始まったが病気には勝てなかった。それでもそれを乗り越えて勝ち得た信頼は昌守にとってこの上ない喜びだった。
光一は最近、浴槽の中に入っていないという事を話してくれた。この前までは浴槽まで入っていたのだが今は入れなくなってしまったと教えてくれた。昌守は光一が浴槽に入れなくなったという事を聞いて驚きはしなかった。浴槽に入るためには足をあげる動作が必要であり、光一にはその筋力が無いことを知っていたからだ。光一はシャワーのみで入浴を済ませていた。それでも昌守には入浴に対して不安に思っている事がいくつかあった。
【20】
昌守は光一の依頼もあり、入浴の介助をすることになった。入浴が追加された事で日常生活においてトイレ以外の事はほとんどの手伝う事になっていた。
光一は入浴をするために脱衣所まで歩いた。その後ろを昌守は付いて行った。居間から脱衣所まではほんの数メートルだけだったが、光一の歩く姿を見てさらに歩き方が悪くなっていると感じた。左足はつま先が床から離れる事はなく、左足に体重が乗ることさえも難しかった。左足に体重が乗らなければ右足も前に出しにくくなり、歩幅は小刻みになって、右足が前に出るたびに足音が廊下いっぱいに広がっていた。
「バスタオルを取ってくれ。」
脱衣所まで着いた光一は昌守に指示をした。バスタオルは昌守が毎回洗濯をしているので、ある場所は知っていた。洗濯機の少し上にあるのだが、もう光一では取るのがやっとの場所になっていた。
「あっちを向いていてくれないか。」
少し恥ずかしそうに光一は昌守に言った。これから下も脱ぐから陰部は隠しておきたいという意味だと解った。
「すいません。気づかなくて。」
慌てて光一を背にするように向きを変えた。背中からズボンを脱ぐ音がした。しかし、スムースに脱げている音ではなく、何かに悪戦苦闘している様子だった。
「どうしました?手伝いましょうか?」
光一の羞恥心を傷つけないように配慮しながら話しかけた。少し間が合ったが手伝ってほしいという返事が返ってきた。
振り向くと脱衣所にある洗濯機にほぼ寄りかかっている姿があり、右手も近くにある手すりに捕まっていて手放せない様子だった。光一の表情を見ると顔面が蒼白になりつつあり、疲労感がにじみ出ていた。光一の立つ力はズボンが自分で脱げないほど、筋力が低下しているのだった。
昌守は近くに折りたたみの椅子があるのを見つけた。それを広げて光一に差し出した。光一は躊躇するまもなく勢いよく昌守が差し出した折りたたみの椅子に座った。勢いがありすぎて一瞬壊れるのではないかと思うほど、体を椅子に預けながら座った。ギシギシ何度か音を立てて止まった。
もう一度、光一に立ち上がってもらい、昌守は急いで光一のズボンとパンツを脱がした。あまり時間をとらせないように手際よく脱がせてあげかったが、ズボンのチャックが上手く下ろすことが出来ず少し時間がかかってしまった。それでも光一は文句を言わず、全部脱がすことに成功した。そして再び椅子に座って求刑した後、光一は浴室へと移動しようと立ち上がった。立ち上がって浴室に向かおうとした時、光一は下を見つめ始めた。
「ここの段差がちょっとな。」
光一は段差が気になるようだった。ここの段差とは浴室にはいるために一段上がっている段差だった。階段よりも小さいが敷居よりも高い段差だった。以前、どこかで浴室は水が逆流しないように段差をつけて家を建てる、という事を誰かに教えてもらったことがあった。その構造上必要な段差が今の光一には苦労の一つになっていた。
光一が転ばないように昌守は光一の脇を抱えて倒れないように心掛けた。しかし、その段差を昇るとき、光一の体がふらついた。昌守は少しヒヤッとしながらも、力で光一が倒れないように支えた。予想以上に重く、今まで一人でお風呂に入っていたのかと考えると恐ろしく思えた。
「やっぱ浴槽の中には入れないよな。」
光一は浴槽を眺めながら確認するように昌守に聞いた。昌守は即答せずに一つ間を置いて、難しいという返答をした。まるで今改めて考えたかの様に昌守は光一に返答をしていた。
「やっぱりそうか・・・。」
答えは解っていたのだろうか。理由などは聞かれなかったがとても寂しそうな表情を見せていた。
「この椅子がやっかいなんだ。」
浴室には体を洗うときに座る椅子があった。一般的によく見る形状をしていた。しかし、光一にとってはとても使いづらい椅子だった。立ち上がるときにとても不便な椅子だったからだ。
座った状態から立ち上がるには自分の体重を足の力で踏ん張る力が必要だった。それは低ければ低いほど足の力が必要だった。光一が使用しているその椅子は、とても低い椅子だった。それは特別な椅子でもなく、ごく一般的に使用している高さ約30cmの浴室用の椅子だった。背もたれもなく、肘掛けもない。小さい楕円をして座るために必要な面積しかない椅子だった。座るときでも一歩間違えば、床に転げ落ちてしまう、今の光一が使いにはかなり厳しい椅子だった。ここが昌守にも予想できた光一が一番苦労しそうな動きだった。
昌守は光一に他の椅子は無いかと尋ねた。しかし、光一は首をふり、「無い」と言った。しかたなく、昌守は光一の脇を抱えながら慎重に小さい楕円状の低い椅子に座らせた。いつもどういう風に座っているのか聞こうとしたが、先ほどの椅子でもかなりの勢いで座っていることを考えると、概ね予想がつき、光一からの詳細な答えが怖くなって聞くのを止めていた。
昌守は光一の髪の毛から洗い始めた。人の髪の毛を洗うのは初めてだった。温かいお湯になるまで自分の手で温度を確認した。光一の髪の毛は皮膚から出る油で満たされていた。しばらく洗っていないらしく、1回目のシャンプーでは泡立たなかった。2回目にしてようやくシャンプーの泡立ちがよくなった。触ると良くわかった事があり、髪の毛の一本一本が油の様なベトベトしたものでくっつき合っていた。洗う度に徐々にほどけていき、髪の毛が解放されていく様な感触だった。
光一も気持ちよさそうだった。きっと久しぶりの入浴なのだろうか。毎日シャワーだけは入っているという事も違う気がした。体の方も皮脂で満たされ、シャワーのお湯を弾いていた。
昌守は次に体を洗い始めた。陰部だけは自分で洗ってもらい、その他は昌守が洗った。背中、腕、足と分けて洗った。やさしく洗っていたら光一から、もっと強く擦って欲しいという要望があった。それに答えるように力一杯洗った。すこし皮膚が赤くなったがそれと同時にさらさらとした皮膚が戻ってきた。もう一度最後に背中を洗おうと、スポンジを背中に当てた。昌守もやっと余裕が出てきたのだろうか。光一の肩甲骨が異常に浮き出ていることに気付いた。不思議に思いながら昌守は背中を洗い続けた。背中を洗いながら昌守はこの肩甲骨が浮き出て見える原因を考えていた。そして考える中でこの原因は、回りにある筋肉がやせ衰え、小さくなった結果、肩甲骨を抑えている筋肉もなくなり、浮き出てきたのだとわかった。肩甲骨の回りにある肋骨もはっきりと浮き出ている事を確認した。洗いながらゴツゴツとした感触を感じるのはこれが原因なのだと改めて理解した。
体を洗い終わり、光一を再び立たせるために光一は勢いよく立とうとした。しかし、あまりにも力む姿を見た昌守は光一の脇を抱えて立たせようとした。光一は拒否することなく昌守の手助けに甘えた。そして、ほぼ昌守の力で何とかその場を立ち上がった。
光一はゆっくりと歩いて浴室から出た。移動やシャワーで疲れたのだろうか。光一は疲れた表情をしていたため、体を拭くのもほぼ昌守が行った。そこからソファーまで歩くのも大変だった。途中力つきて倒れてしまうのではないかとも思ったほど、光一の体力は無かった。光一は倒れ込むようにソファーに座ると、そのまま横になりゆっくり目を閉じた。そのままにしていたら光一はスヤスヤと眠ってしまった。
昌守は浴室の整理をしていた。光一が座った目の前に鏡があった。その鏡は座ったときに全身を映してくれる大きめな鏡だった。昌守は光一の言葉を思い出していた。
「毎日入るのが楽しみなんだ。」
今日の様子からすると毎日は入っていないと思った。入っていないというよりも一人で入るのが恐くなったのだろうと思った。きっと動きにくくなったという理由だけではない。この鏡で毎日自分の全身の姿を見るうちに、変わり果てる自分の姿が恐くなったのだろうと思った。この椅子に座った後の光一は、確かに目を開けることは無かった事を思い出していた。
【21】
昌守は光一の家へ休むことなく週3回訪れる事を守って行った。少し風邪を引いたこともあったが休む事はなかった。その時には光一からは風邪が移るから来るなと言われてしまったが、それでも光一の家に行った。光一は抵抗せず、昌守を受け入れてくれた。引き続き買い物など日常的に困ることを頼まれては行っていた。
その中で一つ気になる事が起こり始めた。買い物のメニューの中に最近、酒類が入るようになったのだ。前までは家にあってそれを飲んでいたのだろうか。それとも最近飲み始めたのだろうか。確かなことはわからないが確実なことは光一が飲んでいるという事だった。前までの部屋の様子を昌守は思い出したが、酒を飲んでいる様子は少しも感じられなかった。昌守は自分自身が気付かなかっただけかと振り返った。しかし、ゴミを出し始めたときには酒の種類が入っていなかったことを思い出し、そんなことはないと思い直した。ゴミ出しもしている昌守にとって、光一が最近飲み始めたことが確信に変わった。
光一が酒を飲み始めていることを知りながら、昌守は敢えて気付かない振りをしていた。光一はきっと今、自分自身、心の信念と真逆のことをしていると思ったからだ。これまでずっと、息子のために財産を出来るだけ残したいという気持ちで色々と我慢してきたはずだったが、それを少しだけ緩めているのではないかと思っていた。昌守が酒を飲んでいる事を触れれば、光一は自分の行動が曲がっている事を指摘されることで愚かさを感じ、自分の事を攻めることになりかねないと思ったからだ。プライドの高い光一にとって何よりも言われたくない一言だと考えていた。
昌守は酒ぐらい飲んでいいと思っていた。毎日、閉ざされたこの家の中の空間で過ごしている光一にとって、それだけで精神的に病んでしまうものではないかと思ったからだ。
(一つくらい快楽があっても罰は当たらないですよ。)
昌守は今日も静かにゴミをマンションのゴミ収集所まで運んで行った。
その後も酒の量は増え続け、とうとう昌守の目の前でも飲むようになった。酒が部屋中に臭うようになり、少し気持ち悪くなることもあった。しかし、昌守は平常心を保って光一と接するようにした。光一は酒が強い方なのだろうか。あまり酔っているような様子を見ることはなかった。ただ酒の勢いを借りて、自分じゃない自分を演じている様には見えた。まるで、そう振る舞う事で光一自身の精神状態を安定しているように思えた。光一はきっと、しっかりとしなければいけない父親としての心を持たなければならないのに、病魔に襲われ動かなくなっていく心に負けてしまっている様な気がした。その負けている自分自身も客観的によく理解できるからこそ、酒で誤魔化そうとしている様に昌守には思えた。
昌守は光一の酒にあまり振れないように接した。酒の話題になったとしても、そっと話題をそらした。それでも、光一への病魔は進行し続けた。そして、とうとう病魔は来るところまで光一の体を蝕んで行った。
ある日、昌守はいつものように玄関から入り、いつも光一がいるソファーまで行こうとした途中で声が聞こえた。その声は光一のだと解り、ソファーまで行くのを止めた。光一を探そうと思って声の元をたどるとトイレの方から聞こえた。トイレに入っているだけだと思い昌守は外で待とうとした。しかし、光一はトイレのドアを開けてくれと言っているのだ。何事かと思い、恐る恐る開けると、光一は普通に便器に座っていた。昌守は紙が無くなったのかと思い、トイレットペーパーを補充しようと取りに行くと、光一からは、
「違う。」
と言われた。確かにトイレットペーパーはまだあった。昌守は何を訴えようとしているのか不思議に思い、光一の顔をよく見た。光一は少し涙を浮かべていた。
「とうとう、この便器からも立てなくなっちまった。」
昌守は光一が酒の飲み過ぎで立てなくなっているのだと思っていた。浴室とは異なり、トイレには手すりが沢山あった。手すりを使えば光一の力で立てなくないと昌守は思っていた。しかし、光一は酒を飲んでいなかった。いつもの臭いは光一から感じられなかった。
「お酒の飲み過ぎじゃないですか?」
昌守は少し誤魔化すように笑いながら昌守は光一に言葉をかけた。
「ああ。そうだな。」
二人とも今日はそれ以上の会話をしたがらなかった。トイレに一人で行けなくなるという事は、これからおむつになるという事を意味していた。しかし、おむつになっても誰が後片付けをしたらいいのかという問題が残っているし、トイレにいけないという事はほとんど寝たきりになるという意味も含まれていた。トイレにいけない。入浴も出来ない。光一が家の中で移動できる場所がどんどんなくなってしまっていた。
昌守は転ばないように光一をソファーまで送った。その移動もいつ転んでもおかしくないような歩き方だった。ソファーに座った光一はそのまま横になって眠ってしまった。その後の会話は一切なかった。昌守は思った。光一のこれからの生き方が予想できない、未知の領域に入ったのだと。そして光一はきっと、その事実を認めたくはないのだろうと思っていた。
【22】
光一はトイレから立つことが出来なくなったことを境に、便の時以外はトイレへ行かなくなった。便の時に行っているという事は、絶対にトイレから立ち上がれなくなったという事ではなかった。その日の体調や疲れ具合によって変わるのだと光一は言っていた。先日立てなくなったのは少し調子が悪かったからだと言い張っていた。しかし、尿は空き瓶に貯めて、窓から捨てていると聞いたので、トイレに行く回数を最小限に留めている事を考えると、やはり病気が進行している事には変わりないのだと思っていた。
光一はなるべく移動を少なくしようと常にいる場所も変えていた。いつもはソファーのある部屋だったが、ベッドがある寝室にいつもいるようにしていた。いつもベッドの周りに居るようにしていて、ベッドから離れない生活に変えたのだった。
ベッド回りも移動しなくてすむ様に、手の届く範囲に日常生活に必要な品々を置いていた。ペットボトルが何本もあり、水分補給を手軽に出来るようにしていたり、保存が利く栄養価の高いカロリーメイトの様なものを沢山置き、冷蔵庫まで行かなくてもすむようにしていた。寝室から本当に動かない生活を実践するように変わってしまっていた。
さらに食事の内容も変わり始めた。光一は食事をなるべく取らないようにしていたのだった。理由を聞くと、
「便が出なければトイレに行く必要がなくなるだろ。」
という事だった。気持ちは理解できるが、食事をしなければ便が出ないというわけではなかった。体内にある排泄物が便として出る以上、食事以外でも体内には様々な排泄物はあるため、便は出続ける仕組みになっていた。その事を光一に説明したが、それでも光一はなるべく回数を減らしたい一心で食事をあまりとらないでいた。今回の食事制限は息子のためよりも、最期まで生き抜く術を考えた結果の行動だと昌守は感じていた。
昌守はトイレで立ちやすくなるように簡易補高便座を作った。座る高さを上げることによって、光一の体重を少しでも少ない力で立てるように工夫をした。金銭面も配慮して近くのスーパーで拾ってきた発泡スチロールで作った。その方が光一も受け入れやすいのではないかという昌守なりの配慮だった。
そうした工夫もあり、少しはトイレから立ちやすい環境が作れた。それでも光一は便が出ることに対して非常に過敏になっていた。
(便だけはトイレに行かなければならない。トイレに行くということは少しでも歩かないとトイレには行けない。でももう歩くことは避けたい。)
そういう光一の思いがひしひしと昌守には伝わってきた。実際に昌守が付いて歩いても時々転びそうになった。本来ならば車椅子を利用して移動するくらいの身体能力だった。
食事を減らした影響なのか。それとも筋委縮性側索硬化症という病気の悪化が原因なのか。顔つきも少しずつ痩せ細っていった。前はふっくらしていた頬の部分はくぼみが目立つようになってきていた。十分に力があると思われた右の二の腕も細く骨が出っ張るようになっていた。
右手の握力にも影響が出始めていた。ペットボトルのふたが開けられなくなってきていた。最初は光一が頼むので片手では開けづらいだけだと思っていたが、右手の甲を見たときに骨と皮だけに変わっていることに気づいた。病魔が右手にも浸透していることがわかった。時々、尿で取った瓶を窓から捨てようとして失敗し、部屋中にこぼしてしまう事がある様で、部屋中がアンモニアの臭で満たされている事もあった。あまり本人には触れなかったがこれが原因なのだとはっきりと理解した。光一にはあまり生きる時間が無いように思えた。残りの時間で、光一に出来ることは何なのだろうか。昌守はそう考えるようになっていた。
【23】
昌守はほぼ毎日訪れるようになっていた。これ以上、人手がない状態で光一が生きて行くことが難しいと考えたからだった。光一は完全にベッドに寝たままの状態になって過ごすようになってしまっていた。そして、とうとう光一はトイレまで歩けなくなってしまった。歩く力が無くなったという事もあるが、光一自身がもう諦めていることの方が強かった。昌守も無理に歩く事を勧めることはしなかった。
便はトイレへ行けなくなったため、完全におむつ対応になった。尿も空の瓶は何とか持つことが出来たが自分の尿が入ると重くなるためほとんど失敗してこぼすようになってしまった。それでも光一はおむつの中に尿を出すことに強い抵抗を感じていたため、光一は失敗しながらも一人で頑張っていた。しかし、とうとう空の瓶も持つことが難しくなりおむつの中にするようになった。
昌守の訪問は一日に一回しか訪れることが難しかった。尿は一日に何回も出るためその度に取り替えることが出来なかった。夜用の尿取りパットを何重にも当てて漏れないようにして対応した。しかし便だけは出たら気持ち悪いのではないかと思い、光一は携帯電話が使えたため、電話で知らせてくれれば取り替えに来ると光一に伝えていた。電話が来るか不安だったが光一は申し訳なさそうに電話をくれた。昌守は快く引き受けて対応していた。
寝たきりの生活で問題になったのが玄関の鍵の問題だった。光一から自分で鍵を開けたくないと言ってきたため、鍵を預かる事になった。本来ならば、金銭トラブルに発展する可能性もあるため、なるべく預からないようにするのが基本だった。しかし、光一に預かって欲しいと直接訴えられ、断ることが出来なかった。
食事も包装してある食品は開封しておかないと一人で開けることが出来なくなっていた。置く場所も選ばないと場所によっては手が届かなくい事もあった。光一の家に訪れるのが一日一回のため、食事を取って欲しい気持ちもあり、3食分の袋を開けておくのだが、変わらず1食分しか食べることはなかった。
飲み物もペットボトル一つ持ち上げられなくなったため、取っ手をつけて指で引っかけるようにして持つことが出来るようにした。ペットボトルを逆さまにする力もないのでストローを使って飲めるようにした。
入浴は浴室まで行くことが出来ないので、温かいタオルで体を拭くようにした。すぐに冷めてしまうので熱めのお湯で温かくするように努めた。
昌守は毎日毎日その内容を繰り返した。普段でも仕事があるなかでも、仕事で訪問しない日は通常業務を終わらせてから光一の家へ訪れた。時々、自分は何をやっているのだろうと我に返る時があったが、それでも光一を一人にすることが恐くなり結局光一宅へ行っていた。
どんなに遅く訪ねたとしても光一の息子と会うことは無かった。本当に居るのかどうかさえ疑問に思うこともあったが、ベランダにある干された洗濯物を見て光一の物と違う服があったので、この服は息子の物なのだと思った。光一の洗濯物は昌守がしているのではっきりとわかった。
たまに夕方どうしてもはずせない用事があるときは、仕事にいく前の朝に光一の家へ行くこともあった。しかし、それでも息子の姿は見られなかった。
きっと息子は夜遅く帰り、朝早く出る。そういう生活を毎日しているのではないかと思った。理由はわからないがとても過密なスケジュールをこなしているのだと思った。
前に孤独死が恐くて光一宅に訪れることが多かったが今は違っていた。自分が毎日行くことでその不安は無くなりつつあった。それよりも、この状況が長く続くわけがないと思っていた。いつか終わりを迎える事になる。その準備をするために動き出すきっかけを、昌守は少しずつ探し始めていた。
【24】
ある時光一の体を拭こうと思いタオルを探したが、いつもある場所にタオルが無いことに気付いた。洗濯してまだ乾いていないのかと思い、ベランダに干してあるタオルが乾いてないか確認しにいった。
ベランダには昌守が干した洗濯物が並んでいた。昌守はベランダに出て乾いたタオルを探していた。その時、ベランダから通じている隣の部屋が気になり出した。その部屋はおそらく、息子の部屋であると昌守は思っていたからだった。
昌守はその息子だろうと思われる部屋を覗いてみた。しかし、ベランダからはカーテンが仕切られていて部屋の中は見えなった。
(もしかしたら息子が居るのではないか。)
そういう期待もあって昌守は窓を軽く叩いてみた。しかし、反応は無かった。誰もいないことが分かり、軽く落胆すると部屋の鍵が開いていることに気付いた。息子の情報を得たいという気持ちが急に昌守の心に押し寄せた。昌守はその窓ガラスを開け、静に中に入っていった。
中にはいると目に入ってきたのがベッドとテレビが主体のシンプルな配置をした印象の部屋だった。まずは本当に息子の部屋かどうかを確認したくなった昌守は部屋をゆっくり見渡した。すると壁に額縁に入れられた賞状があった。受賞者は「岸坂孝」と書いてあった。受賞した時期は小学生の様だった。小学生部門と賞状の文章内に書いてあった。それから受賞年月日も書いてあることを確認した昌守は逆算をして今の年齢を予想した。おそらく今年でちょうど二十前後になる事がわかった。となれば、「岸坂孝」という名前は息子の名前かもしれないと思った。しかし、確信は持てなかった。もっと確かな情報が欲しくなった昌守はさらに視線を横に動かした。
すると複数枚の写真が飾ってあることに気づいた。友達と移っている写真なのだろうか。集合写真がたくさん貼ってあった。光一の息子を捜そうと写真を眺めたがわからなかった。顔が小さいこともあるし、写っている人数も多かったので絞り込むことも出来なかった。日付はわからなかったが最近印刷した様な写真が数多くあった。
さらに視線を横に移すと本棚があった。本棚にはマンガの本が沢山入っていた。その中に教科書のような本もずらりと並べてあった。関連図書は電気という文字が沢山あった。一冊を取り出し見てみると沢山勉強したような形跡が見られた。アンダーラインを数多く引いてあり、それが何ページにも渡って引いてあった。一番最後のページを見ると大学の名前と氏名が書いてあった。やはりそこにも「岸坂孝」という名前が書いてあった。
やはり「岸坂孝」は息子の名前なのだろうと思った。これで息子は大学まで行っていることがわかった。帰りが遅い理由は夜間部なのか、それとも昼間部で夜はバイトなのか。どちらにせよ息子は確実にこの場所に住んでいることがわかった。
さらにゆっくりと中にはいるとテレビの前に小さな机があった。その上に本が何冊かあった。きれいに重ねて置いてあるので一番上しか本のタイトルがわからなかった。一番上の本はヨーロッパサッカーの特集が組まれた雑誌だった。見る暇があるのだろうかと疑問に思っていたが、寝る前でも本は読めると考え直した。そして一番上の本を少しずらし、二冊目、三冊目と本のタイトルを確認した。どれも二十歳前後の男が見るような内容のタイトルだった。
(あまり遅くなると光一に怪しまれる。)
そう思い本を元の位置に戻そうとしたとき、最後の一冊の本のタイトルが目に飛び込んできた。「介護の仕方 ~ヘルパー2級のテキスト~」だった。
昌守は本のタイトルを見て動揺した。昌守は息子が父に対して無関心であり、避けていると思っていたが、息子「孝」は父を避けるどころか、父のことを思い、大学という場所に通いながら、介護の勉強をしている様だった。確認のため、テキストを開いた。そのテキストにはアンダーラインがたくさん引いてあった。昌守は勉強している「孝」の姿を想像した。目まぐるしいスケジュールの中で、合間を見て介護の勉強をしている「孝」の姿は父に無関心なのではなく、きっと父思いの息子なのだろうと考え直した。
しかし、ここで昌守の中で矛盾が生じた。なぜ息子「孝」は介護の勉強までしているのに、実際に父親にしてあげないのだろうかと考えた。いくら父が断ったとはいえ、それでもするのが息子であり、親子ではないかと思った。
疑問に思う中、我に返り、光一に怪しまれるのではないかと不安に思った。急いで光一の元へと戻ると、光一は
「遅かったが何してたんだ?」
と遅くなった昌守の姿を見て聞いてきた。昌守は洗濯物で干してるタオルはまだ濡れていたので、別のタオルを探していたのだが何処にあるのか分からなくなって探していたら時間が掛かったのだ、と説明した。光一は少し疑問に思っていたが、深く追求することもなくその話題は終了した。
光一の体を拭き終わると、光一はそのままスヤスヤと眠ってしまった。起きているだけでも疲れるという光一の言葉を思い出した。最近は昼間に寝過ぎてしまい、夜寝れないという事もよくあるのだといっていた。光一の体は起きるだけでも体力を奪われるほど進行していた。
光一が眠っている間に、昌守はもう一度息子の部屋へ行こうとした。しかし、光一の気持ちを裏切る事にもなるのでやめた。それでも息子の考えが気になり、昌守は息子「孝」に手紙を書くことにした。最初は「なぜ介護をしないのか。」という内容にしたかったが、そこには触れないで、今の光一の現状をお知らせするような内容に留めた。今の状態を知ったら息子「孝」は動き出すのではないかと思った。手紙を書き終えた昌守は手紙を息子の部屋の扉の前に置いた。開かずの扉が少しでも開くことを願っていた。
【25】
息子に手紙を置いて暫く経つが息子からの返事はなかった。手紙に気付いていないのかと思い、息子の部屋に光一に気付かれないよう入ったが手紙が読まれた形跡はあった。テレビの前にある小さな机に広げられて置いてあった。しかしそれ以上何かが起こることもなかった。1週間が過ぎ、2週間が過ぎた。
光一は薬で死にたいと話してきた。光一の状態はもう完全に足が動かないまで筋力が低下していた。昌守が少し体を動かすだけで痛がるほど、関節は硬直し固くなっていた。光一は精神的に病んでいて、マイナスな事を多く考え、言葉にこぼすようになっていた。「生きる気力が無くなった。」とか「死んだ方が世の中のためだ。」など、毎日のように昌守に話しかけてきた。昌守は光一に息子の孝と接触しようとしていることを伝える事で、光一の生きる希望になるのではないかと考えた。しかし、それを伝えることによってマイナスに働く可能性もあるとも考え、話さずにいた。何度も息子の事を話そうとするたびに、息子の事に関しては光一にとってとても神経質な話題だったことを思い返していた。息子の話題はとても慎重に事を運ばなければいけないと考えていた。
一番いい方法は父親の光一と息子の孝がお互いに歩み寄れるようなきっかけを作る事が大切なのだと考えていた。特に息子にはその気持ちがあるような気がしていた。大学で電気の勉強をしながら、介護という正反対の勉強をしている事がなによりも証拠だと昌守は思っていた。
(必ず二人が歩み寄れるきっかけを作り出そう。)
昌守はそう考え、光一の自殺願望を宥め続けていた。
しかし、光一も徐々にエスカレートしていった。言葉が荒くなり、「なぜ持ってこないんだ!」と、昌守を攻める事も多くなった。最初は持ってこられない理由をなぁなぁにして話の話題を変えていたが、それも出来なくなった。自殺のために危ない薬を渡すわけにもいかないし、法律的にも許されていない事を正直に伝えた。そこを何とか頼むよと光一は涙ながらに話し始めた。本当に必死に死にたいという気持ちがあるのだと昌守は感じた。確かに、毎日同じ場所で過ごし、徐々に死に近づく自分がわかるのであれば、もう一層の事殺してほしいと思うのも不思議ではないと思った。しかし、昌守はその自殺願望に対して決して手を貸してはいけないと思った。息子との関係を修復し、最期まで生きる意味を見出してあげたかった。そのために昌守はやはり息子「孝」とはやく連絡を取りたかった。しかし、連絡は来ない以上、光一になんて言ったらいいのか迷っていた。それでも殺すことは出来ないと思い、
「ごめんなさい。たとえ誰かが許したとしても、僕にはそれだけは出来ないんです・・・。」
昌守は声を震わせて光一に伝えた。光一も昌守の気持ちを察したのだろうか。それ以来、その事は話さなくなった。
【26】
光一が薬の事を話さなくなってからほとんど会話をしなくなった。昌守が質問をしても返事を返さなくなった。昌守が買いに行ってくるための買い物のリストも言わなくなったため、昌守は以前からよく買っている品を買うことしか出来なかった。その他の介護も通常どおりに淡々とこなしていた。光一の要望が無くなったのは買物だけではなかった。携帯電話で知らせてくれる排便の処理依頼の電話が無くなった。便を放置すると乾いてきてしまい、皮膚が被れてきてしまっていた。それでも光一は昌守に向けて言葉を発する事はなかった。
「光一さん。お尻の皮が剥けると大変なので、前もって知らせてください。」
昌守は光一に話しかけたが光一は返事をしなかった。
「光一さんお願いです。このまま放置しておくと感染して大変な事になるんですよ。」
昌守は気持ちを前面に出して強く問いかけても光一は目を閉じて沈黙を保った。仕方なく光一は乾燥し臀部にへばりついた便を削るように落とした。便の臭いも少なくなっているほどきれいに乾燥しきっていた。
光一の便は乾燥してしまうほど知らせないことが毎回のように続いた。その度に昌守は皮膚に付着した取りにくい便をとり、赤くなった臀部を昌守が自宅にあった皮膚の薬で保護した。しかし、臀部の赤さは徐々に増し、とうとう皮膚が破けるほどふやけ、脆弱になってしまった。
「光一さん!いい加減にしてください!これじゃぁそのうち病気になりますよ!」
昌守は感情的になり強い口調で光一を攻撃した。それでも光一は沈黙を通した。光一はもうこないで欲しいと思っているのかもしれない。そう昌守は思った。
二人の沈黙を破るかのように、光一の携帯電話が鳴った。沈黙の部屋に音が流れた。携帯電話は光一の近くにあった。光一が手を伸ばせば簡単に届くところにあった。しかし、光一は電話を取ろうとしなかった。
「光一さん。電話。鳴っていますよ。」
昌守は光一に言った。光一は目を閉じたまま、細く、弱々しく答えた。
「もう・・・。ボタンが押せなくなった・・・・。」
昌守は予想もしていない答えに、金槌で頭を叩かれたみたいに衝撃を受けた。慌てて光一の右手を確認した。確かに手の甲は骨が目立ち骨と骨の間は窪みが増えていた。でもそれは毎回、清拭の時に見ているので驚きはしなかった。
「握ってもらえますか。」
昌守は光一と握手をするように手を握った。光一も力一杯昌守の手を握り替えした。昌守の皮膚だけを優しく押すような感覚で光一は手を握り、指先は曲がることが無かった。これでは携帯電話のボタンは押せないと昌守はわかった。進行している病魔にどう対応していいのか息を飲んでいた。
これ以上時間が過ぎると命の問題になると思った昌守は息子と接触することが一番だと考えた。これからの重要な事はやはり血の繋がった家族でないと決めることは出来ない。昌守は息子にさらに手紙を書いた。押さえきれない感情で文章にならない文章を書き殴った。何とか光一の最期に間に合うように二人の仲を繋ぎたかった。書き終えた昌守は、光一に内緒だと言うことを忘れていた。光一の目の前で書いたが、たまたま光一は昌守を見ていなかったので気付かなかった。昌守も書き終えたときに気づき、慌てて隠した。
「毎日来ますから。大丈夫ですから。」
昌守は光一に話しかけたが何が大丈夫かと聞かれるのが恐かった。光一は何も言わなかった。昌守は息子宛に書いた手紙を再び置いた。それでも息子からの返事は変わらず来なかった。
【27】
光一との会話は減少傾向に歯止めがかからなかった。携帯電話が使えなくなっただけではない。とうとう声も出にくくなってきた。光一の声量は小さくなり、ときどき聞こえなくなってきていた。聞こえないため、昌守が聞き直すと、「もういい」と口の動きで光一は昌守に伝えていた。目を閉じることも多くなり、活気が一気に減った。
食事も固形物を取らなくなった。これでは餓死してしまうと思い、ゼリー状の高カロリー栄養食品を買うようにした。ゼリー状の食品は喉を通りやすく飲み込む力が少なくても胃まで到達しやすい食形態だと勉強をしていた。それなら大丈夫なのだろうか。光一はゼリー状の食事を食べた。食べると言うよりも吸うというのだろうか。光一自信では口まで運ぶ事が非常に努力を要するので、昌守が食べさせた。食事をすると言う行動さえ、光一にはマラソンをしているのと同じくらい、体力を消耗する行為に変わっていた。
買い物はすでに現金が無くなって居たため、クレジットカードで支払いをしていた。買い物先も名前を確認せず、サインも求められないため、昌守が使用しても問題なかった。心配なのはこのクレジットカードを使用して引き落とされている銀行口座にいくら残高があるかわからない事だった。
(このカードが使えなくなったときに考えよう。)
全て細かい問題は後回しにした。
昌守の賢明な介護は続いた。介護中心になりすぎてリハビリという事をすっかり忘れていることに昌守は気づいた。久しぶりに光一の体をじっくり触るととても冷たく、筋肉の組織もやせ細り、体が骨を中心として構成されるようになっていた。リハビリの内容も体をほぐす以外はベッドの端に座らせることしか出来なくなっていた。座ると行っても光一は自分の体を支えるほど体の筋力は無かった。ほとんど昌守が光一の体を支え、座っているというよりも座らされているというような状態だった。
昌守はスーパーから段ボールを貰ってきて光一が座りやすくなるように背もたれを作った。光一の事を考え、お金の掛からない材料を選んだ。ベッドの端に足を投げ出して座ると寄りかかるところがなかったため、寄りかかれる場所を作ってあげたかった。光一は最初、座ることを拒否していた。しかし、徐々に長い時間座れるようになった。しかし、長いといっても30分程度で疲労してしまうくらい体はすでに弱っていた。さらに安楽に座れるよう肘掛けを同様にして作ったが、それでも座る時間は変わらなかった。
昌守はふと人間は何故座るのだろうかと考えた。光一にとって30分間ただ座るのでは苦痛になるだけなのではないだろうか。となれば、何か別のことに集中できるようにしてあげた方がいいのではないかと考えた。しかし、昌守には何一つ思いつかなかった。時間が過ぎるごとに苦しそうな表情を見せる光一を見ていると、自分は何をしているのだろうかと考えていた。
リハビリというものは寝ている人が居たらまず起こすことから始めるのが一般的だった。そうやって今まで深く考えずに仕事をしてきた。ある人は起きられるようになり、ある人は声が出しやすくなった。そうなるにつれ、立てるようになったり、会話をよくするようになったりもした。座る、起きるという行為は人間が生きる第一歩なのだと勉強してきた。
しかし、光一はどうか。これからそうした期待を持っていいものなのだろうか。昌守が例え願ったとしても、これまで関わってきた光一を見てそうした期待は光一にとって無謀なおとぎ話に過ぎないのではないかと思った。そうした一方的な事を押しつけている事は、光一にとって良いことなのだろうか。
昌守は光一を座らせながら悩んでいた。そう悩んでいるのを光一は見越したのだろうか。光一がボソッとつぶやいた。
「毎日・・・天井を見て・・・いるだけだと、・・・部屋を・・・違う角度で・・・見る・・・のも・・・いいもん・・・だなぁ。」
苦しそうな表情を無くし、光一はそっと昌守に話しかけた。昌守は光一にそう言われ、天井を見上げた。光一はただ真っ白にしかない空間の壁を光一は毎日見ていることに気づいた。変化のないその壁は気持ちも真っ白にしてしまっていたのだろうか。真っ白すぎて毎日空想しか時間を潰せなかったのだろうか。思い返せば携帯電話のボタンが押せないということは、テレビも見られないという事だった。ラジオも聴けないという事だった。光一は今、この部屋に完全に社会から隔離さ、情報を遮断されている状況だった。もしかしたら、感情さえも閉じこめさせていたのではないだろうかと思った。
自分は何のために光一と会っているのだろうかと考えた。孤独死を避けるためだけなのだろうか。昌守は理学療法士という資格を持っているのに、リハビリという大きな社会的役割を担う一員なはずなのに、自分は何をしているのだろうか。光一にとって一番いいことは何なのだろうか。座っている光一の横で、ずっと考えていた。
「ちょっ・・・と・・・、苦し・・・。横に・・・・ならせ・・・。」
気付くと光一は手の指先が青紫色になっていた。チアノーゼという症状だ。全身に酸素が回っていない証拠であり、とても危険な状態だった。慌てて光一をベッドに寝かせた。しばらくすると指先の青紫色は肌色になり、息苦しさも無くなっていた。疲れたのか光一は横になるとすぐに眠ってしまった。もう、光一の命は限界に近い。そう、昌守は思った。
【28】
昌守は車の中でボンヤリとしていた。光一の家を出て、まっすぐ事務所に帰ろうとしたのだが、事務所まで運転する元気も出なかった。交通量の少ない裏路地に車を止めて背もたれを倒して天井を見上げていた。視線は空があるかのように遠くを見つめていた。
エンジンを切ると車も人も通らないため、沈黙が昌守を包み込んだ。耳からの情報も目からの情報も遮っているかのように静かだった。昌守は光一の事を考えていた。今後、どうなってしまうのだろうかと、具体的に考えようとしてはぼんやりとして頭を働かせないようにもしていた。具体的にすると、怖さで押しつぶされそうな気がしていた。逃げたい気持ちが昌守の思考を抑えていた。
今まで昌守は後先考えず、今の状況を凌ぐことで精一杯だった。昌守はそれでもいいとも思っていた。光一との関係を保ち、あの家に潜り込めればそれで十分だと思ってきた。しかし、それもそろそろ限界に近くなっていた。光一の生活という問題から命という問題へと変わってきている気がしていた。
光一はあのまま死んでしまうのだろうか。死ぬとしたらどういう場合なのだろうか。苦しくなってそのまま息絶えてしまうのだろうか。息が止まれば心臓が止まり、血液が回らなくなるということだ。そうなれば、体温は低下し冷たくなる。冷たくなると体の組織は時間がたつにつれ腐敗していく。だからそうなる前に一般の人たちは火葬などで葬って上げるのだろう。死亡届を役所に提出して火葬の許可を得る手続きをする。そうやって人間の体は消えていくのだ。さすがに光一が亡くなったときも息子は動かざるを得ないだろう。動かない限り、死体が家の中で放置されることになるのだから。しかし、そうなると死亡届は誰が書くのだろうか。死亡届は死亡診断書であり、医師が書く書類だ。医師とは誰のことを指すのだろうか。通常であれば主治医である。しかし、今の主治医は書いてくれるのだろうか。
それとも光一は家で過ごすことがもう限界なのではないだろうか。病院で入院してもらうことが一番の解決策なのではないだろうか。あのまま過ごすことのリスクの方が高すぎるような気がした。一度、入院を勧めてみるのも良い事なのではないかと思った。しかし、今までの光一の姿を見ると、とても入院するという言葉は出なそうだった。お金の問題がやはり引っかかりそうな気がした。例え、国の制度で補助が出たとしても、その他の雑費なども光一は計算に入れるだろう。そっとして置いてほしい、といのが光一の本音なのではないだろうか。
となれば、やはり家で最期を向かえることにならざるを得ない。その時が来ても、安心して迎えられる様に準備しておくのも大切な事なのではないだろうか。
昌守はいろいろな考えをまとめ始めていた。具体的に頭を働かせるようになっていた。そして、今自分がしなければ行けないことが明確になった気がした。昌守は起き上がり、事務所へ車を走らせていった。
事務所に着いたのは夜の9時頃だった。今日は光一の家を出たのが8時くらいだったので時間が遅くなっていた。昌守は主治医に電話しようと考えていた。適当な医者ではあるが、主治医は主治医だ。まずは主治医としての意見を聞かなければならないと考えていた。しかし、主治医に話すことが整理できていないため、最初に今日の分の仕事を終わらせた。そして主治医に電話をしようと思い電話番号を調べた。そして、分かったところでかけようと思ったが、今からだと恐らく医師が居ないのではないかと思い、電話をすることを躊躇った。しかし、先延ばしにしていたら光一がいつ危ない状況になるのかわからないと思い、電話番号を確認しながらゆっくり押した。呼び出し音は流れるも、人が出る気配はなかった。諦めて受話器き、もう一度かけようと思ったが止めた。明日かけようと思い直し、電話番号は別のメモ用紙に書いてポケットに入れた。昌守は戸締まりをして事務所を出で家に帰った。
【29】
次の日も夕方から光一の家に行く予定を立てていた。昨日みたいに遅くならずに行ける予定が組めていた。しかし、今日は行く前に光一の主治医に電話をしてから行くつもりだった。電話番号は昨日メモした紙がポケットに入っていた。
もし、今日電話が繋がり、主治医と話すことになれば、今日で2回目となる。1回目は最初に書類を貰ったときで、昌守にとってあまり印象が良くなかった。話すこともあまり気が進まなかったが、それをしない限り前には進めないと思い、ポケットに入っていた紙に書いてある番号に電話した。1コールで若い女性が出た。事情を説明し、主治医へ繋いで貰った。医師はプライドが高い生き物だ、と誰かに教わった事があった。医師の機嫌を損ねないよう話を進めることに昌守は神経を尖らせていた。
「先生より指示をいただき、訪問させて頂いている岸坂光一様の件でお電話いたしました。今よろしいでしょうか?」
「ああ。いいですよ。どうそ。」
なんとか敬語をうまく使いながら主治医と話すことが出来た。その後も失礼のないように会話を進めた。
主治医は昌守の質問に淡々と答えた。かえって不気味な印象を受けた。しかし、そのまま昌守の質問は確信をつくような質問へと変えていった。
「光一様は呼吸器系統も異常が認められるようになってきているため、そろそろ生命の危険が及んでいるのではないかと思います。先生はこの後、どういった対応をしていくのでしょうか?」
この質問に対して主治医からは「死亡した場合は私が死亡確認をして死亡診断書を書きます。」という答えを望んでいた。しかし、主治医は何も変わらず、違う返事を返してきた。
「ああ。今後ですかぁ。実はあの人は最近診察していないんですよ。久しくこちらにも来ていないですし。ですので何とも言えませんが。」
昌守はあまりにも無責任な答えに驚き、そして少しずつ腹が立ってきていた。しかし、ここで腹を立てても光一にとっていいことは何一つないと思い、冷静になるように心を落ち着かせた。そして昌守は単刀直入に質問をした。
「先生はもし、光一様が息を引き取られた場合、死亡診断書を作成して下さるのでしょうか?」
主治医は必要な間もとらないまま、
「いやぁ。こちらではそれは出来ないですね。」
と、私は無関係というような声の質で返答してきた。
「うちの病院は訪問診療というものをしていないんですよ。だから、こちらから出向くことはありません。主治医として今、私がいるみたいですが、最近はこちらには受診されない事から、事実上、私は主治医じゃないと思いますよ。」
「では、どなたが今、主治医なのでしょう。」
昌守は皮肉を込めて質問を返した。すると主治医は、
「私の方では把握しかねます。あなたの方がよく知ってるんじゃないですかぁ。」
(知るわけないだろ)
と言いたいのを我慢して受話器を耳に当てていた。主治医は続けて話し出した。
「最悪、救急車を呼べば何とかなりますから。ちょっと解剖したり、警察が自宅で調べたりするだけですからね。」
主治医は言いたいことを言って昌守の質問を打ち切るかのように電話を切った。あまりにも無責任で身勝手な医者に、昌守は憤りを隠せなかった。
【30】
市役所に行って訪問診療をしている医療機関を探す事にした。どこに行けばいいかわからなかったので、顔を知っている障害福祉課の50代くらいの男に声をかけた。昌守の顔を見ると、またかと仕事が増えて面倒くさそうにしながらも対応してくれた。
訪問診療を行っている医療機関は数えるほどしかなく、この武蔵野市でも3つほどしか行っていなかった。それでも多い方だと50代の男は説明してくれた。
訪問診療は実際の所、一人の医師に頼る事が多く、夜の急な呼び出しに対応しなければならないため、誰もやりたがらないらしく、外来の様に病院に来てくれる患者を裁いている方が気楽だという意見が多いらしい、という情報も教えてくれた。
やはり、まだまだ家で行う医療というものは限られた存在なのだと改めて実感した。
昌守はその3つの医療機関に電話をすることにした。最初の医療機関は事情を説明すると電話対応では難しいので、患者と一緒に一度来てくれと一方的に言われて電話を切られた。
(行けるくらいだったら訪問診療じゃなくていいだろう)
と思いながら二つ目の医療機関に電話した。
二つ目の医療機関は最初に電話に出てくれるのが事務の人なのだろうか。いくら説明しても的外れな回答が多く、最後には、
「はぁ」
と、昌守の電話が理解出来ない、というような返答が帰ってきた。少々お待ち下さいと言われ、耳障りなオルゴールが流れて苛立ち、やっと終わったと思ったら、
「当院でもやはり利用者様からの要望でないとお話は受け入れられません。一度、ご本人様よりお電話いただけないでしょうか。」
とほぼ同様の回答となり、もう本人は話す力が無いから代弁していると何度も説明しているのにも関わらず、その答えが返ってくるため、
「それではいいです。」
と、諦めて電話を切った。
やはり、家族じゃない人間が色々動いても駄目なのだろうか。諦めかけながら三つ目の医療機関に電話した。
三つ目の医療機関は何回もコールを鳴らしても出なかった。診察日を確認してみると今日は休診だった。休診であれば誰もいないのだろうか。それでも昌守は一度切った後に、もう一度電話をした。今の悩みを一日でも早く解消したい気持ちがあった。光一の為と言うよりも昌守自身の為だった。
再度電話してもやはり出る気配はなかった。コールだけがむなしく耳の奥まで響いた。諦めて電話を切ろうとして電話を耳から話した時、電話から誰かの声が聞こえた。あわてて昌守は電話を再び耳に当てた。
「はい。もしもし。」
男性の声だった。年はかなり上の印象だった。少しかすれて聞き取りにくいがやり取りは出来そうだった。
「すいません。休診だと知っていたのですが、どうしてもお尋ねしたい事がありまして、何度も電話してしまいました。少しお聞きしたいのですがよろしいでしょうか?」
昌守は出来るだけ丁寧に電話をした。恐らく電話に出たのが医師である可能性が高い気がしたからだった。
「はいはい。いいですよ。何でしょう?」
電話の男性は声の張りを緩ませて話し始めた。おそらく、何度も電話が鳴るため、急患だと思ったのではないかと昌守は思った。違うとわかり、少し安堵したのだろう。口調も柔らかくなり、最初の声がとても張りつめていたのだとよくわかった。
「私は訪問リハビリをしている者です。今、行っている利用者様の事でお願いしたいことがありまして。」
出来るだけ言葉を整理して話そうとした。昌守はやはり医師と話すと緊張した。
「何でしょう?私でよければ相談にのりましょう。」
電話の男性も昌守の緊張を感じたのか、さらに柔らかい口調で話した。昌守も自分が冷静になれるようにしてくれているのだという配慮を感じ、出来るだけ簡潔に伝えようと頭を整理した。しかし、考えれば考えるほどそれは焦りへと変わった。ここで断られたら最後だという思いが昌守の思考を停止させてしまい、感情だけが表に出た。
「すいません!死亡診断書を書いて下さい!」
昌守は言ったことに冷静さを欠いていたと反省し、すぐに弁解の言葉を言おうとしたとき、電話の男性はやさしく答えた。
「まずは落ち着きましょう。事情をお聞かせ願いませんか?」
電話の男性は優しさで溢れていた。
【31】
昌守は落ち着きと冷静さを取り戻し、詳細に事情を説明した。その部分まで伝えなくてもいいだろうと思う内容までも話した。電話の男性は昌守にも頷く事がわかる様に声に出して「うん、うん」と昌守の話を聞いた。昌守はその頷きの言葉でさらに落ち着いて話すことが出来た。
電話の男性は昌守の話を聞いて整理をし始めた。現状の理解を深めるために、言葉を変えて表現し、別の角度から説明を加え、さらに確認作業もしてくれた。そして、おおよそ光一の状況を理解した電話の男性は、自分の意見を語り出した。
「大まかなことはわかりました。まずは私の自己紹介をさせて下さい。私は、医師の松崎といいます。医師としてその問題に取り組みたいと思いますのでご安心下さい。」
その言葉を聞いて昌守はやっと相手にしてくれる医師が見つかったと思った。涙が出そうなくらいうれしかった。そのまま松崎医師は続けて話した。
「まず最初に問題点の整理をしましょう。どの病気にも担当医と言われる者はいます。その病気を診断した医師が担当医となります。かかっている、かかっていた、など、過去や現在があったとしても時系列で言えば病気は続いているので、一度診断した医師は最初の担当医であります。病気が複数重なり、診断した医師が複数いた場合は、もっとも重要と判断した病気が主治医になる場合が多いです。ただその方はきっと大きな病院から街の小さな病院へと引き継がれているので、その小さな病院の医師がまだ主治医と考えられます。」
「ただ、その主治医はもう診察をしてないからもう違うと話していましたが・・・。」
「暫く診察をしていないからと言って主治医が無くなったとは考えない方がいいでしょう。少なくとも大きな病院で診断された書類を持っているので、少なくとも誰かに引き継がない限り、その病気に対して診ていく義務はあると思います。ただ、一人ひとりの患者さんに気を利かせる事は現実的に不可能です。頼りにして来る人、つまり受診をしてくれる人が医師として診ていると言う事も一つあるかと思われます。」
「その人は自分で行けなくなったから行けなくなったんです。それを・・・・」
「まぁ落ち着いてください。要するに今の主治医ではその方の家に言って診察が出来ない業務形態である事は間違いなさそうなので、それが出来る病院へ移す事が大切な事になります。つまり、主治医を変える事です。そのようなお話はしましたか?」
「主治医を変えるという話まではしてないと思います。」
「おそらくその主治医も訪問診療が出来る医師へ主治医を変更するという提案をしたのであれば、受け入れたと思いますよ。ただ、医師としての責任の話をするとプライドの高い医師は自分が出来ないという事を言うのを決してしない人が多いですから。」
なるほどと昌守は思った。確かに主治医としての責任を追及すると逃げるような発言になりがちだが、その責任を他の医師にしたらどうかという提案は聞いてくれるのではないかと思った。事実、今の主治医は診察自体が出来ないため訪問診療出来る医師へ移行することは賛成するはずだと思った。
「わかりました。では今後はどのように勧めて行けばよろしいでしょうか。」
「主治医を変更する場合は、患者様の意志が重要になります。周りがこの医師がいいからと言って勝手に変更できるものではありません。医療とは患者様主体である以上、どういう理由であれ出来ないのであります。
よって、最初に行うことは『本人の意思の確認』になります。本人が了承すれば次のステップへ移ることが出来ます。しかし、それでもあなたが動くことは出来ません。本人が動けないのであれば家族がいる以上、家族の方に動いて貰わねばなりません。私としても家族の意向を確認しないまま引き受けるわけには行きません。私が突然乗り込んで説得する方法もあるかもしれませんが、まずはあなたがしっかりと説得してみることが一番よい方法だと思います。いかがでしょうか。」
とてもわかりやすく、説得のある説明を松崎医師は説明してくれた。
「わかりました。本人の了承と家族の意向の確認が必要になるのですね。」
「そのとおりです。その二つがクリア出来れば、あとは書類のやりとりだけなので事は早く進められるでしょう。」
話を終えて電話を切った。昌守は覚悟を決めた。
【32】
光一はいつも通りベッドに横になっていた。寝返る力もなく、天井を常に見ている形で仰向けに寝ていた。昌守が部屋にはいると首も回す力がないためか、そのままの姿勢で「おう」と小さく返事をした。
いつものように身の回りの手伝いと体をほぐす事をした。足の皮膚はカサカサに乾ききっていて、古い角質が剥がれ落ち、粉が舞うくらい肌が荒れていた。人肌の温かさもなく、冷たい足を昌守は何度もさすった。少し温かくなったと思ったらすぐに冷たい肌に戻った。自分の手の摩擦で温かい錯覚をしたのだとがっかりしていた。
それでも光一は「気持ちいい」と言ってくれた。それはお世辞だったのかもしれないが、病気からしても皮膚の感覚だけは残っているため、昌守が擦った摩擦は伝わっているはずだった。昌守はそれしか出来ない自分に無力を感じざるを得なかった。
足が終わり、体、肩や腕もさすった。徐々に光一の顔に近づいていくがまともに顔を見ることが苦しくなってしまった。今日は光一に主治医の変更を提案するつもりだった。きっと光一はなぜそのような事をしなければならないのかと聞かれると思った。理由はただ一つ、死という現実を具体的に話さなければならなかった。そう思えば思うほど話を切り出せなくなっていた。
腕も終わり、再び昌守は足をさすりだした。いつもなら腕で終わる手順なのを足に戻る姿を光一は不思議に思っただろう。それでも光一は何も言わずにそのまま仰向けでじっとしていた。ただ動けなかっただけじゃない。光一は昌守が何か伝えたいことがあるのだと、理解していたのかもしれない。
「光一さん。今日は大事な話があります。もし、話すのが苦しいのであればそのままで聞いていて下さい。」
「だいじょう・・・ぶ。・・・・短い・・・言葉・・・なら・・・・話せ・・・る。」
「わかりました。光一さん。これから言うことは光一さんにとって大変重要な事になります。とても言いにくい事を話そうと思います。とても私自身話そうか迷いましたが、それでも今言わなければいけないと思って話すことにします。」
昌守は足を摩る手を止めた。
「光一さん。今、少し話すだけで苦しいという状況は大変危険な状態になります。呼吸をする力が衰えてきているのです。おそらく病気から来るものだと思います。その病気は私の想像を遥かに超えたスピードで、光一さんの体に広がってきています。光一さん。あなたはもうすぐ・・・もうすぐ死を迎えることになると思います。おそらく・・・近いうちに・・・。今日はその準備をしたいと思って話しました。私の聞いてくれますか?」
昌守は言い終えたあと光一の表情を確認した。正直見るのが恐かったが、声を出しにくい光一に対して表情で読みとれるところがあれば読みとって上げたいと思った。そういう思いがあってか、今度はしっかりと光一の顔を見ることが出来た。
光一は天井を見つめていた。唇を噛みしめていた。眉間に皺が寄っていた。うっすら目に涙を浮かべていた。部屋に沈黙が流れ、光一は小さな声で返事をした。
「あり・・・が・・・とう・・・。」
昌守はその言葉に救われた。全てその言葉に凝縮した光一の気持ちが詰まっているような気がした。昌守はうなだれて下を向いた。光一の足に一滴の涙が落ちていた。
【33】
光一に今の主治医で死亡診断書を書いてくれるかどうか確認した事を話した。自宅で死を迎えるためにはそうした手続きが必要になる事を説明した。光一はやはり病院には行きたくないと言い、昌守の予想通り、自宅での死を希望した。
今までの経緯を回りくどい表現は無くし、単刀直入に話した。光一も真剣な表情で聞いていた。今の医師では難しいこと。新しい医師であれば書いてくれそうな事。しかし、家族の同意が必要な事。つまり、息子の同意が必要になる事を話した。光一は家族の同意が必要になるという話を聞いた途端、表情を替え、難色を示した。やはり、息子との関係はあまり良好ではないということなのだろうか。
「息子は・・・関係ない・・・・話だ・・・・・・」
光一は息子をどうしても頼ることを嫌がる様だった。恐る恐る理由を聞いたが返事はしてくれなかった。光一はきっとその理由を墓場まで持って行くのだろうと思った。この状況で頑なに拒む光一を見て昌守は諦めた。
「わかりました。また違う方法がないか、先生に聞いてみます。」
そういって光一には納得して貰った。光一の表情には変わらない決意がにじみ出ていた。
昌守はいつもの介護を終えて光一の家を出た。そして車に戻り、すぐに松崎医師に電話した。今日は休診日ではないため、事務職員と思われる女の人がすぐに電話に出た。先日お話をした者と伝え、松崎医師に繋いでもらえるよう頼んだ。保留中によく流れる音楽が1分ほど流れた後、松崎医師が電話に出た。
事情を話し、本人の意向のみで手配してくれないかと訪ねると、松崎医師は深く悩み出した。昌守にもう一度診断名を確認すると、少し待ってほしいと再び保留中の音楽が流れた。そして1分ほど流れた後に再び松崎先生が出た。
「筋萎縮性側索硬化症、でしたね。」
再び松崎医師は診断名を確認した。何か調べながら電話をしている様だった。そして調べたい項目が見つかったのだろうか。思い出したように、声のトーンを少しあげて話し出した。
「うんうん。そうでした。やはり脳には影響はないので、意志は本人のみでも大丈夫でしょう。」
松崎医師は脳への影響を心配していたらしかった。光一に、自己決定能力があるのかどうかを調べていた様だった。そして、光一の主治医になる事を引き受けてくれた。
「特別ですよ。あなたの熱意に負けました。」
そう言って昌守の努力を労ってもくれた。
「しかし、一つだけ問題があります。」
突然、松崎医師は声質を低くし、慎重に話し出した。
「私が診察をする場合、やはり診療情報提供書という書類がどうしても必要になります。その方が患っている病気は私の力では診断出来ません。診断して下さった先生の情報を頂く必要があるのです。今、主治医である先生が息子様の意向無しで書いて下さるかどうか、なのですが・・・。」
昌守は「何とか書いてもらえるようお願いしてみます。」と言い、光一の氏名と住所と生年月日だけを簡単に松崎医師に伝え、電話を切った。松崎医師も書類が整い次第、すぐに診察できるようカルテなどを準備してくれるとの事だった。
昌守はすぐに今の主治医である病院に電話をした。主治医はすぐに電話に出た。これまでの事情を説明し書類を書いてもらえるようお願いした。しかし、主治医は頷くことはなかった。やはり家族でないと書類は渡せないと言い張ったのだ。渋々、昌守は電話をきった。また、大きな壁が昌守の前に立ちはだかっていた。
車の中で昌守は考えていた。どうやっても光一の息子、孝に動いて貰わなければ事が進まなくなってしまったのだ。まずどうして光一はここまで息子に対して拒み続けるのか。それを理解しなければ何も始まらないのではないか。しかし、どう想像してもわからなかった。
昌守は再び息子に手紙を書いた。今までの手紙よりも重要な内容を書き連ねた。光一がもうすぐ死んでしまう事、主治医を変更したい事、自宅で死を迎えられるようにしたいこと、そうした内容を息子が行動してもらえるよう、願いを込めて。そして静かに光一の家の前まで戻り、光一に知られないように静かにポストに入れた。
次の日も昌守は光一の家に訪れた。昨日、息子に手紙を出したことを隠して光一と接していた。息子からの手紙は見あたらなかった。やはり、もう駄目なのだろうか。光一の姿も日に日に苦しさが増していた。
光一宅を出て事務所に帰った。カルテを整理し帰宅しようとしたとき、自分宛に手紙が届いていることに気付いた。その手紙の送り主は「岸坂孝」と書いてあった。
【34】
昌守は慌てて封筒を開けた。まさか事務所に返信が来るとは思ってもみなかったからだ。いつも机の上にあるハサミを探した。しかし、こういう時に限って見あたらず、隣の机にあるハサミを借りて封筒を開けた。
中にはA4の紙が数枚入っていた。中にはこう書いてあった。
「
拝啓
いつも父がお世話になっています。何度もお手紙を頂き、お返事しなかったことを最初にお詫び申し上げます。我が家には色々な事情があり、現在のような親子の接点がない生活をしています。おそらく、細田様には私がそう言う関係にしたとお思いでしょう。しかし、今の関係を望んだのは、私ではなく父が望んだ事でした。
色々な事情から説明させていただきます。父はご存じと思いますが、仕事一筋の人間でした。とても熱心に朝から晩まで仕事をしていました。休日も仕事をするほど、仕事を愛してきた人でした。
しかし、反対を言えば家庭を顧みない父親でした。私の記憶では父親に遊んで貰ったことはあまり記憶にありません。あるとすれば、一緒にうどんを打つことくらいだったような気がしています。かわりに沢山のおもちゃは買って貰いましたが、一緒に過ごした時間はあまりなかったと思います。
その変わり、私には母が居ました。母は私を熱心に育ててくれました。いつも父が居ないことで拗ねると、母は決まって
「お父さんは孝のために仕事をしているのだから、あんまり文句を言うとお父さん困っちゃうよ。」
と言って慰めてくれました。それでも、ひねくれていた私は
「僕のことを思うのなら少しは遊んでくれてもいいじゃないか。」
と反論すると、母は黙って私を父が勤めるお店まで連れて行き、その店の前で出入りするお客さんを見させられました。そして母は言うのです。
「孝。お父さんはね。ここのお店を出入りしているお客さんにおいしいおうどんを食べさせているの。今見ているだけでも何人もの人が、お父さんが作ったおうどんを食べて幸せを感じているんだよ。孝はお父さんを独り占めしたいと思うだろうけど、そうすることによってその人たちの幸せを取り上げることになるの。お客さんはみんなわかってくれているのよ。孝が我慢してくれているってこと。あのおいしいうどんはお父さんだけじゃなく、孝の頑張りもあって作り上げられているって事をね。」
そうやって言われると自分も一緒に仕事をしているような気持ちになったことを覚えています。そうして慰められ、そしてそのままお店に入り、食事を取ることが我が家の決まりごとのようでした。
お店の人も母が私を連れてくるという理由は察しているかのように、
「いつも悪いねぇ。お父ちゃん借りちゃって。」
と口裏を合わせたかのように声をかけてもらい、そのまま閉店まで居て親子三人で帰るのが定番でした。その帰り道が一番父を占領出来たと思える時間でした。
しかし、そういう時間もあまり長くは続きませんでした。母の体に異変が生じてきたのです。
何でもないところで躓くようになったり、やけに疲れるようになり横になることが多くなりました。私は心配して父に相談しても、「大丈夫だ。」という一言で終わってしまったのです。母もあまり自分の弱みを言わなかったのでしょう。そのまま月日は流れていきました。しかし、やはり体の異変は続いていき、悪化していくだけだったのです。そしてとうとう外出先で転倒し頭部を強打して救急車で運ばれるような出来事がありました。
頭部を強打したのですが、母の意識ははっきりしていました。父も病院に駆けつけ、心配ないと判断したのでしょう。母を連れて帰る支度をしていたのですが、当時担当した医師がなかなか帰らせてくれませんでした。帰らせてもらえないどころか、そのまま入院する運びとなったのです。父は理由が知りたいと医師に相談したのですが、精密な検査結果が出てからお知らせしたいという医師の方針は変わらず、母もせっかくだから色々見て貰いましょうと言ったため、父も渋々入院を承諾しました。
そして後日、父だけが呼ばれました。筋委縮性側索硬化症という診断が母に下されたのです。今の父と同じ病気を母は先に患ってしまったのです。
当時の父はなかなか受け入れられなかった様でした。母に告知をするかどうかも聞かれたみたいでしたが、父はしないという一点張りで、母をすぐに退院させました。きっと父はそんな診断が間違っていると思っていたのでしょう。元の生活に戻ろうと母を退院させた後も家事をいつもどおり行わせました。母も弱音を言わず、家事を行いました。転びそうな所は慎重に足元を見ながら歩いたり、立って料理をするのが疲れるらしく座って包丁を使うことが多くなりました。外を歩くときは押し車のようなものを購入して転ばないようにしたり、買った物を入れたりしていました。押し車は父に見つからないように倉庫にしまっていました。
そうやって、母の努力もあり、半年くらいは通常の生活を送ることが出来たのです。しかし、そうした生活は長くは続きませんでした。母はある時、いつものように食事を作ろうと台所で包丁を扱おうとしました。しかし、その日に限って包丁を使わないで料理をし始めたのです。食材は叩いて砕いたものや、葉類はちぎって鍋に入れられました。父も料理を見てさすがに異変に気付いたのでしょう。母にどうしたんだと問いつめると母は泣き崩れるように言ったのです。
「もう限界です。お願いですから病院に行かせて下さい。」
と。母はもう包丁を握れないほど手に力が入らなくなっていたのです。
母はすぐに入院になりました。我が家で生活が困難であると判断されたため、戻れる環境が整うまで入院する事になりました。しかし、父は戻れる環境を作る事はしなかったのです。父は母が徐々に筋肉が衰え、細くなっていく姿を見ることさえ拒んでいる様でした。お見舞いに行く回数も徐々に減りました。私だけ行く日も多くありました。それでも母は父を攻めませんでした。
「お父さんはおいしいおうどんをお客さんに出しているんだから、私がお父さんを独り占めしたら罰が当たるのよ。」
と笑って私に話していました。
そして母は自分の力で動けなくなるほど弱ってしまいました。もう、死期が近い。母自身も感じるようになったのでしょう。母は父に初めてお願い事をしたのです。母の願い事は二つありました。一つは、また父のお店でうどんを食べてみたい、そして、もう一つは、家で死にたい、でした。
うどんを食べたいという希望はすぐに叶えられました。父は前向きでは無かったのですが、医師の勧めもあり、渋々父も承諾しました。車椅子で父のお店まで行って一緒に食事をしました。まだ飲み込む力があったのも幸いでした。その後、すぐに食べられなくなってしまったのですから。
そして二つ目の願いを叶えられるかどうかという話しになりました。医師は環境さえ整えば可能だと話したのです。しかし、父は承諾しませんでした。とても自分には出来ない、という思いで一杯だった気がします。仕事に私の子育て、そして母の看取りは当時の父にとっては荷が重すぎたのでしょう。母もその気持ちを察してか、それ以来、その願い事を一度も言うことはありませんでした。そして、そのまま母は病院で息を引き取ったのです。
私は父を責めました。どうして母の願いを叶えて上げなかったのだと。子供にはわからないと罵られ、それ以来私と父の間には深い溝が生まれたのです。
そしてその後、父も同じ病気になりました。最初はいい気味だと思い、陰で笑うように父を見ていました。徐々に動けなくなる体をどんな思いで母が過ごしてきたのかを実感しろ、と言わんばかりに遠くから父を見続けたのです。しかし、父は弱音を吐かず、仕事と私の子育てを続けました。たくさんの辛い思いをしながら耐え抜いたのです。しかし、やはりその生活も長くは続きませんでした。仕事で大きな失敗をし、病気が治るまで休職する事になったのです。
私はそれまで遠くで見ているだけでしたが、それをきっかけに家のことを手伝おうと思いました。父に、そう話すと父は思いもよらず、断固として断ったのです。父は
「自分のことは自分でする。だからおまえはおまえの事だけすればよい。」
と、そう言いきりました。それから父は私の前に姿を現さなくなりました。私が気にかけて父の部屋に入ろうとすると、入ってくるなと言うのです。私は最近の父の姿を見ていません。でも予想はだいたいつきます。私は母を見てきたのですから。
それ以来、私も家にあまり居ることがなくなりました。学業も忙しくなり、家に居る時間が減ったのです。私は現在大学の2年生になります。昼間は働き、夜に学校へ通っています。そして土日もバイトをしています。経済的に苦しいだけではありません。家に居るのが辛くなってきたからだと、今は思います。家に居ると、壁一枚向こう側に父が居ます。父はおそらく体を動かすことが大変苦痛になってきていると思います。それを手助けしたいと思う私の気持ちを家に居ることで抑えきれなくなりそうだったからです。
そういう思いをしながら、しばらく過ごしました。そして、リハビリである細田さんが家に来てくれるようになったのです。私は、最初は今さらリハビリをして何になるのかと思っていました。しかし、父が懸命に復職を目指している努力を運動したチェック表で知り、私は心を打たれました。願わくばもう一度、職場に復帰してもらいたい。そう願うようになりました。
それでもやはり、願いは届きませんでした。父は私に障害年金の話をしたのです。私は久しぶりに父と正面を向いて話しました。父も母と同様、体は細くなっていました。もうこれ以上、私は見殺しには出来ないと思いました。父の身の回りのことをさせて欲しいとお願いしました。しかし、やはり父は同じ答えが返って来たのです。
「自分の事は自分でする。だからおまえはおまえの事だけすればよい。」
と。それを言われたときに、私は思いました。父はきっと、この家でひっそりと死ぬ気なんだと。母が叶わなかった希望を父自ら実行するのではないかと。
それ以来、私は父の姿を毎日見るようになりました。しかし、父に見つかるといけないので夜遅い時間、父が寝ている時間を見計らって父が生きている事を毎日確認するようになりました。父はおかげさまで生きてこられたのも細田さんのおかげだと思っています。私は細田さんがこの家に来てくれたからこそ、父も父らしくここまで生きて来られたのだと思います。
何度も手紙の返事をしなかったこともお詫び申し上げます。連絡しないほうが、きっと父のためになるのかと思ったからです。本当に申し訳ありませんでした。
おそらく、父の最期の願いは家で静に息を引き取ることだと思います。私もそれに全力を注ぎたいと思います。
話は長くなりましたが、主治医変更の件、了解いたしました。早速、明後日にでも手続きをしたいと思います。今日中にこの手紙を出すので、おそらく明日にはこの手紙は届くでしょう。これが届いた次の日が手続きをしたいと思っている日程になると思います。早めにした方がいいかと思いまして、職場に休日の願いを出してその日になりました。
そこで、細田さんにお願いがあります。私が休暇を貰った当日、父を外に連れ出してもらえませんか?どうしてもあの部屋で毎日を過ごす父を見て、すごく狭い空間の中で生きているんだと思うと切なくなってしまいました。母は家ではなかったにしろ、病院のスタッフと接することもあり、孤独ではなかったような気がするのです。父はあまりにも孤独であり、あまりにも惨めのような気がしてならないのです。最期にいい思い出を作らせてあげたいのです。無理にとは言いません。でも頼めるのは細田さんしかいないのです。
当日の午前中に今の主治医のところに書類をとりに行って、そのまま新しい主治医へ行ってきます。それが済んだら家に戻ります。その時に父と外で会えるのであれば、私も素直に色々話せるのではないかと思うのです。母が苦労した家の中ではなく、家の外で話せるのであれば、お互いに気遣ってきた小さな事も、青空が消してくれるのではないかと思う気がして。
そして今一度、父の仕事場に行って欲しいのです。あそこには、私たち家族の色々な思い出が詰まっています。数え切れないほど話せる場所があるのです。
父が居なくなれば、私もこれで家族と呼べる人がいなくなります。そうなる前に、今までの思い出話をしたいのです。
父は拒むかもしれません。でも今しかないと思います。どうか、お願いします。父を、最期の父を活かして上げて下さい。
色々とお願いごとばかりして申し訳ございません。明日、お会いできる事を楽しみにしています。
敬具
岸坂孝
訪問リハビリテーション 細田昌守様
」
息子、孝からの手紙だった。読み終えた昌守は手紙の内容を噛み締めながらもう一度読み直し、そっと封筒の中に手紙を戻し、事務所を去った。昌守は次にしなければならない事を頭の中で整理していた。
【35】
昌守は翌日、朝から市役所に向かった。午前中に行く予定だった昌守が担当している利用者は全て翌日以降の空いている時間に移動した。急な願いにも関わらず、全ての利用者は了承してくれた。昌守の必死な気持ちを汲み取ってくれたような気がした。
昌守が市役所に行った理由は車椅子の手配だった。市役所にはある程度車椅子がストックしてあるかもしれないと思い、向かったのだった。
障害福祉課に顔を知っている50代の男性に声をかけた。またあなたですか、というような顔をされたが対応してくれた。理由を話し、車椅子を午前中だけでも借りられないか相談した。50代の男はちょっと待って欲しいと奥の方へ移動していった。そして5分後、奥にある車椅子を持ってきた。これでよいかと出してきたのが通常の車いすだった。光一はもう座る事が難しいため、通常の車いすでは難しかった。背もたれが倒せるリクライニングタイプの車いすが希望だったが市役所にはこういうタイプしか無いと説明された。仕方なく、諦めて帰ろうとしたとき、その50代の男は昌守を引き止めた。昌守が求めている車椅子がないか、もう一度探させて欲しい、と言い出したのだ。昌守は少し驚いた。いつもならその50代の男は面倒くさそうに対応されるのだが、今日は違ってすごく協力的に思えた。昌守も探してくれる人が増えるので内心助かる思いだった。しかし、急に協力的になった50代の男に疑問も少し持っていた。
50代の男は必死に電話をしていた。他の課から業者の一覧表を手に入れてきて思い当たる所から電話している様だった。今までに無く必死な様子だった。昌守はその姿を見て心強く思えた。
10分後くらいだろうか。50代の男は貸してくれる宛が見つかったと言ってきた。しかし、30分くらい待てるかと言われたので、大丈夫だと答えた。そしたら30分後に市役所の玄関まで来てほしい、と言われ、その場を一旦去った。
昌守は30分後に市役所の玄関に来た。50代の男もそこにいた。お互いに挨拶をし、車椅子はもう少しで着くのでもう少し待ってほしいと言われ、昌守はその50代の男と一緒に待つことにした。
50代の男は昌守に突然、お詫びの言葉を言い出した。昌守は何を言い出したのかと思い、事情を確認すると、50代の男はこう言ってきた。
「実は私、おそらくあなたが今対応している人を知っています。実は市役所でも難病に対して担当者が着くのです。病名からしても今現在、市で把握しているのは1人しかいません。なので、私はあなたが今対応している人がそうなのだろうと思っています。
市では保健所と協力して、難病の病状把握や適切なサービスの提供を行うのが役目になります。しかし、私はその役目に対して全うしようと思う気が思えませんでした。
市役所という場所は大体3年に1回は別の部署に移動する事が多い仕事場なのです。障害福祉課にいて今年で3年目になります。もうすぐ移動になると思うとあまり本腰を入れられませんでした。そして今年で定年退職です。静に終わりにしたかったのです。
でもそれは本当の言い訳ではありません。おそらく私は死というものが怖かったのだと思います。私が担当する病名を聞いて、私は本当に現実にあるのかと疑うばかりでした。
就任当初は本人の家に行ったこともありました。しかし、最初の一回会っただけで後は本人に会うことが出来ませんでした。おそらく拒否されているのだと思いました。どうしようかと保健所と相談していたところに、訪問リハビリが出入りしている事を知りました。保健所と相談し、そのリハビリの先生にお任せをしようという事になりました。私自身もあまり積極的になれませんでしたから。
毎月、保健所に報告書を出していますよね。その報告書、実は私も保健所にお願いして最近読ませて頂いたのです。報告書を読ませていただく中で、もう状態が危ないということを知りました。自分ではどうしていいのか分からず、ただもう少し生きて欲しいという願いをするだけでした。そう願う中であなたが今日現れました。そしてあなたの姿を見て思ったのです。私も逃げないで、その人の死をしっかりと受け止めて仕事をしなければいけないのだと。
あなたは最期までその人の人生を活かそうと努力していました。その姿が私にとって悔しく思いました。私にも何かできないか、そうあなたが帰ろうとした姿を見て思いました。逃げるのではなく、頑張って見ようと。
今からくる車椅子は私の罪滅ぼしです。本当に申し訳ない。」
50代の男は最後には声を震わせもう一度「申し訳ない」と昌守に言った。ちょうど車椅子が手元に届くと、昌守は今日の手配に感謝を述べてその場を去った。この車椅子一つにも色々な思いがあるのだと思い、気持ちを引き締め直していた。
次に昌守は光一が勤めていたうどん屋に行った。午前中でまだ時間が早かったせいか、支度中となっていてお店がまだ開いてなかった。昌守は表の玄関をノックして店員を呼んだ。前に接客してくれた店長の娘が出てきた。何事かと思うような仕草で昌守を見つめた。昌守は光一の名前を出して初めから説明をした。最初は唐突過ぎて何も聞き入れられないようだったが、昌守の話はよく聞いてくれた。そして自分一人ではどうしようもないと思ったのか、奥の店長を呼びだした。店長の娘は今までの話を要約するように店長に説明をしていた。
店長も娘の話をゆっくり頷きながら聞いていた。そして驚く様子よりも、そうだったのかと納得するような様子で聞いていた。話を聞き終わると店長は昌守に近づいて行き、深々と昌守にお礼をした。そして店長は説明し始めた。
店長はこうなると予想していた様だ。病名が一緒と言うのは驚いていたが、何となく感じ取っていた様だった。退職願が届いたときから光一宅に電話を何度かしたが、光一は出なかったらしい。家に行っても誰も出なかったそうだ。以前の奥さんの事もあったからだろう。これ以上、店長は光一の家庭事情に踏み込めず、もどかしかった様だった。
店長は昌守に聞いてきた。
「彼はまだ食事が食べられるのか?」と。
昌守は、
「難しいかもしれません。」
と返事をすると、それでは食べやすいような食事を用意しておこうと店長は言った。昌守はゼリーのように喉を通りやすい食事でないといけないと説明した。店長はわかっているとうなずいていた。奥の厨房からこれならどうだと出してきた。よく賄いで出した煮凝りだった。昌守もそれならば大丈夫だろうと納得していた。これで、全ての準備は整ったと、昌守は思っていた。
【36】
これで光一が外に出る準備は整った。光一を移動させられるリクライニング車椅子が手に入った。移動先の光一の元勤務先であるうどん屋には店長と交渉し、食事が取れるよう了解を得た。あとは息子が今の主治医から書類を貰って、新しい主治医の松崎医師に届けるのを待つのみとなった。午前中に松崎医師に届けられれば、午後にでも診察してくれるのではないかと期待していた。そうすれば、もう何時でも看取れる準備は整うと思った。ようやく自分の役目が一つ終わるのかと思うと少しほっとしていた。
昌守は光一宅まで移動した。玄関の前にリクライニング車椅子を運び終えていた。入る前に色々と考えた。まだ、光一には息子と接触したことも話していないし、外に行くことも話していないからだ。どうやって光一に話し、納得して貰うかまだ計画を立てていなかった。
(もうここまで来たら、話の流れで持って行こう。)
そう思っていた。例え、光一が拒否をしたとしても、力ずくでも連れだそうとも考えていた。光一にはもう抵抗できる力さえない。最期に最高の思い出を作って上げたかった。それはきっと、昌守だけしかできない重要な役割だと考えていた。
昌守は光一宅へ入った。いつものように光一の部屋の扉を開けた。開けた瞬間、空気の漂い方が違う感覚に囚われた。何か冷たい箱の中に飛び込んでいくような気持ちになった。足がすくみ、部屋の中にはいるのに体が重くなった。部屋に入る前に今自分の立ち位置を確認した方がいいような気がした。本当に自分が部屋に入って良いものかどうか考えるまで、昌守は混乱していた。ようやく昌守は視線が泳がなくなった。それまで視線が合っていないことも自覚していなかった。部屋の中の様子を一つ一つ確認し、出来るだけ冷静になろうとした。普段と部屋が一緒かどうか確認をした。なぜ自分がそんなことをするのか不思議に思ったが、本能が昌守をそうさせていた。日光はいつものように窓から降り注ぎ、カーテンは開いたままだった。光一には閉められるはずもないので変わっていない事に少し安堵を覚えた。視線は窓から壁を伝い、そして光一が居るベッドに合わせた。ベッドの位置も同じであり、特に異常は感じられなかった。そしてベッドの上にいる光一に視線を合わせた。光一は目を閉じたまま天井を向いていた。そこだけがいつもと違う風景だった。
昌守は恐る恐る部屋の中に入っていった。本当ならば急いで駆けつけなければいけない状況なのだろう。しかし、昌守はその部屋の入り口からベッドまでの距離を出来るだけ時間をかけて歩きたかった。医療従事者としての自分と息子の思いを託された自分を重ね合わせ、今何をしなければ行けないのか考えながら光一に近づいた。しかし、その考えもまだ早いと否定する自分もあり、考えはまとまらず光一の近くまでたどり着いた。
光一は静かにベッドの上で目を閉じていた。一見眠っているように思えたが、肌の血色がいつもと違うことに気付いた。昌守は部屋の明かりが原因だと思い、もう一度部屋の周りを見た。しかし、明るさは十分だと気づき、もう一度光一の顔を見た。光一はやはり血色の悪い顔つきをしていた。
「光一さん・・・。」
恐る恐る昌守は声をかけた。そのまま目を開けて、「また来たのか。」といつものように面倒くさそうな表情をして返事をして欲しかった。しかし、その期待は叶うことなく、静かなままの状態でいた。昌守は手のひらをゆっくりと光一の顔に近づけた。握り拳一つ分の間を開けて光一の体温を感じ取ろうとした。しかし、間が開きすぎているせいか光一の体温は感じ取れなかった。さらに1cmくらいの間隔まで手のひらを近づけた。光一から感じられる体温は冷気だとはっきりわかった。自分の手のひらが間違っているのだと思い、手のひらをひっくり返し、感覚がさらに敏感に感じる手の甲を光一側に向けた。さらに冷気を感じ、手の甲から怖いという感情が伝わった。そのまま、手の甲を光一の鼻まで移動し、息をしていないことを確認した。そのまま手のひらを元に戻し、光一の頬に手をかざした。冷たい感覚が脳まで伝わり、昌守の感覚をさらに鈍らせるだけだった。
昌守の思考回路は光一の皮膚の冷たさで、完全に冷静さとは異なる方向へと誘導していった。皮膚が冷たくなっているということは血行が全身に行き届いていないという事になる。つまり、心臓が停止しているという事を意味していた。それは数時間経過している事になる。心臓が停止してから再び動かすためには、あまりにも時間が過ぎていた。しかし、昌守は
(心臓が止まっているのであればもう一度動かせば良い)
と判断した。それは医学的にも、常識的にもかけ離れた判断だった。
昌守は救急救命の手順を思い返していた。静まる部屋の中で思い返しながら、光一に対して救命行為を続けていた。意識を確認し、呼吸を確認し、そして脈拍を確認した。その手順を追わなくても答えは出ることはわかっていた。それでもやらずにはいられなかった。
脈拍が無いことを確認した昌守は心臓マッサージを開始した。掛け布団をとり、服の上から心臓の位置を目視と触診で確認し、位置が決まると垂直にテニスボールを押すように体全体を使って光一の胸を押した。強すぎず、弱すぎず、力の加減に集中をした。光一の胸が浮き沈みするのがわかった。しかし、ベッドの上だったのでベッドが軋む事で相殺されていた。心臓に到達できる力は実際のところわからなかった。そういった気の廻しは何故かその時の昌守には出来ていた。
何度も行っていく上で心臓の鼓動が戻らないと今度は人工呼吸を始めた。死後硬直をしているため、口は思ったほど開かなかった。昌守は光一の唇にそっと口を当てて昌守が吐く空気が漏れないようしっかりと押さえた。唇からの感触ははやり冷たさを覚えた。それでも昌守は歯と歯の間からでも空気を入れようと、ゆっくりとそして肺の中まで入れるようにそっと力強く息を吐いた。殆どの空気は光一の体には入らなかった。
何分それを繰り返しただろか。昌守の体は汗で服が濡れていた。額から流れる汗を気付かないうちに手で拭っていた。光一の唇は昌守の体温で温かくなっていた。
光一の家の電話が鳴った。昌守はその音に反応し、電話に出た。
電話をかけてきたのはうどん屋の店長だった。待ち合わせの時間を過ぎたが、まだかかるのかどうか、という内容の電話だった。昌守は今現在の状況を淡々と説明し始めた。電話の向こうにいる店長の声が低くなるのがわかった。
「それはぁ、おめぇさん。救急車を呼んだ方が良いんじゃねぇか・・・。」
そこで初めて昌守は救急車という選択があるのだとわかった。店長にお礼を言い終えた昌守は電話をきり、再び受話器を上げて救急車を呼ぶ番号を押そうとした。しかし、昌守は思い留まった。ここで救急車を呼んだとしたら、光一は病院に運ばれ、そこで死という診断を受けることになる。つまり、家で死ぬという妻の思いを果たせない事になるのだ。それでは、今息子が頑張って書類を新しい主治医の所へ届けに行っているのも無駄になってしまう。そう思い、昌守は救急車を呼ぶことをやめた。
店長の言葉を思い返していた。救急車を呼んだ方がいい、という言葉の裏には専門の人に診て貰う方がいいという判断が裏にあるのではないか。そうなれば医師が来てもらえればそれでこの問題が解決するのではないかと考えた。もう、息子は松崎医師の所に着いただろうか。昌守は前に控えていた松崎医師がいる病院の電話番号を押した。
電話がつながり松崎医師に繋いで貰うことが出来た。松崎医師は冷静に話を聞いてくれた。昌守が混乱していて言葉がわからないときも、松崎医師は私が言いそうな事を予測して話してくれた。松崎医師は二重にも三重にも昌守が話そうとしている内容の確認をした。松崎医師が昌守から納得するような情報を得られたとき、今度は松崎医師から話をした。
「おそらく、死語数時間は経過していると思います。もしここで、私がもうすぐ来られる息子さんから書類を頂いたとしても、私は岸坂さんの診察をする事は出来ません。残念ながら出来ないのです。法律では生前の状態で診察をしていれば、死亡確認をして死亡診断書を書くことが出来ます。そうすれば在宅で死を迎えられる事が出来るのですが、岸坂さんは生前に診察をしていたという事実が無い限り、残念ながら死亡確認をする事は出来ません。」
電話の向こう側にいる松崎医師は悔しそうに話していた。そして、こう付け足した。
「実はあなたから話を頂いたときに、私が病院に勤めていたときの事を思い出しました。その時に苦い思いをし、それで在宅で診ていく道を選んだのです。その時、担当していた患者さんは家での死を希望していました。家族もそれを望んでいたのです。どうにか在宅で診てもらえる医師を探したのですが、当時はまだそうした考えがあまり浸透していなかったのでしょう。最終的には数人候補の医師が見つかったのですが、今はいっぱいで引き受けられないと言われました。
ならば自分がと思い、上司に交渉をしたのですが、病院側はそうした仕事は病院の仕事ではないと切り離されました。そうして行き場を失った患者さんは病院で息を引き取ったのです。
そして、恐らく偶然は重なるのでしょう。その患者様の名字は岸坂という女性でした。病名が同じなのではっきりと思い出しました。時期からしてもおそらく岸坂光一さんの奥様だと思われます。まさか・・・、夫婦揃って同じ病気になるなんて・・・・。」
松崎医師は下の名前までは覚えてなかった。しかし病名まで一緒であるということは、岸坂光一の妻で間違いないと思った。
「これからその詳細な情報と家族である息子がこちらに来るので、そこではっきりわかると思います。当時はとても小さかったので顔でわかるかどうか自信がありませんが。」
昌守は少し混乱していた。まさか同じ医師にお願いをしていたとは思わなかった。
「今の状況からすると、当時を振り返って話している場合ではないので、息子さんが来たらすぐにそちらに駆けつけるようお話ししておきます。
ただし、医療従事者という観点から話せば、あなたはすぐに救急車を呼ばなければなりません。これはあなたのためを思って話します。すぐに救急車を呼んだ方がいいでしょう。法的にはまだ岸坂さんは生きているのです。それに対し、救命処置を怠ることは医療従事者としてあってはならないことです。」
昌守は動揺した。せめて息子に会わせてからでも遅くはないのではないかと松崎医師に話した。すると松崎医師は冷静に話し始めた。
「そこには警察が必ず入ります。警察が入るということは殺人の疑いがあるかどうかが一番の理由になるのです。時間が長くなればなるほど、そこで何をしていたのか聞かれます。そしてどうして早く救急車を呼ばなかったのかも聞かれることでしょう。息子を待っていたという理由は、救急救命の観点からすると異なります。私に電話をしているという事実がある以上なおさらでしょう。警察であれば電話の履歴を調べることも必要であればするかもしれませんからね。」
松崎医師は間を置いてゆっくり丁寧に昌守に聞かせるように話した。
「お気持ちはわかります。私もすごく残念だ。でも私たちは個人で動いているのではない。法律があり、そのなかで国家資格というものを与えられ、特別に許可されて働いている。つまり、社会に認められて役割を与えられていると共に、別の角度から言えば社会のルールに従って動かなければならないという事でもあるのです。
たとえそれが状況によって間違っていたとしても、あなたが絶対に違うと思ったとしても、法律に背くということは私たちに与えられた国家資格を否定することに繋がります。」
松崎医師の言葉は昌守の身に染みていった。その通りだと思っていた。
「とにかく、あなたのためです。すぐに救急車を呼びなさい。」
昌守はゆっくり電話をきった。松崎医師に色々言われたが、やはり、すぐに救急車を呼ぶ事は出来なかった。救急車を呼べば全てが終わる様な気がしていた。光一の望み一つも叶えられない事が悔しくなった。昌守は訪問リハビリを始めて、こんなにも苦しい思いをする事はなかった。一人のために、こんなにも気持ちが入ってしまうことはなかった。それでも昌守は理学療法士という国家資格で今、光一宅に訪問している事には間違いなかった。その事は松崎医師が言うように医学的に冷静な判断をしなければならないという事もよく理解できているつもりだった。
昌守は考え始めた。岸坂家という家庭の中に入り、家庭の事情までも入り込んで、そして今は家庭関係にまで入り込んでしまっている。そういう事は理学療法士として正しい行為をしているのだろうか。昌守は今までとんでもない過ちをし、訪問リハビリという業務をしていたのだろうか。強いて言うのであれば、入り込みすぎる事は間違いなのではないだろうか。
昌守は今まで自分がしてきた事に対して後悔し始めた。過ちをこれ以上してはいけないのだと思い始めた。考えて、考えて、そして考えた結果、自分はこの場にいてはいけない人間なのではないかと思うようになっていた。
【37】
昌守は電話の前で動けずにいた。昌守の頭の中には別の考えが浮かんでしまっていた。それを自分で確認するように声を出して独り言を言い始めた。
「どうして自分は光一さんのためにここまでしているのだろう。自分はここに来て、リハビリをするためにここに来たんだ。復職を目指し、色々な事をしてきた。しかし病魔には勝てなかった・・・・。どうしようもなかった・・・。だからもう、リハビリを断ろうとしていたんだ。
そうだ・・・。そうだった・・・。僕はリハビリをするためにここに来たんだ・・・。でも、思い返せば光一さんが退職願を出そうとしたところから狂ったんだ。自分がそこから光一さんの私生活に入り込んでしまったんだ。だから・・・・だからそこからリハビリが狂い始めたんだ。
そうだ・・・。そこからおかしくなったんだ・・・。僕はただの理学療法士だ・・・。リハビリさえすればよかったんだ・・・。もう、十分だよ・・・。ねぇ・・・。光一さん・・・。僕はもう十分頑張ったよ・・・。もういいんだよね・・・。」
昌守は自分に問いただすように一つ一つ確認し、そして頷いていた。一つ一つ、自分自身の迷っていた気持ちを整理していた。そして決断をした。
「帰ろう。自分はここにいてはいけない。これは自分の仕事ではないんだ。松崎医師がいうように、自分は国家資格を得た人間なのだ。法的に縛られて業務を行うのが正解なのだ。だからこれは自分の業務ではない。今の状況は仕事ではない。だから、この場にいてはいけないんだ。」
そして光一は、その場を去ろうと玄関へ歩き出した。玄関まで行き、昌守が靴を履いた。そして外の出ようとしたとき、靴棚のそばに一通の手紙が置いてあるのに気付いた。昌守宛の手紙だった。
昌守は外に出るのを躊躇い、その手紙の封を開けた。そして中の手紙を読み始めた。
「細田昌守様
先日、お手紙を郵送させていただき、読んでいただけたら今日の内容はわかると思います。あまり、悠長な文章を書くことが出来ないことをお断りさせて下さい。
昨日の夜に父の姿を見に行きました。その時、様子がいつもと違う印象があったので気になり、手紙を書きました。声をかけようか迷いましたが、やはりどうしても声を掛けることが出来ませんでした。
細田先生。父をよろしくお願いします。明日、終わり次第、向かいます。
息子 孝より」
短い文章でかかれた一枚の手紙だった。急いで書いた様子がわかるような文字だった。即座に書いたようすが目に浮かんだ。昌守は帰ろうとしていた自分をもう一度問いかけた。このまま帰ってよいものだろうか。本当に、このままで良いものなのだろうか。昌守は自分の靴を見た。まだ踵が靴の中に入っていなかった。入っていないのであれば、もう一度靴を脱いでも同じことではないか。そう理屈をつけた。靴を脱ぎ、再び光一の所へ近づいていった。
昌守は時計を見た。もう、昼食をする約束の時間は十分に過ぎていた。光一を目の前にしてもう一度顔に手を触れた。冷たく、ぬくもりは感じなかった。昌守は1回、2回と頷いた。そして携帯電話をポケットから取り出し、「1」「1」「9」と押した。そのままその場に座り、時間が過ぎるのを待っていた。
【38】
どれくらい時間が経っただろうか。呼び出してから5分ほどで来るのが通常であるが、その時の昌守にはあまりにも長い時間に思えた。人工呼吸をしなければいけないという頭もあったが行わずにいた。精神的にも肉体的にも疲労しきってしまっていた。光一の顔を見ながら光一の髪型を直していた。出来るだけきれいな格好にして上げたかった。いつものように体を拭こうと思い、温かいタオルを用意してきた。しかし、あまり時間もないと考え、顔だけふいて終わった。昌守の手からはタオルを通して冷たい肌の感触が手のひら全体から伝わっていた。
救急車のサイレンの音が聞こえてきた。その音は次第に近づき、光一の家の前で止まった。昌守は外に出て救急隊員に場所を教えた。救急隊は落ち着いた対応で光一を観察した。救急隊は蘇生が困難な事を確認した。しかし、その場では死亡診断が不可能なため、救急隊の判断で光一は救急車に運ばれていった。
光一はベッドから離れ、ストレッチャーへと移された。今日乗るはずだったリクライニングの車椅子はむなしく救急隊に退かされて、光一は車いすを素通りしていった。
「ご家族の方ですか?」
救急隊員が昌守に質問をした。昌守は首を横に振った。救急隊員から同乗できるかとどうか聞かれた。昌守は頷き、同乗する準備をするために光一の玄関の鍵を閉めた。そして救急車に乗ろうとした瞬間、息を切らしながら走ってくる一人の青年が見えた。
青年は昌守と身長が同じくらいだった。清潔な印象を与えるシャツとジーンズをまとっていた。髪型も、長くもなく、短くもない。ただ汗で前髪は濡れていたのでいつもの髪型とは違うのだろう。それでも清潔な印象を十分に与えてくれる姿だった。
その青年は昌守から10mくらい離れていたところで止まった。昌守からは顔の形がはっきりと見えた。どことなく、光一の面影があった。その青年は救急車と昌守、そして救急隊を見て状況を理解したのだろう。救急隊もその場の空気を察したのだろうか。それとも光一と似ていることに気付いたのだろうか。その青年に向かい、
「もしかして、あなたがご家族の方ですか?」
と質問をした。その青年はゆっくりと頷いた。昌守はその光景を見て、その青年が岸坂孝である事と確信した。確信すると同時に、同窓会で久しぶりに会うような不思議な感覚になった。
(やっと・・・・会えた・・・。)
昌守は肩の力が抜けていくのがわかった。責任感から逃れられる気分なのだろうか。
本当は、昌守は孝に色々と話したかった。しかし、救急隊は岸坂孝に急いで同乗するように伝えた。孝もそれを聞き、慌てて救急車に乗り込もうとした。その時間の間に昌守と孝が話す時間は無かった。孝は救急車に乗ろうとした瞬間、立ち止まって昌守の方を向いた。まるで軍隊から習ったかのように、直立し、昌守に向かって深々とお辞儀をした。頭を下げた時間はどれくらいだっただろうか。昌守もその姿を見て同じようにお辞儀をした。顔を上げ、視界には孝の顔が正面からはっきりと見えた。目線も合った。昌守は頷いた。孝も頷いた。孝はそのまま救急車に乗っていった。
昌守は救急車に乗らなかった。後で考えれば乗っても良かったのかもしれなかった。ただ、最期に二人の空間を邪魔したくはなかった。あの人の生き方はきっと、最期はこういう時間が欲しかったに違いないと思ったから。
あの人の生き方