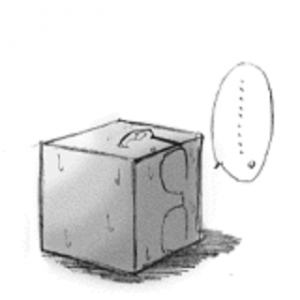謡(うたい)
原案 田代 裕(未完のX680x0用同人サウンドノベル『謡』より)
※ この物語はフィクションです。実在の人物、地名、団体等とは一切関係ありません。作中の猿楽『紫桜(しざくら)』も架空の演目です。
そもそも、花と云ふに、萬木千草において、四季(折節)に咲く物なれば、その時を得て珍しき故に、翫ぶなり。申楽も、人の心に珍しきと知る所、即ち面白き心なり。花と、面白きと、珍しきと、これ三つは同じ心なり。いづれの花か散らで残るべき。散る故によりて、咲く比あれば、珍しきなり。能も住する所なきを、先づ、花と知るべし。
──世阿弥『風姿花伝』花傳第七 別紙口傳より
プロローグ
『伝統の猿楽継承──岩代市錦美町深津地区』
岩代市錦美町で七年ぶりの奉納となる猿楽「紫桜」の合同練習が二八日、錦美町の深津公民館で行われた。この日は宇侘川猿楽保存会の有志二〇人あまりが集まった。奉納される「紫桜」は戦国時代の沓掛合戦に題材を採ったもので、合戦で父を亡くした姫の悲劇を描いた物語。演じる座によって異なる物語が伝わるという。保存会代表の松岡寄与志さん(六九)は、「神楽が盛んな中国山地で、猿楽が民間伝承されているのはここだけではないか。非常に珍しい伝統芸能なので、絶やさないように努力していきたい」と話していた。猿楽「紫桜」は本年一〇月一八日、一九日の両夜、錦美町深津地区の宇侘八幡宮で奉納される予定。
(二〇一×年四月二九日付 西國新聞朝刊地方面より)
第一章 桐葉荘(とうようそう) 〈一〉
終点を告げるアナウンスが流れ始めたと思ったら、列車はまたトンネルの中に入った。
これで何本目だろうか。乗ってからしばらくは数えていたが、あまりに本数が多いので途中で数えるのをやめてしまった。
始発駅を出てから一時間と少々、一両だけのディーゼルカーは川を遡るようにゆるゆると山間をぬって進んできた。
単線だから、途中で行き違いの列車を待ちながらの、のんびりした旅だ。
本当に来たんだな、と僕は改めて感じた。
偏差値だけで決めた広島の大学に入ってからほぼ一年半、僕はこれといって特にやりたいことも持たないまま過ごしてきた。
もともと何か目指すものなんてなかったし、文系理系の選択にしても数学が苦手だったから文系を選択しただけ。受験はそれなりにがんばったけれど、結局はこれも「何となく」で決めてしまった。
だから学業に打ち込んできたわけでもないし、サークルに入って直接の友人関係をひろげてきたわけでもない。講義をさぼったりすることはなかったが、だからといって決して熱心な学生ではなかったと、自分でも思う。
そんな僕が、講義を一週間近くほったらかして旅に出ることにした。こんなことは今までになかったことだ。
暗くなった車窓に、車内の蛍光灯に照らされた僕のぼんやりした顔が映っている。
モラトリアムのモラトリアムだよな、と僕は内心苦笑した。
トンネルを抜けたら、列車はすぐさま鉄橋を渡る。
川面が秋の柔らかな日差しを受けてきらめいている。紅葉にはまだ少し早いが、景色の輪郭がくっきりとしていて、秋の冴えた空気を感じさせる。
これから降り立つ町の景色も見えた。山に囲まれた小さな町だ。
列車は鉄橋を渡り終えると、一本しかないホームにゆっくりと入って停まった。数人しかいない乗客が降りていく。みな高齢者ばかり。僕もそれに続いてホームに降りた。
第三セクター山代鉄道清流錦美川線の終点・尋瀬駅は、岩代市の北東部・錦美町の中心部にある。
平成の大合併で他の五町一村とともに岩代市と合併した錦美町は、中国山地西部に源流を持つ県内屈指の清流・錦美川流域に位置し、いくつかの限界集落を抱える過疎の町である──とネットで調べて知った。
ほんの少し前まで、僕はこの町の存在すら知らなかった。その僕が、今こうしてこの町に立っている。考えてみると不思議なことだ。
僕はコンクリートの階段を下りて改札で駅員に切符を渡した。
狭い駅舎の左側には土産物を販売するスペースがあり、割烹着姿の店番のおばさんがヒマそうにしている。年齢は五〇代後半から六〇代ぐらいで、白髪交じりの髪を素気なく後ろで束ねた、小太りの女性だ。
「あのー、深津峡温泉まではどれぐらいかかりますか?」
「あれ、今バスが出たとこじゃが!」
僕が尋ねると、彼女はすっとんきょうな大声を上げた。
「あーあ、今日は乗る人おらんよ言うたとこじゃのに、あんたがおったんかいね!」
目的地の深津峡まで一日数本のバスが通っているのは事前に調べて知っていたが、間が悪いことに乗りそこねてしまったらしい。
「歩いたらどれくらいかかります?」
「わや(無茶)言うちゃいけん、一時間半はかかるいね。やめちょきんさい」
おばさんがあまりに大声でしゃべるので、駅員がなにごとかとこっちを見ている。なんだか恥ずかしい。
「青ちゃん、青ちゃん!」
おばさんは僕を置いたまま外に出て誰かを大声で呼ぶ。
僕もそれに続いて駅舎を出た。
木曜日の午後ということもあって、駅前はひっそりと静まり返っている。住宅地の中、こぢんまりとした広場があり、白色のタクシーが一台だけ停まっている。左手に色褪せた中華そばののぼりが立った古びた食堂が一軒あるだけで、商店らしきものはほかに見当たらない。
キジバトが二羽、何かをついばみながらうろうろとしている。
まるで時の流れから取り残されたような、本当に小さな町だ。
おばさんはタクシーの運転手に何やら話している。
運転席からおじさんが顔を出して僕に問う。
「あんた、深津峡温泉まで行くんて?」
「はあ、バスに乗りそこねたので歩いていこうと思うんですが」
「あー、あんたぁ若いけえ行かれんこたぁなかろうが、知らん土地で歩くんは結構えらい(きつい)よ」
なんだか人のよさそうな運転手のおじさんは年齢が六十歳くらい、見事に禿げ上がった頭に太陽が反射してまぶしい。丸顔にかけた黒縁眼鏡の奥から小さな目がこっちを見ている。
夏休みにバイトである程度貯めたとはいえ、所詮は学生なので金があるわけではない、できればムダづかいは避けたい。一時間半ならまだ明るいうちに着くことができそうだ。
おばさんはにこやかに僕の荷物を引っ張る。
「まぁま、お兄さん、遠慮せんと乗っていきんさい、うちがサービスさすけえ。な、青ちゃん」
「おいおい、勝手に決めなや」
「ええじゃないの、ほれ、お兄さん乗って乗って!」
「じゃあ、お願いします」
結局おばさんになかば押し込まれるように、僕はタクシーに乗った。
運転手は苦笑いをしながら車をスタートさせた。
「やれやれじゃね……おたく学生さん?」
「そうです」
「若い人がわざわざここに来るたあ珍しい、どうしたんかね?」
タクシーメーターに運転手氏名が掲げられている。青笹繁徳というらしい。見た目の雰囲気とつり合わない重々しい名前がなんだかおかしい。
「七年に一度の猿楽を観に来たんですよ」
「ほおー、よう知っちょるねえ!」
青笹さんが感心したような声を上げた。
「地元でもえっと(よく)知らん者もおるのにから、大したもんじゃ」
「春ごろに新聞に練習の記事が出たのを見たんです」
「それでわざに? あんたもなかなか酔狂じゃねえ」
青笹さんは笑いながら言った。
タクシーは昔商店街だったと思われる通りを抜けて、先ほど渡った列車の鉄橋の下をくぐり、川沿いを進んでいく。両側に鋭く切り立った山肌が迫ってくるようだ。
「ま、日本中どこを探してもここでしか観られん、珍しい猿楽じゃ。わしも出るんよ、地謡方でな」
青笹さんはうれしそうに続けた。
猿楽『紫桜』は、七年に一度だけ、地元の有志によって宇侘八幡宮に奉納される伝統芸能だ。
猿楽というのはいわゆる能楽のことだが、能楽と呼ばれるようになったのは明治時代になってかららしい。ここでは旧来からの呼び名がそのまま残っているようだ。
そもそも中国山地西部は神楽舞が盛んで、秋になるとあちらこちらで上演されている。
実際、大学で知り合った地元の山間部出身の同級生は、小学校の頃から神楽の上演者だったといい、笛の音を聞くと無条件で血が騒ぐと言っていた。去年の秋、一度だけ彼につきあって神楽を観に行ったことがあるが、きらびやかな衣装で激しい動きの舞いを展開し、演目によっては花火を使った演出を取り入れたりしていて、実際にその場で観ると興奮した。
しかし、ここ錦美町では勇壮な神楽ではなく、幽玄な猿楽が上演されるのだ。
「なんか気になったんですよね」
「ふーん、まあなんにせよ関心持ってもらうっちゅうのは、悪ぃ気はせんね、演る側の人間としちゃあ」
タクシーはいったん国道に出て道の駅のそばを通り過ぎると、錦美川の支流・宇侘川沿いを遡っていく。
「ここいらは、山と川のほかは何もないようなとこじゃからなあ」
タクシーの窓からは青々とした山並みと、傾き始めた陽を受けて光るせせらぎが見えた。V字に刻まれた斜面が折りたたまれるように延々と続いている。
道端の観光看板に「山紫水明の里」などという言葉が見えたが、実際に暮らすとなると苦労も多いのだろう。
「あんた、│泊まりはどこにしたんね?」
「えっと、桐葉荘というところです」
「お、桐島のネンコーさんとこか。あすこはええ宿じゃ」
「せっかくない金使うんですから、ちょっとは背伸びしようと思って」
「はは、そらええ。命の洗濯っちゅうやつじゃな。桐葉荘のネンコーさんにはわしもずいぶん世話んなってのう、恩返しもようせん(できない)うちに亡うなってしもうたけえ、わしゃあ、あすこの女将さんにゃあ頭が上がらんのんじゃ」
「ネンコーさんって、もう亡くなられたんですか?」
「はあ五年になるかねえ、まだ若うてから、よいよ惜しいことじゃった。これから、いうところじゃったのに」
青笹さんは心から残念そうにつぶやいた。
タクシーは民家が立ち並ぶ集落を抜けて県道に入り、川を右手に見ながら奥へと進んでいく。刈り取りの終わった田んぼの中を緩やかなカーブが続き、右に左に巧みにハンドルを切りながら彼は話を続けた。
「ネンコーさんには娘が三人おってな、みな微妙な年頃いね。わしじゃったら死んでも死にきれんな」
「ネンコーさんの娘さんって何歳ぐらいなんですか」
「一番下の子が今年高校に入った言うたかの。残された女将さんもあれこれ苦労してじゃが、そがあな様子はいっそも見せんけえ、大したもんいね」
右手に見えている川が大きく右に弧を描くのに合わせて道路もカーブし、僕の体も遠心力で左に振られたと思ったらすぐに逆のカーブで右に振られた。
「──とか言いよったら着いたのう」
そうつぶやくと青笹さんはボタンを押してメーターを「精算」にした。
右側には深津郷温泉宇侘川パレスホテルという看板の奥に大きな建物が見えている。あらかじめ調べたときに桐葉荘とどちらにしようか迷った宿だ。
「桐葉荘はもうちょい入ったとこじゃが、ここからは一応サービスな」
タクシーは右手の細い山道に入った。
急な斜面をぐいぐいと登り、左右の林をかき分けるようにして進んだと思ったら、少し空間が開け、車は停まった。ちょうど木造の門の前だ。
「じゃあ学生さん、またの」
精算を終えて僕が降りると、青笹さんが右手を上げてあいさつしたので、僕も会釈を返した。
タクシーを降りると、ひんやりとした空気が僕を包んだ。尋瀬駅で降りた時よりもさらに少しだけ気温が低いようだ。
深く息を吸い込むと、すがすがしい気持ちになる。
桐葉荘は緑に囲まれた、静かなたたずまいの宿だった。
門をくぐると、苔むした池を中心とした和庭園の向こうから、木造黒瓦葺き平屋建てのこぢんまりとした建物が僕を出迎えた。築年数はそれなりにありそうで、歴史を感じさせる建物だが、大がかりなリノベーションがされているらしく清潔感が感じられる。玄関の脇には若葉色に「桐葉荘」という筆文字が白抜きされた日よけが掛けられている。
建物のすぐ右手に斜面が迫り、時おり鳥の声が聞こえるぐらいのとても静かな場所だ。
「まあ、遠いところようおいでました。ご予約の、森崎浩司様ですね?」
宿の玄関から藤色(淡い青味の紫色)の和服姿の小柄な女性が迎えに出てきた。
年のころ三十過ぎぐらいだろうか、髪を後ろできちっとまとめ、上品な印象を発しながらも黒目がちな大きな目がくるくるとよく動く、チャーミングな女性だ。
「あんまり山奥でからびっくりされちゃったでしょう?」
「いえ、なんか落ち着きますよ」
「ふふ、山と川しかないところですよ」
女性が朗らかな声で笑いながら青笹さんと同じことを言った。
「桐葉荘の女将、桐島蘭と申します。本日は遠いところ本当にようおいでました」
女将さんが深々と一礼した。
「こちらこそよろしくお願いします」
そういうのに慣れていない僕は、少しどぎまぎしながら会釈を返した。
「では、ご案内いたします」
そう言うと、女将さんは自然な所作で僕の荷物を持つと、玄関に僕を招き入れた。
宿帳の記入が済んで案内された部屋は、『桜の間』と名付けられた十二畳の和室だった。
桐葉荘には四部屋しかなく、それぞれ少しずつ造作が異なるのだと、女将さんが説明してくれた。
落ち着いた内装で、床の間には掛け軸が飾られ、一輪差しに花が活けられている。窓からは石庭を挟んでまだ青々とした木々が見え、その向こうには峡谷の山並みとよく晴れた空を見渡すことができる。僕一人で使うにはもったいない部屋だ。
「紅葉のシーズンには窓からよう見えますよ。このあたりは時期が遅いので、半月ぐらい先になりますけどね」
女将さんがそう言いながら僕の荷物を置いてくれた。
「でも、この時期にこんな若い方の、それもおひとりのお客様なんてめったにないです」
「猿楽『紫桜』を観に来たんです」
「ああ、そうでしたか! 『紫桜』、私も一回だけ観たことあります。哀しいお話なんですよね。それにしても森崎様、ようご存知ですね」
「西國新聞で読んだんですよ。なんか珍しいなと思って、一度観てみたくなったんです」
「ふふ、なかなか奇特な方ですね、そんなに有名じゃないのにわざわざ観に来られるなんて。でも、確かに珍しいらしいんですよ。おんなじ主人公なのに、別々の結末になるなんですから」
女将さんはそう言いながらお茶を淹れてくれた。
そういえば、タクシーの青笹さんによれば、女将さんはネンコーさんの奥さんで、ネンコーさん亡きあと女手一つで三人の娘さんを育てているはずだが、今僕の目の前にいる女性は、とてもそんな風には見えない。
「あの、とても失礼なんですけど……」
僕はおずおずと訊いてみた。
「女将さんって、今おいくつなんですか?」
女性に年齢の話をするのはちょっと気が引けるのだが、好奇心の方が勝ってしまった。
「はい?」
女将さんが少し怪訝な顔をした。やっぱりまずかっただろうか。
「あ、いやー、タクシーの運転手さんから色々と聞いて……高校生の娘さんがいらっしゃるとか」
僕が弁解めいた言葉を重ねると、女将さんはちょっとふくれた顔をする。
「あー、青ちゃんじゃね! まったくもう、あいかわらずおしゃべりなんじゃけえ!」
「すいません」
「別に秘密でもなんでもないんですよ。来月で四三歳になります」
「えー?!」
僕の驚いた顔を見て女将さんはいたずらっぽい笑顔を見せた。
「全然見えません」
正直な感想だ。
「よく言われます♪」
女将さんの声は小躍りしそうに弾んでいる。
「そうそう森崎様、お食事はいかがされますか? お部屋でも召し上がっていただけますが、お座敷をお薦めいたしますよ。お泊まりの他のお客様と交流していただけますし、いかがでしょうか?」
「じゃあ、そうします」
普段なら見ず知らずの人と一緒に食事をするのは少し気が引けるところだが、旅先の気安さから、いつもの僕なら絶対にしないような選択をした。
「お風呂は廊下をつきあたって右の手前でございます。当日は午前零時まで、翌朝は午前五時から十時までご利用いただけます。小さいですが、露天風呂もございますので、ぜひゆっくりとおくつろぎくださいませ」
女将さんはそう言うと一礼して部屋から出ていった。
「んー」
僕は声に出して背伸びをした。
お茶を一口すすってから、ふと思い出して荷物から 携帯電話を取り出してみると「圏外」の表示。今どき珍しいが、僕にとってはちょうどいいかもしれない。
僕はぱくんと音を立てて片手で携帯を閉じた。
夕食にはまだだいぶ早いし、風呂に入る気分でもなかった。
少し宿の周りを歩いてみよう、そう思いついて、僕は再び靴を履いた。
第一章 桐葉荘(とうようそう) 〈二〉
「あら、おでかけですか?」
女将さんが出かけようとする僕に気づいて声をかけてくれた。
「ちょっと近くを散歩してきます」
「ではお気をつけて。夕食は六時ごろになりますから、それまでにはお戻りください」
「ありがとうございます」
僕が玄関を出ると、それに驚いたヒヨドリがキーッキーッと鋭い鳴き声を上げながら飛び立っていった。木々の葉ずれの音がかすかに聞こえている。本当に静かな場所だ。
木々の間から、先ほどタクシーで通った県道がだいぶ下に見える。車だったのでよくわからなかったが、かなり上がっていたようだ。
ふと、僕は誰かの視線を感じた。
辺りを見回すと、いつからいたのか、少し離れた生垣の端に少女が立って、僕をじっと見つめていた。
僕は驚いてあやうく声を上げそうになった。
白い着物姿、色白な肌に腰まで届きそうな長くつややかな黒髪、感情が読み取れない能面のような顔立ち。なんだかこの世のものとは思えない雰囲気だ。
その無表情のせいで年齢がわかりにくいが、たぶん十代後半ぐらいだろう。
見つめる目の力が強く、吸い込まれてしまいそうだ。魅入られるように僕も彼女を見つめると、彼女はひとつまばたきをした。
「君は……?」
僕はおそるおそる声をかけたが、彼女は何も答えない。顔色一つ変えずに踵を返すと、生垣の陰に姿を消した。
少女の黒目がちな目は、少し女将さんに似ているような気がする。三人の娘さんの一人なのだろうか。
辺りはなにごともなかったかのようにひっそりと静まり返っていた。
僕はさっきタクシーで上がってきた急な坂道を歩いて下っていった。谷が深いため、日は既に斜面に隠れ始めている。
県道に出ると川のせせらぎが近くに聞こえる。
目の前には深津温泉郷宇侘川パレスホテルの看板がある。
ホテル、といってもこちらもそんなに大きな建物ではない。斜面を利用して建てられた変形三階建、黒い瓦葺の屋根が重厚な気配を醸し出している。
ここまで下りてくれば携帯もつながるようだ。
県道を宇侘川の上流に向かって少し歩いてみた。「深津峡入口」と大書された古いトタンの看板が、なんだか時代を感じさせる。
宇侘川は日本の清流百選にも選ばれたことがあり、温泉のある深津峡のほかにも、寂水峡・乙女淵など、いくつかの峡谷があり、決して有名ではないが、隠れた景勝地だ。
もっとも、僕が得た知識はすべてインターネットで見たものばかり。実際にこうして歩いてみると、なんだかとてもさびしい感じがする、などということはネットには載っていない。
女将さんもタクシーの青笹さんも「山と川しかない」と言っていたが、実際ここには他に何もなかった。温泉郷といっても、歓楽街があるわけでもなく、入浴施設は桐葉荘を入れて四軒だけ、そのうち宿泊できるのは桐葉荘と宇侘川パレスホテルの二軒だ。ネットで調べると最寄りのコンビニまでは直線距離で約一五キロ、スーパーも尋瀬駅の近くまで行かないとないから、一〇キロは離れている。
このあたりの人は一体どうやって生活しているんだろう、と思う。
僕が住んでいるアパートから一番近いコンビニまでは二〇〇メートルぐらいだし、スーパーだって一キロ以内にはある。一人暮らしにはコンビニは必須条件だ。コンビニのない暮らしなど僕には想像もつかない。
まあ、僕の暮らしなんて大学のキャンパスと自宅を自転車で往復する間にコンビニに立ち寄るぐらいでしかない。
そんな狭い世界に閉じ込められた気になったからこそ、僕は思い切って旅に出たんだ。
落ち葉に覆われた細い道を通って川のそばまで下りてみたら、深津峡の由緒を示す古い立て看板があったが、文字はほとんど消えかけていて読むことができない。川のそばには放棄されたあずまやが枯葉になかば埋もれかけている。
透明度の高い水が流れる苔むした岩場の周囲には桜の木が植えられていて、春には峡谷を彩るのだろうが、今は華やかさも感じられない。せせらぎの音だけがずっと続いている。
一体、僕は何のためにここに来たのだろう。
自分が孤独であることを確かめに来たような、ひどくみじめな気持ちになる。
空はまだ青いが、ほんのわずかな間にも日がどんどん落ちていくのがわかる。
少しずつ冷気が忍び寄ってくるのを感じ、僕は宿に戻ることにした。
桐葉荘のひかえめな木製の看板が掛かった入口から上り坂に入ると、少し先の方に自転車を押して歩いている制服姿の少女が見えた。
背中に大きなリュックサックを背負い、黒のブレザー、ひざ上に短くしたスカートに紺のハイソックスとローファー、セミロングの髪をまとめたポニーテールが左右に揺れている。いかにも「女子高生」、という感じの子だ。
僕が坂道を登ろうとしているのに気づくが早いか、彼女は大げさに手招きをしながら大声で僕を呼んだ。
「お兄さんお兄さん、うちとこのお客さんじゃろ? 早よ来て来て!」
僕がなにごとかと思いながらも彼女に近づくと、彼女は満面の笑みとともに自転車を押しつけてきた。
「なーなー、これ押して上がってくれん? ええじゃろ?」
僕がうんとも言わないうちに押しつけておいて勝手だなとちょっとムッとしながらも、僕は仕方なく自転車を押して上がることになった。
前かごにはついさっきまで彼女が背負っていたリュックが載っているのでずしりと重い。
「うちは果林。き・り・し・ま・か・り・ん。結果の果に林で、果林。お兄さん名前は?」
「森崎浩司だけど」
「コージさんか、へー、なんでうちとこ泊まろう思うたん? うちとこ、ぶち(すごく)不便じゃろ? 駅からは遠いし、ケータイも入らんし、こんな急坂上がらんといけんし。はあ、毎日ここ上がるだけでぶちせんない(面倒くさい)けえ、そりゃ足も太うなるいね、あはは」
こちらが答えるより先に果林ちゃんは方言で次から次へとまくし立てる。足が太いと言うが決してそんなことはなく、すらっとしたきれいな足だし、しかも上目づかいで見上げられると思わずドキッとするほどかわいい。
ただ、方言と合わせて出る大げさな身ぶり手ぶりのおかげで、なんだかコミカルな印象だ。
どうやら彼女が桐島家の一番下の娘さんらしい。
小柄な体格や朗らかな声、くるくるとよく動く大きな目は、女将さんに本当によく似ている。
「果林ちゃんは女将さんにそっくりだね」
「じゃろー? 似すぎとってこわいっちゃ。うちの母さん年齢不詳じゃろー? こないだうちが高校入学した時も、勝手にブレザー着てからコスプレしようとしちょったんじゃけえね! ちったぁ歳考えりゃあええのに! うちもそのうちあんなになるんかねー?」
けらけらとよく笑い、よくしゃべる明るい子だ。少々おしゃべりが過ぎるみたいだけど。
上り坂は結構きつく、僕は軽く汗をかき始めた。まだだいぶ登らなければいけないから息も切れそうだ。
「毎日この坂上り下りしてるの?」
「当たり前じゃあ? うちん家からどっか行こうと思うたら、絶対ここを通らんといけんのじゃもん、小学校ん時からずっとよ! ほんと、なんでこんなとこに住むかねえ、冬は雪がぶち積もるし」
果林ちゃんはそう言ってまた笑う。
「友達らあも、うちとこだけは絶対誰も来たがらんのよね。坂上がるんがえらい(疲れる)けえありえんとか言うて。毎日毎日上がりよるうちはどうなるんかっちゃ! もう、マジ腹立つー!」
果林ちゃんはものすごい勢いでしゃべりまくるが、僕はそろそろ息が切れてきた。背中に汗が伝うのを感じながら彼女を見ると、涼しい顔をしている。
「それにしても、よく、しゃべる、ねえ」
僕は切れ切れの息でやっとそれだけ返した。
「えー、いっそ(ぜんぜん)しゃべっちょらんよぉ!」
オーバーなリアクションが返ってくる。
「体は疲れても口だけは疲れんのよねー、なんでかねー?」
僕はもう返事を返す気力もなかった。
肩で息をしながらどうにか坂を上り続けると、左に入る目立たない脇道があった。
「こっちこっち」
果林ちゃんに導かれるままにそちらに入ると、木立の中に隠れるように平屋建ての家が現れた。手前にカーポートがあり、ボンネットに若葉色で『桐葉荘』のロゴが入った白い流線型のミニバンが停まっている。
「自転車はそこに置いちょって。でも、まさかホントに押して上がってくれるとは思わんかった、ありがとー」
果林ちゃんは「が」にアクセントをつけてお礼を言うと、ぴょこんとお辞儀をした。ポニーテールがやっぱりぴょこんと揺れる。
僕は肩で息をし、汗まみれのまま何も言えずに突っ立っているしかなかった。
「荷物置いてくるけえ、ちょっとそこで待っちょって」
彼女は制服のスカートをふわりと翻すと、跳ねるように家の方へ消えた。
待つも何もしばらく動けません、とは声にならなかった。
しかし、なんだか笑える。頬がゆるんでいるのが自分でもわかる。
四~五歳も年下の女の子にいいようにこき使われて汗だくになっている自分が、なぜだか妙にうれしかった。
冷たい空気が肌に心地いい。
少し待っていると、ようやく息も落ち着いてきた。
「お・待・たー♪」
制服のままポニーテールをほどいて、果林ちゃんが戻ってきた。
「近道で案内するけえ、ついてきて」
果林ちゃんは楽しそうにぴょこぴょこと弾むように歩く。その後ろ姿がやっぱりなんだかおかしくて、僕はついにやにやしてしまう。
家の裏手に回ると、コンクリート打ちっぱなしの簡単な階段が上に続いていた。僕は果林ちゃんに続いて階段を上る。
木立から落ちた葉が階段を覆っていて、踏むたびにカサカサと乾いた音を立てる。
「なーなー、ユージさんて大学生?」
「浩司! 今わざと間違えたろ!」
「あー、ごめんごめん。うち、人の名前覚えるん苦手なんよねー」
「今大学二年だよ。ちょっと休んで猿楽を観に来たんだ」
「へー、七年に一度っていうアレ? えっと(そんなに)有名じゃなあのに? コージさんてマニアックぅ」
「マニアックで悪いかよ」
「あはは、怒った怒った」
階段をのぼりながら、いつの間にか僕は果林ちゃんと普通に会話していることに気づいた。まともに女の子とつきあったこともない僕が? 自分で自分に驚く。
「果林ちゃんは観たことあるの、猿楽?」
「あー、どうなんじゃろ、観たんかな? 七年前はまだ子どもじゃったから、ようわからんわ」
「女将さんは哀しい話だって言ってたけど」
「ふーん、そうなんかねえ?」
果林ちゃんはまるで興味なさそうだ。
まあ、郷土芸能なんてそんなものなのかもしれない。珍しがるのは僕みたいなよそ者ばかりだろう。
階段は二回折れ曲がって斜面を登り、桐葉荘の門前に出た。出かけた時とくらべると、だいぶ日が落ちている。
ふと、出がけに会った白い着物の少女のことを思い出した。そういえば彼女の背恰好はちょうど果林ちゃんと同じぐらいだ。
「そういえば、さっきそこで不思議な女の子を見たよ」
「え、どこでどこで?」
果林ちゃんが聞き返す。
「そこ。生垣の端のとこに立ってた」
「もしかして、白い着物じゃった?」
「そうそう、白い着物で、長い黒髪の、無表情な子」
「えー、コージさん、きぃねえちゃんに会うたんじゃあ!」
果林ちゃんが目を丸くする。
「きぃねえちゃん?」
「うちの年子の姉ちゃん。桔梗って名前じゃけえ、こまい(ちいさい)頃からきぃねえちゃんて言うとるんよ。きぃねえちゃん、めったと外に出らんのにから、どうしたんじゃろ? コージさん、ぶちラッキーじゃねえ!」
果林ちゃんが妙に興奮している。
「桔梗さんて家からあまり出ないの?」
「うん、それにいっそしゃべらんくなったんよ。母さんとみず姉が心配してからお医者に診したり、カウンセラーに連れてったりしたけど、いけんじゃった。うちもいろいろ話しかけるんじゃけどね。前はうちとぶち仲良しじゃったのに……」
果林ちゃんは少し憂いを帯びた表情を見せた。
僕はかける言葉がなくて、黙るほかなくなる。
なんだか気づまりになってちょっと彼女から視線を外すと、左手奥にある駐車スペースにシルバーのSUVが一台停まっているのに気づいた。確か僕が出かけたときにはなかったはずだ。前部ドアに「Free Photographer Yusuke S.」という文字をデザインしたけばけばしいステッカーが貼られている。
果林ちゃんも車に気づいたようだ。
「あ、夕介来ちょるじゃあ!」
「ユースケ?」
「うちとこの常連。何がええんか知らんけど、半年にいっぺんは来よるよ。コージさんとおんなじ、マニアックなモノズキさん♪」
果林ちゃんがにまにましながらそう言った。
第一章 桐葉荘(とうようそう) 〈三〉
玄関を入ると、帳場の前にあるロビーで女将さんと三十代半ばぐらいの男が立ち話をしていた。
少し癖のある長髪、細身で背が高く、タイトなデニムに柄物のTシャツ、黒のレザージャケットを羽織っていて、悔しいことにこれがなかなかのイケメンだ。整えられたあごひげがこれまたイラッとさせる。
女将さんがこちらに気づいて声をかけてくれた。
「あ、森崎様おかえりなさいませ──て、なんで果林までおるんかね?」
「コージさんにチャリ押してもろうたんよー」
「あんた、またお客様にそんなことさしてから……申し訳ございません、ご迷惑でしたでしょう?」
「いえ、いい運動でしたよ」
「どーせ果林にいいようにこき使われたんだろ?」
僕が女将さんと話しているところにいきなり男の方が話に割り込んできた。
ぶしつけな奴だとちょっとムッとしてそいつをにらむと、そいつは左手の親指をデニムのポケットにつっこんで斜に構え、にやにやしながら僕のことを眺めている。
「果林は天然ものの小悪魔女だからな、ぼんやりしてると魂抜かれるぞ」
そいつはくくっと笑いながら僕を小ばかにしたような目で見下ろしてくる。
「うちは小悪魔じゃないよぉ!」
果林ちゃんは口をとがらせて反論した。
「本人が気づいてないからこそ天然ものなのさ。小悪魔だなんて自称してるヤツはみんな養殖ものだ」
男はあいかわらずにやにやしながら果林ちゃんに言った。なれなれしい奴だ。
果林ちゃんは納得がいかないらしく、何やらぶつぶつ言いながら腕を組んでむくれているが、その様子も確かにかわいい。
魂抜かれる、というのも本当かもしれないと一瞬思う……いやいや、そういう問題じゃない。
「あのー、どちらさん?」
男があまりになれなれしいものだからこちらもつい無愛想な言い方をしてしまう。
「俺は妹尾夕介。フリーの写真家だ」
夕介と名乗った男は片手で無造作に名刺を差し出してきた。車に貼ってあったのと同じロゴが印刷された、派手な名刺だ。
あまり趣味がいいとは思えない。どうひかえめに見ても胡散くささ全開だ。
「ここにはずいぶん長いこと世話になってるんでね、何かわからないことがあったらまず俺に聞いてくれ」
いちいち言うことがむかつく。正直、一番苦手なタイプ。
「そういうわけで、ひとつヨロシク」
「森崎浩司です。こちらこそどうも」
夕介が握手を求めてきたので、しかたなく僕もそれに応じた。
夕介はガタイもでかいが態度はそれ以上にでかいな、と僕は内心苦々しく思う。
「なーなー、夕介は今日お座敷でご飯にするんじゃろ?」
「ああ、もちろん。いつもそうしてるだろ?」
それを聞いて、僕は自分の軽はずみな選択を後悔した。晩飯までこんなイヤな男と一緒になるのかと思うと、どんよりとした気持ちになる。
「コージさんも?」
「そうだよ」
僕はできるだけ本音を顔に出さないように努めながら答えた。
「じゃったらうちらも一緒に食べたーい。なー、母さんええじゃろ?」
果林ちゃんは甘えた声で女将さんにねだる。
「もう、果林! お客様に失礼でしょうがね!」
「えー、じゃって夕介だけが泊まる時はいつもそうしよるじゃあ? 何でだめなん? コージさんがおるけえ?」
「もう、ええかげんにしんさい。だめなものはだめ!」
女将さんは果林ちゃんを軽くにらんだが、僕からしてみれば地獄に仏だ。
「女将さん、まあいいじゃないですか。にぎやかな方が楽しいですから。僕からもお願いします」
本当は夕介とサシになるのがいやだからだけど、果林ちゃんが一緒なら確かに楽しくなりそうだ。
「よろしいんですか、森崎様?」
よろしいも何も大歓迎です、とまでは言わなかったが、僕は大きくうなずいた。
夕介も何も言わずにニタニタしている。つくづくいけすかない奴だ。
「しょうがない、じゃったら果林、支度を手伝いんさい」
「はーい」
「水菜にもメールしときんさいよ、あの子すぐはぶてる(拗ねる)から」
「うん!」
果林ちゃんはさっそく帳場のパソコンに向かってメールを打ち始めた。そうか、携帯が入らないからか。
「なーなー母さん、コージさんて、きぃねえちゃんに会うたんて」
パソコンの画面をにらみながら果林ちゃんが女将さんに告げる。
「桔梗に? 本当ですか?」
「ええ、さっき出るときに、そこで」
「へえ、どういうめぐりあわせですかねえ!」
僕がそう言うと、女将さんは少し驚いた顔を見せた。
「ふん、そんなこともあるんだな」
夕介は腕を組んで左手であごひげを撫でながら、珍獣でも見るような目つきで僕の方を見ている。
「びっくりされんじゃったですか、森崎さん。白い着物じゃったでしょう?」
「ええ、ちょっと驚きました」
「桔梗はうちの次女ですが、主人が亡くなった後、ものを言わんようになってしまって。ずっとあの白い長襦袢で過ごしているんです。医者によると、声が出なくなるある種の失声症じゃないかって言うんですが、何が原因なのかは結局わからんかったんです」
まずいことに触れたかな、と思ったが、女将さんは事情を淡々と話してくれた。
「ちょっと変わった子に見えるかもわかりませんが、もしまた見かけたら、話しかけてやっていただけませんか?」
「はい、もちろん」
僕は深くうなずいた。
女将さんはすっと息を吸うと、ぱんぱんと二回手を打った。
「さあ、それはそれとして。夕食までまだ少しありますから、お二人ともご一緒にお風呂で旅の疲れを癒してくださいね」
『コイツと?!』
僕と夕介が同時に声を上げた。
「お前先に入れよ、自転車押して汗かいたんだろ?」
「アンタこそ、先に行けば?」
「譲り合っても仕方ないですよ。どうぞ、ゆ~っくりと、おくつろぎくださいね♪」
女将さんはそう言っていたずらっぽく笑うと、ぱたぱたと厨房の方へ消えた。
「まったく、かなわないな、あの人には」
夕介が頭をかきながらぼそりとつぶやいた。
深津峡温泉の源泉は地下千メートルから自噴する天然ラドン温泉です。
泉質は弱アルカリ性で、美肌効果が高いとされています。
放射能泉に分類されるラドン泉は、湯から気化したラドンの放つ放射線によって、体内に潜在している治癒能力が高まる効果があるとされており、療養温泉として活用されています。
国内のラドン泉としては鳥取県の三朝温泉、兵庫県の有馬温泉などが有名ですが、ここ深津峡温泉の源泉は昭和四六年に開湯して以来、隠れた名湯となっています。
さっきから湯船につかったまま二十回は繰り返し読んだので、壁面に掲出されている温泉の説明文を覚えてしまいそうだ。
何も好きこのんで読んでいるわけじゃない。夕介と顔を合わせないようにするためにそうしているだけだ。
ぬるめの湯だが、長く浸かっているとだんだんと体が芯から温まってくる感覚がする。これが温泉の効能ってやつなのだろうか。
露天風呂を楽しもうかと思っていたが、気が散ってとてもそんな気分ではない。
「お前ずっとそんなのにらんでて飽きないかー?」
夕介がのんきな声でからかってくる。まったく、いい気なもんだ。
「お前、『紫桜』を観に来たんだってな」
夕介が不意に僕にそう言った。僕は思わず奴の方を見た。夕介は例によってにやりとして続けた。
「実は俺もそうなんだ」
「え?」
意外だった。単にこの宿、というよりは女将さんに惚れて通い詰めているだけかと思っていたからだ。
「もっとも、俺は仕事だがな。お前みたいな暇人とは違うんだよ」
やっぱりいちいちひっかかる奴だ。
しかし、こいつがなぜ『紫桜』を観に来たのかは気になる。
夕介は少し真顔になって何かをじっと考えているようだったが、湯をすくって顔をすすぎ、黙って湯船から上がっていった。
夕介が出ると、浴室は急に静まりかえったような気がする。お湯が注がれる音だけがやけに大きい。
僕もそろそろ出ることにした。
第一章 桐葉荘(とうようそう) 〈四〉
「えー、浩司さん駅からここまで歩くつもりじゃったん?」
果林ちゃんがだしぬけに大きな声を上げる。
「どう考えても無謀だろ、バッカじゃないのか、お前」
夕介もことさら見下したような声を出す。
「まさかこんなに大変なところだとは思わなかったんだよ!」
僕もムキになって反論した。
「ご連絡いただければ、車でお迎えに参りましたのに」
女将さんが残念そうに言う。
「そんなサービスあるんですか、しまったなあ」
「浩司さん、まぬけー」
僕が頭をかいたのを見て果林ちゃんがけらけらと笑った。
「歩いてたら今頃寝込んでるな、お前」
「~~~っ!」
悔しいが夕介の言葉にはぐうの音も出ない。その様子を見て女将さんまで吹き出す。
「そんなに笑わないでくださいよ~」
ちょっとバツは悪いが、同時に僕はなんだかほっとしていた。
みんな今日初めて会った人たちだということを忘れてしまいそうだ。夕介がいなければもっと気分がいいのだが。
座敷での夕食は予想通りにぎやかになった。
僕と夕介の食事はちょっとした懐石料理だ。
前菜のごま豆腐から始まって、新鮮な刺身、鍋物にはふぐちり(!)、ミニサイズの和牛のステーキ、白身魚の天婦羅に茶碗蒸……と続いて、最後にはちゃんとデザートも付く。
普段はコンビニ弁当ばかりの僕の胃袋が、ビックリしてひっくり返りそうな内容だ。
女将さんが作ったのかと尋ねると、ちゃんと板前さんがいるとの答え。そりゃまあそうか。宿泊料は夕食朝食込みだから、値段のわりに豪華だと思う。
僕みたいな「質より量」な学生が食べるにはもったいないんじゃないだろうか。ちゃんと味がわかっているのか不安だ。
果林ちゃんは当然僕らとは違うものを食べている。
さんまの塩焼きに大根おろし、みそ汁と里芋の煮付け、ひじき煮。王道の日本の晩ごはんだ。こちらは女将さんの手作り。
僕の方がぜいたくなものを食べているはずなのに、果林ちゃんが隣で食べているのを見ると、なんだか妙に美味しそうに見える。
夕介はビール片手に料理をつついている。
コイツには懐石よりも焼き鳥の方が絶対似合うと思う。
アルコールは別料金になるので、金欠の僕はぐっとがまんだ。
「ただいまー」
鈴の鳴るような軽やかな声とともに座敷のふすまが開いて、長身の女性が姿を現した。おかえりー、と果林ちゃんが返す。
白い開襟の長袖ブラウスの上に深いグレーのチェック柄のベスト、黒のタイトスカート──どこかの制服だろうか。控えめな色に染めたストレートの長い髪をバレッタでまとめて額を出している。意志の強そうな眉の下に少し目じりが下がり気味の涼やかな目。顔立ちがはっきりとしいて、左目の下の泣きぼくろが印象的な美人だ。
「あれ、夕介さんだけじゃないの?」
彼女は僕に気づくと果林ちゃんに尋ねた。
「浩司さんも一緒だよー」
「メールには他のお客様がいらっしゃるなんて、一言も書いてなかったじゃない」
「書くん忘れたー」
「もう、それならそうと書いてよね、わたしにだって心の準備ってものがあるんだから」
どうやらこの人が桐島家の長女・水菜さんらしい。果林ちゃんと違って、きれいな標準語で話す。
「ほら水菜、ごあいさつ」
「あ、大変失礼いたしました。はじめまして、長女の水菜です」
女将さんがうながすと、水菜さんははっとした顔をして美しい所作で座り、僕に改めてあいさつした。
「森崎浩司です、はじめまして」
「俺にはあいさつはー?」
向こうで夕介が何やら言っているが、水菜さんは華麗にスルーした。
「果林が何か失礼をしませんでしたか?」
「あんなー、チャリ押してもらったんよー」
「果林には聞いてないでしょ!」
水菜さんはすかさず果林ちゃんに反撃し、僕も華麗にスルーされてしまった。
「森崎さんは夕介さんのお知り合いですか?」
水菜さんが僕に向き直って聞いてくる。不意にふわっといい香りが鼻腔をくすぐる。
見つめられて僕は思わずどきどきした。
「いえっ、ぜんっぜん! ついさっき会ったばっかりです」
「水菜ぁ、俺にこんなイケてない知り合いがいるわけないだろ」
夕介がまたよけいな事を言う。
「うっさいなー、ちょっと黙っててくれよ」
「さっき会ったばかりの割には、ずいぶんと打ちとけてらっしゃいますよね?」
「打ちとけてなんかないですよ!」
「えー、どう見ても仲良しですよぉ?」
水菜さんは奥ゆかしくくすくすと笑う。果林ちゃんとはまったくタイプの違う女性だ。
「コイツと一緒にすんな、コイツと」
夕介がいちいちからんでくるのが面倒くさい。
「うちが見てもぶち仲良しっちゃ。二人でお笑いコンビでも組んだらええじゃ? ユースケコージ♪」
果林ちゃんが世にも恐ろしい提案をする。
「誰がこんな奴とコンビなんか組むか!」
「それは僕のせりふだ!」
僕はかみつかんばかりの勢いで夕介をにらんでやった。その様子がツボに入ったらしく、水菜さんは笑いが止まらない。
「はい、水菜の分。仕事、どうだった?」
女将さんが水菜さんの夕食をお膳に載せて運んできた。
「んー、今の時期は割とひまかな、来月ぐらいになると少し忙しくなるけど」
水菜さんは軽く合掌してから箸を手にとって食事を始めた。所作がひとつひとつ美しいのに感心する。
「水菜さんはどこに勤めてるんですか?」
「岩代市役所の受付をしています」
なるほど、水菜さんなら受付が似合いそうだ。
「車で一時間もかけて通ってるんですよ、もっと職場の近くに住めばええのにから」
女将さんが少し不満そうに言う。
「いいの、わたし運転好きだし」
「でも一時間はちょっと大変ですね。一人暮らしとか、しないんですか?」
「わたしは家が好きなんですっ」
僕の問いかけに対して、水菜さんは少しムキになって答えた。何もそこまでムキになることもないと思うけど。
水菜さんは座布団の上に正座したまま食事を続ける。
果林ちゃんはもうだいぶリラックスして、足を投げ出して座っているから、なんだか対照的だ。
「果林はあいかわらず魚食べるのヘタだよね」
水菜さんが果林ちゃんのお膳を見ながら言う。
確かに、果林ちゃんの食べた後の皿にはサンマの身がぼろぼろに崩れて残っていた。水菜さんの皿を見ると、既に骨と身がきれいに分けられている。
「うち、みず姉みたく器用じゃないもん」
「ちょっとコツを覚えればいいだけじゃない」
「それがむつかしいんじゃもん!」
「大人になってからもそれだと、恥ずかしいよ」
「う~~、みず姉って母さんよりも厳しいんよねー」
果林ちゃんが助けを求めるような目で僕と夕介を交互に見る。
「まあまあ、そんぐらいにしといてやれよ、水菜」
「だって、結局恥かくのは果林なんだよ」
夕介がなだめたが、水菜さんはきっちり反論してからご飯を口に運ぶ。
それにしても、水菜さんは確かに少しばかりきついかもしれない。
女将さんは所作はきちっとしているけど、鷹揚で温かみがある。一方の水菜さんは、標準語のせいもあって、なんだか硬い印象を発してしまうことがあるようだ。
「なーなー浩司さん、みず姉って何歳に見える?」
少し考え込んでいた僕に、果林ちゃんが危険な質問を仕掛けてきた。
そういえば、水菜さんの年齢については全く予備情報がない。
水菜さんの落ち着きぶりは僕よりずっと年上……そうだな、二七歳ぐらいに見える。しかし、女将さんは今四二歳だから、そこまで若い頃の子どもということはないだろうし、判断が難しい。
果林ちゃんは目をキラキラさせながら僕の回答を待っているし、水菜さんも興味深そうに僕のことを見つめてくる。女将さんや夕介までが僕を見ている。
ここはひとつ慎重に判断しなければ気まずいことになりそうだ。
「え、えーと……そうだな、二四……くらいですか?」
僕がそう答えた瞬間、果林ちゃんと夕介が爆笑した。
女将さんまでもが横を向いてぷっと吹き出している。
水菜さんは何か言いたいのをがまんしているような顔だ。
まさか、僕は地雷を踏んでしまったのか?
「みず姉、また年上に見られちょる!」
果林ちゃんが腹を抱えて笑い転げている。
「え? もしかして、僕やっちまった?」
「今年の夏でハタチになったところです!」
心なしか水菜さんの声に棘があるように感じられる。
「マジで? 僕と同級? あ、その……すいません、すごく落ち着いて見えるから」
「よく言われます……」
水菜さんが低い声でぼそっとつぶやいた。
「みず姉の老け顔マジはんぱない、ぶちウケる!」
「もー、老け顔って言うな!」
果林ちゃんが茶々を入れると水菜さんはすぐムキになる。言い合いばかりしているようだが、この二人、仲が悪いわけではないようだ。
「水菜は子どもの頃から結構マセてたからな」
夕介が聞き捨てならないことを言う。
僕はさっきからもやもやしていた疑問をぶつけることにした。
「アンタ、一体ここの家族とどういう関係なんだよ? さっきから聞いてればずいぶん古い知り合いみたいなこと言ってるけど」
「夕介さんは昔、私の夫の部下だったんです」
夕介の代わりに女将さんが答えた。
「一〇年ほど前に私どもがこちらを開業した時からのお客様なんですよ」
「蘭さんの旦那・年光さんがIターンで開業したんだ、この宿は」
僕は驚いた。
桐葉荘はもう何十年も続く老舗の温泉宿だろうと勝手に思っていたからだ。
第一章 桐葉荘(とうようそう) 〈五〉
夕介と女将さんの話によれば、女将さんの夫である桐島年光さんはもともと関東の人で、たまたま訪れたここ・深津峡温泉をいたく気に入り、都会での仕事を辞めて家族でこちらに移り住んできたのだという。それが今から約一〇年前のこと。
夕介にとっては、新入社員として会社に入ったときの最初の上司が年光さんだったのだという。
「カッコよかったなあ、年光さんは。仕事は絶対に手を抜かなかったし、スタッフはもちろん、クライアントの信頼も篤かった。オンのときには熱い情熱と的確な判断でみんなを引っ張るし、オフのときには一緒になってバカ話もできる。本当に、しびれるくらいカッコよかった」
夕介が興奮気味の表情を浮かべている。他人を褒めることなんて絶対なさそうな夕介がそこまで言うとなると、相当できる人だったのだろう。
「それが、ある日いきなり会社辞めるって言いだすんだから、俺も驚いた」
「私も、年光の計画を初めて聞いた時は冗談だろうと思いましたよ」
女将さんはそう言ってふふっと思い出し笑いをした。
年光さんは会社勤めのかたわらじっくりと計画を練っていたらしい。
何度も深津峡を訪れ、バブル崩壊後に廃業して空き家になっていた旅館の建物……つまり今の桐葉荘を見つけた。これを買い取ってリノベーションし、源泉利用権について行政や同業者と折衝し、銀行とやりとりしながら資金繰りや経営計画にある程度目鼻をつけたうえで、縁もゆかりもない土地に家族でやってきて商売を始めた。
これが並大抵でないことぐらいは、いくら世間知らずの僕でもわかる。
十年経った今でもこの宿がちゃんと続いているということは、年光さんと女将さんが相当な努力をしてきたってことだろう。
「夢なんだとはよく言ってましたけど、本当に始めるだなんて思ってもみませんでしたよ」
女将さんが懐かしそうな表情で言う。
「基本的には現実的な人でしたけど、時々人をびっくりさせるようなことを、いきなり思いつくんですよね」
「確かに。あの突拍子もない発想は誰にもまねできなかったな。俺の知ってる中で、他にこんな人はいないね」
夕介は完全に年光さんに心酔している様子だ。
「突拍子もなく死んじゃいましたけどね」
女将さんが少しさびしそうにつぶやいた。
「五年前に、病気でな。わかってから亡くなるまで、本当にあっという間だった。あと少しで四二歳になるとこだったのに」
夕介が悔しそうに続けた。
「ちょうど桜が満開の頃でした。こんなに早くあの人と別れることになるなんて思いもしなかったから、なんだか実感がわかなくて。お葬式の時も、何をどうしたのかよく覚えてないんです。ただ、桜がすごくきれいだったことだけは印象に残ってます」
僕はじっと押し黙るしかなかった。
こんな時にどんな言葉を掛ければいいのかわからない自分が、ひどくもどかしい。
「年光さんにはせめてあと二十年は生きててほしかった。まだまだ教えてもらいたいことが山ほどあったのに」
夕介がそんなことをぽつりと言ったきり、あとは誰も言葉を発しなかった。
みんなが黙ってしまうと、庭で鳴いている虫の音が急に耳に入ってくる。
僕はなんだか気づまりになって、座敷の大きな窓から見える池をぼんやりと眺めた。
ずっと女将さんと夕介が話す年光さんの話に夢中になっていたので気づかなかったが、水菜さんと果林ちゃんはいつの間にかいなくなっていた。お膳が下げられているから、きっと後片づけをしているのだろう。
「蘭さん、ビール……いや、日本酒もらえますか」
夕介が追加の注文をする。
「今日は夕介さんがお好きな『獺祭』、入ってますよ」
「じゃ『獺祭』、冷やでお願いします」
夕介はやけに神妙な顔をしている。少し酔っているのだろうか。
「おい、お前もなんか飲めよ」
「僕はいいよ」
ムダづかい禁止、ムダづかい禁止……と僕は心の中で唱える。
「ケチってんじゃねーよ、金がねえなら俺がおごってやるから飲め!」
どういう風の吹きまわしか、夕介がやけに寛大な提案をしてくる。
一瞬、コイツに借りを作っても大丈夫かな、という考えが頭をかすめたが、さっきから旨そうに飲んでいる夕介を見ていると、僕もなんだか無性に飲みたくなってきた。
まあいいや、タダ酒万歳だ。
「じゃあ、ビール」
「蘭さーん、コイツにもビール持ってきてやって」
かしこまりましたー、と厨房の方から女将さんの声が返ってくる。
「お前、『紫桜』が目的でここに来たんだろ? 奉納は明後日からなのに、なんでこんなに早く来たんだよ?」
「別にいいだろ、アンタに関係ないし」
実を言うと、『紫桜』については事前にネットで調べたが、思ったような情報を得ることができなかった。現地に行けば何かわかるだろうとタカをくくって、明日図書館にでも行って調べるつもりでいたが、別にはっきりとした予定を立てているわけでもなかった。
「お待たせしました、どうぞ」
女将さんが酒とビールを持ってきてくれた。プレミアムの金ラベルがまぶしい。やっぱりこういうところで出るビールは違う。
夕介は早速『獺祭』を一口含むと、実に旨そうに目をつぶってうなっている。
僕は女将さんがグラスに注いでくれる黄金色の液体を見つめながら、明日どうするかを考えていた。
「お二人とも、明日はどのようにされるんですか?」
まるで僕の心を見透かしたかのように女将さんが尋ねてくる。
動揺を表に出さないように気持ちを落ち着けようと努めながら、僕はグラスのビールに口をつけた。
一口でホップのいい香りが口中に広がり、苦みとともに炭酸の心地よい刺激がのどを下りていく。
「俺はいくつか取材をします。今回、月刊誌に八ページのグラビアをもらってるんで、猿楽『紫桜』を紹介するんですよ」
「夕介さんってそんな仕事もされてるんですね」
「よくある紀行グラビアです。普通はライターと組んでやるんですが、今回は予定の合うヤツがいなくて俺一人です」
夕介はドヤ顔でそんなことを言う。
「てことは、アンタが文章も書くの?」
「当たり前だろ」
どう見ても夕介は文章を書くようなタイプには見えないが。
「森崎さんは?」
「僕はちょっと調べ物でもしようかと……」
僕は語尾をごにょごにょとごまかした。
特に何も考えていないなどとは、夕介の前では絶対に言えない。
「どうせ何も考えてないんだろ?」
夕介がにやにやと笑いながら痛いところを突いてくる。
僕はちょっといらだって、グラスに残っていたビールを一気に飲み干した。
「調べものと言っても、この町には大きな図書館はないですしねえ」
女将さんが僕のグラスに二杯目を注ぎながら言う。
この時点で僕の目論見は脆くも崩れ去った。
「でも何か資料ぐらいはあるでしょう?」
僕は女将さんに尋ねた。
「尋瀬の公民館の二階に図書室がありますから、そこには町史なんかも置いてあると思いますけど」
「で、どうやってそこまで行く気だよ?」
夕介に指摘されて僕は初めて気づいた。
そうだった、僕には足がない。いや、文字通り自分の足しかない。
何時間かに一本のバスではとても自由には行動できないし、だからと言ってタクシーは論外、こんなところで使ったら完全に赤字だ。
つまり、どこに行くにもあの急坂を下りて、てくてく歩いていく他ないのだ。
行ったらもちろん、帰って来なければならない。最後のトドメにあの急坂。
考えただけでくらくらする。
「どこまでも浅はかな奴だなあ」
考え込んでいる僕を見て夕介が思いっきりバカにする。
「時間があれば私どもの方で車を出して差し上げたいのですが、あいにく明日は予定がございまして」
女将さんが申し訳なさそうに言うが、むしろ謝るべきは甘い考えだった僕の方だ。
「しゃーねえなあ」
夕介はあぐらをかいたまま後ろにふんぞり返ると、右手の人差し指を前に突き出して僕に言った。
「お前、俺のアシスタントやれよ」
「はあ? なんで僕がアンタのアシスタントなんかしなきゃなんないんだよ?」
「お前『紫桜』について調べたいんだろ? だったら、俺の取材を手伝えばおのずとわかるだろーが。俺はそのためにここに来たんだからな」
夕介があごひげを撫でながら勝ち誇ったような顔で僕に言う。
「ああ、それは確かに名案ですねぇ!」
女将さんまでが手をたたいて夕介に賛成する。
「ま、お前みたいなダメ学生が一匹ついてきたところでどうせクソの役にも立たんだろうが、せいぜいがんばりな」
「ちょ……ちょっと待てよ、まだ手伝うなんて言ってないだろ」
僕は少しあせった。だが、確かに他に手はなさそうだ。
ここで断れば明日は日がな一日、ひたすら歩き続けるか、ぼんやり無為に過ごすかのどちらかだ。
「タダで、とは言わん。そうだな、泊まってる間の酒代ぐらいは俺が出してやるよ」
バイト料にしては安すぎる気もするが、プレミアムの誘惑に、僕は負けた。
「わかった、じゃあ手伝うよ」
「よし、決まりだ。明日朝八時にここを出るぞ」
夕介は一方的にスケジュールを決めてしまった。
八時に出るってことは、遅くとも七時には起きておかなければならない。
「せめて九時にならないか?」
「ぬるいこと言ってんじゃねーぞ、このタコ!」
夕介が僕の頭を思いっきりはたいた。
「なにすんだ、このやろう!」
僕は少しオーバーにわめきたてる。
「あらあら、コンビ結成ですね! ユースケコージ♪」
僕らのやり取りを見ていた女将さんが手をたたきながら茶化した。
僕と夕介は互いの顔をにらんだ後、一呼吸置いて同時に叫んだ。
『コンビじゃねえ!』
〈第一章終わり〉
第二章 桜姫(おうひめ) 〈一〉
目が覚めた時、自分がどこにいるのかを忘れていた。
いつものアパートの白い天井が見えるものと思って目を開けると、まだ薄暗い視界に木目がぼんやりと浮かんきて、僕は一瞬あわてた。
ああそうか、僕は旅に出てたんだよな、と思い出したら急に目が冴えてしまった。
時計を見ると、時刻は午前六時になる少し前。外はようやく明るくなり始めたところのようだ。昨夜夕介が決めた出発時刻まではまだ二時間ぐらいある。
あの後、僕らは十時近くまで座敷で飲んでいた。片づけの済んだ水菜さんと果林ちゃんも一緒になってしばらく談笑した。
「コンビ結成」は大いにネタにされたが、僕も夕介も頑として認めなかった。それがよけいにウケたのはなんだか納得いかないが、盛り上がったからよしとしよう。
姉妹は二一時半ごろに母屋の方に戻り、さすがに夕介と二人で飲む気はしなかったので、そこでお開きにしたんだった。
部屋に戻ると急に眠気が襲ってきてそのまま寝たから、睡眠時間は約八時間。決して睡眠不足ではない。そう思ったら、なんだか寝ているのがもったいない気がする。
僕は布団から抜け出して冷たい水で顔を洗うと、浴衣から着替えて廊下に出た。
厨房の方から明かりがもれている。朝食の仕込みが始まっているのだろう。
僕はそのまま玄関の外へ出た。まだ明るくなり始めたばかりで、外の空気は冷たかった。
十月のなかばだからまだ息が白くなるほどの冷え込みではないが、僕は思わず身震いした。
深く息を吸い込むと、真新しい空気で肺が満たされる。
木々の間から見える空からは既に星は消え、東から中天にかけて美しいグラデーションが描き出されていた。南の空には細い月がかかったままだ。
僕は明るくなり始めた庭を眺めながら門をくぐった。
どこからか、さくっさくっという規則正しい音が近づいてくる。何だろうと耳を澄ますと、落ち葉を踏みしめる音だとわかった。
母屋の方から誰かが上がってきているようだ。
ほどなくして僕の前に現れたのは、白い長襦袢の少女。
「桔梗……さん?」
僕が声をかけると、彼女は僕の前で一度足を止めた。
「あ、あの……おはよう」
僕はあいさつをしたが、桔梗さんは無言のまま僕を一瞥すると、そのまま歩みを進めて僕の前を横切っていった。
「桔梗さん、どこ行くの?」
再び僕が声をかけると、彼女は歩みを止めてもう一度僕を見た。そのまま今度は顔を桐葉荘の屋根の向こう側に向け、また歩き始める。
屋根の向こう、と言ってもそこには山の斜面があるだけだ。
「ちょっと待って」
彼女は僕の言葉を無視して生垣の隅にある小さな木戸を開け、その向こうに消えた。
僕はなんだか気になって彼女を追いかけることにした。
木戸の向こうには桐葉荘の勝手口が見え、その向こうに足踏み道が続いていた。
かなり明るくなっているとはいえ、生い茂る木々で陰になって、足元は見えにくい。少し先に彼女の白い影がぼんやり見える。
僕は見失わないようにあわてて彼女を追った。
落ち葉で覆われた足踏み道はちょっと油断すると滑って転びそうになるが、桔梗さんは着物にもかかわらず慣れた足取りですいすいと登っていった。
僕の方は悪戦苦闘しながらどうにか彼女についていく。
何度か右に左に折れ曲がりながら三分も歩くと、僕の息は早くも荒くなった。いつの間にか桔梗さんの姿も見失った。
本当に彼女はいたのだろうか、といぶかりそうになったところで、ようやく少し開けた場所に出た。
桔梗さんは息一つ乱れることなく、じっと東の空を見つめて立っている。
そこは尾根の途中の踊り場のような場所だった。
石造りの小さな祠が祀ってあり、周囲の木々が低いため、東の空がよく見える。少し下の方に桐葉荘の瓦屋根が見えた。
僕が息を整えているうちに、周囲の明るさはどんどん増していく。
桔梗さんは身じろぎひとつせずに東の空を見つめていた。
僕も彼女の見ている方向を見ようと顔を上げると、まさにその瞬間、太陽が昇り始めた。
山並みが一枚の影となり、金色に縁取られた複雑な輪郭線を描いている。
太陽は力強く昇り、すべてのものを光に包み込む。
象牙色だった東の空は一気に黄金に染まり、地平付近の雲が太陽の光を受けて茜色の輝きを放った。
すぐ隣にいる桔梗さんの長い黒髪がきらきらと陽光を返す。
長いまつげの下で、瞳がかすかに揺れている。
色白な頬には赤みが差し、彼女の呼吸や鼓動までが僕に伝わってくる。
初めて見かけた時にはどこか現実感に乏しい印象だったが、いま僕のそばにいる彼女は生命感にあふれていて、僕は思わず息を呑んだ。
表情を削ぎ落とした横顔は彫刻のように美しいが、彼女はまぎれもなく生きているんだと実感する。
空は僕らが見ている間にも表情を刻々と変えていった。
金色に輝いた東の空は、太陽が山々の輪郭線から離れると、徐々に鮮やかな青色へと変化していく。
僕は何を言えばいいのかわからず、ただじっと黙っていた。
心は大きく揺さぶられ、得体の知れない大きな感動に満たされていたが、今どんな言葉を発しても僕の心を正しくは表せないような気がした。
僕も桔梗さんも、ずっと黙ったまま東の空を見続けた。
桔梗さんはいつもこうして朝日を眺めているのだろうか。
彼女は何も言わないが、彼女の無表情な横顔の奥には、祈りに似た真剣さがあるような気がした。
すっかり周囲が明るくなったと思ったら、桔梗さんは来た時と同じように何も言わずに斜面を下り始めた。
僕も黙ってそれに続くことにした。
桔梗さんは慣れた足取りで足踏み道を下りていく。
登る時ほどは苦労せずに済んだが、それでも僕は何度か転びそうになった。彼女は毎日のようにこの道を歩いているのだろう。
桐葉荘の門前に戻ると、桔梗さんは立ち止まって僕を見た。
あいからず無表情で、彼女が何を考え、何を感じているのか、全く分からない。
僕も桔梗さんを見つめ返すと、彼女は軽くうなずいた。いや、もしかしたら彼女なりの会釈なのかもしれない。
あっけにとられている僕を置いて、桔梗さんは母屋の方へ下りていった。
さっと朝風呂を浴びてから座敷に顔を出すと、まだ浴衣姿の夕介がもう先に座っていた。
「なんだ、昨日グズった割には早起きだな」
寝癖頭の夕介が皮肉をぶつけてきた。
「アンタこそ、二日酔いにならなくてよかったな」
僕も遠慮なく反撃することにする。
少なくとも今日は一日お伴をするんだ、我慢してたらとても身がもたない。
夕介はあいかわらずのにやにや笑いを返してきた。
「おはようございます、お二人ともよく眠れましたか?」
女将さんの朗らかな声が響く。
「おかげさまでぐっすりでした」
「寝過ぎて目が腐ったんじゃないか?」
「それはアンタの方だろ」
「うふふ、ネタ合わせですね」
早速女将さんに笑われてしまった。
てきぱきとお膳が運びこまれ、朝食が始まった。
ご飯と焼き魚、いくつかの小鉢とみそ汁に漬物がついた、模範的な朝ご飯だ。
僕は普段の乱れた食生活を反省した。一ヶ月もここで生活したらきっと驚くほど健康になるに違いない。
「今日は忙しくなるぞ」
茶碗を片手に夕介が言った。
「確認しておきたいことがあるから、午前中に岩代市役所本庁舎に行く。観光協会にはアポを取ってから午後イチで訪問だ。その後、市立図書館で資料を集めて、日が落ちないうちに荷駄町の沓掛山にも足を延ばす。夕方こっちに戻ったら、保存会の松岡会長にインタビューだ。昨日みたいにぬるいことぬかしやがったら置いてくからな」
「望むところだ」
僕も焼き魚を口に運びながら答えた。
何か初めてすることに対して、僕はいつも腰が引けて億劫がるのだが、なぜだか今日はわくわくしている。
夕介という一番苦手なタイプの人間と一緒に行動するということに対しても、むしろ、やってやろうじゃないかという気分だ。
いよいよ戦闘開始、という高揚感が僕の全身にみなぎっていた。
「市役所に行くってことは、仕事中の水菜さんに会うことになるかな」
僕は水菜さんの大人びた顔を思い浮かべながら言った。
「お前、よからぬ下心出すなよ」
夕介が釘を刺してくる。
「初日から美女と美少女に囲まれたからって、鼻の下伸ばして浮かれてんじゃねえぞ! 偶然知り合った女と仲良くなる、なんてのはアニメの中だけだからな」
「わかってるよ!」
少しだけ図星だったので僕はムッとしたが、確かに夕介の言うとおり、現実はそんなに甘くはないだろう。今現在、確実に僕を待ちうけている現実は、「男二人の珍道中」だ。
「ああ、なんてむさくるしい現実!」
「やかましい奴だなぁ」
夕介が手間のかかる生き物でも見るような目で僕を見ながら言った。
女将さんが僕の後ろでくすくすと笑っていた。
錦美町から岩代市の中心部までは約四〇キロ、車でもたっぷり一時間はかかる距離だ。
僕は夕介が運転するSUVの助手席で押し黙っていた。
車は錦美川の左岸を走る国道を右に左に何度もカーブしながら下っていく。川の両岸には山肌が間近に迫り、対岸には昨日乗ってきた山代鉄道の線路が走っている。
谷間のわずかな隙間に時折集落が現れては途切れ、そうかと思えば突然斜面の途中に一軒家がぽつんと建っていたりする。
よくこんな場所に住むよなあと、僕はよそ者ならではの勝手な感想を抱きながら車に揺られていた。
「おい、なんかしゃべれよ」
夕介が声をかけてきたが、しゃべることなんか何もないと思って黙っていた。運転のためにかけたサングラスのおかげで、横顔がどこかのチンピラみたいに見える。
僕が黙ったままなので夕介は戦術を変更し、僕に質問をしてきた。
「お前、そもそもなんで『紫桜』を観ようと思ったんだよ?」
質問されたら答えないわけにもいかない。
「なんとなく、かな」
「なんとなくでわざわざ無い金使って三泊も四泊もするか、普通?」
確かにそうだ。ただ僕自身、『紫桜』の何に心惹かれているのかがうまく説明できない。
「だいたい、地元でもそんなに知られてないのに、どこで『紫桜』のことを知ったんだよ?」
「春ごろに、西國新聞に小さな記事が出てたんだよ」
「そんな記事あったか? どんな内容だ?」
夕介はステアリングを軽く指で叩きながら僕に尋ねる。
「七年に一度の猿楽の練習が始まったって内容。合戦で父を亡くした姫の悲劇で、いくつかの異なる物語が伝わっている、って書いてあったと思う」
「で、その内容についてはまだ知らないわけか、お前は」
「そういうこと」
キイワード『紫桜』でウェブ検索しても、出てくるのは桜の園芸品種の一種・ムラサキザクラばかり、しかもこれは猿楽『紫桜』とはまったく無関係なようだ。上演の模様を撮影した写真などにも行き当たらなかった。だからこそ逆に興味をかき立てられたのかもしれない。
「予備知識なしで観たところで、何が何だかちんぷんかんぷんだろうし」
「まあ、そうだろうな。猿楽ってか、能楽は理解するのにある程度素養が要るからな」
「せめてあらすじだけでもわかればなあ」
「どうせお前、ネットで検索しただけなんだろ?」
「そうだよ」
「これだから平成生まれは」
夕介がおっさんくさいことを言う。
「本当に大事なことはネットにはなかなか落ちてねーんだよ」
夕介は偉そうに胸を張った。
「自分が本当に知りたいことは、足で稼ぐ! なんでもネットに頼ってんじゃねーぞ!」
「はいはい、お説教でしたらまた今度聞きます」
僕は頬づえをついてテキトーに流した。
「年光さんの口癖だったんだよ、足で稼ぐってのは」
夕介は懐かしそうに続けた。
「俺が新入社員だった頃、しょっちゅう年光さんに叱られたんだ。現場にどんだけ足を運んだか、相手とどれだけひざづめで話せたかって。仕事はデスクの上だけでするもんじゃないぞって散々言われた」
夕介が昔サラリーマンだったというのはなんだか想像がつかない。
しかし、こんな軽薄な新入社員がいたら、叱り飛ばしたくなる気持ちはわかるような気がする。年光さんはさぞかし苦労したに違いない。
「アンタ昔何の仕事してたんだよ」
「広告代理店」
ウソだろ、と僕は内心毒づいた。
「その顔は信用してないな」
「当たり前だろ」
「ふん、どうとでも言え。ま、俺のような才能ある人間は、どんな仕事に就いてもサマになるがな」
夕介は鼻息も荒くドヤ顔を僕に向けてきた。まったく、コイツの根拠のない自信はどこから来るんだろうと僕はなかばあきれた。
車はあいかわらず川沿いの風景の中を走っている。ずっと同じような景色が続いているので、どこまで進んだのかいまいちわからない。
「ところで、アンタは『紫桜』がどんな話なのか知ってるのかよ?」
僕は話題を戻すことにした。
「ああ、七年前に一度観てるからな」
「だったら教えてくれよ」
「自分で調べればいいだろ」
「なんだよケチだな」
「足で稼げ、足で」
「その足がないからこうしてアンタのアシやってるんだろ」
夕介がくくっと笑った。
「お前うまいこと言うな」
「お褒めいただきまして誠に光栄です」
僕は思いっきり慇懃無礼な調子で返した。
「よし。いいだろう、どうせ着くまで時間はたっぷりある。昔話のはじまりだ」
やや芝居がかった口調でそう言うと、夕介は語り始めた。
第二章 桜姫(おうひめ) 〈二〉
時は戦国時代、室町幕府末期の弘治元年(一五五五年)十一月。
前月に厳島の合戦で陶晴賢を撃破した毛利氏は、さらに西進していよいよ防長二国への侵攻を開始した。世に言う『防長経略』である。
防長二国の守護・大内氏は陶晴賢の反逆によってすでにほぼ壊滅に追い込まれており、毛利氏はこの好機を逃さなかった。
西へ向かう街道筋の荷駄盆地を治め、大内家の有力な家臣でもあった杉山泰隆は、一旦毛利への恭順の意を示したが、その裏では侵攻を食い止めるべく、大内に援軍を求める密書を送ろうと試みた。すでに滅亡の淵にあるとはいえ、山陰攻めに際しては毛利を支援したこともある大内に対する毛利の振る舞いはあまりに非礼であり、杉山泰隆はどうしてもこれを許すことができなかったのである。
しかし、古くから杉山氏と対立関係にあり、すでに毛利方についていた近隣の豪族・緒方氏が周辺の道筋に兵を配置して警戒していたため、大内への使者は捕えられ、この謀は毛利方に露見するに至った。
同月一〇日、毛利軍は機先を制して杉山氏の居城・沓掛城の攻撃を開始、杉山氏は籠城戦でこれに抵抗した。
寄せ手の毛利方は地元の連歌山城主・檜森高安、田背城主・緒方基安の軍勢も合わせておよそ七千。対する沓掛籠城軍は城主・杉山泰隆及びその父・入道宗瑚以下二千六百余。
開戦より三日間小競り合いが続いたが、籠城する杉山氏は善戦し、毛利方攻城軍を大いに苦戦させた。
毛利方は正面突破による攻略は困難と見て、沓掛城の北に居城・連歌山城を構える檜森高安の先導により、夜陰にまぎれて沓掛城の搦手(城の裏門)に回り、払暁に奇襲攻撃を仕掛けた。
両軍は壮絶な死闘を繰り広げたがやはり多勢に無勢、先に二の丸が落ち、杉山宗瑚は戦死。城主・杉山泰隆も、奮闘空しくついに緒方基安によって討ち取られる。
沓掛城の将兵の約半数である千三百余が壮絶な討ち死を遂げたと言われる。
これが沓掛合戦の概要である。
「で、これがどう『紫桜』に結びつくのか、イマイチわからないんだけど」
「いいからよく聞け、ここからが本筋だ」
討ち取られた杉山泰隆には鶴若丸・亀寿丸という幼い二人の男子があり、大内氏の人質になっていたため生き残ったそうなのだが、実は彼らにはもう一人、姉があったのだという。
「それが『紫桜』の主人公、桜姫だ。桜と書いて『おう』と読む」
物語は桜姫が落城の直前に城を逃れ、山代郡、つまり今の錦美町へと落ち延びた、という設定となっている。
「ところが、いずれも桜姫が主人公なんだが、結末はどれも違うんだ」
「どういうことだよ?」
「同じ主人公でも、それぞれの座が演じる一幕ごとに、全然違うパラレルなストーリーが展開するんだ。ひとつずつ教えてやろう」
まずは第一幕、区別のために別名『桜堤』と呼ばれている。
宇侘川の堤に咲く山桜に旅人が心を奪われていると、美しい乙女が現れ、その桜の由来を語り始める。
山代に落ち延びた桜姫は、都の暮らしにあこがれながらも、戦死した父の菩提を弔いつつこの地でひっそりと暮らすことを選んでいた。
しかし、豪雨の度に氾濫を繰り返す宇侘川の治水のために領主が堤の造営を決定すると、桜姫は自ら人柱になることを望み、和歌を詠んで堤の礎となって消えた。
数年を経て堤は完成し、かたわらに山桜が植えられた。すると、山桜は次の春から七年にわたって鮮やかな紫色の花をつけたといわれる。
旅人が我に返ると、乙女は消え、ただ山桜の花が舞うばかりであった。乙女は桜姫の幽霊だったのだ。
「なるほど、それで『紫桜』──紫の桜なのか。それにしても、女将さんの言ったとおり、哀しい話なんだな。ところで、人柱って何?」
「お前、本当に何も知らねーんだな」
また夕介にバカにされた。
「橋や堤──今でいう堤防だな──を建設する時に、川の神を鎮めるために差し出す生贄のことだよ。人身御供とも言う。生娘が選ばれて、生きたまま埋められるんだ。城の石垣を築くときなんかにも埋められたらしいぞ」
「なんか残酷だな」
「まあな。今の感覚で判断するわけにはいかんが、日本全国あちこちに人柱にまつわる伝説は残ってる。それだけ日本の自然は厳しかったってことだろうな」
地震、洪水をはじめとする数々の天変地妖。昔から日本列島に住む人々は、自然災害と常に向き合いながら、それでもたくましく生き抜いてきたんだ、と夕介は言った。
「それにしても、切ない物語だな」
「まだまだ、あと二つの話も負けず劣らずだ」
夕介はそう言うと話を続けた。
続く第二幕は通称『寂水』と呼ばれている。
山代に人喰いの鬼が出るようになったと聞き、ある武者が退治を買って出た。
宇侘川を遡り、寂水峡でついに鬼にまみえ、激闘の末、武者はこれを成敗する。
里に戻った武者は美しい娘の夢を見た。
自分はあなたに討たれた鬼であると言う。
復讐に狂った挙句、父を討ち取った仇を惨殺し、桜姫は鬼と化したのだ。
己のことも父のことも忘れ果て、ひたすら人を喰らいつつ山代まで流れてきたが、今、あなたに討たれてようやくかつての記憶を取り戻した。多くの罪もない命を喰らい、堕地獄は必定の自分だが、父の弔いもせずに今生を去るわけにはいかぬとさめざめと泣く。
武者は姫を哀れに思い、宇侘八幡宮の一隅に桜姫とその父の供養塚を寄進し、その霊を懇ろに弔った。その塚のかたわらにあった山桜は、その後七年にわたって紫の花をつけたといわれる。
「鬼になって討たれるって……悲惨」
僕はひどく重い気分になる。
「能には女の妖変をモチーフにした物語がいくつもある。超有名な『道成寺』や、『源氏物語』を典拠とした『葵上』なんかはその典型だが、恨みや嫉妬といったマイナスな感情が、女を人ではないものに変えてしまうんだ」
「でも、それって普通に誰でも持ってる感情だと思うけど」
「だからこそ、それを抑えないと大変なことになるぞっていう警告かもしれないな。シテ(主役を演じる役者)は鬼になる時に『般若』の面を着けるんだが、『般若』ってのはもともとは仏教用語で『智慧』という意味だ。面の名前の由来は仏教用語の『般若』とは無関係らしいが、『智慧』をまとったものが『人ではない』ってのは相当な皮肉だな」
それにしても、夕介は資料も見ずに次から次へとよくしゃべる。
本業は写真家のはずだが、一体どこでこんな知識を仕入れたのだろう。
最後の第三幕は『乙女淵』と呼ばれる。
石見国を目指す旅の僧が乙女淵のほとりの廃寺で美しい娘・桜姫と出会った。
桜姫は自分の凶兆の言葉が合戦を起こし、父や千人の将兵の命を奪ったのだと自らを責め、僧に自分を助けてほしいと乞う。
僧は姫を救うため読経するが、桜姫は読経を聞くうちに自分の呪われた運命から逃れるには自ら命を絶つほかないと思い定め、僧の制止を振りきって乙女淵から身を投げてしまう。
彼女の命を救えなかったことを悔やんだ僧は、この地にとどまって桜姫とその父らの菩提を弔おうと決意した。
しばらくのち、僧の夢枕に桜姫が立って語る。
自らの命を絶った桜姫の魂は、僧の回向によって乙女淵のかたわらに立つ桜の木に宿った。
僧が彼女の霊のために読経すると乙女淵には紫の桜が咲き、桜姫は僧に感謝を述べて姿を消した。
「うーん……」
僕は思わず腕を組んでうなってしまった。
「なんか、どの話も救いがないなあ」
どれも不条理といえば不条理な物語で、なんとも後味が悪い。桜姫がそんな苛烈な運命に翻弄されなければならないような悪いことをしたとは、僕には思えない。
「確かに救いはないな。能にはこの世ならざるものが頻繁に登場するが、いずれも非業の死を遂げた者たちなんだ。だから、能舞台ってのはこの世とあの世の境目が交わり、死者が生者にその思いを告げる場所だとも言えるな。ま、どのような形にせよ、桜姫は非業の死を遂げ、その命を受け継ぐかのように紫の桜が咲くってところはどの話も同じだ」
紫色の桜の花ってもし実際に見たら不気味だろうな、と僕は想像した。
「でも、桜姫が死んでしまう理由は、全部違うんだな。本当のところはどうなんだろう?」
「そこだ。猿楽はもともと神に捧げた舞が原型だと言われている。大抵は『源氏物語』『伊勢物語』『平家物語』なんかの有名な物語を典拠として曲が創作されているんだが、『紫桜』についてはほぼ完全なオリジナルと言っていいだろう。単に非業の死を遂げた桜姫を鎮魂、あるいは追善するための舞だとしたら、それぞれの座がわざわざ結末の違うストーリーを演じる理由がわからない。そもそも、能楽では通常、狂言も取り混ぜて複数の曲目が上演されるのが一般的だが、ここでは狂言を挟まず、パラレルなストーリーを持つ曲すべてを合わせて『紫桜』と呼んでいるからややこしい。何か別の意図があったと見るのが自然だろうが、残念ながら今となってはもう誰にもわからない。猿楽『紫桜』の最大の謎はそこであり、そして魅力でもあるわけだ」
「ふーん……」
気がついてみると、錦美川の川幅もだいぶ広がり、周囲に立ち並ぶ民家の数も増えてきた。だいぶ岩代市の市街地に近づいてきたようだ。
「それにしても、水菜は毎日この道を運転してるんだから、まったく大したもんだよ」
夕介がつぶやいた。国道とはいえ急カーブが連続する谷間の道だから、運転するのは決して楽ではなさそうだ。
「運転が好きだって言ってたなあ、水菜さん」
僕は昨晩の水菜さんの言葉を思い出した。思い出すだけで少し頬がゆるむ。
「なんだ、お前水菜がタイプか?」
「そんなんじゃないよ」
実は図星だが、夕介にわざわざそんなことを言う必要はない。奥ゆかしくて、上品で、きれいで。あんな彼女がいたらいいだろうな、と僕は妄想した。
「あいつはだいぶこじらせてるからなあ、気をつけた方がいいぞ」
夕介が苦笑しながら言った。
「高校の三年間で三〇人の男子から告白されて、その全員をことごとくふっちまった恐ろしい女だぞ、水菜は」
「ええ?!」
水菜さんは美人だからきっとモテるだろうとは思っていたが、それにしても全員をふってしまうってどういうことだ? あの水菜さんに、本当にそんな高飛車な一面があるとは、にわかに信じがたい。
「うそだと思うなら果林に聞いてみな。今でも水菜には彼氏はいないはずだ。女友達も少ないんじゃないか?」
僕は酸欠の金魚のように口をぱくぱくさせた。何も言葉にならない。
「驚いたか?」
夕介はさも面白そうに含み笑いをしながら僕に言った。
「お前、少しは女を見る眼を磨いといた方がいいぞ」
「アンタに言われたくはないよ」
僕はそれだけ返すのがやっとだった。
第二章 桜姫(おうひめ) 〈三〉
合併後に建てられたという岩代市の市役所は、ガラスをふんだんに使用した六階建ての近代的な建物だった。
玄関から二階まで吹き抜けのロビーに入ると、さんさんと陽の光が降り注ぎ、正面の公園に植えられた大きなクスノキがよく見える。開放感のある、なかなか気持ちのいい空間だ。
僕は、つい受付に水菜さんの姿を探してしまった。
予想どおり制服姿の水菜さんを見つけると、なぜだかほっとした気持ちになる。水菜さんも僕と夕介を見つけると、微笑しながら小さく手を振ってくれた。
身長が一七〇センチはある水菜さんは遠くからでもよく目立つが、それは単に長身だからというだけでなく、彼女が放つ華やいだオーラのせいもあるような気がする。
さっき車の中で夕介が言ったことが本当なのか、彼女を前にするとやっぱり疑わしい。夕介にからかわれているだけかもしれない。
夕介は遠慮なしにずかずかと受付に近づくと、サングラスを額にずらしたままでカウンターに片ひじをついてにやにやしながら水菜さんに話しかけた。まったく、なれなれしいにも程がある。
「よ、水菜」
「夕介さんに、森崎さん! どうしてここに?」
水菜さんが微笑を崩さずに答える。
夕介がファーストネームで呼ばれたのに僕は名字で呼ばれ、内心なんだか面白くない。
「市の無形文化財登録のことで、確認しておきたいことがあってな」
「では、市民生活部の文化振興課の方へどうぞ。この建物の四階になります。あちらのエレベーターで四階まで上がっていただきまして、右手奥になります」
水菜さんは間髪いれずにてきぱきと答えた。
「サンキュ、ちゃんと仕事しろよ」
「もう、ちゃんとしてますよ! じゃまするなら追い出しますよ!」
水菜さんが夕介をしっしっと手で追い払った。ざまあ見ろだ。
「森崎さんも、アシスタント、がんばってくださいね」
「ありがとうございます」
水菜さんが僕を見てほほ笑んでくれたので思わず頬がゆるむ。
「お前、耳まで赤くなってるぞ」
夕介がにやにや笑いながらよけいなことを言う。
「うるさい、行くぞ!」
僕はごまかそうと思って大きな声を上げた。
「いってらっしゃい」
水菜さんが笑顔で見送ってくれた。
エレベーターの扉が閉まった瞬間、夕介がぼそりと言った。
「あーあ、これだから女ってこわいこわい」
「お忙しいところ大変お手数をおかけします」
夕介は市役所の職員に対して恐ろしくていねいに事情を説明している。僕に対する乱暴な態度とはえらい違いだ。
夕介が確認しておきたいことというのは、奉納猿楽『紫桜』が、岩代市の無形文化財に再登録された経緯だという。
「合併時に旧錦美町からの無形文化財指定がうまく引き継がれず、合併後に再登録されたと聞きましたもので、取材のために事実関係をぜひ確認しておきたいのですよ」
「あー、どうですかねえ。私はその時は違う部署におりましたけえ、そのへんの詳しい事情は、ちょっと」
夕介の相手をしているのは小太りで髪の薄い、人のよさそうな中年の男性職員だ。
やたらと汗をかいていて、ハンカチでしきりに汗を拭いている。そんなに暑いわけでもないからその様子がなんだか滑稽で、僕は笑いを必死でこらえていた。
「再登録の際に提出された書類を拝見するわけにはまいりませんか?」
「そしたら、探してみましょう。少々お待ちいただけますか」
市職員は仕事とはいえちゃんと丁寧に応対してくれている。
「なんでわざわざここまで出向いて調べる必要があるんだよ? このくらいならメールとか電話取材で済むんじゃないか?」
僕は夕介に尋ねた。
「さっきも言ったろ、足で稼げって。現地に来なきゃわからないこともあるんだよ」
夕介は鼻歌でも口ずさみそうな雰囲気でくつろいでいる。そんなもんだろうかと僕は思う。情報なんてどこでどうやって見たって同じじゃないだろうか。
そんな事を考えながら、僕は事務室で働いている職員の動きを眺めていた。
パソコンに向かって一心不乱に何かを打ち込んでいる人、電話で笑いながら話をしている人、そうかと思えば何やら難しい顔をして考え込んでいる人……。
その様子を見ながら、「働く」ってどういうことなんだろうと僕は考えた。
僕はまだ、何者でもない。
それだからだろうか、「働く」ということに対して、どこか尻ごみする気持ちがあるのは確かだ。
「働く」ということは、社会の中で一定の位置を占める「何者かになる」ということだと思う。それは、自分自身というものを確立するために必要なことだと頭ではわかっているが、一方で自分の可能性がひどく限定されてしまうような気がする。
何かを選ぶということは、別の何かを切り捨てることでもあり、その時に選ばなかったものには、もう二度となれないということだ。
僕はそのことをとてもこわいことのように感じている。
一年半後には、僕は就職活動を開始して、選ぶこと、そして選ばれることに直面することになる。でも、一体何を基準にしたらいいのだろう?
僕は今回の旅行のために、夏休みにお中元の詰合わせを作るアルバイトをした。物流倉庫の中で、洗濯用洗剤や食用油、コーヒーといった商品を、ひたすら指示通りに化粧箱に入れていく。
僕でなくても、誰でもできる作業だ。
その単純作業の報酬として、僕はいくらかのお金を手にした。
でも、これは「作業」であって「仕事」じゃない。だから僕が手に入れたのは、あくまでその作業に見合っただけの賃金でしかない。
うまく説明はできないが、「仕事」というのは、それとはもう少し違うもののような気がする。
そういえば、水菜さんはもう既に選んだ側の人なんだよな、僕と同じ歳なのに。
彼女は何を思って市役所の仕事を選んだのだろう。
「いやー、大変お待たせいたしました」
汗をかきかき職員が戻ってきた。
「えーと、宇侘川猿楽保存会の無形文化財申請は平成一×年四月ですね。この前年に当市は合併しておりますから、確かに合併の混乱でうやむやになっちょったんでしょう。特にこのぶんは式年が七年と長いですけえね」
「恐れ入ります、では拝見します」
夕介は職員が差し出したねずみ色のフラットファイルを受け取った。
その瞬間、書類の間から何かがふわりと床に落ちる。
「おっと」
僕は机の下にかがんで、落ちた物を拾って机の上に置いた。
それは一枚の名刺だった。
落ち着いた若葉色の紙で、和紙に似せた細かなエンボス加工が施されており、縦書きで墨色の明朝体の文字が入った、品のあるデザインだ。
深津峡温泉 桐葉荘
桐島 年光
名刺には確かにそうあった。僕は思わず隣の夕介の顔を見た。
夕介も一瞬僕の方を見てにやりとしたが、すぐに渡された書類に目を落とした。
なんでこんなところで年光さんの名刺が出てくるのだろう?
夕介は一通り書類に目を通した後手帳にいくつかメモを取ると、年光さんの名刺をゼムクリップで書類に挟んでフラットファイルごと職員に返した。
「ありがとうございます、大変助かりました」
「お役に立ちましたか?」
「ええ、十分に。お世話になりました」
「こちらこそ、どういたしまして」
夕介は立ち上がると職員に丁寧に頭を下げた。僕もあわてて立って、汗かきの市職員に会釈した。
「な、現地に来なきゃわからないだろ?」
エレベーターに向かいながら夕介は僕に言った。
「何がだよ?」
「年光さんが、『紫桜』の無形文化財再登録申請に関わっていたことさ。書類の申請者は猿楽保存会の会長・松岡さんになっているし、関連する書類にも、年光さんの名前は一切なかった。にもかかわらず、あの名刺だ」
「それってどういうこと?」
エレベーターに乗り込んでから僕は尋ねた。
「年光さんが松岡会長の代わりに表に立って、申請手続きを代行したんだろう。行政との折衝ってのはとにかく面倒だからな。無形文化財登録されていないと市からの補助金が受けられないから、前回の奉納の時、『紫桜』は財政上のピンチだったはずだ」
「つまり、年光さんがそのピンチを救ったってこと?」
「ま、お前みたいなバカにもわかりやすいように言うなら、そういうことだ」
バカは余計だが、何となく僕にも納得できた。
しかし、年光さんは何故そんな面倒なことをわざわざ買って出たのだろう?
エレベーターが一階に着き、夕介が先に降りた。
「よし、次は観光協会だ」
そう言うと、夕介はスマートフォンを取り出して電話をかけ始めた。
第二章 桜姫(おうひめ) 〈四〉
「あー、腹立つ! 何なんだよ、あのやる気の無さっ!」
僕は車の助手席に乗り込むなり、やり場のない憤りを思わず声に出した。
「ま、そう言うな。たいていはこんなもんだ」
苦笑いしながらそう言って夕介が僕をなだめる。あれだけコケにされてなんでこんなに平然としていられるのか、僕にはまったく理解できない。
市役所での調べものが予想より早く終わったので、昼イチの予定だった観光協会の訪問を午前中に繰り上げたまではよかったのだが、そこで予想外の展開に遭遇した。
観光協会は話もそこそこに、僕らを追い返したのだ。
「せっかく地元の観光資源が雑誌に取り上げられるのに、あのリアクションの薄さは何? やる気まったくないだろ、あいつら!」
「若いなー、お前」
夕介は右手を後頭部にあててあいかわらず苦笑いを浮かべている。
「落ち着いて考えてみろ、七年ぶりの猿楽奉納が雑誌で紹介されたからって、次にやるのは七年後だろ。奉納前ならいざ知らず、事後に紹介されてもまったく客寄せにはならんさ」
「それでも、少しは地元の知名度アップには貢献するんじゃないのか?」
「さあ、それはどうかな? 今回ページをもらった月刊誌の旅グラビアは、観光資源を取り上げるタイプのページじゃないしな。ひとまず俺としては記事が載ることをアナウンスすることが目的だったから、これで十分だ」
「アンタ、自分の仕事なのになんでそんなに冷静なんだよ?」
「自分の仕事だからだよ。俺は多少なりとも自分の仕事に影響力があることを知ってるからな」
僕にはどうも納得がいかない。
夕介は悪い意味でもいい意味でも、自分の仕事にはプライドを持っていると思っていたが、そうじゃないのだろうか。
夕介はあからさまに不満そうな顔をしている僕に言った。
「どうでもいいところではけんかしない主義なんだ、俺は。お前も仕事をするようになればわかるさ。自分の思いだけじゃ、仕事にはならねーんだよ」
「それも年光さんからの受け売りか?」
僕はちょっといじわるな気分になって夕介に尋ねてみた。
「いや、数々の経験から導き出されたとりあえずの結論、てヤツだ。まあ、確かに年光さんも同じようなことは言ってたがな。結局、自分であれこれ経験するまでは、俺もわからなかった」
それを聞いても僕にはどうしても腑に落ちなかった。それは僕がまだそういう経験をしていないからなのかもしれない。
「何でも、やってみなきゃわからないだろ?」
夕介はそう言うと車のエンジンをかけた。
「これも、年光さんの口癖だがな」
昼飯は夕介がおごってくれた。
と言っても、ファストフードの牛丼だ。
僕も普段から時々お世話になる、全国チェーン店の、全国共通の味。決して不味くはないけど、いつでもどこでも同じ味だから驚きもない。
たいていの客が店に入ってから出るまで二〇分以内、速さと安さこそが取り柄の、偉大なる我ら金欠の味方。
昼のピークを少し過ぎた時間帯だったが、店の中には営業途中に寄ったと思われるサラリーマンや、建設作業員と思われる人の姿が多かった。多忙な働く人の味方、でもあるのかもしれない。
それにしても、たかだかワンコインで一日中引きずり回されるんじゃとても割に合わない。
僕は、この分を取り返すためにも、今晩の晩酌はとびきり豪勢にしようと固く心に誓った。
市の中央図書館に着いたのは一三時半ごろだった。
岩代市の中心市街地から車で一〇分程離れた住宅街の中に図書館はあった。平日だというのに駐車場はなかなか混みあっている。
「岩代市は図書館の利用者数が県内でも有数らしいぞ」
どこで仕入れたのか知らないが、夕介がそんなことを言う。
まったく、一体どこでそんなどうでもいい情報を拾うのだろうか。
「ここでは何をするんだよ?」
僕は夕介に尋ねた。
「まずは旧錦美町の町史から猿楽『紫桜』に関する記述を拾う。地元の郷土史家が『紫桜』に関して何か研究している可能性もあるから、関連しそうな書籍も確認する。それと、沓掛合戦に関する周辺資料収集、てとこだな。とりあえず、お前はコピー要員な」
つまり、夕介が指定したページをひたすらコピーする作業をしろってことか。
「時間がないからタラタラやってんじゃねえぞ」
「わかってるよ」
夕介は必ず一言多い。
資料のコピーなんて誰だってできるに決まってる。バカにするのもたいがいにしろと言いたいのを僕はぐっとこらえた。
だが作業を始めてすぐに、たいがいにしなければならないのは僕の方だということを悟ることになった。
「おい、なにモタモタしてんだよ?」
夕介は猛烈な速度で資料を選んでは、僕に次から次へと矢継ぎ早にコピーの指示を出してきた。この本の何ページから何ページ、こっちは何ページの図表と何ページの写真、これは何ページから何ページ……僕の処理速度はたちまち限界を迎えた。
「ちょっと待てよ、今やってるから」
「タラタラやるなって言っただろうが」
「うっさいなあ、ちょっと黙っててくれる?」
夕介はイライラしながら僕の作業を見ている。おかげでこっちは妙に緊張してよけいにモタついてしまう。
急いだせいで間違えて枚数ボタンを押したまま印刷をかけてしまった。次々に紙がはき出される。あわててストップボタンを押す。
「へったくそな奴だな、ちょっとは頭を使え、頭を」
夕介は机の縁を指でせわしなくたたいている。
「こっちの指示を全部覚えてやろうとするな。メモぐらい取っとけ」
「だったらリストぐらいくれてもいいだろ!」
「自分が半端なくせに人のせいにするな! だからダメなんだ、お前は」
さすがにこれには反論できない。
「コピーもロクにできないのか、ったく」
夕介が僕に聞こえるように舌打ちする。悔しいが確かに夕介の言うとおりだ。
僕のわずかばかりのプライドは粉々に打ち砕かれた。
夕介は指定した資料のページをさっとメモしてリストにまとめると、僕に手渡した。
「ほらよ。お前、このままだと社会に出てからだいぶ苦労するぞ」
僕は情けなくて、半分泣きそうになりながらコピーを続けた。
夕介が図書館職員にコピー代を支払っている後ろ姿を見ながら、僕はいたたまれない気持ちになっていた。
結局僕は口先だけで、実際には何もできない人間なんだということを、いやというほど思い知らされた。
「ったく、使えねー奴だな」
悪態をつきながら夕介が戻ってきた。僕は反撃する気力もなくじっと黙っていた。
「なんだ、お前凹んだのか?」
「……」
夕介と目を合わせることができず、僕は下を向いた。ついと押されでもしたら涙がこぼれそうなぐらい悔しい。
「先に乗ってろ」
そう言って夕介は僕に車の鍵を渡した。
図書館の外へ出ると、僕の気分とは裏腹に、さわやかな高い空一面にいわし雲が出ている。
どこからか下校途中の小学生がはしゃぐにぎやかな声が聞こえてくる中、僕はとぼとぼと駐車場を歩いた。原色のド派手なステッカーが貼ってある夕介のSUVは遠くからでもよく目立つ。
「はあぁ……」
車の助手席に座ると、思わず大きなため息が出た。こんなところで、僕は一体何をやってるんだろう?
「ほらよ」
夕介が冷たい缶コーヒーを二本持って車に戻ってきた。片方を僕に手渡すとシートベルトを掛け、すぐに車をスタートさせた。
僕は両手で缶コーヒーを握りしめたまま黙っていた。手のひらに缶コーヒーの冷たさがじんわりと伝わってくる。
夕介はステアリングを握りながら右手だけで器用にプルタブを開け、一口飲んだ。
「飲めよ」
夕介は素気なくそう言うとしばらく黙ってステアリングを握っていた。
僕もプルタブを開けて缶コーヒーを一口含んだ。
少しぬるくなった缶コーヒーは、微糖のはずなのに苦みしか感じなかった。
第二章 桜姫(おうひめ) 〈五〉
車は西へと向かって走り続けた。目的地は岩代市荷駄町にある戦国時代の古戦場・沓掛山だ。
『紫桜』のヒロイン・桜姫の父である杉山泰隆がその命を散らした場所。
荷駄盆地は旧山陽道が通る古代からの交通の要衝で、現在でも国道や新幹線、高速道路が盆地を横切っている。
図書館を出てから二〇分ほど走って峠を越えるトンネルを抜けると、視界が開けた。里山に囲まれたのどかな田園風景が目の前に広がる。
「日暮れ前に間に合うな」
夕介がつぶやいた。
車は荷駄町の中心部に入ると、中学校のそばを抜けて住宅街の狭い道に入った。
「車がどっか停められねえかな……」
道端に『沓掛山登山道』と書かれた立て看板が見えた。
「駐車場は町民グラウンド西側を利用のことって書いてあるぞ」
「じゃあ、さっきのとこか」
僕が読み上げたら、夕介は狭い交差点で何度か切り返して車をUターンさせた。
車から降りると、夕介はトランクからアルミ製のケースを取り出す。
「そういえば、アンタってカメラマンだったっけ」
すっかり忘れていたが、夕介がカメラを取り出したのを初めて見た僕は、思わず感嘆の声を上げた。
「なんだ、そんなに驚くことはねえだろ。行くぞ」
夕介はカメラを二台提げて歩き始めた。僕もそれに続いた。
沓掛山は下から見上げるとおわんを伏せたような形の小さな山だ。盆地の中で、沓掛山だけは他の山々からぐっとせり出している。
標高二四〇メートル、山頂までは約六五〇メートルと立て看板にある。
住宅の間を抜け、民家の庭先を通っていよいよ山道に入ると急に勾配がきつくなった。一面落ち葉に覆われた山道はかなり歩きづらい。それでも、一キロもない距離だし、なんてことないだろうと思って歩き始めたが、これがとんでもなかった。
「ちょ……ちょっと、待ってくれ」
「なんだ、また休憩か?」
これで三回目の休憩だ。
僕は全身汗だくになって肩で息をしているが、夕介は涼しい顔だ。
カメラを二台ぶら下げた三〇代半ばのおっさんに体力でも負けているんだから情けない。この旅が終わったら絶対に何か運動を始めよう、と僕は思った。
時々新幹線の通過する音が聞こえてくるが、それ以外は鳥のさえずりが聞こえるぐらいの静かな場所だ。
四五〇年あまり前、ここで合戦が行われて千三百人もの人が死んだとは思えない、のどかな風景。
「ほら、あと少しだから行くぞ」
夕介にうながされて、僕は何とか腰を上げた。
しばらく歩くと、勾配が少し緩やかになった。
少し先に石碑が立っている。夕介はさっとカメラを構えて写真に収めた。
石碑には『古戦場沓懸城址』と刻まれている。
「ここが二の丸の跡らしいな」
城主杉山泰隆の父・杉山宗瑚が戦死したと伝えられている二の丸だ。
本丸があった山頂まではもう少しある。僕は言うことをきかない体に鞭打ちながら、どうにか夕介についていった。
山頂には丸太造りの展望台が設えられており、沓掛合戦の顛末を記した看板がひっそりと立っているだけだった。
展望台もおよそ四メートル四方の小さなもので、天守はもちろん石垣もなく、看板がなければここが城だったとは誰も思わないだろう。
「何も、ないんだな」
僕はまだ荒い息でつぶやいた。
体力的にはかなりきつい感じだが、時間的には休み休みでも二〇分少々で登ってしまえたことになる。
「城と言うよりは砦と言った方がイメージに合うだろう」
夕介がカメラを構えながら返した。
ここからは荷駄盆地が一望にできる。僕は展望台に登ってみた。
下の方にさっきそばを通った中学校のグラウンドが見える。野球部の生徒達が練習しているのが小さく見えた。遠くの方には高速道路が見える。
「あれが連歌山。毛利氏に協力して杉山氏を攻めた、檜森高安の居城があったところだ」
夕介が盆地とは反対の方角を指さした。
木々の間から、こちらよりも少し高い山が見える。トビが一羽、そのさらに上空で輪を描いている。
「向こうからはこっち側がよく見えそうだな」
「檜森氏はいち早く毛利方について、このあたりの地理に不案内な毛利軍の道案内をしたわけだ」
僕は杉山泰隆になったつもりで、甲冑をつけた敵兵が毛利の旗指物を背になびかせながら沓掛山を包囲している様子を想像した。
味方はわずか二千六百に対し、敵方は諸説あるが約七千の軍勢。ざっと三倍弱だ。
この急峻な山肌だけが唯一の防衛線で、しかも敵方の居城はすぐ目の前に見える。そんなに高い山ではないから、包囲されている様子は手に取るようにわかったはずだ。
大内への使者は既に捕えられたから援軍も来るはずはないし、補給路もない。
多勢に無勢、普通に考えればとても勝ち目のない戦になるのは目に見えている。
自分の意志を貫いたのか、それとも周囲の状況の変化によってそう追い込まれてしまったのか。
彼にとって命を賭けてまで守るべきものって、一体何だったのだろう。
「それにしても、あの重そうな甲冑を身につけた上でさらにこの斜面を登って斬り合いするんだから、昔の人ってすごいよな」
僕が素朴な体感を言うと、夕介は可笑しそうに笑った。
「確かに、お前じゃ絶対に無理だな」
僕も思わずつられて笑った。
「さっき図書館でざっと拾った資料によれば、荷駄町では毎年十一月に沓掛合戦を偲んで祭が行われているそうだ。武者行列なんかも行われるらしい」
「じゃあ、地元じゃよく知られたエピソードなんだな、この合戦は」
「だな。麓にはひっそりとだが戦死者を埋葬した『千人塚』も残っている。しかし不思議なことに、荷駄町には桜姫に関する話は何一つないらしい。杉山氏の菩提寺に残る過去帳にも記載はないらしいからな」
「じゃあ、『紫桜』って本当にいたのかどうかもわからない人の物語なのか?」
「桜姫の存在自体、まったくの創作って可能性もあるな」
「ふーん……」
桜姫が実在していなかったのなら、『紫桜』の作者はなぜわざわざこんな哀しい物語を創作して残したんだろう?
桜姫がもし実在していたとしても、三本の異なる物語にはいずれも真実は含まれていないのかもしれない。
「不思議ついでにもう一つ。お前おかしいと思わないか?」
「え? 何が?」
「なぜ『紫桜』がわざわざ秋に奉納されるのか。普通に考えたら、桜の物語なんだから春に演るのが自然だろ?」
「確かに、そういえば」
「舞台装置として使われる『作り物』も、本物の桜の枝から葉を取って、和紙で作った花を一つ一つ貼り付けて作るんだそうだ。何のためにそこまでして秋に奉納するのか、それも全くの謎らしい」
「へえ……なんかますます『紫桜』に興味がわいたよ」
僕がそう言うと、夕介はふふっと笑った。
「俺もだ。まったく、書き甲斐がある。帰ったら資料の読み込みだ」
「アンタ、本業は写真家だろ?」
「ああ、そうだった」
僕と夕介は顔を見合わせて笑った。
帰りの車の中で、だんだんと夕闇に沈む錦美川の景色を眺めながら、僕はじっと考えていた。
たった一日の中で、ずいぶんと色々なことを僕は感じた。
僕が自分で思っている以上に何もできない人間であることを思い知らされたし、桔梗さんの美しい横顔に心揺さぶられたり、沓掛山で絶望的な籠城戦に挑んだ杉山泰隆の心情を偲んだりもした。
同じことを繰り返しているだけの毎日では、絶対に経験できなかったことだ。
ふと、夕介が言った「何でも、やってみなきゃわからないだろ?」という年光さんの口癖が浮かんだ。
確かに、わざわざ足を運んだからこそ僕はこうして色々なことを感じたわけだ。もちろん、いいことばかりじゃないけど。
「何でもやってみなきゃわからない、か」
僕は思わずつぶやいた。隣で夕介が笑う。
「どうした? 年光さんの口癖なんかつぶやいて」
「いや、ちょっとだけその意味がわかったような気がしてさ」
「ほう」
ステアリングを握ったまま夕介が感心した顔でちらりと僕を見た。
「知ってるのと実際にやってみるのとじゃ、ぜんぜん違うのかなって」
今日一日の僕の正直な実感だ。
僕は、自分の人生ではまだ何もやっていないも同然だ。あれこれ聞きかじって知った気になっていただけ。
何者でもないことで、僕はまだこれから何にでもなれるようなつもりでいた。
しかし、気づいていなかっただけで、僕はもう自分の人生を選びはじめているんだ。
だからと言って、これから何を選べばいいのかはまだぜんぜんわからない。
「だから、実際に来てみてよかったと思うよ」
「な、言ったろ。足で稼げって」
夕介はドヤ顔で言うかと思ったが、意外にも真顔だった。
「年光さんは俺の人生を変えた人なんだ。俺がフリーの写真家になったのも、年光さんのおかげだ」
夕介が広告代理店で年光さんと一緒に仕事をしたのはわずか二年だという。
「年光さんは桐葉荘を始めるために会社を辞めちまったからな」
夕介は年光さんが退職した後も個人的に親交を続けた。それぐらい年光さんには影響力があったのだという。
「だから開業当初から桐葉荘に来てたのか」
「そうだ。あれだけ仕事がバリバリできて、それなりの地位もあったのに、それを惜しげもなく捨てて自分の夢を実現させちまう年光さんのエネルギーに、俺はあこがれてたのかもな」
夕介はその後も二年間ほど広告代理店の仕事を続けたが、四年目の冬に転職した。
「お前知ってるか? 学校イベントの写真撮影を請け負う会社があるんだ」
「それって運動会とか学芸会とかの写真を撮るってこと?」
「そうだ、入学式とか卒業式もだ。ちゃんと一人一人の子どもが主役になるように、数人のカメラマンで組んで、ひたすら撮りまくる。俺が転職したのはそういう会社だ」
「へえ、そんな仕事があるんだ」
「今でもたまに手伝うこともある。同時に、有名なカメラマンのアシスタントも始めた。年光さんと出会っていなければ、俺は多分転職までは考えなかったな」
高校時代は写真部に所属していて、プロの写真家になるのが夢だったという夕介だが、大学時代に自分の才能に限界を感じて写真家になる夢をいったん諦めたのだという。
「今思えば、写真家を諦めなきゃならない理由なんてどこにもなかった。ただ、こわかったんだろうな、俺は」
「こわいって、何が?」
「本当に自分にそんな力があるのか、それでやっていけるのか。どこかに所属している方が安心できる、その時の俺はそう思ってた」
「それは、なんかわかるような気がする」
僕には夢らしい夢すらろくにないから、仕事を選ぶということは所属先を選ぶことだと思っていた。でも確かに、年光さんや夕介のように、自分の力で生きていく選択肢だってあるんだ。
「でも、年光さんはそういうのを全部かなぐり捨てて自分の夢を追った。カッコいいと思わないか?」
「確かに、カッコいい」
僕はうなずいた。
「転職の前に年光さんに相談に行ったことがある。一応自分で決めたことなんだが、本当にそれで食っていけるか、正直不安の方が大きかったからな。年光さんは俺の話を最後まで全部聞いて、いつものように言ってくれたんだ。『何でも、やってみなきゃわからないだろ』って。お前の思うように思いっきりやってみればいいって背中を押してくれた」
「それで転職したんだ」
「ああ。収入はガタ減りしたが、後悔はなかった」
夕介の顔は満足げだ。
「去年、その会社も辞めてフリーとして独立したが、その時はもう迷わなかった」
「なんでだよ?」
「年光さんはもうこの世にはいないが、こんな時に年光さんならどう言うか、俺なりにつかんでたからな」
「ふーん……」
僕にはなんだか夕介がまぶしく映った。
ちょっとうらやましかったし、ただの軽薄な奴じゃなかったんだとちょっと見直した。
「僕はまだ自分が何をしたいのか、自分に何ができるのかがわからない」
僕は夕介に言った。
「年光さんなら、こんな僕になんて言うかな?」
夕介はちょっと考えてから僕に答えた。
「それは、自分で考えるしかないな」
「だよな」
予想通りだったけど僕は少しだけがっかりした。
「ただ」
夕介が続ける。
「何でも──」
「やってみなきゃわからない、だろ?」
その続きは僕の方が先取りしてやった。
「わからないならわからないなりにやってみるよ、僕も」
「そうだな。お前にも必ず何か見つかるさ」
サングラスの隙間から、夕介がなんだかうれしそうに目を細めたのがちらりと見えた。
〈第二章終わり〉
第三章 ネンコーさん 〈一〉
錦美町に戻る頃にはすっかり暗くなっていた。
宇侘川猿楽保存会の会長・松岡寄与志さんの自宅は、桐葉荘の入口から宇侘川をさらにもう少し遡った辺りにあった。
大きな古民家の玄関で出迎えてくれたのは、七〇歳ぐらいの小柄ながらも声の大きな作業服姿の男性。この人が松岡会長本人だった。
「やー、ようおいでましたのぅた、遠いところどうもどうもご苦労さまです」
「こちらこそお時間を作っていただきまして、本当にありがとうございます。はじめまして、写真家の妹尾夕介です」
「電話では何べんも話しよったが、実際会うたらなかなかのええ男じゃねえ」
まず夕介が名刺を渡し、満面の笑みで迎える松岡さんと握手をした。
続いて僕も松岡さんと握手を交わした。松岡さんのがっしりした手が、僕のふにゃふにゃな手をしっかりと包みこむ。
「まあ汚いとこじゃが、どうぞ上がってつかあさい」
僕らは太い木の梁が堂々たる雰囲気を醸し出している客間に招き入れられた。
大きな古木で作られた座卓を挟んで松岡さんに正対する形で夕介が座り、僕もその隣に座った。
奥さんがお茶とお菓子を置いてくれ、僕は緊張と恐縮で、借りてきた猫みたいに固まっていた。
松岡さんの隣にはもう一人、メタルフレームの眼鏡をかけた三十代ぐらいのおとなしそうな男性が座っている。
「今回初めて舞台に上がる、稲村君じゃ。こちらは写真家の妹尾夕介君」
「はじめまして、稲村昂です。パン屋ですが稲村と言います」
稲村さんがごくごく真面目な顔でダジャレめいた自己紹介をするのが、なんだか面白い。
「妹尾夕介です。よろしく」
稲村さんは座卓越しに夕介と握手を交わし、続いて僕にも握手を求めてきた。
「森崎浩司と言います」
少し緊張しながら握った稲村さんの手は、やわらかで繊細そうな手だった。同世代の夕介とは全然違い、もの静かで実直な印象の男性。
「さっきまで稽古をしよったもんでな、同席してもらうが、えかろう?」
「ええ、もちろん」
「それにしても、ようこねえな辺鄙なとこまで取材に来ちゃったですのう」
「昔、桐葉荘の桐島年光さんとご縁がありまして」
「はー、それかね!」
夕介の答えに松岡さんが相好を崩した。
「一〇年前、桐葉荘がこちらに開業された時から、ずっと懇意にさせていただいております。『紫桜』のことも、以前桐島さんに教えていただいたんです」
夕介はあくまで低姿勢で松岡さんに接する。市役所の時といい、松岡さんに対する態度といい、普段とあまりに違いすぎて笑えるくらいなのだが、さすがにそんなことは言えない。
夕介の言葉に、松岡さんは懐かしそうな笑みを浮かべた。
「はあ(もう)一〇年も前になるんかねえ。桐島のネンコーさんは、なかなかの変わり者じゃったなあ。だいたい、いきなりこんな何もなあ田舎に来てから温泉宿を始めるなんぞ、そうそうできることじゃなあでの。何者じゃろうか言うてから、わしらも最初はおそるおそる見よったいね。じゃが、実際付き合うてみると、つくづく面白い男じゃった!」
松岡さんはそう言って呵呵大笑した。
「ネンコーさんがおらんだったら、『紫桜』はとうに途絶えとったかもわからん。ネンコーさんにゃあずいぶん助けてもろうてな、役所に行って書類の手続きやらなんやら、わしらが往生する(困る)ようなこともみな手合して(手伝って)くれたいね。その頃はわしもちょうど世話人を請けたばっかりでからな、右も左もわからん中じゃったから、ほんに心強かった。そのネンコーさんに縁のある人が『紫桜』を紹介してくれてんじゃけえ、ネンコーさんもあの世で喜んでじゃろうて」
松岡さんは顔じゅうを皺だらけにして語る。
「ネンコーさ──桐島さんには、僕もずいぶんお世話になりました。Iターンの先輩でしたから」
「稲村さんも移住でこちらに?」
「ええ、八年ほど前に広島から。僕は妻と一緒にもう少し川上で『ラ・ヴィ・ベル』というベーカリーカフェを営んでいます。ここは水がきれいですからね、パン作りにはちょうどいいんです。桐島さんは店の経営や広報展開の方法から、こちらでの生活に至るまで、色々とアドバイスをしてくれました。『パン屋ですが稲村です』というフレーズも、桐島さんの提案ですよ。僕と違ってすごくエネルギッシュで、ちょっと変わった人でしたね」
稲村さんは少しはにかんだような表情をしながら言う。
「ええ、だいぶ変わった人だったと思いますよ」
夕介は稲村さんにそう返して歯を見せて笑った。
「早くに亡くなられたのが、かえすがえすも残念です」
稲村さんがぽつりとこぼす。
「そういのー、わしらの後継者としてネンコーさんほど頼もしい者はおらんかったし、山代全体を、もっともっと元気にできる力を持っちょった。ほんに、残念じゃったなあ。生きとったら今頃何をしでかしよったか。まだまだやりたいことは、ようけ(たくさん)あったろうになあ」
松岡さんは腕を組んでうなった。
「あの……」
僕はおずおずと松岡さんに尋ねた。
「みんな年光さんをネンコーさんって呼んでたんですか」
昨日乗ったタクシーの青笹さんも、年光さんのことをネンコーさんと呼んでいた。
「ほうよ、としみつを音読みして、ネンコーさん。誰が言い出したんじゃったかの、言いやすいもんじゃけ、猿楽の仲間内じゃ今でもみなネンコーさんいうて呼んどる。本人も気に入っちょったみたいじゃしな」
「みんなに親しまれた人だったんですね」
僕の素朴な感想に、松岡さんは大げさなくらいうなずいた。
「地の者よりもよっぽどここを好いちょったし、じゃけえ熱うにあれこれ面白いことを考えちゃあ、すぐにやってみよったなあ。全部が全部上手ういったわけじゃなあが、だんだんに本気じゃいうのがわかったけえ、わしらもいつの間にかネンコーさんに巻き込まれちょった。あねえな者はなかなかおらんて」
松岡さんはにこにこしながら僕にそう語る。
「僕を猿楽保存会に誘ってくれたのも、ネンコーさんですよ。その方が早く地元に溶け込めるからって」
稲村さんもうれしそうにつけ加えた。
「そうじゃったなあ、わしらみたいな年寄りだけじゃあ、よう誘わんかったかもわからんな」
「僕、けっこう人見知りだったんで、誘ってもらえてよかったです。おかげでこの土地にも早くなじむことができましたし」
年光さんはよそ者だったのに、色々な人に大きな影響を与えたようだ。エネルギッシュで、積極的で、どんどん人を巻き込んでいく。僕にはない要素ばかりだ。
「ところで、猿楽『紫桜』についてうかがいたいのですが」
夕介が本題を切り出した。
「伝統のある郷土芸能とうかがっていますが、いつ頃から続いているかは、実は定かでないとか?」
松岡さんは腕を組んでうなずいた。
「文献にゃあ江戸時代の初期にはあったと書いてあるらしいがの、誰が何のために始めたんか、地元でもようわかっちゃおらんのじゃ、これが」
松岡さんによると、猿楽『紫桜』が奉納される宇侘八幡宮が大分の宇佐八幡に勧請して分社したのが十六世紀前半の室町時代後期、ちょうど大内氏の治世だ。
『紫桜』は沓掛合戦が題材になっているから、創作された時期は安土桃山時代から江戸初期ではないかと推測されているが、誰が何の目的で始めたのかは全くわかっていない。宇侘八幡宮と杉山氏にも、直接の関係はない。
この辺りは江戸時代に入ってからは三万五千石の岩代藩となり、毛利氏の分家・吉川氏が治めていた。
現在、地元の郷土史家の間で最も有力な仮説は、かつて敵対した杉山氏に対して、吉川氏がその鎮魂の意を込めて宇侘八幡宮に能装束を奉納したのが始まりではないかとされている。
しかし、ではなぜ杉山氏の居城のあった荷駄盆地ではなく、遠く離れた深津峡の宇侘八幡宮なのか、という説明がつかない。
「だいたい、近辺じゃあ神楽ばかりじゃしなあ」
当事者なのに、松岡さんもそう言って首をかしげる。
猿楽『紫桜』は、舞台上で謡や笛・鼓の音に合わせて仮面をつけた演者が舞うという基本的な形式は同じながら、能楽の常識から外れている点がいくつかあるという。
まず、専門集団による伝承ではないこと。
能楽は主役側を受け持つシテ方、脇役側のワキ方、演奏を受け持つ囃子方……というように、役割ごとにいくつかの演能流派に分かれ、それぞれが専門的な技能集団として伝承を行っている。
中世において形成された「座」が現在も形を変えて引き継がれているわけだが、『紫桜』は「野良猿楽」とも言われ、神楽と同様に一般の庶民によって伝承されてきた。
宇侘川猿楽保存会にも形式上三つの「座」と呼ばれる集団があるが、これは役割とは無関係で、三幕の物語をそれぞれで演じるためだけに便宜上グループ化されているだけなのだという。
例えば、ワキ方がシテを演じるということは普通ないのだが、ここではそういう垣根もない。事実、稲村さんは今回別々の曲でワキとシテ、両方を受け持つそうだ。
番組の構成も固定されていて、『紫桜』というのはこの奉納曲全体を指す題号なのだという。
現代の能楽では舞囃子から始まって、曲の盛り上がるところだけを舞う仕舞を二・三曲、滑稽ものの狂言を挟んでからメインイベントの能を一曲、という番組構成が一般的だそうだ。『紫桜』はすべて通して演じると五時間を超える大作で、室町時代の上演形態に近いとされている。ただ、あまりに長いのでいつの頃からか二日に分けて上演されるようになったらしい。
題材についても謎が多い。
夕介が言っていたように、能楽は古典文学や仏教説話などの著名な物語から題材が採られることが多いなか、ほとんど知られていない戦国時代の局地戦を下敷きに、一から創作されていることはその中でも最大の謎だ。
意外なことに、能楽には創作劇はほとんどないのだそうだ。
「不思議と言われりゃあ確かに不思議なことじゃが、わしらはずっとこれが当たり前じゃと思うちょったからなあ」
「地元の人以外が知る機会が、これまであまりなかったからでしょうね」
それにしても、夕介は松岡さんからするするとこれだけの話を引き出して見せた。
写真家のくせにインタビューまでこなすとは。
夕介のやけに自信満々な態度も、あながち根拠のないものではないのかもしれないとちょっとだけ思った。あくまでちょっとだ。
「本日は奉納前夜のお忙しいところ、お時間をいただきありがとうございました。また追加でお話をうかがうかもしれませんが、その際にはまたよろしくお願いします」
夕介は松岡さんと稲村さんにていねいに取材の礼を言い、僕らは席を立った。
「明日は『桜堤』から始まって、『寂水』、『乙女淵』を演りますでの。明後日がお稚児舞と『霊山』になります」
玄関先で見送りながら松岡さんがさらりと言ったが、『霊山』というのは初耳だ。僕は思わず声を上げた。
「『紫桜』は三つじゃないんですか?」
「いいや、四つじゃ。初日の三つはめいめい(それぞれ)の座で、『霊山』は皆で演るのが『紫桜』の昔からのならわしでな」
「僕はその『霊山』でシテを務めるんですよ」
松岡さんと稲村さんが意外そうな顔で教えてくれた。
午前中車の中で夕介に教えてもらった物語は三つだ。
なんで教えてくれなかったんだよ、と僕が夕介を問い詰めると、夕介もあるのは知っていたが、前回の時は仕事の都合で観ることができなかったらしい。だから夕介もあらすじを知らない、というわけだ。なんだ、知らないなら知らないと言えばいいのに、カッコつけやがって。
松岡さんによると、室町時代の猿楽には座ごとに演目の出来を競い合う「立合」という風習があったそうで、初日にそれぞれの座で演じるのはその名残ではないかという説もあるそうだ。『霊山』では座の垣根を越えて、特に優れた演者を選抜して演じるのだという。
「『霊山』は圧巻じゃけえな、今回はじっくり観たってつかあさいや」
松岡さんがにこやかにそう言って夕介の肩をぽんぽんと軽くたたいた。
「ええ、楽しみにしていますよ」
「はは、こら気合入れんといかんの。あとからまた寄合があるけえ、皆にもよう言うちょこう。もっとも、半分はこれじゃがな」
そう言って松岡さんは右手で夕介と握手しながら、左手で盃を空けるしぐさをした。夕介もそれに応じてにっと笑った。
「明日は朝から支度じゃけえ、そんとに飲めやせんがね。は、は、は」
続いて、僕も松岡さんと握手する。松岡さんの手の温かさがじんわり伝わってくる。
「明日の支度って、どんなことがあるんですか?」
僕は二人に尋ねてみた。
「舞台を設えたり、装束とか舞台道具を運び込んだり、細かいところでは掃除とか……やることはいくらでもありますよ」
稲村さんが丁寧に教えてくれる。まじめそうな風貌とメタルフレームの眼鏡のせいもあって、なんだか学校の先生のようだ。
僕は、一呼吸置いてから思い切って切り出した。
「あの、僕にも何か手伝えることはないですか?」
隣で夕介が意外そうな顔をしたが、すぐににやりとした。
「そりゃあ、若いもんがおってくれりゃあ助かるが、あんたぁええんかいの?」
「ぜひやらせてください!」
僕は即答した。横から夕介も口を挟む。
「松岡さん、俺からもお願いします。コイツ、俺の臨時のアシスタントなんですが、まだ半端者なんで、色々と鍛えてやっていただけませんか?」
「そしたら、せっかくじゃけえ頼もうかの。朝の九時半に宇侘八幡宮集合じゃけえ、ひとつよろしゅう頼みます」
松岡さんは快諾してくれた。
「よろしくお願いします!」
僕は松岡さんと稲村さんに向かって思い切り頭を下げた。
第三章 ネンコーさん 〈二〉
「どうしたんだよ、お前。ヤケにはりきってるじゃねえか」
湯船につかった夕介がにやにやしながら僕に尋ねてくる。
「別にいいだろ。何でもいいからなんかやってみたくなったんだよ」
僕は体を洗いながら答えた。
「年光さんの、何でもやってみなけりゃわからない、を実践しようと思っただけ」
「ふふん、いい心がけだな」
どうしてこう夕介が何か言うと上から目線になるのか。もう少し他の言い方だってあるだろうに、これはもうある種の才能かもしれない。
僕はシャワーで泡を洗い流した後、手桶にはった湯を頭からがばっとかぶった。
「ふー」
濡れた髪を後ろに流しながら思わず声が出る。
今日一日であちこちに行って、何人もの人と会って、ちょっと疲れたのは確かだが、なんだか心地いい。
「今日こそは露天風呂を堪能するぞー!」
僕は雄叫びをあげると、引き戸を開けて外へ出た。
温まった体にひんやりした夜風が当たって気持ちいい。
女将さんが言っていた通り、決して広いわけではないが、大きさの違う天然石を組み合わせた湯船に、竹で組まれたあずまやが一部を覆う露天風呂は、なかなか凝った造りだ。
小さな石庭の向こうには手入れされた竹林が見える。明るければ遠くの山々もよく見えるだろう。
僕は思い切り開放的な気分になる。
「おー、スゲエ!」
僕は単純きわまりない感想を口にした。
「まったく、他に言葉はないのかよ、発想の貧しい奴だな」
来なくてもいいのに夕介も露天風呂にやってきて余計なことを吐く。
「いいじゃないか、思ったことを素直に口にしただけだよ」
せっかくのいい気分も一気に半減だ。
が、湯船につかればそんなことはどうでもよくなる。
しばらくそのまま空を眺めていると、日中の疲れがじんわりと湯に溶け出していくようだ。
夕介もタオルを頭に載せ、目をつぶっている。
「な、誰もおらんじゃろ?」
カラカラと引き戸が開く音がして、壁を隔てた向こう側……つまり女湯の方から声がした。
「にひひ、ちゃあんと宿帳確認しちょいたんじゃけ! ぬかりないじゃろー、うち?」
「そうね、ほんとに、こういうことにだけは知恵が働くんだから」
もう一人の声もする。どちらも聞き覚えのある声だ。
「あー、やっぱ家の風呂とはちがうわあ、足伸ばせるんが最高!」
この声の主は果林ちゃんだ。
「ふふ、ちっちゃい果林でもそんな風に思うんだ」
こっちは水菜さん。
「ちっちゃいはよけいじゃろー! みず姉ってスタイルはええかもしれんけど、性格はほんっとにサイアクよね」
「そんなことないでしょ? こんなに優しいお姉さん、なかなかいないよぉ?」
「あはは、自分でそんとなこと言うかねー?」
僕は思わず声を上げそうになったが、夕介がにやつきながら人差し指を口に当てて黙ってろというジェスチャーを送ってくる。
盗み聞きは僕の趣味じゃないが、しかたなしに僕は黙っていることにした。
「なーなー、みず姉はなんでカレシ作らんの?」
「だって別に欲しくないもん」
「えー、なんでー? せっかくキレイに生まれたんじゃけえ、もっと楽しく生きりゃあええのにから。もしうちがみず姉じゃったら、もうウハウハじゃけどなあ」
「果林て、時々おっさんみたいだよね」
「おっさんじゃなーい! 現役女子高生ですぅー」
「いーや、中身は絶対おっさん! 純粋にエロでできたおっさん!」
「こーんなかわいい美少女をおっさんだなんて、みず姉ひどいー!」
「あはは、ひどくなんかないよぉ、真実を指摘してるだけ」
「むー、みず姉処女のくせに!」
「処女は関係ないでしょ! 果林だって処女じゃない!」
「でも、うちはカレシおるもーん! ぼっちのみず姉に言われたくないですぅ!」
こっちで男二人が聞き耳を立てているとも知らずに、姉妹はあけすけなガールズトークを全面展開している。
「なーなー、浩司さんとかはどんな? 見た感じ、けっこうええんじゃないん?」
僕は思わず全身を耳にする。
「えー、森崎さん? んー、そうだな、ちょっと頼りなさそうかな。頭はいいかもしれないけど、わたしはあんまりタイプじゃないなぁ」
あっさりと一蹴されて、がっくり力が抜ける僕。
いや、ちょっとでも期待した僕がアホだった。そもそも水菜さんみたいにきれいな人が、僕みたいな男を相手にするわけがない。
夕介が声を立てないようにして笑っている。くそ、なんて残酷な現実!
「そうやって選り好みするけえ、ハタチ過ぎてもぼっちなんよぉ! 早よ処女卒業しんさいや」
「だから、わたしはそういうのはいいの!」
「にひひ、こんなに美乳なのにねえ……」
「ちょ、果林! どこさわってんの!」
「う~ん、キレイな美乳じゃけど、どっちかっちゃあ、こまい(小さい)方の微乳かも♪」
「コラ、この! そっちなんか貧乳のくせに!」
「ひゃっ、こそばい(くすぐったい)! あはは、ちょ、やめ……みず姉! あひゃひゃ!」
壁の向こうからぱちゃぱちゃとお湯のはねる音が聞こえる。
僕は壁の向こうで繰り広げられているであろう光景を妄想した瞬間、えーと、諸事情により湯船から出ることができなくなった。
「おーい、全部聞こえてるぞー」
ここで夕介がいかにもおかしそうに声を上げた。
「げ、夕介!」
果林ちゃんが叫ぶ。
「俺だけじゃない、森崎もいるぜ」
「森崎さんも、聞いてたんですか?」
水菜さんが消え入りそうな声を上げた。
「……すいません」
僕も消え入りそうな声で答えた。
「えー、いつから聞いとったん? もう、信じれーん!」
「最初っから全部」
「ぎゃー、おっさんサイテー、ヘンタイ、セクハラー!」
「セクハラも何も、お前らが勝手にペラペラしゃべったんだろーが」
夕介が果林ちゃんに反論する。
いや待て、僕にまで黙ってろって指図したのはアンタだ!
「あー、セクハラしたくせにうちらのせいにしよる! エロ夕介のバカぁ!」
果林ちゃんが大声で夕介をなじる。夕介はあいかわらずにやにやしている。
「あっ、コラ! お前、何そんなとこよじ登ってんだよ! やめろって」
突然、夕介が妙なことを言いだした。僕は諸事情により湯船から出ることができないっつーの!
「うぎゃー、浩司さんがのぞきに来るぅ! みず姉、浩司さんにそのキレイなカラダ見したげんさいや!」
「ちょっと、果林! なに言って……」
果林ちゃんはムチャクチャなことを言ってけたけたと笑い続け、水菜さんの声はだんだん小さくなって途中で途切れてしまった。
「おい、何いいかげんなこと言ってんだよ! 登ってねえって!」
僕は湯船に身を沈めたまま叫んだ。
あー、僕の諸事情は、うー、全く改善される兆候がない。マッタク、男ってヤツはなんでこうなんだろう。
「コラ! 水菜、果林!」
突然引き戸がガラッと開く音がして、女将さんの声が響いた。
「げ、母さん!」
果林ちゃんが悲鳴を上げた。
「もう、あんたたちは! こっちのお風呂には入るなってあれだけ言ってるのに!」
「ふええ、ごめんなさいっ! でも母さん、なんでわかったの?」
水菜さんも小さくなっているようだ。
「ふっふっふー、母をナメたら、いかんぜよっ!」
女将さんがそう言うやいなや、壁の向こうからは水が勢いよく噴き出す音が聞こえた。
「冷やっ! マジ冷やっ! あわわ、母さん反則! 水は反則っ!」
「あっはっはー、これでもくらえー♪」
「冷たっ、風邪ひく! 母さんやめてぇ!」
「やめませーん♪」
どうやら女将さんはホースで水をまいているらしい。
女将さんの声は明らかに面白がっている。
「あれだけぎゃーぎゃー騒いでればわかるだろ、フツー」
夕介が苦笑している。
僕はもう、顔全体が熱くて何も言えなかった。
第三章 ネンコーさん 〈三〉
座敷に顔を出すと、既に別の宿泊客が食事をしていた。
「こんばんは」
「あ、どうも、こんばんは」
七〇代ぐらいの白髪の上品なご婦人が僕にあいさつをしてくれたので、僕もそれに答えた。隣に座る同年代のロマンスグレーの男性も会釈を向けてくれた。
どうやらご夫婦らしい。
「こんばんはー」
遅れて入ってきた夕介もあいさつをした。
「こんばんは。おやおや、今日は若い人が二人も泊まってるのか」
今度はご主人の方が声を上げた。
「それでなんだかにぎやかなんですねえ」
奥さんが穏やかな笑顔で夕介を見ながら言った。
「すみません、騒がしかったですか?」
夕介は頭をかきながら尋ねた。
「いいえ、騒いでたのは果林ちゃんと水菜ちゃんでしょ。さっきちょっと顔見せてくれたけど、あの子たちもずいぶん大きくなったものねえ」
「若い人たちはいいね、元気があって」
老夫婦はにこにこしながら話してくれる。
「あなたがたは観光で?」
奥さんが夕介に質問した。
「いえ、俺は仕事です。コイツはただの暇つぶしですが」
「暇つぶしってなんだよ!」
「うふふ、ほんとに元気ねえ」
僕らのやり取りを見て奥さんが穏やかに笑う。
「お仕事は何を?」
ご主人が興味深そうに夕介に尋ねた。
「写真家です。明日の夕方から、宇侘八幡宮で猿楽『紫桜』という珍しい郷土芸能が奉納されるので、それを取材に来ました」
「僕もそれを観に来たんです。暇つぶしなんかじゃありません」
僕もがんばって会話に加わる。
「ほう、そんなのがあるのか。だったら一日ずらせばよかったな」
「お二人は観光ですか?」
夕介がご主人に尋ねた。
「そうだね、僕らは観光というよりは湯治みたいなもんかな。毎年一回はここに泊まりに来ることにしててね」
「今年でもう七回目ですかね。いつもよくしてくださるから、ゆっくりさせてもらうのよ」
「僕の古い友人が、いい宿だから是非一度行ってみるよう勧めてくれてね。それからずっとファンになったんだよ」
ご夫婦の話を聞いていると、女将さんともう一人、四十代半ばから五十代ぐらいのふくよかな仲居さんが座敷に入ってきて、僕らの食事の準備を始めてくれた。
仲居さんは二時間サスペンスによく出演している個性派女優にどことなく雰囲気が似ている。
「鈴木様、先ほどは大変失礼しました。どうもお騒がせをいたしまして」
「いやいや、にぎやかなのもいいもんですよ」
「そうそう、家庭的な雰囲気がこちらのいいところですからね」
女将さんがお詫びを言ったが、鈴木夫妻はずっとにこにこしている。
「申し訳ございません、本当に恐縮です」
「とか言いながら、蘭さんもけっこう楽しそうでしたよ」
夕介がいらない茶々を入れた。
「うふふ、そうでしたか? でも、盗み聞きはあまりいい趣味じゃないですね、夕介さん」
ぴしゃりと逆襲する女将さん。さすがだ。
「まいったな……」
夕介はばつの悪い顔で頭をかいている。あれだけ口の悪い夕介だが、女将さんに対しては絶対に乱暴なことは言わない。
手際よくお膳が据えられ、僕らも食事を始めた。
「今日は猪肉が入りましたので、ぼたん鍋でございますよー。豚肉よりも弾力がありますが、風味は抜群ですのでお楽しみください」
仲居さんがお膳の上に置かれた簡易コンロの固形燃料に火をつけながら説明してくれた。
「おおー!」
僕は思わず声を上げた。
「なんかぜいたく過ぎて、僕みたいのにはもったいないです」
「だな、お前には牛丼の方がお似合いだ」
「よけいなお世話だ! アンタだって焼き鳥の方がお似合いじゃないか」
僕らのやりとりを見て女将さんも仲居さんも、鈴木夫妻までもがくすくすと笑っている。
「お飲み物はいかがいたしますか?」
「じゃ、ビールを」
「僕も!」
そうそう、今日一日分はきっちりいただかないと。
「では桑田さん、ビールを二本、お願いしますね」
「はい、すぐにお持ちします」
桑田さんと呼ばれた仲居さんがいったん厨房に戻る。
ビールが来て金色の液体を一口含むと、文字通り身体中に沁みるようなうまさ!
僕は今日一日何をしたわけでもなく、ただ夕介にくっついて回っただけだが、やっぱり仕事の後のビールは格別だ。
「くーっ!」
思わず声が出る。
「お前、半人前のくせに飲み方だけはいっちょ前だな」
また夕介にバカにされたが、この際そんなのどうでもいい。
「森崎さん、本当に美味しそうに召し上がりますね。見ているこちらまでうれしくなります」
女将さんがうれしいことを言ってくれる。
僕はヒラメの刺身から箸をつけた。
上品な味が弾力ある食感とともに口の中に広がる。
学生の僕にはちょっとぜいたくすぎる気がするが、やっぱり美味いものは美味い。
「うちらの若い頃は、ビールはイッキ飲みが当たり前じゃったですけど、今の若い人らはそんとなことせんでしょう?」
桑田さんが僕に尋ねたが、僕は「イッキ飲み」というのがどんなものなのか、よくわからない。
「イッキ飲みって、何ですか?」
「ふえー、ショック! その言葉自体がわからんの? 女将さん、どう思います?」
「ふふ、しょうがないよね、私たちとは時代が違うもん」
女将さんは桑田さんにほほ笑んだ。
「あー、でもなんかぶち年取ったみたいで、ショックじゃわー」
桑田さんは両手を頬に当てて顔を曇らせる。
その様子を見ていた鈴木の奥さんが声を立てて笑った。
「うふふ、だいじょうぶよ、桑田さん! 私たちよりは全然若いんだから!」
その一言で座敷にみんなの笑いが弾けた。
「そういえば、今日は市役所でちょっと意外な出会いがありましたよ」
夕介が女将さんにそう言ってからビールを口に含んだ。
「出会い、ですか?」
「年光さんの名刺が出てきたんですよ」
「年光の?」
女将さんが一瞬遠い目をした。
「猿楽『紫桜』の無形文化財登録の時の書類を見せてもらったんです。その時に、書類の間から、ぽろっと」
「あら、懐かしい。私たちもいただいいたわね、その名刺」
「ああ、あの若葉色の名刺か。うん、なかなか凝った名刺だったね。珍しいから僕もよく覚えてるよ」
鈴木夫妻もうなずいている。
「確かに、一回見たら忘れられないデザインですよね」
僕だってそんなにたくさんの名刺を見たことがあるわけではないが、個性的でセンスのある名刺だということぐらいはわかる。
「そういえばあの名刺、出来上がるまで大変だったんですよ」
夕介の三杯目のビールを注ぎながら女将さんは思い出し笑いをしている。
「何回も何回も試作を重ねて、それでも年光はなかなかうんと言わんのです。あの人、変なとこ頑固でしたから。やれ、色が気に入らないだの、エンボス加工はもっとこうしろだの。あんまり年光の注文が細かいもんじゃから、最後には印刷屋さんも、もうこれで勘弁してくれ~って音を上げて」
女将さんは印刷屋の声色まで真似して語る。
「凝り性じゃったですからね、あの人」
「あー、確かに。時々ついていけんことがありましたねー」
桑田さんも女将さんに同調する。
「なんでそこまでこだわるのか、私には全然わからんようなところに、妙にしつこかったりするの。そのくせ無頓着なとこは本当に無頓着で、若い頃はそれでようけんかしたんですよ」
「ええ? 女将さんでもけんかなんかするんですか?」
にこにこしながらそんなことを言う女将さんはとてもそうは見えなくて、僕は思わず聞いた。
「夫婦と言っても、所詮は他人ですもの。色々ありますよ」
「そうそう、そんなもんなのよ。ね、あなた」
鈴木の奥さんが隣に座っているご主人をちらりと見ながら僕に言う。ご主人の方も苦笑いしながらうなずいている。
夫婦ってそんなもんなのだろうか。奥さんどころか彼女すらいない僕には、いまいちピンとこない。
「今は、私も同じデザインの名刺を使うてます。年光のこだわったものって、不思議と人の印象に残るんですよ、なんだか悔しいですけどね。ほんとに、つくづく変な人でした」
女将さんは茶目っけたっぷりにそう言った。
「そういえば、年光さんにとっては、『変な人』っていうのは褒め言葉だったなあ」
夕介はビールの泡を見つめながらしみじみと言う。
「変な人って言われて喜んでる時点で、既に変な人ですよね」
ふふっと女将さんが笑う。
年光さんはそれだけ個性的な人だったということなのかもしれない。
「あの、女将さん」
僕はいったん箸を休めて女将さんに聞いた。
「年光さんの写真ってありますか?」
「ありますよ。ご覧になりますか、森崎さん?」
「見たいです。なんだか色々と話を聞いてるうちに、年光さんって一体どんな人なのか、すごく興味がわきました」
「じゃったら持ってきますね。ちょっとお待ちください」
そう言うと女将さんはすっと立ち上がって座敷から出ていった。
「はは、桐島君は死んでからもモテるなあ」
鈴木さんのご主人がいかにも楽しそうに笑った。
「そうね、私たちも初めてお会いしてすぐに桐島さんのファンになったものね」
「老若男女問わず、年光さんのファンは多かったですよ、会社勤めの頃から。俺だってその一人かもしれません」
「お客様にも、亡くなられたことを知らんといらしてから、びっくりされる方が、今でも時々おられます。本当にファンの多いかたでした」
夕介たちの会話を聞きながら、僕はなんだか不思議な気分だった。年光さんは五年も前に死んでしまったから、僕が今から年光さんに会うことなんてできないのに、なぜだかすごく身近に感じる。
「お待たせしました」
女将さんが小さな写真立てを持って戻ってきた。
「これが私の主人、桐島年光です」
黒縁の写真立ての中から精悍な中年の男性が、満面の笑みで僕を見つめていた。
この人が年光さんか。
カッコいいおじさんという印象だが、少し下がり気味の目じりのおかげで優しい雰囲気を放っている。ああそうか、この目は水菜さんと一緒なんだ。
「いつもカウンターの内側に置いちょるんです。すごくいい笑顔でしょ? こう見えてもこれ、遺影なんですよ」
女将さんが笑いながら僕に言った。
「生前に年光が自分で選んだんです、これがいいって。遺影にするんだからもっと真面目な顔の写真にすればええのにってその時は思ったんですけど、やっぱり、これでえかったんじゃなあと、今は思います。あんまりにもあの人らしいけえ」
女将さんが少しさびしげな微笑を浮かべた。
「なんだかすごく優しそうな人ですね、話に聞いているとおりだと思います」
僕は写真から受けた印象を素直に言葉にした。
「うふふ、一緒におるとあんまりそうは思わんかったですよ。むしろわがままな子どもみたいな人で」
女将さんはいたずらっぽくほほ笑んで続けた。
「だからこそ、いつもわくわくどきどきさせてくれたんですけどね」
僕はもう一度年光さんの遺影を見つめた。
広告代理店の第一線でバリバリと仕事をしていたのに、突然それをなげうって温泉宿を始めてしまう破天荒な人物。
夢を語るだけじゃなくて、それを粘り強く実現する強い意志を持った男。
なぜか色々な人から好かれ、周囲の人をあっと言わせつつも、いつの間にか自分のペースに巻き込んでしまう、不思議な魅力を持った人。
これから自分がどこに向かえばいいのかわからず道に迷っている僕には、年光さんの笑顔がとてもまぶしく見える。
「カッコいいよな……」
僕は思わずつぶやいた。
第三章 ネンコーさん 〈四〉
部屋に戻ってからも、僕はしばらく年光さんのことが頭から離れなかった。
夕介は部屋に戻って昼間集めた資料を読み込むというし、鈴木夫妻も部屋に戻ってゆっくりされるということだったから僕も自分の部屋に戻ったが、やることがない。
テレビもつけず、布団の上にごろりと仰向けになって天井の蛍光灯をにらむ。
僕は、満面の笑みをたたえた年光さんの遺影を思い出しながら、これまで聞いた年光さんのことを思い返してみた。
夕介から見た仕事の先輩・人生の先輩としての年光さん。
女将さんから見た夫としての年光さん、桑田さんから見た経営者としての年光さん。
保存会の松岡さんから見た移住者として、そして稲村さんから見た移住の先輩としてのネンコーさん。
鈴木夫妻や昨日乗ったタクシーの青笹さんだって、今でも強い印象を持ち続けている。
そういう僕だって、年光さんには一度も会ったこともないのに、夕介から教えてもらった「何でもやってみなきゃわからないだろ?」という彼の口癖が、妙に心に引っかかっている。
たくさんの人たちに、たくさんの影響を残して、四一歳という若さで風のようにこの世を去った年光さん。
「でも、どうやったらそんな風に生きられるんだ?」
僕は思わず声に出して言った。
年光さんは確かにすごいけど、なんだか遠い世界の人のような気がする。
あこがれはしても、社会に出る手前でうろたえている僕にはとてもそんな生き方はまねできそうにない。
突然、部屋の扉をノックする音がした。
「あの、森崎さん?」
外から女性の声がした。水菜さんだ。
僕はあわてて扉を開けに行った。
「どうしたんですか、水菜さん?」
「ごめんなさい、少しお話したくて……今、いいですか?」
「ええ、いいですけど」
水菜さんは前髪を下ろし、黒縁の眼鏡をかけていた。水色のパジャマの上に淡いオレンジ色のカーディガンを羽織っていて、ほのかにいい香りがする。最初の印象とずいぶん違うので僕は少しどぎまぎした。
何気なく水菜さんの胸のふくらみに目をやりかけて、はっと気づいてあわてて目をそらす。
さっきの微乳の話がまだ強烈に頭に残っているんだ。くそ、これだから男ってやつは。
「森崎さん、ロビーでお話ししませんか?」
なんだ、僕の部屋でじゃないのか、と僕は少しがっかりする。
水菜さんはロビーに出ると、ソファに腰かけた。
正面に向き合うのもなんだか照れくさいし、隣同士じゃなれなれしすぎる。
ちょっと考えて、僕は水菜さんと直角に向き合う位置に座った。
間接照明のやわらかな光に包まれた水菜さんは、どことなく艶っぽく見える。何もないとわかっていても、それでもどこかで期待してしまう自分が、どうにも面倒くさい。
水菜さんはちょっと間をおいてから話を始めた。
「あの、さっきはごめんなさい、すごく失礼なこと言っちゃって。まさか森崎さんが聞いてるなんて思いもしなくて……。ちゃんと謝っとかなきゃって思ったんです」
「いや、黙って聞いてた僕らも悪いですから。水菜さんは全然気にしないでください」
と口では言ったが、全面的に悪いのは夕介だと僕は内心叫んでいた。
まったく、あのおっさんのおかげでろくなことがない。
「あの、森崎さん」
水菜さんは僕の方にぐっと身を乗り出すと、じっと僕の目を見つめて、はっきりとした口調で言った。
「わたしを、どこか遠くに連れてってくれませんか?」
「え──」
僕は驚いて言葉を失った。彼女の息づかいを目の前に感じ、急に心臓の鼓動が早まる。
どこか遠く──どこか遠くって、でも一体どこに?
眼鏡の向こうから、水菜さんが真剣なまなざしで僕の顔を見つめている。
僕はその視線に耐えきれずに目をそらしてしまった。
すると、水菜さんもすぐに目をそらして下を向いて笑った。
「ふふ、なんてね。うそうそ、冗談ですよ。ちょっと言ってみただけです」
いや、あわてて作り笑いで冗談めかしてごまかしてはいるが、あれは間違いなく本気の目つきだった。
僕には水菜さんが一体何を考えているのかがさっぱりわからない。
気まずい空気が流れる。
水菜さんは下を向いたまま何かを考えているようだ。
お互いしばらく沈黙が続いたが、不意に水菜さんが僕に尋ねた。
「あの、森崎さん、私のことどう思います?」
「どうって言われても……」
正直、唐突すぎて返答に困る。
僕は自分のボキャブラリを総動員して考えた。
「えーと……、そうだな、きれいな人だなって思いますよ。優しそうだし、もしもこんな人が彼女だったらいいなー、なんて」
総動員したわりには我ながら気の利かない答えだなと思いながら、僕は答えた。
水菜さんは両手をひざの上に置いて首を横に振る。長い髪がさらりと左右に揺らぐ。
「わたし、全然優しくなんかないですよ。高校の頃、告白してきた男子を全員ふっちゃったんですから」
午前中夕介から聞いた話はうそじゃなかった。しかし、まさか水菜さん本人からそれを聞くことになるとは思わなかった。僕はぎょっとしてまじまじと水菜さんのことを見つめたが、彼女は僕のことをちらりとも見ようとしない。
「わたし、学校の成績だけはよかったので、岩代の進学校に通ったんです。先輩とか、同級生とか、たくさんの男子から告白されたけど、父が亡くなってすぐだったから、ぜんぜんそんな気になれなくて。それに、『男子とつきあう』ってことが、なんかよくわかんなかったし」
水菜さんは右手を自分の胸元に置き、おさえたトーンで話を続ける。
「告白してきた男子は、みんな森崎さんとおんなじこと言ったんですよ。きれいで、優しそうだって。でも、ほんとのわたしはきれいなんかじゃないし、優しくなんかもない」
「そんなことないですよ!」
僕はあわてて否定したが、水菜さんはかぶりを振った。
「わたしをきれいだなんて言う人は、わたしの外見しか見てないでしょ? 『見栄えのいい彼女』っていうアクセサリーが欲しいだけなんじゃないですか、違います?
わたしのことは、わたしが一番よくわかってます。わたしなんて、本当は醜くて、卑屈で、臆病で。ほんとに、果林の言うとおり性格最悪。人を傷つけてばかりだし。
どれだけ見栄えよくしても、結局外面だけなんです、わたしなんて」
水菜さんは鋭い口調で一気にそう言った。
僕は圧倒されて何も返すことができない。
「わたしは、そんな自分がどうしても好きになれないの。だから、何も知らないくせにわたしのことを好きだなんて言う人のこと、わたしは絶対に信用できません」
水菜さんはそこまで言い終わると、再び下を向いた。
ズキンと胸が痛む言葉だ。
「でも、水菜さんは桔梗さんのためにも色々したんでしょう? 十分優しいじゃないですか」
「森崎さんは、桔梗のことも知ってるんですね──でも、わたしは長女ですから、妹のためにあれこれするのは当たり前じゃないですか。父を亡くして一人でがんばってる母に負担かけたくなかったし、ここにいれば母を手伝うこともできる。
──だから、あえて進学しないで地元で就職するって自分で決めたんです。母は進学を勧めてくれたけど、市役所なら試験で入れるから」
なるほど、水菜さんが市役所に就職したのには、そういう背景があったのか。
進学校からあえて就職を選ぶというのもかなり思い切った選択だ。そういう意味では、水菜さんは相当に意志が強いのだろう。
でも、水菜さん自身の希望はどうなんだろう?
水菜さんは本当にそれを望んでいたのだろうか?
僕がそう言いかけたら、水菜さんは右手を胸元に当てて天井を仰いだ。
「父がこんなところに越して来なければ、早く死んだりしなきゃ、わたしも普通に大学に行ってたのかも──」
僕の背筋に一瞬冷たいものが走る。
もしかしたら彼女の本音は、そこにあるのかもしれない。
「水菜さんって、こっちに引っ越してきたとき何歳だったんですか?」
「一〇歳でした、小学四年のときです。仲のいい向こうの友達と別れたくなくて、めちゃくちゃ泣いたんですよ」
僕は黙ってうなずきながら水菜さんの話を聞く。
「こっちに来てみたらものすごく小さな学校で、全校生徒も数えるほどしかいなくて、何もかもが前いたところと違って、わたし、また泣いてしまって。こんなとこイヤ、友達がいっぱいいた前の学校に帰りたいって。しばらくは前の学校の友達と手紙をやりとりしてたけど、だんだんと少なくなって、いつの間にか途切れちゃいました。新しく友達を作ることもなんだかうまくできなくて。──その小学校も、わたしが卒業した年には休校になっちゃったし」
水菜さんは両手をひざに置いて下を向いている。
「いつかはあっちに帰りたいってずっと思っているうちに、父が死んでしまって、それもできなくなっちゃいました」
そう言ったきり、しばらく水菜さんは黙ってしまった。
僕の方も、なんだかいたたまれない気持ちでいっぱいになって、何も言えずにいた。
周囲の人たちからあれだけ好かれた年光さんが、実の娘からはむしろ恨まれている。
彼自身は夢を実現し、短いながらも充実した人生を歩んだのかもしれないが、少なくとも水菜さんは、こっちに越してくることを望んではいなかった。水菜さんが十年暮らしてもこっちの方言を一切使わないのは、もしかしたらそれも理由なのかもしれない。
しかし、進学や就職をきっかけにして、ここを出ることを選ぶこともできたはずなのに、それでも彼女はあえて外に出ないことを選んだ。一体なぜ?
「ごめん、水菜さん。その、何と言ったらいいのか──」
僕は、何とか水菜さんをなぐさめられそうな言葉を探したが、残念なことに何も思い浮かばなかった。どうでもいい言葉ばかり知っているくせに、肝心な時に言いたい言葉が見つからない。
「いいえ、わたしの方こそごめんなさい。こんな話、森崎さんなんかにしてもしかたないって、わたし自身が一番よくわかってるのに。あーあ、何やってんだろ、わたし。バカみたい」
彼女は僕から目をそらしたまま自嘲的につぶやく。
「あの、森崎さんにはきっと、わたしなんかよりもっとずっとお似合いの人がいますよ」
水菜さんはやっと顔を上げて僕にそう言った。
年光さん譲りの彼女の優しそうな目からは、無理矢理にほほ笑んでいるのがわかって、なんだか痛々しかった。
「ごめんなさい、森崎さん。おやすみなさい」
水菜さんはすっとソファから立ち上がって僕に会釈すると、振り返りもせずに母屋に戻っていった。
僕はしばらくソファから立ち上がれなかった。
何だろう、この圧倒的な敗北感。
謝られたのは僕の方のはずなのに、ひどく心が重い。
待てよ、これってもしかして、告白もしないうちにふられてしまったということじゃないのか?
昼間夕介が言った、「あいつはだいぶこじらせてるからなあ」という言葉が、今ごろになってじわじわ効いてきた。
第三章 ネンコーさん 〈五〉
身体は疲れているのに眠れない。
布団の中で右に左に向きを変えるが、目は冴えたままで、まったく眠れる気がしない。
「あー」
布団の上に両腕を出して僕は声を出した。
無理だ、眠れない。
今日だけで色々なことがありすぎて興奮しているのだろう。
特に、水菜さんの話は強烈すぎた。
だいたい、水菜さんは昨日今日会ったばかりの僕に、なんであんな話をしたんだろう。普通は会ったばかりの人にする話ではないだろう。
それによく考えてみると、彼女は自己否定しているだけでなく、それを通して僕のことも否定している気がする。
あなたはわたしの表面しか見ていない、あなただって空っぽのくせに。
言葉にこそ出さなかったけれど、彼女は僕の正体を鋭く突いた。
水菜さんが指摘したような薄っぺらな願望が僕の中にあったのも確かだし、十代からずっと僕に彼女がいないのも、結局は僕に中身がないからなんだと思う。
どれだけきれいだ、優しそうだ、なんて表面だけちやほやされても、彼女の心は決して満たされない。彼女が本当に認めてほしいのはきっと、そんな外面じゃなくて、素の彼女自身。
中身がないのは僕だって同じことだ。いや、僕の場合、水菜さんとは違って外面すらないから、さらに救いがない。
だからこそ、僕には水菜さんの言葉が痛かった。
それでも。
自分を好きだと言ってくれる人のことを信用できないだなんて、あまりにも悲しすぎる。僕や水菜さんの空っぽの心は、一体どうしたら満たすことができるのだろう。
時計を見ると午前一時を少し回ったところだ。
どうせ眠れないのなら、眠くなるまで起きておこう。
僕は布団を抜け出した。
ちょっと気分転換をしようと思って、僕は浴衣の上にパーカーという珍妙ないでたちで外に出た。時間が時間だから誰かに見られるということもないだろうと思っていたが、玄関を出たところで僕は驚いて思わず声を上げた。
「桔梗さん!」
門のところに、朝と同じ白い着物姿の桔梗さんが立っていた。
常夜灯の光に青白く浮かび上がった彼女の姿は、どこか非現実的で、この世ならざるものを感じさせる。彼女のつややかな黒髪が、光をかすかに返して、やわらかく光っている。
桔梗さんは僕の方を見ると、すっと音もなく歩み寄ってきた。
線香のような香りが僕の鼻腔に届く。
「あなたは、誰?」
か細い声で桔梗さんが僕に尋ねてきた。
僕はまた驚いた。
確か、果林ちゃんの話では桔梗さんは一切しゃべらなくなっていたはずだ。実際、今朝いっしょに日の出を眺めた時も、彼女は一言も発しなかった。
彼女の黒目がちな瞳が、まばたきもせずにまっすぐに僕の眼を射抜いている。
「桔梗さん、しゃべれるの?」
彼女はゆっくりとうなずいて、再び口を開いた。
「あなたは、誰?」
今度はさっきよりもはっきりと聞こえた。
「僕は、森崎浩司。学生だよ」
僕は自己紹介したが、なんとなく彼女が尋ねているのはそんなことではないような気がする。しかし、他に答えようもない。
「こんな時間にどうしたの? 寒くない?」
僕が問うと、彼女はふっと目を伏せて首を横に振る。
「会えるような、気がした」
表情はまったく変わらないままだが、この一言になんだか僕はほっとした。
「ひとまず中に入ろうか、冷えるから」
僕がそう言うと、彼女は黙ってうなずいた。
玄関を入ると、夕介が泊まっている梅の間から明かりがもれているのが見えた。夕介はまだ資料を読み込んでいるのか、それともそのまま寝てしまったのだろうか。
桔梗さんにソファに座るよう促すと、彼女はソファに浅く腰かけて僕を見た。
こうして改めて桔梗さんと向き合うと、やっぱり彼女も女将さんとよく似ていることがよくわかる。
黒目がちな大きな目は一番の特徴だ。じっと見ていると吸い込まれそうな、神秘的な光をたたえている。
桔梗さんは果林ちゃんの一つ上だから、一六歳か一七歳。普通なら高校二年生だ。
果林ちゃんと同じようにちゃん付けで呼んでもおかしくない年齢だが、何と言うか、彼女のまとっている雰囲気がそれを拒んでいる気がする。
彼女の白い顔は、間接照明のやわらかな明かりのもとでは本当に能面のようだ。
能面の表情のことを中間表情と言うそうだが、喜怒哀楽のどれでもないから、逆に雄弁に感情を表現することができると、どこかで聞いたことがある。
桔梗さんも、その無表情の奥から何かを僕に語りかけようとしている気がする。
だが、鈍感な僕はそんな気がするだけで、残念ながら彼女が何を語りかけようとしているのか、まったくわからない。
しかたがないから、言葉で尋ねるほかない。
「なんで、僕に会えるような気がしたの?」
我ながら見当はずれな質問だなと思いながら、僕は桔梗さんに尋ねた。
「わたしが、会いたいと、言ったから」
桔梗さんは僕をじっと見つめたまま小さくそう答えた。
なんだか奇妙な答えだ。
会いたいと言ったから会えるなんて、そうそう都合のいいことがあるはずがない。
彼女は少しも僕から視線を外さずにじっと座っている。
揺らぐことのないその瞳に、僕は少したじろいだ。
が、不思議と彼女から威圧感を感じることはない。
「何故……、あなたは、ここに、来たの?」
桔梗さんは、一言ずつゆっくりと、自分の言葉を確かめるように僕に尋ねた。
「あ、えーと、猿楽『紫桜』を観に来たんだ。明日からあるんだけど、知ってるかな?」
桔梗さんは小さくうなずいた。
「で、何となくそれに興味がわいて、実際に観てみたくなってここに来たんだ」
桔梗さんは表情を変えずにじっと僕の話を聞いている。いや、うなずきもしないから、本当に聞いているのかどうか、少し不安になる。
「この『紫桜』には、いくつも不思議な点があってね、主人公は同じなのに四つも違う物語があるらしいんだ。結末は全部違って、どれが本当かわからないし、主人公の桜姫という人が本当にいたかどうかもわからないんだって。どの話も桜姫は哀しい最期を迎えるみたいなんだけど、合戦でお父さんが死んだ──」
と、ここまで話したところで、桔梗さんが一瞬身体を震わせた。
しまった、調子に乗ってしゃべりすぎた。彼女にショックを与えてしまったかもしれない。
彼女は父親の死後にしゃべらなくなったというんだから、何か関係があるのは間違いないだろう。
もう少し慎重になるべきだった──と反省しても、もう遅い。
「ごめん、辛いこと思い出させちゃったかな?」
僕はおそるおそる桔梗さんに尋ねた。
彼女は首をゆっくりと横に振る。
僕は少しほっとした。
「話を変えよっか。桔梗さんはいつもああして朝日を眺めてるの?」
僕は朝から気になっていたことを尋ねてみた。
桔梗さんはゆっくりとうなずいた。
「どうして朝日を見るようになったの?」
「……生まれ、変わるの」
桔梗さんはすっと遠くを見るような目をして続けた。
「未来の王国。青い、こども。あけぼの。わたしが、持ってきたもの──」
何だろう? 謎かけのような言葉だ。
その先に何か言葉が続くような気がして、僕はしばらくじっと待っていたが、彼女がそれ以上言葉を継ぐことはなかった。
「そっか、生まれ変わるのか」
よくわからないまま、僕は彼女の言葉を繰り返したが、僕の頭の中は疑問符でいっぱいになった。
彼女の言葉はあまりにも断片的すぎる。何か大事なことを示そうとしていることだけはわかるが、具体的に何を指し示そうとしているのかがよくわからない。
それにしても。桔梗さんはなぜ、見ず知らずの僕と話す気になったのだろう?
彼女はやっぱり表情のないまま僕をじっと見ている──いや、もしかして微笑しているのではないか?
一瞬の光の加減のせいかもしれないけれど、僕はそう感じた。
僕がそれを口にしようとすると突然、桔梗さんはすっと立ち上がった。
「どうしたの?」
「ありがとう」
桔梗さんはゆっくりとそう言うと、軽く頭を下げた。
彼女は玄関まで歩いていくと、そのまま外へ出てしまった。
あっけに取られた僕は、立ち上がることも忘れ、彼女を目だけで見送った。
「一体、なんだったんだろう?」
声に出してそう言ってみた。
やけにリアリティのある夢を見て目覚めた後の、現実と夢との区別がつかない奇妙な感覚と、よく似ている。ロビーに自分の声が空しく響くのを聞いて、とりあえず夢ではないということはわかった。
桔梗さんが僕に何を伝えたかったのかは、結局何ひとつわからない。
でも、僕は何となく安心していた。
少なくとも、僕は彼女から拒まれたわけではないようだ。もちろん、変わった子だなとは思うけど。
しばらくソファに座ったままぽかんとしていたが、僕は自分の部屋に戻ることにした。時計を見るとちょうど午前二時だ。
「ふあ……」
さすがにあくびが出てくる。
今度はどうにか眠れそうだ。
僕はパーカーを脱いで蛍光灯を消すと、そのまま布団の中にもぐりこんだ。
何かを考える間もなく、僕はすぐに眠りの底に落ちた。
〈第三章終わり〉
第四章 呪い 〈一〉
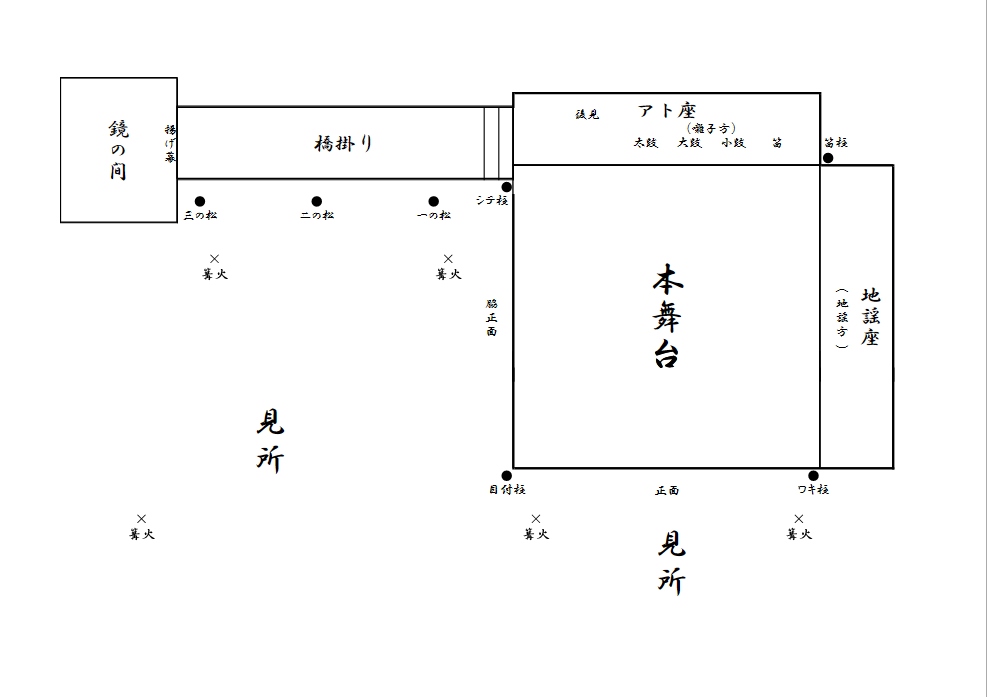
「おう、学生さん、次はこっちじゃ」
「はい!」
「こいつ押さえちょれ」
「了解です」
僕は伊藤さんに指示された通り、青竹を抱えて動かないように押さえた。その間に伊藤さんがあらかじめ地面に打たれた杭に青竹をひもで堅く結びつけ、しっかりと固定する。
空は雲ひとつない快晴で、十月もなかばだというのに気温もぐんぐん上がっている。額に汗が浮かぶのを感じる。
青竹を押さえたまま、僕は空を仰いだ。ここだけ木々が切れて開けているから、遥か上空でトンビがのんびりと輪を描いているのが見える。
「おし、次こっちな」
「はい!」
僕が押さえた青竹は舞台の四隅に柱のように立つようだ。
盛り土の上に組まれた板敷の舞台の上では、松岡さんたち数人の男性が拭き上げの作業をしている。
猿楽『紫桜』は薪能として屋外で行われるのだという。
地域の人々に僕も加わって作業すること二時間、僕はただ指図された通りに物を運んだり置いたりしただけだが、最初はただ盛り土があるだけで、まるで相撲の土俵のようだった場所が、板敷きがされ、宇侘八幡宮の紋の入った白い幕が張られ、みるみるうちに舞台としての姿を整えていく。
「後で篝火が焚かれりゃあ、ぐっと雰囲気も出るぞ」
伊藤さんは僕にそう言ってニッと笑った。
今朝からずっと、僕はこの伊藤さんについて作業している。
四十代後半ぐらいだろうか、普段は森林組合に勤めているという伊藤さんは、短く刈り込まれた髪に赤黒く日に焼けた肌で、腕も胸板もたくましく盛り上がっている。僕の頼りない身体とは根本的につくりが違うとしか思えない。
でも、幻想的な猿楽のイメージと目の前の武骨な伊藤さんのイメージとがどうしても結びつかなくて、なんだか笑える。
「なんか不思議ですねえ」
僕は伊藤さんに言った。
「何もなかったところが、あっという間に舞台に変わっていくのが面白いです」
「じゃろう? 七年に一度、ここでしか観られん、幻の舞台じゃ」
伊藤さんは誇らしげに言うとまたニッと白い歯を見せた。
宇侘八幡宮は鬱蒼とした杉林の中にひっそりとたたずんでいる。
苔むした石垣の上に建つ今の本殿は江戸時代の中期に建てられたものらしいから、築三百年ぐらいのはずだ。
樹齢が数百年はありそうな大きな杉の木が何本もあり、自然と背筋が伸びるような凛とした空気が流れている。
猿楽『紫桜』が演じられる舞台は、宇侘八幡宮の本殿から一段下がった参道脇の、普段は何もない広場のような空間だ。
高さ五〇センチ程度の盛り土の上に組まれた舞台は、本殿に向かって正面となるように設えられている。投光器や発電機なども運び込まれ、今、舞台の周りは活気に満ちている。
先ほど据え付けた四本の青竹は、三間(約六メートル)四方の本舞台を区切る目印なのだ、と伊藤さんが教えてくれた。
舞台に向かって左手前が目付柱、その奥がシテ柱、右手前はワキ柱、その奥を笛柱と呼ぶらしい。面をつけた演者にとっては、舞台の距離感を測る大事な目印になる。
本舞台向かって右側は地謡方が座る地謡座、奥には囃子方や後見が座るアト座と呼ばれる空間がある。
アト座の背後には、元々植えられている枝ぶりの見事な古い松の木が見え、その向こう側には杉の林が広がっている。
アト座から左奥に向かって伸びている通路のような空間は橋掛りと呼ばれ、単なる入退場のための通路というだけではなく、本舞台とは別の演技空間でもあるらしい。盛り土がないところに架台を立てた上に、本舞台と同じ高さに板敷きが設置されている。
橋掛りの手前には三本の若松が等間隔で立てられていて、舞台に近い方から順に一の松、二の松、三の松と呼ばれる。演者にとっては距離感を測る目印であり、演目によっては時間や距離を表すこともあるそうだ。
橋掛りの奥には幕で仕切られた鏡の間が置かれる。
鏡の間と言っても、『深津小学校』という文字の入った天幕を張った周囲を白い幕で囲ってたたみを入れただけで、これはいわば楽屋にあたる空間だ。
中には大きな姿見が置かれた。それで鏡の間と呼ばれる。
昔は奉納の時だけ掘立小屋を建てたんじゃ、と伊藤さんが教えてくれた。
鏡の間の出入り口には揚幕という五色の幕が掛かり、演者が橋掛りを出入りする際には素早く持ち上げられるようになっている。
舞台全体でも十数メートル四方、決して広い空間ではない。
この小さな空間でどのような物語が展開されるのか、だんだんとわくわくしてくる。
「あんたぁ観るのは初めてじゃろうがね?」
「はい、そうです」
「じゃったら、正面の一番後ろのあの辺りから観いや。あんまり舞台の近くじゃと火の粉はかかるし、首は痛うなるし、はっきり言うてええことがないけえな。正面後ろからじゃったら舞台の全体がよう見える」
伊藤さんはそう言ってにやっと笑った。
「伊藤さんも出演するんですよね?」
「おお、わしゃあ『寂水』の大鼓方じゃ。そらあ、観るより演る方が何倍も面白い」
かかか、と伊藤さんは豪快に笑った。
やっぱりどうもイメージが結びつかない。
「勲君よ、そろそろ休憩にしようかいの」
「お、ええな。学生さん、一休みじゃ」
作業服姿の松岡さんが僕らに近づいて声をかけてきた。「いさお」の「さ」にアクセントがついているのがこの辺りの方言の特徴。
「ネンコーさんがおらんようなって、若手がますます少のうなったなあ」
「いやいや、学生さんがおるぞ。のう、学生さん」
伊藤さんはそう言って笑いながら僕の背中をポンと叩いた。僕は思わずよろけてしまう。
「はっはっ、もうちぃと食わにゃあ力が出まあ!」
伊藤さんがよろめいた僕を見て豪快に笑う。
「勲君よ、ちったぁ手加減しちゃれや……学生さん、相方の妹尾君は今日どうしよるんかいね?」
松岡さんが苦笑いをしながら僕に尋ねた。
「なんか今日は寂水峡とか乙女淵の写真を撮ってくるらしいです。徹夜で資料を読み込んだっていばってました」
相方なんて言われるとますますお笑いコンビみたいでなんかいやだ。
「ははあ、熱心なことじゃなあ。さすがはネンコーさんの有縁じゃのう」
松岡さんは顔をほころばせる。
「こりゃあ、わしらも負けんようにしっかりやらにゃあ」
「当たり前じゃ、わしらはいつじゃって全力投球じゃろう」
伊藤さんが熱血ドラマのようなセリフを言うが、僕からすると幽玄な猿楽には場違いな気がしてしょうがない。
「僕も楽しみにしてます」
「はは、なかなかのプレッシャーじゃなあ」
そう言って笑う松岡さんは、『乙女淵』でシテの桜姫を務めるのだという。
目の前の白髪交じりの松岡さんが少女を演じるなんて、やっぱり想像がつかない。
「こんちはー、お疲れ様でーす! 差し入れっすよー!」
境内によく通る元気な女の子の声が響いた。果林ちゃんだ。
「おー、果林ちゃんか! いっつも元気じゃなあ!」
松岡さんが孫でも見るように目を細めた。
果林ちゃんは仕出し屋が使うような大きな白いプラスチックケースを両手で抱えてこっちに駆けてくる。
少し大きめの薄手の黄色いパーカーの下に白のTシャツ、デニムのショートパンツで、髪は初めて出会ったときと同じようにポニーテールにしている。かわいいんだけど背が小さいせいか、なんだか小学生みたいに見える。
少し遅れて水菜さんも同じようにケースを抱えて境内に入ってきた。
上品なふわっとした白い長袖のワンピースに、レースのショールをまとった水菜さんは私服でも華やかなオーラを放っている。
でも、昨晩彼女のこじらせぶりを知ってしまった僕としては、なんだか複雑だ。そんな風には全く見えないのになあ。
果林ちゃんはケースを抱えたまま松岡さんと立ち話をしている。
「母さんに言われておにぎり持ってきたよ。みんなで握ったんじゃけど、うちのもちょっと混じっとる」
「はは、見りゃあすぐわかる。この不細工なぶんじゃろ?」
「えー、なんでわかるん?」
「わかるいね、果林ちゃんのことなら何でもわかる」
こうして見ていると本当に祖父と孫のようだ。
「あのすいません、どこに置きましょうか?」
水菜さんが松岡さんに尋ねた。
「本殿のそばに天幕を立てちょるから、そこに持ってってくれるかいね?」
「わかりました」
「あ、僕も運ぶの手伝いますよ」
僕は水菜さんに声をかけた。
「じゃあ、お願いできますか? 車は裏の駐車場に停めてますから」
「わかりました」
水菜さんは先に奥の方へ消えたが、果林ちゃんはケースを持ったまま僕に話しかける。
「浩司さん、みず姉にふられたんじゃろ?」
果林ちゃんは僕に近寄るとにひひ、と笑いながら耳打ちした。
「な、何もないよ! ふられるも何も、そんなんじゃないし!」
「ふーん、そうなんじゃー。がんばってねー♪」
果林ちゃんは再びにひひと笑うと、スキップでもするように本殿の方へ跳ねていった。
本殿の裏手に回ると、後部ハッチが開け放たれた背の低い軽自動車が見えた。水色と白のツートンカラーで、かわいらしいデザインだ。水菜さんらしいな、と思う。
僕はトランクルームからケースを一つ取り出すと両手で抱えた。中にはおにぎりが三つずつ載った紙皿がいくつも入っている。
車を離れると正面から水菜さんが歩いてきた。
「どうもすいません、森崎さん」
「いえいえ、どうってことないですよ」
と言葉を交わしたところで、ぱたっと会話が止まってしまう。
「あ、あの、いい天気ですよね」
気づまりなので何か言おうと思って無理矢理に言葉をひねり出したが、よりにもよって天気の話か、と僕は自分が情けなくなる。
「そうですねー、暑いくらい。でも、昼からはだんだん下り坂みたいですよ。全然そうは見えませんけど」
水菜さんは空を見上げながら普段と変わりない調子でしゃべっている。微笑まで浮かべて、昨晩のことなどすっかり忘れてしまったかのようだ。
「舞台の準備はどうですか?」
「え、あ、大丈夫です」
何が大丈夫なんだトンチンカンなこと言いやがって、と僕は心の中で自分自身に毒づいた。
水菜さんは微笑を崩さない。
「こらー、手伝う言うちょってサボるんじゃなーい!」
いきなり背後から果林ちゃんに怒鳴られ、僕はビックリして思わず背中を丸めた。
「んもー、なにしよるん?」
果林ちゃんがぷりぷり怒りながらこっちに近づいてくる。
「どうせみず姉に見とれてからぽけーっとしとったんじゃろー?」
果林ちゃんがにまにましながら言う。
「そ、そんなことないよ」
僕は果林ちゃんと目を合わさないようにするが、果林ちゃんは回り込んで僕の顔をのぞきこもうとする。
「あやしーなあ、なんかビミョーな空気じゃったよ?」
「なんでもないって!」
「そうよ、果林。森崎さんに失礼じゃない」
水菜さんは微笑したまま果林ちゃんをたしなめた。まるで微笑の面を着けているようだ。
「ま、いっか。ほら、みな待っちょるよ」
「ごめんごめん」
僕がその場を離れると、背後から果林ちゃんと水菜さんの会話が聞こえてくる。
「で、どうなん、みず姉?」
「何が?」
「浩司さんに告られたん?」
気になって思わず立ち止まって聞き入りたくなるが、僕はぐっとこらえてケースを抱えたまま走りだした。
額に軽く汗が浮くのを感じた。
第四章 呪い 〈二〉
日陰になっている本殿脇で各自昼食となった。
総勢ざっと五十人ぐらい、各地区からの有志が総出で準備に来ているのだが、半分ぐらいが六十代以上の人たちで、三十代より若い人は稲村さんを含めて片手で数えられるほどだ。
僕みたいなよそ者はなんだか居場所がなくて、隅っこの方で控え目に食べることにした。
水菜さんと果林ちゃんもここで昼食にするらしい。
「しかし、つくづく思うが、昔と比べてもずいぶんと人数が減ったもんよなあ」
少し離れたところで、松岡さんと数人の男性がおにぎり片手に話し合っている。
「この分じゃ、七年後はできるかどうかわからんのう」
松岡さんが残念そうにつぶやいた。
「わしもはぁ年じゃけなあ、七年後は生きちょるかどうか」
「はは、そねえなことを言いよる者に限ってけっこう長生きしよるぞ」
僕と一緒に作業した伊藤さんが松岡さんにつっこむと、どっと笑いが起きた。
「しかしまさか、ネンコーさんの方がわしらより先に逝きよるとは思わんかったなあ」
松岡さんがそう言うと、少ししんみりした空気が流れた。
「それいね、ほんまに残念じゃった」
そう言ったのは、あの光り輝く頭のタクシー運転手・青笹さんだ。
「青ちゃんはネンコーさんに仕事の世話までしてもろうたんじゃけえなあ、足向けて寝られまあ」
「はは、まあな」
松岡さんがそう言うと、青笹さんは髪のない頭をかいた。
「稲村君も、ネンコーさんが生きちょったらうかうかでけんかったな。どっちが舞台に上がるか競っとったかもわからん」
「いやー、僕なんかまだまだですよ。ネンコーさんは熱中するとすごかったですし、きっといい舞い手になってますよ」
伊藤さんがにやにやしながら少し離れたところに座っていた稲村さんに声をかけると、彼は少しはにかんだ様子で伊藤さんに答えた。
「はは、まあ世阿弥さんも言うとるが、猿楽にこれでええいうこたぁないけえの。しかし、あんたがよそから来たたあ、はあ思えんのう」
松岡さんが目を細めながら稲村さんを見ている。
「いやあ、うれしいです。いつも嫁さんにもっと積極的になりんさいって尻たたかれてる僕がそう言ってもらえるのも、ネンコーさんが誘ってくれたおかげですね」
稲村さんはにこにこしながら松岡さんに返した。
「のう、もしネンコーさんが生きとったら、何をやらすかいの?」
松岡さんがみんなに尋ねる。
「そらあ、細かいことによう気づいてじゃったけえ、後見じゃろうじゃ」
青笹さんが即答した。
後見というのはシテの装束の乱れを直したり、持ち物の出し入れをするなど、舞台進行を補助する役割のことだ。
「小鼓なんかも似合いそうですね」
稲村さんが松岡さんに返す。
「いやいや、ええ声じゃったけえ、地謡じゃろう」
これは武骨漢・伊藤さんの意見。
「ああ、そう言やあネンコーさんはええ声しとったなあ。確かに地謡にもってこいじゃったかもしれん」
青笹さんも伊藤さんに同意した。
「よう通る太い声じゃった。あれじゃったら、面を掛けても謡えたのう」
「なんじゃ、会長はネンコーさんをシテにしたかったんか?」
伊藤さんが尋ねると松岡さんは大きくうなずいた。
「ほうよ。なんちゅーても、ネンコーさんはわしの一番弟子じゃからの」
「おいおい会長、ネンコーさんに何も教えちゃおらんくせに、いつの間にか弟子にした気になっちょるぞ」
伊藤さんがつっこむと再びどっと笑いが起きた。
年光さんは亡くなって五年の月日が経っても、まだみんなの話題の中心にいる。
「そうそう、そういえば学生さんもなかなかええ声しちょるよなあ」
突然、伊藤さんが僕を見ながら言った。
いきなり話が回ってきたので、飲みこみかけたおにぎりがのどにつかえてせき込んでしまった。
「まあ、見た目は弱げなじゃが、意外に声は太いな」
松岡さんが伊藤さんに同意した。青笹さんも腕を組んでうなずいている。
「のう、会長よ、学生さんに謡を教えるか。七年も鍛えりゃあ、そこそこモノになろうて」
伊藤さんが笑いながら松岡さんに言う。
「そりゃあええな、今から早速仕込んでみるか。なんなら今日の舞台に上げちゃろうや」
松岡さんはもっと無理なことを言って応じる。
「ちょ、ちょっとマジっすか。僕みたいな素人、ぜんぜんダメっすよ」
僕はあわてて断った。
「はは、会長、学生さん本気にしよるぞ」
「ちぃとからかい過ぎたかの、勲君よ」
二人がそう言うとまた笑いが起きた。
「しかし、改めて聞くと、学生さんの声はネンコーさんとよう似ちょうのう」
松岡さんは少し真顔になって僕の顔をまじまじと見た。
「そうですか?」
「わしら謡をやるけえ、声にはちいとうるさいでな。話し方は全然違うが、声質はよう似ちょる。水菜ちゃんは、どう思うね?」
松岡さんが水菜さんに尋ねた。
「えー、わたしですか?」
「そらあ、実の娘に聞くんがいちばんえかろう。ほれ学生さん、何か言うてみんさい」
松岡さんが無茶ぶりしてきたので僕はあわてた。
「何かって、何言えばいいんですか」
「本日は晴天なりでも何でもええから。ほれ、立って立って」
しかたなく僕はその場に立ち上がった。なんだか変に緊張する。
「あーあー、本日は晴天なり、本日は晴天なり」
緊張で声が裏返らないか心配だったが、とりあえず大丈夫だった。
水菜さんは目を閉じて僕の声を聞いている。一体どう感じているんだろう?
「どうかね?」
青笹さんが水菜さんに尋ねた。
みんなが固唾を呑んでその答えを待つ。
「確かに森崎さんの声は父に似てますね、顔は全然似てないですけど。声だけ聞いたらよく似てると思います」
一瞬どよめきが起きた。
なんだか不思議な気分だ。一度も会ったことのない人に声が似ていると言われても、喜んでいいのかどうかよくわからない。
「果林ちゃんはどねえかね?」
伊藤さんが今度は水菜さんの隣に座っている果林ちゃんに尋ねた。
「えー? うち、えっと(よく)覚えちょらんけ、ようわからん」
果林ちゃんはあっけらかんと言い放った。
いくら亡くなってから五年が経つとはいえ、自分の父親の声をそんなに簡単に忘れてしまうものだろうか?
「まぁたまた、なんぼなんでもそんとなこたあなかろう?」
「うーん……やっぱよう思い出さん」
伊藤さんにそう言われても、果林ちゃんは腕を組んで首をかしげている。本当に忘れてしまっているのだろうか。
「果林はいつもそうね、すぐに忘れるんだから」
水菜さんが少し責めるような調子で言った。
「だって、忘れたもんは忘れたんじゃもん。しょーがないじゃあ?」
果林ちゃんがけだるそうにそう言うと、突然水菜さんが立ち上がった。
「父さんに一番甘えたくせに、なんでそんな簡単に父さんのこと忘れられるの?」
水菜さんは果林ちゃんに向き直ると激しい調子でなじり始めた。
「思い出だっていっぱいあるでしょ、果林はこっちに来てからの方が長いんだから。父さんにいっぱい遊んでもらったじゃない! わたしが小さい頃は、父さん忙しくてほとんどうちにいなかったから、あまり遊んでもらったことないのに。運動会だってほとんど来たことないんだよ!」
水菜さんは大きな声でまくし立てると、厳しい目つきで果林ちゃんをにらみつけた。
「それなのに……それなのに、なんでそんな簡単に父さんのこと忘れられるの!」
水菜さんは傲然と果林ちゃんを見下ろしている。握りしめたこぶしが小さく震えている。
「なんでなんでって言われても、うちだってようわからんよ!」
果林ちゃんは座ったまま、涙をいっぱいにためて水菜さんをにらみ返していた。
「果林のバカ! 薄情者! あんたなんて何もかも全部忘れちゃえばいい!」
突然のことにあっけに取られて誰も何も言えず、激しくまくし立てる水菜さんの声だけが境内に響いた。
「まあまあ、水菜ちゃん。けんかせんと」
松岡さんがあわてて駆け寄ってなだめたが、水菜さんは果林ちゃんをぐっとにらんだままだ。
「わたし帰ります」
水菜さんは冷たく言い放って踵を返すと、ふりかえりもせずに歩いていった。
「なんなんよ、わけわからん! 勝手にわあわあ怒ってから! みず姉のばかぁ!」
果林ちゃんがその背中に向かって思いきり叫んだ。
「なーなー、浩司さん、うちって薄情なんかねえ?」
隣でうつむきがちに座っている果林ちゃんが力なく僕に尋ねた。
「うちは毎日が楽しいけえ、本当にそれだけでいっぱいいっぱいなんよね。昔のこととか思い出したりする暇ないくらい楽しいもん。それってみず姉が言ったみたいに薄情なんかなあ?」
「別に薄情ってわけじゃないと思うけど……」
そう言いながらも、僕は違和感をぬぐえずにいる。
「父さんがどんな声でどんなふうにしゃべりよったかなんて、今はいっそ思い出せん。顔じゃって、なんかぼんやりとしか思い出せんし」
「写真があるじゃない」
「えー、そんなん普段見んもん。思い出っても、なんか楽しかったような記憶はあるけど、何がどうとか、詳しいことはようわからんし……うち、やっぱ薄情なんじゃろうか?」
「うーん、そんなことないと思うけどなあ」
僕は何と返したらいいのか困ってしまった。
果林ちゃんは本当に年光さんのことを断片的にしか覚えていないようなのだ。
年光さんが亡くなった時、果林ちゃんは一〇歳だったはずだから、何も覚えていないほど幼かったというわけではない。なんだか不自然な気もするが、僕にはうまく言葉にできない。
逆に、水菜さんは父親である年光さんに対するこだわりがとても強いようだ。
昨晩の話からしても、愛憎相半ばするというか、簡単に一言では言えないような複雑な感情を抱いているのは間違いないだろう。
「やっぱり年光さんの存在って大きかったんだろうなあ」
そういえば桔梗さんも、年光さんが亡くなった後に何も言わなくなったんだ。年光さんが早くにこの世を去ったことが、今でも姉妹三人に大きな影響を与えているのかもしれない。
「──でも、なんで桔梗さんは僕に話しかける気になったんだろ」
「えー! マジで? きぃねえちゃんがしゃべったん?! いつ?!」
僕はひとりごとのつもりで何気なく口にしたが、隣の果林ちゃんは大声を上げた。
その声にビックリして僕は思わずひっくり返りそうになった。
果林ちゃんは目を丸くして僕の顔を見ている。
周りにいた人たちが、なにごとかという目つきで僕らの方を見る。
「あ、ああ、昨日の真夜中に偶然会って。少しだけだったけど、確かに話をしたよ」
「ウソじゃろー、誰が何言うても絶対にしゃべらんかったんじゃけえ! 筆談もしようとせんかったんよ! なんで浩司さんにだけしゃべるんよ?」
果林ちゃんは疑いの目で僕を見る。
そう言われても、僕だってさっぱりわからない。
「なんでかはわからないけど、とにかくウソじゃないって。昨日の朝に会ったときは何も言わなかったけど、夜中に会ったときは確かに会話したんだ」
「えー、昨日の朝にも会うたん?! いつの間に?」
そうか、この話もまだ誰にもしていなかった。
「たまたま早起きしたら出会ったんだ。桔梗さんはいつも朝日を眺めるために外に出ているみたいだよ」
「いっそ知らんかった。うち、いっつもギリギリまで寝ちょるし」
「だろうね」
「なんよー、浩司さんうちのことバカにしちょるじゃろう!」
「そんなことないよ」
「んーにゃ、なんか低レベルな生き物見るみたいな目しちょった!」
果林ちゃんは少しむくれながら僕を上目づかいで見た。
僕が思わず吹き出すと、果林ちゃんも屈託なく笑った。
「んー、考えてもようわからん! うち、みず姉みたく頭よくないもん。毎日ご飯がおいしゅう食べれたら、それでええや」
「そうだね、果林ちゃんには悩んでる姿は似合わないよ」
「それってつまり、ぱっぱらぱーってことじゃろ! やっぱり浩司さんうちのことバカにしちょるー!」
果林ちゃんは頬をふくらませて僕の頭をぽかぽかたたいた。
僕も両手で頭を抱えて逃げ回るポーズを取る。
どちらからともなく笑いがもれた。
「みず姉もきぃねえちゃんも、またみんなで仲よくできたら、ええな」
ふっと落ち着いた後に果林ちゃんがぽつりとつぶやいた。
もうひとつ、果林ちゃんが年光さんのことをちゃんと思い出せるようになるといいな、と僕は心の中でつけ加えた。
第四章 呪い 〈三〉
休憩が明けて見所にパイプ椅子を並べていると、夕介がカメラをぶら下げてやってきた。
「おー、もうほぼ組み上がってるのか、早いな」
夕介が感嘆の声を上げる。
「ったく遅いよ。何もないところにだんだん舞台が組み上げられる様子も面白かったのに。惜しいことしたよな」
「ふん、偉そうなこと言いやがって」
僕が言うと夕介は例によってにやにや笑いで返してきた。
「ちょうどえかった、なー夕介、後でええけえ、家まで送ってくれん? みず姉が勝手に怒って帰ったけえ、おにぎり持ってきたケースが持って帰れんで困っとったんよね」
果林ちゃんが夕介のジャケットの裾を引いて甘えた声を出す。
「なんだよ、顔合わせて早々。ま、しゃーねえ、取材済んだら送ってやるよ」
夕介はそう言うと奥に歩いていった。
「忘れんことよー!」
果林ちゃんがその背中に声をかけると、夕介は振り返りもせずに左手をポケットに突っこんだまま右手を上げて答えた。
「もう、ほんま横着なんじゃけえ」
果林ちゃんが隣で腕を組んで頬をぷっとふくらませているのがなんだかおかしかった。
一四時前には舞台周辺の設営はすべて終わった。
松岡さんたち出演者は集まって上演の打ち合わせを始めた。舞台の周りには少しずつ緊張感が漂い始めた。
一六時半から先に神事が行われ、開演は日没の時刻とほぼ同じ、一七時三〇分頃らしい。
「おーう、そろそろいったん引き揚げるか」
夕介が戻ってきて能天気に声をかけてきた。
「うん! じゃあ浩司さん、よろしく!」
果林ちゃんが空になったケースを指さす。
「なんで僕が持つんだよ?」
「当たり前じゃあ、かよわい美少女にこんなん持たすん?」
「かよわい?」
「か・よ・わ・い。なー、おねがーいっ!」
彼女は両手を合わせて僕を拝むようなポーズをとり、合わせた手の後ろから顔を出すとぺろっと舌を見せた。
か……かわいい。
「しょうがないなあ」
と僕が言い終わるやいなや、果林ちゃんはケースを僕に持たせると、上に一つずつ重ねていく。
果林ちゃんは背が低いから、最後の方は僕が中腰になって重ねること全部で五段。
「さっすが、やっぱり頼りになるわあ♪」
全部重ね終わった果林ちゃんは上機嫌な声でそう言うと、さっさと前を歩いていく。
僕は積み重なったケースを両手で抱えてよろよろと車まで歩いた。
顔の前まで積み重なったケースで足元が全く見えないから、そろそろと歩く。
駐車場までこんなに遠かったっけ?
前から夕介の声がする。
「くくっ、お前また果林にこき使われてるのか?」
「うっさいなあ、積むの手伝ってくれよ。手がふさがってて何もできないんだよ」
夕介は車のトランクを開けるとカメラが入ったアルミケースをいくつか後部座席に移してスペースを作った。
何とかそのスペースにケースを降ろすと僕の両腕はやっと解放された。
「ありがとー、おかげでいっぺんで済んだわあ♪ うちじゃったらようせんよぉ」
果林ちゃんは両手を組んで目をキラキラさせている。
「やれやれだな、ご苦労さん」
夕介が僕の肩に手を置いて言った。
「まったくだよ。果林ちゃんが『天然ものの小悪魔女』っていう意味、ちょっとわかった」
「だろ?」
「えー、なんでー? どこがー?」
果林ちゃんは平然と言い放つ。
『そーゆーとこだよ!』
僕と夕介は同時につっこんだ。
果林ちゃんはきょとんとしている。
おねだり上手、甘え上手、なのに自覚ゼロ。だから「天然もの」なんだ。
果林ちゃんを助手席に座らせ、機材が置かれたせいで狭くなった後部座席に僕が乗り込むと、夕介はゆっくりと車をスタートさせた。
「なー夕介、浩司さんの声って父さんに似ちょると思う?」
果林ちゃんは運転席の夕介に尋ねた。
「は? 誰がそんなこと言った?」
夕介は怪訝な声で問い返す。
「みな言いよったよ、松岡さんとか伊藤さんとか。みず姉も似ちょるって言うた」
「そうそう、僕もなんか変な気分なんだけど」
僕も後部座席から身を乗り出して言った。
「んー、しゃべり方が全然違うからなあ」
案の定、夕介はあまり認めたくなさそうだ。
「しゃべり方とかじゃのうて声! みず姉も顔は全然似ちょらんって言うたもん」
「くくっ、そりゃ傑作だ」
「うっさいなあ」
夕介が面白そうに笑う。まったく、いちいちシャクにさわることを言う男だ。
「ま、言われてみれば確かに声質は似てるかもしれないな、俺は絶対認めんがな」
「アンタのことだから多分そう言うと思ったよ」
車は参道から県道に出た。
朝来るときには二〇分くらい歩いた道だが、車だと五分もかからない距離だ。
「うちはよう覚えちょらんけえわからんて言うたら、みず姉いきなりぶち怒りだして、勝手にキレて帰ったんよ。もー、意味わからん」
「うわー」
夕介は左手を額に当てている。
「相当に重症だな、両方とも」
後ろからだから表情はよくわからないが、苦々しそうに夕介は言う。
「でな、でな、浩司さんきぃねえちゃんと話したんて」
「おい、マジかよ! あいつ絶対に誰とも口きかなかったのに!」
「きゃっ!」
「わあ! 前向けよ、前!」
夕介が僕の顔を見ようと振り返ったから、車が一瞬よろめいた。
果林ちゃんの悲鳴であわててステアリングを握り直した夕介は、それでもルームミラー越しに僕の目を見る。
「本当か? ガセじゃないだろうな?」
「嘘じゃないって。昨日の晩、ちゃんと会話したんだ」
なんだかかみ合ってはいなかったが、会話したのは事実だ。
とはいえ、僕自身もいまだに半信半疑なのだが。
「なー、すごいじゃろ? 浩司さんて魔法かなんか使うたんじゃないん?」
「確かに信じられんな、あの桔梗が言葉を取り戻すなんて」
夕介は少し興奮気味の声だ。僕をからかう余裕すらないようだ。
「アンタも桔梗さんと話そうとしたことはあるんだ?」
「ああ、何度もな。何度やってもダメだった。それにしても、なんでよりにもよってお前なんだよ?」
「僕が知るわけないだろ」
「そりゃ、まあそうか」
夕介はじっと黙って考え込んでいるようだ。
車は宇侘川パレスホテルの入り口の手前から左に曲がっておなじみの急坂に入った。
初日に息を切らして登った坂も、車だとあっという間だ。
「ありがとー、夕介が来てくれたおかげで助かった♪」
「あ、ああ──」
果林ちゃんがお礼を言ったが、夕介はどこか上の空だった。
僕と果林ちゃんが手分けして車からケースを降ろしている間も、夕介はぼんやりと突っ立ったまま何かを考えているようだった。腕を組んで左手でずっとあごひげを撫でまわしている。
「お疲れさまでしたね、準備の方はもうええんですか?」
女将さんが僕らに気づいて表に出て来た。
「もう準備万端みたいですよ。何もなかったところにあっという間に立派な舞台ができて、だんだんわくわくしてきました」
「そうですか、いよいよですね。楽しんできて下さいね」
「はい」
「夕介さん、わざわざありがとうございました、おかげで助かりました。水菜が勝手に帰ってしまったとかで、ご迷惑をおかけしました」
女将さんは夕介に向かってそう言ったが、夕介の方は心ここにあらずで、あいかわらず突っ立ったままだ。
「夕介さん? ……夕介さん!」
「え、あっハイ!」
夕介があわてて返事をする。
「もう、どうしたんです、ぼーっとして?」
「すんません、ちょっと」
「何かあったんですか?」
「あの、蘭さん。コイツの声って年光さんに似てると思いますか?」
夕介はだしぬけに僕を指さすと、いつになく真剣な顔で女将さんに尋ねた。
「え? なんですか、いきなり」
「どうですか、似てますか、似てませんか?」
「そんなこと言われても──」
女将さんは困惑した表情を浮かべた。
夕介がなぜいきなりそこにこだわるのか、僕も事情が呑み込めない。
「おい森崎、お前蘭さんの名前呼んでみろ。そうだな、さんづけせずに、呼び捨てで呼ぶんだ。蘭、って」
「は? なんでそんなこと──」
「いいからやってみろ!」
夕介はものすごい剣幕で怒鳴ると僕をにらんだ。
女将さんのことを呼び捨てにするのはどうも抵抗があるが、僕は夕介の迫力に押されておそるおそる呼んでみた。
「え……と、蘭?」
「もっと大きな声で!」
「蘭」
「まだだ!」
「蘭!」
最後にはなかば叫ぶように蘭さんの名前を呼んだ。
ふと見ると、目を閉じて僕の声を聞いていた蘭さんが、両手で口元を覆って僕のことを見ている。
「もう……いいです、森崎さん。ありがとう」
蘭さんが震える声で言った。
「やっぱりそうか」
夕介がつぶやく。
「若い頃の年光とそっくりです。一瞬、あの人が私を呼びよるのかと思いました」
蘭さんは僕をじっと見つめながら言う。
夕介が蘭さんの言葉にうなずきながら続けた。
「実はコイツ、桔梗と話したそうなんです」
「本当ですか? 誰が何をしても、口を閉ざしたままだったのに」
「僕もまだ信じられないけど、本当なんです」
僕はかいつまんで顛末を話した。
昨日の早朝偶然に桔梗さんと出会って一緒に朝日を眺めたこと、真夜中に再び会って不思議な会話を交わしたこと。
「もしかするとコイツなら、桔梗の止まった時を、動かせるかもしれない」
夕介はそう言うが、僕にはどうしたらいいのかまったく見当がつかない。
「蘭さん、これはあくまで俺の思いつきなんですが、今晩と明日の『紫桜』、家族みんなで観に行きませんか?」
「え? それはちょっと──今日はこれからさらに二組のお客様がお見えになりますし」
「だったら、子どもたちだけでも。何かが変わるような予感がするんです」
夕介の言っていることには何の根拠もないのだが、僕も不思議とそんな気がする。
「うちも行きたい!」
不意に背後から果林ちゃんの声がした。
「うちも『紫桜』観たい。夕介、連れてって」
果林ちゃんは夕介の目をじっと見て言う。いつになく真剣な表情だ。
「途中で寝るなよ」
そう言うと夕介は果林ちゃんの頭をくしゃくしゃと無造作に撫でた。
「わかった!」
果林ちゃんが大きくうなずく。
「では、水菜と桔梗も誘ってやっていただけませんか?」
その様子を見ていた蘭さんが夕介に伝えると、夕介はうなずいて続けた。
「もし明日、時間が取れるようなら、その時はぜひ、蘭さんも一緒に」
夕介は蘭さんの目をじっと見つめて返事を待っている。
「ええですよ、明日のご宿泊は今のところお二人だけですから。桑田さんに留守番を頼んでみましょう」
「よし」
蘭さんが答えると夕介は小さくガッツポーズをとった。
「なんか楽しみー」
果林ちゃんは無邪気にはしゃいでいる。
蘭さんは右手を口元に当ててじっと何か考え込んでいるような様子だった。
第四章 呪い 〈四〉
けんかした後って、なんであんなに気まずいんだろう。
僕はけんかした後に謝ることがどうにも苦手だ。
明らかに自分の方が悪いとわかっている場合でも、いや、だからこそ、よけいにごめんとは言い出すことができない。そうして言い出すタイミングを一度失ってしまうと、ますます言えなくなってしまう。
自己嫌悪とつまらない意地とがぐちゃぐちゃになって、ええいもういいや放っとけ、という捨て鉢な気持ち。
きっと今の水菜さんもそうだろうな、と僕は考えていた。
一人になって冷静さを取り戻した今、自己嫌悪に沈んでいるんじゃないだろうか。
感情にまかせて大勢の人の前で大きな声で果林ちゃんを罵ったこと、止めに入ってくれた松岡さんを無視したこと、あとさき考えずに勝手に帰ったこと──
そのひとつひとつが心の奥に棘のように刺さっているんだと思う。
なんであんなことしたんだろうって後悔しながら、でも自分は間違ったことは言ってないとも思っているから、自分から先に謝ることもできない。
こんなときは、どこにも出かけたくないし、誰とも会いたくないはずだ。それは、僕がそうだからそう思うだけだけど。
果林ちゃんに案内してもらって、僕と夕介は母屋に入った。
木立の中に隠れるように建っているせいで、平屋建ての母屋の中は昼間でも少し薄暗い感じがする。
「車があるけえ、おると思うけどなあ、みず姉」
果林ちゃんがそう言いながら部屋のドアをノックした。
「なーなー、みず姉、おる?」
中からは何も返事がない。
「おい水菜、つまんねー意地張ってないで出てこいよ」
夕介が無造作に呼びかける。つくづくデリカシーのない男だ。
「そんな言い方じゃ、出てきたくても出てこれないだろ?」
僕は夕介を制して、ドアの向こうにゆっくりと語りかけた。
「あの、水菜さん? そのまま聞いてください」
僕はいったん言葉を切って部屋からの反応をうかがった。
しかし、何も返ってこない。
僕は努めてゆっくりと言葉を継いだ。
「今晩の『紫桜』、みんなで一緒に観に行きませんか? 年光さんが必死で存続させようとしたんです。きっと年光さんの思いも表れてると思います。夕方五時半に開演です。あの、みんなで待ってますから」
ドアの向こうからはやっぱり何も反応はなかった。
「みず姉、ほんとにおるんかねえ?」
「いるよ、間違いなく」
果林ちゃんは首をかしげたが、僕は水菜さんが部屋の中で僕の言葉をじっと聞いていたと確信していた。根拠は何もないけど。
「ま、あとはあいつ次第、だろうな」
夕介がぼそりとつぶやいた。
桔梗さんは、年光さんが生前書斎として使っていた部屋でいつも過ごしているのだと果林ちゃんが教えてくれた。
「きぃねえちゃん? 果林じゃけど」
果林ちゃんが扉越しに声をかけると、桔梗さんはすぐに部屋の扉を開けてくれた。
いつもの白い着物姿で、やはり表情は欠けたままだ。
部屋はそんなに広くはないが、壁一面が本棚になっていて、隙間なく本が並んでいるのが見えた。
「なーなーきぃねえちゃん、浩司さんにはしゃべったんて?」
果林ちゃんはまったく遠慮なしに桔梗さんに尋ねた。果林ちゃんの遠慮のなさはある種の才能じゃないかと僕は感心する。
果林ちゃんの質問に桔梗さんは│黙ったままうなずいた。
「えー、ほんまに! うそじゃなかったんじゃ?」
桔梗さんは再びうなずく。
夕介は黙って腕を組んだままじっと二人の様子を見ている。
「なー、なんでうちにはしゃべってくれんの? 前みたいにいろいろ話しようやあ」
果林ちゃんは両手で桔梗さんの手を取って話しかけたが、桔梗さんは今度はゆっくりと首を横に振った。
その様子に、断乎とした意志のようなものを僕は感じた。
桔梗さんは病気ではなくて、自らの意志で言葉を発しないことを選んでいるのではないだろうか。
「もしかして、桔梗さんはしゃべれないんじゃなくて、自分からしゃべらないようにしてるのかな?」
少し迷いながらも僕がそう尋ねると、彼女は一瞬だけ僕から視線を外した。
ややためらったようにも見えたが、桔梗さんはゆっくりとうなずいた。
「おい、そろそろ本題に行こうぜ」
ここで夕介が口を挟んだ。果林ちゃんがうなずいて桔梗さんに話し始める。
「なーなーきぃねえちゃん、今日の晩と明日の晩にな、『紫桜』っていうのをやるんて。でな、でな、みず姉も誘うちょるんじゃけど、うちとみず姉、さっきけんかしたばっかりなんよ。うちが父さんのことよう思い出さん(思い出せない)て言うたら、いきなりキレだしてな。もう、マジ腹立つー。さっきもな、せっかく誘い行ったのに、はぶてて(拗ねて)から返事もせんのんよ、ヒドいじゃろう? なーどう思う、きぃねえちゃん?」
「おいおい果林、話がずれてるぞ」
夕介があきれ顔で言った。
仕方がないので僕が改めて桔梗さんに説明する。
「桔梗さん、あの、僕らといっしょに猿楽『紫桜』を観に行きませんか? きっと何かが変わるような気がするんです。果林ちゃんも夕介も、僕もついてますから、心配いりません」
桔梗さんはじっと僕の顔を見つめた。
僕も彼女から目をそらさないようにして彼女の反応を待った。少し鼓動が早まるのを感じる。
夕介も黙ったまま桔梗さんの答えをじっと待っている。
隣で果林ちゃんがごくりとのどを鳴らした。
少し間を置いてから、桔梗さんはゆっくりとうなずいた。
「行くんじゃ! 浩司さん、見た? きぃねえちゃん行くって!」
果林ちゃんが興奮して叫んだ。
僕も思わず夕介の顔を見上げると、夕介は僕に目配せをした。予想通りだということか。
「すごい! きぃねえちゃんが外に出るん、ほんっとに久しぶりじゃ! えかったー!」
桔梗さんの手を取ったまま無邪気に跳び上がって喜ぶ果林ちゃんを見ていると、僕も少しほっとした気持ちになった。
桔梗さんもそんな果林ちゃんの様子をじっと見ている。
その横顔が、ほほ笑んでいるように見えた。
僕と夕介はロビーで蘭さんの淹れてくれたコーヒーを飲みながら時間をつぶしていた。
ロビーにはさっきからいい香りが漂っている。品のいい珈琲茶碗で出されたコーヒーに、僕は砂糖とミルクを入れ、夕介はブラックのままで飲んでいる。果林ちゃんと桔梗さんとは一六時前に表の駐車場で落ち合う予定だから、まだ一時間近くある。
「さっき、一体何を考えてたんだよ?」
僕は夕介に尋ねた。
「んー?」
夕介は面倒くさそうに生返事を返す。
「ほら、ここに戻ってきた時だよ。ぼーっと突っ立って、何か考えてただろ?」
「ああ、あれか。桔梗のことを考えてた」
夕介は一口コーヒーを含むと続けた。
「なんで桔梗がお前にだけしゃべったのか、それがずっと気になってな」
「僕も不思議なんだよ、なんで僕なんだろう? さっきだって結局一言も言わなかったし」
夕介はソファに身を沈めて脚を組んだ。
「声だ。お前の声が、あいつの心の鍵を開けたんだろう」
「僕の声が年光さんとよく似てるから……か?」
「多分な。本人が何も言わないから確かなことはわからんが──お前、桔梗と会った時にあいつの名前呼ばなかったか?」
僕は桔梗さんと会ったときのことを思い出したが、名前を呼んだかどうかまではよく覚えていない。
「うーん、正直よく覚えてないなあ」
「名前を呼ばれるってのは、特別なんだ。しゃべり方の違いで普段は気づかなくても、声そのものが表に出る」
夕介はソファから身を起こすと、再び珈琲茶碗を手にとって口に運ぶ。
「おそらく、桔梗は驚いたんだ。死んだはずの父親に呼ばれた、と」
夕介はそう言って僕の顔を見た。
「あくまで俺の想像だが、あながち外れてもいないはずだ」
夕介はいつになく真剣だ。僕をからかったりバカにしたりする様子がまったくないから、逆に違和感を覚える。
「なんでそこまでマジなんだよ? 確かにアンタにとって年光さんは大恩人なのかもしれないけど、よその家庭にそこまで深入りすることもないんじゃないのか?」
「お前には関係ない」
夕介は少し不機嫌な様子で言い捨てた。
僕もそれ以上何も言えず、しばらくお互いに黙っていた。
「──お前、ここの│三姉妹のこと、どう思う?」
夕介が窓の外に見える庭を眺めながらぽつりと僕に尋ねた。
「どうって……うまくは言えないけど、なんだか複雑かなって」
僕も庭の方を見ながら答えた。
外は少し雲が出始めたのか、さっきまであれだけくっきりしていた木々の影が、ぼんやりと輪郭を失っていた。
「複雑どころか、水菜はあれこれこじらせてるし、桔梗は│白装束で何も言わない、果林は健忘症ときたもんだ。まったく、呪われてるとしか言いようがないな」
夕介は外を眺めたままつぶやいた。
呪われてる、という言葉に僕はどきりとした。
僕は冷めかけたコーヒーをすすってから夕介に問い返す。
「呪われてるって?」
「あいつらのかかってる呪いは、あいつら自身がかけた呪いだ」
夕介は険しい顔で言った。
左手であごひげを撫でながら夕介は続ける。
「桔梗はあいかわらず俺たちには何も言わないから確たることは言えないが、水菜と果林については間違いなくそうだ」
「どういうこと?」
僕が尋ねると、夕介は身を乗り出して逆に僕に質問してきた。
「お前、水菜にどこか遠くに連れて行ってくれって言われなかったか?」
「な……なんで知ってるんだよ?」
僕は動揺した。昨晩の会話を夕介に聞かれていたのだろうか。
「俺も前に言われたことがあるからだよ。あいつ、本当はここにはいたくないんだ。ここから出してくれるなら誰でもいいと、無意識に思ってる」
夕介は再びソファに身を沈めると、両手を頭の後ろに組んで天井を見上げた。
「にもかかわらず、あいつは自分でここから出ない選択をした。蘭さんは水菜を進学させる気でいたし、あいつさえその気なら、いくらでもここから出ることはできたのにな」
僕は水菜さんの話を思い出しながら夕介の話を聞いていた。
確かに水菜さんは蘭さんから進学を勧められたと言っていた。なのに、それを断って自分で市役所に就職を決めたとも。
「でも、そうはしなかった。本当はここから出たくて仕方ないくせに、変な義務感に駆られて自分で勝手にここに残る選択をしたんだ。自分で閉じ込めておいて出られないって嘆いてるんだから、つくづくめんどくさい奴だよ、あいつは」
僕はなんだか悲しい気持ちで夕介の言葉を聞いていた。
「果林にしてもそうだ。あいつは年光さんのことを思い出せないんじゃない、思い出したくないんだ」
「でも、それは毎日が楽しいからって──」
「違うな。果林は三人の中でも特に年光さんに甘えた父親っ子だった。多分、大好きだった父親がいなくなったという現実を見たくないんだろう」
僕は腕を組んだまま絶句してしまった。
「さっきの様子じゃ、桔梗も多分そうだ。自分の意志で言葉を発しないようにしているらしいからな」
僕もうなずいた。何が理由なのかはわからないが、桔梗さんは自らの意志で、決して言葉を発しないことを選んだんだ。
「桔梗が今みたいになった原因がわかれば、この家族はきっと変わる」
夕介がきっぱりと言った。その目には強い意志が感じられた。
お互いしばらく黙ったまま庭を眺める。
キジバトが一羽、池の周りをうろついているのを、僕はぼんやりと目で追っていた。
「ところでお前、水菜にはもう告ったのか?」
唐突にそう聞いてきた夕介は、もういつものにやにや笑いを浮かべている。
「な……なんなんだよっ、いきなり!」
「まったく、あんなめんどくさい女がタイプとは、お前も苦労するな」
「うっさいなあ、よけいなお世話だよ!」
「で、どうなんだ?」
「──まだ何も。その前に拒絶された」
夕介があきれた顔で言う。
「なんだそりゃあ? お前ほんとにあいつのこと好きなのか?」
「そりゃあ、まあ、そうなんだけど──」
僕は思わずごにょごにょとごまかした。
正直、自分が水菜さんを本当に好きだと言い切れるのか、今のところ自信がない。
確かに僕と同じような部分を持っている彼女のことが気にはなっているが、それを好意と呼んでいいのだろうか?
「なんだ、はっきりしろよ。正面からぶつからないと、動くものも動かないだろうが」
「わかってるよ!」
まったく、夕介は他人事だと思って勝手なことを言う。
が、ここでふと僕の頭に一つの仮説がひらめいた。もしかしたら。
「じゃ、そう言うアンタの方はどうなんだよ?」
夕介の左手薬指に指輪はない。この男、そこそこ遊んでいるかもしれないが、家庭のにおいはどこからも感じられない。
僕はカマをかけてみることにした。
「アンタ、蘭さんのこと想ってるんだろ?」
僕がそう言うと夕介は一瞬ぎくりとした顔をした。
思ったとおり。いつも虚勢を張ってるくせに、意外にリアクションがわかりやすい男だ。
「ああ、そうだ」
ちょっとだけ考えるような間の後、夕介はあっさりと認めた。
夕介はそのまま半ば開き直ったように続ける。
「別に問題ないだろう? お互い大人で、一人の男と一人の女だ」
「ふーん、それでなんだな」
今度は僕がにやにや笑いをする番だ。
「どうりでやけにマジなわけだ。で、もうプロポーズはした?」
「お前に話す義務はないな」
夕介は憮然とした表情で返す。一応平静を装ってはいるが、内心はどうだか。
「俺はお前みたいな半人前と違ってデキる大人だからな、山積する問題を解決できるメドがついたら、そこでケリをつける」
むだにカッコつけて言うが、要するにプロポーズはまだしてないってことらしい。
「ふーんそうか、これからなんだ。ま、がんばってな」
僕はにやにやしながら言った。
「なんでこの俺がお前なんぞにがんばってなんて言われなきゃならないんだ!」
夕介はソファにふんぞり返って腕を組む。明らかに面白くないという表情だ。
僕はここぞとばかりに言ってやった。
「これまでのお返しだよ、お互い様だろ?」
「クソ、なんかムカつく! 納得いかん!」
夕介は顔をしかめた。が、すぐに耐えきれずに吹き出した。
つられて僕も笑った。
僕も夕介も、しばらく笑いが止まらなかった。
第四章 呪い 〈五〉
外に出ると、午前中とはうって変わって空はすっかり分厚い雲に覆われていた。
「天気、大丈夫かなあ」
僕は空を見上げながら思わず声に出した。
「昼の予報だと夜半から雨だって言ってたな。なんとかもてばいいんだが」
夕介も心配そうな顔で雲をにらんだ。
門の前で果林ちゃんと桔梗さんが母屋から上がってくるのを待っていると、蘭さんが表へ出てきた。
「そろそろおでかけですか?」
蘭さんが夕介に尋ねた。
「ええ、いよいよです」
夕介は蘭さんの瞳をじっと見つめて言った。
どこからかトンビが長鳴きをしているのが聞こえる。
下から落ち葉を踏む音が近づいて、すぐに果林ちゃんと桔梗さんが姿を現した。
「桔梗、大丈夫?」
蘭さんが尋ねると桔梗さんはゆっくりとうなずいた。
「水菜さんは?」
「もっぺん声かけたけど、やっぱり返事もせん。よいよ、へんくう(気難し屋)なんじゃけえ」
僕が尋ねると果林ちゃんが口をとがらせながら答えた。
蘭さんが思わず吹き出す。
「ふふ、水菜のそういうとこは父さん譲りね。ほんと、どうでもええところばっかり似てから」
蘭さんはそう言いながらもどこかうれしそうだ。
「心配せんと先に行きんさい。大丈夫、あの子はちゃんと後から来るから」
「そうかねえ?」
「そうよ、母さんにはわかるんよ」
蘭さんはそう言って果林ちゃんにウインクした。
桔梗さんと果林ちゃんには後部座席に座ってもらい、僕が助手席に座ることになった。
夕介のSUVはステップがやや高い位置にあって、背の低い桔梗さんは着物の裾が邪魔してうまく乗り込めない。
夕介が手を添えて、ようやく座席に座ることができた。
「きぃねえちゃん久しぶりの外じゃもん、もし事故ったら承知せんけえね!」
果林ちゃんが後ろから夕介に釘を刺す。
「わかってるって、心配するな」
そう言いながら夕介はエンジンをかけた。
低いうなりを上げるエンジン音を響かせながら車は坂道を下る。あっという間に県道に出ると、先の方には「奉献 宇侘八幡宮」と染め抜かれた大きな幟が点々と続いている。
僕は助手席から振り返って桔梗さんの様子を確かめた。彼女はじっと窓から流れる景色を眺めている。
車はさっきの道を逆にたどってゆっくりと宇侘八幡宮の参道に入り、正面に鳥居を見ながら大きな石灯籠の間を通過したあと、左に曲がって杉林の中の狭い道を登って境内の裏手に出た。今の時間帯、この駐車場は関係者以外駐車禁止だが、夕介は猿楽保存会から許可証をもらっているから堂々と駐めることができる。
「おっと、そうそう、これが要るんだった」
いったん車から降りた夕介はグローブボックスを開けると、緑色の腕章を取りだした。腕章には白抜きで「報道」の文字が入っている。
「なるほど、アンタはプレス扱いなんだな」
「ほかには今のところ地元のケーブルテレビと西國新聞、地域新聞の日刊いわしろが入るらしい。さっき松岡さんに聞いた」
夕介はジャケットの左腕に腕章を巻きつけながら言う。
「なーなー、テレビのニュースにはならんの?」
果林ちゃんが夕介の腕章をしげしげと眺めながら尋ねる。
「さあ、どうだか。それでも、報道各社へのプレスリリースをするようになったのは、前回年光さんが提案してからだそうだ」
「さすが元広告代理店!」
僕は感心して声を上げた。
「ほかにも年光さんの提案でいろいろと変わった部分があるらしい」
「へー、そうなんだ」
夕介はトランクルームを開けると三脚を二台、アルミ製の小型の脚立、それにアルミケースを二つ取り出した。
アルミケースを二個担いだ夕介が先頭を歩き、僕も脚立を左肩に掛け、三脚を両手に続いた。
舞台周辺の見所(観客席)には既に一五人ほどが場所取りをしていた。それぞれ思い思いの場所でのんびりとくつろいだ様子で開演を待っている。中にはお弁当持参の人もいて、なんだかピクニックのようだ。
テキヤが出ていないから祭りに特有の活気はないが、静かな杉林に囲まれた境内の澄んだ空気が、和やかな中にも神聖な時間を感じさせている。
夕介はアルミケースからカメラを取り出し、レンズを選択している。二台のカメラにそれぞれ長さの違うレンズを選んだ。
「おー、夕介ってなんかプロみたい!」
その様子を見て果林ちゃんが感嘆の声を上げる。
「みたい、じゃなくてプロなんだっつーの」
夕介が苦笑いしながら返す。
桔梗さんが夕介の手元をもの珍しそうにじっと見つめている。
「さて、どこに構えるかな」
夕介はファインダー越しに舞台を見ながら、カメラをどこに据えるかを考えている。
「全体を捉えるなら正面の後ろの方がいいらしいよ。さっき教えてもらったんだ」
「ふん、なるほど」
まだ火は入っていないが、篝火が舞台の前で既に大きな存在感を放っている。
「よし、一台はここに据えてくれ」
僕は三脚の脚を伸ばすと夕介が指示した辺りに置いた。
夕介は手早く三脚にカメラを取り付けると、画面でフレームを確認しながら微調整している。
この位置からだと確かに本舞台から橋掛りまで、舞台全体の状況がよくわかる。伊藤さんが教えてくれた通りだ。
場所が決まると果林ちゃんはさっさとパイプ椅子に座りこんでしまった。
桔梗さんはじっと立ったまま舞台の方を見つめている。
白い長襦袢姿の桔梗さんはそれだけで強い印象を放つ。
時々周囲の人の視線を感じるが、彼女はまったく意に介していないようだ。
「なーなー、うちらもお弁当かおやつ、持ってくればえかったね」
「なんだ果林、もう腹減ったのか?」
夕介がからかう。
「違うもん、なんか楽しそうじゃあ? その方が」
「確かに、なんだかピクニックみたいだね」
薪能といとなんだか居ずまいを正して観ないといけないような気がするが、今のところリラックスした空気が流れている。
「まあ、長丁場になるからな。今日は三時間くらいか。全部終わるのは九時ごろになるはずだ」
「えー、そんなに長いん? もしかしたらうち寝るかもー」
夕介がもう一台のカメラの調整をしながら果林ちゃんに言うと、果林ちゃんは軽く肩をすくめて舌を出した。
「浩司さん、うちが寝よったら起こしてよ」
「でも、僕も寝るかもよ?」
「あはは、じゃったらわざわざ何しに来たん? 寝たらいっそ意味ないじゃあ!」
果林ちゃんは笑いながら横に立っている僕の足をばしばしとたたく。
「そうだ、お前ちょっと参道の方に行ってくれよ」
夕介が参道の方に顔を向けながら僕に言った。
「何だよ?」
「観客向けにパンフレットを配ってるはずだ、人数分持って来てくれないか。台詞の内容や装束・舞台背景なんかの豆知識をわかりやすいようにまとめてあるらしい。謡本もついてるから、観る時に参考になるだろう」
「もしかして、これも年光さんのアイデア?」
「よくわかったな。謡にしろ舞にしろ、演じる者が互いに批評し合うために観賞する側面もある。より高度な観賞ができるのはもちろんそういう観客だろうが、それじゃあ一般人からはどんどん遠ざかってしまう。昔の言葉でもあるし、素人はただ聞いただけじゃわからないことだらけだ。能が一見とっつきにくいのには、そういう理由もあるだろうな」
確かに、台詞や所作の意味、舞台背景などがわかれば、僕みたいなずぶの素人でも、ある程度物語を理解することができそうだ。
「それで、初心者でもわかるように色々と工夫を考えたそうだ。アイデア倒れに終わったが、モニターで字幕を流すことも考えたらしいぞ」
「年光さんは古くからの伝統に新しいものを加えようとしたんだな」
僕がそう言うと夕介はにっと笑った。
「『人の心に珍しきと知る所、即ち面白き心なり』(註一)だな。珍しく新しいものだからこそ、人の心に面白いと映るって意味だ」
「なんだよそれ?」
「世阿弥だよ、世阿弥。『風姿花伝』で猿楽の基礎を形作ったおっさん。常に何か新しいものが入らなければ、どんなものでも惰性に陥って、やがては滅ぶ」
「そういえば日本史の教科書で出てきたな、世阿弥の『風姿花伝』」
「あんなもん、テストのために覚えただけじゃ面白くもなんともないだろうが? 現場のダイナミズムの中でこそ、ただの知識だったものが血となり肉となって本当に生きたものになる、てのが年光さんの持論だった」
「つまり、『何でもやってみなきゃわからない』ってことか」
「そういうことだ。知ってるだけなら何の価値もない。知識は実践の中でこそ価値が出るんだ。ま、俺のも所詮一夜漬けじゃあるがな」
そう言って夕介は笑った。
夕介が自分の知識が一夜漬けだとバラしたのが僕には少し意外だった。黙っていればわからなかったのに。
「じゃ、ちょっともらってくるよ」
「ああ、頼む」
僕は参道の方へ向って歩き始めた。
参道からは三々五々観客が流れてくる。
大半は普段着のままふらっと来たような地元の人たち。
スーツ姿の中年男性や和服姿の年配の女性も見える。中には車椅子に乗ったり、介添えの家族に手を引かれた八十代・九十代と思われる高齢の人もいる。
ごった返すというほどではないが、人のざわめきが少しずつ境内を満たし始めていた。
パンフレットをもらって戻ると、夕介が神事の前に松岡さんに取材に行くと言うから僕もついていくことにした。果林ちゃんは場所取りをしておいてくれるというので残ることになったが、意外にも桔梗さんが一緒に行く意思を示した。
出演者たちは鏡の間で順に紋付の羽織袴に着替えている。
松岡さんは鏡の間の脇に立って、僕らを出迎えてくれた。
普段は小柄で平凡なおじさんにしか見えない松岡さんが、今はぐっと引き締まった表情になっている。髷を結っているわけではないけれど、時代劇からそのまま抜け出てきたかのような雰囲気だ。
夕介はさっそく了解を取って紋付姿の松岡さんを撮影する。
「妹尾君、撮影の準備はもうええんかね?」
緊張感は高まってきているが、松岡さんは気さくに話してくれた。
「ええ、おかげさまで。徐々に観客も集まってきていますね」
「そっちの子は?」
松岡さんが桔梗さんに気づいて尋ねた。
夕介が紹介する。
「年光さんの次女の、桔梗さんです」
「ああ、七年前に稚児頭を務めた桔梗ちゃんかね、大きゅうになってから」
桔梗さんは目を細めている松岡さんに向かって頭を下げた。
松岡さんは桔梗さんのいでたちには一言も触れず、すぐに話題を変えた。
「天気が若干心配じゃが、まあ何とかなるじゃろうて」
「もつといいんですが。どうですか、やっぱり緊張しますか?」
「そらあ、緊張するいね。じゃが、ええ緊張感じゃな」
松岡さんは夕介にそう言ってから舞台を眺めると、ふっと笑った。
その表情は、これから戦いに赴こうとする老侍のようにも見えた。
「あの、もし雨が降りだしたらどうなるんですか?」
僕は気になっていたことを尋ねてみた。
「シテは面を掛けちょるから、降り出してもすぐにはわからん。後見が動いて、シテに知らせるんじゃ。演目の進み具合にもよるが、そのまま中止にするか、演目を刈り込んで短こうするかは、後見が判断する」
「後見って舞台を補助するだけじゃないんですね」
「ああ、全部の段取りがわかっとらにゃいけんけえ、なかなかやねこい(複雑な)んじゃ。ネンコーさんはその点、のみこみがえかったからなあ」
またもや年光さんだ。
僕は満面の笑みをたたえた年光さんの遺影を思い出した。凛々しい顔立ちだから、紋付がよく似合いそうな気がする。
「ネンコーさんは晴れ男じゃったけえ、雨が降らんよう、あの世から助けてくれりゃあええが」
松岡さんはそう言って天を仰いだ。
重そうな灰色の雲が空を覆っている。
「そういえば、松岡さんは年光さんとはどういうきっかけで知り合われたんです?」
夕介が質問する。確かにそれは僕も気になるところだ。
「もともとは商工会で知り合うたんよ。わしも建具屋をやりよるからな。都会から来た、わけわからん若造か、と最初は思うた」
松岡さんは苦笑いを交えながら続けた。
「よそから来たばっかりで若いのにから、こっちのやり方にあれやこれや口を出すもんじゃけ、何じゃこいつはと思うて、最初は商工会でもいっそ相手にせんかった」
「無視、ですか?」
夕介が遠慮がちに尋ねる。
「ま、そういうとこじゃな。今思うたらネンコーさんには悪いことしたのう。ただ、そん時はそれまでのこっちのやり方が否定されたような気がしてから、面白うなかったんも確かじゃ」
松岡さんは正直な人だと思う。ネガティブな感情も包み隠さず話してくれる。
「しかしまあ、半年以上毎月のように商工会で顔合わせちょるうちに、こいつはちっと違うかもわからんなと思いだした。無視されようが何しようが、ネンコーさんはあいかわらずああやこうや言い続けちょったからの。深津峡……いうか、この山代のことを、こねえに熱うに語れる者が、わしらのうちにおるか言うたら、わしも含めて誰もおらだった。若い者がおらんいうんじゃない、熱い者がおらんかったんよ」
松岡さんは少し顔を紅潮させながら語り続ける。
「わしら地の者が熱うにならんで何の故郷か。じゃから、ネンコーさんが本物かどうか知りとうて、わしの方から保存会に誘うた」
「年光さんの熱意を、試してみようと思われたんですね」
夕介の言葉に松岡さんは深くうなずいた。
「まあ、考えてみりゃあ失礼な話じゃな、この深津峡を気に入ってわざわざ移り住んだ者を試すような真似をしたんじゃけ。じゃが、ネンコーさんは正真正銘、本物じゃった」
松岡さんは懐かしそうに目を細める。
「桐葉荘の経営が軌道に乗ったんは、ようやっと三年が過ぎてからじゃ。前回の奉納の準備を始めた頃はまだその前じゃったから、ネンコーさんも決して楽じゃなかったはずじゃが、稲村君と一緒に一歩も退かんと裏方に徹してくれた。こまごましたことやらなんやら、それこそ市役所とのやりとりやら、やねこい(煩雑な)ことばっかりじゃったのにな。ああ、こいつは本物じゃと思うた。うれしかったちゅうもんじゃない」
夕介が何度もうなずいている。
「そん時から、今年の『紫桜』にはネンコーさんにも舞台に上がってもらうつもりじゃった。思いもよらず早うに亡うなってしもうたけえそれは叶わんが……、わしは今でもネンコーさんがそこにおるような気がする」
松岡さんはそう言って再び舞台の方に顔を向けた。
僕もまだ誰もいない舞台を見た。
穏やかな風が、舞台の四隅に立つ青竹に結ばれた注連飾りを揺らしている。
「今回の『紫桜』は、ネンコーさんの弔い合戦じゃ。わしも精一杯舞う。しかと見届けてくれ」
松岡さんは力強くそう言った。
僕らに、というよりは、今そばにいる年光さんに直接語りかけるような口調だった。
桔梗さんは、そんな松岡さんの言葉に、じっと聞き入っているようだった。
────────────────────
註一 花傳第七 別紙口傳より(引用は岩波文庫『風姿花伝』野上豊一郎・西尾実校訂から。字体は新字体に改めた)
第四章 呪い 〈六〉
本殿での神事は関係者のみで行われるため、僕と桔梗さんは見所の果林ちゃんのところへ戻った。夕介は引き続き本殿で神事を取材中だ。
見所にはだんだんと空いた椅子が少なくなってきている。
もともとそんなに広い場所ではないが、ざっと一五〇人ぐらいの人だろうか、みんなそれぞれに談笑したり何かを食べたりしてのんびりと開演を待っている。
静かだった境内が今はざわめきで満たされている。昂揚感ではないし、かといって緊張感とも少し違う、うまく言えないが独特の空気が辺りに流れている。
果林ちゃんは座ったままスマートフォンを一心に見つめている。
僕も彼女の一列後ろに腰を下ろした。
桔梗さんは座らずに立ったまま舞台の方を眺めている。
「あ、おかえりー。どうじゃったー?」
「うん、松岡さんから年光さんの話を聞いてきたよ」
「ふーん」
果林ちゃんはスマートフォンの画面から目を離さず、興味なさそうに生返事をする。
「果林ちゃんスマホ持ってるんだ。家じゃ電波届かないんじゃないの?」
「うん、圏外。いちおーWiFiあるからネットはできるんよ。通話はアプリでするしー」
「なるほどね」
「なーなー、浩司さんはなんかSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)とかしとらんの?」
果林ちゃんはまだ画面から目を離さずに僕に訊いた。
「してないよ、ガラケーだし」
「えー、いまどきガラケー? ウケるー! なー、なんでなんで?」
果林ちゃんはやっとスマホから顔を上げて振り返り、古代生物にでも遭遇したような目で僕を見た。
「前はスマホだったけど、いろいろあってさ。面倒になってガラケーに変えたんだ」
「ふーん、そうなんじゃー。えー、いろいろって何があったん?」
果林ちゃんは背もたれに手を載せ、座席の上にひざ立ちになって僕に問う。
まいったな、正直思い出したくない苦い思い出なんだけど。
桔梗さんもいつの間にか座って僕のことをじっと見ている。どうやら興味を持たれているようだ。
「あんま言いたくはないんだけど」
「そんな風に言われたらよけい気になるじゃあ? 聞きたい聞きたい! なー、なになに?」
果林ちゃんはますます目を輝かせる。どうやら僕に黙秘権を行使する機会はないらしい。
僕は観念して白状することにした。
「──実は、炎上させたんだ」
「エンジョー?」
果林ちゃんが怪訝な顔で僕の言葉を繰り返した。
高校で友達が少なかった僕は、大学ではどうにかしてそれを克服しようと躍起になっていた。
大学に合格するとすぐ、いくつかのSNSを駆使して同じ大学の合格者とつながって、何とか友達を増やそうと悪戦苦闘した。その甲斐あって、SNSを通じた「友達」は数十人を数え、僕はその維持のための足あと残しやコメントに忙殺されることになった。それはそれで楽しいつもりでいたし、ここまでは思惑通り。
でも、所詮はリアルな友達ではないから、だんだんとボロが出た。
適当にごまかしながら続けていたが、ある時突然、それは起きた。
「友達」になった違う学部の男子との間で、些細なきっかけでコメントの応酬が始まり、あっという間にそれが他の「友達」にまで広がってしまったのだ。
僕は彼と徹底的に論争する気でいたから、色々なところで彼の言い分の誤りを指摘し、自分の正当性を主張した。しかし、それが逆効果だと気づいた時にはもう手遅れだった。タイムラインが僕に対する否定的なコメントで一気に埋め尽くされたと思ったら、汐が引くようにそれもなくなった。
大半の「友達」から僕のIDはブロックされたのだ。
学部の同級生の中にも彼の「友達」は少なくなかったため、僕はオンラインだけでなくリアルでも孤立することになった。
気づいてみたらひとりぼっち。
友達を増やしたくてSNSを始めたのに、逆に一人も友達がいなくなってしまうという皮肉な状況だ。
さすがに反省した僕はすべてのSNSを退会し、スマートフォンを手放してガラケーに変えた。それで失ったものが戻ってくるわけでもないけれど、自分の中でのけじめのつもりだった。
今年の春先のことだ。
「な、笑えるだろ?」
「なんか浩司さんかわいそー」
果林ちゃんが憐れみの目で僕を見る。同情されるとなんだかよけいにみじめな気分になる。
「ま、しょうがないよ、自業自得だ」
僕は自嘲気味につぶやいた。
「だから僕はガラケーなんだ。ちょっと不便だけど、まあ、これぐらいの方が僕にはちょうどいいや」
「ふーん、なるほどねー。浩司さんもみず姉と一緒で、友達おらん人なんじゃ」
果林ちゃんがにやにやしながら言う。痛いところを突かれてムッとするが、確かにその通りだから仕方ない。
「うちはすぐ友達できるけえ、そういうのいっそわからんなあ。みず姉も浩司さんも、難しゅうに考えすぎなんじゃないん?」
果林ちゃんは椅子の上に逆さまに座りこんだまま、背もたれの両手の上に顔を載せて僕に言った。
「──一切の事は、謂はれを道としてこそ、
萬の風情にはなるべき理なれ。
謂はれを現はすは、言葉なり──」(註二)
何の前触れもなくその言葉は発せられ、ふっとざわめきの中に溶けた。
「え? 今の、もしかして──」
果林ちゃんがそう言って桔梗さんの顔を見た。
桔梗さんはすっと背筋を伸ばして舞台の方を向いている。
遠くを見るような目で何かを回想しているようにも見えるし、少し険しい顔にも見える。
あまりに突然のことに、果林ちゃんは声が声にならず、口をぱくぱくさせるばかりだ。
「え? え? 今のきぃねえちゃん……よね?」
「間違いないよ、桔梗さんの声だ!」
僕も少し興奮気味の声を上げた。
「桔梗が、しゃべったんですか?」
いきなり僕の頭の上から、予想外の声が降ってきた。
「水菜さん!」
振り返ると、水菜さんが立っていた。
傘を五本も抱え、籐のバスケットまで携えている。
「本当ですか、森崎さん? 本当に桔梗が……?」
「うちも聞いた! きぃねえちゃんがしゃべった! しゃべったんよ、みず姉!」
果林ちゃんは興奮して立ち上がった。
当の桔梗さんは、何事もなかったように座ったまま舞台をじっと見つめている。
「信じられない……なんで?」
水菜さんは驚いた顔で桔梗さんを見つめながら立ち尽くしている。
「水菜さん、来てくれたんですね!」
僕も立ち上がると、茫然としたままの水菜さんから傘を受け取って、傍らに置いた。
「え、ええ。これを──」
水菜さんはそう言ってバスケットを差し出す。
果林ちゃんがバスケットの上に掛けられたふきんを取ってのぞきこむ。
「おおー、サンドイッチじゃ! さっすがみず姉、気が利くぅ!」
「わたしが作ったんじゃないよ、母さんに持って行くよう頼まれたの。わたしは持ってきただけ」
水菜さんは少しぶっきらぼうにそう言った。
蘭さんはすべてお見通しで、そんな水菜さんをここに連れ出すためにわざと後から頼んだのだろう。
「いただき!」
果林ちゃんはサンドイッチを一切れ取り出すとさっそくパクついた。
「あ、こら! まだ食べていいなんて言ってないでしょ!」
「まあええじゃあ、どうせ食べるために持ってきたんじゃけえ♪」
「もう、食い意地張ってるんだから」
そう言いながらも、水菜さんはやっと固い表情を崩した。
「それより、さっきの話本当ですか? 桔梗がしゃべったって」
水菜さんは僕との間の椅子にバスケットを置いて座りながら僕に尋ねる。
「うん、間違いなあよ。言葉がどうとかって言うた」
僕の前に座っている果林ちゃんが口をもごもごと動かしながら答えた。
「昨日の晩には、僕と会話もしたんです」
「何があったの? 今まで何があっても絶対に口を開こうとしなかったのに……」
水菜さんは桔梗さんに問いかけたが、桔梗さんは舞台の方をじっと見つめたまま、身じろぎひとつしなかった。
宮司と火入れ奉仕者が入場するとアナウンスが流れた。
本殿の方を見ると、白い装束の神職に続いて、羽織袴姿の男たちが一列になって火のついた松明を持って降りてくる。
舞台正面に神職が立ち、男たちはそれぞれの篝火の脇に控えた。
一同の起立を促すアナウンスがあり、僕らもそれに従った。神職が祝詞を述べ、奉献の儀式を行う間、観客はみな軽く頭を垂れてそれを聞いている。
続いて火入れの儀となり、神職の合図により見所の篝火に同時に火が入った。見所全体が漣のようにざわめき、次いで自然と拍手が沸き起こる。
いよいよ、猿楽『紫桜』の幕が上がる。
〈第四章終わり〉
────────────────────
註二 花傳第六 花修云より(引用は岩波文庫『風姿花伝』野上豊一郎・西尾実校訂から。字体は新字体に改めた)
第五章 紫桜(しざくら) 〈一〉
どこからか笛の音が細く響くと、波が静まるように見所から徐々にざわめきが引いていく。「調べ」と呼ばれる、鏡の間で行われる音合わせ兼前奏曲のようなものらしい。鼓の音も聞こえてくる。
「いよいよ始まるな」
僕の左隣の通路でカメラを抱えて立っている夕介が僕に告げた。
「うん、少し緊張してきた」
「なんでお前が緊張すんだよ?」
夕介が小声で笑うが、そう言う夕介だって少し表情がこわばっている。
今はまだ明かりがなくても十分舞台の様子がわかるが、今日はどんよりと曇っているから、辺りはあっという間に夜の闇に包まれてしまうだろう。既に見所の後方から投光機が舞台に向かって光を向けている。
気の早い虫が鳴く声が聞こえ、篝火からは火の粉のはぜる音が耳に届く。後ろの方からは発電機の低いうなりも聞こえる。
最初に揚げ幕が半分開いて、囃子方が橋掛りを歩いて本舞台に上がる。
続いて舞台後方のアト座右手から、次々と紋付姿の男性たちが舞台に上がり始めた。
舞台は僕たちの見ている場所から一五メートルは離れているはずだが、板敷きを踏む音までが聞こえてくる。
最初にアト座に上がった男性は、竹で組まれた枠型の台座に据えられた桜の枝の作り物を捧げ持っていた。
桜の枝には満開の花。
「よくできてるな、ここからだと本物に見える」
夕介がつぶやいた。
和紙で作られているという桜の花は、夕介の言うとおり本物に見える。本物と同じ薄紅色で、簡素なつくりながらも素朴な美しさがある。
桜の作り物は舞台の正面見所寄りに置かれた。
舞台上には男性が十人上がった。
先ほど作り物を据えた男性は僕から見てアト座の左隅……つまり橋掛り側に座ったから、この人がどうやら後見らしい。
後見の手前には囃子方が正面を向いて並んで座る。
向かって左から太鼓、大鼓、小鼓、一番右に笛の順だ。
太鼓はかなり小ぶりな大きさで、座った状態で台に据えられたものを二本の撥で叩くようだ。
大小の鼓方はそれぞれ合引と呼ばれる床几に座った。
舞台右手の地謡座には地謡方が五人、脇正面……僕らから見て左の方向を向いて板敷きにじかに正座する。
夕介じゃないが、僕もさっきパンフレットを見て覚えたばかりの配置だ。
よく見ると、地謡座に見覚えのある顔……というより頭があった。タクシーの運転手・青笹さんだ。黒縁眼鏡をしていなくてもあの頭ですぐわかる。普段は温和な感じだが、今は緊張からか少しこわい表情に見える。小さな目が脇正面の空間を鋭くにらんでいる。
舞台に上がった全員が昼間一緒に作業した気のいいおじさんたちのはずだが、羽織袴を着けているため今は威厳のある雰囲気をまとっていて、みんなまるで別人のようだ。
後見と笛が目配せをしたと思ったら、一呼吸置いて笛が哀しげな細い音で唄い始めた。
「始まった」
夕介が短くつぶやくとカメラを構えた。
これから始まる悲劇を予感させるように、哀調を帯びた笛の音が杉林の中に響いては消えていく。
ふっと笛の音が止むと、見所の観客の目が一斉に橋掛りの方へ向いた。
揚げ幕がさっと上げられ、いよいよ演者が登場する。
最初に登場したのは主役の相手役となるワキだ。
ワキは面を着けない直面で演じる。しかし、面を着けずに演じるといっても、あえて表情をつけることはなく、自らの顔を面として演じるのだと夕介が教えてくれた。
きちっと着付けた着物の上に茶渋色の水衣と呼ばれる薄い絹の上着を着けていて、旅装であることを表す杖を携えている。こちらはパンフレットから得た情報。
春の雲路の旅衣 春の雲路の旅衣
宇侘の早瀬の 先へ急がん
ワキは謡いながら実にゆっくりとした摺足で橋掛りを進んでくる。足を前に運ぶのだが、何かがそれを押し止めようとしているかのような、抑えた動作。
橋掛りから本舞台に上がったところで、ワキは正面を向いて節を付けない台詞で自己紹介を始めた。
これは 石見の国より出でたる某にて候
商ひにて急ぎ参り仕らんとて
宇侘川をくだり候間 美しき桜の堤にあへり
普段の会話の声とは発声が全く違う。決して大声を張り上げているわけではないのに、周囲にはっきりと響く、力強い発声だ。
第一幕『桜堤』は、石見の国の某という商人が堤に植えられた見事な山桜を褒める場面から始まった。
某は優雅な所作で扇を広げ、大小の鼓の音に合わせて桜の作り物の周囲をゆっくりと舞い謡い、桜の名所・吉野もこのような情景であろうか、と讃嘆する。
今は秋なのに、舞台上だけはうららかな春の日だ。
小鼓はポンとやわらかな音を吐き出し、大鼓はカッという鋭い音を立てる。
大鼓の奏者がとる所作がカッコいい。掛け声を発しながらすっと右手を横に伸ばしたかと思うとすばやく掌が返り、次の瞬間には左脇に抱えた鼓をもう打っている。一連の所作が空気を裂くような鋭い音を生む。
一方、小鼓は奏者の左肩に載せられ、打ち方次第で様々な表情の音を出す。むしろリズムを主導するのは小鼓の方だ。
大小の鼓が独特のリズムを作り出し、某は満開の桜を楽しむかのようにゆったりと舞う。
やがてワキは舞台向かって右側、地謡方の前方に控え、橋掛りの方を向いた。自然と僕らの目も再び橋掛りの方へ誘導される。
そのタイミングを計ったように揚げ幕がさっと上がり、鏡の間から主役であるシテが登場した。
「きれい──」
水菜さんが思わずためいきを漏らすのが聞こえた。
見所には一瞬息をのむような空気が流れる。
シテは若い娘の面を着け、唐織という華やかな小袖を、ワンピースのようにきちんと着付けた着流しの出立で登場した。唐織には赤い色がふんだんに使われていて、見た目にも鮮やかだ。まるで錦秋を描いた日本画を見るような、繊細な美しさ。
パンフレットによれば、紅色の入った唐織は「紅入」と呼ばれ、未婚の若い女性を表しているのだそうだ。
シテは笛の音が流れる中、橋掛りをゆっくりとした摺足でしずしずと進んでいく。
鮮やかな色づかいの装束の中で、白い足袋だけがすっすっと動いていくので逆に印象的だ。
演者は男性のはずだが、橋掛りの上には確かに女性のまとう空気が流れている。
時間の流れまでがゆっくりになったかのような悠然とした、しかし決して緩慢ではない独特の所作で、いよいよシテが本舞台に上がった。
ワキが声をかける。
いかにこれなる人に 尋ね申す事の候
げにも美事なる桜にて候ぞ さても名にし負ふ桜にてや あらんずらん
この桜の謂われ もし存知なれば お教へ候へ
前シテは里女、つまり地元の若い娘という設定だ。
石見の某は、この見事な桜のいわれを知っているなら教えてほしい、と女に乞うた。
里女は桜の作り物の脇に立つと、それに答えて堤の桜の由来を語り始める。
人の世は 早瀬の如く うつろひて
沈める花は 浮かぶ世もなし
里女は最初に哀調のこもった調子で和歌を詠った。
面を着けていてもシテの声は辺りに朗々と響く。
男性の声であることは明らかなのに、調子の付け方がワキとは違ってどこか優美で、確かに女性らしさを感じさせる謡い方だ。笛と鼓がそれに重なっていく。
もはや誰もが忘れたが、その昔、沓懸の山で滅びた武将があった。主君への忠義を貫いて敗北の明らかな戦いに臨み、遂に空しくなったますらおの、その娘がここに沈んでいるのだと。
里女はゆっくりと舞台の前方に移動し、優雅な所作で舞扇を広げた。金色の地に満開の花をつけた桜の古木と流れる川が描かれた柄が目を引く。
隣の水菜さんが、はっと息を呑むのがわかった。
水菜さんは魅入られたように舞台をじっと見つめている。僕が彼女の横顔を見ていることにまったく気づいていない。ものすごい集中力だ。
里女はそのままゆっくりと舞い始めた。
戦を逃れて山代へ流れ着いた娘は、身分を隠して寺に身をひそめ、戦死した父の菩提を弔っていた。
ところが、翌年の夏に宇侘川が豪雨により氾濫し多くの被害が出たため、領主は堤を造ることを決め、人柱となる生娘を募った。
しかし、誰もが顔を見合わせるばかり。
その様子を見ていた娘は、自ら人柱に名乗り出た。
固より甲斐なき命なれ
この身を捧げて もろともに
巌となりて 我が命
世の為に使ふこそ
いみじく浄土の弄引なるべし
元々どうするあてもなかった自分の命、世のために捧げれば、極楽浄土に往生できるだろう、と地謡方が謡う。
堤は数年を経て完成し、堤に沿って植えられた山桜こそが、目の前の桜である、と里女は旅人に告げた。
堤の礎となって身を沈めた娘の名は、桜姫。
ここで里女はふっと舞うのを止めた。某が不審に思って顔を上げる。
人の世は 早瀬の如く うつろひて
沈める花は 浮かぶ世もなし
里女が再び最初の和歌を詠った。
次の瞬間、鋭く空気を引き裂くような高音で笛が哀切極まる調子で唄い始めた。
動きを止めていた里女が今度は激しく舞い始め、裂帛の掛け声とともに大小の鼓が打ち鳴らされる。
里女は舞台を斜めに移動し、数度足踏みを繰り返す。
何かを訴えかけるような所作だ。
広げた扇を両手で持ってかざしたまま、今度は舞台を横切るように移動する。
落ちる花びらを扇で受けるような仕草をしたかと思えば、軽やかに輪を描き、すっと身を沈める。
舞台上には何もないのに、辺りは桜吹雪に包まれているかのように錯覚する。
切なくも美しい舞。
やがて里女は再び舞台を斜めに移動し、後見の手前で立ち止まると、観客に背を向けたまま扇をたたんだ。
地謡方が斉唱する。
はや花風にて舞いたると 思うほどに
花曇にかき乱れて
跡も見せずなりにけり 跡も見せずになりにけり
石見の某が見守る中、里女はそのままつっと橋掛りを渡り、揚げ幕の向こうに消えてしまった。
花吹雪にまぎれて里女の姿はかき消えてしまったのだ。
舞台の上にはあっけにとられた某が立ち尽くしている。
舞台がいったん静まると、辺りが既に夕闇に沈んでいることに気づいた。辺りに白い粉のようなものが漂っていると思ったら、篝火から流れてきた薪の灰だった。
不思議なことに、舞台上で物語が展開されている間は周囲の音は一切耳に入らない。
舞台の上には面をつけない別の役者が橋掛りから登場した。ワキとは違って少し大げさな所作で、酒瓶を捧げ持って橋掛りを歩く。
このあたりの者でござる
宇侘八幡の勧進に 神酒を奉らんとて
急ぎ参る処にて候
通常は狂言方、つまり狂言を演じる者が務める、アイという役回りだ。宇侘八幡宮ではアイのみを演じるのでアイ方と呼んでいるらしい。アイは基本的に地元の住人で、旅の者であるワキにその土地の伝承を詳しく語って聞かせることで、前場でシテが展開した物語が伝承の通りであることを伝える役だ。
某がその姿を認め、呼び止めた。
先ほど里女にこの地の桜の由来を尋ねたところ、さる武将の娘が人柱となった堤に植えられた山桜であると教えられたが、里女の姿は桜吹雪にまぎれてかき消えてしまった。この話はまことであろうか、と。
ワキの問いかけに答えてアイが言う。
仔細は存ぜぬが、いかにもこの桜堤は沓掛山で無念の戦死を遂げた武将の娘・桜姫が人柱となって造営されたものである、と。
堤が出来上がってから七年が間、堤の桜は紫の花をつけたと言われているが、御身は存知であるか、と逆に問う。
某は今初めて聞く話だと驚いて言う。
紫桜とはさても珍しいことだ、自分も見てみたいものだと某は興をそそられる。
しかしアイは、桜姫の無念が紫桜を咲かせたのだ、と言う。
この世を去りがたい姫の魂魄が、御身の前に里女の姿となって現れたのだろう、懇ろに弔うがよろしいと思う、と告げて彼は去っていった。
某はいったん旅を留め、堤の脇で野宿することにする。
夜になり、満開の桜が妖しく咲き誇っている様子を地謡方が謡う。
再び、笛が哀切な旋律を奏で始めた。
揚げ幕が上がり、後シテが登場する。
後シテは前場のあでやかな衣装からうって変わって、地味な小袖の上に白い水衣で橋掛りに現れた。面は前場とは違い、苦悶の表情を浮かべた顔立ちのものに換えられている。
僕は思わず白装束の桔梗さんを連想して彼女の方を見た。
桔梗さんは、整った顔立ちをじっと舞台に向けている。長い睫毛の下の瞳が、白い装束をまとった後シテをまっすぐに射抜いている。
水菜さんも同じことを連想したらしい、桔梗さんを一瞥したがすぐにまた舞台に目を戻した。
一方、桔梗さんの左隣に座っている果林ちゃんはかくん、かくんと首が落ち始めている。
「果林ちゃん、果林ちゃん」
僕は後ろから小声で声をかけ、軽く肩をたたいた。
「ほえ? ──いけんいけん、寝よった」
果林ちゃんは目をこすりながら僕の方を振り返った。
「なんでこんなに眠とうなるんじゃろ?」
「いいから舞台見て」
僕は小声で正面を指さした。
ちょうど後シテが橋掛りから本舞台に差し掛かったところだった。
二ツ切り能という構成に従い、中入りを経て前シテの里女から装束を変えて登場した後シテは、桜姫の幽霊だ。
二ツ切り能とは物語を前後二つに分け、前半に現実界に現れた前シテから言い伝えを聞いたワキが、後半に夢や幻の世界へ迷い込み、その中で言い伝えの当事者(たいていの場合は幽霊だが)である後シテと語らうという構成のことだ。観阿弥・世阿弥親子によって編み出された能の黄金パターンで、複式夢幻能とも言うらしい。もちろん、これもパンフレットに書いてあることそのままだ。
何時まで草の陰 苔の下には埋れん
さらば埋れも果てずして 苦しみはなおも離れず
あら閻浮恋しや 閻浮恋しや
「閻浮」とは仏教用語の閻浮提のことで、要するに「この世」のことらしい。
自らの意志で人柱になったにもかかわらず、桜姫の霊は苦しみが離れることはなく、この世が恋しいと嘆いている。
桜姫は某に問いかける。
御身 わらはを
何処か彼方へ
連れ遣り候へ
僕はどきりとして隣の水菜さんを見た。
昨夜聞いた「わたしを、どこか遠くに連れてってくれませんか?」という彼女の声が蘇る。
水菜さんは両手を口元に当て、目を見開いて舞台を見つめている。
桜姫の霊は続けて語る。
話に聞く都は長い戦乱で荒れたとはいえ、なおも美しいところが多いと聞く、自分もそのようなところに住まいたかったと。鄙にない美しいものを見て、和歌を詠んで雅に暮らせればと願っていたが、戦で父が死に、それも儚い夢となった。
世の為になろうと人柱となることを願い出たが、それすらも科となって自分を苦しめる、一体どうすればよかったのかと切々と訴える。
某がうめくように桜姫に返す。
自分が僧であれば神通力であなたを成仏せしめ、その苦しみを除くこともできようが、卑しき身ゆえそれも叶わぬ、と。
桜姫は某の思いに感謝し頭を下げると、ゆっくりと舞い始めた。
笛が哀切極まる旋律を奏で、前場では演奏されなかった太鼓が加わって重苦しい雰囲気を醸し出す。
前場の軽やかな舞とは違い、この世を去りがたく、しかしあの世にも行けぬ苦しみを表しているような苦しげな舞だ。
水菜さんがその舞をじっと見つめている。
父の菩提を弔うこともできなくなり、自らも苦しみに沈んで、この世に戻ることもあの世に行くこともできない、と謡う桜姫。
せめて父の無念を慰めようと七年の間紫桜を咲かせたが、最早自分にはその力もないと肩を落とす。
やがて桜姫の霊は舞うのを止めた。
笛が哀しげな旋律を奏でる中、ゆっくりと橋掛りを歩いていく。
その背中に向かって地謡方が謡う。
姿形も朧となり行けば いよいよ思ひは 消え消えと
見えつ隠れつする程に 東雲の空も ほのぼのと
明け行けば跡もなく ただ桜の花の舞うばかりとこそ
哀れなりけれ 哀れなりけれ
最後にひときわ高音で笛の音が泣き、桜姫は揚げ幕の向こうに消えた。
見所には切ない余韻が残って、水を打ったように静まり返ったままだ。急に虫の音が大きく聞こえてくる。
ふと隣の水菜さんを見ると、彼女は静かに涙を流していた。
何か見てはいけないものを見てしまったような気がして、僕は黙って顔をそむけた。
「なーなー、どういうことなん? いっそわからん。誰か説明して」
果林ちゃんが大声で話しかけてくる。
舞台から演者が退場し終わると見所から自然に拍手が起こり、緊張も解けて和やかな空気が戻った。。
「やっぱり果林には難しすぎたか」
夕介が左手であごひげを撫でながら言う。
「なんでみず姉泣いたん? どーゆー話なん? もう、さっぱりわからん」
「わたし泣いてなんかないもん」
水菜さんは強がってそう言うが、涙の跡は隠せていない。
「めちゃくちゃ簡単に言えば、自分から進んで生贄になって死んだ娘が、成仏できずにこの世とあの世の間をさまよってる話だ」
「えー、ヒドい! かわいそすぎる!」
果林ちゃんは口をとがらせて夕介に抗議する。確かに大ざっぱに言えば夕介がまとめたとおりの物語だ。桜姫の霊は明け方と共に姿を消しただけだから、成仏できないまま。石見の某も、何ひとつできない無力さに打ちひしがれていた。カタルシスもなければ希望もないエンディング。
「なんか納得できん! なんでハッピーエンドじゃないん? せめて成仏ぐらいさせたげればええのに! かわいそすぎるよ!」
果林ちゃんはまだ夕介に食い下がっている。
「うーん……それは逃げ出すためだったからじゃない?」
僕はなんとなく自分の感じたことを口にした。
「世のため人のためっていうのも確かにあったかもしれないけど、本当は桜姫は色々といやなことばかりのこの世から、逃げたかっただけなんじゃないかな」
言ってしまってから、ずいぶんと自分のことを棚に上げた発言だと気づいた。僕だっていやなことだらけの生活から逃げ出してここに来たんじゃないか。
水菜さんが少し厳しい表情で僕をにらんだ。
「そんなことないと思います。わたしは、彼女は彼女なりに一生懸命に考えて、自分の命を活かす方法を選んだんだと思います」
彼女は右手を自分の胸元に当てながら反駁した。
「もう頼れる人はいない、生きていてもしかたのない自分の命が、少しでも誰かの役に立つならそれでいいって、本気で思ったんじゃないですか?」
水菜さんがあまりに真剣に桜姫を擁護するので、僕は一瞬たじろいでしまった。
「いや、森崎の言うことの方が正しいだろう。厭離穢土・欣求浄土って聞いたことあるか? この娑婆世界を穢れた場所として厭い、清浄な世界を希うって意味だ。『桜堤』にはこの思想が色濃く出ているな。元々都に憧れてた桜姫は父の戦死で世を儚んで、人々のために人柱になることで浄土──そうだな、ここではないどこかへ行くことを願ったのかもしれないが、結果としては間接的に自分で自分を殺したのと同じだ。不殺生戒──つまり殺すなかれという戒律を犯したことになる。成仏はできなくて当然だ」
「そんな──」
夕介の解釈を聞いて、水菜さんは言葉を失ってしまった。
「なーなー、きぃねえちゃんはどう思う?」
果林ちゃんがじっと僕らの会話を聞いている桔梗さんにも尋ねたが、彼女は何も言わずに首を横に振っただけだった。
第五章 紫桜(しざくら) 〈二〉
鏡の間から笛の音が聞こえ、見所は再び静まりはじめた。アト座の背後には演者が集まっている。
そろそろ第二幕『寂水』が始まるようだ。
舞台の上には先ほどの『桜堤』の時に据えられた桜の作り物が、アト座に下げられたまま残っている。
先ほどと同じように、囃子方が橋掛りから入場を始め、それに続いてアト座から後見と地謡方が舞台に上がり始めた。
大鼓を抱えているのは、昼間一緒に作業した武骨漢・伊藤さんだ。昼間はどうしても幽玄な猿楽のイメージと合わないような気がしていたが、こうして紋付姿で舞台に上がっているのを見ると、全然そんなことはない。適度に力を抜きながら、細やかに身体を律して歩いているのがわかる。
全員が舞台に上がり着座すると、一気に緊張感が漲る。
張りつめた空気の中、笛の音が流れ始めた。さっきとは調子が違い、どこか禍々しさを感じさせる旋律。
笛の音が止んで揚げ幕の向こうから登場したのはワキである武者と、ワキツレ(ワキに従う助演者)の従者。ワキを演じているのはあの大人しそうな稲村さんだが、眼鏡を外してぴんと背筋を伸ばして橋掛りを歩く姿は堂々たるものだ。
武者は面を着けない直面で、黒い侍烏帽子を載せている。腰には太刀を携え、裾が大きく広がった大口袴の上に直垂を着けた武人の出立で、重々しく橋掛りを進んでいく。
これから始まるのは鬼退治の物語だから、第一幕の『桜堤』とは全く雰囲気が異なる。狂言を挟まずに上演する上で、観客を飽きさせない工夫のひとつなのかもしれない。
これは 國中第一の武者
阿山三郎次郎左衛門にて候
近頃山代に 鬼の出でて 人を喰らう由承りて
村々人々より 鬼の退治を 仰せつかり候
ワキが雄々しく名乗りを上げた。普段の稲村さんからは想像もつかない、凛々しい張りのある声だ。
「おー、なかなかのイケメンじゃあ♪」
果林ちゃんがはしゃいだ声を上げた。
「さっきは寝てたくせに、イケメンだところっと態度が変わるんだ」
僕が後ろから小声でからかうと、果林ちゃんは振り返ってにまにましながら言う。
「そりゃそうよ。目の保養目の保養」
「彼氏いるんだろ?」
「それとこれとは別ー♪」
両目をハートマークにしている果林ちゃんには何を言ってもムダなようだ。
舞台上では、武者が鬼を探して山の奥深くへと分け入っていく様子が謡われている。
ワキは墨絵の虎が描かれた銀色の扇をかざして力強く舞う。山の奥へ奥へと分け入る様を表しているようだ。
大小の鼓が抑えた音で緊張感を演出する。
大鼓の伊藤さんの所作はきびきびとしていて、見ていてすがすがしい。力強い掛け声といい、鋭い音色といい、大鼓は伊藤さんにぴったりだ。
さても はや寂水峡まで至り候
いまだ物怪には 見えず
さてさて いづ方にぞ 潜みたりけるや
従者が寂水峡に到着したことを告げると、武者はワキ柱の手前で一度立ち止まり、すっと中腰の姿勢をとって扇をかざして橋掛りの奥の方を向いた。従者がその脇に控え、同じように橋掛りの方を向く。
武者が、あれこそ人喰いの鬼かと叫ぶと、それを合図に揚げ幕の奥から派手な装束に身を包んだ前シテが登場した。
赤頭と呼ばれる鮮やかな赤い鬘を着け、面は額の両隅に角が生え、かっと目を見開き口を大きく開けた激しい表情の白い般若。手には打ち杖を持ち、上半身に身につけている三角形の連続模様が箔で施された鱗摺箔という独特の衣装がぎらぎらと光を返し、鬼神の異様さを演出している。
鬼は禍々しい空気を振りまきながらじりじりと橋掛りを進み、本舞台に上がった。
武者は一度身を翻して改めて鬼と対峙する。
果林ちゃんが息を詰めて舞台を見つめている。居眠りする暇もないほど舞台に引き込まれているようだ。
水菜さんも僕の隣で舞台を見つめているが、僕が彼女を見ていることに気づくと彼女はふっとほほ笑んだ。
「なんだか緊張しますね」
水菜さんは小声でそう言うとまた舞台を見る。
先に仕掛けたのは武者の方だ。
太刀を抜くと上段から鬼に斬りかかった。
笛が鬼の咆え声のように鋭く鳴り、大小の鼓が戦闘の緊迫感を表現するように激しく打ち合う。伊藤さんの力強い掛け声が武者の気迫と一体になったかのように舞台の上に響く。
鋭い鼓の音は剣戟の音のようにも聞こえる。
神楽の激しい動きを伴った演出とは異なるが、様式的な所作の中にも、命のやりとりをしている緊迫感が漂う。
両者はわずか三間四方の舞台上を移動しながら死闘を繰り広げる。
武者は鬼の力に圧倒され気味で、ついに橋掛りの手前にまで追い込まれた。
遂に巌の汀に 追はれ給ふが
南無や八幡大菩薩と 心に念じ
剣を構へて 待ちかけ給へば
従者 鬼神の背より 打ちかかりて
振り向きたるを 切り払い給ふ
絶体絶命のピンチに従者が機転を利かせて鬼に背後から打ちかかり、注意をそらした。
その瞬間、身を翻して武者が振り上げた太刀を思い切り斬りおろす。
数歩よろめく鬼神。
踏みとどまろうと足踏みをひとつするが、武者はそこを再び下から払い上げた。
勝負あった。
鬼神は本舞台から下りて橋掛りをじりじりと後ずさりしていく。
武者は手ごたえを確信し、太刀を横に構えて本舞台から鬼をにらみすえている。
十方に 響く鬼神の声絶へて
高き巌の汀より 流れ逆巻く寂水の
水のうちへとどうと墜ち
其の姿形は 白波の
影に呑まれて失せにけり 影に呑まれて失せにけり
鬼は岩から寂水峡に落ち、姿が見えなくなったと地謡方が謡い、前シテはもんどり打つように揚げ幕の向こうへ消えた。
パンフレットによれば、前場でこのようにいきなり立ち合いを行う演目は少ないらしく、これも特殊な構成らしい。
「勝った勝った♪」
果林ちゃんが小さくはしゃいでいる。確かにこういう演目ならわかりやすい。
舞台上にはワキツレの従者と交代するようにしてアイの村長が登場し、武者を称賛している。
村長は、さすがは国中第一の武者である、これで山代の者も安心して暮らすことができ、その武功は千金にも値するであろう、と美辞麗句を並べた。
しかし、鬼の首級を持ち帰ることのできなかった武者はどうもすっきりしていないようだ。
勧めによりしばらくこの地に逗留することになった武者は、ワキ座に控えるような形で座った。
後見が、アト座に下げられていた桜の作り物を改めて舞台正面中央に据える。
場面が武者の夢の中へと移ったのだ。
揚げ幕から現れたのは、美しい娘姿の後シテだ。
『桜堤』の前シテの時のような紅入の唐織だが、色柄は異なり、出立も「脱下げ」と呼ばれる右袖を脱いだ形になっている。これは心を乱す狂女の装いだとパンフレットにはある。
果林ちゃんが少し怪訝な顔で振り返って僕に尋ねた。
「なーなー、どういうこと?」
「鬼の正体は復讐に狂った桜姫だったってことだよ。今からその辺がわかると思うよ」
「じゃったら横で解説して」
果林ちゃんは小声で僕を手招きする。
仕方なく僕は果林ちゃんの左隣に移動した。
舞台上では武者が夢の中に現れた女に、あなたは誰かと問うている。
これは 沓懸の山にて 空しくなりける もののふが娘
桜姫なり
先に寂水にて 御身に うち滅ぼされたる身なり
桜姫は自らの出自を名乗り、私は寂水峡であなたに討たれた身であると告げた。
武者は驚き、あの鬼神はあなたであったのかと問いなおし、桜姫はいかにもその通りだと答えた。
「は? どゆこと? 桜姫ってイケニエになって死んだんじゃないん?」
果林ちゃんが僕に小声で尋ねてくる。
あまりの近さに少しどぎまぎしながら僕は答えた。
「『紫桜』はパラレルな物語なんだよ。同じ主人公なのに、それぞれ全然違う物語が展開するんだ」
「え~、そんなのありなん?」
果林ちゃんの声が段々大きくなるので僕はあわてて人差し指を自分の口の前に立てた。
果林ちゃんはあわてて自分の口を押さえる。
「とにかく、しばらく様子を見てみようよ」
僕はそう言って果林ちゃんの意識を再び舞台に向かわせた。
舞台上では桜姫がゆっくりと舞いながら自分の身の上を謡っている。
辛くも戦を逃れた桜姫は、父を亡きものとした二人の武将に復讐心を燃やしていた。
この身を滅ぼすことになっても、父の仇を討ち果たさずには、死んでも死にきれぬと願い続けた彼女は、ある時正気を失ってしまう。
彼女が正気を取り戻したとき、目の前には男の骸が転がっていた。その無惨な死体は、間違いなく彼女が憎み続けた仇の一人。
両の掌を眺めるしぐさをしたシテの目線の先には何もない。しかし、小さくわななく様子で、骸を前にした恐怖が伝わってくる。
仇の血に汚れた自らの手を見て、彼女は目の前の男をひねり殺したのは自分であるに違いないと確信した。
あれほど仇を討つことを願い続けていたというのに、いざそれを目の当たりにすると、底知れぬ力が自分を駆り立てていることに、桜姫は戦慄する。
しかし、彼女は再び正気を失ってしまい、そのまま鬼神として狂い回ることになってしまったのだ。
太鼓が規則的なリズムを刻み、それに合わせて桜姫は桜の作り物の前をゆっくりと横切る。
ここでは桜の作り物は現実の桜ではなく、夢の中であることを表している。
夢か現か はやも異類となれる身の
重き罪科は 徒波の
寄辺も無き身 濁る心に逆巻きて
慕ひた父も 我が事も 憂しや思ひ出でじ
果てはみな忘れて狂ひけり みな忘れて狂ひけり
地謡方が斉唱する中、桜姫は座り込むと、うつむいて左手を顔の前にさしかけるシオリという所作をとった。
父のことはおろか、自分のことすら忘れて狂ってしまったと泣いているのだ。
自分はあなたに鬼として討たれたことでようやく私が何者であったかを思い出した、しかし既にすべてが遅すぎた、と桜姫は告白する。
隣の果林ちゃんがさっきからじっと黙ってしまっている。少し顔色も悪いようだ。
「大丈夫?」
僕が声をかけると果林ちゃんは小さくうなずいたが、唇をかんでじっと舞台上の桜姫を見つめている。
武者は桜姫を哀れに思い、その供養を約束した。
すると桜姫は、自分は異類(人ではないもの)となって罪もない者の命を奪っては喰らい続けた重い罪科があり、堕地獄は必定であると思い定めている、と言う。
三途の川を渡る前に、あなたに頼みたいことがある、そのために私はあなたの夢に出たのだ、と彼女は告げた。
何なりと申し受ける、と武者が答えると、桜姫は深々と一礼して続けた。
されば恐れながら、沓懸山で儚くも散った我が父の供養をお頼み申したい、と。
私には最早父の供養などできようもない、あなたがわが父を祀る塚を造り、そこに山桜を植えたならば、その礼として七年の間、紫の花を咲かせよう、と桜姫は彼に約束する。
武者は桜姫の語る物語を聞いてもらい泣きし、喜んでその意に添いたい旨を告げた。
笛が細く唄いはじめた。
悲哀に満ちた音色が鋭く杉林の中に吸い込まれていく。
大小の鼓と太鼓がそれに和して続く。
桜姫はゆっくりと舞を舞いはじめた。
父の供養を約束してくれた武者に対する感謝の舞だろうか、ひとしきり舞うと、桜姫は再び正面に直った。
切なくも美しい、短い舞だった。
舞いを終えた桜姫は武者に背を向け、橋掛りをゆっくりと退場していく。
これから三途の川を渡り、地獄の責め苦を一身に受ける覚悟とともに、悔やんでも悔やみきれない後悔をにじませた、哀れな後ろ姿だ。
桜姫は三の松のところで一度立ち止まって正面に向き、改めて一礼した。
僕にはそれがこの世への別れのあいさつのように見えた。
隣に座っている果林ちゃんが、青ざめた顔で去りゆく桜姫を凝視している。
去り難きと見ゆるも 無間獄への道行を
心も堅く進みけり 心も堅く進みけり
桜姫は決心して地獄への道行を進んでいった、と地謡方が謡い、桜姫は静かに揚げ幕の向こうへ消えた。
桜の作り物がアト座に下げられ、舞台に残った武者が立ちあがる。
桜姫との約束通りに宇侘八幡宮の一隅に塚を寄進し、そのかたわらに山桜を植えたところ、彼女が約した通り桜は七年の間紫色の花を付けたと語ると、武者は静かに橋掛りを歩いて退場していった。
隣に座っている果林ちゃんが小さく震えている。
「果林、大丈夫?」
後ろから水菜さんが心配そうに声をかけたが、果林ちゃんはひざを抱え込んで顔を伏せたまま、何も答えない。
すると、果林ちゃんを挟んで僕の反対側に座っていた桔梗さんが、果林ちゃんの肩を抱き寄せた。
「大丈夫、果林は鬼にはならない」
桔梗さんがそっと囁くと、果林ちゃんは肩を震わせ、嗚咽をもらした。
辺りはすっかり夜の闇に包まれてしまい、杉林の間から見える空は分厚い雲にふたをされてしまったかのように見える。
幕間のざわめきの中で、果林ちゃんはしばらく泣き続けた。その間、桔梗さんがずっとそばで肩を抱いていた。
水菜さんはそんな二人のことを難しい顔でじっと見守っている。
僕はどうしたらいいかわからず、うろたえた顔で夕介を見上げたが、夕介も腕を組んだまま何も言わない。
「うち、やっぱり鬼なんかもしれん。あの鬼は、うちなんよ……」
少し落ち着いてきた果林ちゃんがようやくぽつりとそう言った。
「どうしたの? 果林は鬼なんかじゃないよ」
水菜さんが努めて優しく声をかけたが、果林ちゃんは首を横に振った。
「みず姉昼間言ったじゃあ? なんで父さんのこと忘れるんかって」
果林ちゃんは泣きはらした目で水菜さんのことを見る。
「うちは毎日楽しいからそれでええやって思いよったけど、それってあの鬼と一緒なんかもしれん。自分のこともわからんようになって、いつの間にか狂いよるんじゃ……」
そう言われた水菜さんはかける言葉を失ってしまった。
「果林ちゃんは桜姫とは違うよ、復讐に燃えてるわけじゃないし」
僕は何とか言葉をひねり出したが、果林ちゃんは再びかぶりを振る。
「父さんが死んだとき、うちは父さんのこと絶対忘れまあと思うたんよ? なのに、いつの間にか声も思い出せんようになって、顔もなんかぼんやりして。みず姉が言うとおり、思い出じゃってようけ(いっぱい)あったはずなのに、いっそも思い出せん。うち、このまま父さんのこと何も思い出せんようになるかもしれん。じゃったらあの鬼と一緒じゃないん?」
果林ちゃんは真っ赤にした目に再び涙をためている。
「こわいんよっ、自分が何か違うものになりよるような気がして!」
彼女は何かに怯えたような顔で声を絞り出した。
「確かに、自分を自分と確認できるのは、記憶だけだからな。記憶を失くしてしまったら、あの鬼と同じかもしれない」
夕介がそうつぶやくと、いきなり桔梗さんが振り返って夕介をにらんだ。
「果林は、鬼じゃない。鬼になんかさせない」
桔梗さんは強い調子ではっきりと言った。鋭い目で夕介を見据えている。
「あ……スマン、言葉が過ぎた」
突然のことに夕介はややたじろいだ様子で桔梗さんに詫びた。
水菜さんがじっと桔梗さんのことを見つめている。
「本当に、しゃべれたんだね」
桔梗さんはそう言った水菜さんを見て小さくうなずいた。
「きぃねえちゃん、ありがと」
果林ちゃんが桔梗さんにしがみつくようにしてつぶやいた。
「なんか、きぃねえちゃんのこと守らんといけんってずっと思いよったけど、本当は守られとるの、うちの方じゃったんじゃね」
僕は、その様子をただ見守ることしかできない。
周囲の杉林が風で低くざわめき続けている。
「ねえ、母さんのサンドイッチ食べようよ。せっかく作ってくれたんだし」
沈んでしまった空気を振り払うように、水菜さんが無理に明るい声を出して言った。
「そうだな」
夕介がそれに同意すると、水菜さんはバスケットの中から紙皿を取り出してサンドイッチを取り分け始めた。
「母さんのたまごサンド、絶品なんですよぉ」
水菜さんはそう言ってほほ笑みながら、まずは僕に渡してくれた。
「あ、すいません。いただきます」
二幕を終えて今は二〇時前、ちょうどおなかがすいた頃合いだ。
蘭さんのたまごサンドは、口に入れるとふんわりと優しい味がする。
「ほら、果林。食べたら元気出して。めそめそしてるのって果林らしくないよ」
水菜さんはそう言って果林ちゃんにサンドイッチを渡してほほ笑む。
「うん、みず姉ごめんね」
「ううん、わたしの方こそ昼間ひどいこと言っちゃった。ごめんね」
そう言うと水菜さんは果林ちゃんに頭を下げた。果林ちゃんも赤く泣きはらした目のままこくりとうなずいた。
境内を吹きわたる風が少し変わってきた。生暖かく、湿り気を含んだ重い風だ。風は時折強くなって篝火を揺らめかせ、周囲に火の粉をまき散らす。鏡の間に張られた幕もばたばたと音を立ててはためいている。
「なんか今にも降り出しそうな感じだね」
「ああ、何とか最後までもってほしいんだが」
僕が夕介に言うと、夕介も腕を組んだままうなずいた。
桔梗さんを見ると、彼女は風に揺らめく篝火の炎をじっと見つめている。
風が、彼女の長い髪を揺らしていた。
第五章 紫桜(しざくら) 〈三〉
なんだか胸騒ぎがする。
それが何なのかははっきりしないが、何かがもやもやと僕の胸の奥で渦巻いている。
舞台では三幕目『乙女淵』の準備が整いつつある。
桜の作り物はアト座に下げられ、別の作り物が舞台の上に上げられた。ちょうど人が入るぐらいの高さに組まれた約一メートル四方の竹枠の上に板葺屋根がついていて、どうやら質素な庵を表しているようだ。
演者たちが所定の位置に着座し終えた。
『乙女淵』のシテを務めるのは松岡さんだ。
松岡さんはこの舞台を「ネンコーさんの弔い合戦」だと言っていた。一体どのような舞台になるのだろう。
これまでの二幕と同じように、笛が舞台の幕開けを告げ始めた。その鋭い音色が夜の闇に溶けていく。『桜堤』の哀調とも『寂水』の禍々しさとも違う、不安定で心をざわつかせる旋律だ。
風で低くざわめいている周囲の杉林が、まるで通奏低音を奏でているようにも聞こえる。
最初に揚げ幕から登場したのはワキである旅の僧。
直面で質素な紺の衣に身を包み、橋掛りを進みながら旅僧が謡う。
花も憂し 月も憂しと 捨つる世の
鄙の旅路の墨衣 鄙の旅路の墨衣
本舞台に上がった旅僧は、自分は出家して石見の国へと移る者であると名乗る。
元は戦場で多くの武勲を上げた武士であったが、世を捨ててこれまで自分が奪ったすべての命の追善供養をして余生を静かに暮らすつもりであると告げた。
僧は旅の途中、乙女淵のほとりにある小さな廃寺に立ち寄った。
既に日も暮れて暗くなり、旅を進めることはできない。
僧はこの廃寺で一晩宿ることにした。
再び笛が不安な旋律を奏で始め、抑えた掛け声と共に大小の鼓が打ち鳴らされる。
揚げ幕が上がり、前シテが姿を現した。『桜堤』の後シテと同様の、白い水衣。しかし、その下に身に着けている小袖も、鬘の上から結ぶ鬘帯も、そしてもちろん足袋までもが、すべて白で統一されている。
僕は思わずぎょっとして桔梗さんを見た。
「きぃねえちゃん……」
果林ちゃんもそうつぶやいて隣の桔梗さんを見る。
水菜さんも夕介も同じことを思ったらしい、全員の視線が桔梗さんに注がれた。
桔梗さんは僕らの視線などまったく意に介さず、ぐっと目を見開いて橋掛りを進む前シテを目で追っている。
何かがわかりかけたような気がするが、はっきりと言葉にできなくてもどかしい。
しかし、これが本当にあの松岡さんだろうか。
指先まですっぽりと装束の裾で隠し、背筋を伸ばしてゆったりとした足運びで進む姿は、とても七〇歳近いとは思えない。身体の隅々にまで神経が行き届いた、抑制された動きだ。
面はこれまでのシテと同様若い娘だが、よく見ると口が閉じられている。宇侘八幡だけで用いられている『噤』という小面だと、パンフレットにはある。きわめて珍しいものらしい。
白装束の娘は橋掛りをまっすぐに歩いて本舞台に上がると、そのまま庵の作り物の中に身を移した。
旅僧は白装束で現れた娘を不審に思い、庵に向かって問いかける。
さても 奇異なるかな
こなたは 何の故に
死人の装束にて 候ひけるか
娘は問いかけに答えない。答えられないのか、答えようとしないのか。
僧は、自分は旅の者で、夜露をしのぐために一晩軒を借りたいと娘に申し出るが、娘はやはり答えない。
追い払わないということは許したものとみなして、僧は庵の軒先に一晩宿ることにする。
夜半になって、娘が庵から外へ出てきた。
登場してから一言も発していなかった前シテがようやく声を発する。
あら憂しや あら憂しや わが詞
人の命も 奪ひけり
父をも空しうさせ候ひけり
忌むべきかな 呪ふべきかな
娘は夜の闇に向かって一人謡う。松岡さんの太い声が朗々と辺りに響く。
自分の言葉が人の命も、父の命をも奪ってしまった、忌わしい呪わしい、と嘆いている。
眠っていた僧がその声に目を覚まし、立ち上がって娘に問いかける。
あなたの身の上に何があったのか、もしよければ拙僧にお聞かせくださらぬか、自分は修行中とはいえ仏に仕える身、何かあなたの力になれるかも知れぬ、と僧は告げた。
娘はつっと庵から数歩歩くと僧に向き直った。
わらはが詞は 奪命の詞なり
聞かぬが 御僧の為
畏るべし 畏るべし
私の言葉は人の命を奪う、聞かない方があなたのためだ、と娘は言い放ち、再び正面を向いた。
僧は一歩前に出ると、娘の背に語りかける。
自分は既に世を捨てた者である、まして多くの命を奪ってきた罪深い者でもあるから、もしもここで自分の命が白露と消えても何の悔いもない、是非に是非にお聞かせ願いたい、と重ねて求めた。
娘はしばらく黙っていたが、やがて正面を向いたままゆっくりと語り始めた。
ありがたきかな 御僧
されば 我がこと 語り申し聴かせ候べし
これは 沓懸山に空しうなりける もののふが娘
桜姫なり
娘は自分が沓懸山で死んだ武将の娘、桜姫であることを明かした。
戦を逃れて身分を隠してこの山代に住まい、父や祖父、一緒に戦って死んだ将兵たちの菩提を弔おうと思ってひっそりと暮らしているのだ、と彼女は言う。
されば こなたは何ゆゑに 死人の装束にてや候ひけるか
道理なれば 髪を削ぎ 仏門に入るべきにてや候らん
僧は、それではあなたはなぜ死装束でいるのか、と桜姫に尋ねる。父らの菩提を弔うのであれば髪を落として仏門に入るのが道理ではないか、と。
桜姫はしばらく答えない。
わらはが詞の故なり
わらはが奪命の詞の故なり
少し間をおいて、彼女は自分の物語を語り始めた。
予言なのか、呪いなのか、幼いころから彼女が口にしたことは必ず実現する。それも吉兆だけではなく、凶兆も。周囲の人々は桜姫を不吉な子として恐れたが、父は意に介する様子はなかった。
しかし、沓懸山が東より攻められるだろうと桜姫が口にしたわずか半年後、予言は現実のものとなり、合戦が起こった。
父や祖父をはじめ、千人もの兵がそのために死んだのだ、と彼女は僧に語った。
地謡方がシテに和して斉唱する。
忌むべきは 我が詞
畏るべきは 我が詞
わらはにかかわる人は 皆 悉く空しうなりける間
如何にしてか 如何にしてか 其の悪業より逃るべき
ただただ口を噤み 死人として生きんのみ
口を噤んで死人として生きる──ずっと僕の胸の中で渦巻いていた嫌な感じの正体がわかったと思った瞬間、隣の水菜さんも「あ……」と小さく声を上げた。
自然と僕と水菜さんは顔を見合わせ、そして桔梗さんに視線が行った。
背筋に冷たい汗が流れるのを感じる。
昨日夕介が教えてくれたあらすじでは、桜姫はこの後、乙女淵に身を投げてしまうことになっている。
桔梗さんも桜姫と同じように、自分の命を厭わしく思っているのだとしたら──。
桔梗さんは眉一つ動かさずにじっと舞台を凝視し続けている。
彼女の隣に座っている果林ちゃんは、桔梗さんの長襦袢の袖を両手でぎゅっとつかんでいる。
白装束の桜姫が舞扇を広げてゆっくりと舞い始めた。舞扇には満開の花をつけた桜の木と赤い日輪が描かれている。
桜姫は小鼓が作るゆったりとしたリズムに合わせて舞う。
湿り気を含んだ重い風が白い装束の裾をはためかせ、鬘帯が風にたなびいて流れている。
笛が高い音で泣き始めた。
大小の鼓が掛け声を強め、徐々にリズムを早めていく。
御僧 わらはを助け給へ
奪命の詞から 如何に逃れんや 如何に逃れんや
桜姫が苦しみに喘ぐように謡い舞う。
僧はその場に座って数珠を手に掛けて合掌し、桜姫が呪われた運命から逃れられるよう一心に祈っている。
桜姫は僧の周囲で舞うが、彼女の心は一向に晴れない。僧の読経を聴きながら、右へ左へとゆらゆらと歩いては止まり、止まっては歩く所作を繰り返した。何度もそれを繰り返すうち、次第次第に所作がはっきりと一つの方向に定まっていく。
桜姫はすっと数歩正面に向かって歩いて立ち止まり、舞うのをやめて僧に告げた。
是非もなし 是非もなし
わらはのこの世にありて候間
己が詞より逃る術はなし
命を絶つて 閻浮を去らん
そう言うと桜姫は急に僧に背を向けて庵を立ち去る。
僧はあわてて立ち上がり、桜姫を追った。
橋掛りを進んだ桜姫は、三の松のところで一度立ち止まった。
彼女を追っていた僧は二の松の辺りから言葉をかける。
父君の空しくなりけるは 誠に無念にて候ひけるが
戦はこなたの詞の故には候はず
生きて仏門に入り 父君の菩提を弔ひ給へ
僧は桜姫を何とか思いとどまらせようと必死に呼びかける。
あなたが死んでしまっては父上の供養は一体誰がするのか、死んではならぬ、と繰り返し諭すが、桜姫は僧に背を向けたまま振り返ろうともせず、既に死に魅入られたようにその言葉を虚ろに聞いている。
桜姫は乙女淵の汀に立って夢の如くに揺れていると地謡方が謡い、桜姫はじりじりと半歩ずつ前に進んでいく。
僧がどれだけ言葉を尽くしても、桜姫には届かないのか。
これから桜姫が身を投げるとわかっていても、何とかそれを回避できないものかと僕は必死になって考えている。
隣の水菜さんは両手を堅く握りしめ、固唾を呑んでなりゆきを見守っている。
果林ちゃんは桔梗さんの左腕を両手でしっかりとつかまえている。
空気が張りつめる。
桜姫が一つ足踏みをした、と思ったらさっと揚げ幕が上がり、桜姫は吸い込まれるようにその中に消え、すばやく揚げ幕が降ろされた。
ずっと桔梗さんの左腕をつかんでいた果林ちゃんが、「あ」と小さく悲鳴を上げる。
只真直ぐ一筋に墜つるに 為す術ぞなく淵の底
さざめく水の黒々と いづ方へと失せたるか
目を凝らせども 見えず
耳を澄ませども 聞えず
僧の目の前で桜姫は一直線に乙女淵へ墜ち、黒々とした水に呑まれて姿が見えなくなってしまったと地謡方が謡い、辺りに笛の高音が響いた。
橋掛りの上には僧がただ一人取り残された。
水菜さんも果林ちゃんも、がっかりしたようにうなだれたが、桔梗さんはなおも背筋を伸ばしたままじっと揚げ幕の向こうを見つめている。
僧は茫然自失のまま本舞台へと引き返していく。
目の前のたった一人の命を救えずに何の仏法か、と彼は失意に暮れて庵のそばに崩れるように座った。
やがて白々と夜が明けた。
僧は一睡もできずに夜明けを迎える。
地謡方がそう謡い、ワキがうつむき加減だった顔をゆっくりと上げただけなのに、僕には昨日の朝桔梗さんと見た、あの荘厳な日の出の風景が目の前に見えるように感じる。
薪能では、現代劇のように照明が変化するわけではないし、舞台装置もごく簡単なものばかりだ。だからこそ、観る者が舞台上に見えない部分をそれぞれ想像し、補って観ることになる。そう考えると、同時に同じ舞台を見ていても、一人一人見えているものが全く違うのかもしれない。
今、桔梗さんには一体何が見えているのだろうか。
舞台の上では、アイである里の者が登場し、廃寺にいる僧を見とがめて、不審なことだ、御僧はこの廃寺で一体何をしているのか、と問う。
僧が答えて言う。
昨夜白装束の奇妙な娘と出会い、彼女を救おうと必死で祈ったが、その甲斐なく娘は乙女淵に身を投げてしまった。仏に仕える身として悔やんでも悔やみきれない、自分は石見に赴くつもりであったがこれを取りやめ、この廃寺で娘とその父らの菩提を弔いたいと。
里の者は、哀れなことだ、娘は里人との交わりを断って誰とも言葉を交わすことなく、ただ一人でここに住まっていたのでどこの誰ともわからない、仏縁に触れたならばせめて後生の安堵を祈らずにはおれぬ、と言う。
「後生の安堵」とは安心できる境遇に生まれ変わる、という意味らしい。
せめて生まれ変わってから幸せに、なんて言われても、僕にはなんだか納得がいかない。
さっきの『桜堤』でもそうだ、死後の幸せなんて本当にあるのだろうか。死んだらそれきりで後には何も残らないというのが僕のイメージだ。輪廻転生だとか、生まれ変わりだとか、科学的じゃないし全く根拠がないと思う。幸せになるなら生きているうちじゃないと意味がないような気がする。
里の者は、この廃寺は長い間守る者がなかったゆえ、御僧の思うようにされるがよい、と僧に伝えて去っていった。
舞台の上では庵の作り物はそのままに、桜の作り物がまた改めて中央に据えられた。
季節が移ろって春を迎えたのだ。
僧は廃寺に住みつき、桜姫とその父らの菩提を弔うため、日々読経をしながら暮らしている。
そんなある日、僧は夢を見た。
笛の音と共に揚げ幕が上がり、後シテが登場する。
華やかな緋色の大口袴に清楚な白い長絹を緩やかにまとい、ちょうど巫女の装束のようだ。明るく穏やかな表情の若い娘の面を着け、薄紅色の鬘帯を結び、頭には白蓮の天冠を載せている。
南無幽霊成等正覚 出離生死頓證菩提
南無幽霊成等正覚 出離生死頓證菩提
僧にはこれが桜姫の霊であるとすぐにわかったようだ。弔いの言葉を二度繰り返す。
後シテは本舞台に上がると、自分は乙女淵のほとりに咲く山桜の精であると名乗り、優雅な所作で舞扇を広げると僧の前で謡い舞い始めた。
舞扇は前場で桜姫が持っていたのと同じ、桜に日輪。
自ら身を投げし故
地獄の責め苦を受くべきが
御僧の回向に因りて
向かふ七生 人に生まるることは 叶はじと謂へども
生死の道に 戻るを得たり
既に人ではなくなった桜姫は、風で装束をはためかせながら小鼓の音に合わせてゆったりと舞う。
これから先、七回生まれ変わっても人に生まれることはできないが、僧の回向によって地獄の責め苦を逃れ、生死の道に戻ることができたと謡う。
桜の精の白い長絹には、よく見るとうっすらと桜の文様が織り込まれているようだ。
呪われた自分の言葉から解放された安堵からか、桜の精の舞には穏やかさが感じられる。
その舞に見入っていた僧が、うめくように言葉をもらす。
いかに申し上げ候
我が詞の こなたに届かざるは 我が不徳
こなたの 身を投げし所以は 我にありて候
何ということだろう、今度は僧が桜姫を救えなかった自分を責めている。
合戦が桜姫の言葉のせいではなかったように、桜姫が身を投げたのは決して僧のせいではない。しかし、僧は桜姫を救えなかったことを自らの責任ととらえているのだ。
これでは呪われた言葉が僧に乗り移っただけのようだ。
折節咲く花に
折節咲く花に 散る頃あるは定めとて
猶ほ咲く頃も あるべけれ
咲かずに散るは哀れなり 咲かずに散るは 哀れなり
地謡方が粛々と斉唱する中、僧は数珠を手に掛けて合掌した。彼は桜姫を救えなかった苦悩に沈みながらもなお、桜姫とその父らを回向する決意だ。
太鼓の規則的なリズムに大小の鼓の抑えた音が乗って読経を表現する。
ふと、隣の水菜さんが不安そうな顔で僕の顔を見ていることに気づいた。
「あの、大丈夫ですよね?」
「はい? 何がですか?」
「いえ、ごめんなさい、何でもないです」
水菜さんは僕がまぬけな返事を返すとそう言って再び舞台の方を向いたが、その横顔にはありありと不安が見てとれる。
用荘厳法身
天人所載仰龍人咸恭敬
あらありがたやの御経やな
舞台の上では桜姫……ではなく桜の精が、僧の読経に感謝する舞をたおやかに舞っている。
桜の精の舞を見ているうちに、僕にも水菜さんが何を不安に思ったのかが、だんだんとわかるような気がしてきた。水菜さんはきっと、僕をあの僧に重ねているんだ。桔梗さんが今の状態から抜け出すには、あの僧のように僕が身代わりになる必要があると思ったんだろう。
考えてみれば、僕の立場は確かにこの僧とよく似ている。
もの言わぬ少女と偶然出会い、言葉を交わした旅の男。
でも、僕に何ができるのだろう?
そんな事を考えていると、額にしずくが当たるのを感じ、僕は空を見上げた。
とうとう雨が降り出してしまったようだ。
後ろを振り返って夕介を見ると、両手でカメラを抱えたまま苦い顔で舞台をにらんでいた。
舞台の上では桜の精の舞が続いているが、後見がすっと立ち上がってシテの松岡さんに近づいた。もしかして、ここで中止になるのだろうか。
しかし、後見に耳打ちされた松岡さんは、かまわずに舞を続ける。
雨が土を打つ匂いが徐々に辺りにたちこめはじめた。
後見も元の位置に下がって座った。最後まで演じ切るつもりなんだ。
舞台を照らし出している投光機の光の中には無数の雨粒が細かく浮かんで見える。
シテに和して地謡方が謡う。
今この経の徳用にて
今この経の徳用にて あら不思議やな
淵に紫の花咲けり
紫の花の七歳咲けば
生死の大海 廻り渡りて
御恩を必ず報ずべし 御恩を必ず報ずべし
僧の読経によって不思議なことに淵に紫の桜が咲き、桜の精は七年紫の桜を咲かせた後、生死の大海をめぐって必ず報恩すると約束したが、僧は何も答えない。
囃子方の演奏が終わり、桜の精は舞扇をたたんでゆっくりと正面から背を向けると、本舞台を降りて橋掛りをゆっくりと歩いて退場しはじめた。
次第に雨が強くなってきた。桜の精の緋大口がうっすらと濡れて鈍く光を返している。
不意に桔梗さんが立ち上がった。何かを言おうとしているようだが、言葉にならない。
僕がその姿に気をとられているうちに、桜の精は揚げ幕の向こうに姿を消してしまった。
僧がゆっくりと立ち上がり、重い呵責を背負いこむように背中を丸めて、雨の中を退場していく。
雨に濡れたせいで、桜の作り物から偽の花びらが落ちて、板敷きの上で雨に打たれていた。
第五章 紫桜(しざくら) 〈四〉
「あーあ、びっしゃになったー」
果林ちゃんがタオルで髪を拭きながら言った。
「せめてあと少しだけもってくれればなあ」
「本当、惜しかったですよね」
僕がつぶやくと水菜さんも同意する。
「明日にはやむかな?」
「にひひ、浩司さんが雨男じゃなけにゃね」
果林ちゃんが僕をからかうと桔梗さんがくすりと笑った。
取材のために残ると言う夕介に先に帰ってろと言われた僕は、姉妹と一緒に水菜さんの車で桐葉荘に戻った。
蘭さんがタオルを準備して待っていてくれたので、今はみんなロビーで頭や服を拭いているところだ。
結局舞台が終わるまで誰も傘を差さなかったので全員ずぶ濡れだ
雨のせいで舞台の方は余韻も何もあったもんじゃない、終わったと思ったところで観客が一斉に帰り始め、境内はごった返した。
水菜さんが持ってきた桐葉荘のロゴ入り和傘五本は、彼女が傘のない人に二本ほど貸したので一本を夕介に渡し、残り二本で果林ちゃんと桔梗さん、僕と水菜さんが相合傘で車まで移動した。彼女の顔がすぐ近くにあるのに、僕は照れてしまってまともに見ることもできなかったけど。
「森崎さん、よろしかったらお食事よりも先にお風呂をどうぞ。雨でお身体が冷えたでしょうから」
蘭さんが拭き終えたタオルを僕から受け取るとそう勧めてくれた。
「すいません、そうします」
僕はその勧めに素直に従うことにした。
「あなたたちもこっちで入りんさい、今日だけは特別よ」
蘭さんはそう言って水菜さんにウインクした。
「いいの、母さん?」
「久しぶりに三人で入っておいで。たまにはええでしょ?」
そう言って蘭さんは桔梗さんにほほ笑みかけた。
桔梗さんも黙ってうなずく。
「すごーい、三人でお風呂入るのって何年ぶり? 母さんありがとー!」
果林ちゃんが満面の笑みで蘭さんに抱きつく。
「ご飯もみんな揃ってお座敷でしようね。さあさあ、風邪ひいたらいけんけえ早よ行っておいで、着替えも準備しとくから。もしお客様に出会ったらちゃんとごあいさつするんよ!」
「はーい!」
果林ちゃんは返事をするやいなや、ぱたぱたと奥に向かって駆けていった。
「母さん、ずいぶん明るくなったよね」
水菜さんがその背中を見送りながらぽつりと言った。
「ふふ、やっと最近かな、こんな風に笑えるようになったの」
蘭さんは水菜さんを見上げて優しく笑いかける。
「大事なことがわかっちゃったからかも」
「えー、大事なことって何?」
「ひみつー♪ さあさあ、水菜も桔梗も、入った入った!」
蘭さんはそう言って水菜さんの背中を押した。
水菜さんは肩越しに振り返って苦笑している。
桔梗さんがそんな二人の様子をじっと見つめていた。
風呂からあがって座敷に行くと、夕介が先に来て座っていた。早くも手酌でビールをやっている。
「お疲れ、どうだった?」
「散々だな。みんな後始末でてんやわんや、取材どころじゃねーよ」
夕介は濡れた髪をかき上げながら僕にそう言った。
「風呂入ればいいのに」
「先に飯にするって蘭さんに言った。風呂に入ってからだと、その分後片付けが遅くなるだろ」
時間はもう二二時前、確かにのんびりしていたら日付が変わってしまう。
「すみません、お待たせしました」
蘭さんがお膳を持って座敷に入ってきた。
「こちらこそ、遅い時間にすみません」
夕介が軽く頭を下げる。蘭さんは手際よく食事の支度を進めながら夕介に言った。
「本当に残念でしたねー、雨」
「まったくです、あと少しだったんですが。まあ、自然相手だから仕方ないか」
夕介は蘭さんにそう答えてグラスのビールを飲み干す。
「明日にはやむかな?」
「やまないと困る。ここまで来て『霊山』を観ずに帰れるか」
「だよなー」
僕が水を向けると夕介は憤然と言った。
確かに、初日の三幕でもあれだけ圧倒されたのに、松岡さんが「圧巻」と表現した『霊山』がどんなものか観られずに帰るのは悔しい。
「蘭さんは七年前に観たんですよね? どんな物語なんですか?」
僕はブリの刺身を一切れ箸でつまみ上げながら蘭さんに尋ねた。
「ええと、結構長い物語でしたよ。おばあさんが都から来たお坊さんに出会って、ちょっといじわるをして。で、後から若い娘姿で登場して舞うんです」
「姥だな。これまでの三幕とはだいぶ構成が違いそうだ」
「だね。想像もつかないけど」
夕介は吸いものを口に運び、僕はつまみ上げたままだった刺身をやっと口に入れた。
「あー、さっぱりしたぁ」
入口のふすまが開いて果林ちゃんが入ってきた。
桐葉荘の浴衣の上に半纏を着ているのだが、首にタオルを掛けている姿がなんだかおっさんみたいで笑える。
続いて水菜さんと桔梗さんも、同じ浴衣に半纏姿で入ってきた。
桔梗さんはあいかわらず表情が欠けたままだが、浴衣だといつもの白い長襦袢の時のような人を寄せつけない雰囲気はずいぶんと和らぐ気がする。
水菜さんは洗い髪を後ろでまとめていて、白いうなじがのぞいている。
僕は思わず生唾を飲み込んだ。
「おい、鼻の下伸びてるぞ」
早速夕介にからかわれてしまった。
「なんか温泉マニアの女子会五人組と一緒でから、あんましゆっくりできんかったあ」
「普段内緒で入ってるんだから、文句言わないの」
水菜さんが笑いながら果林ちゃんをたしなめる。
「むむ、やはり余罪があったか!」
蘭さんが芝居がかった低い声で重々しく言うと、水菜さんと果林ちゃんは顔を見合わせて苦笑いした。
桐島家の今日の夕餉は鍋焼きうどん。
大きな土鍋を真ん中に据えて、蘭さんも一緒にみんなで囲んで食べている。
「なー夕介、お刺身ちょうだい」
「悪ぃ、たった今最後の一切れ食っちまった」
「あー、うちが言ってから食べよる! 夕介のケチ!」
「じゃあ、僕のあげるよ」
「ありがとー浩司さん、誰かさんと違ってやさしー」
「お前優しいんじゃなくて、実はドМなんだろ?」
「な……何言ってんだよ、誰がドМだ!」
「果林に振り回されて喜んでるくせに」
「喜んでなんかないって!」
「ふふ、二人とも仲良すぎですよ」
「うわ、やめてくださいよ~水菜さん」
いつもは一人きりでただ空腹を満たすためだけの食事をしているが、こうしてみんなで他愛のない会話を交わしながらする食事ってやっぱりいいなって思う。
桔梗さんはみんなの会話にじっと耳を傾けている。少し遠慮気味に見えるが、ちゃんと自分の分を自分で取って食べているから心配なさそうだ。
「そういえば思い出したんだけどさ──」
水菜さんが少し改まって切り出した。
「わたしたち、七年前にも『紫桜』観てるよね?」
「そうよー、中身が理解できたかはわからんけど、あなたたちは私と一緒に二日ともちゃあんと観たんよ」
「やっぱり。なんか初めてじゃないような気がしてたんだよね」
蘭さんが答えると水菜さんはほっとした顔をした。
「そうそう、桔梗と果林は小学生じゃったから、二日目のおちご舞に出たんじゃったね。二人ともかわいかったぁ。憶えちょる?」
蘭さんは懐かしそうに言う。
「んー、どうじゃったっけ?」
果林ちゃんは首をかしげている。
「二人とも巫女さんみたいな朱色の袴でね、桔梗はお姉さんじゃから、蓮の花の冠をかぶせてもらって舞ったんよね」
桔梗さんが黙ってうなずいた。
「あー、そう言われてみればうちときぃねえちゃんでなんか巫女さんのカッコしたような気がする。確か、一ヶ月ぐらいずっと踊りの練習したんよ」
果林ちゃんは少し思い出したようだ。
蘭さんが右手を口元に当てて思い出し笑いをしている。
「桔梗はすぐに舞を覚えたのに、果林はいつまでたってもなかなか覚えれんかったね。右って言うのに左に動いたりして」
「じゃって、右左ってようわからんもん」
「あはは、だから果林は今でも方向音痴なんだ!」
「こっち、そっちでわかるからええの!」
水菜さんがからかうと果林ちゃんはぷっと頬をふくらませた。
桔梗さんがそれを見てくすりと笑っている。
「でも、わたしはもう中学生になってて、おちご舞は見るだけだったから、なんか二人がうらやましかったなあ。おちご舞の衣装、すっごくかわいいんだもん。わたしも着たかったぁ」
水菜さんは心底うらやましそうな口調だ。
僕はつい巫女装束姿の水菜さんを想像してしまった。よく似合いそうな気がする。
「そうそう、水菜その時もはぶてた(拗ねた)んよね。父さんがでれでれになって二人の写真撮りよったから、父さんに八つ当たりして」
「えー、わたしそんなことしたっけ?」
「したした。父さんはどうせわたしのことなんかどうでもいいんだ、なんて言っちゃったもんだから、父さんその後一週間ぐらいず~っと凹んでたんよ、水菜に嫌われた~って。もう、凹んだ時の父さんって、すんごくめんどくさいんだから!」
蘭さんは笑いながらそう言う。
「年光さんでも凹んじゃうことなんてあったんですか?」
僕は思わず聞いてしまった。
「もう、しょっちゅうでしたよ。家族にはめっぽう弱かったんですから、あの人。特に水菜にちょっと何か言われようもんなら、すぐに『あ~俺はもうダメだぁ』なんて言うんですから、笑っちゃいますよね」
これまでの年光さんのイメージが一気にひっくり返ってしまった。
どんどん人を巻き込みながら面白がって仕事をする、人生の達人みたいな人だと思っていたけど、家庭の中ではどっちかと言うと情けないお父さんだったんだ。
「父さんはいっつも水菜に叱られてばっかりじゃったね。どっちが親だかわかんない」
「だって父さんだらしないんだもん」
「ねー」
蘭さんと水菜さんが顔を見合わせて笑う。
「まったく、男は女には絶対にかなわないようにできてるとしか思えないな」
夕介が頭をかきながらそんなことをつぶやく。
「ねえねえ、せっかくだから父さんも混ぜてあげようよ。わたし写真持ってくる」
水菜さんはそう言っていったん席を立った。
「そういえば、こうやって家族で揃って食事することなんて、父さんが死んでからほとんどなかったね」
蘭さんがしみじみと言った。
「この五年、ずっと忙しくしよったもんね。ごめんね」
蘭さんは桔梗さんと果林ちゃんに詫びたが、二人とも首を横に振った。
「母さんすごいもん、仕事も家のこともちゃんとしてから、いつ寝よるんじゃろって思うぐらい」
果林ちゃんが尊敬のまなざしで蘭さんを見つめながら言う。
「大丈夫、家のことは水菜がやってくれるし、仕事は桑田さんがばりばりやってくれるもん。手を抜くとこはちゃんと手を抜きよるんよ。あ、お客様の前で言うちゃいけんかった!」
蘭さんがあわてて口を押さえたので僕は思わず吹き出してしまった。
水菜さんが黒縁の写真立てを持って戻ってきた。昨日僕が見せてもらった遺影だ。
「欠席裁判じゃ父さんもかわいそうだからね」
水菜さんはそう言って写真立てを上座に置いた。
年光さんは写真立ての中からにこやかに笑いかけている。
「そうそう、仲間外れだってすぐはぶてるんじゃけ、ねー」
蘭さんが早速写真立ての年光さんに向かって文句をぶつける。その口調はあたかも年光さんがここにいるかのようだ。
果林ちゃんがしげしげと写真立てを眺めてつぶやく。
「父さんの写真、久しぶりに見た」
「どう、果林? 父さんの顔、思い出した?」
「うん。父さん、忘れちょってごめん」
果林ちゃんは写真の年光さんに対して謝った。
「あらら、これじゃ父さん完全に凹んで立ち直れんね。それこそ『あ~、俺はもうダメだぁ』って」
蘭さんは年光さんの声色をまねて朗らかに笑う。
「でもさ、父さんって果林には特別甘くなかった? よくお菓子とか内緒で買ってもらってたじゃない?」
「え~そうじゃったかねえ?」
水菜さんがちょっと意地悪な声で果林ちゃんに尋ねたが、当の果林ちゃんは首をかしげている。
「全然そんなことないよー、水菜にも桔梗にも完全にめろめろよ。あなたたちを叱るんはいっつも私じゃったでしょ? 嫌な役目を私に押しつけといて、自分は甘い顔ばっかり。まったくもう、ずるいんじゃけえ!」
蘭さんは両手を腰に当てて憤慨している。
年光さんはすっかり立場がない感じだ。なんだか写真の年光さんが苦笑しているように見える。
「あ、でも果林は遠慮せんから、ほかの二人よりは得してるかもわからんね。そう考えたら果林の甘え上手は、確かに父さんのせいかもしれんよねー」
「あ~、わかる! 果林が『あれして』『これして』ってわがまま言うと、父さんいつも大喜びでやってたよね!」
「うち、そんとにわがままじゃないもん!」
「わがままのかたまりが、何を言う!」
水菜さんが笑いながら果林ちゃんの額を人差し指で軽く小突いた。
「父さんにいっぱいわがまま言って困らせたくせにぃ」
果林ちゃんはむくれて水菜さんの顔を見ている。
が、だんだんとその顔がゆがんできた。
「……」
「ん? どうしたの、果林? 痛かった?」
水菜さんが果林ちゃんに尋ねると、果林ちゃんは急にしゃくりあげながら泣き始めた。
「ちょっと……いきなりどうしたの? 大丈夫?」
水菜さんがあわててなだめたが、果林ちゃんは僕や夕介がいるのもはばからずに、大声を上げて泣く。
桔梗さんが果林ちゃんにそっと寄り添うと、彼女は桔梗さんのひざに顔をうずめて幼い子どものように泣きじゃくった。
しばらくの間、果林ちゃんは泣き続けていた。
「──思い出した」
少し落ち着いてから果林ちゃんがぽつりとつぶやいた。
「あんな、母さん。うち、お葬式が終わっても、父さんがおらんくなったって、どうしても思えんかったんよ」
蘭さんが優しくうなずく。
「母さんだって信じれんかったよ。すごく辛かった」
果林ちゃんも涙をぬぐいながらこくりとうなずくと続けた。
「なんかな、『果林、いい子してたか~』って、フツーに帰って来そうな気がしよった。だけん、さびしーなーとは思ったけどな、悲しいとはいっそも思わんかった」
果林ちゃんが鼻をすする。
蘭さんはじっと彼女を見つめて次の言葉をゆっくりと待っている。
「学校行ったら友達もおるし、フツーに楽しいし。頭では父さんにはもう会えんのんじゃって思っちょっても、なんか実感できんくて。でな、毎日目の前のことばっかり考えよったら、いつの間にか父さんのこと忘れかけよった──」
「もう会えないことを認めたくないから、今の目の前のことだけに意識を奪われてたわけだな」
夕介が腕を組んでつぶやく。
「でもな、今日、久しぶりに父さんの写真見て、父さんのことみんなで話して、あー、もう父さんには『あれして』『これして』って絶対頼めんのんじゃって、改めて思うたら──」
果林ちゃんは寄り添っている桔梗さんにしがみつくようにして叫んだ。
「父さんなんで死んだん! なんで? また会いたいよぉ! 父さんに会いたい!」
水菜さんは泣き叫ぶ果林ちゃんを沈痛な面持ちでじっと見つめ、桔梗さんは果林ちゃんの肩を抱いたままじっと唇をかんで聞いている。
「ちゃんと悲しみなさい、果林」
蘭さんが静かに告げた。
「果林は父さんのこと、大好きじゃったもんね。だから、どっかにおらんようになっただけで、いつか帰ってくるって思いたかったんよね?」
果林ちゃんは蘭さんの一言一言に小さくうなずく。蘭さんは包み込むようなまなざしで果林ちゃんを見つめている。
「でもね、いくら待っても父さんはもう帰ってこんの。どんなに果林が会いたくても、会えんの。だから、ちゃんと悲しんであげなさい。でないと、父さんも悲しむよ?」
蘭さんはそう言うと、果林ちゃんのそばに歩み寄り、彼女をぎゅっと抱きしめた。
果林ちゃんは蘭さんの胸の中で静かに泣いた。
傍らに寄り添っていた桔梗さんの目からも、涙が一筋、頬を伝ってひざの上に落ちていった。
第五章 紫桜(しざくら) 〈五〉
「わたし、やっぱり性格悪いのかな……」
水菜さんがぽつりとつぶやいた。
果林ちゃんは桔梗さんに付き添われて母屋に戻り、夕介は風呂に行ったので、座敷には僕と水菜さんと蘭さんの三人だけが残っている。
「どうしたの、水菜?」
食事の後片づけをしながら蘭さんが尋ねた。
「だって、わたし果林みたく泣けないもん」
水菜さんはうつむいたままそう言った。その視線の先には、年光さんの写真がある。
「あんな風に思い切り泣ける果林が、ちょっとうらやましい」
水菜さんは笑顔の年光さんをじっと見つめたままだ。
「水菜は水菜らしくおればええんよ。桜梅桃李、父さんが好きじゃった言葉のまんまでね」
蘭さんはそう言って水菜さんにほほ笑みかける。
水菜さんは顔を上げて蘭さんに問いかけた。
「わたしらしくって、どういうことなんだろ? 何が『わたしらしい』のかな?」
「『自分らしさ』なんてあわてて探さんでも、いつかはちゃあんとわかるようになっちょるんよ。どうやったって、水菜は水菜なんじゃから」
蘭さんはそう言いながらお膳を持って立ち上がった。
「水菜はね、真面目すぎるの。あんまり根を詰めたらいけんよ?」
蘭さんは歌うようにそう言うと、厨房に戻っていった。
「あの、『おうばいとうり』ってどういう意味ですか?」
僕は水菜さんに尋ねた。
「父が生前好きだった言葉です。桜・梅・桃・李。この桐葉荘の四つの部屋も、父がこの言葉から取って名づけたんですよ。どの花も、咲く時期も違えば、咲く花の色も形も違うけど、それぞれに個性があってすてきでしょって意味です。なんか、そんな歌もありましたよね」
「あー、ありましたねー」
僕らが小学生の頃、国民的アイドルグループが歌ってロングヒットした歌を僕は思い出した。
「いづれの花か散らで残るべき。散る故によりて、咲く比あれば、珍しきなり。能も住する所なきを、先づ、花と知るべし……」(註三)
水菜さんがいきなり難しい言葉をすらすらと暗唱したので僕は驚いた。
水菜さんは僕にほほ笑むと続けた。
「ふふ、世阿弥の『風姿花伝』の一節です。どんな花でも、散らずに残ることがあるだろうか。それぞれに散るからこそ咲く時期もあり、だから珍しいのである。能も、とどまるところなどないことが、まず『花』であると知りなさい──。病床の父が、わたしに何度も繰り返し教えた言葉です」
「散るからこそ、咲く時期もある──」
僕はそうつぶやいて改めて年光さんの写真を眺めた。
年光さんは自分がこんなに早く散ってしまうことを知っていたのだろうか。
「さっき、『桜堤』の後で、森崎さん言いましたよね? 桜姫は、色々といやなことばかりのこの世から、逃げ出したかったんじゃないかって」
僕がうなずくと、水菜さんは僕から目をそらし、ふっと自嘲的な笑みを浮かべた。
「あの言葉、ずしん……ときました。わたし、早く散っちゃいたいって思ってたんです。咲かないままでもいいから、早く消えちゃいたかった」
水菜さんは目を伏せたまま低いトーンの声で言葉を継ぐ。
「この家も、この町も、本当は大嫌い。でも、そんなこと誰にも言えないし、どうにもできないし」
彼女は胸元に右手を当てて一つ息を吐くと、天井を仰いだ。
「何もかも捨てて、わたしの知らないどこか遠くに、誰か連れてってくれないかなーって、本当はそればっかり考えてたんです。だから、そんなわたしの心を見透かされたみたいで」
水菜さんは再び自嘲的な笑みを浮かべて目を伏せた。
「僕だって逃げてきたんですよ、ここに」
僕の言葉に水菜さんははっと顔を上げた。
意外そうな顔でまじまじと僕を見ている。
「さっき果林ちゃんにも言ったけど、今年の春先に友達関係でいざこざがあって、なんか全部めんどくさくなっちゃって。だから、『紫桜』だって、本当は逃げ出すための口実だったのかもしれない」
僕の正直な気持ちだ。多分、きっかけは何でもよかったのだと思う。
「でも、実際に逃げ出してみて、わかったことがありますよ」
「え? なんですか?」
「どれだけ遠くに逃げても、自分自身からは絶対に逃げられないってこと」
簡単なコピーも満足にできないで凹んでしまう僕、体力がなくてすぐにへたってしまう僕。認めたくはないけど否応なく認めざるを得ない、情けない僕の姿。
ここに来て、夕介に引っぱり回される中で、何となく感じていたことが、水菜さんと話すうちにだんだんと言葉になっていく。
「どこに行っても、自分は自分のまま。環境が変われば何かが変わるような気がしてたけど、全然そんなことない。……でも、もしかしたらそれでいいのかもしれないなって、今はちょっと思います」
「どこに行っても、自分は自分のまま──」
水菜さんは右手の指先を自分の胸元に当ててそっと僕の言葉を繰り返した。
「何でも、やってみなきゃわからない、ってね」
僕は、年光さんの言葉を口にした。
「あ、その言葉──」
「昨日、夕介が教えてくれたんです。年光さんの口癖ですよね?」
水菜さんは黙ってうなずいた。
「僕は、逃げ出してここに来たわけだけど、やっぱり来てよかったなって思ってます。普段とは全然違う経験をして、もちろんいいことばっかじゃなかったけど、確かにやってみなきゃ全然わからなかったと思うんですよ。自分がこんなにヘタレだとは思ってなかったし、でも案外役に立てることもあったような気がするし、それに、なんかすごい生き方をした年光さんのことも知ったし」
水菜さんはぽつぽつと言葉を吐きだす僕をじっと見つめている。なんだか照れくさくて、僕は頭をかきながら続けた。
「僕は臆病で面倒くさがりだけど、年光さんのこの口癖、すごくいいなって思います」
水菜さんは改めて年光さんの写真に目を落とした。
僕も彼女の視線を追って写真を眺めた。
年光さんは写真立ての中から満面の笑みを水菜さんと僕に送っている。
「どこに行っても、自分は自分のまま──」
その笑顔をじっと見つめながら、水菜さんはもう一度繰り返した。
〈第五章終わり〉
────────────────────
註三 花傳第七 別紙口傳より(引用は岩波文庫『風姿花伝』野上豊一郎・西尾実校訂から。字体は新字体に改めた)
第六章 雨 〈一〉
一夜明けても、雨はまだ降り続いていた。
起きてから窓の外を眺めて、僕は思わずためいきをついた。
目に見えないほどの細かい雨粒が、窓から見える庭の地面を静かに濡らしている。遠くの山並みは厚い雲に覆い隠されてまったく見えない。
座敷がやけににぎやかだったのでなにごとかと思ったら、五人の女子たちが夕介を取り囲んでいた。どうやら昨日果林ちゃんが言っていた温泉女子会の面々らしい。
「お仕事は何されてるんですかぁ?」
「えー、すご~い!」
「なんかフリーってカッコいいですね!」
「一匹狼って感じぃ!」
「肉食系ですよね~」
「あ~、でもはにかんだ表情、意外にかわいー!」
「ねーねー、後で一緒に写真撮ってもらえませんかぁ?」
五人ともアラサー世代だろう、朝からものすごいエネルギーを振りまいている。
夕介は僕の姿を認めると何か言いたそうだったが、女子五人に囲まれてどうにもならないらしく、恨めしそうな目で僕をじろりとにらんだだけだった。
イケメンってのもなかなか大変なんだな、と少しばかり同情しながら、僕は夕介から少し離れた所に座った。
「おはようございます、森崎さん。よくお休みになれましたか?」
蘭さんが僕のお膳を置きながら声をかけてくれた。
「はい。でも雨、まだ降ってますね」
「そうですね。中止にならなければいいですけど」
窓から見える庭を眺めながら蘭さんが心配そうに答えた。
「それにしても夕介、朝から大変だな」
「ふふ、イケメンですからね。この分じゃ連絡先でも交換しない限り、解放してもらえないんじゃないですかね」
僕が夕介の方を横目で見ながら言うと、蘭さんはいたずらっぽく笑った。
「夕介さんもそこそこいい歳だし、ここらで落ち着くのも、いいんじゃないかなー」
蘭さんは夕介の思いにはまったく気づいていないようだ。
そう思うと、あれだけ上から目線でイヤな奴だと思っていた夕介が、少しかわいそうに思える。
食事が終わっても夕介はなかなか五人の女子から解放されないので、僕は先に部屋に戻った。
やることがないのでぼんやりとテレビを眺めていると、不意に部屋の扉がノックされた。
扉を開けると、濃いグレーのスエット姿の果林ちゃんと、デニムのロングスカートの上に白い綿のシャツを着た水菜さんが立っていた。水菜さんは眼鏡をかけ、髪を後ろでまとめている。
「なー浩司さん、今朝きぃねえちゃん見んかった?」
果林ちゃんが真剣なまなざしで僕に聞いた。
「いや、見かけてないけど。桔梗さんがどうかしたの?」
「いないんです、どこかに行ってしまったみたいで」
「え?」
僕は思わず上ずった声を上げてしまった。
水菜さんも少しあせっている様子だ。
「昨日な、うちが寝られんて言うたら、きぃねえちゃん黙ってうちと一緒に寝てくれたんじゃけど、朝起きたらおらんの。いつもの部屋にもおらんし、朝ごはんもそのまんまなんよ」
「蘭さんには聞いてみた?」
「うん。今朝は見ちょらんて」
「夕介には? 僕より早く起きてたみたいだから、何か知ってるかも」
「聞いてみる!」
果林ちゃんはすぐに隣の梅の間に向かった。
「今までこんなことはなかったんですけど……」
水菜さんが困惑した顔をしている。
僕は、反射的に『乙女淵』の桜姫を思い出した。
「……まさか」
僕が思わず声に出すと、水菜さんもすぐに僕が何を考えたのかわかったようだ。
「あの、わたし、車で探しに出ます!」
「いや、それは俺がする」
後ろから夕介の声がした。
「乙女淵までは車でも一〇分近くかかる。もし桔梗が乙女淵に向かったのなら、まだ途中で捕まえられるかもしれない。お前らはこの近辺をあたってくれ」
「わかった、何かあったら連絡する……ってここは圏外だっけ」
「とりあえず俺の携帯教えとくから、固定電話で連絡しろ。もし俺のも圏外だったらここのPCで即メールだ、いいな。水菜か果林がわかる」
夕介はジャケットのポケットから名刺を一枚僕に差し出した。
「了解」
僕は短く言って夕介の目を見る。
「頼んだぞ」
夕介はそう言うとすぐに玄関から外へ出て行った。
僕は念のため、夕介の電話番号を急いで携帯のメモリに登録した。
「僕らも、手分けして探そう」
「うん、うちは母屋の周りを探してみる」
「じゃあ、僕はこの建物の周りを探してみるよ」
「わたしは一度下まで降りてみます。もしも三〇分探しても見つからないようなら、いったんここに戻って夕介さんに連絡しましょう」
僕はうなずいた。
「それと森崎さん、母にはまだ言わないでください、この時間は食事の後片づけとかチェックアウトの準備で忙しいはずですから。あまり心配かけたくないんです」
「わかりました。じゃあ、また後で」
「うん!」
僕らはそれぞれに桔梗さんを探し始めた。
外に出ると少し肌寒い。
あいかわらず霧のような細かい雨が音もなく降り続いている。
庭から斜面を見上げると、山肌を這うように白い雲がまとわりついている。
周囲の景色からは色が消えて、まるで水墨画の中にでも迷い込んでしまったようだ。
この建物の周りと言っても、桐葉荘自体そんなに大きな建物ではない。隠れるような場所があるわけでもないし、桔梗さんの姿はどこにも見えない。
門を出て駐車スペースの方を見ると、普段は母屋のカーポートに駐められている桐葉荘の白のミニバンが雨に濡れている。車の裏側にも回ってみたが、別に不審な様子はない。
傘を差さなければならないほどの雨ではないが、ちょっと雨に打たれているうちに服はしっとりと濡れてしまった。
門の前に戻ると、桔梗さんを初めて見かけた時のことを思い出した。
僕はあのとき桔梗さんが立っていた生垣の隅に足を運んだ。
そこは、一緒に朝日を見た尾根へと続く足踏み道の入り口だ。
何かに呼ばれているような気がして、僕は木戸を開けて木々に覆われた薄暗い足踏み道に入っていった。
濡れた木の葉の青いにおいが漂っている。
落ち葉に足を取られて何度か転びそうになりながら、僕は斜面を一心に登った。
既にあちこち泥だらけ、服は雨で濡れたのか汗で濡れたのかもわからない。靴の中もすっかり水浸しになっている。木々から落ちてくる雫が冷たい。
僕は息を切らしながら、なんとか尾根の上に出た。
桔梗さんが桐葉荘の浴衣のまま、傘も差さずに一人で立っていた。
「桔梗さん……」
僕はほっとして思わずその場にひざを突いてへたり込んでしまった。
桔梗さんは僕に気づくとへたり込んだ僕のそばに歩み寄ってきた。
「どうして、ここに?」
彼女は僕に問うた。
雨に濡れた長い黒髪が彼女の頬にまとわりついている。
「水菜さんと、果林ちゃんが、桔梗さんが、いなくなったって、言うから、探しに来たんだ」
僕は肩で息をしながらなんとか答えた。
「桔梗さんこそ、なんで、こんなところに?」
桔梗さんは頬にかかった前髪を細い指でゆっくりと横に払った。
「祈っていたの。雨をやませるために」
「雨──」
目の前の斜面から風に流されて白い雲が立ち昇っていく。その向こうでは山々が薄墨色に霞んでいる。
桔梗さんはへたり込んでいる僕をじっと見つめた。
彼女の前髪から雫が垂れ落ちていく。
「最後まで、観てほしいと、思った。『紫桜』──」
そう言うと、桔梗さんは空を仰いだ。
僕も空を見上げると、風に流されて灰色の厚い雲が次から次へと送り込まれてくる。
なんだか現実感に乏しくて、夢の中にでもいるような感覚だ。
やっと呼吸が落ち着いた僕は、ゆっくりと立ち上がって桔梗さんに言った。
「桔梗さん、戻ろう。急にいなくなったからみんな心配してるよ」
「身を投げるんじゃないかって?」
桔梗さんは目を伏せて口元だけで笑った。
「わたしは、ここにいるよ?」
そう言ったきり、桔梗さんは雨に煙る山並みを眺めたまま何も言わなかった。
急に雨が強くなった。
雨粒が地面や木々の葉を打つ音が辺りに充ちる。
僕は泥だらけになった手のひらをぬぐって、桔梗さんの白い手を取った。
彼女の手は雨で濡れてひんやりと冷たい。
桔梗さんはその黒目がちな目で僕の顔を静かに見つめる。
「帰ろう、みんな待ってるよ」
僕の言葉に、彼女は黙ってうなずいた。
第六章 雨 〈二〉
湯船に身を沈めながら、僕は桔梗さんの言葉を思い返していた。
何かとても大事なことがわかりかけている気がする。
足踏み道を下りて勝手口からこっそり桐葉荘に入ろうとしたら、タイミングが悪いことに、僕と桔梗さんは蘭さんにはち合わせしてしまった。
「どうしたんですか、二人ともそんなずぶ濡れで!」
蘭さんがあきれた声で叫び、その声で戻ってきていた水菜さんが気づいて、夕介に桔梗さんの無事を連絡してくれた。
僕と桔梗さんは、そのまま蘭さんによって半ば強制的に風呂に送られたんだ。
僕は湯船から両手でお湯をすくって顔をすすいだ。
雨で冷えた身体が、じんわりと温められていく。
桔梗さんは、雨をやませるために祈っていたと言った。それも雨の中、わざわざあの尾根まで登って。
一体、何が彼女をそこまで駆り立てたのだろうか?
どうも自分一人では考えがうまくまとまらない。
夕介や水菜さんなら、僕が気づかないことに気づいてくれそうな気がする。
真新しい浴衣を着て風呂を出ると、女子会五人組が蘭さんとにぎやかにしゃべりながらチェックアウトの手続きをしていた。
雨の中、桑田さんが門のところに停めたミニバンまで荷物を運んでいるのがガラス越しに見える。
僕はなんとなく立ち止まってその様子を眺めていた。
「女将さん、絶~っ対、また来ますね!」
セミロングの明るい色の髪をふんわりと内巻きにカールさせ、ちょっと鼻にかかったようなかん高い声が特徴の女子の言葉に、ほかの四人もうなずいた。
「うふふ、それって実は、イケメン目当てなんじゃないですか~?」
蘭さんが笑いながら言うと、女子たち五人は弾けるように笑った。
「あはは、バレた~!」
「ねえねえ、女将さん、あの男の人、よくここに来るんですかぁ?」
「それは個人情報ですから、お伝えできかねます♪」
「ですよね~」
「あ~あ、惜しいなあ、もうちょっとで知り合いになれそうだったのにぃ」
女子たちは悔しそうに声を上げた。
「大丈夫、世の中にはた~くさんの殿方がいるんですから。がんばってそれぞれいい人探してくださいね! 応援してますよ!」
「あはは~、そうしまーす」
蘭さんが両手でガッツポーズを作ると、女子たちは再び声を立てて笑った。
「この度はまことにありがとうございました。ぜひまたおいでませ」
蘭さんはカウンターから出て少し改まった口調でお礼を言うと、ていねいに頭を下げた。
「ねえねえ、女将さん女将さん、一緒に写真いいですかぁ? SNSに載せたいから」
どうやら最初のかん高い声の女子がこの五人組のリーダー格のようだ。
「いいですよ、喜んで。じゃあ、桑田さん、撮ってもらってもええですか?」
「はい、お任せください。ふっふっふ、私こう見えても、プロの指導を受けちょるんですからね!」
桑田さんは軽く腕まくりをしながらカメラを受け取ると、にこやかにカメラを構えた。
「じゃあ撮りますよ~、一たす一は~?」
「に~!」
それぞれ思い思いのポーズで満面の笑みが弾けた。
続けてシャッターが何度か押される。
「楽しい思い出になりました~、ありがとー」
女子たちが笑顔で手を振りながらお礼を言う。
蘭さんも桑田さんもその言葉にうれしそうにうなずいている。桐葉荘にリピーターが多い理由が何となくわかるような気がする。
「じゃったら、桑田さん、駅までよろしくお願いしますね。安全運転で」
「はい、もちろんです。それではお送りしますので、どうぞ」
桑田さんは、女子たちを門の外へ停めたミニバンへと案内する。蘭さんも玄関を出て見送りをするようだ。
賑やかな声が玄関の外へ出ても続いている。
「森崎、森崎!」
不意に、後ろから夕介に小声で呼ばれた。
梅の間から顔だけ出して僕を手招きしている。
「なんだ、戻ってたのか」
「なんだじゃないだろ、結局桔梗はどこにいたんだよ?」
「尾根の上だよ。勝手口から上がって行ったところ」
「桔梗はどうした?」
「今風呂に行ってる。もう少ししたら出てくると思うけど」
それを聞いて夕介はやっとほっとした顔をした。
「まあ、取りこし苦労で済んでよかった」
「だね。『乙女淵』みたくなったらどうしようかと思ってあせったよ」
「座敷で水菜と果林が待ってる。ロビーで話をしよう」
僕が廊下の反対側を振り返ると、座敷の入口から果林ちゃんが顔を出して笑っていた。
「夕介、女子会帰ったね。はあ隠れんでもええよ」
「バカ、隠れてたんじゃない、蘭さんの仕事を邪魔しないようにしてたんだ」
にひひーと笑う果林ちゃんの後ろから、水菜さんも姿を見せた。
「森崎さん、大変でしたね。汚れた服は今洗濯してますから、午後には乾きます」
「すいません、助かります」
彼女のロングスカートの裾がまだ少し湿っている。
それにしても、僕のパンツまで水菜さんが洗濯機に放り込んだのかと思うと、僕は赤面してしまった。
「あらあら、みんなお揃いで何の悪だくみ?」
見送りを終えた蘭さんがロビーに戻ってきて、思い思いの場所に座っている僕らを見るなり笑った。
「あ、いや、みんなで昨日の感想でも話し合おうと思って……」
「ふふ、夕介さんは隠しごとが下手ですね。目が泳いでますよ」
蘭さんが右手の人差し指を口元に当てていたずらっぽく指摘すると、夕介は頭をかいた。
「桔梗がいなくなって、みんな大あわてで探してたんでしょ?」
「知ってたんですか?」
蘭さんがずばりと言い当てたので、僕は思わず声を上げた。
「様子を見てればわかりますよ、特に水菜と果林はね。私の娘ですもの」
「な~んだ、隠して損したー」
果林ちゃんは両手を頭の後ろに組んでソファの背もたれに身を任せた。
「母さん、わかってて心配じゃなかったの?」
水菜さんが不思議そうに尋ねたが、蘭さんは水菜さんにほほ笑みかけた。
「桔梗は自分から死んだりはせんよ。あの子も私の子じゃもん、五年間ずっと何も言わんかったにしても、そのぐらいわかるよ」
「そうなの?」
水菜さんは納得いかないらしく、ちょっと難しい顔をしている。
「あ、きぃねえちゃん!」
桔梗さんが桐葉荘の浴衣に身を包んで姿を現すと、果林ちゃんがぱっと立ち上がった。
「んもー、心配したんじゃけえ!」
果林ちゃんは桔梗さんに駆け寄るといきなり抱きついた。桔梗さんは少し困惑したような微笑を浮かべる。昨日今日と、桔梗さんは少しずつ色々な表情を見せるようになってきた。
「桔梗、あったまった?」
蘭さんが声をかけると桔梗さんはこくりとうなずいた。
「もう、心配させて……一体どこにいたの、桔梗?」
水菜さんはソファから立って両腕を組むと、少し責めるような口調で尋ねた。
桔梗さんは黙って右手で尾根の方角を指差す。
「ん? どこなの?」
水菜さんが不審な顔をする。
「勝手口から少し山の方に登った尾根の上です。おととい、僕もそこで桔梗さんと一緒に朝日を見たんです」
僕は桔梗さんのかわりに答えた。
「あ、こまい頃によく探検ごっこしたとこ?」
果林ちゃんが声を上げると、桔梗さんは黙ったままうなずいた。
「えー、わたし知らないよ、そんな場所」
「にひひー、みず姉には内緒で父さんが教えてくれたんよ。きぃねえちゃんとうちの秘密の場所!」
「あー、父さんやっぱりわたしより果林や桔梗の方がかわいかったんだ!」
果林ちゃんの言葉に水菜さんが両手を腰に当ててふくれ面をした。水菜さんらしからぬ、子どもっぽい表情だ。
「果林、お前……年光さんのこと、思い出せるようになったのか?」
夕介がソファから身を乗り出して尋ねた。
両手を前に組んでひざの上にひじを置き、真剣な表情で果林ちゃんの返答を待っている。
「あれ、そういえば今うち父さんのこと言うたね? どうなんかな? ようわからん」
果林ちゃんは肩越しに振り返って夕介にほほ笑んだ。
「でも、昨日はぶち泣いたけど、父さんがおってくれたけえ今うちがおるんじゃなあって思ったらな、なんか『父さんありがとう』って、思うたんよね。そしたら、今朝、なんか父さんの夢、見たような気がする」
果林ちゃんはきれいな笑顔で夕介にそう返した。
「そうか──」
夕介はそうつぶやくと、腕を組んで再びソファに身を沈め、左手であごひげを撫でまわしている。
「ふふ、思い出の国、じゃね」
果林ちゃんの笑顔を見て蘭さんがうれしそうにつぶやいた。
「なんですか、それ?」
僕は思わず尋ねた。
「『青い鳥』で、チルチルとミチルが最初に訪れる国です。二人はそこで、亡くなったおじいさんおばあさんや小さいうちに死んでしまった弟妹たちと再会するんですよ。桔梗がちっちゃいころ大好きじゃったから、よう読んであげたね、『青い鳥』」
蘭さんがそう言って桔梗さんにほほ笑むと、桔梗さんも少しはにかみながらうなずいた。
水菜さんがぽんと両手を合わせる。
「あ、わたしもよく二人に読んであげてたから憶えてるよ。『思い出の国』は濃い霧の向こうにあって、そこでは亡くなった人がずっと眠ってるの。生きている人がその人のことを思い出した時だけ目が覚めるんだよね?」
「そうそう、さすが水菜。よう憶えちょるねぇ。果林は、久しぶりに思い出の国の父さんに会いに行ったんじゃね」
「そっか、うちが思い出したから、会えたんじゃ」
そう言って果林ちゃんは勢いよくソファに飛び込んだ。小さな果林ちゃんの身体が二・三度スプリングで弾む。
桔梗さんがその様子を見て微笑している。
「でもさー、きぃねえちゃん、雨降っちょるのになんで外に出たん?」
「……内緒」
果林ちゃんがソファから身を乗り出して桔梗さんに尋ねると、彼女は小さな声でそう答えて頬を少し赤らめた。
「さてと、仕事仕事。あなたたち、いつまでそこに座ってる気?」
蘭さんがいたずらっぽい笑顔で僕らに尋ねる。
水菜さんが不穏な気配を察したらしく、あわてて立ち上がった。
「あ、わたしはもう母屋に戻るよ。洗いものとかやっとくから。桔梗、早く朝ごはん食べちゃって」
「うちも手伝う!」
「果林はいらない、かえって面倒になるもん」
「えー、なんよーそれ!」
水菜さんの言葉に果林ちゃんはむくれる。
「じゃったら、果林はこっちの掃除を手伝おっか」
「じゃあそうするー」
「そしたら掃除機持っておいで」
「はーい!」
果林ちゃんが元気良く返事をして駆けていった。
水菜さんと桔梗さんも僕らに会釈をしてロビーを出た。
「このままここに座ってたら掃除機で吸われそうだな」
夕介がにやにやしながら僕に言った。
蘭さんは両手を腰に当てて満面の笑みで仁王立ちしている。
「だね」
僕も夕介に苦笑いを返す。
「お前どうせ暇だろ? 資料整理するの手伝え」
「しょうがない、手伝ってやるか」
「クズのくせに偉そうに」
「クズとは何だ、クズとは」
「じゃあカスだ」
「うふふ、どっちにしても掃除機が来る前にお部屋に戻られた方がいいですよ~」
「ハイ!」
「今どきます!」
蘭さんににこやかににらまれて、僕らは弾かれたように立ち上がった。
第六章 雨 〈三〉
僕はおととい図書館でコピーした資料にパンチで穴を開けては、次々とフラットファイルに綴じている。
資料にはあちこちにふせんが貼られ、欄外にはピンク色の蛍光マーカーで何やら書かれているが、何と書いてあるのかはほとんど読み取れない。
「よくこんなの読めるな」
「いいんだ、俺がわかれば」
夕介はモバイルPCを使って撮りためた写真の整理をしている。
「へえ、写真で見るとまたちょっと違って見えるんだな」
「光量が少ないから絞りやシャッタースピードをいろいろ変えてみたんだが、なかなか満足に撮れたのはないな」
僕が後ろからのぞき込むと夕介は少し不満そうに言ったが、僕にはどこがどう不満なのかよくわからない。
画面では『寂水』前シテの鬼女が赤頭をふり乱しつつ右手を振り上げている。鱗摺箔がギラギラと光を反射し、振り上げた袖がぶれて写っていて、舞の激しさを感じさせる。
画面上に次々と移り変わる写真を見ていると、僕らが観ていたのとは違う角度からの写真もたくさんある。いつの間に夕介はこんなにあちこち移動していたのだろう。
「ふーん、さすがはプロだな」
「お前に写真の良し悪しなんかわかるのかよ」
「正直よくわからないけど、雰囲気はよく捉えてると思うよ」
「そりゃどうも」
夕介は画面から目を離さずに答えた。まったく、褒めがいのない男だ。
画面に『乙女淵』の前シテが現れると、夕介は画像を送るのを止めてその画像に見入った。
僕も改めてしげしげとその写真を眺めた。
固く口を閉じた面、白い小袖の上に白の水衣、鬘帯まで白……。
背景の夜の闇に妖しく浮かび上がるような白い装束が、強烈な印象を放っている。
「やっぱり、桔梗だよな」
「うん、僕もそう思う」
夕介も僕も、画面の桜姫をじっと見つめた。
多分、旅僧に対して自分の身の上を語っている場面だろう。
松岡さんが演じた桜姫は、心もち前かがみの姿勢で虚空を見つめて、じっとたたずんでいる。
「もしかしたら、桔梗は『乙女淵』の物語をなぞっているのかもしれないな」
夕介がぽつりとつぶやく。
桜姫は自分の発した言葉が合戦を招き、父たちを死なせたと思い込んでいた。
桔梗さんも誰かを死なせた?
「あ!」
僕は思わず声を上げた。
夕介が振り返って僕の顔を見る。
「なんだ、いきなり──」
「ちょっと待って!」
僕は夕介の言葉を制した。何かがつながりそうな気がする。
僕が初めて桔梗さんと言葉を交わしたとき、彼女は僕に会えそうな気がした理由を「わたしが、会いたいと言ったから」と答えた。
果林ちゃんが『寂水』の後に泣いた時には「鬼になんかさせない」と夕介に強い口調で告げた。
そして今朝は、「雨をやませるために」祈っていた。
いずれも彼女の望み、いや、意志を表したものだ。
「もしかしてだけど……」
僕は考えが十分にまとまらないままに言葉を発する。
「単になぞっているだけじゃ、ないんじゃないかな」
僕にも何か確証があるわけではないが、自分の奥の方から勝手に言葉がわきあがってくるのを感じる。
夕介がじっと息を呑んで僕の次の言葉を待っている。
「桔梗さんは、桜姫と同じように、自分の『言葉』が年光さんを死なせてしまったと思ってるような気がする」
言ってみて自分で自分の言葉に驚く。そう……なのか?
「そうか、奪命の詞か!」
夕介が興奮気味に叫んだ。
「奪命の詞、だっけ? とにかく桔梗さんは、自分が口にした言葉は現実になるって思ってるんじゃないかな? 桜姫がそうだったみたいに」
「なるほど、だから五年間一言も発しなかった──」
夕介はそう言ったきり腕を組んで黙りこんだ。
僕は改めて画面の中でたたずんでいる桜姫を眺めた。
自分の言葉を忌わしく呪わしいと嘆き、誰ともかかわらずに死人として生きようとして叶わず、結局は自ら命を絶つことになる桜姫。
「なんか、似過ぎててこわいよね」
「ああ。桔梗がいなくなったと聞いて、俺もお前も、すぐに『乙女淵』を連想したぐらいだからな。だが、あいつは身を投げなかった。なぜだ?」
「そこまではわからないけど……」
僕は桔梗さんの静かな瞳を思い浮かべた。
彼女は僕に一体何を語りかけようとしているのだろう?
じっと考え込んでいたら、突然部屋の電話が鳴りだしたので僕も夕介もびっくりして顔を見合わせた。
「おい、お前出ろ」
「なんでだよ、ここアンタの部屋だろ」
「いいから」
僕はしょうがないなあとぶつぶつ言いながら受話器を取った。
「もしもし?」
『あ、あれ? 森崎さんですか?』
電話の向こうの声は水菜さんだった。
「夕介に出ろって言われて。どうかしましたか?」
『いえあの、二人ともお昼用意してないでしょ? うちでごちそうしようかと思って』
すっかり忘れていたが、桐葉荘は一泊二食の設定だから普通なら昼食は用意されない。
「マジッすか? ぜひぜひ!」
僕は二つ返事で即答した。
『ふふ、二人ともそろそろ和食飽きたんじゃないですか? わたしがパスタ作ります。後でまた呼びますから、そしたら母屋に来てください』
「あざーっす!」
水菜さんの手料理が食べられると思うと自然とテンションも上がる。僕はうきうきした気分で受話器を置いた。
夕介が怪訝な顔で僕を見ている。
「水菜さんが昼にパスタごちそうしてくれるって!」
「おいおい、どういう風の吹きまわしだ? 今まで俺が何回泊まってもこんなこと一度もなかったぞ」
「ふふーん、水菜さんもそろそろ僕の魅力に気づいたのかも」
「いや、それだけはない。絶ッ対に」
夕介は大げさに首を横に振る。
「ま、お前のおめでたい妄想は別にして、何かが変わりつつあるのは確かだな」
そう言って夕介は左手であごひげを撫でた。
第六章 雨 〈四〉
さっきから果林ちゃんが落ち着かない。
足を投げ出して椅子に座ったまま、スマートフォンをにらんでずっとイライラしている。
「あ~もう!」
果林ちゃんはとげとげしく吐き捨てると、何やら一心に打ち込み始めた。スマホなのにフリック入力を使わずに指を連打しているのがなんだかおかしいが、とてもそんなことを言えるような雰囲気ではない。
「おい、何イライラしてんだよ?」
腕を組んだまま果林ちゃんの様子を眺めていた夕介が面白くなさそうに尋ねる。
「夕介にはカンケーない!」
果林ちゃんはぎろっと夕介をにらみつけると、また画面に目を落としてひたすら打ち込み続ける。
夕介は黙って肩をすくめた。
僕と夕介は水菜さんのお招きにあずかって、母屋のダイニングでパスタを待っているのだが、果林ちゃんは僕らが来る前からずっとスマホで誰かとやりとりを続けている。
水色のエプロン姿の水菜さんが立つキッチンからは、食欲を誘ういいにおいが流れてくる。
「どうせ彼氏とけんかでもしてるんでしょ?」
「みず姉うるさい!」
対面キッチンから様子を見ていた水菜さんがからかうと、果林ちゃんはものすごい剣幕で一喝した。
「けんかするぐらいなら最初からつきあわなきゃいいのに」
水菜さんはそうつぶやくと顔をひっこめた。
「あ~もうムリ。別れる!」
とうとう果林ちゃんはそう言って最後のメッセージを打ち込み、ダイニングテーブルの上に電源を切ったスマホをぽいと放り投げた。
「終わり終わり!」
えーと、果林ちゃんはどうやら僕らの目の前で彼氏と別れることにしたらしい。
「なんだ、もう終わりか? 今回は何ヶ月続いたんだ?」
「二ヶ月。ようがまんした方じゃと思う」
そう答えてから果林ちゃんは椅子に座ったまま大きく背伸びした。
夕介はなかばあきれ顔だ。
「やれやれ、あいかわらず続かないな」
「だって陽一センパイぶち束縛するんじゃもん。ちょっと返事せんかったらようけメッセージ送って来てから、ぶちせんない(めんどくさい)! なのに人のこといっそ(全然)わかろうともせんのんよ! 今朝うちはきぃねえちゃんのことで頭いっぱいじゃったのにから、よいよわかってくれん!」
「まったく、果林を束縛できるような度胸のある男がいるなら見てみたいもんだ」
夕介はそう言って苦笑している。
「彼氏と直接話さなくてもいいの?」
「はあええ。学校でも絶対口きかん!」
僕も遠慮がちに尋ねてみたが、果林ちゃんは腕を組んでぷりぷりと怒ったままだ。
「これで五人目だね。みんな果林を扱いかねて、最後は突然一方的にポイだもん。なんかかわいそー」
水菜さんが再びキッチンから果林ちゃんに茶々を入れる。
「みず姉だってみーんな拒否ったくせに」
「わたしはつきあう前だもん。とりあえずつきあってみて、飽きたら捨てちゃう果林の方が、よっぽど残酷だと思うけどなー」
水菜さんもなかなか言う。告白してきた三〇人の男子たちをことごとくふった水菜さんだってなかなか酷薄だと思うが、さすがにそんなことは言えない。
「イケメンとしてはどう思う?」
僕は夕介に水を向けてみた。
「告白されたからってホイホイつきあうからこんなことになるんだ。次はつきあう前によーく考えるんだな」
「えー、うちがいけんの? おいしーかどうかは、食べてみんとわからんじゃあ?」
聞きようによってはかなりキワドイ台詞を、果林ちゃんは無邪気に投げる。
夕介はあきれ顔で続けた。
「お前なー、いいかげん自分が小悪魔女だって自覚しろ。振り回される周りの男からしてもいい迷惑だ。そもそも、どうでもいい相手からちやほやされたってなんにもならないだろ? モテるってのはな、自分が想われたい相手から想われることだ」
「おー、大人!」
夕介がえらく含蓄のある言葉を口にするから、僕は感嘆の声を上げた。
「ふふん、お前みたいな非モテには永遠にわからんかもしれんがな」
夕介はそう言ってドヤ顔を僕に向けた。ムカつく。
「よけいなお世話だ! だいたい、その意味で言ったらアンタだってモテてない──」
と、言いかけたところで夕介に口をふさがれた。前言撤回、都合が悪くなるとすぐに実力行使、まるで子どもだ。
「ま、果林は男とつきあったことはあっても、本気の恋をしたことはないみたいだな」
「えー、なにそれー」
「まだまだお子様だってことだ。悔しかったら本気で誰かを好きになってみな」
夕介は一人で勝ち誇っている。まったく、高校生相手に大人げない。
「えー、じゃあ夕介は本気で好きな人おるん? 誰ー?」
「そのうちわかる」
果林ちゃんはぽかんとして首をかしげている。
夕介が好きな相手を知っている僕としては、笑いをこらえるのに必死だ。
「よし、おっけー♪」
キッチンタイマーがにぎやかに時間を知らせると、水菜さんが上機嫌な声を上げた。
火を止めて大きな寸胴をシンクに返すと、湯気がもうもうと立ち上って彼女の姿を隠す。
「果林、もうすぐできるから母さんと桔梗呼んで」
「んー、わかったー」
果林ちゃんは椅子から立ち上がると内線で蘭さんを呼び、それから桔梗さんを部屋まで呼びに行った。
水菜さんは金ざるで水気を切ったパスタを手際よくフライパンに移して、パスタを茹でている間に作っていたソースと絡めている。
「うまいもんだな」
夕介が感心したようにつぶやいた。
「えへへ、パスタは一番の得意料理ですから」
水菜さんは皿にパスタを取り分けながら答える。トングを巧みに使ってみるみるうちに六皿ものパスタの盛りつけを終えた。
「よし、できた!」
水菜さんが無邪気な声を上げた。
「いいにおいですね! 美味しそう」
「ふふ、本当に美味しいかどうかは、食べてみないとわからないですよ?」
僕が声をかけると、水菜さんは冷蔵庫からサラダボウルを取り出しながら果林ちゃんの言ったことをまねしたので、僕も夕介も顔を見合わせて笑ってしまった。
果林ちゃんに呼ばれた桔梗さんもやってきて配膳を手伝う。桔梗さんはまだ桐葉荘の浴衣のままだ。水菜さんはエプロンを脱いでていねいにたたんでいる。
ダイニングテーブルの上は六皿のパスタに加え、真中に大きなサラダボウルが置かれ、さらにサラダの取り皿ですしづめ状態。
椅子が五脚しかないので、水菜さんはキッチンからスツールを持ってきて座った。
「あらあら、なんだかにぎやかねえ」
ダイニングにやってくるなり蘭さんは朗らかな声で笑った。
「水菜、いつもありがとうね」
「ううん、当たり前のことしてるだけだよ。さ、みんな食べて食べて」
「いただきまーす!」
果林ちゃんが一番に声を上げてフォークとスプーンを取って食べ始めると、みんなもそれに続いた。
水菜さんが作ってくれたのは、ベーコンと山菜、シメジの和風パスタ。上にかけられた刻み海苔が湯気で踊っている。口に入れると醤油とバターの香りがふわりと広がる。ベーコンの塩気とシメジの旨味が絡み合った絶妙な味つけだ。
「どうですか?」
水菜さんがじっと僕の顔を見て問う。
「うまいっす! これだったらいくらでもいけます!」
僕が口をもごもごさせながら答えると、水菜さんはうれしそうな笑顔を浮かべた。
少々行儀が悪いが、それよりもこの感動を早く彼女に伝えたかった。
「懐かしい味だな、よく年光さんがごちそうしてくれたのを思い出す」
夕介がふっと洩らす。
「ふふ、年光はもてなし好きじゃったですからね。よく会社の人や友達を招いてはパスタをふるまってましたね」
蘭さんもそう言ってほほ笑んだ。
「水菜のパスタは私よりもずっと上手! やっぱり、父さんの直伝じゃもんねー」
「えへへ、母さんにそう言ってもらえるとうれしいな」
蘭さんが褒めると、水菜さんはちょっとはにかむ。
「みず姉、カフェでも開いたらええんじゃないん? 味はプロ級じゃと思うけどなあ」
「そんなことないよ、わたしはただ食べてもらうのが好きなだけだもん」
果林ちゃんの言葉に、水菜さんは少し頬を赤らめてさらに照れた表情をした。やわらかな、いい表情だな……と僕はちょっとの間見とれてしまった。
ふと気づくと、桔梗さんが食事の手を止めてじっと僕を見つめている。僕が彼女に視線を合わせると、桔梗さんはあわてて目をそらした。じっと下を向いて、いつまでもフォークをくるくると回してパスタを巻きつけている。
「そうそう母さん、果林また彼氏と別れたんだよ!」
「あらら、また?」
水菜さんの言葉に蘭さんが目を丸くした。
「だってぶち束縛するんじゃもん。はあ耐えれん」
「これで五人目だよ、どう思う、母さん?」
「んふふー、果林はそっちの方は父さんに似ちゃったんだ」
蘭さんが意味ありげな笑いを返す。
「えー、それってどういう意味なん?」
果林ちゃんは両手を頭の後ろに組んで蘭さんに尋ねた。
「父さん、若い頃は結構なたらしじゃったんよ。年中ナンパしたりコンパしたりで、忙しかったんじゃけえ」
「えー、なんかヤだなあ」
水菜さんが軽蔑したような声を上げる。
「そこそこモテたみたいね。でもねー、やっぱり自分が想われたい人から想われないと、意味がないんよね」
蘭さんはさっき夕介が言ったのと同じことを言った。
「あの、蘭さんは年光さんとはどんなふうに知り合ったんですか?」
僕はつい好奇心で聞いてしまった。
「あー、それわたしも聞きたい! 今まで何回聞いてもいつだってはぐらかして、なかなか教えてくれないんだもん。だいたい、なんでそんなたらしと結婚したの?」
「うちも聞きたい! なー、母さん教えてー」
水菜さんと果林ちゃんも僕に同調した。桔梗さんも興味深そうに蘭さんの顔を見つめている。
「えー、今さら恥ずかしいなぁ」
蘭さんは両手を頬に当てて困った顔を見せた。その様子はなんだかかわいらしくて、三人姉妹の母親であることを忘れてしまいそうだ。
「……俺も、聞いてみたいです」
ずっと黙っていた夕介がぼそりと言った。
「聞かせてください、蘭さん。ぜひ」
夕介はそう言って顔を上げると、蘭さんの目をじっと見つめた。
「しょうがないなあ」
蘭さんは少し困ったような微笑を浮かべると、少し間をおいて語り始めた。
第六章 雨 〈五〉
んー、どこから話そっか。
私はね、短大出てすぐ、経理部の事務職として父さんと同じ会社に入ったんよ。
向こうは営業部で、二年先輩。
ええと、私の四つ上じゃからそのとき二四歳……じゃったんかな?
私がハタチ。今の水菜とおんなじ歳じゃね。
最初の印象?
もう最悪。
会社員のくせにラフなかっこうで、いかにもちゃらんぽらんな兄ちゃんって感じでね。
やたらとなれなれしい上に口も悪くて、正直、何コイツって感じじゃったよ。見るからに女グセ悪そうじゃったし。
あの頃はまだイケイケの時代の名残で、会社も結構ゆるかったんよね。私の同僚にも、明らかに花ムコ探しが目的の「腰かけOL」がおったもん。ふふ、今じゃ死語じゃね。
私は真面目じゃったから……ちょっと果林、ここ笑うとこじゃない。
とにかく、私は経理事務の仕事を一生懸命覚えようと思って毎日がんばっちょったけど、父さんの方はたいてい何か変なことして人のこと困らせよったね。書類に不備は多いし、事務方に無理なことばっかり言うし。
そうそう、コンパの領収を経費に紛れ込ませる常習犯じゃったんよ。まーまー、いーじゃん、とか言って。
同じ経理部の先輩からは、絶対だまされないように気をつけなさいってしつこく言われた。
見た目は割とさわやかでカッコええのに、そんなだから事務の女子からもとにかく嫌われちょったね。
もちろん、私もサイテーな奴って思いよったなあ。
もう、ほんとに口が悪かったし。
声はするけど小さいから見えなかった、なんて、新喜劇みたいなことも言われたんよ。
じゃけえ、父さんとはもう毎日のように事務室でバトルしよった。
なんの時じゃったか忘れたけど、上司でもないあなたに指図される覚えはありません! って言い返したこともあったっけ。
その時の父さんの顔思い出すと笑えるけど、今にして思えばかわいくないよねー、私。
でも、仕事はその当時から出来よったみたいよ、父さんは。
なんでかわからんけど、お客さんウケはよかったなあ。偉い人にも気に入られちょったみたいじゃし。
後で本人から聞いたんじゃけど、その頃は仕事が段々と面白くなってきてて、やればやるほど手応えがあったって言いよったね。
ま、とりあえず私としては第一印象があんまりにも悪すぎて、この人だけは絶対に恋愛対象にはならないって思ってた。
実際、そのころ他にあこがれてる先輩がおったもん。もしその先輩とつきあっとったら、今頃ここで女将なんかしとらんかったじゃろうね。
人生って不思議じゃね。
まあ、最初はそんな感じじゃったから、お互いなんとも思ってなかったんよ。
だいたい全然真逆のタイプじゃったしね、私と父さん。
父さんはテキトー・無責任で、私はマジメ。んもー果林、笑わんの。
んー、その頃の私は水菜みたいに……てゆーか、水菜に輪をかけてマジメじゃったかもね。
見た目も、三つ編みでおさげにして、眼鏡もかけちょったから、それこそマンガのイケてない委員長キャラみたいじゃったんよ。
ちょっと、なんでみんな笑うんかね、失礼なねー。
ところがね、次の年が明けたぐらいから急に姿を見んようになったんよ。
最初は全然気がつかんかったんよね。
別に気にもしてなかったんじゃけど、そういえば最近あのうるさい奴見ないなあって思って人事部の先輩に聞いたら、関西に出張してたんだって。
先輩には、あんな悪い意味で存在感のある奴がいないのに、気づくの遅いよって笑われちゃった。私が気づいた時にはもう出張に行って半月近く経ってたからね。
あの頃の私はほんっとに鈍感で。自分の目の前のことだけでいつもいっぱいいっぱいだったなあ。
ま、うるさい奴がいないならいないでせいせいしたって思ってたんだけどね、いないって気づいてみるとなんだかつまんないんだよね。毎日物足りないっていうか。
顔見たら絶対けんかになるはずなんだけど、ふと気がついたら、あいつ今関西で何してるんだろって考えてる。一人で食事してるときに、あいつは向こうで何食べてるのかなーとか思いよって、自分でびっくりしたりして。
でね、そんな風になっちゃった自分にムカついて、同期の女の子にそのこと話したら、それって恋じゃないのって言われてね。
げー、やめてって感じ。
でも、その子は絶対そうだって譲らないんだよね。
トレンディードラマの見すぎだよってその時は聞き流したんだけど、やっぱりそう言われちゃうとよけいに気になるよね。
一〇代二〇代の女子って、どうしても恋愛が人生のすべてって感じになっちゃうじゃない?
水菜はわかんない?
うふふ、案外そういうタイプの方がいざという時どっぷりハマっちゃうかもよ、私みたいに。
私に限ってそんなことは絶対にないって確信してたんだよね。
こういう言い方したらヤな女って思われるかもしれないけど、私は仕事に生きるって思ってたから。
でもさあ、自分が思ってたのとは全然違うことが起きるのが、恋なんだよねー。
とりあえず、あいつのことは考えないようにしようと思って、例のあこがれの先輩に告白しちゃおうって思ってたところに、三月になってひょっこりあいつが帰ってきて。
で、帰ってきたあいつが最初になんて言ったと思う?
ぬけぬけと、あれ、きれいになった? だって。
私は三つ編みに眼鏡のままだから、見た目変わってないはずだよ?
もう、頭きて。
ナンパなら会社の外でやってください! って言ってやったの。
そしたら、いつもは憎まれ口で言い返してくるあいつが、めずらしく黙ーってるんだよね。
あれれ、と思ってたら黙ったまま名刺だけ置いてったの。
見たら、裏にレストランの名前と、場所、日時が書いてあるんだよ。
キザなことするでしょ? こっちが恥ずかしいよ。
絶対行ってやるもんかって思ってたんだけど、その日はなんか落ち着かなかったのかな、経理部の先輩にバレて、白状させられちゃった。
で、その先輩が言うのが、話だけでも聞いてあげなよ、その結果蘭が断るのは蘭の勝手だけど、何も聞かないうちに断るのはいくらあの桐島が相手でもやっぱり失礼だよ、って。
そりゃまあそうかな、って思って、とりあえず話だけは聞いてやるか、と。
指定された日に行ってみたら、あいつが選んだのはすっごくおしゃれなイタリアンレストランでねー、私それまでそんなとこ行ったことなかったから、店の前でめちゃめちゃ緊張して。入ろうかどうしようか、十分くらい迷っちゃった。
でもさ、あいつはこんなところ行き慣れてるんだろうなって思うと、なんか腹が立ってね。どうせ女の子をとっかえひっかえこんなお店で口説いてるんだろうって。よーし、女の敵をとっちめてやるって思ったの。
で、思い切って入ってみた。
あいつ、普段は会社でもめったに着ないスリーピーススーツなんか着て待ってたの。
来てくれると信じてました、なんてやけに殊勝なこと言うんだよ。
私は何にも考えてなかったから、通勤用の地味なワンピースだし、メイクもちょっと直しただけ。もちろん、三つ編みに眼鏡だよ。
ひえー間違ったー、来るんじゃなかったーって、思いっきり後悔しちゃった。
ボトルから注がれる赤ワインもなんか現実感なくてね、私こんなとこにいていいの? って思って全然落ち着かなかった。
あいつが何か言って乾杯したけど、私は上の空。ワインもどんな味だか全然わかんないし。
最初、あいつは仕事の話から始めたの。なんやわからんけどめっちゃ元気になったわー、なんてにわか仕込みの関西弁交えながら。
案件はうまく行ったみたいで、会社としてもそこそこ儲かったみたい。
仕事が面白くてたまらんねん、ってぎこちない関西弁で笑うの。
向こうでも女の子ナンパしてたの? って私が聞くと、最初はしてたって言った。
最初はってどういうことって聞いたら、途中からやめた、だって。
当然、ウソだって思った。
この生まれながらの女たらしがそんな簡単に治るわけがないって。
でも、ほんとにナンパやめたんだって。
で、いきなり、俺とつきあってくれないかって言うの。
あんまりいきなりだから思わず、はい? って聞き返しちゃった。
なんでそうなるのって思うでしょ?
もし水菜だったらどうする?
……やっぱ断るよねー。
だいたい、なんで私なの、私のどこがいいのって聞いたの。
そしたらすんごくマジな顔して、わからないって言うんだよ?
どこが好きなのかもわからないのに、つきあってくれなんて言う軽薄な人とはつきあえません、って断ったら、やっぱそうだよねって見るからにがっかりするの。
それまでそんなあいつ見たことないから、なんか変な感じだったな。
それで、その後ずっとお互い何も言わないで黙って料理食べたの。
いつも大声でしゃべりまくって、いろんな人からうるさがられてるあいつがさ、借りてきた猫みたいにじーっと黙ってる。はっきり言ってめちゃめちゃ気まずいよね。
料理の味なんか全然覚えてない。
でもさあ、食後のコーヒーが来たときにね、あいつ角砂糖を五つも入れて、ミルクもたっぷりの超甘甘にして飲むんだよ? 意外でしょ?
実は、私もおこちゃまだったから、角砂糖五つのミルクたっぷり。
なんと、角砂糖の数まで一緒。
私なんだかおかしくなって、思わず笑っちゃった。
やっと笑顔が見れた、ってあいつも笑った。すっごくうれしそうに、ガッツポーズまでして。
会社じゃ全然笑ってくれないけど、すごくきれいな笑顔だねって褒めてくれた。
私誰かにそんな褒められ方したことなかったし、恥ずかしいからちょっといじわるして、どうせ女の子みんなにそう言ってるんでしょって言ったら、そんなことないよってあわてて否定するの。俺は正直だから本当にきれいだと思った人にしかそんなこと言わないよ、ウソじゃないって、信じてくれ……なんて、汗かきながらしどろもどろで言うの。
もう、おかしくって。
ふふ、なんかそのあわてっぷりを見てたら、ふ~って楽になってね。
なーんだ、意外にかわいい奴じゃん、て思えたんだよね。
そう、それでつきあうことにしたんだ。
つきあいはじめたら、彼すごく変わったんだよ。私もびっくりした。
まず事務方とトラブルを起こさなくなったの。
ちゃんと経費のルールも守るようになったし、書類の不備も目に見えて少なくなった。
ま、私がかなり厳しくしつけたからね。
彼が言うには、俺が好きな人に迷惑かけたくないから、だって。
でも、人ってこんなに変わることができるんだって、本当にびっくりしちゃった。
で、私も変わったの。
ちょっとはおしゃれに気を使うようになって、三つ編み眼鏡はやめちゃった。コンタクトにして、メイクのやり方も変えてみたし、服もかわいいの選んだりしてね。
えへへ、遅ればせながら社会人デビュー。
ちょっとでもがんばると、彼ちゃんと気づいて褒めてくれるんだもん、嬉しいよね。
私、背が低いのがずっとコンプレックスだったけど、彼が、蘭は変なふうに背伸びしない方が断然かわいいよって言ってくれたから、あんまり気にならなくなったな。
おかげでちょっと自信がついたみたい。
お互い仕事は好きだったから、仕事もはかどるようになったよ。
彼、確かにかなり個性的で、尖ってる部分があったから、企画提案みたいな創造的な仕事にはすごく向いてたの。
その分、周りとぶつかることも多かったみたいなんだけど、私とつきあうようになってそれがずいぶん少なくなったよ、って言ってくれたことがあったなあ。
私も数字に弱い彼にアドバイスしたり、逆に彼から意外な発想を教えてもらったりして、仕事がすごく楽しくなった。簿記検定の一級も取ったしね。
会社では二人がつきあってることは秘密だったから、何があったんだろうって思われたみたい。
そうなると、二人ともモテるようになってね、困った困った。
えへへ、自慢かな?
でもね、彼あれだけ女たらしだったのに、きちんと全部断るようになったんだよ。すごくない?
あ、これなら大丈夫かもって思った。
ちゃんと私のこと大事にしてくれてるのがわかったし、私も彼のこと尊敬してた。
ふふ、さっきの「自分が想われたい人から想われないと意味がない」って、実は彼が言ったんだ。
関西に行ったときにね、かわるがわるいろんな女の子と遊んでも全然楽しくないのはなんでだろうって思ったら、ふっと私の顔が浮かんだんだって。
その時に、俺はこの人と一緒にならなきゃダメになるって思ったらしいよ。
この人から想われたいって思ったら、もうそれからはナンパなんかする気にならなくなったんだって。
結婚して、ずーっと後になってから教えてくれた。照れてたんだね。
たった数ヶ月つきあっただけでも、一緒にいてほんとに安心感があったから、彼からプロポーズされたのも、ごく自然に受け止めたなあ。
その年の十一月には籍を入れて、翌年の一月に結婚式挙げたの。
会社の人もみんな驚いてたね。私もこんなに早くお嫁さんになるなんて思ってなかったから、なんかびっくりしちゃったけど、うれしかったあ。
で、式を挙げた年の八月だね、水菜が生まれたのは。
そっか、彼と出会ってからもう二二年も経つんだ、早いなあ。
第六章 雨 〈六〉
蘭さんはそこでふっと息をついた。
年光さんとの出会いをまるで昨日のことのように話す彼女の顔は、いきいきと輝いていた。
「母さん、かわいいね」
水菜さんがぽつりとつぶやいた。
「もう水菜、親をからかわんの!」
蘭さんが照れ笑いをするのを、夕介がまぶしそうな顔でじっと見つめている。
「ねえ、コーヒーでも淹れよっか?」
水菜さんがそう言いながら立ち上がった。
蘭さんが食器を片づけようと立ち上がりかけるのを彼女は制して続ける。
「いいよ、後片づけはわたしがするから。母さんはゆっくりしてて」
水菜さんが食器をシンクに運ぶのを桔梗さんが手伝い、果林ちゃんがふきんでテーブルを拭いた。
「なんかええなー、うちも母さんみたいな恋愛、してみたいなー」
果林ちゃんが蘭さんの腕を取りながら、うらやましそうに言った。
「そういえば父さん、恋は落ちるもんじゃない、落とすもんだ……なんてことも言ってたなあ。私は父さんに見事に落とされちゃった。果林だってその血筋を受け継いでるんだから、色々経験したらええんよ」
蘭さんは果林ちゃんに向けて猫がじゃれつくようなしぐさをして笑う。
「えー、うちって、もしかして男たらし?」
果林ちゃんが首をかしげると、蘭さんは小さく手をたたいて喜んだ。
「ふふ、男たらし、ええじゃない! 果林は男に貢いだりしちゃいけんよ、しっかり手玉に取らんと!」
「あはは、母さん、それって親が言うことじゃないよ!」
水菜さんが笑いながらキッチンからつっこむ。
「むー、そんなんできるかなー?」
「果林なら大丈夫!」
蘭さんから軽く背中をぽんとたたかれた果林ちゃんは、なんだかくすぐったそうな表情を浮かべた。
桔梗さんがそんな果林ちゃんの様子を面映ゆそうに見ている。
「でも、もしかすると悪い男に騙されるかもしれませんよ?」
夕介が少し心配そうに蘭さんに問いかけたが、蘭さんはおおらかにほほ笑んでいる。
「ま、そういうこともあるかもしれんよね。ただね、自分の心に素直になった結果なら、それは自分で引き受けるしかないからねー。厳しいかもしれんけど、それを通じてしかわかれんのなら、それも経験!」
「いや、しかし心配じゃないですか?」
「うーん、確かに心配は心配ですけど、どれだけ心配しても親がそれを代わってやることはできんしねー。それに、どんな経験であれ、必ず意味は見つけられるんですよ、その時はわからんくてもね」
キッチンからコーヒーのいい香りが流れてくる。
「だから、水菜も、桔梗も、果林も、思うように生きたらええんよ、自分が『好き』と思ったものを信じて。私は応援してあげることしかできんけど、あなたたちの人生は、あなたたちのものだもん。『ああしなきゃ』『こうあるべき』なんて肩ひじ張ってたら、疲れちゃう」
蘭さんが三人の娘たちの顔をそれぞれ見くらべながら言うと、夕介はなんだか難しい顔をしてあごひげを撫でた。
「でも、蘭さんはどうなんですか? 子どもたちがいずれ巣立っていくと──」
「最後は私が一人、ここに残るよね」
きっぱりと夕介に返した蘭さんの顔に、迷いは見えない。
「この桐葉荘は年光だけの夢じゃない。私の夢でもあるんですよ? 私はこれからも、この桐葉荘で、私の物語を作っていくの。それが、年光が遺してくれた、一番のプレゼントだと思ってるんです」
蘭さんはテーブルにひじを置いて両手を組んだ上にあごを載せ、夕介の目をじっと見つめた。夕介も目を細めて蘭さんを見つめている。
「でも、わたしはここから出る気はないからね」
水菜さんがダイニングテーブルに一つずつコーヒーカップを置きながら蘭さんに言った。
「ふふ、じゃあ水菜はいずれ素敵なおムコさんをもらって、若女将として桐葉荘を継いでくれるのかな?」
「え……、そこまで考えてるわけじゃないけど……」
蘭さんがにこにことそう尋ねると、水菜さんは一瞬たじろいで言葉を濁す。
蘭さんは急に少し厳しい表情になって、水菜さんをじっと見据えた。
「水菜、心にもないことは言わないの。あなた、本当はここから出たいと思ってるんでしょ?」
水菜さんはぎくりとして蘭さんの顔を見たが、すぐに目をそらした。
蘭さんは、まっすぐ水菜さんを見つめたまま続ける。
「私は別に、水菜に桐葉荘を継いでほしいなんて思ってないからね。どこまで続けられるかはわからないけど、行ける所まで行ってみようと思ってるだけ。父さんと一緒に」
そう言うと蘭さんはコーヒーを口に運んだ。砂糖もミルクも入れず、ブラックのままで。
「あ、砂糖は入れないんですか?」
僕は思わず蘭さんに尋ねた。
「ふふ、人って変わっていくものなんですよ、森崎さん」
蘭さんはそう言って僕にほほ笑むと、再び水菜さんをじっと見つめた。
「水菜にはかわいそうなことしちゃったなって、ずっと思ってたんだよね。父さんも最後までずーっと気にしてた。あなたが本当はこっちに来たくなかったのも知ってたし、この町になじめてないのもわかってたんだけどね。色々なことに紛れて、ちゃんと話すことができなかったね。ごめんね、水菜」
蘭さんは水菜さんの目を見て謝ったが、水菜さんは下を向いたまま黙っている。
「人はね、だんだんと変わっていくんだよ。超甘甘にしなきゃ飲めなかったコーヒーが、いつの間にかブラックで飲めるようになったりするみたいにね。水菜も、いつまでも今の水菜のままじゃないの。もう大人なんだし、誰も気にせんと、思いっきり好きなように生きたらええんよ?」
「でも……」
「私のこと心配してるんでしょ? そんなのよけいなお世話だからね! まだまだ娘に心配されるほどもうろくしてません!」
蘭さんは両手を腰に当てて胸をはった。
「もう、母さんたら!」
その様子に水菜さんは思わず固い表情を崩した。
「なあ水菜、手始めに一人暮らしでもしてみたらどうだ? 職場の近くにアパートでも借りて」
夕介が腕を組んで背もたれによりかかったまま水菜さんに提案した。
「今すぐには……でも、一応考えてみます」
水菜さんがまだ何かわだかまったような表情で夕介に返すのを、桔梗さんがじっと考え込むような顔で見つめていた。
母屋から外へ出ると、雨はいつの間にかやんでいた。
雲が切れてその間から鮮やかな青い空がのぞいている。地面は既に乾きはじめていた。
「おー、本当にやんだ!」
僕は思わず声を上げた。
「なんだ、その『本当に』ってのは」
夕介が怪訝な顔で僕に尋ねる。
「へへ、内緒」
僕が答えると、夕介はなんだ気色悪いな、と苦笑しながらつぶやいた。
空を見上げながら、ひんやりとした風が頬を撫でていくのを、僕は感じた。
〈第六章終わり〉
第七章 霊山(りょうぜん) 〈一〉
日曜日の昼間のテレビはどういうわけか面白くない。
時間をつぶそうと思ってつけたが、ゴルフ、競馬、囲碁、再放送のバラエティ、ゴルフ……結局退屈なので消してしまった。
スマートフォンを使っていた頃は暇つぶしにゲームもしていたが、ガラケーにしてからはそれもやめた。そもそもここは圏外だ。
文庫本でも持ってくればよかったかな、と思いながらたたみにごろりと横になったところ、入口の扉がノックされた。
扉の向こうに立っていたのは桔梗さんだった。まだ浴衣に半纏姿のままだ。
「桔梗さん?」
「あの、これ──」
彼女は左手に持った紙袋を差し出した。
中を見てみると、今朝僕が着ていた服一式がきれいにたたまれて入っていた。
「お姉ちゃんから」
水菜さんに頼まれて持ってきてくれたようだ。
「あ、わざわざありがとう」
乾燥機から取り出されたばかりなのか、洗濯物はまだ温かかった。
桔梗さんが入口の土間に立ったまま、かばんに洗濯物をしまう僕の様子を、じっと見つめている。
「どうしたの桔梗さん、何か用事?」
僕はなんだか気づまりになって桔梗さんに尋ねたが、彼女は両手を後ろ手にしたまま首を横に振った。
うーん、困った。女の子と二人きりの状況で、どのようにふるまうべきかを、僕はあまりに知らない。
しばらく気まずい沈黙が流れる。
「──話が、あるの」
桔梗さんは言葉を発しようとしてためらい、を何度か繰り返しながら、最後にようやく意を決したように切り出した。
「話って、何?」
「わかったの、わたし」
そう言って彼女が僕に差し出したのは、使い古された一冊の教科書だった。
「伝え合う言葉、中学国語、三──これって中学の国語の教科書?」
桔梗さんは小さくうなずく。
見ると、一ヶ所にふせんが貼られている。
僕はそのページを開いてみた。
散文詩のような短い文章の下に、山羊みたいな角のある動物が立ち上がってだんだんと人に変化していく素朴な風合いのイラストが載っている。
魔法のことば(金関寿夫 訳/柚木沙弥郎 絵)
ずっと、ずっと大昔
人と動物がともにこの世に住んでいたとき
なりたいと思えば人が動物になれたし
動物が人にもなれた。
だから時には人だったり、
時には動物だったり、
互いに区別はなかったのだ。
そしてみんながおなじことばをしゃべっていた。
その時ことばは、みな魔法のことばで、
人の頭は、不思議な力をもっていた。
ぐうぜん口をついて出たことばが
不思議な結果をおこすことがあった。
ことばが急に生命をもちだし
人が望んだことがほんとにおこった──
したいことを、ただ口に出して言えばよかった。
なぜそんなことができたのか
だれにも説明できなかった。
世界はただ、そういうふうになっていたのだ。
(イヌイットの伝説より)(註四)
「これは?」
正直なところ、彼女が何を言いたいのかがわからず、僕は当惑した。
桔梗さんは僕の目をじっと見て、一言ずつ言葉を選びながら語り始めた。
「わたし、こわかった。わからなくて──わたしの言葉が、何をするのか」
想像したとおり、彼女は自分の言葉を怖れていたんだ。
「奪命の詞。自分の言葉が、年光さんを死なせたと思ったんだね?」
僕が確かめると、桔梗さんは小さくうなずく。
「でも、そうじゃなかった。それが、わかった」
「どういうこと?」
「わたしは、はぐれていたの。わたしの言葉と」
彼女はそう言って、別のページを示し、声に出して読んだ。
「言葉と自分が一致していない人生は不幸だ。だから、本当の自分はどこにいるのかを、探し求めることになる。しかし、本当の自分とは、本当の言葉を語る自分でしかない。本当の言葉においてこそ、人は自分と一致する。言葉は道具なんかではない。言葉は、自分そのものなのだ」(註五)
女性の哲学者による、『言葉の力』というタイトルのエッセイの一部だ。
言葉は、自分そのもの……?
ここだけではなんのことだかよくわからない。
「わたしは、わたしの言葉を特別な道具だと思っていたの。『魔法のことば』みたいに、わたしの言葉に、言ったとおりになる不思議な力があって、それがパパを死なせたんだって」
桔梗さんは静かに語る。
「でも、『言葉の力』って、本当は、そういう意味じゃなかった。わたしが、間違ってた」
桔梗さんの目が徐々に強い光を帯びてくるのがわかる。最初は言いよどんでいた言葉にも、だんだんと熱がこもってきた。
「わたしが言ったから、現実になるんじゃない。現実は、言葉でできているから、本当の言葉なら、誰の言葉でもそういう力を持っている。伝わるから、言葉は現実になる。伝わるから、不思議なんだ」
特に難しい語彙を使っているわけでもないのに、僕には彼女の言っていることがよく理解できない。
「ちょっと待って、何が何だか──」
混乱する僕を見て、桔梗さんは恥ずかしそうにうつむいた。
「ごめんなさい」
「順を追って話してくれるかな?」
僕がそう言うと、彼女は少し頬を赤らめながらこくりとうなずいた。
桔梗さんは幼い頃から並はずれて読書の好きな少女だったのだという。
小学校四年生の頃には年光さんが読んでいたミステリやビジネス書なども読みこなし、父親に対して自分の意見を言えるほど言葉に早熟だったようだ。
当然、国語の教科書は持ち帰ったその日にすべて読んでしまい、自分の分だけではあき足らず、中学生だった水菜さんの教科書や副読本なども全部読んでしまうぐらいの活字中毒ぶり。
そんな桔梗さんにも思春期は訪れる。
彼女自身にも理由はわからないのに、大好きだった父親・年光さんに嫌悪感を覚えるようになり、あからさまに年光さんを避けるようになった。一緒にお風呂に入るのもやめた。
彼女が五年生になってすぐの頃だ。
思春期の少女なら、誰もが一度は通る道。
パパを嫌がると、パパはすごくさびしそうな顔で笑った、と座卓を挟んで僕の向かい側に座った桔梗さんは言った。
その年の夏、年光さんは余命半年という宣告を受ける。
桔梗さんにはそのとき、その意味が本当にはわかっていなかった。
年光さんが余命宣告を受けたからと言って、桔梗さんの父親への理由なき嫌悪感が消えるわけではなかった。
ある時、年光さんのささいな言葉に反発した桔梗さんは、何も考えずに「パパなんか死んじゃえばいいのに」と口にした。
この時、年光さんは「パパは死なないぞ!」と力こぶを作って笑ってみせた。
ところが、それから彼の病状は急速に悪化した。
入退院を繰り返すうちに年光さんの体重は激減し、その年の晩秋にはとうとう自力で起き上がることができなくなってしまった。
桔梗さんはうろたえた。本気でパパに死んでほしかったわけじゃないのに、なんでこうなるんだろう、と。
自宅で最期を迎えたいと希望した年光さんのために、蘭さんが献身的に彼の闘病を支え、水菜さんが家事を一手に引き受けるようになる中、桔梗さんは誰にも相談できずに一人で葛藤していた。
年光さんは宣告されていた半年を越えて、なんとか梅の花が咲く時期を迎えることができた。
このまま春を迎えられたらパパは元気になるかもしれない、と桔梗さんはひそかに期待した。
しかし、奇跡は起きなかった。
四月一〇日の早朝、年光さんは蘭さんに見守られて静かに息を引き取った。
満開の桜の中、年光さんの葬儀が執り行われた。
通夜も告別式も、多くの会葬者でごった返した。蘭さんは気丈に喪主を務め、中学三年生の水菜さんも懸命に蘭さんを支えた。
しかし、六年生になったばかりの桔梗さんは、年光さんが死去したことを実感できずにいた。
すべてが夢の中の出来事のように、どこかよそよそしく感じる。
葬儀が終わっても、彼女は自分がどこか違う場所にいるような感覚から抜け出ることができなかった。学校で、家で、目の前で起きる出来事すべてに、以前のような手ごたえを感じることができない。
それから逃れるために、彼女は貪るように本を読んだ。
その中でぶつかったのが、さっきのイヌイットの伝説だった。
「わたしの言った言葉が、魔法みたいに、ほんとうになってしまったんだと、思った」
桔梗さんは、何か得体の知れない力が自分の中に隠れていて、それが父の命を奪ってしまったのではないかと深く畏れた。自らの「奪命の詞」を畏れた、桜姫のように。
同時に、年光さんにどうしても「死なないで」と言えなかったことに対する激しい後悔の念もわきあがってきた。
彼女は次第に言葉を発することを怖れるようになった。
自分の放った言葉が、自分とかかわった人に害をなしてしまわないか、よからぬことが起きないか。
注意深く言葉を選ぶうちに、彼女はついに一言も発することができなくなってしまう。
「ママにはもちろん、お姉ちゃんにも、果林にも言えなかった。自分が思ってもみない言葉をふっと放って、何かよくないことが起こるのが、こわかった」
桔梗さんはうつむいてそう言った。
「だから、筆談もしなかったんだ?」
僕の言葉に彼女はうなずく。
「『青い鳥』に出てくる、未来の王国から、わたしは『魔法の言葉』を持って来たんだって、思ってた」
「それって、初めて話した時の!」
僕が思わず声を上げると、桔梗さんは僕を見て静かにうなずいた。
メーテルリンクの『青い鳥』。青い鳥を探してたくさんの国を巡り歩いたチルチルとミチルが最後に訪れる「未来の王国」は、これからこの世に生まれる、新しい命の国。
そこから「あけぼの」という帆船に運ばれて地上に生まれていく青いこどもたちは、未来の国から必ず何かを持って生まれなければならない。地上へ持っていくものは、こどもたちが自分で選ぶ。いいものも、悪いものも、それがどんなものかも知らずに。
桔梗さんは、知らずに自分が選んだものが、とてつもなく恐ろしいものなのではないかとおびえ、深く畏れた。
だから彼女は自らの力を呪い、死を願った。
自分の言葉が現実になるのなら、自分だけにその言葉を聞かせればそれが叶うと信じて。
そのために朝夕あの場所で一人たたずんでいたのだと彼女は言った。
いつの頃からか母の箪笥にあった白い長襦袢を身に着けるようになったのも、いつ死んでもいいようにと思ってのことだった。
「でも、死ななかった。死ねなかった」
彼女はそこで一度言葉を切って僕を見た。
黒目がちな瞳が、じっと僕をのぞきこんでいる。
「だって、わたしの言葉には、そんな特別な力なんて、元々なかったんだから」
桔梗さんは目を伏せてふっと息を吐いた。
「ずっともやもやしてた。なんで死ねないんだろうって。でも昨日、『乙女淵』を観て、やっとわかった。『魔法の言葉』も『奪命の詞』も、ない。だって、自分で身を投げないと、桜姫は死ねなかったでしょ? わたしは全部、七年前に観た『乙女淵』を、なぞっていただけだったんだ」
「でも、じゃあ今朝、僕に言ったことは?」
雨を「やませるために」祈っていたというあの言葉は、彼女が自らの特別な力を信じていたからではないだろうか?
「試してみたの。自分がわかったことが、本当かどうか。雨は、やまなかった」
「やんだじゃない」
僕の言葉に桔梗さんは首を横に振った。
「ううん、わたしが祈っている間には、やまなかった。それに、叶うかどうかも、本当は、どうでもよかった」
桔梗さんはそう言って僕の顔を見つめた。
「おととい、あなたといっしょに朝日を見たとき、もう死ぬのはやめようと思った」
少しはにかみながら彼女は言葉を継いだ。
「生まれ変わるの。わたしは、もう一度わたしになる。本当の言葉で」
そう言った彼女の瞳には、強い光が宿っていた。
桔梗さんが見せてくれた国語の教科書は、水菜さんが使っていたものだという。
ところどころに小さな字で書きこみがされているのはどうやら水菜さんの字らしい。真面目な水菜さんらしく、一字ずつ几帳面に書きこまれているのがわかる。
僕は、『言葉の力』というエッセイをはじめから読んでみた。
わかりやすい言葉で、言葉の起源の不思議から書き起こされ、聖書の言葉も引用しながら、言葉が意味を伝えることの不思議さを語っていく。
例えば、桔梗さんが「水」と言ったら、僕も「水」を思い浮かべることができる。しかし、「水」と「水という言葉」が「同じである」と誰もがわかっているのは一体なぜか。
それは誰が決めたのでもない、言葉の意味が、言葉よりも先に既に「あった」からだ。
毎日のように言葉を使っていながら、言葉なんてものがなぜあるのか、人間にはどうしてもわからない。
言葉を単なる道具だと思っていると、言葉からのしっぺ返しをくうことになる、とエッセイは続く。
言葉を信じていない人は、自分のことも信じていない。
うそをついてだまされているのは、実はうそをついている本人だけ。言葉とは、自分そのものなのだから。
「だからこそ、言葉は大事にしなければならないのだ。言葉を大事にするということが、自分を大事にするということなのだ。自分の語る一言一句が、自分の人格を、自分の人生を、確実に創っているのだと、自覚しながら語ることだ。そのようにして生きることだ」(註六)
読み終えると、僕は深く息を吐いた。
言葉は言葉、何とでも言えると僕は思っていた。心にもないことでも、言葉だけならいくらでも言える、と。
形だけの謝罪、うわべだけの反省、中身のない感謝──。
でも、言葉は、その奥に隠されている本心までも相手に伝えてしまうことがある。うまくだませていると思っているのは、実は表面を取りつくろっている自分だけだ。
SNSでの「友達」とのトラブルは、僕が僕の言葉を信じていなかったから起きた。僕は自分の言葉から復讐されたんだ。
じっと考え込んでいる僕を、桔梗さんが黙って見つめている。
「自分の語る一言一句が、自分の人格を、自分の人生を、確実に創っているのだと、自覚しながら語ることだ……」
「ふふ、それ、わたしも好きなところ」
僕が改めて声に出して読むと、彼女はうれしそうにほほ笑んだ。
「イヌイットの言い伝えを、どこで読んだのか探していたら、さっき見つけたの。すごい、そうだったんだ、と思った。わたしは、自分の人生を、創りそびれていたんだ。不思議なの、前に読んだ時には、なんとも思わなかったのに」
長い沈黙を取り戻すように、彼女は一言一言を自分で確かめながら僕に語る。
「わたしはずっと黙っていたから、今から頑張って、自分の人生を創らなきゃ。たくさん本を読んで、たくさん言葉を覚えたけれど、それだけじゃ、本当の言葉にはたどり着けない。届けなきゃ、誰かに。わたしの言葉を」
彼女は黒目がちな目を何度かまばたきさせながらそう言った。その表情は、思慮深く大人びているようにも、無邪気で幼いようにも見える。
「でも、なんでこの話を僕に?」
僕がそう尋ねると、桔梗さんは急に下を向き、両手をひざの上に置いて肩をすくめた。長い髪が彼女の顔を隠して表情が見えなくなる。
「──知ってほしかったんだ、わたしのことを」
桔梗さんはかろうじて聞き取れるぎりぎりぐらいの小さな声で答えた。
「あの、ありがとう!」
桔梗さんは急に大きな声でそう言うと、あわてて立ち上がって浴衣の裾が乱れるのも構わずにばたばたと部屋から出ていった。
あまりに急だったので、僕は座ったままその後ろ姿を見送った。
「一体なんだったんだろう……?」
僕は声に出してつぶやいてみた。自分の胸の中に、何かあたたかな感情が満ちているのを感じながら。
────────────────────
註四 池田晶子『死とは何か さて死んだのは誰なのか』(毎日新聞社刊)所収『魔法の言葉』より(初出は『伝え合う言葉 中学国語3』2006年度版 教育出版刊、池田晶子著『言葉の力』と併録された)
註五 池田晶子『死とは何か さて死んだのは誰なのか』(毎日新聞社刊)所収『言葉の力』より(初出は『伝え合う言葉 中学国語3』2006年度版 教育出版刊)
註六 註四に同じ
第七章 霊山(りょうぜん) 〈二〉
雲の隙間からだいぶ傾いてきた陽が射し込んでいる。雨上がりの空気はひんやりと冷たく、何か上に羽織るものがないとやや肌寒く感じるぐらいだ。昨日の昼間とはだいぶ寒暖の差がある。
僕は退屈をもてあまして、夕介と一緒に一足早めに二日目の開演準備が進められている宇侘八幡宮に来ていた。
水たまりは水を吸い取って砂で埋められ、板敷きは改めてきれいに拭き清められた。
舞台四隅の四本の青竹に渡された注連飾りも新しいものに取り換えられ、今は冷たい風に揺られている。
夕介が取材している間、僕も濡れた椅子を拭いてまわったりして準備を手伝った。
気の早い観客が場所取りを始めている。僕らも昨日と同じ辺りに座った。
準備の進む舞台の脇では、体操服姿の男女数人の小学生が集まって松岡さんたちから説明を聞いている。中学年から高学年ぐらいだろうか。その後ろには保護者と思われる大人の姿も見えた。
子どもたちはみんな少し緊張気味の面持ちだ。
「二日目は稚児舞から始まるんだ。『乙女淵』の後シテ・桜の精と同じ扮装で、四人の子どもが舞うそうだ。物語はなく、囃子方の演奏に合わせてお稚児さんだけで舞うんだが、もしかしたらこれは神楽舞からの影響かもしれないな。子方だけの演目なんて、他では聞いたこともない」
「男の子もいるけど?」
夕介の説明に僕は素朴な疑問をぶつけた。
「稚児舞も、元々は男子だけで舞ったらしい。女の子が入るようになったのは、過疎化が進んで子どもの数が減ったからだ」
「じゃあ、男子の女装が元々の形ってこと?」
「そういうことだ。猿楽は元来、男だけで行われるものだからな」
「なんだか倒錯的だなあ」
「『紫桜』にはないが、例えば『杜若』や『井筒』には、男装した女が登場する場面もある」
夕介はそう言ってにやにやする。
「昔から日本には男色の風習があったからな、猿楽の歴史の裏側には色々あったに違いない。さすがに俺にそんな趣味はないがな」
「あったら困るよ」
僕はオネエみたいにくねくねする夕介の姿を想像して思わずぞっとした。
大人たちの説明が終わって、小学生たちが鏡の間に入っていくのが見えた。
「そろそろ稚児舞の準備が始まるみたいだね」
「ああ。ところで、お前『幽玄』ってどういう意味だかわかってるか?」
「え? えーと……」
夕介に訊かれて僕は返答に困った。
何となくこんなもんかなというイメージはあるが、言葉では説明できない。
「言葉じゃうまく説明できないな」
「本当は知らないんだろ?」
腕を組んでにやにやしながら僕を見下した目で眺めまわす。夕介の悪い癖だ。
「失礼だな! わかるけど、言葉で説明できないだけだ」
「ふん、半分正解だ。言葉には表すことの出来ない深い趣や情緒を指して『幽玄』と言うんだ」
夕介はドヤ顔で続ける。
「『先ず、童形なれば、何としたるも幽玄なり』(註七)……世阿弥は子どもの姿なら何をしても幽玄だと書き残している。で、ここからは俺の勝手な仮説だが、『幽玄』ってのは、今風に言えば『カワイイ』だな。『萌え』と言ってもいい」
ずいぶんと大胆な仮説だ。
「いやー、いくらなんでもそれは飛躍しすぎじゃない?」
僕は首をかしげて否定したが、夕介は自信満々だ。
「ふふん、かわいいにも色々あるだろ? ブサかわ、キモかわ、コワかわ、何でもあり。『カワイイ』って言うときに、説明なんか不要だ。まして、子どもの姿なら無条件で幽玄だってあの世阿弥が言うんだから、間違いない」
「根拠がないぞ、根拠が!」
「そんなもん必要ない、俺は研究者じゃないからな」
僕が反駁するとそう言って夕介は腕を組んで歯を見せて笑った。
「ただ、そういう視点で『紫桜』を観たら、それなりに『カワイイ』要素があるだろう?」
「そうかな?」
僕は昨日観たいくつかの場面を振り返ってみた。
『桜堤』の前シテの舞は華やかだったし、人喰い鬼の正体が実は美少女だったという『寂水』の展開だって、そのギャップがすごい。『乙女淵』に至っては、地味な少女が華やかな桜の精に大変身……なるほど、言われてみれば確かにそうかも。
「高尚なものだと思って身構えて接すると、本質を見誤ることがある。既成概念から一度離れてみると、案外素直に理解できるかもしれないな」
「うーん、『カワイイ』かあ……」
納得したような、そうでないような。
夕介は調子に乗ってさらに続ける。
「ついでにもう一つ。猿楽に創作劇は少ないって教えたよな?」
「ああ、だから『紫桜』はレアだって」
「創作劇ではないってことは、つまりほとんどの曲は二次創作物なわけだ。有名な物語のエピソードの一部を、切り取ったり翻案したりしてそのエッセンスを強調する……そういう意味で言えば、猿楽は同人誌なんかと同じようなもんかもしれん。別に俺はそっち方面詳しいわけじゃないが」
僕はあきれて絶句した。
夕介はそんな僕の反応をにやにやしながら眺めまわす。明らかに面白がっている。
「例えば、能装束はリアリティーよりもあくまで見た目の美しさを優先している。『乙女淵』のワキは元武士の貧乏僧という設定だが、身につけているのは高価な絹の水衣。それでも観客は何の疑いも持たない。装束は過剰なまでに様式的かつ装飾的である一方、舞台装置はごくごく簡素だし、物語もシンプル。美しければ、かわいければ、かっこよければ、リアルでなくても許される。あえて言いかえれば、『カワイイ』がすべてに優先するデフォルメされた世界ってわけだ」
夕介は左手であごひげを撫でながら得意げな顔で続ける。
「伝統芸能と言っても、始まった時から伝統があったわけじゃない、結果として長い時間を生き延びてきたから今は高尚に見えるだけで、元々のところは庶民の娯楽……つまり広い意味でのサブカルチャーだったんだ。約束事がごちゃごちゃして面倒に見えるのも、その当時とは社会状況が変わって、当然共有できていた常識が変わってしまったからに過ぎない。まあ、猿楽の場合は観阿弥・世阿弥というエポックな人材が出現して、芸術の域にまで高められたわけだが、元をたどれば大衆向けのサブカルチャー、そうだな、今でいえば例えばアイドルやアニメなんかと大差ないのかもしれない」
なんだかむちゃくちゃな気もするが、妙に説得力がある。
「猿楽はいわば、六〇〇年前から続く、元祖オタク文化だ」
専門家から怒られそうな結論を、夕介は平然と言う。
「まさかそれ、記事に書くつもり?」
「くくっ、さすがにそれは無理だな。紙面が足りない」
夕介がそう言って笑った、その瞬間。
「わッ!」
「うわっ!」
「おおっ?!」
いきなり背後から大きな声がしたので、僕と夕介は思わずびくっと背中を丸めた。振り返ると、果林ちゃんが大笑いしている。
「あはははは、二人ともリアクションよすぎー! ウケるぅ!」
お腹を抱えて笑う果林ちゃんはクリーム色に紺色の英字の入ったスタジャンに、ミニ丈のグレーのキュロットスカート、紺のショートソックスにイエローのスニーカーというガーリーなスタイル。キュートだけど、やっぱり小学生みたいに見えてしまう。
「なんだ、果林か。おどかすなよ」
夕介があわてて平静を装うが、果林ちゃんの笑いは止まらない。
「おおっ?! だって! マジウケる!」
果林ちゃんにリアクションをマネされた夕介は、腕を組んで憮然としている。
「あー、びっくりした。意外に早かったね」
「じゃって家におっても退屈なんじゃもん。なーなー、二人並んで仲良く何話しよったん?」
「果林にはとうてい理解できないような高度な芸術論だ」
夕介がにやにやしながら返す。
「あー、夕介またうちのことバカにしよる! うちだってそれぐらいわかるもん!」
「そうか? ま、要約すれば、日本のハイカルチャーはサブカルチャーによる下剋上の歴史だ、ってとこだな」
「???」
にやにやと笑う夕介の言葉に、顔全体を疑問符にして首をかしげる果林ちゃんの様子がおかしくて、僕は思わず笑ってしまった。
「ところで果林、蘭さんたちは来るんだろうな?」
「うちは荷物があるけえチャリ(自転車)で来たけど、みんな後からゆっくり歩いて来るよ」
果林ちゃんはそう言うと、さっさとパイプ椅子に座りこんだ。
「あとで二人とも超びっくりするよ~」
「もう十分びっくりしたけど」
僕がそう答えると、果林ちゃんはあいかわらずにまにまと笑う。
「にひひ、もっとびっくりするいね。絶~っ対、ぶち驚くけえ」
「なんだよ果林、勿体つけずに教えろよ」
「教えーん! いじわるな夕介には絶対教えんもん」
夕介が尋ねると、果林ちゃんはぷっと頬をふくらませた。
果林ちゃんの持ってきたお菓子を食べているうちに、見所がだんだんとにぎやかになってきた。
まだ雲が残る空は、徐々に茜色に染まり始めている。太陽が雲に隠れると雲の輪郭がまばゆい黄金色の輝きを放った。
「森崎さん、夕介さん!」
水菜さんの弾んだ声がしたので僕は立ち上がってそちらの方を見た。
「水菜さん!」
僕は彼女に手を振って答えた。
ネイビーのスキニーパンツに黒のローファー、白いニットのチュニック、ベージュのショートコートに身を包んだ水菜さんが胸元で小さく手を振り返してくれた。まるでファッション誌のモデルのようだ。
背の高い水菜さんの後ろに小柄な二人の女性……一人はベージュに黒のラインの入ったひざ下丈のワンピースの上に、薄手の黒いトレンチコートを前開きのまま羽織り、ヒールの高い黒のミドルブーツをはいている。髪を下ろしているから一瞬わからなかったが、蘭さんだ。髪をなびかせコートのポケットに両手を入れて颯爽と歩く姿は、成人した娘がいるとはとても思えない。今まで和装しか目にしていなかったからとても新鮮に映る。
蘭さんの後ろに恥ずかしそうに隠れるようにして歩いてくるのは……こげ茶色のローファーに黒のタイツ、ダークブラウンのひざ上丈のフレアスカート、黒のTシャツの上に赤いチェックの厚手のシャツをまとい、長い黒髪をワインレッドのシュシュでポニーテールにした少女。
「え、あれ……?」
僕は自分の目を疑った。
僕の隣にいる夕介も声を出しかけて言葉を失っている。
「来た来た!」
果林ちゃんがうれしそうに駆け寄る。
「きぃねえちゃん、ほらこっちこっち!」
果林ちゃんは恥ずかしそうにしている少女の手を引いて僕らの前に連れてきた。
「な、びっくりしたじゃろー?」
満面の笑みを浮かべる果林ちゃんの隣でフレアスカートの裾を押さえてはにかんでいるのは……まちがいなく桔梗さんだ!
「そのカッコ──」
夕介がやっとのことで言葉をしぼり出した。
「うちの貸したげたんよ。サイズぴったし! おっぱいだけはきぃねえちゃんの方が大きかったけど。なー、ぶちかわいいじゃろ?」
果林ちゃんが自慢げに言うと桔梗さんは真っ赤になってうつむく。
「桔梗が自分から果林に頼んだんです、服を貸してほしいって。わたしも一緒になって選んだんですよ」
水菜さんがうれしそうに教えてくれた。
僕も夕介もあ然として桔梗さんの姿を眺めていることしかできない。
「一体何があったんかねえ? どうしたんって聞いても教えてくれんのですよ。せっかく久しぶりに私もおめかししたのに、完全に負けちゃった」
茶目っ気たっぷりにそう言って蘭さんは意味ありげに僕に微笑した。
「おい森崎、何か言ってやれよ」
夕介が僕に耳打ちする。
「あ……すごくかわいいよ。びっくりした」
僕がそう言うと、桔梗さんは上目づかいでちらりと僕を見て恥ずかしそうに笑った。
────────────────────
註七 花傳第一 年来稽古條々 上より(引用は岩波文庫『風姿花伝』野上豊一郎・西尾実校訂から)
第七章 霊山(りょうぜん) 〈三〉
篝火に火が入ると、見所に静かな緊張感が流れ始めた。
西の空は夕焼けですっかり茜色に染まり、わずかに残った灰色の雲を間に交えながら上空に向かって濃い藍色へと変化する美しいグラデーションを描いている。
鏡の間の裏側から男女数人の大人が出て来て脇正面の後方に控えた。中にはカメラを携えている人もいるから、きっと稚児舞に出る子どもの親たちだろう。
「妹尾君、今日もよろしゅう頼みます」
黒のスーツ姿の男性が夕介に声をかけてきたと思ったら松岡さんだった。臙脂色のネクタイを締め、羽織袴の時とはまた違った雰囲気だ。
「いよいよ千秋楽ですね、楽しみです」
夕介は松岡さんに笑いかけた。
蘭さんが立ち上がって松岡さんに頭を下げる。
「松岡さん、いつもお世話になります」
「いやいや、こちらこそ。ほんに、蘭ちゃんはようやってじゃ、もうすっかり経営者の顔じゃね。ネンコーさんもあの世で喜んじょってじゃろうじゃ」
「恐れ入ります。松岡さん、今日は出演されんのですか?」
「はは、年寄りがいつまでもでしゃばっとったらいけんけえな、世代交代ですいね。今日のシテは『寂水』でワキを務めた稲村君が務めます」
「ああ、ひとみちゃんのご主人!」
「そうそう、稲村君もよそから来ちゃったけえ、前回はネンコーさんと一緒に裏方じゃったなあ。もしネンコーさんがおったら、どっちがシテを演るか、競り合うとこじゃったろうがなあ」
松岡さんはそう言って笑った。その横顔はどこかさびしそうにも見える。
「年光は目立ちたがりでしたからね、若い稲村さんに主役を取られて悔しがってますよ、きっと」
「はは、確かに」
蘭さんが穏やかにほほ笑みながら答えると、松岡さんは声を上げて笑った。
「そういえば、今日は桔梗ちゃんは来とらんのかね?」
松岡さんが僕らを見まわして尋ねた。
「いいえ、来てますよ。ほら、あなたたちも松岡さんにごあいさつなさい」
蘭さんにうながされて姉妹も立ち上がった。僕だけ座っているのも変なので、僕も立ち上がる。
「こんにちは松岡さん、昨日せっかくけんかを止めてくださったのにごめんなさい」
最初に水菜さんが昨日の非礼を詫びた。
「いやいや、きょうだいっちゅうのはけんかして当たり前じゃけなあ、気にせんでええよ水菜ちゃん」
「あんなー、みず姉あのあと当分はぶてとったんよ」
「あ、こら果林、それ言うな!」
「にひひ、すぐはぶてるもんね、みず姉」
「もう、果林!」
「……お姉ちゃん、またけんかしてる」
桔梗さんに指摘されて水菜さんは急に恥ずかしそうに下を向いた。
「ほ、こりゃあたまげた、ははは」
ポニーテールの少女が桔梗さんであることに気づいて、松岡さんは目を白黒させた。
「桔梗ちゃん、昨日とは別人じゃなあ!」
三人を見比べながら松岡さんは顔をほころばせる。
桔梗さんはじっと松岡さんの顔を見つめていたが、急にすっと頭を下げた。
「あの、ありがとうございました」
松岡さんはまじまじと桔梗さんを見返した。
「わたし、気づいたんです、自分の間違いに。昨日の舞台を観て」
「ほう?」
「わたしは、ずっと信じ込んでた──桜姫みたいに。自分の言葉は、『奪命の詞』なんだって。それがパパを死なせたんだって、ずっと、ずっと思い込んでた」
桔梗さんはそこで一度目を伏せた後、改めて顔を上げて松岡さんをまっすぐに見つめて続けた。
「でも、『奪命の詞』なんて、本当は、ない。それが、わかったんです。だから、ありがとうございました」
そう言うと、桔梗さんはもう一度松岡さんに頭を下げた。
みんなが桔梗さんをじっと見守っている。
松岡さんは一瞬当惑したような表情を見せたが、ちょっと考えて桔梗さんが何を言おうとしているのかがわかったようだ。
「桔梗ちゃんは賢い子じゃ。七年前と何も変わっちゃおらんね。おじさんもうれしいよ」
そう言って松岡さんは桔梗さんの肩をぽんぽんと軽くたたいた。
鏡の間から細い笛の音が流れ始める。
「さ、そろそろ稚児舞が始まる。ゆっくり観ていきんさい」
松岡さんはそう言って姉妹に手を振ると、鏡の間の方へ歩いていった。
調べがやむと、揚げ幕が半分開いて囃子方が三人、ゆっくりと歩いてアト座に上がった。笛、小鼓、そして大鼓を小脇に抱えているのはあの武骨漢・伊藤さんだ。
おのおのが所定の位置につき、身支度を整え終えて一呼吸置くと、笛が穏やかな旋律でゆったりと唄い始めた。
揚げ幕が上がり、四人の子どもがしずしずと橋掛りを進み始める。
四人とも子どもサイズながら『乙女淵』の後シテと同じ、桜の紋様が織り込まれた白の長絹に緋大口という出立だ。長絹の袂には舞扇を挿している。
先頭に立っているのは男の子で、長い黒髪の鬘に白蓮の天冠を載せている。白粉をつけ、唇に紅をさした顔は、緊張のためか硬くこわばっている。
続いて女の子が二人、最後にもう一人、同じく長い黒髪の鬘を着けた男の子。後ろの三人は天冠を載せていない。
「あれ、桜の作り物がない」
水菜さんが小さくつぶやくのが聞こえる。
「確か、七年前には桜の作り物が真ん中にあったよね?」
水菜さんが桔梗さんに小声で尋ねると桔梗さんが黙ってうなずいた。
舞台の上では四人の子どもが所定の位置につく。
先頭の天冠を載せた男の子が正面に立ち、四人は舞台の各辺の中点に立った。
袂に挿していた舞扇を右手で身体の正面に持ち、軽く左手を添えている。
正面の男の子は舞台に上がり始めた時からずっと硬い表情のままだ。だいぶ緊張しているようだ。
無理もない、普段身につけない装束、それも女の子のかっこうをして大勢の観客の前に出るのだから、緊張と恥ずかしさは頂点に達しているだろう。
大小の鼓がやや控えめな掛け声と共に打ち鳴らされ始め、子どもたちは笛の音に合わせてゆったりと舞いはじめた。
いや、正面の男の子が立ち尽くしたままだ。
緊張のあまり頭が真っ白になってしまったのだろうか、ほとんど泣きそうな顔だ。
他の三人は閉じたままの舞扇を前に捧げ持ち、その場で右回りにゆっくりと回るが、彼だけは身動きが取れずにいる。
急に桔梗さんが立ち上がった。あっけにとられる水菜さん、果林ちゃんの前を横切って通路に出る。
桔梗さんは正面の男の子ににっこりとほほ笑みかけると、フレアスカートの裾を翻してくるりと舞台に背を向けた。
そのまま、右手を前にかざす。舞台上の子どもたちと同じ所作だ。
鼓のリズムに合わせて、桔梗さんはゆっくりと左に向きを変える。砂を踏む音が、僕の耳に届く。
正面で立ち尽くしていた男の子が、桔梗さんに倣ってぎこちない動きで左に向きを変えた。
桔梗さんはその場でゆっくりと一回りしながら右手を胸元に引き寄せ、元の向きに戻ると、両腕を大きく横に広げた。
男の子もそれに続く。
後ろの三人が安心した表情になった。
桔梗さんは今度は右腕を正面に伸ばし、左手を添えた。
舞台上の子どもたちも同じ所作で舞扇を広げ、正面の男の子も少し遅れながらもそれに従った。
四人の金色の扇には、桜の古木に赤い日輪が描かれている。『乙女淵』のシテが持っていたものと同じ柄だ。
桔梗さんは淡々とした表情のまま、見えない舞扇を広げた形のまま、摺足で左回りに回る。そうか、直面……自分の顔を面として演じているんだ。
右に、左に、ゆったりと、たおやかに。
僕はただ茫然と桔梗さんを見上げていた。
間近に彼女の長い呼吸を感じる。
少し遅れて桔梗さんの動きを追いかけていた男の子の動きが、他の三人と合いはじめた。だんだんと呼吸がつかめてきたようだ。落ち着いてきたのか、表情からも硬さが取れてきた。
囃子方の演奏も徐々に熱を帯びる。
扇をかざして舞台上の桜の精たちは舞う。
その舞と寸分のずれもなく桔梗さんも舞う。
両腕を広げて摺足でゆっくりと数歩前に進んだ後、桜の精たちは両手で舞扇を前に捧げ持って弧を描くようにして舞台の中央に集まった。
その形のまま、何もない空間を中心にして四人が円を描く。桔梗さんもその場でゆっくりと一回りした。
桜の精たちは正面を向くと今度は左手に舞扇を持ちかえて高々と掲げ、右腕を前に伸ばして内から外へくるりと回す。長絹の長い袖が腕に巻き取られたと思ったら、今度はまた逆にくるりと回してすぐに袖をほどいた。
満開の桜の花の下、思うままに舞う桜の精たち。
作り物がなくても、舞台の上は暖かな春の日差しが差しているように感じられる。
四人は再び弧を描くようにして元の位置に戻る。
舞扇を正面に構えて右回りに回った後、左手を添えてゆっくりと扇を閉じた。
笛の音がふっと止み、子どもたちは閉じた扇を右手に持ち、身体の前で左手を添えた最初の形に戻った。同時に桔梗さんも同じ形になって動きを止める。
長い掛け声の後、小鼓が舞の終わりを告げるように短く鳴った。
桔梗さんは一呼吸置いてから再びくるりと舞台の方を向いた。ポニーテールにした彼女の長い髪がはらりと舞う。
男の子が上気した顔で桔梗さんを見つめると、桔梗さんは小首をかしげてにっこりとほほ笑んだ。
「すごーい、きぃねえちゃん覚えちょったん?」
幕間に入って、興奮冷めやらぬ様子で果林ちゃんが桔梗さんに尋ねると、彼女は小さくうなずいた。
水菜さんがまぶしそうな顔で桔梗さんを見つめている。
「桔梗、優しいね。あの子にお手本を見せてあげたんだよね? わたしだったら、多分思いつかなかったな」
水菜さんの言葉に桔梗さんは恥ずかしそうに下を向いた。堂々と舞っていたさっきまでの様子とはまるで別人のようだ。
「すまんが、桔梗の舞う姿を何枚か撮らせてもらった。思うより先に身体が勝手に動いてな。こんなことはめったにない」
夕介も少し興奮した様子だ。カメラを両手に抱えたまま、じっと桔梗さんを見つめている。
「美しかった。他に言葉がない」
夕介はそれだけ言って天を仰いだ。
僕も何か言いたかったが、言葉が出てこない。ただ、胸の中にあたたかな気持ちがじんわりと満ちているのはわかる。
「心のこもった舞じゃったね。きれいじゃったよ、桔梗」
「なんか、じっとしていられなかったの。あの子がかわいそうで」
蘭さんがうれしそうにほほ笑むと、桔梗さんは頬を染めながら蘭さんにほほ笑み返した。
「やっぱり、桔梗は桔梗じゃね。全然変わってなかった。優しい桔梗のまま」
蘭さんはそう言って桔梗さんの肩を抱き寄せた。
桔梗さんは肩をすくめて一瞬くすぐったそうな顔をしたが、ふっと息を抜いて安心した表情を見せた。
「……ごめんね、今まで何もしてあげられんで。誰にも言えんと、長いことずっと一人で抱えちょったんじゃね」
「ううん、ママのせいじゃない。もっと早く気づけばよかった……ママ、今までごめんなさい」
桔梗さんが蘭さんの腕の中でつぶやく。
「ええんよ、気づいたんじゃけ。それでもう十分」
そう言うと、蘭さんは目を閉じて桔梗さんを抱きしめる腕の力を強めた。
「歩きだすのに、遅すぎるいうことはないんじゃから」
「うん……」
蘭さんの言葉に、桔梗さんはそっとうなずいた。蘭さんの目にはうっすらと涙が光っていた。
第七章 霊山(りょうぜん) 〈四〉
細く長い笛の調べが、最後の舞台の開幕を告げ始めた。
辺りはすっかり夜の闇に覆われ、投光機の光の中、舞台の注連飾りが風でかすかに揺れ続けている。
虫の音に混じって、時折篝火から火の粉のはぜる音が届く。
見所は水を打ったように静まり返って、じっとその時を待っている。
松岡さんが鏡の間の脇に立って、舞台を見つめている。彼は今、何を思っているのだろう。
僕の前には三姉妹と蘭さんが仲良く肩を並べて座っている。右から蘭さん、桔梗さん、果林ちゃん、一番左に頭一つ抜けて水菜さん。四人の背中はなんだかほっこりとしたあたたかさを感じさせる。
夕介は僕の左後ろの通路に立ち、真剣な顔でじっと舞台をにらんでいる。
今、それぞれがそれぞれの思いを抱えて、舞台が始まるのを待ち構えているのだろう。
僕はなんだか不思議な思いにとらわれていた。
ほんの数日前までは顔も名前も知らなかった人たちが、今は僕にとって親しい人たちになっている。
もしも僕がここに来なければ、桐葉荘を宿に選ばなければ、出会うことのなかった人たち……本当に不思議だ。
調べがやむと、揚げ幕が半分開いて囃子方が橋掛りを進み始めた。
大鼓の伊藤さんを含む、稚児舞で演奏した三人に、さらに太鼓が加わっている。
アト座の後方からは後見と地謡方が舞台に上がる。
地謡方はこれまでどの舞台でも五人だったが、今回は倍の十人が舞台に上がった。中には顔なじみの青笹さんの姿も見える。
地謡方は五人ずつ二列に並んで着座した。
後見は『乙女淵』の時と同じ人が務めるようだ。
松岡さんが言っていたように、これまでの座の枠にとらわれない人選だ。
舞台の上には何も置かれない。
夕介によると、桜の作り物は昨夜の雨で無残な姿になってしまい、一日では修復出来ないので、今日は作り物を使わずに舞台を進行することになったそうだ。
あるはずのものがない舞台が一体どのような展開になるのか、僕には想像もつかない。
舞台の上に十五人の男たちが上がり、張りつめた空気は最高潮を迎える。
それを破っておもむろに小鼓が抑えた掛け声と共に打ち始め、伊藤さんの大鼓がそれに続いた。
揚げ幕が上がり、まずはワキが登場する。
紫色の水衣を身にまとった僧形……つまり身分の高い僧侶ということになる。二人の従僧をワキツレとして従えるのは、昨日『乙女淵』でワキの旅僧を演じた男性だ。
桜花 散り交ひくもれ 老いらくの
来むといふなる 道まがふがに
在原業平が「四十の賀」で詠ったという和歌を朗々と謡いつつ、三人の僧がゆっくりと橋掛りを進んでいく。
昨日初めて観たときにはかなり遅い動きに感じられたが、僕の方も猿楽の悠然としたリズムにだいぶ慣れてきた。
これは都の僧にて候
西國に 紫の桜の花咲くありと聞き及び候
一目見ゆれば 天命を延ぶと聞く
珍しきものゆゑ されば此目にて確かめんと 西へ下りて候
同じ僧でも『乙女淵』の元武士の貧乏僧とは違い、こちらは都の高僧だ。
目にすると寿命を延ばすという紫桜のうわさを聞きつけて、自分の目で確かめたいとわざわざ都から下って来たのだと声高らかに述べる。
ワキツレが続けて、紫桜の咲く場所を仔細に尋ねたが、定かならぬと述べた。
ある者は桜堤に咲いたといい、ある者は宇侘八幡の一隅に咲くという、またある者は乙女淵に咲いたと述べたが、いずれがまことかは皆目わからぬ、と。
折しも満開の桜が咲き乱れる頃だが、だんだんと夕闇の迫る中、僧たちは紫桜の咲く場所を探しあぐねて途方に暮れてしまった。
その時、一行は一人の老婆と出会う。
笛が穏やかに唄い、揚げ幕が上がって前シテが橋掛りに姿を現した。
柔和な顔立ちの老婆の面に白髪の鬘、茶系の渋い色合いの小袖を着流しにした上にこれまた落ち着いた色合いの水衣を合わせ、地味だが品のよい装いだ。
シテを演じているのはまだ三十代の稲村さんのはずだが、少し腰を曲げてゆっくりと橋掛りを歩く姿は老人そのもの。ものまね芸を発祥とする猿楽ならではの表現だ。
老婆は本舞台に上がり、正面左奥のシテ柱のそばに座っている。
高僧が老婆に気づいて、従僧の一人にあの老女に紫桜のことを尋ねるよう命じた。
これなる鄙の人に 尋ね申すべきことの候
これは都より遥々下りし者にて候
こなたは 天命を延ぶと云う 珍しき紫桜の
何処に咲けるかを 存知なるか
従僧のもの言いにはどこか傲慢な調子が混ざっているようだ。大きな声で老婆に尋ねるが、彼女は答えない。
尋ねたきことのあれば
尋ねたき者の 尋ぬるべきにてやあらんずらん
老婆は従僧には答えず、ひとりごちた。聞きたいことがあるなら聞きたい者が聞くべきだろう、と。
これを耳にした従僧は腹を立てた。
高僧の所に戻ると、気難しい老婆で聞こえないふりをしている、ここはひとつ狼藉してでも聞き出すべきではないか、と奏上すると、もう一人の従僧もそれに同調する。
が、高僧はさすがにそれを押し止めた。
仮にも仏法を奉ずる者が狼藉などするものではない、聞きたい者が聞けと言うなら私が尋ねてみよう、と彼は立ち上がると老婆のもとに歩み寄った。
こなたは紫桜を存知なるか
これは都より紫桜を求め 遥々鄙へ下り来る身ゆゑ
存知なれば 是非に是非にお教え候へ
高僧はばかていねいな所作で老婆に尋ねる。
老婆はちらりと高僧を一瞥したが、やはり何も言わない。
老婆の無礼な振る舞いに高僧は一瞬気息を乱すが、さも落ち着き払ったふうを装って重ねて尋ねる。
お教へ給はば
所望のものを とらせ仕らん
重ねて重ねて お教え候へ
老婆は、教えてくれれば好きなものをくれてやろうと言う高僧を改めてちらりと見ると、軽くあごを上げた。ふっと笑ったように見える。
紫桜とは
見及び候こともなくば
聞き及び候こともなく候
御僧の聞き違いにてや あらんずらん
紫桜など見たことも聞いたこともない、あなたの聞きまちがいではないか、と老婆は言い放った。
従僧二人があわてて高僧のそばに駆け寄る。
この老婆、我ら仏に仕える者を愚弄すると大きな罰をかぶるぞ、と脅すように言いそやすが、老婆は気にも留めていない様子だ。
すっと立ち上がると摺足で舞台正面へと移動する。三人の僧はそれを目で追いながら舞台の右側に移動した。
老婆は袂に挿していた舞扇を広げると、おもむろに舞いはじめた。
舞扇の柄は、『桜堤』と同じ、川辺の老桜。
地謡方がそれに和すように謡いはじめ、さらに笛の音が重なる。
満開の桜の下で老婆は舞う。
もちろん地謡方がそう謡っているだけで、桜の作り物もないから、何もないところで舞っているに過ぎない。しかし、舞台の上には暮れ際の薄光の中で舞い落ちる桜の花びらが見えるような気がする。
大小の鼓の音に合わせて老婆はたおやかに舞う。見えない桜の花を愛でるかのように、いとおしむかのように。若女のような華やかさはないが、抑えた動きの中に、長い歳月を生き抜いてきた静かな生命力を感じさせる。
高僧の一行はあっけにとられた様子で老婆の舞を眺めている。
やがて、老婆は見所に背を向けて舞をやめた。
すっと扇をたたむと、そのまま橋掛りを進んでいく。
かくて鄙人老姥の
舞ひて御前を立つと 見えつるが
花散り曇る 桜木に
寄るかと見せて失せにけり 寄るかと見せて失せにけり
地謡方が、老婆は桜の木に近寄ったかと思うと散りゆく桜の花に紛れて消えてしまったと謡い、前シテは揚げ幕の向こうに消えた。
なんだか痛快だ。
どこか傲慢な振る舞いをする都の高僧らを煙に巻いて、老婆は自らの舞を舞ってみせ、ふっと消えてしまった。紫桜なんて、見たことも聞いたこともない、と言い残して。
しかし、だとしたら今までの三幕で桜姫の命と引き換えに咲いたとされる紫桜は、一体どうなってしまうのだろう?
なんだか先の展開が見えない。
舞台の上にはアイがやって来て名乗りを上げた。
自分はこの里に住まう者である、都から身分の高い僧の一行がこの里にお越しになったと聞き、我が家にお招きしようと探しているのだが見当たらぬ、早や日も暮れたゆえ諦めて帰ろうと思う、と里の者は語った。大げさな身ぶりで困惑してみせ、高僧をお泊めしたならば自分にも大きな利益があるだろうに惜しいことだ、などと下世話なこともつぶやいている。
ちょうど途方に暮れていた高僧が通りかかった里の者を見とがめた。魚心あれば水心、両者の思惑が合致して、高僧らは里の者の家に泊まることになった。
従僧が里の者に紫桜について尋ねる。
寿命を延ばすという紫色の桜を求めてこの里に来たが、ついに見つけることができなかった、あなたは知らないだろうか、と。
里の者は首をかしげて言う。年寄りの昔語りとして聞いたことはあるが、自分は見たことがない、と。
従僧は、先ほど老婆に尋ねたところそんなものは見たことも聞いたこともない、聞きまちがいではないかと言われたが、まことだろうかと重ねて問う。
里の者はやはり首をかしげる。が、急に立ち上がって、そういえばあの辺りには一人の老婆が何十年と住んでいた、と言う。里の者らとはかかわりを持たず、子どもらは鬼婆ではないかとおそれていたが、どこの誰ともわからぬまま、昨秋ひっそりと死んだ。御僧が出会ったのは、あの老婆の霊ではないだろうか、と里の者は言うが、高僧らは顔を見合わせただけだ。
夜も更け、僧らは眠りについた。
アイとワキツレ二人は橋掛りを歩いて退場していった。
舞台の上には高僧一人が舞扇を枕に見立てて額に当て、座った形で残っている。
ここからは高僧の夢の中の場面だ。
小鼓がゆっくりとしたリズムを奏で始めた。そこに伊藤さんの大鼓が鋭く重なり、揚げ幕が上がった。
紅入の小袖を着流しにした上に、白い水衣をまとった若い娘姿の後シテが橋掛りに姿を現す。
これは桜姫だろうと僕は直感した。
もの思ふと 過ぐる月日も 知らぬまに
年もわが世も 今日や尽きぬる
娘は橋掛りを進みながら朗々と和歌を詠う。今度は『源氏物語』からの引用だ。
光源氏が死を前にして詠んだ覚悟の和歌らしい。物思いにふけっているうちに知らぬ間に月日は過ぎ去ってしまい、今年も私の命も、もう今日にも尽きてしまうのであろう、といった意味だそうだ。
娘はシテ柱のかたわらに立って正面を向いた。
さても深業の御僧かな
天命を延べて何とする
娘は開口一番、やれやれ業の深い坊さんだ、寿命を延ばしてどうしようというのか、と高僧に対して厳しい言葉を投げかける。
僧は思わず居住まいを正し、さてはあの世からの遣いが年若い娘の姿で自分の前に現れたのか、とおそれおののいた。
娘は舞台の正面に移動し、御僧は沓懸山の戦のことを存知であるか、と問う。
私は都から旅をしてきた身である、数多あった戦のひとつひとつについて仔細を知ることはない、と彼は答えた。
娘はやや顔を伏せて右手を顔の前にさしかけた。
あれほど激しい戦であっても、何十年と経てば憶えている者もなければ識っている者すらもなくなる、哀れなことだ、と彼女は泣いた。
娘が扇を広げると、笛が哀しげな旋律を奏で始めた。
草木繁る沓懸の つはものどもの今生の
残る無念は 止みもせず
物冷まじき 雨の折
幽かに聞こゆ 鬨の声
翻りゆく 旌旗見つ
地謡方が、冷たい雨が降ると敗死した将兵たちの無念が古戦場に鬨の声と響き、幻の旗指物となって翻る、と重々しく謡い、娘は舞扇を前に捧げ持ってゆっくりと舞う。
高僧はじっと娘の言葉に耳を傾けている。
あらあはれやな
今はこの世に 亡き跡の
さても無慙や 敗れける
父は草生ひ茂りたる かの塚の
土の下にこそありてけり
自分の父は敗死して春の草が生い茂る塚の下にいる、と娘に和して地謡方が謡った。
高僧が娘の正体を怪しんで、あなたはいったい誰なのかと尋ねる。
娘はしばし口を噤んだ後、おもむろに、私は沓懸の山で滅んだ武将の娘・桜姫であると名乗った。
桜姫は続けて、私は昨秋、名もなき老婆として一生を終えたが、御僧に頼みたいことがあると告げる。もしもその願いを聞き遂げるのなら、あなたの望む紫桜を見せて差し上げよう、と。
高僧は、さてはこの姫は先の老婆の霊かと合点して、一も二もなく承諾した。
桜姫は、これから一さし舞いつつ物語るので、それを聞き伝えるようにと彼に頼んだ。
高僧は承ったと返事をし、聞きもらすまいと耳をそばだてる。
その様子を確かめると、桜姫は舞扇を掲げてゆっくりと舞いはじめた。
第七章 霊山(りょうぜん) 〈五〉
妾の父は義を貫いて戦に挑み、
空しく倒れ、草深き塚の土となり果てた。
これより後、
風に靡く葦の如く寄辺のない妾は
一体何を便に生きればよいのだろう。
既に母は亡く、
二人の弟は行方も知れず、
妾一人のこの命、何を惜しむことがあろうか。
空しく生きるぐらいならば、いっそ潔く散ればよい、
春の夜に咲く桜花の如くに。
妾は身を投げんとして、高き巌の汀に立った。
しかし、
妾が死んで、何となる?
父を奪った者たちは、所領を広げ、春を謳歌している。
父は茫茫と生い茂る草の下で
冷たい塚の土となってしまった。
仇を討つ、そのためには鬼にでもなる、と妾は決めた。
蛇身となり果てようとも構わぬ、
堕地獄をも怖れぬ。
妾は地に伏して父の仇を討つ機を窺う、蛇蠍のごとくに。
それのみが妾の生きる便。
いつしか、
生きるために妾は恨み、
恨むために妾は生き、
遂には父を忘れ果てた。
狂女となった妾は、
捕えられ、嘲られ、
仇も討ち果たし得なかった。
妾は郷里を離れた。
妾の知らぬ処へ、妾を知らぬ処へ。
妾は石のごとく固く口を噤んだ。
誰にも知られぬように、誰をも知らぬように。
そうして幾年も、幾年も、私は過ごした。
誰にも知られぬように、誰をも知らぬように。
妾を呼ぶのは誰か、
懐かしい声で、私を呼ぶのは誰か。
ああ、その声は、まさに慕わしい
我が父ではないか。
父は死んでなどいなかった、
確かに妾を呼ぶではないか。
そう思ったところで、妾は現に還った。
夢であった。
現に還った妾は、幾年かぶりで己の姿を見た。
花のごとき乙女であった妾は、
いつ知れず芒のごとく
みすぼらしい女となり果てていた。
蛇身となれず、
さりとて人として生きることも叶わず。
夢であるなら、現になど還らねばよかったものを。
いや、凡てが夢であればよかったものを。
生きながらに地獄の責め苦を受くるがごとく、
地に呑まれてしまうのではないかと思われるほどに
この身が重い。
このまま地に呑まれた方が、どれほど安楽だろう。
生きることもできず、死ぬこともできず、
ただ、苦しみ、蛇のごとくに地を這うのみ。
妾には、地を這う我が姿が見えた。
その傍らに、それを見降ろしている男の姿が見える、
ああ、それは我が父ではないか。
父は悲しい貌で、悲しむ妾を見ていた。
父は、悲しむ妾を見て、悲しんでいた。
悲しみが消えることはないが、
それは時と共に薄紙を剥ぐがごとく癒えた。
それでも、悲しみは不意に襲い来る。
その度に
父は妾の傍らで、私が悲しむのを悲しんだ。
妾は生きることにした。
父は常に妾の傍らにある、
何を怖れることがあろう。
名もなき女として生涯を終えればよいと妾は望み、
そして、それは成就した。
所願満足。(註八)
皆已具足。(註九)
……
桜姫は自らの半生を謡いつつ舞った。
舞いこそが彼女の詞。
言葉の意味はよくわからなくても、桜姫が何を語りかけているのか、ありありとわかる。
絶望の舞、怒りの舞、苦しみの舞……しかし、最後に絶望から生きることを選んだ物語を語り終えた桜姫の顔は、晴れやかに輝いて見えた。名もなき老婆として一生を閉じたことに、誇らしさすら感じさせるほどに。
僕は、全身に静かな漣が走るような感覚を覚えた。
苦労の多い一生であったのかもしれない。しかし、桜姫が不幸であったとは、僕にはどうしても思えなかった。
静かに舞をやめた桜姫は、舞扇を閉じると僧に背を向けた。
僧が、ふと我に返る。
のうのう 待たれ候へ
御約束にて候ぞ
紫桜を 紫桜を、御見せ候へ
桜姫は此岸を去って彼岸へ行こうとしている。約束が違う、と彼は憤った。
しかし、桜姫は僧に背を向けたまま告げる。
已に紫桜は 御身の目の当たりにて候ぞ
見むとせざれば 見ゆることなく候
すでに紫桜はあなたの目の前にあります、見ようとしなければ、見えないのです、と言い残し桜姫は橋掛りへと移った。
去りゆく桜姫と地謡方とが掛け合いをするようにゆっくりと謡う。
此岸と謂ひ 彼岸と謂ふも
ただ同じ河の 岸辺にて
河の魚には 自他彼此なし
流るる河水の あるのみか
隔てと見つるは 人の習ひ
花もまた 咲くのみが花にあらず
散るも花なり
実生も花なり
此岸も彼岸も同じ河の岸辺であり、魚にはただ流れる河の水があるに過ぎず、それを隔てられたものと見るのは人の見方でしかない。花も、咲くだけが花ではなく、散るのも花だし、種から芽が出てやがて成長するのも花である。
去りゆく桜姫の背中に向かって、十人の地謡方が力強く謡う。
僕はその声に惹かれて地謡方を一人一人眺めた。異なる声が一つに重なって、舞台から圧倒的な力を発する。
げに紫桜は 身の裡に
身の裡にこそ 咲けるなり
最後に、地謡方の後列一番奥に座っている男性に目が向いた。
青笹さんの目立つ頭の向こうで揃いの羽織袴に身を包み、少し肩をいからせながら脇正面をにらんで謡っているのは……年光さんだ!
げに紫桜は身の裡にこそ咲けるなり、と地謡方が朗々と繰り返す。
下がり気味の目に鋭い光を宿し、真剣な表情で年光さんも謡う。
地謡方の声が、空気を震わせて僕に届く。その声に共鳴するように僕の身体の内側が静かに波立つ。
笛が澄み切った高い音で唄う。
舞台上の僧が立ち上がり、桜姫を追うように一・二歩前に進んだが、思いとどまって立ち止まった。
揚げ幕が上がり、桜姫は静かにその中に消えた。
地謡方に目を戻すと、確かにいたと思った年光さんの姿はなかった。
まばたきしてもう一度見直したが、後列の一番奥に座っているのは青笹さんだった。
僕は幻を見たのだろうか?
舞台の上で正面を向いて立ち尽くす僧のように、僕もしばらく放心して何も考えることができなかった。
────────────────────
註八 「願うところは満ち足れり」と読み下す。神仏に対する祈りが具現化すること。
註九 法華経方便品第二「如来方便。知見波羅蜜。皆已具足。」より。「皆已に具足せり」と読み下す。如来は衆生を導くための方便と智慧とを皆すでに具えている、という意。
第七章 霊山(りょうぜん) 〈六〉
「結局、紫桜なんてなかったんだろうな」
夕介がカメラをアルミケースにしまいながらぽつりとつぶやいた。
舞台の余韻の中、松岡さんのあいさつが終わって、観客は三々五々帰り始めている。
「そうかな?」
僕はちょっとムッとして夕介に言い返した。
「見ようとしなきゃ見れないって桜姫は言ってたじゃないか。何もなかったとは思えないけどな」
「そうですよ、わたしは森崎さんの方が正しいと思います」
水菜さんが僕の味方をしてくれる。
「でも、じゃったら紫桜って結局なんじゃったんかね? うちにはようわからんなあ」
果林ちゃんが両手を頭の後ろに組んで背中をそらしながらつぶやいた。
「いのち……」
「桔梗さん?」
桔梗さんは僕をまっすぐに見つめている。
「わたしは、紫桜は、いのちの花だと思う」
「いのちの花──」
僕は彼女の言葉を繰り返した。紫桜は、生命の花──。
ふと顔を上げると、帰り始めた観客の間をぬって、体操服姿の男の子がこちらに向かって見所を走ってくる。
男の子は僕らの前まで来ると、息を弾ませながら桔梗さんに勢いよく頭を下げた。
「ありがとうございました!」
彼は二・三秒そのままの姿勢でいたが、また勢いよく頭を上げると、顔を真っ赤にして走り去っていった。ちょっとスキップ混じりの、軽やかな足取りで。
「あれ、さっきのおちご舞の子だ」
水菜さんがつぶやく。
「顔、真っ赤だったね」
「うふふ、桔梗が初恋だったりして♪」
蘭さんが桔梗さんをからかうと、彼女は恥ずかしそうに下を向いた。
「にひひ、きぃねえちゃんかわいー♪」
「んー……」
調子に乗って果林ちゃんも桔梗さんの腕をつつくと、桔梗さんは身をよじってさらに困った顔をする。その表情はもう普通の少女と何も変わらない。
「蘭さん、俺は松岡さんにあいさつして帰ります。先に戻ってください」
「あらら、冷たいこと言うんですね、夕介さん。私らもつきあいますよ」
蘭さんは右手の人差し指を口元に当てていたずらっぽく笑う。
「そうそう、夕介はいっつも自分勝手なんじゃもん!」
「お前にだけは言われたくねーぞ」
夕介は苦笑いしながら果林ちゃんのおでこを軽くつついた。
松岡さんはスーツ姿のままあちこちに大声で指示を出して後片づけの陣頭指揮を取っていた。
「松岡さん、お疲れ様です」
「おお、妹尾君か。おかげさんでなんとか無事に終えることがでけた。ありがとうな」
「圧倒されました。負けないように記事にまとめます。色々とご協力ありがとうございました」
夕介は松岡さんに頭を下げた。僕も続けて言う。
「感動しました。やっぱりわざわざ観に来てよかったです」
「いやあ、学生さんみたいな若い者がようけ(たくさん)おりゃあ、猿楽保存会も安泰なんじゃがなあ」
そう言って松岡さんは笑う。夕介も僕もつられて笑った。
松岡さんは続けて蘭さんに声をかけた。
「のう蘭ちゃん、ネンコーさん、おったねえ」
「ええ、おりましたね。ヘタなのに、必死で謡うてました」
蘭さんは松岡さんに答えてふっとほほ笑んだ。
「じっとしちゃおられんかったんでしょうね、きっと」
「はは、イベント好きのネンコーさんらしいのう」
水菜さんと果林ちゃんは二人の会話を怪訝な顔で聞いている。
「あの、わたしも見ました、パパ」
桔梗さんが声を上げた。
「パパ、一生懸命だった。なんか、うれしかった」
「そうか、桔梗ちゃんも見たか。ネンコーさんも桔梗ちゃんを見て安心したじゃろうて」
「はい」
松岡さんの言葉に桔梗さんは大きくうなずいた。
「死んだ者は、おらんようになったわけじゃないけえのう。いつでも、わしらのすぐそばにおるんじゃ。なあ、蘭ちゃん?」
「そうですね、私たちが感じることができれば、いつでも答えてくれますね」
松岡さんがそう言って笑うと、蘭さんも笑顔を返す。水菜さんは何かわだかまったような顔で二人の様子を見ている。
「では、俺たちはこれで失礼します。掲載が決まりましたら、またご連絡差し上げます。本当にありがとうございました」
「そしたら、みな帰り気ぃつけてな。妹尾君、学生さん、縁がありゃあまた会おうて」
夕介が改めて頭を下げると、松岡さんはそう言って手を振った。
「ねえ母さん、本当にさっき父さん見たの?」
先頭を歩いている水菜さんが振り返りながら蘭さんに尋ねた。
「んー、見たよ」
蘭さんはコートのポケットに両手を入れたまま水菜さんに答える。
「えー、幽霊? 父さん化けて出たん?」
自転車を押している果林ちゃんが左手を前に出して恨めしや~とポーズをとると、蘭さんは思わず吹き出した。
「あはは、幽霊っちゃあ幽霊かな。でも、ちょっと違うよ」
夕介は一人で先に帰ると言うから、僕はみんなと一緒にゆっくりと歩いて帰ることにした。
まだいくぶん雲も残っているが、月のない空には落ちてきそうなほどの星がきらめいている。こんな星空はこれまで見たことがない。
「この世に未練たらたらで居残ってるのが幽霊でしょ? あの人は未練なんていっそも(まったく)残しちゃおらんからね」
蘭さんは自信たっぷりにそう言い切る。
「そうなの? じゃあ、わたしたちのことは?」
水菜さんが少し不満そうに尋ねた。
「そりゃ、確かにあなたたちのことは心残りじゃったとは思うけど、あなたたちの人生はあなたたちのものだもん。見届けられんのは悔しかったかもわからんけど、それにしたって早いか遅いかの違いでしかないからね」
蘭さんはそう言って星空を見上げる。
「父さんは、あなたたちを信じてるんだよ、必ずちゃんと歩いて行けるって。きっと幸せになれるって」
桔梗さんが黙って蘭さんの言葉にうなずいた。
水菜さんはなんだか納得いかない表情を浮かべたままだ。
「あの、僕にも見えました、年光さん」
僕は思い切って切り出した。
「本当ですか、森崎さん?」
水菜さんが振り返って驚いた顔で尋ねた。
「青笹さんの隣に座って謡っているのを、確かに見ました」
「えーずるいー、なんでうちには見えんかったんじゃろ?」
「だいたい、森崎さんて生前の父に会ったことすらないですよね?」
果林ちゃんが僕を見上げながら大きな声を上げ、水菜さんは僕に疑いの目を向けている。
「こらこら二人とも、森崎さん困ってるでしょ?」
蘭さんが笑いながら二人をたしなめる。
「僕、年光さんから色々と教えてもらったような気がしてます。なんか、うまくは言えないですけど」
僕の言葉に蘭さんはうなずいた。
「年光は、もう森崎さんの心の中に、おるんですね?」
「はい」
「そっか、うれしいな」
蘭さんは後ろで手を組んで下を向くと、ふっと笑った。
桔梗さんがそんな蘭さんの様子をじっと見つめている。
「年光は、生きることに本当に一途な人でした、若いときからずっと。じゃけえ、早うに逝ってしまったのかも」
蘭さんは再び顔を上げると、僕に告げるというよりも自分に言い聞かせるような口調でそう言った。
生きることに一途、か。僕もそんな風に生きてみたいな、と思う。
「……死んだら、どうなるんだろ?」
水菜さんがぽつりとつぶやいた。
「そんなの、死んでみなきゃわかんないよ」
蘭さんが苦笑しながら水菜さんに返す。
「わかんないから死ぬのが恐いんだよねー。みんな行きつくとこはそこだって知ってはいても、その先がどうなってるのかは誰も知らんもん」
蘭さんはコートのポケットに手を入れたまま、少し歩幅を広げて二・三歩跳ねるように歩く。ブーツのヒールが乾いた音を立てた。
「今生きてる人は、誰一人、死んだことがないから」
桔梗さんが小さくつぶやく。
「そのとおりじゃね、桔梗。でも、その先がわからんでも、せっかく生きてるんだから、生き切らなきゃ。私らだって、いつかはあっちに行くようになるけど、それまで後悔せんようにしっかり生き切らんとね!」
蘭さんは明るい声でそう言うと、再び星空を見上げた。
僕も空を見上げる。
音がしそうなほどに美しい無数の星々が、冴えた空気の中で瞬いていた。
〈第七章終わり〉
第八章 はじまりの朝 〈一〉
「おかえりなさいませ。どんなでしたか、森崎様?」
玄関を入ると、桑田さんが明るい声で出迎えてくれた。
「マジ感動しました。わざわざ来た甲斐がありました」
「それはえかったです、わけわからんでから寝ちょっちゃったらいけん思うて、心配しよったんですよ」
桑田さんの言葉に僕は思わず笑ってしまった。
「ありがとうね、桑田さん。おかげで、ええ時間が過ごせました」
「いえいえ、女将はいつも忙しゅうにしよってんですから、たまにはゆっくりせにゃいけんです。それこそゆっくり温泉にでも浸かってから」
「ふふ、温泉宿の女将が湯治じゃ、カッコつかんね」
蘭さんと桑田さんは顔を見合わせて笑った。
「妹尾様は先にお戻りになっちょってですよ。お食事の支度も出来ておりますので、そのままお座敷へどうぞ」
「さっすが桑田さん、頼りになるねー」
「むっふー、おまかせください!」
蘭さんが桑田さんを褒めると彼女は右手で胸元を軽くたたいて鼻息も荒く胸を張る。
その様子がおかしくて三姉妹も笑った。
座敷のふすまを開けると、お膳が並べられた真ん中に、ダークスーツでキメた夕介が入口を向いて正座していた。鈍いシルバーのネクタイまで│締めている。
「一体何事だよ、スーツなんか着て」
「お前に用は無い」
夕介は僕を鼻であしらう。ムカつく言葉だが、夕介が鋭くにらんだので僕は次の言葉をのみこんだ。
続いて入ってきた三姉妹も夕介のただならぬ様子に驚く、というかあきれる。
「あはは、どうしたん? 夕介サラリーマンみたい! いっそ似合わん!」
果林ちゃんが夕介を指さして笑いながら遠慮のない感想を言うが、夕介は真剣な顔だ。
桑田さんは鍋の固形燃料に火をつけて回った後、入口の近くに控えて座り、ちょっと意味ありげな視線を蘭さんに送る。蘭さんも軽くうなずいた。
「蘭さん、折り入ってお話があります」
コートを脱いで座った蘭さんに向き直ると、夕介は少しかしこまった調子で話を切り出した。まさか──
「単刀直入に言います。俺と、結婚を前提におつきあいしていただけないでしょうか?」
『えー?!』
先に声を上げたのは果林ちゃんと水菜さんだ。
二人で手を取り合ってびっくりした顔で夕介のことを見つめている。
桔梗さんも固唾を呑んで夕介と蘭さんの様子を見守る。
蘭さんは、真剣に見つめる夕介の目をじっと見つめ返した。
「ねえ夕介君、私と結婚するってどういうことだか、わかってる?」
彼女は静かに夕介に尋ねた。
「もちろんです。俺は、あなたを幸せにしたい。そのためなら、何だってするつもりです」
夕介はまばたきもせずに蘭さんの目を見つめたまま返す。
まさかの公開プロポーズだ。
僕は思わず生唾を飲み込んだ。
「自分の好きな仕事を捨ててでもってことかな? 全然わかってないよ、夕介君は」
蘭さんは一度夕介から視線を外してふっと息を抜いた。
「私と結婚するってことは、君が尊敬してやまない年光とも一緒に生活するってことだよ? 彼は、今でもずっと私のそばにいるんだから。夕介君は、本当にそれに耐えられるの?」
そう言った蘭さんから見つめられて、夕介は虚を突かれたような顔をした。夕介にとって全く想定外のリアクションだったらしい。
「え……と、それは──」
「桐島のご両親にあいさつして、桐島の戸籍に入って、子どもたちとは養子縁組して……そういうのは考えてたんでしょ? 桐葉荘の仕事も覚えるつもりだった、違う?」
「そうです、俺は本気です」
夕介はなかばムキになって答える。
蘭さんはそんな夕介から視線を外さずに言葉を継いだ。
「結婚ってさ、なんていうか、そういうことだけじゃないんだよね。普段の他愛ない会話とか、お互い何も言わないときの過ごし方とか、けんかした後の仲直りの方法とか。そんな何気ない時間を積み重ねる方が、実は大変なんだよ? 夕介君は、まだ私のほんの一部分しか知らないでしょ?」
「だから、もっと知りたいと思います」
蘭さんの言葉に気おされてうなずいた夕介だが、負けまいと声を張る。
夕介の真剣な様子に、蘭さんは右手の人差し指を口元に当ててにっこりとほほ笑んだ。
「そっかぁ、でもそうなると、夕介君は年光とライバルになっちゃうね。君は、それでも私を抱けるの?」
「……」
この質問にはさすがの夕介もたじろいだ。次の言葉が出てこない。
「えへへ、ちょっといじわるしちゃった。ごめんね夕介君。でも、私と結婚するって、そういうことだからね」
蘭さんはそう言っていたずらっぽく笑う。
僕はただ、ぽかんと口を開けてことのなりゆきを見守るほかない。
「私はね、夕介君に幸せにしてもらわなくても、今すっごく幸せなんだー。だから、ごめんね、私には結婚する理由がないの」
そう言った蘭さんの顔は、確かに幸せそうだった。
夕介はがっくりと両肩を落とした。
「もちろん、その気持ちはうれしかったよ、ありがとう」
蘭さんはそう言って再び夕介にほほ笑んだ。
夕介はうなだれたままで何も返せない。
「ねえ、いつから私のこと想ってくれてたの?」
蘭さんは笑みを浮かべたまま人差し指を口元に立てて夕介に問う。
夕介が息を呑む。黙って顔を上げた夕介はすっかり憔悴している。
「それは──」
「ふふ、言わなくてもいいよ。だいたいわかってるつもりだから」
答えようとした夕介を蘭さんが遮った。夕介は口を開きかけたまま固まってしまった。
蘭さんもなかなか酷だ、あの夕介からぐうの音も出ない。
「あー、えかったー!」
ずっと緊張した顔で息を詰めていた果林ちゃんが、ほっと胸をなでおろした。
「うち、夕介のこと絶対『お父さん』なんて言えんもん」
「お前、人の傷に塩を擦り込むようなことを平気で言うのな」
夕介が顔を上げて力なくつぶやいた。
「だって、夕介は夕介じゃあ? 夕介がうちの『お父さん』になるなんて、絶~っ対考えれん! もし母さんがオッケーしとったら、うちグレたかもしれん」
「ふふ、果林はきっとそう言うと思った。水菜と桔梗はどう思う?」
蘭さんに水を向けられた水菜さんと桔梗さんは、互いに顔を見合わせた。
「んー、母さんが決めたんなら、わたしは異論はないよ。そろそろ再婚してもいいんじゃないかなーとは思うけど、でもその相手が夕介さんっていうのは、なんか違うような気がするなあ」
水菜さんが夕介の傷をさらにえぐるようなことを言う。
夕介は恨めしそうな顔で水菜さんを見たが、水菜さんは真顔だ。桔梗さんも隣で小さくうなずいている。
実は、僕も内心同じことを感じていた。
言葉では言い表せないとても微妙なところで、蘭さんと夕介の組み合わせはどこかしらしっくりこない気がする。
「あのーみなさん、そろそろお食事を始めんと、せっかくのお造りがぱさぱさになりますよ? 美味しいうちにどうぞ」
「それもそうだね、せっかく今日はみんなでご馳走食べることにしたんだから」
入口近くに控えていた桑田さんが遠慮がちにすすめると、蘭さんが同意する。
「うん、いっただきま~す!」
待ち構えていたように果林ちゃんが箸を取ると、早速お刺身を一切れつまみあげた。
それを合図に、僕らも食事を始めた。
夕介も仕方なしにすごすごと自分の席に着いて箸を取る。なんだか気の毒なぐらいしょぼくれて見える。
「まあ妹尾さん、美味しいもんでも食べて、元気出しんさい! 世の中に女の子はよっけ(たくさん)おるんじゃから! あんたみたいなイケメンじゃったら、なんぼでも相手はおるいね!」
夕介の背中を桑田さんがバシバシたたいて激励する。
いや、今それを言っても逆効果なんじゃ、と思うが、面白いので言わないでおく。
夕介は黙って汁椀をあおっている。きっと味なんかしてないだろう。
でも、夕介の勇気はすごいな、と僕は感心した。
僕に同じことができるかと言えば、やっぱり無理だと思う。本気だったからこそ、みんながいる前で交際を申し込む気になったんだろうし、それを告げるときの気迫も確かにすごかった。
ただ残念ながら、蘭さんの方が一枚上手だっただけだ。
今日は桐島家も僕らと同じ懐石料理だ。
出かけるとなるとさすがに準備は難しいからお願いしちゃった、と蘭さんは笑う。
カレーとかの簡単で作り置きできるのにすればよかったんじゃない、と水菜さんが尋ねると、どうせならたまには豪華にしようと思ったんだ、と蘭さん。今日だけの特別よ、とつけ加えるのも忘れない。
おかげで美味しいもんが食べれるー、と果林ちゃんがうれしそうに言うとみんなが笑ったが、夕介は会話に耳を傾けようともせずに黙々と目の前の物を食べ続けている。
「なー、そういえば全然カンケーないけど、きぃねえちゃん、さっき『紫桜はいのちの花』って言うたじゃあ? あれってどういう意味なん?」
果林ちゃんは隣に座っている桔梗さんに尋ねながら鍋物のふたを取る。思った以上に熱かったらしく、あちちと言いながらあわててふたをお膳の上に置いておしぼりで指を冷やしている。
「いのちに隠れてる、きらきらしたものかなって、思う。……うまくは言えないけど」
桔梗さんは和えものの入った小鉢を左手に持ったまま答えた。
「それで『いのちの花』かあ、私も賛成。確かに、見ようとせんと見れんものじゃもんね」
蘭さんはそう言って海老の天婦羅を口に入れた。サクッという小気味よい音が僕にまで届く。
「でも、私も観れてよかった。今回は前とはぜんぜん違った見え方がしたよ」
「前とは違った見え方って、どういうことですか?」
僕は汁椀を片手に蘭さんに尋ねた。
黙々と食べていた夕介も、手を止めて蘭さんを見つめる。
「私はね、桜姫は合戦で死んだ武将の、娘じゃなくて、奥さんだと思うの」
蘭さんは『紫桜』の前提を根底から覆すような大胆な仮説をさらりと言った。
「えー、全然わかんない。母さんどういうこと?」
水菜さんはそう言って鯛の刺身にワサビをたっぷり載せて口に運ぶ。
さすがにツンと来たのかすぐに両手で口元を押さえて、んーと声を出しながら目じりに軽く涙を浮かべている。
「あのさ、最初に絶望して死のうとして、次に仇を討とうと狂気になって、それもできなくて口を閉ざして──。『霊山』で桜姫が語った物語には、初日の三幕の要素が全部入ってるでしょ? 桜姫は、前の三幕では人生の途中で死んじゃうことになるけど、『霊山』では寿命が尽きるまで生き切った。前に観たときは、なんとも思わんかったんよね」
蘭さんはふっと顔を上げ、一つ息を吸ってから続けた。
「でも、あの人が死んじゃった今なら、わかる。『紫桜』って、大切に思っていた人を、思わぬ形で亡くした女の物語なんだ、きっと」
「大切に思っていた人を亡くした女の物語──」
夕介が蘭さんの言葉を繰り返した。じっと蘭さんのことを見つめる。
しかし、蘭さんの視線は夕介の視線とは交差しない。
「私も、同じだから……」
彼女は、どこか遠くを見るような表情でぽつりとそうつぶやいた。
第八章 はじまりの朝 〈二〉
年光の病気がわかったのは、今から六年前の梅雨時でした。
今年は俺も本厄だし、忙しくなる前に人間ドックでも受けてみるか、なんて軽いノリで受けたら、それがわかって。
その一年ぐらい前……ちょうど前回の『紫桜』の準備をしていた頃から、年光はよく息切れがするとは言ってたけど、それがまさか命に及ぶ病気だなんて、私も彼も、思いもしませんでした。
こっちに来てからは禁煙したし、一日中忙しいのは変わらなかったけど、向こうにいたときみたいに不摂生ではなくなってたから、どうしてって。
いつの間にか身体中に転移が広がっていて、今の病状なら余命半年だろうという宣告を受けました。
医師からは、納得がいくようにとセカンドオピニオンを勧められて、いくつか病院を紹介されたんですけど、受診を断られることすらあって。それぐらい彼の病気は気づかないうちに進んでいたようです。
別の医師からも、残された時間をどのように使うかを、お二人でじっくりと考えてくださいって言われました。
彼は相当なショックを受けました。もう、涙も出ないほどに。
なんで俺が……って。
やっと桐葉荘の経営が安定し始めたところだし、娘たちはまだ育ちざかり。
なのに、こんなのって残酷すぎますよね?
普段、前向きで楽天的な彼が、初めて私の前でうろたえました。
俺、どうしたらいいのか全然わからないって。
やりたいこともたくさんある、やらなければならないことも山ほどある、なのに俺には時間がない、どうしたらいいんだって。
私、彼に何も言ってあげられなかった。だって、私だってどうしたらいいかわからなかったから。
でも、年光は諦めませんでした。
俺は人探しのプロだからな、とか言いながら、医者探しに奔走しました。
彼、前職では人と人とをつなげるのが得意でしたし、あれこれ苦労はあったにしても桐葉荘がなんとかオープンできたのも、結局は彼の人脈作りの力のおかげだったと思うんです。
たくさんの人の尽力があって、夏が始まった頃には、私たちは信頼できる医師に巡りあうことができました。
治療に関する知見が豊富なだけじゃなくて、私たちのメンタルについてもちゃんと理解してくれて。本当に、本当に、やっと自分たちの気持ちを理解してくれる人に巡りあえたって感じて、私も彼もほっとしました。
丁寧に丁寧に、私たちが疑問に思うことには何度でもきちんと答えてくれました。
でも同時に、この病気が治るわけではないということも、はっきりと思い知らされたんです。医療でできるのは、死の時期をできるだけ先延ばしにすること。早い遅いはあっても、この病気は確実に彼を遠くに連れて行ってしまう──
その事実を理解したとき、彼はだんだんと、残された時間を何に使うべきなのかを考えるようになっていきました。読む本も、だんだんと哲学書が増えて、自分がこれから死ぬということの意味を考え始めたようです。
桔梗は憶えちょるよね? 青い鳥を探して巡り歩いたチルチルとミチルが、最後に訪れる「未来の王国」。
……そう、これから生まれるこどもたちは「未来の王国」からこの世に持っていくものを、自分で選ぶんよね。
もしかしたら彼は、たくさんの人をつなげる仕事と一緒に、早く死んでしまう病気を、自分で選んで持ってきていたのかもしれません。
俺は今までずっと「自分がいつか死ぬ」ということを、遠ざけて生きてきたんだな、と彼がしみじみつぶやいたことがあります。
たいていの人はそうだと思うよ、と私が言うと、俺は自分の死をきちんと自分で引き受けて死にたい、と答えました。全部は無理でも、出来るだけのことはやっておきたい、多分蘭には苦労をかけることになるけど、よろしく頼む、と。
私は、とにかく彼を支えることに決めました。
彼に後悔させたくなかったというより、私が後悔したくなかったからでしょうね。
水菜たちには夏休みの終わり頃まで父さんの病気のことは言わんかったよね。
父さんは、あなたたちにどう伝えればええのか、ずっと悩みよったの。
自分がこんなにも早くあなたたちの前からいなくなることを申し訳ないと思いよったみたいじゃし、あなたたちはちょうど難しい時期に入り始めた頃じゃったからね。
あの年、夏休みの終わりに、家族みんなで錦美川の花火大会に行ったの、憶えちょる?
直前になって水菜がやっぱり行きたくないって言うたりしたけど、結局みんなで観に行ったよね。
あれが、家族みんなででかけた最後になったね。
私と父さんの、最後のデート。
三人とも浴衣着てね、桔梗と果林は、父さんにわたあめ買ってもらって無邪気にはしゃいじょったね。
水菜は無理やり連れて来られたけえかしれんけど、ちょっと不機嫌で。でも、金魚すくいにやたら熱中してたよね。
父さんは、そんなあなたたちの姿を見てずっとにこにこしよった。
花火が始まって、みんなで空を見上げて。
その時だけは私も、彼の病気のことなんか忘れて、本当にきれいだなって思えた。
いよいよラストかなって頃に、父さんが私にだけ聞こえるようにぽつりと言ったの。
俺は、来年の今頃にはもういないんだな、って。
驚いて父さんの顔を見上げたら、父さん、花火を見上げたまま、涙を流してた。
私たちの前に仲良く並んで花火を見上げてるあなたたちの後姿を見て、私も泣いた。あなたたちに気づかれないように。
たくさんの花火が次々に上がって、最後は大きな大きな一尺玉。
ずしん……と空気が震えて、空いっぱいに光が広がって。まわりから、ひときわ大きな歓声と拍手が起こって。
父さんも涙を流しながら手をたたいてた。
泣きながら笑って、笑いながら泣いてた。きっと、私もそう。
歓声の中で、俺も一尺玉になるよ、っていきなり言うの。
どうせなら大きくきれいに咲いてやるさ、って。
何かが吹っ切れたような顔だった。
私も、涙を拭いて、父さんに笑ったの。
じゃあ、私がちゃんと打ち上げてあげるって。
お互いそれでやっと、あなたたちに病気のことをきちんと伝える決心ができたんだ。
夕介君は遠くからなのに、病院にも家にも、何度もお見舞いに来てくれたよね。
年光は現場主義だったからね、後輩から仕事の悩みなんか相談されるとすごく生き生きとして、うれしそうだった。
だから、夕介君には今でも本当に感謝してる。
いろんな人がお見舞いに来てくれたけど、どっちが病人なんだかわかんないくらい、彼は来てくれた人を全力で励ましてた。
なんて言葉をかけようかって暗い顔で来た人が、帰るときにはほっこりした笑顔になって帰っていく。なんだか不思議な光景だったよ。
でも夕介君、彼に怒られたことがあったでしょ?
だってほら、帰り際に「がんばって」なんて言うから。
お前、俺が死んだあとに蘭にがんばってなんて言ったら、俺は化けて出て呪ってやるからな、ってすごい剣幕で怒る怒る。
ふふ、いかにも彼らしい怒り方だけど、その頃「がんばって」っていう言葉が、私も年光もすごく負担だったのは確かだよ。二人だけのときにいっぱい泣いた。
なんて声かけたらいいのかわからなくなって、それでつい「がんばって」なんて言っちゃうんだろうけど、彼も私も、もう既にがんばれることは全部がんばってるんだよね。この上何をどうがんばれって言うの、っていう気持ちになっちゃう。
彼の古い友人でね、最初と最後にあいさつをしただけで、あとはずっとうなずきながら彼の話を聞いているだけの人もいたけど、彼はすごくうれしそうだった。
言いたいことが言葉にならないのなら、無理して言葉にしなくたっていいんだなって、私は思ったの。黙ってそこにいてくれるだけでもいいんだ。
言葉にできなくたって大事な思いはちゃんと伝わるし、逆にどんなに美しい言葉でも、そこに気持ちがなかったら何も伝わらないの。
なあ蘭、夕介は俺の跡を狙ってるぞって、夕介君が帰った後に彼が言ったことがあったな。
冗談めかしてはいたけど、目は笑ってなかった。
俺は蘭のおかげでこうしてちゃんと毎日生きていけてる、ありがとうって言った後にね、俺が死んだ後は、蘭の思うようにしたらいいからな、って真剣な顔して言うの。
そんなのわかんないよ、って私は答えたの。
だって、その頃は目の前のことだけで精一杯だったから。先のことなんて全然考えられなかった。
秋が深まり始めた頃には、彼は自宅で最期を迎えたいという希望を医師に伝えて、在宅ホスピス医を紹介してもらった。
看護師さんから教えてもらって、私も日常的な介護についてはある程度こなせるようになった。
桐葉荘は桑田さんたちにお任せでなんとか営業して、大事な判断だけは彼と私ですることにしてね。少しずつ、経営に関する引継ぎもしていった。
その前の年に『紫桜』奉納で忙しくしてたのが、なんだか遠い昔のことみたいだったな。
猿楽の仲間は、冬に入ってからはほとんど毎日のように誰かが入れかわり立ちかわりでお見舞いに来てくれたよ。
特に、松岡さんと稲村さんはよく来てくれた。
それぞれ奥さんと一緒に来てくれることも多くてね。だから、私は一人で抱え込まないで済んだんだ。
松岡さんの奥さんにはよく愚痴をこぼしたなあ。自分の考えを押しつけないで、ずっとしんぼう強く聞いてくれるんだ。
逆にひとみちゃん──稲村さんの奥さんね──には昔からの友達みたいに気楽に話ができてストレス解消になったな。
ひとみちゃん、私と違って若い頃はだいぶやんちゃだったらしいけど、それがよかったのかな。遠慮なしに色々言ってくれるからいいみたい。
私よりも六つも下なのにね、今でもすっごい仲良し。
彼にとって一番の心残りは、もちろんあなたたちのこと。
水菜が中学二年生、桔梗は五年生、果林が四年生。
水菜は気を利かせて私のかわりに家事を全部やってくれるし、桔梗は反抗期に入って気難しくなってたし、果林の無邪気さはなんか逆に辛くて。
彼は、自分が早く逝ってしまうことで、あなたたちの歩みを邪魔してしまうことをすごく恐れてたの。
でも、いくら考えてもこればっかりはどうにもできない。
自分の力で歩いていけるようにって私たちがいくら願っても、あなたたちはそれを受け止めるにはまだ幼なすぎたね。
ねえ水菜、父さんがしきりに教えてた『風姿花伝』の一節、憶えてる?
……そう、さすが水菜だね、一言一句間違えずに憶えてるんだ。
「いづれの花か散らで残るべき。散る故によりて、咲く比あれば、珍しきなり。能も住する所なきを、先づ、花と知るべし」(註一〇)
元々はね、四季のうちに色々な花が入れ替わりながら咲くように、色々な芸の花を身につけて、あらゆる場に対応できるようにしなさい、花はいつか散るからこそ、咲いている間がきれいで珍しいように、能にも「これでよし」というところなんかないんだよ、っていうような意味なんだけどね。
父さんはね、この言葉で命のリレーのことを伝えたかったんだと思うの。
確かに季節によって咲く花は違うけど、それぞれの花が、それぞれの時期にちゃんと咲くでしょ? だから一年中、花が絶える時期はない。
自分はもう散ってしまうけど、だからこそ次の花──つまりあなたたちが、これから咲こうとしている。
そうやって命はずっと咲き続けるの。
とどまるところなんかない、それが「花」。
だからさっき、桔梗が「紫桜はいのちの花だと思う」って言ってくれたの、すごくうれしかったな。
ああ、父さんの思いがちゃんと伝わったんだなって思って。
あなたたちの成長を見届けることができないのは、彼にとってすごく心残りだったろうけど、それでも彼はあなたたちの幸せを信じてた。
あの子たちが咲かないわけがないだろ、俺と蘭の子なんだから。彼はいつもそう言ってた。
あなたたちは、必ず自分の花を咲かせる。
それは、大きくて鮮やかな花かもしれないし、ひかえめだけどかわいらしい花かもしれない。早く花開くかもしれないし、のんびり遅咲きかもしれない。
でも、それぞれのペースで自分らしく咲けたら、それはきっと幸せなことなんだと、私は思うな。
あのね、今まであなたたちには内緒にしてたけど、実は父さんからあなたたち一人一人に、ビデオレターがあるんだ。それぞれ成人式を迎えたら、その日の夜に見せるようにってね。
ふふ、遺言だからまだ見せたげない。
水菜はもうすぐだしね。
水菜の振り袖姿、父さんにも見せてあげようね。
────────────────────
註一〇 花傳第七 別紙口傳より(引用は岩波文庫「風姿花伝」野上豊一郎・西尾実校訂から。字体は新字体に改めた)
第八章 はじまりの朝 〈三〉
だんだんとできることが少なくなっていく彼を見るのは、とても辛いことだったな。
ああ、少しずつ旅立ちが近づいているんだなあって思うと、なんだかやりきれなくて。
彼も少し不安定になった。
憔悴した顔で、やっぱ死にたくはないよなあ、なんて言われちゃうと、私もなんて返したらいいかわかんないよ。
痛みについては、在宅ホスピス医の先生と電話で相談しながら、薬でかなりこまめにコントロールしてたけど、死ぬことに対する不安って、痛みとはまた違うところから来るものなんだなあって思った。
いくら覚悟を決めてても、やっぱり恐いものは恐いって年光は言ってた。
こんなに迷惑かけてまで生きたくないって言ってみたり、そうかと思えばみんなに忘れられたくないなあって言ってみたり。
一日のうちでも、死にたいと死にたくないの両極端を、行ったり来たりするの。
何でもやってみなきゃわからない、が彼の口癖だったけど、自分が死んでいくことについてだけはわかりようがないやって悔しそうに言ってた。
ただ、死の準備をひとつひとつ進めていく中で、これまで生きてこれたことに心から感謝できるようになった、って言うようになったね。
今生きてるのは当たり前のことじゃなくて、本当に綱渡りみたいな奇跡の上にあるんだって実感したって。
私も、彼の姿からそれを教えてもらった気がする。
自分の葬儀のことを彼はずっと気にかけてた。
私にできるだけ負担をかけさせたくなかったみたいで、自分でできるところは自分で仕切っておこうと思ったみたい。
葬儀社の人に来てもらって打ち合わせをしたんだけど、あの頃はまだ今ほど生前予約は一般的じゃなかったし、何より年光の年齢でそんなことをする人はいなかったから、向こうもだいぶびっくりしてたね。でも、彼の思いをきちんと汲んでくれて、費用の面も含めて具体的な提案をしてくれた。
私が喪主を務めるから、それでやりやすいように、あらかじめひとつひとつの手順を決めて、私が連絡を入れたらすぐに対応できるように、万全の態勢を整えてくれたの。
その後も、何か思いついたらこまめに連絡を取り合って、すっかり信頼関係ができた。
連絡してほしい人のリストなんかも自分でかっちり作り上げてね。
会葬礼状とか、連絡しても通夜や葬儀に来れない人のために出すあいさつ状の文面なんかも、彼が自分で考えて、最後まで手を入れ続けたんだよ。
あの笑顔の遺影を選んだのも、その頃だね。
彼と一緒にアルバムをめくってたら、彼の写真ってものすごく少ないんだよね、あなたたちの写真はたくさんあるのに。
俺は撮る専門だったんだな、一度夕介に撮ってもらっておけばよかった、って彼は笑いながら言ってた。
ねえ夕介君、私の遺影、撮ってくれる?
……ふふ、冗談だよ。
色々探して、会社の後輩の結婚式に家族で招かれて出席した時の写真を選んだの。
今でも思うけど、本当に、彼の最高の笑顔。
三月になると、彼はまどろんでいることが多くなって。
そろそろなのかな、って彼は言って、関東にいる桐島のご両親に連絡して、わざわざ来てもらったの。春休みだったあなたたちも一緒にいたよね。
二人とも何も言えなくてね。
そんな二人に向かって彼は、バイバイ、俺はひとまず先に逝くよって。親不孝で悪いね、でもこの世に送り出してくれて本当にありがとう、って真顔で言った。
こんな田舎に引きこもって親より先に逝くなんてお前は本当に親不孝者だ、ってお義父さんが声をしぼり出すようにして言ったけど、彼はうなずいただけで何も言わなかった。
しばらく彼は黙ったままだったんだけど、生きているうちにちゃんとありがとうって言っておきたかったんだって、ぽつりと言った。ご両親は何も言えないでただ泣いてた。
本当は彼、ごめんって言いたかったのかもしれないけど、彼は結局誰に対しても謝らなかった。もちろん、私に対しても。
かわりに、「ありがとう」ってたくさん言った。
いくら「済まない」って謝っても足りないから、せめて「ありがとう」ってお礼を言ってたんじゃないかな。
少しずつ、私にもできることは少なくなっていった。
桜の花を見てから死にたいなあ、ぜいたくかなあって彼が二月頃に言ってたから、桜が咲いた時に果林に頼んで、桜の枝を持ってきてもらったよね。水菜は枝を折るのを嫌がったし、桔梗は父さんの顔見ようともしないし。
桜の花を見て、あー、これで俺の人生に悔いはないな、って少しかすれた声で笑いながら言うの。
それまでなら私もきっと笑ってたけど、その時だけは笑えなかった。
本当に最後が近づいてるのがわかったから。
最後の夜、彼ははじめ少し落ち着かなかった。
あなたたちがおやすみを言った後、ずっとあなたたちのことを気にしてた。
桔梗は反抗期になったばかりだから大丈夫かな、俺がいなくなることをちゃんと受け止められるだろうか。
果林は無邪気過ぎて、そもそも俺が死んだってことを理解できるだろうか。
水菜はがんばりすぎて無理しないといいんだがな、俺のわがままにつきあわせてだいぶ寂しい思いをさせたしな。
そんなことをずっと切れ切れの息でつぶやいてたけど、私は何も答えてあげられなかった。
ひとしきりあなたたちの心配をした後、彼がぽつんと言ったんだ。
でも俺、やっぱり蘭と一緒になれてよかったって。
最初に思った通りだ、蘭と一緒になってなかったら、俺はきっとダメになってた。蘭がどう思ってるかはわからないけど、最後の最後まで俺の好きなようにやらせてくれて、本当にありがとう──蘭のおかげで、俺は最高の人生を送れたよって。
──私、何て言ったらいいかわかんなくて、黙ってうなずいた。
今なら素直に、私も一緒になれてよかったよって、伝えられそうな気がするんだけどね。その時は、それを言っちゃったら彼がすぐにでも遠くに行ってしまうような気がして、どうしても言えなかった。
ちゃんと言ってあげればよかった、私も幸せだよって。
水が欲しいって言うから少しだけ飲ませてあげて、薬の作用もあって彼はまたまどろんだの。彼の呼吸の音だけが、部屋の中に響いて。
私は眠れなくて、彼の手を取ってそばでずっと座ってた。
頭の中でいろんなことがぐるぐる回るんだけど、不思議と涙は出なかった。
時々彼の手が弱々しく私の手を探るから、大丈夫ここにいるよって言いながら握ってあげたら、彼もまた私の手を握り返してくれる。意識があったのかどうかはわからないけど。
何時間もそうしているうちに、彼の呼吸が、だんだんと不規則にゆっくりになって。ああ先生が言ってた通りだなって思っているうちに、すうっと電池が切れるみたいにふっと止まって。
彼が、いなくなったのがわかった。手を握っても、もう握り返してくれない。
お疲れさま、よくがんばったね、って彼に声をかけた。
もう、ここにいないのはわかってたんだけどね。
そこから後は、なんだか夢の中みたい。
とにかく事前の打ち合わせ通り、死亡診断書を作ってもらうために在宅ホスピス医の先生に来てもらって、葬儀屋さんに電話して──
全部彼の仕切りどおり。
早朝に亡くなったから、その日はずっと彼の作ったリストで連絡して。
通夜は次の日の一九時、葬儀告別式はその次の一一時。ちょうど土日にかかって、たくさんの人が来てくれることがわかってね。葬儀社の社長さんが、これもご主人のお人柄でしょうねって感心してた。
通夜も告別式も、本当にたくさんの人が来てくれて、ああこの人はこんなにもたくさんの人に惜しまれて逝くんだなあってぼんやり思った。
でも、私は喪主だから、とにかく段取りをこなすのに精一杯。彼がお骨になっても、なんだか信じられなかった。
葬儀が終わっても、本当に色々な手続きがあってね。
役場に行って死亡届を出して、住民票の抹消をして、国民健康保険の手続きをして……
一番やっかいな相続は、彼がいつのまにか公正証書遺言を残してくれていたけど、それでも彼名義の銀行口座なんかは全部使えなくなるし、本当に大変。
人が一人亡くなるのって、ものすごく大変なことなんだよね。
わあっと色々なことが一気に押し寄せて来て、それに対応するだけで精一杯。
四十九日の法要が終わっても、不動産とか会社の登記やらなんやらで、ずっとばたばたしてた。
悲しんだり不安に思ったりする余裕もないくらい。
彼が弁護士さんとか税理士さんとかにちゃんと繋いでくれてたから、それでもスムーズに行った方だとは思うんだけどね、やっぱり大変なものは大変。
いつまでも臨時休業ってわけにもいかないから桐葉荘も再開したし、しばらくの間は弔問に来る人も結構いたし。
で、そういうのが一段落したら、一気にがくっときちゃった。
厨房から帳場に向かって彼を呼ぼうとして、あ、そうか彼はもういないんだって思った瞬間、ぼろぼろと涙が出て来て。
本当にもう、どうしようもないの。
彼の桐葉荘はこうしてちゃんとあるのに、なんで彼だけがいないんだろ、って。
そのまま私、立ち上がれなくなった。
驚いて桑田さんが来てくれたけど、その場に沈んでしまうんじゃないかと思うぐらい、体が重くて動けなかった。
桑田さんが何か言ってるんだけど、何を言ってるのかもわからない。周りのものがみんなぺらぺらの絵になったみたいだった。
桑田さんが松岡さんご夫婦を呼んでくれてね、泣き続ける私に奥さんが何も聞かないで一晩中ずっとつき添ってくれた。
松岡さんのご夫婦は、二〇年ぐらい前にまだ二十代だった息子さんを事故で亡くされたんだって。生きてたらちょうど年光と同じくらいの世代だよ。
いっぱい悲しんだ先輩として、私の悲しみに静かに寄り添ってくれたの。
私の心の中にはもう悲しみしか残ってないんじゃないかって思うくらい、何も感じることができなくなった。
何を見ても、すべてが彼の思い出と結びついて胸が締めつけられる。
毎日彼のそばにいたのになんでもっと早く病気のことを気づいてあげられなかったんだろうって自分を責めたり、急に苛立たしくなって何もかも壊してしまいたい気持ちに駆られたり。
何を食べてもおいしくないし、あれだけ楽しかった桐葉荘の仕事も、全然手につかなくなって。
あなたたちのために私がしっかりしなきゃ、って無理矢理にでも思おうとするんだけど、身体に力が入らない。どうしたらいいのかわからない。
自分で自分をコントロールできなくて、彼のことを思い出すと涙がぼろぼろ出てくる。
誰とも会いたくなくなるし、この仕事を続けていけるかどうかも、自信なくなっちゃった。
この時期は水菜にすごく負担かけちゃったね。
家のことは全部やってくれるし、桔梗と果林の面倒も見てくれて、本当に何もかも全部水菜が背負っちゃったもんね。
あなたは賢いから、こんなとき自分がどうしたらいいのか、ちゃんと考えたんだよね? 高校を卒業する時も、本当はここから出ていきたかったのに、あえてそうしなかったのは、私を心配してくれたからだよね?
……ありがとう、優しい子だね。
でも、私にあなたの人生をゆがめる権利なんてないんだ。
今さらこんなこと言っても遅いって思うかもしれないけど、あなたの人生は、あなたのもの。
だから、もっと自分の心に正直になりなさい。
水菜の人生は、水菜にしか作れないんだから。
私なら、もう大丈夫だから。
桔梗が何も言わなくなっちゃったときは、すごいショックだった。
なんでって思うよりも先に、ああ、私のせいだって思って。
私がしっかりしてないから、桔梗のことを何もわかってあげられない。
もう、死んじゃいたいって思った。
早く彼のそばに行きたい──それしか考えられないの。
……ううん、桔梗のせいじゃないからね。その時は本当にぎりぎりだったんだと思うな。
でも、ひとみちゃんにそれを言ったら、なぐさめてくれるどころかめちゃめちゃ叱られた。
蘭ちゃんはそれでよくても、子どもたちはどうなるん、蘭ちゃんはお母さんなんよ、って。逃げとるだけじゃないって言うの。
私だって言い返した。
ひとみちゃんには昂さんがいるじゃない、ちゃんと支えてくれてるじゃない、私にはもう何もないの、って。
大声でけんかして、それから二人でぼろぼろ泣いた。
ひとみちゃんとけんかしたのって、あのときだけ。
──ひとみちゃんに言われたんだ。
あたしは蘭ちゃんの気持ちを全然わかってあげれんと思う、だってあたしの旦那は元気だし、子どもだっておらんし、って。
しばらく黙った後、でも大切な命を喪った悲しみなら、わかるつもりだよってぽつんと言うの。
私、その言葉を聞いてはっとした。
そっか、私はひとみちゃんの悲しみをちっともわかってなかったんだ。こんなに悲しい目に遭ってるのは自分だけなんだって、思い込んでたんだ。
ひとみちゃんは、なかなか子どもができんくてね。その前の年の夏、せっかく宿った命も流産しちゃったばかりで。
一番の仲良しなのに、私、そんなこともわかってあげれてなかった。
お願い、何もないなんて言わんで……ってひとみちゃんに言われた。
あたしの悲しみと蘭ちゃんの悲しみを比べることなんてできんけど、蘭ちゃんにはまだ大事な命が三つもあるんじゃろ、蘭ちゃんがおらんようになったら、娘さんたちはもっと悲しい思いするんよって。
それに、もし蘭ちゃんがおらんくなったらあたしも悲しいから、って言ってくれた。
目が覚めたみたいな気持ちだった。
悲しい気持ちがなくなったわけじゃないけど、ひとみちゃんのおかげで、私は立ち上がろうって思えたんだ。
彼が遺した桐葉荘を、潰してしまうわけにはいかない。
子どもたちも必ずきちんと育て上げる。
それが、残された私の役目。
悲しみは不意にやってくるけど、それに負けてなんかいられない。
私が、守るんだ。
私は前にも増して、仕事に没頭するようになった。
誰とも会いたくなくなる日もあったけど、そんなときでも、無理矢理お客様の前に出るようにした。そうやって女将として仕事をしていれば、立ち止まらずに前に進めてるような気がしたから。
目の前のことだけを考えよう、私がなすべきことをまっすぐにやるんだ、って呪文のように何度も繰り返してからお客様の前に立つようにした。
幸い、お客様は以前と変わらず桐葉荘に来てくれた。
新しいお客様も少しずつ増えて、前と比べてもぐっと忙しくなった。
仕事に没頭してれば、彼がいない悲しみを忘れられる──そう思ってたんだよね。
……でも、そんなことはなかった。
ふっと一人になった時、つい彼がいてくれたらなあって思ってしまう。
だめ、今は悲しんでる場合じゃないんだって、自分を叱ってなんとか仕事を続けたけど──やっぱり無理だった。
一周忌の法要が終わった後、疲れ切ってふさぎこんじゃった。
──なんで?
私は早く立ち上がりたいのに、なんでできないんだろう。これじゃあ桐葉荘も、子どもたちも、守ることができないじゃない。
夜、一人で泣いた。
そしたら。
蘭が一人で全部守らなきゃいけないわけじゃないんだよ、って声が聞こえた。
彼の声。
蘭は真面目だからなあ、って笑うの。
え、と思って私は顔を上げた。
部屋には誰もいない。でも、確かに彼の声が聞こえた。
ごめん、私もう限界──ってつぶやいたら、また声がした。
大丈夫、蘭は一人じゃないんだから、って。
私の言葉に、彼がちゃんと答えてくれる。
幻聴? なんて思う余裕もなかった。
胸がいっぱいになって、私また泣いちゃった。
あいかわらず泣き虫だな、蘭は、って彼がそばで笑うの。
だって急に声かけられたら驚くじゃない、って私は泣いてるのか怒ってるのか笑ってるのかわかんないけど、彼にぶつけた。
おいおい、そりゃないだろ、って彼は苦笑いしてる。
懐かしい感じ。
彼が生きてた時のやりとりと、全然変わらない。
ああ、なんだ。
彼はちゃんといるんだってわかった。姿は見えなくなったけど、いるんだ。
それからずっと、彼は私のそばにいるの。なんだか生きてた時よりも近くに感じられるぐらい。幽霊みたいに│不確かなものじゃない。私の心の中に、しっかりと生きてる。
ねえどうしようって尋ねたら、それはこうしたらいいんじゃないかって答えてくれるし、時々私のことをからかったりもする。
もちろん、さびしくて泣いちゃう時がなくなったわけじゃないけど、そんな時も、しょうがないなあって言いながら、彼がそばで見守ってくれてるのを感じる。
すぐに立ち上げれたわけじゃないけど、彼のおかげで、ゆっくりと、だんだんと、私は元気を取り戻した。
彼の言うとおり、私は一人じゃなかったしね。
松岡さんのご夫婦は本当に色々な面で助けてくれたし、ひとみちゃんにも大感謝。
桐葉荘のスタッフはどこにも負けない実力派ぞろいだし、お客様も本当にいい人ばっかり。
猿楽保存会のみんなは、私たちがここで生まれ育ったみたいに接してくれる。
彼が会社にいた頃につながりのあった人が突然ひょっこり訪ねてきたりするし、お世話になった主治医の先生とか、在宅ホスピス医の先生、それに│葬儀社の社長さんとも、今でも色々なこと話すんだよ。
忘れられるどころか、彼は今でも、たくさんの人の中で生きてるの。
そしてもちろん、あなたたちがいてくれる。
私は、本当に幸せ者だなあって思う。
年光が結んでくれた、たくさんの人の縁。
その中で私は生きてる。あなたたちも、その中にいるんだよ。
私はもう、大丈夫。
だから今度は、あなたたちが幸せになる番だからね。
第八章 はじまりの朝 〈四〉
蘭さんはそう言って心から幸せそうな笑顔を娘たちに向けた。
じっと耳を傾けていた水菜さんは、目じりに浮かんだ涙を指でぬぐっている。桔梗さんは何かを決心したような顔で蘭さんの目をじっと見つめ、果林ちゃんもいつになく神妙な面持ちでうなずいた。
「森崎さん、長い話をずっと聞いてくれてどうもありがとう。桔梗がもう一度歩きだすことを決めた今日、どうしてもこの子たちに話しておかなきゃって思ったから」
蘭さんは僕に丁寧に頭を下げた。
「いえあの、なんて言ったらいいかわかんないけど、こちらこそありがとうございます」
僕はなんだかとんちんかんな言葉を返してしまった。胸の中に言いようのない気持ちが満ちていて、うまく言葉にできなかったからだ。桔梗さんがそんな僕にふっとほほ笑みかけてくれている。
「夕介君も、本当にありがとう」
蘭さんは押し黙ったままの夕介にも感謝の言葉をかけた。
「断っといてこんなこと言うのもなんだけど、正直何度かぐらっときたことはあるんだ。でも、私といる時の夕介君は、どこか無理してたでしょ? それぐらいわかるんだから。素でいられない人と一緒にいても、お互い辛くなるだけだよ。私は、夕介君にも、ちゃんと幸せになってほしい。これは、本当に心からそう思うんだ」
蘭さんはそう言って夕介のことを真顔でじっと見つめた。
夕介はその言葉に顔を上げると、小さくうなずいた。
庭から虫の音がかすかに聞こえてくる。
「なーなー、みんなで写真撮らん?」
突然、果林ちゃんが蘭さんに提案した。
「いいね、撮ろう撮ろう」
蘭さんは二つ返事でその提案に│乗る。
「なんでいきなりそんなこと思いつくわけ?」
「んー、なんか今日のこと忘れんように残しとかんといけんような気がするけえ。なー夕介、撮って」
水菜さんの言葉に果林ちゃんは真剣な顔で答えてから、夕介を見た。
「なんで俺が……」
「夕介プロなんじゃろ? どんな状況でもちゃんと注文に応えんさいや!」
「金払うわけでもないのに偉そーに」
「文句言わんの!」
果林ちゃんと夕介のやりとりに、蘭さんと水菜さんが顔を見合わせて思わず吹き出す。
「よし、じゃあロビーで撮るぞ、カメラ持ってくるからその間に支度しろ」
夕介がいつもの調子で言うと立ち上がった。
「どうせならスタッフの皆さんも一緒に写りましょう。呼んであげてください」
「そうね、じゃあみんなで準備しよっか」
振り返りながら夕介が声をかけると、蘭さんも立ち上がって言った。
「じゃあ、母さん真ん中で、父さんの写真持って。きぃねえちゃんとうちがその両側に入るけえ。みず姉はたっぱ(背丈)があるけえ、母さんの後ろ! 桑田さん、遠慮せんでええから。にひひ、浩司さんはきぃねえちゃんのそばね! ええから早く! ほら、楠本さんも芦野さんも、入って入って!」
果林ちゃんがてきぱきとみんなの並ぶ位置を指示する。みんな思い思いのことを言いながら果林ちゃんの指示に従って並んでいく。
夕介は三脚に据えたカメラのファインダーをのぞきながらあれこれ調整している。
「準備できたかー? よければ撮るぞー」
「だめ、夕介も入るの」
夕介がやる気なさそうに尋ねると、すかさず果林ちゃんがダメ出しをする。
「なんでだよ、俺は今そんな気分じゃ──」
「夕介の気分なんかどうでもええ! セルフタイマーで撮って」
夕介はなんで俺まで、と不満そうに言いながらセルフタイマーのセットをすると、のそのそと後ろの列の端に加わった。
僕の左前にいる桔梗さんが振り返って僕を見て、ちょっと恥ずかしそうに笑う。
「ほら、きぃねえちゃん、ちゃんとカメラ見て!」
すかさず果林ちゃんの声が飛んで桔梗さんは小さく肩をすくめた。
赤い光の点滅が徐々に速くなって、シャッター音が響く。
「あー、目つぶってしもうた」
桑田さんの声にみんなが笑う。
「もう一回!」
果林ちゃんが夕介に容赦なく指示を飛ばす。
夕介は面倒くさそうにカメラに戻り、改めてセルフタイマーをセットした。
「だいたい、何の記念写真だよ」
列に戻った夕介がぶつくさとつぶやくと、果林ちゃんが大声で答える。
「そりゃ、夕介のふられた記念に決まっとるじゃあ?」
その言葉にみんなが思わず吹き出した、と思ったらシャッターが切れた。
「あらら、グッドタイミング!」
蘭さんが笑いながら振り向いた。胸元に大事そうに抱かれた年光さんの写真も、幸せそうな笑顔だ。
やっぱり似合いの夫婦なんだな、と僕は思った。
「あーあ、夕介さんかわいそ」
水菜さんも笑いながら夕介に同情する。
「でも、いい記念になったね」
水菜さんの言葉に、桔梗さんもほほ笑みながらうなずいた。
「じゃろー? うちって天才かも」
「天才的小悪魔だ」
「だーかーらー、うちは小悪魔じゃないもん!」
夕介がネクタイをゆるめながら面白くなさそうに混ぜっ返すのを、蘭さんがにこにこしながら眺めている。
「蘭さん、写真は後日プリントして送りますから」
「ありがとう、夕介君。楽しみに待ってるね」
「おい、お前にも送ってやるから住所教えろ」
「わかった、ちょっと待って」
僕は蘭さんがカウンターから出してくれたメモ用紙にアパートの住所を書いて、夕介に渡した。
「言っとくが特別大盤振る舞いだからな」
「わかってるよ」
まったく、夕介らしい言い方だ。
「よし、じゃあ片づけよっか。お二人は先にお風呂へどうぞ。さあ、あなたたち、手伝ってよ」
蘭さんが明るい声で言った。
「なー母さん、今日はこっちでお風呂、だめ?」
果林ちゃんが甘えた声を出す。
「ざんねーん、今日は女性のご宿泊がないから、女湯はお湯を張ってませーん!」
「えー、そんなぁ」
蘭さんが勝ち誇ったように声を上げると、果林ちゃんは全身で残念がった。
「なんなら俺と一緒に男湯に入るか?」
「わや(滅茶苦茶)言う! 絶ッ対イヤ! セクハラエロ夕介となんか、死んでもイヤ!」
夕介のからかいに、果林ちゃんは身をよじって思いっきりあかんべーをする。
その様子に、ロビーは再び笑いに包まれた。
「お前、このまま帰るつもりか?」
夕介が湯船に浸かったまま僕に尋ねる。
「何が?」
「何が、じゃねーだろ。お前も明日には帰るんだろ、水菜とのことはどうすんだよ?」
夕介はそう言って左手であごひげを撫でた。
露天風呂からは黒々とした山並みの上に満天の星がまたたいているのが見える。湯船から立ちのぼった湯気が、星空に向かって溶けていく。
穏やかな風が周囲の竹林をかすかにざわめかせ、どこからか虫の音も聞こえてくる。静かな夜だ。
僕は湯船の中で声を出して手足を大きく伸ばした。
「もちろん、このまま帰るつもりはないよ」
明日は月曜日だから、僕がチェックアウトする頃には水菜さんはもう仕事に出かけてしまっているだろう。行動を起こすなら、今晩しかない。
「自分の思いに、自信を持つんだな」
夕介がぼそりと言った。
「あいつがどう思おうが、それはあいつの勝手だ。お前はただ、お前の思いをあいつにぶつければいい」
そう言って夕介は湯船のお湯をすくって顔をすすいだ。
「がんばれよ」
「あ……ああ、ありがとう」
まさか夕介が僕の背中を押してくれるとは思わなかった。
決めた。風呂から出たら、打ち明ける。その時何を言うかは、自分の心に聞けばいいんだ。
夕介は僕に背を向け、黙ったままぼんやりと石庭を眺めている。
「よし!」
僕は大きく深呼吸をしてから腹に力を入れて声を出した。
そうと決まれば、一刻も早く行動するだけだ。
僕は浴衣ではなく、風呂に入る前に着ていた服をもう一度着た。
夕介みたいにスーツで、とはいかないが、大事な時に浴衣ではなんだか気合が入らない気がしたからだ。
ロビーは既にメインの照明が落とされて間接照明になっている。座敷をのぞいてみたが、きれいに片づいた後だった。
やっぱり厨房かな、と思って座敷を出ると、ちょうど厨房から桔梗さんが出てきた。
「あ──」
桔梗さんが小さく声を上げる。
「ちょうどよかった。桔梗さん、水菜さん知らない?」
僕が桔梗さんに尋ねると、桔梗さんは少しうろたえたような表情を見せた。
「──お姉ちゃんなら、まだ、中に」
一瞬言いよどんだ後、彼女は小さな声で教えてくれた。
「呼んでもらっても、いいかな?」
僕が頼むと、桔梗さんはためらいながらうなずいて、厨房の暖簾の奥に消えた。
中から、森崎さんがわたしに? と聞き返している水菜さんの声が聞こえる。
僕は鼓動が少し早まるのを感じながら、彼女が出てくるのを待った。
「何ですか、森崎さん?」
暖簾から水菜さんが姿を現した。
彼女のすぐ後ろから桔梗さんと果林ちゃんが僕らの様子をうかがっている。
「あの、二人だけでお話ししたいんですが、いいですか?」
「え? いいですけど」
水菜さんはほほ笑みながら僕に答えた。
「桔梗と果林は先に母屋に戻ってて。盗み聞きなんかしたら怒るからね!」
水菜さんは振り返ると、先回りして二人に釘を刺す。
「えー、せっかくおもしろそうなのにぃ」
「もう、だからイヤなの! ほら、早く!」
水菜さんは果林ちゃんをしっしっと追い払う手ぶりをした。
「あーあ、ざーんねん。じゃあ浩司さん、がんばってねー♪ おやすみー」
果林ちゃんはにひひーといたずらっぽく笑いながらスキップして勝手口に向かい、ドアから手を振った。桔梗さんも何か言いたそうな顔だったが、おやすみなさい、と小さくつぶやいてから小走りに果林ちゃんの後を追った。
「さ、これでジャマ者はいなくなりましたよ」
そう言って水菜さんは僕にほほ笑みかける。
「すいません、なんか無理言っちゃって。じゃあ、ロビーで話しましょう」
僕と水菜さんはおとといの夜に座ったのと同じ位置に座った。
「で、話ってなんですか?」
水菜さんはすらっとした足を上品に折り曲げた上に両手を組んで置き、ソファに浅く腰かけた。背筋を伸ばして僕のことをじっと見つめている。
心臓の鼓動がさらに早まる。
「あの、水菜さん」
僕は大きく息を吸った。
「……好きです。僕と、つきあってください」
言えた。
「え……でも、先日言ったでしょう、わたしはそんな気は全然ないって」
「わかってます。それでもいいんです」
彼女は少し探るような目でじっと僕の目を見た。僕も彼女の目を見つめる。
「なんていうのかな、たった何日か一緒に過ごしただけでこんなこと言うのは、なんかばかみたいだなって、僕も思います」
口の中が乾いてうまくしゃべれない。落ちつけ、と自分に言い聞かせながら、僕は言葉を継ぐ。
「でも、おととい話した後、僕は色々な水菜さんを見ました。果林ちゃんとけんかしたり、『桜堤』の桜姫に涙したり、年光さんと蘭さんの思い出話を興味津々で聞いたり……きっとそれは、素の水菜さんだろうと、僕は思ってます」
水菜さんは両手をひざの上に置いたまま、僕の言葉をじっと黙って聞いている。
「今日、パスタを作ってくれたときの水菜さんの笑顔、本当にいいなって思いました。やわらかな笑顔でした。水菜さんはおととい、自分には外面しかないなんて言ってたけど、そんなことないと、僕は思います」
自分の掌が汗ばんでいるのがわかる。次に何を言うつもりなのか、自分でもよくわからない。が、とにかく言わないと何も始まらない。
「ちょっとめんどくさいなって思うところもあるけど、そういうところも含めて、僕は水菜さんのことが好きです」
僕はなんとかそこまで言っていったん言葉を切った。
「めんどくさいって、わたしそんなに性格悪いですか?」
水菜さんが少し厳しい口調で僕に尋ねた。腕を組んで軽く僕をにらんでいる。
「あ、いや……そうじゃなくって、その──」
僕はそのリアクションに頭が一気に真っ白になってしまった。何を言えばいいのか懸命に考えるが、うまく言葉が出てこない。冷や汗が出そうだ。
しどろもどろになっている僕を見て、水菜さんが急にふっと表情をゆるめた。
「ふふ、ごめんなさい。ちょっといじわるしちゃった」
え?
「母さんのいじわるなとこだけは絶対似たくないって思ってたのに。もう、いやなとこばっかり似ちゃったな」
水菜さんは組んでいた腕を下ろして笑っている。少しほっとする。
僕は、改めて深呼吸をしてから続けた。
「えっと、すぐに返事がもらえるとは思ってません。僕は明日帰るけど、メールでもいいので、連絡もらえるとうれしいです」
「でも──」
僕は何か言おうとする彼女の言葉をさえぎって立ち上がった。カウンターからメモ用紙を取って自分のメールアドレスと電話番号を書くと、両手で水菜さんの目の前に差し出す。
「よろしくお願いします!」
僕は何とかそれだけ言って頭を下げるのが精一杯。
水菜さんは僕が差し出したメモを、そっと受け取る。
僕が顔を上げると、水菜さんは黙ってうなずいた。
「果林、桔梗。そこにいるんでしょ?」
水菜さんが僕の背後をにらんで低い声で告げる。
「げ、バレた!」
カウンターの陰から果林ちゃんが小声でつぶやくのが聞こえた。
「もう、あんたたちは!」
水菜さんが立ち上がって二人のところにずかずかと歩み寄る。
「やば、きぃねえちゃん逃げよ!」
果林ちゃんと桔梗さんがあわてふためきながら立ち上がって、カウンターの中から逃げ出した。
「ごめんみず姉! だってみず姉が心配だったんじゃもん!」
「うそばっかり! 戻りなさいって言ったのに、もう!」
水菜さんは顔を真っ赤にしながら果林ちゃんと桔梗さんを追う。口調は怒っているが、顔は笑っている。
桔梗さんも果林ちゃんも、きゃあきゃあと声をあげながら身をかわしてロビーの中を水菜さんから逃げ回る。
「こら、待ちなさい!」
水菜さんもソファの間をぬって、逃げ回る二人を追いかけ回す。
僕はぽかんとしてその様子を眺めた。
捕まったのは桔梗さん。
袖をつかまれてその場にぺたんと座りこんだ桔梗さんに、水菜さんが両手を回して覆いかぶさった。そのまま二人で笑い転げる。
そこに果林ちゃんがダイブ!
三人とも、僕がいることも忘れて、まるで幼い子どものように笑っている。
ふと気づくと、少し離れたところから蘭さんがその様子をうれしそうに見つめていた。
第八章 はじまりの朝 〈五〉
座敷の窓からは朝のやわらかい日差しが差し込んでいる。庭の緑が目にまぶしい。すべてのものが、あらん限り自らの生命を主張しているかのようだ。
朝食が運ばれてくるのを待っていると、夕介が入ってきた。
トレードマークのあごひげが、ない。
「おはよう、なんだかやけにすっきりしたね」
「ああ、これか? 今朝剃った。何年かぶりだ」
どっかと腰を下ろした夕介はそう言ってひげのないあごを左手で撫でる。
「ちょっと落ち着かんが、まあすぐに慣れるだろ」
「そっちの方がいいと思うよ。胡散くささがだいぶ薄れた」
僕がそう言うと夕介は苦笑いで答えた。
「おはようございます。夕介さん、昨日は眠れましたか? ……あら、ずいぶんさっぱりされたんですね?」
蘭さんがお膳を持って座敷に入ってくるなり、夕介を見て驚く。
「長年の重荷を降ろしたような気分です。俺も、自分でかけた呪いに、縛られてたのかもしれません」
夕介はそう言って蘭さんに笑みを返した。
「次に来るときは、俺一人じゃ来ませんよ」
「ふふ、じゃあ楽しみにしてますね」
蘭さんはそう言って僕の前にお膳を置いた。
「夕介さんの分もすぐにお持ちしますから、少々お待ちくださいね」
二人とも、昨夜あんな真剣なやりとりをしたばかりだとは思えないほど普段通りの表情だ。僕も経験を重ねたらこんなふうになれるのだろうか?
僕は夕介を待たずに食事を始めた。夕介もそれを気にする様子はない。
「お待たせしました」
声がして座敷の入口を見ると、立っていたのは蘭さんではなかった。
「桔梗、お前──」
夕介が絶句する。
桔梗さんは蘭さんと同じ藤色の無地の和服に前掛けを着け、長い黒髪を後ろできちんとまとめている。
「まだ声がこまい(小さい)ね、桔梗。お客様の前に立つんじゃったら、ちゃんと声を出せるようにならんと」
後に続いて入ってきた蘭さんが指導すると、桔梗さんは振り向いて小さくうなずいた。
「ちゃんと返事」
「はい」
「よろしい」
蘭さんは厳しい口調ながらもちょっとうれしそうだ。
桔梗さんが夕介のお膳をゆっくりと置く。摺足の立ち居ふるまいは、稚児舞の時のように美しい。
「桔梗がここの仕事を手伝いたいなんて言うとは、思ってもみませんでした。早速今日から仲居修行です」
蘭さんの言葉に、桔梗さんは少しはにかみながらうなずいた。
「そうそう森崎さん、水菜からこれを預かっています」
そう言って蘭さんが僕に差し出したのは小さな封筒。淡いグリーンの地に四つ葉のクローバーが描かれている。
「今朝出がけに私にことづけたんです。渡してもらえばわかるからって」
「ありがとうございます」
僕は心臓が高鳴るのを感じながら封筒を受け取った。
朝食どころではない、あわてて封筒を開ける。
中には同じく淡いグリーンの一筆箋が一枚。そこに手書きの小さな文字で一言、こう書いてあった。
ごめんなさい。
みずな
僕は思わず肩を落として息を吐いた。
桔梗さんが僕の手元に目を凝らしている。
封筒には昨晩僕が書いて渡したメモも入っていた。つまり、そういうことだ。
僕は一筆箋を封筒に戻すとお膳の脇に置き、茶碗を手に取った。
「どうだ?」
夕介が僕に尋ねる。
「ごめんなさい、だって。多分そうだろうって思ってたけど」
「そうか」
夕介はそれ以上何も言わなかった。
座敷の入口に控えて座った桔梗さんがじっと僕のことを見つめている。
「ご飯はおかわりもありますから、必要でしたら桔梗にお申しつけください」
蘭さんはすべてを察した上であえて触れず、座敷から出ていった。
昨日の寝る前には、もし断られたらぼろぼろに泣くんじゃないかと思ったりもしたが、全然そんなことはなかった。むしろすっきりした気分だ。
「ま、結果はどうあれ、お前は一歩踏み出した。それだけでも十分だろ」
夕介はそう言ってみそ汁をすする。僕は黙ってうなずいた。
座敷の外からばたばた足音が近づいたと思ったら、入口のふすまが勢いよく開いて果林ちゃんが顔を出す。
「あーえかった、間に合った! あ、きぃねえちゃんかわいー! なーなー浩司さん、どうじゃったん?」
ふすまを開けると同時に大声でしゃべる果林ちゃんは、初日と同じようにブレザーにポニーテール。ローファーを脱ぐのを面倒がって、ひざ立ちで座敷に入ってきた。学校に出かける前にわざわざ顔を出してくれたようだ。
「だめだった」
「あーあ、やっぱり。ごめんね、みず姉へんくう(気難し屋)じゃけなー」
果林ちゃんは僕に手を合わせて謝る。
「いや、やっぱり僕じゃ水菜さんにはつりあわないよ。でも、ちゃんと言えてよかった」
「うん、昨日の浩司さん、カッコえかった」
果林ちゃんは左手をたたみに突いて、僕に向けて右手の親指をぐっと出した。うれしいことを言ってくれる。
「果林、お前がコイツとつきあえばいいじゃねーか」
夕介が茶化す。
「それとこれとは話が別ーっ!」
果林ちゃんは夕介に舌を出した。
「あれ、夕介のひげがない!」
「なんだ、いまごろ気づいたのか。ま、ちょっとしたイメージチェンジだ」
「母さんにふられたけえ?」
「それは関係ない」
にやにやする果林ちゃんに対して、夕介は腕を組んで憮然としている。
「うちはそっちのがさわやかでカッコええと思うよ」
「そりゃどうも」
無理に難しい顔をしている夕介がおかしくて、僕は笑いをこらえるのに必死だ。
「あ、そうだ果林ちゃん」
僕は果林ちゃんに言おうと思っていたことを思い出した。
「元彼と、きちんと話した方がいいよ。大事なことは、メールとかじゃなくて、やっぱりきちんと伝えた方がいいから」
「うん、そうする」
果林ちゃんは軽く肩をすくめてうなずく。
「次はつきあう『前に』考えろよ!」
「もー、わかっちょるっちゃ!」
夕介が釘を刺すと、果林ちゃんは夕介に向かって再び舌を出した。
「あ、やば! 遅れるけえ行くね。きぃねえちゃん、がんばって! 二人とも、ありがとね!」
果林ちゃんは一方的にそれだけ言うと、僕らの返事も聞かずにばたばたとあわただしく出ていった。
「やれやれ、朝から嵐みたいなやつだな」
夕介が苦笑しながらつぶやいた。
尋瀬駅までは夕介が送ってくれることになった。
「森崎さん、よろしかったらぜひまたいらしてくださいね」
チェックアウトの手続きをしながら蘭さんはそう言った。
桔梗さんは桑田さんと一緒に僕と夕介の荷物を車に運び入れてくれている。
「なんか、人生を変える旅になったような気がします」
「ふふ、光栄です。今度はかわいい彼女と一緒に来れるといいですね」
「へへ、だといいですけど」
蘭さんの言葉に僕は思わず照れ笑いをしてしまった。
「夕介さんも、今度は彼女同伴じゃなかったら、予約受け付けませんからね」
「ええ、がんばります」
蘭さんが右手の人差し指を口元に当てていたずらっぽく笑いながら言うと、夕介は頭をかきながら苦笑いを返した。
カウンターの上から年光さんの写真が僕に笑いかけてくれている。
お前の人生は、今、ここから本当に始まるんだ。
やりたいと思ったことは、何でもやってみたらいいさ。
彼の笑顔はそう言って僕を励ましてくれているような気がする。
「また、年光さんに会いに来ます」
「ええ、いつでもお待ちしていますよ、年光と二人で」
僕がそう言うと、蘭さんもにっこりとほほ笑んだ。見えないけれど、その隣で年光さんが一緒に笑っているのを、確かに感じた。
「この度は、桐葉荘をご利用いただき、本当にありがとうございました。是非また、おいでませ」
蘭さんがカウンターから出てていねいに頭を下げた。荷物の積み込みを終えた桑田さんと桔梗さんも玄関脇に並んで、僕らにお辞儀をする。
「お世話になりました」
僕も精一杯の気持ちを込めて言葉を返した。
ありふれた言葉でもいいから、とにかくなんとか感謝の気持ちを表したかった。
「よし、じゃあ行くか」
夕介がどこか晴れやかな表情で言った。
蘭さんと桔梗さん、桑田さんが門の前に整列して手を振ってくれる。
夕介が車をゆっくりとスタートさせると、僕は窓を開けて振り返った。
桔梗さんが二・三歩駆けだして僕に大きく手を振る。
「ありがとう!」
頬を赤く染めた桔梗さんが大きな声で叫んだ。
僕も手を振ってそれに応えたが、下り坂に入って三人の姿はすぐに見えなくなってしまった。
「やれやれ、終わってみれば、ふられ男が二人、か」
夕介がステアリングを握りながらぼそりとつぶやく。
「まあ、いいんじゃない?」
僕はサングラスをかけた夕介の横顔にそう返した。
「確かに二人ともふられはしたけど、やるべきことはやったんじゃないかな?」
「やるべきこと、か。まあ、確かに俺は後悔してないな」
「僕だって。だからいいんじゃない? 何でもやってみなきゃわかんないわけだし」
「なんだ、年光さんに影響されたか?」
「ああ、多分。さっき写真の年光さんから『お前の人生はここから本当に始まるんだ』って言われたような気がした」
僕がそう答えると、夕介はサングラスの下で少し神妙な目をした。
「まったく、大した人だ。死んでからも人に影響を与えるんだからな。俺なんかじゃ全く歯が立たないわけだ」
雲ひとつない、いい天気だ。開けたままの窓から入るさわやかな秋の風が頬に心地いい。
「さあて、帰ったら締切と格闘かあ」
「記事が載るときには教えてくれよ、僕も読むから」
「ふん、お前なんかにわかるのか?」
「失礼だな、一応僕だって現場で観たんだ。それに、アンタの撮った写真を見てみたい」
「じゃあ、昨日の写真を送る時にでも教えてやるよ」
車は朝の陽光を受けてきらきらと光る宇侘川のせせらぎと並走する。
ふと、道端に咲く一群のコスモスが目に入った。来たときには全く気がつかなかった。
薄紫色の花がひとつひとつ、空に向かって力いっぱい伸びあがって風に揺られている。
それに気づいた自分が、なんだかうれしい。
尋瀬駅に着いて、自分の荷物をトランクから下ろすと、僕は運転席の夕介に声をかけた。
「色々ありがとう、おかげでいい旅になったよ」
夕介はサングラスを額にずらしてにやっと笑う。
「サボったせいで留年すんなよ」
まったく、この男はこの期に及んでもこんな憎まれ口をたたくんだ。
「そっちこそ、記事落とさないように気をつけろよ」
僕も負けずに言い返した。
「くくっ、まあもう二度と会うことはないだろうが、せいぜい元気でやるんだな」
「ああ、そっちも」
「じゃな」
夕介は短く言うと軽く右手を上げた。
夕介のSUVは駅前の広場から道路に出て、すぐに見えなくなった。
第八章 はじまりの朝 〈六〉
僕は切符を買うと狭い階段を通ってホームに上がった。一両だけのディーゼルカーの中には数人の乗客がまばらに座っている。
ボックス席に腰かけ、荷物を横に置いて発車を待つ。窓から日の光がさんさんと降り注ぎ、まぶしいくらいだ。
「あの、ここいいですか?」
「あ、あいてます、どうぞ」
後ろから若い女性に声をかけられ、振り向いてから僕は驚いて言葉を失った。僕に声をかけたのは、市役所の制服姿の水菜さんだ。
「え……なんで? とっくに出たんじゃ?」
発車を告げる録音のアナウンスが流れ、ドアが閉じる。
「えへへ、職場には途中で車が故障して清流線で行くから遅れるって、うそついちゃいました」
水菜さんは僕の耳元に顔を寄せてささやくと、僕の目の前に座った。ふわりといい香りが僕の鼻腔に残る。
彼女が席に着くのを待っていたかのように列車がゆっくりと動き始めた。
「やっぱり紙切れ一枚じゃ失礼かなって思って。仕事をずる休みするのって、初めて。ちょっとどきどきしますね」
彼女はいたずらっぽい表情で僕に笑いかけてくる。
列車は鉄橋を渡るとすぐにトンネルに入った。
「あの、森崎さんに『どこに行っても自分は自分のまま』って言われて、わたしいろいろ考えたんです。ずっとここから逃げたい逃げたいって思ってたけど、なんで逃げたかったんだろう、ここの何が嫌だったんだろう、って」
暗くなった車窓に、水菜さんのもの憂げな顔が映る。
エンジン音がトンネル内に反響するから、彼女は少し声を大きくした。
「でも、わかったんです。わたし、この町が嫌いだったわけじゃないんです。嫌いになるほどこの町のこと知らないし。父さんが好きだったこの町を、わたしは見ようともしてなかった」
水菜さんは一度言葉を切って、右手を胸元に置いた。
「本当は、わたしは自分が嫌いだっただけ。いつまでも前の学校の友達にこだわって、新しい友達を作れなかったわたし。父さんの夢を素直に応援してあげられなかったわたし。母さんのため桔梗のためって言い訳して、自分から目をそらしてたわたし。逃げ出したかったのは、本当は、そんなわたしからだったんだって」
列車はトンネルを抜けて再び明るい陽の光の中に躍り出た。
錦美川の川面が陽光を反射して水菜さんの顔を照らし、彼女は少し目を細めて窓の外を眺めた。彼女の細い髪が、陽の光を受けてきらきらと輝く。
「自分から逃げ出すことなんて、できるわけないのにね」
彼女は右に左に蛇行する錦美川に寄り添うように並走する国道を、ぼんやりと眺めながらつぶやいた。
「わたし、人柱になろうとしてたのかな。誰に頼まれたわけでもないのに、勝手に自分を犠牲にしようとしてたのかも」
僕は黙ってうなずきながら彼女の話を聞いていた。
彼女は僕に何を伝えたいのだろう?
録音のアナウンスが車内に流れ、列車はゆっくりと駅に入って停車する。
「わたしの時間は、ずーっと止まっていたんだ。きっと桔梗と一緒、心を凍らせてたんだ」
水菜さんはそこまで言うと、少し黙りこんだ。
小さな無人駅のホームに乗客の姿はない。
ドアの閉まる音がして、列車はエンジン音を上げながらホームを離れた。
「でも、桔梗だって変わることができた。あの子を変えるなんて絶対無理って思ってたけど、そんなのわたしの勝手な思い込みだった」
そう言って水菜さんはじっと僕の目を見つめた。
僕はわざと彼女から目をそらして、窓の外を眺めた。
シラサギが一羽、錦美川の川面を滑るように飛んでいく。
「わたしも、変わろうと思うんだ。すぐにはできないかもしれないけど。今まで逃げてきたわたしと、ちゃんと向き合おうって、決めたの」
水菜さんはまっすぐ僕を見つめてそう告げた。
「だから、ずる休みしちゃった」
「ええ? なんでそうなる?」
それまで息を詰めて聞いていた僕は、その一言に思わずコケた。
そんな僕を見て彼女はふふっとほほ笑む。
「今までだったら、絶対こんなことしなかったと思うんだ、わたし。自分で言うのも変だけど、わたしマジメだったから。でもそれは、ラクしてただけなんだと思うな」
「ラクしてた?」
「だって、自分で心を働かせなくていいでしょ? 場の『空気』に従ってるだけでいいもん」
水菜さんは胸元に右手を置いてそう言う。
「マジメな子を演じてたってこと?」
「んー、演じてたんじゃなくて、自分で自分がわかんなくなってたのかな。何が欲しいのかとか、何がしたいのかとか」
僕には彼女が一体何を思ってこんなことを打ち明けてくるのかがわからない。
「でも、森崎さんがちゃんとまっすぐ好きだって言ってくれたんだから、だめならだめでわたしもちゃんと答えなきゃって思ったら、なんだかじっとしていられなくなって──ごめん、期待させちゃったかな?」
そう言って肩をすくめてはにかんだ水菜さんは、初めて会ったときの落ち着いた印象とはずいぶん違う。
「けど、めんどくさいって言ってくれたのはちょっと──ううん、ぶち(すごく)、うれしかった。ちゃんと素のわたしを見てくれたんだなって」
彼女はぎこちなく方言を交えてそう言ったが、言った後に自分で照れている。
「でも、僕とはつきあわないんだろ? なんで?」
僕としては一番確認しておきたいところだ。
彼女の態度はなんだか言っていることとちぐはぐな気がする。せっかく諦めようとしたところなのに、このままでは断ちきれなくなりそうだ。
「だって、恋愛なんかしたことないのに、いきなり遠距離なんてハードル高すぎだもん」
「そこかよ……」
彼女の無邪気な答えに、僕は思わず脱力した。なんだかあれこれ考えていたのがばからしく思えてくる。
「わたしね、まず友達が欲しいと思うんだ。恋愛は難易度高すぎだから。どうしたらいいのかよくわかんないけど」
「そんなこと僕に言われても……僕だって友達いないのに」
僕がそう答えると、水菜さんはうれしそうに身を乗り出してくる。
「じゃあさ、わたしたち友達いない同士で友達ってことで!」
「なんだよそれー、すっげーネガティブ!」
水菜さんが満面の笑みで変なことを言うから、僕も思わず笑ってしまった。笑いながら、ずっと心の中でこわばっていた何かがほぐれていくのを感じる。
「今のこのままでいいんじゃないかな? こんな風に素を出していけば、きっと友達もできると思うよ」
「そっか、そうだよね」
彼女は僕の言葉に素直にうなずいた。
水菜さんはそれから小一時間たっぷり、いろいろなことを僕にしゃべり続けた。
仕事のグチをつぶやいたかと思うと、小さい頃の思い出を話してみたり、突然好きなタレントの話をしてみたり。
あっちこっちに話が飛ぶから全体として何が言いたいのかはよくわからないけど、しゃべっている彼女は、なんだかとても楽しそうだった。
「ごめんね、わたしばっかりしゃべって。わたしって、こんなにしゃべりたい人だったんだなあ」
「いや、いいよ。話聞くのは別に苦にならないから」
「父さん以外の男の人とこんなに話したの初めてかも。父さんにはいつもたくさん聞いてもらってたんだけどね」
水菜さんはそう言ってふわりと笑った。
こんな感じの脈絡のない話に毎日のようにつき合ってたんなら、年光さんもなかなか大変だったろうなあと、僕は内心同情する。
車内に終点を告げるアナウンスが流れ始めた。
列車が住宅街を抜けて建設中の高層マンションをかすめながら左カーブを曲がると、前方に終点の岩代駅が見えてきた。
僕はここで乗り換え、水菜さんは仕事に向かう。僕の旅も、もうすぐ終わりだ。
列車はゆっくりとホームに入って静かに停まった。
「じゃあ、僕はここで」
「うん、ありがとね」
立ち上がった僕に、水菜さんは同じように立ち上がって、右手を差し出してきた。
僕は一瞬ためらったけれど、彼女の右手を軽く握った。
「じゃ、また」
「うん」
僕が告げると、彼女も軽くうなずいた。
握手した右手はすぐにほどけた。彼女の体温がうっすらと僕の右手に残る。
ホームに降りると、僕は乗り換えのために階段に、彼女は改札口に向かう。
振り返って彼女を見ると、彼女も僕を見て小さく手を振ってくれた。僕も手を振り返す。
改札口を出た彼女は、雑踏の中、背筋を伸ばして歩いていく。
もう振り返らない。
僕はまだ彼女の手のぬくもりがかすかに残る右手をちょっと見つめてから、階段を上った。
こうして、僕の短い恋は終わった。
〈第八章終わり〉
エピローグ
ご招待状
拝啓 花の便りがうれしい今日このごろ、みなさまにおかれましてはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。
平素は深津峡温泉・桐葉荘に格別のご厚情を賜り、心より御礼申し上げます。
さて、早いもので、私どもの創業者である故・桐島年光がこの世を去ってこの四月で六年、本年は七回忌の節目を迎えることとなります。
昨年の創業十周年の折には、特にお知らせしなかったにもかかわらず、たくさんの方から数々のお祝いの言葉を頂戴いたしました。
創業者が遺したこの小さな小さな桐葉荘が、みなさまにかわいがっていただいていることを肌で感じるとともに、従業員一同、改めて身の引き締まる思いでございます。
そこで、十周年の際の御礼も兼ねて、創業者にゆかりのあるみなさまに何かご恩返しをと思い、この度宇侘川パレスホテル様にもご協力をいただき、『桐葉荘 観桜の宴』を催すことと相成りました。
何よりこのようなイベントが大好きだった創業者に倣い、様々に趣向を凝らした催しを予定しております。
みなさまにおかれましてはご多用中かとは存じますが、お時間が許せばぜひ和やかな雰囲気でゆっくりとお楽しみいただければ幸いです。
末筆ながら、みなさまのご健康とご多幸をお祈り申し上げ、まずは取り急ぎご案内申し上げます。
かしこ
平成二×年三月吉日
桐葉荘 桐島 蘭
四月の穏やかな錦美川沿いの景色の中を走る一両だけのディーゼルカーに揺られながら、僕は改めて招待状を読み返していた。
三月にこの招待状が送られてきたときにはびっくりした。
「創業者にゆかりのあるみなさま」に、年光さんに一度も会ったことのない僕が含まれていてもいいのだろうか。
でも、素直にご招待を受けることにしたのは、僕の今の姿を蘭さんたちに見てもらいたいと思ったからだ。
あれからもう、半年が経つ。
大学生活に戻った次の週から、僕は近所のコンビニでアルバイトを始めた。
アルバイト募集のポスターを見て即決で面接を申し込んだ。今まで短期のバイトはいくつかやってきたが、継続的に働くのは初めてだ。
それまでは自分には接客なんて無理だと思っていたが、やってみると案外できるもので、店長からはあいさつの声がいいと褒められた。
バイト仲間たちともだんだんと打ちとけて、今では何人かで時々一緒に飲みに行ったりもする。
中にはちょっと気になっている子もいる。
同じ学部の後輩なんだけど、彼女は一浪してるから同じ歳で、でもバイトは彼女の方が半年ばかり先輩。はっきりとしたもの言いをするので、仕事上では全然頭が上がらない。
口の悪い同僚からは、あんな気の強いやつなんかやめとけなんて言われるけど、僕はふとした時に見せる彼女の何気ない表情がかわいいと思うから、近いうちに絶対デートに誘おうと思っている。
夕介からは、一ヶ月ぐらいしてから約束通り写真が送られてきた。
みんなが笑顔の中、夕介だけがそっぽを向いてぶすっとしている写真。思わず笑ってしまった。
お礼のメールを送ったが、返事は返ってこなかった。いかにもあいつらしい。
年末には、あいつの記事が載った雑誌も買った。普段だったら僕が絶対手に取らないような、お堅い月刊誌だ。
あれだけたくさんの写真を撮ってたくさんの資料を用意したのに、記事はたったの八ページ。しかし美麗な写真とていねいな文章であの時の感動が甦る、読みごたえのあるものに仕上がっていた。
認めるのはなんだか悔しいが、確かに夕介には才能があると思う。
記事には稚児舞の時の桔梗ちゃんの写真も載っていた。小さな写真だったが、遠い目で舞う彼女の横顔は、すがすがしい美しさを放っていた。
実は、桔梗ちゃんとはあれからずっと文通している。
このIT全盛の時代に、手書きの手紙をやりとりすること自体が珍しいのに、「ペンフレンド」なんてほとんど絶滅危惧種だと思うが、十日に一度くらいの割合で彼女から手紙が来るので、僕もせっせと返事を書いている。
最初に来た手紙ではたどたどしかった字が、最近はだいぶしっかりしてきた。時々いきなり難しい言葉が出てきたりするから、国語辞典は手放せないが、内容は十代の女の子らしいもの。
桔梗ちゃんは、水菜さんや果林ちゃんの近況も知らせてくれる。
今年一月の成人式で中学校時代の同級生と再会した水菜さんは、「昔はなんかとっつきにくかったけど桐島さんずいぶん変わったよね」と言われたことをうれしそうに桔梗ちゃんに話していたそうだ。
成人式が終わった後に、長かった髪をだいぶ切ったというから、今はずいぶん印象が変わっているだろう。最近は、話していると時々方言も混じるようになったそうだ。
三月には市役所から徒歩十分の所にアパートを借りて、一人暮らしを始めたという。
果林ちゃんはあいかわらずたくさんの友達に囲まれて、毎日にぎやかに過ごしている。
水菜さんが家を出てからは桔梗ちゃんと二人で家事を分担しているが、果林ちゃんのとんでもない失敗を、桔梗ちゃんがいちいち面白おかしく報告してくれる。
そして桔梗ちゃんは、この四月から高校生になった。
果林ちゃんの通う県立高校の分校ではなく、数年前に錦美町に開校した通信制高校に通うそうだ。
桔梗ちゃんが進学すると決めてからは、水菜さんがつきっきりで勉強を見てくれたという。
学業に支障が出ない範囲で、仲居修行も続けていくつもりらしい。
手紙の文面からは、新しい生活にわくわくしている桔梗ちゃんの様子がよく伝わってくる。
彼女からの報告をひとつひとつ喜んでいる自分を発見してうれしくなる。
それぞれが、それぞれのスタートを切っている。
列車が満開の桜のそばを通り過ぎ、窓辺に薄紅色の花びらが舞う。半年前に来た時には沿線にこんなにたくさんの桜があるとは思いもしなかった。
「散る故によりて、咲く比あれば、珍しきなり(註一一)……か」
僕は覚えた『風姿花伝』の一節をつぶやいた。
年光さんは最後の桜の花を、どんな気持ちで眺めたのだろう。かすれた声で笑ったという蘭さんの話が、今でも鮮明に甦る。
四季を移ろうなかで、かわるがわる咲き続ける花。
彼はきっと死んでなんかいない。今も生き生きと僕に語りかけてくれているのだから。
彼の言葉は、彼とかかわった人たちの中で、今も生き続けている。
そして、僕もその言葉を受け渡されたんだ。
何気なく錦美川を挟んで走る国道を眺めていると、見覚えのある車を見つけた。側面に原色のド派手なステッカーを貼り付けたシルバーのSUV。
「あれ?」
忘れるわけもない、夕介の車だ。
僕はすぐさま携帯で電話をかけた。
『もしもし?』
少し不機嫌な声で夕介が出る。
「なんでアンタがこっちにいるんだよ」
『ああ? お前今どこだ? は……なるほど、清流線か』
「運転中の携帯電話は道路交通法違反だぞ」
『バカ、ハンズフリーだ。あいかわらずよけいなことばっかり……だいたいお前こそ何でこっちに来てんだよ?』
「へへーん、僕も観桜の宴にご招待を受けたんだよ」
『はあ? 俺はわかるが、なんでお前が?』
「いいだろ、別に。蘭さんが招待してくれたんだから」
『ふん、まさかまた会うことになるとはな』
半年ぶりに話す夕介は以前と全然変わっていない。あいかわらずの憎まれ口に、僕は思わずにやにやしてしまう。
携帯から、ねえねえ誰なのと尋ねている声が聞こえる。少し鼻にかかったようなかん高い女性の声。
「なに今のアニメ声? 誰か一緒なのか?」
『もしもーし! はじめましてぇ、わたし裕美っていいまぁす、あなたは夕介君のお友達ぃ?』
かん高い声が響いて、僕は一瞬携帯から耳を離した。
「友達じゃないけど知り合いです」
『コラ、裕美! 運転のジャマだ、どけよ。だいたいお前、俺よりも五歳も下なんだから、いいかげんその夕介君ってのやめろ』
『えー、夕介君は夕介君じゃない!』
思わず苦笑いがもれる。あの夕介が完全に振り回されている。
「ゆみさんはもしかして、夕介の彼女さんですか?」
『はいはーい、もしかしなくても夕介君の彼女さんでーす! 旅行雑誌の編集部に勤めてまぁす!』
尋ねてもいないことにまで彼女は勢いよく答える。僕は再び携帯から少し耳を離した。夕介の困惑している顔が目に浮かぶようだ。
『桐葉荘は二人の思い出の場所だもんねー』
『はあ? 何言ってんだお前? 俺はお前と桐葉荘に行ったことなんかないぞ』
『んふふふふー、やっぱり忘れてるぅ! 夕介君、わたしとは仕事で出会ったんだと思ってるんでしょ?』
『違うのかよ?』
『教えなーい! さー、二人の思い出の場所へ、ゴーゴー♪』
『なんだよ気になるだろ、勿体つけずに教えろよ!』
「……まあ、二人ともお幸せにね」
僕はあきれながら電話を切った。
錦美川の川面が、春の柔らかな日差しを受けてきらきらと輝いている。
列車が桜並木にさしかかり、車窓はさっと一面の薄紅色で覆われた。
僕は窓に顔を付けて桜並木を見上げた。
鮮やかな青空のもと、桜の花びらがはらはらと舞い落ちていく。本格的な春は、まだまだこれからだ。
列車は線路の継ぎ目で軽快な音を立てながら、満開の桜並木の中を駈け抜けていった。
了
────────────────────
註一一 花傳第七 別紙口傳より(引用は岩波文庫「風姿花伝」野上豊一郎・西尾実校訂から。字体は新字体に改めた)
資料編
◆参考文献一覧
『青い鳥』モーリス・メーテルリンク著 堀口大學訳 新潮文庫 新潮社(1960)
『一歩進めて能観賞 演目別にみる能装束』観世喜正・正田奈津子著 青木信二撮影 淡交社(2004)
『NHKテレビテキスト100分で名著 世阿弥 風姿花伝』土屋惠一郎 NHK出版(2014)
『お能の見方』白洲正子・吉越立雄著 新潮社(1993)
『劇場に行こう 能にアクセス』井上由理子解説 淡交社(2002)
『死後のプロデュース』金子稚子 PHP新書 PHP研究所(2013)
『死者との対話』若松英輔 トランスビュー(2013)
『自然が舞台の野外劇 薪能入門 かがり火が照らし出す幽玄の世界』婦人画報あるすぶっくす12 婦人画報社(1994)
『死とどう向き合うか』アルフォンス・デーケン NHK出版(1996)
『死とは何か さて死んだのは誰なのか』池田晶子著 わたくし、つまりNobody編 毎日新聞社(2009)
『魂にふれる 大震災と、生きている死者』若松英輔 トランスビュー(2012)
『能がわかる100のキーワード』津村禮次郎 小学館(2001)
『能の女たち』杉本苑子 文春新書 文藝春秋(2000)
『能のデザイン』井上由理子 青幻社(2009)
『能・謡曲選』松田存・西一祥編 翰林書房(1993)
『風姿花伝』世阿弥著 野上豊一郎・西尾実校訂 岩波文庫 岩波書店(1958)
『ふるさと玖西の歴史と民話』玖西青年会議所編 玖西青年会議所(1988)第一篇二章「鞍掛合戦」(pp.47-76)内田陽久著
『僕の死に方 エンディングダイアリー500日』金子哲雄 小学館(2012)
『法華経方便品・寿量品講義 上・下(普及版)』池田大作 聖教新聞社(2013)
『「喪」を生きぬく』石村博子 河出書房新社(2005)
『和の色手帖』武井邦彦監修 石田純子著 グラフィック社(2004)
(書名50音順)
◆参考映像資料
『能楽 観阿弥・世阿弥名作集』シリーズ(NHK DVD)
宝生流『通小町』宝生九郎/観世流『自然居士』梅若六郎(玄祥)
観世流『求塚』観世清和
金春流『高砂』金春信高/金剛流『清経』廣田陛一
喜多流『班女』友枝喜久夫
観世流『砧 梓之出』関根祥六
喜多流『融』友枝昭世
◆引用一覧
エピグラフ
「そもそも、花と云ふに、萬木千草において、四季(折節)に咲く物なれば、その時を得て珍しき故に、翫ぶなり。申楽も、人の心に珍しきと知る所、即ち面白き心なり。花と、面白きと、珍しきと、これ三つは同じ心なり。いづれの花か散らで残るべき。散る故によりて、咲く比あれば、珍しきなり。能も住する所なきを、先づ、花と知るべし。」
世阿弥『風姿花伝』(岩波文庫)p.92 花傳第七 別紙口傳
第四章 五
「人の心に珍しきと知る所、即ち面白き心なり」
世阿弥『風姿花伝』(岩波文庫)p.92 花傳第七 別紙口傳
第四章 六
「一切の事は、謂はれを道としてこそ、萬の風情にはなるべき理なれ。謂はれを現はすは、言葉なり」
世阿弥『風姿花伝』(岩波文庫)pp.83-84 花傳第六 花修云
第五章 六
「いづれの花か散らで残るべき。散る故によりて、咲く比あれば、珍しきなり。能も住する所なきを、先づ、花と知るべし。」
世阿弥『風姿花伝』(岩波文庫)p.92 花傳第七 別紙口傳
第七章 一
「ずっと、ずっと大昔/人と動物がともにこの世に住んでいたとき/なりたいと思えば人が動物になれたし/動物が人にもなれた。(後略)」
池田晶子『死とは何か さて死んだのは誰なのか』(毎日新聞社刊)所収 p.225『魔法のことば』金関寿夫訳/柚木沙弥郎絵 (初出は『伝え合う言葉 中学国語3』2006年度版 教育出版刊。初出時に池田晶子著『言葉の力』と併録されたため、訳と絵も併せて同書に採録されたものである)
「言葉と自分が一致していない人生は不幸だ。だから、本当の自分はどこにいるのかを、探し求めることになる。しかし、本当の自分とは、本当の言葉を語る自分でしかない。本当の言葉においてこそ、人は自分と一致する。言葉は道具なんかではない。言葉は、自分そのものなのだ」
池田晶子『死とは何か さて死んだのは誰なのか』(毎日新聞社刊)所収 pp.223-224『言葉の力』より(初出は『伝え合う言葉 中学国語3』2006年度版 教育出版刊)
「だからこそ、言葉は大事にしなければならないのだ。言葉を大事にするということが、自分を大事にするということなのだ。自分の語る一言一句が、自分の人格を、自分の人生を、確実に創っているのだと、自覚しながら語ることだ。そのようにして生きることだ」
池田晶子『死とは何か さて死んだのは誰なのか』(毎日新聞社刊)所収 p.224『言葉の力』より(初出は『伝え合う言葉 中学国語3』2006年度版 教育出版刊)
第七章 二
「先ず、童形なれば、何としたるも幽玄なり」
世阿弥『風姿花伝』(岩波文庫)p.13 花傳第一 年来稽古條々 上
エピローグ
「散る故によりて、咲く比あれば、珍しきなり」
世阿弥『風姿花伝』(岩波文庫)p.92 花傳第七 別紙口傳
あとがき
「自分というものが『ない』と知ることによってこそ、人は個性的な人になる。こうとしかできない自分を知る」
池田晶子『知ることより考えること』(新潮社)所収『探すのをやめよ』より
◆出典一覧
作中の猿楽『紫桜』の詞章は、現存する謡曲等から引用または改変して作者が創作した。原典のあるものを以下に明示しておく。
『桜堤』
「春の雲路の旅衣 春の雲路の旅衣/宇侘の早瀬の 先へ急がん」
『求塚』 ワキ(次第)「鄙の長路の旅衣、鄙の旅路の長路の旅衣、都にいざや急がん」
「これは 石見の国より出でたる某にて候/商ひにて急ぎ参り仕らんとて/宇侘川をくだり候間 美しき桜の堤にあへり」
『求塚』 ワキ・ワキツレ「これは西国の方より出でたる僧にて候、我いまだ都を見ず候程に、只今思ひ立ち都に上り候」
「いかにこれなる人に 尋ね申す事の候/げにも美事なる桜にて候ぞ さても名にし負ふ桜にてや あらんずらん/この桜の謂われ もし存知なれば お教え候へ」
『求塚』 ワキ「いかにこれなる人に尋ね申すべき事の候、生田とはこの辺を申し候か」
「はや花風にて舞いたると 思うほどに/花曇にかき乱れて/跡も見せずなりにけり 跡も見せずになりにけり」
『融』 地「潮曇にかき紛れて、跡も見えずになりにけり跡をも見せずなりにけり」
「何時まで草の陰 苔の下には埋れん/さらば埋れも果てずして 苦しみはなおも離れず/あら閻浮恋しや 閻浮恋しや」
『求塚』 地「あら閻浮恋しや」 シテ(上歌)「(中略)何時まで草の陰苔の下には埋れんさらば埋れも果てずして、苦しみは身を焼く、火宅の住処御覧ぜよ」(順序異同)
「姿形も朧となり行けば いよいよ思ひは 消え消えと/見えつ隠れつする程に 東雲の空も ほのぼのと/明け行けば跡もなく ただ櫻の花の舞うばかりとこそ/哀れなりけれ 哀れなりけれ」
『隅田川』 地「いよいよ思ひは真澄鏡、面影も幻も、見えつ隠れつする程に東雲の空も、ほのぼのと明け行けば跡絶えて、(中略)哀れなりけれ哀れなりけれ」
『寂水』
「遂に巌の汀に 追われ給ふが/南無や八幡大菩薩と 心に念じ/剣を構へて 待ちかけ給へば/従者 鬼神の背より 打ちかかりて/振り向きたるを 切り払い給ふ」
『紅葉狩』 地「(中略)南無や八幡大菩蔭と、心に念じ、剣を抜いて、待ちかけ給へば、(後略)」
「夢か現か はやも異類となれる身の/重き罪科は 徒波の/寄辺も無き身 濁る心に逆巻きて/慕ひた父も 我が事も 憂しや思ひ出でじ/果てはみな忘れて狂ひけり みな忘れて狂ひけり」
『藤戸』 後シテ(サシ)「憂しや思ひ出でじ、忘れんと思ふ心こそ、忘れぬよりは思ひなれ、さるにても身は徒波の定めなくとも、科に寄辺の水にこそ、濁る心の罪あらば、重き罪科もあるべきに、(後略)」
『乙女淵』
「花も憂し 月も憂しと 捨つる世の/鄙の旅路の墨衣 鄙の旅路の墨衣」
『忠度』 ワキ(次第)「花をも憂しと捨つる身の、捨つる身の月にも雲は厭はじ」
「南無幽霊成等正覚 出離生死頓證菩提」
『通小町』 ワキ「南無幽霊成等正覚 出離生死頓證菩提」
「折節咲く花に/折節咲く花に 散る頃あるは定めとて/猶ほ咲く頃も あるべけれ/咲かずに散るは哀れなり 咲かずに散るは 哀れなり」
『風姿花伝』 花傳第七別紙口伝より 「そもそも、花と云ふに、萬木千草において、四季(折節)に咲く物なれば、その時を得て珍しき故に、翫ぶなり(中略)いづれの花か散らで残るべき。散る故によりて、咲く比あれば、珍しきなり」
「用荘厳法身/天人所載仰龍人咸恭敬/あらありがたやの御経やな」
『海士』 シテ「用荘厳法身」 地「天人所載仰龍人咸恭敬あらありがたやの御経やな」
「今この経の徳用にて/今この経の徳用にて あら不思議やな/淵に紫の花咲けり/紫の花の七歳咲けば/生死の大海 廻り渡りて/御恩を必ず報ずべし 御恩を必ず報ずべし」
『海士』 シテ(ノル)「今この経の徳用にて」 地「今この経の徳用にて、天龍八部、人与非人、皆遥見彼、龍女成仏さてこそ讃州志度寺と号し(後略)」
『霊山』
「かくて鄙人老姥の/舞ひて御前を立つと 見えうるが/花散り曇る 櫻木に/寄るかと見せて失せにけり 寄るかと見せて失せにけり」
『遊行柳』 地「かくて老人上人の、御十念を賜はり御前を立つと見えうるが、朽木の柳の中塚に寄るかと見えて失せにけり、寄るかと見えて失せにけり」
「草木繁る沓懸の つはものどもの今生の/残る無念は 止みもせず/物冷まじき 雨の折/幽かに聞こゆ 鬨の声/翻りゆく 旌旗見ゆ」
『陰徳太平記』(毛利氏の記録文書)「玖珂之鞍懸城没落事」より 「今も彼の鞍掛の古城の跡には、日暮れ雨降て物冷じき折からは、山頭に旌旗翻り、鬨の声幽かに聞えて恐ろしきことども多かりけり、これ古戦場なり」
「あらあはれやな/今はこの世に 亡き跡の/さても無慙や 敗れける/父は草生ひ茂りたる かの塚の/土の下にこそありてけり」
『隅田川』 (クドキ)「(中略)今はこの世に亡き跡の、標ばかりを見る事よ、さても無慙や死の縁とて、生所を去つて東のはての、道の傍の土となりて、春の草のみ生ひ茂りたる、この下にこそあるらめや」
「皆已具足」 法華経方便品第二より
※ 作中の「沓掛合戦」にまつわる記述は、史実「鞍掛合戦」に基づくものだが、地名や人名などの固有名詞については一部を架空のものに改変している。
※ 第八章の第二節・第三節については、主として、2012年に肺カルチノイドのために死去した故・金子哲雄氏の著書『僕の死に方 エンディングダイアリー500日』、及び金子哲雄氏の妻である金子稚子氏の著書『死後のプロデュース』を参考としている。金子夫妻が取り組んだ死への準備や病状の変化などについて類似する表現が少なからずあるため、ここに明示しておくこととした。
謡(うたい)