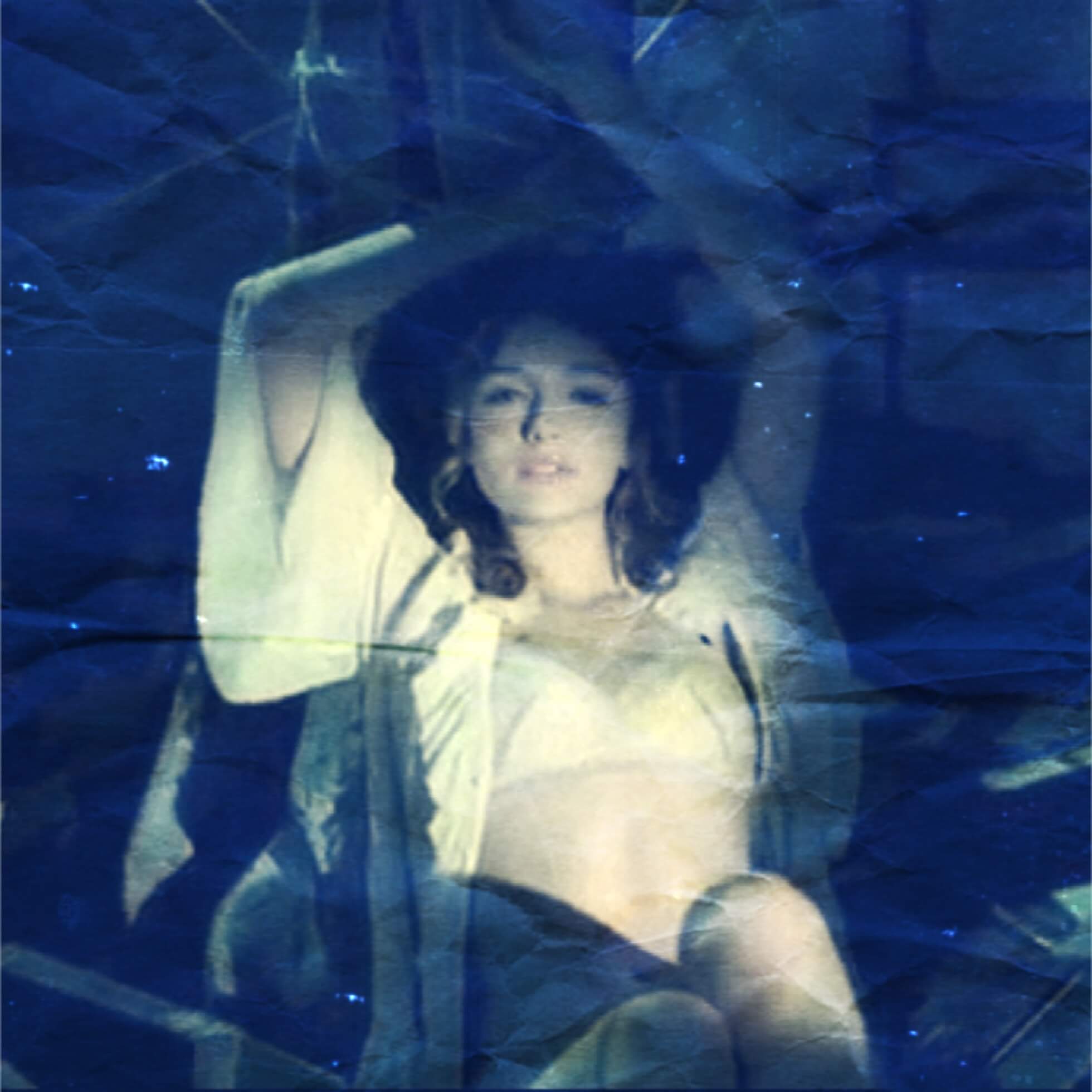
マネー・ドール
偽りの夫婦
午前零時半。深夜ラジオが俺に伝えた。
明日、いや、正確には、もう今日の打ち合わせの資料を書き上げ、クラウドへアップした。少し目が霞む。見た目は若いけど、こういう老化には勝てない。目薬をさし、十八階の窓から夜の街を見下ろす。しばらく眺めていると、マンションの前に白いプリウスが止まった。助手席から女が降りてきて、続いて運転席から男が降りてきた。そして、男が女を抱き寄せた。女は男の胸に顔を埋める。五秒か、十秒か……わからないけど、俺は、霞む目でその光景を眺めていた。霞む目が、疲れたからなのか、目薬のせいなのか、それとも……とにかく、目が霞んでいた。でも、あの、ベージュのトレンチコートは、つい数時間前に、見た気がする。いや、でも、あんなコートはどこにでもある。よくある、ベージュのトレンチコートだ。
男は名残惜しそうに女を離し、女は軽く手を振り、ゲートへ入っていった。
俺達は、美男美女のセレブ夫婦。どこに行っても、妻は美しく、華やかで、社交的。俺の半歩後ろに立ち、腕を絡め、優しい笑顔で相槌を打つ。
会社では企画部長を務め、ステイタスも高い。自立した、大人のオンナ。俺は妻が褒められるたびに、満足そうに笑う。
そう、俺は満足なんだ。お前は、俺のアクセサリーだから。そうやって隣で、俺好みの女で、笑ってればいいんだよ。俺を引き立てろ。そのために、俺は下げたくもない頭下げて、二十四時間働いてるんだ。お前の好きなカルティエやグッチ、なんでも買えよ。お前はそれで満足なんだろう?この家を見ろよ。都心のタワーマンション、ドイツ製のシステムキッチン、イタリア製の家具。車はベンツとBMW。俺はお前の愛を金で買う。お前は俺の金の奴隷なんだ。そう、どんなに俺がお前を愛しても、お前は、金しか愛せないオンナだからな。もういいんだ。俺達は俺達の『アイテム』で愛し合う。そうやって……もう、十五年……十五年。
それでいいと思ってた。
……玄関ドアが開くまでは。
リビングのソファに座る妻は、相変わらずいい女で、フロアランプとテレビの光で、白い肌が、妖艶に暗闇に浮かび上がっている。
「遅かったな」
「うん」
妻はテレビの画面に向かってぼんやりと返事をした。俺は、さっきの男のことを聞こうと思ったけど、もちろん聞けるわけもなく、飲みたくもない水を冷蔵庫へ取りに行った。バカでかい冷蔵庫の中には、缶ビールとインスタントコーヒーしかなくて、水はなかった。
「水、ない」
「そう、買っとく」
妻はもの想いに耽っている。いつもと様子が違う。女っぽいというか……エロい。そうか、あいつに抱かれてきたのか。あいつの体でも、思い出してるのか。
俺達は、もう何年もセックスをしていない。妻に欲情しないわけじゃない。いい女だからな。フツウに、隣にいればやりたくなる。
だけど、妻は俺を避ける。セックスは嫌なんだと。俺は妻への欲求不満を外にぶちまける。手当たり次第にオンナを抱いた時期もあった。でも、抱いても抱いても、俺の欲求不満は解消されないどころか、余計に虚しくなる。あからさまにオンナの匂いをさせていても、こいつは無関心。バカバカしい。他のオンナを囲う金は、妻につぎ込むことにした。そうすれば、お前は笑う。人形のような、血の通わない顔で、お前は笑う。
そう、そんな女なんだよ、こいつは。他のオトコの金の匂いはさせても、オトコの体の匂いはしない。ずっとそうだった。金にしか興味がないと思っていた。金さえ出してれば、こいつを俺だけのものにしておけると思っていたのに、今、目の前にいる妻は、他のオトコに抱きしめられ、少女のように顔を胸に埋め、もの想いに耽っている。
嘘だろ? お前はそんな女じゃないだろう? お前をそんなにしたのはどんな男なんだよ? もう……勝てないだろ? 俺はそいつに、絶対勝てない。二十年、ずっと欲しかったものは、あっさり他の男に持って行かれた。
そうか、そうなんだな。もう、もういいよ……
俺はソファに座り、久しぶりに、妻の名前を呼んだ。
「真純」
妻は、テレビに向いたまま、返事をした。
「何?」
妻の唇から、口紅が消えている。誰かの唇にうつしてきたか?
俺は、絶対に言わないと決めていた言葉を言った。
「離婚しようか」
軽トラとセルシオ
教習所から帰ると、電報と書留がきていた。どうやら合格したらしい。俺は合格通知を持って、大学へ手続きに行った。
学生課はすごい人で、部活の勧誘を鬱陶しく断りながら、手続きを済ませた。東京大学。勉強など、した覚えはない。ガキの頃から頭が良くて、難関中学になんとなく受かり、ずっとトップの成績で、すんなり日本一の大学に合格した。
親父は有名な代議士で、家は金持ち。何不自由なく育てられたけど、俺は次男というだけで、マジメしか能のないイケてない兄貴との差別をヒシヒシと感じていた。兄貴ははっきり言ってバカで、中学も親父の『力』で入って、エスカレートで大学に入り、バカのくせに親父の地盤を継ぐために政治家修行中。
そう、政治家なんてバカでもできる。だから俺は、バカではできない道を選んだ。公認会計士。金を思うように操る会計士に、俺は憧れた。
頭脳明晰な上に俺はイケメンで、女にイヤというほどもてた。そりゃそうだろう。金持ちで、次男で、東大で、イケメンなら、もてないほうがおかしい。俺はいつも流行りのブランドの服を着て、最新の髪型で、親父のセルシオを乗り回し、カワイイ子を隣に乗せて、セックスに勤しんだ。
バイトなんかしなくてもよかったけど、社交性をつけて来いとかうるさいから、塾で講師のバイトを始めた。ここでも俺はモテモテで、派手な女の子達はこぞって俺にすりよってきた。たぶん、ほとんどのコと寝たと思う。女には不自由しない。狙った女は、間違いなく落ちる。付き合うとか、彼女とか、俺にはそんな概念はなくて、惚れるとか、好きだとか、そんなことはどうでもいい。目的はセックス。ただ、それだけ。
そんな俺の前に、二学期が始まった頃、あの女が現れた。
「門田真純です。よろしくお願いします」
頭を下げた女は、訛りのキツい、田舎丸出しのダサい女だった。同じ学年だけど、俺のほうがチョット先輩。俺と同じ数学担当だっていうから、俺達はセットで講義をすることになった。
門田真純は頭がいいのか、すぐに仕事を覚え、訛りはあるものの、講義もうまかった。わかりやすいと生徒から評判になり、やる気のない俺のほうが、サブになりつつあった。
大学は、中堅どころの私立大学で、奨学金で通っているらしい。大人しくて、訛りを気にしているのか、あまり会話に入って来ることもない。ちょっと近寄り難い雰囲気で、都会の大学生には、あまり馴染めていなかった。
「門田さん、歓迎会したいんだけど。空いてる日ある?」
あー、なんで俺が幹事なんだよ。めんどくせえ!
「すみません、私……あんまり遅なれんので……」
はあ? 俺が誘ってやってんのに、断るって? ムカつく女だな! ダサいくせに!
「どうして? 一人暮らしでしょ? ちょっとくらいいいじゃん」
「いえ……私、彼氏の社宅にすんどりまして……門限が……」
え……同棲してんだ! あー、ビックリ。どんな男なんだろう。
「へえ、彼氏いるんだ! どんな人? 写真とかないの?」
「そげなもん、ないです。あの、こんげなこと、言わんでください……」
「なんで?」
門田真純はそれ以上何も言わず、レポートを書いて、立ち上がった。
あれ? よく見ると…今まで気づかなかったけど、タイトスカートから伸びる脚は細くて、ケツは上がっていて、白いブラウスの胸元はけっこう、いや、かなり膨らんでいる。意外と……いい体してんじゃん。顔も、そんなに悪くない。っていうか、すっぴんでここまでなら、化粧したらかなり美人じゃねえの?
今まで、『すでに』いいオンナにしか興味がなかったけど、俺好みに変えるってのも、おもしろいかもな。あ、これって光源氏的発想か? ヤバイヤバイ。何考えてんだ、俺?
「お先に、失礼します」
門田真純は、小さな声で挨拶して、職員室を出て行った。
そして俺は、歓迎会を断られたことをみんなにいじられ、レポートを適当に提出して、不機嫌にタイムカードを押して、職員室を出た。
外に出ると、先に出たはずの門田真純が、まだビルの前でぼんやりと立っていた。
何してるんだろう。もしかして、俺を待ってたとか?
「ねえ、門田さん、送ってくよ」
俺は興味と下心から、なんとなくそう言ったけど、門田真純は気まずそうに俯いた。
「あの……」
何か言おうとした時、反対側の車線に軽トラがハザードを出して止まった。そして、軽トラの窓が開き、中から男が手を振った。
「真純!待ったか!」
門田真純は軽く会釈して、軽トラへ走って行った。ああ、カレシを待ってたんだ。軽トラに乗り込む前に門田真純はもう一度俺に会釈し、運転席の男も、俺に会釈した。顔はよく見えなかったけど、笑っていたような気がする。
軽トラは軽くクラクションを鳴らして走り出した。なんだよ、なんか、振られたみたいになってんじゃん、俺。あんな軽トラやろうに、負けてんじゃん。
クサクサしながらセルシオに乗り、門田真純の体を思い出した。
マジていい体だったよな……ていうか、アイツら、同棲してんだよなぁ。てことは、今から一緒の部屋に帰るわけだ。で……やるんだよな、やっぱり……ヤバイ、ちょっと興奮してきた。え? 俺があんな地味な女に? マジか? あー、イライラするぜ。なんなんだよ、一体!
それから門田真純を何度かメシに誘ったけど、一向に応じる気配はなく、講義が終わったらレポートを書き、そそくさと帰っていく。
はあ、なんでこんな女に、俺は拘ってるんだ? 自分で自分がわかんねえ!
冬休みに入り、冬期講習会が始まった。バイト講師も朝から晩まで教室にカンヅメになる。俺は風邪で二日間休んでいて、すっかり出遅れてしまっていた。
昼休み、バイト講師達は連れ立って隣の喫茶店に昼飯を食いに行く。
「あれ? 門田さん、誘わないの?」
「ああ、お弁当なんだって」
一人になった職員室で、門田真純はデスクで弁当を広げていた。へぇ、弁当とか、作るんだ。
「門田さんね、毎日カレシのお弁当作ってんだって」
ニヤニヤしながら俺にそう言ったのは絵理子。夏あたりに一度『ホテルデート』した記憶がある。
「そうなんだ」
「いいよね、なんか。ラブラブなんだよね、きっと」
ラブラブ……なぜか俺はイライラして、無造作にタバコに火をつけた。
「門田さんのカレシって、どんな感じなんだろ」
「田舎から出てきたんだろ? 絶対田舎クサイ、ダサい奴だよ」
あの時も訛ってたしな。
「まぁ、確かに、門田さんも……ダサいもんね。なんか、イケてない。一緒に遊びに行くとか、ちょっとないよね」
そんな言い方……普段は仲良くしてるくせに、女って残酷。絵理子の言葉に同じテーブルの奴らがクスクスと笑った。俺も笑ったけど、内心は穏やかじゃなくなってた。なんでかわかんないけど、門田真純がかわいそうだった。
翌日から、俺も職員室で昼メシを食うことにした。
「採点、残ってんだよ。中で食べるわ」
なんで、この俺が言い訳しなきゃいけねえんだ?
コンビニでおにぎりを三つ買って、職員室に戻った。
職員室には、女子中学生が何人かいて、門田真純と盛り上がっていた。ふぅん、生徒とは喋るんだ。結構、笑うと……カワイイじゃん。
「おーい、お前ら。今は先生も昼休みなんだよ! ほら、教室帰れ!」
ガキどもは、えー、佐倉ってムカつくよね、と言いながら教室へ戻って行った。俺は女子講師にはもててたけど、生徒には全くもててなくて、なんなら嫌いな先生ナンバーワンに毎月に輝いている。
「佐倉くん、今日は食べに行かないの?」
「え? ああ、採点残っててさ」
あ、また言い訳……何緊張してんだ、俺?
門田真純は弁当を広げた。オカズは卵焼きとウインナーとブロッコリー。俵型のおにぎりが並んでいる。
「弁当、つくってんでしょ?」
「え、ええ……節約しないといけんし……」
「ねえ、卵焼き、ちょうだい」
「え! お、おいしくないけえ、たぶん……」
黄色にキレイに巻かれた卵焼きは、塩味で、ダシが効いてて、はっきり言って、うまかった。
「おいしいじゃん」
「そ、そうかな……」
門田真純は真っ赤になって俯き、ウインナーを口に入れた。なんか、エロ……て、俺は何を考えてんだ! でも……ちょっと、マジで、欲情する。
隣で黙々と弁当を食べる門田真純が、軽トラ野郎とセックスする姿を想像する。口に入れる箸が違うもんに見えてくる。門田真純はどんな顔で軽トラ野郎に抱かれるんだろう。どんな声を出すんだろう……
「あの、佐倉くん?」
はっ! 完全に妄想の世界に入ってた!
「いやぁ、門田さん、いいお嫁さんになるだろうなって思ってさ」
「そ……そんなこと……」
「カレシとラブラブなんでしょ?」
門田真純はさらに真っ赤になって、俯いて、首を横に振った。耳や首筋まで赤くなって、俺はもう、たまらなくて、門田真純の手を握った。
「カワイイな、門田さん」
いつもオンナを口説く時は、こうやって耳元で囁くんだよ。ブルガリの匂いと俺の甘い声と、なによりこの顔で……
「デートしたいな、今夜」
こんな田舎娘、イチコロだよ。
「離して」
あれ?
門田真純は俺の手を払いのけるように立ち上がった。
ちょ、ちょっと……マジで? この俺が、あんなイケテナイ、ダッサイ女に振られたのか?
門田真純は上がったケツを向け、給湯室へ行ってしまった。
そうか。わかったよ。お前のカレシはそんなにいい男なんだな? そんなにセックスがうまいのか? イイモンもってんのか? 門田真純、絶対落としてやるよ。何が何でも、軽トラ野郎から奪い取って、俺のモノにしてやる。いいか、絶対に俺に夢中にさせてみせる。夢中にさせて、お前を捨ててやる。覚えてろよ、門田真純!
「悪かったな」
俺の言葉に、妻は思わず俺の顔を見た。
「え?」
「金で、幸せにできると思ってた」
妻はテレビに向き直り、俯いた。
俺はこの女の横顔が好きだ。長い睫毛、通った鼻筋、ふっくらとした唇。十五年間、ほとんど横顔しか見てこなかった。いや、俺だけじゃない。俺達はずっと、俺達の横顔しか見なかった……見れなかった。
「お前は、俺の金に惚れてたからな」
そう、こいつは、俺じゃなくて、俺の金に惚れていた。最初から、わかってた。それを責めることは、俺にはできない。だって俺は、お前を変えてしまったから。
「だからお前の見た目を変えようと思った」
「変えたよ、慶太の、好きな女になるように」
そうだな。お前は変わったよ。俺好みの『見た目』の女に。最高の見た目の女に。悪魔に魂を売るなんてさ、そんな陳腐なダサい言葉、俺は使いたくないけどな、でも、お前は、魂を売った。悪魔ではなく、金に。お前の目にも脳みそにも心にも、金しかなくなってしまった。
策に溺れた俺
二回生のゴールデンウィーク、講師仲間で、川へバーベキューに行くことになった。メンバーは、国語担当の中村、社会担当の直美、英語の絵理子、そして数学担当を降ろされ、理科担当になった俺。中村は直美を狙っていて、俺はキューピッド役を買って出たってわけだ。
「ねえ、門田さん、どうする?」
先輩や後輩はいいとして、同学年の門田真純だけを誘わないのは、さすがに気が引ける。
門田真純は、少し化粧もし始めていたけど、相変わらず地味で、垢抜けない田舎娘で、あまり皆と打ち解けていなかった。
「奇数になっちゃうしねえ……」
直美と絵理子は、誘う気なんて、さらさらないくせに、どうやら俺達が、もういいじゃん、って言うのを待っているようだった。
いや、待て。ゴールデンウィークってことは、会社も休みだよな。これは……
「カレシも来てもらえばいいじゃん」
俺の提案に、女二人はあからさまに食いついた。
「それいい! 門田さんのカレシ、どんな感じか見たいし!」
直美と絵理子はニヤニヤと笑っている。明らかに悪意あるよな……二十歳になってもコギャルが抜けない絵理子と違って、直美はいいとこのお嬢様って感じで、金持ちしかいない、私立の女子大に通っている。いつも門田真純を見下した感じで、上から目線が俺は気に入らなかった。
「でも、門田さん、帰省とかするんじゃない? 年末年始も、特訓で東京にいたし」
いつも気遣いを忘れない中村は、家が小さなタクシーの会社をやっているらしく、金持ちでもなく貧乏でもなく、中流家庭の長男。イケメンてわけじゃないけど、普通に優しくて、本気でいい奴で、生徒にも人気で、門田真純はこいつだけには、気を許していた。こんないい奴が、なんで直美みたいな高飛車な性悪女を選ぶのか、俺にはさっぱり理解できない。
「中村、お前、聞いてみてくれよ」
「え? 俺が?」
「門田さん、お前となら喋んじゃん」
情けないことに、俺はあの日以降、思いっきり門田真純に避けられていて、ろくに会話もしていない。
中村、お前と直美の仲、取り持ってやるんだからさ、お前も俺に協力しろよ。
「まぁ、聞いてみるけど……」
講義が終わった門田真純は、いつものように黙ってレポートを書き始めた。俺達は、気の進まなさそうな中村の背中を、無理矢理押した。
「ねえ、門田さん」
「は、はい」
「ゴールデンウィークさ、なんか予定ある? 三日に、みんなでバーベキュー行くんだけど、門田さんもよかったら参加してよ」
俺達三人は、少し離れた場所から、二人の会話を耳をダンボにして聞いていた。
「予定はないけど……あの、私……あんまり……ごめんなさい……」
空気を読めば、当然だろう。でも、中村、ここは押せ! 俺達は口パクで、カレシカレシと中村に叫ぶ。中村は本当に嫌そうな顔で、首を横に振ったけど、直美の『期待の目』を見て、腹を決めたようだ。
「よかったらさ、カレシも一緒に、どう?」
俺達は息をのんだ。
「いいん、かな……」
「もちろん! 同い年なんでしょ? だったら、みんなで友達になろうよ、ね?」
俺達が言えば嫌味なセリフも、中村が言えば、優しく聞こえる。人格って、大切だ。
「……聞いて、みるね」
やった! でかした、中村! 俺達は三人で悪意満載のガッツポーズをした。
バーベキュー当日、俺は親父からワンボックスカーを借りて、中村と直美と絵理子と、バーベキューセット一式を載せて、川へ向かった。
キャンプ場の駐車場には、あの夜俺を置き去りにした軽トラが止まっていて、俺達を見ると、おしゃれとは言えない普通のTシャツにジーンズの門田真純が、食材を持って軽トラから降りてきた。そして、運転席が開き、門田真純のカレシが降りてきた。
えっ?
俺達は一瞬、目を疑った。
「あの、カレです……」
少し顔を赤らめながら紹介されたカレは、俺達の予想と全く違っていた。
「杉本将吾いいます。よろしく」
杉本は、百八十超えのガタイのいい男で、まだ五月だっていうのに、小麦色に日焼けして、髪の毛は短い金髪で、眉毛も短くて、『現場のやんちゃなにいちゃん』感を思いっきり醸し出していた。イケメンというより、ワイルド。いや、はっきり言おう。ヤンキー。俺とは正反対、そして一番苦手な人種だ。
見た目は引いてしまったが、杉本は気さくな奴で、訛りを逆手に場を盛り上げまくっていた。楽しそうに笑う女二人と、ちょっと満足気に笑う門田真純。俺はイライラして、バーベキューの準備を始めたものの、何せ初めてだから、何をどうすればいいのかわからない。
「中村、火、どうやったらつくんだよ」
「え? お前、知らないできたの?」
「わかんねえよ。ああ、携帯で検索してみるか……」
と、携帯を出したものの……圏外! マジかよ! どうすりゃいいんだ!
「ねえ、まだぁ? お腹空いたんだけどー」
一向に進まないコンロの準備に絵理子が文句を言い出した。
「あの、俺、ちょっと見てもいいか?」
杉本はそう言って、コンロを難なく組み立て、炭をおこした。さらに、隣に河原の石で、カマドを作った。
「ちょっと、鍋持って来たんでぇ。おい、真純、薪、もってこい」
門田真純が軽トラからマキを持ってくると、杉本はマキをくべ、火を起こした。
「将吾くん、すごーい!」
直美と絵理子は杉本にベタベタとつきまとい、都会の男二人は、ボンヤリするしかなかった。
くそっ! こんなつもりじゃなかったのに!
俺の予定では、ダッサイ彼氏が、都会の男二人に辱めを受けるという、なんとも浅はかで、バカな計画だったのに!
それなのに、中村ときたら……
「杉本くん、すごいじゃん! アウトドアできる男はかっこいいよな!」
おい、中村、お前、どこまでいい奴なんだよ……お前の狙ってる女まで、この、田舎男にやられてんだぞ!
「田舎もんだけ、こんくらいことしかできんから」
杉本は嫌味なく笑って、門田真純が準備した野菜やら肉やらを焼き始め、カマドでカレーを作り始めた。料理をする二人はまるで、夫婦で、俺はなんとも……完全に負けてんじゃねえか!
そして、さらなる敗北が俺を襲う。
その日は五月のくせに夏日で、太陽がめっちゃ暑かった。
「マジで暑いよなぁ!」
ここで、俺の鍛えたスリムな体を見せつければ……
俺は、間違いなくオシャレなTシャツを脱いだ!
バーン! ジムで作ったこの細マッチョ! 門田真純、どうだ? 俺は顔だけじゃないんだぜ?
「あー、俺も脱ぎてえ!」
「バカ、やめなよ、かっこわるいけ」
「ええだが。佐倉くんも、脱いどるだけ」
門田真純は、もう知らんと、目を背け、杉本は黒いダサいTシャツを脱いだ。脱いだ……
嘘だろ!
絵理子と直美の目がハートに輝く。
杉本の腹筋は隆々のシックスパックで、真四角の大胸筋、背筋はボコボコで、俺の見せかけ筋肉など、もう、ひとたまりもなく、恥ずかしくて、川に沈みたい……
「ねえ、腹筋、さわっていい?」
「え? ああ、ええけど……」
絵理子と直美は杉本の腹筋やら胸筋をペタペタサワサワと触ってはキャーキャー言っていた。横で門田真純が、ちょっと不機嫌そうに、肉を焼いている。
そうか……そうなのか……あんな体に抱かれてたら、他の男になんか興味ないよな……あの細い体があのマッチョに……エロい……エロすぎる……
「すげー、杉本くん! 鍛えてるの?」
「仕事が、力仕事やけ」
中村……お前まで……はあ……一体このバーベキューは誰のための会だったんだよ……
後片付けも、俺達、都会の男が、ヒーヒー言いながらやっと積んだ荷物を、杉本は難なく一人で、さっさと車に積んでくれた。
「今日はほんまに楽しかったけ。ありがとう」
杉本は爽やかに笑って、頭を下げて、門田真純と軽トラに乗った。
「将吾くん、また遊ぼうね!」
直美も絵理子も、杉本に夢中で、なんなら軽トラで帰りたいなんて言い出す始末。
「こんな田舎もんでよかったら、また遊んでつかあさい! じゃ、お先に!」
頭にタオルを巻いた杉本は、くわえタバコで、横にはちょっと得意気な門田真純を乗せて、とてつもなく悔しいけど、またそれがカッコよくて、軽くクラクションを鳴らして、山を降りて行った。
俺は、人生で初めて、『敗北』を感じていた。そして同時に、『嫉妬』も感じていた。門田真純など、その時はどうでもよくて、何が何でも、杉本将吾という男に、男として勝ちたかった。リベンジ、してやる。絶対、リベンジしてやる!
けど……今の俺には、あの杉本に勝てる要素なんてどこにもなくて、親父のワンボックスカーの後ろに、爆睡する女二人を乗せて、隣には、退屈そうにタバコを吸う中村を乗せて、俺達は、都会へ帰った。
タンス
頭いてぇ……ここ、どこだ?
俺は窓から見える、ベランダに干してある洗濯物を見た。駐車場の街灯に映るのは、杉本の作業着と、トランクスとTシャツと……おそらく門田真純のパンツとブラジャー。
ああ、ここ、杉本の部屋か……あ、やべ、トイレ、トイレ行きたい。
あの屈辱のバーベキュー以降、絵理子は本気で狙っているのか、杉本を誘えとしつこくねだり、今日は絵理子の友達二人と、俺と中村と、そして杉本の合コンだった。
女が自分より可愛い女を連れてくるはずがなく、予想通り、絵理子の連れてきた女は、コギャルの腐ったみたいな女で、俺はもうウンザリしていたけど、やっぱり杉本は俺よりもてて、腐ったコギャルと言えども、やっぱり全くおもしろくない。おもしろくない上に、杉本は酒が死ぬほど強くて、せめて酒ぐらいはと頑張りすぎて……記憶がない。はあ、つくづく情けないよな、俺って……
猛烈な頭痛が、尿意に押されつつあり、仕方なく起きあがった。まだ酒で、頭がクラクラする。襖の隙間から、隣の部屋の明かりが漏れていて、一緒に隣の声も漏れて来た。
「……女の子がおるとか、知らんかったんじゃけ」
「嘘じゃ。知っとったやろ」
ああ、ほんとに杉本は知らなかったんだよ。だって、合コンとか言ったら絶対来ないし。
「ほんまじゃて。……でも、なんもしとらんで」
確かに、なんにもしとらん。まとわりつく絵理子と腐ったコギャルの相手を、嫌な顔一つせずしていただけだ。俺と違って。
「……前のバーベキューん時も、デレデレしとったが」
ケンカか? おもしれえ、やれやれ!
「デレデレなんかしとらん!」
「大きな声出さんで。佐倉くんが起きようが」
もう、起きてるって。
「真純……俺はお前だけじゃて」
「知らん」
「好きやで」
「……信じられん」
「真純、俺がもっと稼げるようになったら……一緒になってつかあさい」
「え?」
「贅沢はさせてやれんが、幸せにするっちゃよ」
「将吾……ほんに、ゆうとる?」
「ああ。真純、愛しとる」
なんだよ……つまんね……つまんねえ!
しばらくすると、なんか湿った音が聞こえてきた。
これって、キスしてんのか?ちょっと……ちょっとくらい、見てもいいよな?
俺は注意深く襖を開けた。一ミリ、二ミリ、三ミリ……おおっ!
襖の向こうの二人は、座ったまま抱き合っていて、思いっきり濃厚なキスをしていた。
「生理、終わったか?」
「何ゆうとるん。隣に佐倉くん、おるがよ?」
「寝とるて。だいぶ酔うとったから……」
「そやけど……あ……いけんて……」
杉本の日焼けしたごつい手が、門田真純の胸を弄る。門田真純はタンクトップが伸びたようなワンピース一枚で、相当洗濯してるのか、もうヨレヨレで、脇の辺りから中がチラチラと見え、パンツの線と、胸の突起がありありと映っている。杉本は風呂上がりのままなのか、トランクス一丁で、バキバキの体を、さらにバキバキにさせ、門田真純の首筋や耳を必死で噛んだり吸ったり舐めたりしている。時々小さく門田真純が色っぽい声を出す。
俺はもう尿意も頭痛も忘れ、妄想ではない、リアルなその光景に見入っていた。
「真純……舐めてくれ」
杉本が、胸の突起を指先でつまみながら、トランクスをずらした。
うわぁ……すげぇ……デカ!
門田真純は座ったままの杉本の前に四つ這いになり、驚愕サイズのアレを、口に入れた。杉本は後ろのタンスにもたれて、うっとりと門田真純の顔を見ている。残念ながら、俺からは杉本のバキバキの太ももと、門田真純の長い髪で顔は見えない。時々、杉本が天井を見上げて、体をひくつかせる。
顔……門田真純の顔……顔が見たい……
しばらく、門田真純は一生懸命、杉本の希望通りにして、顔を上げて呟いた。
「将吾……私のこと、好き?」
その横顔は見たことのない、オンナの顔で、俺はその顔がエロすぎて、思わず股間に手をやってしまった。杉本は門田真純の髪を掻きあげ、さっきまで自分のアレを咥えていた唇に、しゃぶりついた。
「好きに決まっとろうが」
門田真純が両手を上げると、杉本がヨレヨレのワンピースを剥ぎ取った。
……て……峰不二子かよ!
門田真純の体は俺の妄想を遥かに超え、ハタチとは思えないほどの色気と香気を発していた。二人はもつれながら薄い布団に倒れ、卑猥な音をたてながらキスを交わし、杉本の唇が胸の頂についたピンク色の蕾に吸い付く。門田真純は頂を揺らしながら震え、聞いたことのない、ねっとりとした声で杉本の愛撫を受ける。
「かわいいで……」
杉本の手が門田真純の花柄のパンツにかかると、微かに腰が浮き、そこには何もなくなった。杉本は躊躇なく門田真純の膝を開き、そこに顔を埋めた。びくっ、びくっと門田真純は体を震わせ、杉本の金髪を掴む。やっぱり俺からは門田真純のエロい太ももでそこは見えないし、長い髪が顔にかかっていて顔も見えない。
「めっちゃ、濡れとるで……」
杉本はそう言って、タンスの一番上の引き出しからコンドームを出した。
「俺はつけんでもええんじゃけどな」
「……大学出るまではいけん」
「わかっとるよ」
ああ……入れんだ……杉本が、門田真純に……入っていく……
門田真純は血走った男の下で、高い掠れた声を出す。杉本はバキバキの体に筋を立て、暴れる女の体を抱きしめる。
「真純……好きじゃ……好きやで……」
杉本……本気で門田真純のこと、好きなんだな……
「東京の女なんかより……お前の方がええ女じゃ……」
杉本は愛おしく門田真純の唇にキスをして、ウナジに顔を埋めた。そして……
一瞬……ほんの一瞬、門田真純の目が俺の目を見た。
いや、わからない。目があった気がした。そして……笑った? 一瞬だし、俺は三ミリの隙間から覗いているし、もう門田真純は杉本の下でエロい顔でエロい声をあげて、エロい体を震わせているし……もう、なんか……俺、何やってんだ……
虚しさと共に尿意が蘇り、俺はどうしようもなくなったけど、この部屋を今出ることはできない。おそらく、トイレにはセックス部屋を通らなければたどり着けない。とりあえず、二人が落ち着くまで布団で待機しよう。そうするしか、俺に道はない。
「真純……イクで……」
はいはい、早く終わってくれよ。俺は猛烈にトイレに行きたいんだよ。
門田真純の声が聞こえなくなり、ティッシュを取る音が聞こえた。
ああ、やっと終わった……トイレトイレトイレ!
「真純、最高やったで」
「うん」
「溜まっとたわ」
「そうやね」
セックス部屋からは、二人の笑い声が聞こえて、ますます俺は惨めになって、とにかく、漏らさないことだけを考えて、三ミリの隙間から覗くと、杉本がトランクスを穿いて、門田真純がワンピースを着終わっていた。
今だ!
「あー! トイレ!」
俺は寝ぼけたフリで襖を思いっきり開けた。
「お、おう、こっちやで」
杉本はちょっと焦った感じで、トイレの電気をつけてくれた。
はぁ……もう限界だったな……
セックス部屋には、セックスが終わった直後のカップルが、乱れた布団の上で白々しく離れて座っていた。
「杉本、悪かったなぁ。俺、記憶ねえわ」
「ええっちゃよ。大丈夫か?」
杉本は黒いTシャツを着て、いつものように笑った。その横では、門田真純が三角座りで俯いていた。
六畳の和室には、小さなタンスと、でかい作業着のかかったハンガーラックと、十四インチのテレビデオと、壁に布団のないコタツが立てかけてあった。
なるほど、そりゃ弁当作ってくるわな……
暗くてわからなかったけど、俺の寝ていた部屋は四畳半の和室で、畳んだ洗濯物と、たぶん、杉本のダンベルと、仕事道具が置いてあった。
はっきり言って、貧乏だ。貧乏……俺は金持ち。筋肉も、男っぷりも、アレのサイズも、アウトドアも勝てないけど、俺は勝てる。たった一つ、勝てるものを見つけた。
杉本にないもの、それは、金。
翌朝、門田真純は朝飯を作ってくれて、俺たち三人はコタツで味噌汁とご飯と目玉焼きを食べた。杉本は朝から丼茶碗でご飯をおかわりし、薄いお茶を飲んでタバコを吸い始めた。そして、俺もタバコを咥え、ここぞとばかりに財布から、カッコ良く一万円札を出した。
「なんや、これ」
「泊めてもらって、朝飯まで食わせてもらって、タダってわけにいかないじゃん」
「なんじゃ、そんなこと気にせんでええ」
杉本は笑って、一万円札を俺に押し付けた。
「俺の気持ちだから」
「そんなんええ。友達じゃけ、金なんかいらん」
当然ながらガンとして受け取らない男っぷりのいい杉本に、門田真純が言った。
「もらっとこうよ」
あっさりコタツの上の一万円札を取り、シミのついたエプロンのポケットに入れ、ありがとう、と言った。
「真純!」
「佐倉くんもこれで気が済むんやから。またいつでも来てね」
門田真純は、初めて俺に向かって笑った。俺だけに、笑顔を見せた。その笑顔は、ハッキリ言って、かわいい。あのガキどもと職員室で笑っていた門田真純より、かわいかった。
もしかして……この女、金か?金が欲しいのか?
キッチリ髪を一つにまとめ、口紅だけをつけ、白いブラウスに、紺色のタイトスカートの地味な女。俺はこの地味な女を落とす唯一の方法を見つけた。味噌汁を啜る唇は、昨夜この筋肉男のアレを咥えていた。こんなに地味な女なのに、あんなに情熱的な体で、顔で、声でセックスをする。全部俺のものにしたい。その胸も、ケツも、アソコも、唇も、声も、顔も全部。なあ、俺のアレも咥えてくれよ。俺の下でよがってくれ。そしてあの顔で俺を見つめてくれ。
「そうか、そんだら、今日はありがたくもうとくで」
杉本は申し訳なさそうにそう言うと、作業着を着た。
「仕事行くけど、ゆっくりしていきんさい」
「ああ、ありがとう」
門田真純は玄関で杉本を見送ると、コタツに戻り、食器を片付け始めた。
「夫婦みたいだね」
「幼馴染なの」
「そうなんだ」
門田真純は、黙って食器を洗う。その顔にはもう、笑顔はなくて、いつもの、暗い、大人しい門田真純だった。
「手伝おっか?」
古臭い台所には、せまい流し台と、小さな食器棚と、昭和な冷蔵庫。
「いつまでも田舎者でしょ。私も将吾も」
なるほど。そうなんだ。門田真純は、杉本に満足してるわけじゃないんだ。
俺は、門田真純の反応を試した。
「そんなことないよ。お似合いだよ、二人」
ビンゴ。門田真純は明らかに不満そうな顔をした。俺は確信した。
『都会と金』
これで、この女は俺のものになる。間違いない。
そして俺は、杉本に勝つ。勝って、あいつの一番大切なものを奪い取って、俺に泣きつかせてやる。
『真純を返してくれ』ってな。
ロレックスの左手
「花火に誘ったこと、覚えてるか」
「隅田川?」
「そう」
「未だに、なんで私が誘われたのかわかんない」
……そうだろうな。お前は俺のことなんて見てなかったからな……いや、俺も、見せてなかった。俺は杉本からお前を奪い、その体を俺のものにすることしか考えてなかった。考えないようにしていた。
だって、お前の心は……お前の心には、俺の心は絶対に届かないと思っていたから。あの杉本には、あの純粋で、お前だけを見て、お前だけを愛して、必死でお前を守っていた男には、絶対適わないと思っていたから。
でもな……本当は……
「好きだったから」
相変わらず、塾の中での門田真純は大人しくて、あの日以降、俺と話すこともない。でもその姿が余計に俺をそそった。あの姿を知ってるのは杉本と俺だけ。脱いだらすごいんです、どころの騒ぎじゃない。俺は他のオンナを抱きながら、門田真純とのセックスを妄想するくらい、門田真純の体に夢中になっていた。
そして、最大のチャンスがやってくる。
その日、俺は杉本が会社で花火大会にいくことを知っていた。そして、講義もない。
「ねえ、門田さん。明日、花火見に行かない?」
「えっ?」
「隅田川の花火大会。いったことある?」
「ない……です」
「ねえ、行こうよ」
うんって言えよ。門田真純、うんって言え!
「……うん」
やった! ついに俺の誘いに乗った! これでもう、俺の勝ちも決まったな!
「明日、五時に迎えに行くね」
「うん」
門田真純は、それ以上は何も言わず、俺も何も言わず、いつものようにレポートを書いてさっさと帰って行った。
次の日、朝から洗車に行き、限定デザインのかっこいいTシャツと、クロムハーツのネックレスと、ヴィンテージのジーンズでバッチリきめた。グッチの財布には、親父のキャッシュカードで引き出した一万円札を十枚詰めて、親父のロレックスをつけて家を出た。
四時五十分に社宅の前に着くと、窓から門田真純が手を振り、すぐに降りてきた。門田真純はグリーンのTシャツに、デニムのショートパンツ、白いモカシンを履いていて、いつもと違って、長い髪はポニーテールに結んであった。
「ありがとう」
「ううん、なんか、門田さん、今日かわいいね」
いや、お世辞じゃなくて、ほんとにかわいい。なんたって、そのショートパンツからの脚。助手席に伸びるその脚、たまんねえ。
「佐倉くんも、なんかいつもと雰囲気違うね」
門田真純はクロムハーツのネックレスとヴィンテージのジーンズをしげしげと眺めた。やっぱな、気合い入れてきてよかった! 都会の匂い、するだろ? あんな筋肉盛男とは違うだろ?
会場までの道は当然渋滞していて、近くまで行くことは諦め、少し離れた駐車場に車を停めて、人混みの中を歩いた。途中でかき氷とわたあめを買ってやったら、門田真純は子供のように喜んでいた。
「離れないでね」
そう言って、俺はさりげに手をつないだ。これくらい、基本だけど。でも、つないだ手は柔らかくて、細くて、はぐれまいと俺の手を必死で握るから、ちょっと痛くて、俺は門田真純がかわいくて仕方なかった。
俺達は花火を見て、手をつないで車へ戻って、ロイヤルホストで飯を食った。その間ずっと、門田真純は、興奮した様子で、花火の感想を話していた。よほど楽しかったらしく、一生懸命話すその顔はとってもかわいくて、講義の時みたいにハキハキしていなくて、なんだかちょっと舌っ足らずで、本当の門田真純が、見えた気がした。
もちろん、俺が支払いをして、社宅まで送った。財布を出すたびに、わざとらしく一万円札を見せつけた。でも門田真純は財布の中身には興味を示さない。
やっぱり……そっか、俺の勘違いか。金とかじゃなくて、本気で俺とのデート、楽しんでくれてんだ。あー、なんかほっとしたな。
「楽しかった?」
「うん。ありがとう」
部屋に電気はついていなくて、杉本はまだ帰っていないようだ。
「門田さん」
俺は、左手で門田真純の右手を握った。門田真純はその手を見て、左手を重ねた。
「キス、していい?」
門田真純は俯いたまま、微かに頷いて、目を閉じた。
俺は右手で肩を抱き寄せ、口紅の落ちかけた唇に、俺の唇を重ねた。
……柔らかい……舌、入れていいかな……
「う……うん……」
俺の舌が絡まると、門田真純は小さな声を漏らした。
駐車場の街灯に照らされた門田真純は色っぽくて、ガマンできずに、右手を太ももの間に入れた。
「ダメ……」
「ダメ?」
「うん」
「違うとこ、行こうよ」
「……たぶん、もうすぐ帰ってくるから……」
そうか……杉本が帰ってくるんだ……
でも、イヤってわけじゃないんだ?
「そうだね。ごめん」
俺は素直に手を離したけど、門田真純は俺の手を離さなかった。いや、門田真純が離さなかったのは、俺の手じゃなくて……
「この時計、すっごい高いヤツだよね?」
門田真純はにっこり笑って、車のドアを開けた。そして、降り際に言った。
「この車、すっごい乗り心地いい」
「そ、そう? また乗せてあげるよ」
「うん、またね! おやすみ!」
そうなんだ……俺とのキスじゃなくてそこなんだ……
部屋に戻る門田真純の後ろ姿を見送り、車を出した。でも、なんか……俺、あの女のこと、好きかもしれない。わかんないけど。だって、俺、女に惚れたことないから。手に入れられないものが欲しいだけかもしれない。わからない。わからないけど、門田真純に会いたい。顔が見たい。笑って欲しい。唇の味が忘れられない。何より、筋肉軽トラ野郎が憎くて仕方ない。今頃、もう帰ってんのかな。帰ってまた……
あっ! しまった!
ガシャン! という音と、衝撃に我に返った。ぼんやりしていた俺は、電柱に思いっきり左バンパーをぶつけてしまった。
ヘッドライトが無惨に粉々に飛び散り、バンパーがベコっとへこんでいる。
あーあ……なんてことだ……親父になんて言おう……
そして、この車の悲劇が、俺の、いや、俺達の運命を変える。
How to 団地妻
夏期講習会が終わって、中学のガキ共は二学期になったけど、俺達大学生はまだ休み。
でも、あの事故以来、俺にはセルシオ禁止命令が出ていて、アシはチャリしかない。ということは、ナンパもできないし、デートもできない。
はぁ……暇。
特に、昼間。家にいても、煙たがられるだけで、つまらないし、俺は何をするでもなく、チャリでウロウロ。ウロウロしながら、考えることは、情けないけど、やっぱり……門田真純……
相変わらず、門田真純はよそよそしい。あの花火の夜が、もう夢だったような気がする。
俺の手をぎゅっと握る門田真純、嬉しそうにかき氷を食う門田真純、目を花火の色に染める門田真純、舌っ足らずに一生懸命話す門田真純、そして……街頭に照らされた、門田真純と……あの唇……
なんでだよ……あんな、ダサい、イケてない……田舎臭い女……
俺は、そんな自分が余計に悔しくて、門田真純への歪んだ思いを助長させていた。
昼間の公園のベンチには、くたびれたサラリーマンが、タバコを吸ったり、弁当を食ったり、昼寝をしたり。
あー、やだやだ。俺は絶対、あんなうだつの上がらないおっさんにはならないぜ。て、いうか、お前ら仕事中じゃねえの? うん? 仕事中? 社会人は、仕事中?
てことは……杉本も仕事だよな? 門田真純も、暇なはずだ。杉本は仕事でいないはずだ。チャンスは昼! こんなチャンス、逃がすわけにはいかない。団地妻って、こうして出来上がるのか!
ここから、チャリならそんなに遠くないはずだ。行ってみるか……とりあえず、行ってみるか。
俺はチャリを二十分ほど走らせ、汗だくになった頃、杉本の社宅の前にいた。
……いるのかな? まあ、いなきゃ、いないで……別にいいか。でも……
ドキドキしながらチャイムを押すと、あのワンピースを着た門田真純が出てきて、驚いた顔をした。
「佐倉くん、どうしたの?」
どうしたの? そうだよな、聞くよな。返事、用意してなかった。
「えーと……近くまで来たから……」
そんなわけない。でも、門田真純は、汗だくの俺を見て、うん、と頷いた。
「まぁ、どうぞ」
あっさり俺は、杉本のいない部屋に上げてもらった。
九月だけど、すっげえ暑くて、でもこの部屋にはクーラーがない。古ぼけた扇風機が、ぶんぶんと回っているだけ。
俺はセックス部屋に座り、落ち着かないので、わかりきった質問をする。
「杉本は?」
「仕事」
「何時まで?」
「定時は六時やけど……だいたい八時とか九時とか」
なるほど。最低でも、六時までは時間があるわけだ。今は……二時か。まだまだ時間はある。
「なんもなくて」
門田真純は麦茶とポテチを出してくれた。
「いただきまーす」
向かい合って座る俺達は、何を話すでもなく、しばらく黙ってポテチを食った。パリパリと乾いた音と、時折外を通る車の音が聞こえる。
あのタンスにもたれて座る門田真純はいつもと違って、髪の毛がちょっと乱れていて、後れ毛が汗で首筋や胸元に張り付いていて、それがまたエロくて、俺はどうにか隣に行けないかとあれこれシミュレーションした結果、タンスの上に置いてあるティッシュを見つけた。
ポテチの手の油を拭くために、ティッシュを取りに行く。自然。ナチュラル。
俺は立ち上がって、タンスのそばまで行って、ティッシュを取った。
「言ってくれたら取ったのに」
門田真純が見上げる。上から見ると、ヨレヨレのワンピースの胸元から、ブラジャーの中で苦しそうにしている乳肉が見えた。
たまんねえ……
さりげなく、隣に座って、俺もタンスにもたれた。あの夜、杉本がもたれていた場所に、もたれた。門田真純は戸惑った感じで俺を見て、ちょっと離れた。
「この前の花火さ」
この前の『キス』さ。
「どうだった?」
「うん。すごかった」
「そうだね」
門田真純は三角座りになって、俯いた。
「アレ、覚えてる?」
門田真純の、顔が赤くなった。
「……あの……内緒に、してね……」
「うん。当たり前じゃん」
俺は、門田真純のお尻に俺のケツがつくまで差を詰めて、首筋にへばりついた髪を指で剥がした。
「もっかい、する?」
門田真純は俯いたまま、顔を真っ赤にして、
「東京の人は、遊びで、キスとかするんやね」
と言った。
いや……そんな風に言われると……
「冗談だよ。ごめんね」
怒らせちゃったかな。
「やっぱり、遊びなんだね」
え?
「そうよね。私みたいな田舎モン、佐倉くんのタイプじゃないよね」
それ……どういうこと? もしかして、俺のこと、好きなの?
「そ、そんなことないよ」
「私みたいな地味な女は、将吾みたいな、田舎の男が似合っとるよね……」
「杉本、いい奴じゃん」
悔しいけどな。あいつはいい奴だ。
「将吾は優しいし、一緒におったら楽しいけど……」
そうなんだ。優しいし、楽しいんだ。
「なんか、嫌なことあるの?」
「将吾、中卒でね。一生懸命働きよるけど……」
門田真純は、部屋の中を見回した。俺も、見回した。相変わらず、何もない。畳もちょっとケバケバしていて、門田真純の汗ばんだふくらはぎに、イグサのカスがついている。
やっぱ……貧乏が嫌なんだ。門田真純は、優しくて楽しいけど、稼げない杉本が不満なんだ。
「佐倉くんのお父さんって、政治家さんなんやってね」
「え? ああ、まぁね……」
「お金持ちなんよね、佐倉くん」
俺は……俺は金持ちじゃない。俺の親父が金持ちなだけ。俺の一番認めたくない現実。中卒の田舎モンの杉本は、少ないけど自分で稼いで、こうやって彼女を養ってる。
俺は……親父の金を見せびらかしてるだけ。現に、セルシオに乗らなくなっただけで、ナンパの成功率が一気に落ちた。デートに誘っても、断られまくり。
俺の価値なんて……親父なんだよな。親父の金がなけりゃ、俺なんて……カスみたいなもんだ。
「お金持ちに、なりたいの?」
「……うん。そのために、東京に来たんやもん」
そうなんだ……やっぱり、門田真純は金がほしいんだ……
「佐倉くんみたいな都会のお金持ちの男の子は、どんな女の子が好きなん?」
都会の……お金持ち……俺のタイプじゃなくて、都会のお金持ちの男のタイプ。俺は、門田真純にとって、『都会の金持ちの男』の一人、なんだ。
「そんな男と、つきあいたいの?」
「無理、やよね」
「例えば、俺とか?」
「……うん」
「俺が、金持ちだから?」
門田真純は、答えなかった。
答えないってことは、そうなんだ。金持ちだから、俺とつきあいたいんだ。
俺は、なぜか、無性にイライラしてきてた。
なんだよ、優しいとか、楽しいとかないのかよ。俺は金だけかよ。俺の魅力は金だけかよ。じゃあ、お前を俺のものにするために、金を出せばいいのかよ。杉本から、お前を買えばいいのかよ。
門田真純はスッピンで、伸びた長い黒い髪で、ヨレヨレのワンピースで、俺の隣で俯いている。
ダサい。貧乏くさい。田舎くさい。そんな女がなぜ欲しいんだろう。わかんねえ。わかんねえけど、お前が欲しんだよ、門田真純! ああ、金なんて、いくらでもやる。じゃあ、お前は何をくれるんだ? 俺のために、何をしてくれるんだ? そのカラダ、エロいカラダ、俺に捧げるか? 俺の性欲を処理しろ。俺に抱かれろ。いつでも、どこでも、俺の言いなりになれ! 正直に言うよ。お前みたいなイケてない女、連れ歩くのは恥ずかしいんだよ。俺の女は、イケてないとダメなんだよ!
だから、だから……
「俺のカノジョになりたいなら、イケてる女になれよ」
きっと、それは、間違いなんだけど、その時の俺は、そういうしか、そう言わないと、俺の存在がなくなる気がしてたから、そんなことを、言ってしまった。
「イケてる女?」
「そ、オシャレで、かわいい、俺にふさわしい見た目の女」
「オシャレで、かわいい……それが、イケてるの?」
「そうだよ。俺は見た目重視だから」
ガキみたいな顔で、ガキみたいな、バカ男の発言をした。怒ってくれたらまだよかったのに、門田真純は、俺をじっと見て、うん、と頷いた。
「イケてる女になったら、佐倉くんのカノジョになれるのね?」
「うん」
「わかった。約束だよ」
門田真純は、俺の手を握って、俺の唇にキスをした。
そのキスは、軽くなくって、門田真純は俺の舌を舐めたり、噛んだりして、俺は、門田真純のおっぱいを握った。
門田真純は俺の膝に跨って、耳とかうなじとかを噛んだりして、俺は門田真純のワンピースを肩から外して、ブラのホックを外して、間近でその迫力を目の当たりにした。
胸元は少し日に焼けていたけど、胸は真っ白で、真ん中は真っピンクで、俺は無意識にしゃぶりついて、吸ったり、舌でコロコロしたり、指でクリクリしたり、谷間に顔をうずめたりして、門田真純のおっぱいを堪能した。
扇風機の回る音に混じって、門田真純の声が漏れて、俺の息も荒くなって、俺達はただ、目の前の俺達に夢中だった。
「ガマン、できないよ」
俺は門田真純を硬い、古ぼけた畳に押し倒した。門田真純は、血走った俺の目を見て、目を閉じた。
いいんだよな……なあ、俺もう、無理だよ? もう、止まらないよ……
俺は、スカートの中に手を入れて、地味な無地のパンツに手をかけた。
門田真純が、微かに腰を浮かした瞬間、けたたましく、チャイムが鳴った。
俺達はドキッとして玄関を見た。何回かチャイムが鳴って、門田真純はブラをつけて、ワンピースを着て、髪をまとめ直して、玄関へ行った。
「回覧板ですー」
「ああ、すみません……」
「ねえ、真純ちゃん、今度の工場長、知ってる?」
どうやら社宅の回覧板が回ってきたようだ。近所のおばさんらしき人は、十五分ほど新しい工場長の噂話をして、帰って行った。
「回覧板?」
「うん」
残念ながら、もうそんな感じじゃなくなって、門田真純は、そろそろ買い物に行くと言った。
一緒に部屋を出て、自転車置き場に行くと、車じゃないんだね、とちょっと残念そうな顔をした。
「修理中なんだよ」
セルシオあっての俺、か。
俺は自転車を押して、駅前のスーパーで、また明日、バイトでね、と別れた。
しかし……門田真純……エロかった……俺のこと、好きなのかな。
だって、キスしてきたのは門田真純からだし、膝に跨ったのも門田真純だし、わかんないけど、嫌いじゃないことは確かだ。あんなこと言っちゃったけど、明日会った時に、冗談だよって言えばいいよな。
でも、次の日から、門田真純は塾に来なくなった。どうしたんだろう。風邪とかかと思ってたけど、結局、そのまま門田真純は塾を辞めてしまった。
とりあえず、俺は門田真純が受け持っていた数学もやることになったけど、相変わらず俺はガキどもから嫌われていて、授業もわかりにくいと保護者からもクレームが来て、塾長からも、イケメンを生かせるバイトの方がいいんじゃない? なんてクビ通告されて、俺も二学期いっぱいで塾を辞めた。
その間も、ずっと門田真純のことは気になっていて、時々昼間に社宅に行ってみたけどいつもいなくて、事故にでもあったのかと思って、少し遅い時間に家へ電話をかけてみたら、杉本が出た。
「あの、佐倉だけど……」
「おお、久しぶりやのお」
杉本はちょっと元気がない。
「あのさ、門田さん、いる?」
「え? 真純?」
やば……もしかして……あのことがバレて、別れたのかも!
「今、バイトいっとるんよ」
「バイト?」
「なんや……いかがわしい店で働いとるみたいで……」
い、いかがわしい店!
「風俗、とか?」
「そこまでやないけど、ホステスとかコンパニオンとかやっとるみたいじゃ」
「そうなんだ……」
「昼間も学校いっとらんみたいやし、どうしてもうたんか……」
まさか……俺のせい?
「真純に、何か用事やったんか?」
「え? いや、あの、急に塾辞めたから、なんかあったのかと思って……」
「心配してくれたんかあ。悪いなあ。まあ、元気は元気じゃけ」
「なら、安心だよ」
「電話、あったことゆうとくけ」
「ああ。また、飲みに行こうぜ、杉本」
「そうじゃなあ。今、年末で忙しくてな。年度末までは忙しそうじゃ」
杉本は社会人ぽい発言をして、ため息をついた。
「大変だね。頑張れよ」
「ああ、ありがとう」
電話が切れて、俺もため息をついた。
門田真純……やっぱり、俺なんかに頼るのはバカらしくなって、自力で稼ぎ出したのかな……そうだよなぁ。俺なんか、所詮、親父の金でできてんだもんなぁ……
お引越し、しますか。
そのまま正月が過ぎ、俺は行きつけの渋谷のショットバーでバーテンを始めた。
最初からこっちをやっとけばよかった。酒は飲めるし、金ももらえて、女ももらえる。なんて素晴らしい仕事なんだろう。もう会計士なんかやめて、水商売しようかな。親父に頼めば、店の一つや二つ、出してもらえるだろう。
ああ、いかん……俺はまた、こんな甘い考えを……
春が来て、三回生になり、本格的にゼミが始まった。それなりに勉強しないとさすがに国家試験は厳しい。昼は真面目に学校に行き、夜は渋谷のバーでバイトして、夜中は日替わりデート。家には着替えに帰るくらいで、面倒だし、ホテル代もバカにならない。
そうこうしている間に、俺はついに、親父の秘書の松永さんに呼び出された。松永さんは、親父がまだペーペー議員の頃からの秘書で、俺達兄弟の親父代わりと言っても過言でなく、親父だけじゃなく、佐倉家は松永さんに頼りっきりで、俺も松永さんだけは、信頼している。
「最近、家にちゃんと帰ってないみたいだねえ」
どうやら、俺の素行は、あちこちで目撃され、親父の耳に入り、激怒しているらしい。松永さんは、面倒そうに、俺の前に座ってため息をついた。
「バイトが遅くなるんで、終電に間に合わないことが多いんです」
「塾、辞めたらしいね」
「あんまり、合わなくて……」
「先生の事務所でアルバイトするかい?」
松永さんは、言わされてる感満載で、俺みたいな厄介者を押し付けられて、本当に迷惑そうな顔をしていた。
「あの、俺……一人暮らししたいんですけど……もう二十一だし、勉強も頑張ります。ちゃんと、しますから」
な、わけない。もちろん理由はホテル代わり。まぁ、バレバレだったけど、親父も松永さんも、ホテル街をウロウロされるよりは、とすんなり許可してくれた。というより、三行半を押され、俺は実家を出た。
門田真純が消えてしまってから、季節がまた変わって、梅雨があけて、夏になった。無料ベッドができた俺は、悶々としながら、いろんなオンナを抱いたけど、やっぱり門田真純を超えるオンナはいなくて、中途半端なあの日のセックスが余計に俺を興奮させて、俺はまた、違うオンナで門田真純を抱いていた。
あれから、社宅に行ってもないし、電話もしていない。きっと杉本と仲良く暮らしてんだろうな。十一時か……飯食って、今頃布団の上で……
「隅田川の花火、行ってたの」
ああ、それでか。浴衣の女の子が多いと思ったんだよ。はぁ、あれから一年かぁ。あのキスから一年も経つのか……
「ねえ、浴衣、イケテルでしょ?」
この子は常連のコ。うーん、一回か二回……『アフター』したかな?
目の前のギャルギャルしい渋谷のオンナより、なぜか地味な門田真純のことばかり考えてしまう。
やっぱり……俺、門田真純のこと、好きなんだろうなあ。
「ねえ、ケイタくんって!」
え? ああ、ボーっとしてた……
「ごめん、聞いてなかった」
「何それー。ムカつくー」
一応、客なので頑張って機嫌をとっていると、女の客が一人で入ってきた。その女は、とてつもなく、いいオンナで、長いストレートの茶髪に、黒いミニのワンピースに、黒いピンヒール。耳にはシャネルのイヤリングが光っていて、バッグもシャネル。女はカウンターに座って、その長い脚を組んで、惜しげもなく太ももを晒した。
「いらっしゃいませ」
「マティーニ」
女の声は、ちょっと舌ったらずで、ちょっとハスキー。パールピンクに光る唇が、猛烈に、エロい。
「かしこまりました」
周りの野郎どもがチラチラと見る。そりゃそうだろう。こんなにいいオンナ、こんな安物バーにはめったに来ない。
モデルか、女優のタマゴか……そんなとこかな。銀座のホステスかもしれないなぁ。とにかく、ガキじゃ到底手を出せない。みんなチラチラ見るだけで、誰も声をかけようとはしない。多分、この俺でも客なら、絶対無理。
だけど、俺はバーテン。客と喋るのが仕事。だからやめられないんだよなぁ、この仕事!
「お待たせしました」
女はにっこり笑ってグラスを上げて、俺もカッコ良くハーパーのロックグラスを上げた。
「初めて、ですよね?」
「……うん」
女は、ピンクの唇でマティーニを飲んでいる。胸元からは、たわわな谷間が……たまんねえ……今夜、お願いしたい!
もう浴衣のギャルも、汗臭い野郎どもも、俺には邪魔でしかない。早く帰れ、お前ら。
「待ち合わせですか?」
「ううん」
「お一人ですか?」
「うん」
俺は、またもや、カッコ良く、マルボロをくわえて、どっかの女に貰ったジッポで火をつけた。
「俺、ケイタっていいます。お名前、聞いてもいいですか?」
決まった……今の俺、超渋くね?
最高にカッコ良く言ったつもりだけど、女はクスクス笑った。
あれ? なんか、おもしろかった?
「佐倉くん。私だよ?」
へ? 私? 誰? えーと、ナンパしたコかな……でも、こんないいオンナなら、絶対忘れないけど……
「もう、忘れちゃったの?」
女は、ちょっとほっぺたを膨らまして、上目遣いで俺を見た。
忘れ……うん? あれ? もしかして……
「えーと……門田……さん?」
「やっと、思い出した?」
その女は、門田真純。あの、門田真純。めっちゃめちゃ……
「うふっ。久しぶりだね」
「う、うん……あの……」
「中村くんにね、ここでバイトしてるって教えてもらったの」
いや、まあ、そこもだけど……
「ねえ、どう?」
「え?」
「イケてる?」
そりゃ、もう……かなり……
「うん……なんか、変わり過ぎてビックリした」
門田真純はうふっと笑って、マティーニをもう少し飲んだ。
「お店、何時に終わるの?」
「一時くらいかな」
「待ってて、いい?」
「もちろん」
ますます、他の客が邪魔になって、十二時半に無理矢理追い出して、店を閉めた。
「いいの?」
「いいのいいの。どうせなんも頼まないし」
俺は、変化した門田真純を連れて、夜の渋谷を歩いた。門田真純はゆさゆさと胸を揺すりながら、ケツをプリプリと振りながら、歩いている。男どもがチラチラ見る。腰に手を回すと、門田真純は、俺に体を寄せた。
見ろ見ろ。俺のオンナ! 最高だろ?
お腹がすいたというので、ファミレスで飯を食った。夜中だっていうのに、結構混んでて、ザワザワうるさい。
「家、帰らなくていいの?」
門田真純は、夜中のこの時間に、サーロインステーキセットを食べながら、軽く言った。
「うん。今日はお友達のお家に泊まるって言ったから」
泊まる? 泊まるって、言ったよな?
「一人暮らしなんだよね? 佐倉くん」
「うん」
「お部屋、見たいな」
「いいよ」
いつもはチャリ通勤だけど、今夜はタクシーに乗って、家へ帰った。鍵を開ける時に、ちょっと散らかってることを思い出したけど、そんなことを理由に入れないわけにはいかない。
「わあ、広いんだね!」
門田真純は十六畳のリビングと、最新のシステムキッチンを嬉しそうに見ている。
「もう一部屋あるよ」
「そうなんだぁ。すごいなぁ、こんな広いとこに一人で住んでるなんて……」
門田真純はソファに座って部屋の中を見渡した。クーラーをかけて、ビールを持って、俺も隣に座る。
「まだ、あの部屋に住んでるの?」
「うん」
「杉本、元気?」
門田真純は、その質問には答えなかった。俺も、それ以上は聞かなかった。その代わり、俯いたまま、呟いた。
「耳、痛かったの」
イヤリングを外して、耳たぶを押さえる。
「大丈夫?」
「どうか、なってる?」
「どれ?」
門田真純は、明らかに俺を誘っている。俺は、その誘いに乗った。長い髪をかきあげて、左の耳たぶを見ると、確かに赤くなっていた。
「赤くなってる」
「イヤリング、苦手なの」
耳たぶをそっと触ると、ちょっと熱い。
「反対も、見て」
「こっちも、赤くなってる」
「痛いの」
「治してあげる」
俺は、ふうっと息をかけて、耳たぶを唇で挟んだ。
「うん……」
そのまま首筋に唇を這わせて、俺の唇は、門田真純の唇に到達して、俺達はゆっくりキスをした。ゆっくり、唇と唇が、溶けちまうんじゃないかってくらい、俺達は、甘くて、熱い、キスをした。クーラーのウィーンっていう音に混じって、門田真純の吐息が聞こえて、俺はもう、どうしようもないくらい、門田真純に欲情していた。
「もう一部屋、見る?」
もう一部屋は、もちろん、寝室。セミダブルのベッドと、クロゼット。ベッドは今朝起きたままで、朝脱いだTシャツと短パンがそのままになっていた。
「おっきなベッドだね!」
門田真純は子供みたいに飛び込んで、その拍子に、ピンクのパンツがチラッと見えて、俺はそのまま、スカートをたくし上げて、そのピンクのケツに顔を埋めた。
「もう、やだぁ!」
「かわいい、オシリ」
うつ伏せに押し倒して、ふわふわのおっぱいが掌に溢れる。
「おっぱい、おっきいね」
「そう?」
開いた胸元から、ブラの中に手を入れて、人差し指と中指で、突起を挟んでクリクリすると、門田真純が俺の下で、ぴくっと動いた。
髪をかき分けて、赤い耳たぶとうなじを舐めて、俺はもうギンギンで、ジーンズ越しに門田真純の内腿に擦り付けた。
「わかる?」
「うん」
「いい?」
「アレ、ある?」
「あるよ」
俺は枕元の引き出しからコンドームを出して、門田真純に見せた。
「いいよ」
門田真純はにっこり笑って、両手を上げた。
「脱がして」
ああ、そういえば、セックス部屋でもこうしてよな……
背中のファスナーを開けて、ワンピースを脱がしてやった。レースのピンクのブラジャーとパンツはお揃いで、相変わらず、ブラジャーに詰め込め過ぎだと思った。
「俺も」
俺も両手を上げた。門田真純は笑ってTシャツを脱がしてくれて、ベルトも外してくれたから、ジーンズも脱いだ。
俺達はしばらくそのままで、キスをしたり、カラダのあちこちを触ったり舐めたり噛んだりしあった。門田真純は、演技じゃなくって、ほんとに敏感のようで、うっとりとした顔で、カラダを時々ピクピクさせながら、俺の愛撫を受けて、膝を開くと、割れ目の部分のピンクの布地に少しシミができていた。
「シミ、できてるよ」
「……言わないで……」
シミはどんどん広がっていく。布を横からずらして、指を入れると、ちょっと酸っぱい匂いがして、その香気にクラクラして、気がつくと、俺のパンツにもシミができていた。
そのまま、門田真純の中に人差し指を入れて、またシミを広げて、ついにそのピンクの布を全部取り払った。
あの夜、三ミリの隙間からは見えなかったそこが、目の前にある。杉本にしか、見えなかった門田真純が……
杉本、俺はお前の女を手に入れたぜ。なあ、杉本。見ろよ、お前の女、俺の下で、こんなに感じてるぜ?
俺は門田真純の膝を大きく開いて、あの夜の杉本のように、そこに顔を埋めた。
門田真純はちょっと掠れた声で、カラダをビクビクさせて、俺の髪を掴む。
舐めても舐めても中から液が流れてくる。そして、門田真純の声がどんどん大きくなる。
顔……顔が見たい……
舌と指を、交代させて、門田真純を抱き寄せた。門田真純は潤んだ目で俺を見つめて、恥ずかしそうに目を閉じた。
かわいい……今まで抱いたオンナの中で、一番かわいい!
こんな……こんな顔を、杉本は抱いていたのか……独り占めしてたのか……
「マスミ……」
俺は、杉本みたいに、名前を呼んだ。
「ナニ?」
門田真純は、人差し指を噛みながら、甘えた声で言った。
「俺のモノになれよ」
そんな言い方、なんでしたんだろう。
門田真純は、伏目になって、俺の耳元で囁く。長い睫毛が、俺のほっぺたに微かに触れた。
「私ね……住むところが……ないの……」
門田真純は、俺の恥ずかしいシミができた部分を、親指と人差し指で握った。
「うん……」
門田真純の指が動く。
「どうしたら……いい?」
門田真純は消えそうな声で、掌で俺を扱く。
どうしたら……どうしたら?
俺は、気づいてしまった。頭のいい俺は、気づいてしまった。
門田真純は、ここに住みたいんだ。俺と住みたいんじゃなくて、クーラーのある、広いベッドも、システムキッチンもある、この部屋に住みたいんだ……
モノにされるのは門田真純じゃなくて、俺。いや、俺の、金。門田真純は、そのカラダで、きっと、杉本も、モノにしたんだ。俺という、生活の糧を見つけたから、門田真純は、ここに引っ越そうとしている。
「お部屋、借りるお金ないし……」
門田真純の手が止まる。
ここで、終わりってことか……
「やっぱり、帰ろうかな……」
腕の中には、ブラだけの、最高にいいオンナが、熱いカラダで、俺の指を濡らしながら、元の部屋に、あいつの所に、帰ろうとしている。
帰せるかよ……もう、ここで終われるかよ……
俺は、負けた。門田真純に、いや、目の前の欲望に、負けてしまった。
「ここに、住めばいいじゃん」
ああ、言ってしまった……
「ほんとに? いいの?」
「真純、つきあおうぜ」
門田真純はにっこり笑って、俺の唇に吸い付いて、嬉しい、と言った。
そして、カラダを起こして、俺のボクサーブリーフをずらして、上を向いた先っぽに唇を当てた。
「あっ……」
俺は思わず声を出してしまって、門田真純は、舌で裏側をチロチロと舐めて、たぶん、先から出てる液を吸い取って、口の中に入れた。
確実に、杉本より、サイズダウンしている。満足させられないかもしれない。どうしよう。
門田真純の口の中で、ぼんやり考えているうちに、門田真純は、長い茶色に光る爪でコンドームを開けて、準備していた。
もうちょっと、口の中にいたい……でも、門田真純の中にも入りたい……
マゴマゴしてる間に、門田真純は、俺の上に跨って、俺を中に入れた。
うわ……すげぇ……キツ……ヤバ……
「ちょっと、待って……」
「うん?」
門田真純は呟いたけど、俺の上で動き始めた。
ああ、うん、と声をあげながら、おっぱいがブルブルと揺れる。
「おっぱい、苦しい?」
「うん……とっていい?」
「いいよ」
ホックが外れ、、乳肉が溢れだす。ピンクの突起は、赤くカチカチになっていて、俺は両手で両突起を摘まんで反撃したけど、全然効かなくて、このままだと、何もせずに終わってしまう……
そんな、カッコ悪いことできるかよ……杉本みたいに、暴れさせないと……杉本みたいに……
「真純……バックしていい?」
「うん……」
門田真純は俺から降りて、四つ這いになった。もう、猛烈に後悔。ケツを突き出した姿は、もうそれだけで、エロすぎた。
「恥ずかしいよぉ……」
俺は恐る恐る、結合させた。
ううっ……もう、ダメかもしんない……
門田真純はカラダを反らせ、俺を締め付ける。
「真純……めっちゃエロい……」
もう長くはもたないし、俺は思いっきり門田真純を攻めた。攻めて攻めて、攻めまくった。あの夜、杉本が門田真純を押さえつけていたように、俺も門田真純を必死で押さえつけた。妄想じゃない、本物の門田真純を、俺は必死で抱いた。必死で、ずっと抱きたかった体を、俺は抱いた。
門田真純は悲鳴みたいな声をあげて、俺も声を漏らして、俺達は、たった一箇所しか繋がっていないのに、全身を震わせた。
「めっちゃ、気持ちよかった」
「うん」
「真純は?」
「うん」
ほんとかよ……ほんとに満足したのかな……杉本と、どっちが……よかった?
バカバカしい嫉妬を感じながら、門田真純を抱きしめて、キスをして、タオルケットをかけた。門田真純の体は、俺の妄想以上で、もう他の女を抱いても感じないんじゃないかって思う位、最高だった。
「かわいい、真純」
門田真純は、うふっと笑った。
「ねえ、佐倉くんの、好みの見た目になった?」
「うん。めっちゃ、好み」
「がんばったんだよ。イケてる女の子になるために」
「俺の、ために?」
「カノジョになりたかったの」
それは……俺のことが、好きだから? それとも……
それ以上は聞けなかった。答えは、聞かなくてもわかっていたから。
そして、門田真純も、俺の気持ちを聞かなかった。
杉本に聞いたみたいに、私のこと好き? って、俺には聞かなかった。
「もう、カノジョだよ」
門田真純は、嬉しそうに笑って、俺の胸に顔を埋めた。長い髪からは、甘い匂いがして、目の下に、少しマスカラが滲んでいた。
「眠くなっちゃった……」
「うん、寝よっか」
「おやすみ……なさい……」
門田真純は、全裸のまま、俺の腕の中で目を閉じた。
寝顔はかわいくて、俺はしばらくその顔を見て、ほっぺたにキスして、腕枕の腕がしびれてきたので、そっと抜いた。
杉本は、朝まで腕枕、できるんだろうか……
ぼんやり考えてるうちに、俺もいつの間にか、眠っていた。俺達は全裸で、体を絡めたまま、朝を迎えた。
こんな、こんな始まり。
俺達は、俺達の目の前の欲望を満たすために、お互いの体をつなげて、心は置き去りで、こうやって、始まった。そして、大切なものを失って行く。
でも、俺達はまだ若くて、ガキで、そんなこと、全くわからなかった。
時間も、金も、若さも、何もかも無限で、俺達は、ずっとこのまま、このまま永遠にいられると、思っていた。
家族写真
午後七時四十八分。十八分の遅刻。何かあったのかと思ったけど、まあ、普通に、渋滞だったようだ。
ロビーに降りると、妻が待っていた。黒いタイトスカートのスーツに、白いフリルのブラウス。グッチのピンヒールを履いた、極上の女が俺の妻。
一瞬目が合ったけど、すぐに逸らされた。いつもそうだ。目が悪いのか?
「遅かったな」
声をかけると、ちょっとびっくりした顔をする。
「渋滞だって言ったじゃん」
俺達は無言で会場へ行き、ドアの前で腕を組む。氷のような顔の妻は、とたんに輝くような笑顔を見せる。そして俺も、ハリソンフォード並みの笑顔で、俺達は会場へ入る。
「本当に、佐倉夫妻は素敵だわ」
背中に肉の盛った女が俺達に声をかける。妻とそんなに歳は変わらないだろう。横に立つダンナもその腹。どうにかしろよ。
俺は聞き飽きたお世辞にうんざりしながら、笑顔を振りまく。隣の妻は満足気に笑っている。
そうだろうなあ。お前はこうやって、チヤホヤされて、綺麗だなんだ言われるのが好きなんだからな。そのために、エステやらブランド品やらに金かけてんだろ? ステイタスのために家庭を捨てて、仕事してんだろ? こんな上辺だけのくだらない人間達の集まりには、お前のような見栄と体裁しかない女はとても便利だ。
「主人の協力のおかげで、私も思う存分仕事させてもらえますのよ」
何が協力だよ。家事は家政婦がいて、面倒ごとは松永さん。俺達は夫の役目も妻の役目も何も果たしていない。何をやってるんだろうな、俺達は。
お互い、部屋に閉じこもって、俺達は、何をやってるんだろうな。
時間と労力の無駄でしかない、くだらない政治家先生のパーティが終わり、俺達は笑顔で挨拶をしながらタクシーに乗った。タクシーに乗ってしまえば、もう俺達は他人。
腕を解き、無理な笑顔をリセットし、窓の外を見る。
「どちらまで?」
運転手が聞いてきた。
「仕事あるから、会社戻るんだけど」
はいはい、またお仕事ですか。部長さん、お忙しいことで。
「運転手さん、駅で降ろして」
「どちらの?」
「一番近いとこで」
一刻も早くこのタクシーから降りたい。というより、この女の隣から解放されたい。
俺は妻に無言で一万札を渡し、タクシーを降りた。妻は黙って受けとり、俺が降りると、運転手に地図を見せていた。会社じゃねえのか? まぁ、いいけど。
あの女には男のニオイはしない。あの女は、人を愛せない。あの女が愛しているのは自分だけ。自分さえ幸せならそれでいい。人のことなど、どうでもいい。
九時半か……
適当なオンナに電話をしようかと思ったけど、明日の資料ができていないことを思い出した。おとなしく帰ろう。
改札へ向かうと、くたびれたスーツのサラリーマンに声をかけられた。
「佐倉?」
「……中村か?」
「やっぱり、佐倉かぁ! 懐かしいなぁ!」
二十年ぶりの中村は、すっかりオッサンになっていた。腹も適度に出て、髪の毛も寂しくなりつつある。
「どっか行くのか?」
「いや、帰るとこだ」
「時間あるなら、ちょっと飲もうぜ」
資料が気になったけど、懐かしい話もしたい。純粋に俺は、中村と話したかった。
俺達は近くの焼き鳥屋に入り、カウンターに座った。中村は親父さんの後を継いで社長になったらしい。三十で結婚して、子供は二人。小二と年長の女の子だそうだ。
「で、お前は何やってんの?」
「ああ、俺? コンサルタント、かな」
俺は名刺を出した。だいたい、反応はわかる。
「所長? 独立したんだ!」
「まあな」
「すげえなあ……」
「お前だって、社長じゃん」
「いやぁ、俺なんか……名前だけで、俺もタクシー乗ってるしな」
だろうな。その、スーツ。
「なあ、門田さんと結婚したんだろ?」
「え、まあな……」
杉本から聞いたんだな。
「杉本、覚えてるだろ?」
「ああ」
杉本……俺はいつまでも杉本から逃れられないのか。
「あいつ、今、うちで運転手やってんだよ」
「えっ! 鉄工所は?」
「五年くらい前かなあ。潰れてな。あいつ、本社の資材部長やってたんだけど……経理部長が資材横流ししててな。しばらくは警察からも事情聞かれて……休みもなく必死で働いてたのに、かわいそうだったよ」
「そう、なんだ……」
杉本とも、もう何年も会っていない。あれきり、だな……
「聡子さん、だっけ、奥さん」
「そうそう。聡ちゃん、うちの事務やってくれててさ。杉本、なかなか仕事が見つからなくて、少しの間でもいいからってうちに来たんだけど、あいつ、人当たりいいし、評判いいんだよ。運転もうまいしな」
「でも、いかつくない?」
「あれくらいがいいんだよ。最近は物騒だからなあ」
中村は笑って、ビールを飲んだ。
「ああ、そう、写真見る?」
中村はスマホを出して、画像を出そうとしたが、老眼が進んでいるのか、若干画面が遠い。
「あったあった。夏の慰安旅行のやつ」
そこには、杉本一家が笑っていた。何年かぶりの杉本はガタイのいいオッサンで、聡子さんは地味なオバサンで、いい父ちゃんといい母ちゃんといった感じになっていた。
杉本の隣には、杉本に似たガタイのいい男の子がいて、聡子さんの両手には女の子が二人手をつないでいる。一人は杉本に似て、もう一人は聡子さんに似ている。
「上の子は中一で、あと、小二と年長。うちと一緒だから、子供も仲良くてね」
幸せそう。五人とも、多分ユニクロの服で、聡子さんはほとんど化粧もしていなくて、パーマもあてていない。
でも、笑っている。本当に笑っている。俺達のような、仮面の笑いじゃなくて、素顔で笑っている。
「ちなみに、これが俺の家族」
中村の嫁さんは、ちょっと太っていて、娘二人もちょっと太っていて、中村の腹の理由がわかった気がした。
「いいなぁ、なんか、みんな幸せそう」
「そうかあ? 毎日食費やら塾代やらでケンカだぜ?」
ケンカ……ケンカなんか……いつしたかな。
「佐倉、子供は?」
「え、ああ、いないんだよ。できなかった」
「そうかあ。まあ、仕方ないよな。でも、その方がラブラブでいれるだろ? 子供いると、もう家族だからなぁ」
家族……家族がいるんだ、こいつには……
「写真、ないの?」
俺はさっきのパーティで撮った、Facebook用の写真を見せた。
反応は、だいたい……わかる。
「ええ! これ、門田さん? えー、見違えたなあ!」
そうか。中村は変化後の門田真純を知らないんだ。
スマホの中には、極上の笑顔の俺と妻が並んでいる。腕を組み、妻は俺の肩に寄り添って、赤い口紅で、幸せそうに笑っている。俺達の左手の薬指にはカルティエのマリッジリング、妻の胸元には、嫌味なほどキラキラとダイヤの並んだティファニー、俺の左手首にはロレックス。仲睦まじいセレブ夫婦。しかも美男美女。雑誌に取材されたこともある。それほど俺達は似合いで、美しくて、皆が羨むセレブ夫婦。
「いいなぁ、セレブじゃん! しかし、お前も変わんないなあ。イケメンだよ、相変わらず」
中村は、本心で言ったんだと思う。嫌味を言うような奴じゃないし、俺もイケメンだし、セレブだし、妻も美人だし。
「そうかな」
「羨ましいよ」
中村は屈託なく笑った。俺も屈託なく笑ったけど……俺は、中村が羨ましかった。杉本が羨ましかった。
小一時間程して、中村の奥さんから電話がかかってきて、二十年ぶりの飲み会はお開きになった。
「また、ゆっくりな」
「ああ、杉本にもよろしく」
電話番号を交換して、中村は定期で改札を通り、俺も切符を買おうと思ったけど、なんか面倒で、駅前に出て、タクシーに乗った。
家に着くと、十一時半。妻はまだ帰っていないようで、リビングは真っ暗で、冷え切っていた。シャワーを浴び、歯を磨いて、リビングの電気を消して、部屋にこもった。
明日の資料、作らないと。三十分。三十分で仕上げよう。
PCを開いたけど、眠気が襲った。眠い。どうしよう。もう明日にしようか。いや、ダメだ。やってしまおう。
眠気覚ましのガムを噛んで、キーボードを叩いた。カチャカチャと、わざとらしいほどの大きな音が、静かな部屋に響く。
Excelの画面に打ち込まれる十ポイントの数字。カチャカチャの音。数字。音。数字。音。
……見えない。数字が見えない。キーボードの上の指に、涙が落ちた。
俺は、何をしているんだろう。
この十五年……いや、二十年、何をしていたんだろう。そして、これから二十年、何をするんだろう。
杉本も中村も、家族を持った。金はないかもしれない。賃貸マンションかもしれない。でも、家族がいる。ケンカできる、嫁さんがいる。金のかかる、子供がいる。
俺は? 俺には何がある?
もし俺が、歳をとって、ボケちまったら、あいつは俺のオムツを変えてくれるんだろうか。もし俺が失業したら、あいつは俺を励ましてくれるんだろうか。もし俺がハゲて、太鼓腹になったら、あいつは俺と腕を組むんだろうか。
金。金しかない。
俺は、ボケたら介護ホームに入って、失業したら親父に頭下げて、ハゲて腹が出たら……ヅラでも被ればいいか。それは大したことじゃないな。
なんだ、全部、金で解決できるのか。
じゃあ、あいつはなんのためにいるんだ? 逆に、俺はなんのためにいるんだ?
こんな、息の詰まる、ため息しかでない生活、死ぬまで続けるんだ?
なんのバツゲームだよ。バカバカしい。
こんな生活……いつまで続くんだろう……
お忘れ物です
真純が俺の部屋に来て、一週間。
俺達は、デパートやホームセンターやスーパーをまわって、真純の生活用品とか、服とか、食器とか、いろんなもんを、親父のクレジットカードで買いまくっていた。
ずっと禁止令が出ていたセルシオも、松永さんに、次に事故を起こしたら、免許証を更新しない、実家に戻る、親父の事務所でバイトする、の三カ条の誓約書を書いて、ようやく取り戻した。
だけど、俺には、どうしてもスッキリしないことがあった。
それは……
「杉本とは、話したの?」
「何を?」
真純は、オシャレなカーテンを見ながら、面倒そうに答えた。
「いや、だから……俺の所にいること……」
真純は答えない。答えずに、笑顔で言った。
「ねえ、お腹すいた。なんか、食べに行こうよ」
いや、真純、お前……それでいいのか?
真純は携帯を持っていない。たぶん、杉本に連絡すらしていない。
そんな……薄い関係じゃ、なかったはずなのに……
俺はちょっと、杉本がかわいそうになったけど、もしかしたら、冷め切ってて、お互い、もう終わりにしたのかもしれない。持ち前の逃避思考で、そう考えることにした。
だから、俺の所に急に現れたんだ。なるほど、そうか。別れたんだ。なんだ、それなら気にすることないか。
目の前で、真純はトマトソースのパスタを美味そうに食っている。ピンクのTシャツに、ちょっとソースが飛んで、赤いシミができた。
「ソース、飛んでるよ」
「あっ、ほんとだー。もう、落ちないんだよね……」
「新しいの、買えばいいじゃん」
「うん、そうする」
俺達は、オシャレな服屋で、新しいTシャツを買って、親父のクレジットカードで支払いをして、カーテンもついでに買って、家に帰った。
「よう」
久しぶりに、中村が店に来た。
「久しぶりじゃん」
中村はいつものようにビールを飲んで、タバコを吸っている。でも、なんか、様子がおかしい。
「元気してたのかよ」
「まあな」
しばらく、たわいない話をして、中村が気まずそうに切り出した。
「あのさあ、佐倉……」
「何?」
「探してんだよ……」
「何を?」
「……門田さんを」
来た……ついに、恐れていた現実が……
「だ、誰が?」
「杉本」
やっぱり……やっぱりか……やっぱり真純は、黙って出て来たんだ……別れてなんか、なかったんだ……
「念のために聞くけど……違うよな?」
どうしよう……でも、中村に嘘はつけない……ついたって、いずれはバレる。
「ちょっと前に、お前宛に、塾に門田さんから電話があったんだよ」
「な、なんて?」
「いるかって」
「それで……」
「もう辞めたって言ったら、連絡先教えてほしいっていうから、勝手に教えるのもどうかと思って、この店のこと話したんだよ」
「そうなんだ……あのさ、その時に、その、俺が引っ越したことも言った?」
「どこに住んでるのか聞かれたから、一人暮らし始めたからわからないって言った」
そうか……それで……
「なあ……まさか……いるのか?」
もう、正直に言うしかないけど……バカ正直に言えるわけがない。この俺が、正直に言えるわけがないじゃないか。
「す、住むところがないって言うから……」
「お前……だからって……」
「知らなかったんだよ。そんな、そんなつもりじゃなかったんだ。俺はてっきり、もう別れたのかと……」
「門田さんがそう言ったのか?」
「いや、それは……」
中村はため息をついて、呆れた顔で、俺を見た。
「杉本、すげー心配してるぜ?」
そんなこと……俺のせいかよ!
「門田さん、この半年でなんか様子が変わったらしいんだ。……お前のせいじゃないのか?」
「そ、それは知らないよ。ほんとに、その、先週、突然ここに来たんだよ。それまでは、ほんとに一回も会ってなかったし、連絡もしてない。ほんとだって」
いや、知らないことはない。きっとそれは……俺のあの、バカ発言のせい……
「とりあえず、門田さんは元気なんだな?」
「あ、ああ、それは、元気だから……」
「杉本にそう言っとく」
「えっ! 杉本に、言うのか?」
「当たり前だろ? あいつ、心配して、夜も寝ずに探してんだぜ? まあ、これは俺が言うことじゃないかもしれないけど、つきあうんなら、ちゃんとしろよ。このままじゃ、杉本がかわいそうだ」
中村はそう言って、千円札を置いて、出て行った。
はあ……なんてことだ……そんなこと、俺は知らないじゃないか。勝手に真純が俺んとこ来たのに……
猛烈に憂鬱な気分で家に帰ると、真純は俺のTシャツを着て、スヤスヤ眠っていた。新しく買った、ふわふわのダウンケットにくるまって、クーラーの効いた寝室で、眠っていた。
杉本は、寝ずにお前を探しているというのに……
シャワーを浴びて、ビールを飲んで、寝ようと思ったけど、気が重すぎて眠れない。
結局、そのままソファで朝を迎え、気分は最悪で、ぼんやりテレビを見ていると、昼前に真純が起きて来た。
「おはよう、慶太」
ちょっと寝ぼけ眼で、軽くキスをして、ああ、やっぱりかわいいな……
「うん、おはよう」
「やっぱり、クーラーがあるとよく眠れる。前の部屋は暑くて、夏は寝不足だったの」
真純は、昨日買った菓子パンと、缶コーヒーを持ってきて、隣で食べ始めた。
「真純……あのさ……」
「何?」
真純はテレビを見て笑っている。
こうしてる間も、杉本は……
「ここに、いるんだよね?」
「いていいって、言ったじゃん」
「それなら、杉本に、ちゃんと言わないと……心配してるみたいだよ」
真純は一瞬、表情を固くして、でもすぐにテレビを見て笑い出した。
「おっかしいの、これ」
「真純、ちゃんと聞けよ」
「もう、うるさいわね! わかったわよ。行けばいいんでしょ?」
「今日は日曜だし、杉本、家にいるんじゃないかな」
真純は黙ったまま、不機嫌にパンを食べて、化粧をしに行った。
杉本の社宅の前に車を停めると、不機嫌なままの真純が言った。
「なんて言えばいいの?」
なんて……それは……
「別れたいって」
「それで? 理由を聞かれたら?」
「……他に、好きな人ができたからって……」
「そう言えばいいのね?」
「ちゃんと話せば、杉本もわかってくれるよ」
「あー、めんどくさい!」
真純は不機嫌に車を降りて、バンッてドアを閉めて、杉本の部屋へ行った。
どうしよう……大丈夫かな……杉本が逆上したりしたら……いや、もしかしたら、元サヤとか……やっぱり俺も行った方が良かったかな……
ウジウジ考えている間、約十分。
不機嫌な顔の真純が出て来た。
えっ、もう?
真純はチラリと停めてある杉本の軽トラを見て、セルシオのドアを開けた。
「お待たせ」
スモークガラスの向こうには、部屋の窓からセルシオを見ている杉本がいた。
呆然と、悲しそうに、絶望した顔で、セルシオを眺めていた。
「杉本、なんて?」
「知らない」
「真純……ちゃんと、話したんだよな?」
「言われた通りに、言ったよ」
真純は、ヴィトンのシガーケースから、細いタバコを取り出した。タバコを吸う女は、あまり好きじゃない。
「タバコ……いつから?」
「都会のイケテル女の子は、タバコ吸うんだよ」
真純は、ふぅっと煙をふかした。
「タバコ吸う女の子は、あんまりなんだ、俺」
「イケテルのに?」
「イケてないよ」
それを聞いて、真純は火を消して、ゴミ袋にシガーケースごと、突っ込んだ。
「じゃあ、やめよっと」
真純は、変わっていた。俺が、変えてしまっていた。何かを、失くしてしまっていた。
きっとそれは……俺が一番、欲しかったもの……
ブランドのエプロン
セルシオから降りると、冬の北風が俺を冷たく吹き抜けたけど、寒さなんて全く感じない。そんなどころじゃない。
震える手で親父のクレジットカードから三十万引き出し、封筒に詰め込み、パーカーのポケットに入れた。いざとなれば、これを渡して逃げればいい。
そう、ついに来た。真純と暮らし始めて半年。ついに、恐怖の瞬間がやってきた。
金曜の夜に、携帯にかかってきた、知らない番号からの電話。それは……杉本からだった。
待ち合わせの公園につくと、杉本は、ベンチでタバコを吸っていた。半年ぶりに見た杉本は、さらにパワーアップしていて、格闘家と言ってもおかしくない仕上がりになっていた。
「久しぶりやな、佐倉」
「お、おう」
怖い……めっちゃ怖い。
俺はパーカーの中の三十万を握りしめた。
「単刀直入に聞く。お前、真純んこと、本気なんか」
本気……本気かどうか……そんなことわかんねえよ。でもここで本気じゃないとか言ったら、殺されるかもしれないしな……
「本気だよ。決まってんじゃん」
杉本は俯いて、深いため息をついた。
「そうか……本気なんじゃ……」
どうしよう。俺、お前ほど、真純のこと、好きじゃねえかも……
「あ、あのさ、杉本……」
俺は言いかけて、言葉を飲んだ。純粋な、いかつい筋肉男は、さめざめと泣いている。くだらない、ナンパ男の前で泣いている。
「俺と真純は、幼馴染なんや」
「知ってるよ」
「真純の家は、母親一人でな……俺は二親そろとうたけど、親父はチンピラで……おんなじボロボロの長屋に、すみょうったんよ」
なんだよ、そんな昔話で、女を取り戻す気か? 意外とちっせえな、杉本。
「俺らはガキんころから、貧乏で、食うもんものうて、いっつも腹空かせて……泣いたら親に殴られてなぁ。真純の母親は男にだらしねえオンナで、家に男連れ込んでは、真純んことほっぽらかして……オトコに逃げられたら、お前のせいじゃゆうて、一日中でも殴られよった。俺はそんな真純がかわいそうで、公園やら駅やらに遅まで二人でおって、スーパーやら、食いもん屋のゴミ箱あさりよった。俺は男やけ、まだよかったんやけどな、真純は女やのに、サイズの合わん、着古した汚ねえ服着さされて、かわいそうじゃった……」
なんだよ、そんな話……聞かせんなよ……
「俺は中学に入る前くらいから荒れ始めてな、街でカツアゲやら盗みやらして、真純に金渡しとった」
杉本は遠い目で夕日を見た。西の方、故郷の方を見ていたのかもしれない。
「真純は保護施設を出たり入ったりしよってな、中二の時、家に帰ったら、母親の連れ込んでた男に……泣きながら、俺のとこきて、もう家には帰りとうないゆうて……でも、俺はどうすることもできんかった。できんかったから、その男ボコボコにして、真純のこと連れて逃げたけど、すぐ捕まってな。俺は鑑別所で、真純は施設に入って。でも、それで俺らぁは、立ち直れたんよ。真純は施設から高校に行けて、めっちゃ勉強して、東京行くゆうて、奨学金もろうてな。俺は鑑別所から仕事世話してもろうて、住み込みの職人始めて、おかげで東京来てからも、すぐに仕事見つかった」
杉本と門田真純は、思っていた以上に絆が強くて、過去が重くて、俺はもう……
ムリ。杉本、門田真純は、俺にはムリ。返すわ。てゆうか、返せって言いたいんだろ?
「杉本、真純のこと、マジで好きなんだ」
「そうじゃ。俺は真剣に真純に惚れとる。真純のためやったら何でもする」
杉本は立ち上がって、俺の前に立った。
な、殴られる!
「ま、待てよ、杉本。あのさ……」
ポケットの三十万を出そうとした時、杉本が頭を下げた。
「真純んこと、幸せにしてやってくれ」
は? いや、待てよ。俺はそんな……そこまでじゃ……ねえんだよ。
「あいつは、貧乏から抜け出したいんじゃ。俺はそれ以外のことじゃったら何でもしてやれるが、それだけは……無理かもしれん。俺には、学歴もないし、前科もあるし……東京じゃあ、俺みたいなもんは、なかなかな……」
ていうか、俺にはそれしか無理だよ。
「真純は、ええ女じゃ。大事にしてやってつかあさい」
杉本は涙を、頭に巻いていたタオルで拭いて、軽トラの荷台から小さな段ボール箱を二つ、ベンチに置いた。
「真純の荷物やけ」
たった二箱。二年間暮らして、たった二箱……
「じゃあ、佐倉、頼むな。真純のこと、よろしくな」
杉本は、右手を出した。その手は、冬だって言うのに、真っ黒で、爪の間には黒い油が染み込んでいて、アカギレの絆創膏も、黒くなっていた。
いや、違う……違うんだよ、杉本……俺にはそんな……そんな覚悟は……
固まる俺の手を、杉本は無理矢理握って、俺達は、固く……握手をした。
「わ……わかった……幸せにするよ、絶対……」
「そうか……そんだら、俺も安心じゃ。真純に、幸せになれ、ゆうといてくれ」
杉本はいつものように少し笑って、軽くクラクションを鳴らして、軽トラを出した。
どうしよう。これからどうしよう。
軽はずみな気持ちで、他の男の女に手を出し、他の男から奪い、他の男の女を手に入れた。俺は、杉本将吾という男の人生をほぼ埋めてきた女を奪ってしまった。金で、杉本の一番大切なものを……買った。
箱の中には、着古したあのタンクトップのワンピースとか、シミのついたエプロンとか、白いブラウスとか、タイトスカートとか、今の真純には無用のものが詰まっていた。
家に帰ると、部屋に真純はいなくて、とりあえず段ボールを押入れに入れた。杉本と会ったことは、言わないつもりだった。ていうか、言えるわけない。
俺は、『責任』という現実から逃げたかった。あの花火の日に、戻りたかった。花火に誘わなかったら、俺達はこんなことにはならなかった。
「ただいま」
真純がスーパーの袋を抱えて帰ってきた。
「ふう、寒かったぁ。ご飯、作るね」
笑顔でシステムキッチンに立ち、ブランドもののフリフリのエプロンをして、真純は料理を始めた。いつの間にか、キッチンには調理器具とか食器が増えていて、ドイツ製の包丁とか、イタリア製の鍋とか、フランス製の食器とか、真純は上機嫌に料理をして、四人がけのダイニングテーブルに、夕飯を並べた。
今日の献立は、肉じゃがと、味噌汁と、茶碗蒸し。どれも美味くて、俺は飯をおかわりした。
「美味しい?」
「ああ、美味い」
真純は微笑んだ。俺はこの真純の笑顔が好きだ。押し入れの段ボールをどうしようか考えていたけど、なんか、もうそんなことどうでもいい。やっぱり俺は真純が好きなのかもしれない。杉本ほどじゃないけど、好きなんだ。
俺は、目の前で俺だけのために笑う真純に見惚れ、舌ったらずに一生懸命、今日の出来事を話す真純の、ちょっと掠れた声に聞き入っていた。そしていつの間にか、オーブンの話になっていた。
「ねえ、オーブン欲しいの」
「オーブン?」
「オーブンがあればね、色々お料理できるし、ねえ、いいでしょ?」
「明日、電器屋、行こうか」
「うん。行く」
俺達は二十一の学生のくせに、セルシオで電器屋に行って、二十万近くする最新のオーブンを、躊躇なく買った。もちろん、親父のクレジットカードで。
次の日、オーブンが届き、真純は早速ローストビーフを作っていた。
この肉、いくらなんだろう。たぶん、和牛の、めっちゃいい肉だよな。
「どう? 美味しい?」
「うん、美味い」
残念ながら、真純は本当に料理が上手くて、家事も上手くて、掃除も洗濯も、学生なのに完璧で、俺は杉本の気持ちがわかりつつあった。離したくない。真純はそう思わせる女だった。
そして、欲しい物を手に入れた夜は、俺の誘いにすんなり応じる。いつしか、真純とのセックスは、何か物を買った見返りのようになっていた。俺は真純を抱きたくて、親父のクレジットカードを使いまくった。俺は親父の金で、真純の体を買っていた。
「慶太くん、これ……まずいなぁ……」
しかし、松永さんに呼び出された俺は、現実を目の当たりにする。
「今月だけで百万超えてるよ? いったい何に使ってるの」
ヤバイ……調子乗りすぎた……
目の前にはクレジットカードの請求書。
「あの……親父、これ、知ってますか……」
「まだ先生には見せてないけどね。ここ半年、ずっとこうだよね? 今月はさすがにね……」
親父の金の管理も松永さんがずっとやっていて、親父のキャッシュカードを持ち出した時も、セルシオをぶつけた時も、いつも松永さんが処理してくれていた。
そして、予想通り、メインは金の話ではなかった。
「慶太くん……女の子と住んでるらしいね」
「はい……あの、でも、俺……」
どうしよう。もうここは……逃げ道はこれしかない。
「その子と、結婚するつもりなんです」
松永さんは驚愕の目で俺を見ている。そりゃそうだろう。頭はいいけど、フラフラ女と遊びまくってる俺が、急に結婚とか。
「本気なの?」
本気……かどうか……もう、わかんねえよ……
「は、はい」
「まさか……妊娠、じゃないよね?」
「違います。違うけど、俺、本気なんです」
ああ、俺はいつまでこうやって口先だけで逃げるんだろう。逃げて、逃げまくって、結局追い込まれるだけなのに……
「そう、わかった。そこまで言うなら構わないけど……今度会わせてもらえるかな。その子に」
「ど、どうして……」
「佐倉代議士の息子の嫁として、ふさわしいかどうか、ね」
「わ……わかりました……」
どうせ、身元調べるんだよな……真純の身元……身元? そうか、もし、これでアウトってことになったら、俺は無罪放免、真純と堂々と別れられる。杉本、仕方ないだろ。俺達の世界はそんなもんなんだよ。
「それから、クレジットカードね。しばらくは禁止だから。いいね」
カード、取り上げられてしまった……どうしよう……真純とセックスできないじゃん。でもまぁいいか。これで真純が出て行けば、それはそれで。
真純が出て行くんだからな。俺に責任はない。
なんとなく、真純が重く感じ始めていた俺は、無責任な逃げ道を見つけて、ちょっと気が軽くなっていた。
「おかえり」
真純は新しいブランドの花柄のエプロンで、俺を出迎えた。
「今日はね、ローストチキンだよ」
あれ以来、真純はオーブン料理にはまっていて、出てくるもんがいちいち美味くて、俺は遊びもせず、家で飯を食っていた。
「美味しい?」
「うん。美味しい」
真純は嬉しそうに笑って、今日の出来事を一生懸命話す。そして、俺の横に来て、おねだりをする。
「ねえ、今日ね、超かわいい指輪見つけちゃった」
「指輪?」
「うん。ティファニーのね、ピンキーリング。すっごくかわいいの」
買えってことか……もう、しばらくは無理なんだよなぁ。
「あのさぁ、真純。今日、実はさ……」
「なになに?」
身を乗り出した真純の胸元は大きく開いていて、中の黒いブラジャーに詰め込まれた乳肉がモロに見えた。
「いや、なんでもない」
やっぱり……こいつの体、たまんねえ……
「今日、クロ?」
「やだぁ、見えたぁ?」
「うん。色っぽい」
恥ずかしそうに笑う真純を抱き寄せて、胸元に手を入れて、唇を奪う。
「したいの?」
「うん」
「お店、いつ行こっか?」
ああ、そうか……でも……
「土曜日、かな」
また、俺は……
「うん。約束だよ」
「約束」
指切りゲンマンをして、真純の手を引いて、ソファに移動して、エプロンをはずし、布地の少ない割に値段は高いワンピースを脱がして、黒いレースのブラジャーとパンツだけの姿にする。
もちろん俺はもう止められなくて、ソファに押し倒して、真純の体にむしゃぶりつく。マネキンのような体の真純は、俺の下で、天井を見上げている。俺の顔は見ないで、あん、あん、と言いながら、天井を見上げている。あの夜、セックス部屋で杉本を見たように、俺のことは見てくれない。
あの顔……杉本に、私のことが好きかと聞いた時の顔……
俺はあの顔が欲しいのに、真純は俺には見せてくれない。
「真純、口で……」
なあ、俺にも、あの夜の杉本にしたようにしてくれよ。その唇で、俺のアレを……そして、俺に聞いてくれよ。私のこと、好きかって……だけど……
「土曜日、私からのプレゼントにしてあげるね」
くそっ! なんだよ! 杉本は指輪なんて買わなかっただろ! お前は誰に抱かれてるんだ? 俺か? 杉本か? それとも……金か?
「真純、俺のこと、好きか?」
情けねえ……何聞いてんだ……
「慶太のことね、好き」
真純は極上の笑顔で答えた。極上の、仮面のような笑顔で、血の通っていない人形のような笑顔で、真純は俺を好きだと言った。
「どこが?」
「うふっ。うーんと……お金持ちなところかな」
そう、俺の、金が好きだと。真純は、はっきりと、俺の金が好きだと言った。
なんだよ……所詮、俺は……金だけかよ……
俺は自分が金で杉本からこの女を奪い取ったことを棚に上げ、この極上にいい女が憎くなった。
わかった。じゃあ、お前は……
「そうか。俺の金が好きか」
極上の見た目のお前は、俺の金の人形になれ。俺にその体を差し出し、俺に美味い飯をつくって、俺の靴下を洗って、俺の極上の女でいろ。俺の隣にいて、恥ずかしくない、イケテル女でいろ。
一生、お前は俺の金の奴隷だ。
「慶太は? 私のどこが好き?」
俺は、そっけなく言ってやった。
「見た目だな」
怒れよ、真純。見た目だけ? って、怒れよ。怒ってみせろよ! そうじゃないと俺は……
でも……真純は、笑顔で言った。嬉しそうに、笑って、言った。
「そうね、やっぱりね。だってね、私、慶太のためにキレイになったんだもん」
袋小路
二週間後、松永さんが家に来た。
「はじめまして、門田真純です」
真純は、いつもとちょっと違う、薄いピンクのふんわりしたワンピースを着て、メイクも可愛い感じで、俺的には、こういう感じも似合ってるなって、また、ちょっと欲情してしまっていた。
「松永といいます」
ソファに座った松永さんは、部屋を見渡し、新しいオーブンとか、ブランドの食器とか、オシャレなカーテンとかを眺めていた。
「どうぞ」
真純は、お気に入りのリバティのティーセットに紅茶を入れて、朝から作っていたフルーツケーキを出した。
「うん? これ、手作りかな?」
「はい。上手にできたかわからないんですけど……」
松永さんは、意外そうな顔をした。どうやら、俺の彼女なんて、イマドキの、家事なんてできない、バカみたいなギャルかなんかだと思ってたようだ。
「へえ、お菓子なんて作るの」
「お料理、好きなんです」
真純はにっこり笑った。今日のワンピースは、おっぱいも太ももも強調してないけど、やっぱりなんかエロくて、松永さんも、その膨らんだ胸元をちょっと見ていた。
「ところで、今日ここに来たのはね」
「はい」
「慶太くんと、おつきあいしてるってきいたからなんだけど」
「はい、おつきあい、させていただいています」
「……ここに、住んでるんだよね? 親御さんはご存知なのかな? 学生で、男の子と一緒に住んでるなんて、どうなのかなあ」
なんだよ、もうわかってんだろ? 真純の身元くらい。
「あの、松永さん……」
「慶太くん、君には聞いていないよ」
真純は、俯いて黙っている。
「門田さん、答えてくれるかな」
なんて言うんだろう。嘘をつくんだろうか。でも、松永さんに嘘なんて通用しない。取り繕いなんて、できない。
少し沈黙があって、真純が顔を上げて、小さな声で、言った。
「私、虐待されてたんです」
その言葉に、俺も松永さんも、びっくりした。まさか、そんなことを言うなんて、さすがの松永さんも思ってなかっただろう。
「うちは母子家庭で、私は子供の頃からずっと、母から虐待されていました。施設出、なんです」
そうか……お涙頂戴戦法か。でもそんな話、松永さんは慣れっこなんだよな……
「ほう、それで?」
「だから私、一生懸命勉強して、大学の奨学金を貰って、東京に来ました。母から離れたくて、実家は広島なんですけど、広島から出たくて、がんばりました。高校卒業してから、幼馴染の男の子と一緒に東京に来て、半年前まで、一緒に暮らしてました」
そ、そんなことまで言わなくても……
「でも、生活が苦しくて、仲が悪くなって……私、彼のところを出ようと思って、スナックとかでアルバイトしてお金を貯めてました」
わかってるんだ。もう、全部調べられてること。
「じゃあ、どうしてここにいるの」
「佐倉くんのお店に、会いに行ったんです。私、東京に来てから、全然友達もできなくて、悩んでたんです。でも、佐倉くんだけは、すごく優しくしてくれて……いけないことなんですけど、私、佐倉くんのこと……好きだったんです。彼がいるのに、よくないですよね……」
真純は、また俯いた。俯くと、睫毛がすごく長くて、目をパチパチさせる、人形みたいで、なんだか、せつなくなる。
「前の彼のこと話したら、佐倉くん、ここに来たらいいよって言ってくれて……だから、私、甘えてしまって……すみませんでした。非常識ですよね、ご挨拶もせずに、勝手に……」
松永さんは、まさかの真純の言葉に、ずっと黙っていた。
「もう少しお金が貯まったら、お部屋を借りるつもりです」
「……あては、あるのかな?」
「ありません。でも、こんな素敵なお部屋じゃなかったら、なんとかなりそうなので」
マジで? 出て行くつもりなの?
「ところで、慶太くんは君と、結婚するつもりだと言ってるんだけどね」
「えっ? 本当ですか? ねえ、本当に?」
真純は驚いた目で、俺の方を向いた。
「あ、ああ、本当だよ」
だって、こう言うしかないから。
でも、真純はまた俯いた。
「嬉しいけど……ダメですよね……私みたいな、施設出の、家庭環境の悪い子が、佐倉くんみたいな立派なお家の息子さんと……」
そうなんだよね。それが、今日の趣旨だ。ああ、杉本、悪いな。こんな世界なんだよ。真純、ごめんな。今日で、お前とも……
「そんなことは関係ないんだよ」
はあ! 松永さん! どうした!
「君は立派に頑張ってるじゃないか。そんな風に、自分のことを卑下するもんじゃない」
ど、どういうことだ……何が起こったんだ……
「松永さん……でも……」
「がんばったんだね、真純ちゃん」
ま、ま、ま、ま、真純ちゃん……!
「はい……頑張りました……私、佐倉くんにつり合うような女の子になりたくて、つい、お洋服とかアクセサリーとかたくさん買ってしまって……ご迷惑をおかけしてしまいました」
「うんうん、それがわかってるんなら、僕は何も言わないよ」
「あのオーブンも、私、佐倉くんに美味しいって言ってもらいたくて……ごめんなさい……ご迷惑をかけたお金は、ちゃんと、少しずつでも、お返しします」
俺は、横で、たとたどしく、弱々しく、でも確実に話す、この女が怖くなった。
嘘ではない。でも、真実でもない。真純は、曖昧な部分を、物理的には調べられない、曖昧な部分を、真実に作り変えていく。明らかな真実に、曖昧な色のペンキを先にぶちまけて、微妙に違う色の真実に塗り上げていく。金のことだって、俺は一言も言わなかった。でも、真純はわかってたんだ……松永さんが、何を言いに来たのか、何を見に来たのか……そして、試されてることを……
「真純ちゃん、本当は、内緒で、君のことを調べさせてもらったんだ」
「え? 私のことを……?」
「気を悪くしないで欲しい。悪かったね」
「いえ……当然ですよね……」
「もし、今日君が嘘をついたなら、すぐにここを出て、慶太くんとの交際はやめてもらうつもりだったんだ」
「そ、そうだったんですか……」
白々しい。わかってただろ、そんなこと。
「でも、君は正直で、言わなくてもいいことまで話してくれた。君は信頼できる女性だ」
ちょっと待て……この展開は……
「慶太くん、真純ちゃんを、大事にしなさい。彼女のようないい子は、そうはいないよ」
嘘だろ……まさか、こんなことに……
「真純ちゃん、若い女性が、セキュリティもないような所に一人で住むのは危険すぎる。君が嫌じゃなければ、ここにいなさい」
「本当ですか? 私、ここで佐倉くんと暮らしてもいいんですか?」
「慶太くんのこと、よろしく頼むよ」
「はい……松永さん、ありがとうございます」
「それから、お金のことは、もういいから。これから、気をつけて」
「はい、反省しています」
「生活費は、慶太くんに仕送りするから、それを使いなさい。スナックとか、そんなお店で働くのは感心しないよ。もうすぐ卒業なんだし、しっかり勉強しなさい。わかったね?」
「はい、アルバイトは辞めます。その代わり、お家のこと、全部します」
「まあ、そんなこといいんだよ。困ったことがあれば、すぐ僕に相談しなさい。いいね?」
「はい。私……なんだかお父様ができたみたいで、とても嬉しいです」
「ははは、お父様か。そうだね、父親だと思って、なんでも言いなさい」
松永さんは、ケーキを食べて、美味い美味いと言った。その後、二人は本当の親子みたいに仲良くなって、松永さんは、帰って行った。
「松永さんって、いい方ね」
「そう、だね……」
笑顔で食器を片付けて、今日の夕飯は何がいいか聞いた。
「カレー、かな」
「カレーね。ねえ、私、お家のこと、頑張るね」
「う、うん、無理しなくていいからね」
「優しいね、慶太。大好き!」
真純は俺に抱きついて、チュッてキスして、ピンクのワンピースから、いつもの胸元の開いたTシャツと、ショートパンツに着替えてきた。
逃れられない……もう、俺は真純から逃れられないんだ……真純のことは好きだけど、やっぱり俺は、真純から逃げたいと思っていた。真純という、重い現実から、いつものように、逃げ出したかった。
キッチンには、上機嫌で、カレーを作る真純がいる。フリルのついた、ブランドのエプロンで、真純は笑顔でカレーを作っている。杉本の部屋の、小さな台所で、シミのついたエプロンで、不満気に後片付けをしていた門田真純は、もういない。そこにいるのは、最新のシステムキッチンで、イタリア製の鍋が似合う、都会の、女。
「お料理、もっと勉強するね」
望んでいたはずなのに。俺がそう言ったのに。オシャレでかわいい、イケテル女になれって、俺が、言ったのに……
なぜか、そこにいるのは、俺の欲しかった門田真純じゃなかった。杉本から奪いたかった、門田真純じゃなかった。
「真純……」
「あっ、もう、危ないよ」
包丁を持つ真純は、後ろから抱きしめる俺の手を、左手で握った。
「キスしよう」
「どうしたの?」
「キスしたい」
真純はちょっと笑って、俺の方を向いて、目を閉じて、俺達は、キスをした。軽いキスじゃなくって、濃厚な、ディープキス。濃厚だけど、なぜか、真純の唇も、舌も、なんの味もしなかった。まるで、人形とキスしてるみたいに、なんの味もしなかった。あの花火の帰りの車や、九月の暑いあの部屋でした時は、真純の味がしたのに……
「好きだよ」
「私も」
真純は、笑った。にっこり、笑った。そして、言った。
「包丁ってね、お料理の味に影響するんだって」
そんなこと……今は……
「やっぱり、日本製がいいんだって」
「そっか。じゃあ、今度買いにいこっか」
「え? いいの?」
「だって、美味い飯、食いたいし」
「嬉しい! ずっとね、欲しかったのがね……」
真純の声が聞こえなくなった。
真純の声……真純……好きなのに……お前は……
「欲しいものがあったら、これで買いなよ」
俺は、財布から、キャッシュカードを出した。
受け取らないでくれよ……真純……受け取れないって、言ってくれよ……
「ダメだよ、そんなの」
「俺が持ってると、使いすぎちゃうからさ。ちゃんと管理してよ」
「……お買い物、一緒に行きたいの」
「うん、一緒に行くよ」
「よかった。約束だよ」
真純はキャッシュカードを受け取って、エプロンのポケットに入れた。入れた……
じゃあ、セックス、するよな……
「真純……今日、いい?」
「うん」
俺達は、カレーを食って、二人で風呂に入って、セックスをした。相変わらず、真純のカラダは最高で、でも……俺は……
どうしてだろう……真純……好きなのに……お前を感じなくなってるよ、俺……真純……感じない……お前は、誰なんだ? いったい、お前は……生きてる人間なのか?
それすら、もう、わからなくなり始めていた。それくらい、俺は、真純を見失い始めていた。
他人な家族
卒業の年、大卒の就職率が最悪で、周りにも就職浪人する奴や、院に進む奴が多発していた。
が、俺はそんなことは関係ない。在学中に税理士試験に受かり、親父の『紹介』で大手の公認会計事務所に就職した。仕事は多忙で、毎日毎日、九時十時まで残業で、空いた時間は公認会計士の勉強をして、家には寝に帰るだけの生活になっていた。
一方、真純は、中堅の家具メーカーに就職し、広報部に配属された。カタログや広告のモデルに抜擢され、真純の美貌は、さらに洗練されていった。とにかく社内外問わず、モテるらしい。俺の買った覚えのないブランド品が次々に増えていた。真純の物欲はどうやら満たされているらしく、俺には何もねだらなくなった。となると、俺は真純を抱けない。休みの日やたまに早く帰った日は、真純をベッドに誘ったけど、真純は生理だとか、頭が痛いだとか言って、あからさまにセックスを避けた。
他にオトコができたのかと思って、情けないけど、携帯を見たり、部屋の中を物色したけど、それらしきものはなくて、オトコのニオイはまったくしない。どうやら、この見覚えのないブランド品達は、見返りのないプレゼントのようだ。
このプレゼントの送り主達は、真純の体が欲しくて、安月給をはたいて買ってんだろうな。バカな奴ら。
俺はわけのわからない優越感に浸っていた。浸っていたけど、俺の体は浸らない。風呂上がりのキャミソールとホットパンツで歩く、リアル峰不二子がいるのに、俺は手を出せない。ベッドの隣にいるのに、何もできない。そんなバカなことがあるか。
仕方がない。その悶々としたストレスは、他のオンナにぶつけた。
……いや、待て。セックス部屋でケンカしてたじゃないか。女が酒の席にいたって。
ヤキモチ。そう、オンナはヤキモチを妬く。
バカな俺は、わざとらしく真純の前で他のオンナと電話したり、ホテルのボディソープの匂いをさせてみたり、シャツの首に口紅をつけてみたりした。だけど、真純は見向きもしない。携帯をリビングに置きっ放しにしても、興味も示さない。イライラした俺は、オンナを家に連れ込み始めた。ベッドにオンナの髪を落としてみたり、口紅の残るグラスを流しに出してみたり。
でも、真純は、俺が他のオンナと寝たシーツを平然と洗濯し、シャツの口紅を一生懸命落とし、当たり前のようにグラスを洗った。
そう、真純は俺になんか興味はない。俺が他の女と寝ようが、二人のベッドに入れようが、関係ない。
そうだった。真純が欲しいものは、金だったんだよ、忘れてた。ああ、バカみたい、俺。
あの女が俺に気持ちをよこすわけ、ないんだよ。
そんな生活が二年ほど続き、俺達は、時々の買物と、時々のセックスをするだけの、薄い関係になっていた。
なのに、なぜか真純は、おかしなことを言う。
「妊娠、したの」
……嘘だ。絶対に嘘だ。真純は嘘をついている。
俺は『それ』だけには気をつけていたから。昔兄貴がそれで、痛い目にあっているのを見て、いい加減な俺だけど、それにだけは、本当に気をつけていた。
「どうしよう……」
嘘だと確信したけど、目の前の真純は、今まで見たこともないような不安な目で、俺を見ている。
いや、ゴムだって、百パーセントじゃない。もしかしたら、破れていたかもしれない。もしかしたら、ずれていたかもしれない。もしかしたら、本当かもしれない。
診断書を見せろと言おうかと思ったけど、言えなかった。だって、五年も付き合って、一緒に暮らして、こんな嘘を言うなんて、いくらこの真純でも、そこまではしないだろう。
いや、そうじゃなくて、俺と一緒にいたいのかもしれない。俺が他の女とフラフラしてるから、俺を不動のものにしたいのかもしれない。
俺は、真純の最後の良心に賭けた。
「どうしようって……結婚、するよ」
目の前の真純は驚愕の目で俺を見た。まさか、結婚すると言うとは思っていなかったか?
「結婚しようよ、真純」
真純は黙って頷いて、俺の胸に顔を埋めた。
やっぱり……そうか、俺のこと、好きなんだ。本当は俺が遊んでるの、辛かったんだ。ごめんな、真純。俺、お前のこと、金の奴隷とか思って。幸せにするよ。子供は……いるんだよな? その細いウエストの中に。
俺達は、松永さんに妊娠を告げた。松永さんは、よかったな、と本心から喜んでくれた。真純はマリッジリングだけ熱心に選んで、後の手配は、松永さんが全部やってくれた。
でも、真純はずっと体調が悪そうで、青い顔をしている。ツワリとかなのかもしれない。俺は真純に優しくした。すごく優しくしてやった。だって、本当にお腹に子供がいるなら、俺、嬉しいから。女も全部清算した。仕事にも身を入れ始めた。俺はやっぱり真純が好きだ。真純だって、子供ができたら少しは変わるかもしれない。きっといいママになる。俺も、いいパパになる。きっとなる。
「今度、検診いつ?」
「……なんで?」
「俺も行こうと思って」
「いいよ、昼間だし、忙しいじゃん」
「そうだけどさ」
真純は俺の首に抱きついて、キスをした。
「迷惑、かけたくないの」
俺はもう、たまらなくなって真純を抱きしめた。
なんか、俺達、ほんとの夫婦じゃん! よかった……好きだよ、真純。俺、がんばるから。仕事もがんばるし、マジメになる。もう二度と、浮気なんかしないから。幸せになろう。幸せな家庭、一緒につくろうな。
式が終わり、婚姻届を出し、門田真純は佐倉真純になった。俺達は親父の『融資』で都心の最新のタワーマンションに引っ越して、ついでに、新しいベンツも『お祝い』してもらった。ドイツ製のシステムキッチンに最新の設備。家具も家電も全部新しくして、俺達は家族三人で、新しい生活を始めるはずだった。俺達は、家族になるはずだった。
赤ちゃんか……女の子かな、男の子かな。どっちに似ても、絶対美人だし、イケメンだよな。俺はどっちかっていうと、やっぱり男の子がいいかな。あー、でも女の子も……
俺はずっと、生まれてくるはずの子供のことを考えて、ニヤニヤしていた。仕事が終わったらすぐに帰って、ちょっとだけど、家事の手伝いもしたし、買わなきゃいけないものとか、保険のこととか、ネットで調べたり、先輩に聞いたり、真純と話したり、とにかく俺は、子供が生まれてくるって、信じていた。
でも、もう、えーと四か月? あんまり体型も変わんないし、かえって痩せてるような感じがする。大丈夫かな。相変わらず体調も悪そうだし……ちょっと心配になって、先輩に聞いてみた。ツワリが酷いと、痩せることもあるって。お腹も、人によっては七か月くらいまで、わからないこともあるって。
なるほど、そうか。真純は元々スリムだし、そのタイプなのかもしれない。きっとそうだ。ツワリが酷いんだ、きっと。かわいそうに。辛いんだ、きっと。
先輩に教えてもらったベビー用品の店で、ベビーシューズを見つけた。真っ白で、ふわふわで、すごくかわいいベビーシューズ。こんなちっこいもんが? って思う位高かったけど、それを買って、家に帰った。ちょっと早いかな。でも、腐るもんでもないし。真純もきっと、喜ぶよな。
「ただいまー」
真純はリビングにはいなくて、ベッドにぼんやり座っていた。顔は青ざめていて、目は虚ろ。
「大丈夫か? 体調、悪いのか? 病院、行くか?」
真純は俯いて、首を横に振った。
「そうだ、これ、見てくれよ」
俺はベビーシューズの紙袋を真純に見せた。でも、真純は目を逸らして、俯いて……一番聞きたくなかった言葉を、言った。
「流産した」
絶対に、聞きたくなかった。それだけは、聞きたくなかった。妊娠も、嘘なら嘘だと、謝ってくれれば、それでよかった。
なんでだよ……なんでまた嘘なんだよ……
俺は知らず、泣いてしまっていた。
「嘘……だろ……」
真純、まだ、まだ間に合う。嘘だったと、正直に言ってくれ。俺は、それでいいから。お前を責めたりしないから。
でも、真純は気まずそうに俯いて、口の中で何か呟いた。よく、聞こえなかったけど、たぶん、ゴメンって、言ったんだと思う。
そうか……お前は……金なんだな……信じた俺が、バカだったよ……金でも取って、逃げるつもりだったのか? なあ、そうなのか?
「仕方ないよ……悲しいけど、仕方ない」
何が仕方ないんだ? 悲しい? 悲しいのか?
隣で俯く真純の横顔はやっぱり綺麗で、Tシャツにうつるデカい胸は上向きで、俺は、なぜかわからないけど、欲情していた。
「真純……」
久しぶりに抱いた真純の体は冷たくて、無抵抗で、霧かなんかを抱いている気がした。もう、そこに、真純は完全にいなかった。
翌朝、会社に行く途中に寄ったコンビニのゴミ箱に、開けないままのベビーシューズを、紙袋ごと、捨てた。俺達の、家族ごっこは、あっけなく、終了した。
間もなくして、真純は企画部に異動になったらしく、仕事に没頭し始めた。毎日毎日遅くに帰って来て、家でも部屋に閉じこもって、企画書を書いていた。料理もしなくなって、ドイツ製のシステムキッチンにはいつしか埃が積もり始めて、食材で溢れていた巨大な冷蔵庫も、賞味期限切れの物を捨てると、何もなくなってしまった。掃除も洗濯も、ほったらかしで、仕事に没頭していた。もちろん、俺との時間も……一秒たりとも、なくなった。
ある日の出張帰り、直帰の許可が出て、四時頃に家に帰った。家に帰ると、洗濯機と掃除機の音がしていた。
「真純? いるのか?」
その声に寝室から出て来たのは、見知らぬおばさんだった。
「あ! ご主人ですか! あの、今日からお世話になります。森崎と申します。よろしくお願いします」
え? もしかして……
「佐倉です……あの、家政婦さん?」
「はい、週三日、こさせていただきます」
森崎さんはそう言って、寝室へ戻って行った。
まじか……あいつ、勝手に家政婦なんか!
「あの、森崎さん、何の契約してるんですか」
「お掃除とお洗濯です」
「そうなんだ……あの、俺の部屋はいいから。それ以外、よろしくお願いします」
信じられない。家に他人をあげるのに、相談もなしに!
「旦那様、それでは失礼いたします」
「ああ、ご苦労様でした」
森崎さんを玄関で見送って、コーヒーを淹れた。キッチンの埃は無くなっていて、家電も綺麗になっていた。俺は真純に一言いいたくて、ずっと待っていたけど、真純はなかなか帰ってこなくて、腹が猛烈に減ったし、コンビニに弁当を買いに行った。温めてもらった弁当とビールを買って、ちょっと雑誌を立ち読みして、家に戻ると、真純が帰っていた。真純はノートPCを見ながら、リビングで菓子パンを食べていた。
「帰ってたのか」
「うん」
俺と真純はリビングのソファに座り、黙って『夕食』を食った。
「家政婦、勝手に契約したのか」
「ああ、今日からだっけ」
「一言くらい、相談があってもいいだろ」
「したくてもいないじゃん。いっつも」
「そ、そうだけど……」
「松永さんから連絡あると思ってたの」
「は?」
「松永さんにお願いしたから」
なんだよそれ……俺じゃなくて、松永さんに相談かよ……
「真純、そんなに仕事忙しいのか」
「うん」
「家政婦、雇わなきゃいけないのか」
「あのさぁ……じゃあ、あなたがやるわけ? 掃除やら洗濯やら。何もしないじゃん。今まで、家事なんてやったことないじゃん」
「忙しいんだよ!」
「私だって忙しいの」
「じゃあ仕事なんかやめろ!」
「あなたの稼ぎだけでやっていけるならね」
「なんだと!」
「大声出さないで。明日、大事なプレゼンがあるの。準備しないと」
真純は食べ終わった菓子パンの袋と缶コーヒーを、ゴミ箱へ捨てた。
「真純、話はまだ終わってない」
「もう、何? 手短かにお願いします」
「家政婦、いくらかかるんだ」
いや、ほんとは金の問題じゃないんだ。
「月、十万だったかな」
「十万……自分でやればいらない金だろ?」
金が惜しいわけじゃない。
「私にやれっていうの?」
「俺も協力するから」
他人にこの家に入られるのが嫌なんだよ……俺達の家に、他人が……
「協力って……あくまで嫁さんの仕事って前提ね。バカバカしい。話す時間もムダ。もういいかしら?」
真純はそう言って、ノートPCを持って、部屋へ行ってしまった。部屋から、誰かと電話する声が聞こえた。仕事の話をしている。本気で仕事に没頭しているらしい。
これって……もう、夫婦の意味、ないよな……
一緒の空間にいるってだけで、もう他人と変わらないじゃないか。お互い違う部屋で違うことをして、金で雇われた他人が掃除と洗濯をして、別々の物を食って……違うことを考えてる。
俺は、こんな生活をしたいわけじゃなかったのに……真純、お前はこれでいいのか? お前は、これで……幸せなのか?
俺はまた、オンナを抱き始めた。そうするしか、俺の気持ちを抑えることができなかった。そうしないと、俺は自分がどうなってしまうのか、怖かった。行きずりのオンナや、店のオンナ。誰でも抱いた。見た目のいいオンナなら誰でもいい。でも、俺の気持ちは埋まらないどころか……虚しさはどごでも深く、広がっていった。だから、俺は酒を飲んだ。
体はオンナで埋め、心は酒で埋めた。
その日は、事務所で怒鳴られ、クライエントに怒鳴られ……最悪の一日だった。
ああ、もう、疲れた……もう、うんざりだ……もう、何もかもイヤになった……
ヤケ酒は深くなり、俺はもう、泥酔状態で、後輩に迷惑がられながら、家まで送ってもらった。
「帰ったぞ!」
寝室のドアを開けると、真純はもう眠っていた。相変わらず真純は仕事ばかりしていて、俺が先に寝るか、真純が先に寝るか、そんなすれ違いの生活が一年ほど続いていた。
「おい! 起きろよ!」
俺は真純を無理矢理起こし、スーツとシャツと靴下を脱ぎ捨てて、ベッドに体を投げ出した。
「随分……酔ってるわね」
なんだよ、その目……そんな、そんな目で俺を見るな!
「水! 水持って来い!」
「……はいはい」
真純は汚ないものを見るかのように、目を細め、酒の臭いに口を押さえ、俺の前に、冷蔵庫から持ってきたペットボトルを置いた。
「じゃ、おやすみなさい」
白い花柄のタオル地のパジャマ。きっと高いヤツなんだろうな。そのパジャマ、誰の金で買ったんだよ? 俺の金だろ? この水だって、俺の稼いだ金だ!
「真純」
「もう、何なの? 眠いんだけど」
「やらせろよ」
俺は、酔っていた。
「……何、言ってるの」
「やらせろっつってんだよ!」
完全に酔っていて……限界だった。真純は黙って、毛布を持って、ベッドから出た。
「どこ行くんだ!」
「リビングで寝るの」
「待てよ!」
冷たい目で見る真純の腕を掴んだ。その腕は、細くて、白くて、弱々しかった。
「やめて。触らないで」
触らないで? ふざけんな。お前の体は俺のものだ!
「俺らは夫婦だろう。セックスしようぜ。夫に体で奉仕するのが妻の役目だろう!」
真純は蔑む目で、俺を見ている。
……俺はもう、本当に……真純……助けてくれ……
「最低」
「はぁ? お前、誰のおかげでここに住めてると思ってんだ?」
「お父様のおかげでしょ」
「なんだと!」
「アンタの稼ぎだけじゃ無理でしょ。稼いでもいないくせに、偉そうにしないでよ。だいたい、今の事務所だって、コネで入ったんでしょ? 何が奉仕よ。バッカみたい」
真純はスラスラと、ハキハキとそう言って、背中を向けた。俺は、俺は……
「ふざけんな! このアマ!」
俺の手は、真純の顔を殴っていた。一回、二回、三回……
手が、痛い……
たぶん、記憶の限りだと、女を殴ったのは、いや、他人を殴ったのは、生まれて初めてで、でも、もう……止められなかった。
「もう一回言ってみろ!」
「何度でも言ってあげるわ! 稼ぎのない、バカ男!」
真純は俺を睨みつけて、その目は、見たことがないくらい、冷たくて、悲しくて……でも、俺は……
「離して!」
俺は真純をベッドに押さえつけ、白い花柄のパジャマを剥ぎ取った。
「やめて! やめてよ!」
……何度か、殴ったと思う。首を絞めたと思う。気がついたら、顔を赤紫に腫らした裸の真純が俺の下にいて、泣きもせず、虚ろな目で天上を見上げていた。
わからない。俺は何をしたんだろう。
いつの間にか裸の俺は、強烈な頭痛と吐き気に襲われていた。
多分、セックスをした。やばい、吐きそう。セックス……吐く……やばい……
トイレに駆け込み、思いっきり吐いた。食ったものがドロドロの薄茶色い液体になって、俺の口から出て行く。俺はマッパで、トイレで吐き続けた。涙と鼻水が一緒に流れた。トイレの中は俺の吐瀉物の強烈な臭気が充満し、俺の口の中は吐瀉物の味で、俺はマッパでトイレの床に座り、トイレットペーパーで口を拭いて、ふらふらしながらトイレを出て、風呂に入った。風呂には真純の高そうなシャンプーやらボディシャンプーやら、よくわからない化粧品らしきものが並んでいて、甘い匂いが風呂を埋める。俺はまたちょっと吐き気がして、熱いシャワーを出した。熱いシャワーを浴びると酒が覚めてきて、口の中をゆすぐと、目の前に現実が襲った。
俺は、とんでもないことをしてしまった。真純を殴った上に、無理矢理セックスをした。これは……レイプだ。俺は真純をレイプしたんだ。妻を、犯してしまった。どうしよう。俺は……犯罪者だ……
引き出しの中にはキレイに森崎さんがたたんだボクサーブリーフと、スエットが入っていて、ふわふわのバスタオルで体を拭き、それを着て、歯を磨いて、寝室へ戻った。
真純は、花柄のパジャマを着て、毛布にくるまっていた。泣いているのかと思ったけど、泣いていなくて、俺は逆に辛くて、謝ろうとした。本当に、謝ろうとしたのに……
「ま……真純……」
「夫婦間でもレイプは成立するのよ。訴えれば、あなたは犯罪者だから」
真純は毛布にくるまったまま、背中を向けたまま、冷たくそう言い放った。
謝ればよかった。素直に、ごめんって言えばよかった。謝らなきゃ、だめだったんだ。
「勝手にしろよ。レイプの裁判は過酷だぜ? それに、お前は犯罪者の妻になる。いいのか? ここに住めなくなっても」
そんなこと言って……誰が幸せになるんだよ……
「ほんとに、最低」
「お互いさまだろ」
俺は真純の背中に背中を向けて、目を閉じた。目を閉じたら、涙が出た。もう止まらない。マクラが涙で濡れて、顔がかゆい。鼻水も出る。啜ったら、泣いているのがバレるから、啜れない。息を殺して、ただ体を丸めて、壁に向かって、俺は泣いた。
ああ、頭が痛い。割れるように、頭が痛い。もう、いっそのこと、このまま頭が爆発して、死んでしまいたい。
朝になったら、死んでいればいいのに。
だけど、朝、目が覚めた。残念ながら俺は生きていて、頭も痛くなくて、真純はいなくなっていた。時計を見ると十時半。
しまった!……あ、そうか、今日は土曜日か……
一度目が覚めるともう眠れない。胃もたれを感じながらベッドを出た。
謝ろう。昨日のこと、謝ろう。まだ間に合う。素直に、ごめんって、謝ろう。
ドイツ製のキッチンでバカラのグラスに水を汲み、胃薬を流し込む。冷蔵庫にはヨーグルトがあったけど、消費期限が切れていて、そのままゴミ箱に捨てた。
「真純?」
部屋をノックしたけど、返事はなくて、そっと開けてみたら、ノートPCがなくなっていた。
仕事か? だけど……なんか……
クロゼットを開けると、少し空いていた。スーツケースも無くなっている。
嘘だろ……
慌てて洗面台に行くと、真純の化粧水やらクリームやらがなくっていた。震える手で電話をかけた。かけたけど、真純は出なくて、何回かしつこくかけた後、メールがきた。
『しばらくホテルに泊まります』
俺は携帯を放り投げた。
もう、どうでもいい。あいつは出て行った。よかったじゃないか。これで俺は無罪放免だ。
その日一日、俺はパチンコ屋で過ごし、店内でカレーを食って、誰もいない家に戻った。放り投げた携帯には不在着信が何件かあって、期待して確認ボタンを押したけど、全部適当に抱いた、どっかのオンナからだった。
夜になると、部屋が冷えてきて、押入れから布団を出して、ふと、思い出した。
あの段ボール、どうしたかな……確か引越しの時にそのまま持ってきたよな……
押入れには引越しの時から開封されていない段ボールが何個かあって、俺はその中から、あの日、杉本から受け取った段ボールを探し出した。ガムテープを切り、中を開けると、当たり前だけど、六年前のままで、セックス部屋で着ていたヨレヨレのワンピースはカビ臭くなっていた。
俺は、いったい、何が欲しかったんだろう。門田真純が欲しかったのか、門田真純の体が欲しかったのか……俺は何を杉本から奪ったんだろう。結局、俺は杉本から何も奪えなかった。門田真純を奪ったんじゃなくて、門田真純が変わって、俺の所に引越してきただけだ。そしてまた、佐倉真純はどこかに引越していく。
俺は捨てられたんだ。あの日、杉本が捨てられたように、俺も捨てられた。
次の日、杉本に謝りに行くことにした。杉本との約束は、もうこれ以上守れない。
あの社宅にまだいるんだろうか。いなければいないでいい。どっちか言うなら、いないほうがいい。
六年ぶりの杉本の社宅は、外壁が新しくなっていた。ドアの横には『杉本』とテプラシールが貼られた、ネームプレート。残念ながら、杉本はまだこの部屋にいた。チャイムを押すと、はーい、と女の声がして、地味な女が出てきた。どことなく、ここに住んでいた頃の門田真純に似ている。
「どちら様?」
「佐倉と申します。杉本くん、いらっしゃいますか」
女は、はあ、と言って、奥へ入って行った。カノジョ、かな?
「おお! 佐倉! 久しぶりやの!」
六年ぶりの杉本は、ヤンチャ感は抜けていたけど、相変わらずのバキバキの体で、上下黒にゴールドのロゴの入ったアディダスのジャージで出てきた。
「久しぶり。ごめんね、突然」
「ほんまに、びっくりしたわ。まぁ、あがれよ」
外壁は変わっていたけど、中は全く変わっていなくて、ただ、六年前よりは家具が増えて、エアコンもついてて、テレビも大きくなっていた。
セックス部屋に通され、あのコタツを囲んだ。女がコーヒーを出してくれて、杉本が言った。
「嫁さん。聡子や」
「はじめまして」
聡子さんはにっこりと笑って、俺に頭を下げた。笑った顔は、本当に門田真純そっくりで、俺は思わず目をそらしてしまった。
「こんにちは」
気まずそうに頭を下げた俺を見て、聡子さんは、ちょっと買い物行ってくるね、と出て行った。
「結婚、したんだ」
「ああ、今年の初めにな」
俺は出された、おそらくインスタントコーヒーを飲んだ。杉本はあのタンスにもたれて、タバコに火をつけた。
「真純と、まだ一緒か」
「ああ」
「そうか。元気か」
「……元気だよ」
言いたかった。真純とはもう無理だって。謝りたい。悪かったって。
俺は、もしまだ杉本が一人で、まだ真純のことを思ってるなら、真純を迎えに行ってくれって、頼むつもりだった。でも、杉本は門田真純によく似た女とすでに結婚していて、その女はなんかいい人そうで、俺はもう、言えるわけがなくなっていた。
「似とろうが、真純と」
「ああ、そうだね」
「真純と別れてからな、なかなか整理がつかんで……荒れとった時に、中村が紹介してくれたんよ」
中村! ああ、そういえば……あれきり、連絡もしてないな。
「中村と、連絡してんだ」
「今でも時々おうとるよ。ええ奴じゃけ、あいつ」
確かに、中村はいい奴だ。
俺は、ちょっと嫉妬した。元は俺と中村だったのに、いつの間にか俺は外されていた。って、当たり前か。
「中村、今どうしてんの」
「親父さんの会社で働いとる。聡子は、そこの事務員や」
「そうなんだ」
「最初はな、真純と顔が似とるってだけで付き合いよったけど、ええヤツでな。素直で、優しくて……考えとることがわかる」
「考えてること?」
「真純は、わからんじゃろ。何考えとるんか」
確かに……俺はあいつの気持ちとか頭ん中とか、まったくわからない。
「佐倉、悪かったな」
「え?」
「あん時はな、真純んこと手放すのが辛うて、お前に背負わせてしもうて……」
そんな……今更……
「あの女は、背負うには重すぎる」
ここで……ここで、重いからもう下ろすって、言えよ。俺、言え! 今言わないと、もう一生言えないぞ!
「でも……真純のこと、好きだったんだろ」
「好きじゃった。本気で、死ぬほど……じゃけんど、どっかな……重かった。あいつとおるとな、しんどかった」
ほら、今だ! 今しかない! 俺もしんどいって、もう嫌だって言えよ!
「あのさぁ、杉本……俺さ……」
杉本はふと、俺の左手を見た。
「結婚、したんか?」
しまった! 指輪……指輪してたんだ……
「あ、ああ……」
「そうかぁ! 結婚したんかあ! いやぁ、よかった! 真純も、幸せになれたんじゃなあ!」
いや、そうじゃなくて……
「杉本、俺、お前から真純のこと……奪ったのがずっと……」
「ええんじゃ。そんなこと、もうええ」
そして杉本は、衝撃的発言をする。
「どのみちな……俺と真純は一緒にはなれんかった」
「な、なんで?」
「なれん、というより、なったらいけなんだ」
「どういう、意味だよ」
「たぶん、じゃけどな……俺と真純は……兄妹かもしれん」
な、な、な、な、なんだそれ!
「意味、わかんねえ」
「真純の母ちゃん、男にだらしないゆうたやろ」
「あ、ああ……」
「田舎でな、若い男と女なんか数が知れとる」
「いや、だからって……」
「なんとなくな、そんな気がしとった、ずっと。俺の親父と真純の母ちゃんは、関係があった。それは間違いない」
タンスにもたれて、淡々と話す杉本が遠くに見える。俺は何て言えばいいのかわからなくて、とにかく安物のマグカップに入った、冷めかけたインスタントコーヒーを飲んだ。
「わからんけどな。もう、誰もわからんじゃろ。真純の母ちゃんでさえ、わからんと思う」
「それ……知ってて、真純と……」
「そうじゃな。それでも、真純が好きやった。いや、だから余計やったんかもしれん。余計に真純のこと、誰にも渡しとうなかった」
目眩がする。もう、何がなんだかわからない。俺にとって、杉本は最後の免罪符だった。杉本に申し訳ないって理由で、真純と別れる言い訳ができたはずだった。
「逆に、感謝しとる。真純を離してくれて」
感謝……感謝って……
「そのこと、真純は……」
「さあなぁ。もしかしたら、わかっとるかもしれんけど……真純は母親のこと、心の底から嫌っとるけ……そんな話、したこともない。なあ、佐倉。真純はワガママで、ようわからんとこがあるけど、性根は、優しくて、素直で、かわいい女なんじゃ。広島で、いろんなことがあって、あいつは変わってしもうた。東京に来て、さらに変わってしもうた。でも、ほんまは……もう、思い出じゃけどな」
杉本は遠い目でベランダを見た。
何を、見たんだろう。過去なのか、真純なのか……聡子さんなのか……
「飯も、上手いじゃろ?」
「え? ああ、そうだね」
「聡子はな、あんまり上手ない」
杉本は小声で言って、内緒じゃ、と笑った。
「もうすぐ、引っ越すんじゃ」
「そうなんだ。どこに?」
「埼玉。転勤になってな」
「へえ、そうなんだ」
「工場の、責任者にな」
「出世したんだ!」
「本社に戻ってこれるかどうかわからんけど、まあ、今よりは給料もようなるし」
「そうかぁ。おめでとう。頑張れよ」
「佐倉は、何しとるんや」
「俺は……」
俺は、親父のコネで入った会計事務所の見習いのペーペーで、安月給で、嫁さんに逃げられた、完全な負け犬。自力で生きてる杉本が、とてつもなく大人で、立派で、俺は情けなかった。
「サラリーマン。普通の」
「そうか。お互い、嫁さん食わせていかんといけんし、がんばらんとな」
そうだ……そうなんだよ。俺は、真純を食わせていかないといけなかったんだよ。もしかしたら、この先、本当に妊娠して、子供が産まれるかもしれない。こんなフラフラしてたら、ダメなんだよ。
「そうだな。引越したら、住所教えてくれよ。遊びに行くから」
俺は電話番号を書いたメモを渡した。たぶん、かかってくることはない。杉本は、完全に真純と別れた。兄妹とかいう話も、本当かどうかわからない。杉本の作り話かもしれない。確実なのは、杉本は聡子さんと新しい生活を始めていて、屈託のない幸せを掴んでいて、真純のような面倒な女のことはもう忘れてよくなって、俺は、真純から逃れられないということだけ。
聡子さんが帰って来て、よかったら夕飯でも、と言ってくれたけど、俺は帰ることにした。
「真純が待ってるから」
バカバカしい嘘をついて、俺は笑顔で杉本の部屋を出た。駐車場でベンツに乗る俺を、杉本と聡子さんが、あの窓から笑顔で見送ってくれて、二人は手を振ってくれた。
いったい、俺は何をしに行ったんだろう。杉本の最後の整理を手伝っただけじゃないか。
でも一つ、気がついた。
俺は、真純のことをわかってなかった。わかろうとしていなかった。あいつは重い過去を背負っていて、貧乏から抜け出したくて、派手な都会の女になって、過去を捨てたいんだ。そうだ。結婚式も、母親は呼ばすに代行で両親を雇った。
なのに俺は……あいつの顔や体だけしか見てなかった。もう、セックスも、飯も掃除も洗濯もいい。俺は真純を待つ。真純があの舌ったらずで、ちょっと掠れた声で、今日の出来事を話してくれるようになるまで、俺は待つ。
絶対に、離婚はしない。
俺は、ベンツの中で、そう決めた。決めるしか、俺には道はなかった。もう、真純と離れることはできなかった。
昨日放り投げた携帯には、やっぱりくだらない女からの着信しかなくて、真純からの着信はなかった。
謝りたい。昨日のことは、本当に悪かった。俺が百パーセント悪かった。
電話をかけたけど、当然、真純は出ない。だからメールを送ることにする。
『悪かった。本当にごめん。話し合いたい。帰って来てくれ』
ソファの上で、三十分かけて送信ボタンを押した。
『送信完了』
もちろん、こんなメール一つで、許してもらおうなんて思っていない。いないけど、このまま終わるのは嫌だ。だって、六年間、一緒にいたんだから。
しばらくして、電話がかかってきた。
「真純? 悪かった。ほんとに……」
「ご主人ですか?」
え? 誰? 男?
「え……あの……」
「こちらは世田谷警察です」
ど、どういうことだよ……まさか……
「佐倉慶太さんですね」
「そうですが……」
「佐倉真純さん、奥様ですよね」
訴えたのか……
「はい」
「奥様なんですがね、一昨日、レイプ被害に合われましてね……」
終わった……俺の人生、終わった……
「お心当たりはおありですか」
もう、ダメだ……俺は、婦女暴行と強姦罪で逮捕されて、一生そのレッテルを貼られて、生きて行くんだ……なんて、バカなことをしたんだろう。ごめんな、真純。俺は本当に……
「……くん、慶太くん」
目の前には、スーツを着た男がいた。ああ、刑事か……逮捕されるのか……
「慶太くん、起きて」
え?
目の前にいたスーツの男は刑事じゃなくて、松永さんだった。
夢か……よかった……
「松永さん、どうしたんですか」
「どうしたって、君が呼んだんじゃないか」
「え?」
「部屋に鍵をつけたいからって、真純ちゃんから連絡あったよ?」
なんのことだ?
「空き巣に入られたんだろ? 大変だったねえ」
空き巣?
「真純ちゃんが一人になることが多いから、真純ちゃんの部屋に鍵をつけるって、君が言ったんだろう」
鍵……部屋に鍵……
「まあねえ、家の中だからって安全ってわけじゃないから」
真純の部屋から鍵屋っぽい男がやってきて、何やら松永さんと話している。
「ドアノブ変えたらいいみたいだから、手配しとくね」
「あの、真純……真純に会いましたか?」
「いいや、昨日から出張で名古屋なんだろ?」
「え、ええ、そうです」
「真純ちゃん、美人だから、気をつけてあげないとね」
「はあ……」
松永さんは鍵の工事日の打ち合わせをして、帰って行った。真純の部屋の鍵は、水曜日につくらしい。
水曜日なら森崎さんがいるな。ていうか……鍵つけるんだ、部屋に……でも、帰ってくる気はあるんだ。帰ってくるならそれでいいか。部屋に鍵なんて、珍しいことじゃないしな。
水曜日に、予定通り鍵が取り付けられたけど、真純はまだ帰ってこなくて、電話も出なくて、メールもなくて、俺は何かあったんじゃないかと不安になったけど、もし無断欠勤なんかしてたら会社から連絡があるだろうし、警察からも……そんな想像はやめよう。
そして、金曜日。Xデーから一週間。俺は禁酒を決めていて、八時に家に帰った。マンションの前にはでっかいトラックが停まっていて、俺のベンツは駐車場に入りにくくて、ちょっとイライラした。でも……真純のスーツケースが玄関に置いてあった。
「真純!」
俺は思わず真純を探した。
「あら、おかえりなさい」
真純は笑顔で俺を出迎えた。顔の腫れは無くなっていた。
そうか、許してくれたんだ……真純……
「真純、あの……」
でも、真純の後ろには作業着の男が二人立っていて、俺を見て頭を下げた。
「主人です」
真純は男二人に、にこやかに俺を紹介した。
「配送部のね、山根さんと、高邑さん」
配送部二人組は、どうも、と言った。
「ほんと、助かった! ありがとう! 急なお願いしちゃって、ほんと、ごめんなさいね」
「いやー、佐倉ちゃんの頼みだからね。それより、ダンナさん、噂通りイケメンじゃん」
「そうでしょ?」
真純は笑って、俺の腕に、腕を絡めた。
「美男美女かぁ。こんないいマンションに住んでさ、羨ましいよ」
真純は、うふっと微笑んだ。
「私、とっても幸せなの」
「はいはい、もう聞き飽きたよ」
俺以外の三人は笑っている。なんなんだよ、これ……
「しかし、偉いねえ、佐倉ちゃんは。仕事も家庭もちゃんとして」
「そうかしら」
「ダンナさんの睡眠の邪魔したくないからって、ベッドまで買うなんてねえ」
え? ベッド?
「主人も忙しいの。お互い、ビジネスマンとして、もっと成長したいし。私もまだまだだから……」
「みんな佐倉ちゃんのこと、褒めてるよ。仕事もできるし、気配りもできるし、マジメだし、何より美人だし!」
「もう、やだぁ、高邑さん!」
「じゃあ、そろそろ。また来週ね」
「うん、ありがとう」
「ご主人、失礼します」
「おつかれさま!」
真純は玄関で二人を見送って、振り返った。振り返った真純は、もう笑っていなくて、俺を避けるように部屋へ向かった。
「ベッドって、なんだよ」
「部屋に買ったの。うちの会社で。割引きくから安いのよ」
「そういうことじゃなくて……」
「安心して眠れないの」
真純は、俺の顔も見ずに部屋へ入り、鍵を閉めた。かちゃん、と、冷えた廊下に鍵の音が響いた。
そういうことかよ……なんだ……そういうことか……
そう、俺達は、離れてしまった。でも、新しい俺達を見つけた。仮面夫婦。俺達は、仮面夫婦。本当の顔は見せない、仮面夫婦。美人の妻とイケメンの夫。
幸せなんだ、お前は。それで、幸せなんだ。そうか、わかった。俺はお前が幸せならそれでいいよ。俺達は仮面夫婦として、生きていこう。それが、俺達の形なんだ。もう、待たなくていいかな。だって、お前はもう幸せなんだから。
真純。なあ、真純。お前は……金と見栄しか、それだけしか見えない女なんだな……
便利屋、はじめました。
午前六時。
朝のジョギングも、ちょっと寒くなってきた。そろそろ、冬物のウエアを出さないとな。
シャワーを浴びて、ヒゲを剃って、髪を整えて。この時間にやらないと、洗面台が使えなくなる。
部屋に戻ると、隣の妻の部屋から目覚ましのアラームが聞こえた。妻は朝が弱い。何度かスヌーズを繰り返し、微かに音楽が聞こえる。
起きないなら、かけるなよ。
三十分ほど、アラームと音楽が交互に鳴り、ガタガタと音がする。やっと起きたんだろう。
ああ、しまった……今日のパーティ、伝えてなかったな……
リビングに行くと、エアコンが効いていて、妻はいなくて、どうやら洗面台にいるようだ。ドイツ製のシステムキッチンで、ティファールに水を汲む。妻も使ったらしい。中の湯がまだ熱かった。
インスタントコーヒーを作っていると、妻が戻ってきた。でっかいコスメボックスを持っている。寒がりだからな。エアコンの下で顔制作ですか。
「何時に仕事終わる?」
「どうして?」
「吉村先生のパーティがあるんだよ」
「何時から?」
「七時半」
「どこで?」
「ニューオータニ」
「わかった」
ビジネスパートナーは、ビジネス以外の話はしない。だから、おはよう、とか、今朝は寒いね、とか、俺達には不必要。俺達は、夫婦という名の、ビジネスパートナーだから。
俺はコーヒーを持って、部屋へ戻った。
さて、何を着ようか。やっぱりグレーだな。俺はグレーが似合う。ネクタイは紺。ダイヤのタイピンとブルガリのカフスをつけて。ああ、しまった。洗面台に、指輪を忘れてきた。お飾りの、マリッジリング。
洗面台に向かう途中、首から上が完璧の妻とすれ違った。ふうん、今日もいい女だな。俺のアクセサリーとして最高だよ。
さあ、今日も働くか。
いってきます? そんな単語、もう忘れたよ……なあ、真純。お前も、いってらっしゃい、なんて単語、忘れただろ?
なあ、真純。俺達はこれで、幸せなんだよな?
俺達はずっと、これからも、こうして行くんだよな?
真純が企画部に異動して五年目。企画した商品がヒットし、真純はチーフに昇進した。さらに三年、真純は次々にヒット商品を出し、中堅企業だった真純の勤務先は、上場した。同時に真純は部長に昇進し、三十三で、しかも女で、異例の出世を遂げた。部長になってからも、業績は右肩上がりで、佐倉部長は、会社に莫大な利益を与え続けた。
俺は真純の会社の忘年会やら慰安旅行やらバーベキューやらには必ず同伴させられ、俺達は社員の前で、ハリウッド映画並みの演技をする。佐倉部長は家庭も大切にし、仕事もバリバリこなし、オシャレで美しく、部下思いで、明るい、社交的なパーフェクトウーマンで、女性社員はもちろん、男性社員からも憧れの的。その中でも、ずば抜けていたのが田山という、中途入社三年目の二十八歳。真純のチーフ時代からのアシスタントで、見た目はまあまあイケメンで、クールにしているけど、俺に明らかな敵意を持っていた。真純に惚れてるんだろう。
だけど、残念だな。お前の憧れの佐倉部長は、お前になんか興味はないんだよ。佐倉部長が愛せるのは、わが身と金だけ。かわいそうだけど、諦めろ。
その夏の慰安旅行は沖縄で、真純は三十三の爆裂ボディを、白いビキニで如何なく披露していた。ビーチで皆に囲まれる佐倉部長を、田山は遠くから見ている。どうせ、エロい妄想してんだろ?
「田山くん、どう?」
俺は、笑顔で田山にビールを差し出した。
「ありがとうございます」
「君も大変だね。あんなキツイ上司にこき使われて」
「いえ……尊敬、してますから」
田山は美大出のデザイナー崩れで、未だに建築デザインの世界に未練があるらしい。
「真純から、聞いたんだけどね。君、デザイナーだったんだろ?」
「ええ、まあ」
「知り合いにさあ、ショップデザインやってる奴いてね。よかったら、紹介するよ?」
田山は俯いて、ぼそっと言った。
「部長と、離したいんですか」
「え?」
「いえ。今の仕事、気に入ってるんですよ」
「そうなんだ」
遠くから、佐倉部長の笑い声が聞こえる。田山は眩しそうに、その光景を眺めていた。
「佐倉さん。俺、八時間、毎日部長と一緒にいるんですよ。泊まりの出張も、二人で行きます」
なんだよ、それ。
「部長、俺にはすごく笑うんですよ。あんなことがあった、こんなことがあったって。一緒に飯食ってると、楽しそうに、いろんなこと話してくれるんですよ」
「へえ、そうなんだ」
「ご主人のこと、いつも自慢してます。優しくて、いい人だって」
「照れるなあ」
「……本当かな」
なんだ、こいつ。
「どういう、こと?」
「俺には、部長が本当に家庭で幸せを感じているようには思えません」
田山は細身で、色白で、神経質そうで、全然違うけど、俺は一瞬、田山が杉本に見えた。
「田山クーン!」
遠くから、佐倉部長が走ってきた。パーカーの前がはだけて、白いビキニがブルンブルン揺れている。
「ビーチバレーするよ。田山くんも来て」
「日焼け、できないんで」
「ええ、そうなのぉ? 田山くんが入ってくれたら、絶対勝てそうなのにぃ」
真純は田山の前にしゃがんで、白いビキニに収まりきれていない乳肉を突き出し、内腿の隙間から白いパンツをちらつかせた。田山はクールに目を逸らし、しょうがないですね、と立ち上がった。
「わぁい! 部署対抗なんだよ。優勝したら、エアコン変えてもらえるんだって!」
真純は田山と腕を組み、ビーチバレー会場へ行った。俺はぼんやりと二人を見送り、隣に座っていた経理部長のじじいに営業をかけた。
夕食はビュッフェで、俺と真純は隣の席に座ったけど、当然自然に会話はなく、俺は企画部の女の子達と楽しく過ごし、真純は田山とずっと話していた。
「市場でね、すっごい色のお魚、見たよ」
「南国の魚は、色鮮やかですからね」
「おいしいのかなぁ」
「あんまりだそうです」
「そうだよねぇ。見るからに、あんまりだもんねぇ」
「部長、何かとってきましょうか」
「うん、なんか、フルーツ食べたい」
「わかりました」
「あ、やっぱり一緒に行く。待ってぇ、田山くん」
真純は田山を追って席を立った。後ろのテーブルで、女の子達が、あの二人、いい感じだよね、と言っているのが聞こえた。真純は一生懸命、今日の出来事を話していた。舌ったらずに、ちょっとか掠れた声で、笑いながら、田山に今日の出来事を話す。田山は、笑顔で、そうですか、それはすごいですね、それは大変でしたね、の三フレーズを駆使し、相槌をうつ。たぶん、花柄のワンピースの胸元をチラ見しながら。
「カラオケ、行きません?」
女の子の一人が言い出して、みんなで行くことになった。
「あー、私はパス。もう眠いの」
真純は来ないと言った。
「すみません、俺も、パスで」
田山も来ないと言った。
何人かは来ないと言って、女の子四人と野郎一人と、俺、で、夜中の三時くらいまでカラオケをした。
もしかしたら、真純は田山と……
カラオケ中、ずっとそればかり考えていて、俺は得意のミスチルもGLAYもイマイチ上手く歌えなかった。
部屋に戻ると、真純は眠っていた。寝顔が、可愛い。
あんな風に、田山には話すんだ。
つきあい始めた頃、あれが欲しい、これが欲しいと俺にねだっていた頃、俺は真純の話に、いや、真純の笑顔と声に、夢中だった。
真純……俺……やっぱり……
眠る真純の頬に、手を触れた。あの、事件の夜から七年。真純は別の部屋で、別のベッドで、眠る。
俺達は、極力顔を合わさない。リビングでも洗面所でもキッチンでもトイレも風呂も、俺達はできるだけ、互いの姿を見ないように、見せないように、相手の動きを凝視し、空気を感じる。俺達は、顔も見ずに、朝起きて、仕事に出かけ、無言で部屋に戻り、風呂に入り、眠る。息の詰まる生活。顔を見るのは、声を聞くのは、ステイタスを保つため。俺は真純のアクセサリーの一つで、真純も俺のアクセサリーの一つ。だけど、なぜか、俺はあの寝室で眠る。あのダブルベッドで眠る。
いつか、気まぐれでも……
いや、情けない。もう考えないことにしよう。
「おやすみ」
俺は人形のような寝顔に呟いて、隣のベッドに入り、スタンドを消し、目を閉じた。
「ねえ」
暗闇の向こうから、真純の声が聞こえた気がする。
「あのさあ」
いや、間違いない。
「何?」
「余計なこと、しないでよね」
「は?」
「田山くんに、デザイン事務所を紹介するとか言ったらしいわね」
冷たい。冷たい言い方。
「田山くんは優秀で、うちには欠かせない人材なのよ。まだこれからなのに」
……好きなのか? あの田山のことが?
「彼の夢なんだろう、デザイナーは。叶えられるなら、協力してやりたいだろ」
「バッカじゃないの? 夢ですって? そんなもので、ご飯が食べていけるの?」
「お前、あいつのこと、男として見てるだろう」
「はあ? あのねえ、私はあなたみたいに、ビジネスとプライベートを一緒くたにはしないの。男だとか女だとか、そんなこと考えないの。田山くんは私の信頼できる部下で、会社には大切な存在。わかる? 大切な存在ってのはね、利益をもたらすってことよ。社員は会社に利益をもたらすために働いているの。その見返りに、お給料をもらっているの。あなたのように、異性を性の処理道具としか見れない人にはわからないかしら」
暗闇の向こうから、真純の声だけが聞こえる。その声は、舌ったらずでも、掠れてもなくて、ハキハキして、低くて、小さいけど、よく通る、声……
「今後一切、私の部下に余計なことしないで」
悔しい。悔しいけど、正論だ。何も、言い返せないけど……でも、田山は、お前のことを……
「田山くんの、一生を奪うのか」
「どうしてもその道に行きたいなら、自分で行くでしょう」
自分で……真純は、自分で来た。東京にも、俺のところにも、会社にも。自分で決めて、自分で来た。俺はどうだろう。何か自分で決めただろうか。俺は逃げることしかしていない。親父の庭から、出れていない。この女との生活も、終わらそうと思えば終わらされる。でも、できない。ダブルベッドで、俺は、待っている。俺は、あの寝室からすら、出れていない。
真純……こんな俺……情けねえよな……
「真純」
「何よ」
そっちに行っていいか? 抱きしめていいか? なあ、真純……キス、したいんだ……お前のこと……好きだから……こんな俺だけど、やっぱり、好きなんだよ、真純……
「セックス、しようか」
また……バカだなあ、俺。
「いいよ」
え?
「またレイプされるの、嫌だし」
そうか……そうだよな……
「冗談だよ。お前なんか、興味ない」
「よかった。興味持たれてなくて」
終わらせなくても、もう終わってる。俺達はもう、終わってるのに。
なぜ、どこにも行かないんだ、お前は。なぜ、あの部屋にいるんだ? 何から逃げてるんだ? 決めろよ。決めて出ていけよ。もう、終わりにしようぜ。
佐倉部長が誕生してから二年。次期社長じゃないかと噂されるくらい、佐倉部長は利益を上げ、ビジネス雑誌にも何度か登場するようになった。しかしながら、俺は公認会計士になったものの、先輩の先生方の下で、ヘコヘコ頭を下げ、入社したころと、さほど変わらない生活をしていた。
日曜日、真純は仕事に出かけ、俺は一人で家にいた。リビングでテレビを見ていると、真純からメールが来た。
『家にいるなら、デスクにある書類の住所をメールして下さい』
どうやら忘れていったらしい。鍵がついてから、真純の部屋に入るのは初めてで、俺はちょっと緊張していた。
書棚は、インテリア関連の本や、自己啓発本が詰め込まれ、デスクにはUSBが整然と並ぶ。勉強している。そんな部屋。
USBの隣に、クリアファイルに挟まった書類があった。
これか。
俺は写真を撮って、真純にメールした。少しして、『ありがとう』と一言の返信があった。
もう少し、この部屋を見たい。
クロゼットにはオシャレなスーツとかスカーフとかバッグが入っていて、引き出しにはダイヤとかルビーとかのアクセサリーが入れてあって、何冊かファッション雑誌が積まれている。デスクの引き出しには、仕事のファイルとかCD-ROMとか、なんかのACアダプターとか、古い携帯とかが入っていた。
何かない。この部屋には、何かがない。
……娯楽。
この部屋には娯楽がない。小説も、音楽のCDも、映画のDVDも、マンガも、エロ本も、ない。
真純は、何が楽しくて生きてるんだろう。友達と遊びに行く姿も見たことないし、電話で長電話しているのも見たことない。そもそも、真純には友達がいるんだろうか。
そして俺は、禁断の封筒を開ける。給与明細。佐倉部長が、いくら稼いでいるのか、知らない。夫婦だからな、見ても、いいだろう。封はすでに切られていて、俺は……中身を広げた。
マジ……か……
見なければ、よかった。そこに印字された数字は、俺の給与明細の数字を遥かに超えていて、何度も見直したけど、やっぱり変わらなくて、見間違いじゃなくて、現実だった。
俺はその現実を封筒に入れ、元に戻し、引き出しを閉めた。
おそらく俺は、あの事務所で雇われている以上、これ以上の収入は望めない。雇われの士業の給料なんて、たかがしれてる。どうしよう。どうしたらいいんだろう。稼げないなら、俺の存在価値は、もうマイナスになる。ゼロどころか、マイナス。
……独立。
もう、俺に残された道は、これしかない。
俺はここ三年ほど、松永さんの仕事を手伝っていた。兄貴が都議選に出て、なぜか当選して、松永さんは親父と兄貴の両方の秘書になっていた。俺の担当はもちろん経理処理。見てはいけないものも見た。不思議なことに、俺の散財は、キレイに経費に変えられていた。
なるほど、そういう風になってるのか。
これだ。俺の道は、これだ。これに決めた。というか、もう、俺にはこれしかない。
「松永さん、ご相談があるんです」
「何。女じゃないだろうね」
「違いますよ。あの、俺、独立しようと思ってるんです」
「事務所、辞めるの?」
「はい。で、コンサルタント、やりたいんです」
「まあ、ねえ。流行りだけど……そんなに儲からないよ」
「表向きは、コンサルタントです。でも、実際は、先生方のお力になりたいんですよ」
松永さんは、ほう、という顔をした。
「松永さんにいろいろ教えていただいて、お困りの先生方の問題を解決して差し上げたいんです」
「本気?」
「本気です。松永さん、協力してもらえませんか」
「真純ちゃんには話したの?」
話してるわけない。
「はい。真純も、賛成してくれています」
「そうか、いいだろう。やってみなさい」
「ありがとうございます」
「まずはクライエントだね。何人か掴めば、後は数珠繋ぎだ。先生に、相談してみなさい。話はしておくから」
「はい」
そして、俺は、親父に呼ばれ、久々に実家へ戻った。応接間には親父と兄貴が座っていた。
「松永から聞いたけどね」
「はい。頑張りたいんです」
親父と兄貴は、蔑んだ目で俺を見下し、ニヤニヤと笑う。何がそんなに面白いのか。でもここは……
「資金と、クライエントを融資してください」
俺は、ソファから降り、床に膝をつき、手をつき、頭をつけた。屈辱。その単語しか頭に浮かばない。
でも、こんな俺の土下座で人生が変わるなら……変わるなら、それでいい。
「お願いします」
「今回は、本気のようだな」
「はい」
「三年で結果を出せ。それでダメなら、廃業して、悠太の秘書をやれ。いいな」
兄貴の秘書? 冗談じゃない。
「わかりました」
三年。この三年に俺は人生をかける。生まれて初めて、俺は決めた。自分で道を歩く。親父の庭から、出れるかもしれない。そして、あの寝室から、出れるかもしれない。
「独立、するよ」
「えっ! これからどうするの! お金は? お金は大丈夫なの?」
真純、三年後、お前はこの家から出て行くことになるかもな。でもお前は大丈夫だろ? 俺がいなくても、もう、金も地位も、手に入れただろ? 俺なんか、いらないだろ?
俺は真純に頷いて、退職願を書いた。退職願はあっさり受理され、特になんの支障もなく、俺は事務所を辞めた。十二年勤めて、俺の功績など、どこにもなかった。佐倉部長のような、輝かしい功績は、俺にはなかった。
三年、俺は死に物狂いで働いた。電話一本で、いつでもどこにでも行く。休みでも、寝ていても、飯中でも、風呂中でも、セックス中でも。家に帰らず、ほとんどオフィスで過ごしていた。酒を飲むと仕事ができなくなるので、酒はほとんど飲まない。その代わり、オンナを抱いた。誰をいつどこで抱いたか、覚えていない。それくらい、オンナは俺の処理でしかなかった。
ああ、そうか、忘れていた。俺は頭が良かったんだ。東大出だった。日本の脳みそが詰まった東大出だった。
使える人脈は全部使った。警察、弁護士、官僚、医者、どっかの社長、怪しげな団体、エトセトラエトセトラ。俺が処理するものは金だけじゃない。厄介事の仲裁、女の始末、ガキの就職、ジジイの手術、交通違反、面倒事はなんでもやった。法外な報酬と引き換えに、上っ面の、なんの意味もない、薄っぺらい地位と名誉と金を守ってやった。
そして、俺には、真純という最強で最高のアクセサリーがある。どんなパーティでもどんな集会でも、俺は真純を連れて行った。真純はあの笑顔で俺を売った。ついでに自分のクライエントも獲得した。俺達は、仮面夫婦から、ビジネスパートナーに変わっていた。
半年ほどして、裏稼業ばかりはやっていられないことに気づき、『表稼業』を任せられる、山内という会計士を雇うことにした。こいつは、大学の後輩で、初めて、俺が俺より頭がいいと認めた奴で、会計士としても優秀で、貪欲。金と数字にしか興味のない、会計士以外の仕事はできない奴。
「クライエント一件、いくらですか」
山内はあっさり、大量のクライエントを引き連れて、俺の事務所へ来た。山内のおかげて、俺は裏稼業に専念し、あっという間に、俺の名前は政界に知れ渡った。佐倉慶太の名前は、『便利屋』として、オエライサン達のアドレス帳にインプットされた。
約束の三年で、親父に融資してもらった資金と、忘れかけていたマンションの代金に利子をつけて返済し、ベンツを買い替え、真純にBMWを買ってやった。初めて、俺の金で、買ってやった。カルティエの時計も、グッチのハイヒールも、ダイヤのネックレスも、なんでも買ってやった。俺の金で。俺が稼いだ金で。佐倉部長の、給料明細はあれから見ていないけど、たぶん、超えている。俺は、唯一の存在価値を、やっと、確立させた。やっと、親父の庭を脱出した。
でも、やっぱり、あの寝室からは脱出できずにいた。俺はずっと、あの寝室で、真純を待っていた。待っていたけど、真純は、来ない。ダイヤの見返りにに笑っても、真純の部屋の鍵は、閉まったままだった。
罪滅ぼし
午前一時。夜中に無理矢理なテンションの通販番組が始まった。俺達は、ただテレビに向かい、ただソファに並んで座っている。
隣に座る妻は、俯いて、黙っている。
何を、考えてるんだろう。ああ、そうか。これからの、金、か。そうだよな。お前の考えることといえば、それだけだよな。
俺は黙ったままの妻の横顔に、横顔のまま、言った。
「慰謝料は、払うから。生活費も援助する」
よかったな、真純。これでお前も、満足だろ? あの男と、仲良く暮らせよ。あの男……ああ、あいつか。田山か。そうか……こんな日がいつか来るって、なんとなく思ってたよ。そうか……そうだよな……俺なんか、俺の価値なんか……金だけだもんな……
やっぱり妻は黙っていて、俺ももう、何も言うことがなくて、もう……最後なんだな……
俺は黙って立ち上がり、ドアへ向かった。
「お前がここに住めばいいよ。俺の荷物は、そのうち業者に取りに来させる」
長かった……やっと……俺は、あの寝室から出て行ける。やっと……
「ここを、出て行くの?」
「明日から、ホテルに泊まる。」
このドアを出たら、もう終われる。この生活も、もう、終わりだ。
俺はドアに手をかけた。ドアを開けると、廊下の冷気が流れこんだ。
じゃあな、真純。……幸せにな……この二十年、本当に……悪かったな……
「待って」
……何か、言ったか?
「待って、慶太」
なんだよ……金の話か? 心配するな。お前の望む通りに、してやるから。今の俺には……それだけなんだよ、真純。それがせめてもの……罪滅ぼしだ。
「今日ね……将吾に会ったの……」
将吾?……ああ、そうだ……やっと、杉本からも、離れられる……
「将吾ね、幸せそうだった……」
妻は、小さな声で……
「幸せかってね、幸せかって……聞かれて……私……幸せって……いつもね、幸せって言うの。誰に聞かれても、ええ、幸せですって……」
その声は、舌ったらずで……
「だって、だってこんなにお金持ちになったもん。好きな服も、好きなバッグも、何でも買える。母親がね、お金を無心するのよ……」
ちょっと掠れていて……
「食べるものもなくて、いつもおなかすいてて、でもね、今は、今はね……」
一生懸命で……
「……ねえ、見て、慶太。私、こんなにキレイになったのよ……」
ああ、お前はキレイになったよ。俺の望む、イケてる女に……
なったけど……俺の欲しかった、門田真純じゃ……なくなった……きっとそれは……俺のせいだ……真純……許してくれ……
ドアにかけた手の甲に、涙が落ちる。……寒い……生暖かい涙が手の甲で、氷のように冷えて……
もう、疲れたんだ……真純……俺、もう、疲れたんだよ……このまま、出て行かせてくれ……
でも、妻の声は、少しずつ、大きくなって、静まりかえったリビングに……響いた。
「ねえ、私を見てよ。なんで他の女ばっかり見るの? 私を見て。私を抱いてよ。私のこと愛してよ!」
……なんだよ……見てるよ……ずっと、見てたじゃないか……俺は、ずっと、ずっと……お前を……本当はお前だけが……お前だけに……
「じゃあ……じゃあ、俺を愛してくれよ。金じゃなくて、俺を、この俺を愛してくれよ! この俺に抱かれてくれよ! なんだよ……俺はお前の愛が欲しくて、金稼いできてんだよ! お前はいくら出せば買えるのか、ずっとわからなかったんだよ!」
俺は、初めて、心の中の言葉を、音にした。初めて、真純に……初めて……俺の心を……見せた……
かっこわりい……なんだ、俺……イケてない……何言ってんだ……ああ、もう、寝たい。ほんとに、疲れた。真純、もう、いいだろ? もう……俺、眠いんだよ……明日、大事な打ち合わせがあるんだよ……
「……慶太、こっち、向いて……」
妻の声が、真後ろで聞こえた。近くで、聞こえた。きっと、俺の後ろに立っている。
なんだよ、情けねえ俺の顔、見に来たのか? このまま、こんな俺の顔、見ないでくれよ。もう、このまま……イケメンの夫のままで、終わらせてくれよ……
「慶太、顔……見たいの……」
……ああ、もう、見せてやるよ……こんなダサい、イケてない、薄っぺらい男の顔、見せてやるよ……
俺は、振り返った。俯いたまま、振り返った。涙で、何も見えない。妻の……真純の顔も……見れない……床にポタポタと、涙が落ちる。
「顔……見せて……」
「見なくて、いいよ……」
「見たいの」
かっこ悪いけど、俺は涙をスエットの袖で拭って、顔を上げて、真純を見た。真純は俺の、情けない泣き顔をじっと見て、言った。
「ごめんなさい」
俺はその言葉を、初めて聞いた。そして、真純の泣き顔を、初めて見た。
真純が、泣いている。俺の前で泣いている。あの真純が、俺の前で、本気で、泣いている。
ずっとな、こう言えばよかったんだよ。俺は、こう言いたかった。お前に、この一言を、こんなに簡単なことを、言えずに二十年を過ごしてしまった。
時々、思うんだよ。もし、お前が杉本の部屋を出なかったら、花火に来なかったら、塾に入って来なかったら……東京に来なかったら……杉本の横で笑っているのは、子供たちに囲まれて笑っているのは、門田真純によく似た女じゃなくて、お前だったんじゃないかって。お前は、『杉本真純』になって、幸せな二十年を生きてたんじゃないかって。俺は、ずっと、お前を変えてしまったことに、責任を感じてた。でも、もう、二十年は戻らない。二十年前には、戻らない。戻れないから、俺は言うよ。思い切って。これが最後になっても、もう構わない。
真純、俺達は……
「やり直そう、最初から」
真純は黙って頷いて、俺は黙って真純を抱きしめた。十四年ぶりに抱きしめた真純は、冷たくて、オトコの匂いなんて微塵もなくて、ずっと痩せていて、長いウエーブの髪には、何本が白髪があった。
もう、戻れない。俺達は、戻らない。戻らなくていい。
ずっとな、俺はお前を重荷に感じてた。だけど、それ以上に……俺は、本当は、本当に、好きだったんだよ。お前の笑った顔、お前の舌ったらずな声、お前の料理、お前の体。全部、俺のものにしたかった。でも、一番欲しかったものは、お前の心で、俺はどうすればそれが手に入れられるのか、ずっとわからなくて、お前のことを傷つけてばかりいた。お前のことを、わかろうとはしなかった。くだらない、ナンパな俺は、いつも、いつも逃げてばかりで、お前に……俺達に向かい合おうとはしなかった。
「そばに、いてくれ」
「……いいの?」
「愛してるんだ、真純」
愛してる。そんなこと、初めてだな。そんなこと、初めて言ったよ。
なあ、真純。お前は? お前は、俺のこと……
「聞いていいか?」
「うん」
「俺のこと……好きか?」
真純は、涙で濡れた目で俺を見つめて、小さな声で、舌ったらずに、でも……はっきり、言った。
「慶太、愛してる」
ありがとう、真純。俺は、その言葉だけで十分だ。もう、何もいらない。お前さえ、いてくれたらそれでいい。
「もう、遅いな。寝ようか」
「うん」
俺は寝室へ行き、真純は風呂へ行った。シャワーの音が聞こえて、風呂場のドアが閉まる音が聞こえて、ドライヤーの音が聞こえて、隣の部屋のドアの閉まる音が聞こえて……寝室のドアが開いた。
最後の夜 (完)
「ここで、寝ていい?」
白いバーバリーチェックのパジャマで、ふわふわの靴下を履いた真純は、目覚まし時計と、スマホを持って、入り口に立っている。
「うん」
真純は、恥ずかしそうにベッドに入って、枕元に目覚まし時計とスマホを置いた。俺達は、なんとなく照れくさくて、少し離れて座った。
「今日ね」
真純は俯いて話し始めた。
「部下の子がね、うつ病で休職することになったの」
「そう、大変だったね」
「それでね、お家の人にね、迎えに来てもらうまで、田山くんのところにいさせてもらったの」
「うん」
「パーティの後ね、私、田山くんの家に行って、その子のこと、見送ってね」
「それで、遅かったんだ」
「それでね……」
俺は、その続きを聞きたくなかったけど、真純は一生懸命話そうとしていたので、黙って聞くことにした。
「田山くんね……好きだって、言ったの……私のこと」
そんなこと、俺はだいぶ前から知ってたよ。
「十年、一緒に仕事してたのに、全然気づかなかった」
「そう……」
「……キス……したの」
「うん」
「慶太と付き合って、初めて、他の人とキスしたの」
「……うん」
「私ね……田山くんに、そんな無理しなくていいって言われて……泣いちゃったの……慶太とのことも、言われて……」
「なんて?」
「うまくいってないって、噂がたってるって……」
「そうなんだ……」
「私、なんかもう……寂しくて……田山くん、私のこと、慰めてくれようとして、ベッドにね……でもね……目を閉じたらね、慶太のことしか、考えられなくてね……」
俺も……そうだったのかもしれない。他の女を抱いても、満たされないのは、真純のことしか考えられなかったからなのかもしれない。
「何も、しなかったの」
「わかってるよ」
「ごめんね」
俺は右手で真純の左手を握った。真純の手は、痩せていて、冷たくて、ピンクとベージュに塗られた爪には、ラインストーンが光っていて、布団カバーに、涙が落ちて染み込んでいく。
「いいんだよ」
俺は、もう何回もお前を裏切って来たよ……本当に……こんなに辛いんだな……お前はずっと、こんな思いしてきたんだよな……ごめんな、真純。本当に……傷、つけてきたな……
真純は俺の肩におでこをつけて、俺は左手で真純の肩を抱き寄せた。真純の髪からは、風呂場と同じ甘い匂いがして、なんだか、二十年前の、あの花火の夜に戻ったような気がした。
「キス、していい?」
「……うん」
真純は顔を上げて、俺は真純の涙を拭って、俺達は見つめあって……十四年ぶりのキスをした。近くで見た素顔の真純は、目元に少し小じわがあって、薄いシミも少しあって、頬が痩けている。
そして、あの花火の夜のキスみたいに、真純の……味がした。
俺の掌にはいつの間にか、真純のおっぱいがあって、慌てて手を引っ込めた。
「ご、ごめん……」
真純は少し笑って、体を倒して、俺の首に、細い腕を絡めた。
「欲しいものがあるの」
「……何?」
真純は、恥ずかしそうに笑って、俺の耳元で囁いた。
「……慶太……」
真純……そんなこと……初めて言ってくれた……
「うん」
俺はめっちゃめちゃ緊張して、指が震えて、なかなか真純のパジャマのボタンが外せなくて、俺達はちょっと笑ってしまった。
「緊張、しちゃって……」
「私も」
やっとボタンが外れて、開いたパジャマの下は素肌で、首には少しシワがあって、鎖骨は痩せていて、おっぱいは少し小さくなっていた。だけど俺は、この二十年間、いや、四十年間で、最高に欲情した。
「真純……愛してる」
俺はスエットを脱ぎ捨てて、ズボンもボクサーブリーフも脱ぎ捨てて、真純のパジャマのズボンとパンツを一緒に脱がして、ふわふわの靴下も脱がして、体を合わせて、舌を絡めて、首筋を噛んで、もう、よくわからないけど、真純の体が俺の体と溶接されるんじゃないかと思うくらい、俺は、俺達は、俺達の体を貪った。テクニックも、スタイルも、何も考えずに、俺は真純が感じるように、切ない声を上げるように、あの九月の暑い部屋のように、俺達は、目の前の俺達に、夢中になった。真純は俺の腕の中で、身を捩って、掠れた高い声で、うっとりと体をひくつかせながら、虚ろな目で、髪の毛が何本か入った半開きの唇で、俺の指を濡らしながら……呟いた。
「慶太……私のこと、好き?」
俺の下で、そう言った。二十年間、ずっと言って欲しかった言葉を、やっと、やっと言ってくれた。その顔は、最高に色っぽくて、かわいくて、愛おしくて、あのセックス部屋の横顔より、ずっと、ずっと、俺は……真純……
「好きだよ、真純……好きだよ……」
あの夜、杉本が門田真純を抱きながら呟いたように、いや、もう、それ以上で、俺は真純の耳元で、心から、そう言った。
真純はにっこりと微笑んで、目を閉じて、私も好き、って呟いた。
俺はもうガマンできなくて、真純の中に入ろうとしたけど、中は少し固くて、真純は、少し、痛そうにして、顔を歪めた。
「痛い?」
「うん……」
「大丈夫?」
「……ゆっくり、して……」
俺達は舌を絡ませ合いながら、唇と唾液を舐め合い、手を握り合って、ゆっくりと、少しずつ、一つになっていく。
「どう?」
「うん……いい……」
俺は段々速くなって、いつの間にか、真純の声は大きくなっていて、俺は息を弾ませながら、時々声を漏らしてしまっていて……
「慶太……」
「うん?」
「私ね……今ね……すごくね……幸せなの……」
「どう……して?」
「慶太にね……抱かれてるから……」
そう、俺は初めて、真純を心で抱いていた。きっと真純も、心で俺に抱かれている。俺達は初めて、本当の俺達を感じている。真純は俺の腕の中で、切ない声をあげて、俺はもう、感じすぎて……もうダメだ……早いかな……でも、もう……
「真純……もう……」
「うん……」
多分、それは俺の最短記録で、こんなに、セックスを感じたのは、初めてで……ちょっと、恥ずかしい……
「ごめん……早かったかな……」
「ううん」
ほっぺたも体も、ちょっと赤くなった真純は、クスクス笑って、俺はその笑顔がかわいくて、ちょっと照れくさくて、真純をきつく、抱きしめた。そこにいるのは、紛れもなく真純で、俺がずっと、ずっと欲しかった、真純だった。
「初めて、真純を抱いたよ」
真純は嬉しそうに笑って、子ネコのように俺の胸に丸まって、上目遣いに俺を見つめた。
「キス、して」
そんな……何度でもしてやるよ。
俺はキスを覚えたてのガキみたいに、真純の唇とかほっぺたとかおでことかに何度も何度もキスして、真純のおっぱいを触って、くすぐったいって笑う真純がもう、食べてしまいたいくらい、かわいくて、かわいくて、思わずほっぺたを噛んでしまった。
「もう。痛いよ」
「だって、かわいくて……」
「四十のオバサンだよ」
「四十だろうか六十だろうが、かわいいの」
「バッカみたい」
真純は笑って、舌ったらずにその口癖を言って、俺の脇腹の肉を摘まんだ。
「おにく」
「一緒にジム、行こうか」
俺も、真純の脇腹の肉を摘まんだ。
「うん」
俺達はクスクスと笑いあって、もう一回キスをして、俺はちょっと復活しかけたけど、真純はもう眠そうだったので、ガマンすることにした。
「何時?」
「もう三時だね」
「寝るか」
「うん」
俺達はオッサンとオバサンなので、体が冷えると良くないよね、と言って、パジャマを着て、ふわふわの靴下を履いて、スエットを着て、もう一回キスをして、おやすみっていったけど、やっぱり最後にもう一回キスをして、手を繋いだ。
「おやすみ、なさい……」
真純はそう言って、目を閉じた。すぐに寝息が聞こえて、俺はもう今日はこれで終わりとほっぺたにキスをして、おやすみ、と呟いた。真純の寝顔はやっぱりかわいくて、俺はなんとなく眠れなくて、しばらく真純の寝顔をつんつんしたり、耳の穴に指を入れてみたり、ちょっとおっぱいを触ってみたり、そのたびに、真純はうーん、って言ったけど、目は覚まさなくて、俺は真純を抱きしめて、二十年ごしの片思いを思い返して、もう、忘れ始めていた。
そして、いつの間にか……目を閉じていた。
真純、朝起きたらさ、おはようって言おうな。だって、俺達は、夫婦なんだからさ。
コーヒーメーカー、あったよな。うまい豆を売ってる店、知ってるんだよ。今度買ってくるから、一緒に飲もうぜ。
あー、そう。実はさ、ゴルフコンペで、ホームベーカリー、もらったんだよ。事務所にずっと置いてあるんだけど、持って帰って来ていいかな? 昔、パン焼いてくれたじゃん。また、焼いてくれよ。
真純、俺達は、今夜からだよな。目が覚めたら、新しい俺達が待ってるんだよな。
真純、じいさんとばあさんになっても、こうやって手を繋いで寝ようぜ。
真純、俺を選んでくれて、ありがとう。俺を捨てないでくれて、ありがとう。
真純、俺……俺、お前のこと、愛してるからな。大切にするよ。もう、傷つけたりしない。絶対に、しない。
真純……。ずっと、ずうっと、一緒にいよう。二十年後も、四十年後も、俺達は、夫婦でいよう。永遠に、夫婦でいよう。
あと三時間で、目覚ましが鳴る。でも、もう、明日からいらないよ? だって、俺がちゃんと、起こしてやるから。
真純……おやすみ。
<完>
マネー・ドール


