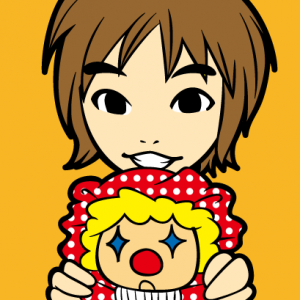夜をかけぬけろ
石田衣良先生『sex』より「夜をあるく」へのオマージュ作品です。
パロディですが原型はほとんどとどめておりませんこと何卒ご了承ください。
とてもいい作品ですので、こちらの小説が気に入りましたらオマージュ元も是非お読みください。
「用意はいい?」
カズアキはドアノブに手をかけていった。春の夜、金属の扉は確かに冷たいがじくじくと熱いパトスがカズアキの手から放出されドアノブは一瞬にして消滅した。
そのパトスは彼の体内で醸造されている精子のスタンドのようなモノで、カズアキが昂ぶると具現化する第二の人格であった。
「ちょっと待って」
エリカがスカートの丈を調節していた。どこまでも短く、もはや痴女直前まで辿り着いたその下品なたたずまいは誰もにヤレそうと思い近づかせる強力な磁力を放っていた。もうシャワーはすませている。ブローも夜の化粧も完璧だった。
「これくらいでいいかな」
AKBを意識したような服装は、どこを歩いても目立つ。暖色系のギンガムチェックのスカートに大きめのリボン。そして黒髪のセミロングより少し短いくらいのボブ。媚びという言葉を全霊で体現したエリカがたまに見せる上目遣いは日夜練習のたまものであり、20メートル周辺にいる童貞は5人までなら同時になぎ倒すことが出来るのであった。
背は152センチと低いがムッチリとした太ももと適度な吊り目は、カズアキの大好物であり基本的に太ももをなめてなめてなめ続けるプレイがカズアキ無上の喜びであった。17歳のカズアキは、太ももを枕にして寝、太ももの上で食事をし、太ももの上で音楽を奏で続けていたい、そう思って生きているのであった。
カズアキは太ももをじっとりとなでた。
「あつつ、あつ」
カズアキの体温は高い。
「あつい、あついの、きもちいい」
エリカは熱いのが大好きである。風呂はだいたい60度前後、天ぷらは揚げたモノよりも油を飲む方が好きであった。その上極度の冷え性で、指先からは常に冷気がほとばしっている。
「ふも、ふも、ふもおおぉん べろびちゃ」
カズアキは体温が高いせいか、興奮すると脳が緩くなる病気であった。目の前のモノしか見えなくなり、言葉は幼児化する。その病気を持つ者は多いがカズアキのそれは人格障害のレベルであった。
尻や股間に興味が無いわけではない。決して無いわけではないが、太ももが好きすぎて素股が好きすぎるのが、完璧とも言えるカズアキの人格の、数少ない欠点であった。
彼らのセックスは常人の数百倍の快感を伴うすさまじいモノであるが、その特殊性によりカズアキは童貞、エリカは処女であった。
カズアキはのどが渇いてしかたなかった。
べろべろ、べべろべろべろ
ぴちゃびちゃぬっちゃねちゃ
その渇きを潤すようになめるなめるなめる。おおよそ20分にわたりなめ続け、エリカは熱気持ちよさによがり続けたがそんなモノはこれから始まる2人の趣味の序章に過ぎなかった。
夜の散歩。いや散歩という言葉でくくれるのだろうか。それは、一般的に述べれば奇行であり乱痴気であり言うならば世界の理への挑戦であった。いや、彼らには挑戦などという意識は無い。それは極めて自然な行為であり人間的なことこの上ないが、大自然の摂理からは大きく外れた見事なまでの青春狂い咲きであった。
カズアキは金属の扉を開けようとした。だがドアノブはすでに蒸発していたためやむなく横の窓から出たのであった。
エリカは実家住まいである。
田園都市線二子玉川駅から歩いて7、8分だった。お嬢である。なので、ドアノブは毎回消失しても親が買ってくれるのであった。
二子玉川はおしゃれな郊外の街として有名だが、駅から少し外れてしまえば、空き地も畑も林も樹海もまだ残っている。のんびりとした土地柄だ。
駅から高島屋に向かうルートは、夜遅くまで人出でにぎわっていた。振り向くと、駅の上の空は腫れたように赤黒く地上の灯に染まっている。だが、マンションからさらに離れていけば、いきあう人はごくわずかだった。自動車もたまに通り過ぎるだけだ。
エリカは16歳になる。その足は白く眩く、街灯の少ない道でも足元を明るく照らす。限界に挑むスカートの短さであるが、それでもまだ露出と痴情が足りないらしく、盛んにスカートを膨らましながら歩いている。
「誰も見てないよ」
「えっ」
おどおどとうるんだ目で、カズアキを見つめた。この目がカズアキには特別だった。豊かな乳房やひらいた脚よりも、強烈な吸引力を持っている。エリカはむこうの世界にいってしあうと、この目つきになって、困ったように両の眉をさげる。性のスイッチがオンからフルスロットルにシフトチェンジしたときの目だ。オフは基本的に無い。
カズアキはスケートボードに仰向けに乗り、エリカを下から覗き続けたまま移動している。たまに歩調とタイミングがずれ、ランダムのタイミングで顔を踏まれるのが大好きなのであった。
深夜の人通りの少ない路上、ガラガラと台車のような音を立てながら二人は移動し続ける。
カズアキは、口をすぼめ強めに息をはいた。カズアキの肺活量は人類の限界を少し上回る程度である。エリカのスカートは一瞬で逆さになり、パンツはぎゅっと食い込みその盛り上がりの形が明らかになった。そしてスカートは爆風で吹き飛び、エリカは少し宙を飛んだ。
「やめて」
エリカは心にも無いことを言った。
「どうして? せっかく完全に透明なショーツをはいてきたのに、みんなに見せてやるといい」
最近、特注で手に入れた品だった。生産者の元へ幾度となく足を運び、職人と綿密な打ち合わせを重ね、1年半の年月と数百万の資金を投入して開発した品である。まだ商品化するにはコストがかかりすぎるが、研究を重ね実用化レベルまで洗練させ、市場に投入し、3年以内に回収しようとエリカは考えるのであった。
「だって、カズがそっちのほうがいいっていうから」
「ほんとに、それだけ?」
「いや実用試験を兼ねている」
からみつくように甘えた声だった。カズアキはすでに3つボタンを外したブラウスに手を伸ばした。もちろんブラも完全に透明な品である。服の透明度をどこまで抑えれば逮捕されること無くギリギリまで露出できるか、というのがエリカの目下の研究課題でもあった。32%で外出したときには残念ながら拘置所に入れられてしまったが、父親にお願いして不問としてもらった。エリカはまだあきらめない。この世界に新しい価値を産みだし、社会にイノベーションを起こすのだ。
「ダメだったら……まだ」
エリカは心にも無いことを言った。
「ダメだって、ダメだって」
エリカは肩をすぼめ、ブラウスを下げていった。そして肩甲骨を器用に操作しブラ(透明)のホックを無手で外す。一方のカズアキはただひたすらに太ももに鼻を押しつけながら、三点倒立の状態で右足指でエリカの乳首をこねるのであった。もちろんカズアキの足も灼熱である。
「あつ、あつ、きもち、きもち」
「スーハースーハー」
街灯がまるでスポットライトのように二人を照らし、そこは前衛芸術のステージのようであった。様式を外れたところで新たな美のバランスを取り直す、人類を新たな領域へと導くのは彼らのような人間なのかもしれない。近くを通った佐々木はそう思ったのであった。
なぜ女の乳首はビロードのようなのか。と、カズアキはビロードをよく知らないがそのように思っていた。おそらく滑らかでちゅるりとした感触なのだろうが、エリカは少し違い、猛烈な体温の低さである。どちらかというと大きな雪見大福にドライアイスをのせたような感覚である。一般人には。
「スーハー?」
カズアキは、おそらく「感じる?」と言った。
エリカは声を漏らさないように努力するふりをして、身体をよじるのであった。
「あ、あふ、いいの、ちろちろってして」
ここは二車線の車道である。街灯はある程度明るくスポットライトのようであるが、エリカには物足りないようであった。あと数分も歩けば、小高い丘がありそこならば天然のステージとなる。そこまではこんな感じでいいだろう。夜の乱行はまだ始まったばかりだ。
「どうして」
エリカが泣いているような目で問いかけてきた。
「どうして、外でさわると感じるの」
「きみがスーハー宇宙と一体化したがってスーハーるからだ」
カズアキは、一切顔の向きを変えずに言った。エリカは、そんなカズアキの言葉が何よりも快感であった。幼少期より自由に振る舞いすぎてきたエリカは、生を受け15年にして、ようやく自らを導いてくれるグルとなる資質を持つ男に出会えたのだ。だがまだ足りぬ。不安定で、未熟である。この者は私の手で宇宙大僧正としての格を持つに至るまで育て上げねばならない。
カズアキは、いじわるをしたくなって、足指に力を込めて乳首をつまんだ。甘い声でエリカが言った。
「きゃるるん☆」
「外の方がスーハー感じるのは、エリカがスーハー宇宙と溶け合いその身を社会というスーハー形式ばかりが肥大化した人類の歪な集合体スーハーから離脱させようと本能が叫んでるじゃないのか。自らを解放しスーハー全宇宙の意志と一体化しようとスーハーきみの身が心が魂がゴーストがスーハー叫ぶんだ」
「違うもん」
カズアキは、三点倒立を解除した。自由になったエリカは、離れず逆に身を寄せてくる。梨の木の下枝を揺らしてきた風が、やわらかにふたりのあいだを抜けていった。エリカはすでに下着上下(透明)と前の開いたブラウスとギンガムチェックのベストのみという完全に逮捕な格好であった。スカートは先ほどバラバラになって吹き飛んでいる。
もうすぐ曲がり角だった。灯台のように夜に浮かぶ自動販売機の青い灯が目印だ。
「自分だって、興奮してるくせに」
エリカは、再びスケボー上に仰向けとなったカズアキの顔の上に、後ろ向きになるようにしゃがみ込んでいる。
左手を舟形に伸ばして、ジーンズのまえ立てを探った。カズアキのペニスはこれ以上無いほど、本当にこれ以上無いほどに硬直していた。運動会の時の旗を立てるためのあの下が丸くてその上に穴の空いた棒が立っている金属製の結構重いアレみたいな感じになっていた。エリカはつけ根から先端に向かって、ゆっくりと指を走らせた。いたずらっぽい目をして言う。
「なんだか先の方がメルトダウンしてるよ」
少し粘性のものが漏れ出していた。
カズアキも負けていなかった。ショーツ(透明)のうえからあやふやな形をなぞるかと見せかけて、太ももを執拗になで回す。エリカのパンツ(透明)の中は、もはや氷が溶け出したかのように水浸しである。
「やぁにゃん☆」
思わず声を出したエリカに、カズアキはいった。
「すこし太ももを執拗になで回しただけなのに、もう床上浸水じゃないですか」
顔を赤くしてエリカはしたをむいた。
「どうして、そんなに濡れてるんだ」
「誰だって、こんなふうにさわられたら、そうなるよ」
カズアキの太もも責めは、少々特殊である。手指舌のみでなく、全身のありとあらゆる器官を使用し攻める攻める攻める。特にカズアキの舌は、先が2つに分かれておりそれがさらに自在に動くという人の限界を少し超えた特殊な構造であった。その斬新な構造で幾多の女をイカセ倒してきたがカズアキは童貞であった。
自動販売機の角で、カズアキは静止した。ローファーの中はとても淫靡な臭いがするんだろうなと考え、剛直はさらに成長した。
「のど渇いた。半分ずつ、なにかのもう」
青い蛍光灯を映して、エリカの開いた胸元の中の透明のブラがその質感を示すように青く光っていた。うっすらと汗ばんでいるようで、鎖骨のくぼみに濡れた光が溜まっている。
「じゃあ、メローイエロー」
「わかった」
若者はメローイエローである。
灼熱の体温で暖まった小銭を、ジーンズのポケットから抜いていれた。ガタンッとおおきな音が響く。カズアキはアルミ缶をとりだし、リングプルを開けて、喉を濡らして冷たい炭酸を飲もうとしたが口に入れる先から蒸発し、結局一滴も飲むことは叶わなかった。
しかしその気化したメローイエローをエリカの身体で受け止めることで、空中で凝固し雫となり雨となり恵みをもたらすように降り注ぐ。そしてその下にいるカズアキから再度蒸発し、それを繰り返すことで二人の間には虹と雲が発生した。新たな人類の幕開けだ、と、通りがかった佐々木は思ったのであった。
「ふん…ぬッ!!!」
カズアキはエリカのブラ(透明)を思いっきり引きちぎった。試作品だが、そのような細かいことは気にしないのだ。両の乳房が直接夜の空気に触れる。カズアキは硬く立ちあがった乳首に吸い付いた。乳首はまるでアイスボックスのような甘味である。いつまでもいつまでも舐めていられる、と、2又の舌を持つ伝説の男は思うのであった。
右と左、それぞれの舌が時にはこよりのように、時にはサーモンのように自在に形状を変化させながら乳首を攻め立てる。この波状攻撃に陥落しない城は無い、無敵の矛であると称されたカズアキの2点責め(ダブル・アルティメット・パイソン・タンズ・ガトリング)である。
しかしエリカも、ニコタマの盧舎那仏と三国に恐れられる絶対的不感少女であった。これまであらゆる類の男たちが、その性的人生をかけ挑んできた。父の開催したエリカをイかせる選手権は、挑戦して失敗したら死刑である。これまで、命を賭して果敢に向かってきた男は4桁にも上る。現人神と名高い練馬区在住の加藤さんが、この挑戦で命を落としたというのは有名な話である。
乳首における絶対的矛×絶対的盾の頂上決戦は、これまで互いに65535勝65535敗0分け。この日の勝負に、互いのプライドをかけて臨んでいた。
この夜の闘いは後にサーガとなり伝承されていくものとなるが、それだけで1冊の本になる内容の濃さなのでここでの記述は概略にとどめることにする。結果から言うと、初めての引き分けであった。互いに認め合う漢たちの闘いは、道を行くものたちの足を止め、気づけばそこに熱狂が生まれていたのであった。炎と氷、蛇と盧舎那仏の人智を越えた闘いにより、乳首を舐めるという行為の概念が完全にシフトした。まさに、人類の進化に必要な闘いだったのである。
「ダメー☆カズ、立っていられなくなる☆」
おそらく演技であろうその声で、カズアキは乳首から口を離した。過去に勝利した際、困ったことになっていたのだ。エリカのリミッターが外れることにより周囲の温度が絶対零度まで下がり、その街はその後凍結したまま時が止まっている。
カズアキはメローイエローをさしだしながらいった。
「まだ残ってる。のむ?」
「うん」
平然とした顔でエリカがうなずいた。汗一つかいていない。やはり演技だったのだろう。エリカは立ったまま、自動販売機の青い光を浴びて、金属の缶から冷たい炭酸をのんだ。初めて見る女性のような気がして、カズアキはエリカのシルエットを見つめていた。もうつきあい始めて一年半になる。良く人はセックスの相性と言うけれど、互いに自らを至高であり究極であると思い生きてきた二人にとって、はじめて認め会える好敵手─とも─であった。初めて夜を共にしてから一年以上。まだカズアキとエリカの能力はじりじりと向上している。生きることと同じ不思議が、セックスにはあるのだ。
「なにを見てるの」
カズアキは照れていった。
「すごくいい身体だなと思って」
「やぁんやぁん☆うにゅー」
カズアキは殺意を覚えた。
「やらしいのは嫌い?」
エリカはそのキツ目童顔巨乳むっちり太ももという最強の身体を寄せてくる。
「好き☆カズアキがぁやることならぁ…、どんなやらしいことも、好・き、ダゾ☆」
空っぽの缶を受け取り、そのまま全力でエリカにぶつけた。缶はマッハに近い速度で発熱し、まるで隕石のようである。
しかしエリカもその肉体に当たる直前で物理シールドを張り、缶を正面から跳ね返す。ズン、という重い衝撃音が夜の静かな住宅地に響き渡った。
「さあ、いこう」
腕をからませて、丘に続く道をふたりはあがっていった。
路地の道幅は二メートル足らずだった。最初はゆるやかだが、途中からは急なのぼり坂になる。頭上に張り出すように青竹が伸びていた。
のぼって行くにつれて徐々に眩さを増し、そこはさながらブロードウェイのステージのようであった。それもそのはずである。エリカは軍事用のヘリを手配し、強力なスポットライトを自分たちに当てるよう指示を出していた。赤青緑、さらにはレーザービームにプロジェクションマッピング。贅を尽くした照明がそこには準備されていた。またカズアキも、アジア最高とされる演出家に依頼をし、場を盛り上げるオープニング映像、生楽曲、炎と電飾による演出を街全体に施していた。500インチの街頭ビジョンにテレビやネット生放送。世界150カ国同時放送である。
カズアキは、エリカを抱き寄せその唇をちろりと舐めた。
そして、湧き起こる大地を揺るがすような大歓声である。もはや昼のようなニコタマの街に、今、全世界の注目が集まっていた。
エリカはカズアキの首筋に右手をそえ、恥じらいつつも舌をねっとりと絡めてきた。唇から前歯の裏、口腔上壁へと丹念に舐めていく。相手は伝説の蛇である。一瞬の油断が命取りになることを、エリカはピリピリと感じていた。
ゴクリ…という音が響き渡る。全世界、20億人ほどが同時につばを飲み込む音である。
「あふ…、はっ、ん、ちゅ、ぅむ…」
ぴちゃりぴちゃりと水音が響く。合計400本ほどの集音マイクがふたりの唾液交換を狙っていた。
「ん…ふぅ…、むふ、ふん」
「ほふん むちょ くちゅるぬ」
その接吻は長く長く続いた。カズアキの手は肩から背中、腰、そして引き締まった尻へと伸び、またエリカも左脚でがっちりとカズアキの腰をホールドした。天を突かんばかりに反り返るカズアキの剛直が、二人の間で強烈な存在感を放っていた。二人の舌は、互いに求め合う原始生命体のように蠢き、脈動し、神経を刺激しあいじゅくじゅくと脳髄に快信号を送り続けるのであった。
「可愛いわ、カズの陰茎」
上気したエリカの顔は、盧舎那仏から菩薩へとその様相を変えていた。おおぉ…と街中にどよめきが広がる。仮面を纏った氷の女と形容されたが、その生命定義を変容させつつある瞬間であった。
「こんなに怒張させちゃって…貴男の肥大化したエゴが凝縮されてるのね」
エリカは、愛おしそうにカズアキの表面を撫でた。
「ほ ほ ほ」
その瞬間に、カズアキの全身に鈍く緩慢な電流が流れた。
「おふぉー くぬ むぐん」
カズアキは、自他共に認める早射ちである。高校生の頃は歩いているだけで射精してしまうため、常にオムツを着用していた。だが、早射ちには早射ちの闘い方がある。世界最速の早射ち、その逆境が産みだしたのが“蛇”としての彼なのであった。
強く強く下唇をかみしめる。瞬時に、嫌いな男のアクメ顔を想像する。この瞬間に彼の脳髄に走ったのは、醜悪なハムのような男たちの乱舞であった。メルトダウン直前の剛直が、一瞬失速する。
「ぬ ぐ むぐぐぐぐ」
圧倒的な突破力を誇る蛇の弱点は、無に近い防御力であった。完璧な矛は、盾としての能力は一切持ち合わせていない。しかし、カズアキは当然その弱点を克服するため日夜努力を重ねていた。脳の引き出しには、一瞬で萎えさせるような画像映像音声が膨大に保存されている。そのリストアップが、彼を絶望的状況から救い出すのである。
しかし、どんな精神的防御も、肉体的干渉には無力であることは自然の摂理である。
エリカは、接吻の舌をそのまま抜き出し、顎、首筋へとその位置を下げていった。首筋を通る際、軽く舌を上下させ柔らかい神経帯に刺激を与えることを忘れてはいない。右脚は、カズアキの尻周辺から左脚へと絡みつき絶妙な刺激を与え続けている。
れろれろ ちゅぷり ちろりちろり つつー
唾を出し、より滑らかに舌を駆動させる。左手は背中に回し、右手は剛直の表面を触るか触らないかギリギリの位置でゆっくりと動かしている。その僅かな空気の動きがむしろ、カズアキには危険な刺激となる。
「あぐ あぐ ぐぐ」
カズアキの下唇から一筋、二筋と血が流れ落ちる。額はにじみ出る汗でびっしょりである。苦悶と悦楽の表情を浮かべ、カズアキは耐え抜く。耐え抜く。
そしてエリカの舌は、肩口から鎖骨、そして胸部へと進出する。カズアキはもはや白目を剥き、口からは血筋と唾液が絶え間なく垂れ流され続ける。このままでは危険である。しかし、エリカはその流れを止めることは無かった。胸部中心、感度が頂点に達するポイント。そのワンポイントに、エリカの舌が到達した。そして同時に、陰茎をなぶっていた右手を、左のポイントへと移動し両突起を同時に刺激した。
「○×♂…!! ΔΣΩΩΩΩ…!」
人間の可聴領域の外側の音を、カズアキは発した。
ずずず… ぎゅ びく びくびく びくん
一瞬、カズアキの全身が硬直した。射精はしていない。だが腰に冷たい棒を差し込まれたような感覚と共に、剛直を締め付けられるような感覚、そして脳髄が冷えていく感覚をカズアキは味わっていた。
ドライオーガズム──
早射ちたちが必ず通る道である。耐え抜き続けた結果、射精はしないまでも絶頂を迎える現象をいう。すぐに逝ってしまっては顔が立たない…しかし、それでも絶頂を迎える男の身体の深奥である。
ドライオーガズムを迎えると、何とも言えない腰の重さと共にイった後の倦怠感が襲ってくる。そして、だらりと精液の一部が流れ出るのが何とも言えない情けなさなのである。射精していないのに萎えてくる。この空虚感は味あわない限りは理解には至らないだろう。
しかし。
カズアキは伊達に蛇の称号を得ているわけでは無かった。乳首を舐めるエリカの上目遣いを見下ろした。その、黒目がちの目と、少し汗ばんだ額に張り付いた数本の髪。黒髪は艶やかで、手入れは完全に行き届いている。肩口から鎖骨にかけての肌が、照明を反射し淫靡に鈍く光る。マットな肌質が、匂い立つような蒼く若い草のような色気を発散していた。唇は、少しグロスがはがれかけぬらりと不規則に蠢く。胸にかかる甘く温かく湿った鼻息と、腰に回された手の、五本の指がさわりとなで続ける感触が、カズアキの剛肉を0.3秒で復活させた。
エリカは、喜びに目をすっと細め、舌の動きを再開した。ドライとはいえ一度オーガズムを迎えたカズアキは、冷静さを持ってエリカの甘い感触に浸れるのであった。
エリカの顔は、可愛い。少し吊り目がちで、全身から下品な媚びがあふれ出ているが、近寄れば近寄るほど、その完璧から少しだけ外した隙のある造型にあらゆる男が下半身を奮い立たせるのである。高嶺の花で半端な男は相手にしないっぽいけど、もしかして意外な趣味があってヤラせてくれるんじゃないか…そんな微妙な男心をくすぐる針の穴を通すような空気感を醸造することにエリカは成功しているのである。
カズアキはエリカのあごをおさえ、その唇に指を這わせようとした。
「んんぅん…だーめ、だよぅ☆」
言って、エリカは濡れそぼった唇で指を甘く挟み込んだ。閉じきらない唇の端より、唾液が少し垂れ落ちかける。
びく ひぐひぐ ぐ ぴくん
カズアキは二度目のドライオーガズムを迎えた。もはや指先すらも性感帯であり、目に入るあらゆるものが性衝動を喚起させるモノとなっているのであった。
オオォォ…
観客が響めく。予想よりやや早い、カズアキの態勢崩壊である。もはや次は無い。次を迎えたら、一国が傾くレベルの経済的損失が発生しかねない。
カズアキの脳髄は熱くたぎっていた。
「お、おお、おれは」
「かーずくん☆どう、したのぉ?」
言葉を発しながら、唇を耳に近づける。語尾をかすれさせ、甘い吐息と共に耳を刺激する。カズアキの金剛力士が、元の1.1倍にまで回復し脈動を繰り返す。
「おお おれはおれはおれは」
「おれは エリカを」
エリカの目が紫色の光を帯びる。性欲がリミットを振り切ったときに達する、フロー状態である。エリカの性欲は、男を掌握したときに最大値に達する。嗜虐の喜びに、周囲の空気が帯電する。
「エリカを ええええりカを」
エリカは、胸元からつつりと舌を這わせ、腹部、そしてさらに下へと指と舌とでテンポ良く刺激を続ける。左手でベルトを外し、ジーンズのジッパーを下げた。まろびでた剛力彩芽は、金色のオーラを纏い天に向かって隆々と高く逞しくそそり立っていた。エリカは、息を吐きながら彩芽の周辺を口で往復する。触らず、空気感のみを彩芽に感じ取らせているのである。
「かーずくーんはぁ」
わざと息を吐きつけるように言葉を発する。カズアキは白目を剥き、全身が彩芽になったかのようにびくりびくりと胎動を繰り返している。3メートルほど離れた街路樹が発火点を突破し炎にまみれた。赤子の泣く声が聞こえてくる。アスファルトが溶け出し、空気が不自然な対流を開始した。
「えい、いっちゃえぃ」
あむ、と口を開き、ぱっくりとくわえ込んだ。
刹那──
かっ、とカズアキの目は開かれ、衝撃波で20メートル四方の建築物は一瞬で消し飛んだ。けたたましく警報が鳴り響く。報道ヘリがバランスを崩す。空が赤く染まり、待機していたパラシュート部隊が次々と空から舞い降りてきた。
じゅぷぷ ぐじゅっ ちゃぷり ちろり
40本残った耐熱マイクが、赤く染まる世界の中で響き渡る水音をとらえていた。付近の耐衝撃装甲車に乗り込んでいたエリカの父親は、娘の運命の男との行為に滂沱の涙を流すのであった。
「ああああああ、イク、イク、くおおおお、エリカ、エリカ、おれはおれはおれは」
むぐむぐとしながら上目遣いでカズアキの方を向く。その深紫に輝く目が、さらにカズアキの心底を射貫いた。
「エリカおおぉぉおおお、す、ずうぎいいだああああああああああ」
世界が光で包まれた。
しばし、時間軸は理から外れ、空白が訪れた。時間とは相対的なもの。全生物に同時に与えられたその空白は、ある者には一瞬に、ある者には無限大にも感じられた。各々に与えられたその福音を享受し、そしてまた時は動き出すのである。
カズアキの彩芽は爆発した。
溜まりに溜まった膨大な量の精液が、辺り一帯に四散する。瓦礫より這い出してきた犬、匍匐態勢の自衛隊員、通りがかった佐々木などに煮えたぎるような熱い白濁液が振りかかった。エリカは、瞬時に物理シールドを展開し、すべての精液を受け流していた。
しばしの時が流れた。
そこに立っていたのは、神々しい黄金色のオーラを纏った全裸の男であった。
「──我、此処に至れり」
男の口は動いていない。聞く者全てに畏敬の念を抱かせる低い重低音。それが、生きとし生ける全ての者の脳へと直接響き渡ったのであった。
天上より降り注ぐ光、光、そして歌──男の周囲には、羽根を生やした童女たちが傅いていた。
「ずっと、この時を待っていた」
紫色の波動を発するエリカが、その目の前に立っていた。その佇まいには、もはや下品さは微塵も感じられない。純粋な色気そのもの、それが今のエリカという存在だった。
「我を高みへと導いてくれたこと、礼を言う。ただ愛を注ぐため、今の私はここにいる」
「私は私のために行動しただけ。貴男が新たな生命の領域に辿り着くこと、それこそが私のすべて」
「いざ参らん。原始の領域へ」
カズアキは、寝台を具現化しそこにエリカを横たわらせた。エリカは、慈しむようにカズアキの両頬に手を当て、そっと導いた。カズアキはエリカの下唇を軽く噛み、ちゅ、ちゅっと甘い刺激を与えた。
「ん、ふぁ、きもち」
カズアキは、エリカの腔内に舌を挿入する。お互いの味を感じあい、それぞれを満たすためにゆっくりと舌を絡ませ合う。
カズアキの右手が、エリカの丘陵へと辿り着く。ぴく、とエリカは反応した。指先と掌全体を慎重に動かしていく。ふんわりと、柔らかく。
「ん、んっ、あ、いいよ、気持ちいい」
首筋をなめ、カズアキは徐々に下へ下がっていく。左手を右胸に、そして左の乳首を大きく口に含んだ。唇は直接は触れていない。ちろちろと舌を動かし、乳首を優しく刺激する。同時に、左手は円を描くように右乳房を揉んだ。右手を、エリカの柔肌に触れるか触れないかギリギリの位置を保ったまま、お腹からさらに下へと移動させる。
カズアキは、中指をエリカの中へと埋めた。
「きゃうっ、はっ、ぁはっ」
エリカは高く短い声をあげ、背中を少し浮かせた。
「そこ、ちょっ、いや」
カズアキは答えず、両乳首と濡れそぼった膣内を同時に攻めた。攻めた攻めた。あふれ出るエキスはカズアキの指をぐちゃぐちゃにし、またエリカの右乳首もカズアキの唾液でぬらぬらであった。
カズアキは、中指を曲げ、ざらりとした内壁を刺激した。
「ああぁっ、ダメ、ダメダメ」
首を左右に振り、もがくように動くエリカ。だがその下半身は逃げるどころか、さらに求めるようにいやらしく脈動するのであった。カズアキは、さらに人差し指を投入した。
「あっ、すご、違うとこあたって、んっ」
手首を固定し、指の上下運動でエリカの内壁を刺激する。もちろん左手と舌のちろちろもぬかりない。
カズアキは体勢を回転させ、顔を足の間へと近づけた。身長差があるため少し身体を曲げなくてはならないが、ペニスがエリカの顔のまえに来るように逆さを向いたのである。エリカはノータイムでむしゃぶりついた。それは下品そのものであり、それこそが人間であった。
「んちゅ、んちゅ、んちゅ、あっ、んちゅ、や」
さらにより舐めやすいよう、エリカが上に来るように横回転した。カズアキはクリトリスを中心に、柔らかくそして時に強く、舌の形を自在に変えながらエリカの絶景ポイントを攻め続ける。エリカはもはや頭など使っていない。本能の赴くままに口と舌をとにかく動かしている。
猫が顔を洗うように。蟻が列をなすように。人間は本能で生きるべきなのである。
ぴちゃりくちゅりと、粘性の快感に二人は酔いしれた。
「あ、あ、いい、んちゅ、んぐうぬ、あぁ」
一度爆発した後のカズアキのペニスは、強く逞しく生まれ変わっていた。さなぎから蝶になるように、鮮やかな進化を遂げたのである。エリカのツボを心得た攻めにもびくともしない持続性を手に入れたのである。
「あ、あ、あ、あ、あっ……!… 」
びくん、と身体をのけぞらせ、しばしエリカは静止した。そしてそのまま、惚けたような顔をしてぐたりと横になる。
「軽くイった?」
「…う、うん。で、でもまだ軽くできゃうん☆」
言葉の終わるまえに、カズアキはエリカの首にむしゃぶりついた。舐めて舐めて舐めまくった。新生カズアキは、太もも以外の領域に目覚めたのである。
「いいよー、いいよぅー」
犬のように全身を舐め回す。手、口、それだけではなく足そして剛直、すべてを駆使してエリカを刺激し続けた。
「あはは、いい、きもちい、カズ、いいよ」
じゃれ合う二人は仲の良い仔猫たちのようで、ほほえましいなと通りすがった佐々木は思ったのであった。
「ね、ねえ、エリカ」
「うん、うん?」
「おれ、おれもう」
「…うん」
「入れたい」
「うん」
カズアキのカズアキは、これ以上無いほどにいきりたちその本分の全うを待っていた。エリカはうっとりとそれを眺め、そっと脚を開いて迎え入れる姿勢となった。むわりと漂う雌の臭いに、カズアキは目眩すら覚えた。剛力はもう1.1倍強度を増した。
「で、でで、では」
「インします」
包まれたくて震える剛直を、少しずつ近づけていく。その近寄っていく光景が、カズアキの脳髄をびりびりと刺激する。セックスは脳でするもの、そんな祖父の言葉がリフレインした。
しかし、入り口に辿り着いた瞬間にそんな記憶は粉々に吹き飛ぶのであった。
敏感な部分が、濡れた入り口に接触する快感。甘く密のような瞬間であった。
「ん、うう」
少しずつ、未踏の肉洞窟にカズアキのペニスが挿入されていく。探検の喜び。帰還の喜び。あ、ごめん爺ちゃん、やっぱり脳だわ、とカズアキは思った。
「ううー」
「痛い?」
「ううん、あったかくて」
カズアキはホッとした。もう、今すぐにでも腰をむちゃくちゃに振りまくりたい衝動に駆られていた。だが、二人はどちらも初回である。ゆっくりとゆっくりと馴らしていかなくてはならない。
「動きたい…いい?」
「うん…大丈夫、だと思う」
カズアキは抽送を開始した。人の本能は不思議で、したことの無いことでも摂理が教えてくれる。小柄だが胸が大きく、締まるところがしっかり締まっているエリカの身体を見下ろしながら腰を動かす。一体人はどんな善行を積んで、こんな快感を手にすることが出来たんだろうとカズアキは考えるのであった。
「はっ、すごっ、いい、きもち、いっ、きもち、いいっ」
カズアキの腰を振る速度が速くなる。エリカの髪は乱れ、大きな胸が弾んでいる。カズアキはエリカの両腕を持って上体を起こさせ、そのまま腕を自分の首に回させ、腰を支えた。この方がエリカの顔がよく見える。可愛い童顔が、快楽にとろけている。目は濡れ、半分ほど開いた口から少し舌が出ている。だらしない顔がますますカズアキを刺激し、剛直の強度は1.1倍増した。
ぐっと自分に抱き寄せ、深く密着したまま腰をグラインドさせる。小刻みに脚を動かし、細かな刺激をエリカに与える。
「あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、」
エリカの首ががくがくと前後する。汗の玉が顔にかかる。エリカはもう何も考えられなくなっていた。ただ繰り返し押し寄せる波状の快感に身をゆだねるばかりである。
「ダメ、ダメダメ、もう、うう」
エリカの全身が一瞬電気が走ったように弾けたかと思うと脱力し、膣壁がひくひくと蠢いた。
「うおお、お、お、おれも、い、い、やば、」
「あ…、なか、に…」
「…ぅあっ…」
カズアキは自らをエリカの中に解放した。熱い熱い情欲のたぎりが今、新年の門開きダッシュのように噴出していったのである。
エリカの中は収縮して狭く、どく、どくと脈打つペニスをギュッと締め、最後の一滴まで搾り取ろうと律動するのであった。
あらぬ限りの情欲をぶつけ合った二人。くたりと横になり、途切れ途切れの息を整えるのであった。
「…おめでとう」
パチパチと手を叩きながら、エリカの父親が現れた。
「…え、パパ?」
「おめでとう」
「…姉さん?」
次に現れたのは、カズアキの姉であった。
「おめでとう」
「おめでとう」
「おめでとう」
二人の親族、友人たちが続々と手を叩きながら現れる。そこには、過去にエリカに挑んで死んでいった男たち、加藤さん、カズアキがイかせた女たち、佐々木らの顔もあった。皆、満面の笑顔で二人を祝福している。
「おめでとう」
「おめでとう」
「これって…」
そう、二人の童貞・処女喪失を、皆が祝福しているのである。
ワッ…!! と歓声が湧いた。ニコタマの住人たち、そして世界中からやってきたオーディエンス、自衛隊の皆さん。さらにはテレビの向こうで息をのんで見守っていた全世界の皆。それら全員が立ち上がり、史上最大のオベーションを二人に送っている。
喜びは世界を包み、幸せは連鎖する。
それは途切れること無く続いていくのだ。脈々と。どこまでも。どこまでも──
夜をかけぬけろ
よくわからないことになってしまいました。