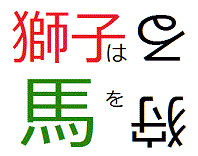
獅子は馬を狩る
「起」承転結

*
社会とは集団の集団によって形成されている。その社会に適合するために、教育されているのだ。
社会不適合者には憐みの目と恥を、社会適合者には期待と足枷を。
社会を円滑に回すため、欠けてもいい歯車の一部として今日も動くのだ。
嫌悪しても何も変わることのない、この、歯車。
*
電車に揺られていると、ふと思う。
どうして彼はほほ笑むのだろう。どうして彼女はほほ笑むのだろう。
そして、どうして、自分もまた、笑うということをするのだろう。
一説によれば、「敵意がありません」という証拠らしい。
嘘だ。
自分には敵意がある。
自分以外の他人なんて、すべて目障りな障害物でしかない。
嫌悪の対象だ。ぜひとも、消えていただきたい。
そう思うのに、いざ一人ぼっちの世界を想像すると四足がすくむ。
孤独は怖い。
取り残されるのが怖い。
だからこうして、社会適合者のふりをして足並みをそろえている。
押しません、駆けません、正しく乗ります、だから電車に入れてください。
*
外気が入ってくる。
自分が降りる駅だ。
不思議だ。昔は駅というものは自分の足で赴いたものだ。
今は便利な道具がある。
カポ、カポ、カポ、
カポ、カポ、カポ、
カポ、カポ、カポ、
カポ、カポ、カポ、
いくつもの足音が重なる。
蹄の雑踏。
乗客すべての四足の下半身が前進する音だ。
*
いつも通りのデスクワークをこなし、いつも通りの残業をこなし、部下には罵倒、同僚に笑顔、上司には会釈をふりまいて一日が終わる。
それで金を得て生活を回すと、経済が回り、社会が回る。
台本もないのに都合よく運ぶ社会である。
今日もひとり、コンビニ弁当を買ってマンションまでの帰路につく。
カポ、カポ、カポ、
自分ひとりの足音は煩い。
どんなに静かに歩く方法を試しても、成功することはない。
しかし、不思議なことに自分以外誰も「蹄がうるさい」と気にするものはいない。
当たり前だ。
音が鳴ることが当たり前なのだ。
心臓の脈打つ音を平素、聞き取れないように、自分の体臭が常に嗅げないように、蹄が鳴ることをうるさいと思う仲間はいないのだ。
だから自分は変わっていると思う。
そう信じることで、社会不適合者の烙印を押される数歩手前でとどまっているのだ。
*
染谷は深呼吸をした。
自分の足音があまりに不愉快で、他のことで気を紛らわすためである。
そうだ、星を見よう。
夜空に輝くあのキラキラしたものたち。
遠い世界から何のためともなく届く光たち。
染谷は小さいころから星が好きだった。
月や太陽ではだめなのだ。
なぜ星が好きなのか、と聞かれても答えられるだけの追求もしていないが、 好きなのだ。
星座を探し、星の名前を思い出して口に出さずともつぶやいてみると、少しずつ自分の足音が気にならなくなってくる。
自分の下半身が四足であることも忘れ、ひたすら夜空を見上げる。
その日、雲もなく晴れていたため、大好きな星を沢山見ることができた。
季節の移ろいを感じさせる星も見た。
相も変わらず定点で輝く星も見た。
星座にまつわる神話も思い出す。
幼心に必死に読み覚えた数々。
自分の知っている範囲では、自分以上に星に関して詳しい者がいなかった世界。
*
チェーンソー。
鈍い音がした。
その直後、鋭い痛みが走る。
と、同時に立っていることが不可能になった。
染谷は何が起こったのか理解するよりも前にバランスを崩して地面につっぷした。
「後ろ足が、ない・・・!」
うめき声をあげながら、自分の体に何が起こったのかを確認すると、後ろ足がなくなっていた。
後ろ足と胴体の境目からは血があふれだし、前足にまで届くほど広がっている。
喉が張り裂けるほどの大声が出た。
そしてそのまま、地面に倒れて、気を失った。
*
上半身は、人間。下半身は、馬。
一度は聞いたことがある神話の生き物の、繁栄した世界。
彼らの住みよい社会での、猟奇的事件。
「後ろ足切断事件」の幕開けである。
起「承」転結

*
そのあとはどうなったのかは覚えていない。
善良な市民が、染谷の悲鳴を聞きつけて救急車を手配してくれたらしい。
バランスを失った馬の下半身をどうにか支えて、手術された。
そして、灰色の空を白い病室からぼんやりと見る、今に至る。
なんとも無様なのだろう、
なんともかわいそうなのだろう。
欠損した染谷を憐みの目を向けてみてくる。
なんだ、老馬はみんな、車いすで生活をしている。
それが早く、自分の番がきただけだ。
だけだ・・・。
最初、気丈に振る舞うも、染谷は車いすの生活になった自分を憐れに思ってしまった。
*
こうして、社会から逸脱してしまった。
後ろ足をふたつ失っただけで、あっさりと社会の歯車ではなくなってしまった。
失って、不自由に動き回ることができるようになり、社会から逸脱するくらいなら、最初から自分の精神の異常さを発揮して自由なまま逸脱した方がどんなに楽なことか。
考えるだけで、後悔する場面が何度も押し寄せる。
小学校、中学校、高校、大学、会社ー・・・。
どの場面も歯を食いしばって必死に自分を保ってきた。
周りの期待に応えるために必死に世界に食らいついてきた。
どうやら仮面と思っていたのは顔ではなく、後ろ足だったようだ。
二本失っただけで、自分はあっさりと今までの自分から剥がれ落ちてしまった。
世界に食らいつていた(口のようだ)が、世界に置いていかれないように、必死に駆けていたのかもしれない。
どうやら、自分は、後ろ足だったのかもしれない。
鏡通さないと見えない、本当を見られない部分。
*
一方、世間では社会の脱落者を作っては回る犯人を探すことに躍起になっていた。
「後ろ足切断事件」はちらほらと続いていたのだ。
しかし、後ろ足を切られた者はほとんどが死んでしまう。
後ろ足を切った瞬間に、馬のバランスを崩し内臓をつぶしてしまうことがその主な原因だった。
もちろん、精神的ショックによるものや、出血多量によるものもあったが、とにかく、すぐに「死」に直結してしまう。
染谷は悲惨な事件のたった一人の生き残りとして、警察もマスコミも沢山近づいてきたが、医師が「精神的ショックで話せる状態ではない」というと渋々引き下がるとか。
自分のことに手いっぱいで、この事件に無関心の染谷は、いつもどんよりしている空を見ていた。
*
病室からも、狭い星空を見ることができた。
あの日も、こうして星空を見ていた気がする。
残念なことに、ショックで少し意識がとんでいる。
それでも、そういえば、あの日みた空よりも、また少し、寒い方向の星空になった気がする。
なぞりたくなる星座が視界に映る。
病室の外では夜勤の看護婦が二人ほど、
カポ、カポ、カポ、
カポ、カポ、カポ、
カポ、カポ、カポ、
と歩く音がする。
相変わらずうるさいと思う。
そうだ、自分はどのような足音を立てるようになったのだろう。
染谷は狭い病室を歩くことにした。
ゴロゴロゴロ、
ゴロゴロゴロ、
ゴロゴロゴロ、
急誂えの車いすが少しうるさいぐらいだ。
足音がしない。
車いすにかき消されているからだろうか。
今度は、自由な前足だけ持ち上げておろす足踏みをしてみることにした。
カツカツカツ、
カツカツカツ、
カツカツカツ、
あのうるさく仰々しい足音ではない。
なんということだ!
後ろ足を失ったら、自分の望んでいた生活が手に入ったではないか!
もしかしたら、もっといい車いすを用意すればもっと静かに移動することができるのではないだろうか!
そう考えた瞬間、雲が晴れた。
さっきまで絶望的だったというのに、染谷の気持ちは途端に明るくなった。
さあ、退院したらどうしよう。
染谷は考えを巡らせるようになった。
窓辺により、定点の星を探す。
そのとき、ふと思い出した。
あの時も、星空を見ていた。
今も、星空を見ていた。
あの時ほどではないが、今も集中してみていた。
それでも、看護婦の足音をうるさいと思った。
あの時は、聞こえなかった。
さっき通った看護婦は二人で、
あの時は犯人一人だったから聞き逃した?
いや、自分の足音も聞こえていたから、犯人と合わせると二人。
今と同じ人数だ。
聞こえたはずだ。
足音が。
でも、
聞こえなかった。
だから、凶器の刃が鳴るまで気づかなかったのだ。
染谷の心は高揚した。
犯人は、もっと足のならない方法を知っている。
耳障りのこの世界を、閉ざしてくれる。
そんな気がした。
*
上半身は、人間。下半身は、馬。
一度は聞いたことがある神話の生き物の、繁栄した世界。
彼らの住みよい社会での、猟奇的事件。
「後ろ足切断事件」が世間のトップニュースであったころである。
起承「転」結
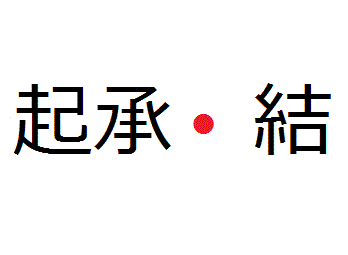
*
今まで神秘のヴェールに隠されていた被害者は語り出した。
いつ、どこで、どのように襲われたのか。
それでも、凶器のことと足音のことは黙秘した。
いや、社会にいる彼らは、染谷とは違い「音」に敏感ではない。
だから盲点であり、聞かれることもないので語ることが不要なのだ。
しかし、うっかりチェーンソーと言ってしまえば、あのうるさい凶器が唸るよりも前に足音を聞いたのでは、なんてなるかもしれない。
勿論、ならないかもしれない。
犯人が、誰で今も何を切ろうとしていようとも構わない。
警察にも協力するふりだけで、本当は情報を聞き出しているにすぎない。
世間の目に公に晒されたことをよしとするのも、犯人がもう一度来てくれるかもしれないという望みからだ。
出会う必要がある。
静かに移動する方法を聞き出すために、なんとしても自分が見つけなければならない。
願望が義務になってしまったことも分かっていた。
それでも、もうなんでもいいか、会いたくて会いたくてたまらなかった。
ひょっとしたら、震えていた。
*
ある日、車椅子を連れて公園へ散歩に出かけた。
好奇の目、哀れみの目を浴びても気にすることはない。
それ以上に、静かに移動できることが嬉しくて嬉しくて仕方なかった。
空は高く、風は凪いで、世界が やさしく包んでくれている。
清々しくて心地よくて幸福そのものだった。
幸福に感じないこともある。
カーブは昔以上にできなくなったし、些細な段差も障害となった。
不自由な点も増えた。
精神的に解放されただけで、体は今までと同じく縛られた身のように感じる。
そこで染谷は、この障害はどこまでついて回るのかを把握しようと考えた。
公園の片隅に存在する、雑木林に踏み込んでみることにした。
*
石の転がるこの土地に踏み入れるものも少ないのだろう。
自分以外の気配はない。
しかし、どこまでも続いている。
木が遠くまで視界を埋め尽くしている。
いつもの生活よりも多くの障害が足元にあるというのに、不思議とすらすら乗り越えていくことができた。
まるで呼ばれているように、足が進む。
まっすぐではつまらないので、曲がるのも気の向くままにした。
この雑木林はそう広くないと踏んでいたので、すぐに戻れると思っていたのだ。
だが、この様子では完全に迷ってしまったようである。
それでも不安はあまりなく、静かな足音を楽しみながら長い長い散歩をする。
*
どれくらい歩いたのだろう。
時計をしていないので、時間で測ることはできない。
歩数も数えていないから、距離で測ることもできない。
とにかくたくさん歩いた。
たくさんたくさん、歩いた。
*
やがて、雑木林は終わりを告げた。
視界が開けたのだ。
そこは雑木林の中にある、小さな小さな空間。
円形に、木が生えることを遠慮して出来上がった空間。
その中心に、ぽつんと木の家がった。
足は止まることなく家へ向かう。
そのとき、ふと不思議に思った。
なぜなら、歩き始めたときと今と、あまり陽の位置に変化がないような気がする。
それほど歩いていないのか?
確かに、疲労感もあまりない。
いや、そんなはずは・・・。
だが、寝ずに一日歩いていたとも思えない。
となれば、自分は思ったよりも進んでいないのか?
染谷は後ろを振り返る。
いや。
雑木林は暗い。
容易に向こう側をみることもできない。
*
「だあれ?」
雑木林に目をとめていると、傍らから女の声がした。
「あ、えと・・・」
彼女の存在にあまり驚きはしなかった。
むしろ、あみだくじを引き当てた気持ちになった。
「あなたは、だあれ?」
彼女はもう一度聞く。
「こんにちは、突然お邪魔してすみません。自分は、染谷と申します。」
俺はあらかじめ用意しておいたような言葉を発する。
「そめや、さん」
女は名を繰り返した。
「わたしのすがたに、おどろかないの?」
子供という年齢ではないが、しゃべる言葉はたどたどしい。
「驚かないよ、自分も、後ろ足がないからね。」
「それだけじゃないのよ、わたし。
おうまのからだもないの。おうまのあしでもないの。まるでおさるさんなのよ。」
今にも泣きそうな声で、女は布に包んだ自分の体の先端を見せる。
「素敵じゃないか!」
雑木林を震わせるほどの大声で言ってしまった。
彼女はびっくりした表情で見る。
「君は、足音を立てずに歩けるのだろう?」
「ええ、できるわよ。でも、みんなはなかまにいれてくれないの。」
哀しそうにほほ笑んだ。
美しいと思った。
*
彼女は自分の名前を知らなかった。
だけれど招き入れてくれた家のコップにはイニシャルの「 I 」が書かれている。
それについて問うたが、彼女はその記号の読み方すら知らなかった。
彼女の家には、後ろ足に必要な設備は全くなかった。
むしろ、しゃがむという行為を必要とする生活で、自分にはできないと落胆するばかり。
寝るときは地面に背中を預けるのだ。
我々の社会では、死んだときすら背中をつけることがない。
初めて会ったというのに「 I 」とはすぐ仲良くなって、たくさんお喋りをした。
また明日くるよ、と約束をしてその日は別れた。
*
「 I 」と自宅との行き来をする生活になって、どれくらいたつだろう。
世間で起こっていた後ろ足切断事件はすっかり終わっていて、犯人を勘ぐるマスコミはいなくなったし、警察もお手上げ状態だった。
僕は「 I 」が犯人だとは思えなかったけれど、もしそうだとしても驚きはしないだろう。
むしろ、「 I 」が犯人であってほしいと思う日もある。
生きてきた中で、彼女と会話しているときが一番幸せなのだから。
自分にとって特別な存在になってほしかった。
今日はどんな話をしようか。
本も持っていこうか。
実は。
この日が、僕と犯人が会う日になるのだ。
起承転(結)

*
何度も通い、何度も話をし、何冊も本を読み、「 I 」は学習をした。
僕は純粋な「 I 」が好きだし、「 I 」も今まで出会った仲間の中で一番話をよく聞いてくれた。
いつも帰るときにもの寂しそうにする。
しかし、なんとなく、夜をともに超えることが怖くて僕は自宅へ向かうのだ。
*
「この家は、ここの雑木林から作ったのかい?」
通いなれたある日、ふときになった問いを向けた。
「ええ、そうよ、すごいでしょう。このひろばをつくったときにね。あれ、ひろばをつくるためにきったのかしら、いえをつくるためにきったのかしら。」
どちらでも構わないだろう内容に首を傾げる彼女が可愛くて、ふっと頬が緩む。
「大変だっただろうね」
僕もいたら手伝ったのに、と悔しくなる。
「そうね、ちぇーんそーだけでよくがんばったわ。」
「え?」
うっかり、聞き逃してしまうところだった。
今、なんて?
チェーンソーだって?
*
心臓がどくん、とはねた。
*
「ねぇ、僕も君みたいになれるかな?」
「わたしみたいに?このちいさいおうちでしかすめないのよ。」
同じを嫌がられはしなかった。
ただ、おうまさんを捨てることは社会からの逸脱を示す。
彼女はそれを心配してくれているようだ。
「もっと静かに歩けるように、僕は君になりたいんだ。」
*
医者には問題ないと言われた。
後ろ足を失ったショックと見られたらしく、ひどく止められもしなかった。
僕はおうまの体を捨てる。
僕の半身は死ぬ。
いや、後ろ足を失った時点で「染谷」は死んだのだ。
ようやく彼は、埋葬されるのだ。
*
とうとう僕は、奇妙な目で見られてしまうようになった。
視線よりも足音を気にする僕は、今までにないくらい静かに歩けるようになった喜びで胸がいっぱいだ。
家に別れを告げる。
必要になるものを持って、扉を閉める。
雑木林へ向かう。
公園内を闊歩しているとき、投げかけられる視線をすべて振り払った。
だけど、雑木林に踏み入れるとき、無意識に振り返った。
なんとなく、鋭い視線を感じた気がする。
しかし、それは一瞬でもう気にならなくなった。
*
君と同じ姿をした僕をみて、君は困ったように微笑んで迎えてくれた。
今日から、君と、静かに幸せに暮らすのだ。
*
世間は、もう事件を覚えていない。
カポ、カポ、カポ、
カポ、カポ、カポ、
カポ、カポ、カポ、
雑踏の中に、男の後ろ足は紛れて消えた。
割愛部「後ろ足切断事件」
*
「後ろ足切断事件」の重要参考人が突如消えた。
最後に彼と関わったという医者の話では、支えづらいとのことから第二胴体を切り離す手術をうけたという。
しかし、その後通院予定だというのに彼が来る気配も、電話をかけても出ることもない。
不審に思い、警察に連絡したという顛末である。
*
「事件が解決できない根本的に、犯人がいないからだ。
つまるところ、この事件は「事件」として成り立っていない。」
と、論じる専門家や探偵、そして刑事でもいた。
それは全員、白旗を素直にあげられないプライドの高い者どもだと思う。
そしてまた逆に、燃えている変人も多い。
それはほぼ、暇を持て余している社会的地位の低い者どもだと思う。
*
重要参考人の染谷さんがいたからといって、「後ろ足切断事件」が解決するわけではない。
前向きに、犯人を捜すことを先決とする。
現在、最初の犠牲者から考えて半年。
最初の犠牲者が出てからわずか一か月の間に事件は集中し、27人の犠牲者を出した。
もう事件としては生きていない。
場所は都内。
閑静な住宅街、一人で歩くところを狙い後ろ足を切断するのだ。
凶器は何か。短時間で後ろ足を切断できる凶器。
人に気付かれることないー・・・。
音のない、存在。
ここで一つの仮定が立てられる。
犯人には、蹄がないものと言える。
だが、私は思う。
後ろ足がないのだ。
余計に足音を立てずに済む。
それで、寂しくなり自分と同じ境遇を作ろうと考えるのだ。
しかし、それで?
27人中26人が死んでしまう。
同じ境遇になれることがほぼ、ない。
寂しさはまぎれるのか?
この疑念は先ほどまで残っていた。
染谷さんが消えたことで、疑念も消える。
きっと犯人といっしょになったのだ。
お互い同じ、境遇になることができた。
寂しさをうめることができるようになったのだ。
犯人と染谷さんが接触したことにより、事件も終わったのだ。
まるで、生贄のように。
後ろ足のない存在は目立つ。
都内という限られた中で見つけることは難解ではなかった。
ここだ。
ここに魔物は住んでいる。
息を殺して、突撃のタイミングを見計らう。
*
*
*
*
*
*
不慮の事故により、後ろ足を失ってから世界は冷たすぎた。
同じ格好をしていた少女と公園の雑木林の中に家を作った。
私はもっていたマグカップを彼女にあげる。
まだ世界が嫌悪の目を向けていることすら気づいていない小さな女の子。
言葉もしらない女の子。
私の生きがいの女の子。
やさしい、女の子。
後ろ足の後遺症のせいで、余命は長くない。
悟ってから、彼女がこの後どのように生きていくのかがとても気がかりだった。
だから、動けるうちに新しい世話役を見つけることに尽力した。
自分が後ろ足を失って生きていることが「奇跡」と言われたのだ。
簡単になせるわけではない。
はずだった。
しかし、最初の挑戦で念願がかなってしまう。
その一人で終わりにしようか?
と2日間悩んだ。
いや。
それではいけない。
同じを求めることは至極道理だが、彼女に会わないかもしれない。
また、後ろ足を無くすことが目的であると世間に知られていいものか。
違う。
もっと、猟奇的な事件にする必要がある。
*
*
こっそりと忍び込むと玄関にチェーンソーがあった。
チェーンソーうるさい凶器だと思う。
予想から外れたものの、血の付いた刃物を目の当たりにすればもう疑うことはない。
*
*
玄関で音がする。
もう動ける気力もない。
突入が玄関からなんて、礼儀正しいんだなぁ、とぼんやり思う。
これで私に目が向けば、世間は彼女を疑わない。
これで私の役目は思った。
あとは彼女とあの男が接触していることを祈るがー・・・
最初の犠牲者である彼が見事「手術」に成功したのだ。
知り合いではないが安心感与えてくれる。
私は静かに目を閉じようとした。
*
「なぁ、お前を捕まえて、警察に引き渡して。
あるなら報奨金とか、世間の目とかよぉ。
俺はそういうのをほしいから、お前、もう少し目を開けろ。」
突撃してきたのは、警察ではなかった。
薄汚れて、少し匂い男だった。
おかげで、死ぬタイミングを逃す。
「遅いよ、死にそう」
頼りない声が細々と漏れた。
「いやいやいや、ちゃんとヤリマシタって言ってもらわないと。
俺、どう説明したらいいかわかんねぇじゃん。」
「玄関の、あれ持って行って、私の指紋でるし、血もついているし、きっと。」
ぽりぽり、と男は頭をかく。
フケが落ちてくる。
「じゃあよぉ最後に何かしたいこととかねぇ?
このままじゃ後味悪いじゃん。」
「それじゃあ」
*
彼女の願いは、公園の芝生の上で死ぬことだった。
晴天を見上げて目を閉じた。
後ろ足がないとこういう死に方が選べるのか。
俺も切断しようかな、と思いつつ死体と凶器を警察まで運ぶ。
*
獅子は馬を狩る


