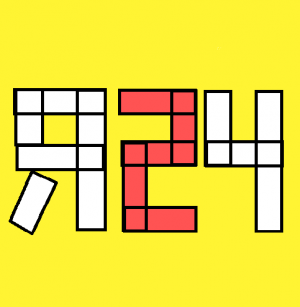39番目の乗客
深夜1時。
夜行バスの運転手である僕は、今、トイレ休憩の為に停車した高速道路のサービスエリアにいる。
12月の風は冷たい。
出発の時刻が近付いてきたので、僕は客席の方へ行って乗客の数を数える。
すると、38名のはずだった乗客が、39名いた。まさかと思いもう一度数え直した。しかし2回目も39になった。
外で待っていた相棒の運転手にそのことを言うと、
「ちょっと……怖がらせないで下さいよ。座席じたいが38席しかないんですから、39名のはずがないでしょう。先輩、図書館で長居し過ぎて、睡眠不足なんじゃないですか?」と笑った。
僕は大阪のバス会社に勤めている。
夜に大阪を出発し、翌朝に東京に着く。東京の宿泊所で寝て、その日の夜に東京を出発し、翌朝に大阪に着く。毎日がこの繰り返しだ。
東京の宿泊所は、ワンルームマンションで、そこを一人で使うことができる。
でも、僕はその部屋ではあまり眠ることができない。
だから朝10時頃に東京に着くと、宿泊所の近くにある図書館に行って眠たくなるまで本を読む。相棒はそのことを言っているのだ。
相棒の運転手は寝ている乗客を起こさないように、慎重な歩調で客席の方へ行った。
――しばらくしてニヤニヤと笑って戻って来ると、僕の肩に掌を置いて
「残念ながら、38名です」と言った。
「でも、規則ですから、先輩、もう一度数えてきて下さいね」とからかうように言った。
二人の運転手がそれぞれ乗客の数を数えて、その数が合わないと出発できないことになっている。休憩場所で乗客を乗せ忘れたまま出発しないように、このような規則がある。
僕はもう一度客席に行く。そして、慎重にゆっくりと前の席から順番に数を数えていく。
しかし、やはり、どうしても39名だ。
相棒が言うように、睡眠不足が原因なのだろうか……。
その時、一番後ろの一番奥の座席に座っていた乗客と目が合った。年頃の若い女性だった。
僕は何か用があるのかと思い、
「どうかなさいましたか?」と声をかけた。
すると女性は僕を見つめたまま、凍りついたように固まった。そして、恐る恐るといった感じで自分の人差し指で、自分の顔を指差して、
「見えるんですか?」と僕に訊く。
一瞬にして全身に鳥肌が立つ。体が硬直する。かろうじて浅く頷ことができた。
女性の隣の席で寝ている男性は、僕達の会話に気付かない。
よく見ると、女性の体は透き通っていた。
僕は確信する。彼女は幽霊だと。
どういうわけか僕にだけ見えて、相棒には見えなかった。
彼女は頬を赤らめて、恥ずかしそうに俯いている。茶色い長い髪が垂れて顔の両端を隠す。
僕の恐怖心はゆっくりと消えて行った。それは、彼女になんとなく人間味があったからだと思う。それに、以前どこかで会ったことがあるようにも感じたのだ。
僕は言う。「あなたがこのバスに乗っているのは、きっと何か理由があってのことでしょうね」。
彼女は「はい」と答える。
しかし、それ以上言葉が続かない。会話を嫌がっているというよりも、とても緊張しているように見えた。
僕はしばらく待ってみる。
すると、彼女が訥々と話し始めた。
「ついさっき、ベッドで眠ったはずでした。東京のアパートです。なのに、気付いたらこのバスに乗っていて……。たぶん、ここにいる私は、生霊(いきりょう)だと思います」
僕は確認する。「つまり、本当のあなたは東京のアパートで眠っていて、そこから抜け出した生霊が、今ここにいるあなた、ということですね」。
「ええ、きっとそうだと思います」
「何かに対するとても強い想いが、あなたをここまで運んで来たんでしょうね」
僕がそう言うと、彼女はまた頬を赤くした。僕はまた暫く待った。
彼女は一つ大きく息を吐いて、言った。
「……好きな人を、追って来たんだと思います」
眠っている隣の乗客をよく見ると、端正な顔立ちの若い男性だった。
彼女は大阪へ行ってしまう彼を追って、このバスまで来たのだろう。ならば、邪魔をしてはいけない。
「無粋なまねをしてしまいました。出発しますね」と僕は言って、運転席の方に戻った。
相棒には、自分の勘違いだった、と謝って、バスを発車させた。
――2時間後に停車した次の休憩場所では、39番目の彼女はもういなかった。
人間ばかり38名の乗客が眠っていた。
*
早朝、大阪の降車場所に到着した。
39番目の彼女に想われている彼は、降り際に、「ありがとうございました。お疲れ様でした」と笑顔で声をかけてくれた。
車庫でバスを洗車し、10時に大阪のアパートに帰る。そして死人のように眠る。
18時、目覚まし時計が鳴る前に、僕は眼を覚まし、シャワーを浴びて、服を着替え、テレビをつけて、スーパーマーケットで買ってきた惣菜と冷凍していたご飯を電子レンジで温めて食べる。
20時、東京に向かうべく、バスに乗り込む。
翌朝7時、東京の降車場所で乗客を降ろし、相棒とファミリーレストランで食事をする。
テーブルにつくと相棒が言った。「今日は図書館はやめて、しっかり寝てくださいね」
僕は彼の忠告に従った。
食事を終え宿泊所に入ると、シャワーを浴びてすぐにベッドに横になった。
しかし、その5分後――僕は、服を着替えて宿泊所を後にしていた。
その図書館は、古い木造建築で、異人館のような情緒ある建物だ。
僕は玄関を入る。
右側のカウンターには男性の職員が座っていた。
階段で2階へ上がる。
背の高い書棚がドミノ状に整然と並んでいる。客はまばらだった。
僕は棚と棚の間を端から一つ一つ順番に確認していく。
そして現代小説のコーナーで、一人の職員がカートで運んで来た本を書棚に戻していた。
昨日とは違い、髪を後ろで束ねていたが、 その人が、39番目の彼女であった。
彼女はすぐに僕の視線に気付き、こちらを向く。
目が合う。彼女は驚く。
僕は言う。「どこかで会ったことがあると思っていたんですよ」
彼女は嬉しそうに笑った。そして「一昨日はびっくりさせてしまって、すみませんでした」と照れた。バスで会った時と同じように頬が赤く染まった。
僕は少し言葉を探してから言う。
「彼、礼儀正しくて素敵な人ですね」
すると彼女はきょとんとして、「彼?」と首をかしげる。
「ほら、あなたがあの夜、追いかけて来た人のことです。大阪で降車する時に、僕に明るく声をかけてくれました」
彼女は虚空を見つめて考えた。そしてすぐに僕に向き直る。
「もしかして、私の隣の座席に座っていた男性のことですか?」
「ええ、そうです」と僕は答える。
すると彼女はぶんぶんと大きく何度も首を振った。そして言う。
「違います。私、あの方を追いかけてあのバスに乗ったわけじゃありません。全然知らない方です。私の好きな人じゃありません」
いつの間にか、彼女は両手で白い封筒を握りしめていた。
そしてそれを僕の前に差し出す。
「これ、読んで下さい」と彼女は言った。
僕は白い封筒を受け取る。
受け取る時に、僕の指が彼女の指に少し触れた。
39番目の乗客