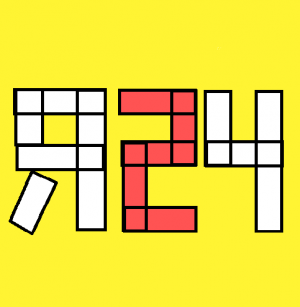分身
11月のある金曜日の夜、妻が家を出て行った。
最近の僕は、様々なことでトラブルを抱えていて、思い通りにならないことへの苛立ちが日増しに膨らんでいた。
苛立ちが堰を切ったのだ。
僕はテーブルの上の茶碗や皿を壁に投げつけて砕いた。
そして妻は家を出て行った。
暫くして、義父から「娘はウチにいるから安心するように」と電話が入った。
僕が、部屋の押し入れの中に、「もう一人の僕」を見たのは、その日から3日後の月曜日の朝だった。
もう一人の僕は、ほとんど物が入っていない押し入れの片隅に、両膝を抱えて丸くなって座っていた。裸だった。
襖を開けて、裸の男の姿を見つけたとき、僕は絶叫して、8畳の部屋の隅まで飛び退いた。そして相手を警戒しながら、部屋の中を素早く見まわして、武器になりそうなものがないかと探した。
しかし、その必要はなかった。
相手は全く動かなかった。しかし死んでいるのではない。呼吸に合わせて肩と背中が上下していた。
男は眼から赤い血の涙を一筋流していた。それが血だと断定する根拠はない。しかし、きっとそうだろうと思う。
俯いていたので、顔が陰になって全部は見えなかったが、短い髪型や、肌の色や質感、そして脇腹あたりにある大きな黒子によって、この男が僕自身だと気付くのに、長い時間はかからなかった。
「押し入れの僕」には、触れることができた。体温があった。夢だと疑う余地は何一つなかった。ただし、呼びかけても、揺すっても、全く反応せず、寝息を立てて眠っていた。
自分の寝顔を見たのは初めてだったが、想像していたそれと、大きな乖離はなかった。
血の涙は、絶えず流れているわけではないのに、凝固せず、いつまでも生々しい光沢を帯びていた。
少し冷静になると、時間が気になった。
部屋の掛け時計を見ると、7時半を指していた。そろそろ準備を始めないと、仕事に遅刻してしまう。
非現実的な出来事に遭遇したとはいえ、僕の生きる現実世界が一時停止したわけではない。
僕は「押し入れの僕」を毛布で包んだ。そして朝の準備を済ませ、家を出た。襖は開けたままにしておいた。
*
小雨が降る中、僕はバイクを走らせた。
国道沿いにあるコンビニに立ち寄る。
店内は数人の客しかいなかった。
僕が自動ドアを入ると、陳列棚の整理をしていた若い店員がちらりと僕を見て、何も言わずに目を逸らせた。
僕は突き当りの弁当コーナーで、幕の内弁当を手に取って、レジカウンターに置いた。
レジの中にいた年配の女性店員は、なんだかふて腐れた顔で、何も言わないで僕の顔も見ずに、手元の弁当のバーコードを読み取った。ディスプレイに450円と表示されたので、僕は財布から500円玉を差し出した。彼女はそれを受け取って、50円玉をかなり高い位置から僕の掌に落とした。まるで、自分の手が僕の手に触れるのを嫌がるように。
「愛想が悪すぎやしませんか? サービス業に携わる者として、恥ずかしいとは思いませんか?」
はっと我に返った時には、言葉はすでに空中に浮いていた。その言葉を発したのが自分であることに気付くのに、しばらくの時間を要した。
なぜなら、僕は今までの人生で、面と向かって相手を批判したことなどないからだ。
争いを避けて生きてきた。
人に嫌われないようにして生きてきた。
それなのに、今日はいったいどうしたというのだろう……。
レジの店員は、一転して怯えたような物腰になって、小さな声で何かを言った。
*
雨は一日中降り続いたが、仕事は概ね順調に進んだ。
ただ、いつもと違ったことが二つあった。
一つは、肩こりが消えていて、体が空気のように軽く、全身に滞りなく血液が流れているような感覚があったこと。
もう一つは、上司の指示に異議を唱えたことである。
退勤時間である18時ちょうどにタイムカードを押して、会社を出た。
「押し入れの僕」のことが気になって仕方がなかった。
雨に打たれながらバイクを駆った。
家に着き、蛍光灯を付けると、「押し入れの僕」は、押し入れの中にいた。
朝のまま、しっかりと毛布に包まって、やはり、赤い血の涙を流していた。
念の為、冷蔵庫の中やトイレ、寝室を見て回ったが、何かが無くなっていたり、動かした形跡はなかった。 どうやら、あの姿勢のまま身動きしなかったようだ。
「押し入れの僕」の姿を確かめ、幻ではないことを確信した僕は、部屋に腰を下ろすこともなく、家を出てバイクに跨り、国道を西へ向かった。
いくつかの交差点を曲がり、山道を走った。
そして出発して20分後には、妻の実家に到着していた。
僕は、ヘルメットを脱いで、門扉の傍らにあるインターホンを押す。
分身