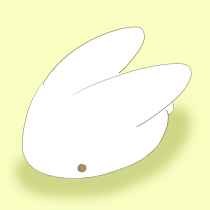ゼダーソルン 学歴社会 (後半部)
学歴社会 (2)
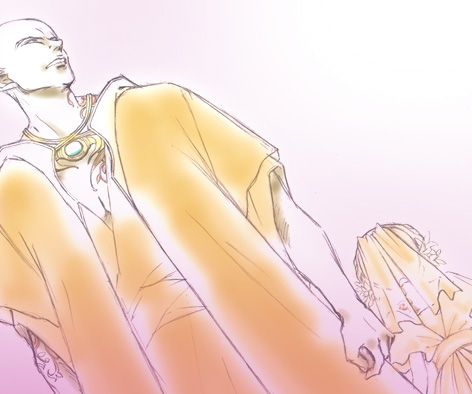
「この世は数え切れないほどたくさんの、パルヴィワンとよばれる非干渉世界、カンタンにいうと別世界のよせ集まりでできています。そしてふつう、1の世界から2の世界へいったりきたりすることはできません。たとえ物理法則がほぼおなじ条件にある世界どうしであったとしても、一度にひとつ以上の世界を認識できるほどの優れた知覚を持つ知性体はそういるものではないのです。ところがわたしたちの祖先は」
「シムという特異知性体で、世界をわたることができました。でしょう? 先生」
「ええ、そのとおり。わたしたちの祖先は全世界的に見てじつにまれな、一度にたくさんの世界を認識する特別な知覚と、世界間をわたる力『ゼダーソルン』を宿していたと伝えられています。古い文書によると、奇跡をも起こすことができたことから、別種族に神や精霊と崇められていたのだそうで」
「先生、神や精霊って? そんな言葉を聞くのははじめてです」
「そうね。アープナイムにはない言葉だから。意味は、ええっと、その文化や環境の法則では説明できない現象を引き起こす物体や生命をしめす総称、と考えるのが一番適当らしいんだけど、この説明はむつかしいわね」
「はい、先生。いくら大昔の、ぼくたちの祖先たちが特別な力を持っていたからって、子孫のぼくたちにその力が受け継がれていないんじゃ、なんの自慢にもならないってぼくのパパが言ってました」
「そっか。いまはこの装置をつかわなくっちゃ、だれも世界をわたれないし物も持ってこれないんだもんな」
「でも知ってる? エーヴィ・キッパーやトループのプロ選手がコマやなんかを思ったとおりの場所へ誘導できるのって、彼らがその力を受け継いでいるからなんですって」
「ウソだろ、そんなのはじめて聞いた」
「シムナイム宙空域に広がった伝染病にかかって全員が『ゼダーソルン』を失くしたんだ。そのあと生まれた子どもも『ゼダーソルン』はつかえなかったって。歴史の本にはそう書いてあったぜ」
「しずかにっ、しずかにしてっ! いいわ、 みんなよく知ってるようだから、この話は終わりにしましょう。では各自配られたタブレットのスイッチをオンにして資料を写して。装置のしくみと機能について説明するわ」
このとき、みんなが授業をもり上げてくれていて本当にたすかったんだ。なぜってそれはぼくがつい大声を上げてしまっていたからだ。迂闊、けど、あれは不可抗力だった。だってフィフってば、持ってたコマのひとつを宙へ放り投げると、そこから連続プラップで下のフロアへ誘導。最後にかなりの勢いをつけてノウプの生徒の額にぶっつけちゃってたんだから。
あわてたぼくは、でもみんなに気づかれないよう、できるかぎりの小さな声で必死にフィフを止めようとしたんだけど。
「ヘイキだって! どうせ、だれがやったかなんてわかりゃしないよ。あいつらペイルの生徒をバカにしてっから、こんな芸当できるやつがいるなんて思いっこないんだ。きっとペイルの生徒じゃない、ほかのだれかがやったって思うはずさ」
「いくら誘導がうまくったって、あんなオモチャのコマ、子どものほかのだれがつかうっていうんだよ! それにあの子、額に手をあてて痛そうにしてるじゃないか」
「エーヴィ・キッパーやトループのコマがあたったよりはずっと痛くないさ」
「痛くないスピードじゃなかったろ!」
なんていってるうちに、フィフはその手に残してたもうひとつのコマも宙へ浮かべて、はじきだしてしまった。
瞬間、一点に意識を集中することでターゲットをはじきとばす。
プラップとよばれる離れ技を自在に操るぼくらアープナイム・イムならではのおはじきあそび『グープ』。そしてその延長にある『サヤ』『エーヴィ・キッパー』『トループ』は、俗にプラップゲームとよばれる大人気のスポーツだ。つかう道具やルールにちがいはあるものの、だれもが気軽にプレイできる。ただしふつうは『できる』だけ。いくら宙に浮きやすくはじきとばしやすいコマをつかうからって、思ったとおりの距離や方向へきっちりはじくためには特別な才能や訓練が必要だ。ともすれば、フィフがやって見せた、一度はじきとばしたコマを再度はじいてだれかの頭にぶっつけるなんてのは、高度すぎて、思いつきで子どもができるような技じゃなかったんだ。けど、それでも。つかったのがグープのコマってんじゃ、だれだって大人がやったとは思わない。そのうえ。
「バッカ。おまえがうるさいから、はじく方向まちがっちまったじゃないか」
そう、フィフはコマの誘導をミスってた。もっと悪いことには、コマの行く先、一階フロアに置かれた展示物のまわりには、数人の観覧客の姿があったんだ。
止めなきゃっ、それがダメなら軌道修正を。
でも、そのころのぼくに、飛行中のコマを誘導できるほどの技術はあるはずもなく。
「ダメだ、人の群れに突っ込んじゃうよ!」
どうにもならない、そう思った。
ところが。
とつぜん、大きな手のひらがコマの行く手をさえぎったように見えたんだ。瞬間、コマがありえない方向へはじかれたような動きをした。そしてそれは驚くべき勢いで、もときた軌道を引き返し、見学用通路踊り場の柵のあいだをスルリと抜けて、ぼくの腹へと突っ込んだんだ。それは、まるで、ぼくをめがけて飛んできたかのようで。
「……ウソ」
ぼくにはこの出来事が現実とわかるのにすこし時間がいったんだ。
ところで例の手のひらには持ち主がいた。それは背が高くて丸刈り頭、黄色っぽい服に身を包んだ大人の男性のようで。顔を確かめたかったけれど、すぐとなりにいた、やっぱり黄色っぽいドレス姿の、たぶん女の子、が話しかけたのをきっかけにして、出入り口方向へと歩いていってしまったんだ。
「あんなに加速していたコマを」
あの二人は一体なんだったんだろう、そうぼんやり考えながらも、ぼくはひとつの結論を導きだした。
「プロだって難しい、これだけの長距離を一発ではじきかえしたってことは」
常人じゃないはずだ。
「なにボソボソ独り言言ってんだよ、キューン。ソッポむいてないでおまえもさがせって。見失なっちゃったんだからさ、俺のコマ」
「えっ、あっ」
コマがぼくの手の中にあることをフィフは気づいちゃいなかった。言うべきか言わないべきか。けど、言ったところで、さっきの出来事をきちんと説明できる自信がない。最悪ケンカになるかもしれないと思ったところでぼくは迷って。そんなとき、すぐ後ろで知らない声がしたんだ。
「やっぱりな。茶色の塊が見えたから、そうじゃないかと思ったんだ。フィフ、さっきのおまえがやったんだな」
ぼくらふたりはあわててふり返り、そうしてようやく気がついた。先生の講義に耳を傾けるクラスメイトたちとぼくらの横をすり抜けるように現れたのは深緑色の二列縦隊。ノウプの先頭集団がこの踊り場まで足を進めてきていたんだ。
ぼくらふたりに声をかけたのは、ぼくよりずっと背が高いノウプの男子生徒で、いかにも勉強できるのを鼻にかけたようすの、冷たい目つきをしたやつだった。額の端が赤くはれていたから、さっきフィフにコマをぶつけられたやつにちがいなかった。
「おまえのエーヴィ・キッパー好きはよく知ってんだぜ?」
フィフはキマリ悪そうに、一瞬相手をにらむと、そいつから手わたされたグープのコマを受けとって、しまりのない笑顔をつくった。
「へえ。さっき思った方向へはじきそこなって見失なっちゃってたんだ。もしかしておまえにあたったの? そりゃ悪かったな」
「ふん、まあいいさ。どうせおまえもあとすこしでウチに編入してくるんだ。たのしみはそんときまでとっとくさ。生意気な編入生への歓迎会のウワサ、おまえも知らないワケじゃないんだろう」
そいつは細い緑色の目で。おかげでこいつがフィフが言ってた、例のいやなやつ本人なんだとどうにか気がつくことができた。
だって編入してまだ四ヶ月しかたってない。それなのに完璧にノウプの生徒になじんで見えて、ペイルの生徒だったとわかるそぶりがちっともなかったんだから。そのうえフィフが編入した早々どうするって?
「どういうこと? まさかリンチなんて、ちがうよね?」
ぼくは答えがほしくって、目の前を横切っていくノウプの生徒たちの列に目をむけた。すると、ひとり、やさしそうな顔をした女子生徒がクスリとわらったのが目に止まったんだ。
「あっ、ううん。ただ、この装置はだれもがつかえる装置じゃないから」
ぼくの視線に気づいたその女の子は、あわててちっとも言い訳になっていない言い訳を返してくれた。するとその子のまわりにいた数人の生徒たちまでが立ち止まってぼくらをバカにしだしたんだ。
「ああ、そうそう。この装置は、アープナイムの教育機関の最高峰ローヴァーツ・ウィッツ・マーを終業して、最高学位を獲得したうえ一部のエリート職に就いてからでないと、使用許可証をもらえないんだったよな? って、こんな説明はペイルの生徒にしてもわかんないか」
「ウィッツ・マーの受験資格は、ぼくたちのいるノウプ・フォリイドか、私立学校のリシュワントの生徒でいい成績を上げた者しかもらえない。ぼくたちでさえ難関だってのに、問題外なペイル・フォリイドの生徒が見学にきてるなんて、おっかしいよなあ!」
このやりとりにまわりにいたノウプの生徒のだれもが一斉にわらいをこらえた。そしてそれがまずかった。なるたけなら事を荒立てずにこの場をやりすごそうと考えてた、そのぼくが、ついカッとなって連中に食ってかかってしまったんだ。
「そんな言い方ってないよ」
「キューン?」
「だってそうだろ。中等部へ上がるまでならどの学校の生徒だって、学力審査やテストの結果次第でほかの学校へ編入できるんじゃないか! だからみんな、ペイルの生徒だって、ノウプやリシュワントへの編入めざしてがんばって勉強してきてるのに!」
「それでも結局は七割が受験資格のないアークリイドかペイルの中等部へ進級するんじゃないか」
「なんだコイツ? フィフ、おまえの子分か? いいけど、おまえもノウプへくるんなら、あんまりペイルのゴミ共となれ合うなよな。バカがうつるぜ」
ここで。急に立ち止まっていつまでも進まないでいる先頭集団にヤキモキしたノウプ側の引率の先生が生徒たちに声をかけたので、連中はあわてて列を進め、ぼくらを通りこして通路を上がっていった。
「フィフ、なんでだまってたんだよ? さっきのは母さんの小言を聞き流すのとはワケがちがう! あいつらぼくらだけじゃなくて、ペイルの生徒全員をゴミだってバカにしたんだよ! そこまで言われてだまってたら、今度はバカなうえに臆病者だって言われちゃうだろう」
「うん。けど、悪い、キューン。いくら俺でも、あと数ヶ月で毎日顔をつき合わせなきゃなんない相手とケンカする気にはなれないんだ。それに、連中の言ってることまちがっちゃあいない。そうだろう?」
「だけど」
「なあ、キューン。おまえだって俺とおなじ編入組なんだぜ。まさかユッディルみたいに、ペイルのが居心地いいから進路変更しようなんてバカなこと考えてるワケじゃないんだろう? おまえだって、最後はノウプかリシュワント、そのどっちかなんだろう」
ぼくはフィフがとてもずるく思えて、けど。
「だったらおまえも俺とおなじだよ」
フィフにそう言われて、ぼくは混乱してしまったんだ。なんだか自分までがずるいような気がして言い返す言葉を見失った。急にフィフと目をあわせていたくなくなって。けど一刻も早くこの場から退場したい気持ちに駆られたのはフィフもおなじだったらしく、とたん、ぼくらは左右に分かれ、クラスメイトが集まる輪の端に移動すると、それからはおとなしくピビシュ先生の声に耳をかたむけたんだ。
ぼくらは校外授業が終わって科学館をでるまで、ううん、そればかりか、一ヶ月後の学力審査で高い評価をもらったフィフがノウプへ編入していくまでのあいだ、ほとんど言葉を交わさなかった。フィフがどんな考えでそうしたかは知らないけれど、ぼくとしては、クラスの人気者でたのもしい仲間と思っていたフィフが、本当は、あのときのノウプの生徒たちとおなじにぼくらを見下していて、一刻も早くぼくらからはなれようとしていたんだと思うと腹が立って、できれば顔も見たくなかったんだ。それでフィフが最後に、ぼくにも別れのあいさつをしたときには、
「ぼくはフィフとおなじじゃないよ。だってぼくはだれも見下してなんかいないんだから」
ぼくはフィフにそう言ってやった。
そのあとの数ヶ月、ぼくはワケもないのに必死で勉強にとりくんだ。たぶんノウプの連中にゴミ扱いされたぼくだって、がんばればすぐにもノウプへ編入できると信じてたし、フィフにそう認めさせてやりたかったんだと思う。けれど、そんな一時の勢いだけでなんとかなるほどノウプへの編入はあまくはなかった。なによりあんな性格の悪い生徒だらけの学校へ入ってまで、高学歴にこだわる気持ちが自分にないことに気がついたのが運のツキ。それからは日に日にやる気を失くして、いったんは急上昇した成績も、四年生に上がったときにはもとにもどってしまってた。
けど、だからこそ。ぼくは、ぼくなりに、自分の未来について真剣に考えるようになったんだ。
なぜって、それは。
アープナイムに生まれ、アープナイムから出ていくことが一生叶わないだろう、結局その程度の学習能力でしかないんじゃないかと思うぼくには、きっと死ぬまで学歴社会が重くのしかかる。その窮屈さは当時のぼくにも想像できて。だったから。その現実に押しつぶされてしまわないための対抗策が必要だと考えたからなんだ。
だったんだけど。
あれから二年。
今年で十三歳になったぼく、サン・シェ・キューンが、今日もあのときとおなじ制服の袖に腕を通すのは、いまだその対抗策に出会えずにいるからだ。
ゼダーソルン 学歴社会 (後半部)
物理好きな人ならなんとなくわかるかもと思うのですが、この物語は超弦理論をヒントに創作しています。
また、基本的な世界観は(数年前にとりあえず完成した作品を改稿して載せているので、はっきり覚えてない部分もあるのですが)ヒュー・エヴェットの多世界解釈(理系でないので概論を読んだにすぎませんが)を参考にしています。
もちろんファンタジーだし、子供が読んでもそこそこわかる物語作りを基本としているので、ずいぶん創ってしまってるのですが、そんなところも(あくまで軽い気持ちで)お楽しみいただければ幸いです。