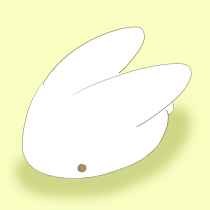ゼダーソルン 学歴社会 (前半部)
この章で主人公たちの年齢が11歳とありますが、見た目はリアル地球人でいうところの10歳前後で、学年的には小学校3~4年生あたりになります。
学歴社会 (1)

「淵に標されたロゴをだれか読めるかしら」
「パルヴィワン移送装置!」
「パルヴィワン移送装置です!」
「パルヴィワンへいって帰るのにつかうヤツだろ。これがそう?」
「これ、動かないけど本物なんだ。こわれてるだけで、五十年前はちゃんと作動してたって」
「あの文字はシムナイム時代の公式文書につかわれていたタヴィ・オン文字よ! ねえ、先生そうでしょう」
「おしゃべりはあとにして! そうよ、よく読めました。それによく知っていたわね。みんなの言うとおりよ。いま私たちが見下ろす先、特設見学路のまん中地下深くに埋め込まれた装置こそが、わたしたちアープナイム・イムの象徴、礎といっても言いすぎではないでしょう。現在このアープナイム文化圏内に百台ほどあると言われているパルヴィワン移送装置、その三世代前の現物です」
五歳から十八歳までならだれでも入学できる一貫教育制の州立学校、ペイル・フォリイドの初等部三年生だったときのこと。ぼくらのクラスは校外授業で街の科学館へ見学にいったんだ。
そこはこのあたりにくらす者なら一度は足を運ぶだろう、ちょっと人気の科学館。
本当なら、ごく少数の大人以外が目にすることは叶わない『パルヴィワン移送装置』の動力炉が旧式とはいえ展示され、一般公開されてることで、観光客にも家族連れにも定番スポットになった施設だったんだ。
もっとも。すでに家族で幾度となく足を運んできていたぼくらにとっては、いまさらすぎる場所だったから、とうぜん楽しめるはずもなく。けど、だからこそ。あの日体験したことは、いまでもしっかり覚えてるんだ。
あのとき、ぼくらがいたのは、科学館の正面玄関から入ってすぐのところに位置する大展示場。
施設のメインフロアでもあるそこは、四階天井までをふきぬけにしたもので。フロア奥から壁づたいに上の階へとつながるスロープ状の見学用通路には、途中いくつかの踊り場が設けられ、中でも館内一番人気の展示物、『パルヴィワン移送装置』の動力炉をまん中に埋め込んだ特設見学路上のふたつの踊り場は、その場で足を止める来館者用に簡易式展示物解説機やゲーム機も置かれた、装置を見学するのにはうってつけの場所だった。
そこでぼくら、男子十二人女子十二人の生徒を引き連れたクラス担任のピビシュ先生が、踊り場のひとつを陣どって、授業よろしく、装置についての講義をはじめたんだけど。
「はい、しずかにして。先生をかこんでこちらに集まって。みなさんも三年生になったことだし、すこしむつかしい話をしてもわかるわね。いいですか? それでは装置についての説明をはじめる前にすこしだけ、まだこの装置が存在していなかった、いまから千年ほどの昔、私たちがくらすアープナイム文化圏がシムナイム宙空域とよばれていた頃の歴史をふり返ってみることにしましょう」
先生の指示どおりにクラスメイトたちがピビシュ先生のまわりへ集まっていったけど、それにぼくは背をむけた。別に先生がきらいだとか、ふざけた態度をとって困らせたかったワケじゃない。ただ踊り場の隅に置かれた幼児専用の簡易式展示物解説機を起動させたばかりだったし、なにより、とつぜん話しかけてきたフィフのほうが気になってたんだ。
「キューン、なにしてんのさ」
ぼくを押しのけ、展示物解説機の天板部分にある四角いモニターをのぞきこむと、フィフは不思議そうな顔をした。とうぜんだ。だってぼくがタッチパネルを操作してモニターによびだしたそれは、いまのぼくらには似合わない、必要のないものだったから。
「これって『パルヴィワン移送装置検定クイズ』だろ。幼年部のガキ向けのやつ、おまえ、いまさらやるつもりなの?」
「ちゃかさないでよ、フィフ。ぼくだって本気でやる気なんてないよ。ただずいぶん前にやったきりだったから、すこしは変わってるんじゃないかと思ってさ」
「変わってた?」
「見てのとおり、全然さ」
どっちかっていうと目立ちやすい、まっ赤な色の髪を持つわりには行動はいたってふつうなぼくとはちがって。
濃い茶色の目と髪を持つ、見かけは地味な優等生男子タイプのフィフは、五ヶ月前におこなわれたクラス再編成ではじめていっしょのクラスになったやつで、おもしろくてあぶないあそびや大人の話をいっぱい知ってるクラス一の人気者だった。そのフィフに話しかけられたぼくはとうぜん悪い気がするはずもなく。それでつい、ピビシュ先生の話はたまに聞き耳を立てるくらいにして、いよいよフィフと話しこんでしまったんだ。
「ええっと、第4問目は。『パルヴィワン移送装置の出現は、私たち祖先らに生きる希望をあたえました。それから約四十年後、シムナイム宙空域に新たな社会制度と都市基盤が創られたのです。それはアープナイム文化圏と名づけられました』○か×か」
「答えは○」
「正解。5問目、『アープナイム文化圏誕生から数年。パルヴィワン移送装置をよりよく活用できる人材を育てるための制度が設けられました。それを検定試験制度といいます』これは×。正解は学校制度だ。本当、ちっとも変わってないのな。いくら幼年部の子どもがターゲットのクイズだからってそりゃないぜ」
「六問目は○。うん、やっぱりここはほかの科学館にくらべてサービスが悪いんだよ。対話式の移動ナビゲーターがあるのは一階の大展示場だけ、アトラクションコーナーだってない。お客を楽しませようってつもりがまるでないんだ」
「そういうところは、子どもは入場無料の州立科学館なだけあるよなあ、×。だから校外授業でつかうのに丁度いいんだろうけど。俺たちの学校だけってんじゃなく、このへんの学校ぜんぶの定番スポットだもんな、○。でも生徒は退屈、いい迷惑さ。みんなもムリにテンション上げて先生の話につき合っちゃあいるけど、本音は外の広場で遊ぶほうがずっとマシって思ってんだぜ」
「うん、ぼくなんかここへくるのは今日で十二回目。もう見たいものなんてなにもないよ」
「俺は四回目かな?」
「えっ、すくないんだね。×、いくらここが退屈ったって、小さいうちは家族と何度もくるのがあたりまえなのに。あっ、それじゃ、エーヴィ・キッパー観戦のが好きだったとか?」
やったあ! 全問正解 合格です
おめでとう! おめでとう!
あなたに装置の使用許可が下りました
合格認定カードを売店で提示すると
ラプンツール科学館特製パルヴィワン装置使用許可証章が受け取れます
気もそぞろで質問に答えていくうち、ぼくらは難なく全問クリア、最終画面までたどりついてしまってた。モニターにプレーヤーを称える言葉が映しだされ、機械の受け取り口から、おもちゃの合格認定カードが吐きだされた。そのようすを見守りつつ、ぼくらは深いため息をつかずにはいれなくって。
「エーヴィ・キッパーのがまだ夢も見れそうに思えたけど、結局んとこそれもパス。俺、現実悟るの早かったから」
「ぼくも初等部の三年生にもなったいまならわかる。学歴社会ってやつだよね。そんなことも知らずにこんな子どもだましのクイズにうかれてたころの自分がうらやましいよ。聞いた? ユッディルが進路変更したがってるの。編入組でいるのにつかれたから進級組にうつりたいって。フィフ、聞いてる?」
「キューン、あれっ! ほら、下のフロアの出入り口んところだ。やなのがきたぜ。ペイル・フォリイドに通う俺たちの天敵、宿命のライバルご一行様のおでましだ」
フィフがなんのことを言ったのかはすぐにわかった。思えばこのときぼくらは十一歳にもなろうかという年齢で。生まれて以来、毎日のように耳にしていた、学歴社会という言葉の意味が、段々と身にしみてわかってきてた頃だったんだ。
「あの列がそう?」
ぼくら二人は大展示場側の柵に張りついて、下のフロアをのぞきこみ、そしてぼくはフィフが指で示したとおりの場所に、ちょうど展示場内に入ってきたばかりのペイルの天敵、あの深緑色の集団を見つけることができた。
「ここからだとノウプ・フォリイド3461校が近いからそこの連中じゃないかな? けっこう大勢なところを見ると、ありゃ一学年全員できたんだろうな」
そうだったんだろう。なぜって、アープナイムにくらす子どもならだれだって一度は腕をとおしてみたいと思うにちがいない、大きな襟にあしらわれている金の紋章、スソの長い上着が特徴的な深緑色の制服に身をつつんだノウプ・フォリイドの生徒たちは、たったひとクラスだけできていたぼくらよりずっと大勢の、けど一学年全員にしてはすくなすぎる人数できてたんだ。体の大きさから見て学年はぼくらとおなじ、もしくはひとつ上なくらいに思えた。
「あれで一学年全部? ぼくら一学年の半分もいないんじゃないか。やっぱりだれでも入れるペイルとちがって、ノウプは生徒数がすくないんだな」
「おなじ州立学校でも、あっちはトップレベルの入学テストや定期学力審査を突破しないと入れない、エリート育成のための学校だからな。だからって、勉強できるのを鼻にかけて俺たちを見下すイヤミな連中さ」
そう言うなりフィフがしゃがみこんでリュックを開けたものだからおかしいとは思ったんだ。だけどそれがあんなことにつながるなんて、このときのぼくは考えつきもしなかったから。
「勉強だけじゃなく、運動も技術もぼくらよりずっと上だよ。けど、へえ、成績優秀で今度の学力審査でノウプへの編入も確実って評判のフィフでもそう思うの?」
「それが一足遅かったんだ」
「えっ」
「四ヶ月前の学力審査の結果がよくって、別のクラスから一人、ノウプに編入したのがいたろ。ほらっ、緑の細目で両親そろって高学歴なのが自慢のイヤミなやつさ。そいつの母さんと俺の母さん、知り合いなうえに仲が悪くって。母さんは俺がそいつに遅れをとったのが気にくわないんだ。そんで俺、このごろ家にいづらくってさ」
「なんだ。それならぼくんちもおなじだよ。となりに住むエウィワンって子が幼年部からノウプの生徒でさ」
「うえっ、そりゃ不幸だな」
「どうってことないよ。だって六年ものあいだ、母さんのキゲンが悪いとこっちもなれてきちゃうんだ。怒られても聞いてるフリしてほかのこと考えてたりしてさ。でもそれでいいんだ。ぼくの父さんがいってた。女って『世界が自分の思いどおりに回ってないと気がすまない生き物』なんだって。それでやったら他人を自分にしたがわせようともするってさ。だからそこを逆手にとって、いかにも服従してますって態度を見せればいい。それでおもしろいくらいうるさいのが半分に減っちゃうんだから」
「へえ」
「カンタンだからフィフィもそうすればいいんだよ」
「それは、うーん、すっごくいいこと聞いたとは思うけど」
「けど?」
「あきれた、おまえってずいぶんちゃっかりしたやつだったんだな。見た目がおとなしそうだから、いろいろ不器用なのかと思ってたのに。だったら俺のほうがずっとダメダメだ」
「なんで?」
「母さんのどんな言葉にも弱いんだ。カッコつけたがりだし、どっちかってぇと根に持つタイプだしな」
カバンの中をさがしまくったあとで、ズボンのポケットの中からようやくなにかを見つけだしたフィフは、得意そうにそれをふたつ指ではさんでぼくの目の前にかざして見せた。けど、フィフがそれでなにをどうしたいのか、ぼくにはまったくわからなかったんだ。だってフィフの指にあったそれは、はじくとピカピカ光る小さなカプセル型のオモチャのコマで。もちろんこれがアープナイム中の子どもに大人気のおはじきあそび、グープにつかうコマだということはすぐにわかった。けど、かりにも、校外授業に参加中のぼくらがつかうには場違いすぎるはずのものだったから。
それでも。フィフにはたしかなたくらみがあったんだ。そして、
「見てろよ、キューン」
なんて言ってニヤッとわらうから、ついぼくはだまってフィフのようすを見守ることに決めてしまった。するととつぜんボリュームが上がったみたいに、ピビシュ先生のよく通る声がぼくの耳をつきぬけた。そういや校外授業中だっけ、と思いだし、横目でようすをさぐってみると、ぼくの予想をうらぎって、授業はずいぶんなもり上りを見せていたんだ。
ゼダーソルン 学歴社会 (前半部)
グープのコマは…… コハルが挿絵に描いたのよりもっとカッコいいんだと思います。
ゴミかな?ってくらいにデザインの才能なくて本当、申し訳ないです。