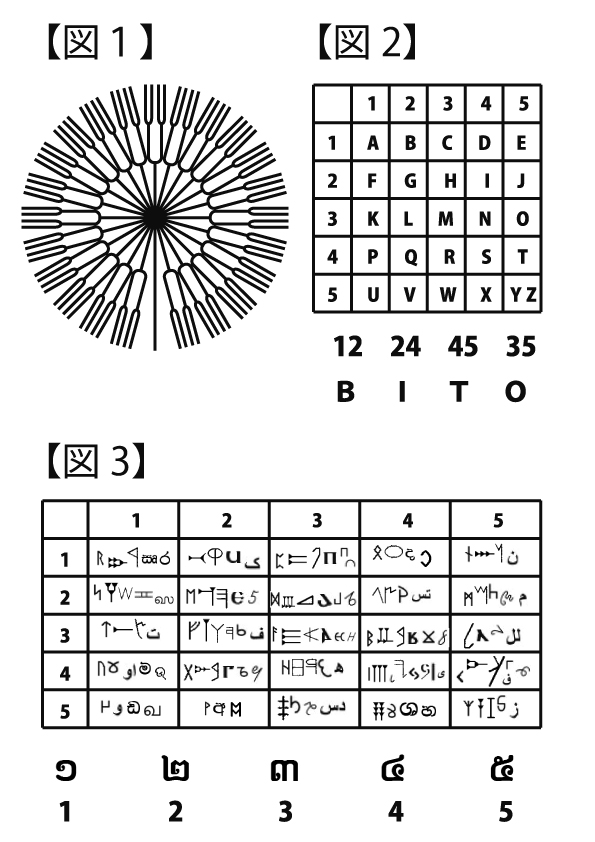
明日の朝、目覚めた時、世界はそこにあるか?
前篇
[一]
新宿駅西口、早朝。
多数の飲食店が寄せ集まった雑居ビルが立ち並ぶ裏通り。
汚れたアスファルトの上に、一羽のカラスが舞い降りた。
このカラス、夜が明けきらぬうちから随分長いこと街路灯の上に留まって、眼下を行き過ぎる人間たちの様子を慎重に伺っていたようだが、人の流れが途切れた僅かなタイミングを見計らい、路上に降り立った。
今、カラスたちにとっては、一日のうちで最も獲物が豊富な狩りの時間。速やかに餌を確保し、空腹を満たさなければならない大事な時間である。
都市に於いて、敵対関係にある人間と共生するひ弱な野生動物たちにとって、身の安全を図るための慎重さは大切な資質であるが、狩りに際しては長々と警戒に時を費やすわけにはいかない。もたもたしていれば、大口を開けたゴミ収集車がやってきて、貴重な獲物を根こそぎ持ち去ってしまうし、同族のライバルが同じ獲物に目を付けてしまうと、空腹を抱えたままで、命がけの空中戦を演じなければならない。
そんな目に遭いたくなければ、慎重さに加えて、いち早く行動を起こすための決断力も必要なのである。
ちなみに、このカラス、今が絶好のタイミングと決断したらしい。
もちろん、慎重さを捨ててはいない。路上に降り立ってからも、念のため一旦その場に立ち止まり、直ぐに飛び立てる体勢を崩さないまま、小刻みに首を振り動かしながら周囲に危険が潜んでいないかどうかを、何度も確認し直していた。
ここまでは都市に住む野生動物として、まずまず模範的な行動である。
最終の安全確認を終えたカラスは、迷わず手近にあるゴミ集積所に駆け寄ったが、そこには付近の飲食店から出されて間もない、新鮮な残飯が一杯に詰まったゴミ袋が山積みにされている。
まさに、最上の獲物の群れ。
毎度のことだが、獲物の上には決まって人間たちの手によって丈夫な緑色のカラス除けネットが覆い被せられているのだが、そんなものは大した障害にはならない。カラスは嘴と両方の足を上手に使って苦も無くネットを捲り上げると、予め街路灯の上から目を付けていたらしいゴミ袋の一つを簡単に引き摺り出してしまった。ゴミ袋は太く鋭い嘴によって瞬く間に引き裂かれ、和洋中が混じり合った残飯、果物や野菜の切れ端、魚の骨、千切れたポリスチレンやビニールなど、あらゆる汚物が路上に撒き散らされた。
狩りのタイミングを見極める決断は成功だったようである。
カラスは誰にも邪魔されることなく不要な汚物を取り除け、間もなく贅沢に食い残された骨付き肉の塊を手に入れることができた。
この一連の作業に要した時間は一分と少々。
感心するほどに素早く鮮やかな手際である。
しかし、動物も人と同じで事が上手く運び過ぎると気の緩みが出やすい。このカラス、無事に狩りを終えることができた安堵感と、食欲をそそる肉汁の臭いによって、注意力が散漫になり、警戒心を薄れさせてしまっていた。
カラスの意識は、獲物を如何に食するかだけに向けられていたに違いない。それまでとは打って変わった鈍間な足取りで、ろくに周囲を確認することもせず、肉を咥えたまま、二、三歩間の抜けた後退りをした。
そして、この束の間の油断が致命的なミスとなった。
非情な死がカラスを襲った。
せっかく手に入れたご馳走を味わうこともなく、
「ギャッ! 」
と、鈍い断末魔の叫びを路地に響かせた後にカラスは絶命し、アスファルトの上で仰向けに転がった。
転がる直前、カラスは反射的に飛び立とうとして、二、三度力無く羽ばたいたように見えたが、おそらくは即死であったろう。両の翼は半開きのまま、両足は宙に向けられ、折れ曲がって横を向いた頭部は潰れて原型を失い、黒光りするドロドロとした液体を滴らせていた。
カラスは何故、死んだのか?
いったい何者が、このカラスの命を奪ったのか?
銃声も聞こえず、得物が繰り出された気配も無い。
おそらく、石礫のようなモノがカラスの頭を打ち砕いたと思われるのだが、それは何処から、何者によって放たれたのか?
何者の仕業であったとしても、石礫の一撃で生きたカラスを即死させる腕前は見事と言うべきかもしれない。
間もなく、
ビルの隙間に潜んでいたらしい一人の男が姿を現した。
小柄で褐色の肌をした二十歳前後の若者。
彼が石礫を飛ばした者に違いない。
その身なりは貧しく、十一月も半ばだというのに、薄汚れた半袖のTシャツに所々擦り切れてシミだらけになったジーンズ、足には辛うじて原型を保っているボロボロのスニーカーを履いていた。
肩に掛かるほどの長さの黒髪はロクな手入れもされておらず、好き勝手な方向を向いて乱れ放題だったが、前髪が左右に分かれているので、何とか若者の人相は窺えた。
南アジア系の外国人らしく、目が大きく彫りの深い顔立ちをしている。
若者はカラスの死骸に歩み寄ると、それを片手で拾い上げ、ジーンズのポケットから使い古してクシャクシャになったコンビニのレジ袋を取り出し、その中に放り込んだ。
そのまま、足早に路地を去っていってしまったのだが、その後ろ姿は、まるで猫科の肉食獣が仕留めた獲物を持ち去っていく様に似ていて、奇妙に印象深かった。
とにかく、アッと言う間の出来事、唖然とさせられる早朝の出来事だった。
「何なんだ、あいつは? 」
尾藤は、ゴミ集積所の真ん前にある雑居ビルの一階、カフェ&バー「クアーク」の窓際のカウンター席に腰掛けて、目の前で起こった一部始終を茫然と眺めていた。
「ああ、食うんですよ。」
カウンターの中で、B5サイズのタブレット型情報通信端末を片手にダウンロードしたばかりの朝刊を読んでいたマスターが、徐に顔を上げて答えた。
「食う? カラスを? 」
「ええ、奴らは何でも食うのよ。」
マスターは再び朝刊に目を向けながら、事も無げに言った。
尾藤は吐きそうになった。
ただでさえ昨夜の深酒が祟って胃袋が捩じられるような不快感に苛まれているのに、カラスを捕まえて食うなどという薄気味悪い行為を、うっかり頭の中で映像として思い浮かべてしまったのだ。
胃の中に残っていた色々なモノが逆流しそうになるのを必死で押し止めた。
「それって、マジの話? 」
「マジよマジ。近頃のホームレスやスコッターは野性的な奴が多いのよ。ああいう手合いはカラスだけじゃない、鳩や鼠、犬や猫も片っ端から捕まえて食うよ。酷い悪食ね。」
マスターは、そう言いながら朝刊を読むのをいったん中断し、鼻に引っ掛けていた安物の老眼鏡を外してポロシャツの胸ポケットに入れた。
只今、時刻は五時三〇分。
ちなみに日付は一一月一九日、火曜日。
終夜営業を終えたばかりの二〇坪ほどの広さの店内に他の客はいない。アルバイト店員たちは始発電車の時刻に合わせて帰宅してしまっていた。入り口には既に「準備中」のプレートが掛けられているし、店内の片付けも掃除も終わっていて、ボックステーブルの上には逆さになった椅子が並んでいた。
後はマスターが一人で、酔い覚ましのコーヒーを飲んでいる我儘な常連客に付き合って時間を潰しているだけだった。
この風景、「クアーク」では良くあることなのだろう。
尾藤に対するマスターの態度は慣れた様子で、特に迷惑そうな素振りは見られない。
もっとも、普通のお客に対するような気遣いをするつもりも無さそうで、カウンターに放置しながら時々声を掛けてやるぐらいの対応しかしていない。
唐突に、
「あれ? 尾藤さん随分と気分悪そうね? お酒は程々にしないと駄目よ。コーヒー、もう一杯飲むかな? 」
などと言って尾藤のカップを取り上げ、サイフォンの底に残っていたコーヒーを残らず注ぎ込んだのも、サービスのつもりでは無さそうである。きれいに整理整頓されたカウンターの中で、たった一人の居残り客のせいで、いつまでも片付けられずに残っているサイフォンが目障りだったに違いない。
だから、残っていた中身を尾藤のカップの中に処分したということらしい。
しかも、無理矢理注がれたコーヒーは、カップの縁を超えて受け皿に溢れ出ていた。
「はーい、大盛りコーヒーどうぞ。」
マスターは、南米系メスティーソ特有の浅黒く派手な目鼻立ちと太い眉毛で整えられた顔に愛想の良い笑みを湛えながら、尾藤の前にカップを置いた。
「ど、どうも。」
尾藤は一応礼を言った。
二杯目のコーヒーを飲みたいとは思っていなかったのだが、勝手に注がれたことに文句は言わなかった。胸のムカつきを抑えるには丁度良いかもしれない。
(しかし、飲み辛い入れ方しちゃって・・・ )
表面張力で盛り上がったコーヒーを溢さずにカップを持ち上げるのは難しいので、テーブルに置いたままカップの淵に口を近付けてズルズルと音を立てながら一口啜った。
(不味っ! )
残りモノのコーヒーは生温くて、焦げたような味がした。
却って胸焼けが助長されそうな味と匂いに、それ以上飲みたくないと思ったのだが、閉店後に好意で付き合ってくれているマスターに申し訳ないので、我慢して少しづつ喉に流し込むことにした。
ところで、
「最近多いのかな? ああいう連中? 」
尾藤は空になったサイフォンを洗っているマスターに声を掛けた。
先程のカラスの一件は衝撃的過ぎて、なかなか頭を離れそうになかった。
まったく、朝っぱらから不気味な記憶が残ってしまったものだ。
マスターはサイフォンの水を切りながら、
「多いよぉ、特に新宿や池袋はね。どちらも元々ホームレスは多かったけど、ここ一〇数年で外国人のホームレスやスコッターがスゴク増えたのよ。奴らジプシーみたいなもんでね、日本人のホームレスよりも随分と大胆な生き方してるのが多いみたい。スリや泥棒はもちろん、ああやって街の中で狩りみたいなことまでするんだから迷惑だよねぇ、気味が悪いよねぇ、困ったもんだよねぇ。」
と言って、眉間に皺を寄せながら首を左右に何度も振った。
「うーん、そう言われてみれば・・・そうかな。」
一〇数年前と言えば入国管理法が改正されて以降のことだろう。
日本政府が少子化による労働力減少に対処するため、二一世紀初頭には総人口の一%に満たなかった外国人労働者数を五~一〇%という欧米並みの比率に増やそうという意図のもとに行った移民政策が実施されてから、確かに巷では外国人が目立つようになった。
マスターの言うように、近頃は野宿生活者の中にも外国人の姿を見掛けるようになっていたのだが、さすがに街中でカラス狩りをするような大胆な奴に出会ったのは初めてのことだった。
「あんな甘っちょろい法律を作ったのが悪かったのよ。いくら労働力が欲しいからってさ、何でもかんでも受入れ過ぎたのよ。」
心情的排外主義者を自称するマスターは、いかにも腹立たしいという口調で言った。
ここで、ちょっと奇妙というか、マスターも実は南米コロンビア出身の外国人であるところが面白い。但し、マスターが日本にやってきたのは二〇年以上前のことで、入国管理法改正よりも遥か以前のことなのだが、それは彼にとって非常に重要な境目であるらしかった。
マスターは、ここ一〇数年で日本にやってくる出稼ぎ系の外国人には非常に手厳しい意見をする。
曰く、
「大した目的意識も無く、予備知識も持たず、満足に言葉も覚えず、ただ仕事にありつきたい、金を稼ぎたいという安易な欲望のままに来日する、ロクでもない奴ら。」
なのだそうである。
かなり偏見に満ちた乱暴な意見だが、その気持ちは分からないでもない。
来日前から必死で日本語を勉強し、来日後は様々な資格を取るために夜学に通い、労働条件の過酷な外食産業で地道な勤め人を続けて永住権を取得し、四〇歳を過ぎた頃に脱サラして、自分の店を持つに至ったという苦労人にとって、安易な出稼ぎ気分で楽々と日本にやってくるような外国人たちは皆が不良に思えるらしい。
「人手が欲しいってのはわかるよ。日本の人口減ってるからね。でもね、尾藤さんも思うでしょ? アジア、アフリカ、それに私の故郷の南アメリカ、どんどん日本にやってきて住み着いてる。もう新宿なんてさ、時々何処の国だか分からなくなることもあるぐらい外国人だらけよ! もちろん真面目に働いてる外国人も多いけど、ホントに不良が多いじゃない! 奴らのせいで治安は最悪よ! スリや泥棒、強盗なんかも多いし、暴力団なんかと結び付いて人身売買や麻薬の密輸してる奴も大勢いるのよ。犯罪者とまではいかなくても、マナー守らない、街汚す、法律分かってないから無視する。そんで、仕事は長続きしないとか、何年経っても日本語覚えないとか、信じられないホントに! 」
若干ヒステリー気味だが、この手の話を始める時のマスターは、決まって鼻息が荒い。
さっきまで尾藤を無視して一人静かに新聞を読んでいたのが嘘のように、よく喋る。
そんなマスターに、尾藤は付き合いで相槌を打ってはいた。
しかし本音では、外国人が増えたからと言って特に反発心など持っていないし、あまり移民問題に興味が無いので、けっこう面倒臭いなと思いつつ聞き流している。
今時、世界中の大都市に多国籍多人種が混在するのは当たり前との認識があるし、東京がニューヨークやパリのような国際色豊かな街になるのは良いこととも思っている。
そもそも、日本の治安が悪くなったのは決して外国人のせいというわけではない。二一世紀に入って以降、入国管理法改正以前、既に日本の治安は悪化の一途を辿っているわけで、警察の犯罪検挙率も全国的に著しく低下しており、その原因を求めるならば不景気やら失業率の上昇やら様々であり、決して一つではない。
マスターの意見は偏り過ぎだと思っている。
だが、ここで異論を挟んで議論するつもりは無い。
二日酔いの頭と胃袋を抱えて、そんな気力も体力も残っていない。
だから、話の腰を折らないように大人しく同意したフリをしながら話を聞いていた。
「だいたい、真面目に働く気の無い奴らが多すぎるのよ。故郷で甘っちょろい夢みたいなことばかり妄想して、ロクに勉強も準備もしないで、勢いだけで日本にやって来たら、世の中そんなに甘くなくって、現実とのギャップで無気力になって、贅沢言わなきゃ仕事なんて沢山あるのに、地道に考えることができなくなっちゃってね。その挙句の果てに不良になるか、さっきの奴みたいにみたいに街を徘徊して食いモノを漁ったりするケダモノに落っこちてしまうのよねぇ。」
これも、一面的過ぎる見方だと思う。
そもそも外国人労働者達は、一部の高学歴者を除くと殆どが専門知識を持たず、日本語の理解力に乏しい者ばかりなのは事実だったが、そんな彼らを受け入れると法律で決めたにも関わらず、日本国内には語学や文化を伝えたり、職業教育を施すための機関が絶対的に不足しているのである。
その結果、彼らは低賃金労働者として扱われ、劣悪な職場環境で働かされるケースも多いらしく、都市部に於いて最低所得者層である彼らが居住する地域は無国籍スラム化し、そのスラムにさえも住めない者たちは、本人の意に反して野宿生活者に陥らざるを得ないというのが実情だろう。それに、数十年に渡って経済的な不安定期が続いている日本では雇用に対する需要供給バランスが安定しないため、これも多くの外国人失業者を生み出す原因になっている。
この現状、誰が悪いのかと問われるならば、尾藤は明らかに日本政府の政策の落ち度であると答えるべきだと思っているのだが、マスターは違う。
「正直言って、あんな奴らがいるおかげで、我々のように真面目に働いている者まで同類扱いされて、世間の風当たりが悪くなるのよ。外国人はみんな一緒だと思われちゃうのよ。ホント、腹立つね! 」
毎度のことながら、彼はこれを強く言いたいらしい。
「わかるでしょ尾藤さん。私は何年も前に日本に帰化しているし、奥さん日本人だし、法律はキチンと守ってるし、税金だって町会費だってちゃんと納めてるのよ。それに、お正月には奥さんや娘を連れて初詣に行くし、盆踊りにも行くよ。靖国神社のお祭にも行ってるんだからね。日本人と全く一緒なのよ! 」
話の内容に個人的な主張が加わり、大分感情的になり始めたので、このまま続けさせたら、かなり鬱陶しいことになりそうだと思う。マスターの憤りは察せられなくもないが、適当に打ち切るタイミングを見つけなければ何時間でも付き合わされかねない。
「おおっと、そろそろ帰って風呂入っとかないと仕事に遅れるな。」
尾藤はワザとらしく腕時計を確認し、半分ほど残っていたコーヒーを無理矢理喉に流し込んでから、椅子の背凭れに掛けていたジャケットを手に取った。
「なんだ、もう帰るの? 」
マスターは話の腰を折られて不満顔をした。
「マスターだってさ、そろそろ家に帰らないとね、娘さんを学校に送って行けなくなるでしょう? 長々と付き合わせてゴメンねぇ。」
「えっ? も、そんな時間? 」
マスターは背後の壁に掛かった時計を振り返って時刻を確認した。
時計の針は六時少し前を指していた。
小学生の娘の送り迎えがマスターの日課と聞いている。
子煩悩な彼の気を逸らすには娘の話を振るのが一番効果的だった。
「それじゃ、ご馳走さま。」
尾藤は勘定を置いて席を立った。
「またのお越しをお待ちしてまぁす。」
マスターの送り言葉に片手を振って応えながら、尾藤は店を出て新宿駅に向かった。
自宅は中野なので新宿からならタクシーで帰っても良かったのだが、既にJRが動いている時間帯では無駄使いをするのが何となく憚られる。
(家に着いたら七時近くになっちゃうな。)
もう眠る時間は無くなってしまったが、せめて風呂にでも入って酒を抜いておかなければ、今日の仕事に差し支える。
(少し急がなきゃ。)
尾藤は早足で歩きながら、上着の内ポケットから鮮やかな赤白ストライプの柄が入った一五センチほどの長さのスティックキャンディを一本取り出し、透明なビニール包装の先端を破いて中身を押し出しすと、歩きながら口に含む。
このキャンディ、明らかに日本人向けの商品ではなく、まるで砂糖の塊りを舐めているような、ただ猛烈に甘いだけで何の捻りも無い味の代物である。
だが、近頃の尾藤にはお気に入りの品だった。
半年前に煙草を止めてから、どうにも口の寂しさに耐えられなくて、飴やガム、タブレット菓子など散々試していたところ、たまたま輸入雑貨店で購入した派手な色のスティックキャンディに嵌ってしまい、今では箱買いし、外出時は数本を携帯するほどの嗜好品になっていた。
尾藤に言わせれば、決して美味しくない所が良いらしい。
「煙草の代用品として嗜好するには、日本製の飴やガムは美味し過ぎて味覚を刺激し過ぎる。まるで、煙草の代わりにケーキを食べているようなものだ。煙草と同じ用途、同じレベルにあって、惰性で何となく口に入れるモノの類は、単純な味で多少不味いくらいが丁度良い。」
それでこそ煙草の代わりになるのだと尾藤は言う。
糖分の過剰摂取にならないかどうかの心配を除外すれば、取り敢えず尾藤の喫煙は止まったのだから、このスティックキャンディとの出会いは成功だったのかもしれない。
近頃は、キャンディに対する尾藤の思い入れが過ぎている感がある。
「飲み過ぎにも利くんだよな。」
などと言って、こうして今も舐めている。
酒で麻痺してしまった舌を、その猛烈な甘さで一気に覚醒させてくれるのだと言うのだが、この意見に対する周囲の賛否は様々であった。
尾藤に勧められるがままに実行した結果、気分を悪くしたり、嘔吐してしまった者もおり、その評判は決してよろしくない。
それにしても、大の男が一人でスティックキャンディを舐めながら街中を歩く姿は美しくない。
アンバランスが行き過ぎて、少々不気味な絵に見える。
特に、ここ早朝の新宿では擦れ違う人々が怪訝そうな視線を送ってくる。
しかし、尾藤はそんなことを意にも解さず、誰に遠慮することも無く、スティックキャンディを舐めながら平然と道を歩いていた。
こうしたところ、尾藤は妙に大胆な男である。
ところで、通勤時間帯には未だ早いはずだが、既に新宿駅を出て街へと散らばる人々の流れが徐々にできつつある。
その流れに逆らうように歩いていると、道すがら擦れ違う人々の顔が目に入る。
(うん、確かに新宿界隈は外国人が随分と増えたかな。)
擦れ違う三人に一人は外国人。日本人と見た目が変わらない東アジア系の者も混じっているだろうから、もしかしたら周囲を行き過ぎる人の半分近くが外国人かもしれない。
(マスターが日本に来たのは約二〇年前か。俺は未だ子供だったが、あの頃は、こんなじゃなかったよな。)
いつの間にか、東京は国際色豊かな街に変わってしまっていた。
入国管理法改正以降、毎年万人単位の外国人が日本にやってきて定着しているのだから当り前のことなのだが、この変化は決して急激なものではなく一〇数年という長い時間をかけて極めて緩やかに進行し、辿り着いた結果だった。
この結果について、二〇年前の街の風景を切り取って現在の風景と比較するマスターのようなタイプの人々にとっては昔を回顧し現在を嘆くためのネタになるらしいが、多くの日本人にとっては気に留めるほどもない微かな日常の変化の積み重ねによって慣らされてしまった現実であり、既に深く考えたり、憂えたりすべき事柄ではなくなっている。
これが、二一世紀半ばの東京なのだ。
ちなみに、変わったのは人間の数だけではない。街の外観や機能も大きく変化した。
オフィス街や繁華街の中に教会やモスク、シナゴークを見掛けるし、ハラールやカシュルートの専門店はもちろんのこと、世界各国の生活習慣に合わせた食料品や衣料品を扱う店が増えた。道路標識や各種インフォメーション、商店の看板には様々な国の文字が列記されるようになっており、
(昔は、日本語以外は英語、中国語、韓国語ぐらいだったはず。)
それが今では、スペイン語、ポルトガル語、フランス語のインフォメーションは当り前で、所によってはインドやアラブ系の文字看板も頻繁に見かけるようになった。新宿や渋谷、池袋などの繁華街は、街を部分的にフレームに収めると、何処の国なのか分からなくなるような場所が多い。
(でもねぇ、これって決して悪いことじゃないと思うんだよなぁ。)
国際色豊かな東京の雰囲気は決して嫌いではない。
かつて、日本人主体で築かれ育まれた東京という街は、モノトーンで塗装された、匂いの無い、無表情で、行儀の良い、整然とした街だった。そんな東京が人種の坩堝となり、多種多様な文化が複雑に混じり合い、錯綜し始めたことによって、街には派手な色彩が生まれ、それまで嗅いだ事の無い新たな匂いが漂い始めた。時には目に痛い色彩もあるし、鼻をつまみたくなる悪臭も混じっていたが、それらは日本人がひたすら抑制し続けていた人というイキモノが本来発する体臭、つまり旺盛な生命力の現れではないかと思う。
確かに異文化との共存は混乱をもたらすことも多く、日本人と外国人、宗教や慣習の異なる外国人同士の社会的トラブルは常に各種報道メディアを賑わせる状況にある。だが、それを許容することができた者にとっては、現在の東京は活気に満ち溢れ、解放感と心地良さを感じられる魅力的な街であるはずだった。
しかし、回顧志向の者たちにとっては違う。
彼らは、これを無秩序、混沌、破壊、時には悪徳とまで呼ぶ。
いつの時代においても変化を望まない者がいるのは致し方ないし、古き日本文化の継承者や精神の語り部となる人々は必要である。彼らの存在によって保たれている道徳や秩序もあり、その口から出る批判は傾聴すべきことも非常に多いとは認めざるを得ない。
果たして、新旧いずれの状態を良しとするか、空論は常に戦わされている。
だが、その間も東京は日々変化を積み重ねつつある。
もはや誰にも止めようのない事実だった。
そんな東京で暮らす約二千万人のうちの一人である尾藤だが、
(おかげさまで、こっちは商売繁盛するわけなんだけどね。)
などと、常々思っている。
尾藤の商売にとっては、外国人が多かろうが少なかろうがどうでも良いことであり、多少の社会の混乱は歓迎すべきことであったりもする。
尾藤は調査員である。
フルネームは、尾藤 誠(おどう まこと)。
調査員とは、いわゆる私立の探偵。
JR東中野駅付近に小さな事務所を構え、その仕事の大半は浮気調査と人探し。
時々下請けで企業絡みの信用調査、裁判の証拠集め、警察絡みの仕事もする。
年齢は三四歳、調査員としてのキャリアは一〇年以上でベテランの部類に入る。
三年前に独立して事務所を構えたが、常勤スタッフは自分一人だけで、他に社員を雇うほど仕事の拡張をしようとはしない。調査員としての腕は悪くないし実績もあるので、スタッフを増やして事務所を拡張すれば多くの仕事を引き受けられ、儲からないはずはないのだが、この男は欲が薄いのか小ぢんまりとした現状に全く不満を持っていなかった。
刹那的と言うほどでもないが、人生無理せず、ほどほどに過ごすことを良しとするタイプである。日々の生活に困窮すること無く、適度に遊び歩けて、事務員兼助手として雇っているアルバイト一名に月々の給料が支払えれば、それで十分に満足できるという男だった。
特別な思想や信仰は持たず、政治的な志向も無い。
もちろん人種や文化に対する偏見は無いし、そういう議論に興味も無い。
仕事に影響の無い範囲で人並みの正義感や倫理観、道徳観を持ってはいるが、理想を抱えて社会を論じるようなことはしない。
いつでも何処でも、目の前にある現状を受け入れることができ、適当に折り合いをつけて、居心地の良さを見付けられる柔軟な男、いや気楽な男と言えるだろう。
だから、先に述べた現状や変化にも、常に好意を持って接することができるわけで、今時の東京向きの男と言える。
新宿駅西口の改札を通過し、未だJR中央線の快速電車が動いていないので、三鷹方面行き各駅停車のホームに立った頃、スティックキャンディの最後の一欠片が口の中でボリボリと音を立てて噛み砕かれた。
ホームの時刻表を確認すると、今し方高尾行きの電車が出たばかりなので、次の電車が来るまでには一〇分ほどの時間がある。
(んじゃ、もう一本、舐めても良いかな。)
そう思ってキャンディを取り出そうと懐に入れ掛けた手が止まった。
不意に視界の中に違和感を感じたのだ。
この時、尾藤は何処か特定の場所に視線を向けていたわけではない。見慣れた新宿駅のホームの何処にも、今更意識を留める場所など無いので、視線はフラフラと宙に漂い、視界は漠然としていた。
そんな、何を見ているわけでもない無意識の中に違和感が生じていた。
二、三度瞬きをしてから、今度は意識的に辺りを見回してみると、違和感の原因が異物感であることがわかった。
目に映る映像の中に異物が混入している。
その異物は、個体、物体ではない。
薄黒い靄、空気中に浮かぶ染みのようなモノ。
周囲にある空間に、立体的な染みが見える。
ホームや線路の上、頭上に掛かる屋根の内側、染みは其処彼処に見える。
近場だけではない。
屋根の隙間から見える空、隣接する駅ビルの壁にも染みが浮かんでいる。
(悪酔いしたかな? )
キャンディを取り出すのを止めて、両手の指で目を擦ってみたが消えない。
(これは、目のせいじゃないな。)
目の向きを変えても染みはついて来ない。
染みは位置を変えず、特定の場所に張り付いたように留まっている。
(おいおい! 目じゃなきゃ、頭がイカレてしまったか? )
幻覚を見ているのかも知れないと思った。
そこまで酔っているという自覚はなかったが、深酒しているのは間違いないわけで、酒の毒が脳に悪影響を与えている可能性を否定する自信は無い。
(困ったな。)
こんなことで駅員に泣きつくことはできないし、駅を飛び出して病院に直行するほどのことでもないような気がする。
(そうだ、正気を確認する作業をしてみよう。)
思いついたのは、素数の暗誦。
(二、三、五、七、一一、一三、一七・・・ )
一〇一まで数えたところで面倒になった。
次に思いついたのは、平家物語の暗誦。
(祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。沙羅双樹の花の色、盛者必衰のことわりをあらわす。奢れる人も久しからず、唯春の夜の夢のごとし。たけき者も遂には滅びぬ、偏に風の前の塵に同じ・・・ )
この先は元々知らないので直ぐに終わってしまった。
取り敢えず、思考回路に異常は無さそうだということがわかった。
これ以上どうして良いのか分からないので、何となく一番近場に見える染み、向かい側の線路の上に浮かぶ、軽乗用車ほどの大きさの薄黒く半透明な塊りを凝視してみた。何の根拠も無いのだが、凝視していれば、そのうちに薄れて消えてしまうのではないかと思ったのだ。
(染みが動いているな。)
尾藤の目の前で染みはゆっくりとだが形を変え、少しづつ移動していた。
その動き方だが、気体が揺らめくような軽いモノではない。
クラゲやナメクジのような軟体動物の蠢きに似た、重く引き摺る動きに見える。
尾藤は、それを凝視しているうちに眩暈を覚えてきた。
著しい不快感に襲われ、いつの間にか全身が鳥肌立っていた。
(もう、見ていられんわ! )
そう思って、きつく目を閉じた次の瞬間。
激しい風圧と金属の軋る音を響かせながら入線してきた高尾行きの電車が、黄線ギリギリに立っていた尾藤の身体をホームの内側に半歩押し戻した。
突然のことに驚き、慌てて目を開けたら、
(・・・消えた! )
つい今し方まで視界の彼方此方に見えていた染みが一斉に消えてしまっていた。
(マジで幻覚だったのかな? )
首を傾げながら電車に乗り込んだ尾藤は、車内が空いているにも拘らず座席に座ることはせず、ドアに身体を持たせて立ち、窓の外を通り過ぎる風景を眺めていた。
現在、視界はクリアであり、何処に視線を向けても染みは見えない。
(・・・治ったのなら、それで良いんだけど。)
少なからぬ不安は残されていたのだが、それは電車が二駅も進んだ頃には薄れてしまっていた。酔っ払いの頭では、何を見たとしても正常な分析などできるはずがないわけで、深く考えるのを諦めてしまったこともある。
車内アナウンスが「間もなく中野、中野」と告げる頃には、
(酒が抜けたら大丈夫さ。)
などと、帰宅して一風呂浴びたなら忘れてしまう程度の些細な出来事に思えていた。
JR中野駅北口を出て、東京でオリンピックが開催された前後に建てられたという無駄に大きな駅ビルを左手に見ながら中野通りを北に向かって歩き、早稲田通りを渡ってしまえば、そこから先は再開発を免れた住宅街である。
建物は二階や三階立てが主体で、所々に五階立て以上のマンションが見える程度。道幅は狭く、複雑に入り組んだ路地が多く、二〇世紀のままと言われる街並みが残されていた。
だから、尾藤の自宅マンションがある中野区上高田界隈は随分と空が開けて見える。
道を歩きながら、ふと思った。
(鳥の数、減ったかな? )
数分前に二羽のカラスが不規則に交差しながら頭上を横切って行ったのを見掛けたが、それっきり他のカラスの姿は見ていない。飲食店の多い中野駅北口の繁華街から然程遠くないので、以前は朝方に煩いほどの生ゴミを狙うカラスを見掛けた記憶がある。
カラスだけではなく、沢山いたはずの鳩の姿も見なくなった。
雀やムクドリの声も聴こえていたはずだが、今は気配もしない。
おそらく、都市環境が鳥たちの生育に適さないような変化を遂げてしまったからだと思われるが、早朝に見たホームレスの若者のような連中が捕まえて食べているのが原因かもしれないなどと馬鹿な考えも過った。
(気付かなかったなぁ。)
都市の日常風景の中に起こる緩やかな変化に気付く者は少ない。
研究者やマニアでもない限り、日々変化する鳥の数を数えながら暮らしたりはしないので、鳥が減っていくという経過については知ることなく、減ったという結果に気付くだけなのである。
(ま、鳥に限ったことじゃないけどね。)
例えば、路肩に積み重なる細かな砂や土埃、縁石の周りを取り囲む雑草、アスファルトに走る細かなひび割れなど、いつ頃から、どのような経緯で量を増やしたかなど誰も知るはずがない。それらが、排水溝を塞ぎ、縁石を持ち上げ、アスファルトに穴を開けなければ、人はそこに結果を見付けることができない。
「いつの間にか街に外国人が溢れている」という現状認識も、これと同じことだろう。
(しょーがないよ。人間の注意力や観察力なんて鈍いもんだからね。)
一般の人々は、何事に於いても経過については殆ど気に留めることをしない。
自らに利害が生じるほどに結果が積み重なった時になって、それに驚き、納得し、折り合いを付けようとする。
時と場合によっては、危機感を語り合うようにもなる・・・
[二]
この日、尾藤が事務所に出勤したのは一〇時半を少し回った頃だった。
ちなみに始業時間は九時。
もちろん、決めたのは尾藤自身である。
帰宅して、酒気を抜くためにシャワーを浴び、ホンの小一時間ほどのつもりで居間のソファーに寝そべって仮眠をとったのが不味かった。
ついでに夢見も悪かった。
目覚めて直ぐに忘れてしまったが、とんでもなく恐ろしい嫌な夢を見た気がする。せっかくシャワーを浴びたばかりだというのに全身汗びっしょりで飛び起き、両手が震えていたほどだった。
そして、目覚めた時には一〇時を過ぎていた。
「また、やっちまった! やっちまったぞ! 」
慌てて飛び起き、あたふたと着替えて家を飛び出した尾藤の姿は、まるで寝坊して学校に遅刻しそうな中高生のようであった。
挙句に、
「怒られる! 怒られる! 」
いい歳をした社会人が、子供のような泣き言を呟きながら、ネクタイを背中に翻し、髪を逆立て、山の手通りの歩道を通行人とぶつかりそうになりながら息切らして走る姿は実に滑稽に見えた。
事務所はJR東中野駅西口から徒歩約八分。
自宅マンションからは徒歩で約二〇分ほど。
タクシーなら一〇分もかからない距離だが、運悪く今日に限って流しの空車を捕まえることができなかったので、ひたすら走っている。
(くそっ! こんな所に信号なんて付けんなよ! )
交差点の赤信号に行く手を阻まれて、尾藤の焦りは一段とつのった。
横断歩道の前で足踏みしたところで、信号が早く変わってくれるわけではないのに、ついつい膝が忙しく上下してしまう。
その時、
「うっ、臭っ! 」
背後から異臭が漂ってきた。
季節は初冬だというのに、夏場の腐った生ゴミと排泄物の臭いが混じり合ったような強烈な悪臭である。
(な、なんだよ? )
振り返ると、酷く汚れた男が立っていた。
尾藤よりも頭一つ背丈の低い男で、裾や袖が擦り切れ、元の色が分からないほど変色してしまった、足元まで隠れる長さのロングコートを羽織り、俯き加減の姿勢でフードを目深に被って顔の上半分を隠している。
どうやら、この男が悪臭の出所であるのは間違いなさそうだったが、異様な男である。
悪臭だけならば散歩中の野宿生活者だろうということで済ませられるのだが、フードの奥で頻りに荒い鼻息を吐き、何が可笑しいのか肩を震わせながら、無精髭の生えた口元を歪ませて、くぐもった笑い声を立てているところが、どうしようもなく不審である。
(ヤバい! 変な奴! 怪人だ! )
咄嗟に尾藤の自己防衛本能が働いた。
(絶対に関わらないようにしよう。)
街で、うっかり怪人と出会ってしまった時は無視するに限る。
背中を向け、怪人の存在を意識的に無かったことにして、悪臭を嗅がないように口呼吸しつつ、少しでも早く信号が青に変わることを祈りながら待った。
「・・・ 」
背後から小さな言葉が聞こえてきた。
(なんなんだよ? )
怪人の声だろうか?
「・・・ 」
再び聞こえたが、小声過ぎて何を言っているのか分からない。
(もしかして、俺に話し掛けてんのか? )
そうだとしても返事をするつもりはない。
このまま無視し続けて、信号が変わったら走り去ってしまえば良いと思っていた。
間もなく、車道の信号が黄に変わり、数秒置いて赤になった。
続いて正面の歩行者信号が青に変わったら、直ぐに横断歩道に飛び出すつもりで準備していた尾藤だったが、又もや背後から聞こえた声に勢いを止められてしまった。
「そう、邪険にしなさんな。これから嫌でも関わり合いになるのだから。」
今度は、尾藤に語り掛けてくるセリフがハッキリと聞き取れた。
その意味は分からないが、何故か無性に腹が立った。
「はぁ? 何だって? 」
無視し続けるつもりが、ついつい威嚇するような口調を発しながら背後を振り向いてしまった。
しかし、
(え? )
今まで背後で語りかけていたはずの怪人は消えてしまっていた。
どれだけ素早く立ち去ってしまったのだろう?
尾藤から見える範囲には怪人の姿は無い。
怪人が立っていた場所には悪臭だけが残されていた。
(くそっ! 今日は朝から色々気味の悪いことが続く。まったく気分が悪いぜ! )
大きく舌打ちを一つしてから、尾藤は再び走り始めた。
「つっ、着いたーっ! 」
尾藤は、今にも泣き出しそうな顔で息を切らしながら、東中野二丁目にあるテナントビル正面の観音開きのドアを、体当たりするようにして押し開けた。
そして、近所迷惑を顧みず、屋内の階段を三段飛ばしで音を立てて駆け上がり、ようやく二階にある「尾藤総合調査事務所」のドアの前に到着した。
そこで一旦立ち止まり、今度は職員室に呼び出された中高生のように頭髪と服装の乱れを直し、呼吸を整えている。
そして、天を仰ぎ、大きく深呼吸した後、覚悟を決めた固い笑顔でドアノブを回した。
その途端!
「いい加減にして下さいっ! この酔っ払い! 飲んだ次の日の遅刻欠勤は厳禁! この社会人の鉄則を何度破ったら気が済むんですかーっ! 」
苛立ちと、怒りと、呆れの交じった、甲高く、激しい怒声が浴びせられ、一気に追い詰められてしまった尾藤の全身には、走っている時以上の汗が噴き出してきた。
怒声の主は事務員兼助手、アルバイトの吉良恵子(きら けいこ)である。
「ごめんなさい! すみません! 」
念のため確認しておくが、朝の挨拶もさせてもらえないまま、ドアの前でペコペコと何度も頭を下げる尾藤の前に腕組みして立ち塞がる彼女はアルバイトであり、決して上司ではない。ついでに言うならば、彼女は雇われ人であり、尾藤は雇用主のはずなのだが、まったく立場が逆転してしまっている。
「いったい何時だと思ってるんですか? クライアントから何時頃に伺いましょうかって電話が三回も掛かってきてるんですよっ! 三回もっ! 携帯に着信入れといたんですけどねぇ、メールもしといたんですがねぇっ! どうせ端末を放りっぱなしにしていて、全く見てないんでしょうけどねっ! 」
まるで、マシンガンから発せられる弾丸のように切れ目の無い、痛烈な怒声。
尾藤は慌てて上着の内ポケットから携帯通信端末を取り出した。
電子機器や家電はオールドタイプのデザインを好む尾藤の端末は、今時珍しいコンパクトタイプの携帯電話型である。
「ごめんなさい、全然気付かなかったよ。あははぁ・・・ 」
引き攣った笑顔を見せながら、尾藤は大急ぎで手汗をジャケットの裾で拭い、着信を確認しようと端末を開いたのだが、焦ってボタンを押し間違え、手が滑ってお手玉してしまったりと、どうにも無様に過ぎた。
その様子を見ていた恵子は事務所内に響き渡るほどの大きな舌打ちをしてから、
「落ち着いて下さいっ! 」
と、きつく先生が子供を躾けるように言った。
ジタバタしながら漸くメッセージに辿り着いた尾藤は中身を確認してから、
「あ、ホントだ。ごめん。」
もう一度謝りながら、恵子に向かって弱々しく愛想笑いをしつつ頭を掻いた。
「まったく、もう・・・ 」
取り敢えず、尾藤がメッセージに辿り着いたところで、恵子の怒声は一旦保留とされたようある。
しかし、ここで尾藤が気を緩めたのは良くなかった。
「ふーん、それにしても三回も電話きてたのかぁ、午前中に打ち合わせしましょうってことだったから、未だ大丈夫だと思ってたんだけどなぁ。この人、いったい何焦ってんだろうね? 」
別に自分の遅刻を正当化しようとするつもりの発言ではない。
仮にも社長が、アルバイト従業員を前に犯してしまった失態と、それに伴う罰の悪さを少しだけ取り繕おうとしただけで、大した意味の無い、些細な大人の見栄を、うっかり口に出してしまっただけなのだが・・・
(あ、しまった! )
ホンの一時収まっていただけの恵子の怒りを、再び沸点まで戻してしまったことに気付いたが、遅かった。
ドドーン!
スチール製の事務机に恵子の拳が振り下ろされた鈍い音と共に、怒声は再開された。
彼女は自分の愚かな雇い主が漏らした、間抜けで、無責任な発言に対し、完全に激昂していた。
「馬鹿なこと言ってんじゃないですよっ! 普通ねぇ、うちの依頼人ってぇ、みんな焦ってるんじゃないですかねぇ? 焦ってるからうちに仕事持ってきてるんですよぉ! 当り前じゃないですかっ! それにねぇ、時計見てください! わかりますぅ? 時計の読み方知ってますぅ? もう午前中は、残り一時間少々なんですけどっ! 」
もっともな怒りであり、言い訳のしようが無い。
再沸騰させてしまった恵子の怒りは、そう簡単に収まりそうになかった。
(ううっ、困ったなぁ・・・ )
尾藤は思わずこめかみを抑えて呻いた。
二日酔いの鈍痛が続く頭には女性の甲高い声は拷問である。
(ダメだ、これ以上聞いていたら命に関わる! )
尾藤は逃げ出した。
恵子の怒声をまともに受けながらも少しづつ後退りするようにして、事務所奥の四坪ほどの広さをパーティーションで仕切った個室、社長室兼応接室のドアに背中を張り付け、後ろ手にノブを握った。
「わ、わかった、わかったからさ・・・あの・・・それじゃ、俺は奥にいるから、ク、クライアントに、今からなら何時でも良いですって電話しといてくれる・・・かな? 」
説教から逃げ出そうとする尾藤の卑怯な態度に対し、恵子が眉間に縦皺を寄せた。いかにも「ああん? 人の話は最後まで聞けよ! 」と、言いたげな顔である。
だが、これによって隙間なく続く怒声の流れに僅かな隙ができた。
尾藤は、その隙を無理矢理に抉じ開けて逃げ道を作った。
「んじゃ、ごめん! よろしくっ! 」
そう言い残すと後ろ手でノブを回してドアを半開きにし、身体を横にして滑り込むようにパーティーションの中へと逃げ込んだ。
追い打ちをかけるように、
「こんのぉ、馬鹿社長っ! 」
恵子の放った最後の一声が、薄っぺらなパーティーション越しに響いてきた。
言葉だけではない。
パーティーション一枚では恵子が撒き散らす憤りの感情を遮ることはできない。
(耐えよう・・・耐えるしかない。)
尾藤は中央に置かれた応接セットを回り込み、奥の窓際に内向きで配置されたワーキングデスクに辿りついた。そして、椅子を引き出して身を投げ出すように腰掛けると両手で頭を抱えた。
長距離走と怒声のおかげで頭痛は一段と酷くなり、まるで前頭部を万力で締め付けられているような苦痛に襲われていた。
「ごめんなさい、もう絶対に飲み過ぎたりしません。」
他人が聞いたら情けなくなるような、惨めな泣き声交じりの呟きが漏れた。
その間も、パーティーションの向こう側では、怒りの対象に逃げられてしまった恵子のドタドタした乱暴な足音、書類を投げ捨てる音、無理矢理引き摺られて悲鳴を上げる椅子のキャスター音などが断続的に聞こえていたが、間もなくして全て収まった。
尾藤にとって不気味に思える静寂が一分ほど続いた後、固定電話のヘッドセットを取り上げる音がした。
カチカチとプッシュボタンを押す音に続いて、
「お世話になっております。こちら尾藤総合調査事務所と申します。」
恵子が、先程までの怒号の主とは思えない、全く別人のような穏やかで滑らかな口調でクライアントに話しかけていた。その声を聞きながら、ようやく緊張から解き放された尾藤はワーキングデスクの上にぐったりと倒れこんだ。
(あとは、この頭痛をなんとかしなくちゃだな。)
クライアントが訪れるまでには頭痛を抑えておきたかった。
(確か買い置きの鎮痛剤があったはず。)
尾藤は、もたもたと起き上がってデスクの引き出しを探り始めた。
(くそっ、見つからないぞ! )
日頃から整理整頓の苦手な性質なので、引き出しの中は混沌とした状態である。
何段目に鎮痛剤をしまっていたかなど憶えていないので、上の引き出しから順に手探りしていくしかなかった。鎮痛剤はなかなか見つからないが、どの引き出しの中にもスティックキャンディが転がっているのが笑える。
それでも、何とか目的の鎮痛剤を探し出すことができた尾藤は、ホッとして思わず、
「恵ちゃん、お水持ってきて! 」
と、うっかり叫びそうになり、慌てて口を塞いだ。
(ヤバい、今度こそ殺される! )
せっかく沈静化したらしい恵子の怒りに再点火してしまうところだった。
現状では、社長室兼応接室から出て給湯室に向かうのも至難の行為である。
(まあ、こういう時のために取っておいた、ミネラルウォーターのペットボトルがあるんだよな。)
こういう時も何も、単にだらしなく飲みかけのペットボトルを引き出しに放り込んでおく癖があるだけなのだが、尾藤は上首尾とばかりに満足気な笑みを浮かべつつ、再び引き出しを開け、その混沌の中から「おいしい天然水」のペットボトルを一本取り出した。引き出しの中には「おいしい天然水」以外にも飲み掛けのコーラやウーロン茶のペットボトルの姿も垣間見えたような気がするが、これらを尾藤はごく自然に無視した。
さっそく鎮痛剤の箱を開け、二粒の錠剤を取り出しミネラルウォーターで流し込もうとしたのだが、
「社長、入りますよ。」
恵子の声がしてドアが勢い良く開いた。
(あわわ! )
尾藤は驚いて、錠剤を取り落としそうになった。
恵子は入ってくるなり、鎮痛剤の箱とペットボトルを一瞥し、
「はぁ、二日酔い? 」
尾藤に対する非難を再開しそうな表情を見せた。
「あ、ちょっと、頭痛がね・・・ 」
尾藤はオドオドしながら頭を押さえる仕草をした。
もはや恵子の声だけではなく自分の声も頭に響くほどに頭痛は悪化していたので、怒号を再開されたら致命傷になりかねない。
ところが、
「もう齢なんだから、ほどほどにすべきだと思うんですけど。」
予想に反して穏やかに窘める程度の口調が返ってきた。
恵子はワーキングデスクの前までやってきて、クライアントとの電話の内容を書き取ったメモを置いた。
(機嫌は直ったみたい・・かな? )
メモを受け取りながら、探るような上目使いと口調で、
「齢って言うなよ、まだ三四歳だぞ。」
馴れ馴れしさを込めた口調で軽口を返してみた。
「もう三四歳でしょ。現役大学生の私から見れば完全なオジサンですよ。」
恵子の言葉に毒や棘は感じられない。
どうやら機嫌は直ったと判断しても良いらしい。
「さてと、」
少しだけ安心して、メモに目を通しながら再び鎮痛剤とペットボトルに手を掛けた。
「あら、そのお水? 」
尾藤が手にしたペットボトルを恵子が指差した。
「ちょっと、いつの飲み残しなんですか? カビ生えてますけど。」
「げっ! 」
半分ほど飲み残されていた水の中に灰色の藻のような膜が漂っている。
(そう言えば、今年の夏頃の飲み残しだったっけ? )
恵子は、尾藤の手からペットボトルを引っ手繰ると、
「もうだらしないんだから、」
と言って、意外に優しげな苦笑を見せつつ、
「お薬飲むなら、お水持ってきてあげます。」
そう言って、社長室兼応接室を出て行った。
思い掛けない優しさを向けられて、
「あ、ありがとう。」
お礼を言う尾藤の声が震え気味だった。
情けないと言うか、馬鹿馬鹿しいのだが、涙ぐんでいたかもしれない。
恵子の態度は先程までの怒声の主とは思えないほどの変わりようだったので、散々罵られ凹まされてしまった尾藤は、そのギャップに激しく感動させられ、思わずホロリとしてしまったのだ。
尾藤の目には恵子の背に後光が差して見えていたほどだった。
だが、給湯室で水を汲む恵子が、意地悪そうな笑みを浮かべ、
「ま、飴と鞭ってことで・・・ 」
小声で呟いていたことに尾藤は全く気付いていない。
吉良恵子は、今時の大学三年生にしては随分なしっかり者だった。
受付業務や事務処理からスケジュール管理まで、与えた仕事はそつ無くこなした。
調査員の業務は外出が多いので、事務所の留守番は信頼できるものでなければ勤まらないが、その点で恵子は実に有用な人材と言えた。
だからこそ雇ったのだが、あまりにしっかり者過ぎて、常日頃だらしなさには定評がある尾藤などは全く頭があがらない。
(見た目は美人だし、あれで性格さえ穏やかなら言うこと無いんだがなぁ・・・ )
確かに恵子は美人である。
大きく切れ長の目、スッキリと通った鼻筋、多少上がり気味の口角、ショートカットが似合うバランスの良い輪郭の小顔。
少々、出来過ぎではないかと思えるほどに整った顔立ちをしている。
身長は推定で一七〇センチ強。
高めのヒールを履かれたら身長一七七センチの尾藤と並んでしまうほどの長身だが、スリムな体型で凹凸に乏しいのが密かなコンプレックスであると(本人に記憶は無いと思われるが)酔った際に愚痴をこぼしていた。
しかし、美人だが、可愛げは無い。
初対面の男にはモテるそうだが、知り合った後に嫌われたり避けられたりして、最後には逃げられることが多いらしいが、その原因はハッキリしている。性格のキツさと賢さが言葉や表情の端々に現れるタイプだし、尾藤に対するのと同じように同世代男子を叱ったり、やり込めてばかりいたら、怖い女だと思われ嫌われるに決まっている。
一回り以上も年上で、一応大人としての自覚? というか心構えがあり、彼女の有能さを知っている尾藤だからこそ耐えていられるのだ。
その点を恵子本人が自覚しているのかどうかは分からない。
尾藤が恵子を雇ってから二年になる。
最近は、彼女が事務所と尾藤を仕切っているのではないかと思えることも多い。
だが、恵子は大学卒業までの間、講義の合間を縫って小遣い稼ぎのために勤めている学生アルバイトである。
一年後には辞めてしまうわけで、その後の事務所の運営を考えると尾藤はかなり辛い。
[三]
ギリギリで午前中と言うべき、一一時五〇分。
恵子に案内されて社長室兼応接室に入って来たクライアントは、見た目四〇代半ばの夫妻だった。
「昨日、電話でお話させていただきました司(つかさ)と申します。宜しくお願いいたします。」
名刺交換を終えてから尾藤がソファを勧めると、二人は腰掛ける前に揃って深々とお辞儀をした。
尾藤は応接テーブルを挟んで司夫妻と向かい合った。
本題に入る前に軽く天気の話などしながら、さり気無く夫妻を観察していたが、二人とも一見質素な装いで目立たないようにしているが、物腰や言葉の端々から育ちの良さと裕福そうな生活環境が感じられた。身に付けている衣服や持ち物は、地味だが決して安い物ではなさそうである。
調査会社に仕事の依頼をしに来る者なら殆どがそうだと思うが、彼らも努めて感情を表に出さないように、平静さを装うように心掛けている様子だった。しかし、落ち着きの無い目の動きと、表情の端々や指先に見える細かな仕草の中に、彼らが置かれている状況の厳しさと心の不安定さが見て取れる。
間もなく恵子がお茶を持ってきたので、尾藤は彼女が部屋を出て行くのを待ってから本題に入った。
「では、司さん。早速、お話を伺いましょうか? 」
夫妻は互いの顔を見合わせて、話の切り出し方に少し迷っていたようだったが、直ぐに夫の方が口を開いた。
「実は、廉子(やすこ)を、いや、娘を探して欲しいんです。」
「娘さん、どうされたんですか? 詳しく伺いましょう。」
尾藤はB5サイズのタブレット端末と入力用のペンを取り、メモの準備を整えた。
「あの、今月の八日のことなんです。いつものように娘の学校の部活が終わる時間に妻が車で迎えに行ったのですが、校門の前でずっと待っていても現れなかったんです。そこで学校の先生に聞いてみたら、とっくに帰ったはずだと言われたらしいんです。」
夫が話している横で、妻はハンカチを握りしめて口元を押さえ、泣き出しそうになるのを堪えている様子だった。
「娘さんは学生ですか? 」
「はい。中学二年生です。」
「なるほど。」
尾藤は素早くメモを取った。
今時は都内全域で治安が悪化している傾向にあるので、小中学生の場合は集団で登下校させるか、特に女子の場合は親が毎日の送り迎えをしている場合が多い。
「一人で帰ったのかもしれないと思った妻は、直ぐに娘の携帯通信端末に連絡してみましたが通じませんでした。急いで家に戻ったらしいのですが娘は帰宅しておりませんでした。私が帰宅してからも、二人で一晩中娘の端末に着信を入れ続けたんですけど、音声通信は全く繋がらず、メールの返信もありません。仲の良い友達の家や、少しでも娘が行く可能性のある親戚や知人の所など全て探しましたが見つかりませんでした。それきり娘は消えてしまったんです。」
「警察には連絡しましたか? 」
「はい。翌日の午前中に捜索願を出しました。でも、警察は簡単に事情の聞き取りをした後は音沙汰無しなので、動いてくれているものなのかどうか全くわかりません。」
おそらく、
(警察は動いていないだろう。)
尾藤は思った。
いや、動けないと言った方が良いかもしれない。
近年の東京は犯罪多発都市と化している。
殺人、強盗、強姦、誘拐など、驚くほどの増加率を示していた。
昔ならば、コンビニ強盗や引っ手繰り事件までもが報道対象として扱われていたはずのテレビ、新聞、インターネットが、余程のインパクトがある事件以外は報道しなくなっているほど凶悪犯罪は多発している。
そんな状況において、公務員人件費の削減対象になり、慢性的な人手不足に陥っている警察が、多発する犯罪の全てに対処できるはずがなかった。限られた人員で対処できる犯罪件数は限られるので、確実に犯罪であると断定され、危険度の高さや社会に与える影響が危惧されるような事件でなければ優先度が低く判断されてしまうのだ。
「おそらく、家出の類と思われたんでしょう。今時の警察は家出人探しまではしてくれませんからね。」
落胆させてしまうだろうが、これは事実である。
失踪者の死体でも発見されない限り、警察は動かない。
司夫妻の話だけでは、警察を動かすためのインパクトが弱過ぎた。
例えば誘拐現場を目撃したとか、身代金の要求があったとか、所持品や身体の一部が発見されたとか、明らかな事件性を見出せないようでは警察は何もしてくれない。
「うちは親子関係も悪くないですし、娘が不満を持つような育て方はしていません。簾子が家出をするなんて考えられません。」
そう口を挟んだ妻の声は震えており、語調が荒かった。
娘を心配する親心、何もしてくれない警察に対する怒りなど、次々に溢れ出す感情を必死で押さえているのが分かる。
(とはいえ、家族に兆候を見せずに家出する子供も多いんだがな。)
思春期の子供が、親の想定外の行動を見せることは多々あるので、両親が何と言っても家出の可能性は否定しようがない。
「お気持ちはわかります。但し、うちに依頼された場合は様々なケースを考えて調査させていただきます。もちろん家出もその一つです。」
そう尾藤が言うと、
「仰るとおりですね・・・お願いします。」
夫妻は共に声を絞り出すように言って頭を下げた。
そこで、尾藤は仕事を引き受けるにあたっての条件の説明を始めた。
「昨日のメールでお送りさせていただきました当事務所の料金の説明をさせていただきます。人探しの調査料は実働一時間単位で税込一万円が基本ですが、これは難易度によって変わってまいります。実費、交通費は別に請求させていただきます。うちは自分と助手の二名が携わりますので・・・ 」
「お金はいいんです! 」
突然、妻の方が叫ぶようにして言った。
その勢いに尾藤は少し慌ててしまった。
「いや、説明するのが規則なので・・・ 」
「お金は必要なだけ、お支払いします! 」
感情的になり身を乗り出して声を荒げる妻の肩を夫が抱えるようにして宥めた。
「これが言うように、費用は幾ら掛かってもいいんです。経費も必要なだけ使って下さい。それで、娘が帰ってくるなら・・・ 」
そう言って夫が鼻を啜ったが、彼も遂には感情を抑えきれずに目が潤んでいた。
「わかりました。でも、取り敢えず見積もりをお出ししましょう。」
尾藤は言うのだが、
「それも必要ありません。契約書があれば、直ぐにでもサインします。知人から、あなたは非常に優秀で信頼できる方だと伺ってまいりました。一切をお任せします。なんとかして娘を見つけてください。」
見積もりのやり取りをする時間など勿体ないと言いたげだった。
(知人って誰だろう? )
たぶん過去の依頼者の誰かだと思うので、これは聞き返すことではない。
それにしても、こうまで強く契約条件など全くお任せと言われてしまえば、尾藤も頷くしかない。
その信頼に応えるしかないわけだ。
紹介者が誰かは不明だが、独立してから三年間に携わった人探しで依頼者の求める成果を上げられなかったことは一度も無いのだから、全幅の信頼を受けるのは当然という自負もある。
「了解しました。それでは、後ほど契約書と調査に必要な書類を記入していただきましょう。当日の服装や所持品などは詳細に記入して下さい。それと、娘さんの写真はお持ちですね? 」
夫人がハンドバックからメモリカードの入ったケースと、サービスサイズでプリントアウトされた写真を一枚取り出し、尾藤の前に置いた。
「拝見。」
尾藤はタブレット端末の側面スロットにメモリカードを差し込み、必要なデータを選んでコピーを始めながら、プリントアウトの写真を手に取った。
そこには、いかにも育ちが良さそうな雰囲気を漂わせた制服姿の少女が、おそらく通っている中学校の校舎をバックにして笑顔で立っている。
「これは、最近の写真ですか? 」
「はい。先月の学園祭の時、友達に撮ってもらったと言っておりました。」
「なるほど。」
尾藤は暫く写真を眺めていた。
(この校舎は確か港女子学園、私立のお嬢さん学校だな。)
裕福な家庭の女子が通う少人数制の中高一貫校である。
(費用は幾ら掛かっても良いなんて贅沢なことが言えるわけだ。)
契約書を取り交わし、全ての書類の記入を終えた後、司夫妻は来た時と同じく丁寧な態度で挨拶して帰って行った。
「この書類、入力頼むよ。後で俺の端末に転送しておいてくれ。」
給湯室で洗い物をしていた恵子に声を掛け、受付の傍にある彼女の事務机に夫婦が記入し終えたばかりの書類の紙束を置いた。
「わかりました! 」
給湯室から聞こえる恵子の声の調子は穏やかである。
どうやら先程までの怒りは今度こそ無事に収まったように思えて、尾藤はホッとしながら社長室兼応接室のワーキングデスクに戻った。
「さてと、」
デスクの引き出しからスティックキャンディを一本取り出して口に咥え、タブレット端末を手に取ってコピーした写真のデータを見直すことにした。
(凄い量を掻き集めてきたなぁ。)
写真は数十枚も用意されており整理に困るほどだったが、これは司夫妻の娘に対する想いの強さであろう。
一人の写真、友人たちとの写真、親子の写真、どれも似たような写真ばかりだったが、何の役に立つかわからないので、全てクラウドと事務所内サーバーにも転送しておいた。
(娘の名前は司簾子。司家のご主人は一部上場企業の役員ねぇ。)
身代金目当ての誘拐ターゲットとしては申し分の無い家庭のようだが、既に失踪から一〇日以上が経過しているにも関わらず犯人から何も言ってこないとなると、その線は薄いかもしれない。
(であれば家出、事故、他の目的のための誘拐、もしかしたら既に殺されてしまっている可能性があるかもしれないってことだな。)
全ての写真の中には、カメラに向かって様々な笑顔を向ける女子中学生の姿がある。
荒みなど全く感じさせない、屈託の無い笑顔を見せた少女だった。
目鼻立ちは母親に似ていて、将来はそこそこの美人になりそうな予感をさせる。
(可哀そうなことになってなければ良いが。)
尾藤は難しい顔をしながら、キャンディの上半分ほどを噛み砕いた。
(取り敢えず動くとするか。下拵えも必要だしな。)
残ったキャンディを全て口の中に押し込んでから、椅子の背もたれに掛けていた上着を手に立ち上がった。
取り敢えずは手始めに現場を見ておこうと思った。
その上で、当日の事件の経過を予測し辿らなければならない。
必要な範囲で聞き込みもするつもりだった。
尾藤が社長室兼応接室を出ると、既に恵子が書類の入力作業に入っていた。
常日頃、恵子は音声入力やペンタブレットでの入力を嫌い、常にキーボードを使用するので、業務中の事務所内ではいつも軽やかなキーを叩く音が聴こえている。
「早速、出掛けて来るよ。」
尾藤が声を掛けると、
「了解です。資料は三〇分以内に転送しますから。」
恵子が振り返って言った。
「助かる。それと、その書類の中にある港女子学園の先生にアポ取っておいてくれるかな。担任か部活の顧問どちらでもいいや。時間は放課後、たぶん三時半過ぎが良いだろうな。もし都合が悪いって言われたら、会ってくれる先生なら誰でも構わないよ。」
「はい。それじゃアポ取ったらメールしますね。」
つい一時間ほど前まで怒声を上げていたとは思えないほど歯切れの良い対応である。
「それじゃ、ちょっと出掛けてくる。」
「え、今からベイジョに行くんですか? まだ一二時半過ぎたばかりですよ。」
「ベイジョ? 」
意味が分からず首を傾げた。
「港女子だからベイジョ。知りませんでした? 」
「知らないよ。それ最近の呼び名だろ? うちらの学生時代には聞いたことないや。まあ、俺と君とじゃジェネレーションが違うんだよ。」
尾藤は苦笑した。
「今回の依頼は誘拐の可能性もあるからね、事前に情報源を確保しとかなきゃならないと思ってさ。だから、最初に木村のとこに寄ってから飯食って、その後にベイジョに行くよ。で、今日は直帰すると思うから、一八時過ぎたら君は引き上げていいからね。」
そう言って事務所を出ようとした尾藤に、恵子が声を掛ける。
「いってらっしゃい! 今夜は飲み過ぎたら許しませんよぉ。」
表情は穏やか。
だが、その声は非常に冷たい。
その一言によって尾藤の背筋は硬直し、脳内に今朝の怒声がフィードバックしてきた。
思い切り動揺して、口の中に残っていた未だ小さくなり切っていないキャンディを、うっかり飲み込んでしまった。
「おごっ、うげっ! 」
硬いキャンディが無理矢理喉を押し通ろうとする痛みに耐え、ギクシャクしながら振り返った尾藤に、恵子の意地の悪そうな作り笑顔が追い打ちを掛けた。
[四]
「随分と忙しそうなんだね。」
「今日は、お前が来てくれなければ飯も食いに行けなかったよ。」
そんなことを言いながら、警視庁公安部の木村警部は、身長一八五センチ、体重九〇キロの鍛えられた筋肉質の身体を揺すりながら、美味そうに生姜焼きランチをパクついていた。
ここはJR阿佐ヶ谷駅近くの洋食屋。
木村と向かい合って座っている尾藤はコーヒーだけ飲んでいる。
未だ二日酔いが残っていて、何も食べたくなかったのだ。
目の前で木村が食べている生姜焼きの臭いを嗅いでいるだけでも胸が焼けてくる。
「ところでさ、何で杉並署なんかにいたん? もしかして公安辞めた? もしくは降格されて飛ばされちゃった? 」
尾藤の不用意な発言に木村の口から飯粒が飛んだ。
「違ーうっ! 短期の出向ってやつだ、馬鹿っ! こういう所で公安とか言うな! 」
小声で怒鳴りながら、木村は尾藤に声を低めるように注意した。
普通、公安警察官は部外者に本名や所属を明かさないようにしているのに、昼飯時で混み合った洋食屋のド真ん中で雑談ついでにバラされてしまっては堪らない。
「すまん! でも近くにいてくれて助かったよ。」
尾藤は苦笑しながら、右手を立て拝むようにして謝って見せた。
「こっちは、とにかく忙しくってなぁ。今朝から管内で殺人事件が二件、殺人未遂が一件、あと傷害事件は・・・数えて無いな。俺は自分の抱えてる案件で一時的に出向しているだけだし、所轄の仕事に関わる義務なんて無いのに、毎日のようにお助け仕事が増えてくんだから堪らんよ! 」
木村は愚痴を言いながらも忙しく箸を動かし、飯と生姜焼きを次々に口に運んでいる。
「ゆっくり食えばいいのに。」
尾藤は嫌な顔をしたが、木村は気にもしない。
「そんなに時間があるわけじゃないからな。のんびり食ってたら、お前と話をする時間が無くなるぞ。」
そう言って、忙しない食事を続けている。
「俺は普段なら弁当持ちなんだが、昨日から家に帰って無いんでな。まさかカミさんに届けてもらうわけにもいかないし、外食したくても何か切っ掛けがなければ席を外せないしなぁ。こんな時に、お前から連絡が入ってホントに助かった! 」
今度は木村が箸を持ったまま、両手を合わせて拝むような格好をして見せた。
「感謝してるの? それじゃあさ、こっちの頼みを快く聞いてもらえそうだねぇ。」
尾藤がコーヒーを啜りながら、薄ら笑いを浮かべた。
実は、木村は尾藤を仕事絡みの来客と偽って、打ち合わせとか何とか適当な口実を作って飯を食いに出てきていたのだ。
「ああん? 頼み? どうせ、お前の仕事のための情報提供をしろってことだろ? 」
木村が、最後の生姜焼きと飯を口の中に放り込みながら面倒臭そうに言った。
「当然でしょ。そうでなければ昼飯なんて奢らんよ。」
生姜焼きランチで一つで警察情報を引き出そうとする不埒な友人に呆れながら、
「しょうがないな。但し、何でもかんでもってわけにゃいかないからな。」
と、木村は取引する前に釘を刺した。
この二人、大学時代の同級生である。
学部は違ったが、同じ柔術部に在籍していたので、いつの間にか親しくなっていた。
ちなみに柔術の腕前についてだが、二人は体重差があるので正式な試合でまみえることは無かったが、道場での練習試合では互いに勝ったり負けたりで、実力はほぼ互角。しかし、木村は自分より二〇キロ軽いにも拘らず、互角に戦う尾藤に一目置いていた。
二人の出身大学は、そこそこ有名な私立大学だったので、卒業後に木村は所謂準キャリア組の警察官となり、現在は警視庁公安部総務課所属の係長。二、三年以内には警視への昇進が予定されているというお堅い人生を歩んでいる。
片や尾藤は、学歴を生かすことなく中堅どころの調査会社に就職。そこを経由して現在は事務所を構えて独立したとはいえ、木村に比べたらフワフワした人生を歩んでいる。
道は分かれたが、二人の腐れ縁は続いていた。
警察と民間という立場を越えて、有益な情報を交換するような協力関係が密かに出来上がっている。本来ならば公安警察官は部外者と親しくしないのだが、木村は尾藤を公安の協力者、つまり「ゼロ」と呼称される外注扱いとして登録していたので、二人の協力関係については書類上は何の問題も無く、常にスムーズに機能していた。
お互いにとって業務上有効なパートナー同士と言うべき間柄であった。
さて、木村が食事を終え、コーヒーを飲み始めたのを見計らって、
「それじゃ、本題に入って良い? 」
尾藤は切り出した。
「ああ、どうぞ。」
木村がテーブルの上に身を乗り出すようにして距離を縮めてきたので、尾藤も釣られて身を乗り出した。
「ところで、ベイジョって知ってる? 」
「知らん。新しい菓子か? 」
木村が知らなくて、少し安心した。
やはりオジサンたちには聞き覚えの無い呼称らしい。
ここで知ったかぶりして若者言葉を教えてやるのも格好悪い気がするし、面倒臭いと思ったので、尾藤は直ぐに言い直した。
「港女子学園ってあるだろう? 」
「ああ、お嬢さま学校だな。昔、俺をフッた女が通っていたぞ。なかなか良い女だったけど、それがどうした? 」
「いや・・・お前の想い出話なんて全然聞きたくないんだが・・・ 」
どうでも良い情報を挟まれて話の腰が折れかけたが、尾藤は踏み止まった。
「今月の八日から女子生徒一名が行方不明になっててさ、その捜索依頼が俺のとこに来てるってわけ。」
「なるほどね、港女子学園は杉並署の管内だが、そう言えば最近、似たような届け出が多いらしいなぁ。その行方不明って営利誘拐か? 」
「それはどうかな。ただ姿を消してしまったってことだから、家出の可能性も無いわけじゃないよ。」
木村が、ヤレヤレと首を左右に振って、
「それじゃなぁ、今時の警察は動けんだろうよ。」
突き放すように言った。
「まあ、そうだろうねぇ。娘の両親は杉並署に捜索願を出しているらしいんだが、何もしてくれないって憤っていたよ。」
尾藤は少々嫌味っぽく言ったので、木村は憮然とした。
「杉並署の肩を持つわけじゃないが、今の警察は人員が年々削減されててな、特に所轄は機能不全に陥る寸前なんだよ。ハッキリと事件性が明らかになった件以外は仕事にできないんだわ。同じ警察官として申し訳ないとは思ってるが、どうしようもない。」
不機嫌そうに開き直る木村を、まあまあと押さえながら尾藤は続けた。
「そういう事情に関しては十分に分かってるから良いのよ。それに警察が手一杯なおかげで、こっちが儲かるわけだから却って有難いわ。うちに依頼が来たからには、これはうちの仕事。警察には渡さんよ。そんなことよりさぁ、たまたま杉並署に居合わせたんだから、幾つか協力して欲しいことがあるんだけどな? 」
「どんな? 」
「まずは、携帯通信端末のトレースをして欲しいんだよ。」
尾藤は紙ナプキンを一枚とって、ボールペンで端末のアドレスをメモしてから木村に手渡した。
「一〇日以上も前の事だろ? もう電池が残ってないぞ。」
「たぶんね。でも、念のためやってみて欲しい。アクセスポイントのログを見れば最終発信地点ぐらいわかるだろう。同時に遺失物として警察に届いていないかどうかも調べて欲しいんだ。あ、機種と特徴も書いとくから。」
「了解。」
木村は追加のメモも受け取り、上着の内ポケットに入れた。
「それとさ、さっき言ってたよな。最近多いのか? 女子学生の行方不明? 」
「ああ、そうだな。杉並署だけじゃなく他の所轄でもそうらしい。数が多いから、署内でも気にしている奴が出始めてるぐらいだ。」
「それって、どのくらい届けがある? 地域は絞られるのか? 」
「広域で発生してるんだが、特に多いのは新宿、中野、世田谷、杉並、渋谷・・・、山手線のこっち側だな。誰が何処でとか、細かいところは調べなきゃわからないぞ。」
もしかしたら、司廉子の件に関係あるかもしれないと思った尾藤は、
「んじゃ、急いで調べて欲しいんだけど。」
当然のような顔で言った。
「おいおい、個人情報の提供はできないって。」
木村も当然渋い顔をする。
「行方不明になった場所と状況、あとは被害者の学校名だけ分かれば良いよ。他は必要があれば、こっちで調べられるしさ。」
非合法な調べ方をするんじゃないかと訝しみながらも、これを木村は一応承諾した。
断わったところで、尾藤なら何らかの手を使って調べ上げるだろうし、下手をすれば警察のサーバーにハッキングを掛けるかもしれない。
尾藤は長年の親友だが、そういう面倒臭い奴だと木村は認識している。
「しょうがねぇな。但し、メールやデータ渡しはまずいな。必要なところだけプリントアウトして明日にでも紙にして渡す。それで良いんだろ? 」
「有難い。んじゃ明日、杉並署に助手を使いにやるから宜しくな。やっぱり持つべきは警察官の親友だな。」
尾藤が木村の肩をポンポンと叩いくと、木村はその手を煩そうに振り払い、
「言ってろ! 」
と、舌打ちした。
「ところで尾藤よ。もう何か掴んでんのか? 」
「いやぁ、今朝に始まったばっかの話なんだから、まだまだこれから。でも大丈夫、サクッと解決して見せっからさ。俺の実力知ってっしょ? 」
尾藤が大げさに反り返って、右手でポンと胸を叩いて見せると、
「まったく、軽々しい奴だよ。」
と言って、木村は嘆息した。
木村は尾藤の話が一段落すると直ぐに杉並署に戻ってしまった。
飯を食い始めてから正味三〇分も経っていなかったが、どうやら本当に忙しいらしい。
(仕事を増やしちゃったのは、申し訳なかったかな? )
現在の時刻は一四時を少し過ぎたところ。
既に恵子からは港女子学園の司廉子の担任と無事アポイントが取れたとのメールが届いていたが、約束の時刻は一五時半である。
港女子学園はJR阿佐ヶ谷駅から歩いて約一五分ほどの近距離にあるので、時間が余ってしまった。
(まあ、いいさ。今のうちに書類に目を通しておこう。)
そう思って、足元に置いていたバックを取り上げ、その中からをタブレット端末を取り出してインターネットに接続した。
転送されてきたファイルを確認してみると、恵子に入力を頼んでおいた資料が全て完成しており、分類も明快で読みやすく整理されていた。
(まったく、恵子の手際の良さには感心させられるよ。あいつが辞めた後はどうしたら良いんだろう? あいつのいない仕事の段取りを考えたら恐ろしくなるわ。)
尾藤の脳裏を恵子のドヤ顔が過った。
捜索対象、司簾子(つかさやすこ)。
年齢、一四歳。
一一月一〇日生まれ、さそり座。
血液型、A。
自宅、荻窪。
港女子学園二年生。
バレーボール部所属。
学校の成績は中くらい。
失踪前までの出欠状況は皆勤。
趣味はアニメとゲーム。
交友関係は良好で、親友は二名。
過去に、いじめ等の対象になった記録は無い。
記入された個人情報を見る限りでは、全く特殊性の無い、歳相応で一般的な少女像が浮かんでくる。事細かに記された家庭環境についても注目すべき点は無く、その内容を素直に受け取るならば、確かに両親が言うとおり家出の可能性は見当たらない。
却って家庭への依存度の高さが目に付くほどだった。
(うーん、家庭が裕福ってこと以外に目立った要素が無いなぁ。)
それならば営利誘拐の線が濃いように思えるのだが、誘拐後に犯人からの接触が無いのでは、その可能性も薄いように思える。
(ストーカー等の気配も無しか。)
学校の登下校時と週二回通っている予備校の送り迎えは母親が自家用車で欠かさず行っているので、これまでに不審者による尾行や接触があったことはない。但し、これは気付かなかっただけかもしれないので、身近な関係者に取材すれば別な情報が得られる可能性はあるかもしれないのだが、
(つまり、現状では目立った手掛かりは無しというわけだ。)
他の可能性、例えば強姦目的などの偶発的で無計画な誘拐だとしたら捜索は非常に困難になるだろう。その場合、既に司廉子は殺されてしまっているかもしれないし、生きていたとしても全く見当のつかない場所に監禁されてしまっているのかもしれない。
(そうなったら、こっちは手の打ちようが無いんだよな。)
そうでないことを祈りながら尾藤は書類を閉じ、次にコピーしておいた写真を見直し始めた。
最初に、屋外で撮影された写真をピックアップし、解像度の限界まで拡大して細部のチェックを行った。万が一、不審者らしき人物が写り込んでいれば見逃さないつもりで、建物の影や窓ガラスの写り込みまで入念に調べてみたのだが、
(怪しい人物は見つからない。)
そもそも、行方不明になることを予測して撮影している写真ではないのだから、画像から被写体の周囲の状況を細かく探るには限界があった。
(中学生なら、携帯通信端末で撮影した画像が沢山あっただろうに。)
残念ながら端末は、本人と一緒に行方不明である。
先ほど木村にトレースを頼んだのは、実は本人の行方を探るというよりも、端末のメモリ内や愛用しているクラウド上に蓄積されたデータの入手を期待してのことだった。誘拐ならば端末は犯人によって早々に捨てられてしまっている可能性が高いが、回収可能な場所に捨てられていたならば、画僧やメール、SNSや着信履歴などのデータが手に入るかもしれない。
だが、今のところは手元にあるデータのみで我慢するしかない。
尾藤は続いて仲の良い友人たちと撮影した集合写真のチェックを始めた。
複数の写真に登場している友人が数名見受けられたので、その点に留意して分類を進めて行くと、特に仲の良さそうな者は二名に絞り込めることがわかった。
(そういえば、書類に書かれていた親友も二名だったっけ。)
当然、この二名は今後の調査対象になる。
何らかの手段を用いて接触してみる必要がある。
まずは写真を見ながら髪型、ファッション、所持品などを確認しておくことにした。それらを確認することで二人の大まかな趣味や個性が推測できるだろう。
(一人は大柄で痩身、髪が長く目の細い地味なタイプ。もう一人はショートの髪型で小柄小太りだが目鼻立ちがハッキリとしていて表情の豊かなタイプと・・・ )
写真を捲っていた尾藤の手が止まった。
(変なアクセサリーだな? )
それは学校の校門近くで撮影された写真の中の一枚。
二人の親友と司簾子が制服姿で並んでいる写真なのだが、小柄な方の友人が持っているスクールバッグにぶら下がったチャームに目が止まったのだ。
(いったい何だろう? この違和感? )
バックチャームの先には白い円形のマスコットがぶら下がっていたのだが、そのマスコットの意匠が奇妙に見えた。
写真は高解像度で撮影されていたので、限界まで拡大率を上げてみると細部まで良く見えるのだが、
(変な模様? イラストか? )
マスコットの中央には、細い線が規則的に絡み合いながら丸く放射状に伸びたマークらしき図形が黒色で描かれていた。【図1】
タンポポの冠毛を図案化したマークのように見えるが、そのタンポポの周囲を小さな記号の配列が取り囲んでいる。この記号、見様によっては例えばアラビアやハングルのような文字に見えなくもない。
(文字だとしたら、なんて書かれているんだろう? )
だが、尾藤がバックチャームを一見して奇妙な違和感を覚えたのは、そんな細かなことに対してではない。
女子中学生が持つにしては全く可愛げが感じられないことに対してであった。
薄いプラスチック板を粗雑な手作業で歪に丸く切り抜いたように見えるマスコットは、到底市販のモノとは思えず、手作りに違いないと思うのだが、その意匠は可愛くも無ければ綺麗でもない。
今時の女子中学生の持ち物とは到底思えなかった。
(趣味は人それぞれだから別に構わないけど、まあ特異なセンスの娘なのかも。)
尾藤は心に妙な引っ掛かり感じていたが、現在進行中の作業の中で、いちいち女子中学生のアクセサリーに構う必要は無いと思った。
(中高生の間で流行っている新手のおまじないか、癒し系グッズの類かも。もしかしたら単なるネームプレートなのかもしれない。お嬢さん学校には帰国子女も多いだろうし、自分の名前を日本語以外で書く習慣があっても不思議はないし。いずれにしても調査に関わるような重要な問題じゃないだろう。)
そんな風に納得してから、次の写真を捲った。
写真を眺めているうちに、いつの間にか時刻は一五時に近くなっていた。
(一五時過ぎたらベイジョに向かうとするかな・・・んん? )
馴染の無い呼称を試しに使ってみたら、意外にシックリきた。
短くて呼びやすいし、語呂も良い。
たぶん、オジサン周辺での会話では使う機会など無いかもしれないが、気に入った。
(んじゃ、ベイジョを訪れる前に、もう少し事前情報を入れとこう。)
手持ち情報が不足していたら、せっかく司廉子の担任に会ったところで、満足な聞き取り調査が行えないかもしれない。
そこで、尾藤は写真を捲る速度を速めたのだが、また先ほどと同じ理由で手が止まってしまった。
(この子、私服でも同じものを持ち歩いているのか? )
今度は浦安の某テーマパークに遊びに行った際に撮影されたスナップ、小柄な方の友人と司廉子のツーショットである。
スクールバックに付いていたバックチャームと同じものが、今度はショルダーポーチにぶら下がっていた。
(これはホントに似合わない! ネームプレートってことも絶対に無いわ! )
テーマパークのオリジナルキャラクターがプリントされたピンク色のポーチにぶら下がる、白地にタンポポマーク入りのマスコットは大きさも中途半端でバランスが悪く、違和感が丸出しで可愛そうなぐらい悪目立ちしていた。
(うーん、誰か指摘してあげる友達はいないのかよ。)
司廉子も含め、他の娘たちの中で同じチャームを持っている者はいない。
(ってことは、別に仲間内で流行っているわけでもないんだな。この娘の個人的なお気に入りなのか? )
今度は、あまり納得できなかったのだが、
(おっと、こんなモノに寄り道している時間は無いって。)
と、自分に言い聞かせ、次々に写真を捲っていたら時刻はあっという間に一五時を過ぎてしまった。
「社会人は余裕を持って行動すべき。」
と、心の声が聞こえてきた。
途端に何故だか背中と掌に冷や汗が滲んできた。
(なっ、なんで冷や汗? これって、今朝、恵子に怒鳴られた後遺症? )
未だビビり続けている自分に呆れてしまった。
尾藤は写真のチェックを現在開いているところまでとしてマークすると、タブレット端末の電源を切ってバックに戻した。
そして、カップに残っていたコーヒーを一気に飲み干すと直ぐに腰を上げた。
「ベイジョ到着予定は約束の一〇分前。これで正しい社会人だよね、恵子さん。」
[五]
ベイジョ、正式には港女子学園中高等学校。
尾藤が訪れた時、正門前の通りには授業が終了する一五時半を目掛けて娘を迎えに来た親たちが車列を作っていた。
今時、未成年が通う学校界隈では当たり前になった街角風景である。
お嬢さま学校に限らず、特に私立の学校では親が子供の送迎をすることが半ば義務化されており、余程の事情が無い限り生徒が徒歩や自転車で帰宅することは無いと聞く。
都内の治安が悪過ぎるのだから止むを得ないことだと思うが、友達や彼氏彼女と連れ立って下校するという、尾藤の世代では当たり前だった風景は失われてしまった。
街をブラブラしてウィンドウショッピングしたり、行き付けの店で買い食いしたり、ゲーセンやカラオケで遊んだり、最早そんなことは出来ない時代になったらしい。
一〇代に付き物だった友情系や恋愛系のリアル青春ドラマやイベントも、始まる切っ掛けが極端に少なくなってしまったのではないだろうか。
(真っ直ぐに帰宅して、自宅に引き籠って遊ぶか、勉強するだけなんてな・・・ )
何とも味気ない、可哀そうな時代になったものだと思う。
(それにしても、この状況下で下校する女子生徒を密かに拉致するなんて、余程上手にやらなきゃ無理だ。)
下校時間に於ける人目の多さは、部活終了後も同様であるに違いない。
そもそも司廉子が失踪した当時、ここには母親が車を停めていたわけで、正門から出てきた娘が誰かに浚われそうになったら気付かないはずがなかった。同じ理由で、娘が一人でこっそり正門を出て、そのまま行方をくらますというのも無理だと思う。
それに、女子が通う学校だけあって、周辺には人間以外の目も多数働いている。
通りすがりに正門付近を目視で確認したところ、五機の街頭監視カメラが作動しており校地正面を通過する際に死角を見付けるのは、ほぼ不可能だった。
(当日の司廉子は正門を通ってない。)
街頭監視カメラの映像記録は、過去二四時間以内であればインターネットを通じて一般に公開されているので司夫妻は真っ先に確認しているはずだったが、そのことに言及しなかったということは映像記録の中に手掛かりが見付けられなかったからだろう。
(彼女が失踪したのは下校する前の段階。仮に誘拐されたとしたなら、正門より内側でということ。)
だとすれば、当日の状況を把握する上で、校地内の検証は絶対に欠かせない。
だが、おそらく警察は未だ手を付けておらず、事件発生から一〇日も経ってしまった今日、たった一人の民間調査員によって初めての現場検証が行われるのである。
(ヤレヤレ、こんなじゃ都内の治安が悪化するのも当たり前だわ。)
尾藤は調査すべき内容を、頭の中で素早く整理しながら正門を潜った。
(・・・おおっ? )
漠然と校地に足を踏み入れた途端、一変した辺りの空気に気圧されるのを感じた。
思考が一時停止してしまった。
ここが女子校であることは当然知っていたわけだが、それに対する認識が甘かった。
一〇代の女子たちが発散するエネルギーが満ち満ちた空間に足を踏み入れるのだから、心の準備ぐらいしておけば良かったと思う。擦れ違うのは制服姿の女子ばかり、しかも皆が自分の年齢の半分以下ということに気付くだけで、かなりの圧迫感である。
何処からともなく聴こえてくる管楽器の音、体育会系の掛け声、なんだか良く分からないハイテンションな女子の叫び声・・・これら懐かしくもある各種効果音の数々も、既に三〇代半ばに達したオジサンとは隔絶された、近寄り難いネクストジェネレーションの世界だった。
尻込みしながらも、尾藤は内心で少しだけホッとしていた。
壁一枚隔てた世間が如何に住み辛くなろうとも、校地の中では昔と何ら変わることのない学校生活が十分に残されていることに安心したのだ。
(でもねぇ、ちょっとオジサンには刺激が強過ぎてビビっちゃうけど。)
これから、校舎正面中央に見える来客用玄関へと向かおうとしているのだが、その足取りは聊か緊張気味だった。
尾藤はロリコンではないから、別に女子校生の目を意識して恰好良く歩こうなどと思っているわけではない。すれ違った途端に「キモイ」とか「ウザイ」とか「クサイ」とか言われたら嫌だなぁと思いながら、ステレオタイプな女子校生のダークサイドを想像して、勝手に被害妄想しているだけなのである。
「お前のことなんて誰も見てないし、誰も気にしちゃいないよ! 」
自意識過剰なのだと心の声に笑われてしまったが、実は尾藤には女性に対して気弱で消極的になってしまうという一面がある。
子供の頃、近所に住んでいた気の強い女の子に苛められたり、散々引き摺りまわされて損な目に遭わされた経験がトラウマになっているのだと自覚している。
(幼馴染の○○ちゃん、可愛かったんだけどねぇ。性格はアレだったけど・・・ )
実は、それが初恋だったりするのだからツイてない。
子供心が大人に成長する過程に於いて、受けたマイナス面の影響は小さくない。
そんな性質なので、恵子のような美人で気の強い女性には、特に圧倒されやすいというわけなのだが、それは余談。
来客用玄関の脇にある受付の窓口で、事務員にアポイントの有無と司簾子の担任名と用件を告げ、入校許可証を受け取った後に会議室のような部屋へと案内された。
「こちらで少々お待ち下さい。」
片側に一〇人程度が並んで座れるほどの広々とした長方形の会議テーブルの端に腰掛けて待っていると、年配の女性事務員がお茶を運んできた。
彼女が一礼して退室した後、担任はなかなか現れず、それから一〇分間程、会議室内の意匠を見回しながら時間を潰していた。
昭和初期に建てられたという洋館作りの二階建て校舎は、外観に歴史的建造物と言っても良いほどの風格が感じられたが、その内部もなかなかのモノだった。じっくりとを時間を掛けて見物してみたいと思うほどに魅力的な校舎だったが、この会議室の中だけも見所は十分にある。
例えば、植物をモチーフにした有機的なレリーフが施された木製の扉と、同様のデザインで年季の入った真鍮製のドアノブ。一般の家屋なら二階建て分ほどの高さがある漆喰で白く塗り固められた天井にも植物柄のモールディングが一周しており、中央にはアンティークな拵えの三灯式ランプが吊り下がっている。校庭に面した壁面に二つ並んだ縦長の窓は、黒い金属製の窓枠にステンドグラスが嵌っていた。
全体的に、アール・ヌーヴォーの影響を受けた時代の古さを生かし、今もなお格調高さを維持し続けることを目指した室内装飾である。
但し、床だけは残念なことにリノリュウム製のシンプルな素材が使われており、そこだけが他と比べて新しく、ビジュアル的にアンバランスだった。この建物が学校として使われている以上、大勢が出入りすることで消耗しやすい床だけは、耐久性と機能性を重視した構造にならざるを得なかったのだろう。
それでも、滅多に見ることの無い珍しい建物であることは確かであり、ボンヤリと眺めているだけで、待たされている時間が気にならなくなるほどだった。
ところで、会議室内には内装以上に尾藤の目を引いたモノがある。
如何にもミッション系の学校らしさを醸し出すアイテム、聖母像であった。
決して古いモノではなく、レジン製のレプリカに決まっているのだが、レトロな内装の室内に置かれていると、価値ある芸術品、霊験あらたかな品のように思えてしまう。
その聖母像は、窓から注がれる西日を背にして、古めかしい木製台座の上に鎮座し、会議テーブルに座る尾藤へ慈愛に満ちた視線を送っていた。
(たいへん、有難いことなんだけどさ・・・ )
相手が生きている人間ではなく作り物の人形だと分かってはいるが、閉めきった部屋の中で一対一になり、無言で見つめられているというのは決して心地良いものではない。
日頃、信心とは縁の遠い所で生きている俗物にとっては、まるで神聖な女子校内で悪さを働かないようにと見張りを付けられているように感じられ、実に居心地が悪かった。
コンコン!
漸く、ドアをノックする音が聞こえた。
「お待たせいたしました。」
少々鼻に掛った甲高い声で挨拶しながら、三〇代後半と思われる地味なグレーのスーツを着た男性教員が現れた。
「お仕事、ご苦労様です。私が司の担任をしております出角(でかど)と申します。」
尾藤は直ぐに立ちあがって挨拶をし、名刺を交換した。
出角の体格は痩せ形で、身長は一七〇センチぐらい。真ん中分けにした短髪、一重瞼の細い目、頬骨が張り、顎は尖り気味、少々気難しそうで、神経質そうな印象を受ける容貌の男である。
二人は名刺を受け取ってから立ったままで二言三言の短い会話を交わしたのだが、その際に尾藤は、出角の丁寧に聞こえるが目線の高過ぎる物言いが気になった。
(まるで、人をいなそうとしているようだ。)
聞き分けの無い生徒を相手にして、いつも高所から見下ろす姿勢で仕事をしなければならない学校の先生という職業では身に付きやすい話し方をする男なのだが、尾藤は即座に苦手なタイプだと判断していた。
出角は司夫妻が調査会社に娘の捜索を依頼したことを知っていた。名刺を受け取る前、挨拶した時点で、目の前にいる尾藤という男が調査員であることも承知していた。
「近いうちに、司さんが雇った探偵が私の所に現れるだろうと思ってましたよ。」
などと、訳知り顔で言う。
「いえ、探偵ではありません。名刺にも書いてありますが調査員です。」
尾藤は言い返した。
探偵も調査員も意味は同じことで、どちらでも良いのだが、尾藤は「探偵」とか「私立探偵」などと言う呼び名が生理的に大嫌いだった。語感が軽々しくて、フィクションに出てくる登場人物と重なりやすく、浮世離れした職業だと思われがちだったりするのが鬱陶しかった。一般社会人としては、自分の職業に重みを持たせたいというか、真面目さを強調したいという気持ちがあり、そういうわけで自分の肩書を「調査員」としている。
だからと言って、クライアントや調査対象者を相手にして、そんな拘りを見せなくても良いと思うのだが、尾藤は出角という男に対して生理的に受付け難い反感を感じており、逆らってみたくなったのだ。
一方、出角の方も、会った瞬間から何故だか尾藤に対して敵意を抱き、身構えているような態度を示している。
もっとも、世の中の善良な一般市民は、調査員、私立探偵などという職業の人間に接するにあたり、多少の警戒心を持って身構えはするものなのだが、
(これは、お互いに、あまり良い出会いじゃないらしいな。)
尾藤は密かに嘆息した。
「さて、その後、司の件について、何か新たな進展はありましたかな? 」
会議テーブルに向い合って座るなり、出角が尾藤に報告を求めるようなことを言った。
ワザとだと思うが、まるで上司が部下に対するかのような口の利き方である。
(おいおい、自分がクライアントでもないくせに、随分と偉そうな口の利き方をする奴だな。俺は報告じゃなくて、調査活動に来たんだよ! )
偉ぶるのが癖なのか、どうにも厄介な性格の男のようである。
尾藤は少しだけ腹を立てていたが、ここで反発してしまっては仕事が始まらない。
平静を装い、事務的に話を進める業務モードに徹することにした。
「私が依頼を受けたのは今朝ですから、未だ進展などという段階にはありません。司さんから聞いた話では、この一〇日間で全く手掛かり無しとのことです。」
すると、出角は大げさに首を振った。
「なんだ、そうなんですかぁ。困りましたねぇ。司のご両親はさぞ心配していたでしょう。まったく可哀そうにねぇ、お察ししますよ。」
と、落胆の溜息をついた。
(尊大な態度 + 定型文的な落胆表現 + 多少芝居がかった態度)
尾藤は、出角の印象に関するメモに、そう書き込んでおいた。
別に意趣があるわけではなく、ごく当たり前の作業として出会った関係者の人間観察をしているだけである。
それにしても、これから自分が受け持つクラスの生徒の安危に関わる話をしようとしているというのに、出角は意外に事件から遠ざかったことを言う。
自分は当事者ではなく第三者であり、傍観者であると言いたげだった。
「うちで事情を知っている教職員は皆が心配していますよ。下校時に行方不明になってしまったからには、学校側にも多少の責任があるかもしれませんからね。」
(なるほど、多少ですか・・・ )
出角の偉そうな態度の裏にある、学校側の意図を垣間見たようだ。
彼の言葉は、学校にも責任があると認めているように聞こえるが、実のところ責任はホンの少しであり、殆ど無関係とのニュアンスを含んでいる。予め責任の有無を問われないよう、言葉の予防線を張っているのだ。
組織に属し、それを守ろうとする者なら「責任回避」は当然用いるべき防衛手段と理解するが、学校の先生、しかも担任ならば、生徒の心配を優先して欲しい。
「ところで、司さんの件、御校の教職員の皆さんは、全てご存じですよね? 」
校内で聞き取り調査をする相手を選ぶために聞いておこうとしたのだが、
「いいえ、管理職と事務局員一名、担任の私、それと部活の顧問だけです。」
その一言で、選ぶ余地が無くなってしまった。
尾藤は「そんな馬鹿な! 」と、言い掛けてグッと飲み込んだ。
校地内で生徒が行方不明になって一〇日も経ったというのに、事件を知らされていない教職員が大勢いるというのは驚きだった。普通ならば緊急教職員会議でも招集して、全員が認識を共有し、父母や警察への対応を考え、再発防止に取り組まなければならない。
それが、学校というモノだろう。
しかし出角は、尾藤の常識の外側を行く。
「あとは、その場に居合わせた同じ部活の生徒数名ぐらいですが、彼女たちには絶対に口外しないようにと厳しく指導していますから大丈夫です。他の生徒には全く漏れていませんよ。」
まるで、事件を伏せておくことが正しい対処方法であり、それが上手くいっていることを自慢しているようだった。
しかも、尾藤に対してまで、
「念のために申し上げておきますが、貴方も、あまり司の件について校内では話されないよう願います。」
などと、部活の生徒たちと同様の口止めをしようとする。
学校関係者相手の調査活動をするなと言っているようなものである。
「伏せておく必要がありますか? 」
尾藤は内心イラッとしながらも平静を装った顔で、当然そこに生じる疑問を投げかけてみた。
「うちは思春期のデリケートな女子生徒を大勢扱っていますからねぇ、このような事件を考え無しに公表してしまっては、大変なパニックに陥りかねませんよ。だから、慎重に様子を見ているところなんです。」
出角は臆面も無く、欺瞞に満ちたセリフを口にした。
生徒に対しては、そういう配慮の仕方があるのだとしても、教職員にまで事件を伏せておくのは全く理解できない。
「いやいや、部外者の方はそう言いますけど、この手の話は興味本位で広がりやすいですからね。恥ずかしながら我が校の教職員にも口の軽い者がおりますから、迂闊なことはしたくないんですよ。」
(違うだろ! 口の軽い者がいるんじゃなくて、学校が事件を隠そうとすることに反発する教職員がいるってことだろ? )
それにしても、このまま関係者の目と耳と口を塞いで大人しくさせていれば、その間に事件が解決されるとでも思っているのだろうか?
もしくは、学校とは関わりの無い、遠いところで事件が有耶無耶になって忘れられるとでも思っているのだろうか?
伝統校、名門校の高いプライドの壁の中で暮らしているうちに、世間一般の常識を忘れてしまったのだろうか?
(何とも呆れた話だね。)
責任回避どころか、事件の存在自体を無かったことにしようとしている。
そんな馬鹿げた考えのおかげで、現在の学校内では事件に対する厳重な隠蔽体制が敷かれ、大勢の先生や生徒がいるにも拘らず、尾藤が接触可能な対象は非常に少なく、数名に限定されてしまったことになる。
(マジ面倒臭ぇ! )
警察と違って、民間の調査員では強権を用いて調査活動を行うわけにはいかない。どんなに重要な調査活動であっても、調査対象の方針には逆らうことができないので、ダメと言われれば諦めざるを得ないのだ。
(しかし、こんな事件の可能性が高い、人命に関わるかもしれない事柄を伏せておくのが学校の、いや教師のすべきことなのか? それって許されることなのか? )
おそらく、許されるかどうかなど考えてもいない。
学校が抱くのは、不祥事に対する過剰な警戒心。
伝統校、名門校の評判に傷を付けたくないという営利的な思惑。
これらの動機によって後押しされ、無計画に行われている消極的な対策なのだろう。
おそらく、先の見通しなど無く、事件が学生や保護者の周知になることをギリギリまで避け続けようとするだけなのである。
(馬鹿馬鹿しいねぇ。)
勝手にすれば良いと思わないでもない。
この先、万が一にも司廉子が死亡していた場合、学校が事件の存在を隠すことを生徒の安危よりも優先していたことがバレたら、被る痛手は不祥事や評判を落とすなどというレベルではない。
学校に有るまじき行為、悪質な非人道的行為として、世間の袋叩きに会うはずだ。
(そんなことも分からないほど馬鹿なら、勝手に自爆すれば良い。)
しかし、仕事を邪魔されるのは勘弁して欲しい。
尾藤は事件の解決を目指している。
司廉子を無事に探し出すために、できる限りの手を尽くしたいと思っている。
そんな尾藤に非協力的だったり、妨害めいた行為を働くなら、犯罪を幇助しているのと何ら変わりはない。それは、もはや道義的な問題ではなく、後々に罪を問うても良いほどの悪事かもしれない。
もし、尾藤が警察官だったなら公務執行妨害に当たる行為である。
(そこら辺を自覚していないのだとしたら、多少大げさに思い知らせて脅しをかけてみるのも悪くないなぁ。)
相手は良心を捨てた教師だが、罪までは犯したくないだろう。
司廉子の安危について大きな責任を取らされるのも嫌なはずだ。
相手の弱みを見付けて、リスクを誇張し、脅したり賺したりするのは尾藤の得意技だったりする。そこまでやるかどうかは、この後の出角の出方次第だが、いざとなったら追い詰めてやるつもりで、その作戦を考えつつ尾藤は本題を進めることにした。
「早速ですが、いくつか質問にお答え下さい。」
そう言ってタブレット端末とペンを持つ。
ついでに、ボイスレコーディングソフトも起動させて取材準備を整えた。
「大してお力になれるかどうか、わかりませんよ。一〇日以上も前のことですから記憶が曖昧ですし、こんなことになるなんて思いもしませんでしたからね。それに、私も忙しい身ですから、司の件だけに関わってられないんですよ。」
初っ端から非協力的な前置きをするので、尾藤はテーブルを叩きそうになった。
何とか堪えて、まずは当たり障りの無い質問から順に始めることにした。
「憶えている範囲だけでかまいませんから、お願いします。」
「まあ、いいでしょう。」
「出角先生が、最後に司さんを見たのは何時頃ですか? 」
「六講時の授業は私でしたので、その時です。」
「放課後は? 」
「見てませんね。彼女は放課後直ぐに部活があるので、授業が終わると同時に体育館に向かったと思います。」
「当日、司さんは部活に最後まで参加されていたんですよね? 」
「顧問からは、そう聞いています。」
「それじゃ、最後に司さんと会ったのは顧問の先生ですか? 」
「いや、道具の後片付けや更衣室での着替えの際には部活の友人たちと一緒だったようです。だから、最後に会ったのは部活の友人たちでしょうね。」
「その部活が終了したのは一七時半頃と伺っていますが、間違いないですか? 」
「それは間違いないです。うちは時間に厳しいですからね。」
ここまでは、既に司夫妻の書類で確認済みのことばかりなので、尾藤は出角の認識に相違がないか確認するつもりで聞いていただけだった。
決まり事ばかりなので出角も躊躇うことなく受け答えしていたが、次の質問からは少々答えが躓き始めてきた。
「では、司さんを最後に見た部活の友人が誰なのか、何人いるのかを教えていただけませんでしょうか? できれば、その方たちに直接お会いしてお話を伺えればと思うのですが、いかがでしょうか? 」
出角が露骨に渋い顔をした。
「困りますよ。せっかく彼女たちには緘口令を布いているんですから。」
(出たよ! )
尾藤は、またもやテーブルを叩きそうになった。
仮に有力な情報を持っている生徒がいたとしても、これでは経過する時間とともに記憶は鮮明さを失ってしまう。
「そもそもバレー部員は二三名もいますし、その中の誰かと最後に会っているとは思いますが・・・でも、誰なのかは知りませんよ。」
「え? 知りませんって、居合わせた生徒の名前を控えてなかったんですか? 」
仮にも生徒一人が行方不明になっているのである。本気で心配しているのならば、学校としても当日の状況を記録しておくぐらいするものだと思うが、何もしていないらしい。
この一〇日間、事件を公にしない手段だけを考えていたようだ。
この答えを聞いた時、尾藤は軽蔑心の籠った呆れ顔を隠し切れなかったらしい。
それを見て、さすがに出角もマズイと感じたようだ。
「我々としては、徒に生徒の恐怖心を煽って動揺させたくないんです。皆、微妙な年頃ですから。」
取って付けたような言い訳をした。
(何を言いやがる! )
自らの卑怯な思惑と怠慢を正当化しようとする態度にムカついた。
それでは、司簾子はどうなるのか?
他の生徒を動揺させないために、見捨ててしまおうと言うのか?
(金持ち相手の伝統校、名門校とは、こんなに冷たいものか? )
心が冷える思いだった。
先ほどまでは魅力的に見えていた校舎が、魔窟に見え始めてきた。
これ以上、この場で事件の関係者に接触させろと食い下がってみても埒が明かないと見た尾藤は質問の仕方を変えてみることにした。
「この中に同じ部活で仲良しの娘がいると司さんのご両親から聞いてますが、どの娘さんか分かりますか? 写真と名前の照合をしたいので協力して下さい。これは司さんのご両親に頂いたデータなので、今更私が名前を伺ったとしても問題は無いと思いますよ? よろしいですね? 」
タブレット端末に、予め取り分けておいた司簾子が友人たちと写っている写真を表示させながら言った。
「まあ、それぐらいならば・・・ 」
出角が渋りながらも承知したので尾藤はタブレット端末を手渡した。
互いの手がタブレット端末を介して繋がった一瞬、尾藤の手に出角から微かな振動が伝わってくるのを感じた。
(こいつ、震えてるのか? )
学園上層部の意向を受けて事件の隠蔽を計ろうとしているヒラの教員が、事情聴取を受けている最中にボロを出さないようにと緊張するのは頷ける。
(だが、震えるほどのことか? )
意外に気の小さい男なのかもしれない。
(ってことは、隠し事をしようとすると態度に現れやすいかも。)
一〇年以上のキャリアを持つ調査員を相手にして、嘘や隠し事を押し通すのは難しい。
尾藤の目は、同業者の中でも鋭いと評判である。
出角の手元や表情に微かな変化が表れでもしたら絶対に見逃すことは無いだろう。
そして、微かな変化を見付けたならば、即追及してやるつもりでいた。
暫くの間、出角は尾藤を前にして黙って写真を捲っていた。
(今のところ、反応なし。)
特に仲の良いと思われる例の二名が写っている写真は後半に配置し、前半はスナップや集合写真を適当に並べて置いただけだったので大した反応は期待していない。
そして、いよいよ肝心の写真を捲り始めたところで、
「ああ。」
出角が声を上げた。
意外にあっさりと反応があったので、せっかく身構えていた尾藤の気勢が削がれてしまった。
出角がタブレット端末を尾藤に向けて写真を示した。
「この右端、確かバレー部ですよ。」
先ほど、喫茶店で尾藤が目を止めた写真。
校門の前で、二人の「仲の良い友人」と横一列に三人で並んだ写真である。
尾藤はタブレット端末を受け取り、右端の友人を拡大した。
出角が指したのは長身の方の娘だった。写真の真ん中は司廉子、左に例の奇妙なバックチャームをぶら下げている小柄な方の友人が立っている。
「お名前は? 」
「里田かおる、クラスも同じですよ。」
その名前は、仲の良い友人ということで司夫妻が記入した資料にもあった。
「よろしければ、この後で里田さんに会いたいのですが? 」
尾藤はメモを取りながら言った。
「それは残念でした。里田はお休み中なんですよ。インフルエンザで暫くは登校停止でしてね。」
出角の声音には微かな安堵感のようなモノが感じられたが、面倒な引き合わせをしなくて済むからなのだろう。
「そうですか・・・ 」
随分タイミングの悪い話だが、
(本当か? 嘘じゃないのか? )
尾藤は疑ったが、追及する手が無い。
「では、里田さんの連絡先を伺ってもよろしいでしょうか? 」
「それは無理ですね。生徒の個人情報はいかなる場合でも外部の方にはお渡しできない規則ですから。」
規則を盾にとって、出角の物言いは些か強気だった。
「いかなる場合でもですか? 但し、今は非常時だと思うのですが? 」
まあ、娘の親友の連絡先なら司夫妻が知っているはずなので、出角から無理に聞き出す必要は無いのだが、試しに尾藤は少し食い下がってみた。
「無理です。規則ですから。」
出角は一瞬うろたえたが、言い切った。
こうハッキリと断られてしまうと、尾藤にはどうしようもない。
「了解しました。里田さんにお話を聞くのは後日にします。ちなみに、この左側の娘はバレー部じゃないんですか? 」
「この娘は帰宅部ですからね。もう帰っちゃったんじゃないですか? 」
さらりと流されてしまったが、
(帰宅部なら、失踪当日も学校にいなかったってことだから・・・ )
急ぎの調査対象にはならない。
写真のチェックはここまでにして、尾藤は再びタブレット端末をデータ入力モードに切り替えて、ペンを片手に聞き取り体勢に戻った。
「それでは、今日は担任の先生に、もう暫くお付き合いをお願いします。」
「まあ、私でよければ。」
出角は軽く答えたが、尾藤を学生に引き合わせるという学校としてはあまり好ましくない要請を、上手に回避できたので気が楽になったようである。
「司さんが姿を消す前に予兆のようなモノはありましたか? 例えば家出したくなるような要因があったりとか、学校外で親しい友人と会うような約束をしてたりとか、悩み事を抱えている様子とか無かったですか? 他にも何か気付いた点があれば、何でも話して下さい。」
「別に変ったことはないなぁ。一応担任ですから、毎日顔を合わせてますがね、予兆なんてものは見当たらなかった。気付かなかっただけと言われればそれまでですが、大勢の生徒を相手にしているんで、一人の細かな変化を見落とすこともありますよ。」
確かに、それはそうだと思う。
こういった質問は先生よりも友人に聞いた方が良いかもしれない。
だが、一応念は押した。
「でも、良く思い出して欲しいんです。虐められてたりしてませんでしたか? 学校外に彼氏が出来たとかないですか? 」
「全く無いですね。毎年調査はしてますけど、虐めの対象になっている様子は無かったですよ。それに、うちは男女交際禁止ですからね。親の送迎もあるし彼氏を作る隙は無いでしょう。」
学校が行う虐め調査に関しては当てにならないが、確かに学校や予備校の送り迎えに毎度親が出てくるような環境では男女が出会う隙は無い。
尾藤は頷いて、次の質問に移った。
「では、校門の外で待っていたお母さんから、娘さんが現れないとの連絡を受けた時の話を伺います。その時、先生はどのように行動し対応されましたか? 校内を探されたと思いますが、その移動経路も詳しく思い出して下さい。」
出角は、少し首を捻りながら難しい顔をした。
「まるで、僕の取り調べをしているみたいに聞こえるな。」
こうした面談での事情聴取など、出会った人間すべてを取調べしているようなものなので出角の言う通りなのだが、それを認めてしまったら喧嘩になる。
「そうではありませんよ。当日の行動を辿ることで、改めて思い出せる記憶があるかもしれないんです。ですから、もう一度、じっくりと考えなおして答えて下さい。お願いします。」
「まあ、やってみますか・・・ 」
出角は腕を組んで時々目を瞑りながら、当日の自分の行動を語り始めた。
「そろそろ帰ろうと思っていた時刻なんで、一九時は過ぎていたと思うな。事務局から内線で、司の母親が娘が出てこないので調べて欲しいって言ってるって連絡があったんですよ。慌てて玄関に下りて行って、事情を聞いて、残っていた事務局員とバレー部の顧問と三人で手分けして校舎内と学校の敷地を一回りしました。」
「最初に探しに行った所は何処ですか? 」
「教室、いやバレー部の部室が先だった。その次が教室。」
「その時、他の生徒は皆帰宅してたんですか? 部室や教室に異常はありませんでしたか? 例えば窓が不自然に開いていたとか、扉の鍵が開いていたとか、物音を聞いたとか無かったですか? 」
「無かったと思う。というよりも、そんなに大げさな事とは考えていなかったから、各部屋の入り口から中を一通り見まわして、声を掛けたぐらいで出て来てしまったよ。だいたい、広い校舎内を数人の教職員で探しまわっているわけだからね、皆が細かな事まで目がとどいていなかっただろうね。」
「そうですか。で、その後は何処を探しましたか? 」
「だから、中等部の校舎を二階から一階まで一回りした。トイレの中も見た。それで全部だよ。」
出角の答えは大まか過ぎて何も見えてこない。
「もっと、細かく話していただけませんか? 例えば、教室やトイレの何処をどのようにチェックしたかとか、校舎内に変わった様子が無かったかとか、窓の外に何か見えなかったかとか・・・ 」
当日の校舎内の様子や人の配置、費やした時間などを話してもらいたい。
「どんな順番で、何処をどんな風に回ったかなんて憶えてるわけないじゃないか。一〇日以上も前のことだぞ! 」
出角は答えるのが面倒になってきたようで、イラつきはじめた。
(短気な奴。)
尾藤は構わずに続けた。
「校舎の外は探さなかったんですか? 」
「外は、事務局員が見まわったんでね。自分は中だけだよ。」
「不信な人物や車を目撃したという方はいませんでしたか? 」
「それは無いな。そんな奴がいたら誰でも必ず報告するでしょう。」
出角が言うように、誰もが事件を予測して動いていたわけではないから、周囲の異常を注意深く観察していなくても不自然ではない。
だが、出角の答え方は淡白過ぎる。
(バレー部顧問や事務局員に聞いてみたなら、もっと違う答えが出てくるかな? )
今一つ協力的でない出角よりも、マシな話が聞ける者がいるかもしれない。
「よろしければ、表を探した方にもお話を伺いたいのですが? 」
「そちらは別にアポイントを取ってもらわなければ駄目ですね。放課後とはいえ忙しいんだから。」
出角はにべも無く断った。
(こいつ、自分が学校の盾になったつもりでいる。)
この調子では、いつまで経っても出角を通して教職員や生徒の紹介をしてもらうのは不可能のようだ。
ここで、尾藤は一石を投じることにした。
「念のために申し上げておきますが、私の職業はご存知ですよね? 」
「探偵、いや民間の調査員でしたかな。そうなんでしょう? 」
出角は「民間」という単語に、幾分力を込めて言った。
国家権力を背負った警察官を相手にするならともかく、非力な民間業者の言うことに一々従ってはいられないと思っているのだろう。能力的にも警察官より劣る相手と踏んで、ハッキリ舐めて掛っているのだ。
このような先入観を持たれることは、様々な調査活動の中で慣れっこになっており、出角の態度も十分に想定内のことである。それについて、ベテラン調査員の尾藤が対抗策を用意していないはずがないのだということを、出角は分かっていない。
確かに、警察の背景にある国家権力という代物は実に使い勝手の良い大きな力であり、後ろ暗い所のある一般市民に対しては効果的な圧力になる。しかし、それを駆使することを許されている警察官は「国家公務員倫理法」により職務を厳しく管理、制限されている。
第一章の総則にある「職務執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する国民の信頼を確保することを目的とする」との文言によって、道徳面や倫理面に関しては、常に模範的な行動を求められる。
ところで、民間業者には倫理法などという法律は無い。
仕事は公務ではなく営利が目的なわけだから、儲けるためには犯罪にならない程度の多少の強引な手段を用いることもあり、それについての規定は自分自身の中にある。
(自慢できることじゃないけど、俺の場合、警察官よりも倫理感覚が鈍いんでね。)
脅しを掛ける場合には、小さなネタを大きく盛り付けたり、火の無い所に煙を起こして相手の弱点目掛けて効果的にぶつけることは常套手段である。
(ここで有効なのは、やはり国家権力なんだろうな。)
尾藤は自分の背後に警察の存在を匂わすことにした。
この際、勢いで多少の嘘を上乗せしたとしても、後で辻褄を合わせれば何とでもなることだと思っており、その点で尾藤には木村という便利で頼もしい友人がいる。
「ま、おっしゃるとおり民間業者なんですけどねぇ、近頃は警察も手が足りないようでして、我々のような者を外注業者として使ったりして、公務を代行させることが多々あるんですよ。」
このセリフを聞いた途端、出角の顔色に若干の変化が見られた。
「それが? 」
聞き返す表情が強張った。
警察が人手不足問題を解消するために民間に業務の外注委託をする事例は多々あり、近頃は別に珍しいことでもなくなっているが、別に尾藤は今回の件で自分が警察の外注を受けているなどとは一言も言っていない。
そのようなニュアンスが感じられたとしても、それは気のせいである。
「今回のような仕事は昔ならば警察が直接携わるべき仕事だったわけです。司さんから杉並署に届け出があった時点で警察官が動いているはずなんです。」
「そ、それはそうなんでしょうね・・・ 」
「でも、今時の警察は多数の事件を抱えて、しかも人手不足ですから直接動けないですよね。困ったもんですよ。」
尾藤は警察が動けないから、代わりに自分が動いているのだとも言っていない。
しかし、こんなセリフを聞かされてしまっては、出角は尾藤が警察の意を受けてやってきたのかもしれないと勘違いし始めただろう。
(んじゃ、ここいらで脅してみようか。)
尾藤はテーブルの上に少し身を乗り出して、声を潜めるようにして言った。
「私は今、失踪人の捜索をしています。そのために必要な事情聴取を行っているわけです。お分かりですね? 」
「・・・承知していますが? 」
「私が調査した内容は全て杉並署の方に提出させていただくことになってまして、もちろん場所や人などは全て実名入りです。誰が、何処で、どのような態度で、どのような話をしていただいたか、警察の方にも分かりやすいように報告書を作成します。」
これは思い切りの出まかせだった。
今のところ警察とは無関係な仕事なのだから、別に調査内容を提出する必要など何処にも無いわけで、事件が無事解決したなら木村には経過説明ぐらいしなければならないと思っているが、その程度のことである。
「予め言っておきますが、報告書に目を通した警察の担当者が、私が聞き取りをした相手に不信を感じたり、情報の不足を感じたりした場合、今度は警察による大掛かりな現場検証や聞き取り調査が行われるかもしれません。その際はご面倒でしょうけれど、宜しくご対応お願いいたします。」
尾藤は「協力しないと警察に言い付けるぞ! 」と言っているわけで、実に単純な脅しである。
そして、ダメ押しをする。
「管内で多発している同様の事件との関連性も考えているようで、私が調査する今回の事件の内容には随分期待していただいているわけです。司さんの携帯通信端末の情報をはじめ、様々な資料の提供をしていただいている手前、私も精一杯働かなきゃと気持ちを引き締めて頑張っているわけですよ。はい。」
尾藤の仕事に期待している者など警察には一人もいない。
同様の事件が多発しているとは木村から聞かされるまでは知らなかったし、それらとの関連性を疑っているのは杉並署ではなく尾藤である。情報や資料も提供していただいているのではなく、木村に強請って出させようとしているわけで、尾藤のセリフの中で真実と言えるのは「気持ちを引き締めて頑張っている」という部分だけだった。
この事実を大きく捻じ曲げたホラ話は、尾藤と杉並署が親密な提携関係にあるという風に思わせるための演出なのだが、出角の様子を窺ってみると狙った効果を十分に上げているようだった。
先ほどまでの尾藤を舐め切った偉そうな態度は鳴りを潜めて、その表情には緊張感が漂い始めている。もしかしたら背中や掌には冷や汗が噴き出しているかもしれない。
尾藤は内心でほくそ笑んだ。
「それでは、これから現場検証のために校地内を拝見させていただきます。よろしいですね? 」
この一言、出角には暴言と聞こえただろう。
怒り、戸惑い、拒絶、危機感など、様々な感情が入り混じった複雑な顔をしていた。
「ちょっと、いきなりそれは、事前の許可を・・・ 」
出角は、面白いぐらいに慌てていた。
事件の存在を隠そうとしている最中に、校地内を調査会社の人間に歩き回られては堪らない。しかも、それを許可したのが自分だということになれば、後で学校の上司からどれほどの叱責を受けることか、考えただけで恐ろしいだろう。
尾藤は笑いが込み上げてくるのを堪えながら真顔で言った。
「それでしたら、杉並署と話してみて、後日私ではなく正式に専門家を伺わせるようにしましょうか? その方が、そちらも納得できるでしょうし、念入りで正確な現場検証が行えると思いますのでね。」
もはや、出角には尾藤の現場検証を断る手段は失われた。
上司からキツイ叱責を受けようが、警察官が大挙してやってくるよりマシだと納得するよりほか無い。
「なら、早速まいりましょう。」
尾藤は勝ち誇った顔で席を立った。
学校という場所は独特の匂いがする。
創立以来一〇〇年以上経過した女子校ともなれば、多くの世代が残した匂いが校舎に染みついていて、不慣れな外部の訪問者をむせ返らせる。
(これがミッション系の女子校ってやつか。昔は憧れたもんだが・・・ )
年季の入った校舎が感じさせる重み、四〇〇名以上いるという女子生徒からの濃い移り香、校舎内の所々に据えられているキリスト像や聖母像が醸し出す緊張感。廊下を歩いているだけで軽い息苦しさを覚えるほどに、尾藤が過ごしている日常とは全く異質な世界である。
(失礼だが、ホラー映画のロケにピッタリだ。)
キリスト教文化に不慣れな日本人ならば、同じ印象を受ける者は多いだろう。
一般的な日本人のいい加減な先入観によると、十字架を見ればキリストよりも吸血鬼を連想するし、ミッションスクールは神様の学校というよりも魔女の巣窟、そしてキリスト像や聖母像はどれも血の涙を流しそうな気がする。
(しかし、こいつはミッション系のイメージに似合わねぇな。)
前を歩く出角の大きく地肌の露出した後頭部を眺めながら思った。
(ただの禿げた中年のおっさんだよ。ホラーの雰囲気はぶち壊しだね。)
廊下で他の教職員とも擦れ違ったが、皆が普通の地味なオジサン、オバサンばかりで、出角に限らず校舎の雰囲気に似合うビジュアルには出会わなかった。
ベイジョの教職員は、皆がカトリックの信者だと聞いていたが、
(まあ、こんなもんだろ。)
日本人にゴシックホラーは似合わない。
「この突き当りに渡り廊下、その先には体育館があって、そこでバレー部が練習してます。申し訳ないですが、部活中なんで外から見るだけでお願いしますよ。運動部の部室は体育館の中ですし、更衣室を兼ねているので、我々は立ち入り禁止です。」
先導する出角は歩きながら簡単に校舎の説明をしてくれる。
会議室を出て直ぐには嫌々な態度を示していたが、諦めて開き直ったようだ。
「その部室から校門までの下校ルートはどうなります? 」
尾藤は歩きながら、タブレット端末に校舎内の略図を描いていた。
「部室からは体育館を通らないと外に出られないですね。その体育館の出入口で部活終了直後に鍵が開いているのは一か所だけ。そこから出て渡り廊下と、今歩いている廊下を通って昇降口に向かうことになってます。」
少し前に通り過ぎてきた廊下の途中に、生徒用の下足棚が並んだ昇降口があった。
「昇降口までの途中で、校舎の外に出入りできるところはありませんか? 」
「渡り廊下からなら簡単ですよ。但し、校則では出入り禁止にしてるので、基本的に誰も出ていかないはずです。それが、ここです。」
出角が廊下の突当りで観音開きの鉄扉を開けると、そこには両側に木製の柵が付いた、トタン屋根の掛かった短い渡り廊下があった。
その渡り廊下は向かい側の体育館入り口までの一〇メートル程の距離を繋いでいる。
但し、この渡り廊下は殆ど校舎外と言って差し支えない。廊下としての仕様はコンクリートの上に張ったプラスチック製のスノコだけであり、渡り廊下という名称は少々大げさで、おそらく内々で言い慣らされている通称なのだろう。
ちなみに、スノコとコンクリートの上から地面との段差は三〇センチほどしかなく、柵の高さも一メートル程度であり、それも体育館の入り口手前で途切れている。
(つまり、昇降口を通らなくても出入りは十分可能なわけだ。)
尾藤は渡り廊下に立って、そこから見える屋外の様子を眺めてみた。
(このまま、校庭を突っ切って正門に行けるし、校舎の裏側にも行ける。たぶん、校舎の裏側から塀をよじ登れば正門を通らずに敷地外に出られるな。)
失踪当日の正門前には母親の車が停まっていたのだから、司廉子は正門から出ていないはずで、他の場所から出たと考えるべきだろう。
「校地内の現場検証はしていないって言ってましたよね? 」
「そうですが? 」
「事件後に警察や他の民間業者が来たってことは無いわけですよね。」
「無いですね。」
そこで、尾藤は面倒臭そうな顔をする出角を急かしながら一旦来客玄関に戻り、スリッパを靴に履き替えてから再び渡り廊下に戻ってきた。
「いったい、何が知りたいんですか? 」
出角は怪訝そうな顔をしながら、尾藤が何をしようとしているのか知りたがった。
「だから、単なる現場検証ですよ。まあ、ついてきて下さい。」
今度は尾藤が先に立ち、渡り廊下の端の手摺が途切れた隙間を通って校舎の裏側に回り込んだ。
「私はこの件が家出なのか誘拐なのか、早々に結論付けてしまいたいと考えています。何らかの誘拐事件である可能性が高いとは思ってますが、実際に裏付けがないと、その証明はできません。だから、確信を持てる証拠を見付けたいんです。」
「誘拐の可能性が高かったら、最終的には警察ですか? 」
出角が困った顔をする。
(当り前だろう! )
これが確実に誘拐事件だったなら、警察に届け出ないわけにはいかない。
学校の思惑で握り潰したり、尾藤の胸の中に収めておくことのできる事ではない。そんなことをしたら、間違いなく犯罪行為である。
しかし、これ以上出角に警戒され身構えられると調査に差し支えるので、少し警戒心をほぐしてやることにした。
「警察も学校側の意向があれば事件を表沙汰にしないでくれますから、そんなに警戒なさることもないでしょう。別に、学校が誘拐の片棒を担いだわけじゃないわけでしょうからね。但し、キチンと情報提供をし、協力を惜しまないということが前提です。」
「それならば、良いんですが・・・ 」
それでも出角は不安げな顔をしていた。
(一ヒラ教員のクセに随分と事件の表沙汰を気にするんだな。学校の経営者に忠実な奴だって考えれば頷けるけど、単なるサラリーマンのすることとしちゃ不自然だ。最初は上司の思惑を気にして非協力的になっているのだと思っていたが、まるで自分が率先して盾になって事件を覆い隠そうとしているように見える。)
今日初めて出会った男の性格や行動原則は掴みようが無いので、その理由を探るのは不可能だった。
しかし、チラリと物騒な疑いが過らないでもない。
(まさか、こいつが誘拐犯じゃないだろうな? )
教師が教え子に対して悪事を働いたという事件は過去に多数あるわけで、その可能性が全く無いとは言い切れない。
しかし、それを今考えてみるのは意味が無い。司廉子の失踪が誘拐事件なのかどうか、それを調べている途中なのだから、事実が判明してから後に考えるべき事だった。
尾藤は芽生えかけた不審を、一旦心の片隅に抑え込んで現場検証を続行した。
校舎の裏側は、大人二人が両手を広げて並んで立てるほどの幅の隙間を挟み、片側は二階建ての中等部校舎、もう片側はレンガ造りの塀が続いている。
見渡したところ、校地外へ抜ける扉のような出入口は無いが、塀の高さは約二メート半で、助走をつければ駆け上がって乗り越えるのが難しい高さではない。古い塀なので所々にレンガの欠けた穴が開いており、よじ登るための手掛かりや足掛かりもある。
「ちょっと失礼。」
尾藤は塀に飛びつき煉瓦の僅かな窪みに足を引っ掛けて登ってみた。
すると、意外に簡単に塀の上に腰掛けることができた。
(男なら簡単に乗り越えられる。たぶん女でも運動神経が良ければ行けるだろう。多少力がある男ならば、誘拐した女子中学生を担いでも越えられそうだし、もし犯人が二人以上だったならば女子一人運ぶのは大して難しくない。)
塀の外を確認すると、そこは一車線一方通行の路地だった。
向かい側はマンションやアパートが並ぶ住専地域で、現時刻に於いて人通りは非常に少なく、夜間ともなれば人通りはさらに少なくなると思われる。この路地に予め車を止めておけば、塀を超えて逃げる経路としては申し分ない。
尾藤は塀の上に腰掛けたままカメラを取り出し、路地の様子と向かい側に並ぶマンションやアパートの並びを撮影した。
(後で付近住民の聞き込みもしたほうが良いな。)
事件が表沙汰になりそうな行為を学校側は嫌がるだろうが構うことは無い。黙って勝手に進めて、クレームが付いても知らぬふりをすれば良い。
尾藤は塀から飛び降りると、次に地面とレンガの壁面を交互に探りながら歩き始めた。
後に従っていた出角が手持無沙汰にしており、
「何か手伝いますか? 」
と、言ってきた。
「いえ、一人で大丈夫ですよ。」
尾藤は出角の申し出を断って自分の作業に没頭した。
校舎裏の地面は土が剥き出しのままだが除草剤を撒いているらしく雑草は少ない。校地の中にある隙間ともいうべき何もない場所だが意外に人通りはあるようで、小さく浅い靴跡が点在している。靴跡の形が殆ど同じものなので、直ぐに生徒たちの上履きによるものだとわかった。
さらに、菓子パンの袋やジュースの紙パックなど、ゴミが転々と散らばっている。
(行儀の悪いお嬢さまもいるんだな。)
これらは真上にある教室の窓から投げ落とされたに違いない。
「ここは、先生方は滅多に来ない場所のようですね。」
「お恥ずかしい、たまに校務員が掃除に入るぐらいでして・・・ 」
出角の言い訳には耳を貸さず、尾藤は散らばるゴミを目で追った。
生徒らしからぬゴミが落ちていないかと探していたのだが、
(お、もしかしてビンゴ? )
白く小さな紙筒が土の中から僅かに飛び出していることに気付いて手に取ってみると、それは煙草のフィルターだった。
(まさか、誘拐犯のモノ? )
重要な手掛かり発見の期待をもって土を掻き分けてみると、他にも沢山の煙草の吸殻が埋まっていた。
(なんだ、この数は? 犯人はヘビースモーカーか? )
しかし、それらが誘拐犯のモノでないことは直ぐに分かった。
何本かのフィルターには薄いピンクの染みが付いていたのである。
(これはグロスだよ・・・なるほどね。)
ここは生徒の喫煙所らしい。
(お堅そうなお嬢さん学校でも、悪戯する奴が多少はいるんだな。)
どうやら、吸殻を埋めて隠している場所を見つけてしまったようだ。
(子供のくせに贅沢なモノ吸いやがって。)
今時、街の不良じゃ一箱1000円以上もする煙草は気軽に吸えない。
裕福な家庭の娘ならではの悪戯である。
「どうしたんですか? 何か見つかりましたか? 」
出角が声を掛けてきたが、
「いえ、別に何も。」
生徒の喫煙を暴くつもりはないので、、
(もっと深く埋めなきゃ、いずれ見つかるぞ。)
土を掛け直して吸殻を隠してしまおうとした。
すると、
(変だな? )
吸殻を見付けた辺りの土が乱れていることに気付いた。
立ち上がって眺めてみると数か所に土が捲れ上がったような窪みがあり、それらは規則的に連続している。そもそも煙草の吸殻は、もっと深く埋められていたはずなのに、土が捲られたために露出してしまったようだ。
「これは足跡じゃないか? 」
尾藤が思わず声を上げると、出角が釣られて寄って来た。
何か聞きたそうにする出角を無視して、尾藤は足跡を辿り、その先にあるレンガ塀を調べた。
(おっ! )
レンガ塀に空いた幾つかの大きめの穴のうち縦に並んだ数カ所に乾いた土がこびり付いており、その土質は足元の地面と同じであることは間違いない。
「普段、この塀を乗り越えて外に出ようとする者がいたりしますか? 」
「まさか! うちは女子校ですよ。頑張ればよじ登れるかもしれないですけど、スカートではやらないでしょう。それに見つかったら始末書、もしくは停学ですから、そんなリスクを犯すと思いますか? 」
よほどアクティブな生徒ならスカートでも塀を乗り越えるぐらいやってみせるかもしれないが、この学校に限っては、そこまでの大胆な行動を取る者は少ないかもしれない。お嬢さま学校に在籍する生徒ならば、たぶん親や先生の目を気にして、あからさまな不良行為は避けるだろう。
窓からゴミを捨てるか、隠れて煙草を吸うのがせいぜいである。
「それじゃ、教職員の方はどうです? 」
「生徒に禁止してることを、教職員がやるわけないでしょう。」
ということは、塀の穴に足を掛けてよじ登ったりする者は学校関係者にはいないと考えて良いわけだ。
「ここら辺を見ていただけますか? 」
尾藤は、出角に土のこびり付いた壁の穴に注目するよう言った。
「古いレンガ塀ですから穴も空いてますよ。それがどうかしましたか? 」
「土が付いてるし、壁に靴底を擦った跡もある。誰かが足を掛けて上った証拠です。」
「ホントだ。これ、まさか誘拐犯が登ったってことですか? 」
「その可能性があるかもしれないという程度ですがね。」
次に、尾藤は自分の肩の高さぐらいにある穴を指差した。
「ほら、この穴には草の切れ端がこびり付いてる。ここは雑草が少ないですけど、渡り廊下の近くにはチラホラ生え残ってたじゃないですか。」
「確かに・・・ 」
「ここを乗り越えて行った奴は、渡り廊下から回り込んできたってことです。」
出角は、怪訝な顔付きだが一応頷いて聞いている。
何かしら不満はありそうなだが、尾藤の推理に異論を挟むつもりは無さそうだった。
「さて、一番重要なことは、この壁の跡が半月以内に付いたってことですよ。」
「どうして、そんなことが分かるんですか? 」
尾藤は出角に少し待つように言って、尻のポケットからタブレット端末を取り出し、インターネットに接続した。
「ああ、あった。これこれ。」
尾藤は気象庁のホームページを開いて出角に見せた。
杉並区内の一一月の天気の推移を表したカレンダーである。
「この程度の跡ならば、一雨降ったら流されてしまいますが、見ての通り最後に雨が降ったのは半月以上も前です。だから、それ以降に付いた跡ってことになるんです。」
最後の雨は一一月三日。ここのところ好天が続いていたので、こうした手掛かりが残されている可能性に予め期待していたのだが、実に運が良かった。
「なるほど、探偵ってのは、ここまで調べるモノなんですねぇ。」
などと、出角が感心していた。
「探偵じゃありません。調査員です! 」
尾藤の現場検証はさらに続く。
(ここをよじ登った奴は、壁の汚れ具合から見て複数いたようだな。)
地面に残されている足跡の数からも、それがわかる。
ちなみに、残されている足跡はどれも鮮明ではないが、一〇日以上も前のモノだとすれば良く残っている方である。靴底の溝の形までは見ることはできないが、形状は判断できる。おそらく、スポーツシューズかスニーカーの類だろう。
(深い足跡が幾つかあるが、これは何か重いモノを担いでいた者がいた証拠。)
尾藤は再びカメラを取り出して手掛かりになりそうなモノは全て撮影しておいた。
(警察の鑑識なら、もっと細かな調査ができるのに・・・ )
だが、今は自分の仕事、できる範囲内で地道な調査をするしかない。
(他に何か証拠は残っていないか? )
その場にしゃがみ込んで、這いつくばるような姿勢で目を凝らし、周辺の地面を探って見たが、残念ながら他には何も見つからなかった。
今日の段階で、尾藤がこの場でできることは、ここまでのようだった。
「いやぁ、やっと終わりましたか。」
現場検証の終了を告げると、出角は露骨に嬉しそうな顔をした。
「用事が済んだらさっさと帰れ」という態度を隠そうともしなかった。
「これで、何か有効な情報でも見つかったなら、私も忙しい時間を割いて協力した甲斐があるんですがねぇ。まあ、精々頑張って司の奴を見付けてやって下さい。お願いしますよ。ああ、せっかくですから玄関までお送りしましょう。」
嫌味たらしく言って尾藤を追い帰そうとする。
(うーむ、出角以外の教職員に対する聞き取りをしたいんだが。)
それに、出角の目を盗んででも生徒からの聞き取りをしたい。
(里田って娘には学校を通さなくとも司夫妻に頼めばアポイントくらい取れるだろうから良いけど、他の生徒たちへの聞き取りは出角や学校を通さないと無理なんだろうなぁ。やっぱり、知らないオジサンが近寄ったら皆が警戒しちゃうよねぇ。)
しかし、尾藤はそれをこの場で再度要求するのは諦めた。
出角一人でも扱い方が厄介だったのに、学校全体の反感を買いながら強引な調査活動をするなど無理だと思ったのだ。下手をすれば、学校が警察に苦情を訴えるかもしれないので、そうなってしまっては尾藤の嘘がバレてしまい、今後の調査活動に差し支えてしまう。
(この学校を相手に調査活動を続けるには、ホントに警察を抱き込まなければならないかもな。)
尾藤は、木村の手を煩わせることを考えた。
(外注扱いにしてくれると助かるんだけど。)
尾藤は「ゼロ」と通称される公安警察内にある協力者運営組織の登録を受けている。
営利誘拐は公安が扱うべき仕事ではないが、木村に無理を言えば、今回の仕事を「ゼロ」扱いにしてもらうことは可能だろう。面倒だの忙しいだのと文句を言いつつも、いつも木村は何とかしてくれる。
先ほどの出角の態度を見ても明らかだが、一般人は国家権力に弱い。民間の調査員には従わない者も、警察発行の紙切れの前では見違えるほど従順になる。
調査依頼書と、ついでに令状さえもらえば尾藤の仕事が公務になる。つまり、非協力的な態度や隠ぺい工作は公務妨害になるので、出角を始め学校関係者は嫌々でも尾藤に従わざるを得なくなるのである。
そんな作戦を考えながら、今日は他にすることもあるので大人しく引き上げてやることにした。
出角は正門まで見送りに来たが、好意で付いて来たわけではない。
尾藤が帰る振りをしながら勝手に校地内を探りはしないかと心配していたのだろう。
(俺の姿が見えなくなったら、塩でも撒くんじゃないか? )
それでも、出角には正門を出る前に一応の礼を言い、校舎裏で見つけた足跡などの証拠には関しては触らずにおくよう指示をしておいた。出角は、尾藤の指図に従うのが気に入らなさそうにしていたが、かなり厳しく言っておいたので、余程のことが無い限り逆らうことは無いと思う。
余程のことがなければ・・・
[六]
時刻は二〇時過ぎ。
今朝方聞かされた恵子のキツイお説教が頭を離れなかったこともあって、仕事を終えてから何となく新宿まで足を運んだものの、この夜は飲み歩くのをやめた。
(飯食うだけにしとこう。)
そう思いながら新宿駅西口ロータリーの手前で信号待ちをしていた時である。
「駄目じゃないか! こんなところで商売しちゃ! 」
いきなり背後で大きな声が聞こえた。
振り返ると、警ら中の制服警察官が二名、路上でモノ売りをしていた外国人の若い男性に向かって怒鳴り散らしている。
「お前、無許可だろう! それに何だこれは? 」
警察官の一人が歩道の上に敷かれた薄いビニールシート上に並べられたアクセサリーらしき商品の一つを摘み上げた。
それは金色に輝く装飾品で、掌の半分ほどの大きさのブローチである。離れて見ていてもわかるほどに丁寧に仕上げられた見事な細工品だった。
「随分立派なもんだな。盗品じゃないのか? 」
威圧するような言葉に、若者は首を振った。
この若者は気丈な性格らしい。警棒を片手に怒鳴り散らす二名の屈強な警察官に両側から挟み込まれても怯えた様子が見えない。
「何とか言ったらどうなんだ? 日本語が分からないのか? それともお前は口が利けないのか? 」
掴みかかる一歩手前の距離で怒鳴り続ける警察官たちは明らかに若者を挑発していた。少しでも反抗的な態度を示したり、身体の一部が触れようものなら直ぐさま公務執行妨害で逮捕してしまおうという勢いである。
(あれ? あいつは! )
若者の顔を見て驚いた。
忘れもしない今早朝、カラスを撃ち殺し、その死骸を抱えて去った若者である。
身なりも今朝のまま、汚れた半袖のTシャツに擦り切れたジーンズ姿である。
「お前みたいな奴が、駅の真ん前で座り込んでいたらな、新宿の街の美観が損なわれるんだよ! 」
それまで、アクセサリーを手に持っていた警官が、力いっぱい地面に叩きつけた。
キラキラと輝く細工がアスファルトの上で砕け散った。
その瞬間、尾藤は若者の目の中に暴力的な衝動が走ったのを見て取った。
(まずいぞ! )
思わず、
「ちょっと待って! 」
と、叫びながら警察官と若者の間に割って入った尾藤だったが、何故咄嗟にそんなことをしたのか、後になって考えてみても理解できなかった。
この得体のしれない外国人の若者に対し、ホンの少しだけ興味を持っていたというのが動機だったが、その程度の動機で気が荒ぶっている警察官と若者の間に割って入って巻き添えを食わされる危険を犯す必要があったのかどうか?
「何だ、お前は? 」
当然のように、警察官の怒りが尾藤にも向けられた。
「すみません! あの、勘弁してもらえませんか? 」
慌てて警察官を宥めようとした。
「お前、こいつの仲間か? 」
警察官が怪訝そうな顔をした。
「いえ・・・ 」
尾藤は言葉に詰まった。
衝動的に飛び出してしまったものの、事態を収めるための手段など何も考えていなかったのだ。
(何か使える手って・・・やっぱ、これしかないよなぁ。)
多少どころではない罪悪感を伴ったが、咄嗟に思い浮かんだのは便利で多忙な友人の名前だった。
「実は、私は調査会社を経営しております尾藤と申します。」
懐から急いで名刺を取り出し、二人に渡すと、
「杉並署の木村警部から、彼を保護するように頼まれてるんです。」
と、出まかせを言った。
さすがに公安警察の木村とは言わなかったが・・・
(木村、ごめん! )
尾藤は心の中で手を合わせた。
自分の名前が、こんな乱暴な使い方をされたと知ったら、さすがの木村も怒る。
「保護って何のために? 」
相変わらず威圧的だが、案の定同業者の名前を出したことで、警察官の声が幾分落ち着いたように感じられる。
「その辺の事情は私も詳しく伺ってませんが、何か職務上の理由だと思います。私は単に保護するように言われただけですから。何なら杉並署に問い合わせていただいてもかまいませんよ。」
決して問い合わせて欲しくなどないのだが、この程度のハッタリを利かせないと警察官たちが納得するはずがない。
「まあ、いいでしょう。」
警察官たちがあっさりと引いた。
自分たちよりも階級が上の人間とやり取りをするのが煩わしいと思ったのだろう。
元々、彼らにとって若者を逮捕しなければならない必然性は無かったわけで、職務遂行意識が全く無いとは言わないが、その場の気分と外国人への偏見で絡んでみただけなのである。面倒な対応をするぐらいなら、さっさと引き上げた方が良いに決まっている。
尾藤は、去っていく警察官たちの後ろ姿を見てホッと一息ついた。
(良かったぁ。木村を怒らせずに済んだ。)
こんなことで怒らせてしまったら、今回の仕事を外注扱いにしてもらうも何も無くなってしまう。
これからは木村の乱用はできるだけ控えようと自分に釘を刺した。
「さてと、」
尾藤は警察官の姿が見えなくなってから若者を振り返った。
彼は無言でビニールシート上のアクセサリーを片付けていた。警察官に壊されたブローチの破片も、一つ一つを丁寧に拾い集めていた。
「手伝おうか。」
声を掛けたが返事が無い。
(言葉が分からないのか? )
尾藤は戸惑ったが、関わってしまった以上、放っておくのも今更なので、こちらも黙って破片の拾い集めを手伝い始めた。
それでも若者は黙ったままだったが、お節介を拒否するような態度も見せなかった。
数メートル四方に飛び散った細工を夜間の街灯の下で拾い集めるのは難しかった。かなり細かなパーツが多く、拾い集めたところで復元するのは難しいと思う。だが、それらを若者が真剣に拾い集めようとしているので、仕方なしに倣った。
地道な作業が一〇分以上も続いた。
「どうも、ありがとうございました。」
全ての破片を集め終わった若者が、唐突に流暢な日本語で礼を言い、頭を下げた。
「いや、別に、なんだ、日本語話せたのか? 」
尾藤は、若者の意外な礼儀正しさに驚いた。
カラスを撃ち殺し、その死骸を持ち去った野性的な行動と、先ほどの警察官たちを相手に爆発寸前と思われた暴力的な瞳の輝きから、尾藤は若者に粗野で乱暴なイメージを抱いていたが誤解だったらしい。
話してみれば普通の青年である。
「杉並署の警部さんが、僕を呼んでるの? 」
若者が心配そうな顔をして尾藤に聞いた。
「ああ、あれは君を助けるために咄嗟についた嘘だよ。気にしなくていい。」
尾藤は心配するなという風に笑って手を振って見せた。
「助ける? 何故、僕を助けたの? 」
「何となくかな、別に深い意味は無いなぁ。」
実際に深い意味などこれっぽっちも無い。
本当に何となく助けようとしてしまったのだから、そう言った。
「そうなんですか? 」
若者は首を傾げて納得できていない様子だったが、それ以上の追及はせず、次に路上に置きっぱなしになっていたアクセサリーを乗せていたビニールシートを片付け始めた。
警官に目を付けられてしまったからには、今日は店仕舞いするしかないようだ。
ビニールシートを折りたたみながら、
「でも、同情されたのなら嫌だな。」
ポツリと若者が言った。
そのみすぼらしい外見からは思いがけないほどのプライドを持っているようだ。
この不思議な若者に興味が湧いてきた尾藤は、もう少し話をしてみたいと思った。
「気に障ったなら謝るけど、僕は今朝の君の早ワザを見てしまったんだよ。それがずっと気になっててさ。」
その件は若者のプライドを傷つけてしまう可能性があることなので、言うべきではなかったのかもしれないが、気遣いよりも興味の方が勝ってしまった。
「早ワザ? 」
若者は、尾藤が何を言っているのか分からないようだった。
「カラスを撃ち殺しただろう? 」
若者は直ぐに思い出したらしい。
やはり、思い切り嫌な顔をした。
「ごめん、決して悪気があって言ってることじゃないんだ。何故、君がカラスを獲らなければならないのかとか、色々と気になってて・・・ 」
「野鳥を獲るのは珍しいことじゃないよ。」
尾藤の言葉を遮るように若者が言った。
「仕事が無くて食えない奴は、自分で食べ物を見付けるしかないじゃない。カラスでもハトでもスズメでも、犬や猫だって食べなきゃならない時は食べるよ。ゴミを漁って残飯を食うよりは余程マシだと思う。」
「確かにそうだ。」
その理屈が正しいと思ったわけではないが、何となく頷いてしまった。
「それじゃ。」
若者は一礼して立ち去ろうとした。
「あ、ちょっと待ってくれよ。」
尾藤は若者の腕を掴んだのだが、
(あれ? 何故、俺はこいつを引き留めようとしているんだ? )
自分が取った行動なのに理解に苦しんだ。
おそらく、直感のようなものが閃いたのかもしれない。
根拠は無いのだが、この若者との出会いが非常に大切なことのように思われたのだ。
「何だよ! 」
イライラしたような言い方で振り返った若者に、
「ちょっと、話をしないか? 飯でも奢るよ。」
と、持ち掛けた。
すると、飯という単語に対する若者の表情には明らかな反応があった。
(たぶん、腹が減っているに違いない。)
失礼な考えとは思うが、尾藤は食いモノで引き留めようとした。
若者の姿を一目見れば、まともな収入が無く、食うに困っているのは明らかだった。カラスを獲って食わなければならない状況にあるのだから、切実なはずだ。
その狙いは間違っていなかったらしく、尾藤の一言で空腹が思い出されたようで腹の鳴る音が聞こえ始めた。
「そこいらで何か食おうよ。」
尾藤は若者に逡巡する暇を与えないようにするのが手っ取り早いと判断した。
始めは警戒心を見せていた若者だったが、まともな飯を食えるという誘惑には勝てなかったようで簡単に引き摺って行けた。
手近な所にあった焼肉屋を選んで入ったら、案内に出てきた店員が若者の身なりが汚いので嫌な顔をしていた。
入店拒否はされずに済んだが、迷惑な客と思われたのは間違いない。
幸い若者は身体を小まめに洗っているようで、異臭がするようなことは無かったが、この身なりで臭いが酷かったら何処の店も入れてはくれないだろう。
外国人である若者の嗜好が分からなかったので何が食いたいか聞いてみたが、遠慮なのかプライドからか、
「何でも良い。」
と、言う。
日本語のメニューが苦手なのかもしれないと思って、親切に説明してやろうとしたのだが、やはり何でも良いとだけ言って、自分からは何が食べたいとは言わなかった。
なかなか頑固な若者だったが、尾藤は却って好感を持った。
出会ったばかりの得体の知れない外国人に対して好感を持つのは不思議なことだが、ここまでに交わした僅かな会話と彼の態度を見るにつけ、尾藤は彼が決して悪い人間だとは思わなくなっていたのだ。
さて、若者の頑固な痩せ我慢は、尾藤が適当に頼んだ肉が遠赤外線のロースター上に乗せられ、食欲をそそる匂いを漂わせ始めたことで捨てざるを得なくなったようである。
若者は、一旦肉に食いついたら勢いが止まらなくなってしまったらしい。
(それにしても、よく食うな。)
胃袋が本調子に戻り切っていない尾藤は、ビールを飲みながら時々キムチとカクテキをつまむ程度で、あとは若者の食いっぷりを眺めて感心していた。
カルビ、ハラミ、ロース、そして飯、皿が次々空になっていく様子は微笑ましかった。
そして、最後の肉の皿が空になった時、
「・・・すみません。」
若者が小さく言った。
腹が満たされて我に返ったらしい。
自分の食い意地を恥じている様子だった。
尾藤は可笑しさを堪えながら、
「別に構わないよ。他に食べたいもの無いの? 」
さらにメニューを勧めたが若者は遠慮した。
「まともな飯なんて久しぶりだったから、我を忘れちゃって・・・ 」
と、尚も恥じ入ろうとする。
「だから、気にするなって。僕が奢ると言って誘ったんだから良いんだよ。大して高いモノ食わしたわけじゃないし。」
何度も宥めているうちに、若者が少しづつだが打ち解けた様子を見せ始めた。腹が膨れたせいかもしれなかったが、素直に会話に応じるようになった。
若者の名前はアディティヤ。
呼び辛いのでアディと縮めて良いかと聞いたら、問題無いと言う。
バングラディシュ出身で年齢は二二歳。
飯を頼むついでにビールを勧めたら、酒は飲まないからとお茶を頼んでいたのでイスラム教徒なのかと思ったが、それは違った。彼自身は大して熱心な信者ではないがクリスチャンの家庭で育ったと言う。
飲酒については空腹時だから避けただけだったらしい。
アディが来日したのは一九歳の時。
日本で働いて金を稼ぎ、その金で学校へ通おうと思っていたと言う。
入国時には仕事も決まっており、最初の一年間は問題無く日本で働き生活していた。ところが勤めていた運輸会社が経営不振で倒産、失職してしまった後は悲惨だった。会社の寮で生活していたので住む家も同時に失ってしまったのだ。
その後も日本に留まり次の仕事を見付けようとしたのだが、外国人の求職活動は困難を極め、苦労して貯めた僅かな貯金は、日々の生活の中で半年も経たずに底を尽き、ついには落ちぶれて日雇い仕事を探しながら新宿区内の廃屋でスコッターになり、辛うじて生き延びていたらしい。
「苦労したんだなぁ。」
アディは同情されるのは嫌だと言いそうだが、そんな話を聞いてしまったらついつい口から出てしまう。
そもそも、この国は返済不可能な額の借金を抱え、経済破綻寸前で踏み止まり続けて数十年、安定しない景気に振り回される企業の多くは疲弊し、人件費削減を繰り返すのが常となっていた。だから、日本人でさえも職を失い路頭に迷う者が多い有様なのに、流入する外国人の数に見合うほどの仕事を提供することは無理なのだ。
しかも、来日して最初の職を失った外国人の再就職など不可能に近い。
そんな実情は知られているはずなのに日本に流入する外国人の数は減らない。
かつて好景気だった時代の残光に期待しているのかもしれないが、やはり入国審査基準の緩和が魅力なのだろう。それに、景気や治安は悪化の一途を辿っているのだが、何故だか政情だけは常に安定しており、クーデターやテロが頻発し、生命の危機に怯えながら暮らさなければならない自国よりはマシとの思いで流れてくる外国人も多いらしい。
アディの故郷であるバングラディシュを初めとして、多くの途上国の中には自然災害や疫病、水質汚染で人々の生活が脅かされている国もある。それに比べれば、日本はインフラが整い、衛生面の管理が行き届いているので病気の心配も少ない。それだけでも、十分に移民する価値があると考える者も多いのだ。
今や日本に限らず世界中が不況の真っ只中にある。
かつて好景気だった国々が軒並み低迷しており、世界中の経済が混乱の最中にある。何処へ行っても苦労するのならば、暮らしやすさと安全面を考えて日本で暮らそうと考える者が多いのも頷ける。
アディもそうした外国人の一人だった。夢は破れたが、五〇%を超える失業率の中で貧困に苛まれながら生きる自国に戻るよりは、日本でその日暮らしをすることを選んだ外国人の一人だった。
「尾藤さん。お金が無いので、お礼にこれ差し上げます。」
アディが売り物のアクセサリーの中から、金色に輝く直径三センチほどのコイン型ペンダントヘッドを一つ選んで取り出し、テーブルの上に置いた。
「そんな、気にしなくていいのに。」
尾藤は遠慮したが、アディは尚も勧めるので恐縮しながら受け取った。
ペンダントヘッドを手に取ってみると、改めてその細工の見事さに感心させられると共に、ずっしりとした重みにも驚いた。
「もしかして純金細工か? 」
尾藤が聞くと、
「はい。」
と、アディが答えた。
「おいおい、高価なもんじゃないのか? 飯代にしちゃもったいないだろう。」
尾藤は慌ててペンダントヘッドをテーブルの上に戻した。
アディの持ち物にしては高価すぎると思ったのだ。咄嗟に先程の警察官が言うように盗品の可能性があるかもしれないと思ってしまったのだが、そんな尾藤の様子を見たアディが悲しげな顔をして言った。
「これ、盗んだモノじゃないですから。職人だった祖父の手作りです。日本に来るときに、万が一の時に売って生活の足しにしろって餞別に渡されたんです。」
アディの目が潤み、小刻みに瞬きしていた。
悔しかったのだろう。
「そうだったのか・・・ごめん。」
警察官が壊したブローチの破片を丁寧に拾い集めていた理由がわかった。
尾藤は悲しげな顔のアディを見ていると、盗品かもしれないと一時疑いかけたことが恥ずかしくなった。
「それじゃ、これは気持ちとして一応預かっておくよ。でも、もし君が必要になったら、いつでも返すからな。」
尾藤は優しく言って、再びペンダントを手に取り、
「こんな立派なモノ、僕には似合わないよな。」
胸に当ててみながら、おどけた顔で笑って見せた。
アディが釣られて笑い、互いが少し和んだところで、
「ところで尾藤さんは、なんでこんなに親切にしてくれるの? 今まで親切にしてくれた日本人は外国人を騙そうとする悪人ばかりだったけど、尾藤さんは何となく違う。」
アディが不思議そうな顔で言った。
「理由を聞かれると正直言って困るんだけど、ホントに何となくって感じなんだよ。」
尾藤は苦笑しながら頭を掻いた。
「ああ、知りたいことが一つだけあった。今朝のカラスを一撃で仕留めた技は何だったんだろう? 」
そもそもアディに興味を持ったのは、そこからである。
「パチンコみたいなもんだよ。」
アディはジーンズのポケットから太いゴム製のバンドを取り出した。
「これで鳥を落とすのは、子供のころから得意だったんだ。」
ゴムバンドを人差し指と親指に巻き付けて固定し、もう片方の手で一杯に引いて見せるとパチンコと同じような格好になった。
「へぇー、上手いもんだな。僕にもできるかな? 」
尾藤が感心すると、アディはゴムバンドを渡してくれた。
「石を飛ばすぐらいなら誰でもできるよ。命中させるのは難しいけどね。」
アディがやってみせたようにゴムバンドを指に巻き付けて引いてみたのだが、その硬さに驚いた。
「自転車のタイヤチューブに使うゴムだからね。」
ゴムバンドを引き延ばせずに、ブルブルと手元を震わす尾藤を見てアディが笑った。
「なんの、このくらい平気さっ! 」
尾藤は強がりながら何とかアディの半分くらいまでは引っ張ることができた。
だが、このまま狙いを定めて何かを発射するなど無理なことだった。
「すごいな。そうとう指の力が強くなけりゃできることじゃないよ。」
尾藤は感心しながらゴムバンドを外してアディに返した。
「こんな特技、何の役にも立たないけどね。」
アディがポケットにゴムバンドをしまいながら苦笑した。
尾藤も、
「まあ、そうだよな。」
と、答えて笑い返した。
「尾藤さん。知り合ったばかりで、いきなりこんなこと言って申し訳ないんだけど、仕事探してるんだ。尾藤さんは社長なんでしょ? 尾藤さんの事務所で僕にできる仕事ってないかな? 尾藤さんが駄目なら何処か人手を探している会社を知らないかな? 僕、落ち着いて真面目に働きたいんだ。」
アディが思いつめた顔で何度も頭を下げた。
「大事に取っておいた祖父の金細工、本当は売りたくなかったんだ。できれば売らずにいたい。」
「うーん、気持ちは分かる。」
尾藤は腕組みして天井を仰いだ。
だが、外国人を雇ってくれそうな会社は直ぐには思いつかない。
アディは日本語が達者なので、身嗜みさえマトモにすれば仕事は見つかりそうな気がしないでもないが、安易に期待させるような発言は控えなければならない。
「何とかして、今の生活から抜け出したいんだ。まるでケダモノみたいな生活だから。まわりにいる連中も同じような境遇の人間ばかりだけど、奴らは皆犯罪者と気狂いばっかりだ。平気で盗みや人殺しもやるよ。もう、あんな奴らと一緒に暮らすのは嫌だよ! 」
まさに切羽詰まっている感じだった。
「僕は乞食はしたくないし、盗みもしない。どっちも一度やったら止められなくなるって聞いてるから絶対にしない。神様に誓ってしないよ。」
尾藤は人を見る目には自信がある。
調査員なのだから当然だが、そんな尾藤の目から見ても、アディが本心で言っているのはわかる。
(うちの事務所で雇ってやれれば良いのだがな。)
最近、外国人絡みの依頼も増えており、そういった場合は同じ外国人が対応した方がクライアントや調査対象者の心を開きやすいという利点もある。
しかし、現状では人手を増やせるほど稼ぎに余裕が無かった。
それに仕事柄、適性があるのかを見極めないと助手には雇えない。
尾藤は、ふと「クアーク」のマスターにでも頼んでアディを雇ってもらえないものかと思った。いつも忙しくしているのに、スタッフはマスターと大学生の週末勤務のアルバイトが二名いるだけである。先月、アルバイトかパートの募集を出していたはずだが、その後に新たなスタッフが補充された様子は無い。
マスターは自分が外国人なのにも係わらず、外国人に強い偏見を持っているのが少々厄介だが、頼み込めば相談に乗ってくれないわけでもないだろう。
「直ぐに働き口があるかどうかはわからないけど、心当たりに相談はしてみるよ。」
期待させ過ぎてもまずいので、この程度にしておいた。
いずれにせよ、直ぐに口を利いてやるわけにはいかない。
「クアーク」のマスターに紹介するには、もう少し尾藤がアディの為人を知ってからでないと無責任である。
「ところで、君に連絡したいときはどうすれば良いんだろう? 」
アディが通信機器を持っているはずがないと思ったのだが、
「大丈夫、仕事探しの時は、これ使ってるよ。」
そう言ってミニタブレット型の携帯用通信端末をポケットから取り出した。
定額のプリペイドカードを購入し、カードに書かれたパスコードを入力して使用するタイプの機種だ。
「ああ、それなら連絡できるよね。」
考えてみれば、求職者に通信手段は必須である。通信手段が無ければ仕事を探しようがないわけで、飯を食うよりも連絡先の確保が優先される。真面目に働こうとしているアディなら携帯用通信端末ぐらい持っていて当然だった。
尾藤は直ぐにアディのアドレスを聞いて登録した。
「何か良い働き先があったら必ず電話するよ。でも、その前にもう少しアディのことを知っておきたいから、うちの事務所の使い走りでもしてもらおうかな。」
常時雇うことは難しいが、単発の仕事を渡すことなら可能である。それを何度か繰り返せば、アディの為人もわかってくるだろうし、そうなれば仕事の紹介がしやすくなる。
「ありがとう! 尾藤さん、僕、何でもやるからね! 」
屈託の無い笑顔で笑うアディの顔を見ていたら、尾藤はついつい嬉しくなって、もう一つか二つお節介をしたくなった。
「ところで、これは本当は幾らで売っているモノなんだい? 」
ポケットにしまっていたペンダントヘッドを、もう一度取り出して聞いてみた。
すると、
「五〇〇〇円くらいで売ってます。」
その安価に驚いた。
「いくらなんでも安過ぎだろう! そんな値段じゃお祖父さんが怒るぞ! 」
尾藤は専門家ではないが、職業柄貴金属に関わることも少なくないので、多少の鑑定眼を持っている。
手にしたペンダントヘッドは間違いなく二四金製である。
それを五〇〇〇円とは、針金細工並みの価格だった。
「そんな値段じゃダメだ。俺が他に一個だけ買ってあげるよ。そうだな、五〇〇〇〇円でどうだい? 」
勢い良く申し出たのは良いが、
(細工も見事だし、このペンダントヘッドの大きさや重さは一オンス金貨並みだ。現在の金相場は知らないが、おそらく五〇〇〇〇円でも安過ぎるのでは? )
しかし、現在の手持ちの現金で支払える額は五〇〇〇〇円が限度だったので、考え無しに口から滑り出てしまったのだ。
(やはり、キチンと適正価格を調べてからでないと・・・ )
申し出を訂正しようとした尾藤だったが、間に合わなかった。
アディの大喜びによって口を塞がれてしまったのだ。
「本当ですか? 嬉しい! 五〇〇〇〇円ですか! 尾藤さんなら喜んで売ります! どれが良いですか? 」
テーブルに金細工を並べ始めてしまった。
「あ、ああ、そうだな・・・ 」
あまりの喜びように、今更適正価格も何も言えなくなってしまった。
五〇〇〇円で売っていた商品に一〇倍の値がついたのだから喜ぶのは当然だなのが、尾藤は罪悪感で冷や汗が出た。
意図せずして、無知な貧乏人の財産を安く買い叩くような格好になってしまった。
(アディ、ごめん! この罪滅ぼしに、何とかして就職の世話を・・・ )
と、尾藤は思わざるを得ない。
金細工は七個。ペンダント、ブローチ、イヤリング、ブレスレット、どれも手作りらしい精巧な細工が見事である。どれが良いかと問われても、大きさにバラつきがあるので、一律五〇〇〇〇円というのはどう考えても間違っている。
手を出すのに躊躇している尾藤に、何も知らないアディは熱心に勧める。
やむを得ず、尾藤は、
「それじゃあ、お言葉に甘えて・・・ 」
中では一番小さく安価に見えた細身のブレスレットを取り上げた。
「オーケー! 毎度、ありがとうございます! 」
嬉しそうなアディの顔を見ながら、すまなそうな顔をして五〇〇〇〇円を渡す。
(ペンダントヘッドほどじゃないにしても、なかなかに高価な品だぞ。)
受け取ったブレスレットを掌に置き、その見事な細工を鑑賞した。
(凄いな、米粒に絵を描くよりも細かな仕事だ。)
径が小さいので女性用と思われるが、三ミリほどの幅の中に草花をモチーフにしたレリーフと規則的にならんだ記号が刻んである。
尾藤は細工を良く見ようと、バックからルーペを取り出した。
「これって文字かな?」
「バングラディシュのベンガル文字です。日本人から見たらインドなんかの文字と一緒に見えるんだろうけど。」
そう言われても、尾藤にはインドどころか南アジア系の文字は全て記号にしか見えておらず、何処に違いがあるのか分からないし、文字として認識することも難しい。
「うーん、違いはわからないなぁ、なんて書いてあるんだろ? 」
「それは聖書の一説です。コーランやヒンドゥーの言葉の方がバングラディシュっぽいんだろうけど。うちの祖父は熱心なクリスチャンだったから。」
アディは母国語でブレスレットに彫り込まれているという聖書の一説を暗誦してくれたのだが、尾藤の耳には魔法使いの呪文のようにしか聞こえなかった。
(でも、こんな形をした文字を何処かで見たよな? )
昼間、司夫妻から預かった写真の中で見たバックチャームを思い出した。
「あ、ちょっと待って。」
タブレット端末を取り出し、例の司廉子の小柄な方の友人が写っている写真を開いた。
「ここ見てよ。これも文字だよね。」
バックチャームのマスコットを最大限に拡大して、アディに見せた。
どれどれと覗き込んだアディだったが、マスコットを見るなり顔色が曇った。
「尾藤さん、この娘、尾藤さんの知り合い? 」
非常に険しい顔をしながら聞いてきた。
「いや、仕事で預かった写真なんだけど、ちょっと気になってさ。」
アディの様子が変だった。
何か嫌なモノを見てしまったという感じだった。
難しい顔をして、尾藤に何かを言うべきか迷っているようだった。
「何だよ? 言ってくれよ。」
尾藤は説明を求めた。
「それ危ないモノだと思うよ。」
アディが写真を手で覆い隠し、声を潜めた。
「それが何なのか、ハッキリしたことは分からないし、ベンガル文字じゃないから読めないけど、すごく危ないモノだってことは聞いたことあるんだよ。」
「危ないって、どんな風に危ないんだい? 」
説明が足りないので良く分からない。
「それと同じマークの付いたアクセサリーやカード持ってる人を知ってた。その人の所属してるサークルのシンボルって言ってた。そのサークルは時々集会やってて、話を聞いた限りじゃ、決してマトモじゃない頭の変な連中の集まりで、集会の度に死人が出るらしいんだ。しかも、完全な秘密主義で、会員はサークルの存在を絶対に他言しないように誓わされてて、その誓いを破ったら殺されるかもしれないって言ってた。その人はね、酔っ払った時に僕に話してくれたんだけど、暫くして交通事故で死んじゃった。」
「それって、殺人サークル? 」
殺人志向者の地下サークルがあるなどという話は都市伝説的な噂では聞いたことがあるが、実際に存在を示唆するような話を聞いたのは初めてだった。
「殺人サークル? 良く分からないけど、そんなに小さなモノじゃないよ。もっと大きな団体、いや組織みたいな・・・ 」
アディが適当な単語を探そうとして詰まった。
「つまり、大っぴらに持ち歩くモノじゃないわけだ? 」
アディの言う通りならば、女子中学生のアクセサリーなわけがない。
「サークル参加者のサインのようなモノらしい。表で身に着けるのは特別な時だけだって言ってたね。」
「サイン? 」
「うん、野球のサインみたいな感じ。関係ない人には分からないけど、サークルの人なら一目で、その意味が分かるらしい。」
初めて見た時から妙に気になっていたのだが、司簾子の件とは結び付かなかったので深く考えずにいたバックチャームの重要度が一気に高まったような気がする。
もちろん、現段階では推測というより予感でしかないのだが、
(もしかしたら、その物騒なサークルが司廉子失踪に絡んでいるんじゃないか? 信じられないことだが、この小柄な方の娘がサークルの会員で、たまたま写真撮影した時に仲間にサインを送っていたとしたら? )
尾藤は、バックチャームの写っている二枚の写真の撮影日を確認した。
(テーマパークの写真は失踪した日の一週間前、もう一枚は三日前。日付が近い。有り得ないことじゃないな。)
尾藤はゾッとした。
殺人サークルではないが、過去に殺人志向者による犠牲者には出会ったことがある。犠牲者の幾人かは、知性も理性もある人間が手を下したとは思えないほど残虐な手口で嬲り殺しにされていた。
そんな過去の忌まわしい記憶と司廉子失踪の件が重なりそうになった。
(いやいや、今聞いたばかりの情報で、そんな風に考えるのはプロとして短絡的過ぎるぞ。そもそも、アディの話は噂の類だし! )
尾藤は最悪のイメージを無理矢理掻き消した。
[七]
一一月二〇日の昼下がり。
尾藤は事務所の社長室兼応接室で地図作りに専念していた。
恵子が杉並署まで出掛けて木村から受け取って来てくれた資料を見ながら、コンビニで買ってきたB1サイズの東京二三区道路地図を応接テーブルに広げ、これまでに行方不明になったという女子学生の通っている学校の場所に印をつけながら、その日付を記入していた。
司廉子が所持していた携帯通信端末のトレースに関しては、残念ながら最終発信が日中の学校内だったので失踪以降の手掛かりにはならず、端末も発見されなかったようだ。
(失踪当日からGPSでの追跡ができなかったということは、端末が破壊されたということだろう。誘拐の線が一段と強まったことだけは分かったな。)
今手掛けている地図作りは、誘拐犯の実像を探る作業である。
まるっきりのアナログの手仕事だが、PCを使って手早く効率的に行うデジタル作業よりも、考え事をしながらする作業には向いている。
行方不明の届け出は、練馬、杉並、世田谷、中野、新宿の四区が多い。木村は行方不明になった当時の状況資料も一緒に付けてくれたので、それを基にすると司簾子と似た状況での行方不明女子学生は、この四区に限って発生しているのが分かる。
その数、一一名。
内訳は、高校生が三名、中学生が六名、小学生が二名で、私立の有名校や偏差値の高い所謂お嬢様学校に通う生徒ばかりだった。
尾藤は日付をチェックしているうちに奇妙な事に気付いた。最初に届け出があったのは昨年の一二月、それ以降は月一名が行方不明になっており、もっと注意深く日付を見てみると三〇日前後の間隔で事件は起きていた。
全く規則的に女子学生の行方不明者が発生していることになる。
(何者かの意図が絡んだ計画的な誘拐事件? )
昨日、アディに聞いた殺人サークルが頭を過る。
(そのサークル会員が、毎月一回、女子学生を誘拐して殺している? )
そうだとしたら、これはとんでもない事件である。
(非合法団体による組織的な犯行だとしたら、これはホントに公安が扱う類の事件かもしれない。木村に相談すべきかな? )
そんな考えが頭を過ったが、尾藤にもベテラン調査員としての色気がある。
(もう少し、事件の内容をハッキリさせてから話すべきだな。)
但し、何かあった時に木村の協力を求めやすくするため、軽く臭わせておくぐらいのことはしておいた方が良いだろう。
(少し肩が凝った。休憩しようか。)
低めの応接テーブルに前屈みの体勢で作業していたので腰も痛くなってきていた。
「恵ちゃーん、コーヒーちょうだい。」
パーティーションの向こう側にいる恵子に声を掛けると、
「はーい」
と、間延びした返事が返ってきた。
(さてと、)
地図から離れて、今日一〇本目のスティックキャンディの包みを解いて口に入れた。
今日の夕方には、出角から聞いた司簾子と同じバレー部に所属する里田かおるという女子生徒に聞き取り調査することになっていた。
今朝方、司夫妻に段取りをお願いしたら、簡単に承諾してもらえたらしい。
(まったく、なんなんだよ出角って奴は! 何がインフルエンザだ! ピンピンしているらしいじゃないか、嘘つきめ! )
嘘を吐いてまで生徒と会わせようとしない露骨な妨害行為には本当に腹が立つ。
(里田って娘には、もう一人の友達のことも詳しく聞いておかなければならない。)
バックチャームの娘である。
(アディの言うことが本当なら、あの娘はサークルの関係者ということになるが、こんな普通の女子中学生と物騒なサークルとの間に接点なんてあるんだろうか? )
尾藤はキャンディを銜えたままタブレット端末を手に取って、バックチャームの子が写っている写真を開いた。
何処にでもいる普通の子に見えるが、もちろんベイジョに通っているならば、そこそこ裕福な家庭の子に違いない。司簾子に比べると見栄えのしない顔立ちだが、元気そうで明るい雰囲気を漂わせた娘である。
「尾藤さん、難しい顔してますねぇ。顔色も良くないですし。でも、仕事熱心なのは良いことですよ。」
生意気なセリフを言いながらコーヒーカップを置いたトレー片手に恵子が入って来た。
顔色が悪いのは、昨夜快眠できなかったからだと思う。
(いい歳をして、ホラー映画まがいの不気味な夢を見てしまった。)
夢の内容は良く憶えていないが、昨日のベイジョ訪問やアディから聞いた殺人サークルの話のおかげで、ホラーかスプラッタもどきのイメージが憑いてしまったらしい。
そんな夢見の後で、女子学生の誘拐地図を作っているのだから、
「難しい顔をしたくもなるさ。」
と、いうわけなのである。
尾藤はソファの背凭れに背を付けたままでタブレット端末をソファの上に放り出し、手を伸ばしてコーヒーカップを受け取った。
約三分の二の長さになったスティックキャンディを、一旦口から出しコーヒーを啜る。
「ん、美味い。」
作業中に惰性で舐め続けていたキャンディのおかげで口の中に定着してしまっていた甘味が洗い流されていくようで心地良かった。
「ホント、好きですよねぇロケットフィズ。いったい何本目なんですか? 」
恵子は尾藤が手にしている派手なカラーリングのキャンディと、ゴミ箱の中のビニール包装を代わる代わるに見ながら呆れていた。
「別に数えてないや。たぶん七、八本。」
過少申告してしまった。
「そんなに? 糖尿病になりますよっ! 」
「でも、健康診断じゃ血糖値は普通だったから大丈夫だよ。」
「今の話をしてるんじゃありません。この先の話をしてるんですっ! 」
「はい、気を付けます。取り敢えず、これ一本舐めたら今日はオシマイにする。」
まるで、子供が母親と話しているようである。
「ところで、杉並署じゃ木村は忙しそうだった? 」
「忙しそうでしたけど元気そうでしたよ。直ぐに出てきてくれたし、自販機ですけど、お茶をごちそうしてくれました。」
そう言えば、木村は恵子を気に入っていた。
しっかり者の美人女子大生として認識しているらしい。
尾藤が毎日見ているキツイ性格のことは知らない。
たまに木村が尾藤の事務所に遊びに来る時、ケーキやアイスクリームなどの手土産を持ってくることがあるが、そんな時は恵子に会うのがお目当てだとハッキリわかる。それを承知しているので、尾藤は木村が渋りそうなお願いをする時や、小言を言われそうな用事がある時は恵子をお使いに立てるのだが、恵子が相手なら、いつも木村は好印象を与えるために愛想良く対応してくれるのだ。
(妻子持ちのクセに、スケベな奴。)
警視庁公安部の警部殿であり、長年の親友だが、木村は意外に隅に於けない。
「ところで司さんの件、家出じゃなくて誘拐事件っぽいんですね。」
恵子が向かい側のソファに腰掛け、地図を覗き込んで言う。
(・・・恵子さん、中身が丸見えですね。ありがとうございます。)
今日の恵子は、ほどほどに胸の開いたグレーのチュニックワンピースを着ていたが、前屈みになると胸にボリュームが無いので胸元が大きく開いてしまい、推定Aカップのブラジャーを通り越してヘソまで素通しに見える。
「まだ、わからないけど、その可能性が高くなってきたって感じかな。」
尾藤は恵子に気付かれないようにチラチラと目の保養をしながら、さり気無くコーヒーを啜った。
「ああ、コーヒー美味い。」
尾藤はコーヒーの味には鈍感だったが、砂糖もミルクも無し、薄くて量はたっぷりというのが好みだった。ついでに猫舌なので温めの方が良い。
恵子は、そんな尾藤の好みに合わせて入れてくれるので、事務所で飲むコーヒーが何処よりも一番美味いと思っている。
(時々、こいつに飼い慣らされているような気がするけど・・・ )
事務所内での雑務諸々を全て恵子に頼り切っているだけではなく、コーヒーや蕎麦屋の出前の好みまで知られているが、それらについて決して悪い気はしていなかった。
(大げさかもしれないけど、恵子無しで仕事している自分が想像できないや。もはや彼女は仕事を超えて俺の日常の一部だよ。)
興味深そうに地図を覗き込む恵子の様子を眺めていると、彼女が辞めてしまう一年後の寂しさが前倒しされてきて、ぼんやりと胸が苦しくなる。
(俺、惚れてんのかな? )
たぶん、そうだろう。
しかし、そんな尾藤の気持ちを、たぶん恵子は知りもしない。
「それにしても怖いですよねぇ。最近は女の子が一人で歩くのって勇気が要りますよ。私も帰りが遅くなった時は、武蔵小金井駅から自宅まで一五分歩くのが怖くてタクシー乗りますもん。」
恵子が肩を竦めながら姿勢を起こした。
(あーあ、残念・・・ )
チュニックの胸元が閉じてしまったので、これにて本日の目の保養は終了。
「やっぱ君でも一人歩きは怖いのか? 」
尾藤が茶化すと、
「当たり前じゃないですか! 」
恵子が、ふくれっ面をする。
「だって合気道の有段者だろ? それに剣道じゃ三段なんだろ? 」
恵子は剣道場を経営しているという祖父に子供の頃から鍛えられており、先月には昇段試験で三段を取得し、これで師範にもなれると大喜びして散々自慢していた。
「私にいつも竹刀や木刀持って歩けって言うんですか? 」
恵子が木刀を担いで街を歩いている姿を想像したら可笑しくなった。
恵子は美人だが、真顔でキツメの表情をして凄むと、尾藤などは萎縮してしまうほどの迫力がある。そんな顔をして木刀を構えたら、大抵の男は避けて通るだろう。
「ビジュアル的に面白いし、痴漢とか強盗よけになるだろうし、木刀持って歩くのも良いんじゃないの? 」
尾藤は笑いながら言ったが、恵子はカチンと来たらしい。
「会社に木刀持ってきて良いってことですかぁ? 良いですよ。私、一度で良いから柔術の人と他流試合してみたかったんですよねぇ。」
冗談で言っているのだと思うが、目付きは本気っぽくて怖い。
「それは、勘弁! だって、剣道に素手の格闘技じゃ勝負にならないよ。」
尾藤が逃げ腰になったので、恵子は勝ち誇った顔をする。
「ホッホッホッ、いつかは勝負しましょうね、尾藤社長。それじゃ、仕事の邪魔しちゃ悪いから失礼しますねー。」
恵子は意地悪そうに笑いながらソファを立ち上がり、手にしたトレーで尾藤にバイバイをしながら社長室を出て行った。
(あの性格さえなければなぁ・・・ )
それさえなければ、完璧に好みの女なのにと尾藤は嘆息した。
コーヒーカップを片手に暫く寛いでいたら、携帯通信端末に音声着信が入った。
着信表示は司家のアドレスだった。
通話ボタンをタップすると、直ぐに母親の方の声が聞こえた。
「お世話になっております。司です。」
おそらく通信端末を手に頭を下げているであろう丁寧な挨拶の後、
「申し訳ありません。今日の里田さんとのお約束が駄目になってしまったんです。」
申し訳なさそうな、そして悲しげな言い方だった。
「どうかしたんですか? 」
「あの・・・里田さん・・・亡くなったんです。」
「え? 」
尾藤は何と言って良いのか言葉が出てこなかった。
「どうして? 」
「通学途中、歩道橋からの転落事故だったそうなんです。」
お互いに言葉を失い、暫く会話が途切れた。
(どうして、こんなタイミングで事故? 不自然じゃないか! )
最も忌まわしい推測が頭を過った。
(まさか、これって殺人サークルとやらが、今日予定していた事情聴取をさせないための口封じをしたのか? )
里田かおるが今日の夕方に尾藤と会う約束をしていることを知っているのは、司夫妻だけだと思っていたが、もしかしたら例のバックチャームの友人も?
(もし、里田かおるが司廉子失踪の件で何か重要な情報を持っていたとしたら? その情報と今日の夕方に俺と会う約束を、軽はずみに親友へ話していたのかもしれない。)
尾藤の脳裏に、バックチャームの娘が里田かおるを歩道橋から突き落とす映像が浮かんだ。
(彼女が本当に殺人サークルの会員なら、それも有り得る! )
写真に写っていた明るい笑顔の影に恐ろしい素顔を隠し持っているのかもしれない。
「司さん、突然ですみませんが、もう一人の友達を紹介して欲しいんです。」
尾藤は聞き取り調査のターゲットを変えた。
「名前は知らないのですが・・・ 」
預かっている写真の幾つかに写っているバックチャームの娘を指示した。
向こうも同じ写真を開いているはずなのだが、口頭で指示を出すのは難しい。
「それじゃ、今から写真にマークして送信しますので、それで確認して下さい。」
尾藤は音声通話を一旦保留にして、バックチャームの娘にマーキングをしてから写真を送信した。
暫くしてから、母親から写真を受け取ったとの返事があった。
「そのマークの娘です。お願いできますか? 」
尾藤が確認を求めると、母親の当惑した声が聞こえてきた。
「あの・・・尾藤さんが印しを付けている子が、里田さんなんですけど・・・ 」
「はあ? 」
今し方、纏まりかけた推測が一瞬にして打ち消されてしまった。
(あの子が里田? しかし出角は別な子を里田かおるだと言っていた。それは、単なる間違いだったのか? いや、自分の受け持ちの生徒の顔を間違えるはずがない! )
おそらく、出角は意図的に偽りの情報を渡したのだ。
(何故、そんなことをした? )
冗談や嫌がらせではない。
尾藤の調査活動を本気で妨害しようとしているらしい。尾藤が混乱し、手間取るよう、嘘の情報を渡したとしか考えられない。もし、出角が意図的に里田かおるを偽ったとしたなら、これは不祥事の隠ぺい工作などという生易しい理由ではなくなる。
(昨日、俺は出角に対して「もしかしたら、こいつが犯人かもしれない」との不審を感じたが、それは正しかったってことか? )
尾藤の現場検証に付き合っていた時に出角が取った非協力的な態度と、極端に事件の表沙汰を嫌がる態度が思い出された。それらは、出角自身が犯人であるならば当然取り得る行為だった。
尾藤はバラバラに浮かんできた考えを素早く整理した。
(まず、里田かおるは殺人サークルの一員だと仮定しよう。司廉子の失踪にも深く関わっていることにしておこう。その彼女に事情聴取をしようとする厄介な調査員が現れた。サークルにしてみれば気が気ではない。彼女はサークルの一員とはいえ、所詮は非力な女子中学生。手練れの調査員が強引に問い詰めたなら、サークルに関する秘密を話してしまうかもしれない。そうなっては困る! だから手を打った? )
手を打ったのは誰か?
これを出角とすれば辻褄が合う。
尾藤に偽りの情報を渡したのは、里田かおるの口封じを段取りをするための時間稼ぎをしようとしたのかもしれない。
(それじゃ、出角も殺人サークルの一員? 誘拐犯人の一人? )
もちろん、現段階ではサークルの存在も含め、これらはあくまでも推測であり、証拠は何一つないのだが・・・
(だが、これが真実だとしたなら危険極まりない! )
出角は教え子の一人を誘拐し、もう一人を口封じのために殺した。
サークルが事件の完全な隠ぺいを目指すならば他にも犠牲者を求めるかもしれない。
その先には事件を煩く嗅ぎまわる調査員の存在、尾藤の名も挙がるだろう。
(こうなったら、出角に直接会って抑え込むべきか? いや、そんなことをしても惚けられてしまってはどうしようもない。)
民間調査員の尾藤では、どう足掻いたところで警察のように強制的な捜査を行うことはできないし、容疑者の身柄を確保することもできない。
そもそも、そこまで断定できる証拠が無い。
(いや、もしかしたら判断材料ぐらいはあるかもしれないか? )
校舎裏に残されていた証拠を改めて調べてみようと思った。
あの証拠を直に見て確認したのは尾藤と出角だけである。もし出角が犯人だとしたら、誰にも報告せず証拠を隠滅し、惚けようとするだろう。
(つまり、現場の証拠が消されていれば出角が消したと考えて良いわけだ。)
それが確認できれば、事件の証拠が失われてしまっていても出角の関与を特定することはできる。出角に対する攻め方は、その後で考えれば良いのである。
(そうと決まったら確認は急がなければならない。だが、これから出角を訪ねて行っても門前払いを食らわされるに決まってるし、あいつが一緒にいたら邪魔だ。)
母親との音声通話を終えた後、尾藤は時計を見た。
一六時半。
(学校が終わって教職員が全て帰るのが、確か二〇時過ぎぐらいと聞いた。今から三時間半後に学校は無人になる。昨日見た限りでは、自動警備システムは職員室やコンピュータ室など、校舎内の一部にしか設置されていない。校地内には監視カメラも動体センサーも設置されていなかった。夜間の校地侵入は決して難しいことではない。)
それが泥棒紛いの行為であることは重々承知しているが、今は緊急時である。
司廉子の捜索を先に進めるには方法を選んでいられない。
(ものの数分で終わる作業だしね。)
尾藤は決心し、早速準備を始めた。
社長室兼応接室には、尾藤が置きっぱなしにしている仕事着と様々な業務用器具が収められているロッカーがある。
尾藤はロッカーの中から、マグライト、カメラ、手術用のゴム手袋などを取り出し、これらをウェストポーチに詰め込みながら、ふと思った。
(用心のために見張り役でも立てとこうかな? )
[八]
尾藤がベイジョ、港女子学園裏手の路地にやってきたのは二二時。
路地に人通りは見えず、住宅の門灯やマンションの窓から僅かに漏れる灯り以外には街灯も無い。
間近で擦れ違った誰かの顔の確認も不自由なほどの暗さである。
(住専地区なんて、こんなもんだろ。)
司廉子が行方不明になった時間帯も大差無かったに違いない。
(目撃者がいないわけだ。)
昨日、ベイジョを出てから早速周辺の聞き込みをしてみたのだが、全てが不発に終わっており、何の情報も得られていない。
(さて、そろそろ始めようか。)
尾藤は、再三周囲を注意深く確認してからレンガ塀を見上げた。
仕事は短時間で済むはずだが、こうした不法侵入行為を働く際には用心のために見張り役を立てておくべきである。尾藤はアディに頼むつもりでいたのだが、彼の携帯通信端末に何度着信を入れても捕まえられなかった。
「二二時頃に港女子学園裏に来て欲しい」
とのメッセージを入れておいたのだが、結局伝わらなかったようだ。
アディにも都合があると思うが、昨夜の勢いなら喜んで飛んで来るか、来ないまでも返事ぐらいは寄こすかと思っていたのにガッカリした。
(せっかく、仕事にしてやろうと思ったのに・・・ )
見張りを置けなかったのは残念だが、仕事は単なる現場のチェックだけなのだから作業自体に人手はいらない。
尾藤は助走を付けてジャンプし、レンガ塀に両手を掛け、その勢いのまま壁を蹴って忽ち三メートル近い高さを登りきった。
そして壁の上で身を伏せ、内側の様子を伺う。
(人のいる気配は無し。)
尾藤は昔から身軽さと身体の柔らかさには自信があった。筋力と体力、それにスピードに関してはトレーニングを怠らないように心掛けているので、三〇代半ばの今でも二〇代前半の頃と同じように身体が動いてくれる。
壁の内側に誰もいないことを確認した後も、決して勢い良く飛び降りたりはせず、壁面をつたうようにして静かに内側の地面に降りた。足元の暗さを用心したのと、深い足跡を付けないための配慮だった。
(さてと、)
昨日見付けた誘拐犯の痕跡が残る壁面のある場所に移動すると、背中にまわしたウェストポーチを開いてマグライトを取り出した。
そして、照らす範囲を絞り込みながら、ゆっくりと壁面を探った。
(やはりね。)
昨日見付けた痕跡は消されていた。
こびり付いていた土や雑草は払い落され、靴を擦ったような跡も綺麗に消えていた。
(随分、丁寧に作業したようだな。)
地面に残されていた足跡も綺麗に均されていて、侵入者の退路を証明するための証拠は全て無くなっていた。
(これで、一つ重要なことが決まったぞ。)
こんなことをする必要があるのは犯人だけ。この場所に証拠が残されているのを知っている者は尾藤の他には出角しかいない。
里田かおるを偽って紹介したり、ウンザリするほどに非協力的な態度を取っていたことなども思い合わせると、出角が犯人の一人である可能性が非常に高くなった。
(出角を追い詰めれば、背後にある共犯やサークルが見えてくるかもしれない。)
尾藤は確認作業を終えると、マグライトをウエストポーチに戻し、直ぐに壁をよじ登って路地側に人影が無いのを確かめ、静かに飛び降りた。
その時、
(うっ! )
壁の上からは気付かなかったが、向かいのマンションの隙間に人間が潜んでいた。
それも、大柄で逞しい体形のシルエットを持つ男が四人。
(なんだ、こいつら? )
四人は何も言わず素早く移動し、尾藤を取り囲んだ。
皆が手に光沢のある凶器らしきモノを握っており、暗くて顔も見えないが尾藤に危害を加えようとしているのは明らかだった。決して夜の学校に忍び込んだ不審者を捉えようとする正義漢の雰囲気ではない。
通り魔のような殺気を孕んだ男たちであった。
(そうか! )
尾藤は直ぐに状況を理解した。
(こんなに早く口封じに来たのか! )
予め予測していたことである。
事件を煩く嗅ぎまわり、誘拐の証拠を指摘した調査員など邪魔に決まっていた。
誘拐の証拠を決したら、その次は尾藤を消しに来るのは当然だった。
(おかげさまで、こっちの推測が正しいことが分かったよ。)
男たちの襲撃は、尾藤の調査が的を得ていたことの証明である。
それにしても、いずれ口封じに現れるなら出角本人と手伝いが一人か二人だと思っていたので見積もりが甘かった。
目の前の四人は随分と手荒な仕事に慣れた者たちのようだ。
(だがプロじゃない。たぶんセミプロだな。)
プロの殺し屋ならば尾藤は今頃、爆弾で吹き飛ばされるか、機関銃を乱射されてハチの巣になってしまっている。
こんな、絵に描いたような忍者式の暗殺をしようとする者はセミプロだろう。
どちらにしても、あまりお目にかかりたくない類の連中ではある。
(もちろん、こっちを殺すつもりなんだろうね。)
既に里田かおるを殺している連中なのだから当り前である。
(助けを求めて叫んでみるか? )
だが、夜間の住宅地で叫んでみたところで直ぐに助けが来たりはしない。家の中で警察に電話してくれる人がいるぐらいだろう。
(そんなじゃ間に合うわけないから、何とか自力で切り抜けなきゃ。)
尾藤はジリジリと後退りして、レンガ塀を背負うようして立った。
退路を断ったわけではない。
背後から襲われるのを避けたのだ。
(前に二人、左右に一人づつか・・・キツイな。)
逃げ道は完全に塞がれており絶体絶命のピンチだが、尾藤は意外に冷静だった。
大学時代は柔術、高校時代は空手で鍛え、共に四段の腕前という自信の裏付けがあってのことなのだが、刃物を持った四人が相手では分が悪過ぎて、戦って無傷で突破できる自信は全く無い。
にもかかわらず、恐怖心は無い。
全身の血流にアドレナリンが満ちて来るのが分かる。
自分が殺されるという想定は全く浮かんでこないし、どちらかと言えば仕事をしているという実感が湧いてきて、この危機的状況を嬉しくも感じられた。
(俺って、変な奴かな? )
だが、こういう時に度胸が据わっているのは利点である。
(さて、こいつら、どうやって襲ってくるつもりか? )
たぶん、四人一度に掛かってくることは無い。
刃物を持って乱闘すれば同士討ちの恐れもあるので、一人、又は二人程度が順に打ち掛かってきて、残りはバックアップに回らざるを得ない。
尾藤は凶器の的を小さくするために背を丸め、姿勢を低く身構えた。
(まずは、最初に掛かってくる奴を一撃で仕留めるのが肝心! )
尾藤は静かに気合を入れ、手足の震えを抑え込んだ。
ザッ!
アスファルトを蹴立てる音と共に、左側にいた男が手にした凶器を突き出し、飛び込むように間合いを詰めてきた。
「っとぉ! 」
凶器が身体に触れる一瞬手前で尾藤は身体を捻る。
突進をかわされた男の凶器が、レンガ壁に当たり鈍い音を立てた。
それと殆ど同時に、
「グウッ! 」
と、呻いて男は凶器を取り落とし蹲った。
相手の攻撃をかわしながら渾身の力を込めて放った尾藤の拳が、見事に男の鼻先に突き刺さったのである。
鼻骨が砕ける感触を拳に感じながら、
(上出来っ! )
尾藤は心の中で叫んだ。
しかし、喜んでいる暇は無い。
間を置かずして正面の二人が同時に襲ってきた。
尾藤は素早く体制を整えて迎え撃ち、一人を咄嗟に繰り出した前蹴りで転倒させた。
ところが、
(しまった! )
迂闊にも、もう一人の凶器を持つ手を掴んで組み止めてしまったのだ。
複数の敵を相手にする場合、こちらの動きを止めてしまっては勝ち目が無い。常に動き回って、的を絞らせないことが肝心だったのに大失敗だった。
これをチャンスと見た右側の男の凶器が素早く迫ってくるのがわかる。
(殺られる! )
さすがの尾藤にも死の可能性が頭を過ったのだが・・・
ヒュッ!
風を切る鋭い音が聞こえた。
続いて、
ビチッ!
鈍い打撃音が聞こえた。
尾藤に迫ってきていた右側の男が動きを止め、凶器を取り落とした。
(何が起こった? )
考えるのは後回しだった。
尾藤は固めていた相手の腕を引き寄せ、膝の裏側を狙って足払いを掛けた。
男は宙を一回転して肩口からアスファルトの上に落下し、そのまま気を失ってしまったらしく動かなくなった。
(よしっ、残るは一人! って・・・え? )
いつの間にか、もう一人増えていた。
但し、そいつは四人の仲間ではない。
残る一人の凶器を叩き落とし、ボクシングスタイルで追い詰めている。
「アディ! 」
尾藤が叫ぶと、アディは嬉しそうに、
「遅くなってごめんなさい! 」
と、返事した。
どうやら右側の男の動きを止めたのはアディのパチンコモドキだったらしいが、カラスを即死させる一撃は男の顔面を血塗れにし、既に戦意を喪失させていた。
尾藤は泣き出したいほど感謝した。
遅れてきたことなど、どうでも良かった。
これで、アディは命の恩人である。
四対一で優勢だったはずが、二対一の劣勢に立たされた最後の男は逃げ腰になった。
「アディ、無理すんな! そいつは逃がせ! 」
尾藤が声を掛けると、アディは直ぐに一歩引いた。
すると、男は脱兎のごとく路地を駆け去って行った。
それに続くように傷ついた二人の男も逃げて行った。
この場には尾藤の足払いを食らい、脳震盪を起こして転がっている男が一人残された。
「こいつを捕まえるぞ! 」
尾藤はアディに合図して、男を取り押さえにかかった。
男は直ぐに意識を取り戻したが朦朧としているようで、腕を振り回して奇声を発しながら抵抗しようとしたのだが、一対一の喧嘩ならば尾藤に問題は無い。
簡単に男を引き摺り倒し、両腕を殺して地面に抑え込んだ。
「お前ら、何者だ? 」
尾藤の問いに、良く分からない言葉が返ってきた。
「こいつ、日本人じゃないな! 」
マグライトで照らしてみと、そこにはアフリカ系人種の顔があった。
「どうしよう? 警察呼ぶ? 」
アディが携帯通信端末を手にして一一〇番発信する準備をしていた。
「それはマズイな・・・ 」
夜の女子校に忍び入ったことがバレてしまう。せっかく捕まえた手掛かりを、直ぐに警察に引き渡してしまうのは惜しいかもしれないとも思った。
男は聞いたことも無い言葉で意味不明なセリフを繰り返している。日本語どころか、英語も全く通じないが、尾藤は他に話せる言葉が無い。アディがフランス語はできると言うので話し掛けさせてみたが、これにも反応が無い。
全く尋問のしようが無くなってしまった。
「困ったな。」
尾藤は路地のど真ん中で男の腕を極めたまま窮してしまった。
「あれ、何か落ちてるよ・・・ 」
アディが道に落ちている何かに気付いて拾った。
「カードだよ、ほら。」
アディが差し出したカードには文字が書かれているが、暗過ぎて何語で何と書かれているのかは読み取れない。
「名刺? 会員証? こいつらのか? 」
「たぶん、そういうことなんじゃないのかな? 」
アディはカードを裏返した。
「なるほど。」
尾藤は唸った。
(里田かおると同じ、サークルの連中だ! )
名刺の裏には、白地に黒でタンポポマークが書かれていた。
「こいつも持ってるのか? 」
アディに男のポケットを探らせると全く同じカードが出てきた。
「これで、尋問の手間は随分省けたな。」
そう思って気を抜いた瞬間、路地に爆音が轟いた!
「尾藤さん、危ない! 」
アディが三人の男たちの逃げた方向を指差して叫んだ。
一台のヘッドライトを消した車が黒い塊となって猛スピードで走ってくる。
狭い路地を塞ぐほどの広い車幅を持つRV車が、何度か電柱や塀に接触し火花を散らしながら迫って来る。
「ヤバい! 逃げろっ! 」
アディがマンションの隙間に飛び込み、尾藤は素早くレンガ塀の上に駆け登った。
残念ながら、せっかく捕まえた男は逃げられず、助けてやることもできなかった。
ドドン!
という重い音が聞こえたかと思うと、男の身体はRV車のボンネットで弾み、屋根の上を乗り越え、転がりながらアスファルトの上に落ちた。
RV車はブレーキも掛けず、そのまま一気に路地を走り去ってしまった。
尾藤は絶句し、塀の上で茫然としていた。
アディも何が起きたのかわからずにキョロキョロしている。
しかし、いつまでも茫然としているわけにはいかなくなった。
周辺のマンションやアパートの窓が次々に開き、玄関には灯りが点いた。
車が走り去った爆音と衝撃音に気付いた付近住民が動き出したのだ。
「やはり、警察に連絡だな。」
尾藤は道端に腰を下ろし溜息した。
[九]
結局、尾藤は警察に連絡せざるを得なかった。
やってきたのは杉並署の警察官たち。
死人が出てしまっては、民間ではどうしようもない。
然るべき届出をしなければ、こちらが犯罪者にされてしまう。
ある意味幸いだったのは、尾藤がベイジョに忍び込んだことを知っている者は逃げるか死ぬかしてしまったため、事情聴取の際には、その部分を省けたことである。そこを省けば、こちら側には全く罪のない話であり、調査業務の遂行中に暴漢に襲われた不運な被害者という説明で落ち着く。
だが、現段階での警察の介入は、どうにもタイミングが悪い。
尾藤の当初の計画を進めるには少々面倒なことになりつつあった。
木村に頼んで今回の仕事を外注扱いにしてもらうという計画のことである。
今夜の出来事のおかげで、尾藤は警察に調査活動の内容や進捗状況の説明をせざるを得なくなってしまった。暴漢たちが残していった二枚のカードのうち一枚を取り上げられ、(もう一枚は隠し通したが)薄っすらと存在を現しつつある謎のサークルについて報告しなければならなくなった。
誘拐や殺人などの犯罪を犯すサークルという話に、警察は当然食いついてきた。
存在を実感したというだけで未だ殆ど何も掴んでいないのに、まるで尋問ではないかと思える程しつこく質問され、手に入れた僅かな情報を全て吐き出させられた。
その結果、
「これは民間の扱うべき事件ではない! 」
との、結論を下されそうになってしまったのだから堪らない。
これでは外注扱いにしてもらうどころの話ではない。
「後は警察が引き継ぐから、民間は関わるな! 」
これは殆ど命令であり、
「命令を無視して無断で事件に関わったなら公務執行妨害で逮捕するぞ! 」
と、いう警告も含んでいる。
(それは困る! 事務所の信用にも関わるし・・・ )
仕事を取り上げられては堪らないので、尾藤は当然のように木村に縋ることにした。
ところが、その木村も今夜の事情を知ってしまった上では尾藤の頼みを軽々と聞き入れてやるつもりは無くなってしまっていたらしい。
事情聴取を終えてから、
「いやぁー、まいっちゃったぁ。」
と、気楽な調子で杉並署内で残業中の木村のところへ顔を出しに行った尾藤は、いきなり奥襟を掴まれて強引に引き摺られ、たまたま空いていた取り調べ室の一つに放り込まれてしまった。
そういうことで深夜の杉並警察所内、取り調べ室。
「怖い顔しちゃって。」
木村の渋面を面倒臭そうに横目で見ながら、尾藤はウエストポーチからスティックキャンディを一本取り出して口に銜えた。
すると、木村が何も言わず強引にキャンディをむしり取った。
尾藤はムッとしながら再びウエストポーチに手を入れ、もう一本スティックキャンディを取り出して包装を破こうとしたのだが、またもや乱暴に奪い取られてしまった。
ドドン!
木村は奪い取ったキャンディを握った手を机上に思い切り叩きつけた。
(あーあ。)
尾藤のスティックキャンディは粉々である。
「お前、どれだけヤバい件に首を突っ込んだのか分かった上で、関わらせてくれなんて言ってんのか? 」
スチール製の机を挟んで尾藤と向かい合った木村は、これ以上無いぐらいのキツイ渋面をして怒鳴った。
「手を引けっていう署の連中の意見には俺も賛成だね。これは民間レベルの仕事じゃない。非合法な犯罪結社かもしれないんだから、所轄の仕事でさえないかもな。そんな相手を民間業者に任せて失敗したらどうする? 万が一、お前が殺されでもしたらどうするんだ? 警察は責任を追及されるし、被害は拡大した挙句、サークルは一層深く潜っちまうんだよ! 」
そう言って木村は、上着のポケットからファスナー付きのビニール袋を取り出して机上に放った。
袋の中には、事情聴取の際に取り上げられた例のカードが入っていた。
(こいつ、カードの持つ意味を知ってるな。)
尾藤がピンときたとおり、木村はサークルの存在まで知っていた。
「そいつはな、公安が目をつけてる地下サークルの一つさ。今年の夏ぐらいから要注意指示が来てるんだ。」
但し、公安も未だ殆ど情報を持っていないようで、かなりの数の入会者を抱えたサークルであり、暴力や破壊行為に走る恐れのある凶暴な団体の可能性があるという以外には、主催者は不明、拠点も不明、主義主張や活動内容も不明という困った状況にあるらしい。
(そんなんで、ヤバいとか、要注意とか、何故わかるんだろ? )
尾藤は首を傾げたくなった。
「死人が出てんだよ。」
木村は脅しを掛けるような言い方をした。
死人と言えば、民間調査員如きはビビると思っているのだろうか?
「ああ、それならアディも言ってた。集会の度に死人が出るんだって。サークルの秘密を漏らしても殺されるってさ。」
尾藤は平然と答え返してやった。
既に聞いていたことだし、改めて驚きはしない。
チッ!
大きな舌打ちが聞こえた。
「アディって、お前と一緒にいた外国人の若い汚い奴だな? 」
「そうだよ。臨時助手のアルバイトに雇ったんだ。汚い奴ってのは酷いな。」
「アルバイトねぇ。」
木村は抱えてきたノートPCをテーブルの上で開き、移民局のサーバーにアクセスしてデータを引き出した。
「バングラディシュ人、二二歳。不法入国じゃないみたいだな。ビザも更新済み。本国での経歴も含めて特に犯罪歴などの問題は無し。但し、登録されている現住所が古過ぎるな。うーむ、これはまずいなぁ。」
眉間に縦皺を寄せて左右に首を振って見せたが、このポーズも脅しのつもりらしい。
「別に、現住所は申請し直せば問題ないじゃん。」
外国人の出入国や滞在に関する各種法的手続きなど、尾藤は本職の役人並みに熟知しており、木村のハッタリなどで怯みはしない。
「まあ、そりゃそうだ。」
木村は、再び舌打ちしながら片手でノートPCを閉じた。
何とか尾藤を動じさせて、自分が優位な立場で話をしたかったようだが、全く手応えが無いので如何にもやり辛そうな顔をしている。
「で、お前が手に入れたサークルに関する情報は、そのアディからか? 」
「そのカードにあるタンポポみたいな意匠がサークルのモノだって教えてくれたのはアディだよ。」
「まさか、サークルの関係者じゃないだろうな? 」
「いやいや、それは無い。彼が知っていたのは噂の類だけ。」
「ふーん、その噂ってのは、何処から聞いたんだろうな? 」
「知らん。そんなことは、本人に聞けよ。」
暫し気まずい沈黙が訪れた。
(どうやって木村を黙らせて、協力を取り付けようか? )
尾藤は、そんなことを考えている。
一方木村は、どうやって尾藤に調査から手を引かせるかを考えているに違いない。
二人の間に重苦しい空気が流れていた。
沈黙を破って先に口を開いたのは木村だった。
「この仕事、お前には無理だよ。この先、今晩みたいなことが何度でも起こるかもしれないじゃないか? なあ、聞き分けてくれよ。」
今度は強情な子供を諭すような口調で言う。
強圧的に出ても効果が無いので、作戦を変えたらしい。
しかし、尾藤は直ぐに切り返す。
「それじゃ、公安や警察は俺の代わりにサークルの調査を続けてくれるってーの? 」
「も、もちろんだよ・・・ 」
木村の返事は歯切れが悪かった。
尾藤は内心でほくそ笑んだ。
怪しいサークルだからと言っても、現状の不十分で曖昧な証拠だけでは優先的に捜査対象にすることができないという警察のお家事情が手に取るように分かる。
そこで、さらに畳みかける。
「司廉子や他の失踪者も見つけてくれるの? 」
「し、仕事だからな・・・ 」
「これって、人命がかかってんだから、最優先で捜索してくれるんだよね? 」
「いや、最優先とは・・・ 」
語尾が濁ってばかりで、満足な答えが返ってこない。
「ほらねっ、やっぱり警察は動けないじゃん! 」
尾藤は、それ見たことかという顔をする。
明らかに木村は答えに窮しているようで、苦しい言い訳を始めた。
「今晩の出来事で事件性が見えたわけだから、こっから先は警察、いや公安の仕事かもしれない。しかし、最優先に捜査するというわけにはいかない。他にも重要な案件を沢山抱えているし、こっちの目的は組織の存在を明らかにし、必要なら壊滅させることだからな。誘拐事件の捜査は所轄も絡むが、所轄には優先的に張り付ける人手は無い。」
警察の人手不足については聞き飽きた。
切実な問題だと思うが、こう何度も聞かされていたら真面目に相槌を打ってやる気にもなれなくなっている。
それどころか尾藤は、こうした木村の弱みを正論で突いてやることにした。
「それならさぁ、俺が警察に調査活動をバトンタッチしたら娘はどうなるの? 警察が他の仕事と並行して、ゆっくり捜査していたら殺されるかもしれないよ。」
実際、尾藤が仕事を手放したくない理由の第一はそれである。
「人命優先! 」
その明らかな正論の前では、木村は何も言えない。
「人手不足、人手不足って言うけどさぁ、人手ならいるじゃん、目の前に。」
尾藤は、自分を指さして言った。
「お前、危険だって言ってんのがわかんねぇのか! 」
怒声と共に、木村の拳骨が机上を叩く。
元どおりの強圧的な姿勢に戻ることにしたらしい。
その迫力に、思わず尾藤は座ったままで「気をつけ」の姿勢を取ってしまった。
(こいつ、昔から議論で負けそうになると気合いで何とかしようとするんだよなぁ。)
木村に言われるまでも無く、今回の仕事が危険であることは身を持って理解している。
だが、手は引きたくない。自分が手を引いたら司廉子を助ける者がいなくなってしまうではないか。現状で警察に任せておいたら、サークルは最終的に暴かれるかもしれないが司廉子は見捨てられてしまう。
(そんなん冗談じゃないぞ! 少しでも助けられる可能性があるなら、それに賭けてやらなきゃ娘も両親も可哀そうでしょ! )
それと、尾藤が拘る理由は他にもある。
自分の命を狙った奴らに仕返しをしてやりたいという強い敵愾心が芽生えてしまっていたのだ。
いい加減な性格で身の回りはだらしなく、誰からも惚けた奴とみられる尾藤だが、意外に負けず嫌いで執念深い一面を持っている。
例えば学生時代、空手や柔術の試合で負けた相手には執念深くリベンジの機会を狙ったし、試験の成績で自分を追い抜く者がいたら必死で抜き返そうとするタイプだった。仕事の面でも、受けた依頼が不首尾に終わりそうになったら、採算を度外視してでも逆転を試みようとすることが過去に何度もあった。
いわゆる面倒臭い男だったのである。
自分の命を狙おうとした奴らは許せない。だが、敵が大き過ぎて木村の言うように民間調査員が単独で立ち向かえる相手ではないかもしれない。いざという時の保険として警察のバックアップを取り付けておきたい。
だから、尾藤は何とかして仕事を手放さずに、木村を言い負かさなければならない。
「同じこと繰り返すけどさ、そもそも公安や警察が動いたとしても、目的はサークルの調査が主になるんだろ? こっちの目的はクライアントの娘を救うことなんだよね。相手は一緒でも、求める結果は全然違うのよ。例えば娘の死体が出たなら、俺の仕事はそこで終わっちゃうけど、警察はそっから先が仕事なんでしょ? そしたら、俺が手を引いたらさ、娘は絶対に助からないってことじゃない。でしょ? でしょ? 」
木村が唸り始めた。
何か言い返したそうな顔をしているが、それができずにイライラしている。
荒い鼻息と歯軋りが煩い。
(ウンコ詰まってんじゃねぇの? )
ついつい、そんな冗談を言いそうになったが慌てて止めた。
この状況で、下ネタを口に出したらブン殴られてしまう。
(しゃーねぇーなぁ・・・ )
木村がいつまで経っても唸るのを止めないので、尾藤はそろそろ取引を持ち掛けてみることにした。
「どうだろうねぇ? この件に関して人命優先は俺に任せてよ。公安だってさ、やっぱ娘の命は助けたいでしょう? 人の命は大切じゃん。それに、こっちが片付いたら俺の調査した内容は、そのまま公安の仕事に引き継げるのよ。手に入れた情報は途中の段階でも全部提供するからさぁ。それって嬉しくない? 何もできないままじっとしていて、お鉢が回ってきてから一から捜査開始なんて辛いんじゃない? こっちに下拵えさせといた方が、後々楽だよ? ねっ? 」
木村は不機嫌丸出しの表情を張り付けたまま返事をしない。
どうしても、民間が関わるべき事件ではないという考えを変えたくないようだ。民間業者にウロチョロされて、公務の邪魔をされたくないとも考えているに違いない。
但し、そういった業務上の理由以外に、尾藤の身を心配をしてくれているという気持ちも十分に伝わってくる。
長年の親友を危険な目に遭わせたくないという木村の気持ちは素直に有難いと思う。
だが、その気持ちに負けるわけにはいかない。
(もう一押しすれば落ちるっぽいし。)
今度は正義に訴えてみようと思った。
「お前に貰った資料を検証してみても、何らかの組織が意図的に誘拐を繰り返しているってのは殆ど間違いないんだよ。その犯罪組織の存在を明らかにするのは警察の役目。そうだよね? 」
「そりゃ、当り前だ。」
「犯罪組織を壊滅させるのも警察の仕事。そうだろ? 」
「もちろん。」
答えながら木村は訝しげな顔をしていた。
尾藤が口を開く度に「何を企んでいるのか? 」と、露骨に警戒している。
(んじゃ、次は意地悪な質問します。)
「犯罪を未然に防ぎ、都民の命を守るのは誰でしょう? 」
案の定、木村が言葉に詰まったので、
「それも警察の仕事でしょう! 」
尾藤が代わりに言ってやった。
「おいっ! 」
木村は尾藤の意地悪に腹を立てた。
「こっちだって分かってんだよ! 犯罪抑止や犯罪阻止が大事だってのは、この世界に入ってから耳にタコなんだ。馬鹿っ! 」
と、凄んで見せた。
凄んで見せるぐらいしか、することが無くなってしまったようだ。
尾藤は、既にダメ押しの段階に入ったと見ている。
「警察は都民の安全を守らなきゃならないじゃない。例え人手不足でも、忙し過ぎても守らなきゃならないじゃない。ね、守ろうよ。守りたいでしょ? 」
木村は操り人形のようなギクシャクした動きで頷いた。
「よし、決まった! 警察は都民を守る。そのために有効な手段を用いなければならない。さぁ、有効な手段って何? 」
耳に手を当てて木村の返事を待った。
少し経ってから、
「それが、お前だって言いたのか? 」
木村が喉の奥からセリフを絞り出すようにして言った。
尾藤はすかさず親指を立てた。
「あんまり偉そうなことを言うつもりはないけどさ、お粗末ながら尾藤総合調査事務所が警察の露払いを引き受けますってこと。良い手だと思うんだけどなぁ。」
しかし、木村は未だ頷かず、最後の抵抗を試みようとする。
「お前は知っているのか? そもそも地下サークルって奴の中身は様々で、全く無害なサークルも無いわけじゃないが、犯罪性の高いサークルは数多くあるんだ。今年警察が摘発した地下サークルの中には、人の命に関わる危険なサークルが六件もあったんだよ。例えば、思想的に危険なテロサークルもあったし、交換殺人の会、殺人ライブ映像の撮影同好会、死体愛好会、人体破壊を厭わない過激なSMサークルなんてのまであった。お前が絡んでいるのは、こうした危険な団体の一つなんだぞ。」
「そりゃまあ、命を狙われたんだから、そうなんじゃない? 」
事も無げに言う尾藤に木村は「全然分かっちゃいない」と、首を振った。
「お前は地下サークルの恐ろしさを知らん! 大規模なサークルは組織がしっかりしていて結束力が強いんだ。たった一人で攻め落とせるような甘いもんじゃない! まず、地下サークルの奴らに共通して言えることは世間を憚らなけりゃならない集団だってことだが、そのために会員間のネットワークは綿密で強固だし、世間と自分らの間に一線を引くためのガードの堅さと警戒網の感度は異常なほど高い。さらには自らを守るために過激な行動に出ることもある。つまり、お前は口封じに四人も刺客を送れるほどの規模の過激なサークルの網に引っ掛かってしまったんだ。」
これに関して、尾藤には返す言葉が無い。
「例えば、一般市民と暴力団の違いを見分けるのは難しくない。見た目が違う場合が多いし、話してみたり、仕事は何をしているのか調べてみれば直ぐに区別できるからな。ところが地下サークルの場合、一般市民と変わらんのだよ。目を血走らせた異常者が会員ってわけじゃない。普段は平凡な日常生活を営んでる普通の人だから、見掛けじゃ区別が付かない。今後、お前がどれだけ用心して調査を続けたとしても、自分の命を狙おうとする刺客が何処に潜んでいるのかを見付けるなんてできっこないぞ。だがな、奴らにはお前が見える。気付かれないように静かに忍び寄ってきて命を奪うことも難しくない。昨夜は明らかに殺意を持った連中四人に襲われたそうだが、いつもそうとは限らない。一見非力な年寄りや主婦が、お前を満員電車の中で刺殺したり、ホームから突き落としに来るかもしれないんだ。そんな相手とどうやって戦う? え? 」
全く、その通りである。
木村の言うことは正しい。
だが、尾藤に引き上げるつもりは無い。
このまま、お互いの正論をぶつけ合いながら、話はどこまでも平行線を辿りそうな予感がしてきた。
(こっちも情に訴えるしかないなぁ。)
尾藤は訥々とした口調で、しんみりとした雰囲気を醸し出しながら縋るように言った。
「お前が言いたいことはわかる。俺の身を案じていることは本当に有難いよ。俺だって自分の命が大切だし、死にたくなんかない。でもな、これには人の命が掛かっていることを忘れるわけにはいかない。そうだろ? 今、司廉子の命を救うのが俺の仕事として目の前にある。お前が同じ立場ならどうする? 危険だからといって諦められるか? 諦めた後に、後悔を残さず平然として生きていられるか? 」
それについて、木村は何も言わなかった。
そろそろ尾藤を思い止まらせることは難しいと観念した様子が見え始めていた。
(よし、落ちたな! )
本来、警察官の人道意識は高い。
組織としての実情、友人の命に重きを置いた発言等を繰り返していても、決して人命を軽視しているわけではない。
結局のところ、木村は板挟みになっているのだ。
現状では多忙な警察に任せるよりも、尾藤が調査を継続するほうが司廉子の行方を見つけられる可能性が高いということは木村もわかっている。
ここで尾藤が素直に忠告を聞いて調査を打ち切り、その結果少女の命が失われたなら、木村の心の中にも消せない傷が残るに違いない。
「しかし、俺はお前が殺されるようなことがあっても後悔するんだぞ。」
と、木村は言った。
「その気持ちは有難く頂くよ。でも、それならば俺が依頼者の娘の命を心配する気持ちもわかるだろう? 」
「ああ、わかる。だがな・・・ 」
言葉を続けようとした木村を尾藤は制した。
「民間の手に負えない事態になったら、その時は潔く警察にバトンタッチさせてもらうから、それで良いだろ? 頼む、調査を続けさせてくれ。そして、万が一の時には力を貸してくれ。」
尾藤は頭を下げた。
結局、木村はそれ以上は何も反論を述べなかった。
根負けしてしまったようだ。
「不本意だが「ゼロ」の手続きを取ってやる。毎度のことだが報酬は出ない。必要経費ぐらいは出してやるから、領収書を俺にまわせ。条件は、報告を逐一入れること。限度を超えた危険には手を出さないこと。以上! 」
[一〇]
黄ばんだ点滅を繰り返す汚れた蛍光灯が、かつては複合型商業施設であったはずの廃墟ビル内のコンコースを薄明るく照らしていた。
全てのテナントが撤退し、所有者の管理も行き届かず、殆ど放棄された状態のまま随分と時が経ってしまっているらしい。
電気が通じているのは奇跡に近い。
埃だらけの床は割れたピータイルが散らばり、黒と茶色のシミで斑になった天井や壁の所々には大きな破れがあって、そこから配管や配電線が丸見えになっている。
コンコースの所々には、かつて営業店舗で賑わっていた頃の名残を見かけた。
変色しカサカサになってしまった年代モノのポスター、セミナーの案内が貼られたコルク板、もはや廃墟の不気味さを盛り上げるための演出効果でしかなくなってしまった女性タレントの等身大パネルなど。
いずれ、これらの名残はビルと共に朽ち果てて、瓦礫と化してしまうに違いないが、それにはもう暫くの時を要する。
(昭和の築だな・・・ )
尾藤はコンコースを行く大勢の人の流れに従いながら、ぼんやりと建物のデザインを眺めていた。
(ところで、この人たちは何処に向かっているんだろう? )
尾藤は列の中程を歩いていたが、そこから前後を見渡すと、一〇〇名を超える人数が二列か三列になって一つの方向に向かって黙々と歩いている。
皆がフードや目出し帽、サングラス、マスクなどで人相を隠している。
尾藤も、濃いサングラスを掛け、ネックウォーマーを口元まで引き上げて、人相を隠していた。
言葉を発する者は誰もいない。
「共通の意思を持った人の群れが、共通の目的地を目指して行進している。」
そんな感じだった。
不思議なことに、目的地が何処かという事以外に疑問が浮かんで来ない。
何故、自らが無言のまま流れに従っているのかという疑問さえ湧かない。
「一緒に来て。」
先ほどから何度も耳元で囁く声がしていた。
若い女の声だった。
囁きの主の姿は見えない。
声だけが尾藤の耳元で聴こえている。
その聞いたことも無い見知らぬ女の声に、何故だか尾藤は従うつもりになっていた。
逆らおうという意思が、まったく起こらなかった。
この場では大勢の流れに従って歩かなければならないこと、言葉を発してはいけないこと、自らの顔を隠すこと、女の声は尾藤に一々言い聞かせるように囁き、尾藤は当り前のように従っていた。
ところで、顔を隠していても分かることがある。
大勢の中には、男がいて女がいる。
老人も若者もいる。
親に手を引かれて歩く子供の姿もある。
人種も雑多で、日本人、アジア系、アフリカ系、欧米系の諸外国人がいる。
何の統一感も無い、人種も年齢も階層も混沌とした人の群れが、黙々と歩いていた。
間もなく、群れの先頭が階段を下りていく様子が見えた。
(目的地は地下? )
まるで緩やかな滝の流れを見ているかのように、灯りの無い階下の闇に向かって次々に人が下りて消えて行った。
ザラザラと引き摺るような足音と共に、地下二階までの階段を降り、ボロボロに痛んだレザー張りのドアを開け、人の群れが行き着いたのは、
(ライブハウス? いや、映画館か? )
そこは、地下一階と二階を繋ぐ吹き抜けた天井と、細かな丸い穴の開いた防音壁で囲まれた広々としたイベントホールである。
ビルの閉館の際に取り払われてしまったのか、客席らしきものは無い。
正面にはステージが配置されており、この空間の中では唯一の照明であるスタンド式のスポットライトが四基設置されていた。
スポットライトの光は、ステージ中央に盛り上がっている白い布の塊を照らしている。
(何か、イベントでも始まるのか? )
この場にいる尾藤以外の誰もが、これから何が始まるのかを知っているようだった。
勝手がわからず戸惑っている間に、この空間に入ってきた者は皆が迷うことなくステージの前に寄り集まって行ったので、気が付くと尾藤は置き去りにされ、人垣の最後列に加わることもできずに締め出されてしまっていた。
(前に行きたい。)
尾藤は、進路を塞ぐ人垣を掻き分け、少しでもステージに近付こうとした。
ところが、力には自信があるはずの尾藤が、どんなにもがいても人垣に身体半分差し込むのが精一杯で、そこから一歩も前に出られない。
(こいつら、床に足が張り付いてるのか? それとも床から生えてるのか? )
尾藤を妨げているのは決して屈強とも思えない者たちであり、年寄りや女性もいる。
(非力そうな奴らばかりだってのに、何故こんなに強いんだ? )
ステージに近付くのを諦めかけた時、
「大丈夫。」
女の声が耳元で囁いた。
すると、突然身体が浮き上がった。
「おっと! 」
それまで進路を塞いでいた人垣が左右に分かれたのだ。
無理矢理前に出ようとしていた力が余って、尾藤は二、三歩前に飛び出すと膝から崩れ落ちてしまった。
(いきなり、力抜きやがって・・・ )
膝の痛みを堪えて立ち上がった尾藤の前に道ができていた。
(どういうこと? )
尾藤は顔を上げて、自分に道を開いてくれた者たちを見渡した。
ところが、左右に並ぶ人々は誰一人尾藤に目を向けず、顔を真っ直ぐにステージに向けて微動もせずに立っている。
無様に転んでしまった尾藤に対し、誰一人関心を払おうともしない。
(何があるってんだ? )
尾藤は道の先あるステージに視線を移した。
いつの間にか、ステージの上には黒色のローブで身を包んだ一人の人間が立っていた。
背後のスポットライトが逆光になっているので顔は見えず、身体もローブに包まれているので、男女の区別もつかない。
(あいつ、知ってるぞ! )
先日の通勤途中に出会った、悪臭を漂わせるロングコートの怪人ではないか。
黒いコートがローブに変わり、悪臭こそ漂わせていないが、尾藤には直ぐに分かった。
(あんな不気味な奴が他にいてたまるか! それに、あいつも俺を知っている! )
怪人が、人の群れを操って道を開き、尾藤に向かって手を差し伸べていた。
その差し伸べる手が道を開いてくれたようである。
(近くへ来いと言うことなのか? )
尾藤は怪人に招かれるように、ステージに向かってゆっくりと進み始めた。
すると!
突如として、尾藤の左右で合唱が始まった!
(なんだ・・・? )
それは多国籍語が混然一体化したような大合唱である。
アジア、ヨーロッパ、アメリカ、アフリカ、世界中の言語が其々に独自の歌詞と音を唱え、それらが寄り集まりイベントホールを埋め尽くそうとしている。
(まるで、呪文じゃないか! )
始まって間もなく、その大合唱は巨大な音の塊りに変わっていた。
英語やフランス語など耳慣れているはずの言語でさえ、音の塊りの中に溶け込んでしまって、一個のパートを奏でているに過ぎない。
微かに歌詞を聞き取れるのは日本語だけだったが、それさえも途切れ途切れに耳を触る程度でしかない。
「ひと ふた ・・・ いつ む な ・・・ たり、ふるべ ・・・らゆらと ふる・・・」
辛うじて聞き取れたのは、おそらくは祓詞と思われる一節。
(神道関係の儀式なのか? )
ところが、必死で他の言語を拾い出そうとしたら、聴こえてきたのは神道とは異なるラテン語らしき聖書の一節であったり、コーランや仏教の経典らしき音も混じっている。
この場にいる銘々が、勝手に自らの信心を唱えている。
全くの無秩序、無調和、凄まじいまでの混沌、聖なる節の合唱は、もはや狂気の重奏と化していた。
呆然としながらも、ステージに向かって進み続けていた尾藤の足取りが乱れた。
泥やタールのような強い粘着質の感触を持った何かが足首に絡みついて、歩みを妨げようとしている感じだった。我慢して歩き続けようとしたが、遂には縺れた足が身体を支えきれず、ステージを目前にして崩れ落ちるようにしゃがみ込んでしまった。
直ぐに立ち上がろうとしたのだが、手足の力が抜けてしまい、痺れたようになって力が入らない。
(う、動けない! )
どういうわけか、完全に身体の自由を失ってしまった。
その時である!
得体の知れない恐怖感が尾藤に襲い掛かった!
「ギャーッ! 」
尾藤は思わず悲鳴を上げてしまった。
体内の全ての気を吐き出してしまったかのような甲高く激しい悲鳴を発し、頭を抱え込んでしまった。
同時に、尾藤の眼前には激しい映像のフラッシュバックが展開された。
途切れ途切れに現れては繰り返される狂気と混乱、苦痛と絶望にまみれた残虐で吐き気をもよおすほどにグロテスクなイメージの数々が、尾藤の脳内で乱舞を繰り広げた。
尾藤を苦しめるフラッシュバックは、それが現実なのか幻覚なのか理解し難いほどの異変を伴った。
凄まじい地響きと共に崩れ落ちる天井、濛々と舞い上がる土埃、床が割れ、地の底からは熱風と黒煙が吹き上がった。
混乱の中、この場に集う人々は逃げ惑うこともせず、何かに取り憑かれたように只管大合唱を続けている。
しかも、大合唱を続ける者たちの声は徐々に恍惚感を伴い始めていた。
異変の始まりと共に一段と高まった狂気の合唱を背に、ステージではスポットライトが激しく明滅を始めていた。
その光の中で、恐るべき殺人の儀式が開始されようとしている。
「見たくない! 」
尾藤は硬く目を閉じ、来るべき恐怖をやり過ごそうとした。
「見なければ駄目。」
またもや女の声が囁いた。
「嫌だ、見たくない! 」
尾藤は抵抗したが、
「目を閉じても意味は無い。貴方は、これを見なければならない。」
女の声が言う通りだった。
その映像は瞼を閉じているのに見える。
耳を塞いでも音が聞こえる。
まるでイメージを脳に直接描き込まれているようであった。
尾藤に逃れる術は無い。
頭を抱え、身体を丸くして、祈りながら、耐えて全てが終わるのを待ち続けるしかなかった。
「Come ! Power of The Underworld ! 」
黒色ローブの怪人が叫び、右手を頭上に高々と上げた。
その手には怪しい輝きを放つ白刃が握られている。
「This Sacrifice to Power ! 」
見えない力によって、ステージ上に置かれた白布が勢いよく捲られ、宙に舞った。
大合唱に混じって、歓声と喘ぎ声に似た興奮のどよめきが聴こえてきた。
白布の下から現れたのは、仰向けに横たわった見知らぬ東洋系の若い女性の姿。
少女と呼ぶべきであろうほどに幼さを残した美しい肢体は一糸も纏わず、舞い上がる埃や煙の中にあっても、明滅するスポットライトの光によって青白く輝いていた。
激しいスポットライトの明滅に晒されながらも少女の眼は大きく見開かれ、中空の一点に視線を留めたまま瞬きもせず無表情のままで、その全身は人形のように身動き一つしていない。
未だ硬く膨らみ切れてはいない両の乳房が、薄桃色の乳首をツンと真上に向けたまま、微かな上下を繰り返す動きだけが、この少女の生命感を肉体に留めていた。
これから何が起ころうとしているのか?
(まるで黒ミサ、降魔の儀式。それならば、あの少女は生贄か! )
今、尾藤の心臓は肋骨を突き破りそうなほどの激しい鼓動を打っていた。
「Please Receive ! 」
怪人は刃を天に向かって翳しながら叫び、床に横たわる少女の傍らに膝をついた。
合唱は歓声に変わった!
その異常な熱狂に後押しされるかのように凶行が始まる!
怪人は片手で少女の片方の乳房を握りしめた。
指間から白い肉がはみ出るほど、乳房が破裂してしまいそうなほどの力を込めていた。
そして次の瞬間、怪人は手にした刃を乳房に突き立て、一気に抉り取った。
「ギャァーッ! 」
それまで人形の様に無言で身動き一つしていなかった少女が辛うじて口だけを動かし、恐怖と苦痛によってもたらされた凄まじい悲鳴を放った。
同時に、この吐き気をもよおす残酷な映像を、目を背けることもできずに見せつけられる尾藤の悲鳴も重なった。
少女の絶叫と飛び散る血飛沫を浴びながら、怪人は躊躇うことなくもう片方の乳房も抉り取った。
そして、狂気の歓声を上げる人々に自らの手際を誇るように二、三度頭を下げて挨拶をすると、床に置かれた銀色の盆の上に、血の滴る二つの乳房を並べて置いた。
例えようのない残酷さ!
いわゆる黒ミサのように、心臓を抉り出すようなことはしない!
「これは嬲り殺しだ! 」
もちろん、乳房を失っても少女は未だ生きている。
ショックと出血で気を失いかけてはいるが、致命傷を受けてはいない。
力無く開いたり閉じたりを繰り返す唇は既に言葉を発していないが、おそらくは助けを求めているか、耐えがたい苦痛からの解放を願って呟いているのだろう。
そんな少女に対して、更なる凶行が加えられる。
怪人は少女の細い腿を強引に抉じ開けると、今度は股間に刃を突き立てた。
「ググゥーッ! 」
その低く鈍い呻き声は少女のモノだったのか?
それとも尾藤の口から出たモノだったのか?
怪人の刃は少女の股間に深々と突き刺さり歪な円を描いた。刃は少女の体内に秘められた子宮や卵巣など、女性器諸共に抉り出してしまったらしい。
既に少女に悲鳴は無かった。
意識は薄れ、歓声に隠れて聞こえはしないが、血と息を吐き出す、荒く苦しい呼吸音を発することしかできなくなっていた。
その頃には、怪人にとって、もはや少女の身体は不要になっていた。
止めを刺すこともせず、苦痛と絶望に苛まれたまま死ぬこともできずにいる少女を放置したまま、乳房や女性器を載せた盆を手にして立ち上がり、そして叫んだ。
「Please Receive ! 」
怪人の叫びに応えるかのように激震が襲ってきた。
「Please Receive ! 」
怪人は再び叫び、頭上に向かって両手で血塗れの盆を捧げる。
「・・・! 」
怪人の叫びに応える声が聞こえた!
怪人の叫びに、何者かが応えたのである!
それは、声ではなかったかもしれない。
まるで、一〇〇頭の餓えた野生の肉食獣が一斉に咆哮したような、深い地の底で醸成されたマグマが地上に噴出する爆音のような、あらゆる生物が根底に持つ恐怖心を刺激して震え上がらせる巨大な轟だった。
しかも、その轟は確かな言葉を形成していた。
果たして人語と言えるかどうかも怪しく意味不明な言葉だったが、規則的であり可変的な音の配列と強弱は、間違いなく何らかの意味を持つ言葉だった。
「Please Receive ! 」
地の底から噴出する激しい熱風にローブの裾を煽られながら、尚も怪人は叫び続けている。
その叫びに応えるように激震は続き、怪人の周りには破壊された天井や壁の瓦礫が次々と降り注ぎ、濛々と膨れ上がる土埃と黒煙が、その姿を徐々に覆い隠していった。
瀕死の少女の姿も既に瓦礫の下に埋もれてしまった。
明滅を繰り返していたスポットライトもなぎ倒され、辺りは漆黒の闇に包まれた。
その闇の中で、尾藤は確かに見た。
「あ、ああ? 」
漆黒の中で蠢くモノがあった。
それは闇よりも黒い・・・
「事務所に泊まっちゃダメって! 何度言ったら分かるんですかっ! 」
尾藤の身体が一瞬だけ宙に浮き、そのまま半回転して俯せに落下した。
ソファの上から転がり落ち、コンクリートの上に薄いカーペットを敷いただけの硬い床に顔面を打ち付けてしまった。
「ぎゃっ! 」
思わず鼻を抑えながら無様な悲鳴を上げた。
未明まで杉並警察署に拘束されていた尾藤は自宅に帰るのが面倒になり、事務所の社長室兼応接用ソファの上で寝汚く眠っていたのだが、それを出勤してきた恵子が見つけて、ソファの背凭れに一発蹴りを叩き込んで起こしてくれたのである。
「いったい、どうしたんですかっ! 」
もぞもぞと動き出した尾藤が、
「あぁ・・・そっか、夢ね。夢だったのね。」
半泣きで鼻をさすっていた。
鼻の痛みによる涙、悪夢から解放された嬉し涙、その両方である。
「とんでもない夢を見ちゃったよぉ。」
と、情けない声を出す。
恐ろしい、恐ろし過ぎる夢を見てしまった。
あの映像は、当分の間、尾藤の頭を離れないかもしれない。
「はぁ? 何、甘えてんですか? 」
労りの欠片も無い冷めた恵子の口調。
(ああ、現実って嬉しい! )
今のところは、恵子の突き放すようなセリフが何とも心地良い。
「おはよう・・・もう九時か。」
尾藤は、鼻と目を交互に擦りながらヨタヨタと立ち上がった。
(えっと・・・? )
目の前には、肩にバックを掛けたままの恵子が怒りの形相で仁王立ちしている。
間もなく、全然心地良くない現実の厳しさが襲ってくるに違いない。
「事務所の鍵は空きっぱなし! 電気も点けっぱなし! 汚れたジャケットは落ちてるし! それに、誰ですかっ? この人はっ? 」
恵子の指差す先には、目を丸くして床に正座しているアディがいた。
(そう言えば、アディも事務所に泊めてあげたんだっけ。)
警察を出てから、アディの汚れた身なりを整えようと二四時間営業のディスカウントストアで着替えを揃え、コインシャワーに放り込み、そのまま事務所に連れてきて、向かい側のソファで寝かせていたのだった。
汚れを落とし、全体的に綺麗になったアディは、ちょっと驚くほどの美青年だった。歳は二二歳と聞いていたが、童顔なので一七歳か一八歳ぐらいの高校生に見えるので美青年と言うよりも美少年と言った方が良いかもしれない。南アジア系にしては肌の色は薄く、ちょっと日焼けして目鼻立ちのハッキリした東洋人といった感じである。
(そう言えばベンガル人って、人種的な特徴の無い民族って聞いたことがあるな。)
混血民族なので、外見が東洋系に見える者から欧米系に見える者までいるらしい。
(それにしても、アディを綺麗にしといて良かった。)
もし、汚いままの野宿生活者姿でアディを事務所に連れてきていたなら、恵子は一段と荒れ狂っていただろう。
そのアディが、恵子の剣幕に驚いて飛び起き、何が起きたのかもわからず、寝起きで呆けた顔のままオロオロしながら、小さく行儀良く座っていた。
「い、いやぁ、話せばね、長くなるんだけどねぇ。」
夢から覚め、現実に戻れた嬉しさは既に去り、尾藤の目の前には厳しさを取り戻した現実が手ぐすね引いて待ち構えていた。
アディを一旦外で待たせ、尾藤は社長室兼応接室で恵子と小一時間ほど話をした。
全ての事情を聞き終えた恵子は、
「良っくわかりました。」
と、極めて冷静に答えた。
昨夜の四人の暴漢の話や、サークルの話など、それなりに怖い話をしたにも関わらず、狼狽えたり不安を訴えたりするような素振りは全く見せなかった。内心は知る由も無いが表面上は普段通りのまま、表情には些細な動揺も見られない。
本来ならば、今回のような事件性の高い仕事の場合、事務方のアルバイトである恵子に全ての事情を話す必要は無いのだが、この狭い事務所の中で勘の良い彼女に隠し事をするのは、ほぼ不可能だった。
それに、早めに現状を把握して貰っておけば恵子の有能さは役に立つ。
バックアップにかけては、彼女ほど有能な助手はいない。
それに、今後の調査活動の推移次第では、再び昨夜のような事態に遭遇する可能性もあり、その際には万が一にも事務所に危険が及ぶ可能性が無いわけではない。その場合、女性一人で事務所に留守番をさせるのは問題外であるから、恵子に出勤を控えて貰わなければならない事態が生じるかもしれない。
だから、今のうちに事情を知らせて心構えをしてもらう必要があった。
「それで、今後はどのように段取りするつもりなんですか? 今までにはあまり例のない仕事ですから、こちらのバックアップ態勢も良く考えておく必要がありますね。」
恵子は通常業務に携わる態度と全く変わらない冷静な質問を返してくる。
(なんて、気丈な奴。)
これを頼もしく思わないわけではない。
生意気に感じることも多く、時には暴力的で、女としての可愛げは非常に乏しく、常に毅然としていて、その冷静な態度や高圧的な性格には恐ろしさを感じることも多い恵子だが、尾藤は総合的には大へん気に入っている。
今回の仕事は、木村も言っていたように民間調査会社が扱う仕事の限度を超えているかもしれないので、もしかしたら恵子は調査続行に反対するかもしれないと思っていた。だが、そんな素振りは微塵も見せないまま、通常の調査活動と何ら変わりないバックアップをしてくれると言う。
(ホッとした。)
恵子に反対されないのならば調査続行には何の迷いも無くなる。
後は、彼女の言うように今後を如何に段取るかである。
まずはサークルを具体的な存在として捉えて、そこに接近する方法を探らなければならない。
そのための情報収集をする当ては既に考えていたのだが、
「ああ、あのセクハラじじい。」
恵子は尾藤の情報源を思い浮かべながら、嫌悪感を丸出しにした渋面で忌々しそうに言った。
「そ、そうね、そのセクハラじじい。」
恵子が何を考えて渋面しているのか、尾藤は承知している。
そこには迂闊に触れてはいけない事情があった。
「それはともかく、」
と、話を反らす。
「今回は、ヤバそうになったら撤退命令を出すから、そしたら自宅待機ね。」
「わかってますよ。事務所のサーバーに自宅のPCを接続できますから、仕事は何処でもできますしね。だから、欠勤扱いにはしないでくださいよ。」
恵子も、そこは納得済みという顔で答えた。
「あとは、留守番してる時もドアはキチンと戸締りしておくこととか・・・ 」
「それを私に言いますか? 鍵開けたまま、セコムも解除して爆睡してた人が? 」
恵子が呆れ顔で言った。
(ヤバい、説教の続きが来るぞ! )
寝た子を起こしそうになってしまった。
「万が一の時のために護身対策も・・・ 」
「ああ、その点はご心配なく。」
これも、言うまでも無いことだった。
剣道だけではなく、合気道の有段者でもある恵子には、滅多に敵う男はいない。
だからといって自分の力を過信しては危ないので、
「危険に対する時の基本的な姿勢としては・・・ 」
「もちろん、逃げます。」
模範的な解答だった。
他にも何か大人として、雇用主として言っておくべきことは無いかと考えたが、
(もう言うこと無くなっちゃったよ。)
「それじゃ、私から質問。」
恵子が手を上げる。
「ど、どうぞ。」
「尾藤さんが襲われたのが出角って教師の差し金だとしたら、最初に捕まえとかなきゃダメなんじゃないですか? 」
またまた説教を食らうのではないかとビクビクしていたが、質問が調査に関することでホッとした。
「あ、出角なら、たぶん、もう逃げてるよ。」
校舎裏の証拠を消したのは間違いなく出角だと思うし、昨夜の襲撃も出角の差し金だと思う。おそらく、里田かおるを事故死に見せかけて殺したのも出角だろう。尾藤の襲撃に失敗したことにより、その後に警察が絡んできたのは知っているだろうから、既に逃亡してしまっているに違いない。
それにしても、サークルと自分の身を守るためとはいえ、出角は随分と雑で荒っぽい手段を取ったものだ。犯罪者としては呆れるほどの素人である。一連の行動の結果、自分が犯人だと白状してしまったようなものだった。
実のところ、尾藤は出角の件を警察には殆ど話しておらず、疑いを示唆する程度に留めていた。出角の件を詳しく話せば、校舎の不法侵入の件も話さねばならなくなるわけで、それが調査のためであっても違法行為を働いたという事実がバレたら、この仕事は間違いなく取りあげられてしまう。
そういう事情を知るはずがないから、出角は慌てて逃げ出したに決まっている。
「あいつはバカだねぇ、急いで逃げ出す必要なんてないんだけどねぇ。」
尾藤は苦笑いした。
いや、悔し笑いと言うべきか。
残念ながら、これで貴重な手掛かりを一つ失ってしまっただろう。
「それじゃ、もう一つ。」
「はい、どうぞ。」
「アディ君のバイト代はどうするんですか? 時給ですか? 日給ですか? それとも歩合制ですか? 取り敢えず、昨日の分は交通費とかにしときましょうか? 」
大事なことだったが忘れていた。
「えっと、昨日のは、交通費とか、接待費とか、そんな感じで処理してくれないかな。んで、今後の分は、えっと日給かな。ちょっと考えるわ・・・ 」
「できるだけ早くお願いします。それと、最後に一つ。」
恵子は、少し首を傾げて言葉を選んでいるようだったが、
「セクハラじじいに伝言しといて下さい。今度、お尻触ったら殺すって。」
[一一]
「ここって電気屋さんなの? 」
アディは、古ぼけたモルタル二階建てのビルに掛った「新宿電脳中心」の突き出し看板を見上げて言った。
「電気屋じゃないよ。まあ表向き中古パソコンのリサイクルショップってことだ。」
アルミの引き違い戸を開けて店内に入ると、そこは中古パソコンや各種周辺機器が乗ったスチールラックの組み合わせによってできた迷路の空間だった。
「すごーい! 」
アディが口笛を吹いた。
だが、この店、確かに商品の数は多いのだが、ちょっとパソコンに詳しい人が見れば、スチールラックに並んだ商品の殆どが無価値なことに気付くだろう。マニアックな価値を持つ機種は一つも置いて無いし、中途半端に古過ぎたり、規格外の商品だったりして、まず買い手が付くことは無いと思われるゴミばかりだった。
実は、この店のオーナーに商売をするつもりは全くない。
「これはね、いざという時の盾なのよ。人避け、鉄砲玉避けね。」
と、いうことらしい。
いざという時が来るような仕事が本業なのである。
そのオーナーの姿は店頭に無いが、尾藤は特に声を掛けるでもなく、黙って一番奥のレジ前に進んだ。
取り敢えず、アディも黙って後に続く。
「尾藤さん。お久しぶりね。」
いきなり声が聞こえた。
店内の何処かに備え付けられているスピーカーから聞こえる、機械的に処理された音声だった。
声の主が、「新宿電脳中心」のオーナーであるらしい。
「こんにちわ、久しぶり。」
尾藤が答える。
何処かにマイクも仕込まれているらしい。
「今日は見慣れない人連れてるのね。」
「新しく雇った助手だよ。アディって言うんだ。」
尾藤がアディの背中を叩いて挨拶しろと言うので、アディは何処に向かって話せば良いのかと戸惑いながら、
「アディです。よろしくお願いします。」
と、言った。
「はい、こちらこそ、よろしくお願いします。」
姿は見えず、名乗りもしないが、オーナーの口調は丁寧である。
「ところで、二人だけかな? 」
オーナーが、少し怪訝そうな調子で言った。
「見てのとおり、二人だけだよ。」
尾藤は答えたが、オーナーは尚も念を押すように、
「ホントに? 」
まるで怯えたように言う。
「ホントだってば。」
尾藤は面倒臭そうに頭を掻いた。
「良かったぁ。んじゃ、奥の鍵開けるから入ってきて。」
スピーカー越しに納得した声が聴こえると、直ぐに近くでカチッという電子ロックの開く音が鳴った。
「行こうか。」
尾藤はアディに声を掛け、レジ裏にあるドアを開けて奥に入った。
ドアの店舗側は木製だが、裏側は鋼製である。
「表側を偽装した防弾扉だよ。」
不思議そうにドアを見回しているアディに尾藤は教えてやった。
防弾扉が閉じ、再び施錠される音を背中で聞きながら、二人は真っ直ぐに目の前の短い廊下を進み、突き当りの階段を降りた。階段を降り切ったところで二枚目の防弾扉を開けると、そこにはまるでデジタル放送メディアのスタジオのような広い部屋があった。
正面の壁一面を覆うようにして並んだ大小一〇数台のディスプレイモニター。真っ黒い本体に多数のケーブルが接続され、外観が触手を伸ばした生き物のように見える巨大な改造メインフレーム。部屋の両側に設置されたスチールラックを埋め尽くす複数台のデスクトップPCと各種入力デバイス、大量のハードディスク、周辺機器。
これらの機材に囲まれ、忙しそうにキーボードを叩いている男は振り返りもせず、
「尾藤さん、元気そうね。」
と、言った。
「Kさんも元気そうで何より。」
尾藤は笑顔で返したが、それは男には見えていない。
Kと呼ばれた男は東洋人だが、言葉のイントネーションから日本人ではないことが直ぐに分かった。おそらくは中国か台湾、又はモンゴル辺りの東アジア圏出身者と思われる。年齢は五〇歳前後、銀縁で細めの老眼鏡、オールバックにした白髪混じりの長髪を後頭部で縛り、やはり白髪の混じった口髭を生やしている。
尾藤はKと呼んでいるが、それが本名であるはずはない。
「ちょっと待っててね、直ぐに終わらせるから。」
尾藤たちに声を掛けながらも、Kの手は休みなくキーボードを打ち続け、幾つかのモニターに表示されたプログラム言語が引っ切り無しに反応している。
「忙しそうだね。今は何の仕事やってるの? 」
「某国の人民軍のネットワークに小さな穴を開けるのよ。」
Kという男が単なるエンジニアでないことは、サラリと言ってのけた答えの危なさでわかった。
仕事場に「人避けと弾避け」が必要なわけである。
しかし、尾藤はKの答えを聞いても顔色一つ変えず、
「ふーん、大変なんだぁ。」
と言って、アディと一緒に部屋の隅に置かれたベンチに座って待つことにした。
それから数分間、二人はキーボードを叩く音を聞きながらKに気を使って黙って大人しく座っていたのだが、いつの間にかアディがそわそわし始めていた。
「トイレか? 」
「そうじゃないんだけど・・・ 」
どうやら長時間の無言や手持ち無沙汰に耐えていられない性格らしい。
最初は部屋の中をキョロキョロと物珍し気に見回しているだけだったが、どうしても話がしたくなったようだ。
「尾藤さん、聞いても良い? 」
アディが小声で言った。
「何? どした? 」
尾藤も釣られて小声で答える。
「あのKって人、何の仕事してるの? 」
「ハッカーだよ。」
「ふーん、それって犯罪だよね? 」
「あいつのメインクライアントは桜田門と市ヶ谷だからな、国家権力公認の犯罪者。」
「そうなの? 凄い人なんだね。」
「そう、凄い人だよ。」
「でもさ、吉良さんのお尻触ったんだよね? 」
「え? 」
会話がプツリと途切れてしまった。
尾藤の額に薄っすらと汗が浮かんできた。
「お前、聞いてたの? 」
恵子と話していた時、アディは社長室兼応接室の外で待たせていたはずなのに、
「だって、吉良さんの声大きいから聴こえちゃったよ。」
「そか、聞こえたんだ・・・」
(あいつの声、でかいんだよなぁ。)
事務所と社長兼応接室の間の仕切りなど、薄っぺらなパーティーション一枚だから、普通に話していたって聴こえるかもしれない。
(でも、今それを言うなよ! Kに聞こえたらどうすんだよ! )
もし聞こえてしまったら、これから仕事を頼もうと思ってる相手の辛い過去を抉ってしまうことになるのである。
「その話は無し! 」
「え? どして? 」
「とにかく、無し! 」
「だって、あの吉良さんのお尻触ったなんて凄いことだよぉ。」
アディに悪気は全くない。
今朝の初対面で、恵子の迫力に思い切りビビらせられてしまったアディは、そのお尻を触ったというKの勇気に対し素直に感心しているだけなのだが・・・
(ちょっと、違うんだよなぁ。)
恵子のお尻を触ったということ、それだけで話が終わると思っているアディは未だ認識が甘い。
当然、その続きがある。
「もう、その話はするんじゃない! 後でキチンと教えてやるからって、あっ! 」
仕事が一段落したKが、直ぐそばに立って二人の話を聞いていた。
「いったい・・・何の話してるのかな? 」
声が震えていた。
(聴こえてたみたいね。)
実に不愉快そうで、そして泣き出しそうな顔、握った拳がブルブルと震えている。
「おっ、お、お疲れ様です。」
尾藤はKを見上げ、引き攣った愛想笑いをした。
「あの女の話をしてたのね。二人で僕をバカにしてたのね。」
「いやいやいやいや、そんなわけ無いじゃない! 恵子の話なんてしてないよねぇ? 」
慌てた尾藤が、アディに向かって同意を求めたのだが、
「え、何で? 」
状況が呑み込めないアディは首を傾げるだけで、ポカンとしてる。
(はぁーっ、面倒臭いことになっちゃった。)
この後、尾藤はKの傾いた機嫌を直すために無駄な時間を費やさなければならなくなってしまった。
「尾藤さん! あの凶暴な女、早くクビにしたほうが良いよ! 」
散々愚痴と苦情を吐き出したのに、まだKの興奮は収まってくれない。
「そんなこと言わないでよ。うちの貴重な戦力なんだからさぁ。」
もう、Kを宥めるための言葉は使い果たしてしまった。
「あの女をクビにしないなら、尾藤さんとの付き合いも考えなきゃなんないよの! 」
「そんなこと言わないでよ。うちら長い付き合いじゃん。」
「付き合いの長さなんて関係ないよ、あの女と僕とどっちが大切なのか、ハッキリしてもらわなきゃダメなのよ! 」
「そんなこと言わないでよ。俺の気持ち分かるでしょう? 」
「何言ってんの! 夫婦じゃあるまいし言ってくれなきゃ分かるはず無いのよっ! 」
「そんなこと言わないでよ。寂しいじゃん。」
「あの女のおかげで、暫くの間は手も足も腰も痛くて仕事にならなかったのよ! 投げられて、絞められて、死にそうだったのよ! 訴えようかとも思ったぐらいよ! 」
「そんなこと言わないでよ。生きてるから良いじゃん。」
尾藤の受け答えが、明らかにパターン化していた。
もはやKが何を言っていても頭には入って来ず、反射と惰性で宥めているだけの状態になってしまっていた。
そんな尾藤の様子に気付いたKが、
「なんか、言葉に心が籠って無いのね! 僕の気持ち分かってくれてないのね! 」
いい歳をして拗ねたような口を利いた。
(んなこと、分かるわけ無いじゃん! )
もう、すっかり面倒臭くなってしまっていた尾藤は、
「そんなこと言わないでよ。だって、お尻触る方が悪いじゃないって、あっ! 」
うっかり失言してしまった。
再び、Kが握った拳をブルブルと震わせ始めた。
(ヤバっ! )
Kの怒りが振り出しに戻ってしまった。
「尾藤さん! 僕、挨拶のつもりで、ちょっとお尻撫でただけよ! それなのに、あの女に半殺しにされたよ! 」
Kのご機嫌直しは、ここから延長戦に入った。
「そろそろ、仕事の話しよか。」
「そだね。」
長く不毛な時間が終わった。
尾藤もKも無駄に疲労してしまって、アディはすっかり退屈し、居眠りを始めていた。
「メールの件でしょ? ちょっと、待ててね。」
KはノートPCを取りに行くために、一旦部屋を出て行った。
メールとは、尾藤が昨夜事務所に戻ってから寝る前に送っておいたものである。サークルに関する情報を得るため、日頃仕事の度に使っている情報屋数人に渡りを付けておいたのだ。
Kは、その中の一人。
「尾藤さん、ごめんね。」
この頃には、自分が不毛な時間の原因を作ってしまったことを深く反省していたアディだった。
「もう良いけどさ、これからは迂闊なこと言うなよ。」
「うん、もう言わない。」
すまなそうに頭を下げる。
「それにしても、吉良さんて、ホントに怖い人なのね。」
「まあね。」
だから、絶対に怒らせるようなことをしないようにと注意した。
頻繁に怒らせている尾藤が言えるようなセリフではないのだが・・・
「あのKって人も、ホントは凄い人なんでしょ? 」
「詳しい仕事の中身は聞かないから詳しくはわからないけど、只者じゃないってことは知ってるよ。ハッカーとしては超一流だし、裏社会にも顔が利くし、彼ほどの多方面に渡る情報通は他にいないな。」
「へぇ、そうなんだ。そんな人がねぇ。」
感心しながらも、アディは笑いを堪えている様子だった。
そんな凄い男が、恵子のお尻を触って半殺しにされたというのが面白いらしい。
「おい、その話は無しだって! 」
尾藤が、アディを肘で小突いた時、
「お待たせっ。」
KがノートPCを抱えて戻ってきた。
(危ない危ない、またヤバい会話になりかけてたよ。)
尾藤もアディも不毛な会話は懲り懲りなので、今度は二人同時に素知らぬ顔をしてKを迎えた。
「凄く面白そうなメールだったから、ウィルス散布なんてクソ面白くもない国防省の仕事は中断して直ぐに調べたのよ。」
非常に危なっかしい発言を事も無げに挟みながらKは自分の膝の上でノートPCを開くと、早速キーボードを叩き、
「まずは、これね。」
ディスプレイを裏返しにして尾藤たちに向けた。
「どれどれ。」
尾藤が覗き込む。
「ヨガ教室? 」
ヨガ教室の会員募集ホームページである。
「一見はヨガ教室のページよ。んじゃ、まずは有料会員専用ページに入ってみましょ。」
Kはディスプレイを再び自分に向けるとキーボードを叩いた。
この男にとってはアカウントやパスワードなど無いも同然らしく、あっさりとログインしてしまった。
「一応見といて。これが有料会員ページね。」
ヨガ教室の時間割、会員専用サービスメニュー、予約申し込みフォームなどがある。
「一応見たけど? 」
何故ヨガ教室のホームページなど見せられているのか? という尾藤の不思議そうな顔が、これから何らかの種明かしをして見せようとしているKには嬉しかったらしい。
ニヤニヤしながら、
「もう一度、TOPページに戻って、ログインし直してみるよ。見ててよ尾藤さん、ここからが本番なのよ。」
と、言って再度ログイン作業を行った。
そして、指でリズムを取りながら、
「タッ、ダーッ! 」
と、掛け声付きでディスプレイを裏返した。
すると、
「おおっ! 」
現れた画面を見て尾藤は驚いた。
何をどうしたのか分からないが、Kがログイン作業をやり直したら、今し方見た会員ページとは全く異なるページが開いたのだ。しかも、ページのヘッダーには例のタンポポマークが表示されているではないか。
「これっ、これだよ! さっすがK、仕事早ーい! 」
Kは自慢げに鼻を鳴らした。
「ま、僕の手に掛ったらこんなもんよ。このページ、アカウントとパスワードに細工してあってね、特定のコード打ったら全く別のページに飛ぶようになってるの。これは、いわゆる裏サイトね。セキュリティが凄く厳重だから素人には絶対に見つけられないわ。」
「すげぇ、どうやって、こんなページ見つけたの? 」
Kは人差し指を左右に振って、
「チッチッチッ、そこはダメよ、企業秘密を聞いちゃ。」
と、窘めるように言った。
「ああ、そっか。失礼。」
尾藤は直ぐに引き下がった。
Kもプロである以上、自分の情報源や情報網などは聞いても答えるはずがない。
「最初のヒントは公安のデータベースから頂いたんだけど、警察は何もわかってないみたいね。薄っぺらな中身のファイルがあっただけ。ま、それでも取っ掛かりぐらいにはなったけどねぇ。んで、そこから先はナイショなのよ。」
口にチャックをして見せた。
入手経路がどうであれ、結果さえいただければ尾藤に文句は無い。
「それじゃ、このヨガ教室が地下サークルの入り口ってわけだな。」
意外に素早い調査の進展に思わず唸ってしまった。
「ところが、そうじゃないのよねぇ。」
Kが残念そうに首を振った。
「このページね、ヨガ教室のホームページに寄生しているだけだと思うのよ。たぶん、ヨガ教室の人は、自分とこのホームページから、こんなページにログインできることなんて知らないんじゃないかしら。」
「え? それじゃ、このヨガ教室とサークルは? 」
「何の関係も無いんじゃないかしら? よくできたカムフラージュね。」
「そうなのかぁ? 」
尾藤は、少しだけガッカリした。
だが、直ぐに気を取り直した。
「でも、このサイトを見つけてくれただけでも有難い。凄い進展だよ。是非アクセス方法を教えてよ。」
ところがKは、
「それはダメ! 止しといた方が良いわ。」
と、強い口調で断った。
「向こうには、こんな複雑なアクセスプログラム作れるプロがいるの。尾藤さんみたいな素人が迂闊にアクセスしたら、あっという間に逆探知よ。だから、サイトのデータは全部ダウンロードしてオフラインで見れるようにしといてあげたから、それで我慢して。」
「わかった、納得。」
プロのアドバイスには素直に従った方が良い。
「このサイトの監視は、僕が暇見てやっといてあげるから安心して。他に新しい情報に当たったら連絡してあげるよ。」
Kは非常に協力的で、妙にウキウキしていたが、
「地下サークルの調査なんてサスペンスドラマみたいで面白いじゃない。最近、肩が凝る仕事ばっかりで嫌になってたのよねぇ。久しぶりに面白い仕事持って来てくれてありがとうねぇ、尾藤さん。」
野次馬根性丸出しで言った。
「一応、注意しとくけどさ。俺が命を狙われたぐらいで、相手は結構ヤバいサークルだから気を付けてもらいたいんだよね。メールにも書いといたけど、Kが探りに来ていることを嗅ぎ付けたら何をしてくるか分からないよ。」
尾藤の警告をKは一笑に付した。
「僕が相手にバレるようなドジするわけないね。それに知ってるでしょ、この家の周りは、いつだって警察や国防省のボディガード付き。軍隊でも連れて来なけりゃ、私には指一本触れることはできないよ。」
警察も国防省もKの非公式なクライアントである。
「ああ、そう言えばそうだった。」
Kの扱っている案件は国家レベルの重要な機密情報が多数あると思われるので、その身柄は常にクライアントの監視下に置かれている。日常生活の一部始終、店舗に出入りする人間、家の内部での会話など、様々な方法で厳重にチェックされている。だから尾藤はもちろん、今日初めて訪れたアディも、既にチェック対象になっているに違いない。
「いつか、そのボディーガードが、僕の命を狙いに来るかもしれないけどねぇ。」
Kは笑いながら言った。
十分に有り得そうな話なので本来なら笑いごとでは済まないのだが、まるで面白い冗談を言っているようであった。
「一種のマニア、変態オヤジ、重度のオタク、ついでに前科持ち。でも豪傑であることは間違いない。」
尾藤は、そうKのことを評した。
ハッカーや情報屋としては超が付くほど有能であり、国家権力にも一目置かれているプロ中のプロである。その気になれば、いずれかの組織の中枢で出世や金儲けも自由自在なはずなのに、まるで趣味人のように個人での活動に拘り続けている。
その結果、いつかはクライアントに命を狙われてしまうかもしれないという危険を感じながらも、それを笑い飛ばして見せる男だった。
「何となく、わかったよ。」
アディは頷いた。
「でも、前科があるの? ハッキングで? 」
「ハッキングでは一度も捕まったことは無いって本人が言ってた。捕まったのは痴漢行為と盗撮だよ。」
アディが唖然としていた。
「ホントに変態なのね? 」
「だから言ったろ。そういう奴だから恵子の尻にも手を掛けたのさ。」
そして、半殺しの目に遭わされたのだ。
その時、普段はKの周辺を固めているボディーガードたちも、さすがに痴漢行為に対する報復に関しては見て見ぬふりをし、助けてくれなかったというのが可笑しい。
「ところで、Kって何かのイニシャル? 本名はナイショなの? 」
「言ってなかったっけ。あいつ、王秀英って名前だから、若い頃King Excellentとか、King Exなんて、恥ずかしいハンドルネーム使ってたんだわ。今じゃ悲しい過去になっちゃってるみたいだけど、呼び名にイニシャルだけ残っちゃってんだ。」
「それだけなの? 」
「それだけだよ。スパイ映画とかに出てくるコードネームか何かだと思ったか? 」
「うん。」
尾藤は笑った。
「さてと、Kに頂いたデータに早速目を通さなきゃならないな。そのついでに何処かで昼飯でも食おうか。」
時刻は一三時過ぎ。
予定では午前中に済ませてしまうはずだったKへの用件に随分手間取ってしまった。
新宿駅東口近くのファミリーレストランで遅い昼食を取りながら、尾藤はアディと二人でKがコピーしてくれたWEBサイトのデータを読み込んでいた。
「数字とアルファベットばっかりで、具体的な文章とか単語は全然無いよな。」
今、尾藤のタブレット端末に表示されているのは、白い背景に黒いフォントが規則正しく並んだテキストベースのホームページ。
「もっと、デザイン処理とかすれば良いのに。」
ヘッダーに例のタンポポマークの意匠がしてある以外には、色彩の一つも無く、フォントの変化も無く、ひたすら下へ向かってのスクロールが続く、単調過ぎる画面だった。
「この数字って日付だよね。」
アディが言う。
「そうだな。例えばこのJ03は一月三日、F01は二月一日だろう。それじゃ、其々の後に続く数字は時刻だな。J03の後に0408ってことは、一月三日の四時八分。よしっ! 」
「尾藤さん、やったね! 」
二人で喜びの顔を見合わせたのだが、
「でも、それが何の日付なのか全く・・・ 」
「・・・分からないのが問題だよね。」
二人同時に嘆息した。
先程から二人共、溜息を吐いては飯を食い、飯を食っては溜息を吐いている。
解読作業は、あまり順調とは言えなかった。
「ところでアディ、今日は仕事無いのか? 」
「うん、今日は何処からも連絡無いから平気。」
日雇い仕事で食い繋ぐのは難しい。仕事の有る無しにバラつきがあって、到底安定した暮らしなどできるはずがない。仕事の無い日が続けば餓えてしまうので、アディは身の回りの物を売ったり、カラスを捕まえたりして何とか凌いでいたという。
「それなら、夕方まで付き合って貰っても良いか? ちょっとした、仕事の当てもあるから紹介するよ。」
「ホントに? 嬉しい! 全然OK! 」
アディは大きな瞳をキラキラさせながら喜んだ。
「その前に、こいつだよ。」
「了解。」
再び、二人でタブレット端末に向かった。
ところで、今まで、尾藤は一人で仕事をしてきた。
恵子は、事務や雑務担当のアルバイトとして雇っているだけなので、調査業務は一人で行うのが当り前だった。一緒に考えてくれたり、手足になる助手が欲しいと思ってはいたが、その機会が無いまま、ずっと仕事を続けてきた。アディが頼りになる存在なのかどうかは今のところ全く未知数だが、腕は立つし、パソコンの知識もあるので臨時助手としては非常に有難い。
それに、一人でタブレット端末に向かって暗く溜息を吐いているよりは、二人で吐いている方が気持ちが深刻になり過ぎずに済むので良い。
「それにしても日付ばかり、まるで計画表だね。古い日付は一年前まであるけど、先の日付は来月の二三日で終わってるよ。来年以降の計画は無いのかな? 」
「この先で一番近い日付はN24 0237、つまり一一月二四日の二時三七分。ひと月前だと一〇月二五日の一〇時三〇分。その前は九月二五日の一七時四一分。微妙にプラスマイナスがあるけど、ほぼ一か月間隔だな。」
尾藤は一か月間隔ということで、思い当たることがあった。
「ちょっと待てよ、もしかしたら! 」
バックの中から折り畳んだ都内の道路地図を取り出した。
昨日、女子学生失踪者の学校を書き込んでおいた地図である。
「これに失踪日も書いといたんだよ。」
尾藤は両方の日付が一致する可能性があると考えたのだが、
「・・・違った。」
双方の日付は全く違っており、一致する日は一つも無い。
「そう言えば、司廉子の失踪日からして今月の八日なんだよなぁ。さすがに短絡的な推理だったわ。」
せっかく取り出した道路地図をテーブルの上に放り出した。
「日付だけじゃなぁ、地名とか住所とか、そんな記載が欲しかった。」
その後も食後のコーヒーを啜りながら、もう一度二人で画面の隅々まで見渡したのだが新たな発見は無かった。
「このサークルって、どうして女の子を定期的に浚っているんだろう? 」
「アディが一番最初に示唆してくれたことがホントなら、殺人嗜好者のサークルかもしれないだろ。ってことは、やっぱり殺人鑑賞会みたいな催しの中で殺すために浚っているんだろうな。」
「やっぱり、この日付が催しが開かれる日なんだよね? 」
並んだ数字とアルファベットが日付と時間であることが分かった時点で、その可能性は逸早く過っていた。
「どう考えても、その線が正しそうだな。」
「でも不思議だよね、こんなに定期的に一人づつ浚ってくなんて。だいたい一カ月おきでしょ、もし警察が本気出して警戒したら危ないじゃない。催しの日も決まってるから場所を特定されたら、お終いだよ。」
「一人づつ定期的に浚う。二人三人を纏めて浚ったりはしていないし、短期間で連続してはいない。そして日付は重要。うーん、地図に失踪日を並べてみた時以上に、何か強い意思みたいなものを感じるよなぁ。」
尾藤は、もう一度タブレット端末の画面と地図に書き込んだ日付に目を通した。
(もう他に気付くことは無いのか? 司廉子が失踪したのは一一月八日、その前に行方不明になった女子学生は一〇月一〇日、その前は九月一〇日、八月一二日と続く。そこにWEBサイトの日付、一一月二四日、一〇月二五日、九月二五日と差し込んでみると? )
尾藤は普段は持ち歩いているだけで殆ど使うことの無い紙の手帳を取り出して、年間カレンダーのページを開き日付に丸印を付けはじめた。
失踪日を赤、WEBサイトに記載されている日付を青のボールペンで書き込む。
すると、
「間隔は一五日か一五日前後。大きく外れた日付は無い。」
「一五日って間隔に何かあるのかな? 」
「一緒に考えよう。何か思いついたら言ってくれ。」
日付を睨んでいたら何か見えてきそうな気がするのだが、なかなかハッキリとしたイメージに結びついてくれない。
「尾藤さん? 」
「何か浮かんだのか? 」
「ちょっと、インターネットで調べて欲しいんだ、その日付のこと。その日はどんな日なのかって知りたいんだけど。」
尾藤はタブレット端末をインターネットに接続し、
「ちょっと待ってろ。」
と、検索エンジンに日付を入力した。
「何が見たい? ニュースか? 」
「そうじゃなくて、ほら日本のカレンダーの日付の下に書いてるやつとか。」
アディは何を見つけようとしているのか?
「下に書いてあるやつって、大安とか仏滅とかいうやつ、暦注のことか? 」
それなら、適当なカレンダーのサイトを開けば直ぐにわかるが、
「暦注って何?」
バングラディシュ人であるアディが暦注など知っているはずがなかった。
では、暦注以外にカレンダーの下に書いてあるモノと言ったら、
「あ、もしかして月齢のことか? 」
月齢という言葉もアディには難しかったが、
「月の満ち欠けっていったら分かるかな? 」
すると、
「そう! それっ! それ見たい! 」
アディが手を打って言った。
「そうか、一五日間隔と言えば月齢か! 」
尾藤は直ぐに、其々の日付の月齢を調べた。
すると、
「失踪日は、全部満月だよ。」
「WEBサイトに記載された日付は、全部新月だ。」
外れは無い。
全日付が該当する。
「満月に誘拐、新月に殺すってことだよね。それって、まるで・・・ 」
アディが気味悪そうに何かを言い掛けた。
「オカルトだな。」
尾藤はハッキリと確信した。
昔から、満月は人の狂気を呼び覚ます魔力があると言われる。
そして、月の魔力が発動の時を待っているのが新月であるとされる。
月齢に合わせて女子を誘拐し、月齢に合わせて殺す催しを行う動機など、オカルト以外に何があるというのか?
「宗教はヤバいぞ! そこまでやるとなったら完全に狂信的なカルト教団だ。」
「まさか、女の子たちは生贄にされてるとか? 」
「危ない宗教の儀式だったとしたら・・・たぶん。」
その時、尾藤の頭にあるイメージが浮かんだ。
(まさか! )
それは昨夜見た夢のイメージだった。
ステージ上で繰り広げられた怪しい殺戮の儀式。
(そうだ、あれは確かに儀式だった。あんなことが行われているってのか? まさか、あれは只の夢のはず? )
しかし、女子学生を浚っているのがカルト教団だとしたら、夢と似たようなことが行われている可能性は高い。
(洒落にならん! )
それにしても、あれは今思い返してみても実にリアルな夢だったと思う。
どうして、あんな夢を見てしまったのだろうか?
(まさか、予知夢? )
そんな馬鹿なことがあるはずがないと思い直した。
理屈で考えてみれば夢を見た理由が分からないわけでもない。女子学生、誘拐、殺人、地下サークル、それに昨夜の襲撃と、今まで集まった断片的な情報を、尾藤は無意識のうちに脳内で構成していたに違いない。
それが夢と言う形で具体的にビジュアル化しただけなのだ。
(一昨日の朝の怪人まで登場してたしな。)
しかし、あの夢のイメージは決して見当外れではないだろう。
「次の儀式が二四日の二時三七分に行われるとしたら、司廉子は未だ生きてるよな。」
「満月の日に浚った女の子を新月に殺すって推測が正しければ生きてるよ。」
今日は二一日。
この推測が正しければ、司廉子はあと三日間は生きている。
「グズグズしちゃいられない! 何とかして儀式の行われる場所を突き止めなきゃ! 」
尾藤はアディを連れて、追われるように店を飛び出した。
今、できることは限られている。
事務所を出掛けに念のためベイジョに電話してみたら、一番の手掛かりだった出角は無断欠勤しているという。
思ったとおり逃げられてしまっていたのだ。
(だが、できることは、もう一つある。)
司廉子の友人、里田かおるの両親に当たってみることだった。
今までは娘一人を調査対象と考えていたし、それが死んでしまったため、手掛かりは失われたものと思っていた。しかし、この一件がカルト宗教に絡んだ話で、里田かおるという娘が信者だったとしたなら、中学生の娘一人が信者であると考えるよりも、里田家全体が信者と考える方が自然だろう。
(里田かおるの両親も調査の対象になり得る! )
限られた時間の中で地下サークルの存在を明らかにし、司廉子を助け出し、依頼を全うするには気兼ねはいらない。
全ての可能性は見付け次第に即対応していかなければならない。
尾藤はタクシーを拾い、アディと一緒に練馬区の富士見台駅に向かった。
西武池袋線富士見台駅の近くに里田かおるの家がある。
[一二]
里田家は、西武池袋線富士見台駅から歩いて直ぐにある七階建てマンションの五階。
(娘をベイジョに通わせられる家庭が住むような所とも思えないが? )
尾藤は首を傾げた。
目の前にあるのは築五〇年以上は経っているであろう古くみすぼらしいマンションであり、決して裕福な家族が住んでいるようには見えない。
今時、オートロックが無く、入り口に管理人室があるというのも非常に珍しい。しかも尾藤たちが管理人室の窓口を叩き、里田家の娘の弔問に来たのだと嘘を伝えたら、簡単に部屋番号を教えてくれた。
管理人には名前も聞かれず、顔もろくに見られなかった。
(どう見たって弔問の服装じゃないのに、随分と不用心だな・・・ )
管理人は六〇代後半と思われる男性で、インターネットの囲碁番組に集中しており、仕事が疎かになっているようだ。
「しかし、マンションの住人の中で昨日不幸があったばかりだってのに、そんな雰囲気が無いな。」
弔問客の出入りは無さそうだったし、通夜の案内書きの一つも出ていない。
考えてみれば、里田かおるが亡くなったのは昨日のことだから、未だ遺体は警察か病院に安置されているのかもしれない。
それならば、両親は自宅ではなく遺体がある場所にいるはずだった。
(急いでやって来たものの、失敗だったかな? )
里田かおるは一人娘であり、家族構成は親子三人。
両親が病院ならば自宅は当然留守になる。
「取り敢えず、行くだけ行ってみようか。」
間もなくエレベーターのドアが開いたので、直ぐに乗り込んで五階のボタンを押した。
もし留守ならば、今度は警察か病院の場所を調べて、そこに押し掛ければ良いだけのことである。
「里田家は五〇三号室。」
五階でエレベーターを降り、通路の一番奥のドアである。
「留守だったら、また昨日の夜みたいに忍び込むの? 」
アディが気の進まなそうな顔で聞いてきた。
「そんなことしないよ。」
否定しつつ、実はその手も考えないでは無かった。
しかし、二日連続で違法行為を働くのは、さすがに気が引けたので今回は止めておくつもりだったが、
「まずは穏便に行こう。」
尾藤はドアの前に立ち、ネクタイとジャケットの弛みを直し、アディにも身嗜みの注意をしてからドアホンのボタンを押した。
ドアの向こうで、軽快な呼び出しメロディが聴こえた。
「・・・ 」
一〇秒ほど待ってみたのだが、返事は無い。
もう一度押してみたが、やはり返事は無い。
「留守だね、それじゃ他に行くか。」
立ち去ろうとする尾藤を、アディが止めた。
「中に人、いるよ。」
「え? 」
「二人か三人いる。音がするもの。」
尾藤には聞こえなかった物音を、アディは聞きつけたという。
「空耳じゃないのか? 」
「そんなことない、聞こえたよ。絶対にいる。」
アディは自分の聴力に自信があるようだ。
となると、どうしたものか?
両親が娘を失った悲しみにくれ、居留守を使っているのだろうか?
「たぶん両親じゃないよ。靴を履いた男の足音がするもの。」
「そんなことまで分かるのか? 」
家の中を土足で歩き回っているなら泥棒、もしくは!
「これって、もしかしてビンゴ? 」
二人は顔を見合わせた。
今、里田家には調査活動を一足飛びに解決に導くような、大チャンスが潜んでいるかもしれない。
「捕まえよう! 」
「でも、どうやって? 出て来るの待つ? 」
そんな呑気には待っていられない。
「んじゃ、やっぱ強引に押し入るのね? 」
アディが嫌そうな顔をして嘆息した。
罪悪感だけで嫌がっているのではない。
在日外国人としての事情がある。
在日外国人が日本国内で違法行為を犯した場合、国外退去、強制送還とされてしまう可能性があるので、それは困るというわけだ。
「んじゃ、俺一人で踏み込むからアディはここで待って、逃げる奴を捕まえる係な。」
「でも、一緒にいたら共犯だよ。」
「止めようとしたけど、止められなかったって言えよ。何なら殴られたって言っても良いぞ。木村なら、それで納得してくれるから大丈夫だって。」
尾藤は渋るアディを放ったまま、ドアの鍵を調べに掛った。
「古いマンションで良かったよ。ディスクシリンダータイプの鍵だ。」
鍵穴内部に平板が並んでいるタイプであり、これならば不正開錠は容易い。
「最後に確認するけど、間違いなく中に土足の男が二、三人いるんだよな? 」
尾藤は鍵穴にピッキング用のピンを差し込みながらアディに念を押した。
「うん、それは間違いないんだけどさ、尾藤さんって、いつもピッキング道具持ち歩いてるの? 」
アディは、あまり感心しないという顔をしている。
「ま、プロだからな。」
何のプロですか? と、アディが問い返す前に鍵は開いていた。
開錠の音も立てず、なかなかの腕前である。
「中の連中、気付いてると思うか? 」
「全然、大丈夫。」
その答えを聞くや否や、尾藤は一気にドアを開いて飛び込んでいった。
「ああ、行っちゃった。ここで待ってろって言われてもなぁ。」
アディは辛そうな顔をして頭を抱えた。
尾藤が強いのは知っているけれど、男三人相手となると危ないかもしれない。昨夜四人を相手に立ち回った際には、アディが助けに入らないと確実に殺されてしまっていたと思う。
ドアの外に置き去りにされたアディは腕を組んで暫く考えていたが、
「もう、しょーがないや! 」
覚悟を決めたらしい。
里田家のリビングにいたのは宅配便業者を装った男が三人。
他に人の気配は無い。
(アディの耳って凄いな。人数ピッタリだよ。)
この連中、もちろん偽物の宅配便業者に決まっている。
アディの言うように土足で歩き回っていたし、尾藤が飛び込んだ時には部屋中の戸棚や引き出しを引っ掻き回していた。
「大人しくしろっ! 警察だーっ! 」
尾藤は玄関から短い廊下を抜けてリビングに飛び込むなり、思い切りのハッタリをかましてやった。
普通ならば、この一言で相手は怯んだり戸惑ったりして隙を見せる。
しかし、全く効果が無い。
返ってきたのは、早口で捲し立てる意味不明な外国語だったのだ。
三人とも日本人ではない。
「日本語通じない? またまた外国人かよ! 昨日の奴らと一緒か! 」
クアークのマスターじゃないが、東京の国際都市化に反対したくなった。
この連中、いきなり刃物を取り出す攻撃的なところも昨日の連中と一緒である。
しかも、一人は刃物よりも厄介な得物を持っていた。
「高出力のスタンガンの相手は面倒だな・・・ 」
一撃食らったら、それまでである。
尾藤はジリジリと後退りし、リビングから廊下に出た。狭い廊下に立ち塞がって一度に相手をする人数を少なくするためであり、敵の逃げ道を断つためでもあった。
ヒョーッ!
奇妙な掛け声を発し、スタンガンを手にした男が真っ先に襲ってきた。右手にスタンガン、左手にナイフを持ち、狭い廊下を物ともせず自信満々で突っ込んでくる。
フン!
尾藤の前蹴りがスタンガンを持つ右手を跳ね上げた。
続いてナイフを持った左手を掴んで引き寄せながらの目突き、そして金的蹴り。
(あれ、こいつスタンガンなんて立派な得物持ってたのは弱かったからなのか? )
一人目は意外にあっさりと片付いてしまった。
しかし、ここで気を抜いてはならない。
念のため床に落ちたスタンガンを背後に蹴り飛ばし、倒れて蹲る男の腹に蹴りを叩き込み、動きを完全に止めておいた。
「まずは一人確保! 」
昨夜は三人取り逃がし一人は殺された。
その失敗を繰り返すわけにはいかない。
残りは二人。
(こいつらは、少々腕が立つかもしれないぞ。)
ナイフを持つ手の動きが慣れている。
(かつての不良少年か、こういう商売の連中なのかもしれない。)
多少は格闘センスもありそうだ。
(さてと・・・ )
尾藤は素早く周辺を目で探った。
(ちぇっ、使えそうなモノが無い! )
手近に武器になりそうなモノがあればと思ったのだが、敵は待ってくれなかった。
一人が無言でナイフを突き出してきた。
尾藤はかわしながら身を引いたが、間をおかずに次の一突きが繰り出されてきた。
これも間一髪でかわしたが、さらに次の突きが襲ってくる。
攻撃に移る隙が無く、尾藤は防戦一方になってしまっていた。
(格闘技経験者か! )
一度に相手する人数を少なくするためにと廊下にポジションを置いたのだが、同時に逃げられる範囲が狭くなり、却って相手には的が絞りやすくなってしまった。
突きを避けながら玄関まで後退させられた尾藤だったが、うっかり先ほど気絶させた男の身体に躓いてしまった。
(ヤバっ! )
転びそうになった尾藤の手が、咄嗟に重くて硬い何かを掴んだ。
「この野郎っ! 」
何を掴んだのか確認する暇も無く、尾藤は仰向けに転びながら手にしたモノを持ち上げて敵に力一杯叩きつけた。
確かな衝撃が手を伝ってくると同時に、
バリーン!
何かが割れる音が聴こえ、辺りに水飛沫が散った。
続いて目の前を見当違いの方向に向かってナイフが通り過ぎて行き、花吹雪が舞った。
(え、花吹雪? )
自分が何をしたのかも分からず、頭から水を被りながら急いで立ち上がった尾藤は、ナイフの男が気絶して足元に倒れているのを見た。
(ラッキー! )
尾藤は玄関の靴箱の上に置かれていた生け花用の火器を掴んで男の頭に叩きつけていたらしい。
分厚く重いセラミック製の花器の一撃は、石で殴るほどの威力があった。
男の頭蓋骨にヒビぐらい入れたかもしれない。
(ラストっ! )
最後の一人を相手にしようとしたが、
「あれ? いない? 」
直ぐにも襲い掛かってくるものと思って身構えたのに空かされてしまった。
「尾藤さん! こっち、こっち! 」
部屋の奥から声が聴こえたのでリビングに戻ってみると、アディが正面のベランダに立って尾藤を呼んでいた。
その足元には、三人目の男が倒れている。
「なんで、ベランダにいる? 」
「お隣の部屋の人に通してもらったんだよ。」
「通してもらったって、まさか無理矢理? 」
「違うって! 尾藤さんじゃないんだからさ。頼んだら、どーぞって言って通してくれたんだよ。んで、ベランダを伝って来てみたら、こいつが逃げようとしてたんで、やっちゃった。」
アディはボクシングのファイティングポーズを取って見せた。
その時、
キャーッ!
尾藤の背後、玄関先から甲高い悲鳴が聞こえた。
いつの間にか玄関のドアが開き、呆然とした顔の中年女性が立っている。
隣人が、物音を聞いて飛び出してきてしまったようだ。
「ど、どーしたんですか? これっ? 」
外国人の男二人が玄関と廊下に倒れ、水が零れた床に割れた花器や生花が散らばった惨状を見て、驚きの目を見開いていた。
「あ、すみません。これはですね・・・ 」
尾藤は反射的に謝って、適当な言い訳をしようと思ったのだが、
「ああ、先ほどは失礼しましたぁ! おかげさまで助かりましたぁ! 」
アディの妙に丁寧な挨拶が、尾藤の頭越しに投げ掛けられた。
すると、
「あら、あらあら、よろしいんですのよ。お力になれてうれしいわぁ。」
今し方悲鳴を上げていたとは思えないほど愛想の良い声で中年女性が答える。
その顔を良く見ると何故だか紅潮していた。ベランダからリビングを通って玄関先までやってきたアディが微笑みかけると、その顔はさらに赤みを増した。
「こちら、お隣の亜由美さんです。ベランダを通してもらいました。」
(・・・何故、下の名前? )
アディはまるで親しいガールフレンドを紹介するような調子だった。
(この短い時間で、どんな手を使ったのか? いや、想像したくない。)
「あ、それはどうも、お世話になりました。」
かなり間の抜けた挨拶をする尾藤の前で、爽やかな笑顔のアディと、はにかんだ笑みの亜由美さんが見つめ合っている。
(なんじゃ、これは? )
アディの思いがけない特技が見られたということか?
(そう言えば、昼めし食ったファミレスのウェイトレスの様子も変だったっけ。)
注文を聞きに来る時や、水を注ぎに来た時、妙にアディに対する愛想が良かったような気がする。
(こいつ、女誑しの才能持ってやがる。)
アディの美少年ぶりは認めるが、基本的には素朴で真面目な若者だと思っていた。
しかし、意外に危ない奴なのかもしれない。
(今後は注意しなきゃ。)
まあ、それは後のこととして、後始末をしなければならない。
お隣の亜由美さんに警察への連絡を頼むと、尾藤とアディは急いで家探しを始めた。
気を失って倒れている男たちを縛り上げるついでにボディチェックもした。
「こいつらが、なんで里田家に忍び込んでたのか、その理由を見付けるんだ。」
「了解。」
「警察が来る前に、こっちで手に入れられるモノは確保しておくぞ。」
「了解。」
「下手に指紋を残すんじゃないぞ。」
「了解。それよりも上手く説明して下さいね。僕、強制送還にはなりたくないよ。」
「心配するなって。それより、急げ! 」
警察が到着するまでには一〇分も掛らないと思うので、二人は作業を急いだ。
家の中には何も残っていなかったが、ベランダに倒れていた男のボディチェックを初めると直ぐに手応えがあった。
(こいつ、腹の中に何か隠しているな。)
男の上着を捲りあげると、腹にガムテープで巻きつけたビニールのゴミ袋があった。
中には紙束らしきモノが入っている。
尾藤は、これを力任せに剥ぎ取って素早く中身を取り出し、ざっと目を通す。
(チラシの束じゃないか? )
飲食店のチラシが一〇枚と、記号の並んだ表組みがプリントされたA4サイズの上質紙が一枚。
(取り敢えず確保だ。)
他の二名は何も持っていなかった。
昨夜の暴漢が持っていたようなカードを、今日の連中は持っていなかったが、
(昨夜落とし物した反省から、今日は持ち歩くのを避けたんだろうな。)
おそらく、そんなところだと思う。
それにしても、この地下サークルの連中は情け容赦の無い仕事をするかと思えば、素人のように強引で雑な仕事の仕方もする。
「尾藤さん! ちょっと来て! 」
アディに呼ばれて、隣室に行ってみると、
「これって、血だよ・・・ 」
閉じられたクローゼットの扉の下から赤黒い液体が漏れ出していた。
二人は顔を見合わせて頷き合った。
「開けてみよう。」
尾藤はクローゼットの扉をゆっくりと引いた。
「なんてこった! 」
そこには、身体を折り畳まれ無理矢理に狭いクローゼットに押し込まれた男女の死体があった。
尾藤はガックリと肩を落とし、吐き捨てるように言った。
「たぶん、里田かおるの両親だ。」
地下サークルは警察や尾藤の捜査の手が及ばないようにするためには、娘を殺すだけでは不十分と考えて、両親までも殺してしまったのだろう。
もしくは、娘が殺されたことで、教団に不信を抱くか反抗的になる可能性を持った両親を速やかに排除したのかもしれない。
[一三]
杉並警察署の管轄は広い。
かつて、警視庁の有する警察署は東京都内一〇方面で合計一〇〇以上もあった。
だが、現在では半分以下に統合され、減らされてしまっている。
だから、其々の警察署の管轄区域は広がってしまった。
杉並警察署も同様である。
もともとは杉並区の一部を管轄していただけの杉並警察署は、今や杉並区と練馬区の全域、世田谷区、中野区、三鷹市、武蔵野市の一部までも管轄区域としていた。だから、富士見台にある里田家からの急報に際して、飛んできたのは杉並警察署員たちだった。
そして、公安協力者である尾藤からの連絡ということもあり、木村もやってきた。
「お前が関わってから、遂に二度目の人死にが出たか。」
一度目は昨夜の襲撃犯のうちの一人を指している。
木村は意識を取り戻した三人の男を一旦杉並署へ連行する段取りを確認した後、現場検証に当たる警察官の手際を眺めながら尾藤と立ち話をしていた。
「この里田って家は、夏頃に越してきたらしい。前は洗足に住んでたみたいだが、経営していた会社が倒産してな、借金抱えてボロマンションに移り住んだってわけだ。」
木村が杉並署を出る前に調べたらしい里田家の情報を尾藤に伝えた。
マンションを見た時、娘がベイジョに通っているにしては貧乏そうな住処だと思ったのだが、そういう事情なら納得できる。生活が困窮していたのならば、一家丸ごとカルト宗教に入信した動機も想像がつく。
「それにしてもカルト宗教とはねぇ、有りそうなことだが、事は一段と厄介だぞ。」
「信心があれば、人殺しも厭わないって感じかもね。」
今日、ここに至るまでの経緯の報告は外注業者の義務として一応しておいた。
「お前が殺されなかったのは幸いだったな。」
「まあね、アディのおかげだけど。ハッキリ言って一人ならヤバかったよ。」
尾藤は意図的にアディを持ち上げておいた。
何かしらの好印象を残しておけば、何かしらのお目こぼしに預かれる。
「ふん、アディねぇ。在日外国人の行動には世間の目が厳しいからな。ところで最後にもう一度確認しとくが、里田家のドアの鍵は最初から開いていたんだよな? 」
ここがポイントである。
「そうだよ。たぶん、あいつらが開けたんでしょ。」
さらりと嘘を吐いた。
「お前、ピッキング上手いよな? 」
「何を根拠に、そんなことを言うかな。」
「普通、ああいう連中はドア開けっ放しで仕事しないんだがな? 」
「そうだよね。うっかりしてたんじゃないの? 」
木村は尾藤の惚けた返答に明らかな疑いの目を向けていたが、
「まあ良い。別に不都合があるわけじゃなし。」
追及するのを止めた。
「そのアディ君には、今回は別に罪に問われるようなことは無いから安心しろって伝えとけ。お前も含めて緊急時に咄嗟の対応をしたってことで済むだろうさ。」
まずは、ホッとした。
「ところで、あの三人の取り調べ、俺も同席させてくれる? 」
木村は、馬鹿を言うなといった顔で、
「取り調べ室に一般人を入れるわけないだろう。」
と、言った。
「そりゃないよ! あいつら捕まえたのは誰なのさ! それに今は一般人じゃなく公安の協力者だよ! 関係者じゃないか! 」
ドン!
木村が拳でリビングの壁を殴り、
「やかましい! 甘ったれるんじゃない! そして、でかい声で公安とか言うな! 」
ドスの利いた声で怒鳴った。
「はい、すいません! 」
我儘を言って押し切ろうとしていた尾藤だったが、瞬時に迫力負けしてしまった。
「いいか、あの三人は警察に任せておけ。後で取り調べの映像ぐらいは見せてやるし、何か重大なことが分かったら知らせてやるから待ってろ。」
「それは困るよ! 」
司廉子を救うには、もう時間が無いと木村に言ったのだが、またまたドスを利かせて、
「如何なる捜査を行うにも守らなきゃならないルールや法律がある。だから、やって良いことと悪いことがある。俺が、お前に与えてやれるモノがあれば、与えるわけにはいかないモノもある。お互いが、それを了解してこそ協力関係が成立するんじゃないか? 」
などと、全く聞き入れてくれない。
(この堅物野郎め! )
せっかくの宝物も警察の檻の中に入れられてしまったのでは全く意味が無い。
(これまで押収されたらたいへん! )
尾藤はベランダで倒れた男から入手した紙束を、自分の上着の内ポケットに入れて隠しておいていた。
今のところ、これを警察には渡すつもりは無い。
(せっかく入手した手掛かりだ。これが頼みの綱だからな。)
司廉子は三日後に殺されてしまうかもしれないのだから、とても警察のペースに合わせてはいられない。
仕事の最終段階、例えば地下サークルのアジトに踏み込まなければならなくなった時には警察の起動力や戦闘力を頼む必要が出て来るかもしれない。
しかし、今は足枷にしかならない。
その足枷だが、尾藤の貴重な時間を三時間も浪費させてくれた。
尾藤たちは、現場検証に長々と付き合わされ、事情聴取やら何やらで漸く解放された時には一八時を過ぎていた。
「参ったねぇ。」
「ホントですよね、疲れました。」
尾藤とアディが、とにかく一日の疲れを癒したいと、カフェ&バー「クアーク」のカウンター席に座ったのは二〇時過ぎ。
今日は平日の木曜日なので客の数は少ない。
「半日以上、無駄にしたな。」
午前中はKとの不能な会話、午後は警察とのお付き合いである。
「さっき、司さんに電話入れといたけど、やっぱり焦ってたなぁ。」
「娘さんが生贄にされるかもって話、したんですか? 」
「するわけないだろ! 大騒ぎされちゃうよ。」
捜査の進め方を掻い摘んで報告しただけであり、その他のことは伏せておいた。
「無事に救出できる目途が立たないと、本当のことは報告のしようが無いよ。」
途中経過を詳細に報告し続けたら、司夫妻は気が狂ってしまうだろう。
「尾藤さん、難しい顔してるのね。」
仕事の手が空いたマスターが、声を掛けてきた。
「そうだよ、難しい仕事してるんだよ。」
そう言って尾藤は、ストレートグラスの中に三分の一ほど残っていたゴードンジンを一息に煽った。
「もう一杯注いで。それとチェイサーにビール。」
「相変わらず身体に悪い飲み方するねぇ。」
マスターがグラスを下げながら困った顔をした。
「今日は、これ以上飲まないから良いの。」
尾藤は手を振って、放っといてくれと合図した。
「お連れさんは? 」
マスターはアディにも声を掛けた。
「あ、それじゃ僕は普通にビールで。」
OKと言って、マスターは仕事に戻ろうとしたが、
「マスター、ちょっと相談があるんだけど。」
尾藤が呼び止めた。
マスターにアディを紹介するタイミングだと思ったのだ。
丸一日行動を共にしたことで、アディの為人は十分に分かってきた。性格は申し分ないし、素直で義理堅く、行動力と体力もある。
知人に紹介するのに不安は無いだろうと判断したのである。
「つい最近、アルバイトかパートの募集してたでしょ? 」
「ああ、してたよ。でも、良い人来なくて諦めちゃった。」
「じゃあ、良い人がいたら雇ってくれるの? 」
「良い人だったら雇いますよ。この広い店に平日一人ってのも辛いし、週末なんてバイト君二人と一緒でも忙し過ぎて困ってるもの。」
「それじゃあ、」
尾藤はアディの背を叩いた。
アディは飛び降りるようにカウンターの椅子から降りて、その場に起立した。
「彼を紹介するよ。どうだろう? 使ってやってくれないかな? 」
「え、この人? 」
マスターはアディの顔を値踏みするように見て、
「歳は幾つ? 」
と、聞いてきた。
「二二歳です。」
「本当? 未成年っぽいから、お酒出す商売はどうかなって思ったんだけど? 」
確かにアディの童顔は一見して高校生ぐらいに見える。
「大丈夫だってマスター。アディ、パスポート見せてあげて。」
尾藤に言われて、アディは直ぐにパスポートを取り出した。
「あれ、外国人なのね? 日本人かと思ったよ。」
マスターはパスポートを受け取って、ざっと目を通した。
「バングラディシュ出身。今まで外国人を雇って上手くいったことないのよねぇ。」
あまり乗り気でない顔をする。
「こいつは大丈夫だよ。俺が保証するからさ。」
尾藤は強く推してやった。
そして、アディから聞いていた日本に来るまでと、その後の経緯を話してやった。
「貴方、これから先、日本で何をしたいの? 」
「はい、まずはキチンと生活できるようになってから、学校に通いたいです。」
マスターは自分が苦学生だったこともあり、この手の話に感情移入しやすかった。
少し考えてから、
「そうねぇ、尾藤さんが推薦するなら試しに雇ってみましょうか。貴方、ちゃんと働く気ある? 直ぐ辞めたりしない? 」
念を押した。
アディは胸を張り姿勢を正して、
「大丈夫です、頑張ります。」
力強く言った。
マスターは頷いて、
「よし、来週月曜から来てもらいましょう。一週間は試用期間と言うことで、今度来るとき履歴書持ってきてね。」
「ありがとうございます! 」
アディが嬉しそうに、頭を下げた。
「よし、これで決まりだ。良かったなぁ、アディ。」
尾藤も手を叩いて喜んだが、
「でさ、も一つお願いがあるんだけど? 」
「何よ? 」
マスターが、せっかく盛り上がったところで面倒臭い話をされるのは嫌だなという顔をした。
「うちの助手のアルバイト、掛け持ちさせても良いかな? 」
今日のアディは貴重な戦力だった。
できれば、今後も仕事を手伝って欲しい。
「週にしたら何日ぐらいよ? 」
「いや、定期的にじゃないけれど、うちの忙しい時に一日か二日借りる感じで? もちろん、事前の連絡は入れるから、だらしないことは絶対にしないよ。」
マスターは、それならばとOKしてくれた。
「うちの勤務は、早番が一七時から二四時、遅番が二二時から朝の五時まで。休みは週二日で、定休日が水曜日だから残り一日は交替制で取る感じ。もし、それ以外に休みが必要だったら必ず前日までに連絡することね。休みの日に尾藤さんの手伝いしようが何してようが関係ないよ。でも、週末は基本的にうちを優先してもらわなきゃ困るからね。」
そんな感じでどうかと言われたので、
「了解。」
尾藤は親指を立てて見せた。
「クアーク」での勤務は当面時給制のアルバイトだが、一日七時間で週五日も入れば安定した収入になる。
不安定な日雇いの派遣アルバイトを続けるよりも遥かにマトモな生活を送れるはずだ。
アルバイトの件を決めたらマスターは仕事に戻ったので、尾藤とアディは今の仕事の話に戻ることにした。
「これ、見てみよう。」
尾藤が上着のポケットから里田家で手に入れた紙束を取り出しカウンターに置いた。
一〇枚もある飲食店のチラシを調べるのは後回しにして、まずは雰囲気が重要度の高さを予感させるプリント用紙の表組みを先に調べることにした。
A4用紙を横位置にして紙一杯に印刷された表組みは、六行×六段。左上角を一セル空けて、左端に一から五までの数字が入ったセルが縦に並び、最上段にも一から五までの数字の入ったセルが横に並んでいる。そして、これら縦横の数字セルに挟まれた内側の二五セルには、一セル毎に五つ前後の記号が並んで記されている。【図3】
「何かの早見表かな? 」
セルの配列に意味があるのは一目瞭然なので、その読み方を見付けなければならない。
「このセルの中の記号は文字列で単語と考えるべきだろう。で、これらの文字はバックチャームやカード、WEBページにあった意匠の中に書かれていた文字と似ていると思うんだけどどうだい? 」
「同じのもあるみたいだけど、ちょっと違わない? 」
確かに、形の似ている文字はあるのだが、殆どが違った形をしている。
「キチンと見てみなきゃダメだな。」
尾藤はタブレット端末を取り出し、里田かおるがバックチャームを付けて写っている二枚の写真を開いた。それとWEBページのヘッダー、昨夜の暴漢から手に入れたカードもカウンターに並べてみた。
「この中に同じ単語があるかどうか調べてみよう。」
早速、全てを一つ一つ念入りに確認してみたが、
「全然、違うよ。」
「ああっ、これも違ったかぁ、くそっ! 」
尾藤は悔しそうに頭を掻き毟った。
「何が残念なの? 」
マスターが飲み物のお代わりを持って戻ってきていた。
「何これ? パズルか何か? 」
「パズルみたいなもんだけど、遊んでるわけじゃないよ。」
「じゃ、仕事なの? 」
飲み物をカウンターに置いたマスターが、プリントの表組みを覗き込んできた。
「何か難しそうね。この中に書かれているのって文字なんでしょ? 」
尾藤はストレートグラスに手を伸ばしながら、
「たぶん、そうなんじゃないかね。」
気怠そうに答え、ゴードンジンを一口含んでチェイサーのビールで流し込んだ。
ジンとビールの組み合わせは古いハリウッド映画を観て覚えたのだが、この飲み方が学生時代からのお気に入りだった。四〇度超のアルコールと炭酸の刺激で胃の中が暖かくなり、これが何とも心地良い。
「ははぁ、この文字が読めなくて困ってるんでしょ? 」
マスターが表組みをトントンと指で叩きながら、思わせ振りな態度でニヤリと笑った。
「それはそうなんだけど、まさかマスターが読めるとでも? 」
「私じゃないよ、読めそうな人がいるのよっ。」
尾藤は思わず身を乗り出した。
「マジで? 」
マスターが親指を立てて、
「マジよ! 」
と、答える。
「何処に? 」
「今、ここにいるよ! 」
その返事を聞くなり、尾藤が素早くカウンターに両手をついて頭を下げた。
「お願い紹介して! 」
するとマスターは、
「わかった、ちょっと待ってて。」
軽く承諾し、カウンターを出て入り口近くのボックス席に向かった。
そして、そこに座っている客に話し掛けている。
その客は、恰幅の良い南アジア系の顔をした四〇歳前後の男である。日本人らしい若い女性を同伴しているが、どう見ても親子ほどの歳の差がありそうなカップルだった。
「あの男の人が読めるのかな? 」
アディが期待に大きな目を輝かせている。
尾藤も、期待で心臓の鼓動が高まるのを感じていた。
間もなくマスターに連れられて、男がやってきた。
「尾藤さん、こちらニシャーダさん。大学の先生で専門は言語関係なの。」
それは願っても無い幸運である。
(出来過ぎじゃないか! メチャメチャ運が良いって! )
歓声を上げたくなるのを堪え、尾藤が軽く会釈するとニシャーダも会釈した。
「で、こちら私立探偵の尾藤さん。」
探偵と聞いた途端、ニシャーダは突然ブッと吹き出してしまった。
そして、怯えたような顔をして、ジタバタしながら逃げ出そうとするので、マスターが力尽くで無理矢理引き止めた。
ニシャーダは白くキラキラと光る大きな目をいっぱいに見開いて、まるで悪戯を見つかって怯える子供のような顔をしていた。
「勘違いしないで! 尾藤さん探偵だけどニシャーダさんとは関係ないから安心して。」
マスターは言い聞かせるように言った。
(探偵じゃなく、調査員と言ってくれ! )
尾藤は心の中で呟いていたが、少しでも早く本題に入りたかったので口に出しての訂正はしなかった。
「ホントに? そ、それなら良いんだけど。驚かせないでよ。」
ニシャーダはハンカチで額の汗を拭いながら胸を撫で下ろしていたが、探偵と聞いて驚くようなことをしているのだろう。
おそらく、同伴している若い女性に関係があるのかもしれない。
ニシャーダの慌て振りが面白かったのか、マスターはもう少し苛めたくなったらしい。
「ニシャーダさんは悪い先生なのよね。奥さんも子供もいるのにさぁ。きっと、あそこに座ってる娘も教え子だと思うのよ。かわいそうに・・・ 」
マスターは尾藤に耳打ちするようにしながら、ニシャーダにも十分聞こえるぐらいの大きさの声で言った。
「もう止めてよ、人聞き悪い! 」
ニシャーダは周囲をキョロキョロと見回しながらマスターに向かって両手を合わせ、
「勘弁してください! 」
と、拝むようなポーズをした。
マスターは十分楽しんだという顔をしてから、
「しょうーがない人だねぇ。」
話題を尾藤の仕事の話に切り替えた。
「ところで、ニシャーダさん。これ読める? インドっぽい文字でしょ? 」
マスターはカウンターからプリント用紙を取り上げるとニシャーダに差し出した。
ニシャーダは、それを受け取って目を通しながら、
「マスター、言っとくけどね。僕はスリランカ人だからね。インドとスリランカは違う国だよ。」
不満そうな顔で言った。
そのまま暫くニシャーダは無言で表組みから目を離さずにいた。
大きく黒い瞳が上下左右忙しそうに動いていた。
「どうでしょう、読めますか? 」
待ちきれなくなった尾藤が声を掛けると、
「読むようなモノじゃないよ。これは暗号表だ。」
ニシャーダが言った。
「暗号表? 」
「ポリュビオスの暗号表って知ってるかい? 古代ギリシアの歴史家ポリュビオスが発明した換字式暗号だよ。」
「どんな暗号なんです? 」
「説明してあげよう。マスター書くもの貸して。」
ニシャーダは、マスターからボールペンと白紙を受け取ると、そこにフリーハンドでプリント用紙の表組みと同じ六行×六段の表を書き、左上角を空セルとし、最上段と左のセルには一から五までの数字を入れた。そして、プリント用紙では謎の文字が並んでいた内側の二五セルには、AからZまでのアルファベットを横並びで五文字づつ改行しながら五段分書き入れていった。アルファベットは二六文字なので一文字余るが、それは最後のセルにYとZを一緒に詰め込んで済ませていた。【図2】
「こんな感じで出来上がり。さて、使い方を教えようか。」
尾藤、アディ、マスターの三人が一斉に覗き込んだ。
「まずは尾藤さんの名前を書いてみよう。アルファベットではBITOでしょ。」
ニシャーダはスペルを書いて皆に見せた。
「これを、この暗号表に従って変換すると、12 24 45 35となる。」
数字の並びを見て、一番最初に理解したのはアディだった。
「わかった! 数字の交差するセルのアルファベットを拾っていけば良いんだ! 」
「その通り! 若者は理解が早いね。」
ニシャーダはアディを褒めた。
尾藤とマスターも言われてみればなるほどと頷いた。
「それじゃ、今度はこちらの表組みを見てみよう。」
ニシャーダは、再びプリント用紙を手元に引き寄せた。
「これも、もう使い方は分かったね? 」
「使い方は分かりましたけど、ここに書かれているのはアルファベットじゃないでしょう? 何かの単語じゃないですか? 」
尾藤は難しい顔をしてニシャーダを見た。
「これは単語じゃない。やはりアルファベット。同じセルの中に並んでいる複数の文字は同じアルファベットが異なる種類の文字で並んでるだけだよ。但し、解読し辛くするためにアルファベットの並び順は僕が書いた表組みと違って素直に連続してないけど。」
「そうなのか! 」
尾藤は目の前が明るくなったような気がした。
「複数の種類のアルファベットを使っているのは見る人を惑わすためだろう。このセルの中の文字を一種類でも読める人ならば、全てのセルをABCに置き換えできるよ。つまり、この暗号表で作文した文章はアルファベットに変換できるってことさ。」
ニシャーダの話を、ここまで聞けば残された謎も解けた。
「これも見てください。」
尾藤はタブレット端末に開かれたままになっていた里田かおるの写真を見せ、
「これは、数字なんでしょう? 」
バックチャームのマスコット部分を指さした。
「当たり! 」
ニシャーダが言った。
「これはカンボディアのクメール数字だ。別に謎でも何でもない、カンボディア人なら普通に読める数字さ。それにしても、面白いゲームだね。今度、うちの大学でも教材にしてみようかな。」
この謎解きが、どれほど重大なことか分かっていないニシャーダは、同じく状況が分かっていないマスターと楽しそうに笑っていた。
「これで大きく前進できる! 」
尾藤は、この仕事が始まって以来最大の謎が解けたことにより、全身の力が抜けてしまったような気がした。
だが、せっかく専門家がいるのだから、もう一つ頼みごとをしたい。
「できれば英語のアルファベットを各セルに書き添えていただきたいのですが、お願いできませんか? 一から五までクメール数字も教えていただけると助かります。それと、ニシャーダさんはセルの中に並んでいる複数のアルファベットが、それぞれ何語の文字か分かりますか? 」
暗号解読ガイドを作るだけではなく、使われている文字の種類も知りたかった。
昨夜来、尾藤は地下サークルの関係者と何人も出会ったことになるが、どうやら会員には多数の外国人がいるらしい。ここで使われている文字を特定しておけば、後々に有力な手掛かりに結びつくかもしれないと思ったのだ。
「英語のアルファベットを書き込むぐらい直ぐにもできるけど、僕一人じゃアルファベットの種類全部を特定するのは無理だよ。」
「全部じゃなくても、分かるだけで良いですから。」
「それなら良いよ。大した作業じゃなし、やってあげよう。ファンタジーで有名なルーン文字が入ってるから、そこを基準にすれば解読表なんて直ぐに作れるよ。」
ニシャーダは引き受けてくれた。
「今日の先生とお連れの女性の飲み代は、僕が全部持ちますからね。もう好きなだけ飲んでって下さい! 」
尾藤はニシャーダの手を握り締めて、何度も感謝の言葉を口にしていた。
「尾藤さん、尾藤さん! 」
アディが尾藤の肩に手を掛けて揺すった。
「なんだよ、アディ? 」
「携帯鳴ってる。」
尾藤には全く聴こえていなかったが、アディは耳が良い。
「あ、ホントだ。」
上着のポケットに手を突っ込んでみると確かに携帯通信端末が振動している。
「あれ? 事務所からだ。」
ディスプレイに表示されているアドレスは尾藤調査事務所の表示である。
「吉良さんからなの? 」
「たぶん、そうだよ。でも、もう二一時近いってのにどうしたんだろ? 」
尾藤は嫌な予感がした。
最後に恵子と電話で話したのが一八時頃。
その時に今日は事務所を閉めて帰るようにと伝えていたから、こんな時間に電話が掛かってくるはずはないのだが、
(まさか、恵子に何かあったんじゃないだろうか? )
恐る恐る受信ボタンをタップした。
すると、
「ああ、やっと通じたぁ! もう、三〇分くらい呼び出し続けですよぉ! 」
スピーカーから聞こえる声は間違いなく恵子である。
(良かったぁ! 怪しい男かなんかが出たらどうしようかと思ったわ。)
昨日から今日にかけて、地下サークルの凶暴性を散々見せられた尾藤は、そろそろ事務所が襲撃される危険性を考えなければならないと思っていた。
そこで、恵子には緊急自宅待機を指示しようと思っていた矢先だっただけに、つい最悪の状況を想像してしまった。
「こんな時間に事務所の電話で連絡なんて、いったいどうしたの? 」
尾藤はホッとし過ぎて、少し声が震えてしまった。
「いやぁ、ちょっと事務所に戻ってきてくれませんかね? 」
「良いけど、わけを話してよ? 」
「それは、事務所に戻ってきていただいてからお話しします。至急、尾藤さんに見ていただきたいモノもあるので・・・ 」
恵子は、歯にモノの挟まったような言い方をする。
「わかった、直ぐに戻るよ。」
尾藤は電話を切って立ち上がった。
恵子は無事なようだが、嫌な予感は消えなかった。
何か、とんでもない事件が起こっているような気がする。
尾藤は席を立ち、テーブルに置きっぱなしになっていたチラシやタブレット端末を纏めてバッグに放り込みながら、アディに指示を出した。
「俺は急いで事務所に戻らなきゃならなくなったんだけど、後でニシャーダさんから暗号表もらって届けてくれるか? タクシー使っていいからな。ああ、領収書忘れんなよ。」
アディが応えるのを待たずに、今度はマスターを振り向いて、
「マスター、ニシャーダさんのも含めて今日の飲み代は全部つけといて。今度来た時に払うから! 」
そう言いながら、既に店の入り口のドア前まで移動していた。
「OK! 尾藤さん、気を付けて帰るのよ。」
何が起きているのか分からないマスターが心配そうにしていた。
「ニシャーダさん、今日は本当にありがとう! 」
店を飛び出す間際にニシャーダへのお礼の一声を掛け、尾藤は後ろを振り返りもせず大急ぎで甲州街道まで走り、そこでタクシーを拾って事務所に向かった。
[一四]
タクシーを降りた尾藤が事務所の窓を見上げると、灯りが点いていた。
恵子が未だ残っているとしたら当り前のことなのだが、二一時過ぎてから尾藤以外に事務所に誰かが残っていることなど過去に一度も無いので絶対におかしい。
(何があっても構わないから、恵子だけは無事であって欲しい。)
恵子以外に事務所に誰かがいる可能性が無いわけではない。
(さっきの電話は、誰かに脅されて掛けてきたのかもしれないし。)
その割には、声が元気そうで芝居をしているような雰囲気は無かったが・・・
(用心するに越したことは無い。)
尾藤はカバンの中を探って、黒い棒状の道具を取り出した。
スタンガンである。
里田家で倒した暴漢の一人が持っていた得物だったが、警察がやってくる前にこっそり懐に入れ着服しておいたのである。
試しにスイッチを入れてみると、バトンタイプのスタンガンの先端に一〇〇万ボルトのスパークが走った。
(充電はバッチリ! )
尾藤は、スタンガンを後ろ手に持ち、足音を立てないように気を付けながら、ゆっくりと階段を登った。
そして、事務所のドアの前に立って中の様子を伺ってみる。
アディほどの聴力は無いが、今は夜間で通りの雑音は少ないし、狭い事務所の中の様子ぐらいは掴めるはずだった。
(人の動く気配はある。それが恵子なら問題ないんだが・・・おや? )
事務所のドアは閉まっているが、ドアの下半分がフレームから浮き上がって見える。
(歪んでいるんだ! )
良く見ると、本来横を向いているはずのL字型のドアノブが斜めで止まっている。
(ドアが壊されている! 何かあったんだ! )
急激に湧き上がった不安と怒りで、全身の血液が沸騰し脳天に突き抜けた感じがした。
(恵子に何かあったら、俺は絶対に地下サークルの奴らを許さん! )
そう思った途端、身体が勝手に動いた。
スタンガンを握り締め、ドアノブを下げると一気に事務所に飛び込んだ。
そして、喉が千切れるほどの大声で、
「恵ちゃーんっ! 」
と、叫んだのだが、
「え? あ、はい。」
そこにはモップを手に床の拭き掃除をしている恵子の、全く無事な姿があった。
事務所の中は荒れ放題で、床に様々な書類や文房具が散らばり、引き出しや戸棚は開きっぱなし、割れ物も見られたが、恵子は無事であり、いきなり物騒なモノを手にして飛び込んできた尾藤を見て驚いている。
「け、恵子さん? 」
「な、何? 」
ここでは「無事で良かった」という言葉を掛けるのが適切だと思うのだが、恵子が無事だったという現状を喜びつつも、頭に血が上った興奮状態が収めきれず、尾藤は混乱の真っ最中だった。
だからというわけでもないのだが、尾藤はスタンガンを放り出し、何も言わずに恵子の前に進み出て、
「ちょっと、どうしたんですか? 」
戸惑う恵子の肩に両手を回し、力一杯抱きしめてしまった。
そして、
「良かったよ、良かったよー、」
震える声で何度も繰り返していた。
明らかに後先考えていない血迷った行動である。
「あはは、尾藤さん、どうしちゃったんですか? 」
突然の抱擁に驚いてモップを落としてしまった恵子だったが、決して逃げようとはせず、尾藤を受け止めたまま、その頭と背を軽く撫で、
「よしよし、大丈夫ですよぉ。」
子供を宥めるように優しく言った。
「無事で良かった。ホントに良かった。」
同じ言葉を繰り返す尾藤の声は半泣きだった。
「そっか、心配してくれてたんですねぇ。」
恵子は、尾藤が自分を心配してくれたことを素直に喜んでいるようだった。
「凄く心配したよ。だから良かった。ホントに良かった。」
尾藤の抱擁に一段と力が込められた。
「ちょっと尾藤さん、苦しいですよぉ。」
恵子が、弱ったような声を出した。
「ねぇ、苦しいって言ってるじゃないですかぁ、尾藤さんってば。」
それでも尾藤は恵子を離そうとしない。
但し、尾藤の興奮状態は既に収まっているようで、この際だからと少し調子に乗っているような気配が感じられる。
そのうちに、恵子の声色が徐々に変わってきた。
「あの、マジで苦しいんですけど? 聞こえてます? 」
それまでの優しい声が、冷たく苛々した声に変ってゆく。
「ああ、もうっ! 苦しいっつってんのが分かんないんですかぁーっ! 」
恵子の怒りの叫びと、
「痛ーっ! 痛だだだーっ! 」
腕を捩じ上げられ、床に這いつくばった尾藤の悲鳴が隣近所にまで響き渡ったと思われる。
「大人なんですから、もっと冷静にならなきゃダメです。」
「はい、すみませんでした。」
事務所の床に正座させられた尾藤は、恵子の説教を受けていた。
(ああ、今日の説教は何か嬉しい。)
キツイ説教を聞きながらも内心は嬉しい尾藤だった。
「まあ、尾藤さんが私を心配してくれたことは、凄く嬉しかったですけどね。」
最後に飴を舐めさせたところで恵子の説教は漸く終わった。
「質問、良いでしょうか? 」
尾藤が小さく手を上げた。
「はい、何でしょう? 」
「さっきの電話と、この事務所の惨状は何だったんですか? 」
恵子はポンと手を打って、
「そうなんです。大事な話があるんです。でも、まず先に、これを見て下さい。」
社長室兼応接室のドアを開け、
「どうぞ。」
と、尾藤を手招きする。
「何があるのさ? 」
尾藤は立ち上がって、社長室兼応接室の中を覗き込んだ。
「わっ、わーっ! 何よ、これ? 」
昨日から、様々なことで驚かされてきたが、これが一番強烈だった。
社長室兼応接室のカーペットの上には、ガムテープでグルグル巻きにされた人間らしき物体が転がっていたのだ。手首足首はもちろん、両手両足は何重にも巻かれたガムテープで固定されている。しかも、顔面までガムテープが巻かれているので、人相どころか男女の区別さえもつかない状態である。
「この芋虫、もしかして恵子さんがやったんですよね? 」
尾藤は唖然としながら、ガムテープ製の芋虫かミイラにしか見えない謎の塊りを指さして言った。
「そうなんですけどねぇ、まあ話を聞いてください。」
恵子は芋虫を無造作に跨いで、奥のソファに腰掛けた。
「はい、聞かせていただきます。」
そう言って、尾藤も向かい側のソファに腰掛けた。
「最初から話をしますと、まず夕方の尾藤さんの電話を受けた後からですね。」
恵子は暫し視線を空中に漂わせながら記憶の整理作業をしていたようだが、
「よしっ! では、始めます。」
と、顔を上げた。
「尾藤さんの電話の後、洗い物と雑用を済ませて私は一旦帰りました。途中、コンビニで買い物をして、東中野駅に着いたのは一九時一五分前後です。そこで、事務所に定期券を忘れたことに気付いたんです。それで取りに戻りました。事務所に着いたのは一九時半頃です。」
時刻を整然と記憶しているところが実に恵子らしい。
「事務所のドアの前に立って鍵を開けようとした時、指紋認証のタッチパネルが傷だらけになっていて、ドア自体が歪んでいるのが分かりました。たぶん、誰かが力任せに抉じ開けたんだろうと思いました。そこで試しにドアノブを押し下げてみたら、案の定、鍵は壊れていたんです。そこで中を確かめようと静かにドアを開けたら、この人がいて、引き出しとか、戸棚とか、あちこち引っ掻き回していたんですね。で、こうなりました。」
最後の所を思い切り省略されてしまったが、取り敢えず状況は分かった。
尾藤は思わず口を開き、
「危ないじゃないか! どうしてドアを開ける前に警察に連絡しなかったんだよ! 」
と、怒鳴ってしまった。
女性の身で、たった一人で侵入者を相手にするなど危険過ぎる。
「すみません。」
恵子は素直に頭を下げた。
しかし、続く言葉に呆れさせられる。
「それは考えないでもなかったんですが、あまりに事務所の中の荒らされ方が酷くて、せっかく掃除したのにって思ったら頭にきちゃったんですよ。」
まさか、自分が綺麗に掃除した後を汚されたというのが、こんな無謀な行動に及んだ動機だと言うのか?
(何、考えてんだ? こいつ・・・ )
今まで恵子を頭の良い娘だと思っていたが、
(・・・馬鹿だったらしい。)
掃除に命を懸けるとは、呆れてモノが言えない。
そう言えば、さっき尾藤が事務所に入ってきた時も、恵子は掃除をしていたが、
「まさか、泥棒された証拠を掃除したりしてないよね? 」
「それは大丈夫です。さっきは飲み物を溢しちゃったので拭いてただけです。」
「あ、そうなのね。」
尾藤は大きな溜息をついた。
「あのさ、できれば、こうなった最後のところを詳しく聞きたいんだけど? 」
尾藤の問いかけに恵子が思い切りバツの悪そうな顔をし、ついでに舌打ちが聴こえたような気がした。
「やっぱり、聞きますよね? 」
「そりゃ、聞かなきゃならないだろ? 」
今度は恵子が大きな溜息をついた。
「私は飛び込んで直ぐに警告したんです。」
「警告って? 」
「大人しくしろって言いました。」
それで大人しくなるような泥棒なんているわけがない。
「でも、この人が早口で捲し立てる言葉は英語だったと思うんですけど、おかしな訛りが強過ぎて何言ってるか全然分からなくて、こっちの話は通じないし、いきなりナイフまで出されちゃって、尾藤さんを襲った奴らもこんな感じって聞いてたんで、やっちゃったんです。」
恵子は話し終わってプイと横を向いた。
子供が良くやる「私は悪くないもの! 」と、いう顔をして開き直ったようだ。
「・・・やっちゃったのね。」
綺麗に掃除した事務所を汚くされたことに怒って、言葉が通じなくて、そしてナイフを見たから、やっちゃったらしい。
(一応、正当防衛だけど・・・ )
恐ろしい女である。
事務所に戻ってくるまでの間、心配で気が狂いそうだった自分がアホらしくなった。
(こいつ、俺が事務所を汚したら、やっちゃうつもりなのかな? )
それを考えると、ゾッとしてしまった。
「ところで、この芋虫、未だ生きてるんだよね? 」
まあ、途中経過はどうあれ、新しい捕虜が手に入ったのは幸運である。
確認するまでもなく、わけの分からない言葉を話し、いきなりナイフを出すところが、尾藤を襲った暴漢たちと一緒である。
警察に渡す前に、色々と調べてみたいことがあった。
でも、死んでいたら困る。
「殺しちゃいませんよ。気絶させて逃げられないようにガムテープで縛っただけです。あと、反抗されないように両肩の関節は外しときました。」
いつも仕事の受け答えをしている時のように、サラリと過激なことを言う。
尾藤はどうリアクションして良いか分からず、モジモジしながら上着のポケットからハンカチを取り出して、額に薄っすらと滲んできた汗を拭いた。
(過剰防衛だって言われなきゃ良いんだけど。)
警察に連絡するのが心配になってきた。
「せめて、顔面のガムテープだけでも外しとこうか。」
尾藤は芋虫の傍らに膝をつき、顔に巻き付いたガムテープを外し始めた。
(全く、これ何重に巻いてんだよ。)
目と口を塞ぐだけで良いのに、頭の天辺と鼻穴以外はグルグル巻きにしてある。
(さすがに、怖かったんだろうけどな。)
おそらく、ガムテープの厚さは恵子の恐怖心の表れと思われる。平然としているようで実はかなり焦っていたようである。
このおかげで、多少の可愛げは感じられるようになった。
(いやぁ、それにしても顔面が豪快に腫れ上がってますね。)
ガムテープの下から現れた男の顔は両目の下と口元は腫れ、頬には赤紫の痣ができており、白人種と分かるぐらいで、どこ系とまでは区別のつけようが無かった。
(何か、唸ってるな? )
ガムテープを剥がされる痛みで、徐々に意識も取り戻してきたようだった。
「ところで、恵子さんは、この人を何で殴ったんでしょうか? 」
尾藤は苦笑いしながら聞いた。
「私の膝ですけど。」
恵子は自分の右膝をポンと叩いた。
もう、一々驚くのも面倒臭い。
(顎が逝っちゃってたら困るな、話せるのかな? )
恵子は男が英語らしき言葉を話していたというので、まずは試しに話しかけてみることにした。
「your name ? 」
すると、
「アブドル・ハサン。」
と、カタカナっぽい音が返ってきた。
「何だ? お前、日本語話せるのか? 」
日本語が通じるなら尋問は楽である。
「スコシシカ、ワカラナイ。」
少しでも分かれば上々である。
「お前は、ここに何をしに来た? 」
「ソレハ、イエナイ。」
「お前を、ここに寄こした奴か、仲間の名前を言え。」
「ソレハ、イエナイ。」
「随分、事務所を荒らしてくれたようだが、何を探していた? 」
「ソレハ、イエナイ。」
まるで、「ソレハ、イエナイ」以外に言葉を知らないようである。
「お前、自分の置かれている状況が分かっていないらしいな? 」
「ソレハ、イエナイ。」
どうやら馬鹿にされているようだ。
尾藤は「ふざけんなっ! 」と、怒鳴ろうとしたのだが、その前に背後からブチっと何かが切れるような音が聞こえてきた・・・ような気がする。
「なんか苛々してきました! 女性に向かってナイフを振り回すような卑劣な男なんて、少し手荒にしてやって良いんじゃないでしょうか? 」
どうやら、恵子にも尾藤と同じような激しい敵愾心が芽生えてしまったようである。
アブドルを返り討ちにして捕えることはできたわけだが、自分を害そうとした男に対する怒りは多少殴る蹴るしたぐらいでは収まらないようだ。
「ホントに随分生意気な奴ですね。いっそ何処か適当に折ってみましょうか? 」
後ろから覗き込んできた恵子の薄ら寒いセリフに尾藤はゾッとした。
恵子の怒りの籠ったセリフはアブドルにも理解できていたようで、
「ヒッ! 」
と、息を飲むような悲鳴が聞こえた。
アブドルは、このような有様になってしまった経緯を思い出したのだろう。恵子が如何に危険な女であるか身に染みて理解しているようだ。
「お、折るのは無しでしょ! 」
尾藤が慌てて止めた。
「折るのがダメなら肩以外の関節も外してみますか? 両手の指を潰してみるとかどうです? そのぐらいなら事故ってことでごまかせますよ? あ、うっかりポットのお湯をかけてみるとかも有りですね。」
「いやいや、それ無いから! 」
「まったく、尾藤さんは甘いですねっ! 」
恵子は膨れっ面をした。
(この女、いったい何をしたいんだよ? もしかして、これって口を割らせるための脅し? 作戦だったりする? )
恵子は強情なアブドルを脅しているだけであって、決して本気で腹いせのために拷問しようと言っているわけではないと思うのだが・・・いや、思いたい。
脅しを狙った駆け引きだったとしたら、その効果はあった。
このやり取りを聞いていたアブドルが、
「ケイサツハ? ケイサツニ、デンワシナイノカ? 」
情けない声を出した。
まあ、警察に引き渡されたならば拷問は受けずに済むだろう。
「警察? ああ、そのうちね。」
尾藤は突き放すように言った。
「その前に聞いとかなきゃならないことが一杯あるんだよね。全部話してくれたら警察に連絡するわ。」
それを聞いてアブドルは、
「ベンゴシハ? ケンリハ? 」
と、ジタバタし始めた。
「この人、結構、難しい言葉知ってるみたいですね。」
またまた恵子が口を挟んできた。
「そうだね、会話が楽で良いよ。」
尾藤はもう一度、さっき「ソレハ、イエナイ」と、ふざけて返された質問を始めた。
「ウルサイッ! ワタシハ、ハナサナイ! 」
アブドルは、最後の意地を張った。
しかし、これが本当に最後の意地になった。
「やはり、ここは指とか折るべきでしょう。」
そう言って、恵子がアブドルの背中に回って手を伸ばした。
「ちょっと待ちなさいよ! 」
尾藤が止めたら、
「さっきコーヒー飲もうと思って沸かしたんでポットのお湯は十分熱いですけど、持ってきて良いでしょうか? 」
などと、恐ろしい発言が止まらない。
「万が一殺っちゃっても大丈夫ですよ。私、正当防衛にできますから。」
「それ、マジで言ってますか? 」
こうした二人の会話を聞かされるうちに、アブドルは観念して素直になった。
尾藤の携帯通信端末に着信が入った。
「お、木村じゃん。」
アブドルから情報を引き出し終え、それを恵子に入力してもらっていたところだった。
既に、アディもニシャーダが作ってくれた暗号表を携えて事務所に到着していた。
(せっかくだから、木村にアブドルを引き取ってもらおう。)
そんなことを考えながら、受信ボタンをタップした。
「遅くまで、ごくろうさん! その後、警察の取り調べで何か進展はあったかい? 」
「尾藤、お前は自宅か? 」
「いや、今日は事情があって残業。実は・・・ 」
尾藤がアブドルを捕まえた件を言い掛けたのだが、木村に遮られた。
「例の三人の件だが、取り敢えず分かったことだけ伝えるわ。」
「おお、それはサンキュー! 」
せっかくなので、先に木村の話を聞くことにした。
「まず三人の内訳だが、中国人、アラブ人、日系ブラジル人という組み合わせだ。」
「多国籍軍だな。」
「全くだよ。奴らは職場もバラバラで、中国人と日系ブラジル人は日雇い労働を転々。アラブ人は自動車修理工だが、どいつも低賃金労働で苦労してるらしい。不思議なのは、あいつらは自分以外の二人のことを名前も含めて何も知らないって言うのよ。嘘なんじゃないかと思って何度も繰り返し調べたんだが、どうやら本当らしい。」
「それって、あいつらが自主的に纏まったんじゃなく、指示を出している人間や組織が背後にあるってことの証明だよな? それが地下サークルってことなんじゃないのか? 」
「それに関しては、どいつも頑として口を割らないんだわ。だが、アラブの奴が譫言みたいなことをブツブツ唱えてたんだ。それが何かの宗教の教義じゃないかと思ってな、記録しといた。」
それは、かなり興味深い事柄である。
「どんな? ちょっと言ってみてよ。」
尾藤は木村を急かした。
「聖書の一節らしい。詳しい奴に聞いたら『ヨハネの黙示録』の一六章だとか言ってたな。」
「ああ、それって七人の天使が神の怒りを地上にぶちまけるとかいう迷惑な件だな。」
「へぇ、良く知ってるな。」
木村が感心したので、
「まあね、そのくらいはね。」
と、尾藤はちょっと自慢してみた。
但し、尾藤は信心に全く無縁な人間であり、実家は曹洞宗だから友人知人の結婚式や葬式以外でキリスト教と関わり合いになったことなど一度も無い。聖書については、一応新約も旧約も読んだことぐらいはあるが、別に興味は無い。
『ヨハネの黙示録』に関しては、子供の頃からホラー、SF、ファンタジー系の映画や小説、漫画が大好きで、片っ端から漁っていると頻繁に出会うので、何となく憶えてしまったというわけだ。
「新興宗教じゃ『ヨハネの黙示録』は好んで使われるネタだよね。人類滅亡とか信じる者は救われるとかいう解釈ができるから便利みたい。でも、アラブってイスラム教じゃなかったっけ? 何で聖書なんだろ? 」
尾藤が不思議そうに首を傾げると、
「アラブにもクリスチャンがいるんだろ。」
木村はあっさりと違和感を振り払ってしまった。
確かに例外はあると思う。アディもイスラム教徒とヒンドゥー教徒が殆どのバングラディシュ出身なのにクリスチャンだった。
「他にはなんか言ってた? 」
「ちょっと待てよ。」
木村が電話口でメモを捲っている。
「お、あった! これは日系ブラジル人が取り調べ官に毒ついてたセリフ。なんでも、不信心な愚か者は自らが創り出した業火に焼かれるらしい。」
「物騒な話だな。愚か者って警察のことだよね? 」
「何言ってる! お前も一緒に焼かれるってことだよ。」
「やっぱねぇ。」
尾藤は苦笑いした。
「このセリフ、何だと思う? 」
「さあ、聖書じゃないの? 」
業火に焼かれるなどと言う言い回しは黙示録っぽいと思ったのだが、
「残念、クルアーンだよ。」
「ああ、イスラム教の? 」
さすがに尾藤にはイスラム教の知識までは無い。
「これも詳しい奴に聞いたんだが、セリフの基は『最後の審判』だってよ。」
「ふーん。」
出典は違うが、どちらも人類滅亡ネタらしい。
「お仲間同士で一人は聖書、一人はクルアーンねぇ。地下サークルの主催してる宗教ってのは既存宗教のチャンポンみたいだな。」
新興宗教というモノの大方はそんなものだろう。様々な宗教の教義を集めて、都合の良い部分を抜き出して繋げて、尤もらしい一つの教義に纏めてしまうのである。
「たぶん、取り調べを続けてたら、そのうちブードゥー教とかゾロアスター教なんかも出て来るんじゃないの? 」
「うぇーっ、気持ち悪りぃな。」
木村も尾藤同様に宗教など冠婚葬祭以外の役に立つとは思っていない類の人間であるから、思い切りの嫌悪感を表した。
だが、これによって地下サークルの正体が分かった。
カルト宗教の教団であることはほぼ間違いないだろう。
「他には何か言ってないかな? 例えば、そいつらが行っている生贄の儀式の話とか? 」
「そう言う話は無いぞ。これから出て来るかもしれないけどな。」
「それじゃあ、その話が出てきたらチェックして欲しいんだけど、生贄の儀式が行われる条件を細かく聞き取ってくれよ。だいたい儀式なんてモノは、信者の雰囲気を盛り上げるためにロケーションを大切にするだろうから、条件がわかれば会場を特定できるかもしれない。司廉子を助ける手掛かりになると思ってね。」
「よし、分かった。それじゃ、また何か情報を手に入れたら連絡する。」
木村が電話を切ろうとしたので、
「ちょっと、待って! 」
尾藤が慌てて止めた。
「なんだ? 」
「またまた、警察に引き取って欲しい奴がいるんだけど。」
「はぁ? 」
木村が疲れた声で答える。
「いったい、今度は何処で狙われたんだ? 」
「俺の留守中に事務所を荒らしにきたんだわ。それを、うちの吉良くんが見つけて捕まえちゃったのよね。そいつの名前はアブドル・ハサン。名前は中近東系だけどアメリカ人だったよ。」
「アメリカか、全く困った多国籍軍だな。ところで吉良って、吉良恵子君のことか? 」
「そうだよ。」
「大丈夫なのか? 怪我とかしてないか? あんなか弱そうな娘に泥棒を捕まえるなんて危ないことをさせちゃいかんぞ。でも、凄いじゃないか。感謝状ものだよ。」
心配しながら随分と褒めまくる。
今まで、木村の元を訪れる際には恵子も余所行きの顔をしていたんだろうが、か弱そうに見えるとは、かなりな猫の被り方をしていたようだ。
(たぶん、今回でイメージは壊れちゃうかもしれないけどね。)
アブドルの有様を見れば、か弱いなどというイメージは吹っ飛ぶだろう。
「で、至急引き取りに来てくれるかな? 」
「ああ、直ぐに向かう。」
電話の向こうで、木村が近くにいる署員に指示を出している。
「一応さ、ちょっと断っておくけど、けっこう大乱闘だったみたいで、救急車も呼んだ方が良いかもしれないんだわ。」
「なんだ? 吉良くんが怪我でもしたのか? 」
まあ、普通ならば、そう考えるところだろう。
「そうじゃないんだけどね。」
現場を見せられた時の木村の驚く顔が目に浮かぶようだった。
[一五]
一一月二二日を迎えた。
おそらく、司廉子に残された時間は今日を含めて二日と少々。
昨夜のうちに調査は大きく進展したが、未だ救出段階には至っていない。
焦りは増すばかりだが、尾藤は努めて冷静さを失わないよう心掛け、仕事に臨むようにしていた。
それにしても、アブドル・ハサンの件は恵子の大金星だった。
アブドルを締め上げたことで知ることができた地下サークル、いや、ここから先はカルト教団と呼ぶべきだろうが、その概要は次のとおり。
一、関東を中心に二〇万人以上の信者を要する大規模な教団である。
二、何を信じているのか、主神の名などは不明。
三、教祖は不在のようだが、数人の実力者が幹部となり、教団の運営は彼らの合議により行われている。
四、信者の構成は日本人が半数以上を占めるが、残りは多人種、多国籍状態である。
五、信者の職業は様々で、一部の思想団体や労働組合との繋がりもあるらしいが、大部分を占めるのは低所得者層である。
六、主な資金源は一部の裕福な信者や、その関連企業からのお布施。
七、教団のためならば如何なる犯罪、テロルも肯定され、女子学生の誘拐は教団の指示のもとで組織的、計画的に行われている。
八、浚われた女子学生は、毎月の新月の日に教団が司る儀式の生贄とされるが、生贄に選ばれる者は容姿に優れた異教徒の処女でなければならない。
これらは有益な情報だった。
二〇万人以上もの信者を抱える巨大なカルト教団が、人知れず日本の地下に潜伏しているというのは驚愕の事実であり、木村が言っていたとおり民間調査員程度が一人で立ち向かえるような相手ではなかったということだ。
正面からぶつかれば敗北は必至。搦め手から侵入し、最小限の目的を果たした後に離脱して、後は公安に任せてしまうというのが正しい。
その最小限の目的である司廉子救出に関する情報も得られていた。
アブドルの話によれば、彼女は確実に生存しているということだった。
次の新月まで、生贄とされる女子学生は決して危害を加えられることも無く、儀式の会場となる場所に大切に監禁されるらしい。但し、儀式は毎回異なる会場で行われ、一般信者には開催直前まで知らされないということなので、単なる下っ端兵隊でしかないアブドルから監禁場所を聞き出すことはできなかった。
だが、これで調査開始時には掴みどころが見えず、手探りの調査と推測を積み重ねていくしかなかった事件の輪郭と首謀者たちの姿が浮かび上がってきた。
この成果は大きい。
もう一息、あとは司廉子の監禁場所さえ見付けることができれば尾藤の勝ち、調査は無事に完了する。
そのためにも尾藤は、これまでに入手できた幾つかの手掛かりの中で後回しにしていた件、里田家で暗号表と共に手に入れた飲食店のチラシ一〇枚を徹底的に調べ上げなければならなかった。
チラシの全てが高円寺にあるアジア系レストラン「シクラニ」のものであり、コピー機で刷った手作り広告である。主たる内容はランチメニューの案内だが、持参の上で来店すれば一〇パーセントの割引サービスが受けられるチケットも兼ねている。
その一見何の変哲も無い広告紙面の中に、尾藤は教団の暗号が刷り込まれていることを見付けていた。
「ニシャーダさんに感謝しなきゃ。」
彼の作成してくれた暗号解読表のおかげで、チラシに隠された暗号を見付けることができたのである。
さらには、里田かおるが身に着けていたバックチャームのマスコットに記された暗号の解読にも成功していた。
これによって、司廉子誘拐に至るまでの教団の動き方や、それに携わった人員の規模までが明らかになった。
さて、暗号の内容であるが、まずはチラシの機能について。
個々のチラシには割引チケットとして使える有効期間が記載されていた。
その期間は全チラシ共通で僅か三日間づつ。個人経営の飲食店が手作りで発行する割引チケットの有効期間としては短過ぎる。デザインやレイアウト、メニューの内容までもが一〇枚全て同じなので、三日刻みで有効期間を変えたチラシを作る必然性が全く感じられない。しかも、奇妙なことに全てのチラシの有効期間を並べてみると、一カ月間に渡って隙間無く連続していることが分かった。普通に考えるならば、一カ月の有効期間を設けた割引チケットを一種類作れば済むはずあり、一〇種類も作るなど経費と手間の無駄遣いでしかない。
ところで、割引チケットの有効期間が三日刻みということは、これらのチラシは三日毎に配布されていたことになる。
おそらく、配布されたのは有効期間初日の午前中までということになり、店舗や街頭での手配り、郵便受けへの投げ込みという手段で人手に渡ったのだろう。
たいへんな手間だと思うが、そうしなければならない必然性があったようだ。
実は、これらのチラシは教団が司廉子誘拐の実行犯たちに支持を伝えるための連絡手段として用いられていたらしい。短期間で有効期間が更新されているのは、一定の期間内で情報を往復させるために必要だったからなのである。
そのことに尾藤が気付いたのは、最も新しい有効期間が書かれていた一〇枚目のチラシを調べていた時である。
そのチラシの有効期間は一一月九日から一一日まで。司廉子が浚われた翌日に配布されたチラシだった。
『神は歓びたもう』
ニシャーダ氏作成の暗号解読表によると、このようなメッセージが一〇枚目のチラシには書き込まれていた。
それを尾藤は、犯行の翌日に教団が里田かおるを含む実行犯たちへ送った成功のメッセージであると読んでいた。
チラシの暗号は、全紙異なる位置に目立たないように書き込まれていた。
それは、メニューを取り囲む飾り罫線の一部であったり、イラストカットに絡めて手描きで書かれていたり、アジア料理店らしさを演出するビジュアルの一部にしか見えないよう工夫されていた。
しかし、既に暗号解読表を手に入れていた尾藤が、これらを見逃すはずはない。忽ち全てのチラシから暗号が拾い出され、直ぐに解読作業が行われた。
意外なことに、それらの暗号は様々な国のアルファベットを介していながら、いざ解読してみるとローマ字表記の日本語として読むことができた。
つまり、そのメッセージの受け手は明らかに日本人なのである。
まず一枚目は、
『ni ni nana hituji wo torite kago ni ireyo』
と、変換されたが、
『二二七 羊を取りて籠に入れよ』
と、読むことができた。
続いて二枚目から七枚目までが、
『tugi no hituji wo motomeyo(次の羊を求めよ)』
という、同じ内容である。
そして八枚目、
『sono hotuji wo tatematuru(その羊を奉る)』
九枚目は、
『asatte ni san go no siji ni sitagai go iti ni to go iti san ga suru
(明後日、二三五の指示に従い、五一二と五一三がする)』
そして最後の一〇枚目に至る。
『kami ha yorokobi tamo(神は歓びたもう)』
以上がチラシに書かれていた暗号メッセージだった。
「これらは、メッセージというより段階的な指示、命令だ。」
誰が誰に向けた命令なのか?
「教団が、二二七という奴に向けた命令だろう。」
二二七とは何者か?
「おそらくは里田かおる、もしくは里田家の者全員だ。二二七とは信者の背番号のようなモノじゃないかな? 」
カルト教団が里田かおるに命じて羊を探させていた。
羊とは生贄にする少女のことと考えて間違いない。
三枚目から七枚目までのチラシは、里田かおるが提示した少女が彼らの基準では適当ではなかったという回答である。
八枚目に漸く適当な少女(おそらくは司廉子)が見つかったとの回答がされている。
このように読み解くと、司廉子が浚われる前に五人の少女がターゲットにされ、密かに選別されていたことが分かる。
五人の少女は、皆が里田かおるの親しい友人だったに違いない。彼女は友人を一人づつ連れ歩き、何処かで見張っていた教団関係者の目に晒していた。その際には、例のバックチャームを目立つ場所にぶら下げ、マスコットにメッセージを書き込んでいたのである。
テーマパークで司廉子と並んで撮られた写真では、マスコットの中に、
『Sheep of the sixth(六番目の羊)』
と、あった。
このメッセージは英語なので受け手は外国人である可能性が高い。
里田かおるは司廉子を六番目の少女として教団関係者に照会したのである。
そして、八枚目のチラシで決定の回答を受け取り、犯行前々日に撮影された写真で身に着けていたマスコットでは、
『asatte gogo roku ji(明後日、午後六時)』
と、書かれていた。
今度は日本語だからメッセージは日本人向けだと思うが、これは実行犯に司廉子の姿を最終確認をさせ、犯行に及ぶ日時の確認をしたモノだろう。
里田かおるの協力で司廉子の誘拐に及んだ実行犯のリーダーは、九枚目のチラシにある二三五。五一二と五一三の二人は二三五の部下、又は手伝いと思われる。
この二三五だが、日本人でありメッセージを受け取りやすいポジションにいた者であるならば出角だったのかもしれない。
そして、誘拐は成功し、里田かおるは一〇枚目のチラシにあった、
『kami ha yorokobi tamo(神は歓びたもう)』
の、メッセージを受け取った。
「こんな解釈で、ほぼ間違いは無いだろう。」
結論として、里田かおるは友人を残酷な死の儀式へと導いていたのである。
(彼女に迷いはなかったのだろうか? )
それは、今となっては分からない。
何処にでもいるような普通の女子中学生が、カルト教団への信仰心を基に自らの友人を殺す役目を果たしていたという事実だけが残された。
まさに恐るべき盲信、狂信である。
暗号の解読によって結論付けられた事実はもう一つある。
一連の暗号の発信源である「シクラニ」こそ、教団のアジト、又は連絡場所の一つとして考えられるということだった。
遂に尾藤は、司廉子を浚った連中の具体的な一角に取り付くことができたのである。
今、尾藤はアディを連れ、敵のアジト乗り込むべく、「シクラニ」に向かっていた。
来週月曜日から「クァーク」で働く予定のアディだが、それまでは尾藤の臨時助手を務めることを快く了承してくれていた。この二日間で尾藤の危機を二度も救うという大活躍を見せたアディだが、いよいよ山場が近付いてきた調査活動の助手を彼が務めてくれるのは本当に心強い。
(そのレストランに、司廉子が監禁されていたりするのかな? )
そんなに都合良くはいかないだろうと、尾藤は思っていた。
司廉子が監禁されている場所は、儀式の会場となるべき場所である。信者が大勢集まって秘密の儀式を行うならば、ある程度の人数を収容する能力があり、内部の状況が漏れ難く、外部から干渉を受け難い場所を選ぶはずだった。
ところが、この「シクラニ」というレストランは個人経営の小規模店であり、通りに面した雑居ビル一階のテナントである。しかも、JR高円寺駅北口商店街のド真ん中にあるので、店の周辺は夜遅くまで人通りが途切れることは無い。
儀式の会場としては、決して適当な場所とは言えない。
「それじゃ、これから「シクラニ」に行って何をするつもり? 」
アディは敵のアジトに乗り込むに当たって、尾藤の意図するところと作戦を聞いておきたかったのだろう。
ところが、尾藤からは拍子抜けする返事が返ってきた。
「取り敢えずは昼飯を食う。カレーが美味いらしいからな。」
アディは驚いて目を丸くした。
「ええっ! 教団のアジトで作っているカレーを食べるの? 尾藤さんも僕も、とっくに顔なんか割れちゃってるのに? 出された料理に毒が入ってるかもしれないよ! 」
アディが反対するのは尤もなことであるが、尾藤は意に介しない。
「大丈夫だって、真っ昼間に客を毒殺するわけないだろ。」
と、平気な顔をしている。
現在、時刻は一一時五〇分。
昼飯には丁度良い時間だった。
「シクラニ」は、グルメサイトや専門紙にも紹介されている人気店なので、平日のランチタイムならば客も多いだろう。その客の全てが教団関係者でもない限り、尾藤たちを毒殺することなどできるはずがないと言う。
「これは偵察行動なんだよ。敵のアジトの中に入ってみれば、新たな発見があるかもしれないからね。」
尾藤は尻込みするアディを急かしながら「シクラニ」に急いだ。
思ったとおり、ランチタイムの「シクラニ」はサラリーマンや主婦で混み合っていた。
尾藤たちが入店したのは正午を少し回った頃だったが、既に二〇坪ほどの店内は昼食を求める客で混み合っていて、五つあるボックス席は満席で、辛うじて入口近くの狭いカウンター席が二席空いていたので、そこに我慢して腰掛けた。
「言っただろ、この状況で毒殺なんかされっこないって。安心して飯を食おうよ。」
尾藤はランチタイムメニューを開き、そわそわと落ち着かないアディに見せた。
「ここはパキスタンカレーの店らしいな。ほら、何にするか決めろよ。」
アディはメニューもろくに見ようとせず、
「んじゃ、日替わりランチで。」
面倒臭そうに言うと周囲に目を配り続けている。
尾藤は全く平然としたものであり、
「日替わりはナスとキノコとチキンのカレーだな。俺もそれにしようかな。」
などと、全く普通の客になりきっていた。
「尾藤さんって、度胸があるのか、鈍感なのか、どっちなんだろ? 」
心配顔のアディを放っておいたまま、尾藤は注文を伝えるために店員を捕まえようとしていた。しかし、店員は皆が忙しそうにしていて、いくら呼びかけても尾藤たちの席まで来てくれない。その都度返事はしてくれるのだが手一杯という感じだった。手の空いていそうな店員が一人だけいたのだが、これは声を掛けても手を上げても横を向いたまま一向に気付いてくれない。不慣れな店員なのか、動きも緩慢である。
「ちゃんと仕事しろよな! なんなんだよ、あいつ? 」
尾藤は苛々しながら、その店員を睨みつけた。
それでも、めげずに何度も声を掛け続けているうち、漸く近くを通り掛かった女性店員を捕まえることができた。
「日替わりを二つね。」
「はい、日替わりランチをお二つですね。ランチにはコーヒーが付きますけど、食前と食後のどちらにお持ちしましょうか? 」
「ああ、コーヒーは先に持ってきてくれるかな。」
「はい、では少々お待ちください。」
女性店員は一礼して去っていったが、この短いやり取りの中で尾藤は妙な引っ掛かりを感じていた。
(彼女の声、聞き覚えがある! )
女性店員の声が、悪夢の中で尾藤に囁いていた声にそっくりだったのだ。
実は昨日に続き、今朝も尾藤は同じ悪夢で飛び起きていた。二度も同じ夢を見たので、本来は曖昧であるはずの夢のディテールが、耳元で囁いていた女性の声も含めて現実の出来事であったかのように明瞭に記憶されていた。
しかし、
(偶然? いや、気のせいだと思うけど・・・ )
夢の中に、今日初めて出会った女性が登場するはずがない。
(今回の仕事のおかげで、きっと神経質になってるんだな。)
真面目に考えて拘るべき話ではないと振り払った。
ところで、その女性店員だが、
「いやぁ、綺麗な娘だなぁ。」
尾藤が感心して、ついつい後姿を見送ってしまうほどの美人だった。
歳は二〇代前半ぐらい。彫りが深い南アジア系の顔立ちで、黒く光る大きな瞳と艶のある長い黒髪が美しく、実に印象的な女性だった。
「尾藤さん、余裕あり過ぎだって。」
敵のアジトで女に見惚れている尾藤にアディは呆れていた。
「お前は、余裕無さ過ぎなんだよ。」
と、言い返したらアディは膨れっ面をした。
「ちゃんと冷静になって、周囲の状況を観察しておくぐらいしなきゃダメなんだぞ。」
「じゃ、尾藤さんは何か見つけたっていうの? 」
この問いに、尾藤はニヤリと笑って親指を立てて見せた。
「え、何か見つけたの? 」
呑気に若い女性に見惚れていただけではなかったらしい。
「警戒ばかりしててもダメなんだぞ。ちゃんと店内を観察してさ、何でも良いから気付いたことがあったら記憶しといてくれよ。」
アディに注意した。
一応プロらしい発言だったので、アディは納得して大人しくなった。それからは、彼なりに店内の観察を始めたようである。
間もなくしてコーヒーが出てきたが、一口飲んだところで直ぐに日替わりランチも運ばれてきた。
「けっこうイケるじゃないか、このカレー。」
ほどよい辛味にコクがあって具材も癖が無くて食べやすい。これがカルト教団と無関係な店ならば掘り出し物のレストランだが、敵のアジトなのだから実に残念な出会いだと思った。
カレーに舌鼓を打っていたら、気になる会話が背後のボックスから聴こえてきた。
「ねぇ、今日はアブドル休みかい? 」
「体調が悪いって、休んでるんですよ。」
驚いた尾藤とアディは思わず食事の手を止めて顔を上げた。
振り返ってみると、サラリーマン風の常連客らしき男と男性店員が会話している。
「尾藤さん、アブドルって? 」
「シッ! 声に出すな。」
アディを押さえて、再びカレーを口に運びながらも耳だけは背後に向け、二人の会話を細大漏らさず聞き取ろうとした。
会話の内容に注目すべきことは無かった。単なる常連客と店員の雑談だったのだが、「アブドル」とか「ハサン」とか、チラホラと聴こえてきたことにより、
(あのアラブ人、この店の店員だったらしいな。)
「シクラニ」とカルト教団とのは繋がりは決定的になった。
体調が悪いなどと嘘を吐いているが、現在のアブドルは杉並警察署の留置場(もしくは警察病院)にいるはずである。
この情報は、既に教団関係者ならば掴んでいるだろう。
「ライード! 」
突然、奥の厨房から顔を出した男が雑談中の男性店員に向かって怒鳴った。
「はーい、すみません。」
ライードと呼ばれた男性店員は慌てて会話を止め、小走りで仕事に戻った。
「忙しいんだからなっ! 」
怒鳴っている男は店長か経営者と思われる。
ホールスタッフは全員南アジア系や東南アジア系の外国人ばかりだが、この男は日本人のようである。
「尾藤さん! 僕、今大事なことに気付いたかもしれない。」
アディが囁くように言った。
「俺も気付いたことがあるぞ。たぶん同じことじゃないかな? 」
ライードが怒鳴られた瞬間、ホールスタッフ全員に緊張感が走っていた。
その緊張感は一瞬で解けてしまったので、素人ならば気付きようが無い微妙な変化だったが、さすがにプロの調査員である尾藤は見逃さなかった。アディが同じことに気付いていたとしたら、その観察力は助手として有望だと思う。
「だが、その話は後でな。まずは急いで飯食っちゃえ。」
そのまま二人は黙々と食事を続けた。
「ありがとうございます。日替わりランチ二つで一八〇〇円になります。」
レジに立っていたのは、先ほどの女性店員だった。
接客時の愛想笑いとはいえ、笑顔が素晴らしく華やかである。
(この笑顔でリピートしようって客も多くなるんだろうね。)
そんなことを考えながら、尾藤は財布から一〇〇〇円札を二枚を取り出してカルトンの上に置いた。
女性店員は二〇〇〇円を受け取ってレジの上に置き、直ぐに引き出しから小銭を取り出すと、三つ折りになった一枚のチラシを添え、
「二〇〇円のお返しになります。それと、こちら割引券になりますので次回いらしたときにお使い下さい。」
と、言って、レシートと重ねて差し出した。
「え、あ、はい。」
カルトンが置いてあるにも関わらず、それらを纏めて直接手渡ししようとするので、少し戸惑ってしまった。
(でも、顔だけじゃなく手も綺麗だなぁ。指細いし。)
触れるのも申し訳ないので尾藤は遠慮気味に右手を差し出したのだが、その手を彼女は両手で挟み込むようにしてレシートと釣銭を渡してきた。
美人に手を握られたなら男は皆嬉しいと思う。
尾藤も敵のアジトにいることを忘れて胸がときめきそうになったのだが・・・
(あれ、何かある? )
手の中に異物の感触があった。
チラシの下にトゲトゲした小さな枝のようなモノが隠れているらしい。
危険物ではなさそうである。
女性店員は尾藤の指を軽く折り曲げて、その異物を落とさないよう、誰にも見られないようにして欲しいということを無言で伝えてきたので、思わず顔を上げて「これはどういうことか? 」と問いたかったのだが、それは無理なようだった。
手を放してからの彼女は尾藤と目を合わせようともしない。
そして、何事も無かったかのように平然とした口調で、
「ありがとうございました。」
と、尾藤たちを送り出してしまった。
取り敢えずは、渡されたモノが何なのか確認しなければならない。
決して無意味なモノではないはずだ。そうでなければ、周囲の目を遮るような、意味ありげな渡し方は理解に苦しむ。
それに、渡された場所がカルト教団のアジトと思われる「シクラニ」だけに、それが重要な代物と考えてほぼ間違いなさそうである。
尾藤は右手に謎の物体を握り締めたまま上着のポケットに入れて、「シクラニ」を離れると、それほど遠くない場所にある喫茶店を目指した。そこで落ち着いてから、手の中にある物体を取り出して確認し、アディとの情報交換と作戦会議をするつもりだった。
「まず、アディが気付いたことを言ってみな。」
喫茶店の一番奥にあるボックス席に腰を落ち着けてからも、尾藤の手は未だポケットの中にあった。アディは尾藤が女性店員から何かを受け取ったことに気付いてはいないし、尾藤も話していない。
いきなり大物を披露してしまっては、他に店内で気付いた細かな事実があったとしても記憶が薄れてしまいそうなので後回しにしようと思ったのだ。
「ライードさんって人を怒鳴りつけた男の人、たぶん店長さんなのかな。怒鳴りながら僕らの方に探るみたいな視線を向けてたよね。」
「ほぉ、一瞬だったのに良く気付いたな。」
それは尾藤も察知していたことだった。
僅か数秒の間に、男の視線が泳ぐようにしながら尾藤たちを何度か捉えていたのだ。
「実は店に入ってから誰かの視線を感じて気になってたんだけど、あの時に店長さんの視線だったってのが分かった。その店長さんが怒鳴った時、ライードさん以外に男女二人づつの店員さんがいたけど、女性一人は驚いて店長さんを振り返ってた。もう一人は尾藤さんが綺麗だって言ってた娘だけど慌てて厨房に駆け込んでった。そして、男性二人は慌てながらも立ち止まってハッキリと僕らに視線を向けてたよね。ライードさんが怒鳴られたのは僕らに全然関係ことの無いはずなのに。」
一瞬の出来事を、そこまで観察できていたならば素人には十分である。
「よし、それをアディはどう推理する? 」
「店長さんが怒鳴ってた理由を理解したのはその男性二人だったってこと。店長さんは僕らにアブドル・ハサンの名前を聞かれたくないんだって直ぐに分かったんだよ。」
「つまり? 」
「あの店、全員が教団関係者ってわけじゃないかもしれないね。もし、全員が関係者だとしても、店長さんと二人の男性店員は別格って感じかな。アブドルを事務所に送り込む段取りを付けたのは彼らだろうし、暗号チラシを作っていたのも彼らでしょう。それなら彼らは教団からの命令を、この辺にいる信者の兵隊たちに伝えて実行させる立場にある人たちってことになるよね。つまり、あの店長さんは教団の幹部クラスなんだよ。それで、二人の男性店員は直属の部下。他の店員さんが信者かどうかは分からないけど、ライードさんなんて僕らの直ぐ傍でアブドルの話をしてたぐらいだし、店長さんたちと同じ情報を共有していなかったのは間違いないね。彼らが信者だったとしても大した立場じゃないと思うな。」
尾藤は良くできましたと言ってアディを褒めてから、
「俺はプロだから、もう一つ気付いたんだよな。」
少し自慢げに言った。
「アディが言うところの店長直属の部下のうち一人な、どんなに呼んでもうちらの席には全然近付いてこなかった奴がいただろ。そいつの左米神の上、前髪で隠してたけど髪の生え際に怪我してたのさ。」
「あっ、それって一昨日の夜の? 」
アディが、指パチンコを放つポーズをして見せた。
「たぶん、ベイジョじゃなくて港女子学園の裏でアディのパチンコを食らって逃げた奴の一人だよ。」
アディが、うんうんと頷いた。
「以上により、あの店がカルト教団の荒事に携わる兵隊さんたちにとって、指揮命令系統の中継点になっていることは間違いないとの結論に達しました。」
「やったじゃない、尾藤さん! 」
アディが音を立てずに小さく拍手をした。
「そこで、アディにお願いがある。」
「何かな? 」
「儀式には、店長も参加するだろう。」
その一言で、直ぐにアディが心得たという顔で頷いた。
「明日まで、僕は「シクラニ」を見張ってれば良いんだね? 」
「店よりも店長だ。」
儀式は一一月二四日の二時三七分。
そして、「シクラニ」の営業時間は二一時まで。
「それじゃ、二三日の閉店後、店長が何処へ行くかを調べるんだね。」
「閉店後とは限らないけどな。」
店長が儀式に向かうとしたら閉店後かもしれないが、彼が幹部だとしたら当日は店を他のスタッフに任せて早めの会場入りをするかもしれない。それ以前に、幹部ならば既に当日の会場を知っている可能性もあるわけで、準備やら何やらで前日にも出入りするかもしれないので、上手くいけば儀式の日を待たずに司廉子を助け出せるかもしれない。
「それじゃ、僕は店長を見張ってて、出掛けたならば後をつければ良いんだね。それで、会場らしき場所に入ったら尾藤さんに連絡する。了解ですっ! 」
アディは張り切って敬礼のポーズを取った。
「さて、作戦が決まったところで、次はこれの話をしよう。」
ここで、漸く尾藤はポケットから「シクラニ」の女性店員から渡された物体をテーブルに置き、アディに見せた。
「また、チラシ? 」
「チラシも調べなきゃならないけど、気になるのはこっち。」
それは一〇センチほどの長さの小さな木の枝だった。
先端が二つに分かれ、それぞれに黄色みを帯びた細長い葉が一対づつ付いている。
「どうしたのこれ? 」
「レジで美人の店員に渡されたんだよ。」
アディがヤレヤレと溜息を吐いた。
「まさか、プレゼントじゃないよね? 」
「そんなわけないだろ。仮にも敵のアジトで渡されたんだぞ。何か意味有り気だと思わないか? 」
「それは、そうだよね。」
アディは頷きながらも、木の枝よりもチラシの方が気になるようで、手に取って開き、食い入るように隅々まで目を通した。
「割引の有効期間は昨日から明日までの三日間、相変わらず短いね。あ、ほら暗号見付けた。ニシャーダさんの表と書くモノある? 」
尾藤が上着の内ポケットからニシャーダ氏作成の暗号解読表とシャープペンシルを取り出して渡すと、アディは直ぐに解読作業を始めた。
「もう、すっかり手慣れたもんだな。」
アディは、昨夜から尾藤を手伝っているうちに暗号解読の作業が気に入ってしまったようである。
「できたよ。」
と、一分も掛らずに作業を終えてしまった。
「どれどれ。」
尾藤は手を伸ばしてチラシを受け取った。
「new moon」
それだけである。他には何も書かれていない。
「新月だってか? 」
「そうだね。儀式直前のチラシだから、皆に忘れるなって言ってんじゃない? 」
「ちぇっ、直前のチラシなら会場の場所ぐらい載せとけってんだ。」
「そうだよね。それにしても信者の人たちって、どうやって直前に会場の場所を受け取るんだろうか? 」
「うーん、わからん。」
何らかの連絡網や合図があるはずなので、できるものなら入手したい。
「で、その枝は? 」
チラシの話が終わったので、アディが枝に話を戻した。
「何か重要なヒントのようなモノじゃないかな? 」
「何のヒントかな? 」
「それが分かったら苦労しないよ。」
またまた、新しい謎解きを始めなければならなくなったようだ。
[一六]
事務所の固定電話が鳴り続けている。
恵子は今日から大事を取って休ませたので事務所には尾藤しかいない。
「うっ、うわーっ! 」
尾藤が社長室兼応接室のソファから転がり落ちるようにして飛び起きた。
アディと別れてから、ドアの取り換え工事の確認もあって一旦事務所に戻ってきた尾藤だったが、昨日からの疲れもあって少し仮眠をとろうと横になっていた。
(また、あの夢を見てしまった。)
実は今朝方の短い睡眠の中でも同じ夢を見てしまったので、これで三度目である。
内容は三度とも全く同じだが、二度目からは尾藤の意識と記憶がハッキリとしていたので、夢の中で夢を見ていることを認識できていた。それなのに、夢だとわかっているにも関わらず、恐ろしくなって悲鳴を上げて飛び起きてしまう。
そう言えば、火曜の朝や水曜日にも悪夢で飛び起きていたような気がする。
この時の夢の内容は憶えていないが、もしかしたら同じ夢だったかもしれない。
「くそっ、悪夢に憑りつかれたみたいだ。」
尾藤は電話の呼び出し音を無視して、汗だらけの顔を洗おうと洗面所に向かった。
水道の蛇口を捻り、冷たい水を手ですくって何度も顔に叩きつける。
「ふぃーっ! 」
一息ついて、タオルで顔を拭った。
(ここ二、三日はハードだったからなぁ。)
鏡を見ると、目の下に隈ができている。
(この仕事が終わったら、休んで爆睡してやる。)
そう内心でボヤキながら、指で目の下の隈を労わるように摩っていた。
(なんだ、あれ? )
鏡越しに、尾藤は自分の背後に目を移した。
(どうして、あそこだけ暗いんだ? )
尾藤の背後には白っぽい大理石模様の壁が見えるのだが、その下半分が異様に暗い。
照明は真上にあるから、その位置に自分の影が落ちたりはしない。
(壁には照明が当たってるはずだぞ? 鏡の汚れか? )
じっと、鏡を凝視し、その不自然さの理由を探そうと思った。
後ろを振り返って確かめてみれば良いと思うのだが、そうしたくなかった。
(振り返ってはいけない! )
心の中で警告が聞こえていた。
得体の知れない不安が徐々に押し寄せて来ているのが分かった。
(まさか、あの影は動いている? )
見詰めている間に、じわじわとインクが繊維に染み込むように広がっている。
(いや、ただ広がっているわけじゃない! )
影は形を整えようとしているのだ。
(そんな、馬鹿な! )
尾藤の目は鏡に釘付けになったまま動かなくなった。
瞬きすることもできずに身体ごと硬直してしまっていた。
そのうち、影は明らかに具体的な形をとり、尾藤の背後に存在していた。
(人間? 違う、これは人じゃない! )
人の形に似ているが、何処かが、何かが違う。
大まかなプロポーションは人間だが、其処彼処に歪さを感じる形状の狂いがある。
感想を言うならば、不自然で、不快に見え、汚らしく、悪しき形状。
(・・・バケモノ! )
身の危険を感じた。
硬直した身体を動かすことはできなかったが、僅かに自由になる喉と舌を使って、必死に叫んで誰かに助けを求めようとした。
だが、上手く声を出すことができない。
(助けて! 助けて! 助けて! )
必死に足掻く尾藤をあざ笑うかのように、影は膨らんでいく。
そして、背後の壁を埋め尽くすほどに広がりきった影が、徐々に尾藤を包み込むように覆い被さってきた。
「グギャァーッ! 」
遂に喉が潰れんばかりの悲鳴が発せられた。
その悲鳴が、尾藤を再び覚醒させた。
(ああ、夢・・・夢だった! )
尾藤はソファに仰向けに寝転がっている自分に気付いた。
(これは現実? )
混濁した意識を正常に取り戻すべく周囲の様子に目を見張り、現実の感触を確かめ、意識を正常に戻すための自問自答を幾つか試みた。
(ここは何処? 今は何時? 何時からここにいる? )
その結果、
(これは現実、今度は間違いなく夢から覚めたんだ。)
尾藤はソファから身を起こし、手足を伸ばしてみた。
(自由に動く。)
ホッと息を吐いた。
寝る前にソファの背に掛けていた上着が床に落ちていたので、これを拾い上げるついでに内ポケットに入っていたスティックキャンディを取り出して口に含んだ。
忽ち強烈な甘さが口の中一杯に広がり、寝起きの頭が覚醒していく。
そして、完全に目覚めた尾藤の耳に、固定電話の着信音が聞こえてきた。
(そうか、夢の中から、ずっと鳴ってたんだっけ。)
立ち上がって社長室兼応接室を出て、恵子の机上に置かれた電話のヘッドセットを付けてから通話ボタンを押した。
「尾藤さん! 電話取るの遅いよ! ずっと鳴らしっぱなしだったのよ。」
Kの声だった。
「ごめん、ちょっと寝てた。」
尾藤は素直に謝った。
「もう、呑気に寝てる場合じゃないのよ。新しい情報よ! 」
Kは興奮気味に言った。
尾藤は調査の進捗状況と知り得た情報を小まめにKへ送り続けていたが、Kも情報屋としてキチンと仕事をしてくれているようだ。
「これは知り合いの情報だけど、どんな知り合いかってのはナイショね。尾藤さん、シロシベ・クベンシスとかシロシベ・メキシカーナって知ってる? 」
「何だい、それ? 」
「じゃ、シロシンとかシロシビンは知ってる? 」
「それって確か幻覚剤だよね。」
「ハラタケ目のキノコに含まれるインドールアルカロイドの一種で、強い幻覚性作用をもたらす成分のことよ。シロシベ・クベンシスやシロシベ・メキシカーナは、その成分を含むキノコ。つまり、マジックマッシュルームのことね。」
尾藤に薬学的な知識は無いが、マジックマッシュルームという名称ならば知っている。幻覚作用のあるシロシンおよびシロシビンを含有し、麻薬原科植物として規制対象になっているキノコの類である。
「そのマジックマッシュルームの違法栽培業者にね、ここ一年の間に月一で大量の発注をかけているトンデモナイ奴がいるのよ。その納品先を私がバッチリ調べてメールしといたから見ておいてね! 」
Kが興奮しているので、凄い情報らしいのだが、尾藤にはピンと来るものが無い。
「マジックマッシュルームを月一で? それは俺の仕事に何か関係があるのか? 」
尾藤が驚きもせず、反応に乏しいことに不満を感じたのか、Kの声が一転して不機嫌になった。
「もぉーっ! 尾藤さんは勉強不足! マジックマッシュルームが、どんな時に使われてきたかキチンと調べてごらんなさい。これは歴史の勉強よ! キチンと調べたら絶対にピンと来るはずよ! 」
いきなり、歴史の勉強をしろと言われても困る。
「ちょっと、どういうことか教えてくれよ。」
詳しい説明を求めたのだが、
「そこまで甘えなさんな! 」
Kに突き放された。
「インターネットで調べたら幾らでも情報が手に入るんだから、自分で頑張んなさい! それじゃ、健闘を祈るわ。」
Kは言うべきことを言い終わると、一方的に通話を切った。
(まったく、不親切な奴だな。時間が無いってのに・・・ )
取り敢えず尾藤はKが送ったというメールをチェックしようとしたが、自分のワーキングデスクに戻るのが面倒だったので、近場にあった恵子のデスクトップPCの電源を入れ、起動するまでの間に洗面所に行き、寝汗でベトベトする顔を洗った。
顔を洗っている最中、背後が気になって何度も鏡を見直したが、夢で見た影が現実に現れることは無かった。
『マジックマッシュルーム』
体調や精神状態によって様々だが、このキノコを食した者は三〇分から一時間ほどで幻覚症状が起こり始め、多くの場合、静止しているはずの床や壁が波打ち始め、瞳孔が広がり周囲の色彩が鮮やかに見え、明るく輝き始めるなどの幻覚を見る。感情のコントロールが難しくなり、偏執に捕らわれる。多幸感を伴うこともあるが、ネガティブなパニック症状に陥ることもある。そして、肉体的には、寒気や麻痺の症状を起こし、吐き気や呼吸困難などが続き、時には死に至ることもある。
メソアメリカ先住民にとってマジックマッシュルームは、呪術師やシャーマンが神託を得るために食べる神聖な食物であり、病気の治療などに用いる薬物でもあった。一六世紀以前に栄えたアステカ王国では、ナワトル語で「神の肉」を意味する「テオナナカトル」と呼ばれ、有名な生贄の儀式の際にも用いられていた。儀式の際、犠牲者はマジックマッシュルームを与えられ、その幻覚作用の中で陶然とした状態のまま、手脚を抑え付けられ、黒曜石のナイフで心臓を抉り出されたという。
スペインによる征服後、キリスト教が布教されるに伴い、生贄の儀式とともにマジックマッシュルームの使用は禁じられ、弾圧されたが、人里離れた地域では現在でも用いられている。日本国内では観賞用として販売されていた時期もあったが、二〇〇二年からは「麻薬原料植物」に指定され、所持、売買、栽培は全て違法とされている。
この内容を一読し、Kの言わんとしていたことが分かった。
Kのメールによると、違法栽培業者から毎月新月の日の前日に数キロ単位のマジックマッシュルームが納品されている場所があり、該当する杉並区内にある九つの住所が記載されていた。
Kはメールで、これらの住所の何れかがカルト教団の儀式の場であると断言していた。
「月によって納品場所が変わるから今月の住所を特定はできないけど、この中の何処かであることは間違いないわ。あとは尾藤さんが頑張って調べることよ! しっかりね! Kより 」
と、付記されていた。
(アステカ式の生贄の儀式か行われているってことだよな。)
尾藤の目の前のPC画面上には、アステカの生贄の儀式を挿絵付で解説したページ、幻覚キノコの彫刻が施されているアステカの神像やキノコの形をした偶像の写真が表示されている。
(キリスト教やイスラム教のチャンポンってだけじゃないわけだ・・・ )
考えてみれば、野蛮な生贄の儀式を行おうとするぐらいだから原始宗教までもが絡んでくるのは当然かもしれない。
(大昔ならともかく、今の世の中で、この儀式を本気で実行しているとしたら完全な気狂い集団だな。)
インターネットで急遽見つけた資料を読み込んだだけでも、その残酷さと野蛮さ、悍ましさに身震いするほどだった。
(それにしても、儀式が行われる場所の候補が九つもあるってのはキツイな。)
この九ヶ所は杉並区内に広範囲に散らばっている。
当日の朝に違法な荷物が到着すると言われても、それを一斉に確認するのは難しい。
おそらく、荷物の到着以前には、そこが儀式の場であると確認できる外観上の手掛かりは見つけられないだろう。
儀式の犯罪性の高さを考えれば、徹底した隠蔽工作がなされているだろう。
(では、ヤマをはるべきか? )
ヤマが外れてしまった場合、慌てて他の八ヶ所の何れかに駆け付けていては手遅れになってしまう。
(人手が足りない。木村に人手を借りられたらな。)
これは、返事を聞くまでも無い。
儀式の場が特定できたなら、警察は直ぐに駆けつけてくれる。だが、不確かな民間の情報だけで警察の人員を九ヶ所に長時間張り付けるなどできるわけがない。
懇願すれば木村一人ぐらいの手は借りられるかもしれないが、警察が大挙して登場してくれるのは儀式の現場が確定してからである。
(さて、どうしたものか? )
最善策を見付けなければならない。
アディと二人で九ヶ所を巡回し続けることは無意味である。
そんなことをしたら、却って納品の瞬間を見落としてしまいかねない。
(人手不足の打開策は無いし、やはりリスク承知でヤマを張るしかないのか? )
現場情報を仕入れておかなければならないので、尾藤はPCに向かい3Dストリートビューを開くと、九つの住所を一つ一つ入力し、そのロケーションの確認を始めた。
二一世紀初頭から始まったストリートビューサービスは、近年に於いてハードウェアの発達に伴い世界中の人口衛星と街頭監視カメラによる高解像度撮影データをリンクして構成された立体的な空間情報サービスにまで発展した。
その名にあるストリートを超えて屋外でさえあれば、あらゆる場所に立ち入った状況が確認できる。ビルの屋上や屋根の上を見下ろすことも可能だし、人里離れた山奥や陸地から遥か離れた海上への移動も可能である。画質も非常に優れており、街頭に貼られたポスターの細かな文字や、街路樹に付いた蝉の姿まで確認できた。
リアルタイムの情報ではないが、現地に足を運ばなくともロケーションの詳細な取材が可能な優れたシステムである。
ストリートビューによると、九つの住所には、共通して廃ビル、もしくは現在使用者がいない空きビルがある。
老朽化し放置された商業施設ビルやオフィスビル、閉店したパチンコ店、倒産した予備校などであり、どの建物も外壁に著しい痛みや汚れが見られ、閉鎖されてから随分長い年月を経ているらしいということが分かった。
近頃の都内では珍しくも無い風景である。
多くの場合、こうした建物はスコッターの住みかとなるのだが、
(秘密の儀式を行うにはお誂え向きだな。)
廃ビルと見せかけて、密かに教団が管理しているのかもしれない。
(ストリートビューから何か気付くことは無いか? )
建物の写真に接近し、視点を変え、上下左右全てを見渡してみた。
(外観だけじゃ何も分からないよなぁ。)
諦めかけた時、
(これは何? )
それは閉鎖された五階建てのオフィスビルの写真だった。
このビル、正面入り口はガラス製の観音開きのドア、その取っ手には太いチェーンが巻きつけてあり、外部からの侵入者を物理的に防いでいるのだが、
(正面入り口の庇の上に何か乗ってる? )
一メートルほど突き出したコンクリート製の庇の上に、ビーチボールほどの大きさの丸く茶色い塊りが乗っていた。
ビューの視点を上げ、庇を見下ろしながらアップにしてみた。
(ゴミ袋? いや、花束か? )
最初は錆びた針金が丸まっているのかと思ったが、良く見ると植物のようである。
丸くアレンジされたドライフラワーに見えるが、
(ドライフラワーにしては全然綺麗じゃない。回転草に似ているけど違う。)
良く見ると、一本の太い枝から沢山の細かな枝が放射状に伸びているのがわかる。
その細かな枝の先端には対になった細長い葉が付いている。
「ああっ! 」
尾藤は、その枝の形状に見覚えがあった。
「シクラニ」で女性店員から渡された小さな枝である。
その枝は喫茶店を出る時に再び上着のポケットに入れ、そのままになっていた。
直ぐに取り出してストリートビューの画像と見比べてみると、
(同じ枝! )
そして、何の枝なのかもインターネット情報から直ぐに分かった。
(これは、ヤドリギだ。)
ヤドリギは大きな樹木の枝の上で生育する寄生植物であり、都内でも街路樹などに付いているのを良く見かける。
(でも、何でビルの庇の上なんかに? )
庇の上にヤドリギが育つわけがないし、誰かの悪戯だろうか?
だが、庇の上にヤドリギを乗せる悪戯というのも妙である。
尾藤は、暫くの間ヤドリギを凝視していたが、
「ああーっ! わかった! わかったぞ! 」
歓喜のあまり、思わず大きな声が出てしまった。
「タンポポじゃなかったんだ! ヤドリギだったんだよ! 」
里田かおるのバックチャームの意匠を思い出したのである。
丸く放射状に伸びた複数の線の形状は、タンポポよりもヤドリギに似ている。
「ヤドリギは教団のシンボル、そして特定の情報を伝えるサインなんじゃないか? 」
この推測が正しければ、かなりダイレクトな手掛かりを入手できたかもしれない。
尾藤は確信を得るため、再びストリートビューに目を移した。
(ストリートビューが撮影されたのは今年の六月一四日、新月の日だ。で、撮影された時間帯は影の伸び方を見る限りでは早朝。)
ちなみに、六月一四日の新月の時間は二〇時一七分である。
(もしかしたら、ヤドリギは儀式の会場を信者に知らせるサインなんじゃないか? )
そうだとすれば、二四日の新月は二時三七分なので、今日から明日に掛けて会場となる場所にはヤドリギが据えられるだろう。
(かなり確信に近付いてきたけど、ヤドリギと儀式って何か古い言い伝えがあったんじゃなかったっけ? )
小説や映画などで得た雑学の中にヤドリギに関する話があったような気がするが、遠い記憶を掘り起こすよりもインターネットで調べた方が早い。
(あった、これだよ。)
それは宗教というよりもファンタジーのイメージが強い情報だった。
キリスト教の布教以前のイギリスで、ケルト人社会における祭司ドルイドたちがオークの木に付いたヤドリギの下で神聖な儀式を取り行っていたという昔話である。ドルイドはヤドリギには特別な力があると信じていたらしい。
尾藤は子供の頃に遊んだ中世の騎士やドラゴンの登場するRPGを思い出した。
(実際のドルイドは生贄の儀式も行ったっていうし、これも宗教なんだよな。)
カルト教団がヤドリギをサインに使っているとしたら、それはドルイドの故事から引用したものなのだろう。
キリスト教、イスラム教、アステカの儀式、そしてドルイド。
(見境無いというか、こいつら何でもありだな。)
信者たちの多彩な国籍による影響なのか、里田かおるのような弱年齢層の信者に受けるようファンタジーゲームなどから多様な解釈を持ち込んだのか?
このまま調査が進めば、世界中の宗教やフィクションが混淆するカルト宗教の全貌が見えてくるかもしれない。
(それにしても「シクラニ」の女性店員、何故俺にヤドリギの枝を渡したんだ? )
彼女が教団関係者だったとしたら、敵対人物である尾藤にヒントを与えるようなマネをするだろうか?
気になることではあるが、今はそこまで考えを広げる余裕はない。
儀式の会場を特定することが最優先である。
(よしっ、まずは出掛ける! )
尾藤は上着を取って立ち上がった。
九ヶ所の建物を全てを回ってみて、現時点でヤドリギのサインが出ているかどうかを確認するつもりだった。
時刻は一七時半。
現時点でサインが出ていなくとも構わない。
時間を変え、根気強く何度でも回るつもりだった。
[一七]
一一月二三日、一五時三〇分。
司廉子に残された時間は一二時間余り。
JR荻窪駅の近くにある七階建て複合型商業施設ビルの廃墟、そのシャッターの降りた正面入り口へと繋がるピロティの端、壊れかけたプラントボックスの空っぽで土が剥き出しになった植え込みの中に「ヤドリギ」は置かれていた。
これを発見するまでには、Kに教えられた九つの住所を二巡させられた。
一人で携わる作業としてはかなり厳しかったが、アディを「シクラニ」店長の見張りに付けたので、どうしようもなかった。
もちろん、徹夜になった。
三巡目に入ったのは今日の正午少し前。
それから三カ所目で、漸く「ヤドリギ」を見付けることができた。
ほぼ丸一日を儀式の会場探しに費やしてしまったわけだが、これが見当はずれの無駄足に終わっていたら致命的なミスになっていたので「ヤドリギ」を発見した時は心の底から安堵した。
念のため、他所にも目晦ましのため「ヤドリギ」が置かれているようなことがあったら困るので、三巡目の残り六カ所も一応回ってみたが、置かれていたのはこの廃墟ビルだけだった。
(さて、中に入ってみるべきだな。)
幸い、廃墟ビル周辺の人通りは多くないし、自動警備システムが設置されているわけでもないようだ。
尾藤は正面入り口の前に立ち、閉じているシャッターの取っ手に両手を掛けて持ち上げてみたが、ガシガシと金属が軋み合う音が響くだけで、施錠されているシャッターは全く開きそうになかった。
(他に侵入口は無いのか? )
側面に回ってみると、ピロティから直接ビルの二階フロアへ入ることのできるコンクリート製の屋外らせん階段があった。
階段の幅は三メートル程、入口はロープで固定された三台の工事用バリケードと立ち入り禁止の注意書きによって塞がれていたが、これらを跨いで乗り越えるのは簡単だった。
しかし、バリケードを乗り越えて登ってはみたものの、かつては飲食店街だったらしい二階フロアの入り口は、白地に黒ペンキで「味の名店街」と書かれたシャッターによって閉ざされていた。
(こんなシャッターのロックぐらいピッキングするのは簡単だけど・・・ )
強引に侵入した形跡を残せば、敵に余計な警戒心を起こさせてしまう。
現在は隠密行動中であり、未だ強行突入すべき時間ではないので控えることにした。
それでも一応鍵穴の形ぐらいは確かめておかなければと、シャッターの前にしゃがんでみたのだが、
(おっ、証拠発見! )
埃や自動車の排気ガスで全面が薄黒く汚れているシャッターなのに、鍵穴の周辺やプラスチック製の取っ手の窪みの中だけが妙に白く汚れが少なかったのだ。
試しに指先で取っ手の窪みを拭ってみると埃のザラつきが殆ど感じられない。続いてシャッター上部に目を移すと付着していた蜘蛛の巣を取り払った跡まである。
これらは、過去数時間以内にシャッターを開閉した証拠である。
(ここから例のキノコが納品されたのかもな。)
このらせん階段、建物の側面にあるため通りからは非常に見えにくい。
コンクリート製の手摺りは、尾藤ほどの身長の大人でも屈めば頭まで隠れてしまうほどの高さがある。
(怪しい連中や荷物の出入りには最適だ。)
だが、今は施錠されている。
(中に人はいるのかな? 儀式の準備は始まってるんだろうか? )
無人ではないだろう。
今夜、このビルに大勢の信者が集まるならば、何らかの会場整備を初めていても不思議は無いし、アブドルの言っていたことが本当ならば、ここは司廉子が監禁されている場所でもある。
当然、その見張り役として常時数名が詰めているだろう。
(気付かれずに侵入することができるだろうか? )
尾藤は階段を降り、今度はビルの側面の隙間を通り抜けて裏手に回ってみた。
ここは商業施設ビルなのだから、従業員の通用口や商品の搬入口、非常階段など、目立たずに出入りできる場所は幾らでもあるはずだった。
問題は、それら全てが施錠されているだろうということである。
(結局はピッキングするしかないかも。)
しかし、建物を一周してみてわかった。
通用口や搬入口は裏通りに面しており、この時間は若干だが通行人もいるので目立ずに作業するのは難しい。
(侵入できるとすれば、あそこからだ。)
尾藤が目を付けたのは、通用口や搬入口と同様に裏通りに面した壁面に設置されている開放型の非常階段である。
最上階である七階の非常口まで上れば、下の階の踊り場や手摺りが重なって通行人からは見え難く、そこは周囲の建物よりも高い位置にあるので、多少ピッキングに手間取っても注目されることは無い。
それに、教団の連中が、わざわざ最上階の非常口を使って出入りすることなど考えられないので、うっかり鍵を傷つけてしまったとしても直ぐには気付かれないだろう。
(そうと決まれば、早速行動! )
通行人が途切れるのを見計らって、非常階段入口の鉄柵を乗り越え最上階を目指した。
雨曝しのまま長年放置されていた非常階段は全体が赤錆びだらけで、塗料も殆ど剥がれ落ちてボロボロの状態だった。強度的な問題については不明だが、上るのに不自由は無いので気にしないことにした。
ところが、尾藤が上の階へと移動するにつれ、金属の接合部がギリギリと煩い音を立て始め、階段全体がブルブルと振動を始めたので焦った。
(これじゃ、中に人がいれば気付かれてしまうじゃないか。)
五階と六階の間の踊り場まで上ったところで一旦足を止め、振動が収まるのを待った。
(静かに登らなきゃダメだな。)
振動が収まったのを確認してから、今度は、できるだけ慎重に一段一段ゆっくりと登り始めた。これなら完全に振動を抑えることはできなくとも煩くはならない。
そのまま六階を過ぎようとした時、
(ん? )
尾藤は非常階段の振動音に違和感を感じて立ち止まった。
ゆっくり静かに上っていたので、尾藤が止まれば振動も直ぐに収まるのだが、
(なんだろう? 足音が重複して聞こえたような気がするんだけど? )
自分の足音以外に、もう一つの足音と振動が重なって聞こえたような気がしたのだ。
(誰かに後をつけられてる? )
階下を確認しようと、六階の手摺りから身を乗り出してみた。
(良く見えないな・・・ )
踊り場が重なっているので、直下の五階以外は殆ど確認しようもないが、見える範囲に人影は無い。
さらに身を乗り出して確認してみたかったのだが、
(これ以上体重を掛け過ぎると、手摺りが壊れて落っこちそうだ。)
階段の強度に問題は無くても手摺りは所々腐っており、途中の階では溶接部が外れたり穴が開いている箇所もあった。
そこで、試しに次の踊り場まで上ってみることにした。
再び振動が始まり、尾藤が立ち止まると少し間を置いて止まった。
そのまま暫く耳を澄ましていたが、
(気のせいか? )
遅れて付いてくる足音も振動も無かった。
(尾行している奴がいたとしても、ここじゃ迎え撃つのに具合が悪いな。)
普通に上っているだけで振動や軋みが煩いのに、万が一格闘にでもなったら近所に響き渡る大騒ぎになってしまうし、手摺りの脆さを考えれば危険に過ぎる。
(こんなとこでグズグズしてるよりも、とっとと中に入ってしまう方が良いや。)
尾藤は七階に上り、非常口のドアの前に屈みこんで作業を始めた。
この商業施設ビルは築五〇年から六〇年以上も経過していると思われるが、その間に非常口の鍵の更新はされていなかったようだ。ピッキング対策の甘い旧式の施錠など、尾藤の前では何の障害にもならない。
あっという間に解錠して、ドアノブに手を掛けたのだが、
(ううっ、硬いなぁ、これは! )
滅多には使われない非常口のようだが、そのためにドアがフレームに固着してしまっているらしく、蝶番も錆びついていて簡単には開いてくれない。
(力任せに開けたら、大きな音を立ててしまいそうだし・・・ )
尾藤はドアノブを強く握りしめ、大きな音を立てないように注意しつつ、ドアを慎重に上下に揺すりながら少しづつ手前に引いた。
(こんなドアに鍵なんていらないよっ! )
ドアを開くだけなのに、ピッキングよりも手古摺っている。
それでも何とかドアを引き抜くことに成功した尾藤は、
「失礼します。」
冗談ぽく呟いてから七階のフロアに足を踏み入れた。
「・・・くーっ! 」
カビと埃が混じり合った悪臭を鼻を突いた。
我慢して目を凝らし辺りを見回してみると、そこは催事等に使われる広々としたフリースペースだった。フロア内の各部屋を仕切る壁は取り払われており、所々にコンクリート製の柱が残っている以外は全体が一つの空間として見通すことができる。非常口から見て左右の壁際には什器や椅子、テーブルなどが集められており、それらは二度と使用されることが無いにも関わらず比較的整然と積み重ねられていた。
(取り敢えず、ここに人のいる気配は無い。)
尾藤は建物の外観に侵入の形跡を見せないようにとドアを閉めた。
(真っ暗だ・・・ )
ここは廃ビルなのだから、基本的にガラスの窓は全て危険防止のため板で塞がれているに決まっている。
尾藤はマグライトを取り出し、その灯りを頼りにフロア中央に見えたエスカレーターの乗り口を目指した。
歩を進める度、剥がれかけた床のピータイルがパリパリと音を立て、降り積もったカビや埃が舞い上がってマグライトの光の中でユラユラと揺れた。
これを吸い込まないように片袖で鼻と口元を覆い、足元に危険物が転がっていないかに気を付けながら進んだ。
エスカレーターに辿り着いてから一旦立ち止まり、下階の様子を伺おうとした時、
(おや、音がする? )
エスカレーターの吹き抜けを通してブーンという微かなモーター音が聴こえてきた。
どうやら空調機器が立てる音のようであり、音源は遥か下の階にあるらしい。
(このビル、電源は生きてるようだな。)
空調機器が動いているならば人がいる可能性が高い。
先ほど、非常階段で大きな音を立ててしまっているので、尾藤の侵入は気付かれてしまったかもしれない。
しかし、誰かが七階に駆け上がってくるような足音は無いし、ビル内にはモーター音以外には何も聞こえない。
(ここで立ち止まっていても、どうにもならないし。)
尾藤は意を決し、光を細く絞ったマグライトで進行方向を照らしながら足元を探るようにしてエスカレーターを階段代わりにして静かに降りて行った。
運良くなのかどうか、各階に人の気配は無いまま無事に一階エントランスまで辿り着くことができたのだが、エスカレーターはそこで終点だった。
(モーター音は、さらに下の階から漏れてきている。)
七階で気付いた時よりも、かなりハッキリとした機械音がフロア中に響いていた。
(地階に降りるための階段かエスカレーターあるはずなんだが。)
そう思って、正面入り口の横に見えた一階フロアの見取り図を確認しに行った。
エントランスには完全に塞がれていない窓も幾つかあったのだが、そろそろ陽が西に傾いている時刻なので採光は殆ど望めず、見取り図を前にしてもマグライトで部分的に照らさなければならない。
アクリル板に光が反射するので非常に見辛かった。
(えーと、地階へはエレベーターを使いなさいって感じか。)
地階は映画館になっており、エレベーターで地下二階まで降りれば目の前がチケット売り場になっている。
しかし、エレベーターの電源は落ちているようだし、そもそも隠密行動中に堂々とエレベーターを使うわけにはいかない。そこで一階フロアの中央に陣取ったアパレル系のテナントスペースを迂回し、その奥にある階段を使うことにした。
階段までの道順を確認するため、マグライトで見取り図を辿っていたら、
(妙だな? )
突然、既視感が生じた。
(右、左、もう一度左に曲がって、その正面に階段。)
尾藤は通路の配置を記憶している。
階段を降りた先の道筋も分かるような気がする。
(これって? )
ブツ切りの映像として幾つかの記憶が浮かびあがってきた。
同時に、身体中がブツブツと鳥肌立つのが分かった。
(あの夢と同じじゃないか! )
そう思った時、尾藤の背後で、
ヒュン!
と、風を切る音が聴こえた。
「うっ! 」
間一髪、その場に尻餅をつくようにして転がった尾藤の頭上を金属製の凶器が掠め、見取り図が描かれたアクリル板に突き刺さり、これを打ち砕いた。
尾藤の既視感は、突然の殺意によって掻き消されてしまった。
床に転がった尾藤は、そのまま這うようにして凶器が飛んできたのと逆方向に逃げるとマグライトで殺意の主を照らした。
「出角っ! 」
見覚えのある嫌な顔が、殺気に満ちた目で尾藤を睨みつけ、鉄パイプを握っていた。
「こんのやろーっ! 」
出角は叫びながら尾藤を追い掛け、更なる鉄パイプの一撃を加えてきた。
尾藤は再び身を躱したが、マグライトを弾き飛ばされてしまった。
(しまった! )
暗闇に目が慣れるまで視界は闇に閉ざされる。
次の攻撃を避けるためには、もっと距離を取らなければならない。
しかし、急ぎ後退った尾藤の逃げ道は遮られた。
ドスン!
鈍い音を立て、尾藤の背は正面入り口のガラス扉にぶつかってしまった。
「出角っ! この人殺しっ! 教え子を浚って! 殺すなんて! てめぇ、それでも教師かっ! 」
尾藤は闇の中にボンヤリと黒く見える出角に向かって必死の悪態をついた。
「ひっ、人殺しではない。私は可愛い教え子に素晴らしい名誉を与えたんだ! 」
言い返してきた出角の声は興奮のあまり震えていた。
顔は見えないが、凄まじい狂気が伝わってくる。
学校で会った時には嫌な奴だと思ったが異常さまでは感じなかった。
しかし、今は全く別人、いや狂人だった。
「バカ野郎! 何が素晴らしい名誉だ! てめぇらのようなカルトに捕まって生贄にされる娘はたまったもんじゃないぞっ! 」
尾藤は悪態を続けた。
出角を口論に持ち込んで、暗闇に目が慣れるまで、反撃の糸口を見付けるまでの時間を稼ごうとしたのだ。
出角は激し過ぎて冷静さを失っている状態だが、思考が尾藤に対する敵意一本で単純になっているならば乗せやすいかもしれない。それに、激しい運動には不慣れと見えて、ヒィヒィと息切れしそうな呼吸音が混じっていたので、隙を作れば逆転は可能である。
「だっ、黙れーっ! 娘たちは捧げものになるんだ! これは素晴らしい名誉なことなんだぞっ! 」
出角が期待通りの反応を見せ、こちらの誘いに都合よく乗ってきた。
「はん! 何が名誉だ! お前らのような奴はな、世間じゃロリコン、サディスト野郎って言われんだよ! 」
尾藤は畳みかけたが、もちろん出角と違って計算づくである。
だから、罵声を浴びせると同時に出角の隙を窺うのを忘れていない。
「うっ、煩いっ! 世間の無知な奴らなど、偉大な力が発動された暁には、皆殺しにされてしまうのだ。虫けらのように死ぬよりも、名誉ある捧げものとして死ぬ方が娘たちのためなのだっ! 」
「馬鹿馬鹿しい! カルトの信心なんて、どうせイカサマに決まってる! 」
「い、イカサマではない! その凄まじい力は我ら信者を救い、この世の不信心で無知なる者どもに苦しみと災いを齎すのだ! 」
一撃で尾藤を片付けてしまうつもりだったであろう出角が、それを忘れて尾藤の吹っ掛けてくる罵声に一々反論を始めていた。
(馬鹿な奴め! 狂信者なんて、こんなもんさ。)
自分の正当性を否定されれば、激昂して反論したがる。
「尾藤っ! 貴様は邪魔だっ! 我らの神聖な儀式を邪魔するような奴は、私がこの手で滅ぼしてやるーっ! 」
「お前なんかに、滅ぼされて堪るか! バーカ! 」
ここいらで尾藤の思惑に気付いたわけでもないだろうが、出角は返事をせずに口論を打ち切ることにしたらしい。
両手で鉄パイプを握り尾藤に向かって勢いよく振り下ろした。
しかし、尾藤は既に十分な時間を稼いでいた。悪態の応酬をしているうちに目はすっかり暗闇に慣れており、素人の振り下ろす鉄パイプなど脅威ではなくなっていた。
出角の渾身の一撃は難なく躱され、その鉄パイプは勢い余ってタイルが剥がれてコンクリートが剥き出しになった硬い床に激しく打ち付けられた。
その衝撃に耐え切れず、出角は鉄パイプを取り落としてしまった。
「ハハッ、笑っちゃうぜっ! 偉大な力が鉄パイプだってかぁ! 」
尾藤は足元に転がってきた鉄パイプを遠くへ蹴り飛ばし、床に散乱しているタイルや壁在の破片を幾つか拾い上げると、それを出角の顔目掛けて投げつけた。
「うぉーっ! 」
出角が苦痛に叫びながら、顔を両手で覆って後退りした。
「出角っ! いい加減に大人しくしやがれっ! 」
尾藤は立ち上がって一気に距離を詰め、出角の左膝裏を狙って一切力の加減をしない下段蹴りを放った。
ビキッ!
骨の折れる鈍い感触が尾藤の足を伝ってきた。
「うぎゃーっ! 」
出角は、その場にしゃがみ込み、左足を押さえ激痛に悶え苦しんだ。
「足、痛い! 痛い! 助けて! 助けて! 」
無様にも、今し方まで殺そうとしていた相手に泣いて助けを求め始めた。
「情けねぇ奴だな。」
尾藤は、ツカツカと出角の傍に歩み寄り、
「教え子を殺すような悪党が、これっぽっちの痛みに耐えられないってのか? 」
そう言うと、いきなり出角の顔面を靴の踵で蹴り飛ばした。
「いゃーっ! 鼻がぁ、鼻が折れたぁ! 」
出角は仰け反るようにして床に倒れ、噴き出した鼻血が涙と混じり合って顔面を醜く濡らしていた。
「さて、俺の聞きたいことに答えてもらおうか? 」
尾藤は極めて残酷な口調で言いながら、出角の負傷した左膝を押さえている手の上から思い切り踏み躙った。
「ギャッ、ギャーッ! やめっ! やめてぇーっ! 」
出角の悲鳴がフロア中に響き渡った。
「やめて欲しければ、俺の質問に答えな。」
尾藤は足の力を少し緩めてやった。
「こっ、これは拷問だぞっ! 違法だぞっ! 絶対に許されないっ! 」
出角は痛みに耐えながら必死で抵抗する。
「ハハハッ、さすが学校の先生だねぇ、法律に詳しそうでいらっしゃる。」
尾藤は笑いながら出角の左膝に全体重を乗せてやった。
「アッ、ギャーッ! アウッ、グゥーッ! 」
言葉にならない悲鳴をあげ、出角の上半身がジタバタとのた打った。
「四の五の言わず、答える気になった? 」
痛みに言葉を発せない出角は、何度も頷いて恭順の意を表した。
それならばと、尾藤は出角の左膝の上から足を下ろしてやった。
「お前、表にいる時から俺のことつけてたんでしょ? 」
出角が首を縦に振った。
「やっぱりね。」
非常階段で感じた気配は、出角のモノだったようだ。
「きっ、貴様が余計な事を嗅ぎまわるから俺の立場はヤバくなってんだよ! 貴様を殺さなければ、俺が殺されてしまうんだ! 」
「なんだ、そりゃ? 」
カルト教団内では失敗した者は殺されてしまうということだろうが、
(里田かおると、その両親みたいにってことか? )
殆ど悪の秘密結社である。
「そうは言われてもねぇ、俺も仕事だし。そもそも、そっちの誘拐の手際が悪かったから、俺に嗅ぎまわられてるんじゃないの? 」
出角は応えず、悔し気に呻いた。
「さて、それじゃ肝心なことを聞こうか。司廉子は何処にいる? 」
「そっ、それは・・・ 」
出角が答えを渋ろうとしたので、尾藤は再び左膝に足を掛けようとした。
「わ、わかった言う! あの娘はこの下に閉じ込めてある! 」
「この下? 地下何階の何処? 」
「地下っ、地下二階の階段の脇にある用度倉庫の中っ! 」
これを言い終わった途端、出角が大きな溜息を吐きながらブルブルと震えだした。
この震えは膝の痛みによるモノではなさそうである。
「おっ、お願いだ。絶対に俺が話したなんて言わないでくれ。」
(何だ? こいつ怯えてるのかよ? )
「こんなこと話したなんて知れたら、俺は殺されるぅ。」
「どうせ、お前は警察行きだよ。心配しなくても警察が厳重に守ってくれるさ。」
司廉子が無事ならば、誘拐だけでは死刑にならないから安心しろとも言ったのだが、
「ダメだ! 警察なんかじゃ、俺を守れない! 頼む! 俺を逃がしてくれよ! 」
出角は泣きながら手を合わせて懇願している。
とても先程まで鉄パイプを振り回していたとは思えないほど弱気な様子である。
「お前は分っちゃいない! 同志たちの恐ろしさを分っちゃいない! 彼らが本気になれば警察の中だって関係ない! 刑務所だってそうだ! 海外に逃げたって、宇宙や海の底に隠れてもダメだ! 同志たちが手出しできない所なんて何処にも無い。だから、ひたすら逃げ回るしかないんだよぉ! 」
尾藤は嘆息した。
(こいつ、教団の力が絶対的だと信じていやがる。)
この話を鵜呑みにすれば、その同志とやらが超能力でも持っていることになる。
(カルト教団って奴は、一度入信したら二度と離れられないようにマインドコントロールを仕掛けるっていうし、こいつもそうなんだろう。)
この手のマインドコントロールは簡単に解きようがない。
今、尾藤が何を言ったところで出角は決して安心することは無いだろう。
「まあ、取り敢えず地下二階の用度倉庫までは一緒に来てもらおうか。引き摺ってってやるからさ。」
尾藤は有無を言わさず、出角の上着の襟首を掴んで階段まで引き摺って行こうとした。
二、三歩進んだところで、
「ああぁ・・・ 」
出角の、か細い悲鳴が聴こえた。
振り返ると、出角が力無くユラユラと手を差し出し、宙を掴むような、何かに縋りつくようなポーズを取っている。
「何してんだよ、調子狂うような声出しやがってっ・・・ひうっ! 」
突然、舌が引き攣って口が利けなくなった。
舌だけではない、手も足も痙攣して言う事を聞かない。さらに脇腹に焼けた火箸が押し当てられたかのような激痛が走っていた。
「・・・? 」
尾藤は立っていられずに、その場に崩れ落ちてしまった。
床に這いつくばった自分の脇腹から細い二本のケーブルが伸びているのが見えた。
(やられた! テーザーガンだ! )
テーザーガンは離れた位置から有線式の電極を発射するタイプのスタンガンである。
迂闊だった。
出角に気を取られているうちに、暗闇に紛れて別の敵が近寄ってきたことに気付かなかったのだ。
「ああ、助けて・・・助けて・・・ 」
出角の哀願するような声が聴こえてきた。
(いったい何に哀願してんだ? お前は仲間が来て助かったんじゃないのか? )
俯せに倒れてしまい、背筋が引き攣って動かないので、出角の哀願する相手を確かめるために振り返ることもできなかった。
「こいつは、どうしましょうか? 」
若い男の声が聴こえた。
「せっかく汚名を返上する機会を与えてやったにも関わらず失敗し、その挙句に大事な秘密まで漏らすとは見下げ果てた奴だ。」
もう一人は年配の男の声だが、こちらの方が目上の立場であるらしい。
「このような無能な男は必要ない。処分して良い。」
「かしこまりました。」
年配の男の指示に、若い男の声が恭しい態度で言った。
「お慈悲を・・・お助けを・・・ 」
泣きながら懇願を続けていた出角を、おそらく若い方の男が強かに殴りつける音が聴こえてきた。
尾藤には、何が起こっているのか見ることはできなかったが、どうやら暴れる出角が若い方の男に無理矢理に押さえつけられているようである。
ドタバタと床を叩く音が十数秒間続いた後、
ゴリッ!
と、鈍い音が聴こえてから辺りは静かになった。
(首を折られたのか? )
出角の気配が、この場から消えてしまっていた。
(ホントに自分たちの仲間を簡単に殺してしまうような連中なんだな。)
里田家の者たちに続いて出角まで、教団内の失敗者や邪魔者を許すことはせず、本当に排除してしまうらしい。
(それって、マジに悪の秘密結社じゃん! )
正義のヒーローが主人公の映画や漫画で、世界征服を企んだり悪事の限りを尽くす敵役そのままの冷酷さである。本人たちが分かってやっているのかは知らないが、まったく感心するほどの見事な悪役っぷりである。
(で、次は俺を殺すつもりか? )
間もなく、一仕事終えた二人の男の会話が聴こえてきた。
「さて、これが例の探偵ですか? 」
「はい、我らに逆らう悪しき男です。いかがいたしましょうか? 」
床に横たわる尾藤を見下ろしながら話しているらしい。
(探偵じゃない! 調査員だっ! )
今にも殺されそうだという時に、ハッキリ言ってどうでも良い尾藤の心の叫びだが、男たちには聞こえるはずがない。
「待ちなさい。問うてみましょう。」
年配の男がブツブツと呪文のような言葉を呟き始めた。
上手く聞き取れなかったが、男の呟きが中国語であることだけは理解できた。
尾藤の処断方法を神さまにでも問い合わせているのだろうか?
その間、若い男は無言で控えている。
呪文は数分間続いてからピタリと止まり、少し間を置いてから年配の男の声が日本語で聴こえてきた。
「何故なのだ? 応えが無い! 」
多少大げさに感じられるほどの驚きと失意を口にした。
(神さまに無視されたのか? )
それにしても、年配の男は自分のセリフに無理矢理強い威厳を持たせようとしているようで、言い回しに芝居がかった抑揚がつけられている。
「おお、そんな、どうしたというのでしょう? 」
若い方の男も、驚きで全身が震えているかのような臭いセリフを返す。
この二人のやり取りは、こんな状況に置かれてさえいなかったら失笑してしまうほどの下手糞な三文芝居に聞こえた。
しかし、演技が学芸会レベルでも彼らはカルトの狂信者である。
この下手糞な芝居は、寒気がするほどに不気味であり、決して笑い事では済まない。
「やむを得ません。この男は儀式の後で火にすることにします。」
「はい、それがよろしいでしょう。」
神さまが応えてくれないので、面倒臭いから燃やしてしまおうというのか?
(ヤバいぞ! 司廉子を助けるどころか、このままじゃ俺は火炙りにされちまう! )
焼き殺されては堪らないので、何とか逃げ出さなければならないのだが、
(初めて食らったけど、電撃ってのは強烈なもんだな。)
ダメージが大き過ぎて、逃げたくても身体が全然言う事を聞いてくれない。
「この男は地下牢に入れておけ。」
「はい、仰せのままに。」
おそらく若い方の男だと思うが、床に倒れている尾藤を片手で引き起こして軽々と自分の肩に担ぎあげた。
(なんて馬鹿力だよ! )
このまま地下牢とやらへと運んで行かれるらしい。
(こいつ、プロレスラーかアメフト選手並みの体格してやがる。)
尾藤に見えるのはフード付きの黒いローブを身に付けた男の背中だけだったが、床までの高さから推測すると、この男の身長は二メートル前後もあるようだ。さらに筋肉の盛り上がった腕と幅の広い肩の感触が伝わってきて、この状況下で多少の抵抗をしたところで全く無意味な相手であること分かった。
(くそっ、今は大人しくしているしかない。どうせ身体も言うこと聞かないし、火炙りまでには時間もあるようだし・・・ )
尾藤は無抵抗のまま、地階へと運ばれていった。
後篇
[一八]
男たちが地下牢と言っていたので、格子の嵌った牢獄をイメージしていたのだが何のことは無い、尾藤が放り込まれたのは屋上にある給水タンクに水を汲み上げるためのポンプ室である。
この廃墟ビルのポンプ室は、建物の最下層である地下三階にあり、壁も扉も厚いので監禁場所としては都合が良さそうだ。水道は止まっているようなのでポンプ室としての機能は既に失われている。
男たちの会話によると、地下三階全体が「地下牢」という名称で呼ばれており、尾藤のような厄介者を一時的に監禁しておく場所として使われているらしい。
(司廉子も、このフロアの別室に監禁されているのだろうか? )
出角は地下二階の用度倉庫だと言っていた。
(おそらく、俺に痛めつけられながら吐き出した出角の言葉は正しいだろう。)
彼らがアステカの儀式を真似ているならば生贄は神聖とされているはずで、司廉子は好待遇で迎えられているはずだった。
尾藤のような厄介者とは監禁場所の状態も別格に違いない。
(まあ、女子中学生が、こんな不潔なところに何日も監禁されていたなら、生贄にされる前に病気で死んじまうわ。)
ポンプ室の環境は最悪である。
暖房が無いため底冷えするし、室内の空気には赤錆とカビの臭いが充満して呼吸をするのも憚られるほどである。しかも、灯りの一つも無いため、目が慣れることも無い。自分の鼻先さえも見えないほどの真っ暗闇だった。
(まさに地下牢だよ。)
時代劇などに出て来る地下牢同様、こんな所に閉じ込められて長期間放置されたなら、普通の人間ならば病気になるか気が狂うかしてしまうだろう。
(長居する気は無いけどね。)
テーザーガンによる麻痺からは大分回復していたので、身体を起こしたり手足を動かすぐらいは問題無くできた。しかし、両手は手錠で繋がれ、室内中央の給水タンクに繋がる水道管の一本を後ろ手に抱え込まされていたので、自由に動き回ることはできなかった。
だが、調査員などという商売をしていると、思いがけないピンチに陥ることも多々あるので、緊急時の様々な脱出法は用意している。
(ふん、素人どもめ、ロクな身体検査もしないで。)
尾藤は足の踵を後ろに持ち上げて、手錠を掛けられたのままの手で靴に仕込んでいた一本の細長いピンを抜いた。
(警察が使ってる電子ロック式の手錠ならヤバいけど、こんな古臭い鍵式の手錠なんかチョロ過ぎだよ。)
後ろ手のまま、ピンを鍵穴に差し込んでカチャカチャと音を立てながら一〇数秒、あっさりと片方の輪を外した。
(ま、こんなもんじゃね。)
続いて、もう片方の輪も簡単に外し終わった。
(せっかくだから、この手錠はいただいとくとするか。)
外した手錠は何かの役に立つかもしれないので、捨てずに上着の内ポケットに入れた。
(いやぁ、それにしても酷い目に遭ったわ。)
長時間不自由な体勢を強いられていた身体を思い切り伸ばした。
(さて、こんな汚い所からは早めに退散するに限るんだが。)
携帯通信端末をはじめ、身の回り品は全て奪い取られてしまっているので外部と連絡を取る手段が無い。
(あいつらキャンディまで取り上げやがった。)
口の寂しさは我慢するとして、何とか自力でここを逃げ出さなければならないので、まずは現状の確認から始めることにした。
手始めにドアである。
暗闇の中、壁を伝ってドアを見付けると、ノブに手を掛けて回してみた。
(鍵が掛ってる・・・って、当り前か。)
手錠で拘束しているとはいえ、鍵も掛けずに捕虜を放置する牢屋などあるわけがない。
もちろん、鍵が掛っていたとしても尾藤のピッキングの腕前ならば大概の鍵は開けられるはずだったのだが、
(くそっ! 内側に鍵穴が無いぞ! )
外側からしか施錠できないタイプのドアだった。
(そうだよな、ここはポンプ室なんだし・・・ )
ピッキングの手は使えなくなった。
(力任せにドアをぶっ壊すか? )
できないこともないだろうが、一撃で破られるほど脆いドアでもないだろう。
牢屋破りに手間取れば、その音を聞きつけて尾藤を捕えた連中がやってきてしまう。
(他に出られるとこは無いのか? )
手探りでポンプ室中を調べてみたのだが、どこにも脱出路は見つからない。
尾藤は肩を落とし、給水タンクに背を凭れてコンクリートの床に腰を下ろした。
(今、何時かな? )
時計も奪われていたので、正確な時間が分からない。
(このビルに侵入してから四、五時間は経過してる感じだから、たぶん一九時から二〇時の間ってとこだろう。)
儀式が始まるまで残すところ六、七時間。
(もう、そんなに余裕は無い・・・ )
司廉子を助け出すつもりで忍び込んだのに、手も足も出ない状態に置かれてしまった。
(なんて、ドジなんだ! )
しかし、焦ってジタバタしても意味が無いので、無駄な体力を使わないように大人しく暗闇の中で頭だけを捻ることにした。
ポンプ室に閉じ込められてから一時間ほど経過した気がする。
尾藤の状況に変化は無い。
どんなに頭を捻っても脱出の手段は見付からなかった。
(アディはどうしてるかな? )
今日の昼頃までは、お互い二、三時間置きに連絡を取り合っていたので、それが途切れたままの状況を不審に思っているはずだ。
(アディが助けに来てくれたらなぁ。)
もはや、外部からの救出以外にポンプ室を出る手段は無さそうに思えていた。
しかし、尾藤がヤドリギ探しをしている最中も、アディには「シクラニ」の店長の見張りに専念するように言い付けておいたので、真面目なアディは今も「シクラニ」周辺で律儀に張り込みを続けている可能性が高い。
但し、もし店長が早めの会場入りをしていたとしたならば、この近くにアディが来ているかもしれないのだが、
(でも、俺がポンプ室に監禁されていることなんか知らないわけだし・・・ )
例え近くに来ていたとしても、現状を伝える手段が無い。
(困ったなぁ。)
ポンプ室内は尾藤が動き回らない限り物音一つしない。先ほどから時々聞こえるのは尾藤の落胆の溜息ばかりである。何も見えず、何も聞こえず、まるで無の空間に放り出されてしまったようだった。
五感のうちの二つを封じられただけなのに、人間とは随分心弱くなる生き物だと思いながら、またまた嘆息しかけた時だった。
「・・・ 」
空気が動くのを感じた!
(何かいる! )
真っ暗なポンプ室で突然の気配がした。
それまで、鼠一匹いる気配のしなかったポンプ室内に、何かが存在感を表した。
「ヒ・・・ 」
耳を欹てていなければ聞こえないほどの小さな息を吐くような音がした。
微かな笑い声のようにも聞こえた。
「ななっ、何っ? 」
尾藤は飛び上って、声のする方向に向かって身構えたのだが、
「ヒヒッ・・・ 」
今度は背後で笑い声が聞こえ、首筋に息のかかる悍ましい感触を覚えた。
「だっ、誰だーっ! 」
慌てて振り返りながら後退った。
(俺は何も見えていないのに、こいつは俺が見えているのか? )
全身を痺れるような悪寒が包んだ。
(こっ、怖い・・・ )
それは、滅多に覚えることの無い感覚だった。
正体不明の何かが、ポンプ室の何処かに潜んでいる!
そいつは自分を襲ってくるかもしれない!
何も見えない自分には、対処の仕様が無い!
目が見えないということが、どれほど人を混乱させ、恐怖感を煽るものか、尾藤は今痛切に実感していた。
(どっ、どうしよう! どうしたら良いっ? )
ナイフやスタンガンを持った暴漢に襲われても怯まなかった男とは思えないほどの怯えっぷりだった。
(こっ、腰が抜けそう・・・ )
恐怖に対する尾藤の忍耐力が限界に達する直前、
「あ・・・あれ? 」
気配が消えた!
現れた時と同じようにして、突然消えてしまった。
カチン!
今度は金属音がした。
(えっ? )
その物音はドアの方から聞こえた。
鍵の開く音のようだったが、少し待ってみてもドアが開く様子は無い。
(今度は何っ? )
殆ど泣き出す一歩手前まで追い詰められていた尾藤だったのだが、勇気を振り絞って壁伝いにドアがある方向へと向かった。
(情けねぇ、膝が震えてるって! 心臓も飛び出しそう! )
どんな危険が待ち受けているかも知れないので、ドアに辿り着いても直ぐにノブには手を掛けるようなことはせず、耳をドアに押し付けて外の様子を窺った。
すると、ドアの向こうで何者かが階段を駆け上がっていくような足音が聞こえた。
足音が去ってから、尾藤は一分ほど動かずにいた。
その間、耳をドアにピッタリと張り付け外に向けていたが、他には何の物音も聞こえてこないし傍に人がいる気配も無い。
そのうちに膝の震えも止まり、気持ちも大分落ち着いてきた。
(このドアの鍵、開いてるのか? )
ノブに手を掛けて回してみると、先ほど調べた時の抵抗感は無くなっている。
そのままノブを一杯に回してから軽く推してみるとドアは音も立てずに開いた。
(どういうこと? )
尾藤は人一人が横になって通れる程度までドアを開き、外の様子を伺ってみようとしたのだが、
(こっちも真っ暗か。)
ドアの外にも光は無い。
そこはポンプ室と同様に真っ暗であり、どのような形や広さをした空間なのか全く分からない。
(でも、誰もいないことだけは感じで分かるんだけど。)
何者かが潜んでいたとしても、こちら同様に何も見えるはずはない。
暗視装置でも使わなければ一寸先も見えないだろう。
辺りに人の気配が全然感じられないので、そんな便利な装置を着けて潜んでいる者などいないはずだった。
(じゃ、じゃあ、さっきのはいったい何? 誰が何のためにドアの鍵を開けたの? )
ポンプ室内の気配はともかく、これは罠かもしれないと思った。
罠でなくとも、何らかの誘いであることだけは間違いない。
(敵の仕業? それとも味方なのか? )
現状で味方が近場にいるとは到底考え難い。
どうにも不可解だが、ドアが開いた以上ポンプ室に留まっている意味は無い。
警戒はすべきだが消極的になる必要は無いと思った。
(よしっ、出る! )
覚悟を決めてドアの外に一歩足を踏み出した。
カツン!
靴の爪先が何か小さく硬いモノを弾いた。
(なんだ? )
そのままにしても良かったのだが気になったので、その場にしゃがみ込んで床を手探ってみた。
すると、今度は手の指先が何かを弾いた。
(おっと! )
遠くへ飛んではいなかったので、その何かは直ぐに見つかったのだが、
(使い捨てライターだ! )
拾って握り締めた感じで直ぐに分かった。
(有難い! )
これで灯りが確保できると喜んで点火すると、小さな炎の光が辺りを覆っていた暗闇を薄く取り払い、それほど広くない地下三階フロアの様子がボンヤリと浮かび上がった。
地下三階フロアは上階のフロア面積よりも狭いようで、おそらく部分地下構造になっていると思われる。見えるドアの数は尾藤の背後にあるポンプ室と、その向かい側にあるドアの二つだけ。
(一応、向かいを見てみる? )
この階に司廉子が監禁されている可能性は低いのだが、見落としては不味いので念のために確認だけはしておこうと思った。
尾藤は向かい側のドアに近寄って、これも慎重に中の様子を窺いながらノブに手を掛けてみた。すると、この部屋に鍵は掛っておらずドアは直ぐに開いた。
(倉庫か? )
大量の什器や事務用設備、パーティーションなどの各種資材置き場になっており、人が居られるほど容積に余裕は無い。
当然、人の気配はしなかった。
(司廉子が監禁されていないなら、この階に用は無い。)
尾藤は倉庫のドアを閉め、ライターの光で足元を照らしながらポンプ室のすぐ横にある階段前まで移動した。
(それにしても、使い捨てライターが偶然ドアの前に転がってたなんて、やっぱり都合良過ぎるよな? )
その使い捨てライターは、ほぼ新品で明らかに長く放置されていたモノではない。
汚れも錆も無いし、オイルは満タンに入っている。
尾藤を運んできた連中が落としていったライターである可能性も考えられるが、それだって都合が良過ぎる想像だと思う。ドアの外に足を踏み出した途端に引っ掛かる場所に置いてあったというのも妙にわざとらしい。
(鍵を開けてった奴が置いて行ったと考えるのが妥当だな。)
何者か分からないが親切な奴である。
(ポンプ室内で俺をビビらした意味はサッパリ分からんけどね。)
これを味方と考えるのは早計に過ぎるが、
(ま、せっかくだから、この親切は有難く頂いとく。)
そう割り切りながら、足音を忍ばせて階段を登って行った。
階段を上がりきったところで再びドアに行く手を阻まれたが、これの鍵は開いていたので問題は無い。
但し、警戒を怠ってはいけない。
又もやドアに耳を押し付けて外の様子を伺ってから、静かに少しづつ開くようにした。
(ここは少し明るいぞ。)
ドアの外に出てみると、目の前には細長い通路があり、何処からか灯りが漏れているようで、ライターを消しても通路の様子が薄っすらと見えていた。
そこは、出角の襲撃を受ける前に一階エントランスの見取り図で確認していた地下二階の映画館フロアである。目の前の通路を進めば正面のチケット売り場に通じているはずだった。
(通路の先には間違いなく人がいるんだろうな。)
この階の用度倉庫には司廉子が監禁されているはずなので、見張り要員がいるに決まっている。
(人数にもよるけど、見張りをぶっ倒して司廉子を助け出すってのはどうかな? )
まるで特攻作戦だが、残されている時間は少ないので少々の強引さは止むを得まい。
尾藤は足音を忍ばせたまま小走りで通路を進んだ。
曲がり角で一旦立ち止まり、その先の様子を確かめると、そこは広々としたホールであり映画館の待合所のようであった。ベンチやテーブルが残ったままになっているので障害物が多く、身を隠すのには都合が良かったが、
(けっこう明るい・・・ )
ホール全体で数本の蛍光灯が生きているだけだったのだが、暗闇に目が慣れていたせいで思わず尻込みしそうになるほどの明るさに思えた。
(しょうがない、我慢だ! )
この明るさなら用度倉庫の場所ぐらい直ぐに確認できるだろうとホールを見渡した。
(出角は、階段を下りて直ぐだと言ってたよな。)
階段の位置はホールを突っ切った先に見えた。
用度倉庫かどうかはともかく、確かに階段を降りて直ぐ横の奥まった場所に、何の表示も書かれていないドアが一つある。
(たぶん、あれだな。)
有難いことにドアの近くに見張りはいない。
そもそもホール全体に人影は見えない。
(こいつはラッキー! )
尾藤は直ぐに姿勢を低くし、ベンチやテーブルなどの物影に身を隠すようにしながら階段の横まで進んだ。
(さて、漸くピッキングの腕前を披露できるな。)
靴の踵に戻しておいたピンをもう一度取り出そうとした、その時、
「うっ! 」
いきなりドアが開いた。
そして、中から一人の男が現れたのだ。
目の高さは尾藤と殆ど同じ、見た目は日本人か東アジア系の東洋人で、フードの付いた黒いパーカーを羽織った三〇歳前後の男である。
もちろん尾藤は驚いたが、その男も目の前にいる尾藤に驚き呆然としている。
互いに向かい合った状態のまま言葉を発するのも忘れて動きを止めた。
しかし、それは一秒にも満たない一瞬である。
忽ち我に返った男は、目の前の尾藤を敵と判断するなり大声を発しようと口を開けた。
しかし、尾藤の動きは更に素早かった。
男が声を発する前に開いた口の中に右手を突き刺したのだ。
その右手にはポンプ室で捨てずに取って置いた手錠が握りしめられていた。
ガツン!
鈍い衝撃音が鳴り、歯と顎の骨が同時に砕ける音がした。
声を発することができなくなった男が低い呻き声を漏らした。
尾藤は、衝撃と痛みにより瞬時に戦意を喪失してしまった男の背後に回り込むと、その首に二の腕を絡めて一気に締め上げた。
ホンの二、三秒後、男は意識を失って崩れ落ちた。
(はーっ、ビックリした! )
争いは一〇秒も掛らずに蹴りがついたので殆ど物音は立てていない。
だから、誰かが駆けつけてくる心配は無い。
しかも、男は一人きりで他に相棒はいなかった。
一息吐いた尾藤は、男の身体を引き摺ってドアの中に入った。
(司廉子は? )
ドアの中は確かに用度倉庫だった。
照明は蛍光灯一つだけだが、一〇坪ほどの広さの室内は十分に明るい。掃除が行き届いていて、空調設備や暖房も稼働しているらしく、尾藤が閉じ込められていたポンプ室のような悪臭もせず、ほんのりと暖かかった。
部屋の手前に並んだ空っぽの業務用ラック越しに倉庫の奥を覗くと、何も置かれていない空間が見えたので入ってみた。すると、そこには薄いカーペットが敷かれ、壁際に折り畳み式のシングルベットが置かれた簡単な寝室に仕立てられていた。
しかし、
(司廉子はいない・・・ )
ベッドの上に敷かれた寝具の様子を見ると、明らかに誰かが寝起きをしていた形跡が残っていたが、それが司廉子であることは疑う余地が無いだろう。
空調や暖房の効き具合から察するに、彼女が倉庫を出てから間もないであろうことも分かった。
しかし、その姿は何処にもない。
(もう儀式に連れ出されたのか? いったい、今は何時なんだ? )
尾藤は部屋の入り口に転がしておいた男から時計や携帯通信端末を手に入れようと、その懐を探ったのだが、
(こいつ、何にも持ってねぇ。)
ガッカリしながらも、何か使えるモノが無いかと探り続けていたら、ズボンのポケットからバタフライナイフが出てきた。
(物騒なモノ持ちやがって。)
さっき、これを持ち出されていたら危なかったが、余りに短い戦いだったので使い損ねたのだろう。
(それじゃ、これはいただいときます。)
尾藤は取り上げたバタフライナイフを掌の上で二度開閉して使い勝手を試した後、クルリと一回転させてからズボンの尻ポケットに差した。
バタフライナイフの他には目ぼしい道具は無さそうだったので、尾藤は懐を探るのを諦めて、今度は男の着ているパーカーを剥ぎ取りに掛かった。
この廃墟ビルの中を司廉子を探して歩き回るには変装が必要である。
尾藤をポンプ室に運んだ大男もそうだったが、フード付きの衣服を着るのが教団の決まり事なのかもしれないと思い、パーカーに目を付けたのだ。
(こいつ、クソ重たいな・・・ )
パーカーの剥ぎ取り作業に手古摺っていたら、
(上の階で足音がする? )
聞こえるのは一人や二人の足音ではない。
大勢の人間が古くなった床のピータイルを踏み鳴らしている音だった。
(もしかして、儀式の会場は地下一階か? )
そうだとしたら、こんな所でグズグズしてはいられない。
直ぐにでも上の階に駆け付けなければならない。
尾藤は男のパーカーを脱がす手を速めた。
(なかなか良いパーカー着てんじゃん。)
脱がし終わったパーカーを両手で持って目の前に翳してみる。
男の身長は尾藤と同じぐらいだったが、体型が肥満気味だったのでパーカーのサイズは少々大き過ぎるように感じる。
(でも、ジャケットを着たままなら、ちょうど良いんじゃないか? )
試しに今着ているジャケットの上に羽織ってみると、身体を動かすのに多少の不自由はあるものの胸や腹周りは男のシルエットと似た雰囲気になった。
フードを被ってみたら顔の上半分が隠れるので、これは意外に好都合である。
部屋を出る前に、尾藤は男の隣にしゃがみ込んで、その首筋に手を当てて脈を診た。
男は完全に気を失っているが命に別状はないようだ。
だが、目覚めた時に騒がれたら困るので、部屋の隅にある太めの配管に手錠で繋ぎ、口にはシーツを破って作った猿轡を噛ませておいた。
(これで良し。)
準備を完了した尾藤は、早速倉庫を出て上の階へと向かうことにした。
人気のない地下二階から、人の気配がする地下一階へと続く階段を、今度はコソコソとせずに自分も信者か関係者であるかのように堂々と上っていった尾藤だったが、そこには思ったよりも沢山の人がいたので慌ててしまった。
地下一階は映画館へ降りる途中の踊り場的なスペースなので大して広くは無いのだが、そこに一〇〇人以上の人間が集まっていたのだ。
下の階にいた時は精々二〇か三〇人ほどと見積もっていたのだが、聴こえていたのが足音だけであり、人が集まれば伴うはずの騒めきが一切無かったことで実際よりも少なく感じてしまったのだろう。
奇妙なことに、その場にいる者は誰一として人口を利かず、黙って突っ立っているだけだったのである。
尾藤が男のパーカーを着ていたのは正解だった。
その場にいる者たちは皆が帽子やフードを被っており、サングラスを掛けている者やマスクをしている者も多く、これは顔を隠すのが当たり前の集いであるらしい。
こうなると、人数が多いのは幸いで簡単に人の群れに紛れ込むことができる。
尾藤は誰に見咎められる心配も無くなった。
(さて、これから何が始まるのやら。)
まさか、この狭い踊り場のような所で儀式が始まるとも思えないので、この人の群れは準備が整い次第に他の場所へ移動するつもりに違いない。
尾藤は成り行きを見守ることにした。
それから間もなくして、群れの背後から新たな足音が聴こえてきた。
足音の主は、フードを被った黒いローブ姿の者たちである。
(あれは、俺をポンプ室に運んだ奴と同じ衣装だ。)
彼らが身に纏っている黒いローブは、どうやら教団内での立場を差別化するユニフォームであるらしく、この場に群れている者たちとは明らかに異なる仰々しい態度をした連中だった。
(つまり、こいつらが幹部連中ってわけ? )
黒ローブたちは人の群れを掻き分けてフロアの最も奥へと移動し、予め用意されていたらしい演壇代わりの木箱の上に立った。
木箱の上で横一列に並んだ黒ローブは四名。フードを深く被り顔を隠しているので、人相も性別も分からない。
(如何にもわざとらしい演出効果。)
尾藤は昔イタリアを観光旅行した時に見た修道僧の服に似ていると思った。
おそらく雰囲気作りのため、そうしたモノを真似ているのだろう。よって、見た目から感じられるオリジナリティはゼロだった。
(所詮は有名宗教のチャンポン、イカサマカルトか・・・ )
ところが、この場にいる大勢の人々にとって、黒ローブの四人は絶対的な信仰の道標であるらしい。四人のうちの一人が壇上で語り出すと、それまで無言でいた人々の中にドヨメキが起こり始めたのだ。
「同志諸君! 我らが一年間に渡って積み重ねた信仰の証しにより、遂に約束された奇跡が示される! 今宵、偉大なる力が発動するのだ! 」
語っている黒ローブの顔は見えないが男の声だった。
尾藤を捕えた男たちと同様の芝居がかった口調で、この場にいる人々のテンションを持ち上げようとしている。
「長年に渡って我らを虐げ、苦しめ続けてきた愚かで罪深き者どもは罰を与えられるであろう! この薄汚れた世界は大いなる災いと苦痛に見舞われ、滅亡に向かって歩み始めるのだ! 」
そう言えば、警察に捕まっている教団の兵隊も同じようなことを言っていたらしいが、 黒ローブの言葉を簡単に言い直せば、世の中に不満を持っている連中の代わりに今夜何かが現れて復讐をしてくれるということらしい。
「しかし、信仰心厚い我らだけは、その偉大な力によって守られ、この世の高みに導かれるのだ! 同志諸君! 来るべき世界の滅亡を、歓喜を以て称えようではないか! 」
まさに、「信じる者は救われる」式のカルトだった。
うんざりするほどに典型的な新興宗教の教えである。
周囲の人々が揃ってブツブツと呪文のような祈りを唱える中、尾藤は押さえきれぬ嫌悪感に何度も身震いしていた。
そのうち無性に腹が立ってきて、信者に紛れて潜んでいる状況でさえなければ、大声で喚き散らし、唾を吐き捨てていただろう。
(ああ、うぜぇ! )
黒ローブたちを今すぐ壇上から引き摺り下ろしてやりたい衝動にも駆られた。
そうした感情が剥き出しになった尾藤の表情は、フードのおかげで誰にも見られていないが、もし見られてしまったなら直ぐに正体を見破られてしまっていたに違いない。
この時、尾藤は場の雰囲気に気を取られ過ぎてしまっていたらしい。
現在の自分の姿が完全に周囲に溶け込んでいるものと思い込み、油断していた。
だから、突然背中に硬いモノが押し当てられた時には、身の危険よりも自分の甘さに対する後悔と腹立ちの方が先に現れていた。
「静かにしなさい。」
耳元で囁く声がした。
聞き覚えのある声。
それは、夢の中で何度も聞かされた女の声ではないか?
だが、直ぐに思い直した。
その声の主が夢の女ではなく、現実に存在する「シクラニ」の女性店員のモノだということが分かったからである。
尾藤にヤドリギの枝を渡した、あの女性店員である。
「黙って、後ろに下がりなさい。」
尾藤は指示に従うべきか迷った。
隙を見付けて反撃の機会を探ろうとした。
その考えを察してか、背中に押し当てられる凶器らしきモノには有無を言わさぬ強い力が込められた。
「これは熊用のスタンガンよ。余計な事を考えないこと。」
この場に集まる人々の最後方に位置していた尾藤は言われるがままに後退りし、下り階段の降り口に立たされた。
「降りて。」
少しだけ広い空間に出られたので、この女を力任せに突き飛ばすか、一気に階段を飛び下りるかすれば、逃げ出せるだけの距離が生まれそうだった。
但し、その後で一〇〇人もいる教団関係者の中をどうやって逃げ切るかまでは考えていないという注釈付きの行動であるから、これを迂闊に実行するわけにはいかない。
(それにしても、この女の様子は変じゃないか? )
女は教団関係者であり、侵入者である尾藤を捕えたという褒められるべき状況にある。
しかし、彼女は尾藤を人の群れから連れ出すにあたっては、何故か周囲に気付かれないようにと注意を払っていた。教団幹部や他の信者に協力を求めようともしないし、引き渡そうとする意志も感じられない。
ただ、尾藤を自分の指示に従わせようとしているだけだったのだ。
「早く降りなさい! 」
なかなか動こうとしない尾藤に対し、女は少し焦るような口調で言った。
「私に敵意は無いから安心しなさい。だから今は黙って言う通りにすれば良いのよ。」
敵意が無いと言いながら、背中を突く力は徐々に強まっている。
「敵意が無いなんて、ホントかね? 」
尾藤は反撃を一時的に思い止まることにし、女の指示に従ってみることにした。
「どういうことか、話を聞かせてもらおうか! 」
背中を圧迫していた凶器から解放され、女と向かい合った尾藤は憤然と言い放った。
互いに顔を晒し、正面から相手の顔を凝視している。
緊迫した状況にありながらも、女の容姿はついつい見惚れてしまうほどに美しく、できれば敵対したくない相手だと思ってしまうのだが、私情を絡めている場合ではない。
女は階段を地下二階に降りてくるなり、尾藤を映画館の中に連れ込んだ。
この映画館はイベントホールも兼ねており、スクリーン手前にはステージが置かれ、その両袖には演者が出待ちするためのスペースが設けられていた。
今、二人は分厚いカーテンによって客席の目より遮られたステージ上手の袖にいる。
(まったく、わけが分からん! )
足元には男が一人倒れているが、これは女が袖に入るなり尾藤の背に押し付けていた殺傷力の高いバトンタイプの高出力スタンガンで倒したのである。
何の確認もせずに、その場にいた男の心臓にスタンガンを突きつけ、有無も言わさず、ヒグマなどの大型野生動物でさえ気絶させるほどの最高出力の電撃を見舞ってしまった。
「こいつは指導者の一人で会場の見張り番よ。」
そうするのが当然といった口調で吐き捨てたが、彼女も教団関係者だろうに、これは明らかな敵対行動である。
(仲間割れって感じでもないよな? )
戸惑いを隠せないでいる尾藤に、女は平然として言った。
「助けてあげたんだから、お礼の一言ぐらい欲しいと思うわ。」
女は、その美しく整った顔の中で特に印象的に見える大きく黒い瞳で尾藤を真っ直ぐに見据えながら、右手の人差し指で尾藤の胸を小突いた。
尾藤は、その指を払い除け、逆に女を指差す。
「礼だって? わけがわからん! まずは、この状況をキチンと説明するのが先だろ! そのうえで必要だと思ったなら礼ぐらい行ってやるさ! 」
場所が場所だけに尾藤も大声で噛みついたりはしないが、その顔を見てもらえれば激しい剣幕が十分に伝わるだろう。
女は両手を広げてヤレヤレというポーズを作った。
「もう、時間が無いってのにまったく! 」
舌打ちが聴こえた。
「お前、そもそも俺が誰だか分かってて助けたのか? 」
「分かってるわよ、探偵さん。」
女はわざと生意気そうな言い方をして口角を上げた。
「探偵って言うなっ、調査員だ! 」
尾藤はいつもの癖で訂正を求めたが、無視された。
「貴方は、あの女の子を助けに来たんでしょ? 私が手伝ってあげるわ。」
突然の協力申し出に尾藤は唖然とした。
(どうして、この女が俺に協力なんかする? )
当然、喜んで受け入れられるわけがない。
疑って掛るに決まってる。
「まあ、疑うのは当然ね。アディティヤさんもそうだったし。」
「アディだって? 」
何故、女はアディの名前を知っているのか?
「彼は、このビルの外で待機して貰ってるわ。嘘だと思ったら確かめてみるのね。」
女は着ていた茶色いフード付きロングコートの前を開けてペンダントヘッドタイプの携帯通信端末を取り出すと、片手で素早くボタン操作をし、現れた画面を尾藤の目の前に突き付けた。
「ほら、彼のアドレスでしょ? 」
そう言われても、尾藤は数日前に交換したばかりのアディのアドレスを未だ暗記していないので確認のしようが無かった。
「何なのもう! 掛けてみれば分かるわ。」
女は苛々しながら発信ボタンをタップして呼び出し音を確認すると、そのまま携帯通信端末を首から外して尾藤に放ってよこした。
受け取って直ぐにスピーカーを耳に当てると聞きなれた声が聞こえてきた。
「おい、何だよ? 尾藤さん、見つかったのかよ? 」
不機嫌そうな声で嫌々話している感じだが、間違いなくアディの声だった。
「おお、俺だよ! 」
尾藤が声を聞かせると、その態度は一変した。
「尾藤さん! 無事だったのね! 良かったよーっ! 」
「俺は無事だけど、何でこの女が、お前の電話番号知ってんだ? 」
「ゴメンね、僕ドジっちゃってさ。その女に見付かっちゃったんだよね。」
アディは済まなそうに言った。
自信満々で出掛けて行ったが、所詮は素人の見張り役だったらしい。
「いきなり後ろからスタンガン突き付けられちゃったから、どうにもならなかったよ。でも、彼女は僕を捕まえようとしてんじゃなくて、司廉子さんを助けるのに協力してくれるって言って、そのビルの場所を教えてくれたんだ。」
この女、背後から忍びよってスタンガンを突きつけるというのがスタイルらしい。
非力な女性としては有効な攻撃手段ではある。
「尾藤さんが捕まってるって連絡くれたのも彼女だよ。自分が助けるから心配するなって言ってた。信じられなかったけどホントだったんだね。」
そこまで話したところで、携帯通信端末は女に引っ手繰られてしまった。
「後で、また連絡するから待機しといて。 それじゃ! 」
女は音声通話を切ってしまった。
「おい! 」
「何? もう十分でしょ? 」
アディと女が協力体制にあるらしいことは分かったが、
「まだ、説明が足りないぞ。」
納得して彼女を受け入れるには情報が足りない。
「それじゃ、良く聞いて探偵さん。貴方に「ヤドリギ」の枝を渡して、このビルを探すヒントをあげたのは私。無様に捕まった貴方が監禁されてた部屋の鍵を開けたのも私。暗いと困るだろうと思って親切にライターを置いといたのも私よ。分かった? 」
女が尾藤を教団の手に渡さず映画館に連れ込んだ時点で、そんな気はしていたが、
「ポンプ室で、俺をビビらして遊んだのもお前か! 」
「へ、何それ? 」
「惚けんなよ! 」
「あなた、何を言ってるの? 」
女が馬鹿にしたような顔で首を傾げた。
「・・・違うのか? 」
女は答えないが・・・違うらしい。
ポンプ室の中で感じた恐怖が甦りそうになって、尾藤の背中に再び悪寒が走った。
(ダメだ! アレについて考えるのは止そう! )
ここが廃墟ビルということもあり、うっかり拘ってしまったら頭の中が怪奇現象の方向に向いてしまう。
今は、そんなことに気を取られていて良い状況ではないのだ。
「つまんないこと言ってないで! 時間が無いのよ。」
先ほどから女は苛々し続けている。
「時間? 」
現在の正確な時刻を確認するのを忘れていた。
「今、何時? 」
「〇時三〇分。あと二時間ほどで集会が始まるわ。」
尾藤が思っていたよりも時間は進んでいた。
女が言うように、こんな所でグズグズしている場合ではない。
急いで司廉子を見付け出し、助け出さなければならないではないか。
「あの女の子なら、ここにいるわ。」
女はステージの真ん中に向かって指をさした。
「えっ? 」
映画館の中は一部の補助照明が点いていたので完全な暗闇ではない。
幅一〇メートル奥行き五メートルほどの広さを持つステージ上の様子もボンヤリとだが見える。
ステージの中央には幅二メートルほどの演台が配置されており、その上には白布の掛った物体が乗せられていた。そして、演台の周囲を今は未だ点灯されていない六機のスポットライトが客席側に開いた半円状に取り囲んで・・・
(夢で見た! ここで儀式が行われていたんだ! )
演台の上に見える白布の下に何があるのかも知っている。
尾藤は演台に駆け寄り白布を捲った。
そこに現れたのは間違いなく司廉子である。
写真でしか見たことは無いが、その顔は記憶に刻み込まれていたので決して見間違えようが無い。
「司さん! 司廉子さん! 」
直ぐに抱き起して、その名前を呼んだのだが返事は無い。
体温は高く、呼吸もしているので命に別状は無い。
眠っているだけのように見えたので、肩を掴んで揺すりながら名前を呼び続けた。返事が無いまま何度も揺すっているうちに、滑らかで重みのある上等な生地で仕立てられた白布が、まるで水が流れ落ちるように解けて床に滑り落ちてしまった。
「わわっ! 」
尾藤の腕の中には一糸も纏わない全裸の少女がいた。
薄い照明の中でも、その白い肌は目に焼き付くほどの明るさを持っていて、小さく息づく乳房、下腹部に薄っすらと覗く陰毛、滑らかに曲線を描く腰から足の爪先にかけての輪郭が露わになっていた。
尾藤は驚いて、半分持ち上げていた司廉子の身体を取り落としそうになった。
「馬鹿っ! いい大人が、子供の裸ぐらいで狼狽えるな! 」
追い掛けてきた女が司廉子の身体を尾藤から奪い取り、自分の着ていたコートを脱いで包んだ。
「ゴ、ゴメン・・・ 」
素直に謝った尾藤だったが、その態度が女には面白かったらしい。
「裸に驚いてる場合じゃないのにねぇ。」
女がクスクスと小さな笑い声を立てた。
「この娘、一旦スクリーンの裏側に運ぶから手伝って。床板の一部が外れるようになってるからステージの下に隠すの。狭いけど直ぐには見付からない場所よ。」
尾藤は再び司廉子の身体を受け取って両手で抱き上げた。
けっこう乱暴に取り扱われていたと思うのだが、少女は随分と深い眠りの状態にあるようで、目を覚ます気配が無い。
「このまま逃げられないのか? 」
「無理ね。出入り口は銃を持った連中で固められてるから、私らだけじゃ突破できっこないわ。」
そう言いながら、女は尾藤を手招きしてスクリーンの裏側に回り込んだ。
そこは板壁とスクリーンの隙間にできた僅か一メートルほどの空間である。
「ちょっと待ってね。」
女は手探りで一枚の床板を探し当てると、その板の端を拳骨を握った両手で真上から押し込んだ。
すると、シーソーの原理で床板の反対側が跳ね上がり、尾藤も手伝って床板を取り外すと、そこには長さ一〇〇センチ、幅三〇センチほどの隙間ができた。
「壁に近いところの床板は湿気なんかでボロくなってるから、細工しといたのよ。」
女は尾藤を振り返ってニヤリと笑った。
「これじゃ狭いから、もう一枚外さなきゃ。」
隣り合ったもう一枚の板を取り外すと スクリーン裏の床に四角く黒々とした穴が開いていた。穴の深さはステージの高さと同じなら一五〇センチほどだと思うが、中は真っ暗なので底無しにように見える。
「この中に入れて。」
女は言うが、半裸の少女を隠すのが憚られるほど床下は不衛生に違いなく、虫や鼠が当たり前に生息していそうな空間である。
「殺されるよりはマシよ。」
確かに女の言うとおりである。
尾藤は自分が先に床下に降りて、司廉子の身体を受け取った。
真っ暗な穴に降りるのは不気味で一瞬だけ躊躇したが、もちろん底無しではない。直ぐに足が付く深さである。
「こんな不気味な穴の中で目覚めたら騒ぎ出すと思うよ。」
「大丈夫。身体を切り裂かれない限りは当分目覚めないから。この子、逃げ出さないように強力な薬で眠らされてるのよ。」
「あっ、キノコだな。マジックマッシュルームってやつ。」
「へぇーっ、良く知ってるわね。さすが探偵さん。」
探偵と呼ぶなと言いたいところだが面倒臭いので放っておくことにした。
「生贄になる女の子たちは儀式の直前までキノコ漬けにされるの。可哀そうに丸一日ぐらい連続でね。この子、後遺症が残らなきゃ良いんだけど。」
「残ったりすることもあるのか? 」
「知らないわ。儀式の後で生きてた娘なんていないもの。」
「・・・ 」
尾藤は司廉子を床下に横たえてから、女の手を借りて再びステージに上がった。
床板を元に戻し終えた後、二人は再びステージの上手袖に戻った。
「この後の作戦はあるんだろうね? 」
「もちろん。」
女は言って、今度は床に転がっている男の上着を脱がそうとした。
彼女一人では脱がすのが大変そうだったので尾藤も手伝った。
「こいつって、死んでる? 」
男の身体はピクリとも動かず、呼吸をしている様子もない。
「死んでるでしょ。そのつもりで心臓直撃したもの。」
女は当然のように言い切った。
激しい怒りを押し殺しているような口調でもあったが、アブドルを捕えた時の恵子に少し似ているような気がした。
「これって、僧服だよな。」
脱がした上着を持ち上げてみれば、それは先ほど上の階で見た幹部らしき連中が来ていた黒いローブである。
「こいつは指導者の一人だからね。さ、死体を隠そう。」
女が指導者と言うのは幹部のことらしい。
男の死体は、下手の袖に山積みされていた廃材やガラクタの裏側に押し込んでおいた。
「さて、これで良しと。それじゃ、貴方はそのローブを着て。」
尾藤に黒ローブを着るように指示すると、
「私はこっち。」
と、言いながら、いきなり着ていたモノを脱ぎ始めた。
「おい、ちょっと! 」
尾藤が止める間もなく全て脱ぎ去って全裸になると、脱いだ衣服を尾藤に渡した。
「その辺の邪魔にならないとこに隠しておいて。」
先ほどの司廉子の幼い身体を見た後で、今度は大人の女性の全裸姿である。
こんな状況でさえなければ有難く思うところだが、
「今は女の裸見て喜んでる場合じゃないでしょ。私も恥ずかしがってる場合じゃないからお互いさまよ。」
何がお互いさまなのか分からないが、女は全く恥ずかしがる素振りを見せず、演壇の上に横たわって仰向けになり、
「その白い布、さっきみたいに掛けてちょうだい。」
と、言った。
司廉子と入れ替わってどうするというのか?
代わりに殺されてしまうではないか?
「ちょっと待てよ。そろそろ、どうするつもりなのか話しても良いんじゃないか? 」
一方的に指示をするだけで女は何も話してくれない。
何か作戦があってのことだというのは分かっているが、黙って従っているだけでは納得できない。
「キチンと準備を整えてからゆっくり話したいわ。それとも、私の裸を暫く見ていたいというなら構わないけど? 」
女は悪戯っぽく笑うと仰向けの姿勢から身体を回して横向きになり、そのまま尾藤を見上げて肩肘を付いた。この姿勢を取っただけで、女の柔らかで美しい曲線を描く肢体が殊更に強調されて実に艶めかしいというのに、さらに片方の足を軽く曲げて開き加減にしつつ、小振りだが形の良い乳房を突き出すようにして尾藤を挑発する姿勢を取った。
これを見ていたくないといえば明らかな嘘になるのだが、
「馬鹿言え! 」
尾藤は慌てて白布を取り、素早く女の身体を覆った。
[一九]
一一月二四日、午前一時四五分。
都内は快晴だが見上げる空に月は無い。
既に人通りの無くなった商店街。
現在尾藤が潜入中の廃墟ビル正面、通りを挟んで向かい側にある空き室だらけのテナントビル。その非常階段五階に身を潜め、携帯通信端末を手に話し込んでいる男を中心に廃墟ビルの図面を囲み、何やら重要な打ち合わせしている数名の人影があった。
「突入は二時三〇分。本当にそれで良いんだな? 」
携帯通信端末を持ち、心配そうな声で念を押しているのは警視庁公安部総務課所属の木村警部である。
「そのタイミングでなければ、教団幹部を一網打尽にするのは難しいらしいんだ。組織を完全に潰すのが公安の役目だろ! 」
電話の相手は廃墟ビル内部に潜入中の尾藤。
今、二人は最終局面を迎えようとしている事件の決着を如何につけるか、携帯通信端末を通じて意見を交わし合っていたのだ。
木村は、尾藤が主張する段取りを信用していないわけではなかったのだが、これは非常に危険な賭けだと思っていた。
生贄が切り裂かれるのは二時三七分だという。ほんの少しでも突入が遅れたり、教団の阻止行動に遭遇し手間取ってしまったなら、手遅れになってしまうギリギリのタイミングである。司廉子だけではなく、指導者の一人に化けている尾藤、突然現れた協力者の命も危険に晒される。
「しつこいようだが、そのアイシュとかいう女の言葉、信じられるのか? 」
アイシュというのは、司廉子の代わりに演壇の上で白布を被っている例の女の名前。
出身はインド、年齢二六歳、日本の大学院生だそうである。
今、尾藤は演壇の傍らで、アイシュの携帯通信端末を使って木村と話をしていた。
「信じられると思うよ。彼女には嘘を吐く必然性が無いし、そうしなければ彼女の今後の身の安全に差し支えるってことも理解できた。」
「そうか。それならば、お前の言う通りにするが・・・ 」
「無理をするなって言うのは無し。もう既に無理な状況だから。」
尾藤は笑った。
ここで笑うこと自体、十分に無理をしている。
「分かった。もし、時間前にトラブルが発生した時には、何とかして合図をしろ。」
「合図? 」
「お前が今持ってる端末を使うしかないだろ! 着信一コールで切れても良いから直ぐに掛けられるようにしとけ。それで直ぐに突入する。」
「たぶん、それは無いと思うけど、一応了解。それじゃ、もう切るぞ。」
そう言って尾藤がスピーカを耳から話そうとしたら、
「ちょっと待って! 」
慌てて叫ぶ声が聞こえた。
「尾藤さん! 絶対に殺されちゃダメだよ! 」
ストレートな心配の言葉、アディである。
「わかったよ。長話はヤバいから切るぞ。木村によろしく。」
尾藤は続けて何か言いたそうなアディの言葉を遮って通話を終わらせた。
木村たちが使っている携帯通信端末はプリペイドカード式でアディの私物だった。
緊急事態だからやむを得ないが、木村と尾藤は互いに借り物の携帯通信端末を使って、一般回線で現場突入の打ち合わせをしている。教団内に専門知識を持っている者がいたら盗聴される可能性もあるので、これは非常に危険なことだった。
尾藤との打ち合わせを終えた木村は、傍らにいた配下の警察官に突入作戦に関する指示を与える。
木村の指示に無言で頷いた警察官は速やかに非常階段を駆け下りていった。
今、廃墟ビルの周辺には木村とアディ以外にも多数の黒い影が潜んでいた。
完全武装の公安特別機動隊二個中隊一八〇名が、小隊又は分隊毎に分かれて密かに廃墟ビルを取り囲んでいたのである。
階段を駆け下りていった男も隊員の一人だった。
ちなみに、公安特別機動隊は警視庁公安部の機動捜査隊に属する特殊部隊で、テロやスパイ活動など国家規模の武装組織犯罪に対抗することを主な任務とする。国家体制を脅かすほどの大掛かりな犯罪が頻発する昨今の情勢の求めに応じ、数年前に内閣の承認を得て成立したばかりの武装組織だが、イメージとしては特別急襲隊SATの重武装版と言ったところである。
インテリジェンス機関に所属する特殊部隊という性質上、その概要の殆どが機密扱いになっており、一般犯罪に姿を見せることは無いので市民にとっては公安警察同様に謎の組織と思われている。
噂では国防軍並みの装備を保有しているとも言われている。
今回、特別機動隊の出動要請をした木村の判断は正しい。
数時間前まで木村はアディと二人で張り込んでいたのだが、廃墟ビルに入っていく人数を数え始めたところ、あっという間に三〇〇名を超えてしまった。さらに人数は増える一方で、木村が増援の必要性を感じ始めた頃には七〇〇名前後がビル内部に入ってしまっていた。しかも、数カ所あるビルの出入り口を注意深く観察していると、拳銃や自動小銃などの銃器類を抱えた見張り役と思える男たちの姿が確認されたのである。
「あれだけの武器を何処から掻き集めたのか? 」
このカルト教団には物騒な援助者もいるということの証しだった。
たった二人で太刀打ちできる相手ではなくなっていた。
現在、敵の総数は八〇〇名を超え、規模は不明だが武装状態にある。
その敵というのは、関東一円に組織の網を張り巡らし、誘拐と殺人を繰り返すカルト教団である。
木村は、これを明らかに公安特別機動隊が出動すべき事件と判断した。
一介の民間調査会社に持ち込まれた人探しから始まった事件は、遂に木村の、というよりも公の認知する大事件とされたのである。
一時間ほど前に遡る。
尾藤は黒いローブを着込み、白布を被って演台に横たわるアイシュの話を聞いていた。
「今夜の儀式には指導者全員が集まるから、奴らを逮捕できれば教団は壊滅するわ。」
アイシュは言う。
だが、それならば今すぐにアディや木村に連絡して、この廃墟ビルを急襲させてしまえば良いのではないか?
危険を覚悟でアイシュが司廉子の身代わりになったり、尾藤が僧服を着てステージで待機する必要がどこにあるというか?
「教団の指導者は一二名。さっき一人片付けたから今は一一名だけど、彼ら全員が指導者の印である黒い僧服を着て一堂に会するのは儀式が始まる直前なの。それまでは一般信者に紛れていて、誰が指導者なのかは特定できないのよ。今の段階で警察が突入しても指導者たちは一般信者に紛れ込んで逃亡を計るでしょう。もし、捕まったとしても一般の信者と幹部じゃ逮捕後の扱いも違うし、一般信者なら運が良ければ起訴を免れるかもしれない。そんなことになったら教団はさらに地下深く潜って存続してしまうのよ。だから、指導者全員が正体を現したタイミングじゃなきゃ突入してもダメ! 」
司廉子一人を助け出したら自分の仕事は終わりであり、後は木村にバトンタッチするつもりでいた尾藤だが、いつの間にかアイシュに乗せられてカルト教団壊滅の手伝いをさせられている。
「女の子一人助け出しても仕事は終わらないわ、探偵さん。教団は敵対した者を絶対に許さないもの。女の子は後に必ず殺されるだろうし、貴方も貴方の関係者もこの先々に命を狙われることになるわ。それが嫌なら、ここで教団の動きを止めるしかないの! 」
アイシュは有無を言わさぬ口調で強く断言した。
言われてみればその通りかもしれないと思うので、尾藤は頷かざるを得ない。
「ところで君たち一般信者はトップにいる連中の顔は知らないってことなのか? 」
「指導者たちが何者かなんて一般の信者は誰も知らないわ。常に顔を隠しているもの。別に指導者だけじゃない。信者同士でも身内や知人関係にある者以外は互いの顔や個人情報を知られないようにしているの。信者同士で縦横の繋がりは殆ど無いのよ。」
「そんなんで、よく組織が成り立つな。」
この数日で、教団の組織的、計画的な犯罪行為を何度も見せつけられていた尾藤は首を傾げた。全てが何らかの命令系統と協力関係を必要とする犯行であり、情報の共有が無ければ実行は難しいと思うのだが、
「何も知らないのは一般信者だけ。上の者は下の者を完全に把握しているのよ。簡単に組織の構造を説明するけど、まず教団を直接運営している一二名の指導者たちがいて、彼らはお互いが何者かを知っているけど、これは当然ね。そして、彼らは直属の部下としてHUBと呼ばれる中間幹部を掌握している。そのHUBは教団が作った地域の区割りの中に数名づつ配置されていて、自分の所属する区割りの中にいる大勢の一般信者の個人情報を管理しているの。だから、HUBは指導者からの命令であれば誘拐でも殺人でも信者を手足のように動かすことができるわ。それが教団の命令系統なのよ。」
「うーん、なるほど。」
尾藤は頷いた。
下から上は見えないが、上から下は丸見えになってる組織というわけである。
それならば、教団の上層部に位置する連中ほど、自分たちの都合で簡単にトカゲの尻尾切りなどもできるわけで、保身には最適な構造になっている。
そんな一方的で理不尽に思える組織構造に、黙って従っている二〇万人の一般信者たちの盲信ぶりには呆れるしかない。
「それじゃ、「シクラニ」の店長はHUBというわけだ。店のチラシで信者に命令を伝えてたんだからな。」
「そういうことね。それと貴方が最初に接触した中学教師、あいつも同じ区割りの中にいるHUBよ。」
出角は同じHUBである「シクラニ」の店長と共謀して、司廉子の誘拐に当たっていたということだった。
「教団の組織的なところはだいたい分かった。次に君が教団を裏切る理由を教えてくれないか? それを聞かなきゃ、どうも落ち着かない。」
成り行きでアイシュに従ってきたが、彼女の行動は未だ目前の謎である。
「裏切ったと言われると変な感じがするけど、私はもともと教団の教えなんか信じちゃいないの。「シクラニ」の店長に誘われて自己啓発セミナーとか言うのに参加したら、それが教団の主催だったわけ。何度か呼ばれて顔を出していたら、いつの間にか教団の秘密を沢山知っちゃって逃げられない状況に陥っちゃったのよ。それ以来、信者のふりをしているけど常に逃げ出すチャンスを伺っていたわ。無理矢理逃げ出しても必ず追手が掛って殺されるだろうし、貴方が私にとって最後の望みなのよ。」
カルト教団に捕まった経緯も、そこから逃げ出したいという動機も有りがちなことで別に疑う余地は無いと思われる。
しかし、一般信者に過ぎないアイシュが、どうやって司廉子誘拐に絡んで教団を嗅ぎまわっていた尾藤の存在を知り、何故頼ろうと思ったのか?
彼女は店長たちの行動をチラシの暗号で知ってはいたとは思うが、立場的には下っ端だったろうし、実行犯ではないで尾藤の顔を知るような命令下にはいなかったはずである。
「夢で見たのよ。」
「はい? 」
唐突に飛び出したアイシュの言葉に、尾藤は驚いて返す言葉を失ってしまった。
「このところ、何度も夢で貴方と会ってるわ。だから、貴方が店に来た時には直ぐに分かったのよ。この人が店長たちが躍起になって殺そうとしている探偵だってね。」
それで、「ヤドリギ」の枝を渡したのだと言う。
しかし、夢で見た男が現実に現れたからと言って、その男を信じて大事なヒントを渡すなど常軌を逸した判断である。
夢の男と同じ顔をしていたぐらいのことなど、普通ならば単なる偶然、又は気のせいと捉えるべきことであり、自分の命を賭けるべき協力者にしようなどと考えるはずがない。
「それは自分でも不思議。でもね、貴方は信じられるって知ってたのよ。」
何の根拠も無く、ただ直感的に思ったのだと言う。
しかし、考えてみれば尾藤も散々不平を溢してきたが、ここまでのところアイシュに逆らってはいない。初対面で得体の知れない彼女の指示に、首を傾げながらも従ってきた。
それは、尾藤もアイシュが信ずべき相手だと既に知っていたからではないのか?
(そうなんだよ。俺もアイシュの夢を見ていたんだ。)
あまりにも薄弱な根拠だが、それ故に彼女を信じることにしていたのだと思う。
「君が俺と会った夢って、儀式の夢のことだよな? 」
尾藤は自分が見た夢の話を切り出した。
「知ってるの? 」
今度はアイシュが驚いた。
「俺も夢を見てる。君の顔は知らなかったが、儀式の最中に何度も耳元で囁かれたから声だけは知っていた。」
「そう、私は貴方に何度も囁いた。」
見ず知らずの二人が同時に同じ夢を見るなど、そんなオカルトめいた話は信じたくないのだが・・・
「どういうことなんだ? まさか、君は超能力者なんてことじゃ? 」
「ばっ、馬鹿馬鹿しい! そんな非常識なこと言わないでよ! 」
「なんか、インド人ってそんなイメージが無くも無い・・・ 」
結跏趺坐を組んで空中を浮遊したり、未来を予言したりとか?
「失礼なっ! それは民族差別よっ! 」
被っている白布が揺れるほどアイシュに力一杯否定されたが、尾藤も言った自分が恥ずかしくなった。
日頃の尾藤は徹底した現実主義者である。ホラーやSFは大好きだが、あくまでも娯楽としてであり、現実と混同することは愚かだと思っている。もちろん、宗教観も同様であり、その考えを基にカルト教団のような存在は集団妄想、集団恐慌の一種と断じている。
(夢の件については失言! 油断した! やっぱ、俺は疲れてるんだよ! )
この事件が無事解決したら、必ず長期の休暇を取ろうと決心した。
何処か遠くの、北海道か九州の温泉地にでも出掛けて行って、心身共に休めなければならない。
「でもね・・・ 」
アイシュが気になることを言いだした。
「この教団、何か変なのよ。」
「変って何が? 」
カルト宗教なんて大抵は変に決まっていると思うのだが、
「狂信とか盲信とかいう並みの言葉では言い表せないほど信者の熱意は凄まじいわ。知ってると思うけど私の母国は信心深い人が多いし、国民の生活習慣から思想まで、宗教が大きな影響力を持っている。でも、敬虔な信者であっても教義の全てを信じ切って、例えば予言なんかを一言一句まで疑わない人なんて殆どいない。教義に対する解釈の方法も沢山あって、宗派や学説も様々に分かれてる。私は信心って、そういうものなんだと思ってる。人それぞれ様々な信仰の形があって当たり前だってね。ところが、この教団の人たちにはブレが無いの。皆が偉大な力を発動させるためとか言って同じ方向を向いているし、違法行為や残虐行為を働くことに対しても一切の迷いが無い。」
「でも、そういうところがカルトじゃないの? 」
尾藤は二〇世紀の後半にアメリカや日本でカルト教団が起こした殺人事件やテロ事件の例を挙げた。
だがアイシュは、そうしたカルト事件とは少し違うのではないかと言う。
「そうなんだけどね、例えば一九六〇年代にアメリカで殺人事件を起こしたカルトは教祖が強烈なカリスマで信者はLSDなんかで洗脳されてたじゃない。一九九〇年代に集団自殺事件を起こしたカルトも教祖が強権を以て指導していたでしょ。日本でテロ事件を起こしたカルトもそうよ。ところが、この教団は知ってのとおり教祖がいないの。一二人の指導者も絶対的な強権を持っているわけではないしカリスマはいないのよ。入信した当初のセミナーで黙示録的な教義を語られるけど、その後は月一回偉大な力を発動させるという儀式を続けるだけ。教団の運営資金は信者の寄付によって賄われているというけど、一般の信者は一円も支払ったことが無いから金銭的な強迫感や繋がりも無いわ。全体的にボンヤリとしていて捉えどころのない曖昧な教団なの。それなのに、互いの顔もろくに知らない信者同士の結束は硬くて、さっき話した組織の命令系統は途轍もなく強固。それに、貴方は儀式を見たことがないから知らないでしょうけど、信者たちの祈りの合唱は凄まじいわ。まさに一体感というやつね。一緒の会場にいると気が狂いそうになるほどよ。」
長いこと教団内部にいたアイシュは、これまで自分なりに教団に対する観察や分析を行っていたようであり、思うところもあるようだった。
しかし、教団に対する尾藤の考え方は至って単純である。
「カルトはカルトだろ? 奴らが有害な教団だってことが分かれば、それで十分なんじゃないか? 」
それ以上、考える必要は無い。
カルトについての分析は、事件が解決した後に然るべき専門家に任せておけば良い問題だと思っている。
「私も、そう思う。でもね、ちょっと気になって考えていたのは、儀式の時に何度も見た信者たちの奇妙な一体感のこと。儀式の度に数百人の思考が、まるで一つの強力な意思に統合されてしまうみたい。儀式の会場には毎回一〇〇〇人に満たない人数しかいないけど、信者の総数は二〇万人以上もいるでしょう。彼らは儀式の場にいなくても、同日同時刻に祈りはしているの。ということは二〇万人の思考が一つに統合されているってことなのよね。この教団、そういうことが目的なんじゃないかしら。統合された強烈な思考、思念のようなものを作り出そうとしているんじゃないかしら? 」
尾藤は苦笑しながら、アイシュを窘めた。
「おいおい、それじゃ超能力の話に近くなってきたぞ。」
アイシュは先ほど自分で思い切り否定した類の話を始めていたことに気付き、白布の下で苦笑いをしていたようである。
「でも、思考や思念に物理的なエネルギーがあって、それが二〇万人分も集まったらってSF的に考えたら凄いわよね。山ぐらい動かせちゃうかも。」
アイシュは恥ずかしそうにしながら最後は冗談を言って、この話題を打ち切った。
[二〇]
二時を過ぎた頃から、廃墟ビルの映画館には徐々に信者たちが姿を現し始めた。
この映画館の収容定員は三〇〇名ほどと思われるが、客席は全て取り払われてしまっているので、立ち見状態だと一〇〇〇人以上も収容可能なスペースがある。
信者たちはステージを正面に見る二つの入り口から五人、一〇人と固まって入ってくるのだが、皆が何らかの方法で顔を隠しているので外見から区別できるのは大人か子供かというぐらいである。
(子供か? )
明らかに親に手を引かれた小学生や、抱き抱えられた幼児の姿も見えた。
儀式の参加者には家族連れも多いという事はアイシュに聞いていたが、意外なほどの子供の多さに驚かされた。
(子供だけで五〇人近くもいそうだ。まったく、人殺しの儀式に子供を参加させるなんて、どういう神経してる親なんだか・・・ )
と、普通の感覚の持ち主ならば思うのだろうが、彼ら狂信者たちにとって神聖な儀式に自分の子供を参加させることには何の抵抗も感じられないのだろう。
(これは最悪の情操教育だよ。子供心に一生治らない後遺症を負わせてしまうことになるじゃないか。)
尾藤は、今直ぐにでも飛び出して儀式をメチャメチャに壊してしまいたい衝動に何度も駆られたが、その度に何とか堪えていた。
ところで、信者たちは会場入りする際に子供も含めて映画館の入り口手前に設えられた大きな樽の中に柄杓を入れ、水のようなモノをすくって口に含んでいる。
それが、ただの清めの水なのかどうかは疑わしい。
口に含んで映画館に入ってきた者は、少し間を置くと皆が一様に酔っ払ったような不安定な動きを見せ始めている。
(あれは酒? いや、あれもキノコか? )
そういう段取りはアイシュに聞いていなかったが有りそうなことだと思った。
Kに聞いた話ではマジックマッシュルームは大量に発注されているというから、生贄に与えるだけではなく儀式の参加者までもキノコ漬けにされるのかもしれない。
幻覚剤や酒で理性を失った催眠状態にある狂信者の集い。
(それって、魔女の夜宴、サバト? )
サバトは中世ヨーロッパで行われていたと伝えられる悪魔崇拝の集会である。
霊媒が自らの身体を悪魔に憑依させ、参加者は麻薬や酒で得た陶酔感のもとに神を冒涜し、黒ミサ的な生贄の儀式を行い、人肉を喰らい、乱交を行う背徳の集会とされる。魔女狩り時代に行われていたとされるが、文献に書き残されている内容は殆どが虚構であり、それが実際に行われたという記録も証拠も残されていない。
現代で言うところの都市伝説の類だろうと言われている。
(こいつら、サバトを再現しようとしているのか? )
そうだとすれば、かなり稚拙な志向を持った教団ではないだろうか?
ちなみに、現代の悪魔崇拝は宗教的信条として実際に存在するが、それらの殆どは理論的であり、思想的でもある。悪魔主義者たちは神を否定し疎んじているが、決して悪魔が地上を支配することを望んではいないし、暴力的でも無い。悪魔主義者の中には悪魔さえも否定し、あらゆる宗教的教えに従うことを拒否し、自己中心的に、無理せず自然に生きることを是とするだけの平和主義的な団体もある。
だから、現代の悪魔信仰ではサバトのような儀式など存在しない。
サバトの存在を真顔で信じるような連中は、そもそも悪魔を宗教的な概念として捉えてはおらず、小説やマンガ、テレビ、映画、ゲームなどで憶えた虚構を基にした悪のオリジナルキャラクターとでも考えているに違いない。
今、目の前にいる連中がサバトを実際に行おうとしているのなら、空想の世界と現実の見境を失った馬鹿げた妄想集団である。
(一般的な宗教とか信仰というものとは少々違うような気がしてきた。)
アイシュが首を傾げていた教団の不自然な点が見えてきたような気がした。
これまでは、既存の宗教を選り集めて格式を作り、信者たちには終末論的な教義を与えて救済を求めさせるという基本的なイカサマカルトのセオリーを踏襲している教団だと思っていた。だから、彼らが行う生贄の儀式とは、過去の凶悪なカルトが信仰上の必然であるとして引き起こした様々なテロや連続殺人などの暴力行為を、格調高い儀式という形に置き換えただけであり、基本的に同質のモノだと考えていたのだが、
(それは違うかもしれない。)
そもそも、教祖がいないとか信仰の対象が明確ではないとか考えることが間違いで、このカルトは信仰を基にした団体ではないのかもしれない。
尾藤は木村が取り調べで聞いたという様々な宗教のフレーズを思い出していた。
キリスト教やイスラム教などで用いられる説教が、部分的とはいえ殆どそのままの言葉で登場していたという。
(イカサマなカルトであっても寄せ集めてきた教義を独自の解釈で再構築ぐらいするだろう。他の宗教の教義を自分らにとって都合の良い内容や結論に置き換えぐらいするはずだ。いくらなんでも聖書やクルアーンの有名なフレーズを、そのまま使うってことは無いんじゃないか? )
アイシュは、教団独自の教えというべきものは非常に曖昧で、定期的に行われているのは生贄の儀式のみと言っていた。
(実は、この連中、何も教わっていないんじゃないか? )
個々の信者が言うところの「偉大なる力」とは、キリスト教、イスラム教、仏教など、其々の神が発する力ことであり、新たに教団から提供された神の力ではない。皆が共通認識する同一の神と言う存在は無く、『偉大なる力』という単語だけが共通で用いられているだけであり、その力の源になる神は各自が其々自前の信仰で賄っているのではないだろうか。
(この教団に、信仰の柱となるべき神は存在しない? )
そうなのだとしたら、このカルトは宗教団体ではなく宗教的な生贄の儀式を執り行うためだけの集団である。
参加者は儀式を見物し、その結果を独自の価値観や信仰心を以て消化し、受け入れているのかもしれない。
(まさしく殺人サークル! )
もちろん、完全に宗教と切り離されているというわけではない。
中心にいる指導者たちには何らかの信仰や信念があるような気もする。
指導者のセリフの中には参加者の信仰心を煽るような言葉もあった。
これまで集めた情報によると儀式の主旨に終末思想が絡んでいるのは間違いないし、救済を求めて儀式に参加し、これを自らの信仰としている者も少なからずいるに違いない。
しかし、それは教団を維持するためのポーズ?
(それがこのカルトの目的じゃないってことだ! )
では、このカルトの目的とは何か?
(偉大な力の発動、それも悪魔的な力を発動させること。)
一二名の指導者とは、世界中の宗教やメディアにおける悪魔的なモノを呼び出すための手段や方法論を集めて儀式の形を作り上げた研究者、演出家たちではないだろうか。
(異教徒同志が、神さまじゃ纏まらないけど、逆に悪魔なら纏まれるってこと? )
如何なる信仰にも悪の象徴は必ず存在する。
キリスト教であればサタン、イスラム教ならシャイターン、仏教ならマーラ、民間信仰も含めればあらゆる宗教には多数の悪魔が存在する。そして、神の教えについて各宗教ごとの隔たりは大きいが、悪魔に関する認識については意外に隔たりが少ない。
それは、民族や生活環境が異なっていても人としての理性や道徳観はほぼ共通しているということの表れでもあり、特に現代社会に於いては人が忌み嫌う悪の認識やタブーは世界的に共通する。
つまり、悪魔という考え方を上手に料理すれば、既存の伝統的な宗教の信者を引き込んでカルトを作ることが可能なのかもしれない。
(でも、仮に悪魔的なモノを創造して、その後はどうする・・・ )
人が集まって集団を結成している以上、何らかの目的があるはずで、それが見えなくなってきた。
(分からんなぁ・・・ )
尾藤が深く被ったフードの内側で悩んでいるうちに、映画館の中は一〇〇〇人近い儀式の参加者で満たされていた。
遂に時刻は二時三〇分をまわった。
あと数分で新月の時刻になる。
儀式の始まりを待つばかりになったステージの上には、尾藤を含む一二名の黒いローブを着た者たちが、白布を被って横たわるアイシュを中心にして左右に六名づつ等間隔で並んで立っていた。
尾藤の位置はステージのほぼ中央で、アイシュの右隣の位置である。
左端に抜きん出て大きな黒ローブ姿が見える。ローブを着ていても分かるほどのガッチリした筋肉質の巨体であり、身長は二メートル前後、体重は一〇〇キロを軽く超えているだろう。
(あいつ、俺を担ぎ上げてポンプ室まで運んだ男だな。)
そして、尾藤の反対側、アイシュの左隣に立っている者が儀式の主役であり、おそらく一二名の指導者の中でもリーダー格を務めていると思われる。
(こいつは、たぶん出角の殺害や俺を燃やしてしまえと指示してた年配の男だ。)
その男は尾藤よりも頭半分ほど背が低く、少々猫背気味の姿勢で、その手には三〇センチほどの長さの抜き身の短刀が握られていた。
(あれで、生贄を切り刻む。そして・・・ )
アイシュの横には今は何も乗せられていない銀の盆が置かれている。
(切り取った生贄の身体の一部を盆に乗せて捧げる! )
信じられないことだが、尾藤が夢で見たままの儀式が始まろうとしていた。
尾藤の背に、止まらない冷や汗が幾筋もの流れになって滑り落ちる感触があった。
(予知夢だって? 有り得ない! )
だが、夢の中の女であるアイシュと現実に出会ったことから、既に有り得ない出来事に遭遇してしまっているわけで・・・
(くそっ! なんだか良く分からん! こんな馬鹿げた仕事はさっさと終わらせて休暇だよ! 絶対に休暇で温泉行ってやる! )
尾藤が現実主義者の立場を守ろうと頑張っていた時、映画館内に集まった信者たちが徐々に呟きを始めた。
(合唱だ! 合唱が始まった! )
これも、夢で何度も見たので知っている。
そのうち、信者たちの呟きは見る見るうちに大きくなり、館内を埋め尽くす巨大な声の塊りになるのだ。
やはり、信者たちは各自が勝手に様々な宗教の祈りの言葉を唱えていた。
そこに、信仰の統一感は全くない。言葉も様々で、日本語、英語、スペイン語、フランス語、中国語、その他にも参加者の出身国の数だけ入り混じっている。
(・・・うっ! )
尾藤は眩暈を覚え、続いて頭痛と吐き気が伴われた。
(今まで、何ともなかったのに? )
突然の体調異変だった。
(場の異様な空気に当てられたか? )
そういえば、夢の中でも尾藤は倒れてしまったことを思い出した。
(そこまで、同じにならなくても・・・ )
ここで倒れてしまっては正体がバレてしまうし、木村たち公安の突入と同時にアイシュを助けて逃げるという段取りに支障を来たす。
どうにかして耐えなければならない。
そろそろ公安特別機動隊の突入が始まっている時刻だが、それらしき物音は未だ聞こえてこない。
(木村よ、もう捕まえなきゃならない奴は揃ってるぞ! 早く来い! )
尾藤は心の中で叫んでいた。
もっとも、ここは映画館なので防音壁に囲まれているおかげで、外の物音が聞こえる環境には無い。
しかも、今は凄まじい大合唱の真っ最中である。
突入した部隊が直上の階に達していても分からないだろう。
おそらく、隣にいる者から話し掛けられても何事かを聞き取ることは難しいほどだ。
ところが、それだけの凄まじい大合唱の中で一つだけ館内に響き渡る声があった。
「Our Mighty Power ! 」
それは儀式の始まりを告げる男の声だった。
明らかに発しているのはアイシュの左隣で短刀を握っている者である。
短刀を持つ手で頭上を指し、この男の声は、どういう声質なものか全く大合唱に遮られることなく耳に届いてくる。
(あの時の男の声に間違いない! )
テーザーガンに撃たれた尾藤を、ポンプ室に閉じ込めておくよう大男に指示していた年配の男の声である。
そう言えば、随分偉そうな態度の男だったが、カルト教団のリーダーだったらしい。
「Praise be ! 」
男が館内の人々に呼びかける度、合唱のボリュームは一段と高まる。
大人も子供も、女も男も、只管声を張り上げて、聖書やクルアーンの一節を唱え、経を読み、祝詞をあげる。
全くの無秩序だが、奇妙な一体感が会場の全員を包み込んでいる。
いつの間にか彼らの声は徐々に混じり合い、合唱と言うよりも巨大で凄まじい咆哮へと変わっていった。
(何だ? この吠え声は? )
明らかに合唱は人間性を失っていた。
今館内に響いているのは、荒れ狂う暴風や火山が噴き放つ炎の鳴動のようでもあり、建物や土砂が崩れ落ちる破壊音にも似ていたが、それが獰猛で悪意に満ちた一匹のイキモノの咆哮に聞こえてきた。
(なんなんだ? こいつらいったい何者なんだ? )
果たして人間の口から、これほどの凶暴で野蛮な音声を発することができるものだろうか?
(もうダメだ! 我慢できない! )
尾藤の目の前の空間が歪み始め、ハンマーで後頭部を連続して殴られているような激しい頭痛が続き、もはや立っていられる状態ではなくなってきた。
尾藤は遂に頭を抱え、苦痛に耐え切れず、その場で膝を突いてしまった。
「・・・? 」
まず、ステージ上にいた指導者たちが一斉に尾藤を振り向いた。
次に、館内を埋め尽くしていた咆哮が止んだ。
「何者っ? 」
リーダーの男が叫ぶと同時に、
「探偵さん! 」
甲高い女の悲鳴のような叫び声が聞こえ、白布を払って飛び起きた全裸のアイシュが尾藤に駆け寄って、そのしなやかな腕で肩を抱きかかえた。
これは信者たちにとって予期せぬ異変だった。
館内は一斉にどよめき、今未明の儀式は中断、いや失敗したのである。
異分子である尾藤の侵入を許して、生贄の少女が別な女に摩り替ってしまっていたのでは、もはや儀式の続行は不可能である。
「おのれ! なっ、なんということを! 」
短刀の男の声が怒りと憎悪に震えていた。
男の怒りは他の指導者にも瞬時に伝わったらしく、忽ち尾藤とアイシュは一一名の黒ローブたちによって取り囲まれた。それに呼応してステージの下にいた一〇〇〇人が、二人の逃げ道を塞ぐように押し寄せてくる足音も聞こえた。
「神聖な儀式を台無しにした罪は、その命で償ってもらうしかない! 」
男が手にした短刀を一振りすると、三名の黒ローブが尾藤とアイシュを取り押さえようと前へ進み出た。
「もう、ダメ・・・ 」
尾藤の耳元でアイシュの諦めの囁きが聴こえ、肩に掛った彼女の手に力が籠められるのが分かった。
これで万事休すと観念したのだろう。
しかし、尾藤は観念などしていなかった。
(公安が突入するまでの時間稼ぎをすれば良いだけだ! )
深く被ったフードの奥で不敵な笑みを浮かべながら、
「俺の背中にくっ付いてろよ・・・ 」
そうアイシュに囁いた。
「え? 」
アイシュは、体調に異変をきたして蹲っている尾藤が、いったい何を根拠に強気の発言をするのか分からないという顔をした。
それをアイシュが言葉にして問うよりも、尾藤が動き出す方が早かった。
片膝を突いたまま、もう片方の足がステージの床を這うように伸ばされ、不用意に前に進み出た二人の黒ローブの足を同時に払って激しく転倒させた。
そして、直ぐに立ち上がると懐の中に隠し持っていたアイシュから預かった高出力スタンガンのトリガーを引き、目の前で起きた逆転劇に呆然としていた、もう一人の黒ローブに押し付けた。
目前の三人が忽ちのうちに倒されてしまったことは黒ローブたちを驚かせたが、ゆっくりと立ち上がって身構える尾藤の背に張り付いていたアイシュをも呆然とさせていた。
「もう、大丈夫! 」
まったく原因不明だが、合唱が止むと同時に尾藤を苦しめていた眩暈も頭痛も吐き気も嘘のように消え去ってしまっていたのだ。
「これなら木村が来るまでの時間稼ぎに、一暴れぐらいできそうだよ。」
尾藤は、暴れるには邪魔になりそうな黒ローブを素早く脱いでアイシュに渡した。
「こういう状況じゃなきゃ嬉しんだけど、今は目のやり場に困るから、取り敢えず着た方が良いよ。」
「あ、うん。」
アイシュが素直にローブを受け取り、頭から被った。
今は心の余裕が無いのだろう。大胆な作戦を立てて、尾藤を指図していた時の気丈さと生意気さな口の利き方は忘れてしまったようだ。
「さてと、次は誰だ! 」
尾藤はスタンガンの火花で周囲を取り囲んだ黒ローブの男達を威嚇していたのだが、
「あれ? 」
火花が徐々に弱くなり、そして消えた。
トリガーを引き直しても何の変化も無い。
「電池切れ! 」
高出力なだけあって、連続使用は通常のスタンガンよりも短かったらしい。
尾藤は即座にスタンガンを諦めて床に捨て、代わりに尻のポケットに差していたバタフライナイフを取り出し、手元でクルクルと回しながら派手なナイフ裁きをして見せた。
(アクション映画を観て、散々裁き方の練習したかいがあったな。)
そのナイフアクションだが、黒ローブたちの気勢を弱めるには多少の効果があったようで、尾藤たちを取り囲む輪が一歩か半歩分広がったような気がする。
(痛い思いはしたくないだろう。)
しかし、全く意に介さない者もいた。
尾藤を担いでポンプ室に放り込んだ、あの大男である。
大男は、その巨体を丸めて、相撲のブチかましのような姿勢で尾藤を目掛けて突進してきた。
「うぉっ! 」
尾藤はアイシュを抱いたまま床を転がって突進をかわした。
その際に、尾藤はバタフライナイフを大男の腰の辺りに突き立てたのだが、その効果は全く見られなかった。
ブレーキを掛け損ねた大男のブチかましは、勢い余って尾藤の背後に控えていた二人の黒ローブを撥ね飛ばし、不運な黒ローブの一人はステージの袖まで飛ばされ、もう一人はステージの下に転げ落ち、共に気絶してしまったようだ。
凄まじい破壊力である。
バタフライナイフは尾藤の手からもぎ取られ、大男の腰骨の上に根本までしっかりと刺さっているのに、大男は何のダメージも受けて無いようで平然と次の攻撃に移る準備をしている。
全身を覆う筋肉が厚すぎるのだ。
「バケモノめ! 」
尾藤が吐き捨てると、
「殺してやる! 」
と、大男が返した。
もう一度ブチかましをやる気でいるらしい。
最初の一撃は運良く躱せたが、まだ動ける黒ローブが七名もいる狭いステージ上には逃げ場は殆ど無い。だからと言って、大男の突進をモロに受け止めたら尾藤もアイシュもバラバラになってしまいかねない。
「大ピンチだ! 」
大男が雄叫びを上げながら、再び身体を丸めてブチかましの姿勢を取った。
その時、
ガッ、ガン!
ステージの上に硬くて重い物体が落ちた音がした。
ゴロッ、ゴロッ!
物体の転がる音もする。
「あっ! 」
その場にいる者の中で、音の正体に気付いたのは尾藤だけだった。
大男はブチかましを仕掛けるために狙いを定めている真っ最中であり、他の黒ローブは巻き添えを食わないように大男の動きを見張っている。
ステージの下にいる人々には何も見えていない。
「目を閉じて! 耳を塞いで! 口を開けて! 」
尾藤が背中のアイシュに向かって叫び、自分も耳に手を当てた。
次の瞬間、ステージを中心にして一〇〇万カンデラの閃光と、二〇〇デシベルの爆音が轟いた。
公安特別機動隊の閃光発音筒が凄まじい威力を発揮した瞬間である。
[二一]
一一月二四日、午前三時過ぎ、JR荻窪駅に程近い商店街。
大して広くもない表通りの車道が、多数の警察車両で埋め尽くされている。
これは、付近の裏通りや路地も同様。
もちろん、商店街に通じる交通は完全に遮断されていた。
停車中の警察車両は、回転灯を点けっ放しにした各種パトカーや装甲車、ところどころに消防車の姿も交じっているが、最も多いのは護送用車両である。見える範囲内だけで二〇から三〇台は停まっており、どの車両も身柄を拘束された大勢のカルト教団関係者でパンク状態だった。
車種は大型バスタイプからマイクロバスタイプ、さらには小型のワンボックスやミニバンタイプの車両までが混在しているところを見ると、手近で手配できる限り全ての護送車両を短時間で掻き集めた担当者の努力が伺える。杉並署管内の護送車量の殆ど全てが出動し、それでも足りなくて近隣の所轄からも緊急動員されたであろう台数である。
現在、これら多数の警察車両が廃墟ビルを取り囲む中、大勢の制服警察官や公安特別機動隊員と思しき重装備に身を包んだ武装警官が、引っ切り無しに建物の出入りを繰り返して、忙しなく周辺を走り回っていた。
既に作戦は終了していたのだが、事後の始末にはまだまだ時間が掛りそうである。
この騒然とした現場から、多数の停車した警察車両の隙間を縫うように走り去る一台の救急車があった。
救急車には廃墟ビルから無事救出されたものの、大量に服用させられたマジックマッシュルームの影響で未だ意識の戻らない司廉子が乗せられていた。
(助かってくれよ・・・ )
尾藤は心の中で手を合わせながら、これを見送っていた。
既に司夫妻には娘が救出されたことは連絡済みなので、搬送先の病院で親子は再会できるだろう。
事情聴取が未だなので現場を離れられない尾藤の代わりにアディを同乗させておいたので、娘が救出された際の状況は彼の口から両親に伝えられるはずだった。
果たしてマジックマッシュルームが少女の身体にどの程度の影響を与えたものか見当もつかないが、おそらく命に別状は無いだろうと語った救急隊員の言葉と、これから治療に当たる医師たちの腕を信じて待つしかない。
決して無事救出とは言えない状態かもしれないが、取り敢えずは司廉子が生贄にされるという最悪の事態からは救い出すことができた。
尾藤が調査員として請け負った仕事は、これで終了したのである。
廃墟ビル入り口に横付けされた装甲車に凭れて煙草を吹かしていた木村が、近付いてきた尾藤に向かって、
「一服やるか? 」
と、シャツの胸ポケットから潰れかけた煙草の箱を取り出した。
「いや、知ってんだろ、禁煙中だから。」
尾藤が手を振って断ると、
「ああ、そうだったっけ? 」
と、惚けてから箱を胸ポケットに戻し、肺に溜まっていた煙を満足げに吐き出した。
「言ったよなぁ、先月から煙草は止めたって。」
尾藤は木村が吐き出す煙を煩そうに手で払った。
「煙草止めたってなぁ、お前は生活がだらしないから健康にはなれないぞ。」
尾藤は苦笑いしながら、木村の隣に立って自分も装甲車に疲れた身体を凭れ掛けた。
「別に健康のためじゃない。今時、二〇本入り一箱一〇〇〇円以上もする贅沢品を吹かしてられるのは、お前みたいな高給取りだけだって。」
そう言われた木村は、鼻で笑ってから短くなった煙草を携帯灰皿に捻じ込んだ。
「これは主義の問題さ。俺は一箱二〇〇〇円になるまでは止めないぞ。」
「ちぇっ、どんな主義だよ。贅沢モンめ! どうせ言うなら一〇〇〇〇円までは止めないって言えよ! 」
漸く一息ついた心持ちになっている二人だったが、その周辺は相変わらず走り回る警察官たちと野次馬やマスコミを追い払う拡声器の声で実に騒々しかった。しかし、それらは大きな事件が解決した後には付き物の風景であるから、眺めていると何となく気持ちが落ち着いてくる。
「ほれ、これはアディから渡されてたんだ。」
木村が、ジャケットのポケットから中身の入ったスーパーのレジ袋を取り出して尾藤に渡した。
「ああ、サンキュ。」
袋の中身はスティックキャンディだった。
一〇本ほど入っているが、アディが近場で見付けて買っておいてくれたらしい。尾藤が無事に脱出できたなら渡そうとしていたらしいが、これは嬉しい気遣いだった。
カルト教団に捕まって手持ちの分は取り上げられてしまったので、一〇時間以上ぶりのご対面である。
「ロケットフィズか。そんなモノを喜んで食う日本人の大人がいることが信じられないよな。」
早速一本取り出して包みを破いた尾藤を見て、木村が馬鹿にした。
「ふん、煙草吸うより安上がりで全然良いよ。」
尾藤は気にせず口に入れた。
相変わらずの強烈な甘さが、疲れた身体に染み渡って心地良い。
「まあ、お前は民間にしては良くやったと思うよ。」
木村はキャンディを咥えた尾藤の姿が見苦しいと思っているのか、視線を真っ直ぐ前に据えたままでポツリと言った。
「え・・・? 」
尾藤は、滅多に友人を褒めることの無い木村の意外な言葉に戸惑った。
「いやいや、お褒めに預かり光栄ですねぇ、警部どの。」
ついつい茶化して返したら、
「ふん! 」
と言ったきり、木村は暫し黙り込んだ。
「ところでさ・・・ 」
話し掛けても返事が無い。
ふと見ると木村は腕を組み、俯き加減で考え事をしているような姿勢を取っているが、その眼球だけは周辺を走り回る警察官と同じぐらいに忙しく所を変えている。
視線の先を追ってみると、拘束した教団関係者を護送車に詰め込む警察官たちの手際を観察しているようだった。
武装しているとはいえ、拘束した一〇〇〇人に近い人数を、その三分の一にも満たない数の警察官たちで大小様々な護送車に振り分けるのだから、これは大変な作業である。
中には、逃げ出そうとして暴れる者がおり、これを後々問題にならないのかと心配になるほど手荒に抑え込む。黙秘権がどうのとか弁護士を呼べとかハリウッド映画でよくあるミランダ警告的な逮捕者の権利を主張する者もいるが、これは「馬鹿野郎」「映画の見過ぎだ」「ここはアメリカじゃない」などと怒鳴りつけて護送車に放り込んでいる。
こうした現場の様子を木村は全く動じずに黙したまま見守っている。
その些か冷静過ぎる表情は、全く無感情に見えて尾藤でさえも不気味に感じてしまう。
(なんて目付きだよ。こいつも、すっかり公安が板に付いて来たな。)
善良な一市民にとって、大東亜戦争中の特別高等警察の流れを汲むと言われる公安警察は非日常的な影の存在であり、関わり合いになりたくない種類の人間だと思われている。
当り前のことなのだが組織の実態と活動内容が不明瞭であるため、左翼系団体や人権保護団体、さらには各種市民団体から明確な根拠も無いままで批判や敵意の対象になりやすく、前身とされる特高警察の負のイメージを盛られることも多々ある。
もちろん、置かれている時代性は全く異なるのだから二一世紀半ばの公安警察を一世紀も昔の特高警察などと同列に扱うこと自体がナンセンスであり、組織の性質も役割も全く異なるのだが、それならばCIAやFBI、旧KGBなどのインテリジェンス機関と比較してはどうかと問われたら専門家でもない限り答えられるものではない。日頃携わっている業務の一部に共通性があり、扱う案件の規模、危険性や秘匿性の高さに関して言えば同種の組織かもしれない。
尾藤が見る限り、そういった事情を抱えた公安警察官は、その外見や言葉遣い、さらには性格まで、普通の警察官には見られない独特の危うい雰囲気が漂って見える。
それは一般人には不必要なほどに優れた観察眼、警戒心の高さ、時折垣間見える防衛本能と攻撃性によって形作られたオーラと言っても良いだろう。
(まあ、こいつは公務遂行中だからな、しゃーないわ。)
尾藤は木村の真顔を見ながらヤレヤレと溜息を吐いた。
警視庁公安部の警部としては、これからが本番というわけだ。
木村には悪いが、既に尾藤は仕事を終えた解放感を味わっていた。
これから面倒な事情聴取が待ち受けているものの、自身の仕事に対する責任は果たし終えているので、スッキリしたものである。
ところが、
「おい、尾藤。ちょっと付き合え。」
いきなり木村が顎を杓って尾藤に付いてくるように言った。
問答は無用といった強い口調である。
「へ? どこ行くんだよ。」
逆らうつもりはないが、何処に連れていかれるのかぐらい教えて欲しい。
「こっちだよ。」
そう言って木村は足早に廃墟ビルの正面入り口を通って中に入っていく。
事後処理中の警察官たちと擦れ違う度に「ご苦労さん」と一々声を掛けながら、木村は真っ直ぐに映画館のある地下二階へ向かった。
これに尾藤は黙って後について行くしかない。
開けっ放しにされた映画館のドアを抜けて館内に入ると、そこでは一〇名前後の警察官が現場検証の真っ最中だった。証拠集めをする者、ビデオカメラを構えて歩き回っている者、皆が館内に散らばって忙しそうである。
「こうして見ると、けっこう広いな。」
儀式の最中はスポットライトに照らされたステージ上だけが明るく、客席は薄暗がりの状態だった。
終始明るいステージ上にいた尾藤からは、客席の様子など大小様々な人間の頭が蠢いていたという程度にしか見えておらず、距離感も曖昧にしか捉えられていなかった。
だが、今は警察が持ち込んだ数台の投光器のおかげで、日中の屋外並みに明るい。
そうした環境で改めて眺めてみると、椅子が取り払われて床だけになった映画館の中は学校の体育館ほどもある広々とした空間である。
「こりゃ、現場検証もたいへんだぁ。」
尾藤は、だだっ広い館内で細かな作業を続けなければならない警察官たちに同情した。
「ところで? 」
入り口を潜って直ぐに立ち止まり、ズボンのポケットに手を突っ込んだまま動かない木村を振り返った。
「・・・ 」
木村は無言である。
「おい、何とか言えよ。」
尾藤が面倒臭そうに言うと、
「ちょっと待て。今、考えてる。」
木村はブツブツと独り言を呟き始めた。
眉間に深い皺を寄せ口元を尖らせた難しげな表情は、考え事をしているというよりも現状に何か不満が有りそうな雰囲気である。
「まあ、良いけどさ。」
尾藤は溜息を吐いた。
それから一分ほど木村の呟きが続いた後、漸く声が掛った。
「おい。」
「ん? 」
昨日から満足な睡眠を取っていなかった尾藤は立ったままウトウトしていたので、思い切り気の無い返事をしてしまった。
しかし、木村は尾藤の様子などお構いなしのようで、怒りもしない。
「お前、儀式の首謀者は黒服の一二名だって言ってたよな。」
「あ、うん。そうだよ。」
「そのうちの一名は、お前らが始末したんだよな。」
木村がステージ上に向かって顎を杓ったが、そこには未だ運び出されていない黒いボディバックが置きっぱなしになっていた。その中身はアイシュが最大出力のスタンガンで倒し、尾藤が黒ローブを奪った男が入っているはずだった。
この男が本作戦に於ける唯一の死亡者ということになる。
ちなみに公安特別機動隊の制圧作戦は実に鮮やか、しかも迅速であり、最小限の発砲と閃光発音筒により、多数の負傷者は出したものの死者は一人も出さず、儀式の参加者全員を拘束することに成功していた。
まさにプロフェッショナルの仕事である。
(しょうがないよ。うちらプロじゃないし。)
尾藤は内心で開き直り、木村の苦言を待った。
ところが、
「別に構わんさ。どうせ正当防衛だろう。」
木村は簡単に言い切った。
事情聴取が未だなので、尾藤は男を殺した際の詳しい状況説明など殆どしていない。
だから、木村は何も知らないはずなのだが、尾藤たちを攻めるような素振りは全く見せなかった。
「だが、全員捕まえられたのか? 」
木村が不安な呟きを漏らした。
「え? まさか逃げられた奴がいたりするのかっ? おい、冗談じゃないぞ! 」
尾藤は思わず声を荒げた。
指導者に一人でも逃げられれば、教団は存続してしまうとアイシュは言っていた。
そうなってしまったなら、教団を裏切ったアイシュや敵対した尾藤は命を狙われることになる。儀式の妨害と公安特別機動隊を手引きしたことにより、二人が教団の激しい恨みを買ったのは間違いない。
「いや、間違いなく黒服一一名は捕えているから問題無いはずなんだが・・・ 」
「なんだよ。ビックリさせるなよ。」
尾藤はホッと胸を撫で下ろした。
それならば、指導者を失った教団は組織としての結束を失い分解するとの目論見は成功するはずである。
木村は何処に不満を感じているのだろう?
「そこの君、ちょっと良いかな。」
木村は傍で作業をしていた警察官の一人を呼び止めた。
「はい。」
警察官が答えて木村の前に立った。
「ご苦労さん。ところで、この映画館の図面を持っていたら貸してもらえないか? 」
現場検証に当たっている警察官たちには、廃墟ビル内の見取り図と図面を配布してあるらしい。
その警察官は小脇に抱えていたA3サイズのバインダーケースを開き、映画館の図面を探して木村に渡した。
「ありがとう。直ぐ返すから。」
木村は映画館の図面だけを外してバインダーを返した。
バインダーを受け取った警官は、
「今のところ自分は必要ありませんので、図面はそのままお持ちになって結構です。」
そう言って仕事に戻った。
「さてと、」
木村は尾藤にも見えるように図面を広げた。
「普通はな、これだけのアングラな集会を開く際には万が一のことを考えて、トップにいる連中は緊急時の脱出路ぐらい用意しとくもんだ。」
「まあ、そうだろうね。」
「それが、この何処かにあると思うか? 」
「え? 」
木村に言われて、尾藤はそれを確かめるべく図面に目をやった。
この映画館の出入り口は四ヶ所。ステージから見て正面に儀式の参加者が出入りしていた観音開きのドアが二カ所、左右に一カ所づつ片開きのドアがある。
これらは緊急時の脱出路にはなり得ない。公安特別機動隊は突入時に四つのドアを全て確保し、そこから一斉に館内に雪崩れ込んできたからだ。
「ドア以外に秘密の逃げ道があるかってことだよな。」
それならば、図面を見ても参考にはならない。
「別に秘密ってこともないだろうが、ドア以外に人が出入りできる通路があるかってことだよ。例えば通気口とか。」
尾藤と木村は同時に館内の壁面を見回した。
しかし、壁面に通気口らしき穴は見当たらない。空調や換気のための設備は天井に付いているが、それらは業務用のエアコン装置であり、その奥に広い通気口が続いていたとしても緊急時に取り外した後、元に戻せるような代物ではない。
そもそも、ここは映画館だけあって天井が高い。足場を組むか梯子を掛けなければ天井に触れることもできないだろうが、そんな道具は何処にも置いていなかった。
「床はどうだ? ここから下水に繋がる排水溝があるかもしれないぞ。」
「この下にもう一階あるんだぜ。普通、下水に繋がる汚水層や本管は一番下の階にあるもんだろ。各階にも本管に通じる排水管はあるだろうけど、壁の中の配管で人が通れるほどのは無理じゃないかね。」
「うーん、それもそうだな・・・ 」
木村は口をへの字に曲げた。
「だが、調べてみないと、どうにも落ち着かん。ちょっと付き合え。」
「手伝うのは構わないけど、ちゃんと一一人全員捕まえたんなら、そんなに気にするほどのことでもないと思うんだけどねぇ。」
尾藤と木村は広い映画館内を二人で手分けして秘密の逃げ道探しを始めた。
映画館の構造上、機動隊の突入は三方向の出入り口から一斉に行われ、参加者はステージ側に追い詰められた。だから、逃げ道が設けられるとしたらステージ側でなければならないのだが、図面上ではステージ側から館外に抜けられるような通路は無い。
この映画館のステージは簡易的な構造であり、両袖に客席側からはカーテンで隠れるスペースが設けられているが、本格的な劇場のような舞台裏の構造は無いので、そこから館外へ出るには客席を通るしかない。
(木村の取り越し苦労だと思うけど・・・ )
逃げ道の有る無し以前に、機動隊の突入時には、閃光発音筒の凄まじい光と音の威力で儀式の参加者は行動不能に陥っていたはずである。目と耳を塞いでいた尾藤やアイシュでさえ、多少のダメージは避けられなかったほどなので、全く心構えの無かった者たちは視覚と聴覚を奪われてしまい逃げ出すことなどできなかったはずだ。
だが、木村が随分しつこく拘るので、尾藤も少し気になり始めていた。
(俺も確かに一一人が捕まるのを見た。儀式の参加者で機動隊の壁を突破して逃げた奴は一人もいない。上の階にいた見張りも全員捕まえたと聞いた。だが、一〇〇〇人近くもいた連中を本当に一網打尽にできたと言い切れるのか? )
儀式の参加者数を数えて照らし合わせたわけではない。
確認しているのは一一人の指導者だけだった。
そのうちの一人が黒いローブを他の者に預けて逃げ出した可能性が無いとは言えない。
心のざわめきを覚えた尾藤は、木村と一緒に本気で逃げ道探しを始めた。
客席の床や壁を一通り見たが不審な箇所は無い。古い映画館なので床はコンクリートが打ちっぱなしで傾斜も無くフラットであるが、そこにマンホール的な構造は見られない。壁も吸音壁材を剥がせば裏側はコンクリートであり、隠し扉のようなモノを設けられる場所は無いし、仮に穴を開けても映画館の周りを囲む通路に出るだけなので表で待機する機動隊員と鉢合わせしてしまうだろう。
客席の確認を終えた二人は、次にステージに上がった。
床下は、司廉子を運び出す際に機動隊員が早々に立ち入っており、現場検証の警察官も証拠探しのために散々探った後なので省略することにして、尾藤は下手から、木村は上手からに分かれてステージ上の壁面を順に探るってみることとした。
機動隊突入時の状況から、追い詰められた指導者が逃亡を図るなら、やはりステージ上に逃げ道が用意されていなければならない。
(何かあるとしたら壁板の向こうなんだけどね。)
機動隊の突入時、下手の袖は廃材とガラクタ置き場になっていたので壁は殆ど隠れて見えなかったはずである。
今は尾藤とアイシュが隠していた男の死体を取り出すために一部の廃材やガラクタが片付けられて壁が剥き出しになっていたが、
「このゴミ山を乗り越えて逃げたってことは無いだろう。」
そこで、尾藤は最初から壁の見えていた部分を調べることにした。
尾藤は適当な壁を選んで叩いてみた。
ボコボコと籠った音がするので板壁の向こうに空間があることは分かる。
スクリーンやステージを設備する際、構造上の都合でコンクリートとの間にできた隙間だと思うが、叩いた部分の隙間の広さがどのぐらいあるかまでは見当つかない。
試しに強く叩いたり押してみたりして壁板が外れるかどうか試してみたが、多少のガタつきはあっても、アイシュが床板を外した時のような細工はされていないようだった。
「ここら辺の板壁、全部引っ剥がしてみたらどうだろうね? 」
尾藤は下手にいる木村に向かって声を掛けた。
現場検証の支障になるからと却下されるかと思ったのだが、
「引っ剥がしたいところだが、そうなると道具が必要だしな。」
木村は尾藤の乱暴な提案を否定しなかった。
そして、尾藤と同様に板壁の裏の隙間が気になっているようで、端から順番に壁を蹴りつけている。
「おいおい、そうやって全部蹴ってくつもりか? 」
「取り外し可能な構造になってる部分があるなら、そこは他よりも脆いはずだからな。こうして蹴ってやれば違いが分かるんじゃないか。」
乱暴な奴だなと思いながらも、木村の言う事は尤もなので尾藤も真似して端から順に板壁を蹴り始めた。
二人掛かりで板壁を蹴り続ける音は映画館内に喧しく響き、現場検証中の警官たちは迷惑そうな顔をしていた。
「ん、おっ? 」
木村が声を上げた。
「尾藤、ちょっと来い! 」
呼ばれた尾藤が駆けつけると、木村は目の前の壁に開いた縦長の細い穴を指差した。蹴られた壁板が一枚外れ落ちてできた穴らしい。
「この壁板、他とは違って簡単に取り外しできるみたいだぞ。逃げ道かも。」
元々脆くなっている古い板壁だが、他は多少蹴ったぐらいで外れるモノではなかった。
アイシュが床板にやったように予め細工しておけば別だが・・・
「でも、こんなところから何処に通じてるってのさ? 」
木村が穴を開けた下手袖の壁はスクリーンが張られた壁の延長上にあるが、地下二階の図面によると、その裏側には何の構造もない。
分厚いコンクリート壁があるだけで、その向こうは地下二階分の深さの地面の下?
「まさか、コンクリートの壁ブチ破ってトンネルが掘ってあるとか? 」
木村は険しい顔をし、尾藤は冷や汗が噴き出すのを感じていた。
「おーい、誰かライトを貸してくれ! 」
木村が叫ぶと、何事かと驚いた警察官たちがステージに走り寄ってきた。
そのうちの一人がハンディライトを差し出す前に、木村と尾藤は穴の左右に並んだ壁板を急いで剥ぎ取って穴を広げた。
板壁を剥がすのに力はいらなかった。
少し持ち上げて手前に引けば板は簡単に外れた。
明らかに取り外しが簡単にできるような細工がされているらしい。
壁に開いた穴の中に木村がライトを向けた。
「くそっ、なんてこった! 」
「そんな・・・! 」
その穴は、木村が想定していたような逃げ道ではなかった。
奥に見えるコンクリートの壁まで僅か一メートルほどの窪みである。
壁板が外れやすいように細工されているのは確かなので、後々トンネルでも掘るつもりだったのかもしれない。だが、今のところは一時凌ぎの隠れ場所として利用するのが精々である。
そして、尾藤と木村、そして一緒に穴を覗きこんだ警察官たちは、その中に一人の人間が隠れているのを見つけた。
いや、隠れているというのは間違い、隠されていたと言うべきだろう。
穴の中にいたのは一人の男である。
折り曲げた膝の上に上半身を伏せているので人相は見えず、力の抜けた両腕をだらりと垂らし、コンクリートの壁に凭れて座ったままピクリとも動かない。
下着と靴下以外の衣服は身に着けておらず、靴も履いていなかった。
その男が生きていないことは一目で分かった。
身動きしないだけではない。
男の上半身を包む白い半袖Tシャツの肩口から胸、腹にかけてドス黒い染みが続いていおり、その染みが大量の血液によるものであることは直ぐに分かった。
尻の下には未だ乾き切っていない黒い血溜まりもできている。
木村は穴の中に一歩踏み込み、男の頭に手を添えて顔が見える程度に起こした。
「うっ、くうーっ! 」
穴を覗き込んでいた者たちの口から一斉に呻き声が漏れた。
男の喉は深々と切り裂かれていたのだ。
鋭い刃物で力任せに掻き切られたに違いない。
一見した傷の深さは首の太さの三分の二ほどにも達しており、男の頭部は切り残された頸椎によって辛うじて胴体と繋がっているという状態だった。
「仕事だ! 外にいる連中も呼んで来い! 」
木村は穴の傍にいた警察官たちに支持を出しながら穴を出てきた。
その顔は、強く噛み締めた奥歯の擦れる音が聴こえそうなほどの渋面だった。
「くそっ! 参ったな。」
悔しそうに吐き捨てながら、穴に背を向けて服に付いた埃を払った。
「あれは、誰なんだ? 」
尾藤は穴の中を見つめたままでいる。
声が上擦っていたが、それは最悪の想定が過っていたからである。
「まだ分からん。たぶんカルトの連中じゃないだろ。」
背を向けたまま木村は答えた。
ガリッ!
辺りにいた警察官たちが振り向くほどの大きな音がした。
尾藤が咥えっぱなしでいたスティックキャンディを奥歯で噛み砕いた音だった。
その後、死体の身元は直ぐに判明した。
公安特別機動隊の中で、真っ先に映画館内に突入した小隊の一員だった。
死因は見ての通り、鋭利な刃物で首を切り裂かれたことによる。
男が着ていたはずの隊員服と装備は持ち去られてしまったらしく、廃墟ビル中を探しても発見されなかった。
被害者が見付かった壁面付近の捜索により、殺害に用いられたと思われる凶器が発見されたが、それは血の付いた刃渡り三〇センチの短刀だった。
[二二]
一一月二四日、日曜日、午前。
杉並署警察署内の一室。
この部屋の広さは三坪ほどあるらしいのだが、二方向の壁がデスクトップPCやプリンターなどの周辺機器が置かれたスチール製の大型事務机と、ハードディスクなど様々な記録メディアが詰め込まれた背の高いエレクターラックで埋められているので、実に狭苦しく感じられる。
しかも、この部屋には窓というモノが一つも無く、出入り口も無骨な鋼製のドアが一枚だけという閉鎖的な構造のおかげで、黙って座っているだけでも居心地の悪い圧迫感に襲われる。
今、室内には尾藤と木村の他に二人の警察官がいた。
ただでさえ窮屈な部屋の中で、合わせて四人もの男が互いの膝や肘がぶつかり合うほどの距離感を我慢しながら、椅子に腰掛けて一台の液晶モニターに見入っている姿はかなり鬱陶しい。
しかし、尾藤も木村も部屋の窮屈さを気に掛けていられる場合ではなくなりつつある。
「次が一一人目。最後の一人です。良いですか? 」
この場でPCの操作を担当していた警察官が尾藤に念を押した。
この男の声も少々緊張気味である。
「はい。回して下さい。」
尾藤が答えると、カチッとマウスのクリック音が聞こえ、液晶モニター内で映像の再生が始まった。
流れているのは、昨夜捕えたばかりのカルトの指導者を取り調べた際に撮影された映像である。これは裁判の際に提出される資料映像の一つになるのだが、現段階では身元調査程度の聞き取りを行っているだけなので大して重要な映像ではない。
だが、モニターを見つめる男たちの顔は真剣そのもので、首を前に突き出し瞬きをする間も惜しむように映像を凝視している。
今流れている映像の中で取り調べを受けているのは頭の天辺が禿げた小太りの中年男性だが、都内の私立大学で非常勤講師をしているというこの男は一二人の指導者のうちの一人だった。
それにしても、儀式の際の指導者たちは揃って黒いローブを身に着け、フードを深く被って顔を隠していた。そんな衣装の効果も手伝って、彼らはそれなりに重々しい雰囲気を漂わせていたはずだが、取り調べを受けている男はヨレヨレになった白いワイシャツにスラックスという地味な格好をした中年男である。
重々しさを感じないどころか、冴えない印象しか伝わってこない。
取調官の質問に答える声も小さく弱々しい。
「どうだ? 」
木村が、モニターを食い入るように見つめている尾藤を振り返って聞いた。
尾藤は無言のまま片手を上げて木村に待つように合図すると、一旦モニターから目を外し、俯いて目を閉じた。
「スピーカーのボリュームを上げて下さい。」
PC操作を担当していた警察官が、尾藤の指示に従ってスピーカーの音量を上げる。
そのまま一分間ほど、尾藤は取り調べの会話を集中して聞いていたが、
「もう良いです。分かりました。」
尾藤は目を開けて元の姿勢に戻った。
「・・・で? 」
木村が待ちかねたような顔で聞いてくる。
「いない。」
そう言って、尾藤は首を振った。
「くそっ、リーダー格の奴がいない! 」
木村が机上に拳を打ち付けた。
尾藤は椅子の背凭れに上半身を預け、反り返って天井を仰いだ。
ギリギリと椅子の軋む音が、尾藤の口惜しさを表しているようだった。
この部屋に集まった四人は、儀式の際にステージの中央で参加者を煽っていたリーダー格の指導者の男を探そうとしていたのだ。
機動隊員を殺害したのは、短刀を握っていたあの男に違いないと尾藤は確信していた。閃光発音筒による衝撃の中で、どのようにして屈強な機動隊員を殺すことができたのかは不明だが、他に犯人は考えられなかった。
男の顔は見ていないが、尾藤を捕えた際に若い男に指示を出していた声は未だ耳にこびりついているし、儀式が中断された際に尾藤とアイシュに向かって発した殺意に満ちた怒声も忘れてはいない。
取り調べの映像は一一人分全て見た。
その中には、あの怪力の大男もいた。
元プロレスラーだったという大男も機動隊員を殺害するには十分な能力を有していると思うが、あの大男が犯人だったとしたら被害者は出角のように首の骨を折られるか、絞殺されるかしていただろう。
捕えられた一一人の中にリーダー格の男はいなかった。
奴は逃げたのだ。
一〇〇〇人のカルト集団と一〇〇名近い機動隊員が争う騒然とした映画館の中から、殺した機動隊員から奪った装備を身に着け、ヘルメットを被り、身代わりにした者に黒いローブを着せて自分は脱出していたのだ。
「やられた! 」
木村の呻きと共に、
「至急、手配します。」
隣に座っていた警察官が立ち上がり部屋を飛び出していった。
「奴が逃げたのなら、カルトは存続するのか? 」
機動隊員の突入は絶妙だった。
尾藤はアイシュと共に儀式を潰し、司廉子を救い出すことができた。
この作戦は九割方成功したのだ。
カルトは一二名の指導者中一一名を失った。
組織は壊滅的なダメージを受けただろう。
だが、壊滅ではない。
本作戦の目的は指導者を一網打尽にすることで、カルトの中枢を潰し組織の機能を失わせることだった。
その肝心な一事については、失敗してしまったのだ。
たった一名の逃亡者がリーダー格の男だったことで、カルトは生き残る可能性を残したのだ。カルトの信者が二〇万人以上もいるというなら、儀式に参加していた一〇〇〇人が捕えられたことなど微々たる被害である。
再び活動を開始するには十分な余力を残している。
「念のため、あのインド人の女にも確認してもらう。」
尾藤だけの確認で納得するわけにはいかないと言って、木村はアイシュにも映像を見せる段取りを取った。
アイシュの名を聞いた途端、尾藤の背に緊張感が走った。
カルトが生き残ったとしたら、アイシュは裏切り者として命を狙われる。
それは尾藤も同様なわけだが、彼女が最も恐れていたことだ。
だからこそ、彼女は指導者全員の逮捕を願って、尾藤や木村に情報を提供したのだ。
「アイシュは何処にいるんだ? 」
廃墟ビルを出た後、彼女は外傷こそ無かったが疲労困憊の状態にあったので、事情聴取は日を改めて行うことにして、一旦救急車で病院に搬送されていた。
尾藤はそれ以降、彼女の姿は見ていない。
「心配するな、中野の警察病院だ。」
木村は尾藤の懸念を察して、安心するように言った。
「あの女は重要参考人だ。それに緊急避難対応だったとしても人一人殺しているんだ。逃亡の恐れが無いとはいえ、見張りもつけずに放置しておくと思うか? 」
警察病院の中で見張り付きでいるならば、一先ず安心して良いだろう。
「念のため、暫くの間は彼女に護衛を付けてくれないか? 」
「護衛を付けるなんて面倒なことをするよりも、女は暫くの間、我々の手元で預からせてもらうさ。」
公安の管理下に置かれるなど、あまり気持ちの良い環境ではないと思うが、カルト教団の今後の動向が判明し、危機的状況を脱するまでは我慢してもらうしかないだろう。
尾藤は、それが当然なことだと頷いた。
そんな尾藤の態度を見ていた木村が首を傾げ、
「お前もなんだがな。」
と、言った。
自分の身の不安を棚に上げて、アイシュの心配ばかりしている尾藤を戒めた。
「ええっ! 」
思い切り嫌そうな顔をして驚く尾藤に、
「たまには良い薬だ。好き勝手ばかりしやがって! 」
木村は一切の反論を許さないという高圧的な態度で言い放った。
[二三]
一二月六日、金曜日。
東京都内某所。
その建物の外観は、裕福な者が住むであろう複数世帯型住宅に見える。
その実は警視庁公安部の管理下にある宿泊施設であり、主に重大事件の証人や参考人などの保護対象者を匿うために用いられる施設の一つだった。
常時武装した公安警察官が複数名待機しており、敷地全体に張り巡らされたコンピュータ管理によるセキュリティシステムも万全で、外部からの侵入や内部からの逃亡は不可能に近い。
こうした施設の存在は、公安部内でも役職以上の者と限られた関係者にしか伝えられていない。
だから、施設の内部は世間から完全に隔離された環境にあった。
廃墟ビルでの一件の翌々日から、尾藤とアイシュはこの施設に保護されているのだが、初めは自分たちが何処にいるのかも分からなかった。
連れて来られる過程では、目隠しされた護送車両に乗せられていたし、散々遠回りした挙句に辿り着いたので移動距離の見当もつかず、長野か山梨の山中にでも連れて来られたのかと思ったほどだった。だが、夕方の五時に何処からともなく流れてくる伝統的な防災試験放送の「夕焼け小焼け」のおかげで、自分たちが東京都内にいることが分かった。
現在、尾藤とアイシュは軟禁状態にあるわけだが、この施設での生活は外出ができないことを除けば至って快適だった。
個人の通信端末が一切使えないことが不便といえば不便なのだが、外部との連絡が完全に禁止されているわけではなく、許可を取れば盗聴防止装置付きで発信を暗号化できる通信端末を借りることができる。
但し、尾藤は許可を取るのが面倒なので宿泊初日にアディと恵子に無事を知らせる連絡を入れただけで、以後は一度も使っていない。
基本的な生活必需品は全て揃っているし、必要なものがあれば同宿している警察官が買い揃えてくれる。
食事は各自の自炊に任されているが、その食材の買い出しも警察官にお願いできるので至れり尽くせりの生活を送れていた。
しかも、住宅環境は実に贅沢である。
「元々は、某一部上場企業の役員様が住んでたお屋敷なんだわ。」
木村は言っていた。
広々とした池付きの庭を囲んで、三世帯分の独立した棟が並んでいるが、そのうちの一棟が二階建て五LDK、他の二棟が平屋の三LDKである。三棟の共用部分は門と庭だけであり、複数世帯型住宅というよりも一つの広い敷地の中に三つの独立した個別住宅が並んでいるとしたほうが正しい。
各棟の間取りは広く、家具や調度品もモデルルーム並みに気づかいされた品がならんでいたし、尾藤などは浴室が温泉旅館並みに広々としていたことを無邪気に喜んでいた。
「家具ごと抵当に入ってたのを、うちのダミー会社が競売で競り落としたのさ。」
到着した初日早々、同行した木村が、そんな余談を挟みながら尾藤とアイシュを連れて慣れた様子で屋敷の中を案内してくれた。
果たして公安は、この手の物件を全国にどれほど所有しているのか?
月々の事務所費に頭を抱える民間中小企業経営者としては、こんな贅沢な施設を見せつけられると国家権力に対する不信感を抱かずにはいられなくなっていた。
ちなみに、尾藤とアイシュは平屋の二棟に分かれて宿泊している。
二階建ての棟は警備の警察官たちが宿泊や休憩に用いており、そこは施設の管理棟の役割を果たしていた。
現在置かれている状況を抜きにできたならば、ちょっとした別荘での休日気分が味わえただろうが、尾藤とアイシュを取り巻く現状は寛ぎを許してはくれない。
一日おきに訪れる木村の顔を見る度にそれを思い出し、決して心は休まらなかった。
「だが、そろそろ解放してやれそうだ。」
この日、施設を訪れた木村は、二人を前にして多少緊張感の和らいだ素振りを見せた。
「この一〇日間ほどで、カルトの命令系統は殆ど潰したからな、既に奴らは組織としての機能を失ったとみて良いだろう。」
尾藤とアイシュを前にして言うからには、それなりの自信があってのことだと思う。木村は、どちらかといえば物事を過小に伝える人間で、気休めを口にすることはしないタイプである。
「警察も随分頑張ってるみたいだしな。」
廃墟ビルでの作戦が翌朝に報道されて以来、テレビもインターネット上もカルト教団のニュースで溢れていた。
一年間で十一名もの少女が殺害された凶悪事件であるから、メディアの扱いは大きい。今日は何処の手入れをしたとか、カルト関係者が何人逮捕されたとかいう情報は軟禁状態にあっても毎日のように伝わってくる。
そうしたメディアの報道によると、確かに警察は一定の成果を上げ続けていた。そして報道されることの無い捜査の裏側に於いても、公安が教団を着々と追い詰めているということを木村から聞かされていた。
「逮捕した連中の口は意外に硬かったがな、一人の口を割らせたら、そっから先は芋づる式に組織を暴いて行けたのさ。」
公安がどのようにして逮捕者の口を割らせたのか想像はしないことにした。
彼らの手際については民間人が立ち入れるところではない。
「容疑者たちが自供したとおりに、被害者の遺体は全て奥多摩の山林内に捨てられていた。遺体の損壊状況も奴らが明かした儀式の段取りに沿ったものだったが、遺体発見時に立ち会っていた連中がトラウマになりそうだと言ってたよ。年端もいかない少女が生きたまま切り刻まれてたわけだからな、被害者と同じ年頃の娘のいる警察官の話じゃ、とても冷静ではいられなかったってほどに酷い有様だったらしい。」
これで奴らの罪状はほぼ確定したと木村は言い切った。
今後に残された問題は、指導者たちと誘拐に直接関わった者たちはともかく、一〇〇〇人近い逮捕者と二〇万人以上もの信者をどう扱うかだろう。
子供や未成年を抜きにしたとしても相当数が残されることになる。
さすがに全員に幇助罪が適用されるとは考え難いので、これは警察と検察がどのように事件を扱うつもりなのか、お手並みを拝見するしかないということである。
「リーダー格の男の行方は、未だ掴めないのか? 」
尾藤とアイシュが自由の身になるには、そこが肝心である。
「男の行方は掴めていないが、奴の身元はハッキリした。」
木村はタブレット端末を取り出して、リーダー格の男の情報を読み上げた。
「名前は上井ユン、年齢五三歳、生まれは中国の大連市、一〇年前に移民手続きを経て日本に移住している。永住権は無し。元は中国資本の貿易会社で重役。トラブルを起こして六年前に懲戒解雇。その後は派遣会社に登録して様々な職を転々としている。上井ってのは奥さんの苗字だが、その奥さんとは五年前に離婚。二人いた子供の親権を持っていかれ、現在は毎月の養育費と生活費の仕送りのおかげで多額の借金を抱え・・・ 」
これらは逮捕した指導者の一人から聞き出した情報を元に公安が調査した内容ということだが、木村が読み上げた情報では、上井という男の生い立ち、交友関係、生活サイクルまで、プライベートを殆ど調べつくしてしまっていた。
「ここまで身元を洗い出されてたら、素人が我々の捜査網を掻い潜るのはほぼ不可能だよ。それに、既に教団は組織として壊滅したようなものだから、こいつ一人で抗っても大したことはできっこない。」
まさにインテリジェンス機関ならではの仕事ぶりと言えるが、実にえげつない。
だが、ここまで調べが進んでいるならば、木村の言うように上井という男の行動は完全に封じられていると見て良い。
通信や交通などのインフラ、商店や病院など常時公安の監視下に置かれている施設は元より、国内数万か所に設置されていると聞く監視カメラによるネットワークや監視衛星も上井の容姿や身体的特徴をインプットされ二四時間の自動監視体制にあるという。
もはや、屋内に引き籠っていない限り、上井が捕まるのは時間の問題と思われる。
「元会社重役かぁ。他には大学の先生とかもいたよな。賢い人たちなんだろうに、カルトなんかに引っ掛かるとは意外だよねぇ。」
多くの場合、犯罪者の大半は意外な人物であるとの評価を受ける。
カルトに入信する者も、それ以前は普通の社会人、主婦、学生であったりする。
「人は見掛けによらぬもの」とか「あの声でトカゲ食らうかホトトギス」の類である。
そんな普通の人々が「まさか、あの人が? 」と、世間を驚かせる人になってしまうわけだが、その動機付けは犯罪心理学者や精神分析学者たちの腕の見せ所になるほど不可解だったりする。
「いや、でも今回の動機は単純明解かもしれないぜ。」
木村は言う。
「上井が解雇になった理由は、会社に無断で行った不正取引ということになってるんだが、これは実のところ会社ぐるみで行われた大掛かりな不正でな。それが明るみに出そうになったんで、上井に罪と責任を押し付けて会社を追い出しちまったってことらしい。」
よくあるトカゲのシッポ切り的な話である。
「大学の先生の場合はな、長年助教として努めてきた大学では梲の上がらない無能な奴だったらしい。有能な後輩に尻を突かれる形で助教を辞め、他に仕事を見つけることができないまま、大学のお情けで非常勤講師をやらせてもらってる言わば劣等感の塊りのような男さ。」
これも、よくある話だが、
「まさか、あの教団って負け犬が集まってできたわけじゃないよなぁ? 」
尾藤が呆れ顔で言った。
「ま、そういうことだ。」
「へ? 」
真面目に考えて言ったわけではない一言を、木村がサラリと肯定したので驚いた。
「指導者は他の一〇人も似たような境遇さ。会社をクビになった奴、出世を邪魔された奴、借金の保証人になって財産を失った奴、市会議員選挙に落ちた奴ってのもいたな。指導者だけじゃないぞ、信者の中にもそういう奴が大勢いたと聞いている。ほら、里田家もそうだったろ。」
「なんだよ、そりゃ? 」
尾藤の呆れ顔が顰めッ面に変わった。
すると、一緒に黙って話を聞いていたアイシュが口を挟んだ。
「あのね、シクラニのオーナーもそんな感じだよ。奥さんが愛人作って、貯金持って逃げたって聞いたことがある。」
アイシュのセリフに木村が頷いた。
「あのカルトは、そんな奴の集まりだったってことさ。」
「はぁ・・・ 」
「奴らが共通して持ってる感情ってのがあってな、それは社会に対する怨恨だ。そもそもの憎しみの相手は会社だったり、上司だったり、同僚だったり、友人や身内だったりしたんだろうが、どん底に落ちた自分の境遇を呪ってるうちに社会全部が憎くなっちまったのさ。」
「社会に恨み辛みを持ったカルトってこと? 最悪だな。」
尾藤の呟きに、
「ホントにねぇ。」
と、アイシュが相槌を打った。
木村が、ふとアイシュの顔に目をやってから思い出したように、
「そういえば、カルトには外国人が多かっただろ? 」
と、言った。
「ああ、そうね。」
答えた尾藤も木村に釣られてアイシュを見てしまった。
そんな二人の態度にアイシュはムッとしたようだ。
「ええ私は外国人ですけど、何か? 」
差別されたようにでも感じたのだろう。
尾藤は思わず片手を立てて、ゴメンと拝むようなポーズを取った。
「いや、スマン。君をどうこう言うような話じゃないから。」
木村も慌てて言い訳した。
「でも、俺を襲ってきたのは外国人ばかりだったし、実際多かったとは思うけど。」
それは事実なので、
「まあ、確かに多かったと思うわね。」
アイシュは渋々だが頷く。
「外国人が多いのは当然といえば当然。今時の日本社会に一番不満を持ってるのは外国人だからな。見た目や生活習慣の違いから差別や偏見の対象になりやすいし、低賃金で過酷な労働を強いられている者の多さは日本人の比じゃない。それに、一部の国からは日本に敵意を持ってたり、スパイ活動が目的で入国する奴が大勢いるようだが、そのおかげで全く無関係な外国人が何か事がある度に非難や警戒の対象にされて、時には排外運動なんかで酷い目に遭わされることもあるから、日本社会に対する恨みを持っている者は多いに決まってるのさ。」
そういうことなら沢山思い当たるとアイシュは苦い顔をする。
「たぶん、外国人の半分以上が日本社会に不満を持っているわよ。」
だから、外国人の信者が多いのは当然なのだと木村が言った。
「社会に対する不満を持った連中を救うのがカルトのお題目だったのか? 」
昔からカルトの多くは、人間の心の弱さを突いて攻め落とすのが常套手段としており、弱者や敗者を選民にしてくれるというのが売り文句だったりする。
「ところが救うというのとは違うんだな。」
木村が尾藤の既成概念を、あっさりと否定した。
「奴らの目的はテロリストと一緒だ。破壊分子と言うべきかもしれない。」
そのようなカルトも過去の歴史の中ではあったが、それは信仰の目的を達成する過程に於いて社会秩序に反乱したということであり、信仰の目的はその先の選民と救済にあるのではないかと尾藤は言った。
「違うんだよ。奴らの目的は社会に災いを振り撒くだけなんだわ。その先は無い。皆で社会に腹いせをして鬱憤を晴らしましょうみたいな、そんなカルトだったんだ。」
木村は、そう結論付けてしまった。
「それだけ? 」
「ああ、それだけだ。」
そんな単純な目的しか持たない宗教など、果たして宗教と言えるのか?
尾藤は暫し唖然としていたが、直ぐに、
「ああ、なるほど。」
と、言って膝を打った。
アイシュの顔を見ると、どうやら彼女も漸く合点がいったとの顔をしていた。。
「やっぱり、宗教じゃないってことか。」
「そうかぁ、私が感じてた違和感は、そこだったのね。」
二人が何に納得して感心しているのか分からない木村は、
「お前ら、何か気付いてたのか? 」
と、不思議そうな顔をした。
それについてはアイシュが簡潔に説明した。
「あの教団には教祖もいないし、教義らしい教義も無かったってこと。私がいた間も集会の度に儀式の意義と組織の掟みたいなもんをクドクド説明をされてただけだった。多少は宗教めいた話もしていたけど薄っぺらで、それっぽく装ってただけに思えたのよ。だから、この教団は生贄の儀式を行うためだけに結成されたんじゃないかって気がしてた。」
木村はアイシュの考え方で間違いないだろうと言い、
「それじゃ、どうして儀式を行うためのカルトなんてモノができあがったのか、ついでに推理してみろよ。」
と、二人に質問をしてきた。
「いや、それは皆で社会に復讐をするから集まりましょう、みたいな感じなんでしょ? 」
尾藤の答えが稚拙過ぎたので、
「まるで小学生みたいな答えだな。」
木村は全然ダメと手を振った。
次にアイシュが、
「それじゃ、社会への恨みとかストレスを発散するための同好会かしら? 」
と、答えたら木村に底が浅いと却下された。
「はい、んじゃ次は? 」
木村は、もっとキチンとした推理をしろと二人に言う。
「なんだよ勿体ぶっちゃって! 」
「なんかイラッとするわ! 」
木村の態度が偉そうだったので、二人は揃って反発した。
「どうせ、答えを知ってんだろ。さっさと教えろよ。」
「それは私も知りたいわ。良いから早く話してよ。」
文句を言いながら、出し惜しみせずに話せと急かす。
「少し頭を使わせてやろうと思ったのに! お前らなぁ、大人の癖に会話のキャッチボールができないのか! 」
「大人なら、つまらない質問なんかしないで真面目に話を進めろよ! 」
「そうよ、時間の無駄だわ! 」
木村は二人掛かりのブーイングに負けた。
「ことの始まりは上井が日雇いの仲間を集めた宗教ごっこなんだが、そもそも奴は中国人だからな、宗教なんてモノは信じちゃいない。おそらく新興宗教が金儲けのタネになると思って手をつけたに違いないんだ。」
二一世紀半ばだと言うのに社会主義国としての体裁を守り続ける中国は、表立っての締め付けは厳しくしていないが「宗教はアヘンである」とのマルクスの言葉を律儀に守り続けている。そんな国で生まれて裕福に育ったという上井がカルトの指導者というのは奇妙な話であるが、当然そこには信心以外の目的があったと考えるべきだろう。
「だがな、イカサマ宗教を立ち上げる準備をしている最中に、奴は何処かで何かと出会っちまったのさ。」
「何処かで何かって? それが、儀式を始める切っ掛けになったのか? 」
木村は頷いて話を続けた。
「例えイカサマだとしても新興宗教を立ち上げようとするからには、既存の様々な宗教の知識を習得しなきゃならないだろう。上井は手っ取り早く身近にいた連中から、そいつを学ぼうとしたに違いない。現代日本は人種の坩堝だから、様々な国の様々な信仰が溢れている。ネタ探しには困らなかっただろうな。」
上井が日雇い労働をしていたというなら、他国人と接する機会は多かったに違いないから、様々な信仰に接する機会があっただろう。無宗教者の上井は、そうした信仰の姿を客観的に見て、信者が集まりそうな魅力的な宗教を構築しようとしたらしい。
「ま、俺も、ちっとは勉強してみたんだが、大昔から新しい宗教を立ち上げる際には既存の宗教を参考にしたり再構築するみたいだな。メジャーどころを例に挙げると、インドの古代宗教や民俗信仰を元にしてできたのがヒンドゥー教や仏教だろ。ユダヤ教を元にしたのがキリスト教やイスラム教だもんな。んで、キリスト教を元にしてできたマニ教やコプト教なんてのもあるな。」
「へぇ、ホントに勉強したんだな。」
宗教嫌いにしちゃ良く頑張ったなと尾藤は素直に感心したのだが、木村は冷やかさずに黙って聞けと言った。
「上井も最初は、そんな風なモノを作ろうとしてたらしい。キリスト教やイスラム教や仏教なんかを片っ端からチャンポンにして、既存の宗教から信者を引き抜いてやろうと思ってたんだろう。ところが、上井は途中で道を逸れた。奴は新興宗教作りを途中で止めちまったんだ。」
「何故? 」
「切っ掛けは不明なんだが、上井はある時期から呪術に嵌ってたらしい。」
「じゅ、呪術ーっ? 」
尾藤の認識では、巫女や祈祷師による神託とか、精霊や地霊信仰などの原始宗教全般というイメージだが、木村はその程度の認識で十分だと言った。
「上っ面だけで良いんだよ。上井もたぶん上っ面しか学んでいなかったんだろうさ。その結果があの殺人儀式だったんだ。」
木村は憎々しげに言った。
「おそらく、上井が宗教を学んだ者の中に呪術マニアか専門家がいたんだろう。奴は、かなりインパクトのある出会いをしてしまったようだが、神憑りでも見せられたのかもしれない。あれは生で見たら相当迫力あるみたいだからな。で、呪術の虜になった上井は、肝心の新興宗教作りを棚上げにして熱心に研究してたらしい。まあ、研究って言っても奴は人類学者じゃないから、基礎的な知識は無かっただろうし、所詮は趣味の高じた素人程度。金も無いから、精々身の回りの連中から聞き取った話を纏めて、あとは図書館で資料を漁るぐらいしかできなかったろう。そんな程度じゃ呪術の上っ面しか学べっこないんだが、それが不味かったんだわ。素人に毛の生えたような奴が呪術を見様見真似で中途半端に齧っているうちに、先入観とか自分勝手な思い込みで呪術の肝心な部分がスッポリ抜けて「呪」だけになっちまったのさ。」
それは有りがちな話だねと尾藤は言った。
面白い部分を少しづつ聞き齧って得た薄っぺらな知識で満足し、物事の本質を見損なう中途半端なマニアは多いと思う。
例えば三国志や新撰組の熱狂的なファンを自称し熱心に史跡巡りもするが、実は知っているのは主要人物の相関関係ぐらいで、当時の社会情勢を全く知らないし興味も無いという者たちなどが良い例だろう。
そして、この手の者が最も多いジャンルは超常現象系かもしれない。
宇宙人の存在を力説しながら宇宙科学を知らないとか、未確認生物を語りながら生物学的知識を欠片も持っていない者たちは多いが、これらの人々は大して毒にもならないので時にはおバカなキャラクターとして娯楽メディアを賑やかすネタになる。
しかし、預言書や史書の一部分を抽出して大予言を捏造したり、末法思想やヨハネの黙示録を曲解して終末論を語り、悪気の有り無しに関わらず社会不安を煽るような迷惑な輩もいる。
つまり上井は社会的に迷惑なマニアになってしまったということだ。
「呪(のろい)、これは上井の気持ちにピッタリ合ったと思う。」
「自分を陥れた会社を呪ったんだな。」
「それだけじゃないな。呪術に嵌った頃の奴は、既に会社だけじゃなく自分の置かれた境遇を恨むところまでいってた。」
「つまり、社会全体を呪ってたってことか? 」
「そういうこと。そんな上井の周りには社会に対する恨み辛みを持った連中や、不満を持った同好の士が集まってきた。五年ほど前になるらしいが、上井を中心に根暗で陰湿で劣等感と被害妄想に凝り固まった狂人集団が出来上がった。それがカルトの中心になった一二人ってわけさ。で、連中は社会を呪うために各自が色々な情報を持ち寄った。手に入れられる限り世界中の呪法を掻き集め、既存宗教の中にある破滅的な教えや民間伝承や伝説も取り入れて、この世に災いを齎すための尤もらしい儀式とやらを作り上げたんだ。そして集まった信者に儀式の意義や目的を説教して実施を進めた。言うならば『超常現象テロ』を画策した感じかな。」
超常現象テロとはSFかファンタジーの中で登場しそうなネーミングのようで、言った木村本人が恥ずかしそうに苦笑していた。
「実際に儀式や説教に取り入れたネタの中にはゲームやアニメ、マンガなんかを元にしたモノまであったんだわ。本人たちは大真面目で取り入れてたんだろうが、取り調べをしてみたら指導者の中に元ネタを知らん奴が半分もいたってんだから笑っちまうよな。その一事を見ても奴らの知識が如何に薄っぺらでいい加減だってことが分かるだろ。」
いやはやロクでもない話、これは笑えない笑い話である。
「でも、社会を呪うだけの薄っぺらな儀式を行うってだけで、二〇万人もの信者が集まるほどの需要があるものなのかしら? 」
アイシュが信じられないと言う顔をしている。
「薄っぺらかどうかなんて人其々の判断だし、世の中賢くて冷静な奴ばかりじゃないからな。どちらかと言えば、馬鹿で流されやすい奴の方が多いんじゃないか? そんな奴らにとっては目的が単純なところが分かりやすく魅力的に見えても不思議は無い。日頃、ゲームやアニメなどのバーチャルな世界で生きてるような奴なら尚更で、生贄を用いる儀式が犯罪だって事を理解できず、背徳的な秘密の儀式をカッコ良いと感じるかもしれないだろう。」
「そうなのかなぁ。」
納得しかねるというアイシュに、木村は言い聞かせるように続けた。
「しかも、このカルトには明確な主神はいないし信者を統率する教祖もいない。規範とか戒律だとかの面倒な教義も有るんだか無いんだか分からん。上井にしてみれば、新興宗教を作るつもりは無くなっちまってたんだから当然のことなんだが、そのおかげで先祖代々の信仰を持つ者も改宗しないままで儀式や集会に参加できる。キリスト教を信じていても良いし、イスラム教を信じていても良い。ヒンドゥー教でも仏教でも神道でもゾロアスター教でも何を信じていても構わない。このカルトには宗教の根本的なところである神さまがいないし、あるのは世の中に災いを振り撒くって目的意識と方法論だけだから、自分の神様に不義理をしなくても済むんだ。キチンと毎回の儀式に参加してくれたらお布施もいらないって、これほど単純で敷居の低い教団は他に無いだろう。」
「そんな、非常識だわ! 」
アイシュは木村の話を聞くうちに腹が立ってきてしまったようだ。
生まれながらのヒンドゥー教徒として、日本人である尾藤や木村よりは遥かに高い信仰心の中で生きてきたであろう彼女にとって、それは邪道と断ずべきことである。
この話を聞いたなら、熱心なキリスト教徒やイスラム教徒も腹を立てることだろう。
「まあ、あんたには悪いが、日本って国の宗教観ってのは昔から非常識であり、邪道そのものだったんでね。仏壇の上に神棚が祭ってあったりとかが良い例だ。葬式では仏教、結婚は神式、クリスマスの一週間後には神社に初詣に行くとか、平気な国民性なんだよ。上井は中国人だが、そういういい加減な発想を持ったところは日本人的だよな。」
アイシュは困ったものねと溜息を吐いた。
「敷居が低ければ、次は需要があるかどうかだが、これがあったんだよ。現代社会は不平不満を持った奴だらけだからな。貧富の格差、政治不信、失業問題と就職難、落ちこぼれ、いじめ、こういう類は社会に対する恨みに繋がりやすい。そんな恨みを晴らしたいと思ってる奴は多くいる。だが、表だってデモやテロに走るような極端な奴が少ないのも現代社会だよ。ほとんどの奴が恨みや不満を心の中に抱え込んで鬱屈した思いを隠して暮らしているのさ。そんな奴らには、地下に隠れて大勢で世の中を呪うなんてピッタリの目的だと思わないか? 」
そんな奴なら沢山いそうだと尾藤が言うと、アイシュは内心を表に出さずに溜め込む習性のある日本人ならではかもしれないと辛めのコメントをした。
「敷居が低いってことは動機が甘くても良いってことに繋がるだろ。別に社会に対する激しい恨みや不満じゃなくても良いんだよな。例えば現実逃避なんかも動機になると思うんだ。お前たちだって覚えがあるんじゃないか? 嫌なことがあった次の日なんかには仕事や学校に行きたくないから、今直ぐ大地震が起きて職場や学校が壊滅してくれないかなとか、宇宙人や怪獣が攻めてきて街中がパニックになってくれないかなとか思ったりしたことあるだろ? 」
「ああ、あったねぇ。」
学生時代には良くあることだったし、社会人になってからでも恵子に怒られそうな日は現実逃避したくなる。
ところが、
「何それ? そんな馬鹿なこと考えたことも無いわ。」
と、アイシュが素っ気なく答えた。
「一度も無い? 」
「あるわけ無いでしょ。」
アイシュの視線が冷たかったので、尾藤も木村も、それ以上この話題を掘り下げないことにした。
これ以上掘り下げると、とことん日本人が馬鹿にされそうな予感がした。
育った環境か国民性の違いが出てしまったのかもしれないが、こんな実直型のアイシュが、騙されたとはいえ一時カルトの一員になっていたことが不思議である。
「まあ、その程度の動機でもカルトの一員になり得るってことでさ、だから二〇万人分ぐらい需要はあったんだよ。」
確かにデモやテロを起こすほどの極端な行動力の無い内向きな連中にとって、根暗な仲間に加わって世の中を呪うということならば、ゲームをプレイするのと同じ感覚で安易に参加し易かったのかもしれない。事の重大さを理解できない社会の常識から外れてしまうほどの現実逃避者ならば、このカルトは通信費も電気代も掛らないのでネットゲームやSNSで遊ぶよりも負担は少なくて良いと考えるかもしれない。
木村の話は一区切りついたが、いつの間にかアイシュが塞ぎ込んでいた。
木村の話は十分に説得力があり否定される要素は殆ど無かったのだが、少女たちが殺される悲惨な儀式を間近で見せつけられてきたアイシュにとって、カルト教団成立の動機が軽々しく理不尽に思えて受け入れ難く感じていたのかもしれない。
尾藤にとっても、一一人の少女の命を残酷な儀式で奪ったカルトは決して許されないという思いは強いし、動機が大きかろうが小さかろうが、一〇〇〇人、いや二〇万人全員が有罪にされなければならないと思っている。
「俺も気持ちは同じだが、残念ながら二〇万人を一斉に逮捕することはできない。但しカルトに関係した者たちは、今後様々な形で社会的制裁を受けることになる。少女たちの遺族にも、それで我慢してもらうしかない。」
「それは、しょうがないんだろうなぁ。」
別に二〇万人を逮捕して有罪にしろなどと物理的に不可能なことを求めるつもりは無いので、物分かりの良いことを言わなければならないのだが、尾藤でさえ内心に違和感が残るのは否めなかった。
「私も責めを負うべきでしょうね。」
アイシュがポツリと言った。
彼女はカルト教団を壊滅させた功労者であるが、一定期間カルトの儀式に参加し、決して本意ではなくとも少女たちが殺される様を見続けてきたことに関しては何らかの罪に問われるだろう。
「それは司法が判断するべきことだから何とも言えないが、あんた一人がカルトに逆らったところで少女たちを救えたわけじゃないってことぐらい誰にでも分かることさ。迂闊に行動したら自分の身が危険に晒されただろう。」
そうなんだけどねと、アイシュが力無く呟いた。
どんなに無力だったとはいえ、目の前で少女の命が奪われるのを黙って見ていたという罪の意識は決して浅くないだろう。
尾藤はアイシュを慰めるべきなのか迷ったが、彼女の抱えている罪の意識の重さを測り知ることができない以上、その場凌ぎの気休めにもならないような慰めの言葉は控えようと思った。
「ところでさ、今更どうでも良いことなんだけど、一つ聞いて良いかな? 」
どうでも良いと言いつつ、教団の儀式を知った時から気になり続けていたことがある。
「奴らは、儀式を行った上で何を呼び出して何をさせるつもりだったんだ? 」
「ああ、そのことか。ちょっと待て。」
木村はタブレット端末を操作して尾藤の質問に関連した書類を探した。
「奴らは悪魔的なモノを呼び出そうとしてたと考えて良いだろう。あの儀式だって元ネタが寄せ集めだからグチャグチャになってるが、基本的に伝説の中にある黒ミサやサバトを踏襲してる感じだろ。」
「はぁ、くだらない・・・ 」
あれだけ、大掛かりな儀式を執り行った挙句に呼び出そうとしたものがステレオタイプな悪魔とは稚拙過ぎる。
「ちょっと待って、悪魔とは違うと思うわ。」
俯いていたアイシュが顔を上げた。
カルト内部にいた彼女には別の見方があると言う。
「どういうこと? 」
尾藤が聞く。
「Mighty Power 」
「大きな力? 」
「Mighty Power、Great Power、日本語では御力とか御業とか、そんな呼び方をされてたモノ。」
「それって、具体的じゃないな。」
アイシュが提示したような漠然とした単語ではなく、もっと具体的な名前のあるモノを呼び出そうとしてたと思う。
「その力の素を呼び出そうとしてたんでしょ? 」
アイシュは首を振った。
「力を発するのは何モノかってことは教団内でも人によって捉え方が違ったの。悪魔の力だという人もいたし、神の力だと言う人もいた。精霊だと言う人もいたし、魔人とか怪物だという人もいたわ。太古に滅んだ文明の怨念だとか、大宇宙の力だとか、皆が好き勝手なことを信じてたけど、何が正しいとか指導者たちは言わなかったわ。」
「そんな、バラバラの捉え方で儀式が成立するものかね? 」
木村が首を傾げた。
「力を発するのが何モノかってことは、指導者たちにはどうでも良いことだったのかもしれないわ。彼らの間では特定の存在を共通認識してたのかもしれないけれど、大事なのは儀式が成功すれば御力が発せられて、世の中に災いを振り撒くことができるってことをカルトの参加者に信じさせることだけだったみたい。」
「そんなんで納得するもんか? 」
「皆が納得してたわ。それは儀式の参加者の祈りを聞いても分かるはずよ。あんなに統一感の無い自分勝手な祈り方をしていながら不思議な一体感があったでしょう? 」
尾藤は、儀式の際に聞いた大合唱を思い出した。
一〇〇〇人の参加者が一斉に唱える祈りの声は、合唱と言うよりも巨大な獣の咆哮と化していた。あの時、尾藤が激しい眩暈と頭痛に襲われたのは、その凄まじさに圧倒されたからではなかったかと思えるほどであった。
その後の調査により、映画館内で大麻を燃やした跡が見つかったことで、それが尾藤の眩暈と頭痛の原因になったのではないかと言われてはいるが・・・
「私の印象では、力の大本が実体を持っているモノとは限らない気がするの。悪魔とかじゃなく悪そのものって感じ。実体は見えないけど確実に人間の生存を脅かす力。例えば公害とか疫病、温暖化とか寒冷化みたいな感じかしら。脅威であることは分かってるのに色んな意味で人の能力では抗うことのできないような力よね。」
「それじゃ、災いそのものって感じか? 」
「具体的に何かを起こすってことじゃないけどね。言うなれば人類に対する災い全般みたいなモノなのかしら。例えば、公害や疫病は災害だから何者かが意図的に起こしたわけではないけど、それ自体が巨大な意思を持った怪物に思えないこともないでしょう? 地震や台風みたいな自然現象も人間に対する害意の塊りに見えたりするでしょう? カルトの連中は、そんな感じのモノを呼び起こそうとしていたと思う。」
「分かったような、分からんような・・・ 」
木村が、話が難し過ぎると言って頭を掻いた。
「アイシュが言いたいことは何となく分かるんだけどねぇ。」
尾藤も理解しきれていなかったようである。
アイシュは、そんな二人の困惑顔を見回しながら、
「ああもう、説明するのが難しいのよ! 」
自分の思うところが十分に伝えられずに苛々していた。
[二四]
廃墟ビル地下二階の映画館。
入り口は黄色い規制線によって封鎖されている。
既に現場検証も終わり、ここ数日間は全く人気が無いまま元通りの廃墟に戻っていた。
「よく来たね。」
規制線の隙間越しに声が聞こえた。
甲高い、良く通る声であった。
声の主の姿は見えないが、映画館の中には確かに人の気配がする。
「そんな遠くに立っていられても話ができないじゃないか。中に入っておいでよ。」
その声が映画館の中に入ってくるように誘う。
「・・・。」
尾藤は立ち入り禁止の指示書きに躊躇いながらも、張られてから数日を経過して粘着力の弱っている規制線を数本引き剥がして、館内に足を踏み入れた。
現場検証に立ち会って以降、久々に入った映画館の中は灯りも無く真っ暗闇なはずだったのだが、ステージ上に焚かれた小さな炎が発する弱々しい光のおかげで、足元の不安を覚えない程度には館内の様子が分かった。
「こっちへ。」
声の主が言った。
黒いローブを着てフードを目深に被った男である。
ステージの真ん中で尾藤に背を向けて座り、手元で小さな焚火を熾しているらしい。
薄い光が、黒々とした背景に男の輪郭を浮かび上がらせている。
尾藤は無言で、男に誘われるままステージへと歩み寄った。
ステージの下で立ち止まると、男は背中を向けたまま右手で上がってくるようにと手招きした。
尾藤は男の誘いに抗いもせず、ステージに上った。
男の声は穏やかだったので、特に身の危険を感じることも無かった。
「面白かったよ。」
男は背後に立った尾藤を振り返りもせずに言った。
肩越しに小さな焚火が見える。
埃や木屑のようなモノを固めたらしい火種が音も立てず、煙も出さず、少しも揺らぐことなくボンヤリと燃えている不思議な焚火だった。
ステージの板張りの床の上で燃えているにもかかわらず、焚火は広がりもせず、床を焦がしてもいない。
尾藤は不思議そうに焚火を見つめながら、初めて口を開いた。
「何が面白かった? 」
男は、フフッと息を抜くように笑った。
「もう一息だったのに、と言うことが面白かった。」
中途で儀式が潰されてしまったことを面白かったと言っているのだろうか?
「だが、あれは一時のこと。近いうちに再び始まる。」
だから、楽しみにしていろと男は言った。
「まだ儀式を続ける奴がいるというのか? それは無理だろう。」
男は首を振った。
「まあ、見ていろ。」
男は言い、さらに不気味な笑い声を重ねた。
「お前、上井ユンとかいう奴だろう? 」
尾藤は木村から聞いていたリーダー格の男の名を口にした。
儀式を続けようという意思を持った男など他に考えられない。
ところが、
「そんなくだらない男の名を口にするな! 」
男が憤りを込めて、威嚇するように否定した。
だが、尾藤は臆しもせず、
「じゃあ、お前は誰なんだ? 」
と、言い返した。
「知っているはずさ。」
知らないと言うと、
「お前は愚かな奴だな。俺は世の中の誰もが知っているモノだよ。」
男は、そう言って尾藤を嘲笑った。
まるで餓えた獣が喉をゴロゴロと鳴らすような下品で不気味な笑い声であり、その悍ましさに尾藤は思わずゾッとしてしまい鳥肌を立てた。
「お前たちが会いたいというから、出て行ってやろうというのだ。」
男の言葉尻に、何かを啜り上げるようなズルッと湿った音が続いた。
知性の感じられない人間離れした汚らしい音である。
こちらを脅そうとしているのかもしれないと尾藤は思った。
「誰も会いたいなんて言ってない! 」
不気味に感じながらも、尻込みせずに言い切った。
すると、
「そうかもな。」
男は再び穏やかな口調に戻った。
「しかし、もう一息で俺は枷から抜けられたのだ。それは大勢が俺に会いたいと望んだからに他ならない。そうでなければ、俺は決して放たれることは無いのだからな。」
尾藤は目の前で背を向けたままの男のセリフに言い様のない不安を感じていた。
「もう一度聞くぞ。お前は何者なんだ? 」
今度は、尾藤が威嚇してやるつもりで怒鳴ってやったのだが、男の背中には少しも動じた様子がない。
そして、尾藤の問いに対する答えのつもりなのか、極めて観念的で意味不明な言葉を並べ始めた。
「何モノでもない。あるがままの存在。常に身近にいるべき存在。人の世を侵すための存在。求められ快楽を与える存在。そして人の知恵を曇らせ愚かにする存在・・・ 」
淡々と呪文のようにセリフが続く。
「ふざけるなっ! 」
尾藤は怒鳴り、
「こっちを向けっ! 」
男の被っていたフードに手を掛けて乱暴に脱がした。
それはホンの一瞬の出来事だったので、男が何モノだったのかを尾藤が知ることはできなかった。
男のフードが剥ぎ取られると同時に、焚火の炎が消えて映画館は暗闇に閉ざされてしまったからである。
しかし、フードを剥ぎ取った瞬間、尾藤は大きな悲鳴を聞いた。
おそらく、自分の喉が発した悲鳴だったと思う。
目には見えなかったが、剥ぎ取ったフードの下には禍々しく凶暴な悪が潜んでいた。
突如発せられた凄まじい悪の奔流に、尾藤の意識は押し流されてしまったのだ。
[二五]
「冴えない顔してるのね。」
アイシュが言う。
「そう? 」
尾藤は少し屈んで、停車中の黒塗りセダンの運転席側サイドウィンドウに自分の顔を映してみた。
「はぁ、こりゃ確かに・・・ 」
顔全体が弛んで下がり気味に見えるし、血色も良くない。
力の抜けた眠そうな目の下には隈ができていている。
「うーん、夢見が悪かったからなぁ。」
尾藤は両掌で顔の皮膚を引っ張り上げて、表情筋体操を始めたが、でたらめな思い付き体操なので変顔の百面相をしているようにしか見えない。
「止めなよ、みっともない。」
アイシュが呆れ声で言った。
「ああ、うん。」
空返事をしながら白目を剥いて大口を開けた尾藤の目の前で、いきなりサイドウィンドウがスルスルと開いた。
運転席に座っていたのは、不愛想な顔をした初老の男。
無言で変顔の尾藤を凝視している。
「し、失礼っ! 」
尾藤は慌てて顔を元に戻して、一歩後ろに下がった。
スモークウィンドウ越しで車内は見えなかったし、エンジンが切れていたので誰も乗っていないと思い油断してしまった。
「いえ、別にかまいませんよ。」
男は尾藤の変顔を見て何の反応も見せず、いかにも公安警察官らしい無表情だが鋭い視線を正面に戻した。
その驚きも笑いもしない平然とした態度が、尾藤を小馬鹿にしているように見えて腹立たしく感じた。
(くそっ、何でも良いからリアクションしろよな! この公安野郎め! )
内心で舌打ちした尾藤の後ろで、アイシュのクスクスと押さえた笑い声が聞こえた。
「まったく、不注意ねぇ。でも、今日から晴れて自由の身になるんだし、少しは顔色も戻るんじゃない。」
アイシュが、いつにない明るい態度で話し掛けてくる。
振り返って見た彼女の笑顔が、東の空に上ったばかりの朝日に照らされ、輝いているように見えて眩しかった。
「ま、まあ、そうだよな。」
尾藤は小さな心の動揺をアイシュに悟られまいとして視線を空に向けた。
数羽のカラスが遥か頭上を飛び去って行くのが見えた。
一二月八日、日曜の早朝。
一一日間に及んだ公安による軟禁状態が漸く終わり、尾藤とアイシュの二人に日常生活に戻る許可が下りた。
軟禁中は豪華な保護施設内で何不自由無い生活が送れていたとはいえ、外出もできず施設の敷地内に閉じ籠った生活を強いられていたので、それなりのストレスも溜まり、運動不足で身体も鈍り切っていた。
だから、昨日施設を訪れた木村から軟禁状態の終了を聞かされた時には二人とも声を上げて喜んだ。
そんな浮かれ気味の二人に向かって、
「裁判が始まったら、また色々と面倒を掛けさせることになるから、取り敢えずの解放だぞ。当面の危険が去ったということだけじゃなく、二人に逃亡の意思が無いだろうってことで許されたんだからな。」
木村が釘を刺した。
カルト事件の重要な証人であり、指導者一名を殺害した件については未だ正式に正当防衛が認められたわけではない。
だから、施設を出られたとしても引き続き公安の監察下に置かれることになるのだが、
「表を自由に歩けるだけでも嬉しいねぇ。仕事にも戻れるわけだし。」
「何と言っても自由が一番よね。」
先のことを心配してもしょうがないので、まずは久しぶりに互いの家に帰れるということを喜ぼうという二人の意見である。
「気持ちは分かるけどな。」
木村も別に責めはしなかった。
「ところで、俺は仕事に戻るとしてアイシュは学校に戻れるのか? 」
大学院生であるアイシュは、今後の裁判で罪を問われなかったとしても、カルト教団の一員だったという事実を悪い印象で捉えられれば大学が処分を考えるかもしれない。
学内で好からぬ誹謗中傷に晒される恐れもあるだろう。
「いやいや、それは無い。」
日本にも証人保護プログラムがあると、木村は言った。
「大事な証人の実名と個人情報は非公開だから、大学には何の情報も渡ってない。だから、予め先週の欠席理由を考えとけば他には何の問題も無いよ。司法も我々も、証人が社会復帰する際の妨げになるような扱いは絶対にしないから大丈夫だ。」
それならば、アイシュも元の学生に戻れるはずだが、
「法的に許されるのは嬉しいことだけれど、自分自身としては未だ気持ちの整理がつかないというか、教団の記憶は残るし、罪悪感は絶対に消せっこない。そんなんで、明日から何事も無かった顔をして院生に戻るのは抵抗があるの。今後のことも含めて、暫くは一人になって考えてみるわ。」
これまでアイシュが味わってきたカルトでの悪夢のような体験を考えれば、そうした気持ちになるのは当然のことだろう。
だが、ちょっと待てと木村が言った。
「一応、事件の捜査に携わった警察官の一人として言っとくが、あんたは少女の命を救ったんだ。それは間違いない事実だ。」
尾藤も、
「過去を忘れろって言うのは無理だろうけど、自分を責め過ぎるようなことはするなよな。悪いのは教団なんだから、アイシュが悪いわけじゃないんだから、学校辞めたりとか自分の将来を棒に振るような生き方をする必要は無いんだぞ。」
アイシュの行動が命懸けだったことは誰の目にも明らかであり、彼女の勇気ある行動により救われた命があったのだ。
教団の一員だったことが罪だったとしても、アイシュは十分に罪滅ぼしをしたと思う。
「うん、そう言ってくれて助かる。」
アイシュが尾藤と木村の顔を交互に見ながら答えた。
「私は留学ビザで日本に来てるから、こんなことで落ち込んで大学辞めたちゃったら日本にはいられなくなるし、それは絶対にしないつもり。気持ちが落ち着くまでの間、少し休養するだけよ。」
やせ我慢をしているのかもしれないが、声を聴く限りでは決して落ち込んでいるわけではないようだ。
心配ではあるが、彼女の心の問題に、これ以上の干渉はできない。
気丈なアイシュのことだから、必ず立ち直ると信じ、とにかく頑張れと励ましてやるしかなかった。
「さて、そろそろお暇するとしますか? 」
仮にも秘密の保護施設の前に立ったままで、長話をし過ぎているような気がする。
「そろそろ出勤渋滞の時間だから、少々長めのドライブになるぞ。」
木村が二人について来いと言い、先に立って歩き出した。
「せっかくだから、俺は警察病院に寄って行きたいな。良いだろ? 」
尾藤は司廉子の見舞いをしておきたいといった。
入院中は母親が付き添っているという事なので挨拶もしておきたかった。
「どうせ中野方面だしな。それじゃ、お前は俺の車で送ってやるよ。」
木村は承諾すると、ポケットからアイマスクを取り出して尾藤に放ってよこした。
「また目隠しかよ。別に俺らに知られたって問題無いじゃん。どうせ二度と来ないし。」
「うるさい! ここは秘密の施設だぞ! 」
木村は、文句を言う尾藤を叱りつけてから、
「そっちは、どうする? 」
アイシュに聞いた。
「私は一旦家に帰りたいわ。」
アイシュの自宅は三鷹だと言う。
「それなら、方向違いだから別々だな。」
木村は施設前に停車しているセダンの傍に行った。
運転席のサイドウィンドウをノックすると、先ほど尾藤が変顔を見られた不愛想な初老の公安警察官が顔を出した。
本来はセダンが護送車なはずで、木村の車は随伴車ということになる。
だが、現在地から中野と三鷹を目指すには二台で手分けした方が良いということを、木村は伝えて納得させているらしい。
どうやら、この施設は中央線沿線から遠くない位置関係にあるようだ。
「よし。こっちの高級車は三鷹方面行きだ。」
木村がアイシュを手招きした。
「あ、はーい。」
木村に向かって返事をしたアイシュだったが、直ぐにはセダンに向かわず尾藤を振り向いた。
「尾藤さん、お世話になりました。」
そう言って、ペコリと頭を下げた。
「生意気なこと言って困らせたりもしましたけど、尾藤さんは私の恩人ですから、言葉にできないぐらい感謝しています。」
「そんな、改まって言われると、どうも・・・ 」
一〇日以上も同じ敷地の中で暮らし、毎日顔を合わせていたにも関わらず、尾藤はアイシュの美し過ぎる顔立ちに慣れていない。
元々、女性に対しては引き気味で接してしまう尾藤だが、アイシュと間近で対面すると思春期の中学生のように意識して尻込みしてしまう。
そんな尾藤に、
「あの、色々と、全部片付いたら、また会えますよね? 」
などと、アイシュが言う。
その大きな黒い瞳に見つめられたら、尾藤に嫌と言えるわけがない。
「お、おう、もちろん。必ず会おう、うん。」
そんな狼狽え気味の返事が可笑しかったようで、アイシュが楽しそうに微笑んだ。
それが、これまでに見せたことの無い優しく嬉しそうな笑顔だったので、尾藤は思わず感動してしまった。
(綺麗っていうか、可愛いじゃないか。)
二人の間の距離は一メートルも無いので、尾藤が自分の理性を過信し過ぎて、男の本能に油断したら抱きしめてしまいそうな距離である。
(おいおい、いい歳してホントに馬鹿みたいだぞ。)
尾藤は自嘲した。
そんなことをしたら変質者である。
以前、勢いに任せて恵子を抱きしめた時には関節を極められてしまった。
アイシュはそんなことをしないと思うが、それならば自分で自分をぶん殴って正気に戻したいと思った。
「それじゃ、またね。尾藤さん。」
アイシュが右手を差し出した。
「そ、そうだね。連絡するから。」
尾藤は、突発的な感情の乱れに抗いながら、頑張ってアイシュの手を握り返した。
一二月早朝の寒気に晒されていたせいか、アイシュの手は意外なほど冷たかった。
(それにしても、なんて華奢な手なんだろう。)
折れそうなほどに細い指と薄く艶やかな掌の感触を確かめながら、非力な女性の身でありながらアイシュが振り絞った勇気に対し、新たな敬意と感動を覚えていた。
(初印象では気丈で精悍な美人ってイメージに見せてたけど、やっぱ普通の女の子なんだよなぁ。それなのに、たった一人でカルトと戦おうなんて無茶なこと、並みの正義感でできることじゃない。ホントに凄い娘だよ。)
そんなことを考えていたら、つい名残惜しくなって握手が長引いてしまったらしい。
「そろそろ、出ますよぉ。」
セダンの運転席から声が掛かった。
「あっ、すんません! 」
尾藤は、まるで悪戯を見つかった子供のように慌ててアイシュの手を放した。
アイシュも、
「お待たせして、すみません! 」
と、謝りながらセダンに駆け寄って、そそくさと後部座席に乗り込んだ。
去り際にサイドウィンドウを開けて、
「必ず連絡下さいね、待ってますから。」
先々に期待を抱かせる一言を残し、アイシュを乗せたセダンは先発していった。
「惚れた? 」
銜え煙草で自家用RV車のハンドルを握る木村が、ニヤニヤと意地悪そうな笑顔を浮かべていた。
「うるせぇな。」
アイマスクを掛けさせられ後部シートに座る尾藤は不貞腐れ気味の声を出した。
「ま、美人だし、惚れるかもな。」
木村は、そう決めつけて冷かしてくる。
三四歳にもなって思春期の中学生のように狼狽えている友人の姿を見たことが実に楽しそうだった。
「惚れてないから! 」
尾藤は声を荒げたが、
「おお、怖ぇ。」
木村は却って半笑いで喜んでいる。
(まったく、分かって無いな。)
尾藤は木村の冷やかしに付き合うのが煩わしいから「惚れてない」と言い張っているわけではないし、女性に対して消極的になる性格故でもない。
(たぶん、惚れちゃいない。)
と、本気で思っている。
始めて会った時からアイシュの美貌には魅かれていたし、映画館のステージ上で見た彼女の均整の取れた美しい裸体は今も目に焼き付いて離れない。
一一日間の軟禁生活を共に送ったことで、その為人も随分と深く知ることができたので、彼女に対しては強い好感を抱いている。アイシュと二人きりになると心穏やかでいられなくなることがあるし、彼女の強さを見て感動し、弱さを見て情が動いた。
もちろん、彼女と男女関係になる想像をしたことは何度もある。
(だが、それらは恋愛感情が芽生える切っ掛けにはなるかもしれないが、決して恋愛感情そのものの表れではない。)
今のところ、自分とアイシュの間にある感情は吊り橋効果的なモノだと思っている。
共に危機を乗り越えた男女が、その際に覚えた緊張感や興奮を共有することで恋愛関係に陥るという俗説だが、尾藤はこれを信じていない。小説や映画などで物語を進行させるには都合の良い設定だが、現実に於いては男女間で勘違いを誘発しやすいシチュエーションだと思っていた。
だから、尾藤がアイシュに対して感じる恋愛感情に似た心の動きは、共にカルトと戦ったことによる同志的な感情であり、互いを思い遣る気持ちなのだと思う。
その先に続く感情は、未だ無い。
もちろん、この先にホンモノの恋愛感情が芽生えてきたなら嫌だとか、そうなったら困ると思っているわけではない。
そうなったら、そうなったで、自分の気持ちを素直に受け入れて、失敗しようが成功しようが恋愛を楽しめば良い。
(でも、たぶん俺も彼女も恋愛感情が芽生えることは無いと思う。)
二人の出会いは普通ではない。
異常な状況で出会い、出会って直ぐ運命共同体となり、死地を切り抜け、その後短い間だが生活を共にした。余りにも急激に深まった関係であるため、互いに恋愛感情を持つタイミングを逸してしまったような気がする。
しかも、その間に二人が共有する記憶は決して優しいモノではない。
今後二人が顔を合わせた時、互いを通して忌まわしい記憶を思い出すだろう。
それは、決して恋愛感情を誘発するモノとはならず、逆に恋愛感情を妨げる障壁となるはずだった。
(そういうことさ。)
尾藤は、呑気に煙草を吹かしながら冷やかしを止めない木村に向かって内心で呟いた。
(それにしても・・・ )
冷やかし以上に我慢しかねることがある。
「狭いんだからな、そんなにモクモク煙吐くなよ! 」
目隠しされてるから分からないが、おそらく車内は煙で真っ白になっているに違いない。
「俺の車だぞ! 文句言うな! 」
木村が、思い切り吸い込んだ煙を後部座席の尾藤に向かって吐きかけた。
「ああ、もう! 禁煙中だって言ってんだろ! 腹立つなぁ! 」
「本気で禁煙するつもりなら、他人が吸っていようがいまいが関係無ぇだろ! 」
「もう、いい! ちょっと、一本よこせ! 」
尾藤はアイマスクをしたまま手を伸ばし、運転席の木村に背後から抱き着くと、胸ポケットにあるはずの煙草を奪い取ろうとした。
「馬鹿野郎! 事故るじゃねぇか! 」
「逆らわずに一本よこせば良いんだよっ! 」
「うるせぇ、お前は黙ってキャンディ舐めてりゃ良いだろがっ! 」
「今、持ってねぇんだよっ! 」
尾藤には見えていないが、徐々に交通量の増え始めた通勤時間帯の環七道路。
子供のように燥ぎ騒ぐ二人の大人を乗せたRV車が、前方を走る車の隙間を縫って追い越し走り過ぎていく。
[二六]
一一月二六日から二七日にかけての夜半。
公安特別機動隊の活躍により、荻窪の廃墟ビルで行われていた『カルト教団による生贄の儀式』が阻止された翌々日。
神奈川県北西部丹沢山地において、同一のカルト集団と見られる者たちが行っていた儀式の現場を、神奈川県警第一機動隊の特殊急襲部隊SATが制圧するという、大掛かりな捕り物があった。
その前日、二五日の昼頃。
ヤビツ峠から塔ノ岳を目指して登山中の大学生パーティが、猟銃や金属バットなどで武装した一〇数名の集団に襲われ、男子大生一名が殺害され、女子大生二名が拉致されるという事件が起きていた。
山中に向かって逃走し、そのまま潜伏していると思われる犯行グループの逮捕と被害者救出のため、神奈川県警は二六日早朝から大掛かりな山狩りを開始した。
二六日の夕方。
四名の警察官と二名の山岳ガイドにより編成された一隊が、塔ノ岳登山コースからは北東に大きく外れた山中にて、黒装束を身に纏った二〇名前後が集うキャンプに遭遇。
接近を避け、付近に身を隠してキャンプの様子を窺ったところ、銃器の存在と拉致された女子大生二名の姿を確認。
自隊を数倍する武装集団に単独での対応は不可能と判断した彼らは、その場で待機しながら無線で救援を要請した。
山狩り本部からの急報を受けた神奈川県警は、第一機動隊所属の特殊急襲部隊SAT隊員三〇名を直ちに出動させた。
塔ノ岳北東斜面の四ヶ所にヘリコプターで分散降下したSAT隊員たちは、降下地点よりキャンプまで山中を徒歩にて移動。
二六日夜半に至って、キャンプの包囲を完了した。
作戦に参加したSAT全部隊を指揮するのは山県功警視。
山県は、キャンプの西方一キロメートル地点に一班の隊員八名と共に日没後降下。
所々に薄い積雪が見える塔ノ岳北東斜面を速やかに移動し、夜半前にはキャンプを視認できる位置に到達していた。
少し遅れて、他の三班も東南北の三方向に分かれてキャンプを取り囲む位置に到着し、木々の間や斜面の起伏に身を隠し、万全の体制を整え終わったとの報告が入った。
夕方からキャンプの監視を続けていた山狩りの六名については、報告を受けた後に安全な部隊後方へと下がらせており、現地は作戦開始の合図を待つばかりとなっていた。
山県警視はキャリア一七年のベテランSAT隊員である。
これまでに経験した実戦は数多く、武装強盗やテロリストを相手にした市街戦や籠城攻略戦の経験もある。さらには過酷なことで有名な陸上国防軍レンジャー訓練の参加実績があり、森林戦、山岳戦、野戦訓練では本職のレンジャー隊員に混じって好成績を収めたほどの猛者だった。
それほどの実力者であるはずの山県が、ヘルメットに装着した暗視スコープでキャンプの様子を窺いながら呆然としていた。
山県だけではない。
キャンプの様子を窺っていた歴戦のSAT隊員の全てが、かつて見たことも無い異様な光景を前にして言葉を失っていた。
「なっ、なんなんだ、あれは? 」
山県たち一班が潜んでいる場所から二〇メートルほど斜面を下ったところに、テニスコート二面分ほどの木々の開けた平らな空間があった。
その外縁には大小一〇張りほどのテントが見える。
そこは明らかに武装集団のキャンプ地だった。
キャンプ地の中央にテントは無く、広場が設けられている。
広場の中央には人の背丈ほどもある二本の太い木柱が並んで立ち、それを囲むようにして六つの大きな篝火が燃えている。
現地で調達したらしい長さも大小も不揃いの丸太を膝の高さほどの井桁に積み、その中に薪を詰め込んで燃やした六つの篝火。その炎は、周囲を照らし出すとともに、木々の間を縫って斜面を吹き降ろす寒風に煽られ、大量の火の粉を吹きあげていた。
辺りを橙色に染めながら激しく燃え上がる篝火は一見美しくもある。
しかし、その手前には不気味に蠢く大勢の黒い人影が見えた。
その数、二〇名以上。
皆が激しく身体を動かしており、遠目で見ると踊っているように見える。
しかし、それが踊りだとすれば、実に奇妙な踊りである。
手足を激しくバタつかせる者、首を前後左右に振り回す者、身体を蛇のようにくねらせる者、直立したまま垂直跳びを繰り返す者など、まったく統一感の無い動作を皆が勝手に繰り返していた。
その踊りには、知性や理性は感じられず、美しさの欠片も無い。
動物的であり、品位に欠け、汚く、醜く、邪悪でさえあった。
ところが、踊りによって発散される狂気に満ちた躍動感と異常な興奮状態が伝わってくると、それが何故か見る者の心を捕えて離さない。
魅せられたわけでもなければ、怖いモノ見たさでもない。
それなのに、山県たちは得体の知れない力に引き寄せられるように、それがどんなに不快で悍ましくとも目を背けられずにいた。
延々と続く歪な集団乱舞を眺めているうち、それが地鳴りのように低く震えながら湧き上がる合唱を伴っていることに気付いた。
それが歌ではなく何らかの呪文の詠唱であることは山県にも直ぐに分かったのだが、呪文を唱える者たちの声質が到底人声とは思えず、猛り狂う野獣の咆哮のように聞こえた。
しかも、呪文の合間には雄叫びのような奇声、夥しい快楽を纏った嬌声、狂ったような叫喚が度々発せられ、真夜中の森林を震わせる。
森林が震える度に集団乱舞は激しさを増し、ついにはキャンプを凄まじい狂気が支配していた。
いつの間にか、狂気に駆られ昂った幾人かの男女が、身に着けていた衣服を脱ぎ捨て、髪を振り乱し、身をくねらせながら篝火の前で暴れ狂っていた。
正気を失ってしまっているのか、吐く息が白くなるほどの寒気を物ともしてしない。
「これは悪魔の狂宴か? 」
眼前に展開される奇怪極まる光景に何度も意識を奪われそうになりながら、山県は正気を保つために一旦キャンプから目を背け、暗視スコープを外そうとした。
ところが、スコープが顔面に固着してしまったかのように外れない。
(引っ掛かってるのか? )
と、思ったが違う。
ヘルメットに掛けた手の指が小刻みに震え、力が入らないのだ。
(なんてこった! )
手の震えなど、新人の頃に参加した実戦以来のことだった。
これまでに数えきれないほどの実戦現場を経験し、如何に危険の伴う状況に於いても恐怖心は自制心で制御し、常に沈着冷静を保って任務を遂行するように心掛け、それを実践できていた。
ところが、
(俺が震えてる? )
信じられないことだが、キャンプで繰り広げられる狂宴が山県の心に怖れと不安を感じさせているのだ。
(じょ、冗談じゃない! )
隊長の動揺を部下に悟られてはならない。
山県は、二、三度小さく深呼吸を繰り返した後、平常心を取り戻すために、直ぐ隣で暗視スコープを覗いている部下に向かって無意味な会話を持ち掛けた。
「ストリップまで始めやがって、あいつら狂ってんのかな? どう思う? 」
しかし、意見を求められた部下も激しい動揺の真っ最中だったらしい。
暗視スコープを外し、上司に意見を求められたからには何か話さなければと慌てていたようだが、なかなか言葉が出てこない。
「かっ、完全にイカれてますよ。連中は酔っ払い? いや、ラリってるのか? じゃなくて覚せい剤、まっ、麻薬ですかね? 」
喉を振り絞るような掠れた声で応答しながら、山県ほどでなくとも実戦経験を十分に積んでいるはずのSAT隊員が身を戦慄かせていた。
ふと気が付けば、キャンプを覗いている他の部下の様子もおかしい。
手練れ揃いのSAT隊員たちが、狂宴に圧倒され、飲み込まれそうになっている。
(こりゃ、ヤバいぞ! )
部下たちの動揺を察した途端、却って山県の手指の震えは止まっていた。
(いわゆる指揮官の心構え、責任感ってやつのおかげだな。)
思わず苦笑してしまった。
だが、部下たちの現状は放置できない。
同じものを見ている他班の部下たちの状況も気になった。
精神の不安定さは士気に悪い影響を及ぼし、作戦に支障をきたしてしまう。
(グズグズしてらんないぞ! )
しかし、肝心なことを忘れてはならない。
(拉致されたって女子大生は何処だ? )
女子大生たちの身柄確保が作戦目的の第一であり、無暗に突入するわけにはいかない。
山県は女子大生の所在を確認するよう部下たちに指示すると、自らも再び暗視スコープを覗いた。
既に、この狂宴の参加者全員が素面ではない。おそらく酒や違法薬物の影響で心神喪失状態に陥っているに違いない。
そうであるならば、彼らが銃器で武装していたとしても戦闘能力は高くないものと思われ、三〇名のSAT隊員による制圧は決して難しくないだろう。
しかし、心神の喪失により理性が失われ、凶暴性は著しく高まっているかもしれないわけで、狂宴の真っ只中に捕えられている女子大生たちは非常に危険な状況にある。
些細な切っ掛けで、参加者の狂気が女子大生たちに向けられるかもしれない。
それに、キャンプの様子を一目見た時から山県には気掛かりがあった。
前々日に起きた『荻窪のカルト事件』を思い出していたのである。
女子中学生を誘拐し、生贄の儀式を行っていたという悪夢のような事件の報告書には今朝方に目を通したばかりであり、
(もしかしたら、これも同じような儀式かもしれない。)
そんな不安が頭を離れず、キャンプで繰り広げられる狂宴を見れば見るほど、その確信が徐々に強まっていくのを感じていた。
山県の推測が正しいとすれば、女子大生たちは儀式の生贄にするために浚われてきたことになる。
戦慄が走った。
(気狂いどもめ! )
生きた人間を生贄にするという行為の悍ましさは、山県の顔を怒りで歪ませ、強く噛み締めた奥歯がキシキシと鈍い音を立てた。
「隊長! 拉致被害者二名。左側のテントです。」
部下の声がしたので、山県は急いで暗視スコープを左側のテントに向けた。
すると、黒装束を纏った数名の者たちによって、篝火に照らされたキャンプの中央に無理矢理引き出される二名の若い女性の姿が見えた。
それが浚われた女子大生たちであることは間違いなかった。
二人は後ろに回した両手を手錠のような器具で拘束されており、衣服は全て剥ぎ取られてしまったらしく、何も身に着けていない。
篝火の前を横切った時、厳しい寒気に晒されて震えながらも必死の抵抗を見せる白い肌が、橙色の光の中に艶めかしく浮かび上がった。しかし、女子大生たちの心身の疲労は既に限界に達しているらしく、その抵抗は黒装束たちによって苦も無く抑え込まれ、途切れ途切れに聞こえてくる悲鳴も弱々しい。
そんな女子大生たちに黒装束たちは一切容赦をせず、二人を二本の木柱の前に立たせ、予め用意していたロープを使って其々の柱に縛り付けた。
身動きができないようロープは肉に食い込むほどきつく、何重にも巻きつけられた。
その間も乱舞と合唱の狂宴は途絶えることなく続き、女子大生たちが苦痛に顔を歪ませ悲鳴を上げるたびに歓喜の叫びが聞こえてきた。
間もなく、残酷な作業を終えた黒装束たちは両手を上げて、異様な合唱と踊りを続ける仲間たちに合図を送った。
その途端、狂人たちの発する悪魔的な叫びが辺りの空気を震撼させ、狂宴は最高潮を迎えた。
合唱は一段と高まり、踊りは激しさを増し、狂気が席巻した。
(そうだ! これは生贄の儀式だ! )
山県は確信した。
荻窪で起きた事件と同じことが、今、目の前で行われようとしている。
「隊長っ! 隊長っ! 」
女子大生たちの身が危険な状況にあることを察知した部下たちが、山県を急かすように指示を仰いだ。
さすがSATの隊員たちである。
イザとなれば、心は恐怖や不安に打ち勝ち、動揺は陰に隠れ、使命感が表に立つ。
ヘッドセット無線機のイヤホンからは、東、南、北各班長の、
「直ちに突入されたし! 」
との意見具申が聞こえてくる。
「よしっ! 」
遂に山県は決断し、瞬時に頭の中で突入作戦の段取りを組み上げた。
四つの班の中で、唯一キャンプを見下ろす位置に付けている山県の一班が、女子大生の近くにいる敵を排除。続いて閃光発音筒を発射し、これの爆発を合図に各班は一斉に制圧行動を開始する。射撃は各自の判断で許可する。
以上の命令を受け取った部下たちから一斉に、
「了! 」
の、声が聞こえた。
続いて、山県は自分も含めて六名の狙撃要員を指名し、もう一度暗視スコープを掛けて彼らに狙撃対象の指示をした。
女子大生たちに手の届きそうな位置、つまり篝火の内側には三名の黒装束がおり、まずはこれらを排除しなければならない。この三名は明らかに武装しており、うち二名は猟銃らしきモノを頭上で振り回しながら木柱の周りをグルグルと歩き回っている。もう一名は二本の木柱の間、女子大生たちに最も近い位置に立っているが、その手にはギラギラと篝火を反射する長さ五〇センチほどの金属製の凶器が見えた。
(ハンター用のナイフ! )
ハンターが仕留めた獲物の肉を切り、皮を剥ぐのに使う大型のナイフ。
それが何に使われようとしているのか、山県は浮かびかけたイメージを振り払った。
どうやら、ナイフを手にした黒装束は狂宴の主催者かリーダーのようであり、場の盛り上げ役を務めながら、何やら祈祷師のようなことまで始めている。
但し祈祷と言っても、リーダーがナイフを持つ手を頭上に翳し、天に向かって祈りの言葉らしき叫びを発すると、それに合わせて狂宴の参加者たちが相槌を打つように歓声をあげるということの繰り返しである。
まるでホラー映画かファンタジー映画の一シーンを真似したような絵面だが、おそらく彼らが祈祷を終えた後、又は祈祷の中途段階において生贄の命が奪われるのだろう。
果たして、この儀式がどのような過程を経て生贄を捧げる段階に至るのかは不明だが、状況は明らかに切迫していた。
山県は暗視スコープを外し、狙撃要員の部下たちに「構え! 」のサインを送った。
そして、自らもアサルトライフルを構えて、ドットサイトを覗く。
その途端、
「うぐっ! 」
山県は呻き声を漏らした。
儀式から目を離したのは僅か数秒間のことだが、その間に次の段階に進んでいた。
ドットサイトに映ったのは、黒装束のリーダーが女子大生の片方に向かって立ち、天を仰いで一際大きな呪文を唱えると、片手で裸の乳房を鷲掴みにし、もう片方の手に持ったハンターナイフを頭上に振り上げた瞬間だった。
山県は自らに瞬時の判断を下した。
ダーン!
轟き渡るアサルトライフルの銃声が、悪魔たちの狂宴を打ち破った。
山県のアサルトライフルが放った一撃は、黒いフードに覆われたリーダーの頭部を破壊し、血飛沫と脳漿を撒き散らした。
まさに間一髪!
ハンターナイフは女子大生に達してはおらず、ナイフが彼女の胸を抉ろうとする寸前、頭部を失ったリーダーの身体は仰け反るように転倒してしまった。
「てーっ! 」
間を置かずして発せられた山県の号令と共に、狙撃要員たちのアサルトライフルが五発の重なった銃声を轟かせた。
リーダーに続いて、篝火に囲まれた中で猟銃を振り回していた二名の黒装束も連続して打ち倒され、女子大生たちに近接した脅威は僅か数秒で排除された。
狂宴の参加者たちは、皆が呆然と立ち尽くしていた。
狂気に支配された彼らの脳では、目の前で起こった事実を認識し、状況に対処することなどできるはずもなかった。
しかし、異常事態を察知する獣の本能だけは生きていたらしい。
獣に降伏するという選択肢は無い。
生贄の女子大生に向けられていた彼らの狂気と凶暴性は、忽ちキャンプを取り囲む外敵に対して向けられた。
戦闘開始を告げる歓声が次々と上がった。
怒りに燃えた獣の視線が一斉にキャンプの周囲を取り囲む闇に向けられた。
しかし、彼らが集団で戦闘行動を開始することはできなかった。
SATの圧倒的な武力の前には、凶暴なだけの獣の群れなど無力である。
広場の中央に投げ込まれた閃光発音筒が爆発すると、獣たちの殆どが五感を奪われて行動不能に陥った。続いて四方から突入したSAT隊員が捕らわれていた女子大生の身柄を無事に確保し、あっという間に現場を制圧してしまった。
作戦は極めて短時間で完了した。
敵は武装していたとはいえ、テロリストでも何でもない素人集団だったのだから、プロであるSATにしてみれば当然の結果ではある。
本作戦における逮捕者は男女合わせて二一名。
リーダー格の男一名を射殺。
後日の取り調べで、彼らは荻窪の事件と同一のカルト集団であることが判明した。
但し、リーダーは上井ではなかった。
キャンプからは散弾銃四丁と散弾六〇発、他に金属バットやサバイバルナイフなど多数の凶器と共に、大麻二キロと、神奈川県内の医療施設から盗み出された大量の向精神薬が発見され、これらは全て押収された。
救出後の女子大生二名は疲労困憊しており、急性ストレス障害が心配されてはいるが、幸い目立った外傷は無く、性的な暴行も受けてはいなかった。
SAT隊員に被害は無く、逮捕時の容疑者たちの抵抗は軽微であったとされる。
しかし、視覚と聴覚を奪われながらも刃物や火の点いた松明を振り翳して幾人かの男女がSAT隊員に襲い掛ったという記録もあった。ヘリコプターで下山する途中にも暴れ出し、飛行を妨げようとした者がいたともある。
作戦を総括した山県警視によると、容疑者たちの狂乱振りは全員が下山を完了した後も続き、正気を失い敵意を剥き出しにした彼らと長時間接することになった一部SAT隊員たちに軽い精神的ストレスが見られたらしい。
それから、これは記録外の話だが、
「作戦終了後にキャンプを囲む森の中で巨大な怪物を目撃した。」
と、言う隊員が数名いた。
彼らの診断に当たった精神科医師の判断により、ストレスによる幻覚症状であるとされたが、奇妙なことに其々の隊員たちが幻覚を見た時と場所はバラバラであったにも関わらず、皆が同じ描写を口にしていた。
「黒い霧状の怪物」
それが、木々の間を擦り抜けながら、キャンプの周辺を這い回っていたという。
このような話を、まともに取り合う者などいるはずもなく、初めは本当に怪物を見たと言い張っていた隊員たちも、時間の経過と共に自らの正気を疑い出し、敢えて人前で口にする者はいなくなった。
一一月二五日以降、首都圏では同様の事件が相次いでいた。
その中で主な件を挙げてみる。
一一月二六日、東京都西多摩郡旧奥多摩地区。
一〇年以上前に人口消失し、東京都職員と観光業者以外は無人化した同地区において、廃墟化した山間の集落にカルト信者が集まり生贄の儀式を行おうとしていた。
近隣のあきる野市で女子高校生を誘拐しようとした二名の男をパトロール中の警察官が逮捕したところ、これがカルト教団関係者であり事件が発覚。
直ちに青梅警察署が対応し、廃集落に集まっていた一七名を逮捕した。
一一月二六日、東京都渋谷区宇田川町。
同地区にある雑居ビル内で生贄の儀式が行われようとしていたが、これは違法薬物の監視捜査活動中の厚生労働省麻薬取締官によって阻止された。
現場に踏み込んだ麻薬取締官たちには、そこがカルト教団の儀式会場であるとの認識は無かったが、結果的に拉致された女子中学生一名の救出に成功し、一五名を逮捕した。
一一月二八日、千葉県袖ケ浦の石油精製工場。
東京湾に面した石油精製工場の岸壁で、巡回中の警備員が若い女性の遺体を発見した。
検視により死後二四時間以内と推測されたが、遺体には鋭利な刃物による外傷があり、失血死したものと思われる。
遺体の損壊状況により、カルト教団の儀式によって殺害されたものと判断された。
一一月三〇日、東京都江東区若洲。
違法な居住者が多く、近年は治安の悪化が著しい若洲海浜公園内で生贄の儀式が行われていたのを、同地区をパトロール中の東京湾岸警察署員が発見。
儀式が数百人規模であったことから、警視庁機動隊と水上からは警備艇が出動し、銃撃戦をともなう大掛かりな捕り物が行われた。
その結果、カルト教団関係者一〇〇名以上を逮捕し、大量の銃器と違法薬物の押収に成功したが、儀式の生贄にされた女子小学生一名は既に殺害されてしまっていた。
この若洲の事件においては警察側にも多数の負傷者が発生し、警備艇一隻が沈没するという被害を出した。
しかし、教団側は警備艇を沈めるほどの強力な武器を所有していなかったことと、後日引き上げられた船体は上部構造物以外は殆ど無傷であり、沈没に至った原因が特定できなかったことが、後々の謎として残った。
警備艇沈没の原因調査中、海に投げ出された警察官を聞き取りしたところ、
「黒い霧状の怪物」
が、波間で浮き沈みを繰り返していたと語った者が二名いたらしい。
しかし、これは事件の報告書には記載されず、沈没の原因は操船ミスとされた。
「これが全部カルトの仕業って? なんか変じゃない? 」
およそ半月ぶりに事務所を訪れたアディが社長室兼応接室のソファに腰掛けてタブレット端末で新聞記事を見ながら首を傾げていた。
「そうなのかぁ? 」
PCディスプレイの影から尾藤の生気の無い声がした。
昨日引き受けたばかりの案件、浮気調査の依頼に関する書類整理に掛り切りの尾藤は顔を上げる暇も惜しいようで、先ほどからアディが話し掛けると片言の返事は返してくれるのだが、おそらく話し掛けられた内容の半分以上は聞き流してしまっている。
「ちぇっ、久しぶりに会ったんだから少しは話し相手してくれると思って寄ってみたのなぁ。」
尾藤の愛想の無い態度にアディがガッカリしている。
仕事が忙しいのだから当然のこととは理解してくれているのだろうが、それでも面白くは無いらしい。
まるで、聞き分けのない子供のようにイジけた態度を見せる。
先週から「クアーク」で働き始めていたアディはマスターの評価も上々で、紹介した尾藤の面目も立ったが、慣れない仕事に緊張やストレスを感じていないはずが無く、今日は気晴らししたいがために事務所を訪れたに違いない。
尾藤にしても、アディと顔を合わせるのは久々だったし、時間があれば話相手ぐらいはしてやりたかったのだが、そうもいかない事情があった。
尾藤が公安の軟禁生活から解放され、仕事を再開した日、
「まあ、色々と事情があったわけですけどねぇ、先月は仕事に一週間以上の穴が空いちゃったわけですよ。これを取り戻すには、今月は倍以上働いてもらわなきゃならないんですよ。そうしないと、普通に年越しできませんね。正月の餅代は出ませんよ! 」
そう言って、恵子は復帰早々の尾藤に容赦なく先月の収支を突きつけた。
「はい・・・了解いたしました。」
豪華な施設でノンビリ過ごし、心身ともに鈍りかけていた尾藤を、恵子は忽ち現実に引き戻してくれた。
まったく有難いことである。
そんな恵子が、薄っぺらなパーティーション一枚隔てた隣室にいるわけで、こちらの様子は筒抜けであり、呑気に談笑でもしようものなら怒られそうである。
実際、尾藤は忙しい。
現在、抱えている案件は、浮気調査が四件、身上調査が二件、家出人探しが一件。
一人では到底無理な数なので、七件中四件までは下請けに回して仲介料を頂くつもりでいたのだが、いずれにしろ引き継ぎに必要な準備は自分で整えなければならない。
そういうわけで、一二月一三日の金曜日、時刻は正午少し前。
土日の休日返上が確実になった週末、尾藤は朝から社長室兼応接室に籠り切り、PCのディスプレイを睨み、入力作業を続けるという書類作成業務に忙殺させられていた。
「手伝ってあげられたら良いんだけど。」
アディは同情してくれるが、彼の日本語力では業務書類を預けるのは難しいし、そもそも依頼者のプライバシー関係の書類が多いので人任せにできる内容ではない。
「そうだ、恵子に言って金貰ってさ、弁当買ってきてくれないかな。」
せっかく遊びに来たアディを使い走りにするのは可哀そうに思ったが、本人は手伝えることが見つかったので、喜んで近所の弁当屋へ出掛けて行った。
「さっきの話の続きなんだけどさ・・・ 」
恵子も加えて三人で応接テーブルを囲み、幕の内弁当を食べ、食後のコーヒーを飲みながら束の間の休憩時間を楽しんでいたら、アディが先ほどまで熱心に読んでいた新聞記事について思い出したらしい。
「あちこちで起きてたカルト教団の生贄事件のことだっけ? 何か変だって言ってたよな? 」
尾藤は気になることがあったら話してみろと言った。
「確か、カルトの儀式にはルールがあって、特に生贄には大事な条件があるんだって言ってたよね? 」
「生贄はカルト教団以外の女性で、若くて、容姿が優れていて、処女でなければならないっていうやつだろ。」
「ところがね、神奈川の事件ではさ、生贄にされそうになったのは女子大生だったじゃない。これって変でしょ? 変だよね? 」
アディは、何が変なのか気付いて当然でしょうと言う顔をしていたが、尾藤はアディの言わんとするところが分からずに、
「んん? 」
と、首を傾げていた。
「ああ、確かに変かもね。」
アディに同意したのは一緒にコーヒーを飲みながら話を聞いていた恵子である。
彼女は尾藤よりも先にアディの指摘に気付いたようだ。
「何? 何処が変なの? 」
尾藤は自分だけを置き去りにして、
「そうでしょう。」
「そうだよね。」
と、勝手に理解しあって頷いている二人に向かって、
「俺にも教えろよ! 」
不機嫌丸出しな声で言った。
すると、恵子がまあまあと尾藤の肩を叩きながら、
「学生時代が遠くなっちゃったオジサンは、ピンと来ないんだろうねぇ。」
意地悪そうに言った。
尾藤がムクれそうになったので、アディが笑いながらフォローした。
「処女を探すには女子大生は難しいってことだよ。」
「ん? 」
「いい加減に自分の学生時代の同級生のことを思い出したら? 女子大生で処女って見付けるの大変だと思うわよ。」
そこまで言われて尾藤も、
「ああ、そういうことね。」
漸く理解した。
近頃、尾藤は街を歩いている女子たちについて、中学生、高校生、大学生の区別がつき難くなっている。小学校高学年ぐらいの女子を大学生に間違えたりすることもあったし、その逆もあったりした。しかも、自分の若い頃の同級生女子たちがどうだったかなどということは忘れて、若くて可愛い子は皆が処女に見えてしまったりする。
三〇代半ばになって、すっかりオジサン感覚が身についてしまったということである。
「ああ、そういえば、そうかもねぇ。」
遠い記憶を思い出しながら、少し悲しくなった。
「生贄が処女であることが重要だから、荻窪で逮捕された連中は主に中学生以下で躾けの厳しいお嬢様学校を狙ったんだと思うって木村さんも言ってたよ。」
言われてみれば、その通りである。
浚ってきた女子が処女かどうかなど調べようが無いので、疑わしい対象は避けるのが当然のことと思われる。
尾藤は納得して頷いたが、ふと思って、
「あれ・・・ 」
うっかり恵子の顔を見てしまった。
だから、彼女も女子大生なわけで?
「え、なんでしょうか? 」
恵子が尾藤の視線をキツく跳ね返した。
「いえ、なんでもないです。」
そう言って、尾藤は簡単に引き下がった。
恵子に「処女ですか? 」と、聞いたところで答えるわけがない。
(んなこと聞いたら、ブッ飛ばされるわ! )
そもそも尾藤に処女願望など無い。自分だって童貞じゃないし、恵子が処女であろうがなかろうが、いずれにしろ惚れてるっぽいのだから関係無いと思っている。
そうは思いつつも、ホンの少しぐらいは気になるのだが・・・尾藤は話を元に戻して、
「まあ、神奈川の女子大生は彼氏と一緒に登山していたって言うしなぁ、そんなんで処女とか、今時有り得ないかもな。」
と、意見してみた。
「でしょ。そう普通は考えるよ。処女狙いで小中学生ばかり誘拐していた連中なら、女子大生なんて考えないでしょう。」
尾藤の同意を得てアディ満足げに頷いた。
確かにアディの言う通りだと思うが、それ以外にもルールに合わない点はある。
「満月と新月ってルールもあったよな? 」
「満月に浚って新月に殺すってことだよね。神奈川でも奥多摩でも殺す前日に浚ってるし。全然、関係無くなってるね。」
これは儀式の重要な段取りであったはずだ。
尾藤たちは、この段取りを突き止めたことにより司廉子の救出に成功した。
荻窪で行われたカルトの儀式は、尾藤たちに周囲を嗅ぎまわられ警戒しながらも、この段取りに忠実だったことにより壊滅したのである。
「教団の教えでは、新月の日に何かが発動するということだったから、それ以外の日に行われた儀式って、同じカルトのモノじゃないと考えるべきじゃないかな。」
「うーん、確かになぁ。」
雰囲気だけ似ているが、大事なところに相違が見られる。
荻窪のカルト事件の報道を見た変質者や異常者による模倣犯罪かもしれない。
「そうでもないんじゃない? 」
いつの間にか恵子がタブレット端末を手にして、某ソーシャルネットワークにアクセスしていた。
「これって、アングラな情報交換ページだけど、千葉に上がった女の子の遺体の件と江東区の儀式で殺された女子小学生の状況が記されているわ。読んでみて。」
尾藤は恵子が差し出したタブレットを受け取り、そこに開かれたページに目を通した。
「教団の儀式で、生贄がどうやって殺されるのかは木村さんが言ってたでしょ。それについての情報は一般には公開されていないから、模倣犯が真似できるはずないと思う。」
いったい誰が何処から得た情報なのか、そのSNSには警察内部からの流出情報ではないかと思うほど、破壊された被害者の遺体状況が丁寧に描写されていた。
・・・漂着した女性の遺体は左右の乳房が切り取られ、股間も大きく抉られていた。漂流中に大型の魚などに食われたのではないかという見方もあったらしいが、検死の結果で意図的に子宮と生殖器を切除されたことが判明・・・[千葉]
・・・機動隊が海浜公園を制圧し終えた時、生贄にされた女子小学生は未だ息があったようだが、既にカルトの凶行により彼女の左右の乳房と股間は抉り取られており重体。大量の出血により救急車が到着する以前に死亡・・・[江東区]
これは、スレッドの記述の一部である。
さすがに写真画像まではアップロードされていないが、ある程度は儀式の内容を把握している尾藤たちには十分な判断材料になる。
「つまり、この遺体の状況から判断するなら、荻窪と同一の連中の仕業だろうってことだよな。」
「そうよ。儀式の段取りを知っている者と考えて間違いないんじゃないかしら。」
そうだとすれば、月齢に関するルールを無視しているのはどういうわけかと思う。
教団関係者なら、月一回づつ儀式が行われていた意味ぐらいは知っていたはずだ。
「そういうことって、けっこう大事だと思うんだけど? 」
尾藤の疑問に、恵子が難しく考えずに単純に考えるべきだと言う。
「正式な儀式が潰されちゃって焦ったんじゃないかな。それで、月齢のルールは知ってたけど、辻褄合わせで儀式を取り繕おうとしたのかも。信仰と教義が徹底されている宗教なら、そんなことにはならないと思うけど、あの教団って儀式を成功させることをだけを目的に集まった同好会みたいなもんでしょ。根っこのところがいい加減なのよ。そんなんで指導者の一二人全員が一挙に逮捕されちゃったから、残された連中は、どうして良いか分からなくなって、取り敢えずな感じで儀式モドキを乱発しちゃってるのよ。」
恵子の話に、尾藤もアディも「なるほど」と、頷いた。
「儀式が乱発されるのは怖いし、犠牲になった女の子たちは可哀そうだけど、これはアイシュさんが言っていたとおり、指導者を失ったことで教団組織が崩壊してしまった証拠じゃないかしら。統率、指導する者がいなくなれば、そのうち事態は沈静化するしかないでしょう。警察も頑張ってるみたいだし、いずれ組織はバラバラになって自然消滅しちゃうでしょうね。」
確かに指導者が生き残っていたら、こんな中途半端な儀式は乱発されないだろう。
ルールに沿った儀式が行われなくなったということが教団が機能していないことの証明という恵子の意見は正しいような気がする。
「たった一人で逃亡した上井は、今のところ教団の再結集を計れていないんだな。」
荻窪の事件後半月以上経過した現在に至っても、リーダーである上井の行方は掴めていない。
その点については尾藤たちカルト教団事件に関わった者たちにとって、常に頭を離れない不安要素である。上井が教団の再結集に成功すれば、尾藤たちは復讐の対象として狙われる可能性が出てくるのだ。
「でも、公安と警察の包囲網を掻い潜って活動したりすることなんて個人ができることじゃないから、教団を再結集するなんて無理だったってことね。上井は自分の身を守るために、何処かに引き籠ってるのが精一杯でしょ。」
「そうだな。乱発された儀式に、上井の指導者としての影響力が見られないということは、そういうことなのかもな。」
事件は沈静化に向かっている、そう思って良いのだろうか?
この半月、普通の日常生活を送りながらも、逃亡した上井のおかげで頭の片隅にはカルト教団の影がチラついて不安が燻り続けていた。
それが完全に消えて無くなる日は近いのかもしれない。
「ところで話は変わるけど、司さんとこは、その後大丈夫なの? 」
アディは、先日警察病院を退院した司廉子のことを心配していた。
「ご両親の話では、大分気持ちも落ち着いてきたということだったわよ。未だ自宅療養中で、外出させたり、学校に通わせたりはできないけれど、本人も早めに社会復帰しようって頑張ってるみたい。それに、自宅は警察が二四時間の監視体制を敷いているみたいだから、もう教団なんかが手出しできるような状況には無いでしょう。」
事件後、司夫妻との諸連絡は恵子に任せていたので、彼女が現状を把握している。
もしカルト教団の一部でも生き残っていたなら司廉子が再度狙われる可能性は高いとして、警察は司家の警備を厳重にしているので大丈夫と思われる。
それよりも心配なのは、思春期の少女が心に負った傷の深さについてである。
そのことについて、アディの気遣いや心配振りは尾藤や恵子に比べても大きかった。
アディは荻窪の事件後、司廉子を警察病院に搬送する救急車に同乗し、司夫妻が駆けつけるまで付き添っていたわけだが、そこで親子の涙の再会を見てしまったことで激しく感情移入してしまったらしい。臨時雇いとはいえ調査員の助手として初めて働いた仕事で、いきなり大掛かりで困難な事件の解決に寄与し、その成果として依頼者たちの喜ぶ姿を間近にしたのだから感動は大きかったのである。
司廉子が警察病院を退院するまでの一〇日余りの間、一日か二日おきに見舞いに出掛けていたらしい。
友人に裏切られ、悪魔のような集団に捕えられ、生贄にされそうになった女子中学生が心に負った傷は大きいはずで、そんな彼女の所へ見知らぬ若い男が見舞いを繰り返すというのは不味いのではと、尾藤も恵子も渋い顔をしていたが、どうやら心配は無用だった。
司夫妻から聞いた話では、司廉子はアディが来るのを心待ちにしていたという。
精神的にはかなり辛い状態にあったらしいが、アディが来た時には楽しそうに会話をしていたという。
その原因だが、尾藤が軟禁明けに警察病院を訪れた際、司廉子の母親から聞かされた言葉で納得した。
「アディさんって、ホントに美男子でいらっしゃるから。」
そう言いながら、年甲斐も無く頬を赤くする母親に、尾藤は引き気味になった。
(ああ、そういうわけなのね・・・ )
アディは女子中学生に惚れられたというわけだ。
傷ついた心のケアに恋愛感情が良いのか悪いのか知らないが、本人が喜んでいるのなら問題無いのだろう。
(ま、アディのイケメンが役に立つってんなら、別に構わないんだけど・・・ )
そう言えば、アディが訪れる度に警察病院の女性看護師や女性入院患者たちの様子が変だったという話を木村から聞いていた。
意味も無くアディのいる司廉子の病室付近をウロウロしたり、コソコソと物陰から覗いたり、話し掛けられたら燥ぐとか、特に病院業務に支障を及ぼしたりはしなかったらしいが、病院内に居合わせた男性たちの目から見れば、かなり不愉快で鬱陶しい状況だったと聞いた。
アディは、周囲の女性に対して自分が与えている影響を理解しているのだろうか?
どうやら、モテているという自覚はあるらしい。
今日アディが事務所を訪れて早々、購入したばかりだという最新型のタブレット型携帯通信端末を見せてくれた。
「最近、アドレスが随分溜まったんだ。」
そう言って、自慢げにアドレス帳を起動したら女性の名前ばかりが並んでいた。
(こ、この野郎! )
アディのおかげで、「クアーク」に女性客が増えたとかマスターから聞いていたので、そこが主な出所だろうと思うが、病院で女性看護師と交換した数も少なくないはずだった。
確かにアディは性格も良いし、気が利くし、働き者の好青年なわけだが、同じ男としてはイケメンでモテ過ぎるところは、聊か気に入らない。
(いつか痛い目を見れば良いのに・・・ )
尾藤は心の中で黒く呟いた。
現状でアディのイケメンぶりに動じないのは恵子ぐらいである。
動じないどころか、事務所に於いては不定期のパート従業員扱いであるアディに対する恵子の態度は気持ちが良いほどにビジネスライクであり、尾藤に対するのと同様に厳しかった。
(さすが恵子さん。ホントに素晴らしいです。やっぱりオレが惚れてるのは恵子さんだけですよ。一緒にいれば心が癒されます。そりゃ、散々怒鳴られるし恐ろしい目にも合わせられるけど、そういうとこも含めて気に入っちゃってるんだから、しょうがないよね。確かにアイシュは美人だったけど、あれは一時の感情だったんだわ。うん! )
尾藤は唐突にアイシュのことを思い出した。
公安の施設を離れて以降、一度も連絡を取り合っていない。
必ず会いましょうと約束をしたけれど、それっきりになってしまっている。
木村には、惚れたんだろうと冷やかされたけれど、離れてしまえば恋愛に繋がりそうな感情はついてこなかった。やはり、アイシュに対する気持ちは同志的なモノであり、恋愛ではなかったということだろう。
(このまま、互いに連絡もせず、二度と会わないのが良いんじゃないかな? )
このまま日常生活が続けば、アイシュの記憶も事件の記憶も共に薄れていくだろう。
お互いに、今回の事件のことは丸ごと忘れてしまった方が良いと思う。
(多少、残念ではあるがね。)
やはり、類稀な美貌の持ち主であったアイシュを思い出すと心の疼きぐらいは覚える。
(俺って軟弱だなぁ。こまったもんだよ。)
尾藤は心の中で苦笑した。
[二七]
「カルト教団事件は終息に向かっている。」
未だ完全に終息したとは言えない状況だが、
「身近に迫り来る脅威ではなくなった。」
ハッキリと確信したわけではないが、その可能性に思い至ったことで、通常の生活に戻ってからも心に重く圧し掛かっていた不安が幾分か薄れた気がした。
いずれ、近いうちに不安が完全に取り払われる日がやってくるだろうと期待することもできた。
(今日は久々に安眠できそうだな。)
事件後も、度々悪夢に悩まされている尾藤だったが、それは心の中に蟠っている不安の表れに違いない。
だから、不安が軽減されれば悪夢も見なくなるはずだと思っている。
今日の昼休憩、恵子、アディと三人で意見を交わし合ったのは良いことだったと思う。
自分一人で、あれこれ思い悩んでいたら、消極的な思考ばかりが浮かんできて不安感が日に日に増大してしまい、いつまで経っても事件の後遺症から抜け出せなくなる。
だから、
「カルト教団は崩壊しつつあるのでは? 」
と、恵子に言われるまで、その可能性に考えが至らなかったのである。
調査員としての心構えを忘れ、教団の残党が引き起こす事件の報道を見聞きしても、それを脅威として捉えるばかりで、事件が起こる背景や動機を考え、現状を冷静に分析し、推理することができなくなってしまっていたらしい。
(今回の事件、俺は当事者過ぎてダメなんだな。教団に狙われるかもしれないってことで、被害者的な心理状態に陥ってしまっていたんだわ。これからは事件を客観的に見るようにしなきゃ調査員失格だな。)
そんな反省をしながら、仕事を終えた尾藤は徒歩で家路についていた。
時刻は午前二時を過ぎており、JR中央線は営業を終了してしまっているので歩くしか無いのだが、どうせ僅か一駅なので苦にはならない。
ただ、以前ならば夜遅くなったら路地を縫うように最短距離を辿って帰路についていたのが、今は遠回りを覚悟で夜遅くなっても人通りのある山手通りと早稲田通りを経由している。これは警察から日常生活を過ごす上での注意事項として言い聞かせられていることなのだが、自分でも警戒は十分にすべきだと思っていた事情による。
多少不安が薄れたからと言って、直ぐに警戒心を解くわけにはいかない。
周囲に気を配るのを忘れず、見通しの悪い曲がり角や街路灯の少ない道を通り過ぎる時などは、いつでも不測の事態に対応できるよう緊張し身構えている。
そんなタイミングで突然、携帯通信端末の着信音が鳴ったのだから迷惑なことである。
「う、うぉっ! 」
思わず声が出たし、足取りも乱れた。
喉の奥が引き攣って一時呼吸が止まるほどだった。
「な、なんだよ? 」
尻のポケットから端末を取り出してみると着信の相手は木村だった。
(まったく、驚かせやがって! )
尾藤は再び歩き出しながら、面倒臭そうに受信ボタンをタップした。
どうせ、用件は分かり切っている。
軟禁生活が明けて以降、一日一回必ず掛ってくる様子見の連絡である。
毎度、「無事か? 」「身の回りに異常がないか? 」との二点を確認するだけの短い通話であり、定時は決めていないが普段ならば日中の時間帯に掛ってくる。だから、今日は掛ってくるのが遅過ぎる気もするが、木村も忙しい身なので仕事が立て込んでいたら、そういうこともあるだろう。
一日ぐらい抜けたからと言って問題の無い程度の通話なのだが、まったく律儀で生真面目な奴である。
「はいはい、今日も無事ですよぉ。 異常もありませんよぉ。そちらはいかがぁ? 」
相手の声を聴く前に、毎度決まりきった質問の答えを先に言ってやった。
ところが、木村の声がいつもの調子ではなかった。
いつも通りの質問をしてこない。
「尾藤・・・ 」
そう言ったきり、間が空いた。
異常事態発生の臭いがする。
「木村、何があった? 早く言えよ! 」
通話口の向こうから、苛立たしげな舌打ちと苦しげな喘ぎが聴こえた。
そして、木村が吐き捨てるように言う。
「アイシュが行方不明だ! 教団に拉致されたのは間違いない! 」
「え・・・? 」
尾藤は頭の中が真っ白になった。
木村に返すべき言葉が出てこなかった。
(教団? だって教団は? )
教団は組織としての機能を失い、既に脅威ではなくなりつつあるとの展望が見えてきたはずではないか。
それなのに?
「どういうことだよ! 何が起こったんだよ! 」
尾藤は激しく動揺して、人通りもそこそこあり、マンションやアパートも多く建ち並ぶ深夜の早稲田通りのド真ん中で、迷惑も考えずに大声で怒鳴ってしまった。
「我々のミスだ! 大失態だよ! 」
テーブルを打つ拳の音が聴こえ、続いて木村が詳しい状況説明を始めた。
一二月八日、軟禁生活が明け、公安の施設から解放されたアイシュは尾藤と別の車両で無事帰宅したと聞いていた。
帰宅後も担当の警察官三名が交代で身辺警備を行っていたはずだった。
しかし、想定外の恐るべき事実が判明した。
公安の施設からアイシュを乗せた警察車両の運転手が実はニセ警官であり、カルト関係者だったのだ。
「アイシュは帰宅してはいなかったんだよ! 」
尾藤の脳裏に、サイドウィンドウの向こうで不愛想な顔をして運転席に座る初老の公安警察官の横顔が浮かんだ。
(あいつ! )
「昨夕、ホンモノの運転手だった警察官の殺害された遺体が発見された。遺体の検死により死亡後一週間前後経過していることが分かった時点で、アイシュの自宅マンションには警察官が急行したらしい。」
しかし、アイシュは不在。五日前に帰宅し、その後は日常生活を送っていたとの報告があったはずなのに、その形跡が無かった。
「つまり、運転手だけじゃない。警察内部にも教団関係者がいたんだ! 」
裁判までの間、アイシュの身辺警護と連絡係を担当していた警察官のうち女性一名もカルト関係者だったというのである。
「やられた! 奴ら、警察内部にまで入り込んでいたとは・・・ 」
木村が尾藤に対して毎日行っていた安全確認の連絡も、アイシュとは女性警察官が行っていたという事だが、これは全て誘拐されたことを隠すために偽装されてしまっていた。
尾藤は、出角が死ぬ間際に言っていたセリフを思い出した。
『お前は同志たちの恐ろしさを分っちゃいない! 彼らが本気になれば警察の中だって関係ない! 同志たちが手出しできない所なんて何処にも無い・・・ 』
出角が怯えながら口にしたセリフは本当だったのだ。
「何やってんだよっ! 警察が、そんなこって良いのかよ! 」
木村を相手に怒鳴り散らしたところで、どうなるものでもないことは分かっているが、この腹立ちが簡単に収まるはずがない。
先ほどまで「カルトの危機は去りつつある」などと、気楽な想定をして安心し掛けていた自分にも腹が立ってきた。
(終わってないじゃないか! まだ続いているじゃないか! )
尾藤は通信端末を耳に当てたまま、こんな話を聞いてしまった後で自分がどうすれば良いのか分からず、無駄に通りを行ったり来たりしていた。
(アイシュが殺される? )
相手は常軌を逸した殺人集団である。
裏切り者は必ず殺すだろう。
無事に返すつもりで誘拐などするはずがない。
不意に、公安の施設の前で、別れ際に「必ず連絡下さい。待ってますから」と、言った時のアイシュの笑顔が浮かんだ。
(くそっ! 二度と会わない方が良いなんて思わずに、あの後で直ぐ俺が連絡していれば、アイシュが浚われたことにもっと早く気付いたのに! )
後悔が伴った様々の感情が一気に噴出してきた。
教団への怒り、警察の不甲斐なさに対する憤り、自らの身も危険に晒されているかもしれないと言うことに対する焦り、そして忘れかけていたアイシュに対する感情。
尾藤は混乱のあまり、吐きそうになった。
それでも、何とか木村と話さなければならない。
自分は事件の当事者である。
アイシュを助けるために何かできることはしなければならない。
既に助けられない状況にあるとしたなら・・・奴らに復讐しなければならない!
「その教団関係者だって女、捕まえたんだろうな? 」
尾藤は感情を抑え、喉の奥から絞り出すような声で言った。
「ああ、現在取り調べ中だ。気になるなら、今から杉並署まで来い! 」
「直ぐ行く! 」
木村の誘いに尾藤は即答した。
「それと、これは俺の考えだが付け加えておく。たぶん、アイシュは生きてるぞ。」
アイシュは生きているかもしれないとの木村の言葉。
それは微かな希望を与えるはずの言葉であるはずなのに、聞いた途端に尾藤の背筋には戦慄が走った。
「まさか・・・ 」
おそらく一生忘れられない、記憶に焼き付いてしまった恐怖と著しい不快感を伴う異様な光景が思い出される。
木村が決定的な一言を口にした。
「一二月八日は、満月だった! 」
[二八]
尾藤は杉並署に到着すると直ぐに、情報分析室に案内された。
主に映像情報を元にした捜査活動のミーティングや、容疑者の取り調べを大勢で監視する際に用いられる視聴覚室のような仕様の部屋である。
尾藤が情報分析室に入ったのは初めてだったが、以前に荻窪で逮捕されたカルト指導者たちの面通しをした際に使われた映像情報管理室に比べたら、随分広々としていて贅沢な部屋だと思った。
配置されている機材は大小数台のディスプレイモニターとオペレーション用のPCが一機だけというシンプルな構成だが、椅子は折り畳み式簡易テーブルとドリンクホルダーまで付いた座り心地の良い立派なモノが使用されており、それが小規模な映画館やビデオシアターの観客席のようにディスプレイモニターの並ぶ側の壁面を見下ろすよう雛壇式に並んでいる。
なんでも、警視庁のお偉方や検察庁の役人が取り調べに立ち会う際に使用されることもある部屋だということで、このような作りになっているらしいが、そんな滅多にない機会に合わせたのでは税金の無駄遣いではないかと思えてしまう。
今、この部屋の中には尾藤と木村しかいない。
二人は雛壇の最前列に座り、電源の入っている唯一の大型ディスプレイモニターの前で険しい顔を並べている。
ディスプレイモニターに映っているのは、現在別室で行われている女性警察官の取り調べのライブである。多画面マルチに設定されたディスプレイモニター内には、取り調べ中の室内を見下ろす全景と女性警察官の顔アップ、音声や呼吸、脈拍、血圧など複数の生理現象を表す波形も同時に表示されている。
アイシュが誘拐された事実を隠すための偽装工作をしていたという、この女性警察官の取り調べが始まったのは、尾藤が杉並署に駆け付けて直ぐのことであり、それから二時間ほど経過していた。
その間、アイシュを誘拐した段取りについてや自らが行った偽装の内容については、意外に簡単に自白してしまっていたが、肝心のアイシュが浚われた先、監禁場所などの情報は一切口にしていなかった。
それ以外に取り調べの中で彼女が口にしたのは、社会に対する不満と恨みごと、自己の行動とカルト教団の正当化についてであり、他に役に立つ情報は無かった。
「こいつが知っているのは自分の仕事だけなんだろう。」
取り調べの様子を食い入るように見ていた木村が感想を漏らした。
自分が担当する役割以外は教えられていないのだ。
アイシュの誘拐が司廉子の時と同様、組織的に行われた犯行だとすれば有り得ることだと思う。情報統制と命令系統が際立っているのが教団の大きな特色だった。
しかし、警察の大々的な捜査活動により、教団の重要な拠点は殆ど潰されてしまっており、「シクラニ」に代表される命令系統の重要な機能であったHUBは失われたものと思っていた。
「命令系統の大部分は失われてしまったが、僅かに生き残っている系統があるということだろう。今回は、それが警察内部から伸びた系統だったということだが、それを生かして使うことができるのは、やはりトップにいる人間。つまり、上井だよ! 」
「くそっ! やはり、奴を取り逃がした失敗が原因か! 」
指導者全員を捕えることが教団を壊滅させる条件とアイシュは言っていた。
それなのに、たった一人とはいえ、リーダーである上井を逃がしてしまった。
これは、重大な失策だった。
警察により教団の組織としての機能は殆ど奪われたが、全てではなかった。僅かに生き残った機能に逃げ延びた上井が接触に成功し、再び活動を開始したのだ。
リーダーとはいえ、たった一人では何もできないだろうと考え、指名手配と逮捕を目的とした捜査は徹底的に行われていたが、こうも早く上井が再び行動を起こすとは予測しきれなかった。
恐れていたことが現実になってしまった。
「次の新月は何日だ? 」
尾藤は床に置いたバックを取り上げて、中からタブレット端末を取り出した。
「一二月二三日、一七時七分。」
木村は、尾藤がカレンダーを開く前に即答した。
既に、アイシュ救出に残された日時の計算は終わっているらしい。
「あと一〇日間だ。一〇日後に再び儀式が行われる。」
「一〇日後・・・ 」
何から調べるべきか?
マジックマッシュルーム、ヤドリギ、都内九カ所に設定された儀式の会場候補など、司廉子の時に得た様々な情報を今回も流用できるのか?
「まずは、そこから当たってみるしかないだろうが、一度失敗した段取りをもう一度繰り返すとは思えないよな。」
尾藤の意見に木村は頷いたのだが、
「本件は、警察と公安が最大限の力で捜査を行うことになる。お前は自分の仕事を最優先にしてくれ。」
その木村の突き放すような一言に、尾藤は驚き反発した。
「はぁ? 俺は当事者だぞ! アイシュの命が掛ってるのに、そんな呑気な事! 」
その言葉を遮るように、木村は言った。
「そうだよ! お前は当事者なんだよ。お前が命を狙われているかもしれないという推測は未だ生きてるんだ。アイシュが浚われたことで、身の危険性は今まで以上に高まったと言える。そんな奴に、警察と一緒になって教団の周りをウロウロさせられるわけがないだろう! 」
それは正しい、正しいのは分かっているが・・・
「お前の気持ちは分かるが、司廉子の時とは状況が変わっているんだ。こちらの情報は逐一入れるようにするから自制しろ。いいな! これは絶対だ! 」
尾藤は不満を剥き出しにした険しい表情で木村を睨みつけた。
しかし、言い返すことはできなかった。
ここで下手に逆らえば、木村は身柄の安全を確保するとの名目で尾藤の行動を厳しく制限しようとするだろう。
(木村は、そういう奴だ。ちくしょう、俺はアイシュのために何もできないのか! )
尾藤が悔しがっていることは木村も承知している。
お互いに相手の性格は承知している仲なのだから当然である。
「正直言って、我々の手で必ずアイシュを助け出すと確約するのは難しいのが現状だ。だが、それでも今回は信じて預けてもらうしかない。お前が一緒になって動いたとしても結果に大きな違いは無いだろうし、ハッキリ言って足手纏いになる。下手すりゃ、お前まで教団の手に掛る可能性があるわけで、そんな二重遭難の恐れがある奴に関わらせることはできない。」
返事をしない尾藤の様子に木村は溜息を吐いたが、ふと思い出したように隣の椅子の上に置きっぱなしになっていたA4のプリント用紙の束を取り上げて尾藤に渡した。
「荻窪の事件と、この半月間に首都圏で起きた儀式モドキの記録だ。編集前だから文章は読み辛いと思うが、目を通しておいてくれ。気付いたことがあれば申し出て欲しい。捜査の実働に関わらせるわけにはいかないが、情報分析のデスクワークならば歓迎する。事件解決に結びつきそうな示唆は責任を持って受け付ける。」
それが尾藤ができる唯一の捜査協力だと木村は言った。
この申し出が木村の好意であり、気遣いであることが分かっているので、尾藤は黙って受け取るしかなかった。
尾藤の職業柄と、そもそもの習性からして、自らの手で捜査を行いたいという欲求は押さえ難いものがある。
だからと言って、現在の公安の警備監視下にあるという状況を脱して活動するなどできることではなかった。
[二九]
杉並署を出てから、そのまま自宅に帰って朝まで眠ろうという気分には到底なれなかったので、結局事務所に戻ってきてしまっていた。
事務所に戻ったからといって、何かできることがあるというわけではないので、
「自分には何もできない! 」
と、いう事実を何度も噛み締めながら地団太踏むという、全く無意味な時間を過ごすしかないわけだが・・・
(木村に渡されたプリントがあったっけ? )
今、尾藤ができる多少有意義と思えることは、木村から預かったプリント用紙の束に目を通すことだけである。
そこで、事務所に帰るなりソファに放り出してしまっていたカバンを取り上げて、中から腹立ち紛れに無理矢理押し込んだために端が折れ曲がり、口が大きく破れてしまった書類封筒を引っ張り出した。
幸い中身は折れたりしていないので読むのに支障はない。
クリップで閉じられた一〇〇枚以上もあるA4プリント用紙は、荻窪の事件以降に首都圏で発生したカルト教団信者が関わっていると思われる事件全ての取り調べ過程を記録した書類だった。
図版などは一切無く、A4の用紙をびっしりと埋め尽くしたテキストは、木村が言っていたように打ちっぱなしの未編集状態であり、整理されていないだけでなく誤字脱字も沢山ありそうで、一見しただけで読み難さが分かる荒々しい書類だった。
紙面のあちらこちらに赤や青のボールペンで乱雑な書き込みがされているところから、この書類はおそらく正式な報告書を作成する上での資料として使われ、廃棄されるところを木村が回収して尾藤に渡したモノなのだろう。
果たして、現在の苛立った精神状態のまま、これだけの量の文章を読みこなすのは難しいと思ったが、アイシュ救出のためのヒントを探すためだからと自分に言い聞かせて、無理矢理プリント用紙の束を開いた。
一二月十四日、土曜の朝七時過ぎのことである。
恵子は土日休みなので、この日の事務所には尾藤しかいない。
週末はアディも「クアーク」が忙しいので、事務所に顔を出すことなど無いだろう。
尾藤は九時少し前まで書類を読み込んでいたが、時刻を確認してから一旦プリントを置き、九時過ぎには通常の調査業務に取り掛かった。
元々、今週末は片付けなければならない仕事が多いので休日返上のつもりだった。
木村に言われるまでもなく、自分本来の業務を放り出して警察と一緒になって走り回れるような状況ではなかったのだ。
だから日中は焦る心を抑えて調査員として目の前の案件を片付けることに専念し、再び書類の読み込み作業に戻れたのは二一時頃である。
今日は、現時刻まで木村からの連絡は無い。
いずれ連絡があるかもしれないが、今まで無かったということはアイシュに関する捜査は何も進展していないということだろう。事件が発覚して未だ一日しか経っていないのだから、ここで焦って木村を急かしたところでどうなるものではないと分かってはいる。
しかし、
(プリントを読み込んでも、手掛かりになりそうな事柄は得られなかったし・・・ )
書類の全てに一通り目を通し終えたが、そこに記されている内容に上井の行動が予測でき、アイシュの行方を捜す上でヒントになるような事柄は見つけられなかった。
荻窪の事件に関しては、当事者だった尾藤が知っていた以上の情報は皆無だったし、以降に連続した儀式モドキに関しても予め推測していた範囲の内容でしかなかった。
(気になると言えば、ここぐらいだな。)
全くアイシュの手掛かりになりそうな事柄ではないのだが、心の片隅に引っ掛かる程度の内容を見つけた。
塔ノ岳の女子大生誘拐殺人未遂事件に於いて、SAT隊員の報告。
「キャンプの制圧後、黒い霧状の怪物を付近の森の中で目撃した。怪物は闇の中に消えてしまった。」
若洲海浜公園における女子小学生殺害事件に於いて、沈没した警備艇乗組員の報告。
「警備艇は、黒い怪物の攻撃によって沈没した。怪物は暫くの間、波間に見え隠れしていたが、消えた。」
若洲海浜公園事件後、荒川河口に沈没した警備艇の状況。
「船体は横転して着底。船体側面は着底時の衝撃により破損。但し、船体に穴などは見られず、直接の沈没原因は不明。操船ミスによる転覆の可能性ありだが、沈没時の警備艇は岸壁より一五メートルほど離れた位置に停止中だった模様。操舵室などの上部構造物は圧潰状態? 」
(山と海で怪獣目撃か? )
これについて、実際にカルト教団による儀式を目前にしたことがある尾藤は思った。
(あの異常な現場にいたなら、たとえ熟練した警察官だったとしても取り乱した挙句に有りもしないモノを見てしまったとしても不思議ではないだろう。)
だが、全く異なる現場に於いて、似たような幻覚を見たというのは不思議な話である。
塔ノ岳の事件が一一月二七日ということなので、警備艇に乗っていた湾岸警察署員が、事件の内部報告書を読んでいる可能性はある。
報告書の内容が印象に残っていたなら、その影響で似たようなイメージの幻覚を見てしまうこともあるだろう。
(いや、それは違う。)
塔ノ岳の記録も、若洲の記録も「怪物」に関する記載には共に赤いボールペンでバツが付けられている。
正式な報告書では不適切として削除された内容である。
塔ノ岳の報告書が神奈川県警から湾岸警察署に渡った時点で、「怪物」の目撃に関する情報は掲載されていないはずだった。
(マスコミの報道でも、こんな話無かった。)
報告書以外の方法で耳にした可能性が無いわけではない。
怪談や都市伝説の類というモノは意外なところから漏れ伝わることがある。
(黒い怪物、黒い霧状の怪物。)
状況は違うが、自分も似たような経験をしたことを思い出した。
酔った帰りに新宿駅のホームで黒い染みのようなモノが多数浮かんでいるのを見た。
頻繁に見ていた悪夢の延長だが、一度だけ黒い影に襲われそうになった夢を見た。
(疲れてたり、緊張してたりしたら幻覚ぐらい誰でも見るしなぁ。)
これは捜査には関係無いとして報告書から削除された内容であり、警察は拘るべきではないと判断した。
その判断は尾藤も適切だと思うが、似たような経験がある以上、どうにも心が残る記述である。
怪物以外に気になった点は、もう一つある。
塔ノ岳の女子大生誘拐殺人未遂事件に於いて、SAT隊員の報告。
「意味不明の呪文、合唱。人の声とは思えず。獣の咆哮。地鳴りが聞こえたような気がする。視界の乱れ。頭痛と嘔吐感。催眠効果ではないか? 付近に残留した大麻などの煙を吸引してしまったのではないか? 」
これも、赤で大きくバツが付けられている。
まったく整理されていない雑な文章なので、事件の知識の無い者には意味不明なテキストに見えるだろう。
だが、尾藤には分かる。
(俺も、荻窪の現場で同じような状況に陥ったからな。)
あの異常な大合唱を聞いているうちに、頭痛と眩暈、吐き気がして立っていられなくなった。現場に持ち込まれていた大麻や幻覚剤の影響ではないかということで、事件後に血液や尿の検査もしたのだが、そのような類の反応は無かった。
(俺の時は、合唱が止んだ途端、直ぐに正常に戻ったんだよな。)
まさか、合唱自体に体調に異変を及ぼす効果があったというわけでもないだろうが?
儀式の雰囲気に飲み込まれて催眠状態に陥ってしまったというならば、合唱が止んだ途端に治るというのは変だと思う。
(これも黒い怪物の幻覚と同様に、事件の異常さのおかげで緊張状態に置かれたからと考えるのが妥当かもしれないが・・・ )
しかし、その日初めて事件に関わったSAT隊員が同じ状態に陥ることなどあるのだろうか?
彼らは修羅場慣れしたプロである。
(不可解なことが続く・・・ )
[三〇]
そこは東京湾を一望する広々とした公園の一区画だった。
(若洲海浜公園。)
見たことも無い公園なのに、尾藤にはどういうわけか名称が浮かんでいた。
冬の強い海風が立木を揺らしている。
見渡せる海上は、内海であるにも関わらず台風でも訪れているかのように波高の高い荒波が畝っていた。空を見上げると、激しく渦巻く分厚い雲が幾重にも重なり合って、あらゆる光を遮断しているため、今が昼なのか夜なのか区別がつかないほど黒々としている。
奇妙なことに、これほどの荒れた屋外にいながら、尾藤は風の抵抗を感じていない。
髪も衣服も乱れていない。
岸壁に打ち付ける波飛沫が前後を過っても、どうゆうわけか身体が濡れることは無い。
まるで意識はそこにあるのだが、肉体が存在していないかのようであった。
(それにしても、ここは暗過ぎないか? )
日差しや月明かりが遮断されていたとしても、ここは東京湾なのだから、湾を隙間なく取り囲む様々な設備や構造物、夜間の工業地帯から発せられる人口光などが煌めいているはずだった。
しかし、そうした灯りは一切見えない。
暗闇の中に薄っすらと見える黒い影の形を見て、遠くに見えるのが建物であり橋であることが判別できるだけで、本来、それらの形を夜間に浮かび上がらせるはずの照明は全て消えており、公園内には外灯も点いていない。
屋外にいるはずなのに、まるで洞窟の中にでもいるようであった。
そう言えば、先ほどから公園の中程にある芝生の上に唯一の小さな灯りが見える。
遠目で見る限り、焚火である。
その焚火は尾藤と同様に風の影響を受けず、静かに穏やかに燃えている。
尾藤は、近付いてみることにした。
(また、あいつだ。)
焚火の前に、黒いローブに身を包み、深く被ったフードで顔を隠した男が座っている。
(ということは、これは夢だな。)
似たようなシチュエーションの夢を何度も見ているので、尾藤には直ぐに分かった。
見る度にロケーションが変わるだけで、黒いローブの男はいつも焚火の前にいる。
気味が悪くはあるが、夢だと理解して見ている上では、以前に悲鳴を上げてしまった時のような恐怖感を感じることはなくなったようだ。
「よく来たね。」
男は、自分の背後に立った尾藤を振り返りもせず、右手で自分の向かい側を指して、そこに座るように誘った。
「立ったままで良い。」
尾藤は男の誘いを拒否した。
「ほほぉ、いつもより元気じゃないか。」
そう言って、男はフフッと息を吐くように笑った。
「だが、まだまだだな。ここに近付いてくる足取りが重く緊張している。呼吸も微妙に乱れているしな。」
夢だと分かっていても、この男の気味の悪さは拭えないので、足取り軽く近付くことなどできるはずがない。生理的な嫌悪感を掻き立てるイキモノの傍にいたら呼吸も荒くなって当然だろう。
しかし、男に図星を指されたのでは面白くない。
「毎度毎度、煩わしいから消えてくれないかな? 」
しかし、男は尾藤の腹立ちなど意にも解せず、
「ほほっ、話をしたくはないのか? 」
からかうように言った。
「話って何だよ? 」
「色々さ。今のお前は知りたいことが沢山あるだろう。」
現実に知りたいことは山ほどある。
しかし、夢の中に出て来る男などに聞きたいことは何もない。
「そう言いなさんな。お前が真実を見つけるための手助けぐらいはしてやれるかもしれないぞ。」
「ふん、馬鹿馬鹿しい。」
尾藤は、ソッポを向いて相手にしたくないという態度を示した。
「お前さんは、何故、俺のことを何度も夢に見ると思う? 」
「お前は俺が現実で色々気に掛ってる問題が、夢の中で分かりやすい形になっただけの存在だろう! いずれ、現実の問題が片付いたら消えちまうんだよ! 」
カルト教団の儀式を見せつけられて以来、あの強烈過ぎる邪悪な光景が記憶に焼き付いて離れない。一〇〇〇人の参加者の狂信振りなど思い出す度に背筋が凍りそうになる。今もなお続くであろう狂信者たちの強い執念を感じると心が震える。
だから、自分の悪夢は、そうした現実の恐怖が元になっており、目の前にいる男はカルト教団について抱いているイメージや知識の寄せ集まった姿なのだと尾藤は考えている。
「ハハハッ、分かってるじゃないか。但し、俺はお前が望むから、お前の前に現れたんだぞ。そこを忘れちゃいかん。」
男は小馬鹿にしたように笑ったので、尾藤はムッとした。
「望んじゃいないぞ! できれば会いたくないさ。」
悪夢など誰が見たいと望むものか。
男はヤレヤレといった感じに首を振った。
「それは違うな。俺は望まれなければ現れないはずだからな。」
「はぁ? 」
言い返そうとする尾藤に、男は良いから黙って聞けと言い、話を続けた。
「前にも言ったが、俺は大勢が俺に会いたいと望んだから現れた。大勢が世の中を変えて欲しいと願ったから、俺は世の中を変えるモノとして現れた。何十年もの間、曖昧で現実に存在しきれていなかった俺を、具体的な存在に変えようとする人間の強い思いに応えたのさ。」
「大勢って、上井たちカルトの一団のことだろう。俺は違うぞ! 」
「ああ、上井と奴が仕切っている一団のおかげで、俺が具体的になる切っ掛けができたのは確かだし、奴らの願いの強さは並々ならぬものがあったから否定はしない。しかし、奴らだけの力ではないな。俺を求めている者は数えきれないほどいるのだから、そうした者たちの全ての気持ちに応えて俺はここにいる。もちろん、お前も俺を求めている者の一人さ。」
この男は、全ての人間の深層心理にはカルト信者たちのような怨恨や反社会的な欲求があるとでもいう犯罪心理学を始めるつもりなのだろうか?
「説教を始めるつもりなら勘弁して欲しいな。」
そんな話は、殺人や傷害事件の類が起こる度にニュース番組の解説者が決まって口にする犯人の動機分析で聞き飽きている。
男はそんな大そうな話をするつもりはないから安心しろと言った。
「お前たちも言っていたじゃないか。学校や仕事に行きたくない朝には、突然大地震が起これば良いとか、宇宙人が攻めてくれば良いとか思うとね。俺が言っているのは、そんな話だよ。この程度の願望なら世の中に満ち満ちているだろう? おいおい、そんな願望は軽々しくて些細なモノだと思っているのか? そうではないぞ。学校や会社が嫌だというだけで、人は心の中で何度も街を滅ぼそうとし、妄想の中で国や世界を滅ぼしてしまっている。人も大勢殺してしまっている。これは凄いことだと思わないか? 」
馬鹿馬鹿しいことを言うと思った。
それらは、絶対に起こるはずがないと思っているからできる妄想である。
学校や会社に行きたくないから世の中を滅ぼしてしまいたいなどと本気で思う者がいたとしたら、それは精神的に壊れてしまっている者だけだ。
「ほほぉ、起こるはずがないと分かっているから願ったというのか? そんな風に割り切って願ったというのか? それを願った時に、そこまで考えていたのか? お前の身勝手な願いが実現しないと信じていたというのか? 違うだろう? 」
男は、それが正論であるかのように強引に畳みかけてくるので、尾藤は直ぐに反論が思いつかずに戸惑ってしまった。
「軽く念を押されただけでグラついたか? 」
「そうじゃない! 人の妄想なんて心の中でする遊びのようなモノだぞ。そんな罪のない遊びを本気で受け取ろうとするなんて、お前は馬鹿じゃないのか? 」
「罪のない遊びねぇ。」
男は意地悪そうに笑った。
「仮に遊びだったとしても、本気だったのではないかね? それらの願いが心に生じた時点では、誰もが自らの身勝手な願望よりも世の中は価値が無いモノと本気で考え、自らの都合で滅んでも構わないものと考えているのではないか? 本気で願ったわけではなかったなどと言うのは、願いが実現しなかったということを確認した後で、自らの罪を誤魔化そうととしているだけだと思うぞ。少なくとも願いが叶わなかった事に対しては失望しているはずだよ。」
「そんな馬鹿な・・・ 」
尾藤は言い返そうとしたが言葉に詰まった。
男の話を肯定はするつもりはないが、過去に何度も身勝手な願いを抱いた際、自分の心の中にチラとでも本気が無かったと言えるかどうか?
「本気だったのだよ。ホンの一瞬だとしても強く願ったのだよ。」
男は、そう断言する。
「例えば、お前が正月に神社に詣でて、手を合わせて願掛けするよりも本気だったと思わないかね? そもそも神様に家内安全や交通安全を願うなどという行為は惰性でやっている者が大半だからね。それに比べたら遥かに強く願っていると思うよ。」
男は嬉しそうだった。
尾藤が反論してこないので、言い負かしたと思ったのだろう。
「まあ、気にしなさんな。悪いのはお前さんだけじゃないから、そんなに責任を感じることはない。近頃は、そんな身勝手で無責任なことを願う奴らが多くなってねぇ。人類史上こんなことは嘗て無かったんじゃないかな。まったく悪い病気が流行ったもんだ。」
尾藤は男に見下されたような気がして腹が立ってきた。
これが夢だとしても、このまま言い負かされてしまうのは我慢ならない。
「お前は、俺の一時的な他愛も無い妄想が、上井たちの怨念と一緒だというのか? 」
「一緒だろ? 」
男が当然という言い方をした。
「しかし、俺は世の中を憎んじゃいない。上井やカルト教団の連中みたいに社会に挫折させられちゃいないしな。」
だから、上井たちのような強い復讐の念に憑りつかれたり、世の中に災いを振り撒くための手段を練ったり、人の命を害することに躊躇しないほどに人間性を失った奴らとは違うのだと言った。
「仮に気の迷いがあって世界を滅ぼしたいなどと無責任な願いをしたとしても、俺は自分の身勝手で人が死ぬことなんて考えちゃいない。身内や友人知人が死んでも良いなんて思わない。誰も死んで欲しくないと思っているのだから、そんな願いは端から矛盾してるんだよ。全然本気じゃないってことだろ。」
「気が迷った瞬間には、誰も身近な者の心配だってしちゃおらん。願いの動機は自らの保身なわけだからさ、自分以外の者の都合なんて考えちゃいられんよ。そういった考え方の延長線上に上井なんて奴やカルト教団の連中がいるわけだ。そうだ、一つ教えておいてやろう。確かに、お前と奴らに違いはある。お前は自分の欲望に素直じゃなくて、奴らは素直だってことだ。ついでに言うなら、お前は怠け者で奴らは努力家だってことさ。」
「自分の身勝手な願いを成就させるために、仲間を集めて罪の無い女子を浚って惨殺する計画を立てるのが努力だってのか? 」
「ああ、あの馬鹿げた儀式についてか? あれは俺もどうかと思う。教団の連中には申し訳ないが、儀式自体には何の意味も無い。奴らがあんな段取りを考えてくれたおかげで俺は足止めされているようなもんだからな。望まれれば、いつでも出て行ってやるのに、奴らのやり方に付き合ってやらなきゃならん。まったく面倒な話さ。だが、人の願いを強く纏めるには、ああいう儀式は都合が良いのかもしれない。何事かを達成するにはマニュアルってモノがあれば便利だし、手順が何も示されていないよりは成功に至るまで過程を分かっている方がテンションを維持し続けられるってもんさ。生贄に月齢だの処女だのという尤もらしい理屈を付けたのも賢いやり方だ。素人がでっち上げた儀式に重みを付加することができる。皆で殺人を行うというのも罪の意識を共有することで団結心を高めるために効果的だ。だから、本当は生贄なんて女でも男でも誰でも良いから、人を殺して皆でその達成感を味わえれば十分なのさ。まあ、その程度には評価してやらなきゃぁな。」
おそらく自分を呼び出すために催された儀式に対して、この男は随分と客観的で冷めた言い方をする。
「その言い方、儀式を否定しているのか、肯定しているのか分からないな。」
「否定はしないがね、もっと簡単でも良かったのさ。俺は、既に存在してしまっているのだからな。お前たちが奴らの儀式を阻止した後も、あちらこちらで儀式が行われただろう? あれは上井が考えたマニュアルからは外れたモノだったはずで、上井に言わせれば俺を呼び出すことはできないってことになる。しかし、お前も警察の記録で見ただろう? 俺は儀式を行った奴らが望んだ姿を見せてやったし、僅かながら力も見せてやった。」
塔ノ岳と若洲の事件で黒い怪物が目撃されたという公式には削除された記録のことを言っているらしい。
「あの儀式を行った奴らは、荻窪の儀式を阻止されたことで焦ったんだ。それまでに自分たちが行ってきた努力が全て水泡に帰してしまうと思ったのさ。例えるなら、最後の一段で崩してしまったドミノ積みの心境。いや、レシピ通りに進めてきた料理で、最後に入れるべき大事な材料を床に落としてしまった心境かな。それとも、優勢だった勝負でトン死する棋士の心境かもね。そういうミスを犯した時、人は咄嗟にミスを隠そうとしたり、辻褄を合わせるためジタバタしたりするものだ。奴らは、そんな感じで上井のマニュアルと違っても良いから無理矢理に儀式を行おうとしたんだ。塔ノ岳の連中なんて、荻窪の失敗を取り繕うためにマニュアルでは一人だけだった生贄を二人も用意したんだ。それでミスを帳消しにしてもらおうとしたんだから滑稽だよ。でもね、彼らは真剣だった。下手すりゃ、上井が行ってきた儀式の参加者よりも危機感が乗っかってた分、真剣さは上だったんじゃないかな。だから、月齢だの処女だのと拘っていなかったにも関わらず、生贄が殺されなかったにも関わらず、儀式は成功し掛けるとこまで行ったのさ。」
男の話は続いていたが、ふと尾藤は真面目に聞いている自分が可笑しくなった。
「いやぁ、参ったな。」
「ん? どうした? 」
男が首を傾げている。
「なんだかんだ言ってるけど、これは俺の夢なわけで、お前は俺の心の中にあるイメージだよなぁ。つまり、お前が語ってるセリフも実は俺のセリフなんだろう。俺が自問自答してるんだよな。いやはや俺って随分面白いこと考えてるなって可笑しくなったのさ。」
ついつい、男の話が興味深かったので聞き入ってしまっていたが、こんな不愉快な夢の中で語られる話を真面目に捉えるなど馬鹿げたことだと思ったのだ。
そう考えることによって、目の前の男の存在は全否定されることにも気付いた。
「そうだな。その考えは間違ってはいないよ。俺はお前の中にもいるわけだし、お前が自覚していない内心を語ってやっているという一面もある。」
男は意外に素直に認めた。
その素直さが妙に夢っぽくなくて違和感を覚えたが、
「そうだろう! 」
尾藤は勢いよく言ってやった。
「お前なんて、俺の心構え次第で二度と会うことも無いんだからな! 」
ここに来て一番の強気な物言いで、男が周囲に漂わせ続ける不気味さと不安感を振り払おうとした。
男にリードされていた会話の主導権も取り戻そうとした。
ところが、
「ぐっ・・・! 」
尾藤の喉を目に見えない力が鷲掴みにした。
振り解きたいのだが身体が動かない。
腕も足も同じ姿勢のまま微動だにしない。
(息ができない! )
夢の中とは思えないほどの苦しさである。
「俺はお前の夢の中にいるが、お前の自由にできる存在だと考えるのは間違いだ。言っただろう。俺は既に具体的な存在になりつつあるのだとな。」
気絶する寸前で目に見えない力は尾藤の喉を離れた。
身体も動くようになった。
思わず咳き込みながら二、三歩後退った尾藤だったが、ここで尻込みしてはならないと気力を振り絞ろうとした。
しかし、情けない話だが突然の暴力により先ほど見せたばかりの強気は失われてしまっており、尾藤は恐怖に憑りつかれてしまっていた。
膝が震えているし、手に力が入らず、見っともなく涙ぐんでいた。
(これは夢! 俺の夢! )
何度も自分に言い聞かせるのだが効果無く、背を向けたまま一度も振り返らずに座ったままで動こうとしない男に心底怯えてしまっていた。
「ほれっ! 」
男が顎を上げて、尾藤に何かを示した。
その途端、周囲の風景が変わった。
場所は同じ公園の同じ場所。
しかし、大勢の人々がいる。
数百人の群衆である。
時刻は明らかに深夜だなのが、先ほどとは一変して明るい。
群衆の中心には、暗闇を切り裂くように巨大な篝火が燃えていたのだ。
人の背丈を遥かに超えるほどに燃え上がった火柱は、目を開けていられないほどの猛烈な光と、灼熱を広範囲に撒き散らしている。
篝火の真ん前、群衆のど真ん中で、尾藤は剥き出しの顔の皮膚がチリチリと焼かれる痛みに耐えながら立っていた。
そして、もはや一生忘れることの無いであろう、あの凄まじい獣の大合唱が公園中に轟き渡っている。
尾藤は、いつの間にか黒いローブを着て、フードで顔を隠している自分に気付いた。
(これは? )
両手に、それぞれ違う感触の異物を握り締めている。
(右手に硬いモノ、これは、ナイフか? )
そして、左手に握るモノは柔らかく生暖かい・・・
「うぐああああっ! 」
左手に握っていたのは血の滴り落ちる肉の塊りだった。
悲鳴を上げながら振り返った背後には、木の柱に縛り付けられた少女がいた。
少女は辛うじて生きていたが、もはや死は免れえない状態にあった。乳房を失い股間の肉を大きく抉り取られ、その傷口から大量に出血をしている。
少女が失った身体の肉の一部は、尾藤の手の中にある。
「げええええっ! 」
尾藤は両手を振って異物を放り出し、その場に突っ伏して只管吐いた。
ここは夢の中のはずだから、何を吐きだしているのか分からない。まるで自分の内臓と体液を全て吐き出している気分だった。
とにかく苦しく、悲しかったのだ。
何故、自分が生贄の儀式の場で少女と対面しているのか?
しかも、両手を血に染めている。
「これはな、俺に生贄と交われという意味らしいぞ。」
耳元で男の声が聞こえた。
しかし、その姿は見えない。
「だから、乳房と子宮と生殖器を切り取って捧げてくれるのよ。いや、もしかしたら、これらを器にして、この世に生まれてきてくれと言っているのかもな。」
男の声は楽し気に儀式の解釈をして尾藤に聞かせようとする。
「や、止めてくれ! 俺はこんな儀式知らない! 俺は殺しちゃいない! 」
尾藤は吐きながら、喘ぎながら言った。
「そうかな? お前が殺ったのかもしれないぞ。」
男は半笑いだった。
「ぢっ、違う! 」
「殺ってはいなくとも、殺りたかったのではないか? 」
「違う! 」
尾藤の無駄な抵抗振りが面白いらしく、男はついに高笑いを始めた。
「そんなに頑なになりなさんな。欲望というモノは身を任せたほうが楽しく過ごせると思うぞ。」
再び、周囲の風景が変わった。
そこは今までいた公園ではない。
何処か深い森の奥にある広場のようである。
「ここは丹沢山中? 」
尾藤は直感で、そう判断した。
そこでも、巨大な篝火が燃え、獣の合唱が響き渡っている。
広場の中央には二本の木柱が立ち、既に惨殺され血塗れになった女性の死体が括り付けられているが、その周りでは数十人の狂気に憑りつかれた男女が踊り狂っている。
地面に突っ伏していた尾藤が顔を上げてヨロヨロとその場に立ち上がると、踊り狂っていた女のうちの一人が何を思ったのか奇声を発しながら飛び掛かってきた。
女は驚く尾藤の首に両腕を絡め、身体を預けてきた。
女に害意が無いのは直ぐに分かったが、彼女は衣服も下着さえも身に着けておらず、全裸のまま尾藤に激しく絡みついてきた。
「なっ、何を! 」
立ち上がりかけた姿勢を崩され、今度は仰向けに地面に押し倒されてしまった尾藤の上に女は馬乗りになって大声で喚きながら着ているモノを剥ぎ取ろうとする。
「欲望に身を任せたほうが楽しいぞ。」
またもや、男の声がした。
「冗談じゃない! 」
尾藤は女の両手を掴み、その行為を止めさせようとした。
その時、女と視線が合った。
「アイシュ・・・ 」
見覚えのある大きな瞳、整った美しい顔立ち。そして美しい肢体。
「これは、どういう意味だっ! 」
尾藤は叫んだ。
すると、風景は変わり、篝火は消え、辺りに静けさが戻った。
そこは元通りの公園である。
「面白かっただろう? 」
相変わらず背を向けて焚火に向かったままの男は、尾藤をからかうように言った。
「お前はいったい? 」
「既に分かっているにもかかわらず、それを問うのか? 」
「あ、ああ、ハッキリしときたい。」
尾藤は錯乱し掛けた心を必死に押さえつけながら、震える声で男に問い掛けた。
そこが自分の夢であるという認識は無くしていないが、目の前にいる男が決して自分の自由になるモノではなく、自分が優位な立場であるとは思わなくなっていた。
夢の中であっても、この男は自分を意のままに殺すことぐらいはできるかもしれない。
「あるがままの存在。常に身近にいるべき存在。人の世を侵すための存在。求められ快楽を与える存在。そして、人の知恵を曇らせ愚かにする存在。」
以前も、夢の中で同じ答えを聞いた。
「悪魔とか? 」
「そうでもない。だが、そう受け取る者がいてもかまわない。神様だと言われても否定はしない。」
男が返してくるのは、まるで謎かけのような答えである。
「分かるようで・・・やはり、分からん。」
途端に男は嬉しそうな声で高らかに笑い、その場に立ち上がった。
尾藤が頭を抱えるのが、余程楽しいらしい。
「分かるはずなんだがな。」
さらに尾藤を混乱させるべく、男の口は謎めいたセリフを語り続ける。
「俺は悪魔でもあるし、神にもなれる。但し、黙示録などに出て来るような大災害や大戦争を引き起こして一息に世の中を滅ぼそうとするようなモノではない。人に審判をもたらそうなどという大そうな存在でもない。もっと地道に、毎日少しづつ、お前たちが気付かないうちに、俺はこの世の中にジワジワと沁みとおっていくのさ。そして、お前たちの願いどおりに、この世に災いを齎してやる。もう、仕事をしたくないとか、学校に行きたくないとか、家庭が煩わしいとか、そんな愚にもつかないようなことを考えずに済むようにしてやる。」
男は嬉しそうに笑いながら、尾藤をゆっくりと振り返った。
そして両手でフードを持ち上げる。
「これまで黒い怪物などと実に稚拙な姿で現れたのは恥ずかしい限りだが、あれは俺を呼び出そうとした奴らや、お前の貧困な想像力のせいだから勘弁願いたいな。」
フードの下から現れたのは、尾藤自身の顔であった。
「これも、謎かけさ。」
驚きのあまり言葉を失い、硬直したまま立ち尽くした尾藤に向かって、男は最後の謎を残して去った。
「明日、お前が目覚めた時、おそらく世の中は今までと変わらず存在しているだろう。たぶん、来週も存在しているに違いない。だが、一月後はどうだろう? 一年後は存在しているのかな? 五年後、一〇年後はどう思う? 」
[三一]
一二月二三日、月曜日。
未明の尾藤総合調査事務所。
週末返上の大残業の甲斐もあり、尾藤は抱えていた緊急の案件を全て片付け終わり、せっかくの国民の祝日には仕事を持ち込まずに済むことになった。
今日はカルト教団の儀式によってアイシュの命が奪われるかもしれない日。誰が何と言っても事務所で大人しく構えているわけにはいかない日だった。
(今日一日、一民間人として勝手に動かせてもらう。)
尾藤は、そう決心していた。
そのためにも、一切の仕事を片付けて自由の身を確保しておいたのだ。
そんな尾藤の意図を察してのことに違いない。真夜中だというのに、わざわざ差し入れを持って木村が事務所を訪れていた。
(やはり、俺を止める気なんだろうな? )
ところが、意外にも木村は尾藤の行動を制するような話はしなかった。
敢えて、その方向に話題を持っていくのを避けているように感じられた。
(黙認するつもりなのか? )
尾藤がアイシュの捜査に関わろうとしているのならば木村は立場上反対しなければならないが、知らなければ止めようが無い。そんな雰囲気を漂わせていた。
実際、この時の木村は尾藤のことを「止めたって止まるもんじゃない」と、半ば諦めていたらしい。
この一〇日間あまり、大人しく自分の仕事に精を出していたこと自体が奇跡だと思っており、もはや尾藤を止めるには身柄を拘束するしかないと思っていたが、木村はそこまでする気になれなかった。
親友の気持ちは痛いほど良く分かっている。
自分が何も手出しできないままにアイシュの命が失われたら、途轍もない後悔に苛まれるだろうから、せめて最後の足掻きぐらいはさせてやりたいと思っていた。
尾藤の調査員としての能力に一片の期待もあった。
これまでの警察や公安による捜査状況が芳しくなかったこともあり、尾藤が全く違う切り口からヒントや突破口を見付けるのではないかと淡い期待を抱かないでもなかった。
木村が事務所を訪れた理由には、そういった面もあったようである。
そんな木村にとって、この夜に尾藤が社長室兼応接室のテーブルを挟んで長々と話した内容は期待外れだったかもしれない。
尾藤の話は、捜査の打開には何の役にも立ちそうにない夢の話だった。
黒いローブ姿の男が登場する夢の話である。
そのすべてを木村に語った上で、尾藤は一つの仮説を口にした。
「これは、お前に馬鹿にされるのを承知で言うけどな、もしかしたらカルト信者たちの社会に対する強い怨念が、この世に災いを撒き散らす何かを本当に生み出そうとしているのかもしれないと俺は思ってる。奴らの儀式は成功しつつあるのかもしれないってな。」
尾藤は、社長室兼応接室の中で唯一の暖房器具であるポータブルファンヒーターに手を翳しながら木村の反応を窺った。
予め予測できたことだが、木村は理解できないと言った。
「お前は疲れてんだよ。カルト教団の事件に関わり過ぎて、積み重なった過度のストレスのおかげで、そんな非現実的なことを言い出してんじゃないか? 」
正しい常識を弁え、理性を守って生きる大人であり社会人ならば、これは当然の反応であろう。
カルト教団絡みの事件に関わる以前ならば尾藤もこんな話はしなかった。
自分でも随分と突飛なこと言っていると思うし、誰にでも気軽に聞かせて良い仮説だなどとは、これっぽっちも思っていない。こんな仮説を木村以外の誰かに話したなら、正気を疑われて話半分で病院送りにされてしまう。
気心知れた木村が相手であり、馬鹿にしながらでも尾藤の話には最後まで付き合ってくれる奴だと知っているからこそ口にしているのだ。
「お前がオカルト嫌いだってことは承知してるけどな、それでも誰かに話さずにはいられないんだわ。頼むから俺の与太話に我慢して暫く付き合ってくれよ。」
尾藤は縋るような目つきをした。
木村は返事をしなかったが、一つ大きな溜息を吐いた。
そして、テーブルの上に置きっぱなしになっていた差し入れの入ったコンビニ袋の中から肉まんの包みを二つ取り出して、そのうちの一つを尾藤に放ってよこした。
「まだ温かいうちに食った方が良いな。」
近所のコンビニで買ってきたばかりという肉まんは未だ暖かく、休日出勤の暖房費をケチってエアコンをオフにしていたおかげで、すっかり冷え切ってしまっている尾藤の指先にジワリと沁みた。
「すまんな。」
尾藤は礼を言った。
この夜の尾藤は精神的に病んでいたのかもしれない。
度重なる悪夢や怪夢に悩まされ、夢と現実の区別が曖昧になりかけているのではないかとの危機感を持ち始めていたのだが、遂に昨夜は夢の中の男に謎を掛けられ、現実における示唆まで受けてしまったのだから、ダメージは決して小さくない。
しかも、黒ローブの男の示唆は、夢だからと言って蔑ろにできるものではなくなってしまっていた。
「自己暗示が見せた夢かもしれないだろ? 」
木村が肉まんを頬張りながら言う。
「ま、その可能性は目覚めて直ぐに頭を過っていたんだけどねぇ・・・ところが違ったんだよなぁ。」
尾藤は夢の記憶が薄れる前に、急いでインターネットの3Dストリートビューを使って「若洲海浜公園」と「塔ノ岳北東斜面」をチェックした。
尾藤は、そのどちらも訪れたことは無い。
だから、そこがどのような風景なのか知っているはずがないのだ。
「それなのに、夢の中で見たのと同じ風景が出てきたんだよな。」
特に黒ローブと最初に出会った若洲海浜公園など、遊具や外灯の配置から遠くに見える東京湾岸の風景まで全く同じだった。
「そこまで見ちゃったら、もうひっくり返せんでしょう。」
現実主義者だったはずの尾藤の心は既に折れてしまっていた。
「ふーむ、お前に取っちゃ一大事なんだろうが、どうにも俺には信じられない話だな。まあ良い。で、お前は奴らの儀式で何が生まれたと思ってんだ? 」
言いながら、木村は一つ目の肉まんを食べ終えて、直ぐにコンビニ袋の中から二つ目を取り出した。
「夜中だってのに、そんなに食うと太るぞ、オッサン。」
などと尾藤に注意されても、
「今の俺には夜昼の区別なんか無くなっちまってんだから良いんだよ。」
と、言って木村は構わずに齧りついていた。
「まったく、大男は燃費が悪いよなぁ。」
尾藤は苦笑し、自分は一つ目の肉まんを千切りながらゆっくりと口に運びつつ、木村の問いに対する持論を話し始めた。
「例えば誰かがさ、『人類は悪だから滅ぼすために皆で努力しよう』ってなことを大勢の人に熱心に説いたとするよ。」
「それは教団の指導者が信者に説くみたいな感じか? 」
尾藤は、そんな感じだねと言って頷いた。
「でも、こんな極論に共感するのは一部のアナキストやテロリストだけ。まあ、その一部ってのが二〇万人のカルト信者なわけだけど、大多数は全面否定すると思う。いや、たぶん一番多いのは興味ないからどうでも良いやって感じの人かもね。だから、共感した二〇万人は積極的に頑張るだろうけど、それだけじゃ到底人類を滅ぼせるわけなんてないんだわ。」
「そりゃそうだ。たった二〇万人が頑張ったところで人類滅亡なんて絶対に無理。精々迷惑なテロリストか犯罪者集団止まりだろう。」
「ところで、極論過ぎて共感できなかった大多数の人たちなんだけどさ、頭の中に『人類を滅ぼすのは良いことだ』って説かれたことの記憶は残ってるわけよ。」
「そりゃあ、極論や暴論ってのはインパクトがあるからなぁ。」
木村は腕を組んで何度も頷いた。
公安警察の総務課などに所属していると極端な政治思想団体やカルトを相手にすることが多いだろうから、極論や暴論には常に苦労させられているのだろう。
「さて、その中の一人が、ある日、自分の家の中にあったゴミを処分したいと思うんだよ。そのゴミは産業廃棄物や毒性の強いゴミ。正しい処分の方法を取らなければ人類の生活環境を破壊してしまうような厄介なゴミってのが分かりやすくて良いな。」
「空き缶や紙屑じゃダメなのか? 」
空き缶や紙屑でも良かったのかもしれないが、インパクトに欠けるので却下。
「人間の生活環境を守りたいと考えて正しい処分の方法を取れば多額の費用が掛かる。しかし、人知れず山の中に廃棄すれば人類の生活環境を脅かすかもしれないが費用は掛からない。そこで、そいつは迷う。」
「究極の選択か? 」
尾藤は首を振った。
「何てことは無い軽い選択だよ。ホンの数秒迷うぐらいのことだ。」
「そんなもんか? 」
木村が意外な顔をする。
「そんなもんでしょう。」
警察というモラルの総本山みたいなところで暮らしていると、一般人の考え方が分からなくなるのかもしれないが、個人のモラルなど弱いものだと尾藤は言う。
簡単に魔が差したり、差さなかったりするものだ。
「本当は人の生き死にに繋がるほどの重大事なんだけど、ゴミを処分するってのは一過性の行為だからね。それに、良い行為にしろ悪い行為にしろ一個人分のゴミが環境に与える影響なんて実際大したことないから、そんなに悩むほどの問題じゃない。そう考えて大抵の人は簡単に結論を出しちゃうのさ。」
そんなじゃ、山や川が荒れるわけだよと木村が嘆き始めたが、論点がズレてしまいそうな気がしたので尾藤は先を急いだ。
「こいつの心中で、正しい処分をするべきだって気持ちと金は出したくないし面倒臭いって気持ちが僅か数秒間にせめぎ合うんだが、そのタイミングで突然心の声が囁く。『人類は悪だから滅ぼすために皆で努力しよう』ってね。以前、そんな極論を説かれたことがあるって思い出すわけさ。その場では共感しなかったけど、説かれた内容は記憶の片隅にこびり付いていたんだ。で、その記憶は一瞬のうちに男の選択に影響を与える。『悪い人間が滅びるのなら良いことなんじゃないか? どうせ滅びるなら自分がゴミを捨てたって関係無くない? 』とか。本人は気付かないほど瞬間的で無意識下の影響かもしれないけど、そのおかげで、ゴミを山の中に捨てることの罪悪感が薄れちゃう。自分がゴミを捨てたことにより、人類を脅かすことになっても構わないんじゃないかって思っちゃうのさ。」
「それって『予言の自己成就』に似た話だな? 」
「ああ、近いかもしれないね。」
予言の自己成就とは、予言をした者や受け取った者が、意識的又は無意識的に予言に沿った行動を取ることにより成就に導かれるという現象のことである。
「あれって、過去に銀行の取り付け騒ぎを引き起こしたり、トイレットペーパーが品切れになったり、凄い力を発揮したよな。」
「そういうことだよね。この場合は『人間を滅ぼすのは良いことだ』って論を聞いたことで大なり小なり影響を受けた人が、自分の反社会的行為を何となく肯定してしまうことの積み重ねで、いつの間にか『人間を滅ぼす』ことに手を貸してしまって、その結果人類は滅亡の危機に晒されるかもしれないみたいな感じ。」
「積極的に人類を滅ぼそうとする二〇万人と、いつの間にか人類を滅ぼす手伝いをしてしまっている大多数の組み合わせができるか。理屈としちゃ分かるが、お前が最初に言っていたオカルトっぽい話じゃなくなったな。儀式で生まれたモノってのは、そんな感じの話なのか? 」
木村は怪訝そうな顔をして首を傾げた。
「これは構図、考え方だよ。」
これを踏まえてオカルトっぽい話をするんだと言った。
「カルト教団の目的は社会に復讐すること。そのために儀式を行い悪魔的なモノを呼び出そうとする二〇万人がいる。彼らの怨念は、一年を掛けて一一人の少女の命を奪うほどに凄まじい。まさに狂信と言える。」
だが、それだけじゃ悪魔的なモノは生まれないと尾藤は言った。
二〇万人という人数は驚きだが、人類社会全体に比較してみれば超微々たる数でしかない。この程度の人数では、到底人類に脅威を与えるような影響力を生み出すのは不可能であるとした。
「二〇万人以外の、不特定多数の共感が必要なのさ。」
夢の中に出てきた黒ローブの男は、人類など滅びても良いと軽く無責任に願っている奴は沢山いると言っていた。
「そいつらはカルト信者のような狂信者ではないから具体的に儀式を行ったりはしないけれど、社会には様々な不満を持っていて、反社会的な妄想を頻繁に繰り返している。学校や会社に行きたくないから大地震が起きて欲しいとか、街が壊滅すれば良いとか、世の中の大多数の人が、そんな妄想したことあるんじゃないかな? 酔っ払って物騒な愚痴を溢したことあるんじゃないかな? 」
尾藤は、その大多数の中には自分も当然含まれているし、おそらく木村も含まれているはずだと言った。
「カルト信者たちの怨念は凄まじいし、悪魔的なモノを呼び出したいという具体的な願望や、それを叶えようとする厄介な行動力がある。だから、我々は奴らを特殊な集団と見ているわけで、自分たちとは異質な存在だと認識している。でもね、あの黒ローブの男に言われて分かったのさ。おそらく我々が妄想する軽くて無責任な願望も奴らの願望と同質なんだよ。違うのは、その強さだ。つまり、奴らの願望を突き動かすのは怨念で、我々の場合は不平や不満、さらには倦怠感程度ってこと。その強さゆえにカルト信者は自分たちの願望に素直であり、我々は素直にならない。そういうことなんだよ。」
向いている方向は同じなのだと言う。
「どういう仕組みかは分からないけれど、教団がやらかした儀式は二〇万人の具体的な目的を達成するだけじゃなくて、この世の中に漂っている不特定多数の弱い願望を素材として掻き集めるレンズのような役割を果たしたんじゃないだろうか? 教団の奴らが、それを意図していたかどうかは別として、目的が漠然としていた多くの反社会的妄想に形を与える役割を果たしていたんじゃないかな? そして、大勢の願望や妄想が一つに合わさったことにより儀式は力を持ち、物理的な現象を引き起こそうとしてるんじゃないだろうか? 本当に悪魔的な力を持ったモノを呼び出しつつあるんじゃないだろうか? 」
木村は溜息を吐きながらも、信じる信じないは別として尾藤の言いたいことぐらいは分かったと言った。
「悪魔的なモノを呼び出して世の中に災いを振り撒こうと言い出した奴らがいて、それに共感したのが二〇万人。共感はしていないものの同じ方向を向いている奴が他にも大勢いて、これが教団の目的達成の手助けをしてしまっているってことだよな? 」
だが、それでは前置きした構図に当てはまらないではないかと指摘した。
「世の中の大多数は悪魔的なモノを呼び出そうなんて考えてはいないだろうし、そもそも地下に潜っている教団の存在は知らないわけだし、儀式に接してもいないだろう? 」
「いや、そうでもない。」
と、尾藤は言う。
「確かに教団は地下に潜っていたけれど、その存在は都市伝説として漏れ伝わっていたんだ。アディがボンヤリとだけど耳にしていたぐらいだからね。公安だって今回の事件前に既に存在ぐらいは掴んでいたんだろう? 」
「そりゃまあ、どんなに管理を厳しくしたって、二〇万人もいる信者全員の口を塞ぐことはできないからな。」
「教団の情報は口伝えやインターネットを使って様々な形で広がっていたと思う。殺人儀式を行っている集団があるらしいとか、サバトや黒ミサみたいなものを実行しているサークルがあるらしいとかいう伝わり方も当然してるだろうね。それが真実か単なる噂話かはともかくとして、話題としては十分なインパクトがあって面白いから、一度聞いたら忘れないんじゃないだろうか? 」
「・・・確かに。」
「サバトや黒ミサが何のために行われるか全く知らない人は少ないだろう。細かな知識が無くても、悪魔みたいなモノを呼び出すための儀式だってことぐらいは誰でも知ってるさ。だから、直接に教団の教えを受けなくても、その目的や主張は薄々伝わるんだ。そして、教団の目的や主張が薄っすらと伝わった奴らの中には、興味本位で理解を示したり、内心で応援するような奴もいたりする。その程度の奴なら決して少なくないだろう。」
人は表面上で決して不幸や災いを望まないが、傍観者の立場を保つことができさえすれば、内心では無責任な野次馬と化すことがある。火事場見物をしたり犯罪者を応援したりする類の行為の延長で、自分が不平不満を抱いている社会に手傷を負わせるような行為を喜んだりもするかもしれない。
おそらく、教団の儀式殺人に対しても、この手の野次馬は多数発生しているだろう。
そこが怖いのだと尾藤は言った。
「そういう連中が、先ほどの構図に於いては軽い気持ちでゴミを捨てる奴らに当たるんだ。軽い気持ち、ささやかな悪意で教団を後押しする。さらには、似たような思想信条を持っている全く別なカルトは国内だけじゃなく世界中に五万とあるだろうから、その信者たちは今回の荻窪の儀式を知って共感するかもしれない。」
そういう連中が大挙してゴミを捨てる役割を果たすことになる。
なるほどねと、木村が頷いてみせた。
「お前の言いたいことは十分に理解したし、教団の影響を受けた野次馬の存在ってのはは実施確かなことだと思う。だが、『ゴミを捨てる』イコール『悪魔的なモノを生み出す』って話までは俺は信じちゃいないぞ。そこは、お前の妄想だと思っている。」
「それは分かってるよ。お前に、そこを期待しちゃいない。」
尾藤は嘆息しながらも、少しだけ食い下がってみた。
「大勢が一斉に、そこに「何かが存在している」と強く信じ込んだとしたらどうなるだろう? 元々は何もいなかったはずなのに皆がいると言うんだよ。しかも、「何が? 」と問えば皆で共通の認識を答えるんだ。それを続けることによって、本来は何も存在していなかったはずのそこには、何かが存在しているということにならないかな? 」
これに対する木村の応えは無く、尾藤を憐れむような複雑な笑顔を向けてくる。
「やっぱりねぇ。」
木村にオカルト話の理解を求めるのは諦めることにした。
「だけどさ、奴らの儀式は単なる猟奇殺人事件としてではなく、社会的に見てもヤバいんだってことだけは肝に銘じておいて欲しいな。」
「そんなこと、言われるまでもない。」
「儀式は、あと一回で完成するらしい。それは絶対に阻止しなくちゃならん。儀式が完成したってことが世の中に伝われば、二〇万人プラス不特定多数の影響を受けた馬鹿な連中が力を得て、悪魔じゃなくても、そいつらが世の中に災いを振り撒き始めるかもしれないんだからな。」
[三二]
カルト教団の儀式は、いったい何を生み出そうとしているのか?
尾藤は木村が帰った後も、暫く事務所に残ったまま考えていた。
『黙示録などに出て来るような大災害や大戦争を引き起こして一息に世の中を滅ぼそうとするようなモノではない。人に審判をもたらそうなどという大そうな存在でもない。もっと地道に、毎日少しづつ、お前たちが気付かないうちに、俺はこの世の中にジワジワと沁みとおっていく。』
黒ローブ姿の男のセリフを繰り返し思い出していた。
このセリフの意味について、尾藤は徐々に理解に近付きつつあるような気がしている。
(たぶん、教団の指導者たちは、悪魔的で圧倒的な力を持つ存在をイメージして、そういうモノを呼び出そうとしているに違いない。)
それは分かっている。
だが、実際に生まれようとしているモノは、そんな分かりやすい存在ではない。
そもそも、悪魔だとか神様などという都合の良いファンタジーな存在は、最初から有り得なかったのだと思う。
上井たちが研究を積み重ね、虚実入り混ぜて作り上げた儀式は、彼らが本来望んでいたモノを呼び出してはくれないだろう。
(だが、失敗ではない。)
儀式は彼らも意図しない方向で成果を上げつつある。
悪魔とか神様の代わりになる何モノかを生み出し、この世に解き放とうとしている。
上井たち教団は二〇万人の信者たちために、それを呼び出そうとしていたのだろうが、実際はもっと現実的で大きな影響力のあるモノが生まれようとしている。
上井たちの儀式は、奴らが意図しないうちに不特定多数の邪な意識を取り込むためのレンズの役割を果たしていた。さらには、世の中に漂っている同じ方向を向いた反社会的な願望を取り込んで一つの具体的な形にまとめ上げるスパイスの役割も果たしていたのかもしれない。
過去一一度に渡って繰り返されてきた儀式により、それらは遂に巨大で独立した一つの意思を持つ存在となり、今や解き放たれるのを待つばかりとなっているらしい。
上井たちが自らの手で作り上げた成果に気付いているかどうかは知らない。
彼らは未だに悪魔や神様を期待しているのかもしれない。
だが、尾藤は既に存在している別な何モノかを確かに感じていた。
それは黒ローブの男の姿を借りて、
『黙示録などに出て来るような大災害や大戦争を引き起こして一息に世の中を滅ぼそうとするようなモノではない。人に審判をもたらそうなどという大そうな存在でもない。もっと地道に、毎日少しづつ、お前たちが気付かないうちに、俺はこの世の中にジワジワと沁みとおっていく。』
と、夢の中で自らを称していた。
『悪魔でもあるし、神にもなれる。』
そいつが、巨大で邪な反社会的な意識の集合体ならば、いずれであっても人類にとっては災いでしかない。
果たして、そいつは人類に対して何をしようとしているのか?
いかなる方法で災いを齎そうとしているのか?
(・・・ゴミを捨てさせること? )
先ほど、木村相手に一つの考え方として提示した構図である。
(ゴミを捨てる者の数が増えたら、人類は滅びるよな? )
人の心の中に潜在する悪意を、今よりもホンの少し強めることができたなら、地球はゴミだらけになる。
例えば、
あと一本の鉄骨、一個のボルトを増やせば倒壊させずに済んだはずの建物や都市。
あと一段高く積み上げさえすれば決壊せずに済んだはずの堤防。
あと一ヘクタールの開墾で避けられたはずの飢餓。
あと少しの予算さえあれば開発できたはずの疫病のワクチン。
あと一歩の外交努力さえあれば回避できたはずの戦争。
そんな究極の結果を招く危うい選択肢は、人類の目の前に数多く存在している。
あと一歩先へ進みさえすれば辿り着けた好結果を目前にして、人類が誤った選択を繰り返すようになったら、
(・・・滅ぶだろうな。)
黙示録に描かれているような大掛かりな破壊ではないから時間は要するに違いない。
だが、確実に人類を蝕み、滅亡に追いやることができるだろう。
『常に身近にいるべき存在。人の世を侵すための存在。求められ快楽を与える存在。そして、人の知恵を曇らせ愚かにする存在。』
それは人の心の中にある反社会的な願望、つまり悪意を増幅させる存在。
人が自らを滅ぼすことに対する罪悪感を薄れさせる存在。
人類を緩やかな滅亡に向かわせるための選択肢に導く存在。
(まさに不特定多数の悪意の集合体? )
尾藤は身震いした。
今までに浮かんだ断片的な考えの全てが合致したような気がしたのだ。
(いったい、どういう手順や偶然が重なって、不特定多数の意識を掻き集めるなんてトンデモナイことができたっていうんだよ? )
そんなことを今更考えてみても意味が無い。
もう既に、そいつは存在している。
不本意だが、統合された意識の中には尾藤のそれも含まれているに違いない。
今となっては、夢の中でアイシュに囁かれた理由も分かる気がしていた。そいつが不特定多数の意識の集合体ならば、そこで尾藤とアイシュが出会っても不思議は無い。
アイシュも奴の一欠片なのだろう。
(但し、俺も彼女も奴にとっては癌細胞だな・・・ )
だから、自分は悪夢を見ているのだと思う。
黒ローブ姿の男が夢の中で語りかけてくる理由も察せられる。
自らの一部であるにも関わらず、それを尾藤が認めようとせず、自らがこの世に生まれ解き放たれるのを邪魔するのが気に食わないのだ。
そうなのである。
今、尾藤は、そいつの一欠片となってしまった者の責任として、おそらく脅威を感じることができた唯一の人類として、その務めを果たそうとしている。
そいつが解き放たれる前に、これを阻止したい。
かなり際どいタイミングではあるが、未だ十分に間に合うだろう。
信者たちが儀式の進行によって期待感を高めていき、一二度目に当たる明日の儀式に於いて味わう絶頂感によってそいつが解き放たれるのだとしたら、それを味あわせなければ良いのだ。
儀式は完成せずカルト教団が崩壊してしまったなら、信者が味わうのは失望。
高まった期待感は萎びてしまうだろう。
祈りが途絶えてしまえば、そこからは何も生じない。
不特定多数の悪意もレンズを失えば四散してしまうだろう。
スパイスが失われれば、何も統合されはしない。
儀式を完成させなければ、何も解き放たれはしないのだ。
『果たして上手くいくかな? 』
心の中で黒ローブ姿の男が語りかけてきた。
(上手くいくさ。)
失敗するわけにはいかない。
世の中に得体の知れないバケモノを解き放つわけにはいかない。
『前にも言ったが、俺は既に存在している。もはや、枷が解かれるのを待っているだけなんだぞ。』
(そんなことは関係ない! お前が既に存在していたとしても、その枷が解かれる機会を奪うことはできる。たとえ社会に不平や不満、衝動的な破壊願望や破滅願望が満ちていて、それらがお前を生み出す力になっていたとしても、お前の存在を悪魔とか神様とか具体的に認識し、その出現を強く願い、祈りを捧げる者たちが道筋を作らなければ枷は解かれないはずだ! )
『厄介な奴だ。』
黒ローブは苦笑していた。
カルト教団が、一二回目で完成するという面倒な儀式の形を作ってくれたのは幸いだったかもしれない。それが枷になってバケモノは足止めを喰らい、尾藤には最後のチャンスが与えられた。
(形式に拘ることで信者の意識を高めようとしているのだから、それを今更違えたりは絶対にしないだろうさ。ざまぁ見ろだ。)
満月で生贄を浚い、新月に殺すというルールのおかげで儀式の開催日が明日であることが分かっている。
(あとは会場を突き止めるだけ。)
現状で、その難関が越えられずに困っているわけだが、
(会場を特定する手段は失われているからなぁ。)
Kの話ではマジックマッシュルームの発注は無かったらしいし、儀式の会場にはヤドリギを置くというルールは生きているのかもしれないが、前回のように会場候補が九つに絞られているわけではないだろうとの意見もあった。
(まったく、どうやって会場を決めてるのか、ルールが分かれば良いんだが・・・? )
そこで、尾藤の思考が止まった。
何か大事なヒントが浮かびかけた。
(会場を決める際にもルールがあるのか? )
それは不意に浮かんできた疑問だった。
(逮捕者の証言では、会場を決めるのは上井の役目ということだったが、どうやって決めている? )
わざわざリーダーに一任している役割なのだから、決して適当な決め方をしているわけではないだろう。
カルト教団にとっては、これも大切な形式であるはずだった。
[三三]
JR荻窪駅近くにある廃墟ビルの地下二階。
先月二四日の捕り物以来、規制線によって封鎖されていたはずの映画館の扉が、静寂の中にギリギリと蝶番を軋らせる音を響かせながら開いた。
真っ暗な空間に足を踏み入れたのは一人の初老の男と、一本の蝋燭を手に彼の足元を照らす中年の女性だった。
男は肩に白布で覆われた大きな荷物を担いでいる。
その重さ故に足取りはぎこちなく、時々足が縺れて転びそうになっていた。
「大丈夫ですか同志? 」
女が空いている手を差し伸べて彼を支えようとする。
「大丈夫だ。それよりも私の足元を照らして壇上まで導いて欲しい。」
女は男の言葉に従い、蝋燭を低く翳した。
「もう直ぐだ。もう直ぐ我々の大願が成就する。」
男は歩を進める度に呟きを漏らしていた。
「志半ばで下衆の手に落ちてしまった一〇〇〇人を超える同志たちの無念を思えば、肩の荷の重さなど何ほどのことがあろう。」
苦しげな荒い息を吐きながらも、その口から出る呟きは歓びに震え、汗の浮かんだ顔には愉悦を湛えていた。
男は真っ直ぐにステージを目指して歩いている。
道程は然程遠くないのだが、重い荷を担ぐことに慣れていない男にとって、それは過酷な歩みだった。
廃墟ビルを訪れ、その入り口を潜った時から男は重い荷を肩に負っている。
代わりに負ってくれる者は、今や誰もいなくなった。
非力な女性に背負わせるわけにはいかない。
自分が負って歩むしかないのだ。
映画館の扉を潜り、漸くステージが見えてきたというのに、そこは未だ目の前に霞が掛るほどの遥か遠くに感じられる。
ふと男の脳裏に、茨の冠を戴き十字架を背負って刑場へ向かう救世主の姿が過った。
「そうだ、私は同志たちの魂の救世主になるのだ。私は今日、偉業を成し遂げる! 」
男の口から、くぐもった笑い声が途切れ途切れに聞こえていた。
その声、決して偉業を成し遂げようとする英雄のものではない。
妄執にとらわれた哀れな亡者の喘ぎ声に聞こえた。
「今、何時だ? 」
ステージに上る短い階段の前に立った男は、そこで一旦立ち止まり、肩の荷を揺すりあげながら傍にいる女に問う。
「もうすぐ一七時になります。」
男は強く頷き、残されていた力を振り絞って足を動かし、ゆっくりと階段を上った。
「時間が無い。急がなければ。」
男はステージのほぼ中央を選んで肩の荷を床に下ろした。
すかさず、女が荷の周りを取り囲むように一一本の蝋燭を立て、それらに火を灯した。
闇の中に埋もれていた館内の風景が蝋燭の灯に照らされて薄っすらと浮かび上がり、二人の巨大な影が、幾重にも重なって銀幕に揺らいでいた。
男は一一本の蝋燭の灯を感慨深げに見回してから、
「我が同志たちよ、共に祝おうではないか! 」
高らかに唱え合掌した。
暫し黙祷の後、
「それでは神聖なる儀式を始めよう。」
男の言葉に応え、傍らに控えていた女が黙って深々と一礼し、床の荷を包んでいる白布を素早く解き始めた。
白布が全て取り払われた後、そこに現れたのは仰向けに寝かされた若い女性の均整の取れた美しい裸体。
その女性は生きているようだが、深いこん睡状態にあり身動き一つしない。
胸元の微かな上下だけが、女性に残された唯一の生命の印しだった。
男は裸体の傍らに立ち、その全身を舐めるように見回した後、
「我らの祈りを冒涜した裏切り者。この女こそ生贄に相応しい。」
残忍な笑みを浮かべながらローブの袖に手を入れ、刃渡り三〇センチほどのサバイバルナイフを取り出した。
男はナイフを蝋燭の灯に翳し、その妖しい煌めきを楽しみながら、
「お前は下がっていろ。」
背後で白布を畳んでいた女に言った。
女は両掌を上に向けながら恭しくお辞儀をし、そのままの姿勢で下手の袖へと後退りしていく。
これで儀式の場は整い、頃合いは良しとみた男が両手を頭上に翳して叫んだ。
「Our Mighty Power ! 」
生贄の儀式の始まりを告げる一声だった。
ところが!
突然館内に響き渡った凄まじい騒音によって、始まったばかりの儀式は中断を余儀なくされてしまった。
「なんだ? どうしたというのだ? 」
男が慌てて下手に控えているはずの女を呼んだ。
しかし、返事は無い。
床の蝋燭を一本手に取りあげて、下手に向かって翳してみた。
すると、そこには濛々と舞い上がる埃の中に崩れ落ちた廃材と備品の山が見えた。
女はその下敷きになって気絶していたのだ。
「ばっ、馬鹿者! 何をやっとるか! 」
男の怒声が飛んだ。
女が失態を犯したと思ったのだ。
しかし、それは違った。
間もなく埃が収まると、廃材と備品の山の裏側から人影が現れたのだ。
「上井ユン! 」
その人影は叫んだ。
「もう下らん遊びはおしまいだ! 」
下手の袖からステージ中央に歩み出した人影が蝋燭の灯に照らし出され、その正体が明らかになる。
「お、お前は探偵か! 」
「探偵じゃない、調査員と言え! 」
それは尾藤だった。
「上井さんよ。アイシュを返してもらおうか。」
震える手でサバイバルナイフを構え、ぎこちなく威嚇の姿勢を取った上井に向かって、尾藤はゆっくりと間合いを詰めていった。
突然の出来事に上井は恐慌状態に陥っていた。
今度こその思いで臨んだ儀式だった。
その成功は二〇万人の同志たちが心待ちにしていたはずだ。
それが、再び同じ男によって邪魔され、失敗させられてしまったのだ。
上井は偉業を達成できなかった。
同志たちの救世主になれなかった。
その悔しさと怒りが全身を包み、手足に痙攣を引き起こし、口から泡を噴かせた。
そんな混乱した状態で無暗にサバイバルナイフを振り回すので、うっかり近寄ると危ないと見た尾藤は一旦立ち止まった。
「どっ、どっ、ど、どうして、おっ、お前が、こっ、ここっにぃ? 」
何を言っているのか分からなくはないが、上井は吃音まで出始めていて、まともに話せなくなってしまっている。
「そりゃあ、儀式の会場は絶対にここしかないと思って張り込んでいたからだよ。危ない賭けだったけど見事にアタリだったね。」
上井は何か言いたそうに必死で口を動かしているが言葉にならない。
「どうして、そう思ったのかって? 」
尾藤は上井の口の動きを見て、一方的にそう解釈をした。
「んじゃ、面倒臭いけど説明してやるよ。」
不敵に笑いながら懐に手を入れた尾藤に、上井が慌てて半歩後退した。
「ビビんなよ。」
尾藤はスティックキャンディを取り出しただけだった。
そして、上井の見ている前でビニールを破って口に銜える。
この一見無意味に思える行為は尾藤の計算である。
腰の引けてしまった敵を、さらに追い込むためには精神的にこちらが有利であることを見せつけてやれば良い。少し余裕を見せたり、格好を付けてやるだけで、それなりの効果が得られるものだ。
案の定、大きな刃物を抱えており、一対一では決して不利とは言えないはずの上井が完全に追い詰められた獲物状態に陥ってしまっている。
敵を前にしてキャンディを舐めている尾藤の姿など冷静に見れば馬鹿みたいだが、その余裕ぶった態度が上井の目には脅威として映っているに違いない。
上井の委縮しきった姿を満足気に眺めながら、尾藤は意地悪そうな笑みを顔中に湛えつつ説明を始めた。
「お前らが前回の儀式に失敗した後、慌てふためいてやり直しをしようとしたお仲間が続出しただろう? まるで、うっかり地面に落としてしまった菓子を慌てて拾おうとする子供に似てたよな。「三秒以内に拾って食えば落としたことは帳消し! 」みたいな感じでさ。まあ、そんな慌て者たちの中にお前はいなかったみたいだけど、お前だって儀式をやり直したいんだろ? 前回の分は無かったことにしたいんだろ? 今までに一一回も儀式を成功させてきたんだよな? 良く分からんけど一二回目が最後みたいなこといってたから、あと一回女の子を殺せば儀式は完成するとこまできてたってことだよな? それなら失敗を認めて、また最初っからなんて絶対に辛いよなぁ、嫌だよなぁ。その気持ちは良く分かるわ。」
尾藤はキャンディの先を噛み折った。
そして、奥歯でボリボリと大きな音を立てながら砕いた。
上井は相変わらず腰を引いてサバイバルナイフを左右に振り回し続けている。
(こいつ、俺の話聞こえてんのかな? )
正気を失っている相手に、これ以上話しても意味無いような気もするが、せっかくの大詰なのだから結論ぐらいは言わせて貰うことにした。
「儀式のやり直しをするに当たってだが、お前はリーダーだから絶対にルールを曲げたりしないだろ? アイシュが処女かどうかは知らんが、誘拐したのは満月の日だったから俺はそう確信したのよ。で、そんな奴なら儀式の会場決めにも生真面目さを発揮するだろうと思った。つまり、前回と同じ場所でやると踏んだんだよ。お前は儀式の会場決め担当らしいが毎回どうやって決めてる? 決して行き当たりばったりなんかじゃないよな? お前らって変に形式とか段取りとか仰々しく飾って見せるの好きだから、会場決めも絶対に神様のご託宣とかで決めてるだろ? そんな神聖な段取りで決まった会場なら失敗して都合が悪いからって自分勝手に変更はできないよな? あそこはダメなので別の場所を紹介して下さいなんて神様には頼めっこないよなぁ? だから、一度会場が決まったなら絶対にそこでやり遂げようとするんじゃないのか? それも儀式のルールなんじゃないのか? 前回の失敗を無かったことにしようと思ってんなら尚更だよな! 」
上井は何も言い返してこないが、尾藤の話を聞いているうちに息遣いがドンドン荒くなり、顔色が興奮で赤く染まってきた。
どうやら図星を刺され悔しがっているようである。
(ざまぁ見ろ! )
今でこそ尾藤は、ある程度の自信を持って語っているように見せかけているが、実は冷や冷やモノの賭けだった。
マジックマッシュルームの発注は無かったし、ヤドリギも見付けられなかった。事前に何度も調べたが、九つあった会場候補の全てにアイシュは監禁されてなかった。
おそらく、主だった儀式の実行部隊が逮捕されてしまったので、上井は人手不足になり同じ段取りを取ることはできなくなったに違いないと判断した。
金も無いから高価なキノコも買えず、儀式の際に多数の信者を集めるつもりが無いならヤドリギも不要。生贄は儀式が始まる直前に上井が自分で会場に運ぶだろう。
つまり、司廉子救出の際に手に入れた情報は全て使えなくなってしまったのだ。
教団が弱体化したことで、却って手掛かりを失うという破目に陥ってしまった。
その推測に思い当たった時、尾藤は次に打つ手が見付けられらずに目の前が真っ暗になり、挫折しかけていたのだ。
「上井は、どうやって会場を決めている? 」
昨夜、唐突に浮かんだ疑問を辿ることで、
「儀式の会場は前回と同じかもしれない。」
との推理をしてみたものの、それは決して確信と言えるようなものではなかった。
この他に頼るべき情報が得られなかったので、一か八かの賭けに出たのだった。
だから、実際に上井が映画館に姿を見せるまでは気が気ではなかった。
ドアが開き、上井が白布に包まれたアイシュを担いで入ってきた時には思わず歓声をあげそうになったほどだった。
(なんてったって、木村も信じちゃくれなかったわけだしなぁ。)
警察は上井が一度手入れを食らった場所に再び潜り込んで儀式を行うなどとは思っておらず、独自の情報源から得た別な場所に目を付けており、公安もこの考えに従っていた。
尾藤の意見は取り上げられず、結局たった一人で上井に対することになった。
上井は公安と警察の裏をかいていたことになる。
一応、杉並警察署がこの廃墟ビルの監視や巡回もしていたらしいが、上井が目を盗んで潜り込めたのだから随分と手薄だったに違いない。
この場には尾藤が自分の勘を信じて単独で張り込んでいただけなので、それさえなかったら上井は偉業とやらを達成していたことになる。
「運が悪かったねぇ。」
尾藤は自信満々な態度で親指を立てて見せた。
「最後に言っとくが、お前たちが世の中に災いを撒き散らそうとしてたこと、誰も信じちゃいないが、俺は結構ヤバいと感じてたんだぜ。お前らの猛烈な怨念がホントに悪魔みたいなモノを呼び出しちまうんじゃないかってな。お前らと付き合い始めてから嫌な夢を見るようになったし、体調も最悪だった。マジで呪われてんじゃないかと思ったほどだ。だから、今回は俺の精神衛生と健康のためにホンキで潰しに掛らせてもらったわけ。」
そして、尾藤は上井に降伏を勧告した。
「ふっ、ふふ、ふざけるな、なっ! 」
怒り心頭に達した上井は激しく逆上した。
「わっ、我らの信心を、ぐ、ぐっ、愚弄するのか! 」
「ふざけてんのはどっちだ馬鹿野郎! 色んな宗教を出鱈目にパクって人殺しの儀式なんか作りやがって何が信心だ! 世界中のあらゆる宗教の敬虔な信者に謝れ! 」
「こっ、殺してやるぅ! ぶっ、ふうっ! 」
上井は口から泡を飛ばしながら、尾藤に向かって意味不明の罵声を吐き散らし始めた。
その姿は見ていて気持ちが悪くなるほどに汚らしかった。
「あ、そう。力尽くが良いってことだな。」
尾藤が決着をつけるべく一歩前に踏み出すと、上井が裏返った声で叫んだ。
「こっ、殺すぞ! 」
サバイバルナイフを、尾藤ではなく意識を失ったまま無抵抗のアイシュに向けた。
(うわぁっ! 危なっ! )
狼狽し、冷静さを失った上井なら、躊躇いなくアイシュを刺すかもしれない。
手を滑らして傷つけてしまう可能性もある。
尾藤は焦ったが、それを悟られないように平静を装い、さらに一歩前進した。
そして、
「刺せよ! 」
鋭く冷たい視線を上井に向けて言い放った。
「いずれにしろ、アイシュも俺も殺すつもりなんだろ? 俺は殺されたくないからな。お前がアイシュを刺したら、今度は俺がお前を嬲り殺しにしてやる。お前に殺された女の子たちの仇討ちだ。」
「そっ、そんなことできるもんかっ! 」
上井が恐怖に顔を引き攣らせながら、アイシュの喉元に震える手でサバイバルナイフを押し付けた。
アイシュの喉元にナイフの先端が数ミリ食い込み、傷口からジワリと血が滲んだ。
(ヤバっ! )
それでも、尾藤は鼻で笑った。
「できるさ。俺は警察官じゃない。そもそも倫理観や道徳観の薄い人間なんでね。たぶん、お前を殺した後で正当防衛を主張すれば認められるだろうし。」
そして、さらに一歩踏み出す。
既に、尾藤と上井の間にある距離は二メートルも無い。
ここで、上井がサバイバルナイフを構えて逆襲に転じれば、尾藤には避けようが無かったかもしれない。
しかし、上井はそうしなかった。
上井の手からサバイバルナイフが離れ、重い音を立てて床に落ちた。
震えていた膝からは一気に力が抜けてしまったようで、その場に崩れ落ちるように蹲ってしまった。
尾藤は床に落ちたナイフをステージの奥へと蹴り飛ばした。
「警察には連絡してある。間もなく、ここに到着するはずだ。」
ステージに姿を現す前、木村宛てに「上井発見! 」のメールを発信しておいた。
もはや、上井に返す言葉は無かった。
ショックのあまり呆然自失の状態である。
これで上井は行動不能に陥ってしまったと判断した尾藤は、床に這い蹲る姿を見下ろしながら、後は観念して待てだけと言い、アイシュの傍に寄って上半身を抱え起こした。
アイシュの裸体はピクリとも動かないが、体温は暖かく呼吸も正常だった。
(至急病院に運ばなくちゃ! )
自分が着ていたコートを脱いでアイシュを包み、その身体を両手で抱き上げるとステージを降りた。
映画館の出入り口に向かって歩む尾藤の背に、上井の嗚咽が聞こえてきた。
(ジジイの汚い泣き声なんか、聞きたくないねぇ。)
そのまま無視して映画館を出ようとした尾藤だったが、突然立ち上がってドタバタと走り出す上井の足音が聞こえた。
「逃げんのかっ! 」
尾藤はアイシュの身体を足元に横たえ、ステージを振り返った。
腰が抜けて行動不能に陥ったというのは魅せ掛けだったのか?
いや、そうではなかった。
上井は逃げようとしたのではなく、四つん這いでステージの奥に移動しただけだった。
立ち上がる気力も体力も既に尽きていたようである。
しかし、ステージの奥まで必死で辿り着いた上井の手には、先ほど尾藤が蹴り飛ばしたままになっていたサバイバルナイフが握られている。
「上井っ! てめぇ、まだ抵抗を続ける気かっ! 」
叫びながらステージに駆け寄ろうとする尾藤を上井が手を上げて静止した。
その途端、
(な、なんだ? )
何の前触れも無く、尾藤の足が止まった。
どういう分けか、足に力が入らず一歩も進めなくなった。
「Our Mighty Power ! 」
上井が、先ほど中断してしまった儀式を再開するかのような叫びを発した。
先ほどまで、上擦ってまともな声を出せずにいたとは思えないほど明瞭な叫びだった。
上井の叫びと共に、尾藤の耳に地の底から徐々に湧き上がるような不気味な声が聞こえてきた。
(これは信者たちの合唱? いったい何処から? )
映画館は無人である。
廃墟ビル全体が無人である。
カルト教団の信者どころか、人は誰もいない。
その合唱が何処から発せられ、どのようにして尾藤の耳に届いてくるのか分からない。
尾藤は、自分が錯乱しているのではないかと思った。
だが、意識はハッキリしているし、取り乱すような危うい状況にも陥っていない。
それなのに、唱える者たちの姿が見えない合唱は明らかに聞こえている。
いつしか合唱は巨大な獣の咆哮に変わり、廃墟ビル全体を激しく振動させるに至った。
「Please Receive ! 」
ステージ上では、上井が大きく叫びながら膝を突いたままの姿勢でサバイバルナイフを持つ手を天に翳していた。
その顔が、一瞬だけ尾藤に向けられた。
(笑っている? )
まるで勝ち誇ったような、歓喜に満ちた笑顔だった。
次の瞬間!
上井はサバイバルナイフを、自らの胸に突き立てた。
さらに、胸を深く抉るようにナイフを回すと共に、
「Please Receive ! 」
それは断末魔であったかもしれない。
上井の最後の叫びが映画館内に響き渡った。
同時に獣の咆哮は絶頂を迎え、鼓膜を突き破らんとするほどのボリュームで尾藤に襲い掛かった。
バッ! バリバリーッ!
何かが砕ける音がした。
ステージ真上の天井が裂ける音だった。
巨大なコンクリートの塊り、鋼材やパイプが天井を突き破って、ステージの上に次々と降り注いだ。
上井の姿は忽ち、それらの下敷きになって見えなくなってしまった。
続いて映画館の天井全てが崩れ始め、瓦礫や破片は客席側にも降り注いだ。
尾藤は重たい足を引き摺って未だ意識の無いアイシュの所まで戻り、その身体を庇うように覆い被さった。
アイシュを庇いながら、それでも尾藤は必死に何かを見届けようと顔だけはステージに向け、突如起こった激しい崩壊の嵐から目を背けずにいた。
「あれは何だ! 」
濛々と舞い上がる黒い粉塵の渦の中で、蝋燭の灯が全て掻き消される寸前、尾藤の目は何かを捉えていた。
それが姿を現したのは、ホンの一瞬である。
「動いている! 」
僅か一瞬で尾藤が捉えたモノは、闇よりも濃い黒、一切の光を通さない純粋な黒を纏った人のようでもあり、四足の獣や翼を開いた鳥のようでもあった。
何にも見える、何ものでもないそれは、明らかに生命と意思を持つ存在と確信できた。
それは一瞬の間に悪意と穢れに満ちたイメージを尾藤の心に焼き付け、意識を吹き飛ばすほどの巨大な咆哮を轟かせて蝋燭の灯と共に暗闇の中に溶け込んでしまった。
廃墟ビルを襲った突然の崩壊は間もなく止んだ。
既に跡形も無くなった地階は暗闇と静寂に閉ざされた。
[三四]
一二月二四日、火曜日、早朝。
中野区にある東京警察病院。
一階エントランスに用意された待合用のベンチに尾藤と木村は並んで腰掛けていた。
尾藤は額と顎に絆創膏が貼られ、左手首には包帯が厚く巻かれていた。
廃墟ビルの地階が崩落する中で、アイシュを庇った際に負った名誉の負傷である。
あれから、間もなくして廃墟ビルに到着した警察官や消防隊員の手によって、尾藤とアイシュは崩れ落ちた地階の瓦礫の中から救出された。
地下一階から地下三階まで丸ごと崩壊してしまった現場の様子は、まるで大地震に襲われた後のようで酷い有様だったが、幸いなことにアイシュは無傷であり、尾藤も軽傷を負った程度で済んだ。
崩壊の原因は老朽化だろうと言われているが、現段階では未だ調査が完了していない。
瓦礫の中から、二人の遺体が見つかった。
上井ユンと、彼に付き添っていた身元不明の中年女性の遺体であった。
「事件は完全に終結した。」
木村は尾藤に宣言した。
「上井は死に、儀式が阻止されたことは今朝マスコミを通じて大々的に報じられた。」
指導者を失い、失望した信者たちは、いずれ時と共に儀式を忘れ、教団は消え去ってしまうだろうと言っていた。
それについて、尾藤は黙って意見をしなかった。
ところで、
「アイシュの容体は? 大丈夫なのか? 」
病院に搬送されて後、尾藤はアイシュと別れ、彼女の治療に立ち会ってはいない。
最後に見た時は、未だ昏睡から覚めていなかった。
「付き添った看護師の話では、一時間以上前に意識が戻ったということだ。」
木村の言葉に、尾藤はホッと一息吐いた。
「多量の麻酔剤を投与されてたそうだから、未だ朦朧とした感じだが、そのうちに治ると医者は言っている。後遺症の検査も含めて暫く入院だが、先週から両親が来日しているんでな、付き添いの心配は無い。」
「そうか、そりゃ良かった。」
アイシュが行方不明になったとの連絡を受けた彼女の両親は、すぐさまインドから駆けつけ、これまで警察と行動を共にしていた。
尾藤は一度も会っていないが、木村の話では両親とも娘の身を案じるあまり気が狂いそうになっていたと聞く。
昨夜、娘が無事に救出されたことを知って、さぞ喜んでいることだろう。
「アイシュが、お前に会いたがってたそうだ。」
その言葉に尾藤の目元がピクリと動いたが、返事はしなかった。
「命の恩人に感謝していたらしいぞ。今なら、いや既に彼女はお前に惚れてるかもしれないな。良いじゃないか、会いに行ってやれよ。」
木村は強く勧めるのだが、尾藤は気の無い素振りをする。
「別に良いんじゃない? 身の危険は去ったんだしさ、今更俺が顔出す必要な無いでしょ。両親が付き添ってるなら身の回りの心配もいらないわけだしさっ。」
木村は残念そうな顔をして、
「お前、相変わらず奥手というか、男じゃねぇなぁ。」
と、言った。
(こいつ分かって無いよなぁ。少しは察しろよ。)
一連の事件について可能な限りアイシュは忘れた方が良い。
一一月二四日の荻窪の事件後から抱き続けていた尾藤の考えは、今も変わっていない。
一時アイシュとの連絡を絶ったことにより、彼女が誘拐されたことに気付けなかった点については後悔したが、今ではそうした危険も去った。
事件は、忘れてしまうのが不可能なほどアイシュの心に深い傷を残したと思うが、それでも時が経てば多少薄れはする。だが、尾藤が身近にいれば事件はいつまでもアイシュの心の中で生々しく再現され続け、もしかしたら彼女の精神を蝕んでしまうかもしれない。
確かに尾藤とアイシュの間には恋愛感情を生じさせる切っ掛けが多々あったとは思うのだが、その切っ掛けの全てがカルト教団の引き起こした禍々しい事件に起因する。
これらは、どんなに時が経っても決して良い思い出に変わったりはしないだろう。
(だから、会わなくて良いんだよ。)
心の底から思っていた。
もちろん、一時の未練を感じないわけではない。
だから、尾藤はホンの少しだけ物思いに耽っていた。
しかし、何分も無言でいたわけではなく、精々三〇秒程度のことだった。
それなのに、
「おいっ、木村さんよ! 」
尾藤に肩を叩かれた木村は、
「ん、なんだ? 」
と、言って顔を上げたが、その眼が半分閉じていた。
「まあ、お前も疲れてんだろうしなぁ。」
尾藤は、自分も一つ大きな欠伸をした。
「・・・何か話があんの? 」
木村が、指で目を擦りながら聞いてきた。
「別に大した話じゃないから良いや。」
尾藤は手を振った。
話すべきか迷っていたことがある。
上井が自らの手で命を絶ってから、崩れ落ちる瓦礫と舞い上がる黒い粉塵の中で、尾藤が目撃したモノについてである。
(でも、木村にオカルト話は意味無いかぁ。)
あれは一瞬の出来事だったので、誰に話しても目の錯覚、気のせいだと断言されてしまいそうだった。
(でも、俺は見た。遂に上井は儀式を完成させたんだ。)
結局、尾藤は失敗した。
アイシュを助け出すことには成功したが、儀式を潰すことは出来なかった。
尾藤は、黒ローブ姿の男が語っていたセリフを思い出していた。
『あの儀式自体には何の意味も無い。』
そんな冷めたことを言っていた。
『人の願いを強く纏めるには、ああいう儀式は都合が良いのかもしれない。』
大勢の意識を結集させるためにのみ儀式は有効だと言っていた。
『生贄なんて女でも男でも誰でも良いから、人を一人殺して皆でその達成感を味わえれば十分なのさ。』
そういうことだったのである。
一二月二三日一七時七分。誰かが生贄として殺されることを二〇万人が期待して待ち望んでいた。
それはアイシュでなくても、誰でも良かったのである。
上井は最後の瞬間に、そのことに気付き、自らを生贄として捧げたのだ。自らが殉教者となり、その遺志は信者たちに、そして不特定多数の意識に届いてしまった。
無人の廃墟ビルに轟き渡っていた合唱の凄まじさを尾藤は忘れられない。
如何なる現象によるものか、そんなことは最早どうでも良くなっていた。
個々の信者による祈りの声は廃墟ビルの地下に集まり、凄まじい大合唱、獣の咆哮として、尾藤の耳に届いていたのだ。
咆哮は絶頂に達し、廃墟ビルは崩壊した。
「そして、何かが生まれ、この世に解き放たれた! 」
上井も含めて、カルト教団の信者たちは、儀式の完成によって何が生み出されたのか知っているのだろうか?
悪魔だと言う者がいるだろう。
神様だと言う者もいるだろう。
疫病だと言う者がいるかもしれない。
災害だと言う者がおり、戦争だと言う者もいるに違いない。
彼らには端から具体的な共通認識など無い。如何なる過程を経て、如何なる手段を用いても良いから、彼らの悪意を世界中に振り撒きたいのだ。
その強烈な一念だけは共通している。
「悪意! 」
尾藤が粉塵の中で見たモノの正体は正しくそれだった。
不特定多数が無意識の中に悪意を潜在させる現代社会の中で、自らの悪意を明確にした二〇万人が儀式を取り行った。
皆で社会を呪い、その滅びを願うために強い信念を以て積み重ねられた生贄の儀式は、彼らがどのような結果を意図していたのかは不明だが、既に世の中に染みついていた無数の悪意を統合するためのレンズとスパイスの役割を見事に果たしてのけたのだ。
昨日、統合され完成した巨大な悪意はバケモノと化し、この世に解き放たれた。
尾藤は、信者さえも目にしていない、その瞬間を目撃した。
「あの悪意のバケモノは人類に災いを齎し、人類を滅亡させ得るのか? 」
できるだろうと、尾藤は思っていた。
自然に積み重なった悪意によって人が滅ぶには相応の時を要する。
そもそも人類が長い地球史の中に生じた一つの現象であるならば、放っておいてもいずれは滅ぶ運命にあるのだが、それは一〇〇〇年先、一万年先の話だったかもしれない。
だが、この度の一件で、どうやらその時が早まってしまったらしい。
「社会の崩壊、人類の滅亡は加速させられる。」
近い将来、大勢の人々が知らず知らずのうちに、滅びに向かうかもしれない選択の場に立たされるだろう。
その時、バケモノはほくそ笑みながら自らが生まれた意義を果たすことになる。
バケモノの悪意は人の心を惑わせ、狂わせ、滅びへと向かう道に誘う。
「近々、人類は取り返しのつかない過ちを犯すだろう。」
但し、それは今日ではない。
解き放たれた悪意が全世界に広がり、人の心に強く働き掛けるには未だ間がある。
明日、目覚めた時、世界は今日と変わらずに存在するに違いない。
一週間後も、世界は変わらずに有るかもしれない。
しかし、一か月後はどうか?
一年後はどうか?
「分からない。」
尾藤は考えるのを放棄した。
この話を木村にするのは止めにした。
誰に話しても信じてもらえないだろう。
仮に信じてくれる者が僅かばかりいたとしても、それが何になるというのか?
不安を抱え、悪夢に悩まされる者を増やすだけでしかない。
尾藤は、成り行きを見守ることにした。
暫くは、何も変わりはしない日常が続くはずである。
(それで良い。)
いつかは、昨日見た悪意のバケモノと再びまみえる日がくるかもしれないが、それを危惧して生きて何になる。
尾藤は今日も仕事である。
飯を食い、酒を飲み、恵子の小言を聞きながら、明日もまた仕事。
それは間違いない。
そうした毎日の繰り返しは人類が滅びるまで続くに違いない。
「・・・ん? 」
隣で木村の低い鼾が聞こえた。
先ほどは労わりかけたが、今は何だか無性に腹が立つ。
「寝てんじゃないよ! 」
両手で肩を掴んで、思い切り揺り動かしてやった。
「待て、待てって! 酔うから! 起きるから! 」
尾藤は無理矢理起こした木村を引き摺って、病院の正面玄関を潜って表に出た。
クリスマスイブの天気は快晴、空気は冷たく澄み、午前八時の日差しが降り注ぐ。
「さあ、一本よこせ! 」
尾藤は木村に手を差し出した。
「キャンディなんて持ってないぞ。」
尾藤は違うと首を振り、
「煙草を出せって言ってんだよ。」
自分の背後にあるスタンド式の灰皿を指差した。
木村は寝惚けているうちに、喫煙所に連れて来られたことに漸く気付いた。
「禁煙してんじゃ無いのかよ。いい加減な奴だな。」
木村が懐から、ブルーの箱を取り出して、中から紙巻き煙草を二本取り出し、そのうちの一本を尾藤の口に差し込んだ。
「火は? 」
「はいはい、うるせぇな。」
木村は、使い捨てのガスライターで火を点けてやった。
尾藤は思い切り煙を肺に吸い込んでから、数秒置いて一気に吐き出した。
「いやぁ、美味いね。やっぱ高級品は良いねぇ。」
木村の煙草はハイライト。昔は庶民の嗜好品だが、今時は一箱一一〇〇円、一本五五円もするのだから高級な嗜好品に違いない。
「禁煙は終わりか? 」
木村が、煙を吹かしながら意地悪そうな顔で聞いた。
「今日は、ご褒美だよ。実際、昨日の俺は良くやったと思うだろ? 」
尾藤が自慢げに胸を張ると、木村がフンと鼻を鳴らした。
「あれ、ちょっとクラっときた。なんか眩暈する。」
「何カ月も禁煙してたのに、いきなり全部肺に入れたりなんかするからだ! 」
木村が困った顔をして尾藤の肩を支えた。
久しぶりの煙草は美味かったのだが、刺激が強過ぎて健康には悪い。
明日の朝、目覚めた時、世界はそこにあるか?

