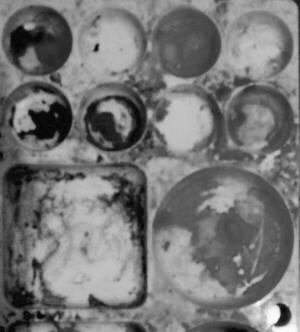何かを記すということ
「良くなれる本を差し上げます」
彼は、夕刻に海辺を通りかかったところ、声を掛けられた。女性だった。
無視したけれども、また呼び止められた。
彼は、この女について、いわゆる如何わしいことを売り物にしているのだろうと思った。
「そのようなものではありません」と女は言った。
普段であれば更に冷たい態度で接するところであったが、彼はこの女との雑談は気を紛らわすのに役立つかもしれないと思い始めていた。
女はにっこりと笑った。
「この本には、あなたのことが書かれています」
彼が海辺を通りかかったのは人並みの理由があった。
彼は悩んでいた。例えばそれは、大切な人との不仲であったり、自分の性格のようなものについての悩みであったかもしれない。
女は今、妙なことを言った。
通常であれば気に留める必要もない一言だったように思う。
しかし、海に沈んでいく日と、波の音などが同時であったから、この世のものとは思えない風景に錯覚をさせたのだと思った。
血の気が引いてきた。呑まれてはいけない。
ページをめくる仕草をしながら、彼は何か気の利いたことを言おうとする。
しかし、本の中に字が見当たらなかった。というより、文字という概念がよくわからなくなった。
突然吐き気に襲われた。足が崩れた。しかし崩れたはずの足がそこに見えなかった。
襲ってきた吐き気や恐怖や心細さは一瞬のことだった。
しかし今度は、何も見えず、音もなかった。
なんとなく水の中にいるようでもあったし、緑の葉がたくさんまわりに茂っているようでもあった。
彼はちょうど、「なぜ視覚も聴覚も正常でないのに理解できることがあるのだろう」といった思考を開始するところだった。
彼は部屋の真ん中で倒れていた。
周りに人が何人かいた。
「とても心配した」といった旨を話しているようだった。
彼の家族だった。
彼は驚いたことに倒れていた経緯を思い出せなかった。
しかし彼は、思い出せない夕刻から現時刻までにあったことについて、後悔し始めていた。
何かを記すということ
2012年3月初稿。