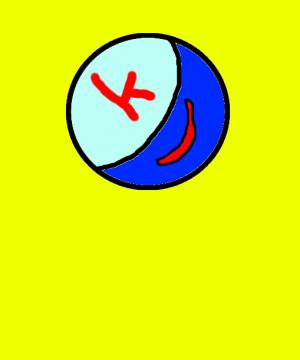遠人
某えぶりん(エブリスタ)からの転載。
自作品なので問題はないだろうとは思いますが、一応記載しておきます。
序章
どれだけ親しい仲でも、何も言わずにいても理解し合えることはない。
テレパシーでも使えない限り、思っていることを伝えることはできない。
以心伝心、なんていう言葉はただの理想で、人間が他人の心を理解することはない。
もしも思っていることを伝えたいのであれば、やはり言葉にしなければならないのだ。
だけど人間は理想を信じてしまう生き物で、相手が親しければ親しいほどに、言わずとも伝わると勘違いしてしまう。
だから時にすれ違いというものが起きてしまう。
言葉にすればそれもすぐに元通りになるのだけれど、言葉にしないままでいるとさらにすれ違いが起きてしまう。最悪の場合、関係が修復できないほどにまで溝ができてしまう。
それでもまだ優しい方だ。
なぜならまだ生きているのだから。
生きていればまだ想いを言葉にし、伝える機会は残されている。
完全には修復できないかもしれない、元の仲のいい関係に戻れないかもしれない。けれど、きっと言葉にしないよりはずっといいはずだ。
だけど。
もしもどちらかがいなくなってしまったら、もう言葉にして伝えることはできなくなってしまう。
残された方はきっと複雑な想いを抱え続け。後悔したり、恨んだり、憎んだり、自分を責めたり。でもどうすることもできなくて、ただ何だかわからないもやもやとした気持ちだけが残ってしまう。
そんな気持ちを抱えたままの人生はきっと切ない。
暗い。
重い。
痛い。
そして伝えたかった想いは行き着く場所もなく、漂い続け、やがて消えていく。想いを抱えていた主とともに、届かない場所へと行ってしまう。
それこそ切なく、やるせない。
だから願ってしまう。
どうかその想いが相手に届きますように、と。
そんなありえないことを、強く願ってしまう。
人間は理想を信じてしまう生き物だから。
第一章
文芸部部室の扉を開けると、風に揺れるカーテンが目に入った。
爽やかな青色をしたそのカーテン布は、ちょうど開けられた窓の中間を区切るかのように、中途半端に引かれている。
今日は風があまり吹いていないはずなのに、どうして途切れることなくカーテンが揺れているのだろうか。
疑問に思いつつ何となく部室を見渡してみると、窓に近い壁の方に白い扇風機が置いてあるのを見つけた。きっとカーテンが揺れている理由はこの扇風機だろう。真新しそうなそれは部室全体に風を送っているわけではなく、ある一点に向かってプロペラを回していた。
長細い部屋の一番奥。長机をくっつけて二つ並べたちょうど境目にノートパソコンを載せ、なにやらカタカタとキーボードを打っている女子生徒。副部長である宮ノ郷琴音に向かってせっせと風を運んでいるようだ。
風の影響で、宮ノ郷の長くて綺麗な黒髪が揺れている。
お勤め、ご苦労様です。なんて心の中で扇風機に敬礼なんてしてみながら、扉を閉めていつもの定席に向かう。宮ノ郷から見て左斜め前の席だ。
机の上に鞄を置くと衝撃を感じたのか、宮ノ郷が顔を上げて僕を見てきた。よく見てみると、彼女は耳にイヤホンを挿しているのがわかった。
きっと作業に夢中になっていたのと、耳にイヤホンを挿していたせいで僕の存在に気がつかなかったのだろう。
「いつからいたの?」
イヤホンを外しながら宮ノ郷が訊いてきた。外したイヤホンから微かに音が漏れていたけれど、宮ノ郷が胸ポケットから出した携帯音楽プレイヤーの電源を切ったため、すぐに音は消えた。
「今来たところ」
「声をかけてくれればよかったのに」
「集中してるみたいだったし」
「アンタが気を遣うなんて、何かいいことでもあった?」
「いいことなきゃ気を遣わないと思ってるのか? 僕だってお前に気を遣うことだってある」
宮ノ郷は僕の幼馴染で、普段なら気なんて遣うことのない間柄であるから、こう言われるのも仕方がないのだけれど。
「それはそれは。どうもありがとう」
「どういたしまして」
宮ノ郷が嫌味ったらしく言って来たので、こっちも嫌味ったらしく返してやった。
「小説か?」
ノートパソコンを指差し、宮ノ郷に訊いてみる。そうしながらパイプ椅子を手前に引いて、そのまま腰を下ろす。パイプ椅子特有の軋む音がした。
宮ノ郷は小さく頷いてみせた。
「正確に言えばライトノベルだけれど。……文集に載せるの」
「あー、文集ね」
「アンタもそろそろ始めないと、間に合わないわよ」
「まるで僕がまだ始めてないみたいに言うなよ」
「じゃあもう始めてるの?」
「……まだです、ごめんなさい」
「やっぱりね」
この幼馴染という奴は本当に困る。僕がどういう状況にあるか、言い当ててしまうことがあるからな。本当にやめて欲しい。
「なんかさ、何やろうか思い浮かばないというか」
特にやりたいことがあって文芸部に入ったわけではない僕にとって、この部活で自分が何をするべきかがわからない。
入ったばかりの頃は他の部員がやっていることを、色々と真似してやってみていた。絵、漫画、論評、そして宮ノ郷が書いている小説。やってはみたけれど、どれも自分にはできなかった。向いていないとでも言うべきだろうか。
「あたしが勧めてしまったのだし、なんだか申し訳ないわね」
言いつつ、宮ノ郷は手元にあったリモコンを操作した。すると、扇風機の首が回転を始めた。結果、僕の方にも涼しい風がやってきた。
リモート式の扇風機とは、また高価そうな代物だな。きっと宮ノ郷が持ってきたのだろう。彼女の家は裕福だからな。本人は否定しているけれど。
小さな声でお礼を言ってから、宮ノ郷の言葉に返事をする。
「いいよ。やりたいことがなかったのは本当だし、退屈しているよりかはマシだ」
「それならいいのだけれど」
やりたいことなんて一つもなくて、放課後はバイトでもして過ごそうと考えていた。そんな時、宮ノ郷がやりたいことがないなら文芸部に入ってみたらと提案をしてくれた。
それで体験入部をしてみたところ、なんだか居心地がよくなって。気がついたら入部していた。
というのが、僕が文芸部に入部した経緯だった。
本当に何も考えることなくここにいると言っても間違いではないはずだ。
だから。こういう活動をしなければいけない時、何をすればいいのかが思い浮かばないのだろう。
何も考えずに過ごすということは、結果的に自分自身を追い込むことに繋がる。現状に至って、そのことを学んだ。
だけど後悔なんてしている場合ではなくて、文集に載せる何かを決めて完成させることを考えないといけない。そうしないと部員全員に迷惑がかかってしまう。これは僕だけの活動ではなく、集団の活動なのだから。
それに。いくらやりたいことがないからと言って、入部してしまったからには、自分のやるべきことはやらないといけない。
いけないのだけれど……。
何をやろうか、全く思いつかない。どうしたものか。
文芸部とは文字通りの文章を書く活動だけをするのではない。文芸とは文学と芸術という意味で、芸術に関係することであれば基本的に何をやってもいい。
だからこの部活の部員たちは、絵を描いたり、漫画を描いたり。小説やライトノベルを書いたり、論評を書いたり。様々な活動をしている。
この何をやってもいいという部分が、僕にとっては難しかったりするのだ。
「……どうしたもんかな」
「そうね……。随筆なんてどうかしら」
「随筆? 枕草子とか徒然草とかのやつか?」
「そうよ」
「そんなもの、僕に書けるとは思えないが」
「アンタならできると思うけれど。というより、アンタだからここできそうな気がする」
僕だからこそ、できる? どういう意味だろうか。
「あたしはね。自分が日頃思っていることを日記みたいに書くのも随筆の一つだと思うの。エッセイとも言うのだし、間違いではないはずよ」
「……、」
日記みたいに、ね。よくわからないのだけれど、随筆というのはそんなに簡単なものなのだろうか。
「そういうの、アンタが得意なことでしょ?」
「でしょって聞かれても、よくわからないんだが」
「だって、昔から考えることが好きだったじゃない。どうでもいいことを深く考えて、それをあたしにつらつらと話して聞かせてくれたこと、忘れてしまったの?」
確かに、そんなこともあったかもしれない。しっかりと憶えているわけではないけれど、微かに記憶がある。
だけど本人でも微かにしか記憶がないことなのに、宮ノ郷はよく憶えていたな。
なにはともあれ、随筆か。本当に僕なんかにできるのだろうか。
「随筆ね、少し考えてみる」
「そうした方がいいと思うわ。と言っても、時間は多くないのだけれど」
「そうだな。夏休みが終わるまでだもんな」
小学生や中学二年生くらいまでの時は、夏休みは長いものだと思っていた。けれど今は夏休みが短いと思える。
社会人に比べればもちろん長いだろうけれど、学生の夏休みだって言うほど長くはないと思う。
だから本当は今からでも作業を始めないといけない。ただでさえ慣れていないことなわけだし。
今さら言ったところで遅いかもしれないけれど。
「ありがとうな」
「……アンタさ、お礼だけはちゃんと言うのよね。不思議なことに」
「どういう意味だ」
「そのままの意味よ」
そう答えながら宮ノ郷はパソコンに目を戻すと、作業を再開させた。
部室の扉が開かれたのはその時だった。
眠たそうな目を擦りながら部室に入ってきたのは、リュックサックを背負った女の子だった。
「あら、春浦さん。今日は遅かったのね」
「日直というミッションがありましてー」
春浦美咲は何故かふらふらとした足取りで僕の隣へとやってきた。ショートヘアの頭の頂点付近から伸びた栗色のアホ毛が、足を進める度にひょこひょこと揺れる。
そのままパイプ椅子を引いて、ドサリと腰を下ろした。
そしてリュックサックを肩から下ろすと、中からスーパーのビニール袋を取り出した。
「ミッションでスタミナを減らしてしまったので、エネルギーをチャージしなければ」
一人でブツブツと言いながらビニール袋から取り出したのは、二つの缶詰だった。一つには鯖の味噌煮と書いてあり、もう一つには焼き鳥と書いてあった。
「相変わらず缶詰持ち歩いているんだな」
「もちろん。……缶詰は人類が生み出した叡智なのですよ、遠坂くん」
春浦は僕の方を見ずに、芝居がかった口調で言った。
「まあ間違ってはいない、のか?」
食品を長持ちさせる意味では素晴らしい発明だと言えるだろうけれど、果たして叡智とまで言ってしまってもいいのだろうか。
「まずは鯖の味噌煮から攻略しましょうかね」
感情が顔にあまり出ないからわかりにくいが、たぶん嬉しそうに缶の蓋を開けた。身体を小さく左右に揺らしている。
「攻略ってなんだよ」
「なんとなく、そっちの方がかっこいい」
なにを言っているのだろうか。僕には理解できそうになかった。
「そのなんだ、僕にはわからないな」
「まだまだ修行が足りませんな」
「何の修行だよ」
「さあ?」
「……さあって」
いつも思うのだけれど、春浦という女子高校生は変わっている。
思ったことを考えなしにそのまま言ってしまうのか、変わったことを言うことがある。訊ねてみてもまた変わったことを言ってきたり、今のように自分でもわからないという意思表示をしたりする。
それだけはなく、缶詰が好きだというところも変わっていると言える。
昼食は弁当箱に白米だけを入れて持ってきていて、おかずは缶詰食品で済ましているらしい。昼食の分だけではなく、おやつとしての分も学校に持ってきていると、少し前に聞いた。
ついでに言えば、これは変わっていることではないけれど、表情が乏しいために何を考えているのかわからない。というところもある。
笑った顔も怒った顔も。泣いた顔も楽しそうな顔も。僕は一度も見たことがない。
無表情で感情を読み取れない春浦ではあるが、不思議とコミュニケーションはとりやすかったりする。
感情が読み取れない人間は何故か近寄り辛いところがある。怖いと思う場合もあるし、何よりどう接していいのかわからないからだ。
けれど、春浦の場合は違った。なんと言うべきか。近寄りたいと思える雰囲気を醸し出しているというか、なんというか。
子どもっぽい容姿をしているからだろうか。守ってあげたいとか、可愛がりたいとか。他人の心をそういう想いで満たしてしまう何かを持っている。そう言った方がわかりやすいかもしれない。
そうして話しかけてみると、変わったことは言うけれど、冗談も交えながら上手いこと言葉を返してくれる。その話し方がまた放っておけない想いにさせてもくれる。春浦の才能と言ってもいいのかもしれない。
そういうこともあって、個人的にはコミュニケーションがとりやすい相手だと感じている。
「そうだ。春浦は文集に何を載せるつもりなんだ? やっぱりいつもの音楽論評ってやつか?」
もうすでに鯖の味噌煮を半分ほど平らげている春浦に、文集の話題を振ってみる。
マイペースそうに見えるし、もしかしたら僕と同じでまだ取り掛かっていないかもしれない。
「んくっ……。うん、そうですよー」
口の中にある物を飲み込んだような音を出した後で、春浦は僕の言葉に返事を返してくれた。
部員になって初めて体験してみたのが、音楽論評というものだった。一番簡単そうに思えたから最初に真似をしてみたのだけれど、意外に難しくて苦労した記憶がある。
「音楽論評って難しくないか?」
「本格的にやろうとすると難しいと。でもわたしは感想のような感じで書いてるから、難しいなんて考えたことないかもです」
「そうか。そういうのも論評って言えるんだな」
「さあ、どうですかね?……そんなのわからないですよ。その道のプロなんかじゃないし」
そう言って、春浦は鯖の身を口に放り込んだ。
「よくわからんが、そんなんでいいのか?」
「別に仕事というわけでもないのだし、厳密にやる必要はないわ。あくまで部活動なのだしね」
春浦の代わりに、宮ノ郷が答えた。
「言われてみれば、そうかもな」
深く考える必要はないのかもしれない。本気でやりたいというのなら別だけれど、楽しみたいという感じであれば厳密にやる必要はないのかもしれない。
「君は何をするのです、遠坂くん」
鯖の味噌煮はすでに食べ終わったらしく、焼き鳥の缶詰を開けながら、春浦が訊いてきた。
「それを今考え中でさ。宮ノ郷が随筆を提案してくれたんだが、どうしようか迷ってる」
「なるほどー。でも迷うよりもまずやってみる方がいいと思いますよ」
「まあ、そうなんだけどさ」
今までいろいろとやってみて、その全部ができなかった。
だからどこかで不安に感じているのかもしれない。今度もダメなのではないか、そう感じているのかもしれない。
そのせいだろうか。とにかくやってみようとは思えない。
「何か思うところでも?」
「いや、まあ……。特に何もないけど」
春浦は僕の方をじっと見つめてきた。
「どうした?」
しばらく見つめてきていたが、何も言わず小さく首を横に振った。
少し不思議に思ったけれど、何もないというのだから気にしないことにする。
「そういえば。今日、棚林先輩と有村は来ないのか?」
壁に設置された時計をチラリと見ると、部活開始時間を十分ほど超えていた。
「部長はいつものやつよ」
「あー、なるほどね」
文芸部の部長である棚林凛花は、彼女の専門である絵画に対して神経質だ。いろいろなこだわりのような物を持っているとでも言うのだろうか。
本人も面倒な性格だと自覚しているようで、時々嫌になると言っていた。けれど、そのこだわりを無視してしまうと描けないらしい。
そのこだわりの中に、その日に思い浮かんだ場所で描かないといけないというものがある。それは毎回バラバラで、しかも思い浮かんだ場所でないと手が止まってしまうらしい。
だから棚林先輩が部室に来ないというのは珍しくも何ともないのだ。
「有村君は風邪で来られないそうよ」
「……本当に風邪か?」
有村深雪という人間は適当な奴だ。髪はいつも寝癖がついているし、鞄の中はグチャグチャだし、まあいいやが口癖だし。見えるところのほとんどが適当に感じられる。
ただ服装だけは適当に選んでいる訳ではないらしい。何でも自分の魅力を充分に発揮させるためには、自分の外見やキャラに合った格好をしなければならないのだとか。
よくわからないけれど、だったら寝癖も直せよと思ったりする。
「まあ、仮病よね」
「有村君はサボり魔ですからねー」
全然信用されていないんだな。少しだけかわいそうに思えてきた。
まあ僕も信用していないけれど。
だって、いつも嘘つくしな。
「じゃあ今日はこれで全員ってことか」
「そうね。でもいつもこんな感じでしょう?」
「まあな」
棚林先輩は滅多に来ないし、有村は部活をよくサボる。ついでに言えば、顧問は部活が終わる頃に少し顔を出す程度。だから基本的に部活動時間は、この三人でいることが多かった。
「さてと。作業に取り掛かりますかー」
焼き鳥を食べ終わったのか、空き缶を先ほどとは違うビニール袋に入れながら、春浦が呟くように言った。
それを合図にしたかのように、僕らはそれぞれの作業に移っていった。
☆
部室内は静寂に包まれていた。聞こえるのはキーボードを打つ音と、シャープペンシルが原稿用紙を滑る音。そして扇風機がプロペラを回すモーター音だけだった。
その静かな空間の中で、僕はスマートフォンを弄る。
随筆というものを本当に僕が書けるのかどうか、その確証のようなものが欲しくて、随筆についてあれこれと調べていた。
というのは最初だけで、気がつくと関係のないものを検索していた。ネットを使った調べ物ではよくあることで、注意をしていても気がつくとやってしまっている。
僕にとっては不思議な現象としか言いようがない。
目が霞んだような気がして、スマートフォンから目を離す。小さく伸びをすると、なんとなく周りを見回してみた。
宮ノ郷はイヤホンを耳にはめてノートパソコンのキーボードを叩き、春浦は細身のヘッドホンを被って原稿用紙に何かを書いていた。
春浦のヘッドホンは少し古いCDプレイヤーに繋がっていて、耳を澄ますとプレイヤーからジジっという音が聞こえてきた。CDプレイヤー特有の機械音だった。
その音は久しぶりに聞いたような気がして、どこか懐かしい気分にさせてくれる。僕が好きな音でもあった。
今では珍しい携帯CDプレイヤー。きっとまだ売ってはいるのだろうし、春浦のように使っている人もいるのだろう。けれど今の場合、もっと小さくてコンパクトな携帯オーディオプレーヤーを使うことの方が多いだろう。
中に入れる音楽もネットで簡単に買えるし、なにより持ち運びに便利だ。だからCDプレイヤーを使っている人はきっと少ないはずだろう。
今でこそまだCDの発売やレンタルをしてはいるけれど、その内CD自体がなくなってしまいそうな予感がする。
なんとなく透明なプラスチックの小さな窓から見える、物凄いスピードで回転を続ける円盤を覗く。白色のCDには赤い線だか文字だかが印刷されているらしく、赤と白の線が走っているのが見て取れた。
「何を見てるのです、遠坂くん」
「ん? あー」
顔を上げると、いつの間にか春浦がこちらを見ていた。頭に装着していたヘッドホンを首にかけた姿は
「いや。そのCDプレイヤー、けっこう傷ついてるなって思って」
「これ?」
春浦のCDプレイヤーには所々に傷が付いていて、それもまた古臭いような見た目をみせていた。
「……昔に買った物だからですかね。小学生の頃からずっと使ってます」
「大切な物なのか?」
「うーんと。というよりはあれですよ、過去の遺物ってやつ? これは伝説(笑)のCDプレイヤーなのです!」
「お、おう。意味わかんねー」
「というのは冗談で」
「だろうな」
伝説のCDプレイヤーとか、ゲームにすら出てこないしな。いや、出てきても困るけれど。
「本当はただなんとなく使い続けてるだけですよ」
「ふうん。それだけか」
「そう、それだけなのです」
そう言った春浦は、じっと傷だらけのCDプレイヤーを見つめているようだった。
何となく使い続けている物というのは、きっと誰もが一度は手にしている。それは意識下ではつまらないものと思っている物ばかりだろう。何となく使いやすいだとか、何となく触り心地がいいだとか。そんな曖昧な理由で持ち続けている場合が多いと思う。
ただそれは無意識下においては全く違う理由であることもある。意識下ではつまらないものと思っていても、無意識下では自分にとって大切な物だと感じているのかもしれない。自覚できなくても、周りから見ればそんな風にわかってしまうこともある。
何となく、また僕も曖昧でしか言えないのだけれど、春浦からは無意識下の思いというものを感じ取れた気がした。
「ちなみに、何を聴いているんだ?」
「今は別れの曲」
「別れの曲?」
「ショパンの名曲ですよ。聴いてみればわかると」
そう言って、春浦は首から外したヘッドホンを僕に渡してくれた。
僕がヘッドホンを片方だけ耳にあてたのを見て、春浦は再生ボタンを押した。カチッという少し硬い音がしたあとで、それは静かに流れてきた。
その音色は美しさと優しさを含んでいて、どこか憂いを帯びたような寂しさを感じさせる。しかし途中で勢いのある、けれど悲しさを孕んだ音を刻み、やがてまた静かな音へと戻る。
確かに聴いたことのある曲だった。
「聞いたことありますよね?」
「ああ。これ、別れの曲っていうのか」
「原題はエチュード10の3。エチュードは練習曲っていう意味ですね」
「へえ、そうなのか」
僕はヘッドホンを外すと、停止ボタンを押した。
その時だった。
ボタンに触れた指先が静電気を発したように、ビリッと痺れた。しかし咄嗟に指を離してしまうほどの痛みはなく、微かに痛みを感じる程度の痺れだった。
何かと思い、ボタンに触れたままの指を見つめる。瞬間、音が揺れた。
まるで水中に潜った時のように、周りの音がボワリと耳の中でで反響する。
『練習曲と――と、みんな意外――顔――るんですけど――』
春浦の声がしたけれど、それもまた反響して聞き取りにくい。
何だ、これは。
そう考えているうちに、今度は頭の中にノイズが走り始めた。不協和音を聴いたように、こめかみの辺りがジリジリと痛みを発する。
けれどそれは数秒で治まった。頭の痛みだけではなく、音の反響も治まっていた。ただ先程痺れた指先だけは微量の熱を放っているように感じられる。
「あ、れ」
間抜けな声が自分の口から零れる。
「どうしたです?」
そんな僕を疑問に思ったのか、春浦が声をかけてくれた。
いきなり間抜けな声を出してしまったら、誰だって疑問に思ってしまうだろう。だから彼女の言葉は当然のことだった。
「い、いや。……ちょっと目眩が――」
目眩がして。そう言おうと口を開けた途端、目前がブラックアウトした。
☆
目を開けると、そこは部室だった。
ブラックアウトする前と同じ状態で、僕は椅子に座っていた。けれど目の前にいたはずの春浦の姿はなくて、それどころか彼女の荷物すら消えていた。
それだけではない。
部室内がオレンジ色に染まっている。窓の方に振り返ってみると、先程まで青かったはずの空が夕焼け色をしていた。
どう考えても時間が進んでいる。
……どういう、ことだ?
「そう言えば宮ノ郷は」
ハッと思い、いつも幼馴染が座る席に目を向ける。
彼女もまた、その荷物と共に消えていた。
「まさか、置いて行かれたのか」
目の前が真っ暗になったということは、今の時間まで意識がなかったと言える。その間に二人は帰ってしまったのだろうか。
……意識を失った割にはしっかりと座っている現状は一先ず置いておくとして、もしそうであるのなら何となく説明はつく。
それ以外に考えられることは、ここが夢の中ということ。現実の僕は気を失って倒れていて、意識自体は夢の中にいる。
現状考えられるのはその二つだと思う。
現実的に考えれば前者なのだろうけれど、はてしてこれはどちらなのだろうか。
改めて部室内を見回してみる。
たとえば前者だとして、いくらなんでも鍵を閉めていったとは考えにくい。どこか、僕が気がつくような場所に鍵を置いていっていることだろう。
けれど、その予想は外れてしまった。
どこを探せど鍵は見つからなかった。
「いや、そもそも……」
そもそもだ。宮ノ郷はああ見えて責任感の強い人間であって、本来は部長の仕事ではあるが、副部長として部員全員が部屋を出たあとで自分の手で鍵を閉める。もちろん鍵を顧問に渡すことも、彼女がやっていた。そして、いつもそうやって部活を終える。
だから宮ノ郷がいる限り、誰かを残して帰るなんてことはないはずだった。
だとするのなら、宮ノ郷と春浦は何かの用事で席を外していると考えるべきだろうか。だけど、一体何をしにどこへ行ったのか。
部室内にある時計を見上げる。時刻は十七時を十分ほど過ぎたあたりだった。
すでに部活動時間は過ぎていた。
何かがおかしい。直感的にそう感じる。
僕は立ち上がると、部屋の扉へと向かう。外に出て、二人を探してみようと思ったからだ。
引き戸を開けようと力を入れる。が、開かない。
「あ、れ?」
何度も開こうと試してみるけれど、一向に開こうとしない。
「……まさか」
僕はあの二人に対して考えを改めるべきかもしれない。やるわけがないと思ってはいたけれど、もしかするとそれは誤りだったのかもしれない。
宮ノ郷と春浦に対して疑いを抱きかけた時、ガチッと鍵が開けられる音が聞こえた。そして開かれる扉。
その先にいたのは、宮ノ郷でも春浦でもなかった。
それは見知らぬ女生徒だった。
栗色の髪をツインテールと見間違えてしまうような、細く長いお下げにしていて。背は僕より少しだけ低い。
最初、僕の胸元に視線を向けていた彼女は、気がついたように顔を上げて僕の顔を見つめてきた。
しばらくの間、僕たちは目を合わせたままで立っていた。
「……誰?」
そう口を開いたのは、お下げの彼女だった。
でもそれは僕のセリフでもあった。
彼女の左胸にある学年章を見てみると【Ⅲ】の形をしていた。
どうやら僕より年上であるらしい。
「ここの部員、ですけど」
「えっと……。入部希望者、でいいのかな?」
僕の言葉に何故か苦笑いを浮かべ、先輩である彼女はそう訊いてくる。
というよりも、何を言っているのだろうか。
「いや、部員って言ってるじゃないですか」
「あはは……。面白いね、君」
何故か変わった人を見るような目を向けられる。
何かおかしなことを言った覚えはないのだけれど。
「じゃあ入部届けを渡してくれるかな。……あでも、こんな時期に入部届けって出せるのかな?」
夏休みだし、とか言いながら彼女は考え出したようだった。顎に右手を当て、その肘を左手で持つという、まさに考えています的なポーズをとっていた。
「いや、だから部員だって……というか、あなた誰ですか」
まるで部長のようなことを言っているけれど、文芸部の部長はこんな人ではない。
そもそもあの人は二年生だ。
「ん? あー、まだ自己紹介してなかったね」
コホンと一つ咳をすると、彼女は改めて僕の顔を見つめてきた。
「文芸部部長の春浦澪。三年生です」
……。
…………。
「はい?」
「どうしたの? 驚いたような顔をして。あ、わかった。部長に見えないって言うんだね。みんなそう言うけど、まさか一年生の子に言われるなんて。失礼しちゃうな、もう」
春浦先輩は、子どものように頬を膨らませた。でもそれはぶりっ子というような感じではなくて、ハムスターが口に食べ物をため込んでいるのを見ているときのような、温かく見守りたくなるような表情だった。
正直、可愛いと思ってしまった。
……ん? というか。
「春浦?」
「あ、うん。そう、春浦」
春浦って……。いや、でも姉妹がいるとは言っていなかったし。
ただの偶然、だよな。
もちろん、僕には言っていないだけかもしれないけれど。
「どうかした?」
「いや、何も。たぶん勘違いだと思うので」
「そう? ならいいけど……。そうだ。君の名前も聞いていいかな?」
「僕ですか? 一年の遠坂稔です」
「遠坂くんね。……それで、遠坂くんはどうして文芸部に入ろうと思ったの?」
「どうしてって……」
「私、部長だし。一応入部理由を聞いておきたいんだ」
どうもさっきから話が噛み合っていない。
この春浦先輩なる人物は文芸部の部長だと言い張っているし、僕が文芸部のメンバーであるということも、冗談か何かだと思っているような反応だった。
一体、どういうことなのだろうか。
ドッキリか何かか。あるいはやっぱり夢の中にいるのか。もしかすると、今までの経験の方が夢で、今が現実という可能性もあるのか?
「春浦、先輩」
「ん? なに?」
「先輩は本当に文芸部の部長なんですか?」
「……え? そうだけど」
春浦先輩は困ったように笑いながら、小さく頷いた。
「僕にドッキリか何かを仕掛けようとしている、とかではないですよね?」
「どういう意味かな? そんなことしてないよ」
気分を害したのか、ちょっと怒っているような表情を浮かべ、彼女は否定をする。
その表情を見て、なんとなくだけれど、彼女が嘘をついているようには思えなくなった。ドッキリという線は低いかもしれない。
だとすると、夢?
あれ、待てよ。たとえば、彼女が思い込みの激しい人間だとしたら……。
自分は文芸部の部長だと思い込んでいて、それが事実であると信じて疑っていない。そう考えれば、夢とかよりも納得ができる。
いやいや、それだと説明できないことがある。
鍵だ。
先程、彼女はこの部屋の鍵を開けた。つまり、鍵を持っていたということになるだろう。
そうなると、この春浦先輩が思い込みの激しい人間だとは言えない。
何故なら、職員室から鍵を借りることのできるのは、部員かまたは顧問だけなのだから。つまり、鍵を持っているという時点で、彼女が文芸部の関係者であると言える。
どちらかと言えば、思い込みが激しいのは僕である可能性の方が高い。むしろそれしか考えられないような気がしてきた。
だとするのなら、僕の知っている他の部員たちは存在しないということだろうか。
「……ねえ、そういえばさ」
そこで、春浦澪が静かに口を開いた。恐る恐るといった感じで紡がれる言葉。
「どうして、鍵のかかった部屋の中に……いたの?」
ゆっくりとした口調で、慎重そうに僕に向かって聞いてきた。
「あ……」
そうだ。どうして僕は鍵のかかった部屋にいたのだろうか。
もし、万が一。僕が思い込みの激しい人間、あるいは長い夢を見ていてまだ寝ぼけているとして。どうやって鍵のかかった部屋にいることができるのだろうか。
本当に、どういうことなのだろうか。
「僕にもわからない、では納得できないですよね?」
実際にそうだしそれしか言えないのだけれど、きっとそれでは納得なんてできないだろう。わかってはいるけれど、ダメ元で訊いてみる。
「……、」
「いやいいんですよ。それがあたりまえだと思いますし」
きっと不審者だと思われているのだろう。自分でもそうなのではないかと思えてくるほどに、僕の現状はおかしかった。
「よくわからないんだけど」
僕をじっと見つめながら、春浦先輩は口を開いた。
「何か困ってるみたいだね」
「……え」
「違う?」
「いや、その。確かにそうですけど」
「じゃあさ、取り敢えず話してみてくれる?」
どんな時にでも安心できてしまうような、そんな微笑みを浮かべて。春浦澪はそう言った。
「でも……。きっと言っても信じられないと思います」
少しドキリとしてしまった心を悟られないように、彼女から目をそらしながら言う。
自分自身ですらわからなくて、信じることさえ難しい。僕はそういう状況にいる。だからきっと、口に出したところで信じては貰えない。言うだけ無駄なような気がした。
けれど。
「いいから。話してみて」
そう言って、彼女は僕を部室に押し戻した。
「さあ、座って」
そして扉を後ろ手に閉めると、僕に席をすすめてくれる。
なんとしてでも、僕の話を聞く。彼女の瞳がそう語っているように感じた。
別に、いいのかもしれない。
話してみて、笑われるかもしれない。馬鹿にされるかもしれない。確かにそんな可能性はあるだろう。
でも。もしかしたら、何か答えのようなものが見つかるかもしれない。
何となく、そんな気がした。
「……じゃあ、聞いてもらってもいいですか?」
「もちろん」
そうして。これまでのことを彼女に話した。事の詳細はもちろんのこと、僕が考えたことも全て。
それほど長い話ではなかったけれど、どう説明したら伝わるのかいまいちわからなくて、考えながら口を動かした。だから少しだけ長くなってしまった。
でも、春浦先輩は最後まで黙って聞いてくれた。そんな彼女の姿勢はどこか安心できて、またその雰囲気が誰かに似ているような、そんな気がした。
☆
「とまあ、そんなわけなんですが」
話し終えた僕は、そっと春浦先輩の顔に視線を向けた。
遠人