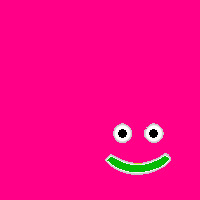猫だって一生懸命に生きているんです。
ある町の郊外、すでに築50年にはなるであろう家が一軒、私の記憶が正しければお婆さんが一人住んでいた…気がする。
その家の庭から白猫が一匹姿を現した。透き通った青い目をしており尾の先端が赤色に染まっている。近所の子供が悪戯してペンキでも塗ったのだろうか、真実は分からない。
そういえば、あの猫。公園をうろついていたっけな。郊外の中にある小さい公園だったか、中央の広い公園だったろうか、餌をもらって喜んで尻尾を振っているように見えた。
全く、猫って気楽でいいよな。
毎日散歩をして、疲れたら木陰で寝転がって、お腹がすいたら周囲の人から餌をもらって、ころんと寝返りをうつだけで、女性も男性も黄色い歓声を上げさせて、ちやほやされるんだから。にゃーって鳴くだけで得なことがいくつでも出てくるんだから。
この前なんて、清楚な女性の服の中に子猫が入り込んで身動きとれずに、けど嬉しそうに、もがいていたけど、俺なんかが同じことすれば犯罪者だ。服から取り出された猫はなーん、なーんって言うだけで撫でられてすべてを許されている。なんとうらやましい限りだ。
もし、俺が生まれ変わるとしたら猫だな。絶対に猫だ。猫になれたら、のんびりと生きて、自由にふるまえる。多くの人にちやほやされて、たくさん子供作ってバラ色の人生を送るんだ。こんな、給与貰うだけに嫌な上司と付き合って将来性の見えない仕事をやることもない。幸せなんだろうな…。
適当なことを考えていたら、白猫が青い瞳を光らせてこちらを見ていた。そして、一言鳴いた。
「あんた、猫だって一生懸命に生きてんだぜ、毎日命を懸けて生きているんだぜ。知った口を利かない方がいいぜ、人間。」
何か、あの白猫。俺に向けて説教を垂れてきた気がする。あ、でも怒っている素振りを見せてないからただの挨拶か…。
俺は時計を見るとあせりだした。もう8時、早く電車に乗らないと遅刻だ。
白猫を後にして俺は駅に向かって走り出した。
そうだ、現実はかくも辛いものだった。このままだと、遅刻して給与が減らされてしまう。
急ごう。
零:早朝の日常
「にゃあ」
「見て。白猫だよ。かわいいー。」
「きゃあ。擦り寄ってくる。かわいい。」
早朝、住宅街の一角に存在する小さい公園。ブランコ、砂場と滑り台、休憩用のベンチ、水のみ場が四角い敷地の四隅に設置してある普通の公園。
登校中の二人組の女子高生が公園の入口にいた白い猫を見つけて、声を掛けたり撫でたりしていた。白猫は人懐っこいのか、先が赤く染まった尻尾を振りながら、二人の女子高生の足に擦り寄ってくる。
「にゃあ」
「かわいいー。」
白猫は女子高生を見上げて一言鳴くと、女の子は黄色い歓声を上げ頬を赤らめる。すると、女子高生の一人がカバンの中から、食パンを取り出した。
「ほら、お食べ。」
女子高生は食パンを半分にちぎり、白猫に渡す。
白猫は「にゃあ」と一言鳴くと、餌を食べ始めた。しばらくの間、何も食べていなかったのか食パンに夢中になってかぶりつく。
そんな白猫を見ていた女子高生たちは幸せな気分につつまれた。
「かわいい。こんな猫飼いたいなあ。でも、お母さんがペット買うの許してくれないんだよね。リナは?」
「犬を二匹飼っているから、これ以上ペットは育てる事が出来ないのよ。」
「そうなんだ。」
「でも、猫も一緒に飼いたいわね。かわいいんだもん。」
「そうよねえ。」
女子高生達はしばらく餌を食べるのに一生懸命な白猫を撫で回し、じっと見つめ、きゃあきゃあ話していた。結構長い時間、白猫と戯れていた。
「サトミ。いけない、遅刻しちゃう。」
白猫をじっと見ていた女子高生の一人が、腕時計をみて驚く。白猫のかわいさに時間を忘れていたようだ。白猫をぽんぽんと軽く触ると、腰を上げて学校に向かって走り出す。
「あ、本当だ。結構やばいかも。じゃあね白猫さん。ちょっと、リナー。待ってよー。」
餌を上げていた女子高生はちぎった食パンを鞄に入れると走り出した。白猫は与えられた食パンを食べるのにすっかり夢中になっていた。
むしゃむしゃと食パンを全部平らげると、白猫は日の光が気持ちよかったのか、のほほんとした面持ちでベンチの下で横になり、体を休める。日の光が穏やかなために気持ち良さそうにあくびをした。
白猫は普通の野良猫だ。青色の瞳を持ち、白猫自身も覚えの無い尻尾の赤い模様が特徴だ。他の野良猫と比べると、少し凛々しくも見えて堂々とした面持ちをしている。
白猫が寝転がってしばらくすると、今度は老夫婦がやって来た。
「あんらま、じい様、猫ですよ。かわええのう。」
「本当じゃあ、ばあさんや。白くてかわええのう。」
ベンチに座ろうとした時に気付いたらしく、老夫婦はベンチの前に屈んで白猫を見つめている。
「にゃあ」
白猫が一言鳴くと、老夫婦は白猫を撫でてきた。白猫は嫌がろうともせず、寝転んだ格好をやめようとしない。
「人懐っこいのう。ほら、ばあさんや。お饅頭でもあげないかい。」
「そうですねえ。」
老婆は持っていた手提げ袋から一つ饅頭を取り出した。餡の部分が少ないのかおばあさんが饅頭を握ると、ふにっとへこんだ。柔らかくてとても美味しそうな饅頭だ。
「ほいじゃあ、お食べなさい。」
老婆が白猫の前に饅頭をあげると、白猫はにゃあと一言鳴くだけで、丸くなった体を起こそうとしない。どうも、先ほど女子高生からもらった食パンでお腹がいっぱいだったようだ。
「食べないねえ。お腹いっぱいなのかえ?」
「ばあさんや。猫にだって事情はあるもんよ。こんだけ、かわええんだ。他の人の餌で満腹なんじゃろうて。」
「それは、残念じゃあ。」
「置いといたら、食べるんでねえか。」
「そうじゃあね、置いておきましょう。」
老婆は白猫の前に饅頭をおいて立ち上がる。それにあわせて、老人も立ち上がる。
「ばあさんや、行こうかね。猫さんの邪魔しちゃいかんし。」
「そうじゃね、じい様や。じゃあね、猫さん。」
二人は白猫に別れを告げその場を離れる。しかし、白猫はまだベンチの下で丸まって気持ち良さそうにあくびをした。
しばらくベンチの下で丸まっていた白猫は立ち上がり、砂がついた饅頭を口にくわえて公園を後にして歩き出した。
いつの間にか、公園には誰も居なくなりどんよりとした雲が空を覆っていた。
猫が離れてから数十分が経つと、小さい粒の雨が降り出してきた。公園は雨によって、肌色の地面が茶色に染まり、映えていた草木から歓喜の匂いが立ちこめた。
一:老婆の猫屋敷
ここは、ある家屋。築六十年は経つであろう木造の家だ。あちこちと傷やら染みやらついてはいるが、雨風をしのぐには十分な家であった。1階建てで、玄関から奥に廊下が伸びており廊下の右側にはトイレと風呂場が設置されている。廊下の先には台所に繋がっており、奥に台所、ちゃぶ台のある部屋、寝室と三つの部屋が存在する。
廊下を抜けると台所に出る。床はベニヤ板が敷き詰められているが、たくさんの傷がついていて、かなり傷んでいる。流し台の隣には古い冷蔵庫が置かれており、上にはコンロが設置されている。コンロへ繋がるゴム製のガス管はネズミがかじったと思われる大きな穴が開いており、使い物にならない。中央には茶色のいすと物を置く面に白のベニヤ板が張られた濃い茶色のテーブルが置かれている。調味料をこぼしたのか、白い面の半分以上が黒く汚れていた。テーブルの上には雨漏り対策の金ダライが置かれている。
ガラス障子を通り抜けると二つ目の部屋が存在する。畳張りの和室でいわゆる団欒の間とでもいう場所だ。真ん中に傷ついた木のちゃぶ台が置かれており、四隅の一角にブラウン管テレビが置いてある。コードはやはりネズミにかじられて使い物にならない。コードの近くに黒いこげ後が見えることから、コードをかじった際にショートしてしまいネズミが黒焦げになってしまったと考えられる。テレビは今ではただの黒い箱と成り下がっている。部屋には座布団が散らかっており、テレビに対する一角には座布団が5枚ぐらい積まれている。どの座布団も穴が開いており、綿が飛び出して座布団の役目は持ち合わせていない。
テレビの横には襖があり、その襖をくぐると寝室に辿り着く。こちらもまた畳張りの和室である。寝室の真ん中には布団が一人分敷いてあり、周囲には棚だったり、箪笥だったりが設置されている。布団の頭のほうに仏壇と小さい御地蔵さんが三つ祭られている。襖の上には神棚を置く場所があるのだが、あまりにもボロボロになってしまったために今は何も乗っていない。部屋には窓がついており、昔ながらの磨りガラス仕様となっている。野球ボールがぶつかったのか、端のほうが欠けて小動物が通れるほどの穴ができている。
この家の主は、戦争が終わって十年後、富豪の夫婦が立てたものらしい。当時は夫婦ともに25歳、働き盛りの二人だった。
年代が進むに連れて新しい機械が生活を色づけ、夫婦は豊かな生活を送っていた。家ができ幸せに8年ほど生きた二人の間に、娘が二人、息子が一人できた。まさに幸せの絶頂期に会った。
ところが、息子娘が小学校に上がった頃、飲酒した運転手が乗る暴走トラックに跳ねられ三人の子どもの命が奪われた。子どもらの死によって、精神的に過度の負担を背負った夫は病にかかる。仕方なく早期退職を余儀無くされ、病院に通いつつ治療に励んだ。保険金やら退職金やらでお金に余裕はあるものの、生活に色が無く質素な生活を余儀無くされた。
妻の看病の結果、五十が峠と思われた夫の命は六十三まで伸びた。夫婦の親は他界、親戚は遠い地に住んでいたため、大きな葬式は行わずに火葬だけしてもらい、妻がお経を読んで供養をしただけで清ます事にした。
そんな妻は、残されたお金で日々を過ごしていたが、贅沢はできなかった。
一週間分の食事を買い、自炊して食べるといった日々を過ごした。しかし、寂しさに耐えられなかったのか、妻は猫を家に招きいれ、一緒に食事をする習慣がついた。最初は一匹、二匹だったが、いつのまにか十匹ほどの猫に囲まれながら食事をすることとなった。近所から、猫の匂いがきついとか、猫の鳴き声がうるさいと蔑まれたが妻は何も気にせず、過ごしていた。
そして、その家屋は近所から「老婆の猫屋敷」と言われるようになり、だれも近づかなくなっていった。
窓ガラスの割れ目から、白猫は饅頭を加えつつ猫屋敷の寝室に入った。入ると白猫は布団で寝ている老婆の枕元に饅頭を置いた。
「ご主人様、食事もって来ました。」
白猫が一言鳴くが、老婆は反応しない。
「今日も起きないか。ずっとこんな感じで起きやしねえ。月の満ち欠けが一回と半分ぐらい変化するほどの歳月が流れているというのに。心配だ。是非起きて元気な姿を見せてほしいものだ。」
白猫が老婆の顔をなめる。元気になってほしいとのおまじないだろう。そんな白猫に一匹の三毛猫が襖から寝室に入ってきた。
「おお、赤助じゃあないか。いつ戻ってきたんだい。」
赤助と呼ばれる白猫は三毛猫に返答する。
「ああ。雨が降りそうだったから、雨宿りするため戻ってきたよ。」
「そうかい。まぁ、ちゃぶ台でくつろぎましょうぜ。」
「ああ。行くよ。」
三毛猫が出て行くと赤助は襖をくぐり、丸い物置(ご主人様がちゃぶ台といっていたので、ちゃぶ台と呼んでいる。)のある部屋へと入っていく。外から湿った空気が流れ部屋を包み込む。
ちゃぶ台の部屋(特徴が思いつかないのでちゃぶ台の部屋と呼んでいる。)に入ると赤助の他に4匹の猫がくつろいでいる。ちゃぶ台の上に先ほど赤助に話しかけてきた三毛猫が、そばの座布団の上に一匹ずつ黄土色の虎猫と黒猫が、高く積まれている座布団に首輪がついた毛並みがよく珍しい模様をした灰色の猫がいた。赤助は黒い四角の物体(ご主人様がテレビと言っていたのでそう呼んでいる。)に飛び乗り、物体の上にまるまった。
「赤助ー。そんなにテレビの上が好きかい。俺っちは好きになれねえな。そいつさ、何か変な波動というか、感覚というか…。気味の悪い感じがするから嫌いでさあ。」
三毛猫が話しかけてくる。
「ネズミが紐をかじった後、嫌な感覚が消えたから平気だ。先入観で判断するのはよくないぞ、八六。」
どうやら三毛猫は八六と呼ばれているらしい。
「そうかい。まあ、俺っちはちゃぶ台でいいよ。」
すると、そばに居た黒猫が話し出す。
「八六さん、もう少し知恵をつけないと、人間に捕まるわよ。」
「うっせいな、お桃ちゃんよ、俺っちは生まれた時から、江戸っ子でぃ。」
「江戸っ子って…。人間ですら使っていない言葉でしょうに。」
八六は立ち上がり毛を逆立てふーっと威嚇する。相当気にしている事を言われたようだ。気を遣うように、赤助が話しかける。
「おちつけ、八六。しょうも無いことで怒っていると、早死にするぞ。」
逆立てていた三毛猫は、落ち着きを取り戻し机の上に座り込んだ。すこし恥ずかしいと思ったようで、黒猫のお桃に鳴く。
「俺っちが悪かった。」
「いいえー。」
お桃は、立ち上がるとガラス障子の割れ目を通り抜け台所に向かった。
その様子を見届けた赤助は部屋全体を見渡す。座布団の上で優雅に寝そべっている毛並みの綺麗な灰色の猫を見つけて、八六に尋ねる。
「おい、八六。あいつは誰だい。」
「さぁ。」
ここは猫屋敷。どんな猫がいても迎え入れる。
赤助は老婆が食事を与え始めた時から居るので、屋敷内の猫に対して敏感になってしまう。
どうも赤助には首輪の猫は癇に障ったらしい。さらに首輪には大きな光る石が付いており、異質な雰囲気はさらに異質なものへと変化した。すると、一ヶ月前から居候となった虎猫が鳴いた。
「今日、ご主人様から逃げてきたんだとよ。小さい人間に毛やら尻尾やらを強引に引っ張られて、腹を蹴られたそうだ。毎日体に痛みを伴う仕打ちを受けるので、耐え切れなくなって家から逃げたんだとさ。逃げているうちに、雨の匂いを感じ取り雨宿りしたいと入ってきたんだと。」
「ほう。よく小鳥も許したものだな…。」
「まあ、あいつのご主人様に似てしまったのか高く座っている感じだが、話してみたら悪い奴じゃなさそうだと分かったから。いいかなと思って。」
「ふう。まあいいか。」
赤助は安堵のため息をついた。別段、この屋敷を荒らしに来たわけでもなさそうだ。じゃあ、問題ないかと納得をし、さらにあたりを見渡す。
「おい、小鳥ちゃんよ。お竜は何処いったんだ。姿が見えないけど…まさか…。」
最近、愛を語らった灰色毛の虎猫のお竜が気になるところだ。赤助があたりを見回していたのはそれが理由だった。
「お竜かい?多分、オメデタだったんじゃあないかい。でも…、もう生きていないんじゃあ無いかな…。」
赤助は、小鳥の様子がおかしく体が震え出したので、何か不穏な事を知っているようだと感じ取る。意識を緊張させて小鳥に質問を投げかけた。
「どういうことだい?」
震える体を抑えながらも、赤助の質問に答える。
「昨日、寝ていたら夢に出てきたのよ。人間が乗る光る鉄の箱があるじゃあないかい?車っていうのかえ。その黒いのに轢かれたらしくってね。報われ無い心だけが私のところに子どもを引き連れてきたんだよ…。」
「そうか…。」
「そうなのよ。さらにさ、さっき寝てた時にも、お竜が来てね。私に触れた人間がいるから、そいつを道連れにしてやるって言って私から姿を消して行ったよ。かわいそうなもんだよ…。」
「そうか…。」
人間の身勝手さに怒りを感じ、お竜に悲しみを感じたが不思議と涙は出なかった。男と女の性別の差なのか、自分が猫だからか分からないが、深い感情移入はなんとなくすることはなかった。
仲間は食べられたり、人間に捕まったりと、毎日死に際に立っているのである。いちいち泣いてもいられないのが猫の世界なのだ。
「成仏できるといいな。」
「そうさね…。」
話が終わると八六が立ち上がり、
「はぁー、悔しいねー。」
と一言鳴き、台所へと向かった。
二:平日の市営公園
ここは広々とした公園の一角。赤助は噴水のある水辺で尻尾を水たまりに浸し、暑さをしのごうとしていた。日当たりも良好…。だが、日差しは強い。自分が生まれて、最初の暑い季節はそんなに暑いと感じなかったが。ここ最近、日差しが強くなったのを感じる。人間はこの日差しの強弱を感じ取る事ができないらしい。
実際、赤助が見ている世界では人間が一番偉いはずなのに、生物としてはとてつもなく鈍感な生物らしい。猫でも気付くような異臭を感じ取って犬が吠えているというのに、何事かと思うだけで犬の前を素通りする。地面全体から危険な波動を感じ取り逃げ出すものの、人は逃げようともせず変わりない日常を過ごしている。そのあと大きな地響きが来て、逃げ惑う人間の姿がおかしいくらいだ。空を飛ぶ鳥でさえ感じ取っているのに…。なんとも不憫な生物だ。
人間の鈍感さはつくづく哀れに思える。自分達が作った機械から発している変な波動さえ感じられないようだ。たまに、あの波動で頭痛がするというのに…。本当に鈍感な生物のようだ。
特に人間が持っている変な板だ。あれほど、気持ち悪いものは無い。あの周囲には必ずといっていいほど不快な波動を感じ取る事ができる。それにもかかわらず、顔に近づけ光を見ていたり、耳に当てて独り言を言っていたり、落としたら慌てた顔をして大事そうに拾ったりと、理解に苦しむ事が多い。
そもそも、光や音を発する板という時点でおかしな話なのだが。
だが、人間にとってはあのうすい板が大事らしく、壊れたら一瞬にして、どんよりとした青にも黒にも近い波動を出してくる。哀れな生物だ。
なにげないことを考え、のらりくらりと過ごしていたら、いつの間にか日が落ちていた。夜になろうとしている。赤助はそろそろ屋敷に戻ろうと考えた。お竜が亡くなってから日がもう日が三回沈んだ。残念だが気にしていても仕方が無い。今日こそご主人がは起きてくれることを祈ろうか。
この大きな公園は盛況の時と閑散の時があり、閑散としている時が五回続くと盛況になり、盛況な時が二回続くと閑散になると言ったサイクルで人間の満ち欠けがある。
今日は閑散な日で、日向ぼっこ中に触ってきた人間は男と女の一組みの『つがい』ぐらいだった。盛況の日に近づけば、人間が俺を触ってばかりいるため、疲れが溜まってしまうので出来る限り避けている。
赤助に触れてきた『つがい』なのだが、しばらく赤助を撫でながら間に挟み、話をした後に手を繋いで去っていった。二人は黄色の幸せな波動に満ちており、とても幸せそうだった。
今の赤助の気分の問題なのだろうか、あの二人にほんのりと殺意を覚える。
まあいい。今日は食事が手に入らなかった。屋敷付近をうろつく虫やネズミを食べて今日は凌ごう。
「ごめん、ごめんね…。飼ってあげたいんだけど…。お父さんがね、お母さんがね…。」
小学生だろうか。公園の門の付近で花柄のワンピースを着た女の子がしゃがみながらダンボールに向かって話しかけている。
ダンボールの中には子猫が3匹入っていた。毛並みは白、虎、虎、と親のどちらかの血を受け継いでいるようだ。。今にも泣きそうな顔をして子猫を見つめる。子猫たちは女の子が持ってきたようだ。
「ごめんね。お腹すかないように牛乳とパンを持ってきたから。」
女の子は布の手提げ袋から、深いお皿と浅いお皿を取り出し、深いお皿に牛乳を、浅いお皿に耳を取り払った食パンを置きダンボールの中に置いた。
「にゃあ」
「にいにい」
「にゃーん」
子猫は食事に目もくれず、女の子を見つめる。三匹の子猫は目を光らせながら、お母さんは何処?と聞いてくるような雰囲気で、目の前の少女に訴えている。
「そんな目で見ないで…。ほんと、ほんとうに…。う、うう…。」
女の子は子猫を見ながら、涙をこぼした。
飼っていた猫がしばらく行方不明になったと思ったら、子どもを連れて目の前に現れた。女の子はとても嬉しくてはしゃいだのだが、生活的に余裕が無いからと両親によって仕方なく捨てる事となった。
悔しさと悲しさでいっぱいになった女の子は、目に涙を溜め込みながら子猫をじっと見つめる。
女の子が子猫たちをしばらく見つめていると、「にゃあ」と鳴きながら白猫が近づいてきた。女の子は涙を腕で拭くと、近づいてきた白猫を撫でた。
「にゃあ」
「お前が、この子たちの親…。じゃあないよね…。シロは白いし、どう考えても相手は虎猫だし…。疑って、ごめんね。」
「にゃあ」
猫は顔を女の子の足にすりすりと擦りつけた。
泣いている女の子は白猫が空腹なのだと気付き、持っているパンを白猫に与えた。
「そうだよね。自分のことで精一杯だもんね…。はい、パンだよ。」
白猫は女の子からパンを受け取ると、むしゃむしゃとパンを食べた。
女の子は、その姿を見て、胸をえぐるような感覚にとらわれた。自分のやっていることがどれだけ残酷な事なのかを幼いなりに感じ取ったようだ。
「ごめん…」
白猫とダンボールから一歩後ずさる。
「ごめんね」
さらにもう一歩後ずさる。悲しそうな目でダンボールを見つめる。
「本当に…ごめんね!」
白猫とダンボールに背を向けて一目散に走り出す。他の人に目もくれずに猫を放置していく罪悪感と早くその場から逃げ出したい焦燥感に煽られて、急いでその場を離れていく。
パンを食べ終えた赤助は紙の箱の中を覗き込んだ。するとまだ小さい白猫と虎猫二匹が一生懸命鳴いていた。
「おかーさん」
「お腹すいたよー」
「どこにいるの?」
三匹の猫は節々に親を求め、母乳を求めている。
「生まれてから、まだ月が新月から半月になったぐらいの時しか経っていないだろうに…。まだ母乳が恋しかろう…。」
子猫は赤助を見て反応する。
「おかーさんはー」
「おかーさんはー」
「おかーさんはー」
返答に困るので赤助は子猫の声を聞き流して、紙の箱の中に置かれている牛乳と食パンを見つめた。
「つん、とくるこの匂いは……牛だな。たまに人間が飲み物としてくれる乳だな。生まれたばかりの子猫に牛の乳を与えるとは…。人間ってのは、馬鹿なのだろうか…。俺ぐらいの体つきにならないとあれはきつい。」
人間からはある種の波動が出ている。悲しいときは青い波動、幸せな時は黄色い波動、悪意に満ちた人間や死にそうなぐらいに悩みを抱えて苦しんでいる人間、これから死のうと考えてる人間は気持ち悪い黒い波動を出している。多少ではあるが赤助はこの波動の移り変わりを感じることが出来る。
先ほどの小さい人間は、悲しみに満ちており死にそうなぐらい悩んでいたのだろう。暗い青の波動を出していた。自分の意思で捨てたわけでは無いことは分かるのだが。
「お乳がほしい」
「お乳がほしい」
「お乳がほしい」
捨てられた子猫が不憫に思えてきた。しかも敷居が高い箱の中に入れるとはさらに酷な話だ。この体格では、この箱から抜け出す事すらできないではないか。
「どうしようか…。小鳥でも連れてこようか…。最後に子どもを産んでから、発情しなくなったって言ってるが、まだ母乳は出るはず…。でも、なぁ…。どうやって箱から救おうか。」
あれこれ考えているうちに、この周囲は危険な匂いが発している事に気がついた。どうも、この場に居たら、自分の命が危ない事を悟った。
「仕方が無い。逃げよう。」
そう考えた赤助は箱から飛び降り全力で逃げた。
後ろを振り返る事ができないが、森の木の間から梟か木菟といった鳥が子猫に襲い掛かる音が聞こえてくる。一匹の子猫が無残な断末魔をあげた気がする。
もうあの子猫たちの命はないだろう。何と人間は酷な事をする。すまない、子猫たち。
「おかーさん」
「おかーさん」
「」
赤助は猫屋敷に戻ってきた。家に帰る前に食料にありつけたことから、食事を捕まえる心配が無くなった。全力でこの家に向かっていたため、喉が渇いている。とりあえず、台所に向かう事にしよう。
台所に入ると、机の上に鉄のタライが置かれており、そこに雨漏りによって垂れてきた水が溜まっている。なぜか、人間が飲んでいるような銀の管から出る水とは違って、透き通っていておいしい。先にお桃が水を飲んでいた。赤助は向かいにすわって、反対から水を飲む事にした。
「いやあ、屋敷の近くの木の下でさー、茶色羽の虫がたくさん居てねー。五匹は捕まえて食べちゃった。」
お桃の鳴き声がとても嬉しそうに感じた。どうも、ここ最近のお桃の成績がよくなかったため、空腹の日が続いていたようだ。
「ああ、あのコロコロコロって鳴く虫か?」
「あれじゃないよ。ほら、長い毛が二本頭から生えて、かさかさ動く奴よ。」
「あれか。うーん、おいしいのか?」
「いやぁ、意外といけるわよ。今度食べてみなよ。」
どうもあの茶色羽の虫が苦手で食べようという気にはなれなかった。八六も意外といけると言う感想を言ってたっけ。本当においしいのだろうか…。生きているうちに口にすることは無いだろうな。
「今夜は、八六いないんだな。」
「ああ八六かい?あいつなら、女の尻追っかけていっちまったよ。」
「御盛んなこってい。」
女の盛りの泣き声を聞いた時、男はいてもたってもいられなくなる。八六の気持ちは良く分かるので、何もいえないものだ。そう考えると水を飲み喉を潤す。
三:シャロンという猫
今日もまた、ご主人様が目覚めない。
体が冷たいが、ハエがたかったりとか変化が無いところを見ると、まだ目覚める可能性はあるだろう。
ご主人様が作ってくれる『ねこまんま』がどうしても恋しい。赤助はご主人様の顔を舐めるとちゃぶ台の部屋へ移動した。
ちゃぶ台の上に気品のある灰色の猫が座っている。どうも、人間にはシャロンと呼ばれていたようで、赤助たちもそう呼ぶようになっていた。
「シャロンさん、どうしたんでい。とうとう、断食に耐えられなくなって狩りでもするか。」
シャロンは鼻を清まして、赤助に返す。
「フン。あんな野蛮なもの食べていられませんわ。まぁ、赤助が持ってきた甘い食べ物、あれはおいしかったですわ。」
「ああ。ご主人様の隣に置いたのに、なくなっていたのはお前の仕業だったのか。」
ご主人様用に持ってきた饅頭を食べてしまうとは、図々しくも感じるが事を荒立てるのは好きでもないのであきらめる。
このシャロンという女、なかなかの偏食家である。
普通、猫が饅頭を口にすることはない。よほど腹が減っていたと見られる。
「あれは、人間が食べておいしいと思えるものなのに…。物好きだなぁ。」
「え?あれは人間専用でしたの?そんな風には全然見えませんでしたわ。」
「しっかし、本当に人間の作ったものを好むなぁ。缶の筒に入った魚の練り物や人間が切り刻んだ魚の塊だったり…。牛の乳の塊だったりと偏食過ぎるだろ。」
「よくわかりませんわ。第一、虫やネズミだなんて逃げ出してから知りましたし、そんなもの口にしたことすら無いですのよ。気持ち悪くて口にするのも嫌ですわ。」
人間に飼われると自分も人間と勘違いしてしまう事は動物の中では、よくあることを赤助は知っていた。
犬だって自分の中で優劣を勝手につけて、人間に逆らうといった話は良く聞く。
人間に噛み付いて嫌われたがために捨てられたと思しき犬は、そこらじゅうにうろついている。あの生物の悲しい習性である。
同じようにシャロンは人間に感化されすぎて猫本来の性質を忘れてしまっているようだ。猫は自分で餌を捕らえて食べる生き物だ。それができなければ人間に飼われるしかない。きちんと理解できてるか疑問に残る。
「なあ、シャロン。お前は人間のそばで生きたほうが幸せになるんじゃないかい。」
「赤助、私は人間にいたぶられて、家にいるのが嫌になって逃げてきたのですわ。またあの地獄に戻れっていいますの?」
「そういうわけじゃないんだがな、姿は猫でも心はもう人間と同じ考えになってしまっている。」
シャロンはちゃぶ台から下り、台所へ向かおうとした。
「ごめん遊ばせ。もうあの頃には戻れないですわ。もう覚悟してますもの。」
「そうかい。でも、猫として生きるなら、その考えは捨てたほうがいい。自分で食事を狩って食べれないようじゃあ、そこいらの犬に食われるだけだからな。」
「お気遣いありがとう、赤助。でも、私は私ですわ。」
シャロンは台所に水を飲みに行った。首についたキラキラする石が反射で光る。赤助は眩しいと感じたので目を逸らす。
「まあ、自分のことは自分で決めないとな。」
赤助はテレビの上に飛び乗り、体を休める。
猫の一生に人間が関係してくるなんてご法度のような気がするのだが、どうしても人間は関わろうとする。
必要だと感じたら、首輪をつけ家に閉じ込め、人間の生活を強要する。不必要だと感じたら、首輪を取り天敵がたくさんいる公園だったり川沿いだったりと捨て去る。噂によると人間の中には町の中をうろついている犬や猫を捕まえては意味もなく殺したり、犬や猫の亡骸を集めては何処かに運んだりする者がいるらしい。別に捕まった猫が人間に危害を加えているわけでも無いのに…。悲しい話だ。
人間によって、仲間が殺される事はよくある。この屋敷にやってきた猫の中にも人間に捕まり殺された猫はたくさんいる。小鳥がいうには、屋敷にやって来てから人間に殺されたという彼女の知る猫は、お竜と腹の子含めて十匹は超えると言っていた。悲しいものだ。
眠りに付いてから目覚めたら、日が沈んで月がはっきりと見える時間になった。シャロンがふらふらとちゃぶ台付近を歩いている。どうも空腹も限界に来ているようだ。このまま放って置くと死んでしまうかもしれぬ。見るに見かねて赤助が声を掛ける。
「シャロン。出かけるぞ。」
「赤助さん…、どこに…行こうと…してますの…。」
シャロンの鳴き声がいつに無く弱々しい。
「食事を求めにだよ。魚形の肉だ。安心しろ。」
「本当に…、魚ですの…。」
「ああ、道も覚えておくと良い。今からいけば丁度良いから。」
ふらふらする頭で考えた結果、シャロンは赤助の後をついて行く事にした。二匹の猫は猫屋敷を飛び出し夜の街を歩き出した。
「ぐはー。今日も売れ残っちまった。どうしたものかねー。」
スーパーの魚売り場で店長が叫んでいる。閉店間際の最終確認にやって来た警備員が店員に話しかける。
「半額なのにね。こうも売れないなんて…。また破棄ですかい?」
「ああ、ったく。もったいねえなー。かと言って、従業員だけで持って帰って処理しきれる量でも無いしな…。」
「今日は十分に貰ったでさ。から揚げ系が余ってるから、今日は酒が進むねぇ。」
店長は閉店間際の売れない魚を見て、しばし考えたが意を決したらしく、ぐわっはっはっはっと甲高い笑い声をだす。
「売れなくてついに壊れたか。」
「違うって。売れないなら、しゃあない。あいつらにやるか。」
「あいつらってえと、誰だい。」
「家出している子猫ちゃんたちにでも分けるんだよ。」
「はー、それで今夜も御盛んに攻めるんですか。そんなことできるなんて羨ましい。」
「え?違う違う。本当の子猫ちゃんたちだよ。そんな浮いた話なんてありますかい。捕まったら犯罪でさあ。」
「ははは。そんなものだと思いましたよ。」
毎日売れ残る食材の処理にはどうするかでいつも困っている。そこで、同じ生ごみなら食べてもらった方がいいと考えが信条として店長は日々過ごしている。
「はぁ、商売だからね。駅前に来ていたあのおばあさんに上げても良いんだけどねぇ。」
「おばあさんて誰よ。」
「ほら、駅に来ていつも日向ぼっこしていたおばあさんだよ。最近めっきり見なくなったからねぇ…。」
「ああ。駅付近で、寝っころがっていたおばあさんか。そういえば見ねぇな。元気にしているのだろうか…。」
「たぶんな…。」
店長は閉店作業を終えると、今日廃棄予定の魚をビニールの袋一杯にして、スーパーの裏の空き地に移動する。空き地には今か今かと待ち構えている猫が7匹ほどいた。黒猫3匹、三毛猫2匹、たぶん外国産と思われる猫が2匹である。店長の姿を見るとなぁなぁと鳴きながら寄ってくる。
「おお、また一匹増えたのかね。どっから嗅ぎ付けてくるのか分かんねえが、嬉しいねぇ。たくさんあるからお食べ。」
そういうと店長はビニール袋から、魚が入ったトレイを開け、中身を猫の群れに向けて投げ飛ばす。
「ほうれ、魚だぞー。」
放り投げられた餌目掛けて猫が飛び跳ねる。落ちる前にキャッチして食べる。
「ははっ。威勢がいいねぇ。ほら、次だぞ。」
店長はまたビニール袋から、魚を取り出し上空に投げる。猫は魚を取ろうと必死にジャンプし餌を取り合う。魚は丸一匹を投げる時もあれば、刺身を投げる時もある。どんな魚であろうと猫はジャンプして魚を取る。
「全く、お前らはのんきで良いよな。笑えてくるぜ。」
猫が餌を取ろうとジャンプする光景が、猫が踊って見えるようで楽しくなってくるようだ。
店長は気分が良くなり、つい笑いがでてくる。
「はっはっはっ、楽しいな……。ん?」
「にゃあ。」
餌を投げつつ鳴き声のほうを見ると、白猫と灰色のシャム猫が近づいてくる。
「おお、またお前か。清ました顔してやってくるねぇ。」
再会した友人のように話しかける店長は、袋の中から鮪の刺身と、秋刀魚一本を白猫の方に投げる。
「へへっ。今日は彼女を連れてお出ましかい。間違いない。俺が見込んだイケ猫だ。その綺麗な猫はお前の彼女かい。おめかししたお嬢様ってところか…羨ましいなぁ。さっすがお気に入りの猫だ。」
そういうと、鰤と鮭の切り身と帆立の刺身、秋刀魚一本を白猫と宝石の付いたシャム猫に放り投げた。
「にゃあ」
「へへっ、お前は特別だぞ。他の猫に気付かれないように食べなよ。」
そういうと、店長は猫の踊りを作るため売れ残りの魚を空き地に投げ飛ばす。白猫とシャム猫は美味しそうに鮪と鮭の切り身を食べだす。
赤助とシャロンは図体のでかい縦縞の人間から貰った鮪や鮭の切り身を食べていた。
「ここに来るとたまに餌にありつける。毎日いるわけじゃないから、たまに来るぐらいだが、確実にいいものが食える。偏食家のシャロンにとって、美味しい場所だよ。」
鮪の刺身にかぶりつきながらシャロンが鳴く。
「本当良く見つけましたわね。こんな場所。あの屋敷から離れていたじゃないの。」
鮭の切り身を食べながら、周囲をうかがう、図体のでかい人間は空き地の猫に夢中になっている。とりあえず、あの猫達はこっちに来ないようだ。
「遅れてくると、なぜか俺にだけ魚類の餌をくれる。贅沢したいなと思ったときとか、近くを通りかかった時にしか来ないんだがな、お前もこんな場所を探して転々とすれば食料には困らないだろう。」
シャロンは鮪の刺身がなくなると、今度は鰤の切り身にかぶりつく。
「探さないといけないのですの?他にも教えてくださらないかしら?」
「人間の手から離れるなら、何とか生きる知恵を身につけないと生きていけない。全部教えるよりか、自分で探すしかないと感じたほうがいい。」
鮭の切り身を食べ終えると、シャロンの食べている鰤の切り身に手をつける。
「そうね。分かったわ。ありがとう。」
赤助は鰤の切り身を食べながら、気配を感じ取る。どうも、図体のでかい人間の魚袋が少なくなっている。
「そろそろが潮時か…。魚を加えてここから離れるぞ。」
「え、まだ貝が残っていますわよ。」
「あの人間が立ち去る。立ち去る前に、ここから離れないと空き地にいる猫集団に襲われてしまうぞ。」
シャロンは鰤を食べ終えると空き地のほうを振り向く。禍々しいオーラが放たれているのに気付く。
「もたもたしていると、あの猫達に何をされるか分かったものじゃない。」
「そう…ですわね。分かりましたわ、逃げましょう。」
赤助とシャロンは与えられた秋刀魚を一匹ずつ加えると全力でその場を離れた。
二匹の猫が秋刀魚を加えて町の中を闊歩する。暗い夜道を通り、車を避けながら、屋敷を目指す。
「赤助。」
「ん?どうした?シャロン。」
「スリルがあって楽しいですわね。」
「そうか?」
「ええ、楽しいですわよ。」
「そうか。」
シャロンが猫屋敷で見せたことのない良い顔をしている。そうとう楽しそうだ。
人間の生活に嫌気が差したのと同時に、生きる気力が奪われていたのだろうか。いまのシャロンはとても輝いて見える。俺にとっては日常だから、特別な感情は持つことはないのだが、彼女の中では新鮮に思われたに違いない。
屋敷までの距離は遠く途中で横取りされそうな気配を感じたので、途中で見つけた車の溜まり場で食べてしまう事にした。車は人間が中に乗っていなければ、これと言って害になる事は無い。その車の下で自分が運んできた魚を食べる事にした。
「美味しゅうございますわ。魚がたくさん食べられるなんて…。」
「シャロンの言う魚の塊とかでは無いが、狩りをせずに魚が食える数少ない場所だ。」
赤助とシャロンは目の前にある秋刀魚に夢中にかぶりつく。
「赤助は、いろいろ物知りですのね。八六なんて、食えりゃあ何でもいいって屋敷の周りをぐうたらしていますのに。」
「まあ、八六はのんびりしてるからな。自分に忠実なのだよ。」
「でもあなたはしっかりしていますわ。」
「猫だって、黒から白までいるさ。良し悪しは猫それぞれだ。」
「うふふ。貴方なら私の王子様として見てもいいですわね。時期が着たら貴方の子どもを作りたいですわ。」
「そうか。その時になったら相手してあげるよ。」
「嬉しいですわ。よろしくお願いしますね。」
秋刀魚を食べ終えると、屋敷を目指して人間が作った光の中を縫うようにして進み、暗闇を駆け抜ける。
四:失踪した三毛猫
今日もまた黒いテレビの上で寝ている。シャロンは外をぶらぶらとしているのか見当たらない。何処へ行ったのだろうか。今日はお桃と小鳥が顔を洗いながら鳴いている。
「そういえば、今日も八六来て無いね。」
「小鳥どうしたんだい。八六に気でもあるのかい?」
「そういうわけじゃないんだけど…八六に何かあったのでは無いかと思ってねえ。赤助は何処に行ったか知ってるかえ。」
「いや。知らないな。」
「そうかえ。赤助も知らないなんて…。いつもなら、この辺をぶらぶらとしているはずなのにねえ。」
「あいつはしぶといから、心配ねえよ。何処かで生きていると思うけどな。」
八六が姿を現さないなんて不思議だが、きっと女の尻を追っているに違いない。まだ日が二回しか沈んでいないし、猫なら良くある事だ。また元気に顔を出してくるだろう。
でもまあ、探してみるのも楽しいか。赤助は立ち上がり、猫屋敷の出口へと向かう。
「おやまあ、どっかへ出かけるのけ?」
お桃の体を舐めている小鳥が離しかけて来る。
「ああ、散歩しに行って来る。」
「気をつけないな。」
「ああ。」
一言鳴くと、赤助は屋敷を後にする。
さて、何処に行こうか。赤助は近くにある小さい公園に来ている。八六のことも気になるがシャロンも今日は見かけていない。まあ、二人とも探しに行くことにしよう。日が雲で隠れていてどんよりとしているから、早く屋敷に戻りたいところだ。早いこと見つけてしまおう。
「なあ、雨宿りができる場所知らねえか。」
突然、猫の鳴き声が聞こえてきた。どうも、滑り台近くから聞こえるようだ。まあ、近づいてみるか。滑り台の下に三毛猫が一匹、黒まだらの白猫が一匹寄り添っている。匂いからして男か。声を出したのは黒まだら猫の方だった。
「なあ、休める場所しらねえか?平七が尻尾を人間に踏まれてさあ。自由に動かせなくなっちまってな。痛みが激しいから安全に休める場所が必要でさ。」
三毛猫は平七というらしい。
尻尾の一部が細い筒状のものに踏まれた後があり、肌が露出し赤い血が出ている。見るからに痛そうだ。
人間の乗る細い乗り物、確か自転車とか言ってたっけ、にやられたようだ。
重苦しい液体の匂いがかすかにして、結構危なっかしい乗り物だ。車は広いところを通るが、あの乗り物だけは神出鬼没で、人気の無い山道でさえ現れる。我ら、猫にとっては厄介なものだ。
「こりゃあ、大変だ。我が屋敷に行こう。」
「すまねえ、助かるよ。あ、おいらはリキってんだ。おい、平七。歩けるか?」
「痛いけど、歩くよ。このままだと、大変な事になりそうだ。雨の匂いもするし。」
「今日は、お桃がいたから、看病するように頼んでやるよ。」
「助かる。」
赤助は二匹の猫を屋敷に案内しながら猫屋敷に向かった。
平七とリキを屋敷に連れて帰った後、お桃に簡単だが見てもらった。
平七の怪我は尻尾の形に異常が出るが生きるのには問題ないとのことだった。
裏面に白い毛がたくさんついた草、よくご主人様が餅を作るときに混ぜていた草だが、それを食べると効率よく直せると言ったが、近くに生えている場所は少ない。まあ、日が二回ほど落ちるぐらい休んでいれば治るだろう。
尻尾はバランスを取るのに必要だが、結構傷つけられる事が多い。最近尻尾の無い猫はめずらしくない。尻尾があると怪我しやすいと体が記憶しているのだろうか。生まれた時から持っていない猫が増えている。これもまた、人間の仕業なのだろうかと思ってしまう。人間によって移動の自由がなくなり、油断すると平七のように尻尾を怪我することが頻繁に起こる。人間が増えすぎるのも困りようだ。
雨が降り出してきた。かなり強く台所ではぽたぽたとタライに水滴が落ちる。止むまで猫屋敷で休もうか。今日はご主人様の布団の側で体を丸くした。
雨は夕方のうちに止み、地面が少し湿っているままだ。空は星が見えるほど晴れており、月があたりを照らしている。
赤助は大きな公園にやって来た。人間の作った光が優しく公園を照らしている。
この公園は、次の日が盛況になる日の夜になると、やたら人間の『つがい』をよく見かける。
男と女がべっとりと寄り添って、顔を重ねる。草がたくさん生えている木の裏に回りこむと、愛を育んでいる『つがい』までいる。
人間が放つ桃色の波動があたりを包んでいて、うっとおしい。人間も猫に負けないぐらい物好きのようだ。
この大きな公園では人間観察が楽しくなってくる。よく探索すると、脆い紙の箱(ご主人様は『だんぼうる』と言っていたっけ)で巣を作り寝ている人もいれば、なんともいえないきつい匂い(酒という飲み物が原因らしい)を放ちふらふらと歩いている人間もいる。人間の『つがい』も様々で、まれに同姓同士で愛を育んでいる姿も見れる。猫でも正気が狂うとたまに男同士で愛を育んでいるのを聞くが、滅多に起こる事は無い。
さて八六とシャロンはいるのだろうか。探してみるか。
赤助は草が生い茂っている場所を見回してみた。すると、人間の『つがい』が愛を育もうとしている。
茶色の髪の女のほうは酒の匂いがきつい。このきつい匂いを放つ人間は大抵思考がまともでは無くなっている。茶髪の女はまだ平静を保てているが、体はふらふらとしている。
「ねえ、マサキ見てー。白猫よ。シロちゃーん。」
どうも、女のほうは赤助に気付いたらしく、指を刺してくる。
「そんな猫放っておいて楽しもうぜ。」
男は桃色の波動でおおい尽くされている。猫も盛りになるとこの波動を出す。あの男は盛りなんだな。もう愛を育む事しか頭に無いようだ。
「ええーっ、あ…そんな…。こんなとこで…。」
「いいじゃねえか。」
「駄目よ。人が見てるじゃない。ホテルにいこ。」
「大丈夫だって…。見てるのは猫ぐらいだしさ。」
「ん…。」
へいへい、御盛んなこって。
さっきから周囲に機械独特の嫌な波動を感じるのが気に食わない。ほかに四人程度の人間の気配も感じる。すべて男のようだ。何か危険な雰囲気があの『つがい』中心に囲んでいる。
気分が悪いや、逃げよう。
赤助は『つがい』を避けて、別の場所を探す事にした。
人間は猫と違って、男が発情をして桃色の波動をだす。女が桃色の波動を出していることはほとんど無い。猫は女が発情して男が女から放つ波動に釣られて、ついていくのが普通だから、人間はやっぱり変な生物だ。
どうも人間は子どもを産みたいからと言って簡単に産む事ができないらしい。子どもが欲しいと思ったら作ればいいだけの話ではと思うのは俺が猫だからだろうか。ますます変な生物だ。
しばらくうろついて、公園の入口付近にやってきた。
人間によって捨てられた子猫がいた場所に男の人間が寝ている。しかも、男の人間の大半が来ている守りの高いの服を身につけている。その人間は『だんぼうる』に包まれながら寝ている。どういうことだ。猫だけでなく人間も捨てる事にしたのだろうか。小さい人間が捨てたのではなく、大きな人間が捨てたのだろう。寝ている人も大きな人間なのだが…。目の前で考えていると、寝ている人間がしゃべった。
「くそ…。家を借りれないなんて…。くそ…。職が無いと…。くそ…。」
もれた言葉から憎しみの黒い波動が感じられた。同じ人間に対しての憎悪だろう。
「くそ…。くそ…。」
人間も人間を捨てる事があるみたいだ。同じ人間だというのに、仲間に嫌われ捨てられる事が人間の世界ではあるようだ。
猫は気ままな生物だから猫同士あまり深くに干渉しないのだが、人間とはそうもいかないらしい。世知辛い生物だ。
さらに探索を進めると、以前あったことのある人間の『つがい』に遭遇する。昼間、噴水で休んでいたら体を撫でてきた人間だ。
「ああー。ねえねえ、今日もいるよシロちゃん。こんばんわー。」
女が話しかけて来た。どうも『シロちゃん』とは自分の事らしい。そんな名前では一度も呼ばれたことが無いのだが。一応「にゃあ」と無き返事をして足元に擦り寄る。食事が貰えれば運が良い。
「本当だ。噴水で尻尾を水につけてた猫だね。ほーら。」
男はそういうと赤助を持ち上げて抱きかかえる。
うーん、黒煙の匂いがする。こいつ、葉巻を吸うんだな。
あんなの良く吸うよな。葉巻から放たれる黒煙はどろどろとした匂いを持っており、長時間浴び続けると気持ちが悪くなってくる。どうして人間は変なものを好むのだろうか。マタタビって呼んでいる草でも吸っていたほうが、気持ちが良いというのに…。
「ああちょっと、私にも抱かせてよ。」
「そうだね、はい。」
「きゃー。ありがとー。」
赤助は男の手から女の手に渡される。
男の人間よりかはマシなんだよな。感触が柔らかくて気持ちがいい。
特に心臓の鼓動が聞こえてくる場所が特に柔らかくて気持ちがいい。猫で言えば、乳が出てくる場所だったような。
でもどうして女の人間はここが膨らんでいるのだろうか。猫としてはどうでもいい質問か。そういや、小鳥も同じこといってたっけ。性別変わりなく心地がいいものなのだろう。
「かわいいー。」
抱いている女が自分の顔を近づけて顔をすり寄せてくる。
おっと、顔の付近はきつい匂いがするんだよな。人間が色々と混ぜて作ったかのような匂いが。それに、べとべとした粉がくっつくしあまりいいことがない。勘弁して欲しい。
顔にべとべとする粉をつけている女の人間は遠くから見るとたいてい整って見える。ああ、たまにすごい顔してる人もいるか…。同じ生物としてあまり体に良くなさそうなのに…。理解に苦しむ。
「んーーーちゅっ。」
「おおシロちゃん、羨ましいなー。キスするなんて。」
まただよ。どうして人間は自分の口を我ら猫の口と重ねようとするのか…。未だに疑問である。男が嫉妬の目で見つめているが、実際そんなにうれしく無い。人間だと嬉しいのだろうか、人間同士は口を重ねあうと桃色の波動を発する事が多い。でも猫はそんなことは無い。重ねてたとしても単なる猫同士の交流でしかない。
女はキスをすると、赤助を地面に置き、男と手を繋ぎその場を去ろうとする。
「じゃあねー。また会おうねー。」
女のきつい匂いによって赤助は思考がぐらついているのを感じた。今日はこれ以上の探索はやめて、猫屋敷に帰ったほうがいいかな。そう思うと、赤助はふらふらする体を正気に保ちながら猫屋敷に向かう。
猫屋敷に戻ってきた。台所にある流し台の付近で平七が怪我をした尻尾を舐めながら、傷を癒そうとしている。
「痛そうだねえ。」
赤助が平七に一言鳴くと、平七が一言鳴く。
「まあ、痛みが引いてきたから後は尻尾が動かせるようになることを祈るばかりです。お桃さんの看護のかいあって良かったです。」
「それなら良かったけどな。ところで、八六ってやつしらねえかい。お前と同じ三毛猫で男なんだが。ちょっと荒っぽく自分を俺っちとか言う奴なんだが。」
「同じ三毛猫ですか…。ああ、そういえば。」
「そういえば?」
「俺と同じ種類で男ってのは珍しいので覚えてるんですがね。茶色で塗られた人間の住処の一部屋から、助けてくれって言う声が聞こえたんですよ。聞き間違えかと、鳴き声を頼りに建物の中を調べたら、男の三毛猫が首輪をして狭い折に中に入れられてたんでさあ。」
「ほう…。」
「透明の板が張られていたから中に入れなかったが、調べてみるといいです。」
「そうか…。ありがとよ。」
赤助は話を聞くと台所を後にして、ちゃぶ台のある部屋へ移動する。
ちゃぶ台の部屋には黒いテレビの上にシャロンが座っている以外に他の猫はいなかった。
「あら、赤助じゃ、ありませんこと。ここは私がいただいていますわよ。」
「そうか。」
赤助はシャロンに構わずちゃぶ台に寝そべる。
「冷たいですわね。もう少し相手してくれてもよろしいのに。」
「いや。別に。」
シャロンが黒いテレビからちゃぶ台に飛び降り赤助のそばに寄り添う。
「私の事、探していましたの?」
「気になったからな。」
「嬉しいですわ。つれない態度を抑えて、もう少し心を開いてくれてもいいですのに。」
「疲れてるだけだ。」
「まあ、たまにつれない所がいいところなんですけどね。」
「そうか。」
赤助は一言鳴くと眠りにつこうとする。
それにあわせて、シャロンも赤助に寄り添いながら眠りにつく。お桃が後から入ってきて
「あらあら、お熱いわねぇ。」
と鳴いたのは二人には聞こえていなかったようだ。
猫屋敷から歩く事数分、外観を無視した全体がダークトーンの茶色いマンションが建っている。そこの一室に三十も後半であろう女性が住んでいた。
体格は普通の女性に比べて大きく…いや、だいぶ大きくラグビーボールを縦にしたような体格である。ずっと人を信用できなかったのか、目つきが鋭く見つめた人を黙らせるほどだった。
傲慢でわがままな性格のため周囲からは孤立していた。
両親はすでに他界、一人っ子のため遺産を引き継ぎ、バイトするだけで事足りるような生活をしていた。
この巨漢の女は猫を飼うのが趣味の一つだが、乱暴に扱うために長生きした猫はいない。餌は毎日は与えず、猫が逆らったりすると檻を振り回し猫に恐怖を与える。檻から出す時は必ず首輪に紐をつけ、部屋を引きずり回す。たまに散歩と称して外に出かける時も逃げないようにと首輪をつけている。猫の気持ちは何も考えていない。
タンスの上に今まで飼っていた猫の死ぬ間際の写真を飾っている。死んだ順に左から並べてられているようだ。感傷に浸るためというよりは、慣習だから供養しましたといった感じで、線香やろうそくを立てる道具が近くに置かれている。
猫が死ぬと新しい猫を捕まえては檻に入れて楽しむ。彼女の中では猫は消耗品のように扱われているようだ。
仕事から帰ってきた女性はぎゃあぎゃあ叫んでいる三毛猫が入ったピンクのプラスチックの檻の近くにやって来た。
「おっかえりー、セバスチャン。元気にしていた。」
「ぎゃー、ぎゃー。」
「元気そうね。明日は待ちに待ったお休みですよ。御散歩に行きましょうね。」
と女が三毛猫が入ったプラスチックの檻を覗く。
中には一匹の三毛猫が入っていた。三毛猫は気に食わないのかぎゃあぎゃあと鳴きながら暴れている。
首にはセバスチャンと名前がついた赤い首輪がついている…いや、無理やり付けられたといったところだろう。
暴れる猫に見かねて巨漢の女が檻を覗く。三毛猫はふーーと睨みつけながら毛を逆立てる。
「暴れちゃあ駄目よ、あんまり暴れると、御仕置きしちゃうからね。ああ、明日が楽しいわ。しかし熱いわね…。冷房がんがんに付けちゃおう。」
そういうと女は冷房を下限の十八度設定にすると灯りを消しベッドに横たわった。ベッド脇に置かれた檻からは猫の鳴き声が止まらなかった。
「俺っちとした事が、こんな人間に捕まるなんて…。しかもあの女から黒と言うか青と言うか、危険な波動しかしてこねえ。今まで何匹の猫を殺したのだろうか…。俺っちでもそれぐらいは気付くか。4匹。あのうち、虎模様の猫は五郎だ間違いない。前回の寒い時期に、ご主人様が見当たらないと心配していたが…、こんな奴に捕まっていたなんて…。」
ちょうど檻の向かいに黒い額縁に入った猫の写真が飾られている。4匹並んでいて、どの猫もぐったりしている所に撮られたと思われる。一番右端に五郎の写真が見える。首輪を付けられ、苦しそうにしている姿がなんとも痛々しい。
「くそっ。逃げる方法がねえ。この部屋、やたらと匂いがきつくて寒いんだよ。このままでは、逃げる体力も奪われてしまう。あいつから与えられた、魚の塊は食べておかないと俺も死んでしまう。くそっ、誰か助けてくれ…。」
八六は体力があればしきりに助けを求めるように鳴いた。唯一の助けは布越しだが日があたってくるという事だ。日があたるって事は透明な板を抜ければ脱出できる。あのでかい人間の隙をつけば逃げれる可能性はあるって事だ。
「誰かー。助けてくれー。」
しばらく鳴いていると、外から同じ猫の鳴き声が聞こえる。
「ここにいたか八六。」
「もしかして、赤助か。」
布と窓を隔ててすらっとした猫の影が映っている。助かるかわからないが、救いの神が降りたように感じた。
「どうしてここにいる事が分かった?」
「風の噂で、人間のつくった檻に閉じ込められているって話を聞いてな。もしかしたらって来てみたら、案の定ってとこだ。」
「そうだったか。」
「ああ。ここは五郎が捕まって、残酷な仕打ちを受けて死んだ場所だ。最低な人間に捕まったな。」
「不覚…。女の尻を追うのに夢中になって…愛を語った後休んでたら油断しちまった。悔しいぜい。」
「しっかりしろよ。ちょっとした気の緩みが命取りだ。猫の一生はそんなに甘くない。」
「すまねえ。」
「でもあの女には、借りがある。五郎の仇を晴らすためにも、お前を助け出さないとな。」
「何か秘策はあるのか…?」
赤助はしばらく黙りこんっだ
「明日は公園が盛況の日だ。それまで待っててくれ。」
「待つって…。」
「今は休んで明日を待て。そうしたら逃げる機会が生まれると思う。」
「それだけか。」
「それだけだ。じゃあな。」
そういうと赤助の影が何処かに行ってしまった。先ほどまでそこにいたのだが…。
「ちっ、あのやろう…。どうしろっていうでい…。」
八六は赤助の言う事が正しいか分からなかったが、鳴くのをやめて大人しく休む事にした。
「ああ、寒い…。俺は江戸っ子、耐えてやる。くしゅ…明日生きていることを祈ろう。」
週末の土曜日の大きな公園。巨漢の女はピンクを基調としたフリフリの洋服を身につけ、三毛猫の入ったプラスチックの檻を片手に公園を歩いていた。
「楽しいわねー。セバスチャン。今日はベンチに座ってのんびりしましょう。」
女はプラスチックの猫かごを左右に振り回しているので、猫は驚きのあまりにぎゃあぎゃあと叫びだす。
巨漢の女性は木によって影が出来たベンチに座って、漫画を読み始めた。膝にはポテトチップスを開けて置き、漫画を持っていないほうの手でつまみ食べている。側には2リットルのコーラのペットボトルが置かれており、ポテトチップスを押し流すためにたまに飲まれる。
「がっはっはっはっはっはー。」
ギャグ漫画を読んでいるのか笑い方がけたたましい。巨漢の女性の横の右側に猫かごが置かれている。ベンチの上に乗っているため多少不安定である。檻の中の三毛猫は疲れているのか、大人しく横たわっている。
女性はすっかり漫画にふけっていしまった。
「ひーひっひっひ、面白いわね。」
猫かごの逆側には読んだ漫画が3冊詰まれており、4冊目である。ポテトチップスも二つ目の袋に突入しようとしていた。
かなり長い事、漫画を楽しんでいるようだ。
三毛猫は完全に眠りにふけってしまった。先ほどまでぎゃあぎゃあ騒いでいたようだが、木漏れ日から振る日の光は気持ちがいいらしいく三毛猫の意識を安らぎへと送っていったようだ。
突然、漫画に夢中になっている女性に喜劇…いや悲劇が起こった。何と上から2匹の猫が女性目掛けて降ってきた。白猫が女性の頭に黒猫が女性の持つ漫画の上に着地した。
「ぎゃあああああああああああ」
女性は立ち上がりパニック状態になった。白猫は頭にしがみつき、黒猫は腕にしがみついた。女性は体全身を揺らし、しがみついている物を振り払おうとする。
「何ー、何なのよー。やめてー。」
体を前後左右に降らし、腕にしがみついてた黒猫と猫かごがぶつかる。ぶつかった衝撃によって三毛猫は目を覚ました。プラスチックの猫かごはベンチから落ち、落ちた衝撃によって出入り口が割れてしまう。瞬間、三毛猫は出入り口から勢い良く飛び出し黒猫と大きな公園を逃げ出す。
「ぎゃああああ、やめてーーー。」
パニックの女性は頭にしがみついている得体の知れないものを取ろうと腕を伸ばす。白猫はその腕を爪で引っかきながら地面に飛び降りる。
「ぎゃあああ。痛い、痛いよぉぉぉぉ。」
巨漢の女性はベンチに寄りかかりながらひっかれた右腕を見つめる。その間に白猫は黒猫と三毛猫が逃げていった方向へと走っていく。
「ぷっ、機嫌はどうだいセバスチャン?」
黒猫のお桃が三毛猫の八六に声を掛ける。ここは猫屋敷の玄関前。大きな女の人間から逃げてきたばかりだった。お桃は八六の首輪を見てげらげら笑っている。
「うっせい。俺っちだって、好きでつけている訳じゃあねえよ。ああ、かっこ悪いなあ。」
八六は首輪を取ろうとするものの、猫の手では外す事ができない。八六は渋々諦めて、怪我の状態を見てみる。檻が落ちた時に体を強打しただけで何処も痛みも感じない。無事生還を果たしたようだ。
「でも、助かったぜい。ありがとな、お桃。」
お礼を言うのが柄でもなかったのか八六は照れていた。
「どうも。でも、一番の英雄は赤助なんだから赤助にお礼をいいな。救出劇を考えたのは赤助なんだから。」
「赤助か…。確かにな。」
すると、噂どおりに赤助が帰ってきた。
「おっ、八六。元気そうだな。」
やっぱりお礼を言う場面になると照れくさくなるのか、手で頭を撫でる仕草をして鳴く。
「おかげさまでな。赤助のおかげだよ。本当に助かった。」
「なに、心配はいらねえよ。俺もやりたいことをついでにやってきたからな。」
お桃は赤助に近づき毛づくろいをしながら鳴く。
「あんた。よくあの女が公園に現れるって考え付いたね?」
「たいしたことないよ…。ただ、すこしでも五郎の仇になったかなってね。」
五郎…。あいつは俺が生まれた時から一緒に過ごしていた。この屋敷にお世話になったのはあいつのおかげでもある。そんなあいつが人間に捕まったのは驚いた。すぐに探し出し見つけた時は、死に掛けで八六と同じ檻に入れられていた。
赤助は五郎と巨漢の人間をしばらく観察して救い出す隙を探していた。しばらく観察する事で、巨漢の人間が大きな公園でいる時が隙だらけだと気付き、救い出す機会を見張っていた。ところが、五郎は救い出す前に死んでしまった。
救出しようとした記憶が、五郎と同じように捕まった八六の救出に繋がるとは思いもしなかった。何が起こるのか分かったもんじゃない。
八六も赤助に近づき毛づくろいをしながら鳴く。
「おまえ、度胸がある上に、意外と義理深いんだな。赤助のこと見直したぜ。」
「ありがとうよ。褒めても何も出ないがな。」
赤助は同様も見せずに清ました顔で屋敷の中に入っていった。
五:人間の心模様
流石に、八六の救出には神経を研ぎ澄ましていたために、長い間眠りについた。いつの間にか日は沈み夜になっていた。平七と八六がちゃぶ台でぐったりと眠っている。二人で何かを話してそのまま疲れたようだ。尻尾を怪我してまだ休む必要がある平七と残虐な人間に捕まっていた八六だから、二人ともぐっすりと眠ってしまっても仕方が無い。
猫は行動中は常に神経を研ぎ澄まし疲れやすいので、猫の起きている時間はそんなに無い。
人間は日にあわせて行動する人間と、日に逆らって行動する人間がいるので性質がバラバラしている。変な生物だ。
しかし、公園のベンチでアクビをして眠たそうにしているのに、嫌な波動を放つ鉄の板と睨めっこをしている人間とか見ていると不思議に感じる。
寝てしまえばいいのにと思うのだが、人間には寝たくても寝れない事情があるのだろうな。
どうしてこんな事感じるのだろう…。まあいいや。月が綺麗に照っている時間だ。夜の散歩とでも洒落込むことにしよう。
夜の散歩は、やはり大きな公園が一番いい。
その前に小さい公園ではたまに小鳥が遊んでいる事がある。昼間暑い時は冷えた砂場で、ごろごろするのが彼女の楽しみらしい。
もし、遊んでいたなら散歩の付き合ってもらうか。赤助は小さな公園に向かって歩き出した。
「マサキ…」
茶色い髪の女がブランコで、小さく揺れながら座っている。まだ十代なのか肌につやがある。いつもならお化粧して綺麗にしているのだが、眉毛が消えていて塗られた口紅が広がっている。シャツとミニスカートが土で汚れている。鞄を右手に下げブランコの縄を持っている。左手もブランコの縄を握っているのだが、ボロボロにちぎれて土に汚れてしまったピンク色の上下の下着を握り締めていた。
「どうして…。私…私…。」
少女はきこきこと力なくブランコを揺らしている。彼女の表情は虚ろで元気が無い。出てくる言葉も力なくお経のようだ。近くの電柱から放たれる外灯の光が彼女の背中を照らし、切なさがみえてくる。
「初めてだったのに…。…できたら…どうするの…。」
彼女の目から大粒の涙が一つこぼれる。
「マサキ…電話に出ないの…私…私…。う…、うう…。」
涙があふれ出してきて、視界がぼやけている。
「にゃあ。」
涙を手にもつ下着で拭い、あたりを見回す。足元に白猫が鳴いていた。その白猫は揺れる少女の足に近づいてくる。少女は白猫を蹴らないようにブランコを止める。白猫は少女の足に擦り寄ってくる。涙と泥と化粧で汚れたぐしゃぐしゃの顔を笑顔にして白猫を抱き上げ、足の上に乗せ頭を撫でた。白猫は少女の膝で丸くなって気持ちよさそうに一言鳴いた。
「フフ。ごめんね。変な所、見せちゃったね。」
少女は鞄の中に泥と涙で汚れた下着をしまい、鞄の中から食べかけのコッペパンを取り出し白猫にちぎって食べさせようとした。白猫は少し匂いをかいで食べ、下で鼻を舐める。
「白猫ちゃん、食べながらでいいから聞いてくれる。」
少女はコッペパンを食べやすい大きさにちぎりながら猫に与える。その間少女は猫に相談するように話しかける。
「私ね、付き合っていた人が居たの。マサキって言うんだけど…」
白猫は少女に撫でられながらパンを食べる。パンに夢中になっているようで少女の話は上の空だ。
「昨日…、もう二日前なのかな…。私、彼とデートでいっぱい遊んだの…。カラオケにゲームセンター、ビリヤード…。夕食も一緒に食べたっけ。すっごく楽しい時間を過ごしたの。本当に楽しかった…。」
撫でられている白猫は気持ちよさそうに手で顔を洗う仕草をする。
「それでね、その二日前。デート帰りに、この近くの噴水のある公園に行ったの。しばらくベンチで喋った後、彼がキスをしてくれたの。すっごく、良かった。私、とても嬉しかった…。」
白猫は何かを感じ取ったかのように、顔を洗うのを止め手を少女の膝にくっつける。
「彼…しようって言ったの…。嬉しくて私ね、うんって言ったの。初めてをマサキにあげたかったから…。でもね…、マサキはホテルに行かず公園の暗い茂みの中に連れて行き、ここでしようって言ったんだ。いくらなんでも、公園でって言うのは恥ずかしいからホテルにいこって言ったんだけど、彼…聞いてくれなくて…。」
白猫は撫でられながら、ただじっとしていた。
「あまりにも乱暴に脱がしてくるから…、私覚悟を決めて公園で結ばれようと考えたの…。怖かったけど彼の行為を受け入れようとした。けど…けど……。」
白猫は体に水滴なのが何回もあたっているのを感じ、撫でていた手が止まっているのに気がついた。
首をねじりながら当たる水の出所を調べようと少女の顔を見上げてみると、彼女の顔は目から顎にかけて涙が流れており顎の辺りからぽたぽたと滴となって白猫の体に落ちているのに気がついた。
「周囲からいきなり男が三人現れてね…。マサキが私を押さえつけたの…。その後は…その後は…。下着を引きちぎられ…、う…うう…。」
撫でていた手で彼女は目を擦る。もう顔の原型が分からないぐらいに目の辺りはぐしゃぐしゃになっている。
「強姦されたの……。三人分…私の体に…。しかも、撮影までされちゃったの…。マサキは見てるだけだった……。う、うう…。」
少女は白猫を抱きかかえ両手で強く、しかし潰れない位の力で白猫を抱きしめる。
「騙されていたのね…。気がついたら、公園で裸で寝かされてたの…。朝日が昇ってきた頃に気がついたわ…。そして、一日中うろついて…うろついて…どうしたら良いか分からずに…う、うう…。」
少女の中で溜まっていた感情が一気に流れ出した。白猫はその感情に気がついたのか少し体を震えさせた。
「うわあああああああああああああああああああああああ…」
少女は大声で泣き始めた。
「あああああああああああああああああああああああああ…」
マサキに騙された自分の未熟さに対しての悔しさの涙か、
「あああああああああああああああああああああああああ…」
大切に思っていた人に裏切られた悲しみの涙なのか、
「あああああああああああああああああああああああああ…」
これから迫り来る運命を予測しての不安の涙なのか、
「あああああああああああああああああああああああああ…」
溜め込んでいたいろんな感情が全身から一気に噴出すかのように彼女は鳴いた。
「あああああああああああああああああああああああああ…」
周りの事なんて気にする事ができないくらいに泣き叫んだ。負の感情を全て押し出すかのように。
少女の悲痛な叫びはしばらく続いた。泣き出した時、白猫は一瞬驚いて体を震わせたが、彼女の気持ちを察したのか妙に落着いて、彼女の耳元で優しく
「ゴロゴロゴロゴロゴロ……。」
と一言鳴いた。
「泣き叫んでも、何もはじまらねえ。人間の事は知らんが猫は辛い事の連続だ。友人も恋人も家族も死んだり殺されたりと悲しい事の連続だ。でも、気には留めねえ。明日には明日の猫が来る。また新しい猫が俺の前に現れる。友人も、恋人も、家族も…。新しい事がやってくるんだ。そのために構えていようぜ。猫だから寝たら忘れるだけだがな。」
少女の鳴き声は止まった。そして抱きしめていた猫を両手で彼女の眼前に持ってくる。白猫はゴロゴロと鳴き手足をぶらぶらさせながら少女を見つめた。
「白猫ちゃん……。」
白猫は「にゃあ」と一言鳴くと、穏やかな表情を見せる。少女はゴロゴロと泣いている白猫が励ましてくれているように聞こえた。
「ありがとう。私の話を聞いてくれて…。ちょっと落着いたかな。そうだよね、明日には明日の風が吹く。子どもができているか怖い所…。だけど、またマサキ以上に素敵な男性が目の前に現れるよね。私には友達も、家族もいるんだ。今日の事しばらくしたら話してみる。まだ人生長いからね。」
少女は白猫に口付けをすると足元に下ろし立ち上がる。
「よし、明日からも頑張るっぞー。おー。」
一言大声で叫ぶと少女は立ち上がり鞄を大きく振りながら全力で家へと走って帰った。取り残された猫は一言鳴いた。
「生きろよ。自分の道は自分で開かないと、生きていけないからな。」
白猫は茶色の髪の人間が走り去っていくのを見届けると、小さい公園の砂場に向かっていった。
大きな公園にいた愛を語らっていた女の人間か。
あの時は桃色で妖艶の波動を放っていたが、今日はどす黒く気持ち悪い波動を感じたな。しかも波動の力が弱い。強かったら何か悪い事をしでかす事を考えているんだが、弱いと自ら命を絶つ事を考えてることが多い。
雰囲気はまだ生まれて若くで元気のいい猫と同等の感じがした。あの女の人間はまだ若い。これからいろんな経験をしていくのだろう。人間の一生…人生か。簡単に終わりにするのはもったいない。もっと楽しい事があるはずなんだ。
良く分からんが元気になって黒い波動を引っ込めてくれたのは嬉しい限りだ。食事までもらえたし何か気分が良い。
小鳥はいないし砂場にも来た形跡は無いが、そんなことはどうでも良くなってしまった。一人で大きな公園を散歩しよう。今日は月と星の光が綺麗な夜だ。
「う…、うう…、くそっ、クボめ。クボのやろうめ…。う…、うう…。」
公園のある一角にダンボールをござ代わりにして寝ている一人のスーツ姿の男がむせび返していた。
三ヶ月前クボという上司にリストラ宣告をされて会社を辞めさせられ、二ヶ月前リストラされたと親にも友人にも連絡ができずに家賃滞納のため家のものを差し押さえられ家を追い出され、ここ一ヶ月家を探すも職無い奴には審査が通らないので貸せませんとか、前金二十万ほど必要になりますとかで住む場所がなく途方に暮れている状態で、とうとう、手持ちのなけなしの金が尽きかけネットカフェ生活を諦め、ホームレスと化した。
「うう…。経営悪化って…。経営が下手くそなのは…、役員だろ…。あいつら…のうのうと生きやがって…くそっ、畜生…。」
風呂に1週間は入っていないだろう。スーツの男からは汗と垢の混じったきつい臭いを発している。顔のひげも一週間はそっておらず、無精ひげが無様だ。男の目は死んだ魚のように輝きを失っている。寝転がっているのに、涙で眠る事ができない。
仰向けになってみる。月と星がちらほらと見えている。外灯の影響もあって見えるのは夏の大三角形ぐらいだが、涙を照らす灯りとしては十分に眩しくなった。
「いっその事…、死んだほうがいいのだろうか…。何のために大学に行って、大企業で八年も頑張ったのに…。もう、後も無い…。母さん、父さん…。」
涙で月が霞んでいる。もはや月の形がはっきりと見えなかった。両親に合わせる顔も無いし、実家に帰る金も無い。
「そういえば、去年妹が結婚したっけ…。姪も生まれているらしい。なおさらあわせる顔が無いな…。」
目が涙で溺れてしまう。自分の不甲斐無さに涙が溢れ出してくる。
「くそっ。」
男は目を思いっきりつぶり眠ろうとする。月が眩しいのか、病気なのか、心が苦しいのか涙が止まらない。
こぼれた涙が耳、頬とつたっていく。
明日のために眠りに着こうとする。もちろん、寝ることができない。
目をつぶってしばらくも経たないうちに、顔を何かに舐められている。しきりに目、耳のそば、頬をざらっとした感触が幾度も伝わってくる。
「なんだ?」
スーツの男は起き上がる。丁度顔があった場所の近くに白猫がいた。どうも、顔に張り付いていた涙を舐めていたようだ。
「な、なんだ…。白猫か。」
男は胡坐を掻いた。すると白猫は男の足に丸くなり「にゃあ」と一言鳴いた。
「なんだよ。お前、俺を笑いに来たのか?餌なんて持って無いぞ。」
白猫は男に顔を向けてにやけた顔をして「にゃあ」とまた鳴いた。
「笑いたきゃ笑えよ。お前も人に捨てられたのか?俺と同じだな。ハハハ。」
白猫は男の言葉を聞き流したかのように「にゃあ」と鳴き、胡坐を掻いた足の上で丸くなる。
「お前、寂しいのか…。いや、寂しいのは俺なのか…。」
それに答えるかのように白猫は「にゃあ」と一言鳴く。
「変な奴だな、お前。」
スーツ男は白猫の体を撫でる。白猫は気持ちよさそうに「にゃあ」と一言鳴く。
「聞いてくれよ。俺さ、リストラされたんだよ。しかも、部の失敗を理由にさ。クボって奴、いや脳の無い課長だがな、部材の発注ミスを全て俺の責任にしてきたんだよ。どう考えても、会社全体のシステムの脆弱性と、部全体の連携の悪さが原因なのは目に見えてるのにさ、俺の発注後の管理の甘さが悪いってな感じにさ。発注指示はクボの指示、管理はクボの責任で合意を得ていたのにな。自分の分が悪いとすぐに責任転嫁してきやがる。」
白猫は手で顔を洗いながら相槌を打つかのように「にゃあ」と鳴く。
「笑っちゃうよなー。判断力も指導力も無いクボが部を纏めているんだぜ?どの部署もクボと同じ能力かそれ以下か…。笑うよ。大企業ってそんなもんかって。頭がおかしい人が会社の重役についてんだ。最終的には、つぶれるのが落ちだ。話になんないぜ。」
そういうとスーツの男は両手で優しく抱え、自分の頬に白猫の顔を近づける。
「お前に言う前に、企業の人間に文句の一つぐらい入れてやりたかったな。ハハハ。」
白猫は、男の頬を一回舐めると小さい声で鳴き出した。
「ゴロゴロゴロゴロゴロゴロ…」
「人間のルールなんて知らん。知らんが猫は自由だ。もっと自由に生きたらいいんじゃないか?猫行く道も一歩からだ。ルールなんて気にせず猫らしく生きろよ。後、涙を流してまで慕う仲間が居るのだろう。猫達の毛づくろいだ。慕う仲間がいるなら、お前を助けてくれる人間もいるはずだ。そいつの所に戻れよ。帰れる力があるのだろう、人間よ。」
スーツ男は白猫を下ろし、胡坐の足に下ろす。不思議と涙が止まって、男の顔に元気が戻ってきた。白猫の鳴き声が励ましの声に聞こえたように感じた。
「ありがとうな。白猫よ。俺、もう少し人を信じてみるよ。何とかお金集めて、明日実家に帰るよ。そして、もっと自由な生き方してみるよ。」
スーツの男は足に乗っている白猫を抱えて地面に下ろし、立ち上がると手を頭上で組み星空に向かっておもいっきり背伸びをした。
「ちょっと、会社の同僚にあって来る。高級スポーツカーを乗り回す、きざな奴で良く飲みに行った奴なんだけど、そいつなら多少お金を貸してくれると思うし…。そうだ。会社で働きすぎて疲れたからなぁ。絵でも描いてみるか、楽器でも習ってみるか、詩でも書いてみるか…何か色々やってみよう。ちょっと楽しくなってきたよ。」
スーツの男は白猫を見下ろして、笑顔で手を振った。
「じゃあな。もし今度会ったら、ご馳走をお前にプレゼントしてやるぞ。待ってろよ。アハッハッハッハッハ…。」
笑い声とともに、外灯の照らす帰り道を歩き出した。スーツの男は何か楽しくなってきたのか笑い声も軽快だった。去り行くスーツ姿に向かって、白猫は一言鳴いた。
「良く分からんが、生きる気になったようだな。頑張れよ、固い服の人間よ。」
今日はどす黒く気持ち悪い波動に満ちた人間に良く会うな。人間とはどうも気楽に生きることのできない生物のようだ。
いろんな波動を放っているから、見てる側としては面白いのだが、あのどす黒く気持ち悪い波動だけは耐えられん。俺だけかもしれないが…。
食事はもらえなかったが、水と塩をもらえただけでも良しとするか。
まあ、もう少し公園を散歩してから帰ることにしよう。今日の夜空は気分を軽やかにしてくれる。赤助は前足をピンとし背伸びをすると、また大きな公園を歩き始める。
赤助は噴水のある広場に着いた。ついたとたんに、また黒く染まった気持ち悪い波動を感じ取る。
この波動はさっき感じた2人のものと質が違う。どす黒い感じではなく、いろんな色が入り混じって、結果的に黒くなってしまっている。感情が複雑になっているのだろう。
うーん、どうしよう…。
噴水には一組の男女のカップルが座っていた。すらっとして背の高い男性と髪が長い小柄の女性のカップルで、良く公園にデートに来るらしく昼夜問わず時間が空いたら公園で喋ったりするのが習慣らしい。ただ今日はいつもとは違う雰囲気のようだ。
「どうして別れようって言うの?5年の間も付き合い続けたじゃない。いまさら別れろって…。わけが分からないわ。」
「………」
女が小さい声で、しかし力強く男に向けてしゃべる。男は何も語らず黙ったままだ。
「何も言わないの…。」
「………」
女の言葉に対して男は口を塞いだままだ。余計な事は語りたくないといった重々しい表情でじっと黙っていた。女はやけになって、男の両肩を持ち大きく揺らす。
「ねえ、結婚しようって行ったよね?あれは嘘だったの?何のためにプロポーズしたの?」
「………」
男は沈黙を保ったままだった。
「いまさら体だけって事も無いよね…。お金だけって事も無いよね…。互いの両親に会った時だって、何も問題になることなんて無かったじゃない。そんな…。どうして…。」
男は女の手を振り払い、タバコを一本取り出す。火をつけて一服すると、ふうーっと煙を女性のいる場所とは逆向きに吐き、地面に捨てる。そのタバコを見つめながら語る。
「飽きたんだよ。お前に…。それだけだ。」
女は両手を脇を閉め口元を隠すように手を持ってくる。その手は怯えるように震えている。
「どう…して…。」
男はタバコを見つめたまま声を張りあげた。周囲にいる人間も注目してしまうほどの力強い声で叫んだ。
「もう、飽きたんだよ!いいから、いいから。いいから俺の前からいなくなってくれ!」
「そんな……。」
女の顔から涙がこぼれ落ちる。激しくあふれ出したといったほうがいいだろうか。一歩、二歩と後ずさりした後、女は公園の出口の方に向かって走り出した。女の姿は外灯に照らされて、段々と小さくなっていく。その姿を見送ると男は噴水の淵に腰をかけ、また一服タバコを吸う。
「飽きたんだよ…。お前に…。」
一言つぶやくと男は、力なく空を見上げる。夜空の光が儚く小さい、男は自分の心の光のように感じた。魂が夜空の暗闇へと消えていく気分になった。
「はあ、これで良かった。これで良かったんだよ…な…。」
心が夜空に溶け込み吸いこまれてしまった感じになった。もう、これで死んでもいいかなと言う気持ちになり始めた。
「にゃあ」
足元から猫の鳴き声が聞こえてきた。そして、足元に体をこすり付けてくるような感触を感じた。男はその感触に驚き正体を知ろうと足元を見つめる。
そこには、彼女といるときによく餌を与えていた人懐っこい水色の瞳をした白猫がいた。
「ははは。なんだシロちゃん、お前だったのか。」
「にゃあ」
男は白猫を抱え上げ目線を自分と同じ位置に持ってくる。白猫はまたかという面持ちで手足をぶらーんとさせている。
「どうした?餌なんて持って無いぞ。彼女とは今日…たった今、別れたからな、ははは。」
抱えていた猫を自分の左隣においた。白猫は、去る事もせず男の横にくっつくように丸まり、大きなアクビをした。
「まあ、お前のおかげでルリとは5年も持ったんだ。感謝してるよ…。」
声がいつに無く力弱い。その言葉に対して反応するかのように一言鳴いた。
「にゃあ。」
しばらくのんきな白猫を見つめていたが、男は息が漏れるようにつぶやいた。
「いいか。お前になら、話しても…。」
左手で白猫の体を撫でながら、ゆっくりとした面持ちで語りだす。
「俺さ…、転勤する事になったんだ…。ブラジルだってさ。しかもプロジェクトの関係でさ、短くても五年は滞在するんだとよ。断わったんだけど、行かないなら会社辞めてもいいんだよ。だってさ。そう言われたなら行くしかないよな…。もう断わる事もできないんだよな…。」
タバコを一本取り出すと火をつけて吸うと右手で吸い掛けのタバコを持って下ろす。
「急遽、ブラジルに行く事が決まったんだ。結婚してもさ、5年も会う事ができないんだぜ。休みの日に会えるとか行っても、彼女を毎日寂しい思いをさせるなんて…、俺にはできない。連れていこうにも、遠い異国の地だ。彼女を危険な目にあわせかねないし、彼女を支えてあげる自信が無いんだ…。」
男の顔から大粒の涙がぽろぽろとこぼれ落ちる。男は涙を腕で拭う。拭った時に涙が白猫の顔にかかった。温かく気持ちのいい水滴がぶつかり、白猫の顔は笑顔になる。
「彼女に別れを告げるしかない。その方が彼女のためでもあり、僕のためでもある。だから、別れを告げた。」
男はむせび泣いた。白猫は男の感情の変化を感じ取ったのか背の高い男の顔をじっと見た。
「でも、駄目なんだ…。彼女が僕の人生だった。彼女のいない人生なんて考えられない、彼女がいたから辛い仕事も頑張れたんだ。ルリが、ルリがいたから、僕は、僕は……。」
顔を両手で隠し体を限界まで折り曲げ泣き叫ぶ。
「あああああああああああああ。ルリ、ごめん、ごめんよ…。ルリー。あああああ。」
白猫は男の鳴き声に驚いたのか急に立ち上がり、男の足を爪で引っかいた。ズボンが切れてしまったが、小さい切り傷程度ですんだ。傷から赤い血が垂れてくる。
「痛い…。」
痛みを感じた男は泣き止み白猫を見つめた。白猫は口を大きく開き警戒しているかのように男を睨み返した。
「ふーーーーーーーーーーーーーー。」
「人間ってのは素直じゃあないねえ。魚をあげれば猫は飛びつく。女が鳴けば愛を育む。猫はいつでも本能のままに生きてるぜい。ぐ、だ、ぐ、だ、ぐだ、ぐだ、ぐだぐだぐだぐだ、色の混じった黒い波動を出していないで、本当の桃色の波動を前面に出したらどうだい。気持ちが悪いんだよ。」
男は猫の怒りを汲み取ったように目を覚ます。死んでいた瞳に光がやどり、凛々しい顔が戻った。
「そうだよな…、俺どうかしていたよ。やはりルリをブラジルに連れて行こう。挙式を早めてブラジルで一緒に暮らそう。もし、彼女が嫌って言うなら会社なんて辞めてしまえばいい。仕事なんて幾らでもある。転職なんてすぐにできる。彼女がいてこその俺の人生なんだ。おれはルリが好きなんだ。」
男は立ち上がり、叫ぶ。
「ルリーーーー、お前が好きだーーーーー。」
男の叫びに驚いたのか、白猫は走り出す。女が走っていった方向に全力で走る。
「ルリ、お前を迎えに行く。待ってろ。」
男は携帯電話で女に電話しながら、公園を走り出す。
ああ、人間とは常に面倒な人間だな。自分の好き勝手に行動が出来ないなんてどうかしてる。自分の意思も貫けず、必要な相手と別れてぐだぐだしてるなんて…。腹たたしい極まり無い。
ああ、むしゃくしゃする。何でいらつくんだろう。せっかく綺麗だった空がどす黒く感じる。心が晴れない。
赤助は男と離れた後、公園の出口方面へと走った。
すると、出口付近から人間の気配を感じる。
丁度、固い服を着ていた男が眠っていた所よりも奥の茂みだ。さっきまで背の高い男といた小柄で髪の長い女の人間だ。目がうつろになってしまって魂が半分抜けかけている。
桃色の波動をぷんぷんさせながら女に近づいている男の人間がいる。
あの男は見覚えがある。確かマサキとか呼ばれていた男だ。人間の中でも最低な部類なのだろう。やはり桃色の波動に黒いものが浮かび上がる。愛を育むことしか考えていないのか…。なんか、むしゃくしゃしてきた。
一丁、やってやるか。
周囲には…あの男と女以外は人間の気配は無いようだ。よし。赤助は二人の人間に向かって走り出した。
「へへへ、かわいいねぇ…。おとなしくするんだぞ。ふへへへ…。」
女に悪の手が伸びてくる。
女は目の前の現象をただ見ているだけだった。
自分の体がどうなろうと関係ないと思っているのか気持ち悪い男を拒もうとはしない。
目の前にいるマサキと呼ばれる男のすることを人形のように、ただただ見つめているだけだった。
「うへへ、いいねえ、俺の子猫ちゃんになるんだぜ。」
マサキと呼ばれる男は顔をにやつかせて、手を女の服に掛けようとする。
「楽しみだねえ、お嬢さん。うへへ…」
悪の手が女の服に手が触れた瞬間
「痛あああああああ。」
マサキと呼ばれる男が飛び跳ねた。
何が起きたか分からなかったが、男の首辺りに何かに切り裂かれたような傷がついていた。
「痛い痛い痛い、何だ何だ何だー。」
男はきょろきょろとあたりを見回す。何かに引っかかれた痛みで自分を忘れている。
すると、少し離れた所に白猫が爪を舐めるように手を口の前に持ってきていた。
青い瞳を鋭く光らせ、赤くなった尻尾を逆立て、男を睨みつけた。
「貴様ーーー。猫の分際でマサキ様をなめるなよーー。」
男は近くにあった木の棒を両手で持ち、白猫に襲い掛かる。
それでも、猫はその場に立ち尽くしていた。
「野郎が。」
大きく木の棒を振り落とすと、白猫は攻撃を上手くかわす。
すかさず、白猫は男の左腕を爪で引っかき、その腕を足場として飛び込み顔を引っかいた。
「ぎゃああああああああ。痛いいいいいいいい。ひいいいいいいいい。」
マサキと呼ばれる男は左手で顔を、右手で首を抑えて、公園を出て行く。出て行く男に威嚇を放つように白猫は毛を逆立てて鳴いた。
「ふーーーーーーーーー。」
「気持ち悪い波動だけ出してんじゃねえ。猫神様がだまっちゃいねえよ。」
毛を逆立てている白猫に近づき女が抱きかかえる。
先ほどまで魂が抜けていたが、彼女の生きようという波動が戻っている。
女は白猫を抱えると、先ほどまでスーツの男が横たわっていたダンボールに膝を曲げて腰をかけ、膝に白猫を乗せて頭をなでた。
「ありがとう、シロちゃん。私を助けてくれたんだね。」
白猫は女に撫でられて気持ちよさそうな笑顔をして女に「にゃあ」と一言鳴いた。
「ごめんね、私が不甲斐無いばかりに…シロちゃんを危険な目にあわせて。」
女は話を続ける。
「シロちゃん、覚えてる?私と一緒にいた彼氏…。背が高くてすらっとしていて…とても頼りがいがあった。格好良かった…。彼といられるなら、どんな事だって我慢した。彼に何でも尽くした。アキトを世界で一番愛していた…。」
女の顔から大粒の涙がぽろぽろとこぼれ落ちる。
涙を腕で拭う。拭った時に涙が白猫の顔にかかった。温かく気持ちのいい水滴がぶつかり、白猫の顔は、またかと笑顔になる。
「でも、今日振られちゃったの。彼と出会ったあの場所でさ…。始まりと終わりの地が同じなんてね…。笑っちゃうよ。結婚の約束までしたのにさ…。飽きたから別れるって。五年も付き合ったのに…。どうして…どうして…。」
白猫は女に向かって一言鳴いた。
「ゴロゴロゴロゴロ…。」
「『つがい』の相手への愛が強いなら、探せよ。猫の世界ではなあ、女が鳴かないと愛は始まらねえ。女が男を必死で求めねえと何も始まらないんだよ。泣いてる暇があるんだったら、もっと、しっかりしないか。」
「えっ…。」
女は白猫の泣き声に戸惑った。
白猫から厳しくも温かい声を感じ取った。
ただゴロゴロとしか聞こえないのにそれ以外の言葉が乗っかっている気がしてならない。
白猫は鳴いた後女の足から降りて、女と向かい合わせる位置に座り、左手を挙げくいくいと手首を曲げる。
「どうしたの?」
女は白猫の行動に不思議なものを感じた。
すると
「ルリ!」
女は呼ばれた方向を振り返る。
そこには背丈の高い凛々しい男の姿があった。
随分息を切らしているので、そうとう公園内を探し回ったに違いない。男のズボンが破れていて、その破れた箇所から血が垂れている。
「アキ…ト…さん」
走って男が近づいてくる。
全力で女のほうに駆け寄ってくる。
女は立ち上がり男の方に体を向ける。
向けたとほぼ同時に男は女に飛び込んで抱きしめる。女は顔を赤らめ、目線だけ男のほうに向ける。
「あ…アキトさん」
「ごめん。俺、嘘ついていた。本当は君と離れたくない。君と一緒にいたい。君と生涯をともにしたい。飽きただなんて嘘だ。」
「アキトさん…。」
女性は抱きしめられて左右の手がおぼつかなく空中を掴んでいる。
「俺、仕事でブラジルに長期滞在が決まったんだ。でも、君をブラジルに連れて行っても守れる自信が無かった。君を一人で日本に置いてずっと海外で過ごすのも悪い気がしたんだ。」
女性は黙って彼の話に耳を傾けた。
「でも、君を一人にはできない。君と離れ離れになる事が出来ない。挙式を早くして君を連れて行きたい。もし君がブラジルに行けないというなら、別の仕事を探す。会社なんて辞めてやる。君は俺の人生に必要な存在だ。だから、だから…。」
女は空を掴んでいた手を男の腰に回し、顔を男の胸に預ける。
「馬鹿…。言ってくれれば良かったのに…。貴方となら、何処にでも行くわ…。」
女は顔を上げて男性の顔を見つめる。男は手を女の肩に添えて女の顔を見つめる。
「ありがとう、ルリ。」
「アキトさん。」
女は足を伸ばしてつま先立ちにして男の方に顔を寄せる。
男は、背を曲げつつ女のほうに顔を近づける。そして互いに顔を少し傾け、唇をそっと重ねた。二人の周りは温かく幸せな黄色い波動があふれ出した。白猫はその波動に浴びながら一言鳴いてその場を離れていった。
「にゃあ」
「熱いぜ。幸せ全開でなによりだ。いつまでも幸せにな。」
赤助は屋敷に戻ってきた。今日は一日中人間の黒い波動を潰していく大変な作業だった気がする。
あのどす黒い波動を浴び続けるのはとても疲れる。猫としては体が限界になるまで動いたためか、疲れが溜まりに溜まっているようだ。
テレビの上に上る気力が無いほど眠気が襲ってくる。仕方ない。今日はちゃぶ台の下で寝ることにしよう。赤助は、ちゃぶ台の下に行くとそこで横たわる。
横たわってすぐに、台所からガラス障子をくぐってシャロンがやってきた。
「あら?今日は随分と疲れておりますのね。」
対応するのが億劫なところがあるが、会話をすることにした。
「まあな。今日は一日中いろんな人間を相手したから、体が限界に達している。」
「そうなんですの?」
「人間ってのは、ちょっとした事で自分の感情を変えやすいらしくてな。すぐに自分の発している波動が変わるんだ。青色の沈んだ波動を発していたと思ったら急に青黒い怒りの波動を発したり。色気じみると桃色の波動を、幸せになると黄色の波動といったように。」
「わかりますわ。私を蹴ったりしてきた人間は常に青黒い怒りと不安の混ざった波動を発していましたもの。明らかに猫当たりですわ。」
「そうでもしないと、生きていけないんだろ。その人間は。今頃、死んでいたりするのかもな。」
シャロンが一瞬、もの寂しい表情を見せた。
だが、気を取り戻したかのように振舞う。
「そう、ですわね。死んでいてもおかしくはないですわ。ふふふ。」
少しだけ疑問に思う。シャロンはご主人様が嫌で逃げ出したと聞いた。
でも、たまに寂しげな表情を見せる。
虐められていても、心の中では以前の生活がいいと思っているのだろうか。痛い思いしてても、幸せだったと感じているのだろうか。……野暮な話だ。
「寝るぞ。」
「そうですわね。今日は貴方のそばで寝てあげてもよろしくってよ。」
「好きにしろ。」
二匹の猫は目を瞑り夢心地に浸っていった。疲れも相まっていつも以上に深い眠りに着いた。
六:白猫の恋路
「灰色の虎猫、灰虎のお友達かい。おめえもこの竹輪食ってみるか。」
「今日も迷子かえ。雨で大変だろうに。少しだけ休んでいきなさい。」
「白猫さんどうしたたんだい。お腹空いたのかい。」
「あれまあ、尻尾の先が赤くなってるねえ、そうだお前を赤助と呼ぼうかいね。」
「赤助さん、今日はねこまんまだよ。本当はもっといいもの食べさせたいんだけどねえ。」
「ごめんな。今日は牛乳とパンしかなくてねえ。」
「おやまあ、友達かい。かっこいい三毛猫さんかえ。幾らでも連れてきなさい。」
「これはべっぴんな黒猫さんだねえ。お前達つきあっているのかえ。」
「今日はあったかいねえ。いい夢が見れそうだよ。」
「お前の友達の灰虎…。帰ってこないねえ。死んで無いか心配だよ。」
「雨漏りかえ。仕方ないねえ。タライでも置いて過ごす事にするかいねえ。」
「ごめんな。今日は、煮干一本で我慢してな。」
「ごほっ。お前たちといると温かいねえ。もうすこし寄ってきなさい。」
「はぁ、あなた…。わたしはまだ生きています。まだがんばるからねえ。」
「ごほっ、ごほっ。ユキ、ユリ、タケル…。今日もおかあさんは元気ですよ。」
「ふー、ふー。きょうはお墓まいりにいかないとねえ。」
「はぁ、はぁ。ごめんなおまえたち。おまえたちにあげるえさないんだよ。」
「ごほっ、ごほっ。はぁ…、はぁ…。もうすぐ…おまえたちにあえるよ。」
「ごほっ。しろねこさん、わたしはだいじょうぶ。いえをでていきなさい。」
「はぁ……、はぁ……。うれしいねえ。いてくれるのかえ。ありがとうな。」
「ひゅー、ひゅー。あなた…しあわせでした。ありが…とう…。」
「…ぁ………ゆき………………ゆり………たける…………」
「………ゆ…き…………け……る……」
「………り……け………」
「…ゆ……」
「…」
「」
赤助は、夢を見た。どうしてだろう。夢なんて滅多に見るものでも無いのに。この屋敷に来てからのご主人様との回想が黒い箱に流れる映像のように勝手に頭の中に現れた。こんな夢をみるなんて、何かが起こる前触れなのだろうか…。いろいろと考えていると毛が逆立ってきた。少し怖くもあった。
起きてみると傍らにはシャロンがいた。シャロンに邪魔にならないように起き上がると、寝室の方に向かった。
寝室ではご主人様が静かに眠っている。
そういえば今日で二回目の満月の日だ。そろそろ暑い日が減っていく頃だろう。
永い眠りだ。
人間も、飛び跳ねる緑のぬめぬめ(ご主人様が蛙とかいってたか)と同じように長い間眠るのだろうか…。人間も長い間眠る事はあるのだろうか。
分からない。
「あ、兄貴。おはようございます。」
屋根のほうから鳴き声が聞こえた。大きな木の箱(たんすと言ってたな)の上にリキがいた。最近、怪我で困っていた猫の平七の相棒だったか……な多分。リキはたんすから飛び降り、赤助に近づいてくる。
「兄貴っていうのは、なれないから止せよ。」
「すんません、この屋敷に来れたのも兄貴のおかげっす。尊敬の意で兄貴と呼ばせてもらってるっす。でも兄貴がいやがるなら親分と呼ぶ事にしまっす。」
「そうかい。」
リキには何を言っても無駄だと思い自分の呼びたいように呼ばせることにした。
「ところで親分、あそこで寝ているシャロンさんなのですが。」
「シャロンがどうしたってんだ。」
「すごく美猫ですねえ。惚れ惚れしちゃいます。」
「まあ、美形だろうな。好きなのかい。」
「そんな滅相も無い。オレには足元にもおよばないっす。それに、赤助さんのお気に入りっすよね。さすがに赤助さんの女に手を出す事はできないっす。」
赤助は、耳をぴくっととんがらせた。いつの間にシャロンは自分のものといった解釈になっているのか、疑問になった。
「どうして、そうなるんでい。」
「八六さんが言ってましたぜ。シャロンさんは赤助のものだから手を出すなって。」
八六の野郎、勝手な事を抜かしやがって。今度あったらとっちめてやる。
「そう、話したいのはそういうことではないです。」
「じゃあなんだい?」
「難しい字で書かれた半円の輪が入口に立つ人間の通路があるっすよね。入ってすぐの所に美味しそうな魚が並べられてる所が…っとっと、話が反れたっす。あそこにシャロンさんらしき猫の綺麗な絵が貼ってありまして…。実際に物を見たことないから分からないんですが、大きな噂になってるようっすよ。面白そうっすよね。」
「ほう…。」
おそらく、人間の通路とはご主人様がよく食事をあさっていた『商店街』と言う所に違いない。リキの話からシャロンのご主人様が探し始めたのだろうか…。確か、『迷い猫です』とか『探しています』とか書かれていて、逃げた犬やら猫やらを捕獲する事だと推測できる。
その張り紙の対象は、たいていは、逃げる方法や危機感知を知らないために、野獣の餌食となり、遺体で発見されてしまう事が大半なのだが…。
シャロンが屋敷に来てから随分と日が落ちている。そろそろ諦めてもおかしくはないと思うが…。人間は常に執念深いのだろう。
猫の世界の常識のようにもうすこしさばさばしてもいいのではと感じてしまう。
それにしても今の話は気になる所だ。遠いけれども、確認しに行くのがいいだろう。
「興味あるな。場所教えてくれ。」
「うっはー、さすが親分。お気に入りの事となると黙って入られないってやつっすね。」
このリキって猫は少し面倒臭いところがあるようだ。まあ、あまり話をしないようにしよう。
「黙って、案内してほしいのだが…。」
「あ、すんません。では付いてきてください。」
そういうとリキは寝室の窓の割れ目から外へ出ていく。
リキに付いていく形で、赤助も屋敷を後にした。
屋敷からだいぶ離れる事になるが、商店街を目指して歩みだす。
「親分、ちょっと遠いんでここで休んでいきませんか。」
赤助はとリキは、地面が砂地の光る鉄箱(人間が作った乗り物で車とか言ってたな)が並ぶ場所に辿り着いた。隣には漢字の十を象った飾りの付いた建物が見える。
「まあ、そうするか。車の下にいれば人間も触ってこないだろうし、丁度いい日よけにもなる。後は人間の気配を感じたら他の車の下に隠れればいいだろう。」
赤助はリキを連れて、一つの車の下に潜り込み体を休めることにした。
「ところで、隣の家覗いてみます?」
「十の字の飾りが付いた建屋のことかい。」
「そうっす。あの飾りがある家の黒い布の人間は高い確率で美味しい食べ物をくれるっす。魚をくれた時は踊りだしてしまったっす。」
「気分でいいだろ。十の字の飾りのある家は、まれに変な集団がいるからな。神に救いを、とか言いながら、桃色の波動やどす黒い波動を出していたり、他の人間の波動を消したりと…。建屋内の人が全員、安らぎの緑色の波動を放っていれば安心して食事をもらえるのだがなあ…。」
「人間も様々っすからね。猫だって白から黒までっす。」
「まあ、いいよ。一眠りしたら行くぞ。」
「了解っす、親分。」
そういうと赤助とリキは眠りについた。人間だって人間の神にすがる必要があるんだなと心の中で考えていた。どうも、昨日までの疲れが取れていないようだ。かなり深い眠りとなった。
「シスター様、来てください。母猫の白猫が子猫に乳を与えてますわ。」
「おお、かわいいねえ。これも主の御導き。大聖堂の中ですが、しばらく様子を見守りましょう。」
「見てください、ミス・サイトウ。子猫がじゃれ合っていますよ。かわいいですこと。」
「本当ですわ、シスター様。もう少ししたら庭に移してさしあげましょう。」
「猫かわいいー。サイトウさんこの白猫だいていい?」
「いいですわよ。あまり乱暴に扱わないことです。子猫も人と同じ命を宿す者ですわ。」
「ああ、親猫がいなくなってしまいましたわ。どうしましょう。白、灰色の虎、三毛…。シスター様、子猫たちをいかがなさいましょう。」
「親猫の元を去るのは自然な事。しばらくしたら教会から姿を消す事でしょう。それまでは教会で様子を見ましょう。」
「わかりましたわ…。仮の名前を付けましょう。そうね…この白猫は青助、灰色の虎は…五郎、三毛は…そうねえ、黒丸。かっこいいですわね。」
「青助、駄目ですよ。茶色い羽のあの虫はゴキブリといって危険ですわ。捕まえて食べては、いけませんですわ。」
「今日はすこし、豪勢にしてみましたわ。御めでたい鯛の刺身を買ってきましたの。口に合いませんでしたらごめん遊ばせ。…よかった。美味しく食べていただけるなんて満足ですわ。」
「青助さん、今日もとってもかっこいいですわね。うふふ、わたしの王子様ですわ。このお饅頭よろしかったら食べてくださいまし。……ごめんなさい。猫ちゃんには口に合いませんですわね。」
「もうすぐでクリスマスですわ。青助には特別に、鮪のお刺身あげますわ。はい、あーん。かわいいですわ、私の王子様。」
「オー、シスターさん。今日からここはワレワーレの教会、アナータガタには去っていただきまショウ。」
「ああ、シスター!ちょっと、何するんですか、乱暴はよしてくださいませ。」
「ホー、ミス。貴方とてもビューティですねえ。この教会の洗礼を受けて、リッパーなシスターに変えてしあげマショウ。」
「何するんですか、離してください。」
「ダイジョーブデース。司祭からお清めの洗礼を受けた後、ブラザーたちへ奉仕をすればそれで終わりデース。」
「いや、止めてくださいませ、助けてください、主よ、私を見捨てないでください。」
「ダイジョーブデース。洗礼の後、貴方は神に乙女を捧げマース。神子となるデース。」
「いや、離して。助けて、いや。」
「サー行きましょう、ミス。怖くないデースよー。HAHAHAHAHAHA。」
「嫌。」
「そんな。」
「主よ、お助けたまえ。」
「お願いします、私を、私めを助けたまえ。」
「離して。い、嫌。嫌あああああああああぁぁぁぁぁぁぁぁぁ。」
「親分どうしたんっすか。悪い夢でも見ました。随分と息を上げてたっすけど…。」
ここは…。
さっきのは夢だったのか。まだ幼い時の記憶を見ていたようだ。
そうだった。
俺はあの十の字の飾りがついた建物で生まれたのだった。随分、過去の話で忘れていた記憶だ。あのシスターさんたち、今は何処で何をしているのだろうか。
「ああ、すまない。気にせずに行こう。」
「了解っす。行きましょう。」
赤助は、歩こうとしたが急に立ち止まった。少し頭の中を整理して、再度リキに話しかける。
「ところで、リキ。」
「はい、親分。どうしました。」
「夢って見るか。」
「夢っすか?うーん、寝てるときに起きてる様に感じるってやつっすよね。見た事ないっすねえ。常に頭空っぽですから。はっはっは。」
ここ最近良く夢を見る。夢とは先祖の語りかけだったり、自分の願望の現われだったり、嫌な思い出や悲しい思い出、懐かしい思い出の記憶であったりする、と小鳥が行っていた。確かに、夢に出てきた思いでは懐かしくも悲しい思い出ばかりだ。猫の世界では滅多な事が無い限り夢に出くわす事は無いらしい。
不思議だな。すこし、怖く感じ体が震えだす。
「どうしたんっすか、親分。ちょっと震えてますよ。もう少し寝てから行きますか。」
「すまん、たいした事無い。気にせず行こう。」
「大丈夫ならいいんすけど…、気分悪かったら言ってください親分。引き返すっす。」
「ありがとう。大丈夫だから、行こう。」
「はいっす。それならば、ちゃちゃっと商店街に行くっす。」
日が照って暑い中を赤助とリキは商店街に向かって走り出した。
日が沈み、空が橙色に染まりだし、商店街の町並みも温かい光が照らしていた。
商店街の入口にある掲示板の前で大学生らしき男2人、女2人が広告をじっと見つめている。
「へえー。猫を探しています、かぁ…。猫って気まぐれだから、もう遠くにいっちゃったかもな。」
「ちょっと、この猫の首輪すごいよ。何か宝石っぽいの付いてるー。」
「うっそお。高そうだよこの首輪。そうとう裕福な人に飼われているみたい。」
「おいおい、すげえよ。見つけてくれた方に200万だって。桁間違えてるのか。」
「遺体でも運んでくれたら、50万…。どんな猫だよ。」
「もしかしてー、この宝石ー?高そうだよねぇ。」
「これに200万以上があるのか…。いやいや、猫だよな…。」
カシャ
「へへー、探してお小遣いゲット。」
「あ、ちょっと。俺も俺も。」
カシャ
「ずっるーい。私も取るー。」
「こりゃ、見つかるまで宝石猫の捜索が続くんだろうなあ。一応取っとくか。」
カシャ
カシャ
捜索の張り紙を写真に取ると、大学生4人は掲示板を後にする。
掲示板から少し遠くに離れた場所に白猫と白黒のまだら猫が掲示板を凝視している。
「あー、あの綺麗な絵は紛れもなくシャロンだねえ。」
「親分、あの板の前でしゃべっていた人間どもの話からすると、シャロンさんは人間が血なまこになってまで探す価値のあるような猫みたいですぜ。見つけたら相当のお金が入るとか話していましたし。」
「どうやらそのようだな。」
「そうなるとシャロンさんの身が危ないっすよ、親分。これは、シャロンさんに知らせないとやばいですぜ。」
「そうだな…。帰るぞ。」
「おい親分待って下せえ。」
人間は勝手だよな。逃げた後も手配をかけて見つかるまで追っかけてくるなんて。
四人の人間の会話から、シャロンのご主人様は本腰入れて捜索に切り出したのだろう。シャロンが捕まるのも時間の問題だ。
赤助は掲示板に背を向け歩き出す。つられてリキも歩き出す。
屋敷に帰ってくると、シャロンがちゃぶ台の下で気持ちよさそうに眠っている。
もう夜になる。今日は何処にも出かけていないのだろうか。
むしろその方が好都合なのかもしれない。今こいつを屋敷の外に出すと確実に人間に捕まる。どんなに逃げても主人の所に戻されてしまう。赤助はシャロンの隣に腰を下ろし体を休める。
「帰っていらしたのね。」
「ん、起きていたのか。」
「貴方が体に触れた事で起きてしまいましたわ。」
「それは、すまない。」
シャロンは少し体を起こし、赤助の毛づくろいをする。
「結構疲れていらっしゃるのね。どこか遠い所へお出かけしましたの。私も連れてってくれればよろしかったのに…。」
「すまない。」
「今度はお願いしますわ。」
シャロンは毛づくろいをやめ、台所に向かう。赤助は急に立ち上がるシャロンの姿を見て自分も立ち上がる。
「屋敷の外に散歩に出かけるのか?」
「違いますわ。喉が渇いたので水を飲みに。また、戻ってきますわよ。」
「そうか…。」
赤助は安心して、また寝転がる。
「一緒にいたいのですの?まあ、寂しがりやさんですわ。」
「まあ…、そうかな…。」
「ふふふ。だんだん貴方が王子様に見えてきましたの。今日は貴方と一緒にいたい気分ですわ。」
「…ありがとう。」
赤助はシャロンを背にして丸くなる。
今、あいつを日のあたる時間帯、人間が動き回る時間帯に、外に出す事ができない。おそらく、飢えた犬のような目つきで襲い掛かってくるに違いない。
シャロンが側にいてくれるという言葉を聞いて安心して眠りに付いた。
人間の気配がしない真夜中、満月が少し大きく光っている時間、赤助はシャロンを夜の散歩に連れ出した。
夕方の件もある。本人に知ってほしいから、人間が狙っている事を伝えたい。
赤助とシャロンは屋敷の近くにある鉄網に囲まれた場所に侵入した。何処行きたいと聞いたときシャロンが希望した場所だ。
普段は中ぐらいの人間が同じ格好で過ごしている不思議な場所だ。建物の中では机を並べて、一人の人間の話をじっと聞いている。
内容は人間の知恵っぽいものだから、猫の自分には理解に苦しむ。
たまに広い砂場で玉遊びしている時もある。人間不思議行動の一つにあたる。
最近ではこのような場所は、馬鹿でかい鉄網で囲うのが流行らしい。それでも、猫には関係なく、隙間さえあれば入れるのだが。俺とシャロンは建物の間にある花の植えてある場所を散歩した。
「ここは一度来て見たかったですの。へえ、結構綺麗ですのね。」
「昼間は、人間がたくさんいるから好きでは無いが。」
「そうですの?たまに食べ物くれるから私は好きですわ。」
「まあ、分からなくは無いが。」
「面白い場所ですわよね。日のあたる時は定期的に流れる音に合わせて人間が行動していますのよ。見ていて飽きませんわ。」
シャロンが楽しそうに花の咲いてる道を歩いてる。無邪気に歩いているシャロンの姿を見ていると安らぎを覚える。
「シャロン…。」
赤助が名前を呼ぶと、彼女は急に足を止める。足を止めたまま、震えた声で喋りだす。いつに無く落着いているが、元気が抜けているような気がする。
「私、貴方と一緒にいたい。貴方は私の王子様ですわ。でも、それも叶わないことですわね…。」
シャロンは急に体をこわばらせた。恐怖に怯えているように見える。赤助は心配してシャロンに近づき声を掛ける。
「どうしたんだ…。急に…。」
「道を歩いていたら、急に人間が私を捕まえようと追いかけてきましたわ…。どす黒い波動を放ちながら近づいてくる。下手したら、殺されかねないですわ…。しかも、昨日で三回も…。今日、屋敷にずっといたのは、人間に追っかけられてかなり体力を消耗したからですの…。」
「そうだったのか…。」
もうすでにシャロンが追われていたことに気付くことが出来なかった。確かに灰色の綺麗な毛並みで首に光る石をつけた猫なんてそうそういない。人間が気付くのは当たり前だ。
「いつ人間に連れて行かれるか分かりませんの。その前に…。」
「その前に…。」
シャロンから、独特の匂いが流れてくる。猫独特の桃色の波動も感じる。
「貴方と…一緒に…。」
シャロンは赤助にゆっくりと近づいていった。赤助はシャロンの誘いを受け、シャロンの首筋を甘噛みし地面に押さえつける。
そしてゆっくり、そして優しく愛を語らった。
子供を作るごく当たり前の動作だ。
夢中で精一杯の魂をシャロンに分け与える。
シャロンの姿は空に輝く満月と星空のように輝いていてとても綺麗だ。
シャロンの心地よい匂いによって、赤助は心の全てを彼女に持っていかれるのを感じる。
空が紫色に染まり、太陽の日差しがあたりを照らそうとしていた。
赤助とシャロンは愛を語り終えると、猫屋敷に向かって歩き出した。帰る途中、太陽の光が眩しく空が黄金色に染まっていた。
「シャロン。」
赤助はシャロンに呼びかけた。シャロンはその掛け声で振り向き立ち止まる。
「ご主人様の元に戻ったほうがいい。」
「どうしましたの?急に…」
「今お前を狙っているのは、どす黒い波動の人間どもだ。恐らく乱暴に扱ってくるだろう。」
「嫌ですわ。戻ったら、小さなご主人様に乱暴にされますもの。」
「小さなご主人様はまだ子猫のようなものだ。我ら猫の扱いが出来ていないだけ。もう少し大きくなれば段々扱いが上手くなるはず…。」
「その保障はありませんことよ。八六だって、巨漢の人間に随分乱暴に扱われていましたもの。」
赤助はシャロンに近づき口を舐めた。
「大丈夫だ。人間だって白から黒までだ。お前のご主人様は大切にしてくれると思う。それに…」
「それに…。」
「それに?」
赤助はシャロンの周りをぐるりと回り出す。
「お前の中に新しい魂が宿るとも考えられるのに、黒い波動を取り巻く人間によってお前とその命を失いたくは無い。だから、考えてほしい。戻るという考えも。」
シャロンは周囲を回る赤助にあわせて顔を向けていたが、赤助に近づき自分の顔を彼の顔へこすりだした。
「少し考えさせてくださらない?屋敷にいるのがいいのか、元のご主人様のところに戻るほうがいいか。そして、結論を出すために赤助も手伝っていただきたいですわ。」
すり寄せてくるシャロンの顔を舐めて、シャロンの不安な気持ちを和らげようとする。
「ああ、なんだってするよ。さあ、日も随分昇りだした。屋敷へ急ごう。」
「そうですわね。人間に見つかる前に帰りましょう、私の優しい王子様。」
朝日が周囲を明るく照らす。空はいつの間にか青色に染まっていた。
太陽が眩しく輝く中、二匹の猫は猫屋敷に向かって走り出した。
ここは住宅地の一角。
中学校と小学校まで歩いて三分と育児をするにはもってこいの場所だ。
門が付いており庭も広く、家は二階建て。恐らく三世帯は住めるのではという家の広さに住む人は、貿易商を営むパパ、薬品会社で研究に励むママ、その二人の間に生まれた子どものミヤコと使用人のカトウ一人の計四人である。
パパとママはいつも仕事に追われミヤコと一緒にいる時間は月に一日あるか無いかの頻度だ。
家事の合間にミヤコをよろしく頼むと依頼されたカトウは、ミヤコの自閉症に悩んでいた。話しかけてもミヤコは心を開いてくれず、会話が成立しない。
遊ぶといっても常に本を読む、テレビを見る、ひとりままごとと自分の中に閉じこもっていく様子がカトウの心をえぐってくる。
カトウはミヤコの自閉症について両親に話すと、パパが一匹の子猫を買ってきた。毛並みはは綺麗で銀色に輝いている。瞳は太陽のように済んだ黄色の瞳を持つ美形のシャム猫だ。ミヤコが5歳になるバースデーの時に、家族とカトウが全員揃った所でミヤコにプレゼントされる。ミヤコは部屋中を飛び跳ね喜びを全身で表し、灰色の子猫を家族に迎え入れた。
「パパ、ママ、ありがとー。」
「お、そうだ。この猫の家族入り記念として、一つプレゼントをしよう。」
パパは一つの首輪を子猫につける。ダイヤモンドの宝石が付いたおしゃれな首輪だった。
「どうだ。これでかわいくなっただろう。」
「うん、パパありがとー。」
「あ、そうだ。ミヤコ、この猫に名前を考えたんだけど、いいかな?」
「ママー、なーに?」
「少し洋風のお嬢様みたいな雰囲気が猫から感じられるから、シャロンなんてどうかしら。」
ミヤコは子猫を抱きながら飛び跳ね、ママに擦り寄ってくる。
「うん、ありがとー。よーし、今日からお前はシャロン、シャロンだー。よろしくねー。」
「みー」
家族は一階の庭に面した一部屋をシャロンの部屋として用意した。
家の中に放し飼いするにはあまりにも広すぎて、迷子になる可能性もあるという事からの両親の配慮だ。
ミヤコはカトウの手助けを受けながら、シャロンを一生懸命育てた。
ミヤコはやんちゃなところがあるのか、走り回って気付かずシャロンを蹴飛ばしたり、尻尾を踏んだり、面白がって尻尾を引っ張ったりして、カトウに叱られていた。
やんちゃになったミヤコを見ているカトウは、シャロンが屋敷に来る前のどんよりとした雰囲気を出さなくなったのは喜ばしく感じている。
シャロンはミヤコがいないときはのんびりと、ミヤコがいるときは少し怯えながら過ごしていた。ミヤコからは気持ちいい感情がするから、嫌いでは無いのだが猫にとって尻尾を握られる、引っ張られるのはとても痛くて、体調を崩し易くなるから猫として危険信号を受け取らざるを得ない。
小学校に上がった頃、ミヤコから黒く気持ち悪い感情がしてくるようになった。
シャロンとじゃれて遊ぶといった行為から、悪意があって蹴飛ばしてきたり、尻尾を引っ張ってきたりするようになった。
「ああ、もう。マキちゃんの馬鹿!」
「嫌だ、嫌だ。学校行きたくない。」
「もう、アキヒコなんて消えていなくなればいいのに。」
その他もろもろ。学校での不満をぶつける様にシャロンに八つ当たりをしてくる。
シャロンは身の危険を感じ、隙があらば逃げようと考えるようになっていた。
夏休み、ミヤコは学校が無いため猫を屋敷内を抱きながらうろつき楽しんでいる。シャロンは自分の部屋以外の様子を始めて見る。他の部屋も見てみたいところだが、この子から逃げる事が先決か。とにかく隙を見つけて逃げ出そうと考えていた。
学校で元気を無くして帰ってくるミヤコを見て、元気を取り戻して欲しいとカトウが手持ち花火を買ってきて、家の庭で遊ぼうと言って来る。ミヤコは喜んで興奮を抑えられなくなる。
「ねーねー、シャロンも連れてきていい?」
「しょうがないですね。絶対見張っておくんですよ。」
「はーい。行こ、シャロン。」
ミヤコは子どもなりにシャロンを逃がさないようにと抱きかかえながら庭に行く。そして花火もシャロンを抱えながら手に持ってカトウに火をつけてもらう。
「わー、きれいー。」
ミヤコは花火の光に夢中になり目を輝かす。夢中のあまりにシャロンを抱えていた手の力が少しゆるくなる。体勢のバランスが無くなったのかシャロンは手の中で暴れだし、ミヤコの手から落ちる。落ちると、花火の火を怖がるかのように全力で走り出す。
「ああ。待って、シャロンー。」
カトウがシャロンを捕まえようと追いかけるが、猫の素早さに追い付く事ができなかった。シャロンは庭に張り巡らしている柵までくると、柵の隙間を上手くかいくぐりミヤコの屋敷から脱出する。ミヤコはあまりのショックに泣き出してしまった。
「うわーーーーーん、しゃろーーん、しゃろーーーん…。」
「お嬢様落着いてください。探し出しますから、落着いてください。」
「うわーーーーーん。」
シャロンが逃げ出してからミヤコは落込んでしまい、彼女に笑顔が戻ってこなくなった。カトウはあの手この手でミヤコの機嫌を取ろうとするが、落込む一方で回復する事は無かった。
「シャロン…帰ってきて、シャロン…。」
ミヤコは自分の部屋とシャロンの部屋を行ったり来たりしてシャロンが戻ってくる事を期待していた。
逃げ出してから、一週間が経とうとしている。彼女を取り巻く空気がどんよりと黒くくすんでいる。この一週間、ミヤコが一度も笑った記憶が無い。今日は珍しく両親二人とも揃っていて、彼女と一緒に食事に出かけようと誘うが、ミヤコの中では嬉しさが黒い空気に消されてしまっている。
彼女の中ではシャロンはかけがえの無い友達だった。シャロンがいたから学校も我慢して通う事が出来たのに。
「ミヤコ、また新しいペット買ってあげるから元気出して。」
シャロンの部屋でうずくまっているミヤコに声を掛ける。パパは困り顔でミヤコの背中を見る。
「いや、シャロンがいい。シャロンが帰ってくるのを待つ。」
「ミヤコちゃん、もう機嫌取り直して、私達と出かけましょう。」
ママがミヤコの肩に触れる。しかし、ミヤコはその手を思いっきり叩き振り払う。顔はうずくまって下を向いたままだ。
「いや。シャロンがいないと駄目なの。シャロンは私の御友達、シャロンがいないなんて死んだほうがいい。」
「ミヤコ…。どうして悲しい事言うんだ…。」
ミヤコは、パパの言葉が癇に障ったらしく、パパを睨みつけ甲高い叫びを上げた。ミヤコの瞳は涙でおぼれている。
「パパなんて、ずーっと家にいないじゃん。私の相手なんてひとっつもして無いじゃん。私の事、好きじゃないんでしょ?シャロンはいつも側にいてくれる。たまに怒っているけど、いつも遊んでくれる。」
ミヤコは今度はママを見つめる。ミヤコの両頬には大きな滝が出来上がっており、顎の辺りから水滴が垂れている。
「ママだって…。学校での話を聞いてくれない。話しても、はいはいの一言。まだシャロンに話しした方が楽しいよ。どうせ、ママも私の事好きじゃないんでしょう?」
声の音量が二倍以上に膨れ上がる。頬に作られた滝の幅が広くなっていく。
「パパもママも大っ嫌い!シャロンも帰ってこないんじゃあ、死んだほうがマシ!」
ミヤコは自分の部屋に向かって駆け出した。
両親も彼女の後を追うが、ミヤコに追いつけない。
広い屋敷の中を子どもと親とで追いかけっこをする。
結果、両親はミヤコから引き離され、ミヤコの部屋に駆けつけたときには、部屋に鍵をかけ閉じこもってしまった。ドアの奥からミヤコの咽び泣く声が聞こえてくる。
「ミヤコちゃん…。」
ママはミヤコの泣き声を聞き、悲しくなって自分も泣き出してしまった。見かねてパパはママの肩を抑え、ママを連れてミヤコの部屋から立ち去った。
ミヤコはベッドの上で足を折り曲げて、小さく縮こまりながら座っていた。シャロンがいない寂しさを自分の体で紛らわそうとしている。
「シャロン……。」
ドアからコンコンとノックがしてきた。反応する元気も無いのでミヤコは無視する事を決めた。
ノックの後に、パパの声が聞こえた。
「ミヤコ…。あれから、ママと話し合ったんだ。俺たちはミヤコにずっと寂しい思いをさせてきた。本当にすまない。もっと、ミヤコといる時間を作る。」
ミヤコはベッドから起き上がり、ドアの前に物音を立てずに近づいた。
「カトウから聞いたのだが、学校であった楽しい事、嫌な事をシャロンにすべて話していたと。その時のミヤコがとても楽しそうだったって。シャロンはお前にとってかけがえの無い家族になっていたんだな。俺も考えを改める。」
ミヤコは静かにドアの前に立つ。耳を傾け静かにパパの話し声を聴いていた。
「シャロンはうちの家族の一員だ。労力もお金も惜しまない。必ず見つけ出してやる。そして、俺たちで迎えてあげよう。だから、泣かないで出てきておいで。」
ミヤコは、パパの出てきておいでの一言を聞いて、涙を流した。
先ほどまで流していた悔しさの涙ではなく、嬉しさの涙だった。
鍵を開け、ドアを開ける。
空けた先にはパパがしゃがんでいた。
ミヤコは嬉しさのあまりパパに飛び込んでいった。
「パパ……パパ……ありがとう……。」
パパはミヤコの体を優しく両手で包み込み、右手で彼女の頭を撫でる。
「絶対、シャロンを見つけ出そう。」
両親は、200万というペットにかけるには膨大すぎる謝礼をつけた。飼い猫が逃げてまともに生きているか分からないので、仮に遺体で発見したとしても50万の謝礼を払うとしている。
ミヤコのために早くシャロンを見つけたいという願望がこの額をつけたようで、両親の真剣度が伺える。
さらに、両親は毎日残業をしないで仕事を早く切り上げ夜は三人でシャロンを探した。
首輪に宝石をつけた猫だから簡単に見つかると思っていたが、そうそう上手くはいかなかった。
ミヤコはパパとママに連れられてシャロンを一緒に探す。子どもながらに、二人が毎日のように仕事を捨てて私に付き合っているのに、戸惑いを感じていた。
「パパ、ママ、お仕事はいいの?」
「大丈夫だ。仕事なんていつでも出来る。ミヤコの大切なお友達を探すのが大切だ。」
「ママもね、ミヤコの事が大切なの。そして、ミヤコが大切にしている友達も私の大切な人なの。だから、絶対見つけましょう。」
心がもやもやとしていたが、パパとママの一言で吹き飛ばされ、嬉しさで今まで作った事も無い笑顔をパパとママに見せる。
「ありがとう。うん。シャロン、待っていてね。」
ミヤコの笑顔をみた両親はやる気に満ち溢れ、日付が変わるギリギリまでシャロン探しに精を出した。
張り紙が出されて三日目が過ぎようとしていた。家族は楽しく懸命にシャロンを探した。ミヤコは子どもながらに、毎日が幸せに包まれていると感じていた。
張り紙が貼られてから四日目の夕暮れ。大きな門のある屋敷の塀のはしっこ。赤助とシャロンは人の目から隠れて屋敷の様子をうかがっている。
「シャロン。御別れだな。」
「寂しいこと言わないで下さらない?また会うこと出来ますわよ。」
「シャロンは人間に囲まれて生きるが、俺は毎日が生の淵にいる。いつ死ぬか分からない。」
シャロンは赤助の顔に自分の顔をすりよせる。
「そうですわね。でも、貴方は私の大切な王子様ですわ。貴方が死んでも、いつまでも私の心の中で生き続けますわ。寂しくなったら、私のところに来てくださって。待っていますわ。」
「そうか……ありがとう。」
「そして、貴方との子どもが私の中に宿っているかもしれないですわ。人間がどうするか分かりませんが、許してくれるのなら大切に育てますわ。そのためにも是非一度は顔を見せに来てくださいませ。」
赤助は照れながら、シャロンに顔を近づけ顔を摺り寄せる。その後、自分の顔とシャロンの顔をキスするかのように合わせて、シャロンを見つめる。
「待ってくれる人が居るのは、嬉しい限りだな。生きてたら、会いに行くよ。」
「嬉しいですわ。待ってます。」
「迎えも来たようだ。」
赤助は、大きな門から大きな人間が二人、小さな人間が一人出てきた。小さな人間がシャロンに気付いて全力で近寄ってくる。
「そうですわね。短い間でしたけど、ありがとう。」
「ああ、元気でな。」
「いつでも、いつまでも貴方の来るのを待っていますわ。」
最後の別れの言葉を言うと、赤助はシャロンがいる場所から距離を取った。
「シャローーン」
家族はいつものようにシャロンを探しに出かけようと家の門を出た時だった。
家の右端の交差点付近に水色の目の白猫と毛並みのいい金色の瞳を持った灰色の猫を見つける。ミヤコは姿を見つけると、一目散に二匹の猫に向かって走っていった。後から、両親が娘の後を付いていく。
近づくに連れて、猫の様子がはっきりとしてくる。美しい灰色の毛並みに夕日に照らされて赤みを帯びた金色の瞳、首輪からたまにキラキラと宝石が輝きを発している。間違いない、灰色の猫はシャロンであった。
「シャローーン」
ミヤコはシャロンの名前を呼びながら灰色の猫に近づく。ミヤコの接近に合わせて白猫は三メートルぐらい離れた。
灰色の猫はご主人様を迎え入れるように、じっと待っていた。
視線は白猫に向けていたが。
「シャロン!」
ミヤコは灰色の猫を抱きしめる。肌触りのいい灰色の毛並み、夕日と同じ輝きを持つ黄金色の瞳に、首に輝くダイヤの宝石。ミヤコはシャロンが戻ってきた事に喜びの涙を見せた。
「シャロン、シャロン。ごめんね。もう離さない。もう、逃がさない。シャロンは私の友達、大切な友達。乱暴な事はしない。ごめん、本当にごめんね。」
優しく両手で抱きかかえ、胸の辺りでしっかりと支える。シャロンはミヤコの涙を舌で舐める。
「ありがとう、ありがとう…。シャロン…ありがとう。」
シャロンがミヤコの手に捕まると同時ぐらいに後ろから、両親がやって来た。シャロンが見つかった嬉しさのあまりに、ママは、パパの胸の中に飛び込み顔をうずめる。パパは優しくママを包み込む。
「ああ…、貴方。良かったわ…。シャロンちゃんが見つかりましたわ…。」
「良かった。本当に良かった。頑張った甲斐があったな。」
「ええ…。」
パパも嬉しさのあまりに、優しく包んでいたママの腕に力が入る。少しだけ、ママのぬくもりを全身で感じ取った後、パパは遠くにいる一匹の白猫を見つける。
「あの白猫は…。こっちを見ている?」
「あら、そうですわ。もしかしてシャロンのお友達かしら?」
「もしかして、恋人かもしれないな。シャロンと一緒にいた猫だし。」
「あらまあ。そうでしたら、シャロンの中には子どもがいるかもしれないわね。」
「いいよ。その時は、迎え入れよう。シャロンはミヤコの大切なお友達、いや家族だ。家族が増えるなんて嬉しい事じゃないか。」
ママは、涙を浮かべながら喜びを表す。
「そうね。シャロンに子どもが出来たら迎えてあげましょう。」
シャロンを抱きしめていたミヤコは遠くでこちらを見つめている白猫を見つけて、声を掛ける。
「白猫さーん。シャロンを連れてきてくれて、ありがとう。今度遊びに来てねーー。」
白猫はミヤコとその家族に対して二言鳴いた。
「みゃあ」
「人間達よ。シャロンを大切にしろよ。シャロンはお前達の家族だからな。」
「みゃあ」
「シャロン、元気でな。またいつか会える事を楽しみにしているよ。」
それに、答えるかのようにシャロンは一言鳴いた。
「なー」
「赤助、いつでもいつまでも待っていますわ。また会いにいらして。私はご主人様のもとで幸せになりますわ。元気に生きてくださいですわ。」
シャロンをかかえたミヤコは両親に肩を支えられ、屋敷の門に向かって歩き出す。白猫は一つの家族が離れていく姿をしばらく見つめ小さな声で一言鳴くと、自分の住処に向かって歩き出した。
「にゃあ」
「あばよ、シャロン」
七:猫を襲う病気
シャロンがご主人様のところに戻って日が三回落ちたが、相変わらず、のんびりとした日常を送っている。
そういえばシャロンの住む屋敷なのだが、内部に侵入する隙間が無い。どうも、シャロンが逃げないようにといった気遣いなのだろうか、ねずみすら入る事が出来ない環境になっていた。侵入する方法はまた後で考える事にしよう。
赤助は寝室で寝ているご主人様の様子をうかがう。やはり起き上がる気配も無く、静かにたたずんでいた。早く元気な姿を見せてほしいものだ。
寝室のたんすの側に八六がいた。三日前から猫風邪を引いたらしく調子が悪く寝転んでいる。普通の猫ならすでに治っているような病気なのに未だに回復しないのはおかしな話だ。
「八六、大丈夫か。」
「おう、赤助。大丈夫だとは…思うが、まだ休まねえと食事も取りに行けねえや。」
「何か悪いものでも食ったか?」
「いや、そんなはずはねえが…。一週間前に掛かった…時は完全に治ったんだが…。」
「一週間前にも風邪になったのか。」
「そう…。しばらく、元気だったのが…。なあに、治るさ…。安静にしていれば…。」
「もしかして、もらっちまったのかい?」
ちゃぶ台の部屋から虎猫の小鳥が入ってきた。
「最近、猫の中で回復力が失われる病気が流行ってるんだってさ。」
「回復力が…失われる…って、どういうことだい。」
「ただの猫風邪が治らないとか、傷がいつまでも塞がらないとか、さらに別の病気が発生するとか厄介な症状だよ。」
「心…当たりが、あまり思いつかねえんだが…。」
小鳥が八六のほうに近づいてくる。赤助は八六の隣に座り尻尾を振り小鳥の話に耳を傾けていた。
「どうも噂によると、子どもを作る際にかかる病があるって話さ。必ずってほどでも無いらしいから一概には言えないが…。最近、どんな感じだい?」
八六は黙り込む。
ああ、この様子だと心当たりがたくさんありすぎて絞れていないといった感じだろう。
まあ男なら仕方ない事のような気もするが。
「……四匹ぐらいかな…。運良く、盛りの猫にばったり会うから…つい…。」
「やはりか。御盛んなこってい。」
小鳥は八六の隣に座り、顔に猫パンチを御見舞いする。
「しょうもない奴だねえ。でも、それだけ相手すればどこかで子どもが生まれるから、男の役目を真っ当したってところかえ。」
「じゃあ…もしかしたら…俺っちは…風邪が治らなければ…死ぬのを待つって事かい?」
「残念だが…。魂になって、その病気にかかったって言って天に去ってく猫はたくさんいるんだよ。まあ、生きるための営みをしてなる病気じゃあ避けようも無いさ。」
八六と小鳥の間に、赤助が鳴いて入ってきた。
あまり病気に疎い赤助だったが、自分もすでに掛かっている可能性もあるから、知っておきたいという感情が芽生えた。
「なあ、小鳥。その回復力が無くなる病気ってのは見た目でわかるもんか?」
「んー、最初は分からないが後になって口や肌が荒れたりするらしい。」
八六の顔が青ざめ、口をはさむ。
「え…、俺…、今口が荒れてて…痛いんだが…。」
「本気かえ。」
「…ああ…。」
赤助は八六の不安を押さえ込もうと、小鳥に話を振る。
「そいつは、人間の持ってる薬で治るものか。」
「それが、人間にも治せないらしいよ。病気にかかって死んだ人間の側にいる猫の魂から聞いたが、治療薬や特効薬は作っているが病気が治るに至ってないって。」
「そうか…。」
人間が直す事が出来ない病気だと、猫の手には一生終えないのだろう。
人間は特別な頭を持っており、生物の中では一番の賢い生物だ。その人間がお手上げなのなら、どうしようもないのだろう。
「八六、元気出せ。俺らも回復するように手伝うから…。」
「ありがとうよ…、赤助。でもなあ、助からねえ時は…助からないもんさ。しょっぺえな…。こんな形で…おわるのか…。」
八六には悪い事したなと、少し反省の入った声で小鳥が呼びかける。
「元気を出しいや。まだ死ぬと決まったわけでも無いし、これから良くなる事だってあるでしょうに。」
「ごめんな…小鳥…。ちょっと弱気になりすぎたな…。もう少し…がんばって…みるよ。」
「そうさな。頑張りいな。回復するように祈ってあげるからさ。」
小鳥は立ち上がり、寝室の窓から外に出て行く。
「大丈夫だ。八六の元気さがあれば、回復する。自分を信じろよ。」
「わかった…。頑張る…。」
赤助は八六を励ますと、屋敷を出る。
赤助は塀に囲まれた砂利道を歩きながら、八六の病気について考えた。
あの病気は直せないものだろうか…。以前にも皮膚がただれて、消化できていない便しか出さず、そのまま死んでいった猫を何匹か見ているが助かる事は無かった。どうしたものか…。人間並みの頭脳があれば少しは直す手立てが思いついてもいいのだが…。
悔しいものだ。
「にゃーん」(ごきげんよう。)
赤助は唐突に挨拶されたので、挨拶されたほうを振り向く。そこにはわらの帽子を被った長い髪の女の人間が立っていた。頭の帽子には太陽のような花がついている。匂いはしないから多分作り物だろう。
「ああー。こっち振り向いた♪。」
何だ、人間が鳴いているのか。頭が太陽の人間はぴょんぴょんと飛び跳ねて喜んでいる。なんだろう。挨拶してくるなんて只者ではないな、この人間。
「にゃーん」(ごきげんよう。)
また挨拶してきた。どういうことだ?この人間、猫と対話が出来るのか。赤助は不思議になって首を傾げる。まあ、挨拶してきたなら返しておこう。
「にゃあ」(こんにちは。どうしたの。)
「あ、反応した。かわいいなあ、猫は。」
どうもかわいいと言っているようだ。
それにしても人間は我ら猫に向かって必ずかわいいと言うが、猫の容姿とか分かるものなのだろうか。気持ちの悪い波動を持つ猫もかわいいの一言で済ます。まあ、人間からすれば猫は猫なのだろうが。
「なーん」(しましょうよ。)
頭が太陽の人間は手を差し出しながら近づいてくる。
なんだと。盛りの時の鳴き声を出したぞ。
人間に誘われてもなあ…。無謀すぎる。
赤助は困惑していると、頭が太陽の人間は彼女の手が届く距離まで近づいていた。
赤助は屈んで、じっと警戒するように見つめていた。
良く分からないので警戒を張らなくてはいけない。
「はぁ…。やっぱかわいいなぁ…。あ、写真撮らせてよ。」
鞄の中から四角い物体を取り出した。
嫌な波動を発する板ではなくて、時たま光る小箱を取り出した。人間がよく使っているが、名前は分からない。とにかく夜の時は高い確率で光る。結構、危険な機械と猫の中では有名だ。
「えっと、待っててね。電源、電源…っと。」
頭が太陽の人間は小箱を構えて赤助に向けた。すると、小箱から丸い筒がにょきにょきと伸びだす。何か出てきたぞ。しかも、嫌な波動を発している。危険だ。逃げなくては。赤助は女性とは逆の方向に走りだす。
「え、あ、ま、待って~。」
筒が伸びた小箱を構えながら、頭が太陽の人間は赤助を追いかける。
何だ、追いかけてきた。
その小箱は何をするものだ。
分からないが、とにかく逃げるしかない。
人間から発する波動は気持ちのいい黄色の波動を出しているが、それ以上に筒のついた小箱は危なっかしすぎる。避けるしかない。
「待ってよー、ぎゃああ。」
頭が太陽の人間は着ている長い布を踏みつけて転んでしまった。
あ、何か悲しみの波動が増えた。痛いんだろうな。きっと…。
「うう…、に、なーん(ねえ、しようよ。)」
人間も盛りってあるのだろうか。
誘われても、なあ…。
良く分からないけど逃げよう。
気持ちいい波動があの人間を包んでいるが、何をしたいのかは理解不能で逆に怖い。
とにかく離れよう。
赤助は、倒れている髪の長い人間を横目にその場を去っていった。
「ああ…、白猫ちゃんの写真~。にゃーん(ごきげんよう)…。」
倒れている女の人間に、頭に大きな蝶を乗せた人間が近づいてくる。
「カナ…。何やってるの。」
「う…、う…。に、なーん(したいなあ。)」
「また犬か猫か追っかけて転んだんだ。ぷっ、カナらしいや。ほらほら、犬や猫ちゃんに迷惑かかるから、こっち来ましょうね。」
「にゃーん。(こんにちわ)」
「休憩終わり。そろそろ撮影の時間だよ。行くよ。」
そういうと、頭が太陽の人間を起こして手を引っ張りながら、来た方向へと帰っていく。
「なーーーん(しましょうよ。)」
人間は恐ろしいものだ。我ら猫の鳴き声をまねして猫を欺く事をする。
あの人間からは心地よい波動しか感じられなかった。我々猫達と遊んでいるのだろうと思うのだが、光る小箱を持っているから目的が読めず恐ろしい。
髪の長い人間から逃げるために走り回って、十字の飾りがついた建物の近くに着いた。
一度リキと一緒に来た事がある場所だ。
走り回ってちょっと疲れたかな。
丁度いい車があるからその下で休む事にしよう。
「ううっ…。汚れてしまいましたわ…。好きな人もできずに…。しかも、たくさん入ってしまいました。シスターとしての資格を失うどころか、どなたか存じませぬ種が私の中に入って…。しかも、ここは教会の地下室。罪を償う断罪の間といいますのに…。独房代わりに使うだなんて…。人間のすることではないですわ。」
「青助。いったい何処から…。あの配管から…。私のために…。ありがとうですわ。でも、ここにいたら貴方の命は…。逃げなさい。配管をたどれば大丈夫ですわ。私の事は気にしないで。さあ、お逃げなさい。」
「うっ、気持ち悪い…。苦しいですわ…。三日間も、三日間も。たくさんの種が私の体を…。嫌ですわ。この後どうなることやら…。ああ、青助…。聞いてくださいませ。私の人生はもうお仕舞いですわ。いままでも、これからも、私の中に悪意に満ちた者の種を受けることになりますわ…。ああ、救いがありません。でも、青助は生まれたばかり、未来がありますわ。さあお逃げなさい。偽善ぶった牧師たちがくる前に…。」
「はぁ、また来ましたのね…。もう、七日。吐き気なのか、つわりなのか、病気なのか、ストレスなのか、分かりませぬわ…。青助、私、貴方のように毎日来てくれる優しい王子様と一生を過ごしたかったですわ。でも、難しいですわね。そろそろ、悪魔がやってきますわ。貴方は、お逃げなさい…。」
「はぁ…、はぁ…。青助、またいらしてくれましたのね。でも…限界ですわ…。今日は、刺されましたの…。口封じとお腹の子どもの抹消…。ひどい方たちですわ…。そのうち天罰が下りますわ…。最後に貴方に会えて、良かったですわ…。もし、生まれ変われるのなら、貴方と同じ猫になり…、貴方の子どもを宿して…、産んであげたいですわ…。青助…、私の…優しい…王子…様…。あい…して…い…ま…す…わ…。」
「…あお……すけ……。」
「」
また夢を見た。
昔の記憶だろう。幼かった赤助は彼女のぬくもりを求めていたのかもしれない。
毎日、危険と分かっても彼女の元に訪れたっけ。
外見が違ったから気付かなかったが、ここはかつて住んでいた教会と呼ばれていた場所。今も呼ばれているのだろうか。
当時は木の匂いのする建物だったが、今は石での建屋になり匂いなんてしなくなった。
赤助がいた時は黄色い波動で包まれ温かい雰囲気がしていたが、今は黒い波動が強く、冷徹な雰囲気がする。思い出の場所も変わり果ててしまった。
何かどっと疲れた気がする。
八六の事に関しては何も分からなかったが、もう屋敷に帰って寝る事にしよう。
屋敷に戻ってくると、寝室に向かい八六の様子を伺う。
「調子はどうだい?八六」
「…ああ、赤助…。俺っちはもう駄目かもしれん。…ふふっ、命って脆いものだな。」
八六の周囲が便で汚れている。立ち上がる事もままなら無い状態だろうか、気温は温かいぐらいなのに四足ががくがくと震えている。息遣いも荒く、死んでしまうのでは無いだろうかと心配をしてしまうぐらいだ。
「まだ、望みはある。生きる希望を持つんだ。」
「へへっ……、希望は持ちたいのだがな……もう体が意思に付いていけん。悔しいが、俺っちの命もここまで…なんだろうなあ。」
「やめろ、八六はそんな弱気な猫じゃあないだろう。」
「いいんだ。俺っちは、赤助や小鳥、お竜にお桃、平七やリキと会えた事を…嬉しく思うよ。お前ら…といると、とても楽しかった…。最後は…一匹で…死にたいが……、ここで死にいくのも……悪くはないな……。へへっ……。」
「柄でもねえこと言うな。八六じゃあなくなるじゃないか…。」
「本当に…柄でも…ねえな……。そういえば、ご主人様もいってたっけ。諸行無常。命あるもの必ず衰えるってな…。…それが今なんだよ……。俺っちは…自分の生涯を…振り返って……満足だ……。だから、悲しむなよ、赤助。それこそ、らしくねえぜ。」
「お前に言われては仕方ないな……。」
赤助は八六と見つめ合った。
いままでの八六と過ごした時間を振り返るかのようにじっと見つめ合った。
いろんな事あったな。
ご主人様御手製のねこまんまを一緒に食べた事、図体のでかい縦縞の人間から美味しい魚を食べた事、大きな公園で白黒の鳥を狩りした事、屋敷の屋根の上でお桃と小鳥とで満月を見た事、どれもいい思い出だった。
赤助と八六は様々な思い出を目で語り合った。
「ふっふっふっ。」
「はっはっはっ。」
「なんか、気分がいいや。俺っちは一足先にご主人様のところに言ってるぜ。」
赤助は八六の発言に疑問を持った。
「ご主人様はそこで寝ているじゃあないかい。」
「いや、気付いているんだろ。もうご主人様は、この世にいない。」
「まだ生きているんじゃあないか。体系に変化が無いぞ。」
八六はふっふっふっと笑いながら話し出す。赤助が妙なことをいっていることがおかしいのだろう。
「もういいだろう。体が変化しないのは人間の食べ物のせいだ。魂はすでに天に昇っている。小鳥にも確認取ったさ。」
「……。」
分かっていたのかもしれない。
もうご主人様は起きないということを。
ただ、赤助は信じたくなかった。
死んでしまったと認めたくなかった。
「ご主人様は幸せだったとよ。俺っちや赤助、お竜やお桃に会えた事が、支えになった。たくさんの友達に囲まれて幸せだったと。」
ただ黙るしかなかった。
赤助の心を全て見透かされている気がして、反応に困ってしまった。
一番長い付き合いの八六には気持ちのごまかしが効かないのだな。
「わかるよ。ここの場所を教えてくれたのは赤助だし、五郎兄貴や、お竜、お桃を連れてきたのはお前だ。たぶんここが俺たちの住処としたのは赤助の努力なのだろう。ご主人様も俺らを優しく迎えてくれた人間の中でも神様の存在のお方だ。特別な想いをもっていても自然だしな。大切な人の死は認めたくないものだ。でも、赤助がしっかりしてくれなければご主人様も浮かばれないさ。」
「ご主人様…。」
「お前は俺っちの最高の友人だ。友人が元気に生きてるよとご主人様に報告しにいくよ。だから、赤助は赤助として、生きろ。」
「ああ、ありがとう。でも、まだお前も生きろ。俺の最高の友人だ。」
「そのつもりではいるさ…。もしものための言葉だ。まだ、最後ではない。安心しろ。」
「ああ。」
そうか…。ご主人様はこの世にいないか…。でも、見守ってくれているんだろうな。今、たくさんの仲間に囲まれてとても幸せだ。
「赤助!八六!大変だよ!」
顔を強張らせて、お桃が寝室に入ってきた。
「どうしたんだい。血相変えて。」
「人間が…人間が屋敷に侵入しようとしてんだよ。」
八:すべての焼失
表札に「高橋」と書かれたボロボロになった家の前で二人の男が立っていた。
二人とも黒とも紺とも言えるスーツを纏い、一人はこげ茶色の髪の男、もう一人は黒ぶち眼鏡をかけたひょろっとした男が玄関で会話している。
「やっぱり……。中に入るか。」
茶髪の男が覚悟を決め、引き戸に手をかける。
すると黒ぶち眼鏡の男が震えながらしゃべりだす。黒ぶち眼鏡の度胸の無さに茶髪の男はかなり苛々しているようだ、
「キノシタさん、入るんですか…、何か出てきませんかね?不気味なんですけど…。」
「マツモト、上司に言われて調査に来ているんだ。年金の給付の手続きが滞っている。ここのばあさんに話をつけねえと帰れねえんだよ。」
「これだけ呼びかけて出てこないなら、もう死んでるか、失踪してますよ。」
「マツモト、失踪ならいいんだが、死亡していたら大変な事だぞ。また孤独死がどうとかって…。ったく、行くぞ。」
茶髪の男は引き戸に手を掛け力任せに開けようとする。
だが、引き戸の鍵が引っかかって開かない。
開かないことにイライラしだして
「ああもう、うっぜーーー。」
と引き戸を蹴飛ばす。
引き戸は勢い良く玄関に倒れ、割れたガラスが飛び散る。
飛び散った破片は男二人の足に当たって床に落ちる。
「ちっ、怪我したらどうすんだよ。」
「キノシタさん、一応人が住んでるかもしれないんですよ。そんな手荒な…。」
「大丈夫だって。あれだけ呼んで、帰ってきたのは猫の鳴き声ぐれえだ。生きた人間はいねえよ。死んだ人間はいるかもしれんが。」
「やめてくださいよ…、冗談でも。」
「それを確認するのが俺たちの仕事だってーの。行くぞ。」
男達は割れたガラスの破片を踏みつけながら屋敷の中に入っていく。
スーツの男達は玄関から風呂場、トイレと調べ台所へと入っていく。
猫の尿や糞の臭いが二人の鼻に突き刺さる。
食卓の下に三毛猫と白黒まだらの猫がふーっと鳴きながら毛を逆立てている。
突然の人間の侵入に、怒りが頂点に達しているようだ。
「うわっ、くっせえー。いろんな臭いが混ざってんな。気持ちわりい。」
「どうも、猫の住処になっているようですね。噂以上に大量にいそうですよ。キノシタさん…。どうしましょう。」
「おらぁ!」
茶髪の男は食卓を力いっぱい蹴り上げる。反動で食卓は少し浮かび周囲の椅子を薙ぎ倒す。6つある椅子のうち5つが倒れ、一つが向きを変える。二匹の猫はすっかり怯えてしまったが、男達を追い返そうと睨みつけてふーっと泣き叫ぶ。
「平七、この人間、やばいっす。下手したら死ぬかもしれねっす。」
「リキ、ひるむな。体が動かなくても睨みつけて追い返すんだ。」
「はは、びびってやんの。ここは臭いだけで人の気配なし。次行くぞ。」
「キノシタさん…。あまり乱暴にしないほうが…。」
そういうと二人はちゃぶ台のガラス障子を開ける。
ガラス障子を開けると黒猫と虎猫が襲い掛かってくる。
「ひぇぇぇ。」
黒ぶち眼鏡の男は怯えてかがんでしまう。
「痛っ。くそっ。」
茶髪の男は不意打ちの攻撃を手に受け、腕に切り傷をもらう。怒りに達した男は黒猫を掴み、虎猫に投げつける。黒猫と虎猫は積みあがった座布団の上に思い切り叩きつけられる。
黒猫と虎猫はふらふらになりながら立ち上がる。
「小鳥、大丈夫か…。乱暴な人間だねえ。ふらふらだよ。」
「お桃、なんとか平気だけどちょっと頭がぐらぐらしてるわねえ。」
「人間様に歯向かおうなんざ、早いんだよ!」
茶髪の男はちゃぶ台を掴み上げ、猫二匹に向かって投げ飛ばす。猫二匹に直撃はしなかったが、頭上の壁にぶつかって足が取れてしまう。足が壊れたちゃぶ台の台部分が二匹に覆いかぶさるように倒れる。
「ひ、ひいいぃぃーー。」
かがんでしまった黒ぶち眼鏡の男は、台所にいた二匹の猫に顔を引っかかれた。あまりにも痛かったのか、顔に傷が付いたのがショックだったのか、慌てて猫屋敷から出て行った。
「ちっ、あいつ減給にでもしてもらうか…って、俺たちは公務員だったか。はぁ、あいつと同じぐらいの給与しかもらえないってのは悲しいね。国が傾いたら賞与カットで公務員締め上げとか。ここの猫が政治やったほうが平和なんじゃね?ああ、それは猫に対して失礼だな。失敬失敬っと。」
茶髪の男はちゃぶ台の部屋を通り、寝室の襖の取っ手に手をかけた。男は寝室の下の部分が破れていることに気がついて独り言をつぶやく。
「襖に穴開けっ放しなんて、神経おかしいね。となると、しばらく人は住んでないと考えてもいいな…。はぁー、とっとと仕事を終わらせて風呂でも入るっかな。」
男が襖を開けると寝室に辿り着く。
中央に布団が敷かれており老婆が眠っているのを見つける。
老婆の体はかろうじて原型は留めているものの、激しく衰弱しており生きていないのが触れなくても分かる。
「やっぱり、死んでたか…。あんまり腐敗が進んで無いのは保存料が蓄積されたとか言う現象か。へっ、報われねえな。」
男は布団の側に行き様子を見る。
「はぁ、寝息も聞こえねえか…。触る気もしねえや。」
布団を捲り上げようとした時、部屋の隅でかがんでいた三毛猫が左手を噛み付いてきた。
さらに頭上から猫らしき存在が飛び掛ってきた。神棚置き場で待機していたようだ。
「ぐわぁ。痛たたたたた。離せ、離せよ。」
右手で左手に噛み付いている三毛猫を取ろうとするがなかなか外れない。噛み付きながら三毛猫がふーっと鳴いている。
「おめえに、汚い手でご主人様に触れさせねえ。屋敷から出て行け!」
さらに神棚から飛び降りた白猫が男の左頬を引っかく。頬に付いた傷口から血が垂れてくる。
「何だ貴様ら!そんなに死体が大切かよ!。」
茶髪男は噛み付いている三毛猫の首を右手で掴み頭上に持ち上げ、仏壇の白猫のいる畳のほうへ向けて叩きつける。
「ぐわっ。」
「八六!」
男はさらに三毛猫を頭上に上げては畳に叩きつけること二回、三回と繰り返す。
噛み付いていた三毛猫から力が無くなり、男の左手から外れた。
亡骸となってしまった三毛猫を男は振りまわす。
「貴様ら、人間様に楯突くんじゃねー。この猫みたいになってもいいのかよ。」
男は痛みと悔しさで寝室で暴れまわった。
箪笥は布団の上に倒れ、仏壇は壊され、三つの地蔵の置物は老婆の頭周辺にひび割れながら散らばった。
猫達は寝室に集まり男に攻撃を仕掛けた。
黄土色の虎猫は右手を引っかき、黒猫は右足首に噛み付き、白猫は左足に噛み付き、襖のあったところから、三毛猫とまだら猫が怒りの鳴き声を発している。
「八六兄貴をよくも!」
「八六死ぬんじゃないよ!」
「よくも八六を!」
男はあまりの痛みに三毛猫を老婆の傍らに投げ捨て、窓を割りながら寝室を飛び出した。
猫達は男の振り払う力によって寝室のあちらこちらに飛ばされる。
「なんで、こんな痛い目に会わなけりゃあ何ねえんだよ!この代償は高くつくから覚えてろよ。化け猫どもが。」
茶髪の男は不機嫌になりながら、頬、足首、左手から血を流しつつ、体中の痛みを堪え屋敷を後にする。
猫達は屋敷から追い出すことに成功した。
が、大切な仲間を失った。
「くっ、八六…。お前は弱ってたんだ。すっこんでれば良かったものを…。」
赤助は悲痛の声を出しながら呟く。
老婆の隣に倒れている猫の姿に屋敷の猫が群がる。
「八六兄貴…、ただでさえ弱っていたのに…無理しないでほしかったっす…。」
リキが八六に近づき鳴いた。
しかし、八六は立ち上がるどころか返事を返す事も無かった。
ただ静かにたたずんでいた。
「同じ三毛猫の男がいて心強かったです。起きて下さいよ。」
部屋の隅で丸まっていた平七が呼びかける。しかし、返事に応じる事は無かった。
「小鳥…、どうなんだい。八六の魂はどうなったんだい。」
お桃は涙を流しながら小鳥に尋ねる。
小鳥も涙を流して八六を見つめた。
「おおらかな魂が私に言ってきたよ。すまねえ、ご主人様のところに会って来るよと残したきり、なにも感じなくなったよ…。信じたくないねぇ。」
赤助は割れて庭が丸見えになった窓の淵に飛び乗った。
「赤助、いったい何処に行くんだい。」
「すまねえ、お桃。なんだか苦しいんだ。命ってあっけねえなってさ。苦しくて耐え切れねえ。ちょっと、外行って頭冷やしてくるわ…。」
「ちょっと、赤助…。」
窓から飛び降り、屋敷を飛び出した。
「お桃、追いかけないのかい…。」
「痛、…あの茶髪の人間から受けた傷が痛くて…。追っかけれねえよ。小鳥は…。」
「ちょっと休まないと無理だねえ…。」
小鳥とお桃は、茶髪男から受けた傷が深かったのか自由に動けなかった。
茶髪男を攻撃する時は結構無理していたようだ。
「姉御、リキがひとっ走り行ってくるっす。」
「リキ大丈夫かえ。」
「何とかなるっす。それより、平七の兄貴の体力が心配っす。」
平七は、寝室の一角で体を丸めている。茶髪男が暴れた際に、体を蹴られたらしく、身動きが取れない。
「わかったよ。見ててやるから、赤助をよろしくな。」
「了解っす。」
そういうとリキは赤助のを探しに窓から飛び出した。残されたお桃、小鳥は平七の横に囲むように並び丸くなった。すぐにでも眠るような体勢だった。
「めんぼくないです。」
「気にしなさんな。それより、どうしようかね。」
「お桃、どうしたかえ。」
「屋敷中が荒らされてしまったじゃないかえ。置かれているものをさ、全て薙ぎ倒していってなあ。あたいたち猫の手ではもとに戻すこともできやしねえ。」
「そうねえ、神様への道と、ご主人様の子供達の化身が割れてしまって…。悔しいねえ。あの人間、呪ってやろうかしら。」
平七は、慰めるようにお桃と小鳥の頬を舐める。
「今は休んで下さい。でないと、命を張った八六さんに申し訳ないです。」
「そうね。ありがとよ、平七。」
「すまないねえ、平七。」
三匹の猫は互いの体を寄せ合って傷を癒すべく眠りについた。
気がついたら小さな公園に着いた。
どうやってここまで来たか覚えていない。あたりはすっかり街灯に包まれ、月が夜空に浮かんでいて満月が少し欠けていた。
目の前で八六が死んだ、しかも人間に殺される形で死んでしまうなんて…。
普段は感じないのにこんなに苦しく感じるのは意外だった。ああ、シャロンに会いたい…。そっか、シャロンの家に行ったけど、屋敷の中に入れなかったか…それすら覚えていないなんて。いや考えが纏まらない寝てしまおう。
寝れば気分も回復するだろう。ベンチの下で丸くなり眠りに着こうとした。
「あー、猫ちゃんだー。」
小箱を構えた太陽の帽子を被った女の人間が覗き込むように目の前に座っていた。
そういえば、以前我々の鳴き方をまねして会話しようとした人間か。赤助は小箱からの嫌な波動よりも疲れの方が優先していたため、丸まったまま、動こうとはしなかった。
「猫ちゃん元気ないね。どうしたの?」
女の人間は赤助の頭をやさしく撫でた。この女性の柔らかい黄色い波動は赤助に安らぎを与えてくれる。悪い気分ではない。
「よいしょっと。」
人間は赤助を抱きかかえ自分の膝元に赤助を置いた。赤助は人間に即されるまま膝で丸くなる。丸くなった赤助の体を優しくさする。
「よしよし、悲しい事飛んでけー。」
ああ、不思議と疲れていたものが飛んでいく。
赤助は心地よくなって、人間の膝に頭をすりすりしながら、目を閉じる。
「猫ちゃん、寝ちゃうの。お休みなさい。」
人間の声が優しい子守唄のように聞こえた。
懐かしい温かい波動を感じる。
そうか、ご主人様や、小さいころに御世話になったサイトウと同じ匂いがするんだ。
こんな感じの人間だけ住んでればいいのにな。
赤助は温かい波動に包まれて眠りに着いた。
「おんやあ、赤助かえ。久しぶりだねえ。どうしたんだいこんな所で会うなんて…。」
「そうだねえ。申し訳ないねえ。挨拶もせずに先に行ってしまって。」
「人間もさ、いつ逝くか分からんものでねえ。いつの間にか天に昇ってしまったんじゃ。」
「寂しかったんだねえ。でも、強く生きないといけないよ。」
「ただいま、ご主人様。」
「あらあら、八六じゃあないかえ。どうしたんだえ。」
「今日、人間に殺されてやってきました。悔しいです。」
「そうかい。痛かったろうに…。」
「ごめん。ご主人様の屋敷、悪い人間に荒らされてしまった。」
「いいんだよ。あの屋敷は十分役割をはたしたよ。私たち家族に楽しい時間を与え、お前たちの安らぎの場になっていた。屋敷も本望でさ。ところで、八六。どうしたんだい。」
「そうでした。赤助。今すぐに戻るんだ。俺を殺した人間がやってくる。」
「だんだん近づいてくるよ。」
「ご主人様、助けにいけないのが悔しいです。」
「しかたないねえ。これも運命だよ。それより…逃げ遅れた猫ちゃんたちが心配で。」
「赤助。急げ。そうしないと俺たちの仲間が…。」
「心配だが、仕方ないねえ。事の成り行きを見守りましょう。」
「やはり、あの人間は呪い殺すべきだったか…。」
「八六、そんな事思うんじゃあ無いよ。赤助…。生きるんだよ。」
赤助は目を覚ました。夢だったのか…。かなり現実味があった夢だった。
もしかして…。
急いで帰らなくては…。
赤助は人間の膝から飛び降りて屋敷の方向に勢い良く走り出した。
嫌な予感が頭の中をよぎる。お桃、小鳥、平七、リキ…。無事でいてくれよ。
「あ、猫ちゃん。どうしたの、待って。ぎゃあ。」
急に飛び出す赤助を追いかけようと頭が太陽の人間は転んでしまう。もっていた小箱が地面に落ちて跳ねる。
赤助が猫屋敷に着くと昼にやって来た茶髪男と黒ぶち眼鏡の男が屋敷に火を付けた後で逃げ出そうとしていた。
傍らに目を開けたままリキが倒れている。体に銀色の物体が突き刺さっており、寝ている体の周りに血だまりができている。
赤助は走る速度を上げ、男二人に襲い掛かろうとする。
猫屋敷の玄関辺りで茶髪男がガソリンを掛けると火を放った。茶髪の男は体のあちこちにテーピングやら包帯やらがついている。猫屋敷の猫にやられた傷が未だに痛むようで頭に血がのぼっている。火はガソリンに点き勢い良く燃え上がる。木造の屋敷はすぐに火の勢いを上げ、玄関、台所、寝室、ちゃぶ台部屋と炎が広がっていく。
「キノシタ先輩やばいですよ。さっさと逃げましょうよ。」
「ぬるいよ、マツモト。俺に怪我させまくった悪い化け猫たちが住む屋敷だぜ。何も問題はねえよ。家主も死んでるし、苦情も多かったんだ。燃えてなくなれば解決じゃねえか。もう少し、浄化の炎を見ていこうぜ。ッヒャハッハッハ。」
「早く、早くしないと見られちゃうよ……。痛い!」
黒ぶち眼鏡は足に痛みを感じる。足元を見ると白猫が足首を噛み付いていた。
「ハハッ。こいつはいい。お前も仲間と一緒に黒焦げにしてやる。」
茶髪男は白猫を火の中に投げ込むため掴みかかろうとする。
茶髪男の攻撃をかわし道路まで逃げる。
大柄の体格の割りにすばしっこく、白猫はだんだん疲れを蓄積させ体の自由が利かなくなってくる。
「いやー。火事よ!」
近所の人の声か火事が発生している事に気付き叫ぶ。茶髪の男は不機嫌そうに、黒ぶち眼鏡の男は挙動不審に反応する。
「い、い、い、急ぎましょう。せ、せ、せ、先輩。」
「ちっ、焼き猫にならずに済んだなあ…。おらあ!」
茶髪男は逃げていた白猫に狙いを定め蹴りを放つ。
疲れきった白猫は反応が遅れてしまい彼の足がお腹辺りに直撃する。
反動で空中に飛ばされ、玄関近くの電柱にぶつかる。
白猫は体中から出てくる痛みの感覚により、立ち上がれなくなる。
「ざまあ、みやがれ。そのまま仲間と死んでしまえ!」
二人の人間は屋敷から、遠のいていく。
白猫は目の前の屋敷を見た。
すでに屋敷全体に火がまわってしまい、黒い煙を挙げながら勢いを挙げていく。
「お桃…」
猫屋敷から物が崩れる音がする。何処かで屋根が落ちた音だろう。
「小鳥…」
屋敷周辺を人間が取り囲む。白猫の視界は集まった人間の足しか映らなくなった。
「平七…」
視界が白くなっていく。ああ、どうも俺も皆と一緒に八六のところにいくことになるようだ。
さようなら、ご主人様の屋敷。俺らの居場所…。
九:白猫の終着駅
「ああ、あの時の白猫…青助ね。覚えているかい。教会であった厚い布で覆われたおばあさん。シスターですよ。でも…今はシスターでも何でも無いですね。何せ、四人もの人間を殺めてしまい、天に召されずに、地にも落ちきれずに、魂だけがこの世に残ってしまってますから…。」
「私の罪を聞いてください。勤めていた教会を異国の牧師に追い出され、乗っ取られた後、ミス・サイトウが捕まってしまいました。私は何度も、何度も、あの子を開放するように牧師にすがりました。牧師は、上質のお嬢様は神へ捧げられます、と言って彼女を解放しなかったのです。ただ単に、彼女を汚したいだけなのに。」
「交渉も進まず悩んでいた私は、交渉の後、必ず教会をぐるりと回ってから帰るようになってました。白猫が教会の側をうろついているのは分かってました。そう、青助。貴方です。貴方は交渉に来るたびに私に姿を見せていました。私は逃げるように促したのですが、貴方は逃げようとしませんでした。芯の強い猫だと感じました。」
「ある日、教会の裏側の配管から青助が出てくるのを見つけました。その白猫は赤い血で汚れていました。私は、白猫をお湯につけて洗いました。尻尾についた血が取れませんでしたが、その他の場所は綺麗に洗いました。そこで私は気がつきました。ミス・サイトウは子を身ごもり口封じのため殺されたと。」
「私は、教会で牧師と私が二人きりになるように待ちました。そして、二人きりになる事が出来た私は、隠し持っていた毒針で牧師を殺しました。教会内を調べた所、ミス・サイトウを見つけました。でも、彼女はもう……。錯乱した私は教会に火をつけ、自殺しました。私と牧師、ミス・サイトウと身ごもった子どもの魂を火葬という形で天に、地に帰してあげようとしました。」
「しかし、私は天にも地にも行く事を許されず、現世に留まる事になりました。天使からも悪魔からも魅入られなかったのです。でも、青助。貴方のおかげでミス・サイトウは幸せになったと天から告げられました。私の長い旅は終わろうとしています。彼女を大切にしてくれてありがとう。」
俺は目が覚めた。
どうしてあの時の人間が夢に出てきたのだろうか。
あの人間の最後の話を聞かされた。そしてサイトウは幸せになったと知らせに来たようだ。
幼いころにお世話になり、幼いなりに愛にも近い感情を抱かせた人間。
サイトウの時は不幸に浸かり死んでいった悲劇の人生だった。
幸せになったと言う事は何処かで彼女の魂が生きているということか、生まれ変わったのだろうか…。そうであるなら、是非幸せになって欲しいものだ。猫には難しすぎる気がする。老婆さん、お休みください…。
さて、俺はいったいどうなったのだろうか。
死を覚悟した時、業火に焼かれる屋敷を横目に死んだのだろうと思ったが、まだ生きているようだ。
ここは何処だろう。かごの中に閉じ込められている。人間の屋敷だろう。薄型のテレビだったり、机だったり、タンスだったりと人間が使う物がたくさん置かれている。人間に捕まったのだろうか。体中の至る所に白い布が撒かれている。布が巻かれている場所は怪我して痛む所と一致する。こんな器用なことができるのは人間のしわざだろう…。
「あは。白猫さんが起きたー。お母さん、見て見てー。白猫さんが起きたよー。」
頭を肩結びしている小さい女の人間がかごの下からいきなり覗き込んできた。
俺が起きた事を確認すると、嬉しかったのか部屋中をぴょんぴょん飛び跳ねていた。
しばらくして、女の子は近づいてきて、話しかけてきた。
「あのね、あのね。わたしね、ヨシコ。ヨシコって言うんだ。君がね、倒れて苦しんでたから病院で見てもらったの。起きたらね、大丈夫って言ってたから、もう大丈夫だよ。よかったー。」
ヨシコという女の子が俺を彼女の屋敷に連れてきたようだ。
頼んでもいない…といった雰囲気で彼女を見つめる。
「ごめんね…。お友達、死んじゃったんだよね。でも、君を放って置く事ができなかったの。猫ちゃん苦しそうだったから…。」
俺の考えている事が分かるのだろうか…。そんなわけ無いが、この子なりの優しさでここまで連れてきてくれたのだ。
そして、生きている。
一応感謝しないわけにはいかないな。
俺はにゃあと一言鳴き、かごに掛けていたヨシコの手を舐めた。
「ありがとう、早く元気になるといいね。」
輝く笑顔を見せられて、安心した。
綺麗な黄色い波動を出している。
悪い人間ではないから、また眠りについた。
怪我を治さないことには何もできないから。
俺はこの幼い人間、ヨシコと、その母親と思われる人間に介抱されることになった。父親は普段は家にいないらしいから、実質ヨシコと彼女の母親に介抱されることになる。
日光を一日中感じることができないが、時計というのが目の前に飾られている。あれは二回一周すると一日過ぎる仕組みとなっている。これからは時計という道具で日を考えるしかない。猫屋敷にいた時もご主人様が使っていたから大体覚えている。
かごに入れられて一日目、ヨシコは自分の名前を決めようとする。
「白猫さん、白猫さん…。おかあさん、白猫さんの名前何がいい?」
「そうねえ、シロなんていいんじゃない?」
「嫌、率直すぎ。うーん。」
ヨシコはきょろきょろと部屋を見回す。部屋にはぬいぐるみや人形がたくさん飾られており、そのうちの目に傷がついた白猫と上に乗る忍者のぬいぐるみを白猫の前に出した。
「よーし、今日からお前は青助だー。この忍者と同じ名前ー。」
「おかしな子ね。青助って猫じゃなく忍者でしょう。猫は白丸じゃないの。」
「ううん。この子は青助がいいっていってるの。目も青いし。だから青助ー。」
「そう?じゃあ、白猫ちゃんは今日から青助ね。」
懐かしい記憶が蘇る。
幼いころに呼ばれていた名前でまた呼ばれようとは、何か運命的なものを感じる。ヨシコは猫心を読み取る人間なのだろうか、不思議な人間だ。
そういえば青助と呼んでいたサイトウと似たような波動を感じる。無意識のうちにヨシコの面影を彼女に合わせていた。
俺を赤助と呼ぶ仲間はもういない。今日から俺は青助で反応する事にしよう。その名前で呼ばれる事になるとは意外だった。俺は尻尾をふり喜びを表す。
二日目だ。どうも体力が回復が芳しくない。一応生活するには問題が無いが、いつ死んでもおかしく無いと感じる。
「青助ー。おはよー。」
ヨシコが挨拶しているようだ。こっちも挨拶をしておこう。
「にゃあ」
「いいこ、いいこー。ご飯あげるねー。」
ヨシコはかごの上部をあげ食事の入った器をゆっくりと入れていく。魚と豆の匂いが香ばしく感じる。懐かしい。ご主人様が良く作ってくれたあの食事、死ぬ前にもう一度食べたい食事だった。
「青助。ねこまんまだよ。これ食べて元気になってね。」
器の中にはご主人様がよく作ってくれた「ねこまんま」という食事が用意された。味はご主人様のくれたものとは少しだけ味が違うが美味しい。これを食べれるなら元気になる気がした。俺はあまりにも美味しくて米粒残さず食べきる。
「うわあ。全部平らげちゃった…。大好物なんだね。じゃあ、毎日のようにあげるね。おかあさーん。」
ヨシコは俺が食べる姿を見て、ねこまんまが大好物と判断したようだ。どうも俺の心を見透かされてる気がする。本当に不思議な人間だ。
三日目、体中が痛みが引かない。体をあまり動かす事が出来ない。もともとかごの中に入れられては動く事も出来ないのだが。俺はじっと眠りながら体の回復を待った。
「青助…。痛いの?大丈夫、痛くなくなるように御まじないをするね。いたいのいたいのとんでけー。どう、直った?」
痛みが引いたわけではないがなんとなく気分が和らいだ。
ヨシコから溢れる黄色い波動は俺に安らぎを与えてくれる。
この波動には元気付けられる。
ありがたい。
四日目、どうも風邪を引いたらしい。
怪我も治ってはいなく、体のあちこちが痛む。
たまにくしゃみをするが、出るたび体が軋む。
毎日食事にねこまんまが出てくるのは嬉しい事だが食が進まない。
「どうしたの。元気ないね…。くしゃみもでているし…。お母さん。」
俺は病院という場所に連れてこられ、白い服の男に体をいじられた。
細いものを体に刺し血を抜かれたり、筒状の機械に入れられたり、機械に繋がった紐状のものを全身にくっつけさせられ寝かされたり、身の毛もよだつ様な事をさせられた。
「がまんしてね。赤助の病気を調べるの。いいこ、いいこ。」
ヨシコが側にいてくれたり、撫でてくれたり、声援を送ってくれたので、何とか耐える事が出来た。
いろいろ体をいじられた後、ヨシコに抱えられてしばらく待っていた。
「怖くないよ。大丈夫だから…。」
優しく体を撫でてくる。
ヨシコの顔が哀しそうに見え、今にも泣き出しそうだった。彼女から溢れる温かい波動が弱々しくなっているのが分かる。
元気を出してもらおうと一言鳴いてみた。
「にゃあ」
ヨシコは目を擦り涙をこらえると、笑顔をつくり赤助に見せた。
「ありがとう。青助、元気になるよね。」
少しだけ波動の強さが戻った。彼女が元気で無いと自分まで沈んでしまう。明るくしておいてほしい。
また、白衣の男の前に連れてこられる。
先ほどの時と表情が険しく腕を組み重々しい空気を放っており、波動も重く堅苦しい。
白い服の男は雰囲気と同じ感じで口を開いた。
「感染症にかかってます。健康ならば耐えられるのですが、免疫力が弱まって怪我の治療中の青助くんには厄介な病気です。しかも………かなり治癒力も低下しています。おそらく、何日も持たないと思います。」
自分の体の病気について述べたようだ。
白衣の男から出る感情が混じりあった暗い波動によって、この世で生きていられるのも少ないのだと読み取ってしまう。
白衣の男話を聞いたヨシコがうわーんと声をあげて泣き出した事が、確信へと運ぶ。
温かい波動が悲しみの波動に切り替わる。ヨシコが元気を無くしたのが俺も悲しい。
「先生。お願いします。青助を…青助を助けてください。」
ヨシコの目は涙の洪水でいっぱいになっていた。彼女の必死さと苦しさが俺にも伝わってきた。
一方、顔色を変えない白衣の男からは暗い波動が出ている。
人間が希望をもてないときに放つ波動である。
どうも、俺の体は深刻な状態のようだ。
「全力を尽くしてはみます。一晩、体力回復のための点滴と感染症の抗体を高める薬を投与して様子を見ましょう。効果は出るか分かりませんが、試してみる価値はあるでしょう。」
感情と言葉が真逆になっている。
ヨシコを元気つけようとしての言葉だろう。彼女の悲しみの波動が和らぎ、本来の温かい波動が少し戻った。
「ありがとう。一晩お別れだけど、元気になるんだよ。」
そういうと怪我をしている猫や弱っている犬が集まった檻のひとつに入れられた。
うすい黄色の服を着た女の人間が開いている檻のひとつに俺を閉じ込めて
「青助ちゃん。今日はここで過ごしましょう。大丈夫ですよー。治りますからねー。」
と言って去っていった。
腕には液体が入った紐がくっついており、俺の体の中に入っていくようになっているようだ。
黄色服の人間も、やはり暗い波動しか出していないから、言葉は俺の不安を取ろうとしただけだろう。仕方ない。もう駄目だとは思うが人間の指示に従っておこう。
檻に入れられてしばらく眠ると、当たりは暗くなっていた。
窓からほのかに月の光が入ってくる。よくは見えないが半月の形をしているようだ。目の前に鏡があり部屋の全体像が見える。俺のほかに三匹の犬と二匹の猫がみえる。
檻の周囲は壁で囲まれているので互いの姿は見えないが、鳴き声は聞こえる。一匹くーんくーんと小さい犬が吠えているが何を言っているのか分からない。
動物だからといって犬の言葉を理解できる猫は早々いない。
ある程度の波動は感じることができるが、ここにいる動物で元気がいい動物はいなく、今にも消えそうな弱々しい波動を発している。
一匹の猫がつぶやくように鳴いた。
「ああ、あたしさ…。子ども作れなくなっちゃった…。発情の感覚もなくなっちゃった。子宮という部分を取られちゃったみたい…。」
聞こえてくる声の持ち主は女の三毛猫だ。自分の真下の檻に入れられている。人間に飼われている様子で、子どもの作る部分を奪われたらしい。悲しいな。気乗りはしなかったが反応はしておこう。
「しきゅう?」
「お腹の中に子どもを抱えるための部分だって。女の猫なら誰もが持ってるものだとさ。人間がそれは不要だからといって、私からとっちゃったのよ。」
「ひどいことするなあ、あんたのご主人様。生きる意味を失うのと同じでしょうに…。」
「そうでもないのよ。子どもが作れるままにしておくと、いつか捉えられて逃げたら確実に殺されるんだってさ。生きていられるんなら、まだいいほうかなって…。」
「悔しくねえか?」
「悔しいけど、生きていられるならマシじゃないかえ。死ぬよりかはいいと思えば。」
「そんなもんかね。」
「ご主人様の元を離れても、生きていけそうに無いからねえ。私は我慢するよ。」
自分達のご都合主義で猫の生涯を狂わすのは気に食わない。
が、人間にだって考えがあるらしい。わざわざ子作りの機能を奪うなんて面倒なことをするということは、意味があるからに違いない。多分、涙を流しながら機能を奪ったのだろう。
なんとなく、今の俺には理解できそうだ。この三毛猫もご主人様の気持ちを汲んでいるのだろう。
「そうか…。頑張れよ…。」
「あんたもね。あんたの方にその紐が向かってるってことはもう死にそうなんだろう。あんたの右の猫、日が七回落ちる時間つけてるんだってさ。大変よ。」
自分の右隣に同じように紐をつけた黒猫が檻の中にいた。
かなり弱っていてもう十回以上季節の移り変わりを見てきているようだ。
体の震えが鏡越しでもわかる。
「んん、ああ。いい年なのに…。点滴とは、大変じゃのう…。」
ご老体の黒猫が鏡越しに自分の様子を見ながら話しかけてきた。
「てんてき……。この紐と袋のことか?」
「ここに入れられ七回日が落ちた。人間の会話から知った事じゃよ。なんでも、元気になる液体らしいが……。気休め程度には効いておるかのう。」
鳴き声も少し弱々しい。今にも死にそうだ。
「なんか…。死ぬのを覚悟しているような…。」
「そうなんじゃあ…。ご主人様が死なせないと白衣の人間に頼んでいろいろ手を施してくるんじゃが…。生かされてる感がしてのう。もう体は死を求めておるのじゃあ。」
老衰して自分は死を覚悟しているようだ。けれどご主人様の手によって命を永らえているようだ。生きていることはいいことだと思うが。
「わしはもう十分に生きたよ。ご主人様に愛されていた。幸せじゃった。だから、いつ死んでもわしは構わないよ。だが、寂しいんだろうねえ。ご主人様は死なせないように努力をしておる。」
「ご老体、ご主人様はどんな感じの人間だ。」
「わしと同じぐらいの年老いた『つがい』じゃあ。二人の間にはなあ、子どもが恵まれんかってのう。わしはその子ども代わりじゃった。長年子どもとしてわしの面倒を見てくれた…。わしが死ぬ事はご主人様にとっては子どもを失うことと同じ事なんじゃろうて…。」
俺は猫屋敷のご主人様を思い出した。
ご主人様はたまに物憂げな寂しい青色の波動を放っていた。
彼女は夫と子どもを失っており、俺や八六、お桃たちを家族のように扱ってくれた。そんなご主人様に出来る事は、元気な姿を見せることぐらいしかなかった。このご老体も気持ちは同じなんだろう。
「でもなあ、わしはいつか死ぬ。生きてるものは死ぬんじゃあ。ご主人様にはわしがいなくても元気でいてほしいんじゃあ。わしが死ぬ事でご主人様の新しい人生が見えてくる気もするんじゃあ。だから、老いぼれは先に死んで二人を待っていたいんじゃあ…。」
水を差すように三毛猫が会話に割って出た。
「老猫さん、死にたいなんて言うもんじゃあないよ。猫は生きて何ぼだろ。ご主人様が老猫を生かしておきたいと感じてるんだ。それに賛同しな。」
「分かっておる。でも、全身の自由が利かなくなってきておる。生きる気はあっても体が追いつかん。悔しいが、死は近い。」
三毛猫は老いた黒猫から固い意志を感じ、苛ついていた感情を押さえ込んだ。
「すまん、悪かった。でも生きてることが重要なんだよ。」
「若い者に説教されるとは、わしも幸せなもんですなあ。ふぉふぉふぉ。」
老いた黒猫から幸せの波動を感じ取れた。生きる気力がまだ残っているようだ。良かった。
「時に、若い白猫や。お主に点滴は早いじゃろうて。大変じゃのう。子守唄変わりに。お主の話を聞かせてくれまいか。」
「そうだねえ。私も聞きたいよ。あんた、結構な苦労猫っぱいし。話しが面白そうだ。」
俺は少し戸惑いもあったが、それで体の震えや痛みを忘れる事が出来るなら、しておこうと感じた。
「ああ、わかった。」
死ぬ間際だというのに、俺には分からない世界が広がっているようだ。
まあ、世界を全て知るためには、魂だけ残り何年も世界を見る事ができればいいが、その時は生きているときの意思は無いらしい。
最後に面白い話が聞けた。俺も面白い話を聞かせよう。
五日目、一晩檻の中で過ごした。
人間の施した点滴やら薬やらは利いている気がしない。くしゃみやら風邪やらが悪化した。目覚めるとヨシコと彼女の母親が自分を引き取りに来た。
「昨日よりも体力が低下しています。薬や点滴は若干効いていますが効果は薄いです。」
「……。」
ヨシコは俺を腕に抱え、沈黙している。彼女から発する波動は悲しく青い。今にも泣き出しそうだ。元気を出してほしいと彼女の顔を舐める。
「どうしますか。点滴と薬を投与するのが最善策ですが…。」
「ありがとう。でも、青助と一緒にいてあげたいから、お家に帰る。」
涙を拭きながら、ヨシコは答えた。白衣の男はふんわりとした笑顔で俺を見た。
「その方がいいでしょう。獣医としては入院を勧めますが…。飼い主の側で息を引き取るのがこの子にとっても幸せでしょう。」
「うん。」
悲しい波動は幸せの波動に色を変え、俺を心地よい気分にしてくれた。
「にゃー」(独りで死ぬよりかはマシじゃよ。よかったのう。)
「なー」(帰れてよかったな。頑張れよ。)
一晩ともに過ごした猫たちも声掛けてきた。
体の痛みはあるけれど、幸せに包まれている感覚がした。
「にゃあ」(ありがとう。)
六日目、俺はヨシコの膝の上で丸くなっている。
彼女が学校やら母に呼び出される以外は彼女が俺を膝に乗せ、常に体を撫でてくれる。
体力がなくなり、全身痛みを伴っているが彼女のおかげで穏やかな気持ちになる。
「ヨシコ。青助の食事だよ。」
出てきた食事はねこまんまだった。
量は少なく食べやすかったので、俺はおいしく平らげた。
窓の外が暗くなり昨日見た半月がまた顔を出している。
「ヨシコ、そろそろ寝なさい。」
「嫌!青助と一緒にいる。赤助を悲しくさせたくない。」
といった会話が繰り広げられ、俺の居る部屋に布団を持ってきて眠っている。
俺は檻の中に入れられているが、ヨシコの枕の上に置かれている。
置かれた位置が窓際であるため、月やら星やらが良く見える。
月の光が心地がいい。
周囲は静かでヨシコの寝息が聞こえる。
たまに、
「青助…、大丈夫だよ…、怖くない…。」
といった寝言が聞こえてくる。
初対面の人間にここまで優しくされたことはなかった。
大切に思ってくれるんだと、感謝の気持ちがいっぱいだった。
しかし、俺は分かった。
もう分かっていた。
体中の自由が利かなくなっている。
体を動かすのもためらわれてしまう。
ここで眠ったら起きないのだろう。
最後まで見守ってくれているヨシコには悪いが、限界なのだ。
目を瞑って、体の痛みを和らげようとする。
「赤助さん、屋敷に迎え入れてくれてありがとう。屋敷での生活が楽しかったです。たくさんの仲間に出会えたし。これも赤助さんのおかげです。ありがとう。」
(ああ、平七。そういってくれると連れてきた甲斐があったよ。)
「赤助、また会ったねえ。よかったよ。お前に会えてさ。」
「赤助、私達の仇はリキが取ったって。あの茶髪男を不幸のどん底に落としたってさ。悲しいね。あいつは私達と別になってしまったよ。」
(お桃、小鳥。お前達はあの炎の中にいたんだな。助けてやれなくてごめんな。またお前達と一緒に入れるのは安らぐな。リキ…。お前の雄姿は俺が見届けた。地に落ちても頑張って帰ってきてくれ。)
「赤助、また俺っちと一緒に遊ぼうぜい。」
(八六、お前と過ごした日々は楽しかった。そっちの世界でも遊ぼうな。)
「赤助、がんばったねえ。こっちに来なさい。」
(ご主人様…。今は新しいご主人様のところに居ます。けど、私のご主人様はあなたです。)
(みんな、ありがとう。ほんとうに、ありがとう。)
目を開ける。
みんなの魂が自分に語りかけてきた。
シャロンの魂が見えない。
ということは何処かで生きているのだろう。
死ぬ前に一度会いたかった。
でも、もう限界だ…。
行こう。ありがとう、ヨシコ。
短い間だったけど最後に人間の愛とは暖かいものだと改めて教えてくれたよ。
こんな気持ちのいい波動に包まれて死ねるのは嬉しい事だ。
楽しかったよ、さようなら。
俺は体を抜け、魂だけになった。
ご主人様と屋敷の仲間が空に登っていく。
彼らを追いかけるように俺は空に上っていった。
十:新しい物語の始まり
葉の色が赤や黄色に染まる十月のことである。
ヨシコは友達に呼び出されて友達の家に遊びに行くところだ。
四葉のクローバーの図柄が載っている手提げ袋を持って、住宅街を歩いていた。
友達が飼っている猫が子猫を四匹産んで、そのうちの一匹が両目の色が違うという。興味が湧いたので見に行く事にした。
お母さんに飼いたければもらってきてもいいと言われているが、青助が死んでしばらく猫を飼う気がしなかったので断った。
ヨシコは友達の家へ行く途中、一つの空き地に来ていた。
二ヶ月前、火事が起きて家が全焼していたのは記憶に新しい。野次馬が家の周りを囲む中、電柱の片隅で苦しんでいる青助を見つけて看護するため家に持ち帰ったのが懐かしい。
倒れていた白猫を家に持ち帰って病院に連れて行き、助からないといわれた時は悲しかった。
それでも、青助に元気になって欲しいと笑顔で接していたのだが、病状が悪化し病院から帰ってきた次の日、青助は天国に行ってしまった。
青助が寂しくならないように眠る時に側にいてあげたのだが、一晩たって朝起きたら、白猫の体は冷たくなっており動く事は無かった。
ただ青助が幸せそうな表情で眠りについていた事から、間違ってはいなかったと思っている。
病院や道端で独り消えてしまうよりかは、幸せな気持ちで天へと召されたのだと信じている。
空き地の地面は灰色に汚れている。
青助を見つけた次の日のニュースでは、屋敷の中にはおばあさんが一人と、数匹の猫の遺体が一つの部屋で見つかったらしい。また、発火場所の近くに、刃物を刺された白黒模様の猫が見つかった。火をつけた人間が殺したのでは無いかと判断を下している。
家に火をつけたのは役所の若者二人で、一人は原因不明の高熱と吐き気に見舞われて意識不明の重体、もう一人は交通事故で重体と、逮捕するにも出来ない状態だという。
お母さんの推測ではおおかた家の中の猫に取り付かれたのでしょうと言っているが本当かは二人に会っていないので分からない。
ヨシコは青助のことを思い出して涙ぐんだが、持っていたハンカチで涙を拭く。
いつまでも過去のことにとらわれていても仕方ない。
友達の家に遊びに行って気分を紛らわそうと考えた。
ヨシコは友達の家に着いた。
家は大きく三組の家族がすんでもおかしくない広さを持っている。ぐるりと高い柵に囲まれており、入口には門が設置されていた。呼び鈴を鳴らすと、割烹着を着たおばあさんが出てきた。
「ミヤコ様のお友達ですね。話は聞いております。どうぞ、こちらへ。」
使用人に案内されるまま、中に入る。
屋敷の広さに驚く事もなく、使用人の後を着いていく。無垢な子どもなのか、友達がお嬢様であるといったことはあまり気にしていない。
ヨシコは生まれた子猫に胸を躍らせながら入っていった。
使用人は一階の屋敷の端にある部屋に案内した。
扉には「シャロンのおへや」と書かれた表札がぶら下がっている。
使用人が扉をノックする。
「ミヤコお嬢様、お友達が参りました。」
どたどたと足音が聞こえ扉の前まで近づいてきた。ミヤコは扉を開けると、ヨシコを見るなり笑顔を見せた。
「あ。ヨシコちゃん。遊びに来てくれてありがとう。カトウは下がっていいよ。」
ミヤコの一言で、カトウは一礼し自分の業務に戻る。ミヤコはヨシコの手を持ち、部屋に案内する。
部屋の中央にふかふかの絨毯が敷かれており、その上に一匹の灰色のシャム猫が横になっている。母猫の前には生後一週間の子猫が親猫の母乳を飲めるように並んでいる。右から白猫、灰色の毛並みの猫、白猫だが灰色の猫と同じ模様がうっすら見える猫、白猫、と四匹の猫が気持ちよさそうに並んでいる。母猫もどうやらお休み中のようだ。
「ヨシコちゃん。こっち、こっち。かわいいよー。」
猫の側でマキちゃんが手招きしている。
一学期の間に大きなけんかをして仲が悪かった二人がこうして友達どうして遊んでいるのが不思議だった。
そういえば夏休み開けた時、ミヤコちゃんが明るくなっていたのが原因かな。
二学期になったとたんに、ミヤコちゃんのイメージが変わった。机に伏して寝ていただけの彼女が、いろんな人に声を掛けたくさんの友達を作っていったのはここ最近のことだった。
ヨシコはミヤコと一緒に灰色の猫を囲んだ。
灰色の猫は毛並みが美しく美形の猫だとすぐに気付く。ミヤコちゃんに似て、どこか気品のあるお嬢様の猫だと感じ取る。
首輪には透明の宝石がついたアクセサリがついていて、猫の気品さを強調している。
名前はシャロンというようだ。
「かわいいー。」
「でしょう?すごいんだよ。えっとね。この端の白猫、目の色が違うんだよ。ヨシコちゃん、良く見て。」
と、ミヤコは右端の白猫を指す。
顔を良く見ると、うっすら開いた白い子猫の目の色が右と左とで違っていた。右は水色、左は黄金に近い黄色をしていた。
黄金の目は母猫のシャロンから来たものだろう。毛並みの白さと水色の瞳は恐らく父猫から受け継いだものだろう。
マキちゃんが子猫を指でつつきながら、ミヤコちゃんに話をした。
「かわいいなぁ。飼いたいよう。でも、お父さんが猫に弱いって言うから飼えないんだ…。残念。」
「そっかあ。でもたまに子猫たちを見にきてよ。いつ来てもいいから。」
それから、ミヤコとマキの会話が始まる。
会話中、ヨシコは子猫の顔たちや雰囲気をじっと見つめていた。二人の会話の内容は上の空になるぐらい、真剣になった。
何か、何かひっかかる。
どうしてだろう。
子猫たちが初めてあったような気がしない。
まだ記憶に新しく懐かしい。
「ヨシコちゃん。どうしたの。」
心配したのか、マキちゃんが私に声を掛けてきた。
「ヨシコちゃん、子猫が欲しくなったの。さっきから、ずっと見てるよ。」
子猫が懐かしく感じる。記憶に新しいという事は間違いない。偶然かと考えたが、子猫の姿はあまりにも偶然とは考えられない面影を見せている。
「青助…。」
「えっ。」
ため息のように赤助の名前を読んだのに反応してマキちゃんが声を漏らす。気のせいか母猫のシャロンがヨシコを見る。
「この子の父親、きっと青助だよ。」
ミヤコが不思議そうに私を見つめた。
「青助って…。ヨシコが拾ったっていう?怪我が治らず天国にいったって言う?」
「うん。」
確実な証拠なんて無い。でも、子猫の瞳、雰囲気、鳴き声、どれをとっても青助に通じるところがある。上手く説明が出来ないが間違いない。父親は青助だ。
「じゃあ、あの時見た白猫って青助のことかな?シャロンを見つけたとき白猫が一緒にいたの。まさに子猫と同じ青い瞳の白猫って言ってた。」
「間違いないよ。父猫は青助だよ。」
持っていた四葉の手提げ袋から一枚の写真を取り出す。青助が家にやってきたときの写真をシャロンに見せた。
「ねえ、この猫。青助って言うんだけど、君の旦那さん。そうだよね?」
「なー、なー、なー、なー」
写真を見たシャロンがしきりに鳴いた。ヨシコの話を肯定するかのように、間違いなく父親が青助だと知らせるかのように。何度も何度も鳴いた。
「シャロンも言ってる。間違いないって。」
「本当に、シャロン?」
「なー」
ミヤコの問いかけに反応するように一言鳴いた。そうだよといっているかのように。
「青助…、青助の子どもは元気に生まれたよ…。」
青助の子どもに会えるなんて思ってもいなかったヨシコは嬉しさのあまりに泣き出してしまった。青助が亡くなって沈んでいた気分が晴れた瞬間に、彼女からでる幸せ黄色の波動が猫の家族をつつんだ。シャロンは幸せの波動を受けて、鳴いた。いや泣いた。目から涙がうっすらとこぼれている。ヨシコを見つめていたマキちゃんもミヤコも貰い泣きした。
「ヨシコちゃん良かったね…。赤助も天国で喜んでいるよ。」
「良かったね…。ヨシコちゃんの猫に子どもができたよ。」
ヨシコは涙でいっぱいの目をこすり、二人を見た。そして、シャロンに声を掛けた。
「青助の子どもを産んでくれてありがとう。青助は幸せだったって、天国にいったよ。」
シャロンは青助の話を聞くと一言鳴いた。
「なー」
「赤助…。最後は青助になってしまいましたのね。何処かしら、懐かしい気分が致しますわ。どっちであっても、貴方は私の素敵な王子様ですわ。あなたの子どもは無事に生まれました。これからすくすくと育っていくと思われますわ。私のいとしい王子様、安らかに眠りくださいませ。」
猫だって一生懸命に生きているんです。
十:新しい物語の始まり
をあとがきとして書きました。