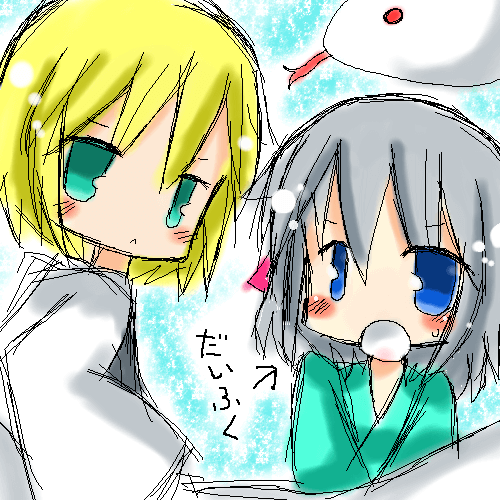
村の守りビト如月

暗闇が空を包み込んでおり、宝石を散りばめたかのように星々が煌き、辺りには夜の帷が降りていた。月の淡い光をわずかに浴びて光を照り返す葉をつけた木々がうっそうと生い茂る森があった。
硬い大地を叩く足音がいくつも響き渡った。
森の静寂を破って疾走しているのは鬼の群れであった。
赤い顔、鋭い牙を持ち頭にはたくましい黒角。村人達に何十年と恐れられてきた鬼達であるが、彼らは必死に逃げていたのだ。
それを追っていたのは一つの足音である。
人だった。鋭い眼光で鬼達の姿を見据え、抜刀する。
鞘から引き抜かれた刀の刃は銀色に輝いており、鬼達を震え上がらせた。
その人物が大きく息を吐き出すと白く濁り、夜風に溶け込んで消えていく。
次の瞬間──刀は鬼の首を刎ねた。
高く飛び、地面に転がり落ちたそれは、まだかすかに息をしており、その目には死の恐怖と自分が今日で死んでしまうという驚きの色をたたえていた。
それを一瞥し、その人物は硬直した他の鬼達に視線を移した。
「次は、其方か?」
──────────────────────────
一、鬼斬りの銀
窓から覗く空は心が溶けてしまいそうなほど鮮やかな青色で明るく情熱的な陽光が差し込んできていた。
薄緑の畳が敷き詰められた部屋には、木製の小さなちゃぶ台と紫の座布団と白い布団が配置されている。
白い布団は膨らんでいて、もぞもぞと何かが動いていた。
そのなかから腕が出てきては引っ込んだり、足が出てきては引っ込んだり。
人が寝ているらしい。
時計の時刻は午後一時を指していた。
古びた襖が開き、一人の娘が入って来る。
銀灰色の髪を肩まで伸ばし、海のように深い青の瞳、愛らしい顔立ちではあるが、なぜか花柄の着物などではなく若草色の袴姿だった。
彼女は、布団を一瞥してため息をつくとその隣にしゃがみ込んで揺すった。
無言で揺すっても何の反応もなく、娘は呼びかける。
「早く起きてください。もう昼ですよ」
しかしそれでも反応がない。
「如月、起きてください!」
それでも反応がなかったので、流石に怒りを覚えて白い布団を掴み、剥ぎ取った。
剥ぎ取ると其処に寝ていたのは青年であった。
糸のように細い金色の髪、白い肌であまり外に出ないのだと伺える。
彼は渋々起き上がると、自然を連想させる新緑の瞳を開いた。
そして娘を見やると、明らかに不機嫌そうに一言。
「何だ?」
「もう昼だから起きてください。昼ご飯は……覚めてます」
「覚ますんじゃない」
「せ、拙者は覚ましておりません! 其方が起きないのが悪い……」
そう反論すると娘はそっぽを向いてしまう。
如月は乱れた髪の毛を手で直すと立ち上がった。そして彼女の肩をぽんと叩く。
「そう怒るな、時雨。何も食わないとは言ってない」
「む、そうですか」
時雨は立ち上がると台所に向かった。
如月と時雨の関係は不思議なものであった。
時雨の父は神社の神主であり、神に仕えるのが役目である。普段は神社に留まり、参りに来る者をねぎらったり熱心に祈りを捧げたり掃除をしたりと忙しい日々を送っている。
しかし、その父はある日浪人に襲われたのだ。
そこをたまたま通りかかった如月が助け、如月は時雨の父の恩人のなのである。
父が如月に礼をしなければと言いつつも毎日忙しく、なかなか機会がないのでこうして時雨が食事を作りに来ることになった。
如月は料理を作ることができないうえ、一人暮らしなのでありがたいことであった。
時雨は、ご飯と味噌汁と茶を盆にのせ、部屋まで運んだ。
ちゃぶ台の上に盆を置くと思い出したように口を開く。
「そう言えば、村長殿が頼みがあるので来てほしいと」
「村長?」
如月は箸を握ったまま固まった。
不機嫌そうにじっと時雨を見つめ、問いただす。
「何を」
「知りませぬ」
如月はため息をついた。
その頼みがどういうものであったとしても、断ることなどできないのだ。
村長と仲違いでもしてしまった日には、村に居づらくなってしまうのは間違いない。
そうなると面倒なので渋々頼みを引き受けるしか道はない。
味噌汁をすすると、時雨がそわそわした様子で声をかけてくる。
「拙者の料理はうまいですか?」
「…………」
黙り込むと時雨はうっと不安そうな表情を浮かべて。
「せ、拙者の料理は……」
「うまいと言っておこう」
そう告げると嬉しそうに頬を緩めた。
時雨は自分の料理を褒められることが嬉しいらしい。
村長の住まう屋敷に向かうことにし、白い羽織を羽織って外へ出た。
目の前に広がるのは眩しいほどの青い空、白い煙のような雲がゆったりと流れており、やわらかい風が頬を撫でる。
空の下には、緑の大きな葉を見せたり、芽だけを出している野菜類が目を映る。
硬めの地面を踏み度にかすかな砂利の音が耳に届く。
古びた玄関からは時雨も出て来た。
時雨は、こちらを見ると一言。
「では、また夕刻に夕飯を作りに来るので」
「そうか」
如月が頷くと彼女は背を向けて歩き出した。
毎日食事を作って片付けをしたら一度帰って──流石に一日三往復は大変ではないかと思ったが時雨は足腰は鍛えてあるので問題ないと笑い飛ばしていた。
空気を吸い込むと一歩、踏みしめた。
十分程歩いたところに大きな屋敷が建っている。
意外にも場所はかなり近いので行くのにそう時間がかからないのはありがたいことだ。
村長の屋敷に足を踏み入れると土壁には豪華な金の装飾が施されており、高そうな壺が置かれていた。薄緑の畳には埃一つ見えないのでよく掃除されているのだと分かる。
入口で女中が挨拶をしてきて、村長の部屋まで案内してくれた。
女中が丁寧な仕草でゆっくりと襖を開くと、紫色の座椅子に腰掛けた老人の姿が目に入った。
髪は真っ白で顎には白髭を生やし、豪勢な着物に身を包んだ人物。
「如月か。さっそく悪いが、頼みがあっての」
「頼みとは?」
「鬼斬りというものがいてな。これはまずいじゃろう」
「鬼斬り……」
如月は眉を潜めた。
鬼というのは、古くから恐れられる生き物である。
通常、鬼は人間の方から手出しをしなければ何の害もないのだが、人間が手出しをしてしまうと話は違う。
鬼斬りというのは、多くの鬼を殺しているのだろう。
しかし、それはまずいのだ。鬼斬りが人であるのなら、殺された鬼の属していた鬼の群れがこの村に牙を剥く可能性がある。
如月は冷静な瞳を村長に向けた。
「つまり……」
「うむ。その鬼斬りに鬼を斬るのをやめさせる、もしくは殺せ」
「ふむ」
そうする他ないだろう。
問題は、その鬼斬りが話の通じる相手であるかどうか。
話が通じなければ最悪殺すしかない。
「鬼斬りが現れるのは夜。鬼の住む森」
「ふむ」
如月は頷くと刀の柄を握った。
その鬼斬りというのは、この村の人間の可能性が非常に高い。
この村の人間でなければ、毎日森まで出向き、鬼を斬るのは難しい。
この村は、人口も少ない小さな村である。村全体の者が全員知り合いと言ってもいいほどで、最悪知り合いを手にかけることになる。
もしかしたら、何度も話したことがある相手なのかもしれない。
村長の部屋を出ると、女中が心配そうに声をかけてきた。
「あの……無理に受けなくても」
その女中は如月のことを心配してくれているようだった。
恐らくいつも村長に頼み事をされて疲れているのではないかと気を遣ってくれているのだろう。
しかし、断るわけにもいかずこの女中に不快感を与えるわけにもいかない。
微笑を浮かべて彼女の頭に手を置いた。
「感謝する。しかし、気にしなくて良い」
辺りは深い闇に包まれていた。
空を見上げても今は星は見えることなく、月の淡い光だけが目に映る。
暗闇のせいで黒く見える葉が目に入る。夜風は肌寒く、息を吐くと白く濁ってしまう。
腰に携えた刀の柄を握り、いつでも抜けるように備えた。
警戒しながら周囲を見回しつつゆっくりと奥へ進んで行く。
──鬼斬りの銀。
村長の屋敷にいた女中達がそう囁いていた。
目撃した者は、その鬼斬りが銀髪だったのを覚えている。
それを聞いて心臓が抉られるような気がした。
この村に住む者で銀髪というと、かなり絞られてしまうのだ。
嫌でも浮かび上がってくる人物。
もちろん、他の者である可能性も否定できない。目撃者の単なる見間違いだったのかもしれない。
音が聞こえた。
草が揺れる音でも風の音でもなく、肉を斬るような鈍く嫌な音だ。
その音を聞き、奥へ奥へと進んで行った。
ようやく鬼の姿が見え、如月は素早くそこに割り込んだ。
そこで相手の刀を受ける。
金属同士が激しくぶつかり合う音が響き、暗闇に赤い火花が散る。
そして、後退して一旦距離を置く。
その場の状況を確認する。足元に転がる鬼の首と身体。
周囲に生きている鬼の姿は見当たらない。どうやら生き残ったものは逃げてしまったらしい。
目の前に立つ鬼斬りを見据える。
銀灰色の髪、青い瞳。それは、よく知る人物だった。
「時雨」
時雨はじっとこちらを見ていた。
「理由を聞こうか」
彼女は戸惑っていたようだが、やがてゆっくりとその声を夜風にのせる。
「拙者の母は、鬼に殺されたからな。これは間違っているか?」
いつもの彼女の口調とは少し違う。
こちらが本当の彼女なのだろう。
如月は静かな口調で彼女に同調することは一切なく言い放つ。
「間違っているな。罪のない鬼まで巻き込むのは罪だ」
「拙者は罪人か」
彼女は苦笑いをして肩を竦めた。
「刀を捨てろ。そうすれば」
「できぬと言ったら」
如月は無言で刀を鞘から抜き放ち、正眼に構えた。
瞬間、時雨が動いた。
彼の目の前まで疾走──大きく刀を振るう。
それを避け、横から刀を振り下ろすが、彼女はそれを予想していたらしく受け止めた。
金属音が響き、お互いに力を込め、弾かれたように離れる。
ゆっくりと息を吐き出し、息を整える。
如月は時雨が刀を扱えることなど一切知らなかった。剣術道場に通っているとう話すら聞いたことがない。
しかし、間違いなく強かった。
刀を彼女に向け、一気に突くが、彼女は身をかがめてかわすとすり抜け、一瞬で如月の手首を切り裂いた。
手首を抉られ、激しい痛みを感じて刀が手から滑り落ちた。
その場に倒れた如月に最後の一撃を浴びせようと時雨が構える。
如月は苦笑いを浮かべて口を開いた。
「時雨は強いな。どうやって鍛えた?」
「独学」
「大したもんだ。最後に一つだけ」
「…………」
時雨は無言で如月を見下ろした。
「貴方を愛していた」
「うっ……」
時雨は硬直した。
様子を伺うと顔を真っ赤にしており、今にも泣き出しそうだった」
「せ……拙者は其方を殺そうとしているんだ」
「知っている」
「こんな拙者になってしまっては、もう愛せないだろう」
「そんなことはない。罪人だろうが改心させる」
「拙者は……」
「最後の最後まで油断は禁物だ」
如月は即座に起き上がると時雨の刀を掴み、取り上げた。
刀を地面に転がすと彼女を抱きしめた。
「如月、拙者は……」
「これからは鬼を殺さなければいい、それだけだ。貴方の母を殺した鬼などとっくにこの世にはいないのだから」
鬼斬りの銀は現れなくなった。
澄んだ青空が広がる日だった。
白い布団の横にしゃがみ込み、時雨は布団を揺すった。
しかし、反応はない。
「如月」
反応はない。
時雨はだんだん腹がたってきて、布団を剥ぎ取った。
「さっさと起きるんだ! 拙者の作ったご飯が──」
渋々起き上がった如月は不機嫌そうに目をこすりながら時雨を見た。
「もう少し優しく起こせないのか?」
「どう起こせと?」
「こう、口づけでな」
「拙者に何をさせる気かぁ! これでも純情な……」
「ふむ?」
村の守りビト如月


