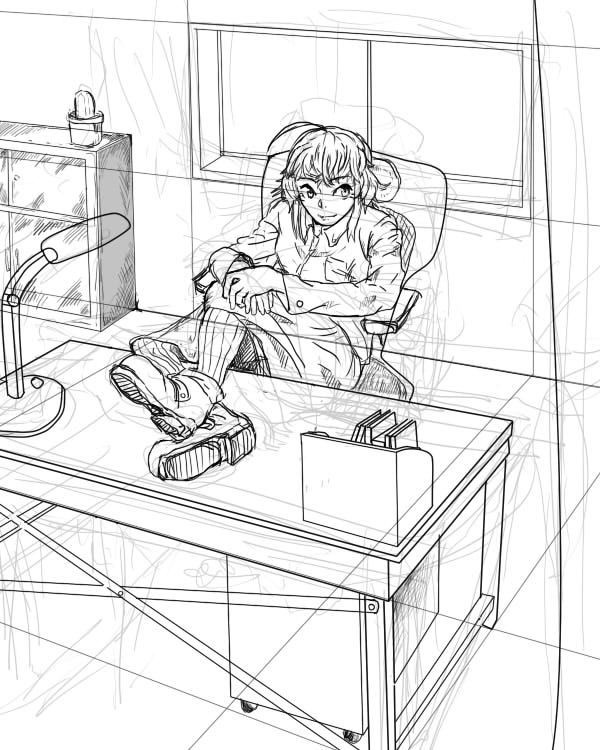
探偵・薄野カオルは屈しない。
人間の心はどこにあるのか。
腹か、脳か。心臓か。
いろいろな人間が長く短い歴史の中で、問うてきた。答えを得た人はどれくらいいるだろうか。自分なりの答えを。
哲学者。生物学者。医学者。それぞれの見解、意見があっていいと思う。あるだけならばいいと思う。その答えを僕たちに押し付けさえしなければ。
だが、結局のところ、それは全て無意味だったと言わざるを得ない。
なぜなら、その答えはどれも的外れだからだ。論外だ。
その問を持った瞬間に、自分のはらわたをこじ開けて、中身を確認すればよいだけである。
そして、当然の帰結。当たり前の結論に至るだろう。
心なんて器官はない。
人間の意識の中にある、気持ちや、感情、そういう類のものは幻想であり、フィクションだ。すべては脳内でペプチドが動的な平衡の中、生み出されては消える過程に過ぎない。記憶物質が存在しないように、心なんてものは存在しない。
そんなことは、魔法使いである僕にとって、あるいは魔法使いである彼女にとっては重々承知のことだった。
存在しないはずの心を空想する。
だからこその、魔法である。デタラメで、曖昧で、発動条件はいつだって細部までこだわらない。それが魔法の魔法たる所以でもある。
我らが二人。相対する、敵対する二人の魔法使い。
梶原奈義。
義洞良縁。
我らは、心を仮想する魔法使いである。
1
夏の終わりに差し掛かった九月二十日金曜日。
大学生はまだ暇を持て余している者も多いことだろう。長い夏休みで羽を伸ばすのはいいが、羽を変な方向へ伸ばす、あるいはそのまま飛んでいってしまう人もいるとかいないとか。僕も暇ではないが、夏休み中の大学生だった。
サークルに精を出すことも、友人と遊ぶこともしないとなると、退屈で死んでしまうのではないか、と数少ない学友に心配されたこともあったが、それには及ばなかった。
僕には仕える主がいる。
その人に尽くし、その人のために行動するという、解かれることのない任務があるのだ。使命といってもいい。
忠実な手先として働かなくてはならなかった。
僕の主は、大学のある期間は、週に四日会うことだけで許してくれる。理解のある人なのだ。ただ、現在のように長期休みに入ると、毎日一緒にいる必要がある。
なぜそこまでするのか。
仕えるとはどういう関係なのか。
いろいろ聞かれることはあるが、その関係は僕と主だけが知っていればいいことで、好き好んで他人に話すものでもなかった。
ただ、そんな僕でも、気の進まない命令をされることがある。普段なら、主の命令があれば一も二もなく、考えた時には既に行動が終わっている程であるが、それでも、出される任務に得手不得手もあるのだ。
特に、主の傍を離れることが命令に含まれているとき、だ。主自身が僕を隣に置かないと判断をしたときが、一番僕にとって苦手だった。
さらに言うと、主の傍でなく、主でない誰かの傍にいる任務が、僕には耐え難いものがあった。
たとえば、そう、今この時である。
車外の山道を眺めながら、アクセルを踏む。
「門間真くん」
憮然とした声で僕を呼ぶ女性が、隣にいる。白いシャツに薄手のカーディガン。一見男性的な服装に身を包んでいる女性。今回は彼女、薄野カオルと行動を共にすることが任務だった。主がなぜそんな命令をしたのかは、僕の知るところではない。
「本人から聞いてね」とのことだった。
さておき。
薄野カオルは国家探偵である。
隣で足を組みながら本を読んでいる姿にすら、オーラがある。雰囲気だけで僕を、否、警察上層部まで認めざるを得ないような、ある種、強迫的な貫禄が彼女にはある。
僕の一瞬の視線に気がついたのか、彼女は口を開いた。
「いつになったら到着するんだ?」
僕を横目に、本のページをめくりながら聞く。
「こっちが聞きたいくらいですよ」
僕はハンドルを握りながら答える。山道をひたすら駆け上るだけの短調な作業に嫌気が差さないのは、助手席にいる彼女のせいである。運転することにうんざりはしない。ただ、これからカオルさんに付き合わされると思うと、気が重くなるだけだ。カオルさんは僕を馬鹿にする。
山頂に目的地があるらしいのだが、一向に到着する気配がない。あたりは依然、鬱蒼とした木々ばかりだ。
「お前、もっと早く走れないのか?」
「無茶言わないでくださいよ。僕、つい最近免許取ったんですから」
「使えないな」
「僕帰っていいですか?」
「好きにするといい。ただし車は置いていけ」
「どうやって帰ればいいんですか……」
「私は帰るなと言っているんだ。真」
僕から望んで助手になった覚えはない。どうしても断れない相手からの命令だから、断れなかっただけで、僕の意思でこの高飛車な探偵に付き添っているのではないのだ。
「今回はなんでまた、こんな山奥に行くんですか。そろそろ説明してもいい頃じゃないですか」
「言ってなかったかい。私は友達に会いにいくんだ」
「それ、僕は必要なんですか」
「やめたまえ。君は自分の必要性なんて考えなくていい。死にたくなってしまうぞ」
「あなたは悪口を言わないと会話できないんですか?」
僕は薄野さんに会うたびに、こういう調子でバカにされる。向こうは愉快でやっていることだろうが、こっちはそれだけ疲れるのだ。僕は圧迫的な態度にかろうじて反応しているにすぎない。
薄野カオル。
探偵という職業の胡散臭さは、彼女の実績により排除される。過去に重大事件の犯人を二人捕まえている。表立った活躍は控えられているが、警察など公権力にもある程度の融通が利くほど、信頼されている。
ただ実績によるブランドが高いだけでない。
僕の主も彼女には一目置いている。会って話した僕の主が認めているのだ。能力の高さは保証されているといっていい。
優秀な人の隣というのは、日頃から慣れているつもりだったが、主ではない人となると、話は別のようだ。先が思いやられた。
「さておき、友達って誰なんですか?」
僕は話を戻そうとする。
カオルさんは少しの間を作り、答えた。
「柊健吾」
「…ひいらぎ、けんご」
僕はバカみたいに復唱した。人の名前だろう。当然、僕は聞いたことのない名だった。
僕には知り合い自体少ない。
「彼は私にとって、一年前に知り合ったんだが、お互いの専門は離れているにもかかわらず、趣味が合ったところがあってね。今日、お招きいただいたわけだ」
「専門、というとカオルさんの場合は、探偵業になるんだろうけど、彼、柊健吾の場合は何です?」
「彼は、プログラマーだそうだ。凄腕らしい」
プログラムというと、ゲームやソフトウェアを作る仕事をしているのだろう。もし、僕が知らないだけで、たくさん仕事をこなしている方だったら、僕もお世話になっているかもしれない。
「どういうお仕事をしている方なんですか?」
「有料のОSを作っているらしい。一部のユーザーからは、熱烈なファンがいるとかな。まあ、全部本人から聞いたことだが」
「なるほど。で、そもそも何で知り合った仲なんですか。初対面というわけじゃないんでしょう?」
「インターネットのボードゲームだ。《ドックファイト》というドイツ生まれの同人ゲームなんだが、オンライン対戦ができるのでな。そこで知り合った。だから、まだ一度も顔を合わせたことはない。だが、彼は恐ろしく強いな。ああ、彼は強い」
「カオルさんがそこまで言うんですか。というか、カオルさん、ゲームとかするんですね……。ちなみにどういうゲームなんですか?」
「縦横上下のある将棋のようなものだ」
「難しそうですね」
カオルさんは優秀な人物だ。
そして彼女に認められている柊健吾。
薄野カオル。我が主。彼らに並びうる秀才であるかもしれない。。
そういう連中を何人か見てきた。
これから会う人物がどの程度の能力を持っているのか。
僕も少し興味がわいた。
2
時刻は午後二時を回っていた。僕の時計は十分ほど進んだ時刻を示していた。主との約束を遅刻することがないように、ずいぶん前に決めた自分のルールだ。
この時間となると、日差しが強い。まだ暑さは抜けていない。
山頂には着いたものの、僕はへとへとだった。暑さだけでなく、長時間に渡る運転と、隣にいる探偵様による言葉の暴力に、完全に疲弊していた。僕が何をしたって言うんだ。
「そうそう。あの建物だ。結構立派じゃないか」
カオルさんは満足げに言ってはいる。確かに建物は大きかった。
コンクリート張りのその住宅は、家というよりは研究棟といった風だった。縦にも平面にも偏っておらず、結構な容積を持っていそうだ。無機質で、特に文化的主張のない建造物。コンクリートの劣化は見られない。そういうコーティングがされているのだろう。
人が住むにはぬくもりが足りないと、僕は感想を持った。
車を止めるスペースは見受けられず、建物のまわりを見渡していると、人影が現れた。
「こんにちは、ようこそ。車は裏地に屋根のあるスペースがあるので、そこに止めてくださいね」
女性にしては低い、男性にしては高い、中性的な声だった。
背の低い、おそらく男性であろう人物。少年のような顔立ちだった。半袖のパーカーにジーンズとラフな格好をしている。
「君が健吾くんかい?」
カオルさんが、助手席から聞いた。
「いえ、俺は柊省吾です。健吾は兄です」
人あたりのいい口調だ。笑顔がよく似合う童顔も合わさり、建物を見たときとは対照的に、緊張は和らいでいた。
彼は車を誘導して、駐車を手伝ってくれた。建物の裏は相変わらず木々が横溢していたが、広かったので簡単に止めることができた。教習所よりも容易でほっとする思いだった。
「こんにちは、あなたが薄野カオルさんですね。……ええと、彼は?」
僕に視線が送られた。
「門間真です。カオルさんの付き添い、……というか運転手みたいなものです」
僕は若干言いよどんでしまったが、それでも省吾さんは愛想のいい対応をしてくれた。初対面の相手と話すのは、苦手だったが、この人に関してはその心配は少なかった。フランクな口調の中にも、大人の慎み深さが認められた。
「そうですか。外は暑いので、中に入りましょう」
そう言って、僕たちは柊省吾について行き、建物の中に入った。
3
暑さにやられて、室内に入ることができる、その言葉にがっついてしまったかもしれない。僕は玄関でなにやらモニターに触れて、数字をいじくり回している省吾さんを急かした。
「それは何をしているんですか?」
その言葉に若干刺があったかも、と少し恐縮した。
「ああ、これはね、パスワードを入力しているのさ。あと少しで打ち終わるから待ってください」
と言いながらもモニターに休むことなく数字を打ち続けている。
パスワードにしたって、時間がかかりすぎている。
僕は額の汗を拭いながら聞いた。
「普通の鍵、差し込んでひねる普通の鍵は使わないんですか?」
「使うよ。三本ある」
穏やかそうに答える省吾さん。
「健吾がセキュリティにうるさくてね。六十四の数字列の日替わりパスワードと指紋認証、あと三本のアナログキーをつけちゃって、もう大変というか、我が家がひとつの要塞みたいになりましたよ」
省吾さんは、はははと笑った。苦労のある笑顔だった。
「その言い方だと、ある日突然、そういう趣味に目覚めた、そんな言い方だな」
カオルさんはそう言って、モニターにまだ数字を打っている彼を見つめた。
「そういえば、そうですね」
省吾さんの手が止まる。考えに耽るのではなく、ただ入力が終わったのだろう。
『認証しました』の文字がモニターに表示されていた。
それから、ポケットから鍵を取り出した。
「俺がここに住むようになってから、すぐですね。もともと健吾は一人暮らしでした」
「それはいつごろの話だ?」
「記憶が曖昧ですが、一昨年の秋か冬でした。寒かった気がします」
それは、ほんとに随分曖昧な記憶だった。カオルさんにとっては、なにか引っかかるものでもあったのだろうか。どっちにしろ、柊健吾にも尋ねればいいことである。
三つの鍵穴に、三つの鍵をそれぞれ入れる。順番に開ける。
さすがに鍵は一つでいい気もするけれど、それも柊健吾に尋ねてみるのもいいだろう。
4
建物の中は、涼しくて快適だった。意外と家庭的な作りになっている。床はフローリングでドアも木製、家具も一般的な製品が多かった。もともと普通の建物で、外装を厳つくリフォームしたようだ。
靴を脱いで、脇の下駄箱に入れるよう指示された。木製の暖かい感じがする床をスリッパごしに感じた。
「中は、結構……普通だな」
カオルさんは言った。それは少し、失礼に聞こえたかもしれない。
「ええ、中はいいみたいです」
省吾さんは、玄関からの通路の右手にリビングがあると、案内してくれた。
ブラウンの落ち着きのあるソファ、適度なインテリア、動物の写真立て、様々なものがリラックスできる空間を作っていた。
「二人共、座ってください。今、紅茶を持ってくるので」
と言って、省吾さんはリビングの奥手にあるキッチンまで行った。
「カオルさん、なんかいいですね。こういう雰囲気」
僕はソファに深々と腰をかけている。
「……そうだな。外から見ても絶対にわからないな」
「ええ」
運転して疲れが溜まっていたのか、妙にくつろいでしまっている。
カオルさんは、なにか考えているのだろうか、車の時よりも口数が少ない。
「お待たせしました」
省吾さんは二人分のカップと砂糖瓶を盆に載せ運んできた。そしてそれをテーブルに音を立てずに置いた。品のある動きである。
「お菓子も持ってきますね」
そう言って、また立ち上がろうとする省吾さんを、
「柊省吾くん」
カオルさんは引き止めた。
「はい」
「君のお兄さんは、柊健吾くんは奥にいるのかい?」
「……すいません。健吾は徹夜続きで、今は寝ています。薄野さんが到着したことは既に知っているので、後で来るでしょう。失礼ですが、待ってもらってもいいですか?」
「そういうことなら、わかった。待とう」
カオルさんが僕に対して偉そうなのは、言うまでもないことだが、初対面の人にもこういう態度をとるのか。ちょっとどうかと思うが、この人らしいといえば、らしかった。
「どうした?」
「な……んでもないです」
僕の視線に気がついたのか、こちらを見た。瞬間、圧倒されそうになる。
カオルさんを自分と同じ物差しで図るのは止そう。
それに、この件では僕こそ、初対面の他人なのだ。
「では、一度健吾を呼びに行ってきます」
省吾さんはリビングから廊下に出て、奥に消えていった。
5
十分ほど、紅茶を楽しみながら、カオルさんと雑談した。
二言に、一回の割合で罵倒されたが、概ねお互いの暇は潰せたという感じだ。
紅茶が鼻腔をくすぐるのが心地いい。罵られるのを我慢すれば、贅沢な時間だったかもしれない。
「というわけさ。わかったかい。無理なら言ってくれ、笑ってやるから」
話した内容は、《ドックファイト》という例のボードゲームのルールだった。
一辺が八マスある正方形が、三層ある。まずすべての駒は最上層に配置され、駒を動かして相手の駒を下層に落としていく。相手のクーニッヒという駒が最下層にきたとき、勝利する。クーニッヒは将棋でいう王将、チェスでいうキングのようなものだ。特殊なルールもありプレイするにはまだ早かったが、観戦くらいはできるようになった。
僕が「むずかしいですね」と返事をすると。
部屋に近づく足音がした。スリッパが床をこする音。
僕たちは注意をそちらに向けた。
廊下から顔を出したのは、省吾さんだった。
「すいません。健吾は今起きたところで、部屋を出る準備をするとのことです。代わりに」
と言うと、省吾さんはリビングまで来て、棚から少し大きな模型のようなものを取り出した。重たいのか両手で抱えて、机の上にゴンと置く。
それは石と木で精巧に出来ていた。
「これは、ドックファイトの盤か?」
カオルさんは言った。一目でわかったようだ。
「アナログでしかも、こんなに精密にゲームの盤を再現できるものなのか」
感動しているみたいだ。ゲームをプレイしているときは、画面越しに仮想的な盤が映し出されていたのだろう。それが、目の前にあるというのは、物語でしか登場しない物体。その模型を見たときのような感覚かもしれない。僕もガンプラは好きだ。
「ええ。自分が来るまでこれで遊んでいるといい、と言っていました。失礼ですが、許してください。ああ、えっと、これは実際にゲームすることもできるらしいです。点数計算とか、駒を動かす作業が少し面倒だけれど」
「確かにな。けれど、これは面白いな」
カオルさんは嬉しそうだった。
柊健吾が来るまで、暇つぶしになるだろう。
ただ、暇つぶしといっても、カオルさんは待たされているという感覚はなく、満足しているくらいだった。僕自身、紅茶を含めたこの部屋の雰囲気にまだ酔っていたい。かなり寛げるのだ。
「僕はさっき教えてもらったばかりだから、省吾さんとカオルさんで対戦してみたらどうですか?」
「いや、俺もやったことはないんですよ。俺は健吾と違って機械やコンピュータに疎いですし、この盤もリビングにあると、さっき知ったくらいですよ」
と、申し訳なさそうな省吾さんだった。
「では、今カオルさんに教えてもらいましょうよ」
「それなら、教えてもらいたいです」
ぱあっと笑顔になる。親しみ深い笑みだった。この人はなんだか人を和ませる力がある。
僕がカオルさんの方を向くと、
「もちろん構わない」
と承諾してくれた。早く、ゲームを始めたいだけかもしれなかったが。
それから、十五分ほど説明があり、僕も先に覚えたルールを復習することができた。対戦するときの簡単なセオリーや、特別ルールなどにも触れ、実際にゲームが行われた。
省吾さんとカオルさんがゲームをしたときは、省吾さんの勝利だった。カオルさんに初心者に気を遣うほど、常識があったことに驚いたが、その気遣いは概ね間違っていなかった。たとえ手加減されたとはいえ、省吾さんは嬉しそうだった。
「しかし、君は本当に初心者なんだな。実は健吾くんが化けているかも、と疑ったのだが」
「あははは、さすが探偵さん。確かに健吾と俺は似ていますが、俺は俺ですよ」
「そのようだな。素人は素人らしい動きをするのだ。たとえ玄人が素人の真似をしても、それは『玄人が真似をした素人らしい動き』になってしまう。技術というのは、一度心得てしまうと、その身から外すことは困難なんだ。まあ、癖みたいなものさ」
「なるほど、たとえそうでなくとも入れ替わったりしないから安心してください」
――ははは、と省吾さんは笑った。特に含みもなく、単純に冗談に笑った……のだろう。
「気にするな。言ってみただけだ。では、省吾くんの次の相手は不肖門間真が相手しよう。この男も一度説明したんだ。省吾くんと同じ実力だろう」
カオルさんは、愉快そうに僕に振った。
「不肖は自分自身を謙遜するとき使うはずですが」
「だから、君は馬鹿なんだ。不肖とは愚かなこと、才能がないことという意味だ。君にピッタリだ。馬鹿」
悪口が雑になってきていないか。ひどい。
と、その瞬間、リビングの向こう、廊下から電子音が聞こえた。ピピピとけたたましく響き渡っている。目覚まし時計のアラームだろうか。
「あ、失礼します。健吾が目覚ましを止めずに、シャワーでも浴びているんでしょう。席を外しますが、ゆっくりしていてください」
「は、はい」
突然のことで、咄嗟に返事をした。
「じゃあ」
慌ててスリッパに履き替えた省吾さん。ぺたぺたと廊下を小走りで行ってしまった。
6
柊健吾という人物の話題を持ちかけようと、カオルさんに尋ねてみた。
「柊健吾さんについて、カオルさんはどう思いますか?」
「変な質問だな。頭の悪い面接官がしそうだ」
うんざりするように言った。
「そんなことより、さっきの言った特別ルールの説明でもしようか。紙とペンでもあるとうれしいが」
「あ、ええ」
僕は手帳から一枚ページをちぎり、ボールペンと一緒に手渡した。
「いいか、最下層と中間層に合計五駒以上が降りてきたときにな……」
「!」
カオルさんは紙に文章を書き始めた。ペン先は速く鋭く動き、紙上に全く違う文意のものを書き始めた。
『この部屋には、監視カメラと盗聴器が仕掛けてある。カメラの角度からでは、この紙は見えないようにした』
「それから、中間層を飛ばして最下層まで二段飛ばしできる駒もあり…」
僕は息を飲んだ。突然訪れた緊張。
「ええ、それから?」
適当な相槌を打つ。
紙に書かれる内容。
『柊健吾には、義洞因子の可能性がある』
僕の脳内は凍りついた。
◆
義洞因子。
これについては、順を追って説明する必要がある。僕もそう説明された。だから、ここから話す内容は僕の理解の範疇を超えることはない。
ただ、これはゲームでも、遊びでもない。もっと現実的で差し迫った、這い寄るような驚異に関する問題だ。
今から八年ほど前、正確には二〇〇五年の六月十三日に、最初の事件が確認された。密室を装い、日常の空隙を狙うように、それは発生した。大学生が自身の大学サークルの部室で殺害されたのだ。実際は密室ではなかったが、非常に巧妙な仕掛けがなされていた。犯人は被害者と同じサークルの級友だったそうだが、動機は不明。取り調べの後、裁判は今も続いているが、現在も動機は解明されていない。本人は一貫して黙秘を続けている。
続けて、一ヶ月後の二〇〇五年の七月十五日、密室を装う殺人事件が同日に全く別の場所で二件発生した。どちらの事件も関係性は見いだせなかったが、密室を装うこと、動機が不明であること、二つの共通点だけが浮き彫りになった。一方の犯人は自殺、もう一方は黙秘を貫いている。
これまでに起きた三つの事件の犯人の共通点はない。一人は大学生、一人はガソリンスタンドの店長、一人は主婦。いずれも動機に関して一切の言及がない。共犯者がいるかも不明である。
そして、一週間後、二〇〇五年七月二十二日、またしても殺人事件が発生した。犯人の名前は筑摩祐也。高校教諭であった。先の事件と同じように、密室操作、動機不明であったが、彼だけは、動機に関する取り調べ時、口を開いたのだ。
『義洞良縁』
――ギドウ、リョウエンと発音した。
筑摩が発した言葉はそれだけであったが、先の事件の犯人たちに、「ギドウリョウエンを知っているか?」という質問をしたところ、無言であったが、心拍や脳波などから微小ながら興奮が見られた。彼らが反応を示した脳の部位と、筑摩の発音の仕方から、《義洞良縁》が人物である可能性が高いと判断した。
それから、密室を装う事件が、今まで二十四件起きた。そのうち解決されたのは十一件。半分以上もの事件が未解決であり、十三人の犯人がまだ捕まっていない。
警察上層部と国家探偵は《義洞良縁》が関わっているとされている事件を『義洞事件』とし、殺人の実行犯を《義洞因子》と命名した。
今も動機解明と犯人捜査が続けられている。
と言うのが、警察が主に、そして薄野カオルに伝達している情報である。この二人を含めた国家探偵は、警察の持ちうる情報はある程度に共有されている。
さらに《義洞事件》について、警察と国家探偵のごく一部しか知らない情報もある。それは僕の主である梶原奈義から発信された予測である。
義洞という人物が、何を成しているか。いったい何者なのか。誰もが追い求める疑問に、主は一定の回答を用意できる。
それは、魔法使い。
魔法の存在。
心の存在。
義洞の力は、心を操る能力があると、僕たちは確信している。それは催眠術にかけられたような犯人たちの様子だけでなく、実例を知っているからである。ありえないことではない、と判断できるからである。
我が主、梶原(かじはら)奈義(なぎ)も魔法使いであり、人を、心を操ることができる能力者である。
このことは、事件に対して大きな影響を与える。
相手が魔法使いならば、こちらも魔法で対抗すればいい。魔法にかけられた人間が犯罪をはたらく。これが《義洞事件》の正体であり、捕まえた犯人が口を割らないのも、魔法が原因だとすれば、魔法を解く必要があるのだ。これが僕の主の主張である。
しかし、本人ができるというのなら実行すればいい、と警察組織は首を縦に振らない。僕と主は魔法を解くことに、三回試み、すべて失敗している。
理由は、事件の実行犯、《義洞因子》の前に主が立つと、奴らは自害をするからである。舌を噛み切る者。自らを極限まで律して、窒息死する者までいた。自殺の方法はそれぞれ違えど、こちらが処置する前に、死んでしまうのでは、何も好転しない。むしろ捜査上、打撃を受けることになる。
そのため、主は、国家探偵であるのにもかかわらず、捕えた《義洞因子》と面会することを禁止された。
現在状況は煮詰まっていると言っていい。
義洞良縁という人物が、それぞれの犯人にとって、どういう存在なのかはわからない。時間だけが過ぎてしまえば、未解決事件を多く残してしまうだろう。この殺人の連鎖がいつか止まる確証もない。早急に手を打たなければならない。
ただ、《義洞事件》と確認するのにも時間がかかるのだ。なにせ逮捕した後に、初めて、動機不明と確認されるのだから。密室操作にしたって、それだけで《義洞事件》と断定できるわけではない。
どうしても対応が後手に回ってしまうのが難題であった。
そして、警察を含めた義洞事件に関わる者、――もちろんカオルさんと主も、今はできるだけ多くの手がかりが必要なのだ。
事件を事前に予防できることは、どの立場の人間からも、理想といえる事件解決だった。
◆
監視カメラがあることを、意識しながらカオルさんの書く文字を追った。
『オンラインゲーム中に、プライベイトチャットで話しかけられた』
文字は走る。だがカオルさんは全く関係ないボードゲームの話をしている。僕の耳に話している内容が届いても、頭に入ってくることはない。それどころではない。しかし、興味深そうに耳を傾けている振る舞いをしなければならなかった。上手な演技だったか心配になる。
『話の面白いやつだったから、しばらく話していた。思いのほか話は弾んだが、突然、
――密室に興味はあるか?
と聞かれた。ある、と答えた。友人ということで遊びに来ているが、今日、向こうはそのつもりかもしれない』
そのつもり、とはどういうことだろう。決まっている。事件が起きるのだ。義洞因子であるなら、それは密室を作り上げるという意味だ。
僕は今更、今回の我が主の意向が理解できた。今回の任務の重要性も。
しかし、それでこそ気になること、疑問も浮かんできた。
「カオルさん、こうなった場合はどうなんですか?」
僕はボードゲームのルールを聞く口振りで、カオルさんからペンを受け取った。紙の上で質問するためだ。
『どうして、そんな大事なことを車の中で話くれなかったのか』
殴り書きになってしまったが、意味は通じるだろう。カオルさんにペンを渡す。
「ああ、そういう時はだな…」
カオルさんは口を動かしながら、それとは別のことを答えた。
『健吾くんの警戒を解くためだ。お前のような何も知らないやつがいたほうが、警戒されづらい。今はもう、さっきの省吾くんが健吾くんに化けている可能性を排除できたから』
ゲームで一戦交えただけで、その人物が本人かどうかわかるのか。確かに、カオルさんと柊健吾は、ネット上で何度もゲームをしているはずである。当然お互いのプレイ上の癖は把握しているのだろう。それ故に、さっきの省吾さんが「柊健吾のプレイではない」ということが確認できたのか。
僕はそこまで、なにかゲームをやりこんだことはないため、ちょっと想像しづらかった。――いや、スポーツでもそういうことが言えるかもしれない。中学でバスケットをやっていたことを思い出す。なるほど。
『ここからは私だけが動くつもりでいる』
「……」
『だが、私になにかあったら、そのときはお前と梶原に任せる』
梶原というのは、僕の主のことだ。
心の中で了解とつぶやいた。きっと主にも届いている。ようやく、なぜ主が僕をカオルさんに同伴させたか分かった。
《義洞因子》を前もって判定できるかもしれない。この希望は僕らにとって、すがりつく他ないものだ。僕が柊健吾と接触して、下手な演技をして探りを入れるよりかは、カオルさんが対峙したほうがずっといい。
『君は、省吾くんと接触して、気になることがあったら私に、あるいは帰ったら梶原にでも伝えてくれ』
僕がこれからすることが決まった。
柊健吾に近づかないこと。
柊省吾に近づくこと。
7
廊下をすり足で歩くような音が聞こえた。僕は少し身構えてしまった。演技力のなさを、後で悔いた。
人物はリビングに足を踏み入れた。顔を見た。やっぱり似ている。
「待たせて悪かったな。俺が柊健吾だ」
省吾さんに顔のつくりはそっくりだ。ただ、中身が違うと直感的にわかる。けだるそうな姿勢は猫背だけのせいじゃない。彼を見ていると心底馬鹿にされているような気分になる。
「お前はきっと……、薄野だな。知的な面構えだ。そっちのぼんくらそうなやつは……」
初対面の相手にけなされる機会はそうそうないが、この際どうでもいい。僕はこの男に近づくことはしない。
「彼は、私の付添だ。私は車の運転をしたくない」
「おうおう、冷たいこと言うなよ。事前に言ってくれれば、あんな貧相な車よりもいいもんで迎えに行ったのによ」
貧相な車…。屋外に監視カメラでもあるのだろう。この建物がどうしてこうも過剰な堅牢さを持っているのか。
「そっちの坊主もよろしくな」
省吾さんと同じくらいの背丈。容姿もかなり似ている。同い年ではないだろうが、坊主といわれるのは、ひどく違和感があった。
「……はぁ」
と、あいまいな返事をして見せる。接点を持つべきではない。それはカオルさんの役目だ。
「無愛想なガキだな。悪くない」
「まあ、そういわないでくれ。楽しくやろう」
カオルさんは珍しくフォローに入る。
「おう……、まあなんだ。疲れただろう。坊主は部屋でゆっくりするといい。俺は薄野と話があるからな」
健吾さんは何気ないつもりで言ったみたいだったが、事情を知ってしまった今では、含みがあるように聞こえた。僕は内心、冷たくつぶやいた。
――話がある、か。
カオルさんがこちらを見てくる。席を外せ。つまり言われた通り部屋に行っていろということだろう。
「じゃあ、お言葉に甘えて」
そそくさと立ち上がり、自分の荷物と、カオルさんの荷物を運ぼうと手を伸ばした時、
「いや、それは持っていかなくていいぞ」
と言われた。
カオルさんに言われたら、普通に聞き流していただろう。だが、声の主は健吾さんだった。僕は、そちらを見た。
「どういうことだ?」
カオルさんは低く言った。
「ああ? 怖い声出すなよ。ビビっちまうよ。いやいや、なんてことはない。君と薄野は別々の部屋を用意したってだけだ。薄野にはあとで案内するよ」
「僕がそちらの部屋を使います」
柊健吾はにやにやしながら――んん? と首をかしげた。
微妙な空気の中、カオルさんは僕を制した。
「真、うるさいぞ。私の友達に何か言いたいことでもあるのか?」
「そいつはうれしいことだね、薄野」
――余計なことはするな。とカオルさんは言いたいのだ。あくまで健吾と接触するのはカオルさんの仕事なのだから。僕はここで引き下がる必要がある。
「……わかりました。じゃあ、先に部屋に行っています」
僕は自分の荷物だけを持って、リビングを出た。
「廊下をまっすぐだ。黄色いドアがある。そんなことはないと思うが、わからなかったら、省吾にでも聞くといい」
少しだけ、悔しい思いだった。
8
そこから、特に急いですることもなかった。省吾さんに頼ることもなく、部屋を見つけて、荷物を中に入れた。部屋は小さな机と椅子、気持ちよさそうなベッド、リビングと同じような落ち着きのある小物が棚に陳列されていた。
「ふう…」
ベッドに腰を掛ける。
リビングから追い出されたとはいえ、しばらくぶりに気を抜いた気がする。
カオルさんが義洞因子の話を紙上でした時から、ずいぶん気を張っていた。
部屋の壁掛け時計の音だけが、聞こえた。時間が過ぎていく。一応三泊はできるだけの準備はしてきたが、正直、どこでこの件に折り合いがつくのかわからなかった。
足は床に放り出して、背中をベッドに任せる。天井を見上げる形になる。
一人になると、主のことが気になった。
携帯電話をみると、着信はない。
僕は自然に、携帯に番号を打った。おそらく一生忘れることのない、一度覚えたら二度と忘れることが許されないであろう、番号だった。
電話の向こう側で、相手が受話器を取るまでにする電子音が、もどかしかった。
相手が電話に出た。
『どうしたのよ。さびしくなっちゃったのかな?』
この声を聴くと、腹の底から安心するのだ。
「はい、我が主」
『報告とか無意味だからね。こちらから電話かけない限り、こういうのはいいって』
「すみません」
『真はすぐ謝るね。大丈夫。真の見ているものは、全部わかっているからね。どんな気持ちかも、全部わかっているよ』
「承知しています。ですが、声を聴きたくなりました」
『図々しい召使いだな。ほんとに、困ったものだよ』
主は笑っている。
「申し訳ありません」
僕はその声に、遠くにいる主から頭をなでられているような感じを覚えた。
『やるべきことがあるんだろう? それを果たさなくちゃ』
「了解です」
『じゃあ、切るよ』
電話は切れた。僕は携帯電話を見つめながら、心地よい余韻に浸っていた。
午後五時半。窓から夕日が覗けるような時間になっていた。
僕はそのまま、布団の上で眠ってしまった。
◆
主との馴れ初めを聞かれたら、僕は今でも鮮明に答えられるだろう。ただ、そこには劇的なエピソードはなく、ちっぽけな少年のちっぽけなコンプレックスがあっただけだった。
なんていうことはない。きっかけは、どこにでもあるようなつまらない出来事だった。
父親が心臓麻痺で死んだのだ。短期出張で中国まで飛び、現地で不運を被ったらしい。僕は日本にいたから、まさに遠くのような出来事だった。遠くの誰かが死んだ。その程度の認識しか持てない僕であったが、電話越しに声を殺して涙を流す母親をみて、何とも思わなかったわけじゃない。
それでも涙は出なかった。
父親が嫌いだった?
そんなことはありえない。肩車だってよくしてもらった。ゲームも一緒にやった。普通の、愛にあふれた父親だったと思う。彼は、あたりまえのこととして、家族のために仕事をしていたはずだった。
それでも……泣いた記憶は、僕にはなかった。悲しかったはずだけど、涙が出なかった。
一週間後、父親が小さくなって無言で帰ってきた。壺の中の彼は、吹けば飛んでしまいそうな粉になっていた。それが僕から実感を奪い去る。つらいこと、つらくあるべきことなんだろうな。と他人事のように思った。
それが異端だと気が付いたのは、葬式前夜だった。いつも泣かない兄貴が泣いていたからだ。強いと思っていた兄までが、一人で涙を流していたのだ。
僕はそれを見て、心臓をつかまれたような罪悪感にとらわれた。泣く練習もした。無駄だったが。
葬式当日。いろいろな知り合いにあった。近所の人、学校の先生、うろ覚えの親戚。全員まじめそうな黒い服を着ていたのが、なんだか腹立たしかった。
『お前らまで、そんなに悲しそうにするのかよ』
そう、頭の中でぶつくさ言っていた時だった。
ささやき声が聞こえた。
「ねえ、あの子。お父さんのお葬式なのに、ムスッとして。悲しくないのかしら」
僕に対して言ったことだとすぐにわかった。
血が沸くような、小さな箱の中でぶつかりながら高速で跳ねるような、気持ちが渦巻いた。立ちくらみがした。どんな声色だったかは今ではもう、思い出せない。
でも、強烈だった。
僕は、その場から立ち上がり、建物から飛び出した。人をかき分け、どこまでも走った。
思いを頭の中で、ぶちまけた。
『悲しくない?』
『悲しくないだって?』
『どうしてお前にわかるんだ!』
『知ったようなことを言うな!』
『死んだのは僕の父親だ! 僕の父親が死んだんだ!』
多摩川沿いまで走った。
夕日がまぶしかった。体のいたるところから汗が、水分が噴き出しているが、目からは依然、なにも出てこなかった。
近くで電車が通る音がした。体の底に響くような轟音が、いろんな音をかき消した。
僕の鼓動とか。息遣いとか。刹那的に聞こえなくなった。
影が思ったより伸びていた。太陽を見ると、すでに赤い波長だけ選び取って、地表に届けていた。
「はあ……はあ……」
息が切れていた。今思うと、小さな体でよく走ったものだった。
水が見たくなった。水辺まで歩く。近くまで行くと、一人、しゃがんだ人影が見えた。近づかなければ見えなかっただろう。
少女が一人いた。背丈は僕と同じくらい。おとなしい紺の洋服だったが、髪飾りがきれいだった。
声をかける必要も感じなかった。水辺には彼女、先客がいたため、僕は黙って別のところを探そうとした。
「ねえ」
僕はぎょっとした。話しかけられるなんて思ってもみなかった。
「君が来たせいで、魚が逃げたんだよ」
「ごめん……」
「なんですぐ謝るの?」
「え?」
「私が嘘ついているかもしれないのに」
「……ごめん」
「もういい」
僕は、いたたまれなくなってしまった。敵意に慣れていないころだった。そのまま去ってしまえばいいものを、僕はその子の機嫌を直そうとしたのだった。
「あの……ほんとにごめん」
「……」
無視された。そりゃそうだ。僕だってそうする。
「その……きれいだね。それ」
「え?」
少女を少し驚いたようだった。僕は少女の髪飾りに指をさしていた。
本当にきれいと思ったんだ。夕日の赤に反射して、輝いて見えた。
「とっても、きれいだ」
僕はそのセリフでようやく、彼女の眼を見ることができた。丸く見開いて、そこにはおどおどした僕が写っていた。
彼女は自分の膝に顔をうずめた。気に障ってしまったのだろう。失敗した。
「あなたが嘘つきでないことは、わかったわ」
こもった声で、彼女は言った。意味が分からなかった。
「私ね。人の心が読めるの。近くにいる人は、その言葉が本心から言っているかわかるの」
そういう妄想なのかとも思った。からかわれているだけかと、思った。それでも、彼女の反応は尋常じゃなかった。顔を上げた彼女は泣いていた。
「それはそうと、なんで君はそんな恰好してるの? お金持ち?」
僕は今、喪服を着ていた。走って崩れてしまったが、品のあるように見えてしまうのだろうか。
「これは……さっきまでお葬式で」
逃げ出したけれど。
「そう」
彼女はしゃがみながら、こちらに手を伸ばした。
――?
僕はその手をつかむ。
「……立たせてよ」
とっさに理解して、彼女の腕を引っ張った。体は軽かった。
「よっと」
彼女は服をパンパンと叩いた。
「あなた……今悲しいの?」
「……なんでそう思うの?」
僕は頭がざわついた。涙が出ないこと、悲しめないこと、それが原因で僕は葬式から逃げ出したのだった。父親の顔や、言葉が反芻していたが、それでも、ただそれだけだった。僕はあそこに戻る資格はない。父親に対する申し訳なさと、異端であることの罪悪感が、混ざり合っていた。
「私は、心が読めるのよ。あなたに触れたらそのくらいわかるの」
「僕は……悲しくないんだ」
誰に言うでもなく、呪いのようにつぶやいた。
「そんなことないよ? あ! あなた、お葬式に出ていたって言ったよね。きっとそれね」
「!」
葬式に出ていたから、悲しいと推測したのではなく、悲しいことがわかっていて、後から理由を探したのか。
彼女は……心が読めるのか?
「だって、あなた、お父さん大好きじゃない」
誰が死んだなんて言っていないのに。
「それに泣きそうよ。そんな顔している」
泣けないんだ。僕は……それができなくて。
「大丈夫。あなたの涙は私には見えているもの」
僕の頬は塗れていない。だけど、その言葉に、彼女に言われたその言葉に、
――救われた気がしたんだ。
気が付くと、辺りは暗くなっていた。視線を川から住宅に移すと、街灯がともり家々には明かりが付いていた。
「君は、なんて名前なの?」
この子のことを知りたい。一緒にいたい。だけどこれは恋じゃない。
「私は梶原奈義。内緒にしてくれるなら、もう一つ教えてあげる」
「知りたい!」
自然に出た言葉。
「私はね、実は――魔法使いなの」
この気持ちは恋じゃない。付き従おうとする、忠誠心だった。
◆
ドアのノックが聞こえた。省吾さんだった。
「失礼します」
彼はお盆を持ってきた。食事が乗っていた。部屋には食欲を刺さる空気が広がった。洋食の香り、バターの香だ。大きなステーキとサラダ、シチューのようなスープとパンが運ばれた。
「食事です。もうそんな時間ですよ」
「みんなで一緒に摂らないんですか?」
「ええ、なんだか健吾とカオルさんが二人で話をしたいらしいです」
カオルさんが、仕事をしている。なにかを掴もうとしている。
「じゃあ、僕は省吾さんと、食事するわけにはいかないですかね?」
こっちはこっちで、ちゃんと働かねば。主に時間を割かせてしまったのだ。その甘えの分、僕は成果を出さなくてはならない。
「それならいいですよ。僕もここに自分の食事を持ってきますね」
「カオルさんたちは、もう食べましたか?」
「いえ、二人はまだ談笑中です。場所は健吾の自室に移動して、お酒も入り楽しそうですよ」
「そうですか……。それはよかった」
うまく話が運べているようだった。それにしても、談笑中とは……。もともとインターネットで会話している二人なら、現実に会ったとしても話は弾むか。柊健吾が義洞因子でなかったに越したことはないのだ。
それにしても、リビングから去るときの僕の言動は失敗だった。お互いに変な緊張感を抱かせることになっていたかもしれない。
「じゃあ、俺は自分の分を運んでくるので、待っていてください。もしよかったら先に食べていてもいいですよ」
「いえ、待っています」
省吾さんは、僕のお盆をおいて部屋を出て行った。
僕はその間に、気をつけねばならないことを思い出した。
リビング同様、この部屋にも盗聴器の類が仕掛けられている可能性に。
9
省吾さんは戻ってきた。同じメニューだ。同じ食事なら距離も縮まるかもしれない。省吾さんに近づくのは僕の仕事だ。
机をテーブル代わりに使い、僕はベッド、省吾さんは椅子に腰かける。僕の食事はまだ温かかった。
食器と食器が小さく打ち合う音が小さく鳴り続けていた。
「省吾さんと健吾さん、二人は双子なんですよね」
「ええ」
「子供のころからよく間違われたでしょう」
「その……僕と健吾は最近出会ったばかりでして、子供のころは一緒に暮らしてなかったんですよ」
「そうですか……すみません」
「いえいえ! 謝らないでください。もともと僕は健吾と別々で暮らしていました。そこで一緒に暮らしていた両親が亡くなってしまったので、健吾の家に来ました」
「……」
「こういうことは自分から話すほうがいいのです。気を使われるのは嫌なので」
省吾さんは照れるように言った。
「それに、僕はその病気持ちなので、一人で暮らすには少し難がありまして」
「……そこまでで、いいですよ。もっと明るい話題にしましょう」
なんだか、むりやり言わせているような気がしてしまった。今は一つでも多くの情報がほしいところではあるが、空気の読めない僕ではない。相手に気を使わせないようにしている省吾さんは誰より気を使っていたように見えたのだ。
それから、僕は省吾さんと会話をした。
お互いの趣味の話や、専門の話。
僕は化学を専門にしているが、省吾さんの専門は科学史だった。とても面白い話が聞けた。
食事の後の会話もそこそこに、省吾さんは食器を片づけ始めた。盆にひとまとめにする。
「じゃあ、僕はそろそろカオルさんたちの夕食を用意しますね」
「もう、そんな時間ですか」
ずいぶん短い時間に感じたが、僕の時計の針は午後七時ぴったりを指していた。
「では、僕はこれで」と省吾さんは退室した。
10
ほぼ同時刻、午後六時五十五分。
「悪いな。待たせちまって」
「いいさ、これのおかげで退屈していない」
カオルはドッグファイトの実物盤を指して言った。
真がリビングから追い出された後、どうなったかというと、事態は急速に進んでいた。
カオルは現在、リビングではなく柊健吾の自室にいた。スチールラックがいくつものパソコン画面を乗せていた。机上にはキーボードだけでなく、いくつか他類の入力装置が佇んでおり、まさに仕事場といった風だった。
「しかし薄野、お前、酒にめっぽう強いみたいだな。ケロッとしているぜ」
「あんまり好きじゃないけどね。体質的に大丈夫ってだけさ。一人じゃ滅多に飲まないよ」
カオルはさっきまで、この部屋で一人にされていた。その間、健吾は夕食の支度をしていたという。カオルの印象では、健吾が料理するような性格に思えなかった。むしろ、それは省吾の仕事とばかり思っていた。
真が去った後、リビングで、アルコールを嗜みながら、何回かボードゲームをしてから、カオルは泊まることになる部屋に案内された。
以下回想。
ドアは木で出来ていて、ぶつかったら壊すことができそうだ。とカオルは自身の対比経路を確認する。ただ、妙な仕掛けがあった。ノブの少し上部に小さなモニターがついていた。そこだけが妙に大仰で、不自然だった。当然、質問するほかなかった。
『これはなんだ?』
『ああ、部屋の鍵さ。俺が作ったAIとドッグファイトで戦ってもらうんだ。少なくとも中級者以上じゃなければ外からは開けられない。この場で考えればお前しか入れない。来客は内側から開ければいい。内側にはこんなもの付いていないからな。例外で、ここの家主の俺は当然正当な手続きで、つまりクリアして入ることができる。どうだ?実用性もなかなか捨ててない面白い仕掛けじゃないか?』
『真が、私の助手が入れないようにする意味はあるのか?』
『中から開ければいい』
ここで争うのは得策でない。疑いを確信にするには慎重さが不可欠だった。カオルはこのことを真に、梶原奈義に伝える必要があると思った。もし、自分に何かあった時のために。
『じゃあ、さっさと開けて、荷物を中に置け。そのあと俺の部屋に招待するぜ』
『ああ』
カオルは三分程度で、AIに勝利した。たしかに、初心者には手におえないレベルではあった。
11
不自然なセキュリティがある自室に荷物を置いたカオルは、健吾の部屋に招待されたが、健吾は夕飯の支度をするらしく、一時間ほど席を外した。健吾は人を待たせることに、躊躇しない性格だった。このような山奥に住居を構えているせいか、客人を招待することに慣れていないのかもしれなかった。もちろんそれは、義洞因子でないことを前提とした話だ。かの犯罪者集団が、どのような性格をしているかは誰も知る由もない。この家の堅牢な仕掛けも、彼の性格も、すべて義洞因子であるが故であるかもしれないのだ。
先のカオルが泊まる部屋も、本人のユーモアと判断するか、単純に『助けを呼べなくする』ためなのかもしれなかった。カオルはその後者を想定する必要があった。
――条件はそろったかな。
「なんだ……これ」
柊健吾の部屋に招待されたカオルは、異様なものを見た。人の部屋を探るのは気が咎める、という普通の神経すら忘れてしまいそうになる。部屋は電子機器、モニター、入力装置が規則的に並び、とても仕事しやすそうな印象を受けたが、それとは無関係に部屋の隅に積まれたいくつもの「器具」に目を奪われた。持つとなかなかに重く、両手で一つ持つのが限界だった。一辺が七十センチほどの正方形。色は黒い。中は空洞なようだが、内側に通じる直径二十センチほどの穴がぽっかり空いていた。
感覚でわかった。この穴には人間の首を入れるのだ。全体を俯瞰で見ると、拷問器具のようだった。頭に嵌める重い箱。
「これは……なんだ。健吾君」
「あーえっと、引かれちゃうかもしれないな。隠しときゃよかった。それは拘束具だよ。人間の身動きをとれなくするためのもの」
「どうしてこんなものがあるか……聞いてもいいかな」
「玄関のセキュリティは知ってるか?」
「ああ」
「俺は用心深いんだ。もしこの家に強盗なんかきてみろ。俺と省吾でなんとか取り押さえたとしても、こんな立地だ。警察が来るまで時間がかかるだろ。拘束する必要があるんだ」
「そうか……取り押さえるための道具はあるのか?」
「もちろんだ。電気ショックできる刺股とかあるぜ。防犯グッズはかなりの種類ある」
「なるほど。だが拘束具にしても、いささか大げさじゃないか。なんだか重いし。拷問するみたいだ」
「……さすが探偵だ。いいとこついてる」
「……というと?」
「これは、犯人を拘束するための道具であると同時に、処刑器具でもあるのさ」
「!」
「ああ! すまない! 違うんだ。引かないでくれ。たとえば、俺と省吾が家に押し入った犯人を捕まえたとするだろ。これを装着しても、抵抗できるにはできるだろ。足とか使って、頑張れば逃げることもできる。だから、相手にそうさせないように、命を握る必要があるんだ。もちろん殺さないぜ? 犯人より重い罪に問われるからな。重要なのは、相手の生殺与奪を握ることなんだ」
「その口ぶりからすると、これはきみが作ったのか?」
「そう! 買ったとかじゃなくてね。俺が自分で作ったんだ」
「すごいな」
「中に、電子機器が積まれていてな。外部からのリモコンで処刑を実行するんだ」
「へえ」
「内側で人間の頭をつぶす仕組みが入っている。簡単だ。物理的に圧をかけるのが一番コストがかからず作れたんだぜ。万が一、処刑を行うことがあれば、専用のリモコンで遠隔操作して行うんだ」
健吾は、自慢話をするように嬉々として語った。
カオルはこのことを頭に叩き込んだ。この拘束具の仕組みを忘れないようにする。
険しい顔をするカオルをみて、健吾が珍しく心配するような口調になった。
「……気分を悪くしたら、謝る。すまない」
カオルは自身の腕時計に触れる。
「いや、いいんだ。ところで、健吾君」
「なんだ薄野?」
「この家はどうして、こうも鍵やら、パスワードを使うセキュリティが多いんだ?」
「そいつに答えるには、抵抗があるな。心の準備がいる」
健吾は頭を掻いた。
「それなら、無理して答えなくていいぞ。友達だからな」
「おお、待ってくれ。友達というなら答えさせてくれ。友情に隠し事は似合わないからな」
「そういってくれるなら聞こう」
健吾は一呼吸置いた。
「数年前、俺は人間不信になったんだ」
「……」
「どいつもこいつも、何を考えているかわからない。隣のやつは次の瞬間、その隣のやつを、もしくは俺を攻撃するかもしれない。隣の仲間は次の瞬間、平気な顔して裏切るかもしれない。他人の気持ちが理解できないなんて悩みのやつは、腐るほどいるが、それは他人が気持ちを理解させないからだ。敵がいれば腹を隠し、味方がいれば背中を隠す」
「……まあ、そういうやつは少なからずいるだろうな。私も、だれかれ構わず信用することはしない」
「だろう。だったら、隠すしかない。守るしかない。閉じるしかない。セキュリティはそのためだ。どんなに仲のいいやつも、壊そうとして壊せない関係じゃないはずだ。約束は破るためにあると言った悪役も、その次は自分の部下に裏切られる。じゃあもう、他人と約束なんかしなきゃいい」
「それじゃ、孤独になるぞ」
「実際、そうなった。俺はなんでこんな山奥で暮らしていると思う。誰も信用できない俺は、誰からも信用されなくなった。きっと、このまま死ぬものだと思っていた。省吾がいるおかげで、かなりマシな生活をしてはいるが、あいつがいる前はひどいものだった」
「……」
「省吾と俺、合わせて家族だ。だが、それだけだ。大切だが、省吾だけでは人間関係は乾いたままだ。俺は、さびしがり屋だ。孤独はいやだ」
「ああ」
「繋がりがほしい。絶対に裏切ることのない、いざとなったら助けてくれる人間との繋がりが」
健吾は、にやにやした薄ら笑いを殺し、訴えるようにカオルをみた。
「なあ、薄野。そういう人間になってくれないか」
カオルは一呼吸おいてから、答えた。
「それを答えるのは今じゃなきゃダメか?」
すると健吾は、
「そんなことはない。俺はそこまでお前に求めてないぜ。俺は、辛抱強いんだ」
そこまで強情にこの話題に拘泥しているわけではなかった。その場の引きは早かった。
「そろそろ、本題に入ってもいいか?」
「本題っていうとなんだ? 薄野」
「おいおい、君が私を呼び出した口説き文句だよ」
インターネットゲームの途中、健吾はカオルに私的は回線で『密室に興味はないか?』と聞いた。この言葉があったから、カオルはここに来ようと思ったのだった。そして、カオルは、そこにこの男の考えが集約しているはずだと踏んでいた。
「ああ、それか」
カオルは腕時計に触れる。触れた後の一連の流れとして、腕を組んだ。できるだけ偉そうに。それはカオルが持っていた、自分の手の内を明かさないための手立てだった。そのため、警察からはオーラがあるなどと誤解されていた。
「私を呼び出すようなことだ。さぞかし有意義なんだろうな」
冗談半分、脅し半分な口調を心掛けた。
カオルが探偵であるために、必要なものは勇気だった。彼女の知性は、地に伏せる狙撃手のように落ち着いていたが、思い切りが足りなかった。臆病と言えなくもない。カオルはそのことにずいぶん前から、自覚的だった。できるだけ偉そうに、と自分に言い聞かせて、いわゆるオーラという近寄りがたく高潔な雰囲気を手に入れた。
「まず、一つに警戒を解いてもらいたいな、薄野よ。さっきも言った通り俺はこんな性格だ。怖がっちまうよ」
「それはすまなかった」カオルは全く悪びれない。
「そして、お前は誤解している。俺がお前に話しかけたのは、お前の探偵という職業が理由になっていると思っているな。お前が何やってようが、俺はお前に話しかけたよ」
「……ほう」
「推理小説が好きとかぬかすアホどもは、すぐ密室を殺人っていう単語に結び付ける。お前もそうなのか?」
「じゃあ、密室がなんだというんだ?」
「密室というと、閉じられた空間のことだ。それに続く言葉は、殺人だけじゃない。お前は聞いたことないか? 密室的人間関係とかな」
「人間関係?」
「俺はわざわざ、密室に興味が……なんて言い方したのは、お前の探偵的な部分に鎌をかけただけ。あの言葉の要約は、さっき済ませたんだ」
「つまり、君は、私に密室的な人間関係を築いてくれとそう言っているのか」
「さっきからそのつもりだったぜ。誤解を招く言い方だったことは謝る。でも、そうしないと、お前はここまで来なかったろう」
「密室的な人間関係というと……私は健吾君以外と話してはいけない。そうなるのか?」
「そこまで要求するつもりはないぜ。ただ、本心で話してはいけない」
「本心?」
「仮の自分を想定して、仮の立場からものを言う。そうしてほしい」
「それが君のいう繋がりか?」
「ああ、そうだ。もっと簡単に言ってやろう」
健吾は、どこか不貞腐れた、不敵な笑みを浮かべた。
「俺と結婚してくれ」
12
夕食の後、僕はカオルさんに会うため部屋を出た。省吾さんは、僕が夕食を済ませた後に、カオルさんと柊健吾の分を用意すると言っていたから、僕は少し待ってから部屋を出た。今は午後十時。この時間だと、さすがに夕食は終わっているだろう。なるべく柊健吾と接触は避けるべきなのは今も変わらない。不自然のない範囲で僕はあたりを注意しながら、廊下を歩いた。
「こんなところで、何をやっている坊主」
心臓がはねた。動揺を隠すことに全神経を注いだ。
「その口調は健吾さんですか」
振り向くと、案の定不機嫌な面構えの童顔が立っていた。
――失敗した。なんとか乗り切るか。
「驚かせないでください。僕は今、トイレを探しているところで……」
「薄野が心配になったのか?」
「――!」
「まあ、そう構えるな。何もしちゃいないさ。お前らが俺に疑いを持っていることはわかっている」
疑い、という言葉に際どい線引きを感じた。義洞因子である疑いという意味で、健吾が言ったとは現状では判断できない。仮に、柊健吾がまさに義洞因子であり、疑われていることに感づいていたら、この捜索は完全な失敗となる。最悪のケース、僕とカオルさんが密室の中、遺体で発見されることだってあり得る。その場合、主は多くの情報を得るだろうが、僕が主を失うことになる。それだけは、僕は許容できなかった。
「カオルさんはここに、探偵としてじゃなく、あなたの友人として来ています」
「本当にそうだといいな。それだと俺も助かるぜ」
不自然な探り合いが、始まろうとしていた。しかし、それは自分の仕事でないことを思い出した。
「ともかく、カオルさんはどこですか?」
「ははは、トイレじゃないのか?」
「どっちも教えてくれるとうれしいです」
「大人がなんでも答えてくれると思っている顔だな。気に食わねえな」
「じゃあ自分で探すので結構です」
「本当に無愛想なガキだぜ。トイレは廊下を突き当りに右だ。薄野は二階だ。階段を上がったすぐ右手だ」
「……ありがとうございます。じゃあ、僕はこれで」
「まあ、待てよ」
「……」
「おいおい、怖い顔すんなよ」
「なんですか?」
「薄野の部屋には入れないぞ」
「どうして?」僕は即座に反応した。
「俺の趣味っていうか。まあ、例のボードゲームだよ。あれをプレイしないと入れない仕組みにしたんだ」
「はあ?」
「行ってみるといい。俺の自信作なんだ」
13
言われた通り、階段を上がり、右手をみると、そこには木製のドアがあった。ドアノブの上部に大きなモニターが付いていた。ここがカオルさんの部屋だろうか。
モニターに触れると、画面が光った。スリープモードから起動したのだろう。数秒の読み込み表示のあと、画面の光が強くなった。そこにはリビングで見た三層のゲーム版があった。
――プレイしないと入れない。つまり、勝たなくてはいけないということだ。
二分後、僕は惨敗した。ルールを知っていただけに、自分の弱さが浮き彫りになっただけだった。こんなに早く負けるものだろうか。おそらく、「もう一度対戦する」とドイツ語で書いてあるアイコンに触れる。
すると、
「そこに誰かいるのか?」
カオルさんの声がした。
「はい、門間真です」
ドアの向こうから、近づいてくる気配がした。ガチャリとロックが外れた音。ドアが開いた。
「真か。入れ」
僕は言われた通り、部屋に入る。部屋は僕と同じような作りになっていた。大きめのベッドと机、小さな椅子があった。部屋の隅に、カオルさんの荷物があった。
「カオルさん。ドアについているあれは……」
「彼なりのユーモアだそうだ。内側からは開けられるから、用事があるときはノックしてくれ。君じゃ勝てなかったろう」
「はい、強かったです」
「君が弱すぎるんだ。……と言っても誰にせよ、初心者には難しいだろうな」
カオルさんはベッドに腰を掛けた。僕は椅子を丁度いい場所に動かし座った。
「食事は済ませました?」
「ああ、それなりにうまかったよ」
「ですよね。さすがは省吾さんといった出来でした」
「省吾君が作ったのか。私は健吾君のを食べたよ」
「へえ、どうでした?」
「うまかったよ」
カオルさんは、なかなか他人の食事に口をつけない。探偵という職業柄、気を付けるべきことだった。それでも、カオルさんは今回、口にせざるを得なかったに違いない。今回は謎を解きに来ているのではなく。謎を暴きに来ているのだ。
「なにか……言われましたか?」
「この家には、人を遠隔的に殺す装置がある」
「!」
カオルさんは、柊健吾が所有している、拘束具もとい万力の話をした。リモコンで操作して、嵌めている人間の頭を砕く処刑器具。
「そんなものがあるなんて……カオルさん……もう……」
「関係ない。私たちはここに何しに来ている?」
「……はい」
「わかればいい。ああ、それと、プロポーズされたよ」
「は? プロ……はあ?」
「結婚しましょうってな。どうしていいものか」
「断りましょう!」
「私の判断するところだ、お前が口を出していいことじゃない」
「するんですか? 結婚」
「落ち着けよ。答えを出すのに、時間はくれるそうだ」
カオルさんはカバンから何かを取り出した。手帳くらいの大きさの薄い本だった。
「ドッグファイトのルールと戦略、詰め練習が書いてある本だ。不自然な訳で読みにくいが、一応日本語だ。これで練習して、この部屋のドアに勝つといい。ここから帰った時、梶原にでも自慢すればいい」
カオルさんは、主の名前を出した。
「いつまで、ここにいるつもりですか?」
「長くて一週間、短くて明日だ。それでことは解決する」
「僕は、今答えを聞くわけにはいかない。……そうですか?」
「察しが良くて助かるよ」
「わかりましたよ」
「私に何かあったら、と心配になっているんだろう?」
「はい、僕はあなたと行動することを命令されていますから」
「ははは、そうだったな。お前は私でなく梶原を慕っていたんだった」
「ええ」
「安心しろ。私はこの部屋から出ないよ。誰がきてもこのドアをあけない。君でもだ」
「柊健吾が……彼が義洞因子だったら、この部屋はその舞台になります」
「そうなったら、確定でいいじゃないか。この部屋を空けることができるのは、健吾君だけなのだから、君と梶原で捕まえればいい」
「カオルさんは、どうなるんですか?」
「……門間真。いいか?」
カオルさんは僕を見た。鋭い視線。この人の雰囲気はいつも圧倒的だ。だけど。
「……」
「絶対に思考を止めるな。そこで、その時、その瞬間、探偵は敗北する。義洞因子に負けるんだ。梶原も見ているな。絶対に屈してはいけない。それでも現実は続いていくぞ」
だけど、この時だけは、優しさがあった。
カオルさんはそういって、僕はもらった本を片手に、部屋を出た。
ドアを閉めると、自動でロックされる音が聞こえた。もうドアは内側からしか開かない。
ただ、これは木で出来ている。
僕は自分のこぶしをみた。こぶしで鈍器を持っている。そんな想像をした。
――いざとなったら、これを壊してしまおう。
廊下を歩きながら、ボードゲームの本をぱらぱらめくる。紙が一枚挟まっていた。
僕は自分の部屋に戻り、長かった一日を終えた。
◆
深夜、車を走らせる男がいた。陽気そうな口笛を吹いて、ハンドルを切る。郊外ということもあって人気は少なく、運転は快適だった。
彼はある山のふもとまで車を飛ばしていた。山頂には知り合いが住んでいる。
知り合いの名は柊健吾。会って間もないが、男にとって家族のような存在であった。
山を登ることはなく、柊健吾とふもとで落ち合うことになっている。
家族に会うのに理由はいらない。
男は口笛を吹いていた。
14
目を覚ましたのは午前七時、悲鳴を聞いた時だった。顧みると、時間なんて正確には覚えていない。ただ、頭が痛かった。思い出してみると、その風景は、自分を含めた現実を俯瞰してみているような感覚にとらわれた。僕は部屋を大急ぎででた。
予感。誰の悲鳴かはすぐにわかった。
僕は階段でよろけたようだった。口元を抑えた。きっと臭いでもしたんだろう。臭い? どんな? 思い出せる? わからない。
地面がぐらついて前に進めなかったのかもしれない。それでも、僕は足を動かした。
二階についた。
僕は真っ先にカオルさんのいる部屋、階段を上った右手をみた。
部屋は閉じられた。相変わらずのモニターがあった。
「え?」
僕は、誤解をしていた。カオルさんに何かあったのかもしれない。そんな疑念が僕の体を前に進めていたからだ。起き抜けの運動でも、走ることができた。
カオルさんの部屋は閉ざされたままだった。僕は安心した。
カオルさんはまだ中で寝ているかもしれない。あるいは、僕より早くに、悲鳴のもとに駆け付けたかもしれない。
当たり前だ。人が簡単に――でたまるか。僕の父親じゃあるまいし。
つかの間の安堵、すぐに僕は次に目指す場所を意識した。悲鳴の元へ。
さっきの悲鳴は省吾さんのものだった。
僕の鼻腔には、嫌なにおいが蔓延っていた。それが現実だった。
廊下に立っている省吾さんをみつけた。口を押えて目を見開いている。何かあるんだろう。知っている。僕は知っている。
僕は省吾さんになにか話しかけた。「どいて」と言ったのかもしれなかった。部屋の前に立つ。部屋はモニターや入力装置など、機器が多くあった。そのなかに、小さな、見覚えのある、それでいて別物が、あった。
――柊健吾が死んでいた。
すぐに例の拘束具だとわかった。頭を突っ込んでいた。リモコンを片手にして。
腐敗臭のもとはここだと、直感的に理解した。
死体を見るのは初めてじゃない。主のもとで任務をこなす際に、何度か見てきた。被害者も、自殺する加害者も。それらと何ら変わりなく、これも完膚なきまでに絶命していた。なにせ、首から上が見えていなかった。万力によって潰されていた。ベッドの上に万力を乗せ、床に膝をつきながら、頭を砕かれていた。頭を……砕かれていたのだ。万力の淵からは小量の血液が溢れていた。
血液は赤黒く変色していた。固体と言っていいかもしれない。
生命を失ったそれは、体の大きさも、服も、あの憎たらしい男のものだった。
ただ、今は顔をみることはできない。万力に挟まれて、つぶれているのだから仕方がない。
「……カオルさん。カオルさんは?」
「ぼ……僕はまだ……みていません……」
僕は正気になってきた。視界の淵がはっきりとしてきた。僕は歩いて、カオルさんのモニターのある部屋に向かった。モニターを一瞥する。今はゲームに興じている場合ではない。
ドアをノックした。
「カオルさん、起きてください。有事です」
返事がない。
もう一度、強めにドアを叩く。
「……カオルさん?」
――密室。
僕の頭に浮かんだ単語は不吉なものだった。
今まで何を相手に戦ってきたかも思い出した。
『――密室に興味はないか?』
『義洞因子である可能性が高い』
血の気が引いた。
僕は近くにあった消火器をもちあげた。
「はあああああ!」
全体重を乗せて、ドアに向かって振り下ろす。耳を劈く破壊音と飛び散る木片。二発目は自然にでた。とにかく目の前の障害を破ることに必死だった。
四発で、ドアはその機能を失った。前に倒れるように、モニターの付いた木の塊が道をあけた。
僕の眼前に広がっていたものはすでに見たことがあるものだった。
予感は間違っていなかった。
安心は間違いだった。数秒前の自分を責めたい。地獄はここからだ、と。
探偵、薄野カオルが死亡していた。
万力に挟まれた顔の見えない身体。血はこぼれていない。ベッドの上で、眠るように胸で手を重ねて、頭を丸呑みにされていた。
「あああ……あ」
声にならない声がでた。言語にできない。
――なんだこれは?
――どういうことだ?
ひたすら混乱した。いけない。思考が止まってしまう。直視できない。怒りよりも、憎しみよりも、悲しみよりも、混乱が頭脳を支配した。
よろめくように、後ずさりをした。
だめだ。ここは。
この家はすでに、閉ざされている。
15
僕はリビングでソファに座っている。省吾さんも目の前にいる。目を閉じてなにかをぶつぶつ呟いている。顔は見えないが、顔の鉛直下方向が濡れている。泣いているのだ。
僕もあれから数回吐いた。
主に電話しようとしたが、出ない。きっと先に警察に連絡してくれているのだろう。
主の顔を思い出す。僕に任務を任せている。カオルさんと行動することを命じられていた。それはもう叶わない。要は失敗だ。信頼を裏切った。謝りたい気分だった。
誰かに謝って、そして断罪してもらいたい衝動に駆られた。
ごめんなさい。
『なんですぐ謝るの?』
それは主の言葉。聞きなれた声で再生された。
『それでも現実は続いていくぞ』
その言葉は……。
『思考を止めるな』
カオルさんが言ったんだっけか。
幸い涙は出ていない。苦しくても、悲しくても、出ることはない。それは僕の強さを意味しない。体質のようなものだ。ただ、僕はごくまれにこの体質に感謝することがある。
僕に泣いている暇を与えないことだ。
もう一度、頭の中で再生される声。
『思考をとめるな』
今度こそ、カオルさんの声で聞こえた。
「省吾さん」僕は立ち上がる
「…はい」うつろな顔で僕をみた省吾さん。
「これから、二人の周辺を調べます。警察が来るまで、やれることをしましょう」
「それは、俺らの仕事でしょうか」
省吾さんは目を再び伏せた。
「何も知らないこと、何も知らないままでいること。それ自体が罪だ。何も知らないまま、身内が殺されたんだ。僕たちは何かを知る義務がある」
「……なにも知らない」
「思考を止めてはいけない」
「何も……知らないんだ。俺は」
省吾さんは聞こえるか聞こえないか際どいくらいの声で、自分を責めるように言った。涙を浮かべていた。
「俺は……健吾のことを何も知らない」
「……」
「健吾がどんな気持ちで、何を抱えて、どんな心でいたか、知らない。俺はここにきて、まともに健吾と会話したことがないんだ。健吾は俺を受け入れてくれたけれど、健吾がどうして、あそこまで閉ざしてしまっているのか、俺は知らない」
「うん」
「知りたい」
「ああ――」
現場検証だ。
16
僕と省吾さんは再び、死体のある二階に来た。
「もしもし、主?」
『もしもしはいらないって言ってるじゃん、全く。大丈夫わかっているよ。私がもうそっちに警察を送ったから、君たちはそこでやるべきことをやってね。指示はこちらから出すから、電話は切らないでね』
「はい」
『じゃあ、二つの死体を見てくれるかな』
僕はまず、柊健吾の死体をみた。最初に見つけられた死体。首から上はない。血は黒く染まってしまったが、先ほどまでは赤かった。部屋にある電子機器に血は全く付着していない。
「荒らされた様子はありません」
省吾さんは言った。僕は元の状態の柊健吾の部屋を知らないが、省吾さんは今の部屋と、事件前とを比較できる。
「モニター類、入力装置、すべて元の位置のままです」
『データとしてなにか盗まれたかもしれないよ』
僕は赤黒い池を跨いだ。少し助走が必要だったが、足を汚すことはなかった。いや、昨日まで生きていた人間の血で「汚れる」はないだろう、僕。
パソコンを起動する。ハードディスクの回転音が小さく鳴り出し、いくつかのモニターが一斉に光った。表示された文字は日本語で、少し安心した。しかし、知らないOSだったため、操作に苦労した。
『バックアップはなされているみたいだね。再起動して』
僕は言われた通りにする。再起動し、ブート画面で主に指示されたキーを入力する。なんだかよくわからない文字列が溢れかえるように表示された。
『USBの挿入履歴はないみたいだ。つまりデータを抜き取られたわけじゃないね』
殺人犯は、部屋をあさった形跡がないこと、データを抜き取られた形跡がないことから、柊健吾の持ち物に対する、窃盗が目的だったわけじゃないはずだった。もちろん、もしそうだったとしても、カオルさんを殺害した理由がわからない。
カオルさんの死体。同様に首から上が万力に飲まれている。
僕たちは、カオルさんの部屋に行った。腐敗臭が強烈だった。
『薄野カオルの死体だね……』
主はゆっくりと噛みしめるように、事実を受け入れるように、言った。
昨日の服のままだ。血が床一面に広がり、壁や天井にまで、血が付着していた。視界のあらゆる部分が赤かった。まだ、新鮮な赤だった。
『おかしいね』
「ええ」
そう、謎があるのだ。この殺人現場は存在しえない。不可能なのだ。
主は解説するように言った。
『薄野カオルはここで殺された。死体の鮮度と昨日の状況から想像はつく。しかし、この家で薄野カオルの部屋のロックを外せるのは柊健吾だけだよね』
その柊健吾が死んでいる。死んでいるのだ。
『真が薄野カオルの死体を発見した時、ドアを破壊したはずだね。その前まではドアは閉ざされていたね。きれいな状態で、無理やり開けた形跡がなかったはずだよね。つまり薄野カオルを殺害するためには、薄野本人に開けてもらうか、ドアのゲームに勝つか、しかないわけだね。そして真も柊省吾くんもあのゲームにおいては初心者だよね』
ドアは僕が破壊するまでは、きれいなままだった。だからこそ、後から発見されたのだ。腐敗臭は柊健吾の死体一つから発生していると、思っていたのだ。
「……」
僕は頭の中で頷いた。
『したがって、犯人は薄野と顔見知りか、ドッグファイトに熟達しているプレイヤーということになるね』
「理屈はそうです。しかし主」
『なに?』
「カオルさんは、あの日の夜、絶対にドアを開けないとまで言っていたんです。僕でも開けない、と」
『つまり、薄野の顔見知りでも、あのドアを開けることはできないということかい?』
「はい。これは論理的ではないかもしれませんが、カオルさんは言葉を撤回する人ではないです」
『そうだね。ただ頭の中にはとどめておいてほしいね。私の召使ならね。そうなると、だれもこの部屋に入れなくなってしまう。柊健吾は死んでいるのだからね』
「申し訳ありません」
主に対して、感情論で意見をしてしまったことに、僕は謝る。
――誰も入れなくなってしまう。密室の発生。
『そんなことよりも、重大なことがあるよ。そもそも薄野のいる部屋まで、どうやって犯人がたどりついたかだね』
そして、もう一つの密室。
『この家には無数のセキュリティがあるんだろう? それをくぐって入ってこられるような人間がいるのかな。しかも何も破壊することなく』
省吾さんは廊下に立っていた。
「あ」
柊健吾の部屋のモニターを眺めている省吾さんから声が漏れた。
「なにか気が付きましたか?」
「監視カメラです。玄関に監視カメラがあります。それで……うっ」
「どうしました?」
「なんでもありません。それより、カメラの映像が残っているはずです」
確かに、この家には堅牢な仕掛けが多くある。侵入すること自体困難であるが、現に事件は起きた。どのようにして侵入したか、あるいは犯人の姿まで写っている可能性もある。なにより先にチェックするべきことだった。
省吾さんは少し具合が悪そうだった。それはそうだ。自分の肉親が死んだのだ。悲しいにきまっている。それは僕が一番共感できることでもあった。
それに彼の持病のことも気になる。
『監視カメラは、どこに仕掛けてあったの?』
主の質問を、僕は省吾さんに伝達する。
「たしか、山頂付近の門に一つ。駐車場に一つ。そして室内、リビングに二つです。映像はこの部屋のパソコンに届いているはずです」
「見ましょう」
これで事件は解決するかもしれない。
それから、主の指示で、パソコン内ファイルをいくつか検索し、それらしいファイルを見つけた。《監視カメラログ》と記されたフォルダーの中に日時が記されている映像ファイルを多く見つけた。主の指示がなかったら、この作業は難しかっただろう。
『……九月二十日の午後十時からを見ようか』
僕は昨日の夜、カオルさんと午後十時まで会話していた。生きている姿をみていたのだ。
その時間には少なくとも、カオルさんは死んでいない。その少し前には柊健吾にも廊下で会っていたので、二人が死んでいるとしたらこの時間からなのだ。
僕が主に指示されて開いたファイルは、どうやら駐車場の監視カメラのようだ。
「実は駐車場にも家に入る裏口があります。ドアは玄関よりも重く頑丈ですが、鍵は一つしかついていません」
省吾さんは言った。つまり、駐車場から二人を殺害可能な第三者が家に入ってきたという可能性。そいつは、主が言うところの「薄野と顔見知りか、ドッグファイトに熟達しているプレイヤー」だろう。
もっとも、犯人が一人という確証もないが。
モニターに動画が映し出された。午後十時過ぎということもあり、暗く辺りの色までは把握できないが、物体の輪郭は容易に確認できた。駐車場には車が二台。そのうち一台は、僕たちの車だ。
『早送りにしよう』
十六倍速にして、動きをみる。
すると。
「あ、今」
駐車場の裏口から人影が表れ、車に乗ったことが認められた。人物は僕たちのではなく、もともと柊家で使っていたものに乗った。
『巻き戻して』
動画を巻き戻し、人影が表れたときから一倍速にしてみる。
「柊健吾……ですね?」
「これは健吾です。間違いありません」
省吾さんはそういった。
駐車場のカメラに映っていた人物は柊健吾だった。時刻は十二時四十分。山に出るのは危険な時間でもあった。なんのつもりなのだろうか?
柊健吾は車に乗り、出かけて行った。その後、約五十分に戻ってきた。大きな荷物を持っていた。台車を倉庫から持ってきて、それを乗せ、裏口から部屋に入る。
この行為が行われる最中に僕らは寝ていた。これから見る地獄も知らずに。そう思うと、カメラの中にいる柊健吾に問いただしたい気持ちになった。今起きている大きな問題。謎。矛盾を。
確かに、柊健吾は外出していた。昨夜一番怪しい行動をしたのは誰かと聞かれたら、間違いなく柊健吾だ。疑われたとしても仕方がない。
――しかし。
だが、しかし、その柊健吾も殺害されている。
あまりに不可解だ。
カオルさんを一番殺しうる、義洞因子でありうる人物は彼なのだから。
17
『さて』と主は仕切りなおした。
『あと、確認するべきことは、そうだね……死体の状態だね。本当にあの死体が薄野のものか。確認するべきだよ』
「……はい」
まずい。動悸が速く、鼓動が強くなる。目を背け、逃げ出したい。監視カメラなどを調べているときは、傍らにある柊健吾の死体をも見ないようにしていた。それはあまりに残酷で、ただ痛みを象徴しているような気がしたのだ。たとえこの万力を開いても、生き返ることはない。死をより強く意識するだけだ。
『真……万力を開くんだ』
「ひっ……」
僕はその声に、恐怖を感じた。死体の状態を調べるというのは、まさにその行為そのものだと理解しておきながら、脳みそは全力で拒否している。理性を凌駕する嫌悪感。
目を背けていたい。
『はあ……、これだけのことがあって、まだお前はわからないのか?門間真』
「……主……?」
『薄野カオルの死体だ。早く開け』
主の口調が強くなる。顎が震え、歯がガチガチなっていることに、僕は気が付いていない。だって……こんなこと。
「ですが……主」
『甘ったれるな』
電話の向こうで静かな檄が飛んだ。省吾さんも察することができたかもしれない。
『薄野はなんと言った? こういうとき薄野はお前になんと言ったんだ?』
「……」
『思考停止するなと言ったんだよ。どんなに悲惨なことでも視線をそらすな。どんなに辛いことでも背を向けるな。目先の感情に狼狽えるな。理性でもって、現実に爪を立てろ。お前に今、何ができる?』
涙は出ていない。そういう体質だから。僕に泣く暇はない。
思考を止めるな。目を背けるな。自分に直接届く言葉。酷いことだと、悲しいことだと、いくら訴えていても、義洞は止まらない。僕たちは、敵に屈するわけにはいかないのだ。
「カオルさん……の部屋に移動します」
『そうだ……それでこそ、我が忠烈』
18
万力には血液が外に溢れない仕組みが施されている。異臭こそ放つものの、周りの家具やベッドは汚れてはいなかった。
人間の頭部を粉砕するための器具。あまりに残酷で痛ましい姿の死体。カオルさんの体は力の抜けた人形のようにだらりと横たわっている。万力は電動で閉まるようにできているが、開くときは自分で手をかけて開かねばならない。
カオルさんの近くまで歩く。どんなに近づいても、この死体は紛れもないあの人のものだとわかってしまう。
『じゃあ、開くときは両手が必要だろう?いったん電話は切るよ』
「はい、主」
向こうから、一方的に電話は切れた。逃げ道をなくすように、プツリと切れた。
僕の見たものは主と共有できている。だから、僕はできるだけ多くのものを見なくてはならない。目をそらすことは許されない。
僕が、主の眼球になると、僕の心は眼球にあると、誓ったはずだった。
この視覚は主と共にある。
万力のくぼみに手をかけた。かなり重い。質量を感じたのはきっと、人間の頭一つ分の重さが加わっているからだろう。命の質量。
つぶれた人の頭をみるのだ。
僕は腕に力をいれてゆっくり開く。粘性のある液体が音を立てた。にちゃ、と気分の悪い音。少し開いたとき、中から赤が溢れだした。ベッド一体が真っ赤になるほどの血液量が氾濫した。
「あ……ぁ……」
思わず声が出る。手を止めてしまいたかった。どうしてこんな……。この部屋から逃げ出したいと、腹の底から思った。
――違う! そうじゃない!
目をそらすな。恐ろしいものから、目を。
一気に力を入れる。中で血が固まっていないのか、予想以上の力はいらなかった。ゆっくりと開いた。
肉と血。骨と脳漿。悪臭。タンパクの腐った臭い。人間。これが人間。人間の頭。新鮮な肉。血液。骨の欠片。眼球の離脱。歯の破片。肉。血。血。血。血!
「うぅう…うぅうううう」
カオルさんの中身を確認した。僕は目を開いている。逃げなかった。逃げることだけはしなかった。中身の隅々まで見つめること二十秒。きっとこの光景は主に届いたはずだ。
僕はゆっくりと、手を離し、再び万力を作動させず、自然におろした。
19
それから、僕はカオルさんの私物の確認をすると言って、部屋に残った。省吾さんにこれ以上ストレスを与えないため、先にリビングに行ってもらった。
カオルさんの私物は何も盗まれていなかった。
僕は昨日貰った、ボードゲームの本を思い出す。挟まっていた紙。
そこに書いてある指示通りにした。
『じゃあ、私はこれで電話を切るよ。薄野の持ち物とか、警察にはいろいろ私から言っておくよ。じゃあね』
「はい」
僕と省吾さんは死体発見から少し気分を落ち着かせることができた。省吾さんにとってみたら、主の人物像は全く想像つかないだろう。
僕と省吾さんは再びリビングのソファに座った。その後、監視カメラを確認したが、人影らしいものはもう映っていなかった。そのまま朝になっていた。
二階のほかに、盗まれているものはないか確認した。家に現金や金品はいくらかあったそうだが、そのいずれにも手はついていなかった。犯人の目的は純粋な殺意だとしか考えられない。僕は狂気を感じた。
「あの……真さん。電話で話していたアルジというのは……?」
「僕のお仕えしている人さ。アルジじゃなくて、漢字の主ね。国家探偵なんだ」
「探偵さんだったんですか……。通りで的確な指示だと思いました」
国家探偵というのは、日本において、怪事件、難事件を解決することを国家資格として承認している制度、役割である。警察が管理している情報を閲覧する権利と、担当している事件の捜査方針を決める権限が与えられる。この資格保有者のほとんどは刑事や警察官である場合が多く、仕事の延長として取得するケースが大多数だ。しかし、その門は狭く、推薦条項も試験もかなりの難関だ。
義洞事件全体で、三十四人の国家探偵に捜査要請が出されており、これは過去に類のない規模である。
「お名前は……?」
「それは言えない。秘密ってわけじゃないけど、僕からは言えないんだ。すまない」
「あ、いえ。偉い人だとそうかもしれません。はは」
「それより……。具合は大丈夫ですか?」
「え?」
「言っていいのかわからないけれど……、さっき具合悪そうにしていませんでした? 頭痛のような……。死体を見たから仕方ないのかもしれませんが」
僕は申し訳なさそうに、予防線を張りながら言った。
探るようで少し自分をとがめるが。
僕は僕自身の無罪を知っている。僕は二人を殺していない。それこそ、どうしようもないほどくだらない、使い古されすぎて擦り切れてしまっている、推理小説の二重人格じゃあるまいし。
すると、消去法的に、省吾さんを疑うしかないのだ。
昨夜、一番怪しい動きをしたのは、柊健吾だった。その柊健吾が死んでいる。となると、柊健吾に一番近かった人間、柊省吾を疑うのは当然であった。柊健吾が、省吾さんに《なにか》を託したという可能性。殺意の絡む何か。
「ああ、僕は頭痛持ちなんです。日常生活で支障がでることは少なくなりましたが、今でもストレスを感じると、発作が起きたりします」
僕はここで罪悪感を押し殺した。今は少しでも多くのことを知っていたい。
「ストレス? たとえば?」
失礼な質問だ。だが。
「……僕は、小さいころの記憶がほとんどありません。ここに来てからのことしか鮮明な記憶にないんです」
「それを思い出そうとすると、頭痛が?」
「はい。だから、僕は少しの親戚と健吾と過ごした思い出しかありません」
「……」
「健吾のことをもっと知りたかった。思い出を作る相手は健吾のはずだった。それなのに、僕は健吾の孤独に立ち入ることができなかった」
「孤独?」
「健吾はいつも言っていました。隠すしかない。守るしかない。閉じるしかない。なにかに怯えるようにしていました」
「今からでも……遅くないかもしれない」
「…今から?」
いなくなった人の影を探す気持ちは、わかる。追いすがりたくなる気持ちは、わかる。
「省吾さん、警察がここに到着するまで、僕と……、ドッグファイトで僕と勝負しましょう」
20
僕は柊健吾の部屋にゲーム盤があったことを思い出した。死体がある部屋に、省吾さんをもう一度向かわせるのは酷な気がしたため、僕が取りにいった。リビングでなく柊健吾の部屋にゲーム盤があったのは、昨夜カオルさんと対戦でもしたからだろう。
警察が到着するのはまだ先だろう。僕もここまで運転してきた身だ。どれくらいの時間がかかるかは察することができる。死体発見時は朝だったから、ここに着くのは昼前だろう。
盤をリビングまで運び、二人の席の間に置いた。予想通りそれなりに重かった。
ルールも覚えたての二人。
指摘し合いながら、盤上に駒を正確に並べようとする。
僕は昨日寝る前に、カオルさんから貰った本を読んだ。成長したと思いたい。
僕と省吾さんはそれぞれ身近な人は失ったのだ。もう会話することも、文字通り顔を見ることもない。当たり前みたいに、突然、いなくなった。
彼らの残り香を探すように、彼らの生きていた証拠を直に感じるように、僕たちはゲームを始めた。
ゲームの提案は僕からだったが、それは省吾さんを落ち着かせ、弔わせる意味があった。さらに、もう一つの意味。僕自身もカオルさんの姿を、このゲームに見出そうとしていた。
省吾さんはルールをところどころ思い出しながら、プレイした。間違っているところがあったら互いに指摘した。ルールの食い違いはなかった。それはそうだ。同じ人から教えてもらったのだから。
黙々と駒を動かす。
十五分後、お互いミスが多く、時間が引き伸ばされたが、僕が勝った。
「はあ、すごく頭を使った気がします」
省吾さんは言った。確かに僕も疲れた。
「そうですね。あの時、こうすればもっと……」
僕たちは、終了した駒を対戦中の一局面を再現して、反省を共有した。もちろん僕にも反省すべき点があり、省吾さんに指摘された。お互いのレベルはある程度拮抗していると考えてよかった。
その後、十五回に渡って対戦することができた。山に車が走るかすかな振動音が大勢聞こえ、十六回目は中断された。警察が到着したのだ。
僕は十回勝つことができた。カオルさんから貰った本が役に立った。
僕にとってはこれが形見のように思えた。
初めは拮抗していたと思えたが、僕は勝てた。僕は成長している。今は亡き彼女にそう報告したかった。
21
屋外では夕方の日差しが影を引き伸ばしていた。僕ともう一つ、大人の大きな影。
「梶原の御嬢さんから電話が来たと知った時は、正直参ったで。お前が関わっとるとすぐにわかったからな。……あれを見ても、狼狽えなかったところを見ると、さすがなんやろうな」
「うれしくありませんよ」
「まあ、そういうな。俺も正直、これには参っているんや」
「これ……?」
「国家探偵の死。薄野カオルは、複数の義洞事件の捜査責任者でもあった。刑事から見ても、これは二人の人間が殺害されたこと以上に、やっかいな意味を持つんや。もっとも、お前らにとってもそれは変わらないことやろうよ」
お前らとは、僕と主のことだろう。
「……」
午後四時。警察が来てから、あっという間だった。五十人は下らないであろう人数が家に押し寄せた。僕と省吾さんは長い時間、取り調べを受けた。衰弱していた。
そこに、宇津木刑事が現れた。僕にとって顔見知りである。主の配慮だろうが、この男はあまり好きではない。
宇津木宗太郎。国家探偵としてのカオルさんの部下に当たる刑事の一人である。国家探偵には担当補佐官という名目で、刑事課の一人が駆り出される。宇津木はカオルさんの担当補佐官であり、最もカオルさんを慕っていた刑事だった。しかし、そのせいで、僕を馬鹿にしてもいいと勘違いしている大人だった。
宇津木は胸ポケットから煙草を取り出して、火をつけた。煙を吸い込む。
吐き出して、
「薄野は、最後なんと言って死んだんやろな」
遠くを見ながら言った。
そんなこと、僕も知りたい。
人の死体はたくさん見てきたが、ここまでの喪失感は僕も初めてだった。義洞因子とこれからどう戦っていけばいい? 国家探偵の死は僕たち自身もっとも恐れるべきことだったはずだ。
「梶原奈義から、電話がきた。いろいろ指示をされたわ。相変わらず国家探偵ちゅうやつは、命令口調やな。ほんと」
「……」
「なあ、門間」
「なんですか?」
「絶対許すな。義洞因子を絶対に許すな。これでとうとうお前も事件の当事者や。甘えは許されん。」
暗い感情を噛みしめるような言葉だった。
「今回のこと、義洞事件と断定したんですか?」
「正確なことは、調査中や。義洞因子の犯行でなくとも、国家探偵を狙ったことが重要なんや。こんなことをして得するのは、連中以外考えられん」
「……」
「そりゃ、視野が狭いってもんでしょう刑事さん?」
背後から声がした。
「いくら上司が殺されたからと言って、理性を失うのはどうかと思いますよ」
「誰や」
振り向くとそこには、見知らぬ顔の男がいた。大きな丸い眼鏡をかけていた。背が低い中年の男。
「あ、私ですよ。宇津木さん。山寺です」
「山寺先生ですか……。山寺先生!」
「ん?」
「どうしてここにいてるんですか?」
「今回の事件、担当するのは私の班だからね。見に来たの」
誰だろうか? 僕には馴染みがない。警察関係者だろうか。宇津木が先生と呼ぶところを見ると……。
「ああ……。紹介する。山寺隆先生や。解剖医で、今回の事件も先生の班に受け持ってもらうことになっとる」
「はじめまして。門間真君」
手を握られた。しわのある年季の入った手だった。顔はそれに比べれば若い印象だ。
「薄野さんのことは残念だったね。ってこれじゃあ他人事みたいだ。違う違う、これからも一緒に頑張ろうねって言うんだ、こういう時は」
手を握ったまま、僕の目をじーっと見つめてきた。目を細めて笑っている。初対面の大人はやっぱり苦手だ。
「はあ……」
「じゃあ、私はこれで」
そういって、山寺先生は口笛を吹きながら、家の中に入っていった。
「宇津木刑事」
「なんや」
「解剖医の先生が現場に来ることってあるんですか?」
「あるわけないやろ。俺もあの人のことはよう知らん。何せさっき会ったばかりやったからな」
「さっき?」
「急やったからな。いつもは別の先生に頼んどる」
◆
「契約をしよう」と彼女は言った。
出会ったばかりの多摩川沿い。梶原奈義は楽しそうに、いたずらをたくらむ子供のように、僕に自分のことを話してくれた。
辺りは暗くなり、人気が少ない。川が流れる音が心地よかった。
葬式から逃げてきたしまったため、今頃母さんや親戚が僕を探しているかな、と申し訳なく思った。
ただ、その気持ちも彼女の言葉でかき消された。僕は今に夢中だった。
「契約?」
「そう、契約」
「契約ってなにをするの?」
「私があなたに魔法をかけるの」
「すると、どうなるの?」
「私はあなたのことがどこにいてもわかるんだよ。悲しいときも楽しいときも全部、それが私に伝わってくる魔法。契約するの」
「どこにいても? 今はだめなのかな?」
「今はだめ。契約していない今でも、距離が近ければ、ある程度は効果があるわ。でも離れたらそれでおしまい」
「……」
「魔法をかけて契約すると、もう距離は関係なくなるの。どこにいてもあなたのことがわかるようになる」
彼女との無制限のつながりを得ることができれば、僕はこれ以上うれしいことはなかった。契約は履行される。
「私、もうすぐ目が見えなくなる」
「え……」
「そういう病気。あ、これは魔法とは関係ないよ」
水面に映る僕たちを眺めながら、彼女は言った。
「だから、私は目を探していたの。私の新しい目になる人を」
「目になる……?」
「契約の内容はこうよ」
彼女は立ち上がった。僕を見下ろす。この瞬間に、梶原奈義は僕の主になる。
「『いつどこにいても、あなたの視界が、私にも見えるようになる』
人の視界は、感情によって変化するの。うれしくて高角が上がれば、視界の両端が狭くなる。興奮すると視界が広くなる。これはあなたの感情をふくめて、あなたの見たものを観測することを意味するの。
あなたの心はどこにあるの?」
「心?」
「そう……魔法ってそういうものだよ」
「心がどこにあるか……なんてわからない」
「正解だよ。それが答え。心なんて器官はない。だから、仮想する。心を。あなたは魔法に同意してくれる?」
「同意します」
主は、僕の肩に手をあてゆっくりと押し倒した。僕は寝転がるようになる。主は僕に覆いかぶさるように、地面に腕をついた。お互いの息遣いまでわかる距離だった。
「『門間真。貴様の心をその眼球に仮想する』」
契約は果たされた。
22
九月の二十二日、日曜日だ。僕は本来僕がいるべき場所にいた。帰るべき場所があるというのは心地いいことだった。帰って来られない人を僕は知っているから、そう思うのかもしれない。
ここは病室。正確に言えば、梶原医大第三病院の最上階の一室、京王国領駅から徒歩二十分で着く立地だ。大学の帰りに寄り安いのは、僕にとって都合のいいことだった。
「具合はどうですか、主」
「んー、悪くないね」
病室には、一般的で簡素な外装と打って変わって、大きな私用ベッドがある。そこに寝ているのが、僕の主、梶原奈義だ。
あの日の髪飾りを今でもしている。僕はこれを見るたびに安心するのだ。
ずっと病室にいる僕の主。目を常に閉じている。病状について僕は何も知らされていない。そこは主の叔父様がすべて管理している。この病院は梶原家によって経営されている。バイオ系やエネルギー系など、他の事業にも進出しているらしいが、元は医療会社として成功したらしい。
主の病状は知らなくてもいい。それは僕の仕事ではない。
主が見たいものを見て、主の人生に潤いと刺激を提供することが、僕に下された、最も基本的な命令でもある。その内容に疑問をはさむ余地はない。目が見えない意外に、不自由があるかもしれない。
「なんだか、真に会うのは久しぶりな気がするよ。会ってなかった時間は五十時間程度なのにね」
「僕には、もっと……長く感じました」
あの異常な空間を脱してから二日が経った。昨日は事情聴取などで、寝かせてもらえず、疲労と一緒に糸が切れるように布団に飛び込んでしまった。一通り用事が済んでから、ようやく主の病室まで足を運ぶことができた。
警察の見解は驚くべきものだったが、それ以外がないようにも思えた。
宇津木の話によると、
「警察は、あの夜、柊健吾が薄野カオルを殺し、自殺したと考えています」
ということらしい。僕は続ける。
「あの時、カオルさんの部屋に、入れる人間は、ドアの仕組みから柊健吾だけだということ。万力もスイッチさえ入れれば、自分で使うこともできます。頭をいれて、手でスイッチを押すのでしょう。ドアの仕掛けを用意していたことから、計画的な犯行だとみているようですが、自殺することでそれも確かめようがありません」
「……」主は黙って考えているようだ。
「そして、……その……、今回、警察は……この事件を義洞事件とは見ていません。……密室がないという見解です」
義洞事件は密室であること、そんな不確定で曖昧な基準でしか、現状判別がつかないのだ。犯人の様子をみないとわからない。今回も警察は例によって後手に回ることを強いられていた。僕が責められることではないが、今までの事件簿から、わかっているだけに悔しいことでもあった。
「うん、私も大体聞いたよ。それについてなんだけどね」
「ええ」
「それはありえない。間違いだよ」
◆
梶原医大第三病院に待ち合わせがある彼は、定時に間に合うように、ロビーに着くことができた。
大規模な病院であることが、ロビーの人の多さからもわかる。事務的な用がある人、医療関係者、患者、いろいろな目的を持つ人が無作為に散らばって、動いている。
これも社会の形だと、彼は感慨に浸った。
彼は体が悪いわけではなかった。至って健康体。肉体に不自由なところは見当たらない。
ただ、精神を患っていると言えば、彼はしぶしぶ肯定する。
他人から見れば精神の病気であるかもしれないが、自分の基準にあててみれば、それは性格であり、彼自身の個性と判断できた。
確かにこの性格で、あるいは病気で、不利益を被った時もあるけれど、我慢できる範囲、そういうこともあるか、と納得できる範囲のものだった。
それだけ、彼の精神的な病と、彼の生活環境は軋轢を生みやすいことも事実ではある。それは認めている。
だが、たとえ、そうであっても彼は自分の個性に誇りを持っていた。周りからどんなふうに揶揄されようが、彼には揺るがないだけ成熟したパーソナリティがあった。
このロビーにはびこっている人々は、それほど、自分が正しいと、胸を張っていえるだろうか。他人の目を気にして、足並みをそろえることだけを優先しているのではないだろうか。
そうなるくらいなら、精神疾患と中傷されるほうがマシ、と彼は考えていた。
自分の考えを曲げるくらいなら、間違いを認めるくらいなら、異端でいい。
間違いと、指を指されても、彼が彼自身を間違いと思わなければ、彼自身を見限らなければ、それでいい。
成熟とはそういうものだ。他人にどうこうできるものではない。
目が不自由で床に杖を振り回している者。手に包帯を巻いている者。片足を浮かせて杖に体重を預けている者。
彼らのように、明確な傷はない。
それに比べれば、自分が患っている精神の傷のほうが、胸を張れる。包帯で隠すようなものでもない。
彼はその劣等、異端に何の負い目もなく、エレベーターのスイッチを押した。
23
「間違い?」
「そう、間違い」
主は警察の見解を、ものの数秒で切って捨てた。何が違うのだろうか。
「密室でないという判断が間違っている。すなわち、義洞事件でないと判断することが、誤りだね」
――!
僕は、宇津木から義洞とは関係がないと言われたときに、ショックを受けた。せめて、カオルさんが殺されるなら、義洞であるべきだと考えていた。そのほうが、手掛かりをつかむ可能性があるのだから、カオルさんも本望だ。いや、――そうじゃない。これは理性的ではない、エゴかもしれないが。
そんなこととは関係なしに、義洞事件であることは、生きている僕たちにとって重大な意味を持つことは、再三意識してきた。
警察が捨てた可能性。主はそれを掘り起こしたという。
「理由は簡単だよ。それは真、お前が示したんだよ」
「僕が?」僕は自分に人差し指を向けた。
「そう。あの万力について思い出して。思い出したくなくても思い出してね。血の色は赤かったろう?」
「ええ」
「そして私はお前に、柊健吾の万力は開くように命じていない。それはなんでだと思う?」
「……」
「柊健吾の万力からは微かに血が溢れていたからだよ。万力の仕組み上、空気穴があり、閉じていようが開いていようが、零れていようがそうでなかろうが、血が外気にさらされることは回避できないの」
僕は、気分が悪くなることを覚悟で、あの赤い光景を思い出した。確かに、開く際に万力に蓋の重さ以上の質量は感じなかった。それは外圧がかかってないことを意味し、空気穴の存在を示していた。
「柊健吾の血液、薄野カオルの血液、どちらの鮮度が高かったか。覚えている?」
「柊健吾のほうは……すでに黒ずんでいた。カオルさんのは、まだ赤かったです」
「その通りだよ。だから、こう言えるんだ。
薄野カオルよりも柊健吾は先に死亡している。したがって、柊健吾は薄野カオルを殺し得ない、とね。」
「なるほど」
血液の鮮度から、確かな死亡推定時刻が割り出せなくとも、どちらが先に死亡したかは判断できる。そこから先は鑑識の仕事である。
「それが、この事件のはじめの基礎問題みたいなものだ。これだけでは十点ももらえない」
「じゃあ残りは……」
「焦っちゃだめ。柊健吾は薄野カオルを殺していない。とすると、次にどうなる?」
「……それは」
それは僕にもわかった。さんざん考えてきたことだった。
「カオルさんをだれも殺すことはできない……」
「そうだ。要するに、これは密室の復活を表すんだよ」
密室。義洞事件における必要条件だ。
カオルさんの部屋にはモニター付きの鍵が備え付けられていた。外側からドアを開けるには、中から開けてもらうか、ボードゲームで勝利しなければならない。あの家にいたカオルさんを殺し得る人物は、僕、省吾さん、柊健吾だった。その内、柊健吾だけが、ボードゲームに勝利することができる。もっと言うと勝負する必要はなく、鍵を外す方法を知っていたかもしれない。だが、その柊健吾は、カオルさんよりも先に死んでいる。
柊健吾には、薄野カオルを殺害することは不可能。
この矛盾。これが今回の密室。
「薄野カオルという人間は、探偵は、どんな理由があろうと、決して自殺を選ぶような弱さは持っていなかった。あの女は、臆病でこそあれ、逃げ出すことはしなかった」
カオルさんは死亡する前夜、僕たちに言った。
『絶対に思考を止めるな。そこで、その時、その瞬間、探偵は敗北する。義洞因子に負けるんだ。梶原も見ているな。絶対に屈してはいけない』
カオルさんが負ける姿は、僕は想像できなかった。
「その通りです」
宇津木も言っていた。薄野カオルは自殺するほどヤワじゃない。
「つまり、密室が復活する」
「ええ」
今までは、問題があるかもわからなかった状態から、解くべき問題を探り当てたということだ。この密室を解く必要がある。
「私は、すでに犯人が誰かわかっているよ」
主は、誇張なく、冷静にそう言った。
◆
真たちの会話より、十五分ほど未来。
彼はエレベーターに待ちあぐねて、階段を上ることを選んだ。
体力は人並み以下であることに自覚はあった。
しかし、エレベーターを待っていて、待ち合わせに遅れることを彼は恐れた。階段を使うのがベストであると、確信があった。
階段を使う理由はもう一つある。
それは、待ち合わせに遅れること以上に、大きな理由であり、彼の精神疾患に関わることでもあった。
他人と閉塞された空間に、居たくない。いつも根底にある衝動を思い出したのだ。エレベーターには当然他の人も乗り降りし、時には密着することもある。すぐ近くで感じる他人の息遣い。それが彼はたまらなく不快だった。拒絶反応なんて生易しいものじゃない。発狂しかけない事態だ。
そんな大事なことをエレベーターのスイッチを押してから、気が付くなんて、自分でも抜けているところがあるな、といささか内省し、階段を上ることにしたのだった。
24
「犯人が分かっている?」
「うん」
「だ、誰ですか?」
「それを言って、納得できるなら、言うけど、今の真には難しいかな」
主は勿体をつけるように、言った。
「正直、犯人が誰かなんて、大して大きい問題じゃないんだよ。不可思議な点はもっと、別の部分にある。仮に犯人を答えたとしても、何の加点にもならないだろうね」
「別の部分?」
「考えてもみてよ。私たちのように、現場にいた人間は、簡単に柊健吾が薄野カオルを殺していないことがわかる。それなのに、そうして現時点で警察は柊健吾が薄野を殺して自殺したなどと考える?現場を見ればそれは自明なほどなのに」
「どうしてって……」
「今日は事件から、二日経った、九月二十二日。事件からまだ日が経っていなないから、捜査が進んでいないのはしょうがない、なんて言うのはやめてね。警察もそこまで無能じゃない。死因くらいや死亡推定時刻くらいはその日のうちに解析される」
「じゃあ……どうして」
「自然に考えるなら、データを改竄した奴、裏切り者が警察にいる、と考えるのが妥当だね」
「!」
「問題は、警察全体を二日間、二日もの間、騙しおおせているということだ。放置しておけば、そうだね、明後日にはばれて、捜査方針も変わるだろうね」
「いずれ、ばれるなら、どうしてそんなこと……!」
「この時間に、逃げようとするんだろう。すでに敵は目的を果たしていると考えたほうがいいね。あるいは二日という日に意味があるのかな」
「目的というと……薄野カオルの……殺害?」
「それもあるだろう。だけど…確証はないけれど、もう一つ……」
「もう一つ?」
「それはあとでわかることだよ」
「?」
「ここまで話したし、勿体つけるのも難だし、犯人の名前くらいは言っておこうか」
「……」
「犯人は柊健吾だ……。彼は生きているよ」
◆
階段を上る彼は、心臓の高まりを感じていた。階段は疲れる。それに加えて、彼の持ち物があまりに重かった。上着の内側にしまってあるが、これをなくせばいくらか歩も早くなるだろう。
息が上がってはいるが、それは彼のただ脆弱な体力だけを意味しない。彼は興奮していた。待ちに待ったイベントがこれから起こると思うと、高まり、息遣いを抑えきれないのだ。
しかし、それにしても、階段の段数は半端ではなかった。最上階に病室があること自体が驚きだったが、待ち合わせがそこなのだから仕方がない。
これだけ苦しくても、思い立ってしまったら、今の階からエレベーターを使う気になれない。汚らわしいとさえ思う
汗をぬぐいながら、笑みをうかべて、足を動かしていった。
25
「柊健吾が……生きている」
簡単なことだった。あの場では、第三者の侵入は見られなかった。もともと誰かいたわけでもない。警察だって監視カメラを確認しているはずだ。
極々当たり前の結論。柊健吾しか犯行できないのだから、柊健吾が犯人というわけだ。
「そう。じゃあ私たちが発見した柊健吾のだと考えられていた死体はなんだったのか。簡単だ。柊健吾は生きている。すなわち、あれは柊健吾の死体ではなかったということだね」
「……あ」
「思いついたようだね。真」
「主が先ほど言った、警察内部にいる裏切り者。そいつの目的は、柊健吾が先に死んだことを隠ぺいすることではなく、本当の目的は、柊健吾の死体そのものを偽装すること!」
「そのとおりだ。現在警察が騙されている罠の正体はそれなんだよ」
「じゃあ、あの死体は……」
「……」主は黙っている。僕は雷に打たれたような衝撃を受けた。
そんな。
とんでもないこと。とんでもないことだ。
ふざけるな! そんなことがあってたまるか!
「あの……死体は……省吾さん?」
◆
彼は、最高潮に高鳴った鼓動を抑えるとこで必死だった。
最上階まで着いたのだ。この瞬間から彼の何かが始まる。素晴らしい何かが。
漠然と高揚している。言葉にできないうれしさ。
彼は満面の笑みとともに、最上階の奥手にある病室に向かった。
26
「柊健吾の死体は……実は省吾さんのものだった……」
「……」
「万力で潰されたのは、省吾さんだったんだ。顔が見えなければ、同じ体格だからわからない。いや、たとえ顔が見えていたって、気が付かなかった。双子だから」
「……双子の入れ替わり」
僕は万力にはさまれた死体を思い出した。そしてその直後にフラッシュバックする省吾さんの顔、声。
腹の内容物が逆流しかけた。
――最悪だ。くそ。
その瞬間、僕の電話が振動した。
頭が記憶の海を高速回転しているとき、それはとてもうっとうしく感じた。
電話は……宇津木刑事からだった。
「はい」
『あ、真か』
「ええ」
『近くに、梶原探偵がいるやろ! 代われ!』
「え、はい?」
僕は電話を主に渡そうとすると、主は首を振った。
「真、お前が聞いてよ」
主は少し大きめの声でそう言った。宇津木にも聞こえただろう。
「僕が聞きます。用事は何ですか?」
『あ? まあ、それでもええやろ。捜査開始日の夜から、お前の主様から指示があったんや。解剖医の山寺隆という男に注意しろ、とな。そしたら、昨日未明、山寺隆が失踪した!』
「!」
『連絡にも応じん。家までいったが、もぬけの殻やった。おい、今度こそ梶原に代われ! あれはどういう意味やったんや!』
僕は主をみた。主は頷いた。僕は電話を渡す。
「山寺の捜索ももいいが、検視をやり直して。山寺は義洞因子、あるいはやつらの味方である可能性が高いよ」
主は、宇津木から受け答えをいくつかし、――そう、いいや、と短い返答を介して電話を切った。
「主の推理通りでした。……省吾さん……いや、柊健吾を捕まえないと」
「そう早まっちゃだめだよ」
「え」
「これは、まだ事件の六十パーセント。ここからが、最も大事なところだよ」
「犯人はわかった。共犯者もわかった。他になにがあるんですか?」
「端的に言うと、柊省吾は死んでいないんだ」
――え。それはどういう……。
浮上した絶望を、瞬時に払拭する望みの出現。頭が追い付かない。
「私の勘の域をでないと言ってしまえば、確かにそうなんだが、きっと、薄野も私と同じ推理をすると思うよ」
「カオルさんも……?」
「そう。おっと、そうだった。これについては、お前を褒めなくちゃいけないね。よくやった」
主はベッドから身を乗り出して、僕の頭を撫でた。小さい手だった。撫でられた僕の頭は、振り回された思考を取り戻そうと躍起になっている。
褒められる?
「例のボードゲームあったよね。ドッグファイト。あれで事件後に柊省吾と対戦したことが大きかったんだよ。あれは私の指示じゃなかったね。お前が自分の意志でやったことだ」
「それは、僕の中でカオルさんの死を無駄にしたくなくて……」
「うん。無駄にならなかった。無駄にならなかったんだよ。あの時お前がボードゲームをしたとき、あの人物が、柊省吾である確証を得たの。ゲームやスポーツ、競技をする際、人には必ず癖がある。あの時のボードゲームの実力は、紛れもなく柊省吾のものだったよ」
思い出したのはカオルさんの言葉。
――素人は素人らしい動きをするのだ。たとえ玄人が素人の真似をしても、それは『玄人が真似をした素人らしい動き』になってしまう。
つまり、あの時、あの家に一緒にいた人物は省吾さんだということ。省吾さんは死んでいない。
「ちょっと待ってください。それじゃあ振り出しに戻ります。省吾さんが生きているということは、双子の入れ替わりをしていない。死体は柊健吾のもので、つまり密室が復活することになります」
「いや、密室は解消されているよ」
主は指折り、説明した。
「一つ、犯人は柊健吾であること。二つ、朝に生きていたのは柊省吾であったこと。この二つを満たす方法があるよ」
頭が混乱してきた。どういうことだ。
「まあ、それについては、彼に聞くのがいいだろうよ」
◆
彼は待ち合わせの病室のドアに手をかけ、ガラリと引いた。
27
主の発言のまさに直後、病室のドアが開いた。
「やあ、こんにちは、はじめまして」
「あなたは……」
彼は、照れるように
「初めまして、梶原奈義さん。そして久しぶりです、門間真君。俺はは柊省吾です」
と言った。
「省吾さん!」
「久しぶりと言っても、二日ぶりですけど、元気そうでなによりです」
はは、とあの時と変わらない、気さくな笑い方だった。
「……あの、俺なにかしましたか?二人ともちょっと怖いですよ」
僕は煮えくり返るものを感じていた。カオルさんを殺したかもしれない男。それだけで、正気を保つのに苦労した。今にも飛びかかってやりたい。
「真、やめてね。彼には今日は話を聞かせてもらいたくて、ここに呼んだんだよ」
「二日前に、梶原奈義と電話で聞いたときは誰かと思いましたが、あなたが門間君の主でしたか。あのときは……その、ありがとうございました。俺も精神的に参っていたところ、冷静な判断力は助かりました」
「それには及ばないよ。柊省吾くん、まあいいや椅子があるから座ってよ」
主は僕をむいて、顎で指示を出した。僕は省吾さんに病院用のパイプ椅子を渡した。
「ありがとう」と人当たりの声で省吾さんは言った。
一度、知ってしまったら、省吾さんに裏があるような気がしてならなかった。前のように接することは難しい。
「さて、話と言いますと、俺は何から話せばいいのでしょう?」
「うーん、難しいことを聞いても、しょうがないし」
僕は気が付いた。主の瞼が、開こうとしているのを、僕は見た。
「じゃあ、話を変えよう。柊健吾くん?」
――!
――柊健吾だって?
主の瞼は完全に開いていた。瞳は外気にさらされる。透き通った白色だ。その視覚には暗闇しか映らないが、主は目を開くことがある。
「健吾?健吾は死んだじゃないですか……。そういう冗談はあまり好きじゃ」
「あの日の死体は一体誰なんだい? 健吾くん?」
「したい……? 俺は健吾じゃありませんよ。なんですか?俺が入れ替わっているとでもいうつもりですか? 薄野さんのように」
「いいから答えるんだ。柊健吾。お前は私に嵌められたんだよ」
「だ……か、ら……俺は……健吾じゃ……、うあぁ、あああぁあ」
省吾さんは椅子から崩れ落ちて、頭を抱えた。
「痛い。頭が……」
「いいか! よく見るんだ、真! この醜悪な実態を!邪悪の正体を!」
「!」
僕は立ち上がる。省吾さんの様子がおかしい。彼の持病のせい……?いや、これは。
「ああああああああ」
省吾さんは地面に頭を打つように倒れこんだ。鈍い音がしたが、彼の悲痛な声で、かき消された。
「あああああああああ! もう!」
瞬間、立ち上がった。
「なんでかなぁ! くっそお! ああああ、もう!」
「なんだ……?」
僕は唖然と――。
「なにが失敗だったかなぁ! 畜生!」
雰囲気をガラリと変えた彼をみて――。
「こんなはずじゃなかったんだけどなぁ!」
失望の念を隠しきれなかった。
「ああ、そうだ。あんたの言うとおりだ。探偵さん。
俺は柊健吾だ。初めまして」
28
「この際、べらべら白状するけどよ。要するに、俺は二重人格だったんだよ。探偵であるアンタには簡単なんだろう」
「……」主は黙って聞いている。
「そして、さらに言うと、人格がパラレルに共存なんかしちゃいない。俺と省吾は、表裏一体じゃあない。省吾は、俺が作った仮の人格。ダミーなんだよ」
「……なにを言って……」
「探偵さんにからすると、あれか? 全部御見通しなんだろうよ。ちくしょう。警察内部に裏切り者がいるってことまで知っているのか」
「山寺隆……」僕はゆっくりつぶやいた。
「マジかよ。そこまで知ってんのか。侮れないもんだな」
「私には、まだわからないことがあるよ」
主は目を開いて、じっと健吾に顏を向けている。見つめているように振る舞う。
「あの死体、私たちが柊健吾だと思っていた死体は一体、誰の死体だ?」
「検視、って言うのか? それがいずれははっきりさせると思うぜ。だが、まあここまで来たら、話してやるよ」
柊健吾は、自慢話をするように、雄弁になった。どういう意図があるのかわからない。
「どうせ、俺は捕まって、裁かれるんだろう。極まっちまったら、死ぬことぐらい受け入れられるんだぜ。で、なんだっけか。そうだ。あの死体のことか」
「あの死体は……監視カメラに映っていた、駐車場口から入れた大荷物だな……」
主は確認するように、問いかけた。
「ああ! そうだ! 監視カメラ。あれが誤算だった。もとはと言えば、あれのせいだ。失敗はあの瞬間からだった。省吾のせいだ。ああ、もう」
柊健吾は、頭を掻きむしった。もはや自分に語りかけるような口調になっていた。
「……俺と省吾の関係は完全に優劣がはっきりしているんだ。俺が主人格であり、省吾はオマケ。俺が変われと言えば、あいつは言うことを聞かざるを得ない。そして、自分が作られた人格という自覚もない。いうなれば、あれは無知を演じるモードだった。俺の記憶や経験は、省吾に反映されることはない。逆にあいつの経験していることは俺に筒抜けだ。こりゃ、便利ったらなかった。俺という人格は、心の中の安全圏で、他人に悟られることなく、外界を観察できるんだもんな」
「省吾さんは、二重人格という自覚がないだと」
カオルさんと離れたあの夜、僕に省吾さんは持病のことを言った。事件が起きた後にも、持病のこと、記憶障害があることを言った。記憶が飛ぶことがある、というのは人格が入れ替わったということなのか。
僕は、自分の内側に、圧倒的に湧き上がる嫌悪感を覚えた。
――こいつは、異常だ。関わりたくない。
「だけど、便利なものが便利なままかというと、そうでもないのが難しいんだ。くそ。柊省吾になった俺は、無知を演じ切るために、全身全霊を賭けるんだ。俺の制御下を離れる時もある。そういうときは強制的に俺という主人格に入れ替える。無理やり元に入れ替えるんだ。そうして暮らしいてきた。他人と接してきた。ああ……もう。あの状況はだめだろう。俺が薄野を殺した後、省吾になるしかなかった。あの時だけは、俺は強制的に入れ替わることができなかったんだ……。そりゃ、ばれちまうからな。俺ができることと言えば、余計なことを言わないように、頭痛を起こすくらいだ。畜生。仮の人格ってのを思いついたときは、うまくいくと思ったけど……ああああ、なんだよ、くそ」
椅子に座り、柊健吾は、前にうなだれるように、膝を抱えた。人に話している振る舞いとは程遠い、反省と後悔を自らにぶつけているようだった。
――気持ち悪い。なにを考えているんだ。この男。
主は黙って見ている。いや、見えてはいない。主に見えているのは僕の視界だ。僕の目には歪んだ男の、自責の姿だけだった。
「ああ、探偵さん。ええと薄野……じゃなくて、梶原さん、だっけか。すまんな。人の名前を覚えるのは苦手でな。俺の代わりに死んだやつの話だったな。あれは事件の夜、運び入れたんだ。監視カメラをみれば映っているよ。もう見たんだっけか」
「それは知っている。誰かと聞いているんだよ」
「……山寺隆だ」
――!
「そういうことか」と主は言った。
「山寺という男は、実際は裏切り者ではなかったんだね。実在する人物だ。だからこそ、私は確証を得られなかった。怪しいと思って個人のデータをみても、実在しているのだから、経歴も疑うようなものじゃなかったんだ。まっとうな解剖医だった」
「察しがいいな、さすが探偵」
「山寺の皮をかぶった偽物は、私たちを、二日間という捜査上短くない期間、まんまと騙してみせ、一方で本物の山寺はすでに死んでいたのか……。万力で殺されていた……」
「ああ、正解。すでに死んでいる状態で、運び入れたからあいつに限っては苦しくはなかったんじゃないか」
「よくもぬけぬけと!」
僕は立ち上がった。声を荒げてしまった。本当はこんな男と会話もしたくない。
「カオルさんを、どうして……殺した! 殺す必要があった!」
「お、俺に話しかけるな!」
「なぜ殺した!」
この男だけは……許さない。柊健吾の性格は、計り知れないけれど、何か欠損していることだけは確かだ。
僕の激昂を遮るように、主は言った。
「そうだ。そこなんだ。すでに事件の八十パーセントは明らかになっているとしていい。しかし、残りの二十パーセントがないとダメなんだよ」
「残り?」
「動機をはっきりさせるときが来たんだ」
動機。――僕たちを含めた、捜査に携わる者たちが一番重要としているところだ。
犯人が義洞因子かどうか、それが僕たちにとって最も注意するべきだった。
義洞因子は動機を話さない。この話を振った瞬間に、なにか、心の中枢のなにかを閉ざしてしまう。
「柊健吾、お前はどうして、薄野カオルを殺したんだ?」
「……動機? 動機っていうのはそりゃ……」
この時間、僕たちの戦いを大きく左右する時間。この質問ですべてが決まる。事件の核が見えてくる。
「…………言えない」と、突然に虚ろになった表情で柊健吾は言った。
「真! こいつを殴れ!」
僕は、椅子を後方に吹き飛ばす勢いで立ち上がり、柊健吾に突進した。彼の顔面、左頸部をこぶしで吹き飛ばした。壁に背をぶつける柊健吾。否、義洞因子。顎を攻撃したのは、怯ませるため、相手の反抗心を折るためだが、もう一つは自殺を防ぐためでもあった。義洞因子は主と顔を合わせると、舌を噛み切って自殺する。
義洞因子は主が魔法使いとわかった瞬間に、自殺を図るのである。
だから、先手を採る。顎を弱らせて、舌を噛み切れないようにして、尋問する必要があるのだ。
僕は沸々と湧き上がった嫌悪感を拳に込めた。私情を混ぜ込んだ攻撃は、手加減を忘れていた。
「私たちは、どうして、義洞因子が魔法をかけられていると知っていて、何も手を講じることができなかったと思う?」
主は、倒れこんだ柊健吾に問いかけた。
「それは、お前たちが、目の前に立った私を魔法使いと知った時、自殺するからだ。私は、義洞良縁と同じ、魔法使いだ。義洞因子が、魔法をかけられ、心を仮想された人々ならば、私はその上から魔法を解くことができる。貴様は義洞の命令で、口を割ることができないのだろうが、私がそれを可能にする。これが、私たちの義洞良縁に対する反撃だ!」
「命令じゃ……ない」
柊健吾は口を開いた。僕は硬直する。義洞因子が口を開くことは珍しいことだ。滅多にあり得ない。
「俺たちは、俺たちの意志で……同意のもとだ。選んでこうなった」
「ならば、選びなおせ。もう一度、お前に選択の権利をやるんだ。魔法にかかったままか、魔法を解くか。操られていることを言い訳にするな。自分の頭で考えろ!」
「……答えは……ノーだ」
柊健吾は、倒れこんだ姿勢のまま、上着の内側に手を入れた。
右手には拳銃が握られていた。
29
手に持った拳銃が、9ミリ口径のベレッタМ9であるとか、どうやって日本に持ち込んだのとかはこの際どうでもいい。対処するべき問題は厳然としてそこにあった。
拳銃を見て「ビビった」僕は、目の前の男が、拳銃のスライドを引き、立ち上がることを許してしまった。
「俺に……近づくな」
先の一撃で噛み合わせが悪くなっているのだろう。声が弱々しい。
ただ、男には並々ならぬ覚悟が感じられた。
――この男は、すでに全てを捨てている!
口から少量の血を垂らしながら、睨んでくる柊健吾に、僕は怖気づいていた。こうなったら、どうなってもおかしくない。
「俺はなにも……喋らない。知っているぞ……。魔法には……『同意』が必要だってことはな」
「……」
無言の肯定。主の表情には小さな焦燥が浮き出ていた。事態のまずさに関しては、僕より何倍も認識しているだろう。
人の心を仮想する技術、魔法はただではかからない。人の心を扱うのだ。一人で勝手にかけられるような便利なものでない。
魔法をかけられる対象者の『同意』があって初めて、魔法は完全に機能する。そうでなければ心には届かない。そういうものなのだ。
今まで僕たちが、収容されている義洞因子に対して、『魔法解除』をできなかった理由は、単に義洞因子が自殺を図るからではない。たとえ自殺を防いだとしても、彼らが『魔法解除』に同意しなければ、成功しない。何度か試みは失敗し、挙句の果てに僕たちは、義洞因子との接触を禁じられてしまった。それは警察だけでなく、主が魔法使いだと知っている、他の国家探偵たちの判断でもあった。
今、この場は願ってもいないチャンスだった。
義洞因子と接触することは悲願だった。
しかし、そのハードルの高さは、前と変わらない。
「これで、この事件は……終了する」
柊健吾は拳銃を自分の頭に向けた。引き金に指をかけていた。
終わる。僕たちは何の成果も得られないまま、カオルさんを失って、また敗北する。
今回も……失うだけ失って、かき回されて終わる。
そういうものなのか……。義洞には……これ以上は……。
「真!何をしている!」
――主。
「思考を止めるな!」
それは、誰の言葉だったか。
あの時、万力を開いたあの時見たのは、この世の終わりの如くおぞましいもの。地獄だった。あの朝は確かに地獄だった。死を怖いと思ったのは、何度目だったか。まだ慣れない。きっとこれからも慣れることはない。しかし、僕が慣れようがそうでなかろうが、カオルさんの死は確実にそこにあって。彼女は終わってしまった。
終わる?
このまま?
嫌なことばっかりだ。
終わるとか死ぬとか、拳銃とか。
本当に見たくないものばっかりだ。
畜生。
だから?
見たくないものは見ない?
考えたくない?
カオルさんは、どうだったかな。
カオルさんなら――。
引き金が動くその直前、僕は柊健吾に飛び掛かった。
思考を止めるなと、言われた後だったが、思考を置き去りに体は動いた。やるべきことは一つだった。拳銃を取り上げる。自殺を防ぐことを第一にする。あとのことは……あとでどうにかする!
今は。
この時だけは!
拳銃を持つ手首をつかんだ。抵抗される力は決して弱くなかったが、制することができないほどではなかった。細身の体に相応した腕力だ。
「くそ……離せよ」
「それはお前だ!」
僕は膝で腹を突かれたが、その足を抱えることができた。相手はバランスを崩す。そのまま倒れこんだが、まだ拳銃はその右手にある。僕は上に覆いかぶさる。拳銃を手首こと床に押さえつける。右肩を殴りつけた。腕力に損傷を与える。
「さっさとそれを手放せ!」
その刹那、右手が開く。
――よし!
だが、相手はとっさに上体をやや起こし、左手に拳銃を握りなおした。
「くそ!」
早くそれを――。
直後、銃声が鳴った。
病院にはとても場違いな、張り詰めた発砲音だ。
「あ……」
僕と柊健吾は唖然とした。時間が止まったような錯覚すらあった。
しかし、すぐに時間は動き出す。
声を漏らしたのは、僕だった。
ただ、下腹部が熱かった。ただの違和感と思ったが、どんどん痛みになっていく。
見なくてもわかる。服を貫通してくる赤だ。あの時と同じ赤色。僕は撃たれたのだ。
痛い。
痛い。
――関係ない!
「はぁああああ!」
発砲は不本意なものだったのか。柊健吾は驚きを隠せていない。
愉快だ。こいつ、僕に恐れているな。
怯んでいる彼を殴りつけた。拳銃を離す。
力んだ時に、僕の胴体からも血が噴き出した。気にすることじゃない。不思議と痛みに集中しない。目の前のこいつに、僕の注意は集まっていた。
がはっ。柊健吾は吐血した。口の中に相当出血があるに違いない。ざまみやがれ。
柊健吾越しにみた床は真っ赤に汚れていた。大半が僕のものだろう。
不思議と頭は冴えていた。
「立て」
僕は殴られて満身創痍の柊健吾を持ち上げた。唸るような声を零したが、意識を失ってはいないはずだ。視界が揺れているのだろう。立ち上がるのに難儀な様子だ。
僕は柊健吾の両腕を抱え、首の後ろで手を結んだ。拘束した。動けまい。
僕の血は、密着する相手にも多量に付着していた。床は歩きづらいくらいだ。
「主……魔法を……」
僕はこいつを主の前に差し出す。
主は渋い顔をしている。僕を心配しているのか、事態を重く見ているのか。苦虫をかみつぶしたような表情。
「真、こいつの同意がなければ、魔法は……」
――だから、今はそいつを離せ、とでも言うのか。そうなれば、こいつは今までの義洞因子と同様に自殺を図る。そこで、僕たちはまた負けてしまう。
今、ここでどうにかしなければ、僕たちにはこいつに会う機会もないだろう。収容された義洞因子と接触できることはもうない……。
「俺は……同意しな……い」
ペッ、と血を主に向かって吐いた。殺したい。だが捜査は進まない。それにカオルさんは殺された。僕は殺さない。彼女に誇るために、殺さない。
「主……僕たちには今しかないはずです!」
残されたものはもうない。状況は極まっている。
打開策はない。
◆
血まみれの二人。ベッドで佇む無力な魔法使い。ここにいるだれもが、予想できなかったことがあった。一番知っているべき、柊健吾すらも気が付かなかったことが致命的だろう。どうしようもないと言えば、確かにそうなのだが、ただ、奇跡が起きたと勘違いをするのは避けるべきだった。
誰も予期できなかった奇跡のようなことでも、事象の裏側で奇跡の根拠は絶対的にあった。観測する目には映らない、地中深くに眠る一つの蕾。
それが萌芽を迎えたとき、三人はそれを信じられないだろう。どちらに有利に傾くかは置いておき、驚くべき事という点は、双方とも変わらない。
第一の萌芽として、柊健吾が義洞良縁の魔法にかかる際に結んだ、契約事項が上げられる。これは二重人格の発生を意味する。柊省吾の誕生だ。
第二に、柊健吾が、柊省吾を多用しすぎた点にある。人間関係のスキルを集約した、誰からも好かれる振る舞いをする柊省吾は、宿主にとって、便利すぎたのだ。二年もの間、ことあるごとに、省吾を使ってきた健吾は気が付かなかった。生まれたころはまだ、自己に関する記憶がなく、「人当たりのいい赤ん坊」のような省吾を、長期間育んできた結果、省吾自身が、健吾の心の中で確かな地位を確立しつつあることを、彼は気が付かなかったのである。
第三に、柊省吾が宿主の操作から離れつつあったことを引き金に、省吾が自身のアイデンティティを考え始めたことだ。自分とはなにか。どうして記憶がないのか。そこで突き当たるのは当然、柊健吾という主人格のことである。省吾はこのころから、自分は作られた副人格であることを、無意識に理解する。「言葉にできない、操られている違和感」程度のものだろうが、これも立派な思考だ。確実に柊省吾は成長していた。宿主である柊健吾とコンタクトを図りたいと思うほどに。
この三つの段階を経て、三人の病室に奇跡が起きたのだった。
否、奇跡ではない、必然が訪れたのである。
30
僕は柊健吾を抱えているが、ものの十秒程度で、意識が飛びかけた。血を失いすぎたのだ。立っているのがやっとだった。僕の体は危機を自覚してきている。
主も打開策も見いだせずにいたその時、声がした。
聞き覚えのある、親しみ深い声だった。
「俺が、同意します」
主は目を丸くして驚いている。予想外だった。理解が追い付かなかったのかもしれない。僕だって、信じられない。でも、彼はまだ生きていた。
「君は……柊省吾……かい?」
主は尋ねた。
「ええ、早く、魔法を……」
柊健吾の中に、まだ……『彼』がいた。
主人格である、柊健吾を押しのけて、そこにいる。
「頭痛が……!早く!梶原さん!」
「わ、わかった!」
頭痛は、内側で柊健吾が仕掛けているものだ。体を奪い返そうとしているのか。
「抑えていろよ、真!」主は声を張った。
「はい!」
「はや……く……」省吾さんは目を開いた。
「『柊健吾、貴様の心をその眼球に仮想する』」
魔法は、解除された。
僕の腹の銃痕は、全治三か月ということらしい。痛いったらなかった。
どういうわけか、数日たち、柊健吾の取り調べが開始されたときには、省吾さんはもう、彼の中にはいなかった。
もしかしたら、二重人格は、省吾さんの存在は、義洞の魔法によって生み出されたものかもしれない。だとしたら。
だとしたら、義洞の魔法を解除したあの瞬間に、柊省吾は消滅したのか。
消えていなくなった。
死体はない。当たり前だ。
だから、死んだのではなく、消えていなくなった。
それで彼はよかったのか。
健吾のことを知りたいと泣いた彼は、満足して消えたのか。
誰も知ることはできない。
◆
九月の終わりも近づき、涼しさが顔を出し始めた。気持ちのいい風を感じながら、男はコーヒーを飲んでいた。喫茶店のパラソルの中は、快適に寛げる。
男は連絡を待っていた。しかし、携帯電話は震えない。
約束の時間はとっくに過ぎていた。
「そうか……だめだったか……」
口元は笑っていたが、残念そうに言った。
男は独り言をよく言う。気持ちがすぐに口に出てしまう、というよりも、単純に人と話すのが苦手だった。自分が極度の人見知りであることはなによりも知っている。
心を開く相手は家族ぐらいなものだった。
「でも……そうすると……彼女が……」
今度は、明らかに嬉しそうな独り言。コーヒーをひと口飲んだ。
笑いが込み上げそうになるくらい、嬉しい。
「今回の失敗は僕にあるよな……健吾君は悪くない。僕があの解剖医を気絶させずに、殺しちゃったのがいけなかったな……」
反省が表情に出ていた。
「それにしても、嬉しいことだな……。梶原奈義っていうのか……」
男は、その名前を、今後一生忘れないつもりで、愛おしさの限りを込めて呟いた。
男は口笛を吹いた。
エピローグ
終わってみたら、ほんの数日の出来事なのだと、意外に思ったりもした。ただ、怪我は数日で治るものではなかった。
僕が主と同じ病室でないことは、本当に遺憾な限りだが、そうはいっていられない。僕とは待遇が違うのだ。僕の胴体には厚く包帯が巻かれており、傷は開く様子はない。僥倖なことではあるが、蒸れるのが悩みだ。早くまともに風呂に入りたい。
そろそろ大学も始まる。後期に何を履修するか、などと日常的な考えを起こしていた時、病室のドアが開いた。
宇津木刑事だ。
「よう、具合はよさそうやな」
「おかげ様……でもなんでもない。あんた達の無能のせいだ。見ろ。この包帯を」
僕は服を捲って見せた。正直体をよじるのも痛みが走るが、嫌味を言うためなら惜しくない。警察のせいでこんな目にあったんだ。
「まあ、そう言うな。死体の身元も判明した。山寺隆。四十三歳。見た目より若く見えると言われたりもしたらしいが、梶原医大法医学科の助教授だったよ。あの時、俺たちの隣にいた人間と同じ顔をしていた。どうやったかは知らんがな」
「他人に化けるなんて、簡単にできることじゃないでしょう」
双子でも、二重人格でも、同じ振る舞いはできるものではない。
「どうかな。同じ顔と認識しているだけで、実際並べてみたら違うのかもしんで。お前も俺も、見たやつら全員、もうそう簡単には、あの野郎のご尊顔は見ることはできないんやからな」
「見つけ出してくださいよ。仕事でしょ?」
「ぐちぐち言うなや。今日はいい知らせを持ってきたっちゅーのに」
「退院するまでは、嫌味に接しますから。で、知らせってなんですか?」
「あ、こういう言い方するか。おいしいニュースと、まずいジュースがある。どっちが先がいい?」
「まずい方で」
「ほれ」
渡された水筒。ゴクゴク。
「まっずい」
「じゃあ、次はおいしいニュースや」
「なんで飲ませたんですか?」
「まあ、聞け」
「聞きます」
……この野郎。
「柊健吾の取り調べなんだが、説明の要領が得ないんや。どうにも、奴自身、事件の記憶が曖昧なんだと。それでも、まあ概ね得られた情報はある」
「……」
落胆はしない。少しの情報を得ただけでも、僕たちにとって勝利だ。カオルさんの死を無駄にするわけにはいかない。それは部下であった、宇津木も同じ気持ちだろう。
「まず、初めに一番大きいことや。義洞良縁という人物が存在することがわかった」
「……そうですか」
今まで義洞良縁は、仮想的に定めた敵というだけであった。それ以上ではない。人物である仮定を置いてきただけだったのだ。これでようやく、実態のある相手と意識できる。バックにいる黒幕の姿を垣間見たのだ。
「そして、動機なんだけどな……。これがなんだが合理的な理由がないようなんや。柊は殺そうと思って殺した、とか、殺したくなったから殺した、とか曖昧なもんや。義洞は一種の催眠術で、殺したい衝動を操っているということなんやろか」
魔法だ。
魔法の存在を知っているのは、警察の上層部と、一部の国家探偵だけだ。宇津木は知らない。ただこの場合催眠術というとらえ方で間違っていない。
「共犯者……つまり、山寺の偽物のことはなんも知らないらしい。事件の当日、すでに死んでいる山寺の本物の体を渡したとき、その一回しか会ってないそうや」
「義洞因子同士で共犯したということですよね」
「ああ」
「過去にありましたか?」
「いいや、どれも単独犯や。未解決のものはわからんけどな。もしかしたらあるかもしれん」
面白い話はそこまでだった。あとは、柊健吾の親族や山寺の人間関係などが伝えられた。
そして、遺留品の話になった。カオルさんの私物はカオルさんの妹の手に渡るらしい。それが一番いいことだ。
「で、だ。門間」
「なんですか?」
「薄野の私物……お前、一個持ちだしてへんか?」
問いかけられた内容は、あまりに突然だった。いや、聞かれることはわかっていた。いずれ自分からいうつもりだった。もちろん、主と相談してからだ。
「心当たりはあると思うんやが……」
「きっと、調べてから聞いているんでしょうね……そこまで無能なわけないですもんね、警察って」
「ああ、ちゃうちゃう! 俺は責めようってわけじゃないんや、勘違いはやめとき」
「……すいません。盗みました」
「よし、逮捕しちゃお」
「ふざけろ!」
「お、れ、は、責めようってつもりはないだけや。ばーか。俺じゃないもっと偉い人が、ひいては法治国家がお前を責めるっちゅーんや」
「……この野郎」
「まあ、なんや。せいぜい、梶原に工面してもらうんやな、はっはっは」
「……」
これは冗談じゃないぞ。差し出がましいことではあるが、主に頼み込むしかないのか。
「冗談や」
気が付くと、この大人は煙草をプハーと吸っている。病室をなんだと思っているんだ。というか、僕の周りの大人はこんな奴ばっかりだ。カオルさんの真似のつもりかよ。カオルさんは……もっと、こう……すっきりとイジってくれたよ。
「なにを盗んだんや」
僕は、左腕の袖を捲った。それを外した。
「……カオルさんの腕時計です」
事件前夜。僕はボードゲームに関する本をもらったのだ。その時点でカオルさんは、事態を把握していたのかもしれない。
本の間にメッセージを書いたメモが挟まっていた。そこに、『もし私になにがあった場合、腕時計を回収すること』と書かれていた。それを確認した際に、僕の視界を通じて、主もこのことを知っている。僕が入院することがなかったら、この腕時計に関する話題は、誰よりも先に、主とするはずだったのだ。
この腕時計がどういう意味を持つのか、主なら知っているかもしれない。
「貸してみい」
僕は渡す。回収されるのだろう。そりゃ、国家探偵の使いだろうが、法に触れていいことと悪いことがある。良いも悪いもあるのかよ。
「これは、盗聴器が入っているんや」
「!」
カオルさんは……自分がどういう目に遭ったのか、記録していたのか。確かにそれは重要な手掛かりになる。
それにカオルさんは、死ぬ直前、どんな思いで、どんな覚悟であったのか、僕は大いに知りたかった。知るべきだ。彼女の生きた痕跡を、心に焼き付ける必要がある。
「薄野探偵は、傲慢で、狡猾で、疑り深くて、図太い女やった。俺以外の警察関係者はみーんな彼女をこわがっとった始末や」
「それは……なんとなく知っています」
「俺もお前と同じや。事件の前から、もしものことがあった場合、腕時計を回収するように言われとった。彼女らしいと思わんか?」
「……」
「ただじゃ終わらんというか、徹底しとるというか」
「時計に録音された音声は聞けますか?」
「ああ」
宇津木は鞄からノートパソコンを取り出した。さらにポーチから、片方がUSBメモリ、もう片方が見たことない差込口のコードを取り出した。
「なんですか?」
「みとれ」
腕時計の裏側のネジを、専用と思われるドライバーで外した。それほど時間はかからなかった。端末の差込口が見られた。
「!」
「知らなきゃわからん仕様やろ。ここら辺が懐疑的な性がよう出とる」
宇津木は音声を再生した。
音声はクリアに聞こえた。
柊健吾の精神の乱れから、話が変わり、カオルさんが結婚を申し込まれる会話になった。僕はこのことについては聞いていたが、宇津木はかなり驚いた様子だった。この時点では依然、柊健吾の動機は見えてこない。
しばらく会話がなくなり、布のこするような音、ペンで何かを書く音、なんでもないような様子が聞いて取れた。そして、場面が飛んだ。録音機の電池残量を気にしているのか、容量を気にしているのかは分からないが、無駄遣いはよくないとのことだろう。
数分後、僕たちは全て聞き終わった。大した量ではなかった。全内容で三十五分程度だった。それでも、圧縮された濃密な時間だった。
『お前は、俺が義洞因子だって疑っていたからきたんだよな。実際その通りなんだが、自分が殺される可能性を考えなかったのか、探偵。なあ、薄野……自分がどうしてこうなっているか……理解できるか?』
『さあ、なんでだろうな』
カオルさんの声が籠っていた。すでに万力の中に顏が挟んであるのだとわかった。胸が締め付けられる思いだった。
『お前らが言うところの義洞因子っていうのは、思っているほど崇高な目的で動いていない。俺がお前を殺そうとしているのは、大した理由じゃねえ。そうしたほうがいい、と思ったから、殺す。こんな程度の意識だぜ。俺は』
『それで、どうして私はこうなっているんだ?』
『悔しくないのか?』
『質問しているのは私だ』
『悔しくないかって聞いてんだ! 自分の立場わかってんのか? お前はもうすぐ死ぬんだぞ』
『死ぬのは嫌だ。怖い。だが、それは置いておいて、私にどうやってこれを装着した?』
これとは、万力のことだろう。
『飯に睡眠薬を混ぜたんだ。お前は疑いもせずに、食べてくれたおかげで、すんなり計画が進みそうだ』
『そりゃ……よかった。どうして私は殺されるんだ?』
『知ってどうするんだよ』
『もし、私が死ななかったときに、多くの情報を持ち帰れるからだ』
『やっぱり、お前はわかってねえ。死ぬってことがわかってねえ。俺も異常だが、お前も大概だ! どうしてそんな冷静でいられるんだ! 命乞いでもしてくれよ!』
『お前、私を殺したくないのか?』
『殺すっていってんだろうが! ぶっ殺すぞ!』
『まあ、殺すのはいいから、私はどうして殺されるんだ?』
『……くそ。……魔法って言ったら、馬鹿にするか?』
『これから、死ぬだろう人間に馬鹿ににされるもないだろう』
『それもそうだな。俺は……魔法をかけられた』
『へえ。義洞因子っていうのは、魔法と関係あるのか。それで?』
『魔法にかけられたものは……家族になるんだ。《家族》になると、価値観が共有される』
『価値観っていうのは?』
『共有される価値観は《排他》と《防衛》だ。《家族》以外の他人と徹底的に距離を置き、壁を作り、心を許さず、疑うことだ。《家族》の中では、価値観の同じ人間しかいない。気分のいいことだ』
柊健吾の声はどこか感情がなくなった。無表情な声だ。
『ほう』
『しかし、それは自己完結を意味しない。家族を増やす行為を行う。同じ価値観を共有しうる境遇、精神状態を持つ同類を常に探している。家族を増やすために、《母体》からの指示を仰ぎ、最終的に選ばれた同類に対して、価値観の移植を目指す。価値観が共有されたとき、《家族》となる。』
『母体……というのは、義洞良縁のことか?』
『肯定する。《母体》の計画を実行に移し、価値観を同類に移植する。その際には、移植対象者に《同意》を求める。《同意》がなされ、そこで初めて《家族》になる。その際に、《母体》に立ち会ってもらう必要がある。すなわち移植対象者は《母体》に対して《同意》をするのである。この作業を《魔法》と呼称する』
『梶原と……同じ……?』
『梶原という名前を記憶した』
『お前は誰だ。柊健吾か?』
『私は、柊健吾の知識を基底とする、《家族》共通で統合されている思考援助システム、価値観と呼ばれるもの、私たちの敵が義洞因子と呼ぶ人間の核を成すものである』
『義洞因子は、全員お前を内側に抱えているということか?』
『肯定する』
『梶原が……敵も魔法使いと言ったが……こういうことか!通りで捕まらない!義洞因子は合理的でないが、そいつらを巣食っているお前が支援していたのか!』
『おしゃべりはここまでだ。ここまで話した同類は初めてだ』
『まて!どうしてお前らは人を殺す!』
『《母体》が《魔法》を行う際に、《同意》を断ったものには……《排他》と《防衛》を実行する』
『殺すのか』
『肯定する。さあ、選べ。同類。我々の《家族》になるか。今、この瞬間まで《同意》を受け付ける』
僕は、聞きながら、叫びそうになった。そこで同意しなかったら、カオルさんは殺される。そして殺された。記録媒体の中でのカオルさんに死んでほしくない。論理的でないことはわかっている。カオルさんがどういう人かもわかっている。
それでも生きてほしかった。
信念を曲げてもいい。敵の手に落ちてもいい。
それでも生きて――。
『それは、違うよ』
『違うとは、何が違う?』
『いやね、お前らと同じ《家族》になってまで生きるのは違うってことさ。くそくらえだ。社会に甘えたゴミどもめ』
『処置を行う』
スピーカーの向こう側で、キリキリと音がした。それは万力の駆動音。僕の精神をズタボロに引きずり回すような音だ。死が訪れた。
『《母体》にお前の死体を見せれないのが残念だ』
『なんだと! 母体が近くにいるのか!』
キリキリキリキリ。
『そういうことか!この事件には共犯者がいるな!』
キリキリキリキリキリキリ。
カオルさんはどうして悲鳴を上げない。どうして、この期に及んで思考する。
『そいつが義洞良縁だな!』
『肯定する』
『はははは、私たちの勝利だ! 私の部下、同僚がお前らを必ず捕まえる! 私はその後押しをできたことを光栄に思う! 追いつめられたのはお前たちのh……』
グシャ。と破壊音が聞こえた。潰されたのだ。頭を。
「う……う……ぁ……」
僕は、泣いた。泣けないけど、心で泣いた。主だけにはきっと見えている。
得られた情報は多かった。これだけあれば、十分戦える。義洞の尻尾をつかんだといってもいい。
僕たちは義洞良縁に会っていた。あの山寺隆の偽物だ。やつが義洞良縁。
でも……今はそんなことより、感情が抑えきれなかった。
どうして、そこまで……最後まで戦った?
どうして、戦えた?
カオルさんはどうして、命乞いをしてくれなかった。
死ぬことはないじゃないか。
生きている僕たちばっかり、得している。
どうして、あそこで……信念を曲げてでも、生きたい、と思ってくれなかったんだろう。
「勘違いするな、門間。薄野は死にたかったわけじゃない。最後まで敵と戦った。屈しなかった。それだけや。矜持をもって死んだんや」
「……そうだけど」
「思考を止めるな」
「……」
「何があっても、そう言われた。お前もそうやったと思う」
「ええ」
「じゃあ、どうする?」
「戦います」
「そういうことや」
こうして、この事件は終了した。
国家探偵、薄野カオルの手によってもたらされた情報。義洞因子の殺害の目的、義洞良縁の存在、やつらの心の核にいる怪物がはっきりした。それらは、警察が義洞事件始まって以来、のどから手が出るほどほしかった情報だった。
彼女の高潔により、僕たちは、義洞に対して初めて、大勝を果たしたのだった。
探偵・薄野カオルは屈しない。
長かったと思う。やりすぎ。
展開が拙い。

