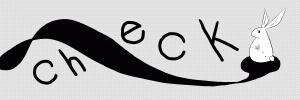愛しい彼らに幸があらんことを
愛しい彼らに幸があらんことを
スルリと、通り抜ける手。
それは存外あっけなく、彼らの肩を突き抜けた。とはいっても、物理的に貫いたわけではない。水に手を入れても通り抜けるような、そんな感じだ。
しばらく、通り抜けた何も感じない透けた手を見て、すっと目を細める。いつからか始めたこの習慣。
今日は触れられるんじゃないか、明日は触れるんじゃないかと、ありもしない希望に縋り付いているこの習慣。
あの日身を投げたのは、自分だというのに。
全てをかなぐり捨ててでも守りたかった彼らに、最後は全部裏切るように身を投げた。
泣きながら俺を止めに入る彼女も。怒りながらこちらに突進してくる彼も。驚きで動けない彼女も。強すぎて、こちらが目を逸らしたくなるような眼光を向ける彼も。
「……帰りたいなぁ」
思わず呟いた言葉。後悔先に立たず、とはよくいったもので、この拷問のような状況に膝をついてしまいそうだ。自分で選んだ道のくせに。
ふ、と耳に入る涙声。自分の名前。ああ、そういえば今は葬式の最中だった。
鬱々とした空間に、鼻を啜る音や、お経が相まって、そこには悲しみと陰鬱な空気が漂っていた。
もし、ここで俺が現れて、「うそだよ、ごめんね?」っていえたら、どんなに幸せだろうか。あんな奴のために死ぬんじゃなかった。まあ、俺が死ななかったら、今頃彼らも死んでたけれど。それを考えると、やはり死んでよかったのかもしれない。触れれないのが辛くて、存在を認識されないのが苦しいけど。
こんな未練タラタラでも、やはり彼らには幸せになって欲しいと想うのは、いけないことだろうか。
最後の遺言だとでも思って受け取ってくれないかな。彼らはきっと受け取らないだろうけど、そもそも聞こえてすらいないだろうけど、
「君たちの幸せを永遠に、願うよ……」
呟いた時に、彼らがこちらに振り向いたのは、気のせいじゃないと信じたい。
もう、確かめるすべはないけれど。
愛しい彼らに幸があらんことを
この作品をお読みいただきありがとうございます!
もしよろしければ感想などもぜひ