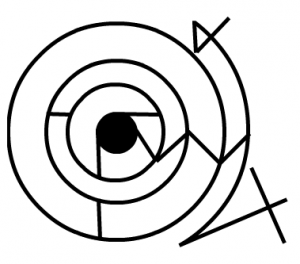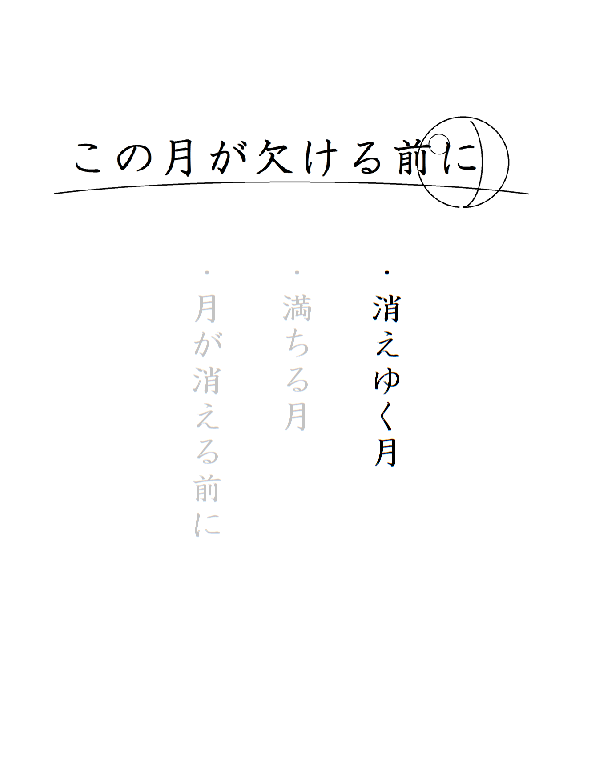
消えゆく月
新シリーズです。全3話ですが。 地球とはまた異なる星、科学技術が進んだ惑星サイクラウドの月でのお話です。
灰色の大地を駆ける彼は、やがて彼女と初めて出会ったクレーターにたどり着いた。
灰色の大地を駆ける彼は、やがて彼女と初めて出会ったクレーターにたどり着いた。
惑星サイクラウドの周囲には無数の人工衛星が飛び回り、惑星に資材を提供し続けてきたこの月はその役割を終えようとしていた。
「搾り取るだけ搾り取って、空になれば捨てる。この世界は変わらないね」
窓の外には灰色の大地。黒い宇宙が広がる中で、造られた輝きをもって光る星は大きく、母なる大地から逃れることはできないとでもいうかのように思えた。
窓の外から目線を逸らさず、黒い病室のベッドに座るハークは言った。見舞いに来た兄から伝えられたこの衛星の運命は、そこに住む人々に決断を迫るだろう。しかしハークは、また別の問題を抱えていた。
「それで、兄さん。僕はあと何日持つんだい?」
窓に映るハークの視線を受けて、兄であるジークは顔を伏せた。
「ハーク、すまないな。研究のテストを頼んだばっかりに、俺は取り返しのつかないことを」
「いいんだよ。僕たちが生きていくには、兄さんの研究しかなかったんだから。それで、あと何日持つのかな?」
ハークは顔色一つ変えずに応えるが、弟の無理しているであろう姿がかえってジークの心を抉る。
「お前の寿命だが、この部屋で延命してせいぜい30日。いずれにしても、この衛星が欠ける前には」
絞り出すようなジークの答えにも、ハークはこれといった反応を示さなかった。自分の運命を悟り、受け入れたかのように寂しい笑みを浮かべ、ただただ窓の外を眺めた。
すぐ戻ると言ってジークが部屋を出てもなお、ハークは窓の外を眺め続けた。
灰色の大地には様々な窪みがあるが、そのほとんどは人の手によって開けられたもので、目の前の荒らされた大地と自分の身体を重ね合わせていた。
生活補助用の意思を持った機械。兄が人生をかけて進めてきた研究。その頭脳のモデルはもちろん人間であり、一から作るよりも生身の人間のものをそのまま真似る方が手っ取り早いことはわかりきったことだった。
それまで倫理観が抑止してきた人体実験の壁をジークが越えてしまったのは、誰もが抱く単純な理由、明日を生きるために他ならない。ジークはハークにテストと称して研究開発に参加させていたが、ハークは自分が実験の材料にされていることを察していた。
余命一か月の命。月よりも先にこの体が消えていくと考えると、彼は自分でも不思議な程に、待ち構える死の運命に恐怖しなかった。それはこの世界にある種の失望を感じていたからかもしれないが、もはやその理由さえも彼は必要としなかった。ただただぼんやりと窓の外を眺める。
脇に飾られていたアンティークな写真立てが落ちたのは突然のことだった。ガラスは飛散し装飾が砕けて床に散らばる。幾ヵ月ぶりかの外気に触れた写真には、ハークと若い女性が少し恥ずかしそうに並んで写っている。
ハークは写真を手に取り、彼女との思い出を振り返った。写真に写るクレーターで、母星が見えなくなる時間、二人は毎日のようにそこで会っていた。何をするでもなく、ただ二人でいただけだが、少なくとも彼はその時間にかけがえのないものを感じていた。しかし、最後に会ったのは数か月前である。彼女から母星へのいつ帰るかわからない旅に出なければならないと聞いた時、彼は彼女を抱きしめた。それは彼女をこの体に刻み込もうとするかのように強く。
窓の一部がディスプレイに変わり、臨時の放送が入ってくる。この衛星の未来を担って交渉の旅をしていた一団が帰ってくるらしい。画面には直近の交渉の場で代表が向こうの総代表と話している姿が写っている。
ジークが再び弟の病室へ向かった時、病室の扉が開いているのを見て、彼は息をのんだ。急いで部屋の中に入るが、寝台の上に弟の姿はない。床に散らばった写真立ての装飾。そしてベッドの上に置かれた写真を手に取ると、おそらく少し前のハークと同じように緊迫した表情で病室を後にしたのだった。
消えゆく月