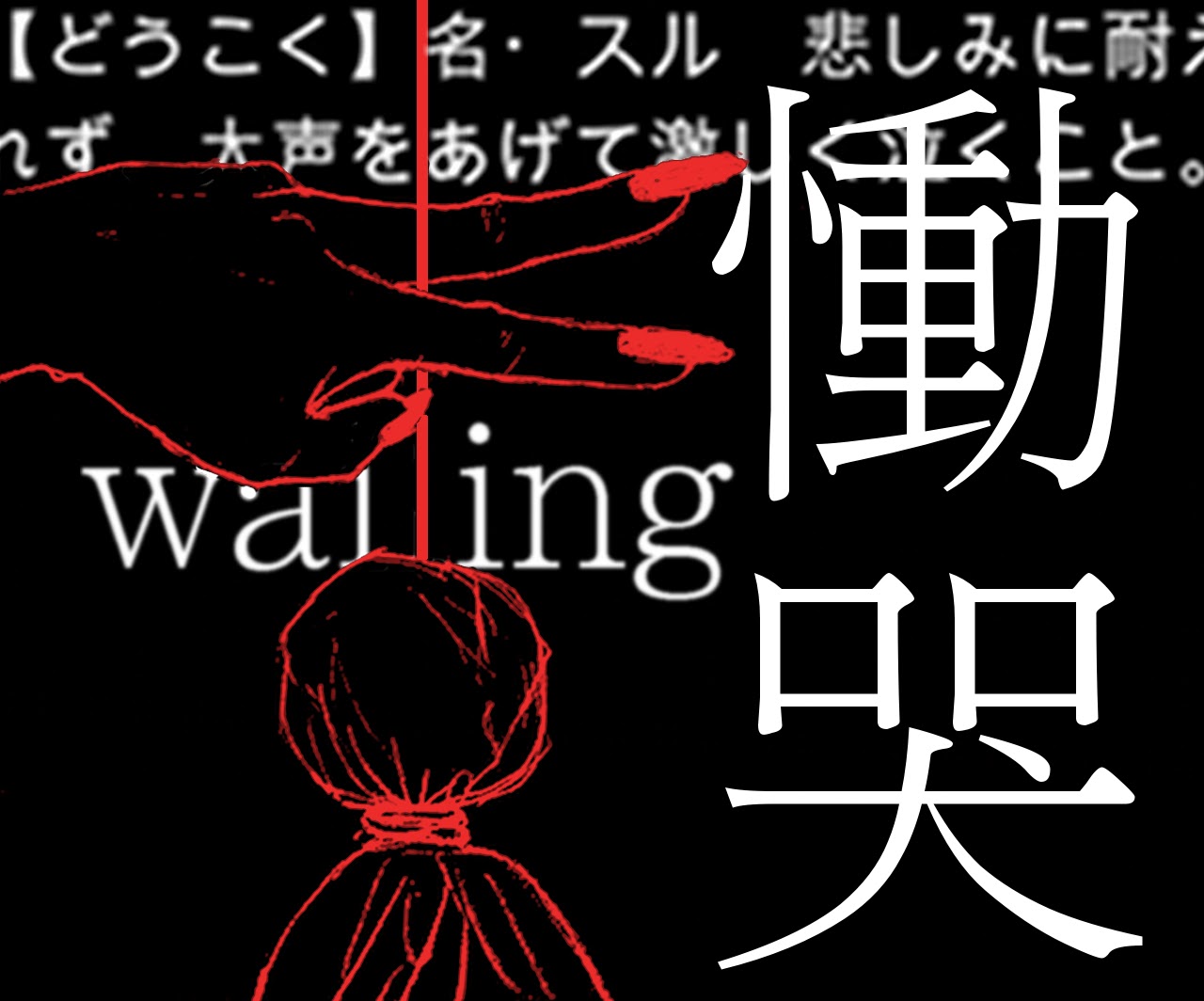
慟哭
2013年作品。
「俺、さっさと首根っこかっ切って死にたい」
真昼のカフェテラスで、思わず日頃から思っていた本音が漏れた。
「は?じゃあさっさとかっ切って死ねば?」
友人の楓は笑ってさらりと流した。
自嘲めいて答えた。
「それが出来たら苦労はしねぇよな」
二十歳そこそこで人生に飽きた俺はわざわざ上京して進学した大学を中退し、短期のアルバイトをしてはぶらぶらとフリーター生活を送っていた。
大学二年までは結構順調な人生だったと思う。
そりゃそれなりに思春期の悩みとか人並みに苦労したこともあるけど、当時あれほど悩んだ事も今では本当にどうでも良い事ばかりだった気がする。
今の悩みに比べれば、彼女が出来ないとか金がないとか人間関係が上手く行かないとか学校がだるいとか、取るに足らない。思い通りにならない事ばかりでむしゃくしゃしたけど、そこそこ遊んでまあまあ楽しい日々を暮らしていた。
なのにある日突然、そう二十一歳の誕生日を越えてひと月くらい経った頃、急に人生の何もかもがつまらなくなった。
それまで好きだった音楽も聴かなくなったし、どんな漫画を読んでも、映画やドラマを見ても面白く感じない。連れたちとカラオケに行こうがボーリングやビリヤード、ダーツバーに行こうが、心の底から楽しいとも思えなくなっていた。
「春樹、今度皆で温泉旅行にでもいこーよ」
仲が良かった元大学のメンバーで一時期恋心を抱いていたジェシカに誘われたときも、正直かったるいなと思った。
ジェシカは今流行のハーフモデルの卵で、最初出逢った頃は是が非でもお近づきになりたいと必死だった。
同じ学部の楓と仲良くなって、楓の友人の彼女つながりで、ジェシカたちのグループとよくつるむ様になった。
当時はラッキーだと思った。如何に他の奴を出し抜いて二人っきりのデートに誘えるのかそればかりに躍起になっていた。
だがその後楓の友人の柏原が泥沼三角関係の末ジェシカのハートを射抜いて付き合う様になってからは、そのグループも四散して交流も少なくなっていた。
彼女への想いも薄れ、都会の遊びに明け暮れ、ちょっと怪しいが割のいいバイトで稼いだ金でまた遊んで、それでも欲しいものを買うと足りなくていつも金が欲しいと呟いていた。
在学中に一人だけ付き合った彼女ともひと月で合わなくなって、クラブでナンパを試みても全然スカばっかり。それでも楓と街をぶらぶらするだけでもなんとなく楽しかった。
今を思えば。
「なあ春樹、それで旅行の件どうすんの?早く決めねーと」
「んー……」
ジェシカが柏原と別れたと聞いて女友達含めて久々に集まろうと声を掛けたのは自分自身だ。
それからまたジェシカたちとも交流が復活した。
まだ人生に絶望などこれっぽっちも抱いてはいなかった。でも、こんなにも突然人生が詰まらなく感じるなんて。
「お前最近変だよな。前はあんなにがつがつしてたくせに」
楓もめっきり付き合いの悪くなった自分に対して多少の苛立ちを感じているようだった。
「とりあえず特に予定もないなら強制参加な。……お前チャンスなんだぞ?最近ジェシカ絶対お前の事気にしてるって。巧くやれば付き合えるかもじゃん」
「……あぁ、そうだな」
適当に答えて話を合わせた。面倒くさいがこの際断るのも面倒くさい。
用事があると言って楓と別れたが、実は特に何の用事もなかった。レンタルショップにぶらりと立ち寄ったものの何も借りる事無く自分のアパートに戻る。
築三十年にして早くも古めかしい雰囲気の外観に薄い壁の安めのアパート。
上京した当初はもっと上等なマンションに住みたいと思っていたが、今は風呂と用を足せて横になれるところがあれば充分だと感じていた。
もう何日も確認していなかった郵便受けを見ると、溢れる程のチラシの束が無理矢理突っ込まれていた。
思いっきり引っ張ったが引っかかってなかなか取れない。
ヤケクソに力を込めると持った部分が破れた。びりびりと破りながら突っ込まれていたチラシを取り出すと、それを全部まとめて指定のゴミ袋の中に押し込んだ。
敷かれたままの布団の上に崩れる様に座り込んだ。このところろくに掃除もしていない。散らかり放題の室内を目の当たりにして深いため息が漏れた。
膝の間に沈めた頭を両腕で抱えた。
——死にたい。
自殺撲滅運動のキャンペンカーの上で襷を掛けて熱弁を振るう中年女。
「一人一人の命、それはとても尊い物なのです。一人で思い詰める前に、まず、誰でも良い、誰かに想いの内を吐き出しましょう」
駅前のスクランブル交差点の真ん前で、幟を立ててチラシを配る集団。
見向きもしないで通り過ぎる人々が多い中、数人のスーツを着たリーマン風の中年親父や、ちょっとオタクっぽい男、真面目そうな若い女が遠巻きに足を止めていた。
「知り合いにはなかなか相談出来ない、そう言う方もいらっしゃると思います。そんな時はぜひ相談ダイヤルをご利用ください」
クスッ——。
余りにも皮肉で思わず笑ってしまった。
死にたい奴は死なせとけば良い。
本当に死にたい奴はわざわざ相談ダイヤルなんてかけるもんか。友達に死を仄めかしても冗談程度にしか受け止めてもらえない人間の気持ちなんて分かる分けない。
毎日死にたいと思いながら生き続ける事が、どんなに苦しいか。
潔く死ねる奴が羨ましい。
何度か、いっそ死のうと手首を切ろうとしたが、助かってしまったときの事を考えるとみっともなくて出来なかった。
首をくくろう、そう思った時には死後の悲惨さを思い描いて断念した。
薬剤で死のうとネットで調べたが、最近は睡眠薬も確実性が低かったり青酸カリなどの毒物も規制が厳しくなって入手が困難な様で諦めた。
でも本気を出せばどうにかして入手することも出来るはずだ。
まだ覚悟が、足りない。
頭の中では何度も自分を殺した。想像するだけで少し気が楽になるからだ。
そして最近辿り着いた答えは、死ぬなら首を走る頸動脈をズバッと切り裂くやり方。
手首みたいに万が一発見されて救急車を呼ばれても助かる確率も低いし、確実性が高い。
ただ難は、マジで恐いってこと。
一度、もういっそ試してみようと百円ショップで購入した包丁を首に当てたが、いざとなると本当に恐ろしくて力が入らなかった。
歩き疲れて入ったカフェでカフェオレを注文した。
携帯電話を見ると、母親から着信が来ていた。それを無視してネットニュースをサーフィンする。芸能ネタ、スポーツ、政治。どれも特に関心が無い。
なんて詰まらない世の中なんだ。
諦めて携帯をテーブルに置くと、ガラス越しに人ごみを観察した。
多くの人間が携帯電話を構いながら歩いている。時々待ち合わせのグループが手を振って、そしてそのままどこかへ消えて行く。
もうほとんど空のグラスに入ったストローの口を咬みながら、ボーッと外を眺めていたときだった。
「あれ?春樹じゃん?久しぶりー」
ふと名を呼ばれて振り返ると、大学時代のグループの1人だった。
「……あぁ美夏、久しぶり」
「あれー?最近楓と一緒じゃないの?」
「いや、今日は一人でぶらぶら……」
「そうなんだー。あ、もしここ空いてるんなら一緒していい?」
無言で頷きながら携帯電話をテーブルの隅に移動させた。
「ごめん友達も一緒だけど」
「こんにちは、初めましてー」
美夏には連れの女子がいた。華穂と名乗ったが正直名前なんてどうでもいい。
「大学の友達。あ、そう言えばこの前二人でハナヤンのライブ行ったんだー!超最高だったよ!」
「あ、そう……良かったじゃん」
辛うじて笑い返した。
以前はよく好んで聴いていた音楽グループだ。美夏も好きで音楽の話でよく盛り上がっていた。
その後美夏は色々楽しそうに話しだしたが、ほとんど耳に入って来なかった。適当に聞き流して適当に相づちを返していた。
「ねーねー、春樹この後暇?一緒にカラオケ行かない?サークルの仲間とオケパなんだ」
「……いや、今日はいいや。なんか気分じゃないし」
「ふーん、そっかー。っていうか春樹メアド変えた?この前楓にメールしたのに全然返信来なくってさー、マジおこなんだけど」
「あー、変えた」
「じゃ教えて?」
「ん……」
面倒だが仕方なくアドレス画面を見せた。
「春樹いい加減LINEやんなよー。電話もタダだしさぁ」
思わず、めんどくせぇ……と呟いた。
「え?」
「あ、いや……。なんか既読とか色々面倒そうだから、いいわ」
美夏は少し拗ねた様に唇を尖らせたが知らん顔した。
「最近SNSも全然見てないよね、春樹」
不満そうな表情に嫌気が差して、さも思い出したかの様に口を開いた。
「あ、そう言えば俺この後ちょっと用事あんだ。悪いな、まあまた誘ってよ」
心にも無い事を平気で言うものの、笑顔を作るのもしんどくなって来た。
立ち上がって足早に店を出ると自然と舌打ちした。
何をする気にもならない。
ただひたすら道を歩き続ける。
気がつけば全然知らない住宅街まで足を踏み入れていた。
辺りはもう真っ暗だ。
引き返してまた駅に向かって歩き続ける。繁華街まで戻って来て古びた中華料理店の店先に、手書きでアルバイト募集と書かれたチラシが貼ってあった。
そろそろなにか仕事しないと所持金が尽きる。分かっていても何もやる気にならない——。
いっそこのまま道路に飛び出して、車に轢かれて死んでしまえれば良いのに。
死ぬ気になれば何でも出来ると言うが、実際に死ぬ覚悟も勇気もない自分には何も出来る気がしなかった。
いっそドラッグに手を染めたい。
LSDは悪く無いと聞くが、今は流行らない。
脱法ドラッグも多いがいまいち惹かれない。
酒は特に飲む気がしない。
最近は性欲も失せる。
脳内麻薬、アドレナリンが分泌されない。
その日は一日中家の中でただ座ったまま無為な時間を過ごしていた。
電話が鳴っても出る気力も無く、本日3回目の母親からの着信にようやく出た。
「……はい」
「春樹!?ちょっと、あんた電話くらいでなさいよ。折り返しだって掛けて来ないで!」
「何……?」
「先週あんた宛に送った荷物、不在で戻って来たのよ。不在票とかちゃんと確認しなさいよね」
恐らくこの前まとめて捨てた中に混じっていたんだろう。
「悪い」
「……なんか元気無いけど大丈夫?ちゃんとやれてんの?就職先は決まったの?いつまでもぶらぶらしてる訳にはいかないでしょ?」
またお説教が始まった。だから出たく無かったんだ。
「ああ、わかってるよ。他に用事無いならもう切るよ」
「ちょっとまちなさ——」
聞くや否や電話を切った。そのまま電源ボタンを押して携帯電話の電源をオフにした。
独断でさっさと大学を辞めた事を内緒にしていた親に知られたのは三ヶ月前だった。
相当怒られたが聞き流して地元に帰る気もなかった。
でもやりたい事も無く、無意味に生きる日々。
三角座りでうずくまって項垂れた。
無性に泣けて来る。情けない様な恐い様な不安で不安で堪らない。
生きていたく無い。死にたい死にたい。でも死ねない——。
数日後、美夏からお誘いのメールが来た。
その日は珍しくなぜか気分が良かった。
このところ美夏から頻繁にメールが届いた。内容はたわいもない世間話ばかりだが、ほとんど返信してないのに、数日後にまたメールが届いた。
それは美夏が送ったテレビ局の観覧希望の当選はがきだった。
「駄目元だったからすっかり忘れてたんだけどぉ。はがき届いてたの気づいたのが前日とかだったから華穂も都合つかなくって、助かったぁ」
美夏は嬉しそうにはしゃいでいた。
バラエティ番組のスタジオ収録で、自分も結構好きな芸人や芸能人を間近で見られたのもあって久々に興奮を感じた。
二時間あまりの収録を終えて美夏は興奮冷めやらぬ様子で振り返っていた。
「生サノケンマジカッコ良かったー!アリソナもちょー可愛かった!もう人形みたい人間じゃ無いよあのスタイル!」
自分も案外楽しかったし、子供みたいに喜ぶ美夏の姿を見て思わず笑った。
その後遅めのランチをしてカラオケに行ってゲーセンで遊んだ。
久しぶりにそれなりに楽しめた気がした。
「今日、春樹誘って良かった」
帰り際に細い路地を歩きながら美夏が嬉しそうに笑った。
「え?」
「……最近春樹なんか、元気無さそうだったから」
思わず足を止めた。
「前はさ、もうすんごい一番くらいテンション高くて皆の事盛り上げてくれてたし、元気で明るくって……。なのにこの前会った時人違いかと思うくらい沈んでて……心配、してたんだよ……」
「美夏……」
少し意外だった。美夏は結構お馬鹿キャラのくせに実は計算高くて自分の事しか考えてないマイペースな娘だと思ってた。
「何かあったの…?あ、別に無理に言わなくてもいんだけどさ。……私にできる事あったら力になるし。うちら友達じゃん?」
探る様な視線。
リップグロスに近くのラブホテルのネオンの光が反射している。
何故かコイツが言うと友達って言葉が薄っぺらく感じる。
お前に何ができるって?かつて友達だと思ってた奴に男寝取られたくせに。
「じゃあ、金貸してよ」
「え?……えっと、幾らくらい?」動揺して声が震えてた。
「十万、かな」
「えっ!そんなに?ごめん……すぐにはちょっと無理かも」
美夏はそう言って誤摩化す様に笑って目線を逸らした。
「そっか。じゃあ代わりに、今から俺とホテル行こうよ」
美夏は目を丸くして小さく、えっ、と呟いた。
鼻で笑って言ってやった。
「冗談だよ。別に、お前にできる事なんて何も無いから。良い奴のフリしなくて良いよ。俺お前の本性知ってるし」
「……え」
「自分の事しか考えてないから親友だと思ってた奴に男取られるんだよ」
「何ソレ……ヒド……」
美夏が少し俯いた隙に唇を奪ってやった。別に美夏の事は好きでも何でも無いけど、虐めてやりたかった。
当然美夏に突き飛ばされ、思い切り平手打ちを喰らった。
「意味分かんない!最低!」
怒って反対側に歩き去る美夏の後ろ姿を見て思わずにやついた。これでもう連絡してくる事も無いだろう。清々する。
帰り道、自分の最低さを感じて笑えた。
そんな中、声を掛けてきた人物がいた。
アパートの最寄り駅で、変な女二人組に引っかかった。
「手相の勉強をしているんですけど、少しあなたの手相を見せていただけませんか?」
いつもならシカトするところだが、今日は何故か立ち止まってしまった。
舌打ちをして、面倒くさいと思いつつも、右手を差し出してしまった。
女の柔らかい手が右手の平を開いた。
「あなた、芸術系のお仕事をされていませんか?」
てんで大はずれだったが、悪ノリした。
「えっ?なんで分かるんですか?」
「あ、やっぱり?芸術線が出ていますね、感受性が強い方ですね。あ、お助け十字も出ています」
まったく興味ないくせに、さも興味あるかの様なフリをしてみせた。
「へえー、そうなんですかー。俺将来成功出来ますかねー?」
「そうですね、今のところ近い将来とても良い事が起こりそうですよ。運気が上昇していると思います」
何の根拠があってそんな事を言えるのか分からないが、無責任にも程がある。
「そうですか……!」ふいに声を荒げた。
「じゃあ俺、近いうちに楽に死ねそうですか?今凄い死にたいんですよ。どうやって死ぬんですか?ねぇ?未来が読めるんでしょ」
強い口調で詰め寄ると、二人は驚いて後ずさった。
「将来なんてこれっぽっちも興味ねーんだよ。っていうか、芸術系のお仕事なんてしてねーし、いい加減な当てずっぽも大概にしろよ」
唾を吐き捨ててその場を去った。
女相手に本当に最低だ。
わかってやってる。
部屋に戻ると、感情に耐えきれなくて大声で叫んだ。
頭に血が上ってクラクラする程何度か叫んだ。
すると隣の部屋の壁から大きな音がした。うるさくて壁を叩いたんだろう。
思わず思い切り叩き返した。
するとなんの反応も返ってこなかった。
俺はもう、いい加減死ねば良いと思う。
久しぶりにボーイのバイトを再開した。
裏でヤクザと繋がってるちょっとヤバめの店だったが、色々融通が利く店で、大学時代よく稼がせてもらってた。
女の子たちは結構頻繁に変わる。枕営業とかは多分当たり前の、そういう店だった。
気が向かなかったが、このままだと家賃が払えないので先輩に口利きしてもらってすぐに日雇ってもらった。
「いや助かった。ちょうど何人か辞めて人手が足りなかったんだよ」
金髪に剃り込みの入った強面の先輩が優しく微笑んだ。
錦先輩は見た目よりも優しいが、切れるとヤバい人だった。だから絶対怒らせちゃいけない。
「それにしても春樹、お前暫く見ねー内に、ちょっと良い面構えになってきたじゃねーか」
「へ?いや……とんでもないっす」
「お前ガンズで働いてみねーか?勿論フロアでさ」
「俺がホストっすか?イヤイヤ、無理っす」
ガンズはいわゆる姉妹店ってやつで、結構な女泣かせのホストクラブ。
この店の女の子たちも何人か通ってるが、男を騙して得た収入の殆どを今度はホストクラブにつぎ込むなんて、どうかしている。
四日も働けば、月六万弱の家賃なんて楽勝で払える。
その代わり夕方六時から深夜を過ぎて五時六時、最早早朝に至るまでの労働は気苦労の方が絶えない。
「お疲れ。おー春樹、ちょっとこれから付き合えよ」
四日目の朝、錦先輩の誘いを断る事もできず、二十四時間営業のラーメン屋にいた。
朝っぱらからここの濃厚スープはハラワタにしみる。
「お前さ、大学辞めたんだって?どうしてたんだよ?」
「どうって……。まあ適当にぶらぶら……イベントとかで日雇いのバーテンやったり」
「ふーん。それでやってけんの?」
「あはは、それはまあ、なんとかボチボチぐらいで……。あーでも、結構楽しくやってますよ?」
嘘をついたのは、錦先輩にまたヤバイ世界に誘われないか不安だったから。
「ははは、そうかー。ウソつくんじゃねーよ」
でもすぐに見透かされた。
思わず唾を飲み込んだ。分かってた。この人にはどんな小細工も通用しないし、どんなに巧妙なウソだってすぐバレる。伊達に店のナンバーツーは仕切ってない。
その後特に会話もなく、先輩に風俗店に連れて行かれた。
「適当に選べ」
そう言われて選んだ子は少し美夏に似ていた。
やる気にもならないのに知らない女と狭い部屋に二人っきりで、天気だの職業だのたわいもない会話をしながら手慣れた手つきの女に下着まで脱がされた。
一緒にシャワーを浴びて固いベッドの上でまるで粘土細工の様に下半身を弄ばれる。
決して気持ちよくはなれなかった。
ごめんちょっと疲れてるんだ、なんて言い訳をしながら、余った時間女の身の上話を聞いた。
年齢は自分と同い年だった。
「こんな仕事してて辛く無い?」
「えー、べつに?だってお給料も良いし、好きな物買えるし。それに色んな人と出会えて楽しいよ?まあ時にはちょっとヤバい奴もいるけどさー」
「生きてて、楽しい?」
恐る恐る訊いた問いに彼女はウソぶる事も無く満面の笑みで答えた。
「モッチロン!だってさ、皆幸せになる為に生まれて来たんだよ?幸せには色んな形があると思うの。私は今の生活で全然幸せ感じてるし、後悔なんて全然してないよ。人生楽しく無かったら、死んでるのと同じだよ」
——ああ。
まったくその通りだ。
俺はきっと生きてるけど、もうすでに死んでるんだ。
多分セックスなんてここ一年まともにしてない。
ちょっと前は彼女いないから、って感じだったけど、今は一人エッチすら回数が激減した。
とりあえずたまにはしとかないとという義務感で無理矢理するが後味悪くて落ち込む。
心と裏腹に体はそういうの求めてるのか、ごくたまにもの凄いエロい夢を見て朝勃ちしてるときもあるがそれを沈めるのすら面倒くさい。
男って、性欲=生命力っていうじゃん。
だから生きる気力が無い自分は、当然のごとく性欲も減退して何もかも意欲を失って行く。
誰かの為に頑張るとか無いし、今更彼女とかどうでもいいし。目の前に裸の女がいても、何にも思わないって、もう終わってるよ。
楓からメールが届いていた。
『ジェシカたちとの旅行、来週の金曜に決まったから。久しぶりに騒ごうぜ』
了解、との短い文を返してまた虚無感に浸った。
楓も大学の授業が忙しくなって、このところ殆ど会ってない。
旅行の当日になって、その日だと思い出した。服装なんてどうでも良くて、適当にその辺の洗濯した服をバッグに詰めた。
約束の時間を地味に五分過ぎて駅に到着したが、まだ二人来てなかった。
「遅いなー美宇司と早紀の奴」
十分後、電車ギリギリの時間に二人はやって来た。
「ごめんごめーん!忘れ物して途中で引き返してさー」
二人はグループの中で割と大人しめなキャラ同士、いつの間にか付き合ってて同棲を始めていた。
乗り込んだ電車の中、道中久しぶりにあった早紀が顔を覗き込んで来た。
「春樹ってさー、なんかちょっと大人っぽくなったよね」
小動物を連想させる様な可愛い声で早紀が微笑んだ。
「今日の服装もさ、ゆるゆるな感じだけど、何気にオシャレだよなー?オッサレー」
美宇司が茶化した。
殆ど寝間着にベスト羽織ってアクセを慌てて付けただけですけど、って感じだ。
「ギラギラ感が押さえられてノーブルな感じになったっていうかー」
単に生きて行く気力が無くなっただけだし。
早くも帰りたいくらいたるかった。
それでも宿について、早速温泉に浸かると心が少しほぐされた様に癒されていった。
風呂上がりに楓が缶ビールを手渡してくれた。
あんまり飲む気分でもなかったが、せっかくなので頂く事にした。
久しぶりに飲んだその味はちょっと強烈で、でも後を引く美味しさで、結構な勢いで半分くらい飲み干した。
「風呂って何気に喉乾くよな?」
ちょっと気分が良くなって、皆で夕食前に卓球したりなんかした。
ジェシカ、久しぶりに会って良い女っぷりが増してた。
「今度シャンプーのCM出るんでしょ?」
「でも映るのほんの数秒だよ。他にも何十人もいるしメインは売れてる女優だし」
「えー全国区だし充分スゲーじゃん」
「でも、もう結構若い子に色々取られちゃってるし……」
ジェシカの事務所は毎年まとめてオーディションを行う。所属タレントの平均年齢は十七•五歳くらいで、ジェシカは結構年上な方だ。
出逢った頃はジェシカも十代で自信満々だったのに、近頃は『でも』とか後ろ向きな発言が多くなっている気がする。
夕食後は皆結構強かに酔っぱらって、美宇司と早紀はいつの間にか雲隠れしてよろしくやってるっぽかった。
三人で遊技場でビリヤードと部屋に戻ってカードゲームをした後、楓はもうひとっ風呂浴びて来る、と言って部屋を出て行った。
ジェシカと二人っきりになって、少し気まずかった。
「っていうか、ホント久々だよね。春樹と会うの」
「そだね」
「早紀も言ってたけど、ホント雰囲気変わったよね。大人っぽくなったっていうか、妙に落ち着いたっていうか」
ジェシカはそう言って笑ったけど、それには笑い返さなかった。
「なんか前は結構遊びとか誘ってくれてたじゃん?柏原と付き合ってから暫く皆と交流無くなっちゃったけど、またこうして旅行とか来れて楽しいっていうか」
そう言えば思っていた事をなんとなく尋ねた。
「そう言えば、なんで別れたの?好きだったんでしょ?柏原の事」
「うん……」
ちょっと黙ってジェシカは答えた。
「柏原ってさー、他に好きな子いたっぽいんだよね」
「え、なにそれ」
柏原は当時付き合っていた美夏の事捨てて、ジェシカ選んで、七人グループだったの一気に分裂させた張本人。なのに、ジェシカと付き合って半年で別れるとか、正直ブチ切れた。
「私って多分、柏原に取っては結局見た目だけだったっていうか。いつも私の容姿ばかり気にしてたもん。こっちも気負っちゃってさ、デートの度に新しい服買いに行って。楽しい部分もあったけど、ちょっとしんどくて。でも、柏原に好きでいて欲しくて頑張ってたのに……」
ジェシカは切なそうな表情を浮かべていた。
「まあ、今はもう柏原の事何とも思ってないんだけどね?でも、やっぱり自分が信じてる相手に裏切られるって、しんどいよね」
彼女は少しだけはにかんで、すぐに表情が消えた。
「……美夏の事?」
美夏の名前を口に出すとジェシカの顔が強張った。
何も言えないでいるジェシカの代わりに代弁した。
「親友に裏切られた美夏の気持ちが、少しは分かった……?」
彼女はハッとした様にこちらを振り返った。怯えた様な目をしていた。
「わ、私だって、最初はそんなつもり無かったの……!美夏の大切な彼氏だって分かってた。でも、自分の気持ちがだんだん抑えられなくなって、ちょっと落ち込む事があって気が緩んで……そしたら彼が……!」
なんとか自分を正当化したいのだろう、必死に言い訳を口にした。
泣きそうな顔のジェシカの頭を優しく撫でてやった。
すると潤んだ瞳の彼女が自分を見つめた。
「春樹……」
ちょうどその時メールの着信音が響いた。
楓からだった。
『俺、従業員の子ナンパしたから、今夜その子と過ごすわ。お前はジェシカと上手くやれよ』
無言で携帯電話の画面を見つめた。
「……どうしたの?」
「……楓、暫く戻らないみたい」
「えっ?」
少し戸惑うジェシカに微笑みかけた。
彼女の肩に手を掛けると特に何の躊躇も無く、ジェシカに口づけた。
彼女は驚いた様に自分を見つめた。
だから、言ってやった。
「ジェシカはさ、そうやって今度は俺を利用しようと思ってるんだよね」
「……え……?」
「自分が美夏にした事、言い訳して人に責任押し付けて。確かに美夏にも柏原に捨てられた原因あると思うけどさ、でもそれを良い事に柏原に甘えたのはお前。最初からそれで長く幸せにやっていけるなんて思ってなかったんだろ?すぐに捨てられるって勘付いてた。だから外見だけでも柏原の気を惹こうと必死だった。それで今度はフラれたら、美夏の気持ちがわかった様なフリをして俺に同情引こうとした。柏原の事なんとも思ってないなんてウソ、本当は忘れられなくて誰でも良いから忘れさせて欲しいって顔してる。それと同時に本当は復讐してやりたくて堪らないんだろ?」
ジェシカの顔を見れば分かる。
女を武器にして今まで生きて来た顔だ。
絶句してた。
「本当はずっと前から、俺の気持ち気づいてたんだろ?」
ジェシカの顔に触れると、ビクッと震えた。
「……今夜楓は戻らないよ」
彼女に顔を近づけた。
「抵抗しないつもりなら、このまま襲うけど、いいの?」
彼女の呼吸数が上がった。
「わっ……私……気づいてた、春樹の気持ち……でも……」
言葉を塞き止める様に彼女の口を塞いだ。
ずっと、憧れ続けていた女の唇だ。
髪の毛の感触、匂い、柔らかな体が自分の腕の中にあった。
分かっていた事だが、彼女は何の抵抗も見せなかった。
ここまで見透かされて、ジェシカのプライドは結構傷ついたと思うのに、それでも美夏への後ろめたさからなのか、少しでも自分に好意を抱いていたのか分からないが、最後まで言葉を発さなかった。
二人の吐息だけが部屋に響いていた。
久しぶりのセックスだった。
しかも、片想いしていた相手との。
それでも結構淡々としていた。どこかで冷静沈着な自分もいて、彼女の体にあるほくろの数を数えたりしていた。
終わった後、横たわる彼女の髪をそっと撫でた。
多分ひっそり泣いていたと思う。
あんなことを言ったけど、彼女が特別卑怯だとは思わない。だって自分自身だって、彼女を追詰める様なことを言っておきながらちゃっかり彼女とセックスしてる。
このところ、妙に冷静に世界が見渡せる様になった気がした。
見えなかった部分が見える様になった、ただそれだけだ。
ジェシカとの朝を迎えたあと、何食わぬ顔で戻って来た楓と朝風呂に入った。
「で、やったの?」
「……ああ」
「マジか!やったじゃん。で、付き合うんだろ?」
「さあ、それはどうだろうな……」
妙に冷めた様子に楓は困惑しているようだった。
何事も無かったかの様に東京に戻ってそのまま解散した。
錦先輩に頼まれて、しばらく店に出なきゃ行けなくなった。
本当は凄く気分が重い。
「悪いな、次のバイトくんが決まるまで頼むよ。どうせ金なんていくらでもいるだろ?」
何日も長時間労働が続けば体も疲れるが、それよりも心に鉛を積んでいるかの様に気が重かった。
ジェシカからは何の連絡も無く、美夏からの連絡も途絶えたままだ。
「錦先輩は将来の事とか考えてます?」
「あ?将来?んなもん考えてどうすんの?」
錦先輩は無邪気に笑った。
「まあお前はまだ若いしな」
そういう錦先輩もまだ二十代半ばのはずだ。
「俺もなんか考えてた時期あったけど、考えるだけ無駄ってやつだよ。結局今どうにか生きて行かなきゃ将来もクソも無いしな」
「そうっすね……」
今がなければ未来も無い。
その通りだが、なにかすがれる未来がなければ今を生きて行くのはしんどい。
楽しい事も喜べる事も無い。未来をまったく想像出来ない。
このままだらだらと無意味に生き続けるだけならば、早めに終わらせるべきでは——?
「……まあでも……」錦先輩は思い出したかの様に呟いた。
「何か守らなきゃいけないものができたら、また違うのかもしんねぇけどな……」
遠くを見つめる錦先輩の瞳は、少し寂しそうでもあった。
気がつけば年も末、繁忙期に差し掛かり、新しいバイトくんが入ったのにも関わらず人手不足でずるずるとボーイの仕事を続けていた。
いつの間にか自分も年功序列で後輩を教える立場になっていた。
「お前このままずっといればいいよ。俺も助かるし。頼りにしてるぞ」
錦先輩にはそう言われて思わず苦笑しかけた。
「ちゃっす春樹先輩、これどこに置いたら良いっすか?」
新しいバイトの一人は体育会系のガタイの良い奴。まだ幼さの残る顔の未成年だった。この春大学進学で上京してきて一人暮らしの生活費を稼ぐために入って来た。
かつての自分の様だ。
場所を指示してついでに幾つか仕事を頼んだ。
簡潔に返事をし、素早く仕事をこなす使える奴だった。
忙しいのは却って良かった。
毎日部屋に帰ると疲労でそのまま倒れ込む様に寝て、起きてまた仕事に出るという日々は余計な事を考える暇も与えない。
「春樹、今日暇だから早めにあがっていいぞ」
ここ最近忙しいのにも関わらず錦先輩の機嫌が良かった。
「ここだけの話、錦さんこれができたらしいぜ」
バイト仲間がこっそり小指を立てた。
「俺がなんだって?」
錦先輩はご機嫌そうに両腕を自分たちの肩に回して来た。
「いやいや、何でも無いっす!」
あの切なそうな表情を思い出し、楽しそうな錦先輩を見て少し安心した。
クリスマスのイベントも無事に終え、ようやくほっと一息ついた頃錦先輩に言われた。
「春樹、お前年末年始休んで良いぞ。どうせ暇だから」
「えっ?」
「よく頑張ってくれたよ」
今月分の給料袋を渡され、ずっしりとした重みを手の平に感じながら呆然とした。
「正月は地元にでも帰って、親に美味いもんでも食わせてやれよ」
一週間の休みを貰って、とりあえずひたすら睡眠を貪った。
ふと気がつくと大晦日の朝で、壁に寄りかかりながらボーッとしていると、脇に落ちていた給料袋が目に入ってそれを拾い上げた。
「……二十八、二十九、三十……」
改めて数えると色々差し引かれても手取りは猶に三十万を越えていた。
前はあれ程金が欲しかったのに、今は使い道も思いつかない。
呆然と、ただ時計の秒針が響く音だけを聞いていた。
頭の中は真っ白で、今更実家に帰る気も起きなかった。
突然携帯電話の着信音が鳴って驚きの余り体がビクッと震えた。
「——春樹?」
電話の声は母親だった。
「あんた正月は帰らないつもり?」
「……あぁ……」返事をしたつもりは無かったが、ただ他に言葉が出なくて黙っていると、母親はそれを帰らないと受け取った。
「ったく、正月くらい帰りなさいよね。盆にも帰らないで。なんだったら、こっちで就職先探してもいいんじゃないの?」
無言でいると、母親は呆れた様に結んだ。
「……まああんたの人生だから任せるけど、もう子供じゃないんだし。でもちゃんと色々考えとかないと、後悔するのはあんたなんだからね。じゃあ良いお年を!」
ブッ!プーッ、プーッ、プーッ——。
終話音が響いた瞬間、見捨てられた様な気がして涙が頬を伝った。
冷め切った心と体に熱い涙だけが止めどなく溢れ、こぼれ落ちて行った。
嗚咽して暫く泣いていたが、ふいに涙をぬぐって立ち上がった。
素早く着替えてブルゾンを羽織った。
外に出て、気がついたら、踏切の前にいた。
目の前はうっすら薄化粧していて、赤いランプが交互に点滅している。
——白地に赤がよく映えるなぁ。
小さい頃、母親に赤いちゃんちゃんこを着せられた事を思い出した。父親はそんな自分と母を写真に押さえてくれていて、高校の時姉の結婚式の前日にアルバムを無理矢理見せられたが、その写真を見たときは全然思い出せなかった。
——おかあちゃん——。
——はるき。
ふと、母親の声が聞こえた気がした。
「おい!あぶねぇッ!!」
突然もの凄い力で腕を引っ張られた。
次の瞬間電車が轟音の警笛と共にもの凄いスピードで走り去って行った。
尻餅をついて電車を見届けると、向かいの制止バーがゆっくりと上がっていくのが見えた。
「死にたいの!?死ぬなら他所でやってくれよ、迷惑だから!」
そう言って三十代くらいの男は怒って去って行った。
自分の後ろで制止バーが降りたのに気づかなかったのか、本当に死ぬつもりだったのか、自分でもよく分からなかった。
吃驚して、立ち上がると普通に踏切を渡って歩き始めた。
空は少し灰みがかった白で、頭の中もまっしろだった。
それでも無意識のうちに信号は確認しながら渡って、何事も無かったかの様に歩き続けた。
どこに行くのか電車に乗って、どこかの公園のブランコに揺られて、気がついたら美夏の部屋の前だった。
なんで美夏のところだったのか分からないけど、多分、会いたかったんだと思う。
また、思いっきり平手打ちされたかった。
迷いながらインターホンを押したけど返事が無くて、そうか正月だもんな、と一人で笑った。
でもそこから動く事ができなくて、駄目だなと思いつつも部屋の前に座り込んでしまった。
昼間なのか夕方なのか分からないまま時が過ぎ、何度か同じ階の住人が出入りしていたけど、皆無関心に目の前を通り過ぎて行った。
帰って来る見込みは無い。そう思いながらも、夜になっても動けないでいた。
後もう少しで今年が終わる。
早くしなきゃ行けないのに——。何を——?
早く、死を。
「きゃっ……!」
小さく叫び声がして見上げると、三メートル先に美夏の姿があった。
「……美夏……」しゃがれた声が出た。
恐ろしい物でも見る様な顔だったが、美夏は恐る恐る一歩また一歩と近づいた。
「は、春樹……?何やってるの?こんなところで……」
すぐにでも追い返されると思っていたのに、美夏は心配そうに声を掛けてくれた。
「寒いよ、ここ……」
ゆっくり立ち上がると、ふらりと体が揺れた。
「顔まっしろなんだけど……。とりあえず、中入りなよ……」
ドアの前を明け渡すとカチャリと音がして部屋に招き入れられた。
部屋の中は暖房も効いていなかったが相当暖かく感じた。
すると体が震えて歯がガチガチと鳴った。
「一体いつからいたの?体めちゃくちゃ冷たいじゃん……」
美夏は驚いた様に顔に触れると暖房を付け、暫くして温かい飲み物を出してくれた。
やがてテレビをつけたのか小さく特番の音声が聞こえた。
今夜は実家に帰らないの?
そう尋ねようとしたが寒過ぎて言葉が出なかった。
「なかなか体暖まらないね」
美夏が手をさすってくれたがまだ震えが止まらなかった。
とっさに美夏の手を掴んだ。
「えっ何……!」
「みか……っ」
「えっ!?」
「おれのこっ……こと、うらんでないのっ……?」
「えっ?恨むって、なんで」
「……酷い事言っただろ」
「……ああ、あれ。……でも、別に、恨む程の事でもないし」
美夏は自嘲めいて笑った。
「親友に彼氏とられちゃったのは事実だしさぁ……。そりゃ、自分の事しか考えてないって言われたのはちょっとショックだったけど……」
美夏は俯いた。
「……ごめ……ん」
そう言って美夏の手を離した。
「ね、そうだ、いっそお風呂入っちゃったら?暖まるんじゃない?」
美夏は笑って立ち上がると、向かった先で水音が響いた。
暫くして戻って来ると、美夏は自分の事を話し出した。
「今日さー本当は実家に帰ろうと思ってたんだけど、バスに乗り遅れちゃってさ。もう面倒くさくなって戻って来ちゃったんだよね。そしたら部屋の前になんかいるんだもん、超ビビったぁ」
自分が飲み終わったカップにまたホットココアを注ぎながら笑った。
「……はい」
差し出されたカップを受け取ろうとして力が入らず落としてしまった。
「きゃあ!ごめん!」
中に入っていたココアが溢れて自分のスウェットを濡らした。
「アツッ……!」
流石に驚いて少し脱いでずらした。
美夏は慌てて布巾でココアを拭き取ろうと必死だったが、思わずその手を止めた。
ハッ——という美夏の息づかいが聞こえた。
優しくキスすると、一瞬唇が震えたが、抵抗は無かった。
美夏を抱きしめ深く口づけをすると、それに応えるように美夏の腕が体に触れた。
暫く穏やかな時間が流れた後、唇を離した。
俯き加減の長い睫毛。美夏の頬が紅潮していた。
その時、もっと早くこうしてやれば良かったと思った。
「ねえ、美夏……」
「……な、何……?」
か細い声。美夏は今まで見た事無いくらい可愛い顔をしていた。
「俺の事、嫌いじゃない?」
「嫌いじゃ、ないよ……!」
「じゃあ、頼みがあるんだけどさ」
「えっ、……なぁに?」
ゆっくり目を閉じて微笑んだ。
再び目を開けてお願いした。
「——俺の事、殺してくれる?」
暫くの沈黙が流れた。
「……何言ってんの?えっ?」
美夏は笑ってしまった。
「死にたいんだ、俺。出来れば、新しい年は迎えたく無い」
真顔で伝えた。
「ヤダ。ホントマジで何言ってんの?もうすぐ新年だよ?」
「だから、もう今ここで殺して欲しいんだ」
「冗談でしょ?」
「今すんげー久しぶりに穏やかな気分。今なら多分恐くない」
美夏の顔から笑みが消えた。
「自分でやると、失敗しちゃうかも知んないから頼むよ。死んだ後は適当にバラして川に捨ててくれれば良いから」
「……はあ?……春樹…?」
美夏の両手を掴んで自分の首に重ねた。
「大丈夫、結構簡単だから。ほらこうやって……」
温かい美夏の手の上から力を込めた。
グッと頸動脈が圧迫されて、ふわーっと意識が遠のく様な感覚がした。
「や、やめて……」
美夏が少し抵抗して、もっと力を込めたら逆に自分の手の力が抜けて来てしまった。
美夏にそのまま突き飛ばされて、横に倒れた。
自発呼吸が再開して小さく咽せた。
「……馬鹿じゃないの?マジウケるんだけど……」
美夏はお風呂のお湯止めて来る、と言って一旦その場を離れた。
ちょっと痛い体制だったので仕方なくゆっくりと起き上がった。
すると左腕が痺れていた。
見ると美夏が壁の影から怯える様にこちらの様子を伺っていた。
「さっきの……ただの冗談だよね……?」
「楓にも、冗談だろって笑われたんだよな。俺本気で言ってんのにさ」
美夏の顔は真っ青だった。
「あ、そっか、やっぱ自分でやなんきゃ覚悟足りてないって思うよな。悪いけど包丁貸してくれる?大丈夫、風呂場でやるから」
——バチンッ!
って、何の音かと思ったら、美夏に頬を殴られた音だった。
「そう言う悪い冗談言うの、いい加減にして」
美夏は本気で怒っている様だった。
かなり強くぶたれたのか、左頬がジンジンとうずき出した。
「……俺、本気で言ってるのに……」
涙が込み上げて来て、もう止まらなかった。
「俺もう死にたいんだぁ……。今生きてるのすんげー苦しんだよ……なんでかわかん無いけど……もう生きていたく無いんだよ……ずっと死ねなくて」
涙で目の前が見えなくなってたけど、少し見えた美夏の表情はもの凄く怖い顔だった。
「痛いんだよ!?包丁なんか刺したら!」
美夏がもの凄い剣幕だった。
「今殴ったよりも何倍も!何百倍も!」
次の瞬間美夏に強く抱きしめられていた。
「駄目だから……!死ぬとか、駄目だから!」
「……ゔーっ……!」息が苦しくて呻き声しか出ない。
「とにかく、今は死んじゃ駄目!人ん家で死ぬとか馬鹿でしょ!超迷惑だし……!っていうか死んじゃヤダ!……やだよぉ~っ……!」
美夏まで泣き出した。
「っていうか、なんで?なんで?ね、なんで……!」
美夏は自分の顔を見つめながら何度も尋ねてきた。
自分でももうよく分からなくなって、ただひたすら泣き続けた。
美夏は途中で泣き止むのを諦めたのか、泣きながら頭を撫で続けてくれた。
体中の水分が無くなっちゃうんじゃないかというくらい泣き続けて頭が痛くて意識が朦朧とした。
このところ良く泣いていたけど、こんなにたくさん泣いたのは赤ん坊の頃以来だろう。
頭の血管が脈打つ度ガンガン激しい鈍痛がした。
だけどずっと美夏の手が優しく頭を撫でてくれていて、ちょっとだけマシだった。
気がつけば美夏の膝枕で横たわっていた。
特番はすでに新年を迎えて毎年恒例のアイドルのコンサート模様を映し出していた。
頭の中はもう真っ白で何も考えてなかった。
薄目でそれをただひたすら見つめていた。
暫くして、頭を撫でながら美夏がそっと声を掛けてきた。
「……はるき。ずっとこうしててあげるから、寝て良いよ……」
そう言って美夏にキスされると、なぜだか凄く安心してそのまま深く眠りに堕ちてしまった。
何の夢も見なかった。でも時々意識だけ目覚めて美夏の声を聞いた気がした。
夜中にあまりの寒さに美夏にベッドに誘導された。
二人ともカタカタ震えていたが、抱き合っていたら凄く暖かくてまたすぐ眠りについた。
——どのくらい寝ていたのか、寝返りを打ったら凄く気持ち良かった。
安らかな気持ちで目を開けると、目の前で美夏がこちらを見ていた。
吃驚して一気に目が覚めた。
外から真っ白な光が入り込んでいて部屋の中はとても明るかった。
美夏の右目の目尻の近くに小さな泣き黒子があるのを初めて知った。
「……おはよう。はるき」
柔らかな声がした。
「……おは。みか……」
同じベッドの中で朝の挨拶を交わした。
美夏は少し嬉しそうに微笑んだ。
女神っているんだなぁ、なんて思った。
「っていうか、あけおめだよ?」
「……あけおめ……」
美夏の言葉を反復した。
「新年、明けちゃったね」
その言葉にハッとして起き上がった。
布団の外は寒かった。
エアコンは効いていたが、それでもブルッと身震いした。
ベッドに腰掛けて辺りを見渡した。
ピンクとかベージュ色で統一された女の子らしい美夏の部屋だった。
自分のスウェットにはうっすらと夕べのシミが残っていた。
喉が痛くて咳き込んだ。
「今お水持って来るね」
美夏が起き上がって布団から飛び出した。
キッチンでカチャカチャと音を立てながら用意する美夏を呆然と見た。そして再び部屋の中を見渡した。
瞬きすると目の中がネチャネチャして両目を擦った。
すると目ヤニがボロボロ落ちた。
あぁ、夕べあんだけ泣いたからな…。
そこで一部始終思い出して焦った。
「はい、お水」
美夏にグラスを差し出されて受け取った。
一気に美夏が飲み干すのを見て自分も口にした。
すると喉が渇きすぎていて全然足りなかった。
「もう一杯いる?」
頷くと美夏は再びグラスの中に水を入れて持って来た。
受け取ってまたすぐ飲み干した。
「もう大丈夫?」
溢れた口元の水を拭いながら頷いた。
美夏はガラステーブルの上にコップを置くと、ベッドの上のすぐ横に座って来た。
その時気づいたが、いつの間にかピンク色のチェックの寝間着に着替えていた様だ。
「春樹」
呼ばれて横を見た。
「キスして良い……?」
思わず頷いてしまった。
頬に手を当てられ、冷たく濡れた舌が自分の舌にするりと絡み付いた。
しっとりとした感触が気持ちよかった。
やがて美夏がキスを終えて頬から手を離したが、もうちょっとで勃起してしまうところだった。
というか、美夏が自分からキスしていいか尋ねて来るなんて驚いた。
美夏は満足そうに微笑むと、テーブルの上にあったリモコンを操作してテレビの電源を入れた。
テレビ画面の時刻は0:58を表示していた。
いつの間にやら昼らしく、元旦イベントの生中継を放送していた。
ボーッとその放送を見ていると、いつの間にか美夏が服を着替えていた。
「春樹お腹空かない?」
返事もせず見つめていると、美夏は食べに出掛けようよ、と言った。
鏡の前で髪をいつものツインテールにしながらこちらを見た。
「近くの商店街で元旦イベントしてるはずだし、行ってみよ?」
返事の代わりに頷いた。
美夏の部屋を出る頃には午後二時前だった。
商店街は本当に歩いて五分のすぐ近くのところだった。
『賀正』と書かれた垂れ幕が下がる商店街のアーチの先はたくさんの人で賑わっていた。
目から入る情報が頭の中で処理しきれないのか、少し混乱して人混みが怖く感じた。
少し息が荒くなって、美夏が大丈夫?と声を掛けてきた。
軽く数度頷くと、美夏が手を繋いでそっと引っ張った。
手を引かれて歩く自分が情けなかったが、美夏が昔の姉とかぶって見えた。
今日の美夏は姉ちゃんみたいだ。
夕べずっと頭を撫でてくれていた事を思い出して、胸がキュッと切なくなった。
「適当に買って帰って食べよっか」
美夏は道行き屋台を見てはこれ買う?と自分に尋ねては購入していた。
イカ焼きはせっかくなので焼きたてを食べ歩きした。
くじ引きの近くの神社ではお神酒が無料で配られていたのでそれを貰って、屋台で貰った抽選券で二回くじを回した。
一回ずつ回して二人とも箱ティッシュだった。
三十分くらいで回って部屋に戻ると一息ついた。
たった少しの時間だったのにどっと疲れた。
テレビを見ながら屋台で買った物を食べた。そう言えば全部美夏が買っていた事を思い出して返そうと財布の中を開いたが、千円札が一枚しか入ってなかったのに驚いた。
そういえば給料はそのまま部屋に置いて来た。
「ごめん、今度返すから」
「え?別に良いよーこんくらい。私お金に困ってないし……」
それは美夏なりの皮肉だろうか。
その後も二人横に並びながらベッドにすがって何の気無しにテレビを見ていた。
ふと横を見ると美夏が普通に笑っていて、なんだか不思議な気分だった。
あの美夏と、付き合っても無いのにキスしたり手を繋いでみたり、一緒のベッドで一夜を明かしたり。
——今キスしたら、駄目だよなぁ。
ずっと黙っていたが重い口を開いた。
「美夏、色々ごめんな」
「えっ?なにがー?」
美夏は振り向きもせずあはは!と言ってテレビを指差して笑っていた。
テレビの方に顔を戻し少し黙った後、再び美夏の方を見て言った。
「昨日俺が言った事とか、全部忘れて……」
「……ヤダ」
美夏は振り向きもせずに強い口調で返した。
「えっ……」
「何言ってんの?春樹。自分の事しか考えてないのはどっちよ……」
「……それは……」
返す言葉が思い浮かばず。
美夏がこちらをまっすぐ見た。
「私に、春樹を殺せる訳ないじゃん」
——ドキリとした。
自分の事しか考えてないのはどっちよ——。
さっき美夏が言った言葉がまた聞こえた気がした。
「大体、殺した後バラして川に捨てろとかぁ?マジ意味分かんないよねーっ!人間解体すんの、こんなやわな女に出来る訳無いでしょ」
「……それは、楓とかに来てもらって手伝ってもらうとか……」思わず冗談を返してしまった。
美夏がキッと睨んだ。
「今度また死にたいとか言ったら、今度はグーで殴るから」
「……それは、ヤだな」
「じゃあもう二度と本気で死にたいとか言わないで」
胸が締め付けられる様に苦しくなった。
追詰められる様でキツい。
呼吸が苦しくなって、息が荒くなった。
「……分かった。もう二度と美夏に迷惑かけない……」
目の前がちょっと暗くなった。
気分的にというより、実際開いているはずの目の前がぐらりと暗くなった気がした。
少し吐き気がして来た。
「……春樹……?」
このままここにいたらヤバい気がして、思い切って立ち上がった。
「俺、そろそろ帰る……。色々迷惑かけてご免な。ありがと」
そう言いながら手早く荷物をまとめて玄関に出た。
すると時間差で立っていられない程のもの凄い立ちくらみがして、ガクガクと体を震わせながら玄関先の壁に倒れかかってしゃがみ込んでしまった。
「——春樹!」
美夏に見られてしまって慌てて外に出ようとした。
「待って春樹!」
「……ごめんもう迷惑かけないから」そう言うだけで精一杯。
体が重くて立ち上がるのが精一杯。
「なんかヤバいよ、春樹。フラフラじゃん……!」
「大丈夫……大丈夫だから。ホレこの通り!」
必死に笑って両手を広げた。
「じゃ!」
片手を上げて挨拶を済ませると右手で玄関のドアノブに手をかけた。
「春樹!迷惑かけないってそう言う意味じゃない!」
後ろから抱きしめられて思わず固まった。
「私、春樹の事が好きなの。……だから春樹に死んで欲しく無い」
美夏に告白された。
そう言えば、夕べ寝てる時何度も同じ事を言われた気がする。
——春樹の事が好き。死んじゃ駄目。死んじゃ嫌だよぉ——。
ドクン、ドクン——。
「……いや、駄目だろ……」
我に返って美夏の腕を引きはがした。
「今更俺なんか好きになるなよ。マジでヤバいからやめとけって……」
自分でも激しくそう思う。もう多分引き返せないとこまで来ている気がした。
怖くなった。このまま美夏に甘えたら、きっと美夏を不幸にする。
「やだっ……!春樹……!」
抵抗する美夏に思い切って言ってやった。
「俺、ジェシカと寝たんだよ……!」
美夏の体がビクッと震えてあっさりと腕が離れた。
「ウソ……」
クソッと思いながら大きく息を吐いた。
「この前、みんなで旅行に行って……俺が誘った」
美夏は聞きたく無いとばかりに首を振った。
ドアを開けた。
「だから、お前とは付き合えないよ」
そう一言残して、扉を閉めた。
三賀日はまるで地獄のようだった。
自己嫌悪でただひたすら死にたかった。
殆ど飲まず食わずで、時々気まぐれに年末に食べかけていたビスケットみたいな物を口に含んでは力なく飲み込んだ。
泣いては疲れて寝て、また目が覚めると絶望感で涙が溢れた。
頭の中は最早死ぬことしか考えてなかった。
三日の午後、もう涙も枯れたのか殆ど何も感じなくなっていた。
部屋の床の上に小さな虫が歩いているのを発見したが、それがどう行動するのかをただずっと見つめていた。
空腹感も特になく、喉が渇いて時々水道水を少しだけ口に含んだ。
口の中から臭いにおいがした。
まるで加齢臭の様なカビ臭いにおい。
美夏と過ごした短い時間を思い出した。
なんと言うか、ほんの少しだけど多分幸福だった。
ああいう何気ない日常っていうのか、誰かがそばにいてくれている安心感はとても幸せに感じた。
でもあれでもう充分だ。
美夏には、感謝したい。死ぬ前に少しだけ幸せだったから。
おもむろに立ち上がって、電気スタンドのコンセントをはさみで無理矢理ちょんぎった。
首切りは、そんな力も残ってないと諦め、やはり一番スタンダードなやり方で終える事にした。
カーテンレールと窓の隙間にコードを通して短めに何度もキツく結んだ。
首にちゃんと食い込む様に結び目を回して、強度を確かめた。
大丈夫、これならいける。
カーテンを閉めた窓の方に向かって、頭を輪の中に通そうとした瞬間だった。
——ピン、ポーン!
思わず固まった。
再びインターフォンの音が鳴った。
——ピンポーン!
運送業者だろうか?また母親が荷物を送りつけて来たのだろうか。ふいに母親の顔が浮かんだ。
コードに手をかけたままじっと息をこらして音が止むのを待った。
暫く様子を伺っていたが鳴らなかったので、もう去ったのだろうとホッとした。
気を取り直そうとして息を吸うと、またピンポーン、ピンポーンと鳴った。
気が散って仕方ない。
間もなくドンドンドン!とドアを叩く音が聞こえた。
イラッとした。
何もこんな時に邪魔しに来なくても良いものを。
仕方ないのでコードから手を離し、ドアの方へ近づいた。
ドアの向こうから声がした。
「おーい、春樹いねーのかー?」
楓の声だった。
「——楓……?」
楓は確か年末実家に帰ると言っていたが、正月にわざわざ来る様な用事があるとは思えなかった。
迷ったが、そのままドアを開ける事にした。
ゆっくりと隙間から外の様子を伺った。
「おーっ!いんじゃん!早く出ろよ。うんこでもしてたの?」
楓の他に人影は見えない。
「……あー、まあ……わるい」
「何隙間から見てんだ?入るぞ」
楓はドアを引っ張ってズカズカと部屋の中に入って来た。
「あー、っていうか散らかってんぞ……」
慌ててさりげなく窓際に寄ると、輪になったコードをカーテンの向こう側に隠しつつ、もう片方のカーテンを少し開いた。
すると室内に薄暗い明かりが入り込んで明るくなった。
「えー何、もしかして寝てた?」
「……うん」
「あー、起こしてわりぃな。っていうかケータイ繋がんないんだけど、電源落ちてんじゃね?」
本当はずっと電源を切っていたのだが、充電切れてたかも、などと言い訳をした。
「っていうか、どうしたの?」
少し迷惑そうに尋ねると、楓も少し面倒くさそうに、あーそれがさぁ、と口を開いた。
「美夏覚えてるだろ?」
ドキッ——!とした。
「昨日美夏の奴がわざわざ電話して来てさ。前メール来てたの面倒くてシカトしてたんだけど、今すぐ春樹の様子を見て来て欲しいとか言ってきてさ?俺実家だよ?すぐ行ける分けねーじゃんって切ったら今朝またメールが来て、東京戻ったらすぐ春樹のところに行けってしつこくて。んでお前にメールしても電話しても繋がんねーから仕方なく来たんだけどさ」
呆然とした。
美夏の奴——。余計な事を、とも思ったが、何故か凄くショックだった。
「連絡つかなくてお前の様子が心配だとかなんかちょっとパニクってて意味分かんない事言うから。っていうか普通じゃん…まあちょっと顔色悪い気もするけど……大丈夫?」
楓には、ああ、と苦笑して返した。
「お前実家帰らなかったんだろ?最近またバイトで忙しいって言ってたもんな。大丈夫か?働き過ぎなんじゃね?」
「ああ、でも休み貰ったから……」
「そっか。じゃあ今から飯でもいかねぇ?」
楓に誘われて仕方なく出掛ける事にした。
駅前のカツ丼屋に行ったが全然食欲無くて、それでも怪しまれない様に無理矢理詰め込んだ。
ジェシカの事とか話したり美夏の事とか訊かれて適当に答えたり、楓の大学仲間との遊びに誘われて乗り気がしなかったが適当に行くと約束してさっさと別れた。
家に帰った後、トイレで全部吐いて苦しさと情けなさのあまり涙が滲んだ。
楓に、美夏にお前から連絡しとけよ、と念を押されたのを思い出して、しぶしぶ携帯の電源を入れた。
すると不在着信や受信メールが大量に通知された。
殆どが美夏で、母親からのも一件、楓からのメールと着信と、他にジェシカからのメールが一件届いていた。
驚いて真っ先にジェシカからのメールを開くと、それは初詣のお誘いメールだった。
『この間はごめんなさい』とか、悪いのは多分こっちの方なのに、『色々反省してる』、という内容だった。
それで良ければ昨日一緒に初詣に行かないかという内容だったが、思いっきり無視した形になった。
勿論、それを昨日見たからと言ってとても行ける状況じゃなかった。
今更返すメールが思いつかなくて、美夏のメールを見たら、自分を心配してくれている事が痛い程伝わった。
だけど連絡するのはとても気が重くて、それでも楓にまた迷惑かけられないと思って思い切って美夏に短いメールを送った。
『心配させてごめん。大丈夫だから——』
送って数分ですぐに美夏から電話がかかって来た。
電話には出たく無くて、留守電になるまで眺めて待っていた。
再び不在着信1件の文字が表示されて、その表示を消そうと指さしたら急にまた着信が来て受話してしまった。
1、2、3……通話時間のカウンタが動いて、微かに美夏の声がした。
激しく動悸がして、恐る恐る携帯電話を耳に当てた。
「ねぇ……はる、き——?」
その優しい声に安堵した。
「——聞いてる?春樹」
「うん……聞いてる……」
向こう側で美夏の安堵するため息が聞こえた。
「ねえ春樹。今から、会いに行って良い……?」すがる様な声だ。
「……それは、ちょっと……」
「部屋までは行かないから。ただ、近くまで行くからちょっとだけ会ってくれるだけでいいの……」
返事に困っていると、また美夏がしゃべりだした。
「……別に付き合って欲しいとか言わないから。ただ心配なだけなの……お願い……!」
「ごめん……もう外に出たく無い……」
本気で嫌だった。凄く疲れるし、ユニットバスにもたれかかったままの体が動きそうにも無い。
「やっぱり……やっぱり私行くね?住所教えて?」
そう言われてももう何かを話す気力も無かった。
無言で返すと、じゃあ楓に聞くから、と美夏は勝手に決めてしまった。
「今から会いに行くから。じゃあね……」
その後電話が切れて、仕方なく終話ボタンを押した。
眠気が襲って来て、そのまま風呂場の中で眠りに堕ちた。
——ピン、ポーン!
チャイムの音で目が覚めた。
一体どのくらい寝ていたのだろう。
ゆっくりと重い体を動かして玄関の鍵を開けてドアを開いた。
そこにはいつもより化粧っけの薄い美夏が、慌てて乱れた髪を手で撫で付けて笑っていた。
「ごめん、遅くなって……!」
美夏は律儀に入っていい?と尋ねてから玄関に足を踏み入れた。
美夏ってこんな子だったっけ……?と思った。
結構今時のわがままで世間知らずのイメージしかなかったから、ここ数日の美夏の側面に動揺してしまう。心無しか口調や表情すら違って思える。
室内の電気をつけると自分でもちょっと憂鬱になるくらいゴミ袋とか脱いだ服がそのままになっていた。
荒んだ室内の状況に美夏は少し戸惑った様な様子だった。
「……ごめん、ずっと掃除とかしてなくて」
「あー、ううん!気にしないで。急に来ちゃってこっちこそごめん!」
美夏はそう言って明るく笑った。
「あ、ちょっと消化良さそうなもの慌てて買って来たんだけど、食べれるかな?」
美夏はまるで自分の状況を把握していたかのように、胃に優しそうなインスタントのスープとかゼリー状の食べ物などを大量買いしていた。
「……あ、食欲とかある?もっとガッツリしたものの方が良かったかな?」
慌てて首を振った。
美夏は適当にキッチン借りるね、と言ってケトルを取り出して湯を沸かし始めた。
さっき吐いたばっかりで食欲は無かったが、美夏が用意してくれたスープは温かくて優しく懐にしみた。
数日前にあんな台詞を言って部屋を出て行ったくせに、美夏がそばにいてくれることがもの凄く救われる様な気分だった。
俺って馬鹿だなぁ——でも駄目なんだよ——。
分かってる、これ以上美夏を巻き込んじゃいけない。
情けないと分かっていつつも膝を抱えて俯いていたが、気がつくと、美夏は手っ取り早くゴミをまとめて不要な物は玄関に出し、洗濯物や洗い物など、さっさと掃除を済ませてしまっていた。
思わず美夏は良い奥さんになるな、なんて言ってしまった。
しまった、調子に乗るかも、なんて思っていたら、美夏は勝手に色々構ってごめんね、と少し微笑むだけだった。
風呂まで掃除してくれて久々にシャワーを浴びると少しリラックスした気分になった。
「また明日来るから、今夜はもう休みなよ」
そう言って美夏はあっさり帰って行った。
美夏の手によってシーツを替えられた布団の中でゆっくり眠りについた。
優しくされると、余計に辛い——。
翌日も確かに美夏は来た。
でも自分の体じゃないみたいに重くて、殆ど寝ていた。
自分の部屋で、美夏はまるで家政婦みたいに洗濯物を畳んだり食事の用意をしてくれていた。
そして一日の半分以上を自分の為に費やし、夜になるとまた来るね、と言って帰って行った。
翌日の午後、美夏が買い出しから部屋に戻って来たとき、出掛ける支度をしている自分の姿を見て驚いていた。
「春樹、大丈夫なの?どこ行くの?」
「どこって……今日からバイト行かなきゃ……」
「無理だよっ……?春樹バイトなんて無理に決まってんじゃん!」
美夏はそう言ったが、起きたら体が楽になっていて、大丈夫だと思った。
「無理じゃないよ。別に今までだってやってきたんだから、多少体調悪くてもイケルよ」
「……そうじゃなくて……!」
「俺が休むと人足りないんだよ。先輩にも迷惑かかるし」
そう言ってさっさと下履きを履いた。
「ほら、美夏も早く出る支度して。もう鍵閉めちゃうから。あれ、鍵は?」
いつもと変わらない調子が戻って来て、普通に動けた。
すると美夏が開けたドアをガチャンと閉めた。
「行かせないよ?」
美夏はにっこり笑っていた。
「は?いや、どいてよ。遅刻しちゃうんだけど」
「じゃあ私にキスしてくれたら」
美夏はもう笑っていなかった。
この期に及んで美夏にキスなんて、出来る訳が無い。
だって俺は、美夏の事を裏切ったジェシカを抱いたんだぞ?
そんな、美夏の事をもっと傷つける様な事、出来る分けない。
「無理。早くどいて」
美夏は口を一文字に結んで、瞳は涙で潤んでいた。そんな美夏の肩をそっと退けて再びドアを開けた。
「……じゃあ、私待ってる…。この部屋で帰って来るの待ってるから」
突然変な事を言い出すので苦笑した。
「えっ?いや、朝になるから……」
「もし何かあったら、すぐに連絡して」
真剣な顔をして送り出されたので、それ以上どうにかできるきがしなくて、わかった、と言って部屋を後にした。
部屋を出て駅に着いたところまでは調子が良かった。
でも電車を待っているとだんだんと体がしんどくなり、立っているのが辛くなった。
店に着く頃には息が切れて、背中が痛くなって来た。
それでも気合い入れて前と変わらずに開店準備に急ぎ、次々と早番の女の子たちを迎え入れた。
途中であんまりにもしんどくなってきたので抜け出して薬局で滋養強壮剤とか痛み止めを買って飲みまくった。
持ちこたえて少し回復して来た頃、一人目の客が来て、久しぶりに錦先輩の姿を見た。
少し怖い様な気分になったが、必死に元気を繕って挨拶をした。
「あけましておめでとうございます」
「おー、あけおめ。しっかり休んだかー?また今年も頼むぜ」
「あっはい、あざーっす!」
後輩に色々と指示を出しながら回す中、だんだんと頭が回らなくなってミスり、言葉がうまく出なくなって来た。
「おい、春樹どうした?体調悪いのか?」
「……あー……すいません、ちょっと……」
「なんだ大丈夫か?ラストで上がらせてやるから、気合い入れて頑張れ!」
錦先輩に背中を強く叩かれた。
激励に耐えれる程の体力は最早無くて、思い切りよろけてしまった。
慌てて、すみません、と謝ると店の裏口に出た。
もの凄い吐き気に襲われて、立っていられなくなった。
まだ深夜零時を過ぎたばかりだった。
後もう少し、三時間がもの凄く遠く感じた。
でも必死に何度も深呼吸して目眩と戦いながら立ち上がり、ふらついた足取りで店内に戻った。
それからの事はよく覚えていないが、とにかく必死に立ち続けていた。
ふらりとお客さんにぶつかりそうになり、錦先輩に頭を掴まれて裏に連れて行かれた。
「お前、もう帰れ。使えねぇならいても迷惑だ」
「……すいません、大丈夫っす……」もはや呂律が回らない。
「帰れっつってんだよ……!っ馬鹿!」
頭を強く小突かれた。
正直もう目の焦点が合わなくなって、立っているのがやっとだったので、これ以上怒らせないうちに着替えて店を出る事にした。
マジですみません、すみません、と何度も頭を下げると、良いからさっさと帰って寝ろ!と怒鳴られた。
とは言え、電車のある時間でもなくタクシーを拾って帰るしか無かった。
車通りの無い通りだったので大通りまで出ようとしたが、途中で何度もこけて倒れた。
必死に歩こうとするのに体がついて来ない。
意味が分からなかった。
視界に入るものが全然理解出来なくて、他所の店の看板に頭から激突した。
危うく二十四時間営業のラーメン店の店員に救急車を呼ばれそうになったので、必死で断った。
泣きそうになって、どうしようもできなくなって、携帯電話を取り出した。
友達に迎えに来てもらうから、と言い訳したが、電話も掛けられない状態だった。
ラーメン店の店員に代わりに電話をかけてもらうしか無かった。救急車がいいと言われたがお願いだからやめてくれと頼んだ。
店員は、とりあえず一番最近の履歴の人に掛けるよ、と言って連絡してくれたが、その時は邪魔になるので店の隣のシャッターの降りた電器店の前に座り込んでいた。
体がガクガクと震えていた。
ラーメン店の店員は忙しくなって、代わりにラーメンを食べに来ていた客が自分の側についていてくれた。
電話が通じたらしく、友達がタクシーで迎えに来てくれるそうだ、という伝言を聞いた。
それからどのくらい経ったのか、大通りから1台のタクシーが入って来てラーメン店の少し手前に停まった。
タクシーの中から人影が走って来て、自分の名前を読んだ。
「春樹!春樹……迎えに来たよ……!」
美夏だった、我慢出来なくて泣いた。
彼女はラーメン店の店員と客に頭を下げてお礼を言うと、客と一緒に自分をタクシーに担ぎ込んだ。
「ありがとうございました……!」
扉が閉まると美夏はアパートの住所を運転手に告げた。
意識が朦朧としていて、呼吸をするだけで精一杯だった。
手はずっと美夏の手に握られていた。
アパートの部屋は一階だったので、タクシーから降りると美夏はおぼつかない足取りの自分を一人で支えて部屋の中まで連れて行ってくれた。
布団の上に寝かされて、頭がぐるぐると凄い勢いで回った。
どうしてこうなってしまったのかさえ、考える事も出来ない。
「何も考えずにもう休んで春樹……」
美夏がまた、自分の頭を撫で始めた。
そして自分に沿う様に体を横に倒した。
美夏の温もりが伝わって来た。
また涙が流れてこめかみを濡らした。
眠り続けて夜になって、流動食の様なものを食べさせられて、再び眠ってまた朝になった。
カーテンの隙間から光が射しているのが見えて、ようやく永い眠りから覚めた浦島太郎の様な気分だった。
起き上がって辺りを見渡すと、美夏の姿は無い。目がしばしばして痛い。
頭痛はかなりマシになっていた。
ポリポリと頭を掻いた。
結構汗をかいていて、トレーナーを臭うと臭かった。
シャワーを浴びようと服を脱ぎ捨てて風呂場に行き、頭から温水を浴びた。
頭と体を洗ってさっぱりすると、誰かが外から入って来て鍵を閉めた音がした。
美夏の奴、まだ帰ってなかったのか——?
恐る恐るユニットバスのスライドドアを開けると、部屋の真ん中にいる美夏と目が合った。
美夏は自分を捜していたのか、ホッとした様な顔をした。
「あ……悪いけど、タオル取ってくんない?」
「うん」
ドア越しにタオルを受け取ると髪を拭いて体を拭いた後、腰に撒いて外に出ると少し肌寒かったが頭がスッキリしていた。
下着を探そうと部屋を見渡していると、美夏が、服ここ、と言って透明な衣装ケースを指差した。
そう言えばそうだった、と思い上段から下着を取り出して他の段からシャツとスウェットを取り出して着た。
ふと思って美夏の方を振り返ったら、さっき自分が脱ぎ捨てた服を拾っていた。
「……っていうか、下着まで洗濯してくれたの?」
「えっ……?」
美夏は少し赤くなった。
「だって、洗濯物たまってたんだもん」
そんな美夏の服装を見てぎょっとした。
そう言えば美夏、もう何日も前から同じ服着てる——?
「……美夏、家に帰った?」
「か、帰ったよ?」
「いつ?」
「……おととい?……その前……?」
「着替えてないでしょ」
「あっ!ごめん、臭う?一応シャワーは借りてたんだけど!下着はちゃんと替えてるよ」
「いや…そう言う問題じゃなくて……」
ショックだった。明らかに自分のせいで、美夏に迷惑かけまくってるどころの話じゃない。
あのファッションとかメイクとかにうるさかった美夏が——。
——そんなダッサイ服着て来ないでよー!こっちまでダサイ奴に思われるじゃん。
——お風呂入れないとかマジであり得ない!
——地球最後の日でも絶対メイクはかかせなぁーい。
自分が大学にいた頃の美夏が脳裏に蘇った。
「美夏、お前もう帰れよ。俺平気だから」
「えっ?なんで、別にまだ良いじゃん。昼だし」
「そう言う問題じゃなくて」
「……えー?何、同じ服でいるのが気に入らないってこと?じゃあ、ちょっと駅前のスーパーで買って来るから待ってて」
「……スーパーで服買うとか、お前が?」
つい大声を出してしまった。
「だってここスーパーしかないじゃん。ダサイ服なりにちゃんと選ぶわよ……!」
「メイクも、いつもと違うじゃん……。目とか小さいし」
「うるさいなぁっ。近くのコンビニで買った奴だから限界あんの!ツケマとかバリエーション少な過ぎだし、ファンデとかコンシールとかババ色しか無いし。何で近くにドラッグストア無いワケ?」
そうそう、いつもはこんな感じだ。
美夏は気にするタイプなんだ。なのに何でだ。
「お前、服とメイクだけは譲れないんじゃなかったのかよ……。ポリシーじゃないの?……っていうか、なんでまだ俺んちにいるんだよ……」
「……なんでって……」
美夏の声が涙声になって震えた。
しまったと思って口をつぐんだ。
原因は自分にあるのは分かり切った事なのに。
このところずっと看病してくれたのは俺の為だ。でも自分のせいで美夏がポリシーまで失ってしまうのは違う気がした。
いくら自分の事を好きだからと言って、毎日来るとか家に帰らないなんて、そこまで過保護になる必要があるのか。
一人首を振りながら、カーテンを全部開いた。
「ほら美夏、いい天気だぞ。お前そのまま渋谷まで買い物にでも行け——」
思い出して、心臓がひやりとした。
「——ば……」
ここにあるべきはずのものが、無い。
呆然とカーテンを開け放たれた窓を見た。
「——捨てたよ……」
後ろから美夏の声がした。ゆっくり振り返ると、美夏は静かに涙を流しながら目線を落としていた。
「あんなもの、さっさと捨てたから……!」
美夏が小さく叫んだ。
「……そか……」
「ごめんね、何かのコードだったのに」
「いや…いいよ。俺が切っちゃったから、そのランプ、もう使い物にならねぇよなー」
部屋の床に視線を落とした。
「っていうか、今気づいたら、色々配線コード無くなってるんだけど……」
そう言うと、美夏がハッキリと答えた。
「ごめんね、色々と預かってるから。ベルトとか、包丁とか、長めのタオルとか、他にも色々」
返す言葉も無かった。
今日は、なんだか調子が良くて、すっかり昔のような気分になってた。
でも俺そう言えば死にたいんだった——。
そうか、だからか。
俺がいつ死のうとするか分からないから、目を離せなかったのか。
美夏はあの日部屋にやって来て、洗濯物を干そうとベランダを開けた時、あれに気づいてしまったんだろうな。
大晦日のは冗談とか狂言とか言い訳出来るけど、あんな生々しいもの見せつけられたら不安にもなるか。
美夏が近寄ってシャツの端を掴んできた。
「春樹。……一緒に病院に行こ?」
無理矢理連れて行かれた病院は、割と近所の内科院だった。
「総合病院とかの方がいいんじゃ……」
自分のこのところの体調の悪さを考えると、何か重い病気である可能性も捨てきれなかった。
「最初はあんまり大きく無いとこでゆっくり診てもらった方がいいよ。それに近い方が楽だし」
初診で書かされる住所と名前、生年月日。続いて問診票に記入するのは結構面倒くさかった。すると美夏が読み上げるから答えて、と言って手伝ってくれた。
今まで特に大きな病気にもなったこともなくて、病院なんて殆ど縁がなかった。
わざわざ女に付き添われて病院に来るなんて、少し情けなかった。
月曜日で混んでいたのか三十分くらい待たされた。
やっと名前を呼ばれて立ち上がると、診察室まで美夏が付いて来た。
「え?一緒に入るの?」
美夏はコクンと頷き、看護士もどうぞ、と言って二人を誘導した。
メガネを掛けた優しそうなオッサンの先生で、医師はこんにちは、と言って挨拶をして来た。
思わず挨拶を返して座ると、幾つか質問された。
「最近、落ち込む様な事はありましたか?」
「えっ?……さあ、特には……」
「朝なかなか起きれないとか、体がだるいとか」
「朝は、仕事が夜からなのでいつも寝てます。昼過ぎに起きる感じです。あ、でも最近はちょっと体調が悪くて、殆ど寝てます……」
「体調が悪いのはどんな症状ですか?」
「えーっと……。それは……」考えようとしたが、なかなか頭に思い浮かばなかった。数十秒黙ってしまい焦った。
「すみません、ちょっとなんか今頭回んなくて……」
「いいですよ、ゆっくりで」
思わず美夏を見た。美夏は何も言わず微笑んだので、余計に焦った。
慌てて声を張る。
「えっと、体がだるくなって重く感じたり、急に吐き気とか目眩とか。年末年始は休みを貰って休んでたんですけど、数日前に久しぶりに出勤したら、全然体が思う様にいかなくて、その早退したんですけど倒れちゃって」
そういえば、夕べもまたバイトを休んでしまった。
メールすら打てなくて、美夏が代わりに錦先輩に欠勤メールを打ってくれた。
手を挙げたり瞳孔の動きを確かめられたり、触診や体内の音を聞かれたりした。
「……特に問題がある感じでは無さそうですね」
その後幾つか問診が続いて、暫く黙った後、医師がこう尋ねてきた。
「最近、死にたいと思う事はありますか?」
まさに図星でドキリとした。
恐る恐る答えた。
「……あり……ます……」
「それはいつ頃から思う様になりましたか?」
「……去年の春過ぎ……からです。誕生日を過ぎて、ひと月くらいした頃からかな。……なんかよく分からないんですけど、全然楽しく無くなって。通っていた大学も辞めて、フリーターやってたんですけど、気がついたら…」
その先が出なくて黙ったが、医師は頷いて何かを書き記していた。
「ここつい最近、死のうとした事はありますか?」
——何でこんなにピンポイントに訊いてくるんだ。
最近まで誰にも話せなかった事なのに。誰にも相談出来ず、楓にも冗談程度でしか受け止めてもらえないで。
胸が苦しくなって涙が溢れた。
「……はい……!」
零れ落ちた涙を慌てて拭うと、医師は、大丈夫ですよ、と言って優しく微笑んだ。
そして診断された結果医師の口から出たのは、『うつ病』だった。
「……うつ、病?」
思わず笑ってしまった。
「でも、体調不良とか……」
「なりますよ。人によっては頭痛とか目眩とか吐き気とかしますし、神経性のものなので体の自由が利かなくなる事もあります」
「……どのくらいで治るんですか?」
「どんなに早くても半年、長いと二、三年、それ以上です」
驚愕した。そんなに?半年もかかる?
「薬とかで早く治らないんですか?バイトとかあって、体調不良とか早く直したいんですけど」
「残念ながら、投薬しても早く治るものではありません。体の不調はしばらく安静にして休めば改善出来ると思いますよ」
「しばらくってどのくらい?」
「わかりません」
「それって困るんですけど。一人暮らしだし、生活費もあるし……」
必死に言い訳した。
「とりあえず今は無理しないように。色々事情もあるだろうけど、今は安静に。時間はかかりますけど、ゆっくり治して行きましょう」
「本当にうつ…病なんですか?どっか体の中が悪いとかじゃなくて?」
「ご心配ならもっと大きい病院で検査してみますか?紹介状は書きますけど、でも間違いないと思いますよ。最近多いから。…風邪みたいなものだから結構誰にでもなるんだよ。流行があるのかもしれないね」
凄くショックだった。
とりあえず何かの薬を出されて、総合病院宛ての紹介状ももらって帰ったけど、様子を見たいから一週間後にまた来る様に言われた。
「あの先生、元々精神科にいたこともあるらしいから大丈夫だと思うよ。信頼出来ると思う」
帰り道、美夏が自分の手を繋いでコートのポケットに手を入れながら話しかけて来た。
ポケットを見ると、こうすると暖かいでしょ?と言って笑った。
「……美夏は気づいてたの?俺が……うつ病とか……」
美夏はうーん、微妙な返事をした。
「途中からなんとなく、ネットで調べたりしてたら、そうかなって」
「ネットで調べたの?何を?」
「……春樹の症状とか?……死にたい、とか」
一瞬足を止めた。
「検索したらうつ病の事とか出て来たの。やっぱり今結構多いんだね」
ゆっくり歩き出すと、なんだか凄く落ち込んだ。
自分がうつとかあり得ないし。他人事だと思ってたし、うつ病がこんな辛いものだとは知らなかったし、でも自分が特別という訳でもない。誰にでもなるというのも落ち込んだ。
「実はね、実家にいる弟も、今うつ病なんだって……」
「え……?そうなの?」
「私も暫く会ってなかったんだけど、去年の秋くらいから様子がおかしくなってうつ病って診断されたらしいんだ。私もうつ病がどんな病気が全然知らなくて、結構他人事に思ってたんだけど……」
「実家に帰らなくて大丈夫だったの?……俺のせいで」
「弟は大丈夫だよ。親とかがいるもん。それに春樹みたいに死のうとまではしてないみたいだし……」美夏はそう言ってハッと気づいた様にごめんと謝った。
「いや……」
部屋に戻って遅めの昼食を取った。
凄く意外だったが、美夏が手料理を作ってくれた。
「簡単なものしか出来なくて……」
そう言った割には酢の物とか親子丼とか立派な食事だった。
結構甘めの味付けだった。
「食べれる?」
「うん、美味いよ」
こんなにちゃんとした食事は久しぶりだった。
食事の後早速薬を飲まされた。
うつ病の薬と痛み止めや吐き気止め、胃腸薬など数種類。
「こんなに飲まなきゃいけねーの?」
「良いから飲むの!」
しぶしぶ従ったが、薬を飲むのは余り得意じゃなかった。
うまく飲み込めなくて数回に分けて飲んだ。
夕方に差し掛かり突然携帯に着信が来た。
錦先輩からで、慌てて電話に出ようと立ち上がって美夏がいたので部屋の外に出た。
「……もしもしっ……!」
「春樹?お前今日は出れる?オーナーの知り合いが来るから早めに来て欲しいんだけど」
「えっと、今日は……」
慌てて答えようとしたが、悩んだ。
「……分かりました。えっと、じゃあもう早めに向った方がいいすかね……?」
「ああ、頼む。一応和雄にも出来るだけ早めに来る様に伝えといてくれるか?」
「あっ……はい……。あの……」
急に頭が痛くなってだるくて行きたく無くなった。
でも断れない。
すると急に後ろの扉が開いて背中を打った。
驚いて振り返ると、美夏が、貸して!と言って手を出した。
え?と思っていると、持っていた携帯を奪われた。
「すみません、春樹、暫く出れません。病気なんです」
携帯に向って話しかける美夏の言動に驚いて取り返そうとした。
「……何やってんだよ!」
「本当にすみません。でも本当に出れないんです。倒れたんです」
美夏は必死に奪われない様に体を反転させて通話を続けた。
「落ち着いたらちゃんと挨拶に行かせますから。でも当分は無理です。ご迷惑おかけしますが、お願いします」
なんて毅然とした態度であの錦先輩に物を言うんだ。
あの人の恐さを知らないくせに。
気がついたら美夏は電話を切っていた。
「入るよ春樹」
そう言って携帯を持ったまま部屋の中に戻ってしまった。
「ばっ……!何やってんだよお前……!」
部屋の中に入って美夏を責めると、美夏はツンケンした態度でシカトした。
ふざけるなよ、何勝手に人の電話取り上げて勝手にもの言って切ってんの。何様のつもりだよ。先輩の恐さ知らねーくせに勝手な事してんじゃねぇよ。
「じゃあ、本当に死んでもいいの?春樹今度こそ倒れて死んじゃっても良いの?そんなに死にたいの?」
——そんなに生きたく無いの——?
美夏が消え入る様な声で泣き出した。
突然弱る美夏を見て狼狽えて、つい抱きしめかけた。
抱きしめる資格なんて無いのに。
「わ、悪かったよ……」
その後暫くして美夏は泣き止むと、先生も無理するなって言ってたじゃん、頑張っちゃ駄目だよ、と無理矢理笑った。
美夏は晩ご飯まで用意してくれて、一緒に食べた。
夜は処方された睡眠薬も飲まされて、早めに寝る事になった。
「美夏、今日は帰れよ。このままだとお前の方が体調崩す」
「うん、分かった」
病院に行って薬を貰って安心したのか素直に応じた。
「大学も授業始まってるだろ?ちゃんと行けよ」
「うん、大丈夫。ありがと」
「美夏……!」
帰ろうとして靴を履いた美夏が振り向いた。
「……ありがとな」
ずっと言ってなかった御礼を言うと、美夏は目尻に涙をにじませて笑った。
「うん。いいよ。……じゃあまたね」
美夏はそう言って扉の向こうに消えた。
うつ病だと判ったからと言って、良くなる訳じゃない。
寧ろ自覚してしまうと余計に症状が酷くなった。
総合病院に行くどころか本当に一歩も外に出れなくなった。
一日中気分が落ち込む。
何日も寝ては起きてボーッとして落ち込み、自分を責めて泣いて、また寝るの繰り返し。
美夏は毎日様子を看に来てくれた。
彼女が来ると少し気が紛れて、心配かけまいと極力元気に振る舞った。
でも美夏が帰ると途端に孤独感を感じて、何でこうなってしまったんだろう、と情けない自分に泣けて来た。真夜中泣き続けて朝になるとやっと安心して寝る。
三日間くらいそういうのが続き、その後は毎日十五時間以上の睡眠を取る様になった。
薬のせいか、眠くて仕方が無かった。が、寝ている間は余計な事を考えなくて済んだ。
一週間して再診に行く時も、美夏が起こしに来てくれるまで寝ていた。
美夏はいつの間にかスペアキーを常時保管していた。
もう完全に通い妻状態だった。
でもそんな事も気に出来ない程、自分の事で精一杯だった。
一月中は毎週病院に通った。
美夏が言っていた通り、近くの病院で助かった。
自分がよく寝る様になってから、美夏は日中は余り来なくなった。夕方前に少し顔を出して食事の用意や掃除洗濯を済ませると、すぐに帰って行く様になった。
時々寝れない夜があると寂しくて寂しくて堪らなかった。
美夏に来て欲しかったが、そんなこと言えなくて、ひたすら孤独に耐え忍んだ。
二月に入り、楓が様子を観に来た。
「春樹ー?おー、調子どう?」
楓にはうつ病の事はちゃんと話して無かった。
ただ誘われていた遊びの約束を果たせないので、体調を崩して長期療養中だと伝えた。
あまりうつ病だとは知られたく無い。
「病気の割に部屋奇麗だけど、お前彼女出来たの?」
「いや……」
返答に困った。まさか美夏が毎日来てくれている、なんて言えなかった。
「そーいやさ、ジェシカはどうしたの?おっ、先週学校であってさ、お前の事訊かれたんだよ。正月初詣誘われてたんだって?なんで返信しないんだよ?」
「——あっ……!」
思い出した。すっかり忘れていた。
「忘れてた。ヤベー……」
「おいおい、いい加減にしろよー。お前ジェシカの事好きだったんじゃないのかよ。もう興味ないってこと?」
正直それどころじゃない。
「今度ちゃんと謝っとくよ……」
「ジェシカもさー、結構参ってるみたいだったぜ、お前にシカトされて。あいつお前の事好きだよたぶん」
「えっ?まさか……」
「だって、最近一人で携帯いじってる事多くてさ。遠くで見掛けただけとかで声掛けなかったけど。ジェシカも柏原と別れてからなんてーの?元気無かったから、お前と付き合ったらいい仲なんじゃないかと思ってたのによ」
「でも流石に彼氏とかいただろ。……もうすぐ一年だぞ?」
「いるんだかねー?まあでもジェシカって見掛けによらず一途なタイプだから」
もし楓の言う様に本当にジェシカが自分の事を思ってくれていたとしたら、複雑な心境だ。
とても前の様には戻れない。
今は誰かと付き合う事も考えられないし、ジェシカにはさっさと他の奴とくっついてしまって欲しい気もした。
そうすればジェシカの事を気に病む事も無い。
楓が帰った後はどっと疲れが襲った。
こうやって誰かに会う度に疲れるのはしんどかった。
それでも誰にも会わない日があると、気が狂いそうなくらい鬱だった。
『ごめん、ちょっと今日は行けそうに無いの。明日の朝行くね?』
美夏からのメール。
それを見た瞬間ショックで涙が出た。
自分でも信じられないほど弱っていた。
自分はこんなにも弱い人間だったのか、情けなくて早く死んでしまいたかった。
いっそもっと重病だったら良かったのに。ガンとかで余命半年とか宣告されれば良かった。
毎日どっかで誰かが死ぬのに、何故早く自分の番が来ないのだろう。
明日なんか来なければ良いのに。
そう思いながら眠りについた。
美夏が訪れると増々憂鬱になった。
「昨日は来れなくてごめんね」
「別に……無理して来なくていいのに。俺なんかの為にわざわざ時間取られる事無いよ……」
「なんでそんな事言うの?私は来たくて勝手に来てるの」
「でも誰にも会いたく無い時もあるんだよ……」
以前は全くそうではなかったのに、もの凄く暗い人間になってしまっていた。
自分で言うのも難だが、結構明るく前向きな性格で、嫌な事も一晩寝たらどうでも良くなってた。
根拠の無い自信もあった。有言実行、やれば何でも出来る気がした。
大学を卒業したら、こっちで大手の会社に入ってバリバリ働いて、同窓会とかで地元に帰ったらちやほやされる未来を想像してた。
なのに何でだろう。こんなはずじゃなかった。
こんなはずじゃなかった——。
俯いて泣き出してしまった。
こうやって美夏に情けない姿見られたく無い。
美夏は困った様にずっとこちらの様子を伺っていた。
たった一日会わないだけでこんなにも距離を感じるなんて。
突き放したい、けど、側にいて欲しい。
翌日、美夏はバイトを始めた事を告白して来た。
「ごめんね、一昨日は授業に出てから寄ろうと思ったら、バイトに間に合いそうになくて……」
そっか——、と答えてまた少し落ち込んだ。
自分もいい加減働かなくては。
「わざわざバイトなんてしなくていいじゃん。仕送り貰ってるんだろ?」
「うん、そうなんだけど……。春樹って貯金あるの?」
「……殆どないよ」
「そっか……。流石に二人分の家賃までは払えそうに無いなぁ……」
美夏が少し困った様な顔をした。
あっ!と思い出して押し入れから給与袋を取り出した。
すっかり忘れていた手つかずの三十万。今思うとこの金はありがたい。
「美夏、今までの食費代とか交通費とかここから全部返す。今まで負担させっぱなしでホントごめん」
「えっ?それはいいよ、大丈夫。そのためにバイト始めたんだから」
「何言ってんだよ、俺の為に金使ってるんだから俺の金使えば良いよ」
「……うん、でも……」
「美夏が余計な負担背負う必要なんてどこにもねぇよ。彼氏でもない相手の世話して金まで使うなんて馬鹿だよ」
美夏は困惑しているようだった。
「でも、春樹。そのお金は取っておいた方が良いと思うの。どうしても家賃とか光熱費とか、払わないといけないものがあるでしょ……?」
その言葉は説得力があった。
事実、美夏が来る直前、管理会社から家賃の催促電話が来たばかりだった。
月末に振替口座に預金する事も忘れていた。
「携帯代とか……病院代とか……」
その通りだ。全然働かない訳にはいかない。前の様に短期でも良いからまた稼がないとやっていけない。
「……大丈夫、今月中になんとかするよ……」
「なんとかって?」
「またバイトする。短期とかなら何とかなりそうだし」
「まだ無理だって!まだ体調回復してないじゃん……!」
「やってみないと分かんないだろ?」
「またそうやって春樹……!なんだかんだ頑張っちゃうところ、春樹のいいところだけど、もう前の春樹とは違うんだよ?」
「違うって、何だよ……」
「だって……」
急に怒りが込み上げて来て頭の中がぐちゃぐちゃになった。
「違うって……何だよぉ!……俺だって、俺だって好きでこうなった訳じゃない!……ゔああぁああぁぁああぁぅあっっっ!!」
気がついたら叫んでいた。
「あっごめっ、春樹……!」
「もぉいいよぉ、お前!帰れよ!もう二度と来るなっ!」
とにかくもう頭に血が上って押さえきれなかった。
「俺なんてっ俺なんて……!俺がっ俺がっ俺がぁっ!」
近くにあったミキサーを掴んで叫びながら一心不乱に頭に殴りつけた。
よだれが飛び散るのもおかまいなしだ。
こう言う激しい自傷行為は初めてだった。
ムカついて壁に頭をぶつける事とかはあったが、正常なら痛いので理性が利く。
でもこの時は空っぽの容器の中に突然塞きを切って流れ入ったかのように、アドレナリン的な物が出ていたのかも知れない。
美夏の悲鳴の様な声が聞こえて、腕を掴まれたので思い切り突き飛ばした。
再び自分を殴ろうと思ったが、がしゃあんっ!というもの凄い音と共に美夏が倒れたので驚いて身動きが停まった。
美夏の体が打ち付けたのは本棚や物置の代わりに使っていたスチールラックだった。
クァハッ——!
苦しそうな美夏の吐息に、持っていたミキサーをずるりと手から落とした。
俺はなんて事を——!
少し冷静になって頭を抱えた。
「美夏……!」
狼狽えて美夏の背中に手を伸ばしたが、美夏は苦しそうにその手を払いのけた。
ガン!とした衝撃が頭を襲った。
美夏を傷つけた——!美夏を傷つけた!
美夏を——!
脳裏に美夏の笑顔が浮かんで、それにバツ印がされた。
その時もう美夏の笑顔は二度と見れないと思った。
いわゆるパニックになった。
激しく呼吸困難になって、部屋を飛び出した。
裸足で駆け出して、夜中の住宅街を変な呻き声の様な物を出しながらひたすら走り続けた。
途中で酸欠になって目の前がブラックアウトし、ふらりと倒れ込んだ。
公園の地面に両手両膝を付いた状態で、意識が戻った。
頭の血が引いているのが分かった。
座り込んで少しずつ呼吸を整えた。
泣きそうになって顔を歪めた。けれど涙は出なかった。
美夏——。美夏はどうなったのだろう。
きっともう美夏に嫌われたに違いない。絶対嫌われた。当然だ。
でも謝らなきゃ——。
帰ってももう美夏はいないかもしれない。
妙に冷静沈着になってゆっくりと元来た道を歩き出した。
先ほど自分で殴った箇所が少しズキズキしたが、気分はもの凄くスッキリしていた。というより空っぽだった。
何か溜まっていた物を全部吐き出してしまったのかも知れない。
十分くらいで部屋に戻ると、部屋の鍵は開いたままで、電気も付いたままだった。
でも部屋の中に入ると美夏の姿は無かった。
そんなの当たり前なのに、愕然として膝を落とした。
しかし、通り過ぎた風呂場から何か音がして、慌てて扉を開いた。
そこには上半身のシャツをまくりあげて、下着姿でタオルを水に濡らしている美夏の後ろ姿があった。
ブラジャーのすぐ上の肩甲骨の付近が真っ赤に腫れ上がっていた。
美夏は痛そうにその打撲傷を濡れタオルで冷やそうとしていた。
「ゔっ……!」
タオルを当てようと体をよじらせたら激痛が走ったのか、眉間に皺が入った。
中に入ると慌ててタオルを取ってそっと腫れている部分に当てた。
美夏は息を止めて痛みを我慢している様に時々息を吐いた。
美夏の体は熱を持っていて、冷たい水で濡らしたタオルはすぐ温くなってまた水で濡らした。
彼女をバスタブの縁に斜めに座らせて、暫くそうやって傷を冷やした。
痛みがマシになって来たのか、美夏が深呼吸したので、ごめんな、と小さく呟いた。
美夏は無言のままだったが、一旦部屋の方に戻る事にした。
今度はタオルを保冷剤に撒いて座った美夏の背中に当ててやった。
少しでも痛みが紛れればと思って、テレビを付けた。
ちょうど美夏が好きなお笑い番組がやっていた。
寒いだろうと、タオルを傷に当ててシャツを下ろしてやった。
三十分くらいそうしてたのか、お笑い番組も次回予告に入り、保冷剤もすっかりぬるくなった頃、美夏がこちらを気にする様に少し振り向いた。
すかさず、救急外来なら開いてるだろうから病院に行く?と尋ねたが、美夏は首を横に振った。
「明日でいい」
低いトーンの声に、美夏の傷の深さを思い知った。
「……さっきは本当にごめん……。俺、急に分け分かんなくなって……。言い訳なんかしてごめん……」
すると美夏は、小さな声で答えた。
「……今日はちょっと帰れそうも無いから、ここに泊めて?」
「……わかった」と返事をするしか無かった。
体が冷えて来たのかタオルで冷やすのはもう良いと言われて止めた。
美夏は自分の頭の方こそ大丈夫?と心配してくれたが、こちらは自分でやった事だし全然大した事無いと首を縦に振った。
深夜になり、美夏が寝泊まりの準備を始めた。
美夏は以前何日か泊まった時にコンビニでクレンジングや化粧品を買って、台所の流し台の下に隠していたらしい。
当然ながらまったく気づいてなかった。
背中をかがめると痛いらしく、呻きながら顔を洗ってメイクを落としていた。
美夏にタオルを持って行くと、美夏が顔を拭くのを眺めていた。
それに気づいた美夏は恥ずかしそうに後ろを向いた。
「やめてよ、あんまり見ないでくれる?」
これ以上怒らせたく無かったので大人しくその場を離れた。
身支度を整えた美夏は、いつの間にか自分の倉庫番スウェットに身を包んでいた。
買ってからタグすら取っていなかった未使用品を、美夏はいつの間にか発掘して着ていた。
最早この部屋の主よりも部屋にあるものを把握していると言えた。
いざ寝ようとした時に困惑した。
よく考えたら布団は一組しか無いのだ。
自分が倒れていたとき美夏はどうしていたのだろう。
「スウェットの上にアウターとか気重ねて、仕舞ってあった薄い毛布にくるまって寒さを凌いでた」
わかった、と仕舞ってあった毛布を取り出して、服の上に上着を重ねた。
部屋の隅の方で横になろうと毛布にくるまると、美夏がこちらを見ていた。
「言っとくけどかなり寒いよ……?」
「美夏もこうしてたんでしょ?いいよ」
「でも多分今の方が寒いよ。雪降ってきちゃったし」
美夏の言葉で暖房を付けてもこの寒さなのに今更納得した。
「さっき予報で今年初マイナス行くかもって」
少し憂鬱になった。
でも、最近寒さには慣れた。
日中暖房を付けないで過ごす事も多い。
「……こっちおいでよ、春樹」
美夏が声を掛けてきた。
「いや、いいよ」
「一緒に寝た方が、暖かいよ?知ってるでしょ」
ふと、年明けに美夏の部屋で一晩を過ごした事を思い返した。
「……そうだけど……」
口ごもっていると、早く来い!と叫ばれて慌てて側に移動した。
美夏は毛布と布団の間に薄い毛布をもう一枚はさみ、一番上にアウターを気持ち程度掛けてセッティングした。
はい!と言われて布団の中に誘導されると、恐る恐る布団の中に入った。
「春樹、もっとこっち来なよ。背中でてるじゃん」
「いいよ、大丈夫」
「隙間開いてこっちが寒いんだってばぁ」
仕方なく潜り込み、美夏との距離が一層縮まった。
なんだか緊張する。
「背中痛くて仰向けで寝られないの」
「……ごめん」
美夏は自分の体に体半分を俯き加減に重ねる様にしてくっついた。
温かかったが、体が反応しないか心配だった。
幾らうつ病だと性欲が薄れると言っても、完全になくなるわけじゃない。
それでもやがて緊張感が心地よさに変わって、安らかな気持ちになった。
「良かった、美夏……」いてくれて、良かった。
思わず呟いたが、そのまま眠りに堕ちて行った。
翌日は雪も積もらずよく晴れていた。
最近気づいたのは、気分がかなり天候に左右されるということ。
今日はかなり気分が良かった。
鏡を見ると左の額の生え際部分が少し内出血してふくれていた。昨日のせいだ。でも押さえない限り痛くなかったし大した事は無かった。
美夏の傷も一晩で結構痛みが和らいだようだ。
でも打撲箇所が紫になっていたし、左腕を動かすとかなり痛いみたいだった。
美夏が病院に行くので自分もついて行く事にした。
歩いても行ける様な距離だったがバスを利用した。
割と近所に形成外科が存在していた。
この辺りは大きな商業施設こそ無いが、病院や学校など、福祉施設も多い地区で住民に取っては割と住み易い環境なのかもしれない。
ただ調剤薬局は近いのに、量販店のドラッグストアは少し遠い。そこは美夏が駄目出しをしていた。
美夏の傷はそれほど体した事は無く、もう自己治癒で回復に向っていた。
薬が塗ってある湿布と痛み止めを処方されていた。
「本当にごめんな……」
帰り道改めて深く謝罪した。
「いいよ、もう気にしないで」
美夏はそう言ってくれたが、自分自身のショックは癒えなかった。
またいつかああやって美夏を傷つけてしまう事があるかも知れない。
このまま美夏に側にいてもらう事はお終いにした方がいいんじゃないだろうか。
薬のおかげで体調はだいぶ良くはなって来ているし、今日のように調子がいい日は自分が病気だという事も忘れそうだ。
「美夏……、そろそろさ」
「えっ?」
「他に彼氏とか、作った方が良いんじゃねぇのかな……?」
「……なんだ。何を言うかと思った……」美夏はガッカリした様に肩を落とした。
「友達だからって色々良くしてくれてるのはありがたいよ。でも、昨日みたいにまた俺が傷つけちゃう事があるかも知れないだろ?俺もう嫌なんだよ、そう言うの、……なんか」
美夏は少し怒った様に声を被せた。
「まだジェシカの事好きなの?」
「いや……それとこれとは……。なんであいつが出てくるんだよ」
美夏は口先を少し尖らせてゆっくりと雲が流れる空を見た。
「最近ね、楓経由でメールが来たの」
えっ?と驚いて、誰から?と尋ねてしまった。
「ジェシカから。今更光輝の事謝られてもって感じ。あの子だって別れてからもう一年以上経つんだよ?光輝も今ごろ全然知らない子と付き合ってるってのに」
ジェシカの話題は暫く黙っている事にした。
「それで、今度会えないかって言われたの……」
意外だった。でもきっとジェシカも美夏との事はずっと心残りだったのだろう。
二人は中高一緒でジェシカは高校二年の途中でスカウトされ上京したのだと聞いていた。
「……春樹、ジェシカとエッチしたんだよね……?」
あえて過去に葬り去ろうとしていた事実を急に美夏が掘り返して来た。
「……それは……!」
「光輝の事はもう気にしてないんだ。でも、私どういう顔してジェシカに会えば良いんだろうって思って」
美夏が立ち止まって振り返った。
「春樹、私とエッチしよ……?」
「バカ言うなよ……。こんなところで」真っ昼間の住宅街だ。近所の家の庭では主婦が洗濯物を干していた。
「それに、出来ないんだ……」思わず俯いた。
ジェシカの時はまだ平気だったが、近頃は薬のせいか全然性欲が湧かない。
「分かってる……。だから、元気になったら、私と……」
埒があかない話だ。
「俺なんかお前にはもったいないんだって!いい加減目を覚ませよ」
美夏はきょとんとした。
「え?意味分からない?……あれ?俺間違えた?」
お前には俺なんか勿体ない?いや、お前なんか……?あれ?
「とにかく!お前にはもっと良い奴がいるんだから」
「どこに?」
「どこって、それは知らん。でも、間違いなく俺はふさわしく無い」
「……私、迷惑?」
「そんな訳ないに決まってるだろ?俺はお前がいなかったら今ごろ……!」
今ごろ死んでたっておかしくないような最低の人間だ。
「俺は最低の人間だ……。お前には散々世話になったけど、俺はお前に何もしてやれない。多分この先も何も出来ない。何かあってもお前守ってやれる自信が無い……!」
寧ろ傷つけてばかりだ——。目の前で美夏が悲しそうに唇を震えさせている。
「今まで本当にありがたかった。でももうそろそろ大丈夫だから……」
近くを犬を散歩中の老父が通りかかった。
それをつい二人して見送ると、美夏が何事も無かったかの様に明るく言った。
「お腹減ったね?帰って何作ろっか?」
「……美夏ぁ!」
小さく叫んだが、美夏は素知らぬ顔をして微笑んだ。
翌々日、そろそろ病院には一人で行くと言って美夏は同行させなかった。
美夏も本当は大学の授業があったらしく、引き返して行った。
「あの先生、俺どうしたら良いか分かんないんです……」
後ろで待機して事務仕事をしている看護婦が気になったが、美夏がいない今日思い切って相談した。
「いつも一緒に来てくれる彼女とはただの友達で、付き合ってもいないのに、毎日家に様子を看に来て身の回りの世話をしてくれるんです。彼女は俺に好意を抱いてくれてるみたいなんですけど、俺は今の状況ではどうしても彼女とは付き合えなくて……」
オッサン医師は、ふんふん、とこちらを見て話を聞いてくれていた。
「俺じゃあ絶対に幸せにできないじゃないですか?働けないし、うつだし。大学には他に将来有望で良い奴がいっぱいいるのに、もう来なくて良いって言っても聞かないんで、どうしたらいいのか……」
「君は本当に彼女にはもう来て欲しく無いの?」
「……それは……。いえ……本当は、側にいて欲しいです……」
つい、泣きそうになってしまった。
「じゃあ今は先の事とかは考えずに、彼女の好意に甘えてたら良いんじゃないのかな?男と女なんて、頭で考えてどうこうなるもんじゃないし、君が元気になれば彼女も喜ぶと思うよ?」
「でも、俺この前彼女の事傷つけちゃって……。パニックになって思い切り突き飛ばしたんです。思い切り背中強打して痣になって……彼女は許してくれてるみたいなんですけど、俺ショックで……これ以上傷つけたく無いんです。怖いっていうか……」
不安をぶちまけると、医師はじっと目の奥を見据える様に見つめてきた。
「君は、彼女の事が好きなんだろ?だから傷つけたく無いってこと?」
「え……それは……」口ごもっていると医師は少し意地悪そうな顔をして言った。
「自分も、傷つきたくないよな。彼女が自分から離れて行ってしまったらと考えたら、不安で悲しくならないかい?」
そんなことを言ったら駄目だ。想像するだけで涙が止まらなくなる。
「ああ、ごめんよ」涙をこぼす自分の肩に手をかけて優しく謝った。
「君が今彼女を突き放したいと考えるのは、彼女が自分から離れてしまう前にいっそこちらから断ち切ってしまいたいと思ってしまっているからかも」
確かにそうかも知れなかった。でもそれを人に見透かされると、もの凄く惨めだ。
「でもそういう風に思えるのは少しずつ心が回復して来ている証拠だろう。前の様にまではいかなくても必ず元気になれるから。春になると元気になる患者さんも多いんだ。もう少し様子を見てみたらどうかなぁ?」
医師はにっこり笑った。
「でもお金の事とか、彼女にも負担させてしまって。暫くはなんとかなりそうなんですけど、それもそう保ちません。少しでも良いからバイトとかしないと……」
「そういう難しい事は今はあまり考えない方がいいな。今はなんとかやれているならもう少しこのまま休養していないと駄目だ。無理は禁物なんだよ」
そんなことを言ったって、他人事だと思って——!
「彼女に正直に気持ちを伝えてみたらどうだい?先の事は分からないけど、今君には彼女の力が必要だと思うよ。精神的にも経済的にも支えてもらえるならそれに越した事は無い。いつか元気になった時に、恩を返せる時が来たらその時で良いんだよ」
結局相談したがどうすればいいか答えは見つからなかった。
二月の末になり楓からの電話が着信した。
「春樹、その後調子どう?」
「ああ、結構良くなって来たかな」
「バイトとかしてんの?」
「いや、まだ……医者から止められてて」
「マジで?そんなにヤバいの?」
「いや、もうだいぶ良くなって来てるから大丈夫」
「そっか。あ、そういやさ」
「うん何?」
「この前久しぶりに美夏にあったんだけどさ」
「え……。うん……」
「なんか暫く見ないうちに、すっげー良い女になってたんだよ……」
楓が含み笑いをしたのが聞こえた。
「あれは男のせいかな?女って付き合う男で変わるもんだな」
かなり動揺した。
えっ——美夏いつの間に——?俺が知らないだけで本当は他に彼氏がいたのか?
でも、大学に行ってバイトもして毎日俺のところに来てくれて、空いた時間に男と会う?そんな時間があるとも思えなかった。
「美夏って前はただ明るくて自己チューのイメージあっただろ?それがさ、この前大学のサークル関係の飲み会があって美夏も来てたんだけど、スンゲー雰囲気落ち着いちゃっててさ。飲み物とか率先して采配したり飲み物が足りないと気遣ったりしてさ、別人かと思ったわ」
楓はかなり意外そうに話していたが、それはむしろすぐ想像出来た。
美夏はいつも気を遣ってくれるし、優しい雰囲気に一緒にいると安らいだ。
「そうかな……でも美夏って……」
前からそうじゃなかったっけ?と言おうとして思い出した。
そう言えば美夏は前は確かに今と雰囲気違ってた。
ガンガンのギャルで見た目重視の馬鹿に明るくてうるさいタイプの女だった。
ジェシカと並ぶとかなり目立って、他の大学の奴に告白とかされて、微妙に二股とかしてて、でも柏原とラブラブで——。
思い出して少しショックを受けた。
あの時のままの美夏なら確実にご免だ。今は一緒にいるだけで振り回されて疲れそうだ。
「今日これからお前んち行って良い?他にも話したい事あるし」
了承して楓を待ちながら、何か飲み物が無かったかと冷蔵庫を開けると、美夏が買って来た食材の使いかけが入っていた。
美夏の料理は最初の頃よりずっとバリエーションも増え、味も良くなっていた。
セロトニンが減少して引き起こされるうつ対策に、牛乳や豆乳などのセロトニンを多く含む飲食物は毎日欠かさず食卓に出してくれた。
ふと美夏に感謝して温かい気持ちになった。
俺の為に色々と頑張ってくれているんだなぁ——。
母親にも抱いた事の無い感情を美夏に抱いてしまった。
ふいに、母親にずっと連絡していない事を思い出して反省した。
たまには連絡してやらないとな——。
とは言え、今の状況を正直に伝える勇気は無かった。
本来ならば美夏に頼らず、親からの仕送りを宛にすべきなのかも知れないが、それを言えば絶対実家に戻れと言われるに決まっていた。それは嫌だった。
楓の好きな炭酸でも買って来ようと、財布を捜して部屋を出ようとすると、ちょうどそこへ美夏がやってきた。
「あれ?春樹どっか出掛けるの?」
「あー、ちょっとコンビニに。あ、楓がくるんだ。だからその……」
「そっかぁ……!今日すき焼きにしようかと思ってたんだけど……」
美夏は渋谷でも歩いていそうな服装に釣り合わない所帯染みた買い物袋を釣り下げて、可愛くネイルをあしらったツケ爪の付いた指を口元に当てた。
「あ……悪いな……」
「まいっか、明日にしよ」
美夏はさほど気にする素振りも見せずに、ちょっと冷蔵庫に入れて来るねー、と部屋に入っていった。
「今日ご飯どうするの?楓とどこか食べに行く?お金出そうか?」
あの三十万は全額美夏に預けていた。それでも美夏はバイトを辞めない。
「あっごめーん!今日家賃口座に入れてきたから財布の中身すっからかんだった!コンビニまで一緒に行って下ろすね?」
成り行きで今日は一緒にコンビニデートする事になった。
デートと言ったのは美夏の口だ。
コンビニに一緒に行くくらいデートにはならない。
「それでも病院以外に春樹と一緒に歩くってなかなかないもん」
美夏は嬉しそうに腕に捕まって来た。
最早それを振りほどこうとも思わなかった。
ゆっくりとコンビニに時間を掛けていたら結構な時間になっていた。
慌てて美夏に下ろしてもらった金をもらって別れた後、とりあえず部屋に急いで帰った。
すると、部屋の前にちょうど楓が来ていて、よお!今来たとこ、と言って笑った。
久々の楓の顔にホッとして部屋の鍵を取り出すと、すぐに後から美夏が鞄の中をごそごそと探しながら走って来た。
「ごめーん、なんか携帯部屋に置いて来たっぽ——」
美夏が楓の方を見て呆然とした顔をした。
「——い……。やだ、楓……」
一瞬の間の後、気づいた楓が驚きの声を上げた。
「えっ!?美夏ぁ?なな、なんでいんの?」
楓は微妙に顔を赤くした。
「あ、ごめんね、この前は奢ってくれてありがとう」
こんな場面で思い出したかの様に美夏は楓にお礼を言っていた。
自分もこんな場面で、奢ったって何だろう?と、少し勘ぐってヤキモチを妬いてしまった。
「いや、それはいいけど…。何でお前んちに美夏が来てんの?えっ?いや、確かに住所教えたけどさ……」
楓は動揺している様だった。
「お前ら俺に内緒で付き合ってたワケ?」
「いや、付き合っては無い」即座に返した。
美夏を見ると、少しふてくされた様な顔をした。
「じゃあなんでそんな仲良さそうに一緒にいる訳?」
楓は少し怒っていた。
「俺はこちらの美夏さんに、ただいまご奉仕いただいておりまして。まあボランティアと言うか……」照れくさくてつい冗談っぽく話してしまった。
「はぁ!?何っ?セフレ?」
「ちがーっう!」慌てて訂正した。
「お前ジェシカと寝といて何美夏にまで手ぇ出してんだよ!?ジェシカまだお前の事マジで……!」
「あっ!?」慌てて楓の口を塞いだ。これ以上場を混乱させる様なことを言うな!
美夏は案の定、どういうこと?という感じの顔で見上げて来た。
「ちょっ、とりあえず中に入れよ……」
近所の目もあったので部屋の鍵を開けるとなんとか二人に部屋の中に入ってもらった。
すると美夏が、あったー!と言ってカウンターの上の携帯を取り上げた。
「どういう事か、説明しろよ!」
「まあまあこれでも飲んで!」
慌てて先ほどコンビニで買って来た炭酸飲料の蓋を開けて手渡そうとしたが、炭酸の泡が溢れて美夏が布巾を持って来てくれた。
氷あるよ、と言って美夏はそれを受け取り手早くコップに氷を入れると三等分にして二人に渡してきた。
「はい、どーぞ」
二人とも受け取ると暫く黙ってにらみ合っていた。
「…で?これどういう状況?」
美夏は走って喉が渇いていたのか、ゴクゴクと炭酸を飲み干していた。
飲む気にならず、手が冷たくなったのでしゃがみ込んで座卓の上に置いた。
楓もしゃがんで座り込んだのであぐらをかく事にした。
楓は部屋の中を見渡して、下顎をジグザクと交互に動かしながら頷いて言った。
「なるほどねー、最近やけに部屋が整頓されて奇麗だったのはこう言う事?」
楓はゴクゴクと一気に炭酸ジュースを飲み干した。
コンッ!と音を立ててテーブルに突き立てると楓は苛ついた様に口を開いた。
「いつから?まさか正月から?」
「うーん……まあ……」はっきりしない返事を返すと、楓は嘲る様に笑った。
「はっ!マジか!そーいや美夏もお前も様子がおかしかったもんなー」
美夏の方を見ると、暇そうにカウンターに両肘をついて頬杖していた。
「でもなんでお前?しばらく美夏と交流なかったんじゃねーの?」
「うん、そーなんだけど……。いや、秋くらいに一回たまたま街で会ってからちょっと……」
「旅行の後?前?」
「えっ?……後……?」ドキドキして横目で美夏の方を見たが、美夏はふいっと後ろを向いてしまった。
「いやまーいいけどさ。でもお前美夏と付き合ってんなら——」楓は顔を近づけて美夏を気にする様に小声で言った。「ジェシカは?」
「だから……っていうか付き合ってる訳じゃないけど。……ジェシカの事はもう……」
「その気がないならハッキリ断れよ、可哀想だろーが。それとも何か、股にかけるつもりか?」
「……ジェシカの事は、連絡しない、じゃ駄目なのかな……」
「潔くねーな。男ならハッキリ断ってやるのも優しさだろ」
楓は基本遊び人のくせに、たまに男らしいことを言う。そう言うところは男として好きだ。
「というか、ジェシカの事ハッキリしてねーのに美夏のこと弄んでんの?」
楓が睨んだ。どうやら楓に取ってここが一番のポイントの様だ。
もしかしたら、楓は——。
問いつめられて言葉が出なくなって来た。
「……分かった、今すぐジェシカに連絡する……」
そう言って立ち上がるとすれ違い様、美夏が驚いた様な顔をしていた。
部屋の外でジェシカに電話をかけた。
出るか分からなかったから、メールにすれば良かったかとも思ったが、直接口で伝えるべきだと思った。
七回目のコールでジェシカが慌てた様に出た。
「もしもしっ?……春樹……?」
「うん、久しぶり。ずっと連絡返さなくてごめん」
「ううん、連絡くれて嬉しい。なんか今体調悪くてずっと休んでるんだって?」
「うん。ちょっと長期の療養が必要で……」
「そうなんだ。色々困ってない……?」
「大丈夫。友達が良くしてくれてるから……」
「……もし良かったら、今度お見舞いに行っても良いかな?何持って行く?春樹チョコ好きだよね?この前ニュージーランドに行った時のお土産、春樹に渡そうと思ってとってあるの!」
楓が言う様に、確かにジェシカは自分に好意を持っているのかも知れない声のトーンだった。
本当かどうかは本人しか分からないけど、ずっと言わなければならなかった事を言った。
「ジェシカ、旅行の時のことだけど……」
「——っ!……あ……、あのね……あたし……」
「申し訳ない事をしたと思ってるんだ。俺はあのとき、その、色々むしゃくしゃしてた時期で、結構酷い事してた。だからジェシカにもわざと傷つける様な事言って、あんなことして……今は後悔してる」
向こうから声が聞こえなくなった。
「ジェシカの事、好きだったのは事実だよ。でも、あのとき、好きだからした訳じゃなかったんだ……」
言葉に詰まった。
電話の向こうでは沈黙が続いていた。
「……今は他に好きな人がいるんだ……。俺は今その人に何もしてやれない状況だけど。……これ以上誰かを傷つけたくは無い」
改めてジェシカに詫びた。
「ごめん、ジェシカ。本当にごめん、って言っても許される事じゃないけど、ジェシカには早く良い奴と巡り会って幸せになって欲しい」
「……春樹の馬鹿!ほんと、ごめんじゃないよっ……」涙声だった。
「だったらなんでもっと早く言ってくれなかったの?私……春樹の事……」
ジェシカはそこまで言って言うのをやめた様だ。
「……ううん、なんでもない。……いいの、もうわかったから。……はあ、私ってホント男運ないのかな?あははっ……」
ジェシカは力なく笑った。
本当に申し訳ない気持ちで一杯で、胃が痛くなって来た。
「ジェシカ、お前は俺じゃ吊り合えない程良い女なんだよ。自信もって。絶対他のどんな奴より幸せになれるんだ。努力家だから。俺すぐ近くで見て来たからさ、お前が必死に頑張ってるとこ」
「はるき……!」泣いている様な吐息が聞こえた。
「ごめんな、ジェシカ。でも俺ずっと応援してるからさ。後輩なんかに負けんなよ。お前は一等輝いてる…って、ちょっと臭過ぎか」
そう言って無理矢理笑うと、ジェシカも鼻をすすって笑った。
「はー、やっぱり言っとこ……。……春樹、私春樹のそういうところ、凄く好きだった。思い返せば仕事とか恋愛で落ち込んだ時もいつも春樹が側にいて励ましてくれてたもんね。柏原と別れた後すぐ連絡くれてまた会えたとき嬉しかったよ。明るく振る舞ってたくさん笑わせてくれた。だから私気がついたら春樹のこと好きだったの。でも……」
ジェシカが深呼吸した。
「でももういいや!ありがと春樹。私この前春樹に色々言われてショックだったけど、でも感謝してるの。おかげで目が覚めたよ。色んな事誰かのせいにして逃げてるだけだったんだよね、私」
「ごめんな……気持ちに応えてやれなくて……」
「ううん、いいの。この告白、ただのけじめだから。自分自身へのけじめ」
「うん……そっか……」
その後ジェシカとはお互いにこれからの健闘をたたえて電話を終えた。
はあぁ~っ!と大きく息を吐いて両手で顔を覆った。
——この告白けじめ。自分自身へのけじめだから。
外見だけじゃなく、ジェシカのこう言う強さに惹かれたんだよな。
いつの間にかジェシカは大人になっていた。
このところの自分とは大違いだ。自分はどんどん退化している。
もっとガキだった頃の様にすぐキレたり、やる気を無くして病気になって働けずに女の臑をかじって……。生きる価値無い。そう思うと凄く落ち込んだ気分になった。
部屋に戻ると、心配そうに楓が声を掛けてきた。
美夏はちらりとこちらを見るとすぐに目をそらして、夕食の準備を始めていた。
「ちゃんと話したか?」
「ん……。ちゃんとけじめつけてきた」
「……よし」
だがしかし、もの凄く気分が落ち込む。
無言で座り込むと、楓が声を掛けてきた。
「……お前本当に美夏とは付き合ってないのか?」
美夏を見た。ギャル服にエプロンの後ろ姿だ。
「あぁ……」
「じゃあなんで美夏、エプロンして料理作ってんの?」
なんでって言われると、返答に困った。
「……俺が病気になって、同情してくれてんだよ。ほぼ毎日来てくれてる……」
「毎日っ!?」流石に楓も声を上げた。
「同情じゃ、ねえだろそれは。完全に通い妻じゃん!結局お前が否定してるだけでデキてんだろ?」
楓が声を荒げると、エプロン姿の美夏がやってきた。
「ご飯、食べるよね?あと三十分待ってくれる?ご飯炊けるまで」
「お、おうっ!」楓が狼狽えた様に答えた。
振り返って、台所の方に戻ろうとして、美夏が足を止めた。
振り向き様にこう言った。
「付き合ってないのは本当だよ。キス以上の事はしてくれないの」
「って、キスはしたのかよ!」楓がむりくり突っ込んだ。
「……不可抗力、でもないか……」一度目は自分からキスしたもんな。
「でも手は出して無い」
「ウソ言えよ、毎日会ってて何も無いとかありえねぇ!」
「春樹は、手を出せないんだよ……」
美夏がぽつりとこぼして向こうに戻って行った。
「手を出せないって、インポでもあるまいし……」
ドキリとして答えた。
「……それが、そうでもない」
「は?だってお前ジェし——」声を潜めた。「ジェシカとやっただろ」
楓にはそろそろ本当の事を言うべきだと思った。
「……俺さ、うつ病なんだ」
「——は?」
やはりうつ病と言ってもよくわからないだろうな。
「薬でさ、性欲なくなっちゃうんだ」
「は?マジっ?」
頷くと楓は再び、マジ?と言ってにわかに信じられない様子だった。
「じゃあ美夏なんでお前なんかと一緒にいんの?使い物にならない訳だろ?」
インポとかやったとかやらないとか、使い物にならないとか、正直そう言う事を言われてさっきからどんどん心が重くなるのを感じた。
勃起不全でも全然意欲すら無くなってしまってよりはまだマシだった。
最近は美夏のパンチラを見ても何にも思わない。
なんとか必死に楓に返答した。
「そうなんだ。馬鹿だよな。さっさといい奴見つければ良いのに」
思いついて提案した。
「……お前、美夏の事どう思う?最近良い女になったって言ってたじゃん」
「ばっ……!うるせーな」楓はあからさまに反応した。
きっと美夏のこと好きだな。
楓だったら良いな。
浮気とか手の早いとこさえ自粛してくれれば、根は凄く良い奴だから。
男気もあるし、精力もあってきっとこのまま商社マンになってバリバリ働ける。
美夏の事守ってやれる。
「……お前が、美夏の事守ってやってくんねぇ……?」
心からの願いだった。
「ふざけんな。男のくせにそんな泣きそうな顔で頼むんじゃねえ」
ごもっとも。情けないのには容赦ない。
食事の準備を手伝って、三人で夕飯を食べる事になった。
「いただきまーす」
「材料足りて良かった。あ、楓ビールとか飲みたかったら自分で買って来て?うちら飲まないから」
「おー、じゃあちょっと後で行くわ。とりあえず飯!ハラ減った!」
美夏が丹誠込めて作ってくれたすきやき。美夏の少し甘めの味が好きだ。
でもどうにも食欲がわかなかった。
暫くして、美夏が心配そうに声を掛けてきた。
「……春樹、大丈夫?食欲無い……?」
「……ん……ごめん」
「疲れちゃった?」
「あぁ……。今日ちょっと色々あったから……」
その間楓は自分の分も食べる勢いでご飯とおかずを交互に口に入れていた。
「無理して食べなくていいよ?」
美夏が優しく腕に触れた。
「何言ってんだよ、春樹。美夏がわざわざ作ってくれた料理だろ?無理にでも食べろよ!」
楓のでかい声でお説教を喰らった。うんざりした。
すると美夏がいいの、と言って楓を睨んだ。
「いいよ、無理しなくて。明日食べてくれれば……」美夏の優しい声が心にしみた。
「はあ?マジでぇ?おこちゃまかよ。美夏そんなに甘やかすなよ、春樹が腐っちまう。まま疲れたぁ~、食欲なぁ~い、食べたく無ぁ~い。はいはい良いのよはるきちゃん良い子ねぇっ」
「楓、いいから黙って。それ以上言うなら今すぐ出てって」美夏が強めに叱咤した。
「えっ、美夏?」楓は吃驚した様に肩をすくめた。
美夏と真剣に見つめ合い、揺るぎない瞳の力に楓は根負けした様に、すんません、と謝った。
美夏は自分の為に、卵とすきやきの具を細かくした物と一緒にご飯を鍋に入れて、おじやの様な物を作ってくれた。すると、少しだが食べれる気がしてそれを戴いた。
「……マジかよぉ……」
楓はショックを受けた様に首を傾げていた。
「美夏を変えたのって、お前だったんだな……」
えっ——?それってどういう——。
結局楓は夕飯を食べると、今日はもう帰るわ、お邪魔様!と言って帰って行ってしまった。
三月に入ると、暖かい日も続き、確かに調子がみるみる良くなって行った気がした。
「そろそろ短時間のバイト始めようと思う」
あのオッサン医者に相談した結果、短い時間なら無理をしない程度働いてみるのも良いかも知れないと言われた。
「無理しないでね」美夏は笑って賛成してくれた。
それで近所のスーパーのレジ打ちのアルバイトが募集されていたので、一日四時間の短期アルバイトを始める事にした。
四時間なんて、昔十二時間労働当たり前だった頃余裕に感じていたが、久しぶりに外に出て立ち仕事をすると、終わる頃には身も心もくたくたになって歩くのも精一杯になっていた。
あれからたった二ヶ月半、されどもこの決して短くは無い月日、もう何ヶ月も経ったのではないかと思うくらい色々な事があった。
確かに今の自分は以前の自分とは全く違うという事を認識しなければならなかった。
以前なら頼まれて当たり前にできていたことが、上手く出来なくてもどかしい気持ちになることもあった。
前の自分に戻りたい、そう焦る気持ちもあったが、美夏に強く言い聞かせられていた。
「前出来ていたからって出来ると思わない事。何かちょっとした事でも出来たら自分を褒めてあげて?」
やはり情けなさも感じたが、気持ち的にだいぶ前向きになれるようになってきて、とりあえず今は頑張り過ぎないで頑張ろうと思うことにした。
そして、美夏に助けられて三ヶ月。心のほんの奥底に、ささやかな希望と言うか叶いもしない欲みたいな物が出て来た。
もしも出来る事ならば、いつか美夏と結婚したい。
こんな事は一人の時でも絶対に口に出来る事じゃなかったが、それでもひっそりと咲くその心の花をそっと大事に大事にしまっていた。
美夏はネットや本で調べてうつ病の事を良く理解してくれていた。
焦らせる様な事は言わないし、失敗しても強く責めたりはしなかった。
ただ、最近は次のステージに来ている様で、積極的に物事に取組もうとする自分の意志を尊重してくれている様だった。
自意識過剰かも知れないが、美夏の愛を感じた。
そんな中、月末になって美夏が慌てた様に賃貸物件の情報マガジンを読みあさっていた。
「なに美夏、引っ越すの?」
「うん、実は今月でマンションの契約切れるの」
「え?更新しなかったの?」
「うん」
「今月って、もうあと三日しか無いよ?引っ越し間に合う?」
「ん~、わかんない。なんかバタバタしてたらすっかり月末になっちゃって」
美夏が見ている物件はどれも美夏に似つかわしく無い様な賃料の安い狭いアパートばかりだった。
「え、美夏、こっちの方がもっと良い部屋いっぱいあるよ?」
別の情報誌を差し出すと、それは契約料とか高いから、と言ってはね除けた。
不安になった。
もしかしたら自分のせいで美夏の負担が大きくて、引っ越しの費用すら捻出するのもやっとなのではないか。
「美夏……もしかして、お金足りないんじゃ……俺のせいで……」
「……ストップ!」美夏が急に口元に手を当てた。
「はい、俺のせいとか言わないの。俺のせいじゃないよ~」美夏はそう言ってまた雑誌に目を戻した。
体はだいぶ元気になったと言っても、まだほんのちょっとした事でも一気に死にたくなるまで落ち込むので、美夏はなるべくそう言う事を避けようとしてくれていた。
「だって美夏、こんな安いアパートばっかチェック付けて……。この部屋より安いじゃん。美夏ユニットバスじゃお風呂入れないよ?」
「そーなんだよねー。部屋は狭くても良いからトイレ風呂別でもっと安いとこないかな?」
「でもあんまり探してる時間ないんじゃない?」
「そうだよ!やっぱりもうここでいっかぁ~……」
美夏がペンをトントンと突いたところは比較的新しい築年数の六帖一間ユニットバス付きで家賃はほぼここと同じくらいだった。
「それならこっちの方がいいんじゃ」
隣のページを指差すと、それはだめ、と言われた。
「ここから遠いもん」
「……え?」
美夏はわざわざこの近くに引っ越して来ようとしている事を悟った。
やはり毎日ここまで通うのは遠いし時間も電車代も相当かかるのだろう。
自分がまたどんよりとした空気を醸し出していると、美夏はそれを察してトン、と肩を軽くぶつけてきた。
「もっと春樹と一緒に居たいの。だから遠いと移動の時間勿体ないんだぁ」
美夏の優しさに心がとろけそうだった。
その翌日、美夏が物件の問い合わせをすると、その物件はもう売れてしまった後だった。
「どうしよ、時間無いのに。明日には確実に部屋を明け渡さないといけないの。引っ越し業者にもう頼んであるのに」
焦る美夏に提案した。
「それならとりあえず、荷物はまとめてここに運んでもらったら?急いで探してもいいとこ見つかんないと思うし……」
「えっ?でも結構な荷物だよぉ?」
「俺の不要なもん捨てれば良いよ。こんな狭いとこでしばらく寝泊まりは嫌かも知れないけど……」
と、言うか一番の不要物はこの俺だよな——。
自分の言った事にいちいち落ち込んでしまうのはうんざりだったがどうしようもなかった。
「マジで?じゃあもうそうさせてもらっちゃおうかな。時間無いし」
美夏が頷いたので早速ゴミ袋を取り出してスチールラックにあった荷物を手当たり次第放り込んだ。
「なにやってんの?本とかCDまで捨てちゃう事無いじゃん」
「うん、でもなんかもう必要ないし……」
いつのまにか暗くなっている自分に美夏は少し困った顔をして笑った。
「何なら俺も一緒に……」
超マイナス発言を連発する自分の頭を美夏は優しく撫でて、抱きついてきて笑った。
「……じゃあ私も一緒に……」
そんな美夏の態度に日々救われていた。
美夏は結局荷物を自分の部屋に運んだ。
部屋の半分は荷物で埋め尽くされ、さてどうしたものかと悩んだ。
居住スペースは二人で三帖半。夜はひとつの布団で寝るしかなかった。
「毎日春樹と一緒に寝れるなら、ずっとこのままでもいいかな」
なんて冗談を言っていた。
でも、じゃあいっそこのまま一緒に住む?と冗談を返したら、美夏は真顔で首を振った。
「なし崩しで同棲は嫌なの。だってまだ春樹に彼女にしてもらってない」
その一言は相当堪えた。
例えば自分が美夏の立場だったら、一体どれだけ待たせるんだ!と怒り狂ってしまいそうだ。
ハッキリとしない関係のまま何ヶ月も一緒に生活をしている。泊まりはしないが毎日ほぼ同じ物を食べて半同棲みたいなものだった。
四月に入って、気がついたら自分の誕生日が訪れていた。
「春樹、誕生日おめでとう!」
真っ先に言ってくれたのは他でもない美夏だった。
日付が変わると同時に、どこで買って来たのかオシャレなホールケーキを運んで来た。
もう二十二になるんだなぁ、と感慨に耽った。
一年前は楓たちとカラオケに行って祝ってもらったが、今年はどこかに行かなくても十分だった。
ブルーベーリーやカシスの乗ったヨーグルト風味のケーキはおいしかった。
朝になって珍しく母親にこちらから電話をかけた。誕生日くらい、たまには声を聞かせてやりたくなった。
「春樹?どうかしたの?珍しい!」
「いや、今日俺誕生日なの」
「知ってるわよ!誰が産んだと思ってるの?」
思わず笑った。今日は気分がめちゃくちゃ良かった。
母親に誕生日おめでとう、と言ってもらった。
「就職決まったの?今度いつ帰ってくるの?」
「……うーん」
そう言う話題になると急に気分が重くなった。どうしてもこれはしょうがない。将来の話とか、お金の話とかされると無条件に落ち込んでしまう。
「まあ、元気にやってるならそれでいいけど。まあ元気でがんばりなさいよ?」
「……うん、ありがと」
すんなり言葉が出て来て自分でも驚いた。
母親に『ありがとう』なんて、言ったの初めてかも知れない。
母親も驚いた様だった。
「……ま、まあ、そう言う事よ。じゃあね」
響く終話音に、思わず微笑みかけた。
すると、いつの間にか聞いていた美夏も嬉しそうにニヤリとはにかんだ。
「楓たちが誕生日祝いしてくれるって言ってるんだけど、どうする?」
「え?」
「無理して行かなくても良いと思うけど。体調とか気分はどう?」
「あー、でも今日はかなり調子いいんだよね」
「そう?じゃあ行ってみちゃう?」
その日は日曜日で二人ともバイトは休みにしていた。
結構意気揚々で出掛けたのだが、皆の集まるレストランカラオケに着くと、急に緊張感が増してそわそわした。
美夏に大丈夫?と心配されたが、今更戻る事も出来ずに強がった。
美夏もオシャレに気合いが入って久々の遊びにテンションが上がっているのが分かった。
だから美夏の残念そうな顔は見たく無かった。
部屋に入ると、クラッカーとか鳴らされて正直心臓が飛び出しそうになって驚いた。
「春樹誕生日おめでとー!」
そこには大学時代仲の良かった奴らが7、8人集まってくれていた。
早紀や美宇司たちもいて、旅行以来だねー?と早紀が相変わらずの萌え声で笑った。
必死に笑顔を取り繕って挨拶を交わした。
内心ドキドキハラハラ不安が止まらなくて、手の平に大量の汗をかいていた。
あんなに気分が良かったのに、その会は楽しいというより、怖いだった。
たくさんの料理が運ばれて来て、アルコールとか飲まされて、無理矢理カラオケ歌わされて必死に笑って必死に会話を聞いているフリをして。
みんな楽しそうに笑っていた。美夏も楽しそうに笑っていた。
だんだん気持ち悪くなって吐き気がした。
突然肩を強く叩かれた。
「おい聞いてるのかよ春樹!お前の事だぞ」
「えっ?ごめん、聞いてなかった……」
「いつ空いてんの?」
「な、何が?」
「おいおい。今度またみんなでキャンプ行くぞって話じゃん。来月のGW何日から都合いい?」
——言葉が頭に入って来ない。
あー、とか、えっと、などと言って場を繋ごうとしたがそれ以上言葉が出て来なかった。
美夏に助けを求めようとしたが、美夏は以前紹介された華穂という子と楽しそうに話している。
「……ごめん、ちょっと俺、トイレ……」
そう言って立ち上がると立ちくらみがして、それでもバレない様に必死に部屋の外に出た。
洗面所の場所を通路の壁に寄りかかりながら必死に探した。
目の前がぐるぐると回っている様な気がした。
目の焦点が合わない。
なんとか辿り着いたトイレの前で、自動販売機があったので小銭を取り出して緑茶を買った。
それを飲んだら少しは落ち着くかと思ったが、胃から逆流して、トイレに駆け込んだ。
先ほど無理矢理食べた物を全部吐き出すまで、何度も何度も苦しい思いをした。
余りの苦しさに涙とよだれがごっちゃになって、ようやく落ち着いた頃にトイレットペーパーで顔を拭いた。
結構時間が経ってしまっていたので慌てて立ち上がって何事も無かったかの様に表情を整えた。
かなり無理をしていた。
すると慌てて洗面所に向う美夏と華穂とすれ違った。
「……どうしたの……?」平静を装って笑いかけると、「ジュースこぼしちゃったの!これ高い奴なのに!」と走り去って行った。
そのまま部屋に戻ろうとすると、少し開いたドアの隙間から会話が聞こえた。
「っていうかマジで体調悪いの?全然元気そうじゃん」
「自殺しかけたとか、本当なの?」
「狂言自殺じゃね?死にたいとか言って美夏の気を引こうとしただけかもよ?」
「働けないからって女に金遣わせるとか最低じゃん」
「いやでもさー、体的には元気な訳でしょ?頑張れば普通に働けんじゃん?」
「最近多いらしいよね。従兄もそれで会社休職してるけど、普通に元気だし嫌みとか言うし、しかも給料もらえるし、ただの怠けって感じ」
「頑張れって言ったら駄目らしいよ、うつ病患者って」
「大学の授業もバイトもヤダー。俺頑張りたく無い。頑張れって言わないでっ……!」
「俺もうつ病になろうかな。……はははっ!」
皆の笑い声が聞こえた。
「春樹?入らないの?」
後ろで声がして、美夏が扉を開けた。
すると笑い声が止んで、みんなの表情が一気に怖くなった。
美夏に背中を押されてもぴくりとも動けなかった。
ああ、美夏が心配する。何か言わなきゃ——。
「……あー、俺、ホント最低だよなー……。……は……」
「……春樹?」
堪え難い沈黙の中、また吐き気がして口を両手で覆った。必死に飲み込む。
手を離して冗談でも言えば何事も無かったかの様に、さっきみたいに皆また笑いだすかな?
「俺、やっぱり死んで来るね……!」
口に出た言葉はそれだった。
とっさにその場から走り去った。
もうとにかく早く!早く!その場から逃げた。
遠くで、待ってぇ!と叫ぶ声が聞こえた。
おかまい無しに店の外に出て、必死に左右を見渡した。
適当に左に曲がって、また左に曲がり、今度は右に曲がった。
人通りの無い入り組んだ狭い路地。
立ち止まった近くの自動販売機の側に空瓶が落ちていた。
それを拾って叩き割ると、破片の一部を手にした。
それをしっかり握った。
きっと失敗なんかしたらまたわざとだって思われる。美夏が惨めになる。
膝をついてグッと手に力を込めた。
頸動脈に当てて刺そうとするが、手の平の血で滑ってなかなか上手く行かなかった。
焦った。——なんでだよ!焦って破片を落としてしまった。
もう一度拾って試みようとしたら、急に人影がやってきて驚いてしまった。
咄嗟に立ち上がって別の場所へ移動した。
何か無いか——!
ぐるぐる見渡した。
とにかく探しながら大通りに出た。
街中に自殺出来る様なものは無かった。
道路の反対側にある割と高めのオフィスビルが目に入った。
あそこから飛び降りよう。
駆け寄ろうとした。
するともの凄い勢いで車の急ブレーキが聞こえて、振り返るとおじさんが青い顔でこちらを見ていた。
そのまま道路を渡ろうとしたが、車通りが多くてなかなか渡れなかった。
仕方なくそのまま突っ込もうとした。
すると車が律儀に急ブレーキを踏んで、その後方車両が危うく玉突き事故になりかけた。
大事になるのが怖くなって、そのまま道路の反対側に逃げた。
運悪く、たまたま駐禁の切符を切っていた警察官に声を掛けられた。
警官は両手が血に染まっているのを見て、犯罪者だと思ったらしく、ホルターから拳銃を取り出して自分に突きつけた。
「手を挙げて、この車にうつぶせになれ!」
そのまま逃げても良かったのだが、もう疲れてしまい、諦めて大人しく血だらけの手を挙げた。
——いっそその拳銃で撃ってくれれば良いのに。
「なんだと?」
思った事をそのまま口にしていたらしく、警官は怪訝そうに首を傾げた。
挙げた手を下ろし、そのまま膝から崩れた。
その後警官はゆっくりと近づいて手を見せろと言った。
——自分の血です。
——何故だ。
——死のうとした。
薬でもやってるのかと聞かれたので首を振った。
警官は拳銃をしまい、もう一人の警官に事情を説明していた。
そのまま警察車両で保護される事になった。
何度かポケットに入れていた携帯のバイブが鳴ったが見ようとはしなかった。
近くの交番に連れて行かれて、名前と生年月日を尋ねられた。
「今日が誕生日じゃないか。何もこんな日に死のうとしなくても……!」
警官たちは同情してくれていた。
静かに涙が止まらなかった。
背中をさすられて、同情されるのが情けなくて嫌だった。
手の平を応急処置してもらい、心配だからと病院まで送ってもらう事になった。
日本の警察ってこんなにおせっかいなんだな。
死にたい奴は勝手にのたれ死にさせておけばいいのに——。
また涙が流れた。
車の中で、巡査部長さんに励まされた。
色々辛い事もあるだろうけど、まだ若いんだから、何もかもお終いだと決めつけてしまう必要はないんだよ。
人生には絶対まだ何か良い事が残ってるんだから。
お説教という感じではなく、本当に心から励まそうとしてくれているのが分かった。それでも、耳が痛くて辛かった。
連れて行かれた総合病院では救急外来に通されて、看護士に手当をしてもらった。
手の平の傷自体は軽い物だったが、頸動脈の部分に小さな刺し傷があったので、すぐに帰る事は許されなかった。
その頃何度も何度も携帯のバイブが鳴った。
「ご家族とかご親戚とか、親しいお友達とかは近くにいないの?」
少し気まずそうに訊かれて、首を横に振った。
でも数十回目の着信のバイブ音に看護婦さんがしびれを切らしてポケットから携帯を奪った。
「ごめんなさい、出るわね?」
そう断りを入れて看護婦が電話に出ると、美夏のキンキンとした声がここまで聞こえて来た。
しばらく看護婦が事情を説明していていると、別の看護婦が水のペットボトルと何かの錠剤を持って来て、ベッドに座らせた。
空腹じゃないかと訊かれ、首を振るとなぜかチョコレートをくれた。
これを飲んで暫く横になって、と言われたので言う通りに従った。
鎮静剤だったようで、少し気分が落ち着いて来て、うとうととした。
暫く寝て少し意識が戻ると、治療室の外で美夏の声が聞こえた。
今薬を飲んで寝ているので、もう少し休ませてあげてください——。
美夏には会いたく無かった。
また迷惑をかけてしまった。
あの後皆はどう思ったろう?
死んで来る、なんて宣言してきっと頭がおかしい奴だと思われたに違いない。
いっそ本当に頭がおかしくなれば良かった。
死ねないで病院にいるなんて、これをまた知られたら色々言われるんだろうな——。やっぱり今からでも死にたいな——。
頭がズキズキした。
たまり兼ねて起き上がると一瞬ズキズキが強くなってつい呻き声が漏れた。
カラリと扉が開いて、看護婦が、気分はどうですか?と尋ねて来た。
外に美夏の姿が見えた。
ここに長くいても意味が無いので立ち上がって外に出た。
すると美夏の顔は涙で腫れ上がっていた。
警官はもう仕事に戻っていていなかったので、看護士にお世話になりました、と言って頭を下げた。
美夏はタクシーを呼んでくれていた。帰り道もずっと2人とも会話は交わさなかった。
もう夕方を過ぎて夜になってしまった。
今日が誕生日だという事もすっかり忘れてしまっていた。
部屋に入ると美夏は真っ先に、ゆっくりと後ろから抱きしめてきた。
「……ごめんね、春樹ぃ~……」絞り出す様な声だった。
「私が皆を誘ったばっかりに……。春樹に無理させてるのも全然気づかなくて、浮かれて……!」
美夏はしゃくり上げる様に泣いていた。
——皆に聞いたの。
春樹の事誤解して悪口言ってるの、春樹が外で聞いてたって。
私おしゃべりに夢中で春樹が途中で抜けてるの気づかなくて、春樹がなかなか帰って来なかったって、楓が言ってた。
春樹が飛び出してから追いかけたけど、どこにもいなくて、皆にも一緒に探してもらったけど見つからなくて——。
電話しても全然通じないしさ。
警察に電話したら、何かあれば通報が来るからとか、言っちゃってさ。
何かあってからじゃ意味ないのに——!
たくさん電話してやっと繋がったよ。
看護婦さんに聞いたよ。
最初空瓶で首を切ろうとして上手く行かなくて、道路に飛び出して車にはねられかけて、本当はビルの屋上から飛び降りようとしてたのを、警察の人に保護されたって。
凄いね、春樹はそんなにしてまで死のうと思ったのに、全部死ななかったんだね。
まだ死んじゃ駄目ってことなんだよ——。
話を聞いてたらこちらまで涙が止まらなくなった。
美夏の腕を掴んで美夏の方を向いた。
「……俺の方こそ迷惑かけてごめん。……もう皆とは会えないな……。俺のせいで美夏も惨めになるな……」
「私は全然平気だよ……?」鼻をすすりながらこの期に及んで美夏は笑った。
「春樹がまだ生きてくれてるから。私はまだ幸せでいられる……」
美夏の前髪をそっと指ですくった。
「目を閉じて……?」
そう言うと、美夏はゆっくりと目を閉じた。
美夏の額に唇を寄せて、口づけをした。
自分にはそれが精一杯だったから。
でも美夏は額から離した唇を、自分の顔を掴んで今度は唇に合わせさせた。
唇と唇を合わせるだけのキスでも、こんなにも心を通わせる事が出来るんだなと感じた。
「ちょっと元気になったからって、やっぱ油断しちゃ駄目なんだね」
今夜はレトルトのリゾットを食べてお終いにする事にした。
トイレで吐いた後チョコレートくらいしか口にしてなかったから、なにか胃に入れておかないと行けなかった。
「体が元気になると、今日みたいに強行出来てしまう。本で読んだ事あったのにな……」
美夏は自分の至らなさを並べて行った。
「今日はとっても調子が良さそうだったから誘ったけど、却って裏目に出ちゃったね。無理できちゃうから無理しちゃうんだもんね」
美夏は美夏自身をひたすら責めていたが、責めるべき点は自分にもあった。
「ゆうべ、薬を飲み忘れてたんだよ」
処方は始めの頃に比べて変わったが、抗うつ剤と呼ばれる安定剤を飲ま無かった自分にこそ非があった。
後で知った事だが、抗うつ剤はうつ症状を改善する物ではなく、波幅をなだらかにして、ガクンと落ちる事が少なくなる様にするためのものだった。
だから朝はとてもすっきりと元気な気分だったのに、振り幅が一気に逆転して自殺未遂を図るところまで落ちてしまったのだ。
「じゃあ今日は忘れずにちゃんと飲まなきゃね?」
そう言う美夏の、洗い立ての髪に触れて臭いをかぐった。
このところ臭いに敏感になった。シャンプーの良い香りがする。
先ほど鎮静剤をもらったからか気分は落ち着いていた。
それでもいつもと違う不思議な高揚感を抱いていた。
それが何なのか何となく思い出していた。
薬を飲んだと偽って、自分もシャワーを浴びた。
右手の平の傷に水が入り込まない様に気を遣った。
利き手が使えないと不便だ。
美夏と同じシャンプーの臭いがして高揚感が増した。
もしも明日こそ、本当に死んでしまっても、美夏を悲しませる結果になっても、それでもどうしても確かめたい事があった。
あの、逃げ出したくなる様な緊張感とは、また異なった。
いつもの様に同じ布団に入る事すら躊躇した。
あの感じが蘇る感覚がした。
薬を飲むと、うつ症状は抑えられるが、それと同時に性欲までも失ってしまう。
体がどうこうというより、気持ち自体を持たなくなってしまうのだ。
だからずっと、美夏にはきっと寂しい思いをさせて来たと思う。
誕生日に逆にプレゼントという訳ではないが、少しでも、美夏を喜ばせてやりたかった。
美夏は今日泣きつかれたのか、すぐに寝そうだった。
でも、今日を逃せばもう次はいつになるか分からない。
半身を起こし、横になる美夏の頬に触れた。
「……?どうしたの……?」
眠そうに掠れた美夏の声。
ゆっくりと頬から指先を美夏の唇に持って行った。
美夏は驚いた様に目を開いた。
暫く美夏を見下ろしながらするりするりと唇をなぞった。
指先に美夏の柔らかい唇が触れ、徐々に気持ちが昂って来た。
美夏の右目の目尻をなぞった。
小さい黒子——。
右耳をなぞって耳の後ろに手の平を回した。
——どんなにこの時を待ち望んだのだろう。
美夏の頭を支えて彼女の唇にゆっくりと口づけた。
すると、美夏の体は弾ける様にそれに応えた。
心と体って一致するとこんなにも気持ちの良い物なんだな。
キスだけでも随分と時間を掛けた。
美夏のつるんとした舌の感触が気持ちよかった。
キスが一段落すると、前もって言っておかなければならなかった。
「あのさ……」
「うん……」
「その、上手く出来るか分かんないんだけど……」
「いいよ……!……上手く出来なくてもいい……。でもどうして……?」
「ごめん、さっき薬飲まなかったんだ。終わったらちゃんと飲む。でも、多分今日しか出来ないから……」
「無理しなくても良いのに……!」
「美夏がまたしたいって思っても、きっと出来なくなると思うよ……。また寂しい思いさせると思う。それでもいいかな……?」
美夏は少し涙目になって、いいよっ!と笑った。
美夏の体は柔らかくて気持ちよくて、抱き合ってるだけでも気持ちがよかった。
男って基本絶頂が全てみたいなところがあって、不燃焼だと却ってストレスが溜まってしまう事もあったが、今の自分にはこうして誰かと体を合わせる事が出来るだけでも結構な充足感だった。
こんなにも時間を掛けてしたのは初めてで、殆どが美夏への愛撫だった。
普段のお礼の気持ちみたいなものもあって、気持ち良さそうな表情をする美夏の顔を見ているだけでも満足感みたいな物を得られた。
時間を掛けた割に最後はあっけなくて、それでも勃起出来て最後まで出来たのは奇跡的だった。
途中で少し疲れて、自分は無理だなと思っていたのに。
終わった後美夏はもう寝そうだった。自分も疲れ果ててそのまま意識が朦朧とした。
でも美夏は眠たそうに唸りながらも、力を振り絞って起き上がった。
気がつくと、美夏に口移しで薬を飲まされていた。
温い水と一緒にそのまま飲み込んで目を閉じた。
美夏もお役目ごめんとばかりに横に倒れる様にして眠った。
五月を過ぎ、レジ打ちのバイトもかなり慣れて来て、後輩が入って来た。
大学生になり立ての若い女の子で、自分も入っても間もないのに主任から色々教えてあげてと頼まれた。
「若い方が話易いでしょ?」そう言う考えの元だ。
後輩の女の子は下の名前がミカで吃驚した。
でも割とありふれた名前だ。
打ち解けて仲良くなった頃、帰り道に少しお茶した。
「どう?慣れた?」
「まあまあです。でも結構忙しいんですね」
「この辺の主婦がしょっちゅう買いに来るからね」
ふーん、とミカちゃんは喫茶店の外の様子をキョロキョロと眺めた。
「そういえば、春樹先輩は彼女とかいるんですかぁ?」
性格まで美夏に似てるのか積極的に質問された。
「いるよ。……今一緒に暮らしてる」
「……。そうなんですかー」
思わず笑いそうになった。今明らかに少しチッ、て顔した。
大人しそうだが見掛けによらず結構気が強いタイプの様だ。
「実は……美夏って名前なんだ」勿体ぶって教えた。
「えっ?私と同じ名前……!」
「そう、少し吃驚した」
「へー、そうなんですかぁ。ちょっと会ってみたいなぁ。先輩の彼女ってどんな人ですか?」
「うーん……」その質問には少し考えて答えた。
「頑張り屋さん、かな?」
会いたければ今度一緒に買い物に来るよ、と伝えた。
バイトから部屋に戻ると、まだ美夏は帰って来ていなかった。
今日はバイトで遅くなると言っていた。
買って来たペットボトルの水を一口飲み、冷蔵庫にしまった。
一人暮らしのミカちゃんは、最近料理に目覚めたと豪語していた。
簡単に作れるレシピを教えてもらったので、今日はたまには料理を作ってみようかな、と考えた。
しかし調理器具や調味料はどこにしまってあるのかさっぱりだった。
色々探し当てたが、包丁だけは見つける事が出来なかった。
誕生日の自殺未遂以来、今度は刃物という刃物を隠しているのかも知れない。
「百円ショップの包丁は超切れ味悪いよ」
美夏がそう言っていた通り、確かに近所の百円ショップで購入してきた包丁は切れ味がよくなかった。
それでも無いよりはマシと、バラ肉や野菜を切った。
切りながら、きっと美夏は自殺に使わせない様にそう言ったんだろうなと思った。
出来上がった料理は見た目いまひとつだった。
一応美夏の分もと思って多めに作ったつもりだったが、分量が分からなくて大量になってしまった。
しかも食べてみると、味も微妙だった。
食べれない事は無い。しかし、美味くは、無い。
まあ、普段料理しない奴が思いついて作る料理なんてこんなものか、と生ゴミに捨てた。
勿体ない。美夏に任せたらもう少し味付けを整えてくれたかも、と後悔した。
帰っててきた美夏は案の定、
「捨てるなんて勿体ない!それなら私が味付け直したのに!」と叫んだ。
「っていうか、春樹の手料理、食べたかったなぁ!」
「悪い悪い。でもマズかったんだよ」
「まずくてもいいのーっ。……でも春樹偉いじゃん。自分で料理作ろうとするなんて。いっそ料理教室とか通ってみたら?」
美夏は今までした事の無い様な新しい事に挑戦する事を勧めた。
前は出来たのに、とか比較しなくて済むからだそうだ。
音楽とか本とかも、昔の記憶と密接する様な物はなるべく置かなくなった。
自分があの頃はどうだった、とか思い出して憂鬱になるのを減らしたいのだそうだ。
新しい趣味として、最近は読書をするようになった。
しかも漫画じゃなく小説だ。自分がハードカバーとか驚きだ。
古本屋で中古のハードカバーを買って、読んだらまた売ることにしている。
このところ雨が続く。梅雨入りはまだらしいが、やはり天気が悪いと少し陰鬱とする。
そういう時は美夏のオススメのリラクゼーションソングを流しながら推理小説などを読む。
なんとなく、昔の名作から攻めてみた。
江戸川乱歩にアルセーヌ・ルパン。金田一シリーズ、意外とこれが面白い。
バイトも割と順調で、かなり元気を取り戻したが、完全に元に戻るにはまだほど遠い。
ひょんな事で急に落ち込む事はしょっちゅうだし、バイト中に変な客にいちゃもんつけられると、時々どうしようもなく泣きたくなる。
そう言う時は美夏にメールして、出来る限り電話してもらうようにした。
「じゃあ今日は帰ったらラーメン食べに行こ」
美夏の声を聞くと少し元気になる。
今の人生に取って、美夏は希望の塊だった。
美夏は最近バイト帰りに風呂に入って帰る事が多くなった。
美夏は入浴好きなのだが、この部屋はユニットバスで、風呂の湯を溜めて入るのは結構困難だった。
バイト先の近くにあるスパが月会員になると二千円でいつでも入浴が出来るのだ。美夏はそこに目をつけた。
「でもまたメイクし直さないと行けないのは面倒くさいよ。最近はせっかくお風呂に入ってもまた汗で汚れちゃうしね」
今度近くの〝戸沢湯〟で銭湯デビューを果たそうか、二人で検討中だ。
「……そろそろ薬の量減らしてみましょうか。今度は二日に一錠で様子を見ましょう。調子が良ければ三日に一錠でもいいです」
毎月一回の通院になった病院で、医師にこう告げられた。
それは凄く嬉しい出来事だった。
毎日飲まなきゃいけない不安から、少し解放された。
「君は結構回復が早い方だと思うよ。献身的に世話をしてくれる彼女のおかげだね」
恐らくうつになってから一年が過ぎていた。
去年の今ごろはもう大学も中退して、何もかもやる気が無くなっていた。
人生に絶望して、毎日口を開けば死にたい死にたいと呪文の様に唱えていた頃だ。
今も正直死にたいと思わない日は無い。
美夏が知ったらショックを受けるかな。でも、きっと美夏も相当辛い時期があったと思う。
心の闇なんて、きっと他人に分かる訳が無いんだな。
「大学で、新しい学部の先生に言われたの。お前悩みなんてないだろうって。ちょいヒドくない?」
美夏は相変わらず他所でも明るい性格を保っている様だ。
「それって、ある意味凄い証拠だよ。美夏って苦労とか外に出さないもんな」
「えーっ?そうかな?でも私だって、結構色々悩んだり考えたりしてるよ……?」
「知ってるよ。だから偉いなぁって思って」
今年に入って、美夏が自分の事で泣いているところを見た事が無い。
時々不安になる。
「美夏、頑張りすぎてない?元々美夏って明るいけど、俺の事で結構しんどい事もあっただろうに、なんでそんなに明るいの?」
「何でって……なんでだろ?自分勝手に生きてるからかな?」
「え?……でも」
「私自分の事で我慢とかしないの。嫌な事は嫌だってハッキリ言うし、自分の気持ちとか言わないといられないの」
「我慢してないとか、ウソだろ」
「嘘じゃないよ?だって春樹の事も全部私がしたくてして来た訳だし、そりゃ最近になってバイトでは我慢しなきゃ行けない事もあるけど……でもそれって普通の事でしょ?」
美夏はあっけらかんとしていた。
以前はただ明るいだけだと思っていたが、この明るさは天性の才能に近い。元々自分には無い様な根幹の部分のポジティブ精神。
「私実は失敗してもあんまり落ち込まないし。反省はするけど、落ち込まないかも」
美夏はそう言って笑った。
晴れて気持ちのいい休日に、美夏と海に行った。
電車を乗り継いで、三、四十分くらいで簡単に太平洋が見に行ける。
でも、泳がないのに海なんて殆ど来た事がなかった。
「私の実家は日本海側だから、なんか雰囲気違うねやっぱ」
意外だった。
「あれ?美夏って地元どこ?」
「新潟。長野との県境近く。糸魚川市ってとこなんだけど」
知らなかった。大学時代も出身地の話とかあまり話した記憶が無い。
「この間の話なんだけどさ……」
美夏が海浜公園のベンチに腰掛けて話し出した。
「私って……明るい?」
「うん、少なくとも今の俺よりはね」冗談めいて笑った。
「落ち込まないって言ってたけど、本当は落ち込んだ時もあったんだ……」
「そりゃ普通に落ち込むだろ。人間なんだもん」
「春樹に色々言われた時も落ち込んだなぁ……」
去年の事を思い出して反省した。
「あの時はごめん……」
「ううん、春樹のせいだけじゃないの。ちょうど弟がうつ病になったって親から連絡があってね」
美夏はベンチの上で膝を抱えた。
「お前のせいだって責められたんだよね」
「え?なんで」
「……私昔から、自分で言うのも我が儘でさぁ。やりたい事しかしなかったし自分勝手に生きてきたの。大学も当然東京の大学に行くって決めてたし、上京したらもう実家には帰るつもりもなくてね。責任とか全部弟に押し付けて来ちゃったの。でも弟も本当はやりたい事とかあって、でも私に全部押し付けられてずっとずっと我慢し続けてたの。そしたらうつ病になっちゃったんだって」
美夏は悲しそうな顔をしていた。
「でも私だって責められたのショックで、自分のせいだと思いたく無くて、でも春樹に自分の事しか考えてないって言われて本当にショックだった。だってその通りだったんだもん」
「あのときは俺も……」
「いいの、もう謝らないで。春樹には感謝してるの」
美夏はにっこりと微笑んだ。
「正直言うと、春樹って私の運命の人だと思うんだ」
「えっ!?なにそれ。ちょっと俺には気が重いよ?」焦って苦笑した。
でも本当は自分もそうだったら良いなと思っていた。
「初めて春樹にあった時、実はなんか気になってたんだよね。それで春樹が大学辞めたとき、なんかすごくショック受けてて。自分でもなんでかよく分からなかったんだけど、春樹に再会した時に、あぁ、私この人の事好きなんだ、って思ったの。だから春樹に言われて凄く心に響いて、あの大晦日の日、本当は帰ってちゃんと弟と向き合わなきゃって思ってたけど、怖じ気づいちゃって乗り遅れて、逃げて帰って来たら春樹がいて……」
自分でもあの日の事を色々思い出した。
あのとき美夏のところに行かなければ、自分は今ごろどうなっていたのか想像も付かない。
「私春樹のおかげで頑張ろうって思ったんだ。頑張ってた春樹みたいに色々頑張ってみようって」
「……俺、別にそんなに頑張ってたつもり無いけどな……はは」
「ううん、でも、春樹はいつだって頑張ってたよ。だるいとか面倒くさいとかいいながら、それでも頑張る人だった。……だからこうなっちゃったのかもしんないけど」
海からの風が涼しい。
暫く二人で黙ったまま海を眺めた。
とても気持ち良くてまるで世界の全てが愛おしい。
風も空も海も光も。
そして今隣にいてくれる人も。
こんなに穏やかな気分は初めてだ。
「春樹は私の事守ってくれなくても良いの。その代わり私が春樹を守ってあげる」
その言葉を掛けられたとき、情けないとかではなくて、単純に嬉しかった。
夏がやって来て、増々元気を取り戻して行った。
人混みももう怖く無くなったし、近場の納涼花火大会に出掛けたりもした。
美夏は今年は浴衣を着る余裕が無いからと行ってワンピースを来た。
それは自分が初めて美夏にプレゼントした物だった。
美夏はもの凄く喜んでくれた。だからとっておきのときまでとっておいたの、と一緒に行ける事になった夏祭りに心を躍らせていた。
人混みの中離れない様、手を繋いだ。
その間ずっと心がドキドキして、部屋に戻ると美夏を抱いた。
以前のときよりも精力が戻っていて本当に久しぶりの感覚だった。
九月に入って、もう薬を飲むのを止めていた。
通院も二ヶ月に一度にしてもらって、そろそろちゃんと就職の事を考え始めていた。
いつまでも美夏に頼っている訳にもいかなかった。
今までろくに就活もしたことなかったもので、書店やネットで関連の書籍を買って勉強した。
美夏には内緒で就職先が決まったら話すつもりでいた。
ある時、小さなコンピューター関係の会社に面接に行った。
未経験者でもプログラミングを一から教えてくれるらしい。基本給は安かったが、研修期間も少し給料がもらえるというのはありがたかった。
ちゃんとした面接は初めてで、近くの衣料品店で安めのリクルートスーツを買って着て行った。
この頃はかなり行動的で、自分でもなんとかなるんじゃないかと 思っていたが、いざ面接では緊張して頭が真っ白で、何を受け答えたか覚えていなかった。
「新しい事に挑戦してみたくて」と言ったのは覚えている。
帰り道ほっと一息ついて昔良く立ち寄っていたカフェでカフェオレを飲んでいた。
スーツ姿の自分なんて見たら、美夏はなんというだろう。帰ったら美夏が戻ってくる前にしまっておかなきゃ。
ふと外を見ていると、前を歩く男と目が合った。
驚いて目を見開いたのは楓だった。
あれから殆ど連絡を取ってなかった。
一度メールで簡単にごめんと一言だけくれたが、それには何も返して無かった。
楓が店の中に入って来た。
「……春樹」
すぐ横に立つ楓を少しだけ見上げて「お、おう」と答えた。
ここ座っていいか?聞くや否や楓は既に着席していた。
楓の顔を見ると今すぐ逃げ出したくなった。
あの時、楓もあの部屋の中にいて、一緒に自分の事を笑っていたのだ。
友達だと思っていたのに、自分の中で楓に対しての一線が引かれた瞬間だった。
「スーツなんて来て、一体どうしたんだよ春樹……」
「あ、いや……。就職の面接に……行ったんだよ」
「へえ。すごいじゃん…」
ぎくしゃくとして気まずい雰囲気の中、それでも楓は立ち上がらなかった。
「俺、お前にちゃんと謝らなきゃ行けない」
楓は急に立ち上がって頭を下げた。
「あの時は本当にごめん。俺も一緒にお前の事悪く言ったのは事実だ。お前が聞いてるなんて思わなくて……」
「……いや、もういいよ。こんなところで頭下げるなんて、みっともないだろ……」楓はそういうダサイの嫌うから。
「いや、こういうのはちゃんとけじめつけないと。このままお前とはもう会えなくなるのは嫌なんだ。だから頼む、許してくれ」
「許すも何も、皆本心を言ってたまでだろ?俺だって、自分がこの立場じゃなきゃ、同じ様に勘ぐってたかもしれない。もう済んだ事だから……」
今更掘り返して欲しく無かった。
自分は早くうつ病を過去にしてしまいたかった。
「許してくれるのか?」
「……ああ、もう気にしてないよ」少し嘘を言った。
楓はホッとした様に笑って席に着いた。
「良かった。……俺も今まだ就活中でさ。この前日建の説明会と集団面接に行ったんだけど、面接官がおっかなくってさー」
その後は楓の方が一方的に話す様な感じだった。
「ジェシカと美夏、仲戻ったみたいだな。この前久しぶりに大学内で一緒に笑いながら歩いてるの見た」
そうか、と相づちした。美夏からジェシカと仲直りしたと聞いていた。
全てが無かった事にはならないし、お互い就活や進路の事もあるし以前の様にべったりとは行かないだろう。
それでも世界は、物事は変わりながら先へ進んで行く。
同じ様に見えるこの店も、店員が変わりメニューが変わり、以前は無かった店ができ、あった店が潰れている。
通りを行き交う人もまた、一年前にいた人が故郷に帰っていたり、一年前にはいなかった人が上京してこの道を歩いているのだろう。
その流れに置いて行かれたく無かった。
自分も前に進みたい。遅れた分早く取り戻したい。
楓とは以前の様には行かないかも知れないが、また新しい関係を築く事も出来る。
少しだけ会話をして席を立った。
「まあ、楓も就活頑張れよ。お前なら良いとこ入れるよ」
もう、遊びの約束はしなかった。
今はお互い進むべき未来に向かってやるべき事をやらないといけないからだ。
「ああ。春樹も……」何かを言おうとして躊躇った。「春樹も、頑張れよ……」
振り向き様に微笑んで立ち去った。
採用の連絡が来た時、驚いてスーパーの外で大声を出した。
電話を切ってガッツポーズをしているところをバイトに来たミカちゃんに見られた。
「先輩どうしたんですか?ガッツポーズなんてしちゃって」
「あっ、ミカちゃんおはよう」
「おはようございます。あ、そう言えばこの前彼女さんが来た時になんか変な事聞かれましたよ?」
「え、美夏に?なんて?」
「最近春樹の様子が変なんだけど何かしらなぁ~い?って……私に聞かれてもぉ……」
ミカちゃんと美夏はバイトと常連客で、紹介すると同じ名前なのもあって意外と打ち解けて仲良くなっていた。
「あ、実は内緒にしてたんだけど、俺就活してたの」
「そうなんですか?ここ辞めちゃうんですか!?」
「うんまあね。さっき受けたとこから電話来て採用だって」
指でVサインをした。
「えー、そうなんだぁ。おめでとうございますぅ。でも寂しくなるなぁ」
「辞めても買い物には来るからさ」
上機嫌だった。
帰ると早速美夏に報告した。
「実はさ、俺内緒にしてたんだけど……」
「あーっ!やっぱりなんか隠してたの?何?何をやったの?まさか浮気とか言ったら殴るからね?」
「浮気なんて出来る訳ないだろ?……就職が決まったんだよ」
美夏は呆気にとられた様な顔をした。「へっ……、春樹就活してたの?」
「コンピューター関係の小さな会社なんだけどさ。プログラマー募集してて学歴とか不問だったし、一から勉強出来るから一石二鳥だろ?」
すると美夏は意外な顔をした。
てっきり喜ぶ顔が見られると思ったのに、心配そうな困惑した表情を見せた。
「なんだよ、喜んでくれないの?」
「……そうじゃなくて、……凄いと思うけど、ちょっと心配かなって……」
「なんでだよ。俺もうほとんど元気になったじゃん。医者だって太鼓判押してたし。薬だってもう飲まなくても平気になったし」
「う、うん……でも……」
美夏の態度に腹が立った。
なんだよ、美夏だって自分がちゃんと働くようになれば心配も減るし、お金の事だって、美夏の進路だってちゃんと考える余裕ができるのに。
就職の準備をしようと携帯電話を新しい物に変えた。
会社の都合のいい携帯会社に変える事にした。
電話帳を整理していると、いくらかもう使ってない連絡先があった。
その中に錦先輩のアドレスがあった。
——そう言えば、正月明けに一度行ったっきり、その後もちゃんと詫びにも挨拶にも行けてなかった事を思い出した。
先輩にはかなり迷惑をかけただろう。
迷ったが、就職の報告がてらちゃんと謝罪しようと思った。
二十分くらいかけてメールを打ったが、メールはエラーメッセージで返って来た。
あれから半年以上も経っているから当たり前か。
翌日スーパーのバイトを辞める手続きをしてから、本当に久しぶりに店に行ってみる事にした。
手土産は夜の人たちに人気の店のフルーツジュレ。ちょっと高ついて懐に痛かったがここは渋っていられない。
店に行くと相変わらず誰かが開店準備に勤しんでいた。
近づくと、同じバイトだった和雄だった。
「和雄?」
相手は自分の顔を見ると、びっくりして、ひさしぶりだなー!と笑って声を掛けてきてくれた。
ホッとして、色々迷惑かけたのに来るの遅くなって悪かったな、と返した。
「そーだよ、お前すんっげー大変だったんだぞ!」
「ワリィワリィ!……ところで、錦先輩はまだ来てない?」
尋ねると、急に表情が曇った。
「あれ?今日は来ない?」
「……錦さん、亡くなったんだ」
「……へ……?」一瞬耳を疑った。
「六月くらいに、ヤクザの抗争に巻き込まれて……」
周りの音がすっと消えた気がした。
「……なんで……」
「ニュース見てない?池袋の銃撃事件」
あっ、と思い出した。
部屋でテレビを見ながら、物騒な事件だなー、とか言って美夏と話していたのを思い出した。まさかあのとき……?
「ちょうどその日は錦さんオーナーの代わりに上納金を持って行った帰りだったみたいでさ。錦さん他の系列店の売れっ子に手を出してたらしくて、それを妬んだオーナーがわざとかち込み入れられる日って知ってて行かせたらしいよ」
ショックが過ぎた。
何も言えずに呆然とするしかなかった。
「しかもさ、切ないのが、待ち合わせてた女を錦さん守ろうとしてかばったらしいんだ。もしかしたらかばわなければうまく逃げれたかも知んないのに。なんでそんなとこで待ち合わせなんかしたんだろうって。もしかしたら女も仕組まれてたのかもな」
和雄の話では今はオーナーが変わって、店内も改装して違う名前で営業をしているらしかった。
キャストとかスタッフはそのままで和雄はそのまま新しい店で働いているのだという。
——あんまりだ。
手土産はどうすることもなく和雄に渡してその場を去った。
信じられない思いもあった。だってもう何ヶ月も前の話じゃないか。
帰り道とぼとぼと歩いていると涙がにじんで来た。
錦先輩の声と笑い顔が浮かんだ。
——おい春樹、今から飯行くぞ。
——守らなきゃいけないものができたら、また違うのかもしんねぇけど。
——お前、もう帰れ。使えねぇならいても迷惑だ。
あの時で最後になるなんて。
錦先輩はまだ二十代そこそこだったのに、こんなに突然死んでしまうなんて。
自分が死にたい死にたいとのたくってた間に、死にたくも無かったはずの錦先輩は死んでしまった。
女が出来て幸せそうだった。
愛する人を守る為に、自らの命を賭したのか。
和雄の言った話が本当かどうか分からないが、とにかくもう顔を上げて歩けなかった。
家に帰ると、美夏が明るい声で迎えてくれた。
でも、正直その声が癇に障る程、心の中はどす黒く深淵の中に沈み込まれそうだった。
「今日ねー、お祝いっていうか、ちょっと頑張って色々作ってみたんだけどぉ~」
美夏は嬉しそうに料理を並べていたが、黙り込んだまま座った。
「……どうしたの?」異変に気づいて心配そうな声を掛けてきた。
「……ごめん、今日ちょっと食欲無い……」
心の中がずっしりと黒い液体で重くなる感覚がした。
この世の全てが最悪に感じた。
こうやって自分が生きている事すら罪だ、何故自分が死ななかったのか。
どうにも気分を立て直せる物じゃなくて、部屋を飛び出して近所の公園のベンチに座り込んだ。
息をするのすら気が重い。
両手を組んで頭を支えた。
もう、何もかも嫌になった。
今まで自分がどれだけ愚かだったかもよく分かった。
生きなければならなかったのに、死のうとして、周りにたくさん迷惑をかけて、それなのに、大した価値も無いくせに生きている。
死んではいけないとわかっていても、自分は死んだ方が良いという考えは消し去る事ができなかった。
錦先輩の代わりに、自分が死ねば良かった——。
二回くらい、美夏から電話が来た。でも、取らないでその場に佇んでいると、美夏が自分を見つけた。
「……春樹……」
美夏は何も言わずにぎゅっと自分を抱きしめた。
そうされると、急に涙が溢れた。
俺なんかこんなことしてくれる価値なんて無いのに。
数日後、新しく就職先で働く事になった。
毎日毎日会社に行ってひたすらプログラミング言語の勉強をする日々。
だんだんと、行き帰り人混みの中電車に揺られ続け、会社で少ない在中社員と特に会話を交わす事もないままひたすら無言で勉強し続けた結果——。
——また死にたくなった。
悪化したのには訳があった。
殆ど回復していたとは言え、完治していない場合何かがきっかけでまたぶり返す事があるのだ。
新しい環境で焦って少し頑張りが過ぎたのもあるが、それ以前に錦先輩の事がショックで落ち込んだまま、また無理をしてしまった事が原因だ。
同じ事を繰り返すというのは本当に絶望感がハンパない。
確実に治りかけていたはずなのに、あっという間に戻ってしまった。
長い時間を掛けて少しずつ回復して来たのに、崖から突き落とされたみたいにまた谷底を這いつくばるような生活が始まった。
バイトをしていたときよりも収入が減った上、さらに三ヶ月足らずで依願退職した。
これでまた美夏に経済的にも大きな負担をかけることになってしまう。
もう年の瀬が近づいていた。
街がクリスマスムードで一色になる頃、テレビも付けずに部屋でうずくまっているのが当たり前の日常だった。
美夏は何も責めなかった。
文句のひとつも言ってくれれば良いのに。
籠ってないで少しは働けよ、バイトくらい出来るだろ。なにまた元に戻ってんだよ、進歩しないクズだな。
死にたいとか言いながら風呂にも入るし食事を出されれば食べる。
今は自殺する気力も無い。
楓は就活うまくいっただろうか?
ジェシカや早紀や未宇司たちは、それぞれの道に向って歩き出しているのだろうか?
自分には未来なんてない。
本当にこの病気が治って、また前の様に元気になれる気がしない。このまま地獄の様な日々が続くなら、さっさとのたれ死んだ方がマシだ。
一年、たった一年?もう一年?
一体なんだったんだこの一年は。
何もしてない、何も進歩していない、何の意味も無く無駄に過ごした一年だったのか。
陽が落ちても美夏が帰ってくるまで電気も付けない。
部屋の外から入り込む街灯の光、青白い光が部屋の中をうっすらと照らす。まるで深海のようなイメージの光景。
それだけが自分の世界だった。
いつか海外の世界遺産とか巡る旅行をしてみたかった。
映画のワンシーンに出てくる様な豪華なホテルに泊まったり、見た事も無い景色を見に行ってみたかった。
でもきっと無理だろうな。
きっと自分は灰色の世界に呑まれたまま、やがて死んで行く。
弱肉強食、弱い物は生き残っていけない。
美夏と来年一緒に行こうと約束した沖縄旅行ですら、今は現実味も無い。
病院に行ったと言って、嘘をついていたのがバレた。
「薬飲んでるところ見てないもんね。駄目だよいかなきゃ。明日絶対一緒に行こう」
「もういいよ……。どうせ治らない」
「治すつもりが無かったら、治るものも治らないよ!あんなに嬉しそうにしてたじゃん……完全に治ったらもっといっぱい頑張っていろんなことしていっぱい楽しむんだって。……寒くなると、悪化してまた逆戻りしちゃう事ってよくあることなんだって。だから……」
「薬を飲んだところで、治る訳じゃない……。後何回同じ事を繰り返さないと行け無いの?俺もう疲れたよ……もうやだよ……」
「……春樹、頑張らなくても良いの。でも諦めないで、お願い」
いい加減美夏の優しさにうんざりした。
「もうさぁ、美夏は俺の事構わないでくれない?もう、ほっといてよ。……もうこれ以上優しくされてもさ、俺、美夏の期待に応えられそうに無い……」
「……そんな事言ったら、本当に私、いなくなっちゃうよ?……それでもいいの……?本心なの……?」
きっと美夏も長い間献身的に面倒見てくれてそろそろ疲れて来たのだろう。
その問いには頷けなかった。
自分自身本当は美夏に去られたら本当にもうのたれ死ぬしか無い。
自分が今まで生きて来た人生は、何もかも全てが無駄になる。
何の為に生まれて来たのか、何の為に生きて来たのか、結局何の意味も理由も無いのか。
翌日病院に行くと、あのオッサン医師に優しく言葉をかけられた。
「せっかく頑張ってたのにまた逆戻りしちゃうとショックだよね。……でも、焦ったら駄目だから。焦るとまたこうなる。焦らずに、でも諦めずにまた一歩ずつ進んでみましょう。必ずまたよくなるから。私は君の力になりたいんだよ」
そしてもし良かったら行ってみて欲しいと、一枚のチラシを渡された。
地方局主催のクリスマスライブの告知広告だった。
「うつ病だった元患者さんが出るんだ。彼女もかなりの苦しみを相手に戦ってね。元々歌手を目指していたらしいけど、両親が交通事故で亡くなってしまって、それでうつ病になってしまったんだ。今は良くなって、元気にライブ活動をしているんだよ」
クリスマスライブは二十四日だった。
それまではほとんど薬を飲んで寝る日々が続いたが、やはり薬の効果でかなり良くなった。
「お薬ってさ、実際の効能だけじゃなくて薬を飲んでいる、治すんだって気持ちが効果を増させるんだよね」
イブの朝、美夏はニコリと笑ってカーテンを開いた。
好天候で少し眩しいくらい。今夜はホワイトクリスマスにはなりそうに無い。
久しぶりにゆったりとした気持ちで過ごした。
美夏が隣にいてくれるだけで充分だった。
今の自分には美夏が居なくなってしまったら、という想像もつかない。
一年前自分の中の彼女の存在は本当にごく僅かなものだった。
それでもこうして今彼女といられるのは、なにかの運命なのかもしれない。
会場は電車で数駅、どこかの大学近くの公園だった。
サンタクロースのコスプレをした人が子供たちにバルーンを配っていた。
午後のライブに併せて来ている人が多い様だった。
「そう言えば知り合いのダンスサークルも出るみたいな事言ってたんだよねぇ。もう終わっちゃったかも」
出店で適当につまみを買いながら、二人してノンアルコールビールを飲んだ。
大して美味しくは無いが、気持ちだけ。
誰かのライブが始まると、割と人気なのか会場は盛り上がっていた。
ビジュアル系っぽいバンドとか、アコースティックの弾き語りの女の子二人組とか、久しぶりにまともに音楽を聴いた。
どれもアマチュアながらなかなか良かった。
インディーズでデビューしているグループもいる中、例の元患者の女の子の出番になった。
エントリーは一人だったが、本格的なバックバンドが付いていた。
どうやら春にメジャーデビューが決まっている様だ。
マイクに向って口を開いた瞬間、その声に惹き付けられた。
「こんにちは。はじめまして、山井モエノと申します」
見た目は割と普通の女の子という感じだ。まだ若く恐らく自分たちよりも年下で、前髪を一部ピンク色のメッシュに染めていた。
「今日はこのクリスマスイベントに参加させてもらえて光栄です」
前方でファンらしき男達がモエノー!と叫んだ。
「あ、ありがとう!……今日はクリスマスイブという事でクリスマスに因んだ曲を、とも思ったんですがそういう方も多そうなのでちょっと変えました」
一見して明るくて、とてもうつ病だったとは思えない。
「クリスマスは家族や友達、恋人たちと一緒に過ごす大切な日ですよね。その大切な、大切にしたい人たちに向けての曲を何曲かしようかな、と思います」
そして明るい感じの演奏が始まった。
ノリが良いロックな感じの曲で、歌唱力が半端なくて歌詞が印象的だった。
サビではその少しボーイッシュで力強い歌声に、なんだか熱いものが胸に込み上げて来た。
短めの明るいけどどこか切ない曲調の曲が続いた。
前向きだけど切ない歌詞に、明るいけどその裏に、今までの苦しみとか辛さとかを乗り越えて来たんだろう強さを感じた。
四曲目では、私を育ててくれた天国のお母さん、お父さんのために歌います!と言って笑った。
なんだか自然と泣けて来て、でもどこか勇気づけられる様な曲だった。
自分のためとか、誰かの為とか、そんな事はどうでもよくって、ただみんなが幸せな気分で笑っていられたら良いな、そんな光景を思い描いた。
音楽って人の心を救うんだな……。
奇麗なメロディーが歌詞をすっと心に届けてくれる。だから心に響く。
昔、美夏と好きなミュージシャンの話で良く盛り上がっていた事を思い出した。
最近はもう全然聴かなくなったけど。
——美夏、また一緒にライブに行かないか?
思わずそう尋ねたくなった。
帰り道、なかなかの幸せ気分だった。
「ねえ、春樹」
「ん?」
「また一緒にライブとか行きたいね」
少し驚いて笑った。「それ俺も言おうと思ってた」
「行けるかな?」
「……まあ、行けるんじゃない?」
前向きに笑った。
心のどこかで強く動いた部分があった。
頑張ろう、俺も諦めないでここを乗り越えよう。
あんな風に強くなりたい。
「春樹は、私が守るから」
美夏も自分と同じ様に勇気でも貰ったのか、急に手を繋いで来てそんな事を言い出した。
「どしたの急に」
「前にも言ったでしょ?春樹は私が守る。だから、安心して?」
「なんだよ、俺男だよ?普通逆だろ」
美夏はううん、と首を振った。
「愛してるから。春樹の事、愛してるよ」
驚いた。
電車の中でこんな事。
目の前のおっさんが思わずにやけたのが分かった。
「おお、おう……!」
恥ずかしくて、とても自分も愛してるなんて返せなかった。
大晦日を数日後に控え、美夏がごめんね、と言って来た。
「私、どうしても正月は実家に帰らなきゃいけないの」
「ああ、そう……。……別にいーよ?」
美夏はお盆時期にも一泊だけ帰っていた。
その頃は自分もかなり回復していた頃だったから特に何の心配も無かったのだが。
一年前の悪夢が蘇るのか、美夏は本当に心配そうだった。
「一泊だけしてすぐ帰って来るから……」
「別にゆっくりしてくればいいのに……」
「春樹は実家にはずっと帰ってないよね?今年も帰らないの?」
「……ああ、うん……」
本当は帰って来いと言われているが、事情も説明してないのに帰ってまた何か言われる事を思うととても帰る気がしなかった。
やっと就職したと言ったらもの凄く喜んでいてくれていたのに——。
最近少し親に対する気持ちが変わった。
前はただ面倒くさいとかうざいとか、そう言う理由で避けていたが、近頃はたまに親のありがたさというものを感じる様になった。
そして大晦日の朝、美夏は大きめのバッグを持って部屋を出て行った。
「駅まで送ろうか?」
「ううん、大丈夫。あ、また乗り遅れちゃうと行けないから、もう行くね?」
美夏に手を振って見送った後、一人っきりになった部屋で少し立ち尽くした。
今更、美夏のいない間に死のうとは思わないが、少し寂しい気がしてじわりと涙が浮かんだ。
思えばこの一年、美夏と一緒にいなかった日は数える程しか無い。それほど美夏の存在は日常の当たり前のものになっていた。
美夏は大学を卒業後、どうするのだろう。
進路の話は余りしてない。美夏は自分が落ち込まないためにか、そう言う話は持ちかけても何となく濁すばかりだ。
一人になるとどうしても色々考えてしまう。
夜ご飯も自分でなんとかしないと行けない。むしろそれが当たり前だ。
今まで何でも美夏に頼り切ってきたせいで、自分はどうする事も出来ない。
美夏がいなければ、わざわざ何かをしてやろうとも思わないし、とても詰まらない。
ふと、自分がなぜうつ病になったのか、その原因が思い浮かんだ。
自分は何故か二十歳になると、世界の全てが変わると思っていた。
小学生くらいの頃、少し情緒不安定だ、とか言われて、人見知りも結構あって余り積極的に行動出来るタイプではなかったはずなんだ。
でも中学生になって、気がつくとリーダーシップをとるようになっていて、時々落ち込む事もあったが、勉強して高校受験を乗り越えて、大学受けて、上京してからはもう人生バラ色の様に楽しくて、きっと人生これからもっともっと楽しくなるんだと思っていたんだ。
努力すればきっともっと良い事しか起きない。世の中はそういうもので、苦労は報われる世界のはずだった。自分はそれを自分で体感してきたつもりだった。
でも、夜のバイトを始める様になってから、世の中の色んな部分が見えて来た。
理不尽で横暴な裏社会の人たち、お金をいとも簡単にお酒に変えて行く、お金を何とも思ってない人たち、そのお金にたかる人たち、お金がなくて犯罪に走る人たち、人を平気で騙して金品を巻き上げる人たち、世界は全然不公平で、勝ち組か負け組かの二通りしか無いと決めつける社会。
暴力か金か、そのどちらかで全てを解決して来た様な人たちの生きる世界は自分が信じる世界とはあまりにもかけ離れていた。
そして二十歳が過ぎて、これから何がどう変わっていくのか待ち続けた。
しかし、気がつけばあっという間に一年が過ぎていた。
世界は何も変わらない。幻想だった事に気づいた。
そして、そういう理不尽な世の中の方が正しいのだと気づいた時、もう全てが砂上の城ように崩れさって、世界は灰色に変わった。
それからだ、何もかもが詰まらなくなったのは。
必死に勉強して進学した大学も通うのが馬鹿馬鹿しくなった。
学歴社会と言っておきながらブラック会社が魔の手をのばし、世の中はニートとか社会不適合者と呼ばれる人が急増していた。
思い描いていた理想は現実の遥か彼方だった。
世界に興味が無くなったら大学で学ぶ意味も無くなった。
もしこれが根本的なうつの原因なのだとしたら、自分はこれから世界を、社会をどう受け止めて行きて行けば良いのだろう。
考えれば考える程わけが分からなくなり混乱する。
はあ、とため息をついて座り込んだ。
そうしているうちに、ピンポーン!と誰かが尋ねて来た。
こんな大晦日に一体誰が何の用だ?
不審に思いながらドアを開くと、そこには楓たちの姿があった。
「春樹ー!遊びに来てやったぜ~」
春樹久しぶり!といって早紀と美宇司もそこにいた。
「なんで……」
驚いて呆気にとられていると、楓たちはさっさと部屋の中に入って来てしまった。
「今夜美夏いないんだろ?ならたまには俺たちとも遊んでくれよ」
美夏が頼んだのか?いや、でもそれならちゃんと前もって伝えてくれているはずだ。
「……どうして。美夏に頼まれたの?」
「ちげーよ、俺が二人を誘ったの」
「えっ……?」
「春樹1人で年越しなんて、寂しいだろ。俺たち今年は実家には戻らなかったからさ」
「でぇーす!」早紀が笑ってピースをした。
今晩飯どうする?あ、出前でもとる?と楓が勝手に色々決めはじめた。
結局スーパーで飲み物や惣菜を買ってピザなどの出前を取る事にした。
「なんか久々だな、こうやって集まるのも」
「そうだねー、うちら就活で忙しかったもんねー」
2人もあれから何事もなかったかのように楽しそうに話をしていた。
でも、みんなでピザを食べながら特番を見ている途中で、二人もあの時の事を改めて謝罪して来た。
「春樹本当にごめんね。私たちも理解が足りなくて。春樹色々無理して元気そうに振る舞ってたのに、狂言だとか言って……」
実際に狂言だと言ったのは早紀ではなかった。
「俺も悪かったよ。あの後皆で反省したんだ。いないからって心無い事言って……」
二人の気持ちは伝わった。
そして、楓も改めて詫びを入れてくれた。
「俺はさ、お前の親友で、一番にお前の事信じて助けてやらないと行けなかったのに。本当に申し訳なかった……!」
三人に頭を下げられ、今度は楓の時見たいに嘘配合じゃなくて心からの百パーセントの気持ちで許そうと思った。
だって皆、こんなにも自分の事を想ってくれているんだから。
楓に『親友』って言われて嬉しく無い訳無かった。
大学に入ってからの友人だ。でも多くの時と思い出を共有したし、お互いにいなくてはならない存在だったのも確かだと思う。それがまた自意識過剰でなければ。
「楽しかったよ、お前と遊びまくってるとき。最高だった。これから社会人になったらあんな風に遊べなくなると思うけど、きっと生涯忘れられない良い思い出になると思う。だからお前には感謝してるんだ」
「うちらもだよ。春樹いつも遊びのプランか考えてくれて、面白い事言って笑わせてくれたり、超最高だったよ」
「俺ら大学卒業しても、また一緒に遊びたいよな」
彼らの言葉を勘ぐる事も無く、素直に気持ちを受け止めた。
大学時代の楽しかった日々の事が次々と思い浮かんだ。
胸が熱くなった。
ああ、俺はなんて馬鹿だったんだろう。
「……お礼を言うのはこちらの方だよ。……楓」
「え?俺?」
「一年前楓が来てくれなかったら、多分俺その時にもう死んでたから……」
美夏が連絡してくれなければ楓がここに来る事も無かったが、直接自分の命を救ったのは紛れも無い楓だった。
まさに死のうと覚悟を決めたその瞬間、今日みたいにピン、ポーン!って『待った!』を掛けてくれたのは楓自身。
つい涙がこぼれた。
友達の存在が、こんなにもありがたく感じたのは初めてだ。
何でもっと早く気づかなかったんだろう。自分にはこんなに大切なものがあったじゃないか。
何も無い詰まらない世界なんかじゃない。
大切な友達がいて、大切な恋人がいて、大切な家族がいる。
そんなかけがえの無い人たちが笑って暮らして行ける世界を、自分が守らなくてどうする。
全てが繋がっていて、全てが大切だという事に、そんな当たり前の事にどうしてもっと早く気づかなかったんだろう。
「春樹……!」
三人とも自分を励ましてくれた。
「また元気になったら皆で遊ぼうよ。私たち、ずっと友達でいられるよね?」
「きっと来年あたりまた皆で騒いでんじゃないか?」
泣きながら笑顔に変わった。
年が明けると近所の稲荷神社にお参りに行った。
深夜だが流石に元旦なだけあって明るくて人もたくさんいた。
参拝して今年の豊富をお祈りして、お神酒を飲んでいか焼きを食べた。
久しぶりに心から楽しいと思えた。
一人だったらきっと今ごろ落ち込んでさっさと寝ていただろう。
それでも良かったかも知れない。
でもどちらかと言われたら、断然こちらの方がいいに決まってる。
皆は狭い部屋に横になって一晩明けて帰って行った。
「楓!」
帰り際、楓だけを引き留めた。
「……ありがとう」
楓は一瞬少し泣きそうに眉をひそめて笑った。
「……おう!」
「就職、内定どこに決まったの?」
「聞いて驚け、YK商事」
「マジで?凄いなさすがだなぁ、超大手じゃん」
「んまーっても、どうなってくかわかんねぇけど、やるしかないじゃん?まあそのうち課長就任していつか部長クラスになったら手に入らないもんは無いかも知んないな?ははは!」
「……頑張れよ。俺の分まで」
すると楓は肘でゴスッと脇腹を小突いた。
「なに言ってんだ、お前だってまだ頑張んなきゃ、まだこれからだって頑張れるよ」
そうかな——と言って頬を指でかいた。
「それに、お前美夏とのことちゃんと考えとけよ?」
「えっ?」
「あんな女他にはゼッテェーいねえからな?ちゃんと捕まえとかねぇと駄目だ。どんなことがあっても。……いつかはお前があいつを守るんだろ?」
少し衝撃だった。「俺が……」
「そうだ。お前が、美夏を守るんだ」
いつかは、なんて心の中にしまっていた小さな小さな花が、一気に大きく花開いた気がした。
「……俺、美夏と……!」
「その先は本人に言えよ?」楓に悟られてしまった。
少し恥ずかしくなって俯くと、楓はじゃあそろそろ帰るな、と言って手を挙げた。
その日の夜、美夏は慌てた様子で帰って来た。
「ただいま!大丈夫だった春樹?」
「お帰り。何が?」
すっとぼけて答えた。
「え?色々……晩ご飯まだでしょ?今から作るね?」
美夏は帰って来たばかりだというのに上着を脱いですぐに支度を始めようとした。
「……あれ?」
美夏は気づいた様に笑った。
「これ、もしかして作ってくれてたの?」
頷いて立ち上がると、自慢げに腕を組んだ。
「まあ、味は期待しないで」
美夏は、喜んで食べる!と叫んだ。
そして夜眠りに就く時、美夏に腕枕をした。
こうして自分の腕の中にいる美夏が愛しくてたまらない。
傍らに温もりを感じる事がこんなに安らかなものだという事を、改めて感じた。
あの事をいつ言おうか悩んだ。
美夏は一体どう思ってくれているんだろう——?
正月が過ぎて、穏やかな日々が続いた。
初春雪の季節。憂いではなく、心静かに景色を眺める事が多くなった。
最近は近くの神社に足を運ぶ。
あの独特な雰囲気が心を落ち着かせ穏やかさを与えてくれる。
バイトの事はまだ考えてなかった。
だが、春になって暖かくなれば、また何か始めようとは思っていた。
気になるのは美夏の事だった。
昨夜も大学卒業後の進路を尋ねると、考えてはいるよ、と言ってそのまま黙ってしまった。
この先の事、二人の事、そろそろ本気で考えないと行けない時期が来てる。
いつまでも自分はこんな状態でいられない。
早く大切なものを守れる強い自分になりたい。
でも美夏にとって今の自分は負担でしかない。この先自分が彼女の未来を支えて行けるという保証は出来ない。
——悩んだ。
今更だが、美夏の為を思うのなら、やはり別れるべきなのか。
美夏はまだ若い。
きっとこれから幾らでも出会いもあるだろうし、もっと素晴しい人に巡り会えるかも知れない。
こんな前途も多難な自分は捨てられても文句は言えない。
むしろ感謝しか無いけど…、でももしこのまま美夏が自分の元を離れて一人になったら、と思うと不安で怖くて仕方ない。
そんな不安も打ち明けれないまま、あっという間に二月になった。
「春樹に、大切な話があるの。……今日帰って来たら、話すね?」
そう言われた朝、覚悟した。
春節の頃、外は粉雪が降っていた。
音も無くさらさらと、まるで雪が全てを覆い隠す様に辺り一面は真っ白だった。
屋根も樹木も、道路も電信柱も。
その真っ白な世界を歩く自分の息づかいだけが、やけにハッキリ聞こえる。
既にバレンタイン商戦が始まっていて、至る所でハートマークを見掛ける。
クリスマスには何も用意出来なかったし、代わりと言ってはなんだが今時男から渡すのも珍しく無い。
今夜、もしかしたら別れを告げられる様な気がして、足を急いだ。
最後になるかも知れないプレゼントに、一体何を選ぶべきか考えた。
大層なものは買えない。
指輪とか今更だし、処分に困るものは渡せない。
全然思い浮かばないくせに、どうしても何か渡したかった。
最後の思い出として、美夏に何かひとつくらい残しておきたかったんだ。
街に出てショーウィンドをぶらぶらと眺めて歩いた。
時々店に入っては店員に、プレゼントですか?とか訊かれて気まずい感じで逃げ去った。
もとより、女へのプレゼントなんて何を渡せば良いのかさっぱりだ。
普通ならジュエリーとかブランドものバッグとか?
でも今更美夏がそんなものを受け取って喜ぶ姿は甚だ想像出来ない。
いや、喜んでくれるだろうが、そんなものはこれから別の男が幾らでもプレゼントすれば良い。
自分の気持ちを一番現せる様な何かはないのだろうか。
——愛って、なんだろうな?
ふと思った。
それは形にできないもの、かもな。
愛してると言ってくれた、美夏の気持ちは何の形も無くても深く心に刻まれた。
一緒に居てくれるだけで、良かった。
それだけで、気持ちが伝わった。強く感じた。
胸が詰まって苦しくて、涙がにじむ。
そんな美夏とももうお別れなのか——?
どうせ、消えてしまうのなら。
どうせこの雪の様にやがて消えてしまうのなら。
一生に一度くらいしかしないだろう事をしよう。
やがてひとつのプレゼントと、ある事をする為の道具を買って準備した。
こんな事、冷静に考えたらきっと臭過ぎだしいつか誰かの笑い者になるな。
それでも良いんじゃないかな。
ありきたりかも知れないし、凄く馬鹿な事かも知れない。
美夏が帰って来た。
心無しか緊張している様な面持ちだった。
さあ、いよいよ美夏の口からどんな事を言われても、受け止めなければならない。
美夏は自分の前で正座をした。俯く様に呼吸を整えてから、美夏が口をゆっくりと開いた。
「……私ね、新潟に帰らなきゃ行けなくなったの」
心臓がドキドキしていた。それでも冷静に美夏の言葉を聞いていた。
「大学を今年無事に卒業する事になって、卒業式の後、すぐに実家に戻る事になりそう……」
美夏の緊張が伝わる。こちらまで手の平に汗が滲む。
「本当は私、こっちで就職して春樹と一緒に居たかったんだけど、今父親が長期入院してるの」
「えっ?」
「私の実家、実は酒蔵でね?弟が跡継ぎなんだけど、今はまだそれどころじゃないでしょ?今は引退したはずのおじいちゃんが色々仕切ってやってくれてるけど、歳だし体力にも限界あって、もうそろそろ誰かが手伝わないときりもりしていけなくなったの」
新潟の糸井川、どんなところか想像もできないけどきっと日本酒の製造が盛んなところなんだろう。
「私なんかさ、大学に行っててもほとんど遊んでばっかりで、勉強って言ったってお酒作りとか経営とかの役に立つ様な事殆ど勉強して来なかったのに、今更私が?って感じじゃん?でも、それでもやんなきゃいけなくってさ」
美夏は髪を構いながら笑った。
「今まで散々弟任せにして遊んで来た分、ツケが回って来たんだ……」
——だから——。
と、美夏は急に涙声になった。
「だから……春樹とは来月でお別れしなくちゃ行けないの……!」
分かっていたくせに、美夏に言われたらその言葉が胸に突き刺さった。
でも涙は流さない。そんなの美夏に悪いから。
「ごめんねぇっ……?」泣きながらしゃくり上げる美夏。
「正月に帰った時には多分こうなるだろうって分かってて、もっと早く言わなきゃいけなかったけど、でも、どうしてもなかなか言えなくて……!」
美夏の気持ちは痛い程分かる。
もし逆の立場でもそう簡単に話せなかっただろう。
本当にごめんなさい、と泣き止まない美夏の背中をそっと撫でて笑った。
「もう泣くなよ、美夏。俺、なんとなく覚悟してたからさ。気にすんなよ」
そうは言った物のショックも隠しきれなくて、それ以上美夏に声を掛けてやれなかった。
「ごめん、ちょっと待っててな」
そう言って立ち上がると、予め用意していた道具を持って部屋の外へ出た。
近所の公園に向って、予め準備していたところに色々とセットした。
今更こんな事をしても何になるのだろうという気もあったが、それでもやらないわけにはいかなかった。
二十分くらい経ってしまっただろうか。そろそろ美夏が心配しているかもしれない。
準備が整ったところで携帯電話で美夏に電話をかけた。
「今からちょっと公園まで来てくれる?」
もう辺りはすっかり真っ暗だった。
暫くして美夏がやって来ると、美夏は吃驚して口元を手で覆った。
公園の雪を使って小さな鎌倉をたくさん作った。
その中に小さなキャンドルを1つずつ入れて灯を点していた。
中央には何十個ものキャンドルで作ったハート。その真ん中にはひとつだけ赤い蝋燭を点していた。
見つけて欲しくて。それが自分の想いだという事を伝えたくて。
「……少し早いんだけど、バレンタインのプレゼント。……ついでにこれも」
そう言って涙を流す美夏にラッピングされた布袋を渡した。
美夏が慌てて中を開けると、それはひまわりの絵が描いてあるマグカップだった。
なんとなくこれを見た時、美夏っぽかったから買ったのだ。
自分にとっては太陽の様な存在。いつでも明るくいてくれて、励ましてくれた。
それがどれほどありがたかったか。——救われたか。
本当は離れたく無い。もう会えなくなるなんて考えたくも無い。
でも、美夏はそんなわけにはいかない。それぞれの人生があるし、やらなければならない事が美夏にはある。
「美夏の大切な人生だもん。美夏の決めた事俺は口出しなんて出来ないよ。貴重な時間を自分に費やしてくれた事、感謝しても仕切れない。今まで本当にありがとう」
そう言いながら、美夏の顔が見られなかった。
思わず頭に浮かんだフレーズを口にした。
メロディーと共に想いが溢れた。
昔カラオケで良く歌った歌だ。
女ウケが良いから必死で覚えた。その時は歌詞の意味なんて深く考えもせずに。
でも今それを歌うと、歌詞があまりにも心情と重なって、涙が流れた。
大サビを歌い終わって、唇を噛み締めた。
「……俺、ほんと何もしてやれなくてごめん。結局何もしてやれなかったな……」
美夏は俯いたままだ。
「ってかプレゼント、すんげーしょぼくてごめん。なんかもっと気の効いたバッグとかアクセとかの方が良いのかなーと思ったけど、大して金持ってないし、後で質屋に売り飛ばせそうな代物も買えなくてさぁ」
無理矢理強がった。
「かっこわりぃよな。ってかダサイよなこんなことし——」
美夏が急に胸に飛び込んで来た。
「——ありがと春樹……。伝わったよ……。ちゃんと伝わったから春樹の気持ち……」
思わず強く抱きしめた。
苦しい程愛おしくてたまらない。
「……これからもきっと美夏は色んな奴に愛されるだろ。俺その中の一人でいいからさ。でも、俺の事忘れて欲しく無くて……」
美夏が強く抱き返して来た。
「忘れない。絶対忘れない。私にとって一生の中できっと他には無いくらいの大恋愛だもの……!」
美夏が腕の中で自分を見上げた。顔が近くて彼女の暖かい息がかかった。
「私あなたのおかげで変われた!もっと強くなりたいって思った。大切な人を守りたいって心の底から思ったの……!」
美夏の目からたくさんの涙の粒が溢れた。
「離れたく無いよ春樹……!ずっと春樹の側に居たいよ……!」
「美夏っ……!」
二人とも涙を止める事なんて出来なくて、何分も何十分もそこで抱きしめ合って泣いていた。
気がつけばキャンドルの火も消え、辺りは粉雪が風に舞って空高く渦を描いていた。
白い蝶々が目の前で笑った気がして、心の奥で、夢だったらなって思った。
——もしかしたら、俺は長い長い夢を見ているだけかも知れない。
本当はまだ大学に入学したてで、楓に出逢って、ジェシカたちに出逢って、美夏はまだ柏原と付き合い始めた頃で、皆仲良くつるみ始めた頃で——。
でも、もし今目覚めても、美夏は今の美夏とはまだ違って、まだ柏原の事が好きで、俺はジェシカに想いを寄せている。
もしもあの時、美夏と柏原が順調に付き合っている時、俺が無理にでもジェシカを振り向かせる事が出来ていたなら、今とは全く違う未来があったかも知れない。
でもきっとあの時ジェシカは俺を選びはしなかっただろう。
ジェシカが柏原の事を好きにならなかったとしても、美夏は別の理由で柏原と別れていたかも知れない。
柏原と別れた直後に、美夏が俺への気持ちに気づいてすぐ告白してくれていたら、美夏と付き合っただろうか?
多分その頃の美夏の事を、俺は好きにならなかった。
美夏を変えたのが俺ならば、俺はきっと病気にならなければならなかったんだ。
そして美夏は、そんな俺を救う運命だったのかも知れない。
そう言う事なのかも知れない——。
ゆっくりと瞼を開けて青い空を仰いだ。
自分がこうなったのにはきっと大きな理由があったんだ。
こうならなければ気づかなかった事、変わった事。
よく考えたらとてつもない大きな力によって世界が動いているように感じた。
ぐるぐると太陽の周りを回るこの地球の様に、運命もまたぐるぐるとあるべきところへなるがままに自分たちの周りを周回しているのかも知れない。
「春樹……。最後にお願いがあるの」
美夏は手を繋いで訪れた神社の境内で穏やかに笑っていた。
「春樹、実家に帰って。独りでいちゃ駄目」
もう、出逢った頃の美夏はいない。
何も考えてなさそうで、自分の事が一番大事で、オシャレに命を懸ける典型的なギャルで、外見とただ明るいだけが取り柄とか言われる様な少女だった。
目の前にいるのはしっかりと自分の運命を受け止めて、力強く一歩を踏み出そうとしている大人の女だった。
泣けてくる程良い女に見えた。
「……わかった。美夏がそう言うなら、そうする」
これからどう説明するか、それを想うだけでも億劫だけど、確かにこのまま一人で暮らして行ける自信はどこにも無い。
固く約束をして、翌日母親に電話をかけた。
「……母さん?俺だけど……」
「やだ春樹じゃない。また正月も帰らなくて、お母さんもうずっと顔も見てないわ。最近お姉ちゃんも忙しいみたいで、余りこっちに帰って来てくれなくなったのよ……?」
久しぶりに聞いた母の声は、細くて寂しそうだった。
「そっか……。……あのさ俺、色々あって、やっぱりそっち帰る事にしたから」
そう言うと母は嬉しそうに笑った。
「早く帰って来なさい、はるき」
——はるき。
母の優しさはいつだって変わらなかったんだ。
自分が気づこうとしなかっただけ。
そして三月の中旬。
ついに大学の卒業式の日がやって来た。
大学の構内から聞こえた卒業生たちの歓びの声。
ああ、終わったんだな——。
楓たちが出てくるのを少し離れたところで幾暫く待っていた。
「春樹!」
力強い楓の声。
「春樹ー!」
早紀と美宇司、そして——美夏の姿があった。
「みんな、卒業おめでとう」
自分が遂げる事の出来なかった大学の卒業。
彼らは卒業生として最後の門をくぐる。
皆、卒業の達成感と充実感で光り輝く笑顔をこぼしていた。
今日が終わればもう皆別々の人生に歩み出し、離ればなれになって行く。
「長い様で短かったかもなー、この四年」
「いろいろあったねぇ~」
「ホント色々あったなぁ」
「一番色々あったのは、お前ら二人だけどな」
楓はそうやって嫌味なく笑った。
「ねえ、せっかくだから、春樹も卒業式しない?」
「えっ?俺?」
「そうだな、春樹も俺たちの仲間だもんな。今日一緒に卒業しようぜ」
「いや、意味分かんないけど……」
そうこう言う内に彼らは卒業式で有名な歌をアカペラで合唱し始めた。
戸惑って美夏を見たが、美夏も笑いながら歌っていた。
五人手を繋いで輪になって、ガキかよっ!なんて笑ってるくせに少し泣きながら歌っていた。
通り過ぎる人々がそれを見ながら新しい明日へ足を進めて行った。
「春樹も卒業おめでとー!」早紀が無邪気に叫んだ。
「おめでとう!」
「おめでとう、春樹」
「……ありがと……」
「ジェシカも一緒にいられたら良かったのに!」
「そうだな」
ジェシカは大学をやめて専門学校に編入していた。
「でも、ジェシカ頑張ってるもんね」
「そうだよ、今度ドラマの準レギュラーだぜ?すげーよ」
ジェシカはモデルから女優に転身しようとしていた。
周りのせいにせず自ら行動した結果、オーディションを受けまくってやっと企業のキャンペーンガールから幾つかのCM出演を経て、ようやくドラマ出演が決まったのだった。
その傍らで専門職の資格を取ろうと必死に勉強している。
「将来の事も見据えて資格取得かぁ~。本当恐れ入るよ」
「あっ、ジェシカから」
美夏が電話に出ると、ありがとーっ!と言って嬉しそうにジェシカと話していた。
「みんなにもおめでとうが言いたいってさ!」
そして美夏の携帯を順々に渡して行った。
各々がジェシカへのお礼を言いながらジェシカへの激励も忘れなかった。
やがて自分のところにも回って来て、美夏が頷いた。
「……もしもし、ジェシカ?」
「——春樹!……久しぶりだね?調子はどう?」
「うん、まあボチボチ。暖かくなって来たから調子はいいよ」
「そうなんだ、良かった……!」
「頑張ってるんだって?仕事」
「うん、今日もドラマの撮影でね、そっちに行けなくて残念だけど……」
「本当に、頑張ってるんだな……」
「春樹も……今日で実家に帰っちゃうんだよね……?」
「ああ、俺は深夜バスで帰るよ。部屋も昨日引き渡して夕べはホテルに泊まったし」
「またいつかきっと……会えるよね?」
「……会えるさ。でも、その頃にはジェシカが売れっ子になりすぎて、俺なんてお近づきにもなれないかもな」
「あははっ。……そうだといいけど」
「向こうでも応援してるから。……ジェシカ頑張れ!」
「ねえ、あれ言って?」
「えっ?」少し悩んで言ってやる事にした。
「……どんな新人が出て来たって、ジェシカが一等輝いてるぜ!……もっと言う?」
改めて臭い台詞にジェシカは笑って喜んでいた。
「ううん!もう充分、美夏に悪いから。ありがとう」
美夏をチラリと見ると、嬉しそうに笑っていた。
「じゃあ、美夏に代わるよ。またね、ジェシカ」
「うん、また……」
そう言って携帯電話を美夏に返した。
「ジェシカ、帰って来たときはいつでも寄ってね。うちのお母さんとかもジェシカにまた会いたがってるから!じゃあまた、向こうで会おうね」
美夏が電話を終えると、寂しさがひとしお襲ってきた。
美夏は今日大学を卒業した。そして、これから新潟の実家に帰る。
「お腹減ったね。ご飯食べに行こっか?」
皆で最後のランチに選んだのは、在学中に良く皆で立ち寄った大学近くのカフェレストランだった。
同じ考えの卒業生たちが多く、辺りはごった返していた。
テラス席を確保し、皆で笑いながら昔話に花を咲かせ、これからのお互いの道筋を語った。
楽しさの中に埋もれる寂しさと悲しさ。
それを隠すように皆笑っているかの様だった。
そしてその後、美夏を見送る為に五人で東京駅へやって来た。
「寂しくなるね……」
早紀が号泣していた。
「またこっちに遊びに来たときは買い物とか付き合ってよぉっ?絶対また連絡するから」
「うん……わかったぁ……」
美夏の小さな荷物。大きな物は全て昨日のうちに発送してある。
美夏が帰る頃にはもう家に届いているはずだ。
バスではなく新幹線を選ばせたのは、自分だった。
少しでも早く、実家に帰って家を手伝ってあげたらいい。そう言って勧めた。
なのに、この期に及んでも離れたく無い……。そんな気持ちからか、美夏の鞄をずっと手に持ったまま、ギリギリまで側にいたかった。
手を繋いでいた美夏がゆっくりと自分の方を見つめた。
胸が締め付けられる様に苦しくなって、言葉が出なかった。
これから自分がどうなっていくのか、自分でも分からない。
でもどうしても後悔したく無かった。
「春樹……」
そろそろ、と時間が迫って来たのを目で語った。
そんなの分かってる。でも——この手を離したら。
「……美夏。今まで本当にありがとう……。でも俺、これでもう美夏に会えなくなるなんて思いたく無い」
「……当たり前じゃん、会おうと思ったら会えるよっ?海外じゃないんだから……」美夏はいささか泣きそうに顔を歪ませた。
「俺、絶対に治すよ、病気」
「うん」
——思い切って言葉にしたかった。
「治したら、お前の事迎えに行っても良いかな?」
「え……」
美夏の唇が震えた。
「どのくらい時間がかかるか分からないけど、絶対に前みたいに元気になれるように、必死に治す。お前の為に、絶対治すから、それまでちょっと待っててくれない?」
「はる——」
美夏は、もう言葉もでないくらいに口元を押さえる手を震わせて、涙をこぼし始めた。
あの二文字はまだ言えない。
でも今の自分の精一杯の気持ちだった。
両手を離して美夏を最後にギュッと愛おしく抱きしめた。
そして彼女に強く抱き返された。
「——愛、だな……」
「愛だね……」
周りの三人が口々にそれを言葉にした。
言葉にしか表せない物があるとしたら、それはきっと——愛だ。
そして彼女は別れ際笑って言った。
「待ってるからね、春樹。でも、おばあちゃんになっちゃわない内に必ず迎えに来てね」
だから最後に笑って返した。
「愛してるよ、美夏」
エピローグ
凄く意外な事だったが、俺の親父は結構偉大だった。
岡山の実家に帰ると、家族は俺を当たり前の様に迎えてくれた。
「暫く見ないうちに随分と大人びたんじゃない?」
能天気ではない雰囲気を、大人っぽいというのは安直過ぎる気もする。
父親は俺の異変に気づいていたのかも知れない。
そっと遠目から、以前は生やしていなかった顎の髭を構いながら黙ってこちらを見ていた。
二、三日して落ち着いた頃、やはり母は就職先を探すのを急かした。
「実家だからってニートなんて絶対許しませんからね。社会人なんだからちゃんと家にもお金入れないさいよ?当然でしょ!」
なので、どうしても話さない訳にはいかなかった。
味方がいない今、自分でこんなことを言うのは情けないが、ちゃんと伝えなければならなかった。
心臓が爆発しそうになりながらも必死に自分の状況を説明した。
「——えっと、それってちゃんと治る病気なのよね……?」
時間はかかるかも知れないが、必ず治すと約束した。
母親はさすがにショックを受けていた。
大学辞めてふらふらしていた息子がやっと帰って来たと思ったら、いきなり心の病です、なんてどんな親だってショックだろう。
とにかくすぐに近くの専門医院を探した。
意外と近くに何件かあったが、結構相性という物が肝心らしく評判を頼りに母がひとつの病院を探して来た。
田舎はすぐ噂が広まるから覚悟しなければならなかった。
近所を歩けば、行きつけの店に行けば、スーパーに買い物に行けば。
母は行く先々で息子の事を話題にされ、社交辞令に『お気の毒ね』と言われる事にうんざりしていた。
「もう、本当にいい加減にして欲しいわ……」
食卓で思わずため息をつく母に、何も声を掛けてやれない肩身の狭い自分もまた、心が痛んでため息が出た。
「影でどんな噂してるか分かったもんじゃない……」
そんな時、親父はどこか可笑しい様子でこう言った。
「周りの目なんてほっとけばいいさ。どうせただの他人だ。人様の家族の事に口出せる訳じゃない。それよりも、お前はもっと息子の病気についても関心を持つべきじゃないのか?こいつが東京にいるときはあんなに毎日心配そうにしてたのに」
内心、親父っ!て叫んだ。
元々そんなに厳格でもなかったし、自分も自由にするからお前らも自由に生きろ、みたいな適当な感じの父親だと思っていたが、まさかこう言う状況で味方になってくれるとは想像もし得なかった。
家の庭の桜が咲く頃。
毎年四月の上旬から中旬に掛けて咲く我が家の桜の木。
母は害虫被害などを嫌がり、早めに切ってしまいたいと言っているが、親父が唯一それは絶対に許さなかった。
殆ど飲みもしない酒だが、初めて晩酌に付き合った。
「お前が生まれた時も、この桜は花をつけていたよ」
誇らし気に庭の桜を眺めながら親父は酒を呑んだ。
「春、桜の樹の花が咲く頃に生まれたから、春樹……。安直過ぎるか?」
「いや……」
酔って嬉しそうに笑う親父の横顔を見て少し笑った。
すると、親父はうつ病について個人的に少し調べたと言った。
結構辛い病気みたいだな、とも。
「俺は別にお前の事、可哀想だとも思わない。お前は病気になって失った物もあったかも知れないが、得た物もあったんだろ?」
まるで心を覗かれた様な気分だった。
親父ってこんな凄かった——?
「他人には無い経験なんだ。何もかもが悪い事じゃない。実は俺だって若い頃、似た様な事あったんだぞ」
意外と言えば意外、でも不思議と納得も行く気がした。
「男兄弟から何やってるんだもっと頑張れと言われても、それが精一杯で。誰にも理解されなくて、焦る気持ちと辛さで結構苦しんだよ。経験しないと分からない、絶体絶命の絶望感」
まさにその通り、かも知れない。絶体絶命——。後ろは山火事、目の前は波荒れ狂う断崖絶壁の海、って感じだ。
そして親父は俺にこう語った。
「夢って言うのはさ、叶えるだけが全てじゃない。父さんは、夢を持つって事自体に意味があると思うんだ。例え結果的に叶わなくとも、夢は絶対に必要な物なんだ。どんな些細な夢でも、夢があるから、目標があるから頑張れるだろ?絶体絶命、って思っても、夢を持つだけでそれが光になる。翼になる。だから皆、夢を持てって言うんだ」
——夢、光——。それは自分にとって確かに力を与えてくれる物だった。
少し前なら馬鹿馬鹿しいと鼻で笑ってゴミ袋に突っ込んで捨てていた。
でも今の自分は確かにそれを感じている。
今は遠く離れたかけがえの無い、大切な物。
そっと胸の辺りで拳を作った。
——何でも良いから夢を持てよ、春樹。
親父に小さい頃から良く言われていた言葉。
「今のお前になら、俺の言っている事が、よく分かるんじゃないか?」
親父の前で悔しいけど、じわっと溢れた涙が目尻から一雫落ちた。
でもきっと見て見ぬ振りをしてくれている。
「……親父。俺、治したら、紹介したい人がいるんだ……。会ってくれる……?」
彼はこちらを振り向いて、にいっと笑った。
——END——
慟哭
※現在では副作用の少ない薬が開発されています。


