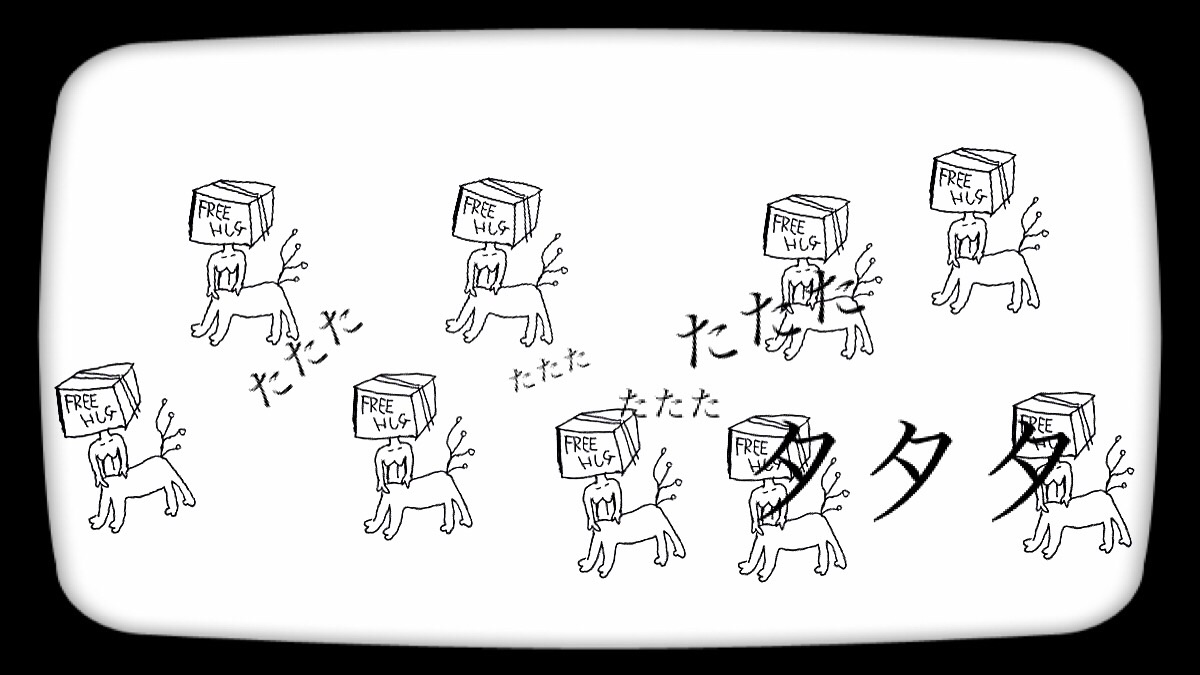
たたた
世の中の憧れは自由
1
ファーストフードのポテトは俺に優しかった。
脂っこくて安っぽくて汚らしい。俺はコレを求めていたのか。さんさんと照りつける太陽で布団をジュージュー焼いた。そのような気分であった訳よ。二日酔いという名の俺にとって一番怖いやくざが俺に拷問をひたすら。こんな日はだるくて汗が止まらなくて、ただでさえ汗が止まらないのにぺたぺたと周りの熱がうざったい。目が開かない。頭の中で誰かが「ギャーーー」とか言ってる。多分。「出してくれーー!!」って。ムリ。出さないも何も、出てってくれたまえ。
おえっとなり、脳みそどろっ。そんな気分。
みーんみんみんみん。あ。ゴミ出すの忘れた。布団は取り込んだけど。
携帯が鳴る。うるせぇな…
【何曜日に来る?】とメッセージ。あーなんか今週行く気にならねぇなぁ。用事も特にないんだけ【いけない】
渋谷ハチ公前広場。異常なくらいの人の量。みんながみんな額に汗で、ハゲとなればぴかぴか光る水晶のよう。すれ違いざまに「ジャマ」と叫びたくなるような人が100万人。もしかしたらこの中に一度すれ違ったことのある人が居るかもしれないが、どうでもいい。例え、見た目直球ドストライクの可愛い可愛いビッチでもそれは運命じゃない。出会いじゃない、じっと見つめ話しかけて知り合って愛想笑いのカーニバルから脱走して二人向かい合って、ご飯をいやらしく食べるまでは出会いじゃない。『フリーハグ』というダンボールを持ってニヤニヤする青年。こいつはもはや意味がわからない。
いや違う。今日の俺の見た目を見てみろ。ツイストパーマにヒゲ。細身の黒ずくめ。タイトなりにタイト。
「聞いてる?」
こいつの話はつまらない。先日の話だ。まあまあ涼しい夜に、彼女の梨乃と飯を食っていた。たまに行く古臭い焼肉屋さんだった。
「あー聞いてる」
「だるそう」
「・・・」
「つまんないって顔」
「あーはいはい」
俺の彼女はと言えば顔は格を付けるとすれば中の中で、童顔のもちもちしたチビだった。茶色の髪がまっすぐ伸びてずっといい匂いがした。服装は童顔と裏腹にビッチ寄りで、刺繍の入った白い半袖に黒のスカート。チビなりのヒール。なんのへんてつも無ければ、ビッチでも無かった。ビッチですらなかった。
「てかご飯粒ついてます」
梨乃が俺のティーシャツに目をやる。俺は目線をシカトして、ご飯粒を取り「それで?」と話しかけた。てーかやめてくんないかなぁ。そのビッチスタイル。そんなことばかり考えていた。ほんっと、そんなことばっかり。さかむけ。俺のメインは梨乃よりさかむけだ。
「りき!」
「ああ、はいはい」
「それでね、昨日ね、お母さんから電話が来て。旅行券を」
ふーん。
あっそ。
それとそれで梨乃。
爆音のミュージック。梨乃ゴメンな。クラブでたしなみ程度にタランチュラという名の超凶悪なテキーラをイッキ。ずーん。
「どこから来たの?」
爆音の中耳元で囁くヘソだしレディ。お前こそどこから来たんだ。爆乳不二子ちゃん。グロスがテラテラと、光に任せて唇に艶を出す。
あらもぅず べるえいすずうぇいあおぃ あらもぅ えにも
洋楽は意味不明だ。いつだってそう。こんな平凡な俺だった、携帯が鳴る。あーうっせ。たまに梨乃が気分転換にひらひらふわふわした服を着てる日が俺は好きだった。お前の顔面はそれだ。きっとだけど、きっとだけどね?お前は世間体で言えばちょっと下なんだ。なぜなら普通だからだ。俺みたいな似ている芸能人を聞くとなんとなくイケメンばっか出てくるやつとはもしかしたら釣り合わないのかもしれないよ?きっとだけど、きっとだけど
カノジョ、カレシの定義は何かしら。俺は正直、面倒だった。はじめっから恋愛をやり直すのが。
「遊ばない?」
ビッチが俺に微笑みかける、なんて美味しそうなビッチなんだ。好きな食べ物、ビッチ!!コレは浮気じゃない。食事だ。梨乃、だいなり、ビッチ!梨乃<ビッチ。自分に問題があると思いなさい。
「いいよ」
あぁ、うるせ。電話か。
ビッチを美味しく召し上がった俺の朝は誰よりもすがすがしかった。ディープすぎるキッスの深夜。そんなトンネルを抜けた静かな朝に、バスローブにパンケーキ、目の前には朝にふさわしい牛乳とスッピンのビッチ。名前なんて覚えるか。肉に名前があるか?魚ならどうだ。お前はビッチだ。
涼しい空気を吸って、何故か白い空を見つめた。煙草に火をつけ、ビッチが寝返りをうって誘ってきたのをフルシカトしてぼーっとしていた。早朝の風はなんだか懐かしくて気持ちが良い。ビッチを食べた昨日を忘れておばあちゃんの家とかそうゆう綺麗な思い出が蘇る。なんて、都合が良いんだ。
もう朝だというのに俺の電話は鳴り続けていた。名前は変わらず【梨乃】だが、梨乃はと言えばそんなに束縛するタイプでも、干渉するタイプでもなかった。ナゾの鬼電に違和感を覚え、やっと舌打ちをして、電話に出た。
頭から黄色い音がでるようにキーンとした。そうだ。俺は昨日、タランチュラを、ずー「もしもし?」
「なにしてんの?」
頭がずっきんずっきんずっきんと
「北海道。行こうって言ったよ」
ohーーーーーーーーーーーーーーーーーーー?
なぜなら、俺は基本的に梨乃の話なんか全く聞いちゃいなかったのだ。全く。全くだ。
俺はなんとなんの荷物も持たず羽田空港に直行した。初めて、東京というこの臭くていやらしい街から出るというのに。そう、東京生まれ、東京育ち。田舎物を羨んだことなんて一度も無いさ。帰るところがあっていいなぁ~なんて思うやつも居るだろうがそんなの、交通費がかかるだけ。そうだろ?ビッチにすらなれない梨乃ちゃん。
「手ぶらで来たの?」
「ああ、ねみい。向こうで買えばいいかな」
金はまあまああった。
「迎えに来るって言ったのに、忘れてたの」
「まーあるっしょ。」
「・・・ないけど」
ちょっと不機嫌な梨乃は、俺の好きなバージョンの梨乃だった。パステルカラーでビッチ感ゼロ。準備万端で化粧もばっちり。もち肌。最高。今日のあんた、最強。あんたが大将。
ピーーーーーーーーーーーーーー
荷物検査の横にあるトンネルを通った瞬間、俺から変な音が鳴った。
「ちょっとポケット見せてもらっても」
舌打ちをしそうなのをぐっと堪えてポケットを見せた。変なキーホルダーのついた自転車の鍵が出てきて、少し恥ずかしくなり「すみません」と言った。隣のゲートでは、梨乃がもう通過していてこっちに向かって来ていた。
もう一度、トンネルをくぐるがまた同じ音が鳴った。さすがに、眉間にしわを寄せる。
目の前では、梨乃がそんな俺を真顔で見つめていた。スゲー荷物だな。
虫眼鏡みたいなアイテムを持った人が、俺の体に虫眼鏡もどきをあてた。
股間に到着したそれは、反応を見せた。
どっかで見たことあるコントのように、そいつが首をかしげながら何度も俺の股間にそれをあてがうので、俺はソイツの頭を叩いた。するとそのはずみで、それを俺の体のどこにあてがっても反応するようになった。空港の虫眼鏡もどき担当兄ちゃんが、首を傾げる。それを、梨乃は真剣に。いや、見下すように見つめていた。
「通れないよ、きみ」
急に、梨乃が言った。
俺は、硬直し梨乃を見つめた。
こんなに見つめあったのは何年ぶりだろうか。時が止まって、静かに。梨乃が見たこと無いくらい大声で笑い出した。無邪気な笑い声だった。
「私、北海道行ってくる。りきちゃん。」
りきちゃんなんて、今まで一度も呼ばれたことが無い。これは、本当に梨乃だろうか。俺に笑顔で手を振り遠ざかっていく梨乃をポカンと見つめた。旅行券・・・。なんつってたっけな。梨乃の話の内容も、何故北海道に行く羽目になったのかも全然聞いてなかった。覚えてないどころか、記憶すらしていない。
呆然と立ち尽くす俺に「あの・・・」とお兄さん。はっと我に返り、「帰ります」と言って後ろに下がった。
落ち着け。
なんだか夢でも見てるかのようだ。なんとなく、トイレに入って顔を洗おうという気になった。それにしてもなんで通れないんだ。なんか細工でもされたのか・・・。トイレで鏡を見て、首のところにある変なアザに気がついた。殴られたような、青タン。首を・・・?そんな覚え、全く無いが。
とりあえず、寝込むことにしよう。
電話の音で起きた。気がついたら、しばらく爆睡していた。梨乃からだった。なんだか、鳥肌が立つ。梨乃は、実は俺に大きな恨みでもあるのか、それとも浮気がばれたか。浮気・・・?あれは食事だ。浮気じゃない?肉に名前があるか?魚だったらどうだ。
「もしもし」
しばらく着信画面を見つめた後、おそるおそる、出た。
「もっしもーし」
ご機嫌な梨乃の声に少し安心した。安心とは、愛情じゃなくて、罪逃れと恐怖心。
「ついたの?」
「ついたよ」
「・・・あそう」
「なんでゲートくぐれなかった?(笑)」
「・・・え?」
「そんなことってあるん」
梨乃の、いつもの無邪気な笑い声がした。梨乃だ。これは、いつもの梨乃。『通れないよ』と自信満々に笑っていたさっきの女は誰だったのだろうか。それにしても、ゲートをくぐれなかっただけで俺を置いていくなんて。なんて意地悪だ。そんなの、梨乃のすることじゃない。梨乃は普段、そんなアドベンチャーなイタズラや意地悪をすることなんて無かった。明らかに、いつもと違う空気を見逃したい気持ちで俺は黙っていた。
「てか、電気屋さん行ってきてもらっていいかな」
「電気屋さん?」
「りきの鞄の中に、封筒に入った三千円あるから、それで電球と、それから・・・」
驚いて鞄の中を漁る。まるで俺が北海道に行けないのをわかってたかのように、封筒に入った三千円があった。
「あった?三千円」
「お、」
「ん?」
「・・・おう」
「じゃーよろしくね。ごめんね」
なんだか今日の俺らの立場は逆転していた。しばらく動く気になれなかったものの、動かなきゃ何も始まらない。深呼吸した。なんだか、今日という日はとってもとってもとーってもヘンだ。どこにでもいる何のへんてつも無い様な梨乃ちゃんに魅力を感じないのは全くいつも通りだが、違和感を感じるのはいつも通りでは無い。しばらく天を仰いだが、すぐに立ち上がりまた鏡を見る。アザが大きい。うーん。金縛り?呪い?『フリーハグ』またいるよ。気がつけば中野駅前の電気屋さんに俺は居た。紙には【電球、電池、充電器】
「すいません」
だるそうに店員に話しかける。何で俺があいつなんかのために。でもこんな自分が好き。ポンコツっぽい若者の店員ともやしっ子のチャキチャキ動くおっさんの店員がいたので俺はチャキチャキじじいをとっさにクリーチャーに選んだ。
「電球の、このサイズと・・・」
「あぁ。はいはい。お待ちくださいね。」
早歩きのおっさんになんとなく着いていった。アクビが出た。なんて眠たいんだ。
「こちらのタイプと・・」
電球コーナーにて、なんでこんな時間をバリンッ!!!!!
俺の触ろうとした電球が粉々に割れた。
沈黙
「・・・・・・・・お客さ「触ってないすよ」
・・・・
沈黙
何故か俺は動いてはいけない気がして口だけを動かしていた。やな予感がする。気を紛らわそうと俺の股間でピーピーなるあの虫眼鏡もどきのことを必死で考えた。なんてばからしい。唾を飲む。何も喋らないチャキチャキじじい。脳裏を横切る梨乃の乳。なぜだ。いや、エロくない。
バンッッッ!!!!!
俺の体内から銃声のような音がたくさん聞こえてしまいにはすごく大きな爆発音がした。
そして
バンッッッ!!!!!!!!!
もう一度爆発音がして電球コーナーが大爆発した。
チャキチャキじじいは、びびって腰抜かして「お、お、お、お客様あぁぁ」とか叫んでいた。何も聞こえない。何がおきてる。何がおきとんねん。何が。音を聞いて店員がかけつけ、目が合ったので最強に走った。逃げた。理由もわからなければ、よくわからない。心臓が・・・ばく・・・・
って鳴ってない!ばくばくしてない!息もきれない!!え?えっ???えっ!?!なにこれ。えっ!?
ババババババババババ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
俺の体内で何かがナニカしてる。いや、完全にナニカが何か。
「ヴぉーくたちは~きらきらひかるあたま殴りつけて~やるんだ~」
全力疾走してる俺の口から叫ぶように意味不明な歌が止まらなかった。ばかみたいな歌だ。よーく、歌詞を聴く。落ち着いて目を瞑った。
【はなのさきからつまさき
ぼくたちはきらきらした
ぼくたちはきらきらした頭殴りつけてやるんだ
せっくすよ、みらいにはばたけありがとう
マリーと言う名の彼女が欲しい
マリー!!マリー!!!マリー!!!!!!!】
つまりは、目を瞑って絶叫(熱唱)しながら俺は全力で走っている。はたから見たら、頭のおかしさレベル100。100。そう、ひゃく!!!
電話が鳴った。梨乃だ。
「もしも・・・マリー!!マリー!!!!」
普通に喋れないほど歌が止まらなかった。
『・・・なにいってるの』
「ヴぉーくたちはきらきら」
『…爆発。』
「…は」
『臓器提供してあげようか?』
いきなり大きな声で人が変わったように梨乃が叫んで
『…ぶっ!!はっはっはっ』
その後続けて電話の向こうで大笑いした。
おれは、数日前に思った。きみの魅力がみつからない。そんなことを、突然、思い出したんだ。こんなの、消滅寸前。わかっている、愛なんて、寂しさなんて。別にそれが、梨乃じゃなくたってもっと最高な女はいっぱいいるのだ。むしろ、梨乃じゃない方がつまらなくない。きっと、消滅寸前。好きじゃない。寂しくない。お互いがお互いを…。ん?
突然、電話が切れた。俺は、今度は訳もわからずズボンを脱いでよりによってすごくダサめのパンツを披露。ズボンを振り回して何故か息を止めていた。誰か、俺を止めてくれやしないかね。自分の行動の意味も、この心臓も、あの女も、もう、何もわからない。何がおきてるんだ。何がおきとんねん。夢か?
夢?
もう一度電話が鳴って、画面も見ずに出た。
一瞬の沈黙の後、雑音をはさんで聞き覚えの無い声がした。
「霧谷 李貴さんのお電話でお待ちがえな・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「刺された?」
あらもうず うぇるれいず あいうぉんていぉんうずぃ ずんちゃ ずんずんずちゃ
あの時の洋楽が目に染み込むようだった。
た
梨乃が刺された。一体誰に。
心臓の近くを刺されて重症だった。
な ん だ こ りゃ
俺はと言えば全く心配じゃない自分にげんこつを入れてやりたかった。こんな俺でも向こうの親御さんたちの前で心配したフリができるのだろうか。梨乃の親に会うのも、実家の友達に会うのも初めてだった。俺は梨乃の何も知らなければ話されたとしても興味がなかった。つまりは、最低だ。
病院に向かうタクシーの中でウトウト目を瞑ると、「フリーハグ」と書いたダンボールを持った青年がこちらを見て不気味に笑っていた。
ちゃっら。お前ちゃっら。
病院の前に到着するとなんだか緊張して胸が破れそうだった。具体的に言えば破れた。辛い顔の練習をして、梨乃の顔を思い浮かべる。ああ、なんのへんてつもない女。その顔は、すぐにビッチの顔に摩り替わった。なんだかそれが寂しくて、胸が痛くなった。空気の重たい病院のエレベーターの中で何度も梨乃の好きなところを考えた。果たして、そんなところあったのだろうか。足が重たい。
例えば梨乃と焼肉を食べているのなら、俺が夢中なのは焼肉だった。きっと。
病室のドアを開けた。
空気が硬直した。
若い男、それからおじさん。親御さんは、まだ来てないのか。俺は気にせず梨乃のもとへ寄っていった。梨乃は、くだだらけ。それだけ、いつもの梨乃の寝顔だった。俺は安心してため息をついた。
「おきろよ」
若い男とオッサンを無視して近寄った。梨乃はもちろん返事をしなかった。幼い頃から知ってるわけではないが梨乃は明らかに人に恨まれるようなタイプでは無かった。刺されたって、一体誰に。通り魔・・・か。また俺はため息をついた。しばらく時が止まって、若い男が泣き始めた。兄妹だろうか。いとこかなにかか、友達か。俺はそちらを見ずに、梨乃の寝顔を見つめていた。
「・・・うっうっ・・・」
「・・・」
「・・・みらいちゃん・・・」
「・・・」
「・・・みらいちゃんてば」
「・・・」
「みらいー!!!」「梨乃だよ」
泣き叫び始めたので、振り返ってしまった。一瞬、目が合ったまま時が止まった。
「病室間違えてますよね?」
「みらいちゃんだよ」
「梨乃ですよ。俺の、あの。一応・・・カノジョなので。」
「お前の・・・お前のカノジョな訳あるか。みらいちゃんはみんなのカノジョだ。みらいちゃん・・・」
「・・・」
「みらいちゃんー!!」
「・・・・・・・・・・・・・・・みらい・・・?」
誰?
違和感が生まれるくらいの舞台口調なコイツは普段役者でもやっているのだろうか。くっきり二重のすごい目力で、髪の毛も不自然なくらい七三でぴったりと分けられていた。
「みらいーーー!!!!!」
もうそいつは発狂していた。いや、誰だよ。そっくりさんでしょうか。そいつをしばらく薄目で見ていると、いきおいよく病室のドアが開いた。
デブでメガネのリュックの青の髪のつまりは見るに見かねる女が息を切らしながら、走って梨乃に駆け寄っていった。
「なんて・・なんでなんで?!なんてことなの・・・
やだ!目を覚まして!いや・・・いやよ・・・!!
メリーゴーランドちゃあんっ!!!」
「・・・」
「歌ってよ。ほら!♪出し巻き卵のつくりかたぁ~きゅんきゅんいちご~いれちゃって~?びーむびーむぽよよよん…ほらぁ!!!」
「・・・」
ひいた。
言葉が出なかった。そいつは大声で泣きながら世界一不気味な歌を歌いながらダンスしていた。つまりは、この病室の光景は異様だ。いや、待てよ。二人も居るんだから病室を間違えてることはきっとないだろう。つまりは、みんな今こうやって泣いているのは梨乃のためだろう。
「梨乃ちゃん・・・」
老人が呟く。この老人は普通の知り合いだろう。そう考えると、こいつらは俗に言う普通じゃない関係のやつらなのだろうか。普通じゃない関係ってなんだろうか。ふと、青い髪の毛のヤツに問いかける。
「あの・・・」
「触らっっないでっっ!!!男きらい!!!びえーーーーーーー」
※触ってません
もう、言葉が出なかった。
しばらくして、また扉が開いた。体育会系の少年が大きな鞄を持って入ってきた。顔は真っ黒で背は小さかった。駆け寄るわけでもなく梨乃の近くに来て、くだだらけの梨乃を黙って見つめていた。しばらく見つめた後、少年は俺のほうを見た。
「りきさん?」
無愛想にそう俺に問いかける目は俺の瞳ではなく、俺の首のアザを見つめていた。なんとな手でアザを隠すと、少年の目は俺の瞳に写った。あ、
似てる。
「そうです」
「・・・俺、弟の昌司っていいます。」
「あ・・・どうも」
「弟!?」
青髪がこちらにいきおいよく食いつく。もう、ふんがふんが言ってる。昌司くんは表情も変えずに「ええ」と淡々と返事をした。
「メリーゴーランドちゃんに弟がいたなんてかんわいい~~~~」
おい俺のときと全然ちげえな
青髪は嬉しそうに派手なリュックからPCを取り出し、なにやらいじり始めた。動画を出すようだ。青髪は、「少々お待ちを」を連呼してキーボードを打つとき無意味に指を高く弾ませていた。つまりは癖があるとしか言いようがない。
「見てよコレッ刺される直前よ」
青髪が再生ボタンをいきおいよく押す。
動画は、ピンクのお部屋というか・・・個室にセーラー服にツインテール。セーラー服のスカートにはたくさんのぬいぐるみがくくりつけられていて、ぶかぶかのカーディガンを羽織っていた。顔は間違えなく梨乃だった。
あれ
待てよ
全然北海道にいねえじゃん・・・。
「みなさんこんにちわん~~♪♪メリーゴーランド星からやってきました。メリーゴーランドちゃんだよぉ」
そのまますぎて。
「きょうわわたしのミニチュアコンサートにきてくれてありがとぷんぷん。それでは聞いてください!メリーゴーランドちゃんの新曲で、たまごまる!
出し巻き卵のつくりかたぁ~きゅんきゅんいちご~いれちゃって~びーむびーむぽよよよん…」
アカペラで、棒読みで、棒立ちでした。
それまで、ノリノリだったってのに。
「深いなぁ」
オッサンが呟いたので、そっちをとっさに見てしまった。昌司くんは、動画を見ながら小さな声で「あ、気持ち悪い」とボソッと表情も変えず呟いた。青髪はというと動画に出ている本人よりもずっとノリノリで、その姿は踊れる豚にしか見えてこなかった。梨乃のことを【みらい】と呼ぶ若者も、その光景にだいぶひいていた。
どうやら梨乃は俺に内緒でコスプレアイドルをやってたらしい。アイドルといっても、メディアに露出するわけでもなくどこかの小さな会社の動画サイトで人気が出て歌を出すようになったらしい。まあ、小遣い稼ぎかね。この光景が本当に刺される直前だとしたら刺したのはファンっていうのもあり得るだろう。
「昌司くん。もしかしてメリーゴーランドちゃんを刺したのはこのメリーゴーランド系男子のひとりかもしれないわっよ!女子もいるけど!男のほうがあやしいわ」
「ん~ちょいまち」
若者が突然、手を挙げた。
「俺、前の日の夜・・・
みらいちゃんとセックスしてます」
エッ
俺はそのとき、ビッチを食べていた。ビッチビチにしていた。ビッチのけつやらなにやらビッチビチにしていた。それで上から目線で「ごめんな梨乃」とか「ビッチにもなれない梨乃」だとか抜かしていた。
あたもぉ あでぃもうず あでぃあでぃ もうずえにもう
洋楽が頭にこびりついている。
「みらいちゃんって誰よ!メリーゴーランドちゃんはそんなはしたないことしないわ!」
「いやいや、みらいちゃんは女王様だから」
「・・・女王?」
「つんでれSMパブの【みらいちゃん】だよ」
「なに言ってんだよ!これはみんなのアイドルメリーゴーランドちゃんよ!」
「うっせーなブス!!!これはみらいちゃんだっつってんだろ!!!!!!!」
「・・・美味しかった?」
「は?」
「は?」
俺はもう言葉が出なかった。足の力が完全に抜けてしまっていた。つまりはふにゃふにゃ人間だ。放心した俺は、梨乃を俺の好きな食べ物に例えて呟いた。
「あいつは・・・美味しかったか・・・聞いても・・・いいですか・・・」
その男の目は、とても見れなかった。少しの沈黙の後、男が少し恥ずかしそうに頭をぽりぽり掻いた。
「・・・・・ま、まぁ。・・・食べたというよりは・・・食べられましたが・・・」
「・・・あぁ・・・・そう。」
昌司くんが、俺のほうを見ていた。見なくたってわかる。こっちを見ていた。もう、腰が砕けそう。ていうか、きっと砕けている。そのうち、オッサンが追い討ちをかけるように拍手しながら口を開く。
「梨乃さんはたくさんの顔を持ってる。さすがは舞台女優。」
腰が砕けそうな俺は、笑うほど真剣にまっすぐ立って冷静を装っていた。
たた
少し落ち着いてから昌司くんが一緒にご飯を食べようと言い、二人で病院から近い洋食屋さんに向かった。青髪と老人と変態(自己判断)はこれ以上居ても喧嘩になりそうで、ご帰宅なされた。俺はいたって冷静だった。それよりかは、どうでもよかった彼女の魅力がどんどん引き出された気がして今の気持ちでは何故かどうしようもなく大好きになっていた。バカみたいだ。同時に、今ここに梨乃が居ない実感と悲しみが俺を襲った。やっとやってきた、この感情が。むしろ、梨乃がカノジョであるという実感すら遅れて今沸いてきた。都合がよくて結構。俺は気がついたらビッチをカノジョにしていたのね。
そんな風にうぬぼれていると、昌司くんは俺をじっと見た。
「姉のことはどこまで知ってるんでしょう、りきくんは」
とっさに【りきさん→りきくん】になったので少し違和感があったが、迎え合わせでこれだけ真剣に見つめられると緊張が違和感に勝ってしまった。目の前にあるナポリタンを少し豪快に頬張りながら、俺は正直に答えた。
「知らない。弟が居ることだって知らなかった」
「話さなかったですか?」
昌司くんは、姉のことを名前で呼ぶ。
「・・・話したのかも」
どおだっていいのさ。
今俺にあるのは、もしかしたら好奇心だけなのかもしれない。梨乃という俺のカノジョである存在が実はものすごく人気者で愛されているという事実にすごく天狗になっていた。ただひとつ、あの若者とセックスをしていたのは俺のプライドへしおれ。っていう感じだがあんなブス知るか。あ。ブスだって。
「仕事の色んな、顔があることは。知らず?」
「知るわけがないね。弟の昌司くんが知ってることに驚くわ。特にSMなんちゃら?とか」
男同士で洋食屋に来てるわけだが、昌司くんも俺に負けずとオムライスを頬張っていた。おっさすが体育会系。口にケチャップを付けたキュートな昌司ぽんは、一度止まってまた俺を見つめた。そして、別に嫌味なわけでもないが鼻で笑った。
「梨乃の将来の夢なんだと思います?」
「・・・」
「発明家」
「・・・へえ。」
「なんだと思った?」
「アイドルとか。あの様子じゃ」
「りきくん」
「あ?」
「血」
正面から人に指を指されるというのは、意外にもものすごく恐怖を感じた。俺はとっさに食べるのを止め、昌司くんと目を合わせた。よーく見ると梨乃に全然似ていない。そもそも、梨乃の顔を真心こめてじっくり見たことなんてあっただろうか。俺の口からナポリタンが溢れ出たままの、しばらくの沈黙の後、昌司くんの指差す俺のお腹を見た。
白いティーシャツが、真っ赤。
俺は立ち上がる。アザが痛む。耳がキーンとなって、また心臓の音がしなくなった。俺の口から飛び出たナポリタンがそこらじゅうに。や、待てよ?これはナポリタンのケチャップか?・・ちがう。ちがう。落ち着け。
「ちょ、トイレ」
焦る俺を見て、昌司くんはいたずらっ子の子供のように微笑んだ。その顔は、梨乃にそっくりだった。
トイレの個室に入って深呼吸した。恐る恐る、お腹の服をまくる。ヘソからどぽどぽ、血が止まらない。なんだ。なんだこれは。生理か?!痛みは無い。なんなんだ。何か俺の体に細工でもされているのか。貧血な、訳でもない。俺は死ぬのか?でも、ピンピンしている。電気屋さんでの、爆発音がフラッシュバックする。俺の体が、爆発?また歌が止まらなくなったら、恥ずかしいどころではない。逮捕。捕獲。それ決定。
とりあえず、便器にヘソを預ける変なポーズで待機してみた。よっこいしょ、ほーらヘソで立ちしょん出来たぁ~
はい。
とっさに鞄をまさぐった。ビッチの街で配られていたポケットティッシュを大量に。へそにあてがって、ベルトを巻いた。きっとこれでとりあえずは、昌司くんの話が、聞けるはずだ。なんだかそう思うと血も収まってきていた。きっと、呼吸も万全だし、大丈夫。後で病院に行こう。近いし。
そう便器の水を流す(大)。してから、個室のドアを開けると
「キャーーーーーーーーー!!!!!」
目の前に昌司くんがいた。ニヤニヤと笑っていた。これから何かしでかすクソガキのようだった。黄色い声が出ました。
「大丈夫かなと思って」
「いやっ、まあ。なんか、ケチャップじゃないか」
「面白い話がまだ、あったので」
「まだ」
二人トイレから出て、また席に着いた。ゲイだと思われたらたまったもんじゃない。相手は高校生。完全に変態なのは俺だ。なんだか短時間しか一緒に居ないのに、昌司くんと昔から仲の良い兄弟のような距離感になっていた。そう感じたのは俺だけかもしれないが。昌司くんは、俺がバカみたいに自分のオヘソと格闘してる隙にもうオムライスを食べ終わっていた。ひたすら、ホットミルクを飲むというナゾのパフォーマンスを繰り広げていた。
「スポーツ」
「え?」
「なんか、やってたんですか?りきくん」
「やー・・・別に。学生時代野球・・・とかかな適当に」
「・・・・俺サッカーやってて。すげー小さい頃からサッカーが恋人じゃないけど、小学校の頃とか、ボールと寝てました。」
早口で真正面を見ながら言う姿はなんだか、俺にとっちゃ笑えた。その瞳が、きらきら輝くのを見て、俺はこんな目をすることなんて一生無いだろうと思い、またナポリタンと愛し合った。よく、あんな血の量を目の当たりにしてナポリタン食べれますね。私。
「ふーん。サッカーに童貞でもあげたの」
正直、少しいい話だと思ったが。ワンクッション置いて、昌司くんは先ほどと同じきらきらした瞳で笑った。
「んで、中学校入ってすぐ、足怪我して、出来なくなりました」
一度食うのをやめてそちらを見た。が、昌司くんは言い終わっても微笑んでるような顔つきだった。
なんじゃそりゃ。同情すれと?フォローミー?俺を試しているのか?
「・・・やーあるって。俺も野球ずっとやってたけどさ。花咲かなかったしそうゆうもんよいつかは」
「でも姉が発明家になりたいという夢があったから」
「そんなの(笑)」
「タイムマシン」
「タイムマシン?」
「作ってくれるって言った。俺に」
「・・・」
・・・はい?
「足がこうなる前の俺に戻したる~って言って」
「え」
「丁度ほら、発明家になりたいから」
「・・・?・・・・・・??」
「で俺が今高校三年なんで、丁度去年」
「…」
「なんか梨乃ガチのタイムマシン作って。俺足、治っちゃって」
「・・・」
ナポリタンを、のどに詰まらせました。
涙と咳が止まらず喋れない俺に、まじめな顔で昌司くんは続ける。
「そもそも・・・俺の足は交通事故でだめになって。ひき逃げでした。後でなんか適当に謝りに来たけど梨乃はめちゃくちゃキレてて」
「・・・」
意地っ張りなところが、梨乃にはある。我慢強いところも、知っている。それを、最低な俺はバカにしていた。こころのどっかで、つけ込んで、梨乃は平気だろうってひとりにして。つまんなくなって、好きじゃなくなって、それでもキープして。
そんな自分との葛藤を隠すべく、水を飲んだ。昌司くんはそんな俺を見つめて、顔色も変えずに口を開く。
「そんで梨乃、そいつのこと家に呼び出して・・・・・・ぶん殴って殺しちゃって」
水を、全部吹き出した。
赤く染まったティーシャツは、水浸しでさらに汚れる。
「でも。自称発明家の卵だったから」
「自称ね」
「やっべ。と思ったらしくて適当に男に電気とか色々仕込んで生き返らせれちゃって何故か。本当にまぐれの、まぐれですが。」
「それは果たして人の形をしてるのか」
「してますよ」
「・・・」
「・・・」
「・・・あり得な 「りきくんだよ」
あの日のビッチのあえぎ声が、黒くなってフラッシュバックした。
ぎこぎこぎこ
じとじとじと
絡みつく汗
汗が止まらない。これは果たして、汗なのか
「発明品が、りきくん」
また、おれ自身から爆発音が鳴った。
バンッ
ばんばんばんばんばんばんばんばん
♪ばばんばばんばんばん(湯)
「嘘だろ」
しばらく笑って昌司くんを見ていたが、すぐにゆっくり立ち上がった。思い当たる節しかなかった。つい最近の、俺の体。嘘だ。気がついたら、いきおいよく昌司くんの胸倉を掴んでいた。店員が、爆発音を聞きつけてやってくる。心臓が、ばくばく、鳴っていない。嘘だろ・・・。何の音もしなければ、呼吸すら荒れていない。
「りきくん。まって」
昌司くんの声が遠ざかる。
不思議そうに爆発音の主を探しに来た店員ともとっくのとうにすれ違って、気がついたらまた走っていた。古臭い田舎くさい商店街。漫画みたいに果物屋さんや野菜屋さんがあって、俺はその中のどれかの山にぶつかって謝る余裕も無い。周辺を走ってみると、この病院の回りはすっかり田舎。俺は都会が好きだ。都会が向いてる。ビッチの村が好きで、ビッチを愛している。なんだこれは、今の俺に果たして性欲と言うものはあるのか。食欲ならどうだ。それは、ナポリタンによってゼロに近いはずだ。だが俺は止まれなかった。走るのをやめられない。もしここで止まったら、へそからまた液体が出て、臓器が爆発する音がするだろう。俺の体の中で花火でも上がってるんだろうか。ああ、こんなこと、あり得るか?梨乃ちゃん梨乃ちゃん。許してください。
信号が赤だ。
俺の赤いティーシャツを不思議そうに見る小さな子供がいたが、俺は息も切らさずその場で走っていた。子供は、指をしゃぶって子供らしく首を傾け俺を見る。外は、よく晴れている。人通りは多くないが、車が通る。なんて厄介なんだ。俺がかいてるのは、本当に汗だろうか。他人から見たらカメムシみたいにくさいが、俺にはその臭いが嗅げないかもしれない。
昌司くんの話は、はたから見たらすごく馬鹿馬鹿しくて、嘘だとわかりきってふざけるような内容だ。でもその感覚は、きっと今の俺には無い。
本当にあり得ない事などこの世に存在しないのかもしれない。ゴジラだって本当は居るんだ。ウルトラマンも。地球だってきっと本当は四角だったりとか。信号が
青だ。
「りきくん」
昌司くんがいた。真後ろに。少しだけ、体が強張る。
「昌司くん、俺だめだ。止まったらなんか…」
「止まってみなよ。大丈夫だよ、ずっと走ってたほうが逆に・・・
聞ききる前に、俺の意識が飛んだ。
たたた
意識が飛んだなんて、意識が飛んだ本人は気がつかないものだ。
よくあるオーケストラのような平穏な音楽が聞こえる。ここはどこですか。俺の体は、今一体何で出来ているんだ。
目開けた。薄暗くて古臭い臭いのする古き良き家の中だった。たたみ臭いくせにフローリングで違和感がある。誰の家だろう。俺は、どんだけ寝ていたんだ。なんだか、暗くて夕日が差し込んできていて、ほんのりシチューのにおいもした。頭から「ずーん」と音がした。またどうにかなっている。また・・・。俺の体の何割が一体人間じゃないのだろう。「ずーん」の音と同時に、少し痛みがした。
「おはようございます」
昌司くんだ。
「お、おはよ」
起き上がる。なんだかまだまだオーケストラの泣き声が聞こえる。アコーディオン シンバル なんかよくわからないラッパ なんかよくわからない指揮者。これはきっと、俺だけに聞こえている。その音にあわせてピエロが踊る。なんて可愛いピエ
「青い髪の毛のやつ」
昌司くんが話すと、オーケストラは音を外し静かになった。ふと顔を上げると、真剣な顔の昌司くんが、俺を不思議そうに見つめていた。
「かなぁ」
「なにが?」
「梨乃を、刺したの」
「・・・」
「どう思う?」
「違うと、思うけど」
「なんで」
「なんとなく」
「てえか、やばいっすよ。おなか」
とっさに服をまくり自分のお腹を見た。痛みは全くしないがぐちゃぐちゃのどろどろでこげこげ。へその周りがいびつにへこんでいた。もし俺が、普通の人間ならこの光景を見て嘔吐でもしてしまうんだろうが吐き気すら来ないのが普通の人間ではない証拠になっていた。「うっわ」とひいては見たものの、一番ひいたのは何も起きない自分だ。
昌司くんは異常に真顔だ。見慣れているのだろうか。
「じゃあ誰だと思いますか?」
昌司くんの顔にオレンジ色が差し込んで、それは青春の色をしていた。
そんなときに、狭い部屋のドアが開いて、おばさんが出てきた。おばさんはおばさんのようなピンクのエプロンをして見た目は若かった。
「ご飯、できたわよ」
その笑顔を見て、梨乃の母親だとすぐに気がついた。もちろん、何も思わなかった。
久しぶりに、食卓という空間でご飯を食べることになった。階段を降りるとシチューのいい香りがどんどん増していった。居間のジャラジャラしたのれんをくぐると、おじさんが居た。きっとお父さんだろう。頑固そうな白髪で新聞を読んでいた。「こんにちは」と頭を下げたがこっちには一切見向きもしなかった。そして、予想通り晩御飯はシチューだ。
四人で、食卓を囲んだ。多分だが、いつもの梨乃の席に、俺は座っていた。渡された箸も、赤のギンガムチェックだった。おじさんは新聞を読み終わると、俺に意外にも気さくに「ども」と言った。俺はかしこまってまた頭を下げた。そこからは四人で「いただきます」をして食器のぶつかる音だけが響いた。シチューは、味がした。こんな俺にもおふくろの味があった。こんな俺にも、というよりかは、俺は基本的にマザコン思考。俺にも姉がいるが、姉のことも大好きだった。尊敬していた。そんなことをふと、考えさせられたときに思った。俺がもし本当に中身が人間じゃないならこれを治せるのは梨乃しか居ないんじゃないか。ってことは
俺は無くなるのか。
「あなた」
おばさんが、おじさんのほうを姿勢よく見つめた。
「梨乃は、どうも起きないわ」
「そんなわけ、あるか。いつかは・・・」
「あんな変な子が誰に恨みをもたれたのかしらね」
「俺だってわからんよ」
「誰に」
食器がぶつかる音が、大きくなったように感じた。何故か、体が強張った。おじさんとおばさんの一言一言の間には独特な間があった。そしてどちらも不思議なくらい姿勢が良かった。黙々と昌司くんはシチューを頬張って、会話なんか聞いちゃいないようで俺も面倒だからそうしていた。結局のところなんでここで飯を食っているのかもわからないんだが。
「誰に」
はっと顔を上げると、三人とも俺のほうを見ていた。食器の音なんてとっくに消えていて、俺は動けなくなった。おじさんの首が、不自然に傾いたように見えた。
「誰に」
「・・・」
「私はあの青い髪だと思うわ私はあのおじさんだと思うわ私はあの青年だと思うわ私は」
早口で話すおばさんは、そこで一瞬固まった。
「貴方だと思うわ」
眼球の丸さがわかるくらいに開かれた目に俺は唾を飲んで何も言い返せない。息が詰まりそうに怖かった。呼吸が、荒くなっていく。こんな俺の呼吸が、ちゃんと生きてるみたいに荒くなっていく。
「ち、違いま・・・」
「わからない」
おじさんが口を開く。
「いまは、誰にもわからないだろう?」
俺の目をまっすぐ見ながら、また首が不自然に傾いた。あまりにも静かだった。
「誰にわかるって、いうんだ」
「それは・・・」
「探せよ」
おじさんが少し、俺から視線をはずして天を仰いだ。ふわふわと、虫でも目で追ってるかのような動きをしてから次第に口元に力が入っていった。俺は、昌司くんのほうをゆっくりと見た。昌司くんの顔はあまりにもいつも通りであまりにも冷静だった。
思い出した。もし、昌司くんの話が本当だったら俺は昔、昌司くんの足を・・・
「・・・いいから探せェ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!」
突然、おじさんは大きな声で怒鳴って俺に皿を投げた。息が荒かった。人間の、怖さを見た。人の狂気を見た、そんな気持ちだ。おばさんも無表情で俺を見つめて、冷静な昌司くんのようだった。それにしては眼球が飛び出そうな目をしていたが。時が、完全に止まっていた。ストップしていた。おじさんの荒い呼吸しか聞こえなかった。それが、切なく怪しげに響き渡っていた。
たたたた
気が付いたら俺は走っていた。いや、走ることしかできなかったのだ。きっと。
「りきくん、待って」
五分前。
昌司くんが、走り出す俺に冷静に声をかけた。片手には米。片手には箸。じっと俺を見つめる冷たい目。
「何かあったら、電話する」
なんで俺の番号知ってんねーーーーーん。
俺は走り出した。あてもなく。いや、俺はきっと今青い髪の毛のあいつの家に向ってるはずだ。ああ、どこでもドアがあったらこんな全力ダッシュせずにテレレレッテレー♪ってやつの家に参上して・・・ん?
PPPPPPPP
そこで携帯が鳴った。走ったのに汗もかいていない俺だった。相手は一人しかいない。
「はい」
『りきくんさ、どこいくの』
昌司だった。(もう呼び捨て)
「てかお前、タイムマシンって言ってたよな?さっき」
『まあ。』
「使わせろよ」
『……そうゆうタイムマシンじゃないんで。』
「なんだそれ、時間巻き戻したり進めたりできるっつう他にどうゆうタイムマシンがあんだよ」
『りきくん』
「え?」
『なめた口きくと莉乃に殺されるよ』
・・・・。
「えっ」
『タイムマシンを持ってるのは莉乃だけ』
「・・・じゃあ、刺されたって別に」
『いいから探しなさい』
そっから、俺の意識はとんだ。
【青い髪の毛】
走りまくったのに息切れもせずぐらぐら揺れる俺。俺?目をつぶっているのか開けているのかもわからなければ意識があるのか無いのかも。めまい。
ハンバーガー屋さんの透明なガラスに映る人魚のしっぽ。水の音。俺の中での人魚のしっぽって、こんなにキレイな色をしてたんだ。しっぽ。
人魚?
ぼーっと見ていた俺の人魚は、ようく見ると人面魚で、その水色からは光る二つの窓がはみ出しそのなかの景色は真っ赤だった。いいえ。真っ赤な顔した青髪の見るに見かねるデブがガラスに張り付きぺちゃぺちゃ言いながらポテトを食ってんの。
ポテト、食ってんの。
「うわあ・・・」
「△◎あ×ぬA◆!!」
「口の中・・・」
とある俺が大嫌いなファミレスのガラス窓だった。
メリーゴーランドちゃん
きれいだな。こんなにきれいなもの。見たことないのだ。
まず私には携帯電話があるでしょう?これはなんでしょう。誰かと連絡を取る機器でございます。小さな小さな連絡帳。ばれる。ばれる。私の居場所が。ここにいるのが。ばれる。恥ずかしい。
ちがうんだってば。
雨の日だったんです。しとしととしてた。みんなに好きだって思われたくて全部内緒にしてたけど、アイドルになりたかったし、ボーイズラブの漫画は大好きだし、オナニーは止まらないし。ほんと参った。自分に甘いし。小さなことだってすぐ気にする。自分の顔、この角度が誰に似てるとか、綺麗な芸能人にたとえていつも写真撮っていた。それも、携帯電話。私はこの便利な機器が大嫌いだった。
「笹川ちゃん」
そう呼ばれてたずっと。まあだけど、それも、雨の日。【中学校】
「卒業したら私のことなんて、忘れちゃうんだ」
「そんなことないよ」
私は顔は綺麗じゃなくとも、細くておしゃれ。で明るくて優しくありたかったのでそれなりに努力をしていた。割と女の子の友達も多くて告白されることも人並みにあった。付き合うかどうかは別として、つまりは順調で普通の中学生だったってわけです。
「うそだー」
「泣くんじゃないよ。私がミオちゃんのこと忘れるわけないじゃーん」
「ほんと?」
「あたりまえだよ。卒業、おめでとう。お互い。」
涙を浮かべたミオちゃんは、大きく頷いた。けど【高校一年生夏】
「あ!ミオちゃ」「誰?」
早かった。彼女の瞳からは私のデータが即座に抹消されていた。つまり印象に残らなかった。でも早かった。いやー早かった。私は必死に普通の人ごっこをしていたのに、世間一般的理想女子を演じていたのに。
気を使って生きるのはやめて、自分らしく!が一番だって学んだのサ。だから堂々として腐女子にあるかんじの大好きなアニメストラップとかぶらさげて男らしく「私はこお!」って言う生き方に変えたの。そしたら
「笹川ちゃん」
「あ?」
気が付いたら自分のこと「俺」って言ってた。つまりは最高としか言いようがない。女が話しかけてきた。つまりはありのままでも私は友達ができたんです。そう、思ってた。
ら
キスされた。それもべろっべろのぬっちょぬちょの
「あたし笹川ちゃんのこと好きでした・・・」
付き合い始めた。( 原因不明)
そして、すべてをさらけ出した。が、何かのきっかけでその女に病み期が到来。ツイッターで様々な性的な部分の秘密を言い触らされ、誰もかれも私と話すとき「へー」「う、うん」の二択。そして
刺された。
というよりは切られた。寝てる間に手首をつかまれカッターが当てられた。「イテ」と起きると、「死んでやる」と言われた。死のうとした場合お願いだから自分の手首を切ってくれと死ぬほど思ったがおれは彼女の目をいかにも真剣に見た。すると、彼女は泣きながらこう言いました。
「笹川氏はちんちんいつ付けるんだようっ!!( 絶叫)」
ちんちんなんてあってもどうします?
それから学校に行けなくなった。居場所がなくなった。が、私にとっちゃ天国だ。腐女子全開ミサイル発射ヒキコモリ万歳そして心療内科にGO
優しいおじさんが私を見守る。何も聞こえねえ。何も聞いちゃいなかった。そしておじさんの目を見つめてるうちに思ったんです。
「パフェ食べたい」
気づいたら口に出していました。
気づいたら髪の毛は伸びて、すっごい太ってた。ナルシストだった私は、外に出るのが怖くなって恥ずかしくなった。お母さんは学校に行かない私の部屋のドアの前にいっつも大きなパフェを無言で置いていくのでいつもパフェはどろどろ。マンガ読みながら、私の夢はずっと
「アイドルになりたい」
でも私は、こんな風に笑えない。
気が付いたら初音ミクになりたかった。声優もアニメもボーイズラブ以外はそこまで好きじゃないのに、なんでだろう。そう聞かれると、表情がないからだ。こんな私でも初音さんにはなれる気がしたのです。アイドルみたいに、笑えないけど。いつか、いつか・・・。
水色。こんなきれいなもの。見たことないのだ。もう、生き方なんてわからなくて気が付いたら私は生きていなかったのかもしれません。
そして出会ってしまった。
『皆様はメリーゴーランド星ってしってるかな??しーらーなーいー?バカッ!ばかばか』
彼女に。
ビビッ!!!!ビビビッ!
私はそれから彼女に会いたくて会いたくてコメントを続けました。メリーゴーランドちゃんにドはまりしてからというものボーイズラブの漫画を私は全部細かく破って窓から捨てた。
おかあさんに、怒られた。
花咲か爺さん。
路上の紙くずを拾い集めながら母は泣いた。いえ。泣き狂った。
とにかく三食、パフェを食べた。
【メリーゴーランドさんへ。ささりんです。アイドル目指してます。今日の生ライブ見ましたよ。てか、いつも見てます。だいすきです。メリーゴーランドさんみたいになりたい。どうしたらいいですか??】
返事は来ない。けど毎日
【メリーゴーランドさん。ささりんです。毎日毎日、メリーゴーランドさんを見てます!配信がない時も再生して・・・元気もらってます。実は私学校に行ってなくて、高校生なんですけど・・・つらいことがたくさんあったんです。今度その話も聞いてください。】
【ささりんです!今日ね、朝ご飯がいつもよりバージョンアップしててクッキーがはいってた!メリーゴーランドさんにも見せたいな!】
【初音ミクって知っていますか?魅力的なキャラクターです、わたしもああなりたいな】
返信は、来なかった。
「どうもーメリーゴーランドちゃんだよお~~~」
いつも通り、彼女は生きているのに、私が見えていないのだろうか。
【私もメリーゴーランドちゃんのように踊りたいです。どうしたらいいですか?】
【メリーゴーランドちゃんに会うには、どうしたら】
なんで
なんで返事をくれないの?
私のことが、きらいになっちゃったの?
ビビ、ビビビッ!
そんなとき、デスクトップが光ったのです。
「ハッ!!」
メリーゴーランドさんから返信がありました。と、その優秀な機器は言っていた。急いで震えた指で、そのメッセージを開いた。鼓動が高鳴る。初めて私の投げたボールが返ってきた。どっくん。どっくん。
【うるせえな】
メリーゴーランドちゃんは、笑顔のアイコンでそう私に言ったのです。
キュートなアイコンで、私に。自然と、傷つくというよりは驚きでした。なんでかな?私に心を開いてくれてるって、思った。初めて言葉で私の中に、入ってきた。言い放ったというよりは、私を見て言ってるようだった。仲間が一人もいなくて社会不適合者の私を。見てる。あなたは、見てる。
会ったことなんてないのに。
人は、文字だけに、同じ文字だけに何かを感じる時もあるのです。
メリーゴーランドちゃんは外にいる。私は、じーっとこの部屋の中に。この四角い箱の中に。つまりは、会う確率はゼロ。私はそれが悔しかった。つまり
パフェを食べた。外で。
私は一歩、箱の外に。
人の目が、暗闇に潜むコウモリの瞳のように怖かった。髪の毛で顔を隠して、髪の毛はぐちゃぐちゃ。おどおどとゆっくり、爪をかみしめた。昔普通だったことが、最も出来なくなっていてそれが怖いとも思わずただ、恥ずかしい。みんな私を見ないで。こんな私を好きになる人なんているはずがない。この世に。でぶでぶすで性格が悪くて腐女子でおまけに爪まで噛んでいるんだ。働けもしなければ貧乏でお金もない。
涙も出ない。誰もいない。
誰も。
家の近くの急な坂を息を切らして登っていた。わざと危険な街に行こうと暗闇を這って歩いた。こんなところに、私の幸せは隠れてるのだろうか。
「ぷひっっ!!!」
突然派手に転んで、変な声が出た。周りのみんなが笑っている。膝からは小学生以来の血がどばどばと出た。なんてみすぼらしいんだろう。いつから私はこうで、なんでこうなんだろう。死にたくもないし、死ぬ意味も分からない。もう死ぬのもめんどくさい。箱の中に戻りたい。そう思ったら、涙が出た。高そうなスーツを着た、偉そうな男が通りかかって私を見て笑った。横には、女を連れていて、私に聞こえるように見えるように笑って
「どんまい」とバカにしたように言ったのだ。
ドンマイで済んだら警察はいらない。私は世界で一番みじめで、可哀想で汚い。いいところなんて一つも…
すると隣にいた高そうなドレスを着た女が、その男の人をビンタした。驚きのあまり、地面を見つめていた私もそちらに視線を移す。
「アンタがどんまいだろ」
高そうな鞄から水のペットボトルを出して一気に飲み、その女は残りを男の人にぶっかけた。
その顔は液晶で見るより艶やかだったが、間違いなく私の神様。メリーゴーランドちゃんだった。
たたたたた
「なれそめを聞いてるわけじゃねえんだけど」
俺は強制的にオススメされたパフェを食べられずにいた。こんな女の目の前で飯が食えるか。と思ってしまったのである。
ポテトで艶やかになった青い髪の毛の女のクチビルを見て今にもゲボっちゃいそうだったが、昔の痩せた姿を見てみたいとも思った。青い髪の毛が少し伸びて根元が黒い。こいつのこの話しぶりで、もしこいつが犯人だとして莉乃を刺殺してしまったとすれば理由なんてたくさんある。恐怖も感じなければ奇妙さもなかった。彼女の前には俺の目の前に置いてあるものと全く同じ容器が空になって汚く置かれていた。
「私にはアリバイがあるの」
半べそを描きながら青い髪の毛の女は俺に語りかけようとした。
初音ミク。
俺の彼女が、神様だと?
青い髪の女
私の神様は私を守ってくれたのかと思いきや、私すらも睨み付けた。まるでメリーゴーランドちゃんの時の彼女とは別人で、挑戦的な目をしていた。
【うるせえな】
あの文字を思い出した。間違えなくこれは、私の神様だ。服装、行動、仕草が別人だとしても私にはわかるのだ。神様の香りがするのだ。男はべしゃべしゃのまま何も言わず、二人はホテルへと消えていった。わざと危険な街に来たのに、そこには神様がいた。
「おい、邪魔」
はっと振り返ると、怖そうな刺青だらけの若者数名が私をドラマみたいに囲んでいて、私は突然の恐怖に起き上がれなくなった。足から、傷からどばどばと音がしてきそうだ。ずっきん。ずっきん。
そいつらは笑い、私はサッカーボールになった。
早朝、でぶでぶすでみじめな箱の外に出たまま目が覚めた。なんだかすっきりとしていたが、体は血にまみれて更にみすぼらしい。危険な街で危険な目にあったことによって、足のどばどばが聞こえなくなったんだから、なんでだろう。すっきりした。だって私だって蹴るよ、こんなダメな女。
空が水色の早朝だった。涼しくて空気がきれいだが街は汚い。おっさんとキャバ嬢がいろんな方向から歩いてきていて笑っていた。笑うってことは、きみは楽しいのか。静かだなあ。
キイ、と扉があく音とともに少し離れてラブホテルのドアが開いた。朝になるとこんな色をしていたんだな、あの建物。
そこから神様が出てきた。化粧が崩れていなかった。相変わらずいらいらしたような顔つきで、昨日水をぶっかけられた男の人は居なかったが、私もラブホテルが何をするところかは理解していた。神様は私に気が付いて立ち止まる。軽蔑する目とは違う哀れみの目。
しばらく見つめあって私は自分が血だらけなことをやっと思い出した。私は神様に会いたくて箱から出ました。そしたらこんなに危険な目に
「あ、あのぅっ!!!」
勇気を出して、声を出した。神様は、しばらくして
微笑んだのだ。
メリーゴーランドちゃん!!!!!!!!!!!
「私、見てます。あなたのこと、」
「朝から甘いもんばっか食べたらだめだよ」
メリーゴーランドちゃんは私が見えていた。ゆっくり近寄ってきて、私を見下すようにしたが、微笑んだ。
「会いにこれたのに、踊れないの?」
「…え?」
「私みたいになりたい?もしくは、初音ミクみたいになりたい?」
私が血だらけなのを自分自身にも忘れさせるくらい、優しい声でメリーゴーランドちゃんは言ったのです。私は涙が出そうで、大きく頷きました。下唇を噛んで、涙は仕方がなくあふれ出しました。それを見てメリーゴーランドちゃんは私に視線を合わせてしゃがんでくれました。
そして微笑んだの
「嘘つき」
優しく。
「どこが似てるんだよ。なりたいなら、なればいい。髪の色すら違うのに、近づけてもいないのに何がなりたいのになれないだよ。笑わせないで。私から見たらあんたなんか豚にでもなりたいように見えるけど」
「…」
「『なりたい』なんて言葉知らない。『なる』って言ってしまえ。勝ちなんだから。ほら。会いたかったでしょ、会えないでしょ?どうしたら。って会いに来たんでしょ?来れたじゃん。この世にありえないことなんて存在しない、不可能なんてないってそれは間違えでこの世には不可能だってあるしあり得ないことだってどうにもならないことだってあるよ。それが果たして会いに来ることかね?私になることかね?完成系は無理だとしても私はそうは思わない。それをしないで私可哀想?まあ確かにかわいそうですね。生きてることが」
そう言い放ってから、メリーゴーランドちゃんはまた立ち上がって、いつもみたいに微笑んだ。そしてマイクを手にしたように
「みなさんこんにちは~メリーゴーランド星からやってきました~メリーゴーランドちゃんだようう★それでは聞いてください新曲で、いりびたり行進曲♪
流ぅ行ぁりぃの唄も聞こえなくてダサイはずのこの俺~~」
つんくだった。
人生で一番最高のライブを目の前で、独占した。
そこから私の人生は一変した。まずは髪の毛を水色に染めて初音ミクのコスチューム。そして腐女子の漫画も復活。パフェはお母さんに作ってもらわず、外で食べた。太ったままでも、自信が持てるようにメリーゴーランドちゃんを液晶で見ながら踊りの練習すらするようになった。そうしたら、アイドルになりたいだなんて思わなくなった。わたしは
わたしだ。
今ではパフェ屋さんをお母さんと経営していて看板娘になり、お店のキャラクターはぽっちゃりとした初音ミク。店内BGMはささりんが話すオリジナルラジオで曲は
メリーゴーランドちゃん。
「ちょっと」
「えっ」
メリーゴーランドちゃんがご来店。
「勝手に使わないで?」
その次の次の日です。メリーゴーランドちゃんが刺されたのは。
たたたたたた
「え?」
それだけ?
「感動すんだろ(巻き舌)」
青い髪の毛の奴は不気味に泣いていた。今の話を聞くとアリバイも無ければ、怪しい点すらない。というよりかは、莉乃と別人の話をしているようだった。
「ていうよりどうやって知ったんだよ。莉乃が刺されたこと」
「動画で出てたんだよ」
「動画?いったい誰が」
「俺です」
ふと窓を見ると、昌司君が張り付いていた。
「でもさ、メリーゴーランドファンはひとりじゃねーだろ?病室にはこいつしか」
「こいつってゆうなぁ!!!」
怒鳴る青い髪の毛の女を俺は二度見した。窓に張り付いていた昌司君は店内に入ってきた。いつもの無表情だった。
「ささりんは犯人じゃないよ、りきくん」
「信じられない、疑ってたの?!こんんの変態」
「なんだよこの無駄な時間は。アンタは当日、何やってたの?」
「お店の買い出しとか、いつも通り」
「だからささりんは犯人じゃないってば、りきくん」
「もーっっ!!むかむかー!!!」
「だからなんだよこの茶番は」
【あばばばばばばばばば
あばばばあばばばばばばばば】
体内からおばさんの呻き声のような音がして俺は飛び跳ねた。その瞬間、なごやかだった空気が一瞬にして火の消えた蝋のように固まった。俺の腹から、また血のような液体が出てくる予感がしたので俺は
「キャーッ!!なんなのよう!!!」
叫ぶ青い髪の女をよそに、また走り出した。昌司君はゆっくりと冷静に立ち上がり、お会計をしていた。モンスターにでもなった気分だ。店を出ると俺のきらいなベルの音が鳴りなぜか俺は目を瞑った。頭の中は、とあるラブホテルの一室だった。下着姿の莉乃が、血走った目でこう言った。
「あたしの胸ぐら掴んでよ」
その眼は純粋にも見えて、猟奇的にも感じた。
たたたたたたた
青い髪の毛の女は、はたして事件当日本当に仕込みをしていたのだろうか。そんなことは俺にだってわからなければ本人しかわからないが、昌司君が「ささりんは犯人じゃない 」と言い切ることに何故か絶対的な確信が込められていた。ように
聞こえた。
てーかあいつ、犯人知ってんじゃねえか?あーお腹がすいた。ビッチを食したい。ビッチビチに。
ガチャン
目が覚めると真っ暗な場所で俺は眠りについていた。どこか見たことある場所だ。怪しい光が暗闇をカラフルに照らす。実験室のような・・・。実験室?まさか。
「目覚めた?」
聞き覚えのある舞台調の話し方に振り向くと、そこには男がいた。俺はやっぱりお腹が血だらけで手は手錠で拘束されていた。男は、病室で莉乃のことをみらいちゃんと呼ぶ男だった。そして突然背中からカッターを出して、俺の目を見て少し舐めてから舌を切ったらしく嫌な顔をして
「俺は犯人じゃない」と言った。複雑な気持ちで俺は「まあ話は聞こう」と言った。
みらいちゃん
歌舞伎町の目立たない通りの地下にみらいちゃんは居た。異常に真っ赤に口紅を塗ってそれはテラテラと光っていた。
俺には彼女が居た。俺は役者の夢破れサラリーマン。収入も安定していてそこそこ美人な彼女と同棲もしていた。上司からもそこそこに気に入られていたムードメーカー。だが俺は役者の夢破れた記憶を自分の中で抹消していた。もう一つ、抹消している記憶があった。それは
高校生の時に付き合っていた彼女をレイプした記憶だ。
「おかえりなさい」
今の彼女とのセックスは至って普通だ。傷つけたくなくていつだって果てたフリをしていた。本当の俺は違った。自分を目覚めさせないように、付き合いで行った風俗もすべて女の子のお膝で寝ていた。
涙を流しながら、子犬のように。悪夢からは目を逸らして。
「ただいま」
彼女が、大切だった。結婚も考えていたが、そうするにはすべてをカミングアウトしなければならない気がした。それは、大切だからだ。お分かりだろうか。たまに夢を見てうなされる。レイプをする夢だ。犯す夢だ。俺はあの時のようにことが終わった後に吐く。吐いてしまう。すべてを忘れたくて、吐いても吐いても毒なんて出きってくれないんだ。毒なんて
毒なんて
「愛川」
「はい」
愛川秀三。誰に話しかけられてもハキハキと答えるのは劇団に入ってた頃の癖だった。いつでもキラキラとした白い歯で笑顔だったしよくあるうさんくさいドラマのイケメンのようなイメージだ。それが俺の
ポリシー。
「今夜、一杯行こうか」
課長と、なんとなく偉そうな人と、本当に偉い人と、俺の部下。五人でよくある居酒屋で飲んでいた。俺は部下からも慕われ、実を言うと自分に悪いところが一つも見つからなかった。しいてゆうなら、あの邪悪な泥だ。毒さ。俺の中で一生鍵をかけた、あの毒。
いつもの流れというか、わかってはいたが、帰りは風俗に行くというコースになった。やれやれ、と思いながら笑っていると、酒に酔ってべろべろの部下が突然の挙手。
「俺!!実はドMなんです!!」
街中でそんなことを大声で言いだしたので俺はそいつの頭をとっさにぶっ叩いた。
周囲が吹き出す。大爆笑の渦だ。俺だって笑いが止まらなかった。
「皆さんを連れていきたいお店がありますっ!!」
突然狂ったようにそいつは言いだしたので、からかい半分、皆でそいつについていった。俺はやっぱり、やれやれという様子だったが部下は俺に耳打ちする。
「バケモノが居るんですよ、先輩エロですか?」
「男はみんなエロに決まってるだろ」
「あんな美人の彼女が居るのに・・・ひひひ」
「そっちのほうが健全だろ。男として」
「先輩、」
そこでだ。
「みらいちゃんを指名してください」
たたたたたたたた
「出会ってもいねえじゃねえか」
手錠をかけられた手首は痛みもせず。だんだんと自分がロボットのように思えてきた。何かの絵本を読み聞かせられてるようにワクワクした気持ちで、お腹からはオルゴールの音がしそうだった。ていうか
した。
「今の俺と全然違うとか思ったか」
「まぁそこは申し訳ないけどどうでもいいんですよ」
「まあ俺は思うんだよ」
「何を」
「みらいちゃんの彼氏がお前みたいにつまんない奴の訳ない」
俺自身が思ってたことだった。俺の彼女がこんなにつまんないなんて・・・。そんな風に、俺は莉乃に対して思っていた。自分を棚に上げて。そいつは、身動きが取れない俺の顎を掴んだ。
「エムなんですかエスなんですかね」
「人は皆両方」
「・・・あそ」
愛川秀三
歌舞伎町の地下に入ったところで怪しいカーテンを抜けると【ツンデレSM喫茶】といかにも怪しくて汚い字がお出迎えしてくれた。古びたビーズのカーテンをくぐると強そうな男が俺らに微笑んだ。無駄に声が高かった。
入り口で見た写真の【みらいちゃん】という名前の女の子はずば抜けて可愛くも無ければブスでもなかった。自己PRには【あなたの心癒します】と至って普通。こいつは、俺をハメているんじゃないかと部下を睨んだ。
「感想、宜しくお願いしますよ」
ヤらねえけどな。そう思いながら俺はニヤニヤして見せた。タイプじゃなかったとでも説明しておけばいいだろう。近くのホテルに向かった。バケモノとはなんのことだろう。なんだか笑える。はしゃぐ課長や偉い人たちと一緒にはしゃいでるふりをした。これも、いつも通り。ホテルに着くと、俺はネクタイを外した。みらいちゃんという女性はSなんだろうかMなんだろうか。どうせなにもしないからいいのだが、Sっ気出されて突然暴れだしたら面倒くさいな・・・。
なんだかユウウツで、帰りたくなった。
ホテルの室内はそこまで広くはなくて、御洒落かというとそうでもなかった。エメラルドグリーンと青を基調とした色でまとめられた神秘てきな・・・
ガチャと音がした。
写真より背の小さな、みらいちゃんが、童顔スマイルで入ってきた。少し純粋そうに照れて「はじめまして」という唇は真っ赤だった。なんだか、店の名前とイメージが違いすぎて困惑しつつ「どうも・・・」と言った。心臓が久しぶりにバクバク鳴っていた。わざとだろうか。偶然だろうか。彼女は
女子高生の制服を着ていた。
「緊張しちゃいますよね、突然」
「いえ、あはは」
「どうかしました?初めてかな?」
「いえ。別に」
彼女は、俺の目を見つめて何かを見透かしてるようだった。直視できない俺の隣に、彼女は座った。
「こんな恰好なんで、高校の時の思い出でもきかせてもらえませんかね?」
俺は一瞬固まって唾をのんだ。みらいちゃんは俺の手を握り不自然に首を傾げた。
「あの、俺、実はそうゆう気分じゃなくて。付き合いで来てるんです」
握られた手を振り払って、いつものように少し離れた。
「そんな訳ない」
「・・・」
「こんなに・・・」
淫靡に俺の股間を触る【みらいちゃん】。
「違うんだ!すまない。」
確かになぜか俺はムラムラしていた。とっさに浮かんだのは彼女の顔だ。ぐるぐるてらてらと、みらいちゃんの唇と家で待つ彼女の顔が俺の頭の中を巡っていて、その中に高校生の時の彼女もいた。
変な汗をかく俺の隣で、みらいちゃんはずっと首を傾げていた。そしてしばらくの沈黙の後、こう言ったのです。
「知ってるよ」
そして、俺の震える手を掴んだ。
「話してごらん」
は な し て ご ら ん 。
知ってるのに、話してごらんなんて言わないでしょ。まあ、風俗嬢に昔の話を相談するのは慣れたものだ。俺は子犬のような泣きそうな瞳で話すがきっと、風俗嬢は「ラッキー」「何このキモ男」って思ってるんだろうな。
世の中・・・なんて汚いんだ。
「覚えてるの?」
「えっ?」
クラシックの音楽が流れる舞台で悲劇のヒロインだった俺は、現実世界に引き戻された。
「その子の顔」
「・・いや」
「自分が吐いたことと、後悔しか覚えてないんでしょ」
「・・・え、あ」
「ダッサくて最低な男だねー!!!!」
と、明るくみらいちゃんは、俺の目を見て言った。
【高校生】
俺の彼女はバドミントン部だった。高校生の俺は童貞で、初エッチはもちろんこの彼女だった。ポニーテールの黒髪で、彼女の処女も俺が奪った。クラスで人気の清楚系美人、自慢の彼女だった。のだが
ある日いつも通り彼女の部活を待っていたら、異常に帰りが遅い日があったのです。
心配した俺は、校内を探した。メールも来なければ電話も出ない。俺は探し回った。もう外は真っ暗で肝試しのようだったが俺はそれも気が付かなかった。真夏だった。汗が顔から噴き出した。そこで、ふんわりと理科室に小さな灯りがついているのが見えた。俺は息をのみ、思い切りドアを開けたのです。すると、そこに彼女は居ました。ポニーテールは乱れ、口にはガムテープ。理科の授業の先生に抑えつけられて挿入される寸前でした。理科の先生はといえば見た目はドスケベの若白毛。授業中と別人で、涎を垂らしていたが俺を見て真っ青な顔をしていた。俺の女に何をする。普通の神経ならそう思うじゃないですか??でも俺はその光景を見た瞬間「いいなぁ」って思ってしまったんです。AVでよくあるシチュエーションに燃えちゃって。涙でぐちゃぐちゃになった彼女の顔を見て最高に嬉しくなってしまって。つまりは私は異常なんです。ドエスなんですよ。そして
参戦しました。
終わった後、手が震えました。彼女は私を睨み付けてその視線は私を逃がしませんでした。理科の先生は嬉しそうだったが私は彼女の目の前で何回も吐きました。何回も。何回も。涙が止まりませんでした。彼女は学校に来なくなりました。当然です。俺は、誰なんだ。何回も毒を体から、出そうと吐いて 吐いて 吐きまくれ!!!!
「いて」
ビンタされた。(グーで)☆ もはやビンタじゃない ☆
みらいちゃんは、俺を現実世界に無理矢理引っ張り出して胸ぐらを掴んでニヤリと笑った。俺をベッドに押し倒し、今度は不安そうに俺を上目づかいで見つめた。
「今度は私が犯してあげるよ秀三君」
『秀三君』。確かあの子も俺をそう呼んでいた。助けてくれと叫びそうになった。手が震えて全身動かなかった。フラッシュバックして吐きそうになった。とでも言えたら、どれだけ楽だったか。どれだけ気持ちが楽だったか。でも俺はそのスリルを体に焼き付けてしまった。わざとかのように女子高生の姿をするみらいちゃんはあの時と同じにおいがした。順序行動すら、あの時の俺を見ているようだった。乱暴だが猟奇的な言葉を浴びせるわけでもなく、ただゆっくりと、ねっとりと。
楽しそう。あの女は、彼女は、楽しかったのだろうか。だが同じことをされた俺はみらいちゃんをあんな風に睨み付けることがあるだろうか。俺を睨むあいつの、あんな目で。俺は何で吐いた。なんで毒を外に出そうと必死だったんだ。つまりは
俺はドエムなのか。
みらいちゃんは
秀三君を
ぶんなぐった
「私の中に入れたいならもっといい男になってね」
最終的に手だけでさいっこうに飛んだ!!
目が覚めるとすごく頭がぼーっとしていた。
ぶんなぐられたからなのか快感によるものなのかわからないが、信じられないほど心地良かった。窓から朝日が差し込む。隣には制服を脱いだ君。高校の時の、校歌でも歌いたい気分です。なんて優雅なんだ。俺は
ドエム、だったのか。
「あはは」
なんて優雅で ♪ヨーレイヒー
「あははっあははは♪」
朝一でみらいちゃんにハイキックされた。
俺にハイキックした後のみらいちゃんは「うるさくて寝れやしねえんだよ」とボソボソ言いながら寝床に戻っていった。
「ねえ、もっかいエッチしない?」と自信なさげに言ってみると「一人でしてろよ気持ち悪い」と言われた。俺は思ったのです。なんだこの最高な女は。あんなにセックスが嫌いだった俺は、その店の常連になった。が
「離婚しましょう」
俺は変わってしまったのです。みらいちゃんを自分のものにしようと思った訳ではないですが
「えぇっ?」
俺ははっきり言えば理想の彼氏で、彼女もきっとそこが好きだった。普通のカップルには必ず訪れるマンネリ化も俺らには無かったし、仕事は安定。浮気もしないで風俗も行かず優しくて・・・。それが作り物だったわけではないが、俺は誰もに隠していた過去を打ち明ける相手が彼女の他に出来てしまったことで性格も何もかも、つまりは日常が一変してしまった。もちろん、無意識ですが。というよりもともと離婚とはいっても結婚はしていないんですけどね。彼女は、泣いていた。まっすぐ俺の目を見て。純粋に虚しい気持ちにもなったが、俺は、またもや彼女を犯したい衝動に駆られて手が震えました。痙攣して、止まらない。俺は鬼なのかそれとも子犬なのか。
たたた

