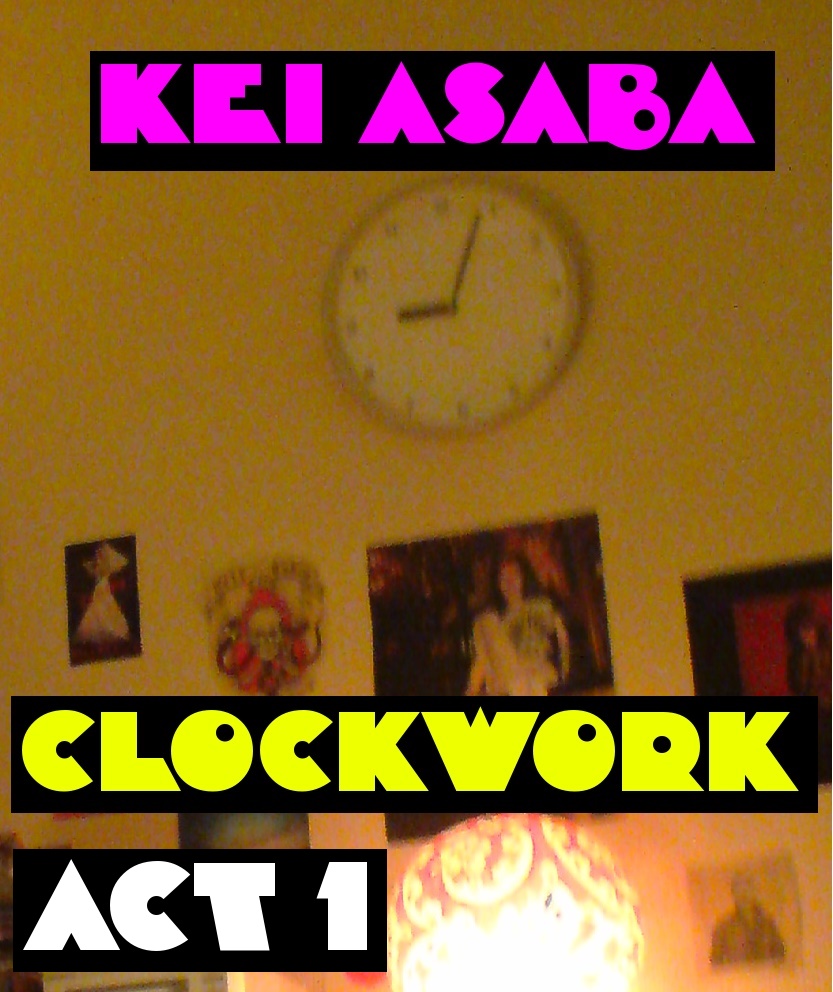
クロックワーク(上)
第1章
阿理沙は美しい二十歳の女だった。幼い頃に海難事故で両親を失い、母親の姉夫婦に育てられた。おじさんとおばさんは優しかったが、あまり裕福ではなく、加えて阿理沙より年下の娘を二人抱えており、一日でも早く誰の世話にならないで独立したいという想いは彼女が成長するにつれ大きくなっていった。
幸いにも彼女には人並み優れた容姿が備わっていた。中学を出てすぐに上京し、大型アイドルグループの一員として活動するようになった。
当時は人気に火が点く直前で、間もなく国民的な知名度を得ることになるそのグループにおいては、個人的な支持をどれだけ獲得できるかというメンバー同士の競争原理が命題的に組み込まれていた。彼女はチャンスを掴むべく精力的に芸能活動に打ち込んだ。元来の努力家であり、何かを成し遂げるということに対する貪欲さもあった。
しかし時代は阿理沙を選んではくれなかった。端正な顔立ちとモデル並みに高い身長、天性のスタイルの良さはアイドルのイメージにそぐわず、外見の強気な印象とは裏腹に自分が目立つような場面になると気後れしてしまう性格も災いして、大して人気の出なかった彼女はやがてグループを脱退した。
小規模なプロダクションに所属し、いつか芽が出ることを望みながらモデルや女優の真似事で食いつないできたが才能の乏しさは如何ともしがたく、徐々に肌の露出が多くて頭を使わなくてよい仕事ばかりが回ってくるようになった。ライバルは蹴落としていかねばならない芸能界で、阿理沙は少し優しすぎた。
生活費の足しにと水商売めいたこともやってみたが、性格的に長くは続かなかった。彼女は地元出身のアイドルとして期待されていた。親戚だけでなくもっと大勢が活躍を見守っているはずだった。それがあっという間に、週刊誌の低俗なグラビアであられもないポーズをとるようになって、制服風の衣裳で巧妙に隠されていた豊かな乳房は最早紙面からはみ出しそうな勢いだ。
このままでは帰れない。だが焦りや苛立ちが募ってきて、次第に仕事上の人間関係もうまくいかなくなり、業界における彼女の立ち位置は望まぬ方向へ進むばかりだった。プロダクションはもう自分を単なる商品としか見ていない。腹を割って話し合える仕事仲間にも恵まれず、言い寄ってくる男は例外なく体が目当てだった。
次第に部屋に閉じこもりがちになり、まるで切れ味がだんだん鈍っていく包丁のように性格も暗くなっていった。健康的な肢体の上に乗った顔には日に日に見えない皺が刻まれ、用意される衣装はだんだん過激になっていき、彼女に期待される役割はもはや性的な興味を惹くだけの大量消費型の商品でしかなく芸術性の欠片もなかった。阿理沙の境遇は、あとはもうAV女優にでもなるか、というところまで来ていた。
季節は春、天気のいい土曜日。阿理沙は昼近くに起きて眼鏡にジャージ姿で日課のオンラインゲームに精を出していた。
ほとんど仕事のない彼女は時間を持て余しており、どちらが本職か分らなくなるくらいゲームの世界に没頭していた。ナイトとして仲間の先頭に立ち魔物を倒している最中、携帯電話が鳴った。普段ならもちろん無視してダンジョンを進んでいくところだが、画面には育ての親の名前が表示されていた。仕方なく阿理沙は、チャットで「電話きた」と打ち込み電話を取った。
元気でやってるか、最近仕事はどうだと一人暮らしの娘を心配する一連のやり取りのあと、母の姉は意外なことを阿理沙に依頼した。
親戚に若くして彫刻家を志す男の子がいた。それが東京のどこかにいるはずだが所在が分からないので、今日一日かけて探してほしいというものだった。
それは行方不明になっているということか、と聞くと、こちらではあまり聞かない地元九州の訛りで、そういうことやね、という返答が返ってきた。警察には届けたのか、と阿理沙が真剣な声になって聞くと、ちづるおばちゃんは呑気に答えた。
「あの子のわがままは、昔からやもの。堅苦しいのが嫌になったか、ちょっと羽を伸ばしたくなってふらふらしてるに決まっちょるんよ」
有馬総一郎、という小説家がいて、どこの本屋に行っても著書が置いてあるくらい有名だった。ただし難しい内容の話ばかりで、阿理沙は一度も読んだことはない。その小説家は、死んだ父親の従兄弟にあたる人物だった。
有名人を親戚に持つということは阿理沙にとって少しだけ自慢の種だった。父方の家系をたどると、古くから地主をしていた有馬家という一族に行き当たる。
本家の跡取りである総一郎は若い時から無頼漢で、ボンボンのドラ息子と周りに揶揄されていた。本家と言えど、もはや持っている土地も少なくなっているし一族の威厳や繋がりも昔ほど大したものではない。それでも親戚一同は、有馬家もこれで終わりかと心配していた。だが、若くして作家としての地位を確立してからは多少分別がつき、一族の長兄としての自覚も身についたようだった。
総一郎は、従兄弟の遺児の学費等を援助すると申し出て、ちづるおばちゃんにお金を送ってくれていた。ちづるおばちゃんは頑として最低限の額しか受け取ろうとしなかったが、それでも十分な額を毎月送ってくれていることを阿理沙は知っていた。
総一郎は地元を離れ、東京で執筆をしながら派手に遊んでいたようだが三十六歳のときに恋人だったカヤという若い女に子供を身籠らせ、そのまま結婚した。画家であり自由奔放な性格をした母親との間に生まれた子は、幼い頃に彫刻の才能に目覚めた。国内外のコンクールでいくつも賞を取り、まだ一七歳だが、すでに世界を股にかけて活躍している。
阿理沙のハトコにあたる泰河は、阿理沙が上京するのと時を同じくして中学生になった。カヤは子育てはもう十分だと考えたらしく、創作活動を再開し一年の大半を海外で過ごす生活を始めることにした。それを受けて総一郎は、自分と息子の創作活動のために静かな環境がほしいと、地元のかなり奥めいた場所に山荘を建てて移り住んできた。阿理沙と泰河は、東京と九州で丁度入れ違いになったのだった。
執筆活動で忙しい父親と中学生が二人暮らしをするその山荘は家事が常に滞りがちで、ちづるおばちゃんが毎週押しかけるように通って世話をしていた。その日の午前中にも行ってきたばかりだが、数日前から一人で東京に来ている泰河が行方をくらましたという電話が山荘にかかってきたのだという。
まさに芸術家の鏡というやつで、泰河は変わり者であるだけでなく、昔から何でも自分の思い通りにならないと気が済まない性格だった。親戚の集まりでは決まって大人たちを困らせ、葬式があった時などは自分が死に化粧をやってみたいなどと言い放ち、福岡の田舎で一生を終えたおばさんをマリリン・モンローみたく仕立てあげてみせた。
「プチ家出みたいなもんか、じゃあ心配ないね」
阿理沙は安堵したが、泰河は外国の美術関係者との重要なアポイントメントをすっぽかしているらしい。
放任主義の総一郎は、またかと呆れるだけでまるで気にしておらず、ちづるおばちゃんも大して心配しているわけではないが、泰河の将来性のために一応阿理沙に声をかけてみようと思ったという。
「あんた最近泰河君の顔みてないやろ? どうせ最近暇って言いおおったし丁度いい運動になるが。写真送っとくから、見かけたら逃がさんごとつかまえとって」
そう言われ電話は終わった。この人は、東京を一体なんだと思っているのだろうかと呆れ、再び魔物を討伐する作業、いや冒険に戻った。おそらくちづるおばちゃんは半分以上本気で言っているのだろうが、阿理沙は本気だと思わないことにした。
次に携帯を確認したのは、日が暮れてきて家を出ようとするときだった。
ひょうきんな悪ガキだった泰河は、ミュージシャンみたいな線の細い優男になっていて、顔はまあまあ悪くなかった。千鶴おばちゃんからのメールには、特徴=背が高いと一言だけ。そんな男は東京じゅうどこに行ってもいる。今更ながら少々罪悪感を感じたが、探偵でも何でもない自分に探すことなど到底不可能だと分っている。それでも一応、目的地に向かう途中ですれ違った通行人や電車の同じ車両に乗り合わせた人の顔は律儀に確認した。
阿理沙の用事は、かつて同じアイドルグループに所属していた仲間と定期的に集まる、いわゆる女子会だった。渋谷駅で待ち合わせて小洒落た居酒屋に繰り出す。阿理沙のように芸能活動は続けているがいまいちパッとしない子もいれば、完全に引退してフリーターをやっている子、OLになった子、専業主婦になって茨城県に引っ越し、わざわざ今日のために出てきた子もいる。
阿理沙の数少ない、というか唯一の心許せる親友たちだった。皆明るく笑い、よく飲みよく食べた。起きてから寝るまで一言も発さないこともある阿理沙だが、その晩は一か月分くらいまとめてお喋りした。
どんなに苦しい境遇にあっても、このメンバーで集まる時だけは昔の自分に戻ることができる。かつて志を共にし、同じステージで戦った戦友たち。ゲームの中で毎日毎日長い時間を共にする戦士や魔法使いにもそれなりに友情を感じてはいるが、実際に会い、生身の声や肌で触れ合うのはやはり特別な感じがする。
誰もがまだ若く生命力に溢れていて、こまめに集まっているからなかなか気付きにくいが、着実に年齢を重ね目に見える部分も見えない部分も少しずつ変わっていた。その変化を寂しいと感じる気持ちもあるが、かけがえのないこの子達と一緒に年をとっていけるということは、なんて素晴らしいことなんだろうと思っていた。
「私たち、おばあちゃんになってもこうやって集まろうね。そして再結成して歌って踊ろうか」
「また阿理沙は、酔っぱらうとすぐそれなんだから」
周りが爆笑に包まれる。お酒のせいで体がふわふわしている。テーブルの周りにはそれぞれが今日のために持ち寄った汗とか涙とか、それからお互いを好きだという感情が漂っているみたいな気がする。全てに、乾杯だ。
やがて会はお開きとなり、彼女たちは渋谷駅へ向かって歩いていた。酔っ払いは阿理沙たち以外にもたくさんいて、肩を組んで歌っているおじさんなんかもいる。この時間のスクランブル交差点は、ちょっとしたお祭り気分だ。信号が青になり人の流れが動き出した瞬間、ある異変に気付いた。
悲鳴や不穏な物音とともに、人の群れの端っこが崩れていくようだった。よく分らない黒い塊のようなものが、阿理沙たちの方へ近づいてくる。一瞬の出来事だった。
それがよく見える距離まで近づいた時、阿理沙は声を失い体を強張らせた。人が跳ね飛ばされ、宙に浮かび、血を吐いて薙ぎ倒されていく。小山のような黒い塊は大型トラックで、土曜のスクランブル交差点に速度を出して突っ込んできていた。
トラックは金属的な音を上げ阿理沙の目と鼻の先を掠めて走り去り、駅前交番にそのまま吸い込まれるように向かっていった。ガラスが割れ建物が揺れる大きな音がして、一瞬の静寂の後、呻き声も泣き声ともつかない奇妙な音が現場一帯を覆いはじめた。
阿理沙は転んで腰を強く打ったが、特に怪我はないようだった。服が誰かの血で汚れている。とっさに友達の姿を探したが、すぐに見つけることはできない。
トラックの付近からひときわ大きい悲鳴が上がりはじめた。銃声のようなものも聞こえた。一人、また一人と交番の逆方向に全速力で走って逃げていく。そこに近い人間から順番に事態を察知し始め、現場は混乱の度を増していった。次第に人の壁が薄くなり、阿理沙の目に映ったのは信じがたい光景だった。
特殊部隊のような黒づくめの服を着た連中がトラックの荷台から降りてきて、大きな刃物で片っ端から人を刺していた。連中は二、三人ではなくもっと大勢いた。全員目出し帽を被っていて顔は分らない。傷口から溢れる血は映画のように派手に吹き出したりはせず、赤というより黒に近いどろっとした色をしていて、静かに大量に地面に流れていった。
阿理沙はいつの間にかその場にへたり込んでいた。誰かが彼女を抱え起こそうとしてくれたが、石のように動けなかった。逃げろ。早く逃げろ。そう聞こえた気がしたが頭の中で意味を結ばなかった。
やがて彼女は、目の前に横たわっているのが親友の一人であるのを発見した。綺麗な巻き毛の後頭部をこちらに向けて、手足が四本ともあらぬ方向に折れ曲がり、片腕の肘から先はなくなっており、腹からピンク色の内臓が飛び出ていた。親友の体に駆け寄ろうと、彼女は這った。地面は揺れていて、地震かと思ったがそうではなく自分の体が震えているのだと分かった。息が苦しかった。
必死の思いでようやく彼女の肩に手をかけられるところまできた。死んでいると思った。事故で今死んだばかりの人間をこれまでに見たことはないが、そんな状態で生きているわけがないと思った。実際に触れると、その肩の感触は生きているときと変わらなかった。奇跡を信じて阿理沙はゆっくりと顔を覗き込んだ。
彼女とはグループに加入したのも、そして脱退した時期もほとんど同じだ。脱退する前は、仲が良かったわけではない。だから悩みを相談したりされたことはない。だが脱退してから話をするようになって、似たような悩みや苦い経験をしていたということが分かり、もう他人だとは思えなくなった。
身長は同じくらいで顔立ちも少し似ていて、昔ファンから姉妹じゃないのかと疑われたこともあった。仲が良くなってから、阿理沙が会話の中で冗談めいたことを言うと、いつも率先して的確な相槌や突っ込みを入れてくれた。最近でも誰かとコミュニケーションしたくなると、真っ先にメールを送るのは彼女だった。それが、鼻と口から血を流し目を開けたまま死んでいた。
駆けつけた数台のパトカーを認め、連中は肩掛けにしていたサブマシンガンを向け躊躇せずに撃った。パトカーの近くにいた白髪の老女の頭が赤い風船のように膨らんでしぼんだ。阿理沙はその風景を、音の無い、涙で滲んだ映像として見ていた。
もう阿理沙は怖くなかった。感情は怖いというレベルを既に越えていた。自分も死ぬと思った。今夜自分が死ぬことになっているのであればもう逆らえないと思った。阿理沙の中に残っていたのは、ただ一つだけ、これ以上自分の大切な人を奪うな、という意思だった。
警官たちは劣勢にあったが、黒づくめの連中の一人に数発の弾丸を命中させることができたようだった。数名の警官がそれに飛びかからんとした時、黒づくめはポケットから素早く何かを取り出した。
黒づくめと警官は、爆発音とともにバラバラの肉片になって飛び散った。連中は警官と応戦する勢力と、一般市民を惨殺する勢力に分かれ、阿理沙の方へ少しずつ近づいてきていた。
数メートル先に座り込んでいる女が、はっきりとは分らなかったが、別の友達であるように見えた。これ以上、自分の大切な人を奪うな。阿理沙は立ち上がっていた。無意識のまま、ふらふらと歩いていった。
気が付くと、目の前に黒づくめがいて、阿理沙は両手を広げて立ちはだかっていた。あれ、私はいったい何をしているんだろう。逃げろ。早く逃げなきゃ。でももう遅い。一瞬の思考ののち、凶刃が阿理沙の体にまっすぐ向かってきた。
覚悟して、目を閉じた。何も起きなかった。
何者かが横から割り込んできて、それを止めていた。さっきまで無残に横たわっていた巻き毛の親友だった。
腕の骨が折れるばきばきという音がした。二人はしばらくもみ合いになり、やがて黒づくめが仰向けに組み伏せられる形になって、見覚えのある靴のヒールがその喉元に深く差し込まれた。
一番近くにいた別の黒づくめが異変に気付き、発砲した。親友の体は大きく揺れたが、あとは何事もなかったように立っている。顔を見ると、先程と同じで、無表情で土気色で、目に生気がなかった。
「よしみちゃん?」
阿理沙は呼びかけてみた。よしみちゃんは悲しそうにうつむいたように見えた。そして緩慢な動作で離れていき、発砲した奴の喉笛に噛みついた。
異変は至る所で起きていた。死体が次々に起き上がり、猛烈な力で黒づくめを制圧しようとしていた。女の死体も子供の死体も、成人男性のそれよりはるかに強い筋力を得ているようだった。そして刺されても撃たれてもまるで意に介していない。
兵隊の数は、黒づくめの方が圧倒的に少数だった。連中はじりじりと後退を始めた。追い詰められた黒づくめの一人が手榴弾を取り出し数体を巻き添えにして自爆したが、死体は上半身だけになっても這い回り、黒づくめの脚にしがみつき組み倒して頸動脈に食らいついた。
もうよしみちゃんは死体の群れに紛れ見えなくなっていた。それでも阿理沙は立ち尽くしたままその背中を追っていた。暑くも寒くもない春の夜だった。嫌な感じの熱や匂いが充満していたが、一陣の風が吹いてそれを取り払った。
黒づくめはやけくそになって敗走を始め、散り散りになって逃げていく。そして蟻の群れに食われる虫のように、無数の死体に取り囲まれ一人また一人と四肢を引きちぎられていった。
阿理沙のところへ、包囲網をすり抜けて走ってくる黒づくめがいた。すれ違いざまに阿理沙を襲おうとした刹那、今度は死者ではなく、生きた人間がそれを救った。
男は離れた場所からありえない速さで阿理沙の横まで移動してきたように見えた。そして刃物が振り下ろされるより先に、数発のパンチを叩き込んだ。それも速すぎて阿理沙には何をしたかよく分からなかった。
阿理沙はその男を見た。背丈はゆうに一八〇センチはありそうで、線が細くミュージシャンのような雰囲気を醸し出している。顔にはどこか見覚えがあった。そして、その男は自分が探していた人物だと気付いた。
「運が良かったな。頼むから、俺のことは警察に言わないでくれ」
男は落ち着いた様子で歩き去ろうとした。阿理沙は、その背中に声をかけた。
「泰河、くん?」
男はぎくりとして振り返り、阿理沙の顔を認め、ばつの悪そうな表情になってみせた。
「もしかして、阿理沙ねえちゃん? いや……こんなところで奇遇だね」
呆然としたままの女と、無理矢理作った笑みを顔に張り付けた男が惨劇の真ん中で数秒間の奇妙な対峙をした。泰河は、どうすべきか迷っているようだった。
泰河が背を向けている方向に連続して銃声が聞こえた。死体の動作が緩慢なことに気付いたのか、黒づくめの残党は至近距離で発砲し死体の動きを止め、うまく逃げ切ろうとしていた。人間に構っている余裕はないだろうが、流れ弾が当たる可能性はある。泰河はポケットに手を突っ込み、こんな時に何をしているというのか、じゃらじゃらと小銭を取り出した。
次の瞬間、泰河が親指で小銭をはじくと、遥か彼方の黒づくめがのけぞるように倒れた。またも阿理沙には、何が起きたのか分からなかった。
「チッ、ねえちゃんはあとで先生の”お仕置き”を受ける必要があるな。俺がいいって言うまで、そこで伏せてろ」
不可解だったが、阿理沙は言われたとおりにした。地面にうつ伏せになり、両手を頭に乗せた。泰河はコインをはじき、残党を片付けていく。それはなめらかに行われ、動いているのは片手の肘から先だけなので他の者が見ても何をしているか分からないだろう。
しかし、残党は自分たちが銃撃のようなものを受けていることに気付いたようだ。一人がマシンガンを腰だめで構えたのを阿理沙は見た。
ぱんぱんぱん、と乾いた音がして、泰河はあっけなく倒れた。大量の血が噴き出す直前、胸に風穴が空いたのが阿理沙には見えた。
思わず立ち上がろうとした阿理沙に、泰河は落ち着いた声で言い放った。
「いいから伏せてろ。危ないから」
どこかで、きりきりきり、という音がした。時計のネジを巻くのに似た音だ。
阿理沙は忠告を聞かず、倒れている泰河に駆け寄った。ぽっかり空いた穴からは白い骨が見えていた。撃たれたのは心臓だ。血溜りがみるみる広がっていき、阿理沙の手や膝にぬるぬるとした生温かい感触が伝わる。
彼女が怒りを込めた眼差しを連中の方に向けた瞬間、阿理沙の肩を泰河の腕が掴んだ。再びきりきり、という音が聞こえた。
「思い通りにならないってのが、一番ムカつくぜ、まったく」
信じられないような光景をすでに沢山見た阿理沙だったが、次に見たのはその夜のうち、とびきり非現実的なものだった。
泰河の銃創が、みるみるうちに治っていった。血が止まって、半分になってしまった心臓が形成され、周りに血管が張り巡らされ、骨が生え筋肉と皮膚が再生されるのを阿理沙は目の当たりにした。
「どいてろ、あぶねーから」
泰河は仰向けのまま、険しい顔で言った。阿理沙が体をどけた途端、泰河の姿は消えた。」
泰河が起き上がったことは分った。まるで映像を早送りしたような、人間離れした俊敏さだった。そして一歩分だけ足音が聞こえ、忽然と視界からいなくなった。
再び彼方に目を遣ると、黒づくめの連中が数人吹っ飛ばされて宙に浮いたまさにその瞬間だった。連中はほとんど顔の下半分を粉々にされて、死体の群れの方へ放り出された。その中心に泰河がいたような気がするが、すでに見えない。
見えないと思った瞬間、阿理沙は背後に泰河の気配を感じた。そして首の辺りを強く打たれ、彼女の意識はゆっくりと遠のいていった。
第2章
渋谷駅でテロが起き一般市民一六九名が死亡したという事実が大々的に報じられた一方で、全員がその場で射殺された犯人グループ三二名のうち、実際はほとんどが射殺ではなくゾンビによって噛み殺されたり撲殺されりしたということは全く報道されなかった。目撃者は多数いるはずで、写真や動画が残っていてもおかしくないのに、ネット上ですらほとんど話題にのぼることはなかった。また、三二名の中には生存者もいたがその存在は徹底的に闇へと葬られた。
人間は自分が信じられることしか信じない。事件は新興の国際テロ組織の仕業であり、日本のエネルギー政策に抗議してのものだと発表された。
阿理沙が目覚めたのは、新宿の高級ホテルの一室だった。彼女を見守るように、泰河と小さな子供がベッドの傍らに控えている。
「気分はどうです、僕が誰だか分かりますか?」
泰河はまるで初対面のような丁寧な喋り方をした。阿理沙は半分だけ体を起こし、声を発する前に考えた。別に気分は良くも悪くもない。あの現場から泰河が自分をここまで運んできたのだろうと推測できる程度に頭も冴えている。昨日の出来事はしっかり覚えていた。少なくとも自分では、そう感じた。しかし不思議なほど恐怖は感じていない。
人がたくさん死に、私の友達も一人死んだ。他の子たちも無事かどうか心配だ。それも気にかかるが、再会した親戚の体に起きた奇怪な現象も同じくらい重大な事柄だと思えた。
「ねえ、泰河くんって、ただの人間じゃないよね」
半分寝ぼけているようなぽかんとした表情のままで、阿理沙は言った。泰河は他人行儀な態度を改めて答えた。
「おう。美の才能に溢れているし、度胸はあるし、ケンカもちょっとは自信があるぞ」
「なんだよ美って。あの土偶の出来損ないみたいなもののことかい」
泰河は枕をつかんで、皮肉を吐いた子供を叩こうとする。いかにも幼稚なやり取りで、子供は笑いながらちょこまかと逃げ回っていた。
「いや、そうじゃなくて。撃たれても死ななかったよね」
泰河の動きが止まり、目が点になっていた。
「先生、ちゃんとこいつの記憶を消したのか? やけにたっぷり眠ったくせに、俺のことをばっちり覚えてるぞ」
「消したってば。惨たらしいネガティブな場面なんかは。だけど記憶の中に、まるでネジを巻くときみたいな強いポジティブな感情があって、まるきり全部は消せなかった。複雑に断片的に消してしまったから、より睡眠が必要だったんだよ」
苦虫を噛み潰したように泰河は子供を睨む。先生と呼ばれた子供はなんら悪びれることなく無邪気に微笑んでいた。年齢は小学校の高学年くらいで、性別はどちらかよく分らない。泰河は一人っ子だから、先生が何者なのかは見当もつかない。
「いいじゃないか。このお姉ちゃん、なかなか見どころがあるよ」
「馬鹿、こいつは赤の他人じゃねえんだよ」
泰河は頭を抱え、この事態をどう収拾するか考えを巡らせた。
「チッ、先生が変な予知さえ見なければよかったんだ」
「オレは面倒事に首を突っ込むなって言ったじゃないか。まあ面白いから別にどっちでもいいんだけど」
先生はまったく心配する様子もなく、鼻歌すら口ずさみつつ懊悩している泰河を眺めていた。
やや間があって、何の前触れもなく、ぐう、という間抜けな音が部屋に響いた。二人が阿理沙の方を見ると、顔を真っ赤にして居心地悪そうにもじもじしている。
すでに時刻は夕方近くになっていた。先生が、弾けるような笑い声をあげた。
「恥ずかしがることないって。人間は腹が減ってなんぼだよ。泰河、ルームサービス取ろうよ。オレずっと食べたかったんだ」
泰河は観念したようにため息をつき、ひょろ長い体で大きく背伸びをした。
「仕方ないな……実は、俺も以前から食べてみたかったんだ」
軽食がトレーに乗せられて恭しく運ばれてきた。普通の店で頼むのと大して変わらない代物だが、値段は倍以上だ。それでも泰河と先生は食べたいものを何種類も注文し、まるで長い間我慢でもしていたみたいに、がつがつと貪った。
対照的に阿理沙の気分は深く沈んでいた。ルームサービスが到着するまでの間に携帯や新聞をチェックしたところ、友人たちは多少の怪我はあれどおおむね無事であるようだった。ただ一人を除いては。
阿理沙はオムレツを半分程度しか口に入れることができなかった。泰河が自分の皿を大方平らげたのを見計らい、話を切り出した。
「ねえ、色々と教えてほしいことがあるんだけど」
「阿理沙ねえちゃん、それはこちら側としても、是非聞いてもらいたいことばかりだ。だが確認しておく。口は堅い方か?」
泰河の口調は真剣だった。そして威圧するような眼差しの奥には、迷いや恐れも含まれている。答えようによっては、いやそれだけでなく、聞いてしまったあとの自分の行動次第では泰河も阿理沙もかなり困ったことになるのだろう。
今更ながら阿理沙は戸惑った。何も知らずにいた方が、はるかに楽なのかもしれない。きっと今自分は重大な決断を迫られている。ここは私が立つべきステージではない。だとしたらすぐに降りてしまった方がいいのではないか。
彼女は俯き、黙りこくってしまった。肝心な時、阿理沙はいつもそうだった。
「そんな怖い顔するなよ。女の人を怖がらせるなんて男の風上にも置けないやつだな」
ソースを口の周りにべたべたくっつけた先生が、オレンジジュースで口の中のものを飲み下しながら空気を読まない呑気な調子で口を挟んだ。
「もうそこのお姉ちゃんは、こっちの世界に首を突っ込んでしまってるんだ。あやふやな都市伝説なんかを参考にされるより、ちゃんと説明したほうがいいと思うね。察しの通り、泰河はただの人間じゃないよ。ついでにオレも」
改めて突き付けられたその言葉に、阿理沙は息を呑んだ。胸に大きな穴を開けられても死なない人間たちと今、自分は共に食卓を囲んでいるのだ。
「正確に言うと、同じホモサピエンスだけど、少しだけ違んだ」
空腹がおさまり、阿理沙の思考力は平常に戻りつつあった。三人がいるツインの部屋は清潔で、大きな窓からは新宿のビル群を一望できる。内装もしっかりしており、かなり高級なホテルだと思った。阿理沙はまだ仕事でもプライベートでもこんなホテルを利用したことはない。ルームサービスを頼んだのも初めてだ。
しかしこんな経験にあずかれるのは、泰河がただの人間ではないから、という訳でもないだろう。泰河の両親は、控えめに言って金持ちの部類に入る。一人息子が東京に滞在するのに、これくらいの部屋をあてがうのはそこまで特別なことではないのかもしれない。一緒にいる子供は、たまに大人びた話し方こそするものの、今のところは何の変哲もない只の子供だ。わがままなで気まぐれで変わり者の泰河にとって、友人として対等に付き合うことができる人間の幅は平均より広いのかもしれない。
ひょっとして、二人は自分に悪い冗談を仕掛けているのかもしれないと阿理沙は考えた。しかし、昨夜目の当たりにした、逆再生の映像みたいに元通りになった泰河の胸の大きな穴は一体何だったのだろう。阿理沙は地面に広がっていった血溜りに埋もれた自分の手や膝の感触を確かに覚えている。
泰河は立ち上がり、黙って部屋の隅の方へ歩いていき、何かを手に取って戻ってきた。
「昨夜俺が来ていたシャツの柄は覚えているか? まあ覚えちゃいないと思うが」
そう言って広げたシャツは左の胸に大きな穴が開き、大量の血で汚れている。
「おい、食事中にそういうことはやめろよ」
あらかじめ三杯頼んでおいたオレンジジュースの二杯目を飲み下しながら、先生が文句を言った。泰河は聞こえていないふりをして続ける。
「死体が動いたことは覚えているか? 新聞やネットにそのことが一切出ていないのは、夢まぼろしやトリックだったからじゃなく、俺たちのような存在を知っている一部の権力が強固な情報統制を行っているからだ。死体が動くことを知っているわけじゃない。あくまで俺たちのような存在を、だがな」
確かに死体は動いた。トラックに跳ね飛ばされて死んだ親友は、立ちあがって私が殺されるのを止めてくれた。
「俺たちは不老不死ってわけじゃないが、簡単には死なない。誰でもできるわけじゃないが、死体を動かしたりすることもできる。面倒臭いから証明はしないぜ。どうだ、信じたか?」
彼女のことを思い出すと、涙が溢れた。彼女は死んだ。そして確かに、最期に私を守ってくれた。だから私はこうして無事でいるのだ。これまで何かの拍子で抑えられていた感情が堰を切ったみたいに、阿理沙は涙を流し嗚咽を漏らした。呻くような鳴き声は長く続いたが、誰も彼女に声をかけることはできなかった。
「こういうシチュエーションは、苦手だ。先生、あとは頼む」
泰河は汚れたシャツをしまい、阿理沙が寝ていたのと違う方のベッドに身を沈めた。
しばらくして阿理沙がようやく顔を上げると、二杯目のジュースを飲み干した先生は、三杯目に口を付けず待っている様子だった。
「ごめんね、もう大丈夫。話を聞かせて」
先生は待ちくたびれたと言わんばかりに勢いよくコップに口を付け、それから話し始めた。空はすで赤く染まり始め、丸い夕陽がオレンジジュースに映り込んでいる。
「ヒマラヤの雪男って知ってる? あれは実在するんだよ。一人じゃなくて、男も女も何人もいる。自分たちは住むことができて、自分たち以外は住むどころか足を踏み入れることすら容易じゃない場所を選び、コミュニティ単位で隠れ住んでいたんだ。彼らが移住し、他の共同体と一切の接触を持たなくなったのはもう何万年も前の話だから文字通り人種が少し変わってるけどね。だけど、彼らはオレたちと同じ存在なんだ。進化を遂げたホモサピエンス。いつからか"クロックワーク”と呼ばれるようになった。
その特徴は、脳なんだ。まず、食事で摂取した栄養をエネルギーに変換する機能が、脳にも備わっている。そしてその変換効率は、脳以外の何百倍にも匹敵するんだ。扱えるエネルギー量が多いから、合わせて体も少し変化していて、おかげで怪我はすぐに治るし過酷な環境の変化にも適応できる。食事もほとんど摂らなくていいんだ。
その仕組みはある程度はっきりしていて、脳幹のうち中脳付近に未知の器官があるらしい。ここまではオレも泰河も、そしてヒマラヤの連中もまったく同じだよ。アリウス・サピエンス説というのを研究して発表した学者がいたんだ。すぐに学会からも社会からも抹殺されちゃったけどね。
その器官は遺伝するんだ。オレたちは"ネジ”って呼んでるよ。可哀想な学者さんによると、自然発生的に胎児にネジが備わる確率はごくわずか。だけど父親だけがネジを持っていた場合、夫婦の子供にもネジが備わる確率は二五パーセントに跳ね上がる。そして母親だけあるいは両方が持っていた場合は、一〇〇パーセントになる。だからわずかずつではあるけど、ネジを持っている人間の割合は増えていってるんだ。ただ、ネジの成長が途中で止まってしまったり、成長しても機能しなかったりする確率がすごく高い。だからネジを持っていても死ぬまで機能しない奴もいるし、なにかの弾みで突然機能し始めることもある。
そして、もう一つ特徴がある。クロックワークががホモサピエンスとうまく共存できない理由は、むしろこっちにあるんだ。ネジは脳全体に作用して、新しい機能を増やす。人間は脳の一割程度しか有効に使えてないっていうだろ? 有効に使っているのが、オレたちってわけ。どんな機能が目覚めどんな特徴を持つようになるかは、個体によってかなり差がある。差があるというか、十人十色って感じだな。
だが、子供は親に似る。性格や体格、得意なことに不得意なこと。先祖代々受け継いできた遺伝子が、子供の特徴に大きく影響している。ホモサピエンスと全く同じだよ。ネジによって備わる特徴は子に受け継がれていく。もちろん、彫刻の才能に突然目覚めた泰河みたいに、親になかった新しい特徴を備えるやつもいる。ほとんどのクロックワークは複数の特徴を持っている。遺伝する特徴は、遺伝するくらいだから強力なものが多い。泰河の”死体を動かす”って特徴もそうだ」
「先生、そいつはちょっと喋りすぎじゃないか」
泰河がベッドに横になったまま、話を遮った。
「ちぇっ、ケチなやつめ」
先生は、コップに半分以上入っていたジュースを喉を鳴らして一気に飲み、ビールのコマーシャルみたいにぷはあ、とやって見せた。
「ええと、どこまで話した? オレはオレンジジュースばかり飲んで生きてる、ってところだったっけ。あ、今のは別に泰河がたまに言うような下らない駄洒落じゃないよ。実話だから。念のため」
泰河が枕を投げようとする仕草をして、先生は笑いながらテーブルの下に隠れた。この二人は本当に仲がいいのだろう。そして、悪戯だとしても人を騙すためにこんなに手が込んだことをするような者達だとは思えない。
もし話が全部本当なら、目の前の子供を縛りつけてどこかしかるべき場所に連れて行けば、ノーベル賞ものの大発見になるのではないだろうか。しかし先生が言うには、研究を発表した学者は口を封じられてしまったという。雪男の村がヒマラヤに実在するとして、その雪男が東京にもいるなんて言い出したら、荒唐無稽すぎて言った方が精神病院などのしかるべき場所に連れて行かれるような気がする。
阿理沙は混乱しそうな頭の中を整理しながら、慎重に言葉を選び話そうとした。
「なかなか素敵じゃない……あなた達。でも、昔からいるんだったら、何故これまで世の中に広く知られていないの?」
「それは、オレたちがただの人間からずっと迫害されてきたからさ。現在進行形でね。ヒマラヤみたいな場所は珍しすぎて特殊な例だよ。みんな正体を隠し、普通の人間としてうまく生き延びてきたんだ。人類の歴史の中で、有名な権力者や偉人にはオレたちの仲間が結構いるんだぜ。権力者でも何でもなく、幸福ですらなかった者も、それ以上にいるけど」
先生はいとも容易く言ってのけた。我々は、異質な存在とずっと昔からある部分で共存し続けていたのだと。
「一体どうして……迫害なんて」
阿理沙はそう口にしながら、自らの質問に対する答えを身を持って痛感していた。外見上はなんら普通の人間と変わりない二人を、たとえ一瞬でも気味が悪いと感じ、恐れおののいていた自分に罪悪感を感じた。
だが同時に、それは仕方がないという思いもあった。乱暴な片づけ方だが、それは人間の習性、本能のようなものではないのか、と。肌の色が違うという理由だけでも我々は、同じ人間を数えきれないほど迫害してきたではないか。
「まあ色々あるけど、あっち側の人間もこっち側の人間も、互いに手を取り合おうとしたことは何度もあったんじゃないかな。だけど、必ずある時点で気付いてしまうんだよ。オレたちの存在自体が、存在を許されない程危険だということに。
ネジが生み出す特徴は、遺伝を繰り返すたびどんどん強力なものになっていくんだ。”死体を動かす"特徴も、はじめは一度に一匹だけ、しかも小動物しか操ることはできなかった。泰河の子孫は、もしかしたら生きている人間すら操れるようになるかもしれない。
ネジを持っているオレたちは、生物として同じなのにどうして個体によって異なる特徴を備えているのか? そして交配を繰り返せば繰り返すほど、強く危険な特徴を備えるようになっていくのは何故か? それは、まだオレたちが進化の途中段階であり、遺伝子が最適な特徴を探しているということなのさ。他の種を滅ぼし、生態系を変え、住みやすい環境を整えるために便利な特徴をね。大して役に立たない特徴は淘汰されて受け継がれず消えてしまうけど、役に立つ特徴は子孫に脈々と受け継がれていき、しかも遺伝する度に強力になっていく。
早くて五世代、遅くとも九世代に渡り同じ特徴が遺伝した場合、いわゆる天変地異かそれに準ずる事態が引き起こされるようになると言われている。幸か不幸か、まだ証明はされていないけどね。迫害主義者は、その際旧人類は駆逐され絶滅するか、家畜として利用されるようになると考えている。オレたちは時限爆弾みたいなものさ。放っておけば爆発して、地球をめちゃくちゃにしてしまう。だからコミュニティが安定的に維持されるなんてとんでもないし、隠れている奴らもなるべく皆殺しにしなきゃならない。でもオレたちのほとんどは、地球を自分たちの都合の良いようにつくり変えようなんて大それた野心は持っていないのさ。普通の奴と同じように暮らして、普通に幸福になれればそれでいい。
ヒマラヤの例は、かなりうまいやり方だったんだ。おそらく歴史上もっとも長く続いたコミュニティだしね。もし同じ特徴が遺伝し続け、四世代目が現れてしまった場合、その本人と三代目、つまり親とその兄弟は生涯に渡って異性と交配することはおろか一切の接触が許されない。コミュニティにとって神聖で特別な存在ということにされ、男は男だけ、女は女だけで隔離されて村の隅っこで一生を過ごすのさ。色んな宗教で教義の中に禁欲が掲げられていることの起源はヒマラヤにあるという噂だ。
それでも禁を破り、子を成してしまった場合は容赦なく親子共々殺される。雪男たちは厳しい掟を守り続けることで、いわば自分たちのコミュニティだけでなく地球の生態系バランスを保ち続けてきた偉大なる平和主義者なのさ。あんな不便な場所に自らを隔離して、それでも容易に外に秘密を洩らさず、自然交配を続けなかったのはいつか旧人類と共存できる日が来ると信じていたに違いない。脱走はもちろん、外界との接触も露見すれば死刑。この情報は数十年前、村にミサイルを撃ち込む計画の立案に際し極秘で調査されたものさ。判明した数々の事実は、人類にとって様々な意味で貴重な財産だったはずだけど、どう解釈されたのか、ミサイルの発射ボタンは結局押されてしまったけどね。
ミサイル発射は、まだ冷戦が続いている時代に米国、ソ連、その他複数の国家が共同で実現させた極秘プロジェクト。人類の裏の歴史さ。それを操っていた黒幕は、SACと呼ばれる迫害派の組織。昨夜の無差別テロを起こしたチンケなテロリストとは比べ物にならない歴史と力を持った秘密結社さ。奴らは自分たちのことを博愛団体、と呼んでいるらしいがね。泰河は"死体を動かす”特徴を引き継ぐ家系の四世代目なんだ。仮にそんな奴らが泰河の存在に気付いたら、草の根分けてでも探し出して始末しようとするだろう。一族もろともね」
阿理沙は全身に冷や汗をかいていた。現在、世界中には数えきれない程の核爆弾が眠っているが、それらを全部ひっくるめても太古の昔に恐竜を絶滅させ生態系を変えてしまった一つの隕石の威力には到底届かないという。
この子供は、そして泰河は、その隕石に匹敵する威力を持つ時限爆弾なのだ。こんな話、やはり聞かなければよかったと阿理沙は深く後悔した。こんな秘密を知ってしまっては、もはやこれまで通り生きていくことはできないように思えた。
ようやく彼女が自らの置かれている状況を認識するに至ったということに二人は気づいていた。泰河はベッドの上で身を起こし、阿理沙の表情をじっと見つめている。その視線が、痛かった。
「ところで、オレは”記憶を消す”という特徴を持っているんだ」
先生の表情は、変わらない。常に微笑を浮かべ、リラックスしているようだ。
「お姉ちゃんが望むなら、今オレが話したことは全部忘れさせてあげる。だけど、昨夜のお姉ちゃんの記憶はうまく消すことができないんだ。泰河が殺しても死なない人間だということは勿論、そういう人間を見たことがあるってだけでも、お姉ちゃんが口を滑らせちゃうとかなり困ったことになる。で、もしオレが昨夜の記憶を無理矢理消そうとすると、過去に遡って色んな記憶をまとめて消してしまわないといけなくて、多分幼稚園児レベルまで戻るか、人格が崩壊してしまう。泰河、大事なところだけどそろそろバトンタッチしなくていいかな」
「続けてくれ、俺はあんまりメンタルが強くないんだ」
「ふん、この腰抜けめ。お前には責任感ってものがないのかよ」
もう先生が憎まれ口を叩いても、泰河は枕を投げつけようとはしなかった。それどころか、泰河は背を向けて黙り込んだ。
やがて、その体が小刻みに震え始めた。責任感がないわけではない。泰河は後悔しているのだ。自分がミスって撃たれてしまったせいで、阿理沙に重過ぎる秘密を背負わせてしまったことを。
この子は、この子達は、やはり先生が言ったように世界を自分の都合がいいように変えてしまおうという気などさらさらなく、普通に暮らしていきたいだけなのだ。そもそも、何故泰河は正体が露見するリスクを抱えてあの現場に現れ、縁もゆかりもない人々を助けようとしたのか。重大な秘密を知った阿理沙の口を手っ取り早く封じるため、あの場で殺すことも簡単にできたはずなのに、どうしてそれをしないでわざわざこんな話をするのか。
彼は純粋で、未熟なただの一七歳の青年なのだ。阿理沙には、泰河のことがかけがえのない家族であるように思えた。自分が守ってやらねばならない、愛しい弟のように思えた。
「一つ目の選択。一か八かで、お姉ちゃんの記憶を消す。可能性は低いけど、消すのは二、三年分の記憶でなんとかなるかもしれない。二つ目の選択。オレたちは、お姉ちゃんのことを信じる。昨夜のことは墓場まで持っていくと約束して、お姉ちゃんはそれを守る。三つ目の選択。オレたちには仲間同士横のつながりがあるんだ。オレより強い特徴の持ち主か、記憶を書き換えたり上書きしたりする特徴の持ち主がどこかにいるかもしれない。オレたちがそれを見つけるまで、悪いけどお姉ちゃんの行動には制限や監視をつけさせてもらう。さあ、どうする?」
四つ目の選択肢はないのかと阿理沙は期待したが、いくら待っても先生の口からそれが出てくることはない。泰河も背を向けたままだった。三つめの選択肢は、おそらく無理矢理つくり出したものだと彼女は直感した。あてがないということは、いつまで経っても、もしかすると私が死ぬまで見つけられないかもしれないということだ。選択肢の中には、私が甘えることのできる限界のラインが最初から提示されていた。
もちろん二つ目を選ぶに越したことはなかった。口が裂けても誰にも言わないと決意することは容易い。だが、この秘密は阿理沙が背負うにはあまりに大きすぎる。
今聞いた話の記憶を消してもらうにせよ、そのままにするにせよ、ただでさえ精神的に不安定な自分に万が一のことが起こってしまう可能性はゼロではない。そう彼女は考えた。それに、阿理沙にいくら自信があっても、会ったばかりのこの二人が安心して自分を信用するだろうか。それは彼らにとって大きな心の重荷になってしまうに違いない。
何故、自信を持って秘密を守ると宣言することができないのか。それは阿理沙の自分自身への不信であった。自己評価の低さの現れであり、マイナス思考が性格の一部にまでなってしまう悪循環であった。それを彼女が自覚したのは、今に始まったことではない。
泰河を苦しめているのは、自分だ。どうせ今の自分には、どこにも居場所はない。何事もなかったかのように日常へ戻っても、それは日常という名の地獄であるかもしれないのだ。阿理沙は悩んだ末、自分なんて、もう少し早い段階でいなくなっておけばよかったのだという境地に達した。彼女は、大きく息を吸った。
「一つ目の選択で、いいです。私の記憶を消して。お願いだから」
言い終えると、不思議な充足感のようなものに阿理沙は包まれた。やっと楽になれる、これで良かったんだ、と。
「へえ……本当にそれでいいの? オレ、あんまり気が進まないんだけどな」
こんな状況になっても、先生は表情を崩さなかった。泰河も背を向けたまま、押し黙っている。
「いいの。これは昨夜のことだけじゃない。私の個人的な事情によるところが大きいんだから、全然あなたたちの責任じゃない。むしろ、好都合よ。死ななくても人生やり直せるチャンスなんて、そうそうないでしょ。だいいち、あの子の葬式に行くのも行かないのも、どちらにしても気が滅入って仕方ないと思ってたの。いますぐやって」
「お姉ちゃん、やっぱり見込みがあるね。残念で仕方ないよ」
記憶を消した後は、残った記憶を脳が整理するために眠りっぱなしになるらしく、彼女は再びベッドに入ることになった。今度は数日に渡って眠り続けるかもしれない。その前にシャワーを浴びて、身を清めておくことにした。
鏡の前に立って、阿理沙は自分の裸を眺めた。おそらく、美しさのピークは今だろう。阿理沙は、自らの顔には自信があった。阿理沙は美しさだけで勝負する世界に自分が最初に入らなかったことを後悔していた。失敗したアイドルという烙印は、どんなに美しくてもその世界への入門を容易には許してくれない。
肌は白磁のように透き通り、血管が見えてしまいそうなほどだ。日焼けなどとは無るで無縁のように見える。ストレスのせいもあり、十代の頃より若干木目が粗くなった気はするがそれでも十分に若々しい。黒子も傷跡も、全身くまなく探しても目立つものはただの一つもなかった。胸も腰も尻も絶妙なバランスを保っている。
彫刻作品のようなふくよかな比率ではない。過度に膨らんだバスト、内臓が窮屈そうなウエスト、そして世の男どもが追いかけてやまない魅惑的な質量と質感を備えたヒップ。そこから下には、精密な曲線を描きながら長い脚が伸びていた。
処女ではないが、あまりろくな男と付き合ったことはないが、好きでない男に身を任せたことは一度もなかった。汚されるようなことになる前に、汚れてしまう前にやり直すことができてよかったと彼女は思った。
どうせなら生まれたままの姿で新しい朝を迎えようと、阿理沙は一糸まとわぬ姿でベッドに入った。太陽がまさに沈まんとするその光が差し込む部屋の中で、一歩一歩踏みしめるように歩く姿は荘厳ですらあった。彼女はそんな光景にも、深く満足した。
「こんなにスムーズにいくとは思わなかったよ。短い間だったけど、さよなら」
先生はそう言って、阿理沙の顔の上に手をかざした。阿理沙は目を閉じた。
自分のすぐ上で、何かが物凄い勢いでぶつかる音がした。驚いて目を開けると、泰河が先生に拳を向けていた。それは先生の体に届く三十センチほど手前で止まっており、振り抜こうとする直前で何かの力によって押しとどめられているかのようだった。
「やめてくれ、先生。これは俺の問題だ。俺が責任を持つ」
「へえ、どうやって? 選択肢は本当にあの三つしかないんだよ。他に何かあるの?」
ぐぐ、と泰河が拳に力を込めているのが分かる。顔には汗が粒になって吹き出している。拳と先生の間に、見えない壁のようなものがあった。
「二つ目だ、二つ目に決まってるだろ。俺は阿理沙ねえちゃんを信じる。阿理沙ねえちゃんが自分を信じることができないのなら、俺がその分まで信じてやる」
二人の間に火花が散るような緊迫した空気があった。泰河はさらに力を込めていくが拳はそれ以上前に進まない。先生の顔にも、初めて笑顔以外の表情が浮かんだ気がした。しばらく二人は、そのように対峙していた。
「なんだよそれ、全然理屈が通ってない。本当に小学校出たのかよ、お前」
泰河が徐々に力を抜き、その場にへたり込んだ。全力を出し尽くしたという様子で、肩で息をしている。かたや先生は、何食わぬ顔で平然としていた。
ひざまづくような体勢になっている泰河の体は、尋常ではない熱を発しているようだった。膨大なエネルギーを使っていたのだろうか。サウナから出てきたみたいに大量の汗をかき、湯気が立っていた。
「おい……先生……一応聞いとくけど、こうなること分ってただろ……」
息も絶え絶えになりながら、泰河は言う。
「まあね。いちいち演技するのも結構神経使うんだよ」
先生はけろりと元通りの表情になり、軽い調子で答えた。
「嘘つけ、ほとんど棒読みじゃねえか、この大根役者……」
阿理沙は布団を剥ぎ取り、泰河に駆け寄った。一度は守りたいと思ったのに、逆にまたしても助けられてしまった。背中にしがみつき、胸を押し当ててその存在を感じた。もう枯れたと思った涙が、再び流れ出していた。
「傷つくようなこと言うなよな、繊細な時期なんだから。それに、いいもん見れたから良かったんじゃないか」
阿理沙は自分が全裸なのを思い出し、頬を赤く染めた。泰河の顔も、真っ赤だった。
第3章
1
阿理沙は、姉のような存在として泰河を守っていこうという決意の最初の表れとして、泰河がエージェントとの約束を完全にすっぽかしたのをフォローするため先生と結託して携帯を奪い、謝り倒して翌日の午前中にアポイントを取りなおした。会いたくない、と泰河は終止不服そうだったが、阿理沙が強く言うとおとなしく引き下がった。
もう一度お腹がすいてきたので、今度は年上の自分がごちそうする番だと、新宿で贔屓にしている蕎麦屋に二人を招待した。
「あなたたちはさっき沢山食べたばかりだけど、きっと消化も早いんでしょう。私はほとんど食べてなかったから、付き合ってくれない?」
「いや、普段あまり食べないもんで、むしろ小食なくらいなんだ。実は今、結構苦しいんだよ。でもデザートだったら入るぜ」
「むしろ、オレたちはあんみつを食いに行くぜ」
そんなわけで、泰河と先生がクリームあんみつを慎ましく頬張る隣で、阿理沙が天ぷら蕎麦に稲荷寿司のセットを勇ましく平らげるという妙な取り合わせが実現した。泰河が食傷気味になっている一方、先生は食欲が旺盛らしくお代わりを注文していた。
阿理沙を育ててくれたおじさんとおばさんには、彼女より年下の二人の娘がいた。阿理沙は姉として振る舞うことを心がけ、おじさんとおばさんは彼女を実の娘のようにして育てたが、二人の妹は阿理沙に本当に心を開いてくれることはなかった。親の前では一見仲良さそうに振る舞っていても、子供だけになるとはっきりと距離を置かれているのを感じた。上京してからは、妹たちとはほとんど顔を合わせていない。
一点気になったことを阿理沙は尋ねた。泰河と阿理沙はハトコ同士で、ネジとやらは遺伝するそうだが私の父や祖母はどうだったのか、と。
「そっちの家系には、遺伝してないみたいだぜ。阿理沙ねえちゃんはどっからどうみても普通の人間ってわけだ。ちょっとばかし色っぽいけどな。いや、かなり色っぽいぜ」
「馬鹿。何言ってるの……もう。早く忘れなさい」
急に不機嫌になってしまう。泰河は水着のグラビアなんかのことを指して色っぽいと言ったのだが、どうやら裸で抱きついたことを揶揄していると阿理沙は解釈したようだ。泰河はそれを思い出してしまい、耳まで真っ赤になる。横から先生がからかって、幼稚な小競り合いがまた始まった。こら、お行儀よくしなさい、と阿理沙が怒りも込めた強い口調でたしなめると、二人とも恐縮してすぐにおとなしくなる。
出来たばかりの二人の弟みたいな存在が、すでに阿理沙には可愛くて仕方なかった。駅まで見送ってくれた彼らに、気を付けてホテルまで戻るのよ、と言ってから、こいつらはあたしより進化しているのになあ、と変な気分になった。先生が、小さい手を差し出してきた。色々悪かったな、仲直りの握手だ、と言って。阿理沙はむしろ助けてもらったという意識しかなかったが、この子達は、私たちとあくまで対等でいようとしているのだろう。何も言わずその温かい手を握り返した。
翌日の葬式で、阿理沙は親友たちと再会した。痛々しく包帯を巻いている者もいれば、まだ入院している者もいたが、彼女たちは再び生きて会えたことを喜んだ。
その多くは、あまりに凄惨な事件のショックで心を痛めていた。先生に記憶を一部消してもらっていた阿理沙は、私はみんなより平気なんだから、私が支えてあげねばならないと考え、そこでも姉のような存在に徹して皆をいたわった。
死んでしまった親友は、遺体の損傷が激しくもうその姿を見ることはできなかった。その代わり写真の中で、アイドルだった頃と変わらぬ満面の笑顔をたたえていた。阿理沙は、彼女は自分の身代わりになったのではないかという思いを抱いていた。だが、その写真を見て、もしそうだとしても自分を責めるのではなく、彼女の分まで強く生きて行こうと考えることにした。アイドルの笑顔は、どんなときもファンに元気を与えるためにあるって、昔よしみちゃんは言ってたっけ。来るのが少し怖かったけど、ちゃんとお別れができてよかったと思った。
阿理沙は完全にやめはしないまでも、オンラインゲームに費やす時間を大幅に減らし、掃除や料理、運動など健康的なことに時間を使うよう心がけた。散らかりがちだった部屋が片付き明るい印象になると、雨上がりの空のように心も晴れやかになっていくようだった。
気が向いたら連絡しなさい。うちに遊びに来てもいいわよ、と泰河には住所を教えていたが、二人は連絡などせずいきなりやってきた。掃除していたからよかったが、ちゃんと前もって言いなさいよと阿理沙が言うと、「うるせえな、俺は俺の行きたいときに行くんだよ」と生意気なことを言うので、叱り飛ばしてやった。
久しぶりの仕事があって、阿理沙はじきに来る夏に向けた、明るい色の水着で撮影に臨んだ。男を挑発するような、若干愁いを帯びたアンニュイな表情をつくるようにマネージャーからもカメラマンからも言われていたが、親友の遺影を思い出し、阿理沙はアイドル時代の天真爛漫な笑顔を積極的にしてみせた。現場は最初困惑していたが、生命力の躍動すら感じさせるその表情の良さに、すっかり魅せられてしまったようだった。男たちに従うのではなく、男たちを従わせるように、軽やかに阿理沙は振る舞った。
やがて、泰河がホテルを引き払い、福岡に戻る日になった。阿理沙は空港へ見送りに行く前に、なけなしの貯金から捻出して、二人へのプレゼントを購入するべく百貨店に寄っていた。悩みに悩みぬいた揚句、空港へ向かわなくてはならないタイムリミットの直前までかかってようやく買い物を終えたとき、泰河から電話がかかってきた。
内容は、ちょっと早めに帰りたくなったので、飛行機の時間を変えてしまい、もう出るところだから見送りは結構、というものだった。思わず周りに人がいるのも忘れ大声を出してしまう程に阿理沙は憤慨したが、途中で先生にバトンタッチされてしまい「お姉ちゃんごめんよ。オレ、本当に悪いと思ってるんだよ」と言われ一方的に電話を切られてしまった。
阿理沙はほとんど怒りが頂点に達しかけていたが、寸前でそれは免れた。そして、すぐさま送られてきたメッセージを読んだことで、ほんの少しだけ気持ちは収まった。
メールアプリを通じてそれは送られてきた。差出人は「ティーチャ」となっており、プロフィール写真はポンジュースのロゴマークだった。阿理沙は先生が携帯を持っていることを知らなかった。このアプリやってるんだ、と阿理沙は意外に思った。
”おれ、本当に悪いと思ってるんだよ。たいがが、またわがままいいだしてさ。流石のおれも止めてみたがこうかナシ。勘弁してね”
プレゼントも台無しになり、時間も持て余してしまった阿理沙はとりあえず目についたカフェに入って一息つくことにした。そこで本でも読もうと思った。そんな休日の過ごし方を以前は結構していたのに、最近はしなくなっていた。彼女は、まあこれもいい機会か、と思うことにした。カウンターでコーヒーを受け取り、狭い店内をかきわけるようにして席につく。
本より先にまずは携帯をチェックし、友人のツイッターや、ニュース記事を読む。あれから泰河たちのような存在のことを少し調べてみたりしたが、都市伝説の類がわずかに出てくるだけだった。それも死なない人間がいるというだけで、泰河たちのことを刺しているかどうかは判然としない。
今この店内にも、そんな存在がいたりするのだろうか。可能性は十分あるにしても、実感は全くわかない。彼女はコーヒーに関しては一貫してブラック派だった。淹れたのは全自動の機械だが、悪くない香りがする。うん、なかなかいいものね。もっと一人で色々お出かけするようにしなくちゃ。と阿理沙は思った。
しばらく小説を読んでいると、先生から再びメッセージが届いた。
”なんと、馬鹿たいがはチケットがうまくとれてなくて、結局予定より遅い飛行機にのることになった。やっぱり空港に来てくれませんか? とマヌケなたいがも言っております”
阿理沙は振り回されているようで不満だったが、とにかくプレゼントが台無しにならなくてよかったと思った。二人に会えるなら、それだけで充分だけれど。
2
福岡に戻ることになっている日の前日、泰河と先生は阿理沙に何か気の利いたものを贈るべく、銀座の百貨店を訪れていた。二人とも二十歳の女に贈り物などしたことはなく、買い物は熾烈を極めた。恵まれた財力を存分に活かしてしまおうとする泰河を、先生はうまく諌めなければならなかった。
「あっちは見送る側なのに、エルメスのバッグを渡されるのは流石にひくんじゃないかな。オレだったら、ひくかな」
「うるせえな、俺は俺が贈りたいものを贈るんだよ」
二人は、そもそも阿理沙の好みもまだよく知らない上、二十歳の女性の一般的な好みや習性についても全くの不得手であり、こんなシチュエーションの際に喜ばれる贈り物が何かということをうまくイメージできていなかった。
「オレは、こういうのがいいと思うんだけど。一度見てるからサイズも大体分かるし」
「馬鹿かお前は。ブラジャーはいくらなんでも非常識だろうが」
それでもなんとか、閉店間際になって買い物を終えることができた。数時間のショッピングで疲れるような彼らではないが、慣れないことをやり遂げた達成感もあって、三日に一度のペースで食べに行くチョコパフェを、昨日食べたばかりなのにまた食べに行ってしまった。その夜、泰河は自分が空港で阿理沙ねえちゃんにプレゼントを渡し、めちゃくちゃ喜んでもらえたという夢を見た。それくらい、渡すのが楽しみだった。
泰河は、いつも通り朝四時に目覚めた。泰河にとって睡眠は二時間もとれば充分だった。彼らが生きていくためには、食事より睡眠よりさらに重要なものがあった。
先生は寝るのが好きで、いつも朝までたっぷり寝ている。まだ薄暗い部屋の中で、泰河は日課のアシュタンガヨガを行っていた。独特の呼吸を行いながら、新宿の街にだんだん光が差しはじめ、電車が動き出し、人々が活動を始めるのを眺めるのが好きだった。
ふと、泰河は先生がうなされているのに気付いた。
先生は”未来予知”という特徴を持っていた。翌日に半径およそ百キロ程度の範囲内で、赤の他人が一度に十人以上死ぬか親しい者が生命の危険に晒される場合、その場面が夢となって表れる。
その場面は最初はとても曖昧にしか見えず、先生が特に続きを見たいと思わなければすぐに消えてしまうらしい。阿理沙を助けた日の朝、先生はいつも通りの時間に起き、昼頃になってから夢を見たことを泰河に伝えていた。
泰河は、息を呑んだ。うなされているのは、先生が夢の続きを見ようとしている証拠だった。見ている時間が長ければ長いほど、詳細を知ることができる。続きを見ようとするということはつまり、生命の危険は赤の他人ではなく先生の親しい誰かに訪れようとしているということだ。
しばらくして先生は目を覚まし、傍らで心配そうに見守っていた泰河に気付いた。
「一応聞いてみるけどよ、先生はこの辺りに他に知り合いとかいるのか」
「多分いない。久しぶりに寝苦しい夜だった。オレはシャワーを浴びるからルームサービスでいつものやつを頼んどいてくれ」
布団に入ったまま涼しい顔で言い放ったあと、先生は欠伸しながら浴室へ向かった。冷蔵庫に入ってるぞ、と泰河は言ったが、濃厚で新鮮なやつが飲みたいんだ、と先生は答えた。
窓から見下ろす東京はすっかり朝になっていた。テーブルに腰掛け、先生はオレンジジュースに口を付けて話し始めた。
「お姉ちゃんを空港に来させてはいけない。巻き込まれてしまうから。オレたちは予定通り空港に行って、待ち伏せている奴を返り討ちにする」
「阿理沙ねえちゃんは狙われてはいないんだな?」
「残念ながらそうとは言い切れない。でも狙いはあくまでも、泰河だと思う。オレたちが情報を持っているということが悟られないように動いた方がいいだろうな」
二人はネットで空港の見取り図を検索し、対策を立てた。そして予定通りの時刻に電車に乗った。
品川駅で乗り換えるとき、阿理沙に電話をかけて見送りには来なくていいと嘘をついた。プレゼントを渡すのは、少し先延ばしになっただけだ。嘘をついたことを、あとでなんと言って謝ろうか。物事が自分の思い通りにならないのは、泰河のもっとも忌み嫌うところだ。邪魔する奴には、相応の報いを与えてやる。
「阿理沙ねえちゃんは、おとなしく言うことを聞いてくれたかな。確認してくれ」
先生が予知することのできる未来は、予知夢として翌日の出来事を見る他にもう一種類あった。「握手」したことがある人物のおよそ半日先までの未来を見ることができる。それはいつでも好きな時に予知することができるが、まるでうたた寝をするように数秒意識を遮断しないといけない。見えるのは短い夢のような一瞬だけだが、鮮明だった。
どの瞬間を見るかはある程度正確に指定できるが、予知の対象が目で見えない場所にいる場合にはかなり大きな誤差が生じてしまう。例えば今、阿理沙の十分後の未来を見ようとすれば、およそ五分後から一五分後までの間のどこかの場面が一瞬だけ見える。
先生は数秒後の阿理沙の未来を見た。数分の誤差は生じるが、この場合不都合は特にないだろう。
「喫茶店でコーヒー飲んでるよ。すげえ機嫌悪そう」
「まあ、ひと安心だな」
次に二人は、電車の中で先生が見た予知夢の内容を再度確認した。それは薄ぼんやりとした、断片的な情報だった。泰河が搭乗ゲートを通過した後、何者かが現れ、飛行機に向かうのとは別の道に連れて行く。待合ロビーまでは先生と一緒だが、連れて行かれるのは泰河一人だ。阿理沙は展望デッキに向かうが、何故か飛行機が離陸する前に自らの足へどこかへ行ってしまう。そして、陽が完全に落ちて暗くなった滑走路の風景で夢は終わっていた。他に分かるのは、搭乗ゲートを通過するのは当初の予定通りの時間であることくらいだ。
「俺と先生は、どうして分断されてしまうんだ」
「お姉ちゃんを人質に取られているか、オレの体が操られてしまうか、あるいはゲートをくぐる直前に始末されてしまうのかもしれない。最初の可能性は、すでに排除した。だが油断はできない。空港の中、できればセキュリティ・ゲートを通る前に、こちら側が先に相手を探し出してオレが”暗殺”するのがベストだろう。それが出来なかった場合、どうにかして二人一緒に搭乗ゲートをくぐる」
「別にビビってるわけじゃねえけどよ、今日空港に行かないって選択肢もあるんじゃねえか」
「予知の内容は、こちらが一方的に不利になるほどじゃない。むしろ予知したオレたちの方が有利に動けるはずだ。降りかかる火の粉は早めに払っておくに越したことはない」
先生の言うことはもっともだった。相手が阿理沙のことも知っているのであれば、時間が経つにつれ巻き込まれるリスクも大きくなっていくだろう。だが、先生の身に何が起きるのか分からないのが泰河には引っかかった。
「こんなことになるなら、先生の分の携帯を契約しとくべきだったな」
「後悔先に立たずだ。オレはどうせ、使えない。空港に着いたら、とにかくオレたちが何かに気付いているということは悟られないようにしよう。何食わぬ顔で予定通りの飛行機に乗ろうとするんだ。オレは迷子になったフリをして、姿を消しつつ相手を探す。泰河はオレを探しているフリをするんだ。長い間はぐれていると怪しまれるからあまり時間はかけられない。歩くルートは、予め決めておいた通りに。だがうまい具合に事は運ばないだろうな。もし相手が空港のスタッフに紛れ込んでいるとしたら、オレたちの入れない場所にいるだろうから探しようがない。ちなみに、お前を連れて行くやつは結構ユニークな格好をしているからあまり驚くな」
「そいつは楽しみだな。正体を隠すために変装するのはむしろ自然だが、まさか空港の中を目立つ恰好で不用心にうろついたりはしていないだろうよ。俺たちはどうやって、そいつを見つければいいんだ」
「オレだって見当はつかない。相手は一人きりじゃなくて、オレたちを親切にずっと見張っててくれるやつがいるかもしれない。怪しいと思うやつがいたら揺さぶりをかけてみるしかない。結局予知の通りになってしまったら、泰河は現れる相手を全力で迎え撃て。少なくとも滑走路に出るまでは、一方的に殺されることはない」
あと一駅で空港に到着するというアナウンスが聞こえた。もうすぐ作戦開始だ。
「おい、もう一度阿理沙ねえちゃんの様子を確認してくれよ」
「なんだよ、やけに心配性だな」
泰河は、そんなんじゃねえよと困ったように照れてみせた。次の瞬間、先生の顔色が変わった。
「一体なんだ、これは。クソッ、奴らすでに動き出してるのか」
どうしたんだ、と泰河も慌てて聞く。先生は車内に貼ってある路線図を見上げた。
「やっぱりそうだ。おそらく、お姉ちゃんは空港に向かってる。オレたちが乗ってきたのと同じ電車に乗ってる」
「別の用事ができたのかもしれないだろ。行き先が空港とは限らない」
「だといいんだがな。すぐに電話をかけてくれ」
丁度電車は羽田空港に到着したところだった。泰河が電話を掛けると、阿理沙はすぐに出た。車内なので周りに気を使っているのだろう。声がくぐもっていた。
「何よ、今そっちに向かっているところ。すぐかけ直すからちょっと待ってて」
「やっぱりそうなのか? 来なくていい。もう飛行機に乗るところなんだ」
阿理沙はやや押し黙ってから、答えた。
「……なんなのよ、ちょっといい加減にしてよ。とにかく空港まで行くから」
「よく聞いてくれ。来たら危険なんだ。悪い奴らが俺たちを狙ってる。だから来なくていい。家に帰って鍵を閉めてるんだ」
先程と同じように、少し間を置いてから阿理沙は答えた。
「どうしてそんなでたらめばかり言うの。からかってるわけ? もう切るよ」
何を言っても彼女は泰河の言葉を信じようとはしなかった。そして一方的に電話を切った。
阿理沙が言葉を発するとき、考えているにしては不自然に長すぎる間が常にあった。泰河は妙な胸騒ぎを感じた。
「どうだった」
「全然こちらの言うことを信用してくれない。何か、様子がおかしい気がする」
先生は考えを巡らせた。阿理沙はすでに操られているのかもしれない。迷っている暇はなかった。
「作戦は全面的に変更だ。オレはお姉ちゃんのところへ行く。携帯を渡せ。そしてお姉ちゃんに電話を掛ける方法を分かりやすく教えろ」
先生は、文字の入力もできないくらい極端に機械が苦手だった。簡単に電話がかけられるよう、履歴から発信する方法を教えた。
「分からなかったら、人に聞け。今時老人だって使いこなせる。お小遣いは持ったか」
当然だ、と言わんばかりにがま口の財布をポケットから出して見せる。
「心配は無用だ。お前も十分に気を付けろ」
先生は、折り返していく電車に飛び乗った。
3
阿理沙が席を立とうとした時、テーブルの向かいに女が腰をおろした。知り合いかと思ったが見覚えはなかった。
「ごめんなさい、丁度出ていくように見えたから。もう席が空いていなくて」
ゴスロリ調の目立つ格好をした若い女だった。スカート部分の膨らんだ漆黒のワンピースは至る所にフリルがついており、艶やかな黒髪をショートカットにして、分けた前髪で片目がほとんど隠れている。羽根つきの小さなハットをちょこんと頭に載せていた。
「いいんです、本当に帰るところだったから」
女は阿理沙のコーヒーがまだ半分残っているのを見て、言った。
「彼氏に呼び出しでもされたんですか? うらやましい」
「そんなんじゃないのよ。生意気な弟がいるの」
女は阿理沙の顔をじっと見つめて、言った。
「あなたの弟なら、さぞかしイケメンなんでしょうね。私このところずっとご無沙汰だから、紹介していただきたいわ。ところで、その携帯にかかってくる電話は、全部嘘っぱちだから気を付けたほうがいいですよ」
変なことをいう女だ、と阿理沙は少し不快に思った。
言動とは裏腹に、品の良い顔立ちをしている。かつ少しだけボーイッシュで、凛とした印象を与えていた。珍妙な洋服よりきっと和服の方が似合うだろう。うらやましいほど肌が綺麗だ。年齢はまだ十代かもしれない。育ちが良すぎた反動が性格とファッションに出ているのだろうと阿理沙は推測した。
阿理沙は答えずに店を出ていき、まっすぐ駅へ向かった。電車に乗る頃には、もうその女のことは忘れていた。
車内で泰河から着信が入った。ドア付近まで行って口の周りを手で押さえ、電話を取る。
「何よ、今そっちに向かっているところ。すぐかけ直すからちょっと待ってて」
「やっぱりそうなのか? 来なくていい。もう飛行機に乗るところなんだ」
「……なんなのよ、ちょっといい加減にしてよ。とにかく空港まで行くから」
「よく聞いてくれ。来たら危険なんだ。悪い奴らが俺たちを狙ってる。だから来なくていい。家に帰って鍵を閉めてるんだ」
「どうしてそんなでたらめばかり言うの。からかってるわけ? もう切るよ」
阿理沙は、まったくといっていいほど泰河の言葉に耳を貸せなかった。まだ心の中で、苛立ちが完全に収まっていなかったのだと思った。これからしばらく会えなくなるのに、下らない争いはしたくない。阿理沙は一方的に電話を切ってしまった。
本の続きを読んでいると、また携帯にメッセージが入った。
”こちらから迎えに上がります。たいがが甘いものをおごるといっております! 乗り換えの一つ手前の駅にいい店があるから、そこの改札を出て待ってて”
わざわざ迎えに来てくれるなんて結構いいとこあるじゃない、と阿理沙は思った。甘いものも楽しみだが、二人が自分のために何かしてくれるということが、体がむずむずするくらい嬉しかった。
言われたとおりにして待っていると、今度は電話がかかってきた。
「お姉ちゃん、電車は降りた?」
出たのは先生だった。泰河は私と話すのが怖くなってしまったのかもしれない。
「はいはい、降りましたよ。そっちは着いたの?」
「よかった。そろそろだと思ってたんだ。今、品川駅のどこにいる?」
「何言ってるの? ちゃんと言われた通りの駅で降りたよ」
「……お姉ちゃん、そこはどこ? なんていう駅?」
何故か先生は焦っている様子だった。大体、品川の手前で降りろと言ったのは他でもない自分のくせに、いったい何を言っているのか。
「分かってるくせに、どうしてそんなこと聞くの。今日のあなたたち、ちょっと変よ」
「あまり時間がないんだよ。お姉ちゃん、頼むからオレの言うとおりにして」
「何よ、たっぷり時間はあるくせに。そんなに急がなくてもいいじゃない。飛行機は何時?」
もう何を言われても、先生が事実と逆のことを言っているようにしか感じなかった。自分の機嫌を損ねてしまったことで動揺しているのだと思った。まったく、なんと可愛い弟たちなんだろう。
しかし簡単に許す態度を見せては、今後の示しがつかない。阿理沙はお灸を据えるつもりになって意地悪な返答を繰り返した。さっきのゴスロリ女がずっと自分のあとを尾けていることには全く気付いていなかった。
4
一人で空港に着いた泰河は、まずカバンをコインロッカーに放り込んだ。搭乗手続きもやめてしまおうかと思ったが、敵にこちらの状況がどれほど知られているか分からない以上、当初の行動予定を大きく変えないほうがいいと判断した。
手持無沙汰なので、そこらじゅうを歩いて回る。元来落ち着きのない泰河にとって、それはさして不自然な行動だとは思えなかった。人が多く集まる場所を一通り回ってみたが、怪しい人物はいなかった。尾行されている様子もない。
泰河は、展望デッキへと向かった。阿理沙は泰河たちの乗った飛行機を見送るためいったんここまで来るが、それが離陸する前に自らの意思で歩き去って行ってしまう。飛行機を見誤ったとか、何でもない理由であればいいのだが、と泰河は切に願った。
やはり普通の人間と関わることは、大きなリスクだ。泰河と先生はこれまでに多くの者の記憶を消してきた。都合の悪い記憶だけ消した後で、これまで通りの関係を続けることは息苦しかった。
罪悪感ではない。安全に生きていくために特徴を有効活用するのは、彼らの道から外れることではない。少なくとも泰河はそう考えていた。だが、同じ人間同士が関わりあい、助け合ったり影響を与えあったりして生きていく横のつながりから自分だけが外れてしまったような気がした。それは食物連鎖のような、縦のつながりだと感じた。
秘密を知られても記憶を消さなくていい普通の人間。泰河はそんな存在に出会えることにずっと憧れていた。たとえ全く同じように食べて眠ることができなくても、対等な立場で話ができて、同じように時を重ねていく。それすら出来ないから、雪男たちは雪山に隠れ住み、自分たちだけのコミュニティを作ったのだろう。
だからどんなに憧れても、普通に生きていけるかもしれないと虫のいいことは考えない。だが、阿理沙の存在だけは守っていきたいと思った。一人だけでもそういう存在がいれば、自分は救われる。そしてその想いが、いま阿理沙を危険に巻き込んでしまっているのだ。
泰河は初めてこの場所に来て、飛行機が思っていたより近くで見れることに感心した。これなら確かに、本人の姿が少しも確認出来ないとしても見送りをしようという気になる。大きなカメラを構え、違う目的で来ている者もちらほらいた。
周りに何もない広い空間で、群青色の海と京浜工業地帯の工場群だけを背景にして空に浮かんでいく機体。あっという間に遠く離れその姿は小さくなっていく。離陸の瞬間はまるで一つの短いドラマだった。そして卑しくも彫刻家である泰河は、何の支えもなしに大空に吸い込まれるように浮かび上がる巨大な造形物に深く感じ入るところがあり、置かれている状況を一時忘れ航空ファンに交じりしばらく飛行機を眺めていた。
それからふと、俺たちはあの飛行機のようなものではないだろうかと気付いた。飛行機が空を飛ぶ理屈は実は厳密に解明されていないらしいが、とにかく飛んでいる。空を飛ぶための特徴が、確かに備わっているからだ。
実際には人間がそれを作り操っているのだが、離陸の瞬間を繰り返し何度も眺めているうち、飛行機は自立して意思を持った生命体のように見えてくる。人間は飛行機に勝つことができないばかりか、心を通い合わせることも到底不可能だろう。俺たちは何食わぬ顔で地上に紛れ込んではいるが、圧倒的な力で空を征服している。人間を安全に運びもすれば、大量に殺すことだってある。
写真を撮ろうとしてポケットを探り、携帯を先生に預けていたことを思い出した。すでに陽が暮れようとしている。泰河は展望デッキから出て行こうとして、男に声をかけられた。
「やあ、誰かと思えば泰河くんじゃないか」
知らない顔ではなかった。城ヶ崎淳吾は、泰河が二か月半だけ通った高校の美術部の先輩で、今は東京で大学に通っているはずだ。もともと田舎育ちにそぐわない洗練された空気を身にまとっていたが、さらに垢抜けた感じになって、ファッション誌から抜粋したような洒落た洋服を着こなしている。
部活動はおろか学校に顔を出すことすら滅多になく、結局中退してしまった泰河は親しい友達をつくることができなかった。周りは皆、まるで最初からある程度予想はついていたかのように、泰河の性格に平凡な学校生活が合わなかったのだと信じて疑わなかった。そもそも中学校だって、義務教育だから卒業できただけでほとんど行っていなかったのだ。
実際、泰河が高校にうまく馴染むことができなかったのはどの生徒から見ても明らかだった。生徒会長でもあった淳吾は、その問題児のことを気にかけ、機会を見つけては積極的に話しかけてくれるような存在だった。
「久しぶりですね先輩。お元気そうで何より。これから飛行機に乗るところなんで、また」
「相変わらずつれないねえ。少しくらい話をしたっていいじゃないか。泰河くんこそ最近どうしているんだい? 活躍は耳に入っているよ。また有名な賞を取ったらしいな。凄いじゃないか。自慢の後輩がいて僕は鼻が高いよ。さらに背が伸びたようだが、痩せたんじゃないか。もう少し肉を付けたほうがいい。きっと忙しいんだね、あまり無理をしてはいけないよ。ところでお父様は元気かな?」
悪気はないのだろうが、淳吾には多少おせっかいが過ぎる傾向があった。そして、あくまで上品に、かつ饒舌に喋る。
わずか二か月半の学校生活で結局あまり仲良くはなれなかったが、泰河が退学したあと、淳吾は様子を見に来たと言って受験勉強の合間を縫い、何度か山荘に足を運んでくれていた。
泰河は本当は学校で友達がほしかったのだが、誰かと関わりを持つことに必要以上に不安を感じていた。泰河は、福岡に越してきてから初めて、淳吾に対して特別な感情を抱くようになった。しかし常に一定の距離を置いて接し続け、淳吾が大学に合格した報告を受けたのを最後に連絡は取っていない。
泰河の中には再会を喜ぶ気持ちがあった。だが、成績優秀で品行方正、しかも面倒見もいいという優等生の淳吾に泰河は引け目を感じていた。もう少し距離を縮めたいという想いは昔からあったが、淳吾の人生にあまり自分は関わってはいけないのではないか、といういう考えが頭をよぎり、心にブレーキをかけてしまっていた。
だから素直に笑顔になることはできなかった。まして、今は特殊な状況である。再会のタイミングは非常に悪いと言えた。
「……先輩こそ、こっちの生活はどうです。なんだかすっかり溶け込んでいるようですが」
「ああ、逆に心配してくれるなんてきみは本当にいい奴だ。僕にはよく分かっているよ。大丈夫、皆親切にしてくれるし、最近はクラブ活動のようなものに打ち込んでいて充実した日々を過ごしているんだ。こうやってまた会えたのも何かの縁だ。今度予定を合わせてゆっくり話をしないか。僕もきみに話したいことが山のようにあるんだ。泰河くんも僕もまだ未成年だが、まあこっそり酒を酌み交わしたとしてもバチは当たらないだろう」
「……はいはい、じゃあ今度メールしますよ。悪いんですが、ちょっと急いでるもので」
淳吾がまだ何か言い続けているのを背中で聞きながら、泰河は足早に立ち去ろうとした。しかしあることを思い付き、歩みを止めて淳吾の方に向き直った。
「先輩、俺が屋上から絵を飛ばしたこと、覚えてますか」
「よく覚えているよ、泰河くん。きみは彫刻は人並み外れて上手なのにデッサンがあまりに酷いものだから、僕が控えめに指摘をしたんだったね。そしたらすっかり不機嫌になって、スケッチブックを全部紙飛行機にして屋上からバラ撒いてしまった。今でこそ、いい笑い話だが」
泰河もその時のことを回想して、懐かしい気分になった。控えめな指摘なんてとんでもない。一時間もみっちりデッサンの基礎を叩き込まれたのだった。
そしてポケットに入れていた空港のマップをその場で折り畳み、滑走路の方角に飛ばした。
泰河は"死体を動かす”だけではなく"加速”という特徴を持っていた。遺伝ではなく、独自に備わった特徴だ。投げたり弾き飛ばしたりした物体の速度を、好きなだけ速くすることができる。最高速度はプロ野球選手の投げる球とは比べ物にならないくらい速いが、野球ボールほどの大きさの物体は加速することができず、それより小さい物でなければなかった。ただし例外として、自らの体の一部を加速することはできた。
投げた瞬間、紙飛行機は尋常ではない速度で飛んだ。しかし吹いている風と空気抵抗によって途中で勢いを失い、くるりくるりと放物線を描き、展望デッキの柵を越えたあたりで落下していった。
明らかに不自然な現象だったようには見えない。だが一部の人間には、泰河が何らかの特徴を用いたということが分かるかもしれなかった。泰河は、淳吾の表情を注意深く観察した。
淳吾はため息をついて、言った。
「ゴミのポイ捨てをしてはいけないよ。まったくきみは、子供っぽさが未だに抜けないんだね。もう立派な社会人だという自覚はあるのかい?」
淳吾はやれやれという感じで口を少しだけ曲げて笑ってみせた。泰河は自分の思い付きが的外れであったことを確かめ、その場を後にした。
5
先生は、阿理沙が品川駅に到着する頃を見計らって電話をかけた。
「お姉ちゃん、電車は降りた?」
「はいはい、降りましたよ。そっちは着いたの?」
「よかった。そろそろだと思ってたんだ。今、品川駅のどこにいる?」
「何言ってるの? ちゃんと言われた通りの駅で降りたよ」
先生は阿理沙の数秒後の未来を見た。誤差があるのでどれくらい先のことかは不明だが、阿理沙は電話を切って駅の中を歩いている。そこは品川みたく大規模な駅ではないようで、一体どうしてそんなところにいるのか見当はつかない。異変が起きているという疑いが、ほとんど確信に近づいた。
「お姉ちゃん、そこはどこ? なんていう駅?」
「分かってるくせに、どうしてそんなこと聞くの。今日のあなたたち、ちょっと変よ」
変なのはそっちだと内心呟きながら、自分は今焦っているということが伝わるように言った。
「あまり時間がないんだよ。お姉ちゃん、頼むからオレの言うとおりにして」
「何よ、たっぷり時間はあるくせに。そんなに急がなくてもいいじゃない。飛行機は何時?」
何を言っても、のらりくらりとかわされてしまう。すでに阿理沙は敵に接触されたのかもしれない。そうであるなら、猶更もたついてはいられない。
いったん未来を見てしまうと、その時間が過ぎてしまうまで次の予知はできない。阿理沙が電話を切って歩き出すのは数分先のことだろう。だから数分が経過するまで予知はできなかった。先程見えた映像では、阿理沙はさして大きくないどこかの駅にいるということしか分からない。
敵は阿理沙を確保しようとしつつ、同時に自分と泰河を引き離そうとしているのだと先生は考えていた。先生は、自分の身に起こる出来事を予知することはできない。だから、何者かが自分に近づいていることは例え事前に察知しようとしてもできなかった。
「ねえボク、車内で電話するのはやめようね」
女の子が先生に声をかけた。歳は先生と同じくらいか、少しだけ上だ。せいぜい中学生にしか見えない。通話を切らずに隣の車両に移ろうとした先生に、女の子は言った。
「言う通りにすれば、荒っぽい真似はしないよ」
先生は、子供を見据えた。長い黒髪をツインテールにして、ピンクのTシャツにホットパンツ、黒いニーソックスといういでたちのまだあどけない子供だった。
「やん、そんなに怖い顔しないで。品川の次で降りて、地下鉄に乗り換えましょう。そこでゆっくりお話しようよ」
まさに天真爛漫といった感じの喋り方だ。外国人の血が少し入っているのかもしれない。ちょっと日本人離れしたエキゾチックな顔立ちをしている。
地下鉄に乗れば、携帯の電波はかなり繋がりにくくなってしまう。先生は電話を切り、警戒を強めながら言った。
「何者だ、お前は」
「あたしは兎って呼ばれてる。でもラビットって呼んで。どっちもどっちだけど、ラビットの方があたし的にはかわいいんだよね」
傍から見れば、同年代の子供が他愛もないお喋りをしているようにしか見えない。先生は五感を研ぎ澄まし、状況の把握につとめていた。ラビットに目線を合わせたまま、車内の様子を窺う。
「心配しなくても、あなたの相手はあたしだけだよ。ねえ、言うことを聞いてよ。綺麗な大人のおねえさんに何かあったら、困るでしょ。もし怪我なんかしたら、なかなか治らないんだから。ところで、あなたは一体どっちなのかな?」
こいつもオレたちと同じか。ウサギの顔をあしらった小さなカバンには、刃物にせよ拳銃にせよ小型のものしか入らないだろう。しかし、オレが普通の人間ではないと疑った上で単独行動している以上、戦闘向きの特徴を備えていることはほぼ確実だ。先生はそう考えた。すでに阿理沙は人質に取られていると考えたほうがよさそうだ。
先生は一言も発さず、電車に乗り続けた。三分経過したところで再度阿理沙の数秒後を予知した。駅から出てどこかへ歩いて向かっている。拘束もされておらず、取りあえずは無事なようだ。
この場でラビットを始末することは可能だった。しかし人目につくし、阿理沙の安全が確認できない以上、言うとおりにするしかないと判断した。
二人は地下鉄の駅に入っていった。会社員の帰宅ラッシュがすでに始まっていて人通りが途切れることはなかった。ラビットは乗車口のないホームの端まで先生を連れて行った。数メートルの距離を置いて、向かい合う。
「ラビット、お前たちの目的は何だ。正直に話せば殺すことはしない」
「うわ、あなたってもしかしておバカさん? どっちが不利な状況か、まだ分かんないかな」
「オレはここから一歩も動くことなく、お前の両手の爪を剥ぐことができる。嘘かどうか、一枚だけ試してみようか」
「んもう、みんな何だってそんなに野蛮なのかしら。あのね、もっとラブアンドピースな考え方をしなさいよ。話せば大抵のことは分かり合えちゃうんだから」
「質問しているのはこっちだ。お前たちの目的を話せ」
先生の言っていることは嘘ではなかった。先手を打たれてしまっている以上、強気に出るのが得策だと判断した。もし交渉が決裂してもラビットを確保すれば、人質交換が出来る。
「もっと肩の力を抜きなさいよ。……やれやれ。いいわ、質問は交互ということにしましょう。大サービスで先に答えてあげる。有馬泰河をあたしたちのサーカスに招待したいの。死体を動かすことができるなんて、かなり素敵じゃない。別に取って食おうってわけじゃないわ」
「サーカス、だと? どういうことか、ちゃんと話せ」
時期的に考えて、やはり渋谷の事件が元凶なのだろう。あの夜、死体が動いたという事実を知ることができ、それが何を意味するのか理解できる組織の中に、泰河まで辿りつける者がいたに違いない。
「だめだめ。次はあたしの番なんだから」
ラビットは先生の質問を遮る。交互なら、それはそれで話し合いの意味があるかもしれないと先生は考えたが、次の言葉を聞いてすぐに取り消した。
「あなたもこっち側の人間なんでしょ? どんな特徴を持っているの?」
「ふざけるな。そんなこと、口が裂けても教えられるか」
ネジを持つ人間同士が、相手に特徴を知られることはそれだけで大きなリスクだ。弱点を推測されてしまえば、生死を握られてしまったも同然になる。だからお互いに詮索しないのが、あらゆる時代あらゆる地域でずっと続いてきた暗黙のルールだった。ネジを持つ人間たちのあらゆるコミュニティが閉鎖的な側面を強く帯びていたのは、それによるところが大きい。
ラビットは両手を合わせて片目をつぶり、首を傾けて茶目っ気たっぷりのポーズをとった。まるでアイドルの振付の真似だ。そして芝居がかった口調で言った。
「それじゃあ、綺麗なおねえさんの口が裂けちゃうかもしれないよ。つまらない特徴だったら、誰にも言わないでおいてあげるから。お願い、教えて」
冷静であることを心がけていた先生の胸に、静かな怒りが込み上げてきた。こいつは、ただの子供だ。蟻の列を踏みつぶしちゃうよ、みたいな無邪気な残酷さで明確な悪意もなく、普通の人間を軽々しく傷つけようとしてしまうガキだ。
「あと一つで、終わりだ」
「え、なに? 今、ちょっとよく聞こえなかった。もっと分かりやすいように言って」
「お前がオレの質問に答えて、話し合いとやらは終わりだ。お姉ちゃんの居場所を教えろ。さもないと指を順番に粉々にしていくぞ」
「可愛げのないボクちゃんね。ちゃんと教えてあげるから、先に私の質問に答えなさい。ただし、教えるのは有馬泰河の招待が済んでからよ。それが済んだら、無事に返すと約束するわ」
論外だった。先生は答えなかった。
二人は視線を合わせたまま微動だにしない。間もなく構内アナウンスが流れ始め、列車が間もなくホームに入ってくることを伝えた。彼方から轟音が少しずつ近づいてくる。
ラビットと先生の横を猛スピードで地下鉄が通り過ぎた。その瞬間、ラビットの指先から火花が散った。
先生は驚いた。気配はおろか、姿すら見せることなくラビットの小指を確かに掴んだはずだ。
火花は、先生の特徴によるものではない。掴んだはずが、痺れるような衝撃を受けてそのまま弾かれた。
「痛い! 何してくれんのよ、この野蛮人! もういいわよ、招待が終わるまで、一人で東京中を探し回りなさいよ。運が良ければ見つかるわよ。物凄く運が良ければね」
逃げるつもりか、と先生は身構えた。位置的に追い詰められているのはラビットの方だ。逃げるとすれば線路に降りてトンネルの方へ行くしかないが、線路に降りようとする瞬間に捕えることが出来ると先生は考えた。さっきのように弾かれたとしても、簡単には逃がさない。
列をなして並んでいた乗客が、押し合いへし合い車両に乗り込んでいる。ラビットはカバンから何かを取り出した。それは小型のスタンガンだった。近づかないと使えない武器なら、先生にとって脅威ではない。
ラビットは逃げようとせず、その場でスタンガンのスイッチを押した。すると電流が青白い筋になって、先生の体めがけて長く伸びてきた。電流の威力は、本来とは比べ物にならないくらい強力になっているようだ。
不意を突かれ、避けるのがやっとだった。目を離してしまったほんの一瞬の間に、ラビットの姿は消えていた。
辺りを見回すと、どうやって移動したのか、ラビットは列車の屋根に登っていた。先生は列車の方へ走って行ったが、すでにドアは閉まっており動き始めるところだ。そして列車は先生から離れていった。
ラビットは屋根の上から先生の姿が見えなくなるのを確認した。さっきの火花で指が焼けただれ、赤黒く変色していた。カバンから薬と包帯を取り出して、応急処置をする。
「こうすれば数時間で治るでしょ。でもいちいち怪我してたら、キリがないわね。もっとうまくコントロールできるようにしないと。それにしてもあいつ、女の子相手に手加減ってのを知らないのかしら」
カバンにしまおうとした包帯が手から落ちてそのまま線路に吸い込まれていった。ラビットの機嫌はさらに悪くなった。
ラビットは、電流を操作し、増幅することができた。先生の攻撃を弾いたのは、あらかじめ自分の体の静電気を調節しておいて、触れるものがあれば自動的に勢いよく流れるようにしていたのだった。そしてスタンガンのような強い電流なら、増幅した上で好きな方向に伸ばすことが出来る。
取りあえずあたしの役目は終了ね、と一息ついたラビットの視界に、ありえないものが飛び込んできた。
先生が屋根の上に立っていた。列車は一度もスピードを緩めてはいないのに、一体どうやって追いついてきたというのか。
「へえ、やるじゃん。ますます質問に答えてもらいたくなっちゃったな」
「電気か、お前の特徴は。なかなかいいな」
「そうでしょ? まだちょっと慣れないけど」
ラビットは舌を出し、ばちばち、と先生を威嚇するように放電してみせた。こいつは、電気を操作し始めてからまだ日が浅いのではないかと先生は思った。ネジを持って生まれても、独特の特徴が開花するのは第二次性徴の前後であることが多い。
「ねえ、もし痺れて下に落ちて列車に轢かれちゃったりしたら、いくらあなたでも死んじゃうかもよ? 大人しく次の駅で降りた方が、いいと思うんだけど」
「それはこっちの台詞だ。体中こんがり焼けても、走る列車の上でしっかり立っていられるかな」
言い終わるか終らないかのうちに、先生は攻撃を繰り出していた。見えない何かが猛烈な勢いでラビットに襲いかかる。
スタンガンから電流が伸び、夜空に閃く稲妻の如く複雑に枝分かれして、ラビットの体を包むように張り巡らされた。静電気ではなくそれで防御すればダメージはない。
トンネルの中が、明るく照らし出される。先生の実力は予想以上だった。早いだけでなく圧倒的に手数が多い。ラビットは身を守るので精一杯だった。
一定の間隔で生じるわずかな隙間を縫って、ラビットは素早く電流を伸ばした。先生はそれを紙一重でかわし、徐々に間合いを詰めていく。
スタンガンで防ぎきれない攻撃が静電気を誘発し、ラビットの服や皮膚を焼いていく。髪止めのゴムも焼け、長い黒髪が背中で一列になった。
ラビットは不可解だった。電流の上下左右自在に伸びる動きは不規則かつ俊敏であり、たとえ誰であれ見切ることなどできないはずだ。仮に見切れるとしても、こんな短時間で出来るわけがない。しかも相手は、さっきまで普通の顔で喋っていたというのに、戦闘を始めるとまるで欠伸でもしそうなくらい眠たげな顔になっている。
片手でカバンから乾電池を取り出し、先生の方に放り投げた。電流を爆発的に増幅させられ、乾電池はまるで手榴弾のように閃光を炸裂させる。
動きを止めた先生の上と左から、すかさずスタンガンの電流が伸びる。それもかわされることは、あらかじめ承知の上だ。ラビットは乾電池を同時に二個投げていた。死角となる位置から、もう一方の電池が爆発するようにして襲いかかった。
わずかに手ごたえを感じ、ラビットは後ろに跳躍した。車両の端から端まで一気に飛んでいく、人間離れした脚力だった。ネジを持つ人間の身体能力はただの人間より非常に優れているが、圧倒的に違うわけではない。ラビットの脚力は、彼女に備わった独自の特徴だった。離れた電車の屋根に飛び乗ることなど造作もない。
線路はカーブに差し掛かっていた。ラビットは慎重に様子を窺っている。轟音に交じって足音のようなものが聞こえる。先生の姿は見えない。気のせいだと思った。直撃は防いだとしても、しばらく動けない程には電撃を浴びせたはずだ。
ラビットめがけてまっすぐ走ってくる先生の姿が、不意に現れた。驚いている暇はなかった。再び見えない何かが、息つく間もないほどの勢いで襲いかかってくる。
もう先生はすぐ目の前まで迫っていた。距離が近くなればなるほど、ラビットが受ける衝撃は大きくなり、もはやスタンガンだけでは防ぎきれなくなっていた。散る火花の数がどんどん増えていく。服ははもう全身ボロボロになってしまっていた。
二人の距離があと三歩というところまで来た時、攻撃が止んだ。
「ゲームオーバーだ。観念しろ」
諦めたような仕草で、ラビットがスタンガンを持つ手を降ろす。
その瞬間、スタンガンの先端ではなくバッテリーが入っている持ち手の部分から、目を開けていられないほど眩しい光が発せられた。
ありったけの電気を消費してラビットが発生させたのは、自然現象の落雷に匹敵する電撃だった。二人とも、避けることはできない。ラビットは自分の体に流れる電流を操作できるが、全くの無事というわけにはいかなかった。だからこれは、相討ち覚悟の最後の手段と言えた。
「まったく、どれだけ手を焼かせるのよ。こんなの初めて使ったわ」
視界がかすんで何も見えない。眼球が焼けてしまったのかもしれない。先生を仕留めたかどうか確認する余裕はなかった。たとえ直撃を防いだとしても、しばらく動けない程には電気を浴びせたはずだ。あとは得意の跳躍で、遠くへ逃げればいい。先生の存在は、ラビットたちの組織にとって思わぬ収穫だった。
しかし、足に力が入らなかった。筋肉が思ったよりダメージを受けている。内臓も損傷しているようだ。
「ちぇっ。ついてないや」
ラビットは膝をつき、そのままバランスを崩し、走る列車の屋根から転落した。
列車が通り過ぎ、トンネル内には再び暗闇と静寂が訪れた。乗客たちは自分たちの頭上で起きていたことに全く気付かないまま、次の駅に到着しようとしている。
線路にラビットの体は転がっていなかった。それは、トンネルの側壁に張り付いている先生の手に抱えられていた。
6
泰河は、一人で放浪の旅をしていた。ちょうど一年くらい前のことだ。沖縄の小さな島で、ある子供と出会った。
親の援助は一切あてにしない貧乏旅行だった。貧乏というか、ほぼ文無しだ。泰河には食費もほとんど必要なければ、金を出して借りねばならないような快適なベッドも不要だった。自分の体一貫で、どこまでできるか試してみたかった。夜通し歩き続け、道端で眠り、どうしても必要になれば力仕事をして最小限の金を稼いだ。
そうして辿りついた南の果て。沖縄の離島の中には、人口もほとんどいなけばインフラも充分整っていないところがある。そこには物好きな旅人や、事情があって日本のどこにもいられなくなった者たちが、粗末な小屋やテントを建てて自由に暮らしていた。
泰河もそこで寝泊まりするようになった。潮騒だけが聞こえる静かな場所だった。住人のほとんどは大なり小なり他の者とコミュニケーションを取りながら暮らしているようだったが、完全に孤立している者もいた。その中に、自分と同じように文字通りの野宿をしている奴がいた。
最初にそいつに出会ったのは、島の奥深いところにある滝だ。住人の一人から噂を聞いて、好奇心を刺激されその場所を探し回った。ガジュマルの樹に囲まれたその神聖な滝には精霊キジムナーが住んでいるというが、そこへ向かうと言って出ていったまま二度と帰ってこなかった者もおり、足を踏み入れることは住人たちの間でタブーとされていた。
ほぼ半日かけて辿りついたその場所は、確かに精霊がいそうな神秘的な雰囲気だった。滝は一階建ての家くらいの高さしかなくこじんまりとしており、水飛沫が霧のようになって辺り一面に舞い上がっている。木が鬱蒼と生い茂った中にあるが、木漏れ日が差して水面に反射していた。そして何より、落下する水の下には確かにキジムナーがいた。
そいつは、まるで修行僧みたく滝に打たれていた。泰河は顔がはっきり見える距離まで近寄ることができた。集中しているのか、無心になっているのか、じっと目を閉じて座っている。まだ泰河の半分しか生きていないのではないかというくらいの子供だった。性別もよく分からない。やがてそいつは閉じていた瞼をゆっくり開いた。泰河の存在に気付いていたが、文句を言うわけでもなく、姿を隠しもしなかった。泰河は、幻想的とも言えるその風景の前で、ただ立ちすくんでいた。
そいつは体を起こすと、跳躍してあっという間に滝の上から樹の上に飛び移っていった。泰河は足の速さには自信があった。自らの足を"加速”するのだ。まさに野生児という言葉がぴったりの、猿のように樹上を移動する子供を走って追いかけた。移動する速度は、地上の泰河の方が早い。しかし子供は途中で忽然と姿を消してしまった。本当に生きている人間だったのだろうか。まるで狐につままれたような気分だった。
泰河は滝まで戻ってみた。不思議と心落ち着く場所だった。滝に打たれてみようとは思わなかったが、腰を下ろしてその場所の雰囲気に心を委ねた。
泰河は両親に愛されて育った。とりわけ、母の注ぐ愛情は立派なものだった。一人っ子であるからとか、普通の人間ではないからとか、そんな理由はおまけみたいなものだった。守らなければならない血を分けた自分の分身として、同時に尊重すべき一人の人間としてカヤは泰河に優しく、時には厳しく接し、そして深く慈しんだ。
そんな母親が中学生になろうとする泰河から離れて行こうとした時、泰河は己惚れていたわけではなかったが、それでも多少せいせいしていた。母から受け取るべきものは、もう人並み以上に十分すぎるほど受け取ったのだと。
離れて暮らしていても寂しくはなかった。それに泰河はすでに自分の世界を持っていた。引っ越した頃は友達がほしいなんてことはあまり考えなかった。空想をしたり、彫刻をしたり、本を読んだり、探検に出かけてみたりと好きなように生きていた。自分の望み通りに生きているようで、それは両親に育ててもらい、今も守ってもらっているから出来ることだ、と心の片隅では思っていた。
中学二年に上がった頃、泰河は自分はどのような人間になるべきか、と考えるようになった。わがままで気まぐれな性格は一層ひどくなったが、心の一番深いところでは悩んでいた。いくら考えても、よく分からない。
泰河は、相談できる友達がほしかった。助言を与えてくれなくても、話を聞いて気持ちを分かってもらえるだけでもいい。だが、そんな友達をつくることは到底無理だと最初から半分諦めていた。中学を卒業した泰河は、悩んで出した結論を人生に反映させねばならなかったが、結論は出ていなかったので様々な回り道をする羽目になった。放浪の旅は、その現在進行形の集大成であった。
自分がただの人間でない、ということが泰河の悩みの核にあるように思えた。しかし、そんなことを克服した存在はいくらでもいる。両親だってそうだ。社会における自分の立ち位置について、各自折り合いをつけた上でまっとうな人生を送っている。二人とも変わり者ではあるが、きちんと仕事をして税金を納めている。父親の著書は日本中の書店に並んでいるし、カヤの絵を気に入って買ってくれる客は世界中にいる。カヤは泰河と離れて暮らすようになった後、東京でNPOを立ち上げクロックワークの子を持つ親たちの育児相談所的なサークルまでつくっていた。まだそんなレベルで悩んでいる自分は、他人より特別なようでいて、実はただ幼稚で弱いだけの存在ではないかとも考えることがあった。
だが、自分と親の場合で大きく異なっているのは、自分は"死体を動かす”という特徴をすでに四代に渡って受け継いでいるということだった。
小学六年の秋、泰河は飼っていた鈴虫を誤って死なせてしまった。虫篭をベランダに出しっ放しにしているのを忘れ、日光に晒してしまったのだ。泰河が学校に行っている間が母親が気付き、帰ってきた泰河はひどく落ち込んだ。虫篭を手に泣きじゃくる泰河を後ろから抱きとめていた母親は、やがてり、り、りという鳴き声が聞こえてきて言葉を失った。
小学校の卒業式の後、大事な話があると言って両親から聞かせられた。五代に渡って同じ特徴が受け継がれたクロックワークは、生態系を変えうるほどの力を持つことがある、と。
それは古い言い伝えのようなもので、明確な根拠はないがクロックワークたちの間では長い間信じ続けられているという。禁じられた力の発現を恐れてか、はたまた迫害主義者に命を狙われてのことか、五世代目の子孫がこれまでいたという記録は残っていない。
泰河の子供は"死体を動かす”という特徴を受け継がないかもしれないし、受け継いだとしてもそこまで強い力は持たないのかもしれない。そう話して、どう思うか、と母親は聞いた。泰河がそのことをどれだけ深刻に受け止めているか、判断するための質問だった。
泰河は、じゃあ僕は、子供をつくっちゃいけないの、と聞き返した。両親は、何も言えなかった。やがて頬に涙が伝い始めた母親が、大丈夫、なんとかなるからね、きっと大丈夫だからね、私が何とかしてあげるからね、と言ったところで、父親が母を外に連れ出していき、そこで話は終わった。
泰河の一番の心の支えは、母の存在だった。カヤは外国と東京を行ったり来たりして生活している。総一郎と泰河がいる福岡には年に三、四回やってくる。
仕事に没頭して泰河のことは放任主義を決め込んでいる父親とは違い、母は自分が悩んでいることを鋭く感じ取っており、たまに会えばちょっと一杯付き合いなさい、と言って酒を飲みながらじっくりと相談に乗ってくれようとする。泰河はいつも素直になれず、うまく話すことはできないが、母は遠い海の向こうからでも心配して手紙を寄越してくれた。
その手紙を読んでいるときが、泰河は最も心慰められ、勇気付けられる。そしてそれ自体が新しい悩みにもなっていった。自分は一人前に悩んでいるようでその実、親の庇護のもとモラトリアムをしているだけのガキじゃないのか。ただの甘やかされた坊ちゃんではないか、と。
泰河が考え抜いた次の一手は、自分が地球上でどのような存在なのか、生物であるのかを突き詰めたいというものだった。そして自分の存在は許されるべきものなのか、自分なりの答えを見つけたかった。そのためにまずは裸一貫で家の外に出たときどうなるのか、身をもって知りたかった。いくら本当の裸一貫になりたくても、親とのつながりがある限り決してそうはならないが、そこに折り合いをつけることも試練の一部だと考えた。
ガジュマルの樹を通して見る空が、茜色に染まり始めていた。思い描いていたのに近い場所まで、泰河は辿りついていた。だが答えを出すにはまだ程遠い。
その後も何度か滝に行ってみたが、もうキジムナーの姿を見ることはできなかった。泰河は精霊に会ったことを誰にも言わなかった。
長時間の睡眠をとらない泰河たちの夜は長い。ある日、泰河はほら穴のようなところで雨風をしのいでいた。
台風が接近しており、外では樹の幹や葉が強い風を受けひっきりなしに鳴いている。ようやくまどろみ始めた頃、異様な気配を感じて目が覚めた。
起き上がろうとした瞬間、腕に鈍い衝撃を感じた。ボウガンの矢のようなものが突き刺さっている。矢には毒が塗ってあるらしかった。わずかでも気を抜けば意識が深い谷底に落ちてしまいそうだ。
灯りはなく真っ暗だが、泰河たちは夜目が利く。三人の屈強な男たちがこちらを窺っていた。クロックワーク狩りだ、と泰河は直感した。普通の人間ではないということがばれてしまっただけで命を狙われることもあると、両親から教えられていた。同じクロックワークが欲望のままに襲ってくることもあれば、自分たちを狩ることを使命とする組織に嗅ぎ付けられることもある。その夜泰河のもとに訪れたのは、後者だった。
男たちはみすぼらしい旅人や釣り人のような服装をしており、首から下は一般人と何ら変わらないが、顔には目と耳をすっぽり覆うヘッドセットを装着していた。暗視スコープの役割を果たすと同時に、視覚と聴覚を制限することで人間の常識では考えられないクロックワークの特徴から身を守るための道具だった。組織され訓練されてはいるが、ただの人間だ。
「やったか」
「効いているようだ。一発で熊とか眠らせる薬だからな」
男たちはゆっくりと近づいてくる。泰河は自らを"加速”させ穴の出口まで駆けていった。しかし、見えない何かに体を絡めとられてしまう。高圧電流が全身を駆け抜けた。すでに出口には、網がかけられていたようだ。
「驚かせやがって、まさかまだ動けるとはな。お前はすでに捕獲されているんだよ。大人しくしろ、化け物」
一人の男が倒れている泰河の髪を掴み、顔を上げさせてから拳を叩き込む。泰河がぐったりしているのを確かめ、他の男が後ろに回って泰河に拘束具をつけようとする。
人間に捕えられたクロックワークは、死ぬまで実験動物のように扱われるという。様々な刺激を与えて脳の反応を見たり、どれだけ過酷な環境で耐えられるかテストしたり、体中を切り刻んで治っていく様子を観察したりされるそうだ。
泰河は、自分の人生はここで終わったと思った。自分の身に本当にこんな怖ろしいことが起こるなんて考えもしなかった。強い大人に助けてもらいたかった。自分は何も悪いことはしていない。誰か俺の味方をしてくれ。何もしていない俺を苛める悪い奴らを、誰か正しく裁いてくれ。
こんな事態を招いたのは、両親の制止を振り切り、自分の思うままに無軌道で無防備なことを繰り返してきた自分自身の責任だとも言えた。だが、泰河は自力で何とかするのではなく、誰かが自分を助けてくれることを願った。誰か俺を、助けてくれ。
ここから自分で何とかできるほどの力も知恵も、泰河はない。それは良く分かっていた。両親でも誰でも、知恵のある者が自分にもっと様々なことを教えてほしかった。危険を察知する方法、危険の真っ只中から抜け出す方法。だが、教えてもらうことを拒否したのは、他でもない自分自身かもしれなかった。教えてほしいのであれば、自分からそう言えばいい。そう行動すればいい。何もせずに結果だけを否定する自分は、なんて弱くて卑怯なのか。
図体ばかりでかくなって考えの足りない自分が、こうなることは自業自得なのかもしれない。だが、いくら考えてももう取り返しのつかないことだ。朦朧とする意識の中で、泰河は背中に不快な生温かい感触が広がっていくのを感じた。男たちの声が、泰河の耳に入ってくる。
「そいつから離れろ、異常種かもしれん。まだ危険だ」
「もう一発撃ち込むか。死んでしまうかもしれんが」
「タケ、聞こえるか。返事をしろ、タケ」
「駄目だ。急所をやられてる。なあ、こいつ殺してしまってもいいだろう? 正当防衛ってやつだ」
泰河の両手に拘束バンドを取り付けていた男が、膝をついて自分にもたれかかっている。すでに事切れているようだ。
慌てふためく男たちが持っている水中銃のようなボウガンが宙に浮かび、まるで見えない糸に引っ張られているように穴の出口の方へ運ばれていった。
「おうい。この網を外せ。さもないとお前らを撃っちまうぞ」
子供が立っている。あの野生児だった。
男たちは顔を見合わせ、ヘッケラー&コッホのサブマシンガンを構えフルオートで撃った。銃身の先端には短いサイレンサーが取り付けられている。倒れている泰河の上に薬莢が降り注ぐ。その熱さで、少し意識を取り戻した。
くぐもった銃声が止むと、硝煙の向こうに子供の影があった。ばらばらと激しい夕立みたいな音がした。ほら穴の中に雨が降りこんでいるのではなく、空中で止まっていた銃弾が地面に落ちる音だった。
「ずいぶん荒っぽい外し方だね、オッサン達。でも言うこと聞いてくれて、ありがと。島の中を嗅ぎまわってるでかい鼠がいると思ったら、やっぱりSACの連中かよ」
子供は悠然と男たちの方へ向かってくる。
「クソッ、仲間がいたのか。来るぞ、油断するな」
「こいつは返すぜ」
ボウガンが先程と同じように宙に浮き、持ち主の手元に吸い込まれるように飛んでいった。派手な音を立てて地面に落ちる。鉄屑同然になったボウガンには目もくれず男たちは走り出し、子供の左右にそれぞれ回り込もうとする。腰から大きなナイフを取り出していた。
まだ体の自由が利かない泰河には、戦闘の様子は分からなかった。やがて返り血を浴び真っ赤になったキジムナーが、意識を失った男を片手で引きずって泰河の元へ歩いてきた。
「まったく、でかい図体してるくせに間抜けなやつだなあ。こんなところで寝てたら、自分から罠にかかるようなもんだろ」
「あんた、神様か何かか」
子供は、吹き出した。久しぶりにこんな面白い冗談を聞いたというように、腹を抱えて笑っている。
「あるいはそうかもな。でも実際には、人間だよ。ちょっと変わっちゃいるけど。お前も同じなんだろ?」
答えに窮している泰河の眼前に、子供は掴んでいた男の体を投げ出す。
「ほら、さっき無抵抗のお前を殴った奴だ。まだ息がある。自分で始末しろ」
ヘッドセットが外れ素顔を晒していた。いささか精悍な顔つきをしてはいるが、どこにでもいそうな三十前後の男だ。泰河の手首を縛っていた拘束バンドがぱちんと音を立てて外れた。
「嫌だ……俺にはできない」
「はあ? どんなお坊ちゃんだ、お前」
子供は、顔をしかめて言う。
「こいつを生かしておいたら、島から出たとしても追手が際限なくやって来る。家族や友人にも危険が及ぶ。さっきの装備を見たか? 警察や自衛隊はあんなの持っていない。そもそも、政府はオレたちの存在を認識はしているが対策は何もしていないからな。あんな代物を扱うただの人間は一種類しかいない。SACくらい知っているだろう」
「いや……知らない」
「スポイル・オール・クロックワーク。すべてのクロックワークをぶち殺せ。もう何世紀も前から世界中で活動している、迫害派の元締めだよ。どんな教育を受けてきたんだ、小学校に行ってない俺でも知ってるぜ。あ、学校では教えてくれないのか」
泰河は、物を知らない自分を恥じた。だが、そういった知識を泰河は知りたかった。いくら調べてもクロックワークに関する情報はどこにも載っていないし、親もはっきりとは教えてくれなかった。
「そうでなくても、オレたちがクロックワークってだけで殺そうとしてくるような連中は、しっかり片付けておかないと後が面倒できりがない。自分は良くても他の奴にも迷惑がかかるからな。そんなの常識だろ」
確かにそうだ。母親から幾度となく聞かされていたし、旅に出る時も特にきつく言われていた。だが、自分が人を殺さねばならない時が来るなんて、どうしてもうまく想像ができなかった。母親は、これは守らねばならないルールだ、と言った。俺たちのような存在が生きていく上で避けては通れない道だと。今が、その道を通る瞬間だった。
泰河は半分身を起こして横たわる男を眺めた。さっき体の自由が利かないときに思い切り殴られたことを思い出して、怒りという感情が湧き上がってくることをイメージした。切れてしまった口の中はすでに治りかけているが、痛みは残っている。
だが、いくら頑張ってみてもそのイメージはうまく形にならない。しまいには男の顔が、中学の担任の顔に似ていることに気付くという始末だった。
「……自分が殺されようとしているときなら、殺せるよ。そうでなくても、誰かを殺そうとしている悪い奴とかなら殺せるかもしれない。だけど、殺さなくてもいい人間を手にかけるなんて、俺はしたくない」
「何甘っちょろいこと言ってるんだ、お前」
子供は、泰河の頬を平手で殴った。乾いた音が穴の中に響く。
「家族がいるんだろう? 伸び伸びと育ちました、って顔してるぜ。ろくな教育をしなかった母親の顔が見てみたいな。そんなことは、自分のケツは自分で拭きましょうってレベルの、ごく当たり前の義務みたいなもんだ。そんな覚悟すらできないなら、一生外に出ず家の中でぬくぬくと暮らしてるんだな」
「……うるせえな、俺は俺のしたくないことは、しねえって言ったらしねえんだよ」
泰河は、ようやく怒りのイメージを完成させた。だがそれは自分を狙ってきた男に対してではなかった。
「おい、お前が怒らなきゃならないのは、オレじゃなくてそいつだろう。オレは助けてやったんだぜ」
「俺は、思い通りにならないのが一番嫌いなんだよ。いくら自己中のクソガキって言われようが、嫌いなものは嫌いなんだ」
泰河は立ち上がり、険しい顔で子供を睨んだ。子供はすっかり呆れ顔だ。
「まったく、救いようのない馬鹿に出会っちまったぜ。いいよ、後はオレがやるから、お前はさっさとおうちに帰ってママのおっぱいでも吸ってろ」
「そんなことはさせねえし、母親の悪口を言う奴は許さねえ」
泰河は拳を振り上げ、子供に殴りかかっていった。
7
"さっきはごめんよ。もう少し時間がかかるんだ。北口にあるサファリっていうお店で待ってて。地図のURLを送信します”
よく分からないまま電話を切られてしまったが、とにかく地図が無事に送られてきたので、阿理沙は店に向かった。しかし駅を出るまではいいが、地図に書いてあることを正確に理解するのは彼女が大いに不得意とするところだった。
しばらく路地を行ったり来たりして、諦めて泰河に電話をかけ道を聞こうと思ったとき、阿理沙に話しかけてくる者がいた。
「またお会いしましたね。もしかして、約束すっぽかされちゃったんですか?」
喫茶店で会ったゴスロリ女だった。阿理沙は少し顔をしかめたが、どうやら女は店の場所を知っているようだ。これも何かの縁、渡りに船と案内をお願いすることにした。
そこは女子なら誰でも思わずうっとりしてしまうような、ファンシーな内装のパンケーキ屋だった。店先に置いてあるメニューの写真も、心がそわそわしてくるようなものばかりだ。
「わあ、やっぱり素敵。ねえ私もお店に入っていいですか? 素敵な弟さんが来たらすぐに退散しますから、それまで二人で一つのケーキを食べましょう。何てさみしい女たちなんだって思われちゃうかもしれませんけど、どうせ半分は当たってますから。いいでしょう? 私が奢りますから。この店、大好きなんです」
厚かましいとは思ったが、それほど悪い気はしなかった。黙ってさえいれば、虫も殺さないような人物に見える。ちょっと世間知らずなんじゃないかという呑気な雰囲気もあった。親切にここまで案内してくれたことだし、それくらい別にいいかと思って阿理沙は申し出を受けることにした。人見知りな阿理沙だが、こんなものを見せつけられて店内で生殺しにされるよりは、かなりマシだった。
一歩店の中に足を踏み入れただけで、チョコレートのような、マシュマロのような甘い匂いが鼻孔をくすぐる。初対面の人間と共に過ごすことの不安は、すぐに吹き飛んでしまった。
主義主張の異なる二人の女子が互いに熟考し、一つのケーキを選びとる作業はそれなりに絆を深めあう経験だった。いささか心安くなったところで、阿理沙は聞いた。自分から話を始めるのは苦手だが、おそらくは年上である自分がリードしなければと気を遣ったのだった。
「ねえ、あなたの名前はなんていうの?」
「申し遅れました。私は手品師、と呼ばれています。全然マジックなんて出来ないんですけどね」
ぴん、と背を伸ばして自己紹介する。阿理沙は面食らったが、ゴスロリ仲間の中でのあだ名なんだろうと、勝手に解釈した。
「呼びにくかったら、加奈子でいいですよ」
案外平凡な名前に、内心ほっとした。
「今、けっこう普通な名前じゃねえかこいつ、って思ったでしょ? 仕方ないんです。普通の女の子にはそれなりの相応しい名前が与えられてるのが世の常なんです。私、亜理紗さんをどこかで見たことがありますよ。もしかして、芸能人なんですか?」
手品師は身を乗り出して、阿理沙の顔をじっと見つめる。こういう強引な相手はちょっと苦手だが、会話をスムーズに続けるにはかえって丁度いいかな、と阿理沙は思った。
一応はプライドを持って仕事をしているのだから、別に正直に打ち明けてもよかったのだが、きっと加奈子は携帯でネットを検索し刺激的な自分の姿にたどり着くだろう。こんなに女の子っぽいお洒落をしている子の前でそれを披露するのは、かなり気が引けた。阿理沙は適当にお茶を濁しておいた。
加奈子の素性を尋ねてみたところ、年齢は一八歳で、早生まれの泰河とは同学年だった。ただし泰河と同様、高校には通っていないらしかった。そしてそれ以上は聞くのをやめた。
今日の阿理沙の服装は、大学生の普段着みたいなどちらかと言えば地味なものだった。加奈子は服装だけではなく顔も人並み外れていたが、阿理沙はそんな恰好をしていても加奈子にまったく引けを取らないくらい美しかった。まず、スタイルが根本的に違う。体の線を強調しない服を着ていても、布の下から十分な主張が発せられていた。そんな二人は、店の中で浮いていた。
そんな両者の間に、芸術品と言っていいほどの見事な盛付と装飾が施されたパンケーキが置かれた。目を細め、一口一口を遠慮がちに食べる阿理沙とは対照的に、加奈子はぱくぱくとケーキを口に入れていく。そしてあっという間に半分を食べ終えてしまった。
その様子を途中から眺めていた阿理沙の視線に気づき、加奈子はフォークを置いて顔を耳まで真っ赤にした。
「ごめんなさい。私、とっても大食いなんです。はしたないよね。服装もへんなの分かってるけどやめられないし、こんなんじゃきっとお嫁にいけない」
口の端にピンクのクリームをが付いているのに気付き、ハンカチを取り出して恥じらう加奈子を見て、阿理沙は笑った。
「そんなことない、とってもかわいいよ。その服も最初はちょっとびっくりしたけど、加奈子ちゃんによく似合ってるし、きっといい人が見つかると思うな」
そう言われて、加奈子はさらに恥ずかしそうに俯いた。阿理沙は、まだ残っている自分の分を加奈子に譲ることにした。
「どうせ私はまた食べるし、それに加奈子ちゃんが美味しそうに食べるのが見たいから」
「いいんですか! ありがとうございます。途中でやっぱりナシ、っていうのはやめてくださいよ。持ち上げておいてどん底に突き落とすみたいな。そんなことされちゃったら、私本当に病みます」
感情の起伏の激しい子だ、と微笑ましく阿理沙は思った。加奈子が一瞬でケーキを平らげるのを見届け、二人はコーヒーを注文しガールズトークに花を咲かせた。どうやら、不思議とウマが合う組み合わせのようだった。
コーヒーが少なくなっても、阿理沙の携帯には電話もメッセージも入らなかった。それを気にしている様子を見せると、加奈子は言った。
「弟さん、なかなか来ないですねえ。イケメン過ぎて、女の子につかまっちゃってるのかも。それか、逆にナンパでもしちゃってるんじゃないですかね」
「きっと違うわ。第一、彼にはそんな度胸ないもの」
「ふうん、じゃあ来るまで何かして遊びましょうよ。トランプとかどうです?。お約束すぎますけど、ババ抜きとか」
その前に一度泰河に連絡を入れたかったが、大丈夫ですって、きっとそのうち来ますから、と急かされた。バッグからすでにトランプを取り出し、カードを配り始めている。リボンがあしらわれており可愛らしいデザインだが、何故そこまで、というくらいサイズは大きい。まあ、このゲームが終わってからでもいいだろうと、阿理沙は自分の札を手に取った。
始める前に、手品師はある提案をした。
「面白くするために、こんなルールを加えるのはどう? 負けた方は勝った方のお願いを一つ聞くの。何でもよ」
どうせ弟の連絡先を教えろ、とか他愛のないお願いをするのだろうと思い、阿理沙は軽い気持ちで了承した。
ゲームは、手品師の勝ちだった。よほど勘がいいのか、加奈子は無駄のない引きで早々と勝利を収めた。
「わあい。約束だよ、私のお願い聞いてね」
どうぞお好きに、と阿理沙は言った。一方的な展開だったため、阿理沙は正直あまり面白くなかった。お願いを聞いてやったら、さっさと泰河に連絡してしまおうと思っていた。
手品師は、阿理沙の顔をじっと見て言った。
「じゃあね、もう一度勝負して。今すぐにだよ」
そう言われると、阿理沙は不思議なくらいお願いを聞かねばならないという気になった。
「分かった。今度は私がカードを切るね」
次のゲームは、かなり時間がかかった。ジョーカーをお互いが持ち合い、一進一退の攻防となった。最終的には、手品師の勝ちだった。そしてお願いも先程と全く同じものだった。
阿理沙は、ゲームの最中は早く泰河に連絡しなければと思っていても、加奈子に「今すぐもう一度」と言われると、きれいさっぱり忘れてしまった。そして「今度は絶対勝つんだから」と悔しがりながら笑顔すら見せ、次の勝負に挑んだ。
手品師はそのあとも勝ち続け、ゲームは日が暮れるまで延々と続いた。肝心な局面になると、加奈子は「こっちにしなよ、いやこっちがいいかな」となどと揺さぶりをかけてくる。阿理沙はいつもその通りにしてしまい、次は勝てるかな、と思っても結局負けてしまうのだった。
手品師はある時刻になり連絡が入ったら、わざと負けて切り上げる予定だった。それで彼女の役目は果たされる。有馬泰河の乗る飛行機が搭乗を開始し、空港にいるもう一人の仲間から電話がかかってくるのを加奈子はずっと待っていた。
有馬泰河が招待を断った場合、阿理沙を人質に取っていることを示し、招待を受けさせる。それが彼女たちの描いたシナリオだった。加奈子も普通の人間ではなかった。ラビットと同じように、サーカスと呼ばれる組織に属する進化した人間だった。
彼女の特徴は"相手に何でも言うことをきかせる”というものだった。加奈子がひとたびカラスは白いと言えば、相手はずっと白いと言い続ける。しかも、強制されて言うわけではなく自然にそう考えてしまうのだった。自分が何かおかしいということに、決して自分で気づくことはできない。
一人に対して一つだけ、指示したことに無理矢理従わせるのではなく、そうしなければならないと考えてしまうよう相手の思考を操る。それが手品師と呼ばれる加奈子が備えた特徴だ。ただし、具体的な行動を指示するには、予め説得をしておかねばならない。説得の度合いは内容によって変わるが、阿理沙にゲームを続行させる程度の指示であれば、ゲームに勝った方のお願いを聞くという言質を事前に取っておけばそれで十分だった。
加奈子が勝ち続けているのは、ごく単純なイカサマによるものだ。トランプは、裏面の図柄でどのカードか分かるようになっていた。もしカードが残り少なくなって自分がジョーカーを持っていたら、阿理沙がジョーカーを取りたくなるような指示をすればいい。カードを取れという指示ではなく、どちらを選ぶかという指示なので特に説得は必要ない。新しい指示を出せば古い指示は消えてしまうが、すぐにまたゲーム続行を宣言する。
駆け引きを演出して楽しげな雰囲気をつくり、最後には自分が勝つ。連絡が来るまでそれを繰り返しておけばよかった。飛行機が遅れたりしていなければ、あとほんの数分で予定の搭乗時刻だった。もう何回目か分からないくらいの同じやり取りをして、配られた手札からペアになっているカードを捨て終わったとき、ふいに手品師は、ラビットの失敗と、自分の役目が増えてしまったことを知った。
「ごめんよ、遅くなっちゃった」
先生が店に現れたかと思うと、まっすぐ二人がいる方に向かってきて阿理沙の横に堂々と座った。
「どこに行ってたの、ずっと心配してたのよ。泰河はどうしたの」
加奈子にお願いをされるたびその心配を打ち消し、率先してゲームを続けていた阿理沙だが、本心からそう言った。
「ちょっと二人でケンカしちゃってさ。さっきまで色々あったんだ。泰河は気まずくてここには来たくないみたい」
「ふうん。まあ、仲がいいほどケンカするっていうしね。あ、加奈子ちゃん。この子が、あたしの弟みたいな男の、弟分って感じの子」
「なんだよそれ。オレじゃなくて、あいつが弟分って感じだろ。どっちかっていうと」
平静を装うとするが、手品師は混乱していた。どうしてこいつは、私の前に平然と座ることができるのか。阿理沙が自分に操られていると予想はついているはずだ。
敵対するクロックワーク同士が不用意に接触するのはどんな場合であれ危険だ。しかも、私の特徴は言葉によって行使される。目を見て言うのが一番いいが、肉声を聞いただけで指示は通る。万が一ラビットが自分の特徴をバラしてしまっているなら、猶更接触などすべきではない。
「早くここから出よう。そうしないと、飛行機に間に合わなくなるんだ。悪いけど」
「そうね。だけどあと一回だけババ抜きするって約束したから待ってて」
「ダメだよ、悪いけどもうあんまり時間がないんだ。ほら、泰河の手紙だよ。どうしても店には来たくないっていうからオレが書かせたんだ」
何を言われても、阿理沙はゲームを続けようとする。それは特徴が行使されているからだ。先生は加奈子の存在など意に介さず阿理沙に話しかけている。特に警戒している様子は見られない。
手品師は迷った。こいつは自分を瞬時に操ったり、特徴を封じたりすることができるのかもしれない。だがすでに接近を許してしまっている。逃げようとしてももう遅い。加奈子は腹を据えた。そして動揺していることが悟られぬよう、なるべくのんびりとした口調で笑顔を添えて言った。
「あと十分だけ、私たちのゲームを邪魔しないでもらえる? 私、こんなに楽しいのは久しぶりなの。その代わり、何でも好きなの食べていいわよ」
これでもう先生は阿理沙を連れ出すことはできなくなったはずだ。自分に攻撃を加えることもできない。手品師は、先生の表情を注意深く観察した。もし指示が通っていなければ、今すぐにでも始末されてしまうかもしれない。テーブルの下で脚が震えだしていた。
先生は、やっと合点がいったとでもいうように、少し明るい表情になり言った。
「なるほどそういうことか。いいよ、オレは邪魔しない。どうせしたくても出来ないようになってるんでしょう? そういう特徴の持ち主なんだね。そして指示は一人に一つしか出すことができない」
何を言われているのか、分からなかった。やはりこいつは、自分の特徴に気が付いている。しかし正確に把握したのは今この瞬間だったようだ。
「だが、あと一回で終わりだ」
「何なのよそれ!」
加奈子は思わず、立ち上がって大きな声を出した。もはや焦燥を隠す余裕もない。阿理沙だけでなく、店内の客や店員も驚いて加奈子に注目した。
「だから、楽しいゲームとやらはあと一回で終わりと言ったんだ。今すぐやるんだろう? 早く始めなよ。そう言うのをさっき入り口で聞いてたんだ」
阿理沙は、まだいまいち状況が呑み込めていないようだった。泰河の手紙と言って渡されたメモとトランプを握ったまま、他の客と同じようにぽかんとして先生と加奈子を交互に見ている。
先生は、子供らしい無邪気な表情から真剣な顔つきになって加奈子を睨み、言った。
「終わったら一言も喋るんじゃないぞ。喋ろうとした瞬間、息すらできないようにしてやるからな」
自分がゲームを不自然に引き延ばそうとすれば、今すぐゲームをするという指示と矛盾が生じ、阿理沙の思考が正常に戻ってしまう。今すぐ出て行け、と先生に言ってみようにも、予め説得をしておかなければその指示は通らないだろう。新しい指示を上書きしようとしただけで、それが成功しても失敗しても古い指示は消えてしまう。つまり、ゲームを続行するしかなかった。手品師は椅子に座りなおす。
しかし、要はこれまでと同じように自分が勝ちさえすればいいのだ。先生はゲームが続いている以上、邪魔をすることはできない。トランプがイカサマ仕様であることに、阿理沙が疑いを持つようなことはこれまでなかったはずだ。
唯一不利になったのは、自分のカードが残り二枚になってジョーカーを持っているときに阿理沙に指示ができないということだ。先生は、ここへ来てすぐに店を出るよう阿理沙を説得していた。加奈子が指示をすれば、ゲームを続けるという古い指示は消えてしまう。そうすれば阿理沙はすぐに店を出て行くだろうし、ゲームが終わった以上は先生が加奈子に手を出せないということもなくなる。
手品師は改めて手札を確認した。運の悪いことにジョーカーを持ってしまっていた。落ち着け、勝ちさえすればいいのだ。
ゲームが再開する。あっという間に手品師のカードは二枚になった。阿理沙は残り一枚だ。手品師には、祈ることしかできなかった。右か、左か。阿理沙の指が空中を彷徨う。
阿理沙はジョーカーを引かなかった。次の瞬間、見えない何かによって加奈子は唇が押さえつけれるのを感じた。呼吸はできるが言葉を発することはできない。肩のあたりにも力を込められている感覚があって、席を立つことすらできなかった。
「お疲れ様。さあ、今度はオレの言うことをおとなしく聞いてもらおうか」
次は、阿理沙が混乱する番だった。完全に指示が解けたので、もう加奈子に構っている理由はない。
「一体、どういうことなの? それにこのメモって……」
その手に握られたメモの内容を見て、加奈子はすっかり観念してしまった。どうやったのかは分からないが、相手の方が一枚上手だった。メモには"残り二枚になった時、ババは左”と書いてあった。事前にそれを知り、ゲームを邪魔するなという指示の前にすでに阿理沙に渡していたのだ。
「泰河が悪い奴に狙われている、って言っただろ? お姉ちゃんは今までこいつに人質として拘束されていたんだよ。こいつもオレたちと同じで普通の人間じゃない。言ったことを、相手に強く信じ込ませるような特徴の持ち主なんだ。おそらく、電話の内容は全部嘘だとでも言われたんじゃない? 何を言っても、全然言うこと聞いてくれないんだもん」
「加奈子ちゃん、そうなの……?」
まだ信じられないという目で、阿理沙が手品師の方を見ている。加奈子はその視線に応えることができなかった。
「もうすぐ空港から連絡が入ってくるんだろう。電話を出すんだ」
言われて、手品師は渋々携帯電話を取り出した。ロックを解除して机の上に置く。
「お姉ちゃん、メールやなんかを一通りチェックしてくれ。 オレは機械音痴で使い方が分からないんだ。」
「え、そうなの? じゃああのメッセージは何?」
阿理沙は自分の携帯を先生に見せた。
「ちぇっ、オレになりすましてやがったのかよ。これを送ってたのは、きっとこの女だぜ」
加奈子の携帯をチェックすると、確かにそうだった。ようやく自分が騙されていたことを理解したのか、阿理沙の顔が青ざめてきた。
純粋に連絡用の端末なのだろう。何も情報は入っていない。履歴に残っている番号を念のためメモするが、そこからはおそらく何も分からないはずだ。
その携帯に、着信がかかってきた。阿理沙が先生の方を見る。
「取るんだ。何も心配はいらない」
手品師は観念した様子で、じっと俯いたままだ。着信を受けるとテレビ電話になっており、泰河の顔が映し出された。周囲は暗く、どこか屋外にいるようだった。
「阿理沙ねえちゃん、無事か?」
泰河がほとんど叫ぶように聞いた。目には恐怖の色が浮かんでいる。阿理沙は、何を言えばいいか分からないといった様子でおどおどしている。先生は身を乗り出して、自分の顔が泰河にも見えるようにして言った。
「大丈夫だ。オレがしっかり、守っている。お前は予定通りそこにいるやつをぶっ倒せ」
泰河の顔色が変わった。置かれている状況に恐れを抱くことなく、すでに勝ちを確信しているような笑みを浮かべ、了解、とだけ言った。
画面が暗くなって揺れる。泰河は携帯を放り投げて持ち主に返したようだ。異形の者の姿が、画面に一瞬だけ映り込んだ。
そいつは通話を音声のみに切り替えて、言った。
「手品師と兎は、どうした」
「知るかよ、馬鹿。オレに言えるのは、あとは自分の心配だけしろ、ってことだ」
先生は、泰河に負けないくらい不敵な笑みを浮かべて言った。
8
沖縄の果て、台風が接近している離島の洞窟の中で、再会を果たした二人のクロックワークが戦いを始めようとしていた。
「真正の阿保か、こいつ」
子供は、泰河の攻撃に備えて身構える。しかし、思いがけなく左右から襲ってきたナイフに気付き、跳躍して避けねばならなかった。
始末したはずの二人の男が起き上がっていた。目は虚ろで顔に生気はないが、生きていた時以上の力と俊敏さが備わっているようだ。
「これは……お前の特徴なのか」
「そうとも。二人くらいなら、俺ほどじゃないがかなり素早く正確に動かせるぜ」
男たちは、無駄のない動きで子供に襲いかかる。連携して、一方のナイフの死角からもう一方が仕掛けてくる。肉を切り裂き骨を砕いても、まったくひるむ様子がない。手こずる程の相手ではないが、素早く位置を変え、最も反撃しにくい角度から突きや蹴りを繰り出してくる泰河が厄介だった。どうやら、多少空手の心得があるらしい。
回し蹴りの構えを取り片足を上げようとして、膝ががくんと崩れ落ちた。臍の横あたり、横っ腹が貫かれてしまっている。
普通の人間なら致命傷だ。子供は勝負がついたことを確信する。だが、すぐに泰河は立ち上がり何事もなかったかのように攻撃に転じる。
「しぶとい奴だ。馬鹿は死ななきゃ、って言葉知ってるか」
「ごちゃごちゃうるせえんだよ。ガキが夜中に出歩いてんじゃねえ」
先程の麻酔の影響も含め、怪我はもうほとんど治っているようだ。普通の人間よりはるかに強靭な肉体を"加速”して繰り出す打撃は、体にまともに当たれば当たった部分ごとちぎれ飛んでしまいそうだ。
三人の男がせわしく動き回っている。その間を、子供はさらに速く上下左右に動いている。のろすぎて欠伸でも出そうだぜ、と言わんばかりの表情で全ての攻撃をかわすか防ぐかしており、ほぼダメージはない。その子供の姿が、忽然と見えなくなった。
虚を突かれ、辺りを見回す泰河の首が物凄い強さで締め上げられる。そのまま持ち上げられ、天井に叩き付けられた。意識がほんのわずか遠のく。そして数メートル下の地面に勢いよく落とされた。胸骨が折れる音がし、口から血を吐いた。
「本当にイカれてるぜ、お前。まあ逆に見込みがあるかもな」
ゾンビになっていた二人は、ただの死体に戻ってしまったようだ。それでも泰河の目つきは、まだ戦う意欲をなくしていない。
「馬鹿は馬鹿なりに根性があるってのはよく分かった。だがオレには勝てないよ。どうだ? 気は変わったか?」
うつぶせに地面に押し付けられている泰河の喉からは、血がごぼごぼと溢れている。折れた骨が肺に刺さったのだろう。言葉を発することはできないが、キリキリと泰河の頭の奥で音を立てているネジが、まったく気など変わっていないということを代弁していた。
「その音……。お前、自分でネジを巻けるクロックワークなのか。珍しいこともあるもんだな。道理でゴキブリ並にタフなわけだ」
首に巻きついている見えない何かが泰河の体を起こし、楽な姿勢にしてやる。子供は泰河の拘束を解き、まだ合点がいかないという顔つきで聞いた。見下すような言い方ではなかった。
「なあ、教えてくれよ。何故そこまでしてこんな奴を守ろうとする? 確かに辛いかもしれないが一瞬のことだ。あとは痛い思いも、面倒な思いもしなくて済むんだぜ」
泰河は、息も絶え絶えになりながら振り絞るように言った。
「だってよ……死ぬのは一瞬でも、ずっと悲しむ家族や友人が、きっとこいつにもいるんだぜ。俺は死なずに済んだんだ…… それでいいじゃねえか。こいつも俺たちと同じ、人間だろ」
身の毛もよだつような綺麗事だと、言いながら泰河自身そう感じた。そんな綺麗事が自分の頭の中にストックされていたなんて、驚きだ。だが、その時泰河は、余計なことは一つも考えられない状態で、純粋にそう思ったのだ。
ふざけるな、オレたちとこいつは同じ人間じゃない、と一蹴され、罵倒されると思った。だが子供から返ってきたのは、そんな言葉ではなかった。
「馬鹿野郎、そんなことはよく分かってるよ」
ほら穴の空気全体が震えるほどの、叫び声だった。
「じゃあお前は、こいつやこいつの仲間や、家族や友人、世界中から殺したいほど憎まれ、疎んじられ、呪われても全て受け止めて生きていけるのか? そんなにお前は強いのか? 立派なのか? 悟れるのか? オレたちが地球のどこかでひっそりと呼吸をすることすら認めようとしない奴の家族や友人の幸福にまで責任を持とうとするなんて、一体お前は何様のつもりなんだよ。確かに同じ人間なんだよ、出来ることと出来ないことがあるって違いしかない。だけどオレたちは、どこかで線を引かないといけないんだ」
最後の方は、まるで自分に言い聞かせるみたいにゆっくりと子供は喋った。ああそうか、こいつは俺よりも、沢山辛い思いをして、沢山考えたんだなと泰河は思った。何も言い返せない。やっぱり自分は、クソガキだ。
「ちぇっ、分かったよ。お前に免じて、出血大サービスだ」
子供は、もう付き合ってられるか、と観念した様子で言う。
「オレは"記憶を消す”という特徴を持っているんだ。こいつの頭の中から、クロックワークに関する全ての記憶を消してやるよ。他の膨大な記憶も合わせて消えてしまうだろうから、その後ボケ老人みたいになったこいつのことは、流石に面倒見切れないけどな」
泰河は、うまくものを考えることができない呆然としたままで、子供が男の顔の上に手をかざし、じっとしている様子を見ていた。しばらくして、子供は立ち上がって言った。
「一丁あがりだ。と言ってもこのままだと怪我で死んでしまうから、あとはお前がなんとかしろよ。鍛えてるみたいだから、まあ大丈夫だろ。かなり記憶を消したから最低でも一週間は眠りっぱなしだな。ああ、疲れたからオレも眠くなってきた」
そう言って、いかにも子供らしい大きな欠伸をした。ほとんど眠らなくていいクロックワークは、通常疲れたからといって眠気を覚えたりはしない。
「なんだよ、あんた、実は結構いいやつじゃねえか」
「繊細な時期なんだ。軽々しくそういうこと言うなよな。照れるから」
子供は、もう背を向けて歩き去ろうとしていた。
「オレがわざわざ苦労して生かしてやったんだ。ちゃんと世話して、殺さないようにしろよ」
「大丈夫だ。俺がしっかり、守っている」
泰河がきっぱり言い放つと、子供は足を止めた。
「甘ったれのくせに、自分で決めた事だと妙に説得力があるやつだな。なかなかいい言葉だ。このご時世、なかなかそんな台詞使う機会がないぜ。念のためもう一つ、知らないかもしれないから教えておく。自分の特徴は基本他人に知られるな。戦うときも、なるべく悟られないようにしろ。あとで色んなトラブルの元になるからな」
「あんた、名前はなんていうんだ」
「名前は持ってない。これから持つつもりもない」
「じゃあ、これから先生って呼ぶぜ。俺は有馬泰河っていうんだ。なあ、これからも色々俺に教えてくれよ」
泰河は後片付けをした。動けるようになってもまだ体中が痛かったので、死体に動いてもらって薬莢や壊れたヘッドセット、出口にかけられていた網なんかをまとめ、やはり死体に穴を掘らせて埋めた。死体にはその中に一緒に入ってもらった。手を合わせ、成仏してくれよな、と話しかけてから自分で土をかけた。
生き残った男は泰河の看病の甲斐あって、数日後には目を覚ました。男はボケ老人というより、ちょっと頭の足りない子供みたいになってしまっていた。ヒラという自分の呼び名は覚えているようだったが、他のことはうまく思い出せないらしい。時間が経てば故郷や家族のことを少しずつ思い出すかもしれない。泰河はヒラと共に島で生活を続けた。
先生はヒラの様子を見に来たと言って、時折訪ねてきた。いつもすぐに立ち去ってしまう先生を、泰河は走って追いかけた。あの夜も、先生は答えずに去っていった。心なしかその背中は笑っているようだった。
二人の追いかけっこは何回も続き、ついに泰河は先生の生活空間のようなものを突き止めた。それは葉っぱを重ねてつくった、住居というより巣だった。滝を中心として、こまめに場所を変えているようだ。先生の暮らしぶりには年季が入っていた。鳥を捕えては器用に解体し、焚火で焼いて食う。体がなまらないように、と気の向くままジャングルみたいな山を駆け回り、あとは一日の多くを修行僧みたいに滝に打たれて過ごしていた。
泰河はすっかり回復したヒラと共に、先生と一緒に暮らすようになった。先生は迷惑そうだったが、文句らしい文句はヒラと一緒に食事をするせいで太っちまう、くらいしか言わなかった。
先生はクロックワークとして生きていくための知識や、キャンプというよりサバイバルな生活の知恵をいろいろと教えてくれた。泰河は、文明からほとんど隔絶された日々の中で、俺たちにはこんなふうに生きていく方法もあるのか、と自分探しの答えのヒントを少なからず得たが、ヒラがいたせいで結局よく分からなくなった。ヒラは普通の人間の中では人並み外れて屈強な男だった。ひどい生活にも動じないし、大飯食らいだ。ワナの作り方を自己流で編み出し、自力で食料を調達するようになっていた。
三人のサバイバル生活は続いた。精神年齢が近いせいなのか、なかなか楽しい毎日だった。見た目の年齢と精神年齢が真逆になっているような妙な三人組はすっかり意気投合していた。ずっとこんな風に生きていたいとも思ったが、季節が冬になる頃、泰河はついに家に帰る決心をした。お前たちも一緒に来ないか、と泰河は申し出た。
ヒラの記憶はまだ戻らないが、思い出す手がかりは掴めるかもしれない。しかし、いくら説得してもヒラは島を離れようとはしなかった。島の暮らしがすっかり気に入ったらしい。記憶が戻った時のためにと、泰河は両親から預かっていて手つかずだった緊急用の金を無理矢理渡した。
「まあ、ヒラは多分大丈夫だろう。オレは一緒に行ってみようかな」
先生が承諾する可能性はほとんどないだろうと考えていたので、泰河は驚いた。
「都会の暮らしを経験してみるのもいいかもしれない。今ヒラに渡した金の額といい、お前はきっと金持ちなんだろうしな。色々教えてやるから、代わりに贅沢な暮らしとやらを味あわせろ」
「今の俺んちは全然都会じゃないけどな。確かに、有難いことに金には全く不自由していない。たまには東京でも連れてってやるよ」
別れの日、船の前でヒラが大泣きするので泰河もつられて泣いてしまった。事情を知っている先生は、こんなことって本当にあるんだな、と他人事のようにほくそ笑んだ。
「うるせえ、感動の場面で水を差すようなことを言うなよ。大体なあ、お前もうちょっとうまくやれなかったのかよ。ほとんど記憶消えてるじゃねえか。思い出したことと言えば、訳の分からん外国語だけだぞ」
ヒラは、もともと語学に堪能であったらしく、突然ドイツ語を喋りだしていた。だが精神年齢は子供のままだ。
「泰河…… 先生…… マジで今までありがとう。いつでも遊びに来てくれよな。アウフヴィーダーゼン!」
「ア……あうふいーせん! 俺たちはお前のこと絶対忘れないから、お前ももう何も忘れんなよ」
「まったく、よく言うよ」
うるせえ、と先生の頭をはたこうとしたが、先生の目が少し潤んでいることに気付いてやめた。
遠く離れていく島を見ながら、船の上で先生は改まった様子で泰河に話かけた。
「実はずっと、沖縄からいつか出てみようと思ってたんだ。礼を言うよ」
先生がどこで生まれこれまでどう暮らしてきたのか、過去のことを泰河はこれまで何も詮索しなかった。
「一つだけ言っておくけど、もしオレが危険に巻き込まれても、お前は必要以上に関わるなよ」
「ああ、そうするよ。お互いやるべきことをやったら、あとは自分の心配だけしろ、ってことだよな。あとはどれだけ、相手のことを信じられるかだ」
「なんだ、お前ちょっと大人になったんじゃないか? 相変わらず、鳥肌が立つくらい青臭いけど」
船の通った後に、白い波がたって軌跡を残していく。泰河は先生の頭を全力ではたこうとしてかわされ、あやうく海に落ちそうになった。
9
お待たせしました。福岡空港行き、一五七便は定刻通りの出発になります。一五七便の搭乗をこれより開始いたします。ご搭乗のお客様は六番ゲートまでお越しください。
ガラス窓の外で、飛行機の大きな影が行ったり来たりしている。泰河と同じようにその時を待っていた人々が、列をなしてゲートに吸い込まれていく。
泰河は、静かにその時を待っていた。まるで体が椅子にくっついてしまったみたいに、じっと座って待っていた。阿理沙と先生のことは、考えなくても勝手に頭の中でぐるぐると渦巻く。少し前なら、慌てふためいてこんなに落ち着いていられる自分ではなかったはずだ。
自分を狙っている奴が、すぐそこで待っている。そんな経験をしたことは、泰河にはあまりない。自分の足で、これからそこへ行こうとしているのだ。何が起こるか分からない。恐ろしい。今にも体が震えだしそうな瞬間は、幾度となく訪れていた。震えを押しとどめているのは、先生が別れ際に放った、心配は無用だ、という言葉。そしてそれを信じようとする自らの意志だった。立ち上がった時、泰河は二本の足がしっかりと床を押しているのを感じた。歩いているという実感があった。俺は俺の行きたい場所へ、これから行くのだと思った。
搭乗ゲートを抜け、長い道を歩くと分岐点に差し掛かる。一五七便へ向かうのとは逆の方向の道に、そいつはいた。
泰河は、我が目を疑った。身に着けているのはデザインが奇抜すぎて、服というより衣装というべきかもしれない。顔には美術の教科書か何かで見た、ヴェネツィアの伝統工芸品みたいな白塗りの素っ頓狂なお面。加えて独特な形状の帽子と靴を身につけた、サーカスのピエロみたいな奴がそこに立っていた。
通り過ぎる人々は、皆驚いたことだろう。だが一部の隙もないその見事な立ち姿に、そういう職業の者なのだと信じて疑わなかったに違いない。前もって聞いておいて良かったぜ、と泰河は思った。
「有馬泰河くん、今晩は」
そいつは、仮面を着けたまま仰々しい礼をしてみせた。男の声のようだが、ボイスチェンジャーでも使っているのか、機械的な不気味な声になっている。
泰河はむっつりした表情のまま、じっと見据えている。仮面が奥の方へついて来い、という仕草をして、泰河は後ろから付いていった。やがて行き止まりになる。
「折角驚かせようと思ったのに、どうやって私たちのことが分かったのかな? 奮っておめかしをしてきたというのに」
「一体何なんだ、お前は」
「私は、道化と呼ばれている。今夜の役回りには特にぴったりさ」
「へえ、笑わせてくれるじゃないか。俺は飛行機のチケットを買ったつもりだったが、間違えてサーカスか何かのチケットを買っちまったのかな」
道化はかん高い声で笑った。泰河も、口の端を上げてにやり、と微笑む。
「いいや、これはまだほんのご挨拶さ。今夜は、まさしく君にチケットを持ってきたんだよ。受け取ってくれるかな? すんなり受け取ってくれると、私は嬉しいのだが」
封筒を取り出して、泰河の方に差し出す。泰河は距離を置いたままで受け取ろうとはしない。
「どうしたんだい? 怖いのか? くれぐれも失礼のないようにと蝋で封までして持ってきたんだ。せめて中身を見てくれるだけでもいいじゃないか」
「知ったことか。郵便もインターネットもあるこの時代に、わざわざ押しかけてくるという方が無粋ってもんだぜ。何か用事があるなら、お前がその妙ちくりんな声で言いやがれ」
「おお、怖い怖い」
道化は両手を上げて肩をすくめてみせ、指をぱちんと鳴らした。
「だけど泰河君は私たちが見込んだ通りの、立派な紳士のようだ。そんなことを言いながら、ちゃんと受け取ってくれている」
何を言ってるんだ? お前、と言いそうになって、泰河の背筋に鳥肌が立った。自分も道化も、確かに一歩も動いていない。今も二人の間には、数歩分の距離があった。封筒を受け取るためには、どちらかが歩いていかねばならない。
封筒は、すでに泰河の手の中にあった。何をされたのか、全然分からなかった。
「どうやったんだ、これは。お前はやはり、クロックワークか」
泰河の声は、上ずってしまっていた。
「おっと、そんな軽はずみな言葉使いをしてはいけないよ。壁は耳を持っている、と昔から言われているからね。どうだい、今宵は月のいい晩だ。風もある。二人で静かなところで話をしないか。案内するから、こちらへ来てくれたまえ」
「ふざけるな、手短に用件を言いやがれ。誰がお前なんかに近づくかよ。おい、お前も動くんじゃないぞ」
道化の動きをわずかでも見逃すまいと、泰河は神経を尖らせた。妙な動きを見せたら、"加速”の特徴を使ってぶん殴ってやる。
「では、壁に聞かれても支障のない範囲で話すとしよう。少々込み入っていて、手短に話せるかどうか自信はないがね」
おどけるどころか、優雅で流暢な様子で道化は話し出した。
「私たちは、泰河くんやその周りの人々に危害を加えたくはない。それどころかむしろ、志を共にする仲間になれないか、と思っているんだ。ただ、君を取り巻く状況は、君が思っているよりも複雑なことになっていてね。私たちの中でも、意見が分かれているんだ。あまり時間もないので、結果的に少々スマートではない招待の仕方になったことは詫びよう。ただ、私はできれば穏便に済ませたいと思っているんだ。どうかね、興味は湧いたかい?」
「全然湧かねえよ。お前たちは、一体何なんだ」
「パンとサーカスの、サーカスの方さ。持ちあわせている特別な特徴を、平和的に、有効に使いたいと考えている。これ以上はこんな場所では話せないな。どうだ、今宵は満月。生憎十分なもてなしは出来ないが、眺めのいい場所を見つけてある。ご一緒できないかね。面倒はかけない。あと五、いや四歩くらいこちらに近づいてくれるだけでいい」
「ハッ、まったく話にならないな。もっと華があって面白い人物は他にもたくさんいる。悪いが、他を当たってくれ」
「そうか、ではこちらから行こう」
道化がぱちん、と指を鳴らす。来るか、と泰河が身構えた刹那、道化はすでに泰河の背後に移動していた。
やはり何をしているか、分からない。泰河の横や頭上を通る気配もなかった。とにかくこんな妙な奴はぶん殴るしかないと、振り向きざまにパンチを繰り出そうとした。道化が再び指を鳴らした。
次の瞬間、泰河は建物の外にいた。
遠くの方に空港らしき建物と、飛行機らしい影が見える。周りには、誰もいない。どうやらここは滑走路の端っこのようだ。フェンスを越えたすぐ横は海になっていて、夜空に浮かんでいる大きな満月が海面に映り込んでいた。
「どうだね、いい眺めだろう。気に入ってくれたかい」
音もなく、道化は暗闇の中から姿を現した。
「礼を失してしまわぬよう、自己紹介代わりにきちんと説明しよう。私は"瞬間移動”という特徴を持っている。指を弾くだけで、私の近くにあるものや私自身をどこでも好きな場所に移動させることができるんだ。流石に福岡の山の中まで連れて行ってあげることはできないがね」
泰河は、息を呑んだ。おかげでさっきの謎は解けたが、自分の特徴をぺらぺら喋るとは、一体どういうつもりだ。自分の住所なども、すでに調べがついているのか。
「私は君と対等に話がしたいんだよ。私たちは、君のことを知ってしまっている。どんな特徴を持っているかということも、家族のこともね。だからあくまで、フェアでありたい。この特徴は私の先祖代々受け継がれてきたものさ。高祖父はせいぜい同じ部屋の端から端までしか移動させることができなかった。だが遺伝する度、段々距離が長くなっていって障害物もすり抜けられるようになり、今では数百メートル先まで動かすことができる。祖父の代からは、こんな芸当も出来るようになった。よく使い込んだ道具なら、他の場所から持ってくることも出来るのさ。こんなふうにね」
道化が指を連続して鳴らすと、空中からテニスソフトボールくらいの赤い球が複数落ちてきた。道化は器用にそれをキャッチして、お手玉をしてみせる。
「父の代になると、持って行くより持って来る方が長い距離を動かすことができるようになった。それでも父は、あまり重いものは持ってこれなかった。私の場合は、こうさ」
ボールを投げる合間に素早く一つ指を鳴らす。ずしん、と地面が揺れるほどの衝撃と共に膝の高さくらいはあろうかという大きな鉄球が現れた。道化は、お手玉をしたままそれに飛び乗る。球はゆらゆらと揺れるが、道化は絶妙なバランスでその上に立っている。
「なかなか愉快なファミリーだな、お前んとこは。……おい、待てよ。さっき高祖父って言ったか?」
「そう。"瞬間移動”の特徴は、私で五世代目だ」
満月を背にしてその光を浴びながら喋っている道化は、全てのボールを強く上に放り上げたかと思うと、鉄球の上でくるりと体を一回転させてから見事にキャッチした。地面に降り、拍手を求めるように両手を広げるポーズを取る。
泰河の頭の中は、それどころではなかった。数秒の沈黙のあと、不服そうに道化は言う。
「このボールも、実は鉄で出来ているんだよ。拍手くらいしてくれたっていいじゃないか、折角うまくいったのだから。それにしても、玄孫のクロックワークを見るのは初めてか? あまり驚かないでくれたまえ。まさか、存在しないと思っていた、なんてことはないだろうな。案外、いるところにはいるものなのだ」
そんなのが同じ時代に生きているなんて、泰河は信じていなかった。普通の人間にとってヒマラヤの雪男がそうであるように、泰河にとって同じ特徴を五代以上にわたって引き継いだクロックワークは想像や噂話の中にだけ存在する生き物であったのだ。
「君の"死体を動かす”特徴はひいおじいさんから受け継いだそうだな。戦前、有力な地主の跡取りだった有馬優一郎。君のお父様の自伝に登場しているね。なかなか骨のある大人物だ」
江戸時代から続く大地主だった有馬家は、跡取りに恵まれなかったため明治の終わり頃になって隣県の医者の家系から養子を迎えた。一族の男の中から誰を選ぶか、決め手になったのは幼い頃から人並み外れて丈夫な体だったという。
その養子の息子が、有馬優一郎だ。短気で豪快だが地主には向かない優しすぎる性格で、土地という土地を戦後の混乱で困窮する人々にタダ同然で分け与え、後世に恩着せがましく名を残すことは好まず、若くして病で壮絶な一生を終えた。最初に死体を動かしたのは彼であるらしい。
「彼にとって泰河くんはグレート・グランド・チャイルド、四世代目の子孫つまり曾孫にあたる。我らサーカスの入団資格は、曾孫以降のクロックワークにのみ与えられるのだよ」
「何だと……まさか、お前たちは」
泰河はそれ以上言葉を続けることができなかった。飲み込まれてしまった言葉は、諸刃の刃だ。道化の口調が、やや感情的になる。
「私たちがどうしたというのだね、有馬泰河くん。この広い世界で、父と母が奇跡的に出会い、愛し合ったが故に生まれてきた私たちが一体どうしたというのだ」
風で大きな雲が流れてきて満月を覆い隠し、滑走路は闇に包まれた。夜目が利く泰河にはそれでも道化が見えているが、色がなくなってしまう。
「どれくらい、いるんだ」
ぽつりと、泰河が呟くようにして聞いた。
「うむ?」
「お前たちサーカスの団員は、どれくらいいるんだ」
「十人。それと団長だ。団長が何世代目かは、誰も知らない。しかし恐ろしく長生きだ。団員の中には小さな子供もいるし年齢は様々だ。曾孫の子は玄孫。さらに来孫、昆孫、と続く。それぞれ何名かいる。八世代目の仍孫が一名。九世代目の雲孫はまだいない」
「……よくもまあ、そんなに集められるもんだ。全員家族ってことか?」
「同じ特徴が必ずしも子に受け継がれていくとは限らない。現に私にも兄弟がいるが、"瞬間移動”の特徴を備えているのは私一人だけだ。我々は、常に仲間を探している。日本中から有能な人材を募っているというわけさ」
「へえ。ただの客に対して、随分親切に教えてくれるんだな」
「もちろん、ここまで知ってしまったからには否応なく丸盆の上に上がってもらうつもりさ。今の私の考えを率直に言おう。私は、力づくでも君をサーカスに迎え入れたいと思っている。その首根っこを捕まえて、檻に入れて鍵をかけてしまうことになろうとも、君を私たちの小屋へ連れて行く。どうか理解してくれないか、これが君を守るための唯一の手段なのだ」
「ふん、誰がそんな得体の知れない集団に入るかよ。そんなに仲間を集めて、お前たちは何がしたいんだ」
彼方で一機の飛行機が着陸しようとしていた。他にも、空には数機の姿が見えている。海を挟んで工業地帯の灯りが見える。どの工場も、ライトアップされた観光地のお城のように赤々と光を発している。実際には、休む暇もなく働いているに過ぎない。雲の流れが速度を増し、不規則な影が泰河と道化の上を通り過ぎていく。
「我々が、生態系のバランスを崩そうとしている危険な集団だとでも思うかね? 確かに、ある意味ではそうだ」
飛行機は高度を下げながら、ゆっくりと地面に吸い付くように進んでいく。どこからが飛んでいて、どこからが走っているのか分からないスムーズな着陸だ。そうして夜空から一つの飛行機が姿を消したかと思えば、また別の機体が滑走路に躍り出ていく。
「五世代目以降のクロックワークには、天変地異に匹敵する現象を起こしうる者が現れるという。それは厄災と希望をもたらす者、と古くから呼ばれている。九世代目になると、ほぼ確実だともね。我々は、その禁じられた力をクロックワークと旧人類が共存するために用いようとしているのだ。しかし世の中には、本当に多種多様な考え方があるものだ。SACのようにクロックワークを根絶やしにしようとする旧人類もいれば、旧人類を地球上から退場させ、まだ見ぬ理想郷の実現を目指すクロックワークの組織もある。我々は大小無数に存在するそのような組織を、総じてマンイーターと呼んでいる」
道化は、指を二本立ててみせた。
「サーカスの目的は二つ。一つは、旧人類我々が共存できる世界をつくるために、厄災と希望をもたらすクロックワークを見つけ、あるいは産み育てること。もう一つは、そんなクロックワークが現れても手遅れにならないように、あらゆる手段を用いてマンイーターの正体を突き止め、解体すること。マンイーターも我々と同じように、代々同じ特徴を受け継いだ者を組織しているのだ。理由は全く違うがね」
「どうだか。あんた、ビジュアル的に正義の味方って感じじゃないぜ。悪いけど素直に信じることはできないな。俺に一体何をさせようってんだ」
道化は、泰河に背を向けて月を仰いだ。
「我々は都内で近年活発に活動しているマンイーターを調査しているうちに、NPO法人むさしの子育てネット、つまり有馬カヤが主催する団体にたどり着いた」
泰河は、不意打ちを食らったようにうろたえた。
「……おい、どんな悪趣味な冗談だ、それは」
確かにカヤは、表向きはただの育児サークルとして、クロックワークの子供を持つ親同士のネットワークを立ち上げている。
母は気まぐれで奔放で、行動力がある。一旦やるといったら他人の意見は聞かないし、考えたことを瞬時に行動に移し終える。泰河が中学生になった途端早々に育児を切り上げたかと思えば、東京でそんなことを始めた母が何を考えているかは、よく分からなかった。
サークルの活動内容は、普通の人間がやるのとさして変わりない、子育てに関する技術的あるいは精神的な助け合いだと聞いていた。他にはクロックワーク狩りなど、危機管理の情報をシェアする。クロックワークの特徴を使って何か大それたことを計画するなど、到底ありえないことのように思われた。しかし道化たちは、泰河の母たちを危険きわまりない集団だと捉えているようだ。
「詫びねばならないが、君には以前から監視がついていたのさ。そんな矢先、君の"死体を動かす”特徴を目の当たりにした。見ず知らずの人間を助けようとする、勇敢な行動もね。私は君を敵ではなく仲間にしようと思った。だがその意見に賛同しない団員も多い。組織というのは概して一枚岩ではないからね。だから私は、こんなふうにして君の前に姿を現さざるを得なかった。少なからず心が痛むが、人質を取るという手段をもってね」
道化は携帯を取り出し、どこかに電話をかけてぱちん、と指を鳴らした。話が唐突で、考えがまとまらない泰河の目の前に携帯が移動する。
地面に落ちる前にキャッチすると、すでにテレビ電話が繋がっており阿理沙の顔が映し出されていた。待っている間ずっと思い浮かべていた顔だった。あまりいい表情ではないが、拘束されている様子はない。どこか飲食店のような場所にいるようだった。
「阿理沙ねえちゃん、無事か?」
ほとんど叫ぶようにして聞いた。泰河の目には恐怖の色が浮かんでいる。母のみならず、阿理沙や自分までが捉えどころのない大きな何者かに、絡めとられようとしている。泰河はどうすればいいか、分からなくなった。
阿理沙は画面の向こうで、困った表情になっている。すると先生が横から身を乗り出してきて、泰河にきっぱりと言った。
「大丈夫だ。オレがしっかり、守っている。お前は予定通りそこにいるやつをぶっ倒せ」
それを聞いて、泰河の顔色が変わった。怯えるような表情はすっかり消え、不敵な笑みを浮かべて了解、とだけ言った。
泰河は携帯を放り投げて持ち主に返す。こんな展開は想定していなかったらしく、道化はなかなか言葉が出てこないでいる。表情は仮面で読み取れないが、きっと苦虫を噛み潰すような顔をしているのだろう。そして通話を音声のみに切り替えて、電話口に向かって静かに言った。
「手品師と兎は、どうした」
「知るかよ、馬鹿。オレに言えるのは、あとは自分の心配だけしろ、ってことだ」
丁度二人の頭上に差し掛かった飛行機のせいで、先生の声が泰河に聞こえることはなかった。だが、泰河はすでに理解していた。自分が何を感じ、何をすべきかということを。
道化は携帯をしまい、感心した様子で言った。
「ふむ。君のことを少し見くびっていたようだ。いい友人を持っているじゃないか。"信頼できる仲間をつくる”ということも立派な特徴だ」
泰河は何も答えず、いかにも不愉快そうな、しかし迷いのない目つきで道化を睨んでいた。
「そろそろ返事を聞かせてもらおうか。招待を受けるんだ、泰河くん。そうすれば君の家族を悪いようにはしない」
「やかましい。俺は今、率直に言ってお前を思いっきりぶん殴りたい気分だぜ」
「……成程、血は争えないというわけか。ひいおじいさんにそっくりだな、君は」
道化の足元で、鉄球がゆっくりと回転を始めていた。
10
「さて、こいつをどうしてくれよう」
まるで独り言のように先生は言った。目の前では手品師がうなだれて座っている。
「お前は、見事に自分の役目を果たせなかったわけだな。このあとどうなる? まさか失敗したからと言って、始末されたりするんじゃないだろうな」
手品師は、首を横に振ってみせた。
「じゃあどうなるんだ? さっきまでしてたように、お姉ちゃんの携帯にメッセージを送って質問に答えろ。念のため言っておくが、妙なことはするなよ」
首を縦に振ってうなずく。先生は加奈子の方に携帯を差し出した。隣で阿理沙が、呆然とした様子でじっと手品師を見つめている。
「別にどうもならない。人質を取ろうとしたのはあくまで保険のようなものだし、そもそも私たち三人の本意ではなかった」
手品師は、携帯をテーブルに置いたまま片手の指先で素早く文字を入力し、目の前の阿理沙の携帯に送信した。
「どういうことだ? お前たちは自分たちの組織に泰河を迎え入れる、と言っていたな。サーカスとか何とか。一体どんな組織なんだ?」
やや考えているような間があってから、手品師は指を動かした。
「それをあなたに言っていいかどうかは、私には分からない。ラビットはどうなった?」
「おい、質問しているのはオレの方だぜ。今は自分が人質だってことを忘れるな」
先生は、手品師を拘束している力を強めたようだ。俯いている加奈子の表情が、少し苦しげになる。
「お願い、やめて」
阿理沙が、小さな声でつぶやく。
「加奈子ちゃんをいじめないで」
先生は、阿理沙の顔を見つめる。ショックからまだ立ち直ってはいない様子だが、毅然とした表情で先生を見つめ返す。
「ちぇっ。そんなつもりじゃなかったんだ。ごめんよ」
いかにもばつが悪そうに、先生は言った。まるで叱られた子供のようだ。
「おい、何か飲みたいものはあるか。オレが奢ってやる。こう見えても、小遣いはたんまり持ってるんだ」
「温かいココア」
加奈子が携帯を通して答える。先生は、店員を呼んでココアとコーヒー、それにオレンジジュースを注文した。店内には、Jポップをボサノバ調にアレンジした曲がかかっている。客は女同士とカップルばかりで、何度か足を運んでいる者よりは、評判を聞きつけて初めて来た者が多いようだった。皆一様に気分が浮わついている。
「ラビットは、この店の場所だけ教えてどこかへ消えたよ。まったく、逃げ足の速い奴だ」
やってきたジュースを一息で半分以上飲み干し、先生が仲間の無事を伝えてやると加奈子の顔に安堵の表情が浮かんだ。温かいココアを頼んだくせに猫舌なのか、加奈子はなかなか口がつけられないでいる。
先生は、瀕死のラビットを抱えて線路内の安全なスペースまで移動した。傷の回復を待ち情報を聞き出そうとすると、ラビットは素直に阿理沙の居場所を教えたが、これで借りは返したからね、と言って大きく跳躍し、あっという間に地下の闇に消えて行ってしまった。
「質問を続けるぞ。泰河に何をするつもりだ? 今、空港では何が起きている」
手品師は、ココアを冷まそうとするのを中断して携帯を操作する。先生は手品師が喋れない程度の拘束はあくまで継続しているようだった。
「正確には分からない。私たちは、彼に危害を加えることが目的ではない。むしろ、危険を取り除きたいと考えている」
「つまり、泰河には別の危険が迫っているということか? それは何だ」
「それも私が言えることではない。みんなに迷惑がかかるから」
「お前はまだ誰も傷つけてはいない。だがオレはお前たちを脅威だと認識しているし、脅威から自分や仲間を守らないといけないんだ。そのためなら、お前を傷つけない保証はないぜ」
「構わない。責任は取る」
「いいだろう、覚悟はできているというわけだ。お前もなかなか見込みのある奴だ。とにかく話せることは可能な限り喋ってもらおうか」
「出来るだけ話す。それから、一つだけ言わせてほしい。阿理沙さんには本当にすまないと思っている。あなたにも」
「そう思っているならなるべく情報を出せ。オレが興味があるのは、オレと仲間の安全だ」
苦いコーヒーを胃に流し込んだ阿理沙は、次第に自分の身に起きた出来事の整理がついてきた。目の前にいる肌が綺麗な一八歳のゴスロリ女は普通の人間ではなく、泰河を仲間に引き入れる交渉材料として私を知らず知らずのうちに拘束していた。
今度は、先生が私を守ってくれた。だが加奈子は、心の底から私を憎んでいたり、傷つけようとしていたのではないようだった。私が存在しているために、泰河や先生が、そして目の前の女の子までが迷惑しているのではないだろうか。阿理沙はそんな風に考え、いつものように罪悪感を感じた。
阿理沙は、自分の行動はすべて間違っているのではないかという確信に近い疑念があらゆる思考の前提になってしまっていた。それはおそらくアイドルを辞める前後、自分でも知らないうちに始まったことだが、元をたどれば母の姉夫婦に引き取られてからずっと、その疑念は心の深い場所に沈殿していた。
気丈に姉を演じようとしながら姉にはなりきれなかった。どこまでが生来の性質で、どこまでが外的な要因によるものか分からないが、一つだけ言えるのは彼女がそういう女だということだ。
うまくいかない芸能活動、ひび割れだらけの人間関係。その渦中にあって阿理沙は常に誰よりも早く、容疑者の中から真犯人を見つけることができた。動機も証拠も、自分が自分であるだけで十分だと阿理沙には常に思えた。だが、今夜の事件は常日頃と少しばかり異なる様相を呈していた。
容疑者は大抵、自分のことしか考えていない奴ばかりだった。自分の利益のため、保身や世間体のため、こまかなプライドのためなら進んで人の皮を被った豚となり美辞麗句並べ立て、白々しい顔で責任を転嫁し、自分を正当化し、問題をすり替える。そしてそれは、何ら特別なことではなく、人間なら誰しも呼吸をするように自然に行う行為なのだと阿理沙は思っていた。
だが、どう考えてみても目の前の二人は、自分の利益や保身を最優先して行動しているようには見えなかった。
先生が困った声をあげて阿理沙の方を見る。どうやら、加奈子がトイレに行きたいと言い出したようだ。
「仕方ない、トイレのドアの前までオレが一緒に行く。それから一旦拘束を解いてやる。終わったらまたすぐに口をふさぐから、ゆっくりドアを開けて出てくるんだ。いいな」
手品師は、少し恥ずかしそうに首を縦に振る。それから大きなカバンを持って立ち上がる。
「携帯は、そのまま置いておけ。お姉ちゃんは念のため戻ってくるまで耳を塞いでおいて」
それくらい一人で行かせてやればいいじゃない、と言いたいところだが、加奈子の肉声は聞いたものの思考を操ることができる。二人は店の端にあるトイレまで連れ立って歩いていった。
言われたとおり耳を塞いだ阿理沙の視界には、音を失った世界が広がる。聴覚を遮断してみると、目は同じものを見ていても全体の印象は大きく異なる。阿理沙は、皆が楽しそうな顔をして砂糖の塊を頬張っている様子を幾分冷めた心境で眺めた。
阿理沙は職業上、甘いものはあまり頻繁に口にしないようにしている。皿の上に載っているものは、見るものをいい気分にさせ、安心させるような外見をしているが、実際には肉体を錆びつかせる毒だ。いったいこの中の何人が、それに気付いているというのか。仕事や学校がきついとか、誰それが気に食わないだとか、やれ政治家が悪いだのやれ税金が高いだの言いながら、明日の命の心配など露ほども感じることなく、のうのうと生きている。すぐ隣に、特別な人間がいることなど全然気付きもしないで。
これまで阿理沙は、自分を含めたあらゆる人間を不愉快に感じることはあっても、そんなふうに考えたことなどなかった。人間たちの世界の安全や秩序が、同じ人間が決めたルールなどではなく、もっと根本的な何かによって守られていると感じたこともなかった。
さっきまで阿理沙は、加奈子と分け合って一つのケーキを食べ、お喋りして、トランプに興じていた。操られていたという自覚はないし、もしそうであったとしても、加奈子に対して抱いていた感情は嘘ではない。
私たちはきっといい友達になれるだろう。心からそう思う。だが一方では、加奈子や先生たちは自分たちと同じ世界に生きているようで、実はまったく異なる世界に生きているのではないか。友達になるどころか、意思の疎通すらまともに図れないのではないのか。そういうふうにも思えてくる。
阿理沙は、たとえ一瞬でも泰河や先生のことを化物のように感じたことを深く後悔していた。だが、やはり彼らと私たちは、異なる生物なのではないかという思いが鎌首をもたげる。加奈子の行動次第では、先生は残酷な行動に出るだろう。普通の人間には真似出来ないような特徴を行使して、私には分からないような方法で、想像もつかないことをするに違いない。それはきっと加奈子も同じなのだ。今の均衡状態がもし破られる時が来るとすれば、何が起きるのか。阿理沙は泰河と再会した渋谷での出来事を思い起こさずにはいられなかった。
決して華麗でも美しくもない。綿密に準備と計画がなされたショーとは程遠い、血腥い暴力的な世界。反知性的な、反道徳的な、何もかもめちゃくちゃな世界。彼らは、そんな場所からひょっこりと阿理沙の方に顔をのぞかせているのだ。
そうだ。あの夜だって、泰河はただの人間を沢山殺していた。こんなのは慣れっこだといわんばかりに、片っ端から殺していた。それはもちろん無差別テロの犯人に対してのことで非常事態とは言えるけども、あんなに平然とした様子で人を殺すということは果たして誰にでも出来るものだろうか。
どいつもこいつも私の前では理性的に振る舞っているが、本性は人間臭いつまらない嘘や冗談も言えないような、冷血な奴らなのかもしれない。見ず知らずの他人が殺されようとしていてそうなのだから、もし自分が狙われたとすればもっと凄まじいことになるのかもしれない。だいいち、私を記憶を消したのだって、何の相談もせず勝手にやったのだ。実際には、他に自分たちが見られて困るような場面も消されているとしたら、どうだろう。
そこまで考えて、阿理沙は自分の想像が、いくら頭の中だけのこととはいえ、越えてはならない一線を越えたような気がして怖くなった。先生と泰河は、自分のためを思ってやってくれたのだった。その後で残りの記憶を消すか消さないかで迷った時も、破滅願望がピークに達した私のことを、リスクを負って引き受けてくれた。そんな人たちを疑うなんて、とんでもないことだ。
阿理沙は、そんな疑いを持ってしまった自分を、これまでより一層激しく嫌悪した。そして誰か自分を救ってくれたらいいのに、と願った。どうして、私だけがこんな目に遭わなくてはいけないのか。一体誰のせいで。
他力本願かもしれないが、うっかり連れて来られた世界から自分の力で脱出できるような気はしなかった。やはりあのまま記憶を消されていた方が良かったのかもしれない。誰か私をここから出してくれ。誰か私を、助けてくれ。
加奈子がトイレのドアを開けて出てくるのが見えた。二人は阿理沙のいる席の方に戻ってくる。不意に、音だけではなく光までもが失われてしまった。
店全体が停電してしまったようだ。客たちの慌てる様子が伝わってくる。阿理沙は思わず耳から手を放してしまう。直後、ダメだ、という先生の声と共に何かが阿理沙の耳をふさぐ。
一時店内は騒然とした雰囲気に包まれたようだが、やがて客たちは自分の携帯で手元を照らし始め、各テーブルに一つまた一つと灯りがともされていった。店員はきっと大慌てに違いないが、客の中にさしたる混乱はない。
阿理沙もほっと胸を撫で下ろすが、耳を抑えている何かが外されるとともに、切羽詰まった先生の声が聞こえた。
「お姉ちゃん、こっちに来て。オレたちを照らしてくれ、早く」
携帯を懐中電灯のように操作して声の方へ向かうと、先生の横には見知らぬ男性が立っていた。先生に口などを拘束されているのか、まるで訳が分からないというように立ち往生している。
阿理沙が向けた灯りのもとで、改めて先生はその男を頭のてっぺんから足の先まで眺める。この店にはあまり似つかわしくない、筋肉質な中年の男だ。手品師とは体格も身長もおよそ似つかない。口をもごもご動かしているが、言葉を発することはできない。
「クソッ、どうなっているんだ」
苦々しい顔をして、先生が拘束を解く。男は暗闇の中で二人と自分の周りを不思議そうに眺めていたが、やがて各テーブルの灯りを頼りに、どこかへ歩いて行った。
間もなく停電は復旧し、店内は元通りになった。先生と阿理沙は店の中央で辺りを見回すが、手品師の姿はない。
大変失礼しました、もう大丈夫ですと店員が大きな声でアナウンスする。店員たちは、トイレの方に集まっている。先生がそちらに向かっていって状況を確認した。
どうやら停電の原因は、トイレ内のコンセントがショートしたためのようだ。ほぼ間違いなく、手品師の仕業だった。
席に戻ると、手品師の携帯が消えており、代わりに千円札が一枚置かれていた。折りたたまれたメモ用紙が添えられている。先生が息をのみ、席について紙を開く。
「ケーキ美味しかったですね。ココアはご馳走様です。色々ご迷惑をおかけしました」
そう書いてあった。普段から端正な文字を書くのだろう。急いで書いたような走り書きだが、漢字の形は崩れていない。
「まんまとやられたな。だがオレは一度も拘束を解かなかった。一体どうやったんだ、あの男と瞬時に入れ替わりでもしたのか?」
再び先生が店内を見回す。途中で何かおかしいぞ、という表情になって、立ち上がり何度も念入りに見ていた。そして、やっと合点が行ったとでもいうように、深く座り直して大きなため息をついた。
「さっきの男が、いない。あれから会計を済ませた客はまだいないのに」
「……まさか、食い逃げってこと」
「違うよ。奴は自分の払う分はちゃんと置いていった」
先生は、目の前の千円札を両手で持ち上げる。
「さっきの男が、手品師本人だったんだ。巧みに"変装”できる特徴の持ち主なんだろう。顔や体型まで変えられる奴がいてもおかしくない。服は、オレがお姉ちゃんに気を取られている隙に着替えた。手品師の名にふさわしい早業でね。そして停電から復旧する前に、何食わぬ顔で店を出て行ったんだ」
阿理沙は、加奈子のカバンが不自然に大きかったことを思い出した。そして、暗闇の中で早着替えをする加奈子のことを想像した。
瞬時に衣装が変わる早着替えは、阿理沙もアイドル時代に経験がある。うまく出来れば録画した映像をコマ送りしたとしても、何がどうなっているか分からないほど見事で、華やかで美しいものだ。暴力なんて少しも使わないでうまくこの場を逃れるなんて、この上ない鮮やかな手口ではないか。
それから、堰を切ったように勢いよく笑い始めた。これまでのもやもやを全て吐き出すかのような、腹がよじれるくらいの大笑いだ。
「な、なんだよ。何がそんなに面白いんだ」
「ああもう……。加奈子ちゃんってば、嘘つきなんだから……。マジックが出来ないなんて、全然そんなことないじゃない。あはは」
奇妙なものを見るような目つきで、先生は阿理沙を眺める。阿理沙はよほどおかしいのか、目には涙すら浮かべている。
「そんなつまらない嘘つくなんて……。冗談じゃない、ほんと馬鹿馬鹿しいったらないわ。騙される先生も、先生よ。そんな単純なトリック、仕掛ける方も仕掛けられた方も、両方大いに滑稽だわ。加奈子ちゃんの早変わり、さぞかし見事だったんでしょうね……」
笑いは、だんだん泣き笑いに変わっていく。阿理沙は先生の手を、そっと握りしめた。先生の手は、まだこんなに小さい。どうして私に何もできないなんて思ってしまったのか。先生の手は、私と同じように温かい。加奈子の手も、きっと同じだったのだろう。
「うーん、大人の女の考えていることは、やっぱりよく分からないや」
困ったようにそう呟いた声は思ったより大きかったらしい。周りの客が、目を丸くして先生と阿理沙を凝視する。
阿理沙がさめざめと泣きじゃくる横で、先生はぽりぽりと頭を掻いた。
11
体を捻って加速させ、寸前でかわしたと思ったが一瞬遅かったようだ。鉄球はかすっただけで、泰河の左足の骨を粉々に砕いている。
道化の足元の鉄球は、地面に触れている部分を支点にしてコマのように回転を始めた。泰河が拳を振り上げて向かって行った瞬間、道化はそれを蹴り、鉄球は回転の速度をさらに増しつつ勢いよく泰河の方へ向かってきた。
苦痛をこらえて踏ん張るが、道化の姿はすでにない。風を切る音が後頭部に迫っているのを感じた。右足で横に大きく飛ぶ。赤いテニスボール大の鉄球がアスファルトにめり込み、めり込んだままでまだ回転を続けていた。
どこかでぱちん、と指を鳴らすのが聞こえた。道化は泰河の左側に出現したかと思うと、」すぐさまパンチを繰り出してくる。その速度は普通の人間とさして変わらない。泰河は左腕を加速させ、手の平でそれを受け止める。
受け止めた瞬間、道化の拳がぎゅる、と力強く回転したように感じ、パンチよりもはるかに強い力で泰河の体はバランスを崩される。今度は手の平が支点となって、体全体が大きく宙に浮く。そのまま一周半ほど回転し、大の字になって地面に叩き付けられた。
またぱちん、という音。先程の巨大な鉄球が泰河の真上に現れ、重力に従って落ちてくる。
これはやべえ、と呟きつつ、頭の奥でキリキリという音がしているのを聞く。すでに左足の骨は固まっている。泰河は素早く身を起こし、鉄球をかわす。ずしん、と大きな音を建てて地面が揺れる。鉄球は数センチほど地面にめり込んでいた。冷や汗が吹き出る。立ち上がれずあのままだったら、両足の膝から下はぺしゃんこに潰れていただろう。
「何てことだ、これは驚いた! 私の耳にも届くぞ、その力強い音楽が」
赤いボールはまだ回転を続けている。アスファルトが溶ける匂いが、鼻につく。
「驚いたのはこっちだ! お前、まだ何か隠しているな」
指を鳴らすと、ボールは道化の頭上に瞬間移動し、道化はそれを受け取ってお手玉を始める。
手から離れて放物線を描くはずのボールが、不意に大きく軌道を変え泰河の方に向かってきた。一球目を避けても二発目、三発目と次々に襲ってくる。はじめは直線的な軌道を描いていたが、カーブ、フォークと変化球のような動きでそれらは飛んできた。
最後の四発目をかわしきれず右肩に食らってしまう。骨が砕ける音。泰河は空手の構えを取り道化の方に向き直るが、右手はだらんと垂れ下がってしまう。しかしまたキリキリ、という音がしたかと思うと、肩はすっかり治癒してしまい、何事もなかったかのように構えを取りなおす。
「ふむ。なんと格式高い、上品な響きだ。聞き惚れてしまうじゃないか」
ボールは再び移動し、道化の手元に集まって落ちていく。
「やかましい。やたらと物騒な特徴をまだ隠してやがるようだな。さっきのフェアでありたい、なんてのはどの口が言ったんだ。まさかその不気味な仮面が勝手に喋ったわけじゃあるまいな」
機械的に変換された声が、高らかに笑う。笑い声は辺りに反響して、さらに不気味な印象を帯びる。
「これは失礼した。別に隠していたわけじゃないさ。終わりまで話す前に、血の気の多い無礼な男が殴り掛かってきたのでつい言いそびれてしまった」
「へっ、よく言うぜ」
構えを取ってはいるが、骨折した箇所にはまだうまく力が入らない。右肩と、それにパンチを受け止めた左手もグシャグシャになってしまったようだ。傷が治っても、痛みが消えてなくなるわけではない。
「私は察しの通り、もう一つ特徴を持っている。遺伝ではなく独自に身についたものだ。触れたものを自在に"回転”させることができる。シュートもスライダーも思いのままだ。自分では持ち上げられないくらい重い物でもな」
道化がつま先でちょん、と巨大な鉄球に触れると、それは道化を中心にゆっくりと円を描きながら転がり始めた。
「まったくもって、愉快な血筋だ、お前らは」
たっぷり皮肉を込めて言い放つが、痛みに全身を支配されているようで、立っているだけで精一杯だ。
「愉快なのは、君だよ! その怪我は並のクロックワークなら、最低でも丸一日はベッドで横になっておくべきものだ。まるで古い立派な柱時計の歯車のような、ストラディバリウスの弦を締める時のような、歴史に裏打ちされた芳醇な音色……。君はネジを巻けるクロックワークなんだね? 玄孫の私なんかより、君の方がはるかに珍しいと言える。まさに機械仕掛けと呼ぶにふさわしい、誇り高い遺伝子だ。さすが泰河くん。私の目に、狂いはなかったぞ」
「何を言ってやがる。この音は、昔からむしゃくしゃしたときに勝手にしやがるんだ。てめえのような訳の分からん奴に絡まれて、思い通りにいかないときなんか特にな」
「これはいよいよ滑稽だ。指揮者自身、奏でている音楽の価値が分からんとは」
道化は片手で四つのボールを鷲掴みにして持ち、手の平を上にして胸の高さまで掲げてみせる。指を一本も動かさないのに、ボールはくるくると位置を変え、まるで四つで一匹の生き物のように手の中で蠢いている。
「ならば教えてやろう。音がしている最中、怪我がいつもより早く治ったり、体に力がみなぎったりするのを感じていただろう? ネジを巻くとはそういうことなのだ。君のひいおじいさんは早くに亡くなったようだが、おじいさんはどうだったのかな? 失礼は承知であえて聞こう。多くのクロックワークは、普通の人間に比べて寿命が短いんだ。我々の脳は、体のサイズに見合わない膨大なエネルギーを生産するからその影響だと考えられている。不完全なネジは、体のどの部分よりも先にガタが来てしまうんだよ。だが、自分の意思でネジを巻ける完全なクロックワークは別だ。傷を治したり特徴を行使するために大量のエネルギーを生み出しても劣化することはない。むしろ普通の人間より、ずっと元気に長生きできるのさ」
「どうだろうな。もう九十近いがおかげさまでまだピンピンしてるぜ。普通の人間であるばあちゃんも、同じだがな」
「それは大いに結構。お二人とも、どうか健やかに長生きされるといい」
「孫を今まさにぶち殺そうとしている奴が、しれっと言うんじゃねえよ」
「フン、君は簡単には死なんよ。そうと分かれば、首に縄を、いや鎖を巻き付けてでも連れて帰りたくなった」
指を鳴らすと、ボールを持っていない方の腕に奇妙な武器が現れた。じゃらじゃらした長い鎖の先に分銅が取り付けられている。
道化が鎖を軽く動かすと、先端がドリルのように回り始めた。分銅は鎖とは独立して回転できるようだ。
「おいおい、また随分といい趣味をお持ちのようじゃねえか」
あんなの食らったら、骨だけじゃきっと済まないぜ、と考えて泰河の顔は引きつっている。道化の仮面の下は、どうやら泰河とは逆の意味で引きつっているようだ。
「我々は、まさしく君のような人材を探し求めていたのだよ。厄災と希望をもたらすクロックワークは、その条件として完全なネジを持ち合わせてなければいけない。いくら同じ特徴が続けて遺伝しても、それだけではまだ駄目なのだ。完全なネジを持つクロックワークの子孫は、やはり完全なネジを持って生まれてくる。泰河くん、君の子供は我々に、いや人類すべてに恩恵をもたらしてくれるかもしれない。どうだ、気は変わったかね」
「……何だって? そんなのは初耳だ」
先生は、どうしてそんな大事なことを教えてくれなかったんだ。泰河は胸のうちで呟く。
島での生活を思い出す。ヒラが大いびきをかいて寝静まった後、長い夜の間に二人はいろんな話をした。話し始めるのは常に泰河の方からだ。泰河は自分の悩みを包み隠さず先生に伝えた。先生は多くは語らなかったが、真剣に最後まで話を聞いてくれ、泰河が知りたいこと、必要としていることを教えてくれた。
別に結婚したい相手がいるわけではない。子供が特別に好きというわけでもない。だが、あらゆる生物の存在意義というものは、突き詰めれば子孫を残すという一点に尽きるはずだ。
それなりの事情や信条に基づいて子供をつくらない者もいれば、体に障害があってつくることが出来ない者もいる。だが、生殖機能を持たない働きアリだって女王蟻の子孫を残すために生きていると言えるのだから、人類という群れの一員にさえ含まれていれば、何らかの形で種の保存に貢献していると言えるのだろう。
社会的な存在としてではなく一匹の生物として、自分はどんな群れに属しているのか知りたかった。その答えはきっと世界中どこを探しても用意されていない。泰河にはそんな気がしていた。それが疑いから確信に変わってしまえば、諦めもつく。諦めがつけば新しい一歩を踏み出すことができる。そのために泰河は、先生の教えを欲していたのだった。
あまり考えている暇はなかった。道化は鎖分銅をくるりと頭上で一回転させる。雲はかき消え、夜空には月だけでなく星が浮かんでいるのが見える。鎖が月光を反射して煌めき、ぢゃっ、という音をたてて襲いかかってくる。
反射神経は並の人間と変わらない。それでも直線的な動きの分銅をかわすのは泰河にとって造作もないことだ。厄介なのは、まるで泰河が動こうとする方向が予め分かっているみたいに、あらゆる方向から飛んでくる四つのボールだ。
泰河はポケットの小銭を親指で"加速”させて飛ばす。しかし、銃弾のような威力を持ったそれを命中させることは出来ない。立ち止まって狙いを定める暇もなければ、標的は移動を続けてもいる。移動に関しては、相手も相当に得意としている。
二人は、人間の基準で言えば致命傷にあたる攻撃を互いに繰り出しながら、高速移動と瞬間移動を繰り返す。泰河は距離を縮めることも、逆に離れることも出来ない。だが、泰河はあえて一定の距離を保ち続けていた。それだけでなく、場所もほとんど動かずにいた。
気づけば泰河の辺り一面、まるで爆撃にでも遭ったかのようにアスファルトが砕け散ってしまっている。
ボールや分銅で一度や二度砕かれただけでは、その破片はまだ結構大きく、手頃なサイズではない。一度に数十個を手で握れるような、小さな塊になるまで泰河は待っていたのだった。
赤いボールが道化の手に戻っていき、両手が塞がっている瞬間。それを見計らって足元の破片を掴み“加速”させて投げつける。道化は腕を十字に組み頭部を守りながら跳躍するが、破片はまるで散弾銃のようにその肉を抉った。
やったか、と思ったのも束の間。道化は指をぱちんと鳴らして泰河の背後に現れる。攻撃は最大の防御と言わんばかりに、泰河は素早く振り返って突きを放つ。
拳が到達するより早く、道化は再び指を鳴らした。
「うおおおお!」
泰河は、夜空に放り出されていた。眼下に広がるのは海。叫び声を上げながら、まっさかさまに落ちていく。
落ちた後は、無我夢中で水面に浮上した。だがそれは不用意と言えた。道化は泰河を落とそうとしたのではなく、浮かび上がらせようとしたのだった。
海に浮かぶ泰河の腕に、鎖が伸びてきて巻き付いた。
水際に立っている道化の利き手が、今にも千切れそうになって垂れ下がっている。もう一方の血だらけの腕で、鎖を操っていた。
泰河は鎖を掴み、力比べで相手を水中に引きずり込もうとする。だが、道化はあっけなく手を放した。
泰河は、目を疑った。鎖の反対側には先程の巨大な鉄球が取り付けられている。
「おい…… ちょっと待てよ、何する気だ……」
「先程は見事だったぞ。心配するな、魚の餌になる前にちゃんと引き上げてやる」
問答無用で道化が鉄球を蹴る。鉄球は勢いよく海の方へ飛んでいき、その重みで泰河は海の底へと沈んでいった。
波紋だけを残して、静寂が訪れる。
傷は浅くない。残った片腕も十分には動かせない。とっさに庇った頭部以外、体中ほぼすべて破片を食らっている。出来ることなら、もう戦いたくなかった。
しばらく夜空でも眺めてから、鉄球ごと泰河を回収するつもりだった。クロックワークは溺れたくらいでは簡単に死なない。酸素が供給されなくなってチアノーゼの症状が始まると、肉体はすべて仮死状態になってしまうのだ。一晩海の底に沈めておくなど大したことではない。それに完全なネジを持つクロックワークともなれば、仮死状態のまま十年以上は生き続けられるかもしれなかった。
道化は、意外だった。こんなに手こずるような相手だったとは。自分の知っている泰河は虚勢を張ったただの子供でしかなかった。
自分たちが追っていた集団が、有馬泰河の母親が主催するものだと判明した時には耳を疑った。親はともかく、泰河にそんな大それた野心があるようには思えない。
泰河を見捨てるような真似は、道化にはできない。監視を続けつつ機会を窺っていたが、渋谷における泰河の行動が転機となった。"死体を動かす”という特徴は応用が利き発展性が高い。サーカスの目的に沿った方向に遺伝子が変化していくとは限らないが、道化は皆を説得できるような理由を半ば強引につくり上げ、これまで主張してきた懐柔策を強固に押し通した。
泰河と接触する直前になって、強硬派が出した条件を呑まざるを得なくなったのは、それまでずっと中立だった"人形遣い”が突然懐柔派に転向してきたからだ。団員の中で最古参である彼の影響力は強い。自分たちが一般人を人質を取るなんて、道化は考えたことすらなかった。団長も団長だ。いくら多数決が嫌いとはいえ、どうしてそんなタイミングで強硬派の意見を通さねばならないのか。
泰河がネジを巻けるという事実は、降って湧いた幸運のようなものだ。もし同じ特徴が九世代に渡って遺伝しても、完全なネジを持つ者が現れなければ意味はない。クロックワークと旧人類が共存する世界。それは道化の一族が代々追い求めた理想でもあるし、道化自身もそれがどんなものなのか、大いに興味があった。
何故自分たちは、こそこそと隠れるように暮らしていかねばならないのか。長い間守られている旧人類との均衡は、決して適切なものではないと道化は考えていた。そして適切にするためには、我々はもう少し進化を推し進める必要がある。
これでサーカスの団員は、泰河を歓迎することになるだろう。しかし或いは、有馬カヤ率いるマンイーターの駆逐を推し進める結果になるかもしれない。それはそれで仕方なかった。組織の目的が我々と相容れないのであるなら、消えてもらう以外に選択肢はない。
海面に満月が映り込んでいる。不意にその形が変わった気がした。海が揺れているようだが、特に風があるわけでもない。
突如、轟音と共に海中から水柱が上がった。道化は、わが目を疑う。
まるで間欠泉のように勢いよく数メートルも噴出し続ける海水。その上に泰河は立っていた。手首に巻き付いた鎖はすでに外されている。息をするのも忘れてしまうような荘厳な眺めだ。
「先生が、教えてくれたっけな……。海の中にはプランクトンの死骸がうじゃうじゃいるって」
霊長類のような高等な生物だけでなく、微生物まで操れるというのか。末恐ろしい程に将来有望だ。
新しい水柱が上がったかと思うと、海水はそのまま道化めがけて、まるで生きているようにうねりながら落ちてくる。道化は身をかわすことができなかった。局所的な津波の如き激しい流れに飲み込まれ、指一本自由に動かせない。
海水は渦巻きをつくりだし、その中心に道化の体がわずかに見える。クロックワークが窒息で死ぬことはないという事実は、泰河も知っている。巨大な洗濯機にぶち込むみたいで気の毒だが、しばらく我慢してもらう他ない。
何かが渦の外側に浮かんでいる。覗き込んでみると、白塗りの奇怪な仮面だった。海に引きずり込む際に外れてしまったのだろう。泰河はバランスを崩して、水柱の上から落ちそうになってしまう。頭の奥で鳴るキリキリという音は、かなり弱くなってしまっていた。
プランクトンの死骸を通じて海水を操るのは、ただの死体を操るよりも膨大なエネルギーを必要とするようだ。泰河はネジを巻くことによってそのエネルギーを調達していた。ネジを巻くのは確かに自らの意思によるものだが、泰河はまだそれを自由にコントロールできていない。
やがてネジの音が止んでしまうと、疲労感は数倍ひどくなる。もう道化は気を失ってくれただろうか。ついに全身に力が入らなくなり、水柱も渦潮も消えてしまった。
泰河はばしゃんと音を立てて海に落ちた。体はまるで石になってしまったように重いが、そのまま潜って道化の体を探し、抱きとめる。あとは、こいつを担いでほんの五メートルくらい先の陸に上がるだけだ。
ゆっくりと泳いでいく。もう少しのはずなのだが、なかなか進まない。やはりこいつはいったん沈めておこうか、とも思うが、あとで探すのが面倒だ。それにしてもどんなツラしてやがるんだ、こいつは。
泰河は月光に照らして、道化の素顔を見た。それは、知らない顔ではなかった。
高校の先輩であり、数時間前に展望デッキで会った男。青白い顔で泰河の腕の中にいるのは、城ヶ崎淳吾であった。
事態をうまく理解できずに、泰河は目を白黒させている。仮死状態になっている道化の片腕が、少しずつ動いていることに気付く由もなかった。
そして泰河は、飛行機の格納庫の中にいた。道化、いや淳吾の特徴によるものだとすぐに悟り、自分を瞬間移動させた淳吾が追ってくるのではないかと身構える。
果たして、淳吾はやってきた。しかし先程と変わらず意識は失ったままだ。泰河から数メートル離れた場所で仰向けになり、ぴくりとも動かない。一体どういうわけだ。念のため、そちらには近寄らないで周囲を警戒する。
いくら待ってみても格納庫の中に他の人間の気配はない。辺りは真っ暗で、夜目が利かなければ何も見えないだろう。泰河が外に出て行こうとしてシャッターを持ち上げると、不意に男の声がした。
「しばらく待っておれ。じきに行く」
すぐ耳元に、誰かがいるのかと思った。だが、仰向けに寝たままの淳吾以外ここには誰もいない。どうやら頭の中に直接話しかけているようだ。声の感じからすると、歳は淳吾や泰河よりかなり上のようだ。
空港にいる敵は、一人ではなかったのか。自分の思い通りに事が進まないことに泰河は苛立った。
やがて、男が歩いてやってきた。少なくとも還暦は越えているであろう老人だった。腰は曲がっておらず、足取りはしっかりしている。作業服のようなものを着ているが、空港の整備士ではないようだ。道化のそばで立ち止まり、煙草を取り出して火を点ける。
深く息を吸って、大きく煙を吐く。肉体労働者が一服している様子そのものだ。頭はほとんど禿げあがっており、白い口髭をたくわえている。一昔の俳優のように彫りの深い顔をした、気難しそうな爺だ。
まるで泰河のことなど眼中にないかのように、心置きなく煙草を味わっている。同じように力づくで連れて行かれるのでは、と身構えていた泰河は、なんだか拍子抜けしてしまった。
「なんだよ、こいつを迎えに来ただけか? 有難い、やっと肩の荷が下りたって気がするぜ。俺はもう、帰っていいかな」
男は答えない。どうやら、長距離を歩いたのがこたえているようだ。腰のあたりを手でさすったり、軽く背伸びをしたりしている。しびれを切らし、泰河は本当に帰ってしまおうとシャッターに手をかける。
すると、足がまるで地面に張り付いたように動かなくなってしまった。疲労のせいなどではない。膝から下が自分のものではなく、まるで石にでもなったようだ。
「おい、これはあんたがやってんのか?」
そう聞くと、男は不機嫌そうな顔で泰河を一瞥し、いいからそこで大人しく待ってやがれ、というように片手を振って見せた。犬か何かに命令するときのような、ぶっきらぼうな仕草だ。
馬鹿にしやがって。奴にとって、すでに戦いは終わっているというわけか。やっとクソみたいな鉄球や鎖から解放されたというのに、次は指一本触れずに拘束されている。キリキリと、再びネジの音が聞こえ始める。
泰河は素早くポケットの小銭を取り出した。この距離で落ち着いて狙えるなら、煙草の先端だけを撃ち抜くことが出来るだろう。
"加速”させて親指で弾く。すると、まるで見えない糸に引っ張られるように泰河の手はあらぬ方を向いた。小銭はほぼ真上、格納庫の屋根に命中して金属的な音を立てた。
「物騒な真似をするでない。あそこからここまで、どんだけ離れとると思っちょるんじゃ。いいから一休みさせろい」
また頭の中で声がする。老人は煙草をふかし続けている。
「道化に勝つとは、見上げたボウズよ。こやつの特徴は便利なんじゃが、自分と相手を同時に"瞬間移動”できないのが玉にキズじゃ。今の音は、お前じゃな? 天にも昇る気持ちがしたわい。どれ、一つワシの思うがままに鳴らしてみるかい」
そう言って老人が泰河の体を見つめると、真ん中から割れてしまうのではないかという程に、頭が痛くなった。
「ぐあっ、何のつもりだ。やめろ」
「むう? これは奇怪な。さてはお前、自分の意思でネジを巻いているわけではないな? 自分でも巻き方を知らんのじゃろう。お前もワシも知らぬのならば、動かしようがない。そういえば、お主の特徴では仮死状態の体は動かせんのかな? ちと、試してみるか」
痛みがすうっと消えたかと思えば、体全体が急に重くなり、死体を動かしているときに感じるのと同じ疲労感に襲われた。まるで、自分の意思とは関係なく特徴が行使されているようだ。こいつ何をしているんだ、≪まさか《、、、》≫。
「ふむ、ちと無理のようじゃな。まあ何事も、まずは試してみるのが肝心よ」
男の足元にある淳吾の体は、相変わらず動かない。へっへっへ、と老人は声に出して笑う。下品な感じではない。なかなかダンディな笑い方だ。こいつはダンディなクソッたれだ。
「お前、俺とは逆の特徴の持ち主か? "生きている人間を操れる”んだな」
「ご名答。サーカスの仲間からは"人形遣い”と呼ばれとるよ」
泰河は、険しい顔で睨む。人形遣いは余裕の薄ら笑いを浮かべながら、ポケットから携帯灰皿を取り出し火を消した。そして普通に声を出して言う。
「泰河ちゃん。心配せんでもワシももう疲れた。大分体に、ガタがきちょるんじゃ。手短かに済ませようや。無理に仲間になれとは言わんから、明日にでもワシらんとこに、顔を出せい。父ちゃん母ちゃんには、まだ何も言っちゃならんぞ」
「嫌だと言ったら、どうする。また卑劣な真似をするのか」
人形遣いは、渋い顔になり怒気を込めて言った。年季の入った、凄みのある声だ。
「おう。泰河ちゃん、もうちっと大人になれや」
二人の視線が交差する地点に、見えない火花が散っているような緊迫感。さらりと特徴をバラしてしまうあたり、泰河を倒すことなど簡単だと思っているのだろう。確かに、体を自由に操られてしまえば文字通り手も足も出ない。しかし泰河は、一歩も引かず真っ直ぐに相手を見つめる。
「チッ、若いのう」
人形遣いはやれやれという感じで蓄えた口髭を僅かに歪める。くい、と指を動かすと、寝ている淳吾がごほっ、と音を立てて意識を取り戻す。仮死状態から覚めたようだ。二人の顔を交互に見やり、状況を把握している。
「長居は無用。引き上げるぞ」
有無を言わせぬ、ドスのきいた命令口調。この場はこれ以上問答無用と判断したようだ。淳吾もその呼吸を心得ているらしい。ぱちんと指を鳴らすと、人形遣いの姿は消える。
泰河と淳吾は、改めて対峙した。互いに複雑な表情を浮かべている。言いたいことは、お互いに喉の奥からうまく出て来ずにいた。
「……どうやら、あれから大分成長したようだ。心配するな、俺がいる限り、きみを悪いようにはしないさ」
沈黙を破ってそう言った淳吾の顔は、あの頃と全く変わっていなかった。
次の瞬間、泰河は空港の入り口に立っていた。
淳吾が自分をここまで移動させたのだろう。夜とはいえ人の数は多く、泰河が突然現れても気に留める者はいなかった。静かな場所から突然飛ばされたので、まるでさっきまでのことは夢でも見ていたのかというくらいに、非現実的なものに感じられた。服はところどころ破れているが、怪我も完璧に治っているしネジを巻いたせいか体にはむしろ力がみなぎっている。
それでも、ここへやってきた時と比べ、自分を取り巻く状況はまったく異なったものになっている。引き返せないくらい深刻だ。そんな実感があった。
だが、とにかく今は先生と阿理沙に会いたかった。コインロッカーに行き荷物を取り出す。二人で阿理沙のために買ったプレゼントを、渡さなくてはならない。
泰河は、公衆電話から自分の携帯に電話をかけ、変わらず自分を待ってくれている者の存在を確かめ、それから空港を出て行った。
第4章
1
泰河がタクシーで阿理沙のアパートまで乗りつけ、部屋のドアを開けると阿理沙は先生と酒を飲んでいた。目が、完全に据わっている。
「おい……酔っぱらってるのか?」
阿理沙は答えず、首を横に振るだけだった。テーブルの上には缶チューハイ等の可愛らしいお酒ではなく、ウォッカの瓶が力強く鎮座している。
「おかえり泰河。まあお前もこっち来て、一緒に飲もうよ」
「飲まねえよ、飲んだこともねえし。うっ、まさかお前」
先生の手元に置かれているのはオレンジジュースだが、顔が赤くなっている気がする。よもや、ウォッカを混ぜているのではないだろうか。
「スクリュードライバーっていうカクテルなんだって。お姉ちゃんが教えてくれたんだ。なかなかうまいよ、これ」
「いやいや、未成年にも程があるぞ」
「大丈夫だよ、オレたち普通の人間じゃないし。そもそも普通の人間だって、オレの生まれたところでは小さい頃からみんな飲んでたぞ」
呆気にとられている泰河に、阿理沙は無言で抱きつく。
「ちょ、ちょっと待て! くっつくなよ、おい」
髪の毛から、いい匂いがする。阿理沙の肌は、赤くなるどころかむしろ白さを増していた。
「……危ないめにあったんだって?」
「まあな、でももう心配することねえよ。いいから離れろよ」
阿理沙は、答えることも体勢を変えることもしない。
「ししし。お姉ちゃんって面白いよ。顔色全然変わんないし口数も増えないけど、普段絶対言わないような過激なこと言うんだぜ。さっきなんか」
「……先生、いいから黙って飲みなさい」
ホテルは引き払ってしまったので、今夜二人は阿理沙のアパートに泊まることになっていた。先生と阿理沙は、泰河を待っている間に打ち上げと称して飲み会を始めてしまったらしい。
「そうだ。渡せるうちに、あんたたちに渡しておく」
そう言って阿理沙は、泰河から離れて部屋の隅に行ってしまう。
「おい、阿理沙ねえちゃんがさっき一体何を言ったってんだ」
「ヒヒヒ。子供にゃまだ早え」
先生は悪戯っぽく笑って、オレンジ色の液体に口をつける。泰河は、自分でオレンジジュースを紙パックから注いで飲んだ。
「あんたたちに似合うと思って、買ってきたの。気に入るかどうか分からないけど」
デパートの紙袋から出てきたのは、お揃いのパジャマだった。色は鮮やかな水色で、柄はサイケデリックな水玉模様だった。そのまま夢に出てきそうなアバンギャルドな代物だ。
「うおお、すげえイカしたデザインだ。これ何? 寝るときに着るの?」
「こ、こりゃちょっと前衛的すぎるんじゃねえか。大体、俺たちあんまり寝ないんだって、言ってなかったっけか」
「いいじゃない。短いからこそ、その瞬間を大事にするのよ。今日はみんなでこれに着替えて寝ましょう」
阿理沙は、もう一着同じ柄のパジャマを取り出した。どうやら、三人分ちゃっかりと買い揃えていたようだ。泰河は複雑な表情になり、先生は大はしゃぎで喜んでいる。
「そうだ、俺たちからも渡したいものがあるんだ」
泰河はカバンの中から、プレゼントを取り出す。先生からは、香水。泰河は口紅だった。
「あらあ、素敵じゃない……。どれどれ」
二人は、年頃の女性が喜ぶものを店員に聞いて、なるべく無難なものにジャンルを絞った。あとはそれぞれ何を選ぶかだが、そこは各自のセンスに委ねるしかない。
「いい匂い。なんだか私のイメージにぴったり。先生、これで何人も口説いてるんじゃないの。口紅は……ちょっと派手ねえ」
泰河の選んだ口紅は、真っ赤なルージュだった。阿理沙の顔には、これくらい派手な色が似合うのではないかと思ったのだ。だが、二十歳でこの色の口紅をつける機会というのはそうそう訪れないだろう。
反応が今一つだったことに落胆を隠せない泰河を見かねて、先生が言う。
「確かにこんなの、そう頻繁には使えないよな。でも、オレもこの色はお姉ちゃんの魅力をさらに引き出すと思うぜ。今以上の、大人の魅力ってやつ」
「そうかしら、ちょっとつけてみるわ」
阿理沙は、手鏡を取り出しその場で真っ赤なルージュをひいてみせた。俯いたその顔を上げたとき、思わず泰河も、そして先生すらもどきん、と胸が高鳴るのを感じた。
「こんなの、私初めてよ。ちょっとおばさんっぽくない? どう?」
「いや、いい。すごくいいと思うよ。なあ先生」
「あ、ああ。なんて言うんだろう。うまく言えないけど泰河に連れてってもらった美術館で見た絵みたいだ」
「なによ、それ。まあいいわ。嬉しい」
阿理沙はさらに上機嫌になった。表情はあまり変わらないが、目がとろんとなって口数が多くなってくる。先生も顔を赤くして楽しそうに喋っている。
泰河は、島での生活を懐かしく思い返した。あの頃と同じように、ただ楽しいだけではなく自分の居場所が確かにここにあるという気がする。普通の人間も交じっているというのに。しかも最果ての島で野宿をしているわけではなく、ここは普通のアパートの一室だ。
改めて泰河は気付いた。自分が欲しているのは、こういうごく当たり前の暮らしなのだと。普通の人間と変わらない、極々平凡な営み。自分だけではなくすべてのクロックワークが、多くを望まず、そして何も求めないというわけでもなく、普通の人間と本当の意味で対等に暮らしていける世の中。
それを脅かす要素は、否定されて然るべきだ。サーカス、マンイーター、そして自分の血。目指す方向性は見えてきた。だが、大きな混乱がもたらされたのも事実だ。今一度それらを、深く見つめ直さなければならない。
気付くと、阿理沙は座ったまま寝ていた。泰河と先生が、ベッドまで運んでいき布団をかけてやる。
「なんか最近も、同じシチュエーションあったな」
「そうだ。そしてこのままいけば、また裸で抱きついてもらえるかもしれない」
泰河は先生の頭をはたこうとする。先生は千鳥足になりながら、狭いワンルームの部屋を逃げていく。
クロックワークの夜は長い。今日の出来事を話し合いたかった。寝ている阿理沙への配慮と、酔い覚ましのためということで、二人は近くの公園まで夜の散歩に出かけることにした。
泰河と先生は、よっぽどでない限り暑さも寒さも感じないが、今夜が散歩するのにちょうどいい塩梅の気候だということは分かった。
淳吾と戦ったとき真上にあった満月が、大分低い場所に移動している。もう終電なんてとっくに終わっているというのに、月の光に照らされて街は結構明るい。電信柱の裏側すら、仄かに薄明るい。
二人は住宅街の中にある小さな公園のベンチに腰掛け、互いの身に起きたことを報告し合った。古くなった街灯が点滅を繰り返している。
「兎と手品師、か。そいつらもきっと四世代目以降なんだろうな。姿を現した団員は全部で四名、ってわけだ」
泰河が淳吾から聞いたことを話すと、先生は黙り込んでしまった。珍しい反応だ。なにか考え事でもしているのだろうか。
「そう言えばよ、さっき生まれたところがどうとか言ってたな。これまで聞いたことなかったけど、やっぱ先生は沖縄で生まれたのか? 泡盛とかすげえ飲むんだろ、沖縄の人って」
これまで泰河は、先生の過去の話を聞いたことがない。質問が気に障ったのか、先生は面倒臭そうな表情になって、引き続き沈黙を崩さなかった。
わけも分からずそんな態度を取られると、泰河もあまりいい気はしない。少し苛立った口調で、泰河は言った。
「なあ、俺はちょっと怒ってるんだぜ。どうしてネジのこと、教えてくれなかったんだ。知ってたんだろ」
「……別に。聞かれなかったから教えなかっただけだ」
「いやいや、おかしいだろ。絶対何かあんだろ」
「何もないよ。オレは知ってることを余すところなくお前に伝えないといけないのか?」
「そうじゃねえけどよ。ほら……島で色々話したじゃねえか。思い出すと結構恥ずかしいけどよ。俺は四世代目だから、他の奴らより特別なんじゃねえかって。その、自分の存在意義みたいなのについて悩んでたんだ。今もそうだけどよ。先生がちゃんと耳を傾けて聞いてくれただけで、俺は結構救われたんだぜ。そして自分なりに、ほんの少しだけだが答えに近づくことが出来たよ。だけど淳吾の話を聞いたら、ほとんど振出しに戻っちまった。しかも俺は、五世代以降のクロックワークより珍しい存在だと? 加えて、それも遺伝するだと? 聞かれなかったじゃ済まされねえ。俺の気持ち、分かんないのか?」
先生は、残酷な目つきになってじろりと泰河を見返した。
「自分が特別な存在、だと? どうしてそんな風に思うんだ。別にたいしたことじゃないだろう。お前、周りにちやほやされたくって、特別ぶりたいだけなんじゃないのか」
「はあ? なんだよ、その言い方」
泰河もカッとなって先生を睨むが、戸惑ってもいた。先生が泰河にこんな態度を取るのはまったくの初めてだった。
「だって特別なんだから仕方ねえだろ! あいつの話が本当ならな。厄災と希望をもたらすクロックワークの出現には、先祖と同じ特徴だけでなく、完全なネジの遺伝も必要だと? 俺は、そんな化け物みたいな存在に、やっぱり物凄く近いってことじゃねえか」
ばきっ、という音とともに泰河の体がベンチから飛んだ。先生が、見えない何かを使って泰河の顔を殴ったようだ。
「何すんだ、てめえ」
泰河は立ち上がり、先生を一発ぶん殴ろうとした。
これまで同様の場面で無事にぶん殴れたことはないが、完全に頭に血がのぼってしまっている。しかし、あることに気付いて我に返った。
切れかけた街灯のじじじ、という音に交じって、キリキリというネジの音が聞こえていた。自分の頭ではなく、先生の頭から。
「……何だよ、その音は」
「さっき自分で言ってただろう。完全なクロックワークが、ネジを巻く音だ」
先生の顔つきは、見たことがないくらい険しくなっている。その小さな体から、殺気すら放っている。
「癪に障るから教えてやるよ。ネジの秘密については、道化とやらが言った通りだ。持ち合わせているクロックワークの数が少ないから、あまり知られてはいない」
泰河は、冷や汗をかいていた。確かに先生は強い。飄々と振る舞ってはいても、いざとなれば誰と戦っても負けることはないだろうと思っている。そして、今の先生にはこれまでに感じたのとは比べ物にならない凄み、迫力のようなものがある。ネジを巻く音を発しながら、触れれば切れる刃物のような危うさを醸し出している。
「ネジを巻くには方法がある。自分が強く否定したいこと、それこそ命をかけてでも、こんなのは御免だっていう事柄を強くイメージするんだ。お前はどうしようもない我儘だから、自分の思い通りに物事が進まないとき勝手にネジが巻かれてしまう。自分でコントロールできるわけじゃない」
言われてみると、確かにその通りだった。むしゃくしゃした時、いつの間にかその音は鳴っており、体中に力がみなぎっていつもより早く怪我が治る。
街灯が一瞬強く光り、音を立てて割れた。先生の発する空気に呼応しているのか。
破片が地面に落ちてしまうと、あたりは静寂に包まれた。
「……悪い。オレもまだ自分の感情をうまくコントロールできないみたいだ。でも決めたよ。泰河、今までありがとう」
張りつめていた空気は、元に戻っている。ネジの音も止んだ。
「あ? 何言ってやがるんだ、お前」
「オレが沖縄から出たかった理由の一つだ。オレもお前の言う存在意義とやらで、少々悩んでいるのさ。一緒に行動するのはここまでだ。お前は自分の為すべきことをしろ。そしてお姉ちゃんを、守ってやれ」
そして先生はくるりと背を向けた。泰河は、先生が言っていることを理解するのに時間がかかった。
「おい、馬鹿言ってんじゃねえ。なんだよそれ、お前今までそんなこと一言も言わなかったじゃねえか。俺はお前に助けられっぱなしで、まだ何も返せてねえ」
「……お前は自分に降りかかる火の粉を振り払うので精一杯だろう。今は自分の心配だけしてりゃいい。お互いに、な」
先生の小さい背中が、一瞬ひどく頼りなげに見えた。そして、跡形もなく消えてしまった。足音すら聞こえない。
「駄目だ、戻って来てくれ、先生」
そこらじゅうを、泰河は走り回った。公園の中を、その周りを、町内をくまなく走り回った。
追いかけても見つかる見込みは薄い。泰河もまだ知らない特徴のせいかもしれないが、先生は姿を隠すのが大の得意だ。
だが泰河には、角を曲がった先で、びっくりした? なんて言いながら先生が悪戯っぽく笑っているような気がしてならなかった。
遠くから見る分には深夜のランニングと映るかもしれなかったが、泰河の形相は異様だった。怒るのと泣くのを同時に我慢しているような顔で、泰河は走り続ける。交番の前を通った時、流石に警官はその異様さに反応し、自転車で追いかけてきた。
"加速”の特徴は使っていなかった。いくら彼らの基本的な身体能力が高いといっても、自転車に乗った警官と単なる追いかけっこをすればそのうち追いつかれる。泰河は追いつかれるどころか、追われていることにすら気付かず走り続けた。
頭の奥で鳴り響く音のせいで、走っても走っても力はみなぎってくる。だが、いくら走ってもその身で実感できるのは、もう先生はいないということだけだった。
やがて、警官をいつの間にか振り切って公園に戻ってきた。汗だくでそのまま倒れこむ。
「……ふざけんじゃねえよ、馬鹿野郎」
泰河のネジの乾いた音だけが、闇の中に響いていた。
2
「この道は、さっきもう通ったよ。こっちじゃないかな」
「あら、あなたってすごく勘がいいのね。まさかそんな選択があり得るとは考えもしなかったわ。だって、その道は最初に私たちが通ってきた道よ」
「……あのねえ。お聞きしますけど、道案内は得意だから一人でも大丈夫って言い張ってたのは、一体どこの誰かしら? この、役立たず」
「ひっ、ひどい。あなただって単にサボりたいからついてきただけじゃない。分かってるんだからね」
「はあ。やっぱり淳吾にも来てもらった方がよかったなあ。ねえ、これから会いに行く人って、アイドルだったんでしょ。綺麗だった? あたしもそのうちオーディションとか受けてみようかな。絶対いけると思うんだよね。うわっ。あのコンビニ、もう前を通るの三回目だよ。ねえ、年上なんだからアイス奢ってよ」
「えっ、さっきハンバーガー奢ったばかりじゃない。そんなに食べるとぶくぶく太って、アイドルっていうよりお笑い芸人になっちゃうよ」
「沢山食べたのはそっちの方じゃない。どれだけ食べても太らないなんて、羨ましいったらありゃしないわ。つべこべ言ってないで、さっさと買ってきてよ。甘いもの食べれば、きっとエブリシン・ゴナ・ビーオーライだよ」
「何それ。どういう意味。簡単な英語も分からず、彼氏も出来ないあたしへの当てつけですか」
「後半は全然関係ないでしょ? それは、自分に問題があるのよ」
「……あなたは、アイスのことを考えると、気分が悪く……」
「ちょっとやめてよ! それは反則!」
早朝の住宅街。髪の毛をツインテールにした小さい女の子は、爽やかな朝の空気を浴びて軽やかにスキップをした。若さと生命力に満ち溢れた、みずみずしい場面だった。たまたまその場を通りかかった老婦人が、微笑ましくそれを見ている。
そのスキップは確かに生命力に溢れていた。少しばかり過剰ではないか、という位に。少女は一足飛びで、隣を歩いていた黒い服の少女から十メートルも離れた場所に移動したように見えた。
「こ、こらっ。こんな場所でそんなのやったらダメでしょ」
「先にやろうとしたのは、そっちでしょ? 悔しかったら、あたしを捕まえてみなさいよ」
少女は無邪気に笑いながら、ぴょんぴょんと飛び跳ねている。ツインテールが揺れてまるでウサギのようだ。
それにしても、何というジャンプ力なのだろう。少女の体は陸上選手のように細くしなやかで、ホットパンツからすらりと伸びる脚には無駄な肉はただの一グラムもついていないかのようだ。そこに女らしい豊かなカーブが加えられるのは、まだまだ先のことのように思える。だが、少女はおへそが見えてしまうくらいジャストサイズのTシャツを着ており、飛び跳ねるたびに決して小さくはない胸が揺れていた。老婦人は、最近の子はなんて発育がいいのかしら、と思った。
ラビットと手品師は、蛇が調べた住所に向かっていた。二人はいわゆる地図が読めない女であった。いくら歩いても、走っても目的の場所にたどり着くことはできないでいる。
やがて自力で辿りつくことを諦め、お巡りさんに道順を教えてもらおうと交番に行った。お巡りさんは、昨晩大捕り物でも演じてみせたのか、何やら疲労困憊が抜けきらない様子であったがそれでも職務を立派に遂行してくれた。
かくして、二人はついに目的地に到着した。アパートの手間で、なにやら思案している。
「じゃあ、例の作戦で行くね。あなたはいたいけな子供を黙って演じてるのよ」
「ちょっと待って。あの鋭いチビがいたら、すぐに正体が見破られちゃうかもしれない。"変装”抜きで正々堂々と行った方がいいかも」
「大丈夫、バレたらバレたで、何とかなるよ。きっと」
「んー、まあそうだね。あいつら悪い奴じゃなさそうだし」
チャイムが鳴り、ドアを開けた阿理沙の目に飛び込んできたのは、親子連れの姿であった。
母親の方は三十代半ばくらいであろうか。黒いドレスのような服を着て、厚化粧と作り笑いで出来たお面のような顔をこちらに向けている。
子供は、小学校の低学年くらいで、きちんとした身なりの母親とは対照的に、髪の毛はぼさぼさで、着ているものはサイズが合っておらず、いかにも薄幸そうな表情でじっと俯いている。
「おはようございます。あなたは神を信じますか?」
阿理沙は、寝起きのまだ充分に脳が働いていない状態で、不用意にドアを開けてしまったことを激しく後悔した。流石にチェーンはかけているが、この親子が発しているプレッシャーから逃れることは決して容易ではなさそうだ。
昨夜は久しぶりに飲みすぎて、まだ頭がガンガンする。朝の日差しだけでも眩しいのに、おばさんの厚化粧がそこに加わると、もう溶けてしまいそうな心地さえする。
酒の力で度胸のついた自分をもう一度思い出し、強く追い返すという手段もあったが、傍らに控えている子供の手前それは憚られた。
「この世界はいつか終わるのです。終わりの日は近い。ジーザス・クライストの言う通り最後の審判が行われ、選ばれた者だけが行ける新しい世界は、あなたにも開かれているのです」
阿理沙は、ただすっぴんであるばかりでなく、朝から真っ赤なルージュを落とすために入念に顔を洗ったばかりであった。わずかの脂も残ってはいない。
もちろん彼女には、それでも人前に出るのに耐えるほどの美貌が備わってはいるが、着ているものと言えばゆったりとしたパジャマだけでブラもつけていないし、精神的にも無防備なこの状態では適当な相槌を打ちながらひたすら話を聞くことしか出来なかった。
困っている阿理沙を見かねて、部屋の奥から泰河が出てきた。
「やい。何を言ってやがるんだてめえら。さっきから聞いてりゃ、そんな都合のいいことあるはずねえだろう」
「いいえ、そんなことはありませんよ。救いは求める者に平等に差し伸べられるのです」
あくまでにこやかに、勧誘女はすらすらと答える。
「そんな優しい神様だったらよ、どうしてこの世には障害を持って生まれてくる人間や、社会からつまはじきにされることが予め定められた人間がいるってんだい。おかしいじゃねえか」
「ああ。それは試練なのです。慈悲深いジーザス・クライストによって、罪深い迷える魂に課せられた、浄化され楽園に向かうための」
「誰が罪深いだと?」
「生きとし生けるものは、皆罪深いのです」
「ハッ、そりゃいいや」
泰河は口を斜めに歪めて笑った。目はまるで寝不足かのように赤く、腫れぼったかった。
「確かにあんたの言うとおり、俺たちは例外なく罪人なんだろうな。生きていくためには罪を犯さねばならない。愛し合おうとすれば罪を犯さねばならない。黙って見過ごすことも罪なら、無関心であることも、知らないことも全部罪ってわけだ。これぞまさに八方塞がり、ってやつだな」
勧誘女は、微笑を浮かべたままぴたりと喋るのをやめてしまった。子供も、顔を上げて泰河の方を見た。
「だけどよ、俺は神様やら天変地異やらの助けなんて、クソくらえだと思うよ。だってそうじゃねえか。何百万年もの間、人間の世界はなんだかんだで今まで続いてるわけだろう。もしかするとこれまでに危機的な状況があったのかもしれないが、結局俺たちはこうしてイカしたパジャマでお寝んねできてるんだ。数あるクソパジャマの中から選び抜いた、とびっきりのクソパジャマでな」
横では阿理沙が目を大きく見開いている。泰河は勧誘女の目を真っ直ぐに見据えて、きっぱりと言い放つ。
「だとしたら、残ってるのは家畜のように生きるか、悩みながら苦しんで生きるかって選択しかねえよ。神様の助けなんて要らない。俺は自分の罪と向き合いながら、てめえの頭でどうするか考えていくよ。親切に教えてくれる奴もいるが、いつかは俺の前からいなくなっちまうんだ。本当にそうなるまで、想像もできなかったよ。気付かないうちに、甘えちまっていたのかもな。だからあんたたちの話は必要ない。悪いが帰ってくれ」
泰河は、ドアノブを掴んで扉を閉めようとした。しかし、力いっぱい引いても何故か閉まらない。
足元を見ると、いつの間にかドアの隙間に子供が足を突っ込んでいる。か細い足のくせに、かなり強い力で抑えているようでびくともしない。折りたたまれたパンフレットを泰河に差し出してきた。
「……あんたの言うことは、立派だよ。でも、先人たちの教えにはもう少し耳を傾けてもいいかもしれない。これを受け取って、読んでほしい」
泰河が黙ってそれを受け取ると、子供は足を引っ込めた。勧誘女は、顔が本物のお面になってしまったみたいに言葉を失っている。子供が、ほらもう行くよ、と声をかけると、ぺこりとお辞儀をして二人とも去って行った。
「まったく、何だってんだ朝っぱらから」
阿理沙の姿が見えない。見回すと、部屋の隅の方を向いてうずくまっていた。
「おい、どうしたんだよねえちゃん。あいつらに何か気に障ることでも言われたのか」
「パジャマ……パジャマ……」
泰河は、完全に機嫌を損ねてしまった阿理沙をなだめるのに時間を要し、パンフレットに書かれているのがサーカスのアジトの場所だということに気付いたのはもうすっかり昼になってからだった。
勧誘の親子は、他の部屋を訪ねることはせず、そのまま階段を降りてアパートから離れていった。敷地を出ていく頃には、母親は手品師に、子供はラビットの顔と体格にそれぞれ戻っていた。
「ねえ見た? あのパジャマ。あんなのどこに売ってるんだろう。よく普通に話し続けられたわね。せっかくすごく綺麗な人なのに、あたしのっけから笑いを堪えるので大変だった。奥から同じパジャマが歩いてきた時なんて、もう腹筋が千切れるかと思ったわよ。それにしても、一つ屋根の下で男女が同じパジャマって、なんかすっごくいやらしいというか、なんというか、ちょっと羨ましいかも。……ねえ、聞いてる? さっきから、加奈子なんか変だよ」
「……やばい。あたしやばい。あれが弟さんか。想像以上だわ」
「どうしたの? 顔赤いけど、風邪でもひいた?」
「いや。そうじゃない。あたし……あの泰河って男の子、ちょっといいかも」
ぽかぽか陽気の住宅街に、絶叫にも近い少女の声がこだまする。用事を終えて帰路についていた老婦人は、それを耳にし、ふっと微笑んだ。
3
城ヶ崎淳吾は、幼い頃はいじめられっ子だった。大きな家の坊ちゃんだからと言って、体の大きな奴から目の敵にされていた。どことなく漂う上品な風格や、都会的な目鼻立ちも標的にされる要因だった。
母は物心つく前に死んでしまい、父は仕事でほとんど家にいなかった。淳吾は弟と妹と共に、厳しい執事に育てられた。自分が他の人間と違うということは、事あるごとに口酸っぱく言い聞かせられていた。秘密が守れる年齢になるまで、親しい友人をつくることすら許してはくれなかった。
たまに帰ってくる父は、淳吾たちを甘やかした。山のようにおもちゃを買ってきて、様々な手品を自ら披露し、遊園地や映画に連れて行った。淳吾たちは父のことが大好きだった。帰ってくるのをいつも首を長くして待っていた。
執事は芳村という名のいつも怖い顔をした老人で、代々城ヶ崎家に仕えていた。淳吾たちは父に対して、もう芳村とは一緒にいたくない、お父さんがいつも一緒にいて、と別れの時が来るたび真剣に懇願した。横で聞いていた芳村は眉ひとつ動かさず、文句の一つも言わなかった。
自分にちょっかいを出してくる貧乏人のクソガキを、黙らせるくらいの腕力は本当はあった。だが、自分の体が他人と違うことを悟られるな、目立ってはいけないと芳村には言い聞かせられていた。そういった点でも、淳吾は芳村を疎ましく思っていた。
小学四年の冬、下校途中に石を投げられ、淳吾は額から流血した。体の大きいガキどもは、それを見てげらげら笑っていた。淳吾は怒らなかったがその代わり、ガキどもを目が回って歩けなくなる位コマのように回転させてやった。そのうちの一人が、巻いていたマフラーが首に絡まってしまい窒息して救急車を呼ぶ事態になった。
大事には至らず、子供同士がふざけていた際の事故ということで処理され事なきを得たが、淳吾は芳村に厳しく罰せられた。十日間蔵に閉じ込められ食べ物はおろか水すらも与えてもらえなかった。何を言っても、芳村は淳吾に一片たりとも同情などしようとしなかった。血も涙もない男だ、と淳吾は思った。
春になると、淳吾は家出をした。東京で仕事をしている父の元へ向かうべく、自分で切符を買って新幹線に乗った。
父が暮らしているはずのマンションへ辿りついた頃には、あたりは暗くなっていた。部屋のチャイムを押したが、反応がない。ドアのカギは空いており、淳吾は中へ入って驚いた。まるで泥棒に入られたかのように部屋が荒らされていた。
あとで知ったことだが、父はビジネスのためではなくある目的を持った組織の一員として活動しており、淳吾が訪ねた時には、SACに存在を嗅ぎ付けられ行方をくらましていたところだった。
不意にやってきた息子を、SACは見逃さなかった。マンションには監視が張り付いていた。駆けつけた三人の男たちにその場で捕まえられ、猿ぐつわをされ胴体をすっぽり覆うような拘束具をつけられて車に放り込まれた。感じた恐怖は、蔵に閉じ込められた時とは比べ物にならなかった。
走り出した車が、突然大きく揺れて停止した。タイヤが全てパンクしてしまったようだ。男たちが外に出ると、そこには鬼のような形相をした芳村がいた。
芳村は"空気を飛ばす”特徴を持ったクロックワークだった。空気の塊を指先からまるで銃弾のように飛ばすことが出来る。だが、本物の銃を所持し訓練された三人を相手にして身を守れるような特徴ではなかった。
決着は一瞬でついたようだった。ぱすん、と弱弱しい音を立てて、淳吾の拘束具が解かれた。
SACの男たちは体にいくつかの穴を開けて、皆死んでいた。芳村はそれと比べものにならないくらい大量の銃弾を浴び、血の海の中でほとんど虫の息だった
「坊ちゃん、お怪我はありませんか」
淳吾が頷くと、芳村は顔面が半分無くなっていたが、これまで見せたこともないような笑顔になって言った。
「それは良かった。何よりです」
震える手を、淳吾に触れようとして空中に伸ばす。もう目も見えていないのかもしれない。淳吾はその手を抱きとめた。カフスボタンが千切れて淳吾の足元に落ちた。
「坊ちゃん、私のことは放っておいて、すぐにここから立ち去ってください。そして真っ直ぐ家に帰るんです」
淳吾の目からは、とめどなく涙が溢れてきた。
「嫌だ。芳村と一緒に帰る」
「いいんです。どうせ老い先短い身だったんです。坊ちゃんは優しいですね。その優しさを、どうか坊ちゃんの助けを必要としている人に向けてあげてくださいませ」
芳村は淳吾の腕の中で息を引き取った。淳吾は泣きながら言われたとおり指を鳴らしてその場を後にし、大きな公園で一夜を過ごし始発で福岡に戻った。
やがて淳吾の父親も戻ってきたが、無事ではなく体が不自由になってしまっていた。もう組織の活動はできなかった。サーカスと呼ばれるその組織は、代わりに淳吾が加わってくれることを望み、淳吾もその意思を継ぐ決意をしたが、父の意向で高校を卒業するまでは普通の人間と同じように暮らすことになった。
芳村が死んでからというもの、弟と妹を躾けるのは淳吾の役割となった。彼の中には、芳村と父を傷つけた人間たちへの復讐心があった。しかし誰かを傷つけることよりは、自分の助けを必要としている者に手を差し伸べることが重要だと淳吾は考えていた。
淳吾は芳村のカフスボタンを、形見として今でも肌身離さず持ち歩いている。古い喫茶店で、もう何杯目かのコーヒーを飲み、待ちくたびれてそれを取り出し眺めていると、店の扉が開いてひょろ長い男が入ってきた。
「やあ、ずいぶん遅かったじゃないか。うちのレディたちは迷子にでもなっていたのかな」
「なんだよ、ここがそうなのか? まさか、店員みんな関係者、ってことはねえだろうな」
どかっ、と泰河は向かいの席に座る。
「しっ。慎みたまえよ、泰河くん。ここは僕の気に入っている普通の店さ。といってもコーヒーの味は、普通ではない。めくるめくような芳醇な香りと味わいを備えた絶品さ。まあ君も何か頼みたまえ」
「俺、コーヒー飲めないんだよな。阿理沙ねえちゃんなら喜ぶかもしれねえが。すみません。クリームソーダください」
淳吾が、やれやれ、という表情で苦笑する。相変わらず子供っぽいな、とでも言いたげに。
地下にあるこじんまりした店。つくりは古く、ところどころ木の匂いがした。壁に貼ってあるのはうんと昔のポスターか、小さな油絵。
店内には小さな音量でジャズがかかっている。店員はぴしっとした制服を着ているし、まるでおとぎ話の中に迷い込んでしまったと錯覚しそうな雰囲気がある。ここなら本を持ち込んで、何時間でも過ごせてしまいそうだ。
沈黙を破って、泰河が口を開く。淳吾は片腕を三角巾で吊っており、包帯が至る所に巻かれ痛々しい様子だった。
「ゆうべは悪かったな。体は平気か」
「心配ないよ。むしろ丁重に扱ってくれたことに感謝せねばならない」
泰河は、淳吾をじっと見つめる。
「どうした? 僕の顔に何かついているかい」
「いや別に。あのさ、いっこ聞いてもいいかな」
「勿論さ。何でも聞き給えよ」
「先輩ってさ、一体どんな気持ちで、あんな衣装着てたの」
「あれは城ヶ崎家に代々伝わるもの。僕にとっては、正装みたいなものだ」
泰河は、顔を半分しかめてみせた。淳吾はそれに気付かないで続ける。
「再会を祝す気持ち、それに非礼を詫びたいという気持ちもあった。だがそれ以上に、何というかな。上手く言えないが……君とあんな話をするからには、正装が一番ふさわしいと思った」
淳吾は、微笑みながら泰河を見つめ返した。二人の間に親密な空気が流れる。
やや間があって、泰河は何故か照れたような気分になってしまった。
「は、はあ? やっぱりお前たちは、愉快な一族だぜ。今度家にでも招待してくれよ」
丁度、泰河の飲み物が運ばれてきたところだった。気を取り直し、話題を変える。
「言っとくが、仲間になると決めたわけじゃねえ。まずは話を聞かせてもらうぜ」
「よかろう。ところで、小さな友人がいると聞いたが」
泰河の目に、暗い影が落ちた。そしてすぐに、思いついた出まかせを口にした。
「あいつを危険な目に巻き込むわけにはいかねえ。よく言い聞かせて、家に帰らせたんだ」
4
「いってらっしゃい。気を付けてね」
いつもと変わらない日常の風景だった。夫は神経質に靴を履く。靴べらでしっかり踵を通して、座っていちいち紐を締め直す。汚れや傷を発見してしまうと、その場で手入れを始めてしまう。
今日も、そんな夫の背中を見ている。地方公務員の長男で、臆病で神経質。だけど、誠実だし卑怯ではないし、美雪には到底理解できない位うじうじと先のことばかり考えているのは、将来のために計画的だからであり、人一倍慎重なだけなのだ。美雪はそれをよく分かっている。
そんな彼が、玄関を開けて外の世界に出ていこうと靴を履く小さな背中を見ているのは、守ってやりたいような、応援してあげたいような、抱きとめて今日はどこにも行かないで、と言ってしまいたいような、そんな気分がいつもしていた。靴を履き始める時間は、六時半ちょうど。結婚してから五年、まだ一分たりとも誤差は生じていない。
美雪は、夫の様子がいつもと違っているのに気が付いた。紐の結び目はどう見てもしっかりと締まってはいないのに、いつまでも結び直そうとしない。
しまいには、そのまま立ち上がってこちらを向いた。何年かに一度の、履いた瞬間しっくりきた奇跡の感覚が訪れるたかもしれない。美雪は毎日しているのと同じように、いってきますのキスを要求して目をつぶった。
「いいのか、本当に一緒に行かなくて」
夫の声は震えていた。眼鏡の奥のいかにも気弱そうな目が、ひどく怯えていた。
「大丈夫よ。どうってことないわ」
「でも」
「いいのよ」
もう何も言わなくていいの。美雪は夫の口を、自分の口で塞いだ。
夫は今年三十二歳になる美雪より一つ年下で、千代田区に本社がある中小企業に勤めていた。知り合った頃は、どうしてこんなに臆病で、あらゆることへのアプローチが回りくどい人間が存在するのか、理解に苦しんだ。
そして、そんな男が何故自分と正反対で竹を割ったような性格の美雪のことに執心しており、その気持ちに美雪が気付いて一年以上も経つのに未だに自分ではばれていないと思っているのか、あまりに不可解すぎて眠れない夜があるくらいだった。結局、美雪は自分から夫に交際を申し込んだ。
結婚式のこと、新居のことなど、美雪は何かある度にやきもきさせられた。石橋を叩くにも程があるというか、人間の頭というのはそこまで回るものだったのかと、呆れるのを通り越してただただ感心するばかりだった。
保険のことだったか住宅ローンのことだったかもう忘れたが、苛立ちが募って家を飛び出したことがあった。どれも同じようなものなのだから、少しの違いはあれどさっさと決めてしまえばいい。結婚してからそんな風に不満を爆発させたのは初めてのことだった。仕事仲間の家に泊めてもらい、翌日夫が会社に行っている時間に帰宅した。
食卓の上には、謝罪の言葉を綴った長い手紙と、夫の唯一の得意料理で美雪の好物である大学芋が乗っていた。きっと夜遅くまでかかって、気持ちを整理し手紙を書いて大学芋を拵えたのだろう。しかし、その時の美雪の気持ちはそれでは収まらなかった。
いくら何でも、もう限界かもしれない。そう思って、美雪は普段入らない夫の書斎を覗いてみた。美雪が何もしなくても、床だけでなく机の上もいつも完璧に片付いている。本棚もジャンルやサイズ別にきっちり整頓されていて、夫の性格をよく表していた。
その机の上に、見慣れないノートがあった。書類が数枚はみ出している。いつもなら、書類は必要な部分だけ切り取ってノートに糊付けするか、クリアファイルなどに別で保管するはずだ。少しためらったが、美雪はそれを開いてみた。
そこには、自分と夫の将来計画が事細かに記されてあった。子供の人数、教育にかかる資金。まだ存在すらしていない三人の子供が、受験に失敗した場合のことも複数パターン考えられていて、美雪は苦笑するしかなかった。勉強では落ちこぼれの美雪と違い、夫はストレートで国立の大学に合格していた。
「私の子供は、きっと落ちるってのかよ。てか三人もいらないし」
そのノートには、いつまであるのか分からない会社の退職金の使い道から、しまいには老後のことまで記してあった。二人は適度な運動と美雪がつくるバランスの良い食事によって、介護をそれほど必要としない体で人生の起承転結を終え、やがて美雪を自宅で看取った夫は家を売り、介護付き有料老人ホームで余生を過ごすのだという。
「おい、私を勝手に先に殺すなよ。それで自分は介護付き有料老人ホームかよ」
神経質で胃痛持ちの夫が、どう考えても先に弱っていくに決まっている。それでなくても、幼い頃は病弱だったことをちゃんと知っているのだ。
だが、夫は自分を最期まで看取ることを真剣に考えているようであった。道に迷ったときや物騒な場所を通るときなど、物怖じせずにずんずんと先に進んでいくのは美雪の方で、夫はきょろきょろしながら後ろを付いてくるのが常なのだ。それに、仕事で失敗をした次の日や重要な商談がある日などは、まんじりともしない夜を過ごし、会社についてきてくれないかと本気で泣きついてくる時だってある。美雪は、子供をあやす母親のようにして、大丈夫、私がいつだってついているからね、と慰めてやらねばならなかった。
そんな夫を、一人で老人ホームに入れるなんて、あまりに心配すぎてきっと自分は墓からよみがえってしまうだろう。おちおち死んでもいられない。
突っ込みどころが多すぎて、何度もページを行ったり来たりしながら美雪はそのノートを熟読した。書類が挟まっているのは夫婦喧嘩の原因になった部分で、書き込みがいくつもしてあった。きっとああでもないこうでもないと手直しを繰り返していたのだろう。
子供が怪我や大病を患った場合のことや、資産運用がうまくいかなかった場合のことも何通りも考えられていたが、いくら読み込んでも夫が先に死ぬ場合のことはシミュレートされていなかった。美雪は、夫のプロポーズの言葉を思い出した。
「頼りない僕ですが、あなたが死ぬまで、一生懸命そばにいます」
美雪は、それを言葉通りに受け止められていなかった自分を恥じた。気付かないうちに頬に涙が伝っていた。
美雪が新型出生前診断を受けることになったのは、そんな夫の性格上当然のことのように思えた。子づくりをする前から、二人で何度も話し合った。その結果は、妊娠している間に胎児に染色体異常が認められた場合には中絶を選択するというものであった。
まだ妊娠していない美雪には、あまり現実味が湧かなかったし、腹を痛めるわけでもない夫がああだこうだと考えを巡らしているのは奇異だとすら感じた。
実際に子づくりを始めてみると、なかなか美雪は妊娠しなかった。夫は美雪が三十歳になる前に一人目を設けたかったようだが、それもあっけなく過ぎた。二人で不妊の検査も受けたが両方異常なし。なんとなく気まずい日々を過ごしたが、美雪は、そのうち出来るだろうと楽観的に構えていた。
そして五ヶ月前、ついに美雪のお腹に生命が宿った時には、夫は小躍りして喜んだ。もちろん美雪も嬉しかった。子供ができたという実感よりも、あまりに待っている期間が長かったためか、これで二人の幸せプランは出来上がったも同然、という思いの方が先に来た。
夫は、待ってましたとばかりにマタニティグッズを用意したり、病院や検診のことなんかをチェックし始めた。美雪には、そういった気配りには感謝こそすれ、あまり必要性を感じていなかった。生まれつき体が特別丈夫な自分の子供なのだから、多少のことは問題ないと分かっていたからだ。
なかなか妊娠できなかった間に、羊水を採取しなくてもいい新しい検査が始まっていた。血液を採取するだけだが、それでもかなりの確率で胎児の異常が分かるという。すべての染色体異常を検査するためには、やはり羊水を取らねばならないので二度手間になると思い、費用も決して安くはなかったので美雪はあまり気が進まなかった。だが、夫は少しでも不安を払拭するためだといって検査を勧めた。自分は採決が苦手で、健康診断の時はいつも気分が悪くなるくせに、と内心呟きながら夫婦で病院を訪れた。
「もし結果が陽性だったら、必ず羊水検査を受けてくださいね」
清潔な白衣を着た医者にそう言われ、美雪は急に怖くなってしまった。やっぱり帰ります、と言い放って診察室を出て行った。
取り残されてきょとんとした夫が後を追うと、美雪は待合室で泣いていた。
どうしたのか、と声をかけると、急に不安になったの、と美雪は答えた。こんなふうに漠然と不安を抱えることは滅多にないことだったし、そんな美雪を見るのは夫にとって初めてのことだったので、二人はどうしたらよいか分からず、そのまま病院を後にした。
二人は検査を受けること、そして検査後の対応についてさらに話し合いを重ねた。夫の主張は一貫しており合理的だった。生まれてくる子供に重大な障害があった場合、自分達や親類にかかる負担は並大抵のものではない。避けられるものなら、避けるに越したことはない。美雪もそれで一度は納得したはずだった。
ずっと長い間待っていたから。生命が宿っているという実感があるから。自分の心境の変化について、納得のいく理由はなかなか見つからなかった。
誰にでも得意不得意があり、それぞれ異なる特徴がある。障害というのは便宜的にそう呼ばれているに過ぎない。障害があろうとなかろうと、生命そのものの本質は変わらないのではないか。
子供にもし障害があったとして、それは誰のせいにでもないのに、親の意思で産まれてくることが出来ないのは、親の勝手が過ぎるのではないか。生命の尊厳を無視しているのではないか。
どこかで聞いたような言葉ばかりが出てくる。自分で口にしながら、ひどく空虚な感じがする。夫を説得したいわけではなく、まず自分の考えをはっきりと形にしたかった。
「子供が親を選べないように、親が子供を選んではいけないのではないかしら」
美雪は、理屈をこねるのではなく原則論のようなものを持ち出してみた。僕の考えはこうだ、と夫は答える。
「経済力をはじめとして、育児の能力がなく責任も持てない親は、そもそも子供をつくるべきではない。親は子供を選ぶというより、子供が産まれてきたときの環境を整えるという選択に責任があるんじゃないか。それはほとんど義務と言ってもいい。重大な障害を抱えていることが分かっていて、そのまま産むというのは、子供にひどい環境で生きていくことを無理矢理強いることになるんじゃないかな」
「そんなこと、本人に聞かないのにどうやって分かるのよ」
「子供というのはそういうものだ。大人が判断しなければならない」
「障害を持っていても幸せそうに生きている人や、その家族だっているわ」
「本人たちがどう思っているかは本人たちにしか分からないし、幸せの定義は人それぞれだ。今の僕の価値観とは、相容れない」
「何よ、結局あなたのエゴでしかないじゃない」
「障害を持って産まれた子供が、淘汰されず生きていけるのは現代が豊かだからだ。社会にそうした子供を受け入れる余裕があるから、そんな選択肢があり得るんだ。本来淘汰されるべきだった子供を生かそうとすることも、僕と同じくエゴイスティックではないだろうか」
美雪は、手放しで納得することも出来なかったが、きっぱりと否定する気にもなれなかった。これが他人事であれば、すっぱりとどちらかの立場に偏ることも出来たかもしれない。だがおそらく、どちらの立場も間違ってはいないのだ。当事者であるからこそ、簡単に立場を決めることはできない。
原則論の是非で言えば、夫が持ち出してきた淘汰という考え方には一理あるような気がした。ジャングルや雪山や貧しい農村ではそんな子供は生きていけない。
「だけど、かつてなら淘汰されていた存在を生き延びさせることは、大きな視点で見れば、人類という種がとっている戦略みたいなものではないかしら」
「残念だけど、僕は神様じゃなくて不安定な中小企業に勤めるサラリーマンなんだ」
「要するに、あなたは幸せになりたいんでしょう? そして子供も幸せにしたい。だけど、何の悩みも苦しみもない金持ちより、貧乏や病気で苦しんだ人の方が、実は幸せになれるっていう考え方もあるわよ。外国では、ハンディを抱えた子供のことを、天からのギフトを持つ者たちって呼んだりするらしいし」
夫は、しばらく目を閉じて考え込んだ。
「そう思える人は、強くて心が美しい人だと思うよ。でも今の僕は、そうは思えない。僕は息子とキャッチボールがしたい。娘の手料理が食べたい。皆でキャンプに行ったり、顔を突き合わせて将来の夢について語り合ったりしたい。偉くなってほしいわけじゃないけど、子供にはちゃんとした教育を受けさせ、教養ある大人になってもらいたい。特に、一人目の子供にはね。これが、偽らざるありのままの気持ちだ」
その言葉を、美雪は頭の中でじっくりと反芻するように吟味した。
「それは、自分や子供が、他の大多数の親や子供と同じようにありたい、ということではないの?」
夫は、目を閉じて腕を組んでさらに考えた。
「いや、違うよ。僕はそういうことを、君といつか一緒に行く旅行のことを考えるみたいにして、ぼんやりと、とても楽しみに、真剣に空想していたんだ」
美雪は、それで少しだけ気持ちの整理がついた気がした。夫の考えに同意したわけでもないし、夫のように子供が出来た後の生活を具体的にイメージしたことがあるわけでもなかった。
自分の子供は絶対に異常なく産まれてくると思っていたし、仮にそうではなかったとしても、楽観的な美雪にとってさしたる支障は無いように思えた。
障害と呼ばれる特徴だけではなく、容姿や才能など、あらゆる点において子供は平等に生を受けるわけではない。親がある程度手助けすることはできる。だが、結局どんな生物でも、淘汰されないためには自分でどうにかするしかないのだ。
美雪は淘汰されてしまうような存在をこの世界に放り出したくはなかった。病院で涙を流した理由は同情の涙かもしれなかった。母親に同情され、父親に拒絶される。そんな子供は、可哀想だと思った。
そんな自分を否定できるもう一人の自分は、今のところどこにもいない。美雪にとってそれが明確な答えだった。
夫を見送り、午後になってから美雪は病院へ向かった。
待合室で居合わせた、将来の希望に溢れていそうな妊婦たちの中で、美雪はひたすら祈っていた。
幾多の困難を乗り越え淘汰されず生き残った精子。淘汰されることなく体内にとどまり続けた卵子。あなたたちの生存競争は、まだ始まったばかりなのだ。これは長く険しい道のりの第一歩でしかない。無事に産まれてきたとしても些細な怪我や病気で、偶然の事故で、ひょんなことで淘汰され死んでしまう者は数限りなくいる。
頑張れ。まだ名も無く、生命と呼んでいいかどうかも分からないような何者かよ、頑張れ。
5
喫茶店を出ると、地上へ上がる階段がある。誰もいないことを確認して二人は"瞬間移動”を繰り返す。何箇所かを経由し、やがて古い洋館のような家にたどり着いた。
「そうだな、泰河くん…… これが君にとって有利になるかどうか分からないが、一つ忠告をしておこう。君は自分の意思でネジを巻くことができる。そういうことにしていた方がいい」
「よく分からんが、別に構わんぜ。淳吾がそう言うなら」
「"道化”だ。有馬泰河を連れてきた」
淳吾が扉を開けると、そこは食堂みたいな大広間で、テーブルの席に人形遣い、手品師、ラビット、それと男が二人、女が一人座っている。団員が皆揃っているわけではなさそうだ。
人形遣いは一人だけ煙草をふかしている。泰河の顔を見てにんまりと笑った。なんだか小馬鹿にされているような気がする。まったく、いけ好かない爺だ。
自分と同じ年頃の女と、小学生か中学生くらいの女は最近どこかで見たような服を着ている。一体どこで見たのか、思い出せない。黒い服を着た女が、泰河と目が合いそうになり慌てて顔をそむける。
それから、白いタンクトップの上にデニムのオーバーオールを着たプロレスラーみたいにガタイのいいおっさん。年は四十代と言ったところか。隣にいる男は、とりわけ異彩を放っている。規格外の、まるでアメリカ人力士のような立派な体格だ。髪の毛は伸びっ放しでぼさぼさで、目がほとんど隠れてしまっている。顔にはいくつも古傷があった。でかい図体をしているが、まだ若いようだ。
最後の一人は、仕事のできるOLみたいに利発そうな顔つきをした女。手元にはノートパソコンが置かれている。おでこを出したロングの黒髪に赤いセルフレームの眼鏡をかけており、広い額と太い眉が知的な印象を醸し出している。派手ではないが、高級なものを身につけているようだ。一つボタンを外したシャツから、豊かな胸の谷間がのぞいている。口火を切ったのはそいつだった。
「私たちのアジトへようこそ。私は"蛇”と呼ばれています。よろしくね」
女は礼儀正しく、だがどこか冷たさのこもった声で泰河に挨拶した。
「こちらこそ宜しく。自己紹介はしなくても、きっと俺のことはすでによく知ってるんだろう?」
「まあね。だけど、直接触れ合ってみないと分からないことも沢山あるわ」
片目をつぶり笑顔をつくって泰河に椅子を勧める。作り笑いのような気もするが、それがかえって艶めかしい気もする。年齢は、十ほど上か。泰河は、阿理沙に対して感じるのとまた別の種類の女らしさを感じた。
「では、これからあなたの母親について私たちが知っていることを、あなたに教えます。きっかけは、ブラックマジックが北京で計画していたテロ活動を、SACが未然に察知して止めようとしたことにある。一年ほど前のことよ」
「何だ、そのブラックマジックってのは」
「究極にイカレた奴ら。奴らには国籍も主張も何もない。世界各地で無差別テロを計画し、その"犯行声明”を、オークション形式で誰にでも販売する文字通りの死の商人。値が吊り上がれば上がるほど、奴らの装備は充実してテロは大規模なものとなる。あなたはよく知っているはずよ。だって、ブラックマジックの日本デビュー戦を途中で止めたのは、あなた自身なのだから」
泰河は、渋谷駅での出来事を思い出す。特殊部隊みたいな黒づくめの戦闘服に目出し帽まで被っていた、あの連中。
「奴ら、金のためにあんなことやってやがったのか」
「それならまだ人間味があるわ。構成員の大部分は、単に無差別殺人を犯したいだけのクズどもよ。軍人上がりとか、母国で猟奇殺人を犯した逃亡犯とか」
「誰にでも自分に合った職業が見つかる社会、ってわけか。ありがたすぎて反吐が出るぜ。でもどうしてSACはそれを止める?」
「そりゃあ、彼らは平和を何より愛する団体だからよ。主な活動内容をクロックワークの駆除に絞ってはいるけど、彼らの基本思想はテロリズムと大きく対立するものだわ。絶対に公表はされないけど、彼らがクロックワークの捜索をする過程で未然に食い止めた事件、壊滅させた団体は星の数。彼らの存在は、国際社会では"益虫”であるかのように扱われている。毒を以って毒を制す、平和の戦士たちという感じでね。そうやって、彼らはますます大手を振って私たちの駆除に精を出すってわけ。色んな筋から密かに多額の援助を受けてね」
「ふん、奴らは普通の人間たちにとってのダーク・ヒーローってわけか」
「笑えないジョークだけど、大体合ってるわ。非合法の組織として、歴史も規模もSACに匹敵するものはない。だけどこの時はSACの方が劣勢だった。テロを決行する日時が判明する前に手痛い返り討ちにあってしまい、その日が来るのを指を咥えてただ見ているしかなかった。やがてXデーがやってきた。SACは決行三十分前になってようやく場所を突き止めた。慌てて現場に駆け付けた彼らが見たのは、ブラックマジックがテロではなく、単に集団自殺をする場面。奴らは仲間同士で互いに殺し合いを始めた。殺されたはずの者が、起き上がって生きている者に襲いかかっていた。一般市民に怪我人は一人も出なかったわ」
「妙だな。大方、色恋沙汰のもつれか、取り分を巡って揉めてたんじゃねえのか」
「ドラマティックな展開が好きなのね。刺激を求めている女子にモテるんじゃないかしら、あなた。でも真実は、クロックワークが介入したということなの。SACよりも先に、奴らの動向を突き止め、その特徴を行使して自滅という形に追い込んだ。泰河くん、あなたがこの間やったことに、とてもよく似ているわね」
「死体が動いたってことか? ふうん、うちの家系と同じ特徴を持つ奴がこの世にいるなんて、そんな偶然もあるんだな」
「そんなこともあり得るでしょうね。確率は物凄く低いでしょうけど」
「……おいおい、待ってくれよ。親父はわざわざ外国まで行ってそんなことするような柄じゃねえ。じいちゃんはまだピンピンしてるけど、流石にそんな骨が折れることはできねえだろう」
「現場では、クロックワークと思しき人物が一人目撃されている。日本人の少女だった。私たちはその少女のことを調べてみた。まるでSACの手助けをしたみたいでその点は納得いかないけど、もし黒幕がそいつで、使えそうなやつなら仲間にしようと思ってね。すると、たまたま同じ時期に私たちが注目していたクロックワークの団体とその少女が結びついた。NPO法人むさしの子育てネット。育児サークルという名目にかこつけて、年端もいかない女児のクロックワークの膨大なリストを作成していた。少女は、そのサークルの幹部の娘だった」
「ほう。で、その女の子が黒幕だったって証拠はあるのか?」
「ないわ。だから長い間、様子を見ていた。そのうち同じような活躍をするんじゃないかと思ってね。だけど何の動きもなかった。どんなに素性や行動を洗ってみても、ただの中学生だった。今年高校生になったけど」
「なんだよ。ただ成長を見守ってただけじゃねえか。それに、本当に黒幕だったとしたら、むしろその子がこそが平和の戦士じゃねえかよ。まったくおめでたい奴らだな」
「無論それだけじゃないわ。あなたの母親は、私たちとは異なるアプローチで優秀なクロックワークを探しているように見えた。つまり、有望な才能を一本釣りでスカウトするのではなく、可能性のある若者を片っ端からあたっていくということね。私たちにとって、そんな動きをする者は邪魔でしかないけど、場合によっては手を組めるかもしれない。そう考えたのが、甘かったかもしれないわね。だから内偵者を送り込んで、サークルの目的を調査していた。この音声を聞いてもらうのが一番手っ取り早いと思うわ」
蛇が手元のパソコンを操作すると、ボイスレコーダーで録音したような女の声が流れ始めた。聞き違えるはずもない。その声は泰河の母親のものだった。
「……分かりました。そんなに言うなら、あなたには私の目的とクロックワークに関する秘密を先に打ち明けておきましょう。決して、口外しないようにお願いします。だけど、その前に私の問いに答えてください」
カヤは誰かと話しているようだが、相手の音声は処理されて消されていた。カヤが喋る声だけが、独白しているみたいに部屋に流れている。
「私たちが子供を産んで育てる。その子供たちが、また子供を産んで同じようにする。その繰り返しで、人間の社会は、いや生物の歴史というのは続いていくんです。そんな当たり前の営みができない世の中について、どう思いますか?
……私たちにはそんな権利はない。そう思いますか?」
会話の相手と、短くないやり取りがあったようだ。しばらくの間、音声が乱れていた。 「……この世界は、歪んでいる。私たちだけではなく、普通の人間にとっても。
……全ての生命に平等に権利が与えられているなんて、荒唐無稽なことを言いたいわけではありません。それは淘汰によって獲得する、あるいはソフトな言い方をするなら、分配されるものではないかしら。
……私たちは、滅びることなく、着実にその数を増やし続けている。その間に人間たちの科学は発達し、結果、物理的に人類を破滅に導きうる兵器が出来上がった。それは兵器ではなくもはや生活に欠かせないインフラとしても使われている。遠くない未来、最悪の事態が起こらないとも限らない。正直言って、私たち、いや人類全体にとって、この二十一世紀という時代がターニング・ポイントなんじゃないかと思っているわ。
……完全なネジの遺伝、同じ特徴の五世代から九世代に渡る遺伝。私たちが進化を完了させるには、それだけの条件が必要だと言われている。だけど進化というのは、ある種の突然変異によっても起こりうる。私はそれをうまく活用することで、進化を遂げようと考えているのです。
……それは厄災と希望をもたらすと伝えられています。もしかすると、旧人類との決別につながるのかもしれません。勿論そんなことになるのは、私だって辛い。だけど、先へ進むには多少の痛みが必要です。このままでは旧人類たちと共倒れにならないとも限りません」
そこまで聞いてから、蛇は一度音声を止めた。
「どう? 何か感想はあるかしら」
「何とも言いようがねえが、これまで知らなかった母親の一面を見てしまったって感じで、ちょっと気味が悪いぜ」
「それだけ? 今と同じような内容を、直接聞いたことはない?」
「いや、むしろ俺に対してあまりそういうことは話してくれなかった。完全なネジのことも、ゆうべ初めて知ったんだ」
泰河がそう言うと、デニムのオーバーオールを着たおっさんが立ち上がった。
「おい、それは本当かね。にわかには信じられん。少年、ちょっと見せてみてくれないか」
おっさんは、目をきらきらと輝かせながら身を乗り出して聞く。
「鈴木さん、無礼ですわよ。まず自己紹介をしてください」
蛇が、さらりと冷たく言い放った。
「おい、その苗字を軽々しく口にするのはやめてくれよ」
さも迷惑そうにおっさんは言い、泰河の方に向き直り恭しく手を胸に当てて言った。
「少年、失礼した。私は"猛獣使い”と呼ばれている。血に飢えし暗黒の獣の魂を、運命という名の舞台の上で紅蓮の炎と共に解き放つビースト・マスター」
「鈴木さん、いい年して中二病はやめてくださいね」
「ぬう。いいじゃないか。これがしっくりくるんだ」
女の子二人が、口に手を当てて笑いを堪えている。
「どうなんだ? 永劫の時を越えて繋がれた仲間同士、そこは確かめておきたいし、何より天空から舞い降りる蒼き天使の羽ばたきのようなその音色を、是非とも聞きたいのだ」
淳吾が、腕組みしてこちらを見ている。泰河がどうしていいか分からず往生していると、人形遣いが口を開いた。
「落ち着かんかい。道化も聞いたと言っておるんじゃ。ワシの耳がいささか古くなったからとて、よもや聞き違えるはずもあるまい。あれは、クロックワークの本能的な部分に訴えて来よるのか、まったくもって官能的じゃ。ワシなど、うちのばあさんがまだ若かった頃を思い出すわ。それより、このボウズの言っていることが嘘か誠か、見極めるべきではないかね? 団長は来んのか」
「一任する、と言われております」
蛇が淡々と答えると、人形遣いはケッ、と吐き捨てるように言って足を組んだ。
「どうかしら、泰河くん? お母さんの言葉を聞いて、何か思い当たることはない?」 「いや、何も無いな……。だけど」
「だけど、何?」
「まあ、あんまり不自然じゃないっつうか、いかにもこんなこと言いそうな気はするな。ほら、母ちゃんってちょっとエキセントリックだから」
泰河もあまり人のことを言えたくちではないが、若いころから世界中を放浪し、奔放に生きてきたカヤの感覚は並外れていて、常識と呼ばれるものや場の空気にとらわれない振る舞いを常にしていた。手料理なんて、各国の文化を好き勝手に取り入れ、もはや元々の料理が何か分からないくらいだった。
「そうね。特にここから先の内容は、まさにブッ飛んでるわよ」
手元のパソコンを蛇が操作すると、カヤの声が再び再生された。
「近親交配は、昔から忌み嫌われる行為とされてきました。ですが、兄と妹、あるいは姉と弟とで為される交配は、場合によっては通常の交配よりも、種が存続し進化するための条件に適するということが分かっています。実際にいろんな動物たちが、類人猿すらも一定の割合でこれを実際に行っているそうです。
……私たちクロックワークの社会においても、五世代を越えて同じ特徴を引き継ぐかもしれない交配と同様に、近親交配はタブーとされてきました。ヒマラヤのコミュニティでも、沖縄の呪術師たちのコミュニティでも、近親交配で生まれた子供は即刻殺されてしまうそうです。その理由がお分かりですか?
……そうです。同じ特徴を持ったクロックワーク同士が子を成せば、遺伝子に記憶された同じ先祖の情報が複雑に絡み合い、より強い特徴を備えることが出来る。人間の生物学の基準で言えば、四世代目の個体同士が交配すればその遺伝率は一気に九世代を越える。
……日本のイザナギ・イザナミをはじめ、世界各地の神話において、古代の始祖神とされるものの多くは兄妹の神様です。イシスとオシリス、アブラハムとサラ。それらの正体が、普通の人間ではなくクロックワークだったとしたら、どうです?
……ええ、確かに遺伝学的には理に適っていても、現代の私たちの道徳観念においては、そんなことはとんでもないと感じるのが普通です。身に付いたその感覚も、人類の進化の一部と言えるでしょう。私も、兄妹婚は決して許されるようなことではないと考えています。 ……だけど、人類は感覚だけでなく手先も繊細に、器用になりました。兄妹で結ばれることが社会的にタブーなのは変えられないとしても、要は遺伝子さえ濃くなればいいのです。産まれてくる子供の遺伝子を操作することくらい、倫理的には問題があるとしても技術的にはすでに可能になっています。
……いいえ。そんな人体実験紛いのことをしようというのではありません。
……そうではなく、それが≪私にはできる《´》≫のです。無理矢理つくりだした方法などではなく、私には自然とその能力が備わっている。誰から与えられたわけでもありません。ここまで言えば、もうお分かりですか」
蛇は、そこで音声を止めた。
「大事な内容はここまで。この音声を入手したのは、団員ではないけれど有能だった我々の協力者よ。そして二ヶ月前に、駿河湾で変わり果てた姿で見つかった。深海魚に内臓を散々食い荒らされてね」
部屋の電気が消え、プロジェクターから壁に向かって画像が映し出された。場所は船の上のようだが、魚釣り用の餌ではないだろう。もはや人の形をとどめぬ肉片が、大写しにされていた。
泰河は、思わず顔をしかめる。他の団員は、もう見たことがあるみたいで驚いたりはしていない。蛇の方を見ると、目をぎょろりとさせて、狂気じみた表情でこちらを睨んでいた。
「有馬カヤが行っているのは、十中八九"花嫁探し”。あなたの母親が"遺伝子を操作する”特徴の持ち主だとすれば、それで辻褄が合う。言っておくけど、タダでここから帰れると思わないことね。淳吾はやたらあんた達の肩を持つけど、もう私はあんた達を憎んでしまっているし、有馬カヤとサーカスの考え方に、歩み寄る点があるとは思えない」
蛇の前髪の生え際辺りが、逆立っている。ぴんと空気が張り詰めるのが分かった。顔は体温を感じさせない不気味な青白さを帯び、呪いの言葉を吐くようにして泰河に言い寄る。
「次は、あなたが知っていることを教える番よ」
6
名前を呼ばれたとき、美雪は自分が断頭台にでも登るような気持ちだった。
美雪は、何度も医師に聞き直した。結果は、何も問題がなかった。軽やかにスキップしながら病院を出て行こうとする彼女は、何度か看護婦に注意されたがそれすら耳に入らなかった。
美雪は夫にメールを打ち、駅前で買い物をしてから帰路につこうとした。お腹は膨らみ始めており、白いワンピースの上から一目で妊婦だと分かるがまだ日常生活に支障はない。
スーパーで今夜の食材を見つくろう。どうせ夫は、いつものようにしょぼくれた顔で帰ってくるに違いない。今日はとりわけ思いつめた顔をしているだろう。そして、検査の結果を尋ねるのだ。
どんなふうに打ち明けてやろうか。少し意地悪に、ずっと暗い表情をしているのはどうだろう。電気は豆電球だけにして、いかにもな雰囲気を演出してやろうか。
最後は、どうせ二人とも笑顔になるに決まっている。だから少しくらいやりすぎたって構わない。その分、夫が喜ぶものを今日はつくってやろう。美雪は型にはまった料理をつくるよりも、ありあわせの食材を組み合わせて料理をする方が得意だった。あまり余裕があるとは言えない家計のことを今日は気にしないで、夫が好きな食材ばかりを買い込んだ。
買い物袋を両手に下げて歩いていると、人気のない路地で柄の悪そうな男たちが老婆を取り囲んでいるのが見えた。スナックや風俗店が立ち並ぶ盛り場で、夜は賑わっているが昼間は散乱したゴミとカラスくらいしかいない場所だ。
異様な雰囲気を察知して、美雪はそちらへ向かっていった。
男たちは高校生くらいで、ろくに学校へ行ってなさそうな格好をしていた。煙草をふかしながら三人がかりで老婆を小突いて金を巻き上げようとしている。
「あなたたち、何やってるの。警察を呼ぶわよ」
美雪が声をかけると、斜めにキャップを被り、腐っているのではないかというくらい汚いスニーカーを履いた少年が、あっち行ってろ、邪魔すんじゃねえと凄む。美雪は臆することなく目の前まで近づいていった。
「これは俺のおばあちゃんなんだよ。いいから放っとけよババア」
明らかに嘘だったし、老婆は怯えていた。美雪は汚いあばた面の頬を思い切り張った。
少年たちは、美雪の気迫にひるんだようだった。老婆に駆け寄り、無事を確かめる。
そこへ一台の車がやってきて停まり、いかにも水商売をしてそうなけばけばしい女が窓から顔を出した。止めに来てくれたのかと思ったが、まったくの逆だった。
「グズグズしてないで、さっさと済ませなさいよ。やりすぎるんじゃないよ」
女が何を言っているのか、理解しかねた。次の瞬間、美雪は背中に大きな衝撃を受け、一瞬息ができなくなった。
少年が後ろから飛び蹴りをしてきたのだった。その場に倒れこみ、すんでのところで手を付いた。買い物袋の中身が散らばる。
車は、美雪がやってきた方角から、少年たちが人目に付かないように隠す形で停まっていた。
「あんたたち、一体」
言いかけて、美雪は拳で顔を殴られた。口の中に鉄の味が広がる。
「この人、妊婦さんだよ。やめとくれ。お金ならあたしがあげるから」
「ならさっさと出せよ、面倒くせえ」
ガムをくちゃくちゃさせながら、グラサンの少年が老婆の髪の毛を掴んで引っ張る。女は細長い煙草に火を点けて、涼しい顔で携帯をいじっていた。
少年たちは、保護者同伴で恐喝を行っているのだった。むしろ親が指図しているのかもしれない。頬を張られたことに激昂したキャップの少年は、猿のような叫び声を上げながら倒れている美雪に蹴りを見舞おうとする。美雪は、思わずお腹だけを両手で守った。腐ったスニーカーは、容赦なく美雪のこめかみに食い込む。老婆が声を上げて泣き始めた。
次に少年は膨らんだお腹に狙いを定めたようだ。美雪には周りがスローモーションのようにして見えた。こんなことで、と美雪は思った。こんなことで、この子たちは淘汰されねばならないのか。
朝は快晴だった空が、いつの間にか灰色に染まって今にも雨が降り出しそうだった。美雪は、少しだけ手を前に差し出した。
勢いよく振り降ろされたスニーカーは、少年の足首ごと美雪の頭を越え、飛んで行って車のドアにぶつかった。女が窓の下を覗き込むと、切断された膝下が転がっている。
ぺっ、と血を吐き美雪は立ち上がった。
少年は一瞬遅れて自らの身に起きた異変に気付き、ぎゃあと情けない声を出しながらうずくまった。他の二人は、慌ててポケットから折り畳みナイフを取り出す。
「まだ名前もないあなた。私が母親で良かった。街の汚いゴミどもは私がきれいに掃除してあげるわ」
美雪の手には、何も握られてはいない。片足のつま先だけで立ち、バレエのステップのような動きをした。
軽やかに、呆気にとられた少年たちの間を美雪は通り抜ける。手首から勢いよく血を吹きだして二人ともその場に倒れこんだ。純白のワンピースには、一滴の返り血も浴びていない。
「命は取らないでいてあげる。だけどもうこれまでと同じように世界を見ることはできないわ。こっちを向きなさい、クソゴミ共」
美雪は、くるくると回転した。芸術的なダンスの振付のように、両手を動かしながら。
それを目にした少年たちは、血溜まりの中で正気を失って涎を垂らしながらだらしなく笑いはじめた。
「あんた達に、名乗るような名はないわ。出血多量で死ぬ前に誰かに見つけてもらえば儲けもの。人気のない場所はあんたたちが選んだのだから。助かったとしても、一生精神病棟行きでしょうけどね」
車から降りた女が、恐怖の眼差しでこちらを見ている。
「あなたは母親か、何かなのかしら」
「そうだよ。てめえ、一体何してくれてんだよ」
涙目になりながら、精一杯の虚勢を張って言う。
「ゴミ製造機か。私たちの街にそんなものは必要ないわ」
美雪が再び舞うと、女も極彩色の夢の中に落ちていった。泡を吹いてどさっと倒れる。
いっちょ上がり、とでもいうように美雪は両手をぱんぱんと打ち払う。それから腰が抜けてしまった老婆を抱き起し、微笑みかける。
「おばあさん、大丈夫ですか? まったく災難でしたね」
「あ、ありがとうございます。あんたは一体」
「私はただの主婦。職場では"舞踏家”と呼ばれています。と言ってもこんなことを覚えておく必要はない。気を付けて帰ってくださいね」
老婆の前で、片足立ちになり手を上に上げてゆらゆらと動かす。すると老婆は半分眠っているようなぼんやりとした様子になり、とぼとぼと歩き去って行った。
美雪は乱れた髪を直し、散乱した荷物を拾い上げ、何事もなかったかのようにその場をあとにした。使えなくなった食材の分、今夜の献立を練り直しながら。
携帯に、職場から電話がかかってきた。人手が足りなくなりそうで、そろそろ安定期に入る頃だろうから少し手伝ってくれないか、という内容だった。美雪は、ぺろりと舌を出して答えた。
「まったく、人使いが荒いわね。まあいいか。ちょっと退屈だったし。久々に血を見たら、またやる気出てきちゃった」
7
「待ってくれ、うちの親があんたたちの仲間を殺したっていうのか? とてもそんなことがあり得るとは思えねえ。それに、母ちゃんが俺の嫁さんを探しているだと? 俺はそんなこと頼んだ覚えはこれっぽっちもねえぞ。馬鹿も休み休み言いやがれ」
「泰河くん、落ち着き給え。沙彩女史も、折角の美貌が台無しじゃないか」
淳吾が、二人の間に割って入る。蛇は、ヒステリックな金切り声をあげた。
「淳吾、あなたに何が分かるっていうの。麻里さんは私にとって母親も同然だった。加奈子もラビットも、沢山お世話になったじゃない。どうしてこんな奴の肩を持とうとする?」
場がしん、と静かになった。皆口を重く閉ざしてしまったようだ。どうやら、泰河の母親のせいでサーカスは深く引き裂かれつつあるらしい。
「とにかく、整理しよう。泰河くんのお母様は"遺伝子を操作する”という特徴を持っている可能性がある。どうだい? そのことは知っていたかな?」
「いや、それが特徴のことはまったく教えてくれたことがねえんだ」
「ふむ。一体どんな特徴をお持ちなのだろうか」
「俺も気になって一度しつこく聞いたら、自分でも分からないんだってはぐらかされちまった。もしかしたら、母ちゃんは実は普通の人間じゃないかとすら思ってたんだ。逆に聞くけどよ、そんなクロックワークがいるのか。何の特徴も持たないような」
「いや。あらゆるクロックワークは遅くとも第二次性徴の前後に、必ず何かしらの特徴が発現する。ネジ自体の発育が遅れていたり、生殖に関わるホルモンに異常があったりすると、稀に成人してから発現する場合もあると聞くが。ふむ……団長が言っていた通り、妊娠出産という体の変化をきっかけにして特徴に目覚めたという可能性もあるな。母は強し、というやつだ」
「嘘をついている可能性もある。仮に真実だとしても、どのみち少年の母親を団長に会わせればすぐに済む話ではないかね」
「鈴木氏、物事をあまり短絡的に考えるのは問題ではないか。有馬家が人類にあだなす存在と決まったわけではないし、これはサーカスの理想に大きく近づくチャンスかもしれないのだ。泰河くんが完全なネジを持っていると分かったならば猶更、慎重に行動すべきだ」
「むう。生意気なヒヨッコめ。先代の顔を立てて好き勝手言わせてはいるが、あくまでも新入りだということをわきまえよ。それに私のことはビースト・マスターと呼べ」
「承知した、ムッシュ。だがサーカスの意思決定は、対等な立場の全団員による評議制であろう。なにも私はでかい顔をしているわけではない」
何やら言い争いが始まりそうな剣呑な雰囲気になってきた。人形遣いが渋い顔をして、口髭をいじっている。蛇は相変わらず殺気立った視線を泰河に向けているし、手品師とラビットは悲しそうな表情で俯いている。力士のような男は、腕組みしたままで何を考えているのか分からない。
そこへ、扉を開けて何者かが入ってきた。全員の視線がそちらに向き、場の雰囲気が一変した。
「団長、我々に一任すると言われたはずでは」
現れたのは、ホテルマンのようなきっちりしたスーツに身を包んだ老人だった。
「いやいや、やっぱり心配でねえ。居ても立っても居られなくなったのだよ。年寄りの冷や水というやつかねえ、グハハ。沙彩ちゃん、どうしてそんな怖い顔をしているのかな? そんな調子では、君ではなくこの花の方が主役になってしまうよ」
黒い蝶ネクタイを締めて、ふさふさと豊かな顎髭を蓄え、サングラスをかけている。言葉は流暢だがどうやら日本人ではないようだ。片手にステッキを持ち、長い白髪を後ろで束ねている風体は、粋というか非常にファンキーだ。
団長が手を空中に伸ばすと、その指の中にどこからともなくピンク色の一輪の薔薇が現れた。
「……お見事!」
手品師が声をかけると、それが合図であるかのように団員は揃って拍手を始めた。団長は、ご満悦のようだ。蛇がしぶしぶ花を受け取る。してやられた、という顔をしているが、薔薇を手にすると幾分表情は和らぐ。
「もう、誤魔化さないでください。相変わらず、口がお上手なんだから」
「言っとくが、今のは淳吾君に手伝ってもらったわけじゃないぞ。サーカスの団員である以上、これしきの手品は全員当たり前にやってもらわんといかん」
力士のように図体のでかい男が動いて、団長の分として泰河の向かいの椅子を引いた。
「どうだ、ベア。お前もいい加減これくらい出来るようになったか」
「いや。どうにも」
「なんじゃ。精進しろよ。ラビットちゃんだってもうこれくらい出来るんじゃから。だがお前のバカ太い指では、ちっと難しいかもしれんな。それにしても、また一段とでかくなったんじゃないのか? 流石はビースト・マスターの息子じゃのう。グハハハ」
団長が豪快に笑うと、他の団員もつられて笑い出した。ベアと呼ばれた男も、口の端がわずかに上がっているようだ。
団長に無理矢理合わせているというわけでもなさそうだ。その老人には、人を楽しませるという天性の才能が備わっているかのようだった。先程までとは打って変わって、楽しいパーティみたいな雰囲気にあたりは包まれている。団長の一挙一動が、場を明るくする気がした。
淳吾が、泰河の傍に寄ってきてそっと耳打ちする。
「いいか。団長の前では決して嘘をついてはいけない。些細なことでも駄目だ。絶対に本当のことだけを言うんだぞ。さっき忠告したことも含めてだ。必ずだよ」
一体どういうわけなんだ、と泰河は聞こうとするが、もう淳吾は素知らぬ顔をして他の団員と同じように団長の方を向いてしまっていた。
「さて泰河くん。初めまして。私がこのサーカスの"団長”だ。お近づきのしるしに、この老人と握手でもしてくれんかな」
団長はテーブル越しに手を差し出す。その手は血色がよくつやつやとしていて、年齢を感じさせなかった。淳吾は団長のことを恐ろしく長生きだと言っていたが、人形遣いなんかよりよっぽど若々しい。
「ちょっと待ってください、団長。何をするおつもりです」
淳吾が、慌てて立ち上がって言う。
「なあに、心配せんでもいい。男と男の、単なる魂の触れ合いだよ。どうした、泰河くん? 私が怖いかね?」
まるでギャングのボスみたいな風体だが、泰河にはこの老人が怖いとも悪い人だとも思えなかった。泰河は、ためらうことなくその手を握った。
泰河が手を放そうとすると、団長は強い力でぎゅっ、と拳を握り返してきた。意表を突かれて戸惑う。かなり強い握力を持っているようだ。思い切り力を込められたら、泰河の細長い指はひとたまりもないかもしれない。周囲に、緊張が走る。
「泰河くん、これから聞こえる音を、耳にしたことがあるかね? なんでも、君もこれを奏でることが出来るらしいが」
すると、団長の後頭部辺りからキリキリ、という音が発せられた。
目の前の老人の肌が、さらに生き生きと赤みを帯びていくような気がした。他の団員は皆、うっとりと聞き惚れているようだ。泰河には、聞き慣れたその音に特段の感慨は湧かなかった。
「ああ。俺もそれを奏でることが出来るぜ。俺の美的感覚がずれてんのか、そこまで大層なものだと思ったことはなかったが」
ありったけの握力を込めながら、泰河は言う。にやっと笑いながら、団長は力を緩めて手を引っ込めた。
「ふむ。まさか君は、不感症ではあるまいな。健康な若いもんがそんなことではいかんぞ。私が若い時には、それは多くの女性と濃密な一夜を過ごしたものだ。東洋の繊細な柔肌もいいが、白人のアグレッシブさは、一度味わったら病みつきになる」
蛇が顔を赤らめながら、こほんと咳払いをして言う。
「団長。その、ラビットと手品師のような女子もいるものですから、教育上あまりよろしくないかと」
当のラビットは、セクハラまがいの発言にひるむことなく、むしろ意味ありげな笑みを浮かべていた。加奈子は、かあっと顔を赤くしてしまっている。
「おお、すまんすまん。デリカシーに欠けておったわ。棺桶に半分足を突っ込んだ年寄りの世迷い事と思ってくれ。しかし、ラビットはどうやら興味津々のようだぞ。まさか私や蛇の目を盗んで、泰河くんに色目を使ったりはしておらんだろうな。ちと早すぎる気もするが、仕方ない気もする。何せ、ネジの音はクロックワークの女性を口説くのに効果てき面じゃからな。昔はこの手をよく使ったものよ。……いかん、また似たような話に戻っちまった。グハハハハ!」
流石に全員爆笑とまではいかないが、豪快な笑い方につられて、みんな笑顔になってしまう。蛇と加奈子は相変わらず赤面したままだった。
「泰河くん。君はお母さんの行動について、何も知らんのじゃな? 父上は流石に何か知っているのではないかと思うが、今思い返してみて何か気付いたことはないか? 正直に教えてくれ」
淳吾が、怪訝な顔つきで泰河の方を見ている。頼むから正直に答えろよ、とでも考えているのだろう。
確かに団長は、嘘など簡単に見抜いてしまうのではないかというような気迫を内に秘めていた。だが、いくら考えてみても先程の母親の会話が、本当にあったことだとは信じることができなかった。
「俺だって、あまりにも唐突な話ばかりで、まだうまく頭が整理できてねえんだ。でも誓って言うよ。俺は何も知らないし、両親はあんたたちが思ってるような人間じゃないぜ。確かに、母ちゃんは何をしでかすか分からないような雰囲気を持ってるけどよ。なんか、うまく言えねえがきっと誤解があると思うぜ。でもどうやら、あんたたちはタダで俺をこっから帰してはくれねえみたいだ」
団員たち、特に蛇と猛獣使いは訝しげな視線を泰河に向けていた。
「それは君次第だ。我々サーカスの目的は、すでに聞いたかな?」
「厄災と希望をもたらすクロックワークを見つけるんだろう。旧人類との共存とやらのために」
「よく分かっているではないか。どうかね? この中にお気に入りの子はいるか」
団長の言葉の意味が分からずに、泰河はきょとんとした顔になる。
「だから、好みのタイプの女の子はいるかと言っているんだよ。お節介なママが連れてくるどこぞの馬の骨ではなく、この中の誰かと君が≪つがい≫になれば、我々にとってこんなに喜ばしいことはないのだがね」
泰河の顔は、一瞬で真っ赤になった。
「ば、馬鹿言ってんじゃねえ! つ、つ、つがいだと? それは、子供をつくれってことか?」
思わず泰河は、三人の女子の方を見てしまった。
蛇は、急激に機嫌が悪くなって泰河を睨みつけている。年齢は離れているし、性格もきつそうだが大人の色気があるし、もしも打ち解ければ泰河にとっては包容力があるような気がした。
ラビットは、あまりに子供過ぎてとてもそんな対象になるとは思えない。だが、まるでフランス人形のような顔だちをしており、芸能人だと言われてもおかしくない。あと数年もすれば、見違えるようになるだろう。
加奈子は、泰河と同じくらいうろたえてもじもじとしていた。いささか変わった格好をしているが、ちょっと昔の日本の女優のような、素朴だが凛とした顔をしている。阿理沙にも負けないような白い肌がほんのりと赤くなっているのは、見ているだけで泰河の動悸をさらに早くさせた。
思わず、加奈子と目が合う。視線が重なったことに気付いた二人は、磁石が反発するように慌てて別の方向を向いた。
団長が、とてもいやらしい目つきでニタニタと笑う。
「そうかそうか。年も同じくらいだしな。お似合いだ、うん」
「な、何言ってやがる! 人を馬鹿にするのもたいがいにしやがれ」
「その反応を見ると、童貞だな、お前」
団員たちの間に、どっと笑いが起こった。湯気が立つのではないかというくらい泰河が赤面してわなわな震えていると、団長が泰河のそばまで歩いてきて、ぽんと肩を叩いて言った。
「泰河くん、そろそろ家に帰らんと親御さんが心配するだろう? 帰りたまえ。ただし、君とお父さんには監視をつけさせてもらう。そして、君はサーカスの一員として、両親のことを調べてもらう。それが我々の条件だよ。いいな?」
蛇が、何かを言いかけようとしたのを団長は手を上げて制する。
「おい、俺にスパイになれってのか? 実の親に対して」
「そんな人聞きの悪いものではないよ。要するに、親御さんが何をしているのかを正確に教えてもらいたいのだ。結果はどうあれ、団員の家族に我々は手荒なことはしない。サーカスというのは、大きな家族のようなものだからな。賛成するものは、挙手をせよ」
淳吾が迷わず手を挙げた。それを見て、ラビットも小さく手を挙げる。だが、賛成したのはその二人だけだった。
「よろしい。では決まりだ。いつでも世の中というのは、少数の意見の方が正しいのだからな。では解散!」
ちょっと待てよ、と泰河は叫ぶが、団員たちはもう立ちあがっている。
加奈子は、小走りで部屋を出て行った。ラビットがそのあとに続き、泰河の横を通るときに背中をばちんと叩いた。
「脈は大アリだよ。うまくやんなよ。ラブ・アンド・ピース」
「なっ……」
「良かったな、泰河くん。共に頑張ろうではないか。まずはお母様たちの行動を明らかにすることが先決だが」
淳吾が晴れやかな笑顔で声をかける。手を差し出してきたので、仕方なく泰河は握手を交わした。何とも言葉の選びようがない。
背後に、蛇が忍び寄っていた。目を合わせなくても、痛いほどの視線を感じる。
「団長、まさかこいつを本気で団員にするわけじゃないでしょうね。有馬カヤの調査が終わるまでの辛抱だと考えていいのかしら」
「それは泰河くん次第さ。きっと我々の理想を分かってくれるだろう」
深くため息をついて、蛇は言う。
「分かりました。全く納得はいきませんが。それから、人員の補充。美雪さんがそろそろ安定期に入るはずなので、声をかけておきましょうか」
「おお、そうしてくれたまえ。"純白の血塗れ淑女”の舞がまたそろそろ見たくなってきた」
「はい。ところで、こいつの呼び名はなんとしましょう」
団長は、泰河の顔をじっと眺めて、言った。
「犬、でいいんじゃないか」
誰もいなくなった広間に、団長は一人で座っている。そこへどこからともなく、足音も立てず一人の男がやってきた。
男は、団長が誰にも知られず独自に雇った探偵のようなものだった。裏の世界でちょっと名の知れた、便利屋のクロックワーク。通り名をイチジクといった。
サーカスからも何度か依頼をしたことがあるが、あくまで仕事上の付き合いでしかない。それに、血生臭い世界の住人と接触することは最小限に留めるよう団長自身が命じていた。
「流石プロ中のプロ。時間に正確だな。で、どうじゃった」
「はい。特に団長が心配されているような事実はありませんでした」
鞄から書類を取り出して、イチジクは調査結果を淡々と報告した。金さえ出せば殺しでも何でもやるし、失敗もしないし依頼人の秘密も決して洩らさない。値は張るが、イチジクの仕事ぶりには定評があった。
「短期間で、よく調べたものじゃな」
団長は手を差し伸べた。二人は互いに満足げに握手を交わす。
「ありがとうございます。ギャラを三割増しでいただけるとのことだったので」
「商売のうまい奴だ。まさか、この件で他のところからも同じように報酬を得ているわけではないだろうな」
「ハハ、ご冗談を」
「いや、実は冗談を言っているわけでもないのだ。君の丹念な報告を聞きながら、妙な胸騒ぎを感じてな」
「それは一体、どういう意味で?」
「うん、どうも年を取ると余計なことに気を回しすぎてしまうようだ。年寄りの冷や水といったところかな。グハハ!」
豪快な笑い声に、男もつられて声を上げて笑った。
「で、どうなんだ? この報告書には、本当のことが書いてあるのかね」
「それは勿論。誓って真実ですとも」
イチジクがそう言った瞬間、団長の口から赤黒い舌が長く伸びて、目にも止まらぬ速さで男の口めがけて吸い込まれていった。
それが引き抜かれると、先端には引きちぎられたイチジクの舌がくっついている。男は血を吐いて、一言も言葉を発することなく倒れた。
長く伸びた舌は、鞭のようにしなったかと思うとしゅるしゅると収縮して団長の口の中に元通り収まる。イチジクの舌だった肉片が足元に転がった。
「可哀想に。別に地獄でなくとも、嘘つきはこうなる運命よ」
ぴくぴくと痙攣するイチジクを抱え起こし、血を止めるために口に綿を詰め、椅子に座らせる。
「私は"嘘つきの舌を即座に引っこ抜く”という特徴を持っている。嘘を感知して勝手に舌が伸びる。自分でも抑えることができんのだ。すまんのう。どうか、知っていることを紙に書いてくれんか。もう抜く舌もないが、正直になってくれれば手荒な真似はせん。心配せんでもいい。舌はもともと再生力が高いんじゃ。クロックワークともなれば、またそのうち生えてくる」
団長はイチジクの手を包み込むようにして、無理矢理にペンを握らせる。イチジクは拒否しようとするが、団長の細腕は見た目とは裏腹にかなりの筋力を持っているようだ。
イチジクは声というより奇妙な音を出しながら苦しそうに喘ぐ。その眼には怒りと当惑とが入り混じっている。
「どうした? さっきから何故特徴が行使できないのか、と考えているのかね? 舌を抜かれてもまだ戦おうと? 見上げた根性だ」
席から立ちあがろうとするが、団長の手は力強くその肩を押さえていた。
「さっき握手をしたとき、すでにそれは封じさせてもらった。もう一つの私の特徴は"クロックワークが特徴を行使できないようにする”というものなんだ。今は一時的に封じているだけだが、もう二度と行使できなくすることも出来る。そんなことになれば、商売に差し支えるだろう? いきなり舌を抜いたのは悪かった。だがさっき言ったようにやりたくてやったわけではないのだ。友好的に行こうではないか。嘘偽りない真実を教えてくれ」
イチジクは観念したように俯き、震える手で書いた。だがその眼の光は、まだ衰えてはいなかった。
「腐ってもプロだ。元々の依頼人は売れねえ」
「そうか。すでに先手を打たれていたというわけだな。世間は狭いのう。もしかすると、依頼人というのはこいつではないのかね」
団長は一枚の写真を取り出し、苦しそうに息をしている男に突き付けた。イチジクの震えが、止まった。
「どうなんだ。イエスかノーではっきりと答えてもらおう。物事はいつでもハッキリシャッキリとしなければならん」
イチジクは覚悟を決めたようだった。迷いなくペンを動かし、団長に向かってニヤッ、と笑ってみせた。
団長はサングラスの奥で少し悲しそうにしながら、書かれた文字に目を向けた。
「そんな奴は知らねえ」
読んだ瞬間、団長の舌が伸びて再び男の口の中に収まる。それが探している器官はすでに存在せず、そのまま奥の方、脳髄まで突き抜けていった。
ネジごと首を貫かれて、イチジクは絶命した。
「流石はプロ中のプロ、といったところかの。しかしこの私を欺こうとするなど、いささか調子に乗りすぎたな。惜しいことをした。地獄で会おうぞ」
着ていた上着を死体に被せて、椅子に座り直す。そして写真を眺め、ため息をついた。キリ、キリとゆっくり廻るネジの音が静かな部屋に響いた。
「家族同士で欺きあわねばならん。この世もまた、地獄のようなものだがな」
クロックワーク(上)
2014/7/30 初版公開
ラノベを書こうと思って書きました。


