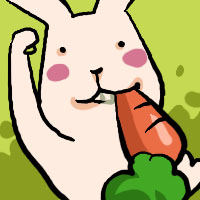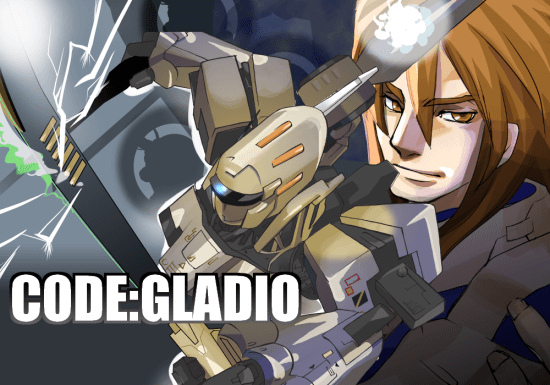
CODE:GLADIO/0章・存在しない娘
1章・1―テシマ立てこもり事件の発生『アクムノハジマリ』
追手は突然暗闇から現れた。
執拗に彼女を追いたてる「何者か」を振り切ろうと、少女は見知らぬ回廊をただ闇雲に走り続けていた。
甲高い靴音、ひたすらに続く暗くて狭い、そして終わりのない迷路。あの精気を失い、死んだ魚の様に虚ろな眼の「何者か」が何の目的で自分を追いかけてくるのか、理由もわからないままに。
「…アヤセ………ッ!」
さっきまで一緒にいたはずの友とは、夢中で駆けている内に逸れてしまっていた。そうとわかっていながらここまで何度この名を呼んだだろう。翼のある彼女ならもうどこか安全な場所を見つけたかもしれないという淡い希望と、もしかすると「何者か」の手に掛った後かもしれないという大きな不安が胸中を埋め尽くす。
息はとっくに切れ、形だけでも必死に吸い込む空気はもはや乾ききった肺の奥まで届かない。出会いざまに「何者か」に締め上げられた際の首元の擦り傷が、脈打つのに合わせてズキズキと痛んで、まるで首輪でもかけられたように呼吸を妨げている。視界はぼやけ、もはや手も足も感覚を失いはじめている。
「誰か助けて、アヤセ、母様…」
背後にべっとりと張り付いたままの寒気がはたして追っ手の気配なのか、それともただ狭い回廊に木霊する自分自身の足音なのか、確かめようにも自由が効かないほどに彼女は疲労していた。どこへ行けば助かるのか、いつまで走り続けるのか。ただわかっている事は、「あの女にだけは絶対に捕まってはならない」という事だけだ。そういえば「何者か」が「あの女」だといつから気づいていたのだろう。顔を確かめただろうか、それともただの思い込みなのか、記憶は朧気だ。
やがて夢と現実の区別もままならなくなってたいぶ経ったころ、ついに両の膝が折れ、少女はよろよろと前へとつんのめった。もはや限界だった。
今度倒れれば再び走り出す事はもうできないかもしれない。絶望感が胸をよぎった時、彼女は背後からひどく大きな力で突き飛ばされた。軽い身体は簡単に宙を舞い、二度三度地面に打ちつけられてからようやく止まった。そのさなか背中を強打したせいで肺が押しつぶされ、視界が急激に白んでいく。そんな霞の中現れたのは、彼女の思う虚ろな眼をした「あの女」の顔だった。少女はありったけの声で悲鳴を上げたが、女は表情一つ変えぬまま再び彼女の視界から消えていった。
代わりに現れたのは、あまりに大きな人の顔。
しかしその大きな眼孔には目玉の代わりに醜悪な形のガラス玉がびっしりと詰まっており、耳元まで裂けた口には歯がなく、顎から生えた突起は皮膚を破り異様な角度で斜め下に突き出ていた。顔色はすこぶる悪い。彼らには温かい血など一滴も通っていないし、追い詰めた獲物を憐れむ心もない。そもそも人殺しの為だけに作り出された戦争人形”重機歩兵”に心などないし、人間を模した頭部など彼らには何の意味もない器官だという事くらい少女も知っていた。
少女は薄れゆく意識の中、これを死神と重ねる。これが本当の死に際であれば、いくら残酷であろうと心を持った死神に立たれた方がまだましだとさえ思う。
魂を一つ刈るのにはあまりに大きすぎる大量破壊兵器を前に、少女は己の末路を覚悟した。
1章・2―最果ての地テシマへ
テシマ島―
地球連邦国領東方、サウスデリフォート州の州都テシャンからさらに南東へ約百五十キロの海岸沖に浮かぶ島の名称だ。
それは島より半島と言った方が正しいかもしれない。大陸とテシマ島の境の海は、まるで巨大な運河のような形状をしていた。人工的に作られたものなのかそうでないのかは、新旧暦を挟んだ今となっては知りようがない。かつてこの付近を極東アジアと呼んだ時代には、このテシマ島にも多くの宇宙移民船の造船場が軒を連ねていたとある。しかし宇宙入植計画の終了からすでに一世紀近く経った今、そこにあったであろう建造物は見る影もなく風化し、あとは太平洋に面して切り出された複雑な浮きドック跡だけがその時代の面影を残すのみだ。
ビルのそのまた上にビルを立てたような、密集し、ひたすら上空へと発展し続ける都市とは違い、テシマはただ平たく、旧世界の情景を今に伝えていた。
地球連邦国東方面軍・第8特種重機歩兵部隊、「ユニットE81」がこのテシマ島付近に到着した時には、すでに時計は翌日午前0時を回っていた。
今はそのユニットとやらの姿はどこにもなく、人影がただ一つ、月明かりすらない荒野に佇んでいた。真夜中だというのにヘッドセットから色の濃いバイザーを目深に下げたままで、歳は二十代半ばだろうか。正規軍と思しき装甲服を身に着けているが、頭髪は長く肩にまで届いている。大柄なシルエットは女性のものとは程遠く、軍隊の事情に通じる者であれば彼が「特種兵」だと即座に見抜くだろう。
男はクラノス=H=ロータスクルーソ中尉、ここテシマまでユニットE81を率いてきた第8特種重機歩兵部隊の指揮官だった。
東方面軍の指揮官としては若い部類に入るのだが、E81の年間出撃回数は重機歩兵部隊全体でも突出していた。戦場指揮の経験は多い方だと言っていい。しかし重機歩兵の高度な索敵機能に頼り、膨大な税金と迷彩信号を辺りにばら撒きつつ行う進軍とは、今日はわけが違った。テシマの平坦な地形もあって、手ごろな隠れ場所が見当たらない重機歩兵輸送機の隊列とはずいぶん遠くで別れ、ひたすらに歩いてきた。コストはまずまずなはずだ。
「一人で遠足だと、何が楽しくて…」
仲間に吐き捨てられた激励の言葉を反芻しながら、クラノスは寒空の下を一人行軍を続けた。
平時なら他の兵科が寄り付かぬような陰惨で危険極まりない戦場で、人語を解するかもわからぬような人種とどちらかが動かなくなるまで戦っている頃だ。別に戦場が懐かしいだとか、歩くことが苦だとか言いたいわけではない。むしろ今の彼にとって一人で輸送機から離れられる事は好都合だし、視界が開けて輸送車両が目立ってしまう事によって、逆に置いていく理由を仲間にとやかく聞かれる煩わしさも省けた。
彼の足取りを重くしている本当の理由は、基地のいかれた連中と自分以外に知る者はいない。それは昼間のソープオペラのようなまどろっこしい仕事だった。そんな任務を押し付けられるくらいなら、いつもの生きるか死ぬかの果し合い(地球防衛)をしていた方が、やはりずいぶんと楽だ。
深夜に東方面軍第3の基地であるサウスデリフォード基地の基地を出発、管轄内南端にあたるここまで最速の大型輸送車両でも一刻強かかった。
この最果ての地、テシマもかつては巨大武器商が別宅を構え、大勢の関係者が島から溢れんばかりに暮らしていたという。武器の流通に始まり、ついには重機歩兵の開発製造を手掛ける一大企業にまでに成長した「井更一族」の栄華は、テシマだけにとどまらず、かつて宇宙連合だった頃の東大陸群に巨額の金と仕事をばら撒いた。彼らの陰と陽の歴史を知らぬ者おそらくこの太陽系にはいないだろう。しかし彼らが滅亡に至るまでの流血の一年を記憶している者は、もう少なくなりつつある。
一族が去り、数十年の月日がたったテシマ島は、もうすでに「忘れ去られし瓦礫の島」となっているはずだった。
だがここへ来て、その情報にクラノスは疑問を抱かずにはいられなくなった。
対岸の砂漠とは一転し、テシマはうっそうと茂る雑木林に覆われていた。時々手入れのいきとどいていない石灰質の大地が顔をのぞかせているが、そのわずか数キロ先に大きな光源が見えるのだ。町と言える程の大きさではないが、それはいくつもの灯りが集まって、まるで何かの催しの最中のようだった。光は時に揺らめき、そこに人の存在がある事をはるか遠くにまで知らせている。放棄されて久しいテシマには昼間は土壌の汚染物質を好んで吸い上げ、日がかげると酷い悪臭を放つと言うゴートパインが群生すると聞いていたが、そんな場所で今人が活動している。
「一体どういう事だ」
事件現場となっている「旧井更家別宅跡地」はここから更に数キロ先、島のほぼ中心にあるとの情報を得ている。その光はクラノスの立っている小高い丘と、現場の丁度中間くらいにあった。
周辺はすでに数日前から州警察が入り規制線を張っている事は承知している。中では犯人が太陽系最悪の兵器、重機歩兵を持ち込んだ上に、そこにいた住人を人質に立てこもっているらしい。駆けつけてはみたものの、重機歩兵相手に手も足も出ない警察が東方面軍に助けを求めたという話だが。
いくら人数を動員したところで、人間が重機歩兵にかなうわけがない。
「警察め、大人しく応援を待っているかと思いきや、まさかのお祭り騒ぎか」
クラノスはバイザー越しに眉を顰め、こめかみに右手を当てる。しばらく考え込むようなそぶりを見せたが、再び歩き出し、速足でその場を去った。
1章・3―交錯する思惑
『テシマ島の旧井更邸別宅跡に重機歩兵で武装した容疑者が一名ないし複数名侵入。
そこに休暇で訪れていた会社役員とその家族を人質に、敷地内に立てこもって一日以上が経つが、犯人の武装が厳重な事から警察が踏み込めず。人質の体力を考慮すれば一刻も早い救助が望まれる。
現在のテシマ島はほぼ無人の状態であり、周辺住民への避難誘導や戦闘区域の確保などは必要なく、至急容疑者同等かそれ以上の武力をもって、人質の安全を確保できるだけの応援を要請するものである。』
―新暦178年8月25日、19時15分―
ここで話は一度、東方面軍第8特種重機歩兵部隊(E81)がテシマ島へ向かって立つ前の時刻へと遡る。
サウスデリフォード基地の頭脳ともいうべき、センターオペレーションタワーにクラノスが呼び出されたのは、運悪く当直最終日の終わりがけの時刻だった。直後に受けた出撃指令の内容は大元はだいたいそんなものだったとクラノスは記憶している。同等だろうとそれ以上だろうと、ここで思いつくものといえば重機歩兵以外にない。容疑者の武装を思えばそれは当然の要請だった。かの全長十五メートルをゆうに超える凶暴な殺戮人形が仮にそこで戦闘でもはじめようものなら、旧式兵器では手の打ちようがない。他の物の侵入を拒む「亜空間」を作り出し、あまつさえそれを戦場とする重機歩兵の存在はそれほどに「特異」なものだった。そんなものが民家に押しかけたとあればもはや気の毒としか言いようがない。
しかし警察が真っ先に要請を打診した第1重機歩兵部隊はすでに他の用事で出払っており、出撃可能な隊が一つも残っていないと言う。さっきコネクションタワーの廊下を悠然と歩くユニットE12のカール=ザイアス中尉とすれ違った気がするのだが、あれは幻か何かだったのだろうか。
「…つまり、また第8が動くしかないという事ですか」
不自然な沈黙の間にせっつかれるようにして、クラノスは何とか言葉を発した。行儀よく疑問形を選択したが、相手の答えは最初からわかりきっていた。むしろ、わざわざもったいぶった理由を聞かされる方が時間の無駄だ。八ある方面軍の兵科の内、重機歩兵科は従来より存在する第1と、アトロフィクシス兵で構成される新設の第8特種とがあるが、この場に呼び出されたのは第8特種重機歩兵部隊の指揮官であるクラノス一人だけだった。
別段驚きもしない。だいたいどこかに警察という文字が一つでもあろうものなら、第1が動く事などないに等しいからだ。彼らいわく、重機歩兵とは神の与えし偶然を人類の英知が形として成し得た究極の兵器であり、それを扱う先鋭部隊を動かす際には大局を見据える器と丹力が必要だそうだ。時代の寵児。最新兵器との偶然に近い適性、それに個別の戦闘に耐えうる強い精神力を持つとこうも人間は尊大になるのかとクラノスは思う。だがその強大な力は国策の裏付けがあって初めて行使できる、という公共精神には大いに賛同したい。
それでも現実は一つではない、クラノスはそう考える人間の内だった。むしろ東方面軍の抱える問題は国策云々より足元に山積しており、一つ一つは小さくとも積もり積もれば足を救われてしまう。まさに今回のように一市民が起こす小さな反乱もその一つだと考えていた。
「君がこの手の仕事を嫌っているのは知っているが、他に頼むわけにはいかなくてね」
目の前のいかにも高価で座り心地の良さそうな椅子に腰かけた男は、そう言うと、ゆっくりとした動作で高い背もたれに上半身を預けた。「君が」と言われればあえて異を唱えたくもなったが、相手の眼光は鋭く、その隙すら与えようとしない。男はエドワルド=ロッシュ少佐、地球連邦国中央軍・方面軍統括本部の特種隊監査官だった。
たかだか少佐といえど、東方面軍での彼の立場は全く異なった。中央軍は地球連邦国軍が発足して最初にできた主幹組織で、方面軍は膨らんでいく連邦国の規模に対応する為、追ってできた後発の組織だ。今では方面軍の各部隊の指揮系統の長は方面軍大将だが、それでも中央の力は絶大だった。そして特種とつく部隊にだけは今も中央軍の影響を強く残し、こうして規模の小さな我ら第8特種重機歩兵部隊にすら専門の士官が送り込まれてくる。おかげで中央の士官が方面の基地内をうろつく結果になり、方面軍将校達にしてみれば中央士官も、彼らを引き寄せる特種部隊もどっちも同じ目の上のタンコブだ。徐々に方面軍に移譲されつつある本土防衛システムだが、上に中央軍ありきの体制はこの先しばらくは続くと見える。
そしてこの中央軍兵ロッシュもまた、その発言の端々に決して方面軍兵士の逆らう事のできない絶対的な権力をちらつかせる人間の一人だった。
もう四十は過ぎているはずだが、ロッシュは未だに綻びを知らぬ精悍な顔立ちと風格を備えている。まさに中央軍士官の見本のような男だった。しかしそれが仇となり、クラノス以下第8特種重機歩兵部隊の人間は必要以上に彼と接触しようとはしない。制服をとにかく青一色で統一された東軍の兵士の目には、艶のない漆黒の生地に繊細で上品な銀細工を施された中央軍の制服がいささか嫌味にも映るのかもしれない。当然向こうのロッシュも監視すべき部隊と慣れ合う気などさらさらないようで、今日もこうしてクラノスとの言葉遊びを終えれば早々とここを後にするだろう。
「州警察長官の話では、容疑者がテシマの旧井更邸に侵入したのは今日の明け方だそうだ。どうやら新しい家主はその時まだ就寝中だったようでね、容疑者達が重機歩兵を持って乗り込んだ物音にも気付かなかったらしい」
含み笑いの後ロッシュが小さくうなずく。それを合図に隣の事務官が手元のディスプレイを操作し始めた。美しい顔立ちで要所に肉付きの良い彼女もまたロッシュ同様の黒ずくめで、今日が初めての顔だった。以前は似て異なる別の側近を連れていた気がするが、まあそういう事なのだろう。
間もなく幾つかの画像が空中投影式によって三人の周囲に映し出され、事務官が指先で弾くようにして寄越したのは目標のテシマ島の全体地図だった。クラノス達は州軍基地への定期巡回中に何度も上空を通過しているのだが、陸路を行くとすればこれが初めてだ。平坦な線で描かれただけの地図だけでは情報が足りない、クラノスは航空写真の追加を求めた。
「これで旧井更邸の位置は確認できます、が、この無人島に新しい住人とは?」
地図と航空写真を見比べながら、クラノスは素直な疑問をぶつけた。
なるほど、航空写真からも昼ならばはっきり確認できるほどの広大な敷地だが、この別宅を所有していた井更家はすでに離散しており、それらを維持する財源だった井更重工も倒産して久しい。まだこの別宅が使用されていた時には、おそらく島全体に屋敷に関わる人間たちが多く住み込んでいたのだろう。周囲に集落のようなものも見て取れるが、どれもすでに風化し周囲の景色とほぼ同化していた。
しかし一族の栄華と崩壊の記憶は連邦国民にまだ新しく、クラノスをはじめ井更の名を知らぬ人間はおそらくこの地球上にほとんどいないだろう。特に彼らが興した重機歩兵工場は地球の兵器市場をたちまち呑み込み、世紀をまたいでここ東大陸に巨万の富と活気を生み続けた。そして倒産の衝撃はいくつもの工業都市を巻き添えにし、大量の街の名を地図上から消し去るほどだった。それほどかの井更家という武器商は大きな力を持っていたのだ。
そんな大組織の名残を継ごうという猛者が今になって現れたのだとしたら、クラノスも是非名前くらいは聞いておきたいと思う。
「土地はここ数年の内にサイバーSIN社が買い取っていたらしいが、実際に住み込む物好きが現れたのはごく最近の事だ。だが、やはりあまりいい趣味ではなかったようだ。まさか今になって以前の持ち主が押し掛けてくる事など想像もしていなかっただろうしな」
サイバーSINとは井更重工と同じ兵器製造を手掛ける、近年急速に成長した新興企業だ。結局住みついたのは同じ穴の狢かと落胆しかけたクラノスだったが、続いて語られた犯人像に耳を疑った。
「…持ち主?では侵入者は井更家の人間だという事ですか?」
どうやらロッシュはクラノスが話に乗ってくると確信していたようで、彼の問いに満足そうな笑みを返した。慌てて興味の色を引っ込めはしたが、すでにクラノスの脳裏には鬼神と呼ばれた男の生前の姿が鮮やかに蘇っていた。逆立つような赤い髪、明るすぎるほどの緑の双眸、皆があれを鬼とはよく例えたものだと思う。まれな長身ではあったが、それが小山ほどにも見えたのは男の持つ覇気にも似た空気のせいだったろう。ただ記憶を手繰り寄せているだけだというのに、早速指先の感覚が薄れ始めている。昔一度対峙しただけだというのに、今になって尚自己防衛本能が過剰に反応するほど、当時の自分は相手に追い詰められていたのだ。
「顔色が悪いぞ、中尉。まさかライデン自身があの世から蘇ってきたとでも思っているのではあるまいな?」
「そのまさかです。自分はあんな人間を二度と敵に回したくはない、もう懲りごりです」
この会話でクラノスが逃げ出すとでも思ったのだろうか、ロッシュは両手を上げて制止するようなしぐさを見せた。話にはまだ続きがあるらしい。
「それが全くの見当違いでもないのだ。どうやら彼には血を分けた妹がいたらしい。もしそれが“本物”だとすれば今までよく当局の目を欺いてきたものだと感心するがね…」
「妹…」
ライデン本人ではないと聞いて慌てて想像をかき消そうとしたが、強烈な鬼神の像から女性への変換など到底かなわず、クラノスは妹という単語のみを記憶しておく事にした。何も心配する事はない。井更一族の正当な末裔でありながら野に下り、当時激戦の中にあった北方面軍で第8特種重機歩兵部隊を率いた“ライデン=井更”はとうに英霊になっているのだ。
「ここで井更家の娘が現れた事は我々連邦軍にとっては絶好の機会だ、侵入者を制圧した後は我々が娘を引き受ける。必ず生きた状態で確保してほしい」
再び回想にひたりかけていたクラノスは慌てて我に返った。重機歩兵部隊に人身を拘束せよというロッシュの要求が常識をあまりに逸脱していたからだ。
「それは無理です」
彼の即答が耳に届かなかったのか、ロッシュの表情は微動だにしない。
「…狐狩りにミサイルを担いで行けというようなものだ。それでは毛皮など到底手に入りません。ここは第2特陸に任せるべきでは?」
しかしこれにも相手は片眉を少し吊り上げるだけで、頑として聞き入れる気などないようだった。それどころかすでに成功後の試算に入ったのか、ロッシュは口角を白い歯が見えるほど歪ませながら声を立てて笑った。
「これはできるできないの問題ではない、連邦軍として捨て置けない事態なのだ。警察にとって娘はただの暴徒だろうが、我々にとっては長年頭を悩ませてきた謎を解く“鍵”となる可能性がある。
…それに何故第1ではなく第8を選ぶのか、今の君の問いこそが答えになっているのではないのか?」
東方面軍第8特殊重機歩兵部隊がテシマ島へと向かうのは、それから間もなくの事だった。
1章・4―瓦礫の孤島に集うもの
―8月26日、01時20分―テシマ島
無数の光源はやはり警察の規制線と一致した場所にあった。
そこでまずクラノスの目に飛び込んできたのは大型車両に取り付けられた自動飛行照明の類だった。それらが車両の荷台部分から伸びる高い柱に、まるで大樹に群がる無数の甲虫のようにひしめき合っていた。この光の湖を作り出しているものの正体は大方それだった。車体はどれも同じように黒くのっぺりと平たい形状で、ところどころに州警察のマークが描かれたもとそうでないものがある。どちらにせよ異様なのはその数で、一体これだけの数をどこから集めてきたのか、これからどこで何をしようというのか、一か所に固められた光景はあまりに不自然そのものだ。
それに移動中襲撃のリスクを避け、ここまでレーダーに頼りひたすら闇の中を来たクラノスとって、かなり刺激の強い歓迎の灯りだった。
だが明るいのはこの一点だけで、あと他に島内に光は見当たらない。やはり本来のテシマは無人かそれに近い状態なのだろう。かろうじてクラノスが理解できたのはそこまでだった。これまでに基地で得てきた情報によれば、島の地形は中心に向かって隆起しており、丘陵ほどの台地のほぼ中心部に犯人達の潜む旧井更邸があるはずなのだが。しかしここからは建物から漏れ出る明かりはおろか、丘の影すら見あたらない。それどころか、クラノスのヘッドセットに取り付けられたレーダー機器ですら正確な影を捉えられず、エラーを繰り返している。どうやら自動飛行照明という奴は低感度のレーダー探知機の妨害になるらしい。そう思うとなおの事光が忌々しく思えた。こんな叩けば埃の出そうな警察の流儀を突き付けられるなら、こちらも遠慮などせずに超大型軍用輸送車両にキャタピラーでも取り付けて乗り込んでやれば良かったとさえ思う。
これまで命綱にしてきた砂まみれの暗視スコープが急に煩わしく感じられ、クラノスは左耳に手を触れるような動作をしてヘッドセットのバイザーを跳ね上げた。すると今度はそれまで偏光レンズによって遮られていた光が一斉に瞳孔に向かって押し寄せ、たちまち彼の視野を奪った。まるでスポットライトを正面から浴びせれらたような気分だ。
彼と同じ“アトロフィクシス”の中には、目の異常発達により夜行性動物のように暗闇でも目が利く者もいる。彼らなら一体どうなっていただろう。幸いにして瞳の色が濃く、視神経の異常増殖に襲われなかった彼の目はすぐに機能を取り戻した。切れ長の造形は母親譲りだが、濃い茶色の瞳の色は父親譲りだ。こういう時には父親に感謝すべきなのだろうか。
それから乱雑に停められた照明車両の間を縫うように、クラノスは喧騒の中心部を探して歩き始めた。
多いのは照明だけではない、ここには人も溢れていた。周囲を忙しなく動き回っているのは警察関係者のようだが、中にはそれとは疑わしい人間も少なからず見受けられた。先に進むにつれ大きな撮影機材のようなものを担ぐ人間までもが現れ、大声で何かを喚き散らす訛りの強いリポーターを追いかけて右往左往する。どうやら地元の放送局か何かが軍より先にここを嗅ぎつけたようで、警察はそのマスコミとすでによろしくやっていたらしい。暗黙の了解など期待していた自分が馬鹿らしかった。
クラノスはなるべく彼らの目につかぬよう褐色の着丈の長い上着を深く被ると、兵隊らしからぬ長い後ろ髪を大きな襟で覆い隠した。それまでに一雨来たのだろうか、一歩進む度に剥き出しの黒い地面がぬかるんで靴底が奇妙な音を立てる。慣れない野戦を想定して陸上部隊御用達の特殊構造の戦闘靴を履いてきたのだが、ただ歩くだけなら決して快適とは言えない代物だという感想を持った。
それから幾許も経たない内に、何処からともなく小銃を担いだ二人の男が現れ両脇を挟まれた。彼らは何かをわめきながら無秩序に動き回る警察官や、もはやヤジ馬と区別のつかぬ人間たちとは違った。迷彩色に身を包み、髪を短く刈り込んだ頭には帽子、そして足音は規則正しい。彼らはサウスデリフォード州兵だと見て取れた。一人はまだ新兵だろうか、口を開く前から物珍しそうにクラノスの風貌を横目で眺めはじめた。なるべくこちらに悟られぬよう努力はしているものの、それでも溢れ出る好奇心は隠せないという体だ。それが何故かクラノスはすぐに察した。健常者は相手がアトロフィクシスと聞けばまずその攻撃性を恐れ、その次には健常者との違いを探しにかかる。彼の反応はごく当たり前の事だが、扱いを受ける側はその度にいい気はしない。
「連邦国軍E81のロータスークルーソ中尉であられますか?」
取り囲まれてなおだんまりを決め込んでいたクラノスに痺れを切らしたのか、あとの一人が切り出した。さっきから好奇の視線を浴びせる小柄な兵士に比べ、こちらは百八十近くあるクラノスよりさらに上背があった。名前までは思い出せないが、おそらくここ以外で一度くらいは顔を合わせた事があるはずだ。こちらの返事を待つまでもない様子で相手は続けた。
「コウザイ二佐が本部でお待ちです。自分は重機歩兵輸送車の位置確認も命じられていますが」
そこでようやくクラノスが足を止めると、二人は周囲を警戒しながらそれに従った。あいかわらず辺りには官とも民ともつかぬ人間が多数行きかっており、その中で武装した三人の姿はよく目立つ。ふいに派手な井出達の女性がこちらを見つけて近寄ろうとしたが、すぐに二人が制止したので事なきを得た。初見の印象はさておき、二人ともよく訓練された兵士だった。
「“ZIXO”を2機、海底トンネル近くの窪地で待機させている。なんなら見に行くといい、君らの足ならばほんの二時間ほどだ。自分は先に行ってコウザイ二佐にお会いしたいのだが」
相手は納得したのかしないのか、しばらく腕時計を眺めてからうなずくと、先に進むよう促した。相変わらずもう一人はクラノスの観察を続けているようだった。アトロフィクシスとはいえクラノスは外見に大きな変化の見られる型ではなく、頭部に大きなコネクタを持つストリング処理も受けてはいない。そこでふと、相手の視線がコートの裾から見え隠れするものに向けられているのだと気がついた。今どき自動小銃ならぬ、金属製の刀をぶら下げているのが、彼にとっては物珍しかったようだ。
「これか、レチルローム製のお守りだ。珍しいか?」
そこで相手は「ああ」、といった風に目を輝かせた。そう言っただけで本当に意味を理解したかどうかは疑わしいが、それなりの返答にはなったようだ。クラノスはやれやれと思いつつ、一刻も早く彼の興味が他に移る事を願わずにはいられなかった。
1章・5―探り合う者たち
『犯人を、井更家の娘を生け捕りにしてこいか。なるほど―おそらく、中央軍は以前のソワーズめと同じ方法で暗号解読するつもりでいるな』
同時に老人特有の乾いた高笑いがこめかみを通じ、クラノスの鼓膜を振動させた。
「…暗号?」
『そうじゃ、大法廷が井更家を追放し重工を取り潰す決定をした直後から、中央軍は井更重工の兵器開発に関する情報のほとんどを“ハイブ”を通じて吸い上げておったらしい。その膨大なお宝の中には中央軍すらも預かり知らん兵器に関するものも混じっていたようだが、どれもこれも複雑に暗号化されていて、それから何年もの間にっちもさっちもいかんかった。それが突如…誰の入れ知恵かは知らんが、当時外郭の研究員だったソワーズの奴めが十夷=井更の十四人の娘の内、生き残っていた婆様三人の生体情報から暗号を解く事を思いついた。おかげで莫大な予算を掛けながら頓挫しかけておった中央艦隊旗艦がハリボテから実用艦になったという噂だ。欲をかいたソワーズは既に他界していた十一人の墓も暴いたそうだが、それは徒労に終わったようじゃ…全く強欲で罰当たりな奴じゃて』
州軍が陣を張るテントへ一行が辿りつくまでの間、彼の話し相手になったのは周囲の二人ではなく、重装軍用車両に居るジェームス=ジェファーソン医長だった。医長はずいぶんと興奮していて、通信機の向こうから忙しなく歩き回る彼の足音が聞こえてくる。ジェファーソンは高齢で、とっくに退役済みだったが、暇を持て余し結局軍属として舞い戻ってくる程の仕事一筋の男だった。それならばと現役時代同様にアトロフィクシス兵の行動監視装置のメンテナンスを頼んでいるのだが、とにかく風体からしてマッドサイエンティストと呼ぶにふさわしい人間だった。若い頃にはアトロフィクシスを人工的に作り出す研究をしていたらしいが、それが花開き犠牲者が出る事なく終わって良かったとクラノスは胸をなで下ろす。今日は負傷者の出るような不測の事態にそなえユニットに同行してもらったが、大事なところでその「マッド」が顔を出さなければいいと思う。
しかし医長の長話のおかげで、ようやくクラノスにもロッシュの意図が見え始めていた。中央軍は井更重工から押収した兵器の設計データを何とかして解読したがっている。それがどんなものかは知らないが、井更重工は常に太陽系で最高の重機歩兵を作り続けてきた技術集団だった。おそらくそれも貴重なものなのだろう。当人たちもよほど他人の手に渡したくなかったと見えて、大事なデータを全て血族の生体情報を使って暗号化していたらしい。井更一族と呼ばれる人間が一体どのくらい居るのかは知らないが、直系長子ライデンの妹ともなれば、その生体情報を試してみる価値はおおいにありそうだ。ただし中央軍の欲しがるような兵器だ、それがこの先一体どれだけの人間を殺すのか、想像は後回しにした方がいい。
まず今考えるべき一番の問題は、その娘をどう捕えるかだ。軍の目的しか眼中にないロッシュは犯人の要求など気にも留めていないようだった。しかし相手が何の目的で旧住居に忍び込んだかがわからない限り、この先の行動が予測ができない。私用で重機歩兵まで持ち出すのだから(一般人には理解できない感覚だが)よほどの事情があるに違いないのだ。娘が重機歩兵を操縦できるか否かの情報はないが、無敗のまま人生を終えたと言われるほど重機歩兵戦に長けたライデンの兄弟なら十分警戒しておいた方がいい。究極の兵器は復讐のための鉄槌か、それとも相手の喉元につきつけるだけの脅しの銃口だろうか。
考えを巡らせている内に、一行はいつの間にか軍人だらけの場所に辿りついていた。二佐に会う前に頭の中を整理しておきたいと思うのだが、ジェファーソン医長はまだまだ喋り足りない様子だ。無理に話を切り上げようとすればこの老練のご機嫌を損ねないとも限らない。それにこの長話だ、そろそろ左右に張り付く二人の視線が気になりだした頃だ。
『はいドック、そろそろいい?ヘンな装甲着込んで一人ノコノコ出かけて行った隊長殿の安否確認をしたいんだけど』
不意に別の回線が割り込み、それが上手く医長の気をそらした。
医長とは別の車両に居る指揮官補佐、ジャッキー=フランツ少尉の声だった。そのけだるそうな話し方から待機中の居眠りが疑われたが、今問い詰めたところでのらりくらりかわされるのが関の山だ。医長を止めてくれた事に感謝して、今回だけは怠慢に目を瞑ってやる事にした。時計を確認すると、定期交信よりも少し早めの時刻をさしていた。
「いいタイミングだ、ジャッキー。ここから旧井更邸が目視で確認できなくて困っていたところだ。自動飛行照明のおかげで簡易レーダーも効かん。726号機アイドルエンジン始動、主計算機演算領域を五パーセント2番車に解放、2番車のシムに地下構造までのサーチと、潜伏する重機歩兵の型を割り出させろ。警察より先に目標建造物の全貌と敵を知っておきたい」
あと医長の話が長くて困っていたとは絶対言ってはならない。クラノスは待機させた隊員に至急情報収集を開始させるよう促した。この賑やかさは全てを知った警察が、こちらを撹乱する為にあえて作り出した状況かもしれないとクラノスは疑いだしていた。しかしまだ寝ぼけているジャッキーにはクラノスの思惑が上手く伝わらなかった。
『なんでわざわざ2番車?…726号機に任せときゃ一発じゃん。もうケリーはスタンバイ済みよ』
726号機とは今ユニットE81と共に待機する重機歩兵、ZIXOの機体通し番号で、操縦士はケリー=ハサラン准尉だ。重機歩兵と言えばそのずば抜けた戦闘能力にばかり目が行きがちだが、それを支える計測機器類も、時代の最新鋭のものが使用されている。地形の探索などそれに任せれば一発なのだが、あえて性能の劣る大型軍用車両備え付けのレーダーに頼るにはクラノスなりの理由があった。
「重機歩兵のレーダーを使えばお互いにカタ(種類)がすぐ割れる。なにせこっちのZIXOは井更重工製だからな、敵は俺たちの知らない弱点を知っている可能性がある。そろそろフェイムダンパーの経年劣化時期だったらどうする。とにかく敵にはギリギリまでこちらの手の内を知られるな」
『…何言ってんだ、社長令嬢が部品の発注なんかしてっかよ』
少しだけ頭が冴えて来たのか、しばらく間をおいてからジャッキーの笑い声がした。
そんな問答を繰り返している内に、一行は州軍のテントの前に辿りついていた。州兵二人は立ち止まり、クラノスが話を終えるのをじっと待っていた。あいかわらず背の低い方はこちらに興味津々といった様子で、ついに兵士は想像以上に高い声で話しはじめた。
「あの、E81にBIZERはないのですか?自分新型を一度この目で間近に見て見たくって」
質問が想定の範囲外だったので、クラノスは少し面食らった。新兵はあいかわらずキラキラした目でこちらを見ている。残念ながら彼の言う新型はE81にはまだ配備がされていないし、当分その予定もない。今日もし重機歩兵を目にする機会があればZIXOと、あと相手の持ち込んでいるアンノウンくらいなものだろう。どうやら今日は彼の好奇心を何度も裏切る日になってしまいそうだ。
井更重工の解体後、国力維持の為に連邦軍には同社が開発したZIXOに代わる主力重機歩兵が必要だった。開発は国を挙げてのプロジェクトとなり、間もなくロールアウトしたのが彼の言う新型機、BIZERだ。その開発期間の短さと飛躍的な性能の向上で、当時は国内外を随分と驚かせた。だが、右肩上がりを続けるBIZER人気の本当の秘密は、性能云々より騎士然とした外見にあるとクラノスは考えていた。彼もまたその外見に興味を持つ一人なのだろうか。
予算不足、配備を急ぐだけの評価点の不足、そこに触れてほしくないような理由はいくつもあるのだが、E81が ZIXOを未だ使い続ける理由はその安定性に尽きる。既にクラノスも数度このBIZERを使用した事があるが、数字で提示されるような性能の向上を実感できないのが現実だった。両者を比較すれば比べれば外見こそ劣るが、整備に手を尽くしたZIXOを新型が超える日はまだ先の事だと思えた。しかしそんな話をおそらく相手は求めてはいまい。
「フフフ、聞いていないのか?あそこに立てこもってるのは井更家の令嬢だぞ。ここにR&Bインダストリー製のBIZERなんか持ち込んでご機嫌を損ねたらどうするつもりだ」
突拍子もないクラノスの返答に兵士はきょとんと眼を丸くした。それを余所に、クラノスはそそくさとテントの入り口をくぐった。
中では多くの兵士が所せましと動き回っていた。外見を思うとずいぶん手狭な印象で、正面奥に座るコウザイ二佐の姿が入口から丸見えだった。片手で白髪交じりの頭をかきむしりながら、反対の手で忙しなく書き物をしている。彼はクラノスの知るサウスデリフォード州軍南東方面第22師団、マモル=コウザイ二佐に間違いなかった。
このコウザイは佐官でありながら実によく動き回るので、傍から見ているとリスなどの小動物を連想させた。彼は州軍の高等指揮官で、重機歩兵部隊との共同作戦には事務方中隊を率いてよく顔を出す。見たところ、今日の本部は彼をトップにして動いているようで、彼以上の階級の人間は見当たらない。コウザイはすぐにクラノスの姿に気付き、書き物をする手を止めて立ち上がった。
「協力感謝しますぞ中尉、E81が駆け付けると聞いて我々も胸を撫で下ろしとったところです」
ひとしきり挨拶を交わすと、コウザイは早速この奇妙な現場について話したがった。警察との交渉は彼に任せれば良いと聞いていたので、クラノスは黙ってそれに従う事にした。どうやらテントには更に奥があるようで、仕切りの向こうへ通された。
奥の間の空気は湿気をたっぷり含んで滞っており、羽織って来た分厚い上着が煩わしく思えるほど蒸していた。コウザイは手に持つ扇のようなものを忙しなくパタパタと煽ぎ始めると、クラノスにも涼むよう促した。しかし下に着込んできたプロテクターや計器類の事を考えると、故障を避けるためにもそのままでいるべきだと判断し、クラノスはその心遣いだけを受け取る事にした。
「ご覧になりましたかな、この人人人…。そうですな、おそらく相当な数民間人がここに入り込んどるものと思われます。これだけの人目じゃやりにくい。輸送車を手前で待機させたのは正解でしたな」
咳払いを一つすると、コウザイは続けた。
「見ての通り警察を押し切ってマスメディアや人質の関係者が規制線を越えてきておるようです。なにせかの井更家の人間が容疑者だというのですからな、マスコミにとっては近年そうそうないゴシップのネタだ…。警察も追い出そうにも追い出せずに往生しておるようです。これではE81が到着しても重機歩兵の展開は不可能だと警察には何度も言っとるんですが…」
コウザイによると、警察はある程度部外者を敬遠しているらしいかった。しかしクラノスはそれ以上報道関係者について話を聞く気はなかった。人払いはできているという相手の説明だったし、これ以上余計な事に気を回して二の足を踏むのはご免だった。ふとにぎわっているのはこの付近だけで、ここに来るまでの間に民間のものらしき車などにすれ違っいないのを思い出した。こういう手合いは一つ来れば後から後から続いてくるものだと思い込んでいたのだが。
「その上この人質の関係者の多さだ。十人や二十人なんてかわいいもんじゃありません。どうも野次馬のほとんどはマスコミ関係者ではなくサイバーSIN社の人間だという話です」
コウザイは首を左右に振ってからゆっくりとした溜め息をついた。
「サイバーSIN…?」
さらに厄介なキーワードが一つ増えた。サイバーSINと言えば井更重工ほどではないものの、軍に居れば何処ぞかしこでよく目にする団体名だった。それでも、たかがとは言わないが重役一家族の為にそんなに沢山の人間が心配顔で詰めかけるだろうか。唐突にクラノスは背後に同業者同士の抗争の様な、何か陰惨で血なまぐさい事件があるのではないかと思い描いた。だがはたしてそんな事に直系の娘自ら武器を担いで乗り込んでくるものだろうか。来るとすれば一体ここにどんな世界を揺るがしかねない秘密が隠されているのか。個人的感情を述べるならば、武器商の抗争になど一切かかわりたくない。しかし連邦国軍にとって必用とあらば例え横槍を入れてでも娘を見つけ出し連れ帰るしかない。
「ところで、この一帯の大量の照明は何です?」
秘密を最小限にとどめようと、クラノスは頭の中とは直接関係の無い話題を振った。するとコウザイの表情が緩み、まるで自分の仕掛けた悪戯を得意げに耳打ちでもするように身を乗り出した。
「まじないです…ここの警察連中は本気でこの光がゴートパインに潜む魔物を退けると信じとるようですぞ、フフフ」
突然そのコウザイが、今度は眉を寄せ顔をしかめた。彼の見つめる一点を振り返ると、部屋の入口に立てられていたつい立がゴソゴソと揺れている。だれかがここへ入って来ようとしているのだ。
「誰だ、後にしろ。取り込んでいる!」
コウザイが少し声を荒げると、入口の憲兵がこの荒っぽい訪問者の名前を告げた。コウザイが戸惑っていると、訪問者は無理やり部屋へと身体を捻じ込んできた。
最初に鼠色のブレザーが見えたと思えば、次は赤いネクタイ、続いてそれに頂点の薄くなった頭がついてきた。それはずいぶんと痩せた印象の、見るからに民間人だった。
1章・6―主張する者たち
「どういう事です二佐ぁ…!」
男は入ってくるなり大声で叫んだ。そして見慣れない格好のクラノスの姿に驚いたのか、しばらくコウザイとクラノスの顔を交互に見比べた。それからまた更に額を紅潮させ、一気に喋り出した。
「重機歩兵部隊を呼び寄せたって、そりゃ何かの冗談ですよねぇ!?中にはウルマン専務とその家族がおいでなんですよ?重機歩兵なんかで乗り込んで…もし彼らに何かあったら一体どうするつもりですかぁ」
結局男はクラノスの正体を見抜けなかったようで、本人を前にE81の到着をなじりだした。どうやら男は例のサイバーSIN社の人間らしい。ほんの僅かな時間接触しただけで、下手に出ているようでどこか人を小馬鹿にしたような話し方が鼻につきはじめた。そして猫背なせいか、常に相手を上目遣いで睨みつけ卑屈な印象を与える男だった。
「ウチの社長は金に糸目をつけるようなケチな人間じゃないんです!身代金ならいくらだって払いますよ」
突然どこの誰ともわからぬ民間人が押し掛けてきてわけのわからない事をまくしたてる、州軍には州軍の苦労があるのだとクラノスは思った。それにこの男、人質を親身になって心配しているようには到底見えない。その後も人質がいかに会社に貢献し不在の間の損失がどうのとかをそれっぽく並べるのだが、どれも上辺だけの白々しいもので、こんな男に命のやり取りを委ねなければならない人質のウルマン氏とやらに同情せずにはいられなくなるほどだった。
「身代金だと?…犯人から要求があったのか?」
話の途中に割って入ったコウザイが、いぶかしげな顔で男を覗き込んだ。男はハタとしてしばらく静まり返り、またその賑やかな口を開いた。
「し、知りませんよ!だ…だから最初から言ってるでしょ?穏便にお願いしますよ、ウチはいくらでも払う用意があるんですって…!」
男はますます茹でダコのようになり、薄くなった頭のてっぺんまで真っ赤にして叫んだ。
「重機歩兵なんか必要ないっ…ホンットに!何の為の警察や州兵ですが、重機歩兵一機くらいお宅らで何とかならないんですかぁ!?」
クラノスとコウザイは顔を見合わせた。あの井更家の生き残りがはたして金銭目的で住居に立てこもったりするだろうか。サイバーSIN社の社員でありながら警察に重機歩兵を始末しろとは薄学にもほどがあるが、とにかくこの男には重機歩兵部隊に来てもらっては困る事情が何かあるのだ。
「君の上司には気の毒だが、身代金だの探偵ごっこは警察とやってもらおう。それに民間人はなるべくここから離れた方がいい、重機歩兵が動き出したら命の保証はできんぞ」
しかしなおも男は食い下がった。
「だから…二佐、私の話し聞いてました?昼間になったら見て下さいよ、この屋敷の資産価値がどのくらいのものかど素人だってわかりますよ!ウチとしてはそんな大事な保養地を重機歩兵部隊なんかに踏み荒らされちゃ本当に困るんですよ!」
何を言いに来たのかと思いきや、最後は資産の心配だ。男からは重機歩兵に喧嘩を吹っ掛けられた事への危機感の欠片すら感じられない。これにはさすがのコウザイも呆れたようだった。
「離れるのはもちろんお宅も含めだ、何なら今から手伝おうじゃないか」
コウザイはそう言うと、部屋の出入り口に控えていたさっきの兵隊二人に目配せをした。男はたちまち彼らに両脇を掴まれ、引きずられるようにして部屋を去る事になった。
「あれはサイバーSINの事務方の人間だったか。名前は…何と言いましたかな、忘れてしまいましたが」
何かをわめき続ける男の後ろ姿を見送っていたコウザイは、三人の背中がつい立ての向こうに消えてからそう呟いた。それから少し声のトーンを落として続けた。
「サイバーSIN社からの交渉役と名乗ってここへ来たわけですが…なんというか、声が大きいばかりで本当に頼りない男でして」
するとそれまでは黙ってそばに腰かけていたクラノスが、突然弾かれるようにして立ちあがった。
驚き戸惑うコウザイを残し、つい立てを突き飛ばしてクラノスは部屋を出た。そして今まさにテントを出ようとしている男めがけて、一直線に向かって行った。
すっかり乾いていた戦闘靴の底が軋んで大きな音を立てるので、男は驚いてこちらを振り返った。そしてクラノスが羽織っていた上着を脱ぎ捨てると、下から特種陸上部隊用の物々しい野戦装備が現れた。動作補助装置を切っている為、無理に動かす度に駆動部分が異様な音を立てる。さらに両差しの太刀の固定具を両手のひらで叩き降ろすと、特殊な構造の鞘が開いて、レチルローム独特の低い共鳴音が辺りの空気を激しく振動させた。間近で見てようやく男はクラノスが連邦軍特種隊の兵士であると気付いたようで、短い悲鳴を上げると、それまで赤く湯立っていた額から急に色が引いていった。
クラノスが両手で男の胸倉をつかむと、それだけで小柄な体は宙に浮いた。視線は相手の怯えた顔に集中させたままだが、目視で確認せずとも小銃を携えた州兵の「攻撃意思」が二人を取り囲んでいくのがクラノスにはわかる。第六感が霊感なら第七感か八感だろうか。
「重機歩兵部隊…」
男は消え入りそうな声で言った。
「そうだ、つまらん隠し事さえしなければ今すぐ侵入者を制圧してやる。犯人は何者だ、お前もその重機歩兵を見たのか?」
少々強引に鎌をかけたが、その返事はおろか相手は恐怖のあまり狼狽し生気を失っていく。予想以上に脆い人間だった。このまま詰問を続ければそれだけで命を落としてしまいそうにさえ思える。萎んでいく男の意思を捉える為にさらに神経を集中させるが、取り囲む兵士の強い警戒感に気押され見失ってしまいそうだった。
「まあいい、お前たちの目分量ではあてにならんからな。数は一機か?それとも複数か?」
「お、俺は見てない、私が知るもんか…」
男は何とか震える声を絞り出した。
「放せ、…このアトロフィクシスめ!」
一瞬スーツの弁償が皺伸ばし程度では済まなくなるまで力が入りかけたが、思い直し、藪にらみ気味に相手を見るとクラノスは拘束の手を少しだけ緩めた。すると現金なもので、男はみるみる精気を取り戻していく。
「い、いい加減にしろ!私は社長直々に交渉を任されてきたんだぞ!戦闘しか頭にない野蛮人に好き勝手されてたまるかってんだ」
そう吐き捨てると、男はクラノスの手を振り払おうと暴れ出した。いつの間にか近くまで来ていたコウザイが狙撃兵を制していたが、それでもまだ燻る州兵の強い攻撃意思が熱風となって背中を焦がし続けている。おそらく彼らは飼いならされたはずの狂犬が手綱を離れ突然走り出したような、そんな恐怖感を以って今のクラノスを見ているに違いなかった。
結局具体的な情報は何も得る事のないまま、男を解放するしかなかった。これでは詰問の半分は失敗だ。クラノスをアトロフィクスだと確信した男は帰り様に彼の暴力に難癖をつけたが、こういう時の火消しにこそロッシュのようなお偉方が役に立つ。
「中尉、めずらしいですな。どうされました…?」
男が去った後、静かにコウザイが尋ねてきた。そのコウザイからもそれまでに感じなかったクラノスへの不信感が現れ、それが冷気のように肌を刺した。どうしたかと聞かれても健常者であるコウザイに上手く説明する言葉が見つからなかった。おそらくアトロフィクスと呼ばれる人間の大半も同じだろうが、クラノスには相手の感情が温度のようなものとして感じられる事がある。それが感情なのかどうかはマニュアルがあるわけでなくクラノスが経験から導き出した一つの答えだった。それも万人が一様ではなく、同じ感情でも冷気を発する者もいれば熱を持つ者もいる。実に曖昧なものだ。これを尋問や心理戦術に利用しようとジェファーソン達があれやこれやしていたのを思い出し試みたのだが、結果は芳しくなかった。そしてそれをコウザイに伝えたところで、不信感がより決定的になるだけだ。
「あの手合いは脅かせば何か話すと思いましたが、失敗です。何も情報を得られなかった」
そしてクラノスはコウザイに騒ぎを起こした事を丁寧に詫びる一方で、ひどい倦怠感に襲われていた。
まるで他人の意思が皮膚を通して浸透し骨まで達するような温度感覚は、本来人間として生まれた時から備わっていた知覚ではないはずだ。そのせいだろうか、疲労がその代償のように感じられる事が時々ある。なんにせよ他人の感情にいつまでも干渉を受けていては参ってしまう。そしてその逆も然り、だ。
その時、ヘッドセットの電子音が響き、突如としてそこに大量のデータが転送され始めた。
先ほどジャッキーに言いつけておいた探索結果が出来上がったのだ。偏光レンズに忙しなく流れていくデータを眺めている内は幾分周囲の雑音が抑えられ、昂ぶっていた気を紛らわす事が出来た。そして転送が終わるか否かのタイミングで、この偵察を任せていたシム=ホーキンス曹長の、通信とも独り言ともつかぬ話し声が聞こえて来た。
『驚いたな、見たか?こいつは家というより研究所か収容所だな。さすが井更邸だ、建物の地下に街数個分相当の電力プラントが埋まってやがる。こんな孤島でもさぞかし文化的な暮らしが出来てたんだろうぜ』
そしてクラノスの目の前に現れた旧井更邸の立体見取り図に、黄色く地下プラントの位置が示された。
「これはまだ生きてるのか?」
『ああ、数割は今でも稼動してる。それにしてもすごい規模だ。これなら家庭用のハイパースペースゲートも夢じゃないな』
そう話すシムはとても生き生きとしていた。情報収集にかけてE81で、いや、東方面軍でこのシムの右に出る者はおそらくいない。ジェファーソン医長といいシムいい、E81には必要以上に仕事に熱心な者が多い。ただの敷地の見取り図にしてはやけに多いデータの大半も、曹長の「もしも」や「これも」という使うか使わないかよくわからない彼の「心遣い」で埋め尽くされているに違いなかった。
「それにしても地下のブラックボックスが多すぎるな、シム、お前にしてはだぞ?」
クラノスがざっと見ただけでも、地下に構造が不鮮明な、レーダーでは中をうかがい知る事のできない個所が十数か所ある。シムの言うように電力が生きているのなら、住人が逃げ込む電子的なパニックルームの類である可能性が高いが、これがなかなか厄介で、重機歩兵のレーダーですら通さない。しかも驚いた事に、場所によっては数十メートル四方にもなろうかという場所まである。もはやこうなると基地サイズだ。
『車載のMODSレーダーじゃこれが限界だ。重機歩兵のTENTOでもダメなら最悪ベジェットカッターで一個一個切り分けて犯人を探すしかないな』
「…冗談じゃない、そんな時間があるものか」
これで廃墟だとばかり思っていた旧邸宅は今でも十分に機能するらしいという事がよくわかった。それは悪い事ばかりではない。パニックルームが機能しているとすれば、生身の人間が重機歩兵の亜空間戦闘領域に巻き込まれないですむ場所があるという事だ。敵の隠れ蓑にもなるが、こちらも利用しない手はない。
『あとな、南西の方角から侵入したって話の重機歩兵だが、どう潜り込んだかは知らねぇが今は北の掘りの地下に居る。上の建屋は多分櫓か何かだ。幸いそこはこっちからも丸見えでな。だが…重機歩兵にしちゃちょっと小せぇ。形状はまだどれとも一致しねぇが、エンジンの位置や装備を見る限り、多分こいつは悪名高い首都防衛軍の“ウィザード”みてぇな奴だ』
「ウィザード…」
そう呟いたところで、会話の半分は聞こえていないはずのコウザイがクラノスの顔を覗き込んできた。
「ウィザード、ここサウスデリフォード州では決して見る事はありませんな。あれも井更重工製だったでしょうか。という事はやはり犯人は井更家に関係する人間だという線が濃くなりましたな」
コウザイの言うとおり、このウィザードという重機歩兵は州軍はおろか、方面軍でさえ姿を見る事はほとんどないものだった。それが首都防衛という特殊な使用条件に向けて設計された、小型で高性能な重機歩兵だからだ。通常の重機歩兵の三分の二程の大きさで、一般的には亜空間戦闘領域での戦闘には不利だとも言われる。しかし亜空間外での機動力は恐ろしく機敏で火力も高く、いわゆる対重機歩兵ではなく、下位の旧式兵器、もしくは対人に特化した兵器だ。民家に立てこもり住人を脅すにはこちらの方が話の辻褄があうだろう。それが侘しい地方勤めが目にできない、都心の選ばれし者のガーディアンだという事はさておいての話だが。
「ご苦労だったな、シム。だが次はもっと早くよこしてくれよ。…俺のジェファーソン式精神知覚尋問がまた失敗に終わる前にだぞ」
するとシムは向こうで笑っていた。これまでの成り行きを全てシムにモニターされていた事くらいはクラノスも気付いていた。この先永遠に笑い者にされない為にも、後は仲間の盗聴に最大の注意を払っていかなければならないようだ。
『言わなくたってウチの親分の話し下手はけっこう有名だぜ。犯人が慎ましやかな深窓の令嬢だったらいいが、ウィザードなんか持ちだすようなおてんばだ。とんでもねぇメス鬼でそこに居る全員を対人レーザーで炙り殺すような冷血なんて事もあり得るぜ。お前も巻き込まれる前に早く戻んな、そろそろみんな待たされ過ぎて痺れが切れそうだ』
そう言ってシムは通信を切った。
1章・7―漠然とした不安
それまで宙空を見つめ、E81の重装軍用車両、こと重機歩兵輸送車・1番車のキューポラでクラノスとシムの話を聞いていたジャッキーだったが、突如その場でバタリと後ろにひっくり返った。
見れば彼のこしかける椅子の背もたれは前もって水平近くまで倒されており、勢いよく後方へ投げ出された彼の頭は、辛うじて床との衝突を免れていた。それから腰を浮かしさらにのけ反ると、背伸びをするように両手を頭上に伸ばす。そして大きな欠伸を一つした。
「ウィーッ、当直終わりがけの出撃なんてマジ悲劇…」
その後しばらくの間目を綴ったが、決して居眠りを決め込んだわけではない。それを証拠に、ジャッキーの右足は踵でコツコツと床を叩いている。いわゆるこれは世間で言うところの貧乏ゆすりというやつだ。
このE81副隊長、ジャッキー=フランツもまたアトロフィクシス兵らしく、長く豊かな頭髪を生やしていた。椅子の上で寝そべっているせいで、その銀色の毛先が床にまで届いているが、そんな細かい事を一々気にする性質ではない。彼が自分をアトロフィクシスだと認識したのはロースクールの頃で、それからやけに頭髪の伸びが早くなり、やがて頻繁に床屋へ行くのが面倒になった。
その髪をいつも気の向くまま、自由な方向に向かってなでつけ、額に濃紺の大きなバンダナを巻くのが彼の定番スタイルだ。バンダナは元々新兵の頃に付けた頭部の傷を隠すためにはじめたもので、それを今日に至るまで何となく外せずにいるのが本当のところだ。
それにしても活動的な彼にとって、雑木林の中でただ風のざわめきを聞くだけの待機時間は退屈そのものだった。
次の行動に出たくても、一人で交渉に行くと言って聞かず、勝手に飛び出して行った上官クラノスはまだ当分戻って来そうにない。
今回の作戦は敵のせん滅ではなく捕獲という何とも歯がゆい、かったるい内容だった。だいたい行動が先行しがちなアトロフィクシス兵には一番向いていない仕事としか言いようがない。偏屈で容量の悪いクラノスがいかにも拾ってきそうな仕事だった。
そんな作戦のターゲットを首尾よく捕える苦肉の策として、今日はチェリーホックと呼ばれる特殊な銃弾を大量に用意して来ていた。チェリーホックとはサクランボのような姿の形状から名付けられた弾丸の一種で、中身は電気信号を帯びた粒子だ。そしてジャックの役割を果たす先端を重機歩兵の外甲殻に打ち込めば、ヘタのようなコードを伝って妨害信号が流れ込む仕組みになっている。これで一時的とはいえ、重機歩兵の機能低下が期待できる弾丸だ。それにどんな薬剤(電気信号)を詰め込むか、そろそろ決めておかねばならない頃合いなのだが…。
それはそうと、ジャッキーは今回の作戦に何とも言えない違和感のようなものを感じて仕方がなかった。
中央軍のエドワルド=ロッシュ少佐からの注文は道すがらクラノスから聞かされていたし、支障のない範囲でその目的は隊員全員にも周知しておいた。とりあえずそこは除外してもの違和感だ。
それを踏まえて立てたクラノスの作戦はそれっぽく筋が通っていたように聞こえたが、どことなくいい加減なにおいがした。それはどこかと言われてもよくわからなないのだが。
例のチェリーホックを大量に持ち込んだのも彼の指示だった。選択こそ間違っていないが、弾数の計算がざっくりとしすぎている。弾薬庫はまるでサクランボの出荷前のようなにぎわいだ。
父親が連邦中央軍の高官だというクラノスはどこか話し方も気取っていて、私生活上の金銭の感覚もジャッキー達庶民とは少しかけ離れていると感じる事がある。だいだいそういった好待遇な生活にのんびり浸ってきた人間など、脇が甘いとんちきが多いとジャッキーは思うのだが、クラノスもその期待には今まで十分応えてくれてきている。
しかしそれは大体が私生活の中の話で、いくらボンボンだとはいえ彼が戦場で状況を大きく見誤り、隊員を命の危険に晒すような真似だけはしない。アトロフィクシスとなった事で世を拗ね、根暗な人生を歩んできた男にしては上出来だとジャッキーは思っていた。
不意に頭上に気配を感じで、ジャッキーは少しだけ身じろぎした。だがまだ起き上がる気なったわけではなさそうだが。
「そろそろ688にも火、入れときますかね?」
そういってキューポラを覗き込んだのは、整備長デヴィット=サガナワ曹長だった。サガナワはパンチパーマに長い揉み上げと口ひげを蓄えた中年者で、例え夜だとしても決して外す事のない色の濃いサングラスがトレードマークだ。
口数の少ない職人肌で、日に焼けた太い毛むくじゃらの腕で長年東方面軍第8特種重機歩兵部隊をメカニック面で支え続けて来た。すでに旧式となった“ZIXO”が新品同様に保たれているのは、サナガワによるところが大きかった。
「火を入れる」というのは彼にとって重機歩兵を起動するという意味だが、重機歩兵の主な動力は電気であり、機動の際にどこかに点火したりするわけではない。これはサガナワ独特の言い回しだった。
「んー…」
ひっくり返ったままいい加減な返事を返したジャッキーだったが、サガナワはそれだけで何かを察したのか、一つうなずいて顔を引っ込めた。
『おい、ゆっくりくつろいでないで起きろジャッキー!目標をどうするのか、お前もちゃんと考えてるか?それによっちゃこっちの仕事が随分変わってくるんだが』
今度はスピーカー越しに2番車のシムの声がする。2番車というのはちょうど彼らの真後ろに停められた、ジャッキーの乗る重機歩兵輸送車と全く同型の車だった。これらは背の高い重機歩兵を積む為に車高も合わせて高くなっている。その上にキューポラが取り付けられている為、外見からヤカンやアイロンの愛称で親しまれている。さらにグラヴセイバーと呼ばれる足回りは非常に優れたホバーリング走行が可能で、砂漠でも比較的快適なクルージングを可能にしている。通常のサイズなら一機ないし二機の重機歩兵が積めるが、今日は性能を最大限に生かすために一機に絞ってきた。それに人員を半分に分けて乗って来たわけだが、E81の五人の操縦士に医長、整備班三名を加えると若干車内が窮屈になった。
それはさておき、旧井更邸のスキャンを終えたシムは、すでに次のチェリーホックに詰める「劇物」の調合に移ろうとしてるようだった。
『今回は726号機とお前の688号機しかない。ウィザードを先にねじ伏せるとしたらお前かケリーの仕事になるだろう?だったらお前たちの調合リクエストも聞いておいてやるよ』
二台の輸送機に一機ずつ詰まれているのはケリー=ハサラン准尉の726号機とジャッキー自身の688号機だった。しかし別に彼らがスクランブルに向けてクラノスから特別な指示を受けているわけでもない。
「さあ、どうだろう。クラの奴が戻ってきてやっぱり俺が乗って行くって言いだすかもしれねぇし…」
それはない、とシムは即否定した。
確かに、E81にはすべて合わせて7機の重機歩兵があるが、クラノスの隊長機を含め5機は基地へ置いてきた。同じ型の重機歩兵はだいたい操作感覚も同じようなものが多いが、E81では操縦士の個性に合わせ各所を変更しているものがほとんどだった。皆同じ機体を何年も使い続けているのだから、結果繰り返される改造でほぼ原形とは別物のように成り果ててしまうことがほとんどだった。
つまり726号機はケリーが、688号機はジャッキーが扱うのが一番効率がいい。
『それに大将の射撃の腕はあまりアテにならないからな。402号機に短ベジェ砲しか積んでないのはいい選択だ。下手な鉄砲も数撃ちゃ当たるって言うが、チェリーは半有線だからな、あいつじゃ戦場がこんがらがっちまう』
それはそうだという賛同の意味を込めてジャッキーは笑った。さらにあの大量のサクランボの山を思い出して噴き出した。ジャッキーの不安は杞憂だったかもしれない。
そして再びのけ反ると、キューポラの開けっぱなしの扉から奥を覗き込む。そこからではほんの一部しか見えないが、半透明のキーボードの上を滑らかに動いているのは、E81の紅一点、ヘレナ=ラウ曹長の長い指だ。おそらく2番車のシムのデータ照合をここ1番車に引き継いで行っている最中だと思うのだが、作業は難航しているようだった。キーボードを打つ時のわずかなタイミングの違いから、彼女が苛立っているのが見て取れた。そういえば基地への報告も全て彼女に押しつけたままだ、あんまり騒ぐとゲンコツが飛んでくるかもしれない。
「ウィザード、ねぇ………」
ジャッキーは愛機ウィッキー君34号、こと愛用タブレットコンピュータをポチポチと弄りながら、ごく限られたウィザードの目撃情報記事を探り出し、さらにそこから映像を取り出して眺めた。中央首都防衛軍にしか配備されておらず、しかも存在自体が公になっていないせいか、数量はごく僅かに限られていた。
「まぁフルサイズの重機歩兵にとっちゃ大した相手じゃないらしいけど、なにせ俺も見た事すらないからな。チェリーの半分はノード、半分はメインブレン用の毒を詰めとくかぁ…領域展開封じにはどのくらい要るかきっちり計算しといてよ」
ジャッキーはそこでようやくむっくりと起き上がった。
正面のモニターには2番車の中が映し出されており、丁度中央にシムが座っている。感覚としてはガラス越しに向かい合わせに話しているような感じだ。ジャッキーは腰に手をやり、少ししゃくれ気味の顎を得意げに突き出して見せた。反対にシムは眉間にしわを寄せ、そのふくよかな顔に対して随分と小さな縁の眼鏡を人差し指で押し上げた。
『…ジャッキー、そいつはちょっと慎重すぎやしないか?亜空間展開を封じるにはメインブレンの表面だけじゃダメだ、コアまで届く強力なパルスが必要になれば種類増えるし弾数も相当必要になる』
そして少し高さのあるソフトモヒカンの頂上を左手で幾度も撫でる。これはシムが反対の意思を示す時によくする仕草だった。
『いくらお前でも手順が煩雑になりすぎるし、その割には効果が短い。俺はノードを封じるだけで十分だと踏んでる。それにウィザードみたいな奴らは元々亜空間戦を得意とはしてないって話だろう』
「だったら、あっちの得意の重力下で勝負してやろうじゃない。なあに、その半分はお守り部分さ」
シムはまだ腑に落ちないといった表情のままだったが、ジャッキーはモニター越しにも伝わるよう、大げさな仕草で自信をアピールした。
しかし彼の中に立ちこめる靄のようなものは益々色を濃くするばかりだった。
1章・8―それぞれの背後に蠢くもの
―8月26日、04時15分―
州警察が旧井更邸への踏み込みを決断したのは日の出があとわずかまで迫った時刻だった。
しかし決定から今度は実行に移すまで、もう少し時間を必要とするようだ。
半刻ほど前から州警察、州軍の様々な隊の幹部が本部に集まり、雁首そろえて一つのテーブル越しに睨みあっているが、未だに手順は決まらないままだ。特に軍と警察の協力する作戦では互いが譲らず、調整が土壇場までもつれ込むのはよくある事で、コウザイにとってはさして珍しい場面ではない。しかしあのサイバーSIN社の交渉役とやらが激しく腹を下したとかで余計な待ち時間を生んだのは如何なものかと思われた。今になっても男は姿を現さず、結局土地の所有者であるサイバーSIN社を抜く形で進められる事になった。
後はいかにして一番槍を警察からもぎ取るかがコウザイの仕事だが、今のところ交渉は難航していた。警察の出方次第ではE81を投入しない強硬なカードもちらつかせているが、これまでに大きな手ごたえは得られていない。それに一つ気になる顔もあった。警察の特別機構、特殊甲装機動部隊の班長、イム=ホドリーだ。今までにも数度一緒に仕事をした事がある。彼らは強行突入のエキスパート集団で、連邦陸上部隊の高機動歩兵に匹敵する武装を持っていた。しかし高い機動力こそあれ、武装した歩兵が対重機歩兵戦に耐え得るかと言われればいささか疑問だ。もし彼らが先行し、重機歩兵と対峙する事になれば彼らはほぼ捨て駒になる。コウザイは警察の本心を測りかねていた。
当のホドリーは周囲の喧騒に加わらず、じっと腕を組み静かに目を閉じている。なんとなくその横顔がE81のクラノスと重なって見えた。似て見えるのはホドリーもまたアトロフィクシスだからだろうか。
突然ホドリーとコウザイの間に一人の男がドッカリと腰を下ろした。
「今の話、聞いておられましたかな、二佐殿?こうしましょう、突入はホドリー班長以下特攻102団特殊甲装機動部隊に、E81にはその援護をお願いしたい」
男は携帯端末に目を落としたまま言った。男はひどく早口で言葉に独特のイントネーションを持っていた。小太りで常に全体に汗を浮かべた顔はここへ来てもう何度目かになる、肩書は警部で、名前はファンといったか。一体何をそんな忙しげに端末を弄るのだろう、調べものか、それともカンニングペーパーにでもしているのだろうか。そもそも今の話と言われても、ファンはさっきからうつむいて延々と自分のつま先と会話しているだけで、コウザイには彼と話した記憶などない。全く自分勝手な男だった。
「…なんと、重機歩兵に人間の援護をせよと?それは無茶な話ですな。重機歩兵はその活動に亜空間領域を必要とする、そこに人間が居れば一体どうなるか、警部殿はご存知ないのか?」
コウザイが口を開くと、ファンはそれを制するように掌をこちらに向けた。その間も相変わらずうつむいたままで、あまり躾のなっている人間には見えない。
「軍のご協力には感謝します。しかし考えても見て下さい、あなたがたは重機歩兵重機歩兵と言いますが、容疑者も人質も人間なんです。彼らが戦闘に巻き込まれる危険性だってあるでしょう?」
つま先かコウザイか、一体どちらに話しかけているのだろうか。するとそれまで黙っていたホドリーが口を開いた。
「E81には重機歩兵が確認でき次第、追って援護の指示を出す。我々特殊甲装機動部隊が重機歩兵の戦闘領域に巻き込まれる可能性はほぼない。何が出ようと容疑者も人質も我々で確保できる」
「しかし…」
彼らの武装には高機動歩兵同様の抗次元障壁機能が備わっている事くらいはコウザイも承知している。それでも足元をうろつかれればE81の活動に支障が出る事にはかわりはないのだ。コウザイの一任で決めるわけにはいかなかった。その間もホドリーはその細い目で威嚇を続けているが(実際は睨みつけているわけではないかもしれないが)、はたしてE81はこの条件を大人しく呑むだろうか。
そこで初めてコウザイはクラノスの到着がやけに遅い事に気がついた。
「E81のロータスクルーソ中尉はどこか、彼と直接話がしたい」
ホドリーに畳みかけられコウザイは言葉に詰まった。警察側の召集を受け州軍本部を出る際、もう一度部隊と連絡を取り合ってから向かうと踵を返し、奥へ戻って行ったのが彼を見た最後だ。当然後で追ってくるものと思い込んでコウザイはここまで一人でやってきた。
慌てて端末のGPSを繰ると、彼の位置を示すマーカーはまだ州軍本部のテント内にあった。それから何度も呼び出したが、応答がない。
「どうしました…まさか中尉はそこで居眠り中なんて事はないんでしょう?」
ようやく手元から顔をあげたファンの、その脂ぎった顔がにやりと歪んだ。
「これはとんだ茶番劇が始まりましたな二佐、言っておきますが犯人を捉えるのは我々警察の仕事です。軍は我々の指示に従って重機歩兵を駆逐してくれればそれでいいのです。一々意図は聞きませんが、大事な現場を踏み荒らされちゃこっちも黙ってはいられませんよ」
コウザイはひどく混乱し、ここで自分がどう振舞う事が最良かわからず押し黙った。
「我々も容疑者には色々聞きたい事があるんです。出来るだけ生きたまま確保したい、そこはお互い様じゃないんですかね」
ファンはまるで悪徳刑事のようで憎たらしい顔で声を立てずに笑った。
それからコウザイは転がり出るように本部を後にすると、州軍のテントへと駆け戻った。
やはり頼りにしていた通信機は、テント奥の長椅子に放り出されたままだった。
1章・9―単独突入の決行
見上げればそこには真四角に切りぬいたような夜空がある。
昔は地上の夜空にも太陽系よりはるか先の星々が見えたらしい。満天の星空とは一体どういうものだったのだろう。昼夜問わず眩い都会の灯の届かないテシマの空は、ただひたすらの闇だ。
交信機からは誰の声ともつかぬざわめきが雑音のように鳴り続けている。クラノスが仕掛けたGPSのトラップに気付いて以降、州軍本部の様子はずっとこの調子だった。
人の良いコウザイには悪いと思ったが、彼が警察との交渉に出た直後からクラノスは行動を起こしていた。サイバーSIN社の男とやらが思いの外、時間を引き延ばしてくれた事は嬉しい誤算だった。まさか奴の胃腸にまで来るとは思わなかったが、ジェファーソン式精神知覚尋問もあながち眉唾物ではない。そして今さっきコウザイが数人に我らの重装輸送車両を探しに行くよう命じていたが、心配には及ばない。彼らの指示に従い大人しく投降するE81ではないし、時もうすでに遅しだ。
それにファンとかいう男が言ったように、警察も人質救出より犯人を生きて確保したい事情の方が優先なようだ。お互い真っ向からぶつかる可能性が低いのはありがたい。人質のウルマン氏には気の毒だか、我々の決着がつくまでは息を殺して大人しく待っていてもらう他ない。いや、ウルマン氏とやらがサイバーSIN社の重役であるからには、ひょっとするとこのどこかで一枚噛んでいるのかもしれないが。
何にせよ、先手を打っておいて正解だった。あの熱血警察官、イム=ホドリーが追いついてくる前に何とかして始末をつけなければならない。
クラノスは再び上空を見上げた。夜空が真四角に見えたのは、彼の居場所が天井の抜けた直方体をした巨大な建造物の中だったからだ。四方を崖のような壁に囲まれて、それに対し自分がなんとちっぽけなものかとありきたりの感想を内に飲み込む。頭上を吹き抜ける風がまるで大きな笛の音の様な、奇妙な音を立てている。その壁の頂上に意識を向けると、暗視スコープが即座に絶壁の高さを算出した。ほぼ垂直にして二十数メートル、見上げるクラノスからは少し内に反っては見えるが、数値は目測とそう大差はなかった。スコープ内装機器とシムの測量技術に狂いさえなければ、ここは今「目標」少し手前、クラノスは旧井更邸の北の外堀まで来ているはずだった。あとはこの壁をよじ登り、外に出れば犯人の重機歩兵が潜むという「櫓」は目と鼻の先にあるはずだ。
この奇妙な建造物は敷地内外から伸びる複雑な回廊が一所に集まる塔のようなものだった。回廊は迷路のように地上にも地下にも敷地の至る所に伸びており、クラノスも外側まで通じていた地下通路の一つを伝ってここまで来た。しかしどういった意図か、道はこの塔ですっぱりと途切れ、出口はこの切り立った壁だった。幸いクラノスはその中の最下層に出る事ができたが、もっと高い位置に出たとしたら、そしてもしそこから踏み外していたらと思うと背筋が寒くなる。見れば同じような通路の終点がいくつも、まるで大きな窓枠のように壁面の至る所に散らばっていた。ひょっとするとこれは元から人の通路などではなく、水路か何か、また別の目的で作られたものなのだろうか。クラノスが頭をひねったところで答えはでそうにない。連邦きっての大金持ちともあれば、邸宅の作りさえ凡人の理解の範囲を出るものらしい。幸い壁は未知の素材ではなくどこぞから切り出してきたような天然の石材でできているようで、所どころに積み重ねられた形跡さえ見える。大量に雨が降れば立派な貯水層にもなりそうだが、地面はからからに乾いていた。もうこれ以上使い道について考えても無駄だろう。
「俺は高いところがあまり好きではないんだがな」
そう一人ごちると、いよいよクラノスは壁をよじ登る覚悟を決めた。
目についたのは横に一本だけ見える細い非常用梯子だった。しかしそれも所どころに激しい劣化が見られ、見上げただけでも壁からはがれてしまっている個所がいくつもある。戦闘補助装甲を含めると百キロを超えるクラノスの体重を支えるには少し心許ない。今度は壁の構造に意識を傾けると、彼の注意に合わせて再び暗視スコープが働き、表面の様子を探りにかかる。壁は多少風化して脆くはなっているものの、元の材質は堅く充分な強度があった。
クラノスは数歩の助走を取り、おもむろに駆けだした。そしてわずかな屈伸だけで瞬く間に背丈の倍ほどの空間を飛び上がる。不意の行動に驚いた暗視スコープが彼の動きに合わせ探索を開始し、人の手の掛るような壁の凹凸を探す。いくつか候補があるようだが、クラノスは最も離れた真上の通路の縁を選んだ。わずかに飛距離が足りず、急いで靴底のアイゼンを垂直の壁に打ち付ける。そして踵の杭を目いっぱい壁に食い込ませると力任せに上方向へと駆け上がった。石造りの壁がクラノスの体重とアイゼンの杭に切り裂かれ、火花と金きり音を立てた。そして何とか目的の通路に体を潜り込ませると、再び上を目指して切り立った壁からおそるおそる頭だけを出す。しかしこれで登れたのは僅か数メートル程で、残り二十メートル、残念ながらこの先助走なしに這いあがれるような足掛かりを見つける事はできそうになかった。
自分自身の力だけでこれを登りきるのは不可能だという結論に至ると、今度は腰の背中側に両手を回し、クラノスは戦闘補助装甲の起動スイッチを探った。これさえあれば重力をコントロールし、人とは思えないほど高い機動力を発揮することができる。着る者がアトロフィクシスなら尚の事だ。一見非常に便利そうだが、高コストな上に使用中に設計者が想定していない超状現象によって自損他損問わない事故をおこすという少々のリスクも伴う。
そんなこんなでスイッチは誤作動防止の為に、ほぼ同時に押さねば起動しない仕組みだった。基地を出てから何度も試したが、それが功を奏して本番は思いの他上手くいった。各パーツの装甲の隙間が青白く光り、それまで闇に溶け込んでいた彼の姿が輪郭までくっきりと描き出される。こう目立っては危なくて仕方がないが、引き換えにそれまではただの重石でしかなかった装甲が一気に軽くなった。戦闘補助装甲はただの鎧ではなく、電気的に歩兵の白兵戦を補助する、いわゆるバトルスーツのようなものだった。
高い周波数の小型エンジンの音が落ち着くまでしばらく待つと、クラノスはその場で垂直に跳躍し、天井の縁に指の力だけでぶら下がった。それから下半身を肘と膝のつきそうな位まで引き上げると、さらに手の指の力だけで通路の外側まで這い出していく。傍から見ればまるで壁を這う蜘蛛のように見えるだろう。本物の蜘蛛ならここから頭を上にも下にもむけるだろうが、高所恐怖症気味のクラノスにはそれはできない相談だ。その間スーツの背後からは低く唸るような電子音と、大小の青い光がいくつも現れては消えた。光の正体はこのバトルスーツがクラノスに超人的な力を与える際の副産物だ。それがやがで背中の一点に集まり、眩いほどの光球に変化したかと思うと、それに体を押し上げられつつ今度はまるでネコような格好で壁を駆けあがり、ものの十秒もしない内に上へと消えていった。
「おっと…」
辿りついた頂上は思いの外足場が狭く、勢い余って足を踏み外すところだった。
彼の転落を阻むかのように下からは生ぬるい夜風が巻き上がる。塔の頂上で彼を待っていたのはただひたすら広い夜空と、建物の形に沿って吹き荒れる上昇気流だった。外側から見ると塔はピラミッドのような姿をしていた。目を凝らすとピラミッド状に見えたのは地下から地上から塔に向けて走る迷路が複雑に絡み合った集合体で、むしろ大樹の根と表現した方が良いかもしれない。ますますこの建造物に対する謎は深まっていくばかりだった。
しかし苦労して高い場所まで昇って来たというだけあって、見通しだけはすこぶる良い。眼下に広がる旧井更家はあまりに広大で目眩すら起こしそうなほどだった。
敷地の中に張り巡らされているのは不思議な通路だけではなかった。地上には至る所に高い壁が連なっており、それが中心の母屋まで何重にも続いていた。これは住居というより、まるで巨大な砦か大量の囚人を閉じ込めておくための収容所のようだ。しかしそれも月日が経過したせいか、下半分くらいまでは鬱蒼と茂る木々の中に埋もれてしまっている。浩浩たる屋敷をも飲み込まんとする海原のごとく迫りくる木々は、クラノスの立つ塔の真下にまで迫っていた。それらはよく成長した悪樹ゴートパインの木々で、雄羊の角のようにうねる真っ黒な枝葉を競う合うように天に向けて伸ばし、今は夜風に身を任せてたなびいている。建物の下半分が奈落のように暗く見える理由は、幹も葉もタールをぶちまけたように黒い彼らのせいかもしれない。それにしても噂に聞く悪臭が全くといっていいほどしないのは不思議だった。井更家の前では植物すら萎縮し、毒素を撒き散らすのをためらうのだろうか。
さて、ここで一つクラノスはまだ未解決のままの問題を解消せねばならなかった。彼はこの作戦…つまり誰にも断りを入れず単身井更邸に乗り込む計画を味方、それも副官のジャッキー少尉にすら明かしてはいない。明かせばたちまち反対に合い、ここまで迅速かつ思い通りに動く事ができなかったろう。しかしE81がそれに気付いた時、彼らはクラノスの期待通りに働いてくれるだろうか。
重機歩兵の戦闘領域周辺に大量に現れる次元障壁、それに人間が触れればたちまち死に直結する深手を負う。重機歩兵に乗っていれば少なからず、運悪くそれに巻き込まれた生き物の姿を目にする事がある。重機歩兵乗りにとっては戦闘が起こると知ってそこに向かう事は、空爆の始まろうという街にわざわざ入って行くに等しい。
クラノスはそこで静かに目を閉じた。ヘッドセットのスコープが眼前の目標を捉えてけたたましく警報を鳴らし続けている。その影にまだ動きはないが、相手は人間だ。ひょっとすると気配を感じ取れるかもしれないと思い、意識を集中させた。しかし吹き上げる風が集中を妨げるのか、空気はただ生ぬるく変化は感じられないでいる。
そろそろコウザイの部下達が重装輸送車両に辿りつき、ジャッキー達にも彼の行動が伝わっている頃だ。敵に位置を知られない為にもなるべく余計な電波を飛ばさないようにスニーキングモードを取っているせいで、ジャッキー達の様子をうかがい知る事はできない。あとは息を殺して彼らの登場を待っているほかなかった。
味方が見つけてくれるのが先か、それとも敵に気付かれるのが先か。前者でなければここで孤軍奮闘し、二十五年の人生に終止符を打つ事になるかもしれない。そんな彼の思考を遮る程の突風が吹き荒れたのは、その直後だった。その場に立っていられないほどのダウンバースト、続いて空を裂くようなインパクトを合図に、左右の空に閃光が走った。
『…ッ…アホタレー…ッ………!!!』
何もない空間に同時に二つ、最初の光はここから見るとちょうど毬ほどの大きさだった。クラノスを真ん中に挟むようにして、左右どちらも距離にして数百メートルは離れているだろうか。それがみるみる膨れ上がり、少し遅れてどす黒い中空が現れる。球表面の光がまるで卵の殻の様に薄くなった頃、光は突然無の色になった。例えるなら闇夜よりもっと暗い暗黒の色だ。どんどん膨張し続ける無の色の球の表面を、稲光にも似た眩しい閃光が行く筋も駆け巡る。やがて球体の底が地面にまで達したかと思うと、中央にそれぞれ一体ずつの人影が浮かび上がった。
「来たか」
それは確かに人影を思わせたが、それにしてはあまりに大きい。周囲の光がはじけ飛ぶと、中からビルのような巨体を持つ鎧人形が現れた。
連邦国軍の高機動型重機歩兵、通称“ZIXO”、黄褐色の塗装と末端に向けて肥大した肢体、それに円柱を横倒しにしたような頭部が特徴的な重機歩兵だった。転送投入用に展開した亜空間が閉じ二機の巨人に重力がかかると、それぞれが背負うバックスラスターがそれに抗おうと火を噴きあげ、爆音と爆風を辺りに撒き散らした。全長15メートルはあろうかという巨体を支える力は凄まじく、暴風に巻き込まれたゴートパインが根こそぎ宙に吸い上げられ、凶器となって近くの壁をなぎ倒していく。次はもう少し自然に配慮した出撃方法を選ばせなければならない。その間吹き飛ばされぬようクラノスは必死に塔の縁にしがみついていた。
「思いの外早かったな。それより、次からバックスラスターを使う時にはもう少し俺から離れろ、これでは立ってもいられない」
『…ナン…ダ、ト?ぬけぬけとこの野郎!』
左側の巨人の声がヘッドセットを通じてクラノスの耳に届いた。正しくは、ZIXOを操縦しているジャッキーの声だ。
『ついにボケの来たお前が徘徊をおっ始めたって、22師団の皆様が青い顔で報告に来たぞ!だから探しに来てやったまでだ!さあ帰るぞ!』
どうやらコウザイに行動を封じ込められる前に688、726号機の出撃が間に合ったようだ。一つ目の関門は問題なく越えられた。
「断る、苦労してここまで来たんだ。お前らも折角出てきたんだろ、援護しろ」
するとお決まりの罵声がヘッドセットを通じて鼓膜に届いたが、クラノスは気にも止めない。
そしてZIXO二機の両足が地面を踏むと、足元の地面が大きく揺れた。それにつられて垂直の壁が波打ち、振り払われてしまわないようクラノスは再びしゃがみ込んで波が引くのを待たねばならなかった。ジェットエンジンの脅威こそおさまったもののハイバックスラスターに取り付けられた識別灯がストロボの様に発光し、代わって存在感を増した重機歩兵本体のパルスエンジンの、まるで心音のような独特の音が周囲の空気を揺らし続ける。それだけで既に朽ち落ちはじめている井更邸が崩壊するのではないかとさえ思うほどだ。はたしてこの挑発に相手はいつ乗ってくるだろうか。
「敵は目の前の櫓の中だ。もしもの時は戦闘領域をなるべく上方へ開け、相手は一機だ、抵抗されても二機あれば展開位置を修正できる」
『はあ?お前の目よりシオの目の方がずっといいのよ。それにもしもじゃねぇよ、とっくに気付いて相当殺気だってるぜ』
「…なに、動き出したか?」
基地を出てからというもの、しつこいほどに人質も犯人も人間全てを生かしたままにしろと言い聞かせて来た。少々手荒い事を好む部下たちだが、課題に頭を悩ませる時間は十分にあったはずだ。
チェリーホック弾も目立つ場所に積んでおいた。射撃において精度の高いジャッキーの腕があれば作動環境を整える事が困難な麻痺弾も使用できる。それに宇宙軍でストリング処理を受けているケリーならば一機でも戦闘領域展開をリードしていけるはずだ。あとは何とか上手くやってくれる、そう信じるしかない。
『ほら見ろケリー、言っただろ、やはり俺の悪い予感は間違ってなかった!それに俺はさっき夢に見たぞ、この戦闘が終わった後、次元障壁に噛みつかれて半分になった奴の死体が地面に転がってるのをよッ』
「ジャッキーお前、やっぱりさっき昼寝していたんだな…」
クラノスはさっきのジャッキーの寝ぼけた声を思い出して呟いた。普段から口の堅いケリーは意味深な笑い声を静かにたてただけだったが、今の自白は事実に基づいたものだったろう。だとした死体を夢で見たとは不吉な、アトロフィクシスの中には予知夢を見る者もいるらしい。
そんな危険を承知でここへ来たクラノスの成すべき事は、チェリーホックでウィザードが機能低下しているほんのわずかな時間内に、速やかにパイロットを外へ引きずり出す事だ。装甲が薄く対重機歩兵用でないウィザードなら、物理的戦闘不能になる頃には操縦士もまともではいられないだろう。幸い、ジャッキーもケリーもメインウエポンに半有線弾射撃用ライフルを選択していた。仮に688号機がソードブレイカーを握ってでもいれば止むなく撤退せねばならないところだった。
その時、櫓の下で何かが光った。
1章・10―『オワラヌキョウフ』
*****
次に少女が目覚めたのは、冷たい壁の狭い隙間だった。
まるで自分の意思でそこに座り込み、眠りこけていたような格好で。
あの逃げ回っていた時の息苦しさは消え、あれだけ痛んだ首の傷が嘘のように消えていた。夢だったのだろうか。それにしては不思議な場所で目を覚ましたものだった。さっきから下で低く唸る音は何かの機械の駆動音だろうか、床は濁った湖面のように揺らいで見えるが、堅く、まるで温度を感じない。まだ出足の痺れがあるのだろうか、ゆっくりと自分の手をこすり合わせてみれば温かく、これといった痛みもない。もしや自分が本当に死んでしまったのではと思い始めた時、徐々に五感が冴え渡って来た。
足先に何か触れるものを感じて手を伸ばそうとしたが、何ともないと思っていた下半身がピクリとも動かず、不用意に伸ばした右手に痛みが走った。
「アヤセ!」
突然地面が傾き、それが斜面を滑って次の壁に衝突し小さな物音を立てた。そこには辛うじて足元が見える程度の灯りしかないが、今一瞬目の前を通り過ぎたものは確かに鳥の形をしていた。翼を広げれば大人の両腕程の大きさがある、てっきり逸れたと思いこんでいたアヤセの影に違いなかった。その間も床の傾きはどんどん増していき、それまでは気にならない程度だった振動が次第に騒音に変化し、鼓膜を激しく振るわせた。まるで耳元で太鼓を打ち鳴らされているかのような音は頭の芯にまで届き、少女は恐怖のあまり両手で頭を覆った。
そうしている内にも床の傾きは増して行き、やがて縦から横へと回転方向が変わっていく。それでも下半身は石の様に地面に張り付いたままで、自由な上半身だけが隣の壁に押しつけられ、重力が容赦なく肺を圧迫する。心なしか壁が熱を持ったように感じ、その不愉快さから腕で押し返すようにしてあがいた。すると視線の前に、またあの死んだ魚の目を持つ女が現れた。女は複雑に入り組んだ機械の中に埋もれるようにして、唯一頭だけが突き出して露出していた。相変わらずそこには感情の欠片も見当たらなかった。大きく見開かれたままの瞳が左右に素早く動くと、それに合わせて幾つもの映像が空中に投影されていく。女の動きは相変わらずひどく機械的で、二つの目はまるで別々の意思を持つように自在に動き回った。今にもそのぎこちない動きに合わせてぬかるんだ不気味な音までもが聞こえてきそうだ。
浮かんでは消えを繰り返し、めまぐるしく変化する少女にとってはまるで意味のない画像を眺めながら、彼女は徐々に自分の身の上を悟っていった。そこはさっき目の前に現れた死神の中だった。脈打つような低い唸り声は戦争人形の鼓動であり、この女に呼応して動き出そうとしているのだ。
少女はこの場所に見おぼえがあった。あまりにも遠い昔の記憶で、おぼろげでしかないが、場所だけではなくこの女にも。
「ナタリー…」
どこか懐かしいようで、それなのにまるで生気を感じない女にどうしようもない嫌悪感があふれ出た。
「…嫌だ、やめてよ!一体私をどこへ連れて行く気なの?」
戻りかけた力を振り絞って少女は叫んだ。しかし相手の口元はさっきからボソボソ何かを呟くばかりで、こちらの声が耳に届いているかどうかもわからない。相変わらず絶望的な状況には変わりはなかった。
「ここから出してっ!」
咄嗟に出た言葉だった。すると何語だろうか、突然女が意味のわからない言葉を大声で叫んだ。
途端に少女は再び意識を手放しかける。床にそのままめり込みそうな程の強い圧迫感を全身に受けたかと思うと、今度は視界が全方位にグルグルと急回転する。少女は悲鳴をあげようとしたが、代わりに何かどす黒い物を吐き出しそうになり、口を押さえそれを何とか呑みこんだ。そして次の瞬間、背中が何かに激突し、再び視界が白んだ。薄れゆく意識の中、少女はまたあの死神のガラス玉でできあがった目と顎から突き出した牙を見た気がした。
*****
1章・11―動き出した目標
「やはりそこに居たのか、どうやら連邦と一戦交える覚悟ができたようだな」
シムの推測どおり、敵は櫓の真下に居た。そこから垂直に飛び出してきた重機歩兵はZIXOの半分くらいの大きさでしかなかった。それに随分と細身で人というより鳥に近い姿だと言った方がいいだろうか、体はずんぐりしているが、手は極端に短く足は先に行くにしたがって細い、踵が高く前に反りかえって見える脚部はまるでダチョウのようだ。完全なる一致ではないが、各所の特徴からして中央首都防衛軍の使用するウィザードに近い存在と見て間違いないだろう。
地中から飛び出す間際にウィザードから放たれた衝撃波で、櫓の中腹はごっそりくり抜かれたように消えて無くなっていた。支えを無くした梁がバリバリと音を立てて折れ、たちまち全体の崩壊が始まった。クラノスには始めて見る現象だったが、このウィザードというのは次元障壁の脅威をも破壊行為に用いるようだ。失われた部分はとうに異次元の向こうだろう。
ZIXOに対してマウントポジションでも取ろうと言うのか、そこからしばらく上昇すると、ウィザードは二機の頭上に空中停止した。
空中で非常に俊敏な動きを見せるウィザードだが、背後のドーム状の特徴的な飛行推進装置は非常に小型で、移動速度はZIXOより優れていると見える。そんな技術があるのならずっと治安の悪い地方にも分け与えて然るべしだ。しかし流線型を取らない重機歩兵が高速で空を切り裂く音は凄まじく、バーニアから吐き出される噴煙も半端な物ではない。煙幕のように濁った多量の排煙は故障かと疑いたくなるほどだ。そのくせ空中でよく動きだがるから性質が悪い。たちまちクラノスの周囲にも噴煙の波が押し寄せ、塔全体が粉塵に包まれた。そんな中狙撃されてはさすがに避けようがなかったが、あがいてもどうにかなるものではない。
一般的な戦闘を行わないウィザードの両腕にあたる部分は特殊な砲座に置きかえられており、体制を変えずとも一度に多角度にわたる精密射撃が可能だと聞き及んでいる。もし相手がその気ならあっという間に可視砲の餌食になるだろう。圧倒的かつ不可思議な力で次々とテロリストを撃ち抜く様はまるで魔法使いの如し、そう言っていたのは首都防衛軍に居た叔父のコレール卿だった気がするが、その叔父も去年自宅でぱたりと心臓が止まりそのまま死んだ。もし自慢の兵器が民家で暴れている姿をあの世から見ているとすれば、あの自惚れ屋は一体どんな顔をするだろう。しかし彼が一族で唯一、クラノスに重機歩兵に乗る事を勧めた人間だった。
あんな黒ずくめで絞めた鳥の様な不格好な重機歩兵を、叔父上はよく勧めてくれたものだと改めて思う。クラノスは恐ろしい魔法使いに気付かれぬよう、屈んで白いモヤの引くのを待った。
『おいおいシムの旦那、コイツが噂のウィザード様か!?変な格好しやがって、ダチョウが空を飛ぶなんて聞いた事はねぇな!』
どうやらそれに対峙しているジャッキーはこの状況を楽しんでいるようだった。まだクラノスは埃の中だが、ウィザードの注意は今のところZIXOの二機に集中していると見ていいだろう。
ウィザードを彼らに任せ、その間にクラノスは道中通路に放ってきた自律型探索機(マルチプルシーカー)の解析結果を確かめた。まだ二十パーセントも仕事を済ませていないようだが、今のところこれらが人に接触した記録がない。櫓に向かわせていた数機はすでにロストしており、時間から見るに今の衝撃波と一緒に失われたと思って良さそうだった。こちらにも人と接触した記録は残っていない。あのウィザードに乗る人間が侵入者の一味には違いないだろうが、はたしてそこにターゲットである井更家の娘が乗り込んでいるかどうかはまだわからない。
「688、726号機共に待機解除、ウィザードに攻撃を開始する。だが一機と思って油断するな、この先も敵の増援には十分注意しろ。バトルフィールドは水平方位1000に固定。くれぐれも派手に壊すなよ、戦闘領域内で自由を奪ったら後は重力に任せてやればいい」
それを聞いたジャッキーが再び奇声をあげた。
『オイオイオイ、当たり前みたいに指示出しやがって。気を利かせてBB(ブレインブレイク)弾を用意してきてやった方はドナタだ?俺様だろ?』
「…わかった、お前の気転に感謝するよ」
ジャッキーの軽口もどこからどこまでが本気なのか、測りかねるところが難点だった。意外と冷静かと思いきや、やりすぎる事もままある。とにかくマルチプルシーカーが敷地内に残る他の人間の居場所を突き止めるまでは重機歩兵の南下は避けたい。ホドリー達の動向も気になるが、彼らは巧みに隠れているのか未だに影すら見る事はできないでいる。
「ジャッキー、くれぐれもウィザードは真下に落とせよ。じゃあないと俺まで巻き添えをくらうからな」
『はぁ?今お前の丁度頭上ですけど?それより、今からシム様がどっかの大馬鹿野郎の為にBB弾の撃ち込み個所と段数を算出してくださる。その間お前は囮となってウィザードを引きつけろ』
「…それも断る」
当然、彼らが一仕事終えてくれるまでクラノスはどこか安全な場所に身を隠すつもりだ。この喧騒だ、ホドリーも直接ここへ乗り込む程馬鹿ではないと信じたい。そうすればクラノスもジャッキーがウィザードの頭脳を麻痺させるに足りる段数チェリーホックを撃ちんでいる間、心おきなく身をかくしておけるというものだ。
頭上で凄まじい破裂音が数度鳴り響いた。三機の重機歩兵が次元の壁を超え戦闘領域に入り込んだようで、見上げるクラノスの目には彼らの姿が時折透けて見えた。中と外との時間や位置のずれか、像は断片的でぎこちなく目に映る。そして戦闘領域とこちら側との次元の境は視覚でとらえる事が出来ないために、確認するにはヘッドセットに仕込まれた計器に頼るしかない。それは今のところ彼の言いつけどおり、順調に上空に向かって伸びているようだ。半有線のチェリーホック弾の射程を考えるとこれ以上ニョキニョキと伸びていくのは好ましくないが、ここは二人の腕を信じて見守るしかない。クラノスは天を仰ぐようにしてその様子を眺めたまま、今度は前方の断崖絶壁に身を躍らせた。
別に急に高所恐怖症が解消されたわけではない。
彼の背後に再びあの青白い光球が現れる。このバトルスーツはとても高性能で、数十メートル程度の高さからなら人を安全に地面まで軟着陸させる機能が備わっている。それを利用し、クラノスは塔に向かって絡み合う通路の間、その深い闇の縁に姿を消した。
1章・12―『イサラケノムスメ』
少女はフラフラと立ち上がった。
足は…いつの間にか動くようになっていた。また見慣れぬ景色、さっきとは別の場所で目を覚ましたようだが、またしても辛気臭い暗い室内である事には違いなかった。さっきの衝撃で一体今度はどこへ飛ばされたのだろう。まるで何日もここで眠っていたようにも感じるが、体中の痛みはどんどん増えていく一方だ。短いズボンから剥き出しになった華奢な足には、無数の痣や擦り傷でいっぱいになってしまっていた。中には拳大ほどうっ血している場所もある。これでは格好悪くてしばらくは外にも出かけられそうにない。それに買ったばかりの大事な靴もずいぶん底が減ってしまっている。
「もう嫌だ、アヤセ…」
再会を果たした友はあとほんの少し手を伸ばせば届く場所にいた。だというのに、また逸れてしまった。おそらく友だけがあの死神の中に取り残されてしまったのだ。探しに行こうにも今自分の居る場所すらわからない。死神の姿はもうどこにもなく、ただ遠くに大地の鼓動だけが聞こえてくる。一体何の音だろうか、あの死神は今頃なにをしているのだろうか、まだ自分を探しまわっているのだろうか。自分の事など忘れて遠くへ行って欲しい、恐怖から一刻も早く解放されたい気持ちと、囚われたアヤセを取り戻したいと思う気持ちが彼女の胸中を交錯していた。
いつからかは知らないが、死神と女はこの屋敷の中に長い間静かに眠っていたのだ。そしてそれを起こしてしまったのは紛れもなく彼女自身だった。
知りもしない場所で不用意に色んな装置に手を触れたのは彼女の過ちだったが、そうでもしなければ目的のものは手に入らないと聞かされていたのもまた事実だった。しかし結局目的のものを見つけるどころか、不要なものをただ呼び起こしただけで、それからひたすらに追い回されている。
「私、一体ここに何しに来たんだろう…」
小さく溜め息を一つついて、少女は両手で自分の肩を抱くようにしてその場にうずくまった。
すると一旦は閉じ込められかけた死神…そう、あの重機歩兵の操縦席で見た、ナタリーと呼んだ女の顔が思い出されてきた。知らないようでどこか懐かしい顔、ナタリー、誰かの名前のようでどこか地名のような、彼女の中ではそんな曖昧な景色と響きをもつ言葉だ。ただ言えるのはあの女は確かにナタリーと呼ばれる何者かだという事だ。
「キャンベル=井更様、良かったご無事だったのですね」
不意に話しかけられて、少女は叫び声をあげそうになった。まさか近くまで人が来ていたとはこれっぽっちも気付いていなかったからだ。
それはとても穏やかな声だった。もちろんこんなタイミングで聞かなければの話だが。声の主は今キャンベルと呼ばれた少女を最初に屋敷へ招き入れた男だった。まだ心臓は早鐘のように脈打ち、今にも胸の中から飛び出してきそうなほどだ。白髪の男は何とかストンと名乗った気がするが、はっきり記憶していない。そして彼の風貌もまた、印象に残る様な特徴のない、良くも悪くも普通としかいいようのないものだった。ただ一つ言える事は、屋敷の管理を任されていると言うだけあって仕立てのいい服を着てはいた。
「まずい事になりました、この騒ぎで警察と軍が動き出したようです。このままではあなたが警察に拘束されてしまいます。あなたは一旦速やかに身を隠すべきでしょう」
男はあまり表情の無い顔でそう諭した。いや、穏やかな話し方と似通った温和な顔をしていたと思うのだが、彼の背後から射す僅かな灯りがそれをわかりにくくしていた。
「警察…?」
それを聞いたキャンベルの顔には明らかな困惑の色が広がった。
「待って、約束のものを返してもらわない限りここを離れられないわ」
男は一つ頷いた。
「お返ししたいのは山々ですが、それはまたにしましょう。あの扉は我々がサイバーSIN社に頼んでも長年ビクともしなかったものです。慌てる事はありません。おそらく今後も貴方様がたしか開ける事はできないのでしょうから…」
しかしそれでは困るのだと、男の言葉にキャンベルは割って入った。
「そんな…!」
彼女はここへ一族から預かった、かつて自分の物になったはずの宝物を引き取りに来ていた。とても大事なものだった。それがいつの間に彼女の手元を離れ、彼女の生まれる前にとうに手放されたはずの旧屋敷に今はあるというのだ。まるで狐に鼻をつままれたような話だが、取り返しておかねばならないものだった。いつの間にか誰かに盗まれ、誰かがここへ運んだのだろうか。旧家に生まれ、厳格な家訓の中生きて来た彼女には紛失していた事すら知られてはならない一大事であるはずなのだが、それがいつなのか、その記憶はおぼろげだった。
幸いにしてそれが今の家主に発見され、向こうから引き取りに来るよう頼まれた。それを収納した倉庫の鍵を開ける事ができず、彼らにとって不必要なそれらを持てあましているのだという。そう彼女に手紙を送って来たのは、たしかチャック=ウルマンと名乗る人物だった。
そして実際に屋敷を訪れた彼女を地下倉庫へ案内したのは、この何とかストンという初老の男だった。しかし倉庫の扉を開けた途端、中から現れたのはあの女と重機歩兵だった。男もキャンベル同様大そう驚き、二人で逃げ惑っている内に今に至った。しかし再びこうして現れたこの老人をこのまま信頼していいものか、キャンベルにはわからなくなっていた。自分がこれだけ痣だらけになったというのに、一緒に逃げ回ったにしては彼だけが身ぎれいなままだったからだ。しかし警察はさらにまずい。捕まってヘマをした事が母達や他の一族に知れれば、また彼女達の元に引き戻されてしまうかもしれない。
「さあ、こちらへ」と手を伸ばしかけた男の顎を、キャンベルの掌底が鋭く下から突き返した。
男は短く悲鳴を上げると、その場にひっくりかえった。初老だと思っていた男の体は想定していたより重く、その場に崩れるようにして倒れた。そして男の手から滑り落ちたスタンガンのようなものが床でカラカラと音を立て、二三度光ったかと思うと焦げくさいにおいが立ち込めた。
「やっぱりね。…もう案内は結構、後は私一人で探すから」
男は何かを呻いたが、歯が折れてしまったせいかよく聞き取れなかった。キャンベルは怯む男を背に僅かな灯りに向かって駆けだした。
1章・13―ホドリー再び
クラノスが今度は別の地下通路に潜り込み、敷地の中心に向かって走り出して幾許もたたぬ頃だった。
突然体が鉛のように重くなり、直後何か見えない壁に押し返されるようにしてクラノスは後方に吹き飛んだ。一瞬ついに自分も次元障壁に巻き込まれ不運な最後をむかえるのかと錯覚したが、それはすぐに間違いだと気付いた。ホドリー率いる特殊甲装機動部隊の待ち伏せを受けたのだ。ついでにこのバトルスーツが弱点を持つ旧式だという事も知る事ができた。それを着込んだものだけが引っ掛かる電子網のようなものがあるらしい。何の恨みがあってかは知らないが、執念深い彼らはそんなスパイダーネットを張ってクラノスの前進を妨げたのだった。
「随分と行儀が悪いな、火事場に紛れて隠密活動か、中尉?」
クラノスは尻もちをついたまま、笑いだしそうになった。他人を隠密よばわりしながら、ホドリーの格好は全身黒尽くめで、日に焼けた顔に細筆で描いたような目鼻立ちは絵物語でよく見るニンジャそのものだったからだ。周囲を見渡すと他にも十人以上のニンジャに取り囲まれていた。彼らはクローキング処理(透過処理)を施されたシールドの向こうに隠れていたようで、捕まってしばらくはこの団体一行に気付きもしなかった。
ここもマルチプルシーカーが一度は通った場所のはずだが、この様だ。しかし無理もない、ホドリーを始めアトロフィクシスで固められた部隊は同類のクラノスにその気配を悟られる事無く潜伏する事が可能なのだ。例の肌に刺すような温度は感じられないものの、彼らの表情から殺気にも似た緊張感がしっかりと伝わって来た。まあ、周囲をとり囲まれ銃口を向けられれば例えむこうが笑顔でも殺気立って感じるだろうが。
「こんな人間の好き勝手にうろつくような場所に重機歩兵を降ろせなんて無茶な要求を受けてな、やむなくこうして下見に走り回ってる最中さ。別に俺は君らみたいに次元障壁と戯れるスリルを味わいに来たわけじゃない。邪魔は困るな」
クラノスはある程度コミュニケーションをとる姿勢を見せたつもりだったが、相手は全く意に介さなかった。
「犯人は司法の元で裁かれる、軍の勝手な真似は許さないぞ」
協力を要請しておいて何という言い草だとクラノスは思ったが、何が目的だと聞かないだけホドリーはましな大人だとも思った。それに問答している時間はそう残されてはいない。おもむろに立ち上がると、クラノスは両手を上げて抵抗する意思がない事を示した。
「悪い事は言わん、一度ここから引け。ここにはその内重機歩兵が降ってくる予定だからな」
するとホドリーの細い目の上の無骨な眉毛が少しだけ上に動いた。
「勝手に戦闘を引き起こしておいて何だ。ならばE81が重機歩兵を鎮圧し次第、容疑者をこちらに引き渡してもらう」
さらにホドリーはここで待つと付け加えた。何を勝手な事を、と言いかけてクラノスは口をつぐんだ。ここは大人しく容疑者の引き渡しだけでも承諾したふりでもしなければ、ホドリーはテコでも動かないだろう。わかったとだけ返したが、クラノスの心中は穏やかではなかった。いくら戦闘領域範囲を限定したとはいえ、領域内では上も下もなく、方向感覚を失う事はすくなくない。ウィザードの落下予定地点が大きくずれないとは限らないからだ。ホドリー達に捕獲さえされなければここを一気に駆け抜けてあと二区画先のパニックルームに駆けこんでいるところだ。
そしてクラノスの悪い予想は当たった。
ホドリー達がようやく重い腰をあげかけたところで、天地がひっくり返るのではないかというくらいの大地震に見舞われた。
あれからジャッキーは手際は良く、ウィザードにチェリーホック弾を撃ちこんでいったらしい。物理法則の乱れる戦闘領域で質量弾を正確に命中させる事は想像以上に難しい。一部の機能を低下させるために使用される事はよくあるが、重機歩兵の主頭脳にあたるメインブレンを麻痺させるほどの信号を送り込むには、的確な場所を選定し、さらに必要な量を撃ち込む必要があった。それを全てやって退ける事のできる人間は連邦国軍広しといえど、ジャッキーを含めほんのわずかな人間だけだろう。
主頭脳の根幹が混乱する程大量の妨害信号を流しこまれたウィザードはついに戦闘領域での活動を維持できなくなり、次元障壁を突き破ってこちら側に落下してきた。それが今の地震の正体だった。
直撃こそ免れたものの、そこに居る全員が吹き飛ばされ、全身を嫌というほど壁天井床問わず打ち付けていた。幸いすぐ手前にあったにパニックルームが盾となり、地下通路が全崩落し生き埋めになる最悪の事態には至らなかった。それでも脆くなった壁や天井がボロボロと崩れ落ち、拳大の石や岩がいくつも頭上から降って来た。クラノスやホドリー達が大した怪我をせずに済んだのは、そこにいた全員が着込んでいた特殊装甲服やバトルスーツのおかげに他ならなかった。
「…今のがそうか?」
近くに伏せていたホドリーがクラノスに問いかけ、先へ進めというように顎をしゃくって見せた。ゆるい協力関係ができあがったようだが、ホドリーは犯人逮捕を頑として譲らないし、クラノスは中央軍の密命を果たさねばならない。どの道上手く先に裏切り者になった方が勝ちだ。クラノスはにやりと笑うと、振りかかった砂や瓦礫を払いながら立ち上がった。
元来た道をどれだけか戻ると、そこには巨大な重機歩兵、「ウィザード」の顔があった。地表を頭で突き破り、ちょうどそこにあった広い地下室に上半身をうずめるような格好で停止している。その頭部からだけでも幾筋もチェリーホックをぶら下げており、それらがまだ信号を送り込み続けているとみえて、ウィザードの頭部が時折痙攣を起こすように震えた。偶然かもしれないが、これは上手い場所に落としたものだとクラノスも感心する程だ。
倒壊した天井からはいつの間にか昇っていた朝日が差し込み、まだもうもうと立ち込める粉塵に反射し、辺りを白濁させていた。はたして犯人は無事なのか、幸いウィザードの顔の真下にあるコクピットは瓦礫に埋もれる程度で原形をとどめており、このままの体勢でもハッチの開閉が可能かもしれないという希望が持てた。
「本当に大丈夫なのか?もう動きはしないのか」
クラノスの後についていたホドリーが珍しく尋ねてきた。いくら特殊部隊とはいえ、ホドリー達が間近に重機歩兵を見る機会は少ないだろう。それにこのウィザードという機体は表面に特殊な塗料が使ってあるようで、まるでグリスでも塗りたくられているようにギラついて気味が悪い。さらに地面に激突した衝撃でそこにあったであろう顔の突起物が失われて、真っ赤な補修材がそこからまるで血液のように流れ出していた。それが黒い表面を伝って滴り落ちる絵は無機物とわかっていても生々しいものだ。それに完全に停止に至っていないパルスエンジンが時折思い出したように、魔物のうめき声の様な唸り声を立て恐怖に拍車をかけた。
「大丈夫なものか、コイツが気を失ってる時間はごく僅かだ。信号弾くらいじゃすぐにメインブレンは回復してくる。急ごう、手伝ってくれ」
クラノスはあえて振り返りはしなかったが、背後にはホドリーをはじめ、彼の部下がぴったりと後をつけている気配が感じられた。少し意地悪くそう言ってやったのだが、ヘッドセットを通じて目に入ってくる情報だけを見れば、まだウィザードが目を覚ます兆候はない。一行は足早に、それでいて慎重に、頭の向こう側にあるコクピットを目指して粉塵の中を進んでいった。そこには巨大な円盤のような形の黒い金属の塊があった。おそらくこれがウィザードの胸部コクピットだ。シムの送りつけて来た情報によれば、開閉口はその円盤の裏側部分にあるはずだ。
「人型というより、これはまるで鳥の様だな」
ウィザードの両肩部分にある多角度砲が珍しいのか、ホドリーはしばらく熱心にそれを眺めていた。
「それはライフルにもファランクスにもなる変幻自在の魔法の玉だ。おかげで刀や斧を振り回す他の重機歩兵とちがって街中だって活動できるってわけだ。このウィザードは中央軍が首都防衛の為だけに作り出した鉄の番人だ。もう二度と機会はないかもしれんぞ、今の内にしっかり拝んでおくがいいさ。」
ホドリーはクラノスを振り返ることなく眉間にしわを寄せ、その魔法の砲台を睨みつけた。
「…首都だと?まさかあのNID(ネイド)の事を言ってるのか?あそこは確か増えすぎた軍人の巣食う要塞か何かではなかったか」
ホドリーがあまりに真顔でそう言うので、クラノスは笑いだしてしまった。
「どっちでもいいさ、どの道俺たちアトロフィクシスには無縁の麗しき場所だ」
土埃も収まり始めた頃、目的の扉を見つける事ができた。オレンジのラインに彩られた円盤の縁を一部地面にめり込ませではいるものの、床を削っていない裏側の瓦礫の撤去は簡単に済みそうだった。そしてそこにいる全員が土木作業を手伝ったが、その内の何人かが頭上から滴る例の補修材を被り、中にはその不愉快さに声を上げる者も居た。時折思い出したようにウィザードが肢体を振るわせ、その度に多量の土砂が地上から流れ込み、全員の作業の手を煩わせた。その間クラノスは非常時の外部開閉ボタンを探しまわった。普通ならわかりやすいよう目立つ色でマーキングされているものだが、どういう意図か他と場所と同じ色に塗り込められたそれを探すのには少々手古摺った。
「下がってくれ、開けるぞ」
その言葉を合図に、特殊甲装機動部隊の面々が周囲に散った。ボルトで締め付けられた鋼鉄を無理やりこじ開けると、クラノスはようやく現れた緊急開閉用のバルブを捻る。すると中から空気の勢いよく漏れ出る音がした。しかし、肝心の扉は僅かにずれただけで残りはびくともしない。ライフルを構え、操縦士が出てくるのを今か今かと待っていた隊員に動揺が広がった。
1章・14―操縦士の正体
「墜落で扉が歪んだらしい、手伝えるか班長」
ホドリーは無言で扉に近づき、クラノスとちょうど反対側の縁に手をかけた。ホドリーがほんの指先を隙間に掛けただけで扉が軋む。クラノスの着る旧式で黄褐色のバトルスーツとは違い、警察仕様の最新のものは駆動音こそするものの派手に光を放ったりするようなものではないらしい。そしてどちらからともない合図とともに同時に力を込めると、扉は番を大きく軋ませながら徐々に下方向に開いていった。扉は二段式で、今度は淡い色の中扉が現れた。こちらは正常に作動しており、ガクリという音を立てて分厚い扉が今度は逆方向に跳ね上がった。それにも驚いたが、さらに続けざまに、まるで割った生卵から黄身が滑り落ちるかのように「人間」が中から落ちて来た。
ボトリという音がしたかしなかったか、クラノスもホドリーも一瞬事を飲み込めずしばらくはただ茫然と突っ立っていた。全身の力が抜け、地面(というよりウィザードの外扉の上だが)にへばりつくようにそこに寝そべっているのは二十歳前後の若い女だった。
「死んだのか?」
いや、とだけ言ってクラノスは女の顔を覗き込んだ。両目は見開かれ表情もないが、女はまだ微かだが息をしていた。目を開けたまま寝ているのだろうか、こんな場面でまさかそれはあるまい。
上を見上げればそこからウィザードのコクピットが見えた。思っていたより中は狭く、空間としては緊急時には複座にもなるZIXOの半分もない。少し頭を突っ込んで中をのぞいてみたものの、他に隠れるようなスペースもなさそうだ。という事はこの女が一人で乗り、操縦していたのだろうか。元々こんな格好でひっくり返る想定で作られていないのか、座席は開けっぴろげな構造で、操縦士を固定する装置がとても少なく感じられた。一体これでどう操縦するのか、中央軍の兵器には機密が多く、一目みただけではわからなかった。女はまるで訓練で使われるような簡素なスーツしか身に付けておらず、激しい戦闘には不可欠なトレーシビリティプラグすらつけられていない。
クラノスとホドリーは顔を見合わせた。
見たところ女の体には傷一つないようだった。早速数人が女を確保し、地面に押さえつけるような格好になったが、その間も女は一度も抵抗しなかった。それまでZIXOを相手に戦っていたと思えばどこか大事な糸が切れでもしたのだろうか、とても不思議な容姿の女だった。髪は短く刈り込まれているが、根元から鮮やかな紫に染め上げられ、肌は皮下組織が抜けて見えるほど白い。瞳は濃い青だろうか、何故か瞳孔がはっきりせず、表面は油の浮いたような皮膜で覆われていた。手足は枯れ木のように細く、このまま後ろ手にねじ上げ続ればそのうち折れてしまいそうだった。それでも女は表情一つ変えず、ただ艶めかしい肢体を横たえたまま規則正しく呼吸を繰り返している。
「お前がこの事件の黒幕か?お前が井更の娘か、そうでなくても後で嫌でも口をきいてもらうぞ」
ホドリーの脅しにも、やはり女は何も答えなかった。
重機歩兵については、あっけない幕切れとなった。操縦士との連結が途絶えた途端にパルスエンジンの鼓動は、ついさっき完全に途絶えた。このウィザードが再び動き出す事はもうない。とりあえずの危険は去った。
だがこの女が本当に事件の真犯人、井更家の娘なのだろうか。もしそうなら生きて確保する事はできたが、既に警察の手中にあるも同然だ。このままでは作戦の半分は失敗に終わってしまう。この多勢に無勢、もしここで無理やり娘をかっさらい、基地まで連れ帰るとすれば少々の無理がある。それにこの女がただの共犯者である可能性はまだ大いに残っている。警察も軍も娘の姿はおろか、名前すらも知らないのだ。ならば警察が女の尋問に手古摺っているうちに他にいるかもしれない真犯人を探しにでもいくべきか。しかしそれはあまり現実的ではなかった。
しばらく本部と無線を通じ会話していたホドリーが撤収の合図を出した。両脇を抱えられ引き上げられようとも、女は身動き一つせず、地面についた足先はぐにゃりと曲がったままだ。タイトなスーツが華奢な身体にぴったりと食い込み、無理に上方向に引っ張り上げられたあばらが浮きだしてまるで骸骨のように見えた。これがあのライデンの妹だろうか、いいところの娘にしてはやけに痩せこけているいうのがクラノスのもった印象だった。
引き上げはじめた彼らの後ろ姿に気を取られていると、突如クラノスの背後、無人のはずのウィザードのコクピットから黒い影が躍り出した。
驚いて振り返った全員の目に映ったのは、大きなワシのような姿の鳥だった。鳥はたちまち彼らの頭上まで舞上がった。その間鳥からは数本の光が放たれ、クラノスのすぐ脇を掠めて行った。
すると今まで死人のように沈黙していた女の体がのたうつ様してに大きくのけ反った。そして直後サイレンのような音が周囲に轟いた。それが彼らの聞いた、最初で最後の女の声だった。
1章・15―鉄の鳥
光の矢は全部で三本放たれたようだった。
女の着ていたスーツが首から腰にかけて黒く焼け焦げて、僅かに煙の様なものが昇っていた。
「何事だ!」
振り返ったホドリーの顔には疑いの色がありありと浮かんでいた。しかし犯人は別にいてしかもそれがまだ頭上のどこかに潜伏しているとあって、クラノスは天井を凝視しつつ片手を挙げるくらいの事しかできなかった。あの時は見えなかったが、コクピットにもう一人潜んでいたのだろうか。倒れたままのウィザードの外殻の上を、何者かが歩き回っている金属音が微かに聞こえてくる。しかし人にしてはあれは小さな影だった。やはり鳥だったのだろうか、どちらにせよ忌々しい輩には違いない。これで体を張ったクラノスの作戦全てが失敗に終わるかもしれないのだ。
しばらくして容疑が晴れたのか、クラノスの索敵活動に特殊甲装機動隊も数人加わった。それでもまだ犯人を見つける事ができない。
女の方は絶望的なようで、救護担当者が何度も蘇生を試みては徒労に帰している。ホドリーは苛立った様子で忙しなく歩き回り、今度は逆に本部に応援を求めたようだが、到着にはもうしばらくかかりそうだ。
未だに姿を見せない敵をじりじりと待ちつつ、クラノスは腰にぶら下げた刀の鍔に手をかけた。落ち着かない時の癖だった。さっきからいくら意識を集中しても気配が感じられない。犯人はもうここから立ち去ってしまった後なのだろうか、だがかすかにまだ足音は聞こえるような気がする。クラノスはふと子どもの頃に行った動物園での出来事を思い出した。あれはなけなしの小遣いをはたいて買った餌を与えようと鳥舎に入った時の事だ。そこには彼を取り囲み熱心に餌をねだる沢山の色鮮やかな鳥たち。なぜか触れても居ないのに無数の棒の先で全身をつつかれるような変な感覚にとらわれた。それは餌を焦らすごとに酷くなり、ついに耐えきれなくなって餌を放り出しその場を逃げ出した。
どうやら鳥とはあまり良い縁がない。
しかしその経験上、今潜む敵が例え人ではなく鳥だとしても、生き物であればその気配は感じ取れるはずなのだ。
そう思った矢先、再び何かが大きな風切り音を立てて頭上を掠めた。今度向かった先は天井近くの狭い通気口だった。そこには鉄製の蓋がされており、もし動物なら堅い鉄格子に侵入を阻まれ命を落とすだろうと思われたが、結果は違った。鳥は鉄製の格子を切り裂き中へ消えていった。その間一人が数発の弾丸を発射したが、全て虚しく壁を穿っただけだった。衝突の衝撃でねじ曲がった格子が外れ、床に落ちて大きな音を立てた。クラノスは終始目を凝らし姿を凝視していたが、やはりその後ろ姿は鳥以外のなにものでもなかった。
「逃がした…」
鳥はどこへ向かったのだろうか。役目を終えてただこの場から逃げ出したのだろうか。ならばわざわざ狭い通路を選ばずとも上空に逃げれば済む事だ。
「ジャッキー、TENTO索敵、手伝え!」
はぁかへぇか、ジャッキーの中途半端な返事が聞こえた。まだ撤収の号令をかけていないZIXOは、屋敷周囲に待機しているはずだ。
その間もホドリー達はまだ蘇生処置を続けていた。光の矢は女の背中から胸部へと抜けており、剥き出しになった皮膚はスーツの表面と同じように黒く変色し、組織の一部は墨になっていた。傷口は光学小銃を使用したものとよく似ていたが、口径はそれよりずっと大きな物であると推測された。悲鳴を上げる時間こそあったかもしれないが、頸椎を焼き切られていればそう長く苦しまずに済んだだろう。だとすればあれは鳥ではなく、小型の無人攻撃機か何かだったのだろうか。
「自律型攻撃機、飛行型だ。熱傷型のベジェ砲を積んでる、ここから南西へ逃げた。探してくれ」
『………自動で飛行型だと?おいおい、この屋敷の中にそんなもんがいくつ入り込んでると思ってるんだ?』
しばらく間を置いたジャッキーがそう答えた。クラノスの脳裏にここへ来た時最初に見た大量の自走式照明がよぎった。警察が、いやそれだけではないかもしれない、沢山の人間が屋敷に続々と乗り込みはじめているようだった。
「待て!」
走り出した途端にホドリーが背後でそう叫んだが、クラノスは振り返らなかった。彼らは追ってくる気まではないようだった。
索敵が無理なら足で追うしかない。敵の潜り込んだ通気口は狭く、とても通れそうにない。クラノスは別のルートで追い、上手く待ち伏せる場所を探すしかなかった。通気口の真下の通路に飛び込むと、同じように南西を目指す。しかし間もなく瓦礫の山につき当たった。その先の道は重機歩兵の墜落によって崩落してしまったらしい。周囲には同じような場所がいくつもあった。そこから左に迂回し、崩落の起きていない数少ないルートを選び出し先を目指す。もはや誰かの目を気にする必要はない、しばらく直線の続く場所では遠慮なく速度をあげた。それでも入り組んだ通路ではせいぜい全速力の半分くらいが限界だろうか。鳥に引き離されるのではないかと配になった頃、ある分岐路に差し掛かりクラノスは足を止めた。それは地図にはない、TENTOの検索にすらかかっていない通路への入り口だった。今までにも同じような別ルートへの分岐はいくつもあったが、そこだけは通路の材質が石造りから金属に切り変わっていた。照明を向けると鈍く青味がかって光を乱反射させ、光は少し奥で緩やかにカーブした道の向こうに消えていく。薄暗い場所に長くいたせいか、クラノスにはその場所にひどい違和感を覚えた。いや、それだけではない。ほんのわずかだが、確かに人の気配も感じていた。自分の直感を信じこの道に入るのか、当初の予定通り南西を目指すのか。このままつっ立て迷っていてはターゲットを逃がしてしまう。クラノスはその先に意識を集中させたが、再び気配を感じる事はなかった。やはりただの勘違いだろうか。
「誰かいるのか」
唐突に叫んだ。もちろん返事はなかった。
もしこの先に居るのが犯人か人質かのいずれかで、出会いざまに銃弾を浴びせられても面白くない。ハンドガン程度の銃弾ならバトルスーツを貫通することはないが、人質のウルマン氏は薬品から武器まで幅広く手掛けるサイバーSINの重役だ。開発中の変な武器の被験者にされてはたまったものではない。
それでもクラノスは偶然見つけたこの道を選択する事にした。そもそも逃げ出した鳥とおぼしきものを追いかけたのも瞬初的な衝動に駆られての事だ。意を決して歩を進めていくと、道は左にカーブしながら緩く上に傾斜していた。しばらくは慎重に、靴音も立てぬよう静かに歩いた。そこはあまり使われた痕跡がなく、床も壁も天井もまるで荒く磨いた鏡のようで、カビ臭い周囲に比べればここだけ新品同様だった。そのせいか、所どころにある男のものと思われるような大きめの手垢がよく目についた。それもつい最近つけられた物のようだった。
1章・16―交換条件のない人質
それからしばらく行くと、電源の通ったバリケードゲートが現れた。
先にここを通った者はよほど慌てていたのか、内側のコントロールパネルには大量の指紋を残しながら、ロックをかけ忘れて去って行ったようだ。クラノスが前に立っただけで分厚く重い扉がいとも簡単に口を開けた。
通路はさらに先があった。全体が大きな螺旋を描いているとみえて、道は一本でありながらいつまでたっても先が見えない。しかし進むにつれだんだん朝日らしき明るさを感じられるようになり、クラノスはそれを頼りに地上までの距離を測りながら進んでいった。さらに二つ目のバリケードゲートをくぐった時、ついにその先に人影を見た。
彼らは頭から布を被り、迫りくる背後の足音に驚いたのか、身を寄せ合い立ちつくしていた。
「君らは人質か?」
そこには三人の男女が立っていた。彼らに逃げ出す様子はなく、いつの間にか走り出していたクラノスは手前で歩を緩め、息を整えながら近づいた。頭を保護する目的なのか、一人はいかにも高価そうな毛足の長いコートを頭から被った女だった。こけた頬と落ちくぼんだ目には疲労困憊の相がありありと浮かんでおり、落ち着かないのか乱れた髪をしきりに爪の長い指でなでつけている。もう一人は比較的長身の初老の男、その傍らには彼らの娘らしき年ごろの女がいて、こちらも母親と同じように頭から淡い色のコートを被っている。
「け、警察の方ですか…?」
男の言葉からは怯えたような、それでいてかすかな希望のようなものが感じられた。女の方からは強い警戒感を感じたが、こんな物騒な場所で出会えば不自然な事ではない。なにがともあれ、この男が人質になったウルマンならば、変な武器は携行していそうもないし、見たところ三人はどこにでも居そうな、たまたま休暇にここを訪れていた家族といったところだ。
「連邦国軍だ、そちらはウルマン氏か?」
そう尋ねられて相手は少し困惑したような表情を浮かべた。こちらもまさか鳥を追っていて人質に出会うとは思わなかったし、それはお互い様なのだが。
娘の方は緊張の糸が途切れたのか、ガクリと膝を落としかけたが、父親に支えられ何とか持ちこたえた。なるべく穏やかに話しかけたつもりだが、しかし壁に映る自分の泥と埃にまみれた姿を見てクラノスは閉口した。地下で浴びたウィザードの補修材が酸化し、まるで大量の返り血を浴びた跡のようにも見える。これではせっかくのいい男が台無しである。
「そうです、私がウルマンです。何とかここまで逃げてきましたが、我々も娘ももう限界です。早く地上に出て休ませてやりたい」
ウルマンはそう答えた。しかしクラノスには男の話し方に何か妙な不自然さを感じた。一つ一つの言葉がはっきりとせず、ひどく聞き取りにくいのだ。よく見るとウルマンの前歯が数本抜け落ちていた。ここから空気が漏れだし、滑舌を悪くしているようだ。所見からウルマンは物腰外見ともに品の良い紳士といったところで、抜けてしまった前歯をそのまま放っておくような無精者には思えなかった。よく見ると襟元に血が滲んでいる。もしかすると逃げる最中に転倒でもして失ってしまったのか。
ここは新しい住人だけの知る非常口で、あと僅かで地上に出られるのだとウルマンは言った。クラノスは娘を運ぶのを手伝おうと進言したが、ウルマンはそれを断り、想像以上に軽々と娘を抱えあげた。娘は修道女のような濃紺のオーバーの様なものを着込んでいて、そこから僅かに見る足首には大きな擦り傷の様なものが見えた。ウルマンといい娘といい、これまでに何物かと接触し、負傷するような事態に巻き込まれた事は間違いない。彼らの身に何が起きたのか、彼らは何を見たのか、クラノスには聞きたい事が山のようにあった。しかしウルマン一家は何かに怯えるように、地上を目指し一心不乱に歩き続けた。
一行が背後の異常に気が付いたのは、通路のエントランスと思われる場所に辿りついた時の事だった。最初は耳鳴り程度だったものが次第に大きくなり、出口を目の前にした頃には、そこに居る全員が耳触りに感じる程になっていた。さらに金属同士がぶつかり引っ掻きあう音、互いが衝突する音が混じり合い、それが幾度も繰り返されながらどんどん近くなってくる。しばらくは女が最後のバリケードゲートを開こうとパネルを操作していたが、その手際の悪さに業を煮やしたのか、ウルマンが前に割り込んだ。
「何か来る…」
クラノスは振り返り、音のする方を凝視した。足音を伴わない何者かが通路を伝ってきている。もし飛行推進装置を持つ輩だとすれば一つ心当たりがあった。数度目の衝突音は異質で、通路の壁ではなく他の何かに激しくぶつかった音に思えた。もしそれが一つ手前のバリケードゲートだとすればもう残された時間がない。
クラノスは来た道めがけて走りだした。追跡者があのウィザードの操縦士を殺害した鳥に違いないと確信したからだ。上半身を低く固定し、左手をそれまで大事に携えていた右腰の“サンノイ”に掛ける。サンノイは剣術の指導を受けていたブロウド=ケンファーが使用していた刀をクラノスが模して造ったもので、刀身が僅かに反っていて、刀には珍しいレチルロームと呼ばれる金属が使われていた。レチルロームは重機歩兵の外装を切り裂いても刃こぼれしない硬度があるが、剣にするには重過ぎて衝撃に弱い。クラノスは抜刀前のサンノイを水平に保ち走りながら息を殺し、その内現れるであろう相手を見据える。
そしてすれ違いざまに現れた敵を、抜き払ったサンノイの切っ先が正確に捉えた。レチルローム特有の共鳴音があたりに響く。
一瞬視覚で捉えた際には本物の鳥かと錯覚したが、やはり鳥の体はレチルロームかそれに近い硬度の金属でできていた。サンノイの柄に伝わる手ごたえと、レチルロームが結晶を保ちつつ対象物を切り裂く際の独特の共鳴音は、生身よりずっと堅い相手に正確なダメージを与えた証だった。
左の翼の先を失った相手はバランスを崩し、再び右側の壁に衝突し、惰性で大量の火花をあげる。翼の先を失った程度では推進力を削ぐ事はできなかったようだ。しかしこういった手合いは下手に切り裂けば内燃炉の爆発を誘引した。
クラノスは抜刀したサンノイを鞘に戻すと、急旋回して造り物の鳥を追った。剣術の精進にばかり時間を割けなくなった今のクラノスには、抜刀したままの刀を振るってもあまり意味はない。それに金属を切り裂くには砥ぎの力を借りる必要があった。再び同じような状況に陥れば、今度は左側の“ニノカミ”に頼らなければならない。ブロウドの二刀流の教えはそんな事の為ではなかったはずだが。
その後も殺人鳥の進撃は終わらず、多少の飛行姿勢のバランスを欠きながら、一直線に人質達の元へ向かっていった。
クラノスが駆けだした時には、最後のゲートが再び閉じられかけていて、すでにそこに一家の姿はなくなっていた。
1章・17―暴かれた陰謀
クラノスが最後のゲートに体を滑り込ませたのは、大人が一人通過できるかどうかの瀬戸際のタイミングだった。もし挟まれてサンドイッチ程度で済めばいいが、それこそ半分ずつの死体になれば目も当てられない。ジャッキーの予知夢とやらは当たっているようでやはりどこまでも中途半端に終わる代物であればいいと思う。
外界はとうに天高くまで日が昇っていた。久しぶりに浴びる太陽光線は目に眩しく、鋭い日差しに熱せられた地面からは濛々と熱気が立ち上がっている。真夏の気温の高低差が五十度にもなるテシマの過酷な環境の中で、この先あまり活動できる時間は長くない。
そして鳥は太陽を背に上空に高く舞い上がり、機会を今か今かと待ちかまえているようだった。
次なるターゲットは一体誰であろうか、攻撃を加えたにも関わらずしつこく相手にしようとはしない所を見ると、クラノスの優先順位はかなり後の方だと見ていいだろう。最初はこの屋敷を襲った狼藉者ウィザードの操縦士、次にここへ来たと言う事は屋敷の主ウルマン一家だろうか。しかしそれでは矛盾が生じる。鳥は一体何の目的で人質、犯人諸共に殺害しようとするのだろうか。もちろん機械仕掛けの鳥が自らの意思を持っているのではなく、裏で糸を引く何者かがいるはずなのだ。それが犯人でも人質でもないとするならば、今もどこかで手駒を遠隔操作し高見の見物を決め込んでいる第三者が存在する事になる。
非常通路の終着点はヘリの発着場だった。それだけにしては少し大きめで、奥には小型の垂直離陸用飛行機や数台の自家用車が見えた。そしてそれらの手前にはまだウルマン一家三人の姿もあった。すでに鳥は超上空から彼らの頭上を捉えており、今にも急降下にかかろうかという体勢にある。それから二度三度旋回した後、ついに下降を始めた時、クラノスは彼らの身に起こる最悪の事態を覚悟した。しかし先ほど翼の一部を失ったせいか、鳥は大事な所で揚力を得られず、再び放たれた可視光線の矢は目標を大きく逸れた。それが必死に逃げ惑う三人の後方地面に着弾し、地面を穿って大量の砂埃を宙に舞いあげた。
幸い一家は全員小さく吹き飛ばされ転倒こそしたものの、未だに身動き一つしない娘以外は命があるようだった。その間にも鳥は再び大空に向かって急上昇し、今度はさっきより大きな円を描きつつ発着場の上空を旋回しはじめた。
「大丈夫か」
クラノスより少し先にウルマンが娘に駆けより、大声で呼びかけたり揺さぶったりしはじめた。愛娘の生死を確認しようと躍起になっているようだった。
「兵隊様、どうかあの鳥を!あの無人探査機は軍用に作りかえられている。このままでは我々の命はありませんぞ」
突如クラノスを振り返ったウルマンは眉は釣り上げ声を荒げた。無人探査機とはあの鳥の事か、さっきの通路で仕留め損ねた事を責めているのだろうか、あの穏やかなウルマン表情はそれほどに変貌していた。軍用機ともなればクラノスの携行した銃器だけで対処できる代物ではない。クラノスがどうしたものかと頭をひねっている内にウルマンは再び娘を担ぎあげ、駆けだそうとする。奥の飛行機を使おうというのか、機体のどこにも所属を示すような印はなく、自家用であれば彼らは屋敷を捨て去りどこへ逃げるつもりなのだろう。
時折頭上の鳥に注意を移しながらもウルマンの様子を見守っていたクラノスだったが、ふと不思議な感覚にとらわれた。それまでコートに頭を隠していたせいで気がつかなかったが、娘の髪は赤く、明るい朝一番の日を照り返しているだけにしてもよく目を引いた。一方父親のウルマンは白髪が目立つものの元の髪は黒く、母親は赤毛だが娘よりずっと暗い。若い娘の顔をぱっと見ただけで細かく分析できるほどクラノスは器用な方ではないが、衰弱しすぎた娘の半開きの双眸から見える瞳は翡翠のような緑色をしていた。これは両親の何れとも違っていた。
それにクラノスにはこの特徴に覚えがある。姿かたちこそ違え、この組み合わせは昔彼が基地で出くわした鬼、ライデン=井更とまるきり同じだった。
突然背後に感じた熱がたちまち背中を焦がすほどの猛火にまで膨張し、空気がビリビリと震え始める。リコイルスプリングの僅かな軋みを頼りに、クラノスは力いっぱい右手を後ろ方向にのばした。
「…ううっ……!」
銃声が一発鳴り響き、後ろに立っていた女がうめき声を上げた。娘の母親だと思っていた女はクラノスに隠し持っていた拳銃を向けていた。どこの間抜けが渡したのだろうか、それは警察の使用する型式だと一目でわかるものだった。
「もう一度聞くぞ、本当に君らはウルマン一家か?」
硝煙のあがる銃身を掴んだまま、ねじり上げるようにして女の手から拳銃を取り上げると、弾倉を抜き取り、クラノスはそれを力いっぱい遠くへ投げた。ついでにあの忌々しい鳥にでも当たればいいと思ったが、そうはならなかった。
問われた男は往生際が悪く、もう一度そうだと答えた。面倒くさい事になった。基地や警察から渡されていたデータとこの夫妻とは特徴がきっちりと一致するのだ。しかも一緒にいるのかどうかもわからない放浪癖のある彼らの一人娘は姿こそ違え、この赤毛の娘と年齢がほぼ一致する。もしこのデータが最初から偽りだったとしでも、この男は頑として嘘を貫き通すだろう。
その時、突如ウルマンの体が真横に吹き飛び、鈍い音を立てて地面に転がった。
ウルマンを跳ね飛ばしたのは、紺色のスカートから飛び出した細くて白い足だった。不意打ちを食らい気を失ったのか、それとも今の一撃が致命傷になったのか、ウルマンはうめき声も上げぬまま動かなくなった。クラノスが驚いていたのもつかの間、今度は彼の方に強い衝撃が走り、そのまま仰向けに崩れ落ちたかと思うと、全く動く事ができなくなった。あのちっぽけなミュール付きの足に蹴られ、自分もウルマンと同じ末路を辿ったのだろうか。しかしそうではなかった。彼の体の自由を奪っていたのは、右足の装甲の隙間に光っているパルス式拘束具の一種だった。非常に小型だが威力は絶大でたちどころに肢体の自由を奪われる、使い方を誤れば死に至る事もあるという。激しく痺れる頭をそれでも無理やり動かすと、足元に気を失っていたはずの、さっきまでウルマン氏の娘だと思い込んでいた女が立っていた。
「今度はそっちの番ね、いい気味だわ、この変態野郎!」
常人ならば即気絶するところだが、運悪くアトロフィクシスであったクラノスにはこの悪趣味な拘束具にすら耐性があるようだった。目も霞み耳の聞こえも悪くなる中、クラノスは娘が今までこれで気を失っていたのだと悟った。それが何らかの原因で外れ、今度はたまたま近くに居たクラノスに取り付けられたのだ。ここへ来て何たる大失態、しかもただ一緒にいただけで若い娘に変態呼ばわりされるとは。いつの間にか修道女のようだった衣を脱ぎ捨て、娘は休暇中の女学生のような軽装で仁王立ちになっていた。髪と顔、それどころか全身埃まみれだが、大きな瞳を得意げにくるくると動かし、口角のあがった口元はうっすら色づいて若々しさを印象付けた。最初こそイメージが重なったが、あのライデンとはあまり似ていないようだ。
ピュー、という、まるで大型の猛禽類が発するような鳴き声が辺りに響き渡った。娘はそれまでクラノスを見降ろしていた翡翠色の両目を大きく見開くと、空を見上げた。
しまった、という言葉は声にはならなかった。体の自由が効かぬ中、クラノスの頭から背中にかけて強烈な戦慄が走りぬける。なんという事だろう、あの鳥が再びこちらにめがけて急降下してきたのだ。拘束具を取り外せと言っても聞かないだろうが、言葉にすら出せないのが口惜しい。二度目の射撃には失敗しているとはいえ、今度の的は全く動かない。熱傷式ベジェ砲なら難なく命中させる事ができるし、バトルスーツだって貫通できるだろう。
「アヤセ、良かった!」
鳥は二度三度娘の周りと飛び回ると、差し出された腕に静かに舞おりた。不思議な光景だった。よく見れば鳥は精工に作られた鳶の様な姿をしていた。いくら軽量に設計しようと今まで見た性能から相当な重量のはずだが、娘はそれを軽々と支えている。それに華奢でありながらウルマンのような大の大人を吹き飛ばす程の脚力。おそらくこの娘もアトロフィクシスなのだと見て取れた。辺りを気にもせず無邪気に笑い鳥と戯れる姿は普通の少女だが、はたしてその手足で人を傷つければ他の人間とは比べ物にならぬほどの重罪になるのだと彼女は知っているのだろうか。
「…お前の鳥か?これ以上暴れさせるな、銃刀法違反だぞ」
クラノスは何とか声を絞り出した。娘は「あら」と言ったきり、興味深そうにクラノスの様子をしばらく観察していた。
「アヤセは友達よ、あなたマシンドロイドを知らないの?」
それは見ればわかるといいたかったが、その余力は後に残しておく事にした。さすが井更家の娘だ、ロボットの精巧な作りにも感心したが、口径も種類も違法な砲台を積んだ殺人マシンドロイドが友達とは恐れ入ったものだ。ならクラノスの方もそのマシンドロイドの餌食になる前に手を打っておかねばならない。あるいは石化でもしてしまったのではないかと思うほど硬直した右足を無理やりへし曲げ、奇妙な銀色の装置が取り付けられたひざ下を見える位置まで引き寄せる。そして既にその方向に向けておいた頭のヘッドセットから可視光線を数度発射した。なんという腹立たしい設計だろうか、オートメーション照準が利かないまま一度目は見事に外し、それが二度目三度目にもなるとスーツから煙が上がり、嫌なにおいが立ち込めた。叫びだしそうになるのをこらえながら、五度目でやっとベジェ線が彼を拘束していた金属の塊を掠め、そこから外れてはじけ飛んだ。
1章・18―アヤセの死
「無茶苦茶しやがって、お前が井更少佐の妹か?」
拘束具こそ外れたものの、まだ痺れる頭を抱えながらクラノスは体を起こした。
「あなた、どうして私の名前を知ってるの?」
武装した相手が自由になった事を恐れたのか、あるいは身元が割れた事に強い危機感をもったのか、娘は急に真顔に戻った。どうしてと聞かれても、クラノスは返答に困った。おそらく連邦国軍に居てライデン=井更の名前を知らない者がいればかなりの少数派だろうが、おそらく娘が求めているのはそんな話ではない。
全身の痺れから解放され意識がはっきりしてくると、皮肉にも今度は酷い熱傷に見舞われた右足が鋭く痛みだした。光学砲で自らの足を何度も撃つ様は、さぞかし興味深いショーだったのだろう。娘はまだ煙の燻る足とクラノスの顔を交互に見比べながら、さらに数歩後ずさった。さっきまでの無邪気な姿はすっかり形を潜めていた。そしてアヤセという名のマシンドロイドを空に静かに放すと、自分から離れろというように片手を上にかざした。おそらく、彼女が指示を出せばマシンドロイドは再び攻撃に転じるだろうが。
「もうそろそろ観念しろ、屋敷の中も外ももう軍と警察だらけだ。ここに居る人間をどうこうしたところで逃げ切れはしない」
娘は体ごと左右を振り返ると、うろたえるような仕草を見せた。
「警察…軍隊?なんでよ、悪いのはあの地下から出て来た女だわ!」
それが本心からの行動なのか、それとも窮地を凌ぐ為の演技なのか、残念ながら同じアトロフィクシスでは能力を用いて探りようがない。クラノスは続く娘の言葉を待った。ややこしいが、娘の言う「女」とは直感的にあのウィザードの操縦士の事だとクラノスは思った。やはり娘は事の成り行きを知っているのだ。現にあの武装した集団の中でマシンドロイドは操縦士を選定し、無抵抗だった彼女だけを殺害した。
「あの重機歩兵の操縦士はお前の仲間か?何故殺した」
すると娘の顔に明らかな動揺が浮かび上がった。知らない、そんな事を言った気がするが、はっきりとは聞きとれなかった。相変わらずアヤセは彼女の頭上を飛び回り警戒を続けているが、クラノスや倒れたままのウルマン、赤いコートの女の何れも攻撃する気配はまだない。
ところでこのウルマンは一体何者なのか。自由を奪ってまで屋敷を連れ出そうとしていたという事は、ウルマンも娘の味方ではないようだった。ひょっとすると計画半ばで仲間割れでもしたのかもしれないが、どちらにせよ人質は空言だったに違いない。おまけに娘にとっては軍も警察も都合が悪い。警察は警察で腹に何か一物を抱えながら娘を探しまわっているし、クラノス自身も上層部に命じられるままに娘を捕え、よからぬ実験に使われると知りながら彼らに引き渡すつもりでいる。重大な秘密を持ちながらこんな場所に踏み入った娘も浅はかだが、この小さな娘を平然と追い回す武装した大の大人の頭の中身も問題だ。
ふとベジェ砲の直撃を受けながら、まだ小さなランプを点滅させ続けている小さな金属片が視界の隅に入った。
再び拾い上げられ、二度と使われる事のないよう、クラノスはしつこく機能し続ける銀色の物体を踏みつける。もちろん怪我をしていない方の足でだ。すると内装された強力な電池が分厚い靴底の下で小さな破裂音を立てた。まだ頭の芯がズキズキと痛み、あのさっきまで全身を襲っていた痺れは今思い出すだけで吐き気がする。踏みつけた足に自然と力が入った。その様子を見ていた娘は、些細な悪戯を閻魔に見咎められたような目でクラノスを見上げた。あるいはその悪戯すら忘れてただただ偶然の不運を嘆いているだけかもしれないが。
「…やれやれ」
クラノスはけたたましく警報の鳴り始めたヘッドセットの音量を故意に下げると、娘に背を向け、中途半端に口を開けたままのバリケードゲートに目をやった。
今にそれをこじ開け大量の警察関係者がここへ現れる。ホドリー班長も、あのファンとかいう警部や、それにコウザイ達州兵も混ざっているかもしれない。
クラノスはここへ来る間際、最後のマルチプルシーカーを非常通路に放っておいた。通路は特殊な金属で覆われており、レーダーでは外から中の様子を知る事ができない特殊な構造になっていた。だから最初の地図にはなかったのであり、精工な機械でできたはずのアヤセという鳥は正確な位置情報を取得できず、天井や側面に何度も衝突したのだ。そんな電子計器での計測困難な場所でこそ真価を発揮するのがマルチプルシーカーだった。他に比べれば大ざっぱだが、人間の目の代わりになるならそれが丁度いい。そんな彼らが大勢の人間をなんとなく感知し、慄き、主であるクラノスに知らせて来ていた。
「間もなくここに警察が来る。君は一体ここへ何をしに来た?」
「な、なによ!…なんであんたにそんな事教えなきゃいけないの!?」
途端に娘は顔を赤らめると、噛みつかんばかりに身を乗り出して叫んだ。助け船を出すつもりだったのだが、逆に気に障ったようだ。それに今さら理由を聞いたところで何ら状況が変わるわけではない、よく考えればただの興味本位も同じだ。
「あのね、私はここにあの人たちに呼ばれて来たの!おかしいのは後から押しかけてきたアンタ達の方だわ!」
そして娘は未だに倒れたままのウルマンを指差した。幸い命に別条はなかったようで、女の介抱を受けながら二人で何かを話している。再び不穏な動きをしようものなら飛び出すつもりでいたが、どうやらそれも諦めた様子だった。頭上のアヤセというマシンドロイドも上空を旋回するばかりで変化は見られない。
「そうか、まあいい」
クラノスにはもうそれ以上追及する気はなかった。もはや自分にすべき事はここに何も残っていない。ウィザードの鎮静化に部下達は最善を尽くしてくれた、生き延びた娘はその後警察が連行していった、報告はそれでいい。願わくば娘に再び自由が訪れる未来があればいいのだが。
間もなくして、まるで蜂の巣を暴いたように、狭いゲートから大量の人間があふれ出てきた。
たちまち周囲を取り巻かれ、その中にはホドリー達やコウザイの姿もあった。しばらくは皆押し合いへしあいしながら遠巻きに彼らを見ていたが、やがてその中の数人がこちらに向かって歩き出した。ずんぐりむっくりとした、以前どこかで見たような男と、もう一人はホドリー班長、そして彼の数人の部下達だった。他にも何人かが班に分かれ、ウルマン夫妻の救護に向かっていくのが見える。クラノスはその二人こそ逃がさぬよう注意するべきだとは思ったが、手柄を譲ってやった警察に更に助言までしてやる義理もなかろうとそのまま見送った。ホドリー達はクラノスになど目もくれず、ふんぞり返ったままの姿勢で目の前を通り過ぎ、娘の方へと歩いていく。
これで事件の方もかたが付いた。後はZIXOと共にここを速やかに撤退し、州軍と東方面軍に事の次第を報告するだけだ。
踵を返そうとした瞬間、クラノスの目に飛び込んだのは、再び急降下し攻撃態勢に入ったアヤセの姿だった。
「しまった……!」
油断していた。もはや抵抗しないかに見えた娘が再び逃走を試みたのだろうか。おそらくそうではない。あのマシンドロイドには主人に危害を加えようとする人間を自動で攻撃するプログラムが最初から組み込まれていたのだ。個人所有のマシンドロイドには禁止されている殺人プログラムだが、実際に使用している例をクラノスは何度か目にした事があった。
しかしホドリーもそれを想定していないほどの馬鹿ではなかった。まるで見計らっていたかのように四方から空へ向けて、重機関砲の一斉射撃が始まった。重機歩兵の装甲にも穴をあけるほどの弾丸が何十発何百発も放たれ、その中でマシンドロイドは数度の破裂を起こしおびただしい炎を撒き散らすと、たちまち細かな金属片になって四散した。どれだけの間銃声と爆発音が続いただろう。ただ茫然と見上げるだけのクラノスにはそれがとても長い時間に思えた。その間娘がこちらに向かって何かを叫んでいたような気がしたが、声は届かなかった。掃射がようやく止んだ頃、抜け殻のようになった娘がその場にへたり込んだ。
―新暦178年8月25日から翌日朝にかけて起きたテシマ立てこもり事件は、容疑者一名が死亡し、人質三名は無事救出されその幕を閉じた―
一章・存在しない娘<完>
CODE:GLADIO/0章・存在しない娘