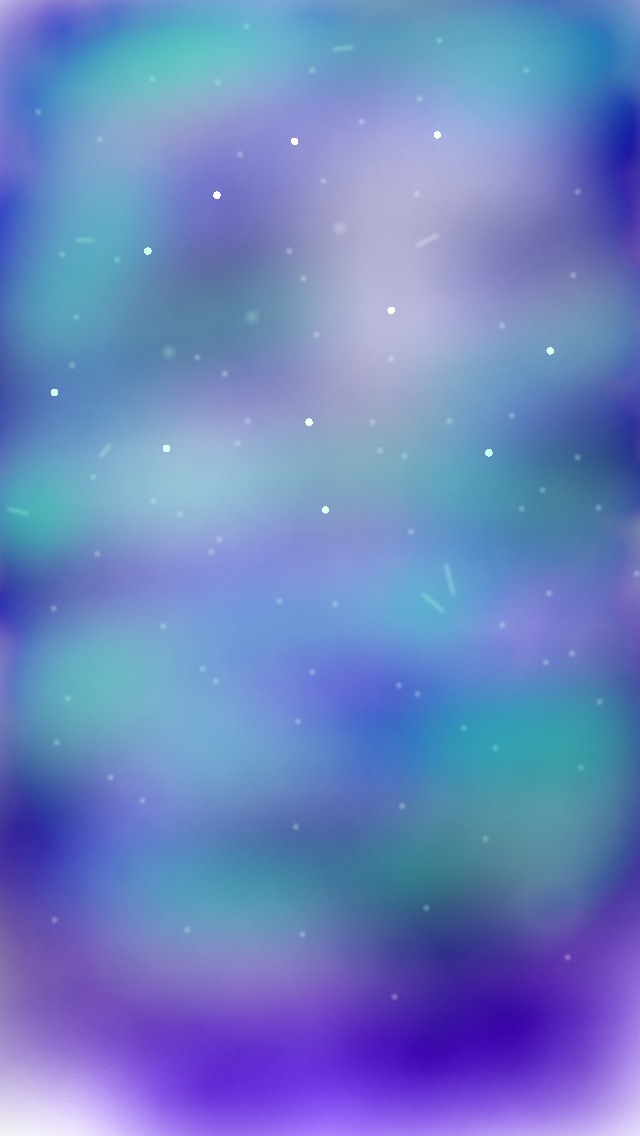
星空に願いをこめて。1
この世にいない君は、今どこで何をしていますか。誰を想っていますか。
君はとても明るくていつも笑っていたね。そうして、皆を笑わせていたね。
でも、僕の目の前にいる君は、怒ったり、泣いたりもしてた。
そんな君のいろんな顔が、僕は大好きだったよ。
君は一体、どこで何をしていますか。今は、誰を想っているのですか。
**
ある夏の日のことだった。
その日は各地で猛暑日を記録していて、朝から気温はみるみる上昇。外になんて絶対に出たくない日だった。
しかし、あっけなく僕は外へ行かなくてはならなくなる。
「淳、卵買ってきて」
母のこの一言である。
「なんでこの暑い日の昼に息子を外へ出そうとするんだよ……」
僕が嘆くと母は笑顔で言う。
「ご飯、いらないの?」
僕もにっこりして返した。
「行ってきます」
玄関を出ると蝉がないていて、太陽の日差しが容赦無く僕を照らす。
「帽子持ってくればよかったな」
だが1度涼しい家の中に戻れば、もう外へなんて出る気にはならないだろう。……よし、行こう。
最寄りのスーパーマーケットまで徒歩十分の道のりを僕は一人で歩く。
社会人にもなっておつかいだなんて恥ずかしいことこの上ないが、実家暮らしの僕にとってはそれが日常だった。
「おお、淳じゃないか」
後ろから名前を呼ばれた。
「優雅」
高校時代の友人だ。
高校卒業後、僕は地元の大学に、優雅は県外の大学に行ったため卒業以来会っていなかった。
「久しぶりだね。県外で働いているんじゃなかったの?」
僕がそう尋ねると優雅は額に汗を浮かべ、笑った。
「実は去年辞めたんだ。1年も続かなかったよ」
「そうなんだ。今はどうしてるの?」
「とりあえず実家に戻ってきて親父の手伝いしてる。家が自営業で助かったよ」
「昔はあんなに、家なんか継いでられるか、俺は都会でビッグになるだ!とか言ってたのにね」
僕が冗談めかしにそういうと優雅は少し顔を赤らめて、もうそれは忘れてくれ、と小さな声で言った。
「ところで優雅はどこへ行くの」
「ん?ああ、暑いからアイスでも買いに行こうかと思ってな」
「じゃあ行き先は同じか」
「お前もスーパーに行くのか?」
「そうそう、おつかい」
「社会人になってもおつかいか、はは。お袋さんは元気か?」
「うん、元気だよ。こうやって僕をこき使うくらいにはね」
そう言うと優雅はまた笑った。
「仕事はどうだ?」
「まあ、ぼちぼちだよ。やることはある程度覚えてきた」
僕は地元の大手メーカーの子会社に就職して働いていた。
「そうかそうか、お前優秀だったもんな。てっきりもっと偏差値の高い大学に行くと思っていたから地元に残った時はびっくりしたよ」
「遠くに行くのもめんどくさかったからさ」
そう答えると優雅はにやにやして僕をつついてきた。
「嘘つけ、どうせ木村さんのためだろう?木村さんとは今どうなんだ?流石にもう付き合ってないか!」
木村さん、とは木村加奈子のことで、僕が高校二年生の時から付き合っていた彼女のことだ。
「……ああ、もう付き合ってないよ」
なるべく平然と、そう答えた。
「あちゃー、ふられたか?」
優雅にそう尋ねられ僕は呼吸が止まりそうになった。
「ふられたっていうか……」
言葉が、上手く出ない。
「死んだんだ」
そうだ、彼女は、もう、いないのだ。この世に。
優雅は言葉を失ったように押し黙った。
僕は続ける。
「去年の今頃だったかな。夜に外に出ててさ、車に轢かれちゃって、そのまま」
優雅は黙って聞いている。じっと僕を見ながら、優雅は言葉を発さない。
「加奈子も何やってたんだろうな。家で大人しくしていたら轢かれずにすんだのにさ」
だんだんと自分の声が湿っていくのを感じた。
そうだ、加奈子は車に轢かれた。
でも、それは事故じゃない。
加奈子は自ら、轢かれたんだ。
まるでもうこの世に未練なんでないかのように。
「ま!昔のことだよ。この話は終わりだ」
自分でも無理矢理なのは分かっていたが、僕はそこで加奈子の話を切った。
優雅はそれ以降僕に気を使っているのか、当たり障りのない話題を振ってきて、僕もそれに応じながら、二人でスーパーマーケットに向かっていた。
星空に願いをこめて。1


