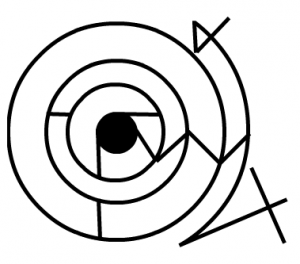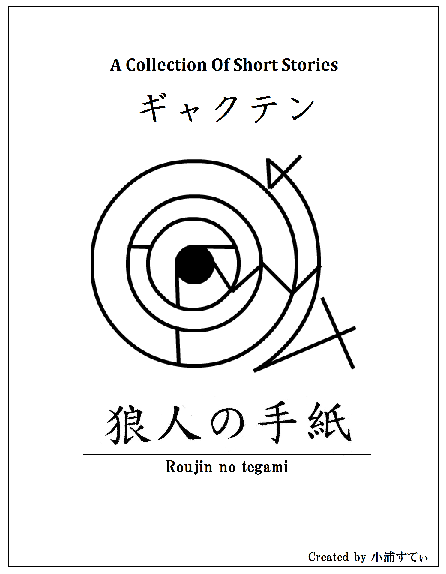
狼人の手紙
短編集「ギャクテン」4作品目となります。「狼人」とかいて「ロウジン」と読みます。獣人をイメージしてもらえればそれであってます。
私の野獣たる部分は日に日に肥大していき、数日もしないうちに飲み込まれてしまうのであろう。
私の野獣たる部分は日に日に肥大していき、数日もしないうちに飲み込まれてしまうのであろう。死をもって償うべき罪は、これから起こる変化とそれに伴う忘却によって消し去られてしまうに違いない。もはや人としてではなく、身体ごと獣になってしまった今では、その生を受け入れ死を待つしかあるまい。
王国が戦禍に包まれ国民が近くの山へ逃れた時、国の研究者であった私も被害を免れるべく、山の中腹に設置された砦の中にいた。狼人が棲むと恐れられたこの山に逃げ込んだのは、その噂により敵が追うのを戸惑ってくれるのではないかという期待と、国に残って死ぬよりとりあえず少しでも生き永らえたいという本能と、あわよくば狼人が攻め込む敵兵を倒してくれればという淡い妄想の為である。この砦の最深部が王族や私たちのような王直属で働いていた者で固められているのも、人ではない敵、狼人の噂のおかげであり、仮にここまで敵兵が攻めてきたとしても外側の民より生き残る可能性は高いであろう。
はたして、数か月間敵兵がこの砦に攻め込むことはなかった。しかし砦での生活は私にとって耐えがたいものであった。着の身着のままに逃げ出してきた私は大半の研究機材を持ち出すことができず、もしその機材があったとしても私の研究では今日目の前で苦しんでいる民を救うことができないことを自覚したためだ。身を押しつぶすほどの無力感。何の役にも立つことのできない私が、砦の安全な場所でのうのうと暮らしていることが許せなかった。そう考えるようになってからは、民の私を見る目もそういったものに感じられ、いつしか私は割り当てられた部屋で何をするでもなく無気力に時間を浪費する一日を繰り返していた。
いつからか、私の頭には常に「死」が取りつくようになっていた。誰の役にも立てないなら、せめて誰の手も煩わせず、後処理といった最低限の迷惑だけを任せて、この世から消えてしまおうと。しかしそう考えるたびに、私を慕ってくれる幼気な少女の笑顔が脳裏に浮かび、私を引き留めた。
この世界に対する未練はない。人々は必要以上に意味を求め、意味の見いだせないモノは必要ないとする態度。社会から必要とされなければ食べることすらままならない社会。そして現に今の私はこの社会、ひいては世界においては役立たずであることを鑑みれば、早いうちに事切れるべきであろうという、自らに対する死刑宣告は自ずと導き出される。必要とされないのであれば、私とてこの世界は必要ないのだ。しかし世界が私を必要としない一方で、少女は私を必要としてくれた。ただそれだけが、私をこの世界に留めさせてくれていた。
人と接する機会が減ると、人間がどのようなものかまで忘れていった。少女のことを頭の片隅に置きながら、自己嫌悪と死について考えているうちに、私は正気を失ってしまったのだろう。ある日、私はただ死にたいと願った。愛しい少女の手で死にたいと願った。しかし私を殺した少女のその後を考えれば、とても勝手な話であると一度は思い直した。少女に罪を着せず、罪の意識に苛むことなく、少女の手で私を殺す方法はないものか……
その日私は数週間ぶりに、小さな研究機材に手を伸ばした。
数日が経ち、私は少女を倉庫に呼び出した。中にはありとあらゆる武器が収められており、その量は狼人でさえもしとめられると確信できるほどだった。少女が用件を尋ねたところで、私は背を向け作った薬を飲みこんだ。たちまち私の身体に変化が起こった。体中の筋肉が急速に発達し、即座に新しい皮膚が生まれ全身が細やかな毛皮に覆われた。尾てい骨は人間にないはずの部位を作り上げ、歯も獣のそれへと変化した。そこから私の意識はぼんやりとし始めたが、 私の野獣たる部分は日に日に肥大していき、数日もしないうちに飲み込まれてしまうのであろう。死をもって償うべき罪は、これから起こる変化とそれに伴う忘却によって消し去られてしまうに違いない。もはや人としてではなく、身体ごと獣になってしまった今では、その生を受け入れ死を待つしかあるまい。
王国が戦禍に包まれ国民が近くの山へ逃れた時、国の研究者であった私も被害を免れるべく、山の中腹に設置された砦の中にいた。狼人が棲むと恐れられたこの山に逃げ込んだのは、その噂により敵が追うのを戸惑ってくれるのではないかという期待と、国に残って死ぬよりとりあえず少しでも生き永らえたいという本能と、あわよくば狼人が攻め込む敵兵を倒してくれればという淡い妄想の為である。この砦の最深部が王族や私たちのような王直属で働いていた者で固められているのも、人ではない敵、狼人の噂のおかげであり、仮にここまで敵兵が攻めてきたとしても外側の民より生き残る可能性は高いであろう。
はたして、数か月間敵兵がこの砦に攻め込むことはなかった。しかし砦での生活は私にとって耐えがたいものであった。着の身着のままに逃げ出してきた私は大半の研究機材を持ち出すことができず、もしその機材があったとしても私の研究では今日目の前で苦しんでいる民を救うことができないことを自覚したためだ。身を押しつぶすほどの無力感。何の役にも立つことのできない私が、砦の安全な場所でのうのうと暮らしていることが許せなかった。そう考えるようになってからは、民の私を見る目もそういったものに感じられ、いつしか私は割り当てられた部屋で何をするでもなく無気力に時間を浪費する一日を繰り返していた。
いつからか、私の頭には常に「死」が取りつくようになっていた。誰の役にも立てないなら、せめて誰の手も煩わせず、後処理といった最低限の迷惑だけを任せて、この世から消えてしまおうと。しかしそう考えるたびに、私を慕ってくれる幼気な少女の笑顔が脳裏に浮かび、私を引き留めた。
この世界に対する未練はない。人々は必要以上に意味を求め、意味の見いだせないモノは必要ないとする態度。社会から必要とされなければ食べることすらままならない社会。そして現に今の私はこの社会、ひいては世界においては役立たずであることを鑑みれば、早いうちに事切れるべきであろうという、自らに対する死刑宣告は自ずと導き出される。必要とされないのであれば、私とてこの世界は必要ないのだ。しかし世界が私を必要としない一方で、少女は私を必要としてくれた。ただそれだけが、私をこの世界に留めさせてくれていた。
人と接する機会が減ると、人間がどのようなものかまで忘れていった。少女のことを頭の片隅に置きながら、自己嫌悪と死について考えているうちに、私は正気を失ってしまったのだろう。ある日、私はただ死にたいと願った。愛しい少女の手で死にたいと願った。しかし私を殺した少女のその後を考えれば、とても勝手な話であると一度は思い直した。少女に罪を着せず、罪の意識に苛むことなく、少女の手で私を殺す方法はないものか……
その日私は数週間ぶりに、小さな研究機材に手を伸ばした。
数日が経ち、私は少女を倉庫に呼び出した。中にはありとあらゆる武器が収められており、その量は狼人でさえもしとめられると確信できるほどだった。少女が用件を尋ねたところで、私は背を向け作った薬を飲みこんだ。たちまち私の身体に変化が起こった。体中の筋肉が急速に発達し、即座に新しい皮膚が生まれ全身が細やかな毛皮に覆われた。尾てい骨は人間にないはずの部位を作り上げ、歯も獣のそれへと変化した。そこから私の意識はぼんやりとし始めたが、おそらくその時身体は既に狼人の姿になっていたのだろう。
目の前のそれは何かを言って手近の武器を取った。鈍い音が部屋に響く。落とされる手足。攻撃の手は休まることなく、身体中が赤に染まるまで続けられた。
はっきりと意識を取り戻した時、私は取り返しのつかない過ちを犯したのを知った。赤黒く汚れた倉庫に横たわる惨たらしい小さな肉塊に人間の跡形が残っているのを目の当たりにした私は、果てしない後悔の念に囚われた。しかし既に私の野獣たる部分はそれを”食糧”として認識しており、私はそれを食べまいとその場から逃げだした。幸い月の無い砦の夜に人の影はなく、闇雲に走っても咎められることはなかった。しばらく走るうちに毛皮を撫でる風の心地よさに我を忘れ、気がついたころにはさっきまでいた砦が反対側の山に見えた。
今にして思えば、これで良かったのだろう。人間を目の当たりにしてしまえば私はそれを食糧と認識してしまうに違いない。事実あれから数日が経った今までに、何匹かの人間を食べてきた。もう後戻りは出来まい。
また、近くに人間のにおいがする。次の食事をもって、私は人間であることをやめる。もう私がこうして過去を思い筆を取ることもあるまい。人としての意識はもうすぐ消える。最後に、あの時死ぬはずだった、死ぬべきだった私に巻き込んでしまったアリッサ。ほんとうに申し訳ないことをした。誤って許されることではないが、私がまだ人間でもある内に書き記しておく。 ――ケランサ・グリンべ
「以上が、昨夜捕らえた狼人の持っていた手紙の内容になります」
兵士の声が仮設審判場にこだまする。容疑者席にいたアリッサから嗚咽が漏れるのを皮切りに、傍聴席から原告へ身勝手な野次が飛んだ。
「やっぱりその子じゃなかったじゃないか!」
「だいたいそんな小さい子が! 一介の兵士をあんな無残に殺せるわけがないだろう!」
「なんだてめぇさっきまであの子のこと魔女呼ばわりしてたじゃねぇか」
「おめぇだって火あぶりだのなんだの言ってたじゃねぇか!」
「皆さん静粛に!」
国王の一喝に再び場内が静まり返った。
「今ので君の無罪は確定した。アリッサ、疑ってすまなかった。諸君。この度のジョーセム検察兵の変死事件の犯人は、行方不明になっていたグリンべ研究員だ。以上で本審判を終了する」
その手紙は見事に形成をひっくり返し、彼女にかけられた容疑を一気に振り払った。しかし彼女の顔に笑みはなく、その場で大声を上げて泣きはじめた。民衆は気に留めること無く、そそくさと自分の小屋へ戻っていった。
目の前のそれは何かを言って手近の武器を取った。鈍い音が部屋に響く。落とされる手足。攻撃の手は休まることなく、身体中が赤に染まるまで続けられた。
はっきりと意識を取り戻した時、私は取り返しのつかない過ちを犯したのを知った。赤黒く汚れた倉庫に横たわる惨たらしい小さな肉塊に人間の跡形が残っているのを目の当たりにした私は、果てしない後悔の念に囚われた。しかし既に私の野獣たる部分はそれを”食糧”として認識しており、私はそれを食べまいとその場から逃げだした。幸い月の無い砦の夜に人の影はなく、闇雲に走っても咎められることはなかった。しばらく走るうちに毛皮を撫でる風の心地よさに我を忘れ、気がついたころにはさっきまでいた砦が反対側の山に見えた。
今にして思えば、これで良かったのだろう。人間を目の当たりにしてしまえば私はそれを食糧と認識してしまうに違いない。事実あれから数日が経った今までに、何匹かの人間を食べてきた。もう後戻りは出来まい。
また、近くに人間のにおいがする。次の食事をもって、私は人間であることをやめる。もう私がこうして過去を思い筆を取ることもあるまい。人としての意識はもうすぐ消える。最後に、あの時死ぬはずだった、死ぬべきだった私に巻き込んでしまったアリッサ。ほんとうに申し訳ないことをした。誤って許されることではないが、私がまだ人間でもある内に書き記しておく。 ――ケランサ・グリンべ
「以上が、昨夜捕らえた狼人の持っていた手紙の内容になります」
兵士の声が仮設審判場にこだまする。容疑者席にいたアリッサから嗚咽が漏れるのを皮切りに、傍聴席から原告へ身勝手な野次が飛んだ。
「やっぱりその子じゃなかったじゃないか!」
「だいたいそんな小さい子が! 一介の兵士をあんな無残に殺せるわけがないだろう!」
「なんだてめぇさっきまであの子のこと魔女呼ばわりしてたじゃねぇか」
「おめぇだって火あぶりだのなんだの言ってたじゃねぇか!」
「皆さん静粛に!」
国王の一喝に再び場内が静まり返った。
「今ので君の無罪は確定した。アリッサ、疑ってすまなかった。諸君。この度のジョーセム検察兵の変死事件の犯人は、行方不明になっていたグリンべ研究員だ。以上で本審判を終了する」
その手紙は見事に形成をひっくり返し、彼女にかけられた容疑を一気に振り払った。しかし彼女の顔に笑みはなく、その場で大声を上げて泣きはじめた。民衆は気に留めること無く、そそくさと自分の小屋へ戻っていった。
狼人の手紙