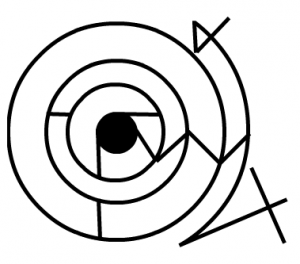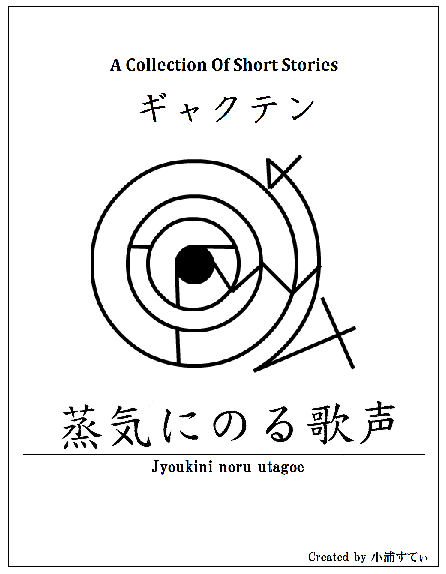
蒸気にのる歌声
短編集「ギャクテン」3作品目となります。今作の舞台はスチームパンクな国。国域を広めんといろんなところに喧嘩を売りにいく国です。ある国は「兵士は畑から取れる」なんて言われましたが、この国は果たして? どうぞお楽しみください。
延々と響き続ける歌声は、蒸気にのって頭の中にまで木霊する。
走る客車の穏やかな揺れに体を預け、男はぼんやりと窓の外を眺める。ガラスの向こうに広がる青々とした世界は絶え間なく目の前を駆け抜け続けていた。窓を開けると強い風が入り込み男の帽子を座席へと追いやったが、彼は気にせず身を乗り出した。
車輪が線路を走る音が気分を高揚させる。風の来る方を向けば、ただただ広がる草原の向こうに小さく都市の姿が見えた。とりあえず今日はあそこで一泊することになるだろうと考えていると、景気の良い汽笛の音と共に先頭車両の煙突から白い煙が立ち上った。
走っているうちに都市の姿が大きくなり、都市の外観と異様さが目に見えてわかるようになった。巨大な砲台が無数に敷き詰められた長城の隙間をすり抜けると、街のいたる所で蒸気が噴き出し、歯車が音を立てて回っていた。先程までの草原はどこへやら、どの建物や道具にも今まで見たことの無い仕掛けが施されており、そのどれもが技術の高さを誇示するようにすぐ触れるところにある。まるで夢の世界に迷い込んだか、それとも未来にタイムスリップしたかのような景色が流れていった。
やがて列車が巨大な駅のホームに入り車輪を止めた。男はまとめた荷物を抱えて客車を降りると、鉄の匂いが鼻をくすぐった。鼻を覆い構内に設けられた椅子に座り周りを見回せば、正装や仕事着の人々の波が戸惑うような鉄の匂いに構わず行き来している。彼はこれほど大勢の人間の中に立つという初めての経験に呆然とした。
男の意識が大衆の波から離れるのに、長い時間を費やした。事実それが現れなければ未だ彼の視線は大衆の波にさらわれていたであろう。彼が無心で眺めていた波間に、鼻歌まじりでこちらに歩み寄る美しい金髪の少女を見つけたのは、駅の中に6度目の汽笛が鳴り響いた後のことだった。
「こんにちは。どこから来られたんですか?」
屈託のない笑みで話しかけてくる少女の首には、絢爛とした歯車仕掛けの装飾品がカチカチと動いている。後ろに引っ張るカバンは少女の腰ぐらいまであり、それも歯車の仕掛けがなければ持ち運ぶことはできないだろうと思えた。美しい髪はゆったりと不規則に揺れ、この空間には無い「自然」を感じさせる。この場には似つかわしくない、いいとこの出のお嬢様といったところだろうと男は判断した。
「あっ、すみません。私はクラムと申します」
観察する男の顔が怪訝そうに見えたのか、少女は慌てて名を名乗る。
「あ、どうも。フェルム・ツーブランと言います」
妙にかしこまった挨拶をかわすと、クラムは男の様子を窺うように隣に座った。彼女も男がどんな人間かを観察しているのだろう。
「フェルムさんは……旅の方、とお見受けしましたが」
彼女のより一回り小さい荷物を椅子の横に置き、片手には周辺の地図、正装でも作業着でもないシャツにジャケットのいかにも旅人といった姿を見れば妥当な判断だろう。おそるおそる尋ねる少女を怖がらせないよう、できるだけ穏やかな口調を心掛けて答える。
「ええ。いろいろあって、アテのない旅をしています」
「いいですねぇ。いろんな都市を見てきたのでしょう?」
「ええまあ、ここより印象的な都市は多分ないと思いますが……」
そう言って周囲を見渡す。波はいっかな穏やかにならず、煙突から吹き上がる蒸気に合わせるかのように押しては引いてを繰り返す。空高くそびえる建造物が立ち並びいたる所で蒸気が吹き上がる様は彼の心を鷲掴みにしていた。
「出身はどちらから?」
「ポートル・グレンバシナっていう小さな港町です。仲間と一緒に船の旅をしてたんですが、他の都市にいたときに戦争に巻き込まれて……」
「まあ、可哀想に……お仲間さん、きっとまた会えますよ!」
意図せず暗い顔になるフェルムを励ますと、彼はばつが悪そうに笑った。
「それにしても船の旅ですか。いいですねぇ。私は生まれてから一度も、この目で海を見たことがないんです。きっと楽しいんだろうなぁ」
少女は薄汚れたガラスの天蓋越しに空を眺め、知らぬ世界に思いを馳せる。フェルムも空を眺め、故郷とこの都市はあまりにも違うというのに、空だけは同じものが広がっているこ
とをどこか奇妙に感じながら長い息を吐いた。
「そういえば、クラムさんはこれからどちらへ?」
「長いお勤めを終えて、故郷へ帰るところなんです。久しぶりに父に会いに行くんですよ」
そう話す少女の瞳は期待に満ちており、人を惹きつけて癒すような彼女の独特の雰囲気を心地よく感じつつも、自分とは合い入れることは無いのだろうと思うと心に風が吹き抜けるようだった。
「私の父も、昔はあなたのような旅人だったんです。私が生まれてから旅をやめてしまったんですけどね……よく話してくれました。あれは忘れもしない 半月の夜。ベッドに横になっていたら、けたたましい轟音が聞こえて、何かと思って外に出たら、馬に乗った騎士たちが城めがけて突進してたんですって。その後国の至る所で火事が起こって、父はもうこの国はダメだと思ったそうです。それで荷物をまとめて裏の路地から逃げ出したんだのが、当てのない放浪の始まりだって」
楽しそうに話す少女の姿は微笑ましいが、話の内容には笑っていられなかった。彼も同じような経緯で仲間とはぐれ、こうして一人旅をしている。あんな経験は自分くらいのものだと考えていたが、話を聞いて結構ありふれているのかと思い直した。おそらく彼女は戦いを目の前で見たことがないのだろう。彼女にとっては戦争も船の旅もお話の中の出来事でしかないと思うと、儚くも切ない感情が沸き上がる。
「ゆっくりしていってくださいね。ここも結構いい街なんですよ? といっても、大通りに出るまで工場の他には何もないんですけどね」
口を開くたびに風に揺れる花のような彼女は、そう言って鼻歌を口ずさむ。立ち上る蒸気が駅中に運び、やがてその音を外に響かせた。
「その歌は?」
「この歌ですか? この歌はですね……ふふ、すぐわかりますよ。この街にいればね」
要領を得ない答えに目を丸くすると、彼女はすっと立ち上がり、ホームに停車している蒸気機関車へと入っていった。その姿を目で追っていると客車の窓から顔を出して手招きするので、フェルムは立ち上がって駆け寄る。
「またどこかでお会いしましょう? 旅をしていれば……きっとまた会えるはずです」
「あ、あぁ。そうだね。またどこかで会いましょう」
「その時は、いろんな旅のお話、聞かせてくださいね?」
機関車の汽笛が鳴り響く。男は笑みを携えて頷き、やがて走り出す列車を見送った。列車の煙突から出る蒸気が、もう少しここにいたいと言わんばかりに長く尾を引く。列車が見えなるまでその後ろを見届けていたフェルムは、気づけば彼女が口ずさんでいた鼻歌を響かせていた。駅のホームで延々と響き続ける鼻歌は、蒸気にのって頭の中にまで木霊する。
フェルムが座るベンチの向かいの壁に、映像が投影される。ナレーションによるとそこで踊っているのはこの国のアイドル、もとい王女だそうだ。彼女は美しい金髪を風に揺れる花のように靡かせ、首に絢爛とした歯車仕掛けの装飾品がカチカチと動いている。彼女を見ていると、この都市には無い「自然」を感じさせる。この場には似つかわしくない、自然に囲まれた中で暮らすのが似合いそうだと男は判断した。彼女の姿や歌声に妙な感じを覚えたが、彼は何より目の前の壁の向こうで踊る姿に夢中になっていた。駅のホームで延々と響き続ける歌声は、蒸気にのって頭の中にまで木霊する。
「もうこんな時間か、仕事に戻らなくちゃな」
男は立ち上がり、始めて来たはずの都市をいつもの通勤経路のように迷いなく歩き出す。彼の口ずさむ歌声は工場地帯の蒸気にのって、もうそこから旅を続けることは無い。
蒸気にのる歌声