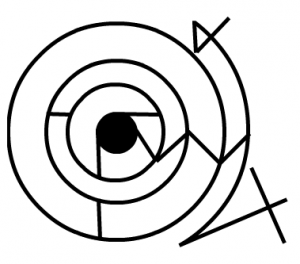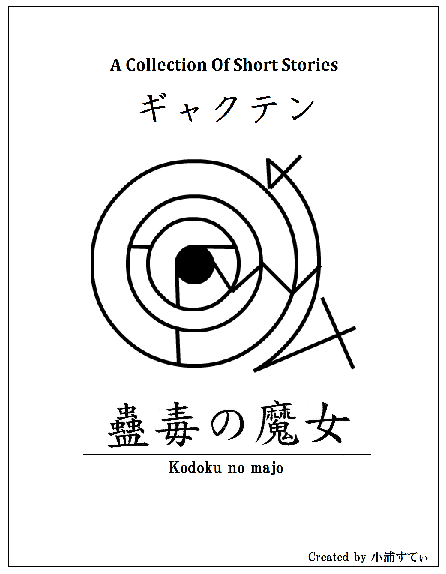
蠱毒の魔女
短編集「ギャクテン」の2作品目となります。ある田舎町に住む青年と、その土地を納める貴族の娘との恋模様。コドクは誰か、魔女は誰か――
もう会えないかもしれない彼女をその身に焼き付けたいと強く抱きしめた。
曇り空の夜、草原を両脇に侍らせた街道で、ガタイの良い男が老夫婦の前に立ちはだかっていた。
「へへっ、じいさんよお! ここは俺の道だ。通るなら通行料を払いな! さもないとどうなるか……」
そう言って腕を回す男に怯える老夫婦。少しして向かい側からボロいローブを頭から被った誰かがやってきて道を通ろうとしたが、同じように男がすかさず立ちはだかった。
「おうあんちゃん! ここは俺の道だぁ。通行料を払いな!」
ローブの主は頭を少し上げると、影に覆われよく見えない顔の眼を光らせ、ごそごそと懐をまさぐる。
「へっ、素直じゃねぇか。お前らも見習いな! こうやってさっさと払っちまえばすぐ通してやるのによぉ! ……お?」
老夫婦に怒鳴る男の手に冷たい感触が走る。差し出した手に乗せられたそれは暗いせいで何かよくわからなかったが、それには貨幣の硬さも輝きもなかった。
「おい! なんだこりゃあ? おれは通行料をよこせっつったんだ。さっさと払わねぇと……」
男は何かを持った手で拳を作り振り上げた。途端、握りこぶしの間から黒い何かが、岩から漏れ出す水のように腕を伝いはじめる。
「うわっ! なんだ! やめろ! ふ、服の中に入ってきやがった! う、うわぁぁぁぁ!」
身体中を無数の何かが這う感覚に耐え切れず、男は草原をあたりかまわず走り抜け、そのままどこかへ行ってしまった。残された老夫婦は呆然としていたが、助けてもらったことに気付くとローブの誰かに話しかけた。
「ああ旅の方、助けていただいてありがとう」
「あのままではいつまでたっても彼、いえ、息子を迎えに行けませんでした」
シルクハットの老父と、顔を隠した声の若い老婆の礼に小さく頭を下げ、ローブの誰かは旅路を急いだ。
シュエンティヴァリアは森の入り口に築かれた、クレンス家が代々治める林業の町である。出る人こそいるものの来る人などほとんどいない小さな町で、ローブの客人がクレンス家の門を叩いたことはその夜のうちに町の者の間で噂になっていた。もっともクレンス家の現当主、ディアハマ・クレンス・シュタットルの人望は厚かったため、王国からの使いが建築材料の交渉に来ただの、古くからの友人が久々に訪ねてきたのだろうと言う好意的な解釈でもって認識されていた。
「一体どんなやつなんだろうな?」
「さぁ? でもこんな田舎に来る奴だ。相当の物好きに違いないぜ」
街灯が照らす広場では数少ない若者たちが噂話をしている。彼らは親の仕事の手伝いを終えるといつものように広場に集まり愚痴を言い合って鬱憤を晴らすのだ。
「あーあ、さっさと都会に出てーなー」
「そうだなー。都会に出てさ、歌でも歌って人気者になりてーなぁ」
「お前の歌じゃ笑いものになっちまうだろーよ」
ケラケラと夜空に笑い声が木霊する。月の隠れた夜は街灯の光を一層強く見せ、その下に集まった青年たちも光り輝く未来をぼんやりと思いながら笑い続けた。
「でも歌って暮らせりゃきっと楽だよなー」
「だろ? 一緒にやろうぜ! あ、ショーン、お前楽器出来たよな? いつも担いでるやつ……なんだっけ? まあとにかくそれで伴奏やってくれよ!」
「ばーか! モッキンっていうんだよ!」
「そう! モッキン! お前のモッキン最高だぜ!」
「いや、俺はここに残るよ」
仲間たちが囃し立てるが、金髪の青年の小さな笑いが混じった答えに、一同は顔を見合わせた。風の音が吹き抜けた後、再び爆笑の渦に包まれた。
「ハハハハハ! 面白いこと言うなぁ! こんななにも無い所じゃ好きなこともできないじゃないか」
「そうだよー。一緒に有名人になろうぜー」
友人たちがそう誘うが、ショーンは小さく笑って続ける。
「いやぁ、なんだか仕事を手伝ってるとさ、この生活も悪くないなーって思えてきてさ」
「なんだよー、若いんだからもっと大きな夢見たって罰当たりゃしないぜ?」
「そうなんだけどね。そろそろ現実も見なきゃなって、思えてきてさ」
「……おい、何かあったのか?」
いつもと様子が違うショーンをついに心配し始める友人たちだが、彼は再び笑ってごまかす。そうこうする中八時を告げる鐘が鳴り響き、青年の集いもハチの子を散らすように帰り始めた。
「あいつら夕飯の時だけは速いな……ショーン、確かにお前の言う通り、現実を見なきゃいけない時期なのかもな……さぁて! 俺も帰るわ!」
「うん、また明日」
「ああ。悩みとかあったら言えよ? じゃあな!」
駆けていく友人を見送り、ショーンは一人街灯の下でため息をついた。
「一番現実を見なきゃいけないのは、僕なんだよな」
クレンス家は数百年前から続く由緒正しい家柄であり、邸宅もアンティークな外見を維持している。現当主が自然に囲まれた中で自然に朽ちるさまを楽しんでいるらしく、塀の一部が脆く崩れている個所もあえて直していない。だからこそ特別優れた特徴のないショーンでも簡単に中に入ることができた。月明かりが遮られていることも幸いして普段より軽々と目当ての部屋の窓までたどり着いた彼は、周囲を確認してから三回キリギリスの鳴きまねをした。
「ショーン! いらっしゃい! 待ちくたびれたわ!」
開け放たれた窓から少女の笑顔が飛び込んでくる。そのまま細い腕で抱きしめられるショーンは倒れないように踏ん張りつつ、両手で受け止めながらゆっくりと部屋に押し戻し、ニコニコと笑う少女に口の前で指を立てる。
「レイ! 静かに!」
「ふふふ、ごめんなさい。嬉しかったからつい」
そう言って笑う彼女に見惚れながら靴を仕舞い窓の縁を乗り越えると、名家のお嬢様らしい煌びやかな内装に見るからに女の子らしい室内の装飾品が溢れかえり、とても田舎にあるとは思えないほど豪華な空間が広がる。しかしショーンは最初こそ装飾に驚いたものの、ここに来るようになって半年が過ぎた今ではすっかり慣れてしまった。
「頼むよ。お父さんには内緒なんだろう?」
「ええ。でも近いうちに紹介するわ」
「それはそれで困るな……」
そう言って差し出されたカップのお茶を一口飲み、一息つく。彼女のオリジナルの紅茶はクセになる独特の苦みがあり、相変わらず美味しいのか美味しくないのかよくわからなかった。それでも愛おしい彼女が出してくれたものなら何でも受け入れたいショーンは、いつも微妙な顔をしながら時間をかけて休み休み口をつけ飲み干すのだ。期待に満ちたレイの視線に軽く応え、ぼんやりと窓の外を眺めた。流れる雲の端に月明かりが漏れている。
「ショーン、今日もお仕事お疲れ様。疲れたでしょ?」
「ありがとう。そうだね、いい汗かいたよ。そういえば今日はお客さんが来てるんだっけ?」
突然の問いにレイはすっとんきょうな声を上げ、目を丸くしてショーンを見る。ショーンの方も彼女の反応に体を強張らせた。
「えっ、なんで知ってるの?」
「えっじゃないよ。もう村中に広まってるよ」
「そうなの!? はやいなぁ……あの人はね、パパの昔の友達で、薬師をやっている方なの。パパったら最近体の調子が悪くて。それで呼んだんじゃないかしら」
「そうなんだ……」
どぎまぎとした返答は納得できるものではなかったが、彼女の機嫌を損ねたくないショーンは下手に追究することはしなかった。
その後最近あったことを話したり、担いできた木琴を弾いてみせたりした。軽快なリズムが夜空に響き、レイは目をキラキラさせて聞き入っている。ショーンは何より彼女のそうした顔が好きだった。演奏を終え、たった一人の客が彼に拍手を送ると照れくさそうに笑った。
「ちょっとトイレ借りるね」
レイの部屋に入って60分が経った頃、ショーンはそう言って廊下へ出た。人がいないのを確認しつつ、音を立てないように進む。もう夜も遅い。そろそろ家へ帰らなければ、家族が心配する。この時間がくると大抵ショーンは名残惜しさを噛みしめつつ、この廊下を歩くのだ。
ショーンはトイレに入って鍵をかけ、深いため息をついた。彼は今後の身の振り方を考えていた。この先親が老い、自分が働いていかねばならないというのに、ここ数年害虫のせいで森の木の減少が急速に進んでおり、若手が後を継いで家族を養えるほどの収入は見込めないことを今日父から教えてもらった。ショーンはずっと親の仕事を手伝ってきた。故に他の仕事ができるだけの知識はない。勉強するには金が必要だ。しかしいまのショーンの家計では、飢えを満たすので精いっぱいなのだ。
そんな彼にも夢があった。都会に出て、音楽を奏でて暮らしていくという光が。しかしそれは現実という風の前にはあまりにも儚い灯だった。幼い頃、誕生日に作ってもらった木琴は今でも大切に使い、この木琴のおかげでレイと出会うことも出来たが、もはや辛い現状を一時的に忘れさせてくれるものでしかない。
死ぬことも考えた。自分がいなくなれば、家族の負担も減る。どうせ役に立たないのなら、なくなってしまった方がましだと。しかし家族の事を、レイの事を考えると、そうするわけにもいかない。彼は進退両難の極地を感じていた。
トイレを出て、暗い廊下を歩いていると、大きな扉から漏れる話し声が耳に入ってきた。とりわけ豪華な装飾の施されたその扉の向こうはレイの父、クレンス侯爵の部屋だ。彼は慎重に扉に近づき、聞き耳を立てた。
「大きな熊を一頭――」
「それはそれは、楽しそうで何よりだ」
答える男の声は侯爵のもの。話をしている女の声が、おそらく黒いローブの客人だろう。女性が熊を一頭仕留めたとかで、楽しそうに話している。
「ところで、例のものは持ってきてくれたかね?」
「ああ、あの薬ならこちらに」
レイは本当のことを言っていたのかと思った刹那、ショーンは続く二人の会話に耳を疑った。
「ありがとう。最近屋敷に悪い虫がついていてね」
「フフ、その薬なら、虫どころか象ですらイチコロですわ」
「それは頼もしい。レイにはできるだけいい環境を与えてやりたいのだ」
悪い虫。ショーンの心臓は脳に響くほどの鼓動をみせていた。彼は出来るだけ音を立てないようにそこから離れ、レイの部屋に戻った。ベッドに座っていたレイは戻ってきたショーンを見て一瞬笑顔を見せたが、すぐさま不安げな表情に変わった。
「ショーン? どうしたの?」
「い、いや、なんでもないよ」
できるだけ平静を保とうとするショーンだったが、その顔は真っ青で体もわずかに震えていた。
「落ち着いて」
差し出された紅茶を飲み干し、息を整えて考える。侯爵はショーンの事を知っていて、取り寄せた薬……いや毒で殺そうとしている。一刻も早くここから逃げなくては。
ショーンおもむろにレイを抱きしめた。もう会えないかもしれない彼女をその身に焼き付けたいと強く抱きしめた。驚いていたレイもゆっくりと抱きしめ返す。痺れるような感覚。全身が熱くなり、一度冷静になった筈の意識が朦朧としはじめ、徐々に息遣いが荒くなる。やがて立っていられなくなったショーンは床に崩れ、死に際の虫のようにもがきながら彼女の足にすがり、全身で汗をかいてうわ言のように彼女の名を呼ぶ。
「ごめんね。新しい虫が入ったから新作を作ってみたんだけど、強すぎちゃったみたい」
見上げた彼女の恍惚とした表情。キラキラとした瞳。唇が五つの文字を発する形を目に焼き付けたショーンは、くしゃっとした笑顔を見せ、あきらめたように息を吐き、やがて動きを止めた。
蠱毒の魔女