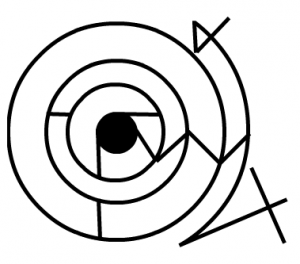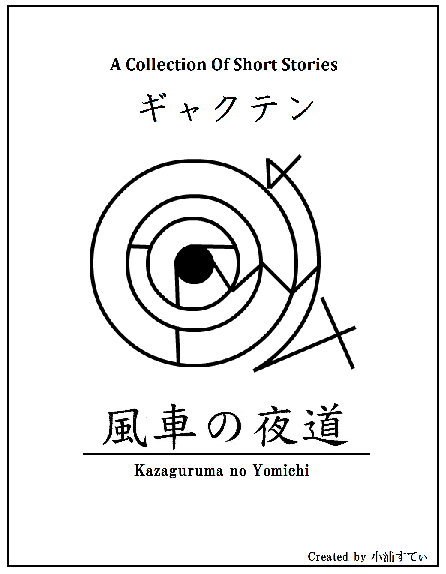
風車の夜道
クレノヤ・カロムはほくそ笑んだ
クレノヤ・カロムはほくそ笑んだ。誰も越えることは叶わないとされる寮の壁をよじ登り、暗い土の地面を踏みしめた。月夜の風は背中を押すように強く吹き、勢いよく回る風車の音は心を奮い立たせる。
寮の外の土を踏むのはおよそ一年ぶりであった。かつてはこの国フーリズムでの生活に心躍らせて寮の門をくぐったが、寮での生活は過酷を極めるものであった。家畜の小屋のような個室をあてがわれ、割に合わない家賃を払うために危険な労働を強いられた。寮は高い壁に覆われ外に出ること叶わず、脱走が見つかったものは気絶するまでグラウンドで腕立て伏せの刑を科せられた。大きなけがをした者、体の弱い者、老人、死体等は区別なく荷馬車で運ばれ、一説には深い谷底へ落としているという噂が囁かれた。そんな環境だからこそ、カロムは寮の外に出たいと願い続け、月が雲に隠れている今日、実行に移したのだった。
小さな国にもかかわらず旅人がよく足を休めに立ち寄るのには、この国が風の信仰における要所であることに原因がある。風は旅人を象徴し、旅の安全を願う意味で全ての民家に風車が設置されている。半ば旅人のために作られたような国のため住民も旅人に対する理解が深く寛容で、夜中でも昼間のような賑わいを見せた。主要な道に明かりを張り巡らせ、その下に豪華な料理の乗ったテーブルと浮かれて踊り騒ぐ旅人たちの姿。もはや毎日がお祭りと言ってもいいだろう。
そんな賑わいの真っただ中に出ようと、カロムは今いる薄暗い路地を駆け出した。草を揺らし毛皮の服を撫でる風は心地よく、裏路地に陽気な風車の音を響かせると、やがてまぶしい大通りが見えた。
明々とした大通りは真昼のようで、豪華な料理に見たこともないようなパフォーマンス、心湧きたつ演奏や活気の良い笑い声は風車の程よい伴奏に乗せられて、凄まじいほどの轟音であるにも関わらずそれを不快には感じず、自然と足がそっちへと向かっていった。
「おい兄ちゃん! そんなとこに突っ立ってねぇで飲もうぜ!」
傍で盃を持っていたモヒカンの男が笑いながらカロムの肩を叩く。一度は驚いたがすぐにこういう物なのだと言い聞かせ、男の言うがままに、小さな酒盛りの集団に分け入った。
「おれたちゃポートル・グレンバシナから船で来たんだ! 俺はジョニー。こっちがデリム、そんでそこの筋肉野郎がグラントだ」
「ボウズ、よろしくなぁ!」
「ジョン、おめーだって筋肉野郎じゃねぇか!」
「あんちゃんそんなちっさな体でホントに男か?」
「バンデ、お前見境無さすぎるぜ?」
体つきに関してはあまり違いの無い筋肉隆々の男たちの中に招き入れられ呆然としているカロムに、向かいに座っていた白いひげの老父が果実酒の入ったジョッキを手渡した。
「すまんな、うちの船員はバカしかおらん。気にせんでくれ。ワシは……クリスでかまわん。ジャッククリスノート号でバカどもの世話をしながら世界中を旅しておる。毒虫の森に屍魚の島、もしかしたらお主の町にも行ったことがあるかもしれんな」
「おっさん話なげーよ! すまねぇな、おっさんは客人が来ると昔話がしたくてたまらなくなるんだ。……えっと、すまねぇ、名前なんて言ったっけ?」
「カロムといいます。」
「カロムか、いい名前だな!」
話を中断されて非難の声を上げるクリスをよそに、モヒカンの男ジョニーと仲間たちはカロムを囲んで酒盛りを再開した。
「気を付けろ、バンデはヤれれば人間じゃなくてもヤっちまうからな」
「さすがに人外はやだよ」
「でもヤれるんだろ?」
「まあその気になればできないことはないけどな!」
心地よい風の賑やかな通りから一際豪快な笑い声が夜空に響く。酒と空気でいい感じに酔い始めてきたカロムはこのまま陽気にのまれて朝まで過ごすのも悪くないと考えていた。しかし、男のある質問で酔いは一気に醒めることとなる。
「そういやカロム! おまえはどっから来たんだ?」
風車の音が演奏と喧騒に呑まれた。よもや自分の事を聞かれると思っていなかったカロムは驚いた顔で男を見て固まる。
「そういや聞いてなかったな! 教えてくれよ! カロムの故郷はどんな所なんだ?」
他の仲間たちも話に乗ってくる。しかし自分のいた所を言ってしまうとまた連れ戻されるかもしれない。どう答えるか悩んでいると、通りの向こうから警鐘が響いた。
「えー、旅人の皆さん! 聞いてくださーい!」
青黒い服の太った男の声に皆は手を止めた。通りには抑えられていた風車の音だけが響く。
「先ほど労働寮から脱走者が出ました! 脱走犯は何をしでかすかわからないので十分に気を付けてください!」
そう言って男が走っていくと、何事もなかったかのように再び酒盛りは始められた。
「脱走犯だってよ! 逃げたくなるほどキツイ仕事なんだろうなぁ!」
「何しでかすかわかんねぇってよ! カロムも気を付けな」
笑いながら言うジョニーに笑顔で返したカロムだったが、内心では怯えきっていた。脱走したことが既に寮監督にバレているということは、じきに寮からの追っ手が来るだろう。これ以上ここにいるわけにはいかない。
「あっ、ジョニーさん。俺ちょっと」
「なんだ? ションベンか? さっきの件もあるし俺もついてってやるぜ」
「おいバンデ、お前が言うとシャレにならねぇんだよ。おう、行って来い。気ぃ付けてな」
勢いのよい風が吹いた。人ごみに紛れながら再び裏の路地へ入り、果物の入った箱の影に身をひそめ一息つくと、箱の向こうにいる男たちの話し声がカロムの耳に入ってきた。どうやら脱走犯の首に賞金が掛かったらしい。いまやここで酒盛りをしている旅人全員がカロムを探しているらしかった。傍の風車の軸が金切り声をあげる
脱走してから間もないと言うのにこの対応の速さ。カロムは脱走したはずの仲間が翌朝グラウンドで気絶するまで腕立て伏せをさせられている理由が理解できた。奴らは寮の壁を越えられることを初めから想定していたのだ。もうあの賑わいの中に戻ることはできない。旅人たちは夜の街を思い思いに楽しんでいるが、その気になれば脱走犯の一人くらい捕まえるのは造作もないだろう。彼は出来るだけ人目のつかない道を選んで駆け抜けた。建物の影を踏み、時には守衛に追いかけられ、物陰に潜んでは追っ手をまき、町中に張り巡らされた賑わいを潜り抜けて、風車の悲鳴はまだまだ止まない。
どれほどの時間が経っただろうか。いつしか国への出入り口たる巨大な門を背後にし、草原を両脇に侍らせた街道のただ中に立っていた。緩やかな風は暗雲を払い、回し車のような音と共に半月が姿を見せた。この国の管理する土地の端を意味する赤い風車は足元で休み休み回る。カロムはその場に大の字に体を倒し横になった。門の向こうでは明々とした光がまだ灯っており、この国が平和な限りその灯は消えることはないだろうと確信させるものであった。カロムにはさっきまでその賑わいの中にいたのがまるで夢のように感じられた。実際彼にとって稀に見る夢のようなひと時であった。
カロムは緊迫した脱出劇を終え、風車を指先で逆に回しながら口笛を吹く。次に行くのはどこの国か、などと考えていると、茂みの中から小さな影が彼に近づき、小声で話しかけた。
「カロムさん、様子はいかがでした?」
その姿は一見老婦のようだが声は少女のものであり、顔をよく見ると作り物のマスクであることがわかる。カロムは苦笑しながら答える。
「迎えに来てくれたんだ、ありがとう。でもそのマスクは似合ってないね」
「それはいいんです。首尾はどうです?」
「ああ、平和な国さ。今はちょうど脱走犯一人を賞金までかけて捕まえようとしてるよ。どうも入り口の守衛まで持ち場を離れるほどの額らしい」
「上出来ですわ」
そう言うと老婦の格好をした少女は小さな筒を空に掲げ、取り付けられた紐を引っ張る。たちまち、夜空に音もなく火花が広がった。
直後、夜空に大勢の人間の雄たけびが木霊した。北の森から聞こえたそれは影となって飛び出しやがて月明かりに照らされ、草原に甲冑の兵を乗せた軍馬の群れを映し出す。
「行くぞぉ! ここを我らグエンプライアの土地とするのだ!」
「うおおおおおおお!!」
先頭の兵が言うが早いかカロムの横を通り過ぎ、それに続いて何十もの軍馬が駆け抜けた。
「お疲れ様です、クレノヤ・カロム潜入員。あなたのおかげでフーリズムの強硬な態度が虚勢であるとわかりましたわ。おかげで兵士長も無駄足にならずに済むし、お父上も目障りな町が焦土と化したのを知れば数日は機嫌の良く過ごせることでしょう。さあ、お父上に報告に参りましょう」
差し出された少女の手を取り、カロムは夜道を歩き出す。風の都市は背後で赤々と燃えさかる。軍馬に踏み砕かれた赤い風車は、もう回ることはない。
風車の夜道