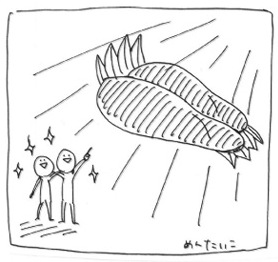
めんたいこ、風に乱れて
舌先で転がしていためんたいこの薄皮を吐きつけたのは、さっきまで桜木本部長を乗せていた安っぽいビニールのサイドシートだった。おれは、自分の耳元で「こんなことをしてやった!」と小っちゃな心の暴走族が、軍艦旗を振り回して雄叫びを上げる声を聞いた。
アクセルを踏みしめるとすぐに信号は赤に変わった。前を走るトラックのテールランプがぼんやりと滲む。未明から降り続く小糠雨がフロントガラスを舐めるように流れていた。ふと時計に目をやると同時にまた大きなあくびが出た。
寝不足なのか、それとも、この人生そのものが退屈の極みでしかないのか。唇の端を歪めて横目で車外を眺めやる。雨に濡れた博多市内はありとあらゆる景色が灰色にくすんでいた。集合住宅、渋滞する車列、鮨屋、運送会社の看板、アパレルのビル、張子や福笹に色とりどりののぼりで飾り付けられた博多祇園山笠の鮮やかな装飾でさえおれには何の色も持たない。
サラリーマンは気楽な稼業だ。
それはおれを見れば分かる。
たいした仕事をしていなくても、毎月きちんと銀行口座にはお金が振り込まれる。ボーナスだってそれなりには、ある。だけど、それは、やりがいとはちがう。毎日工場から送られてくる巨大な段ボールに詰められた無数のソックス。それの表面を特殊な機械を使って平たくパンチングするのがおれの役目だ。靴下パンチャー。「パンチング係長」と書かれた名刺を差し出すと、決まって変わった役職だと言われる。「きみはたいしたハードパンチャーだよ」。桜木本部長はそういっておれの肩を叩いた。プロボクサー志望であったおれに対するあてつけか。しかし腕力と握力に加え上半身に独特の力の入れ方が必要なこの仕事をこなすことができたのは、ボクサーとしてならした基礎体力がものをいったのは確かだ。さすがに最近では仕事終わりにハードなトレーニングをすると息があがるようになったが、プロテスト受験資格を失った2年前と比べても、体力は大きく衰えていない自信がある。桜木本部長の物言いは、未だボクシングへの未練が捨て切れないおれを茶化しているように響いた。それも、まあ、考えすぎた。おれの偏執的な思いが、他愛もない人の物言いを頭の中で歪めているのだ。きっと。
運転席のウインドーを少し開ける。湿った風が吹き込んでくる。最近、下水管の袋小路に追いつめられたドブネズミの夢をよく見る。ここから逃げ出したい。着の身着のままたった一人で、どこかに飛んで行きたい。そんな無意識の希求が夢にカタチを変えているのだろうか。生来の弱虫で臆病もののロマンが疼き出すと、薬指のリングが孫悟空の金環のように頭を締めつけてくる。さしずめ、陰茎は如意棒だろうか。最近あんまり伸びないけど。ふはは、不如意棒だ。尿意ばかりが近いイカれたポンコツだ。もう年なんだ。おれは、まったく、身勝手な野郎だ。
またあくびが出た。
渋滞が続く路上で、おれは涙目をしばたかせダッシュボードに手を伸ばし、漆塗りの木箱をとり出す。背中から皮膚の中を甲虫が這い上がってくるようなスリル。ずっしりとした重みを感じる『中重武治作 紅玉』と焼印が入ったそれを掴み、箱から突き出した細長い「突き棒」をぐっと押すと、木箱の前方、約3センチ四方の四角い穴からにゅるりと艶やかな赤い舌のような一腹のめんたいこが押し出された。
おれは素早くそれに吸いついた。ぴりりとした辛み、そして柚子の爽やかな香りとほのかな甘みが口の中に広がる。潮吹き岩のように頬の奥から、ぴゅっと涎が分泌される音が聞こえた。
あわてるな。
いきなり粒子感へと辿り着くのではなく、歯を立てずまずはねっとりと表面のデリケートな薄皮を玩ぶ。そしてディープスロート、咽喉の奥深くまでめんたいこをまっすぐ入れては再びぬるりと舌先にまで戻す。それを何回か繰り返していると摩擦で表面の薄皮に亀裂が入るので、そこではじめて、昔付き合っていた彼女にチャームポイントだと言われた八重歯の出番となる。牙のように突き立てられた犬歯によって、スケトウダラの卵巣を覆う被膜は破れ、堰を切ったようにあふれ出す鮮度の高い原卵が口腔で踊る。
「ちょっと、控えないとな」。
臼歯でプチプチとめんたいこをつぶしながら、おれは呟いた。そう一日一腹までと医者からも言われているんだった、塩分とコレステロールの高いめんたいこは成人病を誘発する。先だって会社で行われた健康診断でも血圧が尋常ではない数値を弾き出していた。しかしながら、博多っ子からめんたいこ取ったら何が残るんだよ。昨日の夜も妻にそう愚痴をこぼした。
「だけど、最近厳しいしね」
妻はエプロンで手を拭いながらおれが座るテーブルの方へ向き直した。
「ああ……」
右手に茶碗を持ち、残しておいた、最後の白米にちょうど合う分量のめんたいこを上にバランスよく乗せ、一気に箸で掻き込む。
「けどさ、このごろ迫害されすぎじゃねえか?」
「昨日のニュースでやってたわよ。福岡市内はもう『歩きめんたいこ』禁止でしょう?」
「博多はまだだっけ?」
「どっちにしたってもう時間の問題よ。博多だけ免れるなんてことありえないんだから」
「つるし上げだよな。めんたいこだけが悪いのかよ。いくらは? カズノコは? ししゃもはどうなんだよ」
「別に食べるなとは言ってないじゃない。マナーの問題でしょう。公共の場でのべつまくなしめんたいこに吸いつく人がいたら、子どもの教育にだってあんまり良くないわ。中には野良犬みたいな目つきの人も居るもの」
「めんたいこの入ったおにぎりはどうなんだ。めんたいこパスタを路上で食ってても捕まらないのか」
「あたしに言われても知らないわよ。なにか細かい決まりがあるんでしょうよ」
「『めんたいことアスパラガスのクリームチーズ和え』はどうなる?」
「そこまで行くともう法の抜け穴ね。いたちごっこだわ」
「すべてがめんたいこのせいにされているんだ。めんたいこを悪者にすればすべて解決すると思っている。浅はかだよあいつらは」
妻は急須に湯を注ぎ、上がりの入った湯飲みをおれの前に置いた。
「いいじゃない、最近どんどん値上がりしているし、毎月のめんたいこ代だって馬鹿にならないんだからさ。この機会に『禁たいこ』すれば」
「『禁たいこ』だなんてお前、よく言うよ。おれは13の時からめんたいこ吸ってるんだぜ。仲間と体育館の裏でこっそり先公に見つからないようにさ、体に染みついためんたいこの味は、そんなすぐには忘れられるもんじゃない」
「だからそんなお腹になっちゃったんでしょうが」
妻はおれのプリンスメロンのような下腹部をちらりと見て含み笑いした。いや、おれだって2年前までは、ちゃんと毎日トレーニングもしていたし──と言いかけ、何かやましいような気持ちになって口をつぐんだ。
「丈一郎は寝たのか?」
「ええ、今日は帰ってきたらすぐに寝ちゃったわ。公園のお砂場でばあばにたくさん遊んでもらったからね」
「来年の──4月からだっけ?」
「なにが? 入園」
「そう、幼稚園」
「そうよ満3歳になってからだからね」
「いくらぐらい、かかるのかなあ」
「まだ、調べてないの。ごめんね。だけど、いざとなったらウチの両親からちょっとぐらい助け船が出るわよ」
「いや、だめだよ、それは。悪いよ。ここに引っ越す時だってだいぶ援助してもらってるんだから。それだってまだちゃんと返せてないし……店も辞めるんだろ?」
「それはちょっと先の話になりそうよ。七〇になったら引退するって言ってたんだけどね、丈一郎に補助輪付きの自転車を買ってやりたいってまた張り切りだしちゃって。昨日も市場で安いキャベツを見つけたって言って自転車に積んでさ、山盛り仕入れして帰ってきたんだから」
「孫パワーおそるべし、だね」
「ほんと。私たちが結婚するときは、孫なんてオレは欲しくない。何がかわいいのか分からない、なんて言ってた人がね! だから、入学金のことは気にしないで。それより、借金返す方が先でしょう」
おれは微かに頷くしかなった。借金のことを言われるとぐうの音も出ない。下積み時代が長かったおれは、アルバイトを転々としながら、時にヒモのようにして暮らしボクシングに打ち込んだ。才能の芽は出ず、夢はしぼんだが借金だけは膨らんだ。博多市内のデパートで働く妻の収入だけではやっていけず、消費者金融から金を借りた。返済期日になっても返せず、複数社をはしごして金を回したり最後は藁をつかむような思いで怪しい金融にも手を出した。結果、借金は数百万円にまで及んだ。
「私たちは、マイナスからのスタートなんだから」。シンクの蛇口を捻りながらわざと明るい声で話す妻の気づかいは胸に沁みたが、気持ちは一向に晴れなかった。
ふと、視線を感じた。隣の車線に止まっている白い4ドアのセダンから、ヘルメットをかぶった男がじっとこっちを見ていた。おれがちらりとそちらに視線を向けても一向に目を逸らさない。その無遠慮な目線にだんだん腹が立ち、しまいににらみ返していた。薄暗く整然とした車内に、軽く違和感をおぼえた。人形やステッカー、ティッシュなどの装飾・小物類が何もない。異常なほど殺風景な車。信号が変わったので、おれは視界を前方に戻しサイドブレーキを解除してゆっくりとアクセルを踏み込んだ。
ルーフの下に隠されていたパトライトをあらわにして、目を射るほど赤々とした灯を回転させながら、おれの前にさっきの車がぐいっと割り込んできた。88ナンバー。「止まりなさい」と命令されるより早く、おれはすべてを理解した。
路肩に停車して、促されるままに覆面パトカーの後部座席に乗り込む。運転席で妙に背筋を伸ばした青い服の男が振り返りざまおれに「食べてましたよね」と言った。
「急いでるんですけどね」おれは苛々と言い返した。
「だけどー、食べちゃだめでしょう。4月から運転中のめんたいこが禁止されているのは知ってるよね」
「別に止まってる時だから、いいでしょう。こんなに渋滞してるんだから」
「そういう問題じゃないんだよね。ちょっと免許証見せてくれる?」抑揚を殺した声でおれに要求する。その表情は伺い知れないが、年の頃は自分と同じぐらいだろうか。
「ちゃんとサイドブレーキも引いていましたよ」。おれは憮然として抵抗した。
「だけど、確実に食べてましたよね」
「食べてないとは言わないけどさ!」
「お酒といっしょだよ。車を止めている時に飲んだって言ったってそれで運転したら同じことだよね。言い逃れられないでしょう」
「酒とめんたいこは違うだろう! めんたいこを食べたあとで判断力や動態視力が鈍るというのか。運転には何の支障もない」
「いやいや、神経が麻痺しますよ。口の中のね」
「それが運転となんの関係があるんだ!」
「免許証見せてくださいよ」
「悪いけどさ、急いでいるんだよ。忙しいんだ君とちがって」
「お仕事は何されてるんですか」
「……何だっていいじゃない」
「けっこういい体してますね。プロスポーツ関係ですか」
「工場」おれはぶっきらぼうに答えた。
「ああ、そうですか」警官は手元のバインダーに向かい何か書き込むような素振りを見せた。
「もう行っていいですか?」
「何言ってるの。だめだよ。違反行為を見逃すわけにはいかないからね」
「どれぐらい引かれるんですか?」
「点数? まず車内飲食違反で点数が2点ね。それから、6か月以下の懲役又は一〇万円以下の罰金」
「めんたいこで刑務所行きかよ! ありえないだろう。それはちょっと辛すぎますって!」
「辛くないめんたいこがあるのか!」
ピリリとした空気が車内を包んだ。
それまでの車中がたらこであったなら、警官の怒号のあと車中の空気は辛子めんたいこに一変したといえよう。ふざけやがって。おれは、この男を一度なぐってみようかと思った。
「おまわりさん、あのね。あなたがどちらの出身か、知りませんけども、博多の人間にとってめんたいこっていうのは、すごく身近なものなんですよ。気分が晴れない時やムシャクシャした時なんかこれがあれば──」
「私も博多ですから、よく知ってますよ。夜勤の時なんかは手放せないね。眠くなったらよく辛子めんたいこを四五本いっぺんに口の中に放り込みます。眠気ざましのガムなんかよりよっぽど効く」
「そうなんですよ、ぼくも運転中に眠くなっちゃってね、それでめんたいこを口に運んだんですよ。だってそうしないで事故を起こした方が大変ですからね!」我が意を得たりとおれは畳みかけた。
「だけど、運転中には食べません。ルールですからね」この堅物め! おれは憤慨したが同時にこれはもはや押しても引いてもだめな人物だと悟り、渋々と尻ポケットの財布から免許証を抜き取った。警官はヘルメットを脱いで助手席に置き、額の汗をハンカチで拭うと差し出された免許を受け取った。そして彼がおれの名前を見て、顔を確認するのと、細い目と左だけ半分ない眉毛という特徴から、おれがその懐かしい顔に思い当たるのとがほぼ同時であった。おれたちは異口同音に「あっきー?」「カズノリ君?」と互いを指さしながら声を上げたのである。
「あれー、どうしたの何してるの」
「いやいやいや、お前こそ!」
「久しぶりだねえ、最後に会ったのが高校の時だから17年?18年か、いやーびっくりした」
「なんか似てるな、と思ってたんだよ」
「すぐに言ってくれりゃいいのに」
「だけど、まさかと思うじゃない。免許見るまではさ。それにしても太ったね」
「あっきー、なんで警察なんかになってんのよ?」
「なんだかいやな再会だなあ。変なやつ捕まえちゃったよ、まったく!」
意外な再会であった。あっきーこと秋本昭洋とは高校2年と3年の時同じクラスで──といっても3年のとき彼は母親が蒸発してから不登校になりほとんど学校に来ていないが──の中学時代の同級生らとよくつるんで悪さをした悪友の一人だった。体育館の裏でビニール袋に入れためんたいこを吸ったり、店頭販売されている山盛りのめんたいこを堂々と万引きしたりと今考えると子供っぽい戯れなのだけれど、夜な夜なコンビニの駐車場や博多港の埃っぽい空き倉庫に集まっては凍らせためんたいこを女の膣に入れただとか、中洲の繁華街で密売人からシャブ漬けの毒めんたいこを買っただとか他愛のない嘘と見栄の入り混じった思春期らしい偽悪的な冗談で笑いあっていた頃の仲間だった。
「知らなかったの。吉富から聞いてるのかと思ってた」
「全然、全然。吉富と遊んでたのも高校までだもん」
「吉富は今何してるか知ってる?」
「京都で板前してるって聞いたけど。それもだいぶ前の話だけど」
「京都に『神独楽』っていう、有名な料亭あるだろ。今そこの総料理長なんだぜ」
「えーっ、それはすごいな。っていうかありえなくないか。だってアイツおれらとつるんで、めんたいこ万引きしてたやつだぜ」
おれたちは同時に吹き出した。サイドをさっぱりと刈り上げた毛の生え際に小さなニキビがある。そう、こいつは昔から肌が弱く吹き出物が絶えなかった。夏休みにでかいボディーピアスの穴を開けたときも酷くかぶれたっけ。
「だけど、どうしたのよその頭!」
「え、なにが? ああ」と言って髪を撫で上げる。あの頃、あっきーといえば銀色に染めた長い髪がトレードマークだった。強力なブリーチ剤を使っていたらしく、髪の毛は酷い痛み方をしていた。雨に濡れるとどろどろに溶けたようになるようになるのだと。
「さっぱりしちゃって!」
照れた顔に面影が蘇る。雨に打たれる覆面パトカーの中で、おれたちはいつしか共犯者に戻っていた。
「おれは見捨てられたんだよ」あの頃、口ぐせのようにあっきーは言っていた。
朝礼が始まる直前に抜け出して、おれたちは東校舎の屋上にいた。運動場のスピーカーから、教頭の話がこだましている。整然と並ぶ生徒の黒い頭がアイスキャンディーに群がる蟻のようだ。ここから見える校庭の西側には、はしご段と登り棒が見える。朝の屋上のコンクリートは冷たく乾いて気持ちがよかった。二人でそこに寝転んでいた。高い空にすうっと混じりあうようなヒコーキ雲が流れていた。
「カズくん今日の学食の日替わりなんだっけ?」
「ショウガ焼きの定食じゃない? あれ? それは昨日だっけ」
「うそー、ミートボールじゃないのかよ。おれショウガ焼き嫌いなんだよ」
弁当を作ってもらえばいいじゃん、と言いかけて口をつぐんだ。あっきーの家では母親が最近入院したという話を人づてに聞いていたのだ。
静かな博多湾に波が煌めく。朝から気の早いサーファーが鮮やかなボードを担いで運ぶ姿が霞んで見える。
ここを触ってみろよ。あっきーは自分の頭の左側頭部を指さした。痩せて白っぽく退色した銀の髪の毛を掻き分けると、黒々とした根元に触れる。しばらく風呂に入っていないのか脂ぎって、生ゴミのようなにおいがする。「凹んでるだろ?」。なにこれ、どうしたのと聞くと小さい頃、母親に筆箱を投げられたのだと言った。おれの母ちゃんさ、飲んだらなんでも投げるんだよ、と口元にうっすら笑いを浮かべながらあっきーは言った。アル中なんだ。キッチンドランカーっていうの、あっ、親父によく殴られているからパンチドランカーでもあるわけだけれども、キッチン&パンチドランカー? ベルトを2つ持っているんだ。
おれは、笑っていいのかどうか分からなかった。
笑えよ、と促されてようやく唇の端を歪めるのがやっとだった。
ほかに、どういうものを投げたか知りたい? と聞かれておれは知りたくないと言ったが、あっきーはかまわずに続けた。石鹸だろ、ボディ・ソープ、マジックリン。「泡の出るもんばっかりだね」ああ、それは、親父に殴られるといつも風呂場に避難していたからさ。おれが泣きながら母ちゃんを救い出そうとバスルームの扉を開けたら半狂乱になっていろいろ飛んできたってわけよ。風呂桶が目に直撃したこともある。
ザ・フーってバンドお前知っているか。「名前だけは聞いたことある」。イギリスのロックバンドさ。そのバンドのメンバーがクレイジーでさ、ホテルの窓からテレビを投げ飛ばしたんだ。伝説なんだけどね、ロックンローラーだから、まあそんなこともするんだろうけど、投げ飛ばしたつってもせいぜい14型か19型だと思うのね。おれの母ちゃんはさ、32型を投げ飛ばしたんだ。
あっきーさあ、ごめん、その話おれ笑っていいのかどうか、分からないよ。
おれは声を震わせながら訴えた。
にっ、と破顔したあっきーの欠けた歯と歯並びの悪い部分にチーズのように厚い歯垢が堆積しているのが見えた。彼は大げさに手を胸の前で合わせ、頼むから笑ってくれ、と言った。
フェンスの向こうを指さして、ここから飛んだらいたいかな。血が出るとしたら、どのぐらい出るんだろうな。だけどそのときはいたさにのたうちながらやっぱり生きていたんだって気がつくんだろうな。おれたちってなんだか紙切れのようじゃないか? とあっきーは言った。干からびた苔が風に吹かれて転がっていた。おれはそれをちぎって空へ投げた。砂埃が落ちてきて制服の肩を汚した。ここからさ、校長のあの禿げ頭にさ、めんたいこが乗っかるかどうか、試してみない? 御守りとして首から下げている紫色の布袋から、めんたいこをするりと抜き取ると、あっきーは悪戯っぽく笑った。やめとこうよ、意味わかんないとおれは言ったのだけれど、この顔をしているときのあっきーに何を言っても無駄だった。
低空を旋回するヘリコプターのジェット音が響く。狼のように毛をなびかせ、屋上の天窓をピッチャーマウンドに見立てて、村田兆治のマサカリ投法よろしく足を大きく上げめんたいこを振りかぶる。鋭く腕を振り降ろすと同時に、行けぇええ~! と叫ぶ彼に慌ててしっと指を唇にあてて促す。ここに居ることが、ばれるだろうが。
風が強く吹きつける。落下するめんたいこは意外と風の影響を受ける。おれもびっくりしたし、それはめんたいこの親であるスケトウダラとて思ってもみなかった事実だろう。いえ、まさか、食物連鎖の法則によって食べられることは知っていても、爽やかな青空を切り裂いて、校舎の屋上から放り投げられるとは知りえなかっただろう。おどろきの新体験である。この先、これを回避するには、どのような進化を遂げればいいというのだろう。種の未来を担うDNAにとって新たに高いレベルの試練が与えられることになった。
風に乱れて落下していくめんたいこを、フェンス越しに眺めていた。高く盛り上がる雲が夏の終わりを告げていた。着地までの刹那、おれたちはこう言いあって笑った。「もしも、あのめんたいこが校長の頭に見事オンしたら、何定食になるんだろう」。
めんたいこは木工室の前の茂みに消えた。
信号が変わると、おれは運転席の窓から大きく手を振った。あっきーがウインカーを一瞬だけ光らせて応える。勇壮な武者をかたどった山笠の色とりどりの装飾が鮮やかに目に飛び込んでくる。──また、夏祭りがやってくる。そういえば、おれ、あいつが何で警官になったか聞いてなかったな。別れ際にふざけて敬礼する彼の薬指には、小さな青いサファイアが埋め込まれた銀色の指輪が鈍く光っていた。腕時計の下に未だ残る、白く皮膚が盛り上がった何条もの傷痕を見た。笑うと少し欠けた歯が覗く、あいつの笑顔はあの日と何も変わっていなかった。
めんたいこ、風に乱れて


