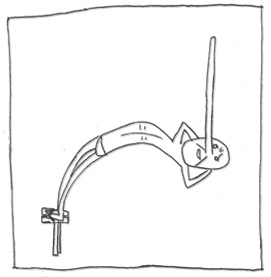
大家 -Taika-
長すぎるリムジンが渋谷Aスタジオの前に止まった。
白い手袋をした運転手が、鋼鉄のウナギのようなその車の後部ドアを開けると、先ずスーツを着た白人のSPが降り、そのあと口髭を生やした黒人の━━恰幅のよい━━おなじくサングラスをかけたSPが降りて共にドアの左右に立つ。車内から細長い紫檀の杖が見え、しばらくそのままで、やがて小刻み杖先を震わせたあと力強くアスファルトに打ち付けると皓髪の老人が緩々とした所作で降りてくる。嬌声を上げ、花束を抱えた十代の少女が熱狂した様子で老人に近づこうとしたが、スーツの上からでもその盛り上がった三角筋がはっきりと分かる黒人のSPに横面を激しく殴打されて路上に倒れ込んだ。どこかで小さな悲鳴が上がったが、老人は咳払いをひとつしただけで造作もなく車から降り、桐下駄を鳴らしながら緩やかな足取りでSPが観音開きに開けたガラスのドアからスタジオに入っていく。そのあともう一人、車から若いマネージャーらしき男が大きな風呂敷包みを抱えて後を追った。
「おはようございます!」
照明が煌めくスタジオのロビーには深紅の絨毯が敷かれ、その左右にパレードのように整列した面々が立ち並ぶ。スタジオのスタッフのみならず、楽屋から彼が来ると聞いて飛び出してきたイギリスの有名作家によるスパイ小説を原作とする洋画シリーズの吹き替えで知られる俳優酒井━━彼独特の低音の美声は、それを聞くだけで女性の生理が三日早まったという━━や、かのアカデミー賞を獲得した五十年代名作ロマンティックコメディ映画におけるヒロイン役の吹き替えを担当したこともあるベテラン声優滝本梓、その他スタジオにいたタレントやエンジニア、音響監督、スタッフ、清掃係にいたるまで深々と頭を垂れながら両端を固める花道を、老人は漫然と歩を進める。
「先生!」と、一人の若い男が手を差し出した。口を大きく一文字に結んだまま、老人が足を止めて男の顔を一瞥する。「何度か、ご自宅のほうにも伺ったのですが、お留守で……」
「西本さん、声優アワード男優賞おめでとうございます!」
老人の後ろからボストンバッグを抱えた小太りのマネージャーが、弾けたように若い男に声をかける。
「ありがとうございます! 本当に先生の指導があったおかげで、ここまでこれました。ありがとうございます、ありがとうございます」と何度もぺこぺこと頭を下げ、老人の手を抱えるように握ってさすり、やがて感極まったのか啜り上げながら雑踏の中に引き下がった。ざわめきが収まる頃すでに老人はロビーの奧へ消えていた。
佐々木義之助は地下一階の演技ブースで、いつ現れるともしれない待ち人を待ちながら、洗いざらしのマドラスチェックのシャツをジーンズの中にたくし込み、梅ドリンクをぐいっと飲み干した。
「あら、ヨッシーいいの、そんなの飲んで?」
これ失敗したわ、ちょっと音が出るのよね、と蝶を象った銀細工のイヤリングを外し杉田繁子は尋ねる。
「今なんか、『そんなの飲んで』の『飲んで』のへんが、往年のアカネちゃんみたいな声だった」
甲高い声で笑いながら杉田は「あの役のオーディションのときね、アタシ熱出して声でなかったのよ。高音が擦れちゃっててさ。それが変にさ、つくってないように聞こえたのね演出家に。もう三〇年も前の話よ——」
ねちゃついた音を立て佐々木は小刻みに唇を開閉させ、丸めた台本で肩を叩きつつ「今日は四言しか台詞がないんだよ。さっきテスト読みの時に確認したら『ま行』がないから、リップノイズの心配もない。それに西園寺さん、いつ来るかわかんないでしょ。いちおうお茶もそっちに用意してもらってるけどさ」佐々木は、アンプやレコーダーやビデオディスプレイといった機材が積まれた潜水艇のようなブースの奧のクーラーボックスへ目を向けた。
「そうそう、アタシねまたストレッチやるようになったのよ。ボイストレーニングやる前に。これで結構違うのね」と、杉田が首を左右に回し筋肉を摘むように揉みほぐしているとスタジオの分厚い二重扉が開き、ベースボールキャップを逆さに被った若い男が顔を出した。
「西園寺さん、まだですか?」
「あら石塚君」
「おはようございます」
無精髭——抜かりなくデザインされた——を軽くさすり、ライトノベルが原作の探偵シリーズでクールな怪盗役を演じ人気を確立した若手俳優、石塚浩平はひょこりと頭を下げる。
「CDありがとうね。娘に言ったらサインもせがまれちゃってさあ」
「いえ、こちらこそありがとうございます。杉田さんにはライブにも来ていただいて——」
「もう、若い人が多くてびっくりよ。年寄りが行くもんじゃないわ、ああいうとこ。それにしても、アタシたちの時代じゃ考えられない。この仕事は顔を見せずに裏方に徹するもんだと思ってたからさ」
「顔を見せないんじゃなくて、見せられないんでしょう」
「ヨッシーあんた人のこと言えた顔なの?」
佐々木義之助は手を叩いて哄笑し「あ、石塚君。西園寺さんは楽屋だよ。まだかかるよ、あの人のことだから」
「自分、いつぐらいからスタジオに入ればいいのかと思いまして━━」
「ああ、まだ大丈夫。ほかのみんなもロビーにいるでしょう?」
「ええ。なにされてるんですかね?」
「マッサージじゃない? ほら、あのいつも後ろをくっついてくる太った人がいるでしょう、お付きの。あの人が咽頭マッサージしてるのよ。声帯保湿器とかも使ってるみたいよ」
「どなたかが呼びに行かれます?」
「だめよ、特に本番前のコンディションに関しては神経質だから、本人が納得いくまでそっとしておいて。それよりさ、挨拶したの木元さんには」
「ええ。それがですね、ひどくご立腹されてて。『新しい陽平を演じる石塚です』って電話をかけたんですけど、『誰だお前は』ってけんもほろろに切られちゃいまして」
「まあねえ。日の出スーパーの陽平さんといえば、木元さんってイメージあるからねえ。だって四〇年かけて積み上げてきたものよ?」
「正直まだ違和感があるんです。いや、自分で言うのもいうのもおかしな話ですが、僕が子どもの頃みてた『ホウライさん』の陽平さんは、木元さんのあの独特の低音のしゃがれた声のイメージだし——実は実家の近くのスーパーにもよく似た声を出す八百屋のおっさんがいるんですよ——それがある日を境に自分の声になっているわけですからね」
「あたしだって、宝来和子役もうそれこそ四〇年━━四十一年か。やってるけど、それだけやってりゃあね、原作読んでても、喋っているのはいつの間にか私の声になるからね。ふしぎなもので」
佐々木義之助は丸めた台本で腰の辺りを叩きながら「しょうがないよね。キーさんは病気したんだから。石塚くんの陽平さんね、僕、悪くないと思うよ。変に、物まねをしなかったのが功を奏したんじゃないかな」
「迷ったんです。最初は、視聴者に違和感を与えちゃいけないと思って、木元さんの演技をipodに録音して毎日聞き込みました。学校に行くときとか━━寝る前にも。そうすると、ふしぎと何か憑依してくるものがあるんですよ。だけどそれは声質を模倣するということじゃなくて、下町育ちの陽平さんの人格というか、その核となる資質ようなものがだんだんと見えてきて━━役をなぞるというより引き寄せる感じっていうか」
「後は時間だね。十年も続けりゃあ、役と一心同体だよ。誰もその前の声優のことなんて思い出さない。まあ、それまでこのアニメが続いてれば、だけどね。その頃になれば、我々も後進に席を譲ることになるだろうけど━━」
「西園寺さんもですか?」
「いや、あの方は━━死んでも現役だよ」
佐々木と杉田は顔を見合わせて吹きだした。
「おいくつなんですか? 西園寺さん」
「聞いてないの?」
「いや、まだまともに挨拶もできてなくて。あの取り巻きは容易に突破できないですよ」
「三年ほど前に喜寿の御祝パーティが青山のアイビーホールであったんだよな」
「篠山さんが酔っぱらって屋上で寝ちゃったときね。変な歌うたってさあ」
「━━ということは、もう大台だよ。いや、この仕事に定年にないとは言うけど、すごいことだよ。一向に衰える気配はないからね」
「アタシたちみたいに数をこなしているわけじゃないのよ、西園寺さん。あの役一筋でここまでやってきた人だからね。そういう人いないわよ。声のバリエーションも凄くて、たとえば同じセリフでも、微妙なニュアンスを使い分けてる」
「声優は四十代になると誰しも声の衰えを感じるようになるんだ。ボイストレーニングしていても高い声が出なくなったり、ケアしていても掠れやすくなるし——声帯を振動させる筋肉が弱まるからね。だけどあの人だけは四〇年前から変わらない。何一つね」
「知ってる? 噂だけど、収録後毎回爪が二センチ伸びてるっていう━━」
分厚いガラスの前をせわしなくスタッフが行き交い、ドアが開いて「西園寺さん間もなく入ります!」と声が上がった。スタジオの隅やロビーでばらけていた演者らがぞろぞろとスタンドマイクの前に集い、ヘッドフォンを装着する。背後のドアがゆっくりと開くと、一斉に視線がそちらに集まり、おはようございます、と口々に声が上がる。深々と敬礼している演者もいる。
老人がゆっくりと歩を進め━━定位置である、等間隔に並べられたスタンドの真ん中に空いたコンデンサーマイクの前に立った。
と、老人が突如声を荒げる。慌てて傍に駆け寄った音響監督の島田が台本で頭を叩かれた。剣幕は収まらず、大きな身振りで何かを説明する西園寺に、繰り返し頭を下げる島田。十数分の悶着があった後、島田は居並ぶ声優陣に「すいません」とまた頭を下げ、腰をくの字に曲げながら足もとに伸びる無数のマルチケーブルを引っかけないようにひょこひょと後ずさった。
コントロールルームのエンジニアがカフボックスのレバーを上げ、本番を告げるキューランプが赤く灯った。
シーン17○宝来家の玄関。扉を開けようとして和子、はたと気づいて
宝来和子「あら、そうだ今日はお魚が安いんだったわ。陽平さんのお店に行かなきゃ。お母さん、ちょっとお買い物行ってきまーす」
シーン18○台所から顔を出して
宝来キヌ「はーい、いってらっしゃーい。傘持っていった方がいいんじゃない。さっき雨降るって言ってたわよ、天気予報で。あれ? もう行ってしまったわ」
シーン19○大勢の買い物客で賑わうスーパーサカエヤ。威勢のよい声が上がる店頭
陽平「らっしゃいらっしゃーい。ウニ・ホタテお買い得だよー、マグロもいいのが入ってるよー」
眼前のスクリーンに映し出される『ホウライさん』は新聞連載の四コマ漫画からスタートした故 安瀬佐知子原作の日本で四〇年以上続くアニメの先駆けである。一九五六年にラジオドラマ化されて人気に火がつき、五八年に東宝により映画化を経て六八年からアニメ化。下町を舞台としたファミリー人情活劇だ。
そのNo.5578『雨の日は早く帰って』において、佐々木義之助、杉田繁子らベテラン声優陣によるミスのないテイクを重ね、シーン20では今年から新陽平役を演じる若手俳優、石塚浩平の出番となった。
シーン20○鈴の音と共に一匹の三毛猫が現れサカエヤ店主、陽平の長靴に擦り寄る
陽平「おっ、ミーコお前も来たのか」
モニターは、尻尾をぴんとたてた三毛猫を映す。赤い首輪。丸い鈴をつけた白・茶色・黒の短いまだらの毛に覆われたしなやかな体躯を持つ動物——アニメでは手足が大きく、ふくよかにディフォルメされて描かれたが——役一筋に四十一年勤め上げてきた老声優・西園寺は突き出た喉仏をごぶりと動かして渾身の声を上げた。
シーン21○ミーコ鳴く
ミーコ 「ニャーーーーーーーー!」
シーン22○陽平、しゃがみ込んでミーコに話しかける
陽平「ごめんよ、今忙しいから後にしてくれよう」
新陽平の溌剌と伸びのある声が響く。西園寺は額に真珠粒の汗を浮かべ、モニターを睥睨(へいげい)。だらだらと垂れ流した涎が首の深い皺に流れ込む。石塚がちらりとそちらへ目を配りぎょっとしたように目を見開くもすぐに自分の台本に目を戻した。西園寺は肩で息をしながら、山猿が果物をわしづかむようにぐにゃと曲げた指を胸郭の前方に突き出して咆哮した。
シーン23○ミーコ鳴く
ミーコ「ウニャニャーーーーーーーーー!」
シーン24○ミーコの喉を撫でながら
陽平「なんでぇ、お前腹空いてるのか?」
シーン25を迎える前に、スタッフが素早く近づいて老声優の額の汗を拭う。続いてボイスケアマネージャーが、スチーム吸入器の広がった吸入口を西園寺の口元に押し当て、ノズルからスチームを噴霧。同時に白い手袋をはめた専門医が官能的な手つきで喉の甲状軟骨近辺を揉みほぐし、咽頭クリニカルマッサージを施術する。そして、精練されたF1ピットクルーチームのように捷速にピットアウト——
シーン25○ミーコ喉を鳴らす
ミーコ「ゴロゴロゴロゴロ……」
陽平「今日はさ、アラがないんだよ。また夕方ぐらいに来てくれるかい」
西園寺は頬をつり上げ目尻に皺を寄せ、その顔面は紅潮、ぽたり、ぽたり、と足元に水たまりができるほど全身から発汗していた。激しくがたがたと震えながら——歯牙を打ち鳴らさないのはさすがのプロ意識といったところか——蒼白となった腕を、首を、背中を搔き毟り、射るような眼光で、本収録において自らの最後の台詞である
シーン26○ミーコ鳴く
ミーコ「ニャオーーーーーーーーーン」
を哭するように鳴いたあと、泡を吹いて卒倒した。
クルーチームが駆け寄り、西園寺に大きな毛布を被せた。ピクピクと蠢きながら、時おり慟哭する西園寺の全身をくるみ敏速に担架に乗せて音を立てずにはける——『ホウライさん』のシーンは、引き続き(何ごともなかったように)進行していく——。
鬱蒼とした森の中の屋敷へ、ちょっと長すぎるのではないか、と思われるリムジンが滑り込んだ。
石塀が途切れ、大きな明かりが煌々と照らす黒い鉄製の門の前でSPが車から降り、蝶番に手を掛けるとレールが軋む音がして門戸がゆっくりと動いた。
車の後部ドアが開けられ、西園寺は杖先をしばらくぷるぷるさせた後降車し、石畳が敷き詰められた日本庭園——その向こうは軒の深い和風建築が墨絵のように黙座していた——へと歩を進める。門が閉まるとSPらは深々と礼をして再び車に乗り込み夜の闇へと消えた。
チリ、と鈴の音が鳴り松の根元あたりから一匹の白猫がまろび出て老人へ忍び寄る。
西園寺は歩を止め、チチチチチチと舌先を軽やかに鳴らし、指先を伸ばして猫の鼻先に向けた。一声、高く鳴いて軽やかに足もとへ寄ってきた猫を老人は躊躇なく鋼鉄の下駄で蹴り飛ばした。
蹴り用に履き替えていたのだ。
大家 -Taika-


