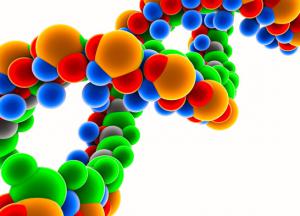ニュウトの月
私たちは遥か上空にいる。狩りを楽しむ猛禽類のフクロウのように、ナイトスコープを備えたその眼をもって、夜の横浜の上空を悠遊と飛びまわり、獲物を探る。夜の横浜をこうして見降ろしてみると、繁華街は無数のネオンでうごめいているように錯覚する。いや、実際に、その無機物の集合体は動いている。地面にへばりついて、うなるような呼吸を繰り返す巨大生物のように。人々はその体内の中で、血のように行き交い、絶えず新陳代謝を繰り返している。
ひととおりその光景を見まわしたあと、私たちはある一区角に焦点を合わせる。幹線道から一本脇に逸れた、少しうす暗い道だ。普通なら見落としてしまいそうなその道に、心細くあたりを照らす壊れかけた常夜灯がみえる。その真下で、背の高い一人の男が、わずかな明かりをたよりに、眉間にシワを寄せ、真剣な面持ちでなにかの本を読んでいる。そこへ一人、きっと待ち合わせていたのだろう。背の低い十代の女の子が迷いの無い足取りで近づいてくる。私たちはタイミングを計り、その道へ急下降する。そして彼らの動向へと溶け込んでいく。
☟
「そんなに怖い顔して何読んでるの?」
女の呼びかけに顔を上げると、男はあまり話がしたくないといったように最低限のセンテンスで応える。
「ドストエフスキーだよ」
「それってそんな顔をしなくちゃならない本なの?」
女はとても幼くみえる。髪をボブにし、ダークグリーンのパーカーの上に黒い革のジャケットを羽織り、色褪せたブルージーンズを履き、汚れた黄色いコンバースを履いている。
「うん。ドストエフスキーの本はこんな顔をして読まなくちゃならないんだ。彼が癇癪持ちだったからかな」
「ふぅん」
「それに没頭しちゃうんだ。ドストエフスキーは天才だから」
「でも他から見てあまり良い気しないわよ。その顔」
「仕方ない。好きで読んでるから」
「そう。じゃあもう言ってあげないけれど。それじゃあなたのその怖い顔は当分おあずけね。今回のはだいぶむつかしい仕事だから本を読む暇なんてきっと無いわよ」女はそう言って革ジャンのポケットから出した茶色い紙を男に渡す。
「うむ。」男は慣れた手つきで受けとった紙を栞のサイズに折りたたみ、読み途中のページにはさみ本を閉じる。
「もうすぐ雨が降るよ。早く帰ったほうがいい」男はわざとらしく空を仰いで言った。しかし雨雲は一切見当たらない。
女は顔をしかめる。「過信しすぎちゃ駄目よ。あなたは調子いいんだから」
「大丈夫。いつも通り慎重にやる」男は本をリュックサックにしまうと、炭坑夫ようにごつごつした右手で彼女の頭を撫でようと手を延ばす。女はさえぎるように口を開く。
「一つ言っていいかしら。もしかしたらあなたを不快にすることかもしれないけれど」
「ん?気にせず言ってみてくれ」そう言いつつも、彼女の身体に触れることを中断された男の右手は、着地する場所を見つけられずにいる隕石のように、空中でむなしく彷徨っている。
「仕事に支障がでても責任とらないわよ。まぁ、もしあなたが聞きたくないって言ったとしても、私の性格上いっさいがっさいしゃべってしまうんだけれどね」
「なんつー野郎だ。前置きの意味がまるで無いじゃないか」
幼い女は笑った。「でも心の準備にはなったでしょ?じゃあ言わしてもらうけれど。…あなたってさ、なんだかねじまき鳥クロニクルに出てくる男の人ってかんじがするのよね」
「驚いたな。君がそんなむつかしい本を読んでいるとも、僕のことをそんな風に思っているとも、まったく思わなかった」男の渇いた喉がゴクリとつばを鳴らした。
「ねじまき鳥クロニクルの個人的な感想を言わせてもらっていいかい?」
「どうぞ」
「世界のネジを巻く鳥のいる世界で、獰悪なセックスに取り憑かれた妻と、絶望的な暴力の古井戸に落ちる夫。そしてその解決法を示唆し、上手に邪魔するとりまき」
「包括し平たく言えばそうかもね」
「これのどこが僕みたいなんだ?」
「あなたは大事なところを読み取ってないわね。あの本には文意やメッセージが沢山ちりばめられてるというのに」女は腰に手をあて、あきれた表情だ。
「なんだか怒られてるみたいだ」
「彼はとても残念ではあるけれど、それと同時に優れた潜在能力を開花させたのよ。妻は他の男とのセックスに溺れて、もう彼の元へは戻らなかったけれど、代わりに彼は「壁抜け」の能力を得たじゃない。「壁抜け」がこの本の肝なのよ。このプロセスとそこから生まれる結果があなたに照らし合わせると似てると思わない?」
今度は男が顔をしかめた。
「歳の離れた君にこんなこと言うと大人げないかもしれないけど、君は僕の事をまるで分かっちゃいないな。彼は順風満帆と言っちゃ誇張に過ぎるかもしれないが、貯金もあるし、親戚からただ同然で譲り受けた戸建てに住んで、猫を飼って、何不自由無い夫婦生活を送っていたじゃないか。物質的には満たされていると言っていいはずだ。たしかに妻が浮気をしていたのは、そりゃあショックだったかもな。きっとセックスが下手くそだったんじゃないか?妻の性的欲求を満たせなかったんだろ。それでも彼には笠原メイって子が支えになっていたし、彼だって加納マルタとまぐわっていたじゃないか。
でも僕は彼と違って一度も女の人と寝たこともないし、浮気以前に彼女も許婚もいないんだよ。産まれてから今の今までそうゆう縁が無いんだ。
お金も持ってないし、ぼろぼろの木造アパートに住んでいる。昨日の夜中だって和室とキッチンの間仕切りを食欲旺盛なシロアリたちがむさぼる音を聞いて飛び起きたくらいだ。社会的な素養だってほとんど無いし、それに僕は「壁抜け」なんて大層なことは出来ないさ。けれども、それでも僕はあそこまで残念じゃない。」
女は今にも声を上げて笑い出してしまいそうなのを、必死にこらえているといったように震えた声で聞く。「残念じゃない?」
「仕事さ。この仕事をしている限り、僕は残念じゃないよ。それが僕を支えているからね。そういえばねじまき鳥クロニクルに出てくる彼は、仕事を辞めてからこんなことが起こり始めたんじゃなかったっけ?」
幼い女は男の目をじぃーっと見る。「確かに、或いはそうかもね。あなたってなかなか面白いわね」それから女は一歩男に近づき続ける。
「先入観で話しちゃってごめんなさい。一体あなたってどんな人なの?とても知りたいわ。だって私たち、こうして仕事のやりとりでこの紙切れを受け渡すくらいしか接点がないもの。」
幼い女は十二、三歳ぐらいだろう。言うまでもなく化粧気は無く、どんな液体も弾きそうな、実に健康的な肌をしている。もちろん、香水も、マニキュアもしていない。ただ、何故だか口紅だけは付けていた。とりわけきわだつ、目の醒めるような真っ赤で光沢のある唇。
それも含め、彼女はどことなく違和感をはらんでいた。満席でにぎわうデニーズの隅っこでひっそり目立たないようにコーヒーを飲んでいても、きっと彼女に目がいってしまうだろう。話し方や会話の内容、纏っている雰囲気、なにもかもがその姿に合っていない。それだけ彼女は他の人とは異なるオーラを放っていた。そしてそのひとつあげれば、思春期にも満たないその身体から、成熟した妖艶さのようなものが溢れ出ているのである。現に男はこの幼い女がセックスで狂うように跳ねるところを少し想像し、急いで払拭する。
女のなげかけに男が返事を返そうとしたときの出来事である。突然、なんの前触れもなく、真空の宇宙に放り込まれたような静けさがあたりを襲った。空をたゆたう雲が岩のように固まり、資源を血液のように循環させその巨大なからだを保持する街が凍った。通りを行き交う人々も催眠術をかけられたように動きを止める。
完璧な静寂。時が止まったようにかたまる世界。
少しすると、オーブのような丸い光が地面からおびただしい数湧き上がった。そしてその丸い光は、明確な目的を持つ魂のように通行人の体へとDNAの螺旋を描き出しながら乱入していく。
およそ一分間それは続いた。
☟
繁華街であるこの通りは、猥雑なネオンライトを浴びて、売春婦たちがタバコと酒でしゃがれた声を張り、のろのろとその前を酔いどれて闊歩する男達を誘惑する。一分前と同じで、何事もなかったように通りはにぎやかだ。
「そろそろ行かなきゃまずそうだな」
「そうね」
「原因はきっとインターコンチネンタルホテルの女天使じゃないか?」
「ご明察よ。勘が働くのね。」
「さっきの話だけれど、僕はつまらない人間さ。特に何も持っていない凡庸な、男らしくない男さ。それより、僕の方こそ君のことをとても知りたかったんだ。この仕事が終わったら食事に行かないかい?お互いのことをゆっくり話したいな」
女はしばらく考え込んで応える。「いいわよ。二日後にここで待ってるわ」
「食べたいものを決めといて」
「スッポン鍋がいいわ。私はいつでもスッポンは食べたいから」
「スッポンか。いいね。日吉に良い店があるんだ。昔お腹が空いてたまらなかったときに先輩の奢りで連れてってくれたんだ。そこなら蝮も熊も食べられる」男がそう言うと、幼い女は男の右手を握った。
「楽しみにしてるわ。さっきのねじまき鳥クロニクルの話だけれど、あなたはやっぱりまだ一番大事なところに気付いていないと思うの。それは今度、スッポンを一緒に食べたときに教えてあげる。気を付けて行ってらっしゃい」
☟
二十分後、男は黒い頭がひしめく駅のホームにいた。体の芯がとても温かい。きっと彼女が手を握ってくれたからだろう。そのぬくもりの質感を確かに感じることができる。電車がやってきて自動ドアが開く。似たような色のスーツを着たサラリーマンが窮屈そうに目配せをしながら出迎える。男はサラリーマンの群れをやさしく掻き分け、連結部に近い三人掛けの席の方までもぐりこんだ。三人掛けの席はレイバンをかけた老婆が独占していた。彼女の荷物はひどく多くて、足元、頭上、席すべてを埋め尽くしていた。足元の麻袋からのぞいたタッパーの中で、一匹の大きな黒い毛虫が身体をくねらせている。男は老婆と麻袋の前に立ち、リュックサックに入れた本から紙を抜きとり広げた。紙には油性ペンで大きく「女天使」と書いてある。文体が細身で、文字の最後を必ずはねるのが彼女の癖だ。
「やっぱりそうか。」と男は思った。
電車が少し揺れ、男は例のごつごつした右手で吊り革に掴まった。それから目前の窓に映る景色を見た。窓の向こうはいつもと変わらない雑多な街の夜だった。乱立する建物の手前で黒い電線が波を打って並走している。その少し上の目線にあるオフィスビルの一室に、誰も乗っていないランニングマシーンが十台くらい並んでいる。すぐに視界から消える。ランニングマシーンのあるフロアには誰一人見当たらなかった。なのに明かりは煌々と付いていた。おそらくLEDだろう。海の底のように鋭く静かな白い明かりだった。夜空では井守の腹のような色をした満月があやしく光っている。
男は車内に視線を戻した。仕事に疲れ切った様子のサラリーマンは充血したするどい視線をスマートフォンや中吊り広告に向けている。男の腹の辺りで「満月じゃて。」と黄色い歯を剥きだして老婆が笑った。男はそれを合図に心を仕事へと切り替え始めた。
☟
改札を出ると男はリュックサックからエメラルドグリーンのレインコートを引っ張りだし、レインフードを頭にすっぽりと被り、コートのボタンを首までしっかり閉め、ランドマークタワーへと力強い足どりで歩きはじめた。もちろん雨は降っていない。ただ、駅前の広場に秋の終わりを告げる冷たい風が断続的に吹き、ディナーとセックスのことで頭がいっぱいになったカップルたちが身を寄せて往来を繰り返しているだけだった。
じつに平和で寒い夜だ。
雨の降る気配の無い街で一人レインコートを着て歩くのは実に奇妙なものだった。
実際にすれ違う人の多くは男の事をいぶかしげに見て通り過ぎていった。
「近づかない方がいいわよ。」と彼氏にささやく女の声も聞こえてきた。しかしいちいちそんなことに腹を立てても仕方がない。彼らはもうすぐ途轍もない土砂降りが続くことを知らないのだから。
男はいささか長く傾斜の強いエスカレーターを強く踏み上がり、ランドマークタワーへ通ずるムービングウォークを止まることなく進んだ。左側に並ぶ黒い頭は、先ほど観た映画の批評や仕事の愚痴を言いながらほとんど自動的にタワーに吸い込まれていった。行列は老婆の持っていたタッパーに入っていた黒い毛虫を巨大化させたものを彼に思わせた。一つ一つの黒い頭は毛虫の細胞で、それが集まり共同体となっているのだ。男の頭の中ではこの巨大黒毛虫が数時間後に土砂降りにうたれ細胞分裂し、慌てふためいて駅や建物の軒下に散り散りばらばらに避難するイメージが浮かんだ。そう、それで間違ってはいない。
タワーに入ると男は「フィレンツェ」というジェラートショップに寄った。店の前のイートスペースで皆色鮮やかなジェラートをスプーンですくったり舌舐めずりしている。その人集りを縫うように丸顔の店員が奔走している。店員は全部で三人見当たった。彼女たちはショーケースに陳列された色鮮やかなジェラートを専用の大きなスプーンですくい、イートスペースのゴミ箱の袋を交換し、注文を聞きながらレジを打つのに集中していた。おそらく皆女子高校生だろう。化粧が薄く、肌の血色が良い。イタリア語でフィレンツェと刺繍された帽子に、後ろで縛った髪を折りたたんで仕舞っている。
レジに並び男の番がくると、有蹄類のような鼻筋のしっかりした子が「ご注文はいかがなさいますか?」と尋ねてきた。
男はシングルコーンでピスタチオとキウイをひとつずつ注文する。
男がジェラートを受けとると、ゴミ袋を交換していた丸顔の店員が振り返り「ありがとうございました。」と笑いかけてきた。彼女は首に三日月のチャームのついたシルバーのネックレスをしていた。
「もうすぐ土砂降りがくるかもしれない。」と男は言った。彼女は不思議そうに男の顔を見つめた。
「だからレインコートなんか着ているんですか?」
「そう。もしかすると地下鉄は駄目になるかもしれないな。」
彼女は「それは大変。私ここからだと地下鉄に乗らなくちゃ帰れないんで。」と言ってカップとスプーンが沢山入ったゴミ袋を握りしめ、なにやら土砂降りと帰り道について考えを巡らせているようだった。
「でもどうしてこれから土砂降りになるって分かるんですか?」
「雲と相談した結果そうするらしいよ。僕はやめるように説得したんだが、最近彼は強情なんだ。」
「ゲリラ豪雨ってやつですね。」といって彼女は少し微笑み、仕事へ戻っていった。
☟
男がタワーをあとにし、ホテルへ向かう途中に見た空は、まだ雨の降る様子はどこを探しても見当たらない。
ホテルまであともう少しのところで、ピエロに声をかけられた。ピエロはツツジの生垣に寄りかかって道端に座り込んでいた。そのせいで身体のあちこちに葉が付いていて、全体的に埃っぽくみえた。ひどく疲れた様子で、化粧はほとんど剥がれている。金髪のカツラは使い古したモップのようにしな垂れて、頭からずれ落ちそうだ。
「まぁ急ぐなよお兄さん。せいては事を仕損じるぜ。一つ問題を出したいんだが、付き合ってはくれねぇか?」ピエロは酔っ払っているようで息が酒臭い。
「悪いけど急いでるんだ。」
「まぁそう邪険にするなよ。昔俺もお兄さんみたいに若いときにあるみずほらしい人を邪険にしたことがあったんだが、実はその人はうちの会社を贔屓にしてくれてた企業のお偉いさんで、わざとそういった汚ならしい格好で人間観察をするのが趣味だったんだな。お陰で身元を徹底的に調べ上げられてその一週間後には会社をクビになり住まいも失った。たったの一度だけ人を邪険にしただけで俺は人生を滅茶苦茶にされたのさ。なぁ、人間っていうのは心底恐ろしいものだと思った。俺は滅多に人が通らない古井戸に突き落とされた気分だったよ。ゆっくり死がやって来る、絶対的な孤独死が近づいてる感覚。お兄さん、なぁ、人は見た目と臭いじゃ分からないもんだろ?そう思うだろ?」
ニュウトの月