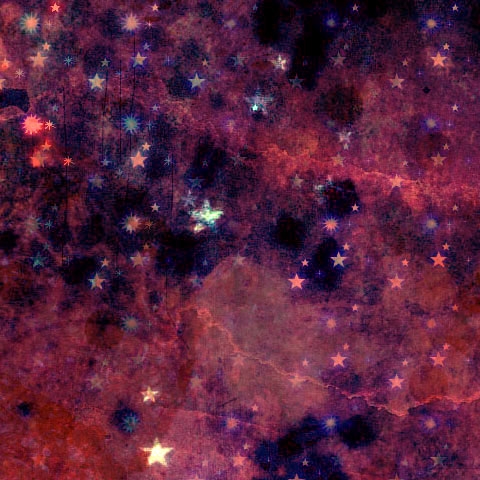
Dye red
騒がしい夜の街並み。
とある工事中の高層ビル前は、毎日日付が変わるまで人の気配が絶えない。
仕事帰りのサラリーマン、OL、大学生、高校生etc.…交通量が多いこの表通りは本当に多種多様な人々が通る。ただ眺めているだけでもしばらくの間飽きることはないだろう。
通行人は様々な表情をして歩いていく。
複数人で歩いている人は笑っていたり怒っていたり表情があるが、一人で歩いている人は大抵が無表情。つまらなさそうな顔をしている場合が多い。かくいう自分も街を歩いているときはその中の一人なのだろうが。
この仕事をはじめて半年。自分の勤務時間内によく通る人の顔と、習慣はもう覚えてしまった。
たとえば、平日同じ時間帯に通るサラリーマンの集団とか、この人はいつもコンビニのビニール袋を持っているとか、新聞を持っているとか、この人はいつもヘッドフォンで音楽を聴いているとか。
名前も知らない他人の小さな習慣はその人が確かにそこに生きて生活しているということが分かって、なんとなく生でドラマを見ているような気分になる。
ドラマといえばこの間、腕を組んで歩いていた男女の女の方が、次の日には違う男と腕を組んで歩いていたのを目撃した。他人のそういう場面を見るのは初めてだった。ひどい女だ、と思うより、男が可哀想だなあと思ったのを覚えている。
しかしそのような出来事があっても、仕事が終わってからも頭から離れない、気になるといった通行人はいない。
否、正確にはこの間まで、いなかった。
その人は荻野の勤務時間の午後10時頃から午前1時頃までの間に週6、もしくは週7で必ず通る。
いつも通るな、と気が付いたのは仕事をはじめてから比較的早い段階だったように思う。
年は自分と同じ20代前半から中ごろあたり。今時珍しい綺麗な黒髪とすらっとした体躯が印象的で、浮かび上がるような存在感があった。
整った顔立ちでおそらく美形と呼ばれる部類なのだろうが、どこか人間味に欠けている感じがした。
職業はわからない。ただ、服装がいつもばらばらで毎日違うことから大学生か大学院生、または制服がある職業なのだろうと思う。
通るときはいつも一人で無表情。
なんとなく冷たい雰囲気を纏っていて、笑っているところが想像できない感じだった。が、いつからか簡単なあいさつを交わすようになってから荻野のそのイメージは一変した。
その人は荻野と話すとき、笑みを絶やさない。だがそれは作り物じみた笑顔で本当の笑顔ではないように見えた。けれど表面上はとても愛想が良く気さくだった。
あいさつをお互い交わすようになっていつしか、荻野の休憩時間が重なれば立ち話もするようになった。
ぎりぎり顔見知り程度の関係から、知り合いと呼べる程度の関係になったのはつい最近のこと。
けれども、話せば話すほどわからなくなっていった。
自分でもなぜその人のことが気になるのか分からない。
ただどうしても、その人のことが脳裏に焼き付いて離れなかった。
* * * * *
夜の帳もすっかり落ちて、病棟が静かになってくる午後10時。
唯一人の気配がある受付やナースステーションは勤務交代の時間を迎え、職員の出入りが激しくなってきていた。
(やばい、引継ぎに間に合わない)
吉原は入れ替り立ち替り行き来する、上司とも部下ともわからない人々を背にカルテを書いていた。集中、集中、と心の中で唱えながら周りの音に気を取られないようにひたすら手を動かす。
時間がない。いつもならばもっと余裕があるのだが、今日その余裕は先刻のとある厄介事によって消し飛んでしまった。
(ああもう、あの勘違い野郎)
キーボードを打つ手は休めず、吉原は心の中で小さく悪態をついた。
***
20分後。なんとか滞りなく業務引継ぎを終え、吉原は狭いロッカールームで白衣から私服へと着替えていた。
看護師になって一年、ようやく日々の仕事が板につき、ほとんどの患者に対して臨機応変に対応できるようになった。だから大抵のことでは動じない。感情的ではなく、冷静な判断ができる、そう自負していたのだが。
今日ばかりはさすがに、冷静な判断ができたのか自分でもわからない。
吉原は普段の愛想の良さから、例外を除いて老若男女、ほぼ全ての患者からの好感度が高い。それは職員も周知のことで何か患者とのトラブルがあれば吉原が呼ばれ、ことが丸く収まるということがこれまでに数回あった。
今回もそうだった。否、そうだと思った。
吉原が患者の就寝前回診を終え、カルテを書こうとしていたとき、先輩看護師に呼び出された。自分が診た患者に何かトラブルでもあったのかと行ってみると、そこは自分が担当している病室ではなかった。その時点で吉原は『ああまたか』と察し、吐き出したくなったため息を飲み込んだ。
「今回はどんな患者さんなんですか?」
「それがねえ…」
そう言って先輩は気まずそうに視線を泳がせた。
「…そんなに厄介な患者なんですか」
面倒臭い、という気持ちが表情に出ないように努めて吉原は尋ねた。
「いえ、患者じゃないのよ」
患者ではないとすれば見舞いに来ている患者の家族・友人とトラブルがあったのか。しかしそう尋ねても先輩は首を横に振る。
「ではいったい何が問題なんです?」
「……言いにくいことなんだけどね」
「はい」
「吉原君に会いに来たっていう退院した患者が来ているのよ」
「?別に普通のことじゃないですか」
先輩の言葉に肩透かしを食らい、幾分気が楽になった。しかし今度は逆に、先輩が先ほどまで口を重くしていた理由が分からない。
「その元患者に何か問題でもあるんですか?」
「うーん、問題って言うかなんて言うか…。とにかく、会ってみれば分かると思うわ」
「その患者さんはどこに?」
「そこの病室の中」
先輩が指した病室のドアの横のネームプレートにはよく見ると名前が入っておらず、空き部屋のようだった。
それにしてもなぜそんなまどろっこしいことをするのだろうか。直接会いに来ればいいのに。
そう思いながらドアを開けようとしたとき、先輩に肩を掴まれた。疑問に思いつつ振り返ると硬い表情の先輩がこちらをじっと見ている。
そして一言、「がんばって」と。それだけ言うと先輩は足早に廊下を歩いて行った。
それからのことは回想するのも億劫だ。
結局その元患者に15分ほどつかまり、カルテを書く時間がなくなるわ、気分悪いわで本当に今日は心身ともに疲れた。
(勘違いもあそこまでいくと妄想だ。気持ちが悪い)
病室に入った後、何があったかを簡潔に一言で済ませるとするならば、吉原は告白された。それが女性だったらまだよかったのかもしれない。しかし現実は男性だった。
その男は入院中に吉原が『業務として』世話をしたことや、優しい言葉を掛けたことを自分のことが好きなのだと勝手に勘違いし、挙句両思いだと思い込んでいたらしい。
自分の都合がいいように事実を屈折して解釈し、しまいには実際にはなかったことまで言い出したりして大変だった。
しかしもう退院しているとはいえ患者だった男を蔑ろにはできない。怒鳴りたい気持ちを抑えに抑えて、曖昧に話を濁して逃げるようにして病室を去った。でも今になって思うと、あのとききっぱり断っておけばよかったのかもしれない。
それにしても自分に非はないはずなのになんとも後味が悪い。
(俺は業務を全うしただけ。一人で勘違いして盛り上がる向こうが悪い)
とりあえずそう自分の中で完結させて、吉原はロッカールームを出た。
***
「お疲れ様でしたー」
職員とすれ違うたびに何度も同じ言葉を繰り返しながら、吉原は薬の匂いのする職場を後にした。
仕事中はずっとマナーモードにしていたスマホの通知を確認しようとしたとき、ちょうど電話がかってきた。
眩しく光るディスプレイを確認すると、今はなるべく話したくない相手だった。電話に出ないという手もあったが、あとで何度もかけてこられても面倒なので、吉原はしぶしぶ通話ボタンを押した。
「…もしもし」
『あ、もしもし?仕事終わった?』
電話相手の男の声は予想通りというか、いつも通りというか、軽いノリで今の吉原の神経を逆撫でさせた。それにしても気持ち悪いくらい仕事終わりとのタイミングがいい。
「今終わったとこ。なに?」
病院での愛想はどこに行ったんだというくらいの嫌そうな表情と低い声のトーンで吉原は言う。
『えー、なになに機嫌悪ぃの?』
「べつに」
『うわー、相当悪ぃじゃん。タイミングまずかった?』
(タイミングとかの問題じゃないし)
「べつに悪くないって言ってるだろ。用件は」
『あ、そうそう、帰り俺の家寄れる?ちょっと晩飯買ってきて欲しいんだけど』
「は?やだよめんどくさい。そのくらい自分で行け」
『そう言わずにさー。コンビニ弁当でいいから、な?』
電話の向こうで男が、へらへらしながら眉を下げている姿が容易に想像できた。
「はあ……しょうがないな、わかったよ。一応確認しておくけど、恋人は来てないよね?」
『恋人って…あー、葵のこと?今日は来てねぇけど。なんで?』
「なんでって…人が気を使ってやってるのに。俺とお前の恋人が鉢合わせして、困るのはお前だからな?」
『…あっ、そうか』
「馬鹿」
『忍が頭いいんだよ』
「はいはい、お世辞はいいから。じゃあ20分以内には着くと思うから」
『りょうかーい。あ、今日はしていく?』
「…してもいいけど。でも俺今日あんま気乗りしないからマグロだと思うよ。それでもいいなら―」
『いいよ、しよ』
「即決かよ。恋人にばれたらどうすんの?」
『ばれねえって、大丈夫』
「…竹田ってほんとクズだよね。尊敬する」
『え、まじで?』
「うれしそうにすんな、嫌味だから。…俺が言うのもなんなんだけどさ、せっかくできた恋人大切にしなよ。馬鹿なお前でもさすがに分かっていると思うけど、セフレ優先なんてありえないから」
『あれ、珍しい。忍らしくない殊勝な発言』
「うるさい、別れるよ」
『ごめんごめん』
本当に軽い男だ。今更ながらなんでこの男とこういう関係になったのだろうと、今でも時折不思議に思う。
『でもさ』
一呼吸置いてから、男・竹田はいつもの調子で口を開いた。
『俺、忍と葵のことは同じくらいの気持ちで思ってるから、どっちが優先とか考えたことないんだよね。時と場合によるっていうか』
「それがダメだって言ってんの」
『なんで?』
「お前の恋人がかわいそうだから」
『ふーん…そんなもん?』
電話の向こうで竹田は本当に不思議そうな顔をしているのだろう。もしかしたらこの男は根本的に他人と恋人関係になることができない思考回路をしているのかもしれない。
「――ごめん、電車だから切るよ」
『はーい、弁当よろしくー』
電話しながら歩いていたら、いつの間にか駅に着いていた。吉原は通話終了ボタンを素早く押して電車に滑り込んだ。
竹田とはいわゆるセフレと呼ばれる関係だった。
お互いが都合のいいときに連絡を取り合って、どちらかの家に行く。吉原は友達でも恋人でもない緩いこの関係が気に入っていた。
ところが最近、竹田に恋人ができたらしい。
吉原は面倒くさいことになる前に彼にはっきりと『別れよう』と言ったのだが、『いや、まだ本当に付き合っているわけじゃないし』となんだかよくわからない曖昧なことを言われて、二人の関係はずるずると今日まで続いていた。今はまだ何のトラブルも起きていないが、どうせそのうち厄介なことが起きるのではないと思って別れたいのだが、彼・竹田が別れさせてくれない。そういうところが竹田の感覚がずれているところであり、また長年恋人ができなかった原因の一つだろう。だが逆に考えてみると、そのくらい軽い男の方が、セフレの相手としてはいいのかもしれない。
とはいえさすがにこのままだらだらとこの関係を続けていくのも限界のように思えた。
(今日あたりちゃんと話すか…)
吉原はぼんやりと考えながら電車を降りた。
よく行く駅を出てすぐのところにあるコンビニに入り、適当な弁当を二つ買った。
レジで会計済ませている最中、吉原のスマホにメールが来ていた。
しかし不運なことに、メールの通知音は騒がしい店内BGMによって掻き消された。
* * * * *
「荻野ー、そろそろ休憩入れってよ」
いつもと変わらない夜の街並み。往来が多ければ多いほど時間の経過が早く感じた。
「おう、了解」
同僚の関に声を掛けられ、荻野はガードフェンスの内側に入った。
「今日飯どうする?」
ヘルメットを外しながら関が尋ねた。
「俺は今日もコンビニ。関は?」
「お前は今日もって言うより毎日だろ。俺は弁当持ってきた」
「弁当?誰に作ってもらったんだよ」
「彼女、とかだったらいいんだけどな。残念ながら今日は俺が自分で作ったやつ」
「なんだ、そうなのか」
「それに弁当といっても、昨日の作りすぎた肉じゃがをタッパーに入れてきただけなんだけどな」
「肉じゃがって…なんかすげえ家庭的だな」
「そうか?荻野も毎日買い食いじゃなくて、時間あるときは自炊しろよ。毎日コンビニ弁当は健康に悪いからな」
「それは分かってんだけどなあ…」
話しながら荻野もヘルメットを外す。
「じゃあコンビニ行ってくるわ」
「おう。あ、缶コーヒーよろしく」
つなぎのポケットに小銭が入っていることを確認してから、荻野はガードフェンスの内側から歩道に出た。
(昨日は駅側のコンビニに行ったから、今日はこっちのコンビニで買うか…)
そう思って歩き出そうとしたとき、
「あ」
背後から短い声がした。振り返るとその声の主が笑顔で立っている。
「荻野君だ。お疲れ様ー」
声の主の男・吉原は軽い足取りで荻野に近づいてきた。
「仕事中?」
「いや、休憩中」
「だと思った。ヘルメット付けてないもんね」
「分かってんだったら聞くな」
吉原はほぼ毎晩この道を通る。同じく荻野は毎日この場所で勤務しているので、気が付けばお互いに軽く挨拶を交わすようになっていた。
荻野の休憩時間が重なると二人はときどき近くの小さな公園のフェンスにもたれかかって立ち話をしていた。やがて何回か話していくうちに、お互いに性格が真逆で合わないということが分かった。なのにまるで腐れ縁のように顔を合わすたびに言葉の応酬していた。
二人は何でもないことを言い合いながら、いつものように公園のフェンスにもたれかかった。
「晩ご飯、いつもどうしてるの」
しばらく話していて、ふと会話の間に沈黙が生まれたとき、吉原が何の脈絡もなく唐突に言った。
「ほとんどそこのコンビニか、駅前のコンビニで割引の弁当買ってる」
「えー、コンビニ弁当ばっかり?自炊しないの?」
「できるけど面倒、つーか、時間がねぇから基本しねぇな」
「もったいないなぁ。健康に悪いし」
「うるせえな。さっき聞いたっつの」
「は?」
「…いや、こっちの話だ」
「荻野君、もしかして彼女いるの?」
「はあ?なんでそうなるんだよ」
「だって荻野君の健康を心配してくれるのなんて、家族か彼女くらいしかいないでしょ?」
「お前な…俺をどんな奴だと思ってんだ」
「聞きたい?言っていいの?」
「いや、やっぱいい。聞きたくねえ」
荻野にはここ数年彼女がいない。
言い訳のようになるが、夜型の生活と仕事をしているので出会いの機会もないし、職場は男ばかりだからこの仕事をしている限りまず彼女はできないだろう。もし奇跡的に彼女ができたとしても、夜型の生活に合わせられずすぐに愛想を尽かされそうだ。
対してこいつ・吉原は十中八九彼女がいそうである。掴みどころがなく飄々としているが、これまで何人もの女と付き合ってきて、女心を熟知している感じがする。
「で、いるの?」
相も変わらず人のよさそうな笑みを浮かべた吉原は、小首をかしげて荻野に尋ねた。
「なにがだよ」
「だから、彼女。いるの?」
「…なんでお前なんかにそんなこと言わなきゃなんねえんだよ」
「でも逆に隠すほどのことでもないでしょ」
「まあそうだけど…」
「いなさそう」嫌にはっきりとした声音で吉原が言った。
「…俺まだ答えてねえんだけど」
「雰囲気から童貞ではなさそうだけど、女性経験は豊富ではなさそう。あと、女の子の心が分かってなさそう。そんで空気読まないこと言って振られそう」
全部あたっていて思わず、なんで知ってんだよ!と言いそうになった。
寸でのところで口をつぐみ、それを悟られないように荻野はポケットからライターと煙草を取り出して火をつけた。
「あたり?」
「知らね」
(無駄な分析力、作り物じみた笑顔…前々から思ってたけどこいつ、詐欺師っぽいよな)
車と人の往来をぼんやりと見つめながら、深呼吸をするように煙草を吸う。吐いた白い煙が夜色の空に霧散して消えていく。
(こいつは…そう、煙みたいだ)
浮かんでは消える、決して掴むこのできない霧のような。
視線を隣りに戻すと、ブレーキランプで片側の顔が赤く染まった吉原が、楽しそうににやにやしていた。
「じゃあ荻野君は彼女いないってことで」
「勝手に決めんな」
「それじゃあ、いるの?」
「…いねえよ」
いい加減隠すのも面倒だし、意味のないことのように思えたので、荻野は投げやりに言った。
「昼夜逆転の生活だからな、ここ数年はいねえ」
「やっぱり。でもせっかくのイケメンが勿体ないね」
「イケメン?お前が言うと嫌味にしか聞こえねえよ」
「酷いなあ。本心だよ」
「お前はいそうだな、彼女」
「そう見える?」
「ああ。とっかえひっかえしてそうだ」
「まさか、そんなことしてないよ。こう見えて俺、結構誠実だから」
「へー?まあそういうことにしといてやるか」
「なんで上から目線なのさ。むかつくー」
むくれながら吉原はコートのポケットからちらっと携帯端末を出して見た。時間を確認したのだろうか。
「今何時」
「11時過ぎだけど」
「じゃあ、そろそろ晩飯買ってこねえと」
「あれ、晩ごはんまだだったの」
「ああ。お前が通りかかったとき、ちょうど買いに行くとこだったんだ」
荻野がそう言うと、吉原は持っていたコンビニの袋から弁当を一つ取り出し、荻野に差し出した。
「はいこれ。あげる」
「なんだよこれ」
「見ればわかるでしょ、弁当だよ」
「だからなんで」
「まあ話せば長くなるんだけどねー。かくかくしかじかで」
「いや全然わかんねえし」
「じゃあ端的に言うと、振られちゃったんだ、俺」
突然の告白に荻野は驚き、しばらく言葉が出なかった。
こんな非の打ちどころがなさそうな(多少性格がひねくれているが)美形でも振られることがあるのだ。世の中意外と平等にできているのだなと一人で納得した。
それにしても吉原ほどの容姿の男が好きになる女とは一体どんな人物なのだろう。やはり彼に負けず劣らずのモデル並みの容姿で仕事ができるのだろうか。また反対に家庭的で優しい保育士とかもあり得る。
…いやいや、他人のそれも男の恋人なんか想像してどうするんだ。
「荻野君?」
声を掛けられてはっと我に返った。自分でも気づかぬうちに考え込んでしまっていたようだ。どうも最近この男に会うと調子がおかしい気がする。自分のペースが乱され、いつもの自分では考えないようなことを考えてしまう。
「悪ぃ、ちょっと考え事して…っ!?」
言い終わる前に荻野はまたもや驚いて上半身を仰け反らせた。なぜならいつの間にか悪戯っぽい表情をした端正な顔が目と鼻の先にあったからだ。
「あはは、驚いてる。ずっと下向いて、ほんとどうしたのさ」
「な、なんでもねえよ」
「ふーん?」
吉原は探るような目で荻野を一瞥したが、次の瞬間には普段の柔和な顔に戻っていた。
「それじゃ、弁当食べてね。俺はそろそろ帰るよ」
「ああ…じゃあな」
フェンスから背を離し、歩いて去っていこうとする彼はいつもよりなんだか希薄に見えて何か言った方がいいと思ったが、結局次の言葉は出てこなかった。
Dye red
人物紹介
・荻野大樹(オギノ・ダイキ)…工事現場警備員。意外と優しいところもある。
・吉原忍(ヨシワラ・シノブ)…看護師。無自覚天然タラシ。竹田とは腐れ縁。
・竹田…軽い男。
・葵…竹田と恋人(かも)


