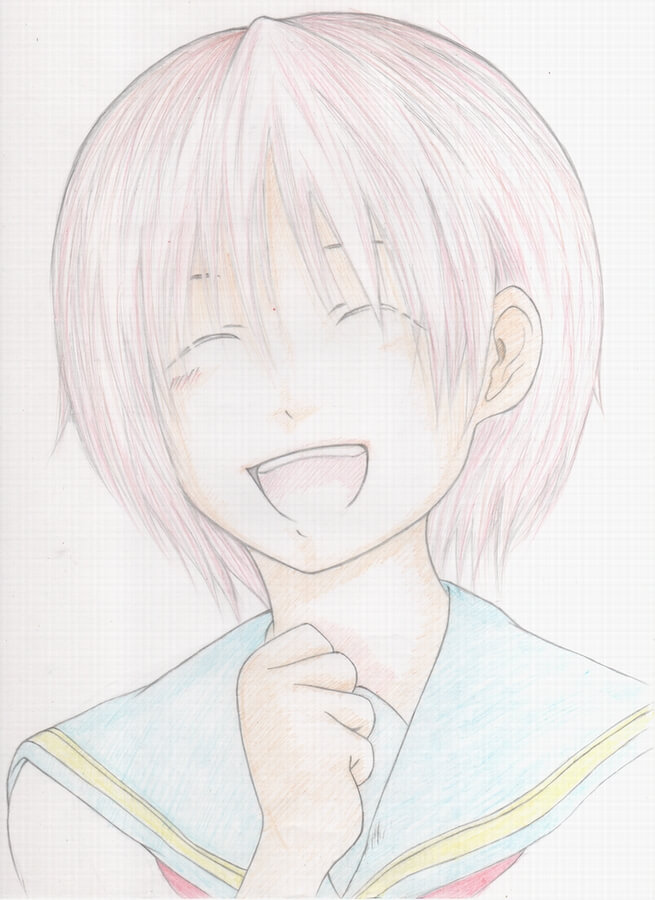
せめて、笑ってくれたなら。
著:優陽 蘭々(yuuhi lara)
もしも、家庭に不和を抱えている子と出会ったら。あなたはどうしますか?
関わらない……それが暗黙のルールであるかのように感じる、今日この頃。
それでは話が始まらないので、関わったら、あなたならどうしますか?
今回のお話は新しい試みで、3人の主人公の視点を借りて、それぞれの主人公が、
それぞれの価値観の元、シリアステーマとどう向き合っていくのか。
それを描きたいと思います。
舞台はゴールデンウィークの5日間。その短い間で、出会い、考え、選択し、行動していく物語。
この3人の中に、あなたと同じ考えを持った主人公はいるでしょうか?
彼(彼女)の選択に、あなたはどう思うでしょうか?
あなたなら、どう行動し少女を救おうとしてくれるでしょうか……。
どうか、美笑ちゃんを救ってあげて欲しい……。
それが、今回一番伝えたいこと。
Section 1 僕の場合。
「私は……もう、嫌なんです……」
少女は泣いていた。
まだ年端もいかない少女は、肩を小刻みに震わせて、両手で顔を覆いながら嗚咽を漏らしている。僕はただ、少女の肩を抱くでもなく、頭を撫でるでもなく、どうすれば少女の心を癒せるのかと、言葉を捜していた。
……見つからない。
涙を止めるだけでは駄目なのだ、少女は救われない。
涙を拭いてあげるだけでは駄目なのだ、少女は救えない。
僕は後に思う。今日この日、雨が降る学校の校庭で、少女は僕に告げたのだ。
助けて欲しい、と……。もしもそれに気づけていたなら……、と。
しかし、もう遅い。
少女はもう……消えてしまったのだから。
その日以来、少女は姿を見せなくなってしまったのだから。
あれは……そう。
5月のゴールデンウィーク。少女の心のように晴れることなく続いた、梅雨空の5日間。
せめて一度でも、笑ってくれたなら。
僕は少女を、生涯守ろうと決意出来たのかもしれない――。
「今日も降りそうだなぁ……」
僕はゴールデンウィークの休みを利用して、実家に戻ってきていた。
現在は一人暮らしだが、実のところ実家はそんなに離れていない。仕事場に近いところということで、隣町に住まいを置いている。
仕事を始めて3年目。20歳になった僕は、久々に地元の母校にでも顔を出そうと考えていた。
今年は5連休だ。大型連休ということもあって、学校にいる先生たちも少ないに違いない。でも僕は事前にアポイントをとっておいたので、当時担任をしてくれていた先生に話は通してある。きっと、門を開けて待ってくれているはずだ。
「……ん? あの子は……」
門を入り、職員室へ行こうとした時。校旗を揚げる支柱の下に、ちょこんと座っている女の子がいた。
ここの生徒だろうか。……でも、初めて見る子だった。
この学校は、中高一貫である。少女がここの生徒であったとしても不思議ではない。
見た目では、小学6年生か中学1年生あたりに見える。その表情はどこか虚ろで、焦点が遠い。考え事をしているのか、疲れているのか分からない。
僕は声を掛けようと、手を上げて……。
「こん……っ」
言葉に詰まる。少女の目から、涙が零れたのだ。
どうしたんだろう。何か、あったのだろうか。僕は人の涙を見たとき、たとえ小さい子であったとしても、楽観視出来ない性格だった。
あの年頃くらいの子なら、誰かとちょっとケンカをしてしまったとか。何かで失敗してしまったとか。そういう楽観には思えないのだ。涙には必ず理由がある。
そして人の涙には2種類ある。一つ目は、安堵。二つ目は、悲愴。
僕は少女を見て、後者だと思った。だから、言葉を掛けてあげよう。辛いことがあったなら、聞いてあげよう。優しさで人は救えると、僕は思っているから。
しかし、もう一度少女に声を掛けようとしたところで呼び止められた。
「ユウヤ君、久しぶりね。3年ぶりかな」
「あ、先生。お久しぶりです」
声を掛けてきたのは、高等部の時の担任。ゆかり先生だった。
当時は新任で初々しさがあったが、3年を経た今はそれなりに落ち着いてきたのか、表情から見て取れる。歳もそんなに離れていないから、先生というより近所のお姉さんという感じがしていた。でもそれを言うと拗ねるので、みんな口にしないという暗黙の了解があったっけ。
「なんだか、逞しくなったねぇ。社会人って感じするよ」
「はは、まだまだ新米です。……ところで先生、あの子はここの生徒ですか?」
「あの子? んー?」
先生は僕の肩越しから目をやるが、いまいち反応が分かりにくい。
僕は振り返り、そこの少女のことだと言おうとしたが……。
「……あれ?」
さっきまで支柱の下で座っていた少女は、居なくなっていた。僕がゆかり先生と挨拶を交わしている少しの間に。
もしかしたら、人が来たことに驚いて帰ってしまったのかもしれない。
ただ、少女が零した涙が頭からついて離れない。まるで、悲しい夢を見たあと寝覚めのようで……。
もちろん夢なんかではなく、目の前の出来事だった。少女の目は虚ろで、涙を零すほどのどんな理由があったのか。それが、魚の小骨のように残り、僕に思考させる。
……。
目は口ほどにモノを言う。心情を察する上で、目は重要な位置を占める。僕の短い人生の中で培われきた色々な不幸が首をもたげてきた。
目が虚ろ。虚無。虚構。虚偽。虚心……。いやあれは、虚無だった。人は物思いに耽るとき、視線が上を向いたり下を向いたりする。加えて、横の動きが重なるとその思い詰め方は倍になる。それは深く、悲しいほどに。
虚無な目で、右下を向いて俯く少女。そして零した、大きな涙。
まるでそれは――。
「何してるのー? 置いてくよー?」
「あ……今行きます!」
思案していると、ついつい周りのことを忘れてしまう。ゆかり先生は歩き出し、ついてこない僕に声を掛けてきたのだ。
慌てて先生のところまで行き、スリッパを借りて校舎の中へ入った。
校内は掲示物こそ変われど、青春時代を過ごした記憶そのままだった。
とはいえ、まだ3年しか経っていない。感慨を覚えるには少し早いだろうか。先生の横を並んで歩く廊下は、3年前の映像を投影すれば、ありありと当時の喧騒が聞こえてくるのだった。
「どう? ちょっぴり懐かしい?」
「そうですね。ゆかり先生も変わってなくて、安心しました」
「……ユウヤ君、女性に対して変わってないって言うのは二つの意味で取れるんだけど?」
「も、もちろん良い意味で、です」
「うふふ。社会人になって、お世辞も学んだってことにしておきましょう」
ゆかり先生は小悪魔の角を生やして笑う。こうして僕をおちょくるのは昔のままだ。
ということは、社会人になっても僕は子ども扱いされているというわけで……。
「さぁ、入りましょうか。あなたが最後よ」
ガラガラっと、教室のドアを開ける。
そこには、学校生活を共にしたクラスメイトがいた。特に仲の良かった男友達二人と、女の子二人。軽い同窓会のような感じだった。
みんなもう成人して、社会に出ている。僕とてそれは同じだ。3年で見違えるほど変わったという友人はおらず、良く言えば大人びた、悪く言えば変わらなかった。
おっと。女性に対しては変わらないは言わないほうがいいと学んだばかりだ。
僕は無難に、皆さんご機嫌麗しゅう、と答えた。
「あはは、優也くんだー。ご機嫌麗しゅう!」
「優也、久しぶりー。咲季(さき)、もっとお上品に、御機嫌よう、でしょ」
「なんだよそれ。普通に挨拶でいいだろー? オホン、久しいではないか、優也殿」
「どこの貴族だお前ら……。優也もご機嫌麗しゅうなんて、誰が来たかと思ったぞ」
「うふふ。あなたたちは、本当に賑やかねぇ。はい、みんな御機嫌よう! 授業始めるよ!」
「そこで乗ってくれる先生も確信犯!」
そして溢れ出す笑い声。僕らは3年ぶりの再会に喜び合うのだった。
あの頃の懐かしさと、楽しかった思い出と。梅雨空が少し残念だったが、僕たちは先生を囲んで3年ぶりの再会を楽しむのだった。
それから早いもので、夕刻。
数時間はあっという間だった。教室やら職員室、体育館など色々と場所を変えて、当時を懐かしみながら歩いた時間は、本当にあっという間に過ぎてしまった。
僕らは、みんなで夕飯を食べに行こうという話になり、校門のところで先生と別れることにした。
「ごめんねー。私も一緒したいんだけど、今日は当番の日だからもう少し居なきゃいけなくて」
「僕たちで何か手伝えるなら、やりましょうか?」
「いいのいいの。それよりみんなは、ゆっくり交友を深めて下さいな」
「縁センセー。そんなに仕事ばっかりしてると、婚期逃しますよー」
「そ、そんなことは、あなたたちに心配される必要はありません!」
「あはは、大丈夫。先生美人だもん!」
「ほらほら、囃すのはそのくらいにして。先生も良かったら仕事終わった後、来てくださいね。私たちはいつものお店にいますから」
「ありがとう。出来るだけ早く済ませて、お店に行くからね」
先生はお約束のウィンクを返して、職員室へ戻っていく。
「……よっしゃ。これで先生のオゴリだぜ!」
「こらー! 聞こえてるぞー! 割り勘だからね、割り勘!」
地獄耳……。まぁ僕たちも社会人だ。いつまでも先生に頼っていてはいけない。
僕はそんな会話を耳で聞きながら、ずっと視線はその先に向いていた。……少女が、やっぱりまた居たのだ。
しかし、数時間前見たときの物悲しさはなく、静かに目を閉じてイヤホンをしていた。
それだけのことなのに、僕は目が離せない。あれは杞憂だったのかと確かめたくて。でも僕の周りにはみんなが居て、少女の周りには誰もいなくて、それがとてつもなく遠い距離のような気がして……。
声を掛けたくても掛けられない、そんな遠い世界の光景のように思えた。
その時、ふと少女は目を開けた。そしてゆっくりと、こちらに振り返る。
「……あ」
目が合う。……光が宿らない目。
瞬き一つ、少女も同じように少し驚いたような顔をした。ちょっぴりだけ生気を取り戻し、慌てて俯く。戸惑うように視線を彷徨わせ、左手で耳を掻き揚げる。肩まで伸びた真っ直ぐな髪が、さらさらと畳まれて小さな耳が露になる。
じっと見続ける僕は、きっと少女からすれば不審者に思われたかもしれない。もう一度、ちらっと僕を見るとおずおずと会釈をした。僕もぎこちなく頭を下げる。
コミュニケーションが取れたことに安堵した僕は、それで良いと思った。コミュニケーションが取れなかったならまだしも、意思を示してくれたのだから僕の杞憂だったと思ったのだ。……そう思ってしまった。
この時すでに、少女はもう追い詰められていたなんて気づける訳もなく……。
それが僕と少女の、出会いだった。
「おーい優也ー、行くぞー」
「あ、ごめん! 今行くよ!」
後ろ髪を引かれる思いで、僕はその場を離れる。少女を残したまま……。
空はいよいよ暗く。あと30分もしないうちに、降り出すだろう。雨が降り出せば、校庭も水溜りが出来、傘が必要になるだろう。
少女は傘を持っていなかった。でも、この天気だからそろそろ少女も帰宅するに違いない。漠然とそう思った。
梅雨空のように曇天で、一抹の不安の残るそんな出会いだった。
「……気になる」
駄目だ、気になって仕方が無い。
僕たちはいつものお店へ向かっていた。その間ずっと少女のことが気になって、みんなの会話に参加出来ずにいる。
あれから15分くらい歩いたのだろうか。雨が降りだしていて、近くのコンビニでみんなしてビニール傘を買った。これが意外と高い……。
雨の音を聞いていると、あの子はまだ学校で傘も差さずに居るんじゃないだろうか……と思ってしまう。いやそんなこと、僕の気にし過ぎだと笑われてしまうだろうけど。
でも、もしも……。そう考えると気になって仕方が無い。それを考えてしまうと、僕の思考はぐるぐると回り続ける。そんなIFの袋小路を、僕は思考の迷路と呼んでいた。
そしていつも思う。出口が分かっているなら、そこへ行けばいい。動かずそこで思考を続けているのは、自ら迷路で彷徨っているのと同じだと。
僕はその出口に向かうべく、みんなに告げた。
「ごめん! ちょっと学校に忘れ物した。先に行ってて!」
「お、おう。転ぶなよー」
僕は、もと来た道を逆走していく。走らなければならない訳ではない。ただ、早く傘を届けたくて、自然と足を急がせた。
「…はぁ、はぁ」
3年というのは恐ろしい。僕の体力は何kmも走らずに息切れした。
校門に掴まって、呼吸を整える。……あの子は――。
「……いた」
僕の想像どおり……ではなく、少女はちゃんと雨がしのげる体育館の屋根の下にいた。
でも傘は持っていない。帰るに帰れないのだろう。僕はゆっくりと、驚かせないように少女に近づいていった。
「こんばんわ。雨、降り出してきたね」
「……」
少女は一度こちらを見て、こくんと頷くとまた遠くを見つめた。
「多分しばらく止みそうにないかもね。傘は持ってきてない?」
「……はい」
むむ……。やっぱりまだ警戒されているみたいだ。
当然といえば当然か。いきなり声を掛けてきたのが、知らない男の人となれば不審者だと思われても仕方が無い。
「…はい、これ。あんまり帰りが遅くなると家の人が心配するよ」
「……それは大丈夫、です……。まだ帰らなくても……いいんです」
「え? でも、いつまでもここにいると冷えるよ。この傘使っていいから」
「で、でも……お兄さんが……」
「気にしないでいいよ。もとより、そのつもりで戻ってきたんだからね」
「……」
不思議そうに、傘と僕の顔を交互に見る少女。
もう一度、使っていいよという意味で頷くと、少女もこくんと頷いてくれた。
「ありがとう、ございます……」
「どういたしまして」
そして少女は、小さく会釈をしてから背を向けた。その後姿を校門を出るまで見送る。
少女に、あまり表情の変化は無かった。歳相応の対応と、淡々とした表情だった。何かの変化を期待したわけではないが、やっぱり元気がないなと思った。
「そういえば、名前も聞いてないや」
自己紹介すらしていない。……まぁ、お見合いを始めようってわけじゃない。また会うことがあったら、その時することにしよう。
「ユウヤ君」
勤務時間が終わったのだろう、ゆかり先生が声を掛けてきた。
「ひょっとして、ユウヤ君。美笑(みえ)ちゃんと知り合いなの?」
「いえ……初めて会った子です。美笑ちゃんっていう子なんですか?」
「うん、結城美笑ちゃん。今年入学してきた子なんだけどね。あんまりクラスに馴染めてないみたいなの。担任の先生も、あんまり熱心な方じゃなくてね」
「……そうなんですか」
あの子の……美笑ちゃんの涙を思い出す。もしも担任が、ゆかり先生だったなら……と思うのはきっと都合のいい考え方だ。
もちろん、ゆかり先生は生徒受けは良かったし、親身になってくれる良い先生だ。だからきっと、自分の教え子にそういう子が居たら放っておかないだろう。でも、先生も社会に生きる人。体面上、中等部の生徒の一人を気にかけることは、はばかられるのだろう。
それに、ゆかり先生に預ければ問題解決、なんて他力本願の極みだった。だから僕はそこまで思考が至って、それを口にすることはしない。
「あの子は夕方……美笑ちゃんは、あの場所に座って泣いていたんです。それはクラスでの不和だけじゃ、ない気がしました」
「……やっぱり君は、優しいね。それでわざわざ戻ってきて、傘を貸してあげたの?」
「そうです。なんだか、放っておけなくて……」
「なるほど、ユウヤ君は年下の女の子が大好きだもんねー。大人の女である私に見向きもしなかったくらいだし」
「な、何言ってるんですか。誤解を招くようなこと言わないで下さい。僕は本当に心配で……」
「ふふ、ごめんごめん。茶化すところじゃなかったね」
先生は茶目っ気のある笑顔でそう言った。
「ユウヤ君には話してもいいかな。本来はプライバシーだからあんまり話せることではないんだけれど、今の君は、もうそういう分別は付けられるよね?」
「……はい」
「うん。実はね、美笑ちゃん……ご家庭が今大変みたいなの」
「家の事情、ですか?」
「家の、というよりはご両親の、かな。今のご両親は再婚された親御さんで、血縁関係は無いみたいなの」
「え? 無いって……」
「法律って残酷よね……。美笑ちゃんの本当のお母さんは、近くに住んでるんだけど、本当のお父さんは都会のほうにいるらしいの。最初の離婚の時は、お父さんに引き取られたみたいなんだけど、そのお父さんとの再婚相手の女性もあまり教育熱心ではなかったみたいで、しばらくして離婚。今度はその義理の母に引き取られて、今この町で再婚して生活してるみたいなんだけど……そうして、今のご両親は美笑ちゃんには無関心。美笑ちゃんの話だと、毎晩のように喧嘩してるんだって」
「……美笑ちゃん」
結婚って、何なんだろう……。幸せの結果、愛のかたち、人生の過程……。
それは理想であって、現実ではないのか……。だからといって、親が子を蔑ろにして良い道理なんて存在しないはず。最愛の我が子のはずが、まるで枷か何かのように親権の押し付け合いが始まる……。
不遇というにはあまりにも、美笑ちゃんの境遇は過酷だった。
「でもね、近くに住んでる本当のお母さんのところには時々行ってるみたいなの。そこではどうなのか分からないけれど、今の家にはあんまり居たくないって、美笑ちゃん言ってた」
「……それで、学校に来たり、お母さんのところに行ったり転々としてるってことですか?」
「うん。そういう、家庭に不和を抱えてる子って初めてだから。私も、どう接していいか分からなくて……」
「先生……」
やっぱり先生は、良い先生だ。担任を差し置いて顔を突っ込めないが、心から心配してくれている。出来ることなら、何か力になりたいと思ってくれている。
「僕は……美笑ちゃんが涙を流した時、およそ人が推し量ることの出来ない何かを抱えてるんじゃないかって思いました。それが今、確信に変わりました。話してくれてありがとうございます、先生」
「ユウヤ君……」
「美笑ちゃんが心から笑えるように、僕なりに模索してみます。話を聞くだけでもいいし、美笑ちゃんが何か望むことがあったら、それに答えてあげたいと思います。もちろん、僕に対する警戒が解けたら、ですけど。やっぱり、女の子には笑っていて欲しいですから」
「うん、ありがとうユウヤ君。君のそういう優しいところ、先生知ってるよ。でもね……」
そこで先生はちょっとだけ、寂しいような、嬉しいような、どっちとも取れる表情をした。
「優しいだけじゃ、ダメだよね……」
「それは……」
「ううん。優しいことがダメって言ってるんじゃないの。……ひょっとしたら、美笑ちゃんは、優しさを求めてるんじゃないかもしれないって、そう思って」
「優しさじゃない、何か……」
「でも、美笑ちゃんの心を開くには優しくしてあげなきゃ、美笑ちゃんも安心出来ないと思うの。女の子としては、やっぱり優しくして欲しいって思うから」
「先生、僕は……」
「大丈夫、分かってる。3年も君を見てきたんだもの。ユウヤ君のことは心配してない。私も君なら、美笑ちゃんの心を開けるんじゃないかって、思ってるよ」
「先生……はい。僕なりに頑張ってみます」
「ふふ。私もユウヤ君にばっかり頼ってちゃダメだよね。生徒とどう向き合えばいいか分からないーなんて、先生がそんなこと言ってちゃダメだよね!」
そういって先生は、両腕を力こぶしを作るように、頑張るぞっというポーズをしてくれた。
「それから、先生。僕から一つだけ、お願いがあります」
「ん? 私に出来ることなら何でも」
「多分明日も、美笑ちゃんは学校に来ると思うんです。だから、そしたら教室に入れてあげてください。外では、可愛そうですから」
「うん、分かった。ありがとう、ユウヤ君」
もう一度、満足そうに頷くと、先生は不安が吹っ切れたかのように満面の笑みを浮かべていた。
「さぁってと! みんなを待たせてるんでしょ? 早く行きましょう」
「うわぁっと! 先生! そんなにくっつくと……」
「んんー? 傘が一つしかないんだから、仕方ないでしょ? 今日は飲むぞー」
「は、はい……」
「あらあらぁ? 異性と腕を組むの初めてなのかなぁ? 初々しいね、少年」
「僕はもう成人してます。少年は勘弁してください」
「ちょっとー。年下の子だけじゃなくて、たまには大人の女にも興味持ちなさいよ。それとも、先生にはそんな魅力がないと思ってるの?」
「い、いえ。先生は、綺麗です……」
「あはは。よろしい。それじゃあ、行くよー」
そういって、僕の腕をぐいぐいと引っ張る先生。そんなに近づくと駄目ですってば先生……ひぃー。
……なんて、思いながら。
僕は先生から傘を受け取ると、少し傘を先生の方に傾けるのだった。
「……朝、か……」
昨夜は先生と友人たちと、飲み明かした。
お陰で目覚めは10時。朝と呼ぶにはいささか遅い起床だった。
ゴールデンウィーク二日目。昨日と同じく、空はどんよりと曇り空。ゴールデンウィーク中の週間予報では、連休が明けるまでこの天気は回復しないらしい。
せめて清々しいくらい快晴になってくれたら、気分も変わるだろうにと思いながら僕は家を出た。
このゴールデンウィーク中、両親は不在。休みを利用して母親の実家へ帰省している。一緒にどうかと誘われたのだが、僕はたまの休みなので辞退し、ゆっくり過ごそうと思っていた。
だから時間はたっぷりある。何に使うのも自由。でも僕には、やらなきゃいけないことが出来た。……美笑ちゃんのこと。
少なくともこのゴールデンウィーク中は、彼女の為に時間を使おうと思っていた。
「……って、こんなことを言うと、また先生にからかわれるなぁ」
僕が年下の子を気にかけるのは、決してそういう興味本位とか嗜好があるとかそういうのではないということを、重ねて追記しておく。なんというか、純粋に放っておけない。ただそれを年齢で加味すると、ある程度歳を重ねた女性は強さを学んでいる。だけれども、まだ幼い子は弱さも脆さも抱えているから、目に付きやすいということなんだ。
まぁ単純に僕は、”綺麗”よりは”可愛い”というほうが好きではあるけれど。
「うん。これなら似合いそう」
途中、商店街に立ち寄った。
雑貨から飲食店まで並ぶ、町にはよくある地域商店街だ。その中の一つのお店に寄って、あるものを買う。これを、美笑ちゃんにプレゼントするために。
名前のとおり、笑ったらきっと素敵な笑顔だろうと思って、笑顔を見せて欲しいという気持ちも込めて、ミムラスの花をかたどったヘアピンを選んだ。
いきなり初対面にも等しい相手に、プレゼントだなんてと思うが、そこは考慮してある。
ヘアピンを買ってみた。受け取ってもらえなかったらやっぱり寂しいが、食べ物とか何かよりは、当たりさわり無い無難なラインだと思うのだけど……。
ちょっぴりの不安も抱えながら、僕は学校へと足を向けた。
「……お」
門を入っての第一声だった。驚きというより、安心したと言ったほうが妥当だろう。
教室の窓を開けて、遠くを眺める女の子が居た。その表情は穏やかで、朝の気持ちよい風に身を任せているようだった。
「おはよう!」
「あ……」
美笑ちゃんは僕に気づき、小さく会釈をする。
「おはよう、ございます……」
「うん、おはよう」
小さい声だったが、僕の耳にははっきり聞こえる。そんなありきたりのコミュニケーションを取れたことに安堵して、僕は職員室に向かう。
ゆかり先生はちゃんと、約束を守ってくれたようだった。美笑ちゃんがここに来たら教室まで案内してほしいという約束を。
先生に挨拶をしてから、僕は教室に上がる。どの教室かは分かってる。僕が馴染み深い、僕らの教室だったからだ。
「おはよう、美笑ちゃん」
「…あ、ごめん、なさい……。勝手に入って……」
「あ、いや謝ることはないよ。ゆかり先生にお願いしておいたんだ。美笑ちゃんが来たら、中に入れて欲しいって」
「……わ、私の名前……」
しまった……。僕はこの子の名前を知っていても、美笑ちゃんは僕の名前を知らない。殆ど顔見知り程度の僕に、名前を知られていたなんて、僕はただの不審人物じゃないか。
これじゃあ余計、警戒されてしまう。
「あ、ごめん。ゆかり先生に聞いたんだよ。僕は優也、ユウヤでいいよ」
「優也、さん……」
美笑ちゃんはおずおずと、僕の表情を伺う。警戒を解くために、努めて笑顔で答えた。
「うん。ここの卒業生なんだ。連休を利用して戻ってきたんだよ。よろしくね、美笑ちゃん」
そういうと、美笑ちゃんはこくんこくんと2回頷くと、警戒を解くように強張った両手を下ろしてくれた。
「……あ、あの。昨日は、ありがとうございました。傘……」
「あぁ。そのまま使ってくれても良かったのに。わざわざありがとう」
「い、いえ……。借りたものはちゃんと、返さないといけないので……」
律儀にも傘を閉じて、ボタンで止めて綺麗な形で僕に返してくれた。こういうところは女の子にしか出来ないよなぁ。しみじみ。男ではこうはいかない。
「そうだ、美笑ちゃんはヘアピンとかする?」
「…ヘアピン、ですか」
「美笑ちゃんに似合うんじゃないかなって思ってね。良かったら、付けてみてね」
「あ、ありがとうございます……。でも、いいんですか?」
「もちろん。これはプレゼントだから、あとは美笑ちゃんの好きにしていいよ」
「……はい」
美笑ちゃんはこくんと頷くと、物珍しそうに眺めたあと、それをポケットにしまった。
そして再び窓辺に行き、遠くを眺める。僕もそれにならって、遠くを眺めた。
「美笑ちゃんは休みの日、よく学校に来るの?」
「……はい。空を見るのが好き、なんです」
空なら家からでも見えるが、美笑ちゃんは家にはあまり居たくないらしい。だから、そういうのは全部端折る。
「…そっか。でも残念だけど、今日は曇りがちだね」
「いいえ。雲も好きです。わた飴みたいで……」
「あはは。僕も昔そうだったなぁ。あの雲は何に似てるとか、ね」
「はい。あれは、ソフトクリーム。こっちは小さいわた飴……」
自然と頬が緩んでしまう。笑顔こそないものの、指をさしてあれは何、これは何と想像をする美笑ちゃんは、純粋に雲を見て楽しんでいるように見えた。
「…あ、ごめんなさい。私、食べ物ばっかり……」
「あはは。いいよ、なんだかお腹空いてきちゃったね」
先ほどから視界に入っては居たが、美笑ちゃんの空の話を終わらせるのは無粋だと思って黙っていた。目の届く距離に提灯が並んでいるのが見える。もちろん、祭囃しが聞こえていた。
今日はお祭りをやっているみたいだ。今からいけば、丁度お昼時。屋台で何か食べるのも悪くないと思った。
「美笑ちゃん。これから用事はある?」
「……いえ、特にはありません」
「よし、それじゃあ一緒にお祭りに行こう」
「お祭り、ですか……」
ほら、屋台が並んでるところ。と指をさすと、美笑ちゃんは遠くを眺める。
「行って、みたいです……」
「あ、ひょっとしてお祭りには行ったことがない?」
「……はい。初めてなので……。何か準備するものとかありますか?」
「ううん、何もないよ。歩いて行って、好きなものを食べたりゲームをしたりするんだ」
「そうですか……。あ、でも私……あんまりお金もってないです……」
「大丈夫。僕が出すから、お金のことは気にしないでいいよ」
「で、でも……」
謙虚で、良識のある素直な子だと思った。だから、そんな純粋さを壊さないように言葉を選ばなきゃいけない。
「それじゃあ、こうしよう。今日はお祭り体験。何か買ったら一緒に食べよう。一緒にゲームをしよう。美笑ちゃんは体験だから初回無料券!」
「初回、無料……いいんですか?」
「うん。その代わり、ちゃんと楽しむこと。これが一番大事」
「は、はい……」
美笑ちゃんは納得してくれたようで、こくんと頷いてくれた。
それから、いつも持ち歩いているのだろう。イヤフォンとウォークマンをハンドバッグに閉まって、忘れ物が無いかを確認する。
「ごめんなさい。ちょっとお手洗いに行ってきます」
「うん、分かった。校門のところで待ってるね」
そう言うと、美笑ちゃんは小さく会釈をしてからぱたぱたと廊下を駆けていった。
しばらくして、校門に美笑ちゃんがやってきた。
驚いたことに、僕があげたヘアピンをしてくれていた。
「……お、お待たせしました」
「あ、うん。……ヘアピン付けてくれたんだね」
ちょっと恥ずかしそうに、ヘアピンに手をかざしながら頷く美笑ちゃん。選んで良かった……。
「どうで、しょうか……」
「うん、似合ってるよ。買ってよかった」
そうして美笑ちゃんは、笑おうとした……んだと思う。でもそれは、どこかぎこちなくて、ちょっと心配になった。
「ご、ごめんなさい。うまく、笑えないんです……」
「……ううん、気にしないで。笑顔って自然に出てくるものだから、笑いたいと思ったときに笑ってくれればいいよ」
「はい……」
出会ったときから、少しずつ変わってきている。そんな気がした。
あの悲しそうな涙から、笑顔を引き出すのは容易ではない。でも、それでも少しずつ美笑ちゃんの心を解きほぐせているのかもしれない。
僕は努めて明るく答えると、美笑ちゃんを祭りへ促すのだった。
祭りの往来に来ると、美笑ちゃんは目新しいものを見るようにキョロキョロとしていた。
本当に、祭りには来たことがないらしい。立ち並ぶ屋台を見ては、何をやっているのか観察し満足すると隣の屋台へ……そうして、目を輝かせていた。
年頃の女の子なら嬉々として、これ食べたい! あれやりたい!と、せがむだろう。でも美笑ちゃんは遠慮がちで、興味はあるのだけど自分から何をしたいとは言わなかった。
「美笑ちゃん、何か食べたいものある?」
「……いえ」
「嫌いなものとかは、ある?」
「多分、無いと思います」
「えらいね。それじゃあ、最初にあれを食べよう。綿飴!」
「は、はい」
美笑ちゃんが食べたそうにしていたのは、ちゃんと見ていた。雲に見ていたくらいだから、ずっと食べたかったのだろう。
早速二つ買って、美笑ちゃんと食べた。そうそうこれこれ、口の中でパチパチする感じ。
懐かしいなぁ、この町のは普通の綿飴と違うんだよね。すぐ口の中で無くなっちゃうけど、このパチパチ感がたまらない。
「わ……。んん……!?」
「あはは。こういう綿飴は食べたことはない? 面白いでしょ」
「はい……うわっ」
しばらく美笑ちゃんは、このパチパチ感に目をパチクリさせながら驚いていた。
そして次は、ヨーヨー風船。スーパーボールすくい。輪投げ……。遊べるゲームは全部教えてあげた。初めてにしては美笑ちゃんは、なんでもソツなくこなしていく。色々な景品を貰えて、心なしか満足気の表情をしていた……。
気がつけば夕刻。結構長いこと、遊んでしまっていたらしい。
小腹も空いたところで、たこ焼きを買ってからちょっと小道のベンチに腰を下ろす。
「よいしょっと。あはは、久々だったけと楽しかったー」
「……はい」
「美笑ちゃんも凄かったよ。初めなのに決めまくりでさ」
「ごめん、なさい……」
「え? いやいや、謝ることじゃないよ。僕もゲームでは負けない自信があったのになぁ」
「あの……」
……ん。少し美笑ちゃんの様子がおかしい。どうしたんだろう。
「私も、楽しかったです。でも……」
「……うん」
「どうしても、笑えないんです……。笑い方を忘れて…しまったんです……」
笑い方を、忘れてしまった……。なんて、悲しい響きなのだろう。
人は笑顔によって、印象を変える。そして、笑顔で誰かに何かを与えることも出来る。……逆も然り。笑顔で救われることだってある。
それを、忘れてしまったら――。きっと本人の胸中は複雑で、もどかしいのだろう。
忘れた、ということは……もとは知っていたということ。
以前出来た事が、出来なくなるということ。喪失感……。
「パチパチするわた飴は初めてで、びっくりしました。ヨーヨー風船も初めて遊びました。輪投げも、射的も、みんなみんな……。すごく、楽しかったんです……」
「美笑ちゃん……」
「ごめんなさい……。それなのに、笑えなくて……。本当は、本当に…楽しかったんです。なのに私、約束守れなくて……」
ぽたり。ぽたり……。
美笑ちゃんが両目から、涙を零す。楽しいのに、笑えない。面白いのに笑顔で返せない。それがものすごく、歯がゆくて、もどかしくて、やるせなくて……。
ここまで思い詰めてしまった美笑ちゃん。精一杯楽しむこと、という約束はひょっとしたら枷になっていたのかもしれない。僕が校門のところで言った、笑顔は自然に出てくるから、なんて……残酷な言葉だったのかもしれない。
「そんなことは無いよ、美笑ちゃん。美笑ちゃんは、ちゃんと楽しんでくれた。そして僕も楽しかった。だから、ほら、こんなに景品があるんだよ。ちゃんと、心の中で楽しんでくれてたのは分かってたよ」
「……ごめんなさい」
悲痛な謝罪を、それ以上言葉にさせたくなくて。
僕はそっと、美笑ちゃんの頭を抱いた。
「大丈夫。きっと思い出せるよ。これからは、色々楽しいことをして遊ぶんだ。そうして、毎日を楽しいことで一杯にしていこう。そうするうちに、だんだん、少しずつでいいんだよ。自分がどういう風に笑っていたか、思い出していこう。鏡に映る自分の顔を毎晩見るんだ。今日は、どんな楽しいことがあったか思い出してニコニコしよう。まぁもちろん、毎日お祭りのように、輪投げとか射的とかは出来ないけど、今日のことを思い出したりしてくれると、僕も嬉しいよ」
「優也、さん……」
美笑ちゃんは嗚咽を漏らしながら、こくんこくんと2回頷いてくれた。
「さぁ、涙を拭いて。冷めないうちにたこ焼きを食べよう」
「……は、はい」
頭を撫でてから、美笑ちゃんの膝の上に置いてあるたこ焼きを食べるように促す。
楊枝で刺して、ぱくんと一口。
「しょっぱいです……」
「あはは。それじゃあ、特製の唐辛子粉末!」
もう一つ、口へ運ぶ美笑ちゃん。
「か、からひ……」
と、当然の反応だった。もしかして、辛いの駄目だったのかな……。
僕も1個食べてみる。これは……辛いな。辛い物好きの僕でもピリリとくる味だ。
「でも、温かいです……」
「……うん」
たこ焼きを食べ終える頃には、美笑ちゃんから涙は無くなっていた。
しばらくして、僕たちはその場を後にした。
「うーーんっと。今日は楽しかったー。帰りは気をつけてね」
とりあえず、学校の校門のところまでやってきた。
美笑ちゃんの家がどこかは聞いていないけど、分かりやすいところということで、ここまで戻ってきたのだ。陽は傾いているが沈んではいないので、まだ少しばかり明るい頃合いだった。
「優也さん……」
「ん?」
「……まだ、帰りたくないです」
僕は最初、まだ遊び足りないんだと思った。それはそれで嬉しかったし、本当の意味でお祭りを楽しんでくれたことの証だったから。それで名残惜しくて、まだ何かをして遊びたいという申し出だと思った。
……でも、違う。
美笑ちゃんには、家に帰りたくない理由がある。もしくは、帰れない理由があるのか。どちらにしても、美笑ちゃんは懇願していた。
「でも……」
「……」
服の裾をぎゅうっと握って頭を垂れる美笑ちゃん。
どうしたものだろうか。夕暮れ時だが、もう少しで辺りも暗くなってしまう。本当なら、家まで送って行きたいところだけど、家庭の事情を抱えてる子の家に行くことは逆に美笑ちゃんに迷惑になってしまうかもしれない。
だから、あえてここで別れようと思ったのだ。でも、今日一日を楽しかった日として持ち帰ってもらうには、ここで突き放すのは酷だと思った。
「…わかった。でも、ちゃんと家の人に連絡を入れること」
「……はい」
「と、言ったところで僕、携帯家に置いてきてたっけ」
ポケットを確認するが、やっぱり携帯は入っていなかった。
幸い、両親は不在だ。少し家で休ませてあげることも出来るだろう。美笑ちゃんは携帯を持っていなかったので、家に帰ってから電話してもらうことになった。
連絡ももちろんだが、年頃の女の子を家に招待するのは恋人でもなければ、あまりよろしくない。誤解を招きやすいし、何より相手のご両親に不信感を与えてしまいかねないからだ。
それも踏まえて、美笑ちゃんには一言連絡を入れてもらわなければいけなかった。
学校からは、15分くらい歩いて家に着いた。
その間、特に会話をすることもなく、静かに美笑ちゃんは僕についてきたのだった。
「電話番号は分かる?」
美笑ちゃんはこくんと頷くと、子機をダイヤルする。
しばらく耳に当ててから、ハッとして僕に子機を譲る。……僕に出て欲しいのだろうか。
突然、知らない男から電話が掛かってきて、お宅のお嬢さんを家で休ませているなんて、ちょっと言いづらかったが仕方がない。
「……もしもし? いたずら電話?」
「あ。……えっと、結城さんのお宅でしょうか?」
「はい、そうですが……」
「今、美笑さんと一緒にいまして――」
「ミエ? うちにそんな子はいませんけど」
「え――」
「掛け間違いじゃないですか? 失礼しますね」
「あ、あの……!」
聞こえる電子音。電話は一方的に切られてしまった……。
「美笑ちゃん……」
「……」
本当に掛け間違いであったかのか聞こうと思ったが、きっとそれは愚問だった。
美笑ちゃんは、力なく首を横に振った。それだけで、何が起こったのか、いや何が起こっているのかを、想像出来てしまった。
「義母の目には、私は映っていないんです。今日は朝から気が立っていましたから、あまり近くに居たくありませんでした。義父は仕事で夜までいません。だから……連絡はしなくても良かったんです……」
そういって俯いた横顔は、少しの寂しさと諦観と失望と。
電話をせずとも、家に居ようと居なかろうと、義母は美笑ちゃんのことを気にも留めていない……。これは、育児放棄とは言わないのか……?
美笑ちゃんからすれば、そうであっても、近くに居たくないのだ。人がイライラしている姿など、見ても聞いてもいたくない。いやそれだけじゃない、関心を持ってもらえないというだけで、どれだけ心の安定が崩れるというのか。
人はコミュニティに生き、コミュニケーションで疎通する。コミュニティとは、そこに居るだけじゃない。コミュニケーションとは会話だけじゃない。それを、親が教えなくてどうするというのか……。
瞬間、業火のような怒りが込み上げる。でもそれは、一瞬で消えた。ここで再度電話をして、相手に怒鳴ったところで何も解決しない。むしろ、無意味に近い。
義母は関心を示さない。美笑ちゃんは失望している。そこにどんな言葉も、届かない……。
「…お母さんは、今日は遅くなるそうなのでそちらの家にも入れないんです。だから……」
どうして……。どうしてここまで美笑ちゃんが……。
「ごめん、美笑ちゃん。色々勘違いしてた。……今日は、泊まっていくかい?」
「い、いいんですか?」
「うん。気の利いたお持て成しは出来ないけどさ。お風呂と夕飯くらいは用意するよ」
「……ありがとう、ございます」
そう言って美笑ちゃんは、深々と頭を下げた。
それから僕たちは、夕飯の買い物に出掛けた。
こう見えても、僕は普段自炊している。ある程度のものなら出来る。美笑ちゃんは、好き嫌いは無いみたいだったので、野菜たっぷりのカレーにすることにした。
経済観念も20歳になればそれなりに付く。スーパーのタイムセールを狙うのはセオリーだ。安くて安心な物を、なんていうのは世の主婦様方の常識を通り越して呼吸にも等しい。それくらいに、自然な行いであるということだ。
良い具合にお腹も空いてきた頃、帰宅して早速夕飯を作ることにした。
その間美笑ちゃんには、準備しておいたお風呂に入ってもらうことにする。着替えは、母親のものを借りることにした。
お風呂から上がって、それに着替えて出てきたときには……なんだか、時代の流れを感じるのだった。
「……わぁ。おいしい」
「ありがとう。カレーにはちょっと自信あるんだ」
「で、でもちょっとからひ……」
「あはは。これでも中辛なんだけどね。辛いのは苦手?」
「いえ……。ひりひりするのがちょっと気になるくらいで、嫌いではないです」
「そっか。僕は辛いの大好きなんだけど、美笑ちゃんが苦手だったらいけないと思って、控えめにしてたんだ」
「……ゆ、優也さんが作る辛いカレーなら、食べてみたいです」
「お、本当に? 激辛になるよ?」
「げ、激辛ですか……。だ、大丈夫です。頑張ります」
「あっはは。無理はしないでね。じゃあ今度遊びに来たときはご馳走するよ」
「……はい」
静かな静かな。だけれども、ありふれた会話というコミュニケーション。
時に人は、言葉ではなく別の方法でコミュニケーションを取る時もある。でも、会話とは人に許された疎通の手段、方法としてだけじゃなく、お互いの関係の表現も如実に表すことが出来る。
少なからずこの数日で、僕は美笑ちゃんの信頼を得られたのだと実感することが出来た。
きっかけは何であれ。美笑ちゃんの心は今、安らかであって欲しい。まず最初にすべき、信頼と心の安寧を築くことが出来たと思う。
もう少しで、笑顔を引き出せるかもしれない。……そう思った。
「優也さんは、音楽って聴きますか?」
ご飯を食べ終わり、月明かりだけの縁側に二人して座っていた。
昼間は晴れることが無かった空に雲は途切れ、綺麗に月を飾っている。
「うん。歌よりも、曲……を聞くかな。ピアノとかヴァイオリンが好きだよ」
「あ、じゃあ……」
そう言って美笑ちゃんはハンドバッグの中から、ウォークマンを取り出した。
「聴いて欲しい曲があります」
イヤフォンを片方だけ借りて聴いてみる。そこから流れてきたピアノのメロディ……。
それはまるで、澄み渡る高い空のようで。燦然と広がる水平線のようで。
爽やかで温かで、だけれども一抹の寂しさも含む……そんな音色だった。
「……素敵な曲だね」
「”beautiful smile”という曲です」
「この曲は……」
「はい……。お姉ちゃんが私のために作ってくれた曲です」
美笑ちゃんは、そのときのことを話してくれた。
お姉さんはピアノが好きで、ピアノ教室に通っていたという。発表会には美笑ちゃんも参加して、いつもお姉さんのピアノを聴いていたそうだ。
そんなある日、お姉さんは美笑ちゃんを呼んでこの曲を聞かせてくれた。美笑の曲が出来たよ、と言って。その時に一緒に録音をしていたらしく、そのデータは大切にCDに保存されていたのだ。
「この曲を聴いていると、お姉ちゃんが近くにいるように感じられて安心出来るんです」
「……美笑ちゃん」
もう片方のイヤフォンを耳に付け、両手を添えるようにして聴いている美笑ちゃんは、心なしか笑みを浮かべているようにさえ見えた。
でも、少しニュアンスが引っかかった。近くにいるように、というのは……。
しかし、思考しようとした瞬間。ドンドンと空から音が降ってきた。……花火だ。
「……わぁ」
「おお。今年もでかいなぁ……」
ちょっとした自慢だが、うちの庭は花火を見るには良い隠れスポットだった。
毎年祭りへ行って、どこか適当な場所を探すよりはうちへ帰って縁側で見たほうがよっぽど良く見える。そんな、僕たちだけの特設ステージで。しばし、空を見上げていた。
縁側の特設ステージに月明かりで照らされた二つの影は、片方ずつイヤフォンを付けながら、ピアノの音色と共に空一面の花火を瞳に映し出すのだった。
「……綺麗、です。本当に」
「綺麗だね。これだけは毎年見ても見飽きないよ」
「うん……綺麗……。綺麗……」
うわ言のように綺麗を繰り返す美笑ちゃん。ちょっと不思議に思い、目を向けると……。
空を見つめながら、大きな瞳に花火を写しながら、ぽたりぽたりと、涙を流していた。
この時、なぜ美笑ちゃんが涙を流していたのか僕には分からなかった。それは悲しみでもなく、懐かしみでもなく。花火の向こう側に、何を見ていたのだろう。
僕は掛ける言葉が見つからず、美笑ちゃんの頭を撫でる。心が見えなくても、自然とそうするべきだと思ったからだ。
そうすると美笑ちゃんは、ゆっくりと身体を傾けてこてん、と頭を僕の胸に預けてきた。顔は空を向いたまま。
僕は手を肩にまわし、同じように花火を見つめなおした。……今は、これでいい。掛ける言葉が見つからなくても、心が分からなくても、今傍に居てあげられるのは僕だということだから。
しばらくして花火は終わり、美笑ちゃんを見ると小さな寝息を立てていた。
起こさないように、そっと抱えてベッドまで移動する。布団をかけると、寝返りをうった。
僕はそれを見届けてから、居間に戻った。
「さて……」
僕は思考する。
時刻は9時過ぎ。これから電話をするのはいささか失礼ではあるが、やはり一報は入れるべきだと思った。それに、あの時は突然で言い返せなかったが、一言……いや、三コトくらい言わなければ気が済まない。
無意味なのは分かっている。頭では理解出来ても、感情を抑えられないこの矛盾。
こんなことがあってはいけないんだ。他所の家の事情とはいえ、これを見過ごすことは僕が自分を許せない。今一番悲しんでいるの誰だ? 美笑ちゃんに他ならない。例え血の繋がりがなかろうと、同じ屋根の下、生活を共にする家族を蔑ろにしていい訳が無い。離婚や再婚のことは、僕にはまだ分からない。だけど、それを理由に美笑ちゃんに不幸を強いるのは間違っている。
僕は思考をまとめ、子機を取る。……しかし。
「……履歴が、消えてる」
いや、消されている? 誰に? ……この家には今、僕と美笑ちゃんしかいない。ということは、ひょっとして美笑ちゃんに……?
僕に、再度電話を掛けさせたくなかったのだろうか……。
「……ごめん、なさい」
その時、僕の持つ子機に手が添えられた。
「ごめんなさい。私が、消したんです……」
「美笑ちゃん……」
目が覚めてしまったのだろうか。そのまま、両手で僕の腕を掴む。
「……優也さんは、優しい人です。だから今しようとしてくれていることは、正しいことなんだと思います。でも、正しいことをしても聞いてくれないこともあります。……もう、いいんです。あの人たちとは、もう優也さんには話して欲しくないんです」
「……」
美笑ちゃんの手に、少し力がこもる。それだけで、僕は大きな間違いをしていたのだと気づいた。
それが正しいことだったとして、世の中評価されるとは限らない。逆も同じで、悪いことだったとしても、制裁を受けるとは限らない。伝えるべき人がいて、それを聞く人が居て、初めて光を浴びる。
僕は正しい行いをしたと、相手を叱り付け、それで満足しようとしていた……?
結果的にそれは、美笑ちゃんの笑顔に繋がると信じて正義感という奇麗事で誤魔化そうとしていた……?
……それは、優しさでもなんでもない。人に与えるべき優しさを、自己満足にしてはいけないのだ。間接的でも、直接的でも、優しさとは受け止めてもらって初めて成立する。
「ごめん……美笑ちゃん」
僕は、優しさで人は救えると思っている。でもそれは、美笑ちゃんに受け取ってもらって初めて、笑顔に繋がるのだ。
美笑ちゃんが望まないことをしたところで、それは僕の自己満足でしかない。でも、それでも……これではあまりにも……。
優しいだけじゃ、駄目なのか……?
先生の言葉が蘇る。――優しいだけじゃ、駄目だよね――。
「……ありがとうございます、優也さん。その気持ちだけで、私はすごく嬉しいです。本当に、ありがとう……」
なんて、健気なんだろう……。こんなにも辛い境遇の中で生きて、笑顔を取り戻したいのに、僕にまで気を遣って……。
優しさというのは、人の心だ。心は、想いを映す鏡でもある。だから、僕には美笑ちゃんの優しさが分かる。だけど……美笑ちゃんの心の奥が分からない……。
美笑ちゃんが望んでいるのは、優しさじゃないのかもしれないと先生は言っていた。
それじゃあ、一体美笑ちゃんは、何を望んでいるのか――。
「私も、ここで寝ていいですか?」
「あ……うん。でもソファーだと身体が痛くなるかもしれないよ?」
「大丈夫です。……一緒が、いいですから」
美笑ちゃんはゆっくりとソファーに身体を預け、目を閉じる。
夢うつつだったのか、寝ぼけ眼だったのかもしれない。
すとん、と。静かに眠りに身を委ねていた。
僕は掛けるものを持ってきて、美笑ちゃんに掛けてあげる。そうする頃には、美笑ちゃんは小さな寝息を立てていた。
僕も反対側のソファーに横になり、天井を見上げた。
「優しいだけじゃ、駄目なのか……」
本当の優しさは、どこにあるんだ……。
僕の知る優しさでは、人を救えないのだろうか……。
言葉で示せる優しさ。態度で示せる優しさ。想いを伝える優しさ。……優しさというものが分からなくなる。
美笑ちゃんの安らかな寝顔に、答えは映らない。
横で寝息を立てる美笑ちゃんが、笑ってくれる日は来るのだろうか……。
翌朝。ゴールデンウィーク3日目。
ソファーの上に美笑ちゃんの姿は無かった。
変わりにテーブルの上に、置き手紙があった。……美笑ちゃんからだ。
”色々ありがとうございました。楽しかったです。またカレー作ってくださいね。美笑”
今日も変わらず、曇り空が朝を知らせてくれていた。
天気予報によると、午後から本降りになるという。昨日は降らずに祭りを終えることが出来たが、今日ばかりは傘を持っていかないといけないだろう。
降水確率80%。玄関を出ると、霧雨が頬を叩くのだった。
自然と足は、学校へ向いていた。
学校に行けば、美笑ちゃんに会えるかもしれないと思ったからだ。こんなにも彼女に毎日会っていると、軽く追っかけのように思われてしまうかもしれない。
初めて見たときの涙が気になって、それで始まった関わり。笑顔こそ出来なかったものの、昨日の祭りを楽しかったと言ってくれた。だから、初対面の頃の警戒心は無くなったと思いたい。
だから……門を入って、教室の窓に目を向けた時。窓から美笑ちゃんが、手を振ってくれていた……ように錯覚してしまった。
美笑ちゃんは、居なかった。
よく学校に来ているとはいえ、毎日来ているとは限らない。そんな日もある。
「…あら。ユウヤ君? 今日も来たんだ。こんにちわ」
「あ……先生。こんにちわ。先生こそ、毎日出勤なんですか?」
「ううん。ちょっと調べたいことがあってね。……ユウヤ君、少し時間ある?」
「はい。何ですか?」
ゆかり先生は、ここだとマズいからと言って校庭のフェンスのところまで行った。
二人してフェンスに寄りかかる。
「実はね、私なりに調べてみたの。ひょっとしたらと思って……」
「……美笑ちゃんのこと、ですか?」
「ううん。……あ、そうとも言えるかもしれない。美笑ちゃんには、お姉さんがいたの」
「……はい。昨日それとなく、美笑ちゃんに聞きました。……ん? 居た?」
「そう。……3年前、交通事故で亡くなってしまったの。丁度、ユウヤ君たちが3年生の時の中等部3年生で、この学校の生徒だったのよ」
「そうだったんですか……」
「うん。名字が違ったから思い出せなかったけど、美笑ちゃんの旧姓が、石川美笑ちゃん。
お姉さんは石川詩織さん。ピアノが上手で、コンクールでも賞を受賞していたそうよ」
「……はい。美笑ちゃんもお姉さんのピアノが好きだって言ってました。……そういえば、全校集会か何かでありましたね。交通事故で亡くなった生徒がいるって」
「うん。私もそれで、石川さんって聞き覚えがあってもしかしたらって調べてみたら……。そうしたら、繋がってしまったの」
「……」
確かに昨夜、美笑ちゃんの語る言葉のニュアンスに違和感を覚えた。
あの時は花火に驚いて思考は途切れてしまったけれど、今ならはっきりと分かった。今は亡きお姉さんを、美笑ちゃんは拠り所にしている。それだけ、大きな存在だったということだ。亡くなってしまった後でも、あの旋律を胸に抱いて。
「それでね、その後ご両親は離婚してしまったの」
「どうして……! 確かに不慮の事故でしたけど、それが理由で離婚なんですか!」
「……察して、ユウヤ君。ご両親も、詩織さんの無念を晴らそうと訴えた。でも、それは裁判では覆らなかった。そのうち、疲れてしまったのね……。人は誰もが、死を乗り越えられるわけじゃない。受け止められるわけじゃない。最愛の娘の為とはいえ、奮起出来る人ばかりではない」
「それでも……。残った美笑ちゃんに愛を注ぐことだって……」
「……先に心が折れてしまったのはお父さんの方だった。でもね、お母さんは専業主婦だったから、稼ぎは無くて。美笑ちゃんを養えるお父さんに引き取られたの。…その後のことは詳しく分からないけれど、前にも話したとおり、離婚と再婚を繰り返して、今は義理のご両親の所にいる」
「……」
「きっかけは、お姉さんの死だったのか……。それとも、ご両親の離婚だったのか。美笑ちゃんは、不遇な人生を歩むことになってしまったのね……」
「もしも、詩織さんが亡くならなければ、美笑ちゃんは笑顔のままでいられたんでしょうか……」
「もしも……それを考えてはダメよ。それが許されるのは、美笑ちゃんだけ……なんだから」
「……初めて美笑ちゃんを見たとき、虚ろな表情で涙を流していました。”もしも”、”どうして”、それを美笑ちゃんは何度も考えていたと思います。でも、起こってしまったことは変えられない。それが叶うなら、きっと世界中の誰もが願うはず。だから美笑ちゃんは、一人で、涙を流すしかなかった……」
悲愴という涙を、誰にも頼ることの出来ない美笑ちゃんは、自分の心に浸していく……。
「美笑ちゃんはね、あまり身体が丈夫ではないの。小学校も、時々休むくらいにね。だから、あまりクラスの子達とも馴染めなくて、友達は作れなかったみたい」
「小学校の頃が、一番残酷な年頃かもしれません。若さ故ではなく、幼さ故に」
「そんな時、頼るべきご両親も傍に居なくて……。美笑ちゃんは幼くして孤独を強いられてしまったのね……」
それは、どんなに寂しい世界なのだろう。
陽の当たる、ごく普通の家庭環境、交友関係を築いてきた僕には想像することすら、美笑ちゃんには失礼かもしれない。
いや、普通という言葉すら適当ではない。何が普通で、何が普通ではないのか。
美笑ちゃんの強いられてきた世界を、僕が想像することなど、出来はしないのだ……。
「心の安らげる場所は、どこにあるんでしょうか……」
「こころ?」
「……美笑ちゃんは、詩織さんのピアノを今も大事にしていて、それを聞きながら安心していると言っていました。それでも、涙を流すんです。寂しさを埋められなくて。それじゃあ美笑ちゃんは、美笑ちゃんの心は、どうすれば癒せるんでしょうか」
「心の在り処……。昔、ユウヤ君言ってたね」
「僕は、いえ僕たちは人コミュニティの中に生きていて、人の中に在り処を探します。そして、心の在り処も人の居る場所にあるものだと思ってきました。でも……美笑ちゃんの世界は違う……。遠いんです。遠過ぎるんです……」
僕は目頭を押さえる。いや、涙を流しているわけじゃない。
まるで自分のことのように、人の不遇を感じてしまう。分かってしまう。……いや、分かっていないのかもしれない。ずっと陽の当たる世界に居た僕に、美笑ちゃんの何が分かるというんだ……。
「……ありがとう、ユウヤ君」
「え……?」
「私からもお礼が言いたい。こんなにも身近に、美笑ちゃんのことを考えてくれる人がいたんだもの。先生もちょ~っとだけ、妬けちゃうなぁ」
「い、いや。僕は美笑ちゃんをそういう目で見てるわけじゃ……」
「ふふ。美笑ちゃんも言ってなかった? ユウヤ君に、ありがとうって」
「あ……はい」
「女の子にとって”ありがとう”って言葉はね、単純じゃないんだよ? 本当の本当に、嬉しいなーって、感謝を伝えたいなーって人にしか言わないものなんだから」
「そう、なんですか?」
「そうそう。それが分からないうちは、まだまだ人生経験が足りないぞー。いや、女性経験が足りないっていうのかな?」
「ちょっと、変な言い方しないでくださいよ……」
「私は教師です。決してみだらな意味で言ったんじゃありません。女の子とも友情を育みなさいってこと。なぁにと勘違いしてるのかなぁユウヤ君?」
「ぅ……」
小悪魔の角を生やして僕を茶化す先生。こういう所は、昔から逆らえないんだった……。
いや、それこそ、その例えのせいでサキュバスの角に見えるのは気のせいか……。
「……あ、降ってきたね」
パラパラと振り出してきた雨。傘を持ってきてはいるが、これ以上は身体も冷える。
「戻りましょうか」
色々話を聞くことが出来た。美笑ちゃんとは会えなかったけど、もう今日は頃合いだろう。家に帰って思考することにする。
職員室の前まで傘を差してあげて、先生と別れることにする。
「ユウヤ君」
先生に呼び止められる。
「笑顔笑顔!」
「あ……はは」
「そうそう、うふふ」
頷いてみせると、先生は満足したように頷き返してくれた。
もう一度、教室を見上げてから美笑ちゃんが居ないことを確認して踵を返した。
時刻は夜7時。雨はいよいよ本降りで、雨音は家の中でも聞こえていた。
美笑ちゃんに傘を貸しに戻った日も、こんな本降りだったっけ……。
「ひょっとして……」
まさかとは思う。今日もあの時と同じように、傘を忘れた美笑ちゃんが学校で雨宿りをしているのではないか。……なんて、自分がここまで心配性になってるなんて、自分でも驚きだ。
でも、そう思ってしまったら居てもたってもいられなくなってしまった。
杞憂でもいい。居なければ居ないで、夜の散歩ということにしよう。
僕は、軽く急いている気持ちを抑え夜の学校へと向かった。
「……あ」
校庭の校旗を揚げる支柱の下。人影が一つ。傘も差さずに雨に打たれていた。
今日は座っていない。空を見上げたまま、立ち尽くしていた。
「美笑……ちゃん……?」
美笑ちゃんは振り向かない。ずっと空を見つめ、あの日と同じ虚無な表情で佇んでいる。雨に濡れて、涙を流しているのかどうか判別が付かない。
まるで泣いているのは、美笑ちゃんを中心とした世界であるかのように。
僕はすぐにでも駆けつけて、傘を掛けようとする。しかし、足が動かない……。
どうして……! この世界が僕の介在を拒むかのように、僕に金縛りを与えていた。
いや、それは僕自身が躊躇っているからなのか?
この世界へは入れないと決め付けている?
違う! この世界もあの世界も無いんだ! 僕と美笑ちゃんは同じ世界に住んでいるはずなんだ。今こうして目の前にいる美笑ちゃんを、どうして放っておける?
今それを払拭しなくて、いつ美笑ちゃんを救えるというんだ!
僕は駆け出す。美笑ちゃんのもとへ。
「……優也、さん」
ゆっくりと、だけれどもしっかりと僕を捉える。そんな目を、僕は逸らさない。
「優也、さん……ゆう……ゃさん……」
美笑ちゃんは次第に、大きな目を細めて涙を零す。それは雨に打たれていても分かるくらいに大粒で。
それがもう抑えられなくて……。嗚咽を漏らしながら、両手で顔を覆う。
しきりに、僕の名前を呼んでいる。かすれて、雨音にかき消されそうなほどか細い声で。
それでも僕の耳には届く。車の騒音も、雨音も、その他の雑音も全てなくなり。美笑ちゃんの嗚咽と声だけが、僕の耳に注がれていく……。
「私は、もう……嫌なんです……。もう嫌……」
まだ年端もいかない美笑ちゃんは、肩を小刻みに震わせて、両手で顔を覆いながら嗚咽を漏らしている。僕はただ、美笑ちゃんの肩を抱くでもなく、頭を撫でるでもなく、どうすれば少女の心を癒せるのかと、言葉を捜していた。
……見つからない。
涙を止めるだけでは駄目なのだ、少女は救われない。
涙を拭いてあげるだけでは駄目なのだ、少女は救えない。
あと一歩が踏み出せない。あと1歩近づけば、傘を掛けられるというのに。あと1歩近づけば、手が届くというのに……。
僕は、何を勘違いしていたんだ……。
美笑ちゃんを会話が出来るようになって、浮かれていた。美笑ちゃんと祭りに行けて、心を軽くしてあげられた気になっていた。楽しかったといわれて、美笑ちゃんが安心してくれたと思った……。
美笑ちゃんはもう、擦り切れる寸前だったのだ……。追い詰められていたんだ……。
それをほんの少し一緒に居ただけで癒せるほど、心は軽くない。心は癒せない……。
「……でも、最後に優也さんと出会えて嬉しかったです。すごく……楽しかった……。パチパチのわた飴、美味しかったです。お祭りのゲーム、楽しかったです。優也さんのカレー美味しかったです。辛いのも、食べてみたかったなぁ……。花火、綺麗でした……。特等席はひみつの場所です。……こんな私に、優しくしてくれてありがとうございました」
最後って……え……。
「私にとって優也さんとの思い出は、2番目の宝物です」
「……美笑、ちゃん……?」
「優也さん」
「……」
美笑ちゃんはじっと僕の目をみつめる。
……見るだけなら長すぎる、何かを伝えるような目。
そして、一度目を伏して、また開かれた目は真っ直ぐに僕を見つめていた。
「本当に、ありがとう……。さようなら――」
その時、美笑ちゃんが笑ったような気がした――。
いや、錯覚かもしれない。美笑ちゃんは泣いていたのだから……。
でも僕はそれに金縛りを受け、声を出すことも、手を伸ばすことも出来なかった。
瞬間、後方から眩しいライトとクラクションが1回。
「…ん? まだ誰かいるのかね?」
「……あ、すみません。教頭先生、ですか?」
「君は……。あぁ、縁先生から聞いているよ。久しいね。ただ、こんな雨の中どうしたんだい?」
「いえ……」
「まぁいい。足はあるのかな? 家まで送るよ」
「あ、すみません。そしたらこの子も……あれ」
そこに美笑ちゃんの姿は無かった。
最後の言葉で何か胸騒ぎのようなものも感じるが、僕は美笑ちゃんの家を知らない。探そうにも美笑ちゃんの行くところは聞いていなかった。
つまり、もう探せない。
「いえ、申し訳ありません。よろしくお願いします」
僕は釈然としない気持ちのまま、学校を後にするのだった……。
突然姿を消してしまった美笑ちゃん。あれは本当に、最後の言葉のようで……。
僕は諦めて、また明日会えることを祈るしかなかった。
翌朝。ゴールデンウィーク4日目。
今日はなぜだか、寝覚めが悪い。昨晩の出来事が頭から離れないからだ。
さよならなんて、挨拶代わりにいつだって使う。でも……あんな顔をされたら、気になって仕方がない。
僕はとりあえず、先生にも話そうと思い学校へ向かうことにした。
しかし、玄関を出た瞬間だった。
「……はぁ、はぁ……ユウヤ君、良かった……」
「せ、先生……。どうしたんですか?」
「美笑ちゃんが……美笑ちゃんが……」
先生が泣き崩れるように、僕に寄りかかってくる。
「美笑ちゃんが……自殺しちゃったの……」
「え―――」
この日のことは、あまりよく憶えていない。
美笑ちゃんとの面会は出来なかった。だから現実感がなく、だけれども心ここに在らず。
気が付けば、また朝が来ていた……。
ゴールデンウィーク5日目。最終日。
昨夜、とあるビルの屋上から飛び降り自殺があった。
そのビルは近々取り壊しが決まっていたらしく、無人の建物だったらしい。
遺体は、頭蓋骨骨折、頚椎損傷で即死だったという。雨の日だったせいか、血溜まりはとこまでも長く引いていたらしい。
全てこういう言い方になるのは、実際に目にしていないからだ。聞いた話を、ただ事実のみを記している。
自殺を図ったのは、結城美笑ちゃん12歳。
美笑ちゃんの遺体への面会は叶わなかった。だから、美笑ちゃんを最後に見たのは、あの雨の中泣いていた姿になった。
”ありがとう”と”さようなら”。その二つの言葉が、頭の中で永遠にループされる。
あの時、僕がしたことは何だったのか。……何もしていない。ただ美笑ちゃんの最後の告白を聞いていただけだ。それに満足に相槌も打てず、ただ名前を呼んだだけ。
あの時美笑ちゃんは、本当は何を伝えたかったのか? 僕の目を見て、何かを訴えるように僕に懇願していた。僕はそれが何なのか、分からなかった。
ひょっとして、僕に連れ去って欲しかったのか……。この理不尽な世界から。
いやそうだったとして、僕は美笑ちゃんを養えるのか? これから中等部、高等部と進級し、大学にいくか就職するか。それまで僕が美笑ちゃんと生活していく……。その為の費用は僕の給料でまかなえるのか? 相手の親のことはどうする? そもそも自分の両親にはなんと説明する? 結局僕は、不遇の少女を、自分は白馬の王子を気取っただけで満足しようとしていたんじゃないだろうか……。
……駄目だ。人と生活をするというのは、簡単なことじゃない……。
そういう思考に至る自分が、ただただ情けなかった。
気が付けば、美笑ちゃんが泣いていた。
気が付けば、放っておけなくなっていた。
気が付けば、美笑ちゃんは消えてしまった。
学校の校旗を上げる支柱に触れる。美笑ちゃんと初めて会ったこの場所。
ここから美笑ちゃんには、どんな空が見えていたのだろう……。
「……冷たい」
僕は額を支柱に当て、泣いた。
僕は、美笑ちゃんを、救えなった……。
どうすれば、彼女を救えたのか。どうすれば、笑顔を取り戻せたのか。どうすれば……。
その答えはもう、出ない。美笑ちゃんはもう、居なくなってしまったのだから。
教室は、いつもどおりだった。
窓を開けて外気を招き入れる。ただ風は虚しく、空は重く。気分は晴れそうに無かった。
雲を眺め、形から何かを想像する。……どうしてだろう。何にも見えない。
今の僕にとって空は、今にも泣き出しそうなほど悲しく、それが僕の心のようで胸が痛んだ。もう、取り戻せない。もう、届かない。……いつだって空は、遠い。
振り返り教室を見ると、机の上にウォークマンが載っていた。
「……これは、美笑ちゃんの」
そういえば、あの時。美笑ちゃん何も持っていなかった。
いつ置かれたものなのか。……いや、今となっては関係が無い。そっと手にとって、イヤホンを耳に当てる。
流れてくる空の旋律。「beautiful smile.」
その時、ハッとする。旋律に乗せて流れてきたのは美笑ちゃんの声だった。
『……こんにちわ、優也さんですか? 美笑です……』
それは間違いなく、美笑ちゃんの声だった。
『ちゃんと、録れてるかな……。ええと、2分しかないのであんまり時間無いんですけど、えっと……ありがとうございました。優也さんと会えて嬉しかったです。本当に、笑えなくてすみません。頑張ってみたんですけど、やっぱりダメ、でした……。でも、本当に楽しかったんです。初めてのことばかりで、本当に。ありがとうございます。優也さんみたいな、お父……ううん。お兄ちゃんが居たら良かったのになって。一緒に、ご飯を食べたりお祭りに行ったり……。もっとしたかったなって……。でも、これ以上は迷惑かもしれないし、えっと、私やっぱりもう辛くて……。もう、歩くのも足が痛くて。時々苦しいのも病気みたいなんです。だから……お別れしようと思います。短い間でしたけど、ありがとうございました。あっ、ヘアピン、可愛くてお気に入りでした。ありがとう……。本当に、私は、優也さんが――』
そこで、録音は終わり、ピアノの旋律が引き継ぐ。
「あ……ぁぁ……」
開かれた両目から、涙が溢れ出す。それは、悲愴。後悔という悲愴の涙。
このメッセージの中に、何回”ありがとう”が含まれていたか……。こんなにも、美笑ちゃんは僕に感謝を伝えたかったんだと……。なぜ、気づけなかったのか……。
僕は嘆きたい。もっともっと、美笑ちゃんのことを気に掛けてあげれば良かった。体面なんて気にせず、もっと深く考えてあげていれば……。美笑ちゃんはこんなにも近くに居たのに。手を伸ばしていたのに。僕が、手を伸ばそうとしなかった……。
「っ……そうか……」
僕は知る。今更になって、ようやく二十歳を過ぎて始めて知る。
涙にはもう一つ、あったのだ……。安堵、悲愴、そして……嘆き。
これは悲愴とは違う。嘆きとは悲しみに浸され、切に願うこと。
切に願う……何を? 美笑ちゃんは最初から、嘆いていたんだ。あの校庭で、初めて会ったときから、初めて涙を見たときから。
僕は最初から、間違えていたんだ……。
悲愴の涙と間違え、救えるものだと勘違いしていた。
嘆きは救えない。その願いを受け止め、叶えてあげること。そして救われたと自らが選ぶこと。
美笑ちゃんは死を選んだ。一抹の願いが潰え、生の幕を下ろした。
美笑ちゃんは初めから嘆いていた。願っていた。この世界から、手を引っ張り陽の当たる場所へ連れ出してくれる人を。両親は手を取ってくれなかった。詩織さんは手の届かないところへ言ってしまった。
だから……。その最後の最後の時。僕が居た。
これは自惚れなんかじゃない。美笑ちゃんは、僕の中に、一縷の望みを抱いた。
「……なんで……なんで僕は……っ」
今までそんな経験が無かった? 優しくしても実ることが無かった? 全て自分の自己満足で良しとしていた……? だから深入りはしないようにしていた?
それが……美笑ちゃんの心を裏切った。思わせぶりな言葉で、突き放してしまった。
優しさで人を救いたい。そんな奇麗事、誰だって願う。でも心のどこかで、僕は信じていなかったじゃないか……。救えたかもしれない命に、優しさを捧げることが出来たのに……。僕の目の前に、それがあったというのに……。
僕は膝をつき、両拳を握り締めながら嗚咽を漏らす。
耳に流れるピアノの旋律は、どこまでも澄み渡り、高い空と水平線の煌きを併せ持つ音色を奏でていた。
せめて、笑ってくれたなら……。
僕は美笑ちゃんを、生涯守ろうと思えたのかもしれない。
責任転嫁と言われればそれまでだろう。なぜなら最後に美笑ちゃんは、さようならという言葉と、笑顔を、僕に向けてくれていたのだから。
それは彼女の心そのままに、美しい笑みを浮かべていたのだ。
これは、僕が彼女の心に、本当の美しい笑顔を見出せなかった悔悟の物語……。
いつだって美笑ちゃんは、笑ってくれていた。
彼女はカルミア。僕は彼女をミムラスだと思っていた。
この世界にカルミアは咲いていたのだ。
素敵な思い出と、美しい笑顔が、彼女を祝福してくれていた。
美しく咲く笑顔、それは彼女だけのもの。
だから彼女は、美笑だったのだ……。
Ende.
Section 2 私の場合。
「ねぇねぇ! そこのあなた!」
私は教師らしからぬ廊下ダッシュで、一人の女の子を捕まえる。
振り向いた少女は中等部の子だろうか。まだ幼さの残る顔立ちで、私を綺麗な瞳で見上げてくる。
「美少女発見! …じゃなくて、おはよう! ごめんね、職員室ってどっちだっけ?」
「…職員室は向こうの校舎、ですよ。1階の東側です」
「あーもう中高一貫校は広過ぎるのよねぇ。まだ把握し切れてなくてさー」
「……」
中高一貫ともなると生徒数が多いのはもちろんのこと、それだけの人が集まる校舎も普通の学校の倍はある。中等部の校舎、高等部の校舎、体育館に無駄に広いグラウンド、
プール施設まであるんだから、このあたりではちょっと有名校らしい。
とはいっても、この地域には学校が少ない。小学校は2つあるが、中学校と高校はこの一貫校だけで、二つの小学校の卒業生はみんなこの学校に進学してくるってわけ。
「っとと、何一人でしゃべってるんだろうね私。確か渡り廊下は、右に…じゃなくて左だっけ……」
「…あ、あの、先生……?」
「ん? あ、そっかそっか。ごめんね。私、新任教師の桜 奏恵(さくら かなえ)。奏恵でいいよん」
実は今日、初めての登校で……なんていうと、ゆかり先輩に怒られるなぁ。
出勤初日から遅刻は免れたけど、職員室に辿り着けないなんて前代未聞の大事件!
私ピンチ!
「か、かなえ先生。良かったら一緒に――」
「あー! いたいた! 桜さん、もう職員会議始まるよー?」
「あーん! 神様・女神様・ゆかり様ー! わざわざ迎えに来てくれたんですね!?」
「あなたがいつまで経っても来ないから心配したのよ。さぁ、今日の主賓はあなたなんだから、行きましょう」
「ありがとうございますー! って、ゆかり先輩。”桜さん”なんて他人行儀です。昔みたいに私の愛する奏恵って呼んでくださいよー」
「あ、朝から変なこと言わないで。学校ではあなたは私の補佐なんだから、しっかりやってよね」
「はーい。…あ、ごめんね。あなたの名前聞いてなかったね。教えてくれる?」
「…はい。美笑です。結城美笑、です」
「ありがと。今度、学校案内してね、美笑ちゃん。それから――」
私は思ったことははっきり言う。昔、そう決めたから。
後悔するくらいなら、大切なことを伝えたい。何もしないで後悔するより、何かして後悔するほうが、よっぽど良いから。見返りは期待しない、今はただ、届いてさえいれば。
「あんまり暗い顔してると、美人が勿体ないよ。悩みがあったらいつでも相談してね。辛いときは、ネガティブグッバイ♪ って言って一緒に笑おう? ねっ!」
ネガティブグッバイ。それが私の、ポジティブシンキング。
「……はい」
それでも彼女は、笑顔を見せてくれることは無かった。
出会いはきっと、こんな先触れ。
この時の私には、美笑に私の気持ちが伝わったかどうかを確かめる術は無かった。表情だけでは汲み取れない。もっともっと深くに、美笑は抱えていたんだ。
私と、そして世界に対して”さようなら”という、別れの言葉を……。
せめて、笑ってくれたなら…。そう思ってしまうのは、私が昔のままだったからなのかもしれない。
私の最初の1歩は、これで良かったのかな……幸枝……?
私は今年の春から、音楽教師としてこの学校にやってきた。
噂の新任教師は美人で若くて愛嬌がある、生徒から注目の的……というのは、私の自称だったりする。
実際には、私の先輩であり尊敬すべき人であり憧れであるゆかり先輩に与えられるものだった。私が大学1年の時に4年生だった先輩とひょんなことから知り合い、親交を深めていたお陰で、先輩のはからいで副担任に推薦してもらった。ゆかり先輩の近くに居られるというのは、私にとって幸せなことで、世間的にもとても恵まれたことだと思う。
教師を志そうと思ったのも、ゆかり先輩の影響だったりする。下心を言ってしまえば、将来はゆかり先輩の近くに居たいと思ったから。仕事も一緒なら、なお幸せなんじゃないかって。
でもそれは表向きのこと。やっぱり私には、生涯背負わなきゃいけないものがある。
それが結局、学校という居場所に縛り付けられているのかもしれない。…ううん、縛り付けられるなんて言ったら怒られちゃうね。ごめんね、幸枝。
それくらいに、私がしたことは重いこと。自戒するのは当然だと思ってる。私の生涯を捧げることが、あの子に対して少しでも罪滅ぼしになればいいなって。
だから、見守っててね。幸枝……。
「ぁぃてっ」
「ここは学校よ。あんまりくっつかないで。それと、学校では”先生”。あなたは桜さん」
「そんなぁ! 私たちの愛は偽りだったんですか!?」
「あ、愛って……。私もあなたが副担任になってくれて良かったと思ってるのよ? ”桜先生”」
「さくらせんせい…良い…。そう言ってくれる先輩が大好きです!」
「ちょ、ちょっと! 歩きづらいから腕にくっつかないでってば。もう…」
「先輩が居ない卒業までの3年間は辛かったんですから…。私もう寂しくて寂しくて…」
「私にどうしろっていうのよ……。ほら、そろそろ教室付いちゃうよ?」
「明日からのGWどこか行きましょう!」
「明日も学校よ。私は当番だから、ほとんど来なくちゃならないわ」
「えー!」
「あなたもよ? 私のお手伝い。副担任の桜先生」
「あ、それならいっか…」
「ふふ。久々にゆっくりお話ししましょ。奏恵」
「……。はいっ!」
そういってウィンクをしてくれる先輩。私もとびっきりの笑顔で答える。
「はい、みんなごきげんよう! 席に着いてねー!」
朝の挨拶。日常の風景。ゆかり先輩の隣で教壇に立つ私。
あのドタバタの初日から、1ヵ月が過ぎていた。学校で迷子になることは無くなったが、それもゆかり先輩が居てくれるからであって、一人ではまだ不安かも?
明日からゴールデンウィーク。
私たちは学校に来なきゃいけないけれど、ゆかり先輩と一緒ならどこだって構わない。
天気予報はずっと曇りで、崩れる日もあるみたい。そんな日は、雨に似合う曲を弾くのも乙かしら。
なんたって今年は5連休! 新曲を書くのもいいかもしれない。ゆかり先輩もいるし、今年はなんだか幸せに過ごせそうな気がする。
…そういえば、美笑ちゃんは元気かな……。
初日に会ってから今日まで、見てない気がする。高等部には居なかったみたいだから、やっぱり中等部の子なのかもしれない。
今度、先輩に聞いてみようっと――。
ゴールデンウィーク1日目。
空はどんよりと曇り空。私の晴れやかな気分とは裏腹に、空はどこまでも不安で物悲しげな表情をしていた。
それでも。私の空は今日も快晴。ゆかり先輩と居られる日は、いつだって清々しい青空。
今日まで雲が陰ったことは一度もないもの。なんたって今日からゴールデンウィーク。ゆかり先輩と二人っきりで――。
「はい。60点」
「うぅ……」
先輩はそんなに甘くなく。なぜか私まで生徒の期末テスト(国語)を受けさせられたのだった。
「あなた……。よくこれで大学卒業出来たわね」
「うー。だって私、音楽専攻ですし……」
「それでも3教科は必須でしょう? それに、あなたは言語力にも難ありよ」
「それは…私オリジナルの愛の囁きが含まれているわけで……」
「はいはい。それから、中間登校日の時のプリント、人数分印刷してくれた?」
「もっちろん! 終わってますよ!」
「ふふ、元気だけはいいんだから。……さて、少し休憩しましょうか」
「はーい! 紅茶淹れて来ますね!」
最近のお気に入りはベルガモット。後味にちょっと苦味が効いた大人の味。それにオレンジを添えて、ベルガモットオレンジティーにすると、柑橘系の程よいさっぱり感とさわやかな後味が口あたりを楽しませてくれる。
これでゆかり先輩も私の虜……。こんな私って質実剛健?
「ん……。女の子なんだからせめて、才色兼備くらいにしておきなさいな」
「あぁ…響きが綺麗ですよね。才色兼備。……至れり尽くせり。出来る女。美しい奏恵。あは、先輩褒め過ぎですって!」
「そこまでは言ってないけど……」
「こ、こんな私ですが、お嫁に貰ってくれませんか!?」
「んー。どうしようかなぁ。あなたにもう少し貞淑さがあればね~」
「私、これから先輩の半歩後ろ歩きます」
「やっぱり元気が一番かなー? 弾ける笑顔、うん! 最高よね」
「私元気には自信があります! いえ、それだけが取り柄です!」
「いやいや、やっぱり私を引っ張ってくれるくらい、かっこいい女性も捨てがたいかな」
「先輩、次の小テストは私が作ります。箱舟に乗ったつもりで居てください」
「箱舟って…私どこまで行っちゃうのよ。はいはい。お芝居はそのくらいでいいから。あなた、入り込むと止まらないのね」
「あはは、やっぱりバレてましたか。でも、先輩への気持ちは嘘偽りありません。それだけは真剣です。私、先輩のこと本当に憧れなんです」
「ありがと。そう言ってくれた後輩はあなただけよ。奏恵」
そういって微笑んでくれる先輩。あぁ、そんな風に見つめられたら私……。
「うん。やっぱり奏恵が淹れてくれる紅茶はおいしいわ。ごちそうさま」
「あ……。お粗末様でした。そういえば、先輩。ちょっと気になることがあるんですけど……」
「ん? どうしたの?」
「あの、美笑ちゃん……。初日に会った子なんですけど、覚えてますか? 職員室が分からなくて、近くに居た生徒に声を掛けたんですけど、その子が結城美笑ちゃんって子なんです」
「あ、うん……。結城美笑ちゃんね、覚えてるわ。その子がどうかしたの?」
「ええと、特に用事があるってわけじゃないんですけど、あれから見ないなぁと思って。高等部で見かけなかったので、中等部の子ですか?」
「そうよ。今年進学してきたばかりだから、あなたと同じ1年生ね」
「やっぱり……。なんだかあの時、暗い顔してたんで今は元気かなぁって……」
「あぁ、美笑ちゃん……」
「先輩?」
先輩の表情が心なし陰る。何か杞憂を含んだ響きだった。
「美笑ちゃんね、あんまり学校生活がうまくいっていないみたいなの」
「うまくいってない……って、友達が出来ないってことですか?」
「うん。私はたまに見かけるんだけど、一人でいることが多くて。休みの日とかは、よく学校に来てるみたいで、ポールのところに座ってるの」
「……そうなんですか。馴染めないのかなぁ。今友達が出来ないと、後々心配です」
「第一小学校の頃の友達とかも、一緒に進学してるはずなんだけどね。もしかしたら、クラスが第二小学校の子が多いのかもしれないけれど、ひょっとしたら……」
「小学校でも、あんまり友達が出来なかった…ってことでしょうか」
「……」
肯定するには抵抗のある言葉だった。私も言葉を選ばなかったことに、反省。
「ごめんなさい。憶測でも失礼でした。でも私、昔そういう子知ってて、放っておけないんです」
「…そうだったね。前に、話してくれたね」
「はい。だから私、どんな理由があってもみんなには、生徒には学校生活を楽しめるものにしてもらいたいんです。疎外感を持ってる子とか、学校が嫌いな子とか、ましてやいじめとか……。もうそういうの、見てられないんです!」
「奏恵……」
「すいません私、ちょっと行って来ます。今日着てるかもしれないんで!」
私は職員室を飛び出して、校庭へ向かった。焦りを抱えながら。
私が焦りを感じてしまうのは、このままじゃ、また同じコトを繰り返してしまいそうだったから。目の前に掴める手があったなら、私は迷わず掴みたい。それが救いを求める手だったなら、なおさら――!
「……っ」
私は、ハッとした。目を見開いていたのかもしれない。
数秒間、その姿に既視感を覚え震えていた。
…………ごめん、ごめんね……。
「さ……幸枝……?」
その横顔は、その涙は、あの頃の姿を彷彿とさせた。
その虚ろな目は、光を失った涙は、あの頃の幸枝のようで。
「……先生?」
どれだけの時間をそうしていたのだろう。美笑ちゃんが私に気づいて、涙を拭いていた。
「……あ、美笑ちゃん。ごめんね、こんにちわ」
「あの、えっと……。昨日あんまり、寝れなくて欠伸出ちゃいました……」
それで涙が滲んだと、美笑ちゃんは言った。涙を見られたことを取り繕うかのように。
私はもう、手遅れなのだろうか? 幸枝に似た美笑ちゃんを見て、動揺してしまったのだろうか。何かもう取り返しのつかないところまで、来てしまったかのような絶望感が一瞬にして込み上げてくる。
「……えっと、奏恵先生?」
「あ、うん。どうしたの?」
「お久しぶり、です。先生こそ、走って、どうしたんですか?」
口調こそ覇気がないものの、もう涙のことには触れて欲しくないという拒絶が見て取れて、距離感を感じてしまった。あまりにもその切り替えについていけなくて、私は言うべきことを見失っていた。
「あのね、えーっと……ゆかり先生に聞いたの。もしかしたら校庭に美笑ちゃんが着てるかもって」
「…そうですか」
「久しぶりだね。もう学校には慣れた?」
あ……。失言だった。私は自分の軽率さに絶望した。
「……はい。移動教室が少し大変ですけど、頑張ってます」
「そっか。学校広いからねー。私もやっと、教室の場所覚えてきたところだよ」
「……」
やっぱり、元気がない。私の失言のせいもあるけれど、初日と同じく美笑ちゃんは暗いままだった。
私も、らしくない。動揺していつもの私を見失っている。頑張れ奏恵。超頑張れ。
美笑ちゃんは笑ったらきっと素敵なはず。物憂げ美人も良いけれど、笑ったらもっと可愛いに違いない。
……よし! ネガティブグッバイ♪ 気合を入れなおして、拳を握る。
「そうだ! 美笑ちゃんさ、明日は予定あるかな? お祭りがあるんだけど、一緒に行かない?」
「お祭り、ですか……」
「うん! 楽しいんだよ! 色んなもの食べたり、ゲームしたり、とにかく楽しいのは間違いなし!」
「……。考えておきます。すみません、私、これから行くところがあるので」
「あ、そっか。ごめんね。明日も学校にいると思うから、良かったら着てね。待ってるよ」
「……はい」
美笑ちゃんはこくりと頷いて、立ち上がる。
校門を歩いていく後姿はとても小さくて、すぐ駆け寄って抱きしめなきゃ倒れてしまいそうで。まだまだ、心を開いてくれるまで時間が掛かるかもしれない、そう思った。
……私、今日何も伝えられてないや。失言して、傷つけて、空回りして。
今日の私、ダメダメだー……。
「ただいまです……」
「おかえり。美笑ちゃんはいた?」
私は倒れるように椅子にへたり込む。
自分の空回り加減といい、やるせなさといい、ヘコみそうだった。
「……それでもう、トリルの連続で指が絡まったような感じで」
「あら、珍しいじゃない。あなたのピアノは天武の才だと思っていたけど?」
「うー。そんな日もあるってことです」
先輩には私の例えがどういうものか、分かっているようだった。
私の辞書には、ピアノ関連の引用が多く含まれている。
「ところで先輩、明日空いてますか?」
「学校よ」
「ですよねー。実は明日、美笑ちゃんにお祭りいかない? って誘ったんです。保留ってことだったのでまた明日来たら聞いて見るつもりです」
「あぁ、そういうことね。それなら、私のことはいいから二人で行ってらっしゃいな。午前中だけ手伝ってくれれば、あとは大丈夫だから」
「えー! 先輩も来て欲しいなぁ」
「んー。今回ばかりは、奏恵と二人の方がいいと思うの。あなたの方が歳が近いのもあるし。実はね、美笑ちゃんにはお姉さんが居たんだけど、不幸があってね」
「そうだったんですか…。って、先輩も私と3つしか変わらないですよ?」
「うふふ。それにね、これはあんまり他の人にしゃべっちゃダメよ? …ご両親も離婚されてて、今は義理のご両親のところに住んでるの」
「義理のご両親?? っていうと、本当のご両親は…」
「うーん。ちょっと複雑でね。奏恵に分かってて欲しいのは、今の美笑ちゃんは一人ぼっちっていうこと。だから、誰かが傍に居てあげないといけない。お姉さんの代わり…っていうと美笑ちゃんがどう思うか分からないけど、あなたならピアノも弾けるし、ひょとしたら……」
「…はい。もしかしてそれが、共通点なんですか?」
「うん。だからもし出来たら、奏恵のピアノ聞かせてあげて欲しいの。私からのお願い、聞いてくれる?」
「はい! そういうことでしたら、私なりにやってみます。何より先輩の頼みでしたら、私なんでもやりますから!」
「ふふ、ありがと。奏恵」
お姉さんが不幸、か……。親御さんもだなんて……。
本当に美笑ちゃんは、ひとりぼっちなんだ……。助けて欲しいと言葉にすることが、どれほど勇気の必要なことか、私は知ってる。言葉に出来ない人の願いを汲み取ることも出来る。あの涙がその理由。
……うん、そうだよね。今がその時だよね、幸枝。
私、決めた。美笑ちゃんのためにピアノを弾く。そして、お姉さんの代わりになれるか分からないけど、美笑ちゃんの傍にいて、ひとりぼっちじゃないよって伝えたい。
私の名前は、奏恵。奏という言葉はたくさんの意味を持つ。
それを一つ一つ伝えていこう。それが今私に出来る、罪滅ぼし。私の禊。
それから私は、ゆかり先輩を強引に連れ出して、音楽室でささやかな演奏会を開いたのだった。
ゴールデンウィーク2日目。
ゆかり先輩のお手伝いをしながら午前中を過ごしたが、美笑ちゃんが姿を見せることはなかった。
私も強要は出来ないので、美笑ちゃんが乗り気でないのなら諦めようと思う。その確認だけしたかったのだけど、学校で会えなければ仕方が無い。わざわざ家まで押しかけて聞く事も出来ないし、ましてや勤務中。さすがに、ゆかり先輩もそれは許してくれなかった。
思えば、美笑ちゃんは祭りという単語に不思議な受け取り方をした。まるで、お祭りがどういうところか分からないという風に。ひょっとして、お祭りに行ったことがないのかもしれない。
それならそれで、私が初めてのお祭り案内人になろう。きっとお祭りの楽しさを分かってくれるはず。ゲームから食べ物まで、奏恵プランでご招待しちゃうんだから。
そんな私の妄想とは裏腹に、一向に美笑ちゃんは学校にやってこない。休憩中に、ちょっと校庭を見に行ったが、やっぱりまだ居なかった。
「美笑ちゃん、今日は来ないのかなぁ……」
「美笑ちゃんにも都合があるのかもしれないね。仕方ないよ」
そこでゆかり先輩は作業の手を休め、私に振り返る。
「ところで奏恵。昨日音楽室に居たとき、変な感じしなかった?」
「変な感じ、ですか? いえ、私は気持ちよく弾いてましたよ」
「そう……。なんかね、誰かからじっと見られてる気がして……」
「だ、誰かって……。今休み中ですし、部活の先生たち……とか?」
「ほら、音楽室って多いじゃない? 怪談みたいの。肖像画とか色々」
「え……。やめてくださいよ、私そういうの苦手だって知ってるじゃないですか」
「奏恵は鍵盤を見てたから気づかなかったかもしれないけど、ひょっとしたらあれは、
私じゃなくて、奏恵を見てたんじゃないかって……」
「や、やだなぁそんなわけ……。なんか急に悪寒が……」
「知ってる? 今噂になってる新しい音楽室の怪談。それはね……」
「ひぃー! やめてくださいよー! 聞きたくないです! 音楽室は私の聖域なんです、怪談も妖怪もいませーん!」
「うふふ、あはは。ごめんなさい、冗談よ」
「……へ?」
「奏恵があんまりにも、美笑ちゃん美笑ちゃん言うものだから。私が目の前にいるのに」
「あ、いえそれは……。えっと……?」
「ほら、噂をすれば何とやら。ポールの所に物憂げな美人が座ってるよ? 奏恵の待ち焦がれた人じゃないの?」
「あ、えと……美笑ちゃんはそういうのじゃないですからね!? 私が好きなのは、ゆかり先輩だけですからね! 誤解しないでくださいよー!?」
私は二人を交互に見ながら弁解をする。
「はいはい。行ってらっしゃい」
小悪魔なゆかり先輩の笑勝ちな様子に、私はあせあせしながら職員室を後にする。
ゆかり先輩はいつも優しくて綺麗で、なんて月並みだけど、こういう小悪魔的ないじわるをするときもある。それは嫉妬か好意の裏返しか、先輩のにこやかな笑顔からは想像出来ない。
でも私にとってそれは、斜に捉える理由は一つもない。それも含めて、私はゆかり先輩が好きなのだ。ちょっとだけ、嬉しいんだからね!
「美ぃ笑ちゃん」
「……先生」
美笑ちゃんは今日も沈鬱な表情だった。せめて、笑ってくれたなら、私がもっと楽しませてあげたい。美笑ちゃんは笑ったら可愛いに違いないんだから。
「どうしたの? ほら、笑顔笑顔♪」
私は少しオーバーに、笑顔を作って”にっ”と、してみた。
この奏恵さんのスペシャルスマイルで、美笑ちゃんもイチロコ! さぁ、一緒に笑おう!
……と、意気込んだのは私だけで、美笑ちゃんは私を見上げるばかりで頬を緩めることはなかった。
「あの……えっと……」
次第に目尻に涙が溜まり始め、目が細められていく。その様子をずっと、私は見ていた。美笑ちゃんもずっと私を見ていた。私たちは見つめあったまま、だけれども美笑ちゃんは込み上げる感情を涙に変えて、とうとう両手で顔を押さえてしまった。
「ど、どうしたの!? ごめんね、ごめんね!? 私、何か嫌なこと言っちゃった!?」
「いえ……違うんです。私、笑い方、分からないんです……。忘れちゃったんです……。ごめんなさい、ごめんなさい……」
「み、美笑ちゃん……」
私は自分がしたことが、ひどく彼女を追い詰めていたことを知った。
笑顔、それは人の表情の一つ。それは、感情表現のごくごく自然な表現。いやもっと、それ以上に笑顔は多くのことを伝え、多くの意味を持つ。
それを、忘れてしまったら……。きっかけは、美笑ちゃんのとりまく環境を考えれば一目瞭然だった。
いや、きっかけは今ではもう、きっかけでしかない。その理由も、意味も、私は理解しなくちゃいけない。今はもう、美笑ちゃんの笑顔は喪われてしまっている。
それを取り戻すのは容易なことではないかもしれない。
忘れたことを、思い出すのってどうすればいいの……?
「ごめん、ごめんね……」
私は自然と、美笑ちゃんを抱きしめていた。気がつけば、私も涙していた。
幸枝は涙を。美笑ちゃんは笑顔を。無くしてしまっていた……。
私は今、涙を流せる。笑顔を咲かせる。でも……何も与えられない……。私は、どうしようもなく、何も出来ないの……?
「…先生。奏恵先生? 泣いてる、の?」
「うん……。ごめんね。私が美笑ちゃんを傷つけてたね。無理言って、ごめんね?」
「いえ……いいえ。私、全然そんなこと、思ってないです。嬉しかったです。私のほうこそ、取り乱してごめんなさい……」
「……」
美笑ちゃんは私の腕の中で、ちょこんと顔を上げて、私を見る。
「……ねがてぃぶ、ぐっばい」
「…え?」
「ネガティブグッバイ。奏恵先生。……嬉しいです。こうしてくれたの、先生が二人目です」
「……二人目?」
「はい。お姉ちゃんも、してくれました。お姉ちゃんの匂いがします。でもちょっと、いたひ……」
「あ、ごめんね。力入れ過ぎちゃったね」
「…いえ。お姉ちゃんもそうでした。ありがとう、ございます」
そう言って、美笑ちゃんは私の胸に顔をうずめた。背中に手を回し、私たちは抱きしめ合う形になる。
ちょっと、恥ずかしいけど……私はこの儚さを手放しちゃいけない、そう思った。
私は、取り戻すことが出来るだろうか。この子の、笑顔を……。
離さない。目を逸らさない。それだけが、笑顔に繋がると信じてる。目の前にあるものを、見るだけじゃダメ。しっかり伝えていこう。
それがあの日の決別。私の決意、ネガティブグッバイ。
「ネガティブグッバイ。ありがとう、美笑ちゃん」
「……はい。あ、あと……お祭りは、ごめんなさい。行ったことがなくて……お金もあんまり持ってなくて」
「あ、そっか。でも、お金のことなら気にしなくていいよ。初めてでも色々案内して上げられると思うよ?」
「…そうですか。でも……」
あまり乗り気ではないみたい。気を使ってくれているんだと思う。気が乗らないではなく、申し訳ないという表情だった。
だから、私はそれを汲み取って美笑ちゃんの気持ちを尊重することにした。
「うん、そうだね。お祭りは毎年あるから大丈夫だよ。ふふふ、そしたらさ、美笑ちゃん。私とデートしようよ!」
「で、デート……ですか?」
「うん! っていっても、遠くに行くってわけじゃなくて、午後から時間あったら私の家に来ない? 奏恵主催! ピアノコンクールに美笑ちゃんをご招待!」
「わぁ……先生、ピアノ弾けるんですか?」
「まっかせて! 入場料は無料、特等席は美笑ちゃんだけ! 飲み物とお菓子も付けちゃう! って、モノで釣る訳じゃないんだけどさ。美笑ちゃんはピアノ好き?」
美笑ちゃんは、こくんこくんと首を立てに振った。心なしか表情が明るくなってきた気がする。
「よっし、決まり! それじゃあちょっと待っててね。ゆかりせんぱ……じゃなかった。縁先生に事情話してくるから」
「……あ、先生」
駆け出そうとする私の袖を、美笑ちゃんが引っ張る。
「ん? どうしたの?」
「えっと、その……」
「うん、言ってごらん?」
「わ、私の為に、色々ありがとうございます。奏恵先生も忙しいのに……」
「ううん、そんなこと美笑ちゃんは気にしないで? 私が美笑ちゃんにピアノを聞いて欲しいの。美笑ちゃんは私が招待したいお客さんだもん。でも、無理にとは言わないよ? どうする?」
「…行きます。聞きたいです」
「そっか、良かった良かった。それじゃあ、待っててね」
私は美笑ちゃんの頭を数回撫でて、その場を後にした。
職員室のゆかり先輩に事情を話すと、先輩は快く承諾してくれた。これで今日のお仕事は終了。早く美笑ちゃんの顔が見たくて、私は急ぎ帰る支度をするのだった。
二人の帰り道は新鮮だった。
いつもはゆかり先輩と歩く道も、美笑ちゃんと一緒だと雰囲気が違って見えるのだ。私は饒舌に紅茶の講釈を交えながら、一緒に歩いている。まぁ、殆ど話しているのは私だけど、美笑ちゃんもちゃんと相槌を打ってくれるし、傍から見れば姉妹のように見えるかもしれない。
うん、妹が居たらきっとこんな感じなのかな。こんなに可愛い妹だったら、私が依存しちゃうかもしれない。物静かだけど、私の声を聞いてくれる、それが嬉しかった。
途中、ちょっと寄り道をして小さな雑貨屋へ立ち寄った。
そこは珍しいものが色々あって、ちょっとした隠れ家的な雰囲気だった。目に留まったのは、色々な種類のヘアピン。花を模ったものが多いようだ。
カルミアとミムラス、どっちにしようか迷ったけど、カルミアを選んだ。二つの花言葉を知っていたのが決め手だった。
お揃いのヘアピンを買って、ちょっとくすぐったいようなドキドキするような。
私の頭の中で、妹とするショッピングを楽しんでいた。美笑ちゃんも笑顔こそないものの、心なしか表情は明るい。初めて会ったときからの暗い表情は、今は無い。
少しずつだけど、打ち解けて来たのかもしれない。
そんなちょっとした変化に嬉しさを覚えつつ、私たちは家に着いたのだった。
「皆さん、こんばんわ。桜奏恵です。今日は私の演奏会にご来場くださいましてありがとうございます。今宵は美しい青い月。ブルームーンの下で、ピアノの音色をどうぞお楽しみ下さい」
私は仰々しく挨拶をする。まるで、舞台女優さながらの身振りを加えて。
美笑ちゃんは私を見つめながら、小さな拍手をしてくれた。初めて見るものに、ドキドキする気持ちはよく分かる。それが美笑ちゃんの表情から見てとれて、くすぐったいくらいに嬉しかった。
二人きりの演奏会。カーテンコールは無いけれど、私は今、舞台の上で咲き煌めいている。私は伝え人。贈る相手はもちろん美笑ちゃん。今夜が美笑ちゃんにとって、有意義な時間であって欲しい。純粋にそう思った。
「私とピアノの出会いはずっとずっと幼い頃。子守唄のように聞いていた音色です。両親がピアノを聞くのが好きだったこともあって、ピアノの演奏会がある時は、ことあるごとに一緒に連れて行ってもらいました。当時はまだ、ピアノに強く関心を持っていなかった私でもその音色は、胸に響くものがありました。そうして幼少時代を過ごし、歳を重ね、大学に入学した時、私は衝撃的な出会いをしました。当時の私は恥ずかしながら、将来の夢も決まっていませんでしたが、その衝撃的なピアノと出会い、音楽教師を志すに至りました。あの時の音色は今でも忘れません。例えるなら、広い大空に煌めく爽やかさと、広い海を青々と染める深さ。それが、クラシックでもなくメジャー曲でもなく、創作曲だったのですから、さらに衝撃でした。あぁ、私はもう一度聞きたい。あの音色を。その曲にもう一度出会うまで、私はピアノを弾き続けるでしょう。あの曲には遠く及ばないけれど、今夜私のピアノを、どうかお楽しみください」
黙礼をしてから、私はスタンバイする。
この静けさは、なんと形容すれば伝わるだろう。ピアノを演奏する瞬間、第1音が発せられるまでの時間。それは演者の呼吸であったり、観客の期待であったり、コンサートホールの空間はこれから始まるだろう世界を受け入れる。
それはプロローグ。物語の始まり。まるで、本を開いたときのような音の世界への誘い。
その1ページ目を開くのは、私。桜 奏恵が紡ぐ物語。
「…………」
美笑ちゃんが息を呑むのが分かる。私はそれを耳で受け止め、物語を開始した……。
私の物語は、後悔から始まった。
高校の頃、私は大きな過ちを犯し自らを戒めた。今でも、なぜあの時私は目を背けてしまったのかと、後悔に押し潰されそうになる。
見ているだけで、何もしなかった私。
助けを求められても、何もしなかった私。
彼女の涙が枯れてしまったことを知った時、私はなんてことをしてしまったのだろうと気がづいた。涙が枯れてしまうなんて思いもしなかった。そのうち終わるだろうと思ってしまった。自分勝手に、自分の都合で、他力本願の極み。
涙が枯れてしまった後、それが終焉を迎えたのは、彼女自身の終止符だった。
彼女の自殺という、最悪の結果だった。私は涙した。自分の行いひどく呪った。
命とは、力強く輝くもの。しかし、脆く儚いものだった。命が背中を見せることはない。生きて、最後の瞬間まで命たろうと輝く。
もしも背中を見せることがあったなら、それは光を失った時、涙を失った時。輝きを失った命を見て人は思い知る。なんて儚く、脆いものだったのだろうと。
それが悲しいことだったとは思いたくない。”心非ず”なんて、それこそ悲し過ぎるから。だから、優しさが生まれ、気遣いが生まれ、思いやりが育まれる。
そして学んでいく、私には何が出来たのか。私に出来ることがきっとあったはず。死は悲しむべきではなく、悼むこと。哀悼を捧げ、十字架を背負うことを決めるのだ。
私は悔やむ、あの時の自分を。だからこそ今、背中に十字架を刻んでいる。
でも十字架は枷ではない。決意なのだ。もしも語ることがあったなら、私は伝えよう。今度こそ、同じことを繰り返さぬよう伝えていこう。生涯を賭して。
それがこの曲、ネガティブグッバイ。私のオリジナル曲の一つだった。
「…………」
演奏後の間。それが物語の結び。
私の物語はここで、本を閉じたのだった……。
「…ありがとうございました。これが私の……あ、あれ? 美笑ちゃん?」
「……あ。はい」
美笑ちゃんは軽く放心状態というか、ぽかんとしていた。
うっすらと涙を浮かべているのを、自分でも気が付かなかったようだ。
「なんだか、すごく哀しくて。でも……優しくて。お姉ちゃんのピアノにそっくりで。えっと……」
片目を擦りながら、感想を言おうとしてくれてるのがとても可愛らしくて、嬉しくて。こんなにも私のピアノで感動してくれたのが純粋に嬉しかった。私までもらっちゃいそうなくらい。
「すごく、懐かしい気がしました。なんというか、とても嬉しかったです。……あ、もし良かったら、奏恵先生。この曲聴いてくれませんか?」
すると美笑ちゃんは、ハンドバッグからウォークマンを取り出した。
そういえば、校庭にいる時はイヤフォンしていたっけ。いつも持ち歩いているのかもしれない。
「うん。さぁて、どんな曲かなー?」
私はワクワクしながらイヤフォンを耳に当てる。
しかしそれは、一瞬にして衝撃に変わった。
「……っ。この曲って――」
「…はい。お姉ちゃんが私の為に創ってくれた曲なんです。曲名は”beautiful smile”」って言います。ピアノの演奏会でも、弾いたことあるんですよ」
「……私、この曲、知ってる……」
「……え……?」
私は信じられないといった表情をしていたと思う。美笑ちゃんも大きな目をこちらに向けて、驚きの表情を向けている。
聞き間違えるはずがない。うん、確かにこの曲だった!
所々、断片で覚えていた旋律。どうしても思い出せないところがあって、耳コピには至らなかった曲だった。当時まだピアノが弾けるレベルではなく、月日が経って、耳コピも出来るようになった頃には、思い出しながら採譜するには限界があった。
でも、電気的に記憶が繋がる。私が衝撃を受けた素晴らしいピアノは、音楽にそしてピアノに惚れ込んだきっかけをくれた音色は、確かにこの曲だった!
でも、待って……。この曲は美笑ちゃんのお姉さんの曲? 確か、演奏会で聞いたときの演奏者さんは、石川……詩織、さんだったはず。
でも、美笑ちゃんの苗字は、結城さんだったはず……。
「…はい、お姉ちゃんの名前は詩織です。えっと、私の親は、離婚しちゃってて……。私、昔の苗字は、石川なんです。石川美笑……」
「っ――。……そっか。やっぱり、そうなんだ……」
こんなことって、あるの……。私が焦がれた音色が、ここにあった……。
でもそれは同時に、永遠に再会の叶わない演奏でもあった。この曲の奏者、石川詩織さんはもう、この世にはいないのだから。
同じ曲を、違う奏者が弾いたなら別の曲になるのはみんな知ってる。なぜなら、奏者とは込める想いが皆違うのだ。詩織さんが弾くピアノと、私の弾くピアノが違うのと同じように。
ましてこの曲は、詩織さんが美笑ちゃんの為に贈ったピアノ。詩織さんが込める想いに勝るものは、もうこの世には、存在しない。
「……奏恵、先生?」
「…………」
永遠に再会が叶わないと知った絶望と、それでもまた耳にすることが出来た幸運と。
私は気持ちは揺らぐ。哀しさに浸りたいのか、もう一度聞けたことを享受するか。
……私は………。
もう一度訪れた幸運を、享受した。
ネガティブグッバイ。最高の贈り物をありがとう、詩織さん。
……うん、そうだよね幸枝。これは私に訪れた幸運で、美笑ちゃんの為に贈られるものなんだよね。そして今はもう、私にしか出来ない事なんだよね。
私は奏恵。私は奏者。誰かの想いを繋ぐ人。でも、それでも……私にも伝えたい想いがある。”奏”は融和の意味も持つのだから。
「…美笑ちゃん、目、閉じててくれるかな?」
「え? はい……」
「良い子……」
私は2,3回美笑ちゃんの頭を撫でてから、ピアノの前に立つ。
目を閉じて、私は世界を再構築する。旋律が身体を駆け巡る。私は、弾く決意をする。
詩織さんの込めた気持ち、すごいなぁ……。私のスペシャルスマイルなんて、全然だったね…。beautiful smile、美しい笑顔、美笑かぁ……。
あの日の感動をもう一度。あの日の後ろ姿をもう一度。詩織さんの背中はとても美しく、ホールを一体として空間が咲き煌めいていた。そして横顔は、とても幸せそうだった……。
私の指が、鍵盤に触れる。その瞬間、私の腕は詩織さんが動かしているかのように軽やかに。自然と、動き出したのだった……。
「お姉ちゃん……詩織お姉ちゃん……」
弾き終わった時、目を閉じたままの美笑ちゃんは涙を流していた。
その涙の量は、愛しさの証。その涙の大きさは想いの大きさ。涙を零しながら、お姉ちゃんと何度も呼びかけていた。
私は、それに応える。それが、私に今出来ること。
「…美笑。もう泣かないで」
「お姉、ちゃん……?」
「ごめんね。家に帰れなくて……。背、伸びたね」
「ううん。ごめん、ごめんね…。私があの日、アイス買ってきてって言ったから違う道、通らなきゃいけなかったんだよね、だから……」
「…それは違うよ、美笑。あの日は雨上がりだったから路面が濡れてた。運転手さんも悪くない。誰も悪くないよ。もちろん、美笑が自分を責めることなんて、ないんだよ?」
「でも…でも……」
「美笑、目開けていいよ」
目を開く瞬間、私は美笑をぎゅうっと抱きしめた。一番伝えたかったことを伝えるために。
「私はここにいるよ。ずっと、ずーっと。これからも、美笑と一緒にいるから。約束する。だから、もう泣かないで? 悲しまないで?」
「おね……」
「うん、美笑は笑ったら誰よりも可愛いんだから。私の大切な妹……」
「…ぷはっ。ちょっと、いたひ……」
「あ、あぁ! ごめんね! 大丈夫?」
「はい、大丈夫です。嬉しいです、すごく…すごく…。ありがとうございます」
すると、美笑は私の背中に腕を回してぎゅっと抱きしめてくる。
その安らかな表情は、薄らと笑っているようにも見えた。それはすぐに、私の胸にうずめられて見えなくなってしまったけど、私の気持ちが伝わったのだと実感出来た瞬間だった。
美笑にはまだまだ、支えが必要なんだ。それを環境が突き放してしまった。
子供の時代は子供でいることが大切だと思う。早く大人になる必要なんて無い。精神的に早熟なのと、早く子供を卒業させられるのとは意味が違う。
大人になったら甘えさせてくれる人なんてほとんど居ないんだから。私は、ゆかり先輩が居てくれることが幸せなんだけどね。
美笑も、環境が彼女を悪い意味で背中を押してしまったから追い詰められてしまっている。まだまだ甘えたい年頃だというのに。
私が、お姉さんの代わり…かぁ……。ゆかり先輩の言葉がよぎる。詩織さんの代わりが、私に出来るかな……。
そうして私たちは、お互いの温もりを確認し合ってから夕飯を一緒に食べることになった。
夕飯を食べ終わった頃、ドンドンという音で私たちは思い出す。
そういえば、今日はお祭りの日。毎年恒例の花火大会も近くでやっていたのだ。
私たちは窓際に行って、月明かりの中寄り添って花火を見る。
「おー! 今年も大きいのが上がってるー!」
「綺麗……」
「これは穴場発見だねー。家からの方が良く見える気がする。二人だけのヒミツだね!」
「…うん。奏恵、お姉ちゃん……」
「え……?」
「ダメ、ですか?」
「あ、ううん。そう言ってくれると私も嬉しいかな」
「良かった…。お姉ちゃん、約束守ってくれた……」
「約束?」
「うん。また一緒に、花火見ようねって約束したんです」
「…そっか。また来年も、再来年も……これからずーっと、一緒に見ようね」
「っ…………。うん…」
私たちの手は自然と重ねられた。寄り添いながら花火を見上げるのは、いつ以来だろう。
それが美笑となら、この先もずっとずっと、毎年見たいと思った。
幸枝とも、こうして見られたら良かったな……。いつかそんな日があれば、素敵かな……。たまには会いに来てね、あの日みたいにさ。私、待ってるから。
花火が終わる頃、肩に寄りかかっていた美笑の頭に気付き、いつの間にか寝息を立てていた美笑を起こさないようにそっと抱く。
安らかな寝顔。心休まる場所でなければ、人は安心して眠れない。美笑は、初めて来た
私の家でこうして寝息を立てている。それは、この場所が美笑にとって心の置ける場所になったということ。
今、美笑の心は安らかであって欲しい。それが今の、私の願い。
姉の私は布団を敷いて、美笑を先に布団にいれる。私も隣に横になり、目を閉じたのだった……。
ゴールデンウィーク3日目。
「昨日はお楽しみだったみたいね」
と、いうゆかり先輩の一言で私の眠気は一気に覚めたのだった。
お決まりというか、お約束というか。やましいことは無いのに、先輩のジト目にたじろいでしまう。もちろんも何も、生徒を自分の家に泊めただけ。それが男の子だったら問題があるかもしれないけれど、美笑は女の子。ささやかなお泊り会といえば、少し洒落る響きもあろうというもの。
現に、美笑の支えになって欲しいと言ったのは、ゆかり先輩の方で私は私に出来ることをしたと思っている。その結果、美笑は心を開いてくれて私をお姉ちゃんと慕ってくれるまでに至った。
それは理想の結果であり、ゆかり先輩も望んでいたことだったはず。
しかし、ゆかり先輩はそのコトではなく、別に咎めたいことがあったのだ。
「奏恵、あなたはもう教師でしょう? 親御さんに連絡は入れたの?」
「あ……。すみません、忘れてました……」
「うん、そうだろうと思って私がしておいたわ。頼んだ手前、私にも責任があるからね。
生徒が家に帰らない、っていう電話が来ることもあるんだから。もし次、同じことがある時は、気をつけてね」
「はい、重ね重ねすみません……」
「あ……でも、美笑ちゃんの家に電話は、ん……」
「先輩?」
「ううん、ごめん。やっぱり奏恵は家のことは気にしないで。今度美笑ちゃんが、奏恵の家に泊まりに行くときは、私に連絡を入れてくれる? 私が電話しておくから」
「そんな……今度からは、私がしますよ?」
「ううん、ごめん奏恵。今は何も聞かないで、私に任せて。奏恵には本当に感謝してるの。本当に、ありがとう」
「ちょ、ちょっとどうしたんですか? 改まってお礼なんて……」
「私にはこのくらいのことしか、出来ないから……。奏恵が美笑ちゃんの支えになってくれたみたいで、本当に良かったと思ってる」
「いえ……私は、私に出来ることをしただけで……。もとより、先輩のお願いです。失敗は許されませんから!」
「ありがとう、奏恵……。いいえ、”奏恵お姉ちゃん”」
「え……えぇ!?」
「あら、認めてもらえたんでしょう?」
「は、はい……。それは、まぁ……って、何で知ってるんですか!?」
「あなたがさっき、お花を摘みに行ってるときに美笑ちゃんが来たの。”奏恵お姉ちゃんは、今日来てますか?”って」
「あわ、わわ……。み、美笑にはちゃんと、学校ではセンセーって、呼びなさいって、言っておかなきゃ、なぁ……はは、あはは」
「すっかりお姉さんね。おかしいなぁ……私は抱きしめてもらった覚えはないんだけどなぁ……?」
「え? えぇー!? せ、先輩がよければ私はいつだって愛の抱擁を! ……じゃなくて、どこまで聞いちゃったんですか!?」
「う~ん、ピアノを弾いたこととか、夕飯のこととか、花火のこととか、奏恵お姉ちゃんが抱きしめてくれたこととかー♪」
「わー! 言葉にされると、なんか恥ずかしい……」
「美笑ちゃんを抱きしめても、私は抱きしめてくれないのね……」
「えぇ!? 違います、誤解です! 美笑に対しては可愛い妹としてで、先輩にはちゃんと愛を込めて飛び込みます! えーと、私を受け止めてくれますか!?」
「はいはい、それは次の小テストで100点取ったらね」
「うぅ……。なんだか、今日の先輩いじわるです……」
「ふふ、奏恵があたふたするのが面白いから、ついね。…そうそう、あなたの可愛い妹さんが教室で待ってるみたいよ」
「教室……? どこのですか?」
「高等部3-C。私の思い出の教室」
「あ、先輩が初めて担任したクラスですね。覚えてます! それじゃあ、すみません。ちょっと行ってきます!」
「はい、いってらっしゃい。……あ、奏恵」
「っと、なんですか? 先輩」
ゆかり先輩は、前髪をトントンと触る仕草をしながら。
「お揃いのヘアピン、お似合いよ。素敵だわ」
「…あ、あはは。ありがとうございます!」
私の顔は嬉しさと恥ずかしさで、高揚していたと思う。
そして私は気づく。この初めての気持ちが胸の高鳴りとなっていることに。
たとえ血は繋がっていなくても、姉であるということ。妹が出来たという喜び。それは何かの小さな芽吹きといえるかもしれない。
その関係は血ではなく、絆。
私の中に芽吹いた小さな決意。姉であろうとすること。美笑の支えであろうとすること。そして……姉と呼んでもらえる喜び。
それがいつか花咲く頃に。私たちは姉妹であると、胸を張って笑い合えると信じてる。
美笑の笑顔、きっと思い出せますように……。
「おまたせっ!」
「……あ、奏恵お姉ちゃん」
振り向いてくれた美笑の表情は心なし明るい。
今の美笑にはこれが精一杯の笑顔なんだと、私は分かっている。それはもう、無表情ではない。それはもう、無感情ではない。少しずつだけと着実に、美笑の中で何かが変わり始めているということ。
自惚れかもしれないけれど、そのきっかけを私が作ってあげられたんじゃないかって、そう思った。
人は誰しも孤独だと思う。塞ぎ込んで、抱え込んで、悩んで苦しんで。そうして自分の殻を厚く厚くしていく。そうして暗くなって、寂しくなって。ふと顔を上げてみると、世界はこんなにも明るいんだって気づくこともある。
でも、全ての人がそうであるとは限らない。
その殻を自分で開けることが出来なくなってしまったら。殻の厚さがもう自分では壊せなくなってしまったら。もうその人は、閉じ込められてしまう?
ううん、違う。きっとそれは、人の力でしか解き放てない。
豪快にその殻を破って助け出してくれる人もいるかもしれない。優しくその殻を撫でて孵化するまで温めてくれる人もいるかもしれない。私は後者でありたいと思ってる。
そうして手を伸ばして、手を伸ばしあって。関わりが生まれ、感情が生まれる。
そして気づくの。殻なんて、無かったんだって。
それは私たち自身が生み出した幻想。そう思い込んでしまった具現。閉じこもった側が見えるものもあれば、接点をもった側から見えるものもある。
いつの日か、それを払拭出来た時、人は笑い合える。
それが、人の力。想いというもの。想いとは、相思相愛であり相手(互い)の心を写すもの。だから生まれるんだ。絆も、愛情も、友情も。
私は駆け寄る、最愛の妹の元へ。
「美笑、ごめんね。学校では、お姉ちゃんじゃなくて先生って呼んでくれるかな?」
「え……」
「あ、お姉ちゃんが嫌ってことじゃないの。私もついつい縁先生のことを先輩って言っちゃって怒られるんだけどね。学校ではやっぱりほら、先生と生徒だからさ」
「うん……」
「でも、二人きりの時はいいよ? だから今は大丈夫!」
「良かった……ごほ、こほんこほん!」
「美笑!? 大丈夫?」
「……こほん! ごほこほッ! ……はぁ、はぁ。うん、大丈夫。すぐ治まるから……」
突然、美笑が咳き込む。何か喉につかえてとかっていう感じじゃなかった。
私はあたふたしながら、美笑の背中をさするしかない。美笑は喘息か何かを持っているのだろうか? それとも何かの持病を?
しかし、今は聞ける状態ではなくしばらく背中をさすり続けるしかなかった。
「……奏恵、お姉ちゃんは、私の二人目のお姉ちゃんだから……」
「…うん。美笑は私の可愛い妹だよ」
「ありがとう……」
少し落ち着いた頃、美笑は私に寄りかかってくる。肩の上下で美笑の息遣いが分かり、呼吸を整えているように見えた。
「美笑、ちょっと待っててもらえるかな。カモミール作ってくるから」
「…カモミール?」
「うん。カモミールにはリラックス効果があって、温かいのを飲むとすごく落ち着くんだよ。香りはリンゴみたいな甘い感じで……って、紅茶なんだけどね。すぐ作ってくるからちょっと待ってて」
私は教室に美笑を残し、職員室へと戻った。
本当なら、美笑を職員室に連れて来てここで飲ませてあげるのが一番いいのかもしれないけど、美笑に無理させられないのもあるし、教室でティータイムっていうのも乙かもしれない。紅茶を持っていくことに目を瞑ってくれた先輩に感謝感謝だ。
教室に戻ると、美笑は窓際で空を眺めていた。大分、回復したみたい。
窓際の席にトレイを置き、同じように空を眺める。
「大丈夫? もう少し座っててもいいよ?」
「…うん、大丈夫。今日は約束の日だから」
「約束?」
「今年は、32年ぶりにみずがめ座流星群が極大になるんです」
「そっかー。でも、今日は雲厚いみたいだね。夜は雨かもって天気予報で言ってたかな」
「…そんな時は、雲を見るのも楽しいです。あれが、ソフトクリームで……こっちはわた飴で……」
美笑は指を指してあれこれと説明してくれた。
そんな甘いものをお茶請けに、二人でティータイムにすることにした。
しばらくして新任初日に言っていた、学校案内をやろうという話になった。
カモミールのお陰か、美笑の回復力の為か、すっかり身体の方は問題無いというので、二人で歩いてみようということになったのだ。
しかし、美笑も案内しようにも限られた場所しか分からないらしい。中等部のそれも新入生だ。私とて高等部の校舎は行き来しているけど、未だに音楽室と図書室くらいしか把握できていない。……なんていうと、ゆかり先輩に怒られそう。
結局、お互い説明出来るほど学校に慣れてないねってことで、小さな学校案内は中止となった。
それから美笑の提案で、もっと私のピアノを聴きたいということで音楽室に移動することになった。音楽室なら高等部の校舎の方が良い。中等部の校舎にも音楽室はあるけれど、グランドピアノが置いてあるのは、高等部の音楽室だけなのだ。
たまにはオルガンや電子もいいけれど、やっぱりグランドピアノは格別だよね。音の響きも違うし、何より鍵盤の感触。重さや弾かれる強さはグランドならでわのものがある。
それに知ってる? ピアノの弦の張力は1本あたり70~80kg重あって、全部で200本は超えるから、全弦を合計すると20トン重を超えるの! それに耐えうるワイヤーがすごいのなんのって。ひとえにピアノというけれど、その構造は奥深く、それだけの力が使われていて初めて、あの音色を出している。
…そんな、私のピアノの知識を美笑に話すと、こくりこくりと相槌を打ってくれた。きっと、詩織さんに教えてもらってことも含まれてると思う。それを懐かしむような、そんな様子だった。
「そういえば、この”beautiful smile”って美笑にプレゼントってことで、詩織さんが作曲してくれたんだよね? 詩織さんはよく即興とかはしてくれたの?」
「…それは――」
数曲弾いた私は、ふと思いついて聞いてみる。詩織さんがいつ頃からピアノを始めていたのかは分からないけど、作曲したり即興をしたり、若くしてその才能は羨ましいと思った。本当に、天性のものだったのかもしれない。
「私が小学生の頃、なかなか友達が出来なくて……。たまに話す子は何人かいたけど、放課後一緒に遊んだりとか、そういうのは無くて。時々、男の子にからかわれて泣いて帰ってくると、いつもピアノを聞かせてくれて…。『目を閉じて。嫌なこと考えないで、私のピアノを聞いて。何も言わなくていいから』って言って。そうすると、不思議と落ち着いたんです。泣きたい気持ちも、辛い気持ちも、すっと無くなって」
「…すごいなぁ。なんだか、魔法みたいだね」
「……うん。弾いてくれる曲は、いつも違う曲でした。なんていう曲なの? って聞いたら、名前は無いよって。なので、多分即興だったんだと思います。お姉ちゃんのオリジナル曲。でも、私にはどんな曲も素敵で大好きでした」
「そっかー。その中に、beautiful smileもあったの?」
「…いいえ。それはもう少し後でした。私が9歳の誕生日の日……。誕生日プレゼントだよって言って、聞かせてくれたのがこの曲でした。詩織お姉ちゃん、すごく嬉しそうで。次のコンクールはこの曲を弾くんだって言って……。そして私に言いました。”どんな時も笑顔を忘れちゃダメだよ。辛いときはこの音を思い出してね”って。それで、録音して焼いたCDをくれました」
「詩織さん……。素敵なお姉さんだね」
「うん……。でも……お姉ちゃんが居なくなって、寂しくなって。この曲を聞くたびに泣いてしまうんです。不思議です。昔は胸の奥が温かくなって落ち着いたのに……。今は、辛いことがあると聞くようにしてるんですけど、どうしても哀しくて……。これじゃあ、約束守れてないですよね……」
「美笑……。よーし、それじゃあお姉ちゃんがこのグランドピアノで弾いちゃうからね!」
「あ、うん……。奏恵お姉ちゃんのピアノも、私大好き」
私は奏でる。もうこの曲は、心で覚えている。
ピアノは弾くもの。音は奏でるもの。私の音色は今、きっと想いが宿っているはず。
詩織さんが伝えたい曲。私が伝えたい曲。美笑が待っている曲。私が架け橋となって、紡ぐ音色。それが私のピアノなの。
美笑にとって詩織さんの存在は大きい、何よりも。だから、詩織さんの代わりにはなれないけれど、私が美笑を支えてあげるからね。
お姉ちゃんが、傍にいるからね――。
「……本当に、素敵な曲。弾いてる私まで惹き込まれちゃう。詩織さんは、すごいね」
「…………」
ふと、背中に軽い感触。何かが触れる感じがした。
すっと、腰から腕が伸び私のお腹の前で交差する。ぎゅ――。
「美笑……?」
「――――」
ぽたり。
美笑に後ろから抱きしめられる。背中の感触は、美笑の頭……おでこ?
「ん? どうしたのー? 美笑は甘えん坊さんだなぁ」
「お姉ちゃん……」
ぽたり。
背中に染みる。……いや、そんなこと知覚出来るわけがない。でも、背中越しに何かが沁みるのを感じる。涙――。
「…泣いてるの?」
「やっぱり、どうしても、涙が止まりません……。でも、不思議なんです。胸がすごく温かいんです。こんなの、初めて……」
美笑は私の背中におでこを当てながら、後ろから私を抱きしめて、泣いていた。
この曲は美笑にとって、すごく大きいものだった。何かとてつもない力を秘めている。
いや、それよりも……。声の感じが、おかしい……?
「嬉しくて、哀しくて。温かくて、辛くて……。目が熱い……涙が温かい……。涙が止まらない時はどうしたらいいの……? お姉ちゃん……」
「美笑……それは……」
「ごめんなさい。もう、これ以上は時間がないみたいです……。短い間だったけど、最後に奏恵お姉ちゃんに会えて良かった……。ありがとう……」
え……。時間……? 最後……?
え? 美笑? どういう、こと……。
「最後まで笑えなくて、ごめんね……。でもすごく、嬉しかったんだよ。学校案内出来なくて、ごめんね。ピアノの演奏会、素敵だったよ。花火、また見ようね。また泊まりにいってもいい? ヘアピン、ありがとう。私の二人目の、奏恵お姉ちゃん……」
「美笑、聞い――」
「お姉ちゃん!」
ぎゅっと、力が込められる。
「お願い。私が手を放しても、振り返らないで。私の足音が無くなるまで、そのままで……。奏恵お姉ちゃんのピアノを弾いてる後姿、見たいから……」
すっと……。
まるで、羽がふわりと舞い上がるように。私から放れる美笑。
待って……。最後って、何? どういうことなの?
もう会えないってことなの? どうして……。私は何か間違いを犯してしまったの? これから何かが始まろうとしていたんじゃなかったの?
美笑の笑顔を取り戻す。私が美笑のお姉ちゃんになって、これから二人で笑い合えると思ってた。
でも、時間が無いって……何の時間なの? それは、私では解決出来ないことなの?
待って……美笑……。何も分からないままで、お別れなんて、そんなのできない!
最後のその約束だけは、守れない……!
「っ…………」
それは数秒か、それとも数分か。
私が思考していたのが、どのくらいの時間だったか分からない。
でも、美笑はまだ、そこにいた――。
「……お姉ちゃん、約束破っちゃダメだよ。私のこんな涙顔見せたくなかったのに……。でも、ありがとう……。そんな奏恵お姉ちゃんが、私は大好きだったよ」
その表情は、笑顔だった……。とても安らかで、頬に光る涙が綺麗で。
とても愛らしく、可愛らしく。恥ずかしさと嬉しさで頬を染めて、目を細めていた。
それはきっと、美しい笑顔。それが、美笑の本当の……。
せめて、笑ってくれたなら……。
私の最初の願いが、今結ばれた。
手を伸ばそうとして、声を出そうとして、私は停止した。
「さようなら、奏恵お姉ちゃん――」
私の視界は滲み、やがて瞬きひとつ。
涙が頬を伝い、雫を作る頃。美笑の姿はなくなっていた――。
ゴールデンウィーク4日目。
私は昨日、美笑に別れを告げられた。あれから美笑の姿を見ていない。
職員室に戻ってゆかり先輩にそのことを話したら、先輩も言葉を失っていた。
今日は朝から雨。天気は私の気分を晴れやかにはしてくれなかった。それでも昨夜は遅く、奇跡的に雲は晴れ星空が広がったという。
私は気分ではなかったので空は見上げなかったけど、みずがめ座流星群が極大になったそうだ。そういえば、美笑は見にいったのかな……。
傘を差して一人で歩く道。今日は隣に先輩は居ない。いつもの待ち合わせ場所に、いつも私より早く来る先輩が珍しく居なくて、結局遅刻ギリギリまで待っていたけど、来る気配が無かったので先に行ったのかと思い一人で歩いている。
天気も雨模様。先輩も居ない。お世辞にも清々しい朝とは言えなかった。
心に引っかかるのは、昨日の美笑の言葉。どうして、別れを告げなければならなかったのか。これから私が詩織さんの代わりに姉になる決意をした。美笑もこれから先の未来が明るいものだと感じてくれたと思った。実際、美笑も私を姉と慕ってくれた…。
それなのに、突然の別れ……。分からないよ、どうして今なの……?
これからもっと、たくさんピアノを弾いてあげたかったし、甘えさせてあげたかったし、美笑に笑顔が戻るように毎日傍にいるって自分に誓ったの。姉になるって決めていたの。
それがこんなのって……。もう、美笑には会えないの……?
いくら自問しても答えは出ない。その答えは、美笑にしか答えられないのだから。
よし、今は考えるのはよそう。早く学校にいって、先輩に相談しよう。うん、もう会えないなんてことは、無いんだから。
しかし、職員室に入った時。先輩が居てくれたことの安堵と、それ以上に、ひどくその背中が小さく見えて、私は声を掛けるのを躊躇ってしまった。
「……どうして……」
先輩はポツリと言葉を漏らしながら、両手で顔を覆っていた。
「……先輩? おはよう、ございます……」
「あ……。奏恵……」
生気が失われていた。先輩のこんな表情を見るのは初めてだった。
次の瞬間、朝から拭えなかった不安が一気に現実のものとなる。
「奏恵、落ち着いて。よく聞いて欲しいの」
「……あの、先輩」
「ごめん、聞いて。私もまだ混乱してて、あなたの質問には答えられそうにないから。あのね――」
先輩は私の両手首を押さえて、それでも言葉を躊躇って。
そして、告げた……。
「美笑ちゃんが、自殺しちゃったの……」
「……え…………」
私の頭は、真っ白になった――。
この日のことはよく覚えていない。
気がつけば、私は教室の窓から雨空を見上げて思考していた。
どうして美笑は、自殺をしてしまったんだろう……。確かに過酷な環境にあった。しかし肯定されるべき自殺なんてあってはならないと思う。でも、それでも当人が選んでしまったのならそれは尊厳死なのだろうか。
いいえ、それはきっと生きている私の傲慢視。どうして? と、嘆くのは残った者の権利だけれど、どうして? と、訴えるのは逃げたいからだ。私に非は無かったという保身。
昔の私はまさにそれ。幸枝を救おうともせず、保身に走り、幸恵の死から逃げていた。でもすぐ気づいたの。それは誰でもない、私の過ちなんだって。
だから私は決別した。今度は同じことを繰り返さないように、美笑の笑顔が取り戻せるように、尽力したつもりだった……。
それでも、私はダメだったの……? 美笑の姉であろうとすること。笑顔を取り戻せるように傍にいること。伝えたいことを、伝えていくためにしたことだったはず。
ごめん、ごめんね……分からないよ。私は、間違っていたの?
私はまた、救えなかったの……? 結局は、同じことを繰り返してしまったの?
……違う、と思いたい。だって美笑は確かに別れの言葉を告げたけど、笑って、ありがとうと言ってくれた。あの瞬間、美笑は自殺を覚悟していたとは思えない、思いたくない。
私たちは同じ空の下にいたはず。同じ空を見て、同じ音を奏で、同じ時間を過ごしていた。
それは決して長い時間ではなかったけれど、それでも優しくて、温かくて、愛しい時間だった。でも美笑には、空は青く見えなかった……?
ううん、それだけは違うと言える。表情は笑顔だけじゃない。そして美笑の目は輝きを取り戻していた。だから、あの瞬間……美笑の中で別れの決意とは別に自殺の決意は無かったはず……。
それじゃあ、自殺でないなら何かの事故……?
さっき、ゆかり先輩はとあるビルからの飛び降り自殺だって聞いたけど、自殺でないなら、どうして美笑はビルの屋上なんかに?
……そういえば、昨日はみずがめ座流星群が極大の日。それに美笑、言ってなかったっけ……。約束の日、って……。
何か大切な約束があったのかもしれない。詩織さんとの? 他の誰かとの?
分からない、分からないよ……。本当に自殺だったの? それとも、なにか予期せぬ事故に巻き込まれてしまったの?
ビルから落ちてしまった美笑。それが美笑の意思だったのか、それとも違うものなのか。
近くにいた男性が救急車をすぐ呼んだらしいけど、ダメだった……。
美笑……。
私は困惑で号泣することも出来ず、梅雨の雨のように静々と、頬に涙を流すのだった……。
ゴールデンウィーク5日目。追悼、ネガティブグッバイ。
私とゆかり先輩は、お通夜に参列した。結城家と石川家と、それから親類だけの厳かなものだった。
ゆかり先輩は私に、あなたはここで待っていてと言って、一人で中へ入っていく。私はお香典を渡し、少し離れたところから掲げられた美笑の写真を見ていた。
昨日最後に会っていたのは私のほうだから、先輩は眠っている安らかな顔ではなく、昨日の顔を憶えていて欲しいという気遣いだったのかもしれない。私はそれを享受する。
憶えてるよ、ずっと。忘れないから。あれが本当の、美笑の笑顔だった……。
帰宅後、私はそれとなくピアノの前に座った。
数日前、このすぐ隣に美笑は座っていて、懐かしみながら思うこともあっただろう。私を見上げ、私のピアノを聴いてくれていた。
あの時、beautiful smileと再会出来たんだっけ……。衝撃的だった、あの旋律。詩織さんの調べ。それがまだ、たった数日前の出来事だったのだ。
数年前に聞いた旋律そのままに、私を虜にした。身体を駆け巡る旋律が、私の手を通して詩織さんが弾いてくれているような気がして、不思議な感覚だった……。
思えば、美笑と出会ったあの日に全ては始まっていたのかもしれない。
私が道に迷ったこと、美笑がたまたま廊下を歩いていたこと、それは運命的なものだった。詩織さんが巡り合わせてくれた、邂逅の始まり。
私は忘れないよ、ずっと、ずっと……。憶えている、美笑のことも、詩織さんのことも、幸枝のことも……。
もちろん、居なくなってしまったのは寂しい。本当は今すぐにでも駆け寄って、抱きしめて、もう絶対離さないんだからって言いたい。そしてずっと続いていくの、私と美笑の物語が……。
こうなってしまった今、これを言うのは不謹慎に思われるかもしれないけれど……。
本当に自殺だったのか事故だったのかも、未だに分からない。だけど、死は受け入れるもの。いつまでも未練を残していては、美笑の笑顔が陰ってしまう。
だから…………。
ネガティブグッバイ、私の最愛の美笑。
美笑の笑顔を忘れない。幸枝の涙を忘れない。二人は私の中で、生きている……。
これからも、ずっと……。生涯を通して記憶に留めていこうと思う。
忘れないこと、それが私の……。
自然と、鍵盤に手が置かれ、そして奏でる。紡がれる旋律は、beautiful smile。
これは鎮魂歌(レクイエム)でも哀悼歌(ネーニエ)でもない。
これが私の……追想曲(カノン)。
私は奏でる、いつまでも、この先ずっと……。
それが私の伝える物語。……ううん、違う。
それが、私たちの奏でる物語……。いつか誰かに話す時が来たら――。
ねぇ美笑? 今度の校内コンクールで私がピアノを弾くから、詩を歌ってよ。
…恥ずかしい? 大丈夫大丈夫、美笑の声ってすっごく綺麗だから。私が保証する!
目指すは姉妹ユニット、CDデビュー!
ねぇ美笑はさー、好きな子とかいないの?
年頃なんだもん、気になる子とかいるんでしょ? お姉ちゃんにも教えてよ。
……え? わ、私!? 本気の本気で? そ、そりゃ私も美笑は好きだけど……。
じゃ、じゃなくて……!
ねぇねぇ、これはどうかな美笑! 向日葵の花飾りー!
…ちょっと大きいかもって? う~ん、逆にアンバランスなのが良いというか……。
それじゃあ、ほら。これでお揃い! これならいいでしょう? うん、決まり!
ごめん美笑! 本当にごめんって……。怒らないで許してよ……。
…アイス食べたい? いいよ。…あのぬいぐるみも欲しい? うん、いいよ。
あと一緒に寝てくれないと嫌? んもぅ、可愛いなぁ! この甘えん坊めぇ!
美笑ー? あれ、美笑いないのー?
って、おぉ!? それは私の高校の制服! そっかぁ、美笑ももう高校生かぁ。
それ着て登校してみる? あはは、さすがにダメか。……え? 私の香りがする?
ちょ、ちょっと何言ってるの! もう脱いで、って逃げるなー! こらー!
…ん? どうしたの、美笑。ピアノを弾いてみたい? うん、いいよ。
それじゃあここに座ってみて。最初は右手からドレミファソラシド弾いてみよっか。
あぁ、ファはね、親指を内側に入れて……そうそう、そうすると高いドまで行けるの。
次は左手なんだけど、今度は親指の次に中指を被せて……。
続いていく……。私と美笑の物語が続いていく……。
美笑の笑顔が戻り、日々がより一層晴れやかな毎日。望んだ日常がそこにはあった。
私たちは記憶していく。日々たくさんのことを。
そこには忘れたいこと、忘れたくないこと。思い出したいこと、思い出したくないこと。大切なもの、大事なもの。蓄積され、淘汰されていく。
記憶は遠い順から思い出に変わっていく。思い出はやがて、想いへと昇華される。
私の想いは、ずっと心の中に。もしも誰かに話すことがあったなら、私は伝えたい。
私たちの物語は、続いていると……。
願わくば、この物語を読んだあなたの心の隅に、記憶して欲しい。そしてどうか、美笑を救って欲しい。
もしも許されるなら、私の物語から何かの教訓を。同じ過ちをもう誰も、繰り返さないように……。
弾き終わった私の頬には、涙が伝っていた。
左には幸枝が居て、右には美笑が居て。私の両手には詩織さんが手を重ねてくれている。
温かい涙だった。それは止まることがなく、顎に雫を作る頃。後ろからゆかり先輩が抱きしめてくれた。
そして私は、声を上げて泣いていた……。
私はようやく知ることが出来た。
幸枝の死から、美笑の死を通して、私はとても大切なことを学んだ。
私はとても恵まれている。私はとても幸せで、嬉しさが溢れてくる。
本当の意味で、私は一人じゃない。独りじゃないんだ……。
私が拾い集めた枝は、確かに幸せだったよ、幸枝……。
ありがとう、みんな……。
それから、ごめんね。救い出せなくて……。
私の物語は、これからも続いていくんだよね……。
さぁ、奏でていこう。
これから先も、ずっと……。
Ende.
Section 3 俺の場合。
「美笑ッ!!」
俺は駆け出した。手遅れかもしれない。届かないかもしれない。
それでも、俺はやっと気づけた大切なものを手放したくなかった。
それが例え、俺自身の過ちだったとしても。
それが例え、彼女の過ちだったとしても。
それがたとえ、終焉を知らせる鐘の音だったとしても……。
せめて、笑ってくれたなら――。
俺は空に飛び出して、落ちる少女の身体を目指しただろう。ただ強く抱きしめて、彼女との約束を果たしただろう。
しかし、少女の目はもうすでに、閉じられていた……。
「っ……」
美笑が俺に笑いかけてくれることは、ついに無かったのだ。
俺は、間に合わなかった……。
彼女との約束も守れず、少女の笑顔さえ導くことも出来ず、約束の日を迎えてしまった。 俺は当然の報いを受ける。少女の時間は有限。限りがあるから命は咲き煌くんだ。
死は、いついかなる時も背後に付いてまわる。たとえ症状が軽くとも、たとえ性急なものでなかったとしても。
その認識の甘さが今日を招いた一つの原因。俺と、そして美笑の過ちだった。
それからもう一つ、俺は大事なことを忘れていた。
約束――。詩織との、最後の約束を……。
今日この日、俺たちは肩を並べて空を見上げているはずだった。そんな未来があったはずだった。
それが詩織の死により閉ざされ、俺の世界も閉ざされた。行き場を失った美笑の心は、虚空に放り出され、壊れてしまった……。
きっかけは何だったのか、今ではもうきっかけでしかない。壊れてしまったものは、やがて朽ちるのを待つしかないんだ。癒せやしない……。
それでも……。だからといって……。
支えになることは出来たはずなんだ。かつて詩織が、俺を救ってくれたように……。
落ちていく、美笑の身体……。
俺は身を乗り出して、手を伸ばして……。涙が一滴、零れ落ちた。
その雫の中に、俺は走馬灯を見ていた……。
中等部2年の春――。ある日の放課後。
「…私は、君みたいな人。嫌いだから」
初めて彼女と話したのは、この時だったと思う。
軽蔑されるのは慣れてる。今更気にすることじゃあない。ただ、一つ補足をするならば俺は不良生徒でも、問題児でもない。単に、全てにおいてやる気が無い男だった。
それはともかく、この時俺は彼女の声にすごく惹かれたのを覚えている。
例えるなら、それは音。まるで音楽を聴いているかのように、彼女の発する言葉は旋律のようだった。楽器で言うなら……そう、ピアノのようで。
とはいっても、俺は音楽にそれほど関心のあるほうではないし、ましてや絶対音感なんて持っているはずもない。聞いた話によれば、絶対音感を思ってる人はこの世界のあらゆる音を、音階で聴き取ることが出来るらしい。
彼女の声が音階で何にあたるかなんて言えないが、すごく綺麗だと思った。
そんなある日の放課後、俺は職員室へ行く用事があって普段より遅くまで校舎の中にいた。空が夕暮れに染まる頃、廊下を歩いていると、ふとしてメロディが聞こえてきた。
それは、音楽室からだった。
ガラス窓から中を覗くと、弾いていたのはあの時の彼女だった。
名前は確か、石川詩織。先日の一件以来、俺はどうも彼女に嫌われているらしい。だから、俺は中へ入らずにしばらく廊下越しにその演奏を聴いていた。
「そんなところに座ってないで、入っておいでよ。別に気にしないから」
演奏が終わるとドアから顔を出した彼女。どういうわけか、俺がいるのはバレていたらしい。俺は一度断って帰ろうとしたのだが、聞いてくれる人がいたほうがいいからと行って、ちょっとだけ付き合うことになった。
その様子から、俺は心底嫌われてはいなかったのだと少しホッとした。
それからしばらく、本当に気にしていないかのように、彼女は数曲演奏していた。
俺は演奏が終わると乾いた拍手を送りながら、うまいなーとか、絶対音感とかで弾くのかとか、素人丸出しのことを聞いていた。
「絶対音感なんて、そんな大層なものじゃないよ。初見奏だって、慣れれば誰だって出来るもの」
そうあっけらかんとして答える彼女は、さも普通であるかのように答える。
「ソルフェージュ」
ふいに意味不明な単語を呟く。
「ソルフェージュ。私のはただ楽譜を詠んでるだけ。譜面を見るだけでこの音はこう出して欲しいとか、この部分は楽しく弾いて欲しいとか、それだけだよ」
俺は後に、それが彼女が持つ独特の感性であったことを知る。それは音楽を学ぶ人が通る道であり、基本的な知識ではあっても、彼女のそれは彼女だけの特別なものだったのだ。
「だから、絶対音感じゃないって。そういう苦手意識っていうか、オレには出来ないーっていう考え、私嫌いって言ったよ。人間やれば何だって出来るんだから」
そのときの俺は、どんな顔をしていただろう。きっと腑に落ちない顔をしていたに違いない。マイナス思考のネガティブ男だったからな。
「どんなプロの人だって、国宝級の偉業を成し遂げた人だって、私たちと同じ人間なんだよ? どんなことだって、人間諦めないことが肝心なんだから!」
そういって詩織は、得意気に笑ってみせた。
……そうだった、詩織はいつも前向きで、俺を導いてくれていたんだ。
高等部3年の春、現在―――。
今はもう過ぎ去ったあの日から、俺の時間は止まっていた。
詩織が交通事故で亡くなってから2年が過ぎたある日、つまり去年の春の出来事。俺の物語が再び動き出す……。
俺の家は、お世辞にも順風満帆とは言えなかった。俺が物心ついた頃には両親は離婚していて、父親のことは殆ど覚えていない。俺は母親と暮らしていたが、この性格が災いしてか面倒は全て押し付けて、母親との距離は開くばかり。いつしか会話というものも聞こえなくなり、同じ屋根の下にいるのに住む世界が異なってしまった。
それでも、朝と夜のメシだけは用意してくれていた。温めて食べてください、という置き手紙がいつも置かれていて、それがひどく俺の胸を突き刺した。
初めは決して、距離を置いていたわけじゃない。邪険にしていたわけじゃない。でも俺はなぜだか、全てのことに関心を持つことが出来なかったのだ。家族でさえも、親でさえも、会話でさえも……。ただ、詩織と出会うまでは。そして、詩織が死ぬまでは。
そうして素っ気無い態度しかしない息子に、母親も無理に付き合うことをやめたのだ。
そんな息子には相談するわけも無く、いつの間にか母親は知らない男と縁があったようだった。
母親が再婚し、父方には連れ子がいた。俺にとって家族なんてものは写真の中だけの飾りものでしかなかった。だから、再婚しようと俺には関係ないと思っていたんだ。
しかし、俺は言葉を失った。生き写しなんてものが、存在するのかと目を疑った。
彼女は石川、詩織……ではなく、美笑と名乗った。紛れも無く、詩織の妹だった。詩織から話はよく聞いていたが、実際に会うのは初めて。それがまさか、姉妹とはいえ瓜二つだったのだ。
俺は驚愕と混乱で、頭がどうにかしてしまいそうだった。初めは、どうして詩織がここにいるんだと我を失いそうになったが、目の前にいるのは美笑という妹で。しかも今日から、血縁関係はなくとも俺の妹になるなんて……。
俺はこの現実をどう受け止めればいい? 詩織に似た少女とどう向き合えばいいというのか。詩織の面影を重ね、それが嬉しいことなのか、哀しいことなのか分からず、俺は美笑を直視することが、それ以来出来なくなってしまった。
そう、俺は受け止めることが出来なかったのだ。詩織は死んだ、この子は美笑という詩織の親愛なる妹。だから、違うんだと、割り切ることが出来なかった。
思い出してしまう、どうしても……。
面影を重ねてしまう、どうしても……。
そうして接していくことは、美笑という子にとって嬉しいことでは決して無い。いつか俺は詩織だと思い込み、詩織として認識してしまう。いつかきっと、詩織でないことに気づき狂ってしまう。
そんな時、美笑はどう思う? 自分は美笑として見られていない。姉として見られていたんだと、自身の否定を余儀なくされる。そして、自分の存在意義を自問するだろう。
でもその答えはすぐに、たどり着く。私は私、美笑は美笑。姉は姉、詩織は詩織。それはごく自然な解答に他ならない。そうして美笑は、自己を確立し自立するだろう。
けど、俺は……。そうすることが嫌だったのだ。俺の幻想も、美笑にそう思わせてしまうことも。俺は過去に甘えたままで、生涯苛まれ続けるだろう。詩織はもう居ないんだと、2年経った今でも、受け止められずにいるんだ。割り切るなんて、出来やしない……。
思考の迷路。俺に出口は、見つけられなかった。
しかし、確かに俺の物語はこの時動き出していた。現実から、美笑から目を背けるという小さな綻びが、大きな禍を生むことを知らずに……。
ゴールデンウィーク1日目。
美笑が中等部に入学してから早1ヶ月。朝一緒に登校することもなく、会話もなく。
あれから俺たちが変わったことは、特に無い。結婚して何かが変わることを期待していた訳ではないが、逆に悪くなることは想像していなかった。
初めは母親と再婚相手の男は仲がよかった。しかし、次第に喧嘩をすることが多くなり、そのとばっちりが美笑にいくこともしばしばだった。それもしばらく続くと、今度は俺も居場所がなくなり、家庭はまた崩壊寸前に追い込まれていた。
そうして親たちも疲れてしまい、気がつけばまた、違う世界に子と親がいる空間が出来ていた。俺の母親は美笑に関心を失い、美笑の父親……ではないらしいが、俺に目も合わせなくなった。同じ屋根の下にいるのに、接点が無い。それを家族だなんて、言えるだろうか……。
そんな生活が拍車をかけて、俺の性格も昔に逆戻りしている。全てにおいてやる気が無い。部活にも入らなかったし、勉強も気が進まない。クラスのイベント事は全て断り、積極的に誰かと交流をすることも億劫だった。
かといって、先生から目を付けられるような不良生徒ではない。ただ、やる気がないだけなのだから。何をする気も、起きなかったのだ。
それでも、学校の行事には強制的に参加しなければならない。億劫だったが、そとはかとなくこなすことは出来た。別にやる気がないだけで、クラスメイトからいじめを受けることもなかったし、積極的ではないが話しかけられもする。
あるがままに、そとはかとなく。それが昔からの俺のスタイルだった。
そんな俺は気がつけば図書委員なんかになっていた。この学校は生徒数もさることながら、校舎が無駄に広い。その中でも図書室はやけに大きい。
このゴールデンウィークも、図書室の管理として交代で当番をしなければならない。俺は特に用事というものが無いので、家に居るよりはマシだと思い承諾した。
とはいえ、交代とは名ばかりで他の連中は出掛ける用事やその他諸々の諸事情は常である。図書室の開放はこのゴールデンウィーク中、午前中の9時~12時までとはいえ、朝から出掛ける人が殆どなのだろう。5日間の日程は組んであるが、用事があるからといって俺に代わってくれと申し出てきた。俺は断る理由もないし、静かに一人で居たほうが居心地がよいので二つ返事で承諾していった。
そんなわけで。今日も朝から俺は図書室に来ていた。
「おはよう、翔くん」
「おはようございます、縁センセ」
顔を出したのは現国の縁先生だった。
俺が高等部に進級してから、現国の担当は縁先生になった。中等部までとは違い、高等部になれば教える幅もレベルも違う。先生の入れ替えもありきだ。
そういった担当教師の入れ替えの中に、現国の担当も入れ替わりとなったのだ。
先生は俺たちと歳が近い分、他の先生よりは融通の利く人だ。さすがにテストの点数を誤魔化してはくれないが、勉強以外にも色々な話をしてくれるみんなのお姉さん的存在である。
「翔くんはいつも、退屈そうな顔してるね」
「……物事に、いちいち理由を求めてたら疲れるだけです」
「まぁ、それはそうなんだけどさ。好きなこととか、やりたいこととか。趣味はないの?」
「無いです。俺はただ、何事もなく平和に過ごせればそれでいいんです」
そう、俺はただ、何事もなく暮らしていければそれで良かった。
「ん~、味気ないなぁ。平和っていうのは大事だけど、ありふれた日常の無意識の享受は精神を疲弊させる。身体の成長が完成する前に、中身がお爺ちゃんになっちゃったらどうするの?」
「退屈で、ありふれていて、何事もなく歳をとって。それが俺の生き方なんじゃないかって、最近そう思うんです」
「自覚があるのならいいのだけど。今の高校生活、生涯に1度だけの日々。それを君なりに享受した結果が、ありふれた日常なのね」
「はい。日常ってのは、日々、常にありふれた生活のことです。それが時に何かを見えなくしたり、逆に何かを気づかせてくれたり。それが大事なことなんだって思うのは自分次第だと思ってます」
「あら、今日は哲学的なこというのね。朝から黄昏てたのかな? ううん、お姉さんそういうの好きだけど」
「お姉さんって……。センセ、ここは学校ですよ」
「…なんかどこかで聞いた台詞だわ。茶化しっこなしよ」
そういって先生は、スッとスカートを調えて座り直した。
「日常っていうのはね、こういう見方も出来るの。常に、日々変化する毎日。一日たりとも同じ日はやってこない。常に変化し続ける。言い換えれば、変化する日常。逆にするだけで、意味も逆になる」
「表と裏ですか?」
「そういうこと。陰と陽、表と裏、上と下。物事は常に2面性である。その時、表であったとしても、常に裏は存在しているの。それを表だと”思い込んでいる”と、いつか裏返ったときに大変なことになるよ」
「俺が、思い込んでいると?」
「君はさっき、何事もなくって言ったね。でもそれは、ある事が起こった後に見出しただろうってことは分かるの。だって、私はずっと前から君と、彼女のことは知っているから」
「……」
「何事もなく日常が続いていたら、今こうして話していたのは私ではなく彼女だった。私もそれを遠くから見て祈っていた。でも……」
「縁先生。もう、いいんです。起こったことは変わらないですから。俺はもう、今の日常だけでいいんです」
「それなら、どうしてなの?」
「え?」
「彼女の死を受け止められたなら、あの子のことはどうして受け止めて上げなかったの?」
「……」
先生のいうあの子とは、一人しか居ない。だからこそ、俺は言葉を返せない。
「私はこの偶然には、詩織さんの想いを感じるの。美笑ちゃんは悲しくも数奇な人生を歩むことになってしまった。だけど、君のところなら安心だと思って、他でもない翔くんの傍に置いてくれたの。でも、君は……」
「……美笑は、俺の妹じゃ……ありません。詩織の、妹です……」
「っ……」
先生は言葉を失う。俺の口からこんな直接的な言葉が出るなんて思ってもみなかったのだろう。
俺自身、引きずっていると言われれば否定しない。今はまだ、整理し切れていないのだ。
「……これから言うことは、教師としてじゃなく詩織さんの友人として言うわ。……正直あなたには、幻滅した。あなたは忘れちゃったのね……。今、美笑ちゃんの表情に覇気が無い。そう、忘れちゃったみたいにね。昔から大人しい子だっていうのは詩織さんから聞いているよ。でも、決して笑顔の見せない子ではなかった。今の美笑ちゃんは、度合いは分からないけれど、うつ病なのかもしれない。それが病気によるものなのか、本当に塞ぎ込んでいるだけなのか、それは傍目からでは分からないけれど。でも、だからこそ支えが必要なの。他でもない、あなたのね。きっと、詩織さんもそれを望んでいたはずだよ。……お願いだから、これ以上美笑ちゃんに” 悲しい思い ”をさせないで……」
「……」
そして先生は、図書室を出て行った。
また図書室を静寂が打つ。誰も来ない、一人の空間。まるで、縁先生の言葉が木霊しているかのように静寂と戯れる。いや、それは俺の頭の中でだけかもしれない。
縁先生の言葉は俺を椅子に張り付けにした。太い杭を打ち込むかのように、俺は頭を、胸を射抜かれる。出来るのは思考だけ。
俺は、美笑と向き合うことを恐れている。そして、俺は何かを忘れてしまっている。それを思い出せない限り、美笑と向き合うことは出来ない気がする……。
しばらくして俺は杭を抜き、ある本を探す。それを読み耽っているうちに時間がやってきた。
12時ジャスト。閉館の時間だった――。
校庭に出ると、校旗を上げる支柱の下に人影を見つけた。
…美笑だった。休みの日はお互い家に居ないが、美笑はこうして学校に来ているのだろうか? 見たところ人を待っているとか、そういう風には見えない。
だがその横顔を、俺はしばらく見つめていた。詩織と似ている、瓜二つなくらいに。当たり前なことだが、あと2年もすれば詩織と同じ歳。姉妹であるがゆえに、あの頃の詩織のように綺麗に、成長するのだろうか。あまり声は聞いたことはないが、詩織ほど通る声ではないにしてもそれに近いものを感じたことはある。
……やめよう。今さっき縁先生に言われたばかりだ。俺は美笑に詩織を重ね過ぎる。
うつ病、か……。世間一般には鬱の気質は誰もが持ちえている。人間誰しも落ち込んだり塞ぎ込むことがあるように。それをうつ状態と呼ぶかどうかは、今の俺には判断出来ない。その横顔からは、汲み取ることは出来そうに無かった。
他にも、躁鬱(そううつ)病というのもあるらしい。これは躁状態――気分が高揚している――と、鬱状態――気分が落ち込んでいる――を交互に繰り返す病気である。でも、美笑に躁状態があるところは見たことは無い。
となると、やっぱり鬱病の方が可能性があるのだろうか……。
その時、突然美笑が咳き込む。その激しさに、思わず駆け寄ろうとして足が止まってしまう。なぜ躊躇う必要がある? それは俺の脚に聞きたい。なぜ考える必要がある? それは俺の心に聞きたい。
俺の心と身体は、切り離されてしまったのだろうか……。駆け寄って「大丈夫か?」と声を掛けたい心と、それを拒絶して動こうとしない身体。そんなもどかしさを抱えながら、俺はただ何をするでもなく、美笑を遠くから見ているだけだった。
しかし美笑の発作も、俺の短い思考の内に治まっていた。今は胸に手を当てて、深呼吸を繰り返しながら、呼吸を整えている。そんな美笑の様子に、胸を撫で下ろす自分がいる。
……。あくまで、美笑の力で立ち直っただけだ。俺は何もしていない。何もしなかった俺が、傍目から何事も無くて良かったなどと思うこと自体おこがましい。
矛盾。……矛盾螺旋。人の思考はいつだって矛盾している。助けたい、関わりたくない、動きたい、近づきたくない、ほっとした、何もしていない、手を伸ばしたい、俺はその資格が無い。
単語の羅列は矛盾螺旋そのものだった……。
中等部2年の夏――。蝉時雨の賑わう頃。
「どうしたら、あの子笑ってくれるかなぁ……」
詩織のネガティブな一面を見たのは、考えてみればこの時が最初で最後だったように思う。前向きな彼女が、そんな一面を見せること自体珍しく、あの日のように周りにはポジティブシンキングを振りまいている。
どうやら彼女の悩みの種は、妹のことらしい。俺は特に受け答えをするわけでもなく、詩織があーでもないこーでもないと、呟いているのを聞いているだけだ。その間、ふとメロディが浮かぶと、ぽろん、ぽろん、と旋律を響かせる。
俺にとってはその音は響いているのだが、当の詩織にとっては心に響くものではないらしい。本人が納得しないのでは意味が無い。素人の俺が口を挟んでも、参考にもなりはしないだろう。
「ところで、今日も来たんだ結城くん。暇なの?」
今日”も”といえば、分かるだろう。俺はあの日から、音楽室に通いつめている。入室の許可は貰っているので、演奏の邪魔をしないように静かに席に座っていた。
だからといって何かが変わることもなく、事も無げに詩織はピアノに向き合って俺のことはしばらく気にしない。俺もただ、詩織のピアノを聞いているだけ。そんな日々が続いていた。
「まぁいいけど。私以外、音楽室にはあんまり人来ないからね。この学校には吹奏楽部も、軽音楽部も、合唱部も無いし。音楽の先生もみーんな男の先生。これだけ生徒がいるんだから、一人くらい音楽に興味もってくれてもいいのになぁ。あー、ピアノが弾ける美人な先生が欲しいなー」
詩織の憂鬱は妹だけでは無いらしい。確かに中高一貫で人が多いにも関わらず、音楽系の部活が存在しない。以前はあったのかもしれないが、今現在、俺たちが入学してからは愛好会すら無かったのだ。
最初は詩織も同志を募ったこともあったのかもしれない。しかし、今の言葉聞く限り空振りだったのだろう。
以前どこかで聞いた話だが、音楽系の部活ではないがある部活を新規で立ち上げたいという有志諸君がいた。しかし、学校も生徒会という組織がある。部活として立ち上げするには、まず部員を最低5名確保。そして顧問の確保。部室とか活動場所の確保。それらが最低条件である。
だが、それだけではない。前述したとおり、生徒会という組織の承認を得られなければ成立しない。しかもその承認というのは、全校集会を経て投票制度を採用している。さらに、一気に部活とはいかない。最低人数が5人というのは愛好会レベルであって、部活として成り立たせるには20人必要なのだ。
重ねて言おう。愛好会から部活には昇進はしない。その間に同好会という最低人員10人という中間点が存在する。
つまり、最低条件をクリアし愛好会を発足。さらに生徒会の承認を経て同好会に昇進。そしてさらに生徒会の承認を経て部活へと昇進する。その間なんと、3年を要してしまうのだ。なぜなら、新規部活動の導入という議題は新年度の春に1度しかないからだ。
ここまで聞けば、学校で新たに部活を作るというのがいかに大変で、根気のいることか分かるだろう。
しかし、俺たちの代でそれをやってのけた人たちがいる。先ほど言ったのは女子サッカー部のことで、ついに中等部3年の今年に女子サッカー”部”として承認された。それが最近のなでしこ影響であることはいうまでも無い。
……と、長くなってしまったが、詩織はそのことを知っている。俺がそれを語るのは蛇足だった。
本来詩織は、自由にピアノを弾きたいだけで部活動として発足したいのでは無いらしい。
彼女は早々に切り替えて、こうして毎日音楽室でささやかな演奏会を開いているのだ。
「結城くんに聞いてもしょうがないんだけど、何か良いメロディ無い?」
俺に聞かれても困る。音楽の心得なんて皆無だ。せいぜい、ドレミファソラシドを口で言うのが限界だ。
「ははっ、そうだよねー。ごめんごめん」
そういって詩織は苦笑した。
その時ふと、俺は詩織の妹のことが気になった。物事に無関心な俺が、そんな興味を抱いたことに驚いたが、それが自然と口をつく。
「ん? 私の妹の名前? みえ、だよ。美しい笑顔って書いて、美笑」
美笑……美笑……。美しい、か……。
美しいものはいつまでもそうあって欲しいと思う。でもそれは飾られたものじゃなく、きっと心に残るものなんだ。思い出とか感情とか、自然もそうだ。あらゆることは観測者によって美しくも、汚らわしくも映る。それが笑顔なら、なおさらだ。大切な人の笑顔は、いつまでも美しいままだ。
「……へぇ。意外、かな。普段は、オレは興味ないって言ってる人が、心ではそんなこと考えてるんだね」
あ、いや。何を言ってるんだ俺は。
俺が何かに感銘を受けたことなんて、これまで一度も……。
「ううん、私もそう思う。うん……そうだよね、うん……」
詩織は何度か頷いてから、目を閉じる。
……? しばらくそうしてから、詩織はスッっと目を開けた。俺は「何か思いついたか?」と声をかけようとして、それを遮る様に詩織は……。
「ありがとう」
と、初めて俺を真っ直ぐ見て笑った。
そして流れ出した旋律。その曲は今まで聞いたことが無いくらいに美しい演奏だった。人を惹きつけて、魅了してやまない、美しいまでに情感の込められた音だった。
「……出来たよ、美笑。曲名は”beautiful smile”これを誕生日プレゼントにしよう」
詩織の満足そうに微笑むのを見て、俺はいつもの詩織に戻ったのを感じた。
一息ついて、詩織はふとこんなことを話し出した。
「ねぇ。結城くん? 魔法って、信じる……?」
え? 魔法? それは今まで出会ったことがないから、なんとも言えないな。
「ははっ。こんなこと言うと夢見がちな人って思われるかもしれないけど……。私ね、ピアノって魔法だと思うんだ。元気になれる。前向きになれる。人を笑顔に出来るって、そう思うの。そういうの、幸せなことじゃない? それはきっと、ピアノの魔法なんじゃないかなって。……うん、ひょっとしたら私がピアノの魔法に掛かっちゃったのかなぁ」
詩織は愛しそうに鍵盤を撫でる。
優しく、優しく……まるで、魔法に触れているかのように。
うっとりしているかのように頬を赤く染めて。艶やかなその表情を見た瞬間、俺の心臓は一つ、大きく脈打った。
俺はこの日、今はもう過ぎ去ってしまったあの日。
俺は彼女に、恋をした……。
高等部3年の春、現在――。ゴールデンウィーク2日目。
本日の日課、午前中の図書室管理の仕事は終わった。職員室に鍵を借りにいった時、縁先生は挨拶だけ返してくれたが、俺のほうを見ることは無かった。その後も、縁先生が図書室を訪れることはついに無かった。
とりあえず、家に帰って昼飯でも食べようと思い帰路につく。
その途中、商店街で美笑の姿を目にした。美笑は誰かと話しているようだ。見たところ俺の知る男ではない。俺と歳は近そうだが、落ち着いた物腰は成人しているようにも見える。
美笑も積極的に発言することは無さそうだが、その男を嫌悪しているわけではなさそうだった。……まぁ、美笑がどこの男と接点があろうと、俺は関与しない。
気になったのはやっぱり美笑の表情だ。縁先生の言葉が頭を過ぎる。
”美笑ちゃんは、うつ病なのかもしれない”
美笑の表情を見る限り、あまり感情の起伏はない。表情の抑揚もない。ただ淡々と受け答えをしているように見える。あぁ、俺も似たようなものかもしれないが。
俺は縁先生の言葉が頭に残っていて、昨日今日と図書室でそれ関連の本を読み漁っていた。うつ病に関してだったり、人間の感情に関しての本だ。
うつ病とは、俺が持ってた知識では気分の落ち込みのことだと思っていた。おそらく世間一般でもそうかもしれない。しかし、それは見られる症状の一つでしかない。
うつ病に見られる症状では例えば、最初に上げたように気分の落ち込み、それから興味の喪失、食欲の減退や増加、外出や人間関係を億劫に感じたり、強い罪責感、自殺願望の芽生えなどがある。……おいおい、上げれば上げるほど俺も他人事とは思えないぞ。
まぁ、俺のことは置いておいてだ。美笑に置き換えても外見からの判断だが、言い得ている。一つ考えたくは無いが、強い罪責感を感じるという項目。美笑が、詩織の死が自分のせいだなんて思ってなければいいが……。それが引き金で自殺願望まで芽生えてしまったら、最悪な事態になってしまう。普段大人しく、あまり胸のうちを話さない美笑からそれを聞き出すのは容易ではない。
昔は、内因性か心因性か、もしくは神経系かなどと分けて考えられていたそうだ。
内因性とは脳内の分泌物やホルモンなどの異常分泌やアレルギーによるもの。心因性とは社会や環境で感じるストレスやショックなどが原因である。神経系は内因性に近いだろうか。
美笑の場合、心因性というのが可能性としては高い。俺でさえ詩織の死のショックは受け止め切れていない。実の妹である美笑にとって、それは俺の比ではないだろう。そして、度重なる離婚と結婚。生活環境の著しい変化。それらがどれだけ美笑に心労を与えていたかなんて、俺には想像も出来ない。
そして美笑の場合、興味の喪失が感情の喪失とは置き換えられないだろうか。元来、うつ病とは気分障害ではなく、昔は感情障害とも言われていたらしい。
そんなことを考えているときに、こんな本を見つけた。「感情の生涯」なる本だ。
この本の筆者は、人の感情は生まれた時から常に少しずつ磨り減らしていると説いた。喜びも哀しみも、怒りも楽しさも、初めての時は100%だが次の経験は99%以下であり、それは人が誰しも持つ”慣れ”によって新鮮な驚きや感動を薄れさせていると。
しかし、人生において様々な経験をする中で新しい感情を発見したり、逆に感情を喪失するとも言っている。そこに出てきた単語の一つに「感情純麻」というものがあった。
感情純麻とは、表情が全く無くなることで臨床心理学の分野の言葉らしい。
俺は漠然と、美笑はこの感情純麻を引き起こしているのではと考えた。人の感情は表情に表れやすい。かなりの演技派か、ポーカーフェイスでも身につけた人でなければ、大抵の人は感情を表に出す。表現する方法として表情を変化させる。それが意識的なものもあれば、無意識的なものもあるが。
いずれにせよ、今の美笑はうつ病を患っている可能性は否定できない。そして感情純麻に近い症状なのは否めないところだ。
しかし……。
社交的ではないにしても、今こうして人と関わりを持っている。淡白だが、心なしか無表情ではない気もする。むしろ普段と比べれば、明るさも垣間見えてきそうなくらいだ。
また矛盾……。どちらが表で、どちらが裏なのか。それとも俺は見当違いの考察を続けているだけなのか……。今の段階では分からない。
それに、あれは――。
ヘアピン、か……。確か詩織も、前髪をヘアピンで止めていたっけな……。
中等部2年の秋――。告白、最後の約束。
「え……? あの、えと……」
俺は深々と頭を下げて、精一杯の想いを詩織にぶつけた。
下を向いているので、詩織の表情は分からない。でも、声の感じから慌てているような、驚いているような、そんな感じだった。
今この瞬間、男、結城翔の一世一代の……そして、最初で最後の頑張り物語だった。
好きだ、石川! ここで石川のピアノを聴いたときからずっと。それから今まで、こんな根暗な俺を、明るく励ましてくれてすごく嬉しかった! これからも、石川のピアノを聴かせて欲しい。出来れば、石川の、彼氏として!
「あぅ……。ほ、本当に私でいいの? でもどうして……?」
それは……。ほ、ほら。前に石川が話してくれたじゃないか。ピアノの魔法の話。
ひょっとしたら俺も、魔法に掛かったのかも、しれないって……。
「……そっか。じゃあ結城くんは、私じゃなくて、私の弾くピアノに惚れたんだ?」
あ、ち、違う! そういうんじゃない! 石川の明るいところとか、いつもポジティブで俺を励ましてくれたりとか! それに、石川がピアノを弾いてるときの顔が幸せそうで……って何言ってるんだ俺は。だからその、ピアノを弾いてる石川が好きなんだ! すごく、綺麗だって……。
「ぷっ。ははっ。ごめん、女の子って意地悪なんだよ。男の子にそう言わせたくて、そう言って欲しくて、言葉を選ぶ時があるの」
え……。じゃあ……。
「ありがとう。私のことそう言ってくれたのは、結城くんが初めて。すごく、嬉しいよ。私も、結城くんがそこで聴いててくれると安心して弾けるんだって最近思ったの」
すると、石川は席を立ち俺の正面にやってきた。
「えっと、こういう時なんて言えばいいのかな?」
石川は普段見せないような表情で、俺を見上げてくる。自然と俺も顔が蒸気する。
「でも、ごめん。その返事と私の答えは、待っててもらえるかな? 今はまだ、ダメなの……」
え……。ダメって……。
「あのね、今美笑がちょっと体調崩してて、放っておけないの。私だけ良い目を見ることは出来ない、から……」
石川……。
「だから、約束しよう? 実はね、4年後の丁度私たちが卒業する年の春。32年ぶりにみずがめ座流星群が極大になるの。それを夜、一緒に見よう? その時、ちゃんと答えるから」
それは構わないが……。4年後って、また遠いな。
「うん……そうだよね。その間に、結城くんの気持ちも変わっちゃうかもしれないし…」
それは無い。
「え?」
俺はこれからも毎日、石川のピアノを聴きに来る。毎日、会いに来る……。
「あ……ははっ。ありがとう。私も、今の気持ちを大切にしたいから。だから、ヒントをあげる。私が好きになる人は、美笑のこともちゃんと考えてくれる人がいい。私が、もしもの時は――」
縁起でもないな。俺に何を言わせたいのか分からないが、石川の口からそれ以上言わせたくない。
「……うん。結城くんが今の気持ちをずっと持っててくれたなら、美笑のこともちゃんと考えてくれるよね?」
約束する。
「……。もう一つ、私の、初めての気持ちも大切にしたいから。キス、しよっか?」
え!? あ、いや……。そうだな。
そして俺たちは不器用に、お互いの今の気持ちを共有した。決して今は、石川の口から聞くことは出来ないけれど。それが石川の、今表せる精一杯の気持ちだったのだ。
「これからは、詩織って呼んで欲しい」
分かった、詩織。
「うん、翔くん……」
かつて交わした約束は、いつしか思い出となっていく。
俺は記憶の中の奥底にしまいこみ、思い出そうとしなければ忘れていたことだった。
このときの気持ちがあるからこそ、俺は詩織を忘れないでいられる。
俺は今でも、詩織のことが好きだ……。
高等部3年の春、現在――。ゴールデンウィーク3日目。
今日も今日とて図書室の管理。午前中だけの開放とはいえ、せっかくの連休中に開放する意味はあるのだろうか? 決して来る人はゼロではないが、生徒だけ見積もってもせいぜい2~3人というところだ。
あとは先生たちが何か資料を探しに来るくらいしか来客はいない。これだけ広ければ一般開放にでもすれば、もっとたくさんの人は集まるだろうと思う。
しかし、そうともなれば生徒だけの管理とはいかない。教員がつくか、図書室担当の臨時職員とかも雇用しないといけないのかもしれない。となると、やはり今の現状が学校側にとっては都合がいいということだ。
今日も、読書好きな生徒数名と先生数名を見ただけで閉館となった。
図書室の鍵を職員室に返し家路に着こうとしたとき、どこからか音楽のようなものが聞こえる。俺は誘われるままに、音のするほうへと足を向けた。
学校広しといえど、音楽が響く場所となれば限定されてくる。たどり着いたのは、やはり音楽室だった。俺は壁越しにその音を聞くことにした。
いつかの光景を思い出す。妙な既視感を覚え、俺はあの日のように廊下の壁に背中をあずけ、ゆっくりと腰を下ろした。
昨夜、俺は夢を見ていた。あの日、俺が告白をした日のことを。
詩織はあの時、三つの約束をした。一つは、4年後一緒に夜空を見上げよう。そして二つ目は、俺の告白への返事はその夜に返してくれると。最後に、美笑のことをちゃんと考えるということ。
……俺は、何をやってるんだ…………。
詩織の死が受け止められなくて、美笑を傷つけてしまうのが怖くて、詩織とした約束も忘れていて……。俺は関心がないという理由で、その実、逃げていただけなんだ。それは分かっていた。自覚があるにもかかわらず、あらゆることを恐れていた。
なぜ? その先のことを想像出来てしまうからだ。確かに可能性の話をしたらキリが無い。物事が俺の想像どおりにばかり動くなんて自惚れるつもりはない。
しかし、俺はその恐怖を拭えない。囚われ、強迫観念を抱き、無関心を装うことで自己抑制をしていたに過ぎない。
まさか、詩織の口をつこうとしていた冗談が本当になってしまうなんて、誰も思っていなかったはずなんだ……。いや、あれは事故だった。誰の思惑も、故意も関与していない。不慮の事故だったのだ。そう思い込もうとして、俺は全ての興味を遮断した。
それが、負の連鎖。俺が作り出した幻想の螺旋。
結局この3年間、何をやっていたんだ俺は……。頭を抱えるしかなかった。
はっとして俺は顔を上げる。
この旋律、この曲……忘れるはずが無い。詩織が一番好きだった、あの曲だ。
まさか今この曲を聴けるなんて思っても見なかった。この曲を弾けるのは詩織だけだと思っていただけに、音楽室内にいる人が誰なのか無性に気になる。
細長いドアガラス越しに中を見る。……あれは、美笑と、先生……? 確か新任の桜先生だっただろうか。
その旋律が踊る空間に、俺は踏み入れたかった。かつての想いを抱き、なぜその曲を先生が弾けるのかと聞きたかった。
しかし……。俺の手はドアに掛からなかった。この空間に俺が入る隙間が見当たらなかったのだ。あの時のように彼女一人ではない。ここには美笑と、そして先生だけの世界が広がっている。そこに俺が入っていくことは許されない。
でも……もう聴けないと思っていたこの曲をもう一度聴くことが出来て、良かった。気がつけば視界がぼやけ、鼻をすする自分がいた。ただ漠然と、この曲を聴くのはこれで最後になるだろうと思った。根拠は無い、ただ、そう俺が、思い込んだだけだ。
演奏が終わると同時に、俺はその場を後にした……。
自宅に戻ると、ゴミ箱に封の切られていない封筒を見つけた。
「……大学病院?」
うちに医者に罹ってる人はいただろうか。母親が病院に行っているか……なんて話をしてないので分からないが。とりあえず、封を切って中身を検める。
「結城、美笑様……」
それは、美笑に宛てた手紙だった。
内容は美笑に対する定期検診の案内。それから、美笑が気管支喘息を患っていること。小さい頃は小児喘息に罹っていたこと。いつの頃からか、定期検診を受けなくなってしまったこと。その後の容態の問診。最後に気遣いの文で結ばれていた。
この医者の先生は、自分が受け持った一人の患者でしかない美笑にとても尽力してくれていただろうことが文面から分かる。小さい頃からの主治医であり、美笑の病気を献身的に治療してくれていたに違いない。
しかし、美笑も離婚や何やらで住む家が安定していない。そして詩織の死のショックもあり、自分の身体のことを気にかけなくなってしまったのかもしれない。大体、いつ頃から検診に来ていないということも書いてある。それはやはり、詩織が事故死してからだった。
そして、気管支喘息についても少し書かれていた。
気管支喘息は、季節の代わり目に症状が出やすい。風邪であったり、花粉であったり、季節柄蔓延しやすい菌などがあるように、喘息という病気も発作が起きやすいそうだ。加えて、天候が崩れているときにも発作率が高い。今のような梅雨空では美笑の体調も不安定なのかもしれない。
喘息という病気を軽く見ていると、大変なことにもなる。気管支喘息は軽度でも、死に至る病気である。これを、喘息死という。幼い頃に小児喘息を患っていたりした場合、適切な治療を施さないと、悪化を防げない。自然治癒は望めないということだ。
美笑の場合は運動誘発型で、小さい頃から運動の後は軽い息切れを訴えていたそうだ。比較的身体も小さく、体力も並み以下だった美笑は、次第に身体を動かすことを自制していった。
そういえば、数日前も美笑は発作を起こしていた。いわゆる、喘鳴も聞こえていた。症状の程度は分からないが、もう深刻な状態なのかもしれない。
小児喘息を患っていた時は、詩織の看病もあった。そのお陰で、症状も落ち着いていたと思う。しかし、詩織の死から家庭の崩壊。生活環境の著しい変化。それが引き金となり、また喘息をぶり返し気管支喘息を引き起こしてしまった。さらに追い討ちをかけるように、精神的なショックからうつ病を併発し、身体も心も疲弊させていく……。
いや、うつ病が先で喘息が再発してしまったのか。……もう、今となってはどちらがニワトリでどちらが卵かなんて関係ない。現に美笑は、もう擦り切れる寸前なのかもしれないということだ。
また美笑は、本当の母親のところに泊まりに行くことが多い。しかし、歩いて往復するには決して近い距離ではないと聞いたことがある。運動誘発型の美笑にとって、その距離を歩くだけでも、相当の疲労があるに違いない。
……。
いつまでも、このままじゃ駄目だよな……。
この手紙が良いきっかけになるかもしれない。一度検診を受けるように言おう。今更かもしれない、なんで今頃かと思われるかもしれない。
それでも……。縁先生の叱咤。詩織との約束。もう一度、面と向き合うのも悪くない。
俺は手紙をそっとしまうと、部屋に戻り美笑の帰りを待つことにした……。
中等部2年の冬――。約束の場所。
「諦めるな! 最後までっ! 諦めたらそこで、人生終了だよ!」
なんて短い人生だったんだ俺……。
ていうか、遅刻ごときで俺の人生が終わってたまるか! どこかで聞いた台詞を詩織辞典にはどのように登録されているんだ!?
俺は朝から廊下を全力疾走で駆け抜ける。教室のドアからは詩織が顔を出していて、おかしな声援を送ってくれる。反対側からは涼しい顔した担任が歩いてくるのが見える。時間には厳しい、1秒のくるいもなく8時30分ジャストに教室にやってくるような先生だ。
遅刻なんてした日には、それこそ人生の終わりになりかねん! 俺は詩織の冗談(声援?)を冗談で終わらせるために、100m走を9秒ジャストで世界記録を更新するかの如くスピードで教室に飛び込んだ。
「セーフ! ほらほら早く、席に座って。…これで、中学MVPは貰ったね」
「詩織さん……酸素マスクが、欲しいです……」
そんな朝の小芝居も、最近では珍しくはなかった。いや、遅刻常習という意味ではない。俺と詩織との関係の変化という意味だ。
あれから詩織とは一緒に登下校したり、買い物にいったり……ということは一切無い。今までと同じように二人きりの逢瀬は放課後の音楽室のみだった。詩織の望みどおり、まだ、彼氏彼女ではないし付き合っているというわけでもない。何しろ、詩織の気持ちをはっきりと聞いていない。俺が告白をした、そこまでなのだ。
変化があったとすれば、教室で前より話すようになったことくらいだ。クラスでも友人の多い彼女が、特別俺に話しかけることは珍しいことではないし、その明るさから誰とでも気兼ねなく接していけるやつだ。
これは余談だが、こういう人は同姓からも異性からも人気がある。クラスにおいて社交的な女の子というのは決して疎まれない。
それでも。以前にも増して詩織は俺に話しかけてくれるようになった。そして事あるごとに、妹の話を交え、美笑のことを大切にしてくれるかと聞いてくる。
それは決して嫌なことではなかったし、むしろ、詩織が俺を好きになろうとしてくれているんじゃないかという気もしていた。そんな彼女にしてはささやかな努力が、たまらなく嬉しくて、自惚れだとは分かっていても俺は次第に詩織に心を開いていった。
そう、俺たちは変わろうとしていたのかもしれない。
詩織は妹を溺愛しているが、異性を好きになることは初めてで手探りだけども慎重に、俺との距離を縮めようと努力をする。
俺は根暗で人との関わりを疎ましく思っていたが、詩織の価値観に感化され、昔ほど卑屈にはならなくなったようが気がする。
それをわざわざ口にするつもりはないが、ひょっとしたらこれが初恋ってやつなのかもしれない。4年後の約束の日に向けて、俺たちは新しい日々をスタートさせた。それを傍から見たら、妙な形の始まりかもしれない。告白が先で、好きになるのが後で。
本当はもっと近道があった気がする。でも、不器用でも俺たちにとっては、相手を、人を、異性を、色んなことを、好きになろうとすることが”はじまり”だったのだ。
俺はもう、詩織が嫌悪するような後ろ向きな人間にはならない。詩織に好かれる人間になろう。そして小さな努力を始めた詩織を、もっともっと好きになろう。……そう、心に誓うのだった。
しかし――。そんな決意をした矢先……はじまりを知らせる旋律が、終わりを告げる鐘の音だったなんて、俺は知る由も無かった。
中等部3年の春、5月3日の出来事。詩織は交通事故で、俺の前から姿を消した……。
だから前日の夕方が、俺が詩織と会った最後の日となった。
その日はゴールデンウィークで学校は休みに入っていた。特に用事もない俺は、夕方散歩に出掛け、頃合いを見て家路につくところだった。
とあるビルの前で詩織の姿を見つける。買い物の帰りのようで、片手にはスーパーの袋を抱えていた。
「…あ、翔くん。こんなところで会うなんて、奇遇だね」
あぁ。詩織こそ買い物の帰りか?
「うん。……このビルさ、近々取り壊しするみたい。でも、日時は未定なんだって」
最近多いよな。大方、過去の残骸ってやつだろ。作るだけ作って収集が付かなくなって、時代が変わってみたらこんなのが溢れかえってたって有様だ。
「……そうだね。でもさ、このビルの屋上から空見たら、一面見渡せるかな?」
空? まぁ割と高いビルではあるな。
「翔くん。ちょっと上ってみよっか?」
え!? 詩織の言葉にはたまに驚くぞ。取り壊しが決まってるんだから、危ないんじゃないか?
「まだ看板だけで中は何もしてなさそうだよ。あ! そろそろ時間! 急ごう!」
そういって詩織は俺の手を引っ張って連行していく。初めは危険だろうと思っていたが、中に入るとまだ手は付けられていなくて、老朽化とかは目立っていない。
階段を駆け上がっていくと、いっきに屋上の扉を開け放った。
「間に合ったセーフ。ほら、翔くん。太陽をじっと見てて」
詩織に言われるがままに俺は眩しさに目を細めながら、太陽を見ていた。
すると、太陽が何かに隠れるように陰り始める。
「日食。今回は、部分日食みたいだね。珍しいのは皆既日食。もっと珍しいのは金環日食。皆既日食っていうのは太陽が月の陰に完全に隠れることを言うの。金環日食はその逆で、月の影が太陽にすっぽり収まるんだけど、その周りの淵から太陽の光がもれて、それをダイヤモンドリングっていうんだよ」
へぇ……。詩織は、天体好きなんだな。
「好きだよ。綺麗で、神秘的で。金環食なんて、サロス周期だと18年、33年、11年、11年…っていう周期だから、運が良ければ人生で数回見ることが出来るらしいよ。それでね! そのうちの2回を恋人と一緒に見ることが出来たら、その二人の魂は永遠に結ばれるっていう伝説があるんだって」
サロ…なんとかというのは分からないが、人生で数回か。なんと貴重な。
「食いついて欲しかったのはそっちじゃないんだけど……。まぁいいや。私は、翔くんと見たいなーって思って。おばあちゃんになっても、また一緒に見られたらいいなぁって」
……あぁ。そうだな。
「決めた。ここにしよう。卒業の年の約束は、この場所で一緒に空を見よう? さしずめ、約束の場所だね。ははっ、なんだかファンタジー世界に来たみたい」
リアル世界に戻すようで悪いが、このビルが取り壊されてたらどうする?
「大丈夫、このビルは壊されない。そんな気がする。私が、このビルの屋上で空を見上げたとき、隣に翔くんが居てくれたなら……。きっと約束を果たせるね」
俺も約束しよう。その日、詩織の隣で、みずがめ座流星群を見上げる。そしてもう1回言うよ、詩織のことが――。
「待って! それ以上はもう言っちゃダメ! そ、そういうのは何回も言っちゃダメだよ。その時まで取っておいて。ね」
はは……わかった。ところで詩織、妹の具合は最近どうなんだ?
「あ、うん。大分安定してきてるよ。でも、いつまたぶり返すか分からない。そういう病気なの」
そうか……。早く良くなるといいな、美笑ちゃん。
「ぷっ。”ちゃん”っていうの初めてだね。私のことは最初から呼び捨てだったのに」
あ、いや。なんとなくそう呼んでしまっただけだよ。次からは美笑って言う。
「ははっ。でも、ありがとう。心配してくれて。……もう何度もしてきた質問だけど、改めて聞かせて?」
詩織はくるりと振り返り、長い横髪を掻き揚げる。
「翔くんは美笑のこと、大切にしてくれる?」
ああ、約束する。もちろん、詩織のことも。
「……うん」
詩織は笑った。優陽(ゆうひ)に照らされた髪は赤く染まり、細められた目は潤んでいた。
少しばかりの、憂いを含んで……。
高等部3年の春――。ゴールデンウィーク4日目。
時刻は6時……6時……。あれから少し寝てしまったのだろうか。外はもう陽が落ちていてるが、美笑は帰ってきただろうか。
自室に居た俺は、ソファーにうずくまるようにしていつの間にか眠っていたのか。美笑が帰ってきたら手紙をきっかけに話し掛けようと思っていたんだ。このままでは駄目だからと、詩織との約束を思い出したんだ。
居間に行くとテーブルに新聞紙。普段は気にもしないのだが、ふと目を落とす。視界に日付が入った瞬間、俺はもう1度新聞紙を見入った。
「5月3日……? あれ、今日は2日のはずだが……」
テレビをつけてニュース番組に変える。やはり5月3日と表示されていた。
母親の姿も、美笑の姿も見当たらない。
「ん……。18時、だよな……」
ということは、俺は丸一日眠っていたのか? 昨日は夕方家について、封筒を開けた。それから自室に戻り美笑の帰りを待っていた。そしたらいつの間にか眠ってしまっていて、気づいたら3日の夕方6時……?
なんてことだ。そんなに疲れていたのか俺は。まぁ幸いなことに、今日の図書室管理は無い。寝すぎてしまったとしても、問題ないだろう。
「…………」
違う、なんだこの胸騒ぎは……。
一日寝ていたのだから、空腹を訴えている? 確かに空腹感はゼロではないが……。いや違う、こんなんじゃない。
あれから美笑は帰ってきたのだろうか? さすがに一日あるんだ。家に帰って着替えるくらいはしていっただろう。……違う、これでもない。
そういえば……。5月3日は、詩織の命日。そして、約束の日だ……。
詩織亡き今、約束の場所にいく理由は無い。しかし……なんか、なんか……。
美笑が居ない。帰ってきていない? それがなぜが大きな不安感として募っていく。なぜだ? この胸騒ぎと嫌な予感がするのはなんなんだ?
俺は今まで、長い長い夢を見ていた気がする。具体的には思い出せないが、詩織と過ごしていたような気がする。
詩織の命日。約束の日。帰っていない美笑……。それでなぜ、俺はあの場所に行かなければいけないという衝動に駆られるんだ?
分からない。しかし、この感覚はやばい。俺の中の何かが警鐘を鳴らしている!
混乱する頭をよそに、俺の身体は気が付けば玄関のドアを開け放っていた。美笑の手紙を握り締めたまま……。
俺の家からあのビルまでは、それほど遠くない。全力疾走で行けば5分と掛からないだろう。俺の地元だ、裏道だって知ってる。学校に遅刻しないために編み出した道だって色々ある。それを詩織に紹介することは、ついに無かったが。
そりゃそうだよな。詩織は遅刻なんてしない。一緒に登下校をすることは無かったが、もしも恋人として歩むことが出来たなら、俺の朝はあんなにも忙しくなかったかもしれない。優しい、それでいて明るい時間が流れていたはずだ。
過去の話だ。今思い出すことじゃない……。
”ねぇ。結城くんは、魔法って信じる?”
詩織の声が聞こえる。魔法か……もしもあるなら、俺の脚をチーターのように俊敏にしてほしいもんだ。そしてこの胸騒ぎを1秒でも早く消し去りたい。
……いや、夢、か。思えば詩織の夢を見たのも、何かの予兆だったのかもしれない。俺に大切なことを思い出させるために。夢に出るという、魔法。
”もしも、守護霊っていうのが本当にいるなら、どんな人がいい?”
そりゃ詩織。詩織みたいに真っ直ぐで綺麗で、俺を間違った道から正してくれるような、そんな人だったらいいな。俺が馬鹿やってたら、1発引っ叩いてくれ。
”私の妹の名前? みえ、だよ。美しい笑顔って書いて、美笑”
美笑……良い名前だな。詩織が愛した妹。俺はかつて、美しいものはいつまでもそうあって欲しいと言った。でもそれは、ただ願うだけだった。
願うだけでは駄目なのだ。守らなきゃ。それは詩織の気持ちの裏返し。本当は詩織は、俺に美笑の笑顔を守ると言わせたかったのだろうか。そして、詩織のことも……。
”人間やれば、何だって出来るんだよ。人間諦めないことが肝心!”
ああ、そうだな。こうして夢にまで出てきてくれるんだから、詩織は本当にすげぇよ。でもそれと同時に、同じくらい俺の不安も広がってる。こればっかりは、詩織の存在に対極してる……。
”君のそういう考え方。私嫌いって言ったよ”
はは……ははは。こんな状況で、思わず頬が緩んでしまう。
思考の迷路。迷路には必ず出口が設けられている。その時点で、抜け出せない道理は存在しないのだ。出口の確証が無いのは、ただ、迷宮である。
出口は分かってる。今日この日、約束の場所へ。あそこに行けば、分かる!
”諦めるな! 最後までっ! そこで諦めたら人生終了だよ!”
ああ、終了させないために走ってるんだよ! まだまだ俺たちはこれからなんだ。すごい遠回りをしたけど、結果美笑を傷つけてしまったけど、まだ終わらせたくない!
俺は今一度、地面を強く蹴った……。
「美笑ッ!」
ビルの屋上を見上げる。無用心にフェンスなんて無いところだ。淵のところに人影が座っているのはすぐに分かった。
見上げた俺は、言葉を失う。それは、あまりにも美しい。空に散りばめられた星たちがいたるところから降り注いでいた。どう形容すれば伝わるだろう、この美しさを。
きっと、言葉で表すことすらこの星たちの煌きに陰を与えてしまうだろう。みずがめ座流星群極大になるというのは、なんて、なんて……。
ずっと梅雨空で、晴れ間なんて無かったここ数日。示し合わせたかのように、今夜は文字通り満天の星空だった……。
すると、ゆっくりと美笑の視線が俺に降りてきて……。
「―――」
口元がかすかに動くのが分かる。……なんだ?
「…………」
お・ね・え・ちゃん? ……違う。―――さ・よ・な・ら!?
俺の目が見開かれると同時に、美笑は激しく咳き込み胸を押さえた。やばい、発作だ!
あんなところに座って発作なんか起こしたら、……まずいッ!!
俺は駆け出した。屋上の美笑を目指して――。
「美笑ッ!!」
屋上の扉を蹴飛ばし、俺は駆け出した。手遅れかもしれない。届かないかもしれない。
それでも、俺はやっと気づけた大切なものを手放したくなかった。
それが例え、俺自身の過ちだったとしても。
それが例え、彼女の過ちだったとしても。
それがたとえ、終焉を知らせる鐘の音だったとしても……。
せめて、笑ってくれたなら――。
ただ強く抱きしめて、彼女との約束を果たしただろう。
しかし、少女の目はもうすでに、閉じられていた……。
「っ……」
美笑は立ち上がっていて、こちらを向いていた。脱力したかのように、ふわりと彼女の身体が中に浮く……。
そう、美笑が俺に笑いかけてくれることは、ついに無かったのだ。
俺は、間に合わなかった……。
彼女との約束も守れず、少女の笑顔さえ導くことも出来ず、約束の日を迎えてしまった。 俺は当然の報いを受ける。少女の時間は有限。限りがあるから命は咲き煌くんだ。
死は、いついかなる時も背後に付いてまわる。たとえ症状が軽くとも、たとえ性急なものでなかったとしても。
その認識の甘さが今日を招いた一つの原因。俺と、そして美笑の過ちだった。
それからもう一つ、俺は大事なことを忘れていた。
約束――。詩織との、最後の約束を……。
今日この日、俺たちは肩を並べて空を見上げているはずだった。そんな未来があったはずだった。
それが詩織の死により閉ざされ、俺の世界も閉ざされた。行き場を失った美笑の心は、虚空に放り出され、壊れてしまった……。
きっかけは何だったのか、今ではもうきっかけでしかない。壊れてしまったものは、やがて朽ちるのを待つしかないんだ。癒せやしない……。
それでも……。だからといって……。
支えになることは出来たはずなんだ。かつて詩織が、俺を救ってくれたように……。
俺の手は、美笑の身体をかすめることもなく、美笑は支えを失った人形のように後ろへ倒れていく……。その眼前の光景が、スローモーションのように慈悲深く、俺に贖罪の時間を与えた。
落ちていく、美笑の身体……。俺は身を乗り出して、手を伸ばして……。涙が一滴、零れ落ちる。
走馬灯を見る慈悲を与えられたのだ。俺の最大の過ちは、何だったのか。
”ねぇ。翔くんは、美笑のこと大切にしてくれる?”
約束はかく語りき。全ての答えは、ここにあったのだと……。
詩織は最初から、俺のことを見てくれていた。俺が踏み外してしまった歩みを正そうとしてくれていた。でも俺は、それに気づくのが遅すぎた……。
「……まだだ!」
走馬灯の涙を弾き、俺は地上に降り立った美笑をもう一度見る。
美笑の周りには血溜りが出来ている。だからといって、放っておけるか!
俺は弾かれるようにもと来た道を逆走する。絶望的かもしない。あれだけの出血をしてたら、助からないかもしれない。だけど……!
119番! 119番! 早く繋がれえぇぇええ!! 救急車を、お願いします!! 止血を! 止血をッ!!
”諦めるな! 最後までっ!”
美笑の人生を終わらせたくない。その一身で、俺は美笑のもとへ駆け寄った。
「……ぁ……ぅぁ……くッ!」
こんな……こんなのって……。首が、首がありえない方向に……。頭が、あたま……が……。血が、あふれ、て…………。
「う……ぅう、うあああぁあぁぁあぁあああッッ!!!!!」
俺は悲愴と後悔と驚愕に咆哮した。泣いたって、美笑はもう帰ってこない……。誰が見たってこれじゃあ、即死じゃないか……。降りしきる美しい夜空とは対極に、地上には凄惨な光景が広がっていた。
俺は美笑を抱きしめる。俺の涙も赤く染まり、いつしか俺も美笑の血を身に受けていた。美笑の過ちも、俺が全て被るように……。
死ぬべきは、俺の方だったんだ……! 詩織でもなく、美笑でもなく、こんなどうしようもない俺が――! 変われるのなら、あの日交通事故で死ぬのは、俺であって欲しかった……! それが、二人にとって一番の幸せだったはずなのに……。
俺は救急車が来るまで、赤い涙を流しながら、ずっと美笑を抱きしめていた……。
ゴールデンウィーク5日目。卒業、強く生きて花は咲く。
「美笑は自殺でも、事故でもない。待ってたんだ、きっと……」
俺と縁先生は、通夜を終え先生の家に居た。なぜかというと、一番最後に美笑と一緒にいた俺に、色々と聞きたかったからだそうだ。俺も親類と晩餐をするより、先生と話していたほうがいいと判断し、お招き預かった。
「そう……。詩織さんとの約束があったのね……」
「自殺にしたい連中もいるようだけど、先生には誤解して欲しくないんです」
「ええ、分かってる。美笑ちゃんは強い子だもの。だって、詩織さんの妹なんだから」
それを、追い詰めたのは俺だ……。
「ねぇ、翔くんは自分が死ねば良かった、なんて思ってる?」
「……」
「駄目だよ。そんなことしたって、誰も嬉しくない。生きてるんだから、生きなきゃ。人が生まれてきたことには、みんな意味がある。でも、それを見つけるのは自分の仕事」
「……じゃあ、死ぬことにも意味があるってことでしょうか」
「うん。自殺であれ事故であれ、ね。ある人は、人の人生の長さは生まれ時から決まっている、なんていう人もいる。ある人は、死は受け止めるもの。そこから立ち直るために人は生きるんだって言った人もいた」
「どちらも、生きてる側からの気持ちですね。死んだ人側がどう思ってるか、考えないんだろうか」
「翔くんは、どう思う? そこを明確にしようと思って、今日呼んだの。美笑ちゃんは屋上で、どんな様子だった?」
「……俺が着いた時は、まだ普通に屋上に座ってました。それで、何かを俺に向かって言いました。それは聞き取れなかったけど、急に発作が起こって、俺が屋上に駆けつけた瞬間には発作は止まっていました。それが、喘息死だったのか、単に気を失ってしまったからなのか分からないですけど、居た場所が悪かったのでそのまま、落ちてしまったんです」
「……うん、そこだね。美笑ちゃんは翔くんに何かを伝えようとしていた。でも翔くんには届かなかった。つまり、生きてる人からそれを想像することしか出来ないの」
「それじゃあ、死んだ人が浮かばれないじゃないですか……!」
「本当にそう思う? 今翔くんの後ろに居るの、分からない?」
「え?」
心当たりは……ある。それが怖いことだなんて、思わない。
「ずっと……傍に居てくれたんだね。ありがとう」
「……」
「守護霊ってね、その人に一番近しい人。もしくは一番気に掛けてくれてる人が憑いてくれることが多いんだって。そんな素敵な人が、美笑ちゃんを見捨てるはず、ないでしょう? だって、彼女は……」
「ごめん! 本当にごめん! 俺は詩織との約束を守れなかった……!」
俺は頭を下げた、謝ったって取り返せない十字架を俺は生涯背負っていかなきゃいけないのだから。
「……翔くん。彼女は謝って欲しいんじゃないと思うよ? 詩織さんも美笑ちゃんも、翔くんを恨んでなんかいないんだから」
「でも……!」
「じゃあ考えなさい。詩織さんは君に、何を伝えたかったの? 美笑ちゃんは、翔くんに本当はどうして欲しかったの? それが分からなかったら、今度は幻滅どころじゃ済まさないよ」
「……はい」
それから俺は1年間。卒業までの日々を、贖罪にあてた。
詩織が伝えたかったこと。美笑が望んでいたこと。俺は精一杯それを考えた。
一年後の春――。卒業式。
「なんだかすごく、あっという間だったな……」
あれから俺は、変わった気がする。人付き合いが億劫ではなくなった。積極的にクラスメイトとの輪に溶け込み、決して一人でいることは無くなった。もともと、クラスメイトは詩織のお陰で、気のいい奴ばっかりだった。詩織が蒔いた種は、ちゃんと咲いていたのだ。誰も詩織のことを忘れてないし、話題に詩織が出てきてもブルーになる人はいない。
それでも、家で一人になると思い出すのは詩織と美笑のこと。俺なりに答えは見出せたと思う。あとは先生が納得してくれるかどうかだ。
そろそろ、先生との約束も果たさないといけない……。
「あ、いたいた。翔くん、探したんだよー」
「……先生。丁度いいところに」
「丁度いいところ? …おやおや? 先生に巣立ちの挨拶でもしてくれるのかな?」
「まぁ、そんなところです。先生との約束、忘れてませんから」
「……うん。それじゃあ聞こうかな。結城翔くん」
俺はすぅっと息を吸い込んで、目を閉じた。これからは、もう間違わない。
「……詩織、ありがとう。今までと、それからこれからも。詩織は最初から、ずっと言い続けてたんだよな。美笑を大切にして欲しいって。それは、俺にも願って欲しいってことじゃなくて、俺に守って欲しかったんじゃないかってそう思ったんだ。もちろん、詩織のことも大切にする。そして一緒に美笑のことも考えよう。身体が弱くて、大人しい美笑に心から笑ってもらえるように。だから……詩織! 俺は詩織が好きだ! 何度でもいう! ずっと、これからも、詩織のことを好きでいる! そして! 詩織と美笑のことを、生涯守ると誓う!」
「うわぁ……どうしちゃったの翔くん。こっち見て言われたら照れちゃうよ」
そして先生は視線を俺の隣に移した。
「って、詩織さんも赤くなってないでこの色ボケ……もとい、なんちゃって色男になんか言ってよ。公衆の面前で告白を叫ばないでって」
「…それから美笑。ごめんな、お兄ちゃんがもっと早く美笑と向き合っていれば良かったんだ。詩織が居なくて寂しかったのに、お兄ちゃんが相手してやれなくてごめんな。今度、一緒に買い物に行こう。ところでそのヘアピンは、どこの男から貰ったんだ? お兄ちゃんにちゃんと紹介するんだぞ? 付け替えが出来るように他のヘアピンも買いに行こう。詩織とお揃いのやつ、あるといいな」
「翔くん……」
そう、これが俺の……守ろうとする物語。
色々と遠回りしてしまったけど、最初から俺のすべきことは決まっていたのだ。
「うん、よろしい。ちょっと見直したよ。幻滅は撤回しておいてあげる」
「男としては、惚れ直したって言ってくれた方が嬉しいです」
「あらぁ? 言ってあげなくもないけど、今の中に私への言葉は含まれてなかったよ?」
「……あぁ。先生に、あの時図書室で”あなたには幻滅した”って言って引っ叩かれた時は、正直立ち直れないかと思いました」
「ええ!? 私幻滅したとは言ったけど、叩いてないよ!? そんな暴力教師じゃないよ!」
「ははっ。教師なのにその美貌を活かして生徒を誘惑しようとするからです」
「な、なにぃ? …おほん。まぁ、前半の部分があったから流してあげましょう。でも、あんまり調子に乗ってると、彼女が黙ってないんじゃないの?」
「うぁいてっ」
な、なんだ!? 空から突然お祝いの花束が降ってきたぞ!? 教室から誰か落っことしたのか?
「翔くん。私からも一言言わせて。あれだけ大胆告白されたんだもの、言っていいよね?」
チラッと俺の隣に視線を送ると、先生はかしこまるように手を前で組む。
「私、ずっと前から詩織さんと翔くんのこと知ってるって言ったでしょう? 実はね、詩織さんから相談されてたの。翔くんのこと。詩織さんね、前向きになった翔くんのことが、好きになったって言ってたよ」
「え……」
「詩織さんも異性を好きになるっていうのが初めてみたいで、顔真っ赤にして、どんどん翔くんのことが好きになっていくのが止まらないんだって言ってた。両思いだったんだね、青春だなぁ」
あ……れ……。視界がぼやける。瞬きが出来ない。熱い、篤い……。
「まだちゃんと言えないのが辛いって言っててね。早く約束の日にならないかなーって、詩織さんすっごく幸せそうな顔してて――」
「先生、先生……もう、十分です……。俺……俺……それが聞けただけで……もう……」
止まらない、嬉しくて嬉しくて……。こんな俺のことを好きになってくれて。
直接聞けなくても、今、この瞬間。それをひしひしと感じることが出来たから……。
「うん、分かった。最後に私から……。もう一度言うけど、詩織さんも美笑ちゃんも翔くんのことを恨んでなんかいないよ。だから……生きなさい。精一杯がむしゃらに。いつかまた、二人と胸を張って会えるように。私は、みんなの幸せを祈ってる」
「はい……はい……」
「卒業おめでとう、翔くん。詩織さん。末永くお幸せに。そして……進級おめでとう、美笑ちゃん。これからは私が担任だから、よろしくね!」
「ありがとう……ございました……っ!」
俺は涙で顔をくしゃくしゃにしながら、深々と頭を下げた。
この素晴らしい先生に見送られ、俺はまた歩みを始める。
あるがままに、そとはかとなく。
そんな当たり前で、ありふれていて、大切な日常を守るために。
変化する日常も、踏み外さないように着実に一歩ずつ。
俺が守ろうとする物語は、まだ2度目の決意を迎えたばかりなのだから。
人に話すことはないと思う。
いや、あるとすれば天寿を全うし詩織が迎えてくれたとき。
詩織と美笑と俺3人で、一緒に見てきた人生を辿ろうと思う。
一緒に歩んでいこうと思う。
そして、守っていこうと思う。
それが俺の、結城翔の守ろうとする物語の始まりなのだから。
Fine.
せめて、笑ってくれたなら。
短編小説第3作目「せめて、笑ってくれたなら」を最後までお読みくださいまして、ありがとうございました。
そして短編なのに3部構成で1部役30000字、計90000字。お疲れ様でした。
シリーズを通して伝えたいのは、どうしたら美笑ちゃんを救えたのか。その一点です。
それを伝えるために3人の違う価値観を持った主人公の視点を用意して、遠回りをして物語を描いてきました。
私自身も初めての試みで最後まで続くか不安でしたが、書き上げられてホッとしていますw
最後の翔の物語は、最後重たくしたくなかったので前向きに明るい感じで結びました。
優也の物語のように辛いのは、1回だけで心が折れましたorz
この3人の視点はいかがだったでしょうか?
皆さんの考えと似てる人はいたでしょうか?
もしもこのお話を読んで、何か一つでも思うことがあったな作者として、こんなに嬉しいことはありません。
個人的に、縁先生が好きなので、番外でSection EXとか作ってもいいかな、なんて思ってますw
それでは長くなりました。
「せめて、笑ってくれたなら」 略は…今のところありません。募集中です。
最後までお読み頂きましてありがとうございました。
また次の作品でお会いできることを、楽しみにしています。
2011.11.13 15時 自室より。


