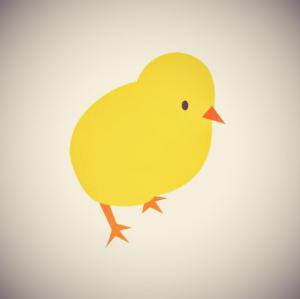おおかみの涙
ご訪問ありがとうございます。
登場人物ならぬ登場“動物”でお送りします。
-1-
ある深い「もり」の奥に、腹をすかせた一匹のおおかみがいた。
集団から外れた孤独な彼はひときわ働く鼻を宙にかかげて、その腹を満たしてくれる獲物を探した。
彼のからだは汚れていた。肉もついていなかった。
もっと逞しく、勇ましかったのだ。数日前、自分の属していた群れを追い出されるまでは。
おおかみは仲間を殺した。
他意はなく、また、乱心しているわけでもなかった。
ただ、その時をうまく思い出せないのだろう、もっぱら今はいのちをつなぐことだけに集中していた。
それが「もり」に住む生物たちの素直で自然な行動なのだから。
季節は秋。冬を控えた空気も次第に静けさを増していく。
おおかみにとってはこれからますます厳しい状況になっていくに違いない。
しかし彼は焦ることをしない。
冬になれば家族でおなじところに行き、おなじところに身を寄せ合い、おなじところに食事をした。
集団だからできたこと、彼はそれを理解できていなかった。
かわいそうなことに、彼は数日獲物にすらありつけていないこの状態で、冬を乗り越えるつもりだ。
毛を逆立て、寒さに震える背中を秋の空が見下ろしていた。
だが、ふと、おおかみの様子が変わった。
地面に鼻を必死にこすりつけて歩調を速め始める。なにやら木の根もと辺りを執拗にかいでいる。
運良く探していたものが見つかったようだ。
目標をとらえた速足はだんだん加速し、飢えがうそのように活発な目をしていた。
とりあえずは安心、とひと息つける。空腹からは解放される。おおかみは走った。
きっとおおかみは分かっているだろう。いのちをつないでくれるその生き物の正体を。
ぎらぎら光る瞳をまっすぐ向けて、おおかみは走る。石を飛び越え、地面を蹴りあげ、直進する。
静かな「もり」の中で彼がかける音だけが響く。
そうしてたどり着いた、その丘の上には、一匹の子ひつじがいた。
-2-
真っ白な小さなかたまりが、丘のてっぺんでうずくまっていた。
空はすっかり薄暗いのに、何故か、そこだけ日の光に照らされているかのように明るい。
おおかみは躊躇しないまま近づく。動かないかたまりに静かに近づく。
そこからでも呼吸を感じ取っているのだろうか、彼は慎重に足を動かした。
もう満腹はすぐ目の前。あとわずか5歩進んだだけで、また2、3日は生きていられることだろう。
我慢する理由はなかった。
おおかみはさっと身を翻すと、たちまち次の瞬間には白いかたまりの上に乗り上がっていた。
驚いた子ひつじが突然の衝撃にばたばた足を動かすが、力も大きさもおおかみに勝てるはずがない。
おおかみはこれまでにも何度こうして小動物を前に牙をむき出しにしてきたことか。
小動物の反応はたいてい、鳴くか、暴れるか、攻撃してくるかである。
もちろん彼に慈悲などはない。すべては自分のいのちの存続のための当たり前の行為。本能だから。
今までは、そうだったはずだ。そうでなければならなかったはずだ。
おおかみはたった今、子ひつじを見て、なにも言えなくなってしまった。
オスの子ひつじだった。最初こそ驚いていたものの、彼の態度は変わっていた。
鳴きもしない、暴れもしない、まして攻撃してくるわけでもない。
ただ、悲しそうな目をしていた。
どうぞ僕を食べてください、そう訴えているようにさえ思えるほど無抵抗な瞳をこちらに向けるのだ。
そうして気がついた。ここは子ひつじが一匹で来れるような場所ではないことに。
この深い「もり」の向こう側には、ちょうどこの丘を境にしてひつじの暮らす草本がある。
ひつじという生き物は非常に臆病だ。単独行動など、自殺行為に等しかった。
生まれたばかりのようなこの子ひつじは、わざわざここへ食べられに来たのではない。はぐれたのだ。
そう考えざるを得なかった。
小さな小さなかたまりを前にして、おおかみに倫理がうまれた。
-3-
子ひつじが黙っておおかみを見上げている。
いつ食べられるのか分からないが、いつでもいいように覚悟はできている様子である。
そんな子ひつじを見下げるおおかみ。何を考えているのだろうか。
獲物の食べ方か、それとも、食べたときの味か。
いずれにせよ、彼はなかなか動かないのだ。動かず、静かに呼吸をしている。
腹の底はとっくに尽きているはずなのに、先程までのぎらぎらした目はもう、光を失っていた。
代わりに、おおかみは半歩退いた。
踏まれていた足を解放された子ひつじは、驚きながらもばたばたして体勢を戻すことができた。
どういったいきさつなのかは誰も理解しない。もちろん子ひつじも。
単純に、逃げる機会を得ることができた、そう考えていただけだった。だから動いた。
それなのに。突然前足で押さえつけられる。
もう、おおかみが何をしたいのかを瞑想するしかない。子ひつじはまいった。変な鳴き声も出た。
おとなしくなった子ひつじ。冷たい風が脇をさっそうと通ってゆく。
「もり」には冬が近づいている。
二匹の毛は、風になでられるたびにいっそう逆立っていく。
そのまましばらくたった。長いような、短いような、不思議な間だった気もする。
おおかみが前かがみになって子ひつじの額に鼻をつけた。それだけだ。
両者は向かい合っている。正確には、子ひつじは押さえつけられてこちらを見ている。
行動の真意を知りたい。彼はあくまで鼻をつけて白玉のにおいをかいでいる。
何か、子ひつじの知らない何かが、目の前で行われていた。
けっして警戒をといているわけではないが、その鼻先が湿っていることを、わりに素直に感じた。
こんな経験をしたことはない。とっさにどう対応するか決められないから、黙っていた。
おおかみがゆっくり子ひつじと目を会わせる。
その目にはふたたび新たな光がやどっていた。
-4-
子ひつじは不思議な感覚に戸惑いながら、小さな鼻をひくひく動かしている。
その時突然、首のあたりにびりっと電気が走ったような刺激が子ひつじを襲った。
当然、鳴き声をあげて暴れるだろう。しかしやはり、この小動物は痛みにも耐えてじっとしている様子である。
なんと強い覚悟を持った子ひつじなのだろうか。
そしておおかみは何をしようとしているのだろうか。
見ると、彼のりっぱな鋭い牙には子ひつじのものと思われる赤い血液がべっとりついていた。
彼はそれを長い舌でなめとると、それから同じように子ひつじの後ろ首めがけて牙を近づけた。
今度こそと覚悟したらしい子ひつじが目をつむると同時に、予想もしていなかった感覚が後ろ首を伝った。
おおかみは、自分のつけた傷跡をなめていた。
謝るかのように優しく、しかしどこか慌てているような、そんなおおかみの姿が開いた視界に映る。
後ろ首に少し痛いような、くすぐったいような違和感を覚えて。目にちろちろ触れる硬く黒い胸毛が不快で。
子ひつじは初めて鳴いた。
おおかみは子ひつじを食べることを諦めていた。むしろ、なにか別の感情がはたらいたらしい。
自身の本性も空腹も忘れた彼がしていたのは、ただ、子ひつじの傷をなめることだった。
しばらくそこに二匹はいた。何をするでもなく。
けれども、子ひつじが寒さに震えれば、おおかみはその身を寄せていた。
小さく鳴けば、何度も何度も気にするように後ろ首を唾液で濡らした。まるで父親のように。
そんな彼の態度だったから、子ひつじは顔を見合わせたのだ。
初対面で向けられた、あの獰猛さに満ちた目はすっかり沈み、ある意味放心状態ともいえる表情を見てとることができた。
丘の反対側の「もり」からは、夜のおとずれを告げる音が響いた。
おおかみはのっそり立ち上がって最後に子ひつじをひとなめした。子ひつじがこたえるようにその鼻をなめ返した。
二匹の間に絆がめばえた瞬間である。
-5-
「もり」の夜は、ひどく静かで穏やかである。
ふくろうう声が時折聴こえる。いや、響き渡っているといったほうが正確なくらいかもしれない。
誰も訪れない、寄りつかない、不思議な不思議な静寂の中で目をこらしても、ただただ、闇が広がるばかりだ。
ここを支配できるのは、やはり、人ではない。
月のひかりさえ十分に届かない場所に、二匹は来ていた。そこにあった小さな洞穴に近づくと、おおかみは立ち止まった。
うながすように子ひつじの尻を鼻先で押し、ひっくり返った子ひつじも素直に中へと入っていった。
今夜もおおかみは食事をすることができなかった。かなり憔悴はしているのに、今の彼は別人のように変わっているのである。
きわめつけに、自分の前足をするどい牙でかぶりつき始める次第だ。激痛に低くうなりながら。
そんな彼を子ひつじも見ていた。
おおかみの前にちょこんと謙虚に控えて、なんの感情もあらわさない瞳で、一部始終をながめていた。
足元に流れてくるおおかみの血を遠慮がちによけては、純白の毛を汚すまいというようにその場をうろうろ歩く。
やがて疲れきったおおかみが、洞穴からおもむろに出ていった。子ひつじもそのあとをつける。
どこにいくのかと思いきや、彼は血だらけのからだを流すために近くの池に身をひたしはじめた。
夜行性の光る目玉とにおいを頼りに、子ひつじは彼のいる場所に小さく腰をおろした。
すっかり信用されたらしいおおかみは、池のふちにすわる白玉に鼻を近づけ、お互いのにおいを確認するように押し付けた。
おおかみの半分の大きさもない子ひつじは、力にはかなわない。
まだ加減を知らないおおかみの少しの作用で、子ひつじはまた、ひっくり返ってしまった。
洞穴に戻った二匹は、もう疲れはてたのか、身を寄せあって静かな寝息をたてているのだった。
-6-
出会って初めての朝が来た。
昨夜の静けさがまるで嘘のように、鳥がうたい、花がおどり、風がなく。
吐いた息は白くなって消え、「もり」の放つ生命力あふれる空気の中にとけこんでいった。
二匹は昨夜の池で水を飲んでいた。飲み方は、そろってひどいものである。
立つ気力すらないおおかみは、座ったまま、舌で飲むことももどかしいのか、池に顔を突っ込んで飲んでいた。
子ひつじはそんなおおかみの行動を真似しているだけでなのであるが。
さすがに空腹状態で本来の獲物を隣におくことは厳しいのだろう。子ひつじが近づくと嫌がるようなしぐさを見せる。
おおかみはすでに、この子ひつじを自分の手で育てていくことに決めていたらしい。
何がそこまで彼を動かしているのかは分からない。
自分と同じ境遇の、ひとりぼっちの白玉に、同情、あるいは、共感が生まれたのかもしれない。
そうはいってもやはり、依然として空腹という状態が続いていることに変わりはない。
まずは自分のいのちの存続を考えなければならないのだ。子育てはそれから十分にしよう。
子ひつじを洞穴に残して「もり」に舞い戻ってきたおおかみは、いつものように地面に鼻を押し当てて探った。
今度は目をぎらぎらさせることはなかった。何故か、今なら何でもできそうな気がしたからだ。
彼の期待を裏切ることなく、獲物は簡単に見つかった。そして幸運だった。
足にけがをおった野うさぎが、仲間に心配されながら倒れこんでいるのである。
ようやく彼に、第二の人生を歩む機会が与えられた。
躊躇はしなかった。子ひつじが待っているのだ。自分の帰りを。
おおかみは、前足を出した。
-7-
口の周りを血だらけにしながらおおかみが洞穴に帰ってきた。
それを迎えたのは、相変わらずおとなしく座っている子ひつじだった。
その時の子ひつじのしっぽが無意識のうちに揺れていたことは、両者とも気がつかない。
おおかみは冷たい地面に腰をおろす。満足したように鼻をならすと、口の周りを長い舌でなめ拭いた。
どうやら狩りは無事、成功したらしい。
活気の戻った目で子ひつじを追っても、もう理性がとんでしまうことはない。腹は満たされた。
久しぶりの幸福にひたることができた。たとえそれが偽りの関係だとしても。
しかし、彼は改めて子ひつじのにおいをかいだ。やはり、仲間という存在は大きいのだろうか。
子ひつじもまた、心なしか嬉しそうにじっとして、頭をなめられているのだった。
今年の冬は、一段と寒くなりそうだけれども、二匹ぼっちなら平気だ。怖くもないし、寒くもない。寂しくない。
心にじわりと熱いかたまりがうまれた。
すると、子ひつじから突然、ぐうう、という音がした。
一度びっくりして体をふるったおおかみだったが、すぐにその音の意味を理解したのか、立ち上がった。
きょろきょろ目を動かしたら、洞穴から出ていってしまった。
今度はあまり長く待たないうちに、彼が帰ってきた。その口に、野うさぎの死骸をくわえて。
子ひつじはまた、血なまぐさいにおいが洞穴に充満するのを感じた。
でも、どうすればいいのか分からなかった。
おおかみが子ひつじの目の前に死骸を落とした。そして何かを待っている。しっぽを振りながら。
でも、子ひつじはどうすればいいのか分からなかった。
おおかみが見守る中、子ひつじはその死骸の横を通りすぎた。洞穴の外に出る。
そうして食べていた。地面に生えている、緑色の草を。
おおかみはわけもわからず、その様子を落ち着かないようにながめていた。
彼は初めて、自分とは捕食対象が違う動物に遭遇したのであった。
-8-
子育てはもちろんしたことがなかった。まして、ひつじを養ったことなんてなかった。
今までひつじは、単なる食材にすぎなかったのだから。
草をはんでいる子ひつじの揺れているしっぽを気にしながら、おおかみは熟考に明け暮れていた。
限界のある頭でようやく導きだした種の違い。
おおかみにとって肉が糧であるように、子ひつじにとっては草が大切な栄養源なのである。
体のしくみなどという難しいことは考えない。とにかく、彼は食べ物が違うという重要なことを認識し始めた。
食事の済んだ白玉は、満足げにこちらに歩いてきた。もうお腹がいっぱい。ふかふかの草の上で昼寝がしたい。
でも、ここにふかふかの草はない。だから、白玉はおおかみの隣に体をくっつけた。
おおかみがひとなめすると、甘えるような声をのどから出して、頭を何度もおおかみの体にこすりつけた。
小さなからだからもちゃんと体温を感じて、おおかみはなんとなく心が軽くなったような気がしたようだ。
子ひつじがまばたきをしてうつらうつらしていると、不意に、あの刺激が首を伝った。
電気のような痛さに驚いて飛び跳ねる。何が起こったのか。やはりおおかみの方に視線を向けてみる。
彼の立派な牙は、赤黒く染まっていた。そう。また、噛まれたのだ。
いい加減、勘弁してほしいとは思うだろう。無意味に未完治のきずを広げられるなんてことは。
そうして退いていたら、おおかみが寂しそうな顔をした。
同じように首のきずをなめ、痛みを慰めようとしていた。
それから彼は、頭を白玉の尻を押し当てて洞穴の奥へと行かせようとするのだ。
ようやく理解した。
おおかみは子ひつじをくわえて運ぼうとしていたのだ。不器用な口づかいで、首の皮だけつかんで。
そのはずだったのに、予想以上に力が入ってしまい、子育てには必要のない牙が食い込んでしまったのだ。
子ひつじが押されるままに奥へ行くと、そこには少しの枯れ草が堆積していた。
おおかみは、冷たい地面で弱ってしまわないように、ここで子ひつじを寝かせようとしていたのだった。
愛情が通じたのかどうかは分からないが、横になって傷口をなめ続けるおおかみに子ひつじが寄り添った。
滅多に鳴かない子ひつじが小さく鳴き、耳をたらして、まぶたを静かに落とす。
二匹の動物の間には、いつまでも平和な時が流れていくように思えるのだった。
-9-
ある晴れた日の午後のことだった。
冬に入りかけた冷ややかな空気が、ほほを切り裂くように鋭く通りすぎてゆく。
そろそろ草木も準備に入っていた。身を隠し、葉を落とす。それぞれが生き延びるために。
寂しかった「もり」の景観は、よりいっそう閑散とし始めた。
ところで、子ひつじは食べ物に困ることになってしまった。
細い前足で地面を掘り返しても、出てくるのは根っこや虫の死骸だけである。むなしく手を黒くするだけだ。
そんな子ひつじにおおかみが寄り添うと、子ひつじはその体重だけで横にころんとひっくり返ってしまった。
また空腹状態に陥っているらしい。心配するおおかみ。
子ひつじを抱くように体をおおって温める。子ひつじが小さなくしゃみをした。その音にびっくりする。
大人しくなった子ひつじの頭にあごをのせ、うっすらと目を閉じかける彼は、しっぽをゆらゆらさせていた。
しかし、そんなことをしていても、子ひつじの空腹はひどくなる一方。なんとか、食料を見つけ出さなければならない。
子ひつじのほうが我慢できずに、無理やりおおかみの腹の下から飛び出ると、また歩き出した。
おおかみも何とかしてあげたいとは思っているのだろうが、何せ植物のことなどまるで知らない。
どんなものを食べるのか、どこを食べるのか、おおかみである彼には何も分からない。何も知ろうとしなかった。
寂しくなって、子ひつじに聞こえない声で低くうなった。
ふと、視界に白い塊が映った。もちろん、子ひつじではない。
おおかみの顔つきが変わった。獲物をとらえた目だった。その視線の先にいるのは、何度も彼の腹を満たしてくれたうさぎだ。
一匹でふらふら動き回っている。やはり、植物を探しているのか。
とにかく、その時は何も考えずに、うさぎを襲った。その肉をかみちぎっていた。
そして、気づいたのだ。子ひつじがやって来て、死骸の腹の辺りのにおいをかいでいるときに。
おおかみが胃袋を食らおうとしたら、苦々しいものが舌の上に広がった。それはいつもことだったのに。
そうなのだ。うさぎも草を食べて生きているのだ。
おおかみは食べかけた胃袋を子ひつじの前に差し出した。
おおかみの涙