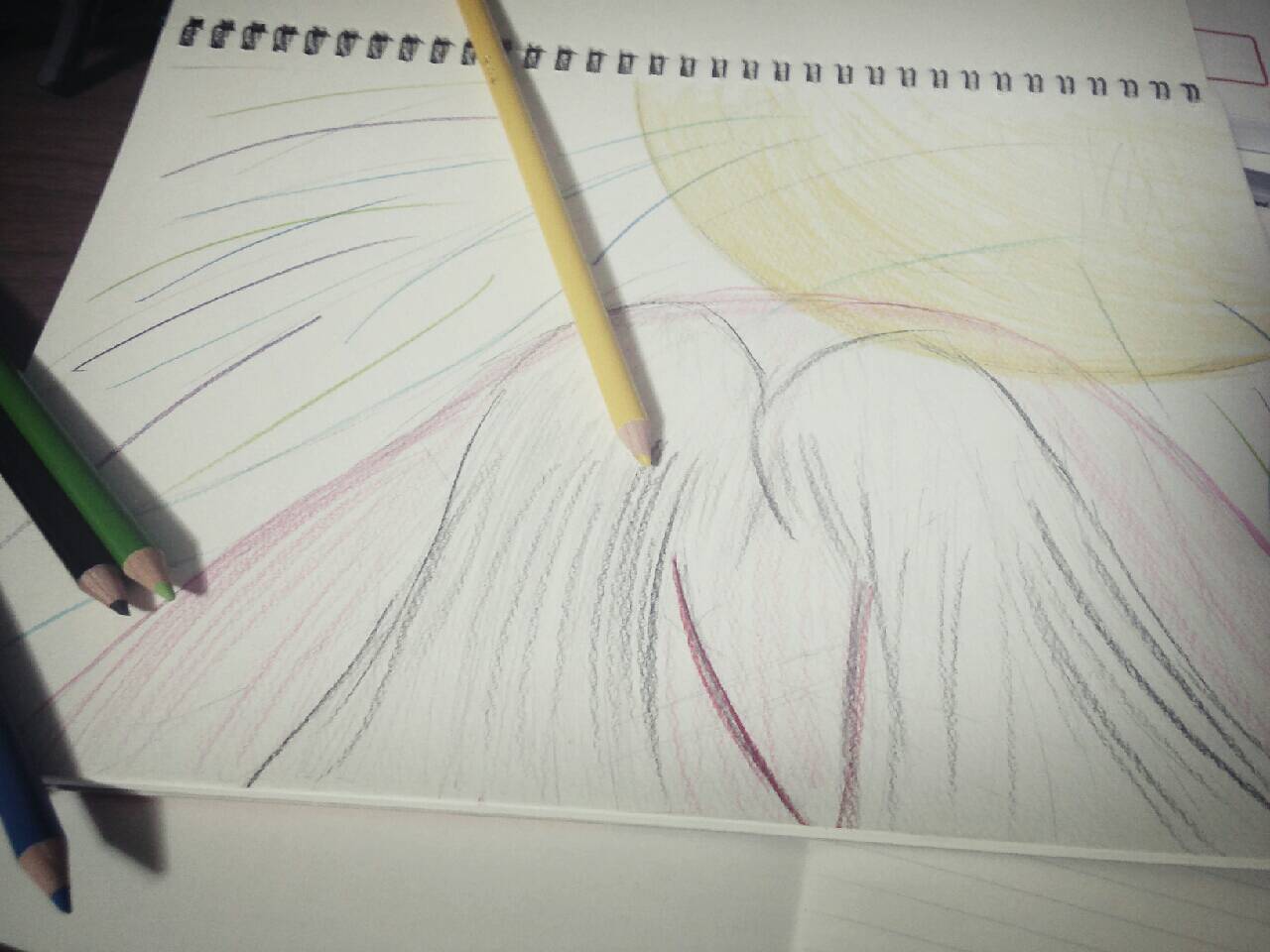
月日の百合
終わりの合図
雨の匂いがする、と私は思った。
だから、雨の唄を歌おう。そんなことを、静かに静かに、思った。
雨の匂いがした。
ここはバス停。森も畑も田んぼもすべて、雨に濡らされていた。
こんなにいつもと違う色。だから、雨の日は魔法がかかる、と小さい頃はいつも思っていた。
また彼女と会うのだろう、と思った。
私は嬉しいような悲しいような気持ちになった。
足音がした。
女の子が、バス停に座る。
それとともに、ぼんやりとした雨の匂いが一層強まった。嗚呼、雨だな、とまた思った。
私は、ぼんやりと、田畑を見つめていた。田畑は雨で霞がかっていた。
しばらくして、私は彼女をみた。すると、彼女も私に気がついていたようで、すぐにこちらを向いた。
だけど、私は一向にそのことに対して反応を示さなかった。私のぼんやりとした気質を、彼女は知っているためか、いつものように、彼女はにこりと微笑んだ。
一分か、二分過ぎたような気がする。
「後輩………」
と私は小さく呟いた。
そうすると、彼女は優しく静かに、答えた。
「何ですか? 先輩」
そういうと、私は、答えずまたぼんやりと、森や田畑を見た。
雨だね、とそういうと、雨ですねぇ、と彼女は静かに言った。
はあ、と私が嘆息をすると。
「どうしたんですか? 先輩」
と、彼女は言った。
「まあ、色々悩みがあってね」
と私がいうと、彼女は、私相談に乗りますよ、というような表情で、長椅子のこちらの方へよってきた。
私は、彼女の雨の匂いとは違うシャンプーの香りを感じていた。
彼女のシャンプー。それは、私のシャンプーの香りと同じだった。だから、私はいつも自分の髪の匂いに気づくとドキドキしていた。
私は、ある人に恋をしている、という話を、他人事っぽくはなした。
彼女は真剣に悲しそうな表情で、私の話を聞いてくれた。
だけれど、途中から彼女は泣き出した。
静かな静かな轟き。
私はワケが分からなかったけれど、だけれど。雨が、雨が降っていたから、ちょっとだけその意味に気がついた。
「実はその好きな人って、君だよ」
と、私は言った。
一層雨音が強まった。
風が吹き、緑が揺れ、翠雨も雨と混じっていた。
彼女の驚いた顔が私の前にあった。
彼女が理解をする前に、私はキスをした。彼女の強ばった緊張が消えたとき、勘違いじゃなかった、と安心した。
いつまでそれを続けていたかは、わからない。
だけど、周りの喧騒がやんだ頃には、私はキスをやめていた。
雨の魔法が振り止んでしまうから。
私は静かに深呼吸をした。
すると、パチパチと言った音が聞こえてきた。
雨の音はまだ振り止まない。雨の音と勘違いしたのだろうと思った。
だけど、違うようだった。
この異様なほどに広い、緑に包まれた学校の庭を見回すと、男が姿を現した。
端麗な容姿だった。色白な少年。弱々しい体躯。だが、憎むべきはその軽薄さ。いかにも、世間一般の女の子に慕われそうな、いわゆるイケメンだった。
敵だ。
「すごいね、その小説? 暗記したの?」
と彼は藪からに訊いてきた。
「自分で作ったの」
ときっかりと答えた。若干怒っている風を装った。
すると、彼は、そのことに気づいたようで、すごいな、と驚いてみせたあと。
「ごめん、盗み聞きするつもりはなかったんだ。用事があって、ここに来たんだ。そうすると、人の声がするからさ」
「どこから聞いてたの?」
「初めから」
と彼はすぐに答えた。よかった、と私は思った。
そうして、私は傘を開いて歩いて帰った。
この雨の匂い。嗚呼、魔法かな、と思った。でも、どうせ魔法なら女の子がよかったな。
だって男は嫌いだもの。
傘を開いて、しばらくすると、雨は弱まった。雨が完全に消えゆく前に駅に着いてしまったから、私は傘を閉じた。雨の艶やかな匂いは消えて、人工的な都会の閉塞的で、なぜか心安らぐ匂いがした。
周りは早々とせからしい足音が続いている。
何に、そんなに急いでるのかしら、と私は思う。
けれど、私の足はもっとせからしかった。音がしばらく続くと、いつの間にか、二つ駅を超えていた。
慣性力で行き過ぎる身体を惰性的に重心を倒すことで、私はバランスを保った。
日本語のアナウンスの後に、英語のアナウンスが聞こえてくる。私は外へ出る。改札を抜けると、雨が止んでいた。
私は、まだまだ雨の匂いでいっぱいの街を照らす日差しの、をかしさに胸打たれながら、歩いて行った。
路地の傍らにある葉っぱの上に、雫がのっていた。少しの風で雫が落ちていく。私の足音で雫が落ちていく。私は、楽しくなって、走り出そうか、と思った。けど、やめた。
だって、頭のおかしな女だって、思われたくないもの。
流石に、衆人の前で、頭のおかしな女だとは思われたくはないのだった。
私は路地裏の喫茶店についた。
人目につかない喫茶店。「まんげつのいろ」という名の喫茶店だった。おかしな名前だった。月の色? それは白だ。しかもひらがな! なんておかしいんだろう! と私は狂いながら思った。おそらく、満月という言葉が私を狂わせたのだ。
私が入ると、鐘が鳴った。ちょうど、エロティックな、ラヴェルの蛾が流れていた。いつもはジャズが流れていたり、時々、おかしな具合に、クラシックが入るのだった。
いつも、この店でクラシックが流れ出す時は、ひとつの曲を続けて何回も流すのだった。だけれど、演奏者は毎回違うようだった。
「…ねえ、月日(つきひ)ちゃん、何考えているの?」
となりの人形のような少女が声をかけにくそうに聞いてくる。どうやら、ボーッとしていたらしい。
月日。それは私の名だ。月と日。相反する気持ち悪さが私らしい、と思った。
「今の私にぴったりだな、って思いまして。この曲。夜の……」
最後は曖昧に濁した。
「そうなんだ……」
彼女は話が続かないことを憂いて言った。
「それより、日和ちゃんは、まだですか?」
「うん……」
水月(みづき)は、答えた。
この人形めいた、それこそ、人魚めいた可愛らしい水月。ルナティックな月ではなく、癒しの月。
おそらく半月なのだろう。どこまでも綺麗な半月。そして、どこまでも、儚い。水面に揺れる半月。一瞬の風でさらわれてしまうほど。
だから、私はさらってしまいたくなる。
この魅惑的な唇も。あどけない肢体も。すべて。それは、私が頭のおかしな女だからではない。もっと、深く、彼女の根源が、本質が、周りの人間をそうさせるのだった。
ここまで考えて私は考えを改める。
彼女は、新月だった。狂わせることを決して主張はせずに、じわじわとその相手を狂わせる。星々の綺麗さにとらわれているうちに、目には見えない新月に取り込められてしまう。
彼女の中には、何もないのに、周りの人間を狂わせてしまう。
それは、一種の呪いだな、と思った。
言葉がなくなって、呪いの人魚の首筋を見つめていた。今では何のあともない。
私は、いつのまにか、昔のことを思い出した。
魔法の吸血
水月と友人となってその日、彼女は今日は家に帰れない、と言った。
だから水月を家に泊めてあげた。
水月と夕飯を食べ、私たちは私の部屋にやってきた。
私たちは夕飯で話したいことはすべて話してしまっていて、会話がなかった。私と彼女は初対面と同義だったので、お泊まり会のノリではない。
だから、寝た。電気を消して。
でも、眠れなかった。
だからベランダに出ようと、私はカーテンを開いた。
満月だった。
「月日ちゃん眠れないの……?」
月明かりに照らされた水月は言った。月の光に揺らめく水月の首筋を私は見ていた。
「うん……」
「月日ちゃん可愛い……」
「え?」
不意を突かれた。私も、水月のことが可愛いと思っていた。
一瞬心を読まれたのかと思った。
「だって、月明かりに照らされて、白いパジャマで……」
水月はうつろな目をしていた。まるで満月に、狂わされてしまったみたい、と思った。
私は、水月に近づいた。
「水月ちゃんのほうが可愛い……」
水月を眺めているとボーッとしてきて、敬語もなくなった。
私は、心底綺麗だな、と思いながら、肩を掴んだ。柔らかく青白い。
女の子だ。
どうしたの、というような目でこちらを見返してくる。
月明かりに照らされる水月。嗚呼、美しい。
なんでこんなに美しいんだろう。食べちゃいたいくらい。
私は、月明かりに照らされた首筋を見た。
魅惑的な首筋。
魅惑的な首筋。
魅惑的な首筋。
私は、そこに唇を近づけた。
気がついたときには、首筋に歯を立てた。
彼女の、新月の匂いが、血の臭いに汚されていく。どんどん、汚されていく。
わたしは、舐めた。はちみつのように甘く舌が、しびれた。
彼女は、小さな悲鳴をあげた。
うっとりと、余韻に惚けていると、彼女はこちらを押し倒してきた。
彼女の首筋から血が胸元をつたい垂れてきた。垂れてきた血は、月の光に刹那、きらめいた。私の白い服は血の飛沫の犯された。
綺麗だ、と眺めていた。
「月日ちゃん、満月みたい………。私を狂わせて……本当に綺麗で。本当……月日。夜は満月………。昼は明るい日の光……」
そうか、私は満月なんだ、と思った。
彼女を狂わせたのは、私だ、とそこで初めて気がついた。
彼女は私と同じように首筋にまるで吸血鬼のように、歯を立てた。
「甘い……」
と水月は言った。
そうして、何度か、彼女は私の首筋を舐めたあと、疲れたように眠った。
私は、惚けたまま朝が来た。
昨日のことはなかったようだった。まるで、満月と新月、二つの月が起こさせた魔法のようだった。
けれど、首筋の傷だけがあの夜を思い出させるのだった。
昼の百合
ジャズが聞こえだし、私の意識は現し世へと戻った。
気づいたら、注文していたアッサムのミルクティーも来ていた。白い湯気が出ている。もう梅雨だ。そうであるのに、じめじめと。
私は、香りを楽しむ。アッサムの濃厚な匂いが、ミルクの香りに負けないように、揺らめいている。濃厚な甘い匂いが嗅覚を刺激した。女の子みたいに。
私は口にする。甘味が広がる。世界も広がる。
私は、目の前の少女を知覚する。水月。彼女が、飲んでいるのは、コーヒーだ。
カフェインの強い匂い。
頭が冴える。茶色の雫。匂いは好きだけれど、私は、コーヒーは嫌いだ。
あの強さが嫌いだ。飲むと眠くなる。カフェインの薬に犯されたみたいに。
そんなことを考えていると、足音が聞こえた。日和の足音。タン、タン、タン、と軽快な音。単調な、ドラムみたいで眠くなる。
「今日遅くなったわ。ごめん」
私と水月の長い髪とは違い、ボーイッシュな短髪。まるで、彼女の太陽を象徴してるみたい、と私は思う。
「大丈夫ですよ」
と私はいった。
敬語な私だ。女の子には敬語なのだ。
好きだから。
窓側へと寄ると、片手で持ちながら肩にかけているバッグをおろしている日和は座る。
ボーイッシュな姿に思わずときめく。
嗚呼、かっこいいな、と私は思う。その癖、きめ細やかな肌。嗚呼、好きだな。
嗚呼、欲しいな。
そんなことを思いながら、私は目を閉じて、ジャズの音が止まるのを確認して、先ほどの唄を歌った。
可愛い女の子の唄。
目を閉じて、浮かんだ映像をそのまま言葉にしていく。いつもより、すんなりと綺麗な言葉がやってくる。
だってさっき、つい、しちゃったし。
終わると、目を開けて、唄の感想を聞いた。
「この主人公のモデルは日和?」
と水月。
「はい、日和です。ついでに言うと、雨の日だけ恋が進展してきたという設定です」
「ああ、だから雨が降ってきたとき、彼女が会うのだろう、ってなったのか」
日和はすぐに気がついた。
「そうです。雨が降ってくると、必ず彼女と出会い、そして恋が進展する、という裏設定です。語る余裕がなかったので、喋りませんでした」
「やっぱり月日ちゃんの小説は詩だね」
「だから、唄、ですよ」
思わず私はふくれた。
しばらくすると、またジャズが流れ出した。私たちはそれを背景に、話した。私たちのあいだに話が途絶えることはなかった。
私たち三人はもちろん仲の良い。
太陽の出てる間だけ。
夜の百合
負野(おうの)日和は天才だった。
あるとき、その場で手渡した本を三十分と経たずに、丸暗記してみせた。
「私はただの落ちこぼれだよ……」
斜陽の貫く喫茶店。その中に佇む、日和の表情はとても悲しげに見えた。
日和の趣味は、絵を書くことだった。とてつもなく貧乏臭い画材で、とてつもない絵を書いた。
素人目に私でも分かった。見ているだけで感情の波が、不規則に波紋を広げた。
彼女の退廃に。
彼女の劣等に。
そのとてつもない劣等感を目にするたびに、私のプライドは傷つけられた。
私は彼女の才能に狂おしいほどに惹かれた。日和は美しかった。
「なんでそんなに巧く、絵を描けるんですか?」
私は訊く。
「別に絵を描いてるわけじゃない。イメージが勝手に白紙に映るんだよ。水面のように、ね。私はただそれを写し取ってるだけだ」
常人には、分からない感覚だった。日和はもう人ではない、そんなことを私は、思った。
ちょうど、水月と出会った頃だっただろうか。
私は日和に対する劣等感から、日和にキスを迫った。拒絶された。新月の魔法にかかったように、拒絶された。
それから、私と日和は二人で会うことがなくなった。
私の家には、二日に一度水月が来た。
初めは気が付かなかった。だけど、何度も何度も、彼女の肢体を眺めているうちに気がついた。
血の人形。
水月の身体には、私の家に泊まった数と同じだけ、切り傷があった。
異様な切り傷。そう、まるで芸術みたいな。
私は、その傷を解釈し、傷を付け加えた。水月の狂おしいほどの美貌に嫉妬して、日和の劣等感の、光に、嫉妬して。
二日後にまた水月が泊まりに来ると、傷はまた一つ、増えていた。私の傷に答えるように、少しだけ大きな傷だった。悲しみに満ちた、劣等感に満ちた傷だった。
だから、この傷をつけたのは、日和だと分かった。
私は、文通相手に手紙を出すように、また水月を傷つけた。
水月は芸術品だった。彼女の中には何もない。なのに、周りを狂わせる。
新月みたい、と私は思った。
水月の傷が増えるたびに、私は日和を理解した。日和がどんなに、優しい人間であるか、理解した。
私には無理だ、と素直に思った。
「月日に罪はないんだよ、月日を作った世界が悪いだけだから」
傷は優しく語りかけてきた。あまりの優しさに、涙が出た。水月に嫉妬して、また、涙が出た。
涙が溢れて止まらない。
どうしよう、と私が思っていたら、水月が静かに抱き寄せた。
「大丈夫。私は月日ちゃんのこと好きだよ……」
妖艶な母の笑みで言った。嗚呼、これこそ、エロティック…、と私は静かに思っていた。
今つけた傷から血が垂れて、私の服を汚した。少しだけ嬉しくなる。
嗚呼、血の人形………嗚呼、新月………嗚呼………嗚呼……なんでこんなに、綺麗なの………。
新月の夜
今夜は、水月の来る日だった。
私と水月は二人で帰る。たわいもない話をする。それこそ、本当、姉妹のように。
新月の中、私たちは家に入る。我が家の匂い。空虚な匂い。嗚呼、好きだな。
衣擦れのさわさわとした音が聞こえる。するりと水月は服を脱いだ。
私は料理に取り掛かる。静かに、素早く味付ける。トントントンっと、板の音。サラサラサラっと、鍋の音。くんくんくん、といい香り。盛りつけ完了、いい料理。
私が、机に料理を出すと、静かに、水月も席に着く。
私は味を確かめて、美味しいな、と我ながら思う。美月の感想を聞こうとはしない。料理は一つの芸術だ。芸術は、本当は一人で成り立つものなのだ。
私たちは食べ終わり、部屋へと入っていく。
私が部屋に入ると、水月は私の方を向いてきた。
嗚呼、血の人形。
傷が一杯、美しい。星に照らされ、素晴らしい。
新月の夜が一番、水月を美しく儚く、見せた。だって、月の光は汚いんだもの。陽の光は汚いんだもの。
白の光は、いろんな色を混ぜた色。光の絵の具を混ぜた色。
だから、白は汚い色。
私は、水月に傷を付けて眠った。水月を抱きかかえて。
ぬくもりを感じていると、寂しさに涙が出てきて、声を立てて泣いた。
私は水月にキスさえしていない。
だけれど、それでいいんだ、と私は思っている。
友人信仰
朝、起きるといつものように、水月の裸体がそこにあった。
血の人形。
私は、彼女の肢体を揺らした。彼女は甘い声を上げる。
「おはよ、月日ちゃ……」
語尾は寝ぼけて聞こえない。
私は階下へ降りて料理を作った。
鼻歌とともに、水の爽やかな音が聞こえてくる。
私はその中、一人で食べて、水月と交代するように、お風呂に入る。
私が、足を浸けると波紋は広がった。どこまでも、どこまでも、と思ってるうちに反射して、不規則に干渉を起こす。
嗚呼、綺麗だな…。
私は揺れが鎮まる前に、身体を浸ける。身体を浸けると、波紋はさらに広がった。
それが、やがて鎮まると、半透明な鏡のように、私を写した。
嗚呼、平凡……。
悪い方ではないけれど、水月のそれと比べれば、平凡な容姿だった。
「狂わなくては………」
私がそういうと、言葉は揺れて広がった。お風呂の壁に反射して。水面(みなも)の鏡に反射して。私の心に反射して。
「月日ちゃん、早くして」
その傲慢な声が家の外から耳に響いて、ようやく私は意識を戻した。
どうやら、考え事をしていたらしい。
私が外へ出ると、太陽の光が、眩しくて目を思わず細めた。鮮明に風景が焼き付く。
「早く行こ、いつもの電車、間に合わない」
水月は、にこりと微笑んだ。人形みたいに。
水月の仕草は完璧で、心をいつも示さなかった。それなのに、私の考えていることをぞっとするような手つきで当てるのだった。
「私のこと考えないで、月日ちゃん」
そう、こんな風に。
彼女には仕草がない。素顔がない。個性がない。個性がなさすぎて、完璧すぎて、とても綺麗。それでいて、狂ってる。
水月は、本当に容姿だけの、そのかんばせだけの、異様な存在だった。彼女の感性は、その容姿に後付けされた矛盾だらけの、物語のようだった。
「水月は、なんでそんなに綺麗なんですか?」
私は、無意識のうちに声を出していた。
水月はいつもの表情になっていた。新月の顔。高貴に狂って、無表情で、それでいてどこか楽しそう。
「それはね、昨日の月があまりにも綺麗だったから……」
そうね、新月は綺麗だものね、私は心の中でそう答えた。
しばらく、歩いていた。私たちの間に、会話はなかった。いつも私たちはぎこちなかった。まるで互いの鋭さに怯えているみたい、と私は思ったけれど、水月は何を考えてるのか、私にはわからなかった。
住宅街の木たちを見ていたら、妙に変な感傷に囚われた。この緑たちは、嫌われ者なんだな、と思った。
ふと、水月の白い肌を見ると、美月の肌に嫌われて反射した白の光が私の網膜を刺激した。嗚呼、こうやって、嫌われて反射した光しか見えない。
「多分、こういう考えをする人たちが狂っていくんだろうな…」
私は、嬉しくてため息をつきながら笑った。
水月は意味のわからない、という目つきで申し訳なさそうに、こちらの様子を伺ってくる。
演技なのかは分からないけれど、得体のしれない恐怖が映って、信仰が宿った。
忘却の水面
私と、水月は歩く。静かに歩く。二人で歩く。
公園があって、私はそこに入っていく。
いつものことではない。イレギュラーな行動だ。
水月もついてくる。ぶらり、ぶらりと、私がブランコをこぐと、ぶらりぶらりと、水月がブランコをこぐ。
「ねえ、水月」
私は、新月の匂いの風を受けながら言った。
「どうしたの? 月日ちゃん」
水月は首をかしげる。
私はこぐのをやめる。
私はいう。
「うん……。……なんでもないです」
………時々、見える。
……いや、見えなくなる。
水月が消えて、水月が私とそっくりになる。
今だってそうで……彼女が私に見える。
目の錯覚だろう、と思うのだけれど、それは、しばらく続くのだった。
「目が悪いのかな………」
「多分ね、それはね、忘れてるんだよ………」
水月は遠くを見て、言った。
月日の百合
2に続く。

