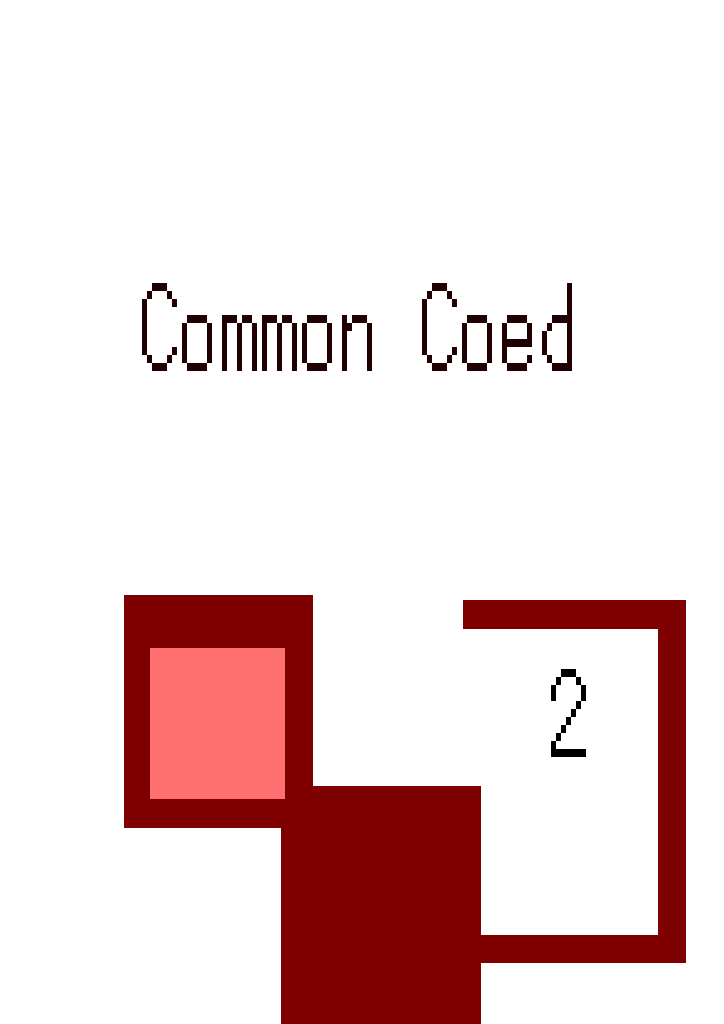
Common Coed 2 ヒヒノヒ
ヒヒノヒ
琺瑯大学二年生の一条恵は、揺れる電車の窓から外を見た。
青い葉を茂らせた山々が映っている。
美しい景色ではあるが、しかし、もはや恵は感銘を受けない。
車窓から見える景色がこうなってから、一時間は経っている。
恵は椅子に座ったまま、大きくあくびをした。
「退屈そうですね」
恵の対面に座った金髪の少女(彼女たちはボックス席に座っていた)が、ペーパーバックをめくりながら言った。
少女は、恵の友人の中学生、シャリー・アグレルだった。東欧のリービッヒという小王国から日本に留学中の、リービッヒの王女である。
恵は、その王女様に答えて、
「山ばっかずーっと見てれば眠くもなるわ。携帶も圏外だし」
「私みたいに本でも持ってくればよかったんです」
「家に忘れてきたのよ、文庫本もDSも」
「それは残念でしたね」
それだけ言うと、シャリーは黙った。
自分の読書へ戻ったらしい。
恵は少しむっとした。
「態度がドライな子ねえ。西洋人だからかしら」
「そういう偏見に基づいた発言はやめた方がいいです」
「はいはいっ」
恵はむくれた。
しかし、大学二年生の自分が、十五歳の少女に言い負かされたきりでは面白くないと思い、
「それにしても、あんたの命を助けたお礼が、山奥への温泉旅行だなんてしぶすぎよね」
彼女たちが電車に揺られているのは、山奥の温泉旅館へ向かうためである。
そして、この旅行は、とある事件で一条恵がシャリー・アグレルの一命を助けたことへの、リービッヒ王国からの『礼』であった。
「別の場所の方がよかったですか?」
「私みたいないまどきのナウでヤングな若者としちゃあ、温泉旅館での湯治よりはヨーロッパへでも旅行する方が嬉しいわね」
「ナウでヤングって、ずいぶん古い日本語をお使いになりますね」
「……あんた、日本に詳しいわよね。来て一ヶ月も経ってないのに」
「色々事前に調べました」
「勉強熱心なことで」
恵は、またあくびをした。
「少し寝るわ。着いたら起こして」
そう言って、腕を組み、目を閉じた。
※
「恵さん、恵さん」
恵は体を揺すられていることに気がついて目を開いた。
電車の椅子にすわっている。
そして電車は揺れていない。
どこかの駅に停車しているようだった。
「……着いた?」
恵の体を揺すっていたシャリーはうなずいた。
電車を降りた。
駅には、一人の年老いた駅員以外は誰もいない。
降りた乗客も恵とシャリーだけだった。
二人は、駅員に切符を渡し駅を出た。
鬱蒼とした森が広がり、細い山道が彼方まで続いている。
「この道を歩くわけ?」
と、恵はシャリーに言った。
「その通りですよ。たった四キロばかりです」
「帰りたくなってきた」
「無理ですよ。今日はもう、この駅に電車は来ません。近くの宿泊施設は私たちが予約した『べっこう屋』さんだけです」
「うげえ」
「恵さん、ずいぶんとやる気がないですね。この前、アンジー叔父さんをやっつけた時とは別人みたい」
「ああいうのと今回は別よ。旅行で辛い目にあいたくないし、山道を四キロも歩きたくない」
「じゃあ、恵さんだけ、ここで寝ます? 今の季節なら、風邪も引かないかもしれませんよ」
「……あんたって本当、嫌な子供よ」
恵はしぶしぶと歩き出した。
細い山道を大分歩いたところで、沢に出た。
「少し足を冷やしていかない?」
恵が提案し、シャリーは承諾した。
二人は川のほとりまで歩き、靴と靴下を脱ぎ、足を水に漬けた。
「ふう」
恵はため息をつきながら、辺りを見回す。
静かな山中である。
鳥の声と川の流れる音の他は、風によって揺れた木の葉の、サラサラという音が響いているのみだった。
そんな静かな山中の景色を、恵は眺めた。
「あ」
眺めている内に、恵は声を出した。
「なにかありました?」
隣で足を水に漬けたシャリーが聞いてくる。
「ちょっと、そこに変なのがいた気がして」
「変なの、とだけ言われても困ります」
「類人猿みたいな生き物が、木の合間にいた気がしたのよ。身長二メートルぐらいのね」
恵は、川の向こう岸の林を指した。
シャリーは一応、そちらを凝視した後、
「気のせいじゃないんですか。都会の喧騒を離れてこんな山奥に来たせいで、神経が敏感になりすぎてるんですよ」
「だといいけどねえ」
と、恵は首をひねった。
しばらく休んだ後、二人は立ち上がり、また山道を歩いた。
宿であるべっこう屋に着いた頃には、既に日は落ちていた。
※
べっこう屋は二階建ての古ぼけた旅館だった。
築何年になるのかは検討もつかない。
大正か、あるいは明治か。
下手をすれば江戸時代からの建物にすら見えた。
さておき、古い旅館に入った恵とシャリーは、一人のしわくちゃの老婆に出迎えられた。
「遠いところをよく来たねえ、お嬢ちゃん方。都会の子には山道は応えたんじゃないのかい」
「ええ、まあ。割と疲れました」
と、恵は答える。
すると老婆はうしゃしゃと笑う。
「そうだろう、そうだろう。まあ、部屋で休んで、風呂にでもつかって、それからゆっくり眠るといい。あんたらの部屋は、二階の東端の松の間だから」
「松ということは、一番いいお部屋なんですか?」
シャリーが聞いた。
「そういうことになるかねえ。明治の頃なんかは文豪さんが泊まってたような部屋なんだよ」
「へえ」
恵は感嘆の声を発した。
「そういえば、おばあちゃん。私たち以外のお客さんは?」
「二組ばかりいるよ。あんたたちと同じように女の子二人――東京の女子大生って言ってたかねえ――と、あとは中年の男の人が一人だけ」
「なんだ、貸切じゃないんだ」
と、恵は言った。
それを聞きとがめたシャリーが、
「そういうことを旅館の人の前で言うのはやめてください。流行ってないことを喜ぶようなものですよ」
と言う。
老婆は気にせず、
「まあ、うちに来るお客さんの半分くらいは、そっちのお嬢さんみたいなことを考えてらっしゃるようだけどねえ」
と、笑った。
恵たちは、きしむ廊下と階段を上がり、松の間へたどりついた。
「……ここが本当に一番いい部屋?」
部屋の電気をつけると同時に、恵が言った。
すえた臭いのする畳、暗い電球、ぼろぼろのふすま、黄ばんだ障子。
お世辞にも居心地のいい部屋とは言えなかった。
「でも、恵さん。テレビがありますよ、こんな山奥なのに」
シャリーが部屋の隅に置かれた、古ぼけた小さなテレビを指した。
「いまどき一時間につき百円払ってまで、そんなテレビ見たくない」
と、恵は答える。
「百円かかるんですか?」
「テレビの横にお金を入れる穴があるでしょ。コインロッカーみたいなさ」
「……本当だ」
シャリーは物珍しげに、テレビの横に据え付けられたコイン投入口を見る。
しばらくしげしげと見つめた後、
「お金を入れたくなりますね、これ」
と言った。
「後悔するだけだからやめな。どうせこんな山奥じゃ、チャンネルだって一つか二つしか映らなさそうだしね」
恵はバッグを下ろして開き、中から入浴用具を取り出した。
「シャリー、お風呂に行かない?」
言われたシャリーはうなずいた。
風呂場は一階にあるので、二人は部屋を出て階段を降りた。
階段を降りきったところで、風呂場の方から、きいきいときしみ音がした。
一人の中年男が歩いて来る。
老婆の言っていた別の客だろう。
苦虫を噛み潰したような顔に黒縁メガネをかけている。
入浴後なのだろう、浴衣姿だった。
「こんばんは」
恵は男に会釈した。
シャリーもそれに続く。
男は、なにも言わずに、頭も下げ返さずに歩き去り、二階へと登っていった。
「無礼な人ですね」
男を見送った後にシャリーが言った。
「一国のお姫様であるこの私に対して無礼者めって感じ?」
「それもないとは言いませんけど、単に礼儀の問題です」
「こっちがあいさつしてんだからてめえもしかえせよコラ、ってことね」
「ええ」
「まあ同感だわ。むかつくわよね」
恵は、とりあえずそう同意をしたが、つけたした。
「でも、ああいうオッサンって、見てるだけで可哀想になるところもあるわ」
「そうですか?」
「一体どこまでつまんない人生を送ってれば、あそこまでクソみたいな表情でクソみたいな態度を取れるんだろうなって、思うもん」
※
風呂は露天風呂だった。
構造から考えて見晴らしはいい――はずである。
なにせ、既に夜だった。
おそらくは広がっているのであろう、山の風景がまるで見えない。
「……すごい損した感じ」
「三泊ですから、明日と明後日に見れればいいでしょう。今日のところは、温まりましょう」
「まあ、そうね」
恵とシャリーは、体を洗った後に湯船につかった。
相当に熱い湯だった。
「あっちちち」
と、湯の中に身を沈めながら、恵が言った。
シャリーはそんな恵を尻目に、平然とした風を装っていた。
とはいえ、彼女の表情も少しこわばっている。
二人とも、数分を待たずして真っ赤になった。
双方とも我慢の限界に近づいていたが、さりとて自分の方から「出よう、あるいは休もう」と言い出したくもない。
やがて恵が言った。
「シャリー? 毎年さあ、温泉地でちょっと嫌な死に方する人たちがいるのって知ってる?」
「嫌な……死に方……ですか?」
シャリーの声は多少うわずっていた。
年少の彼女の方が、のぼせが回るのが恵よりも早い分、辛いようである。
「子供やお年寄りがね、あっつーい温泉に無理して入り続けちゃって、そのままぽっくり逝っちゃうの」
「お気の毒ですけれど…‥なんだか……間抜けな感じもしますね」
「ねえ。遺族も笑えばいいんだか泣けばいいんだかって感じよね」
「遺族は流石に……笑わないでしょう」
「そうか。まあでも、あんまり望ましい死に方じゃないわ」
恵がそこまで言ったところで、二人とも無言になった。
ふうふうと息をする。
恵が続ける。
「別に、私やあんたが、今、そういう死に方をしそうだっていうわけじゃないんだけど、でも、熱いお湯に長くつかってるのは体によくないかなって思うの」
「なにが言いたいんです」
「出よう」
「はい」
二人はさっと立ち上がった。
ざばりという音がした。
※
恵は浴衣に着替えると、脱衣所に置いてある壊れたマッサージ機の上にひっくり返った。
完全にのぼせていた。
シャリーも同じだったようで、ふらふらとマッサージ機の近くまで歩いて来ると、恵の上にどすんと座り込んだ。
恵は思わず、
「ぐえっ」
と言ってしまう。
が、シャリーを押しのける気にもならず、彼女を体に乗せたまま、マッサージ機の上でただ陶然としていた。
のぼせがマシになるまでこうしていようと思った。
十分ばかり経った。
脱衣所のガラス戸がガラリと開いた。
「お風呂もひどそうだなあ。ここ選んだの失敗じゃない?」
「いや、逆に雰囲気あると思うんだけど」
という黄色い声の会話を響かせて二人の女性が入ってくる。
恵が頭をもたげて声の方向を見てみると、やせたポニーテールのメガネに、小太りの巨女である。
年の頃は恵と同じくらいに見えるが、女子大生なのか社会人なのかまでは、見ただけではもちろん分からない。
女子大生たちは、マッサージ機の上の恵たちに気がついたようで、
「こんばんはあ!」
と声をかけてくる。
恵はなんとか声を絞り出し、
「こんばんは」
と返事をし、シャリーもそれに続く。
「お湯の加減はどうですか?」
と、メガネの方が聞いてきた。
「ヤバいです。熱いです」
恵は言った。
「……のぼせたんですか?」
巨女に効かれ、恵は、
「ええ、まあ。そんなとこです」
と答えた。
そして、今度は逆に女性たちに聞く。
「お二人は大学生ですか?」
「ええ。下地大学の三年生です。私は二階堂鈴子」
こう答えたのはメガネである。
小太りもそれに続き、
「私は山中千里でーす。鈴子とは同級生」
「あ、そうですか。じゃあ、私より年上ですね。私、琺瑯大学二年の一条恵です。この腰の上にいるのは……」
「シャリー・アグレル。ヨーロッパのリービッヒからの留学生です」
「ヨーロッパの留学生? かっこいい!」
シャリーが自己紹介をした途端、小太りの千里がはしゃいだ。
まあ確かに珍しかろう、と恵は思い、ちらと、シャリーの顔を見てみる。
かっこいいと言われ、まんざらでもなさげな顔をしていた。
「リービッヒっていうと、東欧の小王国ですよね。それで確か、王家の名前がアグレル家……」
こう言ったのは二階堂鈴子だった。
「私の国をご存知なんですか?」
「ええ、まあ。大学の専攻の関係で」
と、鈴子は言った。
他方、山中千里は、鈴子の言葉を聞いて、ますますはしゃぐ。
「え! じゃあ、シャリーちゃん、お姫様かなにかなのかな!」
こうなるとシャリーもますますいい気分になったようで、
「私、リービッヒの王位継承者です。こう見えても」
と、少々自慢げな臭いを含ませて言った。
「きゃあ、すごい、すごい! あとでサイン下さいね! 部屋はどっち?」
「松の間です」
「一番いい部屋じゃないですか! 流石、王族ですね!」
千里はますます大騒ぎである。
(こんな宿に泊まってる時点でヨーロッパの王族らしくない)
と、恵は思ったが、もちろん口には出さない。
女子大生たちは、しばらく経って去った。
もちろん、服を脱いで露天風呂に向かったのである。
女子大生を見送った恵たちは、なんとかのぼせも冷めたので、ふらつきながらも立ち上がり、浴場を後にした。
※
部屋に帰る途中で、宿の老婆に出会った。
老婆は、ちょうどよかったとばかりに、恵たちに声をかける。
「あ、お嬢ちゃん方。夕飯は食堂でお食べになりますか」
「ここって食堂で食べるの?」
恵が言った。
「一階の広い座敷間を食堂にしとります。もちろん、静かに食べたいなら、私がお部屋までお運びしますけども」
「恵さん、どうします?」
シャリーに問われて、恵は老婆をじっと見た。
腰の曲がった小身の年寄りである。
彼女に、二階まで食事を運ばせるのは悪い気がした。
「食堂でいいわ」
「それだったら、もう、すぐに食べていただけますけれども」
「じゃ、そうします」
恵たちは、老婆に案内されて、一階の『食堂』へと向かった。
食堂は十畳ぐらいの畳間だった。
刺身や煮物で構成された、この手の宿としては平凡な夕飯が、行儀よく並べられていた。
食堂には先客がいた。
先ほどのしかめつらのメガネの男が、黙って食事を続けていた。
恵は内心、
(げっ)
と思ったものの、とりあえずお辞儀だけして、座った。
シャリーは先ほどのことを根に持ってか、頭を下げなかった。
幸いにして、メガネの男と恵たちの席は離れていた。
メガネの男は部屋の北東の隅、恵たちは南西の隅の席である。
恵とシャリーは座って、食べ始めた。
食事自体は、うまからずまずからずといったところで、特筆すべき内容でもなかった。
が、楽しい食事だったかというと、それはノーである。
部屋の正反対にいるとはいえ、メガネの男にどうしても気を使った。
やたらとしかめつらをしているため、下手にはしゃいでは怒り出しそうな雰囲気も感じられ、恵たちとしても黙々と食べざるをえない。
幸いにして、男の食事が先に終わった。
男は、部屋の戸に向かって、
「食い終わった。かたづけてくれ」
と言った。
しばらく経って、老婆がやってきた。
「放っておいてくれれば、後でかたづけますのに」
と、老婆は、男の食器をかたづけながら言った。
男はそれには答えず、別の話題を老婆に振った。
「ばあさん、聞きたいことがある」
「なんでしょう?」
「この辺りの山で、ここ最近、化物の目撃報告がなかったか」
「はあ……狒々のことですか」
「それだ。その猿の化物だ」
「私が子供の頃なんかは、地元のもんがよく言ってましたけど、最近はめっきり、そういうのは減りましたです」
「そうか。じゃあいい」
男は立ち上がって、足早に去っていった。
「変なおじさんですね」
男がいなくなった後、シャリーが言った。
恵もそれにはうなずいたが、気になったことがあったので、
「ねえ、おばあさん。狒々とか猿の化物とか、一体なんのこと?」
と、かたづけ中の老婆に聞いた。
老婆は笑って言った。
「この辺りには、大きな猿の化物が出て、人間を捕って喰らうという言い伝えがあるんですよ。まあ、よくある昔話さね。その名前が狒々」
「じゃあ、あのおじさんは、そんな子供だましのお話を本気にしてるってことでしょうか?」
シャリーが言った。
「あの人は東京で書き物かなにかをやってる人だって話だから、そういう怪談かなにかの記事でも書くためにやって来たんじゃないかねえ」
「そのためには、インチキでもなんでもいいから、最近の目撃談が欲しかった、とか?」
「かも、しれないよ。じゃあ、私はこれで。お嬢ちゃんたちは、食器はそのままにして部屋に戻ってくれていいからね」
老婆は食器を全て盆に載せ、立ち上がり、去っていった。
それを見送ったあと、シャリーが言った。
「恵さん、あの狒々がどうとかいう話、なにか気になるんですか?」
「いや、ほら。この宿まで来る途中に、猿みたいな変なのを見たからさ、私」
「……そういうの信じるタイプなんですか?」
「別にその伝承だかをそのまま信じるわけじゃあないけど。なんか、ああいうことを言われる理由はあるんじゃないのってこと」
「動物を見間違えたんですよ」
「……あんた、もうちょっと子供らしく素直になった方がいいわよ」
「私、日本で言うところの『思春期』ですから」
シャリーはそう言って、みそ汁をすすった。
※
夕飯を食べ終わった恵たちは、やることもないので早く床についた。
布団に入って数時間が経った頃。
熟睡していた恵は、シャリーに揺すり起こされた。
「なによ」
恵は目をこすりながら言った。
シャリーはもじもじと言う。
「おトイレに行きたくなっちゃいました」
「そう。いってらっしゃい」
恵は再び、布団を頭からかぶる。
「恵さんも一緒に行きません?」
「私は結構。眠い」
「いや、あの。だから……」
恵はもちろん、シャリーがなにを言いたいのかは分かっている。
布団をかぶったまま、恵は言った。
「怖いから一緒に行ってくださいって言えれば行ってあげる」
「うー……」
シャリーは唸った。
命のやりとりの場では度胸のいい少女も、暗闇の廊下は怖いようだった。
「ほらほら、どうしたの」
恵は言いながら、布団の中でにやついた。
「……ください」
「ん?」
「……トイレに一緒に行ってください。お願いします」
「よろしい」
恵は立ち上がった。
例によってきしむ廊下を踏みながら、二人は進んだ。
電気はどこにもついておらず、月光を頼りにするしかない。
幸いにして新月の晩ではないので、足元は見える。
ぎしぎしと歩いて、廊下のつきあたりにあるトイレに着いた。
「……ちゃんと、待っててくださいね」
シャリーはそう言って、トイレのドアを閉めた。
恵は、大きく体を伸ばした。
トイレのドアの近くに、窓が据え付けられていることに気がついた。
ガラス越しに、月の淡い光に照らされた夜景が見える。
青黒く光る森と川、そして山。
少し幻想的な風景であり、恵は見惚れた。
しかし、それは長い時間のことではない。
風景に異物が現れたせいで、見惚れることが出来なくなったからだ。
動くもののないはずの風景上に、さっと動く一つの影が現れた。
最初は、森の辺りだった。
恵は気のせいかと思いつつも、影の現れた近辺に目を凝らした。
影がまた現れた。
今度はゆっくりと動いて、月に照らされた野原へと移動した。
必然、影も月に照らされ、形が浮かび上がる。
恵の見覚えのある形だった。
来る途中の沢で見かけた、猿型の化物に瓜二つに見えた。
やがて、影は再び森に戻り、消えた。
そこでちょうど、トイレのドアが開いた。
中から、シャリーが現れる。
「あ、シャリー。あのね……」
恵はシャリーに、今、窓の外で起きたことを説明した。
「恵さん、寝ぼけてるんじゃないですか」
シャリーは彼女らしい回答をする。
「……もうちょっと話を合わせてよ」
「でも、信じられませんよ」
「なるほど。あんたは迷信やオバケなんて一切信じないってわけ」
「全くとは言いませんけど、恵さんの言うのはちょっと」
「この辺りにはオバケや化物なんていないってわけね」
「そうですよ」
「ああ、そう」
恵はそう言うと、廊下を足速に歩き出した。
「め、恵さん。置いていかないで」
シャリーが半泣き声で言う。
恵は立ち止まった。
「オバケや化物がいないなら、なにも怖いことなんてないでしょ」
「その……この廊下が怖いっていうのは、そういう具体的ななにかが怖いっていうんじゃなくて、私の想像の中の恐怖心が、その……」
シャリーはしどろもどろになる。
恵は流石に可哀想になり、シャリーのところまで戻ると、
「わーったわよ」
と言って、その手を引いてやった。
※
翌朝八時。
恵とシャリーは、松の間のふすまがガラリと開く音で目を覚ました。
「よかったら、朝餉をすませてくれんかね」
と、ふすまを開いた老婆は言った。
二人は目をこすりながら、一階の食堂へ降りる。
食堂には誰もいなかった。
「他のお客は?」
席に座りながら、恵はそう聞いた。
「七時には朝食をすませて、外に出て行ったよ」
「外ね。この辺りに、遊ぶところなんてあるのかしら」
「そうですね。温泉でゆっくりするのが目的のお客ばかりだと思ってました」
と、シャリーも同意する。
老婆は笑って、
「大したもんもない山奥だけど、見る物ぐらいはあるよ」
「うーん。たとえば、どんな?」
恵は聞いた。
「そうさね。たとえば、女子大生の二人は、『ヒヒノヒ』に行ったよ」
「言いにくい名前ですね」
「……もしかして、例の狒々に関係があるの?」
「昔、この辺りに出るっていう化物狒々を、南方氏真っていう強いお侍が退治したっていうお話があって、それにまつわる碑石が置いてある場所があるのさ。一応、この辺りじゃあ、名所ってことになるかねえ」
「ふーん……行ってみようかな」
「そうかい? フロントで聞いてくれれば、場所は教えてあげるからね。でも、他所の観光地みたいなのは期待しないでおくれよ。じゃあ、ごゆっくり」
老婆はそう言い、去っていった。
残された恵とシャリーは、朝食を食べ始める。
上手い米と薄い味の味噌汁に、焼いた鮭とたくあんがついていた。
「ね、シャリー。私たちも、その狒々の碑とかに行ってみない?」
「また、狒々ですか。まるでこの辺りの名産みたいですね」
「嫌ならいいわ。他にやりたいことがあるなら、そっちにしましょう」
「別に嫌じゃないです。狒々を信じるわけじゃありませんけど、その狒々の碑が名所旧跡なことには変わりがないでしょうから」
朝食をたいらげた二人は、部屋で着替えるとフロントに降り、老婆に狒々の碑の場所を聞いた。
川ぞいの道を、南に二キロほど行った場所にあるらしかった。
※
狒々の碑までは、小一時間かかった。
舗装がなく、上り下りのある二キロは意外に手間取る道だったのだ。
特にシャリーは中学生である。
ともあれ、碑があるという看板の出た場所に着いた。
案の定というべきか、先客がいた。
例の女子大生コンビ、二階堂鈴子に山中千里である。
女子大生二人は、小さな石の前に立ちつくしている。
恵は、そんな二人に、
「おはようございます」
と声をかけた。
「おはようございます……」
山中千里が元気なく挨拶を返す。
「……お二人とも、元気がありませんね」
シャリーが言った。
「はるばる歩いてきてこれじゃあ、元気もなくなります」
二階堂鈴子が、小さな石を指した。
高さ五十センチばかりの小さな石に、文字が彫られている。
ぼろぼろに崩れているので、なんと書いてあるかまでは読めない。
「…………これが狒々の碑ですか」
「これしかないと思いますよ」
鈴子がそう言い、ため息をついた。
「こんなんだったら、お風呂に入って寝てた方がよかったあ」
千里が言った。
「……期待すんなと釘を刺されていたけど、これほどとはね」
恵も肩を落とした。
が、デジタルカメラを取り出し、碑の写真を撮った。
「文句を言いつつ、撮るんですね」
「ま、一応ね」
恵はまたシャッターを切った。
パシャリとやるのと同時に、背後で、ガサリという音がした。
四人は一斉に、そちらを見た。
木々が林立した深い森がある。
「……今の音、気のせいじゃないですよね」
鈴子が言った。
「少なくとも、私は聞こえましたけど」
恵が答え、残りの二人も無言でうなずく。
彼女はまだ、カメラを抱えたままだった。
また、林で音がした。
恵はそちらにカメラを向け、シャッターを切った。
フラッシュは炊いていた。
直ちに、液晶画面で、撮った写真を確認してみる。
「なにか写ってますかあ?」
横からのぞき込みながら、千里が言った。
写真には木の群れと、その間を歩く、毛の生えた生き物が写っている。
「二足歩行をする猿」
と、恵はつぶやいた。
彼女にはそう見えたのだ。
「また、そんなことを」
シャリーはそう言いながらも画面を見て、
「……確かに、猿に見えなくもないですけど」
と、感想を述べた。
最後に見た鈴子も、
「言われてみれば、猿っぽいですね」
と言う。
「……やっぱり、この辺ってなにかいるのかしら」
「またまた恵さんの狒々実在論ですか?」
シャリーがあきれたように言う。
「ひひ? なんですかそれ」
と、千里が言った。
恵は、
「大したことじゃないんですけど……」
と前置きした上で、これまでのことを説明した。
沢で見かけた猿、老婆の話、そして夜中に見た影。
話が終わると、千里は、
「ええ、こわいなあ!」
と叫んだ。
あまりにも仰々しいので、恵はバカにされたようにすら感じた。
もっとも、当人は至って真面目なようで、
「ここにいたら、私たちも食べられちゃうかも! すぐに帰ろ!」
と、鈴子にすりよる。
「……まあ、ここにいる意味はないかもね」
鈴子は言いながら、千里を押しのけた。
恵たちも、千里はともかく鈴子には同感だった。
四人は、狒々の碑を後にした。
※
「おや、お揃いでのおかえりかい」
宿に帰った四人を、老婆がフロントで出迎えた。
「おばあさん! 出たの! 出たんですよお!」
と、千里が老婆に騒ぐ。
「出たって、なにがだい」
「狒々ですよ、狒々! 恵さん、あれを見せてあげて!」
千里にせきたてられ、恵はデジカメを取り出した。
そして、例の写真をディスプレイに映し、老婆に見せる。
「ね」
「うーん……確かに、狒々に見えなくもないけどねえ」
老婆はどうも、写真に疑問を持っているようだった。
「熊かなにかの見間違いかもしれないですよね」
シャリーが言い、鈴子がうなずく。
この二人は、狒々などという生き物の存在には懐疑的なようである。
「まあ、なんにせよ、大きな動物が、あんたらの近くに来てたことは間違いがないようだねえ。誰も怪我をしなくてよかったよ」
と、老婆は言った。
そして、
「そういえばあんたたち、お昼は宿で食べるかい?」
とつけくわえる。
時刻はまだ、それぐらいの時間だった。
「私たちは、宿でお願いするわ、おばあちゃん」
と恵が言うと、
「私と千里もお願いします」
と、鈴子が続いた。
「そうかい。なんだったら、お昼までの間に、お風呂にでも入っちゃったらどうだい。汗を流しておいた方がいいよ」
と、老婆は言った。
※
シャリー・アグレルは、二階堂鈴子と一緒に服を脱いでいる。
二人は、露天風呂の脱衣所にいた。
宿の老婆の勧めに従って、昼食前に入浴を取ることにしたのである。
二人の同行者である一条恵と山中千里は、入浴を面倒がった。
「食後でいいわ、私は」
とは、一条恵の弁だった。
「シャリーちゃん、私、先に入ってしまうわね」
服を脱ぎ終わり、メガネを外した鈴子が言った。
メガネを外したために目の焦点がぼやけている。
それによって、普段の理知的な印象が多少薄れていた。
シャリーが露天風呂に着いた頃には、鈴子は既に入浴していた。
「んー……」
などと湯船の中で大きく伸びをし、ずいぶんと気持よさそうである。
シャリーは、ひとまず体を洗おうと思い、洗面器を持った。
風呂場の隅にすえつけられた蛇口をひねり、お湯を出す。
「恵さんや千里さんにも困ったものですよね。狒々がどうとか」
と、シャリーは、体を洗いながら鈴子に言ってみた。
「まあ、そうね」
「いい年をして、非現実的な話を真に受けて」
「恵さんの方は、必ずしも頭から信じてるってほどじゃないでしょう」
「それはそうですけど。でも、千里さんの方は?」
「あれは本当に信じてるわね。そういう子よ」
「そういう人ですか」
シャリーは体を洗い終わり、立ち上がった。
湯船へと歩く。
そして、白い湯気が大量にまきあげる湯の中に身を沈めた。
二分ばかりが経った。
シャリーは、早くも大分、のぼせはじめる。
ちらと、鈴子を見た。
平然とした顔をしている。
「……平気なんですか?」
シャリーは聞いた。
「私、熱いのは大丈夫なのよ」
実際、鈴子は顔色をひとつも変えずに、くつろいで目をつぶっていた。
また二分が経った。
シャリーは、いい加減辛くなってきていたので、
「すいません、私、出ます」
と言って、立ち上がった。
恵と違って我慢比べをするような相手でもないと思った。
湯船から出たシャリーは、ふうと息をついて、その場に座り込んだ。
火照った体を冷ましたかったのである。
ふと、湯船の方を見た。
……湯気の向こうに、黒い大きな影が見えた。
「恵さん? ……それとも、千里さんですか……?」
シャリーは言った。
目をつぶったままの鈴子が、それを聞いて、
「シャリーちゃん、あの二人がここにいるはずがないわ」
と笑う。
「でも、そこに誰かが……」
鈴子が目を開いた。そして、湯気の方へと目を凝らす。
「……なにも見えないけれど」
「鈴子さんがメガネをつけてないからじゃないですか」
「まあ、確かに私は、裸眼だと0.1もないけれど」
そんなことを言っている間にも、湯気の中の影は、だんだんと、シャリーたちのいる方へと近づいてきていた。
「鈴子さん、出た方がいいですよ」
「平気よ、シャリーちゃん。きっとあなたも、石碑の事件のせいで考えすぎてしまっているん……」
咆哮の音が、鈴子の声をさえぎった。
獅子の吠え声にも似た大音響である。
「きゃっ!」
鈴子も流石に、音には反応をする。
まずい状況だと判断してか、立ち上がり、湯船から出る。
影はいよいよ、近づいた。
まだ湯気に包まれているとはいえ、その姿ははっきりと判別できた。
「二足歩行をする巨大な猿」
シャリーは、先ほど狒々の碑で恵が言ったセリフを繰り返した。
彼女たちの眼前に現れたのは、現にそういう生き物だったのである。
「鈴子さん、逃げましょう!」
シャリーは叫び、走った。
鈴子も後に続く。
※
「ふむ。素っ裸で部屋に飛び込んできたのは、そういうわけがあったからね」
と、シャリーの話を聞き終わった一条恵が言った。
ざぶとんを枕がわりに寝転んでいる。
風呂場で狒々に出会ったシャリーと二階堂鈴子は、着替える余裕もなく宿を駆け抜け、一条恵の寝転ぶ松の間まで駆け込んだである。
二階の端にあるこの部屋が、露天風呂からもっとも遠かったのだ。
シャリーと鈴子は、恵になだめられて、とりあえず部屋にあった浴衣を着、松の間に座ると、顛末を恵に話した。
たった今、その話が終わったところだった。
「うーん」
と、言いながら、恵は起き上がった。
「鈴子さん、シャリーの言ったこと、本当ですか?」
「私はなにぶん、メガネがないとあまり見えないので……」
と、鈴子は申し訳なさそうに言った。
メガネは風呂場に置きっぱなしなので、今も鈴子は裸眼だった。
「ただ、湯気の中に、動く大きな影を見かけたのは確かです」
「なるほど。まるっきりの見間違いや嘘っぱちってことはないわけね」
と、恵はシャリーに言った。
「当たり前です!」
シャリーはむくれた。
「怒らないでよ。まあ、とりあえず、この目で確かめてみようかな」
恵は立ち上がる。
「お風呂場に行くんですか?」
「うん。あんたらの衣服や、鈴子さんのメガネも取ってこなきゃいけないし」
「私やシャリーちゃんも行きますか?」
「いえ、私一人で平気です。シャリーと休んでてください」
※
脱衣所に着いた。
特段、荒らされた形跡もなく、動物の毛等も落ちていなかった。
「狒々はこっちまでは追ってこなかったのかしら?」
恵は言いながら、浴場へと向かった。
浴場は静かだった。
が、湯船になにかがつかっている。
かなりの体積を持つ生き物のようだった。
恵は油断なく身構え、そちらに目をやる。
とはいえ、杞憂だった。
湯につかっていたのは、山中千里だったからだ。
「……千里さんかあ」
恵は拍子抜けした声を出した。
その声で、千里は恵の存在に気がついたようだった。
「あれ、恵さん、どうかしたんですかあ?」
「いえ、その……千里さん、お風呂は後にするんじゃなかったですか?」
「やっぱり気が変わっちゃってえ」
「そうですか。あの、なにか変な生き物がいたりしませんでした」
「なにもなかったですよお。なにかあったんですか」
「実は……」
恵は顛末を説明した。
説明が終わるか終わらないか内に、千里が叫ぶ。
「きゃー! そんな、怖い、怖い!」
千里はざぱんと湯から飛び出て、脱衣所へと駆けた。
が、脱衣場の目前――すなわち恵の目前で、つるりと水に滑って転ぶ。
前のめりに転んだ千里は、恵に向かって倒れこんだ。
結果、恵は千里にぶっつぶされた格好になり、共に倒れた。
「ごめんなさいねえ」
「……あの……出来るだけ早く、どいてください…………死ぬ……」
と、息も絶え絶えに、千里の下の恵は言った。
結局、浴場の捜索は意味がなかった。
誰もおらず、なにもいない。
ただ、湯の上に何本かの茶色い毛が散乱していたので、それだけは拾った。
あとは脱衣所でシャリーたちの服とメガネを回収し、部屋に戻った。
※
夜になった。
もはや夕飯もすみ、そろそろ日付が変わろうかという時間になっている。
松の間に、恵、シャリー、鈴子、千里の四人がいた。
山中千里が、
「猿のオバケが出るのに、一階の私たちの部屋なんかにいたくないわ。お願い恵さん、私と鈴子もあなたたちの部屋にいさせて下さーい」
と主張したのである。
恵は気が進んだわけではないが、さりとて断る理由もなかった。
だから今、四人で部屋に座っている。
外では風雨が吹き荒れ、窓がガタガタと鳴っている。
「こりゃまた、ずいぶんと荒れ模様だこと」
窓の外を見ながら、恵が言った。
「下手をすると、明日は宿から出られないかもしれないわね」
こう言ったのは鈴子である。
「ええ! 明日には帰りたかったのにい」
「千里ったら……私たち、もう二泊は泊まるはずだったでしょう」
「うん、でも、怖いし……」
「もったいないわ。ちゃんと予定通りの日数泊まりますからね」
鈴子はぴしゃりと言い、千里はしゅんとなる。
「にしても、本当に狒々なのかしら」
恵が言った。
その手に、先ほど風呂場で拾った毛を持っている。
「その毛を調べれば、どんな動物かは分かりますよね」
と、シャリーが言う。
「といっても、この宿で鑑定できるわけでもないしなあ」
「動物に詳しい人なら、どんな種別かくらいは分かるのじゃないかしら」
と、鈴子が言う。
「なるほどね。……でも、詳しい人って?」
恵がそう言うと、部屋にしんとなった。
少なくともこの四人の中にはいない。
「おばあちゃんとかどうかしらあ」
千里が言った。
「あの、宿のおばあちゃん?」
恵が言うと、千里はこう答えた。
「ずーっとこの辺りに住んでるなら、この辺りの動物の毛かどうかは分かるんじゃないかなって、思うの」
恵はシャリーを連れて、廊下を歩いている。
一階のフロントにいるはずの、宿の老婆に会うためである。
結局、毛について聞こうという話になったのだ。
老婆のところまで行く人間は、四人の中からジャンケンで二人を選ぶこととなり、恵とシャリーが負けた。
「おばあさんにはなんて言うんです?」
階段を降りはじめたところでシャリーが言った。
「お風呂場に毛が浮いてた、とでも言うわ」
「それだと、いかにも宿の管理を責めてるみたいになりません? お風呂場に毛が浮いてるなんて、いい感じではないですよ」
「細かいわねえ、あんた。じゃ、山道で拾ったことにする」
二人は階段を降りて、フロントに向かった。
しかし、フロントには誰もいない。
ただ、「私用につき席を外しています。また後ほどお越し下さい」と書かれた看板がかけてあるのみだった。
「どうします?」
「まさか、この天気で外に出たとも思えないけれど」
「おばあさんの私室にでも行ってみますか?」
「こーいう看板かけてるってことは、邪魔されたくないんだと思……」
恵がそこまで言ったところで、電気が消えた。
停電のようだった。
シャリーは無言で恵に抱きつく。
「ひどい天気だからなあ。停電も無理ないか」
「部屋に帰りましょう!」
シャリーが叫ぶように言う。
「あんた、この宿の廊下が相当苦手なのね」
恵はそう言い、手探りで闇の廊下を歩き始めた。
あちこちに頭や脛をぶつけながらも、恵とシャリーはなんとか二階への階段を見つけ出し、登り始めた。
階段を登りきったところで、
「きゃあ!」
という声がした。
二階からだった。
「恵さん、あの声は」
「松の間のあの二人しかいないでしょう」
恵はシャリーを背負うと、闇の廊下を走った。
松の間に着いた恵は、手探りでふすまを開き、
「大丈夫ですか!」
と叫んだ。
「……ええ。大丈夫です」
鈴子の声がする。
「なにかあったんですか?」
「お猿が出たんです! 猿の化物が! 窓の外に!」
千里の叫び声がする。
恵はシャリーを下ろし、窓まで歩いた。
鍵を開け、窓を開く。
外には暴風雨が吹き荒れており、それが恵の顔と体を打った。
恵は気にせずに外を見回す。
――特に、なにもいないように思った。
念のため、窓の近くを手探りで探ってみた。
残念ながら、風呂場の時と違い、毛の一本も見つからない。
恵は窓を閉めた。
「とりあえず、今はもう大丈夫みたいです」
と言い、千里を安心させてやる。
「どんな感じだったんですか」
「とにかく、いたんですよ! 猿が窓の外を歩いてたんです」
「窓の外……つまり、屋根の上をですか?」
べっこう屋にはベランダはない。
二階の窓の外を歩いていたとなれば、空中を歩行したのでない限りは、一階の屋根を歩いていた、ということになる。
「私も、猿かどうかはともかく、なにかが歩いているのは見えました」
と、鈴子も言う。
「野生動物が歩いていたとしても、こんな山奥なら不思議はないけれど……」
恵は腕を組み、考えた。
しかし、なにも思いつきはしない。
「とにかく、今日はもう寝ましょう。この暗さじゃなにも出来ないし」
と、残りの三人に言った。
「大丈夫かなあ。寝ている間に襲われたらどうしよう!」
千里はまだ不安なようである。
恵は、
「私は腕には自信があるの。安心して下さい」
と、言ってやる。
言葉自体は嘘ではない。
もっとも、人外の生物が実在し、外を歩いているとしたら、それを素手でなんとか出来るような当てもなかったが。
※
夜はなにごともなく明けた。
とはいえ、明るい朝が来たわけではない。
空は曇り雨風が荒れ狂っていた。
「結局、今日はここに釘付けになりそうね」
起床直後、窓の外を見た鈴子が言い、千里は肩を落とした。
四人は、一階に降りた。
フロントには老婆が座っていた。
「おや、お早いおめざめだね。まだ六時前だよ」
四人共が二階からやってきたことは、特に気に留めていないようだ。
「ちょっと目が覚めちゃったのよ。ね」
と、恵が言い、
「ええ」
と、シャリーが継いだ。
「悪いけど、朝御飯はまだ出来てないんだよ」
「別に結構ですよ、いつも通りで」
鈴子が手を振る。
「そうですよ。私の部屋にたくさん、お菓子がありますから。取ってきます」
千里が言った。
「千里、朝御飯まで我慢したら?」
「でも、お腹が空いちゃってえ」
「部屋に戻ったら、狒々が出るかもよ」
鈴子が意地の悪い表情を浮かべた。
「え、やだあ」
千里はそう言うと、少し迷った後、恵の方へ救いを求めるまなざしを送る。
「……私、一緒に行きます?」
恵はため息を吐きながら言った。
「ありがとー!」
千里は恵の手を握り、ぶんぶんと振った。
鈴子と千里の部屋には、当然ながら誰もいなかった。
「お菓子はどのバッグに入ってるんです?」
恵は、部屋を見回しながら言った。
あちこちにバッグが散乱している。
大荷物でやってきて、それを部屋中に散らかしたというところだろう。
「えっと……窓際のところにある、あれです」
千里は窓のすぐそばにある、キャラクターバッグを指した。
サンリオのシナモンというキャラクターが印刷されている。
「じゃ、持ってきますよ」
恵はシナモンのバッグまで歩いた。
(このキャラってサンリオの中だと割と新参者よね)
などと思いながら、かがんで、バッグを拾った。
「?」
恵は、急に吹きこんできた風と雨の洗礼を浴びた。
窓の方を見る。
いつのまにか、開いている
そして、一匹の大猿が、窓の向こうに立っている。
恵は猿の方を見ながら、部屋の入口の方へと後ずさる。
「はっきりとあんたの顔を見れて嬉しいわ」
大猿は、咆哮を持ってそれに応えた。
恵は、じっと大猿の様子を見ている。
数秒が経った。
恵が口を開いた。
「……また鳴いてみて?」
猿はたじろいだ様子を見せる。
が、やがて、咆哮が流れた。
口は動いていない。
「なるほどね」
恵は、お菓子の入ったバッグを畳に置いた。
そして、猿に向かって走り、その顔面を右フックで殴る。
猿は、
「ぐおっ」
という声を出して倒れた。
先ほどまでとの咆哮とは、似ても似つかぬ声だった。
猿が倒れた数秒後、どたどたという足音が聞こえてきた。
やがて、手にフライパンや包丁を持った、千里、鈴子、シャリー、老婆が、部屋にどすどすと押し入ってくる。
千里が助けを呼びに行っていたのだろう。
「……恵さん。やっつけちゃったんですか?」
鈴子が言った。
「前の事件の時からお強いとは思っていましたが、素手で大猿を倒されるほどとは思ってなかったです」
と、シャリーも言う。
恵は、大猿の顔をつかんで言った。
「この前よりも圧倒的に楽勝よ。相手は人間」
恵は猿の首を引っこ抜いた。
ぽん、とすっぽ抜けた後から、人間の顔が出現する。
「……この前のメガネのおじさん?」
シャリーが言った。
初日に恵たちと夕飯を共にした、(老婆の話によれば)東京で著述業をしているという黒メガネの男の顔が、そこにあった。
もっとも、今はメガネをかけていない。
「隼雄! 大丈夫かい?」
老婆がそう言いながら、男にかけよった。
「そんなに強く殴ってないわ。もうちょい経てば気がつくわよ」
と、恵は言った。
※
松の間である。
隼雄と呼ばれた猿の着ぐるみに入っていた男と、老婆が座っている。
それを囲むように、旅館の客である残りの四人、すなわち、恵、シャリー、鈴子、千里が立っていた。
「その……問い詰めるみたいで悪いんだけど、ここまでの狒々騒動は、大体、あんたたちの仕業ってことでいいのかな」
恵が言った。
シャリーがそれに、横から口を挟む。
「恵さん、遠慮することないんですよ。被害者はこっちです」
「そうよ、そうよ」
と、千里も同調する。
老婆が口を開く。
「この旅館も、昔と違って湯治なんかは流行らない世の中になっちまったから、経営がどうにも左前でねえ。なんとか客寄せをしたいと思っちまって」
「そのために、狒々の伝説をでっちあげたんですか?」
鈴子が言う。
「狒々の伝説は別にでっちあげでねえ。元からあった伝説だ」
隼雄が言った。
「じゃあ、それに乗っかったって感じかな? 猿の着ぐるみを着て、石碑のところで私たちを脅したり、お風呂に出てきたり」
「前準備として、あんたらの前で、よそ者のフリをさせた隼雄に狒々の話をさせて伝説へ興味を引かせたり、狒々の碑に行かせたりもしたけども」
「最後の仕上げに、私と千里さんの前にはっきりと現れて、噂を確定させようとしたわけね」
「ところが、その仕上げが仇となっちまった。あんた、えらく迫力があるから、向かい合うと怖くなって、逃げるに逃げれなくなっちまって」
隼雄が言った。
「狒々より恵さんの方が化物だったということですね」
シャリーが言う。
「……あーそうよ、悪かったわね」
「警察に言わねえでくれると、ありがたいんだけども」
老婆が懇願するように言った。
「んー。石碑のところはご愛嬌にしても、お風呂場に出たのは痴漢だし、部屋に出たのは不法侵入だし……」
「不法侵入にはならないんじゃないですか。この人達の家だし」
シャリーが口をはさむ。
「えーと、それじゃあ……まあ、とにかくなんかの犯罪にはなんでしょ」
こう言われ、老婆と隼雄は青ざめた。
「……まあ、でも、私個人としては」
恵はコホンとせきばらいをした。
「もうやらないっていうなら、許してあげたいんだけど」
と言いながら、恵は残りの三人を見回す。
鈴子はうなずいていた。
シャリーと千里は、少し納得のいかない様子だったが、少し考え、
「いいです」
と、同時に言った。
※
翌日。
恵とシャリーは、駅のベンチに座っていた。
例の、宿から二キロばかり離れたところにある最寄り駅である。
女子大生の二人は、まだ泊数が残っているので、宿に残った。
「よかったんですか?」
ベンチに座ってジュースを飲みながら、シャリーは恵に聞いた。
ジュースは宿の出がけに、老婆からもらった物である。
「相手に害意まではなかったし。宿代も安くしてもらったし」
「まあ、恵さんがそう言うなら……」
と、シャリーは黙った。
が、しばらく経って、思い出したように、
「狒々は、本当に全部、あの人たちだったんでしょうか」
と、つぶやいた。
「それ以外にないでしょ」
恵はにべもなく言う。
彼女にとっては、もはや『終わった』騒動だった。
やがて、電車が来た。
※
数日後。
恵は、アパートの四畳半一間の自室に敷きっぱなしの布団の上で眠っていた。彼女にとってはやすらぎの時間である。
だが、どん、どんとドアを叩く音がし、その時間はかき消された。
恵は、
「はい!」
といらただしく言って、どすどすと玄関ドアに向かう。
チャイムを使わずにこういう叩き方をするのは、十中八九、隣の部屋に住むシャリーである。
二人は同じアパートに住んでいる。
「おはようございます」
ドアを開けると、シャリーが言った。
「もう昼過ぎなんじゃないの?」
「恵さんにとってはおはようだと思いました」
「はいはい、そうですよ。で、なんの用?」
「この新聞記事を読んでください」
恵は、シャリーの手から新聞を取った。
部数はそこそこ出ているが、お上品とは言えないスポーツ新聞である。
「あんた、こういうの読むの」
「お友達の、橋の下に住んでるおじさんからもらったんです」
「どういう友達よ……まあいいや」
恵は記事を読んだ。
『秘境の呪われた魔物! 伝説の狒々、山中にあらわる!』
という大見出しが書いてあり、更にその先に、
『某地方の旅館、べっこう屋付近で、怪生物の目撃情報があった。発見したのは、下地大学三年生の二階堂鈴子さん、山中千里さんで……』
と記事が続き、携帯電話で撮ったという、猿の写真がついている。
「あの二人の女子大生、お金をもらうか、かわいそうになったかで、おばあちゃんたちのイカサマにつきあうことにしたのかしら?」
「でも、この写真、着ぐるみの猿とは毛の色が違います」
記事に載っている、携帯電話の写真に写った猿の毛は白い。
隼雄がかぶっていた着ぐるみの毛は茶色かったことを、恵は思い出した。
「他の着ぐるみでもあったんじゃない?」
「ああいうのって、たくさん用意するには高いんじゃないんですか。それに、鈴子さんたちがグルなら、着ぐるみを変える必要ってないですよ」
「うーん……ま、いいや。これで宿屋が繁盛するなら結構じゃない」
恵はそう言って、スポーツ新聞をシャリーに投げ返した。
そして、
「じゃ、私は寝るから」
と、ドアを閉めた。
シャリーはまだ、ドアの向こう側でなにかを言っていたが、無視した。
布団に戻りながら、恵は、老婆と隼雄に問いただしたのは、石碑と風呂の件だけだったことに気がついた。
川辺の猿と月光の猿に嵐の夜の猿は、本当にあの隼雄だったのかどうか。
(まあ、重要なことでもないわ)
布団に入った恵はほどなく、眠りの世界に誘われた。
月の光の下で大猿とフォークダンスを踊る夢を見た。
Common Coed 2 ヒヒノヒ

