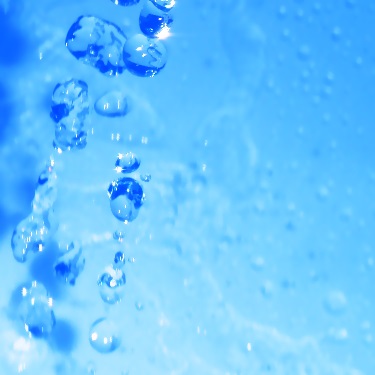
竹内璃遠の忘れ物
・これは実際にあったクトゥルフ神話TRPGの後日談を小説として書き起こしたものです。何卒。
「忘れ物にも気づけない、か……まだ光は遠いかね」
黎明私立第二学園。恐らくだが国内でも指折りの規模と設備を誇る学園ゆえ、増改築はそこまで珍しい話じゃなかった。その結果やはり学校と言う建物の構造上穴は増える。よく怪談話に出てくる開かずの扉や用途不明の地下室の完成だ。
……そう。だからこそ美術室の開かずの間の話だって今に始まった話じゃない。
美術室には、昔はどういう作りだったのかは知らないが開かずの扉が二つある。片方は開かないなんてわけではないのだが、開けると大きな鏡が現れる。ざっと目測したところ縦に2メートルはくだらない。動かそうとした馬鹿は少なくないのだが反対側に何かがあるのか、あるいは重量のせいか一ミリたりとも動くことはなかった。
そしてもう一つ。構造的に考えてこの鏡の向こう側の部屋に繋がっているのだろう、隠し扉のような腰までの高さしかない扉。こちらは木製で鍵は単純なシリンダー一つ。むしろこちらこそ開けられそうな気もするのだが、誰も開けようと試みる物はいない。
単純な話。開けようとしたものは不幸な目にあうなんて噂がまことしやかにささやかれているからだ。現に元クラスメートにとあるお調子者、と言うかその類の話を馬鹿にしている気のある特待生がいたのだが、その扉をぶち破ろうと鉛玉を叩き込んだ次の週の修学旅行で消息を絶っている。それ以前からその扉を開けようとしたものはことごとく不幸な目に遭い、しかもいくら破壊を試みても次の日には扉は元に戻っていると言うことからその小さな扉はかなり長いことタブー扱いされていた。
それでもあの扉の向こうには死体があるだの人ならざる者がいるとかまことしやかにささやかれていた気もするが、竹内璃遠にとってはこれ以上なくどうでもいいことだった。
ある日、聞く必要すら無い授業の退屈さに窓から外を眺めていた時、その小さな扉の中に大荷物を抱えて入っていく久遠の姿を見つけるまでは。
―――――――――――――
取る行動はまぁ一つ。授業を適当に抜け出して様子を見に行くのみだろう。はっきり言って特待生は割とやりたい放題なので授業中に校舎を爆破したりしない限り生徒指導室なんてことはない。むしろ執行部の方が特待生たちからすれば脅威だろう。
そんなことを考えながら、美術室へ。美術室は4,5年前に改装したらしく、前の構造は知らないが三階の突き当りに第一美術室、間に美術準備室(教員室?)を挟んで第二美術室と二部屋存在する。問題の開かずの間は手前の教室と美術室に隣室する会議室の間に存在する。元はどういう構造だったのか知らないが、恐らく手前の美術室は元は違う芸術教室か何かだったのだろう。幸い美術室はどちらも授業に使用しておらず容易に第二美術室に忍び込めた。
美術室は整然と並んだ机と乱雑に置かれた石膏像が目立ち、教室の後ろは画材の詰まった棚が占拠している。聞いた話によれば主に第二美術室は芸術系の特待生が放課後に仕様しているらしい。その結果として教室のあちこちに前衛的を通り越して発想が斜め上なブツが並んでいるが恐らくそれが芸術なのだろう。うん。
そして教室の後ろ、雑然と並んだ棚の隙間にその小さな扉はあった。一見収納棚に見えなくもない小さな扉。大きさとしてはよく学校にある赤い消火設備の扉程だろう。普段は開くどころか誰も触れようとしない扉。そっとその扉のドアノブに手をかけて捻ると、酷く瑞々しい手ごたえと共に扉が開く。林檎や柿のような、水分の多い弾力に富んだ果実に包丁を通すような感触。
真っ先に視界に入ったのは表の美術室にもある木製の棚と、埃を被った画材。そして縦横2メートルはくだらない大きな姿見。よく美術部員がデッサンの時に使っている木製のスケッチブックなどを立て掛ける器具(後で聞いた話イーゼルと言うらしい)が雑に壁際に立てかけられ、丸いスツールが5,6脚ほど重ねられて放置されている。そしてその中で一際目を引くのがちらりと覗く蛍光オレンジのキャリーケース。あんなゲテモノ、持っている悪趣味な人間は一人しか知らない。そしてその悪趣味の権化のような人物は当然のように部屋の奥にいた。
奥の一角はビニールシートが引かれており、そのスペースは諸々の工具や用途不明のバケツ、大きな模造紙の筒が転がっている。その中央に件の久遠在処は胡坐をかいて座っていた。
いつもの不真面目と言うか不敵な笑みは何処へやら、何処か難しそうな顔をして目の前に座らせた銀髪の少女の人形にてきぱきとロリータ調の衣装を着せている。大きさは大体80センチくらいだろうか。よくよく見れば部屋の隅には旅行用の大きなボストンバッグが投げ捨てられており、その中に入れて持ってきたのだろう。
と、不意に久遠はこちらに気が付いたのか顔を上げて振り返る。が、眉間に皺を寄せたまま難しそうな表情を崩さない。無言でじっとこちらを見ている。まるで遠くの見えないものに焦点を合わせようとしているような表情。常に視界が眼鏡頼りの竹内にとってその表情は何処か理解できるものだった。
竹内はその久遠の様子にふと思い立って声を出さずに口の動きだけで「変態」と罵倒する。が、余計に難しそうな顔をされるばかりでどう観察したって明らかに見えていない。その様子に少し面白くなり、適当に声を出さずに罵詈雑言を浴びせてみると、久遠は少し首を傾げて言う。
「んー? その白衣って竹内だっけか? すまん、なんか言ってくれなきゃ区別できないんだが」
「あぁ、ちょっと面白いから黙っててみた」
もうしばらく黙っていても面白かったのだが、火だるまにはされたくないので流石に返事を返す。声を聴いて確信できたのか、久遠は表情を崩して作業に戻る。
「やっぱお前か。あとドアちゃんと閉めてくれよな。出来れば内鍵も」
そう言いながら久遠は人形の服をテキパキと整えていく。リボンの多いロリータ衣装のためか、あちこち角度を変えながら蝶結びを作っていく。
流石にここでドアを閉めない道理もないので、後ろ手に扉と内鍵を閉めながら竹内は問いかける。
「ん、わかった。あれか……ここはお前が人形作るのに都合がいいから人払いしてるのか」
「まぁな。兄貴から鍵貰って引き継いだんだ。ぶっちゃけ授業なんて聞く意味ねえし、大体ここに籠ってる」
久遠の言う事も一理ある。第一今自分も授業をさぼってここにいるんだから何も否定はできまい。
黎明私立学園は少々変わっていて、年に1回約1カ月かけて行われる認定試験で合格点さえ取れれば難なく進級できるのだ。問題はもう1つの4月におこなれる大規模適性試験だがこちらに合格ボーダーは存在しないので例え言語を話せなくても割と何とかなる。
「まぁ、授業がつまらんのはわかる。出なくてもテストさえ受けてりゃ問題ないしな」
「それな。美術史とか知ってるわそんなもん……」
「人形師だもんな。それ以外も授業は必要なさそうだが」
「一応解剖学もとったが役に立たねえしな」
嘆くような口調に、思わず笑いそうになってしまう。この狂人じみた天才性ばかり持ち合わせる特待生に合わせた授業なんかした日には間違いなく一般生徒はテストで最低スコアをたたき出すだろう。
「普通の生徒もいるんだ、大した事は教えれないし理解できんだろう。それにしても……兄貴がいたのか」
「いたよ。去年ココ卒業してった」
「珍しいな、兄妹揃ってなんて」
あれ名残り、と言いながら久遠は大きなガラス棚を指さす。見渡してみると中には久遠とは少し作風の違う、異常なまでのリアリティを持った人形が10体前後おさめられていた。大きさはおおよそ100㎝が限界なのだが生々しいまでの肌の質感と虚ろな目のミスマッチ感が申し訳ないが非常に不気味だ。まだある程度創作感と言うか一見して愛らしい人形である久遠の作風がいくらかマシに思える。
「何ならあの中の人形持ってくか? 兄貴の作った人形は数が少ないから、一体数千万は固いぜ。しかも全部銘入りだ」
「人形は遠慮しておくよ、そうゆう趣味はないしな」
「そりゃ残念。まぁその兄貴も3カ月前に死んだからこのまま2年も放置すりゃ価値は倍だな」
こざっぱりと。驚くほどのすがすがしさと、無関心さで久遠はそう言って笑うと他のガラスケースを開けて人形を着せていた人形をしまう。その棚の中の人形は彼女が常々持ち歩いているアリスと同じような作風の物ばかりだ。数は彼女の兄が作ったものとほぼ横並びであることからしても、彼女の製作ペースはかなり早いことがうかがえる。
「美術館にでも飾ったりはしないのか?」
「さぁ。兄貴がそうしなかったんならオレはやらない。むしろここの人口が減るのはなんか寂しいからな」
「そうか。だったらここの人口は増えるだけだな、そのうち騒がしくなりそうだ」
軽く笑って返した竹内に、久遠は少しの沈黙を置いて首だけで振り返る。
「そうだな。……なぁ、竹内。一つ聞いていいか?」
「ん? 何だ。ものによっては答えかねるぞ」
「オマエ、なんでまだ染まってないわけ?」
どこかきょとんとした、不自然なものを見る目。
「あれ?髪染めるなんて話したっけ?」
少しおどけて見せる竹内に、久遠はますます不思議そうな顔をする。誰もが知っているだろうと思っていたことを誰も知らなかった時、人はそういう顔をする。
「オマエが染めるならグレーか銀だな。似合うと思うぜ、じゃなくて」
きしり、と表情を歪ませて久遠はガラスケースの蓋を閉め、適当なスツールに腰かける。どこか歪んだ自信に裏打ちされた笑みを孕む目元。
ああ、と不意に竹内は理解する。ここは彼女の王国なのだ。今は無き主に変わって君臨した王女。歓迎するモノは皆人形。確かに無理に扉を開けようとすれば呪われるのも当然だ。国を荒らすものは恐らくこの場にいるすべてが許さない。
「そうだな。今度やってみるか」
「……随分とマガイモノばっか見たり触ったりしてるみたいだが、ちっとも浸食されちゃいない。あちら側から遠ざけてる番犬でもいるのかね?」
まぁ座れよ、と久遠は近場のスツールを指さす。特に断る理由もなかったので木製のスツールを手繰り寄せ、ある程度の距離を保ちながら腰かける。どう足掻いたって久遠の攻撃の範囲外で、自分にとっては攻撃なぞ外しようもない距離だが恐らく王国を荒らせば一瞬でオダブツだろう。好き好んでしようとは思わないが。
「そっちのことならよくわからんな。何度も巻き込まれちゃいるが、まだあっちに行きたいとは思わんよ」
「ふぅん……まぁロクに理解もできてないようだが、聞きたいことがあれば答えるぜ?」
足を組み、皮肉げに笑う久遠に向かって「あと、あいつが番犬したら必要な奴にまで噛みつきそうだ」と付け加えて似たような笑みを浮かべる。
むしろあれは番犬、と言うよりも狂犬の類だろう。ユリア曰く角はだいぶ落ちた様だが、相も変わらず他の連中に喧嘩を売っては騒ぎを起こすのはやめてほしい。
「そうだな……俺たちのいる『此処』から何度も隔離されてるんだが、あれはどうやって出来てるのか。とか人形が使ってた炎と元は同じ力なのか……とか聞いてるときりがなさそうだが」
此処と彼方。1回は特例としてカウントしないにしても既に2回は隔離されている。一度は異世界とも呼ぶべき孤島に。二度目は鏡のような水底の町に。
巻き込まれて分かったことは一つ、その壁は恐ろしく薄く脆い物であると言うその一点だけだ。
「空間の隔離はできそうな奴は2人ほど知ってる。まぁそっちは理解不能のままで良いぜ、オレもそう言うもんだとしか思ってねえ。
で、炎と同じ力なのか。微妙に違うな。まぁ理解できないものだっつー点については同じだがな」
「ふむ……厳密には違うがその違いを理解する必要はないと?」
「簡単に言ったら柴犬だろうがチワワだろうが犬は犬だ。種類も構造も違っても犬っつーことと変わりねーのと同じだよ」
「成る程ね。魔術だとか呪いだとか呼ばれてるものでも、その効果は人を殺すものから癒すもの。その使い方は様々か」
魔法。エンジニアなんて科学的立場の人間が戯言を、などと言われそうだが現に目の当たりにしてしまっているのだから仕方ない。
時間を巻き戻す、なんてでたらめな奇跡も。燃料も道具も原理も何もかも無視して様々なものを発火させる暴力的な力も。全て目の当たりにしてきたが、何一つとして未だ理解に達していない。
「そうだな。だがオレがあいつらと違うのは、使ってるのは魔術じゃない。自分の一部、つまり手足と大差ないのよ」
そう言うとにぃ、と口の端を持ち上げて久遠は笑う。瞳の奥で焔のように光がちらついた。
「つまり、それを扱っている大抵の奴は自力じゃなくどっかから引っ張って来て使ってるが、あんたは自力で使っている……と」
その解答に「正解」、と久遠は満足げに声を上げて笑った。酷く楽しそうなその様子には呆れしか覚えない。
今までこの世の物とは思えない化け物はよく目にしてきた。だからこそあの出鱈目な炎もそいつらを使役している、またはそいつらのモノを借りてるのであれば一応腑に落ちる。だがこの目の前の魔女はそれが自分の持ち物だと断言しやがった。
と、なれば彼女は魔女以外の何者でもない。なんて出鱈目な。
「まだ同類は見たことないが、近しいやつなら夕月かね? まぁ気を付けろよ。オレの同族は間違いなくそこいらのマホウツカイなんざ根こそぎ吹き飛ばしちまうから」
「まぁないとは思うがこれ以上に変なやつとは会いたくはないな」
「どうだか。この街もそろそろやばい、オレと同じ臭いしかしねえよ」
わざとらしくため息を吐くと、久遠は満足げににんまり笑う。あまりの発言に真顔にもなるが、入学してから半年もたたない間にこれだけおかしな事件に巻き込まれてたらもう否定もできまい。
「それは大変だな……この街もついにキチガイの巣窟になったか……」
「おめーがいうな爆弾魔」
「悪かったなアイ・アム・キチガイさんよ」
「アイアムキチガイ。まぁキチガイ上等だな」
「あんたがキチガイじゃなきゃ凡人が泣く」
爆弾魔とはあまりにあれな呼ばわれ方だが否定はしない。既に彼女には見抜かれているようだが、白衣の下には常に手榴弾等々常備している。何に使うのかと聞かれたら汚い花火以外に答えようがないので不審者すぎるがあまり気にしてはいない。
久遠はそのやりとりにひとしきり笑うと不意に笑みを消して竹内をじっと凝視する。獲物を狙う猫の瞳。まるで新しいおもちゃを見つけたような光の揺らぎに微かな悪寒を覚えた。
「……それと、もう一つだ。オマエ、焼けた人間の臭いがするんだけど身に覚えは? ……少なくとも火薬の臭いじゃねえな」
焼けた人間の臭い。その的確な表現に、背筋に冷たいものが走る。
「……残念だが、俺じゃあない。俺なら超人以外に普段は投げん……それに威力落としてるから此処までにはならん」
はぐらかすような返事に、久遠は少し首を傾げる。まるで深淵をのぞき込むような炎の宿る瞳。それをじっと無言で見つめ返した。
……轟音、そして爆炎。広がる炎。幼さゆえの曖昧に溶けた視界の中で、見慣れた人間は弾けるように乱舞する機械の中で肉塊へ変わっていく。鼻をつく髪の焼ける臭いと、熱風で焼けた肌が痛み引きつれる感触。そんな背景すら見透かすような、炎の瞳。
「じゃ、問題ないよな。見ても」
久遠は竹内の背後を指さす。
「……今度はなんだ」
そう言いながら背後を振り返ると、例の姿身があった。だが、見える景色は一変していた。
鏡に写った自分の姿は酷く焼けただれていた。炭化して短くなった指に融けて流れ落ちた眼球。顔の半分はケロイドに覆われ、めくれ上がった皮膚が口の動きすら阻害している。どう控えめに見ても焼死体の如き惨状。……見たことがある。人を庇って半身が焼けただれた人間は、ああ言う風に死ぬ。よぎる記憶を振り払うように鏡に映った自分の背後に視線をめぐらすと、傷一つない久遠と無数の人形がじっと鏡を凝視していた。
「へぇ……これは随分と派手にやられてるねー」
取り繕うわけでもなく、本心から大して気にしていない様子で応えた。この手の白昼夢はもうずっと昔に見飽きている。
「それがオレの視界だよ」
そうこともなげに久遠は笑うと、鏡を指していた指を降ろす。すると鏡の中にはいつも通りの自分の姿が映りこんでいた。
「……てぇことはあれか?あんたには周りのやつら全員こんな面してるように見えるか」
「まぁそう言う事だな。特に女は脂肪が多い分もっとひどいぜ? 丸焦げなんてよくいる話よ」
そう言って肩をすくめて笑う久遠に、合点がいったとばかりに何度か頷く。
そうであればさっきの見えていない仕草も納得がいく。周りの人間がことごとく黒焦げかずる剥けなんて有様だったら個々人の区別なんてつくわけもないだろう。女性の方がただれ方が酷いと言うのなら彼女の同性嫌いもどこか納得がいく。
「生まれつきこんなだから気にしてはねえがな。何が困るって人の見分けがつかねえんだ、これが……」
「まぁ……あれだけ焼けてりゃ見分けれんだろうな」
「実際そんなことは重要なことじゃないんだなコレが。……で、だ」
困ったような笑みを浮かべる久遠に同意の意を示すと、久遠は三度笑顔を消して真面目な表情を取り戻す。
「お前にゃ素質がある。油断したら一瞬でお陀仏だ。向こう側はそういうものを求めてやがるからな」
忠犬がいるようだし問題ないかもしれないがな、と久遠は付け足して小気味よく笑う。
「そんなもんなのか。まぁ、そっち側に行きそうな自覚はあるさ。それでもまだそっちに行きたいとも思わないし行く前に戻るさ」
「戻れたらいいな。気を付けろよ、道を踏み外しておかしくなるマホウツカイは十中八九死人を生き返らせようとしてるのが相場さ」
そう言って久遠はいつもの黒い手袋をはめると、にやりとあからさまな作り笑いを浮かべて見せた。……よく笑う女だが、むしろ作り笑いの方が似合っている。
「まだそこまで求めちゃいないから大丈夫だろう。おかしな話だよな……憎悪の方が簡単に強くなるのに、消せないのはそんなくだらない過去だなんて」
最後に自嘲気味に笑い、すぐに元に戻す。一応、自覚はしている。どうしようもなく囚われているのは自分に他ならないと知っていながらなんて白々しい。
「火傷みたいなもんだ。痛みは無駄に長続きする上、高確率で痕が残る。治療法さえ知ってりゃ多少は痛まないものを、爪先で抉るからだろうな」
「そうだな……まぁ俺は痛みも傷も大したものじゃない。それに、そっちに行ったら許されねぇよ」
「どうだかな。消えない傷にこそ痛覚は残るのさ」
……あんたはそう言う傷はあるのか、と聞きかけて飲み込んだ。久遠は何故か人殺しには興味が無いが人死にには敏感だ。そのくせ、実の兄の死にはこれほど無頓着である。そんな人間にまっとうな質問が通用するわけないだろう。
「……次があったらお別れかも知れんな」
「そうかい。そうなったら丁寧に焼いてオレの仲間に加えてやるよ」
あっけらかんと笑って恐ろしいことを言う久遠に、今度こそ呆れの表情を浮かべた。
「うわ、どうせやるならもっと綺麗にしてくれ」
「オレの視界じゃ変わらん」
さすがに言い返せない。
「なら、跡形無く焼いてくれ。そうすれば処分も楽だし誰かの傷になることもなかろう」
「無論だな。そのほうがこっちも後腐れが無くていい」
「それなら気兼ねなくいけるな」
「……ってか人を何火葬屋みたいな扱いしようとしてんだこのボケ」
冗談っぽく笑ってみせると、久遠は猫のように笑いながらいつもの口調で言った。
「人形師だけじゃなく火葬屋もできるとは多才だねぇ」
「うるせぇこのハゲ。髪の毛炎上させんぞ」
余談だが彼女の罵倒語のバリエーションの半分以上が毛根関連で占められているのは如何なることだろうか。そして更に恐ろしい話、彼女に正面切ってハゲと罵倒された人間はことごとくハゲて行ったという報告を聞くのはまた別の時の話。
「ハゲの髪の毛炎上って頭皮燃やしてんじゃねぇか」
「毛根に再起不能のダメージを負ってしまうがいい」
「その前に生死の境をさ迷う」
「大丈夫だ。2度の火傷じゃ死にはせんよ。4度になったらデストロイだがな」
「生きてても相当なトラウマになる」
「その辺は個々人で何とかしてくれ」
2度や4度と言うのは火傷の深さの事だ。確か1度は軽傷、2度3度は炎症~水ぶくれ。4度は炭化ぐらいの分類だったような気がする。無論度数が大きい方が死ぬ。と、言うよりも4度の火傷を負っている段階で周辺の広範囲に3度ないし2度の火傷を負っているのでまず助からない。
「その前に人の頭を炎上させるな。せめてブログくらいにしてやれ」
「それならそいつの頭に火をつけてからTwi○terにそいつのアカウントで『火事なう』って呟けばいい。良いぐらいに燃えるぜ」
「結局燃やしたいのか……」
「熱量はパワーだぜ」
「その熱量で火力発電でもしてろ」
「じゃあ発電所作ってくれよ」
「でかいのは無理だが、携帯充電器くらいなら作れそうだな」
「耐久温度は2000くらいで頼む」
どこかでそんな会話をした気がするな、と思いながら適当に設計図を頭の中で描く。理論上は不可能ではないがこいつさらりと2000度の炎が出せるって自己申告しやがった。
「素材があるならできるが……」
「んー、オレは疎いからなぁ。アレだ。2年のMrクレイジーなら何とかしてくれるかもしれないぜ?」
誰だよ。
「そうだな、面白そうだし今度作ってみるかな。まぁ期待せず待ってろ。できなかったら適当に作る」
「おう。爆発したらお前の額にビワが生えるように呪っといてやるよw」
結局この発電機は完成し、いまだ爆発報告は聞いていない。
だが何の因果か実際に額からビワが生えることになってしまったのだが、それもまた別の話。くたばれこの死体愛好家。
「爆発するとしたらお前が説明聞かずに火力あげた時くらいだ。それからそんな呪いがあってたまるか」
「火力上げたら爆発の前に融けるわ。オレのマジ火力舐めるな。あとそれフラグやで」
「だったらビワが生えることもないな。俺はフラグを折る達人だぞ」
「お前あれだろ。フラグ立てすぎたら逆に折れるってやつを狙ってるだろ」
「そんな事はない、狙ってやったら折れないんだぜ?」
「まぁいいや。生えたら教えてくれよ、燃やして枯れるか見て見たい」
「その時俺に髪がなかったらな」
生木を焼くレベルの火焔とか絶対髪の毛まで巻き込んで焼ける。
そんな先ほどまでの話の空気は何処へやら、雑談に興じているところに授業の終了を告げるチャイムが鳴る。気づけば丸々一時間を潰していたらしい。
「ん、終わったな」
「だな。じゃあそろそろ戻るわ」
そう言って立ち上がるとスツールを元の場所に戻して久遠に後ろ手に手を振る。
「おう。じゃあな」
そんな声に送られ、隠し扉を潜り抜ける。下手に誰かに見つかったら面倒だ。そう思いながら手早く扉を閉めようとしたとき、背後から久遠に何かを言われた気がして。
聞き直すよりも早く、勢い良く扉が閉まる。そしてもう押しても引いても開くことはなかった。
竹内璃遠の忘れ物
キャスト
竹内璃遠:PLC
PL=雨の人
久遠在処:NPC
3月28日収録


