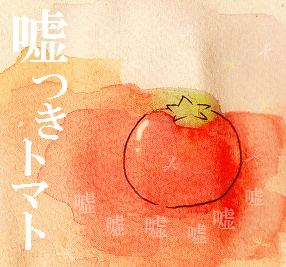
嘘つきトマト
「食べたくありません」
開口一番。目の前に置かれた皿を見つめながら、小柄な身体は呟いた。
ぼそぼそと掠れて聞き取りにくい。しかし、不満に満ちた確固たる意思を感じる、そんな声。
どうした――? そう問い掛けるよりも早く。
一度手に持ったはずのスプーンは元の位置に戻され、「いらない」と拒否されたそれが丸く拓けた机の上をズッと滑ってこちらに近づいてきた。
滑らかさの欠ける、乱暴な動き。揺られ飛び散った少量の液体が、白かった皿の縁を汚した。
思わず自分の分を注ごうとしていた手を止めて、鍋の中を覗き見る。
くつくつと。耳に腹に心地良い音とともに、白くふんわりとした湯気が優しく立ちのぼる。火から下ろしたばかりだったので、まだ少々煮立っていた。深い甘みのある香りが軽やかに鼻孔をくすぐっては、適度に胃を刺激していく。
言わずもがな作ったのは俺だ。もちろん味見もした。決して食べられないものなんかではない。
天井から吊るされたランプの下、レードルで掬い上げてまじまじと確認する。
食事という行為では味覚や嗅覚だけでなく、視覚が満たす効果も大きいらしい――いつだったか。何かの拍子で手に入れた知識を頭の中で復唱する。
古びくたびれた銀の縁で。とろみの強いスープにぷかぷかと浮かぶ緑や黄色に紛れて、焦げ茶色に染まった鶏肉が顔を出した。パリッと照りが強く利いた焦げ目、本に載っていた写真の通りだ。
全くもって悪くないと思うのだが……違うのだろうか?
一口も手を付けられず、拒否された理由がこれっぽっちも分からない。たまらず首を捻る。
と、同時に「くしゅん」と一発、短くくぐもった音が間に響いた。自分ではない。
「なんだ、気分でも悪いのか?」
背にした丸い硝子戸を。ぶっきらぼうに叩いては去っていく風に、昨夜がよく冷え込んだことを思い出した。
寒空のベールからまだ抜け出せていないのか。今夜もなかなかに肌寒い。
気温というものに対してひどく鈍感なはずの己の神経ですら、こうも凍てつき震えるのだから、きっと薄軟い肌ではそれ以上だろう。風邪のひとつやふたつ、背負い込んでしまったとしても仕方がない。
ただ。彼女と俺では例えなんかではなくその言葉通り勝手が違う。身体の作りうんぬんの話ではない。根本的に大きく違うのだ。さらに本音を言えば、彼女のような個体が体調を崩した場合の「対処」の仕方が十分に分からなかったりする。
町外れにある書庫にでも行けば役立つ資料があるのかもしれないが、すぐに探し出せるとは限らない。
いちいち馴染みの薄い文字をひたすら読むのも面倒だし、何より手遅れになってしまいそうで元の子もない。
厄介だと内心微妙に焦りつつ尋ねれば、彼女は目を伏せ静かに首を横に振った。合わせるように灰色がかった髪がオレンジ色の乏しい光を浴びて揺れる。
「……ならいい。ああ、ケープはそのまま羽織っとけよ」
良かった。気が抜けた。体調が優れないというわけではないらしい。
わざわざ「嘘」を吐く必要もない。が、彼らの体温の上昇とともに変わるという、ふっくらとした頬もフリルシャツの袖口から覗く肌も、普段と変わらぬ色味だから「本当」なのだろう。
しかし、だ。ではなぜ食べられないのか?
謎が解けたと先走った思考の糸は、あっけなく絡まり焦げ始めた。否応なしに思考の波が熱を帯びる。
というか、なにもかもが変だ。思えば先ほどの不可解な拒否から一言も口を聞いていない。互いに普段からそんなに口数が多いわけではないが、今日は異常に少なすぎる。そもそも、ひとつたりとも会話になっていないのだ。
迷い込んだ「ケット・シー」に無断で部屋を荒らされただ、書庫近くの森で時間の狂った「人狼」に虐められただの、今までにだって機嫌が悪くなったことがないわけではない。しかし、最終的にはこちらが心配になるほど「従順」だったはずなのに。
(なんなんだ、まったく……)
どこか「安心」さえ感じていたはずの「沈黙」が、どうにも気持ち悪い。勝手な思い込みかもしれない、でも圧迫されているようで落ち着かない。
透明で掴みどころがないまま、鋭敏に自己を主張してくる、そんな空気。息苦しさだけは十分に感じた。シャツのボタンを緩めても消えない。否応なしに満ち満ちては肺を重くしていく。
もういい。聞いてしまえば済むことだ。
目に表せない柔らかな部分に爪を立てられ、「考える」という気力を削がれた俺は前を見た。正確に言えば壁に掛かった時計を見るふりをして、ちらり彼女を盗み見た。
――駄目だった。
「聞く」と言っても根掘り葉掘り問う必要はない。優しく汲み取ってやれば勝手に話し出す、そんな淡い期待を抱いた自分が愚かだと思い知る。目の前の彼女が何か言いたそうな雰囲気を醸し出しているに違いないと踏んでいたのだ。
なのに、現実はなんだ。
なんとも涼しい顔をして。コップに注がれたホットミルクを旨そうに啜っているではないか。しかも、いつの間にか問題の皿がさらにこちらへと近づいていた。
思いがけない状況に目を見張る。
「話す気などない」と言うことか。皮肉なほど飄々とした態度に、一瞬カッとなった。中心から上へと勢い良く昇った血の勢いに合わせて問い詰めてしまおうと思ったが、こちらが負けてしまったような気がして躊躇った。吹けば飛んでしまうような命、ましてや子供相手に張り合うなどいい笑い者だ。
自尊心から溶け出した冷静さが、みるみる内にちっぽけな感情の杯を満たす。一気に下がった熱に感じる、不安定さと眩暈に似た浮遊感。答えは一つだ――割り切るしかない。
仕方なしに燻る気持ちを抑えつつ、ぐるぐると大きく鍋底をかき混ぜながら考える。
と、底で沈んで固まっていた具が潰されたようで一段と色味を増した。構わず円を描き、慣らす。作られた流れに沿って一際濃い筋が溶けて混ざり消える様子に、ふと。
さほど遠くはない記憶が引きずり出され思考を満たした。とっさに口をついて零れ落ちる。
「もしかして、まだ毒とか気にしてんの?」
無意識の内に落とした呟きに細い肩が揺れた。しまった――そう思っても、もう遅い。
「それぐらい分かります。馬鹿にしないでください」
息つく暇もなく、鋭く一蹴された。
「いや、馬鹿にしているわけじゃない。現に一回、ほら、事故みたいなこともあったしさ」
だから、その――。慌てて弁明しようとするも上手く言葉が紡げない。
その間に。直線上、向かい合っていたはずの相手は正面から身体をずらし、むっすりと口元を歪めて黙り込んでしまった。
「拗ねる」を通り越して明らかにご立腹だ。全くもって悪気はなかったのだが、説明することは気が引けた。言わなければ良かったと後悔しても取り消せやしないのだから、意味がない。
違う。
――毒と彼女。
間接的だとは言え、誰よりも触れぬよう拒んでいた部分に自ら触れなければならないのが嫌だった。
逸らし補正したはずの意識が叫ぶ。しかし、長引かせるわけにはいかない。
悪かったと、とりあえず謝る。
「そういう態度だけは、人一倍早いのですね」
しばしの沈黙の後、ぽつりと零された一言が、妙に重く感じた。耐え切れず唾を飲む。己が感じ考えていた以上に見られ、理解されていたらしい。まだ同じ空間を過ごし始めて間もないはずなのに、すでに本質を暴かれていたようでひどく耳が痛い。
「ああ、そうだよ。悪かったな」
「認めるのならば、謝らないでください」
「……」
思うままに無駄口を叩いた自分か、思った以上に素直とは程遠い彼女か。
どちらに対してなのか分からない。けれど、胸の内から強く込み上げてきた溜め息を吐き出して鍋に視線を戻す。湯気の勢いが減っていた。とたんに、襲いかかる空腹感と頭痛。不愉快極まりない感覚に思わず眉間にしわが寄る。
「じゃあ、嫌いなモンでも入ってんのか?」
尋ねながらもこれは無いなと思った。鍋で待つ食材を彼女が残したことは一度もなかったのだ。あまりにも間の抜けた問い掛け、ただ限界だった。食事を始めたい。
レードルを引き上げ自分の皿に取り分ける。深皿の縁沿いまで鮮やかな色をたっぷりと満たした、その時だった。
「どうして……どうして、トマトばかり食べるのですか?」
返事なんかないと踏んでいた。だから「好き嫌いは駄目だ、冷めないうちに喰え」、そう強く言うつもりだった。
「な、なんだよ。急に」
思いっきり出端を挫かれ、悲しくも焦る俺を無視して彼女は続ける。
「毎日、毎日。何故ですか?」
――トマトを使った料理ばかりです。私も、貴方も。
特に後ろの言葉がはっきりと強く聞こえた。が、気付かなかったふりをして答えを返す。
「美味いだろ? 特に理由なんてない」
貴重な微笑みまでつけてやったのに。気に食わなかったのか、向かい合うその眉間にしわが生えた。呆れた色を濃く滲ませた視線がこちらを刺す。
「では。その口からむやみやたらに飛び出ているモノは、お飾りなのですか?」
丁寧な口調のくせに。隠し切れていない、いや隠そうとなんかしていない無数の棘が見えた気がした。そのまま容赦なく突き刺さってくる。まさに不快感。地味に痛い。
ぴんっと伸ばされた細い人差し指が向けられたのは俺の口元だった。指が空中で短い弧を描く。示されるまま、なぞるように唇へと触れた手を動かせば、固く冷たい感触が指先から脳へと伝わった。
「お飾りなんかじゃねぇよ」
正真正銘、自分の一部だ。外れない。
動きやしないだろうと、片側を掴んでわざとらしく揺らしてみせた。ここ一番、渾身のジョーク。
しかし。笑うことなく淡い桃色を浮かべた形の良い唇が動く。伏せられた瞳の色は見えない。
「……血の色だからですか?」
「違う。血なんかよりもずっと美味い」
我慢しているのでしょう?
変わらぬ声色に。不思議と漂う願いが見えた。切り裂くようきっぱりと言い切れば、信じられないモノを見ているとでも言いたげに、彼女の両の目が丸くなった。急いたように、身を乗り出してくる。小振りな両耳にぶら下がったピアスが、涼やかな音を立てた。微かだがやはり頭に響く。
「最高級の贄が、無防備な状態で目の前に居るんですよ?」
こんな状況、今、この世界じゃありえないことでしょう。
諭すような物言い。行き過ぎた自画自賛を口にしているにもかかわらず、その顔は真剣そのものだ。当たり前だ。彼女の言葉に間違いなどひとつもない。
「あの、聞いていますか?」
さっきまで、無視していたのはそっちだろうに。自分を棚に上げてよく言う。はっきり言って滑稽だった。密かに込み上げる笑いを噛み殺す。そして、調子に乗った。
「はいはい。おおいに腹を満たしてくれた人間様は、もういな――!」
いけない、そう思った時には何もかも遅かった。またも口を滑らした自分にほとほと嫌気がさす。
「やっぱり、我慢しているのですね」
「ちがっ――!」
抑揚に乏しかったはずの声が、ひどく煌めいた。
嫌いではないのでしょう?
仄かな甘さを纏った囁きに、脳が揺られ奪われた。止められない。
ちろり、薄く開かれた唇の隙間で濡れた赤色が動いた。夜空を詰め込んだ深い青に、挑むような、誘うような光が灯る。一つ目のボタンの外れたケープとシャツ。蝶結びにされていたタイが、流れるように床へと消えた。支える右手、ぐっと前のめりになる身体。でも視線は変わらない。
壊れたようにこちらを見たまま、小さな頭がゆっくりと傾き、白く細い首筋が露わになっていく。晒された肌の影が薄れて――。
「やめろ。俺はまだ死にたくない」
机に向かって、加減せず振りおろした拳に漂っていた危うい空気が霧散する。とたん、両目に映り込む、さっと青ざめた彼女の顔にあるはずもない心が確かに痛んだ。
「死、ぬ?」
「ああ。一口含めば、終わりだろ?」
そう言った瞬間、言葉になり損ねた息を、堪えるように飲み込む音が自棄にはっきりと耳に響いた。ああ、また傷つけた、そう確信する。止めるための決定打、口にすることは避けたかった禁句だった。
「……不完全だって、役立たずの道具だったって知っているくせに」
怒るわけでも泣きだすわけでもない。淡々とした冷やかさを強く浮かべる青色に睨まれ、たまらず彼女から目を逸らした。
知らなかったと、素知らぬふりをすることができたならばどれほど楽なのだろう。
そうだ。
人間の括りからも魔族の括りからもずれた彼女は敵だ。心を貫く柳の木の枝で出来た杭や、首を落とすための太刀と同じ対魔物道具。
人と同じ見目がどのように創られたのか、なんて興味はない。気が付いた時には、自分たちを追ってくる狩り人の傍に彼らは居た。
か弱く無力な少女や少年の姿をした者が多かった。弱き者と見限って甘い汁を吸いにきた敵を、体内に流れる血に溶け込んだ「毒」と言う武器をもって迎え撃つ、狩り人の盾。彼らは囮専用だった。
なら、そいつらに手を出さなければいい。
そう馬鹿にした奴が命からがら逃げ延びてきたのを見たことがある。逃げ出せたと言うよりも、相手に追う意思など端からなかったことが後から分かった。
死んだのだ。
一日持ったか、良く覚えていない。が、ひどく怯えた様子で、体内を巡った毒に刻まれ苦しみながら逝ったのは酷だった。
何時まで経っても出血の止まらない傷口から弱弱しく漏れ出る呼吸音など、子守唄にはならない。
時折、細く千切れすぎた声とは言い難い音で、そいつはうわ言のように同じ言葉を繰り返した。
どうしようもなく惹かれたのだ、と、ただ自分は襲うしかなかったと。
彼のように、楽な最後を迎えることができなかった哀れな犠牲者は何人もいたらしい。
何よりも恐れるべきは血、そのものだ。盾の体内から零れ出た途端に鋭利な刃物に近い物質となり、口にした宿主の喉を深く抉ることは瞬く間に広まった。大したコミュニティを持とうとしない自分達にも一応の危機感と言うものがあったのだと、他人ごとのように驚いたものだ。
毒で誘い、血を奪う――A counterfeit vampire(紛い者の吸血鬼)
目の前にいるのは天敵とも言える同居人。でも、彼女の血は襲われても固まることを知らない。すなわち敵の自由を奪うほどの威力はない。瞬時的な成果を求められる狩りの場では大きな欠陥だった。
「主人(あるじ)だった人間にとっては、限りなく敵を惹きつけてしまうだけの厄介者、そして魔物と言う種族から言えばこの上ないただの食料。それが私です」
「おい、食料は違うって何度も言っているだろう?」
「いいえ、事実です。なのに、私は、私の血はこんな植物にさえも劣るんですか?」
よっぽど貴方の味覚は落ちぶれているのですね。
小馬鹿にしたように鼻で笑われた。しかし。何と言われようと腹は立たない。
遠ざけていた皿を引き戻し、浮かぶ赤色を指差す顔が余りにも痛々しかった。結び直されたタイはひどく歪んでいる。これで何を言い返せと言うのか。もっと「俺」に対して怒るならば、泣くならば。精一杯宥め、謝ることができるのに……それさえ許されない。
「狂った舌を取り替えに行きましょう。今度の闇市はいつですか?」
「いや、舌は十分健康だから。別に飲まなくても平気なんだ」
「……嘘つき」
責める声色から一変、急に消え入りそうなほど掠れた。どうしてそう思うのか? 問い返しても答えない。視線を合わせることなく、きつく唇を結んでしまった。帰ってきた無言の壁に思わず頭が痛む。
「分かった。もう聞かない」
言いたくなったら、話せばいい。溜め息の代わりに、念を押して自分の席に着く。
湯気の消えた皿を見る。やっと食事だ。匙いっぱい掬い上げ、口に運ぶその前に、
「心配しなくても時期が来たら、喰ってやるよ」
宣言してやった。驚いたような表情を見せた後、何故か一気に仏頂面になった。
「トマトなんて、大嫌いです」
可哀そうに。冷めたスープの中、形の残っていた赤がスプーンの裏で思いっきり潰された。
それっきり賢い彼女は口をつぐんだ。
***
ゆるく頼りなかった灯りでさえも眩しくて痛く感じるほどに、漂う夜の色が増した。
自室に引っ込んだ彼女はいない。食器やら資料を取っ払い、だいぶ広くなったテーブルの上に両足を乗せ、木箱から取り出した小瓶を眺め見る。食器棚の奥に忍ばせた隠し棚から持ち出した。
明かすつもりなどない、秘密のつもりだった。脆く現実味なんてありもしない、矛盾を秘めた隠し事。
「知ってたんだな」
「……嘘つき」そう言った後の問いかけで見せた、唇と視線の動きには見覚えがあった。隠し事をしているときの彼女の仕草だ。
売り手との交渉を見られたか、はたまた「喰らっている」瞬間を見られたか。
どちらにしてもばれてしまっている。その事実は消し去れない。気を配っていたなんて当てにもならない、自分が思っていただけだ。
意味なく手の内で転がせば、ぽちゃぽちゃと間抜けな音を立てて、中一杯を満たす鮮やかさのくすんだ赤色が揺れた。壁面をまどろっこしい速度で下へ下へと滑り落ちていく。一週間分、喉の渇きは癒される。少し飲み忘れたからって簡単に死ぬわけじゃない。我慢すればそれ以上。だから他は必要ない。
「……必要ないんだよ」
背を預けた椅子に体重をかけ、吐き出した息とともに天井を仰ぎ見る。無理な力に古びたそれが、苦しげな悲鳴を上げたが知ったことではない。
――お前が残していったものは、どうしようもない悩みの種になりつつあるよ。
淀む思考でもやつく脳裏の端を、色素の薄い髪が掠めた。
届かないなんて百も承知だ。それでもゆらゆらと湧き立つ苛立ちに任せて、零す。
「そっちはすることなくって、楽だろう?」
だから、愚痴ぐらい聞いていけよ。
前の住人が残した趣味の悪い壁画が目に入る前に、止められない溜め息とともに俺は瞼を閉じた。
――この子の家族になってあげてよ。
むかつくほど、いつもと変わらない微笑みで無理難題を押し付けて消えた。こっちの意見など端っからないも同然だった、そんな日を思い出して。
嘘つきトマト


