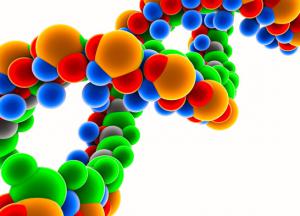蜃気楼
ある晴れた日の昼間、縁側に腰掛けて庭にめぐらせた柵をぼんやり眺めていたら、空から一筋の光を帯びながら、なにか降ってきた。それはちょうど庭の中央へぼとりと重たい音を立てて落ちた。
午後の芝生が、煙を上げている。
幸助は、また近所の童子達が花火でいたずらをしてきたのかと思い、縁側から立ち上がると花火の燃えかすであろうそれを拾いに近寄った。けれど、そこにあったのは花火の燃えかすではなくて、目の醒める光沢を帯びた褐色の玉であった。
「ほぉ。なんて美しい玉なんだ。」
幸助の小ぶりな手からはみ出るその玉は、表面に松毬のような片鱗を螺旋状に広げて、ごつごつと、硬い趣きをしている。その片鱗の隙間から、銀白色をした二本の筋が伸びて、昼下がりの心地よい風がそれをなびかせて弄んでいた。それは煙のようにも見えるし、稲穂のようにも見えるし、また髭のようにも思えた。そうして風に乗り翻った二本の筋が、さらさらした日の光を浴びて虹色に輝いた。
「幸さん。ごきげんよう。へぇー、何ですその持っている綺麗な玉は?」
向かいの家の女将さんが、二階のベランダにもたれかかりながら幸助に声をかけてきた。
「どうも女将さん。今日はお天道様のご機嫌がよかったから、朝から庭に柵をしつらえとったんです。それが先ほどひと段落つきましたので、こうして出来映えを眺めていたら、これがそこへ落っこちてきたんですよ。」
「それは、妙なことも起こるのねぇ。一体何なのかしらん。」
「何でしょうかね。こうして見てみると、なにかの卵や種にも見えるんですが。」
そう言って幸助はその玉を太陽の明かりにかざし、あまりの美しさにその玉に魅入ると、吐息を漏らしたり、生唾を呑み込んだりして、しばらくしてふっと我に返り、女将さんのいた二階に顔を上げた。
しかしそこにはもう人影は無くて、幸助が玉に魅了されている間に、女将さんも褐色の玉めがけて庭まで駆けてきたのである。女将さんは肩で息をしながら幸助に寄ってその褐色の玉をじぃーと見つめた。すると女将さんは目を輝かせながら幸助の方を向き、歓喜の声を上げ抃舞しはじめた。
「幸さん幸さん。あなたすごいものを拾ったわよ。これはきっと、蜃ていう竜の卵よ。私これを古神文献で見たことがあるわ。」
「竜ですか。かぁ。」
普段から女将さんの言う事に妄語は無いと信じ切っていた幸助は、ひどく感心した。女将さんはそんな幸助をみて、水を得た魚のように得意になった。
「そうよ。蜃はね、蛇と雉が交わって産まれるのよ。この卵は何百年も空を飛んでいたのよきっと。私の読んだその文献に、卵の姿で何百年間も大気を彷徨い、出ずる刻地表に根ざすなりって書いてあったわ。」
「かぁ。えらい高尚なものじゃあないですか。」
そして幸助は「女将さんは博学ですね。」と何度も頷いてみせた。
「ここら深沢山一帯はモノノケや神獣が仰山住んでるから、そうゆう学は自然に身に付いていったのよ。厭ね、なんか自慢話みたくなっちゃったわね。でもこの前なんかは河童が脱皮した脱け殻を底なし沼の袂で見つけてね、漢方屋に持っていったら、店主がすごく欲しがって、えらいお金で買い取っていったわ。」
「河童ですか。」
「春になるとね、河童は水底の村からこちらに通じる水路を辿って脱皮しにやってくるのよ。」
「あの底なし沼が水底の村と繋がってるんですか?」
「それはわからないわ。河童は棲家を隠すのがとても上手だから。」
「そうなんですか。」
「幸さん。そんな私の話より、その蜃の卵、埋めてみましょうよ。何百年も旅をしてきたのだから、きっと今すぐにでも出たがっているんじゃないかしらん。」
幸助はまだ女将さんの話を聞いてみたくなったが「そうですね。」と言った。
それから二人は蜃の卵が落ちてきた辺りを手で掘って、そっと埋めてやった。
幸助の庭の中央は、瘤のようにこんもりと堆くなる。
「幸さん。ここへお神酒をかけておやりなさいな。」
「お神酒ですか。うちにはお神酒の用意がないんですよ。」
「そんなんじゃいけません。深沢山のお膝元に屋敷をかまえているのなら、お神酒の用意くらいしておかなきゃ。私たちは、ここに鎮座されておられる自然という神々に生かされているのよ。」
そう幸助を叱咤すると、女将さんは自分の屋敷へ一目散に駆けていった。庭には女将さんの着物の香りだけが居残った。しばらくして、女将さんは屋敷の中から銅鑼をひっくり返したような大きな音を鳴らすと、往きよりも速く駆け戻ってきた。
「ほれ。お神酒持ってきたわよ。」
「えらいありがとうございます。」
「じゃあ、早速かけちゃいましょうかね。」
女将さんは土の瘤に、黴びた一升瓶に入った酒を無遠慮にどばどばかけた。
「こんなにかけてはいくら竜神様でも泥酔されて、出てこれなくなってしまうんではないですか。」
幸助は心配そうに土の瘤を見ていたが、幸助の気持ちとは裏腹に、女将さんは無邪気な振る舞いでお神酒を空にし、瓶の底を覗いてケタケタ笑う。
「少なくしてお怒りになられるよりいいじゃないのさ。」
「かぁ。女将さんをみてるとひやひやしますわ。」
土の瘤はみるみる濡れて、なだらかに崩れてゆく。
幸助は胡坐をかき、女将さんは膝を抱え、お神酒で濡れた土の瘤を、益体のない話をしながらしばらく見つめた。
しばらくすると、二人の頭上に暗雲が立ち込みはじめる。暗雲は渦を巻きながら、ごおおおんという怒号と共に、一筋の青い閃光を、庭の中央の瘤めがけて命中させた。
青い閃光がマントルを貫く音が一帯に響く。
それは厚手の布を裂くような音がした。
その音を合図に漲る光柱が立ち、土の瘤の辺りから、頭が五つある、青大将ほどの金色の竜が、ぬるりと顔を出したのだ。
幸助も女将さんも怒号の勢いで尻餅をついたまま、ぽかんと大きな口を開けて、ただただ呆然としていた。
小さな竜は辺りをぐるりと見回すと、漲る光柱に沿って螺旋を描きながら、するするすると空に昇っていく。
昇天してゆく竜は次第に、その蜷局で深沢山を容易に飲み込めるほどにまで大きくなっていき、
金色の五頭竜は二人の遥か頭上をゆっくりと旋回した。その行為は、まるで深沢山を愛でるような、なんとなく慈愛に満ちた行為に受け取れた。
それから滑るように方向を変え、暗雲をつき破り、大気圏に咬み付くと、宇宙へと飛び出し、
竜は星のあいだを縫うように泳いだ。
火星を一瞥し、木星を優雅に一周し、金粉を振りまきながらその威厳と尊厳を宇宙へと靡かせた。そして素粒子ほどに見える深沢山をギロリと目で捉え、勇ましい咆哮と同時に深沢山めがけて飛んできた。
その姿は稲妻に見えた。
深沢山めがけて落ちる竜は大気圏に鼻がつくと、逞しく茂る背鰭を翻した。水面から跳び上がる魚のようだった。
すると金色の身体は霰のように分裂し、霰は無数の蓮の実になって鎌倉一帯に降り注いだ。蓮の実は乱落しながら鞠のように膨らむと、ポンッという小気味好い音を立てて、ピンクや黄や紫やら色とりどりの、茶腕を包む掌のような新緑の葉を添えた鮮やかな蓮の花の雨を降らせた。
その美しさに幸助も女将さんも目を輝かせながら、親の帰りを巣で待つ燕の雛のような格好で、空に向かって感嘆の声を上げるばかりだった。
女将さんはあとになって、幸助にこんなことを言った。
「ねぇ幸さん。昔この深沢山の底なし沼には、五頭竜という五つの頭を持つ恐ろしい竜が住んでいたの。その竜は山を崩し、病を流行させ、洪水や台風を神通力でどんどん呼び寄せて、ここらにあった村をほとんど壊滅させてしまったのよ。本当に恐ろしい竜だったの。それでも五頭竜は飽き足らずに村の長者の子供達全員を一人残らず飲み殺したりもしたのよ。
でもあるとき五頭竜がいつものように悪行ばかりはたらいていると、鎌倉の海の方に桃色の雲がたちこめて、それはそれはとても美しい天女が空から舞い降りてきたの。五頭竜がその様子を底なし沼から隠れて見ていると、天女は自分の足元に向かって大切なものを愛でるようになにかをささやいたの。するとたちまち桃色の雲が晴れて、天女の足下の海面が突然隆起し、江ノ島ができたのよ。
五頭竜はとても衝撃を受けたわ。そして天女のあまりの美しさに恋に落ちたの。それから五頭竜はすぐに結婚を申し込みにいったの。でも、天女は全てお見通しで、五頭竜が今まで犯してきた残虐非道の行いを理由に断ったの。五頭竜はそりゃあ自分が今までしてきたことを悔やんでえらく落ち込みながら沼に帰っていったわ。でもそれを機に、五頭竜は人間と自然を守っていくことを天女に誓い、翌日からはそこの守り神になったのよ。日照時には雨を降らし木々を潤し、洪水や台風が来たときは神通力で追い返したりして人々に命を尽くしたのよ。結局五頭竜は天女と結ばれないまま死んでしまったんだけれどね。でもね、五頭竜は天女を喜ばすために今も一生懸命になっているんじゃないかしらんって私は思うの。だって今日は五頭竜が天女に出逢い恋に落ちて改心を誓ったその日なのよ。」
縁側に腰掛けながらそう言って、薄暮の風に揺れる庭一面に降り敷かれた鮮やかな花を見つめる女将さんの横顔は、いつもより若返ってみえた。
蜃気楼