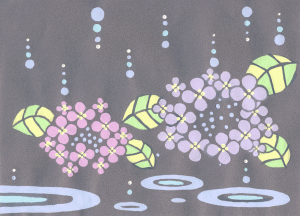詰みかけのゲームみたいな世界に迷い込んで1-1~1-13
1-1~1-13
†††1-1
数日前まではバラ色、とまでは言えないが幸せな人生だった。
数日前までは。
あんなことが起こらなければ俺はこんな山に登らなかったし、こんな事態には陥らなかった。
†††1-2
「ごめん、待った?」
「遅いわよ。何かあったの?」
花蓮がぼやく。俺は走ってきた息を懸命に整える。
「悪い、悪い。目覚ましが鳴らなくてさ」
「どうせまた、止めちゃったんでしょ」
花蓮が素っ気なく言う。
多分、と答えて俺と花蓮は並んで歩き出す。
「時間間に合う?」
と俺は花蓮の左腕の腕時計を指さした。花蓮は時計をちらりと見て、
「余裕よ」
と言った。
†††1-3
「痛え・・・・・・!」
どうやら転んでしまったようだ。もうとっくの昔に寒さなど感じない。この山に入って何時間だろうか。吹き付ける吹雪が情け容赦なく薄着の俺の体温を奪っていく。
もっともそれは好都合なの、だが・・・・・・。
俺は心のどこかで完全にはそう思っていないことに気づく。いや、今気づかないふりをしていたことに気づいたのか。
「早く死なねえかな・・・・・・」
強がってそうつぶやくが歯はがたがたと鳴って、景気付けの意味が全くなくなってしまった。
俺はこの雪山に死ににきていた。
自殺するなら凍死、と俺は昔から決めている。他の方法と違ってきれいだし、あまり迷惑がかからない。死体が見つかることもないかもしれない。カラスにでも食われれば完璧だ。残るは身内が心配することだけだが、生憎俺には身内がいない。
などと考えていたら転んだわけだ。神様が俺に天罰を下さったのだろうか。
そのまま横になって死のうかと伸びていると見てはいけないものが見えた。
洞窟だ。
†††1-4
中に入ってしまった。
俺はふらふらと奥へ進んだ。手頃な岩が地面においてあった。
俺は思い切りそいつに頭突きした。
「俺は・・・・・・、俺は・・・・・・!」
ろくに死ぬこともできない臆病者なのか。あんなことがあっても生きていこうと思っているのだろうか。
約束を破って。
ああ、と天を仰ぎ見る。洞窟のごつごつした岩の陰影が不気味な色合いをなしていた。
くそっ、とぼやきつつも足は自然と洞窟の奥へ奥へと向かう。そんな自分が情けなかった。それでも足は止まらなかった。
世界が抜ける、という感覚を味わった。
地面を見れば草原、だった。イメージ的には春の野、と言っていい。しかし、今は冬だ。というかそもそもここは洞窟の中のはずだ。なのにまぶしい。見上げれば太陽があった。
夢を見ている、という考えが頭の中を占めていく。きっと俺は雪の中に倒れ込んでそのまま死に導かれる前の最後の夢を見ているんだ、そうに違いない。そう思って俺の心を達成感と寂しさが満たす。
ふう、と息を吐いたとき、声が聞こえた。
「お兄ちゃん、何してるの?」
†††1-5
え、と振り返ると女の子が不思議そうな顔でこちらをじいっと見ている。思わず見つめ返してしまった。
「えっと、君は?」
「あたしは向こうの家に住んでるの」
そう言って指をさす。その指の先にはドーム型の家が建っていた。妙な家だな、と思った。
「お兄ちゃんはどこから来たの?」
「俺は・・・・・・」
夢の中でもこんな小さな子供に嘘を言うのはためらわれた。かといってわからないんだよ、あははー、も選択肢としては無かった。
「ハンナー!どこだい?」
そのとき救いの声が俺の耳に届いた。女性の、おそらくはこの子の母親の、声だった
「お母さーん!ここだよー!」
ハンナと呼ばれた少女が母親に向かって手を振る。母親はハンナを見つけて、ついでに娘の隣にいる男を見つけて近づいてきた。
「料理の手伝いをしてほしかったんだけど・・・・・・あんた、誰だい?」
肝っ玉母さん的な感じで聞いてくる。ありがたいことに敵意は感じられなかった。
「坂井翔太と言います。散歩していたらここに来ました」
嘘は言ってない・・・・・・よ。
「へえ・・・・・・。今から昼食なんだ。あんたもどうだい?」
「えっ、いいんですか?」
「いいさ。ハンナ、牛の乳を搾ってきてくれる?」
「わかった!」
そう言ってハンナは母親の頼みを聞いて走っていった。
転ばないようにね、と叫ぶ母親に手を振り返すハンナ。
全く、と母親は苦笑いを浮かべる。しかし、振り返って俺を見た時にはその目に笑みは残っていなかった。
「・・・・・・あんた、本当はどこから来たんだい?」
え、と口ごもる俺に母親は言う。
「ここは崖に囲まれた山の上なんだ。入り口を通れば鈴の音が鳴るようになってる」
「・・・・・・それをなぜ今言うんですか?俺が襲いかかる、とか思わないんですか」
ハンナの母親はにや、と笑った。
「おもしろいことを言うわね。なんとなく大丈夫だと思ったのよ。・・・・・・今なら娘もいないからね。で、あんたは何なの?」
「わかりません。俺もどこから来たのかわからないんです。と言うよりも俺は今ここが夢の中だと思っています」
母親が俺をしばらくぽかんと見つめ、いきなり笑いだした。
「あはははは!あんた本当に面白いね!その夢の世界について後で説明したげるよ!」
そう言って笑い続ける母親の後を俺はややこしいことになってるんじゃあないか、とため息をついた。
†††1-6
昼食のスープをいただき、ハンナが昼寝をしているとき、母親が説明をしてくれた。
何から話そうかね、とつぶやく顔からは何を考えてるのか読めなかった。
「うーん、よし。決まった。ことの起こりは五年前さ。たったの五年。それでこの世界の様相はすっかり変わってしまった」
どうやらただの世間話ではないようだ。
「北西の大陸の端の端、そこに穴が開いたと言われてるわ」
「穴・・・・・・?」
落とし穴だろうか?
「落とし穴ですか?」
「そんなわけないでしょ。穴からね、何かこう、訳の分からないものがいっぱいでてきたの。魔物って言われてるわ」
「魔物・・・・・・」
大分トンデモ展開なようだ。
「そう。その穴から無限にわき出てくるの、この世界のどんな動物よりも速くて、凶暴で、強い生物が。話では人間の三倍もある巨人とか、火を吐く竜とか」
まるでRPGに出てくる魔物そのままだ。できれば一生関わり合いになりたくない。
「それでどうなってるんですか。その穴は。塞がったんですか?」
「まさか」
そう嘲るように言った時の母親の顔が印象的だった。
「穴は塞がってないわ。国は何度も何度も穴を塞ごうと軍を出したんだけどね」
「今、抗戦中?」
「そう聞いてるわ。でももう穴を塞ぐどころの話じゃないのよ」
母親の顔は絶望を垣間見せた。
「もう、この国の七割は占領されてしまった、という噂よ」
†††1-7
「え?ど、どうして」
口ごもってしまった。ハンナの母は遠くを見やるように窓の外を見た。
「何度軍を出しても負けるからよ。終いには兵隊まで逃げ出す始末だと」
「え、それじゃあ・・・・・・」
言おうとした言葉は直前で音になる声にならなかった。
「そうよ」
ハンナの母は今まで腹の底に眠っていた感情を抑えきれずに不気味な声色で言う。
「この世界はね、滅ぶのよ、近いうちにね」
†††1-8
「そんな・・・・・・」
俺は何も言えなかった。
「だからあたしはあの子を、ハンナを連れてここに来たの。多分この辺りが魔物がやってくる最後の場所、国の南東の大陸なの。皆この辺りに移住を始めてるのよ」
そんなことをハンナの母は口元に笑みさえ浮かべて言った。しかし、その目に希望は無い。もう死んでいる人の目だ。今この会話で現実を再認識してしまってさっきまでの目とは比べることもできない。
なんとかしたい、と思った。
なんとも幼稚な感情だった。多分テレビで貧しい子供たちがどうのこうの、とやっているのを見た時に湧く感情に似ていた。
でもひょっとしたら、とも思う。
平凡な人間が元いた世界からひょっこり違う世界に迷い込んでしまって、その世界のために戦ったりして、何かうまいこといっちゃう、というのは物語のテンプレートと言ってもいい。王道だ。
俺は今まさにそんな設定にぴったりの人間ってワケだ。
だったら試してみるのも悪くは無い。
死んで元々。というかそもそも夢の世界かもしれないのだ。何をしたっていいだろう。
「すみません・・・・・・。俺に町への行き方を教えて下さい」
俺は半ば衝動的にそう言った。
†††1-9
ハンナとその母が見送って手を振ってくれた、のは数時間前。山を下りて、なぜか上って、ようやくふもとにたどり着いた。
「ああー、もうやめよっかな・・・・・・」
早くも挫折のきざしあり、だが平々凡々な俺には過酷すぎるハイキングであった。
「あーくそ、足が痛え・・・・・・」
などとぼやきつつ、さらに歩くこと一時間。野に咲く花とか、鹿とか見ながらこの世界は驚くほど前の世界と似ていることに気づく。
「もっと違ってもいいんじゃないのか・・・・・・?やっぱり夢なのかな・・・・・・」
そんなこんなで看板を発見。しかし、読めない。
「なんでだー!会話はできただろーが!」
なお、さっきまでの会話がなぜ成立していたかというと・・・・・・謎だ。テレパシー的な何かだと思う。看板には通じないようだ。
面白くないので足下に転がってた石ころを蹴っ飛ばしながら歩くこと更に三十分。
ようやく町に着いた。
†††1-10
町に着いた。
・・・・・・けどどうしよう。何をするプランがあるわけでもない。ぶっちゃけノリで何も考えずに来ただけだから当たり前だが。
何か魔術師的な格好をしている人を適当に捕まえてみようか、と思っていると。
「ねえ。ねえ、そこの君」
肩をとんとん、と叩かれた。女性の声だったので男性の場合の倍くらいの速度で振り向くと、まさに魔術師っぽい格好をした同い年くらいの女の子(美人!)が立っていた。
頭の大きさに対して不釣り合いに大きな黒くて鍔のある帽子をかぶり、その帽子から流れるように長い金髪があふれ出ている。人形のように美しい顔立ちに、黒いローブを来ていてもわかる均整のとれたスタイル。ただの木の棒みたいな杖もかわいく見える。
要するに俺のストライクゾーンどんぴしゃだったのだ。
(YES!!)
心の中で力一杯そう叫ぶ。女の子がちょっと不思議そうな顔でのぞき込むように俺を見る。
「君、どうかな、レジスタンスやらない?」
「レジスタンス?」
そう、と言いながら少女は紙を差し出す。チラシだった。当然読めない。
「ごめん。俺読めないんだ、字」
ちょっと語弊があるとは思ったが事実なのだから仕方がない。
ああ、と納得したように少女がうなずく。
(説明してくれ。説明してくれ。会話してくれ)
言っておくが下心など全く無い。無いよ。
「じゃあ、説明するわね。立ったままじゃなんだから何か飲みながら」
当然俺は二つ返事でついていった。
†††1-11
俺は微妙にまずい何か黒い液体を飲むふりをして、少女の話を半分くらい聞きながら少女の顔を眺めていた。
「・・・・・・大丈夫?ぼうっとしてるけど」
「!!大丈夫大丈夫。ちょっと寝不足で」
「そう。ならいいけど」
少女は自分の分の飲み物をちびりと飲んだ。
「まずい茶ね・・・・・・。こほん、レジスタンスっていうのわね、世界中にいる魔物を片っ端から倒していく人の集まりよ」
ふんふんとうなずく。
「今ね、この町でその気のある人を募ってるの。それであなたに出くわしたってわけ」
「へえ、奇遇だね。全部で何人くらいいるの?」
「全部で数百人いるわ」
「思ったより多いな」
「熱意のある人が多いのよ。戦況だってちょっとずつ良くなってきてるわ」
「前に会った人はもうおしまいだ、みたいなこと言ってたけど?」
少女は一瞬詰まったがすぐに、最近変わったのよ、と言った。
しばらく俺がレジスタンスについて聞いた後で少女は聞いた。
「ねえ。あなたはこのまま何もしないでいるの?それともあたしたちとこの世界のために戦いたい?」
そう望んであの山を出てきたわけだがこうやって選択肢を目の前にぶら下げられると即答できなかった。
「・・・・・・考えさせてくれないか。少しでいいんだ。長くは待たせない」
少女が、えっ、という顔をした。予想外、だったのだろうか。
「まだ決めるべきじゃない気がするんだ。他のレジスタンスもあるって言ってたよね。そこでも話を聞こうと思うんだ。いいかな?」
少女はまだ信じられない、とでも言うような顔で俺を見ている。俺の顔に何か付いているのだろうか。
「?・・・・・・じゃあ、俺は行くよ。あ、支払いはどうしよう?」
と間抜けな質問をレディにしてしまった時、少女が口を開いた。
「・・・・・・入ってよ」
俺は少女のその声色に凍り付いてしまった。低く、呪うようなトーンだった。
「入ってよッ!」
そう言ってチラシを押しつけようとする。俺は思わずその手を払いのけてしまった。
「・・・・・・ッ!」
「なにをするんだ!」
俺は怒鳴ったが、少女は払いのけられて床におちたチラシを凝視していた。
そして、
「あんたに」
震える指で俺を指し、怒りに満ちた目をして俺に言った。
「・・・・・・勝負を挑むわ」
†††1-12
「勝負?」
「そうよ」
さきほどの可愛らしいだけだった少女はもうすでに真剣な顔つきになっている。まあ、まだ十分すぎるほどにきれいだが。
「あんたは・・・・・・あたしたちの誇りを地におとしめた。その報いよ」
そう言ってちら、と地面に落ちた紙切れ、チラシを見る。
紙切れ一枚で大げさな、とは思ったが、それが気に障ったのなら謝るべきだろう。
「ごめん。ごめんなさい。そこまで大切にしているとは思わなくて」
そう俺が謝っても少女は頑なに首を横に振った。
「ダメよ。もう勝負することは決まった。覚悟なさい」
あまりに頑固なので、ついカチンと来てしまった。
「・・・・・・謝ってるじゃないか!もういいだろう!」
「うるさい!決着をつけるわよ!表に出なさい!」
「わかったよ!やりゃあいいんだろうが!」
俺は勝負に乗ってしまった。
†††1-13
表、店の外で俺と少女は互いににらみ合った。
「勝負のルールはあたしが決めるわよ」
「好きにしろよ」
ふ、と少女が笑う。
「勝負は『ケンカ』。次の鐘が鳴るまで、この町の中から出ずに行うわ。『参った』と言う、あるいは立てなくなった方が負け。あたしが勝てばあんたはレジスタンス入り。あんたが勝てば放免。それでいい?」
「一ついいか?」
「何よ」
俺が口を挟むと少女は冷たい目で俺を見た。
「俺はお前に手を出さない。悪いけど女に手を上げるなんて死んでもごめんだ。あと、俺が勝ったときのうまみがない。だから、勝負のルールを変更してほしい」
少女は腕組みし、少し考えて言う
「どんなふうに?」
「俺は手を出さない。鐘がなるまで俺が立っていたら俺の勝ち。俺が『参った』と言ったり、立てなくなったらあんたの勝ち。で、俺が勝ったら・・・・・・そうだな、金をくれ」
「金?」
「生憎と一文無しなんで」
「・・・・・・まあ、いいわ。それで文句無いわね?」
「無論だ」
「開始はいつでもいいかしら?」
「いい」
「じゃあ、始めるわよ」
そう言うやいなや少女は懐に手を突っ込み何かを取り出そうとした。それを見て、いや、見ずに俺は一目散に回れ右して人気のない路地に向かって走り出した。
女の子のぽかんとした顔が目に浮かぶようだ。巻いてしまいさえすれば俺の勝ちなのだ。
「甘い!」
腹に重い何か、がめり込ん、だ・・・・・・。
俺は思わず膝をついた。少女の細い足が見える。俺の目の前に立って俺を見下ろしている。
「言ってなかったっけ、あたし魔術師なの」
†††
詰みかけのゲームみたいな世界に迷い込んで1-1~1-13