
新・探偵物語 newdetectivestory
新探偵物語 登場人物一覧
・室井直美・・・・この小説の主人公。 都内有数の資産家の娘で今大学一年生の19歳。 まだ子供っぽさが抜けないキュートな少女。 近々父のいるアメリカに行く予定だが、謎のファックスと追跡者に恐怖心を抱き、探偵辻山を依頼する。 なかなかの行動派で、初めは辻山を嫌がっていたものの、彼とともに難事件に身を投じていくうちに、しだいに辻山に惹かれはじめ・・・
・辻山秀樹・・・・直美に雇われた私立探偵。 ヨレヨレのスーツに身を包み、くたびれた感じのハンサムな33歳。 仕事柄上、人間の裏を見すぎたせいか、ニヒルな冷たい感じになりつつあるが、根はやさしい。 過去に妻がいたが、逃げられてしまい現在は独身、ボロ・アパートで生活している。 行動派の直美についていけず、いつもドタバタ状態。
・工藤優作・・・・かの有名な私立探偵、工藤俊作の息子で大富豪の辻山の友人。 辻山と同じく33歳だが大富豪なのにも関わらず、一般人に憧れを持つ変人としても有名。 また古い書物の読みすぎで、「シャーロック・ホームズ」を「シャウロック・ホウムズ」と発音する妙な癖がある。
・森村政男・・・・広域暴力団 森村組の若。 ヘロインのブローカーで何者かに刺殺される。
・森村六郎・・・・広域暴力団 森村組の組長。 息子・政男を殺されたオトシマエをつけるため、辻山と直美を狙う。
・西村清彦・・・・森村組のナンバー2。 森村に尽くしているが裏ではヤクのブローカーもしている。 また、森村の女 美由樹ともイイ仲に・・・
・美由樹・・・・・・本名は大田明日香だが、みゆき族出身のためこう呼ばれている。 森村の女で、政男殺しに一枚絡んでいると森村たちに追われている。
・梅沢&宮下・・・西村の部下。 梅宮は怪力スキンヘッドの大男で、宮下は反対に小男だが、頭のキレるキレ者。
・三村真・・・・・・警視庁捜査一課の警部で、ふわふわマッシュルームカットがトレードマークの45歳。 工藤の古い友人でもある。
・上杉左京・・・三村の部下で、同じく捜査一課の刑事。 ロン毛をオールバックで決めた34歳で辻山の友人だが、ドジで「和製シャーロックホームズ」こと杉下右京とは雲泥の差。
・向田春・・・・室井家に仕える女中で直美の親代わり。 面倒見がよく、ほぼ何でもできる「スーパー・おばさん」 無茶をする直美の身の上を心配している。
序章 コンビニの怪

しとしとと降っていた雨も、今や本降りの大雨となってきた。 ここは東京の某所、都内にしては森林が多く、昼でもしんみりしている。
そんな所の一軒のコンビニに、一人の男が入ってきた。
「いらっしゃいませぇ。」 場所が場所のため客も少なく、見たところ中卒だろうと思える女店員が、いつもと同じ無愛想な挨拶をした。
男はファクスを送っていたが、土砂降りの雨のせいか男はいやに震えている。
男が入ってきてから一分くらいして、全身黒いレインコートで覆い隠した男が入ってきて、ファックス男の後ろについた。
「クゥ」 ファックス男が小さなうめき声を上げたが、ケータイをいじっている店員の耳には、その声は入ってこなかった。
やがてレインコートの男は去ったが、ファックス男は奇怪に突っ伏したまま、ビクとも動かない。
「お客様ぁ」 さすがに不審に思った店員が、男に声をかけて、その肩を揺すった。
すると、男は後ろに寄りかかり、店員にその顔を見せた。
「キャー」 店員は思わず叫び声をあげた。 その男の顔は傷だらけで、大きく目を見開いた彼の脇腹には、木目調の柄の鋭利なナイフが、深々と刺さっていたのだった。
第一章 暗号ファックス
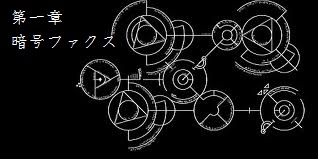
話は進み、ここは日本橋付近の大豪邸。 ここの主人、室井直美のもとへ一通のファックスが届いた。
その紙に文字は無く、ただ「13バン 左 子 親 人 子 右 人 薬 中 子」とだけ書かれた妙な暗号があった。
「何だろう?」 直美はまだ暖かいファックス紙を手にとって、まじまじと見ていたが、やがて「何かの間違いか・・・」と独り言を言って、紙をピカピカと光る銀の冷蔵庫に貼りつけた。
第ニ章 つけられてる・・・

翌朝7:00、直美の頭上で、目覚まし時計が高らかに鳴り響いた。 直美は眠たい目をこすり、ベッドから這い出ると、下へ降りて朝の用意を済ませた。
「おはようございます。 お嬢様。」 人一倍早起きする女中、向田春が台所から挨拶をする。 幼い頃、母親が死別し、ビジネスのため父がアメリカに居る直美にとって、春は親代わりの存在だった。
「たまには、ご飯とお味噌汁が食べたいな・・・」 彼女は大学一年生の19歳だが、とてもそうは見えないほど子供っぽいというか、あどけない感じの少女だった。 顔立ちは「美人」よりは「キュート」に属するようで、常にびっくりしているような大きな目と筋の通った鼻、そしていたずらっぽい愛嬌を残した口もとと言った顔と、つやつやしたボブ・カットの黒髪がよく似合っている。
「そうですね。 和食もたまには良いですね。」と春が言う。
テレビをつけると、ニュースが放送されている。
「昨日未明、○○区のコンビニエンスストアーで男性の刺殺体が発見されました。 警察によりますと男性は広域暴力団 森村組の息子、政男氏で・・・」
「物騒ですね。」と春がつぶやいた。
「ファックス紙はどういたしますか?」 春が玄関で、ヒールに足を入れようとしている直美に聞いた。
「うーん 後で使うからそのままでいいよ。」 そう言って直美は外へ出た。
いつも通っている大学までの道を、直美は歩いていた。 いつもの道なのに、今日は違う感じがする。 ハッとして直美は気付いた。 忘れものではない。 誰かにつけられている。 直接姿を見たわけではないのだが、完全に尾行されている。
いつもは行動派の直美も、この人通りの少ない道だとさすがに恐ろしくなり、いつの間にか走り出していた。
どれくらい走っただろう。 直美が垣根の曲がり角を曲がったあたりで、前から一人の男性が歩いてきた。
直美がそれに気付いたのは、曲がり角を曲がりきろうとしていた時だった上、ヒールの全力疾走で止まるのは無理だった。
案の定、二人は正面衝突、男は尻もちをつき、痛みのあまりうずくまっていて、直美も衝撃でカバンと片方のヒールがどこかに飛び、膝も擦り剥いてしまった。 「いたたた」 乱れた髪を直しながら、大きな目でカバンとヒールを探す直美の頭上で、「あの、もしもし・・・」という声が聞こえた。
「え?」と上を見ると、太陽を遮るようにさっきの男が、直美のカバンとヒール、絆創膏を持って立っていた。
男は30代前半といった具合のノッポのハンサムだが、ヨレヨレのスーツと泥だらけの革靴を履いて、本人も少々くたびれた感じだった。
「ええっと、これがバッグ、そんでヒール、あとここに絆創膏を張ると良いよ。」と男は直美の私物を渡し、膝に絆創膏も張ってくれた。
直美は急に恥ずかしくなって、「あ、ありがとうございます。」とだけ言って、走り去って行った。
男はその後ろ姿をしばらく見送っていたが、やがてお尻をさすりながら歩き出した。
第三章 女子大生とオジン探偵

「それってストーカじゃないの?」 そんな声を出したのは、直美の友人の一人、海老原正美だった。 彼女はクラス有数の「デカ女」で、小柄な直美と並ぶと、その差は一目瞭然だった。
「でも、直接姿見たわけじゃないし、警察、取り合ってくれるかな?」と直美。
ここは直美の通う牛浅大学の食堂。 ここで直美以下5人の女子大生が、昼食をとっていた。 話題は、今朝の道端の話である。
「そうそう、うちのパパの知り合いで、探偵やってる人がいるから、相談してみたら?」という石塚今日子の案に、直美は「ウン」とうなずいた。
「ここかなぁ?」 今日子から紹介された「中村探偵事務所」の前で、直美は首をかしげていた。 そのはず、もらった名刺には「村中」とあるのに看板は「中村」になっているのだ。 そのくせ、立て看板は「村中」なのである。
一か八か、直美は中へと入った。
「ヒドイ・・・」 直美は中の状態を見て、思わず本音が出た。 その通り、ガランとした室内には受付嬢らしき女性が2,3人と、社長らしき態度のデカい男が一人いた。
受付嬢の案内で直美が入った部屋には、テーブルとイスが二つ、それにお茶の湯呑も二つ置いてあった。
湯呑の中を覗いて、思わず目を張った。 湯呑の中の液体はほぼ透明で、まるで絵の具を水に少量溶かしたかのような、黄緑がかった状態だった。
それを一口飲んだ直美は、その味の薄さに思わず吐き出しそうになった。
ちょうどその時、さっきの「社長らしき」男が入ってきた。
「いらっしゃいませ。 私、社長の『村中』と申します。」 と村中が言った。
「え? あ、村中さん・・・ね。」 と直美。 それに気づいた村中が「ああ、看板の話ですね。 あれは看板屋がつけ間違えていった物で、気にしないでください。 で、ご用件は?」と言った。
直美は完全に呆れていた。 ご機嫌を取るつもりだったのかもしれないが、あれだけこの男の本性見せつけられて、この図々しさには腹まで立ってくる。
仕方なく、直美は今朝の出来事を話した。
「しかしねぇ お嬢さん。 探偵はボディガードじゃないんです。 一緒にされちゃ困りますな。」とわざとらしく額にシワを寄せる村中。
「で、でも・・・50万出します。 足りない分は後でいくらでも出しますから、何とか・・・」と直美はバッグから、50万の束を取り出した。
「5、50万・・・。分かりました。ひ、引き受けましょう。」 村中は震える手で50万の束をつかみ、奥へと消えた。
5分くらいして、村中がケーキとコーヒーを持ってやってきた。 「ウチの腕利きの男、辻山が貴方様の身辺警護を担当させていただきますので、彼が来るまで、もう少々お待ちください。」とお決まりの文句を言った。
やがてケーキを食べ終えた頃、一人の男が事務所に入ってきた。
「あっ、辻山さん。お帰り。」 「オウ、ケイちゃん。俺に用だって?」 「ウン、お客さん来てるみたい。」 辻山が帰ってきたようだ。 応接室まで二人のやり取りが聞こえる。 コンコン 外からドアをノックする音がして、村中が「入れ」と言う。
「失礼します。」 入ってきた辻山を見て、直美と辻山は「ああっ」と声をあげた。 辻山は、今朝直美と衝突した男だった。
「あ、今日から身辺警護させていただく、辻山 秀樹です。」と直美に名刺を渡した。 直美は内心、イヤだと思っていた。 確かにハンサムだが、直美にすればただのオジンだし、自分で頼んでおいて何だが、彼がずっとついてくるとなると、話は違ってくる。
「さあ、乗って。」 辻山がバイクの前に立って、直美に言った。
よし、こうなったら存分にこき使ってやろう 直美はそう心に決めた。
~「探偵物語」の曲に乗せて、バイクで走る辻山と、後ろに直美。 彼女の指示で、洋服屋など色々なところをまわる~
第四章 別れた妻

室井邸に帰ってきたのは、夜8時を回ったころだった。
「今日は色々と、申し訳なかったね。」 両手に下げた紙袋を見て、辻山が言う。
「いいえ、こっちだって色々連れてってもらったから。」と直美も両手の紙袋を見て言う。
「おやすみ」 「おやすみなさい」 そう言って二人は別れた。
ボロ・アパートに着くと、辻山はどっと座り込んでハサミを使い洋服の値札を切り始めた。
「ずいぶんと高級なのを買ってもらったな」と思っていると、玄関に落ちている一通の封筒に気付いた。
開けてみると中には、「スピリッツと言う近くのバーで、コールガールやってます。 一度遊びに来てください。 浅子」という手紙が入っていた。
浅子とは、辻山の別れた妻である。 彼女が近くのバーにいるとなれば、顔を見せないわけにはいかない。 辻山は身仕度を整え、バー・スピリッツへと向かった。
四章-2 辻山と浅子と直美?
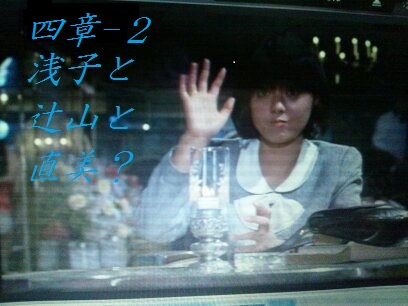
「あのぅ、浅子の紹介で来たんですが・・・」 辻山は、バー・スピリッツに居た。
支配人に話をすると、浅子が来て彼を案内した。 「来ないと思ってた。」と浅子。 「手紙もらって、いかないわけにはいかないだろ?」と辻山。
「あんたって、ホント真面目ね。」 「男なら誰だってそうだろ?」 浅子は席に着くと、酒を注ぎ始めた。 以前と変わらず、おっとりしている。
「元気そうじゃない。」 「バカ言うなよ。 そうでもないぜ。」 「まあ今日は私のおごりだから、存分に飲んできなさいよ。」 二人が楽しいそうに話していると、支配人が浅子を呼びに来た。
彼女の番がきたらしい。 浅子がステージに上がると、辻山は周りをキョロキョロと見渡して「あっ」と声をあげた。
彼が見つめる先のカウンターには直美がこちらを向いて座っていて、「ヨッ」と言わんばかりに片手をあげている。
「なんで君がここに居るんだ?」 直美の隣に座った辻山が尋ねる。
「何でって、家に居ても暇だし、向田さんが電話でパパと私がアメリカ行くって話してるの見たら、なんだか嫌気がさして・・・ バカみたいだけどね。」そう言って直美は、ウィスキーを注文した。
「おいおい、大丈夫か? いいのか?」 未成年の飲酒を目の当たりにして、責任感の強い辻山は心配で仕方がない。
「ウン、でさっき一緒にいた女の人、もしかして辻山さんのカノジョ?」と直美が聞く。
「あれか? まさか、別れた妻の浅子だよ。」 「ふうん、辻山さん、妙にソワソワしていたからさ。」 「尾行(つけて)来てたのか?」 「まあね。 一人前に認めてくれた?」 「探偵ゴッコやってるんじゃないんだぞ。 全く。」 辻山が直美に軽いゲンコツをする。
「ご両親はどっちもアメリカに?」 ふと辻山が尋ねた。 「ううん、パパだけ。 ママは死んじゃったから。」と笑ってごまかす直美。
「失礼だけど、どうして亡くなったの?」 辻山が珍しく突っ込んで聞く。 彼女の言葉の中に、未練を感じたからだ。
「よくわかんないんだけど、私が生まれた時、私、三回目でやっと生まれた子供だからつきっきりで育ててたら、周りからパパの財産目当てで結婚して、それを使い込んで自分は怠けている、なんて責められて、ノイローゼになっちゃって過労死。」 そこまで言うと、直美はまたウィスキーを飲みほした。
辻山は、自分が何か聞いてはいけないことを聞いてしまったような気がして、ただ黙り込むことしかできなかった。
そこへステージで歌い終えた、浅子が戻ってきた。
「誰、その人?」 直美を見て浅子が聞く。 「俺の収入源。」と辻山。
「あんまりにも美人だから、あんたの新妻かと思った。」 浅子の答えに辻山は、「やめてくれよ。 なあ。」と直美の方を見て「あっ」とつぶやいた。
そこには酔って、「もう一杯・・・」と寝言をつぶやく直美がいた。
辻山と浅子は顔を合わせて笑った。 が、その様子をじっと見つめるサングラスの男がいた。
男は音もなくその様子をカメラに収めると、店を後にした。
第五章 名探偵? 工藤俊作

「ん?」 直美が目を覚ましたのは、夜道を歩く辻山の背中の上だった。
「起きたかい? 酔って寝ちまったみたいでね。 家まで送るよ。」 「ああ、どうも。」
辻山は室井邸の前で直美を降ろした。
「くれぐれも大酒は飲みすぎないように。 じゃあ、また明日。」 二人は別れ、辻山は一人歩き出した。
「もしもし、辻山秀樹さんですね?」 あのサングラスの男が、辻山に声をかけてきた。
探偵の感で、相手が同業者であることと、身の危険を感じた辻山は、そっとヨレヨレのスーツの裏側に入っているリボルヴァーガンに手をかけ、「そうですが?」といった。
男は落ち着いた様子で、「いや、ある方に頼まれまして、貴方の身辺調査をしていたんです。」と一枚の名刺を差し出した。
『工藤探偵事務所 代表取締役 工藤 優作』と書かれた名刺を見て、辻山は「工藤優作・・・? あっ、工藤‼」と叫んだ。
「思い出しましたか?」 「いいえ。」 辻山の答えを聞いて、男はコケそうになった。
「わかりました。 では、私についてきてください。」と男は辻山を車に乗せた。 その車、外見はおろか、中に入ると辻山にとってそこは、まるで宮殿に居るようだった。(彼自身、宮殿には行った事は無いが、あまりの素晴らしさにそう感じた。)
ふかふかのシートは、いつも辻山が仕事の時自腹を切って利用する格安タクシーとは、大違いだった。
そのまま走ること30分、車は大きな会社の前へ停まった。 車を降りると、また違う男が立っていた。
「辻山様ですね。 私についてきてください。」 辻山は男について歩くこと10分、いくつもの廊下と階段を渡って、一つの部屋の前に案内された。
古代ギリシャばりの彫刻が施されたドアの中へ入ると、一人の老人が車イスに座っていた。
「君が辻山君だね?」 老人はそう言って部下の持ってきた写真を見た。 「君は相変わらず、仕事熱心だね。」
「あの、貴方はどちらさまでしょうか?」と辻山が尋ねる。
「私か? 声で分からないか?」と老人は聞くが、辻山は首を横に振った。
「ならこれはどうかね。」 老人は手元にあったおしぼりを手に取ると、力任せに顔を拭いた。
そこには老人ではなく、辻山と同じくらいの年の男が車イスに座っていた。 「辻山君、これならわかるだろ。」
この青年こそが、かの有名な探偵・工藤 俊作の息子で、お金持ちの変人探偵として有名な工藤 優作だった。 彼は辻山の古くからの友人で、金持ちのくせして、一般人の生活に憧れ、研究しているほか、古い文学を好み、若いころそれらを大量に読みあさった影響から、「シャーロック・ホームズ」を「シャウロック・ホウムズ」と発音する妙な癖を持っている。
「オレもついに、念願の明智小五郎に一歩近づいたよ。」と工藤が笑う。
「お前も元気そうで何よりだ。」と辻山。 「お前さんも、妙な事件をしょい込んだか?」 写真を見て工藤がつぶやく。
「いやぁ、ただのボディガード兼雑用係さ。 まあそんなもんで50万もらえるって言うんだから。」と辻山。
「ボディガードだなんて、そいつは裏に何かあるぞ。 今度にでも、一度この小娘にあってみたいもんだ。」 そういって工藤は、直美を指差した。
第六章 謎の女と森村組

辻山は、頭の中にガンガンと響くチャイムの音で起こされた。
久々に旧友と会い、居酒屋を5、6軒ハシゴすれば、さすがにヒドイ二日酔いに見舞われる。
何とか力を振り絞って玄関まで這っていき、「はい」と外に顔を出すか出さないいかのうちに、辻山は外からの勢いで押し戻された。
「すみません、助けてください!」 驚きのあまり、辻山は二日酔いなどすっかりすっ飛んで行ってしまった。
そこには、フーテンらしく汚らしいが美人な、辻山と同じくらいの歳の女が立っていた。 女はやけに怯えている。
「大丈夫ですか? と、とにかく落ち着いて。 さあ。」 辻山が女をイスに座らせたが、女はオロオロするばかりだ。
「森村組に追われています。助けて!」 「森村組?」 辻山は「森村組」という言葉に聞き覚えがあった。
森村組とは、広域暴力団の一つでなかなかの権力を持っているらしい。 仕事柄上辻山は、このような話をよく耳にするのだ。
「こんにちは。 室井です。」 そこへ直美がやってきた。
「お邪魔してもいいですか?」 顔を出した辻山に直美が尋ねたが、辻山が返事をする前にさっきの女が、彼を押しのけて出てきた。
「アンタ、誰? 森村の手先?」 「はあっ?」 辻山以上に状況が分からない直美は、いらいらしていた。
「辻山さん、この女 誰?」 「俺も良く分からないんだが・・・」 直美に尋ねられた辻山が、女がここに来た話をする。
トントントン 「辻山さ~ん、いますか?」外で男の声がする。 「森村組だっ。」 女があわてて辻山がさっきまで寝ていた布団に隠れる。 が、膨らんでしまって、全く隠れられていない。
「ちょっと、ここに居て。」 直美が女を布団から引っ張り出し、トイレに入れると、バッグから取り出した「故障中 使用できません」と書かれたステッカーをドアに貼り、自分は緑の上着を脱ぎ、下着姿になる。
あんぐりと口をあけて直美を見つめる辻山を無理やり布団に押し込み、自分も入る。 そして辻山に「寝たふりをして、いいわね。」と言うと、自分はさっさと寝たふりをする。
「クソ、鍵がかかってます。」 「構わん、ぶち壊せ。」 外で男たちの声がする。 やがてドアが壊され、森村組の組員、西村清彦とその部下、梅沢卓郎、宮下賢治の三人がなだれこんできた。 梅沢が力任せに布団をはぎとり、辻山の腕に顔を伏せていた直美の髪を引っ張り、顔をみるやいな「美由樹じゃね。」と悔しそうに言った。 「なんだ、ジャリじゃねか。」と西村。 「誰よ、その女! 居る訳ないでしょ、私がここに居るのに!」怒鳴る直美の口を、辻山が慌ててふさぐ。 「いや、いねえはずねえ。どっかに隠れてるんだ。」と頭のキレる宮下が言う。
手分けして美由樹を探す三人だが、美由樹は見つからない。 西村が辻山を見降ろして、「おい辻山、お前美由樹隠してたら、ただじゃおかねえぞ。」と脅し、部下の二人に「おい、いくぞ」と声をかけた。
「おい姉ちゃん。そんな奴と一緒に居るとロクなことないぞ。 とっととわかれなさい。」 帰り際に西村が、思い出したように直美に言う。
が、これが直美の感に触ったらしい。 負けじと「何よ、人の家に土足で上がり込んできて余計なお世話よ。 それにドア、壊しっぱなしで行くつもりィ~」と怒鳴り返す。 辻山がまた直美の口をふさぎ、「あっ、気にしないでください。」と付け足した。
直美の言葉に反応したかのように、西村はこちらに近づいて来て、スーツの内ポケットから、ギラギラ光る匕首・・・ではなく札束を取り出すと、「全く、うちの娘だったら尻をひっぱたいてる所だ。」と文句を言いながら、ポイッと投げて行った。
第六章-2 「男って情ないのね。」 女の強さ

三人が出て行った後、精一杯の演技に疲れ果てた辻山はその場にバタンとのびてしまった。
コンコン 外でまたノックの音が鳴り、直美は構える。
しかし、外に居たのは工藤だった。 「お邪魔しま~す。」と工藤が入ってきて、彼はぎょっと目を張った。
工藤の目の前には布団の上でのびている友人と、それに寄り添う下着姿の写真の「小娘」がいたからだ。
「一体、君たちは何をしているんだ?」 工藤が直美に尋ねるが、直美の方もヤクザの次は初対面の変な男が入ってきたため怪しんでいる。
工藤が、自分は辻山の古い友達の探偵だと説明し、直美に名刺を渡すと、直美はこれまでの経緯を工藤に説明した。
「そうか。 ということは、この中にその『美由樹』とやらがいるんだな。」と言って、工藤はトイレのドアを開けようとした。
「見ないでよっ。」 工藤がドアを開けた瞬間、女性の声とともに1m先の便器から拳が飛んできて、それを顔面に食らった工藤は、20㎝後ろの壁に頭をぶつけ、「ウ~ン」とのびてしまった。
「ふ~」 工藤を殴った右手をブラブラさせながら、美由樹がトイレから出てきた。
「あれっ? 彼ものびちゃったの? 全く、情ない。」
美由樹が、直美の方を見て笑う。
「どうして、あんな連中に追われてたんですか?」 ふと、直美が尋ねる。
「今朝のニュース、見た? 森村ん所の若が殺された話。 あの話でね、殺された若が私のファックスの番号が書いてあるメモを持ってたらしくてね。
私、組長さんの女なんだけど、なんだか疑われてるらしくて・・・。」
そう言って、美由樹は少し考え込んだ。
直美がなにをしているのだろうと思っていると、彼女は「ねえ、この二人、お風呂場に運んで。」と直美に言った。
「お風呂場?」 直美がポカンとしていると、美由樹の方はもう辻山の足を持って、「さあ」という顔をしているため、直美も慌てて運ぶ。
「じゃあ、次はバケツに水をくんで。」 美由樹が空バケツを直美に渡すと、自分はまたせっせと水を汲み始めた。
直美が水を汲み終わるのを見計らって、「次は・・・。」と言って、男二人の方を見てニヤリと笑う。
直美にも美由樹の目的が分かったらしく、ニヤリと笑った。
少しして、水をかける音と、男たちの悲鳴が外にまで響いた。
第七章 ファックスと消えた女

数分後、アパートの裏階段から、直美、美由樹、T-シャツに半ズボン姿の辻山と工藤が降りてきた。
表から出ると、まだ西村たちが見張っているかも知れないという直美の案で、一同は裏から出ることにしたのだ。
男二人は今まで着ていたスーツはびしょ濡れにされて、仕方なくこの格好だ。
しかし直美の読みは正しく、外ではあの三人が粘りづよく張っているのだった。
「グ~」 不意に梅沢の腹が鳴る。
「兄貴、ちょっと飯食い言ってもいいですかね。 俺、朝から何にも喰ってないんですよ。」
梅宮と宮下は、森村の命を受けた西村によって、朝一で呼び出されていたのだ。
「なら仕方がねえ、行ってこい。」 西村は許可する。
「ありがとうございます。」 梅沢が礼を言って、歩き出す。 が、空腹は彼だけではなかった。
「兄貴、俺も行ってきます。」 梅宮につづいて、宮下も歩き出す。
「おい、ちょっと待てよ。 俺、一人か?」 一人孤独な西村の声は、空腹の二人には届かなかった。
「そういうことだから、よろしくね。」 「かしこまりました、お嬢様。」
話は少し進んで、ここは室井邸。 またもや直美の案で、美由樹を室井邸に匿っておくことにしたのだ。
「そんじゃ、俺はちょっと失礼するぜ。」 工藤が言いだす。
「どして、どこいくの?」 直美が聞く。
「ちょっと家まで戻るだけさ。」 工藤はそこまで言って自分の姿を見る。 「こんな格好じゃ、俺のメンツがないからね。」と恥ずかしそうに言った。
その夜、ディナーを食べ終えた一同は、直美の提案で一日泊ることにした。
「さよならは別れーのー、言葉ーじゃなくてー」 直美が風呂に入ろうと「セーラー服と機関銃」を口ずさんで、服を脱ごうとした時、ポケットに何かが入っているのに気付いた。
「ん?」 出してみるとそれはあのファックスの紙だった。
それを見た瞬間、彼女の頭の中に一つの仮定が成り立った。 もしこのファックスがあの美由樹のいうファックスだったら、このファックスが事件解決のカギをにぎっているとしたら・・・ 美由樹にこのファックスを見せるべきか、と思った時直美は、野性的な直感で美由樹が完全に味方ではないような気がしてきたのだ。
直美はそう考えて、紙を丁寧に畳んでまたポケットにしまったが、まさかこの直感がどんぴしゃりと当るとは、夢にも思っていなかった。
第七章-2 浮き彫りになる事実

直美はいつも通り朝7時に起きた。 しかし正確にいえば、起こされたといった方がよいだろう。
直美を起こしたのは春だった。 「お嬢様、大変です。 お部屋が・・・。」
春に連れられて一階の部屋(室井邸は三階建てで、直美の部屋は二階にある。)を見た直美は、唖然とした。
部屋の中がめちゃくちゃに荒らされて、まるで大地震の後のような状態なのだ。
その中で辻山が、いかにも探偵っぽく虫眼鏡片手に意味もなく物証を探している。
「朝起きたら人がいなかった部屋がすべてこの状態で、あの女性のお客様の姿がなくて、工藤様が今付近をお探しになっているのですが。」
驚くことに直美の感は当っていたのだ。
「見た感じ、特に何かが盗まれたような形跡は無いですね。」 辻山が言うが、直美はこの状態で形跡も何もないだろうと思った。
「ただいま。」 そこへ工藤が戻ってきた。
相当探し周ったのだろう、ゼイゼイ肩で息をしている。
「やっぱり近くにはいないな。畜生。」 工藤の後ろから二人の刑事らしき男がやってきた。
「この二人は俺の古い知り合いでね、話をしたら駆けつけてくれたんだ。」
工藤が二人を紹介する。
どうやら工藤の話では、二人は警視庁の刑事らしく、ペッタリとしたマッシュルーム・カットの男は三村真(名前だけ聞けば野々村真っぽい)という警部で、もう一人は黒髪のペッタリとしたロン毛で、目の小さな男で、三村の部下の杉上左京(名前は杉下右京っぽいが、和製シャーロックホームズとは雲泥の差と言うほどのドジ)という刑事らしい。 しかし直美にはこの二人が、「トリック」の矢部と秋葉にしか見えないのであった。
「こいつはひどいな。」 三村が状態を見てため息をつく。
「あっ、そうだ。 辻山さん、海行かない?」 直美が思い出したように辻山に言った。
ここは東京湾の海水浴場。 今日もなかなかにぎわっているが、その中に直美と辻山、工藤の姿があった。
海の方では、ビキニ姿の直美が、どうにか拒む辻山を海に入れようと、必死にその腕を引っ張っている。 辻山は五歳のころ、家の湯船で溺れかけてから、「大きな入れ物に入った液体の中に入る」ということができなくなってしまったのだ。
海岸の方では、相変わらずスーツ姿の工藤が、二枚の写真を虫眼鏡を使って、一生懸命に見比べている。
「工藤さん、何やってるの?」 辻山を海に入れるのをあきらめた直美が工藤の方へ来る。 慌ててこちらへ向かう辻山。
「いや、この二枚、見てくれないか?」 工藤が見ていた写真の一枚は、昨日撮った美由樹の写真、そしてもう一枚は、西村と腕を組んで歩く、美由樹そっくりの女だ。
「よく見てくれないか。 この二人俺には同一人物に見えるんだ。」
なるほど、工藤の言うように写真の二人は、ほくろの位置や傷など同じ所がいくつもある。
「どうにも怪しいだろ、この女。」 工藤が自慢気にいう。
「うん、辻山さん、西村の住所、調べられる?」 「ああ、もちろん。 これでも一応、探偵やってるからね。」
「いいわ。 じゃあ私はここへ行く。」
直美は傍らにあった工藤の買った新聞の、「おくやみ」の「森村家」を指差した・
第八章 盗聴録音せよ!

翌日、猛暑のなか、喪服を着て政男の葬式に参列する人々の中に、直美の姿があった。
周りにならってご焼香をあげたり、一通りの作業を終えた直美は、あいている席に座り、じっと西村を監視していた。
彼はちらちらと時計ばかり見ていて、やがて3時になると、直美の読み通り、席を外した。 直美のそれに続く。
西村は葬儀場の門のあたりまでくると、携帯電話を取り出してどこかに電話をかける。
直美はポケットから、一見イヤホンにしか見えない盗聴器を取り出す。
工藤の商売道具で、彼曰く「超最新、超小型手持盗聴器」らしい。 使い方は彼から教わっている。
イヤホンを耳につけ、周波数を携帯電話の周波数に合わせると、直美は盗聴器を西村の方へ向けた。
西村の声が手に取るように聞こえる。
「やあ、俺だ。 うん、うん、マリファナか? もうすぐでもっといいのが入る? ヘロイン? まさかおめえさん、あのファックス手に入れたんじゃねえだろうな? おう、分かった。」
そこまで言って西村は電話を切った。 直美は自分の予想が当たっているのを確信すると、その場を後にした。
「もしもし、辻山さん。」 直美は近くでタクシーを拾って、辻山に電話をかける。 「証拠なら掴んだよ。 これから西村の家に向かうから、住所教えて。 うん、うん、じゃあ先に行ってるから後から来てね。」
それから数分して、辻山と直美は西村の家の前で落ち合った。 「西村と美由樹がここに入って行ってのか」 西村逹が居るのは二階の部屋で、辻山の肩に直美が乗ればなんとか届きそうだ。
「オーケー 」直美の合図で辻山がゆっくり立ち上がる。 「上、見ないでよ!」なんだかんだかで二階の部屋まで手が届いた。 盗聴機の電源を入れると二人の会話が聞こえる。
「まさかお前がそんな段階まで進めてるとは、思わなかったぜ。」「でも、アンタの目は麻薬にしか向いてないわ。」「バカ言うなよ。俺が欲しいのは、ヤクでも地位でもねえ、お前だよ。」直美は内心、うんざりしていた。 そろそろ録音を終りにしようと考えていたその時、不意にカーテンが開いて、直美と西村の目が会った。 直美がニコッと笑ったので西村もつられて笑ったが、すぐに真顔に戻って、コノヤロウと言うと姿を消した。
直美はとっさに「ヤバい」と感じ、ピョンと飛び降りると辻山の手を引いて、一目散に走り出した。 見ると、後ろからは幾人の追っ手が迫っていた。
第九章 恐怖の拷問

どれだけ走ったか、いつの間にか直美と辻山は、追手をまいて室井邸についていた。
「大丈夫か?」 疲れ果てた二人を見て、思わず工藤が心配する。
「うん、なんとかね。」そう言って直美はバッグから盗聴器を取り出す。 「これ、分析できる?」 工藤が盗聴器を見て、「ああ、出来るよ。 ちょっと時間かかるけどね。」と言った。
「じゃあ、工藤さんがやっている間、私たちは出掛けてましょう。」 直美の言葉に、辻山は冷や汗をかいた。 またどこを連れまわされるか分からない、しかし依頼人の指示に従うのが探偵だ。 辻山はしぶしぶ外に出た。
駅前のあたりまで来た二人は、店々をブラブラしていた。 その時、帽子を目深にかぶった男が辻山に、「辻山さん、ですね?」と聞いた。
「はあ」と辻山が力なく返事をすると、男は辻山の脇腹に銃口を当てて、「手荒い事はしたくないんです。私と一緒に来てください」と言った。 男の口調は馬鹿に丁寧だったが、直美は身の危険を感じ、逃げ出そうとした。 この際、辻山がどうとかの問題ではない。 しかし、男は直美の腕を素早くつかんで、「あなたも一緒に来てください。」と言った。 男に連れられふたりは人通りの少ない路地に案内され、そこに停まっていた車に乗せられた。
走ること2,3分、車はやけにさみしい場所に停まった。 そこで二人は降ろされ、さっきの男に連れられ、目の前の年期の入った豪邸に入れられた。 外見もそうだが中は全くひどいもので、所々壁が剥がれていたり、やけに湿気っぽいのだ。
「あなたはこちらに来て下さい。」 直美と辻山は別の部屋に入れら、帽子の男 瀬田に連れた直美は、天井から垂れ下がった腕輪をはめられ、拘束されてしまった。 目の前には、鞭を持った瀬田が立っている。
「私だって残酷なことはしたくないんです。悪い事は言いません、美由樹の居場所を言ってください。」 うつむき加減で瀬田が言う。
「あの人の居場所なんて、知る訳ないでしょ。」 怒鳴りつける直美に、男の一人がしびれを切らし、「じれってえな、俺がしゃべらせてやる。」と瀬田から鞭を取り上げると、直美の体にぶち当てた。 ビュンと風を切る音がして、直美の体に激痛が走る。
「ちょっと、女の子叩くなんて、サイテー!」 直美の負けてはいられず、怒鳴り返す。
しかし男は、狂ったように笑い、部屋の中はいつしか、地獄絵と化していた。
九章-2 一か八かの大勝負

「一時間たった、休憩だ。」 ふと、瀬田が腕時計を見て言う。
瀬田が、慣れた手つきで腕輪を外し、直美に軽く会釈した。 直美もつられて会釈する。
「おい、滝沢。」瀬田がさっきの鞭男を呼んだ。
「どうした。」ふらふらと近づいて来た滝沢の顔面を、瀬田が思いっきり殴った。 バタンと倒れた滝沢に「恥かかせやがって」と捨て台詞を言うと、直美に向かって、「ご案内致します。」と言った。
瀬田に案内された部屋には既に辻山がいて、瀬田は直美をそこに入れると、「一時間後にまた来ます。」といって鍵を閉めて行った。
「君も手ひどくやられたのか・・・」 辻山が直美を見て悔しそうに舌打ちをする。
「何とかこっから逃げる方法を考えなきゃ。」 二人は武器になりそうな物を探して部屋中を見まわす。 部屋はなかなか豪華で、ふかふかのベッドが二つあったり、純金の目を持つフクロウの剥製、シャワールームまで付いた外見からは想像できない、一流ホテル並みの設備である。
コンコン 不意にドアが開き、女が料理の乗ったカートを押して入ってきた。
「飯だよ、腹減ってんだろ?」 女はやけに長身で、ひょろとした体の上に乗った顔には、「美人ではあるがひと癖ある顔」が乗っている。 態度もその顔に相応の態度だ。
「無礼者め・・・」 そうつぶやいた辻山が料理に目を向けると、トレーの上にはたぶん黒毛和牛であろうステーキや、恐らく北海道産高級タラバを使用したかに飯など、若干嘘っぽい高級料理ばかりが並んでいて、みな口々に「僕を食べて~」と叫んでいるではないか。
きつい拷問の上、朝から何も食べていない二人は高級料理に飛びつき、ものの五分足らずでそれらを平らげてしまった。
「やっぱ食べなきゃアイディアなんて出ないよ。」 辻山が満足そうに言った頃、傍らで直美が「よしっ」と名案を思いついていた。
直美は辻山の服を脱がせパンツ一丁にすると、自分もまた服を脱ぎ、下着姿になる。
「君、またやるのか?」 ブツブツと文句を言う辻山を、「いいからいいから」とせかしながらシャワー室に入ると、辻山を端にやり自分も入って、ドアの裏に立ってドアを閉める。
不思議そうに直美を見つめる辻山に、直美は自分の口もとに人差し指を当て「黙る」様に指示すると、腕を伸ばして蛇口をひねり、シャワーを出してじっとしていた。
直美の予想通り、さっきの長身の女が食器を片づけるため、部屋に入ってきた。 女はベッドの上に投げだされた二人の服を見つけると、ニヤニヤしながら音のするシャワー室に近づいて、勢い良くそのドアを開けた。
「アチョ~」 次の瞬間、ブルース・リーも顔負けの怪鳥音と直美の拳が女の眼の前に飛び込んできて、失神させる。
直美はシャワー室から出ると、服を着て、女の腰から鍵と、拳銃、弾、携帯電話を奪い取ると、同じように服を着た辻山を連れて、急いで部屋から抜け出した。
九章-3 大逆転

部屋を出ると、直美は慎重に周りを見渡し、先導を歩いて行った。
と、前から二人の人影が近づいてくる。 直美の拳銃を持つ手に緊張が走る。
前から来た二人の男と、直美と辻山の目が合い、お互いに緊張が走った。 ふと男たちの手が、腰に巻いたガン・ホルスターのコルトにかかった。
次の瞬間、直美の手がポケットに忍ばせたリボルバーガンにかかり、目にもとまらぬ速さで撃鉄が叩かれ、男たちに弾丸のシャワーを浴びせた。
「すごいな、どこでそんなすご技覚えてきたんだ?」 直美の早撃ちに驚いた辻山が、彼女に尋ねる。
「これ? こんなの『ネロ』や『イースト・ウッド』を観てればすぐに覚えられるわ。」と直美がすまして言う。
「『モンゴメリウッド』でも覚えられるかい?」 「今は『ジュリアーノ・ジェンマ』よ。」と二人が特に意味のない会話を交わしているとき、敵は刻々と近づいていた。
「ほら、前に居るぞ」 辻山に言われて前を見ると、三人の男が拳銃を構えていた。
「ちょっと電話がしたいから、代わって。」 ふと直美に言われ、辻山が銃をとる。
「上手いじゃない。」 褒められて少し上機嫌になっている辻山に構わず、直美は工藤の番号をプッシュした。
「はい、こちら工藤探偵事務所。 ああ君か。」 工藤が電話に出る。 「ちょっといま大変だから、手短に話すわね。 大至急今から言うところに来て、裏口の前で待ってて欲しいの。 出来れば車で来て。 住所は・・・」 直美が工藤に住所を教えて、電話を切る。
「敵は全員やったよ。出口は?」 辻山に尋ねられ、直美は肝心なことを思い出した。 出口の場所がよくわからないのだ。
「出口、ですか? あちらですよ。」 瀬田だった。 瀬田は一人拳銃片手に立っていて、顔一面に笑みを浮かべていた。 直美はとっさに瀬田の意図に気付き、止めようとした。 しかし瀬田は、ひらりと身をかわし低い声で直美に言った。
「これでいいんです。 どうか止めないで。 お幸せに。」 直美は溢れそうになる涙をこらえ、辻山に連れられ外へ出た。 そこに停まっていた工藤の車に乗った時、後ろの方で銃声がした。 「どうしたんだ…」直美の様子を見て工藤が辻山に尋ねたが、彼は首を振って、「車を出してくれ。」と頼んだ。 工藤は言われた通り、ゆっくりとアクセルを踏み出した。
直美には分からなかった。 なぜ瀬田が自ら命を絶たなければならなかったのか?、自分が騒動を起こさなければ彼は助かったのか? そう考えた時、直美は後ろから追っ手が迫って来ているのに気がついた。
十章 カー・チェイス

「ヤバいよ。後ろ見て!」 直美の声に辻山と工藤の目が後ろに注がれる。
そこには黒塗りの「ヤクザ・カー」が五台、列をつくって工藤の車を追っている。
「おいおい、勘弁してくれ・・・」 拷問の次は追いかっけっこかと思うと、くたびれた辻山にはどうにも重荷だ。 しかし若い直美は、瀬田の仇をとらんと、弾を詰めたリボルバーガンを片手に窓から身を乗り出し、追手に狙いを定めている。
揺れる車内だ。 さすがの直美でもすぐに狙いが定まらない。 狙いを定めようと片目をつぶると、目の前に瀬田の優しい笑顔が浮かびあがった。
「瀬田さん・・・」 そうつぶやいたとたん、不思議なことに狙いがピタリと定まったのだ。 いまだ! 直美はグリップをしっかりと握り、思いっきり引き金を引いた。
ヴァンッ 鈍い音がして、彼女の弾は運転手に命中、舵を失った車はふらふらと電柱に激突、大炎上を起こした。
「君、危ないから下がっててくれ。 後はこっちでやる。」 工藤がそう言って、ハンドルの横のボタンを押す。
「な、なんじゃこりゃ‼」 助手席に居た辻山は、自分と工藤の間に出てきたボタンだらけの基盤を見て、思わず声をあげた。
「見てりゃわかるさ。」 工藤が笑いながら言って、ラジカセのスイッチを入れるとスピーカーから「ルイジアナ・ママ」が流れ出した。
ルイジアナ・ママの軽快なテンポに合わせて、チェイスが始まる。 工藤の運転は慣れたもので、右へ左へ、蛇行を繰り出して敵をまどわしていく。
「さっ 本題だ。しっかりつかまってろ‼」 そう言って工藤は思いっきりアクセルを踏み込んで、基盤の「ミサイル 後」のボタンを押した。
するとバックランプがパカッと開き、その丸い穴からロケット花火みたいなミサイルが、シュンッと音を立てて飛び出す。
ミサイルは見事後ろについていた追手一台に命中、「西部警察」並みの爆発を起こしてパーツがはじけ飛ぶ。 余りの衝撃に、直美と辻山はポカンと口を開けたままになってしまった。 「ちょちょちょちょっと、前、前、前‼」 前を見た直美がおおきな目をさらに大きくさせて、指をさしながら叫んだ。
そこには車が三台、連なってバリゲードをつくっている。 これでは突っ込んで停車するか、降参して停まるかの二択しかない。
しかし工藤は、大胆不敵にニヤニヤと笑っている。 そう、彼にはまだ秘策があるのだ。 工藤が今度は「リビンク・デイライツ」と書かれたボタンを押す。
あいにく007ファンではない辻山は、「りびんぐでいらいつ?」とボタンに書かれた意味不明な言葉を見て、素っ頓狂な声をあげた。
と、次の瞬間、驚く辻山に向かい酒を浴びせるような機能が作動した。 フロントガラスに二つの赤い円が映りだしたと思うと、それが電子音とともに中央に近づき、ピントが合った瞬間、フロントウインカーから小さなミサイルが飛び出し、バリケーゲードを爆破したのだ。 炎の中を颯爽とすり抜ける工藤号。
「どうだ、見たか!! ボンドカー仕様の工藤号だ。防弾、耐熱式だぜ。」と工藤が自慢気にドアを叩いた時だった。 なんと防弾・耐熱のドアが、工藤の軽い平手で、まるでドリフターズのコントの様に、カタンと外れてしまった。 三人の間で沈黙が起きる。
「と、とりあえずどっか停まって考えましょ。」と工藤が弱々しく言う。 「なら、あそこは?」突然、直美が口を開き、真っ昼間なのにも関わらず、ラブ・ホテルを指差して言った。
十章‐2 つかの間の休息?

「で、何でラブ・ホテルなんだ?」 ラブ・ホテルの廊下で、支配人を先頭に工藤、直美、そして辻山と並んで歩いている時、辻山が直美に尋ねた。 「何でって、行ったことないし、なんか面白そうだから。」と直美。 「面白そうたって、こんな所ひとつも楽しくないぞ。 しかもここ、どんな奴が来るとこか、分かってるのか?」 「辻山さんみたいな人が来るとこ。」「バカ言え、こんなとこ、できれば来たくないよ。」「じゃあ来たことあるんだ。奥さんと?それとも浮気相手?」「バカ、仕事でだよ。」二人が後ろでやり取りをしている頃、工藤は支配人の延々と続きそうなセールス・トークに嫌々付き合っていた。 「当店ではお客様に満足していただくために、子供じみた仕掛けは作らず…」 支配人は自信満々で話しているが、聞かされている工藤には念仏にしか聞こえず、うんざりしている。 やがて部屋の前まで来るとこ、三人を部屋に入れて支配人が「では、お楽しみください」と出て行った。
「で、探偵さん、こんな感じのホテルってどんな感じなの?」と直美が辻山に尋ねる。 「ホテルなんて、どこも同じような造りさ。 まあ強いて言えばベッドの真ん中が浮くとか、沈むとか、回るとかだな。」と辻山。 「ホントに、『子供じみた仕掛けは・・・』なんて嘘ばっか言いやがって・・・。」 そう言って工藤がベッドに勢いよく飛び乗った時だった。 「ワ~ッ」 工藤の叫び声とともにベッドの真ん中が勢いよく浮かび、工藤の体を消した。 悲鳴を聞いた二人が上を見上げると、そこには天井に突き刺さった工藤が、足をばたつかせ「たすけてくれ~」と叫んでいた。 工藤は仕掛けのスイッチを切っていなかったのだ。
「よし、引っ張るぞ。 せーのっ」 辻山と直美は、工藤の両足を片方ずつ持って引っ張っていた。 なかなか抜けず、4回目でやっと工藤の体がベッドの上に落ちた。 しかし天井には工藤の開けた穴しかないのに、本人がどこに見当たらないのだ。 探してみると彼はベッドの内側に埋まって、言葉にならない声を出してもがいている。 今度は「沈む」仕掛けにはまって、ベッドに飲み込まれてしまったのだ。
「ぬかりなくやらないとな。」 辻山がスイッチを切って工藤は脱出したが、カンカンに怒って、「あの支配人の野郎、切り刻んでやる。」と言って部屋を後にした。 工藤がいなくなり、辻山と直美は二人っきりになった。 直美はどうにも落ちつかない様子だ。
「何か、変な気分だね。」ふと辻山が口を開く。 直美は黙ったまま、じっとベッドを見つめていた。
「気になるなら、横になってみれば? あいつの二の舞になることは無いさ。」と辻山が言うので、直美は思いっきりベッドに横になった。
「どってことないじゃない。」 「そうか?」 辻山が「回る」仕掛けのスイッチを入れて、自分も直美の傍らに横たわる。 ベッドが回り、支配人に怒鳴る工藤の声以外は、何も聞こえない。 「確かに、変な気分だわ。」 直美がぼそりとつぶやく。 しかし、辻山が返答しなかったため、また沈黙が起きる。
やがて辻山が体を起こし、直美の方へ腕を伸ばした。 はっとした直美は、反射的に避けてしまったが、辻山にはその気がない様で、スイッチを切るとベッドから降りた。 くたびれた体を軽い体操でほぐす辻山の姿を、直美は横になったまま、首をまげてただ見つめるだけだった。
第十一章 ファックスの謎 ついに解明

直美たちが室井邸に戻ったのは、夕方頃だった。 「おかえりなさいませ。お嬢様にしては少しお早いようにも思えますが。」 出迎えに来た春が言う。 いつも遅くまでそこら辺をぶらついていた直美だったため、このくらいの時間に帰ってくるのは珍しいことだった。
「たまにはいい子でいようと思って。」 直美が言う。 「よい心がけですわ。『たまには』ではなく、『いつも』そのようにしていただけると助かります。」春は褒めているのか、そうでないのか、よくわからない。
部屋に上がって、直美がファックスを取り出すと、ファックスの事を知らない工藤は、「なんだい、それ?」と尋ねた。 直美はファックスの話を手短に工藤にする。 「そうか、こいつが発端だったんだな。」 工藤がまるで醜いものを見るようにファックスをにらんだ。
「ちょっとおやつ作ってくる。」 そう言って辻山が部屋から出ると、あのラブ・ホテルの様に沈黙が起きる。
直美はソファーに横になりファックスを見つめ、工藤は本棚にあった「ギター入門 これであなたも今日からプロギタリスト‼」と言う本を読んでいる。
「なぁ君、ホントは辻山に惚れてるんだろ?」 ふと工藤が本を読んだまま言う。 「えっ」 ファックスを眺めていた直美がじっ工藤を見つめる。
しかし工藤は笑って、「冗談、冗談。そうだよな、青春まっしぐらな女子大生が、あんな生きた化石みたいなヤツに恋するわけないか。」と言った。
そこへ辻山が、「ポップコーン、食べるか?」と入ってきた。
「ん、うまいな。 お前、ポップコーン職人か?」 ポップコーンをほおばっていた工藤が言う。 直美もうなずいて、「うん、最高。」と言っている。
そうは言っても、このポップコーン、スーパーで売っている「ガスコンロで膨らむ即席ポップコーン」なのだ。
「俺んとこのシェフが作るポップコーンと同じ味だ。塩加減まで。」 庶民的なポップコーンを知らない工藤は、「シェフ」が即席ポップコーンを彼に出していることを夢にも思っていないのだ。 もちろん直美も。
ポップコーンを食べ終えると、工藤はまた本を読み、直美と辻山はファクスをにらんでいた。 「これ、「13バン」って金庫の番号を差してるんじゃない。」
さえている直美が言う。 「でも森村組の専属の双葉銀行の金庫は、五桁の数字と五文字のアルファベットから形成されているんだぞ。 これは確かに五文字だが、漢字だ。」 辻山に突っ込まれて、直美は行き詰ってしまった。
ふと工藤の方を見ると、彼は話し合いに参加する意欲は無いようで、熱心にギター入門書を読んでいる。
「あっ」 そんな工藤の姿を見た瞬間、直美の頭の中でファックスの謎が解け、全てが繋がった。
「すべて解けた。明日、双葉銀行金庫にいくわ。」 直美の言葉に、辻山を工藤は顔を見合わせた。
「じゃあ、真犯人の目星は付いているのか?」 辻山が尋ねると、直美は自信満々にうなづいた。
第十二章 直美探偵の推理
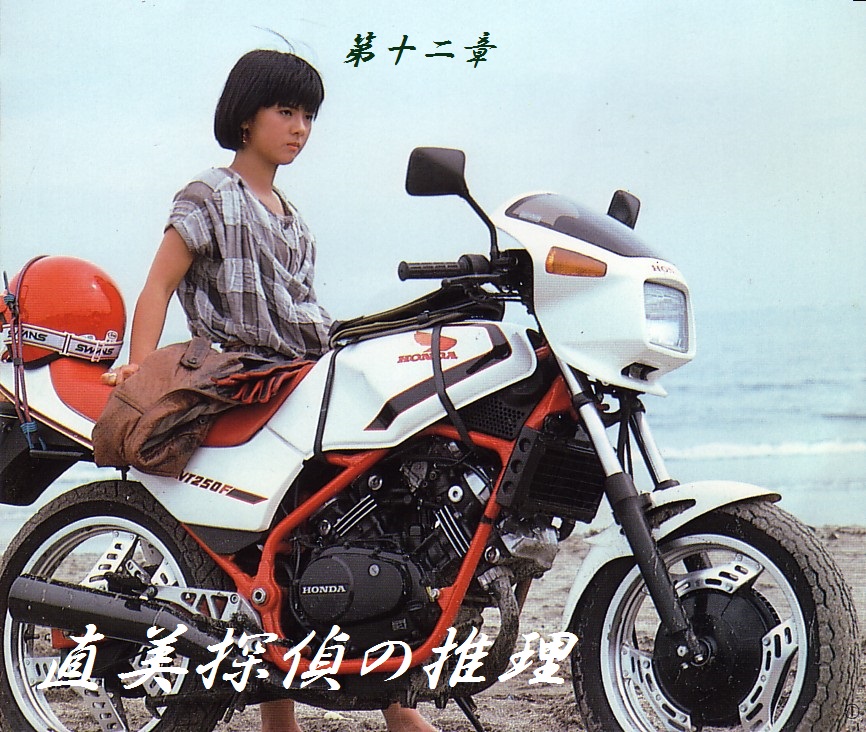
翌日、森村組組長、森村六郎、西村清彦、宮下・梅沢コンビ、そして美由樹の面々が双葉銀行の金庫室を訪れていた。
森村は昨夜突然姿を現わした美由樹に、真犯人が分かったため明日一緒に双葉銀行に来てほしいと言われていたのだ。
「あっ、貴様ら。」 13番金庫の前まで来て暗闇から姿を現わした二人の人物を見て、西村があっと声を上げた。
直美と辻山だ。直美は暗闇から姿を現わすと、口を開いた。 「意外なところでお会いになりましたね。西村さん。」
西村が後ろを見ると、そこには工藤と三村が立っていた。
「これから私が、今回の事件のすべてを解き明かしましょう。」 直美は自信満々に言うと、一歩前に出て一言、
「お前たちのやっていることは、すべてまるっとお見通しだ‼」 しかし、あいにくトリックファンではない森村一派には、何が何だか分からない。
直美はため息をつくと、推理を始めた。
「まず先に真犯人をお伝えしましょう。 そちらの方が話しやすいので。 真犯人は・・・」
両者の間で緊張が走る。 さっと直美の手が動いた。彼女が指差していたのは、西村と美由樹だった。
「貴様~」 森村が西村を睨む。 しかし西村は平然として、「ほう、じゃあお嬢ちゃん、その証拠を見せてもらおうか。」と言う。
「分かりました。 まずあなたが犯人の証拠として、政男氏が殺害された場所が上がります。 政男氏は相当な暴行を受けていた、そうでしたね?」
直美の言葉に、三村がうなずく。 「あの地域は見ての通り、森林が多く慣れた人でないと地図無しで歩くのは難しい。 しかし犯人は暴行をした現場から逃げ出した政男氏に約一分で追いついた。 一分と言う数字を叩き出すということはあの地域に慣れた人間が犯人であることを裏付けている、そう考えるとあの地域出身の西村さん、あなたしかいないんですよ。」
しかし西村は、「証拠はそれだけか? ならなぜ美由樹も共犯になる?」と言った。 直美は首を振って、「まだあります。今度は美由樹さん、あなたは森村氏の情婦でありながら、西村さんの浮気相手でもあった。 辻山さん、テープ。」と辻山に言う。 彼はよし来たと盗聴テープを再生する。
「これが動かぬ証拠です。 このテープは政男氏の葬儀の日、お二人の密会を録音した物ですから。 しかしここで気になるのは、お二人の会話、何やら麻薬の話をしているようですね。どうしてでしょう。しかしこれがこの事件の動機なんです。 実は森村さん、貴方の息子さんつまり殺された政男氏は、ヤクのブローカーだった。 そして何らかの出来事で、大量のヘロインを入手した。 しかしそれが西村さんの耳に入った。同じブローカーである西村さんは、政男氏のヘロインに目をつけ、美由樹さんと共にそれを狙っていた。なんせヘロインは水にうんと薄めて伸ばせば、何億と言うお金になりますから。 そしてあの夜、人目のつかないあの地域で西村さんは政男氏を呼び出し、ヘロインの在りかを言うように拷問した。 しかし隙を見て政男氏が逃げてしまい、あなたはそれを追いかけた。 そして政男氏をあのコンビニで刺殺した。 しかしその直前に、彼はヘロインの在りかを暗号化したファックスを美由樹さんに送った。彼女が共犯だとも知らずにね。 しかし暴行により意識がもうろうとしていた政男氏は、番号を押し間違い誤って私の所に送信してしまった。 それを知ったあなた方は、辻山さんに助けを求めるように見せかけ私の家に潜入し、ファックスを探した。しかし見つけられなかったんですね。 しかしあなた方はふとしたことでこのファックスの内容を知り、ここにヘロインが隠されているのを知った。 そこで森村さんをおびき出し、ここで殺害してヘロインを持って逃走するつもりだったのでしょう。 しかしなぜ、お二人はこのファックスの解読ができたのでしょう。 それはこのファックスの暗号の作りが、ギターの指番号になっているんです。 これ、「13バン」は13番金庫を、「左 子 親 人 子」はそれぞれ左の指番号を表わしているため、4 0、1、4、「右 人 薬 中 子」はi、m、a、chとなるのです。これをギター経験者の美由樹さんは、何なく解いた。 そしてこの通りに金庫を開けると・・・」 そう言って直美が金庫を開けると、そこにはあふれんばかりのヘロインの包みが重なっていた。 直美は勝ち誇ったように、ぐっと西村を睨みつけた。
十三章-2 悪魔の最期

「ふっ お嬢ちゃん、正解だよ。」 不意に土壇場に西村が不敵な笑みを浮かべたため、直美は少し不安になった。
その直後、西村の左手が伸びて森村を抱きよせると、空いた右手でポケットから拳銃を出し、森村の頭に銃口を当てた。
「ヘロインは諦めます。 しかしアンタには死んでもらう。」 西村はそう言って森村を突き放すと、その背中に一発弾丸を放ち、唖然とする工藤と三村を押しのけて逃げ出した。
「待てっ」 さっと拳銃を取り出し、辻山もそれを追う。 廊下に出ると、走る西村の背中に狙いをつけて、辻山が拳銃の銃口を引く。 鈍い音を立てて西村の背中から血しぶきが上がり、彼はその場に倒れた。 こうして直美の推理と西村の死によって、事件は幕を閉じたのであった。
第十四章 そして直美は恋をした

すべてが解決し、祝杯をあげた直美たちが帰ってきたのは10時を少し回ったころだった。
「今日はうちに泊まって行ってよ。」 直美が辻山と工藤にそう言ったが、工藤はやり残した仕事を片づけるため断り、辻山だけが泊ることになった。
シャワーを浴び終え、案内された部屋に入った辻山は思わず目を見開いた。 そこにはどう潜入したのか、別れた妻の浅子が立っていたからだ。
「お前、どうしてここに居るんだ?」 「どうしてって、あなたがあの女の子といるの見たら、あの子に気が移るんじゃないかって思って、抱かれに来たの。」
「バカ言え、俺たちはもう赤の他人だろ。」 「やだ、私あの子に嫉妬してるの・・・」 気付くともう浅子の白い手は、辻山の首元に絡みついていた。
まるで獲物に巻きつく蛇のように・・・
直美は自分の部屋に居たが、じっとしていられなかった。 大好きな音楽のCDを聴いていても、全く歌詞が耳に入ってこない。 辻山だ。彼のことで頭の中がいっぱいなのだ。 そう思うとますますじっとしていられずに、気づいたら直美は部屋を出て、ゆっくりと辻山の部屋の前まで来ていた。
少しあいた辻山の部屋のドアの隙間から、月明かりが指している。 寝ているのかな? 直美はいたずらに彼の部屋を覗いた。
中の様子を見て、直美は何十アンペアもの電流が体を突き抜けるような衝撃を覚えた。 彼女の眼に映ったのは、月明かりに照らされて複雑に絡み合う、浅子と辻山のシルエットだった。 直美はそこに立っていられなくなり、長い廊下を突っ走って玄関まで行くと、ヒールをつっかけて外に出た。 意味もなく繁華街へ向かって歩く直美の目から、不意に涙があふれた。
私、辻山さんが好きなんだ・・・ なんだか複雑な気持ちだった。 今回の事件よりも、今まで読んだどの推理小説よりも複雑だった。
気付いたら、直美はラブ・ホテルの一室に居た。 以前辻山と一緒に来たホテルだ。 ベッドにあお向けになって天井を見る。 傍らでカタカタとパソコンを打つ音だけが聞こえる。 連れの男だ。 繁華街で直美と出会って、お互い名前の知らなかったが直美にここまで付き合わされた、真面目そうな男だ。
「ねえ、いつまでそれやってるの?」 直美がベッドの上から、首を男の方に向けて尋ねる。 「ああ、もう少しで終わるから、シャワーを浴びて、その後やろう。」 男は脇目もふらず、真っ直ぐに画面だけを見つめて言う。 そうはいってもなかなか終わる様子は無い。 そうこうしているうちに疲れていた直美は、ウトウトと眠ってしまった。
どれくらい寝たのだろう ふと直美が目を覚ますと、そこには男の姿は無く、シャワー室の方からかすかに水の落ちる音がする。
直美はう~んと大欠伸をすると、自分の荷物をまとめ、シャワー室に映る男の影に投げキッスをすると、静かに部屋を出た。
第十五章 出発前夜の告白

翌朝、直美は何事もなかったように自分の部屋で起きた。 昨日の男の不思議そうに思っている顔を想像すると、思わず笑いが起こる。
しかしすぐに辻山のことが気になり、急いで着替えて下に降りて行った。 だがそこには辻山の姿も、浅子の姿もなく、春が何気なく朝食の準備をしていた。
「あれ、向田さん、辻山さんどこに居るの?」 直美が春に尋ねる。 「ああ、お嬢様おはようございます。 辻山様なら朝早く工藤様がいらして、お出かけになりましたが。 あと今日がお嬢様のお別れ会だということは伝えておきましたが。」 春はやはり気が利くのだ。
「ありがとう。」 直美もお礼を言って外へ出た。 夏から秋に変わる風が直美の頬をなでた。
「やっぱり無くなったか・・・」 辻山はつい先日まで勤務していた、「村中探偵事務所」の前に突っ立っていた。 探偵社は倒産し、建物だけを残して無残に建っている。 「今日から無職か? なら俺んとこに来いよ。重役に着かしてやるぜ。」と工藤が誘った。 辻山も恥ずかしそうに苦笑いして、うなづいた。
午後五時、室井邸の近くの小さなディスコで直美のお別れパーティが開かれていた。 友人と踊って笑う直美たちにまぎれて、辻山と工藤はバーカウンターに腰をおろしていた。 工藤はウイスキーをがばがば飲んで上機嫌だが、辻山はどことなく元気がない。 「どうした、元気を出せって。」 工藤が辻山のグラスにワインを注ぐが、辻山は相変わらず黙り込んだままだった。
一踊りし終えた直美がバーカウンターに目をやると、そこにふたりの姿は無かった。
午後十時を回ったころ、酒屋を5、6軒回った工藤が、一人千鳥足で夜道を歩いていると、後ろから「工藤さん」と女の声がした。
「ん?」と振り向くと、そこには直美が立っていた。 「やあ、お嬢ちゃん。どうした?」 工藤が尋ねる。 「あの、辻山さんは、どこに居るかわかりますか?」 直美が口を開く。 「ああ、奴なら先に帰ったよ。 疲れているみたいでね。」 工藤の返事を聞き終わるか終らないかのうちに、直美は走り出していた。 「あの小娘、しっかりしてやがるぜ。全く。」 工藤は走る直美の背中を見送りながら、しっかりとした口調でつぶやいた。
辻山はあのぼろアパートで洗濯をしていた。 が、何年も使っていなかったためか、どことなく洗濯機の調子が悪い。 ふと、外でチャイムが鳴った。 「は~い」辻山が声を張り上げ返事をする。 「あ、私です。」 直美だった。その声を聞いて、辻山が玄関にすっ飛んで行った。 「どうしたんだ?」 「あの、上がってもいいですか?」 辻山は直美を招き入れ、居間に案内するとお茶を入れた。 「あの、明日出発なんです。 朝の9時、成田空港。」直美が言う。
「朝九時か、早いね。」 お茶を注ぎながら辻山が言う。 「あっ、そういえば昨日の夜、どこいってたの?」辻山が尋ねる。 「ラブ・ホテル、辻山さんと行ったとこ・・・」 少し沈黙があって、直美が口を開く。 「ラブ・ホテルって、まさか一人でか?」 「ううん、男の人と。」 辻山はすべてを悟った。 「なんで、そんな見ず知らずの男となんか行くんだ。」 辻山が勢い余って怒鳴る。 「だって、好きな人、違う人と、してたんだもん。」 直美が力なくつぶやく。
「だからって・・・」 次の言葉を言おうとした辻山を遮るように直美が反論した。 「でも、ホテルで何もしなかった。 私、辻山さんのこと、好きになったの。だから、もう少しここに居てもいいですか?」 しかし辻山は少しためらうように、首を振って言った。 「今日は疲れているんだ。だから、お茶飲んだら帰ってくれ。」予想外の返事に、直美は少し戸惑った。「一人で…寂しくないんですか…」直美の言葉に辻山は、ため息をついて答えた。 「一人でいて、寂しくない奴なんて…いないよ。 でも甘えちゃいけない時だって…あるんじゃないのか?」 二人の間で沈黙が起こり、ふと直美が「帰ります… 私帰ります。」と 言って立ち上がり、溢れそうになる涙をこらえて、逃げる様に部屋を後にした。 一人取り残された辻山は、遠くで玄関の閉まる音を聞きながら、複雑な気持ちで、動く事なく座っていた。
最終章 エアポート・キッス

翌日、朝の9時、直美は一人タクシーに乗り、成田空港に向かっていた。 あの後ついに辻山は現れなかったのだ。 直美は重い荷物を抱えタクシーを降りると、出国審査を受けに言った。 忘れ物はない、ただ、辻山と言う大きな心残りを残してきただけだ。
そんな事を考えながらエスカレーターを降りる直美が、ふと後ろを見て、驚いた様にかけ上がった。 辻山だ。辻山が成田空港まで来たのだ。 直美が辻山の方に近づいた。 「来てくれたのね。」 「当たり前だろ。 君を一人で旅立たせると思ったかい。」「ちょっぴりね。」 そう言って二人は笑い声を上げた。
「ねえ、最後にお願い聞いてくれない。」「なんだい?」 「・・・キスして。」 直美の予想外の願いに辻山は少し戸惑い、尋ねた。 「キスって、どんなふうに?」 「どんなふうにって、そうね。 じゃあ私をあんパンだと思って。 おなかがペコペコの時に、大きなあんパンにかぶりつくみたいに、ガブガブって。」
直美のかわいらしいたとえに辻山は苦笑しながら、直美を抱き寄せた。 直美も目をつぶる。
成田空港の広場、辻山は直美のたとえ通り、あんパンにかぶりつくような熱い口づけを直美にささげた。
辻山が直美の唇から口を離し、顔をあげても、直美は出発をためらうように辻山の胸に顔をうずくめ、その胸を熱い涙で濡らしていた。
そんな直美を、辻山は何も言わず彼女の腕に自分の腕を回し、ゆっくりとほどく。
やっと顔をあげた直美と、辻山の目が合いお互いを見つめあう。 辻山は直美に少し近づくと、「ありがとう」と言って小さなキスをささげ、また遠ざかった。
直美も決心したようにその場を離れ、下りのエスカレーターに乗り、辻山の姿が見えなくなるまで見つめていた。 彼もまた、そうしていたからだ。
やがて直美を乗せたジェット機が離陸した音を聞くと、辻山はゆっくりと空港を後にするのだった。
それから数日後、アメリカの室井一家のもとに一本の電話がかかってきた。
「直美、電話だぞ。」父が直美を電話口に呼び寄せる。 直美が父から受話器を受け取り、耳に当てる。
「もしもし、直美です。 あっ、辻山さん!」
新・探偵物語 終
新・探偵物語 newdetectivestory
~新たなる「探偵物語」~ 「映画探偵物語」と言えば、皆さんご存知薬師丸ひろ子、松田優作による凸凹コンビで有名なあの角川の代表作ですね。
知っての通り、この「新・探偵物語」も「新」とはついている物のあの映画を下敷きとした作品です。 この作品での最大の魅力は、映画、原作共に登場しないキャラクター、工藤優作ではないでしょうか? この工藤は、あの有名なTVドラマ「探偵物語」で同じく松田優作が演じた、工藤俊作の息子という設定で、その馬鹿っぷりはまさにこの作品に華を添えるものでしょう。 大富豪で、変わり者で、おバカで、そんなキャラクター・工藤優作の存在は、この新たなる「探偵物語」に無くてはならない存在ではないでしょうか? 薬師丸明


