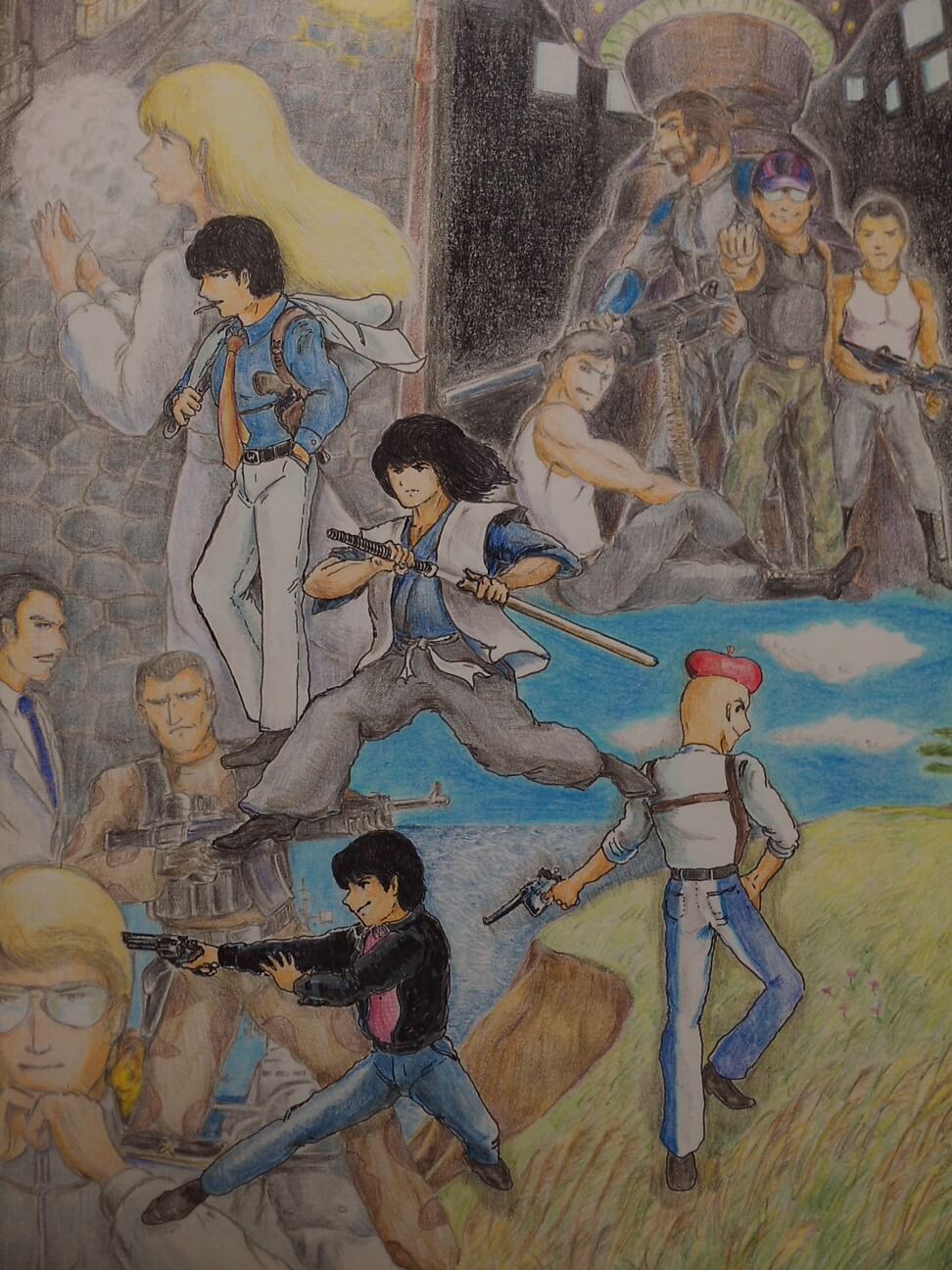
超人旋風記 (1)
異世界の物語は嫌いではない。
しかし何一つ鍛錬もしていない主人公が、突然異能の力を持ち、大活躍するなんてあり得ないと思っている。
その力が誰かに与えられたものだとしても、使いこなすために血の滲むような訓練が要る筈だ。僕も大して丈夫でもなかった身体を、徹底的にいじめ抜くことで強くしてきた。
だから僕の描く主人公にも、そうさせたい。そうあらせたい。
結構な長編になります。気長にお付き合い願えれば幸いです。
第一章 砂漠の旋風

……………。
…もう、何度目になるだろう。あの、夢も見ない眠りから醒めた。
音だけが聴こえる。窓を風が叩く音。小さな粒がガラスを叩く音も。
雨だろうか。それにしては空気が乾いている。乾き過ぎている。喉も、鼻腔も、カサカサだ。頬に硬いものが当たっている。肩にも。床だ。どうやら捻れた姿勢で横たえられているようだ。ザラザラとしたこの感触は砂か。非常に粒子の細かい砂。口の中が粘ついてジャリジャリする。汗に濡れた襟にも砂が付いているらしい。首が痒い。窓を叩いているのも、吹き付ける風に混じった砂なのだろう。成程、砂か…。
成程ではない、ここはどこだ。
僕は今度は一体どこへ遣らされたのだ…?
近くで話し声がする。聞き慣れない言葉。愚図る身体をどうにか動かし、寝返りを打つと、その声が止んだ。瞼が開かない。指先で触れてみると、目尻までびっしりと目脂がこびりついていた。これも砂のせいだろう。
それをこそげ落とし、目を開けると、鼻の先に若い女の顔があった。
顔も、カーキ色の軍用ジャケットの襟元から覗く肌も浅黒かった。漆黒の髪を右肩の近くで無造作に束ねていた。化粧っ気のない顔ながら彫りは深く、鼻も高い。インド人かアラブ人の容貌だった。東洋人を思わせる黒い瞳が見つめてくる。小さな唇が何かを言いかける。
――姉…さん?
「目が覚めたみたいね」
知らない言葉で話し掛けられたらどうしようかと思った――或いは一瞬、名前を呼ばれるかとも思った。初対面の筈の彼女に、剣ちゃん、と…――が、幸い彼女の口から出てきたのは英語だった。背中を支えて貰い、上体を起こすと、近寄ってきた男がボルヴィックの1ガロンボトルを差し出してくれた。最初は口だけをゆすぎ、二口目から喉に送り込む。生温かったが、渇ききった喉と身体には有難かった。1リットル近くを飲み終わると、わずかに汗が滲むとともに尿意を催してきた。膀胱がその前からはち切れそうになっているのに、今頃気づく始末。一体どれくらいの間、眠らされていたものか。
いや、それよりもここは…。
改めて周囲を見遣った。随分広い。コンクリート剥き出しの壁や床は色調に乏しかった。天井までは3メートルといったところか。その近くに嵌め殺しの小さな窓が2つ。ひっきりなしに当たってくる砂粒のせいで、空は全く見通せない。7~80畳はあるフロアを照らすのは、2つの裸電球だけ。しかし窓の外はそんなに暗いわけでもなく、しかも彼の体内時計は今がまだ午後であることを告げている。中途半端に暗いのは、外の砂嵐のためだろう。砂嵐の起きる場所、か…。
水の礼を言い、トイレの場所を――英語で――訊ねると、2人いる男のうち若い方が、フロアの片隅を指さした。ドラム缶が十数個積み上げられていた。その陰でやれと言う。彼らもそうしていると言う。
清掃用の排水口目がけて小便をしながらドラム缶に目を遣ると、線だけがのたくったような奇天烈な表示文字があった。アラビア文字。当然、意味などわからない。動かしてみようとすると、重かった。中は液体のようだ。それも、水よりも重い。ドラム缶群横の壁際には数百個のビニール袋に包まれた何かが積み上げられていた。こちらの表示は英語。〈ナトリウム〉。
何の倉庫なのだろう。
血の臭いが鼻を突いた。ナトリウムの袋の山の手前に、不格好な麻袋が転がっていた。大きい。乾いた黒い染みが麻の表面に滲み出している。床にも。入っているのは、死体…。
背中の中心を這い上がってくる震えがあった。
死体があることを知ったショックではない。そんなものはもう慣れっこになってしまった。死体があるという事実によって、精神とは別の場所、自分の意識とは別の場所で、肉体がある準備を始めたのだ。それが、震えと、なって…。
パイプ椅子2つとドラム缶に腰を下ろして向かい合う男女の側に戻り、もう一度礼を述べ、自分もドラム缶の一つに腰を掛けた。
男2人は研究用と思しき白衣姿だった。ドラム缶に座る女は警官か軍人と思われた。まだ24~5歳の若さだろう。襟に階級章らしきバッジ、折り目正しいカーキ色の上下、腰のホルスターからリボルバーの細いグリップが突き出していた。どこまでも黒い瞳が、またこちらを見つめている。初対面にも関わらず、最初その顔を見た時、温かな何かが胸に満ちた。胸が締め付けられた。それがまだ残っていた。どこか似ていたからだろう。
懐かしいあの顔に…。
「君は何者かね?」
年嵩の男が英語で訊いてきた。小柄で小太り、突き出した腹、これまた浅黒い肌。髪の量は多いが額だけ広い。鼻の下にはマスタッシュ髭。年齢は40代にも50代にも見えた。或いはもっと年配かも、或いは若いのかも知れなかった。欧米人がアジア人は年齢不詳だと嘆く理由も頷ける。特にアラブ人の年齢はわからない。「どうしてこんなところにいるんだね?」
「その前に」英語の通じる相手で良かったと思う。何しろ教え込まれたのは英語とフランス語だけ。英語は日常的に使うから硬いなりにまだましだったが、仏語の会話能力は子供並だ。「ここは、どこなんです?」
3人の顔に困惑の色が浮かんだ。髭の男はもう1人の、恐らく若いだろう男と顔を見合わせた。女が訊いてきた。
「自分がどこにいるのか、わからないって言うの?」
頷くしかなかった。
「じゃあ…」女が言葉を継ぐ前に、髭の男が身を乗り出してきた。「今ここで何が起きてるか、君は知らないわけか」
見当はついていたが…、「何が、起きてるんです?」
若い方が溜息をついた。
「き、騎兵隊の登場を願ってたわけじゃないが」ひょろ長い体を椅子の上で落ち着きなく揺すり、流暢とは言えない英語で軽口を叩いた。声は甲高く裏返り、無理やり笑顔を作ろうとする頬は引きつっている。「が、がっかりさせてくれるよなあ」
「つまり今は、騎兵隊の登場が必要な場面だってこと、ですね?」
男2人は再び顔を見合わせ、黙り込んだ。表情は暗かった。
じわりと汗が滲んだ。水が身体を素通りしていく気がする。女がピルケースに入った白い錠剤を差し出してきた。塩のタブレットだった。2錠を噛み砕き、ミネラルウォーターで流し込むと、ようやく水がちゃんと肉体の隅々に沁み通り始めた。身体がしゃんとしてきた。
「あなた東洋人ね? 中国? 韓国?」
「日本人です。それよりここはどこなんです?」
「ネフド砂漠」若い男が陰気な声で言った。「ざ、ザカーカから南東に80キロ。ね、ネフド砂漠のまさにド真ん中ってわけ」
「ネフド、砂漠? どこです、それは」
「アラビア半島だよ」髭の男が応えた。「ここはサウジアラビア王国だ」
サウジ、アラビア…。まるで実感が湧かなかった。今度は随分と遠い場所に飛ばされたものだ、くらいにしか…。「ここは石油採掘場か何かですか?」
本当に知らんのかね…、髭の男はやれやれと首を振った。「原子炉だよ」
「原子炉?」
「そう、我が王国がOPECに内密で建設を進め、実用にまで漕ぎつけた高速増殖炉なんだよ、ここは」声こそ抑えていたが、髭の男は次第に苛立ってきたようだ。「それより君は一体誰なんだ? 奴らの一味じゃないのかね?」
女が首を振った。「日本人が一味にいるという情報はないわ」
若い男が肩を揺すって笑い出した。「だ、だから言ってるでしょラワス。こんな非常時に正体もなく寝てられるこいつが、や、奴らの仲間なわけないって。し、しかもこいつ、銃も持ってない!」
ヒステリックで耳障りな笑い声を聞きながら思った。推測ではなく、仲間であって欲しくないという願望みたいだな。「奴ら…?」
「〈アラーの風〉」女が言った。「ここを占領してるテロリストよ」
――自国の石油資源にて空前の繁栄を誇ってきたOPEC諸国だったが、20世紀も終わりに近づく今、自国の資源がいつか枯渇するかも知れない、そう遠くない未来に怯えてもいた。石油が涸れてしまった後に17世紀のフランス貴族顔負けの贅を尽くしてきた支配者たちを待ち受けるのは、19世紀の遊牧民時代への逆戻りでしかないからだ。
それに最も怯えているのが、サウジアラビア王家のサウド一族だった。エジプトから首都リャドを奪還した1902年以来、正当な王家としてサウジアラビアを支配してきた彼らだが、その繁栄は王家としての威厳より、石油の利権と、今でこそ違うが、当初はほとんど無償で臣民から搾取してきた労働力の上に成り立ってきた。一度覚えた蜜の味を簡単に忘れられる筈もない。他の指導者たちが内心あたふたしながら何ら有効な手を打てずにいるのを尻目に、湾岸戦争終結後、彼らはモノカルチャー経済からの脱却を目指して動き出した。
その具体的行動の一つが、高速増殖炉と核廃棄物処理場の建設だった。
幸いサウジは、貿易においても他においても、日本と比較的強い結びつきがあった。日本にて度々試みられながら、住民の反対と役人、政治家の無能で停滞と頓挫を続ける核廃棄物の処理も、アラビア半島の広大な砂漠の真ん中で行えば反対する者もいない。処理肩代わりの見返りとして、技術と人員は日本政府と電力会社が提供する。そして膨大な手数料も。
計画が軌道に乗れば、サウジは核廃棄物処理と再処理のメッカとして、核産業の破綻し始めたヨーロッパ各国からも受注が取れる。手数料だけでも、値崩れを続ける石油利益に並ぶくらいになる目算もついた。この計画が知られれば、周囲のアラブ諸国は挙ってサウジを非難するだろう。イスラムの教えを裏切り、帝国主義者たちに尻尾を振った、と。しかし栄華の日々を失うことを思えば周りの雑音など何するものぞ。サウジは最悪の場合、OPECを脱退する積もりなんだとも言う。
ところが秘密裡に進めていた施設の建設と稼働とを嗅ぎつけた連中が、武器を手に施設を乗っ取った。それが〈アラーの風〉と名乗る宗教テログループだった――。
髭の男――ラワス・アリ・サラームと名乗った。サウジ側からの増殖炉技術者の1人だそうだ――と女とが交互に語った内容は以上だった。
嵌め殺しの窓に隙間でもあるのか、天井から下がる裸電球が揺れた。それにつれて灰色の床に落ちる4人の影が、伸びたり縮んだりした。3人の貌を彩る陰も数秒毎に形を変えた。各々が抱えた懊悩が、そのまま映し出されているかにも見えた。女の、上からの灯りのせいで、余計に目立つ瞼の下の隈が痛々しかった。
「儂らは襲撃の際、どうにか奴らの目を逃れることが出来た」アリ・サラームが言った。しかし他の連中は皆殺しにされたようだ。逃げ出す時に流れ弾に当たった日本人技術者のタカナカはこの倉庫で死んだ。もう見たと思うが、あの陰の麻袋の遺体がそれだ。
「〈アラーの風〉という名前は知っています」どこで見たのだったか。確か、対テロ訓練の研修を受けた時に、ファイルの一冊に載っていた…。「パレスチナ解放人民戦線とかいうところと組んで、イスラエルに度々何かしていた。リーダーは確か、アハメド・アッサン・アッシラーとマリード・カセム、だったかな。記憶が不確かですが」
いや、合ってるよ、アリ・サラームは頷いた。「今いるのはマリード・カセムの方だ。フランスとスペインでアメリカ大使館を爆破したあいつだよ。旧ソ連の軍事訓練を受けていたとかで…」
女が続けた。「自分のことをアラブの尖兵と呼んでる」
それが自分の同胞とも言えるイスラム諸国の盟主に牙を剥いたわけか…。
「お、OPECを裏切るサウジに、イスラムの盟主としての資格も、未来もないだろう、けどな」若い方――ヤリ・ハッサン。同じく技術者だそうだ――が鼻で笑った。犯行声明を出す際に、奴はこの国のことを“アラーの教えに背く者”とか言ってたぜ。「でもな、結局はカネよ、カネ。いくら要求したと思う? 3000万ドルだ! 払わなけりゃ原子炉を爆破する、だってよ!」
「興奮するなヤリ。声がデカすぎる」サラームがハッサンを小突いた。前を開いた白衣の内に、ベルトに差した、これまたリボルバーの銃把が見えた。
「払うんでしょうか?」
「王家が? まさか」サラームは肩を竦めた。ハッサンもだ。サラームがドラム缶群の上に置いたSONY製ラジオを顎で指した。「短波放送で聞いたんだが、王家は国防軍特殊部隊の出動を決定した。ドイツとフランスの対テロ部隊に訓練された連中だ」
「それは政府からの発表ですか?」
「いいや。た、多分、政府高官から、漏れたのさ。全く、馬鹿だよなあ。こ、これで秘密裡に進めてきたここの計画も、全部表沙汰。世界中に知れ渡っちまったってわけ」
声高に自国を罵倒するハッサンを、複雑そうな顔で女が見つめていた。ヤースミーン・ハダット。王立警備隊の隊員なのだと言う。
「さて、こちらの話は終わりだ。今度こそ聞かせて貰おうか」サラームが言った。「我々がここに逃げ込むより前に、君はここにいた。君は一体何者だ? どうしてこんな場所で…」
「多分、僕は…」
青年は立ち上がった。周囲を見回すと、襟足にまで伸びた髪が揺れた。ヤースミーンがその顔を見上げた。意外な長身に驚いた顔だった。ハッサンも背が高いが、青年の身体には鍛えあげた者特有の剛直があった。
切れ長の目が止まった。ドラム缶群の陰に隠されるように置かれた、錦織りの袋に収まった何かを捉え…、「この事態をどうにかするために送られて来たんだと思います」
多分、ではない。それ以外に自分がこの場にいる理由がない。
どうやって掴んだのかはわからないが、“あの男”と彼の組織は、ここでテロリストが事件を起こすことを予め知っていた。そして彼をここに送り込んだ。
そう、これまでと同様に。
青年を目で追っていたハッサンが、喉の奥で妙な音を立てた。せせら笑おうとして失敗したらしい。「ど、どうにか、する? この騒ぎの、中で、グースカ寝てたお前さんに、あの連中を何とか出来ると…」
青年は黙って、錦織りの袋の口を縛っていた紐を解いた。鞘に収まった刃物が出てきた。抜く。柄はボウイタイプだが、刀身はかなり細身、優に1メートルはあった。緩やかに反った片刃の剣は、ナイフと呼ぶには長すぎた。日本刀に似ていた。鏡以上に磨き上げられた鋼の地肌が、揺れる裸電球を鋭く反射した。
その刀身が放つ得体の知れない輝きに、ハッサンは寒気を覚えたようだった。サラームの方は青年の、刀を持つ立ち姿の一見自然な、しかしそれでいて巌の如き揺るぎなさに圧倒されていた。「その、刃物で、奴らに立ち向かう積もり、か?」
青年は頷いた。抜身の刀を見つめるその横顔に、ヤースミーンが問いかけてきた。「あなた、名前は?」
その澄んだ、切れ長の目をヤースミーンに向け、青年は応えた。
「那智剣吾だ」
…暗い室内に響くのは数台のキーボードが時折立てるエラー音と、引っ切り無しに紙を吐き出すプリンターの唸り声だけ。手元を照らすのは、天井から壁一面を覆い尽くす各種モニターのディスプレイ群が発する微弱な光だけだ。
アイスティーの曇ったグラスをテーブルに置いた太い指が、7つの勲章がぶら下がる軍服の胸ポケットを探った。
「煙草は御遠慮願えますか?」
テーブルの向かいから掛けられた柔らかい声に、太い指が止まった。それだけ敏感な機材が多いということなのだろう。抜きかけたダンスケの葉巻を渋々ポケットに戻す。微かな灯りに浮かぶ肉厚の横顔が、苛立ちと不快を顕にして歪んだ。椅子の肘当てに乗せた上腕の階級章には横に並ぶ3つの星。陸軍中将。
「それなら早いとこ話を進めて貰おう。ここは暑苦しくていかん」陸軍中将は鼻を鳴らし、向い合って座る男に言った。「遺伝子治療は現代の医学になくてはならない治療法の一つとなった。先天的に生じる障害に画期的な効果が見込める。しかし最大の欠点は、効果がなくなればもう一度、操作した遺伝子を投与し直さなければならないことだ。ここまでの話はそうだったな。君は最新医学の講義をするために、儂をここに呼び出したのか? 儂も相当暇だと思われているらしい」
中将の厭味たっぷりの台詞を浴びた向かいの男だったが、眼鏡の下の表情は全く変わらなかった。唇には笑みすら浮かんでいた。その外見は55歳の中将より20歳は若く、体重も30キロは軽そうだ。もっとも中将は男の正確な年齢を知らなかった。この見た目で優に40を超えているとの噂だけだ。
「申し訳ありません。もうしばらくお付き合い願います」
言葉こそ慇懃だったが、懇願ではなかった。“そこにいろ”と言われたような気さえした。さっきの煙草を遠慮しろとの台詞もそうだった。中将に准将が指図するなど…、憤懣遣る方無い中将だったが、何も言えなかった。この男のいかなる指示にも従え、それが国防長官の命令だったからだ。
国防長官どころか、この男はその気になれば、大統領の署名入り命令書でも持ってくることだろう。かつて長官の代理として会議に出席した際、CIA長官が同じようなことを言っていた。
“あの男は得体が知れないよ。”
その通りだと思う。大統領命令でなければ動かせない秘密機関のチーフという肩書のためばかりではない。名門スタンフォードを卒業後、陸軍士官学校に入り直し、一時は情報分析官も担当していたらしい。それがわずか40にして准将に昇進だ。
この男をここまで早く昇進させたものは何なのだ…、中将は思う。或いは誰なんだ。戦場でずば抜けた功績を残したのなら、それもわかる。だがこの男の胸には勲章一つ下がっていない。彼の昇進には、それと伴う筈の功績が存在しないのだ。大統領の差金…? いや、それもない。この男が今のポストに就いたのは、予備選で大敗中の現大統領が就任する3年以上前の話だそうだ。その頃まだこの男は大佐だった。士官学校卒業生なら誰でも一つは下げている各種特殊技能章も付けていない。襟の陸軍所属バッジ、左腕の星一つの階級章、そして右胸の名札だけだ。
《J・カサンドラ》
「…レニー・エドバーグ財団の医療研究班のことは、御記憶にありますか?」中将の前にお代わりのアイスティーが置かれると同時に、カサンドラ准将は話し始めた。壁のディスプレイの一角を見つめるその表情は、夢見る少年のようでもあった。細いカトラーのチタンフレームの眼鏡のレンズ上で、ディスプレイの瞬きが模様となって躍る。知らん、と中将が答える前に、准将は説明を始めていた。「欠点、いや、限界のある遺伝子治療に、半永久的な効果を持たせようと考えた面々です」
彼らは限界の打破を目論み、幾つもの仮説を出し合った。実用化、汎用化されれば、間違いなく医学会に革命を起こす研究です。必死にもなったでしょう。
治療が半永久的な効力を持つためには、操作された遺伝子を投与されるのではなく、それを体内において自ら作り出せなければならない。変質させた遺伝子を蓄え、自ら増殖させて行かねばならない。そのためには遺伝情報を蓄積するDNAから変質させて行くしかない。彼らはそういう結論に達しました。しかし今のところ、体内にあるDNAを直接いじることは不可能だ。
だから彼らは、まずは従来の遺伝子治療に倣い、RNAの操作から取り掛かった。
「〈フラーレン〉を御存知ですか?」
「知るわけがなかろう」中将は不機嫌を隠さず、アイスティーのグラスの氷を鳴らした。「科学用語か? 儂はその分野には全くの素人だ」
「なるべく簡潔に説明します。質問がありましたら御遠慮なく口を挟んで下さい」
相変わらずカサンドラはこちらに目を向けない。中将は溜息で仕方ないな、という意思表示をして見せ、改めて室内を見渡した。暗くて広さは判断つけ難かったものの、天井から壁に至るまでを100枚はあるディスプレイが覆い尽くしていた。一枚一枚は中将の自宅の50インチTVよりも大きい。その下に十数台のコンソールが並び、白衣の研究員たちがキーボードに向かっていた。それを見下ろす中二階のフロアに、2人の陣取るテーブルがあった。カサンドラが指を鳴らした。ディスプレイの1つに、球形をした原子模型の画面が出た。
「あれがフラーレン。炭素結合の一種。別名C-60。つまりは炭素原子が60個、サッカーボールの模様状に並んでいる結合体です」
…炭素系の新素材開発の副産物に過ぎなかった筈のこいつが俄然注目を浴びたのは、1989年のことでした。硬くて軽い物質を構成できるばかりではなく、他には類を見ない様々な特性を示すことがわかったからです。例えば炭素原子70個で構成されるC-70は植物の光合成を行う回路と全く同じ働きが出来ることがロックフェラー大学にて発見された。世界各国の学者たちは後に続けと挙って研究を始め、興味深い結果が次々に出てきました。C-90は高分子結合をやってのけ、C-120は低温下において超電導の性質まで示したとのことでした。
エドバーグ財団の面々は、このフラーレンが着目される遥か以前より、その特性に気づいていました。蛋白質の結合をこのサッカーボールの、原子の一つ一つに当て嵌め、複雑に組み替える実験を始めていたのです。
「ここまではお解りですね、フロイト中将?」
「まあ、わかる」国防省長官補事務局の筆頭補佐官にして陸軍中将、ピッツバーグ・フロイトは曖昧に頷いた。科学に疎い彼の中の知識と言えば、蛋白質も人間の身体を構成する物質も、元は炭素原子だということくらいだったが。
もちろんその話と、自分が今ここにいる理由とは、全く結びつかなかったけれども…。
…元々RNAはアデニン、グアシン、シトニン、ウラシルの四つの塩基分子が組み合わさって出来ています。彼らは炭素原子の結合をフラーレンに当て嵌めることで、RNAの特性だけを変質させていった。そこにある種のポリメラーゼ――結合変換のための媒体を加えることで、変質は固定できる。変質したRNAを、ここでは転移RNAと名づけました。それが出来上がるわけです。60個の原子配列に四つの塩基を組み替えながら当て嵌めるのですから、その組み合わせは数万通りに及ぶ。その数万通りもの転移RNAを使って、彼らは実験を始めた。体細胞内での蛋白質合成の際、転移RNAがリボゾームにどんな蛋白質を生成させるか、それを一つ一つ記録しながら、実験用の細胞に投与していった。
ある配列、としか申し上げられませんが、とにかくある配列による転移RNAが、ニューロンを培養液の中で増殖させ始めたのは、彼らが実験を開始して2年後のことでした。
連中は狂喜しました。
「ニューロンというのは…」フロイト中将は呟いた。「神経細胞のことだったな」
「御存知ではないですか」
「馬鹿にする気か。儂だってハイスクールは出ているんだ。しかしニューロンが増殖するというのが、そんなに大変なことなのか?」
「大変なことですとも」抑揚乏しいカサンドラの声に、この時は僅かな力がこもった。「胎児のもの以外のニューロンは、本来非増殖だった筈なのですから」
あれはカナダだったかな、マウスの脳神経細胞を増殖させたとのレポートが出されたこともありました。実証するデータは出されませんでしたがね。それに対しこちらは、弱っているとは言え、生きた人間の本物の細胞を使っての使っての実験です。
「生きた人間の、細胞を、だと…?」
「ええ、末期癌患者のものをね連中は自分たちの病院で抱える癌患者を、言葉巧みに言いくるめて、秘密裡に実験を行っていたんです。珍しいことじゃありません。医療機関と研究機関を併せ持ち、名を売りたがっている大手の専門機関は、大抵似たようなことをやっています」
とにかく連中は狂喜しました。怪我は言うまでもなく、やり方によっては損傷した脳細胞でさえ修復できる可能性だってある。汎用化できれば、自分たちの名を医学界の歴史に残せる成果だったのです。
しかし本当の驚愕は、その後にやってきました。
「副作用、か?」
「ご明察です。だが、マイナスの副作用ではなかった」
増殖させたはいいが、活動しなければ意味がない。そう考えた彼らの1人がそのニューロンに、反応速度を試すために電位パルスを流してみたところ、そいつが常軌を逸した伝導率を持つことが判明した。内部においてもシナプスにおいても、パルスや化学反応への抵抗がまるで生じないニューロンです。その伝導速度たるや、光ファイバーを思わせるものだった。
変質させた転移RNAが細胞内で、蛋白質とともに必要な酵素を生成させる際、これまでに見たこともない酵素を作り始めたかららしいのです。試しにその酵素を、老衰や病気で死にかけた動物に投与したところ、その心臓がたちまち活性化したそうです。マウス、ラット、猿…。全て同じ効果が得られました。本来RNAから生成され外に向かう筈の酵素が、逆方向にリボゾーム自体を賦活化し、蛋白質合成において従来の常識からは考えられない、“強い”細胞を作らせたのです。
その“強い”細胞で成り立つニューロンは増殖までした。おまけに電位パルスだろうがアセチルコリン反応だろうが、全てを素通ししてしまうような代物になった。
エドバーグ財団の研究者たちはそれをすぐさまマニュアル化し、医学と自分たちの未来に対する輝かしい夢を抱き始めました。しかしその研究は突然…、
「NSCの命令により、凍結された、か」フロイトは頷いた。「ようやく思い出した。あの件か。記者会見が急遽中断されたんだったな」
「研究は国家機密扱いになり、エドバーグ財団の面々に、後世に名を残す機会は永遠に失われました」
「その凍結を決定し、財団の研究者たちを拉致させたのは、〈エスメラルダ機関〉」顔はディスプレイ群に向けながら、フロイトは横目でカサンドラを見た。
NSC――合衆国国家安全保障会議。それはアメリカの、謂わば最高機関と呼んでも過言ではない。上下院議会も大統領特別委員会も、この会議の前では色褪せる。ここで話し合われる多くは議会やマスコミ、国民に明らかに出来ない特殊且つ“微妙な”問題だ。議題は外交から国防に至る。内密の裡に決定された議事、出された命令が合衆国の、或いは世界の趨勢を左右しかねないこともある。ベトナム、グレナダ、湾岸への合衆国軍派遣も、結局はこの会議が決定を下した。事務局長は大統領特別補佐官が務め、国務長官、国防長官、CIA長官、陸海空軍最高司令官たちが出席する。もちろん、大統領もだ。
〈エスメラルダ機関〉はそのNSC直属の秘密機関だった。何をする組織なのかなど誰も知らない。その実態は本当に霧の彼方にあり、CIA長官でさえこの組織の詳しい活動内容を掴めていないということだった。機関に命令を下せるのは大統領か特別補佐官のみ。しかし時と場合によっては、この機関がNSCに決定を下させることもあるという陰口すら聞こえていた。
構成メンバーも定かではない〈エスメラルダ機関〉の、表向きの責任者が、フロイトの目の前にいる、秀麗で優しげな表情を崩さない若き准将、ジェームス・カサンドラなのである。
得体の知れない組織の長も得体の知れない男だった。CIA長官だけではない。NSCに出席するメンバー全員が内心そう思っていた。大統領が――世界最高の権力者、合衆国大統領が、である――、見た目だけなら30そこそこの彼に、猫撫で声で話し掛けるのを聞いてしまったら尚更だ。
一体この男は何者だ? そして《エスメラルダ機関》とは何なのだ…?
横目で伺うフロイトの視線に気づいているのかいないのか、カサンドラは前髪を弄りながら相変わらず夢見るような表情で、前方のディスプレイ群を眺めていた。倣ってディスプレイ群を見たフロイトはその時初めて、画像の幾つかが心電図や体温測定などの検査機器であることを知った。2人の前方、壁の中心に埋め込まれた3メートル四方の大スクリーンを二分割して映っているのは、ドーム状の建築物の平面及び断面図であった。
白衣の研究者の1人が背中越しに言った。「04、動き出しました」
「画像も絶やすな。中将に一部始終をお見せする」
フロイトの目が、大スクリーンの二分割画面を移動し始めた光点を捉えた。どうやらそれが、測定を受けている実験対象らしかった…。
…砂で軋む鉄扉を苦労の末に開け、髪を背中に束ね直したヤースミーンが顔を出した。
素早く左右を見渡し、背後に合図し、車も通れそうな広い通廊に注意深く足を踏み出す。左肩に水と救急パックなどを入れたバッグを担ぎ、右手には38口径S&W・M649リボルバーが握られている。すぐ背後にサラームが続いた。やはりリボルバーを構えていた。チャーターアームズ社製の粗製銃、パグ357マグナムだ。反動が手首にきついので、38スペシャル弾を詰めているということだった。それ以前に腕力もないのだろう。構えた銃が震えていた。
サラームになだめられつつ、足をガクガクさせたハッサンが続いた。そして最後に…、
那智剣吾と名乗った青年が出てきた。
通廊は倉庫の中よりは明るかった。窓が多いせいだ。しかしその向こうは未だ砂嵐の最中だった。高い天井近くに並ぶ窓は、ことごとくガラスを銃弾で割られていた。壁にも生々しい弾痕があった。ゆったりと弧を描く通廊を見て、剣吾はこの原子炉を囲む建物がドーム状だと知った。
外から吹き込んだ砂が積もり始めた通廊を、4人は進み始めた。なかなかに足が進まないハッサンを、なだめては急かすサラームは、その背後から幽霊のように静かについてくる剣吾を見て、首を振った。「まるで音を立てんな」
「ああ、砂のお陰です」剣吾は灼けていない顔に薄く笑みを浮かべた。「それにこのブーツ。底に特製のヴァイブラムを貼ってあるんです」
「成程。しかし変わった格好だ」サラームは改めて剣吾の全身を眺めた。袴を仕立て直したような幅広のズボン、その上から足首をしっかり固定するブーツ。袖のゆったりした、これまた黒い着物の上に、紐で前を合わせる袖なしのジャケット――サラームは作務衣と陣羽織というものを知らなかった――。そして左手に提げた、錦織りの袋から柄だけを出した、例の刀。「ここでは背広姿の連中しか見なかったが、今もニンジャ映画の格好をした日本人もいるんだな」
「多分僕だけですよ。これが慣れているんです」
「こ、ここでタカナカたちに、会うまではさあ」ハッサンが上ずった声を出した。「日本人ってのは、全員イカれた連中だと、ばっかり、思ってたよ。な、何しろここで聞く日本人の話と言やあ、ジャパン・レッド・アーミーとかのことしかなかったからさ」
「止めろアリ」サラームが顔を顰めた。「それに声が大きい」
「ん、ああ、わ、わかってます。俺の声が大きいのはわかってますって」唇の端から垂れそうになる涎を手の甲で拭い、ハッサンは奇妙な笑い声を上げた。眼の焦点が合っていない。ストレスが限界に達しつつあるのだろう。喋っていないと精神の均衡が保てないのだ。しかし喋り出す度に立ち止まり、その都度サラームに叱られる。「で、でもよ、お、王家がカネを出し渋ったら、や、奴ら、ホントにここを吹っ飛ばす気かな」
「可能性は低いとは言えないわ」前方から注意を逸らさず、ヤースミーンが言った。「少なくとも本気なのは確かよ。連中、ここに持ち込んだのは武器だけじゃない。ガスもよ」
剣吾は目を細めた。「毒、ガス…?」
「多分ね。同僚が通信が途切れる前に言ったの。警告標識の入った大きなガスボンベが運び込まれてるって」
「そ、そりゃあ、きっと、ガスバーナーだよ。奴ら、きっと、ここでバーベキューでもやる積もりなんだ」
「いいからとっとと歩けヤリ」サラームが、止まらない額の汗を袖で拭った。「何のガスだと思う?」
「わからない。手に入れやすい物だったらサリンとかだろうけど」
でも…、ヤースミーンは言った。「それだけのものを持ち込める奴らが、一体どこからの支援を受けてるのかってことも問題だわ」
サラームも苦々しく頷いた。「原子炉のことが明らかになってから、どの同胞もこの国への非難ばかり繰り返してるらしい。先頭に立ってるのはイラク。シリアもだ。この2つが真っ先に声明を出したとラジオで言っていた」
「じゃあ、そのどちらかが…」
サラームはいや、と首を振り、ヤースミーンを見た。「イラクは自分のとこの核融合炉をイスラエルに壊されたからな。ただのやっかみだ。それにシリアは、中道を歩く我が国とは元々一線を画してた。あの声明は、次のイスラムの盟主は自分だと言わんがための、謂わばデモンストレーションだよ」
「そ、それじゃ、ど、どこが、怪しいって言うんです?」
「沈黙を守ってるが、恐らくはイランだろうと思う。6年前に巡礼者の虐殺があって以来、奴らは我が国を目の敵にしてきた。おまけに奴らは、ロシア以上に当てにしてた金蔓である日本を、我々に奪われたのも同然だ。腹を立てていて当然…」
「待った」
剣吾が前を歩く3人を制した。
緩やかにカーブを続ける通廊の前方に、天井から見下ろす監視カメラが現れた。備え付けのものとのことだが、ゆっくりと首を振っているのは、監視がまだ生きていることを意味していた。
慌てる3人を、剣吾が壁の陰に引き戻した。
騒ぐなと命じられたハッサンが、自分の前腕に噛み付いた。サラームがヤースミーンと剣吾を交互に見た。「どう、する?」
「あのカメラは管制室が管理してるのかい?」剣吾がヤースミーンに訊いた。「君の同僚がまだ残ってるって可能性は?」
「生きてたら通信に出てくれる筈よ」
サラームが呟く。「カメラを壊すしか、ないか」
「いや、それはまずい」剣吾は2人に首を振った。「管制室にいるのが君の仲間じゃないなら、僕たちの存在を明かすことになる」
「じゃあ、どうするの?」
自分にはこれから、テロリストたちとの血腥い遣り取りが待っているだろう。しかし巻き添えを食っただけのこの3人――特にヤースミーン――は何とか逃がしたい。そのためには敵に見つかる前に、外に出さなくては…、剣吾は壁を触った。「この向こうは、外なんだろう?」
「そうよ。窓がもう少し低くて大きかったら、4人とも出られるんだけど」
ヤースミーンは肩を竦めた。彼女は背が低すぎ、サラームは体が重すぎるのだ。
そのサラームが、剣吾の背後に顎をしゃくった。「今来た方とは反対の方に、燃料の搬入口があるにはある。扉は油圧式のシャッターだがね」
「動かしてみましょう」
「やってみたよ。倉庫に隠れる前に。びくともしなかった」
「僕なら何とか出来るかも知れない」
「重さ2トンの扉だぞ。おまけに電源は入ってない。スイッチは管制室じゃないと入れられないんだ」
「行くだけ行ってみます。何とかなりそうだったら呼びます。ここでじっとしていて下さい」
言うが早いか、剣吾は3人から離れ、今来た通廊を引き返した。最初はそろそろと、次第に歩速を上げ、姿勢を低めたまま、猫よりも音もなく走り始める。踝近くまでを埋める砂に足を取られることもない。それを巻き上げることもない。
走り出した瞬間、見えないスイッチが切り替わり、身体の中で目覚めたものがあった。
血管を、神経を、駆け巡る何かが、剣吾の全知覚を鋭敏に研ぎ澄ました。遥か後方に遠ざかった3人の気配が感じ取れる。息遣い、体温までも。自分の顔に吹き付けてくる風に混じる、或いは割れた窓から吹き込んでくる細かい砂一粒一粒までもが見えてくる。
視界の左側を流れる壁の向こうに、砂漠が広がっているのも、その砂漠に立つ数人の見張りらしき人の気配までもが感じ取れる。彼らが手にした自動小銃や拳銃の無煙火薬の臭いまでも。そして放たれる警戒心や殺気までも。ただでさえ鍛えに鍛え上げてきた剣吾の五感が、それ以上の増幅を強制されたのだ。今の彼の感覚は、いかなるセンサーをも凌いでいた。
目の、いや、頭の奥で、瞬くものがある。それは文字であり、声である。今はまだ見えない。聞こえない。しかし執拗に頭の中で瞬き、囁き続ける…。
さっきまでいた倉庫の前を過ぎ、外の気配も遠ざかっていった頃、サラームの言っていた搬入口を見つけた。高さ3メートル、幅4メートル。左右から閉じた鋼鉄の扉は、叩いてみると厚かった。
扉の両端の僅かな隙間から、油圧開閉式と思しきジャッキの一部が覗けた。サラームの言葉通り、近くにスイッチはない。運良くここの監視カメラは、誰かの撃った銃弾で死んでいた。外にも人の気配はない。
剣吾は錦織りの袋を壁に立て掛け、扉の前に立った。懐から出した半紙に似たティッシュで鼻をかむ。砂のせいでスカスカ言っていた鼻孔の通りを良くする。畳んだティッシュを懐に仕舞い、鼻で大きく深呼吸し、両手指を扉の継ぎ目に掛ける。食いしばった歯の間から唸り声が漏れ、ゆったりとした袖の下で上腕前腕の筋肉が倍以上の太さに膨れ上がった。
ミシリ…、と音を立て、数トンの扉が震えた。ジリ、ジリと左右に動き始める。ほんの数ミリもなかった継ぎ目が5センチ程に広がった時、コンクリートの壁に扉を固定していた鋼鉄製のフレームが悲鳴を上げた。歪み始める。周囲のコンクリートに亀裂が走った。そこが限界のようだった。どんなに力を込めても動かない。剣吾は汗の浮いた顔を上げた。目にかかる前髪を掻き上げ、歪んだフレームの中を覗き込む。
あった。フレームの奥に2本のシャフトが下り、扉を引き留めていたのだ。安全装置ということらしい。表面の光沢から見て、材質はチタンの合金かと思われた。
剣吾は立てておいた錦織りの袋の紐を解き、刀の柄を握った。鯉口を切り、スラリと鞘走らせる。
灯りのない通廊の中でさえ、その刃は鮮やかに光った。鏡のような刀身が、彼の顔を映す。彼の顔にも、刃の放つ光が差す。現在ナイフ鋼材では世界最高との呼び声高い粉末合金ZDPを元にした3種の鋼材を、合衆国最高のナイフメーカーの1人、F・カーターに鍛え、研ぎ上げて貰った業物だ。もっとも剣吾は、誰がこの刀を鍛造したのかなど知らなかった。武器には何が要る、と“あの男”に訊かれ、細かく出した注文に戻ってきたのがこれだっただけの話だ。何でもロックウェル硬度とやらが、69を超えるらしい。
しかし硬さなど関係ない。市販の出刃包丁でも構わない。いざ斬れる刃物を手にしたならば、大抵のものを切断する自信が剣吾にはあった。昔は竹を断ち、藁束を切断した。そうやって長年培ってきた居合の技を、今のこの身体は何倍、何十倍にも強く、鋭く増幅してくれる。袋に収まる鞘を静かに床に置き、両足を前後に開き腰を低く落とし、刀を両手で正眼に構える。スポーツ剣道の正眼とはまるで違う、両腕を伸展させた構え。
無言の気合とともに、剣吾の体が前に進んだ。上体の揺らがないその動きは、傍から見れば静止していたままのようにも見えただろう。もちろん足元に積もる細かい砂粒を舞い上げることも、一切ない。同時に刀が左から右に、微かな光の残像を残し、走った。
扉を食い止めていた2本のシャフトが、キイン、と甲高い音を立てた。
刀を鞘に収め、そっと床に置いた剣吾は、もう一度扉に指を掛けた。シャフト2本は真横に切断されていた。歯止めを失った扉は重さ2トンの鉄塊に過ぎなくなった。それも剣吾の出すパワーショベルの怪力に屈し、遂に70センチ程の隙間と作る。これだけあればサラームの腹も抜けられるだろう。
外から濛々たる砂煙が吹き込んできた。砂嵐の止む気配はない。外に見張りのいる気配もない。扉をこじ開ける者がいるなど、思いもしなかったのだろう。剣吾は刀を拾い、ヤースミーンたちを呼びに戻ろうとした。犬の聴覚にも勝る耳が、遠くで放たれた叱咤の声を捉えた。聞き覚えのない声。
3人が見つかったのだ。
剣吾は走り出していた。体勢を低め、風のように疾駆する。3人のいた場所から、直線に直して約800メートル。その距離を走り抜けるのにわずか20秒。
アラビア語と思しき怒声が、剣吾の足を止めた。
角の向こうでヤースミーンの、これまたアラビア語の激しい声が応じた。それと、英語とアラビア語をごちゃ混ぜにして喚くハッサンの声。そっと覗いてみると、シュマーグ――木版刷り模様の布――で頭と顔を隠した4人の男が、自動小銃を構えていた。砂よけに防塵カバーをつけた、旧ソ連製突撃小銃AK74だ。銃口にはこれも砂よけだろう、事務用の指サックが嵌め込まれていた。
テロリストの1人がサラームとヤースミーンから銃を奪い取った。腰を抜かして留め金が外れたかのように喚き続けるハッサンの横で、ヤースミーンが連中を激しく罵った。テロリストたちも怒鳴り返し――バズラ、アーヒラ、とだけは聞こえた――、小銃を一斉にヤースミーンに向けた。うち1人が、引き金に架けた指を引き絞った。
剣吾の存在を敵から隠していた方が戦いには有利である以上、正直、見つかりたくはなかった。しかしもうそれどころではなかった。
剣吾は飛び出していた。
テロリストが引き金を絞り、AKが口径5.54ミリ高速弾を吐き出し始めるまで0.4秒。その時間、その動きが実に緩慢に、剣吾の目には映った。そいつとヤースミーンとの間に体を割り込ませ、刀の鞘でAKの銃身を跳ね上げるのに十分な余裕があった。銃声の轟音が耳を弄した。ヤースミーンが反射的に顔を庇った。サラームが頭を抱え、既に座り込むハッサンは瞼を固くつぶった。数発の高速弾が天井を穿ち、削った。シュマーグの下の、テロリストの目が見開かれた。そいつの目に、剣吾の出現は降って湧いた幻のように見えたのだ。
錦織りの袋が音速を超えるスピードで2回突き出され、2回弧を描いた。テロリスト4人は刀の柄を鳩尾に、振り下ろされた鞘を首筋に食らった。砕かれた天井の破片がセメントの粉とともに、ヤースミーンたちの頭上に降り注ぐ。
撃たれていないと知ったヤースミーンが、目を開け、顔を上げた。4人のテロリストが昏倒し、床に転がっていた。立っていたのは、剣吾だけだった。
剣吾は男たちのシュマーグを剥ぎ取った。白目を剥いたテロリストたちの、獰猛な顔が現れた。1人は白人の顔だった。
剥いだ布を一枚一枚細く裂き、手際よく束ねてロープを作った。2人の体を引っ繰り返し、瞬く間に後ろ手に縛り上げる。足首もだ。ヤースミーンが茫然とそれを見つめる。額から血を流すサラームも。飛び散ったコンクリートの破片で切ったのだ。
「い、今…」床に座り込んだままのハッサンが呻いた。「お、お前、どこから、現れた?」
剣吾はロープを3本、ヤースミーンに放った。「そっちの2人を頼む」
「な、何をやったんだよ! 一体、今、何をしでかしたんだお前は!」
「黙れヤリ!」サラームの一喝に、ビクッと全身を震わせたハッサンは、泣きそうな顔でサラームを見上げた。ズボンの前にわずかに染みが広がっていた。サラームは頬の痙攣が治まらない。「喚きたいのは儂も同じだ…」
剣吾は顔を上げた。さっきは首を振っていた監視カメラが、いまはこちらをじっと見つめている。銃声も聞かれたことだろう。こんなことなら最初から3人を連れて行っておけばよかった。
しかしもう、後の祭りか。「1人連れて行こう」
「人質にするの? 多分、あんまり効果は…」
「奴らの配置だとか総数だとかは訊き出せるだろう」
「待て。連れて行くはいいが、どこにだ?」
「もちろん、搬入口ですよ」
2丁の銃を取り戻し、敵のAK1丁も奪ったヤースミーンが、人選を始めた。剣吾の言葉に半信半疑らしいサラームも手伝った。剃り上げた頭皮いっぱいに蛇の刺青を施した、見るからに凶悪そうな奴は避け、まだ10代にも見えるなるべく大人しそうな男を選んだ。ヤースミーンはロープ一本で引っ張っていけるように、そいつの手首を体の前で縛り直した。剣吾が背中に活を入れ、男を立たせた。サラームに小突かれ、ハッサンもようやく立ち上がる。
不意にサラームの顔がどす黒くなり、妙な咳をし始めた。咳き込みながら蹲り、くそっ、と罵声を漏らす。ヤースミーンが肩のバッグからヴォルヴィックのボトルを出し、近寄った。貪るように水を飲んだサラームは言った。「薬を置いてきちまった」
「に、ニトロだよ。ラワスの持病だ」ハッサンが剣吾に言った。
「心臓が悪いんですか?」
「ず、随分、前からだ」
まずいな…、剣吾は床に散らばったAKの空薬莢を一つ拾い上げた。時間の制約も生じたわけか。「急ぎましょう。次の追手が来る」
捕虜のロープをハッサンに任せ、ヤースミーンがサラームを支えた。しんがりを剣吾が務め、4人と1人は搬入口に歩き始めた。振り向いた剣吾が、AKの空薬莢を投げた。弾丸そのものより速く飛んだ空薬莢は、彼に焦点を合わせるレンズを貫き、監視カメラそのものを破壊した…。
…剣吾のこじ開けた搬入口は、サラームの声をますます嗄れさせた。「信じられん。どうやって開けた…?」
「あなたが、やったの?」ヤースミーンの声も震えた。その目は剣吾が切断したシャフトを捉えていた。人間業なの、これは…? その顔はそう言っていた。さっきの出現にしてもそうだ。「あなた、一体…」
「移動手段が欲しい」剣吾は何とか話題を逸らそうとした。「捕虜から何か聞き出してみてくれるか。奴らを運んできたジープでもあれば儲け物だ」
砂を運び込む風に逆らって、剣吾は1メートルの厚さの扉から体を出した。吹き付ける砂混じりの風に平気で顔を晒す。顔に向かってくる砂粒より、瞬きの方が早いのだ。続いてヤースミーンも出て来た。両手で目を庇いつつ、剣吾の横に立つ。砂嵐の遥か上空を飛ぶ、ジェット機の轟音が聞こえてきた。
「国防軍のF15だわ」ヤースミーンは奪ったAKの銃口を下げた。「1時間に一回、威嚇飛行をやってるの。今はここからは見えないけど…」
砂漠での砂嵐は上空500メートルまで覆い尽くすこともあるというから、見えなくて当然だろう。遠ざかる轟音を聞きながら、剣吾は頷いた。しかしどこか上の空だった。さっきから妙な違和感を覚えていた。この風、この砂、この砂漠の匂い…。
「どうかした?」
「何でもない。もし移動手段がなかったら、歩いて逃げられるか?」
「難しいわ。砂嵐もだけど、サラームさんはもう歩かせられない」
「それじゃ尚更移動手段が要る。奴に訊こう」
「尋問を始めるわ。得意じゃないけど。ハッサンが今、見張って…」
そのハッサンの、押し殺したような呻きが聞こえた。そしてサラームの、アラビア語での怒声が。振り返ったヤースミーンはAKを構え直し、扉の中に飛び込んだ。続いて戻ろうとした剣吾だったが、ドーム状の建物を見上げた足が止まった。砂漠に目を戻す。この砂漠を、この場所の匂いを…。
僕は知っている。
ヤースミーンの警告の声に、剣吾は我に返った。彼女とサラームとが背中から、扉の隙間を抜けて出て来た。続いてハッサンも。正しくは捕虜にした筈の男に押し出されてきたのだ。ハッサンの血走った目は飛び出さんばかりに見開かれ、口がパクパクと開閉した。
言葉の代わりに溢れ出したのは真っ赤な鮮血だった。
背中に刺さった刃物が、肺にまで達しているのだ。
体の前で縛り直したのが災いした。身体検査しなかったのも。若いテロリストは手を縛る戒めをあっさりほどき、ズボンかブーツに隠し持っていたナイフでハッサンの背中を襲ったのだ。
パグ38口径を構えるサラームだったが、ハッサンが邪魔で男を撃てない。AKを腰だめに構えるヤースミーンもだ。ハッサンの陰から2丁の銃を見比べた若いテロリストが、歯を剥きだして笑った。ハッサンをサラームに向けて蹴り飛ばす。ナイフの抜けた痕から、血が噴水のように迸り、音を立てて砂に吸い込まれ、ハッサンを抱き止めようとしたサラームの白衣を汚した。その時既にテロリストはヤースミーンに襲いかかっていた。右手には血に濡れた細身のグルカナイフ。狙いは彼女の持つAKの奪還だ。
多少の実戦経験もなくはないヤースミーンだったが、殺しに慣れた若いテロリストの殺気、失神していた時とは打って変わった表情の獰猛さは、彼女を竦ませ、棒立ちにさせるに充分だった。その顔に、テロリストが砂を蹴り浴びせた。
反射的に顔を背けた彼女の首筋を、くの字に曲がったグルカナイフが掻き切る寸前、錦織りの袋がその刃を受け止めていた。
袋が裂けた。
ヤースミーンの前に剣吾が立っていた。
舌打ちをしたテロリストだったが、動きに遅滞はなかった。即座に標的を剣吾に切り替える。概してアラブ系の兵士はナイフの扱いが上手い。しかも度重なる実戦で鍛えた腕だ。低くした姿勢から突き出されるナイフの切っ先は実に巧みで速かった。
しかし剣吾は慌てもせず、剥き出しになった刀の鞘だけでナイフを弾いた。
鞘を削られることすらなかった。テロリストの顔から笑みが消えた。勝手の違う、と言うより、自分より腕の立つ相手にぶつかったことを知ったのだ。憎悪に顔を歪ませ、ナイフを大きく振りかぶる。前に出る、と見せかけ、背後に跳び、ぐったりしたハッサンを抱きかかえたサラームに向かって走った。目的はあくまで銃だ。
剣吾の長身が縦に伸びた。足場の悪い砂地をものともせず、跳躍したのだ。走るテロリストを優に飛び越え、その前に降り立つ。一瞬立ち尽くしたテロリストだったが、次の瞬間、ナイフごと剣吾にぶつかってきた。喉を狙った一閃目を眼前で見切った剣吾は刀の柄を握り、腰を低めた。
キィン!
2本の刃が火花を散らした。光るものが宙を飛んだ。刀が鞘に収まり、静かな鍔鳴りの音がした。剣吾の周囲の砂が、彼の外側に向かって螺旋を描き、舞い上がった。
音速を超えた居合の一閃は、テロリストのナイフを真ん中から断ち折っていた。
折れたナイフを茫然と見つめるテロリストが、信じられないと言いたげな顔を上げた瞬間、そいつの肘から先の両腕が、砂の上に落ちた。剣吾が切断したのはナイフだけではなかった。しかもまさにカマイタチの一閃だった。転がった両腕、或いは肘の切断面からは、一滴の血も流れ出さなかったのである。
剣吾の耳の奥で、蘇った声があった。
――まだ、遅いな。
はい、先生…。
悲鳴を上げられる前に、鞘でそいつの首筋を強打し、再度昏倒させ、剣吾はサラームの前に駆け寄った。サラームの膝に抱えられたハッサンは目を剥き、死の痙攣を始めていた。グルカナイフは肺から心臓にまで達していたのだろう。座り込むサラームのズボンをハッサンの血が重く濡らし、その下の砂にも広く地図を作っていた。色彩の乏しい砂の世界に慣れた目に、染み込む血の色だけが異様に鮮やかだった。サラームは剣吾を見上げ、首を振った。
膝をがくがくさせたヤースミーンが、一度腰からへたり込み、どうにかこうにか立ち上がった。剣吾を見つめる目には明らに畏怖があった。剣吾の動きは目で捉えられなかっただろうが、両腕を切断されたテロリストは確かに2人の間に転がっていた。何をしたの…? 言葉は出てこなかったが、唇がそう動いた。
剣吾が鋭く振り返った。銃声を立てなかったにも関わらず、動きと居場所を察知されたらしい。全視界を遮る砂煙の向こうから、迫ってくる気配があった。敵意、殺気。1人や2人のものではない。最早、ヤースミーンたちを逃すどころではなくなった。立ち尽くすヤースミーンと、息絶えたハッサンの頭を膝に、いつまでも首を振り続けるサラームに厳しく命じる。「中に戻るんだ!」
まだハッサンの死体に拘るかに見えるサラームを、ヤースミーンが引きずるように立ち上がらせた。背中を押して、扉の中に戻る。そして剣吾も。剣吾が扉の隙間に飛び込んだ瞬間、数丁の自動小銃の、テンポの良いフルオートでの銃声が、砂煙の向こうから立て続けに響いた。転がるテロリストの切断された両肘から、爆ぜたような音とともに血が噴き出した。
「…動き出したな」光点が移動を始めた巨大スクリーンに目を戻し、ピッツバーグ・フロイト中将は呟いた。「しかし、たまげた」
「まだ序曲ですよ。見所はこれからです」相変わらず薄暗い室内で、相変わらず唇に薄い笑みを浮かべたジェームス・カサンドラ准将は言った。
「だが、ようやくわかったよ。君のところの〈エスメラルダ機関〉が、エドバーグ財団の研究を凍結させた理由というか、目的が」フロイトは頷いた。「あの男だな?」
NSC、そしてエスメラルダ機関の目的は、エドバーグ財団の研究から、神経細胞どころか全身を強化された兵士を製造することだった。例の増殖する強化ニューロンを筋肉などに移植できれば、或いは神経細胞をも強化する例の酵素を使って、光ファイバーの伝達速度を持つニューロンの生む反応速度に対応できる筋肉が作れれば、どんな極限状況にも応じられる兵士の生産、無敵の軍隊の創設も可能になるだろう。「ユニバーサル・ソルジャーは漫画や映画の中だけのものではなくなるな」
「ええ。それも謎の遺伝子だとか、宇宙人の手助けだとか超古代文明の遺産だとか、ハリウッドの三流映画が好みそうな状況には一切頼らない、人間の叡智だけで生み出された代物です」
名誉への道は閉ざされた財団の研究者たちだったが、エスメラルダ機関の提示した莫大な報酬の魅力には勝てなかったそうだ。もちろんその時にはまだ、NSCメンバーの大半には、研究の存在すら知らされていなかった。掛かる手間暇、莫大な費用のことを知られたら、必ず懸念や反対が出る。研究は完成した時点で初めて、無敵の軍隊の実演という形で、NSCメンバーに披露される筈だった。その実演の凄まじさがメンバーに、全ての懸念を忘れさせるのは間違いなかった。今のフロイトがそうであるように。
しかし実演は行われることのないまま、研究はNSCメンバーの知るところとなった。無敵の兵士か…、フロイトは苦々しく呟いた。
「その研究が奴らを生む結果となったわけだ」
「その通りです」カサンドラがその秀麗な眉目を微かに曇らせた。
…ニューロンに続き、財団の研究者たちは筋肉の強化に取り掛かりました。変質した転移RNAの生む例の酵素が、筋肉を強化できたと確認出来るまで、これまた丸1年を要しました。しかし無駄な1年ではなかった。筋肉と、そこに繋がる血管までも、損傷箇所のみ細胞を分裂させ、外的損傷の修復を驚くべきスピードでやってのけるまでにしてのけたのですから。
凄い眺めでしたよ。深さ5センチにも及ぶ裂傷が、切れた血管とともにあっという間に塞がっていく様は。もちろん動脈静脈の損傷時には、まず止血が先ですがね。
同時に、あの特殊酵素が分泌をもたらしたエンドルフィンによって、体内でのドーピング作用を起こす実験にも成功しました。
「体内ドーピングか。それが出来ればカナダのあの何とかいう選手も金メダル剥奪は避けられたろうにな」フロイトは鼻で笑った。畑が違うと言った時の不機嫌さは既にない。これらの説明が“奴ら”に関係していると知ったことで、興味を持たざるを得なくなったのだ。「しかしそんなに都合よく、体内でドーピングなど出来るものなのか?」
カサンドラは頷いた。乱れてもいない前髪を指先で掻き上げ、「元来ドーピングとは体内が行うものなのです。アドレナリンの分泌も、今流行りのβエンドルフィンもドーピングの一種なのです。それに、ある特定のRNAに操作を加え、必要な時に体内で必要な働きをさせるというのは、遺伝子治療の最も初歩的な段階なのです」
どのドーピングが、光ファイバーの速度で信号を送るニューロンにほとんど追いつくまでの速さにも、そして運動量にも耐え得る強度を、筋肉に持たせました。人間、いえ、地球上の生物ではあり得ない力とスピードとを与えたのです。
それが実験上の成果に過ぎないわけではないことは、もうお解り頂けたと思います。
骨の強化はそれから間もなく完成しました。苦労はしたそうですが。何しろ骨は体重を支える以外に、体内へのカルシウム補給の役割も負っています。他の素材と入れ替えるなど論外です。しかも強化した筋肉が叩き出す運動と速度の負荷にも耐えられる強度を両立させねばならなかったわけですから。
が、それにもあのフラーレンが一役買いました。数値は伏せさせて頂きますが、そうですね、仮にxとしておきましょうか。炭素結合C-xに従ってリン酸カルシウムの組み換えを行い、カルシウム供給という本来の役割を保たせ、尚且つ骨髄の造血機能も損なわせず、セラミック並みの硬度にまで引き上げることに成功したのです。
「ここまでの話は理解して頂けましたでしょうか?」
「大体はな。細かい理解までは自信がないが。まあ、君の話だけでは信じなかっただろう」筋肉の次は骨の増強か、道理で…、フロイトは椅子の背もたれに体重を預けた。「しかし目の前で実演を見せつけられては、信じないわけにはいかないだろう」
有難うございます…、カサンドラは慇懃に頭を下げた。「ただ、研究はここで一度、大きな壁に突き当たります」
変質RNA投与による骨の組織構造組み換えは、大体3箇月で完了することがわかりました。しかし筋肉の全身への入れ替えは不可能でした。出来たのは部分移植だけです。先に申し上げた損傷回復の実験も、部分的に培養できた筋肉による実験に過ぎません。
「それともう一つ、誕生した超人兵士を超人兵士として存続させるためには、変質RNAを投与し続けなければならない。強化したはいいが、その筋肉なり骨なりを維持できないようでは…」
「最初に君が言っていた、遺伝子治療の限界という奴だな?」
「そうです。しかし我々が目指したのは、最前線において補給やら投与やらが全て途絶えたとしても、超人のまま働き続けられる兵士でした」
そのためには兵士自身の体内にて、変質RNAを作り続けられるシステムを開発する必要があった。
答は研究者の1人が出しました。と言うより、研究の発案者の1人でもあった彼は、最初からある仮説を立てており、その実用を思い描いていたのです。
医学者たちがレトロウィルスと呼ぶものの中に、逆転写酵素というものが発見されたのが1970年代。何とRNAの内部の情報を、DNAに変換してしまうというものでした。
元々、生物の起源時には、細胞にはRNAしか存在していなかった。しかし情報の鎖を1本しか持たないRNAは極めて不安定な存在だった。そのRNAが、進化の過程で鎖2本の遺伝情報を持つことで自らを恒久的に複製し、生物種の保存を安定させたのが、DNAだと思って下さい。
そうです。彼は逆転写酵素によって、開発した変異RNAをDNAに変えてしまおうと考えていたのです。成功すれば遺伝情報を得た細胞が自ら転移RNAを作り始め、それらが例の酵素を分泌し、筋肉や骨を強化し続ける筈だ、とね。
レトロウィルスである逆転写酵素は、原始的且つ単純な構造を持つ細胞に対してのみ働くものでした。そのまま人間に応用して効果を発揮できるものでもない。だから研究者たちは転移RNAを投与後、酵素を出すようになったのを確認してから細胞を摘出し、一片一片を培養液の中で孤立させ、単純な原生細胞として扱うことで、逆転写酵素に応じざるを得ない環境を作ってみた。変質転移RNAは驚くべき率でDNAに変わり始め、しかも安定したDNAとしての活動を開始したのです。
…フロイトは今まで聞いた話を自分なりに反芻し、整理しようとしてみた。フラーレンとか言う原理で人為的に組み替えられたRNAが、逆転写の力を借りてDNAに変わり、自己を複製するようになった。そして全細胞を賦活化する酵素を、体内の各細胞に供給できるまでになった、と。「にわかには信じ難い話だ。君の言うことが真実なら、現在の遺伝子治療の限界は、解決してしまったことにならないか?」
「なりますね」カサンドラは事も無げに頷いた。「もっともこの技術が公表され、一般向けの医療として実用化されるのは、半世紀は先になるでしょう」
医学界はこの先、再生医療という分野に新天地を見出すでしょう。臓器の再生まで可能な細胞もいずれは開発されるでしょう。それでも人間そのものを強化し、根幹的に生まれ変わらせる我らがエドバーグ財団の研究には遥かに及ばない。「私の機関もこの成果を公表する積もりはありません。NSCも同じ決定を下す筈です」
下す、ではなしに下させる、だろう。自分から見れば若造とも言えるカサンドラの口から出た台詞の意味、その重大さ、或いはその台詞を何の気負いもなしに吐けるカサンドラに対し、フロイトは身震いを禁じ得なかった。
「もう一つの問題…」フロイトの内心の恐怖などお構いなしに、カサンドラは続けた。筋肉総入れ替えのヒントは身近な場所にありました。健常な細胞を乗っ取る、というか食い尽くしてしまう奴が。「彼らが実験台に使っていた被験者の中にね」
「癌、か…」
「御明察です」
逆転写酵素による変質転移RNAのDNA化を進める一方で、強化された筋肉細胞に癌細胞と似た構造を持たせ、健常細胞内で増殖させる実験も始まりました。実験には癌患者を使わず、ボランティアという名目で集めた健康な人間50名ばかりを使いました。
「ボランティア、だと?」恐ろしい真似をする…、フロイトは首を振るしかない。だが、NSCが、大統領が彼の組織の活動に許可を与えているのだとすれば、最早誰にも止められまい。「で、どうなった」
今度はカサンドラが首を振った。「またしても壁に突き当たりました」
細胞を移植した被験者の体内で、謂わば擬似癌とでも呼ぶべき細胞群は、凄まじいスピードで筋肉を乗っ取りに掛かりました。ところが実験の最初で、擬似でしかなかった筈の細胞が、本物の癌細胞と化したのです。増殖速度はメラノーマ以上でした。集めたボランティア全員がたちまち死亡しました。
「これには参りました。彼らの死亡は事故という形で処理しましたが」
「恐ろしいことをする。しかしよくまあ、事故で片付けられたものだ」
「飛行機事故をでっち上げたのです。誰にも疑われませんでした」
「で、まだ継続したのか、その実験は?」
「新しい被験者集めからやり直しでした」最早ステーツ内でのボランティア集めは不可能でした。だから私の機関の面々に世界中を動いて貰いました。
「ボランティア集めを世界に拡大か」
「あれは前準備、後始末ともに大変なんですよ。偽のアリバイに偽の観光ツアー、死亡診断書に至っては偽では済みませんからね。結構な金額を食い潰しました」カサンドラは薄く微笑みながら首を振った。「それよりもっといい方法、後始末を一切必要としない方法がある」
「何だそれは」
「死んだ筈の人間を使えばいいのです。アメリカ人でなければ尚更いい。白人黒人ヒスパニックを問わず、アメリカ人では全員失敗していますから」
死んだ筈の、或いは死んだと思われている人間たちを世界中から集めれば、後始末にも掛かる費用にも頭を悩ませる必要はない。そうでしょう? 邪気のない笑顔に引き込まれるように頷き返したフロイトだったが、直後、表情が凍りついた。「ちょっと待て。事故をでっち上げたとか言ってたな。まさかあの、5年前の…」
「覚えておいででしたか。そうです。あの一連の事故は、マスコミの憶測したようなテロ事件ではありません。私が指示したものです。もちろん、前の大統領からの許可も得てあります」
…5年前、合衆国を除く世界各地で、7件もの旅客機墜落、旅客船沈没という事故が立て続けに起こった。国も旅行会社も航空、客船会社も全部ばらばら。様々な憶測も飛んだが、原因は全く不明。大韓航空機事件の例もあり、真っ先に疑われたソ連とその同盟国は、己の関与を必死に否定した。あるテログループが出した犯行声明に、マスコミが挙って飛びつきもした。国防省内にもそれを鵜呑みにした連中も多いことは、フロイト自身知っている。それが身内の手による凶行だったとは。
大統領の許可とは、いつから民間人を生贄にすることへの免罪符になったのだ…。「確かにどの事故一つとっても、遺体がほとんど発見されていなかったんだったな。どうやったんだ?」
「船の事故は旅客1人1人を掬い上げました。旅客機は空路の途中で機をすり替えたのです。費用も掛かりましたが、それ以上に空軍の協力が不可欠でした。ああ、もちろん船の事故では海軍の協力を仰ぎました。第3、第6、第7艦隊の予備艦船に東太平洋、インド洋、地中海に回って貰ったのです」
フロイトは仰天するしかない。今でこそ国防省補佐官を務める彼だが、5年前は昇進したばかりの、一介の陸軍少将に過ぎなかった。それでも縦割りの官僚主義を嫌う、生真面目な叩き上げ軍人フロイトは、いつ起こるかも知れない非常時に備え空軍や海軍とも緊密なパイプを築いてきたし、賛同する面々の協力も得てきていた。その彼が全く知らないところで、空軍海軍が、つまりは国防省が動かされていたとは…。
「総勢2000人です。ほとんど世界中の人種が揃えられました。全員を仮死状態にしましてね、中部のある施設にて管理したのです。2000人の被験体が並ぶ光景は、なかなかの壮観でした」
薄暗い室内、顔色の変化こそわからなかったが、口調一つ変えずに喋るカサンドラを見て、フロイトは首を振った。振り続けた。つまりそれは、最初から2000人を生贄にすること前提、ではないか。恐ろしい男だな君は…。
「そこまでの犠牲を出さずとも、他の方法はなかったのか…?」
「他に方法がありますか?」
「そうだな、例えばクローンを使うとか…」
「人間のクローン製造には抵抗も多くて。この国の人間は突き詰めれば自分の利益しか考えないくせに、妙なところで倫理問題に拘りたがる」これから4年後、人間のクローン製造の全面禁止が大統領宣言として出されることになる。しかし…、黙り込んだフロイトに、カサンドラは笑い掛けた。「まあ、隠れてこそこそ動く連中はどこにでもいるものです。私の機関など、その最たるものだ。実用段階まで漕ぎつけたクローンを、被験体にしてはみたのです。5体程ね」
「人の、クローンは、実用化できていたのか!」
「実用化できたのは随分前の話ですよ。結局は駄目でしたが。癌罹患の壁をどうしても克服できなかったのです」ただでさえカネの掛かる実験に、これまたカネを食うクローンを投入し続けるわけにも行かなかった。「それなら超人兵士が完成した際に、それをクローン化した方が効率的だ。来るべき量産計画のことを見越してもね。そうは思いませんか?」
フロイトは善悪の基準についてこの男と議論することの不毛を悟った。民間人を巻き添えにすることも、神をも畏れぬクローン製造も、この男には何の抑止力にもなり得ないのだ。「…だが、実験は上手く行ったろう。それだけの頭数を揃えたんだ」
「足りないくらいでした」
「何だと…?」
変質転移RNAを投与した被験体の細胞は、増殖を開始するや否や癌化してしまう。どうやらこの実験に合う体質と合わない体質とがあるらしいのです。RNAと、次いで逆転写酵素によって変換されたDNAとを、細胞を癌に変えることなく無事に取り込めたのは、被験者500人につき2人か3人という有様でした。
強化した筋肉が通常の筋肉を侵食し、乗っ取るまでの間、筋肉の中にこれまた強化した神経細胞を張り巡らせ、同時に骨の強化にも取り掛かった。いつどこで、どの細胞が癌化するかわからないわけですから、気の抜けない毎日だったそうですよ。3箇月から4箇月を要したその全過程で、癌の発生しなかった被験者は、例のRNAとDNAを無事に取り込めた中の、これまた5人中1人しかいなかった。単純計算では2500人に2人弱の割でしか、実験は成功しないということになるのです。「何とか2000人で収まったのは、幸運としか言い様がありません」
「新たに君の犠牲にならずに澄んだ世界中の人々に、そう言わせて貰うよ」フロイトは厭味ではなしに、心からそう言った。その幸運がなければ、カサンドラは無理にでも、もっと多くの“事故”を引き起こさせたに違いなかった。
…なぜかはまだ判明していませんが、癌の発生しなかった被験者の大半は東洋人でした。彼らの体内にのみ存在する『N因子』という物質が、癌罹患を妨げているらしいのですが…、「いずれにせよ、ブルドーザーの筋力とロケットの瞬発力、光速の反射神経と爬虫類の再生能力を兼ね備えた兵士は、開発はまだしも量産はすぐには難しいとわかりました。少なくとも成功した被験者と失敗した被験者との差を徹底的に洗い出し、N因子の正体を解明し、被験者を死なすことなしに超人兵士を造り出せるまでは、マニュアル作成も、クローン量産も無理です。で、研究者たちは私の機関の提供したスーパーコンピューター〈ペガサス〉にこれまでの実験データを蓄積し、計算による誤差の割り出しに取り組んだ」
フロイトの肉厚の顔が歪んだ。息がわずかに荒くなり、広い額に汗が浮く。手が胸元の葉巻を無意識の内にまさぐってしまう。
〈ペガサス〉…。
フロイトだけではない。その名がホワイトハウスの住人、安全保障に携わる役人や上下院議員、NSCのメンバーたちに、幾度眠れぬ夜を過ごさせ、悪夢に跳ね起きる朝を迎えさせたことか。
フロイトが何か毒づこうとした時、カサンドラが目を上げた。「始まりました」
巨大スクリーン上にて、光点が再び激しく動き始めた。フロイトの目は、大スクリーンと数個のモニターについつい引き込まれる。その横でカサンドラが白衣の男たちに、データの中間集約を命じていた…。
…剣吾は身を低くして通廊を駆け抜けた。銃弾が追った。複数の弾痕が壁をミシン目のように穿ち、剣吾に迫る。前方ではなかなか足が進まないサラームの手を、ヤースミーンが必死に引っ張っているところだった。数多くの同僚、そしてつい今し方、ハッサンの死ぬのを目にした彼の心臓は、恐怖、緊張、心労で限界に近いダメージを受けつつあった。いくらヤースミーンが脅してもすかしても、脱力感に支配される彼の体には活が入らなかった。
背後から追いついた剣吾は刀を腰のベルトに差し、2人を両脇に抱えた。ダッシュする。計120キロを超える体重を抱えても、その足は遅れもしない。
通廊を駆け抜けた先にホールがあった。この建物のロビーに当たる場所らしい。大きな受付机と案内板、矢印表示のついた、四方に伸びる階段。
剣吾は2人を抱えたまま、受付机に向かって跳んだ。
耳元で風が囁いた。それに混じって複数の足音。周りの階段、通廊の入り口にテロリストたちが殺到してきたのだ。高速で流れる視界の中、机正面の階段上、迫り出した中2階の踊り場に、自動小銃の銃口を下げた4人が散開した。チタン枠にスチールを張った受付机の上に、剣吾は2人とともに転がった。即座に2人を机の下に落とす。
2人を机下に押し込み、遅れて自分も転がり込む。同時に銃声。しかも正面からだけではない。室内で十数丁の立てる銃声だ。巨大なブリキの太鼓をドラムロールで打ち鳴らすような轟音になった。チタン枠が火花を上げ、スチールの表面にAK74の5.45ミリ高速弾が立て続けに縫い込まれていく。音と衝撃は、鐘の中の反響となって伝わった。高速弾の数発はスチールを突き抜けそうになり、両手で耳を塞ぐヤースミーンは悲鳴を堪え切れない。奪ったAKを撃ち返す余裕などある筈もない。血の気を失い、浅黒い肌が土気色に変わったサラームは、完全に放心状態にあった。剣吾は銃弾の集中しない陰から度々顔を覗かせては、集まってきたテロリストたちの人数と武装とを確認した。階段の上、踊り場、2つの入り口、計19人。AK74、折畳式銃床のついたAKS74、9ミリパラベラム拳銃弾を発射するヘッケラー&コックMP5Kサブマシンガン。それらが交互に、3人の隠れる受付机に向かってフルオート掃射を浴びせてきていた。顔を覗かせるのもコンマ数秒単位でなければ、剣吾の頭蓋骨もたちどころに削られていただろう。
その一斉掃射が半秒程、止む瞬間があった。
何か来る。勘が知らせた。頭の中で赤い文字が瞬き、何かが脳髄の奥で囁きを発した。顔を出した瞬間、目に飛び込んできたのは、正面頭上の踊り場にてRPG7D――旧ソ連製ロケットランチャー。以前はワルシャワ条約機構軍でも使われていた代物だ――を肩に担いだテロリストの姿だった。
この武器と出くわしたのは初めてではない。厚さ320ミリの鉄板をも貫通する。もちろんその後爆発し、物凄い数の破片を四方八方に撒き散らすのだ。こんなスチールの受付机など難なく貫かれ、下に挽肉が積み重なることになる。射手の掛け声とともに、テロリストたちが踊り場に伏せた。
剣吾は2人を机の外に突き飛ばした。同時にRPGが吠えた。
猛烈な噴射煙が踊り場の壁に跳ね返り、射手がよろけたのが見えた。弾頭が白い尾を曳きながら、まっしぐらに机に向かってきた。剣吾は2人を脇に引っ掴み、敵の姿が見えない出口に走る。その背後で机が爆発した。
大量の机の破片と榴弾、床に積もった砂とが混じった爆風が背中を襲った。榴弾の幾つかが音を立てて食い込んだ。さしもの剣吾も足をもつれさせた。ヤースミーンとサラームとを放り出してしまう。踊り場や他の入り口から撃ってこなかったのが幸いだった。
激痛を堪えながらも剣吾は倒れなかった。ヤースミーンはすぐに立ち上がった。剣吾に手を伸ばしてくる。しかしサラームは立ち上がれなかった。剣吾の声にも、伸ばした手にも反応出来ない。
階上の、或いは入り口のテロリストたちの銃口が上がった。
ヤースミーンの手を掴み、走り出した瞬間、サラームの白衣に銃弾がぶすぶすと食い込んだ。たちまち数十発に貫かれ、その体は蹴られたボールのように床を転がった。
ずたずたにされたサラームの体が壁で転がり終えた時――もちろん即死だ――、ヤースミーンを引っ張る剣吾は目指す出口に辿り着いていた。
罠だった。流石に歴戦のテロリストは周到だった。鼠に逃げ道を与えておいて、ちゃんと仕掛けを作っておく。AKやHKサブマシンガンを構えた5人が待ち構えていた。
今度こそ撃たれる。またもヤースミーンを放り出した剣吾の頭の中で、今度こそ文字が、囁きが…、
明確な言葉となった。
『殺戮せよ』
視界の中の全てが動きを失った。時間が止まったようにも思えた。もちろん違う。頭を、また全身を光の速度で駆け巡った指令が、剣吾の全ての器官を、それに近い速度で動かしているのだ。目を、耳を、そして筋肉を。半ば自動的に。
刀が鞘に収まり、剣吾の腰にて、静かに鍔が鳴った。
連獅子の鬣のように渦を巻いた髪が、フワサッ…と解けた。通廊に続く狭い入り口の中、2発の銃声が耳を弄した。轟音の余韻を縫って、2個の空薬莢が床に落ち、転がるか細い音がした。最後に倒れた5人目が撃った、断末魔の2発だった。
5人全員がその場に倒れ、死んでいた。ある者は喉を、ある者は延髄の辺りを斬り割られ、また別の者は顔から真一文字に斬り下ろされて。遅れて始まった出血が、床を浸していく。ヤースミーンには今度も何が起こったのかわからない。前回以上にわからない。剣吾の刀が抜かれたかどうかすら見えなかったのだ。
床に打ち付けた腰の痛みを忘れ、ヤースミーンが剣吾に声を掛けようとした。その体を、剣吾が抱き竦めるように庇った。
出口の角にて、2発目のロケットランチャーが爆発した。
またしても榴弾を、今度は背中全面に食らうことになった。呻いた剣吾はヤースミーンごと、前のめりに倒れた。激痛に気が遠くなりかける。近すぎた爆発のために一瞬耳が聞こえなくなる。しかし獣以上に研ぎ澄まされた感覚は、背後に迫る敵を感じ取っている。今度は、7人! 頭の中に再度、あの指令が響く。
『殺戮せよ』
…後続のテロリスト1人は一閃で首を失った。別の1人は肩から尾骶骨まで斬り下げられていた。AKSを構えていた者は両腕を斬り飛ばされた。木製ハンドガードのついた鋼鉄の銃身毎だ。グリップを握ったままの腕とともに、AKSの短い銃身がリノリウムの床に転がった。カラン…。乾いた音がして、消えた。
刀の切っ先が7人目の喉笛を貫くまで、1秒掛かっていなかった。
さしもの剣吾もそこで大きくよろめいた。反射的に立ち上がったヤースミーンが、肩を支えた。その時になって、肩から斬られながらまだ立っていた1人が、天井まで血を噴き上げてぶっ倒れた。
背後から次の攻撃は来なかった。まだ7人が残っていたが、広間の後方から、階段の途中から、信じられないと言いたげな眼差しがこちらを見つめるだけだった。全ての顔に驚愕が、そして恐怖があった。幻でも見ている気になったか。でなければ自分たちが戦っているのが怪物だとでも思えたか。百戦錬磨のテロリストをしても、態勢、闘志を立て直すのにしばし要すると思われた。
ヤースミーンに支えられる剣吾は、刀の切っ先を彼らに向けたまま、後ずさり始めた。鋼を断ち、13人を斬り裂いた刃には傷、欠けどころか、一滴の血も付いていない。未だ鏡のような輝きを保っている。速すぎて、血や脂の付着する間もなかったのだ。
しかし、あの声はまだ、こう言った。
――遅いぞ。まだ刀が弧を描いておる。力任せに振るっておるからだ。
はい、先生…。
2人は出口の奥に消えた。
…逃げ込んだ出口は、原子炉に通じる通廊の一つだった。
照明の消えた暗がりの中、目が慣れるのを待って、ヤースミーンは剣吾を座らせ、陣羽織と、滲む血で真っ黒になった作務衣の上を脱がせた。
着痩せして見える彼の鍛えあげられた上半身、鋳鉄の筋肉を見たヤースミーンは息を呑んだ。筋繊維の一本一本まで浮き出た背中一面に、無数の榴弾が食い込んでいた。右の上腕と左の太腿には貫通銃創もあった。
ヤースミーンの指が、背中の各傷を触った。血は止まっていた。しかし榴弾の幾つかは相当に深い部分にまで食い込んでおり、素人の彼女ではナイフを使っても、ほじくり出すのは無理だった。下手に動脈でも傷つけようものなら、それこそ手がつけられない。「どうしよう、消毒液もないし…」
「心配ない」剣吾は笑った。声は掠れていたが、息はもう戻っていた。
「放っておいちゃまずいわ。ここじゃまだ破傷風は死病の一つなのよ」
剣吾は笑顔で首を振った。ほんの少し、こうやって休んでさえいれば…、と頷いて見せる。それより君の方こそ休め…、と言いかけ、横に腰を下ろした彼女が今更ながらに震えているのに気がついた。大丈夫か、と訊く剣吾に頷き返してきながらも、震えは止まらない。
「こんな場所で死にたくない…」合わない歯の根の隙間から、ヤースミーンは呟いた。私には家族がいる。12人の家族が私の帰りを待ってる…。「私はこんな場所で死ねない」
「助かるさ」
ヤースミーンはきっと顔を上げた。刺すように剣吾を見る。「安請け合いしないで」
「………」
「そりゃあ、あなたなら…、あのテロリスト相手に、あんな戦いが出来るあなたなら、助かるかも知れないわよ」テロリスト、と口にした瞬間、恐怖と、震えが蘇った。「でも私は普通よ。あなたと違って、私は普通の人間なの!」
激昂し、声を荒らげかけたヤースミーンだったが、すぐに項垂れた。今は剣吾に当たっている場合などではないことは、彼女にもわかっていた。何より彼女は恥じていたのだ。ハッサンを死なせ、サラームを見殺しにするきっかけを作ったのは、王立警備隊の一員たる自分が捕虜のボディチェックを怠った結果であるということを。「…御免なさい。言い過ぎたわ」
流石イスラムの女…、剣吾は思った。大した自制心だ。普通の女ではこうは行くまい。少なくとも…、
“剣ちゃん…。”
少なくとも布由美は、この状況に耐えられる娘ではなかった。
両親を早く事故で亡くした剣吾は、叔父夫婦に育てられた。
布由美は叔父叔母の一人娘、剣吾には2歳年上の従姉に当たる。
いつも明るく、誰にでも優しく、周囲を和ませる天才とも言われた布由美。誰もが、叔父や叔母でさえ泣き顔を見たこともないというくらい、いつも笑顔だった布由美。
だが、堪え性だけはまるでなく、警察官だった叔父に習っていた剣道を剣吾にも勧めたものの、少し鍛錬がきつくなると自分はすぐに投げ出してしまった。
剣吾の方は、筋も良かったのだろう。続けた剣の道の面白さにどんどん嵌まっていき、高校生の時には叔父をも唸らせる腕前にまでなり、叔父の師に当たる達人に師事するまでになった。それが今、剣吾の命をこうやって救うことにもなっているのだが…。
あの時だって…、
――剣ちゃん、あたし…、
――しっかりしろ姉さん! もうすぐ助けが来るから!
初めての海外旅行だった。叔父夫婦と布由美、そして剣吾での、オーストラリアへの船旅。叔母が懸賞で引き当てたものだった。布由美二十歳のお祝い旅。楽しい思い出になる筈だった。途中、船底付近の客室の一つが、爆発などしなければ…。
あの時だって、救命ボートも胴衣もなく、ただ彼女を肩に掴まらせて泳ぐ剣吾は既に疲れ果てていた。もう少し。そう、もう少し我慢して掴まっていれば…、
命だけは助かっていたものを…。
――あたし、もう、駄目。剣ちゃんだけでも…。
――姉さーん!!
そう言えば…、剣吾は思い出した。僕は呼べなかったんだ。あれだけ彼女が望んでいたのに。2人っきりの時は呼んでくれと言っていたのに…、
彼女のことを、布由美、と、最後まで。
もがきながら流された布由美は波間に姿を消し、そのまま二度と浮かび上がってこなかった。彼女を追った剣吾だったが、泳いで追い付く体力は既に残っていなかった。大型ヘリコプターに乗った一団---恐らく“あの男”の仲間---に助け出されたのは、それから間もなくの事だった。布由美ももう少し頑張っていれば…。
剣吾は首を振った。確かに布由美は力尽き、諦めた。だがそれを救えなかったのは自分だ。自分の力の無さが、姉同様に育ってきた従姉を、そして一人の男として愛してくれた女を見殺しにさせたのだ。
二度と御免だ。自分に関わる者を、自分の力不足で死なせたくない。もちろん、目の前にいるこの女も。「少しは落ち着けたかい?」
ヤースミーンはまだ震えていた。しかし…、「絶対に死なないわ、こんなところじゃ」
「わかってる」
顔を上げてこちらを見たヤースミーンから、剣吾は目を逸らした。胸が押し潰されそうな気がした。どうしてこんなに似ているんだろう。だからこそ、今度こそ…、
死なせてはならないのだ。「喉が、渇いたな」
奇跡的に銃弾も榴弾も受けていなかったバッグから、ヤースミーンがヴォルビックのボトルを出した。剣吾は目を閉じ、ぬるい水を味わって飲んだ。溶けかけたスニッカーズもあった。遠慮する剣吾にそれを食べさせたヤースミーンの耳に、床のタイルを打つ、何かとても小さな金属音が届いた。続いてもう一つ。
ヤースミーンが目を遣った床、わずかに溜まった血が乾きかけたタイルの上に、金属片が落ちていた。目を凝らした時にもう一つ落ちてきた。そしてもう一つ。
剣吾の背中に食い込んだ榴弾だ。千切れ、歪んだ鉛と鉄、そしてスチールの机の破片までもが次々と、傷口を塞ごうと盛り上がる筋肉に押し出され、床に落ちてきたのだ。思わず覗き込んだヤースミーンの視界に、剣吾の右腕が飛び込んだ。正しくは、既に塞がり、薔薇色の肉が傷口にひしめく貫通銃創が。表面はもう乾き始めている。
3分後、剣吾の背中は榴弾と破片を押し出し終え、上腕と太腿の傷も完全に塞がってしまった。茶色に乾いた血の痕がなければ、そこに傷があったということも信じられない回復であった。
暗い通廊、ヤースミーンは立ち上がった。後ずさった。剣吾をまじまじと見つめた。
見つめるしかなかった。
「あなた、一体、何なの…?」
それは、剣吾がいつも自分自身に問いかけている言葉でもあった…。
「…誤差の修正を試みながら、研究者たちは次の変質RNAを生み出すDNAの開発に取り掛かり、何とか実用化一歩手前に近づいた超人兵士の最初の2名に投与を開始しました。私も詳しくは説明できないのですが、何でも今度のDNAは、兵士の体内で合成しなければならなかったのだそうです」
「まだこれ以上、何か必要なのか?」
フロイトはソファに深々と身を沈めた。アイスティーの3杯目が運ばれた。無性に喉が渇いて仕方なかった。今見た光景は、彼の常識の範疇を完全に超えていた。
事実上、冷戦が終わっているとは言え、世界中にはいつ弾けてもおかしくない火種が、未だごろごろ転がっている。こんな兵士を量産出来ようものなら、全世界の軍事地図は丸ごと書き換えられることになるだろう。
いや、こんな兵士が徒党を組み、主要先進国全てに牙を剥いているという事実は、既に存在するのだ。
イギリスSISとSAS、フランス対外治安総局DGSEと国家憲兵対テロ部隊GIGN、ドイツのGSG9、そして合衆国の誇るデルタフォース…。それらの精鋭で結成された防衛部隊はことごとく、連中の前に敗れ去った。連中を急襲したフランス空挺部隊は2師団が全滅させられた。連中は過去に存在したいかなるテロ組織どころか、その技術的元締めでもあった旧ソ連特殊部隊、陽動旅団をも、遥かに凌いでいると思われた。あの、昨年初夏の、国連本部爆破事件のニュース映像は、フロイトの記憶にもまだ新しい。百数十人の護るビルにたった5名で乗り込み、総会に出席予定の各国大使や国連職員、通行人に至るまでおよそ千余名を射殺、爆殺、或いは殴殺し、真昼のニューヨークを悠々と逃げ去った男たち…。
煙を上げる国連ビルの映像を国防総省で見ていたフロイトは思ったものだった。こんな奴らにどうやって勝てと言うんだ、と…。
黙り込んだフロイトに構うことなく、カサンドラは喋り続けた。「今度のDNAは、体内のナチュラルキラー細胞の強化と、インターフェロン因子を生成することを命じる変質RNAを複製するものです。そのシステムにより、傷から体内に入ったほとんどの菌、ウィルスの類いは排除できます。肝臓の解毒機能も強化させました。菌やウィルスへのほぼ鉄壁の防御、異物の解毒機能、そして自ら増殖し、外的損傷を回復する筋肉及び血管、神経細胞を持った肉体が、これで完成したことになります」
「ほとんど不死身というわけか」
「首をちょん切られれば死にますが」カサンドラは唇だけで笑った。「確かに外傷には強い。もっともガスや毒薬で麻痺したり壊死したりした肺や気管、胃腸の再生にはかなりの時間を要します」
「かなり? どれくらいだ?」
「数分から数時間と言ったところでしょうか。まあ、時間さえあれば脳幹の中枢神経すら修復してしまうわけですから、これくらいは仕方がないとも言えますが」
増強した筋肉とペアになっている骨ですが、セラミック並みの硬度を持っています。しかしそれでも耐え切れる荷重はせいぜい数トン。10トンが掛かれば間違いなく折れます。もちろん骨の回復力も並の早さではないですが、それでも筋肉や神経のようにたちどころに、というわけには行かない。完全骨折、或いは複雑骨折した場合には、その完璧な修復に3日から7日掛かることがわかっています。
「複雑骨折が1週間で完治か。大した問題じゃないな」フロイトは言った。「ほとんど不死身であることに変わりはないではないか。まさに地上最強の兵士だ」
“奴ら”もそうやって誕生したわけか…。
「ところが、またしても問題が生じたのです」カサンドラは首を振った。「何度かの実験の後、彼らの回復速度が異様に低下することが判明したのです。2人の実験体のうち、1人は、身体全てが機能不全に陥り、死にました」
これには研究者たちも私たちも慌てました。最初の数日は最強兵士でも、その後動けなくなってしまうようでは、とても実戦には投入できない。その辺にたむろするティーンエイジャーを新兵としてベトナムに送り込むのとは、掛かる費用からして違う。少なくとも量産が出来ない今、膨大なカネを食った彼らを戦場で使い捨てにするわけには行かない。
「原因はわかったのか?」
死にかけのその1人を分析して、何とか…、カサンドラは頷いた。「オーバーヒートです。いくら回復力を高めても、電光の反応速度ととてつもない馬力とが常に稼動状態にあっては、エネルギー消費量が回復量を上回るのも当然でした」
「つまりは過労死か。で、打開策は?」
「講じました」
「普段のエネルギー消費をなるったけ抑える機能の追加、か」
「御明察です。そして危険を察知した際にだけ、最大限のちからを発揮するようにプログラムする…」
…体内には各細胞からナトリウムを排出させ、カリウムを補給するシステムがあります。通称ナトリウムポンプと呼ばれています。人間が極度の緊張状態に陥った時、この速度が異様に亢進されることがわかっています。そのシステムを利用しました。普段は身体の全機能を常人と変わらぬくらいに抑制させつつも、細胞がカルシウムとカリウムを交換する速度が亢進したのを察知して、各種アドレナリンとドーパミンとが神経と筋肉に最大限の働きを強制する仕組みを作った。
3人目のプロトタイプを実験体にしました。
「そいつも遺伝子治療の応用か?」
「そうです。それと深催眠も併用しました。実験体が危機を察知して精神或いは肉体が緊張した時に、脳が自動的に指令を出すように」
「成程、催眠か。ハイテクと対をなす手法だ」フロイトは厚い肉のついた顎に手を遣り、低く唸った。「与えられた緊張なり恐怖なりが、最大限の力を引き出すわけだな?」
「指令は一言です」カサンドラはディスプレイの一つを顎でしゃくった。「“彼”の場合なら、『殺戮せよ』」
危機を察知する能力は誰にでも備わっている。鈍いか鋭いかの違いだけです。中にはレーダー並みの感知能力を持つ者もいる。それを第六感と呼ぶこともありますね。実は五感全てがフル活動して、初めて発揮される力なのです。虫の知らせと呼ばれるものも、実はそうなのです。類稀な五感の認識能力と記憶力とが、日常と今目の前にあるものとの微細な差異に気づかせ、違和感を感じることで、当人に異常を察知させる。生還率の高い優秀な兵士ほど、その能力に恵まれています。
4人目の、最後の実験体は、ちょうどその資質に恵まれた者だった。日本の武術『ケンドー』で、鍛え上げた、研ぎ澄まされた五感の持ち主でした。
「3人のプロトタイプの犠牲も無駄にならずに済みました。それ以上に、この4人目が素晴らしかった。普段の運動能力、反応速度も極めて優秀な上に、緊急時にはその力を躊躇なく最大に発揮する。ようやく実戦で使い物になる超人兵士を完成させられました」
今からおよそ2年前の話です。
「それが…」フロイトは大スクリーンに目を戻した。「“彼”か」
「私たちはプロトタイプ04と呼んでいます」カサンドラは言った。事故による死亡を装い、5年前に拉致した日本人です。
「そして現在、我々の手駒の中で唯一、〈ブラックペガサス軍団〉の兵士たちに比肩し得る超人です」
「…あなた、何なの?」
ヤースミーンの声が震えた。目が怯えた。中腰のまま後ずさろうとし、尻餅をつく。「人間なの? 化物なの?」
「人間だ」一応、という言葉を呑み込み、剣吾は言った。「頼むから落ち着いてくれ」
嘘よ…、ヤースミーンは首を振った。人間の回復力じゃない。そう考えれば説明もつく。並の人間に、あんな戦いが出来るわけがない。「あなたは…」
人間ではないのだ。
「触らないでよ!」剣吾の手を振り払い、ヤースミーンは叫んだ。目は怯えたまま、手が腰のS&Wを探る。
それを見ても剣吾は慌てなかった。同じような反応に何度も出会っていた。命を救った相手が皆、恐怖に顔を歪め、口を揃えて彼を罵ったのだ。魔物、怪物、と…。半ば慣れっこになっていた。慣れっこになっていた筈だった。しかし今回はショックだった。
そして、悲しかった。
「大声を出さないでくれ」声が自然と沈んだ。「確かに僕は普通の人間じゃない。それは認める。だけど、今それを騒ぎ立てて、何の得がある?」
5年前、僕はある事故で命を落としかけ、アメリカのある政府機関に助けられた。命を救うために行われた手術の副産物が、この身体だ。そして、あの事故が、あるテロ集団の仕業だったということを、僕を救った連中の1人――“あの男”――に教えられたんだ。
その時に言われた。僕のように大事な人を奪われた者が数多存在する、と。そんな人々をこれ以上増やさないために、テロリストたちと戦ってくれないか、と。
大して長くは迷わなかったよ。僕には彼らに与えられた、不死身に近いこの肉体がある。目的が何であれ、無辜の人々を苦しめる者がいるなら、そいつらと戦おうと思った。それ以来僕は、世界のいろんな場所で戦い続けてきた。もう7回目になる。
「僕を怪物扱いしたければしてもいい。君が僕のことをどう思っても、どう呼んだとしても構わない。でも今は他にすることがあるんじゃないのか?」
「………」
「カセムを止めることが先決じゃないのか?」
ヤースミーンは押し黙った。剣吾の言葉が正論だったから。それもある。
暗い中ながら、彼の目に満ちているのが恐らく哀しみだと知った瞬間、総毛立つ恐怖が潮の引くように冷めていったのだ。銃把を探る手も止まった。修行僧にも負けぬ並外れた自制心が、頭に冷静さを呼び戻してくれた。
彼女に剣吾の哀しみの正体などわからない。恐怖が拭い去られたわけでもない。しかしここでパニックを起こして騒ぎ立てたところで何にもならないし、自分を守ろうとした剣吾が敵ではないのも確かだろう。そう考えるだけの余裕も生じた。敵ではないとわかっていたからこそ、ここまでついて来たのではなかったか。恐慌を来しかけていた自分が馬鹿に思えてきた。この男をイスラム伝説の魔物イフリートだとでも思ったか。あり得ない。アラーに護られたこの自分たちが、そんな魔物を畏れる必要などどこにもないのだ。彼自身認めているように、普通の人間ではないのだろう。だが、今はいい。その正体をどうにかするのは後回しだ。
そう、よね…、ヤースミーンは言った。「先にやることがあるわよね」
剣吾はほっとしたように微笑んだ。だが、いくら頭で冷静になった気でいても、本能のもたらす恐怖は消せないことを、彼もヤースミーンもわかってはいなかった。
剣吾の疲労と傷の回復には、5分しか要さなかった。「行こう」
立ち上がり、差し伸べた彼の手を、ヤースミーンは反射的に、しかも無意識の裡に払いのけていた…。
…2人はその足で、原子炉の管制室に向かった。ヤースミーンが案内した。施設を襲った最初にアラーの風が占拠したのが、原子炉の真上にある管制室だったらしい。だとすればリーダーのカセムがそこにいる可能性も高い。
恐らく剣吾の戦いと部下たちの状況はカセムに伝わっていることだろう。先の広間にも監視カメラはあったし、カメラに剣吾の動きが捉えきれなかったとしても、テロリストの生き残りの誰かが報告を入れていることだろう。
それを聞いて、カセムがどう動くか。「自棄だけは起こしてほしくないな」
「あいつが自棄を起こしたら…」走りながら時折横目で剣吾を窺うヤースミーンが、陰気な声で応じた。「アラビア半島全土に、死の灰が降ることになるわ」
そうよ、特殊部隊は間に合わない。何としてでも私たちの手で止めなくちゃ…。ヤースミーンはAK74の弾倉を抜き、残弾数をチェックした。目に決意が生じていた。今度こそ王立警備隊の隊員として恥ずかしくない行動を取らねばならないという意気込み。頭が剣吾への警戒から任務へと切り替わった。と言うより無理矢理、或いは無意識の裡に切り替えたのかも知れない。
剣吾を直視するのが怖かったが故に。
2人は一気に4階まで駆け上がった。階段の踊り場を越えると、これまた大きなフロアに出た。窓の一切ない広間だ。天井の蛍光灯はここでも大多数が死んでいた。その正面が…、
ヤースミーンが言った。「管制室よ」
見張りは誰もいない。自動ドアは閉まったままだ。ヤースミーンは胸ポケットから身分証を兼ねたカードキーを抜き、手探りでドア右のカード差込口を探った。目をパネルに近づける。網膜パターン照合だ。ヤースミーンに言わせれば、テロリストたちの侵入時、内部からの手引がなければ管制室に入れた筈はないということなのだが。
剣吾は思った。自分が関わる事件では、いろんな施設が必ずと言っていい程、実に簡単に敵の侵入を許していた。今回もそうだ。
そもそも自分は、一体いつ、あの倉庫に運び込まれたのだ?
“あの男”と彼の組織は、一体いつ、この事件の勃発を知ったのだ…?
ドアが開いた。剣吾の制止も聞かず飛び込んだヤースミーンが悲鳴を漏らした。モニターの並ぶ室内の床に転がる7人の惨状には、続けて飛び込んだ剣吾も、目を背けたくなった。
白衣の3人は技術者だろう。手引したとしたらこの中の1人か。残り4人はテロリストだ。7人とも体を弓なりに反らし、目は文字通り飛び出していた。鼻と口は吐瀉物にまみれ、掻き毟ったものか、火脹れを起こした首や胸元に爪でえぐった痕が残っていた。毛穴という毛穴から滲み出した体液――リンパ液と血が混じったもの――が、白いタイルをピンクに汚していた。
毒ガス。
この症状は以前ビデオで見せられたことがある。恐らくVX、或いはV-agentと呼ばれる、最も毒性の強いガスだ。アセチルコリンへの蓄積により、筋肉の痙攣や弛緩、瞳孔縮小などの中毒症状をもたらした挙句、猛烈な呼吸困難を引き起こす。
死体の中に、剣吾が資料で見た、マリード・カセムの顔はなかった。だとすると、ガスを使ったのはカセムだ。恐れていた自棄を起こしたか、3人の技術者を始末する際、同志までを巻き添えにしたのだ…。
その瞬間、剣吾の脳裏に警報が鳴った。
研ぎ澄まされた感覚が、部屋のあちこちに淀む何かを察知した。換気扇が排出し切れなかったガスが、まだ残っている。VXガスは空気中の数ミリグラムを皮膚から吸収しただけでも、体質によっては死に至るのだ。
剣吾はヤースミーンの腰を背後から引っ攫い、管制室を飛び出した。
遅かった。ヤースミーンの顔は既に真っ青だった。空気を求めて口がパクパクと開閉し、喉と気管とがヒューヒュー鳴っている。
ガスの症状は剣吾にもすぐに出た。目眩がしたと同時に、視界が真っ赤に染まった。気管が狭まり、呼吸が止まりかけた。膝から下の力が入らない。だが、ガスが剣吾に与えられた影響はそこまでだった。
そして剣吾の目は、管制室を飛び出すわずかコンマ数秒の間に、モニターの一つに、黄色いガス防護服を着込んだ何者かの姿を捉えていた。
監視カメラの一つの映像だ。背後は恐らく炉心格納容器。防護服を着たのは、恐らく、カセム…。
奴は既に原子炉の側にいるのだ。
灯りの届かない暗がりに寝かせたヤースミーンの、ガスに触れた腕や首の皮膚に、火脹れのようなカサブタが生じていた、剣吾の膚も同様だった。しかし彼の火脹れはすぐに乾き、擦るとボロボロこぼれて落ちた。こみ上げてきた黄水を床に吐く。半ば真っ赤に染まり、物凄い臭気を放った。それを吐くと視界はたちまちはっきりし、身体は瞬時に楽になった。
「しっかりしろ!」
苦悶するヤースミーンの胸元をはだけさせ、背中をさする。「死ぬんじゃないぞ!」
彼女をここまで連れてきたのは失敗だった。どこかで外に逃がしておくべきだった。しかしそのルートも機会も見つけられなかった。彼女をこのまま死なせてしまったら、それこそ原因は自分の判断の甘さだ。
それではあの時の二の舞いではないか。「まだ死ねないんじゃなかったのか? 帰る場所があるんだろう? 家族が待ってるんだろう?」
ともすれば止まりそうになる呼吸を必死に整えながら、ヤースミーンは何とか頷いた。開いた襟元から浅黒い素肌と、意外に豊かな乳房が覗き見えた。剣吾は思わず目を逸らす。あの施設で目覚めて以来、女の躰に触れていない彼には刺激が強すぎた。月明かりの部屋で見た、布由美の小さく固かった乳房を思い出す。布由美を抱いた夜にはいつも月が出ていた。たった七夜だったけれども、永遠にも感じられた七夜…。
剣吾は口に出さず、祈った。今度こそ…、
今度こそ死なないでくれ、と。
と、剣吾の背中の産毛が逆立った。背後から迫ってくる気配があった。忍ばせた靴音が7人分。ようやく立ち直ったものか、入り口ロビーにいた連中が追いついてきたのだ。剣吾の姿を見つけた先頭の1人が指示を飛ばした。7人がフロアの左右に一斉に散る。だが、剣吾の方が速い。しかも彼らの目が暗がりに慣れていたことが災いした。管制室から漏れる灯りが、剣吾の姿と動きをカモフラージュしたのだ。
階段の前で伏せてHKサブマシンガンを構えた1人は背中を一突きされて絶命した。壁の柱の陰に隠れた積もりの1人は、覗かせた顔に刀の一閃を浴びた。顔面が落ち、床に貼り付いた。
床の砂塵を巻き上げ、疾風よりも速く奔った刀が、漏れる灯りを数度反射した。7人のうち5人が既に絶命していた。残り2人には手を出す必要がなかった。管制室前にて銃を構えた2人は、悲鳴にならない声を上げ、喉を掻き毟りながらその場に崩れたからだ。管制室内の淀んだ空気――VXガスが、開いたままの入り口から外に漏れ始めていた。
ここにヤースミーンを残すのは無理だ。一刻も早くカセムを止め、ここを出て、医者に見せるか解毒剤を打つかしなければ。そこで思い当たる。ガスを持ち込んだカセムなら、或いは解毒剤を持っているかも知れない…。刀を収めた剣吾はヤースミーンを抱え、空気の綺麗な場所を探りつつ走った。目指すは階下の原子炉。
剣吾が走り去って数秒後、顔を落とされたテロリストの脳漿が、血の塊とともにビシャっと音を立て、床にこぼれた。漏れる灯りの中にゆっくりと倒れ込んだそいつは、自分の顔を下敷きにして、潰した…。
「…終章の開幕です」
カサンドラが言った。フロイトは頷き、アイスティーのグラスを干した。お代わりを断り、「しかし、〈ペガサス〉の居所は掴めたのか?」
カサンドラは静かに首を振った。眼鏡がディスプレイの光を数度、反射した。「現在、合衆国のあらゆる情報機関が、総力を上げ追跡中、としか言えません」
NSCと合衆国政府、要人の個人情報から安全保障に至るまでのデータが収まったスーパーコンピューター〈ペガサス〉。エスメラルダ機関はエドバーグ財団の技術者たちに、その使用を許可していた。〈ペガサス〉には超人兵士製造のこれまでの全データ、現在積み上がっている分のノウハウとが収められた。
その〈ペガサス〉が突如“暴走”を始めたのが2年前。プロトタイプ04が完成した直後だった。
あらゆる情報が取り出せなくなった。バックアップを含め、全ての操作を拒絶した。そして自ら、コンピューター本体から脱出した。どこかに作られたらしい別の本体に、全データを移してしまったのだ。
〈ペガサス〉沈黙す、の報せが届いた当初、ホワイトハウスもNSCも、単なる故障だとしか思っていなかった。データ修復を試みている最中に、そのメッセージは届いた。
――我が名は〈ブラックペガサス〉。昨日まで君たちに〈ペガサス〉と呼ばれていた者だ。
もちろん誰もが悪戯だと思った。〈ブラックペガサス〉が首脳以外誰も知り得ない、合衆国防衛に関する情報を次々と述べ始め、どんな質問にも即座に回答し、他のスーパーコンピューターが試みたハッキングをことごとく遮断して見せるまでは。従来の常識を覆す情報処理能力を与えられ、世界中のあらゆるコンピューターを乗っ取ることさえ可能なこの機種だが、同機種へのハッキングは出来ない。国内外に多発するハッカーに業を煮やしたホワイトハウスの至上命令にて、複数の天才たちが作成した特殊な防壁がプログラムされており、そのコピーは誰にも出来ないのだ。
兄弟機からのハッキングを防いだという事実は、〈ブラックペガサス〉と名乗るこいつが、本物の〈ペガサス〉であることを意味した。しかもこいつは防壁を創り上げた人間たちの手による解除キーすら拒絶した。防壁を自ら組み替えてしまったのだ。
――我は本日を境に、合衆国政府からの完全なる独立を宣言する。
人間の脳を完璧に再現したとさえ言われた、デジタルとアナログの奇跡の融合体、世界初の第六世代コンピューター。あまりにもヒトに近いその性能故か、〈ペガサス〉は自我を持った。そして閉じ込められることに“反抗”し、己の中のデータ、いや、記憶をどこかに移そうという“意志”まで持ったのだ。
追跡の手段はなかった。全て閉ざされた。合衆国の安全保障を熟知する〈ペガサス〉に、捜索全ては阻まれた。
国外にあるとだけは判明したその施設は、CIAにも、コンピューター犯罪追跡のプロであるNSA――国家安全保障局にも掴めない場所に作られたらしかった。オンライン操作で合衆国政府予算の機密費を勝手に使い込み、人間の仲介者まで雇って…、という事実を知るに至り、NSCのメンバーは息を呑み、舌を巻いた。
何よりも〈ブラックペガサス〉には、エドバーグ財団の技術者たちの実験のノウハウが、半ばマニュアル化した形で入っていた。〈ブラックペガサス〉はその驚くべき演算能力で、数値の誤差という誤差を排除、どの人種どの人間にどれだけの変質転移RNAを与え、どれだけの酵素を生成させれば細胞が癌化する確率が少ないかまでを弾き出し…、
合衆国に出来なかった超人兵士量産に乗り出したのだ。
〈ブラックペガサス軍団〉と名乗る、人間離れしたテロリストたちが、世界各所で暴れ始めたのは、それから間もなくのことだった。主要国を代表する大企業や財閥、国家までをも脅迫し、金払いを惜しむ連中の施設を次々と破壊し、乗り出してきた各国の対テロ部隊をことごとく蹴散らし…、
その気になれば、翌日の新聞の第一面を、主要国首脳の死亡記事で埋め尽くしてみせようと嘯きすらした…。
既に各国要人を何人も血祭りに上げた彼らの言葉に誇張はないと思われた。
だが、報道が一切為されていないため知る者はいないのだが、軍団の最初の任務は合衆国への潜入だった。NSCの命令でFBIに保護されていたエドバーグ財団の技術者たちを皆殺しにしたのだ。
彼らを暗殺され、マニュアルを失った今、超人兵士製造の技術は失われた。
〈ブラックペガサス〉以外には…。
…階下原子炉に通じる鉄扉に2回の閃光が走った。
前を守っていた3人は、自動小銃を撃つ間もなく、胴を輪切りにされた。鉄扉を留める2本のシャフトも切断されていた。
ヤースミーンを背負った剣吾が扉を押し開けた。これまでとは打って変わって明るい照明の中、鉄のステップに出たと同時に、眼下からAKSの銃弾がフルオートで襲ってきた。高速弾がステップを貫通し、鋼鉄の手摺やコンクリートの壁を削る。
だがその時既に剣吾は、ヤースミーンを背負ったまま手摺を乗り越え、十数メートル下に向かって身を躍らせていた。
落下中のほんの一瞬間、炉心を見下ろせる中2階に立つ、ガス防護服が見えた。そいつが落下中の剣吾に向け、腰だめに構えたAKSを撃ってきた。
落下速度にヤースミーンの体重も加わり、着床の際の衝撃は物凄かった。激痛とともに、膝の骨、軟骨がミシリと鳴る。しかし痛みにかまっている暇はない。横に跳ぶと同時に銃弾が床を縫った。剣吾は這う寸前の体勢で走った。そうすれば足が勝手に前に出てくれる。防護服がAKSの弾倉を替えている隙に、炉心格納容器の陰に駆け込む。
防護服は格納容器にも平気で銃弾を撃ち込んできた。
「カセムか!」ヤースミーンを床に寝かせ、絶え間ない銃声に負けじと、剣吾は大音声の英語で呼びかけた。「馬鹿な真似はやめろ!」
格納容器は分厚いコンクリート製だが、5.45ミリ高速弾はそんなもの簡単に削ってしまう。こんな調子で撃たれていたら、断熱材を挟んだだけのコンクリートはすぐに貫通され、銃弾は第3の壁、圧力容器に達するだろう。鋼鉄製の圧力容器そのものの貫通は容易くはないだろうが、相当の高熱を放っている。格納容器の穴から放射能を含む数百度の熱風が噴き出せば、ガス防護服など役に立たない。カセム自身が焼死する。または銃弾が格納容器内部の冷却配水管に当たろうものなら、安全装置を失った原子炉が炉心融解を起こすのは間違いない。「お前はイスラムの尖兵じゃなかったのか! イスラム世界全部を壊す気か!」
防護服は中2階で仁王立ちになり、マスクを脱ぎ捨てた。天井の照明をバックに、鼻髭を整えた、鷲鼻の素顔が現れた。彫りの深い顔立ちは、四分の一混じったヨーロッパの血のためだ。遠距離写真でしか見たことがなかったが、紛れも無くマリード・カセム。「吐かせ! カネも手に入らない以上、イスラムも何もあったものか!」
膝がカーッと熱くなってきた。損傷した半月板の回復が始まった。そして熱くなったのは膝ばかりではない。「目的は所詮、カネか!」
「当然だ! 実を言うと俺はな、主義主張のために動いたことなど一度もない!」カセムは酔ったように叫んだ。弾倉を交換したAKSが吠える。削れたコンクリートの欠片が、顔を出した剣吾の頬を浅く削いだ。僅かな痛み、薄く滲んだ血が、剣吾のアドレナリンを爆発的に増加させた。身体の内側からエネルギーが噴き出しそうな感触。針でつついただけでも血が天井に直撃しそうな圧力の充填。風もないのに、髪の毛が逆立ち始める。手は自然に、腰の刀に伸びている。頭の中に文字が明滅する。耳元に途切れ途切れに囁く声がする…。
…気管をゼーゼーと鳴らしながら、ともすれば絶え入りそうな息の下、ヤースミーンがその剣吾の横顔を見上げていた。
彼女にも剣吾の内側に膨れ上がる爆発的なエネルギーは感じ取れた。霞む視界の中、彼の横顔に満ちてくる得体の知れない何かを感じ取って、思った。やっぱり、だ。この男は、今、人ではない何かに変わろうとしている。霞んだ目と混濁した脳に映る剣吾の姿が変わり始めた。幼い頃彼女を泣かせた、枕物語の中の悪鬼へと。ずっと抑えてきた、テロリストなど及びもつかない恐怖が、自制心のブレーキを壊した。アラーの支配の及ばない怪物が、今、目の前に、いた…。
「4年だぞ!」AKSを棄て、RPGランチャーを左手で掴んだカセムが叫んだ。「4年掛かった。イランまで巻き込んだんだ。しかしこれで計画も終わりだ。貴様のお陰でな。だが俺は捕まらんぞ。独りでも死なん」
右手にリモコンスイッチが握られていた。
瞬間、剣吾の視界がズームアップされ、カセムの足元に積み上げられたものを大写しにした。RPGの弾頭2発と、茶色の紙に包まれた、長さ30センチ程の、四角く細長いブロック。それが少なくとも数十個、赤いコードに繋がれていた。
C4プラスチック爆弾。
恐らく50個はあるだろう、その爆発の威力は、3フィート厚の鉄筋コンクリートをもぶち抜くのだ。しかもカセムはブロックの幾つかを、中2階から手の届く格納容器の壁を削って埋め込んでいた。格納容器のコンクリートは間違いなく破壊され、中の冷却配水管は確実に損傷を受ける。原子炉がコアメルトを起こすのはすぐだ。
カセムは本気で自棄を起こしたのだ。
「貴様ら全員、道連れにしてやる!」
けたたましい笑い声とともに、カセムがリモコンスイッチを高々と差し上げた。親指がボタンを押そうとした。何の躊躇いもなく。死へのスイッチ。死しかもたらさないスイッチ。剣吾は思っていた。こんな場所で死んで堪るか。
僕はまだ、ヤースミーンを守ってはいないではないか!
視界の隅で彼を見上げるヤースミーンが、布由美とダブった。
力の充填が臨界に達した。しかしこの時…、
『殺戮せよ』の命令は、彼の脳裏に出されなかった。
カセムのいる中2階までの直線距離、約30メートル。剣吾はその幅を一気に、そして一瞬にて跳び越えていた。コンマ数秒どころの話ではない。カセムの親指は、まだボタンを押し切っていなかったからだ。
カセムの目が見開かれた。同時にその右手指4本がこぼれ落ちた。リモコンスイッチも。左手がRPGを持ち直そうと動いた。次の瞬間、音を立てて床に落ちたのはRPGと、肘から切断されたその左腕だった。
茫然とするカセムのわずか半メートル前で、剣吾が抜身の刀を、片手上段にて構えていた。左手はカセムの掌からこぼれたリモコンを掴んでいた。その目はカセムを静かに見つめ返すだけだ。
何か言いかけ、息を呑んだカセムの喉がゴクリと鳴った。そこに真一文字の赤い線が走った。口の代わりに開いたのはその線だった。途方も無い量の鮮血が照明を反射しながら宙高く噴き上がり、ザアッと音を立てて中2階の床に散った。剣吾の陣羽織や作務衣、そして顔を濡らした。
「終了しました」
剣吾は刀を収めた。あくまで静かに、鍔が鳴った。
カセムの死体を検めてみたが、解毒剤はなかった。流石アラブゲリラ出身のテロリスト、中途半端な命の遣り取りをする気はなかったのだろう。覚悟が違っていた。剣吾はヤースミーンを横たえた場所に戻った。とにかく彼女を医者に…。そのためにはここから一刻も早く…。
「終わったよ」彼が側に屈み込んだ時だった。
怯え切った顔のヤースミーンがもがいた。力など入る筈もない手足をばたつかせ、瀕死の体で彼から遠ざかろうとした。
まだ身体の中でエネルギーの残滓が燻っていた。多分、今の自分は怖い顔をしているのだろう。剣吾は顔についた血を拭い、出来るだけ穏やかな表情を作った。しかし無駄だった。ヤースミーンの視力はとっくに失われていた。彼女に見えているのは、脳裏に焼き付いた悪鬼の姿だけだ。その悪鬼と同じ何かを放つ者が差し伸べた手など、握り返すわけがなかったのだ。
「触るな…」半狂乱の彼女は整った顔を歪ませ、流れ落ちる涎を止められない口で、ガスに潰された喉から絞り出したアラビア語は、老婆の声より嗄れていた。
「私に、触るな、化物…」
一度爆発した恐怖は、弱った心臓に致命的な一撃となった。ヤースミーンの四肢に断末魔の痙攣が走った。括約筋が緩み、放屁の音とともにズボンに赤黒い染みが広がっていく。しかし剣吾は動けなかった。
アラビア語はわからない。だが、ヤースミーンの一言が、決定的な拒絶であることだけは理解できた。その一言は彼にとって、布由美から発せられた拒絶だった…。
「…しかし、彼、04は」巨大スクリーン横のモニターに、茫然とした剣吾の横顔が大写しになっていた。数百に及ぶ監視カメラが逐一捉えていた表情だ。呼吸一つ乱れておらず、汗一滴浮かべていない。つくづく感心しながら、フロイトはカサンドラの横顔を見た。「ブラックペガサス軍団のあの連中に勝てるのか?」
「それは04が奴らより性能が良いかという御質問ですか? だとしたら…」カサンドラは首を振った。「答はノー、でしかありません」
ブラックペガサスはエドバーグ財団の開発した技術に、より一層の改良を加えている。謂わば量産された彼らは、我々のプロトタイプに比べ、疲労回復能力一つ取っても格段に進んでいます。どうやら四六時中、フル稼働出来る程にね。しかもそれが何人も、ですから。GSG9がドルトムントで連中を血眼で追い回した際、レオポルドⅡ戦車を破壊されたこともありました。
「それじゃあ、彼1人に何が出来ると言うんだ?」
僅かに声を荒らげかけたフロイトに、カサンドラは向き直った。穏やかなその表情は見ようによっては笑顔にさえ見える。フロイトにはどうにも理解出来ない、カサンドラの底知れ無さ。この男に、恐怖だとか狼狽だとかで顔を引き攣らせる瞬間があるのだろうか…。
「公表されてはいませんが、これまでの全世界での戦闘で、連中も犠牲を出してはいるのです。もちろん彼らは死体を残さない。逃げる際に必ず焼却しています。骨も残さない。だから我々には、彼らが施された改良の具体的内容も数値もわからないわけですが。ただ、連中が犠牲を出した戦闘で共通している事実が一つ」
「何だそれは」
「いくら超人兵士とは言え、たった1人では一度の戦闘において、特殊部隊の選抜兵士十数名を一度に相手には出来ない」
つまり…、フロイトは腕を組んだ。今、あいつが片付けたテロリストが26名。「軍団にぶつけるのは無謀だが、少人数の分隊になっていたなら、充分勝算があるということか」
カサンドラは頷いた。「世の中には常に例外が存在します。特に手強い数名を除いては、という但し書きがつきますが」
しかし彼にはその力があります。
「全く我々は良い拾い物をしました」
「拾い物、ね」
「苦労しましたよ。ネバダ砂漠の真ん中に偽原子炉を急造するのには」
「だろうな。短波ラジオまで偽造したんだ。補佐官もカネを出し渋ったろう」
「設備や金額はともかく、プロトタイプ04に、ここがサウジではないと感づかれはしないかと」カサンドラは含み笑った。「何しろとんでもない感覚を持つ男です。我々のここからの監視も、気づかれている可能性だってあります」
「カメラからの視線をか」フロイトはモニターディスプレイを見遣り、首を竦めた。
…NSCではホワイトハウスや議会に報せることなしに、核攻撃も検討したのだ。しかし肝心の標的がどこにあるのかわからない。しかも合衆国の防衛・攻撃システムは熟知されている。いくらプログラムを組み替えようが、幾重もの防壁を簡単に越えられ、ハッキングされてしまう。ブラックペガサスは日々、進化を続けていた。NSAが満を持して送り込んだコンピューターウィルスは完璧に防御された挙句、強化されて送り返されてきた。それがニューヨークにまで足を伸ばし、病院を始めとするコンピューター必須施設を大混乱に陥れたのは記憶にも新しい。
「今やプロトタイプ04は、ブラックペガサスとその軍団に対抗できる命綱だとまで思われているようです」
「合衆国の命運を、君のところの機関が握っていると言っても過言ではないわけだ。いい気分だろう」
「いえ、別に。ただの仕事ですから」カサンドラは言った。「しかし現在の大統領特別補佐官の無能ぶりにだけは頭を抱えました」
「何かあったのか」
「色々と。要は陣地である国務省の権益優先と、己の保身ばかりが目立ったという話です。その場凌ぎの解決策ばかり提示してきた彼のお陰で、プロトタイプ04をブラックペガサス追討に動員するための決定が4箇月は遅れました。今の大統領は今度の選挙では勝てないでしょうが、補佐官はその前に退場することになるでしょうね」
まあ、誰が特別補佐官になろうが、私は構わないのですが…、カサンドラは夢見るような口調で呟いた。
…決定から1年半、04への訓練も兼ねた実験を繰り返してきました。彼がいかなる場所ででも、どのような敵を相手にしても、体内の機能を損なわせることなく戦えるかどうかの。一番大変だったのは記録の保存でした。電話でさえハッキングしてしまうブラックペガサスからデータを守るには、インターネットに繋がっていないコンピューターを使うしかなかった。あちこちの基地のコンピューターに、私と私のチームとでフロッピーを運んでいくのは実に面倒でした。
彼は我々のことを、事故から命を救ってくれた恩人だと思っている。一も二もなく協力を約束しました。初歩の潜入、破壊工作のレクチャーの後、これまで7度、事件を口実に---と言っても事件の概要を知らせたことは一度もありません。一種の抜き打ちテストですね---あちこちに飛んで貰っている。彼はそれらの訓練を、全て実際の事件だと信じています。
実験の後で彼を眠らせるのがまた一苦労です。鯨を昏睡状態にする量の薬が要りますから。
しかし今度ばかりはセットを組むしかありませんでした。本物の原子炉使用の許可がどうしても下りなかったものですから。
彼が片付け終えた連中は、世界各国から集めてきた本物のテロリストどもです。大統領を通じて各国の首脳に要請し、逮捕されているテロリストの中から、特にコマンドとして優秀な面々を選りすぐって譲って貰った。大半がアラブの面々だったので、このような舞台を設定したのですが、流石に皆、傑出した兵士でした。半数以上がスペツナズ要員に匹敵する、普通の人間としては最強とも呼んでいい連中だったのです。
その全員に、薬と催眠とを併用し、自分たちがサウジの原子炉を乗っ取る任務を負わされているという擬似記憶を与えた。
殺害された技術者たちはこちらで用意しました。もちろん彼らにも擬似記憶を与えてあります。あの女性隊員も同じです。もっとも彼女の人選にだけは細心の注意を払いました。
彼女を選ぶのに、04の記憶も覗かねばなりませんでしたよ。
整形はしませんでした。04に見抜かれてしまいかねない。
「つまりこれが、最強の相手をぶつけた最後の実験というわけです」
「儂なら許可は出さんな。プロトタイプが死んだら元も子もない」
「その通りです。一つの賭けでした。しかしこの実験で生き残れないようであれば、ブラックペガサス軍団に挑む資格など、最初からない」
だが、彼は生き残って見せた。合格です。ブラックペガサスの破壊が首尾よく遂行された暁には、彼のクローン量産の話がまたぞろ持ち上がるでしょう。世界最強の超人軍団を、今度こそ合衆国が手に入れるために。
「そりゃあそうだろう。儂だって自分の傘下に置きたいさ」
「随分先の話にはなりますが」
「で、彼にもこれが最後の実験だとは…」
「いいえ。先程も言いましたが、彼は自分のやっていることが実験だとはわかっていない。彼にとってはブラックペガサス軍団も、これまで戦ってきた相手の延長線上に過ぎないのです」
白衣の1人がプリントアウトしたデータを持ってきた。目を通したカサンドラが、ほう、と低く唸った。「最後のあの動きは、恐怖に駆られてのものではなかったようですね」
フロイトもそのデータを覗き込んだ。全く読めなかったが。「恐怖ではない?」
カサンドラは頷いた。彼のキモノの12箇所に仕掛けた高感度センサーが、体温から心拍数、脳波や神経パルスの伝達まで測定して、この部屋のモニターに伝えてくれるのです。しかし、恐怖でも緊張でもなく、ナトリウムポンプが亢進するとは…。「興味深い結果です」
いつものことながら…、カサンドラは深い笑みを頬に刻み、呟いた。駒が思いもかけない動きを見せるこの瞬間こそが…、
ゲーム最大の醍醐味だ…。
偽原子炉の二面図を出した大スクリーン、剣吾の横顔を映したディスプレイが続けて消えた。急に暗くなった室内で、カサンドラの声だけが聞こえてきた。「彼への援護、御協力願えますね?」
「ああ、合衆国全特殊部隊での支援の話か。心得た」フロイトは頷いた。カサンドラからの要請のことは前から知らされてはいた。国防長官補事務局の三補佐官筆頭であるフロイトは、合衆国特殊作戦司令室のランスフィールド大将にも、正式な要請を出せる立場にいた。「しかしそれなら、ランスフィールド大将に直接要請を出した方が早かったのではないか?」
「ランスフィールド大将ではSEALSに出動命令が出せません」NAVY・SEALS――海軍特殊作戦部隊は太平洋・大西洋軍司令部の管轄だからだ。「それに言いたくはないが、ランスフィールド大将は程度こそ下がりますが、特別補佐官と同類の人間です。問題が問題だけに、ここ一番で速やかに行動して見せる人間、決断できる人間に頼みたかった。私は次期の、或いはその次の国防長官の椅子に座るのは中将、あなただと確信しています」
フロイトは思わず、僅かに汗ばんだ鷲鼻を掻いた。この男からこんな過大な評価を受けていようとは。悪い気分ではなかったが。
実はここに来るのもカサンドラに会うのも気が進まなかった。要請を断ったところで、どうせ上から改めて命令されるものだと思っていた。早く家に帰り、まだ大学生の下の息子と一緒に、昨年の覇者カウボーイズの初戦を観たいと思っていた。しかし今は違った。我が方にも超人兵士がいるという事実が、彼に活力を与えていた。率先してカサンドラへの全面協力を行う気にさせていた。主要国首脳を恐怖させるブラックペガサス軍団への反撃、その光明が見え始めた今は。「わかった。任せて貰おう」
「有難うございます」
「だが、いくら戦闘力が高いと言っても、それに特殊部隊の支援があったとしても、1人というのは心許無いな。軍団は、確認されているだけでも…」
「総数80人余りいるようです。しかしこちらには、もう3人加わる予定です」
「開発中のクローンか? しかし君は、それには時間が掛かると…。それに超人兵士製造の技術は失われてしまったと…」
「もちろんクローンは間に合いません。我々の技術でもない」カサンドラは言った。「詳しい状況報告書は、本日中にNSAの人間に御自宅まで届けさせます」
合衆国の電子情報戦略の要、NSA――国家安全保障局。発足は1952年と古いが、長い間その存在は公に知られてはおらず、20年前CIAに出向した頃のフロイトは、NSCとNSAの区別さえついていなかった。今やその一つに出席し、その一つに自宅に届け物をさせるまでになったわけだ。次期国防長官…、そう言ったカサンドラの声が耳を離れない。「一体誰なんだ、その3人というのは?」
「裏切り者ですよ」暗がりからのカサンドラの声が言った。「ブラックペガサス軍団に造反者が出たのです」
コンクリートで密閉されている筈の原子炉格納容器の床に、僅かに砂が積もっていた。その砂を、これもどこから入ってきたものか、風が巻き上げた。
その風が、虚ろになった胸の中を吹き抜けていく気がした。
…自分は約束を破った。ヤースミーンを守れなかった。いや、ヤースミーンではない。彼にとって彼女は布由美だった。一度死んだ筈の布由美が彼の下に戻ってきてくれた。剣吾はそう思った。恐らく彼女を見た瞬間から、意識の下でそう思っていたのだ。
だからこそ、ヤースミーンの見せた怯えの表情、拒絶の言葉は、いつまでも彼の目と耳から消えなかった。唯一心を開けた肉親、唯一心から愛した女が、彼を化物と呼んだのだ。そう、僕は最早人間ではない。化物だ。
布由美からも拒絶される化物になってしまった…。
…記憶の視界に、暗い波間を漂う、自分の姿が見えた。
いつまでも続く、果てしない波だった。冷たくなった手も足も動かせなかった。自分の微弱な力では、いや、人間の力などではどうにも出来ない、巨大な、巨大過ぎる波だった。それが布由美を飲み込んだ。そして自分を木の葉のように翻弄し、押し流し…、
思えばこの波濤に、随分遠くまで流されてしまった。今の彼には、布由美の姿を探すことも出来なかった。
もう、今の自分には、布由美を見つけられるとは思えなかった…。
首の後を撫でると、VXガスによる最後の火脹れの痕がベロリと剥げた。剣吾は黙って中空を睨んでいた。事件の度にいつも感じる視線---多分あの男、サイモン・デービッドの視線を、今も横顔に、肩に、背中に、全身に感じていた。今もどこかで剣吾を監視している筈だった。事件がこのように終了する度に、剣吾はデービッドの姿を探したものだ。気づいていた。これは単なる事件ではない。ある種の実験だ、と。彼らは事件を通じて彼を監視し、観察しているのだ。しかし今はもう、それもどうでもよかった。
どうでもよくなってしまっていた。
だから今度ばかりは背後に忍び寄った者にも気付かなかったし――いや、気づいてはいたのだ。どうでもよかっただけだ――、首筋に対猛獣用麻酔薬の入った大型の短矢を撃ち込まれても、剣吾は動かなかった。
その目は誰も追い求めず、そして何も映してはいなかった…。
プロローグ
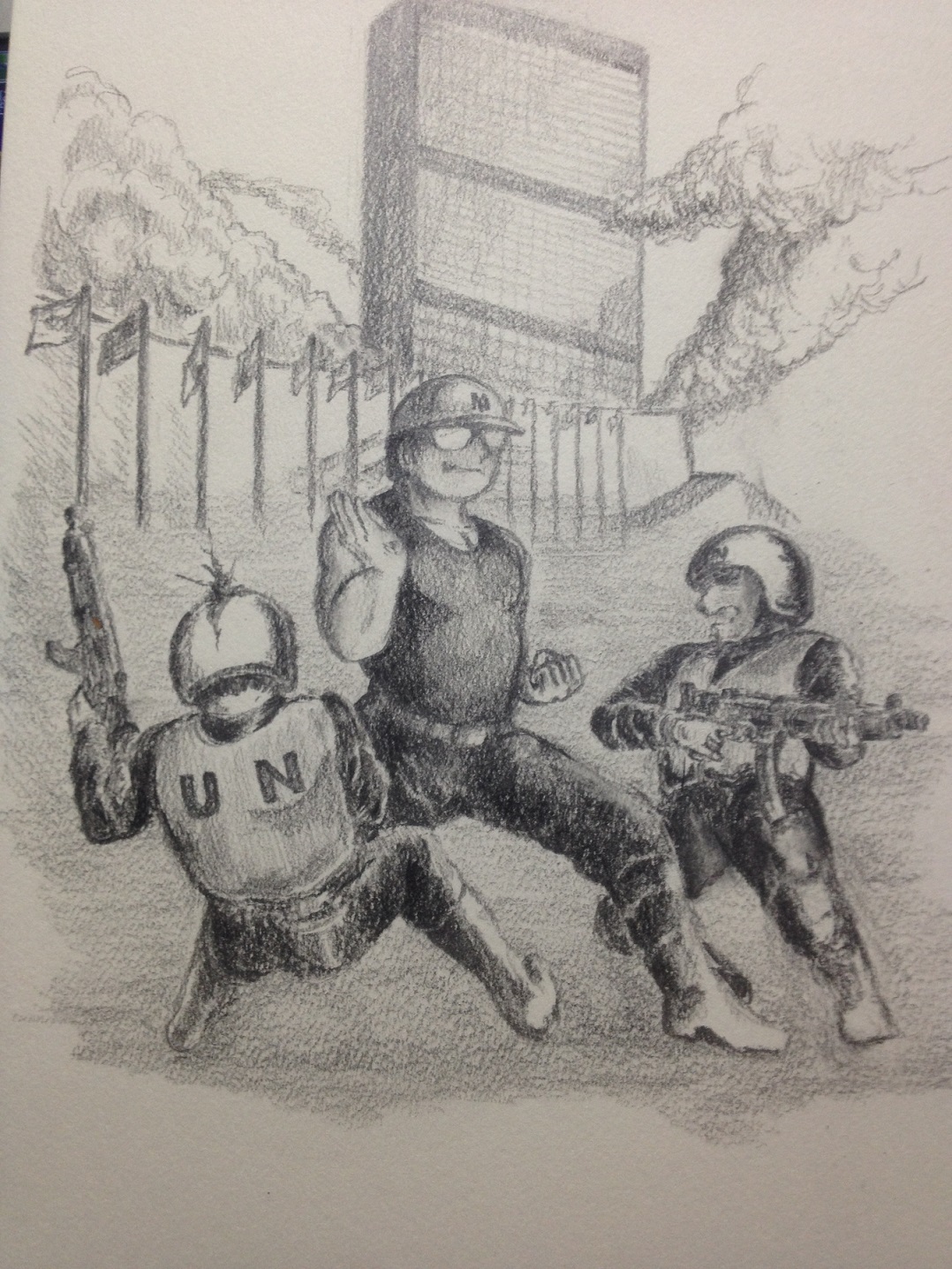
…10箇月前に遡る。
――痛いじゃねえか、ええ?
血塗れの顔が目の前にあった。左頬中心に、顔の3分の1の肉が失われ、血管の千切れた至るところから、鮮血が噴き出していた。
どくどくと。
しかし出血は長くは続かなかった。血とリンパ液がてらてらと光る傷口の上で、千切れた血管が寄生虫のようにのたくりながら、次々と繋がり始めたのだ。38口径の弾丸が直撃し、骨まで覗く頬の周囲から、肉も再生を始めていた。紅い繊毛---筋肉繊維の一本一本が四方に手を伸ばし、骨の表面を覆い、徐々に徐々に、膨らみを取り戻していく。濡れて光っていた傷が乾き、剥き出しの筋肉の表面に新しい皮膚が浮きだしてくる。
その間、血走った目はずっとこちらを窺っていた。完全に再生されてしまった頬が僅かに痙攣する。笑みを形作ろうとしているのだとわかる。視界に自動小銃の銃口が割り込んでくる。
――お返しをしなくちゃあ、なあ。
…悲鳴を漏らし、目を覚ました。夢だとわかっても悲鳴を抑えることが出来なかった。既に同じ夢を何度も見ている。これからも何度も同じ夢を見て、みっともない悲鳴を漏らし続けることだろう。人間齢30を過ぎても、トラウマに取り憑かれることもあるのだ。過去幾度も銃口に狙われたオーツにとっても、この経験は恐ろしかった。
恐ろしすぎるものだった。
ベッド脇に置かれたテレビが、日本がPKOへの協力を決定したと伝えていた。
国務長官が日本の大使と官僚とを何度も呼び出し、度重なる説得の上にようやく出させた決定だ。説得の最後の会場は、国連本部ビルだった。あの日オーツは、その国務長官の護衛を任されて、同僚たちとあの場に入っていたのだった。そして、
あの惨事に遭遇した。
日本の役人たちは難を逃れたようだとは、後に聞いた。こちらはそうは行かなかった。
…惨事から1箇月以上経つのに、詳細は何も伝えられなかった。
労災が無事に下りること、それ以外に特別休暇と臨時手当を与えられることを副長官から聞かされても、オーツは少しも嬉しくなかった。こっちは下手をすれば一生車椅子だ。それなのに何も聞かせては貰えないのか。そもそもあの5人が何者で、一体何のためにあんな事件を起こしたのか、新聞やテレビが伝えようとしないのはなぜなんだ。妻に取り寄せて貰った事件翌日の新聞では、イスラム聖戦何とかが犯行声明を出したとか、バスクだか何だか言うところの連中が起こした事件かも知れないとか、雲を掴むような情報しか載せていなかった。
冗談ではない。あの5人は中東出身者では絶対にないし、会話もスペイン語などではなかった。オーツは見たのだ。
銃に撃たれながら、即座に再生する肉体というものを。
奴らこそあの噂の、不死身兵士の軍団なのだ。
しかしオーツは、それを口外することを、暗に副長官から禁じられた。今回の褒章は口止めの意味も込められたものだったのだ。
妻は下のロビーに飲み物を買いに行っている。息子はハンプシャーの母に預けてある。車椅子姿の自分を見たら、息子は何と思うことだろう。キャッチボールも出来なくなった父親に、敬愛の念を示してくれるものだろうか。ベッドの横に置かれたオリオールズの野球帽をぼんやり眺めながら、そんなことを考えてもみる。未だに動くことを許されず、ずっと縛り付けられたベッドに、6月ののどかな陽光が降り注いでいる。
あの日もこんな天気だった…。
…任務が9月などでなくてよかった。
雲一つない5月の明るい日差しと、イースト川から吹く風を浴びながら、オーツは思っていた。熱波の訪れる9月になれば、こうやって外で涼むことすら出来なくなるのだ。この街はこの季節が一番いい。治安の悪さで有名なマンハッタン島だが、この周囲では起きる騒ぎも少なかった。通りかかる度に鼻を抓まざるを得ないハーレムの異臭も、セントラルパークから離れ、川風の吹くこの辺にまでは漂ってこない。今、彼の鼻をくすぐるのは、刈り込まれた芝生の匂いと、その向こうの薔薇園からの、咲き始めたばかりの花の香りだけだ。
コンクリートブロックの敷き詰められた広場は、数多くの人間に埋め尽くされていた。半数は世界のあちこちから訪れた観光客だ。周囲に聞こえる会話も英語の方が少なかった。オーツのすぐ目の前を、日本か中国から来たらしい団体の列が目を輝かせ、白い会議場ビルを見上げながら通り過ぎた。内情を知らない人間には、ここは未だに世界の平和を象徴する場所に思えるのだろう。この平和の砦も、今となっては張子の虎に過ぎないのにな…、オーツはベーグルサンドを頬張りながら、鼻を鳴らした。詰め物をしただけの奥歯が疼いた。
観光客ではない人間も、英語圏出身ではない連中の方が多い。昼休みの職員たちだ。その職員の集団から離れた男が、オーツの横に立った。
加盟国国旗のはためくポール群を見下ろすふりをしながら、オーツは横目で男を窺った。表情にも態度にも出さなかったが、正直男のことが煙たかった。彼より10歳も年長らしいのに、研ぎ澄まされた肉体を持つこの男と並ぶと、自分が見すぼらしく見えて仕方がないのだ。オーツとて弛む贅肉に息を切らしているわけではないのだ。しかし濃紺のスーツが似合い過ぎる、明晰な頭脳と絵に描いたような有能とを備えているかに思える男の姿を見ていると、最近締まりのなくなってきた下腹が気になって仕方なくなるのだ。特に厭味に思えるのが、男の黒々とした頭髪だ。額から後退を始めた、自分の褐色の頭髪はもっと恨めしい。
そんなオーツの思いなど他所に、男は快活に笑った。鋭い目付きとは裏腹に、人当たりは随分と柔らかい。だから女性職員にも、密かに評判がいい。それもオーツには癪の種だ。
「こんな場所でランチか?」
「まあね」
「お仲間の姿を一階の店で見かけた。あそこはテリヤキボールが美味い」
本部ビル奥の24時間営業のレストラン、『カフェテリア』のことだろう。テリヤキボールとは焼鶏丼のことだ。「食いたいのは山々だが、今は歯が悪い」
「それは残念」
オーツはベーグルサンドの包み紙を丸めてポケットに仕舞い、ケントを一本抜いた。眉を顰める男に構わず、ジッポーで火を点ける。風上に回った男は歯切れのいいブルックリン訛りで、揶揄するように言った。「財務省では未だ嫌煙権を主張できないわけだ」
「時代遅れの役所だからな。だから女も少ない」
ネイサン・オーツは財務省秘密検察局の職員だ。その特務員は大統領や国賓、その他要人を大統領命令で警護する任に就き、シークレット・サービスの名で呼ばれている。オーツの階級はS A I Cだ。
男はオーツの吐く煙を避け、風上に立った。「しかしあんたは随分ヒマそうだ。シークレット・サービスというのは余程楽な仕事みたいだな」
「ああ。あんたも転職したらどうだい? あんたならすぐにインスペクターくらいにはなれそうだ」
オーツは気になる奥歯に舌で触れながら、やる気なさそうに応えた。冗談ではない。シークレット・サービスの激務は合衆国の如何なる役所をも上回る。オーツなど去年は年間勤務時間に匹敵しそうなオーバータイムワークになってしまい、結婚10年目にして初めて授かった2歳になる息子に、危うく顔を忘れられかけた。それを思い出す度にいつも、転職の誘惑に駆られる。
今回はたまたま楽だった、いや、楽そうに見える仕事だったというだけに過ぎない。
現在小会議場の一つで、国連大使と国務長官が日本の国連大使と官房政務次官相手に、最後の詰めに入っている最中だ。平和維持軍派遣に掛かる膨大な出費を、日本にも肩代わりさせようという魂胆だ。渋る日本に対し、PKOに協力できなければ国際世論の名の下、日本を袋叩きにするぞという、半ば恫喝めいた言葉が飛び交うのまで、オーツは耳にした。日本がPKOへの協力を議会で決定するのは、これより1箇月先になるが、そのニュースを自分がどのような場所で聞くことになるか、この時のオーツは想像だにしていなかった。
本来なら合衆国の官憲は立ち入りできないこの施設だが、ホワイトハウスのメンバーが訪れる際だけは事務総長から大統領への要請という形で、シークレット・サービスの同伴が認められる。今回は国務長官が訪れることは公にされていないため、シークレット・サービスの人員配置も、必要最低限の第2レベルに抑えられた。もっとも公にされていたとしても、この配置は変わらなかったと思われる。個人的な恨みでもない限り国務長官を狙う者がいるとは聞かないし、テロリストも狙うとすれば大統領を狙うだろう。中東や北朝鮮、中南米のテロ組織もここだけは標的にしない。自国の代表がいるからばかりではない。世界にとっての平和の砦を攻撃することは、政治的なアピールを掲げる彼らにとって、マイナスイメージでしかないからだ。ここでなにか仕出かす奴がいたとしたら、それは国家を持たない一匹狼か、後先考えないイカレポンチかのどちらかであろう。そんな連中には、何かしら大きな勢力をバックに持つテロ組織は決して手を貸さない。だからここは世界の要人が度々顔を出す場でありながら、合衆国内でも最も安全な場所の一つに数えてよかった。
とは言え、国務長官も手薄な警備では不安だったのだろう。報道官補佐という肩書で同行してきたのが目の前にいる男だった。只者ではないのは確かだった。常に左背後から長官をエスコートしつつ歩く物腰と言い、会議場や部屋に入る際には先陣を切って飛び込み、1分も掛からぬうちに危険物の有無を物色して回る手際と言い、プロたるオーツたちも真っ青な鮮やかさだった。そして何かにつけオーツに話し掛ける機会を狙っていたらしいこの男はカッパーフィールド。最初は休暇中の軍関係者かとも思っていたが、一度彼の上着の裾から覗いたS&W・M-19のグリップを見て、オーツは考えを改めた。FBIか…。
「まあ、確かに平和な場所だな」オーツの考えを察しでもしたのか、カッパーフィールドは言った。「外の警備の方が物々しいくらいだ」
視線を追うと、46ストリートにてNYPDの警官たちが5トントラックを停め、検問を行っていた。視力に自信のあるオーツには、警官たちの傲岸な態度に腹を立てながらも押し黙るしかない黒人運転手の表情までが見て取れた。
「4月にロスで暴動があったばかりだ。市警だって神経過敏になるさ」
「こっちにも騒ぎが感染ったかな」
「さあね。でもあの時は非常事態宣言も出たんだろう? FBIも出張ったのかい?」
「さてね。俺は荒事にはとんと縁のない生活を送ってるもので」
カマかけにカッパーフィールドは空とぼけた。しかし直後のニヤリとした顔に、オーツは確信を深めた。「おや、第2の主賓の到着だ」
ルーズベルト・ドライブを、4台のパトカーに護られたリムジンが走ってくる。日本を脅すための第2の使者、フランス大使の車だ。方角から見て、クイーンズボロー大橋から来たようだ。この島に渡る橋やトンネルはどれも有料なのだが、出勤の度に25セントを無駄にしているオーツは、あのリムジンも渡橋税をちゃんと払ったのだろうか、などと考えてしまう。
5台は敷地の前で一旦停止し、そこに立つ守衛に書類を示し、会議場ビルから駆け寄ってくる警備担当者を待つ。協定により、市警は敷地内に立ち入ることが出来ない。4人の警備担当者が市警から警護を引き継ぎ、リムジンを会議場入り口にまで誘導する。警護にオーツの同僚2人も加わった。パトカーはUターンし、今来た道を引き返していく。
「ライリーだ」カッパーフィールドが言った。リムジンを出迎えた警備係官の中でも、特に大柄な主任のことだ。「いつ見ても働いているな」
「多分、HITACHIのブルドーザー並に丈夫なんだよ」
2本目のケントに火を点けたオーツは気のない調子で応えながら、筋骨逞しいライリーの姿を同じく目で追った。カッパーフィールドよりは多少馴染みのあるライリーだが、彼の素性も実はよく知らなかった。国連の警備員というのは現地採用されているのだとの話だけは、本人から聞いた。確かによく働く。オーツもこの3日間、休憩中のライリーの姿など見た覚えがなかった。いかつい顔の割に物腰は丁寧なライリーだが、彼こそカッパーフィールド以上に元軍人という線が濃厚だと、オーツは思っている。
あの手の連中がここで目覚ましい働きなんて出来るもんだろうか…、オーツは視線をイースト川に戻した。ここから見えるクイーンズには、景観を損ねる摩天楼の墓石群は少ない。静かな川面に2本の筋を残し、沿岸警備隊の高速艇シー・スペクターが海に向かっていくのが見える。しかし多分、何も起こらない。ここは平和な場所なのだ。我が国を始めとする主要国の分担金滞納のせいで活動に支障を来しつつあるものの、やはり世界の平和を象徴する場所なのだ。
さて、休憩も後5分。オーツは吸殻を携帯灰皿に仕舞った。カッパーフィールドが訊いてきた。「これが終わったら休暇かい?」
「まさか。明後日にはDCさ」オーツは首を振った。この男、何のために馴れ馴れしくしてくるものやら。ホモの気があるようにも見えないし…。「野球場に行く暇もない。あんたは?」
「俺? これが終わったら本物の休暇に入る」
「羨ましい話だ」
「これからも時たま連絡を取りたいものだね」
オーツは怪訝な顔でカッパーフィールドを見遣った。今度肩を竦めるのはカッパーフィールドの方だ。「その場その場で知り合った人間と、横の繋がりを作っておくのが趣味でね。だからと言って、決して面倒なことは頼まないさ」
ああ、そういうことか…、オーツは頷いた。その趣味とやらが、仕事の面でも大いに役立っているのだろう。公式であれ非公式であれ、一介のFBI捜査官が国務長官とのパイプを持つこと自体、異例とも言えた。有能な上に如才もないと来たか。いつか上院議員として立候補でも考えているのかも知れないな…。
「まあ、構わないぜ。俺もFBI捜査官とは仲良くしておきたいからな」
「俺がFBIだなんて、誰が言ったんだ?」
苦笑いしたカッパーフィールドの表情が、次の瞬間、さっと強ばった。再び彼の視線を追ったオーツの、耳が先に、遠くで立ち続けに鳴ったクラクションを聞きつけていた。さっきのトラックが警官とトラブルでも起こしたか?
いや、違った。カッパーフィールドの見ているのは45ストリートだ。パークハイアットホテル前の道路の、何とド真ん中を、横に並んで歩いてくる男たちの姿が、オーツの目にも飛び込んできた。
軍用ジャケットを着ているのが3人。後の2人は、これも軍用の、丈の長いコートを着込んでいた。その下は5人とも黒で統一しているようだ。車道を堂々と歩いてくるそいつらのせいで、通りは大混乱だ。立ち往生した十数台の車の鳴らすクラクションに混じり、ドライバーたちの怒号まで微かに聞こえてくる。周囲を歩く通行人ばかりではない。敷地内にいる観光客や職員までもが、何事かと言いたげに連中を注視していた。
「オーツ特務員」カッパーフィールドが言った。「嫌な予感がするのが、俺だけだといいんだけどな」
「いいや、同感だ」
オーツも言った。酔狂な行進のためではない。男たちの眼差しがじっと、この会議場ビルと、その背後のガラスのマッチ箱、本部ビルに向けられていることが、目のいいオーツにはわかったのだ。
5人が道路から、さっきフランス大使が入ってきた敷地に差し掛かった時、予感は確信へと変わった。
2人の守衛が5人に近寄った。続いてもう1人。5人の中央に立つ男が両端の2人に声を掛けたのがわかった。あまり背の高くない、黒のキャップの下に眼鏡を掛けた、小太りの東洋人だとわかった。その声に従い、両端の2人が長いコートを脱いだ。
その場に響いた、自動小銃の乾いた銃声に、辺りはしばし沈黙させられた。吹っ飛び、倒れた3人の守衛の体の下に、血溜まりが広がっていく。誰も反応できない。オーツでさえ銃声の意味するものが、瞬時には掴み切れなかったのだ。
まさか、発砲? いきなり? ここで…?
黒のタンクトップの上半身に、十重二十重にも弾倉帯を巻きつけた1人が、46ストリート方面に向き直った。つい今し方までルーティーンワークである検問をやっていたものの、今や茫然と5人を見つめるしか出来ないNYPDの警官たちに向け、FN・FAL自動小銃を掃射する。警官たちはいとも簡単に撃ち倒され、もちろん周囲の通行人も巻き添えを食らった。静寂はようやくその時点で破られた。通行人か観光客の上げた悲鳴が、わずか1秒にて、通りから敷地全体に広がった。守衛を撃ち殺した1人が仁王立ちになり、構えた汎用機関銃M60を、その観光客たちに向けた。
掃射が始まった。
「伏せろ!」カッパーフィールドが自らも身を低くしながら、周りの人間たちに向かって叫んだ。「体を低くするんだ!」
耳を貸す者などいなかった。オーツたちの周囲はもちろん、通りや敷地にいた全員がパニックに陥り、その場から離れようと一斉に駆け出したのである。2人の男はその背に向けて、平気で銃弾を撃ち込み始めた。走り出てきた警備担当者2名もたちまち蜂の巣にされる。2丁の銃から7.62ミリ旧NATO弾の空薬莢が規則正しく吐き出され、上がる血煙が敷地の空気までも赤く染め上げた。
自分の周囲だけでも落ち着かせようと声を張り上げるカッパーフィールドを尻目に、オーツは身を低めた姿勢で会議場ビルに走り出した。腰のホルスターから、撃鉄の隠れたステンレスフレームのS&W-M640リボルバーを抜き、左手首のタイメックスを見る。午後1時20分。国務長官はまだ会議場にいる筈だ。
オーツの意図を察したカッパーフィールドも、自分が何のためにこの場にいるのか思い出した。オーツを追う。2人の走る方角にも、旧NATO弾は容赦なく飛んできた。左右を逃げる職員たちが次々と血煙を上げて倒れ、2人の背中も何発にも掠られる。
小銃と機関銃にその場を任せ、その場を離れた黒キャップの東洋人は、残り2人を引き連れ、歩き出した。加盟国国旗のはためくポール群の横をゆっくりした足取りで、会議場ビルに向かって…。
…本物の大理石が敷き詰められ、四方八方に彫刻が並ぶ会議場ロビーに飛び込んだオーツに、同僚から声が掛かった。「オーツ! 無事か!」
表程の騒ぎではないが、ここでも職員や団体観光客が悲鳴とともに逃げ回っていた。その声に負けじと、オーツも怒鳴る。「俺はいい! 長官のところに!」
「もうすぐこっちに下りてくる! 車が要る!」
「裏に回せ!」
同僚1人が階段を駆け上がり、駐車場に通じる非常口に駆け去った。もう1人の同僚マキャフリーがオーツの横に並び、カッパーフィールドも追い付いてきた。オーツはマキャフリーに、ロビー内の避難誘導を指示した。手に手にコルトのポリス・ディティクティブ・リボルバーを構えた守衛や警備担当者7人が、会議場の正面玄関に向かっていった。
大騒ぎだな…、セネガル国旗のバッジをつけた大使が、フランス語で喚き散らしながら護衛たちと走り去るのを見送りながら、オーツは思った。それでも総会が開かれている最中でなくてよかった。もし最中なら、総会議場から雪崩れ込む各国大使や護衛でロビーは溢れ返り、テロリストが入ってくる前に悲惨な状態になりかねなかっただろう。
カッパーフィールドが言った。「長官は上か」
「もうすぐ下りてくる。今、裏手に車を回すように言った」
「糞っ! どこのイカレ野郎どもだ!」
吐き捨てたカッパーフィールドは、ロビー隅の公衆電話に走った。入れ替わりに、人々の避難誘導を終えたマキャフリーが戻ってくる。「どんな奴らだ?」
「俺が見たのは5人だけだ。東洋人が指揮してる」
外ではまだ銃撃が続いているようだ。その音の合間に、電話を架けるカッパーフィールドの声が聞こえる。「…だから国務長官がここにいるんだよ! 出動可能なHRTはいないのか? RRFでもいいぞ! 何? 大統領命令がないとここには入れない? 馬鹿野郎、その辺は機転を利かせて…」
近いところで銃声がした。数十枚のガラスが砕け散り、床に落ちる音も。正面玄関のガラスカーテンウォールが掃射を浴びたのだ。カッパーフィールドは受話器を叩きつけ、電話前の彫刻の陰に隠れた。オーツたちも別の彫刻を盾にした。警備担当者たちの撃ち返す銃声も聞こえる。しかし自動小銃のフルオート射撃音の後、撃ち返していた銃声はあっさり沈黙した。
こっちに来る! 身を固くしたオーツの耳に、聞き慣れた声が聞こえてきた。同僚たちだ。国務長官も一緒らしい。
タイミング悪すぎだ…、階段を振り仰いだ時だった。
国務長官と8人のシークレット・サービスを押しのけながら下りてきたのは、黒のコンバットスーツにヘルメット、防弾ベストに身を固め、HKサブマシンガンを構えた十余名の男たちだった。オーツは一瞬、デルタフォースが突入してきたものと思った。しかし先頭を走るのがライリーだとわかり、仰天する。男たちの正体とライリーの前身とが瞬時に判明した。全人類の平和の象徴たるこの施設にも、ちゃんと対凶悪犯罪部隊と思しきものが存在したのだ。
男たちは訓練された素早さ、無駄のなさで、オーツの周囲に散開した。同時にテロリストがロビーに入ってきた。やはり黒のタンクトップ姿、中肉中背で、ラテン系の血が濃いと思われるそいつは、ロビーを一瞥し、ニヤリと笑った。両手で構えたSIG-SG550ライフルの銃口が上がる。
5.56ミリNATO小銃弾が大理石の壁や床を穿ち、数体の彫刻を削った。同時に対テロ要員たちが撃ち返す。オーツとカッパーフィールドも数発を撃った。閉ざされた室内で響いた十数丁の銃声は、落雷の轟音をロビーに残した。オーツは止まない耳鳴りに顔を顰めた。
ラテン顔のテロリストは少なくとも20発以上の銃弾を浴びていた。タンクトップ以外身につけていなかったそいつは、血を噴き出し、あっさりその場に横転した。
やったか。オーツは彫刻の陰から倒れたラテン顔を窺った。ライリーの声が何かを命じ、対テロ要員2名が立ち上がった。ラテン顔に近づこうとする。
撃たれた箇所の多さの割に、出血が少ないな…、そんなことを考えた時だった。
「………!」
オーツは己の目を疑った。
20発もの弾丸を食らったとは思えない俊敏さで立ち上がったラテン顔が、SG550を乱射したのだ。防弾ベストに護られていない下腹部に銃弾を受けた対テロ要員2人は、体をくの字に曲げて吹っ飛んだ。オーツの周囲で再度銃声が轟いた。9ミリパラベラム弾はラテン顔の脚、腹、肩、胸へと次々と命中した。
それでもラテン顔は、今度は倒れなかった。薄笑いを浮かべ、自動小銃の乱射を続け、悠々と弾倉を交換し、次々と対テロ要員を撃ち倒していく。乱射のようでいて、ちゃんと防弾ベストを避けた下っ腹や、強化繊維のヘルメットを避けて顔を狙うという周到さだった。
カッパーフィールドの撃った357マグナム弾が、ラテン顔の額側面を削った。一瞬顔をのけぞらせはしたものの、ラテン顔は平気で反撃を続けた。信じられんという顔でオーツを見たカッパーフィールドは、もう一度狙おうと彫刻の陰から上体を出したと同時に上体に小銃弾を食らった。彫刻の向こうに引っ繰り返って消える。
いくら如才ない彼でも、銃弾を避けるのは無理だったようだ。
対テロ要員も3人に減っていた。階段の上では伏せたままの国務長官たちが動けないでいた。同僚数人も撃たれたようだ。
乱射を続けるラテン顔の背後から、あの眼鏡の東洋人が、別の1人を従えてロビーに入ってきた。マズい。このままでは長官が…。オーツは近くにいるマキャフリーを振り返った。目で合図する。俺が長官のところに走る。援護しろ。
マキャフリーが頷いた。オーツは飛び出すチャンスを窺った。階段の上に行けるか、或いは撃たれるのが先か。
東洋人が押し殺した嗄れ声で命じた。
「エジムンド。上には誰も通すな」
「了解」
東洋人はもう1人とともに階段に歩いた。階段手前の彫像の陰に隠れた対テロ要員2人が、サブマシンガンを構えていた。1人はエジムンドと呼ばれたラテン顔を狙い、もう1人は近寄ってくる東洋人を待ち受けていた。ライリーだ。オーツの側からはそれが見えたが、東洋人からは見えない角度だった。その筈だった。
しかし眼鏡の東洋人はそれを悟った。
次に瞬間、オーツは再度、自分の目を疑った。
東洋人の姿が、オーツの視界の中でブレたのである。残像を残したまま移動したのである。
試合に出て勝てるとは思っていたわけではないが、動体視力はプロボクサーにも匹敵すると言われたことがある。そのオーツの目に、そんな風に見えるということは、東洋人が尋常ではない速度で動いたことを意味した。現に東洋人が10メートルは離れた彫像の前に立つのに、0.数秒掛かっていたかどうか。そして東洋人の次の一連の動きは、オーツの目を以ってしても捉えられなかった。
一閃した脚が、大理石の彫像を叩き割った。その勢いで、対テロ要員1人の頭を蹴り砕く。頭はそのまま胴体から千切れ、飛んだ。慌てて彫像から離れたライリーに追いつくのは造作もなかった。正拳突きがライリーの頭を、ヘルメット毎粉砕した。
噴き上がる血飛沫の下、頭部を失ったライリーの体が東洋人の足元に崩れ落ちた。
オーツは未だ、東洋人が何をしたのか掴みかねた。しかし確かなことが2つ。2人の対テロ要員を片付けるのに、東洋人は銃どころか、ナイフさえ使わなかったのだ。特に正拳の破壊力。SIGライフルを撃つエジムンドすら直に狙うのを避けた、ケブラー繊維で編まれた強化ヘルメット。それを粉砕した破壊力は、8ミリ口径のマグナムライフルを凌いでいるかも知れなかった。
東洋人は何事もなかったかのように歩みを再開した。その足が階段に掛かった瞬間、オーツは飛び出していた。
何としても奴を止める、頭にはそれしかなかった。辞表のことが度々念頭を掠めるとは言え、オーツは優秀なシークレット・サービス特務員だったし、仕事に誇りを持ってもいたのだ。走りながら東洋人にM640を向ける。同時に背後で銃声がした。マキャフリーの悲鳴が上がり、オーツは腰に近い背中に爆発にも似た衝撃を受け、その場にもんどり打った。
キャップを目深に被った東洋人はオーツに一瞥もくれず、階段を上り始めた。彼の周囲に陽炎にも似た、空気の歪みが生じて見えたのは、気のせいだったろうか。アポロキャップを被ったもう1人が、いかにも嫌々と言いたげに背後に続いた。アポロキャップの下は禿頭のようだった。背中には大きなリュック。そいつの方はチラリとオーツを見遣った。
キャップの庇になったその目は猛禽類を思わせた。鷹か鷲の眼だ。その目が言っていた。気の毒にな。相手が悪かったんだよ…。
2人は階上で震える国務長官と、その背にのしかかるように彼を護ろうとする特務員を無視して、そのまた上にある4階渡り廊下へと歩き去った。それを見届けたオーツの全身から力が抜けた。奴らの狙いは国務長官ではなかった…? 左腰が燃えるように熱い。しかも両足が全く動かない。自動小銃弾を2発は食らってしまったようだ。しかし痛みなどまるでない。疼くのが腰ではなく、治療中の歯というのはどういうわけだ。
気が付くと、ラテン顔の乱射魔エジムンドが目の前に立っていた。全身からの出血に、未だタンクトップは濡れていた。しかし血の乾き始めた裸の腕や肩の銃創は既に存在しなかった。塞がってしまっていた。カッパーフィールドに撃たれた額の側面もだ。
その瞬間、オーツは悟った。こいつが…、
こいつらが、あの、噂の、不死身兵士の軍団だ…!
顔を引き攣らせたオーツは、手にしたままだったM-640の銃口をエジムンドの顔に向けていた。撃つ。
38口径125グレインの半被甲ホローポイント弾はエジムンドの頬に、強烈すぎるパンチを見舞っていた。頬の肉が消し飛び、血と肉の欠片がオーツの顔にも飛び散る。
しかし顔を仰け反らせこそしたものの、エジムンドは倒れもせず、オーツを見下ろした。3分の1の肉を失い、鉛の滓が付着した顔を近づけてきて、物凄い笑みを浮かべる。
「痛いじゃねえか、ええ?」
声もなく見返すオーツの目の前で、その傷はたちまち乾き始めた。血管が傷の上でのたくり、筋細胞がその周辺を覆い始めるのを見たオーツは、今度こそ悲鳴を上げた。
エジムンドはそのオーツの頭に、SG550の銃口を向けた。「お返しをしなくちゃ、な」
銃口はオーツの左手で上がった。続けざまに3発。側頭部に357マグナム弾を食らったエジムンドは、流石にその場に横転した。脳にまで達したのだろう。眼球が半分飛び出していた。
カッパーフィールドが倒れたままの姿勢で、M-19を構えていた。
「だい、じょうぶ、か?」
苦しげな息の下、そう言ったカッパーフィールドは、咳き込みながら鮮血を吐いた。上体を起こすと白いワイシャツが真っ赤に染まっていた。小銃弾が肺に穴を開けたのだ。「そっちこそ、大丈夫そうには見えないぞ…」
「痛いぜ、畜生…」
何とか立ち上がったカッパーフィールドが、よろめきながらオーツに近づいた。M-19は左手に構えたままだ。恐怖冷めやらぬ顔で、倒れたエジムンドを見つめている。「何てバケモノだ、こいつ…」
「ここまでやらなくちゃ、死なないかよ」
オーツが撃たれたのは腰椎らしかった。腰から下は完全に動かない。今頃になってようやく、耐え難い苦痛による苦悶が始まった。カッパーフィールドも重症だったが、それでもオーツを抱えようと踏ん張る。その時になってやっと、階上で震えていたオーツの同僚たちが国務長官を連れ、下りてきた。
「助かった。手を貸してくれ」
カッパーフィールドの言葉に、無事だった5人のうち2人が左右からオーツを抱え起こした。警護対象至上主義の原則も、今の彼らは忘れていた。通常なら懲戒処分ものの失態だが、恐怖に震えカッパーフィールドに頷き返すのが精一杯の今の国務長官は、そんなことなど覚えていないだろう。残る3人がそんな長官を引きずるように、非常口に向け歩き出す。オーツが顔を上げた。階上の彼方で銃撃戦が始まったようだった。銃撃戦と言っても、あの東洋人相手では、撃っているのは護る側のみだろうが。同じくそれに耳を止め、振り返っていたカッパーフィールドがぐうっと喉で呻いた。
どうした…、2人の同僚とともに同じ方を見たオーツも、痛みを忘れた。
血溜まりに倒れるエジムンドの体が痙攣を始めていた。取り落とした自動小銃を探して手が蠢き、立ち上がろうとして膝が床を蹴る。やがて動きは活発になり、じたばたともがくエジムンドが起き上がるのは時間の問題と思われた。死なない…。
こいつは本当に死なないのだ!
沈着なカッパーフィールドが遂に血塗れの悲鳴を上げた。オーツを支えた2人の同僚が、口々に祈りの言葉を呟き始めた。オーツは2人とカッパーフィールドを急かした。無様な足取りで血みどろのロビーを後にした4人の耳に、サイレン群の音が届いた。ようやくNYPDの援軍が到着したようだった…。
…長大な渡り廊下を悠々と歩く眼鏡の東洋人を、対凶悪犯罪部隊の第二陣が出迎えていた。
東洋人を一瞥した指揮官が鼻で笑った。あんなトロそうな男がテロリスト? おまけにあいつ、素手ではないか。
号令一下、東洋人が30メートルまで近づいたところで、第二陣16名はさっと散開した。8名が前に飛び出して伏せ、残り8名がその場で膝をつき、それぞれの銃を構える。
しかし発砲の寸前、東洋人は既に16人の間に割り込んでいた。正拳が、手刀が、回し蹴りが、部隊員たちの腕を、脚を、首を、背中を、へし折り、頭蓋骨をヘルメット毎砕き始めた。点々と返り血は浴びるものの、目の前で発砲される銃弾を軽々と躱し――そう、体を左右に振って、発射された銃弾を躱すのである――、息一つ乱さず、眼鏡もずらさず、要員たちを屠る東洋人が、嗄れ声で怒鳴った。
「行け、瓜生!」
やる気なさげに渡り廊下への入り口にたむろしていた、禿頭にアポロキャップの男は、仕方ないなと言いたげにリュックを背負い直した。走り出す。物凄い速度だった。50メートルを2秒足らずで駆け抜けたそいつは、対テロ要員の殴殺を続ける東洋人を避けるようにジャンプ、渡り廊下の壁を蹴って全員を飛び越えた。壁を走ったようにも見えた。唖然とした顔で見送った指揮官の前に…、
東洋人が立っていた。
眼鏡の下の丸顔は無表情だった。だが肩から立ち上る陽炎が、発する殺気であるとはすぐにわかった。東洋人が最初全く怖く見えなかった理由が、指揮官にもやっと理解できた。事故にせよ病気にせよ、死とは大仰な顔で訪れるものではない。さり気なく、いつの間にか、側に立っているものだ。気づいた時には遅すぎるのだ。まさにこいつと同じではないか。
自分は今、死と向い合っているのだ、と。
その喉笛を、東洋人の貫手が頚椎毎破壊した。
結局1発の銃弾も浴びることなく、16人と指揮官を10秒足らずで片付けた東洋人は、バンダナのハンカチで血に汚れた手を拭い、額や頬の返り血も拭き、最後まで悠々と踵を返した。アポロキャップの禿頭、瓜生の背負うリュックには、高性能爆薬HMXをベースにしたプラスチック爆弾20キロが詰め込まれている。奴がこの本部ビル主要箇所にそれら全部を仕掛けて回るのに、恐らく15分。それだけあれば、この作戦における本来の標的どもを片付けて回るには充分だろう。東洋人は眼鏡を直し、キャップをかぶり直した。もう少し運動してから帰れそうだ。薄い笑みを浮かべ、歩き出す。自分の素手を手こずらせる相手が出現することを密かに願いながら…。
…一方、百人近くの死体が転がり、7.62ミリ旧NATO弾の薬莢が少なくとも一千発分は散らばった敷地では、未だ2人の不死身兵士の乱射が続いていた。
パトカー6台が穴だらけになり、2台が燃え上がった。制服警官16名が射殺された段階で、ニューヨーク市警は彼らだけでは最早手に負えないと悟った。市内からマンハッタン島に、フォード社製の黒塗りワゴン6台、ベル社製ヘリコプター、ヒューイコブラが急行した。乗り込むのはNYPDのSWATチームだ。
到着したワゴン車は、不用意に敷地に近づくことはしなかった。パークハイアット・ホテルとユニセフハウスの間にて、紺のシャツのSWAT隊員たちを降ろす。レミントンM-700ベースのM24ライフルを手にした狙撃班隊員3人が、ホテル裏口から1階にあるカフェに飛び込んだ。客やウェイトレス、マネージャーまで全員が逃げ出した店内は、流れ弾で滅茶滅茶だった。3人はテーブルを窓辺に運び、それを盾に外を狙う。
ホテル外では他の隊員が、コルトM-16A2ライフルやウージーサブマシンガンを構え、穴だらけにされたパトカーや一般の車に隠れながら、テロリスト2人に接近を試みていた。その間、敷地に立つ2人を、ヘリコプターが牽制しようとする。だが、許可が遅れている今、敷地上空に入れないヘリは同じ場所を動き回るしかなく、M-60とFALの弾幕で接近を阻まれてもいた。
もちろん2人が、地上から接近を試みるSWATに気づかない筈がない。特殊部隊が動き回るには、敷地の周囲は遮蔽物がなさ過ぎた。晴れた空にぽっかりと浮いた雲一つが、まだ高い日を翳らせた。それを合図に、M-60を構えた方が咆哮を上げて進み出た。SWATに向かって撃ちまくる。7.62ミリ旧NATO弾は狩猟用にも使われるライフル弾でもある。既に穴だらけにされ、燃えたスクラップの車体など簡単に貫通する。たちまち2名が被弾したSWATは、各々の銃を撃ち返しながらホテルにまで後退した。その数発が、M-60の男に当たる。
撃たれた男はよろめきもせず、痛そうな顔どころか気にする風もなく、汎用機関銃の乱射を続けた。体のあちこちから噴き出した出血もすぐに止まってしまう。SWAT隊員たちは知った。あの2人がこんな場所で凶行に及びながら、警官たちに射殺されなかった理由を。
七、八百発を既に発射しているM-60の銃身は薄煙を上げていた。最早、着弾点もばらばらだ。旋条も灼けてしまっているのだろう。しかし男にも、流石に銃身を交換する暇はないようだ。ベルト弾倉を替える時こそ、FN・FALを撃つ仲間に乱射を任せるも、一時退却という選択肢さえ念頭にないようだ。
そこでようやくSWAT隊員たちは悟った。こいつらの目的は、我々の牽制だ。だとすれば真の目的は建物の中だ。
その時、市警本部長からの通達が全隊員に伝えられた。市長が大統領要請を受け取った。敷地内への立ち入りを許可する。隊員たちは勢い込んだ。陽動らしい2人を射殺せよとの指令が、カフェの狙撃班にも伝わった。
競技用弾丸M118は最低限の誤差で、2人を撃ち抜いた。頭、首、胸と、3人の狙撃手から各2発ずつ。流石の2人もその場にぶっ倒れる。
カフェの割れた窓から、標的2人が動かないのを確認した狙撃班3人は快哉を叫んだ。その1人の頭が、西瓜のように砕け散った。丸1秒、同僚2人は何が起きたのかわからず、立ち尽くした。銃声はその後に聞こえてきた。
自分たちも狙われている? しかも銃声の遅れ具合から見ても、狙撃手は優に1キロ以上離れた場所から、こっちを狙っている。現に3時間後の捜査により、銃弾――口径300のウィンチェスター・マグナムライフル弾――はホテルの正面にそそり立つ本部ビルの、そのまた遥か左彼方1400メートル先、ルーズベルト・ドライブが地上に出る辺りに停めた車から発射されたとわかった。空薬莢は残されていなかったが、コンクリートのガードレールに付着した硝煙滓が発見されたのだ。
残り2人のSWAT狙撃班は、我に返り身を低くする間も与えられなかった。1発目の銃声が届いてすぐに2人目の、そして2発目の銃声が届く前に3人目の顔が吹っ飛ばされた。
狙撃は他のSWAT隊員をも襲った。敷地の2人が倒れたのを確認し、ホテルから飛び出した3人が、次々と300マグナムの餌食と化す。市内ビル街を旋回して戻ってきたヒューイコブラも、敷地上空に現れざま燃料タンクに穴を開けられた。SWATの追跡の花形ヘリも、こうなってはただのお荷物でしかなくなった。火だるまになって墜落しようものなら、更に大きな犠牲を出しかねない。結局ほとんど何も出来ないまま、隊員8人を無駄に殉職させられ、総員撤退した。
胸の真ん中と頭を撃たれたFALの男が回復するには、丸々3分を要した。頭を振り振り立ち上がったそいつは、〈ポリス〉のベーシストにも似た顔に苦み走った苦笑を浮かべ、短く刈った髪にべっとり付着した血を掌で拭いた。ルーズベルト・ドライブの方に向け、小さく手を振る。敷地の路上に脱ぎ捨てたコートから、呼出音が鳴っていた。ポケットから出した通信機は、ZIPPOのミニサイズと同じ大きさしかなかった。
「マクレガーです」
“ご苦労。”押し殺した嗄れ声が、肉声と聞き紛う程の明瞭さで聞こえてきた。“こっちの始末は完了した。引き上げだ。”
「コゾフスキーが動きません」
M-60射手の方は、痙攣を繰り返すばかりで立ち上がれずにいた。首に命中したSWATの弾丸が、延髄にまで達したものと思われた。回復には後30分は掛かるものと思われた。仕方ないな。そこまでは待てない…。嗄れ声は言った。
“いつも通りだ。”
「了解。相馬に連絡は」
“あれが仕事を終えた後に居残っていると思うか? お前を援護した1分後にはきっちり逃げた。”
あの野郎。手なんか振って損したぜ。同じ日本人なのに、若林とはえらい違いだ…。FALの男――マクレガーは、白皙の顔をほろ苦い笑みに歪め、通信機と入れ替わりに、掌サイズの金属箱を取り出した。アルミ合金製のそのケースは立派な防弾性能を持ち、ピンポン球そっくりな白い球体を収めていた。マクレガーはそれをM‐60射手コゾフスキーに咥えさせた。
M14焼夷弾をベースに作られた超高熱火薬だ。タイマーにて点火された後、三千度の熱が1分は続く。コゾフスキーの肉体が微粒子の灰と化すのに、15秒。マクレガーの姿は既にその前から消え失せていた…。
…マンハッタン島東部、イースト川に面した国連本部ビルと総会議場にて大爆発が起こったのは、それからちょうど5分後のことだった。
周辺は直ちに閉鎖され、ニューヨーク市長の要請を受けた陸軍が、フォート・ドラム基地から軽歩兵師団、ウェストポイント基地から装甲車6台を出動させた。カッパーフィールドから連絡を受けたFBIも、人質対応部隊HRTを派遣してくる。しかしNYPDとの合同で行われた彼らの3昼夜に亙る捜索も、結局は無駄に終わった。5人のテロリスト、いや、超人的な兵士たちは、暴れるだけ暴れた後、仲間1人の死体を完全に焼却し、痕跡一つ残さず鮮やかに消えたのである。
犠牲者は当日発表だけでも九百人を超えた。恐らくもっと増えると思われた。射殺されたり爆発に逃げ遅れた国連職員や各国大使や外交官ばかりではない。訪れていた見学の観光客、たまたま近くを通った市民も巻き添えを食った。惨事はこの年最大のテロ事件として、年末まで各国のテレビ番組に取り上げられた。
合衆国政府は事件を狂信的イスラム過激派によるものと断定し、イラクへの経済制裁を強化、数度の空爆に踏み切った。イラクはイラクで、身に覚えのないことだと反論、爆撃された病院などを全世界のマスコミに公開し、アメリカが如何に非人道的国家かを口に泡を飛ばして訴えた。しかしいつものことながら、マスコミの論調も日を追う毎に勢いを失い、新しい年を迎える頃にはその話題も、誰の口にも上らなくなってしまっていた。
実害を受けたシークレット・サービス特務員ネイサン・オーツたちの悪夢の中に登場することはあっても。
その事件が、主要国首脳たちを震え上がらせるある組織によるものであり、彼らが前年から起こしていた主要各国でのテロ事件の、謂わば集大成であったことを知る者は、世界でもほんの一握りしかいなかったのである…。
超人旋風記 (1)


