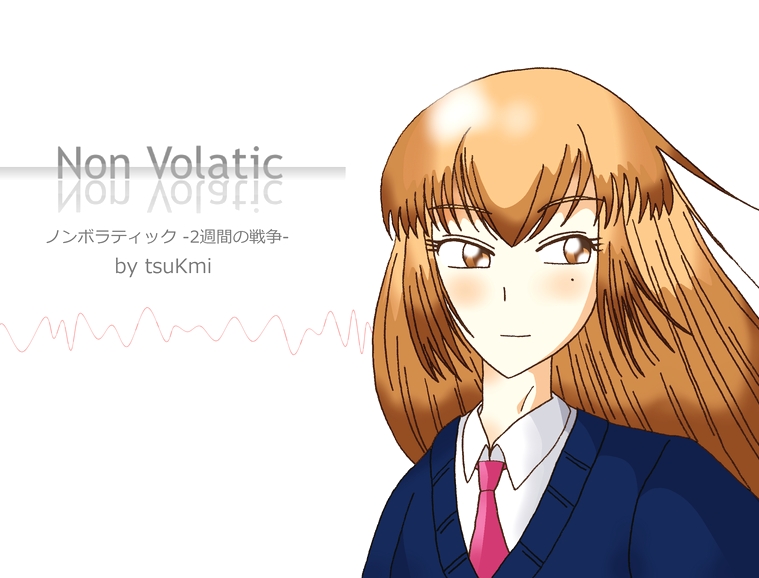
ノンボラティック 2週間の戦争 前編
プロローグ
月明かりに照らされ、数人の集団がそこには居た。
望遠鏡から見える彼らの行動は、恐怖で目撃者の手を大きく震わさせ、目撃者はその震えを止めることができなかった。
季節は秋だったが、空気は寒さで張りつめている。その日の夜は全てが凍ってしまうと思えるほど冷たかった。
目撃者と彼らとは、川を挟んで二百メートルほど離れた距離だ。目撃者は枯れた幾本もの葦の隙間から、恐怖で震えながら望遠鏡の中で起きている出来事を見続けていた。
望遠鏡の中の彼らは、ワンボックスと思わしき車の中から、二人の子供、それも小さい子供らしき影を脇で抱え、彼らが掘った穴に乱暴に投げ入れた。「どさっ」という鈍い音が聞こえてくるような気がした。その子供のような影たちは、乱暴に穴へ投げ入れられても、何も声を発することはない。
死んでいるのではないか、または殺された人間なのか・・・。
目撃者にはそう思えた。
目撃者は恐怖の余り、自分の記憶が確かでなくなってきているような気がした。目の前の光景を現実に起きていることとして認めたくなかった。
そして次に彼らは大人の影を乱暴に車から引きずり出し、そのまま穴に落とした。その影もまた何も抵抗する様子がない。それが二回繰り返された。
リーダー格の人間が周りの人間に指示を出した。数人の集団は手際よく、その四人の遺体を捨てた穴を埋め、枯れ草をまき、偽装を行った。
許させない光景だ。
目撃者は強い怒りを感じていた。おそらく自分達が殺害した人間を何の尊厳もなく、もののように捨てているのだ。許せる訳がない。だが、目撃者は動かなかったし、何もしなかった。恐怖に心が支配されてしまっていたのだ。
望遠鏡の中の彼らはひと段落して安心したのか、ふざけ合い、笑っているようだった。が、それを制止する人間、もしくは疑問を唱える人間が現れたのだろうか、やがて仲間内の一人にリンチを加えているような状況となった。
しばらくリンチは続いていた。
それを見ていた目撃者は、気持ちが悪くなった。
リンチが終わった。だが、その対象だった人間は全く動かない・・・彼はワンボックスの荷台へ雑に放り込まれた。
目撃者は今日この場所に星を見にきたことを後悔していた。ワンボックスで乗り付け、ヘッドライトの明かりを頼りに穴を掘り始めた奇妙な集団の行動を覗いてしまったことに後悔をしていた。
時間の流れが異常に遅く感じられた。
エンジンを掛ける音が聞こる。そして扉を開け、乗り込み、扉を閉める音が聞こえ、車は過ぎ去って行った。
目撃者の震えはまだ止まらない。そして今見た光景が夢であることを願った。
第1章
大木は足元から続く雪の斜面をじっと見ていた。
昨日の大雪の反動か、気温は予想以上に上昇し汗ばむほどだ。春の太陽が雪に反射し、その光はゴーグルをしていても眩しい。大木はスキー板の反発具合を足で何回か確かめ、左右両方のストックを前方に刺し、スキー板後方を跳ね上げ、一気にコブ斜面を滑り始めた。
コブが次々に迫ってくる。体重を前方に預け、膝でコブを吸収し、板で削る雪を最小限にし、コブの斜面を下る。
大木はモーグルスキーが好きだった。初めてスキーを履いたのは幼稚園の頃だから、高校二年のこの冬でもう十二年スキーをやっていることになる。モーグルの腕は、既に日本選手権で表彰台に上るレベルになっていた。
悪くない。
つぎつぎに迫ってくるコブを処理しながらそう思った。そして先日まであった全日本チームとの合宿を思い返していた。
勉強になった。だが、それほど自分との技術の差は大きくない。
そう思った瞬間にまた一つコブを超えた。
来シーズンは自分も世界を転戦するような人間になっているかもしれない。だが、そのときは自分のもっている障害がきっとまた問題になる。
スキー連盟の理事達の発言は大木にとって好ましくないものばかりだった。大木はそのことを思い出し、怒りを抑えるかのようにストックを強く握った。
コブを次々にクリアし、斜面が終わり、大木はエッジで雪煙を立て滑る板を止めた。そして斜面を振り返り、自分の今しがたの滑りを考察した。
悪くない。
再びそう思った。
スキー連盟のあの理事たちは大木に否定的だ。大木の成績は文句なしの成績だったが、大木の障害を持ち出し、彼の選手資格に関して昨シーズンは一騒ぎを起している。大木にはそれが差別に感じていた。
「調子がいいな、大木君」
後ろから声がした。
先に滑り下りて、大木が滑る様子をビデオに撮っていた西原だった。このスキー場のスクールの指導員で、大木が小学生のときから世話になっている。昔はモーグルの上級選手だったらしい。
「ちょっと雪が重くて引っかかりましたけど、調子は悪くないです」
高校生らしいハキハキした返事をした。少し芝居がかっている感じもしたが、大木は昔からそんな感じだ。
「そっか、もう春だからな」
そういって西原は黙って大木が滑ってきた斜面を見返した。しばらく斜面を見ていた。
じっと見ていた。
まだ見ている。
そして大木が長い沈黙に耐えられなくなったそのときに、西原の携帯の呼び出し音が鳴った。人を焦らすようなけたたましさにも関わらず、西原はゆっくりとグローブを外し、胸のポケットから携帯電話を取り出し電話に出た。
西原は相手の話を黙って聞いていたが、すぐに緊張した険しい顔つきになった。そして電話を切った後、
「兎原ゲレンデで雪崩が起きたよ」
とぽつりと告げた。大木は驚いたように西原の顔を見た。
昨日の大雪に加え、今日のこの異常な気温上昇が原因か・・・。
西原は言葉を続けた。
「今、人手を集めている。助けてくれないか? 二人遭難したらしい」
だが大木は黙って下を向いた。さっきのハキハキした様子は何処にもない。まるで別人のようだ。
西原は言った。
「難しいか? お前、四条電機とプロ契約を結んでいるもんな」
「いや、そういう訳では・・・」
大木は答えた。
「僕は・・・障害があるから・・・」
はっとした。大木が苦笑いしているように見えた。
やはり気にしているのか・・・。
スキー連盟ともめていることは知っていた。西原は大木の力になりたいと考えていた。そして彼は大木の滑りを世に出すべきだと強く思っていた。
彼のモーグルスキーは人に勇気を与えてくれる。実際、俺も彼の滑りで相当に元気付けられたんだ・・・。
西原は頷いた。
「いろいろ言われているかもしれないけど、気にするな。お前は俺らの仲間だ。どんなときでも味方になる。それにお前のスキーは本物だと本当に思うぜ」
西原は大木の左肩をポンと軽く叩いた。
「妬む人間はどこにでもいるし、消えることはない。ただ、俺らはみんな君のことを応援している。大木は俺らの仲間だからな」
西原は「仲間」という言葉を二回使った。大木に前から伝えたい言葉だった。
西原の言葉は大木の心に訴えるものがあったのか、大木はやがて頷き、スキーを滑らせ、雪崩のあったゲレンデに向かった。
西原は大木を小さい頃から見ていた。大木のスキーの才能は群を抜いていたし、それは今期の大会の成績からも分かる。その彼を執拗に追い詰めているスキー連盟の理事たちの言動に疑問を感じていた。そして子供のころから持っている彼の前向きで明るい性格を封じ込め、ストレスを掛けているこの状況に同情と怒りを感じていた。
太陽が眩しい。
西原は大木の後を追い、スキーを漕ぎ、滑り、風を受け、雪崩の起きたゲレンデに向かった。
加奈子は風邪で倒れていた。
朝から寒気がして頭も痛い。熱を測ると三十八度を越えている。学校にとても行ける具合ではない。すぐにでも病院に行きたかったが、予約が取れず午後の診察になってしまっていた。春も近いというのに病院は暇にはなっていないようだ。
「はあ・・・」
加奈子は溜息をつきながら居間のテーブルの椅子に座った。
母親はいつものように加奈子が起きる前に仕事に出掛けている。父親は加奈子が中学の時に病気で他界しており、今はこのK地方の小さな都市で弟と母親の三人で暮らしていた。
テーブルの上には母の作った朝食が置いてある。だが、今の体調の悪さからとても食べる気にはなれない。加奈子はメールで熱が出ていること、高校は今日を休むこと、午後に病院に行くことを母親や友人に伝えた。
また具合が悪くなったような気がするわ・・・。
同じ高校に通っている弟が家を出た後は、家は物音一つしない静かな空間に変わる。熱がある状態で、自分だけ家に一人という状況は寂しさを感じさせるものだ。
熱で辛く、テレビも見たくなかったし、音楽も聴きたくない。こんなに具合が悪いのに、家に一人きりだなんて・・・。
体調が悪い上にだんだん気が重くなってきた・・・。
加奈子は蒲団に戻り少し眠ることにした。
寂しいわ・・・。
ゆっくり目を閉じる。病院の自分の診察時間まであと三時間以上もあった。外から鳥の鳴き声が聞こえる。ホトトギスのようだ。
携帯が振動し、メールが入ったことを伝えてきた。加奈子は蒲団の中から手を出し、携帯を手に取った。母親か、もしくは授業中の友人からの返事を期待していた。
加奈子は、携帯を開きメールの内容を読んだ。が、すぐに文字の多さに頭が痛くなった。
「凛の民、民族保存会・・・今週の凛舞踊の練習は中止・・・」
このメールか・・・。
もともと練習には出る気はなかったけど。
携帯をパチンと閉めてまた蒲団にもぐった。そもそも加奈子自身は凛の民ではなく、数合わせのために自治会から無理やり頼まれたものだ。やる気もあまりない。
それにここ最近の民族保存会の言動がおかしいのも、加奈子の関心対象から外れる理由でもあった。メールには凛の民を抑揚させる内容とか、本土批判が必ず書かれている。
何を考えているのか全く分からないわ。もう寝よ。
そう思った矢先に加奈子の携帯には次々にメールが入ってきた。今度は加奈子が返事を期待していた友人達だったり、母親からのメールだったりした。
彼女は暖かい気持ちになった。安心したためか、眠気が襲ってきた。小さな欠伸をして彼女は眠りに入っていった。
既に雪崩の遭難者の捜索が始まって一時間が経とうとしている。
大木はビーコンの反応のあったところや、竹を雪に刺して手ごたえのあったところの除雪の作業を手伝っていた。
遭難者は二人と見られ、一人はスキー場の救助スタッフが集まる前に既に一般スキーヤーによって救助されている。息は確認されており、助かりそうだという連絡が飛んでいた。
だが、もう一人はまだ見つかっていない。雪崩が起きて一時間という時間は、遭難者の生存率が四分の一まで落ちる。三十人はいる捜索スタッフの一人がそんなことを言っていた。
もう駄目かもしれない。
大木はそう頭の隅でぼんやり考えていた。
「いたぞお!」
突然、大木のすぐ後ろの中年のスタッフが大声を挙げた。
その声を聞いて大木は振り返った。そしてすぐに駆け寄り遭難者の周りの除雪を手伝いはじめた。スキーのウエアのようなものが見える。更に雪を掘り続けると、雪の中で丸くなっている若い女性が現れた。
「大丈夫ですか!、大丈夫ですか!」
大木は叫ぶように声を掛けた。
「はい・・・」
小さいながらも声が聞こえる。
周りに安堵の空気が流れた。雪の中で丸くなっていたことで空間が確保され、無事で居られたのだろうか?
「沙織は? 沙織は?」
遭難者はそんな言葉を発した。
「もう一人の女性の方ですか? 僕がこのゲレンデに着いたときにちょうど助けられたところで、ご自分で歩いているのを見ました。ご無事ですよ」
遭難者はまだ不安そうだった。少し取り乱しているようにも見える。
「ウエアの色は? ウエアの色は?」
大木は戸惑った。
「ウエアの色は? ウエアの色は?」
その女性の遭難者は同じ問いを発した。大木の戸惑う様子を見て明らかに苛立ち始めた。周りにいるスタッフは、初めの遭難者が救助された後に集まってきた人間ばかりだ。そのときのことは大木しか知らない。
もう一人を特定して無事を確認したいのだろう。だが・・・。
「濃い色でした・・・」
「だから、何色だったの!」
強い口調だった。パニックになる直前にも見えた。
橇が運び込まれる。そこに遭難者を乗せ、遭難者は毛布を掛けられた。そして橇はスノーモービルに繋がれる。
「あんた、色も分かんないの? 何色か聞いているのよ!」
遭難者は叫ぶように言った。
大木ははっとした。もはや何も言えない気がした。
「すみません・・・」
大木はそう言って言葉を続けた。
「僕の・・・僕の目は色を区別することが出来ません。僕は色覚障害を持っています・・・」
悔しそうな表情でそう呟いた。
苛立ち、騒いでいた若い女性の遭難者は、その言葉の何かに撃たれたように動きを止めた。そして大木の顔をじっと見つめた。
大木は言葉を続けた。その姿は辛く、苦しそうだった。
「俺の見る世界は・・・色が何もない世界です。全てが白黒の世界でしかない・・・」
そう言うと大木は膝を雪の上に落とした。平静さをもう装えない。涙がこぼれた。
そのとき・・・大木には世界が緑色掛かったものに見えた。白いはずの雪は薄い緑に、木々は濃い緑に感じた。但し人は白黒の像のままで、目の前の遭難者も例外ではなかった。
だがそれは一瞬で、また白と黒だけの暗く沈んだ世界に戻っていった。
気のせい・・・なのか?
重くなる気持ちの中で大木はそう思った。
目の前の遭難者は放心していたが、徐々に自分を取り戻している様子だった。彼女は言った。
「ごめんなさい・・・」
すぐに言葉を続けた。
「助けてくれてありがとう」
そしてゆっくりと目を閉じた。それを合図に捜索スタッフの一人がスノーモービルに乗り込み、遭難者が横たわる橇を引っ張って下山を始めた。
白い世界でスノーモービルの回転ライトが回り始める。警告音が鳴り、壮大な山の斜面でその音を何回となく反射させ、スキー場全体に響き渡たらせた。
大木は白い雪山の中でそれを静かに見送っていた。
加奈子の母親は、K地方西北の立原市にある四条電機の子会社の四条電機テクノで働いていた。一年前から工場の現場でプリンターの組み立てを担当している。
加奈子からのメールは午前の休憩時間に見た。風邪を引いて、熱が出て、学校を休んでいるといった内容だった。そして病院に行きなさいとか、蒲団で体を休めなさいとかの返メールを娘に打った。
そして携帯をパチンと閉じて「はあ」と溜息をついた。もうすぐ休憩時間が終わる。あの職場に戻らなければならないかと思うと気が重くなった。
四条電機グループは、親会社が絶対的な存在だった。四条電機の人間は人事的に優遇され、子会社に出向すると平社員でも管理職になる。加奈子の母親の上司も四条電機から来た人間だったが、十人いるチームは既に崩壊寸前の状態だった。
「犬山の言うことは聞けない」
そんな言葉がよく聞かれた。
毛嫌いされていた。
現場で生産の進捗を確認している彼に後ろからネジが飛んできたこともある。彼のノートがゴミ箱に捨てられていたこともあった。複数の大人が、子供がするようないじめを三十歳前の青年である彼に行っていたのだった。
前に犬山が廊下の壁に、右手のこぶしを勢いよくぶつけている瞬間を見たことがあった。誰もいないと思っていたのだろう。悔しさが背中から見て取れた。
それを見たとき、加奈子の母親は言いようのない理不尽さを感じた。犬山の行動は問題があるとは到底思えず、むしろ機敏に臨機応変に仕事をこなしている。一方でチームのメンバーは、極度に閉鎖的で仕事の遅い人間ばかりだった。
正義が通っていない。
そう思っていた。
加奈子の母親が事務所の入り口まで戻ったとき、事務所の異様な雰囲気になっていることに気が付いた。
「どうかしたの?」
加奈子の母親は近くにいた若い男の社員に聞いた。
「いや、犬山主任が、チームのメンバーともめているみたいで」
「え? なんで?」
加奈子の母親は意外な感じがした。
今までずっと犬山主任は我慢してきたはずなのに。
そして遠目に見える犬山とそのメンバーとのやりとりを見た。
「だから、なんで言ったことをしないのですか! それにあなたは生産に責任取れる立場じゃないでしょう。勝手に工程表を変えないでください!」
犬山は強い口調で話をしていた。
「だから、あんたの工程表じゃあ駄目なんだよ」
上司をあんた呼ばわりか・・・確かに犬山主任より七歳は上だろうけど・・・。
加奈子の母親はいつもレベルの低い会話をするこのメンバーに前から嫌気がさしていた。
「なにが駄目なんですか? 工程のコマ数は問題ないでしょう。納期も問題ない。工程の割り振りを何故責任を取らない人間が勝手に変えているのですか?」
犬山は今まで耐えてきた感情が一気に湧き出てくる感覚を覚えた。
「来たり者のあんたの言うことなんか、そもそも聞けないんだよ。しかもあんた、元々は営業じゃねえかよ。うるせんだよ、言うことなんか聞けるか!」
犬山はカチンときた。
ここの奴らはいつもそうだ。話にならない。だいたい「来たり者」というの言い方はなんなんだ。県外者のことなのか? 本土の人間のことなのか?
凛の民と称する彼らは、凛の民以外の人間を疎外し、身内で固まる習性があった。それはいつも犬山に不快感を与えていた。
怒りで犬山の顔が強張っている。
「これまでのあなたの仕事ぶりは、全く評価できるレベルにはありません。いつも何処かでさぼって仕事をしていない。それを棚に上げて、いったい何を仕切ろうとしているのです?」
相手の顔がみるみるうちに赤くなってゆく。加奈子の母親はまずいと思った。
この男は・・・この目の前で奇声を発している中年の男は、凛の民族保存会の青年部世話役だ。根に持たれるときっとやっかいなことになる。
「なんだとお!」
そう言って相手は逆上し、いきなり犬山の顔を殴った。犬山が倒れ、相手は犬山に馬乗りになり、一発、二発と犬山の顔を殴り続ける。
すぐに相手と犬山の間に人が入った。二人は引き離されていたが、犬山の相手は殺気に満ちた目つきで犬山を見ている。その様子を見て、犬山は背筋が寒くなる思いがした。
異常だ。この人間は異常だ。
そう思った。
加奈子の母親は嫌な噂を思いだした。
この地方に多く暮らす凛の民という日本の中の少民族・・・閉鎖的で独善的なところがあり、今の日本では特殊的な存在だわ。
その民族保存会は要注意者リストというもの作っていると聞いたことがある。どこでどう使われているかは知らないが、もし本当に存在していたとしても、決してまともな使われ方はしていないはずだわ。
加奈子の母親は不安に襲われた。きっと犬山はそのリストに名前を載せられ、トラブルに巻き込まれる。そういう予感がしたのだ。
そう、それが正しくないことであっても・・・。
加奈子の母親は不安を紛らわしたかった。この異常で陰気な予感を払拭したかった。犬山を見た。口を切ったのか口を手で押さえている。
嫌な予感が止まらない。加奈子の母親はこれから起こるだろう不条理を全て否定したかった。そしてそれが現実に起きないことを切に願った。
時計は夜の七時を回り、窓から見える外の世界は、星が無数に広がる世界に変わっている。
大木は自分の部屋で机を前に座っていた。目の前には高校二年用の参考書がずらりと並んでいるが、めったに使ったことがない。そもそもモーグルの大会や練習で、勉強どころか高校の出席自体もおろそかになっている。
各モーグルの大会での彼の成績は優勝、もしくはそれに準ずる成績を出しており、スキー雑誌に天才高校生モーグラーとして取材をされたこともある。昨年の秋には四条電機とプロ契約を結び、そのことは彼の自信を大きく高めるのに役立った。
選手としては順風満帆だ。
だが、スキー連盟の一部の理事は、大木の目は滑走に危険があると主張しており、実際、大木は大会出場の自主的な辞退を求められていた。大木はそれをストレスに感じていたが、四条電機とプロ契約してから、その強い風当たりは極端に少なくなってきている。
大人のずるさを見た気がした。
そして大木は昼間、救助したあの女性の言葉を思い出していた。
「色が分からないか・・・」
大木は唇を強く噛んだ。悔しい思いが溢れてくる。
小学校のときは色が見えていた。ただある日突然、大木の目は色を区別することが出来なくなった。いつからなのかよくは覚えていない。
目を閉じるとあらゆる色を思い出す。鮮明な赤、透き通るような青、生命にあふれた緑を・・・。
自分の頭の中には溢れんばかりの色があるというのに、目の前の現実は白と黒の虚脱を思えるような活気のない世界だった。
大木は窓を開け、夜空を見た。幾千幾万もの星が輝いている。
たまに星が降るような本当にきれいな夜空を見ることがある。
だけど今晩の夜空は違うな・・・。
そう思った。
「それにしても、あの一瞬見えた緑の世界はいったい・・・」
一時的に緑の色覚だけ戻ったのだろうか・・・。
考えても分からない。
少し寒くなってきた。窓を閉め、自分の机に座り直すとノートパソコンでメールのチェックを始めた。四条電機から四条電機スキー部との合同練習の誘いのメールが来ている。暖冬で雪が少なかったためか、少し早くK地方での基礎体力作りの合宿が始まるらしい。
昨日ドカ雪はこの気温ですぐ溶けるだろうし、既に雪は重くなっている。ちょうど春休みの期間だ。
「立原市か・・・」
そして、あれこれ考えるそぶりを見せて、頷き、決断して階下の居間に下りていった。
ソファに座ってテレビを見る大木の父親が見えた。
「父さん、この春休みに四条電機のスキー部の合宿に参加するつもりなんだけど、いいかな?」
父と呼ばれたその男はゆっくり振り向いた。
「ん? 場所は?」
「場所はK地方の立原市だけど」
「立原市?」
少し怪訝な顔をした。
「止めといた方がいいと思うよ。なんか不景気で治安が悪いみたいだし」
そう言ってテレビを指差した。大木はその指の先のテレビに顔を向けた。
「行方不明になっているのは、立原市会社員の加藤幸雄さん、妻の加藤律子さん、長男の・・・」
「なんか行方不明が多発しているみたいだぜ。この前は弁護士の家族だったかな・・・大丈夫か?」
そう言われたものの、彼にはそのニュースの内容は全くの他人事に聞こえている。
「四条電機の人と行動すると思うし、泊まるところは四条電機の施設だから大丈夫だと思うよ」
高校二年生の息子はそう答えた。
父はふううんという顔で言った。
「まあいいや。母さんには俺が言っておく。気をつけるんだぞ」
大木の父親は、歳に似合わず、一人で人生のいろいろを決めてくるこの息子を誇りに思っていた。もっとも四条電機とプロ契約を結ぶと言ってきたときはさすがに驚いたものだったが。
今回の提案はやや危険な感じもしたが、まあ大丈夫だろうと思った。彼もまたそのニュースは他人事に聞こえていたのだった。
加奈子の風邪が、すっかり良くなったのは、高校が春休みに入った頃だった。
時計の針は夜の八時を廻っている。窓を開けると気持ちの良い風が加奈子の部屋に入ってきた。
「ふー」
加奈子は溜息をついた。
自分を責める日々が続いている。全てはあのときから始まっていた。忘れようとしても忘れられないことだった。
「加奈子ー」
階下から母の呼ぶ声がした。
加奈子は我に返り、階段を下り、居間に向かった。
「加奈子、ちょっと相談なんだけど」
加奈子の母親はそう言った。書類らしきものをテーブルに広げている。
「うちの会社でバイトしない?」
「バイト?」
加奈子は母親のいきなりの提案に少し驚いた。
「そう、バイト」
そう言って加奈子の母親は書類を指で辿りながら説明をし始めた。
「あのね、この春休みに四条電機のスキー部が合宿に来るんだけど・・・」
加奈子の母親は加奈子の様子を見ながら話を進めていった。
「そのお世話のバイトの人が足りないみたいなの。食事作りの手伝いとか、荷物運びとか、掃除とか雑用みたいね。どう?」
そう言って加奈子の顔を覗き込んだ。
「どうって言われても、急だし・・・」
加奈子は下を向いた。
「気が乗らないわ・・・」
少し間を置いてそう答えた。
それを聞いて、加奈子の母親は不安を感じた。
最近何かおかしいわ。溜息が多く、必要最低限しか外にでない。落ち込んでいる様子も見せる。
加奈子の母親は加奈子に言った。
「加奈子、最近何か心配事でもあるの?」
加奈子はゆっくり顔を上げたが、首を振った。
せめて何に悩んでいるか話をしてくれるといいのだけど。
加奈子の母親はそう思った。そして言葉を続けた。
「じゃあ、バイトしてみたら? あまり詳しくないけど、オリンピック級の選手もいるみたいだし、現役の高校生選手もいるらしいの」
加奈子はやはり首を横に振った。
「興味ないわ・・・」
「その高校生選手っていうのがね」
加奈子の母親は加奈子の様子に構わず、話を進めた。
「何かの障害を抱えているみたいで、でも国内の大会とかでダントツ強いみたいなのよ」
「障害?」
「高校生にして、四条電機がスポンサーについているのだから、相当努力してその障害を克服したんじゃないのかな」
加奈子はその高校生を少し想像した。
同じ高校生で四条電機のスポンサーが付いていて、自分の障害まで克服している高校生・・・。
「私なんて、もうすぐ高校三年生だというのに何も決められていないわ・・・」
加奈子は下を向いて言った。加奈子の母親はその様子を見て、加奈子の手を取り答えた。
「落ち込むことはないと思うわ、加奈子」
そして少し間を置いて言葉を続けた。
「そりゃその高校生スキーヤーはすごいと思うわ。でも普通の高校生は二年生の段階で自分の人生を決めてはいないわ」
加奈子は少し顔を上げて母親を見た。
「これからの人生、ゆっくり、深く考えていくべきじゃなんじゃない? 努力だって、自分のあるべき姿が見つかってからでいいのじゃないかしら」
こんなとき父親が生きていれば、もっと上手く話せるのかしら。
加奈子の母親はいつも感じるプレッシャーにも似た感情を思い返していた。
「ゆっくり考えてみたら? 視野が広がってから、自分に合ったこと、やりたいことを見つけたらいい。大学に行ってから、考えてみてもいいと思うわ」
加奈子の母親はにっこりと笑って加奈子にそう言った。
「母さん・・・」
加奈子は浅くだが、しっかり頷いた。少しの間沈黙があった。
「でも・・・バイトのこと、ごめんなさい・・・」
加奈子の母親はそれを見て、まあしょうがないかと思った。
それから加奈子は母親と少し会話した。なんでもない会話だったが、久しぶりに長く話したように思える。
四条電機と契約している高校生スキーヤー・・・。
やはり加奈子には気になっていた。
いったいどんな人なのかしら? 障害を抱え、それを乗り越えた高校生・・・。
やはり自分とは大きく異なる人間に思えた。加奈子は自分の部屋に帰ってすぐにベッドに倒れ込んだ。
「はあ・・・」
ベッドに仰向けになり、天井を見つめた。
母親に心配されていることは良く分かっていた。
自分は弱い人間だ・・・。
そう加奈子は思った。
この沈んだ気持ちが続く自分の心に嫌気がさしていた。
大木は四条電機スキー部の合宿に参加するために立原市に入った。他の部員は明日やってくる。彼らより一足早く現地に入った形だ。
自分の地元である長野県の空港からK地方の空港まで飛行機で移動し、それからローカル特急に一時間余り乗った。
大木がこの地に来たのは二回目だった。四条電機とスポンサー契約を結んだ直後、昨年のシーズン前の合同練習に参加させて貰った。全く知らない都市という訳ではない。
立原駅でバスに乗り、四条電機グループの工場群に向かう。立原市の山側に四条電機の子会社、孫会社が立ち並び、大規模な工業地帯を形成している。
そこから六キロ程離れた北側の山には立原城があり、そのさらに北側にこの地に多く住む凛の民が信仰する凛宗の総本山が構えている。その東側の平野には市街地が広がり、さらに東側には海が位置していた。西側は深い山になっており、隣県に接している地形になっている。
この都市の人口は約三十万人で、その六割強が凛の民という民族の人間で占められていた。K地方では約六十万人がその民族の人間だと言う話も聞いたことがある。
バスはやがて四条電機の工場群入り口に差し掛かり、大木はそこでバスを降りた。
住宅がまばらにあるものの、周りは田んぼと森ばかりだ。その中に四棟からなる三階建ての四条電機の社員寮が見える。その横には体育館、ジム棟、陸上、及び野球のグランドがあり、実業団の練習ができる設備が整えられており、食堂、ミーティングルームを含んだ合宿所は社員寮の真横に並んでいた。
大木は合宿所を通り抜け、陸上グランドに向かった。根拠はなかったが、誰かが待っているような気がしたのだ。
グランドに出ると、土のトラックが広大な芝を囲んでいるのが見えた。芝と土の香りが気持ち良い。風も心地よかった。
「だが、誰もいないか・・・」
犬山さんに会いたい。
大木はそう思った。
その名前の人間は、大木と四条電機スキー部を引き合わせてくれた人物だった。元は東京の営業で、今は立原の工場に出向している。営業の頃はスキー部の広報も兼務だったこともあり、その頃大木を推薦してくれたのだ
彼は隣の社員寮に住んでいた。半年前の合宿のときは夜になると合宿所の食堂に顔を出してくれていた。新聞や本を読んでいる姿が思い出される。
大木は芝の上に腰を下ろした。
広いグランドに一人だけでいるのはなんともいい気持ちだ。やさしい暖かな風がゆっくりと吹いている。
芝の上で大の字になって寝た。そして目を閉じた。遠くで時折聞こえる車の音以外は、ゆっくり流れる風の音しか聞こえない。
大木は平和な気持ちになった。少し眠くなった。寝てしまったのかもしれない。大分寝てしまったようだ。目を開けたとき、少し薄暗く、周りの雰囲気は夕暮れ近くのそれになっていた。
「あの・・・」
女の人の声が聞こえた。
気のせいに思える。
「あの・・・」
再び同じ声が聞こえた。
高校の制服を着ている女子が、屈んで、大木を覗き込んでいる。髪は長く、おそらく黒なのだろう。春の風でやさしく揺れているのが見えた。
大木は仰向け姿勢のままでその女子を見ていた。女子も屈んでいる姿勢のまま言った。
「あの、四条電機スキー部の人ですか?」
目が大きく特徴的だった。
かわいい子だな・・・
大木はそう思った。大木はゆっくり起き上がり立ち上がった。そして服に付いた芝を手で叩きながら答えた。
「そうだけど・・・いや、違うか、まあ部員もどきかな」
それを聞いて、目の前の女子は何かを言いたそうであったが、黙り込んだ。
「スキー部に何か用? 明日なら他の部員が結構な人数で来るはずだけど」
その女子はまだ黙り込んでいる。少し落ち着きがない様子にも思えた。
大木もこの場をどうしようもなく、言葉も続けられず、あさっての方向を見た。
「あの、あの・・・大木さんですか? 高校生モーグラーの」
大木は自分の名前を呼ばれて、視線を目の前の高校生と思われる女子に戻した。いきなり自分の名前を言われ、彼は少し驚いた。
「そう・・・だけど」
大木はそう返事をした。
「あの・・・」
そう言ってまたその女子は黙ってしまった。大木はこの良く分からない状況に困った。
ファンか何かかな。大会で何度も入賞をしているし、スキー雑誌の取材だって受けたことがある。ファンがいたっておかしくない。ファンだとしたら初めての遭遇だな。
大木はそう考えると少しうれしくなった。口元が緩んでいる。
スポンサー契約とか、代表との練習とか、大人に混じっての出来事が多かった最近だったが、彼自身は高校二年生(もうすぐ三年生だが)に過ぎない少年でもあった。やはり異性に絡むことになると普通の高校生同様、うれしかったりもした。
「あの・・・」
女子はそう言うと、何か思い切ったように言葉を続けた。
「私と友達に、いや、知り合いに・・・なってくれませんか?」
「は?」
大木の全ての動きが止まった。このお願いというか、依頼がどういう意味合いなのか良く分からなかった。
「わっ、わっ・・・」
女子は焦っていた。
「いえ、はい・・・違うんです。大木さんとお話をしたくて」
大木は聞いた。
「僕は大木俊介だけど、間違いない?」
「はい」
女子は頷いた。大木との会話のきっかけを探していたのかも知れない。
「私、劉前加奈子と言います。母が四条電機で働いていて、明日から四条電機の合宿が始まると聞いて・・・大木さんも来ると聞いて、試しに今日来てみたら大木さんが寝ていたので・・・」
まだ混乱している様でもあった。
「ここに来たとき、風が気持ちよくて、芝に横になったら眠くなってさ」
大木は加奈子に笑った。
「私もグランドを見たら、誰か寝ているからびっくりして・・・」
加奈子も大木に笑った。
目が大きくて、かわいい子だな。笑顔もかわいい。
そう大木は思った。そして自分の色を判別が出来ない障害を思い出し、急に劣等感を感じた。
「話をしたいって・・・」
「あの、大木さんってすごいなって思って。お話して勇気を貰えたらなって」
加奈子は苦笑いしながら大木に言った。自分の気まずさを隠すような言い方だった。加奈子の長い髪が春の風に優しくなびく。
その言葉に大木はネガティブな感情を持った。大木の表情は暗くなっていたが、加奈子はそれに気づいていない。
「スキー雑誌に大木さんの特集があったのを見たの。高校生で四条電機とスポンサー契約なんてすごいわ」
「そんなことはないよ・・・」
大木は否定した。
「いろいろ大変なんだ。スキー連盟に僕のことをよく思っていない人もいる。選手として認められないと言っている人だっているんだ・・・」
そう言って大木は黙り込んだ。
だが、加奈子は大木の様子が硬くなっていることに気づいていなかった。
「でも大木さんはすごいと思うわ」
加奈子は言葉を続けた。
「目に障害を持っているのにそれを乗り越えているんですもの」
大木ははっとした。そして拳を強く握った。顔色が明らかに変わっている。
「もう何も言わないでくれないか」
それは強い口調だった。大木は我を忘れていた。
その言葉で加奈子はようやく大木の表情が硬くなっていることに気づいた。大木は自分でも顔が強張っているのが分かっていた。だが感情を抑えることができなかった。
確かにどの記事にも僕の目の障害のことは書いてある・・・。
大木は唇を噛んだ。そして感情を圧し殺した声で加奈子に言った。
「先に送っておいた荷物の整理したいから・・・」
そして大木は立ち上がり、その場から離れる仕草をした。加奈子は自分の発言の不味さに気づいた。
あの雑誌で大木は「障害を乗り越えた」などとは言っていない。「障害と闘っている」と言っていたのだ。
そうだ、この人は今も、この瞬間も障害に苦しんでいるんだ・・・。
「あの・・・」
加奈子は大木に話しかけた。
「ごめん、ちょっと・・・もう話したくないんだ。その障害で僕はスキー連盟から圧力を掛けられているんだから」
スキー連盟の一部の理事は大木に批判的で、彼の目の障害を気味悪く思っている節があった。これまで大会参加の自主的な辞退を求められてきたが、四条電機とプロ契約をしてから彼らは黙認を続けている。だが、おそらく相当に苦々しく思っている違いない。
それに大木は自分の障害のことを言われると、上手く心の処理が出来ないときが頻繁にあった。そしてそういった自分に苦悩していた。
「僕は自分の障害を克服なんてできていない。ただの弱い人間だ」
大木はそうつぶやいて管理棟に向かって歩いていった。
加奈子の頬をつたって涙がこぼれてゆく。
大木を傷つけるためにここに来たのではない。自分の歩む道をはっきり決めている大木という人間と話をしたかったのだ。
「待って下さい!」
加奈子は叫んだ。
「私、大木さんを傷つけるために来たんじゃないんです。そういうつもりじゃなかったんです。助けて欲しいんです。大木さんの強さが私にも欲しかったんです」
大木は加奈子の心の告白とも呼べる声に振り返った。そこには大粒の涙をとめどなく流している加奈子の姿があった。
「私も闘いたいんです。自分の心と!」
大木は驚いていた。そして自分の何かに頼ろうとしているその女子に戸惑いを感じていた。加奈子は泣き続けている。
「私は弱くて、卑怯で・・・」
彼女はそう言って泣き崩れ、グラウンドの芝に膝を付いた。
怒りの感情は何処かに飛び去り、自分が何をすべきなのか、何を言うべきなのか、分からなくなり始めていた。
加奈子のその姿に心を打たれたのかもしれない。
「僕は特別に強くなんかない」
そう呟いたが、彼は既に今さっき取った自分の行動を反省していた。目の前にいる大きな目が印象的な女子を傷つけたことを、それが不条理で自分のことしか考えていなかった行動によることを認識していた。
「合宿所の食堂に行かないか? 飲みものでも奢るよ・・・」
突然の大木のその提案には自分の取った行動の謝罪が含まれていた。
大木は合宿所の食堂にある自販売機でコーヒーを買おうとしていた。ホットとコールドで迷ったが、赤く光るボタンを押した。「がこん」という音と共にホットの缶コーヒーが出てきた。
加奈子はまだ泣いている。
外は薄暗くなってきており、もう六時近い。食堂の中は暗く、大木は食堂の電気を付けた。食堂には加奈子と大木以外は誰も居ない。
大木は加奈子の目の前に缶コーヒーを置いた。
「ありがとう・・・」
加奈子は礼を言った。そして両手でテーブルに置かれたコーヒー缶を触った。
「暖かい・・・」
なみだ目で大木に笑いかけた。
かわいい子だな。大木はそう思った。そして視線をそらして言った。
「僕は多分、劉前さんが考えているような前向きな人間ではないよ。僕の目は障害で色が見分けられない・・・いつもその事実に潰されそうな気持ちになる」
大木は寂しく笑った。
「子供のときは見えたのに今は白黒の世界しか見えない。悔しい思いに悩まされることだってある。それが原因で人と揉めることだってあるんだ・・・」
「でも私は、大木君はすごいと思う。頑張っていると思う。大木君のスキーはいろんな人に励ましやパワーを与えていると思う」
「・・・」
「ネットの動画で感動したわ。生きる強さを感じたの。大木君は本当にすごいわ」
大木は自分という人間を振り返り考えた。
とてもそうは思えなかった。
「僕はそんな人間じゃないよ」
大木はそう呟いた。
加奈子はすぐに首を横に振ったが、続けて何かを言おうとすることはしなかった。
沈黙の時間が流れてゆく。
大木が口を開いた。
「さっき・・・」
大木は加奈子に尋ねた。
「その、さっき言っていた心の強さがほしいって・・・」
加奈子はとっさに両手を自分の口を隠すようなしぐさをした。
そうか、さっき口に出してしまったんだ・・・。
でもたった一時間前に初めて会った人間に相談するなんて出来ない・・・。
加奈子は下を向いた。
遠くで金属製の何かの落ちる音がした。
突然の音に加奈子は怯え「びくっ」と動いた。そして不安そうな目で大木を見た。大木は静かに頷き、音の発生場所を確認するために食堂から廊下に出た。
何かに不安を感じているみたいだな・・・。
大木はそう思った。
廊下には誰も居ない。遠く廊下の先の管理人室に鍵を掛けている人間が見える。大方さっきの音は管理人が落とした鍵の音だったのだろう。
加奈子も食堂から出てきた。その表情は、音のした方角を見た瞬間に安堵したそれに変わった。
廊下の窓から建屋の設備の点検が終わったのか、薄暗い駐車場で立ち話をしているツナギ姿の男たちが見えた。そこにワンボックスの車が廻され、男たちは工具と機材を車中に積み込んでゆく。
さっきの管理人が現れた。
彼らと何かの会話をしている様子だ。そして突然、その集団から大きな笑い声が聞こえた。
どこかで見た景色だ・・・加奈子はそう思った。
そして自分の記憶の底から、忘れようとし続けてきた事実が、凄まじい速さで加奈子の心を駆け抜け、感情は動揺に覆われた。加奈子はそのまま立っていることすら難しくなった。
加奈子は耳を塞いでその場にしゃがみ込んだ。自分がパニックを起こしているのだと思った。小刻みの震えが加奈子を襲う。加奈子は震え続ける。男達は去り、周りは音のない空間に戻ったが、加奈子はそのままの姿勢から動けないでいた。
大木は加奈子の隣にしゃがんだ。
「どうしたんだ?」
その問いかけに加奈子は答えない。大木は自分に問いかけた。
どうすればいいんだ?
加奈子は震え続けている。
大木は思い切って加奈子を自分にたぐり寄せた。そして加奈子を抱きしめた。加奈子は驚いた表情を見せたものの、彼女の震えは徐々に収まってきたように思えた。
加奈子は口を開いた。
「私、人間が捨てられるのを見たの」
大木は全くの予想外の言葉に驚いた。
「私、三ヶ月前に立原川の川べりで・・・大人二人と子供二人が穴に捨てられるのを見たわ。多分、家族で・・・おそらく殺されていたと思う」
「見たって・・・それに殺されてって」
「さっきの風景に似ていた・・・ワンボックスに大勢の男・・・死体を捨てた後、彼らは大声で笑った・・・」
加奈子はあのときの恐れと怒りの感情を思い出していた。
大木は少し混乱していた。
本当のことなのか? いや、とても嘘を言っているようには思えないが・・・。
大木は少しの間考えた。徐々に落ち着きを取り戻していった。
「警察に通報とかはしたの・・・?」
大木のその言葉に加奈子は首を横に振った。
「怖くて・・・何もしていないわ」
「・・・」
「臆病と言われればその通りなの・・・否定はしないわ。通報したら、きっと自分の身が危険にさらされる。あの子達のように私も殺されるかもしれない・・・そう思うともう怖くなって・・・」
加奈子は溜息をついた。
「死体を遺棄していた犯人は、複数の人間だった。顔は暗くて、遠くて分からなかった。だから誰が彼らだったのか分からない。だから誰を信用していいのかも分からなかったわ・・・」
加奈子の声は涙声だった。
ただ、あの川沿いの土手で今も誰にも知られずに眠る被害者たちの無念さを思うと、加奈子は今まで何もしてこなかった自分を責め続けていた。だが、自分がどうすべきなのかは分からないままだった。
大木は思い出した。
「そういえば、この立原は最近行方不明者が多いってテレビで言っていたな・・・その人数と合っている話もあった」
大木はそう呟いた。加奈子はその言葉に反応した。驚いている様子だった。
「うそ、そんなこと聞いたことがない・・・」
「いや、確かに言っていた。この一年で家族での失踪者が二組だったかな・・・独身者も二人くらいとか言っていたな。新聞でも記事を見た覚えがあるし」
「どうして・・・そんな記事見たことない」
加奈子は気味の悪い感覚を覚えていた。新聞はよく読むほうだったから尚更だ。
ローカルなニースは、ローカルが一番飛びつくような気がするのだが。それを当の立原市の市民が知らないっていうのはおかしいな。
大木はそう疑問に思った。
食堂の窓の外には黒と赤の空が見える。夕暮れが終わり、夜が来ようとしている。
加奈子は下を向いて呟いた。
「被害にあった人は、今も誰にも知られずに川べりの土手で眠っている。きっと無念に違いないわ・・・悔しいに違いないわ」
加奈子は更に言葉を続けた。か細い声だった。
「小さい子供だっていたのよ。小さい子供が乱暴に穴に投げ込まれた。二人も・・・このまま黙っていたら、正義なんてどこにもないわ」
「でも、いくらなんでもその行方不明者のニュースが、地元で報道もされていないなんてのはおかしい。この状況で何もしないことは決して臆病なことなんかじゃないよ」
大木はそう言った。
加奈子は再び首を大きく横に振った。
「でも! この三ヶ月、私はいつもあの風景を思い出してしまっていた。私はあの穴に人が投げ落とされた瞬間を今でもはっきり覚えているわ!」
加奈子はそう叫んだ。
「あのとき何も出来なかった自分が本当に許せない・・・何もしないなんて、できないわ・・・」
「・・・」
大木は加奈子の意見が正しいということを認識していた。そして苦しんでいる加奈子の気持ちも理解できていた。
だからと言って、現実は違う。身の危険を伴うのかもしれないのだ。
出口が見えない・・・。
大木はそう思った。
「・・・ちょっと確認させてくれないか」
不意に大木が呟いた。
「え?」
大木は立ち上がり、自分のリュックサックからノートPCを取り出し、開き、ネットに繋げた。
「ここの地方新聞のウェブニースで行方不明者のニュースが本当に扱われていないのか、調べてみたいんだ」
大木はそう言った。
「それだったら・・・立原中央新聞のサイトがいいと思う」
加奈子の声は小さく、弱々しい。
大木は言われた新聞社のホームページに入り、ウェブニースを調べたが、過去をさかのぼっても、加奈子の言うとおり、行方不明者のニュースは一切見つからない。
「やっぱり、行方不明車者の情報がこの地方では制限されている」
大木はそう呟いた。
「何故なんだ・・・」
大木は少し考えて、加奈子に言った。
「念のため、全国紙のニュースを確認してみよう」
「でも、この都市の人は全国紙なんて読まないわ」
「まあ、だからかな」
大木は全国紙のウエブニュースに入り、検索画面で「立原」と打ち、続いて「行方不明」と打った。
検索の結果、四件見つかった。
大木は一番古い記事を確認した。三ヶ月前の記事になる。最初の行方不明者は二人の大人と二人の幼い子供で、弁護士一家だった。
加奈子の目撃した家族の犠牲者に似ている。加奈子の心は重くなり、以降の記事を読むことが出来なかった。
「大木君の言う通り、家族での失踪者が二組、独身者が二人・・・そしてあの子たちは二歳と三歳の女の子だったんだ・・・」
かわいそうでならなかった。
大木はニュースを確認して行くうちに最後の四件目に入った。
「今日の日付だな・・・」
そして驚いた。大木は口に出して記事を読みはじめた。
「K地方の立原市で行方不明だった家族、立原川の土手に埋まっているのを発見。一部白骨化しているものの、所持品から・・・」
大木は加奈子の顔をみた。加奈子は戸惑ったように大木の顔を見ている。
「所持品から四ヶ月前から行方不明だった、弁護士の資格を持つN県立原市在住の川口正継さん三十六歳の一家と・・・」
大木は記事を読み続ける。
「妻、早苗さん三十二歳、みさえちゃん三歳、よしみちゃん二歳の四人の家族で・・・」
「私の見た家族だ!」
加奈子は立ち上がって言った。その記事に驚きを感じていたが、何よりも遺棄された遺体の存在が明らかになったことに安堵した。
もう自分を責め続けることはしなくてもいいのだ・・・見つかって本当によかった。
そう思った。
加奈子は静かに目を閉じた。安堵の気持ちが心の中に広がってゆく。こんな気持ちを久しぶりだった。
大木は記事を読み直していた。
何か引っ掛かるな。そもそも地中にあった遺体がどうやったら見つかるんだ? 他の目撃者が通報したのか? それとも犯人グループの誰かが仲間を裏切ったのか?
記事にはそこまで書かれていない。
外はすっかり真っ暗になっている。窓から見える風景は何もなく、ただ黒い空間が存在していた。
何か変だ。情報が制限されていることといい、行方不明者の多さといい、いったいこの狭い町で何が起きているんだ・・・。
大木はそう思ったところで考えるのを止めた。加奈子の顔色は、憑き物が取れたかのように良くなっている。
問題は解決したんだ。
大木と目が合った。加奈子は頷き言った。
「よかった・・・」
笑顔だった。
もう大丈夫だな・・・。
「もう暗いし、送っていくよ。バス停まででいいかな?」
そう加奈子に言った。
もうこの事件であれこれ言わない方がいい。
大木はそう思った。
この子にまた会うことはあるのだろうか?
大木は少しの寂しさを感じていた。加奈子に惹かれているのかもしれない。
「うん・・・」
加奈子はそう答えた。そして言った。
「大木君はここで二週間、練習をするんだよね」
「そうだよ」
「ときどき練習を見に来てもいいかな? スキー部の練習なんて見たことないから」
「それはOKだよ。歓迎する」
思いがけない展開に大木はうれしそうに答えた。
そしてノートPCを閉じて大木は立ち上がった。
「あ!」
大木は意図せず、大声を出してしまった。とても大切なことを思い出したのだ。
「そうだ・・・寮の鍵、まだ貰ってない! 管理人さん、さっき帰ってしまったような気がする!」
「え?」
「管理人さんに鍵を貰う前にグランドの芝で寝ちゃったから、鍵を貰い損ねた・・・」
それから「あはは」と大声で大木は笑った。
加奈子は一瞬大木の置かれた状況を理解できなかったが、理解すると自分のせいの気がしてきた。
自分が大木を振り廻さなければ、こんなことにはならなかっただろう。
全く関係のなかった大木を悩ませ、迷惑を掛けてしまったことに申し訳なさを感じていた。
「どうするの・・・?」
加奈子は大木に恐る恐る尋ねた。
「うーん、立原の駅にほうに行ってホテルでも探すよ。それかこの寮に知り合いが居るから、その人の部屋に泊めてもらうかな」
加奈子は、それは申し訳ないと思った。
「あの・・・よかったら・・・」
加奈子は自分でも驚くくらいの提案を大木にしようとしていた。
「私の家に来ませんか? 母も大木さんのことを知っているから、きっと喜ぶと思うわ」
加奈子はそう言った後、自分がずうずうしかったのではないかと思った。下を向いた。そしてゆっくり顔を上げ、大木を見た。
赤い顔の大木がいる。
「あ、ありがとう。ご家族の方がよければ、なんだけど・・・」
大木自身もその提案に驚いていた。そして少しの間どうしたものか考え、そう答えた。大きな目を持つ、長い髪の美少女を見るうちに、自分はとても幸せな人間ではないだろうか?とか思ったりもしていた。
加奈子はすぐに携帯で母親に電話をした。電話の向こうは大木の名前を出すと多少のパニックに陥っていたようであったが、ほぼ二つ返事でOKだった。
そして大木はノートPCをリュックにしまい、二人は寮を出た。遠くにバスのライトが見える。二人は顔を見合わせ頷き、春の暖かい夜の中、バス停に向かって走り出した。
やわらかな風が二人を包んでいた。
第2章
夕方を過ぎると立原の工場群周辺の道路は帰宅の車でひどい渋滞になる。薄暗い夕暮れの中で車はピクリとも動かない。いつもの光景だった。
犬山は渋滞を横目に自転車に乗って坂を下ってゆく。犬山は自動車の免許を持っていない。学生時代から自転車好きだったこともあり、自転車で会社に通っている。
これから宅配便の集配所に寄って、実家に荷物を出すつもりだった。
そうだ・・・今日、大木君が合宿所に来るんだったな。
自転車に股がったときにそう思った。
犬山が東京営業だったとき、彼の躍動感あるモーグルスキーを動画サイトで見て、胸を打たれ、感動したのを覚えている。それは大木自身がUPしたもので、当時スキー部の広報を兼任していた犬山はダイヤの原石を見つけたかのように興奮し、四条電機のスキー部に彼を紹介したのだ。
それからの仲だ。メールのやり取りを頻繁にしている。案外高校生と三十前のおっさんでも、友情というものは成立するものなのかも知れない。
山の上にある工場を出て、自転車で坂を下ってゆく。街灯はほとんどなく、辺りは暗く、真っ黒な世界が広がっている。自転車のか細い光だけでは、どこからどこまでが道の幅なのか、どっちが上で、どっちが下なのか、それすらも全く分からなくなることがある。
犬山はこの町が嫌いだった。
県外から来た人間を「来たり者」と呼び区別し、自らを「凛の民」と称し、閉鎖的な文化を守り続ける、この町が嫌いだった。
来たり者に対し、地元の人間は距離を置く。学校も、会社も、あまつさえ買い物する店ですら、彼らの間に見えない境界が存在している。
犬山の部下は皆「凛の民」と自称する輩ばかりだった。中には「凛の民族保存会」の青年部の世話役だっている。
犬山は四条電機からの出向者という妬みも手伝って、露骨な嫌がらせを会社で受けていた。PCの電源が抜かれていたり、靴がごみ箱に捨てられていたり、到底我慢できない子供レベルの嫌がらせを受け続けている。今日の工程が勝手に変更されていた件もその一端だ。
「くそっ、あの馬鹿な連中共!」
罵るような言葉を口に出した。
犬山は表情を硬くして自転車で坂を下ってゆく。自転車は国道と合流し、更に国道を一キロほど走ったところで、目的の場所に着いた。
犬山が受付で東京への宅配伝票を渡すと、パートらしき中年女性は犬山の顔を観察するように眺めた。
「なにか?」
犬山はその小太りの中年女性に聞いた。大方、東京の住所と宛先をみて「こいつは来たり者」とでも思っていたのだろう。実家に荷物を送るだけで、こんなに嫌な思いになるとは・・・。
こういった対応には何度か会っている。本当に嫌だ。
「あなた、来たり者?」
小太りで中年でパートらしきその女性は言った。
その言葉で、犬山は一瞬にして自分の自我が飛んだのが分かった。
「荷物を送る客にそういう言い方はないんじゃないか?」
その中年の女性は「なんで怒っているの?」という顔で、そのまま犬山を無視して荷物の採寸取りを始めた。
犬山はその態度に頭に来たが、我慢した。こんな人間のために自分の気分が害されるのは全く意味がない。そう思い我慢した。それは、犬山がいつも会社で考えるようにしていることだった。
犬山は荷物の代金を払って集配所を出ようとしたとき、犬山の後ろで「ごとっ」と何かが床に落ちる音がした。
犬山はすぐに後ろを振り返った。
犬山の荷物が床に落ちている。
中年のパートらしき女性は何も気にせずに荷物を所定の置き場に置き、そこを立ち去ろうとしていた。 犬山は驚いた。
「ちょっと待ってください。今その荷物、落としましたよね。それ、割れ物に丸をしていますよね。何か俺に言うべきことがあるんじゃないですか?」
その中年の女性はむすっとして何も言わない。
「その荷物、こっちによこしてください。割れていないか確認させてください!」
犬山の声はだんだん大きくなっている。たが、中年の女性は犬山を無視して、荷物を奥にもって行こうとしていた。
犬山はその行動が理解出来なかった。そして思った。これが立原なんだと。来たり者には適当にやっても構わないという態度が何故まかり通っているのか不思議だった。
この町はおかしい、どうかしている!
今日の会社での嫌な出来事が重なった。
「おかしいんじゃないのか!」
犬山は集配所で怒鳴った。遠くにいた宅配便の社員らしき人間がその声に反応し、慌てて大木のところに来た。
「そこの人、僕の荷物を落として侘びもないし、中身もチェックもさせてくれない! おかしいんじゃないのか!」
犬山は強い声で抗議した。
その寄ってきた男性社員は、中年の女性のところに行き、何やら確認をしている。そして犬山の荷物を大木のところに持ってきた。
犬山は箱を開け、中身を確認し始めた。箱の中からは母から頼まれていた焼き物が入っている。犬山が隣の県まで行って、買ってきた大皿だ。
幸いにも割れていなかった。
「割れていないじゃない」
パートの中年女性は大木に対して憎々しげにそう言った。
「それでも、あなたの態度はおかしいでしょう!」
犬山がそう言っている様子をパートの中年女性は一切無視している。その後、男性社員が仲裁に入り、犬山に型通りの謝罪が行われ、犬山も怒りの矛を鞘に収めた。これ以上抗議を繰り返すのも大人気ないと思ったからだった。
犬山は集配所を後にした。
だが、残された集配所の面々はすぐにひと塊になった。そして今繰り広げられた出来事を総括していた。
「柏木さんは悪くないよ」
「凛の民族保存会に連絡だ。あんなやつ、来たり者リスト送りだ」
「そうだ」
「そうだ」
即座に同意する声が聞えた。手際よく犬山の伝票から、名前、住所、電話番号が書き写され、メールでその内容が凛の民族保存会に送られた。
既に自転車に乗り、不愉快な思いを抱えながら、帰路についている犬山はその陰険で悪質な行為を知るはずもなかった。
暗い闇が続いていた。
音の無いその黒い世界に犬山の自転車を漕ぐ音だけが響いている。
黒く陰湿で嫌な世界だった。
自転車を十五分程走らせ、犬山は社員寮の門までたどり着いた。入口の犬山の背丈程はある大きな石には「四条電気立原合宿所」と掘ってある。その下に付け足したように金属製の「四条電気立原社員寮」の看板がはめ込まれていた。
この土地には当初合宿所しかなく、社員寮は別の場所にあった。それが老朽化して、空いている土地があったこの合宿所の土地に社員寮を建てたのだと聞いている。
犬山が自転車のスピードを緩め、寮の門に入ろうとしたとき、突然門から若い男女二人が走って出てきた。
犬山は急ブレーキを掛けて、自転車を止め、怒鳴りそうになった。だが、それを止めた。二人ははかなり急いでいるようで、犬山の自転車には全く気づかず、バス停の方へ走ってゆく。
「あれは・・・大木君か?」
犬山は少し冷静になった。
女の子は知らない顔だな・・・高校生? 犬山君の彼女? まさか。
まあ、戻ってきたら近況でも報告してもらうか。この間の大会の様子も聞きたいしな。
犬山はそう思った。大木が果敢に滑る映像が思い起される。ネットにUPされた彼の滑りは、常に斜面を攻める、前向きで心踊る滑りだった。最近は彼のファンが増えたのか、ほとんどの大会での彼の滑りが動画サイトにUPされている。それは犬山にとってうれしいことだった。
本当に・・・大木君のモーグルは元気付けられる。
何度も挫けそうになっても、犬山はネットの大木の姿を見て、逃げずに踏み止まり、頑張った。大木の滑る姿が、今の犬山を支えていると言っても過言ではない。
その大木自身は四条電機とのプロ契約出来たことで、犬山に感謝していた。そういう内容のメールが今でも犬山のところに来る。
「だけど、救われたのは大木君ではなく、僕なんだ・・・」
犬山はそう呟いた。
犬山はしばらくその場で、大木とその横で走っている女子を見送った。なんだか微笑ましい気がした。
大人を相手に渡り歩き、大人相手に戦っている彼は、とても十七歳の高校生には思えなかったが、遠くに見える大木は、なんだか極普通の高校生に見える。
大木がまたこの合宿所に来たのがうれしく思った。
そして犬山はゆっくりとペダルを漕ぎ出し、社員寮の敷地に入っていった。
大木と加奈子はぎりぎりでバスに間に合い、飛び乗った。腕時計を見ると十九時を過ぎている。二人とも少し息が上がっていた。
「劉前さんの家はここから遠いの?」
大木が聞いた。
「十分くらいかしら。次のつぎのバス停なの」
「そうなんだ・・・」
そう言って大木は少し冷静になった。隣に座るかわいい女子の横顔をちらちら見ながら思った。
劉前さんはかわいい・・・いやいや、そうではなくて、やっぱり殆ど何も知らない女子の家に泊まり行くのは問題ではないのか? いや問題ありだろう。やはり駅前でホテルを探すべきではないのか?
それか犬山さんの部屋に泊めてもらうかな・・・携帯に電話してみるか・・・。
「劉前さん、やっぱりお邪魔じゃないかな。ホテルを探すか、心当たりに当たってみようと思うだけど」
「大丈夫よ。さっき家に電話したときに思ったんだけど、母は大木君に会えるのを楽しみにしているみたい。そもそも、私、大木君のことは母に聞いて知ったの」
「うん?」
「母は四条電機テクノで働いていて、今回のスキー部合宿の補助バイトを私に紹介してくれたの。でも、私は断ったんだけど・・・」
加奈子は急に大木をはずかしそうに大木をみた。
「そのとき母がすごい高校生が来るって言っていたの。ネットで調べてみて、本当にすごい人だなと思って・・・」
大木は加奈子の話を聞きながら、自分が考えている自分と、他の人間が見る自分との間には差があることを感じていた。
目に対するコンプレックスと闘っている自分、それに負けそうになる自分・・・自分のアイデンティティを唯一支えてくれているモーグルスキー。
雑誌やネットの記事に出ている自分は努力家で何事にも折れない強い心を持っている。そう書いた方が大衆受けするのだろう。実際の自分とメディアの中の自分に差が存在し、最近それがストレスに感じ始めていた。
「大木君のスキー、格好よかった」
「グランドに大木君がいたから、私、びっくりして・・・」
加奈子の話は延々と続いた。
元気だな・・・それに話好きだったんだ、この子・・・。
大木はその話の長さに少し苦笑した。
やがて二人を乗せたバスは、加奈子の家近くのバス停に停まった。二人はバスを降りて、春らしいほんのり暖かな夜の中を歩き始めた。
この近辺は昔からの家が多く、肩の高さ程の土塀で囲まれ、それがここの街並みを形作っていた。道路は三十センチ角ほどの石畳で敷き詰められ、古くからの街であることが伺える。
「ここは昔、立原藩の武家屋敷があったところなのよ」
先に歩く加奈子が言った。
土塀に何か貼っている。大木が暗がりの中、近寄ってそれを見ると「立原凛祭り」とあった。
「祭りがあるのかな?」
「一週間後にあるの。K地方でも大きな祭りの一つなのよ」
加奈子はそう答えた。
「出店がいっぱい出て、民族の舞や踊りの奉納があって、山車も出るわ。三日間の最終日は、大きな火柱を建てて、それを倒して終わりって感じのお祭りかな。すごく華やかなのよ」
「ふーん・・・」
大木は、興味があるのかないのかよく分からない返事を返した。
「大木君はお祭りが好きじゃないの?」
「どうして?」
「あんまり興味なさそうだから」
大木は歩きながら下を向いた。石畳を一つ一つ確認するように歩いている。
「・・・僕は色の付いている空間って苦手なんだ」
その瞬間、加奈子は人を傷つけてしまったような感覚を覚えた。
大木は言った。
「僕は障害で色を見分けられない。でも子供の頃は、色というものを確かに知っていたんだ。だから今の僕にとって、いろいろな色が存在している華やかな世界は本当に辛く感じるときがある」
大木は少し溜息をついて、加奈子に笑いかけ、そして言葉を続けた。
「でもこんなことばっかり言っていたらだめだな・・・このコンプレックス、なんとかしないきゃいけない」
「うん」
隣を歩いていた加奈子は大木を覗き込んで、笑って返事を返した。
大木は加奈子の仕草と笑顔を見て、暖かい気持ちになった。
かわいい子だな・・・。
そう思った。大木は自分の顔が熱くなっているのが分かる。
それから五分ほどで、加奈子の家に着いた。加奈子の家は比較的新しい家だったが、街並みを配慮した土塀に囲まれた家になっていた。
玄関の前の道路で加奈子の弟がそわそわして加奈子たちを待っているのが見えた。うれしさいっぱいの顔だ。顔に感情の全てが書いてある。
「大木さんのようなスーパー選手が家に来てくれるなんて、すごくうれしいっす。すごくうれしいっす」
照れない訳にはいかなかった。こういったことはあまり言われたことがなく、実際、言われてみるとうれしいものだと思った。本当に今日はどうかしている。
大木は遠慮がちに加奈子の家に入った。
「大木さん、その歳でプロのスキーヤーって、すごいわね、本当にすごいわね」
加奈子の母親は「すごい」という言葉を連発していた。それに加奈子の表情に明るさが戻っているのを見て、ほっとした感情を覚えた。
大木さんの影響なのかしら・・・だとしたら、本当にすごいわ。
そう思った。
移動で疲れていたからかもしれない。
加奈子の家で夕飯に鍋を食べ終え、居間でテレビを見ているうちに、大木はうとうとし始めた。ずうずうしいのではないかという考えもよぎったが、眠気には勝てず、そのうち寝てしまった。
どれくらい時間がたっただろうか・・・。
「大木君、大木君」
寝ぼけながらも、大木は自分を呼んでいる女性の声を聞いた。加奈子の声だ。
このシュチュエーションは今日で二度目だな・・・。
「うん?」
「大木君、ニュース見て」
ローカルニュースが始まっている。目を擦りながら、居間を見渡した。居間には加奈子と自分しかいない。
もう十一時か・・・。
テレビでネットに流れていたニュースが報道されている。
「本日、立原市塩見の立原川の土手で埋まっているところを発見された四人の遺体は、警察のその後の調べで、四ヶ月前から行方が分からなくなっていた弁護士の川口さん家族四人であることが・・・」
ニュースは淡々と読み上げられている。犠牲者である子供たちが、二歳と三歳の女の子だというくだりで、加奈子は胸が苦しくなり、犯人に対して強い怒りを感じた。
「川口さん家族は凛の民族保存会の理事でもあり、熱心な独立派であったことから、警察はトラブルに巻き込まれた可能性も含め、調査を・・・」
「独立?」
大木は加奈子を見た。今の日本では聞きなれない言葉に驚いたのだ。
「独立っていったい何?」
大木は加奈子にそう聞いたが、加奈子はすぐに首を振って、分からないと答えた。
「続いてのニースです。本日、立原市田町の雑木林で若い男性が埋まっているのが・・・」
同じようなニュースだな。大木はそう思った。
「死後三ヵ月は経っているものと考えられ、遺留品から、行方不明だった会社員の関原さん二十六歳であることが・・・」
「関原さんは熱心な凛の独立派だったことから、怨恨の可能性もあり・・・」
また凛の独立か・・・この日本で、この時代に、そんなことを主張している人がいるとは・・・。
大木は違和感を覚えるのと同時に気味の悪さも感じていた。
「尚、二件の行方不明者の発見に関しては、昨日の警察への匿名の情報により発見されたもので、警察はこの人物が何らかの情報を持っているとして捜索を行って・・・」
加奈子は反応した。
「・・・この通報者って、いったい誰なのかしら?」
「二件の事件を知っている人間って考えると、やっぱり犯人なんじゃないかな?」
加奈子は、大木の言葉に、遺体を土に埋めた後、犯人の仲間内でリンチを受けていた若者の姿を思い出した。
彼なのか・・・だとすれば彼の身は相当危険なのではないだろうか? あの集団は幼い子供も手に掛け、平気で仲間にリンチを加える人間だ。仲間を手に掛けるのも何の躊躇いもなく行うだろう・・・。
加奈子は少し背筋が寒くなるような感覚を覚えた。
しばらく沈黙が続いた。
「あの、劉前さん・・・」
大木は躊躇しながら加奈子に話しかけた。
「凛の民っていったい・・・何?」
加奈子は大木の質問に少し驚いた顔になったが、頷いて答えた。
「元々は奈良時代の渡来人が始まりみたいなの」
「渡来人?」
「そう・・・大陸に凛という国があって、そこが滅んで奈良時代に日本に渡来してきた一族らしいわ。実際、今でも大陸に凛の民族の子孫は存在しているみたい」
「そうなんだ・・・」
大木はそう返事をした。彼は歴史に詳しくはない。
「立原で人口の半分以上、K地方で一割弱・・・くらいだったかしら。今では六十万人がこのK地方に住んでいると聞いているわ」
「奈良時代って話なら、もう千三百年も前の話か・・・」
なんと立派な平城京から逆算した。大木の言葉に加奈子は軽く頷いて言った。
「この立原市に三里が岩っていう凛宗の総本山があって、この地が凛の民の中心なのよ」
聞いてはいけないことのように感じていたが、思い切って加奈子に質問をした。
「劉前さんは凛の民なの・・・?」
聞きにくいことを聞いたような気がした。差別的な印象に取って欲しくなかった。大木は加奈子の顔をじっと見た。
加奈子の様子はそういった大木の様子に気づくことなく、至って普通に答えた。
「違うわ」
加奈子はゆっくりと首を振った。
「私の先祖は、関が原の戦い以降にこの地のきた立原藩の武士なの。凛の民ではないわ」
そして、加奈子は言葉を続けた。
「でも凛の民族保存会には入っているわ。踊りをする人が足りなくて、半年前に強制的にね」
大木はそれを聞いて聞いていて矛盾するような気がした。
「この地は凛の民族が多いから、一応入っておかないとね・・・いろいろあるから」
加奈子は苦笑するように言ってから、最近の民族保存会の言動を思い出した。
最近、凛の民族を抑揚させる内容や、来たり者への批判、本土批判が多いわ。今日に至っては独立って・・・いったいどういうことなのかしら・・・それにそれを阻害する人間まで現れて、殺人まで犯しているなんて・・・。
加奈子はそう考えながら、ふと足元を見た。
「いやっ」
加奈子の声が聞こえてきたと思った瞬間、加奈子が大木の背中にしがみついて来た。しがみつかれた大木は突然のことで「びくっ」とした。
「かえるっ、かえるっ」
加奈子は床のある方向を指差した。そこには二センチを超えるあまがえるが鎮座していた。
かえるの動きはにぶい。目覚めたばかりか? この家で冬眠でもしていたのか?
大木は長野にある自分の家の押入れでてんとう虫が越冬している姿を思い出した。そして笑いが漏れた。
大木はかえるの方向に歩いてゆこうとしたが、加奈子がしっかりしがみついて、重くて動けない。
加奈子の胸が背中に当たっている。生まれ初めてのなんとも言えない柔らかい感覚だった。
「劉前さん、背中・・・僕がかえるを捕まえるから」
それを聞いても加奈子はしがみついたままだった。
大木は少し苦笑した。さっきまでの深刻さが、このかえる一匹の登場でどこかに飛んでいってしまった。
「わたし、わたし、かえるが駄目なの」
加奈子の悲痛な声が聞こえる。
大木があまがえるを捕まえようとしたとき、かえるは大きくジャンプし、壁にへばりついた。
「きゃああああ」
それから加奈子の家ではしばらく「かえる、かえる」とか、「いやあああ」とかの悲鳴が響き渡った。加奈子の弟が階下にどたどた下りる音や、大木と加奈子の弟の、おそらくかえるを捕まえるためのせわしない足音が聞こえてきた。
そして最後は加奈子たちの大きな笑い声が聞こえた。かえるは捕まり、外に逃がされたのだ。ほっと安堵した雰囲気は家の外に追い出されたかえるにも伝わった。
かえるはしばらく加奈子の家を見つめていた。あの中で本当に怖がっていたのは一番非力な自分のはずなのにと思った。
そして辺りは音のしない、静かな夜の世界に戻った。この町の夜は暗く黒く深い。
かえるはそんなことは全く気にもせず、春のやって来た外の世界に高く、高く飛び上がった。
さっきの一連のニュースが気になっていたせいかもしれない。大木はなかなか眠れなかった。
そして突然、大木は蒲団から起き上がり、暗がりの中、自分のリュックサックからノートPCを取り出し、開いて起動させた。そのPCの液晶の光に照らされ、大木の顔が暗闇から浮き出てきた。
ハードディスクのカリカリと鳴る音が聞こえる。そして大木はあるキーワードを打ってネットで検索を始めた。
凛の民・・・。
「凛の民は大陸からの渡来人で・・・」
そこに書いてある文章は加奈子から聞いた殆ど同じ内容だった。大木は小声で読み上げていった。
「西暦六百年代後半に大陸の凛の国が滅んだときにK地方を中心に渡来。当時の規模で数万に及ぶ大移動だった・・・」
「凛の民は民族意識が強く、閉鎖性、選民思想が強かったことから、大和朝廷時代から今日まで差別を受けている。奈良時代、平安時代、鎌倉時代に数回の反乱を起すが、反乱は失敗、多くの血が流れ鎮圧された」
大木はさらに読み続けた。
「特に鎌倉期の反乱は大規模なものでK地方北部全体に広がった。守護の大村義勝が討ち取られるなど反乱は成功したかのように見えたが、幕府軍十万により鎮圧される。このとき多数の凛の民が処刑されたとされる」
大木は歴史に詳しくはなかったが、守護が殺されるというのは、日本の歴史上、大事件であるような気がした。
「凛の民には、奈良時代に大陸から渡来した当時から皇帝が存在していると言われており、この鎌倉期の騒乱も生き抜け、現在も凛の民を統率している・・・」
今の日本で皇帝って・・・なんだそりゃ。現実離れしているぞ。本当なことなのか・・・?
そこまで考えて急に眠気が襲ってきた。
トイレにでも行くか・・・
大木は自分の居る一階の客間から廊下に出た。廊下の電気は消えていたが、洗面場のドアから漏れる光で、トイレの位置は分かった。誰かがドライヤーを掛けている音がしている。
大木は廊下の電気をつけずにそのまま歩いた。すると洗面場から鳴っていたドライヤーの音がぴたっと止まり、ドアがゆっくり開いた。
パジャマ姿の加奈子がそこにはいた。大木は加奈子の髪からシャンプーの良い香りがする。
「あ、大木君・・・」
加奈子はそう言うと恥ずかしそうなしぐさをした。加奈子から何か暖かい雰囲気を感じる。
かわいい・・。
大木はそう思った。同時に大木も恥ずかしくなり、何を話せばいいのか分からなくなった。
加奈子は特徴のある大きな目で大木を見つめた。
綺麗な子だ・・・時間が止まったような感覚さえ覚える。
大木は自分と加奈子との間に、強く引き合う引力のような力を感じ始めていた。ゆっくり大木は加奈子に近づいてゆく。
加奈子も同じ感覚を覚えた。
加奈子はゆっくり目を閉じる。
そして大木は加奈子の唇にやさしく、触れるようなキスをした。
お風呂上りのの加奈子の唇は暖かくて気持ちが良かった。それは加奈子にとっても、大木にとっても初めてのキスだった。
十秒くらいだろうか、それとも三秒くらいだろうか・・・。
キスをした時間はどれくらいだったのだろう。
二人はゆっくり離れた。
二人はなんだか幸せな感じがした。
大木は今まで成功していなかったモーグルのエアが、この場で今すぐ成功するのではないかと思えるくらい幸せな気分になっていた。
大木はそういったハイな自分の感情を抑えつつ、加奈子に「おやすみ」と言って寝室に帰っていった。
加奈子は少しの間ぼーとしていた。
頬が赤くなってゆくのが分かった。
そして少しずつ我に返る。
加奈子も大木の後ろ姿を見送った後、あわてたように自分の部屋に帰っていった。
それはある春の日の、温かい深夜の出来事だった。
四条電気スキー部には、大木が登録されるまでモーグル選手は登録されていなかった。これまではジャンプとクロスカントリーを競う複合の選手が主体で、そういった意味では大木の存在は珍しい。
大木たちスキー部の人間は、合宿所のロビーに集合していた。ロビーの地方新聞を読んでいると「本日から立原市で四条電機スキー部が合宿に入る」と書いてあるの見つけた。オリンピックを経験した数人の選手と共に大木の名前も書かれている。
「天才高校生モーグラーの大木俊介さんも初日から合宿に加わる。大木さんは全く色を見分けられない特殊な障害を抱えており、スキー連盟と選手資格を議論して・・・」
その記事を読んで暗い気持ちになった。プロとなった今はそういう機会が多くなるに違いない。それを選んだのは自分なのだ。
目の前に広がる世界はどんなときも白と黒の世界だ。
絶対に負けたくない・・・。
少し自分が変わったような気がしていた。突然、昨晩のキスを思い出した。
やさしいキスだった。本当に心が満たされる・・・ただ、どうしてキスをしたのか、自分でもよく分かっていない。
あの子が好きなんだろうか・・・。
今朝、大木がバスに乗り込むとき、バス停まで送ってくれた加奈子は「練習、見にいってもいいかな?」と聞いてきた。
大木は即座に頷いた。
来てくれるだろうか。いつごろに来てくれるのだろう・・・。
「大木さん」
突然話かけられて、大木はびくっとした。振り向くと、そこには四条電機テクノの総務部の松田がいた。少し小太りで、暑いのかハンカチで額の汗を拭いている。
松田は大木に言った。
「今日三時からの工場の歓迎会ですが、挨拶をお願いできますか?」
「え? 僕ですか?」
「そうです。大木さんは、なんたって天才高校生モーグラーですからね。いい挨拶をお願いしますよ」
松田はそういってケタケタ笑った。
「いやいや、無理ですって」
「大木さんは春川さんの次ですよ」
「春川さんて、去年のオリンピックで複合の銀を取った超大物選手じゃないですか・・・その次なんて嫌ですよ」
松田はそれを聞いてまたケタケタ笑った。
「もっと自信もって下さいよ。大木さんの成績は十分なものですよ。それになんたって、四条電機と契約した初の高校生プロなんですから」
「うーん」
「僕もね、気になって、大木さんのモーグルスキーを動画サイトで見てみたんですよ」
大木には松田の目が急に輝いてきたような気がする。
「そしたら、感動しました。あの速さと力強さはすごい! いやホント」
調子がいい人だなあ。大木はそう思った。
「大木さんはまだ若いですけど、これから世界へと出て行く人です。いい挨拶を期待していますよ」
松田はそう言って、大丈夫と言うように親指を立て、急いでどこかに行ってしまった。
「うーん」
大木はため息をついた。そして参ったという顔をして、大木は犬山に事の次第をメールで送った。
気の利いた返事を期待していた。
大木君がスキー部歓迎会で挨拶か・・・大丈夫か?
犬山は歓迎会の会場に向かって、工場の白く長い廊下を歩いている最中だった。ついさっき大木からのメールで、歓迎会で大木が挨拶をすることを知った。
歓迎会に参加する人間は、この四条電機の子会社群の主任以上に限られている。そんな大人を相手に高校生が挨拶って・・・俺が高校生のときじゃ考えもつかないな。
それに・・・立原の人間は変わっている。いやな思いをしなければいいのだけど。
犬山は思い出していた。昨日自分のパソコンに貼ってあったA四の紙のことを。
「来たり者は本土に帰れ」
大きく赤色のマジックで書いてあった。
犬山は四条電機からの出向者だった。四条電機からの出向者はテクノなどの子会社の人間と異なり、昇進のスピードが早く、給料も良い。
一方で出向者への子会社の人間のねたみ、反発は強く、それがよそ者であると、さらに毛嫌いされる要因となる。こんな張り紙などはざらだった。足を引っ掛けられるという幼稚な嫌がらせもされたことがある。
短気な俺がよく我慢している・・・
学生の頃の自分、出向する前の自分を思い出すとまるで別人のように思えた。だが、我慢はできているが、悔しさは消えず、溜まる一方だった。大木はこぶしを握り、唇を噛んだ。
会場はもう近い。
大勢の人間が、犬山と同じ方向に歩いていた。主任以上の参加ということで、歳をとった人間が多い。その中で犬山はかなり若い部類に入っている。
会場に入ると、そこには四百から五百のパイプ椅子が置かれていた。小さい体育館くらいの大きさだ。制服から察するに、四条電機テクノだけでなく、他の建屋の四条電機デジタル、四条電機ビジョンからも人が集まっている。席はほとんど埋まっていた。
犬山が前の方に目をやると、去年のオリンピックで見たことのある顔ぶれが、横一列に並んで座っている。大木の顔もあった。座りきれず大木たちの後ろで立っている選手もいる。
まるで記者会見だな。
犬山が小さく手を振ると、大木も気づいて頭をペコンと下げた。
「それでは・・・」
四条電機テクノ総務部の松田が歓迎会の開会をアナウンスした。
各子会社の工場長が挨拶をしたのち、冬季オリンピックの複合に出場し、個人で銀メダルを取った春川が挨拶をはじめた。
「四条電気グループの皆さん・・・」
春川は呼びかける口調で話し始めた。さすがにこういった場が多いのだろう、話が上手い。
ただ・・・犬山は妙な違和感を覚えた。話は上手いのに・・・聴衆側が構えているというか、無反応というか・・・。
「昨年の冬季オリンピックの前に右足のじん帯を痛めたときは、もう駄目かと・・・」
違和感を覚えているのは犬山だけではなさそうだった。ときより混ぜる春川の冗談に対して、周りの反応が薄いのに不安を覚え、司会の松田も周りを見渡していた。春川も違和感を覚えた様子だ。
話が終わった後の拍手は少なくまばらだった。そのまばらな拍手の音を聞いて、犬山ははっと気が付いた。
そうか・・・
来たり者だからか・・・
どこまで閉鎖的なんだ。恥ずかしくないのか? この街はいつもそうだ。閉鎖的なことに何の意味があるというのだ。
犬山は急に大木が心配になった。
この閉鎖的で、陰湿な人間たちに妙なことをされなければいいがと思った。
「それでは次は、天才モーグラーの大木俊介くんの挨拶になります。大木くんは、国内のモーグルの多くの大会で優勝、もしくはそれに準じた成績を上げ、驚異的な強さで今シーズンを終えました。まだ高校二年生ですが、四条電機とプロ契約をした、若きスキーヤーです」
大木は椅子から立ち上がって、マイクを受け取り、まずはお辞儀をした。
「あの・・・こんな大勢の前でお話するのは初めてで、かなり緊張しています。大木俊介です。専門はモーグルスキーです」
大木はもう一度お辞儀をした。
「今日は歓迎会を開いていただいてありがとうございました。私はこのスキー部のメンバーで唯一のプロ契約という形で、四条電機の仲間となりました。プロ契約者として、四条電機の発展に貢献できればと考えています」
高校二年が言うセリフじゃないようなあ。
犬山は大木に感心しつつ、驚いてもいた。
「今後とも応援の程、お願い致します」
大木はそう言って挨拶を終えた。拍手はやはりまばらだった。そして椅子にすわろうとしたとき、遠くのほうでヤジのような声が飛んできた。
よく聞こえなかった。
大木はヤジの飛んできた方角で二人の大人が何か言い合いになっているのが見える。
一人は「ヤジを飛ばすのは止めろ」と言っている様子だった。もう一人は「関係なねえだろ」と言っているように見える。二人は言い合いになって、ヤジを飛ばした人間が、それを止めた人間に突っかかり、ついには手を出した。一方的に相手を殴っているような感じだ。
大木には、ヤジを止めた人間が犬山のように思えた。人だかりになって、もう良く分からないが、おそらく犬山だったのだろう。
かばってくれたのだ。ヤジの内容はよく聞こえなかったが、「生意気」「障害者」「契約金泥棒」のような単語が聞こえた。差別的な内容ばかりだった。
会場は騒然とした雰囲気となった。
テクノ総務部の松田は、大木からマイクを受け取り、静粛にするよう繰り返しアナウンスした。だが会場は静まることはない。
松田はもう一度静粛するようアナウンスをした。そして怒りを感じていた。
ばかじゃないのか、こんな騒動を起して。なんだあのヤジは。来たり者差別にもほどがある。立原事業所がばかの集まりと言っているようなものだ。
松田は未だざわめいている会場の様子をにらめつけるように見ながら、そう思った。
「くそっ」
あの四条電機デジタルの人間に殴られた頬が腫れて痛い。目の上も切れてガーゼを貼っている始末だ。気のせいか右肩も痛い。
夜になって犬山は自転車に乗り、会社を出た。
あのとき大木に差別的なヤジを飛ばしている人間が近くにいた。犬山よりも年上に見えたが、犬山は躊躇なく注意した。
だが結果はこんな感じだ。
何も得ていない、得られなかった。
犬山は昔から正義感が強かった。学生時代にもこういったたぐいの怪我は過去に経験がある。もっとも会社に入ってからは初めての経験だったが。
昼間の出来事でまだ心が動揺していたのかもしれない。犬山はいつもと違う道を選んでしまった。正確には道を間違えたのだ。
ふと道路脇を見ると、二階建ての家くらいの高さはあるかと思われる立看板が、七枚並んで建ってあるのが見れた。どれも新しく、白地に黒で文字が一文字づつ書かれ、ライトアップされていた。
犬山はそこに書いてある文字を読んで、ぎょっとした。その後、強烈な、言いようのない恐怖が彼を襲った。
「日本からの独立」
そこにはそう書いてあった。
犬山は何かに巻き込まれてゆくような感覚を覚えた。この街が不気味に思えた。立原の街は街灯が少なく夜は暗い。明かりがなく、吸い込まれそうな黒い世界が広がっている。
犬山は逃げるように自転車をこぎはじめた。突然、自転車の電灯が切れた。そして周辺が真っ暗になる。焦りから、右と左、上と下の感覚がなくなってゆく・・・。
そして何かに敗北した感情に飲み込まれた。それだけの衝撃をあの看板は犬山に与えた。
急いで携帯を取り出す。何かせかされる思いで大木にメールを打とうとした。一瞬ためらったが、すぐにメールを打ち始めた。
「この街は狂ってる。僕は会社を辞めるかもしれない。この街にもういたくない。僕一人では無理だ。孤独に耐えられない」
犬山はそうメールを打つと言いようのない敗北感に押し潰される感覚を覚えた。
この街はおかしい・・・しかも個人でどうにかできるレベルじゃない。負けて逃げるしかないのか!
犬山はそう思うと自分の正義感と誇りに申し訳なく、嗚咽に似た泣き声を漏らした。
それは暗闇で誰にも聞かれることのない悲しげな泣き声だった。
街に黒い世界が広がっていた。
第3章
「あなたの夢はなんですか?」
どこからか声が聞える。
加奈子は自分がどこにいるのか分からなかった。宙に浮いているような感覚だ。今が昼なのか朝なのかも全く分からない。
また声がした。
「あなたの夢はなんですか?」
子供の声だろうか? 女の子の声のような感じだ。加奈子は声のする方角を見たが、そこに誰かがいるような気配はなかった。
不意に加奈子は足が地に付いたような感覚を覚えた。加奈子はそこを足がかりに歩き始めると世界に少し濃淡が付いてきた。道路のようなものが見える。川べりのようだ。
「あなたの夢はなんですか?」
またあの声だ。加奈子は声のする方角に振り返った。
そこには見たことのある光景が広がっていた。あの夜の出来事が再現されはじめていた。男が子供のような影を穴に放りこんでいるのが見える。そしてまた一人の子供を放りこむのが見えた。
加奈子は自分の呼吸が荒くなってゆくのを感じた。胸を締め付けるような苦しさがやってきた。
「あなたの夢はなんですか?」
あの声がまた聞こえた。
そうか・・・うん、そうか。きっとあの子供たちが言っているのだろう。自分の未来を強制的に終わらされた無念さがそうさせているのだろう。
呼吸が速くなっているのが分かる。熱が奪われ、体温が下がって行く。苦しい・・・ここから逃げださないと私は倒れてしまう。
そう加奈子が思ったときに、加奈子の目が覚めた。
加奈子はゆっくりとベッドから身を起こす。呼吸が荒い・・・汗も相当出ている。長い時間うなされていたのだろう。
一昨日、遺体は見つかった。いったい誰が通報したのだろう。そしてその誰かはもう一つの犯行も通報している。
私は何もしなかった・・・そのことで心に傷が入ってしまったみたいだ。昨日の夜も同じような夢を見た。そして同じように夜中に目が覚める。
時計を見た。午前四時・・・加奈子は階下に降りた。
「ふう」
加奈子は溜息をついた。
加奈子は台所の蛇口から水をコップに注ぎ、ゆっくりと飲んだ。遠くで新聞配達のバイクの音が聞こえる。動いては止まって、動いては止まる音だ。
廊下に出ると大木のことが思い出された。
ここで大木君とキスをしたんだわ。
あのとき何故大木とキスをしたのかよく分からなかった。大木が好きなのかどうか分からない。だが、大木に強い引力のようなものを感じたのだ。
でも彼はここに二週間しかいない。そして彼の目には、私の姿はおそらく白黒の映像でしか映っていない・・・。
そう思うと何か複雑な思いがした。
自分の気持ちが良く分からない・・・惹かれているかもしれないけど・・・。
加奈子は静かに二階の自分の部屋に戻った。そしてカーテンを開け、まだ暗い外を眺めた。
この真っ暗な世界が、これから明るくなり、いつもと同じように朝が来る・・・。
本当に朝は来るんだろうか? 朝が来たらこの暗い世界は全く無くなってしまうのだ。
加奈子には、それがとても不思議なことのように思えてならなかった。
この日の大木のトレーニングは、午前中に背筋強化の筋トレを行い、午後は複合の選手と一緒に七十キロの自転車漕ぎを行うことにしていた。
「幾つかの小さい山を登っては降りて、登っては降りての結構過酷なコースだよ。まあ大木君は若いから問題ないかな」
複合のコーチの田沢は笑いながら言った。黒ふちの眼鏡で、短髪だという以上に、辛くて大変な練習をさらっと指示するのが彼の特徴だった。去年の秋の合宿もそんな感じだった。
いやいや、それ、結構つらいですって。
大木は田沢の笑いにつられるように苦笑いをしながらそう思った。
「他の連中は複合選手だから、あっという間に差をつけられるかも知れないけど、まあ頑張ってみて」
田沢はそう言って励ますように肩をポンと叩いた。
空は少し雲が多かったが、天気予報では雨は降らないと言っていた。窓からは雲がゆっくり動いているのが見える。
大木は午前中のジムでの筋トレを終えるとすぐに携帯を持って外に出た。そして合宿所からグランドに降りるコンクリートの階段に座った。
携帯でメールの確認していた。
一昨日夜の犬山のメールに大木はすぐにメールを返した。
だが、犬山からの返事はない。それどころか、今や犬山とは電話すら繋がらなくなってしまっている。
犬山の身が心配だった。メールの内容がネガティブなものだったのも気になっていた。
大木はゆっくり顔を上げ、流れる春の雲を眺めた。
どうしてしまったんだ・・・犬山さん・・・。
その寂しげな背中が合宿所から見える。春川は足を止めた。
「大木の奴、飯も食わずにあそこで何やってるんだ?」
食堂に向かっている途中だった。春川は横にいた複合コーチの田沢にそう言った。田沢は窓の外に目をやった。携帯を手にして、ぼんやり空を眺めている大木の姿が見える。
元気がないな。
田沢は大木の様子にそう思った。
「元気なさそうですね。彼女にでもメールしているのかな? 振られたとか」
「あん? 大木に彼女なんていたっけか?」
「さあ?」
田沢はとぼけたように答えた。春川はその様子を見て笑いを漏らした。
田沢は春川より三歳年下の三十代前半だったが、何故か気が合う。この田沢という男は、元々は陸上自衛隊の人間で、クロスカントリースキーの選手をやっていた。そこそこ強い選手だったが、膝の怪我で選手を引退し、そのとき自衛隊も退官した。それ以来、四条電機スキー部のコーチをしている。
その田沢はふと思い出したように春川に言った。
「そういえば、この間の四条電機テクノでの歓迎会、なんか異常な雰囲気でしたよね」
「ああ・・・」
春川は自分と大木が挨拶したときの聞き手の反応を思い出した。あんな冷たい反応は初めてだった。聞き手たちは明らかに反感を持って聞いていた。
「排他的だったな。俺のときもそうだったが、大木君の挨拶のときはもっとひどかった。差別的な言葉は出るし、喧嘩は起きるし」
「とても正常な人間とは思えませんでしたよ」
「だよな」
「大木君はまだ高校生ですよ。その彼に大の大人が無神経な野次を飛ばしているのはどうかしているとしか言いようがない。大木君はよく我慢したと思っています」
田沢の声は怒っていた。その様子を見ていた春川はふと思い出したように言った
「そう言えば・・・あの野次を止めた奴って、前、営業でスキー部の広報担当だった犬山に似ていなかったか?」
田沢は大きく頷いた。
「あれは犬山さんでしたよ。よくぞ止めてくれたと思いました」
「そうか、やっぱり・・・あいつ、昔から妙に正義感が強いところがあったからな・・・」
春川は腕を組み、あごの髭を左手で触りながらそう言った。
「けど、今回はその正義感は裏目に出ていたな。結局は喧嘩になってしまったし」
「・・・ですが、私は犬山さんを尊敬していますよ」
春川は少し驚いた表情を見せた。そして軽く頷いた。田沢は言葉を続けた。
「私がクロスカントリースキーの選手を引退して、自衛隊を退官したとき、コーチに誘ってくれたのが、犬山さんだったんです。あの頃は嫁と結婚したばかりでしてね。本当に助かりました」
田沢は照れくさそうに笑った。
「大木さんは本当にいい人だと私は思っています」
「そうだな・・・」
春川はそう返事をして、少し考えた。そしてぽつりと
「犬山の奴、ここで上手くやっていけているのかな?」
と呟いた。
「ここの工場、というかこの街って、なんか排他的っていうか、よそ者に対して攻撃的というか、なんか変だよな」
「そうですね・・・犬山さんなら大丈夫と言いたいところですが、多分難しいでしょうね」
田沢はそう答えた。そして言った。
「凛の民だからですかね・・・」
「凛の民? ああ、この地方に多く住んでいる」
「閉鎖的なのは凛の民だからですか?」
「そうじゃないの? 凛の民が閉鎖的なのは今に始まったことじゃないし、昨日のニュースじゃあ、独立派がどうのこうのって言っている。余り感心しないよな。自分勝手なことばかりで、争いばかりを招く。それで実際に何が得られるって言うんだ?」
春川の言い方は強く、怒っているようだった。田沢も同感だった。そして言った。
「来週の市役所に訪問する件、聞いていますか?」
「ああ・・・聞いている。市長に表敬訪問するんだっけ?」
「そうです。立原市側から、参加者として春川さんをはじめとしたオリンピック経験者を要請されていました。こちらから大木君も加える旨を伝えたらですね・・・」
田沢は窓の外の階段に座っている大木を見つめながら言った。
「先方に断られてしまいましたよ。大木君は遠慮してほしいと。選手資格すら怪しい人間に来て貰っても困ると言っていました」
「大木を差別しているのか?」
即座に春川は反応した。怒っているのが十分に分かる。
「私も怒りを覚えています。凛の民はちょっと・・・いや、かなり変わっていますからね。そういった差別的な発想が堂々と出たのでしょう」
田沢はそう答えた。田沢は凛の民が嫌いだった。彼は子供の頃、父親の仕事の都合で一年だけK地方に住んでいた。彼らは排他的で、閉鎖的で、独善的で、他者を平気で傷つけ、その上自分の権利は強く主張していた。
子供ながらこの民族は最悪だと思っていた。そしてそれが一部の人間のものとはとても思えなかった。凛の民全体がそういう人間の集まりのように思えて仕方がなかった。
田沢は廊下の窓から階段に座っている彼を見た。ゆっくり立ち上がり、合宿所の建屋に向かう様子が見れた。
そして彼は加奈子の家での加奈子とのキスを思い出していた。それは高校生の彼にとって始めての経験だった。
加奈子の大きな目を思い出す。風に揺れる加奈子の長い髪も思い出していた。
弱い風が吹いている。
白い風船が一つグランドに流れてきた。その突然の存在に強い違和感を持ちながら、大木はその風船を目で追った。
風船は空高く浮いたかと思った瞬間、風でグランドに押し戻され、また空へ向かって浮き上がってゆく。
何処から流されてきたのだろうか・・・そして何処へ流されて行くのだろうか・・・。
大木はぼんやりそれを見ていた。
七十キロの自転車トレーニングは予想以上に辛い。
おそらく大木一人での練習であったら、こんなトレーニングは取り入れなかっただろう。
「有酸素運動は持続力のある体力を作るのに良いんだよ」
複合コーチである田沢は教えてくれた。いろいろ勉強になる。
複合の選手と一緒の練習だったが、彼らの持続力は半端がない。幾つかある山の最初の上り坂で、あっというまに引き離された。
「すごいな」
それからの残り五十キロは一人で走った。そしてあと二キロ程で合宿所に着く。
大木は自転車を漕いでいた。
「それにしても、あの犬山さんの会社を退職するっていう弱気のメール・・・」
歓迎会で僕をかばったために周りに攻撃されたのだろうか? 劉前さんが遭遇した事件もそうだが、この街はなにかおかしい。
空は今にも降りそうな曇り空だ。天気予報では雨は降らないと言っていたが、本当だろうか?
そう考えた瞬間に大粒の雨が頬に当たった。そして雨粒は絶え間なく落ち始め、やがて春の大雨となった。
大木が合宿所に到着し、敷地に入った。そして異様な様子にぎょっとした。
合宿所の駐車場に警察の車が数台止まっている。そして何人もの警官が寮の中に居るのが見えた。
「なにかあったんですか?」
大木は合宿所の建屋に入るとすぐにコーチの田沢にそう聞いた。
「おっ到着したな。大木君、雨大丈夫だった?」
「駄目でした。あともう少しというところで降られました」
そう言っているそばから、髪の毛から雫がぼたぼた落ちている。
「そっか。風呂に入って、体を温めといた方がいいな」
「はあ、あの・・・何かあったんですか?」
大木は寮の様子を伺いながら、もう一度田沢に聞いた。
「いや・・・良くは分からないのだけど、寮で家宅捜査をしているみたいなんだわ」
「家宅捜索・・まじですか?」
「そうみたいだね」
「寮の家宅捜査って・・・四条電機の人が疑われているですよね。何の事件なんですか?」
大木は少し不安を感じながら、田沢に聞いた。
「いやあ、良く分からないんだわ。今、春川さんと監督が聞きに行っている。帰ってきたら、もう少し詳しい情報が入ると思うよ」
大木はすぐにでもその情報を聞きたかったが、寒気が少ししてきた。田沢のアドバス通り風呂に行こうと思ったとき、寮の建屋から春川が帰ってくるのが見えた。
「春川さん」
田沢が春川に声を掛けた。
そして大木は春川の顔を見て驚いた。春川の顔が真っ青だったからだ。何か嫌な予感を感じざるを得ない。
春川の足取りは弱く、今にも倒れそうだった。春川は倒れるようにロビーにあるソファに座った。
「どうしたんです、春川さん」
大木が春川に駆け寄って言った。次々に他の部員が春川の周りに集まってくる。
春川は横目で大木を見た。
「犬山さんの部屋が家宅捜査されている・・・」
大木は衝撃受けた。
「犬山さんの部屋・・・家宅捜査・・・」
春川は大木の驚く様子をみて呟いた。
「無理もないか・・・」
「いったいどうなっているんですか? 犬山さんは何の罪で疑われているんですか?」
大木は動揺して、上手くろれつが回らない。不安がどんどん大きくなってゆく。
「信じられない話だが・・・犬山は立原市内で起きていた弁護士一家四人の死体遺棄の罪と、別件の死体遺棄の罪を疑われているらしい・・・」
「そんなばかな!」
大木は周りが動揺する程の大声で否定した。
劉前さんの見た犯人は複数だ。この立原で孤独を感じていた犬山さんが犯人の訳がない。
大木の後ろに立っていた多くのスキー部のメンバーが大木の声に反応した。「行方不明? 何の事件?」とか「犬山さん?」といった声が聞こえてくる。
「ここ連日ニュースで流れていたあの事件か・・・」
田沢はそう呟いた。
「それで、犬山さんはなんて言っているんですか?」
大木は急かすように春川に聞いた。
「それが・・・犬山さん、行方不明でな。警察は捕まるのが怖くて逃げているんじゃないかって言っていたよ」
春川は声を絞るように答えた。
「そんなばかな・・・」
突然、大木は携帯を取り出した。そして犬山の携帯番号に電話を掛けた。
「電源が入っていないか、圏外に居るかのどちらかで・・・」
そんな機械音が聞こえた。その機械音を聞いて大木は両膝を床に落とし、うなだれた。動揺して、自分を支えていた全てを失ったように見える。
「大木君・・・」
田沢は大木の側に屈み、声を掛けた。
「犬山さんの携帯・・・繋がりません」
大木は田沢を見て言った。
田沢は小さく二、三回頷いた。
そして犬山の友人でもあるこの高校生の十七歳の青年に掛ける言葉を必死で捜していた。
家宅捜査は終わったようだった。
寮から警察の人間が引き上げてゆくのが、合宿所の窓からも分かる。春川は窓際に立ち、その様子をじっと見ていた。
合宿所のロビーは沈黙に支配され、重い空気だった。その空気に耐えかねたのか、他の部員は各自の部屋に帰ってゆくか、ジムの方に消えてゆくかして、合宿所のロビーには春川と田沢と大木の三人だけになった。
大木を濡らした雨は既に止んでいて、大木の髪の毛ももう乾いていた。
「僕は・・・」
大木は力のない声で突然話し始めた。その声に春川は振り向いた。
「僕は・・・犬山さんのおかげで四条電機とプロ契約をすることが出来ました・・・」
大木の視線は下を向いたままだ。
「その頃、犬山さんは営業で、僕は高校一年生で、連盟からは僕の目が競技に危険という理由で、大会出場の辞退を求められていました」
その言葉で田沢もその頃を思い出した。いきなり営業の犬山が来て、大木という高校生とプロ契約を結ぼうと言ってきたのだ。一人で上層部と掛け合ったという噂もあった。
「スキー連盟の狭い了見で埋もれてしまうには惜しい人材です」
犬山はそう言って説得を続けた。スキー部広報を兼務しているとはいえ、犬山がスキー部の人事に干渉するのは行き過ぎの感があった。だが、犬山はいろんな部署のいろいろな人間と交渉し続けた。
田沢も犬山からコメントを求められ、大木の滑りの動画を見させられたときは震えが止まらなかったことを覚えている。
「逸材だ・・・連盟の連中の目は節穴だ」
田沢はスキー連盟の一部の理事に白黒しか見えない大木の目を気味悪く感じている人間がいることを知った。そして犬山の強い正義感に感心し、大木のスキーの実力を認め、プロ契約を結ぶべきだと考えた。
四条電機とプロ契約したことで、大会出場の辞退は求められなくなったようだ。だが今後の大会参加は今期の結果を見て議論という形になっていると聞いた。
そういう状態ですら、大木にとって大きく前進している状況だと言えた。
「犬山さんは僕を助けてくれました」
大木は春川と田沢にそう言った。
「あんなに人のために頑張れる人が、犯人だなんて絶対にありえません」
春川は大木の声にはっとした。声が力強くなっている。
「僕は信じています」
その様子から一旦動揺して揺らいだ信頼が、既に大木には戻ってきているようだった。
ああそうか・・・。
春川はそう話をしている大木を見てそう思った。
スキー連盟からの終わることないストレス、自分の目の障害に対するコンプレックスに耐えていられるのは、大木の前向きというべきか、折れても立ち上がれる強い心のおかげなのだろう。
大人である春川が、いまだ折れた心を立て直せないでいるは、自分でも情けなかった。
田沢は別のことを考えていた。一つ気になっていたことがあったのだ。そして両手で黒ふちの眼鏡をかけ直し、口を開いた。
「あの事件、そもそも一人で出来る犯行なのだろうか・・・」
それを聞いて、少し躊躇い、大木は言った。
「犬山さんは排他的なこの街で孤独に苦しんでいました。僕に送ってくれたメールにそういった内容のメールがありました・・・」
そう言ってすぐに大木は後悔に似た感情を覚えた。犬山の名誉を傷つけてしまったように思えたのだ。
そしてそれを聞いた春川は、強いショックを受けた。
あの犬山がそういった状況に追い込まれるなんて・・・。
歓迎会で感じたこの街の排他的な嫌な雰囲気を思い出した。
この街の排他性が大木を孤独に追い込んだのか・・・。
強いショックは強い怒りに変わった。そして
「大木が・・・一人の協力者がいない状態で複数の人間を殺害し、死体を遺棄できるものだろうか?」
と言った。
それを聞いた田沢も頷いた。
思い出した。
「そういえば・・・犬山さんは車の免許を持っていない・・・」
春川と大木は田沢を見た。
「前に犬山さんが営業の頃に一緒に飲みに行ったことがあります。そのとき学生時代に免許を取らなかったのを後悔していると言っていました」
そして続けて言った。
「孤独に悩んでいて、車をもっていない人間が、何人もの死体を遺棄するなんて不可能です」
それを聞いて大木は少しの安心を感じた。犬山の無罪が証明されたような気にもなった。
「それと犬山さんの異動は半年くらい前の話です。犯行が行われたのが四ヶ月前ですから、犬山さんは転勤してからわずか二ヶ月で犯罪に手を染めたことになります。動機を設定することすら難しい気がしますが」
田沢は更に言葉を続けた。
「それに犬山さんの性格からして、疑われたから逃げるということはないはずです。だから、今犬山さんの行方が分からないというのは・・・」
「事件に巻き込まれている・・・」
春川はそう呟いた。
おそらくそうなのだ・・・。
大木が窓から空を見るとあれだけ降っていた雨は止み、雨雲も消え、きれいな星空が見えている。大木は空の移り変わりの速さに多少の不気味さを感じながらも、きれいに輝く星をじっと眺めていた。
空の星は輝いている。人の小さい感情の動きとは無関係にキラキラ輝いている。
嫌な予感がしてならなかった。
大木は眠れないでいた。時計は既に一時を回っている。暗闇の中で目覚まし時計の時を刻む音が響いていた。
テレビのローカルニュースは、死体遺棄の容疑者自宅を警察が家宅捜査した話で持ちきりだった。大木はそのニュースを不快に感じたが、容疑者の名前はまだ明かされていないのが唯一の救いだと思った。
警察は証拠固めがまだ十分ではないと考えているのだろうか?
少し調べれば、犬山さんに免許がないことが分かる。それだけでも疑いはすぐにでも晴れるはずだ・・・。
ニュースでは「凛の民族の独立論に反感を持った容疑者の犯行」と言っていたが、それだけでも犬山の犯行ではないように思えた。
大木には何故犬山が疑われているのか、理由が全く分からなかった。
ありえない選択としか思えない。
大木はそう思っていた。
加奈子もそのニュースを自宅のテレビで知った。ニュースでは青年一人と、加奈子が目撃したあの弁護士家族の四人を死体遺棄した容疑者の家宅捜査が行われたと言っていた。容疑者は県外から来た人間らしかった。
凛の民族の独立を唱えている被害者に一方的に反感を抱いての犯行と言っていたが、加奈子には現実感のない動機に聞こえた。
「違う・・・」
ニュースでは単独犯の犯行と言っていたが、加奈子の目撃したのは複数だった。明らかに異なる。
そもそも独立派って、なに? そんな派閥があったなんて、初めて聞いたわ。
部屋の時計の針は夜中の一時を既に過ぎていた。
そろそろ寝よう・・・。
加奈子は心にあるこの違和感と不安を誰かに話したかった。真実が隠されるという強いストレスに似た感情が、序々に自分を押し潰してゆくのを感じていた。
大木に会いたかった。そして話をしたかった。
そのとき大木は、寮の食堂の自動販売機で飲み物を買っていた。
全く眠れなかった。
大木は食堂の電気をつけず、窓を開け、食堂の椅子に座り、窓の外の星を見上げた。
暖かい春の風が強く吹いていた。
この風が雨雲を吹き飛ばしたのだろうか。
大木の髪が風になびく。
携帯で再び犬山に電話をしてみた。コール音が聞こえたかと思うとすぐに機械音の留守電に変わる。
「いったい何処にいるんだ・・・」
大木はそう呟いた。
無事でいるのだろか・・・いや無事でいてほしい。無事に違いない。
強く思った。
そして大木は加奈子があのニュースをどう見たのか気になっていた。
当然、現在逃走中の県外出身の容疑者が犯人だと思っただろう。いや、でも・・・果たしてそう思うだろうか・・・。
ニュースの内容は矛盾が多い上に、何よりも加奈子の目撃と異なる。ニュースでは「犯人は単独だろう」という警察のコメントを流している。
大木は加奈子に会いたかった。
真実と異なるニュースは加奈子に強い不安を覚えさせていた。
突然、強烈な眠気が彼女を襲う。それは抑えつけるような強制的な眠気だった。加奈子はなんとか蒲団に入り、横になった。
その途端、少女のような声を耳にした。
「あなたの夢はなんですか」
ああ、あの夢か・・・加奈子はそう思った。
「あなたの夢はなんですか・・・」
また声がした。加奈子はこの問いに答えたことがない。答えるのが怖かったのだ。
少女のような声の問いが二回あったが、いつもと違い、あの死体遺棄の事件があった川べりの風景に移らない。気がつくと加奈子は、濃淡のない緑色の世界に加奈子は居た。
大木は強烈な頭の痛みに襲われた。目を閉じ、手で頭を抱えていたが、周りの様子が何か違うと感じた。目を開けると、自分の周りの全てが緑色の世界に染まっていた。
自分の目が色を認識している・・・。
大木は頭痛に耐えながら周りを見渡した。食堂の窓が消え、机が消え、椅子が消え、やがて全ての物が消え緑色だけの世界になった。
大木は椅子が消えた拍子に床に転がったが、やがてはその床の感覚すらもなくなった。
前に一度、この緑の世界、経験をしたことがある。あの雪崩の遭難者を助けたときだ・・・。
耐え難い頭痛の中で大木はそれを思い出していた。呼吸することも苦しく、肩でするような息をしばらくしていたが、やがて頭痛は治まり、呼吸も楽になっていった。
大木は遠くに人影を見た。
間違いようがない。
加奈子だ。
だが、この緑の世界であっても、大木の目では加奈子は白と黒の色でしか彩られていない。大木はその事実に深い溜息をついた。暗い気持ちに支配されそうな気がしたのだ。
加奈子も大木に気づいた。
流れのようなものを感じる。ゆっくりだが、お互いの距離が近づく。そして手が届きそうな距離になると、その流れは急になくなった。
「夢の中・・・なの?」
ただ夢にしては大木の輪郭がはっきりしている。この緑色も鮮明で目に痛いくらいだ。
夢ではないような感じがする。
「いや・・・夢の中じゃない。僕はさっきまで合宿所の食堂にいたんだ」
「じゃあ・・・ここは?」
「分からない・・・急に頭痛がして、この緑の世界が広がっていたんだ・・・」
加奈子は大木の言葉に驚いた。
「大木君、この緑が分かるの?」
大木は少し考えて言った。
「分かる。前もこんなことがあった。頭痛がして周り緑一色になって・・・」
そして表情を硬くし言葉を続けた。
「だけど劉前さんは・・・この緑の世界でも白黒でしか判別できていない・・・ごめん」
加奈子は大木の言葉にはっとした。大木の言葉から、大木の悲しい気持ちが伝わってきた。
「大丈夫よ。大木君」
加奈子は出来るだけ明るい表情でそう言った。
「大丈夫、大木君」
もう一度言った。
しばらくの沈黙があった。
やがて大木は話を始めた。
「あの死体遺棄の事件だけど・・・」
大木は黙った。やはり話すのは躊躇われる。
「疑われているのは・・・僕の知り合いなんだ」
加奈子は驚いて小声で「え」と言ったが、驚きの表情が顔に出るのを抑えた。大木の苦悩する表情が見て取れたからだ。
「僕の恩人なんだ・・・いったいどうして犬山さんが疑われているのか・・・僕の目は白と黒しか判別できない。犬山さんはスキー連盟の圧力から僕を救ってくれた人なんだ」
大木は下を向き、そう言った。泣きそうな表情にも見える。それを見て加奈子は言った。
「私もその犬山さんという人が犯人ではないと思う・・・あのニュース、そもそも動機に無理があるわ」
その言葉で、大木は救われた気持ちになった。
「ニュースでは単独犯と断定していたけど、私が見たのは複数の人間だった。明らかにあのニュースはおかしいわ。まるで・・・」
加奈子はその先に言おうとしていることが正しいのか分からなかった。大木は加奈子の顔を見て、次に続く言葉を待っていた。
「まるで・・・その犬山さんを無理やり、犯人に仕立てているような気がする」
大木はその言葉に打たれるような衝撃を受けた。
警察が犬山さんを無理にでも犯人にしようとしている。にわかには信じられないが、言われれば合点がいく点が多い・・・。
大木は加奈子にいろいろ聞きたい。
考えをまとめていた。だが、話をしようとした瞬間、大木の周辺は一瞬にして寮の食堂に戻った。
「・・・」
まるでテレビの画像がいきなり切れてしまったかのようだ。大木は食堂の椅子に座っていた。
当然、加奈子はいない。
「夢・・・だったのか?」
戸惑いながら自問自答した。とても夢とは思えない感覚が大木には残っている。大木はしばらく呆然としていたが、やがて席から立ち、自分が開けた窓を閉めて鍵を掛けた。
不安で寂しい感情に襲われていた。加奈子に会いたいと思った。
本当にそう思った。
第4章
犬山の部屋の家宅捜査が行われたのと同じ日、四条電機テクノにも捜査員は来た。彼らは犬山のパソコンと机のもの、ロッカーに入っていたもの全てを押収していった。
加奈子の母親は複雑な気持ちにさせられた。
犬山に死体遺棄の容疑が掛かっているという噂が、社内を飛び交い、犬山に反抗的だったメンバーは一連の様子をにやにやと眺めていた。加奈子の母親はその様子を見て気分が悪くなった。
そして思い出した。かつて自分が犬山の身の安全を心配していたことを。
もしかしたらあの連中が、犬山さんが犯人だという嘘の通報したのではないか?
あの連中は正義も何もない。それどころか、行方が分からないとされている犬山さんの居場所も知っているかもしれない。
「いい気味だぜ、ざまあ見ろ」
彼らは何もなくなった犬山の机にはき捨てるようにそう言った。
この連中は何か知っている。
それは直感だった。とても犬山が死体遺棄の疑いを掛けられるような人間には思えなかった。誰よりも正義感が強く、それは考えられないと思った。
それに最初の犯行とされる事件は、犬山さんが立原に来てからわずか二ヶ月後の事件だ。常識的にありうるだろうか?
「劉前さん、事情聴取、劉前さんの番だよ」
加奈子の母親ははっとして振り返った。
「はい・・・」
そう返事をして、警察の待っている会議室に向かった。警察というだけで無条件に緊張する。次第に手が冷たくなり、感覚がなくなってきた。
自分の感じている違和感を伝えるべきなのだろうか?
自分の意思を決定出来ないまま会議室に入った。待っていたのはスーツ姿の三十歳台の若い男の二人組だった。
「県警の須藤といいます。隣は同じく県警の上田です」
そう言って二人は頭を下げた。少し早口であるのが気になった。
「早速ですが、犬山さんの人なりを教えてください。まあこれまで聞いた限りでは、相当の問題児だったようですが」
そう須藤と名乗った警官が言った。目つきの鋭い人間だ。その言葉を聞いて、加奈子の母親の心に妥協をしてはいけないという思いがよぎった。
「そんなことはありません。犬山主任は正義感が強く、良い方だったと思います」
「そうかなあ、他のメンバーの方は、皆さん否定的な発言ばかりでしたよ」
「犬山主任は東京出身の方だったので、凛の民には反感を持たれやすかったのだと思います」
目の前にいる警官二人は顔を見合わせ、この人は何を言っているのだろうという仕草を見せた。
「凛の民はそんなことで人間を否定しませんよ」
上田と紹介された警官は、そうたしなめるように言った。加奈子の母親はそれに対し、強い声で反論した。
「チームのメンバーは犬山主任に対して、陰湿ないじめを繰り返していました。若いよそ者がリーダーとなっていることが気に食わなかったのでしょう。でも犬山主任は耐えていました」
「違いますね。つい先日は口論になって掴み合いの喧嘩になったと聞いていますよ」
「それこそ違います。口論になってはいましたが、メンバーが一方的に犬山主任を殴っていたというのが本当です」
加奈子の母親は引かなかった。が、上田は加奈子の母親の言葉を鼻で笑った。
「だいたい、大人になってもいじめられるっていうのは、犬山自体にそういう理由があったのではないのですか? まあ凛の民はそんな卑劣なことはしないはずですけどね」
なんなの・・この警察の一方的な見方は。しかも私が言ったことはメモに取らない上、録音もしていない。
この警官たちは信用ができない。
「あなたは凛の民ではないですよね? 本籍はこの立原市になってはいますが」
須藤と名乗った警官はいきなり質問した。眼鏡を掛けたその目は何か観察をするような目つきだった。
加奈子の母親はその質問にぎょっとした。警察が聞くような質問には思えなかったからだった。
「凛の民ではありませんが、凛宗の檀家です。それがなにか?」
自分を抑えて、その意図が分からない質問に答えた。
「ああ、そうでしたか。いや、それだったら構わないんですよ。来たり者は犯罪に手を染める奴も多くて、交通事故もよく起こすのでね・・・」
須藤は机に手を組み、加奈子の母親を正面から見た。そして言った。
「劉前さん、我々は日本に頼らず、日本からの独立を目指した方がいいと思ったことはありませんか?」
突然の、しかも全くの唐突の言葉に加奈子の母親は驚いた。
「何を言っているんです?」
それに対して須藤は落ち着いて答えた。
「凛の民は大陸から来た人間です。その関係を使って、このK地方は日本に頼るのを止め、大陸に帰属した方がいいのではないか、と聞いているのです。日本での我々凛の民の歴史は差別と虐待の歴史でした。特に戦時中は炭鉱、軍需工場などへの強制移動、そして強制労働・・・今はこの四条電機に搾取される構図」
須藤は間を置いた。
何を言っているのかしら・・・。
そう考えていることが顔の表情に表れていた。須藤は加奈子の母親の批判的な反応を見て、軽い溜息をし、突き放すように
「もうご自分のお仕事に戻っていいですよ」
と言った。
メモも録音を取られない事情聴取はいきなりそこで終わった。加奈子の母親は憤慨に似た感情を覚えたが、黙って席を立った。そして部屋から出ようとしたとき、もう一人の警官である上田が発言した。
「いやいや、失礼。我々は今回の事件のように、凛の民の独立運動を阻害するような犯罪に憤りを感じているのですよ。今回の被害者は皆、凛の民の独立を切に願った方々でした。それを来たり者の心無い人間が阻害してしまう・・・それは決して許されることではありません」
加奈子の母親は彼らの発言についていけない気がした。
ここ一昨日のニュースからだ。ここ最近の独立、独立の雰囲気は異常だ。会社でもひそひそと話しているのをよく見る。テレビのローカルニュースも独立を推進する発言が急に多くなっている。
「独立推進派」とされる人間を来たり者の人間が殺し、死体を遺棄したというニュースが火付け役と思われた。
加奈子の母親は溜息をついた。
「例え独立したとしても、経済はどうするのですか? 四条電機だって独立したての国に工場をそのまま置くとは思えませんが」
「月岡先生の本を読んでいないんですか?」
上田はそう返した。ばかにしたような言い方だった。
「月岡先生・・・?」
「K大学経済学部の月岡先生ですよ。現在日本の負債は約九百兆円にもなるのはご存知ですよね。このまま行けば数年で経済破し、IMFの傘下に組まれてしまうかもしれません。そうなれば、所得税、法人税、消費税の税率は今より大幅に上がることになるでしょう」
上田は得意げに語っていた。
「そんなお先真っ暗で、法人税で二十五%も取られる国に未来はありますか? 財政再建も出来ず、ただ終わりを待っている。K地方の人口は約千五百万人いますが、凛の民の割合が多く、このK地方を独立させ、凛の民の国とすれば、負債に恐れる必要のない、健全な国をつくることができるでしょう。凛の民の国ということであれば、大陸からの支援も期待できます」
「そんな・・・」
K地方は凛の民族が多いというだけで日本人は当然多くいる。むしろそっちの方が圧倒的に多い。立原市ならまだしも、そういったK地方を凛の民の国として、国を運営することは無理ではないのか? 大陸を嫌う人間だって多くいる。
「まあ、今日はそんな話をするために来て頂いた訳ではないのでしたね。でももう少し勉強された方がいいですよ」
この上田という人間の言い方はどこまでも嫌な感じがした。
「最後に・・・犬山の潜伏先とか知っていたら教えてほしいんですがね」
「いや、分からないです」
加奈子の母親は即答した。この二人の人間は自分が正しいことを言っていたつもりなのだろうか? 犬山主任への偏見、身勝手な独立論・・・。
「失礼します」
そう言って、加奈子の母親は部屋を出た。気分が悪くなる事情聴取だった。
犬山のチームの人間が数人歩いているのが、遠く廊下の先で見えた。彼らは私服に着替えている。
そういえば凛の祭りの準備で早退すると言っていた・・・。犬山主任を陥れることばかりをやって、自分に恥じるものはなかったのだろうか? いい大人が妬み、いじめを行うことに何の躊躇いもなかったのか?
加奈子の母親は事務所にゆっくりと帰りながらそんなことを考えていた。廊下の窓から麓の立原の町並みがよく見える。
彼女が立ち止まってそれを眺めていると、軽い立ちくらみに襲われた。目の前が一瞬白くなった。
自分は誰なのか? 名前、家族は? 家は何処にあるのか?
その瞬間、何もかも分からなくなったが、すぐに思い出した。ここ最近たまにそうなる。
疲れているのだろうか?
犬山さんがいなくなって仕事が上手く廻っていない。残業も多い。
加奈子の母親は立原の町並みをしばらくじっと見ていたが、また歩き出した。
何か嫌なものを見たような気がした。この街で何が起きているのか、あまり考えたくなかった。
もううんざりだった。
加奈子は溜息をついた。容疑者の名前こそ公表されていなかったものの、ローカルテレビは死体遺棄のニュースばかりだった。
凛の独立推進派の人間を心無い来たり者の人間が殺害し、その死体を遺棄をした・・・そんな感じの内容だった。
「本当に来たり者は困った存在ですよね」
差別的な発言が、テレビのキャスターから平気で出ている。何か黒く陰湿な悪意が働いているように見えた。
来たり者への反感を煽るこの雰囲気は、果たして社会として正常な状態と言えるのだろうか? これでは来たり者への差別を煽っているようなものだ。彼らの身の安全も危なくなってゆくかもしれない。
テレビにはK大学の月岡教授なる人物が写っている。研究室での録画なのか、背景はところ狭しと並んでいる本で占められていた。眼鏡を掛け、六十歳手前くらいだろうか、黒い髪に白髪が混じっている。表情に乏しい人間だった。
「来たり者、つまりは本土の人間が、過去に凛の民にしてきた仕打ちは、決して許されるものではありません。だが彼らは過去の行いに対して謝罪をしないどころか、今も尚、罪のない凛の民を傷つけ、殺人まで犯しています」
月岡教授は右手で眼鏡の位置を少し上にずらした。
「私は凛の民ではありませんが、こういった本土の人間の行いには不快感を覚えます。そもそも、本土の人間の政治は失策に失策を重ね、財政にいたっては日本が転覆する寸前にまで追い込んでしまっている。日本国の借金は今や九百兆円ですよ。一世帯で千六百万円もの負担をどうやって返すと言うのですか?」
そういって信じられないと言った様子で首を傾げた。
「約三十年後には日本の人口は二千万人も減ります。国内のマーケットは小さくなり、これから先、税収が上がることはまずないでしょう」
月岡教授は軽い溜息をついた。
「こんな状況でも国会は失言した議員を追い回し、政策を議論せず、政争に明け暮れている。そこで私は提言したい」
月岡教授は強い口調で、周りを引き込むような話し振りだ。さっきまでの表情の乏しい顔つきはもう何処にない。
「このK地方は、大陸に依存した経済に梶を取るべきなのです。そのためには新国家を立ち上げ、日本から独立することが必要となってくるのです」
加奈子は驚いた。
独立を扇動しているのはこの人物だったのか・・・。
「このK地方の経済的安定を求めるには、独立により、本土の人間の失策である日本国の負債を放棄し、且つ大陸との関係を強力にすることが必須です。このK地方に大陸出身の凛の民が多いという利点を生かし、大陸と親密な新国家の建設を行うことが必要と私は考えます」
死体が発見され、容疑者が確定し、この月岡教授という人物が現れるまで、わずか五日間という短い時間だ。
何かおかしいわ。
加奈子は違和感と疑問を持った。
「ここでニュースが入りました。立原市の連続死体遺棄の容疑者である犬山雄五は、本日午後、殺人容疑で全国に指名手配されました。繰り返します・・・」
加奈子ははっとしてテレビの画面を見た。
画面はスタジオに戻っている。
今まで全くの匿名だった容疑者の名前が公開されたのだ。そして容疑は殺人にまで拡大されている・・・。
「どうしていきなり・・・」
あの緑の夢で大木君から伝えられた名前と同じ名前だ。そうか、あのときやっぱり大木君と繋がっていたんだわ・・・。
犬山の顔写真が流れた。
優しげな、それでいて正義感あふれる表情だった。
この人は違う。
加奈子は直感的に思った。
加奈子はすぐにテレビの電源を消した。薄手のジャケットを羽織って外に出た。そして自転車に乗り、急いで四条電機の合宿所に向かった。
大木に会わなければならないと思ってのだ。
大木が心配だった。側にいてあげなければと思ったのだ。
その日の大木は一人だった。
合宿所に残って、体育館の真ん中に置いたトランポリンでモーグルスキーのエアの練習をやっていた。ビデオに録画し、それをチェックし、またエアを飛ぶ、その繰り返しだった。
他の複合選手は、今頃クロスカントリースキーの板の代わりにローラーを履いて、アスファルトの坂道をひたすら登っているはずだ。
大木のトランポリンに着地する音が、定期的なリズムで合宿所内に響く。
加奈子の自転車が合宿所に着いた。急ブレーキを掛けた音が高く鳴る。
加奈子はすぐに戸惑った。何処に行けば大木に会えるのか分からなかったのだ。
今のこの時間は、合宿所はおろか、寮にも全く人が居ない。加奈子はとりあえずグランドに向かって走った。初めて大木に会った場所だ。
そして寮の横を通り、合宿所の前を過ぎようとしたとき、かすかに「ギッ、ギッ、ギッ・・・」という周期的な金属音を聞いた。加奈子は立ち止まって、もう一度良く聞いてみた。
合宿所から聞こえるわ・・・。
加奈子は合宿所の建屋に入った。玄関から入り、管理人の居る受付にゆくと
「本日留守」
と書いた手書きのA四の紙が、受付と訪問者を仕切るガラスに目立つように貼ってあった。
「いいのかしら・・・?」
加奈子は玄関にあったスリッパを借りて合宿所に入った。
気づくとあの周期的な音は止まっていた。どっちの方向に行けばよいのか分からなくなった。
加奈子はしばらく行くべき方向に迷っていたが、また遠くから「ギッ、ギッ、ギッ」という音が鳴り始めた。すぐにその音の鳴る方へ足を向けた。
そして加奈子は体育館の入口に着いた。中を覗いてみると、三、四メートル角くらいの大型トランポリンでモーグルのエアの練習している大木の姿が見えた。
「スキーのブーツと板を付けてトランポリンを飛ぶんだ・・・すごい・・・」
板は通常より短いものに見える。大木の飛んでいるエアはくるくる回っているだけに見えて、加奈子には何の技だかさっぱり分からない。ただ、とても難しいだろうことだけは分かった。
加奈子はしばらく体育館の入口から、大木に気づかれないように練習の様子を見ていた。
しばらくすると大木はエアを飛ぶのを止め、板を履いたままトランポリンを降りた。そして板を外し、ビデオカメラの方に行き、自分のエアにチェックを入れていた。
大木は人の気配に気づいた。そして入口の方に目をやった。
「やあ」
大木は加奈子にそう言った。少し元気がないように見える。
「あの・・・大木君・・・」
加奈子は話すのが躊躇われた。
「こんにちは・・・」
加奈子は挨拶を返した。
これから自分が話そうと思っていることが、非現実なものであり、大木の同意が得られなかった場合を考えると不安になった。
「緑の・・・世界のこと・・・」
加奈子は途切れ途切れでそういった
私・・おかしなことを言っているのではないだろうか・・・。それに大木君は色を認識できない・・・。
自分が緑の世界のことを話そうとしていることに後悔していた。
「ああ、そっか」
大木は加奈子にそう言った。
「あのとき・・・やっぱり僕らはあの世界で会っていたんだ」
大木は少し笑顔になった。加奈子は少し驚いた表情になったが、大木の表情に誘われ、笑顔になった。
「私・・・夢だと思っていた。でも夢じゃなく、本当に大木君と会っていたんだね」
加奈子はうれしい気持ちになっていた。
「そっか・・・僕は現実のような感覚があったな・・・寮の食堂に居て、急にあの世界になって、椅子がなくなって倒れたんだ。あの痛さは夢のものに思えなかった」
「私はあの世界に入る前は夢を見ていたの。暗闇で誰かに呼ばれるような夢だったわ。小さい子供のような声で私の夢を聞き出そうとしていた・・・」
そしてその夢はいつもならば、あの弁護士一家死体遺棄の現場の夢になる・・・加奈子はそのことを大木に言わなかった。あの光景は加奈子にとって本当に辛いものだった。
「でも次第に辺りが緑の世界になって、その声も聞こえなくなって、そして大木君に会えた・・・」
加奈子はそう言って、体育館の窓から見える風景を見た。窓の外は曇り空で、その中で白い細かい雪がちらついていた。
「雪が・・・降ってきた」
その言葉につられて大木も窓を見た。曇り空の中で細かい雪が舞っている。ここK地方は元々雪はあまり降らない。しかも三月末のこの時期に雪が降るのは相当珍しい。
加奈子と大木はしばらく雪が降っている様子を眺めていた。そしてその白い雪を見ながら、大木は呟いた。
「あの世界の緑・・・僕でも緑色を認識できたんだ・・・」
加奈子ははっとして大木の顔をみた。大木の表情は淡々としていた。
白と黒しか認識できない大木君の目が、あの世界では緑の色を認識できた・・・。
加奈子はどう反応していいのか、何を言っていいのか分からなかった。
「あの世界って、いったい・・・」
加奈子はなんとか言葉を返した。
「分からないな・・・」
大木はそう答えた。さらに言葉を続けた。
「でも前にも同じことが一回あった・・・強烈な頭痛があって、そのときも僕はあの緑の世界にいたんだ・・・」
あの女性の雪崩の遭難者を救出したときだった。真っ白い雪の風景と必死の形相だった遭難者の顔が思い出された。そして押し寄せる頭痛と緑の世界・・・。
「僕が劉前さんを巻き込んでしまったのかもしれない」
大木には結局あれがなんだったのか、分からない。そしてそれはこれからも説明出来ない現象なのかもしれなかった。
加奈子は即座に首を横に振った。
「気にしないで、それに大木君のせいとは限らないわ」
そう言って加奈子は沈黙した。そしてこれから話そうとしていることを考えると、どうしても気が重くなった。
加奈子は唇を軽く噛んで、ゆっくりと話し始めた。
「あの・・・犬山さんのこと・・・ニュースで名前が・・・」
加奈子は自分が余計なことを言っているのではないかという不安がよぎった。後悔にも似た感情が加奈子に押し寄せてくる。
「そうか、とうとうニュースで名前が出たんだ・・・」
「うん・・・」
加奈子には、大木の表情が強張ってゆくのが分かった。
「私が、私が証言すれば、もしかしたら犬山さんへの疑いが晴れるかもしれないわ」
加奈子は硬い表情になってゆく大木の様子を見て、たまらず言った。だが、大木はその提案にすぐに首を振った。
「証言をしたら、きっと劉前さんに危険が及ぶ。この事件の捜査は何かおかしい。劉前さんが言っていたように、まるで犬山さんを犯人に仕立てているような感じがするんだ・・・」
ドラマだったり、映画だったりすると主人公が少し動くだけで真犯人の糸口が見えて解決するものだが、実際は全く違う。何が今起きているのか全く分からない状況だった。
「犬山さんは今、何処にいるんだろう・・・」
大木は左手で自分の前髪をわしづかみにし、溜息をついた。
田沢コーチが言うように何らかの事件に巻き込まれているかもしれない・・・そしてそれは警察組織も絡んでいる可能性がある。
だいたい、車の免許もない人間が、どうやって複数の人間の遺体を遺棄できるって言うんだ・・・。
大木は思い悩むような表情になっていた。
加奈子は大木を元気づけたかったが、今の状況で適切な言葉が見つからない。
「大木君・・・私、証言するから」
大木は加奈子の顔を見た。そしてその真直ぐな表情を見て、頭を下げた。
「ありがとう、劉前さん・・・いいんだ。大丈夫だよ。ありがとう」
自分を支えてくれようとしてくれている人がいる。
大木はそう思った。
加奈子の提案は危険で、しかも何も生まない可能性がある。それは加奈子自身も分かっているはずで、危険を承知してそう言ってくれた加奈子に、大木は純粋に礼を言いたかった。
加奈子も大木の顔を見た。
しばらくその状態が続いた後に、加奈子が急に口を開いた。
「私、大木君に会いたかった・・・」
大木はその言葉を聞いて、一気に心の重しがとれ、視界が明るくなったような気がした。
「私、大木君に会いたかったんだ」
加奈子は自分の気持ちの精一杯を伝えたためか、恥ずかしさで下を向き、もうそれ以上何かを話せるような感じではなかった。
大木はその言葉だけで十分だった。目に障害のある、色を認識できない自分にそう言ってくれる女の子がいるだけで、大木はとても幸せに感じた。
大木は加奈子に右手を差し伸べた。加奈子はその手を左手で受け取り、強く手をつないだ。
言葉はもう何も要らないような気がした。大木は強く握り返してくる加奈子の手の感覚を何度も自分の中で確認した。そしてうつむく加奈子の顔を見た。
大木は自分が恋をしているのだと思った。そしてその恋の相手は今、大木の目の前にいる女の子で、その存在は自分を幸せに感じさせている。それは大木にとって初めての感覚だった。
あのとき確かに引かれ合ってキスをしたんだ。あの惹かれ合った感覚は錯覚ではなかったんだ。
そして窓から見える白く舞う雪を大木は見上げた。いつまでもこの幸せな想いを胸に抱いていたかった。
雪はまだ降っている。
細かい雪のためか積もる様子は全くない。
大木と別れた加奈子は合宿所を出て、家に向かい、自転車をこぎ始めた。雪がたまに目に入ったが、気になるレベルではない。
大木と硬く手を繋いだ感覚を思い返していた。
大木君のことが好きなのかもしれない。多分好きなのだろう。いや絶対好きなのだ。
彼はスキーモーグルの選手だ。コブを滑る彼は動画サイトにUPしているものでしか見たことがなかったが、それでも格好のよさは十分に伝わる。
「大木君がコブを滑っているのを実際に見てみたいわ」
加奈子は自転車を漕ぎながら、独り言を言った。そして自分が少しにやけていることに気づいた。
大木君は努力家だわ・・・まだ高校生なのに大人の選手を相手に大会で成績を出して、それに奢らずに頑張っている。
目の障害のこと、それを差別する人間、スキー連盟との軋轢、高校生でプロ契約・・・辛い経験や、大人相手に渡り歩く場面がいくつもあったと思う。
それぞれの問題に立ち向かっている大木には、行動力と努力、そして信念のようなものが感じられる。
それでも自分に劣等感を感じているなんて・・・。
「もっと大木君のことが知りたい。もっと大木君と話がしたい。大木君を支えたい」
加奈子が自転車を漕ぐたびにマフラーが左右に揺れる。
やっぱり私は大木君が好きなんだ。私は恋をしたんだ。
メールのアドレス交換もしたし、電話番号も貰った。今夜早速メールしよう。
加奈子は幸せな気分だった。自分は恋をしている。そして恋をした相手は、自分に恋をしている。
大木の目は白と黒しか判別できない。自分を正しく見てくれるのか不安だったが、その不安感は間違っているような気がした。
大木君の本質はそこじゃない・・・。
そう思うようになっていた。
大木が後十日で合宿所から居なくなることが、加奈子にとって寂しくて寂しくて仕方がないように思えてきた。
「大木君と同じ大学に行きたい」
電話とかメールとかで聞こう、大木君といっぱい話がしたい。
加奈子はもう一度大木と繋いだ手の感触を思いだした。そして加奈子の家の中で交わした大木とのキスを思い出した。
なんだか恥ずかしい・・・。
そう思って加奈子は「ふふふ」と笑った。
そのとき、
それは本当に突然だった。
加奈子の自転車は、後ろから何かに押されるような感覚を加奈子に伝えてきた。
車と接触している。
加奈子がそう思った瞬間、加奈子は自転車から飛ばされ、アスファルトに背中から叩きつけられた。
そして頭を強く打った。衝突した際のアスファルトの硬い感覚がやがて痛みに変化し、髪の毛をつたい、赤い血がアスファルトに広がっていった。
血はなんて暖かいの・・・。
加奈子はそう思った。
痛みを感じている余裕すらない。ゆっくりと意識がなくなってゆく。
加奈子をはねた黒い乗用車は一旦止まり、運転手は窓を開いた。そして
「凛の民の民族舞踊の練習をサボりまくって、来たり者といちゃいちゃしている、おめーがいけねーんだよ」
と吼えた。加奈子の体はもう全く動かない。消え行く意識の中で加奈子は男の顔を見た。
知らない顔だ。
その様子を見て運転者は「ちっ」と舌打ちをし、車のアクセルをいっぱいに踏み込んだ。車は驚いたように左のガードレールに突進し、ぶつかりそうになったが、寸前でハンドルが右に切られ、事故は避けられた。そして動揺し慌てるかのように猛スピードで車は消えていった。
「だからつじつまが合わないって言ってるんだよ」
遠くから携帯に怒鳴るような声が聞こえてくる。それに対して電話の相手は必死に弁解をしていた。
「勝手にひき逃げ事件を起しておいて、こっちの手持ちの人間を犯人に仕立て上げるんじゃないって言ってるんだよ」
その怒鳴り声はそう続けて言った。
「だから免許持っていないって言ってるだろ。こっちの事件でも上手く説明ができなくて、難しくなっているっていうのに、余計な問題を起こすなよ」
電話の相手が言い分を話している様子だ。しばらくうんうんと頷いていたが口を開いた。
「上がそう言っているのか? なんで口出しするんだよ。上が思いつきでやられるのが一番困るんだよ。そうだろ?」
相手は「そうそう」と返事をしている様子だった。
「まあいいや、もうすぐ交代の時間だから、そっちに帰ってからまた話そうぜ」
そう言って怒鳴り声の男は携帯を切った。男は奥の部屋を見た。
そこには拘束されている一人の男が居た。男はぐったりと横になっている。
犬山だった。
顔には殴られた痕がいくつもあり、腫れがひどく痛々しい。犬山の手は背中に廻され、麻紐で硬く結ばれ、同じように足も結ばれていた。犬山は拘束されていたのだ。口はガムテープで塞がれ、自由というものは何もかも奪われている。
水も食事もほとんどさせてねえからな。もうこいつ死ぬかもな。
男は犬山を見てそう思った。
犬山は脱水症状で意識障害に陥っていた。目も視点が合わずうつろな表情だ。
男はもう犬山を監視することに嫌気が差していた。誰でもいいから、この男をどこかに捨てて欲しかった。
男はそう思っていた。
三日毎に監視は交代する約束だった。もうすぐ次の人間が来る。
もう少し我慢すればいいはずだ。
だいたいストリーがいまいちなんだよ。免許も車も持っていない人間が、一家四人の死体を遺棄出来る訳がないじゃねえか? さっきのひき逃げの件もそうだが、上の連中のやっていることは行き当たりばったりだ。
男は時計を見て、見張りの交代の時間を確認した。あと一時間もある。
男の本質は文句を言うだけ言って責任を逃れる人間だった。そして上手くいかないことは全て他人のせいにする。どこにでも必ず一人はいる人種だ。こういった手合いは卑怯である反面、臆病でもあった。
男はもう犬山と同じ空間に居たくなかった。それは食事もさせず、腹いせに殴る蹴るを繰り返した罪悪感からくるものだったが、男はそれを認めることは避けていた。
男は決心した。急に動き出し、慌て逃げるように山小屋のような監禁場所から飛び出した。逃げ出したのだ。じわじわ死んでゆく人間を見て正常でいられる訳がなかった。
あと一時間が待てなかった。あと一時間だからもういいだろうと思った。
男がまさに扉を開け、外に出た瞬間に、白い雲のようなものが彼を突然襲ってきた。男は慌て左に避けた。
「なんだ!」
男は叫んだ。見るとそれは三メートルくらいの龍のような生き物だった。目が鋭く男は恐怖を覚えた。とても現実のものに思えなかったのだ。
辛うじて直撃を免れたものの、右腕にかすって血が出ていた。その白い生き物の顔にその血が付着し、その姿は更に男に恐怖を与えた。
男は震えながら、なんとか車に乗り込み、エンジンを掛け、焦り、恐怖に縛られながら車を出し、山を降りていった。言いようのない恐怖感が彼を支配していた。
「くそっ、俺が悪いんじゃない、俺は悪くない! あの白いのは何なんだ。なんだあれ、なんなんだ」
男は車の中でそう叫んだ。
あの恐怖の白い生き物が、また襲ってくるのではないかという不安で彼はおかしくなっていた。
「なんだあれ、なんだあれ」
細かい雪が降っていたが、男はワイパーを動かさずに車を猛スピードで走らせた。
呟き続けた。
「俺は悪くない、俺は悪くない」
彼は恐怖にとりつかれていた。
雪が降っている・・・。
男は空から雪の降る様子を目で追った。
雪がゆっくり舞い落ちているような気がしたのだ。
そして自分が車を運転していることを忘れてしまっていた。気がつくと目の前に谷沿いのガードレールが迫ってくる。そして車は曲がりきれずに、鉄製のガードレールを曲げ、超え、崖へと落ちていった。
結局、男は犬山よりも先に死を迎えることになった。
犬山に対する暴力の報いが、ここに返って来たような無残な事故だった。
春川はマイクロバスの窓から流れる外の景色を眺めていた。
ローラーを履いて、アスファルトの坂道をひたすら登った。少し疲れている。バスは複合選手らを乗せ、その練習から合宿所に帰る途中だった。
春川は外を漠然と見ていた。細かい雪が降っているのが見える。
犬山のことを考えていた。そして何度考え直しても、自分達が何もできておらず、自分達に何も分かっていないことが分かるだけだった。
「はあ」
春川は溜息をした。
何も状況は変わっていないし、改善もされてもいない。
多くの民家で白と赤ののぼりが立てられているのが見えた。何か文字が書いてある。
「凛の大祭・・・」
そう読み取れた。
「今週末にあるらしいですよ」
後ろの席に座っていたコーチの田沢が春川に言った。
「さぞかし閉鎖的な祭りなんだろうな・・・」
春川は嫌味を含めて、誰となしに言った。あの正義感溢れる犬山を退職の覚悟までさせ、追い詰めたこの町が春川は嫌になっていた。
「噂に聞いたんですけど・・・」
田沢の前の席に座っていた若い選手が後ろに身を乗り出して言った。
「何でも、凛の民には今の時代でも、皇帝みたいな存在がいるそうですよ」
その若い選手は続けて言った。
「確か・・・凛の君とか言っていたような」
「皇帝? なんだそりゃ」
春川は鼻を「ふん」と鳴らして、そう答えた。
「元々、奈良時代あたりに大陸から来た民族じゃないですか、大陸の内乱で凛の国が滅びて、そのとき皇帝が一族を連れて日本のK地方に逃げてきたって話ですよ」
「ふーん・・・で、その子孫がまだ皇帝やってるんだ?」
「おもしろいですよね?」
「面白くねえよ」
「戦時中も、皇帝だけは必死にかくまったって話ですよ。ネットにそう書いてありました」
この若い選手は身近に起きていることをネットで調べまくっていたのだろう。田沢には普段の落ち着きのなさから、その姿を容易に想像することできた。コーチという立場上、個々の選手の性格には特に気をつけている。
「その皇帝って、戦争の終わった今の世は何処にいるんだ?」
田沢は質問した。
「いや、表には全く出てこないんで、幻の存在化していて、よく分かんないです。でも去年に女性が皇位に着いたって書き込みがありました」
「もういいよ、この話は。どうでもいい」
春川はそう言って、田沢たちに背を向けて眠りに入る仕草を見せた。不機嫌になっている。
若い選手は、まだ話足りなかった様子だったが、春川の様子を見て、やがて携帯電話を取り出し、なにやらまた調べ始めた。
田沢は、さっきの皇帝の話が気になっていた。
前に他の人間から聞いた話でも同じことを言っていた。皇帝を擁した民族がこの日本に存在する・・・若い選手に言っていた内容とほぼ一致していた。凛の独立と騒いでいるのは、その皇帝のためなのだろう。
そしてその連中は日本の秩序を乱し、罪のない人間を巻き込み、陥れようとしている・・・。
許せないと思った。
ふと、誰かの呟き声が聞こえた。
「事故か?」
田沢がバスのフロントガラスから外を伺うと、担架に寝かせられた若い女性が、救急車に乗せられようとしている様子が見えた。
スキー部のバスは救急車の後ろにゆっくりと止まった。救急隊員、警官の姿が複数見える。よく見ると救急車の先にはパトカーが二台止まっていた。
担架に乗せられた女性は、田沢からは顔がよく見えず、顔色が良く分からなかったが、ひどくぐったりしている様子だった。意識があるようにはとても思えない。
現場と思わしき場所は、女性のものと思われる血だまりがあった。女性の長い髪の毛は血で固まっており、服は泥で汚れ、破れていた。その脇にはその女性が乗っていたものだろうか、自転車らしきものが、捻じ曲がり、潰され、そのままに放置されていた。
「ひどいな・・・」
田沢は思わず声に出した。粉雪が血だまりにも降っている様子を見て目を背けた。
救急隊員によって、女性に毛布が掛けられた。担架は救急車に乗せられ、ドアが閉められた。それを合図にサイレンが鳴り、救急車はゆっくりと走りはじめ、遠くの存在となり、やがて視界から見えなくなった。
あの女性は大丈夫なのだろうか?
残された風景は、あの女性の血だまりと、無残な自転車、ヘッドライトと思わしき車の破片、複数の警官とパトカー・・・いずれにせよひどい風景だ。
田沢はそう思った。
「ひき逃げなのか?」
誰かが言った。
自転車があれだけ無残な形になっているというのに、その原因となった車はそこにはない。ヘッドライトの破片が落ちているだけだ。
田沢は嫌な気分になった。卑怯な人間のそのものを見たような気分だった。
スキー部のマイクロバスは警官の誘導によりゆっくりと動き始める。そして事故現場から離れ、やがて後ろの窓からは何も見えなくなっていた。
大木の口元は緩みっぱなしで、たまに鼻歌を歌いながら、トランポリンやスキーブーツ、スキー板を片付けていた。傍目で見ると少し気味の悪い人になっていたかもしれない。
加奈子が来てくれたことが起因している。
もうすぐ他のスキー部の連中がバスに乗って帰ってくる時間だ。そうなると夕方のミーティングに参加しなければならないし、自分の時間が作りにくい。大木は練習を予定より早めに終わらせていた。
ビデオで撮った自分のエアの形をもう一度ゆっくり確認したかった。大木は道具の片付けが終わると、食堂に行き、そこでビデオの中の自分を確認し始めた。
そしてノートに今後課題になる自分の癖やエアの修正場所を書き出す。たまに上を向いて想像をめぐらせ、ノートに改善点を書き込んでいった。たまに絵を描いたりもする。
窓の外を見た。
雪は止んでいたが、雪を降らしていた雲は暗く、黒の色を増している。その風景はなんとなく大木に根拠のない不安を与えていた。
嫌な予感がする。
大木は頭痛を感じた。
痛みは弱かったが、徐々に痛くなっている。だが耐えられない訳ではない。そしてかすかに世界が緑掛かってきた。
またこれか・・・。
そして突然、大木の携帯が鳴った。非通知の電話番号だ。
大木は我に帰った。緑掛かった世界はどこかに一瞬にして消え失せる。大木は気味の悪さを感じたものの、すぐに電話に応じた。
「はい、大木です」
「・・・」
電話の相手は何も言葉を発しない。
「大木です」
大木は再度同じ言葉を言った。
「劉前加奈子は立原中央病院に運ばれたわ」
女性の声だ。
大木はその言葉に衝撃を感じ、動揺し、それに回答する言葉が見つからなかった。
病院ってどういうことだ?
大木は出来るだけ自分を落ち着かせようとした。
「何故、劉前さんが病院に運ばれたんですか? あなたはいったい誰なんですか?」
一旦動揺した心はすぐには落ち着かせることはできず、彼の声は少し震えていた。
「彼女は交通事故にあった・・・」
そう言うと電話は切れた。
自分が何をすべきなのか、何を優先してやるべきなのか、心の動揺が邪魔をして、すぐには判断できずにいた。
少し呼吸が荒くなってきている。
大木は急いで加奈子の携帯に電話をした。電話は繋がらない。急いで靴を履いて外に出た。
とにかく病院に行ってみよう。
大木が合宿所の正門から走って出ようとしたときに、複合選手たちが乗ったマイクロバスと鉢合わせした。ちょうど正門からマクロバスが入ってきたタイミングだった。
大木は引き返し、敷地に入っていったバスを追った。バスは止まり、選手たちが次々に降りてゆく。大木はバスに追いつくと、バスに乗り込んで言った。
「僕を中央病院まで連れて行って下さい」
大木の血相を変えた表情にバスに残っていた数人は顔を見合わせた。その中の一人である田沢は大木に聞いた。
「病院って、どういうこと? 大木君」
「僕の携帯に電話があって、僕の知り合いが交通事故に合ったって・・・」
ついさっき事故現場を見たばかりじゃないか・・・。
田沢は嫌な感じがした。
「大木君の知り合いって女の子か?」
田沢が大木に質問した。
「はい」
「髪は長いか?」
「はい」
「その子かどうか分からないけど、さっきここから三キロくらい離れたところで女の子が救急車に運ばれてゆくのを見たぞ」
「な・・・」
大木はその言葉に絶句して何も話せなくなった。
「おい、大木、俺が運転して病院まで連れて行ってやる」
それまで黙って聞いていた春川が大木に言った。だがすぐに田沢が
「春川さんは駄目です。次のオリンピックの候補選手がバスの運転なんて。事故でも起こされたら面倒です。僕が運転しましょう」
と言った。田沢は既に車から降りていた運転者から鍵を貰い、運転席に座った。
「俺も行くぞ」
春川はそう言って助手席に座った。田沢は頷いて言った。
「分かりました。すぐに行きましょう」
田沢はエンジンを掛け、マイクロバスのハンドルを回し、車を合宿所の正門に向けた。
雪はもう止んでいる。
ゆっくりと門から出て、右ウインカーを出し車道に入った。田舎の道路だけに車は殆ど走っていない。
「中央病院って、あの、城の麓にあるでかい病院ですよね」
「たぶんな」
運転席の隣の助手席に座っている春川が答えた。大木は田沢の後ろに座っていた。
「五、六キロくらいの距離かな。すぐに着くと思うよ、大木君」
「はい・・・」
大木の声が後ろから聞こえた。声だけでは大木の様子は分からなかったが、田沢にはしっかりした声に聞こえた。
田沢が言ったようにすぐに病院の建物が見えてくる。車はやがて病院の敷地に入り駐車場で止まった。
「俺らはここで待っているから行って来い」
春川が大木に言った。
大木はその言葉を聞いて頷き、軽く頭を下げた。
「ありがとうございます」
大木はマイクロバスから飛び降り、病院の建屋に入り、暗い廊下を走り抜け、ロビーを抜け、救急外来の場所を探した。
ロビーでは数人の入院患者がテレビを見ていた。慌しく走り抜ける大木の後ろ姿を少しの間眺めていたが、あまり感心のない様子でまたテレビを見始めた。
テレビの中では夜の公園で恋人同士が寄り添っている。そしてお互いの愛を確認しあい、キスをしていた。
「いいねえ・・・」
患者の一人がぽつりとそんなことを言った。
「劉前加奈子さん・・・ないわ。その人、本当にこの病院に搬送されたの?」
救急外来の年配の女性看護士は大木に聞いた。
「交通事故でここに搬送されたって聞いたんですけど」
大木はそう答えたが、誰とも知らない人間からの情報とは、とても言えなかった。ただ、田沢や春川は事故のあった女の人が救急車に運ばれたのを見ている。
「今日は交通事故で搬送された人はいないみたいだけど・・・私も来たばかりだから」
名簿のようなものを見ながら、その女性看護士は答えた。大木は不安を覚えた。
この病院ではないのか? いったい何処の病院に搬送されたというんだ・・・。
つい二時間前の幸せな気持ちは嘘のようだ。今は連絡がつかず、事故にあったかもしれない加奈子の身が心配で、心が押しつぶされそうだった。
「あの・・・交通事故にあった女性が救急車で運ばれていったのは間違いなくて、僕の知り合いみたいなんです。この病院でなければ、どこの病院に搬送されたか教えて頂けないでしょうか?」
その年配の女性の看護士は少し当惑した顔になった。
「そう言われても・・・」
この高校生をそろそろ迷惑に感じ始めていた。そのとき手術着姿の背の低い若い男性医師が、大木の後ろで立ち止まった。
「どうしたんです?」
その男は年配の女性看護士にそう聞いた。女性看護士は
「あの、今日、交通事故で若い女性が怪我をされて、救急車でどこかの病院に搬送されたみたいなんですけど・・・・」
と単調に答えた。それを聞いて医師は「ああ」という顔になった。
「劉前さんと言う名前だったかな? うちに搬送されて、一旦受け入れをして、検査と止血をしたけど・・・」
ここにやはり搬送されて来ていたんだ。
大木はそう思い、少しほっとした。
「ただ・・・すぐに別の救急車がきて、転院してしまった。転院先は家族の希望先なんだけど、教えて貰っていないんだ。申し訳ない」
「えっ・・・」
なんだ・・・それ。
大木はその医師の話を聞いて、驚くと同時に疑問が生じた。
普通じゃない・・・。
「その女性の容態はどうだったんですか?」
大木はその目の前にいる背の低い青年医師に聞いた。医師は少し暗い顔になった。
「頭蓋骨骨折で出血も多かった。すぐに手術をしないと本当にまずいことになるだろうな・・・手術の準備はしていたんだが」
その答えに大木は少しむかっときた。その発言に無責任さを感じたのだ。そして状況は悪い方向に向かっていると思った。
「じゃあ、なんで転院を認めたのですか? 彼女は今、危機的な状態に陥っているかもしれないんですよね」
それを言われ、医師は良心の呵責に責められる思いがした。
「姉という人が現れて・・・この病院に悪い印象を持っていたみたいでね・・・強引に転院させられてしまったんだ」
「姉って・・・」
母親か弟じゃないのか? 姉がいるとは聞いていない・・・その姉と称している人間は本物なのか? あの家に母親と弟と加奈子以外の誰かが存在していたなんて思えない。
大木は大きな不安に襲われた。犬山のように見えない糸に引きずられ、事件に巻き込まれてゆく加奈子の姿が、大木には見えるような気がしたのだ。
「この市内で、その女性の怪我を治療できる病院を紹介してくれませんか?」
大木は何かに急き立てられる思いで、その医師に聞いた。医師は少し驚いて、大木の目を見た。そして彼の意思の固さを読み取り、すぐに左手に持っていた手帳に病院名のリストを書き出し、それを手帳から破いて大木に渡した。
「君が自分で確認してもいいのだけど、僕にも責任は発生している。僕が電話して確認してみてもいいかな?」
大木はその提案を聞き、驚いた表情でその医師を見た。そして青年医師は携帯を取り出し、事務所の壁に貼ってある電話連絡表を見ながら、電話を始めた。
「立原中央病院の杉浦と申します。お世話になっております。そちらに本日交通事故に合った若い女性が搬送されているはず・・・いない? そうかですか・・・どうもお忙しいところ申し訳ございませんでした」
杉浦と名乗った医師は、そう電話を掛け続けた。杉浦は何軒も電話を掛けたが・・・電話の答えは同じだった。
加奈子は何処にもいなかった。杉浦は小さい個人病院にも電話を掛けた始めていた。
「見つからない・・・どういうことだ?」
杉浦はそう呟いた。
更に電話を重ね、探したが、加奈子の行方は分からない。
どうしてあのとき彼女を転院させてしまったのか・・・無理にでも、ここで手術をすればよかったのではないか? あの出血状況で、しかも頭蓋骨骨折を負っていたというのに・・・。
強い後悔の念が杉浦を襲っていた。
「すまない。見つからない・・・」
杉浦は苦しそうに呟いた。
何故なんだ・・・。
杉浦はそう思った。
「ありがとうございました・・・」
突然、大木は杉浦という医師に深く頭を下げ、礼を言った。だが、気が重く、とても顔を上げられなかった。
青年医師は大木の気落ちしている姿を見て、ひどく心が痛んだ。そして杉浦は急いで自分の名刺に携帯の電話番号を書いて、大木に渡した。それは医師として、良心の呵責からの行為だった。
「きっと君の力になれると思う。いつでも掛けてくれ。君は落ち込んでいたら駄目だ。きっと大丈夫だから。私ももう少し探してみるよ」
杉浦はそう言った。大木は下を向いて頷いた。涙がこぼれそうだ。
「不覚だった。すまない」
杉浦のその言葉に我慢できず、涙が出た。手で涙を拭きながら、大木は何度も頷いた。
外は夕暮れて、バスの中は暗い。手元の視界が悪くなってきている。大木がこのマイクロバスから降りて、しばらくの時間が経っていた。
「変なメールが来たんだよ」
突然、春川はそんなことを言った。
「変なメール?」
「今日の朝にな」
春川はそう言って携帯を取り出し、メールを開き、田沢に渡した。携帯の光が夕暮れの中、目を強く刺激する。田沢はメールの文章を読んだ。
「犬山雄五を救出。脱水症状がひどく容態は悪い。病院に運んだ」
田沢は驚いて、春川の顔を見た。
大変な情報だ。全く運がいい。これは大変な情報だ。
何か高まる感情で手が震えた。
「犬山さんを救出って、やっぱり事件に巻き込まれていたのですね・・・」
田沢はそう言った。そして
「大木君に早く伝えた方がいいのではないですか?」
とも言った。
春川は首を振った。
「いや・・・このメールで犬山の無事を確認できたことにはならない。というか、何故俺のアドレスを知っているんだ?」
「アドレスは、犬山さんから聞いたんじゃないでしょうか?」
田沢はそう答えた。
「一応、メールを返してみたらどうでしょうか?」
春川にそうつけ加えた。
「けど、このメールの送り主が犬山を拉致して、犬山を犯人に仕立て上げた本人だったら?」
田沢は少し驚いた。
及び腰だ・・・これでは貴重な手掛かりがなくなってしまう。
「それでもメールを返しましょう。犯人の可能性もありますが、メールの内容の通り、救出者の可能性もあります。犬山さんの唯一の手掛かりです。ここで貴重な情報源を失う訳にはいきません」
「・・・」
春川は迷っていた。
「犬山を犯人に仕立て上げたどころか、弁護士一家と、もう一人の男の人を殺した人間かも知れないんだぞ。危な過ぎる」
それを言われ、田沢は昨年末に結婚したばかりの妻を思い出した。
だが、自分にはやらなければならない役目を負っている・・・。
田沢は唇を噛んだ。
そして春川も大切な二歳になる娘と妻を思い出していた。
自分はまだ死ぬ訳にはいかない。いったい、どうすればいいのか・・・。
「春川さん・・・」
「もう少し考えさせてくれないか・・・」
春川がそう答えた。
何も考えたくない。多分、逃げ出そうとしていたのかもしれない・・・。
春川は左手を額に当て悩んでいた。
突然、春川の携帯電話の着信音が鳴った。春川はびくっと反応し、その電話に出た。
「春川さん・・・大木です」
大木だった。その声は元気のない、ひどく気落ちした声だった。
その弱々しい声を聞いた春川は嫌な予感がした。
「事故に会った僕の知り合い友人ですが・・この病院に受け入れをされていたみたいです。ただ・・・」
大木は途切れ、途切れに言った。
「ただ・・・すぐにどこかの病院に転院したみたいで、今はどこの病院にいるか分からなくて・・・」
「転院? あの出血で転院?」
春川はバスから見た、あの道路に広がっていた血だまりを思い出していた。
驚いた。何か変だ。
「ここから歩いて近いので、今からその知り合いの家に行ってみます」
大木はそう言った。加奈子に連絡が全く取れていない現状に、焦りを感じていた。
「春川さん・・・僕、その子が大切なんです。守りたいんです。でも彼女が事故に巻き込まれたというのに、今、何処にいるのかも分からない、僕は何も出来ていない・・・」
「分かった・・・」
春川はそう答えた。
「大木、気を付けろよ」
春川は電話を切って、溜息を吐いた。
うしろめたさを感じていた。高校生の大木の行動と、メールを送るかどうかの程度で悩んでいる自分を比較したのだ。
そして田沢を見た。
「大木くんの彼女は、この病院からどっかに転院したらしい。その先は行方不明だそうだ・・・」
「転院? あの怪我で? というか、救急車で運ばれていったの、ついさっきですよ」
田沢は下を向いて首を振った。信じられないことだった。
あの怪我の状態で転院なんて殺人行為ではないのか?
田沢は怒りを覚えた。
これもあの連中のやっていることなのか?
「なあ、田沢、この街おかしくないか?」
そう呼ばれて田沢は、顔を上げて春川を見た。
「独立だの、来たり者だの、無実の人間を罠に掛けるだの、皇帝だの、殺人だの、事故で入院したはずの怪我人はどっかに転院させられているだの」
春川は更に言葉を続けた。
「この町で正義が行われていないのが分かっている。こういうときは、いったいどうすればいいんだ? 一個人が闘うものなのか? この町の人間でない者が、この町のために闘うべきものなのか?」
春川は少しいらいらしているような口調で言った。
一般の人間ならば、当然か・・・。
田沢はそう語る春川を見てそう思った。
おそらく春川はジレンマを感じているのだろう。正義を行使することに対し、生命危険を伴うこの状態に。
だが、田沢はなんとしてもこの情報を無駄にしたくなかった。
突然、重い沈黙を破るかのように春川の携帯の音が鳴り、メールが入って来たのを告げた。
春川は静かにそれ読んでいたが
「まいったな」
と少し笑って言った。
「嫁からのメール。娘の由井がぱぱ大好きって言えるようになったってさ」
そして春川は頷き決心した。
「犬山を救おう・・・・」
しっかりした口調だった。
その瞬間、強い風が夕闇で暗くなりゆくこの町に走り抜けた。それはマイクロバスの中に居ても感じる強い風だった。
風が通り抜けた後はその反動のように辺りに静けさが広がる。
何も音のない世界だった。
今日も夕闇を超え、夜がやってくる。黒く深い闇に支配される時間がくるのだ。
ノンボラティック 2週間の戦争 前編

