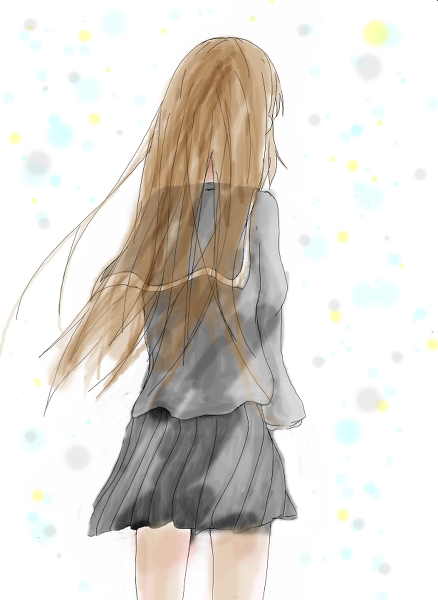
絵の中の少女
こんにちは。または、こんばんは。
はじめまして、夜坂礼です。レイでコウって変換していたりします。
まあ、初心者ですが気長に読んでくれたらとっても嬉しかったりします。
では、このサイトで初作品となる『真夜中clock』をお楽しみください。
チャーハンと酢豚
初恋。
初めて恋をしたのはいつだっただろうか、輪郭のない空気のようなそれは思い出せない。
そもそも、それが好きというありふれた感情だったかどうかもあやふや。
根拠となるものは何一つとして目に見るもので残っていないのだ。
前に好きだった人は中学二年の時の先輩。
吹奏楽部の副部長。いつも放課後に音楽室で一人ピアノを弾いていた。
だけど、それが初恋でないのなら。
きっとこれが初恋なのだろう。
僕は思う。
この世の何処を探してみても、初恋という曖昧なものは存在していないと。
「ねぇ。文兎はどーして、ココにいるの?」
そう彼女は言った。
今にも崩れて落ちそうな腐りきったガラスのない窓辺に腰を掛けながら、静かで雪の降る音すら聞こえないこの場所で。
僕はまたかと溜息を白い息と共について、いつものように目を彼女から外して言う。
「・・・誰もいないから。ココは僕の」
秘密基地なんだ。
そう六年前の僕は言う。
だけど、今の僕はその先の言葉が見当たらず、目線を下げた。
それを目にした彼女は笑って声を出す。
「ココは私達の秘密基地なんだよ」
僕が顔を上げた窓辺に彼女の面影も、何もなく。
ただ白い小さな雪が数センチ積もって、音を吸った。
*
寒い。
冬は暑くないのだから、寒いのだ。
そう鴪川和文兎は思いながら、歩きなれたアスファルトの地面を踏んで一歩前へと進む。
右肩に掛けた学校指定のスクールバックの紐が食い込んで、思わず右手の親指を挟んだ。
「朝から景気の悪い顔しやがって」
文兎の横を同じような格好で、同じような顔をしたクリクリ頭の男が言った。
「うるさいな三河。お前が貯金を叩いて昨晩飲み明かしたせいだ。金欠に寝不足」
そんな冗談にがっはがっはと大口を開けて、中学からの友人、三河は笑う。
冬休みをまじかに迎えようとしているこの時期に、遅刻連ちゃんの罰として刈られた頭は見ているこっちが鳥肌ものだと目線をアスファルトに落した。
「今日って大掃除だけだろ?帰りにどっかで飯食おうぜ。チャーハンか酢豚」
白い息を出しながら三河は言う。
どこにそんな金があるかと問う前に、頭の片隅に置き忘れたことを思い出す。
「無理、部活だ。明日までに仕上げなきゃいかんのがある」
文兎はマフラーを口まで押し上げ、冷え切った親指を制服のポケットの中へと埋める。
「部活って、どーせお前しかいないじゃん」
「それでも部活だ」
間髪入れずに三河へと言い切る。
またもやマフラーが首下まで滑り落ちる。
「お前が部長で、お前が部員で、お前が顧問で、お前の机が部室ってか?」
マフラーを指先でつまんで鼻下まで引っ張り上げて文兎は言う。
「そうさ、それでも部活」
三河はそこで笑った。
三日に一度。まったく同じ会話をしていればどうということはなくなり日常となった。
そうこうしていると、文兎と三河の周りに同じ紺のブレザーを着た生徒がちらほらと現れ視界に入る。
長い少し右曲がりの、今まで二年と半年以上歩き慣れた同じ道。
今まで両方を雑木林にしたこの道も、少しずつ左手が晴れた。
「今日は晴れるな」
そう三河は言った。
後方の山頂付近から、眩い七時前の朝日が足元から一気に辺りを照らす。
同時に前方が開け、視界いっぱいの青。
自分の後方から受ける朝日に反射して輝く海岸線。そして薄く寒さを思わせる澄み切った空が薄青色に何処までも続いた。
密閉された林を抜けたせいか、学校の校舎が見えたせいか、何処となく気力というものが湧いてくる。
「なんか、気力みたいなものが湧いてくるな。一日がんばるぞーって」
三河はそう言って大きく伸びをして息を吐いた。
「・・・まぁ、半日授業だがな。そして寒いことには変わりない」
文兎はポケットに突っこんでいた手を出して、軽く伸びをする。
「文兎はリアリストだなー」
と三河。
「違うと思うよ」
と文兎。
もう、忘れていた。
そんな毎日がずっと続いていくのだと思っていた。
チャーハンか酢豚。そのどちらかを選べば、僕はそう思って疑わなかっただろう。
思い出すことも、出会うこともなかっただろう。
凍てつく紙魚
冬休みまで、あと二日。
外と違って室内は温かく、行に着込んだブレザー下のカーディガンもマフラーも。今は机の背もたれに掛けられた。
そして約一年後に息を潜めた受験のせいか、こんなプリントを大掃除前のHRに担任から渡された。
余白が多いそのプリントには氏名記入欄の下に、第三希望欄までの進路と印刷されている。
「未定だな。うん」
そう言って、文兎の前の席にいる三河は三つの記入欄を無視し、大きく未定とシャープペンシルを走らせた。
それを見た三河の右隣の髪を後ろで縛った女生徒は呆れ笑いをしながらそのちくちくの頭をなでる。
名前は千沙。
千沙と三河と文兎は同じ中学校出身で気の合う仲間と言ったところだろう。
「あ、千沙。今日暇かー?俺と文兎で飯行くけど来る?」
伸びてくる千沙の腕を払いのけて頭を守る三河は言った。
「え?文兎も来るなら行く―!また川下ラーメン?」
千沙はプリントとにらめっこをしていた文兎へ振り返る。
自分の名前が出ると、今まで聞き流していた会話も鮮明に脳へと飛び込み、翻訳される。
「もう川下ラーメンなんか食えるかぁ!今は茂上中華のチャーハンと酢豚を知らんのかぁ?」
「って言ってるけどホント?」
千沙は椅子の背もたれを前にして座り、首を少し斜めにしながら言った。
「今日は部活だから」
と文兎は言う。
「また締切?つい1ヶ月前にも同じよーなこと言ってたじゃない」
「年始にある展覧会に場所が取れたからそこに置かせてもらう」
文兎は第一希望欄に進学(4年大)と記入。
千沙も第一希望欄に進学(4年大)と記入。
「今度は人物画じゃないの?またモデルやってもいいよ?」
「 千沙がモデル 」
千沙の後ろでぼそりと言った三河は自分で言った言葉に吹き出し、机を叩いた。
すかさず、千沙は振り返りながら三河の無防備な頭をシャープペンシルの先で突く。
「今回は風景画にしようと思ってるから、ありがとう」
文兎は第二希望欄に大統領と記入。
あははと少し頬を赤くしながら、千沙はプリントで表情を隠した。
千沙は第二希望欄にお嫁さんを記入。
「まぁ、それはともかく。大晦日の祭り。絶対に空けとけよ」
三河は千沙に刺された頭を撫でながら言う。
大晦日の祭り。それはここらでは一番大きな祭りで年末の31日から新年の一日までを山車が己山から海岸線まで引っ張り歩き、その1年の感謝と来年のご運をお願いする祭りだとか。
己山とはこの町の右手に聳える山で、昔は多種類の茸栽培で有名だったらしい。
その後、明治初頭に己山から鉱物資源が発見されるまでそれは続き、今では鉱物資源すらなくなって、穴ぼこだらけの草木生い茂る山だ。
まぁ、そんな昔の名残りで山と海、その両方に感謝しよう。と言うのがこの大晦日の祭り。
しかし、趣旨なんてものは子供にはどうでもよく目的は海岸線に大晦日並ぶ夜店であるのが本心だ。
「だから今年の展覧会が年始。つまりは大晦日の祭りの後すぐなんだよ」
「つまり?」
「きっと準備で出れない」
そこで三河より速く千沙が深いため息をついた。
「えー!今年こそ最後だし花火をまた3人で見ようと思ったのに」
千沙は第三希望に花火職人と薄く書いて文兎へと詰め寄った。
「もう2年だよ?来年はきっと受験で忙しいし、大学だってきっと・・・」
必死になっていた自分に気づいたのか、千沙はまた溜息をついて消しゴムを自分の机から指先でつまむ。
そのまま力を込めて第三希望の花火職人の上を擦った。
「まぁ、無事に作品が三つとも出来れば大丈夫」
だと思う。
文兎は第三希望欄に美大と書いた。
「じゃあ、今日は茂上中華なしってことで」
千沙は横で氏名欄を記入する三河の頭をぺしりと叩いて笑顔を戻す。
「えーマジかよ!俺昼どーすりゃいいんだぁ?」
「自分の家の海苔でも食べなさい!」
実家が海苔養殖業の三河の頭をまたもや叩きながら千沙は笑う。
最後に千沙と文兎は氏名欄にそれぞれ記入し、三河のも足して教卓へと回した。
担任は一番上に置かれた三河のプリントに気づかない。
「ホントね?約束だよ、花火」
と念を押す千沙。
「ああ」
と文兎。
そのHRの最後に、担任が出席簿を片手に言った。
「この希望調査、来年のクラス分けに使うからなー真面目に書いたよねー」
その声に、動揺したクラスの半数に三河も含まれる。
「ああ、島流しだな」
その日は自分のクラスと、目の前に広がった長い廊下にワックスをたらふく塗り込んで、SHRととなった。
放課後。
といっても日はちょうど頭の真上で雲は何処にもその影をつくっていない。
時計は十二時五分を二本の針で指し示す。
SHRも終わり、バス下校の生徒は我先にと荷物をひっつかんで飛び出る。
「お先にー」
千沙もその群衆に紛れ、正面門に停車中の二台のバスを目指した。
徒歩や電車通学の学生だけが教室に残るこの時間帯に生徒はたったの八人。そのうちに半分は徒歩で、そのまた半分の二人が文兎と三河だ。
「お前今日は何処で描くの?図書室か、ここか、裏庭か」
美術部員は現在、文兎だけで当然部室も部費もない。入学する一年前までは同じように部員一人で運営していたのだが、その年の暮れに卒業。
その卒業した先輩こそが僕を美術部に引き入れた張本人だということは話が長くなるので割愛しよう。
「今日はデッサンだけだし。どっかをふらふらする」
「どこを?」
これと言ってどこを描きたいなどはない。目に入ったものを描いてそれで終わりだ。
「・・・中学校とか?懐かしいし」
と思いつきに文兎は言う。
「今まだ授業中で校内入れないだろ」
そういえば、まだ昼さがり、何処も活動中ではないか。
「てか、お前ついてくる気か?」
「要検討中ってところだな」
三河は一人々と消えてゆく生徒の数を数えながら言った。残る生徒は四人。担任はなし。
そうとわかると三河はブレザーのポケットから中折れの携帯電話を引っ張り出して開いた。
「今日の最高気温は何度でしょうか?」
と三河は液晶画面を見つめながら言う。
ついでにこの高校は携帯電話の持ち込みは禁止だ。
「十八度」
と文兎は言う。
「残念。最高気温十二度、最低気温マイナス二度」
今朝あんなに寒かったわけだ。きっと外はまだものすごく寒いだろ。
「・・・小学校へ行く。己小」
小学校は寒くて授業にならなかった。寒くて休学。そんな日もあったのを思い出す。
「そっか、お前は己山小学校出身だったっけ。でもあそこは結構前に廃校になってなかったか?」
三河は思い出したように携帯電話のワード検索で『己山小』と親指で打った。
「ちょうど僕が卒業した次の年だよ。最後の年なんか五人もいなかったし」
と文兎。
検索結果は思いのほかに多く、その中の一番上のサイトに入る。
○○己山小学校、土砂崩れにより半壊。
八月三日午後二時四十分頃、鉱山で有名な己鉱山の一部が土砂崩れを起こし、山の腹部にあった己山小学校が半壊するという事件が起きた。
幸いなことに夏休みだったため生徒に怪我はなく、教師も同様であった。己山小学校は今年度の生徒五名が卒業すると廃校が六年前より決まっていて今後の授業は同じ町内の中学校で行われる予定であると校長は語った。
土砂崩れの原因は二日未明から三日の早朝まで降った雨であると発表されたが、土砂災害に詳しい専門家、東京異武大学教授、山口正井さんはこう語る。
「引き金になったのはその日まで降っていた雨だが、根本的な原因は己山の状況にある。採掘によって山の内部に多数の亀裂が発生して、それが雨により崩れ落ち、今回の様な土砂災害になった。今後も同様の土砂崩れが起きる可能性はとても高い。調査した方がいい」
これに対し、町の・・・
「そういや、己山の入山禁止ってこれのすぐ後だったよな」
と三河はぼそりと言って携帯の速報欄へとリンクを飛ばした。
「まぁ前から子供が行方不明になったり、穴に落ちたとか、挟まったとか。・・・そういえば去年の大晦日の祭りでお前、軽くはまってたな、穴に」
「ば、ばっか!そんな事思い出してんじゃねぇーよ」
三河は携帯を折りたたんで制服のポケットへ突っ込む。そして机の上に置いていた黒いコートに腕を通す。
「なんだ、帰るのか?」
と文兎はスクールバックをショルダーバックのように背負った三河へと言う。
「養殖手伝えって親父からメール来てたんだよ、マジで飯が海苔系になるとは」
頭をかきながら手を振って、三河は教室を出た。
「じゃあ、な」
どこか違うクラスではしゃぐ男子生徒の声が微かに聞こえる。そんな声に耳を傾けながら一人になった教室で荷物をバックへと無理やりねじ込んで薄茶色のカーディガンを着てマフラーを首元で丸める。
十二時四十分をいつの間にか回った時計を確認してから教室の暖房と照明のスイッチを切った。
昇降口の外靴もまばらで、空き切った扉からすで凍てついた風が頬にあった。
バックにある凹凸を指先で撫でてデッサンの忘れものがないか最終確認。
上履きと黒いローファーを履き替えて、マフラーの先を鼻まで引っ張り上げた。それでも外気に触れる耳やおでこは寒いのだ。
一歩、毎年のことながら寒い季節を感じながら足をとりあえず校門まで進めた。
朝と同じ海岸線を今度は右手に見ながら歩道を歩いた。
雪もないのに足先が冷たくて、肩にかかるバックが痛い。
「小学校。小学校」
目的地は小学校。
廃校になった後、何とも追い打ちをかけるような土砂崩れ。しかし、卒業してからすでに五年が過ぎ去ってもまだ校舎自体は残っているらしい。
そういえば、小学校の卒業式ってどんなものだっただろうか。
もう担任の顔も、声も、友人の顔も、声も。
記憶にあるのは校長が言った卒業式の最後の言葉。
『五年生は来年卒業です。そしてこの学校、最後の生徒ということを心に留めておき、充実した一年間を過ごすように心掛けてください』
それは、おかしいほどに鮮明にその声ごと記憶に焼き付いている。
あれは僕たち卒業生ではなく、五年生へ言ったのだ。
どうして、僕らが最期じゃないのだろうか。どうせなら、最後がよかった。それで終わればよかったのに。
ブービーよりも、ビリの方がいい。
そっちの方が人気になれるから。肩書きがいいから。
「僕はあの小学校の最後の生徒なんだよ」って言いたかったから。
でも、今から思えば。
その最期の五人だって、土砂崩れで小学校自体がなくなった。
いや、そもそも五人もいなかった。
「卒業式。・・・なんだっけか。なんかやったな」
歩くスピードが少しずつ落ちて、自転車や車が後ろから追い抜いて海の見えなくなった道を進む。
思い出せない。
のど元まで出かかった何か。何かが出てこないのだ。
「なんだっけか」
独り言をぶつくさぶつくさ言いながら、石段の山道を歩く。
そうだ、この道は友達の誰かとよく学校への抜け道として使っていたっけ。
確かこの先の柿の木を右に曲がれば三嶋さんの家の塀。さらにその先に学校の林の裏へ出れた気がする。
しかし、三嶋さんはここら一帯で茸の栽培をやってて、よく勝手に入るなって怒られた。
まるで迷路を出口から攻略するような感覚。いつの間にか緩みきったマフラーを直すのを忘れていた。
記憶通りに進むと、これまた記憶通りに柿の木がすぐに見つかった。
足元には落ちて腐りもう何だかわからない柿が転がって、そのさらに下に『私有地につき進入禁止』の立て札が半分以上が土に埋もれて落ちていた。
汚れ具合からして最近のものではない。
それは確かに、当時の僕らはそれを印にしていたのだろう。
「今だから読めるけど、昔は読めなかったのかね」
そう苦笑いしながら文兎は無意識に背を低くして柿の木を右に曲がった。
左右は日光の届かない深い木々が背を高くして生い茂り、肩幅ほどの道は石の間から雑草が生える。
ときどきちょうど顔ぐらいの高さにクモの巣がまるで赤外線レーダーのように張られ、更に腰を曲げて進む。
どれぐらい進んだだろうか。子供のころは一瞬で来れた気がした三嶋さん宅までやっとの思いでたどり着く。
古い和風の家。塀の向こう側に見える瓦屋根は草を生やし、以前あった気がした倉のごつい窓は見当たらない。
いや、当時は塀の向こう側は見えなかった。そこに背の高い倉だけが目に入ったから覚えている。
あの倉は取り壊してしまったのだろうか。
流石に塀を乗り越えて行く勇気は今の僕にはない。
そこで細かいひびの入った土塊の塀をぐるっと一周して、再び既感を感じるものを発見した。
「なつかし」
五十センチほどの穴が塀の下の方にぽっかりと開いていて、そこの地面はまるでブランコの足元のように少しへこんでいる。
「そうそう、ここの穴から」
脱出っていいながらみんなで逃げた。
今から思えば、三島さんもこんな穴塞いじゃえばそれで済むだろうに。あえて開けておく三嶋さんも案外、楽しかったのだろう。
蘇るのは白いタオルを肩にかけて、大声で何かを言いながら追っかけてくるおじさん。
顔だけは未だに出てこそ来ないが、きっといい人だったのだろう。
ふと見上げた右奥に大きな門があった。いや、玄関だろうか。
見覚えのなかったそれを見て文兎は唖然とした。
塀の向こう側に広がっている光景は記憶の中庭ではなく、冬と言うのに草木が乱暴に生え、家も柱や屋根は残っているものの、中は吹き抜けのように風を通して朽ちていた。
「あれから五年が経ってるのか」
五年という得体のしれないものがここにきて何かをぐっと締め付ける。
無性に三河や千沙と喋りたいと、そう思った。
「こんなの、絵にはできない・・・」
単純にしたくなかった。
でも、それを絵に残せたら一体どんなものになるのだろうか?
それを知りたい。
どんなもので、他人にはどう映るのか。それを知りたい。
気がつけば地面に腰を据え、マフラーを取ってバックからデッサン用のスケッチブックを手に取った。
それは生と死を知らない子供が悪戯に蟻を踏み潰すような好奇心だ。
HBの鉛筆が真っ白なスケッチブックの荒い面に黒鉛を乗せてゆく。
塀の向こうは意図して見に行かない。僕の両の瞳が映す範囲ですくい上げて、それすべてを手元へと吐きだした。
冷たく凍えた指先を無理やり動かし、細かい下書きを描き上げるのに三十分は掛けただろうか。
文兎はようやくそこで手を暖かいポケットの中へと突っ込んだ。
出来ることならば、このまま着色まで行きたいがあいにく絵具も筆も持ってはいない。
「疲れた」
白い息を日の下で吐きながら言った。
目的は小学校のはずだったのに、こんなところで集中力を使ってしまった。
だが展示作品は残り二品。それも今日中にデッサンだけは終わらしたい気分だ。
文兎は腰を上げて、冷たくなった尻の砂埃を叩く。
スケッチブックをスクールバックに押し込んで、ばら撒かれた文具をかき集めてポケットへと押し込んだ。
日はまだ十分過ぎるほどに高く、雲もない。
「前進あるのみ」
文兎はマフラーの裾を首に縛って鼻まで上げた。
今年の秋に落ちた落葉で足元は不安定。
それに加えて伸びきった木の枝がちくちくと首元や頭に突き刺さる。
人の姿は当然見えず、木々の間にはまた先の木が見えるだけで一向に記憶の中の校舎は見えない。
「迷ったのか」
見上げると葉を落とした木の枝がびっしりと空を覆う。
寒さはじわりじわりと制服の中まで染み込んできて、手先はすでに感覚がない。
完全に己山に入ったのか斜面が急になり始め、バランスをとるために木の幹を掴む。
どうしてここまでする?
そんな疑問が浮んだ。吐く息が白い。
「こんなことなら、近道なんかしなきゃよかった」
それでも小枝を踏み折り、腐葉土に足跡をつけながら憑かれように進む。
最後は意地のようなもので堪え切って林を抜けた。
「着いたか。やっと」
辺りが開け、空き地のような場所に出る。
元はグランドだ。
その先に横に長い二階建の灰色の校舎が半分をビニールシートで覆われた状態でそこにあった。
六年たっても何ら変わらないその光景に胸を撫で下ろす。
そのままの勢いで文兎は百メートルほどの苔の様な草が生える校庭を横断する。
こんな僻地に人なんているはずがないのはわかっていても、進入禁止と知っていれば足も速くなった。
校舎の一か所しかない出入口の昇降口は当然のように南京錠と鎖、そして『倒壊の危険性の為、立ち入り禁止』と雨風でシミだらけになった張り紙がガラスに張られていた。
南京錠による封印は計算外であった。
「割るか」
すでに昇降口にある一メートル弱のガラス二枚はひびが入っており、割れたないのが奇跡のような状態。
文兎は数歩だけ後ずさりして、校舎全体を見つめる。
グランド側の窓はガラスが割れているものが大半であったが、窓が通り抜けできる大きさでなく、ビニールシートの半壊した部分から入るのは気乗りしない。
迷いに迷った結果、最終的には昇降口のガラスを手ごろな石で割った。
そこで帰るという選択肢を選ぶほどに楽な道のりでもなかったのだから仕方ない。
文兎はマフラーを縛り直して、スクールバックを両手で抱きながら校舎内に入った。
その時、踏み割ったガラスの破片はピシリと音を誰もいない校舎へと静かに響き渡る。
*
文兎を好きになった。
そう自覚した瞬間、頬が熱くなり心臓の音が耳元で聞こえた。
きっとこれが恋で、きっとこれが初恋なんだと思う。
「ねぇ、まぁーた鴪川和君?」
外の街頭を窓越しにただ見つめてい千沙は反射的に仰け反り、後頭部をバスの背凭れへとぶつけた。
寝込みに水とはこのことだろう。
「何よもう、そんなんじゃないわよ」
千沙は窓向こうの街頭から視線を移して吊革につかまっている人物へと言った。
ショートヘアの女子にしてはサッパリし過ぎと言わざる得ない友人、神田は相変わらずにやにやと笑う。
「だって千沙ってば、ずぅーっと鴪川和君ばっか見てるじゃない、授業中だってどうせなんかちょっかい出してんでしょ?」
そう神田は言いながらスクールバックを肩から抜く。
どちらか一人がバスの席に座れたもう一方の荷物持ち。これは去年から神田と千沙の取り決めであった。
「ちょっかい出してなんかいないわよ、それに二人きりじゃなくて三河だっているし」
千沙は神田のバックの上に自分のバックを乗せて言った。
「やっぱりちょっかい出してるじゃない。三河と鴪川和君と千沙って同じ古見中でしょ?」
「うん、そうだよ。ヨミは?」
ヨミとは神田のあだ名である。
神田嘉香のヨミ。
「川向よ。あれ、じゃあなんで三河と鴪川和君ってバス通じゃないの?」
古見北中学、俗に言う古見中は己山を越えた先の内地にある。
内地には住宅が多く、商店街もあるが己山を挟んで反対側の海側には主に養殖業や漁業関係しか残っていない。
「三河は父親の海苔養殖の手伝いとかで、高校近くの掘立小屋みたいなところから通ってるのよ。文兎はもともと海側に家あるし、己小出身」
千沙は自分のバックのファスナーを開けながら言った。
「三河も大変ねぇ、でも愛しの鴪川和君が己小出身ってのは意外ね。わざわざ廃校決定の小学校通ってたのかしら」
神田は興味を持ったように言う。
「愛しのをつけるな、愛しのを」
と千沙は言った。
バックから手探りで見つけ出したマフラーの端を引っ張り出す。
「でも、文兎の母方の実家。その家って己山の土地を半分ぐらい持ってたのが原因かも」
「何それ、知らないんですけど。鴪川和君ってお金持ち?」
ヨミは千沙の見つけ出したマフラーを掴んで自分の首に引っ張り始めた。
内地ではあまり聞かないが鴪川和家という存在は海側なら知らぬ者はいないと三河から聞いたことがあった。
もともと内地と海側の直通路が出来たのも数年前の話で、それまでは閉鎖的な町だったと聞く。
「文兎って自分のことをあんまし言わないのよ。どから詳しくは知らないの」
千沙はヨミの手から素早くマフラーを奪って手早く首へと巻いた。
今頃になって、バスのエンジンがかかりねっとりとした臭みのある温風が車内の暖房から出始める。
「やっぱり、鴪川和君のことが好きなんだー。千沙ったら女の子女の子しちゃってぇもう!」
「なんでそうなるのよー」
巻いたマフラーを緩めながら千沙は言う。
「だって詳しいじゃない、新聞部の私よりも。それが好きってことよ。好きとストーカーはご近所さんなんだから」
笑いながら言った神田に溜息をつきながら千沙は思う。
図星なことに文兎が好きなのだ。
「だから、ちがうってのよー」
そう言ってしまうのはどうしてだろうか。
笑いながら、そう言ってしまうのはなぜだろう。
これだから、文兎に伝えることができないんだ。
私は思う。
この世の何処を探してみても、初恋というほどの厄介な映し鏡はないのだと。
私の根本的な私が、今の私を鏡の中で嘲笑う。
*
○×○○×××○×―。
まるでそれは声のまだ若い人間の低い唸り声の様な音。
耳を欹てれば オーイココタスケ と聞こえる。
まるで子供の児童が校舎で低く、静かな声で言うように。
文兎は廃校の小学校に一人で来たことの後悔の真っ最中にいた。
単刀直入に言うと、怖いのだ。
「おー・・・い」
固まった喉で返るはずのない静かな廊下に低く言う。
と言うよりも返って来たら困るのだ。とても。
しかし、さっき確かに人の唸り声の様な音が聞こえたのは気のせいなのだろうか?
所々に穴のある、いつ腐って抜けてもおかしくない木造の板張り廊下を一歩、また一歩と進む。
窓の日差しも半分以下しか届かない長い廊下はみしみしと音を立て、空気は淀み湿度が高い。
廊下を挟んで左右に教室が見える限りで八つ。それぞれの教室のドアの上には、もう読めない文字で学年と組みが書かれていた。
後方数メートルには、日差しで明るい昇降口が、まるでいつでも脱出可能だと言わんばかりに口を開ける。
「帰る・・・よな。こんなとこじゃ絵も描けないし」
そうだ、こんな人気のないところで生き埋めにでもなったら確実に死ぬ。
そこで、ふと思う。
自分は最後の年は何組で授業を受けていたのだろうか。
気になる。どうしてこんな状況でそんなことが思えるのかと自分自身に渇を入れても揺らぎはなかった。
「おーい。この財布お前のかー?」
沈黙、沈黙、沈黙。
誰かが財布を確認する音も、鳥の声一つしない。
「よし、大丈夫。端っこまで行って帰ってくるだけだ」
沈黙。
もしこれで誰かがいたのなら、いや、外で聞いてでもいたら僕は恥ずかしさのあまりに三河の家まで全力ダッシュをするだろう。
止まった足を再び、進める。
昇降口から一番近いグランド側の教室。そこは記憶に新しく、覚えていた。
「職員室」
昇降口に入る前に、窓から先生がいつも挨拶をして、それを同じような挨拶で返す。そんなことを毎日六年間していたはずだ。ここなら出席簿があるはず。
教室のドアは前後二つあり、近い方は校舎が歪んでいるせいか動きもしないので、遠い方を選ぶ。
「失礼します・・・」
そう小声に出してから、文兎はドアをスライドさせる。しかし、完全に開き切る前にドアごと外れ、倒れた拍子に重力で壊れ、木屑と化す。
舞い上がった少しカビ臭い埃の様な何か得体のしれないものを文兎は鼻から吸い込み、咽て教室内へ飛び込んでしまった。
「うぁっ」
変な声と共に何かに足元を取られ、スクールバックを放り投げた。次の瞬間には視界が真っ暗に染まった。
状況を理解するの数分を要した。
なにせ、突然無重力の宇宙空間に放りだされたような、この世の終わりの様な、そんな感覚だったのだ。
真っ暗で、兎に角、真っ暗だ。
だが、真っ暗の中に自然とぼんやり輪郭が浮かび上がり、尻の異常な冷たさを知った。
どうやら、穴に落ちたようだ。
頭上にあるベニヤ板の剥がれかけた校舎の天井が酷く遠くに見えるのだ。
「まじか」
つぶやいた声が辺り散々に反響し、恐ろしいことにその反響はどこまでもいつまでも消えるまで続いたのだ。
洞にでも落ちたのだろうか。でも、職員室に洞って。
「あり得るのか?」
その声も反響し、どこまでも続く。
文兎はとりあえず、体制を立て直そうと近くにあった職員用のデスクの端を掴んで立ちあがった。
触れる尻は瑞々しくて、冬の寒さで温度はさらに下がった。
よく見ると穴の底は水たまりのようになっていて、床板だろう木片や、職員室にありそうな物品は全て骨董品だが水たまりの土深く生えるようにあった。
職員室はこの謎の洞に食われたということだろう。さながらここは胃袋だ。
「思ったよりも・・・おーい」
おーいと洞は小さく言うが、元の職員室まで高さが二メートル弱もあり、見える限りの側面はよじ登れるほどの傾斜ではない。
幸か不幸かスクールバックはスケッチブックもろもろと共に胃袋にはなかった。
「冷静だ。冷静が一番だよな・・・」
文兎は辺りを見渡し、すぐに妙案を導き出す。
生えている椅子を引き抜いて、浮く棚を引っ張り出して、長机を持ち上げる。
見事に階段をくみ上げて、不安定踏み台に命を預けて、格闘すること十五分。
「だ、脱出」
泥だらけのブレザーを崩れたドアの上に投げ捨てて文兎は床に倒れ込んだ。
腐りカビ臭い廊下の板がとてもきれいに思えるほどに泥だらけで、水を吸った制服はずっしりと重く身体に圧し掛かった。
身体の芯から凍りついて、とてつもなく眠い。
吐く息が白くて、視界がぼやけ始める。
「これ、・・・やばいな」
足先に力を込めて立ち上がろうと思っても、足先の感覚がすでになく意識もどこか変でまるで夢を見ている気分だ。
「せっかく、見つけたのに・・・・な」
制服のベルトに挟んだ卒業写真のアルバム。それは洞にあった棚から見つけてきた代物だった。
紙魚と泥だらけになっているも、中身はきっと数十年分の卒業生の写真とクラス名前。
「こんな・・・・」
こんな物の為に、なんでここまでやってるんだっけ。僕は。
もう眠い。
何か、とっても大事なことを忘れている気がするけど。
・・・眠い。
誰かが、僕の意識をゆする。
そうだ。
思い出した。
淡い白 -前編-
僕は守れなかったんだ。
たった一つ、この牢獄で交わした約束さえも。
「おまえ、大丈夫か?しっかりしろ」
真っ白な風景に、音の波紋が広がった。
それはどこまでも広がって・・・・。
「おいっ!」
頬への痛み。
何かが頬を叩いて、文兎は現実へと引き戻された。
目を開けると辺りが眩しく真昼なのかと錯覚したが、すぐにそれが軽トラのライトだと理解するぐらいには覚醒する。
すると今度は髭を生やした大きな顔が飛び込んできた。
「意識はあるな。あんた、高台の高校の生徒か」
その中年の男はちょっと待ってろと言うと、ポケットから携帯電話を取り出すと、指で三つの数字と発信を押す。
そこでようやく文兎の意識が鮮明になる。
だらりと垂れた腕が反射のように素早く動き、中年の男の携帯電話を指ごと押さえつけた。
「病院は大丈夫ですから・・・、電話は、いいですから・・・大丈夫だから」
滑舌が上手く回らないが、はっきりと文兎は声に出して男に言った。
「何言ってやがる、あんた意識失ってたんだぜ?車にでも撥ねられたんじゃねぇのか?」
男は心配そうに顔をのぞきながら言うので、文兎は無理に笑顔を作って見せる。
「大丈夫です、ちょっと水に落ちて・・・」
そこで文兎は自分の現状にズレを感じて、辺りを見渡す。
確か、職員室の洞に落っこちて。そこまでは覚えているのだ。
しかし、手に触れた地面は板張りの腐った床ではなく、固く冷たいアスファルト。高くがっていた太陽はどこにもなく、軽トラのライトと白線を照らす街頭の明かり。
舗装された道の端っこで目覚めたのだ。その道はいつも学校へ向かうために使っていた道。そのまま進めば海で、反対は己山の裾の実家。
「ふぇっく、しょんっ」
だが確実に季節が冬で、寒いことに変わりなかった。
触る制服は乾いて、付いていた泥がポロポロと消えかかった白線に落ちた。
「大丈夫か、せめて家までぐらい送ってくぞ?」
中年の男は尻もちをついた状態の文兎へごつい手を差し伸べて、言う。
「家は・・・いいです。近し、大丈夫ですから」
市川はその手につかまって立ちあがり、よろけそうになる体を必死に立たせて男に笑顔を送った。
「本当にありがとうございました。ちょっと山に入って遊んでたら転げ落ちちゃって、まさかこんな道まで転がっちゃうなんて、ホントご迷惑をおかけしました」
男が口をはさむ間を与えず、文兎は強引に挨拶と握手をすませると、顔を見ないように一礼をする。
そんな文兎に男はそれ以上の声で負けじと言う。
「そっか、おれも昔は己山を庭みたいに駆け回って、鴪川和のばばぁによく怒鳴られたもんだぁがな。まぁ、でも今は山入禁止だから祭りぃの日まで待つんだな」
男は逃げようとした文兎の背中を叩いてがっはがっはと笑う。
文兎も苦笑いをし、その男がいう『鴪川和のばばあ』とは自分の母方の祖母のことだろうとすぐに察しがついた。
この町に鴪川和家は二つもいない。
「本当に大丈夫なんだな?」
男は思い出したように文兎に詰め寄り言う。
文兎は手を握って開いて、それから笑顔をつくる。
「大丈夫です。歩いて帰れますから」
と言ってはみたが身体は立っているのがやっとで、目の焦点が合わずに男の顔もろくに見えてはいなかった。
しかし、そうとでも言わねば男は引きさがらずに救急車を呼んでいただろう。そっちの方が色々とマズかったりする。
それと同じようなやり取りが文兎と男を四周ほどしてから男は不服そうな表情で言う。
「じゃあ、おれはぁ帰っから。・・・じゃぁな、高校生。・・・名前はなんつったっけ?」
「文兎です、三河」
と嘘を言う。
しかし、町の人間に三河の名前は失敗だったとすぐに後悔する。
「三河?海苔やってる三河の息子かぁ?」
軽トラに乗り込んで、アクセルを踏み込む寸前の男は窓から首を出して言った。
「いえ、人違いです」
「そうかい。まぁ元気でなぁ」
男は手を振り、軽トラは海とは反対方向の山道へと進み、やがてライトの光すら見えなくなった。
それを見送ると、まるでスイッチの切れたロボットのように文兎は膝からアスファルトの地面へ崩れた。
冷たさを背中で感じながら真冬の夜空を見上げた。
マフラーもあればスクールバックも道の端にある。脱いだはずのブレザーは着ているし、濡れていた髪は泥だけ残してカラッと乾く。
そして何より、ベルトには卒業写真のアルバムが重さと共に挟まっている。
「こういうのを、狐につままれたっていうのか」
この気温で水が乾くなんてことはあり得ない。乾く前に凍りつく。
そもそも、僕は己山小学校の職員室にいたはずなのに、何故ここにいる?
文兎は身体を起き上がらせてふらつくし足取りでバックを肩に掛けて、マフラーを首に巻いた。
寒さでまたしても意識を飛ばしてしまったら、今度は身を覚ます保証もない。
重い足を一歩踏み出し、さっき男の軽トラが消えてった方向とは逆に針路を進める。
ポケットに突っ込んだ手は、冷えてぴりぴりと痛い。
「はぁ?記憶喪失ぅだぁ?」
三河は眉を寄せながら、こたつの上のミカンに伸ばした手を止めた。
「そう。気づいたら己山の旧道。六時間ぐらいの記憶がない」
文兎はこたつの中のヒーターへと手を近づけて言う。
風が出始めたのか、トタン屋根に何かが当たって頭上の裸電球が揺れる。
「まぁその話も聞くが、家に電話ちゃんと入れただろうな?」
「さっきお前に携帯借りただろ。大丈夫」
三河は溜息をついてから、立ちあがって天井ギリギリの高さの箪笥を開ける。そこから紺の学校指定のジャージとタオルを引っ張り出して文兎に投げた。
「ドラム缶風呂。ついさっきだからまだ暖かい。速く入ってこい」
文兎は頷き、まだ泥が残る制服で六畳間のその家の玄関に向かった。
半畳もない玄関の文兎と三河の二足しかない一足へ足を突っ込んだ。ドアを開ける前にブレザーとカーディガンを脱ぎ、ネクタイを外してそれらまとめて玄関の横に置かれたスクールバックの上に乗せる。
「そこで全部、脱いで行けよ」
三河は玄関から三メートルも離れていないこたつに入りながら言った。
「嫌だよ」
そう言い捨てると、文兎は意を決してドアを開け、真っ暗な外へと身を投げ出した。
浴槽という名のドラム缶は三河の`家`の煉瓦壁沿いに、右回りするとすぐに見つかる。
一メートルほどのトタンの板が三枚。コの字に立てられ、ドラム缶二個を溶接した浴槽と緑色のホースが雨よけのトタン板に吊るされる裸電球で見受けられた。
溜息をついた文兎は寒さに耐えながらタオルとジャージを抱えてその一角へと小走りで向かう。
*
文兎が外に出て、ドアが音と共に閉まるのをこたつの中で見送った三河は立ち上がり、四面のうちの風呂のある壁のスイッチを入れる。
そのまま止まることなく、寒い室内を一周回ってからさっきまで入っていたドア一番遠いこたつに入る。
潜り込んですぐに腕を伸ばして、壁側の延長コードに繋がった携帯電話を引っ張り抜いた。
閉じた携帯電話を開いて、そのままリダイヤルを押す。
コール音が三河の耳元で鳴る。
先週に切ったばかりの頭に携帯電話の端っこが当たって、少し撫でる。
四回目のコールが鳴りやむ前に止み、ノイズの後に声が入る。
『あ、もしもし?』
少し息の上がった生々しい声を耳元で聞いて、三河は一呼吸置いてから声を受信機に吹き込んだ。
「千沙、悪い。今忙しかったか?」
何かが携帯電話に当たって入る音を聞きながら返事を待った。
『だいじょーぶ。今、お風呂上がったところだから。何か用?』
携帯電話は千沙の声を上部のスピーカーから出力する。
三河は0.1秒の妄想の後に要件を言った。
「今、文兎がうちにいるんだけど、何か知らない?」
『何かって、何よ?文兎がどーかしたの?』
あまりの千沙の声の高さにノイズが走り、三河はたまらず携帯電話を耳から離す。
「別にどうかしたわけじゃないど、記憶喪失だとか言ってるし、泥だらけだし。何かあ」
『き、記憶喪失ぅ?文兎、怪我したの?!大丈夫?!』
三河は耳から離した携帯電話を更に遠ざけ、負けない声で言う。
「怪我してないから!大丈夫だから!まぁ、何も知らないならいいや」
『・・・大丈夫なのね?ごめん、パニックっちゃって』
三河は携帯電話を耳に近付けて音を拾う。
「ああ。でも何かわけありって感じ。泥だらけで自分には昼間の記憶がないんだってさ」
『学校で会ったのが最後よ』
「俺もあの後すぐに帰ったし。今回は鴪川和家絡みって訳でもな・・・」
『今回ってなに?』
三河は口を手で覆い、目を閉じる。
危うく口を滑らせるところだった。
「な、何でもない。・・・悪い、何かわかったらまた電話する」
『え?ちょっと待ってよ!鴪か』
「お休みっ!」
千沙の少し高い声を聞かないように耳から離して、三河は強引に通話終了を押す。
「少し、しべっちまった。・・・どーしよ」
きっと明日問いたださえるのだろうと思いながら、携帯電話を充電コードへと差し込んだ。
*
「ふぅー。生き返るわ」
文兎はシャンプーの匂いの残る頭にタオルを三つ折りにして置き、少し冷え始めた湯船に身体を肩まで沈めた。
頭上の裸電球が風に揺れて、砂浜の影が同じ速さで揺れ動く。
耳を澄ませば近くで海水の退き満ちの音が聞こえ、壁一枚向こうから三河の独り言が微かに聞こえた。
ここは三河の別宅。
別宅と言えば聞こえはいいが、実際は三河の父親のお古の仕事場だ。水と電気は引いているものの、煉瓦とトタンとベニヤ板でできているドラム缶風呂付六畳家だ。
三河の家は複雑で、父親と母親が別居中だ。母親は古見北の内地に家があり、父親は海側の海苔養殖が仕事ということもあって、現在は仕事場で暮らしている。
三河家と鴪川和家は親同士の面識もあって父親とも何度か会ったことがある。なんと言っていいのか、子供がそのまま大人になったような人だ。面白い。
そしてアイツは古見北中学時代までは母方の家に住み、高校進学と共に近い海側の元仕事場に引っ越してきた。誰もがうらやましがる一人暮らしというやつだ。
ついでに言うと、中学の時には母方の家にも遊びに何度も行った。その際に母親にも挨拶したが、何というか、子供をそのまま大人にしたような人だ。面白い。
そんな面白くも大変な三河家別宅に転がり込んだのは単純に鴪川和家に帰りたくなかったからである。
「・・・はぁ、疲れが染み出る、出汁になる」
しかし、風は冷たく気温も低い。
まだお湯が暖かいうちに上がろうとドラム缶の淵に手を置き、砂浜にすのこを引いただけの床に立つと、まるで忘れものをふと思い出したように波紋の浮ぶ湯船へと振り返った。
「あ」
何だっけ。
夢の中の内容を思い出したような映像が脳裏に浮かんだのに。
手の平から砂が毀れ落ちるように消えてゆく。
大切な、大切なものだった気がしたのに。
伸びた前髪の先から水滴が一滴、砂浜に染みをつくった。
一秒づつ逃げる体の熱を感じながら、文兎は小走りで玄関から六畳間の中央にあるこたつへと入った。
「あ、そういや。夜飯まだだった。いや、昼も何も食べてないんだった」
思い出したように文兎はこたつの向かいでミカンの皮を几帳面に剥いている三河へと言った。
「家に帰って食え」
と当然に三河は言う。
「じゃあ昨日の宿題と五円四百二十円をお前に請求するぞ」
と文兎も口を動かした。
「はいはい。インスタントでいいな?」
「それ以外にどうせ何もないだろ」
まあなと言って三河は同じ畳のひかれる六畳間の玄関横の流しへと足を動かす。
「そういや、何だったんだ?記憶喪失ってのは」
三河はガスコンロに火をつけて水道水の入ったヤカンを置く。
「昼の三時過ぎだったかな。己山の林道を抜けて、近道して」
文兎は体の四分の三をこたつから出して玄関近くのスクールバックへと手を伸ばした。
「そんで己小の校舎まで行った」
「校舎まだ残ってたのか」
「ああ。あそこも一応は鴪川和家の分譲地だしな。本家に断りもなく町も手を出せなかったんだろうよ」
文兎は指先にバックの紐を引っ掛けてその上に乗る制服ごと手繰り寄せた。
「まあ己小に入ったはいいけど唸り声はするわ、カビ臭いわで」
「唸り声?まあ己山小ならそんな怪談話、五萬とあるだろうな」
「話の腰を折るなよ。で職員室に入った」
「何で職員室?」
ヤカンが音とを立て、三河は開けたインスタントラーメンの近くにタイマーを置いた。
「出席簿。それがほしかった」
「なんでまた出席簿?」
三河はカップ麺の用器に百度になった熱湯を注ぎ入れる。
「だから話の腰を折るなって。最後の年のクラスが知りたかったんだよ」
「ああ、そういやお前って小学校の時の記憶が曖昧なんだったっけな。悪りぃ、すっかり忘れてた。で、職員室に入ったと。それから、それから?」
三河は二つのカップ麺を両手に持ってこたつへと戻ってきた。
「ありがと。で、職員室に穴があって落ちた」
三河から受け取ったカップ麺を自分の前に置いて割り箸を乗せた。
「落ちただぁ?じゃあその時にでも頭ぶつけたか?」
「いや、その穴から這い上がったのは覚えてんだよ。そこまでは」
先に手を出したのは三河で、三分まだ立っていないカップ麺へと割り箸を突っ込んだ。
「気づいたら旧道の端って話に繋がるのか。不思議だな」
他人事のように聞き流し、三河は縮れる麺を音を立てて啜る。
でも文兎には三河は切っても切れない存在であるのは確かであった。
「今日は鴪川和には帰らない。悪いが泊るぞ」
「最初からそのつもりだったさ。追い返したりしねぇよ。そっちの方が親父にどやされちまう」
流しの横の窓辺付近でタイマーが鳴るのを聞いてから、文兎はカップ麺の蓋を剥がす。
そのころには三河はすでにスープにまで到達していた。
「じゃあ今回は鴪川和家って訳じゃないんだな?」
今まで用器に顔をうずめていた三河は急に視線を文兎に向けて言う。
テレビさえないこの家に隙間風の音が妙に際立った。
「関係ない。記憶はあって困るものでもないし、思い出せるもんなら思い出したいのさ。でも、思い出せそうなんだよ。最近」
そう。
大切な何か。
でも、思い出さない方がいいのかもしれない。
文兎は褐色色のスープの中の麺を見ながら思う。箸はその中をぐるりと廻し、気泡が油と一緒に浮きあがった。
三河はまだ熱いスープを一気に喉へと通し、残りをカスごと飲みこんだ。
「よし。じゃあ俺も行こう。己山小学校。明日でいいな?放課後だ」
こたつから立ちあがった三河は言う。
文兎は思い出したように半分まで開いたスクールバックのファスナーを開け、その中から一番汚く古い黒い背表紙を引っこ抜いた。
「それは構わないがこれ。実は穴の中で見つけたんだ、卒業アルバム」
こたつの上に置いたそれは高そうな黒いカバーのついた厚い本。表紙には金の筆記体で年度卒業アルバム。年は石の様なもので擦ったのか黒い表紙ごと抉れて読めない。
「卒業アルバム?いつのか分かんなきゃお前の年のかどうか分かんないじゃねぇかよ」
それを言われてしまうと元も子もない。咄嗟に見つけたそれが唯一見えた卒業アルバムだったのだ。
「まぁ、何かのきっかけになるだろうし、持ってきて見ないのも勿体ない」
一ページ目を捲ろうと表紙に手を掛けて文兎の手に三河は箸の先を軽く乗せた。
「これで万が一にも思い出すことってあるのか?」
「さあ、僕だって思い出せるなら思い出したいし、どうしても思い出せないならそれでもいいと思ってるぐらいだ」
そう言って、三河も少し不安そうな顔を横目に、文兎は干からびてひっつき合ったページを強引に開いた。
結局、その卒業アルバムに載っていた数人の生徒の顔写真の中に、六年前の自分の顔らしきものはなく、溜息をついたのは文兎だった。
次の日。
朝が特に寒い三河家を遅刻した状態で出発した文兎と三河は高台に位置する我らの高校に着くころにはSHRは終わり、昨日に終わらなかった大掃除を開始する直前であった。
そして千沙は当然のように言う。
「文兎、どーしたのその制服?!」
三河と千沙、三河。そして文兎の後ろの席の眼鏡の女子、椎名さん。
二班が仰せつかった掃除場所、校舎裏のゴミ拾いで千沙は言った。
それは当然、泥だらけでシミだらけの文兎の制服についてだ。
「えーっと。転んだ。ちょっと水溜まりで滑ったんだよ」
己山に入ったなどと言えば、千沙が黙ってはいないと察した文兎は咄嗟に言い訳を口にする。
千沙はなぜだかそういったことに敏感で過剰だ。
「ここ三日は雨なんか降ってないわよ!あ、昨日電話で言ってたやつか!大丈夫?」
千沙は持っていた箒をほっぽり投げてバックを担いだままだった文兎の頭やら腕やらを撫でまわした。
文兎は椎名さんの後ろに隠れるように逃げた三河を睨んだ。
「大丈夫だから。それより早く掃除やろ、また僕たち校門の掃除も残ってるんだし」
千沙が放って地面に転がる箒を拾い上げて文兎は言った。
「うん。わかったわ・・・。じゃあ、私は三河とゴミを環境委員のいる焼却炉に持っていくわ」
そういうと今度は椎名さんの背中に張り付いていた三河の襟元を掴んで千沙はグランドの一番端にある焼却炉まで、まるで嵐のように走り抜けた。
「じゃあ、落ち葉を掃いちゃおっか」
そう文兎はチリトリをもって突っ立っていた椎名さんへと言う。
「そうね」
とだけ小さな声で言うと、木の陰に置かれた三つの落ち葉の入った白いごみ袋へと目をやった。
淡い白 -後編-
「ちょっと、どういうこと?」
そこはこの学校に知る人ぞ知る有名な場所。いや、パワースポットと言うべきだろうか。
伝説によるとこの焼却炉で愛しの人物に告白すると否応なしに相手が発狂するらし。by 浪速の新聞部こと神田嘉香
「いやー。困ったね。こりゃ」
三河はあははと笑いながら風通しのいい頭を掻いた。
「困ったじゃないわよ!文兎はどーしちゃったの?それにあれは本当に大丈夫なの?」
千沙は三河の背服の襟をネクタイごと掴むと、顔を近づけ喉を絞める。
何故に俺をわざわざ経由するのかと三河はいつも思う。
「見ての通りに文兎は大丈夫さ、無事で安泰。今のあいつならきっと大吉を七連続で引き当てるぞ?」
笑って見せる三河を突き放し、長い髪を千沙は振った。
今日は珍しく髪を後ろで結ってはいなかった。その光景を三河が見るのは実に二年ぶりである。
「可愛いなー、やっぱり下ろした方がいいって、マジで」
「え?ホント?じゃなくて、そんなことはどーでもいいの!それに思い出したけど鴪川和家がどうたらって言ってたわね?そこんとこちゃんと私にも説明しなさいよ」
千沙は鼻息がかかるほど三河に近づき、眉を顰めて言う。
そのままキスでもしてしまおうかと思ってもみるが、その真剣な千沙の表情に三河のつくり笑いに罅が入った。
まるで三年前の自分を見ているように錯覚したからだ。
「あ、ああー。それは千沙の聞き間違いだ。文兎はこけて一瞬だけ意識が飛んでたってだけだ、命にも健康にも性格にもカップ麺を食うのだって支障はない」
ピクリとも動かない千沙の瞳は三河の視線と重なって、言う。
「嘘」
まあ、そうだけど。
「本当だって。昨日はそうだな。親に怒られるって言ってたか俺の家に泊めてやった」
「お願い。教えて。最近の文兎はおかしい」
更に、近づけた千沙の体が震えているのを三河はその肌で感じた。
三河の表情から笑顔というものがまるでスイッチを切ったように無くなる。
「文兎はPTSDを持ってる」
観念したというように両腕を上げて、焼却炉のフェンスに背を預けて三河は芝生に腰を下ろした。
「PTSDってなに?」
「座れよ。これ絶対に誰にも言うな。文兎にもだ」
三河は自分の横の芝生から落ち葉を払って手を叩く。千沙も三河と同じように背を凭れて地面に膝を曲げて座った。
「変な風にはとらえるなよ。初めに言っとくと文兎は文兎で文兎なんだ」
「・・・当たり前じゃないの、そんなの」
と小さく千沙は答えた。
「心的外傷後ストレス障害。文兎の小学校の頃の記憶が曖昧になっているのもそれが原因だ。きっと文兎の言っている記憶喪失ってものフラッシュバックの影響かもしれない」
「まって、意味わからない。じゃあ本当に文兎は今、記憶喪失なの?」
「本人が言うにはな。きっと己小学校に行ったのが引金になってフラッシュバックしたんだろう。そのせいで記憶が欠落したんだと思う」
「フラッシュバックって何?」
「フラッシュバックってのは過去の体験を再体験することだ。文兎の場合は体が記憶することを拒否するほどの」
「じゃあ、何を文兎は思い出したのよ?その原因ってのを無くせば普通に大丈夫よね?」
「・・・そんな簡単じゃねぇんだよ。俺が言えるのはここまでだ」
三河は腰を上げて枯れた芝生のついた制服を叩いた。
少し風が出てきて肌寒い。
「待ってよ!何で今まで言わなかったのよ?何が文兎を苦しめているの?・・・私には、何ができるの?」
千沙は少しうるんだ瞳で三河の腕を制服越しにつかみ、もう片手の裾で目元を擦る。
「お前、文兎が好きなんだろ。だから言ってんだ。お前は文兎の傍に居てやれ」
三河はそう言って、千沙の腕をふりほどいて焼却炉から校舎へと歩き出した。
「鴪川和・・・家ね?なんで」
千沙は三河の後ろ姿に思い出して言った。
「・・・俺も半分、三河の人間だからな」
千沙はほかにも多くのことを口に出して言おうとしたが、それは声にならずに口に苦みと共に残って唇を軽く噛んだ。
*
三河と千沙がゴミ袋も持たずに姿を消して十五分。文兎は黙々と椎名の持つチリトリにゴミを箒で押し込んでいた。
「椎名さん。明日って休みだよね?」
ふと文兎は昨日担任の言っていた冬休みのことを思い出し、チリトリを両手で持ち小さく屈んだ椎名へと言った。
「明日から冬休み」
文兎より頭一個分ほど小さな椎名は立ちあがって言う。
「そっか、ありがとう」
文兎がそういうと椎名は頭をぺこりと下げて、千沙の半分ほどの長さの髪を押えた。
常識的な会話しか交わしたことのない二人に沈黙の重い空気が圧し掛かった。
横目でみる椎名の表情は無という他になく、眠いのか閉じかかった瞼に瞳は隠れ、より一層に文兎は声は会話を模索することができなくなる。
風が吹き、草陰に隠れていた落ち葉が自分の前へと飛んで動きを止めた。
昨日に比べると風がある分、今日の方が寒い。
「そういえば、椎名さんって古見北中出身だっけ?同じクラスになったことないよね」
口にしてみると自分でも意図の見えない会話となっただろうと文兎は思う。
「三年の時に越して来たばかりだったから」
そういえば、三年生の時に女子の転校生だと三河がはしゃいでいた記憶がぼんやりとある。
「そうだったんだ。前はどこに?」
文兎は目の前の落ち葉を箒の先で小さく動かして言う。
「遠く」
会話終了。
椎名はチリトリの中にある五枚ほどの落ち葉を開いているゴミ袋へと流し込んだ。
もしかしたら同じ己山小学校の出身者かと淡い希望も含めた質問に椎名はその数手前に大手を掛けたのだ。
そもそも、己小の出身者などこの学校に自分以外で居るのだろうか。
当時は古見北と町を直通する道はなく、旧道から山道をひたすら上る山越えしか行き来する方法はなかった。つまりは己小の生徒は海側の人間しかあり得ない。なんたって海側の老人は三河の父親も鴪川和の祖母だって母だって皆、あの古い校舎で勉学を受けたのだ。
そして現在、海側に住む若い世代は僕と三河ぐらいしか把握していない。
「あれ、」
おかしい。
じゃあ、少なくとも己小、最後の年の生徒。五人はどこに消えた?
生まれてこの方、この町で子どもなんか見たことがない。
記憶の曖昧な時期に転校してきて、そしてまたわざわざ転校したのか?
何かを忘れている。そもそも、僕は最後の生徒ではないのに、ブービーのクラスだったはず。
本当にそうなのか?
「思い出した?」
椎名は言った。
いや、椎名の口が言うのだ。椎名ではない。
「あ、ああ」
椎名の黒い二つの目が、ただこちらを見つめている。
チリトリを手に持って、落ち葉を足元に落としながらそこに立っていた。
「何を言ってるんだよ、お前」
文兎は咄嗟に手に持っていた箒を握って一歩後ずさりした。
聞こえた?そんなはずはあり得ない。
「どうして、忘れちゃったの?文兎」
椎名は言う。
片手を文兎の頬辺り伸ばし、白く小さな指先が数センチで頬を掠る近くまで。
「お前、誰だよ?!」
口が震えて、声のトーンが不安定になったが椎名に言った。
「椎名じゃ、ないだろぉ!」
椎名の表情が笑顔になった。まるでそれは死人に糸を括りつけて作ったような笑顔。
文兎は自分の血管から血がまるで足へと流れ出ているかのように錯覚した。
「待ってるから、今度こそ私を助けてね?」
椎名は言う。
口がそう動いた。声は紛れもなく椎名のそれで、でも違う。
「お待たせー」
まるで金縛りにあったように地面に縛られた体を解放したのはその少し能天気なお調子の聞きなれた声だった。
振り返ると、三河が出しっぱなしのワイシャツで濡れた手を拭きながらこっちに歩いてきた。
血管に血が通うのを感じる。解放感。
「便所に行ってた。掃除しよー掃除。椎名さんも頑張ってなぁー」
三河はそう言って、文兎の肩を軽く叩いてから横をすり抜けて進んだ。
文兎も恐る恐る三河の背中を追って振り返った。
椎名はしゃがんでそこにいる。
両手で地面に生えた雑草を根元から掴んで、うんしょと引っ張り上げていた。
先ほどの面影は欠片もない。
「どうしたの」
椎名は口を開けて自分を見つめていた文兎に言う。
半開きの目に無表情な不思議が漂う。
今年一年間、自分の背後にいた椎名そのものだ。
「あ、いや。何でもないよ」
幻覚?
現実と違和感も何もない。幻覚だったのか?
いっそのこと、椎名の双子の妹ですとでも言ってくれたら信じ込む。
「そう」
声も、椎名で。黒い瞳も椎名だ。
「記憶喪失の次は白昼夢か」
小さくぼやいて、いつの間にか落としていた箒を拾った。
「何か言ったか?」
三河は椎名と一緒になって、この季節に頑固に根を張る雑草と格闘しながら言う。
「いや、寒いなーって。そういや、千沙はどこで何やってるんだ?」
「さぁ、便所じゃね?」
三河はそう言って、椎名と共に尻もちをついた。
辺りに泥が跳ね、それは近くにいた文兎にも被害を及ぼしたのであった。
*
己小。正式名を己山小学校。
己山鉱山の中腹部に位置する市立小学校である。
現在は村の過疎化で廃校となっている。
開校は昭和初期。しかし、そのずっと昔から寺子屋としてあった場所が小学校に名を変えただけである。
なお、改修工事は行われたという記録はない。
そして己小と言えば土砂崩れ半壊事故以外に、怪談としても有名だ。
「己小は第一次世界大戦で空爆を受けた。その当時掘った防空壕が校舎裏手の崖にあり、爆風で何人もの住民が今なお生き埋めになっており、時より地面を叩くそうだ」
三河は自分の椅子に後ろに座り、窓の外を見つめる文兎に言った。
「第一次世界大戦ってまだ爆撃が本格かしてない時代だろ。歴史の教科書を読み返せ」
あっそといって三河は数学の大学ノートのページを捲った。
「あの学校のチャイムは一日に三回しかならない。しかし、放課後の五時過ぎにあの学校に行くと聞こえるはずのない四回目のチャイムが聞こえるそうだ」
三河は声の音量を下げて静かに言う。
「己小にチャイムってないんだよ。そもそも鳴らすほど生徒もいなかった」
それまたきっぱり切り捨てて、担任が黒板に書く冬休み中の予定に目を向けた。
明日から、冬休みだ。来年の六日まで。大晦日の祭りを挟んだ夏休みの次に長いビックイベント。
「校舎の二階には開かずの教室がある。そこで以前、授業中に生徒が消えるという事件が起きたからだ」
渾身の一撃と言わんばかりに、持っていたシャーペンの先を文兎に向けて言う。
「二階にあったよ。開かずの教室。事件もあった。でも、授業中に床が抜けて生徒が一階に落っこちたってオチだ」
こうして思えば結構思い出せるものだ。六年前のあやふやな記憶さえも。
でも、どれもこれもに生徒の顔や、その時の実感が全くない。
三河は弾切れだと言って、ノートとシャープペンを文兎の机へと放り投げた。
「それって全部、情報元は己小の生徒じゃないだろ?」
「柏に耕治、秋瀬に直哉。全員違うな」
元、古見北中学の同級生の名前を挙げて、三河は言った。
「わざわざ怪談なんて集めんなよ。これから行くってのに」
「だからだぜ。文兎は絵を描くからいいけど、俺は楽しみがないじゃねぇかよ」
真顔でそれを言うのだから三河はすごい奴だと文兎は思う。
もう数分後に終わるSHRが終われば、三河とは再び己小へ行くことになっている。
「なぁ、千沙は何か知らないか?己山小の怪談」
三河は顔を右隣の千沙へと向けて言った。今日は千沙の様子が朝からおかしい。
「知らないわ」
とこっちを見ずに言う。
朝は確かに下ろしていた後ろ髪が、今はいつものように一本で縛られる。それは文兎がみるいつもの千沙の後ろ姿だ。
「千沙、今朝から何を怒っているんだ?」
文兎は千沙の背中へと言った。
心当たりがないわけではない、でも今朝の掃除は時間内に終了していた。
つまり、三河と文兎の今朝の遅刻ではない。
「別に、ふつーよ。私」
と千沙。
「何か僕やったっけ?掃除なんの滞りもなく終わって、明日から晴れて冬休みだ。・・・ねえ?椎名さん」
文兎の後ろでボケっと口を開けて冬の空を窓越しに眺めていた椎名へと振る。
「そうね」
半開きの目で椎名は言う。
「別に、私は。ちょっと考え事をしてただけよ」
ふてくされるように文兎を見ながら千沙は言う。しかし、千沙と文兎の視線が合うことはなかった。
そこに割って入ったのは三河。手の平を千沙の頭にぴたりと乗せ、もう片方で文兎の口を押える。
「そこまで。文兎も何、突っかかってんだよ。千沙は、まぁ後でちょっと顔貸せ」
その声は大きく、クラスの半数が窓側の一角へと視線を合わせた。
「おーい、喧嘩かぁ?だったら授業が終わってからやれー」
担任が無意味に書き続けた黒板から手を離し、ダルそうな声で言った。
「違います。三河が僕に早速宿題を見せてくれった言って来たんですよ」
咄嗟にホーローのつもりで入れたそれが逆にクラスを盛り上げてしまう。
「はいはい。静かにしろー。三河は知ってっか?宿題ってのは英語でホームワークっていうんだ。家でやる仕事。覚えとけー」
担任がそう締めくくって、また再び黒板に冬休みの予定の続きを書き始めた。
千沙はその間に三河の手を振り切って、前へと戻り。三河も相変わらずの笑い声でその場を流した。
今年最後のあいさつを担任が教壇で済ませると、夏休み前日並みの歓声がクラスで上がり、皆が一斉に教室を飛び出した。
教室に残った人数は昨日の半分の四人だけだった。担任に三河。文兎に千沙。
みんなは古見北へ遊びに行ったのだろう。海側にはカラオケもボーリングも何もない。
「また午後前に終わったな。飯は茂上中華のチャーハンと酢豚な」
そういうと、三河は帰ろうとバックに荷物を詰めていた千沙の手を引く。
「おう。千沙も来るよな?飯は」
「当たり前だ。引きずってでも連れてくさ」
千沙の代わりに三河が答え、教室の外へ強引に姿を消した。
「・・・あいつら」
何かあったのだろうか。
千沙の不機嫌にはどうやら自分よりも三河が一枚噛んでいるように文兎は思った。
「鴪川和、三河に宿題を見せんなよ。そう彼女にも伝えとけ」
黒板のチョークを消しながら、担任が言った。
「千沙は彼女じゃないですよ」
僕らの担任は去年から千沙のことを二人の時はそう呼んだ。
無論、その度に僕らは付き合っていないと修正を加えているのだけれど変わったことはない。
「そうかい。じゃあな、よいお年を」
そう言い残して担任は出席簿を片手に教室を出た。
「先生もよいお年を」
廊下には担任の足音が響いて、それ以外に何も聞こえない。
千沙と三河はどこへ行ったのだろうか。
黒板の上。壁に掛かった丸い時計の秒針が刻む音が静かな教室へ鮮明に広がる。
「 静かな空へ響け 隠したあの子の子守唄 君に聞こえはしないけど 」
どこかで聞いた歌の歌詞を口ずさみ、少し泥の撥ねたスクールバックに机の中に残った教材を詰め込んだ。
「 この声が 消えるまで 歌いましょうか 歌いましょう 君が眠るその・・・」
その何だったか。
思い出せないそのフレーズはあの子に会えば思い出すのでしょうか?
「あの子って誰だよ」
独り言は自分の耳に入るほどに大きく、文兎は我に返って辺りを見渡した。そこに誰もいない。
手に取ったバックに入れっぱなしのスケッチブックは昨日のままで、開くとそれまた昨日のままの下書きがHBの黒鉛を残してそこにあった。
作品名はまだ決めていない。
古びた土塊の塀のある家。すでに家とは言えないほどに風化してしまっているが、六年前の記憶の中には確かにそれは主人のいる家なのだ。
「おじさんまだ元気にしてるかな」
そう言ってページを捲る。
白紙のスケッチブック。まだ何も書かれていない。後二枚、終わらせなければいけないのだ。
そのために僕はあの小学校へ行くんだ。
「そう。君に会いに行くんじゃないんだ」
『待ってるから』
椎名の低く小さな声で言ったそれがまだ耳の奥の方で残っている。
あれは夢で、現実じゃない。
茂上中華。
店長直筆で描いた赤いペンキの店名が大きく掛かった看板に目立つ。海側にある唯一の中華店だ。
「おっちゃん、チャーハンに酢豚」
三河はラジオが騒がしい店内で声を張って言った。
「ラーメン」
文兎も三河に続いてカウンター向こうの調理場で中華鍋を廻す油の紙魚の白髭の親父へと言う。
カウンター席しかない店内に客は少なく、仕事途中の中年が三つ奥の席に座っていた。
「なぁ、そういや千沙とさっき何しゃべってたんだ?」
文兎は思い出し、スクールバックを傍らの空席に置いて言う。
「別にー。これと言って背骨の入った話じゃないぜー」
割り箸を取ると、まだ来てもいない机を前に三河は二つに裂いた。
「じゃあなんであんなに千沙は不機嫌なんだよ?僕に心当たりはないからさー」
男性レポーターが何処かのラーメン屋をほめたてる上等文句をいう声をらじをで聞きながら言う。
「待って、俺も心当たりはねぇーよ!きっと青い日なんだろう」
と三河が言ったのと同時に店長が両手に皿を二つ、重たそうに持ちながら二人の目の前に影を作った。
「チャーハンとラーメンお待ちっ!」
唾が飛ぶかの様な大声で店内は二人へと言う。ついでに言うとこの店に店員はいない。店長=茂上さんだろう。
「チャーハン!俺!」
と三河。
「あ、ラーメン」
と文兎。
並々に皿の淵、ギリギリまで揺れる脂の浮いたんスープは置かれたと同時に飛沫を飛ばした。
To be continued
絵の中の少女


