
明時闇の願い星
前作「赤い渚に浮かぶ月」読んでいただけた方にはお久しぶり! 初めての方には、初めまして、よろしくです!
作品タイトルの「明時闇」は「暁闇(あかときやみ)」で、ルビを避けるために使った漢字です。
意味は、新月から満月になる前の、月がとっくに沈んでしまって真っ暗な、夜明け前。
月が無いのに、月の存在感がほのめかされてるという、実にナイスな単語ですね。
それに見合うナイスな内容になるよう、がんばっていきたいと思います。
お気が向かれましたら、気楽にお付き合いくださいね。
第一話 天使の居城
僕が”白亜の塔”に入って、二日が経ちました。
嘘みたいです。
実感なんて、まだ全然湧きません。
だって”白亜の塔”ですよ?
魔物を討滅するべく選ばれし天使の軍勢が集う、あの、聖なるお城ですよ?
そんな塔からの使者さんが『あなたは世界で最も強く尊き聖具である”羽根”に選ばれた”羽根使い”です。天使として、世界のためにその聖なる力をお振るい下さい』なんて来た日にはもう、ビックリなんてものじゃありませんでしたよ!
しかも行ってみてもっとビックリなのは、この僕が、よりにもよって、世界に数少ない羽根使いの中でもほんの一握りしかなれないっていう上級天使に、ポンッと加えられちゃったってことですよ!
信じられますか?
言われた僕自身、冗談キツいですねーって大笑いしてしまいました。
だけど、笑いごとじゃなく、本当に、僕は今、聖都の中心にどーんとそびえる白亜宮の最上階の、上級天使しか立ち入りを許されない場所に立っているんです。
上級天使のみんなにも、新しい仲間ですって紹介されたし、塔の番人さんたちには頭がパンクするほど色んな説明を聞かされたし、僕の任務に同行して手助けする役目だっていう随従の3人とも顔合わせしましたし。
僕なんかをおどかすためにしては、いくら何でも大げさ過ぎです。
こうなると、本当なんだって信じないわけにはいきません。
世の中、何が起こるか分からないものですね。しみじみそう思います。
え? 心細くないかですって?
勝手も何も分からないまま、そんなすごい所で、ちゃんとやって行けるのかしらって?
当たり前じゃないですか。不安にならない方がおかしいです。
……でも。
でもね、きっと大丈夫です。
僕はもう、決めましたから。
新しい仲間と、ここで一緒にがんばって行くんだって。
だから、心配しないで下さいね。
ああ、言い忘れるところでした。
塔では僕は、上級天使の八位、星焔(セイエン)の天使アイルと呼ばれています。
……あの!
ここは笑うところじゃないですよ!
上級天使の専用区画は、塔の上層階とは思えないくらい広い。
それぞれの自室はもちろん、舞踏会にだって使えそうな大広間から、壮麗な書棚の設えられた区画や、いくつもの遊戯盤が置かれた東屋などなど。それが何と、日の光がさんさんと降り注ぐ天窓の下、色とりどりの珍しい植物の繁茂する庭園の中に、散りばめられるように配されているのだ。花咲き乱れる小道を少し曲がれば、趣の異なる景色が次々現れるといった寸法で。
自室を出た瞬間から、花や果実の甘い香りが鼻腔をくすぐり、探検気分が大いに掻き立てられる。
が、気の向くままの気軽さで散策に出たアイルは、少々困った事態に陥っていた。即ち、
「困ったな、ここ、どの辺りなんだろ? 先刻から同じ様なとこ、グルグル回ってる気がする・・・・・・」
アイルは明るい金髪の髪をかき上げつつ、若草色の瞳で辺りをキョロキョロと見回してみる。
いくら広いと言っても、たかが塔の上層階のワンフロアに過ぎない、はずだ。
つまり道なりに歩いていれば、そのうち何とかなりそうなものなのだが……適度に視界を遮るよう配置されているらしい植物の間を抜けても抜けても、良く似た景色が立ち現れるばかりで、一向にらちが開かない。
誰かが通りかかることを期待するも、そんな気配は全くない。
「どうしよう、そろそろ大声で助けを呼んだ方がいいのかな・・・・・・」
アイルが少々情けない解決策を真剣に検討し始めた、その時。
澄んだ鐘の音が、庭園いっぱいに響き渡った。
思わず聞き惚れえしまいそうな美しさでありながらピリリと注意を掻き立てられるような、この音色の意味するものは。
「ええと確か、非常呼集の鐘だっけか? 大至急で広間に集合って合図の。・・・・・・でも、広間ってどっちだろ?」
空間全体に鳴り響く音は、あちこちで反響しあって、どの方角から聞こえて来るのか見当もつかない。
それに音の方向が判ったところで、そっちに広間があるとも限らない。
「ああもう、仕方ない!」
木が生えようと草が茂ろうと、とにかく真っ直ぐに突っ切れば壁にぶち当たるはず。
開き直ったアイルが駆け出そうとした、その時だった。
ふっと、白い影が行く手を過ったのは。
「あ! あの、誰かいますか?」
それは間違いなく人影だった。となれば、見失ってしまう訳にはいかない。
「すみません、待って下さい! 待って!」
影を追って植え込みを回り込んだアイルは、立ち止まって振り向いたその人物に激突しかけて、急制動で停止した。
「す、すみません、ホントすみません!」
慌ててペコペコ平身低頭するアイルに、降って来たのは涼やかな声。なのだが。
「それだけ?」
「ほえ?」
顔を上げたアイルの目の前に、小柄な少女の姿があった。
しかも、抜けるように白い肌の、肩口で切りそろえられたプラチナホワイトの髪の、まるで神話の世界から抜け出して来たようなとびきりの美少女だ。
淡い色の清楚なミニドレスが超絶良く似合う。
(うわあ・・・・・・!)
アイルは内心、感嘆の声を上げる。
何しろ彼女はそんじょそこらの美少女などではないのだ。
上級天使の五位、雪華の天使。
聖歌劇のヒロインとして描かれる、人々の崇拝の対象。
しかも演じる側の女優の一人などではなく、役のモデルになった方の、紛れもないご本人だ!
思わずぽけっと見惚れてしまったアイルに、透き通った水色の瞳を向けた少女は、再びほんのり明るい真珠のような唇を開く。
「謝りたかっただけ?」
つまり、それが自分を呼び止めた理由なのか、と。
「ち、違います違います! ええと、僕はアイルって言うんですけど、お、覚えてくれてますか?」
しどろもどろで事項紹介から始めたアイルは、なかなかにテンパっていた。
実際、塔に入ったその日に顔合わせだけは済ませていたのだ。
それ本当にごく短時間だったが。
果たして少女は、こくりと頷いてくれた。
その様子に、幾分気を楽にしたアイルは、早口に本題に入る。
「その、今、非常呼集の鐘が聞こえたんで、広間に行こうと思ったんですけど、ほら僕は二日前にここに来たばっかりで、まだ不慣れと言うか、ちょっと迷ってしまったみたいで、その、もし良かったら、一緒に広間まで行ってもらえませんか!」
ばくばくする心臓の音を聞きながら、アイルはありったけの勇気を動員してお願いする。
これが街角ですれ違っただけというシチュエイションなら、声をかけることすら不可能だっただろう相手なのだが、ここで置いて行かれては迷子を通り越して遭難間違いなしという非常事態である。
緊張するとか照れくさいとか格好悪いとか、四の五の言っている場合ではない。
だが、少女はアイルの話を聞き終わるや、何事も無かったかのようにクルリと背を向けて歩き出した。
「あ、あの・・・・・・」
何か失礼な事を言ってしまっただろうかと、アイルは上擦った声で呼びかける。
「こっち。来ないの?」
少女は歩を緩めつつ、小首を傾げる。
プラチナホワイトの髪がさらりと流れる。
「行きます! もちろん!」
気を悪くして無視されたのではないと解って、アイルは小走りで少女の後を追った。
特に分かれ道や分岐があるわけでもなく、ただ道なりに進むこと約一分。
目指す広間には、実に呆気なく着いてしまった。
一人で迷い倒したのは、何だったのか。
だが広間には、アイルと少女の他に、上級天使の姿は無い。
と、反対側の入り口から一人の青年が姿を現す。
彼はアイルの姿を認めるや、小走りに近付いて来た。
ダークブラウンの髪と瞳に、黒を基調としたかっちりとした身なりの青年は、アイル付きの随従で、名をバイロという。
アイルの前まで来たバイロは、洗練された身のこなしでひざまづくと、
「こちらにおいででしたか、星焔様。恐れ入りますが、急ぎ転移の間までおいで下さい」
「転移の間?」
「はい、そちらにて災厄の・・・・・・いえ、六位様がお待ちになっておいでです」
「ええーっ!? 聞いてませんよそんなことっ!?」
「申し訳ございませんが、事情はそちらにて。まずはお急ぎを」
重ねて促され、今度はバイロの先導の元、転移の間に向かって駆け足である。
もちろん去り際に少女にしっかり会釈することを、アイルは忘れたりしなかった。
転移の間に駆け込んだアイルを出迎えたのは、凍り付くような冷たい視線だった。
遅い。待たせるな。グズ、ウスノロ、マヌケ、今まで何やってた。
刺さって来る視線の意味を解釈すれば、大体そんなところだろうか。
その視線の元を辿れば案の定。
そこには硬質な蒼い瞳と長い黒髪の、アイルよりも一つか二つくらい年上に見える少年の姿があった。
赤を基調にした東方風の長衣を纏い、身の丈ほどもある曲刀を背に負ったその出で立ちは、聖歌劇で不動の人気を誇る災厄の天使ご本人であることに疑いの余地は無いのだが。
不機嫌を隠そうともしない高圧的な態度は、美形俳優が演じる民衆を守るヒーローというイメージとは少し・・・・・・いや、かなりかけ離れたものだった。
それは初対面の瞬間から、それこそ『任務の時は彼と組んで色々と教わるように』と申し渡される前から、全く変わっていない。
「すみません遅れました!」
無言の圧力に屈する形で半ば反射的に頭を下げてから、アイルはあれ? と首を傾げた。
「・・・・・・って、仕方ないじゃないですか、臨戦態勢で転移の間に直行だなんて、ひとっ言も聞いてないんだから!」
何しろ番人から説明を受けた限りでは、『非常呼集の鐘が鳴った時には、広間に集合して任務の詳細と指示を受けること。その上で派遣される者が選ばれる』ということだけだったし、分からないことは質問すれば良いとも言われた。
それなのに相棒となるはずの災厄の天使ときたら、初日に一瞬顔を合わせただけで、打ち合わせどころかまともに言葉を交わしたことすら無い有様だ。これはどう考えたって、落ち度があるのは相手の方だ。
冷やかな視線に負けないよう若草色の瞳に目一杯の力を込めて(見上げる格好になるのが悔しいが)、アイルがさらに言い募ろうとした時だ。
「それは残念だったなー」
投げつけられたのは、勝ち誇ったような声。
災厄の天使にばかり気を取られていたが、転移の間には他にも、黒いローブを纏った番人と呼ばれる技術者らや、その手足となって様々な雑事をこなす従僕らなど、十数人が立ち働いていた。
そんな作業をする彼らに構うことなく道を開けさせ現れたのは、燃え盛る灯火のような色の髪の少年だった。
外見的には、災厄の天使よりもほんの少し年上くらいか。
琥珀色の瞳が、面白いオモチャでも見つけたかのようにアイルに向けられている。
「君は、紅蓮の、」
「おうよ!」
少年の背後には、金色に輝く鎧のパーツを抱えた随従らが従っている。身支度の途中だったらしい。
「無駄足ご苦労。今回の任務はこの俺がいただいた!」
言いながら紅蓮の天使は、災厄の天使の肩をポンと叩くように片手を上げる。が、目標が僅かに身を引いたせいで、その右手は完全に空を切った。
ちっという舌打ち。
だがそれすら、災厄の天使は完全に無視する。
「まあい。どうせ負け惜しみだろうしな」
紅蓮の天使は腕組みすると、ふふんと余裕の笑みを浮かべる。
だが、これで解った。
災厄の天使が不機嫌極まりない顔をしていたのは、紅蓮の天使に先を越されたからだ。おそらくは先着していたにも関わらず、アイルを待っている間に。
「おい、何見てんだよ」
完全無視を決め込む災厄の天使に飽きたのか、紅蓮の天使は今度はアイルに琥珀色の瞳を向ける。
「文句あるのか、”八位”」
アイルが上級天使の八位であることは事実だが、そこを強調して呼ぶとなると、それは新参者のくせにという意味に他ならない。
「僕の名前はアイルっていうんですよ、”七位”」
わざとらしいくらい、にこやかに。
「ちゃんと自己紹介しましたよね? もうお忘れなんですか」
新入り扱いされるのはまだガマンするとしても、アイルにはちゃんと名前がある。
「ガキが付け上がりやがって! ちょっと上級扱いされたからって、この俺と同格だなどと思うなよ!」
「僕の方こそ心外ですよ」
”七位”というからには、つい先日まではこの紅蓮の天使こそが一番新入りだったのだ。
付け加えるなら、”雪華”や”災厄”と違い、”紅蓮”の銘にアイルは馴染みがない。
それもそのはず、紅蓮の天使はつい半年前に上級天使になったばかりだというのだ。
たった半年先なだけで、見下されるいわれはない。
「後輩が僕一人だからって、そんな威張って楽しいですか?」
「ハッ! 達者な口はちょっとでも役に立ってから叩きやがれ、なぁ・・・・・・」
啖呵の語尾を弱めた紅蓮の天使の目は、アイルを通り越して宙を泳いでいて。
「!?」
視線を追って振り向いてみれば。
そこにいたはずの災厄の天使の姿が無い。
転移の間のどこにも、その姿は見当たらない。
二人して言い合っている隙に、とっとと立ち去ってしまったらしい。
「あーあ、馬鹿らしい」
気を削がれたらしい紅蓮の天使は面白くなさそうに舌打ちすると、もう興味はありませんとばかりにアイルを放って踵を返す。
「ちょっと待って下さい! 僕の名前をまだ、」
「知るかよ・・・・・・ま、夏至祭のお披露目まで生き残れたら覚えてやるよ。じゃな!」
「その言葉忘れないで下さいよ! 半年何てすぐなんですからね!」
紅蓮の天使は振り向かぬまま片手を振るや悠然と歩み去り、控えていた随従らがアイルに一礼してその後に従った。
今更ではあるが、主従共々華やかな一団だなと、アイルは思う。
まさに舞台の中央に舞い降りんとする天の御使いそのものだ。
反面、アイルの相棒役ときたら・・・・・・。
「ったく、どういうつもりだよ」
何も言わないどころか指示の一つもしようとしない。
これではまるで、アイルなど不要と言っているようなものではないか。
実際、そう思っているのかも知れない。
「申し訳ございません。私が至らぬばかりに」
その声に振り向くと、背後に片膝で控えていた随従のバイロが、自責の念も顕わに深く頭を垂れていた。
「そんな、君のせいじゃないですよ」
上級天使の任務に付き従い、護衛から身の回りのフォローまでするのが随従の役目である。とは言え、今回の件は予測しようもない事だろう。バイロだってアイルと同じく随従としては新人なのだ。
「ですが・・・・・・」
だが、真面目なバイロにとって、それは何の言い訳にもならないことなのだろう。
その気持ちは、アイルにも解る。
人々の役に立つ。そのために白亜の塔に来たのだ。こんなことで嘆いていたって始まらない。
仲間同士、ここは一団結する場面だろう。
(新しい仲間・・・・・・か)
そう。立場は違えど、バイロは間違いなくアイルの新しい仲間なのだ。
アイルは決然と顔を上げると、
「そうだ、一緒に作戦会議やりましょう! 教えて欲しいことがたくさんあるんです!」
「アイル様、私如きでは・・・・・・」
唐突な提案に困惑顔を見せたバイロだが、アイルはじぃーっとその目を覗き込んで離さない。強引さも、時には必要。
「・・・・・・承知いたしました。では、後程アイル様のお部屋にお伺いしても?」
「やった! モチロンです!」
アイルは満面の笑みを浮かべつつ、
「その前に、部屋への戻り方教えて下さい!」
何をするにしても、まずは足下からである。
第二話 初陣
「ど、どうです、今度は僕の方が、早かったですよ!」
鐘の音が鳴り終わるかどうかというタイミングで転移の間に駆け込んだアイルは、姿を見せた災厄の天使に向かって胸を張った。
もっとも数歩分の差という際どさだったし、さらに言えば盛大に肩で息をしながら真っ新な任務用の上衣に片腕を通している最中のアイルに対し、相手は昨日と同じく準備万端整えた上で息一つ乱さぬ完璧な出で立ちでの登場だったのだが。
それでも勝ちは勝ちである。
これも昨日、バイロを相手に念入りに予行練習した成果。と言いたいところだが、実際はたまたま自室でバイロと打ち合わせの続きをしていた時だったというのが大きい。
用意してあったアイル用の装備一式を手にしたバイロが先導してくれなかったら、これほど早くどころかちゃんと辿り着けたかどうかも怪しいものだった。という事実は、わざわざ申告する必要はないだろう。
白を基調にした動き易そうな、それでいて大きな町の衛士の隊長が着る礼装よりずっと華美な装飾の施されたそれは、アイル専用に仕立てられた物である。
着なれないデザインに加えて装飾金具の留め方も少々複雑なのだが、それにも増して自分には過ぎた代物のようで少し気が引けてしまう。
だからと言ってあまりノンビリしていたら、ウスノロ扱いされかねない。バイロにも手伝ってっもらって、まずは装備と格闘だ。
だが、そんなアイルに一瞥すらくれず、災厄の天使はアイルの眼の前を通り過ぎる。
「なっ!?」
嫌味やツッコミを受けるだろうことは想定していたアイルだが、反応無しとうのはあんまりではないだろうか。
「ちょっと待って下さいよ、僕が・・・・・・」
しかし、アイルが呼び止めようとするより早く、番人の一人が災厄の天使の前に進み出て略式の礼を取る。
「申し上げます。此度の任地はベアトリアス公国北西部の薔薇の小都。昨日未明より魔物の襲来を受け、第四軍の一個小隊五名が対処に当たっておりましたが、数刻前より結界内に追い詰められ上級天使様の助力を乞うております。なお、魔物は火弾による攻撃を得てとし、数多の眷属を従えているとのこと。緊急の案件ゆえ、当該地の聖堂中庭に強制転移の門を開きます。どうか、ご準備を」
任務概要を聞き終えた災厄の天使は、鷹揚に頷いただけで転移の間の中央へ進む。
「だから、ちょっと待って下さいってば!」
自分を置いてきぼりにして淡々ど進む事態に、アイルは慌てて割って入る。
「僕はこれが初めての任務だって知ってますよね? だったら着いてからの行動とか役割分担とか注意することとか、力を合わせてがんばろうとか、何かその、色々あるでしょう! 仮にも君は僕のパートナーでしょう!」
「誰がパートナーだ調子に乗るなバカ!」くらいの反応を期待したのだが。
災厄の天使は振り向きもせず、無反応なまま。
その背の曲刀だけが、鞘に納められているにもかかわらず、無機質な光を弾いている。まるで、威嚇するように。
一瞬怯みそうになるアイルの視界の隅に、跪くバイロの姿が映る。
「アイル様、ご聖務の前でございます。この場はどうか・・・・・・」
恐る恐るかけられた声。
それは、立場が上の者を諌める精一杯であると同時に、アイルの助け舟になるものでもあった。
下の者に配慮するという理由で、メンツを保ったまま引き下がることが可能という意味で。
拒絶に怯んでしまった心が、即座に同意してしまいたくなるような。
だが、と冷静な部分が考える。
ここで黙ってしまったら、いつまで経っても無視し続けられるだけではないか。
それはアイルの望むことではない。
と同時にじわりと怒りが込み上げる。
「いい加減にして下さい! 僕が何か気に障るようなことをしましたか? そりゃあ僕は何も知らない新入りで、その面倒を見なきゃならないのは気に入らないかも知りませんけどね! 僕だって勝手が判らないなりに一生懸命努力しようとしてるんです、せめて挨拶を返すくらいしたっていいでしょう! 僕の言ってること、どこか間違ってますか!?」
気が付けば、怒りをそのまま言葉に変えて、アイルは災厄の天使の背に投げつけていた。
一触即発。
転移の間がシンと静まり返っている。凍り付いたまま動くのを忘れた一同の視線が突き刺さってくるが、気にしない。
これはアイルにとって、譲れないことなのだから。
「そうか」
ため息のように発せられたつぶやき。
それが、初めて聞く災厄の天使の声だった。
「お前は言葉にして聞かせなければ理解出来ない馬鹿だったか」
「なっ!?」
激昂でもなく蔑みでもなく、およそ感情というものを完全に排した声で。
しかしあまりと言えばあまりなその内容に、アイルの頭は一瞬にしてフリーズする。
「俺の邪魔をするな。魔物ごと叩っ切られたくないのなら。それ以外は好きにしろ」
アイルを振り返るどころか一度として目を向けようともせずに言い放つと、話は終わったとばかり災厄の天使は口を閉ざした。
「い、言うに事欠いて・・・・・・!」
何とか思考力をかき集めたアイルが言い返そうとしたところで。
「星焔様、どうか急いでお支度を。もうすぐ門が起動します」
いつの間にか、黒いフードを目深に被った番人の一人がすぐ傍に立っていた。
「でも・・・・・・」
「どうか、ご自重を」
おそらくまだ若い青年だと思われる番人だが、その声は丁寧ながら有無を言わさぬものを含んでいた。
自分が悪いとは思わない。
が、今現在バイロや転移の間に居る者たちを困らせてしまっているのは認めなければならない。
「・・・・・・分りました」
アイルは握りしめていた拳を開いて息を吐く。
確かに、これは自分らしくない。
初めて任務に出るという緊張が、必要以上に気持ちを高ぶらせていたのかも知れない。
「任務優先ですから今は黙りますけどね! 話しは終わったわけじゃありませんから! 覚えといて下さいね!」
捨て台詞のようで格好悪いが、それでも一言付け加えなければ気がすまなかった。
相手が無反応だとは、分かり切っていたとしても。
ともかく、無理やり気持ちを切り替えたアイルは、番人に指示された通りに転移の間の中央に立つ。
だだっ広いだけで何も無いと思われた円形の白い空間は、よくよく目を凝らせば床にも天井にもびっしりと、複雑な幾何学模様を組み合わせた呪印が施されている。
床の法円に内接する五角形の頂点には、それぞれ操作盤が設置されており、盤の中央に嵌め込まれた赤い貴石が、技官の操作に呼応するように瞬いている。
法円の中央に立つのは、不機嫌に背を向けたままのトーヘンボクの他には、バイロの他揃いの防具を身に着けた随従が二名と、先刻の黒いローブ姿の番人。
フードで表情の伺えない番人はどうだか知らないが、随従の三人は一様に緊張した面持ちでアイルの傍に控えている。
程なく、ブウウウン・・・・・・という、羽虫が低く唸るような低い音が次第に大きく響き始め、それはすぐに耳だけではなく身体全体を包み込む波動と化す。
操作盤に嵌め込まれた赤い石が、羽音の高鳴りに伴って虹色の帯へと変化する。
「う・・・わ・・・・・・」
四方から押し寄せる極光のような虹と地鳴りに、思わずうずくまりそうになった時。
アイルの内に在る何かが弾けた。
室内を満たした虹光が治まった後。
転移の間には、輝きを失った貴石の納まる五卓の操作盤と、五人の技官だけが残された。
輝きの暴力から解放されたと安堵の息を吐いたアイルは、その直後に激しく咳込み、思わず膝をついていた。
辺り一面に煤けた煙が立ちこめ、目を鼻を喉を容赦なく蹂躙する。
刺激に耐え兼ね涙で滲んだ視界の奥に、奇妙に歪んだ街並みが映る。
次の瞬間。
ドンッと大きな音と共に背の高い家屋の一角が崩れ、落下する煉瓦片が地面を叩きつつ砕ける。
飛来した火の粉混じりの礫をやりすごし、再び目を上げた先には・・・・・・ぽっかり空いた空間の下、もうもうと立ちこめる砂塵を透かして瓦礫の山が立ち塞がっている。
と、瓦礫と瓦礫の間、吸い寄せられるように視線を向けた先に、人らしきものの陰を見た気がして。
「大丈夫ですか、今、助けに・・・・・・!」
とっさに駆け寄ろうとしたアイルは、あと数歩のところで立ち止まって息を飲む。
助けを求めて伸ばされた腕に見えたそれは、もう人間の形をしていなかった。
歪によじれて折れ曲がって、幾つかの塊に分かたれて。。
焼け焦げた布切れが元はどんな衣服のそれだったのか、想像することさえ難しい。
「・・・・・・!」
思わず目を逸らしたそこにも、ここにも、打ち捨てられた人形のような塊が・・・・・・苦悶に満ちた形のまま二度と動くことのなくなったものが、幾つも、幾つも、転がっている。
凍り付くアイルの耳を、連続した破裂音が襲う。
と同時に、通りを隔てた街並みの向こうに、新たな煙が立ち上る。
パンパンパンッと、乾いた銃声が残響を残して、それきり絶える。
戦場なのだ。
ここは、理不尽に命のやり取りが行われる、無慈悲な戦場だ。
「星焔様!」
背後からのバイロの声に、アイルはハッとして顔を上げる。
すぐ目の前に、灼熱の塊が迫っていた。
とっさには動けずにいるアイルの前に、疾風の速さでバイロが飛び出す。
長槍一閃。
叩き割られた炎弾は煙の尾を曳いて左右に分かたれ、石畳を穿ちながら爆発四散した。
飛び散った小さな破片が、アイルの眼前に立ちはだかっていたバイロを襲う。大部分は簡易結界が弾き返したものの、幾つかは結界を突き抜けてバイロの身体を掠めた。
「ご無事ですか、星焔様」
「バイロ、キミこそ怪我を……!」
「ご心配には及びません。星焔様をお護りするのが私どもの役目です」
ケケケケケッ!
「!」
炎弾を放った元凶だろう魔の眷属が、けたたましく嗤いながら肉迫する。
「このっ!」
反射的に身構えたアイルの腕に、眩い金色の光が宿る。羽根の力の具現である手甲を装着した腕を、アイルは迷わず眷属に向ける。
五指の先から放たれる、五条の光矢。
だが、魔の眷属は嘲いながら光矢の間をすり抜けると、アイルたちの頭上ギリギリを掠めて建物の向こうへと飛び去った。
「・・・・・・っの!」
アイルは燃えるような瞳で、眷属の消えた方向を睨み据える。
頭がぐらぐらと煮えたぎる。周りの景色は視線を向ける一点に収束し、赤い血に染まったように燃え上がっている。
「大丈夫ですか、星焔様。どこかお怪我は?」
どこまでも冷静なバイロの声に引き戻され、アイルはふと我に返った。
「どうして・・・・・・!」
見れば、バイロだけでなく二人の随従もが、アイルの背後を守るように身構えている。
「僕を守る必要なんて無いですよ! 僕は上級天使なんです。どんなに大怪我したとしても、炎の結晶がある限り、すぐに治ってしまうんですから! それよりも、町の人達を・・・・・・」
「いいえ。我らの務めは星焔様をお守りすることです」
「でも・・・・・・!」
「星焔様をお守りすることが、我らの最優先事項です」
「・・・・・・」
有無を言わさぬ強い口調に、アイルは思わずたじろいでしまう。
バイロは本気だ。
本気で、その身をていしてアイルを守るつもりなのだ。
「星焔様、進言をお許しいただけますか」
アイルの左背後から声をかけたのは、掌の上に魔道具である水晶錐を乗せた随従の一人だ。
「予定では結界に守られた聖堂広場に転移門の出口を開くはずだったのですが、何故か位置がずれて開いてしまったようなのです。まずは当初の予定通り、聖堂広場を目指すよう進言いたします。そこで第五軍の小隊と合流いたしましょう」
バイロが指し示す先。背の高い鐘楼を有する聖堂が、しっかりと形を保ったまま聳えていた。
聖堂は普通の家屋よりもずっと堅固な外壁と、呪術防壁に適した呪印を有している。建物に囲まれた広い中庭は、逃げ惑う人々が真っ先に助けを求めて集まる場所だ。
「星焔様、小隊と合流いたしましょうか。それとも、このままここで応戦いたしますか」
「あ・・・・・・」
指示を求められ、アイルは一瞬、視線を泳がせる。
「そう言えば、あいつは?」
今更ながらに気が付いて、アイルは辺りを見回した。
隧道を抜けてからこっち、災厄の天使と番人の姿を見ていない。
「災厄様は、恐らく前線に出向かれたかと。番人様は、先に聖堂に向かわれたことでしょう」
彼の言葉を証明するように、町の一角からドンッと派手な爆炎が上がる。さらに連続して、小さな爆音が。群がっていた魔の眷属が、数体まとめて消し飛ばされる。が、続々と集結しつつある魔の眷属どもは、数を少々削られたくらいではどうということも無さそうに見える。
目を転じれば、聖堂を覆った結界を取り巻くように、数体の眷属どもが群がっている。シャボンの泡のように頼りなく揺らめいている結界は、辛うじて攻撃を受け止めているような状態で、アイルの目にさえもういつ破れてもおかしくないように見える。
きっと、災厄の心配なんて、するだけムダだ。
「解りました。聖堂へ急ぎましょう! みんな、僕から離れないで!」
アイルは決然と顔を上げた。
魔物の気配に高ぶり震える羽根を、身の内に感じながら。
結局、アイルが到着するまでのごく僅かな時間さえ、結界は持ちこたえることが出来なかった。
火弾の集中砲火を浴びた結界は、消滅する瞬間に、大気を揺るがす衝撃を周囲一帯に放った。聖堂近くの建物はことごとく倒壊し、壁外で防衛に当たっていた兵士の怒号や、中に逃げ込むことが出来ないでいた人々の悲鳴が渦巻いた。
なおも襲い掛かろうとする魔の眷属を、まとめて光矢で薙ぎ払って、アイルは負傷者の一人に駆け寄った。
「しっかりして下さい! 助けに来たんです、しっかり・・・・・・!」
「・・・・・・」
アイルが抱き起こそうとしたその男は、黒く煤けた顔を上げ、微かに口を動かすと・・・・・・ふっと全身から力を抜いた。僅かに伸ばそうとしていた手がパタリと石畳を打ち、ずしりとした重量がアイルの腕にのしかかる。
「あ・・・・・・」
男の口からは、一言も発せられはしなかった。だがアイルには、聞こえたような気がしたのだ。「ありがとうございます、天使様」という、助けを待ち続けた者の声が。
悼みに膝を折る間もなく、聖堂の方向からわあっという悲鳴が上がる。
彼らにはもう、どこにも逃げ場はない。
「・・・・・・許さない」
知らず、発せられた小さな呟き。そして、
「許さないからなっ!!!」
身体の奥底から膨れ上がる灼熱に突き動かされるまま、アイルは吠えた。
その後のことは、あまりよく覚えていない。
気が付いた時には、群れなしていた魔の眷属どもは、一斉にドロドロと溶けて崩れ落ちていた。
「・・・・・・何、が? ・・・・・・魔物は?」
身体中から、じんわりした熱が引いて行く。
羽根の力を解放した。それは、確かだ。
「お流石です!」
「素晴らしいお力です、星焔様!」
「あの数の眷属を一瞬で! 見事な大勝利ですよ!」
随従の三人が駆け寄って来るのを、アイルはぼんやりと見つめた。
「!?」
一瞬。
射抜かれるような視線を感じた気がしたが、視線の主がどこかも判らない内に、それは唐突に消え去った。
「・・・・・・今のは、災厄の?」
「どうかされましたか、星焔様。どこかお怪我でも?」
心配そうなバイロに、アイルはいいえと首を振る。
「僕のことより、怪我した人たちを助けないと! 手伝ってくれますか?」
どんよりとした空から、思い出したように舞い落ちてきた雪片が、黒煙のくすぶる瓦礫の熱を冷ましていった。
第三話 災禍の町
町の住人が避難していた聖堂は、辛うじて無事だった。
それは、第四軍の天使らが最後まで結界を維持して防戦したからこそだった。
満身創痍となった彼らは、聖堂の奥の一室に運ばれて手当を受けた。
ほどなくして、水晶錐の法術で町を探索し終えた随従のザハトから魔物の全滅を確認したとの報を受けたアイルは、一刻も早く人々を安心させるべくそのことを告げた。
魔物の脅威が去ったと知った人々は、最大限の歓呼でもって星焔の天使を讃えた。
だが、町の様子を確かめるべく外に出た者から破壊の惨状が伝わり始めると、彼らの高揚は悲嘆へと変わった。
破壊された町には彼らの家や仕事場や憩いの場があったのだし、何より避難が間に合わなかった、あるいは僅かでも防衛に尽くそうとして安否不明となった身内や知人がいたのだから。
動ける者は外へと散って行き、入れ替わるように怪我人が運ばれて来始める。
そのあまりの多さに聖堂に隣接する施療院はすぐ満杯となり、収容し切れなくなった者たちは聖堂の床にも順次寝かされていった。
アイルは貴賓室に案内しようとする司祭の申し出を断ると、人々の手当てを手伝った。と言っても、見よう見まねで包帯を巻いたり、手を握って励ますくらいのことしか出来なかったのだが。
その点、実際に役に立ったのは応急処置の訓練を受けている随従の三人で、後から後から運ばれてくる怪我人にテキパキと処置を施して行った。
それでも、上級天使であるアイル自身が手救護に当たったことで、人々は感謝と崇敬の目を向けた。
災厄の天使が姿を見せたのは、第四軍所属の事後処理部隊が到着し、アイルらの救援活動もひと段落してからのことだった。
フード付きのマントに足元まですっぽりと覆われたその人物が誰なのか、アイルには最初判らなかった。
肩に薄く積もった雪もそのままに、当たり前のようにその場に足を踏み入れ、当たり前のように奥へと歩を進める態度からして、身分の高い役人か教会の関係者なのかと考える。
それにしたって、呻き声を上げる多数の怪我人を前にして、一瞥すらくれようとしない態度に好感が持てるはずもなく。
アイルは、あからさまにムッとした表情で、その人物を睨み付ける。
だが随従の三人は、その人物に対して即座に略式の礼を取った。
さらに、どこからともなく現れた黒服の番人が当然のように背後に付き従ったことで、ようやくアイルにも合点がいった。
「奥にお部屋を用意してございます。何かお持ちいたしましょうか。それとも少しお休みになられますか」
「構うな。それより出立の準備を急げ。もうここに用は無い」
温かさの欠片も無い声を聞いた途端、アイルは思わず立ち上がっていた。
今までどこに行ってたんですか! 君がどこで何をしていたのかは知りませんよ。でも! ここにいるみんなに対して、少しは労りの言葉があってもいいんじゃないですか!?
だが、そんなアイルの様子を察したバイロが素早く近付いて来て、押しとどめるように首を横に振る。
叫ぼうとした言葉は、寸前で声にはならなかった。
もちろんアイルにだって分かっている。どんな理由があれ、大勢の重傷者がいる場所で騒ぎ立てていいはずがないことくらいは。
(あの冷血漢のトーヘンボクめ、後でキッチリ問い質してやる!)
アイルは決意も新たに、聖堂の奥へと消えるマントの背中を見送った。
そして、その機会は意外に早く訪れることになる。
転移門は基本的に、常設された門から門へと往来するシステムである。
例外として、聖都の中央に設置された転移の間だけは、真理の番人の中から任じられた技官が座標を指定することで、任意の地点へ強制的に門の出口を開くことが出来るのだが、それは短時間の一方通行のみである。
つまり、行きはどこにでも(大概の場所には)急行出来るが、帰りは転移門が設置されている場所まで自力で移動しなければならない。
『門の設置場所は、必ずしも大きな都というわけではないようです。一説には古代帝国時代の都市や神殿の置かれた場所に符合するそうですが、私ごときには確かなことは解りません』
『ってことは、場合によっては帰りの門まで長旅になっちゃったりも?』
『ええ。二、三日かかる事は珍しくないそうですよ』
『ふうん。便利なようで、意外に融通が利かなかったりするんだ・・・・・・』
『融通と言えば、特殊な通信珠で座標を特定出来る場合、強制的に入り口を開くことが出来るらしいのですが』
『え、そうなんですか?』
『もし失敗したら、出口に辿り着くことなく門の中を永久に彷徨い続けるという噂ですが、試してごらんになりますか?』
『い、いいです! 遠慮します!』
『それがよろしいかと存じます』
『でも、それじゃあ、転移門の中って通路みたいになってて、そこから外れると迷子になる、みたいなものですか?』
不安そうに尋ねたアイルに、
『実際に行方不明になったという事例の報告は聞いたことがありありません。これはあくまで根拠の無い噂話です』
『噂は噂ってことですか。もしかして、他にも何かありますか?』
『ええ、怖いものから間抜けなものまで、それは様々な噂話が伝わってございます』
『面白そうですね。たとえばどんな?』
そんな会話を交わしたのはつい今朝方、バイロに色々教えて貰う合間の雑談だったのだが。
それから緊急要請を受けて、ここへ着いたのが昼過ぎのこと。
そして魔物と戦って、町の人々を救って・・・・・・。
アイルはぼんやりと窓の外、赤く滲んだ空を見上げた。
冬の日暮れは早い。ということは、この地を踏んでからせいぜい三、四時間くらいしか経過していないことになる。
(嘘みたいだ。塔でバイロと喋っていたのが、もう何日も前みたいな気がする・・・・・・)
薔薇の小都と呼ばれた町から一番近い転移門は、馬車で二時間程度とのことだった。
帰路の準備が出来たからと聖堂の車寄せに出てみれば、調達された馬車がお貴族様でも乗ってるんじゃないかと思うような豪奢なものだった時には、思わず目と口を丸くしてしまったが。
ともかくアイルは今、馬車の窓枠に片肘をついて、窓外に流れる景色をぼんやりと眺めている。
見送りの歓声が、まだ耳に残っている。
聖堂に集った者はもちろん、町中で作業していた者は手を止めて。子供たちは走り寄って。
馬車は、瓦礫の片付けもままならない悪路を避けて、右へ左へと路地を選びながら進んだ。
跳ね上げられるような居心地の悪い揺れは、町の外縁を抜ける頃には治まって、二頭立ての馬車は本格的にスピードを上げ始めた。
後方では、夕日に照らされた聖堂の鐘楼がどんどん小さくなって行く。雪雲の間から差し込む薄紅の光は、破壊の痕跡を柔らかく包み込んで癒そうとしているようにも見えた。
うっすらと雪に覆われた林の間の街道は、整備が行き届いているらしく、馬車の車輪がガラガラと心地よいリズムを刻む。
(それにしても)
手持無沙汰なアイルは窓外を眺める格好のまま、ちらりと視線を走らせる。
いくら車内がゆったりしているとは言え、災厄の天使と差し向かいで座らされている図というのは、何とも落ち着かないものがある。
当の本人は馬車に乗り込んで以来ずっと、軽く腕を組んだ姿勢で瞳を閉ざしている。眠っているカンジではないが、一言も喋らないどころか、話しかけるスキさえ無い。徹頭徹尾アイルを無視するつもりのようだ。
しかも隣には例の特大サイズの曲刀が鞘に収まった状態でドーンと鎮座ましましていて、その威圧感はハンパ無い。
羽根の具現した武器なのだから、四六時中見せびらかしていないで身の内に仕舞えば良さそうなものなのだが。実際、その方が余程便利に違いない。
マントの袷の間からは緋色の長衣が覗いていたが、それは任務に出立する前と変わず綺麗なままで、煤や泥や血糊などで薄汚れているアイルとは大違いだ。
(しまったなぁ。上着脱いで手伝えば良かったんだよな。これじゃ、洗濯する人や繕いものをする人に、余計な手間をかけさせちゃうよ)
それは今にして思うことで、渦中にあっては服のことなど露ほども頭に上らなかったのだから仕方がはない。
そして、車内にはもう一人。
アイル側の座席の端に黒いフードを目深く被った番人が、澱んだ空気のようにひっそりと座っている。
彼もまた、必要のない会話は一切しない人のようだ。
つまりは今日の出来事を反芻する以外、何もすることがない。
(バイロたちも一緒だったらいいのにな・・・・・・)
だが彼ら三人は身分不相応であるからと、分厚いコートを着込んで御者台へと上がってしまっていた。
(あーあ、僕も御者台の方に行きたかったなぁ・・・・・・)
少しくらい寒くても、その方がずっと気が楽だ。
まあ、言ったところで「上級天使としての自覚をお持ち下さい」などと言われて終わったのだろうが。
(上級天使、か・・・・・・)
窓外の静かな景色と揺りかごのような馬車の揺れが、アイルの心を、熱に浮かされたような高揚からゆっくりと解き放っていく。
(重い仕事だよな・・・・・・)
魔物を前にした時も、聖堂に入ってからも、目の前のことだけに無我夢中だった。
その行動を後悔するわけではない。
それでも、慣れない手当てなどよりも、崩れ落ちた建物を押しのけての救助作業を手伝った方が良かったのではないだろうか。町の様子をもっとしっかり見ていれば、そっちを優先していたかも知れない。第四軍の支援部隊や領地の援軍が到着するまでは、生き残った衛士と町の住人だけでは大変な作業だったに違いない。
それなのに、彼らは大して役にも立たなかったアイルを、邪険にするどころか、一挙手一投足にさえ涙を流さんばかりに感激してくれた。
随従の三人にしても、任務など初めてという超超初心者のアイルが思い付きで頼んだことに、何の異も差し挟まずに協力してくれた。けれどそれは、彼らがアイルという一個人の頼みではなく”星焔の天使”の命令と受け取ったからではなかったか。アイルがいいと思ったことをそのまま頼むのではなく、それをどう思うか、まずは聞いてみるべきではなかったか。
(それに・・・・・・)
アイルの腕の中でこと切れた者。
何度も何度も、恐い物はもう来ないかと問い質した男の子。
いつまでも聖堂の隅にうずくまっていた幼い兄妹。
目の奥に焼きついた、いくつもの光景・・・・・・。
「ダメだなあ・・・・・・」
ポツリと、アイルは呟きを漏らした。
「僕がもっとしっかり状況判断が出来ていたら、町の被害はもっと少なく出来たかも知れないのに・・・・・・君が非常呼集に急いだ理由が解りましたよ。僕らに要請が来るってことは、どこかで人々が命の危機に瀕してて、必死に助けを待ってるってことなんですよね」
最初に派遣されていた第四軍の小隊五名のうち、助かったのは聖堂の守りに徹していた羽根使いの青年と、彼を庇い通して重傷を負った年配女性天使の二人だけだった。
それでも。
彼らはアイルの前に畏まって、心からの謝辞を述べた。
見捨てずに来てくれたことが、何よりも嬉しい、と。
「僕はさっきまで、物凄く腹を立ててました。君が、町の人をそっちのけで、どこで何をしてるのかって」
災厄の天使の反応は無い。聞いている素振りさえない。
(あ、やっぱり)
想定内だったし、煩いとも言われなかったので構わずに続ける。
「でも、それは君に怒ることじゃなかった。僕がもっと、ちゃんとやっていればっていう、八つ当たりだったんだと思います。だって君は・・・・・・」
綺麗なままの戦闘服。だが、煙の残り香だけは隠しようがない。
転移門を抜けるなり、戦いの場へと突き進んで行った災厄の天使。
その瞬間に彼がのん気にサボっていたなど、絶対に有り得ない。
アイルが呆然とする暇があったのも、彼のおかげかも知れないのだ。
「勘違いするな」
思いがけない応えに、アイルは驚いて振り返る。
氷のように冴え冴えとした蒼い瞳が、真っ直ぐにアイルを見ていた。
「天使は魔物を討滅するものだ。それ以上でも以下でもない」
アイルに向けられていながら、アイルを映そうともせずに。
「お前が何をどうしようと勝手だが、」
唐突に、瞳は再び閉じられた。
「下らん思い込みで俺を量ろうとするな。迷惑だ」
先刻と全く同じ、全てを拒絶する格好で。
災厄の天使はそれ以上口を開こうとはしなかった。
アイルは。
「・・・・・・」
呆然と、気圧されたまま。
気圧されたものの正体すら解らぬまま。
返す言葉を見つけられずにいた。
「星焔様、星焔様」
「ふあ~あぁ?」
自分自身の間抜け声に、アイルはハッと目を開ける。
「お疲れのところ申し訳ありません。目的地に到着いたしました」
馬車のドアが開いており、遠慮がちな様子でバイロが覗き込んでいる。
いつの間にか寝込んでしまっていたようだ。自分で自覚している以上に、疲れていたのかも知れない。
当然のことながら、向かいに座していたいたはずの災厄の天使の姿は無い。
「あ、はい、すみません! 今行きます」
アイルは慌てて立ち上がると、馬車のステップを無視して一気に地面へと飛び降りる。
わああああーっ!
「え? え? え?」
たちまち巻き起こった歓声に、アイルは馬車から飛び降りた姿勢のまま固まる。
無数の灯火に照らされたそこは、先刻の聖堂の前庭よりもずっと大きく立派な広場だった。
正面にズラリと居並ぶのは、見るからに身分の高そうな教会関係者に、裕福そうな貴族や名士たち・・・・・・その背後には衛士や役人といった一団が並び、さらには広場の外で衛士に通せんぼされている一般市民の、押すな押すなの大歓声・・・・・・と、お祭りどころではない騒ぎである。
逃げ場を失くしたアイルは、「天使様方の御幸行に預かり光栄でございます」とか何とか偉い人の口上など上の空で、キョロキョロと辺りを見回すのが精一杯だ。
と、馬車のステップのすぐ脇に跪いていた随従の一人が立ち上がる。
いや、マントで隙無く全身を覆ったその出で立ちは、随従のものではない。
一身に注目を浴びるアイルを尻目に、何の注意を向けられることもなく、災厄の天使は静かにその場を離れた。黒マントの番人が当然のようにその後に従う。
「あーっ! あの野郎ーっ!」
指差して叫ぶアイルの声は、人々の歓声の中にあっさりと飲み込まれた。
第四話 喧噪の外側で
「あーヒドい目に遭った・・・・・・」
アイルが聖都に帰り着いたのはほとんど夜中。街の代表者たるお偉い方々居並ぶ「歓迎の式典」という名の宴会に、延々付き合わされた後である。
宴会と言っても入れ替わり立ち代わり挨拶に来るお偉いさんへの対応を迫られたアイルは、目の前のパンすらろくに口する余裕もなく、あまり好きでもない酒ばかり勧められる始末。
災厄の天使も番人も不在。現地との折衝係だという第3軍の天使は、助け舟になるどころか、お偉い方々にお愛想するのに余念がない有様。
これはもう自助努力あるのみと意を決したアイルが死に物狂いの言い訳を連ねてようやく、半ば強引に転移門をくぐるのに成功したのだ。
本当に危ないところだった。
「申し訳ございません、あれは私の不手際でした」
そんなアイルに、もう何度目かになる謝罪を口にしつつ、バイロは改めて頭を下げる。
「君のせいじゃありませんよ」
もちろん、上級天使が立ち寄ることが事前に知れ渡ってしまっていたのも、お祭り騒ぎで出迎えられることも、バイロには予測不可能。責めるなんてお門違いだ。
「いいえ。アイル様の筆頭随従として、この程度の事態は予測すべきでした。せめて予備の正装を手配するくらいは当然行うべきでした」
「ええと・・・・・・」
そういう問題でもないのだが。
「とにかく! 何もかもひっくるめて全部、あの野郎が悪いんです!」
怒りをぶつける相手はもちろん、アイルを囮にしてまんまと逃げおおせた災厄の天使である。
しかも腹が立つことに、災厄の天使がいないと判った途端、その場の空気は明らかにトーンダウンした。
いや、仮にもお偉い方々とやらは流石に顔に出したりはしなかったし、新人の上級天使と聞いてそれなりに興味を抱いたようだった。
それでも、隙間風が右から左へ通り過ぎるような間が生じたことは確かである。
「っとに信じられませんよ。あんな野郎に人気があるだなんて、世の中間違ってます!」
かくいうアイルも、塔に来るまでは世間一般のイメージを信じていた一人である。
「いえ、世の中が間違ってるんじゃなくて、あの野郎に騙されてるだけなんだ! 悪いのはあの野郎、間違いなくあの野郎です!」
床を蹴立てて、アイルはずかずかと歩いて行く。
「おそれながら、どちらに向かっておいでですか? アイル様のお部屋は・・・・・・」
「もちろん、あの野郎の部屋に決まってます! とっくに帰ってくつろいで寝てるでしょうから、叩き起こして文句言ってやります! ・・・・・・そう言えば、あの野郎の部屋ってどこでしたっけ?」
考えてみれば、いかに激怒パワー充填中とは言え、自分の部屋の位置すらうろ覚えなアイルが、行ったこともない他人の部屋に自力で辿り着ける可能性はとんでもなく低かった。
「それなのですが、」
困ったように、バイロは声を落とした。
「まだお戻りでないとのことです」
「は!?」
びたっと急停止したアイルは、身体ごとバイロを振り返る。
「まさか! 馬車降りてから随分経つじゃないですか」
「はい。ですが番人様は、そのように仰っておいででした」
「むうー」
振り上げた拳の行き場を失って、アイルは唸り声を上げる。
「ところで、今回の任務についてですが」
アイルが落ち着いたと判断したバイロは、表情を和らげ話題を変える。
「報告書は型通りで構いませんか? 何か付け加える事項がありましたら・・・」
「ほ、報告書?」
「はい。任務毎に書面にて提出いたします」
そう言えば、とアイルは思い出す。
馬車に乗った直後、災厄の天使は紙片に何事か殴り書きするや、番人に押し付けたのだった。
という事は、
「それだ!」
「・・・・・・は?」
思わぬ大声に、バイロは面食らい、返答に窮する。
「書面にして突き付けてやれば、無視は出来ませんよね!」
そういうことならと、アイルはくるりと踵を返す。
「紙とペン、それから景気付に薬酒を持ってきてもらえますか?」
「承知いたしましたが、その、どちらへ?」
「転移の間です! あの野郎が帰って来たら、確実に叩きつけてやるんですよ!」
こうと決めたアイルは、ちょっとやそっとでは諦めないのである。
アイルがいかに宴会の肴状態から抜け出そうかと知恵を絞っていた頃、街中でもちょっとしたお祭り騒ぎになっていた。
「災厄の天使様ばんざーいっ!」
「我らにご加護をーっ!」
「災厄の天使様ばんざーい!」
そこここで乾杯の音頭が繰り返され、ジョッキのぶつかる音が響く。
何しろ新年の祭りはとうに終わったが春の祭りまではまだしばらくあるという、この時節。
旅人の往来も減り、これといった楽しみも特にない。
そんなところに突然降って湧いたのが”災厄の天使来訪”の報だ。
もちろん、転移門を擁するこの町では、天使(天軍の兵士)の往来自体はさほど珍しいことではない。
が、上級天使の来訪となれば話は別だ。
何しろ塔肝入りの宣伝歌劇によって、華麗なヒーローやヒロインとして広く巷に流布されるような存在だ。
娯楽の少ない冬のさ中だ。”災厄の天使来訪”の報が、町中を駆け抜けるのも早かっただろう。
だからと言って一般庶民に謁見の機会が設けられるはずもないし、彼らも無論、そんな期待は最初から抱いていない。
飲んで歌って夜通し騒ぐ口実には十分だ。
沿道で塔の紋章旗を翻した馬車を見物し、ひとしきり聖堂の周りをうろついて気が済むや、連れだって飲み屋街へと凱旋である。
普段は数人の客がこじんまりと座るだけの呑み屋は、今夜に限っては通りにテーブル代わりの樽を並べすほどの満員御礼。
呑み屋ではない軒先でも、酒や肉を持ち寄っての宴会だ。。
違法な商売には口うるさい役人やギルドの連中も、隙を見計らって自分たちもが楽しむ側に回っているのだから世話は無い。
あちこちで振る舞い酒が飛び交う頃には、互いが何者だろうが関係なく、肩を組んで意気投合している有様だ。
だからこそ、フード付きのマントで全身を覆った、明らかに他所者でいわくありげな少年が一人でうろついていようと、あれこれ咎めだてされることもないし、小金の用意が無くとも飲み食いに困らない。
とは言え。
「「「災厄の天使様ばんざーい!」」」
あちこちで繰り返される乾杯の音頭がこれなのは、かなり辟易する。
話題の渦中の当人は、面白くもなさそうに目の前のジョッキをあおった。
この地方の庶民には一般的な麦酒。
酔って騒ぐには十分という代物だが、不味くはない。
そう、こんなイヤガラセじみた喧噪の中であっても、呪術結界だらけの塔よりはるかにマシだというのも事実なのである。
だが。
(そろそろ引き上げ時だろうな)
この街に、長居する理由は見つけられなかった。
あの馬鹿のせいで、塔に戻る必要がある。
それに、祭り気分でも陽気に騒ぐ者ばかりではない。
「おやぁ・・・見ないヤツだなあ・・・?」
声を上げたのは、覚束ない足取りで通りを流れて来た集団の中の一人だった。
「テメェ・・・どっかのお貴族様だろー?」
「お偉ぁいお貴族様がぁあ、お供も無しにぃこぉんなとこで何やってんだぁあ?」
一人が立ち止まったのをきっかけに、数人が少年の周りに群がり始める。
性質の悪そうなゴロツキども、と言うよりは仕事上がりの工人見習いあたりだろうか。柄が良くないのはどっちもどっちだが。
このような馬鹿はどこにでもいる。酒で気分を大きくしては、誰彼構わず絡んで迷惑をかけて憚らない。
面倒なことに、連中の目には、細っこく生っ白い少年のような存在は絶好のカモと映るらしい。
それまで陽気に騒いでいた連中は、迷惑顔で席を立つ。
通りの向こうにいた町人は、明後日の方向に顔を向けたままチラチラと視線だけを送ってくる。
関わり合いにはなりたくないが、見世物は見逃したくない、というところか。
気持ちは分からなくもない。
酔っぱらいの喧嘩なぞ無視するに限る。
当事者でさえなければだが。
「おぉぉい、何とか言っだらどうなんだぁ、んー?」
台詞と同時に伸ばされる、野太い腕。
いかにも腕力で物事を解決するタイプの。
泥酔しているいないにかかわらず、普通レベルの判断力すら期待するだけ無駄だろう。
大きなハンマーを振り回すのが似合いそうなごつごつした拳が少年の胸倉を捉えたかに見えた、その瞬間。
男の身体が風車の羽根のようにくるりと回転し、大きな背中が石畳を強打する音が地響きとなって走り抜ける。
一体何が起こったのか。
予想だ二にしない成り行きに、遠巻きで事態を見守っていた人々の目と口が丸くなる。
そんな衆目を他所に、少年は一つため息をつくと、半分ほど中身の残ったジョッキを残して立ち上がる。
「感謝しろ」
物憂げな呟きは、少年のごく近くにいた者にしか聞こえなかった。
「雪華や紅蓮だったら、こんなものじゃ済まない」
いや、頭に血を登らせた者の耳に、その声が届いたかはかなり怪しい。
「ヤロウっ!」
「何しやがるっ!」
ありきたりな怒声とともに、今度は三人の男が少年の進路を阻む格好で殴りかかる。
マントに覆われた細身の姿は、体格も上背もずっと大きな男らの陰にあっさりと埋没する。
と、見えたと同時に。襲い掛かったはずの三人は、揃って何かに躓いた格好でつんのめり、腹側を強かに地面に打ち付けた。
僅かにマントの裾を揺らした少年は、何事も無かったかのようにゆっくりと歩を進める。
ぐうっとくぐもった呻き声を発してそのまま静かになった仲間を前に、すっかり酔いを吹き飛ばされた面々は、賢明にもリベンジを選択しなかった。
真っ青になった一人が足をもつれさせてべたんと無様に尻餅をつき、それを合図に残りの連中が危なっかしい足取りで逃げ散って行く。
「覚えてろよ!」だかの、ありきたり過ぎる捨て台詞が聞こえたてきたのは、彼らが十分に距離を取ってからのことである。
その様子に一片の興味すら抱くこともなく。
「あのお目出度い奴なら、どうしたろうな・・・」
フードの端から零れ落ちた一条の黒髪を煩さそうにかき上げて、呆然とした衆人が見守る中、少年は静かに歩み去った。
ばんざーい!
と、通りの向こうで杯を打ち鳴らす音が合図となって、凍りついていた空気が動き出す。
「・・・・・・おい、今の?」
ため息のように露店の主人が呟き、
「見た? 見た?」
「黒髪で、お綺麗で」
「お強くて」
酒場の女たちがうっとりとした視線を、少年の消えた通りの先へと投げかける。
「なあ、」
「あれは、その、もしかして?」
顔を見合わせた一同は、頭に浮かんだ名をつぶやく。
「「「災厄の天使様?」」」
「・・・・・・」
「ハハハッ! そんな、まさかなっ!」
「いやでも、この町に来てるのは確かなんだろう?」
「だからって、こんな所に出て来るはずないって!」
「偉い連中が総出で謁見を賜ってるって話だしな」
「ソックリさんとか、仮装とか?」
「ああ、きっとそう・・・・・・」
「やーね、知らないの?」
「災厄の天使様はいつもあたしたちのことを見守って下さってるのに決まってるじゃない!」
「ねーっ!」
「そんなバカな」
「バカとは何よ!」
「謝んなさい!」
きゃーきゃーきゃー・・・・・・
「何だ、何かあったのか!?」
「実はねっ今ねっ!」
「ちょっとっ、何なにっ?」
その後。災厄の天使が残虐な強盗団から大勢の人々を救ったという盛大に尾ひれの付けられた噂話で、街はひとしきり盛り上がることになる。
が、そんな事は当の本人は知る由もなかったし、知り得たところで何の感慨も抱くことはなかっただろう。
聖堂には寄らずに上級天使権限で直接転移門を開けさせて塔に帰還した少年は、あてがわれている自室の扉を一睨みするや、おもむろにガツンと蹴り開けた。
開け放たれた続きの間の先、正面のソファは無人ではなかった。
「そこで何をしている」
酒杯を片手にゆったりと寛ぐ人物は、剣呑な視線を意に介さず、口元に余裕の微笑みを浮かべる。
目深に被ったフードの奥の目が笑っていないだろうことは、確かめるまでもない。
「これはご挨拶ですね。貴方のお帰りをお待ち申し上げていただけですよ。”災厄”の天使様」
番人の例に漏れずフード付きの黒いローブを身に着けたその人物は、相手にも勧めるように軽く酒杯をあげて見せる。
日の光に無縁そうな白い手は、薬焼けらしき染みに覆われている。
そのせいだろうか。年配なのか、そうでもないのか、にわかには断じがたい人物だ。
「番人の長ともあろう者が。物好きなことだ」
真理の番人は、白亜の塔の技術部門探求部門管理部門を一手に預かる。その長ともなれば推して知るべしなのだが。
転移の間で待ち構えていたバカといい、少しは人の迷惑を考えるべきだだ。
跳ね返って来たドアを後ろ手で閉じ、続きの間を三歩で通り抜け、ソファの前を素通りする。
奥の壁際に設えられた刀掛けには、鞘に納められた曲刀が鎮座している。
「そう仰るものではありませんよ。私は報告書の詳細について、お伺いしたかっただけのこと」
なるほど番人の長の手元の卓上、酒器の隣に一枚の紙片が置かれている。
そこには必要低限の文字の殴り書き。
日にち、場所、簡潔な魔物の説明、討滅完了のサイン。半分以上は白紙のまま。
「伺うも何も、そこにある通りだ」
請け負った任務を滞りなく完遂する。
それ以上の何が必要だというのか。
、片手間に留め金を外されたマントが、バサリと音を立てて床に広がる。
「そうですか? 肝心なことが抜けてはいませんか?」
「やはり、わざとか」
両手を重ね合わせて何かを操作した少年の姿がブレる。
その一瞬で彼のまとう緋色の上衣が、革製の長靴(チョウカ)が、模様を打ち出された幅広のベルトが、劫火を潜り抜けて来た後のそれへと成り果てる。
「おや、護符の強度が足りませんでしたか。装備部に言い置かねばなりませんね」
「白々しいことを」
使い物にならなくなったそれらを無造作に床に打ち捨て、黒のチュニックとズボンだけの軽装になった少年は、乱暴にベッドの端へと腰を下ろす。
少年の髪やズボンに付着していた煤埃が真っ白だった寝具を汚すが、もちろん知ったことではない。
打ち捨てられた残骸の間から、ガラス製の小瓶が転がり出ている。
この小瓶だけは、中身の液体もそのままに美しいままだ。
「そんな所にいらっしゃらずに、こちらで一献いかがですか。それとも薬酒の方がよろしいか。今日の分は、まだ召し上がっておられないのでは?」
「要らぬ世話だ。それより、とっとと用を済ませて消えろ」
番人の長に視線を向けることなく、少年は引き寄せたクッションに投げやりにもたれかかる。
「ではまず、火弾の魔物についてですが、」
最初からとはやはり、イヤガラセ決定だ。
火弾の魔物は、さほど強力な類ではない。
分裂し眷属を大量発生させる能力は厄介だが、要は分裂させる前か、させても大した数ではない内に結界で封じで完殺すればこと足りる。
それこそ一般天使向けの案件だ。
逆にいえば、派遣されていたという第四軍の小隊が初動で余程の下手を打ち、手の施しようがないくらいに分裂を許してしまったという事だ。
増えた眷属どもは、魔物本体を討滅したところですぐには消えない。
一日にも満たない僅かな存在ではあるが、最後の余力でもって四方八方に飛び散り近隣の町や村を襲撃するくらいは十分に可能だ。
第四軍の天使らは自力討滅は不可能と見た時点で、上級天使に泣きつきつつ、聖堂に集まった住民ごと結界内に立て籠る方針に切り替えた。
さほどの強度もない結界の内側に大勢の人間がひしめいている状態は、魔物にしてみれば魅惑的なエサが目の前にぶら下がっているようなものだ。人々の血肉と恐怖は魔物の最も欲するところである。
エサで魔物を足止めして、上級天使の到着を待ち、力技による結界術の強化反転で一気に殲滅する。
最後の最後で、どうにか選択を間違えなかった訳だ。
だが、ここで想定外が起こる。
聖堂の中庭に開けたはずの転移門の出口が、敷地外の街路に開いてしまったのだ。
直線距離ではささいなズレ。
だが、結界内に出られなかったことによって、結界術の補強を指揮すべき番人と力の貯蔵庫である上級天使が術壇に向かうために要する時間と手間は、一分一秒を争う状況において無視できるものではなかった。
「そこで、貴方は魔物本体を攻撃に向かったのですね」
報告書の文面に起こせば長いが、面倒な状況であることは門から出た一瞬で理解できた。
とっさの判断で魔物本体を中心に大雑把な範囲攻撃をしてみたものの 眷属を残したまま消し飛ばしてしまうわけにもいかない。結界に取り付いている眷属を狙えば、その衝撃が結界を破壊する一押しになりかねない。
少年の所持する曲刀は、身長程もあるその見た目に反して重さと言う重さもなければ、安定した形状も持ち合わせていない。
流動する鋼のようでもあり、微細な鋼魚の群れのようでもある。
そして一度鞘から解き放たれれば、喜悦のままに魔物目がけて遮二無二襲い掛かる性質を持つ。
その手綱を引き絞って狙いを定めつつ眷属のみを削いでいくのは、なかなかに骨の折れる作業だ。
潰れた眷属が一々爆散するのも、うっとうしいことこの上ない。
「いっそ羽根の力を解放して、街ごと全て薙ぎ払ってやれれば楽だった」
「また乱暴なことを」
羽根は人間そのものは攻撃しない。やれと命令すれば別だが、魔物だけを討ち払うことは十分可能。
だが、魔物の火弾を浴びて破壊が進んだ街の建物の大半は、間違いなく崩壊する。
聖堂以外にも逃げ残りがそこそこ存在する現状で行うにはリスクが高すぎた。
「一番防衛に向かないのをわざわざ呼び戻してまで派遣する時点で乱暴だ。こんな仕事は雪華か翠濫(スイラン)あたりにやらせるべきだろう」
「そこで、星焔の天使の参入があったということですが、」
抗議の声をさらりと無視し、番人の長は整った文字で埋められた紙片をめくる。
結界を補強する時間稼ぎに出てみたものの、番人は未だ結界内に至っておらず、新入りと愉快な仲間たちは眷属相手にモタモタと遊んでいる。
状況的に補強は間に合いそうにない。
となれば、結界が破られることを前提に行動すべき局面だ。
聖堂を覆う規模の結界が破壊されれば、放出される衝撃もそこそこ強いものになるだろう。
その余波を利用して魔物の本体と眷属の大部分を殲滅する。
多少の撃ち漏らしは、第四軍の事後処理部隊にでも押し付けてしまえばいい。
羽根の力でなくば滅ぼせない”契約の魔物”本体とは違い、眷属どもは羽根使いではない一般の天使でも狩れる獲物だ。
そして、限界を迎えた結界は破裂し、その衝撃は次元を超える波となって大気をビリビリと震わせた。
眷属を削りながら位置取りをコントロールした甲斐あって、一撃で最大限の効果を狙える絶好の機会。
だが、まさにその時だった。
街の一角で、金色の光条が炸裂したのは。
膨れ上がった白熱の光球は、火弾の魔物もろとも眷属どもを一匹残らず呑み尽くす。
魔物の体内に在る魔力の源なる”闇の結晶核”が、光圧に抗い切れずにボロボロと砕け散る。
街を覆い尽くしていた瘴気の霧が、光に圧されて消滅する。
ところがだ。
目的を達し終えても、膨れ上がった光球は一向に収まらない。その圧力に耐えかねて、魔物の火弾にどうにか崩れ残っていた建物の輪郭が、音を立てて崩落する。
刃の渦を周囲に展開させることでとっさに防御したものの、灼熱の咢(アギト)はジリジリと容赦なく災厄の天使の身体に食らいつく。
(何だ、これは!?)
新入りの羽根の力によるものであることには疑いようがなかった。
しかし羽根の力は基本的に、魔物以外を傷つけない。
もちろん羽根使いに命じられればその限りではないし、例外もあるが、それでも・・・・・・。
(羽根の暴走か? この程度のことで?)
新入りの方に向かった眷属は、ほんの数体。
力を暴走させるほどの負荷ではなかったはずなのだが。
事実は事実だ。
災厄の天使は手中に戻した曲刀の柄を握り直すと、光球の中心へ向けて振り下ろす。
膨らみ続けようとする光球に食らいつき、切り裂き、呑みこもうとせめぎ合う力と力。
羽根の刃がこじ開けた先に、力を放出し続けている者の姿が浮かび上がる。
アイル。
星焔の天使。
その心臓の位置に、上級天使の力の源である炎の結晶が荒れ狂うほどに輝いて視える。
いや、それだけではない。
灼熱する炎の中心に立ち上る、闇色の陽炎。
(!?)
だが、黒い炎は瞬きを最後に姿を消し、灼熱は穏やかな灯火へと収束していく。
無差別に放出された力の光球が完全に消え去った後で。
虚脱した瞳でぼうっと空を仰ぐ星焔の天使に、足下がよたつき気味の随従たちが駆け寄った。
瞬時に魔を滅し尽くすほどの強大な力を目の当たりにした興奮に酔いしれながら・・・・・・。
「星焔の天使は暴走に近い状態に陥ったものの、防御を度外視してまでの貴方の調律が功を奏し、無事に収束に成功する・・・・・・おや、顔色がよろしくありませんね。薬酒でも持って来させましょうか」
「白々しいことを」
どこかはぐらかすような番人の言を、少年はピシャリと撥ねつける。
微に入り細に渡った、詳しすぎる報告書。
それは同行した番人による物だ。
最初から任務度外視で観察していなければ到底記述不可能な。
目的は、新入りの性能テスト。
テストし記録する必要があった。
つまり、
「あんなものを、一体どこで手に入れた」
あんなもの。
星焔の天使などと呼ばれる存在。
身の内に炎の結晶を宿すことが上級天使の条件であり、それは適性のある羽根使いが炎の洗礼にて授かるものであるとされているが、星焔の天使が有する結晶が特異なものであることは疑いようがない。
番人どもがろくでもない実験を始めたにしては、天使としての常識が無さ過ぎるのも不自然だ。
”炎の洗礼”が人間としての全てから切り離す儀式だという額面通りであるなら、天使として叩き込まれた行動パターンを全て喪失し、天使になる前の世俗的な感覚を残す・・・・・・などという状態はふざけているどころの話ではない。
何もかもが、胡散臭いことこの上ない。
「星焔様は将来を嘱望される上級天使に他なりません。それとも何か気になる点でもおありですか?」
まったく、白々しいことだ。
「素性はともかく、未調教のガキを前戦に放り出すなど正気の沙汰ではない」
あれは危険だ。
危険な上に、純粋で、無自覚で。
このままではいつか必ず、周囲の者を傷つける。
本人の意志とは関係無く。
災厄の名など、あれの前では可愛いと思えるほどに。
「仕方ありませんよ。ただでさえ上級天使は不足しているというのに、近々また空席が出ることが判っているのですから。星焔様には早急に活躍していただかねばならないのは、貴方にはご理解いただけましょう」
黒いフードの奥で、番人の長の目が意味ありげに光る。
「だからこそ、星焔様には良い”指導”役が必要ではありませんか?」
「まだ子守を続けろと? 冗談じゃない」
「そうでしょうか? 星焔様には十分な素質があると見ておりますが」
「馬鹿げている。あれに”任務”が務まるものか。どうしてもと言うなら他を当たれ」
「それは困りましたね、”カリム”様」
ゆっくりと、区切るように。
フードの陰であってさえハッキリと、番人の長の口角が上がるのが見て取れる。
そして、その名を呼ばれた少年の硬質な蒼い瞳には、一瞬剣呑な光が閃いて消える。
「・・・・・・それは命令か?」
「ええ。必要ならば」
「だったら最初からそう言え」
発言する余地が無いのなら、これはまったく無駄なやり取りだ。
完全に興味を失った少年は、それを機に口を閉ざした。
番人の長はおもむろに立ち上がると、暇も告げずにドアの方へと歩み出す。足音は無い。まるで影がうつろうように。
「・・・・・・そう言えば、貴方が八位だった頃ですか」
扉を前に、ふと、といった素振りで番人の長は振り返る。
「当時の六位を、見事討伐せしめたのは」
窺うような視線が、少年の面に注がれる。
「それが?」
僅かにも心を動かされた様子の無い無機質な応え。
「いいえ、何でもありません」
微かな音だけを残し、番人の姿は扉の向こうに消えた。
「当然だ。今更、何を思うことがある」
聞く者の無い応えとともに少年はベッドを降りると、男が出て行ったのとは反対側にある扉へと向かった。
程無く。
部屋の主と入れ替わりに入室した侍女らが仕事を終えた後には。
完璧に整えられた無人の室内を、壁に掛けられた曲刀だけが静かに見下ろしていた。
第五話 雪華と紅蓮
「あの陰険高ビー根性最悪野郎っ! 今度こそ絶対吠え面かかしてやるからな見てろよこんちくしょー!!!」
そんなアイルの雄叫びは、青い空を透かした空中庭園の天井に、吸い込まれるように消えて行った。
静かな朝の庭園は穏やかに静かなままで、アイルははぁと空しい息を吐く。
「どうしたの?」
「わあっ!」
思いがけず、すぐ近くから声をかけられて、アイルは文字通り飛び上がった。
細長い葉の茂みがさわりと揺れて、現れたのは優雅な妖精の如き少女。
「せ、雪華さんじゃないですか! ええと、すみません、お見苦しい所をお見せしてしまって・・・・・・」
思わず見とれてしまったアイルは、我に返るや慌ててピョコンと頭を下げる。
「謝ってばっかり」
「はい?」
「昨日も謝ってた」
「そう言えば・・・・・・嫌だなあ。僕、格好悪いとこばっかり見られてますね」
照れ笑いするアイルにつられるように、少女の瞳が静かに笑う。
天使の微笑みとはこういうのを言うのだろう。
と、次の瞬間、それを向けられているのが他でもない自分一人だと気が付いて、アイルの全身を電気に似た緊張が駆け抜ける。
「どうかした?」
「い、いえすみま・・・・・・じゃなかった、」
後ろめたいことをしてるわけでもないのに反射的に謝りそうになったアイルは、急いで話題を探す。
「その、雪華さんはどうしてここに?」
我ながら、何とつまらない質問だろう。
こんな気持ちのいい朝に散歩しようって気にならない奴がいたら、お目にかかりたいくらいだ。
「セレネ」
「はい?」
一瞬呆けたアイルだが、すぐにそれが彼女の名前なのだと気付く。
雪華と呼んだアイルに対し、名前を教えてくれたのだと。
「セレネさん! 素敵なお名前ですね!」
喜々とするアイルに「うん」と一つ頷いて、セレネは先刻の質問に戻る。
「あのね、こっちが私の庭なの」
「セレネさんの、庭?」
少女が示す細長い葉の連なりの向こうに、清楚な白い花に囲まれた一角が見えた。
日の光を柔らかく受け止める緑の木陰には、曲線を多用したデザインの優美なテーブルセットが置かれている。
「わあ、ステキですね!」
「私のお気に入りの場所」
称賛するアイルに、セレネは先刻よりももっとハッキリと微笑んで見せた。
「アイルに、私の庭への立ち入りを許可します」
「あ、あれ?」
アイルは思わず手の甲で目をこする。
セレネが厳かに宣言した途端、葉の連なりが左右に揺れて、細い小道が現れた。いや、見る角度か何かのせいで、目に入っただけなのか。
「ああ、ビックリした。道が急に出て来たように見えましたよ」
「それが?」
「え?」
肯定の意味で聞き返されて、アイルは大きく目を見開く。
「知らないの?」
セレネは心底不思議そうに、アイルの顔を覗き込む。吸い込まれそうに透明な水色の瞳で。
「ええと、多分、知らないです」
ごく素直にアイルは降参する。
実際、セレネが何について問うているのかすら分からない。
アイルに解るのは、とにかく自分は、ここでの常識的なことを何も知らないということだけだ。
「あのね。塔の中は、魔導技術で管理されてる。この庭園も。私の庭は、私が”許可”した者でなければ入れない。他のみんなの庭もそう」
セレネは慎重に言葉を選ぶように説明する。
「そう、なんだ・・・・・・じゃあ、ひょっとして、僕が散々道に迷ったのも魔導のせいなのかな?」
その可能性を真剣に検討したのだろう。神妙な顔で、セレネは首を傾げる。
「・・・・・・少しは」
ということは、九割方はただの方向音痴。
気を遣った言い方をされても、その事実は変わらない。
まあ、バイロが迷わない時点で考えるまでもなかった。
「・・・・・・それじゃあ、」
軽く凹みつつ、ふと思いついた事をアイルは口にする。
「ここのどこかにあの高ビー野郎、じゃなくて災厄の天使の庭もあったりするんですか?」
「無い」
見事なくらいの即答。
「無いんですか?」
「あの子はここが好きじゃないから」
セレネの答えた理由よりも、災厄の天使に対する”あの子”という呼び方のあまりの似合わなさに、アイルはくらくらするものを覚える。
そう言えばセレネは、外見こそアイルより年下のようでありながら、上級天使の五位なのである。
アイルはもちろん、紅蓮の天使や災厄の天使よりも先輩なのだ。
アイルの握り拳の中で、クシャリと乾いた音がした。
「それは何?」
「え? あ、これですか?」
丸めて握りつぶされた数枚の紙片。実はこれが、先刻の罵声の原因だったのだが。
「いえ、大したものじゃないです、全然!」
「本当に?」
「はいもちろん、何でもないです、本当に!」
その時だ。
「おい、何騒いでんだ?」
「わっびっくりしたっ!」
見れば、灯火のように鮮やかな髪の少年が、不機嫌に腕を組んで立っている。
「ああ、七位さんじゃないですか、脅かさないで下さいよ」
スタンドカラーのかっちりとした橙色の上衣にすらりとしたズボンというシンプな出で立ちなのだが、華やかな印象を受けるのは彼の存在自体が賑やかなせいだろうか。
「その呼び方はやめろ。紅蓮様だ、覚えとけ八位!」
「僕だって、ちゃーんとアイルって名前がありますからね! しっかり覚えて下さいね!」
「何だとコラ! 一回くらい運良く生き残れたからって、デカいカオすんじゃねーよ!」
睨み合って火花を散らした二人の間に、
「ハビィ、うるさい」
澄んだ高い声が、ピシャリと割って入る。
「・・・・・・セレも、いい加減その呼び方やめろよな」
思いっきり気を削がれた紅蓮の天使が、実に嫌そうな顔を向ける。
「あ、ハビィさんって言うんだ」
おそらくは愛称だろうが、妙に可愛らしい呼び名だ。
「違う! ハビエ様だ!」
それだって、十分可愛い。
「いや、やっぱ紅蓮様だな! ハビエ様も悪くないが、灼熱の炎って迫力が最高だろ? ん?」
言ってハビエは、堂々と胸を張る。
「ひょっとしなくても自分大好きな人なんですね」とは、流石のアイルも口には出さなかった。セレネの前だし。
「それで、その紅蓮様が何のご用ですか?」
「用? ああ、そうだった」
思い出して、ハビエは強奪したぐしゃぐしゃの紙片を開く。
「わっ! 何するんですか!」
「ちょっと見るくらい構わねーだろ! えーと、『災厄の天使が怪我人を手当で手伝わないです。腹が立つます。言い返しましょう・・・・・・』って、何だこれ?」
「やめて下さいまだ途中なんだから!」
「何の作文だよ? 文法も単語も無茶苦茶デタラメじゃねーか!」
「いいんですよ通じれば」
「通じるかよ! なあ、セレ?」
「ダメですってば!」
「おーっと、悔しかったら取り返してみなっ!」
「言われなくとも!」
紙片目がけて手を伸ばすアイルを、ハビエは長身を生かして右へ左へと身軽に翻弄する。
「ハビィ、弱いものいじめはだめ」
見かねたのだろう、眉を顰めたセレネがピシャリと叱り付けた。
「違げーよ! イジめてんじゃねーよ」
「違いますよ! 僕は弱いものじゃありません」
反論の声が重なって、ハビエとアイルは互いにふんっとそっぽを向いた。
「それならいい」
何をどう納得したのか。
セレネはあっさりと引き下がる。
「なあセレ、これ読んでみな」
「あーっ!」
慌てて遮ろうとしたアイルだが、リーチの差はいかんともしがたかった。
紙片はあっさりと、ハビエからセレネの手に渡る。
「これ、」
「な、面白いだろ?」
「おかしくなんかありません!」
「間違ってる」
「ほーら見ろ」
「ぐぬぬ」
「報告書には、正式名称を使わなきゃだめ」
「・・・・・・何でそれが報告書だって分かるんだ?」
「・・・・・・何です、正式名称って?」
質問の声が被り、アイルとハビエは顔を見合わせる。
「正式名称ってのはだな、例えば紅蓮の天使様の”様”までしっかり書かなきゃならねー、みたいな」
「君に聞いたんじゃないんですけど。てか、それ嘘ですよね」
「うっわ可愛くね!」
「すみません、セレネさん。それで、どれのことですか?」
「”災厄の天使”は通称。正式には”双月の天使”」
「「えええーっ!?」」
素っ頓狂な叫び声が、見事にハモった。
「何ですかそのあまりにもフツーな名前は・・・・・・って、どうして紅蓮まで驚いてるんですか!」
「仕方ねーだろ俺も初めて聞いたんだから!」
「僕より半年も先輩なのに?」
「るせーよ。てか、何なんだよこの報告書モドキは?」
それは昨夜、初任務から戻った後のこと。
遅まきながら帰還した災厄の天使を、アイルは転移の間の前で待ち構えて?まえた。
『これでどうだ!』
バーンと効果音付きで眼前に突きつけてやった報告書の束に、災厄の天使は一瞥をくれると。
『何だ、この作文は』
『作文じゃありません、報告書です! 君が遊んでる間にちゃーんと仕上げておきました!』
どうだ、とアイルは得意気に胸を張る。
『お前の随従は何も言わなかったのか?』
『もちろん、書き方のコツは聞いてます。任務の日時、場所、魔物の特徴、気付いたこと、感想、ちゃんと全部書いてあります』
『エール語だ』
『それはだって、大陸中で一番通メジャーな言葉だし、第一僕たちが今話してるのだってそうでしょう?』
『・・・・・・』
災厄の天使は突き付けられた紙片を一枚取ると、背後に控えていた番人に手振りでペンを要求し、裏面に短い言葉を書き付けた。
『何ですかこれ?』
『読めないならいい』
『神聖文字だってことくらいは見れば判りますよ!』
古い聖書で目にするその文字は、古帝国時代の流れを汲む神聖な文字だという。それ故に、国ごとに独自の言語が発達した時代を経て、エール語やフェーメ語などが共通語として幅を利かせる現代でも、契約書や外交文書などの重要書類は、内容を神に誓約するという意味を込めて神聖文字で記されるのが通例となっている(と言うか、そうしておけば互いに国の上下関係を争う等の不毛なトラブルを避けられる)、程度のことは、アイルも知識としては知っている。
『ひょっとして、神聖文字で書けってことですか?』
恐る恐る、馬鹿にされること覚悟でアイルは質問する。
『無理することはない』
それはイヤミ口調では全く無かった。が、出来るはずがないと当然のように断定された瞬間、アイルのいい加減疲れてハイになっていた頭は、カチンと大きな音を立てた。
『無理なんかじゃありません! 明日までに完成させてみせますよ!』
かくして無謀なチャレンジャー宣言をしてしまったアイルは、エール語対訳の(一番やさしい)辞書を借りて奮闘始めたまでは良かったのだが、途中からの記憶が無い。つまりいつの間にか机上でぐっすり眠りこけてしまい、目が覚めたら不覚にもベッドの中で、辺りは既に明るくなっていた。
運んでくれたのがバイロか他の誰かかは分からないが、どちらにせよ格好悪いったら無い。
そんなこんなで、部屋で一人うんうん唸るのに飽きたこともあって、自室からほど近い庭園の一角に陣取っていた次第である。
「大体、ちょっと神聖文字知らないからって馬鹿にされるいわれはありませんよ! どっかのお貴族様じゃあるまいし、字が書けるってだけでも十分自慢出来ることなんですからね!」
昨夜のやり取りを思い出すだに、腹立ちが蘇ってくる。
「それに何ですかこの汚い字は! 読みにくいったらありませんよ! 翼だか鷲の尾羽根だかに、頭巾に、数字の五って、これ一体何のナゾナゾですか!」
紙片裏に殴り書かれた短い単語をつなげて読んでも、全く意味が解らない。
「それ、”五枚羽根の冠”?」
「え? 解るんですか?」
控えめな声での指摘に、アイルはセレネを振り返る。
あまり感情的でない少女にしては、何ともフクザツな表情だ。
「古典劇の幕間に出てくる道化の象徴」
「道化? それって・・・・・・」
言葉には往々にして裏の意味があるものだ。非常に悪い予感とともに、アイルは続きを促す。
神妙な顔で小首を傾げるセレネの横で、先刻から肩を震わせていたハビエが、ついい耐え切れずに息を吐く。
「馬ー鹿! ってさ」
そのまま爆笑するハビエと、困ったような顔で二人を見比べているセレネを前に。
「あ、あ、あ、あンの野郎ーっ!」
顔を真っ赤にして雄叫びを上げるアイルだった。
全く何と言う恥をかかせてくれるのか。
「で、さ、何で報告書なんか書こうと思った?」
まだヒィヒィと変な呼吸の治まらないハビエが、そんなことを口にする。
「何でって・・・・・・書けって言われたからですけど?」
「そんなもん、随従に書かせりゃいいだろ。俺はサインしかしたことねーぜ」
「えええっ!?」
「だよな?」
ハビエに同意を求められて、セレネもコクンと頷いた。
「そんな! いや、だからなのか・・・・・・」
思い起こせば昨夜のバイロも、「私が書きましょうか」とか、「お手伝いしましょうか」と、しきりに聞いてきたのだった。
「こりゃいーや! お前、災厄のヤツにいいようにイジられてるんじゃね?」
「・・・・・・」
それには反論の余地が無い。
思わせぶりどころではなく、面と向かって邪魔だとすら言われているのだから。
だが、ひとしきり声を上げて笑った後で紅蓮は、琥珀色の瞳を細めると、
「ところでお前、仕返しとかしたくならね?」
いかにも面白いおもちゃを見つけましたという風情で、アイルの顔を覗き込む。
「仕返し?」
「何なら協力してやってもいいぜ? 例えば、お前があいつの弱点を探って来て、俺が素晴らしくも華麗な作戦を伝授してやるとかな」
「・・・・・・君も、災厄と何かあったんですか?」
「別に。アイツ見てるとイラつくってか、一度くらいあのスカした顔が思いっきり歪むのを見てやりたいって思わね?」
獲物をいたぶる獣の無邪気さで、紅蓮は艶やかに嗤う。
「な、お前もそう思うだろ?」
そんな同意を求められても困る。
いや、別に困る必要は無いのかも知れないが。
(確かに腹立つ奴だけど・・・・・・どうなんだろう? 僕は、どうしてやりたいんだろう? 少なくとも単純に仕返したいってのとは、ちょっと違うんじゃないか?)
ふとセレネの方に目をやれば、彼女は同意するでも咎めるでもなく、ハビエの顔を眺めている。
「で、どうする?」
「どうって、それは・・・・・・」
だが、その瞬間を狙い澄ましたかのように。
高らかな鐘の音が、空中庭園にこだました。
「っわ! 非常呼集、ですよね?」
アイルは椅子を蹴立てて立ち上がる。少しだけ、本当に少しだけ、鐘の音に救われたような気がした。
「ええっと! 転移の間はどっちでしたっけ?」
「ああ、あっちだ」
「ありがとうございます!」
駆け出そうとして、アイルはふと踏み止まった。
何となく、嫌な予感。
「本当に?」
「んー? 何がー?」
「違う。向こう」
とぼけるハビエに代わって、セレネが真逆の方向を指す。
「ありがとうございます、セレネさん! ところで、君は行かないんですか?」
ハビエが災厄に対抗意識を燃やしていることは確か。となれば、アイルに逆方向を教えておいて、自分は先回りするつもりだったのではないか。
「ああ、あれは昨日成功したからもういいや。何度も続けるなんて、面倒だし疲れるだけだ」
「・・・・・・」
任務争奪競争は、単なるイヤガラセだったらしい。
「それより、この紙切れ忘れてっぞ!」
「あ!」
「もう要らねーだろーし、俺が燃しといてやろーか?」
「ダメです! そこ置いて重しに石でも載せといて下さい! じゃ、僕急ぎますんで!」
「アイル」
「はい?」
アイるは駆け足のまま、顔だけ振り向いて返事をする。
呼び止めたのがセレネでなければ、無視して走り去っているところだ。
「今度も、ちゃんと帰って来る?」
「!」
それはセレネ流の心配の仕方なのかも知れない。
無事で帰って来てねという。
「ええ、もちろんです! ここが僕の居場所なんですから!」
笑顔で応えて、大きく手を振って、アイルは今度こそ元気に駆け出して行った。
「うん。いってらっしゃい」
とっくに見えなくなったアイルに向けて、セレネはにっこり微笑んだ。
第六話 一日の始まり

連続で任務に出た慌ただしい日々から一転、嘘のように平和な時が、もう三日も続いています。
ノンビリ贅沢してるのが申し訳ない気がしますが、考えてみたら、僕の今の仕事って魔物退治なんですよね。
ということはですよ?
世界もそれだけ平和だってことになりますよね。
だったらヒマしていられることを喜ぶべきなんですよね。
何もしないで食べられるのは贅沢すぎる?
ああ、それは誤解です。
お祈りだって毎日サボらずやってますよ。
それに塔の決まり事や、任務についての重要事項に、神聖文字の練習とか、覚えることはいっぱいあるんです。
あれは本当だったんですね。どこに行っても学問は大事っていうのは・・・・・・。
ちゃんとやって行けてるのか心配だ、ですって?
嫌だなあ。大丈夫に決まってるじゃないですか!
確かに、一緒に旅をしていた頃が懐かしくないと言ったら嘘になりますけど。
でも、新しい仲間も出来たし上手くやっていけると思うんです。
・・・・・・一人だけ、難攻不落の相棒だけは、なかなか手ごわいですけどね。
今朝の目覚めは、気分が良かった。
何かいい夢を見ていたような気もするが、残念ながらよく覚えていない。
ただ、懐かしい人と再会したような、そんなふわりとした気分が残っている。
そんな余韻のままに、手早く身支度を済ませたアイルは、自室を出て空中庭園へ。
朝の散歩だが、道順を覚えると言う実益を兼ねた日課である。
緑あふれると言えば聞こえはいいが、数歩ごとに植物が変わり雰囲気まで変わる庭園の小道は、数日やそこらでは見慣れそうにない。
だがそれでも、自室が塔の円周沿いにあるという事ふまえれば、とりあえず壁が見えるまで歩いて、そこから壁を見失わないように進んで行けば、自室に帰り着くくらいは何とか出来るようにはなった。
これはかなりの進歩である。
散歩中にセレネに出会って挨拶することもあれば、ハビエにからかわれることもあるのだが、今日は二人とも姿が見えなかった。
『俺は結構忙しいんだ。お前と違って指名任務ってのがあるからな!』
鐘で召集されるのではなく適任者を名指ししての任務もあるのだと、語っていたのはハビエだった。
もしかしたら、それで出かけているのかも知れないし、単に自室でダラけているだけかも知れない。
適当に迷いながら一時間ほどウロウロし、自室に帰り着いては皺一つなく整えられたベッドを横目に、整然と用意された朝食を一人で完食。
書き物机で、書きかけの報告書と神聖語の辞典を広げる。
前回の任務から既に三日。正式な報告書はバイロが仕上げてアイルがサインし提出済である。
だからこれは、アイルなりの報告書日記にようなものだ。
内容は大体、自分の行った事の記録と、災厄の天使に対する不平不満疑問などである。
そう、アイルの当面の目標は、報告書をスラスラと期限内に仕上げ、災厄の天使に突き付けてやることである。
その瞬間を想像すればこそ、試行錯誤の下書きも逐一の辞書引きも、苦痛だと思わずに継続可能なのだ。
一体どれくらいの時間が経っただろう?
「随従バイロ、お召しにより参上いたしました。入室の許可をいただけますでしょうか」
軽いノックに次いで、伺いをたてる声。
アイルが普段使っている庭園とは反対側の奥、部屋係や衣装係らが使う扉の方だ。
空中庭園などの上級天使専用の区画は、たとえ随従と言えども立ち入りが制限されている。
バイロがアイルの私室に出入りする際には基本的に、塔の外周に沿って設けられている従僕用の通路を利用する。
それを聞いた時の「僕もそっちを使いたいなあ。そしたらこんなに迷ったりしなくて済むのに」というため息は、バイロの笑みを誘っただけだった。冗談だと思われたらしい。
どうやらアイルに宛がわれた装備類などの保管場所もそちら側にあるらしいのだが、なるほど、そうでなければ衣装の用意や手入れをしたり部屋の掃除をしたり食事を運んだり、といった仕事をする者が困るのだろう。
それはともかく。
「どうぞ入って下さい、待ってましたよバイロ!」
「許可をいただきありがとうございます」
扉の開閉音に続き、衝立の奥から随従のバイロが姿を現す。
その後にもう一人、後に続いた部屋係の女性が、バイロの目くばせを受けて押してきたワゴンを残して無言で一礼し、すぐに退室していった。
基本、彼女らは入室の目的を告げる以外にほとんど口を開くことはない。
「ありがとう、ご苦労様です」
そのような声掛けは不要と言われたが、やはり感謝を伝えることは大事だろう。
「焼き菓子をお持ちいたしました。他にもご要望があれば、承りますが」
バイロはワゴンに掛けられていたクロスを取ると、自ら給仕の手を伸ばす。
「あ、出来ればお茶に薬酒を入れて下さい。飲むと身体が軽くなって、頭もスッキリするんですよ」
下手に遠慮していたら、却って手間をかけさせてしまうことになるのはすでに学習済み。
ちょっと前までの集団生活とはまた違う意味で、自己主張が必要なのだ。
ゆったりサイズの寝台にソファセット。書き物机に飾り棚。
それだけの家具が置かれていても、まだ十分な広さのある贅沢な部屋。
書き物机を離れたアイルは 三人掛けソファの上に背面ダイビングで倒れ込みつつ、思いっきり伸びをした。
これでもかと手足を伸ばしても、ふかふかのソファは微塵も窮屈さを感じさせることがない。
アイル一人に、本当に贅沢なことだと思う。
そうこうする間に、バイロはティーカップや菓子の小皿を手際よく並べていく。
「ありがとうございます。でもこんなことは、君の仕事じゃないんでしょう?」
菓子の一つに手を伸ばしてから、アイルは身を起こして座り直す。
「いえ、どういったことであろうと、アイル様にお仕えするのが私の仕事です」
まったくありがたい限りであるのだが。
「ええと、これ美味しいですよ。バイロも一緒にどうですか?」
皿の上に盛られた焼き菓子。
「お気遣いありがとうございます。ですが、これはアイル様に供されたものでございますから」
「つまりそれは、僕がどうぞって言ってもダメってことですか?」
「そういう規則でございます」
「そっか。残念だな。一緒に食べる方がきっと美味しいのに・・・・・・」
「お毒見は済ませてありますので、大丈夫でございますよ」
「そういう意味じゃないんですけど・・・・・・」
規則。慣例。決まり事。
アイルは眉根を寄せてかじりかけの菓子を睨む。
徹底して応急天使を上に置くそれは、頭では理解したつもりでも、感覚的に納得するのは難しい。
「ったく、規則を覚えるだけで、記憶力を使い果たしちゃいそうです」
「大丈夫ですよ」
バイロは励ますようにニッコリと笑う。
「上級天使様は、魔物を倒すことのみをお考えになればよろしいのです。その他の些事は私どもにお任せ下さい」
「そう、ですか」
要するに”要らんこと考えてないで自分の仕事をちゃんとやれ”ということだ。
「すみません、本題に入りましょうか。前回の任務で聞きたいことがあるんです」
「そうですね。時間も惜しいことですし」
「・・・・・・」
アイルの知らないところで、バイロにはバイロの仕事があるのだろう。
が、ここで気後れしてはいけない。
アイルには今の所バイロしか、些事(つまらないこと)を質問出来る相手がいないのだから。
だがその時。ふと、といった様子でバイロが顔を上げた。
「アイル様、少し失礼いたします」
立ち上がり奥の扉へ向かったバイロは、誰何と数言のやりとりの後、足早に戻って来た。
その目は心なしか険しさを帯びている。
「何があったんですか?」
「はい。アイル様にご聖務の要請でございます。それも、至急にとのこと」
手が空いている者なら誰でも構わないと言う緊急招集ではなく、上級天使それぞれの持つ特性を考慮して決定される。
つまり、アイルの力量が認められての大役ということになる。
「このまま転移の間までご案内いたします。アイル様の装備類は従僕が持って参ります。他にご要望はございませんか」
「大丈夫です。すぐに行きましょう」
アイルは気を引き締めて立ち上がる。
いつでも任務に出られるよう身支度を整えておくのは、アイルの習慣になっていた。
第七話 出立前の打ち合わせ
転移の間は、忙しく立ち働く技官たちで騒然としていた。
彼らは必要なこと以外口にしないので耳を塞ぎたくなる程ではなかったが、その分ピリピリと張り詰めた空気が狭くはない室中に充満しており、アイルは思わず扉の前で足を止めた。
先導していたバイロが、どうかしたのかと振り返る。
(し、しっかりしろ僕!)
心の中で自分を叱咤し、アイルは気合いで足を動かす。
そんなアイルに気付いた技官らが目礼を寄越す。が、作業の手は全く止まらない。
何気なく室内を見回したアイルは、技官らの向こうで腕組みしながら無言で圧力をかけている災厄の天使の姿を見つけた。殺伐とした空気の元凶はこれに違いない。
(やっぱ、今回も一緒なのか・・・・・・)
まあ、薄々そんな気はしていたのだが。
自分が指名された任務だという期待感があっただけに、ガッカリ度も倍増だ。
(早く一人前扱いされないかなあ・・・・・・)
アイルはコッソリため息を吐く。
「これは星焔(セイエン)の天使様。ご機嫌麗しゅう存じます」
「は、はいっ!」
不意の呼びかけに、アイルは反射的に悪戯を見つかった子供のような返事をしてしまう。
照れ笑いで振り向けば、黒衣のフードを目深に被った番人の一人が会釈で立っていた。
同じような黒いローブに身を包む番人たちを見分けるのはなかなかに難易度が高いのだが、その声には聞き覚えがあった。
そう、確か、アイルが初めて塔に連れて来られた日に空中庭園で出迎えてくれた人物だ。
彼は番人の長とだけ名乗っていた。
「ありがとうございます、長様!」
「そのように畏まられずとも結構でございますよ。白亜の塔においては、神威の代行者たる上級天使様こそが、最も尊いのですから」
番人の長にして、塔の技術管理部門の総責任者たる彼は、穏やかに応える。
初めて会った時にも思ったのだが、落ち着いていて威厳に満ちているのに物腰柔らかで優しそうで、教会の神父様の雰囲気とちょっと似ている。
「星焔様のご活躍は伺っておりますよ。魔物を退位するのみならず、民を助けるため奔走されているとのこと。そのご聖務に対する真摯さには感銘を禁じ得ません」
「い、いえ、それほどでも・・・・・・僕なんかまだまだで・・・・・・」
「謙遜なさらずとも。ですが、その崇高さが貴方の美徳なのでしょうね」
「そ、そんな・・・・・・」
まさかそんな風に褒めちぎられるとは思わなかった。
すっかり赤面したアイルは、頭を掻いて照れ笑いする。
「とは申せ、ご活躍の陰ではご心労も多々お有りでしょう。何かお辛い事やお困り事はございませんか?」
「そんな、大丈夫です! 皆とっても良くしてくれますし! 僕の方こそ、もっともっとお役に立てるようにがんばります!」
「これは頼もしいお言葉。聞けば皆も感激いたしましょう。塔を代表してお礼を申し上げます」
番人の長は、優雅な仕草で深々と一礼した。
「あ、頭を上げて下さい! でも、そう言っていただけると、僕も嬉しいです!」
本当に思いがけない労いと励ましだった。
何より、アイルのことを見ていて気にかけていてくれる人がいることが、素直に嬉しかった。
そんな人がアイルに期待を寄せてくれているのなら、がっかりさせたくない。
絶対に、期待に応えてみせる!
アイルが決意を新たに拳を握った、その時だ。
立ち働く技官らの間を割って、災厄の天使がこっちに向かって来るのが見えた。
しかも、ただでさえ不機嫌そうな顔だというのに、それが今日はいつにも増して虫の居所が悪そうなのだ。
そんなものがずんずんとこっちへ向かって来るのだから、アイルに非が無くとも心穏やかではいられない。
「何です? どうかしたんですか?」
「どういうつもりだ」
だが、災厄の天使が詰め寄った相手はアイルではなく、傍にいた番人の長だった。
「おや、何かご不興でも?」
「トボけるな。何でこいつがここにいる!」
強い口調で、災厄の天使はアイルを指差す。
「は? 僕の何が気に入らないんですか!」
だが、アイルの抗議は、当然のように無視される。
「そう申されましても。お二人が組んでご聖務に赴かれることは貴方も承諾なさったはずですが」
「一体何度こいつの面倒を見たと思っている! こいつには単独で出来そうな簡単な仕事を宛がってやればいいだろう。わざわざ俺を名指しするようなロクでもない仕事に、素人同然の奴を同行させる必要がどこにある!」
「ちょっと待って下さい! いつ僕が君に面倒かけました!?」
言いがかりもほどほどにして欲しい。
大体今まで一緒に任務に出ること三回。その三回とも、災厄の天使は好き勝手に飛び出して行ってしまって、アイルのことなどお構いなしだったのだ。そんな奴に、どうして邪魔者扱いされなければならないのか。
しかも、指名されたのは自分であって、アイルはついででしかないと決めてかかっている所からして腹が立つ。実際その通りなのかも知れないが、それでもやはり腹が立つ。
「これはまた、随分な言われようですね」
番人の長はにこやかと言っても良いくらい、穏やかに応じた。
誰もが思わず後ずさってしまうような、怒気に満ちた災厄の天使に詰め寄られているにもかかわらず。
「これも良い機会でございますれば、ご聖務についての知識などを星焔様にご伝授なさってはいかがですか」
「そう、それです! 最初からちゃんと教えてくれるんなら、僕だってがんばって任務に当たれるってものです!」
こっちだって願い下げだと言いたいところだが、番人の長の手前、アイルはありったけの自制心をかき集めて応じる。実際、任務のコツなり役割分担なり指示してくれさえすれば、任務に出る度に戸惑わずに動けたはずなのだから。
災厄の天使は、かなり無理した作り笑顔のアイルに一瞬視線を走らせると。
「お前、この馬鹿に何を吹き込んだ」
「仰る意味がよく・・・・・・」
「誰が馬鹿でるか誰がっ! それに長様は僕を励ましてくれただけです、無責任な誰かさんと違って!」
なけなしの自制心などひとたまりもなく吹き飛ばし、怒りを瞬間沸騰させたアイルが吠える。
声の大きさでは、間違いなくアイルが一番なのだが。
番人の長を睨み付ける災厄の天使と、動揺など知らぬが如く穏やかな態度を崩さない番人の長の前では、どうにも迫力不足なのである。
「何を仰られましても、」
ややあって、口を開いたのは番人の長だった。
「これは決定事項にございます、カリム様」
「・・・・・・」
まるで何事も無かったかのような。今日はいい天気ですねと聞き間違えたかと思うほどのにこやかな声に、毒気を抜かれでもしたか。災厄の天使の瞳からふっと、溢れ出す程に猛っていたはずの怒気が消える。
あまりの変わりように、却ってアイルの方が度肝を抜かれた心地である。
(うーん、長様大人だなー。格好いいなー。猛獣みたいな災厄の天使を簡単にあしらっちゃうなんて。てか、カリムって名前だったのかー。そう言えば自己紹介も無視しやがったもんなー)
動揺のせいか取り留めない事を考えながら、アイルは二人の様子を見比べる。
しばらく無言で睨み続けた後で。
「・・・・・・相手は魔物か?」
災厄の天使が念を押すように呻く。
(!?)
奇妙な質問だ。
それは当たり前すぎる話なのに。
「もちろんです。天使は魔物を討滅するものですから」
番人の長の答えももちろん、当然すぎるものだった。
「何をわざわざ、どうしたんです?」
だが、アイルが疑問を口にする間も無く。
「・・・・・・勝手にしろ」
吐き捨てるや、災厄の天使はフイと身を翻し、来た時と同じようにずかずかと大股で歩き去ってしまった。
「どうしたんだろう? いっつも無愛想だし不機嫌だけど、今日はもっと、こう・・・・・・」
見送りながら、アイルは首を傾げる。
いつもの雰囲気とは何か違うような気がしたが、何が違うのかと問われれば、良く解からないとしか言いようがない。
ただただ、居心地の悪さだけが残る。
「星焔様、あまりお気になさらずに。あの方気紛れは今に始まったことではありません」
「ええ、はい。そうですね」
言われてみれば、正しくその通りである。
「とは申しましても・・・・・・」
番人の長の穏やかな声が、心なしか憂いを含む。
「あの方はご覧の通りのご気性故に、他者を頼むことなく独断で無茶ばかりなさいます。あのご様子では、いつ足を掬われないとも限りません・・・・・・」
「一度盛大に転べば、考えを改めるんじゃないですか」とは言えない雰囲気だ。
(長様、あんな奴を心配するなんて、本当にいい人なんだな。それに引きかえ・・・・・・)
アイルは顔を上げると、
「ご安心下さい、長様! 及ばずながら、僕が全力で災厄の天使をサポートします!」
番人の長を元気付けるため、力一杯宣言する。
「星焔様がいらっしゃれば、心強いことこの上もありません。どうかよろしくお願いいたします」
「はい、任せて下さい!」
番人の長の口元に安堵の笑みが浮かぶのを見て、アイルは決意も新たにニッコリ笑った。
「心よりご武運をお祈りいたしておりますよ、星焔様」
「ありがとうございます。行ってきます!」
張り切って駆けて行くアイルの後に、無言のまま番人の長に目礼したバイロが従った。
「まだ手間取っているのか? 座標調整如きにどれだけかける気だ」
災厄の天使に怒鳴られて、操作盤の担当技官は遠目ですらハッキリ判るほど大きく肩を震わせた。
「申し訳ございません、慎重を期すためには、もう少しの猶予をいただきたく・・・・・・」
「慎重が聞いて呆れる」
(調整? 慎重? ・・・・・・あのことかな)
アイルは常設の転移門を使った時以外の二回、座標指定による転移で任地に跳んだが、その二回とも門の出口が目標位置とズレて開いていた。
と言っても数十から数百メートル程度の誤差であれば、馬車を乗り継いだり長距離徒歩で目的地に向かうことを思えば、全く大した問題ではないように思う。
「正確に手早くやってのけるのがお前らの仕事だろう。下手な言い訳など聞くに堪えん」
が、災厄の天使はそうは思わないらしい。
叱責を受けた技官のフードで隠れた額には、きっと大粒の脂汗が浮いているに違いない。
「で、連中の撤退状況は?」
「はい、概ね完了いたしております頃かと・・・・・・」
応えたのは、今回初めて見かける実戦部隊風の青年だ。
「あいまいな報告などいらん。とにかく急がせろ。役に立たないだけじゃ飽き足らずに邪魔までするか」
苦々しい舌打ちを挟み、
「完了次第報告しろ。衛士も警吏も余さず全部だぞ。次、」
返事も待たず、視線を向ける相手を変える。
睨まれた者が直立不動で身構える。
「ちょっとその態度はどうなんですか。八つ当たりにしか見えないですよ・・・・・・」
だが、抗議しようとしたアイルの前に、バイロがやんわりと割って入った。
「止めないで下さいよ」
「星焔様、災厄様の采配に異議がおありですか」
「そういうわけじゃありませんけど・・・・・・ものには言い方があるでしょう」
言っていることが間違いではないとしても、ああも高圧的に威張り散らされては、誰だっていい気はしないだろう。
しかしバイロの困ったような目にぶつかり、アイルは少し躊躇する。
ここでも横たわる立場の差。
「・・・・・・ところで、見慣れない方たちですね」
アイルは改めて、災厄の天使の周りの者達に目を向ける。
「もしかして災厄直属の随従ですか?」
だとすれば、今まで見かけなかった理由が謎だが。
「いえ。災厄様に専属の随従はおりません。彼らは第五軍所属の探索班です」
「第五軍っていうと・・・・・・バイロが随従になる前に所属してたって所でしたか?」
聞き覚えのある単語の答えを記憶から引っ張り出して確認。
「と申しますか、私の所属は今でも第五軍ですよ」
「そうなんですか! じゃあ、彼らは君の同僚なんですね」
「全く知らないわけではありませんが、第五軍の任務は多岐に渡りますから、所属班が違えばあまり関わることもありません。それよりも・・・・・・」
アイル付きの随従であるセルジオとサハトが、番人との打ち合わせを終えて戻って来るところだった。
「早速ですが星焔様、任務の詳細をて申し上げても?」
前置き抜きで、セルジオは本題に入る。
「今回の任務地はシノエ伯領の商業都市ゼーレン。討滅対象は”姿なき魔物”でございます」
セルジオの報告によると。
ゼーレンからの要請により調査派遣された第四軍の小隊は、速やかに魔物の存在を特定し、その討滅に成功した。
「ええっ? 成功したんですか?」
「そのはずでしたが・・・・・・」
そのまま事後処理に当たっていた小隊の面々は、”魔物”の奇襲により壊滅的な打撃を被った。
緊急の報を受けて駆け付けた第四軍の増援部隊は、しかし未だ”魔物”の所在どころか存在すら特定に至っていない。
「それで”姿なき魔物”ですか・・・・・・」
「通例では、上級天使様にお出まし願うのは、魔物の襲撃が進行中であるか、少なくとも詳細が特定されてからとなるのですが、今回は天軍の管理下での事件とあって、無為に事態を静観する訳にいかず、」
「で、僕たちの出番ですね」
「はい。事態を考慮して、お二方のご出座並びに第五軍の探索班4名の随伴が決定されました」
「それで彼らが・・・・・・でも、いつもの召集じゃなくて、僕らを指名する理由ってあるんですか?」
「それはもちろん、災厄様のご手腕に期待してのことでしょう」
ごく当然のように、セルジオは答えた。
「探索の手腕? ザハトみたいなですか?」
アイル直属の三人の随従の内、ザハトは任務遂行時において水晶錐を介して刻一刻と変化する戦況を瞬時に読み取り助言する役目を担う。が、
「滅相もございません」
ザハトは慌てて大きくかぶりを振る。
「私めのささやかな能力など、比べることさえ畏れ多い!」
そのうろたえっぷりたるや。
(口数が少なくて、どんな時にも怒ったり笑ったり慌てたりしてるとこ見せないような、冷静さを失くさないタイプだと思ってたけど)
ザハトの普段の一面を垣間見た気分である。
「でも、そんなに違いますか?」
ザハトのみならず、三人が三人とも当たり前だとばかりに頷いているところを見れば、そういうことなのだろうが。
(そう言われてみれば・・・・・・)
ザハトの助言を得てから動くアイル達と違い、災厄の天使はいつも真っ先に飛び出して行く。
もちろんアイルだって、羽根を介して魔物の位置や魔力の大きさを読み取るくらいは十分可能だ。
災厄の天使は塔に来たばかりのアイルより経験値も高く、普段随従を従えてもいない分、相応の探索術は使えて当然なのかも知れない。
「少しは状況を理解したか」
「!?」
アイルに声をかけたのは、何と当の災厄の天使本人だった。
先刻の今で、珍しいこともあるものだ。
「今回は、力任せに魔物をなぎ倒すような、お前向きの仕事じゃない。解ったら、黙って引っ込んでいろ」
結局、それが言いたかっただけらしい。
「冗談じゃありません! これは僕に与えられた任務でもあるんです。黙って見てるつもりなんて、これっぽっちもありませんから!」
「だったらせめて、俺の指示に従え」
「それ、同じことじゃないですか。どっかで延々と待機させるつもりでしょう」
「第四軍の重傷者が施療院に収容されている。奴らが狙われているのなら、また襲撃があるかも知れん。お前、その護衛に着け」
意外なことに、至極真っ当な内容だ。
「ええと、魔物探しは」
「それは手が足りている」
魔物探しを得手としているらしい災厄の天使に加えて、探索専門の天使が4人も加わるのなら、確かにその通りだ。
「・・・・・・魔物が出たら教えてくれるんでしょうね?」
「状況による」
つまり、教える気が無いのは明白。
「じゃあ僕も、行ってから状況を見て、どう行動するか考えますよ」
その途端、周りで聞いていた随従や探索班や技官らの顔が固まった。
(あ、あれ・・・・・・何で?)
そもそもアイルは災厄の天使の部下ではないのだから一方的に指示されるいわれはないし、自分で判断して決められなければいつまで経っても災厄の天使のおまけ扱いのままだ。
しかし災厄の天使の振る舞いに慣れ切った者達から見れば、アイルの言動は単に逆らっているようにしか映らないのかも知れない。
「だったら好きにしろ」
場の空気を知ってか知らずか、災厄の天使はどうでも良さ気に目を逸らせた。
途端に張り詰めた空気が僅かに緩む。
本当に僅かに、ではあるが。
いつ自分に矛先が向くかも知れないという危機感が、依然として彼らを支配している。
(やっぱり、こんなの良くないよな)
アイルは作業に没頭している体を崩さない技官らと、直立不動で畏まっている探索班一同に目をやってから。
「ねえ、いくら僕のことが気に入らないからって、そんなにピリピリしてたら皆が怖がりますよ。カリム」
その瞬間、刃のような蒼い目がアイルを見据えた。
「誰が許した?」
ゾクリと、背筋が凍る。
「な、何をです?」
「誰が、そんな風に呼ぶことを許した?」
「ゆ、許すも許さないも、名前って、呼ぶためにあるものでしょう?」
自分の主張は、ごく正論だと思う。
だが、アイルの意に反して、反論の声は掠れた羽虫の鳴き声ほどにしかならなかった。
「二度と呼ぶな」
アイルの返事も待たず、災厄の天使は再び身を翻した。
その声は終始、さほど大きくも荒げられもしない、どちらかと言えば平坦なものだった。
見据える瞳すら、ただただ深く凪いでいた。
それ故に、何よりも雄弁に、アイルの全てを拒絶していた。
「な、な、な、何ですかアレはっ!」
視線が外れた途端、あの一瞬が嘘のように、口が軽く動いた。
と、同時に理不尽に対する怒りがドッと湧き上がる。
「名前呼ばれたくらいであんなに怒るなんて、何考えてるんだか! 全っ然解らない!」
たとえば「アイル」というのは、塔に入る時に貰った、上級天使としての名前だ。
おそらく「セレネ」も「ハビエ」もそうだろうし、「カリム」という名もきっと。
そんな新しい名前でも、呼ばれるのが嬉しいし、呼び合える仲間がいるのはもっと嬉しい。
(僕に呼ばれるのが嫌なんだろうか。それとも・・・・・・あああ、もう、ホントーに解らない!)
アイルは災厄の天使の背中を、思いっきり睨み付けた。
第八話 現地での情報収集
災厄の天使があれほど念を押したにも関わらず、転移地点はまたズレた。
距離にすればほんの十数メートルではあったが。
そこは目標地点だった聖堂の中庭から、敷地をぐるりと取り囲む堅牢な壁を隔てた石畳の路上だった。
「うわ高っ・・・・・・」
壁も高いが、その向こうに聳える鐘楼もなかなかのものだ。
「この前のボロ小っさ・・・・・・こじんまりとした聖堂とはスゴい違いですね。転移門が常設でないのがいっそ不思議です・・・・・・」
ポカンと口を開けて見上げつつ、アイルは素直な感想を吐く。
冷たく乾いた空気に、ぱっと白い息が咲く。
「転移門が置かれているのは、古代帝国の都市が栄えた地だそうですから」
生真面目な返答をしたのはバイロだ。
古代の都市がそのまま発展するとは限らない。今では小さな村でしかない場所もあれば、記録の中だけの幻の都もある。
都市自体は発展したものの、旧区にポツンと取り残された廃墟の小神殿に転移門だけが佇むようなケースもある。
「理屈では分かってるんですけどね。・・・・・・それにしても、頑丈そうな壁だなあ」
古代とまではいかなくとも古い都市の聖堂は、災害時や外敵が襲ってきた時に備えて住民が避難し立てこもれるような(場合によっては軍が駐留することも想定した)構造になっているものがそこそこ多い。
つまり壁の側面に位置するこの路上から最短距離で聖堂に入ろうと思っても、正門か裏門が見えるまで壁沿いを延々歩かなければならない。
その上、魔物に備えて門扉が閉ざされていたら、中に入るにはかなりの手間がかかりそうだ。
「まさか締め出し食らったりはしません、よね・・・・・・」
「星焔様にそんな大それた真似をする者など、居るはずがありません」
アイルたちがそんな会話を交わしている間にも、災厄の天使は無言で肩をいからせたまま、先をずんずん歩いていく。
もちろん、後を追うアイルらを気にする気配など全く無しだ。
(あーあ、「場を和ませよう作戦」失敗かー。いや、先刻みたいに八つ当たりされないだけマシなのか・・・・・・)
ただしそれは、文句を言う気も失せるほど怒り心頭なだけかも知れないが。いかに恐いもの知らずなアイルでも、ここで不用意に話しかけるほど能天気にはなれない。
探索班の4人は、既にどこにも姿が無い。打ち合わせ通り、到着と同時にさっさと市街に散っている。転送位置が都市内でさえあれば、市街地担当の彼らには何の問題も無かった。
アイルだってもちろん、ノンキに観光に来たわけではない。
「どうです、ザハト。魔物がどこにいるか判りますか?」
移動しながらも水晶錐を睨み付けていたザハトは、眉根を寄せたまま首を振った。
「そうですか・・・・・・僕もです」
身の内の羽根がおとなし過ぎる。
魔物の気配を捉えた時の、熱くざわつく感じが全く無い。
いつもなら後のことなど気にせず飛び出して行く災厄の天使ですら、今回はそうしない。ということは、彼もやはり魔物の気配を掴みかねているのだろう。
もしかしたら不機嫌の最大の理由は、それかも知れない。
「本当に、ここに魔物が・・・・・・」
呟いて、アイルは唇を噛む。
どう行動するか、着いてから決めるとアイルは言った。ならば、決めなければならない。この状況で、何が出来るか。何をすべきか。
「このまま聖堂に入りましょう」
アイルは顔を上げて、随従の三人を振り返った。
「では、負傷者の護衛に着くということでしょうか? 災厄様の指示通りに」
アイルのすぐ後ろを追随するバイロが確認してくる。ハッキリとは言わないものの、その声からは啖呵を切ったアイルの心情への配慮が受け取れる。
「意地を張っても仕方ないですからね。それに、魔物と遭遇した人から話が聞ければ、何か手掛かりが掴めるかも知れません」
「良いご判断だと考えます。魔物を追うことばかりに拘って防御が手薄となっては、我々の方が襲撃を受けないとも限りませんから」
補足したバイロに、アイルは内心目を見張る。
(そっか。その可能性もあるんだ・・・・・・)
補足したバイロに、アイルは内心目を見張る。
(だったら逆に、僕が囮になって魔物をおびき寄せるって手も・・・・・)
しかしアイルはすぐにその可能性を頭から追い出す。
自分だけが狙われるなら構わないが、随従の三人が先に襲われた場合、無事で済むとの確証が持てない。
三人がいかに優秀でも、彼らはアイルと違って受けた傷がすぐに治ったりはしないのだ。
(姿なき魔物・・・・・・)
その名の持つ底知れなさに、今更ではあるが、アイルは小さく身震いした。
正門が閉ざされていたらどうするか・・・・・・という心配は必要なかった。
災厄の天使に少し遅れて開け放たれていた正門を潜ったアイルは、整然と居並び頭を垂れる修道士の一団に迎えられた。
歓待の唱和に圧倒されかかったアイルだが、ふと、彼らの表情や態度にどこかホッとした様子を垣間見た気がした。
それはおそらく、気のせいではないのだろう。
人の都合を考慮する気などさらさらない災厄の天使が、彼らに対してどう振る舞ったか、くらいは簡単に想像できる。
とっとと聖堂の奥に進んで行ってしまった災厄の天使の後を追いたいのはやまやまだが、さりとてアイルにまでスルーされては、彼らの立つ瀬がないだろう。
歓迎の口上を最後までしっかりと聞き、最近習ったばかりの型通りの答礼をトチることなく披露し終えたところで、案内役だという第四軍の天使が進み出て両手を胸に当てながら片膝をついた正式の礼をする。
任務中は公式の場であっても基本的に立ったままの略が認められているから、青年の態度はかなり丁寧だ。
「出迎えに感謝します。でも、まずは施療院まで案内してもらえますか?」
気がせいていることもあり、アイルは儀礼的やりとりを省いて要求する。
「承知いたしました。どうぞこちらへ」
青年に先導され、聖堂前広場の奥の平屋建ての建物に入ると、中庭に面した内回廊に出た。内回廊沿いにはおそらく病室のものだろう、幾つもの閉ざされた扉が並んでいる。
突き当りの角を曲がって一番奥まった扉の前で立ち止まった青年は中の者にアイルの来訪を告げと、そのまま扉の外で警護に立つ。
青年の押し開けた扉をくぐれば、そこは寝台の並んだ簡素な部屋だった。
第四軍付きの呪術医の男と二人の従僕が、正式礼でアイルらを迎える。
だが、アイルの視線は彼らを通り越して、後ろの寝台に釘付けになっていた。
「これは・・・・・・」
寝台の上に載せられている、大きな繭のような白いもの。
近付いてみると、それは顔立ちどころか体格の判別さえ難しい程に包帯と聖布でくるまれた、人間の身体だった。
包帯の隙間から覗く口元には、およそ生気らしいものは感じられず、呼吸の気配すら定かではない。
聖布がぼうっと光って見えるのは、施された治癒術によるものだろう。
それが三体。
「どのような容体ですか」
呆然としているアイルに代わって、バイロが呪術医に問いかける。
「はい。魔物に受けた傷が深うございます。応急的な治癒術と結界術にて容体の悪化を押しとどめておりますが、今はそれが精一杯の有様・・・・・・特にこの者は体内が穢毒に侵されております故、いつまで持ちますかどうか・・・・・・」
「この女性は、羽根使いですね・・・・・・」
アイルの目には、包帯にくるまれた身の内で頼りない篝火のように揺らめく光が視える。まるで、彼女の生命の力を示してでもいるように。
天軍の天使は何人か見ていたが、羽根使いの天使に出会ったのはこれが初めてだった。
羽根の力こそ扱えるが、アイルら上級天使のように炎の結晶と同化してはいない、普通の人間の身体しか持たぬ者。
「小隊はこれで全員ですか? 他に誰か、魔物の話しを聞けそうな・・・・・・」
バイロの問いに、呪術医は無言で首を振る。
いなくなった。助からなかった、ということだ。
「そうですか。私共にお手伝い出来ることはありますか。医療呪術に関しても、多少の心得はあるつもりですが」
バイロの申し出に、ゼルジオとザハトが頷く。
この三人には、随従に抜擢されるに足るだけの秀でた知識と技術があるのだ。
「大変ありがたく存じます。ですが、この程度の設備ではこれ以上の治療は難しいかと。聖都の施療院に搬送出来ますれば、まだ望みもありましょうが・・・・・・」
自らの無力を嗤うように、呪術医の口元が歪む。
上級天使であるアイルの前で、ついそんな表情を出してしまうほど、彼は苦しくて仕方が無いのだ。目の前の怪我人をどうにも出来ない現実が。どうにも出来ない自分自身が。
「申し訳ございませんアイルさま。せっかくのご足労でしたが、肝心の情報は得られないようです」
無駄足を踏ませたと詫びるバイロに、アイルは大きく首を振る。
「そんなことないです! おかげで”姿なき魔物”の所業が良く分かりました」
たとえ天使であっても、一歩間違えればただでは済まない相手だと。これほど雄弁な語り手などいない。
「どうすればいいですか・・・・・・僕は、この方たちに、何がしてあげられますか・・・・・・?」
「ありがとう存じます。星焔の天使様。そのお心だけで、彼らの心も救われましょう」
アイルの言葉に、呪術医は深く頭を垂れる。
(違う、そうじゃない。そんなことを聞きたいんじゃない!)
どんなに役立たずでも、誰もアイルを責めない。悪いとは言わない。
上級天使だから。至高の存在だから、と。
気持ちだけで嬉しい。それだけで満足だ、と。
(そんなのは、役に立っているとは言わない!)
何をすればいいか?
それくらい、他人に聞くまでもなく解り切っている。
彼らを聖都に搬送するためには、まず転移門の常設された街まで移送しなければならない。一刻も早く、安全に。
何故それが出来ないか?
魔物が襲撃して来るかも知れないから。無理に動けば、もっと被害を広げることになりかねないからだ。
ならば、やるべきことは一つ。
一分一秒でも早く、魔物を討滅すること。
アイルはそのために、ここに来た。
「バイロ、ここの守りをどう思いますか?」
「・・・・・・万全だとは申せませんが、結界を強化することである程度対応は可能かと。聖堂は物理的にも呪術的にも、守りに適した構造になっておりますから」
何か言いたそうな素振りを見せたザハトを、バイロは目で制する。
「すいません、僕、やっぱり魔物を探しに行きます。それまで、ここをお願いします!」
「お待ちください。護衛に、」
「ダメです!」
強い口調でアイルは拒絶の意を示す。
「今回だけは、ここにいて下さい!」
言うなりアイルは、クルリと身を翻し室を飛び出した。
制止されないよう、全速力で。
「ご武運を、アイル様!」
追いかけて来たのは、アイルの意を汲んだバイロの激励の声だった。
(冷静に、冷静に、冷静になれ僕!)
勢いで施療院を飛び出したアイルだが、最低限の分別は失くしていないつもりだ。
頭に血が上った状態で突っ走っても、魔物を探す手掛かり無しでは独りよがりなだけ。どころか、探索班の邪魔になりかねない。
そういう意味では、災厄の天使に現状を確認した上で、探索に加わるべきなのだろう。
問題は、「出しゃばるな」と一蹴されて終わる可能性が大いにあるということで。
(いや、でも、説得次第で何とかなるんじゃないかな・・・・・・)
その根拠は、アイルが上級天使だということ、そのものだ。
いくら魔物に対処する力を持ってはいても、一般の天使は傷つきもすれば死にもする。羽根使いであっても、肉体の強さはあくまで人間の範疇だ。
その点アイルであれば、どれほどの怪我を負おうと、同化している炎の結晶がたちどころに癒してくれる。魔物の不意打ちを食らったとしても、あっさりやられてしまうことはないだろう。
もちろん、怪我をすれば痛いし、痛いのは嫌いだ。
それでもアイルが身体を張ることで皆の役に立つのなら、すすんで前に出るべきなのだ。
(よーし! 説得してみてダメなら、独断で行くだけだ。あいつだって平気で独断専行するんだから、僕がしちゃいけないってことないもんね!)
回廊の手すりを飛び越え、植え込みなどの障害物を物ともせず中庭を直線的に突っ切って聖堂に向かったアイルはしかし、そこではたと足を止める。
(ええと、どっちに行けばいいんだ?)
災厄の天使の居所なら、あの独特の威圧感を持つ羽根の気配からして、一般人立ち入り禁止な奥院の一室だろうことは判る。が、それは直線距離の話で、聖堂の奥に続く入り組んだ回廊をどう辿れば行きつけるかは、また別の問題だ。
加えてアイルの方向感覚は、決して自慢できるような代物ではない。
(どうしよう・・・・・・修道士さんか誰か通らないかな・・・・・・それとも諦めてこのまま外に行っちゃおうかな・・・・・・)
行き止まりになった回廊を引き返したアイルは、祈りの間の方まで戻ってきてしまった。
最初に入って来た正門に近い、普段から一般市民も出入り自由な、神に祈りを捧げるための大広間。
正面の扉は、開け放たれているようだ。
「・・・・・・あれ?」
何かが変だ。
変と言うか、違和感がある。
首を傾げつつ大扉から中を覗き込んだ瞬間、アイルは思わず目を見張った。
広い祈りの間には、僅かな人影しかなかったのだ。
祭壇の前に並んで日課の祈りを捧げる修道士達と、その後背の身廊から静かな面持ちで黙祷する市民が十人あまり。
それは、ごくごく平和な日常の風景だ。
避難して来た人々の不安げに寄り添い合う姿など、どこにもない。
(まさか・・・・・・街の人々は魔物のことを知らされていないのか? どうして・・・・・・)
「これは星焔様、この様な所でどうかなさいましたか?」
いきなり声をかけられて、アイルの肩が跳ね上げる。
「ああ、失礼いたしました。脅かすつもりはなかったのですが」
慌てて振り向いたアイルが見たのは、転移の間で見かけた短い黒髪の青年が略礼する姿だ。
「君は、第五軍の? 街の探索に出てたはずじゃ・・・・・・?」
「はい。私の担当区は既に調べ終えましたので」
4人で手分けしたのなら、街の4分の一を調べ終えて戻って来たということなのだろうが、任務遂行の速さを自慢するような口振りが何とはなしに鼻につく。
「それで、”見えない魔物”は見つかったんですか?」
途端に、目の前の細身の青年は、おやという顔をする。
「私共の任は、魔物探しではありませんが」
「え、じゃあ何を調べてたんですか?」
「それはもちろん、私共に課せられた通りの・・・・・・」
疑問符を貼り付けたままのアイルの反応に、青年は根本的なことを説明する必要があると悟ったらしい。
「私の所属は第五軍羽根使い探索班です。俗に天使狩りと呼ばれたりもしますが」
「天使狩り!?」
ここで聞くとは思っていなかった名称に、アイルは思わずおうむ返ししてしまう。
”羽根”とは人智を超えた最強の退魔法具であり、魔物の脅威に苦しむ人間を憐れんだ神がこの世界に遣わされた聖なる力と謳われる。
いつどこで、どんな人物の元へ現れるのか。”羽根”出現に法則性があるのかすら、神ならぬ身には知りえない。
羽根使いを一手に集め管理する白亜の塔であっても、その事実は変わらない。
ただ”羽根”の出現を捉え、探し、見つけ出すのみ。
”羽根”を得た者は羽根使いと呼ばれるが、その出現の仕方も発現の仕方も様々で、時には高齢になってから突然に発現した例もあるらしい。
そのようなものだから、羽根に選ばれた本人であっても、突然我が身に与えられた力が”羽根”によるものだと自覚することは難しい。
アイル自身も、自分が羽根使いだなど、いやそれ以前に”羽根”というものがあることすら認識していなかった。
認識せぬまま、不要なトラブルや怪奇現象を引き寄せる例は珍しくない。
むしろそれが羽根使い探しの目印にもなるほどだ。
つまり、玉石混交の奇妙な現象を精査し、ごく稀に存在する”羽根”の所有者を探し当てて白亜の塔に保護するのが、羽根使い探索班の主要な任務という訳だ。
「じゃあ君、もしかしてリザさんとお知り合いなんですか? 僕はつい最近、リザさんに塔まで連れて来てもらったんです!」
「確かにリザは第2小隊に属しておりますが・・・・・・最近の手柄話じゃ御大層な名前した流浪民のチビくらい・・・・・・」
「あ、それです! それ僕のことです」
後半の口の中だけで呟いたような独り言に、まさか絡んで来られるとは思わなかったらしい。
青年は、見るからにしまったという顔で黙り込む。
「そっか、僕のこと覚えてくれてたのか。嬉しいな。それでリザさん、お元気ですか?」
曖昧に頷く青年の様子に全く気付きもせず、アイルは懐かしげな笑顔を見せる。
「あれ? それじゃ、もしかして君たちが探してたのは、羽根使いなんですか?」
「そ、その通りです。在野の羽根使いが、魔物騒ぎに似たトラブルを起こすこともありますから」
魔物の気配が無いにもかかわらず天軍の羽根使いに致命傷を負わせることの出来る存在として、知られざる羽根使い出現の可能性が考慮されたという事だ。
自分の力に無自覚故に、敵味方の区別もかなわないような。
「残念ながら、この街に新たな”羽根”の気配はありませんでした。後の三人も、結果はきっと同じでしょう」
課された仕事に関して、青年はハッキリ断言した。
「それじゃ魔物は?」
「”羽根”による事象でない以上、それは私共の任ではありません」
「・・・・・・はい?」
アイルはポカンとして目を見開く。
青年はそれを、話の終わりと捉えたらしい。
「では、私はこれにて・・・・・・」
「待って下さい! もう一つ教えてくれませんか?」
そそくさと辞そうとした青年を、アイルは急いで呼び止める。
「街の人々が避難していない理由、何か知りませんか?」
「それは当然でしょう」
全く思案することなく、青年は即答する。
「魔物の討滅宣言は既に出されています。なのにまだ得体の知れぬものが徘徊しているなど、言えるわけがないでしょう」
「なっ!? それ単に、偉い人のメンツの問題でしょう! そんなもののために街の人々が危険に晒されるなんて、おかしくないですか!?」
「”そんなこと”ですか・・・・・・」
青年の低い呟きを、アイルは聞いていなかった。
「そんな危険な状態なのに、衛士の人達を撤収させる? メンツの為に放っておくってどういう・・・・・・それともまさか、街の人達を囮にする気じゃ・・・・・・」
ふと思いついてしまった可能性に、アイルは呆然とする。
「どうかなさいましたか星焔様。この者が何か失礼をいたしましたか?」
そこに現れたのは、任務から戻った探索班の3人だった。
途端に青年が、心持ち嫌そうにそっぽを向く。
「いえ。彼には教えて欲しいことがあったので、それで話をしていたんです」
「ああ、そうでございましたか」
小隊長らしい青年が、いかにも安堵した顔で胸を撫で下ろす。
その後ろでは、仏頂面をした青年の両側に立った二人が、アイルに対してビシっと綺麗な略礼をする。が、その肘元付近ではよくよく注意しなければ判らないくらい僅かな挙動で「この!」「バカ!」「何を!」的な、小突き合いの攻防が展開されていた。
「それで、この者でお役に立ちましたか」
「・・・・・・あ、はい!」
「では、私共はこれより報告に参りますので、」
「! それ、災厄の所にですよね。僕も連れて行って下さい!」
この件に関する采配を振るったのは災厄の天使だ。一体何を考えているのか、こうなったらとことん問い質してやらねばならない。
気が急くままに、アイルは強い口調で訴える。
「承知いたしました。ご案内いたします」
略式の拝命姿勢を取ってから、青年は踵を返して先導するように歩き出す。
そして後ろの3人とすれ違いざま。
青年の鉄拳3連打が彼らの腹にクリーンヒット。
揃って腹を押さえた3人が決まり悪そうに顔を顰める様子を、アイルは少し眩しげに眺めやった。
意匠を凝らした重厚な扉の並ぶ高位聖職者用の区画の中でも、見るからに上級の貴賓室と思しき扉。
取次の従僕を介したやり取りにイラつきつつ。
ようやく扉が動いた瞬間、中に飛び込んだアイルは、豪商の屋敷もかくやという華美な調度品に埋め尽くされた室内で、まるで異質な存在のようにひっそりと執務卓につく黒衣の番人に目を止めた。
今回転移して来た同行者に、番人はいなかったはずだが。
「そんなことより、災厄の天使は・・・・・・!?」
忙しく右往左往したアイルの視線が、壁際の一点でピタリと止まる。
室の隅に置かれたの小卓に、無造作に立てかけられている大振りの曲刀。
他を威嚇するほどの気配を遠慮なく放つそれが、災厄の天使がいつも背に負う羽根の刃であることは、微塵も疑う余地がない。
「な、何でこんな所に・・・・・・」
近寄ってみれば、小卓の上の衣装箱には緋色の上衣と防具類が、まるでたった今用意されたかの如く、きちんと並べ置かれている。
放り出された装備一式を、従僕か誰かが注意深く整え直したのだろう。
問題は、それを放り出した本人が、どこで何をしているかということだ。
「ご苦労だった。それで、」
小卓を睨み付けて絶句しているアイルの背後では、招き入れられた探索班の面々が、番人に促されて略礼を解いていた。
「第五軍探索班第3小隊、報告いたします」
探索範囲と状況、結果。つまり羽根使いは発見できなかった旨の報告を行った青年に、番人は鷹揚に頷いた。
「委細承知した。災厄様も同様のご見解であられた。これにて諸君らの任務は終了である。帰還を許可する」
「はっ」
「待って下さい! それじゃ魔物はどうするんですか!?」
淡々と進行していく事態に、アイルは慌てて割って入る。
いくら彼らが羽根使い探しが専門だとしても、魔物を探さなくていい理由にはならないはずだ。
「星焔の天使様」
番人が、強い口調でアイルの名を呼ぶ。
「貴方は、負傷者の護衛という任をお受けになったのでは?」
「彼らはバイロ達に任せて来ました。それより災厄の天使はどこに行ったんですか? 聞きたいことがあるんです」
「あの方は、自身の任を果たしに行かれました」
「一人でですか!?」
「ご心配には及びません。あの方の”眼”は天軍随一です。我らが下手に動けば、却って妨げになりましょう」
能力があるとか無いとか、そういうことを問題にしているのではない。
「まさか、最初からそのつもりで・・・・・・?」
アイルだけならまだしも、他者を徹底的に邪魔者扱いし、頑なに拒もうとする災厄の天使。
『あの方はご覧の通りのご気性故に、他者を頼むことなく独断で無茶ばかりなさいます。あのご様子では、いつ足を掬われないとも限りません・・・・・・』
番人の長の憂いを帯びた声が、脳裏に甦る。
アイルは唇を噛むと、番人に背を向けた。
「星焔様。どうなさるおつもりですか」
「決まってます! 僕も魔物を探しに行くんですよ! 何か問題でもありますか!?」
「いいえ」
意外にもあっさりと、番人は首を横に振った。
「私めは星焔様の決定に口を差し挟める立場ではございませんので」
「・・・・・・!」
思わず足を止めたアイルだが、それはほんの一瞬のこと。
番人を振り返ることなく、アイルは用の無くなった部屋を駆け出して行った。
第九話 魔物の探索
「どうしよう、迷ったかな・・・・・・」
キョロキョロと辺りを見回しながら、アイルは首を傾げる。
聖堂を出て角をいくつか曲がったあたりで、アイルの方向感覚はあっさりと音を上げた。
広い通りを選んで進んだはずが、どこをどう間違えたのか、道はどんどん細くなっていく。
しかも売り物か個人の所有物かゴミかも判然としない大小のガラクタが、決して広くない通りの真ん中までせり出していたり散らばっていたりする。
通り自体も緩くカーブを描いているようで、見通しは最悪。このままずっと先まで続いているのか、行き止まりなのか、行き止まりに見えて実は曲がり角になっているのか、行ってみなければわからない。
適当に歩き回っていたら、今度はもっと細い通りに入り込んでしまった。
どこからどこまでが一つの建物かも分からないほど密集した家屋の間を、頼りない通路が網目のように繋いでいる。
路地の先どころか、空さえもろくに見えない。
あれほど高いと思った聖堂の尖塔さえ、とうの昔に見えなくなっていた。
こうなっては、引き返し方も分からない。
ただ、アイルの名誉のために付け加えるなら。
真っ直ぐに伸びる大通り沿いに商館や豪邸を集めた新市街と違い、古くからの聖堂や教会や職人街や民家などがゴチャゴチャと軒を連ねる旧市街は、分かり易く整備しようなどとは最初から考えられていない。
むしろ迷いやすいこと自体が、天然の要害と言ってもいい。
この街にとって、アイルは他所者だ。すれ違う人々の視線も、この場に不似合いな奇異な存在を見るものである。
異物として拒絶される不安感が、アイルの足元を一層頼りなくさせる。
(そう言えば、ずっと前にも・・・・・・)
『どうしてこんな意地悪なんだよ・・・・・・』
散々道に迷った挙句にようやく知っている顔を見つけ、泣きべそをかきながら訴えたアレクに。
『昔の人はその方がいいって思ったんだよ。ほら、悪い人に追いかけられた時、隠れんぼしやすい方がいいじゃないか』
悪い人というのが他国の侵略や盗賊団などのことだとは、当時のアレクだったアイルは想像もしなかったのだが。
それでも一向に泣き止まないアレクを、その人はしっかりと抱きしめて、言ったのだ。
『ほら、大丈夫だって! 何を目指すのかさえ分かっていれば、どんなに迷ったってちゃんと辿り着けるものなんだから。聞けば教えてくれる親切な人もいるしね。今だって、こうしてちゃんと会えただろう?』
あれから何年経っただろう。
僕はまだ、迷っているのだろうか。
僕が目指すものは・・・・・・この街のどこかに潜んでいる魔物・・・・・・災厄の天使・・・・・・。
(そんなの誰かに聞いて分かるものじゃないし、ホントどうしたものかなぁ)
細い路地を進んで行った先に、今度は分厚い壁がドーンと立ちはだかった。
取り壊すのが大変なのでそのまま放置されたかつての城壁か何かだろうか。
多少朽ちかけていようが、今なお人を拒み続けている壁は、まるで八方ふさがりなアイルの気分を代弁しているようだった。
同じ頃。
アイルと別方向ではあったが、入り組んだ旧市街を進む、もう一つの人影があった。
黒の袖の短いチュニックと細身のズボンに、フード付きのマントをゆるく羽織っただけの簡素な出で立ちは、どう見ても冷たく乾いた風が吹き抜けるこの季節向きではない。
かと言って、マントから覗く白い腕も、手入れされた長い髪も、簡素ではあっても上質と思われる衣服自体も、防寒着が用意出来ないような下層民のそれではない。
身なりと身分が一致しない他所者とくれば、それだけで十分不審人物なのだが、ここは商業で栄える街だ。
北方出身の商人あたりの使いの者が迷い込むか何かしたのだと思えば、納得できなくはない。
少なくとも、路地を賑やかに走り回る貴族っぽい身なりの迷子の少年ほどには、その人物が人々の注目を集めることはなかった。
その人物が向かうのが、賑やかな商店街とも活気溢れる職人街とも違う方向だったとしても。
庶民の行きかう路地を抜け、排水臭の漂う水路の橋を渡ったところで、辺りの雰囲気は一変する。
すえた臭い。つぎはぎだらけの古い建物。どんよりと停滞する空気。
人の姿はほとんど無い。が、ねっとりと絡みつくような複数の視線が、傾いだドアの向こうや、穴を塞いだ窓の向こうの、そこかしこから注がれる。
街が賑やかに栄えていればいるほど、それに寄り添う闇は深い。
薄暗く澱んだ乱雑な小路には、街の繁栄にあぶれて追いやられた者たちが、なおも僅かなおこぼれに預かろうとひしめいている。
知らぬ者がうっかり迷い込もうものなら、身ぐるみはがされるだけで済めば幸運。どんな災いが降りかかっても不思議ではない。
それを知ってかしらずか、彼が躊躇なくどんどん先へ進んで行く。
そして視線の主達もまた、小路に出て来ようとする気配はなかった。
当然だろう。
このような所で生きる者達の、人を見分ける嗅覚は鋭い。
突然の来訪者が、ただ迷い込んだだけの間抜け野郎かそうでないかを見分けられぬようでは、一日たりとも無事ではいられないだろう。
住人らのビリビリするほど張り巡らされた緊張の糸の中を、しかし見かけ上は全く何も起こらないまま、来訪者は足を速めることも止めることもなく歩いて行く。
散々せっついて出させた報告によれば。
単発的な魔物の被害は、このような小路と市街の境界付近で起こっていた。
元々治安が良くない地域であることに加え、市民でない者の被害までわざわざ記録されないだろうとなると、実際にはどれくらいの犠牲が出ているのか、正確なところは分からない。
魔物の存在が認識されたのは最近のことかも知れないが、魔物の仕業であると断定できるような最初の事案がいつから起こり出したのかも分からない。
人間による血なまぐさい事案に紛れて、魔物は少しずつ成長していた。
だが、依頼を受けて派遣された第四軍の小隊が調査を始めた矢先、おそらくは偶然に近い接触により、魔物の一匹は討滅された。
その事後処理の最中に、小隊は街の衛士らとともに”見えない魔物”に襲撃された。
最初の魔物が討滅された地点から、さほど遠くはない場所で。
となれば”見えない魔物”の目的は一つしかないだろう。それはカリムが聞いている”声”とも合致する。
(ったく、ここの連中にも聞こえるものが、どうしてあいつらには判らないかな)
ズキズキと痛む頭を押さえて、カリムは僅かに顔を顰める。
せめて呪力の干渉を軽減しようと、護法呪術を織り込まれた上衣や装備の類は聖堂に放置してきたのだが、ほどんど焼け石に水だった。
(多重結界や法術が絡まった重圧だらけな塔でノンキにくつろげるような図太い奴らに、言うだけ無駄か)
ボヤいたところで仕方のないと解ってはいても、悪態の一つもつきたくはなる。
転移門を潜った瞬間、塔に施された魔術による重圧は消滅する。
刹那の空白。
踏み出した足が門の地面に触れた瞬間、五感を越えた感覚の全てが津波になって一気に押し寄せる。
その中にあって、ひときわ強烈に響き渡る絶叫。
冷気すらも切り裂くような泣き声。
赤子の如き剥き出しの感情の奔流。
人間は皆、多かれ少なかれ言いたいことを抱えているものだし、その声が特別大きい者もいる。
だが、同時に自分をさらけ出すことを恐れもする。
なのに、一切の外聞を顧みることなく、感情をぶつける相手も定めず、湧き上がる怒りを、悲しみを、恐怖を、そっくりそのまま叫び続けるもの。
暴力的なまでに、絶え間なく。
そんなものが、ただの人間であるはずがない。
それが魔物の気配をまとっていなくとも。
しかしその声は、魔物の気配を真っ先に捉える羽根使いや訓練された術者には、却って聞こえないものなのだろう。
気配を絶った羽根すら見つけ出せる天使狩りでさえ、その点は同様だ。
もっとも、カリムが他者を嗤うことはできない。
カリムが必要以上に様々なものを見聞きし捉えてしまうのは、単に何でもかんでも無節操に映し込んでしまう不安定な炎の結晶を、無駄に魔術感度の良すぎる身体(いれもの)の内に有するが故だ。
つくづく厄介なことに、身の内の結晶から意識を閉ざすことは不可能に近く、ほとんどは意味をなさない雑多な情報の中から目的のものを選り分けて照準を絞ることは、相当に神経をすり減らせる行為だ。
大体、大砲を目標範囲内に撃ちこめるレベルであれば事足りる上級天使に、精密射撃レベルの能力とか、精度設計からして間違っている。
探索担当が必要なら、水晶錐を使いこなす術者を量産運用する方が、よほど実用的で便利だろう。
(本当に視たいものが視えないのなら意味が無い・・・・・・)
内心で呟き、カリムは少し足取りを緩めた。
あの声に近付いていることは確かだが、入って来る音圧が大きすぎて、逆に正確な位置の特定が難しい。
聖堂に飾ってあった絵地図(装飾重視で、主要な建物とメインストリート以外あまりアテにならない代物だったのだが)によれば、このまま行けば新市街との境界である旧城壁に突き当たる。
アテにならないと言えば・・・・・・。
先刻から騒々しい気配が、街の中を走り回っている。
無意味な喚き声に気を散らされて、煩わしいことこの上ない。
ようやく天使狩りの連中が引き上げたと思ったらこれだ。
(まったくあの馬鹿は。よくも人の配慮を簡単に無にしてくれる)
天使狩り連中は命じられて来たのだから、最低限顔を立ててやるのは仕方がない。が、あの馬鹿にこれ以上気を遣ってやる義理など全くない。
大体、羽根使いを擁する小隊が、何故こうも簡単に壊滅的な打撃を被ったのか。今回の任務対象がどうして見えない”魔物”と呼ばれているのか。
少しは考えてみるべきだ。
単純に戦力として比較した場合の上級天使と羽根使いの差など、瞬間出力と継続時間くらいなもので、羽根を扱う能力自体に大きな違いはない。
経験を積んだ羽根使いが技量で級天使を上回ることは十分あり得るし、護身の技においては特別な回復力を持たない分、むしろ長けていると思っていい。
”見えない魔物”は、そんな羽根使いにあっさりと致命傷を負わせた。これは相当な異常事態だ。
”魔物”と呼ばれるものが、必ずしも”魔力”のみで襲ってくるとは限らない。想定外の力に遭遇した場合、あいつは立ち向かえるのだろうか。どんな存在であろうと、討滅する覚悟はあるのだろうか。
(馬鹿馬鹿しい・・・・・・)
どうしてあんな馬鹿のことを気にしてやらねばならないのか。
きっと、このロクでもない任務のせいだ。
それにしても、心なしかあの馬鹿の気配が近付いて来ていないか?
闇雲に駆け回ったくらいでは”道”が辿れるはずはないのだが・・・・・・。
世の中にはえてして、妙な特技を持った奴がいる。
例えば、全く意図していないにも関わらず狙い澄ましたように最悪の場面に出くわしてしてしまうような、最強の悪運の持ち主などが。
もちろん、そんな奴がどこにでもホイホイ居る訳ではないだろうが、嫌な予感ほど当たるものだ。
「・・・・・・急いだ方が良さそうだな」
あの馬鹿がうっかりと、”見えない魔物”に出くわす前に。
第十話 最善の手段
かつて聖堂中心の小規模な町に過ぎなかったゼーレンは、当時の領主が立地を活かした商業重視の整備を行ったことにより、立派な城壁を持つ商業の街へ、更に人が集まるにつれ城壁の外へ外へとその規模を広げていった。
不要となった城壁の大部分は取り壊されたが、新市街と旧市街を隔てる一角にだけは、往時のまま放置された城壁が境界のように残されていた。
造られた当時は頑丈でも長年放置されっ放しだった旧城壁は、随所で亀裂が走ったり崩れかけたりと、崩壊の兆しが忍び寄っていた。
そんな城壁の、路地を少し逸れた目立たない位置に、人一人が通れるくらいの縦長の穴が穿たれている。
崩れて自然に開いたものではない。
注意深く見れば、扉が据えられていたと思しき蝶番の痕もある。
穴の向こうを覗き込んでみれば、そこは地図に描かれていたような新市街の風景ではなく、伸び放題の雑草や雑木が生い茂る広い空間が、更には冬枯れの木立の奥に人の手を離れて久しそうな古風な館が存在した。
特殊な立地の仕方といい、忘れらて久しそうな佇まいといい、おそらくは城壁建造当時の領主の隠邸か何かだったのだろう。
(最近、何かが出入りしているな・・・・・・)
別に不思議なことではない。
金目のものはとっくに持ち出されていたとしても、雑木は焚き付けにもってこいだし、荒れ放題の廃屋も宿に困った者には格好のねぐらとなる。
だがそれにしては、庭園を満たす空気は荒涼とし過ぎている。
うらぶれた路地裏のそれよりも濃い、迷い込んだ愚か者をパックリと呑みこんでしまいそうな、うすら寒い荒涼さ。
叫び声は今も響いている。
間違いなく、あの館の中から。
ざっと様子を確かめてから穴を潜ったカリムは、荒れた庭を足早に突っ切って館に近づくと、枠のみを残した窓の一つからヒラリと音も無く邸内に入り込む。
途端に、叫び声がピタリと止んだ。
奇妙な静寂。
足元に降り積もった埃がふっと舞い上がり、外気とは別種の澱んだ冷気がカリムの全身を包み込む。
埃。いや、正確には細かい粒と化した残骸だ。
干からびて脆く崩れた、無数の遺骸の成れの果て。
その大半は、鼠や鴉などの小動物のものだが、そうでないものも多数ある。
遺骸にこびりついた布切れが、その正体を示している。
状態から見て、数カ月から数年前のものだろうか。
だが、斜めに差し込む薄日すら届かない室の奥に転がる数体は、どう見ても真新しい。
何も知らずに足を踏み入れてしまった者どもの、憐れな末路だ。
静かに足を運ぶたび、床の上に白い煙がふわふわと舞って揺れる。
歪にゆがんだ窓の形に切り取られた薄日を受けて、白い煙が淡く光る。
何も知らなければ、幻想的ですらある光景。
無慈悲な力が造り出した光景の中で。
カリムは、室の隅に佇む者に目を向けた。
夕焼けの紅を映した飾り気の無いドレスを纏い、華奢な肩を震わせながら背を見せている、一人の少女。
「ようやく会えたな」
その声が聞こえているのかどうか。
少女は全く応えない。
それでも通じている手応えはある。
そのために、苦労して”道”を辿って来たのだから。
目的の所まで続く、入り組んだ道。
物理的に最短ルートとはいえない道筋を敢えて辿ったのは、それが相手の心に”橋”を繋げるための初歩的な”道”の魔術だからだ。
ゆっくりと。
ごくゆっくりとした動作で、ほんの少し頭をもたげて、少女はカリムを伺う素振りを見せる。
夕日に染まった長い髪がさらりと揺れる。
ウ・・・・・・グ・・・・・・ァ・・・・・・
少女の口から洩れたのは、言葉どころかただの濁った音でしかなかった。
が、カリムには聞こえている。
「・・・・・・それが、お前の望みか」
手足を縮こめ自身を抱き締めて震えている少女の傍らに、そっと寄り添いながら。
「会いたいのか、そいつに・・・・・・」
ダッ・・・ウァウゥ・・・・・・ダッ・・・・・・ダウゥ・・・・・・
少女は”そいつ”を呼ぶ。
呼び続ける。
泣きながらずっと呼び続けていたのと、同じ声で。
「だが、そいつはもう、ここにはいない。戻って来ることは決してない。お前に、そいつは探せない」
ガッ・・・・・・
それは強い否定。
怒り。
拒否。
「そいつをここに連れて来てやることは出来ない」
グ・・・・・・ガッ・・・・・・ガッ・・・・・・
嫌、嫌、嫌、と。
少女は大きく頭を振る。
「だが、連れて行ってやることは出来る。そいつに会えるかも知れない所へ・・・・・・」
ダ!
即答だった。
どこへと訝ることもなく。
どうやってと問いもせず。
嘘かと疑うことも知らず。
「ああ、連れて行ってやる・・・・・・だが、その前に一つ、頼みがある」
・・・・・・グ・・・・・・
「その顔を、見せてくれないか?」
何を言われたのか。
少女は困惑したようだ。
頼みごと、交換条件。
この少女の姿をしたものにとっては、今まで一度として求められたことも、当然応じたこともない概念だから。
不安と拒絶の色が混乱しせめぎ合う様を、カリムはただ、静かに見つめる。
やがて。
少女の姿をしたものが頭をもたげ、ゆっくりと振り返る。
そうして髪の間から覗いた顔には・・・・・・何も無かった。
闇そのものが、ぽかりと口を開けているように。
「・・・・・・そうか。残念だよ」
その声は、穏やかで優しかった。
一瞬も逸らされることのない瞳は、どこまでも深く凪いでいた。
「それを教えてくれるなら、刺されてやるくらい構わなかったんだがな・・・・・・」
その瞬間、少女の身体がビクンと震えた。
胸元にしっかりと抱え込んでいた両手の中に、蒼い炎が吹き上がる。
ギャアッ
放り出され床に転がったそれは、血泥にまみれて錆びついた、ナイフ状の金属塊。
少女の全身を、恐怖の色が駆け巡る。
動くことも、声を発することも出来ず。
虚空の瞳は、深淵の瞳に絡め取られる。
「約束だったな」
カリムの右手が、少女の細い首に延びる。
「連れて行ってやるよ。お前が会いたいものの所へ・・・・・・」
少女の固く縮こまっていた身体からストンと力が抜け、握り締めていた拳がほどける。
虚空の瞳から恐怖の色が消えていく。
伸ばされた白い手に、存在の全てを委ねるように。
「何してるんだっっっ!!!」
盛大な破壊音と共に。
そいつは辛うじて残っていた窓を枠ごと蹴破って飛び込んで来た。
金色の髪が、残照のように赤く鮮烈な軌跡を描く。
完全な不意打ちに、カリムと少女の意識を繋いでいた”橋”は、一瞬にして弾け飛んだ。
夕焼け色のドレスの少女は消え去り、全く別の姿が現れる。
その小さな身体はカリムの手をすり抜け、あっという間に彼方へと去って行く。
再び伸ばそうとした手の先を、だが、鋭い光弾が薙ぎ払った。
「許さないっ!」
目の前に立ちはだかるのは星焔の天使、アイルだ。
”羽根”の手甲を装着した右腕を伸ばし、カリムを真っ直ぐに睨み付けている。
「キーシャに手を出すなっ! そんなことをする奴は、誰だろうと許さないっ!」
「この馬鹿が」
アイルに対峙しつつも、カリムは呪的空間から消え去ったものの気配を追う。
いた。
広間の反対の隅にうず高く積まれた、古びて壊れた家材の城。
小柄でなければ到底入り込めないような最奥に、息を潜める存在が一つ。
部屋数の多い邸内を逃げ回るでも、外に飛び出すでもなく。
広さがあるとは言え、侵入者と同じ室内に留まったのは、それでもここが一番安心できる場所だから。
あるいは・・・・・・。
「させるものかっ!」
カリムの注意を遮るように、アイルが間に割り込んで来る。
憎悪に燃える瞳を、躊躇もなくカリムに向けて。
同時に、アイルの腕から放たれた光弾が、カリム目がけて襲い掛かる。
(普段からそれくらい出来れば苦労が無いものを・・・・・・)
まるで他人事ののように思いながら、カリムは押さえつけていたものの手綱を、僅かに緩める。
待っていましたとばかり、軛(クビキ)から解き放たれた力の一部が、喜々として狙いを定める。
瞬間、出現した無数の刃が、向かい来る光弾をことごとく食い破って四散させる。
「なっ・・・・・・どうして羽根が!?」
予想外の事だったのか、アイルの瞳が狼狽に揺れる。
「何を驚く?」
敵を威嚇する無数の刃を周囲に滞空させながら、カリムが応じる。
曲刀の形で聖堂に放置されていたはずの羽根が、何故ここにあるのかという意味であれば。
羽根を具現化して切り離していようとも、常に感覚で繋がっている点では、身の内に羽根を収めている状態とさほど違いはない。
だから、曲刀を転移門に放り込んで世界の果てに捨てたとしても、羽根が羽根使いを捕らえている限り、その距離は無いも同じだ。
「いや! たとえ相手が天使だろうと、キーシャに手を傷つける奴は許さない! 僕は必ずキーシャを守る!」
決意も新たに、アイルは鉤爪の付いた手を構える。
(ったく、そこからかよ・・・・・)
状況どころか、誰が相手も判らず乱入してきたとは。
想像を超えたお目出度さだ。
内心で毒づきつつカリムは、牙を剥く忠犬のようなアイルの、燃える瞳を真っ直ぐ捉える。
「そのキーシャってのは、お前の何だ?」
「大事な人です!」
全く思考を通らない条件反射な答えだが、とりあえず会話は成立するようだ。
「どう、大事だ?」
「そんなの、当たり前のことです!」
無茶苦茶な鉤爪の攻撃を受け流しつつ、さらに問う。
「どう、当たり前なんだ?」
「それはもちろん、」
そこでようやく、アイルは投げ返す言葉に詰まる。
「キーシャは・・・・・・」
答えを探すように、若草色の瞳が内なる遠くを見つめる。
「もちろん決まってます! キーシャは僕の大切な人です! 優しくて、賢くて、格好良くて、誰とも知れない僕を拾って育ててくれた、大事な大事な恩人です!」
目を見開き、息を弾ませ、アイルは言葉を絞り出す。
「僕は絶対にキーシャを守る! 傷つける者は許さない!」
「どうでもいいが、」
カリムは興味なさげに肩を竦めると。
「お前の大事なキーシャとやらは、こんな所でお前から逃げ回るようなヤツなのか?」
最後の質問。
「こんな所・・・・・・こんな所って・・・・・・?」
不安げに彷徨ったアイルの視線が、次第に周囲に焦点を合わせはじめる。
「ここ? ここは・・・・・・ええと確か道に迷って、城壁の上だったらよく見えるかなって登って、走って、そしたらオドロオドロしい変な屋敷があって・・・・・・あれ、カリム? 何で君がここに・・・・・・?」
その途端、足を払われたアイルはものの見事にすっ転ぶ。床に積もった埃がもわっと派手に舞い上がった。
「い、痛っ、ペ、ペ、ペ! 何するんですかゴホッ!」
アイルの右手から羽根の具現である手甲が消えたのを機に、臨戦状態でカリムの周りに滞空していた無数の刃も、一振りの曲刀に凝縮されて持ち主の手の中に納まる。
「いつまで幻術に振り回されているつもりだ。いい加減にしろこの馬鹿」
会話が成り立つ相手であれば、問いかけによって意識と現実とのズレを認識させるのは、ごく初歩的な解呪の基本だ。
「誰が馬鹿ですかゲホホッ・・・・・・って、うわあっ! ドクロ? ガイコツッ!?」
両手を突っ張って身を起こしたアイルは、すぐ傍に転がっているものに気付いて反射的に飛び退こうとする。
が、逃げようとした先にも、そのまた反対側にも、乾いた白い物が散乱しているのを目にし、行き場を失くして静止する。
「な、何なんですかここはっ!」
何とかそろりと立ち上がることに成功したアイルは、血の気の引いた顔で、改めて床に散乱している無数の骸を見回した。
「そんなもの、聖堂の地下墓地に行けばいくらでも見られるだろ」
「それを言うなら屋根から壁から骨で造った聖堂だって見たことありますよ僕は! じゃなくて、聖堂墓地のはちゃんと祝福を受けて安置されてるじゃないですか! これとは全然別物です!」
「違う? 何が」
「違います、大違いですよ!」
青い顔のまま、アイルは声高に主張する。
が、流石にそんな場合ではないと多い至る。
「ってことはつまり、ここが”見えない魔物”の棲家なんですか? この館のどこかに魔物が・・・・・・あ!?」
落ち着かなく周囲を見回したアイルは、古びて壊れた家具で作られた砦の奥に、微かな気配を発見する。
アイルはガラクタの山のギリギリ際まで近づいて、身を屈めて覗き込む。と、
壁に切られた、火が入れられなくなって相当経つような暖炉の奥に、うずくまる小さな背中が見えた。
ボロ布の間から覗く、薄汚れた手足。
ぼさぼさと伸び放題で、元の色さえ定かではない程くすんだ髪。
「・・・・・・あんな小さな子供が、どうしてこんな所になんか? いえ、とにかくあの子を保護しなくちゃ、魔物に見つかったら大変だ」
アイルは大きく頷くと、子供を驚かせないようにそっと口を開く。
「こんにちは、僕はアイルです。何も恐くないですよ。僕は君を助けに来たんです。だから、出てきてくれませんか?」
安心させようと微笑みかけるが、子供は振り向こうとさえしない。
見つかってしまったという不安に怯え、小さな身体をさらに縮こめてしまうばかりだ。
「ねえ、そこは寒いでしょう? お腹も空きませんか? ・・・・・・あのね、いつまでもそんなところにいたら、恐い魔物に食べられてしまうかも知れないんです。だから、」
魔物と聞いてか、子供の身体がビクリと震える。
「あっ、ごめんなさい大丈夫です! 魔物なんて僕がきっと退治しますから。絶対に守ってあげますから!」
だがいくら訴えても、子供の様子は変わらない。
「どうしよう、言葉が通じてないんだろうか・・・・・・」
だったらこのまま説得を続けてもらちが開かない。乱暴にならない程度に障害物を退けていくべきだろうか・・・・・・。
「通じてはいるさ」
さらりとカリムは断言する。
曲がりなりにも炎の結晶を宿す者の言葉だ。たとえ言語として解らなくとも、言いたいことは伝わっているはずだ。
「言ってることが的外れなだけで」
「的外れ!? どこがです!」
「お前、本当にそいつが魔物と無関係だと思っているのか?」
「え!?」
頓狂な顔で思わず振り向いたアイルに、カリムは口の端で嗤う。
「ここに、保護対象者など存在しない」
「・・・・・・何を、言ってるんですか?」
断言され、動揺したアイルの声が震える。
「まだ解らないのか。第四軍の小隊がどうやって”自滅”したのか。”見えない魔物”が何を意味するのか」
その口調は、揶揄でも嘲笑でもなかった。
「別に、解りたくないのなら構わない。きっと、その方が幸せだ」
「そんな・・・・・・僕は・・・・・・」
深く蒼い瞳が、アイルを通り越して、小さな子供の姿を映す。
そのちっぽけな子供と契約の魔物が、どこでどうやって出会ったのか。
どんなきっかけがあって、共に過ごすようになったのか。
それはもう、誰にも判らないだろう。
どんな事情があったにせよ、あるいはただの気紛れだったにせよ、両者は出会い、共に時を過ごした。
子供に術をかけたのは魔物だったのだろう。
魔物にとって好ましい者の姿を、その子供に投影するために。
もしかすると、術の媒体とするためだけに、子供は魔物に必要とされたのかも知れない。
だが、それでも良かったのだ。
子供にとっては魔物の傍こそが、この世界で唯一の安らげる場所だったから。
しかし、ある日を境に、魔物は子供の前から消えた。
安息の地は、突然に失われた。
子供はそれでも待ち続け、待ちくたびれて、魔物を探しに外に出る。
魔物と長く過ごしたせいか、それとも子供自身に多少の素養があったのか。
魔物を切望するが故に、子供にかけられていた術は変化を遂げる。
見る者にとって一番大切な者の姿を投影し、保護欲を掻き立てられずにはいられない、魅了の呪縛へと。
しかし、子供自身は何も理解していない。
”他者の目に映る自分”という概念が、そもそも存在しないのだ。
魔物以外の全てが恐怖の対象である子供にとって、目の前に差し出される手が自分を守るためのものだとは、知る由もない。
泣いて怯えて、振り払う。
その恐怖は、幻となって見る者の心に突き刺さる。
第四軍の者達は、自分にとっての大切な人を守ろうと、同士討ちの果てに子供の握る穢毒の刃に切り裂かれた。
疑問を抱くこともなく。
抵抗する術もなく。
恐いものが動かなくなって、子供は少し安心する。
そうしてまた魔物を探し、探し疲れて、魔物が帰って来るかもしれない場所へと戻る。
それが、”見えない魔物”と呼ばれるものの正体だ。
「何をしている? そこを退け」
「嫌です!」
子供の隠れるガラクタの山を背後に、両手を大きく広げて、アイルはカリムの前に立ち塞がる。
術を解いたら解いたでこの面倒さ。
まったく、どうしろと言うのか。
「お前、自分が何をしているか解っているのか? 魔物を庇うのは、塔に対する反逆行為だぞ」
「魔物なんかじゃありません! この子はただの子供です! 魔力なんて少しも持たない、怯えて泣いてるだけの子供なんです! この子に必要なのは断罪なんかじゃない、抱きしめて守ってあげる人です!」
「馬鹿げたことを。そいつは人間にとっての脅威だ。塔の連中だって、とっくに魔物と断定している。この決定は、お前が何をしようと覆らない」
「どうしてですか! 塔の技術があれば、この程度の術なんて簡単に解けますよね!」
塔の魔道技術の高さは一般にも有名だし、アイル自身が何度も驚かされている。
「何のために?」
「!?」
「そいつの術を解くことに、何の意味がある?」
出来る出来ないではなく。
「何言ってるんです! 命ですよ! 人一人の命なんです! 意味があるとか無いとか、聞くこと自体おかしいと思わないんですか!? 命の価値を、神様でもない者が勝手に決めるなんて、出来るわけないじゃないですか!」
「そいつが大勢の命を奪った張本人だとしてもか? ここに転がってる奴らや第四軍の連中の前で、同じことが言えるのか?」
「それは・・・・・・でも、それは本当にこの子の罪ですか!? だって、知らなかったから! 誰も、何も教えてくれなかったから! それなのに、どうやって分かれって言うんですか! 分かる機会すら、貰えないままでいいって言うんですか! そんなの間違ってる! 絶対に間違ってる!」
「仮にそいつを助けたとして、では誰が手取り足取り教えてやる? 誰が四六時中一緒にいて、世話をしてやると?」
「僕が!」
「何だと?」
「僕がやりますよ! ずっと一緒に居て、何も恐くないんだ、怯える必要なんてないんだって教えてあげるんです。この子が寂しくないように。人間らしく生きられるように、いいことも悪いことも、楽しいことや色んなことを、僕がきっと・・・・・・」
「話にならない」
「な!?」
「そんな出来もしない戯言に、これ以上つきあっていられるか」
「僕は真剣です!」
「お前が言ったようなことを、そいつが望むとでも? 俺には、そうは思えない。お前は、そいつの一番じゃない。だから、お前の勝手な願望は、そいつには絶対に通じない」
「そんなこと、やってみなければ分からないじゃないですか! 僕だってキーシャがいてくれたから、だから僕は今・・・・・・」
「そいつは、お前とは違う。自分と重ねて同情するのはやめろ」
「君に何が解るんですか! 誰にも手を差し伸べられない子供の気持ちなんて、君に分かるわけがない!」
「間違えるな。お前の望みなど、そいつにとってはどうだっていいことだ」
「・・・・・・!?」
「どうしても譲れないと言うのなら、それでも構わない。俺は俺の仕事をする」
曲刀を握る腕が、真っ直ぐにアイルに向けられる。
「だが、知っているか。この世界のルールを決めるのは、正しいかどうかじゃない、その為に力を行使するかしないかだ。お前の駄々を通したいなら、力尽くで通してみるがいい」
「何を・・・・・・!?」
間髪入れず繰り出された曲刀の一撃を、寸前でアイルの展開した光盾が受け止める。
羽根の力が凝縮された打撃による衝撃が、アイルの腕から全身へと駆け抜ける。
威嚇などではない、渾身の一撃だ。
「やめて下さい! 僕は君と争いたいわけじゃありません!」
「甘いことを。だったら今すぐ手を引けばいい」
背丈ほどもあろうかという大刀から繰り出されるとは思えないほど素早い、そして重い斬撃が容赦なくアイルを襲う。
腕の骨が悲鳴を上げ、足の筋肉がガクガクと震える。
羽根の力を全て盾に回すことで何とか拮抗しているものの、少しでも気を抜けば、簡単に弾き飛ばされてしまいそうだ。
それでもアイルは歯を食いしばり、斬撃を受け続ける。
「出来ません、そんなこと!」
「駄々っ子め。警告はしたぞ」
頭上から振り下ろされる斬撃を、アイルは展開した盾でがっちりと受け止める。
が、曲刀の先に、それを握る者の姿が無い。
「!?」
次の瞬間、アイルの両足を鋭い蹴りが襲う。
「ガッ!」
ぐしゃりと何かが潰される嫌な音が脳内に響く。
踏ん張っていた足が床からもぎ離され、身体が水平に吹き飛ばされる。
壁に激突してから床に落ちたアイルは、ぶつかった衝撃で落下してきた破砕片を振り落としつつ、身を起こそうと身体をよじる。が、
「ぐうっ・・・・・・!」
激烈な痛みが足から脳天まで突き抜けて、くぐもった悲鳴が喉を鳴らす。
突っ張っていた腕の力が抜け、アイルは再び床に倒れ込む。
涙で滲んだ視界の端に、砕けて有り得ない方向に曲がった自分の両足が映った。
「・・・・・・こんなことで、僕を、止められる、なん、て、思わないで下さい、よ!」
これくらい平気だ。
アイルの内に在る炎の結晶は、この程度の怪我くらい、ものの数分で修復する。
完治まで待たなくとも、骨さえくっつけば、立ち上がるくらい何でもない。
痛みさえ我慢すれば、このままでも羽根のコントロールは出来る。
集中するのに、ほんの数秒・・・・・・。
だが、災厄の天使には、その数秒で十分だったのだ。
一度は繋いだ”橋”を、再び繋ぎ直すには。
「待たせたな。さあ、おいで」
災厄の天使が、子供に向かって呼びかける。
先刻のアイルのように優しくも温かくもない、冷徹な眼差しで。
それなのに。
ふらりと子供が頭を上げた。
確かめるような眼差しが、深淵色の瞳に向けられる。
ゆらりと立ち上がった子供の身体が、細く狭いバリケードの間を潜り抜ける。
災厄の天使待つの方へと、確実に。
「そんな・・・・・・!?」
信じられない光景に、アイルは大きく目を見開く。
アイルの手の中で、今にも災厄の天使に向けて放たれようとしていた光弾が、頼りなく輪郭を崩す。
「送ってやるよ。会いたい奴と、同じ所に」
「嘘です! そいつは君を殺すつもりなんだ!」
だが、差し出された手に向けて、子供は躊躇うことなく腕を伸ばす。
子供の身体の震えが止まる。
「ダメだ行くなっ!!!」
叫ぶと同時に、アイル手の中に瞬時に凝った力が、幾条もの光弾となって放たれる。
狙いも定めず放たれた光弾は、広間の中を縦横に駆け回り、天井や壁に大穴を穿つ。
災厄の天使を直撃するかに見えた数条には、その寸前で微細な刃の群れが襲い掛かり、食らい付く。
周囲に荒れ狂う羽根と羽根との力の奔流に、だが災厄の天使は全く注意を向けなかった。
せめぎ合う力の渦が腕を掠め赤い霧がしぶいても、眉ひとつ動かしはしなかった。
彼はただ、子供だけを見ている。
目の前に在る、小さな子供だけ。
白い腕が、小さな額に伸ばされる。
その手を避けるどころか、子供は更に一歩を踏み出す。
「やめろおぉぉぉ!!!」
叫びと共に放たれた眩い光芒。
光芒目がけて襲い掛かる光刃。
螺旋のように絡み合いながら食らい合う力と力の奔流に、床の白骨は砕かれ、壁材は無残に剥ぎ取られ、辛うじて残っていた調度品はバラバラ打ち砕かれ、弾け飛んだ外壁は立ち枯れの庭園を薙いで突き刺さる。
拮抗するかに見えた二つの力。
金色の光芒は徐々に青白い刃の群れを圧倒し、向かい合う二人に迫る。
だが。
二人を飲み込む寸前で、光芒は力尽きて霧散した。
滴となって消えゆく光の中で。
災厄の天使の白い指が、子供の額にそっと触れる。
刹那、天を仰いだ小さな姿は、青白い輝きに包まれ、そして。
とさり、と。
軽過ぎる乾いた音を立てて、災厄の天使の足元に崩れ落ちた。
「どう・・・して・・・・・・」
止められなかった。
何も出来なかった。
たまらずアイルは拳を握り込むと、思いっきり振り下ろす。
古くなっていた床材は簡単に割れ砕けて、尖った破片が飛び散った。
拳から滴り落ちた血は、すぐにパキパキと結晶化して固まっていく。
砕かれた両ひざの中でも、ミシミシと音を立てて骨が再接合されていく。
決して小さくない痛みと、虫が骨の中を這いずるような感覚さえ、今はどうでもいいと思った。
「出来なかったなんて言わせませんよ。君には出来たはずなんだ。その気になれば、その子を助けることくらい。それだけの力を、君は持っているんだから・・・・・・」
八つ当たりなのは分かっている。
災厄の天使は、与えられた任務を遂行したのだ。
むしろ、力尽くで止めてみろと言われて、止められなかったのはアイルの方だ。
そうと理解はしていても。
「僕は、君が嫌いです! 理不尽でも八つ当たりでも構わない。とにかく、僕は君が大嫌いです!」
どうしても、言わずにはおれなかった。
とにかく、ぶちまけずにはおれなかったのだ。
「それでいい」
たった一言。
何の感慨も無く言い捨てて。
アイルを顧みることもないまま、災厄の天使の足音が遠ざかっていく。
睨み付けていた床の穴が、じわりと滲んだ。
第十一話 嘘と真実と報告書
「こちらでしたかアイル様! 大事ありませんか!?」
災厄の天使が立ち去ってからどれくらい経っただろう。
ぼんやりと座り込んでいたアイルは、ゆるゆると頭を上げて、駆け込んで来た者に目を向けた。
「・・・・・・バイロ、どうしてここに?」
アイルの反応があったことにほっとした様子を見せながら、駆け寄ったバイロは気遣わしそうな瞳を向ける。
「聖堂に戻られた災厄様から、アイル様がここに居られるとの伝言を頂戴いたしましたので、急ぎお迎えにまいりました。ところで、その子供は・・・・・・」
バイロは、アイルの目の前に横たわっている子供の身体と、そしてアイルの手に握られている物とを見比べて、僅かに息を飲む。
非常時用の薬酒の入った小瓶。
「・・・・・・大丈夫です。この子には使ってません」
塔に来て最初に言われたことだ。
薬酒が回復力を与えるのは結晶と同化した命を持つ者に対してのみで、普通の人間が服用すればたちまち猛毒となるのだ、と。
それでも万に一つの可能性を、全く考えなかったと言えば嘘になる。
だが、手遅れだったのだ。
子供がとっくにこと切れてしまっていることは、確かめるまでもなかった。
バイロは小瓶を握り締めたままのアイルと子供とをもう一度見やったが、何かを問うようなことはしなかった。
代わりに。
「星焔様。見事に魔物討伐を果たされたのですね。おめでとうございます」
「・・・・・・」
「任務に多少の犠牲は、止むをえぬことです。あまりご自身を責められませんよう」
「・・・・・・」
「このような子供が魔物の被害者になるとは、いたましいことですが」
「・・・・・・! そうなんです!」
強い口調で、アイルは首肯した。
どんな形であれ、この子が魔物の被害者であることは間違いない。
決して、間違いなどではない。
アイルはもう一度、横たわっている子供の顔を覗き込む。
まるで優しい夢の中に遊んでいるかのような、安らかな顔を。
「バイロ、この子はどうなりますか。ちゃんと葬って貰えるでしょうか・・・・・・」
「どうでしょう。浮浪民の子供のようですから、難しいかも知れません」
市民でない身分の者が、どのように扱われるか。
アイル自身、知らないわけではない。
「何とかなりませんか。僕にはもう、それくらいしかしてあげられない・・・・・・」
「承知いたしました。アイル様のたってのご希望とあれば、丁重に扱われるよう尽力いたしましょう。それに、もう一つ申し上げておきたいことが」
バイロはアイルを励ますよう、微笑みながら。
「番人様のお力添えで、第四軍の負傷者は聖都の高等施療院へ搬送されることとなりました。もう間もなく搬送準備が整うことでしょう。これもアイル様が速やかに魔物を討滅して下さったおかげです」
「・・・・・・」
バイロの励ましに、アイルは黙って目を伏せる。
”魔物”を討滅したのは災厄の天使であって、アイルは結局、第四軍の彼らの為には何もしていない。
むしろ、彼らを酷い目に遭わせた張本人を、助けたいとすら願った。
だが、それでも。
「・・・・・・彼らは、助かりますか?」
助かって欲しいと思う。自分がそれを願う資格があるのかどうかは分からないが、それでも本当に、心からそう思う。
「後のことは施術医と、神のご加護に委ねてただ祈るのみです」
「・・・・・・そう、ですね。僕も祈ります」
『ご報告申し上げます。”姿なき魔物”の討滅が完了致しました。六位様、八位様ともにご健在。暴走の兆候はございません」
中央塔の雑事を統括する執務室で番人の長は、任務に随行者からの報告を受けていた。
「それでお二方は、今?」
『八位様はゼーレンの聖堂に戻っておられます。六位様は・・・・・・八位様に先んじて聖堂に戻られるなり強制転移の要請をなさいましたので、間もなく塔にご帰還なさるかと』
「強制転移の要請を?」
思わずといった様子で書類作業の手を止め、番人の長は通信珠にフードの奥の目を向ける。
通常、強制転移を使用するのは任地に急行する必要のある往路のみで、帰路は常設の転移門まで移動し、塔へと帰還する。
任意の地点から塔の転移の間へ跳ぶ設定は不可能ではないが、高レベルの座標精度が必要であり、術力的にもコストが高い。
実際に使用する側にしてみればコスト云々よりも、間違いなく目的地に跳べるかどうか。
目的地から外れるくらいならまだしも、何処とも知れぬ空間を彷徨うことになりはしないか。
余程でない限り、たまたま”事故”に遭う心配などしたくもないというのが本音だろう。
その例外とも言える一人が、災厄の天使だ。
塔に常駐することを好まない彼は、座標を組み込んだアイテムの携帯を条件に、多少の自由裁量を黙認されている。
が、それだけに、あまり大っぴらに目立つような真似はしない程度の分別は持っているはずだ。
その理由が「番人とのやり取りが面倒だから」であったとしても。
『上級天使からの開門要請を拒否することは出来ませんので』
災厄の天使に限らず、上級天使権限での要請に拒否は出来ない。
それは塔の存在意義に関わる規定であり、そこを否定してしまえば、塔の組織に矛盾を生じる。
誰も敢えて余計なことを伝えたりはしないだけで。
「咎めているのではありません。ただ、最近の座標誤差の発生率が気になっただけです。あの方もそれはご存知かと」
『もしかするとですが、番人様が後発で到着なされた折には、大きな誤差は生じませんでした。それ故に問題無しと判断されたのかも知れません』
「番人を遅行させたということですか、六位様の指示で?」
『はい。追加の装備が間に合わず、やむなくのご判断かと』
「・・・・・・そうですか、ご苦労でした。引き続き八位様の”警護”をお願いします」
幾つかの確認事項の後、番人の長は通信を終了する。
ぼんやりと発光していた通信朱が輝きを失ったタイミングを見計らって、執務室付きの侍従が飛び入りの面会希望者の来訪を告げる。
招き入れられたのは、今回の任で災厄の天使に随行した年若い番人だった。
表情を見るまでもなく、緊張が伝わってくる。
「急な目通りに応じていただき感謝の言葉もございません」
「前置きは不要。至急の用とは?」
「はっ。六位様のことにございます。先ほど強制転移にて帰還されたのですが、その直後に・・・・・・」
若い番人は一度唾を飲み込んでから、思い切ったように口を開いた。
「六位様は転移の間に到着なさるや、ご自身で操作盤をさわられて、お一人で何処かへ跳んでしまわれました。とっさのことでお止めする間もなく・・・・・・全ては私めの落ち度でございます。申し開きの仕様もございません」
報告を終えるや、若い番人はその場に平身低頭する。
状況を補足すべく、ビロードを内貼りした貴重品用の台を手に控えていた侍従が、一礼とともに進み出る。
「今回のご聖務は極力目立たぬことが望まれましたので、六位様は装備類を所持されぬ身軽な状態で任務に出られました。ただ、お戻りになる時も装備を番人にお預けになったままであったとのこと。その中に、これが」
台に載せられていたのは、一般天使用の身分証であるという以外、何の変哲もない銀色のメダルだったが。
番人の長は、フードの下の眉をひそめる。
刻印を確認するまでもない。
それは災厄の天使が私事で出歩く際の仮の身分証だった。
喫緊の問題は、それは転移門を起動する際の座標を特定する目印であること。
今回の任務の調整役である若い番人が、慌てふためくのも無理はない。
「まったく、」
しばし無言でメダルを見つめてから、番人の長はやれやれと肩を竦めた。
「六位様の気紛れにも困ったものですね。あの方の事ですから、じきに悪びれもせず戻られるでしょう。貴方の対応に落ち度は無かったと認めましょう」
「は。ありがとう存じます」
叱責覚悟で平伏していた番人は、見るからにほっとした様子で息を吐いた。
「六位様の件はこちらで引き受けましょう。他に問題がないようなら、任地に戻って八位様の支援を続けて下さい」
「はい、早速」
「それから、報告書にはどんな些細なことであろうと漏らさず記載するように。もちろん、貴方の塔への忠誠には、大いに期待しておりますよ」
穏やにしか聞こえない声の中に含まれるものを感じ取ったのだろう。
「そのご期待を裏切らぬよう、精一杯努めるとお誓いいたします!」
若い番人は襟を正し、しっかりと頷いた。
何も無い所だ。
暑さも寒さも無く、薄暗さも仄明るさも判然とせず、草地なのか石畳の上なのかも区別がつかず、足音すらどこかに吸い込まれて掻き消える。
ただ一つ気になると言えば、古い魔術の残り香のようなものがごく僅かに立ち上っていることだが。
複雑怪奇な魔方陣に埋め尽くされた白亜の塔の、あの灼き尽くさんばかりに神経を苛む光の洪水に比べれば、これなど仄かな蛍火のようなものだ。
別に、どこに行きたいと考えたわけではない。
適当に思い浮かんだだけの座標の先に、思いを馳せたわけでもない。
ただ、少し。
連中の前で”災厄の天使”でいることが億劫だった。
ほんの少し、息が出来る所に行きたかった。
それだけのこと。
(呆れたザマだね。いい気味だ)
そうでもなかった。
すぐ耳元で、何かが囁やく。
人間の気配は無いから、風の音がそう聞こえただけかも知れない。
(あれ、ボクが判らないの? 薄情だなあ)
でなければ、亡霊か何かだろう。
災厄の天使を恨む者を数え上げれば際限がない。
その中には多少声の大きい奴もいるだろう。
(亡霊、ね。もしかして後悔してるのかな? 魔物呼ばわりされた憐れな子を殺したこととか、さ)
どいつもこいつも、簡単に言ってくれる。
命を助けるだけなら、塔に収容するという方法も、確かにあった。
だが、魔物と認定を受けてしまった者は、普通に処分。良くてもせいぜい珍しい術式の生体サンプルとしていじくり回されるのがオチだ。
例え利用価値を認めさせたとしても、一個の人間としての扱いなど望むべくもない。
それは果たして助けたと言えるのか。
自分の手を汚したくないが為の、自己満足にしかならないのではないか。
失われてしまったものだけを、望んでいた子供。
それ以外、何も目に入っていなかった子供。
狂おしいまでに切望していたものは、この世界では届かない。
そもそもこの世界とは相容れない。
望みを手放させるしか、助けられない、矛盾。
助けると軽々しく宣言し、手前勝手な望みを押し付けるなど、傲慢以外の何物でもない。
(そっか。あの子は似てたね。たった一つのものを望んで、他の全てを平気で犠牲にするところ)
(キミにあの子の声が聞こえたはずだよ。世界でも人間でも、望みの前には全てを切り捨てられる、キミの本質こそ魔物そのものなんだから)
(意味なんてあるのかな? 壊れ残った記憶の中の、名前も顔も分からない人を探すなんてことにさ。あんなチャチな幻術にまで縋っちゃって。馬鹿みたい)
(ねえ。キミの想い人は本当に、この世界に存在している思うの? キミを利用するために番人どもが植えつけた偽りの楔だとは思わないの?)
(もういい加減諦めちゃえ! それで早くこっちへおいでよ。キミだって本当は、ずっと、そうしたいと思ってるんでしょう?)
馬鹿馬鹿しい。
(じゃあ、星焔の天使を挑発したのは何の為? 自分自身に言い訳出来るネタを提供してあげた、なんて言ったら笑うよ。”一生懸命がんばったけど、災厄に邪魔されて助けられませんでした。ボクは悪くありません”みたいな?)
知ったことか。
(たく、星焔ってヤツも大概ヘタレだね。攻撃特化って言えば聞こえはいいけど、逆に言えば防御がまるでザルなキミを相手に、攻撃の一つも当てられないんだから。いくらキミを殺せる力を持ってても、あれじゃ到底不可能だね。あーあ、残念!)
どうでもいい。
(どうでもいいなら、黙っててやることないじゃない。世界の正体、塔の役割、キミが何なのか、全部ぜーんぶぶちまけちゃえいばいいんだよ! そしたらあの子、どん顔をするかな? 楽しみだね!)
下らない。
あれも子供だ。
結晶の中に闇を宿しながら、世界の正義を信じて縋る子供。
世界を救えると本気で夢見る、憐れな子供だ。
だから、あれに言うことなど何も無い。
身の内に”炎の結晶”を宿す者は、それ故に薬酒に依存せざるを得ない。
塔を離れては、生きられない。
塔の方針と自らの在り方が反目したとしても、選択肢など有りはしない。
決まっているのだ、最初から。
いつかは運命に追いつかれるのなら、少しでも長く、信じたいものを信じていられる方が幸せだろう。
どうせなら、その”いつか”は、俺がいなくなってからがいい。
子供が泣くのを見て喜ぶシュミなど持ち合わせていないから。
(ふーん。どうでもいいってわりには、気にかけてるように聞こえるけど?)
何だ、心配しているのか?
俺が何かに心を移すと。
要らぬ危惧だ。
その時が来ればちゃんと、お前らに引き裂かれてやるさ。
だから、もう立ち去れ。
今はまだ、その時じゃない。
少し、眠りたい・・・・・・それだけだ。
目覚めた時には、こんなどうでもいい感情なんて、きれいさっぱり消え去っている。
大丈夫、きっとまだ、戦える。
ああ、一つだけ・・・・・・あの子供を見送った時、俺は名を告げただろうか・・・・・・。
(いいんじゃない? 憎むべき者の名前なんて、あの子には必要無いよ。あの子は会いたいものに会いに行ったんだから)
そうか・・・・・・会えるといいな・・・・・・。
その廃墟の存在を知る者は少ない。
かつて離宮と呼ばれる施設があった、遺棄されて久しいその場所を。
砕けて転がった瓦礫の表面は乾いた色へと変色し、触れれば脆く欠け落ちる。
それはまるで、かつてこの地を襲った災と破壊がいかに凄まじいものだったかを、無言で訴えているようだ。
しかし、それだけだ。
雲間から覗く細い月が照らす陰影の世界を、さらさらとした雪が押し包む。
この地で何が起こり、どれだけの運命が飲み込まれたのか。
伺い知れるものは、何も無い。
あの最期の日に立ち会った者にさえ、既に何の感慨も抱かせはしない。
その廃墟の一角に、陽炎にも似た青白い炎が揺れた。
頼りなげな炎はしかし、近付くものの気配に応じ、瞬時に激しく燃え上がる。
折り重り合った瓦礫の上、他者を威嚇する青白い炎が、図らずも浮かび上がらせたのは。
ほどけ散った長い黒髪。
雪がそのまま形を成したと見紛うような細い腕。
吹き寄せる雪に埋もれゆく、精巧な人形のような横顔。
青白い炎だけに守られながら。
否。
そこに在るのは。
自らの羽根の炎にすら近付くことを許さない、誰の手であろうと永遠に拒絶し続ける、酷薄な魂だ。
「いつまでも強情な・・・・・・」
ただ一言。
見下ろす者の唇から漏れ出でた呟き。
それは蔑みなのか、苛立ちなのか、失望なのか。
揺らめく炎の傍らに立った人影はそれきり沈黙し、風に舞う雪はその姿をも景色の一部と変えてゆく。
第十二話 希望に灯る火

それまでの僕がどこでどうしていたのか、何一つ覚えていません。
ただ、寒くてお腹が空いて身体中痛くて痛くてたまらなくて・・・・・・目の前のもの全てが憎かった。
夜を照らす篝火も、楽しそうな笑い声も、容赦なく鼻に侵入してくるスープの残り香も、遠くから眺めるだけで決して手の届かないもの全部、全部!
憎くて、悔しくて、情けなくて、腹が立って、恨めしくて、頭の中がぐらぐらして、目の前がぐるぐるして・・・・・・。
もしもあの時、差し伸べてくれる手が無かったら・・・・・・。
キーシャは僕の恩人です。
僕を見つけ、受け入れ、守り、全てを教えてくれた、かけがえのない大切な、たった一人の人です。
なのに。
どうしてだろう。
”見えない魔物”に出会った日まで、僕は思い出さなかった。白亜の塔に来てからただの一度も、キーシャの名前を呼ばなかった。
こんなに大好きなのに。
忘れるなんて、出来るはずがないのに。
どうしてだろう。
もしかして僕は、何か、大切な事を見落としてしまっているんだろうか・・・・・・。
「アイル、何かあった?」
ぼけーっと空中庭園の小道を歩いていたアイルは、呼びかけられて我に返った。
慌てて振り向けば、プラチナホワイトの髪の少女が、優しそうな女性の手をしっかり握り締めながら立っている。
「あ、セレネさん・・・・・・お早うございます」
言ってから、もうお早うという時刻でもなかったと思い直したが、セレネがその程度のことを気にするはずがなかった。
「・・・・・・ええと、僕、何かおかしいですか?」
「・・・・・・」
少し思案したかに見えたセレネは、女性の手をぱっと放した。
いかにも優しい姉か親しい筆頭侍女かという風情の女性だが、畏まって礼を取る物腰は間違いなく随従のそれだ。
ろ、目の前まで進み来たセレネは、アクアマリンの瞳を不思議そうに瞬かせながらアイルの瞳を覗き込んだ。
「いつもみたいに騒がしくない」
単刀直入にしてシンプルな意見だ。
「ええ? 僕ってそんなに騒がしいですか?」
不本意であるというニュアンスを込めて反論してみるが。
「ブツブツ言いながら報告書書いてたり、ブツブツ言いながら迷って歩き回ってたり、ブツブツ言いながらお菓子食べてたりしてる。あと、」
「ああ、はい、もうわかりましたから・・・・・・」
そんな風に見られていたのかと、アイルはガックリ脱力する。
「アイル、やっぱり変。・・・・・・任務でケンカ、した?」
「ど、どうして・・・・・・!?」
指摘されて、アイルは一瞬絶句する。
前回の任務で災厄の天使と真っ向から対立してしまったことは、バイロにさえ話していなかったのだが。
おっとりしていそうに見えて、なかなかに鋭い観察眼だ。
「ええと、ケンカとはちょっと違うと思うし・・・・・・どう言ったらいいのかな・・・・・」
アイルが塔に戻ったのは昨夜だが、見えない魔物の任務からは既に三日が経っている。
それ以来、とっとと先に帰ってしまった災厄の天使とは、全く顔を合わせていない。
もっとも顔を合わせたところで気まずいだけだから、それはそれで幸いなのだが、ではこの先ずっと無視していられるかと言うと、そんなわけにはもちろんいかない。
まったくもって、気が重い話だ。
「どっちが悪いの?」
言い淀んでいるアイルの態度を肯定と受け取ったらしく、セレネは重ねて問うて来る。
「それは、ええと・・・・・・」
自分が悪いとは思わない。
だが、あの子供の安らいだ顔を思い出すと、「災厄の天使の主張は絶対に間違いである」と言い切る自信が揺らいでしまうのも事実なのだ。認めたくはなかったが。
誰でもいいから、全部ぶちまけて相談してしまいたい。
セレネなら、きっと聞いてくれるはず。
だが、相談するには見えない魔物の真実を話さなければならなくなる。
そんなことをすれば、あの可哀想な子供の眠りは、永遠に妨げられることになりかねない。
(やっぱりダメだ。それだけは出来ないよ・・・・・・)
言葉を続けられずにいるアイルを、同じように眉間に皺を寄せながら、セレネは不思議そうに見つめ続ける。
「どっちかが悪い、どっちも悪い、どっちも悪くない・・・・・・・?」
「いや、え-と、その・・・・・・」
任務の詳細に触れずに説明する方法は無いものか。
考えあぐねるアイルを他所に、セレネは一つ頷くと。
「男の子って、よくわからない」
あっさりと結論付けられた。
「・・・・・・それは、そうかも」
あの野郎が何を考えているかアイルにだってさっぱりだし、それ以上に女の子の発想について行く自信はもっと無い。
同意されたのが嬉しかったのか、セレネはニッコリ破顔する。
つられてアイルも、笑ってしまう。
その時だ。
聞きなれた鐘の音が、アイルの耳朶を打つ。
「非常呼集・・・・・・」
いつものように考える前にタバタと走り出すのではなく、踏み出そうとした足が固まって動かなかったという様子でその場に立ち尽くしているアイルに、セレネは緩く首を傾げた。
「あ・・・・・・何だかハラ立ちますね。僕たちが仲良くするのを邪魔されてるみたいですよ」
セレネの視線に、アイルは慌てて取り繕う。
「一緒に広間まで行く?」
「いえ、転移の間に行きます。あの野郎はそうするだろうし、セレネさんとお話してて遅れたなんて知れたらイヤミ言われるに決まってますからね!」
気遣うセレネに無理やり明るい笑顔を作ると、アイルはその場を後にした。
が、すぐに足取りは重いものに変わる。
どんな顔をして災厄の天使の前に立てばいいのか、その覚悟は全く定まっていなかった。
「お前、何っで広間に来なかったんだよ!」
「な、何でって・・・・・・」
転移の間で所在無げに災厄の天使を待っていたアイルは、高らかな登場音楽が聞こえてきそうなほど颯爽と入って来た紅蓮の天使に、入って来た勢いのまま詰め寄られて、しどろもどろに後ずさる。
「鐘が鳴ったら即転移の間って災厄の天使の行動パターンは、君だって知ってるじゃないですか」
「それは時と場合によるんだよ!」
「時と場合って?」
「申し訳ございませんアイル様!」
こちらも息せき切って走り込んで来たバイロが、走って来た勢いのままに二人の傍らに片膝をつく。
「災厄様は急な任務で出られたとのこと。伝達が遅れましたこと、誠に申し訳ございません!」
言うなりバイロは土下座しそうな勢いで、深く深く頭を垂れる。
まだ微かに息を弾ませているところを見ると、本当に聞いたばかりなのに違いない。
「顔を上げて下さい、バイロ。どうせ何も言わずに出てったあの野郎が悪いに決まってるんですから!」
どこかホッとしつつ、アイルはバイロに立ち上がるよう促した。
「何だ、知らなかったのかよ」
アイルとバイロを見下ろして、紅蓮の天使は拍子抜けしたようにケッと息を吐く。
「ったく、ただでさえツラ見せねーくせに、今度は挨拶も無しにバックレかよ。フォローさせられる身にもなれってんだ!」
不機嫌を隠そうともせずひとしきり毒づくと、
「邪魔したなっ!」
それで気が済んだのか、紅蓮の天使はさっさと踵を返して、装備品を捧げて控える随従らの方へと足を向ける。
その背中を見送ってから、アイルは立ち上がったバイロに目を戻した。
「で、あの野郎がどこに行ったか聞いてますか?」
「いえ。伺っておりません。火急の件だったとしか」
「そう言えば、あの野郎って随従を付けてないんでしたっけ」
周りに他人を置きたがらない災厄の天使は、そんなところまで徹底している。
だが、そのせいで予定の管理がままならず、バイロは非常に苦労することになるのだ。
「ってことは、いつ戻るのかも?」
「はい、それも。事の次第が判り次第、ご報告申し上げます」
「ってことは、お前ヒマなんだ?」
「な、何ですかハビィ!?」
何時の間に舞い戻ったのか、後ろからヒョイと顔を出した紅蓮の天使に、アイルは心底驚いて跳び上がる。
「ハビエ様! か、紅蓮様だ。ったく、何度言えば覚えるんだよ」
言いつつ紅蓮の天使は、がしっとアイルの首に腕を回して逃げられないよう捕縛する。
「な、な、な、何するんですか一体!?」
「いいからいいから! どうせお前、任務に出る気で来たんだろ? だったら来いよ。一緒に楽しもうぜ!」
「紅蓮様、それは・・・・・・」
不意の出来事に面食らうバイロを一睨みで黙らせて、紅蓮の天使はアイルを引きずったまま、ずんずんと転移の間の中央に進む。
「お前の随従らは要らねーからな。ハッキリ言って、あいつら俺の好みじゃねーし」
「楽しむって、何を・・・・・・?」
「決まってんだろ! 狩りだよ狩り、魔物狩りだ!」
転移の間中央の円陣で、揃いの防具で身を固めた五人の綺麗どころ、もとい紅蓮の随従たちが、賑やかな主を出迎えた。
「で、どうしてこうなるんだ?」
転移門を抜けるや開口一番。
見渡す限りの田園風景の中で、険しい目つきの紅蓮が、誰にともなく吠えかかる。
「怯えた市民どもが群れ集う聖堂の中庭に颯爽と! 格好良く! ファンファーレ付きで登場するんじゃなかったのかよ!?」
そんなド派手な登場シーンに付き合わされずに済んだことをこっそり感謝しつつ、アイルは額に手を翳して遠景の街を見やる。
「最近、転移門が不安定なんだそうですけど、こんなに外れたのは初めてですよ」
緩やかな起伏の向こうに、灰色の岩塊のような街並みが広がっている。
「転移門が不安定だ!? ンなこと全然聞いてねーぞ?」
「これってもしかして、僕が飛び入り参加しちゃったせいなのかな・・・・・・」
「まさか。その程度でズレるほどヤワな代物じゃないはずだぞ?」
などと発言するあたり、紅蓮には思いつきで無茶な使い方をした前科がありそうだ。
「にしても、こんな所からどーやって格好良く登場するんだよ? 歩きか? 走ってか? 間抜けにも程があるぞ!」
「気にするところ、そこですか?」
「ああ? 何言ってやがんだよ? 大事だろ登場シーン。最初が肝心って言うだろフツー!」
力説されて、アイルはあいまいに頷く。冗談・・・・・・にしては目がマジだ。
街並みに目を戻したアイルは、あっと小さく声を上げる。
暗い靄に覆われた街並みの一角から、黒い煙がたなびいている。
それに、靄の様子も何だか変だ。
微細な点が、不規則に蠢いているような。
「あれ、もしかして魔物の眷属じゃないんですか!?」
「そのようだな。ったく、あんな細かいんじゃ小動物型か、虫型か。あーあ、どーせなら大物狩りが良かったなー。害虫退治なんてつまんねーしシュミじゃねーよ」
「そんなこと言ってる場合ですか! あ、そだ! 街道沿いならきっと馬停がありますよ! 馬で走ったら速いですよ!」
幸いにも、畑を突っ切って少し行けば、すぐに街道に出られそうだ。
が、街の入り口付近で足止めを食らった馬車が列をなして渋滞を作っているようで、そこを先に進むには強行突破が必要かもしれない。
「畏れながら申し上げます。星焔様の案もよろしいでしょうが、一度聖都に戻って再転位するのが良ろしいかと存じます」
慇懃に発言したのは、サポート役に同行して来た番人だ。
「それだと、またズレたりしませんか?」
「でしたら二手に分かれられてはいかかでしょうか。星焔様が街を目指して行かれる間に、紅蓮様方が再転位を試みられれば確実ではございませんか?」
「ですね。僕もそれがいいと・・・・・・」
「いや、ちょっと待て」
あらぬ方向に目を凝らしていた紅蓮は、ややあってニヤリと口元を引き上げると、アイルをはじめ一同を見回した。
「そんなかったるいマネしてられっかよ! それに、あっちにおあつらえ向きなのがあるぜ?」
「・・・・・・それって、ひょっとしてもしかすると、あれ、のことですかああっ!?」
素っ頓狂な声を上げるアイルの後ろで、紅蓮付きの随従らもあんぐりと口を開けている。
「な、面白そうだろ? 一度乗ってみたかったんだよな!」
一同の反応などこれっぽっちも意に介さず、紅蓮は格好のオモチャを見つけた子供のような、見ようによっては絶好の獲物を見つけたハンターのような、油断のならない笑顔で胸を張る。
さらに驚くべきは、それが決定事項であると受け止めた随従らの、立ち直りの早さだ。
二言三言の簡単な申し合わせだけで、五人はとっとと分担を決め、速やかに行動を開始した。
外見が良いだけでは紅蓮の随従など務まらない、ということだろうか。
「モタモタすんなよ! 俺たちも行こうぜ!」
「ええと、止めなくていいんですか?」
アイルは思わず、助けを求めるように番人を振り返る。
「塔の不利益にならない限り、お諫めする理由はございません」
(そんなテキトーでいいんだろうか?)
アイルが本気で心配したくなるほど、それはあまりにも素っ気無さすぎる応えだった。
街を襲った魔物は、拳ほどもある甲虫型の眷属を数多引き連れていた。
頑丈な角を向け大砲の弾のように飛来する甲虫の群れは、人間の姿を見つけたが最後、屋外であるならそのまま飛びかかり、屋内であれば窓だろうが壁だろうが突き破って侵入し、阿鼻叫喚の地獄を現出させていた。
逃げ惑う人影は、既に通りからほぼ一掃されていた。
聖堂をはじめいくつかの主要な建物は防御結界の展開に成功しており、運良くそこに居合わせた者や逃げ込めた者らを、辛うじて保護していた。
結界の無い家屋に立てこもった者達は、一番奥の部屋の隅で震えながら抱き合って息を殺し、災禍が自分たちの上を通り越して行くことを、ただひたすらに祈り続けていた。
街の防衛に当たっているのは、白亜の塔第三軍所属の中隊。聖別された武器を手にした衛士の精鋭部隊。それに、退魔ギルドに属する雇われ退魔士のパーティが数組。それぞれが各々のポジションを確保しつつ、健闘を続けている。
甲虫型の眷属は、一匹一匹であればさほどの強さは持っていない。退魔士ではない一般の兵士であっても、それなりの武器さえあれば、残骸の山を築くことは可能だ。
が、いかんせん数が多過ぎた。
後から後から集団でわいて出る甲虫は、どれだけ無残に潰されようも全く怯むことがない。僅かな油断を突いて跳びかかり、食らいつき、少しづつだが確実にダメージを与えて行く。
一度仲間と分断されたが最後、四方八方から群がり寄せる甲虫に、抵抗空しく飲み込まれてしまう。
街中で響いていた斬撃の掛け声は、徐々に悲鳴の渦へと変わり行く。
第三軍の羽根使いたちすらも、甲虫に阻まれて魔物の本体を見つけることが出来ないでいる。このまま眷属にのみ力を浪費し続ければ、いずれ力尽きることは明らかだ。
街から人の声は消え去り、凄惨な破壊の不協和音だけが席巻する。
そんな時だ。
ポォーッ ポォーッ ポォーッ!
血なまぐさい空気を切り裂いて響いたのは、力強い警笛の音だった。
身を縮めて隠れていた者が、顔を伏せて固く目を閉じていた者が、家族と抱き合い震えていた者が、思わず目を開け、音の方へと耳をそばだてる。
街の住人であれば、知らぬ者は無い。
港町から物資を輸送する目的で導入されたばかりの最新式蒸気機関車、「黒い雷」号。
その名を思い浮かべた途端、彼らは絶望的な気分になった。
きっと夢か、幻聴に違いない。
希望を求めすぎて、耳がおかしくなったに違いない。
この災禍の中、「黒い雷」号が当たり前のように走っているわけがないから。
だが、そうではなかった。
街路で奮戦を続ける天使や衛士も、警笛音を耳にした。
何事かと訝る暇も無く、彼らの視線の先を黒い巨体が駆け抜けて行く。
(・・・・・・あんなところに線路なんてあったか?)
街を良く知る衛士らは、己が目を疑った。
それだけではない。
後ろにぞろぞろと連なるはずの客車や貨車を置き去りにして身軽になった黒い車体は、軛から解き放たれた悍馬のように大きくジャンプしたり横倒しになりそうなほど傾いたりのアクロバット走行を披露する。
その煙突からは、もくもくとたなびく黒煙に代わって、きらびやかな黄金色の火の粉が噴水のように吹き上がる。
そして。
機関車の先頭には、火炎を纏った槍を翳して敢然と立つ、炎の化身の如き姿。
「我こそは白亜の塔の使者、神威の具現たる紅蓮の天使なり! 薄汚き魔物どもよ、我が聖なる炎に焼かれ、己が業悪を呪うが良い!」
朗々たる声に呼応するように街の五か所で同時に巨大な火柱が上がり、炎にまかれた甲虫どもは、欠片も残さず消え失せる。
高らかに響き渡る宣言と暗雲をも焼き尽くす眩い炎の輝きは、距離も遮蔽物も破壊の轟音もものともせず、街中全ての者に届いた。
第十三話 契約の魔物
「んー、イマイチ地味だったかなー」
次々と襲来する甲虫の群れを、炎槍を繰り出して掃討しつつ、紅蓮の天使は首を傾げる。
「地味って、何がです?」
「演出だよ演出! もっと派手な決め方があったんじゃねーかなー。これが夜なら空が一面炎に染まってすっげーキレーだったんだがなー。・・・・・・お前、どう思う?」
「・・・・・・十分派手だったと思いますけど」
棒読み口調で、アイルは応じる。
ハッキリ言って、そんなことは超どうでもいい。
この、魔の眷属だらけの街中を突っ走る機関車の上に、必死にしがみついている状況では。
街の手前で足止めされていた汽車を、強引な”説得”で接収したまではいいのだが。
一鞭入れれば走り出す馬ならともかく、火室の火を落とされた蒸気機関車が、即座に走り出せるはずが無い。
それ以前に機関車を走らせるには運転する者が必要なのだが、魔物だらけの街に一般人の機関士を伴うなど論外である。
初めて間近に見る機関車の黒光りする車体におっかなびっくり手を触れながら、どうするつもりかと思っていると。
『じゃあお前、動かす係な!』
『は!?』
当然のように押し付けられて、アイルは身体ごと紅蓮を振り返った。
『何でそう無茶振りするんですか! そんなこと僕に出来るわけないでしょう!』
見たこともないようなキカイを、教わる相手も無しに動かせなど、冗談にも程がある。
『馬ー鹿! フツーに動かしたら、コイツの吐き出す煙で真っ黒に燻されちまうだろーが! てかお前、”光の鉤爪”の使い手なんだろ。だったら押すなり引くなりテキトーにやりゃいーじゃん!』
動力機構など最初から無視して、羽根の力で動かせということだ。
『待って下さい! 僕そんな使い方したことないです。そもそも何で僕にやらせようとするんですか、君がやった方が早いんじゃないですか』
『ヤだね、ダサいしめんどくせ。随従の奴らは他に回しちまったし、残ったのはお前だけだし。ま、がんばれ!』
『だから、どうしてそうなるんですか!』
結局、紅蓮はそれ以上聞く耳を持たず、不本意にもアイルは汽車を動かす大仕事に挑戦せざるを得なくなった。
機関車の上によじ登ったアイルは、煙突の後ろの取っ掛かりにしっかりとしがみついて身体を固定すると、大きな手で上からがしっと車体を鷲掴みするところをイメージする。
気分はさながら、オモチャを振り回して駆け出す子供。
自分でも半信半疑だったのだが・・・・・・やってみれば出来てしまった。
ただし、余分な後続車両を切り離して来たとはいえ(文字通り切り離そうとする紅蓮を目撃した機関士らが、悲壮な顔で止めに入るという一幕もあった)これだけの重量物を動かすにはそれなりのパワーと集中力が必要で、余計なことをやる余裕など全くない。
少しでも気を抜けば、つんのめったり傾いたり横っ跳びしたり建物に突っ込みかけたりと、悲惨な状態になりかねない。線路の上を行儀よく走ることなど、もう最初から絶望的だった。
人の気も知らない紅蓮は、機関車がロデオ走行する度に、実に楽しげな歓声を上げていたが。
「お前、誰に向かって言ってんだ?」
流石に態度が露骨過ぎたか。
テキトーな返事が気に入らなかったらしい紅蓮は、ビッと火槍の先をアイルに向ける。
「え、えーと・・・・・・」
ここで対応を誤れば、機嫌を損ねた紅蓮にしつこく絡まれること必至である。何か誤魔化す話題は無いものか。
「君の華麗なパフォーマンスを夜に堪能出来なかったのは残念です・・・・・・と言うか、塔に来る前は僕、魔物は夜に出るものだとばかり思ってましたよ!」
「そりゃそーだろ。魔物は暗-いのが好きだからな」
「え? でも僕らに非常呼集がかかるのって、わりと昼間じゃないですか?」
「そんなの決まってるだろ・・・・・・」
魔物が夜に跋扈するというイメージは、間違いではない。
日中に出没する魔物がいないではないが、闇を味方につけられる夜の方が、より簡単に人間の恐怖を引き出せる上に、効率良く襲撃を重ねることが出来る。身を隠すのもずっと容易だ。
が、不審な事件が続けば、人々は当然騒ぎ出す。
殺人事件なら警吏や衛士の管轄だが、魔物の可能性が出てくれば、退魔ギルドか白亜の塔へ依頼が行く。
いや、どちらかと言えば、事件が起きた時点で速攻売り込みをかけるギルドが、依頼をさらって行くケースの方が圧倒的に多い。
ギルドに依頼するには、ある程度の料金を覚悟すべきだが、それに見合うだけの迅速さと確実さが期待出来る。相手が今回のように羽根でしか討滅することの出来ない殺戮の魔物だった場合、ギルドは速やかに白亜の塔へ要請を送る。事件の詳細を付け加えて。
一見二度手間のようではあるが、実は直接白亜の塔に要請するより調査の手間が省ける分早く対応してもらえるし、ギルドも仲介料が取れるので、誰も損はしないのだ。
だが、初動が遅れたり(責任者が無能で退魔代をケチってモグリに依頼するとか、下らない派閥争いや打算が絡む場合など)一連の過程のどこかで不備が生じたりすれば、魔物は好きなだけ殺戮を重ねて力を付け、姿を隠す必要も無くなり、白昼でも堂々と人間を襲うようになる。
そこまで育ち切っていなくとも、討滅寸前にまで追い詰めながら詰め切れずに取り逃がしてしまった場合、殺戮の魔物は決死の抵抗を試みる。我が身を永らえることよりも、残された時間で可能な限り一人でも多くの人間を道連れにしてやろうと、自らの存在力そのものを糧としてありったけの眷属を召喚する。
「つまり後先考えずに跳びかかって来る眷属の群れは、魔物の断末魔そのものってわけだ。それに慌てた連中が俺たち上級天使に泣きつくって寸法だな。夜中に追っかけっこを始めたとしても、お呼びがかかるのは、」
「早くて次の朝、ってことですね!」
「全く! 天使の質も落ちたもんだよな! 以前はこんなにしょっちゅう呼び出されたりなんかしなかったのに、かったるいったらありゃしねー」
「・・・・・・以前って?」
たかが半年でそんなに変わるものだろうかと、アイルは首を傾げる。
「ああ? 以前は以前だ」
アイルの意図を知ってか知らずか、紅蓮はあっさり言い捨てる。
「ンなことより、お前、大事な事忘れてね?」
「は?」
キョトンとするアイルに、紅蓮はムッとしたような一瞥をくれると。
「だから、口上だよ口上! 今の内に打っとかねーと、後で後悔しても知らねーぞ」
紅蓮が登場早々名乗りを上げた、芝居がかったアレのことだ。
「そんなこと言われても、あんなド派手な口上の後で僕に何やれってんですか。しかもこんな状況で」
大分慣れて来たとはいえ、細心の注意で機関車を走らせ続けているアイルは、いい加減肩で息をしながら反論する。
「それに、僕も災厄の天使も、口上なんて一度もやったことないですし・・・・・・」
「馬っ鹿だなー!」
必然性の無さを訴えようとしたアイルのセリフを、紅蓮はその一言で断ち切った。
「超ドライクール路線でとっくに売れてるヤツと比べてどーすんだよ? お前は知らなさそーだから教えてやるが、俺たちが主役の新作歌劇が封切りになる星祭りまで、あと半年ねーんだぞ。劇作家如きに一方的にウケ狙いなイメージ押し付けられたいのかよ?」
「・・・・・・そんなこと考えてたんですか」
主役と言っても、題材にされるだけで、実際演じるのは役者だし。
「おいハナで嗤わなかったか今!?」
「嗤ってません嗤ってません! ・・・・・・って、紅蓮、もしかして飽きてませんか?」
甲虫の群れを巻き込んで機関車の横を流れ去る火炎の渦が、先刻から鳥や動物などの形に似ていると思うのは、多分気のせいではない。
「ったり前だろ! 俺は狩りは好きだが、害虫退治なんかこれっぽっちもキョーミねーんだっての!」
その主張は、いかにも紅蓮らしかった。
「こんなことだったら、ザハトに来てもらえば良かったかな」
「誰だよそいつ?」
「僕の随従です、探索が得意な。魔物の居場所が判れば、こっちから殴り込みかけに行けるじゃないですか。災厄なんていつも一人で勝手に・・・・・・」
飛び出して行くんですよ、と続けかけて、アイルはつい言い淀む。
前回の任務をのことを、いつまでも気にしていても仕方がないのだが。
「俺は! 狩りを! 楽しみたいんだよ!」
そんなアイルの様子に何を思ったか、紅蓮がくわっと歯を剥いた。
「狩りってのはな、勢子が追い立てて、出て来た獲物を仕留めるもんだ。簡単に見つけて狩っちまったんじゃ、面白くも何ともねーんだよ! 断じて、俺があの野郎に劣ってるからじゃねーからな! 解ったか!」
どうやら紅蓮の探索能力に対する侮りと勘違いしたらしい。
それでなくとも紅蓮は災厄に対抗意識を燃やしている。
ここは穏便に、機嫌を直してもらうに限るのだが。
「勢子って、あの五人の随従のことですよね。もしかしてその為に、わざわざ君の羽根の力を分け与えてるんですか?」
つい、単純な興味の方が先に立った。
街の五か所から上がった火柱は、もう見えなくなっているが。
紅蓮の羽根と全く同じ気配の炎が、甲虫を焼き払いつつ、縦横に移動しているのはアイルにも判る。
「ああ。あいつらの武器に力の媒体となる宝玉を仕込んである」
面倒臭そうに、紅蓮は応える。
「俺が一人で、最大パワーで一帯焼き払ってもいいんだが、それじゃ面白くないからな」
面白いかどうかが、紅蓮には重要な基準であることは解ったが。
「焼き払うって、物騒だなあ」
羽根の力は基本的に人間を傷つけるものではない。が、力を無制限に解放したりすれば、その余波だけで街が壊滅的被害を受けかねない。
と言うか、面白くないと判断されたからいいようなものの、気紛れな思い付きで街を壊滅させかねない紅蓮の言動に、アイルはやれやれと頭を振る。
それはさて置き。
「ということは、君の分身が五人いるようなものですよね・・・・・・スゴいな」
アイルにそんな技が使えたら、バイロ達にかける苦労も少しは減らせるのではないだろうか。
「お前、本っ当ーにフツーの事に感動するのな」
「本当にそう思ったんだから、仕方ないでしょう!」
「・・・・・・ま、俺が凄いってのは事実だしな!」
呆れた様子の紅蓮だったが、アイルの裏表の無さに思い至ってか、すぐに機嫌良く胸を張った。
その時だ。
「・・・・・・あ! あそこ!」
「ん?」
「火ですよ!」
「それが?」
手にした火槍から絶え間なく火炎攻撃を繰り出し続けている紅蓮が、何を今更と首を傾げる。
「じゃなくて火事です! 本物の!」
街の数か所で燻り続けている黒い煙。その一つが、窓の割れる破壊音と共にぐわっと膨れ上がり、黒煙の奥から赤く不気味な炎が吹き上がった。
「俺が燃したんじゃねーぞ! こんだけ虫が暴れてりゃ、フツーに火事も起きるさ」
「君のせいだなんて言ってません!」
紅蓮の炎は火災を起こすものではなかったし、むしろ街に散った随従たちが眷属退治の片手間に火種から炎上する力を奪い取っていたから、到着した時に上がっていた火の手はかなり落ち着きつつあったのだが。
「あれを放っておいたら大変なことになります! 僕、ちょっと行って来ます!」
叫ぶやアイルは、右に左に蛇行しながら走る汽車の上から、ヒラリと身を躍らせた。
「行くって、おい、これどーすんだよ!」
「紅蓮、何とかして下さい! 壊したりしたら機関士さんたちが泣くと思いますんで、くれぐれも気を付けて!」
「だから、何で俺が!」
紅蓮の抗議の声を、アイルはキッパリ無視した。
「誰か! 誰かいませんか!」
もし逃げ遅れた人がいたら・・・・・・と思うと、いてもたってもいられずに。
もくもくと襲い来る黒煙に躊躇も無く、開け放たれた正面大扉から元は商館だったろう建物の中へと飛び込むなり、アイルは大声で呼びかけた。
そうして中に入ってみれば、炎と煙に包まれた外観のわりには、天井の高い一階部分は人が歩けないほど酷い状態ではなかった。
とは言え、建物自体がいつ崩落するとも知れないことに、変わりはない。
金色の手甲に覆われた左手を額の前に翳しつつ、肌を焦がすような熱い煙に満ちた廊下を、アイルは人影を探して進んで行く。
(炎を、小さくする・・・・・・炎から、燃える力を奪い取る・・・・・・)
光の手の圧力を利用して、熱気や煙ごと炎を包み込むようにして、抑え込む。
火炎系の技はアイルの得意ではなかったが、紅蓮の技に間近で接したことで、何となくコツが判った気がする。
直接炎を操るよりも効率は落ちるとしても、建物全体を呑みこもうとしていた火勢は、徐々に衰えを見せ始めた。
にもかかわらず。
胸の奥がじりじりする。
見えない者の手で全身を絞られているかのように息苦しい。
自分でも良く解らない焦燥感に突き動かされて、アイルはとにかく真っ暗な奥を目指す。
「誰も・・・いませんか・・・・・・」
進みながら何度も呼びかけてみたが、建物のどこからも、応えは無かった。
「何やってるかな、僕・・・・・・」
よく考えれば、建物内に人が取り残されている根拠など、全く無かった。
燃える館を目にした途端、居てもたってもいられなくて、考える前に身体が勝手に動いていた。
別に、初めて火事を見るわけではないのに。
(紅蓮の炎を見たせい、かな・・・・・・)
綺麗な炎だった。
美しく、力強く、手を伸ばしたくなるほど温かい。
口ではどれほど悪ぶろうとも、紅蓮が操るのは聖なる炎だ。
火災の炎とは、全く違う。
あらゆるものを飲み込み破壊する凶悪な炎、全てを無かったものにする魔物の力のような炎とは。
(いいや! もう、出よう! こんなところに長居しても仕方ない・・・・・・)
誰かを見つけることは出来なかったが、少なくとも火を消すのには成功したのだから、ここから延焼して被害が広がる心配は無いはずだ。
ひとつ頷いて、アイルが踵を返そうとした、その時。
薄暗い廊下の先、床すれすれの低い位置で、何かが動いたような気がした。
「・・・・・・! 誰か、いるんですか!?」
慌てて駆け寄ってみれば、廊下の突き当たりの大きな扉の前に、煤まみれの黒い塊がうずくまっていた。
手足を折り曲げた、人間の形。
「しっかりして下さい! 大丈夫です! 僕があなたを助けますから!」
アイルの呼びかけに反応してか、黒い人影はゆらりと頭を持ち上げた。
「さあ、こっちに!」
だが、アイルの手がその人物に触れようとした瞬間。
「サワルナ!」
いきなり伸びてきた腕が、アイルの手を激しく払った。
「な・・・・・・!?」
思いもよらぬ反応に、アイルの身体が凍り付く。
「サワルナ! ヲレニサワルナ!」
「僕は何もしません! あなたを助けたい、それだけです!」
「嘘ダ、嘘ダ、嘘ダ! ダマサレルモンカ! オ前モヤツラノ同類ダ!」
もたげた顔の中で、灼熱色の眼だけが狂おしいほどに燃えている。
「何を、言って・・・・・・?」
枯れ木をこすりあわせたようなしわがれ声は続く。
「ヤツラハ騙シタ! スベテヲ奪ッタ! ヲレカラ奪ッタ! 家ヲ! 仕事ヲ! 財産ヲ! 家族ヲ! 娘マデ! スベテ! スベテ! アア! ナントイウ! アア! アア! アア! アアアアア!!!」
「!?」
その男は(男なのだろう、多分)、呆然と立ち竦むアイルに向かって、両手を伸ばした。
煤のように黒く、ゴツゴツとひしゃげ、立ち枯れた灌木のように細い、およそ人間のものとは思えない腕を。
「憎イ! 憎イ! アイツモ! アイツラモ! 嗤ッテ見テイタ連中モ、ミンナミンナミンナ殺シテヤルッ!!!」
「あなたが・・・・・・魔物・・・・・・」
今の今まで、魔力を感じられなかったのも道理。
男のその身体は、身の内に得ていたはずの魔力のほとんど全てを使い果たし、骨と皮ばかりの残骸と成り果ててしまっている。
その眼がアイルを映しているかすら定かではない。
そんな惨めな有様でありながら、眼光だけは爛々として。
ほとんど動けるはずのない身体を、尽きせぬ憎しみだけが支えている。
混じりけのない暗黒の憎しみだけが、朽ちる直前の腕を動かして、その場から動けないでいるアイルの喉元に向かわせる。
「あなたに何があったんですか!? あなたは、どうして、こんな・・・・・・」
不規則に震える手が、それでも確実に、アイルとの距離を詰めて行く。
「僕はどうしたら、あなたを救うことが出来ますか・・・・・・」
「ウ・・・・・・ア・・・・・・」
とっくに濁ってしまった目の奥に、一瞬、何かが閃いた。
が、それはアイルの願望に過ぎなかったのだろうか。
ズバッ!
アイルの頭上すれすれから繰り出された炎槍が、男の身体の中心を貫き、枯れ木を燃やすよりも簡単にその肉体を灰燼へと還す。
浄化の炎が消えた時、アイルの目の前には、何者かがいた痕跡すらも残されてはいなかった。
「馬っ鹿じゃねーのか? こんなヤツに、一言だって歌わしてんじゃねーよ!」
見上げれば、炎槍を一閃させて納めた紅蓮が、不機嫌極まりない顔でアイルを睨み付けていた。
「こんな残りカスでも、しっかり片付けねーと災いの種になりやがる。契約の魔物ってのは始末が悪いぜ」
「紅蓮・・・・・・彼は・・・・・・」
両ひざを折った格好のまま、アイルは縋るような目を向ける。
「人間だったんです。酷いことをされたって、怒って、恨んで・・・・・・でも、人間だったんですよ。なのに、何で・・・・・・」
「だからどうしたよ」
「!?」
「ちゃんと周りを見ろ! 仮にそいつの言い分が正しかったとして、そいつのしたことは妥当だと言えるのか? 正当化出来るのか? そいつはな、自分の執着と引き換えに、この街の住人、いや、この世界に生きる者全てを虐殺することを選んだんだぞ!」
「・・・・・・契約の魔物・・・・・・まさか、それって・・・・・・」
「自分の望みと引き換えに、魔物に生まれ変わることを承諾した人間の成れの果てだ」
「!」
全身を酷く打ち付けられたような衝撃に、一瞬、頭の中が真っ白になる。
予想していなかったわけではない。
あの目を覗き込んだ瞬間に、理解ってしまったこと。
だからこそ、どうしても否定したかったことだ。
「でも、それじゃ・・・・・・僕は、何から、誰を守ればいいんですか・・・・・・人間が魔物になるのなら・・・・・・人間が人間を裁くことなど許されない・・・・・・」
「ハッハッハ! そりゃ大した冗談だ!」
その途端、紅蓮は腹を折って笑った。芝居じみた、大げさな仕草で。
「あいつらは魔物で俺たちの敵だ。そして俺たち上級天使は、敵を殲滅すべく神の力を与えられた選ばれし者。人間だって? そんなわけないだろう! あんな惨めで弱っちい生き物なんかと一緒にするんじゃねーよ! 不愉快だ!」
「そんな・・・・・・!」
「違うなんて言わねーよな」
ギラリとした瞳がアイル捉える。
琥珀の眼光が、容赦なくアイルを射抜く。
「お前は、俺たちの仲間だよな」
第十四話 聖都の風景
「あ、あれ? ここは・・・・・・?」
石造りの白い建物が立ち並ぶ街の、真っ直ぐに伸びた大通りの真ん中で、アイルはキョトンと目を瞬かせる。
「ええと、僕たち塔に帰るはずでしたよね、バイロ・・・・・・バイロ? セルジオ? ザハト?」
身体ごと振り返って見回してみたが、背後に控えていたはずの三人の随従の姿は、影も形も無い。
「冗談・・・・・・」
で、隠れている可能性は皆無だろうし、そもそも隠れる理由が無い。
「・・・・・・何がどうして、こんなことに?」
何度見回してみても、隊列が横隊で行進出来るほどの広い広い凱旋通りの真ん中に立っているという事実に変わりはない。
初めての場所に、アイルは更に目を凝らす。
通りの左右には柱とアーチで構成された回廊が巡らされている。
回廊の要所要所に翻る旗の一枚に目を止めると。
「三叉の矛に翼!」
描かれていたのは白亜の塔のシンボルモチーフだ。
その次の旗には”三叉の矛に三対の翼”の中央に”日輪”をあしらった紋章。さらに”虹の橋”、”聖樹冠”と、上級天使を表す紋章旗が続く。思わず自分の”光芒を曳く星”を探したが、”夕雲”、”雪華晶”、”交差する三日月”の次は塔のシンボル旗に戻ってしまった。
「そう言えば、僕らのお披露目は星祭りの日なんだっけ・・・・・・」
白亜の塔最大の祭事が、夏至に挙行される星祭であり、その日を過ぎなければ自分はもちろん、紅蓮の旗も飾られはしないのだ。
少しばかり落胆しつつ、そのまま旗の列を追って大通りの正面方向に目をやったアイルは、回廊すら見下ろす高い位置に広く張り出したバルコニーと、その後背に幾つもの尖塔が聳える様を目にした。
その形状には、見覚えがある。
それは、アイルがリザという名の羽根使いに連れられて、初めて白亜の塔にやって来た日。
丘の中腹から見下ろした景色の中、「あれが目指す聖都だ」と指差された街の中央で、宝石のように白く輝いていた白亜宮の尖塔群。
(ってことは、ここはやっぱり聖都なんだ・・・・・・)
ぽかんと口を開けたまま、アイルは塔を見上げる。
少し距離があるとは言え、彼方から見下ろすのと足元から見上げるのとでは、その迫力には雲泥の差がある。
今更だが、白亜の塔に上ってこの方、アイルは聖都の街を歩いたことがなかった。
あの丘からの眺望は、初めて聖都に赴く者に対するリザの配慮だったのだろうが、その後は街に入ることなく転移門から直接塔の内部へと連れて行かれたし、数々の任務でも常に転移門を使用していたから、聖都に居るという実感はあまり持てずにいたのだ。
(ん・・・・・・?)
お上りさんよろしくぽけっと見上げていたアイルの耳に、浮き立つような音色が飛び込んで来た。
音の方に目を向ければ、沿道にはちょっとした人だかりが出来ていて、アコーディオンの演奏に合わせて、カラフルな衣装のピエロが宙返りを披露しているところだった。
その足元では、キラキラした上着に三角帽子を被った犬が、後足立ちで器用に玉乗りをしていた。
人だかりの向こうには、路上に置いた小卓に色とりどりの小石を並べた幸運の呪い屋や、人相見、護符売りなどの小さな露店がずらりと並び、その合間を縫って花売り娘が笑顔を振りまいている。
香ばしい匂いにつられて首を巡らせれば、反対側の通り沿いには串焼き肉や蒸し饅頭、砂糖をまぶした揚げ菓子に、フィッシュフライを包み込んだ薄パンに、山盛りにしたリンゴを売る店など、手押し車一つ分の屋台が整然と列を組んで並んでいて、道行く客を相手に談笑したり、安いよ安いよと売り込み攻勢をかけたり、はたまた口角泡を飛ばしての値段交渉を繰り広げていたりする。
(・・・・・・何だか想像してたのとイメージ違うな。聖都ってくらいだから、街ごと修道院みたいなのかと思ってたのに。それとも今日はバザールの日か何かかな?)
フラフラと屋台の一つに近寄った途端、朝ご飯からこっち何も入れていなかったアイルのお腹が、ぐうーっと大きな音で鳴る。
(しまった、任務帰りだったんだ)
当然のことながら、アイルに小貨の持ち合わせなど無い。
(と言うか、僕はどうしてこんな所にいるんだろう?)
最初の疑問に立ち返り、アイルはむうと眉根を寄せた。
甲虫の魔物を退治し終えて聖堂に戻ったアイルを待ち構えていたのは、渋い顔をした随従の三人だった。
強引に紅蓮に連行されたとは言え、無許可で出て来てしまったのに変わりないのだから、当然と言えば当然の成り行きだ。
咎められることこそ無かったが、即刻塔へ帰還するよう促されたのもまた、当然の事だろう。
幸い、街からさほど遠くない教会神殿内に、常設の転移門が設置されていた。
そうしてアイルはとんぼ返り的に、空中庭園に向け三人の随従と転移門を潜った。はずだったのだが。
(ここが聖都なら目的地と大きく外れちゃいないんだけど・・・・・・やっぱアクシデントには違いないよな。とりあえず塔の見える方に行けば、何とかなるかなぁ・・・・・・)
「一つどうです?」
いきなりの、野太い親父の声。
と同時に、目の前に甘辛いタレのたっぷりかかった串焼きが差し出される。
苦りきったアイルの表情が、空腹でたまらないと解釈されてしまったらしい。
香ばしい匂いにアイルのお腹がもう一度ぐうぅーっと音を立てる。が、
「あ、ありがとうございます。でも、それには及びませんので・・・・・・」
アイルの感覚では、貧しい者が食べ物を分けて貰うのは当たり前だが、かなり恵まれた環境にある自分が何の見返りも差し出さずに物を貰うのは、何かが違うように思えるのだ。
辞退しようとしたアイルは、ふと、自分の袖口に目を落とす。
銀色の飾りボタンは、お金の代わりにはならないか。
(ダ、ダメだダメだ! これは僕の物ってわけじゃなくて、上級天使としての装備品なんだから! 飢えてどうしようもないってのならともかく、ちょっとお腹が空いたくらいで好きにしていい物じゃないんだから!)
アイルはギュッと目をつぶってブルンブルンと頭を振ると、決死の思いで誘惑を断ち切って歩き出す。
が、いくらも行かない内に、アイルはいきなり腕を掴まれ、そのままぐいっと引っ張られる。
(わ! もしかして、スリ?)
こんな賑やかな場所で、お上りさん丸出しでフラフラしていれば、それはどうぞ狙って下さいと言っているようなものである。
たとえ持ち合わせが無くとも、アイルの着ている服は一目で上等な物だと判るし、ふんだんに使われている飾りボタンや飾り紐などをむしり取って行くだけでも、いいお金になりそうだ。
しかし、振り払おうとした腕を、アイルは途中でピタッと止めた。
何故なら、アイルの腕を掴んでいたのは、小柄な老婆だったからだ。
目が合ったアイルに、老婆は邪気なくニコーッとほほ笑むと、
「クルト!」
嬉しそうに、名を呼んだ。
「あの、お婆さん?」
「私だよ、クルト、おっ母さんだよ。ずっと待っていたんだよ!」
「え、えーと。すみません、僕はクルトって人じゃないです」
しかし老婆はアイルに耳を貸すことなく、ぐいぐいと引っ張って行こうとする。
「さあ、家に帰ろうね。お腹空いたろう? お前の好物をいっぱい作ってあげようねえ」
思い込みの力はなかなかのもので、簡単に振りほどけそうにない。
「ちょっと待って下さい、僕は・・・・・・」
「よせよ婆さん! そのお方はお前の息子なんかじゃねーよ!」
声と同時に、老婆はドンッと突き飛ばされて、石畳の上に転がった。
「おお、クルト! クルト!」
「だから違うってんだろ!」
石畳に這いながら尚もアイルに手を伸ばそうとする老婆を、集まって来た男らが怖い顔で取り囲む。
「待って! 乱暴なことはやめて下さい! 単に人違いなだけですから!」
足を振り上げた男の前に、アイルは慌てて割って入った。
「ですが、そいつは・・・・・・」
「ほら、クルトだよ。やっぱりクルトだよ!」
「すみません、そうじゃないです」
にじり寄る老婆に向けても、アイルは申し訳なさそうに拒絶する。
このまま押し切られても、ややこしくなるだけだ。
「このババァはいつもこうなんだ。ガツンと言ってやらなきゃ判らなねぇんですよ!」
「だからって、そんな暴力は・・・・・・!」
「何だ、この騒ぎは!」
割って入った居丈高な声に、輪になっていた人波がざっと左右に分かれる。
老婆を囲んだ男らも、ホッとした表情で場を譲る。
「聖都の治安を預かる第五軍である。騒ぎの首謀者は疾く名乗り出よ!」
割れた人波の向こうから姿を現した青年が、高圧的な視線を周囲に向ける。
が、その視線がアイルの上に止まった途端、青年の眼がはっきりと丸くなる。
「お前、じゃない、貴方は・・・・・・」
「ああっ! 君はあの時の!」
忘れもしない。青年は、見えない魔物の任務に同行した探索班の一人だった。
「で、星焔の天使様がこのような所にお一人で、一体何をしておられたんですか」
「えっとそれは・・・はふはふ・・・美味しいですねコレ!」
青年に連れて来られたのは、大通りから少し入った所のごく庶民的な宿屋件食堂で、その一番奥のテーブルで、アイルはほかほかと湯気の立つスープを掻き込むのに余念が無かった。
「・・・・・・まあ、ここの豆のスープは絶品だって評判だから」
青年がこの場を選択したのは、群衆の中にあのままアイルを置いておくわけにもいかず、かと言って事情も知らずに対処も出来ずという状況での苦肉の策だった。
幸い営業時間外とあって、二人の他に客の姿は無い。
「ですよねっ! このパンも美味しいです!」
スープに浸したパンを口に放り込んで、アイルはとろけるような笑顔を浮かべる。
「お口に合ったなら何より・・・・・・」
「あ、えっと、聞いてます聞いてます! 僕が何をしてたか、ですよね」
げんなりしている青年に、アイルは手短に事の次第を話す。と言うか、元々大して長い話ではない。
「・・・・・・というわけで、だから、たまたま、偶然、話しかけられたのがあのお婆さんだったんです」
「たまたま偶然が、何で俺が見回り当番の日なんだよ・・・・・・」
不機嫌を隠そうともせず、青年は水代わりの薄めたぶどう酒を一気にあおる。
「おかげで助かりました。それと、ここのお代は後できっと払いますから」
「要りませんよそんなの。第一、この聖都で上級天使様からお代を取ろうなんて輩がいるものか」
「え? でも僕はまだお披露目前の新人ですよ? そんな知名度があるとは思えませんが」
「ここは天使様の為の街です。貴方が”星焔”様とは知らなくとも、上級天使だということは、誰だって見た瞬間に判ります」
「そうなんですか!?」
青年はアイルの服に付けられた、三対翼の紋章を指す。
「天軍の紋章を無断で使うのは犯罪です。特に二対翼の羽根使いや、三対翼の上級天使の紋章となれば、不敬の罪で死を賜っても不思議ではない。この聖都に、そんな度胸のある馬鹿はいませんよ」
「・・・・・・」
理由は解ったが、暗に自分が馬鹿と言われているようで釈然としない。
「他にご質問は」
問われてアイルは、はいっと手を上げる。
「君の名前を、まだ教えて貰ってないんですけど」
「・・・・・・下々の名前なんか聞いて、どうなさるんですか?」
ただでさえ取ってつけたような敬語が、さらにつっけんどんなものになる。
「どうするって、名前が分からないと呼びにくいですし・・・・・・それとも聞いちゃいけないことでしたか? 僕、塔や聖都の事情がまだ良く解ってなくて、それで失礼してしまったなら謝ります」
知ってか知らずか、アイルはどこまでも真面目に首を傾げる。
こういう邪気の無い相手に、何かを察しろとは言うだけムダだと早々に判断出来てしまう辺り、青年はなかなか賢明だった。
「・・・・・・いえ。ジェドって呼ばれてます」
何だか色々と諦めた顔で、青年は応える。
「ジェドですか。いいお名前ですね。あ、申し遅れました。僕はアイルって呼ばれてます。でも、本当の名前はアレキサンデルなんで、皇帝陛下って呼んでくれても全然構いませんから」
「・・・・・・」
「うーん。やっぱりウケませんか」
押し黙ったジェドに、アイルはえへへと笑って見せる。
「てことは、それ、他のヤツにも・・・・・・?」
お気楽太平なアイルに、たまらずジェドがツッコミを入れる。
仮にも天下の上級天使様が、庶民的な出自を堂々とアピールするのはどうかと思う。
「だって君、この前の任務の時に、僕の事を流浪民のガキ扱いしたじゃないですか」
この邪気の無さが小憎たらしい。
「でも”留まる者”には同じように見えるでしょうけど、流浪民にも色々あるんですよ。僕の家族は”根の無い草の民”って言って、一言で言えば、特技を持った人の集まりです。金細工師とか手品師とか占者とか、他にも色々と。一生涯家族を裏切らないって誓って家長の許しが得られれば家族の一員になれて、名前とか出身とか本人が言わないことは聞かないのが決まりで、そして家長が許せば家族を離れることも出来ました。でも家族を離れても掟を守り通すのが条件で・・・・・・だから僕は、上級天使であるのと同時にあの家族の一員なんです。根の無い草の民であることに、誇りを持っています」
「・・・・・・それバイロに・・・・・・いや他の奴らに話しましたか」
「それが、どうもキッカケが無くて、まだ誰にも。バイロは色々と相談に乗ってくれますけど、マジメ過ぎるところがあるんで、ちょっと・・・・・・」
「その程度の分別は持ってられましたか」
「何か、引っかかる言い方ですね」
明らかに安堵するような含みに、流石のアイルも口元をへの字に曲げる。
「と言うか、君、丁寧語で喋るの、苦手だったりします? いいですよ、無理しなくても」
「苦手ではありません! ただ貴方の悩みが上級天使様らしくないどころか、塔に来たての新米羽根使いと同じ過ぎて、正直調子が狂ってしまうだけです畏れながら! まあ、あの時からそんな気はしてましたが」
「あ、ホントだ。今のはスゴく上手でしたよ!」
下手をすれば不敬罪に問われかねない問題発言をさらりと流され、ジェドはがくりと肩を落とす。
と、そこへ。
「ねえ、難しいお話は終わり?」
「え?」
「おわ!?」
不意に、お下げ髪の少女がテーブル越しにひょこんと顔を覗かせ、意表を突かれたアイルとジェドが、同時にざざっとのけぞった。
「まあ、レディに対して失礼ですこと!」
レディを名乗るには少々幼すぎる少女は、精一杯の気取った足取りで二人の前に立つと、スカートのすそをつまんでおしゃまなお辞儀をする。
「お初にお目にかかります。私、この店の主の一人娘で、デイジナと申します。以後、お見知りおき下さいませ」
「あ、はい。僕はアイルです。よろしくお願いします」
つられてアイルも、立ち上がって深々とお辞儀を返す。
「こ、こんな所に出しゃばって何やってるんだお前は! てかアイル様も、何を軽々しく挨拶など!」
「だって、挨拶されたら挨拶し返すのが礼儀だし・・・・・・あ、もしかしていけませんでしたか?」
アイルがここにいるのは、アクシデントの結果のお忍びである。名乗るのは得策でないかも知れない。
「あら、仕方ないじゃない。ジェドお兄様ったら、いつまでたっても天使様を紹介して下さらないんだもの」
「だからってだなあ、」
「お兄様? じゃあ、君はここの」
「関係無い! こいつがノリでそう呼んでるだけだ!」
「ねえ天使様、お聞きしてもいいですか?」
怖い顔で睨み付けるジェドをキッパリ無視して、デイジナはアイルの前で小首を傾げる。
「はい、何でしょうか」
「天使様は初めてのご聖務で、狂暴な魔物を一瞬で退治してしまわれたんでしょう?」
「は?」
「その後のパーティで踊られた領主のお嬢様って、美人でした?」
「はい?」
「誰にも探し出せなかった”見えない魔物”って、どうやって正体を暴かれたんですか?」
「!」
見えない魔物と聞いて、アイルはドキリとする。
「天使様は災厄様とご一緒されるんですよね。災厄様がお忍びで街に出られて強盗団を退治なさった瞬間は、ご覧になりました?」
「え、ええっ!?」
そんな話は初耳だ。というかイメージが違い過ぎる。
「雪華様のアクセサリーが本物の雪の結晶で出来ているって、本当なんですか?」
「さ、さあ・・・・・・?」
女性のアクセサリーなど、アイルに分かるわけがない。
「紅蓮様が汽車で街中パレードなさったって、ご存知ですか?」
「何でそんなことまで!?」
遠い街でつい今朝がた起こったばかりの最新情報を、どうしてデイジナが知っているのか?
「それ、もしかして彼から?」
「まさか!」
「ジェド兄様が教えて下さらないから、こうして直にお伺いしているんですわ」
デイジナは恨めしげにジェドを見やる。
「いい加減にしないと叩き出すぞ、デイジィ!」
「ジェドお兄様こそ! さっきから聞いていれば、天使様に向かって失礼過ぎませんこと? そんなだからいつまで経っても地味なお仕事しかさせてもらえないんですわ。少しはバイロ様を見習った方が良いのじゃなくて?」
「お前に言われる筋合いは無いぞ! 大体何だそのマセガキ丸出しの喋り方は!」
「あら、これくらいレディとして当然ですわ。そんなこともご存知ありませんの?」
「二人とも落ち着いて下さい。と言うかジェド、こんな可愛いお嬢さんに失礼は良くないと思いますよ」
歳の差も立場の差も何のその。正面切って火花を散らす二人に、アイルは横から口を挟む。放って置けば、延々喧嘩が続きかねないので。
「まあ! 天使様は本当に礼儀正しくていらっしゃいますのね。ステキですこと! ねえ、天使様、私とお付き合い下さいませんか?」
あんぐりと口を開けるジェドを他所に、デイジナはアイルに向けて最強の必殺技を繰り出した。
第十五話 天使の街
「デ、デ、デ、デイジィ、お前、言うに事欠いて・・・・・・!」
「あら、何かおかしい? 天使様のようなお方を前にしたら、女の子ならみんな同じことを言うと思うわ」
デイジナがアイルに対していきなり放った「お付き合いしましょう」宣言に、ジェドは大いに慌てたが、当のデイジナはしれっとしたものだった。
「・・・・・・いやいやいや、まず”お友達になりましょう”ってとこから始めるのがセオリーってもんだろ」
「ダメよ! そんなノンキなこと言ってたら、どっかの誰かに先を越されちゃうじゃない! それじゃ全然意味ないわ!」
「先を越すも何も、お前一体いくつだよ?」
「恋に年なんか関係ないわ」
「いや、無くはないだろ・・・・・・」
「あの、ちょっといいですか?」
すっかり外野に放置されてしまっていたアイルが、二人の会話に割って入る。
一応、お付き合いを申し込まれた当事者なのだし、アイルにだって発言権はあるだろう。
「デイジナちゃんは、僕のことが好きなんですか?」
アイルは身を屈めて、デイジナに視線を合わせる。
「もちろんです! 天使様を好きじゃないコなんて、いるはずがありませんわ!」
デイジナは身を乗り出して力説する。
「それはつまり、僕が天使だから好きだってことですよね」
「それがどうかしまして?」
(正直だなあ)
躊躇の無いデイジナに、アイルは内心苦笑する。
「じゃあ、天使じゃない僕だったら?」
「そうね。嫌いではありませんわ」
「では、天使な所以外で、僕のどこが好きですか?」
「え、ええと・・・・・・」
ここで初めてデイジナの笑顔が固まる。
「ですよね。僕もデイジナちゃんのことを良く知りません。でもそれだと、後で困ったことになりませんか?」
「困ったこと?」
「そう。僕と付き合うって決めた後で、僕よりもっと魅力的な天使に会ったら、後悔したりしませんか?」
「それは・・・・・・」
その時はその時なのだが、流石のデイジナも本人を目の前にして正直に答えるわけにはいかないと思った。
あまり不誠実だと、お付き合いどころか速攻嫌われてしまうかも知れない。
「だからね、やっぱりお友達から始めるのがいいと思いませんか?」
「ええと・・・・・・」
「ダメですか?」
文字通り天使の微笑でニッコリされて、デイジナは心持ち頬を染めながらコクンと頷いた。
「ああ、良かった。では改めて初めまして、僕はアイルっていいます。天使じゃなかった時はアレクって名前だったんで、そう呼んで下さってもいいですよ」
「あ、はい。デイジナです。ジェドお兄様たちはデイジィと呼びますわ」
デイジナははにかみながら笑むと、差し出された手を握る。
場を丸く収めることに成功したアイルは、ジェドに向けてそっとウインクする。
(こいつひょっとして、天性のタラシじゃねーの?)
一部始終を目撃していたジェドは、内心そんなことを思ったが、もちろん口に出したりはしなかった。
「だったら! アイル様、これから一緒にお散歩しませんこと?」
「いいですよ」
「は!?」
唐突な提案を繰り出すデイジナもデイジナだが、あっさり頷くアイルもアイルだ。
「実は僕も、街の案内をお願いしたいと思っていたんで、正直有り難いです」
「まあ、それはよろしゅうございましたわ」
「何をいきなり勝手に決めてるんですか!」
無邪気に手を取り合う二人に、たまらずジェドが声を荒げる。
「何度も言いますが、ご自身の立場を少しはお考え下さい!」
アクシデントで来てしまったというのなら、早急に白亜宮に戻って指示を仰ぐのが妥当だろう。
それを、何をどう考えれば、のん気に物見遊山に興じられると言うのか。
上級天使に意見するなど、分を越えていることは百も承知だ。が、ここは言わずにはいられない。
「すみません、ジェド。でもこれは、大事なことなんです」
「こいつと遊びに行くことが、ご聖務よりも、ですか?」
「こいつじゃないし、遊びでもないわ」
デイジナの抗議を無視し、ジェドはアイルを真っ直ぐに見る。
「先刻君は、僕の悩みが羽根使いの新人と同じだと言いましたよね」
「それが?」
「僕もその通りだと思います。天の主が僕の何を気に入って上級天使にしたのかは分かりません。でも、選ばれたからには求めに応えるのが、この世界に生を受けた者の当然の義務だと思います。だからこそ、選ばれたことの意味を、いつまでも知らないままでいいはずがないんです」
「それとこれと、何の関係が?」
「直接は無いかも知れません。でも、先刻デイジナちゃんが言ってくれたこと・・・・・・天使を好きにならない人はいないって話について、君は何も言いませんでしたよね。それがこの街の、と言うか白亜の塔に集まる人々の当たり前ってことですよね? 僕はその当たり前である根本的なことを、理解出来ていない気がします。・・・・・・君からすれば、僕はきっと、お目出度い事を言ってるんでしょうね。僕達天使は人々を魔物から守ることだけを考えていればいいと、バイロも言うに決まってます。でも。人々の望むものが分からなければ、僕はずっと中途半端に迷ったままだと思うんです。だから今は、我儘を言う時だと決めました。キミには迷惑でしょうけどね」
(確信犯かよ・・・・・・)
半ば呆れつつも、ジェドは遮らずにアイルの言い分を聞く。
「今の僕の家族は、天使の仲間たちで、この聖都に暮らす皆さんで、そして魔物に苦しむ世界の人々です。大切な人たちのことを少しでも知りたいと思うのは、きっと、間違いじゃありません」
「だからって、何で今、ここでなんですか」
「だって、バイロはそういうことを許してくれそうじゃありませんし、君だったら立場至上主義みたいに僕のすること為すこと正しいなんて思わないでしょう? 初めて会った日だって、こんなシロートのガキに何が出来るんだって目で僕の事を見てたじゃないですか」
「いやそれは・・・・・・」
痛い所を直撃され、ジェドは渋い顔になる。
「あ、責任問題とかなら大丈夫ですよ。僕が未熟なのは周知の事実ですし、未熟なヤツが言い出したことだとしても、君の立場上、諌める以上のことは出来ないんですよね。だから”止めたけど聞く耳持ちませんでした”で押し通して下さいね!」
極上の笑顔で言われたその台詞は、どんな脅迫よりも破壊力がある。
「あ”ー」
ジェドは唸って天井を睨み付ける。
異を唱える権限は無くとも、止める手段が無いわけでもない。
それでも。
「ったく、何で俺が当番の日に・・・・・・」
天井を睨んだまま、ジェドは大きな息を吐くと、
「デイジィ、外套を二人分用意してくれないか」
「わあ、いいんですか!」
「いいも何も」
ジェドは大げさな歓声を上げるアイルをジロリと睨む。
「一時間だ。それ以上は一分一秒負からないからな。速攻、白亜宮に送還する!」
「二人分? って、ジェドお兄様も一緒なのぉ!? それじゃデートにならないじゃない!」
デイジナは不満そうに頬を膨らませる。
「当然だ。嫌なら来なくていいからな」
「行くわよ。もちろん行きますわ!」
「ついでに、そのお祭りみたいに派手なスカートは脱いで、普段着に替えて来い!」
「そんな! 酷い!」
「でなきゃ、留守番!」
「・・・・・・どうしても?」
「どうしても!」
真剣かつ熾烈な数秒間の睨み合いの後。
「はーい、分かりましたよぉだ!」
折れたのはデイジナの方だった。
ジェドは絶対に譲りそうにないし、ここで意地を張り過ぎてもアイルの心証を悪くするだけである。
と、判断すれば切り替えも早い。
「じゃあ、少し待っていて下さいね、天使様!」
ジェドに対する不機嫌な態度から一転、アイルに満面の笑顔を残して、デイジナはいそいそと店の奥に姿を消した。
「楽しみだなあ」
そんなジェドとデイジナの攻防を知ってか知らずか、アイルはワクワクした様子で席を立つ。
「アイル様、あまり不用意に窓やドアに近付かないように」
「どうしてです? 何だか賑やかそうですけど」
すかさず注意したジェドに、アイルは不思議そうに首を傾げる。
(何でこう自覚が無いんだ?)
あまりのん気さに、ジェドは思わず額に手を当てる。
(・・・・・・早まったか?)
ジェドは自分の判断に対する自信がグラつきつつあることを自覚する。
しかも恐ろしいことに、未だ一歩も店を出ていない。
店の主に目配せし、ジェドはアイルとデイジナを促して裏口から細い路地に出た。
角を幾つか折れて通りに出てみると、遠くに黒山の人だかりが見える。
「あれはひょっとして、デイジナちゃんのお店ですか?」
「もちろん、そうですわ」
「ああ、そうか。僕がいたから、あの人たちがお店に入れなかったんですね。悪い事しちゃったなあ」
折しも午後の一服時で、軽食を求めて来た客には迷惑だったことだろう。
「店が一軒閉まっていたところで、いくらでも他所がありますよ。それともまさか、中央広場の一件をお忘れではありませんよね?」
「・・・・・・それってもしかして、あの方たちの目当てが僕だったりってことですか!?」
言われてアイルはようやく納得する。噂が噂を呼んでしまい、アイルのことを一目でも見物しようと集まって来た野次馬というわけだ。
「さあ、見つからない内に早く行きましょ”アレク”様」
一番の晴着からよそ行き用のスカートに着替えて来たデイジナは、体形まですっぽり隠してしまうほどブカブカな外套の袖から僅かにのぞくアイルの手を取ると人だかりとは反対方向に引っ張って行く。
「ここは学生さん用の下宿屋やお店が多い通りなの。もうちょっとしたら帰って来た学生さんたちで賑やかになるわ。あの本屋さんは文字ばっかりの本しか置いてないけど、店の中には真っ白な猫が番をしているのよ。ねえ、こっちこっち! この広場の噴水の一番上の右側! 見える? あの羽根を広げた白鳥が私の一番のお気に入りよ! あっちの一段高くなった舞台ではね、お祭りの日にみんなで歌ったり踊ったりするのよ。新年の劇では私がお姫様をやったのよ、すごいでしょう! あのお店には大きな犬がいて・・・・・・」
時間が無いから、デイジナが好きなものを全部紹介しようと思えば、足も口もフル回転させる必要がある。通りに面した広場を抜けて広い馬車通りへと向かうデイジナの説明には、全く澱みがない。その合間にも道行く知人に会釈したり塀の上の猫や寝そべって日向ぼっこする犬を目ざとく見つけて手を振ったりしているのだから、デイジナのバイタリティは大したものだ。
「あ、あごヒゲおじさんが呼んでるわ。ちょっと行って来ますわね! アレク様とご一緒だと、すっごく人気者になった気分だわ!」
すっかり機嫌を良くしたデイジナは、つないだ手を見せびらかすように振ってから、通りの反対側へと駆けて行った。
「あのう、」
元気に駆けて行くデイジナを見送りつつ、アイルはジェドに声をかける。
「僕と一緒だったらって、どういう意味でしょう? それに何だか、先刻からずっと誰かに見られてるっていうか・・・・・・つまりその、もしかして、僕のことバレバレだったりします?」
「当然です」
まさかと思いつつ問うたアイルに対し、ジェドの応えはしごく明快だった。
「この辺りの者は古くからの住民ですから、そういったことには目が利くんです。もちろん学生らと違って礼を欠いた行動を取ることはありませんからご安心を」
「じゃあ、この変装はムダってことですか?」
ブカブカ過ぎる外套の下で、アイルは情けなさそうな顔になる。
「変装と言うより、お忍びだから察しろ、くらいの意味ですかね」
第五軍の制服の上にアイルと同じような外套を羽織った(もちろんアイルほどブカブカではない)ジェドは、軽く肩を竦めてみせた。
なるほど、直接アイルにではなくデイジナにばかり声がかかるのは、空気を読んだ結果というわけだ。
”アレク”の呼び名にしても正体を隠すためと言うより、塔の関係者に見咎められた時の言い訳(星焔の天使様だとは思いもよりませんでした、という)程度なのだろう。
「どこに行っても注目されるなんて、歌劇俳優にでもなった気分です・・・・・・どうしよう、手でも振ればいいのかな?」
真面目に考え込むアイルに。
「出来ればご遠慮願います」
住人が気安く近寄らぬよう目で威嚇中のジェドが素っ気無く答える。
「では、どうすれば?」
「周りなど気にせずやりたいようにしていればいいんです。彼らは天使様を見られただけで幸運だと考えますから」
「そういうものですか」
僅かに苦笑し、アイルは気を取り直す。
(それにしても、綺麗な街だなあ・・・・・・)
改めて周りを見渡し、アイルは心の中で感嘆する。
この界隈は庶民の暮らすエリアだということだが、明るく清潔な街並み、すっきりと歩きやすい通り、穏やかで幸せそうな人々・・・・・・美しい街と言うのなら他にも色々あったし、どう美しいかもそれぞれなのだが。今までに行ったことのあるどの街よりも、この聖都は際立って綺麗だ。強いて理由をあげるとするなら、人の住む場所には多かれ少なかれ存在する猥雑さのようなものが、この街には希薄な気がするのだ。
(教会のお膝元な教区都市とか、街ごと修道院だっていう”聖者の園”とかも、こんなカンジなのかなあ・・・・・・)
アイル自身は行ったことは無いが、以前ステンドグラス職人として教会地区を転々としていたという”家族”の話を思い出す。
(そう言えば、この辺りには聖堂とか教会堂って無いのかな?)
「お待たせしてごめんなさい!」
ぼんやりと考え込んでいたアイルは、息を弾ませたデイジナの声に振り返った。
駆け戻って来たデイジナの両手には、ほかほかと湯気を立てた揚げ菓子の串が二本、しっかりと握られている。
「あごヒゲおじさんが是非アレク様にって。噴水広場通り名物、蜜たっぷり串揚げ団子。とっても美味しいのよ!」
示されるままに通りの向こうを見やれば、車輪の付いた屋台の傍で恰幅の良い顎鬚男が、丁寧に一礼した。
「はい、これ!」
デイジナは香ばしい匂いのする一本を、ぐいっとジェドの眼前に突き出す。
ジェドは当たり前のように受け取ると、指先で印を切ってから、五つ並んだ団子の一つを口で抜き取って咀嚼し、ゆっくりと飲み下す。
「異常ありません。どうぞ」
アイルは差し出された串とジェドとを見比べる。
「ありがとうございます。でも、僕に毒見は必要ありませんよ?」
以前のアイルはあまり丈夫な方ではなかったが、それでも食当たりだけはしたことが無かった。それは”炎の結晶”のおかげだったのだろうが、要するに、毒見が必要ならアイルがやった方が合理的だ。
そもそもこの聖都に、上級天使に仇なすような不届き者が居るとも思えない。しかも、ジェドが厳重警備している目の前で。
「馬鹿なことをと、お思いですか? 俺の警備が節穴だと白状しているようなものだ、と?」
「い、いえ、そこまでは・・・・・・」
「実際、これは単なるパフォーマンスです」
「あ、そう・・・・・・」
あっさり認めたジェドに、アイルは拍子抜けして相好を崩す。
「本気で上級天使様を害そうとする輩がいたなら、この程度では到底防げないでしょう」
「え?」
アイルの表情が、半笑いのまま固まる。
「確かに聖都は天使によって管理された都ですが、逆にそのような行為に出られる者が居れば、相当の手練れだと予想されます。そんな者を相手に、俺の力がどこまで及ぶか・・・・・・」
「冗談、じゃないんですね」
「ご自身が何者なのか、何と戦い何のために存在するのか、常にお忘れなきよう」
「・・・・・・」
「そうすればこっちも大分、気が楽になるんですがね。随従など特に」
「え?」
「言われたことは無いですか。成程、あいつらしい」
「もしかして、君、バイロとは・・・・・・?」
以前バイロに聞いたところでは、ジェドら探索班のことはあまり知らないような口振りだったが。
「特に親しいってワケじゃないが、こーんなガキの頃から顔を合わせてりゃ、な」
「もう、ジェドお兄様ったらズルい! 一体いつまでアレク様を独り占めするつもりなのよ、折角のお菓子が冷めちゃうじゃない! さ、アレク様、こちらをどうぞ!」
と、割って入ったデイジナは、串から外した揚げ菓子をくわえると、キスをねだる格好でアイルの前に差し出した。
「お前また・・・・・・てか、そんなこと一体どこで覚えて来るんだ・・・・・・」
呆れたジェドは、額に手を当てて、頭痛が痛いのジェスチャー。
ふごふごふご!
口の塞がったデイジナの反論は「お兄様には関係ないでしょ」か、「これくらいみんなやってるわよ」あたりか。
ともかくデイジナの注意がジェドに移ったと見るや、アイルはデイジナの手に残った串から揚げ団子を一つ抜き取ると、ポイッと自分の口に放り込んだ。
「ありがとうデイジナちゃん、とっても美味しいです」
デイジナは揚げ菓子をくわえたまま「んんっ!」と抗議の声を上げたが、アイルに笑顔を向けられては、黙るしかなかった。
「それにしても、普段からこんなおいしいものが食べられるなんて、聖都はいい所ですよね」
アイルの感覚では甘いお菓子は贅沢品である。それが城内だけでなく、街中で気軽に売られているのだ。
「あら、お望みでしたらレモンのパイケーキやベリークッキーもおすすめでしてよ。ナッツクリーム入りの蒸し饅頭もいいですわね。ぶどうのジュースも試されませんこと?」
「う、うわあ・・・・・・」
聞いている内に、アイルの目にキラキラ星が浮かぶ。
「聖都の住人は元々、大陸各地からの移住者です。出身地の味にはプライド持ってる者はが多い。てか、何で甘いおやつばっかりなんだ? どうせ勧めるなら炙り肉入りの蒸し饅頭とか、白身魚のフライサンドとか、ガッツリ系も人気あるだろ?」
「あら、アレク様は甘いものがお好きなのですよね?」
「どうしてそれを?」
「好きな方のプロフィールくらい、一般常識の内です。それより、次は中央広場に行きましょうよ! きっとみんなこぞって献上に参りますわよ。そろそろ閉門の時刻だから人通りも少なくなっているでしょうし」
「いい加減にしろデイジィ」
これ見よがしに拳を持ち上げたジェドに、キャッと小さく叫んでデイジナは首を竦めた。
「だってだって! ここがどれだけステキな所かって、アレク様にお見せしたかったんですもの! 食べ物も、それに景色も!」
「ええ、良い所ですね、本当に」
街の遠景・・・・・・聖都の四方を囲んで屹立する雪を頂いた山々を仰ぎ、アイルは溜息のように呟いた。
交通の要衝どころか僻地と言っても過言ではないような立地にもかかわらず、暖かい地方から寒い地方の山海の産物が溢れているということは、本当に凄いことなのだ。
「・・・・・・ところで、閉門時間って何ですか?」
「文字通り、第二城壁の門が閉まる時間のことです。第二城壁の内側は、定住権か居留権を持つ者、もしくは滞在許可を取って宿泊所を定めている者以外は夜間の滞在は禁止されています。これを破った場合の罰則は、永久退去処分。例外はありません」
「・・・・・・!」
「ね? 私の気持ちも解っていただけますよね!」
「デイジナちゃんの気持ち、ですか?」
勢い込んで訴えるデイジナに幾分気圧されつつ、アイルは首を傾げる。
「もうお忘れですか? お付き合いして下さいって申し込んだことです!」
「あ・・・・・・」
アイルは小さく声を上げた。
少し考えれば判ることだ。
この豊かさは、誰もが無条件に享受できるものではない、ということが。
第十六話 天使の子供たち
目の前に綺麗なケーキがある。
三段の中央にはホワイトチョコの翼があしらわれている。
二段目には鮮やかなベリーソースで繊細な模様が描かれ、その周りを栗のグラッセとクリームが彩る。
そんなケーキ全体をふんわりと包み込む、羽毛のように細く繊細な飴細工。
まるで、聖都そのものの縮図のよう。
四方を急峻な山々に囲まれた絶界の地に、奇跡のように現れる白い尖塔群。霧が映し出す幻影のように、儚くも美しい光景。
初めて聖都を目にした時。歓声すらも忘れて、アイルはただ、その光景に見入ったものだ。
『ごく単純な話です。ここは天使の街であるという、ただそれだけのこと』
デイジナを家に帰した後の、第一城門へ向かう道すがら。これは新人向けトークの練習だと念を押して、ジェドは聖都の概要について語り出した。
それによると。
聖都とは、治外法権を認められた、どこの国家にも属さない特別自治区である。
第一城壁の内側は、白亜宮を中心に天軍本部と関連施設が置かれている。入城が許されるのは基本的に、天使の称号を持つ者と、白亜の塔創設当初から天使を補佐してきた氏族のみである。
第二城壁の外側は、塔の力に依って救われようとする者が集まって、いつしか形成された町。故に、納税等の義務も無ければ統治機構にも組み入れられていない。
厳密な意味での聖都とは第一城壁から第二城壁の間の、自治区、商業区、学究区、貴族特区等から成るエリアで、ここに住むには居住権か滞在権が必要になる。
『滞在権ってのは学生や研究者、許可された交易商や技術者なんかに与えられる、一時的な滞在資格のことです。期限や条件が決められていて、その範囲内でのみの行動が許されるものです』
『じゃあ、デイジナちゃんには居住権があるってことなんですね』
『そう急がずに。居住権ってのは塔に対して功績のある者に与えられるもので、天使をはじめ塔の運営に関わる様々な職に就いている者と、その家族などが該当します。居住者には相応の義務が課される代わり、保護と恩恵を保証されています。ただし、』
ジェドは勿体ぶると言うより、言葉を探すように間を置いた。
『居住権は個人に対して与えられるものであり、相続は認められていません』
『・・・・・・それはつまり』
『デイジナの父親は以前天使として塔に仕えていたので、一代永住権が与えられています。これがある限り、病を得ようが寝たきりになろうが、医療と衣食住の保障を受けることが出来ます。その身内であるデイジナも、彼が存命である限り居住権が認められます』
『一代、ってことは・・・・・・』
『そう。父親が亡くなれば、デイジナの居住権は失効する。だから聖都に住み続けることを望むなら、この先デイジナ自身が天使として塔に仕えるか、技術者や職人となって貢献を重ねるか、でなければ』
『・・・・・・それってもしかして、デイジナちゃんが僕と付き合いたいって言ってたのと関係あります?』
『おお有りですね』
『もしかしてもしかすると、家族になるとかいう、そういう方向の・・・・・・?』
『別に結婚どうとかいう話までは行きませんから』
『あ、そうなんですか』
だが、胸を撫で下ろすには早かった。
『子供をもうけさえすれば、それだけで』
『え・・・・・・』
聞いた瞬間、アイルは足を踏み出しかけたままの格好でその場に凍り付き、赤くなったり青くなったりと目まぐるしく顔色を変える。
ある意味正しい反応だと思いつつも深入りせずに、ジェドは続ける。
『羽根使いの資質が遺伝するという例はあまり聞きませんが、老齢になってから羽根を得る者がなきにしもあらず。ここのところの羽根使いの減少を考えれば、まあ、保険と言う意味もあるのかと。もっとも、上級天使を射止めるような強者の話は酒場の戯言ですら聞いたことがありませんから、深く考える必要は無いとも思いますが。デイジナがどこまで本気かは、俺にも測りかねます』
『そ、そうですか・・・・・・』
つい先刻の別れ際、また遊びに来ますと言ったアイルに対し、必ず来て下さいねきっとですよと、デイジナはしつこいくらいに念押ししたのだった。
それにしても、助け舟なのか突き放しているのか、ジェドの助言は正直言って判断に困る。
『えっと、それじゃあ、君も居住権が必要で天使になったんですか?』
それは話題の方向を変えようとしての質問だったのだが。
少し逡巡してから、ジェドは思い切ったように口を開いた。
『その程度の動機で天使を目指す者など滅多に居ませんよ。天使は多かれ少なかれ直接魔物と対峙する実動部隊ですから。居住権を得たいだけなら、もっと楽な仕事が他にいくらでもあります』
『ごめんなさい、侮るつもりなんて無かったんです』
失言だった。それは命がけで戦う彼らに対して、侮辱以外の何物でもない。
『いや、俺の説明不足です。聖都の住民で、自分が聖都に住み続けたいという動機で天使を選ぶ者は少ない。が、第二城門外の者にとってはごく普通のことです。さらに言うなら、子供を幼い内に塔に”預け”れば、その子の親には一代永住権が与えられる。親が存命のうちは、その子の兄弟までが聖都に住むことが出来る』
『・・・・・・預ける?』
『天使となるべく、ね。ゆえに彼らは”天使の子供たち”と呼ばれます』
『・・・・・・』
『何事も幼い頃から鍛えた方が習得は早いのだから合理的でしょう。そうやって高度な訓練を施された中でも戦闘能力や特殊技能に長けた者が、第五軍の実働部隊に配属される。羽根こそ持たないが、その実力は羽根使いにも決して引けを取らない』
聞きようによっては自慢のようですらあるが。
『でも、それって、無理やり家族と引き離されて塔の為に尽くせって、そういうことでしょう!』
幼いというのが具体的にどれくらいの年齢なのかは分からないが、それでも甘えて過ごしたい年頃には違いない。
『それが・・・・・・君が天使になった理由なんですか・・・・・・?』
ジェドの口調は天使になる動機の一例を説明しただけという風ではあったが、もちろんそれだけではないだろう。
『どうしてそこでしんみりした顔をするんですか。親を知らないで育つなど別段珍しいことでもないし、壁の外で孤児になるよりよっぽどマシってもんだろう。どうせ天軍に入るのなら、大人になってからヒラの天使で入って地位があるだけの無能な連中にザコ扱いされるとか、考えただけで虫唾が走るね』
ジェドは本気で嫌そうに顔を顰めた。
『もしかして、僕に話しかけて来たあのお婆さんも・・・・・・』
中央広場でクルトという名を呼び探し続けていた老婆も、かつてそのような理由で息子を手放してしまったのだろうか。
『考えようによっては幸せなんじゃないか。あんな独り身の婆さんが楽に生きられる場所なんざ、他じゃ絶対に有り得ない」
居住権が与えられているから。
身寄りがなくとも、最低限の生活は保障されているのだから。
その通りかもと思う半面、彼女の息子が側にいれば、つましいながらも穏やかに暮らせたかも知れないとも思う。
が、それをジェドに言うことは出来なかった。
(僕は・・・・・・キーシャも家族の皆も大好きだけど、もしも本当のお父さんやお母さんに会えたらって、一度も考えなかったと言えば嘘になる)
キーシャに名前を聞かれた時、「アレクサンデル」という言葉が頭に浮かんだ。
それが本当に自分の名前だったのかどうか、実の所は分からない。だが、『その名を大事にしなさいね。きっとお前のご両親からの贈り物なんだから』と言われたことが、とても嬉しかったのを覚えている。
ジェドにしても、ふとした拍子に両親に思いを馳せなかったと、一体どうして言えるのか。
ジェドが天使でいることが、この聖都のどこかにいるだろう両親の助けになっている。そう思うことが支えでないなどと、一体どうして言えるだろう。
『そんなつもりで話したんじゃないんだがな』
無言で俯くアイルに、ジェドは少し困った顔を向けた。
『貴方だって血が繋がっている者だけが家族だとは言わないでしょうに』
『ええ、もちろんです!』
ガバッと顔を上げて、アイルは勢い込んだ。
その様子に苦笑しつつ、ジェドは。
『家族ついでで知っておいてほしいことが一つ・・・・・・と、これは本人には言わないでもらいたいんだが、』
「いかがされましたか、アイル様。聖都でも指折りの菓子職人が作ったものですが・・・・・・お口に合いませんか?」
控えめではあるがバイロに話しかけられたことで、アイルはふっと我に返った。
フォークを握り締めたまま、ケーキを眺めてボーッとしていたのだ。甘いものを前にした時の普段のアイルを思えば、らしくないことこの上ない。
「あ、いえ・・・・・・食べてしまうのがもったいないなあって・・・・・・」
「お気になさらずとも、お望みとあればいくつでもお持ちいたしますよ」
「あ、じゃあこれもなんだ・・・・・・」
アイルは顔を上げると、すっかり様変わりしてしまった室内を見回す。
無断外出の件について、アイルが叱られるようなことは一切無かった。
それどころか、お帰りなさいませと頭を下げたバイロは明らかにほっとした様子で、要らぬ心配をかけたことをアイルは申し訳なく思ったし、心配してくれたことを嬉しくも思ったのだった。
そして、その日を境に変わったことが一つ。
アイル宛ての献上品が急増したのだ。
お菓子の類は言うに及ばず。様々な衣装や装飾品、壁を彩る絵画やタペストリー、飾り棚がいっぱいになるほどの絵皿や骨董やガラス細工、などなどなど。
つい先刻も、触れるのがもったいないような凝った細工のゲーム盤と駒のセットが届いたばかりだ。
そればかりか等身大の置物や、書き物机にサイドボードといった家具類までもが新たに鎮座している始末。
バイロには気に入ったものだけを受け取るよう言われたのだが、送り主の好意を思えば気軽に不要と言ってしまえるわけがない。
かくして、他人行儀に広かった室内は、今や博物館の収蔵室の如く賑やかな空間になっていた。
(・・・・・・天使の子供たちは、こんなお菓子を貰うことがあるんだろうか・・・・・・。もっと色々聞いておけばよかったな。また機会があればいいけど・・・・・・)
そんな事を考えつつ、意を決してケーキの一点にフォークを突き立てようとした、正にその時。
「おい、邪魔するぞ!」
突然、控えの間に通じる扉がバタンと全開、ずかずかと侵入してきたのは何と、紅蓮の天使である。
「お、何だ何だ、万国博覧会か?」
入るなり目を輝かせて置いてある物片っ端から手を伸ばしていく紅蓮の背後で、アイルの部屋の取次係が青くなって震えている。
闖入者を阻止するのが仕事でも、相手が相手ではどうしようもなかったのだろう。
「どうしたんですか、紅蓮? キミが随従も連れずになんて、珍しいですね」
「あ? 仕方ねーだろ。今すぐ呼んで来いって母上殿のお達しだからな。って、こんなことやってる場合じゃねーな。さ、行くぞ」
当初の目的を思い出した途端に紅蓮は、手にした小物を雑にポイッと放り投げる。
「わ、気を付けて下さいよ。って、行く? どこへ?」
「いいから来いって!」
実力行使とばかり、紅蓮はアイルの襟首をむんずと掴んで歩き出す。
「痛、たたた! ちょっと待って下さい、行かないなんて言ってませんから! その前に、母上殿って???」
「行きゃ分かるって」
フォークを手放す暇も無く、アイルは強制的に自室から引きずり出されてしまったのだった。
アイルが連れて行かれたのは、空中庭園中央の大広間だった。
非常呼集の際に集合するはずの場所だが、転移の間に直接走らされているアイルにとっては、ほぼ無縁になっていたのだが。
そのだだっ広い室のど真ん中に、小さなテーブルが一つ置かれている。いや、実際には十人以上が楽に着けるような大きさなのだが、部屋のサイズとのバランスで、どうしてもちんまりとした印象になってしまうのだ。
それはともかく、テーブルは無人ではなかった。
「おう、若いの。お使いご苦労」
入って来た二人を見てまずそう言ったのは、頭も髭も真っ白な、小柄な老人だった。聖職者のようなローブを纏っているが、どこか気の置けない雰囲気がある。
「まったく。この俺をパシリに使うとはいい度胸だよ、ご老体」
「まあそう言うな。これも母上殿のご意向だからして」
返す老人に、悪びれる様子は微塵もない。
「だからちゃんと連れて来たじゃねーか」
「ハビィ、声が大きい。ニコが怖がる」
今日も綺麗な妖精風ドレス姿のセレネが示したのは、五、六歳にしか見えない少年だ。つんとすました顔立ちに、翠玉色の瞳。居丈高ではないが、ただそこに居るだけで膝を折りたくなるような威厳がある。神童という言葉がしっくりくるような。
「いや、コイツはいっつもこんなんだろ。それより母上殿は? 超特急とか言っときながら、自分はまだかよ?」
「いつものこといつものこと」
チッと舌打ちする紅蓮に、ふぉっふぉっと声を立てて老人が笑う。
「あのう、紅蓮、彼らはもしかして・・・・・・」
「あ? こいつら? 見ての通り、紫峰の天使ヴァルムじいさんに翠濫の天使ニコル。ちなみにじいさんが四位で孫が三位。って、それくらいは知ってるよな?」
「!」
何となくそんな気はしたのだが。
当たり前のように紹介された相手は、アイルにとっては雲の上も上の存在だ。同じ上級天使だと言われても、在位の桁からして違う。
「は、初めまして! 僕は・・・・・・」
上擦った声で名乗ろうとしたアイルの頭を、紅蓮が小突いた。
「そういうのは後にしろよ。どうせ母上殿にも同じこと言うんだし。それよりとっとと席に着けよ」
「何するんですか! って、母上殿っていうのはまさか・・・・・・」
「こらこらこら! 無暗に弟を苛めるものじゃないぞ」
快活な声が広間に響く。
そこに現れたのは、豪華なウェービーヘアに豊かな胸を強調するようなイヴニングドレス、絶世の美女と呼んでも過言でない容姿でありながら、さっぱりとした笑顔が良く似合う一人の女性。
「これは母上殿、今日もご機嫌麗しゅう」
揃って立ち上がり敬愛の礼を取る一同に、一呼吸分遅れてアイルも倣う。ぼうっと見とれていましたと白状しているようで気恥ずかしい。
「待たせたね、子供たち。遠慮は要らない、座った座った!」
バッチリとウインクを決めながら、彼女はトレイを捧げて付き従う侍女の一団を振り返る。
「遠征先でいいお茶を見つけたからさ、今日はみんなに振舞おうと思ってね」
彼女は慣れた様子でポットを手にすると、めいめいのカップに注いでまわる。
「おチビちゃん、今日もご機嫌だね。ご老体、調子はどうだい? 我が愛娘、頬にキスしていいかな。ちょっとは落ち着いたかい、やんちゃっ子」
と、成り行きを見守っている間にアイルの番が来て、目の前のカップに爽やかな香りのする琥珀色のお茶が注がれる。
「あ、ありがとうございます」
恐縮するアイルに、彼女は艶やかかつ爽快に微笑んだ。
「初めまして、末っ子殿。歓迎するよ。私は暁虹のフィロテだ」
世界中の誰一人として知らぬ者は無い上級天使の二位を前に、アイルの緊張は頂点に達した。
「は、初めまして! 僕は星焔のアイルです! よろしくお見知りおき願います!」
アイルは豆が弾けるような勢いで立ち上がると、前屈並みに深々と頭を下げる。
「元気なのはいいことだ」
一瞬目を丸くしたフィロテは、すぐに楽しそうな笑い声を上げる。
「いや、面白がっている場合ではなかったな。もっと早く会いたかったんだが、思いの他遠征が長引いてしまってね。だけど一人で遊びに出られるくらいには慣れたようで安心した」
お茶の横に並べられたのは、アイルが先刻部屋で眺めていたのと同じケーキ。ただし中央を飾るのは、星形のホワイトチョコだ。
「さあさ、今日のケーキは末っ子殿の計らいだからね。よーく味わって食すように」
一同のおおっという目がアイルに集中。さらに隣席の紅蓮に上手くやったじゃねーかと囁やかれて、アイルは照れ笑いする。と同時にバイロに感謝する。
こういうソツの無いフォローをサラリとやってくれるあたり、本当に頭が下がる。
「ところで」
席に着いたフィロテは、改めて一同を見回した。
「一位の日輪が北の前線に出ずっぱりなのはいつものこととして、もう一人はどこで何をしているのかな?」
空席の主はもちろん災厄の天使である。
「あいつだったら、ここんとこずっと出張ってて・・・・・・」
「いるよ」
言い訳する紅蓮に構わず呟いたのは、今まで静かに座っていたニコルだ。
「災厄は今朝がた戻って来ている。彼の部屋の前の花たちがざわついているから」
余計な事をという目を向ける紅蓮など眼中に無い様子で、前を向いたまま事実だけを淡々と告げ終わるや、ニコルは再び静かに口を閉ざした。
「ニコは植物の気持ちが判る」
目を丸くしているアイルの向かいで、セレネがそっと補足する。
「だってさ。ほら、早く彼氏を呼んでおいで」
「ええーっ」
「諦めるのじゃな。母上殿のご意向は絶対だからして」
厳かに宣言するじいさんことヴァルムの目は、完全に笑っている。
「何ですか、その、彼氏って?」
セレネに問うたつもりだが、喜々として振り向いたのは紅蓮だ。
「留守がちの親父殿、口うるさい母上殿、気楽なじいさんと孫、しっかり者の妹に手のかかる弟(アイルを指す)とくれば、残りは彼氏で決まりだろ?」
「・・・・・・それ、幕間劇の設定か何かですか? 兄か弟で十分だと思いますけど」
「冗談! 兄なんて絶対認めねーし、弟は一人で十分だろ?」
だからと言って彼氏扱いとは。男女問わず綺麗どころを随従として引き連れている紅蓮らしいと言えばらしいのだが。
「ほらほら、弟相手に余計な御託並べてないで、さっさと行った行った!」
「チェ。面倒臭せーなー。どうせ呼んだって来やしねーのに」
「あの、だったら僕が行きます!」
「殊勝な心がけじゃが、主賓は主賓らしく座っていれば良いじゃろ」
立ち上がったアイルを、ヴァルムが宥める。
「大丈夫、すぐですから!」
飛び出して行きかけたアイルは、数歩進んだところでピタッと立ち止まると、きまり悪げに振り返る。
「ええと、災厄の部屋ってどう行けば?」
それなら、と一番に声を上げたのはニコルだった。
「道案内するよう頼みました」
「?」
指さされるまま広間の外を見ると、何と正面の木が、大きな葉を揺らしておいでおいでしていた。
「・・・・・・あ、ありがとうございます。行って来ます!」
飛び出して行ったアイルを見送った一同は、さて、と顔を見合わせた。
「末っ子殿はどこまで頑張れるかな?」
「母上殿もお人が悪い」
「そうかな?」
「で、如何かな各々方?」
「ガン無視される!」
「門前払い?」
「怒鳴って追い払われるんじゃないですか」
「食い下がって手足の二、三本折られたりしてな!」
「お前たち手堅過ぎじゃないかね。一人くらい連れて来るに賭けるモンはおらんかの?」
「無い無い無い! 成功率ゼロパーセントの最難関ミッションじゃねーか。じいさんだって昔失敗したって聞いたぜ?」
「むう、つまらん」
「彼が部屋の前に到着しました」
ニコルが差し出した手の上で、小さな陽炎が像を結ぶ。
植物生い茂る空中庭園で、ニコルの眼から逃れられるものなど存在しない。
「それじゃ、お手並み拝見と行きますか」
興味津々、あるいはいつもと変わらぬ平静な面持ちのまま、一同は扉の前で深呼吸するアイルを注視した。
第十七話 定めし居場所
「良かった、みんないい人達で」
災厄の天使の室に向かう道すがら、アイルは会ったばかりの上級天使たちの顔を思い浮かべ呟いていた。
「親切だし、優しいし。僕の事を認めてくれたし」
庭園の植物たちが順番においでおいでと合図してくれるおかげで、気を逸らしても迷う心配は無い。
「家族・・・・・・仲間、か・・・・・・」
にへら、とアイルの顔が緩む。
『・・・・・・これは、本人には言わないでもらいたいんだが』
ふと、別れ際のジェドの言葉が蘇る。
『本人? それって、バイロのことですか?』
思い当たって尋ねたアイルに、ジェドはそうだとうなずいた。
『あくまで噂なんだが。あいつはガキの頃、住んでた町が魔物に襲われて両親兄弟全て亡くしたって話だ』
さらりと告げられた内容に、アイルは一瞬呼吸を忘れる。
『だからどうってことじゃない。そんなのは奴一人に限ったことじゃないし、だいたい天使なんかやってれば仲間の訃報なんて珍しくもない。羽根を持たない天使ってのはそういうものだ。けど・・・・・・全てを失ったことがあるヤツは、危なっかしい事を平気でやる時があるからな。生真面目で仕事熱心ヤツほど要注意だ。たまにはくすぐって余分な力を抜いてやるくらいで丁度いいかもな』
『くすぐっても「何やってるんですか」って冷静に対応されそうですね。それ以前に素直にくすぐらせてくれないかも』
『・・・・・・一応言っておくが、ダイレクトにそのまんまの意味じゃないから』
言いながらジェドは息を吐く。ため息と言うほどではないが、そんな心境ではあったかも知れない。
『君は友達思いなんですね』
『いや』
しみじみと評したアイルに、しかしジェドはあっさり頭を振った。
『別に親しかったわけじゃない。強いて言えば、同じ時期に同じ場所に居合わせたってくらいか。この話をしたのだって、バイロにしてみれば余計なことだろうしな』
『それじゃあ、どうして・・・・・・?』
『どっちかと言うと、貴方が家族やら仲間やらに拘ってるように思えたから、かな。どうせ秘密でも何でもない、嘘か本当かも分からない程度の噂だし。筆頭随従と仲良くしたいんなら知っておいても損はないでしょう。ですが、』
一度言葉を切ってから。
『俺たちはガキの頃から塔に居る。本気で天使に憧れて入った奴も居る。天使になるのが当たり前だった奴も、戦災や飢饉で身寄りを失くして引き取られた奴もいる。理由はそれぞれだが、どっちかって言えば自分が”天使の子供たち”になるなんて、思ってもみなかったのが大半だ。だが、それでもな。羽根に選ばれた羽根使いと違って、条件さえ満たせば俺たちには天使を辞めて塔を離れるって選択肢も無くはないんだ。行くあてが無くても、頼れるものが無くても、、それでも命を賭して戦うことを思えばきっとどこでだってやって行ける。それでも、俺たちはここにいる。天使としての誇りを持って、魔物と戦っている。それはもう、選んでここにいるのと同じだろう? ここに集っているというだけで仲間であり家族だと呼ぶのは、間違っていないと俺は思う』
だからこそ、仲間として気にかけて悪いことなど一つも無いのだ、と。
『僕は、君たちの仲間にはなれませんか・・・・・・』
『アイル様は上級天使ですから、どんな魔物が来ても揺らがぬ支柱として堂々と立っているのが役目です。随従はその力になるため存在する。随従の能力を信じ活かし利用する。アイル様の考える仲間とは違うかも知れないが、そういう絆もあるのでは? それに、差し出がましいことを承知で言いますが、上級天使様には上級天使様としての、仲間のスタンスがあるのでは?』
『そういうものでしょうか』
『少なくとも、アイル様には時間がある。焦らずご自身のスタンスを築かれれば良いのでは?』
その後ジェドは、柄にも無いことを言ったという顔で、明後日の方を向いてしまった。その鼻の頭が赤かったのは、傾きかけた日差しのせいばかりではなかっただろう。
その時のアイルには、ジェドの言いたいことは理解出来ても、全面賛成するには至らなかったのだが。
今日初めて会った上位天使らは、新参者であるにも関わらずアイルのことを家族だと言ってくれた。
そして、一人勝手に振る舞う災厄の天使のことをも心配し、心を砕いている。
きっと、同じ場所に立つ者同士という理由だけで。
「ってことは、やっぱりあの野郎だけが捻くれてるんじゃないか。悩んで損した。ちょっと気に障るとすぐ暴力に訴えるとか、反抗期の子供じゃあるまいし。いくらすぐ治るったって、足折られたらすっごい痛いんだぞ。言いたいことがあるならちゃんと口で言えってんだ!」
前回の任務でのことを思い出し、アイルはついつい声を荒げる。
それは自分を鼓舞するためでもあった。
認めたくはないことだが。
魔物と呼ばれながらも明らかに魔物では無かった子供を前にして、助命を考えた自分と、迷わず討滅を選んだ災厄の天使。
何度思い返してみても、自分が間違っていたとは思わない。
が、それならどうして、あの瞬間、災厄の気迫に抗え切れなかったのか・・・・・・。
そんな気持ちを抱えたままでは、気分がくさくさして仕方がない。
分からないなら、直接本人に会って確かめるのが手っ取り早いに決まっている。
そう結論付けたアイルは、実は昨日までにも数度災厄の室の前まで足を運んでいたりする。が、道に迷って辿り着けなかったり探し当てても不在だったりで、未だ目的達成に至っていない。
というのは言い訳かも知れない。
室の主が塔に戻って来ていれば、在室だろうとなかろうと控えの間のドアが解放され、来訪者は紗幕ごしに取次係りに声をかければいい。
そのドアが閉ざされたままである事に、少しホッとしてしまったことも事実だったから。
でも、今回は。
お茶会に誘うという重要任務が、つまりは災厄の室を訪ねる為の立派な口実がある。
そんなことをつらつら考えているうちに、アイルは目的地に到着した。
(って、ドア閉まってるし・・・・・・)
昨日までならすごすごと退散していたところだが、ニコルは居ると断言していたし、そのつもりで見れば確かに、僅かに羽根の気配がする。
これは要するに、不在云々関係無しにとことん来客拒否の構えなのだ。
(上等だこのヤロー!)
アイルはドアの正面に仁王立ちすると、振り上げた右手をノックどころかドアを叩き壊さんばかりの気合を込めて勢い良く振り下ろす・・・・・・寸前で、ピタッと制止。
これはお茶会に誘うという、重要任務。
今まで誰も成功したことのない難易度MAXのミッションと上級天使の間で囁かれていることこそ知らなくとも、容易くないだろうことは簡単に想像がつく。
(馬鹿か僕は! 正攻法で誘ったって、あの野郎がうんと言うわけないじゃないか!)
今の今までそこに気が付かなかったとは、我ながら実に迂闊だ。
(えーと、まず何て言えばいいんだ? 「こんにちは、いいお茶日和ですね」? それとも「やあ久しぶり、一緒にお茶でもどうですか」? それとも・・・・・・)
ドアに両肘をついて頭を抱え、アイルは脳みそをフル回転させる。
と。
ふっと身体の支えが消失し、その意味を把握する暇も無く、目の前に新たな壁が出現する。
いや、壁ではない。床だ。と気付いた時には、アイルはビターンと見事に倒れ込んでいた。
何が起こったのか。
考えるまでもない。
ドアが勢いよく引き開けられた為、がっつり寄りかかっていたアイルは、そのまま前のめりに控えの間の床へと倒れ込んでしまったというわけだ。
両腕で頭を抱えでいたおかげで顔面を強打せずに済んだことは、幸運と呼ぶべきか否か。
「い、い、いきなり何するんですか!」
ガバッと跳ね起き様に叫んだアイルはしかし、ドアを開けた張本人である災厄の天使の思いがけない格好に、思わずギョッと目を剥いた。
薄手の夜着にナイトガウンを引っかけただけ。普段はキッと束ねている黒髪も、流れるに任せたまま。
それはどう見ても、たった今まで寝ていましたと言わんばかりの艶姿だ。
けれど今は午後のティータイム。
フィロテのようなイブニングドレスには早いが、夜着でいる時間ではとっくに、ない。
(も、もしかして中に誰か!?)
一瞬赤くなって奥のドアを凝視してしまったアイルは、いい加減紅蓮やデイジナのノリに感化され過ぎかも知れない。
(無い無い無い、コイツに限って絶対無い! 任務のせいで徹夜明けってあたりが妥当だよな、うん・・・・・・)
つい思い浮かべてしまったもう一つのイメージを、アイルは慌てて追い払う。
それこそもっと有り得ない。
苦労して入手した希少本を読みふけってうっかり徹夜してしまい、目つき悪く朝ご飯を要求するキーシャに似ている、なんてことは。
「何をしている」
問われてアイルは、ドキリとして災厄の天使の顔を見直す。
一瞬掠めた視線は、まるで知らない相手を値踏みするかのように冷やかで、ひどく居心地の悪いものだった。
「そこに居座られると煩くてかなわない。用件があるならさっさと言え」
あまりと言えばあまりな言われように、アイルの自制心は喜々として霧散する。
「よくもまあ、そんだけ勝手なことが言えますね、七日ぶりに顔を合わせたパートナーに向かって! てか、この前は随分な仕打ちをしてくれたじゃないですか。謝りの一言くらいあってもいいと思いますけどね!」
全く抑揚の無い平静そのものの声で当たり前の事実のようにサラリと言ってのけてくれるあたり、本当にムカつく。厭味ったらしく見下された方が、まだしも平静を保てたと思う。
喧嘩を売りに来たつもりは無かったが、この場合は不可抗力だ。
「この前・・・・・・」
「トボけようったって無駄です。ゼーレンの町での話ですよ、見えない魔物の事件の! あの時はよくも僕の足を折ってくれましたね!」
災厄の天使は、ああ、と一つうなづくと、腕組みを解いて片手をアイルの眼前に伸ばす。
夜着の袖から覗く腕は、華奢と言ってもいいほど白くてすらりと細くて、紅蓮は彼氏呼ばわりしていたがいっそ彼女役でもいいのではないかと思ってしまうほどで、その実、アイルが今何を考えているかバレようものなら容赦なく強烈な鉄拳を繰り出すだろうことは火を見るより明らかで。
「ええと・・・・・・?」
意図を掴みかねたアイルは、目の前に突き付けられている腕と災厄の天使の顔とを見比べる。
「仕返しがしたいのなら、気の済むようにすればいい」
「だからどうしてそう!」
瞬間的に、アイルの頭は沸点を突破した。
「すぐ暴力で解決しようって、その発想どうにかならないんですか! 少しでも悪いと思ったんなら、まず謝ってみるとか、そっちの方が先でしょう!」
「謝るつもりはないし、許しなど必要ない」
「!」
「あの場はそれが最良だと判断したからそうした。が、不服だと言う申し立ては、理解出来ないこともない。だから妥協案だ。腕の一本くらい、くれてやる」
淡々と告げる声には、報告書を読み上げる程の抑揚すら含まれていない。
このまま腕をもぎ取られたとしても、本当に顔色一つ変えないのではないかと思えるような。
そのようなことが、あるはずないのに。
「・・・・・・じ、冗談! もし僕がノコノコ手を出したりなんかしたら、ソッコー反撃する気なんでしょう?」
「して欲しいのなら」
一体どこまで本気なのか。
「だったら、腕一本と言わず、身体ごと貸してくれたっていいでしょう?」
アイルは突き出されたままの腕を両手でがっしと捕まえると、有無を言わさず力任せに引っ張る。
「上級天使のみんなにお茶会に誘われてるんです。妥協するならそっち方面で妥協したっていいですよね?」
だが、予想通りと言うべきか、災厄の天使は一向に足を動かそうとしない。
「ったく、往生際が悪いですね!」
体重をかけて力任せに引っ張るアイルに。
「・・・・・・このナリでか?」
「あ・・・・・・・」
災厄の天使の至極もっともな反論に、アイルは一瞬虚を突かれる。
その途端、しっかり捕まえていたはずの腕がすっと消え失せる。
慌てて振り返れば、災厄の天使は既にアイルに背を向け、自室のドアへと消える寸前だった。
「とか何とか言って、このままバックレる気じゃないでしょうね!?」
返事のつもりかどうか、閉まる寸前のドアの向こうで、白い手がひらりと振られる。
「とっとと着替えて出てきて下さいよ! でないとここにずーっと居座って、昼夜ぶっ通しで大騒ぎしてやりますからね!」
と怒鳴ってやったものの、災厄の天使が素直に出て来るかは怪しいものだ。が、それならそれで本気でイヤガラセしてやるまでだ。
「にしても不親切だなあ」
取次係りのためのスツール一つ置かれていない控えの間を見回してから、アイルは壁に背を預けた。
(ったく、気分が悪い・・・・・・)
控えの間に残してきた星焔の天使に毒づいたわけではない。
身体の芯がぼうっと痺れるような感覚。それに甘くまとわりつく薬酒の残り香。
加えて他者の気配で目が覚めるなど、最悪もいいところだ。
煩わしいもの全てを振り払うように乱暴に頭を振ると、カリムは夜着を床に脱ぎ捨て、小卓の上の衣装櫃へと手を伸ばす。
(七日・・・・・・)
前回の任務から、既にそれだけ経過しているらしい。
ゼーレンでの任務記録を思い起こすことは出来る。が、自分が関わったという実感がまるで湧かない。
塔に戻った所までは記憶に残っているから、意識を失ったのはその後。肉体を損傷した覚えは無いから、きっと感応能力に負荷が掛かり過ぎたのだろう。
別に珍しいことではない。
カリムの身の内の炎の結晶は、他の上級天使らよりもずっと不安定な分、変調を来すことも多い。
そんな時には、ただでさえ零れ落ちやすい感情の記憶が、一気にごっそり持って行かれる。
最近の任務内容、討滅した魔物、訪れた街、パートナーだと言って現れた星焔の天使・・・・・・記憶を手繰れば、事実の詳細は確かにそこにあるというのに。
その事実を確認したところで、カリムはそれ以上の詮索を止める。
欠落したものを惜しんだところで、徒労でしかない。
それよりも。
(ずいぶん時間を無駄にした・・・・・・)
手早く黒の上下を身に着けたカリムは、髪を無造作に一つに束ねる。緋色の上衣と派手な装備品はそこに残したまま。
小卓の引き出しから、仮の身分証であるメダルを取って隠しに放り込む。
後は外出用の簡素なマントだが、そんな物が都合よく用意されているほど、ここの連中は気が利いてはいない。
室を出ようとして、カリムは一度だけ表のドアに視線を投げた。
星焔の天使の気配は、相変わらず動かない。
(迷惑なことだ・・・・・・)
何を勘違いしたかは知らないが、パートナーと呼ばれる意味をはき違えているとしか思えない。
(仮にもパートナーを名乗るのなら、せめて俺を殺すくらいの覚悟を決めてからにするべきだ)
炎の結晶の中に、時折闇の色を閃かせる星焔の天使。
その闇色が暴走した時の備えとして、カリムに白羽の矢が当てられた。
理由は簡単。カリムはこれまで、何人もの命の散り際に立ち会っている。魔物だろうと、魔物と呼ばれたものだろうと、羽根使いだろうと、上級天使だろうと。それが一人増えるくらい、どうということはない。
だが、たとえ名目上でも指導役ではなく対等とするのなら、その逆もまた、求められている。対等であることの、それが本当の意味だ。
(もっとも、俺があんなヘタレに頼ることなど、有り得ないが)
もしも、それが必要な時が来たとしても、あんな奴にだけは、絶対に。
「・・・・・・おい! もうゲームオーバーかかよ?」
「そのようだのー」
雁首を揃えてニコルの手の中の陽炎に見入っていた上級天使一同は、災厄の天使がアイルを残して部屋に消えたところで、つまらなそうに息をついた。
「あーあ、もう少し粘れよなー」
「そんなことない。がんばったと思う」
「一応門前払いはされなかったしのー」
「門前払いの代りに控えの間で待ちぼうけくらわされてるぜ、あいつ」
「じゃあ、呼んで来る」
「いいからもう少し放っておこうぜ。どうせなら何分くらい突っ立ってるか賭けねーか?」
「ハビィの意地悪」
紅蓮を中心にまだ盛り上がっている一同に気付かれぬよう、フィロテはこっそりため息をつく。
「ったく、あそこで喧嘩の一つも出来るなら救いがあるものを。一体どうやったらあんな悲鳴の上げ方一つ知らない子になるんだろうね・・・・・・」
「じれておられるようだの、母上殿。今すぐにでも首根っこ捕まえて引っ張って来たくてウズウズしている顔だの」
気付いたヴァルムが、ひそりと声をかける。
「目ざといご老体だ。が、まあ、そんなところだ。あの子ときたら、どうしてさっさとこっち側に来ないのか、じれったくてしようがない」
「なるほど、末っ子殿に任せて正解のようだの。母上殿が行かれれば血を見そうじゃ」
ヴァルムはおどけて首を竦める。
「まあ、仕方あるまいよ。あれは”永遠”に少しの価値も認めてはおらん」
「誰もが羨む永遠を手にしながら、永遠を認められぬとは・・・・・・人間の意識とはつくづく厄介なものだな」
永遠を望みながらも、未だに年老いた肉体を手放そうとしないヴァルムが、ふぉっふぉっふぉっと低く笑う。
もちろん、自分よりもフィロテの方がはるかに年上であることを含んでの発言である。
「あれを見ていると、ワシらが否定されているようで落ち着かぬ。理解出来ぬものは気持ちが悪い。故にこっちを振り向かせたくなるのじゃろ? それを察しておっても自分を曲げる気が無いから、あれはワシらに近付かぬ。それがあれなりの配慮と言えぬこともない」
「・・・・・・あの子に救いを求めた蒼空は、あの子の事を理解出来たのかな」
永遠を拒絶したが故に今はもうどこにもいない、かつての六位だった蒼空の天使を思って。
「さあ、どうかの」
「じいさんに母上殿、今度は何の相談だ?」
「何でもないよ、悪戯っ子殿。それで、末っ子殿はどうしている?」
「妹殿が呼びに行くとさ。それより家族ネタも飽きたしさ、次は女装&男装パーティはどうだ? 特にセレとアイルなんか、着せ替えして遊んだらきっと面白いぞ!」
「そういうところ少し変わったかな、お前は」
「ん? そうか?」
「気にするな。今を楽しめ」
永遠に去った者もいれば、形を変えて戻って来た者もいる。
ここは、天使の為の場所。選ばれた者だけの楽園だ。
「遅い。遅すぎる・・・・・・」
たっぷり十分は待ってから、アイルはドアを睨み付けつつ呻く。
先刻までは確かに人が動く気配があったし、羽根の気配はちゃんとそこに存在する。
が、しばらく前から妙に静かになってしまった気がする。
「まさか本気でバックレるつもりか。でもドアはここだから他にどこにも行けるはずが・・・・・・」
いや、あった。
アイルの部屋と同じ構造なら、侍女らが出入りするための、続きの間に繋がるもう一つのドアがある。
バイロからは使わないよう言われていたが、それは使用不可能という意味ではないのだ。
「もういいですよね、入りますよ・・・・・・!」
怒鳴ると同時に大きくドアを押し開いたアイルは、目に飛び込んで来た光景に愕然として立ち竦む。
室の主の姿がどこにも無いことは、予感の範囲内ではあったが。
あまりにもだだっ広い部屋だった。
大きさ自体は、アイルの自室と大差無いが、白を基調とした室内には最低限の家具がぽつぽつと置かれているのみで、小さな飾り一つ、私物らしき物の一つも全く目に入らない。
どこまでも空々しい室の中で、衣装掛けに掛けられた緋色の上衣と、刀掛けに留め置かれた羽根の具現である大振りの曲刀だけが、所在無げに主を待っている。
『物をどう扱うかは大事だよ。持ち物を見れば、持ち主の人となりが大体判るからね。その人が何を大切にしているか、よく注意して見てごらん。それが良く当たる人相見のコツさ』
「ねえキーシャ、この室の主は・・・・・・災厄の天使は、一体何を大切に思っているんだろう? あの瞳に、世界はどう映っているんだろう・・・・・・?」
アイルは踏み入ってはならない領域に入り込んでしまった後ろめたさを覚えつつ、しばし呆然と佇み続けた。
第十八話 学生の時間
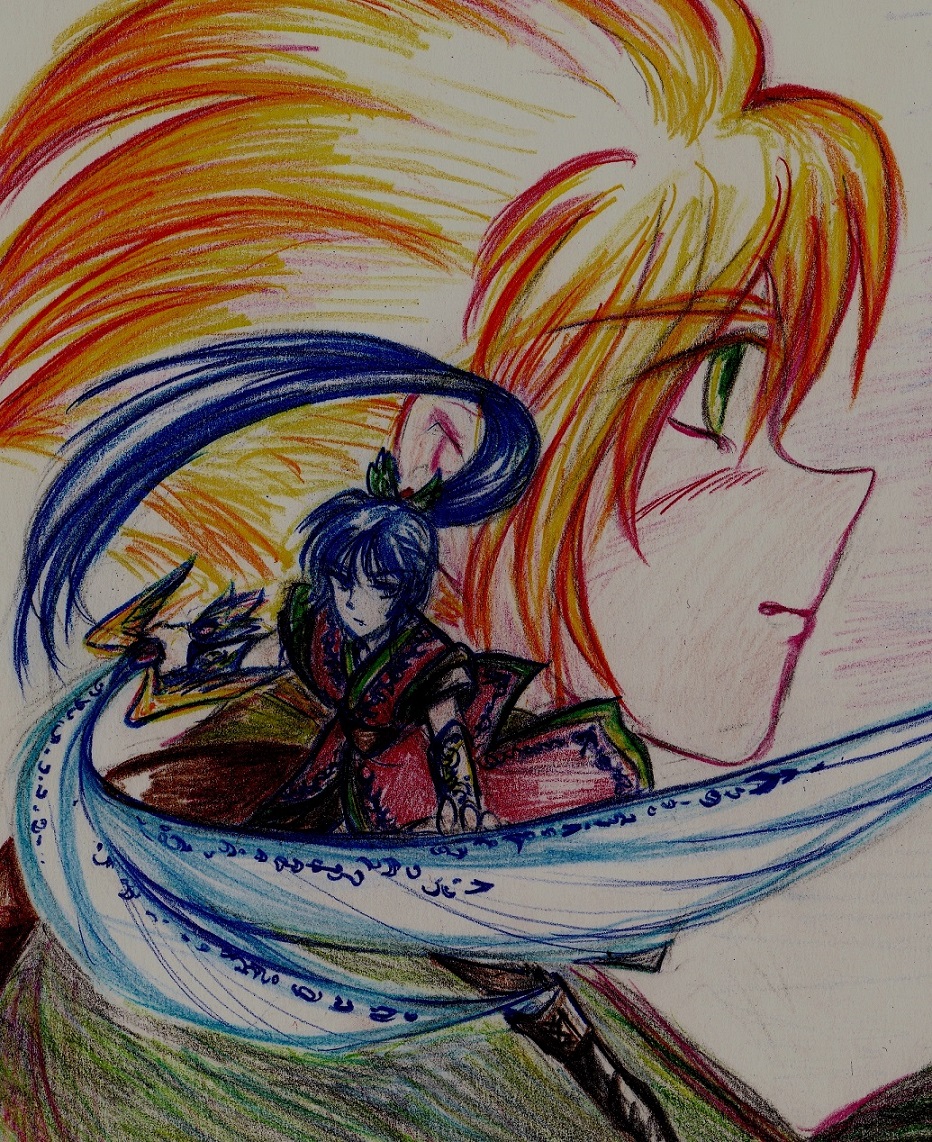
昨日はとても綺麗な星空でしたね。
任務を終えて一泊した宿の中庭からは、はっきりと夜空の川が見えましたよ。街の人も、今の時期にこんなに見事な星空は珍しいって、すごく感激してました。
そう言えば、ゆっくり星を見たのって、すごく久しぶりな気がします。
キーシャと旅していた頃は、あんなに空ばかり眺めていたのに・・・・・・。
もうすぐ二か月になるんですね。
僕がキーシャやみんなと別れて、白亜の塔に入ってから。
毎日色んなことがありすぎて、本当にあっと言う間だったけれど。
時々考えてしまいます。あの頃の僕が今みたいだったら、キーシャやみんなの足手まといにはならなかったのになって。
ねえ、キーシャもどこかで、あの星空を見上げていましたか?
時々は、僕のことを思い出してくれていますか?
太陽が何日も顔を見せないことが珍しくないこの季節にしては、穏やかに晴れた日の昼下がり。
聖都一般住民専用区画”天使の街”は、いつにもまして道行く人々の活気に包まれていた。
もっとも、陽気につられて出て来た者ばかりではない。
特に料金の手頃な軽食屋やオープンスペースの広いコーヒー店や品揃えの豊富さを競う貸本屋や洒落た筆記具も扱う雑貨屋などが軒を連ねる通称学生街では、春の進級う試験という運命の日を前にした学生たちの奇妙なノリと熱気に包まれるのが、この時期の風物詩となっている。
だが。
徹夜で完成させたレポートや試験内容の裏情報や進路に必要なコネ作りや、といった自分のこと以外考える余裕の無い学生たちですらもが思わず戦慄し振り向いてしまうほど。
肩を怒らせ石畳を蹴り飛ばしながらずんずんと速足で突き進んで行く、その青年の威圧感は凄まじかった。
天軍の紋章入りのマントを翻す姿が通りの先に完全に見えなくなるまで硬直状態で見送ってから、学生たちはようやく、竦めていた首を傾げた。
「何だったんだろう、あれは?」
「さあ・・・・・・自暴自棄になったどっかの最終学年生が研究室の魔道兵器持ち出して暴れ始めた、とか?」
「Aクラスの魔獣を喚び出しにうっかり成功したものの、逆に収集つかなくなったとか?」
「教員棟にテロ仕掛ける計画が発覚しちゃったとか?」
その冗談を聞いた誰もが、それを言った本人含めて、さもありなんと頷きあう。
実際その手の噂話は枚挙に暇が無く、それを取り締まる側も常に無い殺気を帯びている。熱病の流行にも似た半年に一度の狂乱騒ぎ。今はまさにそういう時期なのである。
「騒ぎで試験がウヤムヤになるんだったら、俺もやるけどな」
「それで何とかなるんだったらな・・・・・・」
あっさり失敗、きつい叱責を食らった上に運が良ければ放校処分、という未来しか見えない。
学生一同は互いに苦笑し合うと、些細なことはさっさと忘れて、各々目先のの課題へと戻って行った。
一方。
バタン!
賑やかな嬌声飛び交う宿屋兼小料理屋の扉が予告なく乱暴に開け放たれ、その音に驚いた数人の視線が一斉に入り口に仁王立ちしている闖入者に集中した。
のも束の間。
「・・・・・・魔物の眷属には個体差が見られるんですか? 能力差は? 見分けることは可能だと思われますか? 例えば・・・・・・」
「転移門のシステムは、古代機械と魔術の融合で成り立っているんですよね? その魔術の系統について・・・・・・」
「羽根使い様は”炎の結晶”をご覧になられましたか? 具体的な形や色は・・・・・・」
彼らの興味はすぐに輪の中心にいる人物へと戻り、
「ま、待って下さい! そんなに一斉に話しかけられても・・・・・・順番に、あと出来ればもっと簡単な質問から!」
ざっと二十人は下らないと思われる人垣の真ん中で、困惑し切った悲鳴が上がり、
「ちょっとみんな調子に乗るんじゃないわよ! 誰に向かってそんな気安い口をきいているのかしら? いい加減にしないとあんたたち全員出入り禁止にしてやるわよ!」
威勢の良い声の主によって学生用のマントが勢い良く引っ張られ、首を絞められた格好になった一名がたまらず離脱。しかしその隙間をすかさず別の学生が埋める。
「じゃあ、羽根使いには、どうやってなられたんですか?」
「羽根使いになる前と後では何が違うんですか?」
「塔に来られる前は何をされてたんですか?」
質問内容が専門的な話から、個人的なものに変わり、
「あ、それなら答えられます。ええと、いつ羽根使いになったかは覚えてません。気が付いたらそうだったとしか・・・・・・それから塔に来る前は、根の無い草の民としてあちこち旅して回ってました」
それを聞いた途端、ざわついていた学生らは水を打ったようにシンと押し黙る。そして、
「え? あれ?」
答えた本人が首を傾げると同時に、どっと笑いが巻き起こった。
「もう、羽根使い様、冗談キツいですよ!」
「何だそうか! 天使様が流浪民とか、冷静に考えればあるはず無いですよねっ!」
「あーあ、もう少しで信じるところでした」
「え? でも僕は本当に・・・・・・」
腹を抱えて笑い続ける一同に、輪の中心の人物は戸惑いの眼で周囲を見回す。
一体何が彼らを黙らせ、次いで冗談だと判断させたのか。さっぱり解らないという顔だ。
「そんなことより羽根使い様、羽根が発現するところを見せていただけませんか?」
「あ、そうだ、それがいい!」
好奇心剥き出しの学生らの背後で、「おい」という低い声が上がる。
「僕の羽根を、今ここで、ですか?」
「お願いします、羽根使い様!」
「ほんの少しで構いませんから!」
「お前ら」
全く気付かない、あるいは気付かぬフリをする学生らに向けられた声が、更に低く、威圧感を帯びる。
「これは単なる興味本位じゃありません、学問的な問題ですから!」
「って言われても・・・・・・羽根は神様からお預かりした力だから、みだりに発現しちゃいけないって言われてますし・・・・・・」
「そこを何とかお願いします!」
学生の一人が、その場でがばっと伏礼する。
「わわ、止めて下さい! 分かりましたから!」
途端に学生たちからわっと大きな歓声が上がり、
「いい加減にしろよ」
入り口に居た者の怒気を孕んだ声が震える。
と、次の瞬間。土下座から上半身を起こしてガッツポーズしていた学生が、その姿勢のままピキンと固まった。
「お、おい?」
その異変に気付いた者が肩を揺すったはずみに、固まった身体はそのままゴロンと床に転がって、近くにいた者らがヒッと息を飲んで大きく飛び退く。
ここに至ってようやく、彼らは入り口に立つ者へと改まった視線を向けた。
「告げる。羽根使い様に対する狼藉は、すなわち白亜の塔に対する冒涜である。これ以上愚行を重ねるなら不敬罪で処断の対象とするが、その覚悟はあるか」
冷やかな宣告に戸惑った学生らが、互いに目を交わし合う。
「そんな堅い事言わずにさ、」
「これくらい冗談の内だろう・・・・・・?」
彼らにとって入り口に立つ人物、街の治安を担う第五軍の青年は、知らなくもない存在だ。
と言うか普段はむしろ学生身分にものを言わせて、やんちゃの目こぼしなど何かと便宜を図らせたりしているような相手だ。
その思わぬ強硬な態度に、鼻白んだ学生の言葉が、途中で途切れる。
「あーあ、余計なこと言わなきゃいいのに」
少女の嘆息と同時に、一歩踏み出しかけた格好のまま石化した学生の身体が、どーんと鈍い音を立てて床に転がる。
本気だ。
目の前の青年は、完全に本気だ。
「疾く立ち去れ」
短く命じられ、すっかり青ざめ切った学生らは、青年を大きく迂回する格好で一目散に店を後にしたのだった。
残されたのは石化状態の学生二体と、急展開に呆気にとられるアイル、これでようやく独り占め出来ると満面の笑みを浮かべてアイルの腕に飛びついたデイジナ、腕組みしたまま溜め息をつく聖都警備時の制服姿のジェド、それに、何事も無かったかのように椅子やテーブルを整える店の親父のみ。
「君だったんですか、ジェド。お久しぶりです」
気を取り直したアイルが、苦虫を噛み潰した顔のジェドに向かって軽く手を振る。
「ところで・・・・・・大丈夫なんですか?」
床で転がる学生に目を落として質問。
「ただの石化捕縛ですよ」
努めて平静を保ちつつ、ジェドは固まった学生らをゴロリと転がす。
石化を解かれたわけでもないのに、ジェドが触れるとその身体は容易く姿勢を変える。
心得た店主が麻縄を投げ渡し、当然の如く受け取ったジェドは慣れた手さばきで学生二人を縛り上げてしまう。
「ええと、いくら何でもやり過ぎでは?」
眉根を寄せるアイルに対し、
「いいんですよ。こいつらは学生なのをいいことに、ノリで何でも許されると思ってるんです。甘い顔してるといくらでも付け上がる。大体、羽根の力を見たいって言ったのはこいつら自身なんだから、きっと本望と喜びますよ」
いや、それは無い。
アイルは心中でツッコミを入れる。
「心配なさらずとも、後で、しっかり釘を刺してから解放してやりますよ」
ほっとした顔をしたアイルはしかし、試験期間中の学生にとっての「後で」の意味するところに気付いてはいなかった。
ともあれ一仕事終えて立ち上がったジェドは、もう一度溜め息をついてから、
「それで、今日はどんな用件でこちらへ?」
「もちろん、私との約束を守って下さったのですよね? あれからずううぅぅっとお待ちしてましたのに、アレク様ってば全然来て下さらないんですもの。私の事、お忘れかと思いましたわ!」
アイルが口を開く間を与えず、まくし立てたのはデイジナだ。
アレクというのは塔に来る以前の名だが、聖都見物の折にデイジナにはその名を使っていた。
「あ、はい、すみません。また来るって約束でしたよね」
潤んだ瞳で至近距離から見上げられては、早々に降参せざるを得ない。
だが当然ながら、ジェドにそれは通用しなかった。
「まさか本当に、そのような理由”だけ”でお運びになれれたのでございますか?」
これでもかと馬鹿丁寧に問いかけられ、アイルは心持ち背筋を伸ばす。
「実はその・・・・・・任務から戻ってさあ部屋に入ろうかなって時に、ちょっと落し物をしたことに気が付いて、もしかしたら転移の間にあるかもって扉を開けたら、ちょうど装置が作動するところだったみたいで・・・・・・で、気が付いたらここの前に立ってたんですよね」
「もう! そこは嘘でも私に会いたくて仕方がなくてって言うところですわよ」
照れ笑いするアイルに向かってプンと頬を膨らませてから、デイジナはジェドに顔だけ向ける。
「店の外が騒がしいなと思って見たら、アレク様がキョロキョロしてらしたんだもの。本当にビックリしたわ。それで慌てて中にお連れしたんだけど・・・・・・」
時既に遅し。
見慣れない羽根使いの姿を目撃した学生らが、ノリと勢いでどっと集まって来てしまったというわけだ。
その後どうなったかはジェドが目にした通りである。
事態を察した店の親父の速やかな通報が無ければ、もっと大事になっていただろう。
肩を竦めたジェドに、アイルはすみませんと頭を掻く。
「もしかしてまた、君の当番の日だったりしました?」
「時間外に呼び出されたんですよ、わざわざ! ったく、俺は迷子の上級天使係じゃねっての・・・・・・」
さすがに後半は口の中で呟くに留めたので、アイルの耳には届かなかったが。
コホンと咳払いし、ジェドは気を取り直す。
「まあ幸い、貴方の正体はバレなかったようですが」
「え? そんなことも判るんですか?」
「捕縛した者からは、直近の情報を取り出すことが可能です」
言いながらジェドは左手首の腕輪を示す。ごくシンプルなものだが、そこからは確かに羽根の気配が感じられる。
ジェド自身は羽根使いではないから、その腕輪は第五軍の羽根使いが力を分け与えた媒体に違いない。
彼の本来の任務は羽根使いの探索なのだから、媒体に込められた羽根の力が情報収集に特化したものであるのは当然のことだろう。
(どんな力を持たせたいのか具体的にイメージしろって言われたっけ・・・・・・)
羽根の力の媒体への封入は、羽根使いには基本技であるらしいのだが、何度かトライしてみたもののアイルは未だに成功をみていない。
それが出来れば、随従であるバイロ達の仕事がずっと楽になるのだが。
「アレク様、どうかなさいまして?」
ジェドの腕輪を注視し黙り込んだアイルを、デイジナが不思議そうな目で見上げる。
「あ、いえ、何でもないです」
反射的に取り繕って、アイルはデイジナに笑って見せた。
「・・・・・・でもちょっと意外です。あの学生さんたちは僕が星焔だって知らずに騒いでたなんて。僕はてっきり、この前みたいにバレバレなのかと思ってました」
「あら、私たちがそこらの学生なんかに言いふらすなんてヤボなこと、するわけありませんわ」
「いえ、そうじゃなくて、」
前回ここに来た時は、誰に言ったわけではないのに、町の誰もがアイルの素性を承知している様子だった。さっきの学生らもきっとそうなのだと、アイルが考えたのも無理からぬこと。
「彼らは聖都外から学びのために留学を許された連中です。彼らにしてみれば、ただの羽根使いだって珍しくて仕方がない。聖都の者が貴方に対して非礼を働いたと思われるのは心外ですね」
「あのくらい非礼とは思いませんけど。それじゃあ君には、彼らが笑った理由が分かりますか?」
それは、アイルが根の無い草の民だと明かした時のことだ。
「天軍に関するジョークで、魔物襲来の報を受けて現着してみれば、居たのはただの流浪民だったってオチの話があるからでしょう」
「・・・・・・笑い話なんですか、それ」
「アレク様、あんな人たちのことなんて、いちいち気になさらないで」
腑に落ちない顔のアイルを慰めるように、デイジナが声をかける。
「彼らは流浪民など得体が知れないくらいの認識しかありませんよ」
ジェド自身、アイルに接するまで特に深く考えたことはなかったから、彼らのことをどうこうは言えない。
土地にも法律にも縛られず、常識も習慣も異なり、結束が固く独自の掟を順守し、排他的で相容れない。何の前触れも無くある日突然現れて、立ち去る時もまた一瞬。
”言う事を聞かない子は流浪民に連れて行かれてしまいますよ”とは、幼子が叱られる時の定番フレーズである。
流浪民が実際にどういう人々かが問題なのではない。自分たちとは違うという感覚、それ自体が全てなのだ。
そしてこの世界は、定住する民が圧倒的な多数派で、王侯貴族や豪商など権力を握っている者は100パーセント間違いなく定住民なのだ。
つまり、世界の仕組みは定住民に都合の良いように出来ている。
「学生の大半は上位階級の出身か、学位と知識で上位階級への参入を目指す者達です。彼らにとって、流浪民は社会の枠の外の存在でしかなく、興味を魅かれるものではないのでしょう」
「・・・・・・そうでしょうか?」
ややあって、アイルは目を伏せたまま、疑問の言葉を呟いた。
「君のその理屈には、一理あると思います。でも、簡単に決めつけてしまって、解ってもらう努力をしないのは、僕もまた彼らを色眼鏡で見て侮っていることになりませんか?」
アイルは顔を上げると、ジェドとデイジナに笑んで見せた。
「世界は広い。目の前のものだけで量っては、世界はほんの小さなものでしかない。出来るだけ多くの者を見、大勢の人と接しなさい。それこそがお前の世界をより大きく豊かなものにする・・・・・・これは僕の育ての親の言葉です。僕も彼らも世界の一部です。なのに互いに解り合わないのは、自分で世界を狭めることです。それはとても、もったいないことでしょう」
いっそ無邪気なくらい堂々とした力説に、デイジナも親父もアイルに崇拝の目を向けている。
同じくウッカリ聞き入ってしまったジェドだが、ここで安易に同意したが最後、アイルは喜々として学生たちに布教して回るに違いない。
(そんなことになったら、誰が護衛に着いて歩くと思ってやがる。どんだけ貧乏クジだよ。いやそれ以前に上級天使が自らの出自を吹聴して回るとか、有り得ないだろ。まさか監督不行き届きでペナルティ食らうなんてことには・・・・・・ったく、どうしてこう無駄に前向きなんだか)
内心で身震いし、ジェドは反論の糸口を探す。
(それにしても・・・・・・少し天真爛漫過ぎやしないか? 流浪民かどうかに限らず、軋轢の中で生きる者は自分を明かすことにもっと慎重なものじゃないか?)
同じように天使と呼ばれてはいても、羽根使いのような選ばれた存在と羽根を持たない者との間には、努力などでは埋めることの出来ない圧倒的な違いがある。どれほどいい奴でも、どれほど仲良くしていても、どれほど目を瞑っていても、どうしても意識せざるをえない場面など数限りなく存在する。
違うということは、考えるのではない。心が感じてしまうこと、否応なしに思い知らされることなのだ。
(なのにアイル様は・・・・・・)
上級天使という選ばれた存在であるからか、それが元来の気質なだけなのか。
だとしても、周りからしっかりと肯定されていなければ、こうも素直にはなれないのではないか。
「ひとつ、お聞きいたしますが」
「どうしたんです? 改まって」
「貴方の養い親は、どのような方でしたか」
「キーシャですか?」
途端にアイルは、懐かしそうに目を細めた。
「長い灰色の髪をした、ひいき目抜きに綺麗な人で、優しくて、厳しくて、色んなことを教えてくれた、大好きな恩人です。占者を生業にしていましたけれど、家族の中では薬師で教師で相談役で、みんなに尊敬されてました」
「その方は、元から根の無い草の民だったのですか?」
「そうですよ」
一切の逡巡無く、アイルは即答。
「貴方が家族になる以前からという意味でなく。その方も以前は別のことをしていて、ある時家族に迎え入れられた、という事はないのですか?」
「そうかも知れませんね」
「その方が以前どんなことをしていたか、アイル様はご存知ない?」
特に考える様子もなくあっさり認めたアイルに対し、ジェドは辛抱強く質問を重ねる。
「家族の素性は、本人が語らない限り聞かないのがルールですから」
「・・・・・・」
「それがどうかしましたか?」
難しい顔で黙り込んだジェドに、今度はアイルが問い返す。
「これは俺の推測でしかありませんが・・・・・・貴方がご自分の素性を誰彼構わず話されることは、その方の為にはならないような気がします」
元より、アイルの語る内容がどうであれ、強引にでもそっちの方向に結論付けるつもりだったが。
(もしかしたら、本当に・・・・・・)
何も知らなければ単に育ちが良いのだろうとしか思えないようなアイルの素直さが、意図的に、つまりいつかは流浪民でなくなることを前提されたものだとしたら。
アイルが至高の存在だと知っていたならば・・・・・・。
(まさか、な)
そんなものは思い過ごしである可能性の方が、きっとずっと高いはずだ。
ジェドはかぶりを振って思い浮かんだトンデモな考えを霧散させる。
その時、不意にノックの音が聞こえて。
「失礼いたします。アイル様、お迎えに上がりました」
恭しく登場したのは、アイルの筆頭随従であるバイロだった。
アイルの顔に、緊張が走る。
普段のバイロが場の空気を乱すような無粋な真似をするとは考えられず、その意味するところは非常事態、つまり緊急の呼び出しであるのに違いなかった。
第十九話 作戦立案
「すみません遅くなりましたっ!」
山間にあるボノレッティ男爵私領、”白鹿の谷”。
僅かな平地に石造りの壁を持つ家々がくっつき合って建ち並ぶ町は、規模こそ小さいがおとぎの国のように美しいと、訪れる者の称賛を誘う。
だがその町並は今、夜を溶かしたような昏い霧にすっぽりと包まれて、屋根の輪郭すらも定かではない。
町を見下ろす高台に建てられた領主別邸の、眺望を自慢とするはずの広いテラスを横目に駆け抜けたアイルは、作戦本部が置かれた一室に飛び込むなり、大声で叫んでピョコンと頭を下げた。
重苦しい雰囲気を木端微塵にする遅刻学生のような場違いな振る舞いに、室内の人々は虚を突かれ、丸くした目を向けたまま固まった。
だがそれも一瞬の事。
まず立ち働いていた従僕や侍女達が、次いで何度か任務に同行している黒衣の番人が、番人の態度に察しをつけた天軍の関係者が、同じく状況を察した官吏風の一団が、最後に補佐役の耳打ちで無礼な闖入者の素性を知らされた身なりも恰幅も豪勢な男が、アイルに対し次々と貴人に対する礼を取る。
もちろん、部屋の一番奥で領主用のどっしりした椅子に足を組んで掛けたまま、視線一つくれようとはしない約一名は除いて。
「遅れたのは僕が悪いとしても、せめて挨拶くらいあったっていいんじゃないですか? そんな仏頂面だと、みんなが怖がりますよ」
この台詞が、もはや定番の挨拶と言っていいだろう。
災厄の天使のアイルに対する、と言うより他者に対する態度は、初めて会った時から一貫して変わらない。即ち、任務に対しては熱心でも、それ以外には全くの無関心。
そんな態度にもすっかり慣れっこになったアイルは、今更応えが返らないことを気にしたりはしない。が、むしろ。
(何で大人しくこんな所にいるんだろ。僕がいようがいまいが、いつもだったらとっくに魔物に向かって飛び出してってそうなものなのに?)
どういう風の吹き回しかと内心首を傾げたところで。
「これは八位の天使”星焔”様、お目通りかなうは望外の喜び!」
災厄の天使の傍らに当然の如く場を占めていた若い男が、大仰に腕を広げて進み出た。
その出で立ちは一見軍装のようだが、動き易さよりも装飾を重視したものであることは明らか。しかも今しがた身なりを整えたばかりのように僅かの乱れも無い。少し離れて、彼の従者と思しき者二人が控えている。
「申し遅れました。私は天軍第二軍の正統天使、ロベルト=シモンズと申します。どうかお見知りおき下さいませ」
一般天使ではないことを強調しつつ、男は優雅かつ大仰な仕草で一礼する。
(いやでも、この人羽根使いじゃないよね?)
疑問を差し挟む余地の無い彼の雰囲気にたじろぎつつ、大きな?マークを浮かべたアイルに、
「こちらのロベルト卿は、先々代に羽根使いを輩出されたランディール伯爵家に連なるお方で、第二軍の大使として来ておいでです。今回の任務において第三軍小隊の指揮を執っておいででしたが、上級天使様に指揮権が移譲された現在、男爵領を仕切っておられる代官殿との折衝の任にあたっておいでです」
背後に控えたバイロが、必要最低限の情報を囁く。
(あ、そっか。貴族部隊だから・・・・・・)
天軍第二軍は王侯貴族の出身者(下級貴族、豪商、地方地主なども含めて)で構成されれいる。
もちろん塔には上級天使や評議会を頂点とする階級が定められているため、彼らも塔に入城した際に、世俗の爵位を返上したり継承権を放棄したりしているのだが。
現実問題として、民主だ議会だという風潮の賑やかな昨今であっても、各国や各組織のトップは圧倒的に王侯貴族が占めているのであり、彼らと円滑に交渉を進める上で貴族階級の身分や知識は有用なのだ。故に、第二軍は実戦よりも外交が絡むような任務にあたることが多い。
(・・・・・・もしかして、何かややこしい事情でもあるんだろうか? 政治的とか)
一抹の不安を覚えつつ。アイルは、一人元気に場を仕切って代官以下を紹介していくロベルトの声を聞く。
「それで、今の状況はどうなっているんですか?」
気を取り直し、アイルは災厄の天使に目を戻した。
聖都の小料理屋から中央塔の転移の間経由で強制転移されて来る間に、状況をざっとは聞いていたが、最新かつ正確な情報は現地に行くまで判らない。
「それでは僭越ながら、私めがご説明申し上げましょう」
やはりと言うべきか。
一応お伺いを立てるように災厄の天使に会釈し、特に異論は無さそうだと確認してから、自ら説明役を勝って出たのは他ならぬロベルトだ。
災厄本人が黙っているのは当然として、普段は説明役を引き受ける黒衣の番人に助けを求めて目配せしてみても、第二軍の自称正統天使に遠慮してだろう、まるで反応を示さない。
「ここ、ボノレッティ男爵が領有する麗しき”白鹿の谷”を蹂躙せしは、人に憑依し狂わせる魔物。現在、第三軍三個小隊がこの館及び町の二か所で結界を展開し、避難民の収容は既に完了しております」
「それじゃあ、町のみなさんは全員避難してるってことですね!」
だが、ホッと胸を撫で下ろしたアイルに対し、ロベルトは芝居がかった手振り付きで憐みの眼を窓外に向ける。
「此度の魔物は、人から人へと憑依を繰り返し、その肉体を糧として更なる殺戮の刃を繰り出すという、まこと呪われし能力を有する悪鬼。そして憑依体を失い次の憑代を探すまでの間は、正体の無い黒霧と化す。どれほど分厚い扉を隔てようとも、隙間なく閉じこもったつもりでも、ほんの僅かな隙間さえあれば容易く通り抜けることが可能。故に、魔物のテリトリー外である町の外に逃げ出したか、防御結界の中に匿われた者以外、無事でいられるものなど皆無」
「!」
つまり、結界内に逃げ込めなかった者に助かる術など無い。故に避難は完了しているのだ。
「しかも形無きものを相手に、第三軍の羽根使い如きの武器では太刀打ち出来ぬ有様。上級天使様にご来臨いただきましたのは、そのような事情にございます」
(この人のこういう言い方、なんだかなあ)
アイルら上級天使を持ち上げる態度もだが、それ以外の者を殊更見下すような物言いには、どうしたって好意の持ちようがない。
だが、そのように噛みついてみたところで相手には理解不可能なのだろうし、何より時間が惜しいので、今は事実にのみ集中することにする。
ロベルトはあのように言うが、単純に羽根の能力のみを比較した場合、上級天使と一般の羽根使いとの間に、これと言って有意な差は無いのだという。つまり、第三軍の羽根使いがどのように特化された羽根を持つかにもよるが、普通に考えればこれは相当に深刻な事態である。
「それは、もしかして・・・・・・」
思わず言葉を詰まらせたアイルに代わって、随従であるバイロが。
「僭越ながらロベルト卿にお伺いいたします。その憑依する魔物というのは、第二段階に進化した魔物であると考えて間違いない、ということでしょうか?」
「そう判断するのが妥当かと、私めも考えます」
確認したバイロにではなく、ほんの僅かもアイルから視線を外すことなく、ロベルトは重々しく頷く。だが既に、ロベルトの態度にかまけている余裕など、アイルには無かった。
「・・・・・・まさか、本当に!?」
進化した魔物。
それはつい数日前、話題にしたばかりのことだった。
呼集のかからない平穏な日の、アイルの主な日課は二つ。
羽根を使いこなすための自主訓練と、バイロによる塔や魔物についてのレクチャーだ。魔物を倒すには羽根と魔物の両方を知る必要があるからだ。
『いいですかアイル様。魔物は殺戮を重ねることで力を増し、それに伴い能力さえも飛躍的に増大させます』
『より強力にパワーアップするんですね。僕が今まで見て来た魔物よりも、ですか』
上級天使に救援要請が来るくらいなのだから、アイルが遭遇した魔物は、それなりに強力な部類だと思われるのだが。
一撃で地面に大穴を抉る魔弾や、巨大化して襲い来る甲虫型眷属の団体をイメージして、アイルは握り拳に力を込めた。
『その通りではありますが、単純に強弱の話でもありません。魔物は、取り込んだ魔の力とより強く結びつくことによって、魔物本体が更なる変化を遂げるのです。こういった初期形態からの移行を、魔物の進化と呼んでいます』
『進化ですか・・・・・・単に強化するのではなく?』
進化とはまた、大胆な表現だ。
『強化というなら、魔物の全てが発生から刻を経るごとに存在を強化させていると考えられます。進化とはその程度のものではなく、もっと劇的に変化する現象を示しています。もちろん塔の歴史を通しても、報告事例はさほど多くありませんが』
劇的と聞いて、アイルは魔物が脱皮して羽化する様子を思い浮かべる。どどーんとパワーアップ。なかなか派手そうだ。
思えばアイルも、この時はまだまだ気楽であった。
『それに強化と言えば、魔物が物質面でより強固に存在を確立し、物理的破壊力を増大させることだけを想像されるでしょう』
アイルの心中を知ってか知らずか。難しく表現すれば、まさにそういうことである。
『違うんですか?』
『そういった例の他に進化の方向性としてもう一つ。物質としては限りなく希薄な存在になる代わりに、人間の精神に及ぼす影響力が増大した例が報告されております』
『ゆ、ユーレイじゃないですよね、それ』
身をすぼめ背筋を震わせたアイルに、幽霊の方が可愛げがありますねと、バイロは一言で片づけた。
『どちらにしても羽根による武器が唯一の対抗手段であることに変わりありませんが、これまでに倒して来られた魔物のように、単純な力技では済まないと思っておかれた方が良いでしょう』
『・・・・・・そんな相手に、有効な手段ってあるんですか?』
真面目な話。アイルの光弾は実体化した魔物には有効だろうと思う。
が、相手が幽霊のようなものだとすると、どうすればいいだろう。意志の疎通は?
『魔物の能力は個体差に大きく左右されるようですから、あまり先入観を持つべきではないでしょう』
『・・・・・・いっそ、進化する前に何とか出来ればいいのに』
『全面的に同意します』
『ええっ!?』
半ば冗談で言ったつもりだったのだが。バイロの同意に、アイルは目を丸くする。
『実際、魔物が発見されれば天軍が即応いたしますし、強制転移という莫大なコストをかけてでも上級天使様方を迅速に派遣出来る体制を取っているのも、それが理由の一端であると考えられます。魔物の跳梁を許すことは塔の威信に、ひいては存在意義そのものにも関わる、絶対にあってはならない事です』
塔の魔道技術の粋を結集した転移門の運営には、当然多大な魔道のエネルギーが必要不可欠。転移場所の特定から設定出来る強制転移には、常設の転移門よりさらに大きなパワーが必要だろうことは、魔道技術の知識が無くとも簡単に想像出来た。
『・・・・・・なるほど、納得です』
それを金額に換算すればどれくらいになるのだろうと思いつつ、アイルは大きく頷いたのだった。
実際に進化した魔物に相対する時のことなど、深く考えもせずに。
「・・・・・・ああ、それで」
アイルは身震いを隠すように、わざと明るい笑顔を作る。
「災厄の天使様ともあろう者がこんなところでノンビリしてるなんて、おかしいと思いましたよ。流石に君でも、進化した魔物が相手では迂闊に動けないってわけですか。と言うか、その程度の可愛げはあったんですね。少し、安心しましたよ」
「は、八位様・・・・・・」
表情こそにこやかでも、挑発にしかなっていないアイルの言動に、周りの者皆(おそらく番人もが)、一様にぎょっとした目を向ける。
もちろん、約一名を除いて。
(またガン無視ですか。前言撤回、可愛げなんて期待するだけムダですね)
大仰にため息をつきながらも、実はその反応の無さこそ想定内だ。むしろ、まるで変わらぬ態度の方にうっかり安堵してしまうのだから、慣れとは怖いものである。
落ち着いたところで、アイルは改めてロベルトに視線を向ける。
「魔物が進化したのは、大勢の人達を襲ったからですよね。どうしてこんなことになったのか、教えてくれませんか。魔物に対処するヒントになるかも知れません」
「ああ、八位様! 連絡の遅れをお怒りなのでございますね! ですが、私めの判断をお疑いなのでしたら、何と悲しきことか! しかも、私をお責めになるのは、間違いなのでございます!」
「いえ、そうじゃなく・・・・・・」
もっと早くに救援申請があればと正直思いはしたが、そんなものは今更である。云々するつもりなど全くない。
これは説明を求める相手を間違えたかも知れない。いや、うっかりロベルトに目をやってしまったあたり、まだ動揺が治まっていなかったのかも知れない。
だが、芝居がかった弁明の後の説明は、一応まともなものだった。
「白鹿の谷なる男爵私領の小さな町で、住民同士による異様な殺害事件が多発しているとの報を受け、第三軍三個小隊を率いましたる私が到着したその時には、魔物は既に進化を遂げていたと思われるのでございます! 調査いたしましたるところ、近隣の村が二つばかり壊滅させられており、どうやらこの魔物の仕業であったかと」
「壊滅・・・・・・では、村の人達は」
唇を噛んで絶句するアイルに、何か言い足りないことがあったかとロベルトは首を傾げる。
「このような辺境の村では要請が迅速に伝わらず、結果、救援が間に合わぬこともあるのです」
アイルの傍に控えていたバイロが冷静に補足する。仕方のないことだったのだ、と。
「・・・・・・わかっています。今は悔やんでる場合じゃありません。生き残った人たちだけは、絶対に救います。それこそが僕の務めなんだから」
「おお! 下々のことをそこまでお気にかけられるとは、星焔の天使様は何と慈悲深い! 其方らも御心に大いに感謝すべきでありましょう!」
アイルの決意のどこをどう合点したのか、ロベルトが室内の一同を見回し感嘆の声を上げる。
(下々? 慈悲深い? 感謝すべき? 僕ら天使が人々を救うのは当たり前のことなのに、一体何を言ってるんだ、この人?)
アイルはまじまじとロベルトを凝視する。ある意味、ブレない人だ。
無視出来るところは適当に無視することにして、アイルはつかつかつかと、災厄の天使のすぐ傍まで詰め寄った。
「いい加減そのだんまりには飽きました。作戦があるなら、そろそろ教えてくれてもいいんじゃないですか? それとも、まさか何も考えてないなんてことは・・・・・・」
言いつつ、更に詰め寄ろうとした時だ。
先刻アイルが入って来たドア辺りがざわつき出し、従僕の一人が代官の元へと取り次ぎに走った。
どうやら誰かが、入室許可を求めているらしい。
「今は非常事態です! そんな手順なんてどうでもいいから、誰でも早く入れて下さい! もちろん魔物の件なんでしょう?」
部屋中どころか扉の外まで届きそうなアイルの大声に、取り次ぎ係の従僕は狼狽えた視線で主を仰ぐ。
「もちろん、八位様の仰せのままに」
代官の男が口を開くより先にロベルトの指示が飛ぶ。
いちいち仕切るロベルトではあるが、話が早いのは正直助かる。
そして、大きく開け放たれた扉の向こう、衛士に先導されて姿を現したのは五人の男女だ。
俯いたまま入り口の壁際に並ばされた彼らは、室の中央を向いて膝をつくと、さらに一層頭を低くする。
身なりからすれば町の住人のようなのだが、年齢も背格好もバラバラで、どことなくちぐはぐな印象だ。
「大天使様方に申し上げます。たった今、案内役の用意が整いましてございます」
暑くもないのに額に大汗を浮かべた代官が、へりくだって報告する。
「案内って、何のですか?」
誰にともなく疑問を口にしたアイルに、応じたのはもちろんロベルトだ。
「魔物を討滅するにあたり、あの者らの協力は欠かせぬのでございます。それに、これは六位様のご指示にございますれば」
「君が?」
アイルが振り返った先には、空の椅子。
「ようやくか」
と、いつの間にか立ち上がっていた災厄の天使が、アイルの背後を通り過ぎた。
「待って下さい、僕は何も聞いてませんけど! それにあの人たちは誰なんですか」
「どうでもいいことだ。お前は邪魔せず見ていればいい」
「そうはいきません! 君はいっつも黙って済ませようとするんだから! 自分のやり方を通すなら腕ずくで、でしたよね! 教えてくれないんなら、ここで勝負したっていいですよ」
絶対に退くものかとの気迫を込めて、アイルは災厄の天使を睨み付ける。
「塵を集める」
「なっ・・・・・・!」
あっさりしたその台詞は、意味するところを考えれば、ああそうかと受け流すには重大過ぎた。
少し遅れ、災厄の天使の放った言葉の意味を理解した者らの間にどよめきが広がる。
事情を聞かされていなかったのだろう、怯えた悲鳴を上げる五人を、傍らの衛士が鋭い視線で睨み付ける。
「ちょっと待って下さい! それ、人を囮にするって言ってるように聞こえるんですけど!?」
「だからそう言っている」
周りの状況に全く頓着することなく、災厄の天使は肯定する。
「まさか、あの人たちを使おうって言うんですか? 魔物を憑り付かせて斬り捨てる、そういうことですか!? どうしてそんな非情なっ!」
「一番確実で効率のいい方法だ」
「だからそういう話じゃ・・・・・・一番確実? ってことは、もっと別の方法もあるってことでしょう! どうしてそっちを検討しないんですか! 要は、散り散りになってる魔物を全部キレイに消滅させられればいいんですよね! だったら・・・・・・」
アイルは頭をフル回転させて答えを探す。
「だったら、結界の外側一帯を灼き払ったらどうですか! 僕と君が全力で放射状に力を放てば、町の隅々にまで羽根の力を行き渡らせるくらい出来ますよね。ちょっと建物が壊れるかも知れませんが、避難済みなら巻き込まれる人もいないはず」
「無理だな」
「どうして!」
「それくらい、お前の随従にでさえ答えられる」
言われてアイルは、バイロを振り返った。
「畏れながら。人の生活空間には障害になるものが溢れています。幸運のお守りといったようなものでも、一つ一つは微弱ながら配置によっては厄介な遮蔽物になり得ます。そしてほんの一部でも討滅し損なえば、魔物はいずれ復活します。それに、全力を行使してしまった後では、上級天使様といえども不慮の事態に即応出来ますかどうか・・・・・・そのような賭けを、塔が作戦として認めることはないでしょう」
冷静に指摘され、アイルはぐうっと喉の奥で唸る。
「そ、それなら・・・・・・避難所を一つに集中して、空いた人員で町を囲む大きな結界を張ってもらいます! そして結界をだんだん狭めて行けば、灼き払う範囲は狭くて済みます! これならどうですか!」
だが、バイロの表情は硬い。
「それを実行に移すには、結界のエキスパートが相当数必要になります。今この地に居る人員を私共を含めて総動員したとしても、不慣れな連携では、結界を狭める際に隙が出来てしまう危険があります。魔物を確実に討滅するという目的において、六位様のご判断は決して不当なものではございません」
「君まで、そんなことを言うんですか・・・・・・やってもみないで、簡単に・・・・・・」
押し殺した声で、アイルは唸る。
「私の役目は、星焔様が確実に任務を果たされるよう、サポートすることでございます。星焔様がお望みなら、あの者らの代わりに、どうかこの身をお使い下さい」
「・・・・・・な!?」
思いがけない提案に、アイルはバイロを凝視する。
「忌むべき魔物を打ち倒す一助となれるなら本望。その程度の覚悟なら、星焔様の随従を拝命した時より、いえ、力なき身で天軍を志したあの日に決めております」
「・・・・・・僕は、誰であろうと犠牲にしたくないんです」
「十分承知しているつもりです。それが叶うなら本当に素晴らしい、とも」
諭すような口調で、バイロはアイルに微笑みかけた。
そして、
「よろしゅうございますか、六位様」
姿勢を正し、バイロは災厄の天使に向き直る。
「好きにしろ」
まるで関心無さそうに、災厄の天使が応じる。
「待って下さい!」
アイルはとっさにバイロを押しのけ身を乗り出す。
「その役、僕じゃダメですか!? 僕だったら少しくらいのダメージは平気だし、」
「星焔様!」
気色ばむバイロの声に重なって。
「お前をぶった斬るのは悪くないが。たとえ魔物を憑りつかせられたとしても、羽根同士が干渉する。論外だ」
災厄の天使は、アイルの胸に指を突き付ける。そのジェスチャーは”アイルの内の炎の結晶が無事では済まない”という事実を示唆していた。
「星焔様、ご決断下さい」
「・・・・・・」
否応ないバイロに、アイルは下を向いて唇を噛む。
「だが、随従を結界の補強に使えないとなると、更に時間が無い」
「・・・・・・それ、どういうことですか?」
「第三軍の連中の限界が近い。不定形の魔物だけに、結界への浸食力も相当のようだ。一番弱いのは、いつ破れても不思議ではない。それならそれで囮の人選などという手間は省けるが」
「まさか、結界の中の人を使うつもりじゃ・・・・・・!」
「このままだと、確実にそうなるな」
「冗談じゃありません! 一番弱い結界ってどこです? すぐ行って結界の補強をしないと」
「時間稼ぎにしかならない」
「いいから、どこだか早く教えて下さい!」
「町外れの作業小屋だ」
「作業小屋、ですか?」
その響きは、結界を張って逃げ込む場所にしては心もとなさ過ぎはしないだろうか。
何故そんな所にと、アイルが訝しんだ、その時。
「今何て!」
鋭い悲鳴が、広間を駆け抜けた。
叫んで身を乗り出したのは、連れて来られた五人の内の一人。まだ年若い女性だ。
「こら、控えろ!」
無礼があっては一大事と、両脇の衛士が長杖を交差させて制する。が、女性は怯むことなく、更に大きな声で叫ぶ。
「あそこ、弟たち居るです!」
他国訛りのたどたどしい言葉。
「乱暴はやめて下さい!」
衛士に怒鳴りつつ、アイルは女性に駆け寄った。
「あなたは、あなた方は何者なんですか?」
「私・・・・・・村の生き残り、です。魔物が、襲った、村」
そして、女性はアイルを見ながらキッパリと言った。
「囮必要、なら、私がなるです!」
第二十話 ウサギとオオカミ
アイルの制止を受けて、衛士は女性を押さえていた長杖を引いた。
「大丈夫ですか? ケガはありませんか?」
傍らに膝をついて気遣うアイルに、女性は居住まいを正しつつ、気後れすることのない瞳を向けた。
「私の話、聞いてくれまして、感謝です」
憔悴の色は隠せないにしろ、その様子はうなだれて入室した時とは別人のようだ。
それに、最初の印象よりも随分若い。
町娘のようなロングスカートを身に付けてはいるが、雪焼けした肌といい、無駄の無い細身の体躯といい、野外での仕事を生業とする者に違いない。
「大きな獣みたいな魔物、突然襲って来たので、母が、私たちを逃がしたのです。弟たちを守れ言ったのです。・・・・・・狩りに出てた父、兄、おじさん達、話聞いて村に助けに行ったのです。一人も戻って来なかったのです。村も、家も、無くなったのです。弟たち、私が守る、絶対です。囮、必要なら私が、なるです!」
たどたどしいエール語だったが、彼女は一気に言葉を並べた。
彼女がどれほど真剣で切羽詰っているのか、解ろうというものだ。
だが、アイルが口を開こうとしたその時。
『上手く取り入りやがって、この小ウサギが』
小さく、だがはっきりと、彼女を罵る声が聞こえた。
すぐ近く。
連れて来られた、他の四人の誰かから。
すかさず衛士が眼光鋭く長杖を握り直すが、その必要は無いと、アイルは手で合図する。
『堂々と言ったらどうなの痩せオオカミ。そもそもあんた達が魔物が出たことを知らせないから、村のみんなが死んだのよ』
燃えるような瞳で睨み返しつつ、女性が言い返す。
『知らせたさ!』
今度はハッキリと。言い返したのは、痩せぎすの小男だ。
彼も町人風の格好だが、横はダボダボなのに丈はツンツン、つまりサイズが全く合っていない。
『走ったさ。助けを求めにな! だが、すげなく無視したのはそっちの方だ』
『まさか!?』
『人を見捨てておいて、被害者ヅラとは笑わせる』
『町もあてにならないけれど、お前たちはもっとあてにならないわね』
痩せぎすの男に加勢して、壮年の男と、年配女性が声を上げる。
『そんなこと、あるはずない』
援護射撃を求めるように、女性は傍の老人に目を向ける。が、老人は両ひざをついてうずくまっているだけで全く頼りになりそうにない。
『一人良い格好しやがって、どうせ報酬が目当てなんだろう』
『村を失くした憐れな私たちをどうかこの町に住まわせて下さい、ってな。弱っちいウサギらしい発想だぜ』
『それの何が悪いの』
自分が頑張るしかないと決意したらしい女性は、小男をきっと睨む。
『悔しかったらそっちが囮を買って出ればいいんだわ。領主様がきっと、お金をどっさり恵んで下さるわよ。報酬貰ってどこでも行って暮らしなさいよ。小狡いオオカミにはそんな勇気は無いでしょうけど』
『何だと大人しくしていれば付け上がりやがって』
一対三の睨み合いは、さらに険悪の度合いを増していく。
場所が場所でなかったら、激しい罵り合いの掴み合いになっていただろう。だが、そうしない程度の分別くらいは持ち合わせていたようだ。
それでも。声を上げずにいられない。
抑えようとも抑えられない感情。
それは、何にでもいいから怒りをぶつけることでギリギリ正気を保とうとする、自衛行為のように思えた。
とは言え、いつまでもいがみ合っていられても、埒があかないことも確か。
「つまり、あなたとそのご老人が同じ村の出身で、そちらの三人が別の村の出身で、最初に魔物が出たのはそちらの村の方だったってことですね。気持ちはお察ししますが、お互いを責めてもどうにもなりませんよ。悪いのは魔物であって、ここにいる誰かではありません。そうでしょう?」
やんわりと割って入ったアイルに、睨み合っていた一人と三人は、ギョッとした顔で振り向いた。
その驚きようは、声をかけたアイル自身がビックリするほど。
思い当たることと言えば。
「ええと・・・・・・僕、聞くだけなら大体解りますから」
彼らのやり取りは、彼らの言葉で交わされたものだった。話の内容が解らなければ醜い言い争いとまでは分からないだろう、抑えた声で。
それが筒抜けだとは、誰も思わなかったのだろう。
(炎の結晶の力でどんな言葉でも聞き取ることが出来るんです、なんて言えないしなあ)
内心、アイルは苦笑する。
天軍では翻訳魔法の習得は一般常識らしいので、理解は出来ても喋る方までは出来ないアイルなど、実は全く自慢にはならないのだし。
気を取り直して、アイルは目の前の五人に目を向ける。
「では皆さんは、保護を求めてこの町に来られたんですね」
『はい、避難場所として作業小屋を貸して下さるかわりに、事情を説明しに来るように言われて、連れて来られたのがここでした』
「あ、あの、天使様、こ奴らはいつも自分たちに都合の良い適当な事を申します。どうか、あまり真に受けられませんよう・・・・・・」
と、慌てた様子で声をかけて来たのは代官の男だ。
何故だか額に汗をかいている。
「あの、どうかしたんですか? もしかして具合が悪いんじゃないですか?」
大変な状況なのだから無理も無いと、アイルは心配げに声をかける。と、
「ええ、そうでございますね。天使様にこれ以上の醜聞をお聞かせするのは不敬の極み。貴公の興味深い領地経営については、この私が後程ゆっくりお伺いいたしましょう」
そう言ったロベルトは、物腰こそ丁寧だったが、顔に張り付いた微笑は鼠を前にした猫のようだった。
(もしかして、この人たちは・・・・・・)
アイルが現地の言葉を解すると知って慌てたのは、当人たちだけではなかったらしい。
村人の口から都合の悪い事実を聞かれては大変と、慌てて間に割って入ったというわけだ。
魔物の脅威という重大事が進行中にも関わらず、彼らにとっての一番の重大事は、どうやら別にあるらしい。
(何だかな・・・・・・)
うんざりした気分で何気なく振り向いたアイルは、そこにあるべきはずの姿を見つけられずにハッとする。
立ち上がって部屋中を見回すが、目当ての人物は影も形も無い。
「バイロ、あの野郎は?」
「六位様でしたら、先ほど出て行かれましたが」
「気が付いてたなら早く言って下さいよ!」
唸ってアイルは頭を抱える。
鹿の頭のはく製や宝剣やライフルといった物がごちゃごちゃと飾られた壁の中央に、下手なコレクションを圧する迫力の大振りの曲刀が無造作に立てかけられている。
羽根の気配にしてやられた。
災厄の天使が曲刀を持たずに姿を消すことは、今回が初めてではなかったのに。
いくら実体化して見えていても、あれが羽根である限り、召喚一つで瞬時に持ち主の元に顕現する。
それは災厄の天使にしてみれば、羽根がどこにあろうと、持ち歩いているのと変わりないのだ。
「どこに行った、なんて聞くまでもないですね。結界が切れかけの作業小屋に向かったに決まってます」
災厄の天使が無茶苦茶だとは言え、いくら何でも自分から結界を破壊しはしないだろう。というのは楽観的過ぎるだろうか。
だが少なくとも、曲刀がここにあるということは、羽根が必要な事態にはまだなっていないだろうが。
「もうグズグズしているヒマはありませんね・・・・・・」
アイルは瞳を険しくして唇を噛んだ。
(やはり、結界の外だからと言って、何にでも食いつくほど馬鹿ではないか)
黒い霧の立ちこめる町を歩きながら、カリムはそんなことを思った。
別に、それを確かめたかったわけではない。
あのまま室に居続けることに興味が無かっただけだ。
保身に必死であることが見え見えの代官。
領主の弱みを握れるだけ握って、自分の手柄にしようと舌なめずりしている第二軍の羽根無し天使。
魔物が村を襲ったというなら、魔物の正体は間違いなく、最初に襲われた村に関わりのある者のはず。
だが、別に何の不思議もない。
そこに人間の暮らしがある以上、何の問題もなく日々過ごせると信じる方が目出度いのだ。
そんな連中が集まった日には、何がどうなるのか、結果は大体見えている。
それよりも。
「よろしかったのですか、六位様」
すぐ後ろで、そんな声がする。
最近入ったばかりの見習い番人だ。
見習いでも番人を名乗るからには、それなりに魔道能力も高く優秀ではあるのだろう。個人結界の展開の仕方一つを見ても、それは十分裏付けられている。
だが、能力以前に問題なのが、次から次へとつまらない事を話しかけてくる、面倒なその性格だ。
番人なら番人らしく、黙って任務にだけ専念すればいいものを。
随従を付けるかどうかは上級天使の任意であるのと違い、番人は番人の都合により、監視と報告のために同行している。
随従と違い、番人はよほど逼迫した事態にでも陥らない限り、魔物討滅任務に直接介入することは無い。
命令系統も異なるので、任務時の最高指揮権が与えられた上級天使であっても、番人に命令するには非常事態を宣言する必要がある。
非常事態は、おいそれと出せないからこそ非常事態なのであり、つまりはどこまでも面倒この上ない存在なのだ、番人という連中は。
「あのまま放置なさっては、八位様がどんな判断を下されるか分かりませんが。任務に支障を来すようなことになりはしませんか」
その番人が、重ねて問いかけてくる。
しかも馬鹿な質問だ。
判断も何も、選択肢など限られている。
集められた村人に報酬を約束して「協力」させるか、他で「協力」者を探すか。
もちろん他で探すヒマなど無いから、あの馬鹿が口を出せるとすれば、せいぜい報酬を上乗せするくらいのことだろう。
それとも。
一つだけ。他者の犠牲を嫌う、あの馬鹿の希望を叶える方法が存在する。
自分には、それを実行する理由が無い。だからやらない。
あの馬鹿の場合、失敗した時のリスクが大きすぎる。そして、失敗する可能性は、どうひいき目に見てもかなり高い。ゆえに、随従どもはその方法を決して口にはしないし、あの馬鹿が気付いて提案したとしても断固として止めるだろう。
が、土壇場の思い付きでとんでもないことをしでかすのが、馬鹿の馬鹿たるゆえんである。
「それはそうと六位様、今日の分の薬酒はもう召されましたか。これから魔物を相手にするのであれば、一刻も早く召されるのがよろしいかと・・・・・・!」
カリムが立ち止まったことで、すぐ背後を歩いていた番人は、危ういところでたたらを踏んだ。
(うっとうしいことばかりペラペラと・・・・・・!)
怒鳴りつけてやるのは簡単だが、中には怒鳴られることを構われたと勘違いして余計図に乗る輩もいる。
この番人は、間違いなくそういう類だ。
どうにかして追い払えないものか・・・・・・。
「早急に手配せねばならないことがある」
「早急に、でございますか?」
案の定、カリムが声をかけたことにオクターブ高い声で即応した番人だったが、その内容を聞くや、フードの下の表情は戸惑いに変わった。
「お言葉ですが、それは私の任ではないと考えます」
まず反論されるだろうとは思っていた。
「塔の威信に直結する問題であれば、それは全てに優先すると思うが」
魔物討伐に限定した話ではなく、塔の損益そのものに関わる問題ならば、番人とて無視は出来ない。
「これが、そのような案件だということでございますか?」
「裁定に上級天使が関与したとなれば、当然そうなる。だが八位も第二軍の準天使も、そこまで気が回るまい」
人の善意しか見たがらないお人好しの馬鹿は、その指示が必要になる事態を想像すらしないだろう。
鼻持ちならない貴族の頭では、領民の扱いは領主の権利であって、むしろ失態を犯してくれた方が弱みを握れて喜ばしいとすら考えるだろう。
「塔の威信に、僅かの瑕疵(キズ)もあってはならない」
「ですが・・・・・・」
「二度、言わせるつもりか」
この時初めて、カリムは番人に一瞥をくれる。
威圧感を込めた、鋭い一瞥を。
「は、し、失礼いたしました。お言葉通り、直ちに・・・・・・!」
一瞬にして気圧され震え上がった番人は、慌てて踵を返すや、元来た方へと駆け去った。
その姿には、番人としての威厳は欠片も存在しなかった。
(やれやれか)
抱く感想など特には無い。
ただ、番人の仕事の手際が悪いようなら、人員変更を申請する理由にはなるだろう。が、
(面倒だな)
手続きの手間、人選、予想されるやり取り、その他もろもろ。
(監視役など誰でも同じだ。それに、大して長い間のことでもない・・・・・・)
とりあえず、魔物との戦闘を前に、番人を巻くなどという体力のムダ使いをせずに済んだことを、良しとしておくことにする。
迷っている場合ではなかった。
アイルはセルジオとザハトを館以外の二か所の結界の強化に向かわせ、自身はザハトと共に魔物をおびき出す作戦を決行する。
協力者は、村人の四人だ。
いくら羽根が人間を傷つけないとしても、魔物に憑りつかれて無事でいられる保証は無い。それにいくら細心の注意を払ったとしても、魔物に憑りつかれた者によって害されずに済む保証も無い。
だが、最初に名乗りを上げた女性は、弟たちを守るのはもちろん両親の仇を打てるなら構わないと言って譲ろうとはしなかった。
彼女と対立する村の男二人も、ここで逃げたとあっては後で何を言われるかわかったものではないと、嫌々ながら立ち上がる。
口の達者な年配女性は、憐みの声も高く助命嘆願に出たため不参加。もちろんアイルに強制するつもりなど無かったのだが、彼女を宥めて理解してもらうのにしばしかかった。
意外だったのは、終始うずくまったまま無言を通していた老人が、参加を申し出たことだった。
彼らの勇気ある行動への対価として、二つの村の生き残り全員に対し、町で暮らすのに不自由のない援助を、代官自らの申し出で約束されている。
そして、アイルら六人は館の結界を抜け、馬車寄せも兼ねた館の前庭へ場を移した。
ここであれば、魔物と対峙するにも手頃かつ十分な広さがある。
(こうなったからには、僕がしっかりやらないと。魔物が憑りついた瞬間に、光球で包んで魔物だけを灼き尽くす! そうすれば、身体へのダメージは最小限で済む、はず・・・・・・)
魔物を憑りつかせるのだから全くの無傷とはいかないだろうが、被害を少なく留めることなら可能なはずだ。アイル次第で。
本当にそんな楽観的希望通りに事が運ぶかなどは、考えないことにする。今は少しでも、望みのある方に全力を尽くすだけだ。
が、そんなアイルの決意を嘲うかのように。
結界を出ればすぐに襲ってくるかと思われた魔物は、なかなか姿を現さなかった。
ただ、覆いかぶさった黒い霧のそこかしこから、ねっとりとした視線のようなものを感じる。
睨み返そうとすれば、その視線はふっと途絶え、また別の方向から見られている気配が伝わってくるのだ。
まるで、姿の無い肉食獣に狙われている気分。
『あれは狩られるのを待っている獲物。狩人なのは自分自身。それだけ忘れず、いつもの練習通り、的を狙うつもりで、落ち着いて・・・・・・』
呟き声に、アイルは隣の女性を振り返る。
『ごめんなさい。耳障りでしたか』
「いえ、今のは?」
『私なりの狩りの心得です。緊張してしまって、つい口に出てしまいました』
威勢良く志願したものの、やはり緊張していたのだろう。話しかけられたことで少しほっとした様子で、彼女は応える。
「それでは貴方も狩りをするんですね」
『はい、男衆ほどではありませんが、時々は』
「もしかして、それでウサギとオオカミ?」
『ああ、それは・・・・・・』
一応気を遣ったのか、女性は男二人に目を向けたが、緊張の面持ちの隠せない彼らは世間話する気にはなれないようだった。
『私たちが今いるこの町は、昔、大きな村だったそうです』
白鹿の谷と呼ばれていたこの地は、昔から良い鹿が捕れる狩場だった。
だが、先々代の領主がこの地を専用の狩猟場に定めたことで、村の運命は大きく変わる。
領主の行う狩りとは、貴族を大勢集めて獲物の大きさや数を競うスポーツのようなものだ。狩猟は何日もにわたり、夜毎に盛大なパーティが開かれる。
眺めの良い高台には豪華な別邸が築かれ、城下には大勢の使用人を住まわせるための家屋が町を作り、ついには元いた村人を完全に追いやった。
起伏の多い林野に、大きな村が作れるような地形はそれほど多くない。町を追われた村人は、町の東と西に分かれて住むようになった。
だが、その後も村人の受難は続く。
村人が鹿を捕ることは厳しく制限され、獲物を追い立てる勢子などの狩猟の手伝いの褒美として領主から下賜されるものになった。
それも手柄の多かった村の方に、より多くの恩賞が与えられた。
手伝い以外では、西の村では主に小動物を狩るようになり、東の村では鹿を荒らす害獣であるオオカミを狩って領主から報奨金を得ることが多くなった。
元は一つだった村は、そうして完全に別々の村へと変わっていった。
『もっとも、元は一つの村だったなど、今の若い者には全く実感の無い話でございますわい。考え方が変わってしまったのは仕方のないことなれど、せめていがみ合わ程度には仲良く出来ぬものかのう』
と、寂しげに締めくくったのは女性と同じ村の老人で、彼女の話を補足するうち、事情に詳しい老人の方が主な語り手になっていた。
『出来るわけがないだろう!』
老人の言葉が終わるかどうかというところで、痩せぎすの男が吐き捨てる。
『この前の冬だってお前らは、薬草を独占して、少しも分けちゃくれなかった!』
『あの年は薬草が不作で仕方が無かったのよ。それにそっちだって、山で怪我人が出た時に知らんふりしたじゃない。困った時だけ仲良くしようなんて勝手だわ!』
『あれは勝手に境界を越えて狩場を荒らしたお前らの方が悪いんだ。それにあの時は・・・・・・』
なおも言い募ろうとした痩せぎすの男は、しかし次の瞬間、飛び出さんばかりに目を見開き がっと裂けるほどに口を開き、爪を立てた両手で胸から喉をかきむしった。
「な、何が・・・・・・?」
「退がりなさい! 魔物です!」
アイルの声を聞く前に、バイロは呻いて立ち竦む村人らを退がらせながら防壁の魔法を展開する。
彼らを背に庇う格好で、今まさに体内に魔物を取り込みつつある男の前に、アイルは両腕を大きく広げて立ちはだかった。
第二十一話 魔物の闇
「ぐ、が、ごあっ・・・・・・!」
目を剥き身体をのけ反らせ、指で激しく中空を掻き、痩せぎすの男は苦悶する。
男の突然の狂態を目の当たりにした村人らに動揺が走る。
いくら囮になることを覚悟していたとは言え、その様子を想像するのと実際に見るのとでは違う。
眼前で起こっていることに心が拒否反応を起こした彼らは、まさに恐慌一歩手前の状態だ。
だがアイルにはハッキリと見える。
苦悶する男を中心にして、黒い霧がごうごうと渦を巻くのを。
「みんな落ち着いて! 彼なら大丈夫、僕がすぐに助けますから!」
「いけません、星焔様!」
男を救うために羽根の力を発現させようとしたアイルを、鋭い声が制止する。
「まだ魔物は男の身体に入り切っていません。今しばらく、ご辛抱下さい」
言いながらバイロは、残った村人を背にしつつ、魔法具を付けた両腕を眼前で交差させ防壁の魔法を展開する。
「でもバイロ、すぐにでも助けないと彼は・・・・・・」
「お忘れですか。この作戦は魔物の殲滅が目的です。魔物を僅かでも取り残せは、この先何人もの犠牲が出ます。彼一人の身を惜しんで、全てを台無しにするおつもりですか」
「でも、だからって・・・・・・」
バイロの言っていることはよく解る。
だが、男の内に魔物が入り切るのを、彼の苦しむ様を眺めながら待つのは、アイルにとって耐え難いことである。
それは瞬き一つの隙。
「ぐうあああっっっ!」
くぐもった叫びと共に、男の細い腕が伸びる。
細身であるという身体の範囲をはるかに超えて、アイルの脇をすり抜け、一直線に。
つい先刻まで互いにいがみ合っていたことも忘れ、しっかりと寄り添い固まっていた村人たちに向かって。
「ヒッ!」
同士討ちが危ぶまれたため武器の所持を許可されなかった彼らには、対抗手段が何も無い。せいぜいが両手を翳して頭を庇い身体を縮めることくらいしか。
が、男の腕は村人に届く直前に、バイロの展開した防壁に阻まれてギンッと鋭い音を立てた。
見れば、弾かれた男の腕の先は、真っ黒い槍状に変化していた。
魔物に憑りつかれた痩せぎすの男は、虚ろな目を見開き、ぽかりと開いた口からくぐもった唸り声を漏らしつつ、槍と化した両腕を二度三度と振るい、その度にバイロの防壁に弾かれる。
その攻撃は全くの徒労であるように思われる。
しかし、防壁の力も無尽蔵ではない。一撃の破壊力はさほどではなくとも、繰り返し打撃を受け続けていれば、遠からず破られてしまうだろう。
「バイロっ!」
「大丈夫、また保ちます! 星焔様はそこで待機を!」
「は、はい・・・・・・」
魔物が男の内に入り切るまで待つ。
入り切った瞬間を見極め、的確に魔物を屠る。
それがアイルに課された役目。
アイルは今にもあふれ出ようとする羽根の力を押し止めるため、両手で両腕を強く掴む。腕に爪が食い込み、じわりと血が滲み出す。
頭の中で鼓動が脈打つ。息が出来ないわけでもないのに、息苦しくてアイルは喘ぐ。
(まだか、まだかまだかまだかっ!)
篝火に照らされた光景は血塗られたように赤く揺らめき、時間が足踏みしているかのように目に入る光景は変わらない。
(いつまで・・・・・・こんなものを、いつまで・・・・・・っ!)
アイルの鼓動だけが、早鐘となって響き続ける。
だが、それでも。
黒い霧は徐々に男の周りだけに渦を巻いて収束し始める。
バイロの防壁も、まだ何とか保ちこたえている。
(もう少し、あともう少しで・・・・・・)
見守るアイルの腕、羽根の光がその強さを増す。
だが、祈る気持ちでアイルが凝視し続ける中。
ぐしゃり。
くぐもった、耳に障る音。
男の腕が折れ砕けた音だ。
「そんなっ!」
目を見開き息を飲むアイルの前で。
両腕をダラリと垂らした男は。
何事もなかったかのように肩を持ち上げると、遠心力で動かぬ腕を振るう。
ぶおんっとしなった腕が、防壁にぶつかってべきべきと嫌な音を立てる。赤黒い飛沫が辺りを染める。
これまでの打撃で厚みを欠いた防壁が軋み、魔法具であるバイロの腕輪にバキッと大きく亀裂が入る。
「ダメですっ! もう止めて下さいっ!」
アイルは思わず、男に向かって右手を伸ばした。
バイロの防壁の魔法は、あと一撃を待たずに砕け散る。
だが、それよりも。
虚ろな目で、むしろどこか愉悦を含んだ表情で、折れた腕を振り上げ続ける男の姿を、これ以上見ていたくなかった。
もちろん、アイルが少しくらいが手を伸ばしたところで、男との距離は大して縮まらない。
しかし、アイルの命令を待たずに、その意を汲み取って。
羽根は瞬時に手甲となって具現し、眩い光を迸しらせた。
形を成した光は薄布のように、男の身体を抱き留める。
労るように、慈しむように。
アイルの行為は、目の前で倒れた者を咄嗟に抱きとめるといった程度の反射的なもので、ゆえに、それは間違いだった。
「星焔様!」
「!」
バイロの声が飛ぶより早く、アイルは自分の失態に気付く。
どれほど耐え難いことだったとしても。
羽根を解放すべきではなかった。
命令未満の中途半端な発現では、羽根は魔の力に対し闇雲に襲い掛かることしか出来ない。このような霧状の魔物に向けて、それは喧嘩を売る程度の刺激にしかならない。
もしもではあるが。
アイルが男に跳びつき素手で羽交い絞めでもしていれば、その行為が成功しようが失敗しようが、計画そのものに支障は来さなかっただろう。
あるいは、どうせ羽根を使わずにいられなかったのなら、次善の手段として男の周囲を広範囲に一気に灼き払っていれば、魔物の殲滅こそ出来なくとも、その力を大幅に削り落とすことは出来たはずだ。
魔物は一定のテリトリー内の人間を滅ぼし尽くさない限り他の地へ移動出来ないという制約があるから、最初にアイルが提案したように時間と人員をかけて町全体を包囲し殲滅するという手段が、有効になったかも知れない。
そこにかかる人員と手間の大きさを考えれば、災厄の天使が激怒するだろうことは火を見るより明らかだったが、それでもアイルが怒られるくらいで済むのであれば安いものである。
アイルは咄嗟に光の帯を浄化の光球に変化させようとした。
が、間に合うはずもない。
未熟なアイルをあざ笑うかのように、男の体外へと一気に吐き出された魔物は、光の帯をすり抜けてあっという間に拡散する。
一瞬にして、辺りは再び魔物の霧に覆われる。
篝火の灯りさえ意味をなさないほど、漆黒の闇の中に。
作戦は、完全に失敗だ。
「バイロッ! 簡易結界を!」
今はのん気に反省している場合ではない。
こうなってしまっては、残った者の身を守ることが先決だ。
随従であるバイロは普段から簡易結界を所持しているから、彼一人なら何とかなる。
アイルは手甲から発する光炎で黒霧を牽制しつつ、身を寄せ合っているだろう村人たちを探す。
作戦が失敗してしまった以上、同じことを繰り返すのは愚かなことだ。
アイルの予想以上に、憑依の魔物の力は成長を遂げている。
村人一人二人の献身では太刀打ち出来ないほどに。
幸か不幸か、こっちに魔物を引き付けている間は、他の避難場所の結界の心配はしなくてもよいはず。
となれば、防御に徹して援護を待つべきだろう。
(また思いっきり馬鹿にされるんだろうな・・・・・・)
ふと思った瞬間に、アイルの胸中に苦いものが広がる。
(まさか僕は、あの野郎をあてにしているのか? あんな、人を人とも思わない薄情なヤツを、こんな時に・・・・・・!)
そう。必要とあればきっと、災厄の天使はどんな非情な手段も厭いはしない。
だがそうと判っていてさえ。
魔物に憑りつかれた男の姿が、アイルの脳裏に焼き付いて離れない。
あの、背筋が凍りつくような光景・・・・・・。
心が怖気る。
あれをもう一度繰り返すなど、考えただけでどうにかなってしまいそうだ。
(みんなを守りたいのに・・・・・・誰も失いたくなんかないのに・・・・・・もう、二度と・・・・・・二度、と・・・・・・?)
僅かな引っ掛かりが疑問の形を成すより先に。
アイルは、腰が砕けたように地面を這ったまま虚ろな目を見開いている村人らを見つけた。
翳した手甲から発する光炎が、彼らに寄り付こうとする黒霧を払拭する。
「みなさん大丈夫ですかっ!」
彼ら一人一人の内に魔の気配を探ったアイルは、ややあってホッとする。
強い魔気にあてられて正気を失くしてはいるが、誰も魔物に憑依されてはいないようだ。
「バイロ! こっちは無事です! 君は平気ですか? ・・・・・・バイロ、返事して下さいっ!」
重ねて呼ぶが、バイロの応えが無い。
そう言えば、簡易結界を展開した気配も、無い。
と、黒霧を透かした先に、人の輪郭が浮かんで見えた。
「そこですか、バイロッ!?」
だがバイロと思われた人影は、アイルの呼び声に全く応えず、防御の構えすらも取らず、ただそこに立ち尽くしている。
そして、人影の周りには、一段と濃い霧が渦を作り始めている。
「まさか・・・・・・」
悪い予感が脳裏を過る。
『・・・・・・あの者らの代わりに、どうかこの身をお使い下さい。忌むべき魔物を打ち倒す一助となれるなら本望。その程度の覚悟なら、既に決めてございます・・・・・・』
バイロの言葉が蘇る。
魔物に憑依された痩せぎすの男の姿とともに。
「まさか君は、本当にやろうとしてるんですか? 自分から囮になるって言うんですか!? ・・・・・・囮になった彼がどうなったか、その目で見ていて、なのに・・・・・・」
アイルは信じられない思いで、バイロの姿を凝視する。
「どうしてそんなことが・・・・・・」
アイルは失敗したのに。
二度目だから成功するなど、間違っても言えはしない。
バイロが囮になったところで、痩せぎすの男の二の舞になるだけ、下手をすれば命を落とすことにかも知れないのに。
「どうしてそんなことが出来るんですか。何の為に、何を信じたら、そんなことが・・・・・・っ!」
この場に災厄の天使はいない。
アイルが木偶のように何もしなければ、バイロの行為は本当に無駄になってしまう。
「僕が・・・・・・この、僕が・・・・・・っ!」
アイルは強く拳を握りしめると、バイロを取り巻く黒霧の魔物をキッと睨み付けた。
「許さない! お前なんかに、バイロを好きにさせたりしない! そんなに憑りつく者が必要なら、僕に憑りつけばいい!」
その吠え声が聞こえたのか、黒い渦に微かな乱れが生じる。
「どうした! 怖いのか! お前を滅する力のある、この僕が! だけど、知ってるんだぞ。本当は欲しいんだろう! 欲しくてたまらないんだろう! ただの人間など比べものにならない、僕の力が! 力の源である、炎の結晶が! お前には、無視出来ないんだろう!」
ああ、そうだ。
吠えながら、アイルは思った。
どうしてもっと早く、いや、最初からこうしなかったんだろう。
何を迷っていたんだろう。
誰かの犠牲など、要らなかったのだ。
魔物が時間をかけて憑依してみせるのは、デモンストレーションでもあるのだ。
魔物の本能を満たす行為であるとともに、炎の結晶の所持者という魅力的な獲物に対する、示威行為。
だからこそ、アイル自身が、一番囮に相応しかったのだ。
「結晶の持ち主が、タダでくれてやると言ってるんだぞ? 要らないのか? もちろん、そんなことはないだろう?」
凝縮した光球を解き、手甲を消し去り、羽根の力を完全に解除して、アイルは黒霧の魔物に対峙する。
「判ったら、バイロから離れろっ! そしてさっさと僕を食らうがいい!」
無茶苦茶な要求だ。
居直るにも程がある。
が、そんなアイルの気迫に圧されるように、黒霧の魔物はバイロから離れると、アイルの周りに渦巻き始める。
まるでそれが、自らに与えられた責務であるかのように。
黒い霧は静かに急激に、アイルの内へと吸い込まれていく。
その最後の一片までもが消え去った後には。
しんと静まり返った前庭で、篝火の炎だけが、地に伏し横たわり微動だにせぬ人影の群れを妖しく浮かび上がらせていた。
(気分悪い)
前庭の惨憺たる有様を見下ろし、災厄の天使は苦々しく舌打ちした。
別に、星焔の天使に思うところがあって到着が遅れたわけではない。
どうしても確かめたいことを優先した結果として、魔物を後回しにしたことは認める。
だがそれは、カリムにとってどうしても確かめておかなければならないことであり、その結果次第ではカリムの今後の行動決定に大きく影響する問題であったから、どうしても譲ることは出来なかったのだ。
ただ、結果は今回も空振りで、元々「可能性が全くのゼロではない」程度の期待しか持っていなかったにしても、やはり滅入らずにはいられない。
それだけで十分最悪な気分だというのに、戻ってみれば死屍累々(文字通り死んでしまったわけではないが)の惨状である。
(馬鹿が。あれだけ忠告してやったのに、ことごとく無視しやがって)
ほんの僅かの時間稼ぎも出来なかった馬鹿を責めるべきか、馬鹿でも多少は粘れるだろうと根拠なく期待してしまった自分の判断を悔いるべきか。
こうなることを想像しなかったわけではないが、よりにもよって、これはかなり最低な部類と言えるだろう。
魔物を前に、逃げ出すなど。
ここで何があったか、一瞥すれば大体判る。
村人を囮に使うことを了承しておきながら、一度は覚悟を決めておきながら、あの馬鹿は耐えられなかったのだ。
一体何度経験すれば学習するのか。
目の前で行われる非道は、それは許しがたいものだろう。
だが同じように、誰も知らぬところで為される非道も、忘れてはならないし、許されるべきではない。
目にしたものだけに囚われ過ぎれば、根本を見失う。その結果がこれだ。
あの馬鹿は自分に魔物を憑りつかせることで、目の前の苦痛から逃げ出した。
恐慌にとらわれただろう村人たちは、それでも最後まで逃げなかったというのに。
今一度、肝に銘じるがいい。
天使は魔物を討滅するもの。
世界の破滅を救うもの。
断じて、個人を救済するものに非ず。
天使の名の下に、世界の為に命捧げよと命じ、世界に殉じる栄誉を祝福する。
それがこその、天使であると。
(・・・・・・ったく)
やってしまったものを、とやかく言っても仕方がない。
内心で舌打ちし、カリムは思考を切り替える。
今現在問題にすべきなのは、いかにあの馬鹿の内の魔物を滅するかということだ。
どんな魔物でも犠牲者の精神を浸食するものだが、当然のことながら、憑依の魔物は特にそれが顕著である。
あの馬鹿が自分で何とか出来るのならいいが、この期に及んで変な期待を持つ気には到底なれない。
馬鹿ごと一刀両断してしまうのが一番簡単ではあるのだが。問題が一つ、無きにしもあらず。
逡巡する余裕はない。
憑依の魔物が炎の結晶の力を得て更なる進化を遂げる前に、決着しなければならない。
ガタゴト、ガタゴト、ガタゴト・・・・・・
規則正しい揺れが、身体を包む。
敷布ごしに伝わる、車輪が石畳を踏みしめる振動音。
目を擦りながら注意深く寝返りをうつと、目の前に大小の木箱の山。
馬車の揺れに合わせて、側壁の高窓から天井に仄明るい陽光が踊る。
防寒兼内装用のタペストリーを重ねた側壁に沿って、幾つもの木箱や収納箱や本箱が固定されていて、四角い馬車の中に人間用のスペースは二人がギリギリくっついて眠れるほどしかない。と言うか、そもそも分厚い敷布が敷かれている場所自体が、床板ではなく平たい木箱の上という有様である。
ただでさえ衣装箱など日用品の他に薬草類や大きな本の山が幅を利かせているというのに、商売っ気の強いおじさんの荷物まで預かったりするからだ。もちろん、同じ隊商の家族とは言え運び代はしっかり頂く。それにしても・・・・・・。
(何だか懐かしいな)
ふと、そんなことを考えた自分をおかしく思う。
毎日見慣れた馬車の中なのに、まるで長い間どこかへ行っていたような感慨を抱くなど。
ガタゴト、ガタゴト、ガタゴト・・・・・・
カッカッカッカッカッ・・・・・・
荷物を満載した馬車の車輪が、何だか軽やかなリズムを奏でる。バコボコとした揺れも、馬車を曳く「がんばり屋さん」と「ビクビクさん」の歩調もどこか楽しげだ。
これは道がよく整備されている証拠だ。
ということは。
きっと、間違いない!
これから向かうのは、賑やかで大きな街だ。
もしかしたら祭りか何かがあるのかも知れない。
歌い出したくなるような、ウキウキした気分が溢れて来て。
「ねえ、キーシャ!」
両手をついて掛け布の中から身体を起こしながら、アレクは御者台に座っているだろう家族の名を呼んだ。
第二十二話 玻璃迷宮
馬車で移動する時は、悪路や天候の急転や予測不能のアクシデントがつきものだから「荷は出来るだけ固定して小物類は付けておく」と約束したはずなのだが。
昨夜の残りのパンや小鍋、キーシャが読みかけの本や道中でゲットした薬草の袋などが、ついつい床板の上に散らばっていたりする。それらを脇に退けて足の踏み場を確保しながら、アレクは御者台に続く幌を押し開ける。
「ねえキーシャ、次の街はどんな・・・・・・あれ?」
そこに当然あるはずの姿を探し、アイルは広くない御者台に立つ。
「キーシャ、ねえ、どこなのキーシャ!」
だが「どうしたアレク」という返事は聞こえない。
「ねえ、がんばり屋さん、びくびくさん、キーシャを知らない?」
目の前を歩く荷馬の丸い背中に聞いてみるが、二頭は前の馬車に遅れを取るまいと歩くのに一生懸命でヒンとも返事をしてくれない。
二頭の手綱は、綱受けに預けられたまま。
「どうしたんだろう? キーシャが僕に黙ってどっか行くなんて・・・・・・」
居てもたってもいられずに、アレクはえいっと御者台から石畳へと飛び降りる。
”がんばり屋さん”と”びくびくさん”の太い足を追い越して、前を行く馬車に追いつく。
明るい若草色の、箱型の馬車。
御者台には、一人の中年男。
「ねえ髭おじさん、キーシャを知らない?」
のんびりと煙草を燻らせていた髭おじさんこと根の無い草の民の家長は、御者台からアレクを見下ろして「やあ」と片手を上げた。
「どうしたね、身体の具合はもういいのかい?」
「平気。そんなことよりキーシャ見なかった?」
「おや、何を言っているんだい」
髭だらけの顔の中で、おじさんの目が笑う。
「彼女なら、ほら、あそこじゃないか」
煙草を持つ手で指し示されたのは、連なって進む馬車のずっとずっと先の方。
「ありがとう!」
背中で礼を言い、アイルは一目散に駆け出した。
カリムの羽根を用いれば、星焔の天使の内に侵入した魔物を討滅することは出来る。
が、星焔の天使の命と同化した炎の結晶が無事で済む保証は、限りなく小さい。
かと言ってこのまま手をこまねいていては、魔物は星焔の天使の結晶まで浸食してしまう。そうなれば、世界を破滅させるのにこの上ない力を魔物に与えてしまうことになる。
「畏れながら。聖魔道具を使えば八位様の肉体から炎の結晶を切り離すことが出来ます」
年若い番人が重ねて進言する。
「それがお前の判断か」
「監視人としての判断です。経験の浅い上級天使に判断ミスはつきものです。六位様が忠告なさったのですから、結果どうなるかは八位様もご承知のはず。ですから六位様が気に病まれることは何一つございません」
(誰が気に病むものか)
反論を内心に留めたのは、下手に反応して年若い番人が変に絡んで来ては面倒だと思うからだ。
「それに炎の結晶さえ無事なら、八位様を復活させることは可能です。ご心配には及びません」
(何の心配だ)
聖魔道具とは、白亜の塔の魔道技術の粋を凝らして造られた宝具である。魔杖型や宝珠型など用途によって形状は異なるが、込められた魔力の大きさは世間に出回る聖法具と名の付く物の比ではない。高位の魔物や羽根と並んで、炎の結晶に影響することの出来る数少ない法具の中でも最上クラスの代物である。
羽根を使って結晶を切り離すことはもちろん可能だが、聖魔道具で予め切り離せるのなら、その方がより確実には違いない。
あるいはカリムだけに任せては、戦闘中をいいことに冗談抜きで結晶まで消し飛ばしてしまいかねないと思われているのかも知れない。
理由がどうあれ、それはもちろん熟練の魔道師が細心の注意を払って扱う場合に限ってのことであり、聖魔道具が封印の施された保管庫で厳重に管理されている理由は、その影響力の大きさにも増して取扱いの難しさ故とも言われている。
ただし。
肉体から結晶を切り離せば、確かに結晶を破壊することなく憑りついた魔物を殲滅出来る。
かわりに、結晶を切り離したアイルの肉体は回復能力を失う。上級天使の回復能力は、結晶と同化していることが前提なのだから。
羽根で魔物消し去ったとしても、一度蝕まれてしまった肉体を治癒することは出来ない。
つまり、再同化に手間取れば、回復に相当な時間を要することになる。
下手をすれば再同化を諦め、新たな肉体の用意が必要になるかも知れない。
どちらにしても「星焔の天使」は復活可能。
だが、それは必ずしもアイルとしての復活を意味しない。元の人格と記憶が保持される保証はどこにも無いのだから。
(それも悪くない。これ以上馬鹿の面倒を見なくて済む)
一度深淵を覗いて来れば馬鹿も少しは治るだろうし、性懲りも無く馬鹿のままだったとしても、自分とはもう再会することはないだろう。
(ま、申請が通ればの話だが)
当たり前のことだが、聖魔道具の使用は最終手段と言っていい。
その程度には、上級天使の存在は貴重だ。特に「新しい」上級天使は。
断言してもいい。
星焔と災厄が揃って深刻な状況に陥いりでもすれば(そんな事態は断固願い下げだが)一も二も無いだろうが、今の状況で許可が下りることは無いだろう。
要するに年若い番人の提案は、彼自身が聖魔道具の使用資格を有し、いざという時の判断が任される立場にあるという当たり前の(それが上級天使に同行する番人に必須の条件なのだから)事実を、自身で主張したに過ぎないのだ。
「好きにしろ。だがその前にここらに結界を張れ。万一にも魔物を取り逃がすなど割に合わない」
言い捨て、カリムは両手を大きく広げた格好のまま立ち尽くす星焔の天使に歩み寄る。
「お待ち下さい、結晶の分離まではこの私めがお手伝いを・・・・・・」
「番人風情が、出過ぎるな」
言い募ろうとする年若い番人を一顧だにすることなく。
カリムはピクリとも動かない星焔の天使に向け手を伸ばす。
(仕方ない。こんな歪な世界でも、まだ朽ちさせるわけにはいかないからな)
契約の魔物が世界という花に害なすなら、天使は害悪を摘み取る庭師の鋏。
枝葉が害悪に侵されたなら、枝葉ごと害悪を駆除するのみ。
切れ味を失った道具も同じこと。処分し新たなものと取り換える。
ただそれだけの、当たり前のこと。
世界を永らえさせるための必要な処置。
だが、切り落とされるべき枝葉は、ただで切り落とされまいと茎にしがみつき抵抗する。
錆びた道具ですら、磨き研ぐことで切れ味を失うまいとする。
「素直に魔物ごと滅ぼされるか、なけなしの抵抗を試みるか、好きな方を選んでいいぞ」
カリムの手の中に、大振りの曲刀が具現する。
その冷たい微光を纏う切っ先は、星焔の天使の喉元を寸分の狂いなく捉えていた。
「ねえアレク、息せききらしてどうしたの?」
「また熱出して倒れても知らないわよ」
「おい足元気を付けろよ転ぶぞ」
「大丈夫です! すみません、急いでるんで、後で」
馬車の列を追い越して走るアレクの頭の上、御者台や荷台から顔を出した家族の声が降ってくる。
最初こそ一々受け答えしていたのが、誰に問うてもキーシャに対する答えは同じで、いつからかアレクは生返事を繰り返すようになっていた。
どこまでも続く馬車の列を、大きな車輪や荷馬や驢馬の横を、追いついて、追い越して、また次の馬車の横を抜けて、前へ、ただ前へと・・・・・・。
(あれ、家族の隊列ってこんなに長かったっけ?)
アレクはふと、首を傾げる。
途端に。
馬車の列がすとんと途切れ、目の前は一面の草地が広がる。
隊列を止めて休むのにこの上ない。
(きっとここだ! キーシャはこのどこかにいる・・・・・・)
そんな根拠の無い確信が、僅かな疑問の芽を吹き飛ばす。
「キーシャ、いるんでしょ! お願いだから、ねえ、返事して!」
さわさわ
さわさわ
見渡す限りの草の海を、風だけが渡っていく。
「キーシャ・・・・・・僕が悪いことしたんなら謝るから。もう薬が苦いなんて文句言わないから。本読むのがつまらないなんて言わないから。何でもするから。だから、意地悪しないで、出てきてよ!」
「本当に? それは嬉しいな」
不意に耳元で囁く声。
後ろからぎゅうっと、抱きしめられる感覚。
さらりと流れる銀灰色の髪。
「キーシャ!」
すぐ傍らに咲く笑顔。
「どうした。そんなに大声出して」
「だって、ずっと探してたんだよ! 本当に、今までどこにいたんだよ!」
アレクは身体を捻ると、今度は自分がすらりと細い身体を捕まえる。
「ごめんごめん。だから拗ねるな」
いつもと同じさっぱりした笑顔に、アレクはようやく肩の力を抜く。
「それより、何でもするって言ったよね」
「え? それは、だって、ほら・・・・・・」
あなりにも不用意な自分の発言を思い出してしどろもどろになるアレクに。
「それは、こんなことでもいいのかな?」
ドンッという衝撃。
腹部にじわりと広がる熱。
熱い、痛み。
「な、にを・・・・・・!?」
痛みを押さえた手に、異物が触れる。
固く細い、ナイフの柄。
「キ・・・シャ・・・?」
アレクは自分の目でそれを確かめ、視線を上げてキーシャを見る。
「あれ、いけなかった?」
そこにあるのは、いつもの笑顔。
「何でもするってのは嘘だったか」
「どう・・・・・・して・・・・・・」
「なーんてね、冗談じょーだん!」
その途端、腹部に感じていた痛みが消え失せる。
嘘のように、綺麗さっぱり。
ナイフも、傷も、流れ出る血も、全てが跡形も無く。
「びっくりした? 私がお前を傷つけるわけないじゃないか」
屈託ない笑顔がそこにある。
何だ、冗談か。びっくりした。
そう言って笑おうとして。
アレクは口元を歪める。
冗談と受け流すには衝撃が大き過ぎて。
「もちろん、私はそんなことしないよ。だって、」
笑顔を浮かべたキーシャの口元に、一筋の赤い線。
「それをするのはお前なんだから」
「・・・・・・!!!」
キーシャの胸に、鮮やかな赤が広がる。
刺さったナイフの柄を茎にして、大輪の花が裂きほころぶ。
花は瞬く間に広がって。
草原だった大地を赤く染める。
蒼かった空を赤く染める。
赤以外の色を失くした湖面に。
キーシャの身体が、足元からゆっくりと沈んでいく。
声を上げることも出来ず。
動くことも出来ず。
アレクはただ、それを見ている。
沈みゆく、キーシャの笑顔を。
どれくらい経っただろう。
墨色の湖面を眺めていたアレクは、ポンと肩に置かれた手に、ビクッとして振り返る。
帽子の下の浅黒い髭面が、やあ、と笑う。
「・・・・・・髭おじさん?」
「どうしたね、こんなところで」
「・・・・・・」
何も言えないでいるアレクに、家長である髭おじさんが問いかける。
「キーシャは見つかったかい?」
ビクリと、アレクの肩が震える。
「あんなに探していただろう。もういいのかい?」
「・・・・・・」
「なに心配はいらんさ。わしら皆で探しているところだ。キーシャがいないと何かと困るからなあ」
「・・・・・・おじさん、あの、」
言いかけたアイルを、煙草の臭いのする手で遮って、おじさんは顔を上げる。
「おや、見つけたらしいぞ」
「え?」
「キーシャだよ。さあ、行こう。きっとお前を待っとるぞ」
「待ってよおじさん、キーシャは・・・・・・!」
髭おじさんが指さす先を見やったアレクは、喉を鳴らし息を飲む。
池の対岸で、長い髪の女性が笑いながら手を振っている。
「キーシャ!」
立ち上がり、アレクは叫ぶ。
間違いない。キーシャの姿を間違えるはずがない。
「そうか、あれは嘘だったんだ! もちろんそうだよね!」
波打ち際をアレクは走る。池をぐるりと迂回して、一目散に目指す先へと。
「やあ、キーシャ」
「探したよ」
「あんたがいないと私ら困るからね」
「まったくまったく」
その間にも、キーシャの周りに家族のみんなが集い始める。
「おお、間に合った」
そして、最後には髭おじさんが。
大きなお腹を揺らしながら、陽気な笑顔でキーシャに近づく。
何気ない仕草で、まるで握手を求めるように、右手がさし延ばされて。
その手には、一振りのナイフ。
その意味をアレクが理解するのに、一呼吸の間が必要だった。
髭おじさんがナイフを手にするのは、特に珍しい事ではない。
と言うより、ロープを切るのにも、狩った野兎をさばくのにも、チーズを切り分けるのにも、板切れに細工を施すのにも、とにかく普段の暮らしに必要なものだから。
家族の誰もが、当たり前に持ち歩く道具の一つなのだから。
「キーシャ、危ない逃げて!」
アレクが叫ぶのとどちらが早かったか。
髭おじさんの手を離れたナイフは、キーシャの腹へと吸い込まれて。
細身の体が大きく傾ぐ。
それを合図に。
家族のみんながキーシャに詰め寄り取り囲む。
その手には、それぞれのナイフが。
「やめて、サラおばさん! ミリィ! メリッサ! ドミトリ! みんな! どうしてっ・・・・・・・!!!」
伸ばした手は、遠く届かず。
全身を朱に染めたキーシャは、湖へと倒れ込む。
湖面に朱色(あけいろ)が広がっていく。
「どうしてっ!!!」
「仕方ないんだよ」
「!」
叫んだアレクのすぐ傍で、髭おじさんの声がした。
「キーシャはお前を連れて来たんだから、仕方ない」
「・・・・・・それ、どういう」
「そうだ、彼女が」
「キーシャがアレクを家族に加えた」
「僕らの、根の無い草の民の家族に」
「だから、仕方ない」
いつの間にか。
アレクの周りには大勢の家族の者がいて。
口々に呟いている。
柄まで濡らしたナイフを片手に。
返り血に染まった服を纏って。
「分からないよ! 僕を連れて来たから、だからどうだって言うんだよ!」
叫ぶことしか出来ないアレクに、家族の者らは顔を見合わせた。
「だって」
「ねえ」
「お前のせいで」
「そう、アレクのせいで」
「わしらは」
「私たちは」
「こうなったのだから」
「!」
彼らが手にしていたはずのナイフは、彼らの胸に突き刺さっていた。
返り血と見えたものは、彼ら自身が流した血だった。
「アレクのせいで」
彼らは一斉に、アレクに向かって手を伸ばす。
が、アレクに届く前に。
伸ばされた指先がぐずりと崩れて。
彼らの手は、顔は、身体は、ぐずぐずと輪郭を失って。
土くれへと還っていく。
「そんな・・・・・・僕が何を・・・・・・」
へたりと。
アレクの腰が砕けた。
その場にたった一人。
残されたアレクは膝をついて、両手で土くれをすくい上げる。
土塊は灰のようにざらざらと崩れて、手の中からこぼれ去っていく。
ひゅうと吹き抜けた風が、土くれを巻き上げ運び去っていく。
「僕は、何も・・・・・・」
力のない呟きに。
「そうだね」
聞きなれた声が、風に混じった。
「アレクのせいじゃない。アレクは何もしていない」
「!」
「何もしなかったから、こうなった」
風に運ばれてきた霧が一瞬キーシャの姿を浮かべ、そしてすぐに吹き散らされて消えた。
「う、わああああっっっ!」
アレクの絶叫もまた、すぐに風のうなりに攫われて掻き消えた。
重い足を引きずりながらふらふらと靄の中を彷徨い歩いていたアレクは、いつしかその足を止めていた。
「キーシャ・・・・・・。髭おじさん。サラおばさん。ミリィ。メリッサ。ドミトリ・・・・・・」
いくら呼びかけても、誰一人としてアレクの前に姿を見せはしない。
「僕の、せい? 僕が、いたから? 僕が、家族になったから? 僕が来なければ、みんなは無事でいられた? 僕が、何もしなかったから? 僕は、何をすれば良かった? 僕は・・・・・・僕は、何をすればいい?」
ふらりと膝をついたアレクは、自分の手が何かを握り込んでいることに気が付いた。
小さく固くしっくりと手に馴染む、それは自分のナイフだ。
アレクが家族になって一年目の記念日にキーシャがプレゼントしてくれた、柄に鹿の絵が透かし彫りされた綺麗な、そして大切なナイフだ。
塔に行く時に置いてきたはずの。
(あれ、塔って何だっけ・・・・・・どうでもいい・・・・・・それよりも、僕がすべきことは・・・・・・)
アレクはナイフを鞘から抜き放つ。
鞘を投げ捨て、柄を逆手にして両手でしっかり握り込むと。
振り上げた刃を一気に突き立てる。
自分の胸の真ん中へと。
ナイフが重い衝撃となって突き刺さる、刹那。
「ダメだよ、そんなことしちゃ」
しなやかな柔らかい手が、ふわりとアレクの手に触れる。
そのまま、ぎゅうっと抱きしめられ、アレクは思わず息を飲む。
「キーシャ、なの?」
アレクを抱きしめた女性は、僅かに身体を離すと、アレクの顔を覗き込みながらニッコリと笑った。
「もちろんだよ。言っただろう、私は必ず、お前を守ってあげるって」
さらりと流れる銀灰色の長い髪。
透き通った水色の瞳。
しなやかな細身の身体。
花の刺繍が施されたトーガ。
全身を包み込む甘やかな香り。
どれ一つとっても間違えようがない。
「キーシャ、キーシャ、キーシャ!」
なきじゃくりながら、アレクはその胸に飛び込む。
「ごめんキーシャ! 僕、何でもするから! だからお願い、もうどこにも行かないで、ずっと一緒にいてよ! キーシャ!」
もう二度と離したくない。
何があっても、ずっとこのままで。
「もちろんだよ、可愛いアレク。私の宝物」
アレクの金色の髪を梳いて撫でる、細い指の感触。
いつものように。
でも、とても懐かしい。
「だから、一つお願いを聞いてくれる?」
優しい声が、耳朶を打つ。
「もちろんだよキーシャ! 僕はキーシャのためだったら何だってやるよ!」
嬉しそうに笑うキーシャに、アレクは大きく頷いてみせた。
第二十三話 悪夢の果てに
(変わり映えしないな、まったく)
羽根を媒介にして分け入った、魔物による虚構の世界で。
濃い霧の中、ゆらゆら形を成そうとする影を形になる前に薙ぎ払いながら、カリムは深く嘆息する。
地を踏んでいる感触も無く、前後左右も遠近も区別がつかず、水草が絡みついたように四肢に重い抵抗を覚える。
霧というより、不可視の沼と呼ぶ方が感覚的には近いだろうか。
こんな中で、あの馬鹿を探さねばならないとは、まったくもって気が重い。
空間との同調率を上げれば、もっと安定して動きやすくなることは分かっているが、それは術主に自分の存在を声高に主張することに他ならない。
せっかく術主である魔物があの馬鹿をターゲットにしているのだから、わざわざ余計な手出しをすることはない。
幸い、相手は憑依系の魔物とは言え、第二段階に進化し立てのほやほやだ。
第一段階の時より魔力量が増大し、術のバリエーションが増えてはいるものの、練度の方はそれ程高く無い。
要するに、本能的に効率良く魔力を使おうとするあまり、術の構造自体は単純で、しかも主ターゲットでないカリムに対してはハッタリもトラップも設定ナシという雑な対応なのである。
おかげであの馬鹿のおぼろげな予測位置は、進もうとすれば抵抗が増す方向と完全に一致している。
故に、現時点での最大の不安要素は魔物のそれ自体ではなく、大した覚悟も無しに成り行きで幻視空間に踏み込んでしまったのだろう、あの馬鹿の存在そのものだ。
『魔物の声に耳を貸してはならない』
塔に属する者のみならず、歌劇の舞台において必ず口にされるそのフレーズは、誰もが心がけねばならない契約の魔物を前にした時の鉄則である。
魔物は取り込んだ者の記憶に侵入し、心の隙に付け入ろうとする。
強い願いほど狙われやすく、大切に想うものほど利用されやすい。
記憶は容易く塗り替えられ変異させられる。
魔物の術による幻だと解っていたとしても、大切な者の手を振り払えば、激しい罪悪感や恐怖感に苛まれる。
憑依系の魔物と対峙する場合、重要なのはいかに自分の状況と弱点を把握しているかだ。強い意志や理想などよりも。
術にはまっているいるという自覚があるか。自分が何に執着していて、それがどこにあってどこにないのか。見定める程度には、あの馬鹿は冷静でいられるだろうか。
(グズグズしてる場合じゃないな)
そうと断じるのに、カリムは僅かの躊躇いも抱かなかった。
当然だろう。あの馬鹿を信じる要素はどこにも無い。
しかも嬉しくないことに。カリムの危惧が実現するのに、大して時間はかからなかった。
カリムの無駄に鋭敏な感覚すらもが役に立たないと思えるほどねっとりとした霧の中、星焔の天使の気配だけを頼りに進んでいたカリムの”視界”から、不意に、目指す気配が消失した。
正確には、気配自体が無くなったわけではなく、ある一点に集約していたものが限りなく散漫になったのだ。辺りに漂う霧の粒子と化したかのように。
と同時に、もやもやした濃淡の世界が急速に色を増し、地面の起伏や空の境界が鮮明になってゆく。
ぼんやりとした影でしかなかったものが、徐々に目鼻立ちをくっきりさせた人の群れへと変化する。
(根性無しの馬鹿が!)
カリムは忌々しげに舌打ちする。
この状況が意味することはたった一つ。
星焔の天使が陥落したのだ。
魔物の術に屈服し、我を失った。
故に、魔物のターゲットが切り替わった。
星焔の天使から、自分へと。
羽根の刃に引き裂かれるより早く、影は人の造形を色濃くする。
見覚えのあるもの。どこかで見たかもしれないもの。まるで覚えがないもの・・・・・・それは気に留めることもなく行き去った者かも知れないが、もしかしたらあの馬鹿に縁の者かも知れなかった。
が、造詣のモデルがどこの誰であるかなど大した問題ではない。
気に留める価値も無い。
濃度を増した魔物の気配に、自らの羽根が獰猛な殺気を放ちつつ猛り狂うのを感じる。
支配の軛など振り切って、暴れたいと叫んでいる。
普段であれば制御の鎖を締め上げるところだが、今この時ばかりは鎖を緩めるのに何の不都合も感じない。
魔物によって、羽根の力を外部に向けた破壊の力に変換される可能性は、もちろんある。あるが、無視する。
番人には結界を張るように言っておいたし、よしんば結界を破壊してしまったとしても、そこまで知ったことではない。
この地に心を止めなければならない理由など、何一つ無いのだから。
胸糞が悪いだけの紛い物の人影を、カリムは草を刈るほどの感慨すら抱くことなく、羽根は暴れる場を得て喜々としながらことごとく刈り取っていく。
二度、三度、何度でも。
風刃に薙ぎ払われる度、性懲りも無く幻は湧き出し、声を発する間も無く消し飛ばされる。
(いい加減に思い知れ。俺はあの馬鹿とは違う。お前如き魔物に取り込まれはしない。さっさと排除にかかった方が賢明だぞ)
その思考が伝わったのか、幻がゆらりと後退する。
手応えを失った羽根が、不満の唸りを上げる。
「やめて下さい!」
影と幻の合間を縫って、そいつはいきなり出現した。
あの馬鹿そのものの間抜け声。呆け顔。
もちろん構わずに薙ぎ払う。
「何するんです、危ないじゃないですか!」
数多の風刃を全て金色の手甲で弾き飛ばして、星焔の天使が抗議の声を上げる。
思いの外元気そうだ。
「何ですその、いかにも面倒くさそうな顔は!」
内心舌打ちしたカリムに対し、心を読んだように的確なツッコミが入る。
普段からそれくらい察しが良ければ少しは面倒も減るだろうにと、今度は表情に出さないように注意しつつ考える。
「普段からって、いつ僕が君に面倒をかけました? 好き勝手ほざかないで下さい!」
なるほど。魔物との同調が進み始めているようだ。
ターゲットの思考を読むのは当然。魔物の都合でいいように改変されて聞こえている可能性は十分にある。自分にも、あの馬鹿にも。
それは厄介でもあり、手っ取り早くもある。
「俺が、どうしたって? 折角助けに来てやったのに」
カリムが翳した手の先で、無数の白刃が獲物を求めてギラリと光る。
「させません。もう、誰も殺させません!」
言い放ったアイルの手甲が、金色の光を強くする。
その光は、間違いなく羽根のものだった。
「俺が、どうしたって? 魔物を退治しに来たに決まっている」
同時に災厄の天使の周囲に滞空していた刃の群れが吹雪に舞う氷片の如く、人々に襲い掛かる。
あちこちから悲鳴が上がる。
「助けてくれ!」
「やめて、殺さないで!」
「我らが一体何をした!」
刃から逃れようととっさに両腕を翳すしか抵抗する手段のない、無力な人々。
彼らはアレクの良く見知った者達だ。
根の無い草の民として、ともに生き、ともに旅して回った、大切な家族だ。
「させません。もう、誰も殺させません!」
強い決意を込めて、手甲に覆われた腕を真っ直ぐに突き出す。
そう。彼らを守るための力を、今のアレクは持っている。
腕から放たれた光弾が、家族に襲いかかる寸前の刃の群れを、ことごとく粉砕する。
第二波、第三波と。
続けざまに繰り出される攻撃を、曲線を描いて飛ぶ光弾が平らげていく。
その時。影が動いた。景色が揺れた。
アレクはバランスを崩しかけた足を踏ん張り、目を擦って瞬きする。
ここは・・・・・・どこかの町はずれだ。
ゆったり流れる川沿いの道。川にかかる茶色い煉瓦の橋が、遠くに見える。
土手の上に付けられた道から草地の斜面を下りた河原には。川を背にして家族の面々が身を寄せ合っている。
・・・・・・どうしてそんな所に?
アレクが駆け寄るより先に、衛士と思しき一団が河原の上流側から下流側から押し寄せ、家族の皆を取り囲む。
橋は遠い。逃げ場は、無い。
「待ってくれ! 分かるだろう、わしらは魔物なんかじゃない!」
必死の叫びを聞く者はいない。
河原を見下ろす土手の上の道に、銃兵を引き連れた官吏らしき男が立つ。
「お前らは魔物だ。街に害悪を持ち込む汚らわしき魔物だ。これ以上の害悪を呼ばれる前に、魔物はここで退治する」
一片の慈悲もない言葉とともに、官吏の腕が高々と上がり、大きく弧を描いて打ち振られる。
その合図一つで、衛士の構える銃口が一斉に火を噴く。
「やめろ! そんなことは許さない!」
叫び、アレクは光の御手で家族を包み込もうとする。
だが、光の防壁すらかいくぐった銃弾は、一人、また一人とアレクの家族を打ち倒していく。
子ども達を庇おうと前に出たおじさんたちに。身を寄せ合っていたおばさんたちに。一矢でも報いようとした兄貴分たちに。その後ろで縮こまっていた妹分や弟分たちに。
土手の上からは銃弾が。そして逃げ出そうとする者には、河原に布陣する衛士の剣先が向く。
悲鳴と怒号が渦巻いて。
「お前らっ、殺してやるっ!」
傷を負いながらナイフを握り締めているのは、兄貴分であるドミトリだ。
「ミリィ、ミリィ! いやっ! 死なないで!」
血を流して倒れ込んだ少女の身体を抱いて絶叫しているのは、ミリィの姉であるイザドラだ。
「どうして。どうして私たちを魔物と呼ぶの! 何もしていないのに。どうして殺されなければならないの!」
河原が、川が、鮮血に染まる。
「いつもそう」
すぐ傍でキーシャの声がする。
「あいつらは私たちのことを、都合のいい時だけ利用して、そのくせ一度何かあると・・・・・・たまたま病気が流行ったり盗人や人さらいが出たり何か都合の悪いことが起こったりすると、私たちが災いを招き込んだと言って責め立てる。魔物呼ばわりして追い立てる。いつもそう。いつも、いつも、、いつも! 忘れてないよね、アレク」
ああ、そうだった。
キーシャの言う通りだ。
うっかり心を許せば、彼らは突然手の平を返す。とても簡単に、迫害する者へと変わる。
同じ土地にへばりついて生きる彼らは、違うのだ。根の無い草の民である僕らとは、決して相容れることはない。
「アレク、助けて」
アレクの背に、キーシャの腕がかかる。抱きしめられる。
キーシャの息遣いを、耳元に感じる。
「皆を助けて・・・・・・あいつらをやっつけて!」
「・・・・・・っ!」
アレクはギリッと歯を食いしばると、意を決して光弾を放つ。
銃を構えていた衛士どもが、光弾に弾き飛ばされて地面に転がる。
「ダメよ、そんなんじゃ!」
その言葉が終わらない内に、転がった衛士らは何事も無かったように立ち上がると、緩慢な動作で銃を構え直す。
官吏の男が薙ぎ払うように腕を振り動かす。撃て、撃て、撃ち払え!
衛士の指が引き金にかかる。
「あいつを狙いなさい。命令する者を倒さない限り、衛士を止めることはできない。あなたの家族は救えない!」
「!」
官吏の顔がニィーッと歪む。
魔物を殲滅する愉悦の嗤いだ。
官吏の姿に、災厄の天使が重なる。
災厄の天使の前に、数人の男女がうずくまっている。
家族の者ではない。が、見知った者達だ。
魔物の囮を買って出てくれた、ウサギ村とオオカミ村の人達。
彼らの前に、防壁の魔法を展開したバイロが立つ。
「何をするつもりだ! やめろ、やめろおおっ!」
「無理だね。叫ぶだけじゃ、彼は止められない」
すぐ近くで上がった声に、アレクは思わず振り向いていた。
燃えるように赤い髪に、緑色の瞳の少年。
「あれ、知らないの?」
初めて見る顔だ。初めてのはず。だが、何かが引っ掛かる。
「カレは殺すよ」
その言葉が終わらぬ内に、大振りの刃が真っ直ぐに振り下ろされる。
防壁の魔法が一瞬抵抗の輝きを放って消し飛ばされ、バイロも村人の姿もが塵と化して消失する。
「そんな・・・・・・!」
膝をついて呻いたアレクに。
「キミは何にも知らないんだね。カレのパートナーだってのに。可笑しいね」
アレクを見下ろして。緑の瞳が憐れみながら、嗤う。
「カレは誰でも殺せるんだよ。上級天使の仲間でも」
災厄の天使の前に、数人の少年少女が現れる。服装は様々。だが、肩や胸の縫い取りは明らかに天軍の、しかも上級天使の証である三対翼の紋章だ。
正面先頭に立っているのは・・・・・あの紋章は知っている。護符で見たことがある。”天穹を駆ける矢羽根”。街を守って魔物と相打ったと歌劇に語られる、蒼空の天使の紋章だ。
透明な空色の眼差しを向け、青年が何かを囁く。その口がはっきりと動く。頼む、と。
だが、それに対する返答は。
両腕を広げた青年に、凶刃が襲い掛かる。
他の上級天使たち諸共、青年の身体が引き千切られる。無残に、跡形も無く。
「どうしてだ、どうして・・・・・・」
「だって、魔物を殺すことだけが、カレの存在理由だもの」
当たり前だ、と少年が嗤う。
「それが本物の魔物か、魔物と呼ばれてるだけなのか、そんなことは何の関係もないの」
赤毛の少年が、ついと前に出る。
刃を携えた災厄の天使に向かって、歩を進める。
「それが一番大切な友達でも。そう、ボクでさえも。魔物に堕ちたって理由があれば、それだけで十分。だよね?」
その身体を、青白い軌跡が分断する。赤い髪の少年の姿が霧散する。
「知らないわけない。キミも知っているはずだよ」
少年の囁きだけが風に響く。
「だって、見たんでしょう?」
子供がいる。部屋の隅にうずくまっている。
あれは、そう、ゼーレンの町で見えない魔物と呼ばれた憐れな子供。
おずおずと手を伸ばした小さな身体を、青白い軌跡が貫く。
「カレが何者か、キミはとっくに知っているよね・・・・・・」
風が吹き抜け、赤い髪の少年の囁きを散らす。
ギラギラした輝きを放つ刃が、次に屠る相手を求めて低く唸る。
赤と黒の上衣を、白磁色の顔や腕を、滴るほどの返り血が彩る。
口元に、鮮やかなまでに凄惨な笑みを刷き。乾いた瞳が、次の犠牲を求めてぎらつく。
「アレク、助けて! あいつを殺して、私を助けて!」
「キーシャ!!!」
殺戮者の嘲笑を浮かべた災厄の天使が、一瞬でキーシャの背後に迫る。
「アレク、お願い!」
「やめろ! キーシャに手を出すなっっっ!」
アレクの手甲を中心に、光が膨張する。
「今度こそ! 今度こそ僕は、君を倒す! 倒して止める!」
圧を伴う、強烈な光。
今まさに残虐を行おうとする災厄の天使に狙いを定めて。
(・・・・・・違う)
光弾が放たれようとする寸前、何かがアレクの脳裏を過る。
(違う? 何が?)
自分の思考に驚き、アレクは息を飲む。
何が、心に引っかかったのか。
(違う・・・・・・あの顔・・・・・・あいつは、あの野郎はあんな風に笑ったりしない)
思い出す。
あの時、災厄の天使が見えない魔物と呼ばれた子供に見せた表情を。
彼を止めようとして、気圧されてしまった瞬間を。
感情の色を一切持たない冷徹な瞳の中に、だが、ほんの刹那、過ったものを。
憐みとも悲しみとも慈愛ともつかない、どうしても認めたくない、認めるわけにはいかない、冷徹とは真逆の色を。
白亜の塔に入って二か月足らず。
災厄の天使のパートナーとして任務に出る事十数回。
災厄の天使が魔物を倒す瞬間に立ち会った回数は、その半分に満たなかったが。
いつもいつも不機嫌で、冷徹に他者を見下し、周りを一切顧みることもない奴ではあるけれど。それは間違いなくそうなのだけれど。
なのに、彼が魔物を侮蔑するような態度を取ったことは、一度も無かったのではないか。
魔物を倒して勝ち誇ることも、愉悦することも、ホッとした表情すら、見せたことがないのではないか。
それに。
ああ、それに。
『忘れていいよ。辛い事なんて、覚えていていい事なんて一つも無いんだから。嬉しい事だけを、素晴らしい記憶だけを、ずっとずっと覚えておきなさい。お前はそうやって、光の中を歩いて行くべきなのだから・・・・・・』
どんなに辛いことがあっても、苦しいことがあっても、そう言ってキーシャは笑いかけてくれた。
そうだ。覚えている。
どんなことがあっても、キーシャはアレクに恨み言を教えなかった。
誰かに優しくすることの幸せを説いた。
他者を傷つけるような行為を、キーシャは決して許さなかった。
「そうだ。キーシャがあんなことを言うはずがない。僕に誰かを殺せなんて、言うはずがないんだ!」
思い出した。
何のために、”ここ”に来たのか。
自分が何をするつもりだったのか。
「さよなら」
低い呟きと同時に。世界が消える。
アレクの家族が消える。
人影も、風景も。
キーシャも。
「さよなら、キーシャ、みんな。今度は現実の世界で、笑って再会しましよう。きっと・・・・・・」
何もかもが、霧の中に淡く溶ける。
幻影など、こんなにも儚く脆い。
たった一人を残して。
「ありがとう。僕を助けに来てくれたんですね」
自分と対峙して立っている災厄の天使に、アイルは穏やかに微笑みかけた。
「それとも僕を殺しに来たのかな? だったら残念でしたね。目的は、遂げられそうにないですよ」
災厄の天使の、いつもは何の感情も示さない深淵色の瞳が、一瞬だけ驚きに見開かれる。見間違いかも知れないが。
少し気分がいい。
鉄面皮をビックリさせてやったと思うのは。
「どっちにしても、僕はもう大丈夫です。もし君が本物なら、早く逃げた方がいいですよ」
アイルは相手の反応を待たず、災厄の天使に向けていた拳を握り込む。
羽根の光は、少しも衰えていない。
当然だ。
アイルは怒っているのだから。
大切な家族を好きなようにいじられて、怒らない方がどうかしている。
この魔物が魔物になる前にどのような仕打ちを受けたにせよ、それを他人に返していい理由にはならない。
苦しみや悲しみを振りまいていい理由には、決してならないのだ。
「だから、付き合ってやりますよ。僕が、最後まで」
アイルは、金色の光が宿った拳を力任せに叩き込む。
自分自身の、胸の真ん中へ。
憑依の魔物を滅する方法が、憑依された者ごと羽根の力をぶつけなければならないのであれば、憑依される者が上級天使であっても構わない。ただし、他の羽根使いの攻撃は、炎の結晶を破壊する恐れがある。だったら自分自身でカタを付けるのが一番だ。たとえ自身に憑りついた魔物を完全に滅し切れなかったとしても、それこそ災厄の天使がキッチリ後始末してくれるだろう。リスクを負うはアイル一人だけ。問題無い。
溢れ出した光が自身の身を焼き、空間を焼く。
何も無い空間全体に光が広がり、満ち溢れ。
空間に絶叫がこだまする。
魔物の、苦悶する声が。
こいつは村人を、町の人々を、何よりバイロを傷つけた。許せるわけがない。それでも。
(ごめんね、僕には、これしか出来ない。君を滅して解放することしか・・・・・・)
断罪するのは、違うと思う。
自分自身に、そこまでの資格があるとは思えないから。
消えゆく意識の中で、アイルは微笑んだ。微笑むことしか、出来なかった。
第二十四話 魔物の爪痕
「あの馬鹿、無茶苦茶やりやがって・・・・・・」
圧縮された空気が一気に膨張したような派手な爆発が治まりかけた頃。
引き剥がされそうになる意識をほぼ意地だけで繋ぎとめたカリムは、頭をひと振りして上体を起こすと、ゆっくりと辺りを見回した。
手加減なしに放たれた羽根の力は、アイルを中心にして地を抉り、念の為にと張らせておいた防御結界すら突き破って周囲のことごとくを吹き飛ばしていた。
ほんの少し前まで結界の内側、あの馬鹿にすぐ手の届く位置に立っていたカリムは、馬車寄せも兼ねた前庭正面、何らかのモニュメントらしき石像の台座脇まで吹き飛ばされていた。
自らを見下ろせば、戦闘用にと護符を織り交ぜて造られた丈夫な長衣が、ボロ布状態とまではいかないものの見事にあちこち引き裂かれてしまっている。あともう一瞬でも対処が遅れていたらとは、あまり考えたくない有様だ。
館の張り出し窓のガラスは砕け、千切れたカーテンが空しくそよぐ。
静かに雪に覆われていた前庭には、一部破壊を受けた館の建材が散乱し、割れた窓から侵入した突風が室内を蹂躙した名残の家具片や、カーテンやクロスなど色とりどりの布片、それに壁を飾っていた剥製の頭などがゴロリと転がり、その間に頭を庇う格好で地に伏した村人らの身体がチラホラとのぞいている。羽根は人間を攻撃するものではないが、結界の弾ける衝撃に瓦礫の襲来も加われば、気絶もやむを得ないだろう。まあ、余程瓦礫の当たり所が悪くない限り、早々死ぬことはあるまいが。
もしも結界が無かったら。
羽根の直撃をまともに受けて倒壊する館の下敷きになったかも知れないのだから、それよりはマシだと思うべきだろう。
黒衣の番人が見当たらないのは、運悪く何かの下敷きになったか、それともちゃっかり退避済みか。
まあ、番人がどうなろうが館が全壊しようが村の人間が全滅しようが塔の面目が潰れようが、カリムには関係の無いことではあるが。
この地にカリムの求めるものが存在しないことは、既に確認済みだ。
それにしても。
目の前に広がる状況が、かなり無様なものであることは否定し難く。
それは全てあの馬鹿が、自分自身に向けて見境なく全力を叩き込むなどという暴挙に出たせいなのだ。
(ったく。素直に俺を攻撃しておけば良かったものを)
が、力加減はどうあれ、馬鹿がやったこと自体は、決して間違いではない。
他者に魔物を依り付かせて討つことが出来ないなら、自分自身を囮にする以外に無いからだ。
羽根は命じられぬ限り人体を傷つけるものではないが、同時に炎の結晶を破壊し得る武器でもある。しかし唯一の例外として、自身の結晶を破壊することだけはどうあっても不可能だ。
つまりアイルに憑依した魔物をカリムや他の羽根使いが攻撃してはアイルの結晶を損なうリスクが高いが、アイルが自身を攻撃する場合のみ成功する可能性があるということだ。
ただし憑依した魔物を灼き尽くすには、魔物の幻術に打ち勝ち、なおかつ自身を灼き尽くすほどの覚悟が必要となるのだが、それは解っていても難しいことだ。怖気て無意識に攻撃の手を緩めれば、出力不足で魔物を討滅するに至らないどころか、肉体の支配を奪われては魔物に強大な破壊の力を与えてしまうことになりかねないのだから。
あの時、魔物に支配されかかっていたアイルに対して、カリムの選択肢は三つ。
一つは迷わずアイル諸共魔物を破壊し去ること。
もう一つは、アイルの意識に介入して何とか正気付かせること。
そして最後が、一番被害が少なく一番確実だと思われる方法。即ちアイルにカリムを攻撃させること。
憑依の魔物の術中で、アイルは仲間を守ろうと必死だった。
そして魔物の敵と認識されることで、カリムは幻術の中で冷酷極まりない殺戮者にされた。
カリムの眼には小うるさい亡者の群れとしか映らなかったものが、アイルには大切な家族一人一人に見えていたことは、その表情と言動でも明らかだった。
魔物にしてみれば、それは邪魔者を消させる手っ取り早い方法であるのと同時に、アイルに手を汚させることで精神支配をより強固にする意図があった。
しかしそれはカリムの思惑通りでもあった。
カリムはアイルの敵を演じることで、アイルの一撃必殺の攻撃を引き出そうとしたのだ。
羽根の攻撃力は絶大だが、来ると解っている攻撃など、何の脅威でもない。
自分に向けられた攻撃を、力を変質させることなく、攻撃対象だけを変換する。
即ち星焔の内で、今まさに炎の結晶にまで浸食の手を伸ばそうとしている魔物に向けて。
それこそが、カリムの選択した一番確実な方法であったのだ。
そして、作戦は上手くいっていた、はずだった。
なのに最後の最後で、あの馬鹿はカリムへの攻撃を躊躇った。
結果的に、あの馬鹿は自力で正気を取り戻して、自身を攻撃するという当初の目的を遂げた。
結果オーライ。万々歳。新人にしては良くやった。褒めてやってもいいくらい。
なのに。
イライラする。ハラが立つ。罵るだけじゃ足らない。ボコボコにしてやらないと気が済まない。
せっかく、この俺が、わざわざお膳立てしてやったのに、あっさり無駄にしやがって。
胸中で悪態をつきつつ、カリムは星焔の天使を睨み付ける。
円形に石畳のめくれ上がった爆心地の真ん中で、両膝立ちの格好で放心脱力している星焔の天使を。
、特に目立った外傷は無い。
力を使い切った空白状態に、魔物の憑依を受けた余波も少しは入っているだろうか。
だがその程度なら、簡単に薬酒で癒えるだろう。肉体はもちろん、心に受けた傷ですら。
それでも。
後で傷は癒えるとしても、魔物の心理攻撃のさ中に、それに思い至る余裕など無かっただろう。
あの幻視空間で、カリムにはおぞましい魍魎の群れにしか見えなかったものが、星焔の天使の目にはかけがえのない大切な者として映っていたことは明らかだ。
憎しみで爛々と燃える目を、確かに見たと思ったのだ。
なのに、何故。
あの馬鹿は、冷静になれた?
大切な者を蹂躙する相手を、どうして許せた?
今回は運よく幻術だった。
だが、また似たような事態に直面したら?
現実に殺戮が行われるとしたら?
殺戮者が敵の術中に堕ちていようが、正気であり故意であろうが関係ない。説得で止める手立てが無かった時、それでも、お前は躊躇うか?
何を見せつけられれば、お前は決断する?
いつまで、決断を避け続ける?
わかっている。こんなものはただの八つ当たりだ。
あの馬鹿が何をしようと関係ない、そう言い続けたのは自分の方だ。
それを今更、苛立つのは馬鹿らしい。
よく、わかっている。
きっと、不意打ちを食らったのが悔しかっただけだ。
あの馬鹿が自分自身に向け力を放った瞬間、その余波をとっさに回避出来なかったのが。
一瞬の判断を、読み誤ったのが。
本当に?
あれは不意打ちだったか?
全く予想出来なかったか?
難しい判断だったか?
故意でなかったと誓えるか?
(馬鹿らしい)
我ながら、不毛な思考だ。
生きねばならないのに。
この世界でやらねばならないことがあるのに。
回避を躊躇するなど、有り得ない。
あれは不意打ちだったのだ。
とっさの判断でギリギリ直撃をかわしたのだ。
それだけの、ことなのだ。
「馬鹿らしい」
今度は声にして吐き捨て、カリムはそれ以上の思索を投棄する。
まったく、こんな所でのん気に座り込んでいるから、ろくなことを考えないのだ。
カリムはひどく重く感じる腕を持ち上げ懐中を探ると、青い小瓶を掴み出す。
玻璃細工のように華美でありながら、多少の衝撃では壊れることのない丈夫な小瓶には、少量の薬酒で満たされている。任務中に重傷を負った場合を想定して、携帯を義務付けられている代物だ。
瓶の栓を指で弾き飛ばして、中身の液体を一気に喉へと流し込む。
薬酒は嫌いだ。
甘ったるい芳香。舌だけでなく頭の芯まで麻痺させるような酩酊感。
それが治まった頃には、肉体の回復と引き換えに、心のざわめきは連れ去られる。
見た物や考えたことなど知識に全く影響は無いが、感じたこと思ったことを、最初から何の感慨も抱かなかったかのように洗い流してしまう。
炎の結晶と同化した命を持つ上級天使に絶大なる力を与えると同時に、命を繋ぐ唯一の術薬でもある。
どれほど嫌っても、拒否することは不可能な。
しかし、今だけは。
心をかき乱す余計な感情など、さっさと消え去ってしまえばいい。
下らない感情に振り回される暇があるのなら、一刻も早く体力を回復させ、別のどこかへ移動すべきだ。
まだ訪れたことのない、この世界のどこか。
そのどこかは、人の住む場所と限定してさえ全て訪れるには世界は広すぎて、のんびりしてなどいられない。
一刻も早く見つけ出さねばならないのに。
遠い遠い記憶の中にほんの一瞬刻まれた、大切な存在を。
うつろな目を空に向けていたあの馬鹿が、不意に瞬きする。と、次の瞬間バランスを崩してぼてっと横倒しに倒れ込むと、そのまま手足を震わせ、うーんと唸る。目覚める兆候だ。
魔物が消えた以上、長居する義理も無い。
足に力を込め立ち上がったカリムは、それ以上顧みることなく、足早に白鹿の町を後にした。
「う・・・・・・ん・・・・・・」
のびをしつつ寝返りをうったところで、アイルはハッと目を覚ました。
豪華な天井。上等の寝具。
見知らぬ窓から差し込む、まだ頼りなげな早春の日差し。
思わず飛び起きたアイルは、贅沢な設えの室内を見回す。
「お目覚めになられましたか、星焔様」
アイルがここはどこかと口にするより先に、聞き覚えのある声がして。
「お加減はいかがですか。何か欲しい物はございませんか」
ベッドサイドに現れたのは、アイルの随従の一人であるセルジオだった。
「僕は大丈夫、何ともありません。それよりここは・・・・・・」
「はい。ボノレッティ男爵の狩猟館の客室です。魔物討滅の後、星焔様が大層お疲れのご様子でしたので、こちらでお休みいただけるよう手配させました。少々手狭ではありますが、最上位の室は改装中とのことですので、こちらでご容赦いただきたく」
前庭に面した見晴らしの良い部屋は、アイルの力の余波を食らって窓や壁や内装に問題発生中なのだが、それをわざわざ教えるセルジオではない。
「あれからどれくらい経ったんですか? 魔物は? 村の皆さんは? それに、バイロは・・・・・・」
頭がハッキリしてきた途端、疑問が次々浮かんでくる。
「魔物討滅から一夜明けて、今は正午の少し前でございます。魔物は星焔様ご自身が討滅を果たされました。避難していた村人にも町や館の者にも、目立った被害はございません。囮になった村人は、一人が重傷なれど、施術医によって既に手当が施されております」
普段から急ぐ慌てる焦るということには無縁のセルジオは、アイルの問いかけに逐一丁寧に簡潔に答えていく。
「バイロは至急手当が必要でしたので、星焔様のご命令通り、一足先に強制転移にて聖都の高等施術院へ搬送いたしました」
「僕が、ですか?」
「はい。確かに」
断言され、アイルは昨日の記憶を手繰ってみる。
確か、囮を買って出てくれた村人の一人である痩せぎすの男が魔物に憑依されたものの、その状態にアイルが耐え切れなくて作戦は失敗。男の肉体を離れた魔物の前に、ザハトが身を挺して立ちはだかったのだった。
バイロに憑依しかけていた魔物は、アイルの自暴自棄に等しい行為によって何とか討滅を遂げたものの、アイルはもちろん魔物に触れたバイロも無事では済まなかったのだ。
気を失って倒れていたアイルは、セルジオの呼びかけで目を覚ました。そしてザハトの介抱を受けるバイロの姿を目にする。
セルジオの手を振り切り、ふらつく足取りで歩み寄ったアイルの呼びかけに、バイロはうっすらと目を開けて、言った。
一言、申し訳ございません、と。
「どうして謝る必要があるんですか、君は君の責任以上の役目を果たしてくれました。謝らなければならないのは、むしろ僕です」
土壇場で無責任な正義を、アイルは振りかざしてしまった。
徒な同情は他を危険に晒すだけだと、あれほど聞かされていながら。
バイロがこうなると知っていたら、いやバイロの性格なら予測して当然だったと今なら思えるのだが、そんなことすらあの時はまるで考えもしなかったのだ。
自分が犠牲になる覚悟すら、決意したのはバイロが危ないと思った後のことである。
本当に無責任だ。
罵倒されこそすれ、謝られるなど論外だ。
だが、バイロは微かに頭を振ると、掠れた小さな声で、しかしハッキリと言ったのだ。
「いいえ。魔物を前にした瞬間、私は自分に課せられた任務も、アイル様の随従であるという役目も見失いました。魔物の声を聞いてはならないという絶対の禁忌を知りながら、あえて禁忌を侵しました。魔物の闇の奥に・・・・・・もう顔さえ思い出せない両親や兄弟を覗いてしまった瞬間に・・・・・・」
「・・・・・・!」
「あの瞬間、私はアイル様の随従である資格を、いえ天使を名乗る資格すら失った。どうか、アイル様、私を随従から解任して下さい。私に天使の誇りの欠片でも残っているのなら、その誇りを守らせて下さい・・・・・・」
「そんな! ダメです! 家族を想うなんて当たり前のことでしょう! 天使とかそんなのより、ずっと大事なことでしょう! 自分の家族が大事じゃなくて、どうして新しい家族を、仲間を、大事だなんて言えますか! バイロ、聞いてますか? 君は正しかったんです。正しかったと僕が保証します! だから、戻って来て下さい、身体を治して、一日も早く・・・・・・!」
アイルはバイロの腕を握った。
うまく力が入らないながらも握って、呼びかけ続けた。バイロは正しかったのだ、と。
そうしないではいられなかったから。
他の誰が何を言おうと。誰もに間違いだと言われようと。
でなければ、きっと、アイル自身が・・・・・・。
その後のことはよく覚えていない。
多分、アイル自身が再び気を失ってしまったのだろう。
魔物の憑依と羽根による力の放出が、肉体のみならず炎の結晶にも負担をかけたと、言ったのはセルジオだったか。
「バイロは大丈夫でしょうか・・・・・・」
呟くアイルに。
「聖都の施術は世界の先端レベルですから、もちろんでございます」
分かり切った事実を語る表情で、セルジオが応じる。
(そういうことではないんだけど)
真面目以前に仕事に徹する姿勢を崩さないセルジオに、誰かの心配だとか、ちょっとした話し相手を求めるのは無理かもしれない。
いや、普段のやる気満々なアイルであればしつこいくらいに食い下がりもしただろうが、今はそこまでの気力が無かった。
(家族を想うのなんて、当たり前のことです。そうでなかったら僕は・・・・・・キーシャを想わなくなったら、僕はきっと僕でなくなる・・・・・・)
自分でなくなるということが何を意味するのかは解らなかったが、そんな漠然とした確信が、アイルの内に存在していた。
「・・・・・・ところで、外が騒がしくないですか?」
ふと窓外に目をやったアイルは、その時はじめて館の外の喧騒に気が付いた。
大勢が喧嘩腰で怒鳴り合っているような・・・・・・?
「申し訳ございません。すぐに止めさせて参ります」
「ま、待って下さい!」
即座に行動に移そうとするセルジオを、慌てて呼び止める。
「止める前に、まず理由を聞いてきて下さい」
「理由なら存じておりますので、」
「知ってるなら教えて下さい、お願いしますから!」
任務に関係ないものは知ったことではないを地でいくセルジオに、アイルは懇願。
それならと、セルジオは語り始める。それによると。
事の起こりは、魔物討滅の報を受けた領主代行が魔物の被害に遭った村人に対し、町の住人と同等の扱いを約束するという通達を出したことだった。
「それ、別におかしなことじゃありませんよね?」
魔物討滅に出る直前、囮を買って出てくれた村人に対し、代官の名において白鹿の町で不自由なく暮らせる保証が約束されていたのだから、それは約束が履行されたというだけではないのだろうか。
「町の住人と同等ということは、村人にも町の法律を順守する義務が生じるということで、この度の魔物襲来にもそれが適応されると言い出したのです」
意図的であろうがなかろうが、村や町を危険に陥れる行為には、厳罰が課されることはよくあることだ。例えば失火が元で大火になったとか、盗賊や魔物などの危険を引き入れる手引きをするなどだが。
「何ですかそれ! 村の人達は町に助けを求めただけじゃないですか!」
それはもちろん、代官も承知のはずである。
「ただし魔物討滅に貢献した功を考慮して、責任者の拘禁を免除するかわり罰金刑のみを課す。支払えない場合は、財の没収を以てこれにあてる。この場合の財には魔物討滅の報酬分も含まれます」
「褒美を出す約束をしておきながら、同時に罪を着せて没収するってことですか!? それじゃ詐欺だ! あんまりです!」
激昂するアイルを、セルジオは冷静な目で制する。
「はい。ですから今朝になってボノレッティ男爵より書状が届き、村人に対し、この件における一切の罪を問わないと明言を得ました」
「・・・・・・つまり、村人はちゃんと保護を受けられる?」
拍子抜けて、アイルはバフッと背もたれクッションに沈み込む。
「もちろんです。この要請は星焔の天使の名においてなされたものだと、番人様に伺いましたが」
「・・・・・・は? 僕の?」
「ご存知ありませんでしたか?」
「全然、これっぽっちも!」
アイルはぱしぱしと目を瞬く。
「表の騒ぎは、星焔様に一言お礼を申し上げようと詰めかけた二村の村人らと、彼らを館に入れまいとする衛士との小競り合いです。一時はかなり険悪でしたが、星焔様の安静の邪魔にならないようにとロベルト殿が諭されてからは、幾分マシになったのですが」
「そう、だったんですか・・・・・・」
アイルの知らない所で出された要請。
こんな気を利かすことが出来るのは、バイロを置いて他にいない。
何の疑問もなく、アイルはそう確信していた。
「ところで星焔様、お目覚め早々申し訳ないことですが、バイロの後任の筆頭随従をお決めいただかなければなりません」
「・・・・・・!」
「名が挙がっておりますのは星焔様にも面識のある第五軍所属のジェドの他、」
「ちょっと待って下さい!」
更に名を連ねようとするセルジオを、アイルは両手で制止した。
「僕の筆頭随従はバイロだけです。僕は、バイロが復帰するのを待ちたいです」
「ですが、バイロの回復にはまだ時間を要しますし、その間の任務に支障を来しては・・・・・・」
「ええ。でもまだ君とザハトが居るじゃないですか。バイロが戻るまで、二人で協力して僕を支えてくれませんか?」
「・・・・・・星焔様がお望みであれば、そのように報告いたしましょう」
「ありがとうございますセルジオ。これからもよろしくお願いします!」
そしてアイルは、再び窓外の喧騒に耳を傾ける。
アイルを呼ぶ声の中に、昨日の女性の声が聞こえたと思った。
(無事だったんだ。良かった)
アイルはそろりとベッドから降りると、バルコニーのある窓辺へと近づく。
「星焔様、どちらへ?」
「もちろん、皆さんにご挨拶です。じゃないといつまで経っても仕事に戻れないでしょう?」
村の者も、町の者も、本当は自分の身の振り方を考えたり、やらなければならないことで手一杯なはずである。アイルが出て行って収まるのなら、それに越したことは無い。
アイルは、白亜の塔の上級天使としての責任があるのだから。
それはきっと、バイロに報いることにもなるはず。
(帰って来て下さいバイロ。きっと待っていますから)
セルジオが着せ掛けてくれた上衣に袖を通し、アイルは窓を大きく開け放った。
明時闇の願い星


