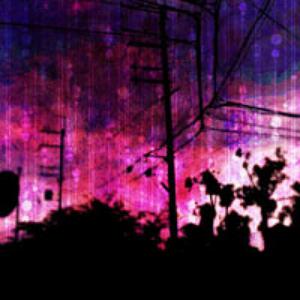光景
グロテスクな表現があります。
目の前で親友が飛びおり自殺したとき私は、うっかり手を滑らせ卵を床に落とし割ってしまったときの事を思い出した。真っ白で汚れていないつるりとした卵はひしゃげ、砕け、穢い中身をぶちまけ跡形もなくなってしまう。全くの別物。興味等々、諸々の感情は消えうせ嫌悪が新たに生まれるのだ。
あの穢い肉は私の親友じゃない。やさしく微笑んだ顔は苦痛で歪み醜く固まり、腹部からは臓物がはみ出ている。青々とした血管や薄いピンク色の脳やオレンジ色の脂肪、悪を溶かし込んだかのような色をした赤黒い液体、血液。どれもこれも否定したくなる、否定しかしたくないものだった。
人間を否定したくなる。醜い物が詰まった意思をもった皮袋が人間だなんて。親友だったなんて。
目撃者達は悲鳴をあげる。逃げる。写真を撮る。動画を撮る。ただ棒立ちの私。
異質な空間の中人間を否定なんて馬鹿な、と我に返った。
私が本当に否定したいもの、拒絶したいもの、逃げたいもの。
それは、親友の死。
理解したところで涙があふれた。認めてしまった。親友の死を。卵じゃない親友が潰れ醜く死んだことを。
親友だった肉塊の前へいき、触れる。にゅるりとしたこれは腸。ぷにぷにしたこれは肝臓。目線の下に転がってるのは眼球。撫でると以前より歪で半分なくなっている頭部。変わらない表情。動かない声帯。握っても握り返してくれない手。どれだけ語りかけ、触れても反応なんかこれっぽちもない。いない。親友はもういない。
生命活動を停止し何もかも終わらせこの世を後にしたのだ。死体を触りながら泣き喚く私を野次馬たちは手に持った携帯電話に記録する。文字で、声で、画像で。私はもっととってほしかった。だって親友の最後なのだから。忘れ去られてしまうのだから。残しておいてほしい。そう思った。
一人遺体の前で微笑みながら泣き喚く少女がいた。
なんとも不気味で不快、とにかく異常。気持ちの悪い光景だった。
俺、あたし、僕、私はその雰囲気にどこか狂気を感じた。
光景