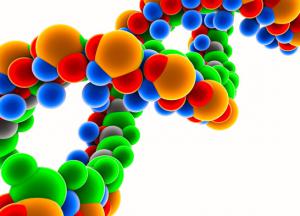ドープ
~男が呪詛のようなことをわめきちらしたのが聞こえた。辺りは猛烈な吹雪でなにも見えない。ただ、目前にそびえる一棟の巨大な建物だけが、厳かな佇まいを幽かにあらわしていた。
僕は朦朧としながら目に入る雪を手で拭った。眼窩にはりめぐる神経が溶けだしてしまったみたいに痛んだ。目を凝らすと、建物のてっぺんには円盤のようなものが付いていた。まるで宇宙船の着陸場だ。一体誰がなんのためにこんなへんてこな建物をこんな酷寒で辺鄙な場所に建てたのだろう?一体誰がこんなところに用があるというのだろう?しかしこの際そんなことはどうだっていい。今は吹雪をしのぐため、このへんてこな建物に避難するしか生き残れない。とにかく、底をつきそうな力を振り絞って、僕は建物まで這いつくばった。今はこのへんてこな建物を建てた人に感謝しなくちゃな。
横殴りの吹雪が右耳をキリキリとしめあげる。すこし先の凍ったガードレールに寄りかかり、地面にへたり込んで動かない夫婦の姿がみえた。顔を覗くとそれは僕の両親だった。凍傷で鉛色の体になってしまった両親は未練がましく手を繋いでいて、雨の日の石像みたいに物憂げな表情を浮かべていた。僕は「南無」と言って手を合わせ、死体を抱き寄せて涙を流し悲哀の言葉を呟くはずだった。しかし両親の死体を目の当たりにしても僕は涙も出さず、何の台詞も思いつかなかった。悲しみは吹雪とともに宙に舞い、ただ呻るような痛みが頭の芯を握り潰し、全身に染み渡った。なぜ両親の死体を目の前に僕は無感情を決め込んでる?そんな愚問が頭を擡げる。僕自身この状況でそんな思考が働くのが不思議ではあったが、それはまもなくこの酷寒の仕業だという結論で落ち着いた。極限の寒さは頭を狂わせ、体を蝕み、人として大切な感情を削ぎ、二度と取り戻せぬところまで吹き去っていてしまう性質があるようだ。幾重の死体をまたいで歩いていくと、人は死に対しての向き合い方が変わる。揺るぎない精神を持たぬ者は慈愛や慈悲の念がうすれ、慣性と麻痺が芽吹きはじめる。慣性と孤独はことごとく似ているし、麻痺とは精神にも起こる。極度の環境でのソリッドな感情の起伏は、命をも脅かす。ならば人間には生命維持装置のようなものがあって、感情のスイッチをひとつずつ切ることによってその命を保つことがあるのかもしれない。或いは、僕は他人の死に対して悲しみなんて最初から持ち合わせてなかったのかもしれない。この環境は、そんな感情欠落者には相応しく厳しい。
吹雪は針地獄のように何も言わずに体を突き刺し、体温を素早く奪ってゆく。もう限界だ。いまさらだが足の力も入らない。これ以上歩くのは厳しいだろう。よろめきながら氷に覆われた地面に尻をつけて靴を脱いでみる。すると、彼ら同様僕の足も凍傷がひどく、水風船のようにふくれあがっていた。苔色に腐った足。黒く血走る血管の模様。マーブル模様の水風船とは似つかないグロテスクなものだった。僕は声にならない声でヵ、ヵ、ヵと笑った。そしてうなだれるようにそこで死んだ。
いくらかの時間が経ち、目を覚ますと裸で真っ暗闇にいた。あまりにも唐突に真っ暗で、僕は全て夢かと錯覚してしまった。しかし酷寒に晒された冷たい痛みが、からだ全体にぼんやりと残ってる。この突然の環境の変化に、奇妙さと恐怖とが絶望を凌駕する。狐に包まれ、なおかつ狐のむこう側が透けてみえて、奥ではよだれを垂らしながら血生臭い死体をくわえた死神でもいるようだった。
大声を出しても無闇に吸いこまれ、何もなかったことにされてしまう。どれだけ歩いてみてもどこへ進んでるのか分からない。僕はためしに泣くことにした。まず自分に、正常とまでは言わないが一応なりとも機能する目がついているのか確認したかったのと、果たして涙を流すための感情が取り戻されているのかが気になったからだ。目頭と眉間の辺りに意識を集中する。するといとも簡単に、泣くことの才気溢れる女優さながらわんわん泣くことができた。目はすこぶる機能し、効率よく塩分を含んだ涙を放出した。しかしそれは感情など無意味なものだというようにだった。結局原因はどうであれ、いくつかの感情はもう手元にはなかった。虚無感の中で流す涙ほど惨めなものはない。また暗闇の中で流す涙ほど哀れなものもない。それでも涙は一度流れはじめたら堰を切ったように止まらなかった。僕はずいぶん長い間これといった感情も感動もなく泣いた。それにも疲れると「このところわけもわからず色んなことに振り回されっぱなしだ。あんな酷い死に方をしたり暗闇の中に投げ込まれたりじゃあ感情だって追いつくわけはあるまいか。また明日には、久しぶりの我が子との再開のように感情をこの手で力いっぱい抱き寄せてやろう。」そう自分を擁護し、決心する。涙というものはなかなか都合よくことを運んでくれる。僕は胎児のように身を丸くして眠ることにした。
深い眠りの中、夢を見た。大きな満月が程よく濡れた地面を優しく照らし、樹々たちが心地良さそうにそよぎ、衛星やオールトの雲が肉眼で捉えられるほど透きとおった夜空。僕は湖畔で樹にもたれかかりながら夜空を眺めている。湖面に写るオリオン座の辺りに、乳房のように一対の島嶼が顔を出している。突然、片方が小刻みに震えて割れ、中から血が吹き出し、僕はそれを身体中に浴びたところで目が覚めた。
目が覚めてもまだ夢の中にいる気がするのは、やはり視界に暗闇しか映らないからなのだろうか。僕はいつまで、暗闇を彷徨うのか。彷徨ったその先に、一体何が待っているのだろうか。そう考えたとたん、みるみるからだが震え始める。終わらないカルマ。
その頃酷寒では、ガードレールの先にあるタマネギ型の建物の脇から、雪男と雪女がしげしげと僕の死に際をながめて、黄ばんだ鋭い歯をむきだして笑った。
「ガハハハハ。ほら、ほら。これで最後の人間が死んだよ。また山積みにするのもこの吹雪じゃあ骨が折れちまう。この人間は、最後の人間だ。」
雪女は雪男の後ろで頷く。
「適応できないものはいつの時代も滅びるのさ。我々だって灼熱の世になれば、ここを退かなければいけなくなるのよ。それまで、ここに、我々の王国を作ろうじゃないか。次にどんな世になろうとも、適応できるように、ここで子孫を鍛えてやろう。この人間は、我々のシンボルだ。」
そう雪男が言うと、
「なんだかワクワクするわ。あなたのその哲学めいたところも、子供達にうつっちゃうのかしらん。」
と言って笑った。
それから雪男と雪女はタマネギ型の建物の入口に分厚く張った氷の壁を、熊掌のような逞しい手で引っ掻きだした。はじめは細い線のような跡しか付かなかったが、しだいに氷は深くえぐられ、黒い建物の壁と赤いドアが露出した。
建物の中は映画館だった。ラメ入りの赤い座席が並ぶ斜面になった上映室の真ん中に、雪男は僕の死体を座らせた。パブリックアナウンス室で雪女は上機嫌に口笛を吹いてフィルムをセットしはじめた。
~
radioheadのidiotequeが車内で流れていた。本牧で貨物船のバイトを終えた帰り道、カイはこんなことを考えて車を運転していた。
彼は日常生活に張り巡らせた思考の網にかかったファクターやマテリアルから、大体においてこのような益体のない妄想にひたることを楽しんだ。さらに元来カイにはネガティヴな妄想癖があった。これは幼いころから病的に起きることがしばしばあり、一時期それがたたり疑心暗鬼に陥りずっと家に引きこもったこともあった。その間友達、先生、家族までもが自分を破滅させようとしていると勘ぐり、「もう二度と朝が来ませんように。」という祈りをこめてカーテンを閉めきり、一日中布団にもぐりこみ、朝か夜かも分からない部屋で気が滅入るまで妄想を繰り返した。風呂に入らず、毛とゆう毛は伸び放題になり、口の中は虫歯だらけだった。食事は月に一度家から歩いて五分のコンビニで冷凍食品を買い込み、部屋のレンジで温めて食べた。部屋はその食べかすの山で埋もれ、みたこともないカビが産毛みたくそこらじゅうに生えていた。
引きこもりが終焉を迎えるころには、添加物が多量にふくまれた冷凍食品ばかりを摂りすぎたせいで栄養はかたよって、胸板はみるみるうすくなり、スイカを飲み込んだように下っ腹と眼球が飛びでて、固有種の両生類みたいな容姿になっていった。
それでもカイは飽きたらずに思考の井戸を掘りつづけ、破滅的な妄想を止めなかった。結果引きこもり生活から脱却した今では、妄想の産物はカイの内に現実のようにくっきりと刻み込まれ、あるところに帰結するまで成長し続けた。種子を拾い発芽させ、開花に至るまでのプロセスを、カイはとても楽しんでおこなった。日常的にそれをつづけることにより、彼は常にいくつかの物語を受胎していた。元々頭の容量が多くはないカイは、そのほとんどを物語りにつぎ込んで生きてきた。人と話をしているときも、仕事をしているときも、頭の中では目に見えている世界とは全く別の物語が繰り広げられていた。だから、周りからみるとカイは知恵遅れのようにもみえた。話しかけてもほとんどまともな答えを求められず、たいていの人は閉口した。自分からはほとんど口もきかず、悪い印象しか周りに与えなかった。しかし彼はそれを理解したうえで、非難を甘んじて享受した。その損失を出してでも物語の輪郭を彫りつづけたかったからだ。そして今日はその思考回路が小説的に、或いは絵画的にカイの頭に働いたのだった。引きこもりから脱却して、一年目のことだった。
本牧の空は炉灰色の雲が一面すっぽりと覆っていて薄暗く、空と地面の間には砂埃と霧の混ざった靄が立ち昇っていた。ときどき分厚い雲の切れ目からピカリと白い光が射し込むと、靄は光を浴びて肌色になる。靄に包まれた町は重力が何倍も働いてるようで、皆足元を見つめながら、肩を落として歩くのが正しい行いのように感じた。この状況ではしゃげる奴がいたら、それはやんちゃで無知な子供か、重力概念から解放された超人くらいだ。しかし人気はさっぱりなく、靄だけが膨張しつづけ、本牧一帯を支配していった。カイは肌色に染まってゆく町並みを車内からぼんやりとながめ、マールボロライトを吸った。進行方向がぼやける。狭い感覚で配置された二つ先の信号機も、かすんで影しか見えない。
山下公園前にさしかかると、見事な黄金色に染まっていた銀杏並木は葉と実をひとつ残らず落として、その枝は空にむかって生える根のようにみえた。道路一面に黄金色の銀杏の落ち葉が絨毯のように広がり、それはこの時期の風情だったが、車や通行人に矢鱈に踏まれ、油臭い匂いをそこらじゅうに発散していた。犬を連れた老婆が鼻をつまみ、犬は息苦しそうに咳き込みながらカイの乗る車のわきを通った。
彼は黄金色の絨毯の切れ目で信号につかまった。前には稲妻の通り道のようないびつな十字をした交差点。振りむくと黄金色のカーペットは静かにそこまで迫ってきていた。「もうすこしで悪臭から開放されそうだったのに。」彼は前にむきなおし、いびつな交差点の中央に突き出た信号機の上にとまる鳩をみた。今日の雲の子供のような炉灰色の身を寄せかたまっていた鳩はいっせいに首をかしげて、しばらく思い思いに首をかしげ、それから一向に埒があかなそうに首をかしげつづけた。
その群れの奥にみえるピアノ教室の看板に、別の鳥がとまっているのがなんとなくわかった。靄がかるそのあたりに焦点を合わせ、おもいきり凝視した。すると鳥は鳩より少し大きい輪郭をぼんやりとあらわし、緋色にとがったクチバシを一回、上下させてきらりと光らせた。浮かびあがる琥珀色の一対の玉が、ゆっくりと瞬きをした。琥珀色の玉の真ん中を、わがもの顔で鋭く横断していたのは黒目であった。
それは羊のような目だった。その目は鳩の群れの奥でこちらを静かに見据え、ゲゲゲッと奇妙な声を出した。
「気味の悪い鳥だな。」
鳥はカイにむかってもう一度ゲゲゲッと鳴いた。その瞬間、彼の創造した物語が崩れていった。時計台がバナナの皮をめくるように崩れてゆく。鉛色の死体の山は鳥の目から照射されるレーザーで焼き払われ、酷寒は酷寒でなくなりはじめる。突然、彼の全身に鳥肌が立ち、へその辺りにじわりと脂汗をかいた。このままでは物語が終わってしまう。一体なんなんだあの鳥は?!なぜ俺の頭の中に侵入できる!?カイはタバコを揉み消した。信号が青になる。へそにかいた汗を上着の上から拭い、カイは車を進めた。
カイは一度新横浜にある自宅に帰り仮眠をとると、加絵子のアパートへ向かった。加絵子は6年前に青森から上京してきた29歳になる色の白いきれいな女だ。仕事を転々としていたらしいが、今は五反田のコールガールと覚醒剤の売買で食いつないでいた。「電磁波」で初めて会ったときも、彼女は覚醒剤をアブってキメていた。
「私のうちすぐ近くだから来てみない?面白いことが沢山できるわよ。」その日カイは初めて覚醒剤を打った。そしてその日のうちに二人はセックスをして深い関係になり、カイは週に2度ほどこのアパートを訪れるようになった。
繁華街を通るどぶ川沿いに建っているブリキ細工のようなそのアパートは、屋根から飛び出したわけの分からないコードを思い切り引っ張ればほどけてバラバラになってしまいそうな代物だった。部屋からは赤とか黄とか汚い緑色のキャバクラのネオンと、風俗や中国式マッサージの猥雑な看板がよくみえた。彼女はこのアパートと別に、分譲マンションも所有していた。川崎市で不動産会社を経営しているパトロンが去年の誕生日プレゼントに買ってくれたらしい。彼女はそのパトロンのことを「じるさん」と言って話しに出した。最近開発が進捗し利便性の良くなった武蔵小杉駅前の高層マンション群の中でも、新鮮な朝摘み野菜を出すホテルのような清潔感のあるマンションだ。「オートロック付きで毎朝清掃員が隅々まで掃除をしてくれて、月一回植木職人さんが敷地の植木を丁寧に剪定してくれて、24時間営業のコンビニが内蔵されているのよ。住人は銀行やゼネコンの役員や自営業者が多くて、何人かの著名人も住んでいるのよ。」ということだ。それじゃあこのアパートとは設備も価格も条件もまさに雲泥の差なのに、カエコはそのマンションには帰らず、ほとんどの時間をこのアパートで過ごしていた。
「いくつか理由があるんだけど、こうゆう汚くて今にもぺしゃんこになっちゃいそうな部屋の方が寂しくないし、なにをするにも楽なのよ。あっちの部屋は周りがファミリーとかお堅い人ばかりだから近所付き合いに気を使うし、新興住宅に年頃の女が一人ってなんだか変じゃない?私はおかしいと思うのよ。でもここは窓を閉め切ってたって中国人の荒げた声がいやでも聞こえるし、ちょっと歩いただけでもナンパされるし、おいしいご飯屋さんも沢山あるし、近くに「電磁波」もあるから楽しいじゃない。」
といって加絵子は瞳孔の開いた目で笑った。
「混沌を求めているのよ。私ってadhdだからこういう場所のほうがあってるのよ。忙しなくてめまぐるしくて混沌としている場所に身を置くべきなのよ。つまり、だから私も混沌もお互いに求め合ってるのかもね。」
カイは暗雲が加絵子を巻き込みながら渦巻いているところを想像した。「なんでそんな場所に自分から行くのか俺には分からないね。」
「混沌はシンプルなのよ。」と彼女はきわめてはっきりと言った。
カイにはそれに対して気の利いた言葉を返す術が無かった。
加絵子のアパートに到着したのは夜の十時ごろ。炉灰色の雲はすっかりどこかへいったらしく、藍色をした夜空に刃物のような三日月が鋭く浮かんでいた。石垣で囲われたアパートの地面に、所狭しとドクダミがかたまって生え、独特の強い匂いを辺りに発した。葉の裏では毛玉のような小さな昆虫が跳梁し、微視的なコロニーがそこで営まれていた。カイは葉をめくって観察した。そして虫を一匹手に取り、力いっぱい潰した。黒く粘ついた体液みたいなものがべっとり手についた。カイは芥川龍之介の「蜘蛛の糸」を思い出した。こんなことをしたら、極楽の蓮池をぶらぶら御歩きになってる御釈迦様も何も施してはくれないだろうな。そう思ったカイは自由な気持ちになっていた。俺は天上天下どこにも繋がれてはいない。それからカイは加絵子と覚醒剤を打ってセックスするところを想像した。そしてチャイムを叩くように押した。30秒後、ドアがギィと軋んだ音をさせ開いた。
「やあ。」
「待ってたわよ。」
部屋からは暖かい加絵子の匂いがした。
人工的な光に身を焦がすほど酔狂する蛾を生き写したように、彼女の匂いに誘われるままに部屋に入ると、加絵子は笑った。
「寒かったでしょう。」
「まぁまぁね。」
「よく来たわね。今コーヒーをいれるから座ってて。」
加絵子の瞳孔はすでに開いていた。声が奇妙に響いて、部屋の空気がゆがんだ。彼女は薄ピンクのスリップに灰色のカーデガンを羽織って、髪をポニーテイルにして、落ち着きなく眉毛を上下させていた。
「まさかもう何かキメてる?」
カイは床に散らかった荷物を足でどかして座ると、瞳を覗き込むように聞いた。加絵子は開いた瞳孔でカイを吸い込もうとしながら、質問を予期していたようにすぐ返した。
「もちろんよ。これからカイにもそれをふるまおうと思って。」
加絵子はそう言うとカイの手の上に手を重ね、その手にぐっと力を入れて立ち上がり、そのまますり足で台所へ向かって墨汁のようなコーヒーをマグカップに注いで戻ってきた。マグカップには真っ赤なペイズリー柄が施してあった。加絵子はカイの目前にすわり、にやにやしながらlsdをマグカップに落とした。
「このlsdはオウムって種類ので、オウム真理教が作ったんだって。」
「なんだそれ。」
前にムツゴロウさんの栽培した大麻だと言われて買ったものが、実は知人が栽培したものだった経験があるカイは間に受けなかった。ドラッグ業界は末端になればなるほどこういった出鱈目商品が蔓延している。このlsdだって怪しいものだとカイは思った。加絵子がそれを信じきって言ってるのか、はたまたそういって服用することで何かしらの相乗効果を期待しているのかカイには分からなかった。
加絵子はそんなカイの顔を察して、自信に満ちた語気で言った。
「確かなルートから引いてきたから間違いないわ。それに実際に今の私、すごくいい感じにキマってるよ。」
「そうかい。知っていたつもりだったけど、やっぱり君は危ない子だね。とんでもない獰悪人間につかまった気がするよ。」
「何よそれ。それがご馳走してくれる人に対しての態度なの?」
加絵子は眉毛をはげしく上下させながら言った。
「すんません。」といってカイは加絵子の瞳孔の中でにたにた笑いコーヒーを啜った。
体に異変が訪れたのは、コーヒーを飲んでから一時間ほどたったころだった。
最初は全身の毛細血管が痺れた。ジリジリと身体全体に唸るその痺れは、苦痛には程遠い土地で顔を赤らめた快楽であった。次に口が渇き始め、順に喉が渇き、みるみる渇きは食道まで拡がった。「水もらうよ。」と放った言葉が変換されて「ミ 図 漏 螺 ぅ 夜」とカイに跳ね返ってきた。気を抜いていたカイは跳ね返ってきた文字をもろに受けてしまったが、あまり害のある文字に変換されずドッジボール球程度の威力だったので、なんとかふんばって、水をとりに冷蔵庫へと立ち上がった。洋服とごみが無惨に散乱する下に、ひっそりと姿を見せるくすんだフローリングを踏み出すと、フローリングが足の裏をくすぐるように波打った。カイは飛び上がりたくなったが、その衝動を抑えて冷蔵庫を目指した。目前の冷蔵庫は奇怪にも蝋人形のような無機質な細い手を生やし、三日月のようなうすら笑いを浮かべている。すると冷蔵庫はカイにむかってあんぐりと大きく口を開き、ホオジロザメのようなヤマギリ歯をむき出しにして、中からペットボトルの水、オレンジジュース、古くなったキュウリ、瓶入りの梅干し、マーガリンを覗かせて、「ハハハハハハハハハ。」と厭味っぽく笑った。カイは冷蔵庫が憎たらしくなってきた。燃やしてやりたくなった。すると冷蔵庫はさらに笑い声を強めながらシュウシュウ煙を出し始め、しばらくするとゴウッと勢いよく発火し、みるみるうちに火を纏い、大気焔を吐いた。
「ハハハハハハハハ。君の望み通り燃えてみたんだけど、どうでしょう?それとも君自身の手で燃やしたかったですか?ハハハハハハハハ。しかしそう簡単にはいきません。願望と言うものは自分の望んだ形でやってくるとは限らないのです。」冷蔵庫は笑い続けた。
「なになに?今までも何度かlsdをやった事があるが、こんな莫迦みたいな幻覚を目の当たりにしたのは初めてだ。なるほどなるほどきっとそうでしょう。だってあなたが服用したlsdは通常の濃度の三倍のリキッドがたらしてありますから、だいぶ効くでしょう。そうしてあなたが今見ているものはあなたの心が顕在化されたものなのです。つまり私はあなたの心の一部なのです。ハハハハハハハハハハハハハハハハ。」
カイは肝を潰した。正面にいる冷蔵庫を見ていると、下半身の力が抜け、小便を漏らしてしまいそうになった。冷蔵庫を見ていられなくなったカイはやテーブルの上の灰皿に視線を逸らした。すると見られるのを待っていたかのように灰皿の中のわりと長い吸殻が話し始めた。「なぁ、これから俺たちはどうなるのかな?」それを聞いたキャスターがセンチメンタルに「先は暗いでしょう。公の場所は禁煙ばかりですし、値段もまだまだ上がっていくでしょう。体には害がある、金もかかる、しかも吸える場所は日々縮小している。どれをとっても煙たがられる要素じゃありませんか。それなのに我々は存在し続けている。今後も国家予算収集の名目を背負い。そして政府直下の公認商品として健全な国民に有害物質を吸引させ代わりに金を吸収する。あぁ。私は自分の存在価値に打ちのめされそうです。」と、ほとんど一呼吸で言った。「そういう意味なのか?俺ら吸殻になっちまったが、このままごみくずみたいに捻り捨てられて終われるか!って事だろ?」と言ったショートホープがみるみる捻れていく。キャスターはあぁ。と言って力なく二度うなずいた。それを聞いたメンソールの吸殻は鼻で笑いながら言った。「ふんっ、けれど俺らは結局のところこのまま吸い捨てられる命なんだよ。吸い捨てられてそれで終わり。そうでしょ!?」「まぁそうかな。」とわりと長い吸殻がひくつきながら言う。「俺を見てみろ!こんなに短いじゃねーか!!これはな!人間が最後の最後まで味わえるように改良された結果だ!俺がタバコ界の究極進化態だ!」ショートホープがぶちっとちぎれた。周りにタバコの葉っぱが散らばった。メンソールは呆れ気味に笑いながら体をくの字にさせた。「やれやれ。」ちぎれたショートホープはタバコの葉っぱを散らばせながらメンソールに向かってのしかかった。「なんだ貴様突然!?」くの字の吸殻がばたつく。「うるせぇ!お前みたいなスカした奴にはこうしてやるのが一番効くんだ!!」「おい落ち着けよ!」ひくついた吸殻はわりと長かった。「あんたは黙ってろ!!!」なぜかのしかかられたメンソールが仲裁を拒否した。灰皿の中は散らばったタバコの葉っぱと吸殻と灰で騒然となった。隣で見ていたマールボロライトの箱が歓声を上げた。カイは混乱してきた。
もう一度冷蔵庫に視線をむけた。すると冷蔵庫は笑いながらドアポケットの卵入れを無機質な細い手で雑巾のように絞り、コンセントプラグを元気の良いゴールデンレトリバーの尻尾のように振り回していた。
「ハハハハハハハハ。支離滅裂とはこのことですね。まさに君の人生そのものだ。しかし私は思うのですがね、そういった人生の方が面白味があるというもんです。品行方正。ハハハハハハハ。確かに素晴らしいものです。しかし私には素っ気無いものに感じてしまう。人生が最終的に黒で塗りつぶして終わる絵だとしたら、最初から一貫して黒を塗り続けて完成させるのと、様々な色を混ぜて最後に黒を塗りつぶして完成させるのでは意味が全然違います。後者には最初から一貫して黒を塗り続けたものには無い深みがあります。ハハハハハハハハ。だから私は結構君が気に入っているんだよ。おや?のどが渇いていらっしゃるようで。水なら中に入ってますからどうぞお取りください。遠慮など要りません。私はあなたの気持ちがよく分かるんです。そしてそこからアドバイスを見出すことも出来ますよ。最高のパートナーになれると思いませんか?どうぞ水をおとり下さい。なになに?噛み付きやしないよ。ハハハハハハハハ。」
カイは混乱のあまり、冷蔵庫のように口をあんぐり開けて、よだれを床にぼたぼた落としてしまいそうになった。けれど幸いにも口の中はからからに乾いていたので、よだれを落として床を汚すことはなかった。
「どう?すごい?」
カイは加絵子の声にギョッとしたが、彼女の姿を認めすぐに安堵した。
「これは効くわ。無機物に説教たれられたわ。」
「でしょう!私なんかハンガーに求婚されちゃって、私あなたとは結婚できないわって言ったら今もそこでしくしく泣きながらこっちを見てるのよ。」と困った顔をしながら加絵子は笑った。
「加絵子は垣根なくゲテモノに好かれるのかもな。今度は洗濯ばさみに告白されるんじゃないか?」
「嫌ね。ハンガーの求婚はわりとスマートだったわよ。それに洗濯ばさみに告白されるのもわるくないかも。」加絵子はそう言って眉毛を上下させた。
「ははぁ。加絵子はもの好きだな。だから俺みたいなやつも受け入れられるんだな。」
「あなたはほんと偏屈ね。そうゆうとこは、まぁきらいじゃないけどね。」
加絵子と話したおかげでだいぶ意識が現実に戻ってきたカイだったが、しかしまさか冷蔵庫に諭されるなんて思ってもみなかったので、虚勢を張ってなんとか立っていた。狼狽しているのを加絵子に悟られまいと、カイは震える息を肺にねじ込むように深呼吸をして、痺れた手で冷蔵庫から天然水のペットボトルを取った。冷蔵庫は言ったとおり噛み付いてこなかった。キャップをひねり天然水を一気に口に含むと、口の中で水の元素記号が蠢いた。となりでは加絵子がそのようすを嬉々としてみていた。元素記号が口内でとび跳ね、普段飲む水よりも舌触りがざらざらした。
「味の奥の奥まで分かるでしょ?」
とび跳ねる水を飲み込むのに手こずっているカイは、ようやく飲み込めてから答えた。「なんだかケミカルの味がするね。」
「本当の天然水なんてコンビニとかスーパーじゃ売ってないものよ。どうせナトリウムとかバナジウムの粉末を派遣のバイト君達が眠たい目をこすって水道水にかき混ぜて作ってるんでしょ。だいたい出回ってるものってそうゆうものよね。だから私はそれを分かっていて受け入れるわ。分かっていて受け入れるのと何も分かってなくて受け入れるのってかなり違うことだと思わない?」
そう言うと加絵子はカイの首に腕を回してキスをした。加絵子の舌がどんどん侵入してくる。二人はお互いの舌を味わった。口の中に残っていた元素記号がとび跳ねるのをやめ、加絵子の唾液で融解していった。カイは左手で加絵子の右乳を優しく掴んだ。かさねた唇の隙間からいい匂いの吐息が漏れた。開ききったお互いの瞳孔を見つめあいゆっくり唇を離すと、混ざり合った唾液がしなる吊り橋のように糸を引いた。
「この世は嘘と本当の混沌よ。今日も明日も明後日も、きっとこの先ずっとよ。私が欲しい?」
「君が欲しいな。」
「好きよ。でもまだ駄目よ。もうひとつ段階を踏みましょう。」
「我慢できそうにないな。」
「我慢して。我慢すればもっとよくなるから。」
「わかった。君の言うとおりにするよ。」
加絵子はもう一度カイにキスするとベッドの横の棚にある引き出しを開けて生理食塩水と注射器を二本持ってきた。そしてポニーテイルにしていた髪を解いて髪を束ねていたそのゴムで左腕を縛った。粉々になった硝子のような結晶の粉末を外筒の中にメモリ6まで入れ、生理食塩水をカイの飲んでいた天然水のキャップ一杯分入れた。結晶は水をかけられて怒ったように踊り、それからバターのように静かに溶けた。加絵子は忘れられた深い古井戸のような瞳でそれを確認すると、押子をはめ込み静動脈へ一気に針を刺した。「カイ、私を見てて。」と加絵子が言う。ゆっくり押子を押す加絵子の瞳が恍惚に鈍く光った。カイはその瞳の中に落ちた人が助けを求めて懐中電灯を空に向かって振っているのだと思った。注射器を腕に刺した加絵子は、か細く呼吸していた。小さな胸がふくらんだ。針を抜くと鮮血が一滴、加絵子のきめ細かい白い肌に浮かんだ。
彼女は今にもほどけてしまいそうなほど儚く、国宝級の絵画を見ているようにうっとりと空を見ていた。しかし彼女は空を見ていながら何も見ていなかった。或いはまったくの別世界をそこに見出していた。カイは息を呑んだ。美しい。その美しさは散らかったこのアパートの部屋にはそぐわない美しさだった。しかしそれについての答えは加絵子からとっくに聞いていた。
「私も混沌もお互いに求め合ってるの。」つまり彼女は自分から求めてこうしているのだと。世の中は不思議なことばかりだ。とカイは思った。
「次はカイの番よ。私がやってあげる。」加絵子の声がカイの短い髪をなびかせた。カイは我に返った。
「自分でやる。ゴムを貸して。」
加絵子はゴムをカイに渡すと「セッティングは私がするから。」と甘ったるい声をだした。カイの髪が午後の芝生のように揺れた。カイは左腕にゴムを縛った。そして静動脈が浮き上がるのを静かに待った。次第に浮き上がった血管は、ミミズのようにくねくね動いて自分とは別の核で動いている生き物みたいになった。
「お前も快楽と絶望の混沌を味わいたいんだろ?求めてるんだろ?」ミミズがくねくね動いて言った。お前の言う通りかもしれない、ミミズ。
「出来たわ。はい。」
「うん。」
カイは注射針をミミズのような血管に刺した。鈍い痛みが左腕に走った。カイは「やっぱりこいつは俺か。」と暗に嘲笑した。押子を押すと薄荷のようなスゥーっとしたものが身体に入ってきた。二、三秒後脳味噌がガツンと揺れ、そこからは寝起きの良い朝のような爽快感が全身を覆った。
「君が欲しいな。」
「いいわよ。」
それから二人は獣のように貪り合った。
カイは加絵子の顔をみつめ、六度目の絶頂に同時に達した。
身体のあちこちが痙攣し、頭の中は真っ白だった。
カイは加絵子の注文通りに膣の中で何度も射精した。
加絵子が痙攣しながら腕をカイの背中にまわした。カイは挿入したまま、陶器のようにつるりとした加絵子の身体にもたれかかった。加絵子も意識がそこにはなく、暗闇の中を手探りでものを探すようにカイの身体を撫でまわした。しばらくして加絵子の意識が戻ってくると、カイの背中にいたずらっぽく足をからめ、カイの胸に顔を潜り込ませ、乳首を愛撫しはじめた。カイの股間がまたうずいた。
加絵子はその体勢で
「私は本当に好きな相手にしか中出しさせないのよ。」
と微笑した。
「本当に好きな相手が100人居たら?」
「本当に好きな相手に出会えるのなんて、生きてるうちにせいぜい3,4人ってところよ。」
「でも俺達の人生はまだ始まったばかり。」
「せいぜい3、4人ってところじゃないかしら。に訂正するわ。それに少なくとも今の私はカイ以外好きな相手はいない。」
「俺は生まれてから加絵子以外好きな相手はいない。」
「嘘よ。」「嘘じゃないよ。」「いいえ嘘よ。」「どうして。」「分かるのよ。私もだから。」
加絵子は笑った。彼女の瞳の井戸に落ちた人は懐中電灯を振るのをやめ、空に向かって手を伸ばしていた。
「私ってadhdだから頭の中でやりたい事が一気に出てきて忙しいわ。今、何からしようか整理してるの。部屋の掃除もしたいし友達から頼まれたネタの仕分けもしなきゃ。あっ、その前にお風呂に入るべきかしらん。カイに沢山汚されちゃったもの。」
と加絵子はこめかみの辺りを軽く手で押さえた。
部屋は洋服と食器と空き缶が散乱し、いつのか分からない飲みかけのジュースがこぼれて床がべとついていた。部屋の角には埃が綿あめみたいに溜まっていて、化粧品が靴と一緒に玄関に投げてあった。閉じたノートパソコンの上に醤油さしと埃を被ったシナモンの瓶が場違いに置いてあった。奥の窓からタクシードライバーと酔っ払いの喧嘩が聞こえた。
「そうだね。それがいい。」
カイがさっきまで硬くなっていた陰茎を膣から抜くと、加絵子は小さく声を上げた。その声が奇妙に誇張されてカイの頭を痺れさせた。カイは加絵子の膣口から垂れる白い粘液を見つめた。
ドープ